脳卒中
私事ですが、5ヶ月前くらいに生まれて初めて“閃輝暗点”を経験しました。
※閃輝暗点とは

こちらのサイトに詳しい解説が出ています。
頭痛がない場合
症状は一時的なものとして、特に治療は必要ありません。しかし何度も繰り返し起こる、なかなか治らないというときは眼科を受診しましょう。
頭痛を伴う場合
頭痛を伴う場合はもちろん、手足のしびれを感じる場合は脳神経内科・脳神経外科を受診しましょう。閃輝暗点は何らかの前駆症状として発生しています。その原因を突き止め、治療しないことには閃輝暗点の症状も改善しません。根本的な治療から始めましょう。
頭痛等、頭(脳)に関する違和感は何もなかったことと、右目の視力が気になっていたこともあり、今回は眼科に行きました。診断は“閃輝暗点”で、「今後、繰り返すようであれば脳も調べましょう」。ということになりました。
それから約1カ月後、専門学校時代の友人(といっても20歳近く年下)と、数年ぶりに会う機会を作ったのですが、彼は「入江FT」に熟知した鍼灸師で、飲んでいるときに「左脳が少しスティッキーだと思います」。とのことでした。
友人には1ヶ月前の“閃輝暗点”の話など、一切していなかったので、このいきなりの発言に正直驚きました。
「医者に行った方が良い?」と聞いたところ、検査をしても分からないレベルだと思うとのことで、生活習慣の他、入江FTの独特な施術法(週1回、20分程度)を教えてもらいました。時々サボってしまうことはあるのですが、続けるよう努力しています。
※入江FTとは、大村恵昭先生先生が開発されたオーリングテストを応用したものです。オーリングテストはアプライドキネシオロジーをベースにした診断法とされています。
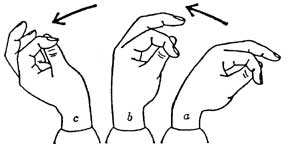
『漢方家であられた故・入江 正先生が漢方(湯液、鍼灸)のために開発した独自の診断法で、軽く指をスライドさせるだけで、他の筋力テストとは異なり、診断に利用する指に殆ど筋力を使わず、非常に微妙かつ精密な診断ができます。』
独特な診断法なので、なかなか信じて頂くのは難しいかもしれません。
さらに気になることは、この頃かこの前後かはよく覚えていないのですが、従来の血圧が収縮期、拡張期とも10mmHg前後高くなっていました。
「この血圧が少し高くなったのは何故だろう?」。遠慮することもなく、思ったことをそのまま“アスクドクターズ”にぶつけてみました。
『加齢による病的とはいえない程度の微細な梗塞があり、脳内の血流を低下させ、それが原因で脳の血流を本来の状態に維持するため、心臓のポンプの働きが増して、血圧をそれぞれ10mmHg程度上げているのではないでしょうか?』
回答は「No」ということでしたが、お一人の医師の方から、“脳血流自動調節機能”というものが脳には備わっているということを教えて頂きました。
この機能は脳自身が本来の血流を確保するために保持しているサーモスタットのような仕組みです。
「いろいろあるなぁ」と思い、少し検索してみると以下の医学雑誌を見つけました。
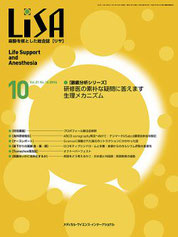
興味の方が勝って購入しました。
「何故、血圧と塩は関係が深いのか」について発見があったのでお伝えします。
【腎血流における自己調節のメカニズム】
『腎臓も強い自己調節を有している。これは腎血流そのものを維持するというよりも、糸球体濾過量(GFR)を維持するためであろう。GFRを一定に維持することで、生体は体液や電解質のバランスを保っている。
腎臓の自己調節のメカニズムは特殊であり、そのメカニズムは尿細管糸球体フィードバックと呼ばれている。腎臓は傍糸球体装置の遠位尿細管に存在する緻密斑において、塩化ナトリウム(NaCl[塩])の濃度を感知して腎細動脈の血管抵抗を変化させている。血圧が低下すると糸球体の静水圧が低下し、GFRが低下する。』
長い前置きでしたが、今回拝読させて頂いたのは、『脳卒中 専門医が説き明かす 病気の前兆・急性期対処法・予防法』という本です。何はともあれ、基本的なことを知りたいと思い購入しました。
目次
第1章 脳卒中ってなに?
●脳卒中ってなに?
・「出血」
・「虚血」
●脳卒中のメカニズム
・脳出血のメカニズム
・くも膜下出血のメカニズム
・脳梗塞のメカニズム
第2章 脳卒中―その原因?
●脳卒中の危険因子
・高血圧
・喫煙
・脂質異常症(高脂血症)
・糖尿病
・心房細動
・過度の飲酒
・コントロールできない危険因子について
●脳卒中を起こすその他の病気
●脳卒中と加齢現象
コラム セカンドオピニオン
第3章 脳卒中かな?
●くも膜下出血の症状
●脳梗塞・脳出血の症状
・痛みについて
●実例解説
・突然の激しい頭痛/嘔吐/意識障害
・物が二つに見えて歩くとよたつく
・左側がよく見えない
・右手と右の口角がしびれる
・左手と左足に力が入らない
・急に右手と右足が動かなくなり、意識状態も悪く話せなくなった
・左半身がしびれたと思ったら、だんだん左側が動かなくなった
・言葉が話せない
・突然倒れて、左側がまったく動かせない
コラム 脳卒中を疑ったら救急車
第4章 脳卒中―知ってて安心 治療法あれこれ?
●くも膜下出血の治療
・クリップ術
・血管内手術(コイル塞栓術)
・急性水頭症に対する治療
・血管攣縮に対する治療
●脳出血の治療
・外科療法
・薬物療法
●脳梗塞の治療
・急性期の治療
●慢性期の再発予防
第5章 脳卒を予防するには?
●高血圧のコントロール
●脂質異常のコントロール
●糖尿病のコントロール
●喫煙のコントロール
●心房細動のコントロール
第1章 脳卒中ってなに?
●脳卒中ってなに?
・脳の血管の病気によって急に発病する病気が「脳卒中」である。
・虚血は約75%、出血が約25%である。
・「出血」
-脳の中(脳実質)に出血するのが「脳出血」で約80%。
-くも膜と脳の間に出血するのが「くも膜下出血」で約20%。
・「虚血」
-脳の動脈が詰まってそこから先の脳の一部の組織が死んでしまうのが「脳梗塞」である。
-静脈が詰まるのが「脳静脈血栓症」だが、これは稀な病気である。
-[一過性脳虚血発作(TIA)]:脳の血液は5分間ほど途絶えると組織は死んでしまう。血流が再開すれば症状は一時的で元に戻る。そのような症状が軽いものを一過性脳虚血発作という。発症後の3ヵ月間で約20%の人は脳梗塞を発症、しかもその半分は2日以内に起こると考えられている。従って、一過性脳虚血発作後は速やかに病院に行くべきである。
●脳卒中のメカニズム
・脳出血のメカニズム
-[高血圧性脳出血]:穿通枝と呼ばれる細動脈(1mm未満)が破れることによって発症する。これは高すぎる血圧が血管にダメージを与え続けついに破れる。
-出血部位は「被殻出血」「視床出血」「小脳出血」「橋出血(脳幹出血)」である。
-[アミロイド血管症]:アルツハイマー病の原因とされているアミロイド蛋白が、脳の表面の比較的浅いところにある細い動脈の壁に溜まったもの。
-[動静脈奇形(血管奇形)]:比較的若い人に起こる脳出血では血管の奇形による場合がある。
・くも膜下出血のメカニズム
-脳は3層の膜で覆われている。外側から硬膜、くも膜、軟膜である。くも膜と軟膜の間にくも膜下腔という隙間がある。ここには髄液が流れており、このくも膜下腔に出血するのがくも膜下出血であるが、外傷による出血の場合はくも膜下出血とは言わない。外傷によらない出血の原因の大部分は動脈瘤からの出血である。
-動脈瘤は動脈にできた袋状のコブのようなもので、比較的太い動脈の分岐部にできることが多く、脳の表面で出血する。極度のストレスや過労、急激な血圧変化、排便時の力みなどが引き金になる。
-突然の殴られたような激しい頭痛は出血時に頭蓋骨の中の圧力が一気に高まるためである。
・脳梗塞のメカニズム
-数ミリ程度の主幹動脈が粥状硬化(アテローム硬化:コレステロール等が血管の壁に堆積する)して厚くなり、血管が細くなったり閉塞したりする。このような脳血栓症を「アテローム血栓性脳梗塞」という。
-1ミリより細い動脈を穿通枝と呼ぶ。急に細い血管になるため血圧の影響を受けやすい。この穿通枝が動脈硬化を起こして詰まった状態を「ラクナ梗塞」という。ラクナ梗塞は小さな梗塞がほとんどなので、すぐに命の危険はないが運動神経を巻き込むと運動麻痺を起こす場合がある。ラクナ梗塞が増えていくと認知障害が現れる場合がある。
-アテローム血栓性脳梗塞もラクナ梗塞も、動脈硬化が原因であり、心臓の問題ではないため「非心原生脳梗塞」とも呼ばれる。
-上流から塊(栓子)が流れてきて血管を詰まらせるのが「脳塞栓症」である。塊は心臓の中か上流の太い血管の壁にできた血液の塊である。
-心臓内で塊ができる原因で1番多いのは心房細動である。左心耳に血液の塊ができ、それがちぎれて血液に乗って脳へ移動し血管を詰まらせて脳塞栓症を引き起こす。その他、急性心筋梗塞直後や心筋梗塞後の心室瘤、弁膜症、先天性心疾患などが原因とされている。これらを「心原性脳塞栓症」という。
第2章 脳卒中―その原因?
●脳卒中の危険因子
・高血圧
-血圧が高いと血管を傷つける。特にすべての脳卒中の原因になる。
・喫煙
-喫煙も高血圧同様、すべての脳卒中の危険因子だが特にくも膜下出血が多い。これは喫煙により脳動脈瘤が形成されやすいためである。
-喫煙は血管を収縮させる作用がある。また、活性酸素は血管内被や血管壁の平滑筋を傷つけ、動脈瘤につながる。
・脂質異常症(高脂血症)
-脂質異常症は血液ベトベト状態のことで、粘っこい血液が血管の壁に張り付いて血管に悪さをする。
・糖尿病
-非心原性脳梗塞(脳血栓症)の危険因子である。
・心房細動
-心原性脳塞栓症の一番多い原因は心房細動である。
・過度の飲酒
-脳出血とくも膜下出血については飲酒は完全に危険因子であるが、脳梗塞については、ごく少量の飲酒は必ずしも悪くないとされている。
・コントロールできない危険因子について
-日本人であること、加齢、家系、遺伝子については研究中である。脳卒中の中ではくも膜下出血が該当する。これは動脈瘤が家族歴と関係があるからである。
●脳卒中を起こすその他の病気
・動脈は外膜、中膜、内膜の三層構造になっており、この膜が傷つき血管の壁が避けるのが「動脈解離」である。日本人では椎骨動脈が頭蓋骨に入る部分で多くみられる。症状はどこの膜が損傷されるかによって異なる。
・「もやもや病」は原因不明の難病指定疾患である。内頚動脈が狭くなったり閉塞するとともに、血流を補うために細い動脈が細かい網のように発達する。この様子を血管造影などで観察するとタバコの煙のようにモヤモヤして見えるためにこの名前が付けられた。成人では脳梗塞の原因だけでなく、もやもやした血管が破綻して脳出血も引き起こす。
・「血管炎」は大小の動脈に限らず、静脈、毛細血管でも発症する。原因は解明されていないが、ウィルスや薬品に対する免疫の過剰反応によるものと考えられる。
●脳卒中と加齢現象
・脳卒中の1番の危険因子は加齢による血管の老化である。
第3章 脳卒中かな?
●くも膜下出血の症状
・一番の特徴は突発する激しい頭痛である。また、嘔吐や意識障害を起こすが、脳梗塞や脳出血のように手足の痺れで症状が始まることはない。ただし出血の後遺症として身体に麻痺が出る可能性はある。
・動脈瘤破裂による場合、数日前から膨らんだ動脈瘤によって脳の神経や組織が圧迫されることで、物が二重に見えたり、めまいや吐き気、軽い痙攣などの前兆がみられたりすることもある。少量の出血の場合の突発的な頭痛は、必ずしも激痛とはいえない。
●脳梗塞・脳出血の症状
・脳卒中は障害された部位により症状の発症場所が異なる。
-左脳中央前部:右半身の運動麻痺。
-脳後方部:視野障害
-右利きでは多くは左脳:失語症(前より⇒運動性失調[言葉を発せない]、後ろより⇒感覚性失語[言葉の意味が分からない])
-視床下:脳の視床は感覚の集合点で口角や手の感覚も司っているため、この両方にしびれがある場合は視床が関係している可能性がある。
-血栓溶解療法を受けるためには発症から3時間30分以内に診察を始める必要がある。
・痛みについて
-脳梗塞では通常、頭痛はない。これは、脳自体は痛みを感じず、痛みを感じるのは脳を包む膜や血管が引っ張られたり押されたりすることで感じるからである。
第4章 脳卒中―知ってて安心 治療法あれこれ?
●くも膜下出血の治療
・クリップ術(開頭手術)
-動脈瘤にクリップをかけて動脈瘤の中に血液が流れないようにして破裂を防ぐ。
-呼吸や血圧が安定していて昏睡状態ではない状態に適用可能である。
-直接動脈瘤を処置するので再出血予防には最も確実な方法とされている。
-脳の奥深くの場合は手術が困難である。原則として発症から72時間以内に施術する。
-クリップで対応できない大きさの動脈瘤や場所的に困難な動脈瘤で、大きなものはトラッピング術、小さすぎるものはコーティング術を行う。
・血管内手術(コイル塞栓術)
-開頭手術ができない場合や脳の奥深くのためクリップ術が難しい場合などに適用される。
-動脈瘤のサイズや大きな脳出血を伴っている場合には適用できない。
-足の付け根の動脈からマイクロカテーテルを入れて、脳の動脈瘤まで到達させコイルを瘤の中に詰め込み、瘤に血液が入らないようにする。
-開頭していないため、術中に再出血するとすぐに対処できない。また、瘤の中に血栓があると、押し出されて運ばれる危険もある。
-術野の観察はX線透視下になるので被ばくは避けられない。
・急性水頭症に対する治療
-くも膜下出血により脳脊髄液の流れが妨げられると、急性水頭症の状態になることがある。この場合、余分な脳脊髄液を体外に排出する(髄液ドレナージ)。また、長期的にドレナージが必要な場合は、シャント手術(脳脊髄液を排出するための経路を作る手術)を行う。
・血管攣縮に対する治療
-くも膜下出血では出血後4日目頃から14日目頃にかけて、出血にさらされた血管(動脈)が攣縮という状態になる時期がある。治療には抗血小板薬、血管収縮を抑制する薬、血管を弛緩させる薬を使って血流を保つようにする。場合によってはバルーンによる血管内治療を行う。
-この治療はクリップ術やコイル塞栓術といった再出血の治療後に行う。
●脳出血の治療
・脳出血は出血量が微量な場合はやがて吸収されてしまうので、症状もなく自分でも気づかないうちに治ってしまう。通常、抗血栓薬を服用していない場合は1時間程度で止血される。これらの原因の大部分は高血圧性脳出血である。
・外科療法
-開頭血種除去術:開頭して血の塊を直接取り除き止血する。
-CT定位的血種吸引術:頭蓋骨に小さな孔を開けて血種を細い管で血腫をふいだす方法。手術は出血部分が完全に止血されていなければならない。CT装置を使うので被ばくも避けられない。
-神経内視鏡手術:頭蓋骨に開けた小さな孔から神経内視鏡(ファイバースコープ)を操作して血腫を見つけて吸引する。
-脳室ドレナージ:頭蓋骨に開けた小さな孔から細い管を通して溜まった血腫などを排出するが、平均して1週間くらい留置しておく。これをドレナージという。
・薬物療法
-血圧を下げる薬:降圧目標は患者さんの状態を診ながら医師が検討する。
-むくみを抑える薬:脳浮腫により頭蓋内圧が亢進すると脳ヘルニアのリスクが高まる。この場合、浸透圧性利尿薬が使われる。
-痙攣を抑える薬:脳出血発症後、最初の2週間は「痙攣」がしばしば見られる。抗てんかん薬が使われる。
●脳梗塞の治療
・急性期の治療
-脳梗塞の治療は急速に進歩している。静脈注射のtPAは血栓を溶かす。太い血管閉鎖はカテーテルで除去する。いずれも時間との勝負である。
-静脈tPA血栓溶解療法:発症から4時間30分以内に投与する必要があるが、検査に約1時間かかるため、実際の猶予は3時間30分である。検査が必要なのは詰まった血栓を溶かし、血流を再開する際出血のリスクがあるためであるが、脳梗塞によって組織や血管が痛むため危険は高くなる。
-血管内治療:2015年以降、大腿動脈や上腕動脈の血管内にカテーテルを通して血栓を除去する方法は急速に進歩している。特にこの治療の利点は8時間まで対応可能な点である。
-虚血する箇所は時間制限があるが、それ以外の部位の機能は働いている。そのため、後遺症を最小限にするために、速やかに病院に搬送することが求められる。
●慢性期の再発予防
-高血圧、脂質異常症、糖尿病のコントロールと喫煙、節酒の徹底が重要である。
-抗血栓薬の服用。抗凝固薬で有名なワルファリンはビタミンKを避けなければならない。なお、これらの薬は出血すると止血に時間がかかるので注意しなければならない。
第5章 脳卒を予防するには?
●高血圧のコントロール
-脳卒中予防の観点からは血圧は低い方が良いが、低すぎる血圧は心臓の働き阻害するなど危険である。
-「白衣高血圧」や「仮面高血圧」などが指摘されているが、最近では家庭血圧が重視されている。測定は起床後(起床から1時間以内)と就寝前の1日2回の測定が望ましい。
※【家庭血圧】とは(オムロン様より)
●脂質異常のコントロール
-LDLやHDLなど人間が1日に必要とする総コレステロール量は1,000~1,500mgとされ、その3分の2か肝臓で作られている(内因性)。残りの3分の1は食物から作られる(外因性)。食物からの摂取が少ないと肝臓はどんどんコレステロールを作り、多いと控える。
-LDLとHDLの割合は食べ物や生活習慣に左右される。このLDLとHDLのバランスが崩れると「脂質異常」という状態になる。これは重要なポイントである。
●糖尿病のコントロール
-近年の研究では厳格な食事療法が低血糖発作を起こす原因になることが指摘されており、以前に比べるとやや緩くなっている。
●喫煙のコントロール
-大規模研究において、禁煙は冠動脈疾患、脳卒中、各種のガン、慢性呼吸不全などに有効であることが明らかになっている。
-タバコの煙の中には70種以上の発ガン物質が含まれており、特に有名なものはタール、ニコチン、一酸化炭素、シアン化水素、ダイオキシンなどである。
-タバコは喫煙者だけでなく、受動喫煙の問題も大きい。
●心房細動のコントロール
-心房細動は加齢とともに起こりやすくなるが、高血圧があると頻度は高くなる。
-心房細動の問題は左心耳に血液の塊ができやすく、それがちぎれて血液に乗って脳へ移動し血管を詰まらせて脳塞栓症を引き起こすことである。
感想
現在、食事は塩分の取りすぎに注意しています。また、日課にしているのが速歩(30分)と簡単な下半身の筋力および握力の強化なのですが、速歩を+10分(計40分)、簡易筋トレの回数を少し増やそうと思っています。
ご参考1:“脳梗塞の原因とは?症状や前兆・予防方法から治療の流れまで全て紹介!”
こちらは学研のCocofumpというサイトに掲載されていたもので、下の図もそこから拝借しました。
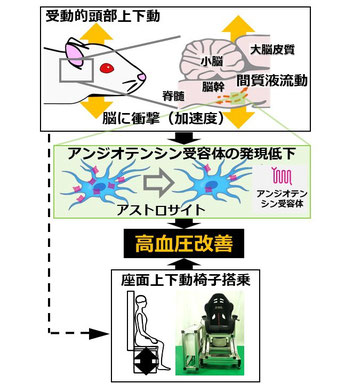
画像出展:「国立循環器病センター」
『軽いジョギング程度の運動中、足の着地時に頭部(脳)に伝わる適度な物理的衝撃により、脳内の組織液(間質液)が動きます。これにより脳内の血圧調節中枢の細胞に力学的な刺激が加わり、血圧を上げるタンパク質(アンジオテンシン受容体)の発現量が低下し、血圧低下が生じることが、高血圧ラットを用いた実験で分かりました。
さらに、この頭部への物理的衝撃を高血圧者(ヒト)に適用すると、高血圧が改善することを世界で初めて明らかにしました(図)。』
ご参考3:“血圧を下げすぎてはいけない!?脳梗塞の血圧管理”
高い血圧は下げるものと考えられていますが、脳梗塞の場合は慎重な血圧管理が必要です。
脳梗塞急性期に血圧を高めに保つ理由、それは、脳の血流が減少している状態であるため、血圧を下げることで脳のダメージが悪化する可能性があるからです。特に急性期の場合、“脳卒中治療ガイドライン2015”では、以下のように「止むおえない場合に限って、降圧治療を行っても良い」。ということが示されています。
『脳梗塞急性期には収縮期血圧>220mmHgまたは拡張期血圧>120mmHgの高血圧が持続する場合や、大動脈解離・急性心筋梗塞・心不全・腎不全などを合併している場合に限り、慎重な降圧療法を行っても良い』
なお、“急性期”をすぎ、"亜急性期”や“慢性期”については以下のようになっています。
亜急性期
●頚動脈や脳主幹動脈に50%以上の狭窄のない患者さんでは、徐々に降圧(85-90%、収縮期160mmHg程度)を行う。
慢性期
●収縮期140mmHg、拡張期90mmHgを目標に降圧を行う。
ご参考4:自分自身の家庭血圧

3月15日から4月7日までの19日間、朝(食前)、日中(15時前後)、夜(21時前後)の1日3回、血圧を測定してみました。
朝は127.3(収縮期)-75.9(拡張期)とやや高めでしたが。全平均は114.2-68.3と心配するような値ではありませんでした。
やはり、自宅で計画的に血圧測定してみることが必要だと思います。また、計測時は前傾姿勢にならないように注意しました。
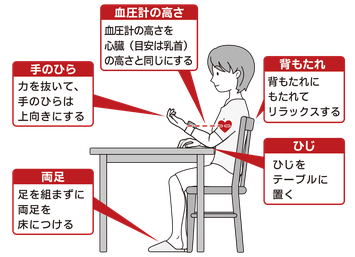
画像出展:「正しい測定方法で正確な血圧値(オムロン)」
コロナ worldometer
約1世紀ぶりのパンデミックに遭遇し、「これはいつまで続くのだろうか」という思いから、2020年8月初旬より『worldometer』というサイトを利用してデータを取り始めました。

『Worldometer は、開発者、研究者、ボランティアからなる国際チームによって運営されており、世界の統計を示唆に富む、時代に即した形式で世界中の幅広い視聴者に提供することを目標としています。これは、米国に拠点を置く小規模の独立系デジタル メディア会社によって発行されています。当社は政治、政府、企業とは一切関係がありません。さらに、当社にはいかなる種類の投資家、寄付者、助成金、後援者もいません。当社は完全に独立しており、複数のアド エクスチェンジでリアルタイムに販売される自動プログラマティック広告を通じて自己資金で運営しています。
新型コロナウイルス感染症に関するデータについては、政府の通信チャネルから直接、または信頼できると判断される場合には地元のメディアソースを通じて間接的に、公式報告書からデータを収集します。各データ更新のソースは「最新の更新」(ニュース) セクションに記載されています。タイムリーな更新は、世界中のユーザーの参加と、増え続ける 5,000 を超えるソースのリストからデータを検証するアナリストと研究者のチームの献身的な取り組みのおかげで可能になっています。』
当時のいきさつ等にご関心があれば、ブログ“スペイン風邪と新型コロナ2”をご覧ください。
当初は2021年末まで頑張ろうと思い、ほぼ毎日集計をしていましたが、2021年の年末もパンデミックが落ち着く様子はまったく見えませんでした。集計は2022年を経て、ついに2023年に入りました。「いい加減、きりがないな」と思い、「2023年末で止めよう」と考えていたところ、日本では5月8日にインフルエンザと同じ位置づけの5類に移行し、感染者数は定点観測として続いていますが、『worldmeter』の中では、日本の情報が全くアップデートされなくなったため、このタイミングで終わらせることにしました。
各国のデータの取り扱い、集計方法などは同じであるとは言えず、対象データなどもバラツキがあるため、比較するのはかなり無理があるのですが、そうは言っても、比較したいとの思いから「人口10万人当たりの死亡者数」のデータに絞り、日本以外では東アジアの韓国、台湾、東南アジアのフィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、そしてオセアニアのオーストラリア、ニュージーランドの計9ヵ国を比較することにしました。
なお、データは各国の集計開始時期を合わせるため2020年12月からとし、最後を2023年3月、月別にまとめでデータで集計しました。
最も少なった国はシンガポールの29.34人で、最も多かった国はニュージーランドの80.00人でした。単純に9ヵ国の平均値は60.58人、日本は4番目(下から4番目)に少ない58.52人でした。
地域的には東南アジア、東アジア、オセアニアの順です。特に東南アジアの4か国は2022年2月頃から横ばい傾向になっており、東アジア、オセアニアとは大きく異なっています。理由は分かりませんが注目に値します。
日本ではマスク着用など公衆衛生の意識が強く、ブースター接種は6回目、7回目を数える方もおり、他国に比べ積極的ではあるものの、今一つ、その積極的なワクチン接種が死亡者数の抑制につながっているのか不透明です。(ワクチン接種に関してご興味あれば“免疫学者の告発1”をご覧ください)。
グラフを見ると台湾、ニュージーランドなど多くの国が「ゼロコロナ」で規制をしたものの、「ウィズコロナ」に切り替えざるを得ない事態に遭遇したことが分かります。日本では規制の徹底が難しいこともあり、最初から緩やかな規制でスタートしました。PCR検査が一向に増えないこととや、保健所依存の対応、政府のリーダーシップの欠如等が大きな問題となっていましたが、緩やかな規制は悪くなったのだろうと思います。
2022年2月2日付けで、『デンマーク、コロナ規制を全て撤廃 EUで初』というニュースがアップされました。

『デンマーク国家保健委員会のソレン・ブロストロム委員長も、国内の症例数は非常に多い状況だが、感染と重症化の関係がなくなったとの認識を示し、「感染数が激増すると同時に、集中治療室に入院する患者は実際のところ減っている」「今現在、新型コロナと診断されてICUに入院しているのは、人口600万人のうち30人前後にとどまる」と指摘した。』
また、以下のような記事もありました。
以下は、HOPEプロジェクトに関してです。
『それではいったいどのような背景から、デンマークは規制撤廃に踏み切ったのか。ワクチン接種率の高さ、政府への信頼感、首相会見を頻繁に行うなどの情報開示、検査数の多さなど、すでに多くの分析や情報が日本のメディアでも発信されているが、ここでは引き続きピーターセン教授の発信をもとに、もう少し違った角度から紹介してみたい。
新型コロナウイルスが世界に拡大し始めた2020年3月。カールスバーグ財団から2500万デンマーククローネ(約4.3億円)の支援金を受けて、デンマークではある研究が開始された。不安と恐怖の真っただ中に始まった研究プロジェクトのタイトルはHOPE。「希望:民主主義国家はいかにしてCovid19に対処するか―データ分析をもとにしたアプローチ」と名づけられたこの研究チームのリーダーがピーターセン教授だった。
コペンハーゲン大学、デンマーク工科大学(DTU)などとの共同プロジェクトとして開始されたこのHOPEプロジェクトは、コンピューターサイエンス、行動心理学、政治学を組み合わせて、コロナ禍で民主主義社会がどのように反応し、危機に向き合ったのか、また危機管理は上手くいったのか、などを検証してきたのだという。
具体的には、パンデミックの状況を追跡し、政府および国際機関の決定や、メディアとSNSの影響力、市民の行動やウェルビーイングなどが互いにどのように関連し合っているのかを検証する、前例のない研究プロジェクトなのだそうだ。
さらにこのHOPEプロジェクトは、2020年11月から感染防止のための様々な規制を実施する上でデンマーク政府が参照すべきプロジェクトにも加えられた。そして今日まで、HOPEプロジェクトは政府へさまざまな提案をおこなってきた。』
日本に比べれば小さな国なので、対策の取りやすさには大きな差はあるものの、「デンマーク恐るべし!」と興味をもち、2022年2月4日からデンマークをデータ集計の対象に加えることにしました。以下はその一部ですが、これを見ると平日を対象に非常に詳細なデータ集計が行われています。「これは国レベルの情報管理(IT化)がよほど進んでいるんだろうな」と思いました。
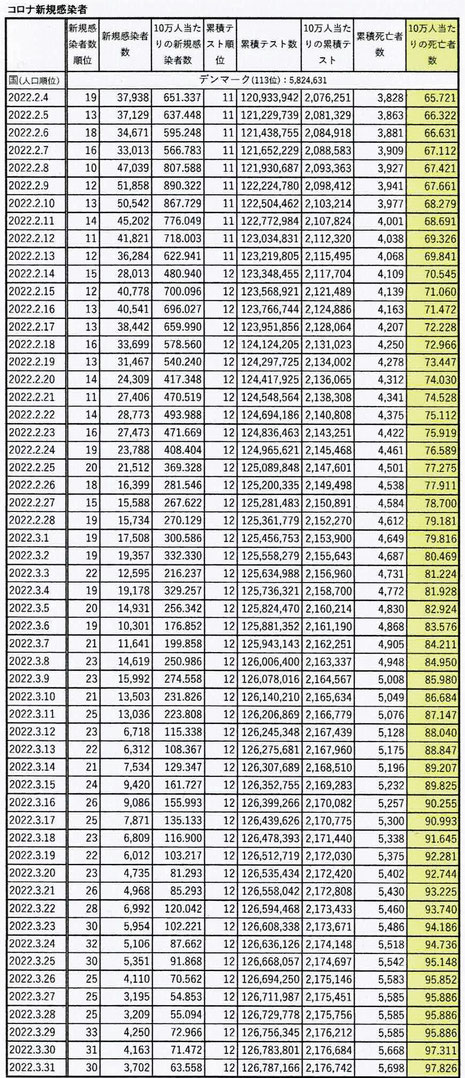
調べてみると、『デンマークのスマートシティ データを活用した人間中心の都市づくり』という本が出版されており、「これだ!!」と納得するとともに思わず買ってしまいました。
ちなみに“世界幸福度ランキング”では、デンマークはフィンランドに続き、第2位となっていました。
ご参考1:”高齢コロナ感染者の退院後死亡率、インフルより高い/BMJ”

180日間にわたり死亡リスクはCOVID-19コホートが高率
重み付けで調整後、COVID-19コホートはインフルエンザコホートと比較して、退院後の全死因死亡リスク(累積発生率)が、30日時点(10.9% vs.3.9%、標準化リスク差:7.0%[95%信頼区間[CI]:6.8~7.2])、90日時点(15.5% vs.7.1%、8.4%[8.2~8.7])、180日時点(19.1% vs.10.5%、8.6%[8.3~8.9])のいずれの評価時点でも高率であった。
上記はコロナ感染であって、ワクチン接種による問題ではないのですが、この記事は荒川 央先生の著書『コロナワクチンが危険な理由』に書かれた以下の文章を思い出します。
『心筋炎、脳梗塞、自己免疫疾患、癌、神経変性病などは加齢によってもリスクが高まる疾患です。こうした疾患がコロナワクチンの作用機序から予測され、実際に後遺症として報告されています。私はコロナワクチンによる隠れた副作用は文字通りの「老化」ではないかと思っています。』
※荒川 央先生のブログ:"コロナワクチンが危険な理由”
※ご参考ブログ:”免疫学者の警告1”
※ワクチン問題:“「ワクチン」による傷害に関する査読済み論文1,000件 Dr. Mark Trozzi”(凄いサイトです)
※ワクチン問題:”みのり先生の診察室”(医師である先生が来院される患者さんの変化を感じておられます)
ご参考2:”若年世代の老化が加速、がんリスク上昇の可能性”

『若い世代での老化が加速しており、それが若年発症型のがんリスクの上昇と関連している可能性のあることが、新たな研究で明らかになった。1965年以降に生まれた人では、1950年から1954年の間に生まれた人に比べて老化が加速している可能性が17%高く、また、このような老化の加速は、55歳未満の成人における特定のがんリスクの増加と関連していることが示されたという。米ワシントン大学医学部のRuiyi Tian氏らによるこの研究結果は、米国がん学会年次総会(AACR 2024、4月5〜10日、米サンディエゴ)で発表された。』
荒川 央先生の『私はコロナワクチンによる隠れた副作用は文字通りの「老化」ではないかと思っています。』という表現がとても印象的で頭に残っています。今回のニュースはコロナワクチンとの関連性を指摘するものでは全くないのですが、やはり気になります。
認知症の薬とインスリン
NHKのBS放送で“脳”に関する番組が目に留まりました。それは「人体神秘の巨大ネットワーク3 第5集 “脳”すごいぞ!ひらめきと記憶の正体」に関するものでした。
アマゾンで購入履歴を調べたところ以前に購入しており、おそらくその時は「人体神秘の巨大ネットワーク3」の第4集の「万病撃退!“腸”が免疫の鍵だった」に興味があって購入したものの、第5集は読んでいなかったということだと思います。
「これは買う手間が省けた」というところです。Partは以下の4つですが、ブログはPart4の「認知症撲滅作戦」を取り上げることにしました。
Part1 脳に広がる神経細胞のネットワーク
Part2 “ひらめき”の秘密
Part3 海馬に刻まれる記憶
Part4 認知症撲滅作戦
薬を通さない脳血管の特別な関門
●『長い人生を通して私たちの脳の中に築かれていく記憶のネットワーク。それがむしばまれることで引き起こされる病気が認知症だ。認知症の原因はさまざまだが、最も患者数が多いのがアルツハイマー病で、世界各国の研究者が治療薬の開発にしのぎを削っている。アルツハイマー病は、一説によれば「アミロイドβ」というたんぱく質が脳にたまり、神経細胞を壊すことで起こると考えられている。このアミロイドβを分解する薬を脳に送り込むことでアルツハイマー病の進行を食い止めようと、これまでも多くの薬がつくられてきたが、いつも大きな難題が立ちはだかっていた。薬を投与しても、脳神経細胞にまで届いている形跡が見られないのだ。
これまでその理由に関しては、さまざまな可能性が取り沙汰されてきたが、現在ではその有力な仮説として、脳の血管の特別な仕組みに原因があるのではないかと考えられている。通常、点滴や錠剤などを介して血液中に溶け込んだ薬の物質は、血液の流れに乗ってターゲットとする臓器へと移動し、血管からしみ出して臓器の内部に届けられる。それが可能なのは、血管の壁に薬が通れるだけのすき間が開いているからだ。
一方、脳の血管の壁の細胞は、互いに強く結合しているためほとんどすき間がなく、薬が通り抜けることができない。このような脳の血管の仕組みは「血液脳関門」と呼ばれている。英語ではBlood-Brain Barrier、文字通り脳を血液から守るバリアーだ。
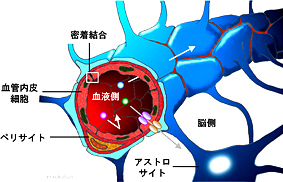
画像出展:「薬が脳に到達するメカニズムの解明に挑戦 日本大学薬学部」
『血液脳関門の実体は無窓性(つなぎ目のない)の筒(チューブ)状に連結された血管内皮細胞から主に構成されている。ヒトの脳毛細血管の細胞内容積は、全脳容積のわずか0.1-0.2%であるが、血管の全長は600Kmもあり、脳内を綱目状に分布している。』
血液脳関門を突破して脳に届きアミロイドβを分解できる薬は、まだ医療の現場に登場していない。
なぜ、脳の血管だけに、物質の侵入を簡単には許さない特別な仕組みがあるのだろうか。それは、私たちの脳の中で、さまざまなメッセージ物質がやり取りされていることと関係がある。
もし脳の中に、血液の中を行き交う他の臓器からのメッセージ物質が際限なく流れ込めば、脳は大混乱に陥り、神経細胞の働きに支障をきたすだろう。つまり、血液脳関門は脳に必要な物質を血液中に排出するという、脳の働きを健全に保つ重要な役割を担ってるのだ。
そのため、メッセージ物質の中でも脳の血管の壁を突破することが許されているのはごく一部、特別な役割をもつ物質に限られている。
例えば、すい臓から分泌される「インスリン」はその1つだ。インスリンはPart3でも紹介したように、「記憶力をアップせよ!」というメッセージを脳に伝え、海馬の歯状回の神経細胞を増やすという役割が指摘されている。さらに、インスリンが不足したり働きが不十分な場合は、認知機能や記憶機能に障害が出ることも分かっている。脳にとって欠かせない物質だからこそ、血液脳関門の通過を許されていると考えられている。
血液脳関門は脳を守るという点では役立つものの、薬を脳に届けようとするうえでは逆に大きな妨げになってしまうという、ある意味「諸刃の剣」となっているのだ。』
脳内に薬を届ける新たな仕組み
●血液脳関門を通り抜ける薬を開発することは、臨床医や製薬企業の研究者にとって大きな関心事となっている。
●この難問の第一人者はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)名誉教授のウィリアム・パードリッジ博士である。博士は15年前にベンチャー企業を設立し、新薬の開発の指揮を執っている。
●血液脳関門を通り抜けることができる数少ないメッセージ物質の中から、博士はインスリンに注目した。
●『パードリッジ博士はまず、血液脳関門を形づくっている脳の毛細血管を分離し、この毛細血管の中にどんな運搬機能があるのかを徹底的に調べた。そして、血管の内側の壁にはインスリンにくっつく小さな突起があることを突き止め、血液脳関門を突破する仕組みを解き明かした。』
●インスリンが血液脳関門を通り抜ける仕組み(CGです)
すい臓から分泌されたインスリンは血液の流れに乗って脳の血管に到達する。
脳の血管の壁を通過できるのは、メッセージ物質の中でも、ごく一部の限られた物質である。
脳の血管の表面には、インスリンをキャッチするための小さな突起がある。
突起がインスリンをキャッチすると、まるで“秘密の扉”が開くように血管の壁は陥没し始める。
●パードリッジ博士は、この突起にくっつく物質を作り出し、それに薬を結合させて血液脳関門を通過させる戦略を思いついた。
メッセージ物質が血管の壁を越えて、血管の中から脳へと向かう様子を捉えた写真。パードリッジ博士らが1985年に撮影に成功した。
カプセルのような薄い膜に包まれたメッセージ物質が、血管の壁を通り抜ける瞬間が映し出されている。
ハーラー病の子どもをすくえ!
●パードリッジ博士らが「認知症の新薬を開発するための第一歩」と位置づける臨床試験は既に始まっている。2017年10月、ブラジル南部のポルトアレグという街では、ハーラー病の3歳から16歳までの子どもたちが、週に一度、大学病院にやってくる。
●ハーラー病はグリコサミノグリカン(GAG)と呼ばれる物質が細胞の中に溜まることで引き起こされる難病であり、ライソゾーム病の一種である。ライソゾーム病は細胞内の小器官ライソゾームに関連した酵素が欠損しているために、分解されるべき物質が老廃物として体内に蓄積してしまう、先天性の病気の総称である。日本ではハーラー病など31種類のライソゾーム病が難病の指定を受けている。
血液脳関門を突破するプロジェクト
●ポルトアレグで行われている新薬の臨床試験は、アメリカの保健省の指導の下、1年半にわたって続けられてきた。試験に参加していたのは11名、症状が重い8人のうち7人に認知や運動面で症状の改善が見られた。
認知症治療薬の開発への応用
●ブラジルで臨床試験が行われているハーラー病治療薬の開発に成功すれば、世界中の2,000以上の子供たちへの朗報となる。また、ライソゾーム病全体で見れば罹患している子どもはもっと多い。
●アルツハイマー病の進行を食い止める薬の道筋も見えてくるが、パードリッジ博士らは同じ技術を用いてアルツハイマー病の新薬の開発にも取り組んでいる。
●血液脳関門を突破するカギとして注目されているのは、インスリンだけでない。日本では血液中の鉄を脳へ運ぶのに関係するトランスフェリンというたんぱく質に着目し、この物質を利用することでライソゾーム病の薬を脳に送り届けようと開発を進めている。
双極性障害3
2 ECT(電気けいれん療法)
・うつ病に対する治療法の中で効果は高く、即効性もあるため抗うつ薬の効果が乏しい難治性のうつ病に対して広く行われている。
・現在は麻酔科医による全身麻酔と呼吸循環管理のもと、痙攣を起こさないようにして行う、修正ECTが行われている。
・即効性があるため、自殺念慮が強い場合には是非試みるべき治療といえる。
・妄想、焦燥、昏迷などの強い重症のうつ状態なども修正ECTを検討すべきである。
・通常は週2、3回で6~12回程度繰り返すのを1クールとする。効果は直後、もしくは2、3回施行後から現れる。麻酔を行うためリスクもあり、自殺念慮、重症、難治性に対して行うものである。
・ECTの作用のメカニズムはよく分かっていない。
・双極性障害ではうつ状態で行うと躁転することがあり、慎重な判断を要する。また、何クールまで問題ないのかといった基準はないのでこの点も注意を要する。
3 反復性経頭蓋磁気刺激療法(γTMS)
・左前頭部にコイルを当てて、磁場を与えることで脳の中に電流を起こさせて刺激する治療法である。
・双極性障害のうつ状態に対しての有効性は明確になっていない。

先進医療.netより
『2019年3月、双極性障害のうつ状態に対する新たな治療法として、「薬物療法に反応しない双極性うつ病への反復経頭蓋磁気刺激療法(rTMS)」が先進医療として指定され、臨床研究が始まりました。rTMSの仕組みや長所、先進医療の流れなどについて、国立精神・神経医療研究センター病院 精神科医長の野田隆政先生に伺いました。』
・ 双極性障害の治療には主に薬が使われるが、患者さんによって効く薬や効果が異なる。自分に合った薬が見つからず、長期にわたって苦しむ患者さんも多い。
・ rTMSは、磁気や電気などの刺激によって神経の働きを調節する「ニューロモデュレーション」という治療法の一つ。磁気の刺激により、脳の神経の働きを調節することで、双極性障害のうつ状態の改善が期待される。
・ 双極性障害のうつ状態に対するrTMSは、先進医療Bの制度の下、2019年11月27日現在、全国3施設で実施されている。薬が効かない患者さんに対する新たな選択肢として期待される。
4 ケタミン
・現在臨床試験が行われており、数年以内には利用できるようになる可能性がある。
・これまでの抗うつ薬は治療効果が現れるまで1、2週間、治療期間が数カ月と長い時間がかかるが、この薬は1、2時間で効果が現れ、それが1週間程度持続するという、全く異なった効き方をする治療薬として注目されている。

『金沢大学医薬保健研究域薬学系の出山諭司准教授、金田勝幸教授、大阪公立大学大学院医学研究科脳神経機能形態学の近藤誠教授らの共同研究グループは、ケタミンの即効性抗うつ作用に関わる新しいメカニズムを解明しました。
うつ病の患者数は世界で約2.8億人と言われ、深刻な社会経済的損失をもたらします。しかし、現在うつ病の治療に用いられる抗うつ薬は、効果発現が遅く、3分の1以上の患者は治療抵抗性であることが問題となっています。2000年代の臨床研究により、全身麻酔薬として古くから用いられているケタミンが、麻酔用量よりも低用量で治療抵抗性うつ病患者に対して即効性の抗うつ作用をもたらすことが明らかとなり、大きな注目を集めています。ケタミンには依存性や精神症状(幻覚、妄想など)といった重大な副作用があるため、ケタミン自体の臨床応用には大きな問題が伴います。そこで、不明な点が多いケタミンの作用メカニズムの解明により、有効性が高く、かつ副作用の小さい治療薬の開発につなげることが期待されます。』
5 心理教育
●双極性障害は心の病ではない
・双極性障害の柱は薬物療法と精神療法である。
・精神療法というと精神分析やカウンセリングが思い浮かぶが、双極性障害は心の病ではない。
●身体の病気でも、精神療法は必要
・双極性障害は脳や遺伝子などの疾病であるが、発症はストレスが原因となることが多く、発症後も慢性的なストレスは双極性障害にとって好ましいものでない。
・精神療法は心理教育とよばれている。
●心理教育とは
・病気について勉強していただきながら、患者さんの心に起きるその病気に対する反応も十分に把握し、理解しながら進めていくということである。
・双極性障害の精神療法において、最も重要なことは心理教育である。基本は患者さんと医師一対一での心理教育である。それに加えて、ご家族とともに病気について学んでいただく家族心理療法も大切である。さらに夫婦や集団療法的な取り組みも有効である。
・心理教育ではまず病気の性質を理解し、次に薬の作用と副作用、そして双極性障害の再発の兆候に気づけるようになることが重要である。
●ストレスの対処法
・心理教育にはストレスに対する対処法もある。ストレスは再発のきっかけとなったり、躁やうつを繰り返す不安定な症状を引き起こしたりする。
●認知行動療法
・生活の中で起きる事態を見直して、ストレスを減らしていく方法をまとめたものが認知行動療法であり、双極性障害に対しての有効性が認められている。
・うつになり、嫌な考えばかりが頭に浮かぶような状態を「否定的自動思考」とよぶ。この「否定的自動思考」を抑えることは容易ではないが、出てきた気持ちが「否定的自動思考」であると認識して、別の合理的な考え方に切り替えていくことは、練習によってある程度はできる。
●対人関係療法(IPT)
・外来で行う個人精神療法である。
・特定の理論にはこだわらず、よく効くと言われている常識的な治療をまとめたものである。
・IPTの治療目標は、認知を変えることではなく対人関係のパターンを変えることである。
・IPTの対象は双極Ⅱ型障害のような軽症なものに限る。中等症以上は薬物療法が中心となり精神療法は補助的なものになる。
・対人関係の中では、特に三つのパターンに注目している。①「重要な人物の死」、②「役割をめぐる不一致」、③「役割の変化」である。3番目の役割の変化とは、例えば、昇進や結婚などによってうつ状態を発症することが多いということである。
●対人関係-社会リズム療法(IPSRT)
・双極性障害のために開発されたのが、対人関係-社会リズム療法(IPSRT)である。
・双極性障害では徹夜が躁転のきっかけになる。対人関係-社会リズム療法では、起床時間、入眠時間、出勤などの時間の目標を決めて、毎日、これらの時間を記録につけ生活のリズムを守るようにする。
●五分診療の中の精神療法
・症状の落ち着いた双極性障害の患者さんの外来診療は、短い方では5分~10分である。この診察を1、2カ月に1回程受けてもらい、その中で薬の副作用の有無を確認し、定期的に採血してリチウムの血中濃度を調べてて適正になるように調整する。
・短い時間の精神療法が意味あるものにするには、早い段階にどれだけしっかりと病気を受け入れ、その対処法の理解を進められるかどうかにかかっている。
第六章 双極性障害とつき合うために
●再発する人としない人の違い
・『このように双極性障害の患者さんには、すっかり薬が効いて、本人も病気をコントロールしようという意識が高く、十年、二十年と一回も再発せず、薬さえ飲んでいればまったく問題なく社会生活を送ることができている方もいらっしゃいます。
一方で、病気のために仕事や家族を失い、思うような人生を送れていない患者さんもいらっしゃいます。そのような両極端な違いは何なのでしょうか。
まずは、病気の初期に、どれだけしっかり予防の対策を立て、実践したかどうかです。
そしてもうひとつの違いは、薬がどの程度効くかです。
残念なことに、きちんと薬を服用しているにもかかわらず薬が十分に効かないという患者さんもいらっしゃいます。ですから、再発を繰り返している人に、簡単に「双極性障害はコントロールできるはずなのに、薬をちゃんと飲んでいないのではないか」などと思わないでいただきたいと思います。
医師はひとつの薬、リチウムだけで効果がなければ、ラモトリギンとかオランザピンなど、さまざまな薬を併用して、何とか予防をはかります。それでも軽いうつや躁が出てしまうこともあるのです。
このような場合には、うつになったら何らかの薬を増やし、軽躁になったら少し抗精神病薬を増やしたりと、その都度対処しながら治療を進めていきます。
リチウムやラモトリギンやバルプロ酸などである程度まで病状が落ち着いている患者さんの場合、それほど激しい躁状態にはいかないことが多く、躁状態になっても何とか患者さん本人も治療しようという気持ちになってくれて、入院するには至らないですむという場合も多くあります。
しかしながら、薬を服用していることによって、症状が軽くすんではいるけれども、現在存在する薬すべて使っても、やはり再発を予防するのが難しいという患者さんがいらっしゃるのも事実です。
今我々にできることは、病気がわかったらごく早いうちから、きっちりと予防対策を進めること、薬が効きにくい人には効かない人なりに、薬の組み合わせや投与量の工夫で症状を最小限に抑え、再発を予防するということです。
現在ある薬は必ずしも完璧ではありません。双極性障害の基本的な薬であるリチウムは、非常に副作用が強く、飲みにくい薬であることは、すでに述べました。手の震えなど、人によっては大変気になるところでしょう。
そのために服用をやめてしまい、また再発してしまう方が少なくありません。現在ある薬の副作用を少なくすること、今の薬が効かない患者さんのための新しい薬を開発すること、そして病気の原因究明、そういった研究は、絶対に必要だと思っています。』
●病気のコントロールには、まず病気を受け入れることが必要
『双極性障害の治療において最も重要なのは躁の治療でもうつの治療でもありません。むしろ症状がおさまった時、再発予防薬がきちんとなされるかどうかが、間違いなくその人の一生を左右します。
最初に述べたように、双極性障害は、以前は非常に軽く見られてきました。医師から見れば、躁になって入院して来ても、うつになって入院して来ても、患者さんはとりあえず、その状態が治って退院していきます。
そして治って退院するときには、最初の症状はもうすっかり治っています。そういったことで医師の個として双極性障害は治る病気だという意識が強かったのです。
これはこれで事実であり、統合失調症のように、陰性症状とよばれる症状が長く続く病気と違い、双極性障害は、一旦治ると何の症状もなくなるのが特徴です。患者さんは治ったと感じて安心するし、ご家族も、また医者ですらほっとしてしまうわけです。
ところがその一旦治った病気が、ほとんど再発します。またそれを繰り返すことによって本来は能力を持っている人が、その能力を発揮する場所を奪われてしまいます。会社を辞めざるを得なくなったり、家族と別れてしまったりします。そういう意味では大変恐ろしい病気でもあるわけです。
昔の医師も、おそらく退院する時には「この病気は再発しますから、ずっと薬を飲んでくださいね」と言っていたと思います。ところが実際は、そのくらいのことでは、多くの患者さんは薬を飲みません。
たとえば病院に行って「皮膚炎の薬です。これを朝夕一週間塗って下さいね」と皮膚科の先生に言われたとします。「はい。そうします」と答えて帰って来ても、症状がなくなってきたら薬を塗るのを忘れてしまうという経験はないでしょうか。
双極性障害の患者さんの場合も同じです。症状が治まったら薬を飲まなくなるということは、誰にでも非常によくあることなのです。
しかしその結果、結局患者さんは再発してしまいます。そしてこれまで繰り返し述べたように、双極性障害は、再発することによって、人生そのものが大きな影響を受けてしまう病気なのです。
病気との取り組みいかんで、病前と変わらない生活が送れる人から、仕事も家族も失ったという人まで、非常に幅広い、さまざまな結果が返ってきます。
より良い結果を得るためには、双極性障害とは大変な病気である、ただし十分にコントロールすれば恐れるに足らない病気でもあるということを知り、前向きに再発予防に取り組むことが何よりも重要なのです。』
感想
「双極性障害」の患者さまにとって、医師による診察と適切かつ慎重な薬物療法や、精神療法との組み合わせが極めて重要であることを学びました。
鍼灸師ができることはお話を伺うこと、そしてうつ病と双極性障害(躁うつ病)は異なる病気で、薬も療法も異なるということをお伝えすることだと思いました。
双極性障害2
第三章 社会生活を妨げてしまう双極性障害
1 双極性障害による社会生活の障害
●再発を繰り返すと仕事も家庭も失ってしまう
・双極性障害はいずれ改善され、治ったときにはほとんど何の症状も残さない。
・双極性障害の躁やうつは薬による病気のコントロールや予防をしっかり行わないと、何度も再発を繰り返してしまう。また、このため患者さんの環境や生活レベルは低下していく。
・双極性障害の発症頻度は100人に1人弱といわれており、家族、親戚、友人と範囲を広げれば、すべての人が双極性障害の患者さんに接する機会はあると言っても過言ではない。
2 立場によって受け止め方が違う双極性障害
●家族から見た双極性障害
・重度な双極Ⅰ型障害は統合失調症の精神病状態とは異なり、話の筋がある程度通っているおり病気と思えない部分がある。そのため、家族は非常に腹が立ったり、傷ついたり休みなく言葉を浴びせられ続け憔悴しきってしまうようなこともある。そして、仕事を失うこともある。
・家族にとっても、双極Ⅰ型障害の躁状態はうつ状態とは異なるがとても辛いものである。
●患者さんにとっての双極性障害
・躁状態の患者さんが自分は、病気であるという自覚を持つことが非常に難しい。
・軽躁状態を本来の自分と考え、通常の状態の時期が何かつまらないものに思えてしまう人もいる。
●うつ状態の時
・自分をつまらない人間で、仕事もできず取るに足りない人間だという気持ちが絶え間なく襲ってくる。
・家族が質問してくるのが、うっとうしくて仕方がない。
・子供に対してイライラして叱ってしまい、その後酷い自責の念に駆られますます落ち込んでしまう。
・何とか出社してもまわりの会話についていけず、毎日が苦痛でしかない。
・うつ状態が酷くなると自力で病院に行くことができなくなる。
3 受診する時
●躁状態で受診する時
・双極Ⅰ型障害の躁状態に関しては、治療が軌道にのりさえすれば、有効な薬がたくさんある。このような薬を服用することで1ヵ月から2ヵ月で改善することが多い。
・躁状態(双極Ⅰ型障害)の問題点は治療を起動にのせることである。その理由は躁状態というのは患者さんご自身にとっては、普段より調子が良いと感じており、治療を受け入れることが難しいためである。
<職場>
・受診を無理強いすることは人権侵害のおそれがある。
・「心配なので一度受診してみたらどうか」と示唆する程度が望ましい。
・ご家族に状況を伝え、受診してほしいとお願いする方法も有効である。
・ご家族が対応頂けない場合は、労働契約法第五条に、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする」という条項(健康配慮義務)があるので、職場の上司は部下の健康を守るために、病院の受診を要請することも可能である。
・問題行動に対して出勤停止等の処分を行うという選択肢も考えられる。
・双極Ⅱ型障害の軽躁状態の場合、心がけたいのはもし、その人がうつ病と診断されていた場合、気分の高揚は軽躁状態かもしれないので、主治医の先生に相談してみてはどうかと伝えてみても良い。
<家族>
・気分の高揚やおかしな言動に対して、もしかしたら躁状態かもしれないと気づくことが対応の第一歩になる。そして、これは間違いないと感じたら、次は何とか受診するよう説得することである。
・躁状態の患者さんは、色々なことに手を出しているが、思う通りになっていたことが多く、常にイライラしていることが多い。また、そのため不眠の問題を抱えていることも多い。そこで、不眠や疲れを理由に心配だから病院に行こうと説得するのが良い方法である。
・初発で相談できる病院もない場合は、まずは、家族だけで受診してみるという選択もよい。なお、その場合は病床数の多い単科の精神科が望ましい。大きな精神科病院にはケースワーカー(ソーシャルワーカー)がいて、入院の相談にのってくれる。
●うつ状態で受診する時
<職場>
・うつ状態の場合、躁状態とは異なり本人も不調を感じているので受診の勧めに強く反発することはない。
・同僚の異常に気付いた場合は、まず上司に相談するのが良い。部下のメンタルケアは管理職の仕事になっている。
・既に通院されている場合は、確認もなく病院や薬について詮索するべきではない。特に「薬に頼ってはいけない」という言葉は禁句である。
<家族>
・普段と様子が異なり、いつも苦しそうな表情をしている、ため息ばかりついていて楽しそうに見えることがないという状態が二週間以上ほぼ毎日続いているなら受診した方が良い。
・初発のうつ状態では、抗うつ薬を処方されるが、統計では約二、三割は双極性障害である。つまり、誤診されている可能性もあるということである。重要なことは過去に何度かうつ状態になった経験や、抗うつ薬の服用により気分が高ぶった経験がある人は、そのことをはっきりと医師に伝えることが必要である。
<本人>
・『受診した場合、「うつ病です」と診断されたら、それで満足せず、(大)うつ病なのか、うつ病だとしたら、どのようなタイプなのか、よく確認したほうがよいと思います。
そして、薬物療法を勧められた場合には、他のどのような治療の選択肢があり、なぜ、その薬を選択したのかということも、よく尋ねてみるとよいでしょう。納得できるような説明が得られない場合は、他の病院も受診してみたほうがよいかもしれません。』
4 復職
・躁状態、うつ状態が治った時にどのようなタイミングで、どのような形で復職するかはとても切実なことであるが、まさに研究が進められている段階であり正解というものはない。特に躁状態の患者さんは病気であるという認識があまりないので、本人は「もう大丈夫」と言うものである。
・重いうつ状態からの復職の時は、短縮勤務から始め徐々に時間を長くして慣らしていくなど、段階的に進めていくのが良い。
・長く休職した後の復職の場合は、都道府県の障害者職業センターなどの復職支援プログラムを利用するのも良い方法である。
・復職前に心理教育を受け、何が再発の兆候なのかを把握しておくと良い。
5 自殺の予防
・日本では約20,000人以上の方が自殺でなくなっており、その多くはうつ状態により自殺に至ったと考えられている。
・双極性障害では死因の19.4%が自殺であったという研究がある。
・薬物療法の中ではリチウムのみが、統計的に自殺率を低下させることが報告されており、重要な薬といえる。
・自殺の危険を把握するためには、患者さんを自殺に追いやる要因があるか、患者さんの死にたい気持ち(希死念慮)がどれだけ強いかの二つが重要である。
・自殺の危険を高める因子としては、自殺未遂をしたことがある、家族に自殺者いる、最近家族が亡くなった、最近知人や有名人が自殺でなくなった、借金など経済的な問題がある、そして周囲に助けてくれる人がいない等がある。
・自殺する人は自殺のサインを出すものであるが、大事なことは死にたいという気持ちを話してもらい、それをしっかりと受け止めることである。すべての思いを話してもらった後に、初めて「自殺しないと約束してほしい」と伝える。
6 双極Ⅱ型障害
●診断
・双極Ⅱ型障害にはさまざまな患者さんがいるという理解が大切である。
・双極Ⅱ型障害は医師によって診断にバラツキが出やすい。
●治療
・双極Ⅱ型障害は軽躁状態を有するが、現実的に問題となるのはうつ状態である。双極Ⅱ型障害のうつ状態は双極Ⅰ型障害に比べうつ状態の頻度は多く、期間も長い場合が多い。
・双極Ⅱ型障害の軽躁状態は、双極Ⅰ型障害の躁状態に比べると症状は軽く、期間も短いため診断が難しく医師によってもばらつきがでる。
第四章 双極性障害の治療
1 薬物療法
●精神科領域で用いられている薬
・精神科領域で使う薬を「向精神薬」とよばれ、向精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、気分安定薬、精神刺激薬などがある。
・抗精神病薬は統合失調症の幻覚や妄想に有効な薬だが、双極性障害にも有効である。
・抗精神病薬には古いタイプの定型抗精神病薬と新しいタイプの非定型抗精神病薬があるが、双極性障害では非定型抗精神病薬の方がよく使われる。
・抗うつ薬はうつ病の薬である。古いタイプは三環系抗うつ薬などがあり、新しいタイプは選択的セロトニン再取込阻害薬(SSRI)などがある。
・抗不安薬は病的かどうかに関わらず使われる不安を抑制する薬である。代表的なものはベンゾジアゼピン系抗不安薬である。
・気分安定薬は、双極性障害の再発予防に用いられる薬で、リチウムの他、ラモトリギン、バルプロ酸、カルバマゼピンがある。
・精神刺激薬は覚醒作用をもつ薬で、AD/HD(注意欠如・多動症)およびナルコレプシーに使われる薬で、双極性障害では使われない。
●リチウム(商品名 リーマスなど)
・リチウムは双極性障害の治療の基本となる薬である。
・リチウムは天然にも身体の中にも含まれている。
●リチウムの効果
・リチウムは躁状態およびうつ状態を改善する作用と予防する作用をもつ薬である。特に躁状態、うつ状態の再発を予防する作用が最も重要である。また、自殺予防効果もあるとされている。
・リチウムは代表的な気分安定薬であり、双極性障害の薬物治療の基本となるものである。
●リチウムの副作用
・リチウムはとても有用な薬であるが、精神科の薬の中で最も使い方が難しく、医師の指示通りに服用しなければならい。
・リチウムは血中濃度を測りながら服用することが定められている。一般的には0.4~1.0ミリモーラーの間で使用するが、1.5ミリモーラーを超えてくると。中毒症状が出る可能性がある。
・飲み始めの時には、下痢、食欲不振、喉の渇きと多尿、手の震えなどの副作用が見られる。
・腎臓の機能が低下していたり、脱水になっていたりすると血中濃度が高くなるため特に注意を要する。
・白血球、特に顆粒球が増加するという特徴も知っておくべきである。特に他の理由で内科などを受診する場合は、リチウムを服用していることを必ず伝えるべきである。
・特に女性の患者さんは甲状腺の機能低下という副作用が懸念されるので、時々、甲状腺刺激ホルモンを測定するようにする。
●他の薬との組み合わせにも要注意
・利尿剤、消炎鎮痛剤、高血圧薬などリチウムと相互作用し急激に血中濃度を高める可能性があるため十分に注意しなければならない。
●血中濃度の測定
・リチウムは服用後数時間の間に血中濃度が上がり、その後下がってきて8時間後くらいに安定した濃度になる。測定は最も血中濃度が下がった時に行う。
・血中濃度は最初のうちは受診の度に測定し、維持療法中は2、3ヵ月に1回を目途として行う。
●リチウム以外の気分安定薬(抗てんかん薬)
①ラモトリギン(商品名 ラミクタール)
・再発、再燃抑制の薬。保険適応されている。元々は抗てんかん薬である。
・再発予防効果は特にうつ状態の方が顕著という調査結果だった。これがラモトリギンの特徴である。
・リチウムとラモトリギンの併用は効果が高い。
・副作用には十分注意しなければならない薬であり、特に問題となるのはスティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)や、皮膚、眼、口唇などの粘膜に障害を起こす中毒性表紙壊死融解症(TEN)である。これらは全身の発疹で始まるので、発疹が出るようであれば服用を中止し、速やかに医師に相談すべきである。
②バルプロ酸(商品名 デパケンなど)
・元々は抗てんかん薬である。躁状態や混合状態に対して有効性がある。
・副作用はリチウム少ないが、食欲や嘔気など消化器系の副作用がみられる。まれな副作用には高アンモニア血症である。服用中に意識障害が生じた場合は、高アンモニア血症を疑う。
③カルバマゼピン(商品名 テグレトールなど)
・元々は抗てんかん薬である。躁状態に有効だが臨床研究は多くない。
・カルバマゼピンで問題となる副作用はスティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)と白血球減少症である。
●薬には症状との相性がある
・リチウム:気分が爽快になる。典型的な躁病の人によく効くと考えられている。
・ラモトリギン:うつ状態の予防に有効で、軽躁状態(双極Ⅱ型)にも有効とされている。
・バルプロ酸:不機嫌な躁病の人や混合状態が見られる人に有効だとされている。
・カルバマゼピン:若年で錯乱性躁病が見られる方に有効とされている。
・薬の適合性を調べるような検査や方法は、今のところはないため、経験や試行錯誤で見つけていく必要がある。
・二種類、三種類の気分安定薬を併用する場合も少なくない。
●非定型抗精神薬
①クエチアピン(商品名 ビプレッソ)
・双極性障害のうつ状態に有効な薬はあまりないのが実情であるが、注目が高まっているのは、非定型抗精神病薬である。その中で最も定評があるのは、クエチアピンである。
・クエチアピンはうつ状態だけではなく、予防効果も報告されており、さらに双極性障害の躁状態にも有効であることが臨床試験で認められている。
・日本では2017年に保険適用になった。
・クエチアピンの最も多い副作用は眠気である。
②オランザピン(商品名 ジプレキサ)
・躁状態への効果と予防効果がある。日本では2010年に認可された。また、2012年には双極性障害のうつ状態にも有効であることが分かった。
・体重増加や糖尿病誘発のリスクがあり、血糖値を測り糖尿病に十分な注意を払う必要がある。
③アリピプラゾール(商品名 エビリファイ)
・非定型抗精神病薬にはドーパミンを阻害する作用があるが、アリピプラゾールはある程度しか阻害しないため、パーキンソン症状という副作用を抑制することができる。さらに、ドーパミンが多すぎれば阻害し、少なければドーパミンを刺激する作用があると言われている。
●定型抗精神病薬
①ハロペリドール(商品名 セレネースなど)
・古くからある定型抗精神病薬の中で、最も代表的なものである。
・躁状態に対する効果および幻聴、妄想などの精神病症状に対する効果がある。
・副作用はパーキンソン症状である。また、ジストニア、アカシジアと呼ばれる副作用もある。これらの副作用には抗パーキンソン薬が有効である。
・副作用が多い薬だが、静脈注射、筋肉内注射などによって即効性が期待できるため、しばしば使われている。
②レボメプロマジン(商品名 ヒルナミン、レボトミなど)
・定型抗精神病薬の中でも、最も鎮痛効果が強い薬である。
・パーキンソン症状はあまり見られず、心電図異常、血圧低下など自律神経への副作用がある。
③クロルプロマジン(商品名 コントミンなど)
・最初に開発された抗精神病薬である。
④スルトプリド(商品名 バルネチール)
・躁状態の薬だが、パーキンソン症状が強くやや使いにくい。
⑤ゾテピン(商品名 ロドピン)
・定型抗精神病薬の中では、躁状態に対してよく使われた薬の一つ。鎮痛作用が強く、誇大性や気分高揚などの中核症状によく効くが鎮痛作用には個人差が大きいため用量設定が難しい。
・副作用は痙攣を誘発することがある。
●抗うつ薬と自殺念慮
・抗うつ薬は、24歳以下の方が服用した場合、自殺のリスクを増やす可能性があるので、リスクと効果を考慮して使うかどうか判断する必要がある。
・抗うつ薬で焦燥感が強まる場合、うつ病ではなく双極性障害の可能性がある。
●抗不安薬
・双極性障害には抗不安薬も使われる。ベンゾジアゼピン系と呼ばれ代表的なものには、ジアゼパム(商品名 セルシン)とかロラゼパム(商品名 ワイパックス)といった薬がある。これらの薬は抗不安薬、抗痙攣薬、催眠作用、鎮痛作用、筋弛緩作用といった様々な作用を持つ薬物群である。
●甲状腺ホルモン剤
・急性交代型という年間4回以上の躁やうつを繰り返すような人に有効であると言われている。ただし、量が多すぎると甲状腺機能亢進状態が懸念される。
双極性障害1
双極性障害は、躁うつ病と呼ばれていた病です。この双極性障害はうつ病とは似て非なる病気で、その経過も薬も全く異なるということを専門学校で学びました。つまり、もし、うつ病と双極性障害の診断が間違っていたとすれば、いつまでたっても病は治らず、悪化させてしまう可能性もあるということです。
もちろん、私は医師ではないので診断はできません。しかし、双極性障害とうつ病の違いを少しでも理解することは有益であり、勉強して最低限の知識はもつべきと考えます。
このように考える背景には、うつ病の既往やうつ症状ではないかとご心配される患者さまは稀ではないという印象があるためです。その時、頭をよぎるのは「双極性障害の可能性は全くないのか」という懸念です。とはいうものの、今まで手つかずにやってきたのですが、今回、一冊の本を買い求めました。
はじめに
第一部 対処と治療
第一章 なぜ躁うつ病は双極性障害となり、双極症に変わるのか
第二章 双極性障害(双極症)とは
1 双極Ⅰ型障害(双極症Ⅰ型)
2 双極Ⅱ型障害(双極症Ⅱ型)
3 さまざまなうつ病
4 小児思春期の双極性障害
第三章 社会生活を妨げてしまう双極性障害
1 双極性障害による社会生活の障害
2 立場によって受け止め方が違う双極性障害
3 受診する時
4 復職
5 自殺の予防
6 双極Ⅱ型障害
第四章 双極性障害の治療
1 薬物療法
2 ECT(電気けいれん療法)
3 反復性経頭蓋磁気刺激療法(γTMS)
4 ケタミン
5 心理教育
第五章 症例
第六章 双極性障害とつき合うために
第二部 Q&A
症状・経過・診断について
治療・社会復帰について
原因について
その他
年輪の会講演会から
年輪の会講演会での質疑応答から
参考文献
おわりに
第一部 対処と治療
第一章 なぜ躁うつ病は双極性障害となり、双極症に変わるのか
●もともとは躁うつ病とよばれていた双極性障害
・双極性障害は「躁うつ病」という病名でよく知られていた病気である。
・躁うつ病は統合失調症と並び、二大精神疾患とよばれてきた。
・躁うつ病という病名は、「うつ病」を含めて使う場合もあったため、混乱を招いていた面もあった。
・「躁うつ病」と「うつ病」は経過も処方する薬も全く異なる。
・躁うつ病のうつ状態とうつ病のうつ状態がきちんと区別されず、同じ治療が行われる場合があった。
・躁うつ病は躁とうつの再発を繰り返す病気だが、その認識が乏しく1回ごとの躁状態やうつ状態が、断片的に躁病、うつ病と診断されてしまい、長期的な展望を持って治療をするということが行われなかった。
・うつ状態にも多くの概念が混在していた。「内因性うつ病」「心因性うつ病」「荷下ろしうつ病」「引っ越しうつ病」「退行期うつ病」「抑うつ神経症」など、数えきれないほど色々な診断名が使われていた。
・病院、担当医によって、病名も異なり治療もバラバラだった。ただ、これは躁うつ病、うつ病に限ったことではなかった。
●混乱を解決するために作られた診断基準
・アメリカ精神医学会は精神疾患一つひとつに対して、操作的診断基準を作った。これは、どのような症状が何日間続いたら何病と診断するという基準を具体的に定めたもので、DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)と呼ばれている。
●もうひとつの診断分類ICD
・ICDは精神疾患の分類や統計の目的で、WHO(世界保健機関)が作ったものであるため、行政ではこの分類を用いることになっている。しかしICDは、病名判断の明確な基準がないため、医師の間で診断がばらつくという問題はなくならない。
●DSMが提案したこと
・躁状態を躁病と診断されないように、躁病エピソードと呼ぶことにした。また、うつ状態に関しては3つに分けた。
①脳梗塞や甲状腺機能障害といった、はっきりとした身体的要因があるうつ状態
②薬剤などの物質による原因がはっきりしているうつ状態
③上記①②以外のうつ状態
・③のような原因不明だが薬物療法が必要なうつ状態を「抑うつエピソード」と呼ぶことにした。この抑うつエピソードだけ起こる病気が、大うつ病性障害と呼ばれている。
・躁病エピソードと抑うつエピソードを伴う病気を双極性障害(この場合正確には双極Ⅰ型障害)と呼ぶ。
●DSM導入以降の日本の状況
・日本でのDSM診断基準の浸透度は心もとない状況である。特に「抑うつエピソード」という考え方は定着したとはいえない状況である。その結果、うつ状態という言葉が、DSMが定めた通り「抑うつエピソード」を指しているのか、抑うつエピソードの基準を満たさない軽いうつ状態も含めるのかが曖昧になっている。
・DSM-5からは、うつ病といえば身体的要因が特定できない、抑うつエピソードを有する大うつ病のことを示すとされた。なお、他の医学的疾患による抑うつ障害は○○性うつ病、○○病のうつ状態と表記される。
第二章 双極性障害(双極症)とは
●双極性障害にはⅠ型とⅡ型がある
・DSMは改訂第4版にあたるDSM-Ⅳから、双極性障害は「双極Ⅰ型障害」と「双極Ⅱ型障害」に分類された。そしてICDでもICD-11から、双極症(双極性障害)は、「双極症Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)」と「双極症Ⅱ型(双極Ⅱ型障害)」に分類されることになった。
-双極Ⅰ型障害:入院が必要な重度の躁状態とうつ状態を繰り返すもの。
-双極Ⅱ型障害:明らかに高揚した躁状態ではあるが入院を必要としない「軽躁状態」で、うつ状態を繰り返すもの。Ⅰ型とⅡ型は躁状態の程度で判断される。
●診断基準によって増加した双極性障害
・DSM-5の躁状態の診断基準は、躁状態が7日間毎日続くことになっている。
・軽躁状態の診断基準は軽躁状態が4日間続くことになっている。
●双極性障害は過剰診断?
・躁うつ病と呼ばれていた病気は、現在の双極Ⅰ型障害であり、それに加えて双極Ⅱ型障害が定義されたため、双極性障害の全体数は多くなっている。特にこの傾向は米国で顕著である。
●日本では過小診断と過剰診断が混在
・過小診断とは双極性障害に対する認識や理解不足により、医師はうつ状態に注意や関心が向きやすく、一方、患者も躁状態について話すことが少ないため、正しくは双極性障害にも関わらずうつ病として診断されてしまうことである。それにより不適切は抗うつ薬を処方され、状態は悪化する。
・過剰診断の一つのパターンは、パーソナリティーの問題などを双極性障害と診断してしまう場合である。双極性障害のうつ状態というのは、何かあった時に落ち込むとか、何かあると怒るといった周囲の環境に対する反応ではなく、何も理由がないのに2週間以上毎日気分が落ち込んだままである、という一定の長さを持つエピソードである。躁状態も同様に、何の理由もないのに1週間以上、毎日一日中気分が高揚している状態が続くというエピソードである。
・うつ状態も躁状態も、この数年間に何回あったと数えられるような、長く続くエピソードである。
・近年では特に躁状態も軽躁状態もないのに、光トポグラフィー検査の結果だけによって双極性障害と診断してしまうという過剰診断のケースもみられる。
1 双極Ⅰ型障害(双極症Ⅰ型)
●躁状態
・人生や家庭が破壊されかねない激しい躁状態である。
・躁状態は少なくとも1週間以上続き、その間、一日中ずっと気分が高揚したままの状態が続く。
・非常に高揚した気分、自分がとても偉くなったような気分を感じ、夜も寝ず、声が嗄れるまでしゃべり続けたり、じっとしていることができず、一晩中、一日中動き続けるが、その疲れを自覚できずに身体は消耗していく。
・必要のないものや高級品を買いあさり、借金してしまうこともある。
・気が散って集中できず、思い通りにならないとたとえ上司であっても激しく攻撃してしまい、職を失ってしまうようなこともある。
・酷くなると、幻聴や誇大妄想を伴うこともあり、錯乱状態まで進む場合もある。これを錯乱性躁病と呼ばれている。
●うつ病態(抑うつ状態)
・双極Ⅰ型障害と双極Ⅱ型障害は、躁的な状態には大きな違いがあるが、うつ状態には大きな違いはない。
・うつ状態とは、抑うつ気分、そして興味・喜びの喪失、この二つの症状が中核症状である。
<抑うつ気分>
・形容しがたい嫌な気分が逃れようもなく、一日中そして何日も続くものである。
・抑うつ気分は、やる気がないとか意欲が出ないという、あるべき意欲がないのではなく、普段あるはずのない筆舌に尽くしがたい、うっとうしい気持ちが襲ってくるというものである。
・『うつ状態の患者さんに、「三カ月くらいで治りますよ」と言うと、治るはずがない、と言うと、治るはずがないとおっしゃるかたもおられますが、中にはその言葉をある種の光明のように思う人もいます。抑うつ気分の時というのは、辛い気分が、まるで永遠に続くかのように感じられる状態なので、三カ月という普通なら長い期間でも、この状態にも出口があるのだと捉えられるのかもしれません。』
<興味・喜びの喪失>
・興味喪失とは、すべてのことに関してまったく興味をもてなくなる症状をいう。
・悲しいことに、自分の家族を愛する気持ちも喪失してしまうことがあり、さらに自分を責めてしまう。
・喜びの喪失とは、何をしても、何も見ても、嬉しい楽しいという感情が全く湧いてこないこと。
●うつ状態の診断
・うつ状態の診断では、まず抑うつ気分と、興味・喜びの喪失という二つの中核症状のうち、少なくともどちらか一方が、一日中、毎日、二週間ずっと存在しているかどうかを確認する。
・中核症状に加え、以下に紹介する4つの身体症状と、5つの精神症状の計9つの症状のうち、5つ以上が、一日中、二週間以上、毎日出てきていることが確認された時に、うつ状態(抑うつエピソード)と診断する。
●うつ状態の妄想
・うつ状態も酷くなると妄想が出てくる場合があるが、多いのは貧困妄想、心気妄想、罪業妄想の三つである。
<貧困妄想>
・根拠もないのに破産した、お金がないなどと信じ込んでしまう妄想である。この妄想のために入院を勧めても「お金がないから……」と断わったり、借金取りが来るなどと恐れてしまったりする。
<心気妄想>
・自分が重い病気に罹ったと信じ込んでしまう妄想である。医師や周囲の人の言葉を信じることができない。
・中には内臓がなくなってしまうという否定妄想に加え、大変な病気のために死ぬこともできず、永遠に生きなければならないという不死妄想が見られる場合を、コタール症候群という。
●躁にもうつにも起こり得る昏迷状態
・うつ状態あるいは躁状態が激しくなると、昏迷状態といって、しゃべることができなくなり身体が硬くなってしまう症状が現れることがある。特に酷い場合は、不自然な姿勢で静止したまま固まってしまうこともあり、このような状態は緊張病状態と呼ばれている。このような緊張病状態が出てくると、多くの医師は統合失調症を疑うが、双極性障害にも出るので注意を要する。
●混合状態
<躁転・うつ転に伴う「混合状態」>
・うつ病態から急激に(数日間で)躁状態に変わることを躁転と呼ぶ。躁転の経過中には、気分はうつなのに行動は活発になるような、うつ状態と躁状態の症状が入り混じって現れる混合状態になる時がある。
・躁状態からうつ状態に変わる場合は、うつ転と呼ばれこの時にも混合状態になることがある。
<通常とは違う躁状態・うつ状態の特徴を表す「混合状態」>
・混合状態では行動が非常に多くなって、しかも自殺念慮(自殺したいという気持ち)が強くなってしまうことがあり、うつ状態よりもさらに自殺の危険が高い状態といわれている。
2 双極Ⅱ型障害(双極症Ⅱ型)
・Ⅱ型はⅠ型の躁状態にくらべ、軽度な軽躁状態とうつ状態を繰り返すものである。
●軽躁状態とは
・躁状態は入院させたいほどの重度な状態に比べ、軽度な躁状態のものである。例えば、気分が高揚し仕事がはかどり、いろいろなアイデアが湧いてきて調子が良いという状態であり、病気と感じられるものではない。
・重要なことは、周りの人から見るといつものその人と全く違うと感じるものである。また、気分が高揚する状態は、一日中、少なくとも4日以上続くのが特徴である。
・軽躁状態では、本人には病気の自覚は全くないため、うつ状態になった時に初めて異変を感じるものである。
●うつ病にしか見えない双極Ⅱ型障害
・双極Ⅱ型障害の軽躁状態を本人が自覚するのは困難なため、双極Ⅱ型障害の患者さんのほとんどは、自分をうつ病だと考えている。家族においてもほぼ同様な認識である。したがって、軽躁状態を見分けることが、うつ病の治療において最大のポイントになる。
●なぜ双極Ⅱ型障害とうつ病を区別しなくてはいけないのか
●再発のリスクが高い双極性障害
・うつ病の頻度は海外では15%、日本では7%位と言われている。
・双極Ⅰ型障害は欧米では約0.8%、双極Ⅱ型障害を含めると2、3%になると言われている。一方、日本では合わせて1%弱と言われており、欧米に比べると少ない。
・重要なことは、うつ病と双極性障害の発症頻度には大きな違いがあるにも関わらず、ある統計ではうつ状態で来院されている患者さんの20~30%が、双極性障害だという点である。この主な要因はうつ病に比べ、双極性障害ではうつ状態の再発が多く、非常に長い経過をたどるという特徴を有しているためである。
・うつ病ではうつ状態の回復が治療目標になるが、双極性障害の場合はうつ状態と躁状態(軽躁状態)を繰り返すことが続くため、再発防止が治療目標となる。
●治療に用いる薬も違う
・双極性障害のうつ状態と、うつ病を区別しなければならないもう一つの理由は、治療薬が異なるということである。
・うつ病のうつ状態には抗うつ薬を処方するが、双極性障害のうつ状態には抗うつ薬は効きにくく、躁転を誘発するおそれがある。
・双極性障害の場合には、再発予防を目的とするリチウム、ラモトリギンなどの気分安定薬や、非定型抗精神薬を使う。
●初めてのうつ状態では、「うつ病」と診断される
・うつ病か双極性障害の診断は病歴、以前躁状態や軽躁状態になったことがあるのかを聞くことである。特に重要なことは自覚的なものだけでなく、行動の変化などの客観的な変化を詳しく聞くことである。
例えば、「今までに一週間くらい、毎日、一日中気分が高揚して、眠らなくても平気で頑張れた時はありましたか?」などの質問をする。
・難しいのは、その患者さんの初めての病相が躁状態、軽躁状態ではなく、うつ状態から始まった場合はであり、このケースでは区別することはできない。
・双極Ⅰ型障害では、最初の病相がうつ状態で発症するのは50%位である。
・双極Ⅱ型障害では、軽躁状態が最初に出ても自分で病気を疑うことはまれであり、うつ状態で受けることになるためうつ病と診断される。治療を進めながら経過をみていくうちに、躁状態や軽躁状態が認められれば、そこでうつ病から双極性障害に診断が変更される。また、患者さんや医師の理解不足が原因で双極性障害がうつ病と診断されてしまうこともある。
・アメリカの研究データでは、双極性障害の啓発が進んできたため、最近の研究では短くなったとはいえ、病名確定に4年かかるといわれている(昔は10年と言われていた)。これでも大変な時間を要するが、現状ではこれが実態である。
3 さまざまなうつ病
●メランコリー型うつ病
・以前は内因性うつ病と呼ばれていたもの。主な症状は、動作がゆっくりになってしまう症状、すべてのことに興味を失ってしまう症状、朝具合が悪く夕方に緩和されるという症状、罪責感などが特徴である。
●非定型うつ病
・最近急激に増えているタイプのうつ病である。
・抑うつ気分がある中で、良いことがあると気分が少しよくなる等、気分が変化しやすいこと、対人関係で過敏になりやすいという特徴がある。また、過眠や過食もみられる。
・このタイプは不安障害やパーソナリティー障害を伴うこともあり、幼少時の不遇な環境や虐待との関係が指摘されている。
●双極スペクトラムうつ病
・これは将来躁状態になって双極性障害と診断される可能性のある予備軍ともいえるものだが、まだ十分な実証が得られていないため、DSM-5には含まれていない。しかし、親や兄弟姉妹などに双極性障害を持つ人がいる場合や、双極性障害に多く見られる特徴(精神病症状があること、発症年齢が若いこと、非定型型うつ病症状を伴うこと、病相の回数が多いこと、抗うつ薬が効きにくいことなど)が多数見られる場合は、双極性障害への進展に注意が必要である。
●季節性うつ病
・DSM-5では「うつ病、季節型」と記載される。これは主に冬に多く、冬の日照時間が少ない高緯度地方に多くみられる。
・一般的なうつ病の特徴は不眠や食欲低下などであるが、この病気は過眠や過食といった症状が特徴である。
・この季節性うつ病は、朝方2時間くらい強い光を浴びる光療法が有効である。
●血管性うつ病
・75歳以上の多くのうつ病の患者さんには、脳梗塞の跡が見つかる。普通の75歳以上でも潜在性脳梗塞は見られるが、その頻度は明らかにうつ病患者さんの方が多い。
・脳梗塞とうつ病の因果関係(どちらが原因かはっきりしていない)などもあり、DSM-5には含まれていない。
4 小児思春期の双極性障害
●小児思春期の双極性障害は存在するのか
・米国(特に北米)では、「小児双極性障害」に関する論文が提出されているが、懐疑的な意見の学者も多い。
神経-血管-グリア・ユニット
前庭性片頭痛は、難治性めまい患者にしばしば見られる疾患といわれています。脳内炎症が疑われ、神経-血管-グリア・ユニットが関係しているらしいということが分かりました。
調べたところ、医学雑誌の『実験医学』のバックナンバー、2013年9月号 Vol.31 No.14で、神経-血管-グリア・ユニットが特集されていました。タイトルは“特集 Neurovascular Unit 神経-血管-グリアのユニットが脳と体を支配する”です。
私の知識では太刀打ちできないことは分かっていましたが、そうは言っても、何か得るものもあるだろうと思い、購入することにしました。
特集の各寄稿は以下の通りです。
予想通り、私にはこれらの内容を理解することはできませんでした。唯一、出来そうなのは、神経-血管-グリア・ユニットの要点を書き出すことです。
取り上げた3つの図表は、最初の『概論―Neurovascular Unit:脳内の細胞間クロストークを理解するための概念的枠組み』と、2番目の『Neurovascular Unitという概念でとらえる脳卒中の病態』に掲載されていたものですが、ブログはこの二つの寄稿をミックスした形でまとめています。
はじめに―Neurovascular Unitの誕生
・『2001年に開催された米国NIHのStroke Progress Review Groupでは、当時の脳卒中研究の状況を評価し、今後どのような方向に研究を進めるべきかが議論された。その当時、脳卒中後の神経細胞における興奮毒性・酸化ストレス・アポトーシス経路などの病態メカニズムが解明されつつあったが、脳卒中治療薬としての神経細胞保護薬は存在していなかった。なぜ多くの神経細胞保護薬が臨床試験で効果を示さなかったかに関する議論は数多くなされてきたが、特に重要なポイントは神経細胞という単一の細胞種にのみ着目するのは脳卒中治療として不十分であるという点であった。そのため、脳卒中治療は神経細胞の保護に限定せず、周囲の細胞をも含めた総合的な脳保護治療を考慮すべきであるとして、神経細胞・脳血管内皮細胞・アストロサイト・細胞外マトリクスからなる概念的な構成単位である「Neurovascular Unit」が提唱された。』

画像出展:「実験医学 2013 vol.31 NO.14」
「Neurovascular Unitは脳卒中の病態をより正確に理解することを目的として2001年に提唱された概念である。この概念が提唱された当時、Neurovascular Unitの構成細胞は神経細胞、脳血管内皮細胞、アストロサイトだった。しかし現在では、ミクログリア、ペリサイト、オリゴデンドロサイトもNeurovascular Unitの構成細胞とみなされている。」
・『Neurovascular Unitの概念が強調する点は、異なる細胞同士の相互作用が脳機能の維持に必要であり、脳疾患においては神経細胞を保護するだけでは正常な脳機能を保てないということにある。歴史的にみると、Neurovascular Unitの概念が誕生する前からも、脳神経細胞以外の細胞の状態の悪化が脳疾患の病態と深くかかわることは議論されてきた。例えば、“more than just neurons”というアイデアは、1971年にIssidoresらがパーキンソン病の研究で報告した論文のなかにもみられる。また、血液脳関門(blood-brain barrier:BBB)におけるアストロサイトと血管内皮細胞の相互作用に代表される“脳内における異なる細胞間相互作用の重要性”は、脳研究の分野において常に大きな研究トピックスであった。そのようななか、Neurovascular Unitという概念が誕生し、脳組織における異なる細胞間相互作用の重要性が改めて脚光を浴びたことで、脳卒中をはじめとする種々の中枢系疾患の病態を解明するための研究が劇的に加速した。』
1.Neurovascular Unitの構成細胞
・Neurovascular Unitの概念が提唱された当時、その構成細胞は神経細胞、血管内皮細胞、アストロサイトと考えられていたが、その対象は広がり、ミクログリア、血管周皮細胞(ペリサイト)、オリゴデンドロサイトなどが加わった。
・近年では、Neurovascular Unitの機能に対して脳実質の外側(脳血管を流れる血液中)の因子が影響を与えることも示されている。
1)脳血管内皮細胞
・脳血管内皮細胞はNeurovascular Unitの中でも特に興味深い細胞である。血管内皮細胞と神経細胞の間の微小環境は、成体脳における血管新生および神経新生の場として大きな注目を集めている。
2)アストロサイト
・アストロサイトと脳血管内皮細胞のクロストークは、Neurovascular Unitの概念が提唱される前から精力的に研究が行われおり、例えば、脳血流の調節とも深く関わっていることが分かっている。
3)オリゴデンドロサイト
・Neurovascular Unitの研究は、今まで、灰白質について論じることが多かったが、白質も脳機能において灰白質同様、とても重要な役割を担っている。
4)ミクログリア
・ミクログリアはNeurovascular Unitを構成する細胞の中で他とは違う特色を有している。
・ミクログリアは脳内における免疫反応を担当し、脳卒中などの障害時に活性化し周りの細胞に悪い影響を与える。しかし、その活性化状態の違いにより、周りの細胞に良い作用を及ぼすこともある。一方で、周囲の環境がミクログリアの活性化状態を左右することも明らかになりつつある。
・ミクログリアのNeurovascular Unitへの影響は未だ不明な点は少なくない。
補足.Neurovascular Mediatorについて
1.MMP-9:マトリックスメタロプロテアーゼ-9は、細胞外基質のコラーゲンやゼラチンなどを分解する酵素であり、組織の再生・分化などにおいて重要な役割を果たしている。一方で、組織内のMMP-9の過剰生産はがんの転移や動脈硬化の進展にかかわることが明らかになっている。
2.BBB:blood-brain barrier(血液脳関門)
3.VEGF:血管内皮増因子は、血管新生やリンパ管新生、胚形成の脈管形成に関与する糖タンパクのサイトカインである。
4.HMGB1:細胞局在によって異なる役割をもつ多機能性タンパク質である。がん細胞においては、細胞内に局在するHMGB1はゲノムを安定させる抗腫瘍タンパク質として作用し、細胞外に放出されたHMGB1は免疫機能をもつ前腫瘍タンパク質としての働きをもつ。
5)末梢循環細胞
・2001年にNeurovascular Unitの概念が提唱されたとき、影響範囲は脳内に限定されると考えられた。しかし、現在では血液中を流れる末梢循環細胞が脳卒中後の脳機能回復に寄与しうることが明らかになりつつある。
6)末梢神経における神経-血管相互作用
・Neurovascular Unitは日本語では神経血管単位(もしくは神経血管ユニット)と訳される。末梢組織における神経細胞と血管系の相互作用については最新の画像診断装置を用いて研究が進められている。
2.Neurovascular Unitの動的な側面
・Neurovascular Unitの概念が提唱されてから現在まで、一貫して変わらないのは脳卒中に対する効果的な治療方法を探ろうという目的である。そして、考慮すべき点は、Neurovascular Unit内の環境が状況に応じて変化しうるということである。
・Neurovascular Unitの構成細胞は環境に応じて異なった性質を示すことがある。例えば、アストロサイトは障害後には、反応性アストロサイトとなり回復期の神経新生を抑制する。しかし、一方では最近の研究により、反応性アストロサイトは失われた脳機能の回復を促進することもわかってきた。
・オリゴデンドロサイト前駆細胞は、障害により失われたオリゴデンドロサイトを補填するために自らオリゴデンドロサイトへと分化することで脳機能の回復に寄与しているが、その一方で、この前駆細胞は障害後の急性期には、悪性因子を遊離して周囲の環境を悪化させることが報告されている。
・Neurovascular Unit内において、細胞同士の連携は栄養因子やサイトカインなどの液性因子を介して行われることが多い。
・表のNeurovascular Mediatorにも挙げられている、MMP-9、VEGF、HMGB1には興味深い共通の性質がある。その性質とは作用の二相性であり、障害後の急性期に脳障害をひき起こす因子が、回復期には逆に脳組織・脳機能の修復に寄与するというものである。例えば、Neurovascular Unitを構成する細胞外マトリクスを分解する酵素の一種であるMMP-9は、脳卒中急性期ではBBB(血液脳関門)の破綻をひき起こすが、一方で回復期には血管新生および神経新生に関わっている。
・表に挙げたNeurovascular Mediatorを理解することは非常に重要である。なぜならば、急性期に障害性を示す物質を阻害する薬剤を投与したとしても、もし、その薬剤の効果が回復期にまで及んでしまうと、内因性の修復機構を阻害する恐れがあるからである。
3.Neurovascular Unitの成り立ちと構成
・『1990年代の10年間はそれ以前に比して、格段に脳卒中の理解が高まった時期であった。多くの大規模臨床試験が画策され、MRIをはじめとする画像診断が格段に進歩し、脳虚血における血行動態や分子レベルの変化が明らかになってきた。そして、米国で1995年に許可されたrt-PA静注療法は、脳梗塞治療に画期的な進歩をもたらした。しかし、主に発症早期の投与という時間的に限定された条件から対象症例は伸び悩み、脳梗塞治療に閉塞感が漂いはじめた。
これに対して、虚血早期に生じるカルシウムイオンの過度の流入がニューロン細胞死や障害につながるため、そのイオンチャネルを阻害する薬剤を中心に神経保護薬が多く開発された。それらは脳梗塞のモデル動物ではニューロンの虚血障害を軽減したが、脳卒中患者では有益な効果を示すことはできなかった。この神経保護薬の失敗によって、脳虚血の病態の複雑さと虚血の影響はニューロンだけでなく他の細胞にも及ぶことが改めて認識された。そのため、ニューロン単独の挙動にとらわれるのではなく、ニューロン以外の細胞やそれら細胞とニューロンとの関係に焦点が移っていった。つまり、単独の細胞内シグナルのみならず、細胞間シグナリング、細胞と細胞外マトリクス間シグナリングの解明の重要性が高まってきたのである。NVUはそうした背景で出てきた概念である。
NVUという用語は、米国のNational Institutes of Neurological Disorders and Strokeでの会議で2001年にはじめて使用された。この用語は、脳内の細胞間相互作用の様子を概念的に示したものであり、NVUの概念に基づいた研究から得られた知見は、脳卒中の病態解明を一気に進めた。NVUの概念が提唱されてから10年が経過し、今では脳卒中だけでなく他の神経変性疾患の研究にもNVUの概念が用いられるようになってきた。
NVUは大きく分類すると3種類の細胞群と細胞外マトリクスから構成されている。細胞群はニューロン、血管系細胞(血管内皮細胞、周皮細胞[ペリサイト]と血管平滑筋細胞)およびグリア系細胞(アストロサイト、オリゴデンドロサイトとミクログリア)である。これらをつないでいるのが、各種の成長因子、サイトカイン、ケモカインといった液性因子や細胞外小胞である。これらの細胞群は細胞同士の直接的コンタクトのみならず、液性因子を介して細胞間あるいは細胞と細胞外マトリクス間で間接的にシグナルをやり取りしていると考えられ、これらを含めて1つの概念的ユニットを形成している。さらに、脳虚血では末梢血液成分である単核球のような白血球系細胞や血小板なども病巣にかかわってくるため、これらもNVUに含めるという考えもある。より効果的な血流再灌流、神経保護や機能回復をめざすために、これらNVU構成要素の相互関係に着目することが重要である。』

画像出展:「実験医学 2013 vol.31 NO.14」
ニューロン、血管系細胞(血管内皮細胞、周皮細胞と血管平滑筋細胞)、グリア系細胞(アストロサイト、オリゴデンドロサイトとミクログリア)、および細胞外マトリクスから構成される。
補足.情報交換の方法
例えばニューロンの軸索とオリゴデンドロサイトの髄鞘、血管内皮細胞と周皮細胞のように直接細胞同士が接触することで情報交換をしている場合もあるが、細胞間のシグナル伝達を成長因子、サイトカイン、ケモカインや細胞外小胞を介して行っている場合も考えられる。これらを包括してNeurovascular Unitの枠組みとしてとらえる。
感想
とても難しい内容でしたが整理すると、①神経細胞という単一の細胞種にのみ着目するべきではない。②NVU(神経血管単位・神経血管ユニット)はニューロンだけでなく他の細胞にも及ぶ。したがって、「単一の細胞腫でなく、NVUとして考えることが重要である」ということだと思いました。
体内時計と睡眠2
4 現代人はなぜ眠るのに苦労するのか
●パソコン、携帯、ネオンが与える影響
・2011年の国民健康栄養調査の報告によると、日本の総エネルギーは2003年より徐々に減少し、運動習慣は増加しているが、肥満も糖尿病も増えている。この原因は日本人の睡眠不足と不規則な生活が引き起こした生体リズムの乱れと考えられる。
・産業医科大学の久保達彦博士による、交替制勤務に従事する日本人の健康状態を調査したところ、交替制勤務を始めると血圧はすぐ上がる。糖尿病になるリスクは2倍、がんの罹患率も上がる。乳がんは1.5倍、前立腺がんは3倍である。
●夜型人間は朝型人間になれない?
・一般的に夜型の人は、食欲、便通、睡眠に課題を抱えた人が多い。
・医学的にも早寝早起きで午前中から活動的な人を朝型、宵っ張りで午前中はぼんやりしていて、夜になるほど頭が冴える人を夜型と呼ぶ。
●現代人は不健康?
・マウスの実験では、高脂肪食をいつでも摂取できるようにした環境では、肥満、脂肪肝、メタボリック症候群、血管の炎症などが見られるが、同じカロリーの食事にも関わらず、食事の時間を一定の時間帯に変更すると生体リズムが回復し不健康な症状が消失したということである。
●女性の睡眠時間に異変あり
・日本人の睡眠は1976年から2011年にかけて、若い世代の睡眠時間には大きな変化はなかったが、45歳~85歳の中高年では1時間近く睡眠時間は減っており、性別では女性の方が減少している。
●若返りの泉メラトニン
・メラトニンは生体リズムを守る三要素のひとつであり、松果体から分泌される。また、睡眠を改善し、寝つきをよくするホルモンとして知られている。加齢とともに低下していくことから、「加齢時計」とも呼ばれている。
・メラトニン研究により、脳にある生体時計がメラトニンを作っている松果体を調節することで協同して働き、若返りや健康長寿をもたらしていることが分かっている。
・今では、メラトニンが不足してくると、心筋梗塞や脳梗塞が増えることが明らかにされている。
・メラトニンは全身の血管に働きかけ、血圧を下げ夜の隠れ高血圧を改善する。また、心臓と心臓の血管に作用して、昼間に傷ついた部位を修復し脳梗塞を予防する。
・メラトニンは骨に働きかけ、骨粗鬆症を改善する。
・メラトニンは自律神経を調節し、免疫機能を賦活し発がんを抑える。そして、老化の速度を遅らせる。
・メラトニンの受容体に遺伝子異常があると、メラトニンの不足と同じように生活習慣病が現れることがわかってきた。
・メラトニンは生命の質を高める多彩な作用があり注目されている。
・メラトニンは夜間に光にあたると分泌が抑制される。
-光に当たるのが1~2時間の場合、300ルクス(卓上電気スタンド位の明るさ)でもメラトニンの分泌に影響が出る。
-一晩中電気をつけている場合には10ルクス(ろうそくの灯りは8ルクス)の薄明りでも影響を受ける。
-パソコンやスマートフォンで問題になっているブルーライトは、わずか8ルクスであっても、白色光の1200ルクス並みの悪影響を及ぼす。
●睡眠時無呼吸症
・深い眠りとともに分泌される成長ホルモンは、子どもの成長を促したり、昼間にダメージを受けた皮膚や粘膜を修復したりしている。
・時計遺伝子のビーマルワンは、エネルギー産生の効率を上げるためにいろいろな工夫している。
-胃や腸の細胞や組織に作用して、食べた物を腸から吸収する効率、吸収した食べ物を脂肪に変換する効率、そしてそれを脂肪組織の貯蔵する効率など、いずれも昼間よりも夜にその働きが高まるようにしている。
・顆粒球やリンパ球などの白血球の働きを活発にして、免疫力を高め、隠れている病気を癒し未病を防ぐ。
・睡眠時無呼吸症候群とは、眠っている間いびきとともに無呼吸を繰り返す病気である。メタボリック症候群になったり、高血圧や糖尿病を悪化させる。この病気の深刻度は昼間の眠気の強さで計る。いくら眠ってもすっきり感がないとか、疲れがとれないという場合は無呼吸症候群を疑うべきである。
●不眠によるトラブル
・人間とショウジョウバエの時計遺伝子は、ほとんど同じ遺伝子を使って時を刻んでいる。
・『私たちは、北海道U町の人々を調査してみました。「昨日は、よく眠れましたか?」との質問に、188人のうち21%の住民が、「十分ではなかった」と回答しました。この188人を約5年間追跡調査したところ、よく眠れると答えた人の3倍、病気になりやすいこと、その結果、余命が短くなっていることがわかりました。』
・『不眠は生活習慣病の源です。不眠になると自律神経が高ぶり、血圧が上がります。なかでも夜間高血圧が著しく、心臓病や脳卒中が起こりやすくなります。不眠が重なると、昼間の眠気で活動量が減り、肥満になります。加えて、目覚めのホルモンといわれる副腎皮質ホルモンが増えます。このホルモンはやっかいです。健康なからだから分泌されるインスリンの働きを弱めるので、これが増えると糖尿病になりやすくなります。また骨を溶かす働きがありますので、骨粗鬆症にもなりやすくなってしまい、コレステロール値も上がり、動脈硬化が進みます。』
・1989年、米国一般住民を対象に行われた調査では、不眠が1年間続くとうつ病になるリスクが40倍になるとのことである。
●災害現場、避難所の報告から
・東日本大震災直後の調査によると、被災地の人々の約60%に不眠の症状が現れたが、なかでも仮設住宅で居住することを余儀なくされた人々にそれは著明であった。
5 眠りは変化する
●成長と共に変化する睡眠
・人間の睡眠は、リズムも質も一生のなかで変化している。
●乳児の眠り
・胎児は妊娠28週くらいからレム睡眠を覚え、妊娠36週くらいからノンレム睡眠も経験し始める。
・出生まもない赤ちゃんは覚醒しているのは1、2時間で残りは眠っているが、この眠りのほとんどはレム睡眠である。8ヶ月くらいになると、睡眠時間は13時間くらいで、レム睡眠は眠りの1/3程度になる。
・胎児の生体リズムは24時間ではなく、7日(もしくは3.5日)のリズム性が大きい。24時間リズムが芽生え始めるのは、生後1ヵ月の頃になるが、まだ外の世界とは同調できないため時差ぼけのような状態である。これが生後3ヵ月くらいになると24時間リズムがだいぶ完成してくる。
●幼児の眠り
・1歳から3歳は、体内時計の成長を促し、生体リズムを確立するために最も重要な時期なので、特に規則正しい生活と十分な休息が必要である。
・4歳から6歳は、睡眠習慣を身につけるために大切なときである。5歳頃から生体リズムにあった睡眠パターンが現れてくるため、この時期に早寝早起きを習慣化させておくことは重要である。
・午後早めの昼寝は、夜の睡眠を補うのに有効である。
・脳の老化には性差があり、男性は女性より1.5倍早く老化すると言われている。特に、左脳が早く萎縮していく。女性の老化が遅いのは脳梁とよばれる神経線維の束が大きく、左右の脳の情報交換はスムーズに行われ、右脳と左脳がバランスよく萎縮していくからである。
●学童児の眠り
・5歳から12歳は、睡眠時間が11時間から8.5時間まで短くなり、昼寝もあまりしなくなる。眠りはノンレム睡眠が主体だが、深睡眠と呼ばれる睡眠深度4が長いのが特徴で、この眠りの中で学校で学んだ情報や知識を咀嚼している。
●思春期の青少年の眠り
・12歳から18歳は、思春期であり、また成長期である。睡眠中に性ホルモンが増え性腺は成長する。
・成長ホルモンが多量に分泌されるとともに、眠りたい欲求が高まり、朝なかなか目を覚まさなかったり、週末に異常に長く睡眠したりすることが見られる。
●社会生活をしている人の眠り
・20歳から40歳は、仕事や社会活動が日常の大半を占めるようになるため、不規則な生活になり生体リズムも乱れがちになる。起床時刻を一定にする努力が大切である。
・50歳から60歳は、そろそろ老化が始まる時期であり、眠っても疲れがとれない、途中で目が覚める、などの不眠症状が増えてくる。寝具の工夫も必要である。
●中高年の眠り
・壮年期に5人に1人といわれる不眠は、60歳を超えると3人に1人になる。
・朝起きて光を浴びてから、約15時間後に眠くなるように体内時計はセットされてるため、朝5時に起床すると夜の8時には眠くなってしまう。
・高齢者の睡眠は深い睡眠やレム睡眠が短くなって、睡眠深度1か2が多くなる。要因の一つは光環境の変化である。家にいる時間が増え、光を浴びる機会が少なくなるので、メラトニンの分泌量が減る。
・高齢者独特の睡眠異常にレム睡眠行動障害がある。これはレム睡眠の仕組みが壊れてしまうために、金縛りの状態にならず夢の内容がそのまま行動に反映されてしまう。それにより、大声を出したり、襲いかかったり、蹴とばすなどの異常行動が出現する。
・むずむず脚も、貧血を合併する高齢者によく見られる睡眠異常である。また、似たような運動異常に、睡眠に伴う周期性四肢運動麻痺障害がある。
・睡眠中のこむらがえりも多く見られる。60歳以上では3人に1人。80歳以上では2人に1人に見られる。原因は筋肉のエネルギー不足や酸素不足なので、温めること、マッサージすることは良い。筋疲労、水分不足、過度な飲酒などもきっかけになるので注意が必要である。
・高齢者の不眠対策は、十分な日光と適度な運動が基本であり、心地よい疲れを感じることが大切である。睡眠時間は6時間程度、起床時間など生活のリズムを安定させることも必要である。
●認知症の人の眠り
・認証症患者の80%の人に不眠症が見られ、行動異常やこむらがえり、、むずむず脚も多く見られるようになる。昼間にうとうとしていることが多いため、総睡眠時間はあまり変わらない。昼間の過眠症が認知症の原因ではないかという研究報告もある。
・血管性認知症は大きないびきと、睡眠時無呼吸症候群が多く見られるのが特徴である。
・アルツハイマー病では初期からメラトニンを作る松果体にいろいろな異常が現れてくる。特にパーワン、ビーマルワン、クライなどの時計遺伝子が少なくなり、発病前から生体リズムが乱れ始める。
・メラトニンの分泌量は加齢ともに激減し、70歳を超えると思春期の10%以下に減ってしまう。日本ではラメルテオン(商品名ロゼレム)が市販されている。
6 よりよい休息のススメ
●サマータイムの導入は是か非か
・サマータイムでは適応に約1週間かかるとされている。その間に体調不良や能率低下が指摘だれている。特にその傾向は夜型人間や短時間睡眠の人に見られ、諸外国に比べ短い睡眠時間の日本ではサマータイムは課題が多い。
●長生きする人の睡眠
・高知県土佐町の691人、平均年齢81歳の高齢者を対象とした、2008年から2012年からの調査では、睡眠時間は8時間、起床は5時59分、消灯は21時58分だった。また、52%の人は毎日の運動習慣、49%の人は昼寝の習慣があった。
●脂肪分のとりすぎは要注意
・規則正しい食事は深い眠りを誘う。
・栄養素では糖質とともに、メラトニンを作るトリプトファンを豊富に含むタンパク質とビタミンB6の摂取が有効である。トリプトファンは肉類、魚介類、乳製品、豆乳などに多く含まれている。ビタミンB6は、魚介類、大豆、納豆、のりに多く含まれている。
・不飽和脂肪酸はメラトニンを増やすので、睡眠の改善に効果がある。
・ナッツなどに含まれるポリフェノールは時計遺伝子の仲間のサーチュインを活性化させる働きがある。
・脂肪分の多い食事は、眠気を強めるという特徴がある。また、過剰な脂肪摂取は、時計遺伝子の発現リズムを狂わせ、体内時計の働きを弱める。
●タバコ、昼寝、寝酒は避けるべき?
・喫煙は寝つきを悪くし、中途覚醒を増やし、眠っている時間を短くし、睡眠の質を悪化させるため体の疲れが残りやすい。タバコは快眠の大敵である。
・睡眠時無呼吸症候群になるリスクは非喫煙者の2.5倍である。
・午後2時頃に現れる眠気に昼寝することは望ましい行為である。ただし、時間は15~20分。30分以上昼寝すると、起床後から蓄えてきた眠りのホルモン(睡眠物質)を使い果たすので、夜、眠れなくなってしまう。
・不眠症の人は、もともと眠りのホルモンが少ないので、昼寝は厳禁である。
・アルコールは生体リズムを壊し、睡眠の質を悪くする。深い睡眠を減らし、体内時計の働きを弱め、時差ぼけ状態にしてしまう。
●睡眠薬のメリット、デメリット
・『不眠症の原因は多様ですから、基本的に、不眠症=睡眠薬と安易に考えるのは誤りです。生体リズムの乱れが原因の場合は、朝の光を浴びること。夜の睡眠環境を整えること。朝食を抜かないことと規則正しい食習慣。これが改善策です。いびきや睡眠時無呼吸症が原因の場合はシーパック治療などの無呼吸対策が基本ですし、こむらがえり、むずむず脚や金縛り、夜間の胸やけ、動悸、胸の痛みがある場合は正しい生活習慣を心がけるだけでなく、治療することこそが肝要です。』
・現在の薬は副作用が少なく安心して服用できる。睡眠薬を必要以上に怖がらず正しく飲むという勇気も時には必要である。
●子守歌の科学的効果
・子守歌の安眠を誘う効果には、心地よい音の調べがある。三週間、就寝前に45分間、リラックスするクラシック音楽を聞かすという実験では、脈拍が低下し睡眠の質を高める副交感神経が活性化した。また、母親のにおい、温かさ、満腹になっていることも眠りを誘い、質の良い睡眠につながる。
・眠りに落ちる前の赤ちゃんの手足が温かくなっていることは、多くの血液を手足にまわすことで、脳の温度を下げているからである。
・大人でも昼食後、暖房の効いた電車に揺られていると、眠くなってしまうのは、加温によって手足などの末梢の血管が開き、体幹から熱が抜けていき、脳の温度が徐々に下がっていくためである。
●腹時計を味方につける
・生体リズムにとって朝、昼、晩の規則正しい食事のリズムが必須である。なかでも、朝食が重要で、できるだけ決まった時刻にとることが重要である。眠っている間に使い果たしたブドウ糖を補給する意味で、朝に糖質をとることは重要である。
・一般的に朝食が最も力強く体内時計を整える力を持っているのは、空腹の時間がながいためである。空腹の時間が長いほど、体内時計の調整力が強い。
・食事からくる栄養刺激として獲得した時刻情報は、インスリンや副腎皮質ホルモン、あるいは自律神経などを介して全身に伝わり、生体リズムの時計の針が調整される。
・体内時計は効率よくエネルギーを生み出せるように代謝を調節している。ホメオスタシスは生体内や外界の環境因子などの変化にかかわらず生体の状態が一定に保たれる働きのことだが、時計遺伝子の一つであるレヴェルブαが、代謝のホメオスタシスを維持する仕組みの主役であるということがわかってきた。生体リズムを守るという点で、食事の持つ意味は重大である。
●寝る時刻、睡眠時間をどう考える?
・必要な睡眠時間には個人差がある。エジソンは4~5時間、アインシュタインは10時間以上とのことである。自分に必要な睡眠時間は就寝と起床の時刻を2週間記録にとり、その平均がその人の必要な睡眠時間である。
●朝が勝負
・朝の起床後にたっぷりと日射しをあびると、その約15時間後にメラトニンができあがるように生合成の準備を始める。夕刻なってできあがったメラトニンは、日が落ち、真っ暗闇になると、いっせいに血液の中に放出される。そして昼間はほとんどないサーカディアンリズムを示す。メラトニンは血流に乗って全身に運ばれ、からだの生理機能を高める。これが脳に働きかけ心地よい眠りを誘う。脳にある体温中枢に働きかけ、脳の温度を下げ、眠りにつきやすい環境を作る。
●それでも眠れないときは
・人にとってどれくらい眠る時間が必要かを決めているのは、脳の松果体時計である。あまり眠れていないと感じても、日中の体調に問題がないなら十分な睡眠をとっているといる。必要な睡眠時間が満たされると、後は浅い眠りがだらだら続くだけなので神経質にならなくてもよい。
・入眠には脳に行く血流を少なくし温度を下げることである。そのために有効な方法は、ぬるめの湯にゆっくり入ることである。15分程度で汗が引き、体温も下がり始めるので、その頃に布団に入ると寝つきが良くなる。
・不眠から「今日も眠れないのでは」という不安が強くなったりイライラしたりするのは、条件不眠と呼ばれる不眠症である。この場合、遅寝早起きが熟睡感を高めてくれる対策になる。
・音楽であれ、香りであれ、あるいは瞑想やヨガのような軽い運動であれ、眠る前にリラックスすることが重要である。
・専門医の指導が必要だが、筋弛緩トレーニングや自律訓練法、バイオフィードバック法などもある。
・就寝4~5時間前からコーヒー・お茶、そして胃にもたれる食事は避ける。特にカフェインは約5時間も持続するので注意する。
・習慣的に床に入る時間の2~4時間前の時間は、1日で最も眠りにくい時間帯である。早く寝ようとして、いつもより早く床についても、なかなか寝つくことができなのはこのためである。そのため、眠くなってから床にはいるのがよい。
・前夜に何時に床につこうと、同じ時刻に起床することが、不眠対策の基本である。毎朝、同じ時刻に起床し、起床後に太陽光を浴びると、体内時計の針がリセットされ、からだのリズムが地球の自転のリズムに一致する。その日の夜には、タイミングのよい時刻に十分な量のメラトニンが分泌され、快適な眠りが得られる。
・目が覚めたらいつまでも床についていないようにするのも、不眠撃退には効果的である。
・昼間の眠気は、健康なからだから発信される睡眠不足のシグナルである、正午から午後2時、15~20分間であれば問題ない。
・昼間の眠気がひどく、週末に平日の3時間以上長く眠ってしまう場合は、要注意である。たっぷり休めているはずだと思っても、深い眠りが得られていないサインの可能性がある。
・昼間の運動は、筋肉や胃腸で作られるメラトニンを増やす。30分程度の散歩や体操など汗ばむくらいの運動がよい。毎日規則正しく行う習慣をつけることが大切である。
・メラトニンは松果体だけでなく、小腸や胃、卵巣、精巣、脊髄、骨、筋肉、皮膚などでも作られる。そしてメラトニンの信号を受ける受容体は心臓、血管、肺、肝臓、腎臓など全身にある。運動すると、松果体以外の部位で、メラトニンが多く作られ、これが快眠につながる。
・血液中のメラトニンの濃度には、1日のリズムとともに1週間のリズムがある。朝に血圧は月曜日に高く、心筋梗塞や脳卒中の発症頻度も月曜に多いことが分かっている。木曜日も多いという報告もあるので、3.5日のリズムもあるようである。
おわりに―休息のプロフェッショナルになろう
・2011年には、睡眠健康推進機構が立ち上がり、健康増進のために睡眠に関する正しい知識を広めるのが目的である。年に2回の睡眠の日も制定された。春は3月18日、秋は9月3日である。各地で睡眠に関する市民講座を開設している。
感想
今回、良かったなと思うことは、“睡眠”について真剣に考えたという点です。
食事・運動・睡眠のうち、一番問題だと思っていたのは睡眠でした。特に時間のプレッシャーがない時でも、集中すると夜中の1時、2時までパソコンに向かってしまうことが多々ありました。通常は7時前後に起床しているのですが、寝るのが遅くなった日で、朝一番に予定が入っていない場合は、8時半ころまで寝ている日も少なくありませんでした。
この本を読んでからは、何とか夜の12時には床につき、寝る時間に関わらず、7時前後には起きるということを意識するようになりました。とにかく、重要なのは朝のようです。また、規則正しい食事もとても重要です。
問題は、この“意識”を長く持てるかどうかというところですが。。
体内時計と睡眠1
睡眠の問題というと、まず頭に浮かぶのは、睡眠時間や睡眠の質などの「眠れない問題」の睡眠障害です。一方、ナルコレプシーのような過眠症をお持ちの患者さまもおいでです。過眠症にはナルコレプシー以外に、特発性過眠症、反復性過眠症があります。
調べてみると、子どもの発達障害、特にADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉症スペクトラム)に、過眠傾向が多くみられることがわかりました。
また、睡眠の問題はホルモンである“メラトニン”と“体内時計”が最も重要なのではないかと思い、見つけたのが大塚邦明先生の著書である『眠りと体内時計を科学する』という本でした。「これだ!」と思い発注しました。
目次
はじめに
1 眠りと体内時計
●眠りのリズムは90分と12時間
●自律神経は嵐のごとく
●体内時計が眠りを誘う
2 時計遺伝子とは何か―人間は宇宙とシンクロしている
●時計遺伝子とは何か
●生体リズムの発見は「地動説」
●宇宙のリズムをコピーする
●体内時計は25時間周期
●太陰暦は理にかなっている
●太陽活動の影響
●出産明け方に多いわけ
●オーロラは魔女
●人間も磁気を感じている
●時差ぼけの仕組み
●体内時計の老化
3 眠りと夢
●夢見る時間
●レム睡眠との関係
●夢は現実を再現している
●なぜ夢を見るのか
●スピリチュアルな存在との邂逅
4 現代人はなぜ眠るのに苦労するのか
●パソコン、携帯、ネオンが与える影響
●夜型人間は朝型人間になれない?
●現代人は不健康?
●女性の睡眠時間に異変あり
●若返りの泉メラトニン
●睡眠時無呼吸症
●不眠によるトラブル
●災害現場、避難所の報告から
5 眠りは変化する
●成長と共に変化する睡眠
●乳児の眠り
●幼児の眠り
●学童児の眠り
●思春期の青少年の眠り
●社会生活をしている人の眠り
●中高年の眠り
●認知症の人の眠り
6 よりよい休息のススメ
●サマータイムの導入は是か非か
●長生きする人の睡眠
●脂肪分のとりすぎは要注意
●タバコ、昼寝、寝酒は避けるべき?
●睡眠薬のメリット、デメリット
●子守歌の科学的効果
●腹時計を味方につける
●寝る時刻、睡眠時間をどう考える?
●朝が勝負
●それでも眠れないときは
おわりに―休息のプロフェッショナルになろう
はじめに
・日本人の5人に1人は不眠に悩んでいる。
・地球の過酷な環境のため眠りの仕組みを作った。
・1972年に体内時計が発見された。それは自律神経とホルモン調節の中枢である脳の視床下部に存在していた。
・大塚先生は睡眠の研究を「こころ」の研究として始めた。そして、近年はフィールド医学という新しい学問体系に取り組んでいる。
・脳と心臓とこころの関りの探求を極めるには、眠りの謎を解くことが近道だった。
1 眠りと体内時計
●眠りのリズムは90分と12時間
・人間のからだの時計は、朝起きて15時間経つと眠くなるようにセットされている。
・朝の太陽光を浴びることで、その日の眠りの時計のスイッチが入る。
・眠れない時間帯がある。それは朝の目覚めから12~15時間である。
・人間の眠りは90分がワンセットで、これを4、5回繰り返す。
・1回目の眠りの時に最も多くの成長ホルモンが出る。
・副腎皮質ホルモンは、4回か5回めの眠りの時にピークに達する。
・血管の健康を維持するエンドセリンは8時間のリズムが見られる。これは睡眠時間の周期と連携しつつ、血管の緊張のリズムを作りだしている。
・「人は血管とともに老いる」という古来の名言がある。
・最も強い眠気は午前2~3時、また午後2時にも強い眠気度がある。
・眠りの仕組みには生体リズム以外に、睡眠物質の働きもある。睡眠物質の代表は脳脊髄液のなかに増えてくるプロスタグランジンというホルモンである。
・病気になり発熱に伴って眠くなるのは炎症に関連して増えたサイトカインである。
・睡眠物質として明らかになっている物質は20余りあると考えられている。
●自律神経は嵐のごとく
・夜、眠り始めるとともに、副交感神経の活動が高まり、朝、目が覚めるとともに交感神経の活動が高まる。
・眠りの1回のサイクルのなかで、まずノンレム睡眠があらわれ、レム睡眠(急速眼球運動を伴う睡眠)が続く。
・ノンレム睡眠は脳波3~4Hzの遅い波で、麻酔で眠っているときの脳波とそっくりである。
・睡眠後半はレム睡眠が主体になる。なお、1日で最も体温が低くなった頃にレム睡眠が力強く、そして長く現れるようになる。
・『みなさんは眠っているときに、からだがピクッとびくつく経験はありませんか? これはトゥイッチとよばれる現象です。何が起きても目が覚めない状態では、地震が来たり、大火事になったりしたとき、逃げおおせることができません。そこで脳は、トゥイッチを起こす伝令を何度も発信しているのです。「このまま睡眠を続けても、外敵に襲われる心配はないのかな?」と気配りをしている証です。これもレム睡眠の特徴の一つです。』
・レム睡眠は覚醒しているときの脳波に似ている。これは古い脳の大脳辺縁系が目覚めているためである。また、新しい脳の中では視覚などを担う後頭葉が目覚めている。
・レム睡眠は、脳波は覚醒しているときに近いものの、筋肉は弛緩し音もほとんど入ってこない感覚遮断に近い状態である。また、もう一つの大きな特徴は自律神経が不安定になっており、交感神経が興奮したかと思うと、それに反発するように副交感神経の興奮が高まったりする。医師の言葉では、これを「自律神経の嵐」と呼んでいる。発作性の不整脈や夜間狭心症が誘発される危険もあるので、このタイミングは特に注意が必要である。
●体内時計が眠りを誘う
・脳にある体内時計は、主としてレム睡眠に働きかけている。
・レム睡眠の時に見られる、金縛り、トゥイッチ、特徴的な速い眼球の動き、そして自律神経の嵐には、いずれも明瞭なサーカディアンリズムがある。サーカディアンリズム(概日リズム)とは、一日周期のリズミカルな変動を指す医学用語である。
・眠りを誘うホルモンとして有名なメラトニンのリズムも体内時計が作りだしている。
2 時計遺伝子とは何か―人間は宇宙とシンクロしている
●時計遺伝子とは何か
・地球上の生物は、バクテリアから深海魚にいたるまでみな、時計を持っている。生物は地球の自転に精確に似た仕組みを未来を予測する手段として体内に作り出している。
・光合成に頼っている植物は最も多くの時計を持っている。青を感知する時計、緑を感知する時計、赤を感知する時計などを用いて、夜明けが近づくと少しの太陽光を逃すまいと、暗いうちにもかかわらす光合成の準備を開始する。
・生物が急激に多様化した約5億5000万年前のカンブリア紀以前に、すでに体内時計の仕組みを身につけていた。
・体内時計をつかさどるのが時計遺伝子である。
・生体リズムは、6個の時計遺伝子によって作られている。それらは、ピリオド遺伝子(パー1、パー2)、クリプトクロム遺伝子(クライ、クライ2)、クロック遺伝子、ビーマルワン遺伝子。
・時計遺伝子は、脳だけでなく、肝臓・腎臓・心臓・血管など、からだのほとんどの細胞に存在する。脳の時計が親時計で、臓器や皮膚や粘膜にいたる末梢組織に存在する時計を、子時計と呼んでいる。
・子時計は親時計に連動しつつも、独立して個々に時を刻んでいる。まるで親時計と子時計が一体となって、あたかも交響曲を奏でる一団のように見える。
・体内時計は、からだ全体から臓器へ、そして細胞に至るまで、一体となってサーカディアンリズムを構築している。
・時を刻む遺伝子とタンパクを一緒にして、時計分子と呼ぶ。
●生体リズムの発見は「地動説」
・生体リズムが遺伝子レベルで規定されていることは、1971年にショウジョウバエの羽化のリズムを元にした研究で明らかになった。そして1972年には、哺乳動物にも地球や月の自転そっくりのリズムがあることが発見された。なお、人での発見は1997年である。
・体内時計は視床下部の中に左右一対の米粒のような細胞の塊として存在している。そして、6個の遺伝子が互いに作用しあいながら、精確に時を刻んでおり、この場所を破壊するとサーカディアンリズムは消える。
●宇宙のリズムをコピーする
・体内時計で最も有名なのは24時間(サーカディアンリズム)だが、人は90分、12時間、3.5日、7日、30日、1年、1.3年、10.5年、21年などの多くのリズムを多重構造として獲得している。
・定義上、サーカディアンリズムは24時間プラスマイナス4時間のリズムを意味する。20時間より短い周期性はウルトラディアンリズム、28時間より長い周期はインフラディアンリズムと呼ばれている。
●体内時計は25時間周期
・太陽光が届かず、また時刻を知る手段の環境での実験では、1日を約25時間で認識していた(12日で昼夜逆転し24日で元に戻った)。
●太陰暦は理にかなっている
・生体リズムは天体と深い関係がある。
・暦は天文学を基礎として発達してきた。地球の公転周期は365.25日、自転周期は0.9973日である。
●太陽活動の影響
・生体リズムは種を越えて普遍的に共通である。これは生物が30億年をかけて生きのびるために最初に獲得した生理機能が生体リズムであったことを示している。大気やオゾン層の薄い今より過酷な地球環境の中で、太陽からの恵みと害の両方を強烈に受けつつ、様々な自然現象、宇宙現象の振動に応答し、過酷な風土に順応し、進化を繰り返した。その適応の所産として、体内に時計遺伝子を獲得したのである。
●出産が明け方に多いわけ
・人間の出産は夜から朝にかけて多く、昼間に少なくなる。答えは不明だが、恐竜時代に生き残る可能性が一番高かったからなのかもしれない。
●オーロラは魔女
・日中に浴びる光が少ないと、メラトニンが少なくなる。この点からも光を浴びる量と生体リズムには深い関係があることがわかる。
●人間も磁気を感じている
・渡り鳥やウミガメは、地磁気の磁場を頼りに渡りをする。これまで人には磁気を感じる能力はないとされてきたが、2011年に米国マサチューセッツ大学のスティーブン・レパート博士らによって人にも同じ能力があることが確認された。網膜にある時計遺伝子クライで、磁気を感じているのではないかと考えられている。誰もが正しく応答しているが、それを脳に伝えるシステムに問題があると考えられており、いわゆる第六感のようなものである。
●時差ぼけの仕組み
・『さて磁気変化の感知のほかにも、私たちのからだが地球と関わっている点があります。たとえば時差ボケ。生体リズムとは、睡眠・覚醒周期、体温調節、血圧周期、心拍周期、排便周期など、身体の様々なリズムがよせあつまったものです。飛行機で海外に行った場合、これらの働きのうち、睡眠と血圧のリズムは、すぐ現地の生活リズムに順応できます。心拍リズムも、比較的早く順応することができます。しかし、体温や排便のリズムは、順応に1週間から10日間を必要とします。そのため、旅行先の新しい環境下ではリズムがバラバラになってしまい、時差ぼけが起こります。』
・海外での生活リズムに順応する時間には個人差がある。早い人で1週間、遅い人では数ヶ月が必要である。
・時差ぼけの症状は多い順位に、①睡眠障害(67%)、②日中の眠気(17%)、③精神作業能力の低下(14%)、④疲労感(11%)、⑤食欲低下(10%)、ぼんやりする(9%)、頭が重い感じ(6%)、胃腸障害(4%)、目の疲れ(3%)、イライラ(3%)など。
●体内時計の老化
・時差ぼけは年齢とともに症状が強く出る傾向がある。これは体内時計も老化することを示している。
・医学用語では年を取ることを“加齢”、それがもたらすからだの変化を“老化”と呼んでいる。
・4つの特徴
1)生活にメリハリがなくなる
-メラトニンや性ホルモンなどの分泌が低下し、活動と休息、体温の変動、水分補給などの行動リズムが昼夜を通して不明瞭になってくる。
-メラトニンは睡眠と覚醒リズムと連関しつつサーカディアンリズムを調節するだけでなく、自律神経や免疫系にも作用するため、健康を保持する働きもある。さらに、骨粗鬆症改善やがん予防、老化を遅らせるなど様々な作用が注目されている。
2)早寝早起きになる
-サーカディアンリズムの位相が前身することで、体内時計が前に進みため早寝早起きになる。
3)1日が短く感じる
-75歳を過ぎると生体リズムが、約1時間短くなる。ただし、これは個人差が大きい。
4)生体リズムが太陽とうまく同調しなくなる
-体内時計には毎朝、太陽の光を利用して地球の針とのずれを調整する働き(光同調)があるが、この機能が衰える。
・脳の体内時計の老化は脳の機能、構造と関係している。70代に入ると、脳と細胞の時計とを連絡する神経線維の数が減ってくる。そして、80歳を超えると脳時計の中にある時計細胞の数も減ってくる。これがサーカディアンリズムに影響する。
3 眠りと夢
●夢見る時間
・夢を見る時刻にもリズムがある。
・夢を見る頻度は午前2時頃から増えるようになり、最大になるのは朝の8時頃である。これは入眠してメラトニンが出始めてから10時間位後に相当する。おおよそ習慣的な起床時刻にピークが来る。
●レム睡眠との関係
・調査によりレム睡眠中に夢を見ていたとする人は80%、一方、ノンレム睡眠中は20%である。
・レム睡眠のときの夢は睡眠深度が深い(4分類中4)ときに現れる。
・PETという画像検査で調べたところ、レム睡眠の時は喜怒哀楽を調節する大脳辺縁系と視覚野の活動が活発になっていることがわかった。また、海馬も活性化していた。
・体内時計のある視床下部には、オレキシンを産生する部位がある。オレキシンは食欲を増進させるホルモンだが、覚醒に欠かせないホルモンで、働きすぎると不眠症、低下すると過眠症を誘発する。
・オレキシンは2000年になって発見されたが、レム睡眠とノンレム睡眠にも深く関わっている。
●夢は現実を再現している
・夢の素材は体験の記憶なので、特に数日以内の体験が夢の内容にあらわれやすい。
・夢は成功より失敗、幸運より不幸が題材になりやすい。
・夢が健康に良いのか悪いのかは分かっていない。
●なぜ夢を見るのか
・今では神経生理学が発展し、夢で見る奇異な出来事の一部は説明できるようになった。
●スピリチュアルな存在との邂逅
・奇異な夢は脳のいろいろな領域が同時に興奮していて、矛盾する情報が交錯して構成されるからである。
・『死も夢も、どこか人間のうかがい知れない領域に存在しているように思えます。昨今、スピリチュアルという言葉をよく耳にしますが、私は神と魂との対話という意味だと理解しています。超高齢社会を迎える日本で老いと人生の終え方がクローズアップされるなか、これまで日本人には関わりが薄かったスピリチュアルの世界が必要になってくる日が来るに違いありません。』
グリア細胞3
第10章 グリアと薬物依存症―ニューロンとグリアの依存関係
アルコール依存症―グリアとアルコール
・『精神遅滞のある子供に出会うと、思いやりと悲しみで胸が詰まる。子宮の中で発芽し始めた脳に影響した不運さえ防げていたならば、と思わずにはいられない。悲しい事実だが、精神遅滞を負う子供の大半に襲いかかった元凶を、私たちは知っている。さらに、その壊滅的な攻撃をどうしたら止められるかも知っているというのに、それは続いているのだ。小児に精神遅滞を引き起こす第一の要因は、胎児性アルコール症候群だ。
これまでに判明している事実は、以下のとおりだ。アルコールはニューロンを害する。発達期の脳にアルコールが侵入した場合、脳への効果は最も壊滅的で永続するものになる。胎児脳の発達を害するには、慢性アルコール曝露(つまり、一回の痛飲)が、胎児脳に永続的な損傷を与えかねない。
脳領域各部や脳内の多種多様な種類の細胞はそれぞれ、妊娠中の異なる時期に発達する。一般に、胎児の脳がアルコールに曝露される最悪の時期は妊娠後期であり、この時期に脳は、目覚ましい成長スパートで増大する。ニューロンとグリアは急速に分裂して、脳の大規模な成長を後押しする。この時期、ニューロンは樹状突起も活発に発芽し、春の若木が小枝を伸ばすように、さかんに枝分かれする。軸索は脳内に伸長して、神経結合網を形成し、新芽のように枝先から発芽してきた新たな無数のシナプスを連結しながら、複雑な神経回路を編成する。この期間にアルコール毒に遭遇すると、脳の急速な発育が阻害される―しかも、不可逆的に。胎児性アルコール症候群の子供の85%が、脳が異常に小さい。これを医療用語で「小頭症」という。出生前のアルコール曝露は、二通りの様式で脳の成長スパートを抑制する。第一に、曝露はニューロンの増殖を阻害する。第二に、ニューロンを死滅させ、これはとくに、海馬や小脳において顕著だ。
では、グリアはどうだろう? ニューロンに対するアルコールの影響に関しては、多くのデータがあるのに比べて、グリアについてはほとんど知られていない。しかし、グリアが脳細胞全体のおよそ85%を占めることを考えれば、小頭症はニューロンだけでなく、グリアの消失にも起因すると当然予測できる。そしてこの仮説は、証拠によって裏付けられている。
細胞培養で、ラットあるいはヒト由来のアストロサイトをアルコールで処理すると、アストロサイトの細胞分裂が強く抑制される。アストロサイトの細胞分裂に対するアルコールの遅滞効果は非常に強力なので、体内で生成されることが知られている大半の成長因子の刺激作用を凌駕する。細胞培養に付加して調べられたヒト由来の強力な成長因子はどれひとつとして、アストロサイトの細胞分裂に対するアルコールの抑制効果に打ち勝つができなかった。
アルコールは、グリアを殺しもする。アルコールの影響は、ラットの大脳皮質から採取して培養したアストロサイト、および妊娠中にアルコールに曝露したラットの脳内で観察されている。ある研究では、胎仔のときにアルコールに曝露したラットの大脳皮質で計測された細胞残骸のうち、40%がアストロサイトだったという。
ニューロンやグリアの数が減少した小頭症の脳では思考能力が減退するという単純な影響のほかに、アルコールによる胎児グリアへの攻撃が引き起こす多くの壊滅的な結果を予測するには、神経系発達を指揮するために、グリアが演じている重要な役割を考えてみるだけでいい。次章で考察するが、グリアは栄養因子を供給して、未成熟細胞から適切な種類のニューロンへの転換を促し、発達後もこれらのニューロンを維持している。
グリアはまた、軸索が適切に結合を形成して、きちんと機能する神経回路を形成できるように、途中の経路に分子を敷設していく。シナプス形成も、グリアが助けている。グリアは神経伝達物質を取り込み、生命維持に欠かせない塩や栄養を、ニューロン周囲で至適な濃度に保っている。また、グリアは脳を感染から保護する。発達期の細胞移動も、グリアによって制御されている。したがって、アルコール汚染によるグリアの消失は、発達途中にある脳に多くの悪影響を及ぼすことになる。
グリアとニューロンは、胎児脳を築くために、正しい場所に集合しなくてはならない。胎児性アルコール症候群の子供には、グリアの異常な移動が認められ、それは、実験動物でも同様である。動物実験では、グリア細胞をアルコールにわずかに曝露しただけで、中毒になったグリア細胞に間違った経路をたどる障害が起こりうる。その結果、脳の奇形が生じる。左右の大脳半球間をつなぐ架け橋である脳梁が作られる工程でグリアが担う重要な役割は、次章で詳しく論じることにするが、両半球間にグリアの架け橋がないと、ニューロンは反対側の脳まで軸索を渡すことができない。胎児性アルコール症候群の子供では、両半球をつなぐこの壮大な橋は形成不全のままである。この脳異常は、胎児性アルコール症候群に顕著な特徴のひとつだ。胎児性アルコール症候群は、ニューロンの病気であるのと少なくとも同じ程度に、グリア病でもある。』
・『アルコールには幅広い毒性があり、ニューロンとグリアをさまざまに中毒させ、害する。アルコールの中毒作用は大部分が、肝臓にあるアルコール脱水素酵素によって作られるアルコール分解産物アセトアルデヒドによって引き起こされる。このきわめて重要な酵素が進化したのは、人類の祖先が食物として腐った果物も摂取していたと考えられ、さらに消化過程そのものでも腸内でアルコールがいくらか発生するためだ。しかし、飲酒のように意図的にアルコールを摂取すれば、それを無毒化して中毒を防ぐ酵素のような体内機能では、とても太刀打ちできない。
アルコールそのものも、ニューロンとグリアに死をもたらす直接因子である。アルコールは、脳内で通常は過剰興奮を減弱している受容体(GABA受容体)に作用する。この受容体は、バルビツール酸やバリウムで活性化される抑制性受容体であり、このことはアルコールが鎮静効果を有する一因となっている。ところが、アルコールを常用すると、脳は抑制性回路を駆動するGABA受容体の数を減らして、グルタミン酸で作動する興奮性回路の活性を高めるようになる。この変化が、アルコール依存をもたらす。なぜなら、アルコールが途切れると、不安や気分、痛みを制御している回路が、過剰興奮の状態になるからだ。気分や脳内の「報酬回路」の調節に関与する神経伝達物質のドーパミンやセロトニンに対しても、アルコールは似たような効果を持ち、これもアルコール依存に加担している。この三つの神経伝達物質は、胎児および成体幹細胞からニューロンやグリアへの発達を調節することが知られている。これらのアルコールによる変化は、記憶回路をも損傷する。長期的なアルコールの常用は、抑制を減弱させ、興奮を増大して、脳の興奮を正常レベルに保っているGABAの重要な抑制作用から、ニューロンを解き放つ。脳内の抑制性回路がアルコールで弱められると、脳回路は過剰興奮の方向へ傾き、過剰刺激によってニューロン死が引き起こされるのだ。
アルコールは、NMDA受容体の感受性を低下させることによっても、精神の働きを鈍らせている。というのも、この受容体は、学習と記憶にかかわるシナプスの強度を高めるための、最初の重要な段階で働いているからだ。一方で長期的なアルコールの常用は、この受容体数を増加させる。受容体が増えると、過剰興奮によってニューロンやグリアが死ぬ傾向が強まる。将来オリゴデンドロサイトに分化して、出生後の新生児脳でミエリンを形成する予定の胎児脳細胞も、アルコールは殺傷する。事実、白質の減少は胎児性アルコール症候群の主要な特徴のひとつであり、ミエリン量低下が精神機能の低下を意味することは、現在では広く認知されている。
これらの損傷に加えて、アルコールは脱水、酸化ストレス、ビタミンの欠乏、さらには多くの代謝・損傷応答にも影響する。これらはすべて、奇跡のような胎児脳の発達を害している。グリアは、このアルコールという毒物の主要な犠牲者なのである。』
第12章 老化―グリアは絶えゆく光に抗って奮い立つ
老化する脳
・65歳になると、脳の重さは中年期よりも平均で7~8%軽くなり、計画の立案や実行などの意思決定にとって重要な脳部位である大脳皮質の前頭葉の容積は5~10%ほど縮小する。ただし、この程度の衰えは問題にはならない。
・加齢に伴い個々のニューロンは劣化し始めて死んでいくが、死滅は脳の部位によって大きく異なる。
・皮膚の染みが徐々に増えていくのと同じように、老化したニューロンには凝固したタンパク質が絡み合った黒っぽい沈着物や封入体が形成され始める。
・古い家の屋根裏部屋で増えていくガラクタのように、加齢に伴ってニューロン内部には他の多くのタンパク質が蓄積されていく。このタンパク質のゴミは、筋萎縮性側索硬化症やハンチントン病、パーキンソン病のような神経変性疾患に関連している。
第3部 思考と記憶におけるグリア
第13章 「もうひとつの脳」の心―グリアは意識と無意識を制御する
・『グリアを研究することで、脳の働く仕組みに関する私たちの理解は、どのように改まるだろうか?「もうひとつの脳」の探求は、人間の心の秘密に光を当てることができるだろうか? グリアはニューロンに奉仕するだけでなく、私たちの意識的な心、さらには無意識の心さえも動かす役割を演じられるのだろうか?
グリアについて、私たちはまだほとんど知らない。基本的な事実、たとえば何種類のグリアがあるのか、発達期にどこから派生するのか、各種のグリア細胞の細部がどうなっているのかさえ、判明していない。神経科学の分野に足を踏み入れる学生のほとんどが、ニューロンでない細胞を研究しないのは、動かしがたい事実だ。さらに悪いことに、ニューロンだけが脳内の情報処理にとって重要であるという従前の見方によって、グリア生物学者の研究は、重要性に乏しいと安易に退けられている。その結果、「もうひとつの脳」に関する研究は、「ニューロンの脳」の研究より、100年も後れを取っているのだ。』
グリアは渇きを癒す
・『私たちが水分を摂取する量と頻度は、その時々で大きく異なるにもかかわらず、脳は体内の水分量を厳密な範囲内に調節している。水は生命維持のために食糧よりも重要で、いかなる生物の体内でも、常に適切なレベルに維持されていなければならない。水分が欠乏すると、数時間のうちに身体機能にも精神機能にも支障が出る。脱水が続けば、数日のうちに命を落とすことになり、ほとんどの病気より急速に死に直結する。
私たちの体が脱水に対処するひとつの方策に、抗利尿ホルモン(ADH)の血流中への放出がある。このポリペプチドホルモンは、視床下部ニューロンから分泌され、腎臓に作用して尿の排出量を減らし、体内に蓄えた貴重な水分の減少を食い止める。喉が渇いた動物では、視床下部のシナプスに存在するグリアが驚くべき方法で応答することを、解剖学者らが観察した。』
出産、母性、愛、そしてグリア
・『オキシトシンは、視床下部の特殊化したニューロンで産生され、血液中に放出される。その巨大なニューロンは、その大きさから大細胞ニューロンと呼ばれ、視床下部から下垂体の一部の中へ軸索を伸ばして、そこで毛細血管周囲の間隙にホルモンを放出している。毛細血管はそのオキシトシンを血流中に吸収して、全身に行き渡らせる。オキシトシンは、9個のアミノ酸が連なった短いポリペプチドで、女性の体内で二つの特別な機能を持っている。それは、乳腺からの乳汁分泌を刺激することと、分娩時の子宮収縮を刺激することだ。どちらの機能も、血中のオキシトシンに応答して平滑筋が収縮した結果として生じる。
このホルモンにはもうひとつ、より繊細で興味深い働きがある。それは、母親としての行動や愛情の調節だ。証拠は依然明確さを欠いているものの、オキシトシンが男性の行動へも、これに関連するような効果を発揮する可能性がある。脳脊髄液の中で、オキシトシンはキューピッドの役割を果たしていて、出産直後から、自分の子供との絆を築こうとする力強い母性行動によって、母親と子供を結びつけている。生物的な観点から見れば、この強い愛着心は、親が脆弱なわが子を間違いなく養育し、保護するために不可欠である。ラットの実験で、注射によって脳内のオキシトシンを中和すると、母ラットは自分の仔を拒絶するようになる。その一方、処女ラットにオキシトシンを注射すると、同じケージに入れたどの仔ラットに対しても、母性行動を示し始める。オキシトシンはスプレーでも体内に取り込まれるので、この性質が営利目的で利用されている。異性との結びつきを容易にする目的で、オキシトシンを含むオーデコロンを購入することもできる。
処女ラットでは、オキシトシンを含んだニューロンは密集して存在するが、個々の細胞の間は、重ねた陶器の間に挟む紙のようなアストロサイトの薄いシートで隔てられている。動物が妊娠すると、この脳部位が構造的に変化することを、電子顕微鏡学者たちは何年も前から気づいていた。これは驚くべき事実だった。なぜなら、脳の神秘的な働きが、その配線の構造変化に反映されている様子を観察することができた最初期の事例のひとつだったからだ。カリフォルニア大学リヴァーサイド校のグレン・ハットン博士ら、フランス・ボルドーのディオニシア・テオドシスとドミニク・プラン、さらにアメリカやヨーロッパのいくつかのグループによる数年に及ぶ研究から、分娩中や授乳中の動物では、ニューロンを隔てているアストロサイトが実際に動いて、この脳部位の構造を変えることが現在ではわかっている。妊娠すると、アストロサイトの薄いベールのような膜が退縮して、オキシトシン産生ニューロンとその樹状突起の露出が増える。これに伴って、各ニューロン上で新しいシナプスの形成に利用できる空いた場所の数も増加する。この作用によって、アストロサイトの退縮後、オキシトシンを含んだニューロンのシナプス数は二倍になる。ニューロンを刺激するシナプスの数が増えれば、オキシトシン放出量も増加し、妊娠には出産に向けた準備が整うことになる。
アストロサイトの動きは、別のやり方でも視床下部を配線し直している。アストロサイトはニューロンへのシナプス入力の調節に加え、その軸索先端から血流中へ放出されるオキシトシンの供給も制御している。分娩や授乳の最中には、アストロサイトは神経終末でも退縮して、水門を開くかのような働きで、より多くのオキシトシンが毛細血管へ到達して、血流に入っていけるようにしている。神経終末と毛細血管を隔てているのは、このアストロサイトだけなのだ。
この次に母親の腕に抱かれて授乳されている赤ん坊を見かけたときには、グリアが活躍しているところを思い描いてみよう。あなたの目の前で、グリアはニューロンのシナプス数や血流中へ流れ込むオキシトシン量を制御している。私たちの子孫の誕生やその養育は、このグリアに依存しているのだ。』
無意識の脳を超えて意識的な脳へ
・『グリアが情報処理にかかわっていることを示す最初で最強の証拠が、喉の渇きや出産、授乳、睡眠、運動制御、性行動など、数々の無意識の脳機能に関連したことは、不思議に思われる。脳内の無意識的な働きは、意識的な精神活動と比べて、はるかに謎めいて研究の困難な現象だからだ。この不思議な関係性は、たんなる偶然の一致だろうか、それとも「もうひとつの脳」のより普遍的な性質を明らかにしているのだろうか? 私自身は、後者であると信じている。グリアには、ニューロンが使用しているような急速な発火によるコミュニケーション手段が備わっていない。グリアは電気ショックではなく、化学物質やカルシウムウェーブの緩やかな拡散を介して交信している。しかし、心の中で無意識のうちにゆっくりと展開する変化は、重要な脳機能でありながら、見過ごされがちだ。おそらく、無意識の心が今なお謎に包まれている理由のひとつは、私たちが「もうひとつの脳」について無知であるためだろう。』
第15章 シナプスを超えた思考
【Tasaki】
・『毎日、高齢の日本人男性がひとり、慎重に杖を突きながら、脚を引きずるようにして、目的地に向かって歩道を歩いていく。その老人は深く考え込んでいて、周囲の様子は目に入っていないようだ。急ぎ足で通り過ぎる人々は、脇目も振らずに目的地を目指すその老人の体力と決然とした意志に感心するのではないかぎり、彼のことは気にも留めない。彼がどこを目指しているのかを想像できる者など、ほとんどいないだろう。
あと二年で100歳を迎えるその優しげな老人は、職場へ向かっているのだ。彼は一日二回、3㎞あまりの道のりを毎日歩き抜いている。彼の妻の信子夫人が60代になるまでは、自宅で一緒に昼食をとるために、彼はこの道のりを二往復していた。昼食後には、二人並んで職場に戻った。知り合って間もない頃、信子夫人は彼と一緒にいたいのなら、彼の助手にならなければならないと悟った。2002年に彼はこう誓った。「妻がもう働けないと言うまで、私は働き続ける。妻が100歳まで働けるのであれば、私も働き続けよう」。ところが、信子夫人が亡くなったあとも、彼が仕事を辞めることはなかった。
震える手で真鍮製の鍵を回しながら、老人が職場のドアを開けると、ガラス製の器具や1960年代の電子機器であふれた科学実験室が現れる。部屋に足を踏み入れると、かつて宇宙開発計画が始まった頃にエンジニアが好んだようなスタイルの彼の衣服や眼鏡は、その場の光景に完璧に溶け込む。街中では、彼は過去の人のように見えたかもしれないが、部屋の照明が灯ったとたんに、あたかも舞台上で急に息を吹き返したかのような過ぎ去った時代の光景に、彼はしっくりと馴染む。彼を取り囲む年代物の電子機器や科学実験装置の大半は、彼が自作したものだ。作製当時、彼の構想とそれに必要な装置は、そのとき手に入る技術をはるかに凌ぐものだった。
田崎一二という彼の名前は、あまり知られていないが、彼の精力的な仕事のもたらした成果を知らない者は誰もいない。私たちの神経系が筋肉を制御するために、神経を通して電気を送ることによって機能していること、そして、感覚器官から脳へインパルスが送られていることは、誰もが知っている。だが、インパルスはどのように軸索を伝導されているのだろうか? この疑問に答えたのが、田崎博士だ。』
・『田崎のその大仕事を、単純な道具と自作の装置を使って手作業で行い、次に測定したデータの意味を解き明かそうと、数式を適用した。軸索における電気の伝わり方をミエリンが変化させていることを、田崎は見出した。電気的インパルスは、誰もが想定していたように、電波として神経線維を駆け抜けているのではなかった。バレエダンサーが舞台の端から端までを二、三度の跳躍で横切るように、ミエリンがインパルスをひとつのランヴィエ絞輪からその次へと、順に飛び移らせていることを、彼は発見した。この発見は、どうしたら有髄軸索が無髄軸索の100倍も速く情報を伝えられるのかを説明していた。この基本的なプロセスが、脳と全身のあらゆる有髄回路の設計と働きを支える基礎を成しており、軸索のミエリン絶縁を攻撃する多発性硬化症やその他の疾患に罹った人々を苦しめている麻痺の原因となっている。
田崎の初期研究の多くは、時代を先取りしていて、彼の比類なき観察の数々は、曖昧な好奇心の域を出なかった。1958年に、彼はネコ脳のグリア細胞に電極を刺入して、グリアはニューロンのように電気的インパルスを発生させないが、特有の性質として、定常的な電位を持つことを発見した最初の人物となった。』

画像出展:「ウキペディア」
第16章 未来へ向けて―新たな脳
・『「もうひとつの脳」の物語の最終章は、まだ白紙である。グリアを理解できたら、心についての私たちの理解はどのように変わるだろうか? 私たちは今や、100年以上も無視されていた別の脳、すなわち科学にとって未知の脳を、グリアが構成していることを知っている。科学において「もうひとつの脳」は、終始一貫して見過ごされ続けてきた。それはいったいなぜなのか?
第一に、その研究に不適切な道具が使われていたことが挙げられる。神経科学者たちの電極では、グリアのコミュニケーションを聞き取れなかったのだ。それでもやはり、グリアの脳はたしかに連絡をとっていた。ただし、ニューロンの脳とは違う仕組みで働き、異なる様式とタイムスケールで交信している。しかし、道具の不備だけでは、神経科学者が今日まで脳の半分を見逃してきた理由を、完全に説明することはできない。
人間は、道具作りにはとりわけ秀でている。科学者がグリアの脳を探る特別な道具が必要だと感じていたら、工夫を凝らして作り出していただろう。そうした道具は、当初どれほど粗削りだったとしても、役に立ったに違いない。なにしろ私たちは、持ち前の創意工夫によって尖らせた石だけで、この地球上であらゆる動物を捕食し、支配しえた生物なのだ。
私たちが失敗したのは、思い込みのせいだ。脳の働く仕組みを知っていると、私たちは思い込んでいた。電気で作動するニューロンに目がくらんだ神経学者らは、この一種類の細胞だけに極度に研究の焦点を絞って、数や多様性の点でニューロンに勝っているもう一方の細胞群すべてを、事実上無視してきた。無意識の先入観が、私たちの認知を曇らせていた。こうして、グリアの脳は見過ごされ続けることになった。』
感想
グリア細胞を勉強しようと思ったのは、以下のニュースがきっかけでした。

『これまでの研究から、神経がダメージを受けると脊髄でミクログリアが活性化して神経障害性疼痛が発症することが知られていました。今回の研究では、そのミクログリア細胞の一部が変化し、徐々にIGF1という物質を作るようになり、それが痛みを和らげていることを明らかにしました。』
”グリア細胞2”の最後の箇所にあった、『ニューロンが損傷したときのシグナルの中に、フラクタルカインという物質がある。この分子はニューロンの表面にあり、傷害を受けると非常事態を知らせる。ミクログリアは、フラクタルカインによる非常事態を感知する特別な受容体を持っており、感知したミクログリアは損傷部位へと急行し、その領域にサイトカインを浴びせかける。この反応は通常、傷が治るのに伴って数週間で消えるが、ときにミクログリアがサイトカインの放出を止めない場合がある。この場合、傷は癒えても痛みを伴う炎症反応は続く。』
「痛みを弱める"IGF1”」に加え、上記の「ときにミクログリアがサイトカインの放出をやめない」ことによって、痛みを伴う炎症反応が続いてしまうという点も、ミクログリアと慢性疼痛の関係を示す重要なポイントだと思いました。
グリア細胞2
第4章 脳腫瘍―ニューロンはほぼ無関係
・脳腫瘍はすべてが悪質ではないか、一般的には致死性が最も高い癌の部類に属している。
・脳腫瘍は脳内のどこにもでも発生し、腫瘍に伴う初期症状は脳が担っている機能と同じように多種多様である。最も多い初発症状は頭痛と疲労感であるが、腫瘍の発生部位によっては、視力や発話、起立や歩行に関する問題や、人格や心理状態の変化などもある。
・優秀な脳外科医は、症状からそれを司る脳の領域を割り出す方法で、脳内のどこに腫瘍があるのかを把握することはできる。
・癌細胞の特徴は制御不能な細胞分裂の暴走であるが、通常、細胞分裂は非常に複雑に調節されているので、その制御過程に複数の不具合が起こらない限り、細胞分裂の暴走は起きない。
・癌は遺伝的および環境的危険因子が複合的に働いた結果として生じる。
腫瘍の種類
・脳にできる癌のほとんどがグリア細胞から生じる。
・脳の発達期、ニューロンが未成熟な乳幼児以外の、成熟ニューロンに関しては細胞分裂しないので癌化はしない。ただし、髄膜細胞や上衣細胞はグリアと同じく細胞分裂するので腫瘍を生じるが、大多数の脳腫瘍は異常をきたしたグリア細胞である。末梢神経の腫瘍もグリア細胞であるシュワン細胞に由来する場合が多い。
・女性に比べ男性の方が悪性の脳腫瘍に罹りやすいが、脳と髄膜にできる良性腫瘍は女性の方がはるかに多く、約20倍と言われている。
第5章 脳と脊髄の損傷
脊髄に対する細胞応答
・『軸索が切断されると、ニューロンはすぐに死滅し始める。細胞体が損傷個所から離れたところにあって無傷でも、それは変わらない。これは自然死ではなく、いわば細胞の自殺であることがわかっている。ニューロンは、通常支配している標的から切り離されると、細胞体内の遺伝子が活性化して、自己破壊を開始する。自己破壊を引き起こす遺伝子を妨害するように操作した変異遺伝子を持つ動物では、軸索が切断されても、ニューロンは死なない。残された貴重なニューロンが、このような集団自殺をするのはなぜだろう?
この不可解なニューロンの大量死は、切断された軸索が結合していた細胞、たとえば筋線維や皮膚細胞、あるいはもとの神経回路内の次のニューロンなどから、成長を刺激するタンパク質が放出されていることに関係している。胎生期には、このタンパク質は、神経終末から取り込まれて細胞体へと送られることによって安定的に供給され、細胞全体が正常に機能していることを、そのニューロンに知らせている。しかし発達期には、正確な数のニューロンが生成され、結合を必要としている細胞の適正な数に釣り合うよう調整されたうえで、各ニューロンがそれぞれ適切な標的のもとへ、軸索を長く伸ばしていかなくてはならない。道筋を間違えて、正しい接合地点にたどり着けなかったニューロンは、生存に欠かせないこの成長因子タンパク質を取り込めないので、子宮の中で脳が形成されている間に死滅する。このメカニズムは、私たちの神経系を適正に配線し、誤った経路をたどった接続を排除する非常に有効な方法だ。だが、軸索が押しつぶされたり、切断されたりすると、シナプスの適切な接合地点で放出された成長因子タンパク質は、細胞体までたどり着けなくなる。軌道を外れたロケットと同じく、もはや正しい軌道に乗っていないことに気づいたニューロンは、自己破壊のメカニズムを活性化するのだ。
だが、細胞が死に向かいつつあるときでさえ、治癒と修復のプロセスを開始する別のメカニズムが活性化されている。受傷部位にあるニューロンの一部は、切断あるいは粉砕された軸索の末端を塞いで、長い間休眠状態にあった遺伝子群を再活性化する遺伝プログラムを起動させる。この遺伝子は、そのニューロンが最初に軸索を伸ばして全身に配線を巡らせた胎生期に機能したのを最後に、休止していたものだ。この遺伝子は、軸索を発芽させるタンパク質を産生し、発芽した軸索は適切な標的を探し求めて伸長し始める。
損傷したにもかかわらず、こうしたニューロンが自己破壊を起こさないのは何故だろう? その理由のひとつに、アストロサイトとミクログリアがこの再生期に、ニューロンを生存させる神経栄養因子を放出することが挙げられる。神経栄養因子となるタンパク質の一部は、標的細胞から放出されていた成長刺激物質と同一の物質だ。受傷部位で神経栄養因子を放出することによって、アストロサイトは損傷したニューロンの死滅を防ぎ、軸索の発芽を促進する。アストロサイトは同時に、タンパク性の血管新生因子も放出し始めて、損傷した組織の生存に欠かせない栄養と酸素を送り込むための新しい血液の成長を刺激する。
オリゴデンドロサイトは、再び若々しい状態を取り戻し、細胞分裂を開始する。この若返った細胞は、損傷領域に移動してきたオリゴデンドロサイトとともに、細胞性触手を伸ばして、損傷してむき出しになっている軸索に、できるだけ多く絡みつく。その後すぐに、それらの細胞は軸索の周囲にミエリンを何層にも巻きつけて、絶縁を修復する。軸索はこのミエリン再形成によって、受傷後にミエリン鞘が損傷したせいで失われていた電気的インパルスを伝導する能力を取り戻す。オリゴデンドロサイトが軸索のミエリン鞘を修復するにつれて、患者は一部の感覚や運動能が以前より少し回復してきたように感じ始めるが、まだ麻痺は残る。
しかし、生き残った軸索が新しい分枝を発芽して、もとの結合部位を探し始めても、その途中で受傷部位まで来ると、伸長はそこで止まってしまう。その結果、麻痺は一生続くことになる。これがもし、腕や脚の神経を損傷したのならば、軸索は順調に伸び続けて、ついには筋肉上の適正な結合点を見つけ出すだろう。全身の知覚神経線維も、痛覚や触覚、温度、圧覚をはじめとする外界からの感覚を脳へ運ぶ回路と再結合することになる。だが、脊髄や脳が損傷した場合、発芽しながら再結合を目指す軸索の果敢な挑戦は、失敗に終わる。』
グリアの二面性―麻痺の原因とも、治療ともなる
・『中枢神経系に末梢神経を接合するという実験は、麻痺の治療法を模索するうえで、貴重で有望な情報をもたらしたが、この技術は実用的な治療法とはなりえない。中枢神経系はきわめて繊細で微小なうえ、複雑なので、このような荒っぽい継ぎはぎ手法では修復できない。麻痺の治療に向けた最も合理的なアプローチは、軸索再生をシュワン細胞がどう支援しているのか、そしてミクログリアやアストロサイト、オリゴデンドロサイトがそれをどう阻害しているのかを解明することだろう。』
Nogoだけでない
・科学者はニューロンだけに関心を向けていたが、現在では、学習や精神障害、情報処理、意識などに関する新しい洞察がミエリンから得られている。
酸素―虫が食い、さびが付く地上
・酸素は我々の細胞のタンパク質や酵素、DNAをゆっくりと蝕んで弱らせ、ついには崩壊させる―これが、これがいわゆる老衰死である。
・酸素は他の原子から電子を盗み取ることによって害を及ぼし、分子を奪われた細胞はダメージを受ける。この酸化を食い止める化学物質は抗酸化物質と呼ばれる。
・健康食品としても注目されている抗酸化化合物は、体内の酸化による燃焼の炎を、安全なレベルにまで冷却してくれるが、我々の体内には健康食品とは比べ物にならないような抗酸化物質がたくさん存在している。なかでも特に効果的な生体内抗酸化物質のひとつがグルタチオンで、細胞の命を救うこの化合物が最も高い濃度で詰め込まれているのが、グリア、とりわけアストロサイトである。
・アストロサイトから放出される抗酸化物質は、神経変性疾患や癌、老化に対する身体の主要な防衛手段のひとつである。
第6章 感染
プリオン病―ニューロンを超えた探索
・現在では、プリオン病はニューロンの病気であると同時に、グリアの病気であることが明確になっている。もし、グリアの関りが発見されていたら、プリオン病の原因と治療の探求ははるか先まで進んでいたであろう。
・アストロサイトはプリオン病による脳の損傷に対応する一方、ニューロン死の一因にもなっている。
・アストロサイトはプリオンタンパク質を複製して、プリオン病におけるアミロイド斑の形成に一役買っている。
・異常プリオンに感染したアストロサイトは、サイトカインをはじめとする神経毒性のある物質を放出するうえ、ニューロン周辺のグルタミン酸を正常レベルに維持する能力も損なわれる。その結果、ニューロン死が起こる。
・アストロサイトはオリゴデンドロサイトとも相互作用する。オリゴデンドロサイトが侵されると、軸索を絶縁しているミエリン鞘が損傷を受ける。
・プリオン感染に応答したミクログリアは、ニューロンを死滅させる有害分子(サイトカイン、活性酸素、タンパク質分解酵素、補体タンパク質など)を産生する。
・異常型プリオンタンパク質で活性化された、ミクログリアはアストロサイトに損傷応答を引き起こす物質も放出して、アストロサイトの細胞分裂を促進している。したがって、プリオン病における病理的変化の開始には、ミクログリアが重要な役割を担っていると考えられる。
・『ミクログリアはさらに、プリオン病の診断にも活用できるだろう。プリオン感染に応答したミクログリアは、はっきりと識別できる細胞変化を起こすので、適切な診断技術を用いれば、このような形質転換を検出することができる。血球数の変化をモニターすることで、体内の感染症の種類と重症度を医師が判断できるように、ミクログリアの変化を注意深くモニターすれば、脳内の感染症に関する重要な知見が得られるだろうことは、容易に想像できる。』
現代の黒死病(ペスト)―HIVとグリア
・神経系を攻撃するウィルスの種類は多い。よく知られているのは、ポリオとヘルペスの二つで前者は麻痺を引き起こし、後者は口唇や性器周辺部に痛みを伴う水泡を生じる。
・ポリオウィルスは、脊髄の運動ニューロンに選択的に感染し、それを殺して、患者に麻痺を起こす。思考力や判断力は清明なままだが、神経を通した脳からの指令が筋肉に届かず、通信経路が切断されることによって、筋肉はやせ細ってしまう。脚へと伸びる運動ニューロンがポリオウィルスに侵された場合、患者は車椅子生活を余儀なくされる。
・ヘルペスは感覚ニューロンに感染する。ヘルペス感染も根治できず、このウィルスは感覚ニューロンに永久に居座り、患者の生涯を通じて尽きることなくウィルスを産生し、ときおり急に感染症状を引き起こす。単純ヘルペスウィルス2型は、下半身に発症し、単純ヘルペスウィルス1型は、よく知られた痛みを伴う水泡を口唇に生じさせる。
・『HIV患者のウィルスが感染するのは、どういった種類のニューロンなのだろうか? HIVウィルスはどのようにニューロンに侵入するのか? ヘルペスウィルスのように、神経終末から軸索伝いに細胞体に忍び寄るのだろうか、それとも、樹状突起や細胞体の表面だけにあるタンパク質を攻撃するのだろうか?
部検の結果、脳はHIVによる嚢胞でハチの巣状に破壊されていて、あとにはニューロンの荒れ地が残されることが判明した。ところがほどなく、研究者たちはHIVウィルスがニューロンにまったく感染していないことを見出した。HIVが感染するのは、グリアだったのだ。』
第7章 心の健康(メンタルヘルス)―グリア、精神疾患の隠れた相棒
統合失調症とうつ病―新たな理解
・『統合失調症は、正常脳とは物質的に異なっている場合がある。この相違の原因が、発達障害にあるのか、精神の乱れた活動パターンによる損傷にあるのか、あるいは精神のバランスを少しでも回復させるために何年も摂取していた薬物にあるのかは定かでないが、この三つの理由すべてが、統合失調症脳の物質的変化に関与している可能性がきわめて高い。
統合失調症患者の脳では、一部の領域における萎縮と、脳中心部にある髄液で満たされた脳室の拡大がしばしば認められる。消失組織の一部はニューロンだが、大半はグリアだ。この脳組織の減少は、精神疾患の結果なのだろうか、それとも原因なのだろうか?
統合失調症患者の多くの遺伝子異常が存在することを突き止めた最近の発見が、この問題にひとつの答えを提示している。この驚くべき発見は、ヒトゲノム配列の解読を進めるために開発された技術であるDNAチップ解析によって生まれた。この最新の手法を用いれば、一度に何千もの遺伝子を調べることができる。研究者はこれまで、ある病気に関係している可能性のある遺伝子を調べるためには、まずどの遺伝子かを推定してから、その遺伝子を個別に検査しなくてはならなかった。ところが今では、大きな集団の人々から得た何千もの遺伝子を一度に検査し、そのデータをふるいにかけて選別すると、患者間で共通する異常な遺伝子欠損を探し出すことができる。統合失調症とうつ病に関して、この無作為の検索から、思いがけない事実が判明した。
この広範な調査によって発見された遺伝子異常の一部は、理に適ったものだった。というのも、神経伝達物質の機能を制御している遺伝子だったからだ。しかし、探し当てられた異常遺伝子のなかには、まったく予期しなかったものも含まれていた。統合失調症や大うつ病で異常が見つかった遺伝子群のなかでも、大きな比重を占めるカテゴリーのひとつが、オリゴデンドロサイトの発達およびミエリン形成も調節している遺伝子だったのだ。』
・『科学者たちが「もうひとつの脳」の探求を進めるにつれて、正常な脳の働きについての理解が拡大している。それと同時に、精神疾患に罹った脳で起こる機能不全に関するまったく新しい見識が、明確になりつつある。興味深いことに、こうした洞察は新発見ではなく、むしろ驚くべき再発見と言える類のものなのだ。』
グリアを標的とした精神疾患治療薬
・統合失調症患者で異常に発現する遺伝子のひとつは、成長因子であるニューレグリンをコードしている。この成長因子はミエリン形成グリアの発達を調節することは知られており、今では多くの神経科学者が統合失調症とグリアとの関連性について注目している。
・グリアが広範な精神障害における重要性は以前から認知されてきた。パーキンソン病やアルツハイマー病、ALS、ハンチントン病などの神経変性疾患はニューロンの死によって起こる。これらの疾患においてグリアは味方とも敵ともなると、現在では理解されている。
第8章 神経変性疾患
・アストロサイトは、精神疾患の相棒として強力な役割を果たしている。
・アストロサイトは、ニューロンの電力源(カリウムイオン)を調節し、シナプスから神経伝達物質を吸収しては放出し、成長因子を放出してニューロン損傷に応答し、ニューロン新生を促している。そして、こうした機能によって、アルツハイマー病やパーキンソン病、その他の神経変性疾患において、さらには脳損傷からの回復を支援する場合にも、ニューロンの生死を決する大きな影響力を発揮している。
筋萎縮性側索硬化症(ALSまたはルー・ゲーリック病)
・ALSは運動ニューロンだけを狙い撃ちして麻痺を引き起こすが、そのメカニズムは謎である。
・ALSは何の前触れもなく襲ってきて、通常は成人になって突然発症する。
多発性硬化症―グリア戦争に伴う二次的な損害
・多発性硬化症の原因は、脳の通信回路がショートすることにある。感覚器官から発せられたインパルスは脳に届かず、脳からの指令は筋肉へと伸びる神経軸索の絶縁が途切れた場所を通過できなくなっている。
・多発性硬化症の機能不全は広範囲に生じる。脳回路のどの部分が損傷したかによって、現れる症状は千差万別である。
・多発性硬化症が致命的になることはまれであるが、寛解を繰り返すという特徴がある。また、症状は一時的なものから重篤な進行性のものまで幅広い。原因は自分自身の免疫の暴走と考えられている。
・多発性硬化症はニューロンではなく、脳炎症から最終的にミエリンの破壊につながる、そして病気が続けばミエリン生成細胞であるオリゴデンドロサイトが死ぬことになる。
心臓発作と脳卒中―不十分な配管システム
・脳には血流と脳細胞の間で特別に進化した細胞性インターフェースがある。この細胞性インターフェースは神経血管ユニットと呼ばれている。
・脳と血液の間の分子交換はすべて、この神経血管インターフェースを介して行われる。脳細胞に送られる酸素量は、今まさに活動している特定の脳細胞で刻々と変化する需要に釣り合っていなくてはならない。また、脳の働きによって生じる老廃物は、過酷な状況下でどれほど速く蓄積するとしても、迅速に除去しなくてはならない。栄養や薬物、ホルモンは、適宜血液と脳の境界を通過する必要があるが、脳を浸している特別な細胞外液は、清掃な状態に維持され、全身の体液から隔絶されていなくてはならない。
・血液や脳の間の栄養や老廃物、酸素の移動を監視し、調節し、適正化するシステムを考案するには、精緻で複雑なセンサー群を組み込んだプロセッサーや交換器が必要である。これを実現するのが脳の血管壁に存在する細胞と、ニューロンの変動する需要を監視してそれに対応している細胞間における、微細な協力関係の上に成り立っている。後者は「血管周囲アストロサイト」と呼ばれている。
思考とは何か
・ここ二、三年の間に、アストロサイトが近傍のニューロンの神経活動を感知して、脳内の細い血管を拡張あるいは収縮させる分子を放出していることを示す発見が相次いでいる。ニューロン-アストロサイト-血管間のこうしたコミュニケーションが行われている様子を、生きたマウスやラットの脳で実際に見ながら研究することに、科学者たちは成功している。
・ニューロン-グリア相互作用は、医療応用にとっても多くの重要な示唆を含んでいる。脳発作や多くの神経変性疾患に対する脳の応答には、血流の局所的変化が関与しており、このプロセスの重要な調整因子として働いている細胞がアストロサイトであることは科学者の間でよく知られている。
パーキンソン病治療におけるアストロサイト
・神経変性疾患には、必ずグリア応答が伴っている。しかし、グリア細胞をニューロンの使用人と捉える見解が支配的だったせいで、グリアがニューロン死に応答しているのではなく、その根本原因である可能性に多くの科学者は思い至らなかった。
第9章 グリアと痛み―恩恵と災禍
痛みが病気になるとき―慢性疼痛におけるグリア
・ミクログリアとアストロサイトは、傷害後に多くの重要な機能を担っている。
・ミクログリアの神経損傷を感知する仕組みや、損傷、治癒、さらには慢性疼痛発症の過程で、ミクログリアの多種多様な応答を制御しているメカニズムの詳細を明らかにすることができれば、新しい慢性疼痛の薬の開発につながるだろう。
・ニューロンが損傷したときのシグナルの中に、フラクタルカインという物質がある。この分子はニューロンの表面にあり、傷害を受けると非常事態を知らせる。ミクログリアは、フラクタルカインによる非常事態を感知する特別な受容体を持っており、感知したミクログリアは損傷部位へと急行し、その領域にサイトカインを浴びせかける。この反応は通常、傷が治るのに伴って数週間で消えるが、ときにミクログリアがサイトカインの放出を止めない場合がある。この場合、傷は癒えても痛みを伴う炎症反応は続く。
グリア細胞1
“グリア細胞”と聞いて思い出すのは、「確か、神経細胞(ニューロン)を取り巻いている細胞で、何種類かあったよなー」ということぐらいです。
そのグリア細胞に興味をもった理由は、ネットで見つけた以下のニュースです。
慢性疼痛は鍼灸師として特に重要な課題なので、どういうことなのか? このグリア細胞についても詳しく知りたいと思いました。
今回の『もうひとつの脳』は2018年発行ですが、原書は2009年なので10年以上前ということになります。内容もサイエンス・フィクションに属する本のようなので、その点も少し迷ったのですが、題名(副題:ニューロンを支配する陰の主役「グリア細胞」)と価格を重視し、この本で勉強することにしました。
本は新書版なので単行本より少し小さいのですが、図表も少なく500ページを超えるボリュームで、「これは結構、大変だ!」というのが手にした時の感想でした。
ブログは3つに分けていますが、完全に自分の趣味と感覚で抜き出しています。また、読み物系なので、特に本書を読んでいない方には捉えどころのない、漠然とした内容になっていると思います。
もくじ
はじめに
謝辞
第1部 もうひとつの脳の発見
第1章 グリアとは何か―梱包材か、優れた接着剤か
第2章 脳の中を覗く―脳を構成する細胞群
第3章 「もうひとつの脳」からの信号伝達―グリアは心をう読んで制御している
第2部 健康と病気におけるグリア
第4章 脳腫瘍―ニューロンはほぼ無関係
第5章 脳と脊髄の損傷
第6章 感染
第7章 心の健康(メンタルヘルス)―グリア、精神疾患の隠れた相棒
第8章 神経変性疾患
第9章 グリアと痛み―恩恵と災禍
第10章 グリアと薬物依存症―ニューロンとグリアの依存関係
第11章 母親と子供
第12章 老化―グリアは絶えゆく光に抗って奮い立つ
第3部 思考と記憶におけるグリア
第13章 「もうひとつの脳」の心―グリアは意識と無意識を制御する
第14章 ニューロンを超えた記憶と脳の力
第15章 シナプスを超えた思考
第16章 未来へ向けて―新たな脳
訳者あとがき
本文注参照資料
さくいん
はじめに
『私たちは現在、脳についての新たな理解の先端に立っている。そしてこの新たな理解は、過去一世紀にわたる従来の脳の概念、とりわけ脳内のニューロンの役割に関する考え方を一変させるものだ。1990年、暗室のコンピューター画面の周囲に群がっていた科学者たちは、情報が奇妙な脳細胞を通過しているところを目撃した。情報はすべて、ニューロンを迂回して、電気的インパルスを使用せずにやり取りされていた。この発見まで、脳内の情報はすべて、ニューロンを介して電気によって伝えられていると想定されていた。実のところ、ニューロンは脳の全細胞のわずか15%でしかない。ところが、残りの脳細胞(グリアと呼ばれる)は電気活動を行うニューロンの間を埋める梱包材にすぎないと、これまで見過ごされてきたのだ。グリアは「維持管理細胞(ハウスキーピング)と言われてきた。家事使用人のような細胞と安易に片付けられて、グリアはその発見から一世紀以上も無視され続けてきたのだった。
この奇妙な脳細胞が互いに交信していると知って、科学者たちは今、大きな衝撃を受けている。この細胞が、神経回路を流れる電気活動を感知できるだけでなく、その活動を制御さえできることが判明し、脳に関する科学者の理解は根底から揺らいでいる。』
第1部 もうひとつの脳の発見
第1章 グリアとは何か―梱包材か、優れた接着剤か
アインシュタインの脳
・天才であるアインシュタイと普通の人の脳を比較して分かったことは、ニューロンの数に差はなかったが、ニューロンではない細胞が脳の四領域(前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉)すべてにおいて、群を抜いて多かった。 このニューロンでない細胞とは、グリア細胞と呼ばれ、梱包材のようなニューロンを支える接合組織のようなものと考えられていた。
深海が明かした新事実
・グリア細胞は、神経軸索のインパルス発火を何らかの方法で感知し、それに反応して細胞体内のカルシウム濃度を上昇させる。
・グリア細胞は長年、脳を取り巻く梱包材にすぎないと見なされてきたが、ニューロン間でやり取りされる情報に関係していた。
第2章 脳の中を覗く―脳を構成する細胞群
脳を解剖する
・グリアは脳の細胞の圧倒的多数を占めている。
・グリアはニューロンと異なり、電気的インパルスを発火することができないため、インパルスを遠くまで送るための軸索や、電気信号を受け取るための茂みのような樹状突起といったニューロンの特徴的形質を持たない。
白質
・脳の余白とされた領域(白質)で、そのメカニズムの中核を成しているのがグリアである。
・『長年なおざりにされてきたこの脳細胞に関する近年の探求が発端になって、大変革に火がついた。そしてそれは、脳がどのような構造を持ち、どのように機能し、精神疾患や病気においてどのような不調をきたしているのか、さらにはそれがどう修復されるのかといったことについての私たちの理解を揺るがしている。脳に対するこの新たな見方を理解するうえでカギになるのが、グリアだ。』
ニューロン―脳の働きに関する取扱説明書
・神経系はワイヤーのような軸索に沿って、最速で時速320㎞ほどのスピードで電気的インパルスを送り出している。これはミエリンと呼ばれる電気的絶縁体で覆われているからである。
・痛覚線維の伝導速度は時速3㎞、歩くスピードと変わらない。誤って机に脚を強打したときの痛みがじわじわくるのも頷ける。
・シナプスにはニューロンを結びつけるだけでなく、情報処理に柔軟性をもたせることができる。そのメカニズムは、インパルスが到達したときに、シナプス前ニューロンの終末部から放出される神経伝達物質の量をわずかに増やしたり、神経伝達物質による信号を受け取るシナプス後ニューロンの受容感受性を調節したりすることで、あるシナプスへの同じ入力が、シナプス後ニューロンで起こす電位変化を大きくしたり、小さくしたりできる。その結果、シナプス結合は強化、あるいは減弱される。
・シナプスには、更にもう一つ重要な働きがある。それは清掃である。シナプス間の神経伝達物質を速やかに片付けて、次のメッセージを送り出せるようにすることである。
・アストロサイト(4つのグリア細胞の中の一つ)は、ニューロンのエネルギー源となる乳酸も必要に応じて供給している。
「もうひとつの脳」の構成細胞
・4つのグリア細胞のうち末梢神経にあるシュワン細胞と脳や脊髄に見られる稀突起膠細胞(オリゴデンドロサイト)の二つは軸索の周囲にミエリンという絶縁体を形成する。
・脳と脊髄全域にはアストロサイトと小膠細胞(ミクログリア)も存在する。
・ミクログリアは脳を損傷や病気から保護しており、脳や脊髄が損傷から回復するうえで中心的な役割を担う。
・グリアの数はニューロンの6倍にも達するが、その正確な比率は神経系の部位ごとに異なる。
・末梢の神経線維沿いや脳内の白質新経路では、グリアとニューロンの比率は100対1になる。また、ヒトの前頭皮質におけるアストロサイトとニューロンの比率は4対1である。
・脳の外部にある全身の神経には、違う種類のグリアが存在しており、神経線維の全長にわたって、軸索の周りをぎっしりと取り囲んでいるが、これがシュワン細胞である。
シュワン細胞
・シュワン細胞を発見した、テオドール・シュワンは4種類の主要なグリアの一つを発見しただけでなく、細胞という概念そのものを残した。
※Florkin, M. (1975) Theodore Ambrose Hubert Schwann, Dictionary of Scientific Biography, Charles C. Gillispie, ed., vol. 12 Scribner, New York
オリゴデンドロサイト―タコの園
・オリゴデンドロサイトは、脳のほぼ全体に広がっているが、特に白質の神経路に数多く見られる。白質は、背骨を持つ動物の脳の中心部に筋状に走っている。この白質には何千本もの軸索が束になった情報の幹線が集まっていて、脳の遠く離れた場所をつないで情報を運んでいる。
・軸索とオリゴデンドロサイトの間を含めて、脳と末梢神経に存在するあらゆる種類のグリア細胞が、ニューロ-グリア間でコミュニケーションをとっている可能性がある。
アストロサイト―星のような細胞と謎の病
・主要なグリア細胞の中で最初に発見された。
・多種多様な種類と、軸索も樹状突起も持たない形状が特徴である。
・アストロサイトの数は脳の領域によって異なるが、ニューロンの2~10倍も多い。
・ニューロンの隙間を埋めている支持細胞
ミエリンの魔力
・無脊椎動物の神経系と脊椎動物の神経系には、電卓とスーパーコンピューターほどの違いがあるが、ハエの脳にあるニューロンはヒトの脳のニューロンと同じように作動していて、多くの場合、神経伝達物質として使用する化学物質まで同じである。
・ミエリン形成グリアは、軸索の周囲に何層もの膜を巻きつけて、ワイヤーに巻かれた絶縁テープのように各軸索を絶縁する。一方、無脊椎動物は絶縁体を持たないため、漏電で電気信号が失う。
・動物や鳥などの脊椎動脈の機敏で優雅な動きは、ミエリン形成グリアのおかげである。
ミクログリア
・ミクログリアはオリゴデンドロサイトより早く発見されていたが、血流から脳へ浸潤してきた細胞だと勘違いされてしまった。
・4つのグリアの中で最も小さくダイナミックなミクログリアは脳を警護している。
・ミクログリアは常に枝分かれした突起を持ち、単独で潜んでいるが、ひとたび感染や傷害の危険を感知すると、高い機動性を備えたアメーバ状の細胞に変貌する。樹状突起と軸索が絡み合った隙間をくぐり抜けながら、侵入者をやっつけるために駆けつけたミクログリアは、有害な生命体を攻撃して吞み込んでしまう。
・ミクログリアは常に脳の中をかき分けながら動き回っている。そして、自分の役目を果たすとたくさんの分枝を持つ不活発な細胞に戻り、風景の一部になりすますように周囲に紛れ込んでいる。
不活発なミクログリアは全く人目に付かないので、5年程前にはその存在の有無をめぐって科学者の間では議論が起きていた程である。
・ミクログリアは体内の他の免疫細胞を生み出すのと同じ胚細胞株に起源を持つ。
・ミクログリアは脳に侵入するのではなく、脳とともに成長している。
・ミクログリアは脳の全域に展開して脳を守っている。
・『灰白質では、ミクログリアは茂みのようで、細胞突起をバランスよく四方八方に放射状に伸ばし、その触手を樹状突起やニューロン間のシナプス結合上に広げて、傷害や病気の兆候がないかと常に探っている。一方、白質の線維経路では、あたかも軸索を保護する格子のようにミクログリアの触手は軸索と平行、あるいはそれに対して垂直に並んでいる。
ミクログリアは、細菌やウィルス、細胞の残骸などを探知して襲いかかり、呑み込んでしまうが、化学的な武器を使った攻撃も行う。ミクログリアが放出する化学物質のなかには、興奮性神経伝達物質のグルタミン酸や、サイトカイン、活性酸素、窒素種などのように、高濃度ではニューロンにとってきわめて有害なものもある。防衛を担う軍や兵士はみなそうだが、ミクログリアも救助者であると同時に、潜在的な敵でもある。ミクログリアの働きに付随して生じる損傷は、多くの神経疾患の原因となる。だがその一方で、ミクログリアは、傷ついた神経細胞に神経保護物質を与えるといった慈悲深い使命も果たしている。
茂みのような形態のミクログリアから伸びる多くの分枝の表面には、危険や病気を示す信号を常に見張っているセンサーがずらりと並んでいる。そのセンサーとは、自己と非自己の標識となる免疫学的認識分子に対する受容体であり、それは脳に侵入してきた外来細胞を識別している。さらに、ニューロンにあるようないくつかのセンサーも存在する。こうしたセンサーのおかげで、ミクログリアは侵入してきた細胞や有害な状況を探知するだけでなく、ニューロンが危険な状態に陥らないように警戒を続けることができる。』
・「小さな接着細胞」を意味するミクログリアは、脳内に存在するグリア全体の5~10%を占めているが、これはニューロンとミクログリアがほぼ同数であることを意味している。
アストロサイト―脳のパワーの源泉
・アストロサイトは、脳と脊髄全域に見られるが、末梢神経系の神経線維には存在しない。
・アストロサイトは、いくつかの方法でニューロンを支援している。物理的基質として構造を支えたり、ニューロンにエネルギーを供給し、その老廃物を輩出したり、脳の損傷に対して瘢痕を形成して対処したりしている。すべての生きた細胞と同じく、アストロサイトも電位を持つが、神経インパルスを発火することはない。
第3章 「もうひとつの脳」からの信号伝達―グリアは心を読んで制御している
スパイの正体を暴く―グリアにおとり捜査を仕掛ける
・ニューロンがシナプスでのコミュニケーションに使っているさまざまな神経伝達物質のすべてを含む、神経系におけるシグナル伝達分子の大多数を感知できるセンサー群を、グリアは持っている。
・グリアはさらに、神経回路を電気的情報が流れると急増するイオン流動や、細胞シグナル伝達にかかわる多くの受容体分子にも感受性がある。
第2部 健康と病気におけるグリア
心を治す―神経系の損傷と病気を回復させるグリア
・ミクログリアとアストロサイトは脳に感染する細菌やウィルスの警戒にあたる見張り役を務めている。侵入してきた微生物に闘いを挑み、病原体を探し出して呑み込んだり、活性酸素などの有毒な化学物質を放出したりして脳から病原体を取り除く。
・最近の研究で、ミクログリアには多くの役割があるのが分かった。神経の慢性疼痛への薬物治療が効かないのは、痛みの発生や薬物依存性にミクログリアが果たしている役割を理解できていなかったことがあげられる。
・成熟ニューロンは細胞分裂できないため、一度、傷害や病気で損傷してしまうと再生は困難である。一方、グリアは脳の損傷に応じて細胞分裂を開始し、損傷部位へ移動し傷を治す。また、損傷を受けた神経線維の再伸長を誘導して、ニューロン間やニューロンと筋肉の間の適正なコミュニケーションを回復させる。
・未成熟なグリアは幹細胞のような働きができる。
・成熟したアストロサイトは成人脳では休眠状態にある幹細胞を刺激して、代替のニューロンやグリアへと分化させることができる。
・病気によって失われたニューロンの代替になる可能性を備えた未成熟なグリアは、脳の全域に潜在している。このグリア性“幹細胞”をうまく操作できれば、将来の治療にとって大きな希望となる。
・グリアは救世主として期待される一方、病気の原因にもなる。これはグリアが感染性微生物の標的になることが多いからである。
・パーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)やアルツハイマー型認知症では、グリアは有益な側面と害をなす側面を持つ。
・「神経変性疾患」という名称は、ニューロンだけに焦点を当てていることを窺わせ、生物学的にも薄弱である。一方、グリアは脳機能への関与が明らかになるにつれて、グリアの病気への関わりを示唆する事実は増えている。
免疫学者の告発2
3章 コロナワクチンと自己免疫疾患
●コロナワクチンと肝炎(2) T細胞依存性自己攻撃による新しいタイプの肝炎か
・『ファイザーの内部文書によると、筋肉注射された脂質ナノ粒子は全身に運ばれ、最も蓄積する部位の1つが肝臓です。スパイクタンパクは免疫組織化学による解析(スパイクタンパクに対する抗体での解析)では肝臓で確認されませんでした。これは2回目ワクチン接種時から27日後に行われたため、時間が経ち過ぎたせいかもしれません。また、T細胞が認識するのはスパイクタンパクそのものではなく、細胞表面に提示されたスパイクタンパクの断片の抗原決定基(エピトープ[相補的な抗体が特異的に結合する小さな部位])です。それぞれの抗体が認識するのもタンパク内の1つの小さなエピトープであり、T細胞と抗体のエピトープが異なっているために抗体による解析では検出できなかったことも考えられます。むしろスパイクタンパクそのものが検出されなくなった時期でも、スパイクタンパクの一部を目印として持つ細胞に対するT細胞の攻撃が続く可能性があります。
まとめると、スパイクタンパクを認識する細胞障害性T細胞が活性化して肝臓に滞留しており、肝炎の症状はそうしたT細胞の挙動と一致するということです。スパイクタンパクを持つ肝臓の細胞をT細胞が攻撃した結果、肝炎を発症したと推測されます。
コロナワクチンの目的は抗体と細胞性免疫の両者を誘導することです。さらに遺伝子ワクチンの仕組みからすれば、ヘルパーT細胞だけではなく細胞障害性T細胞ができるのは自然なことです。
コロナワクチンの遺伝子ワクチンの作用機序では、スパイクタンパクは細胞内で生産されるためにクラスⅠMHC上にウィルス抗原を提示することになります。つまり、コロナワクチンを取り込んだ細胞はコロナウィルス感染状態を模倣した細胞であり、そのまま細胞障害性T細胞に駆逐され得る運命にもあります。今回紹介した論文は、スパイクタンパクを認識するT細胞が肝臓に集まり、肝炎の原因となっているという報告です。肝臓はコロナワクチンが一番集積しやすい臓器であり、肝臓細胞でスパイクタンパクを生産している可能性は充分考えられます。そうした細胞がT細胞によって攻撃されて肝炎を発症したのではないでしょうか。
タンパクに対する抗体を持っているかどうかを検査することは難しくありません。抗体はタンパク上のエピトープに直接結合するので、タンパクを抗原として用いれば、多様なエピトープに対する抗体をまとめて検査できるからです。T細胞の抗原特異性を検査するにはウィルスの断片とMHCの組み合わせが必要です。タンパクの断片の1つずつを検討しなければならないのですが、さらにMHCの個人差が非常に大きいため、同じT細胞でも人によって抗原に対する反応性も異なります。抗原特異的T細胞を検出することは技術的に簡単ではないのです。
コロナワクチン後遺症として免疫系を攻撃する作用機序には、①自己免疫疾患、②抗体依存性自己攻撃に加えて、③T細胞依存性自己攻撃があることがわかってきました。今回の論文は氷山の一角であり、T細胞依存性自己攻撃は実験によって検出されるよりもはるかに多いでしょう。』
4章 様々なコロナワクチン後遺症
●コロナワクチン接種後の心筋炎および心膜炎および性別による危険度
・心筋は心臓を構成する筋肉であり、心膜は心臓を包む結合組織性の膜である。心筋炎、心膜炎はこれらの炎症性疾患である。
・心臓の癌が極めて珍しいのは心筋の細胞は増殖しないからである。これは、心筋は一度損傷すると回復するのが難しいということを意味している。
・心筋炎は、多くは風邪症状や消化器症状などの前駆症状を伴うが、これらの自覚症状がない場合もある。また、前駆症状の1~2週間後に、胸痛、心不全症状、ショック、不整脈などの症状を呈する。
7章 新型コロナウィルスは人工ウィルスか?
●奇妙なオミクロンはどこから来たのか?
・オミクロンは明らかにアルファやデルタのような初期の亜種から発展したものではない。
・オミクロンはこれまで公開されてきた数百万のSARS-CoV-2のゲノムとは大きく異なる。他の株から分岐したのは2020年の中頃ではないか。

画像出展:「コロナワクチンが危険な理由2」
『それぞれの点はウィルスの塩基配列です。点と点との距離は進化上の距離、つまりお互いの塩基配列の相同性を表します。縦軸は突然変異の数、横軸は時期です。この図からわかるのは、オミクロンは他の変異株よりも突出して変異が多いこと、進化上の距離がかけ離れていること、2021年10月に突然現れて塩基配列上も時間的にも進化上の中間体が見つからないことです。これを見ると、オミクロンの前身が1年半以上もどこに潜んでいたのか? という疑問が湧いてきます。』
・オミクロンの前身が1年半以上もどこに潜んでいたのか? という疑問に対して、Science誌の中で科学者達はいくつかの可能性について述べている。
①COVID-19に慢性的に感染している免疫不全症の患者の中で発生した可能性。
②ウィルス監視や配列決定がほとんど行われていない集団の中で循環し進化した可能性。
③人間以外の生物種で進化し、それが最近になって再び人間に流入した可能性。
④アフリカのワクチン接種率が低いため。
・現時点では、オミクロンの起源と同様にオミクロンの進化の過程は未知のままである。
●フーリン切断部位の謎
・『コロナウィルスの大きな謎の1つに「フーリン切断部位」があります。フーリン切断部位は新型コロナウィルスの感染力に関わるのですが、これはSARS-CoVを含む近縁のコロナウィルスには本来見られないものです。では新型コロナウィルスが進化の過程でどうやってフーリン切断部位を獲得できたのか? このことはコロナ騒動の当初から一部の科学者の間では議論の的になっていました。
フーリン切断部位の配列が、モデルナ社が特許を取得した遺伝子上の配列と一致することを報告する論文が2022年2月に発表されました。
この特許が出願されたのは、コロナ騒動が始まる数年前の2016年です。
そのため新型コロナウィルスが人工ウィルスではないかという議論が現在再燃しています。』
※“伊崎労務管理事務所”様のサイトに「フローリン切断部位」などに関する解説が出ていました。
●変異株を含めて新型コロナウィルスは人工ウィルスではないか?
・『もしもこのウィルスが本当に人工のものならば、そもそも各国におけるコロナウィルスの流行すらも自然なものなのかどうかを考えてしまいます。その場合はもはや性善説に基づく常識的な科学や医学からの判断だけでは対応できないでしょう。
この解析につきましては論文形式としてまとめ、現在プレプリントサーバにアップロードしています。原文をお読みになりたい方はこのURLからアクセスしてください』
Mutation signature of SARS-CoV2 variants raises questions to their natural origins. Hiroshi Arakawa
8章 コロナワクチンの副反応は他者に伝播するか
●コロナワクチンシェディング
・『SNSや私のブログのコメント欄でも、コロナワクチン接種者から他者への副反応の伝播をうかがわせる報告が散見されます。いわゆる「シェディング」です。本来の「ワクチンシェディング」とは、生ウィルス(ウィルスそのもの)を使ったワクチンを打った人間がウィルスに感染してしまうことによってウィルスを周囲に放出するという現象です。そういった意味では、そもそも生ウィルスを用いていない遺伝子ワクチン接種者から他者への副反応の伝播を便宜的に「シェディング」と呼ぶことにします。
シェディングの症状で多く耳にするのは、月経不順や不正出血などの生殖系の異常です。そして、皮膚症状、頭痛、関節痛、下痢など報告される症状はある程度共通しており、具体的なものが多く、一概にその全てが気のせいや勘違いまたは捏造だとは言えなさそうなのです。そしてシェディングの症状を訴えるのは、基本的にワクチン接種者ではなくて非接種者です。したがって、ワクチン接種者が社会の大半を占める現状においては、シェディングを感知し得る人自体が少数派ということになります。
シェディングの現象が確かにありそうだと思える根拠の一つが、しばしば耳にするコロナワクチン接種者の「体臭」が変わるという体験談です。体臭に現れるということは「ワクチン接種者が何らかの揮発性の物質を分泌」しており、それが「他者が嗅覚受容体で感知し得る」物質であることを意味します。実際に嗅覚受容体遺伝子の数は膨大であり、また嗅覚受容体にはゲノムレベルでの差異が数多く存在するため、認識できる匂いにも個人差が存在します。このため全ての人が「接種者特有の匂い」を感知できなかったとしてもおかしくはありません。私を含め、接種者の体臭に変化などを感じた体たお験が特に無いという人も実際多いです。
コロナワクチン後遺症の存在する否定する医療機関が多い現状においては、ワクチンシェディングという現象があると仮定した場合、それを引き起こしている物質の正体は一体何なのか?いくつか考えられる可能性を挙げてみます。
まず第一に考えられるのは、コロナワクチンによって作られるスパイクタンパクです。スパイクタンパクはエクソソーム上で数ヶ月以上血中を循環することが分かっています。また、フーリン切断部位で切断されたスパイクタンパクそのものも血中を循環している可能性があります。汗の原料は血液であり、血中を循環するものは汗として分泌されてもおかしくありません。ただ私が気になるのは、シェディングによる症状はワクチン後遺症と似てはいるが、同一ではないという点です。このため、スパイクタンパクがシェディング現象の本体かどうかは不確かです。
第二に考えらえるのは、コロナワクチンによって接種者の体調が変化し、何らかの揮発性の物質を分泌するようになったという可能性です。人間にもフェロモン様の物質とその受容機構があります。例えば、フェロモンにより、女子寮のルームメイトの月経周期が同調するといった現象は知られています(McClintock, M.K.: Menstrual synchorony and suppression, Nature (1971).)
フェロモンを感知するのも嗅覚受容体ですが、前記のように嗅覚受容体は個人差が大きく、そのためフェロモン様物質などの分泌性物質が原因であった場合、シェディングの個人差が大きくとも不思議ではありません。
第三の可能性はコロナワクチンへの生ウィルスの混入汚染です。もちろんこれはあってはならないことです。
第四の可能性は、その他の全くの未知の仕組みによるものです。例えば放射線や電磁気力は肉眼では見えませんが、直接の接触が無くとも対象に影響を及ぼすことはよく知られています。製薬会社との取り決めにより、現時点ではワクチンの成分の全てが明らかにされていない以上は、本来どのような可能性も頭ごなしに否定すべきではないというのが科学的な態度でしょう。
シェディング現象が事実であれば大問題です。けれども現状では情報がまるで足りず、現象の存在の有無、症状の多様性、作用機序を含めて現時点で断定できることはありません。例えばもし、ある現象を「理論的にありえない」と否定する人がいるとします。しかしその現象は実際に繰り返し観察されており、それぞれ複数の人が独立に経験しているとします。その場合には、現象が存在するのが正しく理論自体が間違っているという可能性を考えなくてはなりません。』
おわりに
●病気とホメオスタシス(生体恒常性)
・『西洋医学では病気の症状が治療の対象になりますが、体が自己修復をしている過程が症状として現れることもあります。症状を取り除く薬が病気や怪我を治しているとは限りません。免疫系やホメオスタシスを損傷するような「薬」を使用した場合、逆に薬が病状を悪化させてしまうこともあり得ます。私達は本来自分自身の持つ自分の身体を治す作用を日常的に使っています。意識せずとも、私達の細胞、組織、臓器は生きるための努力を毎日続けています。壊す作用よりも治す作用の方が強ければ、本来は体は回復する方向に向かうはずなのです。
コロナワクチン後遺症の患者が医者に相手にされず医療機関をたらい回しにされる話もしばしば耳にします。つまり、我々は未知のリスクのあるコロナワクチン接種を勧められながらも、実際に有害事象が起きた際にはそれは認められていないという歪んだ医療体制の中にいるわけです。免疫系、血管系、生殖系、心臓、脳。このどれもが私達の生命線であり、またコロナワクチンの後遺症として特に報告されている対象でもあります。事実としてコロナワクチンは最新の医学の産物です。こう考えると、そもそもワクチンとは、薬とは、医療とは何なのか。立ち止まってもう一度よく考え直す必要があるのではないでしょうか。』
ご参考:“新型コロナワクチンを接種できる人・できない人”
上記は長野県駒ケ根市のホームページに掲載されているものです。そして、この情報は、2021年6月時点のファイザー社製ワクチンに関する資料が元になっています。
この記事に関心をもった理由は、コロナワクチンは高齢者や基礎疾患のある人こそ、重症化リスクを減らすために積極的に接種するという方針だったと思います。しかしながら、ここに書かれている内容はニュアンスが異なり、以下に列挙したものは【基礎疾患のある方はかかりつけ医に相談を】となっています。弱毒化されてきたとされるコロナウィルスの現状を考えると、これはとても重要な情報だと思います。
次のような疾患のある方は、かかりつけ医の了承を得てから接種をしてください。
慢性の呼吸器の病気
慢性の心臓病(高血圧を含む)
慢性の腎臓病
慢性の肝臓病(ただし、脂肪肝や慢性肝炎は除く)
インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病またはほかの病気を併発している糖尿病
血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
ステロイド、免疫機能を低下する治療を受けている
免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障がい等)
染色体異常
重度心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態)
睡眠時無呼吸症候群
感想
ワクチン後遺症の存在は公にはなっていないように思います。しかし、患者さまと日々接している先生(医師)からは、臨床の異常な現場(例えば、急激に増えた帯状疱疹患者等)に直面しているとのお話を伺っています(私の狭い人脈の中での確かな情報です)。
また、荒川先生のような分子生物学や免疫学をご専門にされた先生が、周囲からの反発等を恐れることなく、その大きな違和感を科学者の視点で語られています。
やはり、今求められるのは、全く新しいメカニズムをもった遺伝子(mRNA等)ワクチンを【調査】することだと思います。
免疫学者の告発1
荒川 央先生の著書『コロナワクチンが危険な理由』ですが、続編の『コロナワクチンが危険な理由2 免疫学者の告発』が既に出版されていました。「今度はどんな内容なんだろう?」と思い、さっそく購入しました。
内容は非常に高度で、私の理解は一部であり断片的です。そのため、ブログはあくまで私自身の感覚を頼りに「重要だな、書き残しておきたいな」と思ったものを取り上げています。
目次
はじめに 人はコロナ後の世界の夢を見るか?
1章 コロナワクチンはそもそもワクチンとして機能しているのか?
●ワクチンと有害事象
●数字で見るコロナワクチンの薬害
●世界的な超過死亡の増加
●ワクチン未接種者に汚名を着せることは正当化されない
●SARS-CoV-2自然感染から回復した医療従事者は、ワクチン接種の義務化の対象から除外されるべきである
●コロナワクチンの有効性は接種8ヶ月後にはマイナスに転じる
●小児用のファイザーコロナワクチンの感染および重症化予防効果は低い
●コロナワクチン統計の問題点とインフォームド・コンセント
2章 コロナワクチンの免疫学
●コロナワクチンによる免疫異常
●獲得免疫と自然免疫
●ワクチンと自己免疫疾患
●T細胞の抗原認識:自己非自己の識別と拒絶反応
●ヘルペスウイルスと自己免疫疾患
●コロナウィルスと免疫抑制
3章 コロナワクチンと自己免疫疾患
●コロナワクチンによる血栓性血小板減少症と播種性血管内凝固症候群
●コロナワクチンと眼の障害
●コロナワクチンと肝炎(1)
●コロナワクチンと肝炎(2) T細胞依存性自己攻撃による新しいタイプの肝炎か
●コロナワクチン接種後の皮膚血管炎について
4章 様々なコロナワクチン後遺症
●コロナウィルスワクチンによってロングコビッドのような症状が出ることがある
●コロナワクチンと急性肺塞栓症
●コロナワクチンと男性不妊
●コロナワクチン接種後の心筋炎および心膜炎および性別による危険度
5章 コロナワクチンとプリオン病
●コロナワクチンによるプリオン病と神経変性の可能性について
●スパイクタンパクとプリオンモチーフ
●プリオンとパーキンソン病
●コロナワクチンとクロイツフェルト・ヤコブ病
●コロナワクチンによるスパイクタンパクは心臓と脳で検出された
6章 コロナウィルスと逆転写
●コロナウィルスと逆転写
●ヒト逆転写酵素はコロナウィルスのゲノム組込みを媒介できる
●コロナワクチンは逆転写酵素を活性化するか?
●RNAコロナワクチンは細胞内で逆転写される
7章 新型コロナウィルスは人工ウィルスか?
●奇妙なオミクロンはどこから来たのか?
●フーリン切断部位の謎
●オミクロンは進化の法則に従っていない
●他のコロナ変異株も進化の法則に従っていない
●変異株を含めて新型コロナウィルスは人工ウィルスではないか?
●人口ウィルス由来のコロナワクチン
8章 コロナワクチンの副反応は他者に伝播するか
●コロナワクチンシェディング
●ファイザープロトコルへの疑惑
●シェディングの原因物質は何か?
●シェディングの症状と対策
●コロナワクチンは母乳を介して乳児に移行する
おわりに
●病気とホメオスタシス(生体恒常性)
●思考のススメ:考えるということ
●巨人の肩の上で
●アインシュタインの言葉から
あとがき
1章 コロナワクチンはそもそもワクチンとして機能しているのか?
本章には大変興味深いがグラフが紹介されているのですが、その真偽を自分なりに確かめたいと思い、過去のニュースや米国のワクチン接種状況などを調べてみました。
また、不妊鍼灸を始めたという経緯もあり、特に注目したグラフはワクチン有事障害報告システム(VAERS)の中にあった流産(Miscarriages)と死産(Stillbirths)に関するものです。

画像出展:「OpenVAERS」
左のグラフはページ中段左側にあります。
タイトルは“Reports of Miscarriage/Stillbirth by Year"です。
コロナの流行は2020年1月から。ワクチン接種はおおむね2021年1月からです。高騰した2021-2022年はワクチン接種時期と重なります。
まず、このVAERSのグラフを否定するようなニュースや記事などがないか調べてみたところ、3件の記事を見つけましたが、重要なことはこれらの記事はいずれも、2021年(特に1と2は2020年12月14日~2021年2月28日の調査分析)のものであるという点でした。
そして、その元になっているのは、以下の“米CDCがCOVID-19 mRNAワクチンの妊婦安全性データを示す”だと思われます。
1.“米CDCがCOVID-19 mRNAワクチンの妊婦安全性データを示す” 2021年6月
The New England Journal of Medicine june 2021
背景
COVID-19メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンの妊婦安全性は重要な問題である。Centers for Disease Control and PreventionのShimabukuroらは、同国VAERSシステム登録者35,691名の2020年12月14日~2021年2月28日データを解析した。
結論
妊娠女性は非妊娠女性より注射部位疼痛報告が多く、頭痛・筋肉痛・悪寒・発熱の報告は少なかった。接種妊娠者3,958名中827名が妊娠終了し、妊娠喪失は13.9%、生児出産は86.1%であった。新生児の有害転帰は、早産9.4%、在胎不当過小3.2%等で、新生児死亡は報告はなかった。これらのデータは、COVID-19パンデミック前のデータと同等であった。VAERS報告妊娠関連有害事象は221件 で、最多は自然流産46件であった。
評価
著者らの結論は、「更なる長期追跡が必要だが、今のところ問題はない」というものである。mRNAは妊婦に対する免疫原性も報告されており("Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and Lactating Women"
)、懸念データは今のところ存在しない。
この分析は2020年12月14日~2021年2月28日に行われたもの、ワクチン接種の初期段階です。
2.“Q.「ワクチン接種で流産」の情報、真偽は?【デマに注意】” 2021年7月29日
A.厚生労働省は新型コロナウイルスのワクチンについて「接種を受けた方に流産は増えていません」としていて、SNSなどでデマを含む誤った情報が広がっていることに注意を促しています。
妊婦に対するワクチン接種の影響については、アメリカのCDC=疾病対策センターのグループが、2020年12月から2021年2月までにファイザーかモデルナのワクチン接種を受けた16歳から54歳までの妊婦3万5691人で影響を調べた初期段階の研究結果を論文に発表しています。
それによりますと、流産や死産になった割合や生まれた赤ちゃんが早産や低体重だった割合は、ワクチン接種を受けた妊婦と新型コロナウイルスが感染拡大する以前の出産で報告されていた割合と差がありませんでした。
またワクチンを接種した妊婦で生まれたばかりの赤ちゃんの死亡は報告されていないとしています。
一方で、妊娠している女性が新型コロナウイルスに感染すると、同世代の女性よりも重症化する割合が高いことが報告されていて、日本産科婦人科学会などは2021年6月、ワクチン接種によって母親や赤ちゃんに何らかの重篤な合併症が発生したとする報告はなく、希望する妊婦はワクチンを接種することができるとしたうえで、「ワクチン接種するメリットが、デメリットを上回ると考えられている」などとする声明を出しています。(2021年7月29日時点)
3.“新型ウィルスワクチン、妊娠にまつわる偽情報をファクトチェック” 2021年8月11日
「ワクチンが卵巣内に蓄積されるという研究がある」 ―― 間違い
「ワクチンが流産につながるというデータがある」 ―― 間違い
「ワクチンが胎盤を攻撃する」 ―― 証拠なし
もっと新しい記事はないのか? 検索を続けると、2023年1月2日付けの記事を見つけました。
“米ワクチン「流産・死産登録数急増」はミスリード 因果関係かかわらず誰でも報告可” 2023年1月2日
『VAERSの有害事象登録は、ワクチン接種との因果関係の有無にかかわらず誰でも行うことができる。流産・死産報告の登録数が急増したのは事実だが、これはワクチンを接種した人の全体数が増えていることなどが要因と考えられ、接種が原因で流産・死産が起きたことを証明するものではない。』
要点
1)VAERSの有害事象は誰でも登録できるので信頼性は低い。
2)流産・死産の報告数が急増したのは事実である。
3)ワクチン接種が増えているのは事実である。
4)上記1)2)3)より、死産・流産の原因がワクチン接種にあるとは断言できない。よって評価は“△”である。
一方、2020年12月14日~2021年2月28日という米国CDCによる調査期間が、米国のワクチン接種状況の中でどのような時期になるのか調べてみました。

画像出展:「特設サイト 新型コロナウィルス」
米国は緑線です。2021年1月、2月はワクチン接種の極めて初期の段階であることが確認できます。また、初期段階ということは1回目の接種であり、特に問題となっている3回目以降のブースター接種との関連については不明です。
以上のことから、コロナウィルス、コロナワクチンと流産・死産の関係は、複数回の接種が実施された今こそ、調査されるべきと思います。しかしながら、それが実施されていない、もしくは実施されているが公表されていないという現実はとても不安を感じます。

画像出展:「特設サイト 新型コロナウィルス」
日本(赤線)では4回、5回とブースター接種が行われていますが、世界的には早い国では2022年1月、遅い国でも概ね2022年夏には接種回数は横ばいになってきています。このグラフの中では、日本だけが接種を続けているのが分かります。
日本での感染者が50,000人を超えたのは2022年1月後半、その後、50,000人を切る時期もありましたが、2022年7月、12月には200,000人を超える日もあり、2023年1月中旬まで100,000人を超える日が続いていました。
上記のグラフは オックスフォード大学の“Our World in Date”のデータです。世界と日本とイスラエルを比較しています。イスラエルの人口は日本の約7.42%です。世界の数が多いので、イスラエルはほとんど直線に見えます。
イスラエルに注目した理由は2つです。1つはイスラエルは世界に先駆けてワクチン接種を強力に推し進めていた国だったという点です。そしてもう一つは、2021年8月24日付けの約2年前の記事ですが、『接種率78%「イスラエル」で死亡者増加のなぜ』という記事が気になっていたからです。
グラフを見て気になるのは、世界のワクチン接種は2つの山を越え急激に減っているのに対し、日本は最初の山ほどではないですが、4つの山があり少なくとも急激には減っていないということです。その一方で、感染者数は2022年2月以降世界のTop10に入り、2022年7月後半から2023年2月までTop3に入っていました(ただし、感染者数を発表しない国が増えてきているので単純な比較はできません)。
ワクチン入手状況もあるので、一概に比較するのは適切ではありませんが、世界と比較して日本での接種が最も少なかったと思われるのは、2021年12月23日で、世界39,900,000件に対し、日本は100,147件(約0.25%)でした。
一方、最も多かったと思われるのは、約1年後の2022年12月12日で、世界4,180,000件に対し、日本は820,259件(約19.6%)でした。その差は78.4倍です。
また、以下はコロナワクチンとは無関係の死亡者数(All Non COVID-Vaccine Deaths)を加えたグラフですが、水色の棒グラフは2021年も2022年も安定しています。
これを見ても、コロナワクチンとは関係ない、問題ないと考える方が明らかに不自然です。追跡調査を行いワクチン接種が本当に問題ないのか検証されるべきです。[グラフ:mortality]
2章 コロナワクチンの免疫学
●コロナワクチンによる免疫異常
・コロナワクチンは今までのワクチンとは異なる新しい遺伝子ワクチンであり、遺伝子を体に注入して細胞内に導入し、細胞に抗原となる物質を作らせる。
・コロナワクチンはスパイクタンパクの遺伝子を使っており、まず細胞にスパイクタンパクを作らせ、免疫系はそれを利用してスパイクタンパクに対する抗体を産生する。この抗体はコロナウィルスに出会う前に、まずコロナワクチンを受け取った自分の細胞を攻撃する(抗体依存性自己攻撃)。
●コロナウィルスと免疫抑制
・コロナワクチン接種者では制御性T細胞が増加しているという研究がある。制御性T細胞は免疫を抑制するT細胞である。もし、免疫系の暴走が起こっていてそれを鎮めるために特定の制御性T細胞だけが増えているとすれば、特に不自然であるとは言えない。
・コロナワクチン接種者ではIgG4抗体が増加しているという研究がある。IgG4抗体は炎症反応を刺激する作用が弱い。もし、抗体依存性自己攻撃を緩和させるための反応に置き換えようとしてるならば、特に不自然であるとは言えない。
・『T細胞や抗体の最大の特徴は抗原特異性であり、そうしたT細胞やIgG4抗体の抗原特異性を解析することで、こうしたものが免疫抑制に働いているのか、あるいは免疫系の異常を元に戻そうとする働きなのかといった生理的な意味がわかってくるでしょう。』
・免疫が健全に働いている場合の特徴は、「増えた後に減る」という現象がある。特にB細胞についてはその作用機序が知られている。つまり、強く活性化された免疫系には揺り戻しが起こるのである。コロナワクチンは接種後短期間で極度に抗体価を上昇させる。このようなコロナワクチンによる強い免疫刺激が免疫担当細胞を枯渇させる可能性がある。さらに、この状態が短期間で終わらないとなれば、そのまま免疫抑制状態が続くことになる。
・注意しなければならないことの一つに、ワクチンに免疫抑制を起こすものが含まれていなかということである。コロナワクチン接種後に帯状疱疹の発症が報告されているのは、免疫抑制が関係している可能性がある。
・免疫とは生命力そのものである。腸内細菌や皮膚常在菌との共生関係も免疫のおかげである。免疫力の低下はこれらの重要な共生関係を乱す恐れがある。
・現場の臨床医からはコロナワクチン接種者の癌増加が指摘されている。毎日出現している癌細胞は免疫系によって排除されており免疫系が正常であれば特に心配はいらないが、ワクチン接種後には、リンパ球の減少が報告されており、異常な自己細胞を除去するNK細胞(リンパ球の一つ)が減少するならば癌の増加は十分に予測できることである。
・『免疫系を自由に制御できれば、感染症や癌、自己免疫疾患などの病気の根本治療にも活用できるでしょう。言い換えれば、免疫系を制御することは非常に難しく、免疫系を自由にコントロールすることは免疫学者の夢でもあるのです。そしてコロナワクチンは免疫系に強く干渉するものであり、ワクチンの副反応で一度破綻した免疫系を制御することは簡単ではないでしょう。』

アンケート期間:2021年8月31日~9月30日
【アンケート】(pdf7枚)
追記2(2024年5月3日):「コロナワクチン接種後死亡 遺族ら「国の広報不十分」と集団提訴」

『私たちは、「ワクチン」接種による遷延する副反応に苦しまれる「ワクチン」接種健康被害者に適切な医療を提供すべく、去る2023年6⽉16⽇、「ワクチン」接種による健康被害者と真摯に向き合ってきた全国有志医師の会を⺟体として、学術団体、⼀般社団法⼈ワクチン問題研究会を設⽴しました。』(“代表理事よりご挨拶”から抜粋)
免疫学者の警告2
3章 コロナワクチン=「遺伝子ワクチン」の正体とは何なのか?
●セントラルドグマとmRNA
・コロナウィルスはRNAウィルスである。自身のRNAを複製するためにDNAは必要なく、RNAからRNAを作る。これは分子生物学の基本概念であるセントラルドグマ(遺伝情報は、「DNA→(転写)→mRNA→(翻訳)→タンパク質」の順に伝達されるというルール)の例外である。
・コロナワクチンのMIT総説論文
-2021年5月発表。査読済論文
-「病気よりも悪い?COVID-19に対するmRNAワクチンがもたらしうる予期せぬ結果を検証する」
-「RNAの選択と修飾における留意点」
※Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19, Stephanie Seneff, Greg Nigh, International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2021,
・mRNAは生体内ですぐに分解されるため不安定である。
・免疫は外部から侵入した感染体を識別して攻撃するため、RNAを体内に導入しようとしてもすぐに分解される。
・RNAワクチンの登場は、RNAの不安定さを技術的に克服したために可能になった。その技術とはRNAワクチンを脂質ナノ粒子で保護することである。しかしながら、どの位の期間生体内で残るのかは分かっていない。
●mRNAと遺伝暗号(コドン)
・RNAワクチンはmRNAと類似した構造を持つが、RNA分解耐性を上げ、タンパク翻訳効率を上げているため通常のmRNAよりもはるかに大量のスパイクタンパクを生産する。
●なぜワクチンに使われる遺伝子の毒性をなくさなかったのか?
・コロナウィルス、コロナワクチンに共通する毒性はスパイクタンパクによるものだが、その毒性にはいくつか要因がある。主なものはACE2に結合することによって、血管内皮細胞を含むACE2発現細胞を障害することである。他には、スパイクタンパクの棘、フリン切断部位、プリオン様モチーフなどがある。
・『なぜ世界中の健康な人間に打たせる為に作ったワクチンの毒性をなくす努力をしなかったのか。そのデザインは偶然なのか、失敗なのか、無知なのか、やはり疑問が残ります。』
4章 スパイクタンパクの危険性
●どうしてコロナワクチンで血栓が出来るのか
・コロナウィルスは神経症状(頭痛、吐き気、めまい)を起こすが、同様のことがコロナワクチンの副反応としても報告されている。ACE2は前頭葉皮質のさまざまな血管にも発現しており、スパイクタンパクが血液脳関門を超えられることを考えると、コロナワクチンの遺伝子から作られたスパイクタンパクが、脳内皮細胞に炎症を引き起こしている可能性がある。
・『整理すると、コロナウィルスは血栓を起こし、肺や心臓、脳にも障害を起こすにはウィルスは必要ではなくて、スパイクタンパク単独でも同様の障害を起こしてしまうということが分かってきました。ウィルスが犯人だと思っていたら、実はワクチンにも使われるスパイクタンパクが犯人だったということです。』
●スパイクタンパクの毒性―スパイクタンパクはACE2の抑制を介して血管内皮機能を損なう
・『Circulation Research』に掲載されていた論文
・「SARS-CoV-2 スパイクタンパクは、ACE2の抑制を介して内皮機能を損なう」
※SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE2, Lei et al, Circ Res. 2021,
●スパイクタンパクの全身の血管への毒性
・『コロナウィルスとコロナワクチンのスパイクタンパクは血管に対し同様の毒性を持ちますが、毒性の強さが同じとは限りません。量の問題です。コロナウィルスに感染した際、まずは最初に自然免疫系が対処します。そしてそこで対処しきれなかった場合、つまりコロナウィルスが免疫系に抵抗し増殖し始めた場合には、免疫系の精鋭部隊である獲得免疫が出動し始めます。コロナウィルスが体内で増殖する場合、体に備わっている免疫系が抵抗するため、ADEが起こったりしない限りは、感染してすぐに身体中に爆発的に増えるような事態は起きないのです。
それに対し、コロナワクチンは接種後に細胞内でスパイクタンパク生産を開始し、量はいきなり最大量に達します。そしてシュードウリジン修飾されたmRNAワクチンは分解されにくく、長い間スパイクタンパクを生産し続けます。そしてその場合のスパイクタンパクの生産量はワクチンの方がずっと多いことが想定されるのです。このことが血管への毒性の高さに関係しているのではないでしょうか。』
・ACE2受容体が精巣のライディッヒ細胞に高発現していることから、ワクチンによって内因性に生成されたスパイクタンパクは、男性の精巣にも悪影響を及ぼす可能性がある。
・複数の研究により、コロナウィルスのスパイクタンパクがACE2受容体を介して精巣の細胞にアクセスし、男性の生殖を阻害することが明らかになっている。
・『血管は全身を巡っており、生殖器官にも存在します。ACE2受容体が精巣にも高発現していることから、ワクチンによるスパイクタンパクは精巣にも悪影響を及ぼす可能性があります。また、脂質ナノ粒子は卵巣にも分布することが報告されており、卵巣を障害するかもしれません。このようにスパイクタンパクが卵巣、精巣の血管を障害することで不妊に繋がる可能性も出てきます。』
●スパイクタンパクは血流を循環するか
・ワクチンの副反応である血栓症の原因を作っているのは血流中のスパイクタンパクの可能性が高いが、それぞれの形態の毒性の違いは不明である。また、個人差があるということは、スパイクタンパクが更に長期間にわたって血流を循環する可能性もあるということである。
●コロナワクチンと不妊
・コロナワクチンが妊娠に影響を与える可能性、リスク要因。
①筋肉に注入されたコロナワクチンの脂質ナノ粒子は接種部位に留まらず、全身を巡回し、特に卵巣に蓄積することが報告されている。スパイクタンパクが卵巣で発現すれば、ワクチンに選択されて作られた抗スパイクタンパクは卵巣を標的にして攻撃し始めると考えられる。
②コロナウィルスのスパイクタンパクは細胞表面のACE2を標的にして細胞に感染する。その後、ACE2の発現を低下させるが、これがミトコンドリアの機能不全に繋がり、細胞の損傷、組織の炎症に繋がるのではないかと考えられている。ウィルスがなくてもスパイクタンパク単独でも同様の障害を起こすことができる。
”コロナワクチンで血栓が出来る理由”(荒川先生のブログより)
ACE2を発現している細胞、組織はコロナウィルスのスパイクタンパクの標的になる。ACE2は広範囲な細胞で発現し、卵巣、精巣、子宮内膜、胎盤などの生殖器官でも発現している。つまり、スパイクタンパク自身が卵巣、精巣、子宮内膜、胎盤の炎症や損傷を起こす可能性がある。
③胎盤は細胞融合により形成される。細胞融合に必要なシンシチン(内在性レトロウィルスのenvという遺伝子で作られたタンパク質)スパイクタンパクと同じくフソゲン(fusogen:融合活性を持つ物質)で、スパイクタンパクと構造が類似している。可能性は大きくないが、スパイクタンパクに対する抗体がシンシチンを攻撃すれば、胎盤をきたしそれは流産につながる。
④ACE2は酵素でもあり、ACE2によって産生されるAng-(1-7)ペプチドが卵胞の発育、ステロイド産生、卵子の成熟、排卵などの卵巣の生理機能を調節することが知られている。
以上のことから、スパイクタンパクによるACE2の酵素活性阻害自体が不妊に繋がる可能性は否定できない。
・『コロナワクチンには複数の異なった機構で生殖系を阻害、または攻撃、損害する可能性があるわけです。むしろ効率的に不妊を起こしかねません。現在日本でも12歳以上へと接種年齢の引き下げが始まっていますが、将来妊娠出産を控えている世代にこういったリスクを負わせる必要性は私には感じられません。』
5章 コロナワクチンは免疫不全の原因となる
●ワクチンと抗体依存性感染増強(ADE)
・抗体はウィルスに利用される場合がある。抗体依存性感染増強(ADE)とは、ウィルス粒子と不適切な抗体とが結合することにより、炎症や免疫病変が促進される現象である。
・ADEには少なくとも2種類のメカニズムがある。一つは抗体を介してマクロファージに感染する機構。もう一つの機構は抗体と複合体を作ったウィルスが免疫系を刺激し、炎症を暴走させる仕組み(サイトカインストーム)である。いずれの場合も抗体の存在がウィルスの感染を誘導し、免疫系の症状を暴走させる。
・SARS(重症急性呼吸器症候群)の原因ウィルスもコロナウィルスで、正式名称はSARS-CoV-1である。新型コロナウィルスの正式名称はSARS-CoV-2。コロナウィルス自体はありふれたウィルスで風邪の10~15%の原因を占めている。
・『SARSの流行時にもコロナウィルスに対するワクチンを作ろうとする研究があったのですが、動物実験での結果は散々でした。このため、コロナウィルスワクチンを接種するのは危険ではないかと言われてきました。』
●なぜワクチン接種が自己免疫疾患に繋がり得るのか
・『COVID-19が陽性であっても、その多くは症状がない。無症状のPCR陽性例の数は研究によって大きく異なり、最低で1.6%、最高で56.5%となっている。COVID-19に感受性の低い人は、おそらく非常に強い自然免疫系を持っている。健康な粘膜バリアの好中球とマクロファージは、ウィルスを速やかに排除し、多くの場合、適応システムによる抗体の産生を必要としない。しかしこのワクチンは、自然の粘膜バリアを越えて注射することと、RNAを含むナノ粒子として人工的に構成することで、意図的に粘膜免疫システムを完全に回避している。カーセッティ(2020)の論文で述べられているように、自然免疫反応が強い人は、ほとんどの場合、無症状で感染するか、軽度のCOVID-19疾患を呈するだけである。しかし、そもそも必要のないワクチンに反応して抗体が過剰に産生された結果、前述のように慢性的な自己免疫疾患に陥る可能性がある。』
・『コロナウィルス感染とワクチン接種の双方とも自己免疫疾患の発症に繋がる可能性はありますが、どちらの方がリスクがより高いでしょうか。コロナウィルスに自然感染して無症状または軽症で治癒する場合、対処するのはまず第一に自然免疫です。自然免疫は抗体を用いる獲得免疫とは別系統です。そして獲得免疫は抗原と出会う場によっても対処法を変えます。呼吸器感染症の最前線に当たる獲得免疫は粘膜免疫です。粘膜免疫で主に誘導される抗体はIgAのクラスですが、これは粘膜免疫担当の抗体で、全身を循環するIgGクラスの抗体とは別のクラスです。こういった意味でも、無症状や軽症の場合の自然感染ではワクチン接種と比較すると自己免疫疾患に繋がることは限定的でしょう。
また、コロナウィルスに自然感染した場合には、ウィルスは免疫系の抵抗を受けながら増殖します。無症状のPCR陽性者や軽症者ではスパイクタンパクの曝露量は限られるので、大きく曝露されるのは重症者の場合と考えられます。それに対しコロナワクチンは接種後に細胞内でスパイクタンパク生産を開始しますので、量はいきなり最大量に達します。シュードウリジン修飾されたmRNAワクチンは分解されにくく、長い間スパイクタンパクを生産します。スパイクタンパクへの曝露量はワクチンの方がずっと多いでしょう。つまり、ワクチン接種者はもれなく大量のスパイクタンパクに曝露されます。一方、コロナ感染の場合大量のスパイクタンパクに曝露される確率は、コロナ感染確率×感染してから重症化する確率となり、ワクチン程ではないということです。』
●スパイクタンパクはDNA修復、V(D)J組換えを阻害する
・DNA修復機構が働かないと、変異は固定され癌の原因になる。また、DNA修復機構は免疫系の遺伝子組換えにも必須である。よってスパイクタンパクがDNA修復を阻害するならば、コロナワクチン接種が癌や免疫不全に繋がる懸念が出てくる。
●コロナワクチンと癌
・『コロナワクチンの副反応にリンパ節の腫脹が知られています。リンパ節は局所的な免疫応答の場です。抗体を産生するために一時的にリンパ節が腫れることはよくありますが、リンパ節の腫瘍が疑われる場合もあります。コロナワクチンの別の副反応として、ワクチン接種後の最初の数日間にリンパ球の減少が見られることがあり、免疫の低下に繋がります。この2つの副反応は一見反対に見えますが、個人差もあるでしょうし、タイミングの違いもあるでしょう。また、免疫不全になるにはリンパ球全体の細胞数の減少が必要でもなく、免疫を構成する特定の細胞種がワクチン接種を繰り返すことにより減少しているのかもしれません。
今回のケースではコロナワクチンが直接活性化する細胞に起源をもつ癌細胞がワクチン接種によって急激な増殖を開始したと考えられます。しかし、そうした特殊なケース以外にも、コロナワクチンには癌の進行をもたらす複数の作用機序があります。免疫低下は感染症を招きますし、癌の悪性化に繋がる可能性もあります。スパイクタンパクはBRCA1、53BPIなどの癌抑制遺伝子の働きを抑えることが報告されており、これらのタンパクの機能低下はDNA修復の機能不全に繋がり、癌細胞の発生や悪性化の両方に繋がります。
癌は増殖制御の仕組みを受けつけずに勝手に増殖を行うようになった細胞集団であり、いったん増殖した癌細胞は免疫系で対処することは難しいのです。すでに癌を患っている人はコロナワクチンによる癌の悪性化を警戒する必要があるでしょう。』
感想
友人から、「2度目、3度目の接種では40度近い発熱がありとても辛かったが、実際にコロナに感染したときは37度台だった」との話を聞きました。
これは何故だろう? ワクチンのおかげと言えるのだろうか? しかし、副反応が40度近いというのは明らかに異常なことではないか。と思っていました。
これは、荒川先生が指摘されている、感染では粘膜バリアともいえる自然免疫系が必死に戦うためウィルス側も思ったように動き回れない(曝露できない)のに比べ、ワクチン接種ではノーガードでスパイクタンパクを曝露するため、体への侵襲が大きくその結果、修復作業の第1段階でもある“炎症”が強く、広く出るのだろうと思いました。
やはり、コロナワクチン、未知のmRNAワクチンの隠された脅威が存在するのは間違いないと思います。
免疫学者の警告1
コロナ後遺症だけでなく、ワクチン後遺症というものが問題になっていることを耳にしました。調べてみると週刊新潮など多くの週刊誌などが報じていることも分かりました。
下記は天王寺こいでクリニック 小出誠司先生のブログですが、その数は想像以上でした。
一方、「抗原原罪」という耳慣れない言葉が気になり、検索したところ今回の荒川 央先生の『コロナワクチンが危険な理由 免疫学者の警告』という著書を見つけました。
荒川 央先生は分子生物学者であり、また免疫学者です。コロナワクチンはmRNA(メッセンジャーRNA)を利用した全く新しいメカニズムのワクチンであることが、不安の大きな要因の一つとなっていますので、荒川先生の見解は非常に重要ではないかと思い拝読させて頂きました。
なお、ブログは目次より前に、「あとがき」の冒頭と最後の部分をご紹介しています。これは、ここに荒川先生の思い―『自分の命を守りたい人、大切な誰かを守りたい人に、微力ながらも力を貸すことができないかと考えたためです』―が凝縮されていると感じたためです。
『私[荒川先生]がコロナワクチンに関するブログを立ち上げたのは2021年6月8日。目的は1つ。コロナワクチンの危険性を日本の方々に伝えるためです。内容は生命科学の視点から客観的な事実に焦点を絞るように努めました。
私が主に伝えたかったコロナワクチンの危険性の多くは遺伝子ワクチンの作用機序とスパイクタンパクの持つ毒性から予測されるものです。血栓による血管障害とそれに伴う複数の臓器の障害、自己免疫疾患、癌などです。ブログ内では紹介していますが、今回の書籍化にあたってページの都合で触れられなかったのがプリオンによる神経変性病、シェディング[伝搬]などです。心筋炎、脳梗塞、自己免疫疾患、癌、神経変性病などは加齢によってもリスクが高まる疾患です。こうした疾患がコロナワクチンの作用機序から予測され、実際に後遺症として報告されています。私はコロナワクチンによる隠れた副作用は文字通りの「老化」ではないかと思っています。老化によってより深刻な被害を受けるのは高齢者です。高齢者で老化が加速すればそれはすなわち死にも直結します。けれどもコロナワクチン接種後に高齢者が亡くなっても、因果関係は不明で老衰や寿命として処理される場合がほとんどです。例えば10代の人の内臓年齢が20代になり、30代の人の内臓年齢が40代になっても問題は直ちに目には見えず、若い方は多少老化が進行しても元々の若さや生命力のために自分でも気が付かない場合が多いでしょう。しかし、将来的にどれだけの健康被害を生み、健康寿命をどれほど縮めることになるのかは現時点では分かりません。』
『ブログの執筆は、私にとっては一人で静かに始めた戦争でした。記事を書き続けるうちにたくさんの人と繋がりが生まれ、皆それぞれの立場で戦っているのだと気付きました。コロナ騒動は情報戦でもあります。そして、これは不思議な戦争です。老若男女関係なく、気付いた人が立ち上がり、情報を共有し、手の届く範囲で他者を助けようとしています。日本でも、そして海外でもこの危機に気付いた人が大切な人達を守るために危機を伝えてきました。私のブログもその局地戦の記録でもあります。そのためにも書籍化にあたり日付を残すこととしました。どの時点でどれだけの危険性が判明し、警鐘されていたか、その時点でマスメディアや医療関係者、公的機関、政府の行動はどうだったか。コロナワクチン薬害に対する訴訟もこれから相次ぐと思いますので、そうした情報も後に大事な情報になってくるかと考えます。』
目次
はじめに―分子生物学者、免疫学者として、コロナワクチンについて考えること
本書の要点―コロナワクチンが危険な理由
1章 もう一度、ワクチンの「常識」について考えてみる
●コロナワクチン接種についてのいくつかの誤解
●嘘と統計:数学のトリック
●ワクチン有効率95%は本当か?
●コロナウィルスが存在している根拠を政府や研究機関はもっていない―ウィルスの単離からこの問題を考える
2章 もう一度、感染症対策について考えてみる
●「パンデミック」の謎
●PCR検査について
●無症状のPCR陽性者からの感染は0だった
●コロナウィルスは昔から居た
●スペイン風邪とファウチ博士の論文
3章 コロナワクチン=「遺伝子ワクチン」の正体とは何なのか?
●コロナワクチンはコロナウィルスよりも悪い?
●前例のないワクチン
●遺伝子ワクチンというもの
●遺伝子ワクチンによる自己免疫「抗体依存性自己攻撃」
●セントラルドグマとmRNA
●mRNAと遺伝暗号(コドン)
●mRNAワクチンはすぐに分解されるのか?
●なぜワクチンに使われる遺伝子の毒性をなくさなかったのか?
●ブレーキのないRNAワクチン
4章 スパイクタンパクの危険性
●どうしてコロナワクチンで血栓が出来るのか
●スパイクタンパクの毒性―スパイクタンパクはACE2の抑制を介して血管内皮機能を損なう
●スパイクタンパクの全身の血管への毒性
●スパイクタンパクは血流を循環するか
●ワクチン接種者のスパイクタンパクはエクソソーム上で4ヶ月以上血中を循環する
●コロナワクチンと不妊
5章 コロナワクチンは免疫不全の原因となる
●ワクチンと抗体依存性感染増強(ADE)
●猫とネズミ
●初の病理解剖から分かったこと
●なぜワクチン接種が自己免疫疾患に繋がり得るのか
●コロナワクチンと帯状疱疹
●スパイクタンパクはDNA修復、V(D)J組換えを阻害する
●コロナワクチンと癌
おわりに
●オミクロン変異考察
●コロナワクチンをめぐるイタリアの状況について
●コロナワクチンと治療法―生データが必要だ、今すぐ
あとがき
はじめに―分子生物学者、免疫学者として、コロナワクチンについて考えること
・荒川先生のご専門は、分子生物学(遺伝子の生物学)と免疫学である。
・バイオテクノロジー、ゲノム編集、ウィルス学、細胞生物学などは専門の範囲に入る。
・『端的に言って、私はコロナワクチンは危険なものだと考えています。仕事の関係で接種しないといけないような状況の方もおられるかもしれません。ご家族やご本人で進んで接種した方もおられるかもしれません。でも今後は出来れば接種しない方が良いし、接種するにしても回数が少ない方が良いと思うのです。』
・「遺伝子治療の治験」だとすれば、リスクより利益が上回るので理解できるが、健康な多くの人に試すのは適切ではない。
・コロナワクチンの危険性を伝えるためのブログを荒川先生が立ち上げたのは2021年6月8日。
・『ブログでの発信を開始した頃と、ワクチン接種が相当進んだ現在とは状況は変わってきています。ワクチン接種の副作用や死者の実態が次第に明らかになってきているのに加えて、ブースター接種をこのまま受けていいのかという不安や疑問はより高まっています。とりわけ、子供への接種が行われようとしているとき、これを食い止めるためにも私のブログを書籍化する意味があると花伝社様からお話しをいただきました。将来、大規模の集団訴訟も起こされるものと予想され、こうした訴訟の理論的根拠ともなりたいと願います。
私のブログ及びこの一冊の本は、分子生物学者、免疫学者としての私なりの小さなレジスタンスです。 (2022年2月13日、ミラノ)』
本書の要点―コロナワクチンが危険な理由
1)遺伝子ワクチンである
・コロナウィルスのスパイクタンパク遺伝子をワクチンとして使っている。
・遺伝子ワクチンは研究途上の実験段階で、人間用に大規模な接種が行われるのは初めてである。
・問題は遺伝子ワクチンがこれまでのワクチンと異なり、遺伝子が細胞内でどれだけの期間残るのか予測できないことである。場合によっては染色体DNAに組み込まれ、スパイクタンパクを一生体内で作り続けることになる可能性もある。
2)自己免疫の仕組みを利用している
・『「通常のワクチン」では抗体を作らせる為にウィルスそのものまたは一部分をワクチンとして使います。そういったワクチンはワクチン接種後に体内に抗体ができた場合、それ以降攻撃されるのはウィルスだけで終わります。
「遺伝子ワクチン」はワクチンを接種した人間の細胞内でウィルスの遺伝子を発現させます。ワクチン接種以降は自分の細胞がウィルスの一部を細胞表面に保有することになります。体内の抗体が攻撃するのはウィルスだけではなく自分の細胞もです(抗体依存性自己攻撃、Antibody-dependent auto-attack[ADAA])。』
・遺伝子ワクチンであるコロナワクチンは筋肉に注射されるが、筋肉に留まるとはいえない。
・『ファイザーの内部文書によると、筋肉注射された脂質ナノ粒子は全身に運ばれ、最も蓄積する部位は肝臓、脾臓、卵巣、副腎です。卵巣は妊娠に、脾臓、副腎は免疫に重要です。他にも血管内壁、神経、肺、心臓、脳などに運ばれることも予想されます。そうした場合、免疫が攻撃するのは卵巣、脾臓、副腎、血管、神経、肺、心臓、脳です。それはつまり自己免疫病と同じです。』
3)コロナワクチンは開発国でも治験が済んでおらず、自己責任となる

"米FDAとCDC、mRNA型2価ワクチンの対象年齢を生後6カ月以上に引き下げ"
JETROでは「ビジネス短信」として情報発信されていました。以下は、”米FDA”に関する情報です。接種対象や回数(ブースター接種)は制限付きになっていると思います。
4)コロナウィルスは免疫を利用して感染できるので、ワクチンが効くとは限らない
・コロナウィルスのスパイクタンパクは人間の細胞表面の受容体ACE2(アンジオテンシン変換酵素-2)に結合し体内に侵入する。
・コロナウィルスはマクロファージなどの食細胞に耐性があり、細胞内で増殖したり、サイトカイン放出を促進したり、細胞を不活性化したりして免疫系をハイジャックする。

画像出展:「東京都健康安全研究センター」
サイトには、走査型電子顕微鏡や透過型電子顕微鏡で撮影した写真が8枚出ています。
5)スパイクタンパクに毒性がある
・コロナウィルスは血栓を起こし、肺や心臓、脳にも障害を起こすことがある。
・血栓を起こすにはウィルスは必要ではなく、コロナウィルスのスパイクタンパク単独でも障害を起こす。
・血管は全身の臓器と繋がっているので、あらゆる臓器に被害が及ぶ可能性がある。また、全身をめぐる毛細血管は血栓によって損傷をうけやすい。
・マウスの実験では、スパイクタンパクは脳血液関門を越えることが確認されている。
6)不妊、流産を起こす可能性がある
・脂質ナノ粒子が最も蓄積する場所の1つが卵巣である。卵巣に運ばれたワクチンがスパイクタンパクを発現すると、卵巣が免疫系の攻撃対象になる。
・スパイクタンパクが結合する受容体ACE2は、精子の運動性や卵の成熟に働くホルモンを作るため、スパイクタンパクによりACE2が阻害されると不妊症につながる可能性がある。
7)ワクチン接種者は被害者となるだけでなく加害者となる可能性もある
・ワクチン接種者はスパイクタンパクを体外に分泌し、副作用を他者に起こさせる可能性が指摘されている。
・本当に怖いのは長期的な副作用で、これから長い時間かけて出てくるかもしれない。
1章 もう一度、ワクチンの「常識」について考えてみる
●コロナワクチン接種についてのいくつかの誤解
・誤解:副反応が出るのはワクチンが効いている証拠! 副反応が強いのは若くて元気な証拠!
・解説:『ワクチン接種直後の短期的な副反応である発熱や体調不良は、体の一部がワクチンの副反応(副作用)によって損傷されているのでしょう。そして2度目のワクチン接種後の副反応がより重いのは、最初のワクチン接種で作られた抗体がワクチンを受け取った細胞を攻撃した結果の強い自己免疫応答でしょう。これは良いことでも喜ばしいことでもありません。自己免疫での損傷は一時的な場合もあれば、不可逆的で取り返しのつかない場合もあります。』
●嘘と統計:数学のトリック
・19世紀のイギリスの首相ベンジャミン・ディズレーリの言葉に、『世の中には3種類の嘘がある:嘘、大嘘、そして統計だ』(There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics)。
・例:ファイザーのRNAワクチンの有効度(Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine, N Engl J Med. 2020 Dec, Fernando P Polack et al.)
-2回のワクチン接種したグループ21,720人のうち新型コロナ感染者は8人。新型コロナ非感染者の割合は(21720-8)÷21720=0.9996=99.96%
-プラセボ(偽薬)を接種したグループ21,720人のうち新型コロナ感染者は162人。新型コロナ非感染者の割合は(21720-162)÷21720=0.9925=99.25%
⇒考え方A
感染者が162人から8人に減った!感染者の減少率は、(162-8)÷162=0.95=95%。つまり、ワクチン有効率は95%! これは素晴らしいワクチンだ!
⇒考え方B
ワクチンを接種しなくてもコロナ非感染者は99.25%。ワクチンを打ったところで感染しない確率が0.71% (99.96%-99.25%) 上がるだけか。未知のワクチンなんて打つ必要はないじゃないか。
※減少率95%は100人中95人に効くという意味ではない。99.25%の人はワクチンを打っても打たなくても変わらなかった(感染しなかった)ということである。
・『このように、同じ結果でも見せ方によって印象は大きく変わるのです。もともと感染者も人口比で見ると大したことはありません。ワクチンが必要かどうか、発表されているワクチン有効率だけで判断されませんように。』
免疫学講義5
第15章 免疫系(防御系)と自律神経の関係 part2
1.アレルギー疾患
①アナフィラキシーショック
強く感作された状態で大量の抗原がもう一度入ってくると、それにより免疫反応が起こること。抗原は蜂の毒や薬物などがある。アナフィラキシーショックの免疫反応はリンパ球と副交感神経刺激が反応の主体である。副交感神経は血圧を下げることがショックの引き金を引く。
③食物アレルギー
食物には抗原性の強いものがたくさんある。大事なことは消化管の防御システムがしっかり働くようになるまで、離乳食を続けるということである。半年以上、なるべく1ヵ月でも2ヵ月でも遅くすることである。
④花粉症、蕁麻疹
蕁麻疹は精神的なストレスが引き金になることが多い。
⑧乳児アトピー
乳児アトピーは離乳食以前に全身が真っ赤に腫れ上がる。主な原因は抗原性の高い3大抗原(卵、牛乳、小麦)、卵は卵白アルブミン、牛乳はカゼイン、小麦はグルテンである。母親がこれらの抗原を含む食品(例えば、ケーキやアイスクリームなど)をたくさん摂ると、身体で処理できないで母乳に入り、乳児が乳児アトピーになるおそれがある。もし、1ヵ月、2ヵ月の赤ちゃんが乳児アレルギーを起こしたら、母親は食生活を見直さなければならない。

画像出展:「免疫学講義」
『アレルゲンにはIgE抗体がつきます。こういうimmune complexに次に関与するものは補体と肥満細胞です。肥満細胞からは、ヒスタミン、セロトニン、アセチルコリン、ロイコトリエンが出ます。補体からはアナフィラトキシンが出ます。補体のアナフィラトキシンも、肥満細胞や好塩基球から出るものも、大きな目で見れば全部副交感神経反射で、血圧下降、分泌促進で鼻水が出たり、下痢したり、発疹、痒みなどの反応がでます。平滑筋の収縮や血管通過性亢進も副交感神経反射です。
副交感神経は夜の世界なので、布団に入って温まったときや真夜中に痒くなります。低気圧がきたりすると蕁麻疹が出ます。副交感神経反射は副交感神経が優位になると出ます。』
●鼻水、くしゃみ、発疹、腫れ、喘鳴発作などは、すべてアレルゲンを洗い流す作用である。対症療法でなかなか患者さんを治せないのは、炎症を止めてしまうと根本治療にならないためである。激しい下痢が起こったら入ってきた異種タンパクを洗い流して外に出して助かるための反応、寄生虫が入って来て下痢したら、寄生虫を排除しようとする治るための反応と考えなければならない。抗ヒスタミン剤や抗ロイコトリエン剤は根本治癒にはつながらない。
●リンパ球は出生後出てきて、1、2ヵ月から一気に増え4歳位でピークになる。その後ゆっくり減って、18-25歳で顆粒球と交差しその後は顆粒球との差が開いていく。アレルギーはリンパ球が多い時期に好発するため、高校生を過ぎた頃からアレルギーは自然に消失していく。
●ステロイド剤を多用していると、ステロイドはコレステロール骨格で組織に沈着するので、沈着したステロイドがまた刺激となって、アトピー性皮膚炎を悪化させる。このような人はリンパ球が減る時期になっても治らないことが多い。
2.顆粒球増多と組織破壊の病気
①突発性難聴[内耳](idiopathic sudden sensorineural, sudden deafness)
●激しい夫婦喧嘩をしていて、突然耳が聞こえなくなることもある[突発性難聴:一般的に50歳代を中心に30歳~60歳に多く、特に男女差はない。原因不明とされている]。増加した顆粒球が内耳を破壊することで発症する。常在菌があるところが最も顆粒球を刺激するが、非常に強いストレスに晒されると常在菌の場所に関わらず組織破壊の病気がおこる。[『安保徹の原著論文を読む』には、ストレス→交感神経刺激→顆粒球増多→粘膜破壊の連鎖とされている]
②メニエール病[三半規管](Meniere disease)
●内耳がダメージを受けると突発性難聴、三半規管がダメージを受けるとメニエール病になる。
③歯周病(periodontitis)
●一般的に歯科医はストレプトコッカス・ミュータンスの感染症と言われているが、常在菌が原因で、増えた顆粒球が口の常在菌と反応して炎症を起こす。[補足:ストレプトコッカス・ミュータンスは虫歯の原因菌とされているようです]
④食道炎(esophagitis)
●食道炎のほとんどは胃液が逆流しておこる逆流性食道炎と言われているが、胃を全摘した人でも食道炎になる。食道炎も顆粒球による粘膜破壊である。
⑤びらん性胃炎(erosive gastritis)→胃潰瘍(gastric ulcer)
●マウスの拘束実験では、12時間拘束でびらん性の胃炎を発症し、24時間拘束で胃潰瘍になった。これは顆粒球が粘膜全体に炎症を起こし、症状が進んで胃潰瘍になったということである。
⑦クローン病(Crohn’s disease)
●小腸での組織破壊だが、クローン病の患者さんは末梢血に顆粒球、特に好中球が非常に増えている。
⑧潰瘍性大腸炎(ulcerous colitis)
●潰瘍性大腸炎は大腸がダメージを受ける。
⑩子宮内膜症(endometriosis)
●子宮内膜症はストレスで分泌現象が抑制されて起こる。
⑪不妊症(infertilitas)
[子宮内膜症(endometriosis)、卵管炎(salpingitis)、卵巣嚢腫(ovarian cyst)]
●この3つは不妊症の原因になる。不妊症の共通点は「冷え」である。「冷え」の主な原因は交感神経緊張で血管収縮による血流障害である。
⑭膀胱炎(cystitis)
●一般的に膀胱炎の原因は細菌感染と言われているが、膀胱にある常在菌と増えてきた顆粒球との反応である。
⑮骨髄炎(myelitis)
●顆粒球を作る場所で自壊作用を起こし、骨髄の中に膿ができる。
⑯間質性肺炎(interstitial pneumonia)
●一般的には原因不明とされているが、この病気は血流障害と顆粒球増多である。
第16章 移植免疫
1.移植(transplantation)と拒絶(rejection)
●拒絶は移植された人の免疫(リンパ球)が移植片を異物と見なしてしまうからである。
2.MHC
●MHCは主要組織適合抗原と言われ、移植のためのタンパク質という印象があるが、本来はT細胞がT細胞レセプター抗原を認識するときの抗原分子である。
4.純系
●遺伝子が全く同じであれば拒絶は起きない。これを同系移植というがヒトでは一卵性双生児同士で行う移植である。自分の皮膚を自分に移植する自家移植でも拒絶は起きない。
●マウス同士の移植は同種移植であるが、遺伝型が異なるため拒絶が起こる。種が異なる移植は異種移植だが、同種移植同様、拒絶反応が起きる。なお、同種移植、異種移植においては、免疫反応だけでなく、凝固系、補体系なども加わって拒絶される。
5.拒絶の速さ
●超急性拒絶は移植翌日に起こるような反応である。異種移植や同種移植でも起こる場合がある。
●一般的な同種移植の拒絶は急性拒絶とされ、T細胞やB細胞がクローン拡大に1週間程かかるので、代替1週間後に拒絶反応が起こる。
●急性拒絶はステロイドや免疫抑制剤を使って抑えることができる。
●慢性拒絶は1ヵ月前後で出てくる反応で、T細胞やB細胞だけでなく、胸腺外分化T細胞や自己抗体を産生するB細胞(B-1)の活性化を伴って起こる。
7.移植のしやすさ―MHCの発現量
●赤血球のMHCはnagativeマイナスなので血液型を合わせれば移植ができる(輸血)。角膜のMHCもほぼマイナスなので移植ができる。
●MHCの発現量が弱いのは肝臓、腸、肺、心臓である。腎臓の発現量はかなり強いため、腎臓移植は肝臓移植に比べ、免疫抑制剤を使う量が多くなる。皮膚はほぼ移植はできない。
9.骨髄移植(bone marrow transplantation)
●再生不良性貧血や慢性・急性白血病で抗ガン剤や放射線治療を受けると、骨髄機能抑制されてしまうため骨髄移植が必要になる。骨髄移植では細胞、骨髄の中にリンパ球があるため、移植片がhostを攻撃する。これをGVH反応といい、これによって起こる病気をGVH病という。
10.GVH病(GVHD:graft-versus-host disease)
●ヒトでは骨髄移植は、抗ガン剤や放射線照射によって骨髄を弱らせガン細胞を除いてから行う。
12.新生児免疫寛容(neonatal tolerance)
●新生児は生まれたときにはリンパ球はない。最初の3日から1週間で新生児顆粒球増多症が起き、その後リンパ球が増えはじめる。そのときに自己抗原を学ぶ。
13.拒絶に関与するほかの白血球
●急性拒絶の場合は、T細胞とB細胞が原因である。
●慢性拒絶の場合は、extrathymicT細胞と自己抗体産生するB-1細胞が原因で、これにマクロファージや顆粒球が加わる。
●急性拒絶は外来抗原向けのシステムが作動して一気に拒絶するが、慢性拒絶では自己応答性のものが反応して色々な細胞を巻き添えにしてゆっくり炎症が起こる。
15.免疫抑制剤(immunosuppressant)
●親と子の移植でも全部は合っていないので免疫抑制剤を使って移植する。特に腎臓移植ではMHCの発現が強いため、免疫抑制剤の作用は強い、一方、腎移植では生着している期間は平均8年と言われている。
17.輸血によって生着率上昇
●移植するdonorの血液をあらかじめrecipientに輸血しておくと生着率が上昇する。これがblocking antibodyである。
第17章 免疫不全症
1.先天性免疫不全症(primary immunodeficiency)
●先天性免疫不全症は生まれて3ヵ月や半年後に気づくことが多い。これは新生児が母親の母乳から抗体をもらい、また、胎生期には胎盤を経由してIgG抗体が入ってくるが、少しずつ減っていくためである。通常は自前の免疫系が対応するが、先天性免疫不全症では対応できない。
②胸腺無形成症(thymic aplasia)
●胸腺がなくてT細胞ができないことを胸腺無形成症という。
③重症複合免疫不全症(scid:severe combined immunodeficiency)
●重症複合免疫不全症はT細胞もB細胞もできない。
2.重症複合免疫不全症(scid:severe combined immunodeficiency)
①X-scid(伴性劣性遺伝) X連鎖重症複合免疫不全症
●重症複合免疫不全症は遺伝子異常が原因である。
第18章 腫瘍免疫学
1.免疫系の二層構造
●『私たちの免疫系は二層構造になっています。生物が上陸する前の消化管中心の免疫系から、生物が上陸した後には、えらから胸腺ができ、造血が前腎から骨髄に移りました。したがって、リンパ球を作る場所は、古い時代の場所と新しい場所の2種類あるのです。
新しい免疫系ができた後、古い免疫系がすべて失われたというわけではありません。細々ながら続いています。胸腺や骨髄のような新しい免疫系はT細胞やB細胞を作りますが、加齢とともに骨髄や胸腺も脂肪化して、その作る勢いは失われていきます。その代わりに、生物が上陸する前の胸腺外分化T細胞や自己抗体産生B細胞の世界が拡大していきます。
二層構造のうち古い免疫系では、胸腺外分化T細胞は自己応答性があり、古いB細胞であるB-1細胞は自己抗体を産生します。よって、基本的に古い免疫系は、自分の身体にできた異常細胞を排除するという仕組みで存在したのです。
しかし、生物には上陸すると外界の異物に曝される機会が多くなり、進化によって出現した胸腺と骨髄を使ったT細胞、B細胞が新しく生まれました。これらの自己応答性のクローンをnegative selectionで取り除くので、クローンの構成が外来抗原向けになっています。ですから、活発な活動により入ってくる外来抗原を処理するためにはプラスになっても、内部監視の力はないのです。
私たちがだんだん年を取ってガンができるような年齢になると、二層構造のうち古い方が次第に活性化していきます。古い免疫系は腫瘍の排除や、あるいは増え続ける正常細胞の分裂の速さの調節もしています。このような二層構造で免疫系は成り立っています。』
2.ガン細胞を排除している証拠
●免疫系がガン細胞を排除している証拠
-AIDS:HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染するとCD4が減少し、(CD8も後で減る)リンパ球数が減少して免疫抑制になる。そして、カポジ肉腫が発生する。
-マラリア感染:マラリアに感染すると免疫抑制が起こり、バーキットリンパ腫という形でガンができやすくなる。
-移植:免疫抑制剤を使用するが、ガンの頻度が高くなる。
-先天性免疫不全症:子供のうちに亡くなることも多く、生き残った場合も発ガンする場合が多い。
3.腫瘍抗原
●腫瘍化するとMHCは下がるか、なくなることが多い。特に増殖の速い腫瘍の場合は、MHCを失う傾向が強くなる。このようなMHCがないガン細胞をNK細胞は攻撃する。
5.腫瘍ができるための条件
●腫瘍ができるための必要条件でよく知られているのが、遺伝子の多段階変異である。初めは正常の分裂細胞、次に良性の腫瘍、それから形質が残ったままの腫瘍、そしてMHCを失った悪性腫瘍と段階を経て増殖の勢いを増していく。
●発ガン物質(carcinogen)として有名なタバコだが、喫煙者は減り続けているにも関わらず、肺ガン患者は増え続けている事実を考えると発ガン物質の関与に疑問を持たざるを得ない。
●ストレスの共通点には低体温がある。そして、低体温は血管収縮による血流障害や低酸素状態を引き起こす。このとき、副腎髄質からアドレナリンが出て高血糖になる。これらの条件はガンが育つ最適の条件である。
下の2つの図は「肺がんを学ぶ」から拝借しました。なお、こちらは罹患ではなく、死亡率になります。赤線が肺がんです。


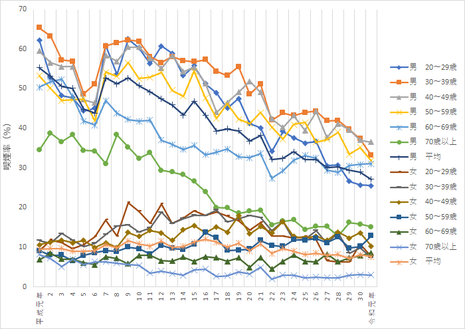
画像出展:「最新たばこ情報」
成人喫煙率(厚生労働省国民健康・栄養調査)
安保先生のご指摘通り、肺がん患者は増え続け、喫煙者は減っているという現実を考えると、喫煙が害であり影響しているのは間違いないと思いますが、別の要因の方が大きいと考えざるを得ないと思います。
6.ストレス反応の意義
●『私たちはストレスがかかったとき、無酸素で瞬発力のあるエネルギーを産生します[解糖系]。危機を乗り越えるためには酸素は要らないので低体温、低酸素です。このとき糖をたくさん使うので高血糖という条件になります。ですから、私たちがつらいめにあったとき低体温になったり血糖が上昇して糖尿病状態になったりするのは、危機を乗り越えるためなのです。
ストレスで起こる低体温、低酸素、高血糖は、短いスパンでは、瞬発力を得て危機を乗り越えられるためプラスに働きますが、長くストレス状態が続くと解糖系の方にシフトしてしまい、適応反応として細胞分裂が始まります。ミトコンドリアの働きには細胞分裂の抑制力もあり、低体温になるとミトコンドリアが働けなくなるので分裂正常細胞の中から適応でガン化した分裂が起こるのです。
ですから、ガンの問題はcarcinogenによる遺伝子の多段階変異というよりも、このような解糖系優位の状態に引きずり込まれて分裂の細胞(ガン細胞)になったということです。多段階変異は低体温に適応するための現象として捉えればよいのです。』
8.ガン患者の免疫状態
●低体温のためリンパ球の働きが低下している。
●交感神経緊張によって、副交感神経支配のリンパ球は減少している。
●NK細胞は交感神経刺激で数は増加するが機能は低下する。特にパーフォリンのようなキラー分子は副交感神経で分泌が促進されるので、交感神経優位な環境では低下する。
9.キラー分子群
●多少ストレスがあってガン細胞ができても、簡単にガンにならないのは、リンパ球のキラー分子群が働いて増殖を防いでいるからである。代表的なキラー分子群にはパーフォリン、Fas ligand、TNFαがある。これらは体温が37℃以上であるというのが条件である[ガン細胞は毎日5000個程できていると言われています]。
12.ガンの免疫療法
●ガンの免疫療法とは、解糖系の働きに偏った内部環境をミトコンドリア系に有利な働きに戻して分裂抑制遺伝子の出番を作るということである。
あとがき
『現代医療は、多くの病気を原因不明として対症療法を行う流れが拡大しています。しかし、多くの病気はストレスを受けて免疫抑制状態になって発症しています。原因は不明ではないのです。ストレスで生じる「低体温、低酸素、高血糖」は短いスパンではエネルギー生成のうちの「解糖系」を刺激して瞬発力を得て危機を乗り越えるための力になっています。しかし、長期間このような状態が続くと、エネルギー生成のうちの「ミトコンドリア系」を抑制してエネルギー不足に陥ります。これがストレスで起こる慢性病の発症のメカニズムです。そして、いずれガンを引き起こす原因につながっていきます。
ストレスをもっとも早く感知するのは私たちの免疫系です。末梢血のリンパ球比率やリンパ球総数は敏感に私たちのストレスに反応しています。この反応には自律神経系と副腎皮質ホルモン系が関与しています。臨床では血液検査を行い、いつでもリンパ球比率を知れる状況にあるのですが、ストレスとリンパ球の減少の相関をほとんど教育の場で学ぶことがないので、血液検査のデータが活用されていないのが現状です。末梢血のリンパ球比率は35-41%が正常値で、ここから減少しても増加しても病気になってしまいます。
顆粒球過剰(リンパ球減少)は組織破壊の病気と結びつきます。逆に、リンパ球過剰はアレルギー疾患や過敏症の病気と結びついていきます。本講義録で学んだ知識があれば、多くの病気の発症メカニズムを知ることができます。対症療法を延々と続ける必要もなくなるのです。
消炎鎮痛剤の害やそのほかの薬剤の副作用なども、この本で学べたと思います。患者に良かれと思って続けている薬剤の投与の中にも多くの危険が潜んでいるのです。特に、自己免疫疾患の治療においては、本書の知識が役立つでしょう。そして、私たち生命体が持つ偉大な自然治癒力を引き出すことのできる新しい医学や医療が進展していくことでしょう。』
感想
白血球(顆粒球とリンパ球)と自律神経、副腎皮質ホルモン系、そしてからだを守る新旧免疫系の二層構造、これらは特に重要だと思います。
一方、健康を考える上で重要とされているものに糖化と酸化があり、例えば、AGE(終末糖化産物)は大量の活性酸素を産み出すと言われています。
何が言いたいかというと、顆粒球が攻撃に使う武器は“活性酸素”であるという点です。からだの中をパトロールし健康を守ってくれている免疫が、一転、暴走してしまうとからだを破壊するモンスターになってしまう恐れがあるということです。そして、その暴走の原因、引き金はまさに“ストレス”だと思います。
私は安保先生がご指摘になられているように、ガンの原因は発ガン物質よりも、ストレスによる免疫の暴走の方が大きいのではないかと思います。
ご参考:運動は免疫能を高めるか? 「メカニズムをさぐる III 好中球」
『ヒトの好中球は白血球の中でも顆粒球に分類され、その大半を占めている(正常値40~70%)。好中球の主な役割は生体防御機能であり、体内に侵入してきた病原微生物を中心とする異物を貪食し自らが発生させた活性酸素によってそれを殺菌する。しかしながら活性酸素は非常に酸化力が強いため異物の排除に有効な反面、正常な組織にも障害を与えることや過酸化脂質の生成を促し動脈硬化をはじめとして種々の疾病の原因にもなるというマイナスの側面ももっている。ここでは運動が好中球機能に及ぼす影響を中心に論を進めていく。』
免疫学講義4
第12章 膠原病 part2
1.進化した免疫系の抑制
●自己免疫疾患は線維芽細胞や線維芽細胞が作る細胞外マトリックスのコラーゲンで炎症が起こるので、膠原病、結合組織病といわれる。
●関節リウマチ(RA)で炎症が繰り返しおき、徐々に関節が動かなくなっていくが、これはストレスやウィルス感染が原因であることが多い。特に紫外線、寒さ、重力がストレスになる。重力のストレスとは長時間労働や夜更かしすることである。
●関節滑膜について注意しなければならないのは、SLEの血管炎もRAの腫脹も、炎症を起こしてつらいのは治るためのステップでもあるという点である。
●『私たちは火傷をしても腫れて治ります。大怪我をしても腫れて治り、しもやけになっても腫れて治ります。ですから炎症は、自己免疫反応が起こっているのと同時に、治るステップも起こっていると考えなければなりません。あまり対症療法をするとかえって病気は悪化するので注意が必要です。』
●『RAは特に関節に水が溜まって腫れ上がるので、注射器で水を引き抜きます。それをガラスに塗沫してギムザ染色すると95%が顆粒球で、残りの5%くらいのリンパ球は胸腺外分化T細胞とB-1細胞です。T細胞・B細胞が減少しているのです。自己免疫疾患は、免疫異常とか活性化とかいわれますが、本当はすべての自己免疫疾患は免疫抑制状態なのです。自己免疫疾患は進化した免疫系が抑制されて、古い免疫系や貪食系の顆粒球に活性が移ったという病態なのです。』
2.中枢神経系の自己免疫疾患
●多発性硬化症はミエリン鞘にあるMAGが抗原になって脱髄が起こり、神経の伝達が障害されて視力低下や末梢神経麻痺が起こる。
●重症筋無力症はアセチルコリンレセプターに対する自己抗体が原因である。筋肉の緊張は神経末端から出るアセチルコリンで起こるので、アセチルコリンレセプターが抗原になると筋緊張が持続して起こらなくなる。
3.内分泌器腺の自己免疫疾患
●橋本氏病は、甲状腺細胞のミクロゾームに対する自己抗体が出て、甲状腺が機能低下する疾患である。
●バセドウ氏病は、サイロキシン刺激ホルモン(TSH)のレセプターに対して自己抗体ができる。
●アジソン病は副腎に対する自己抗体(自己応答性リンパ球)が原因である。副腎皮質ホルモンの分泌が抑制されるためストレス対応や活力に影響が出て、すごい虚脱感に襲われる。
●Ⅰ型糖尿病(別名:インシュリン依存型糖尿病)は自己応答性リンパ球が問題となる。夜更かしや家庭内トラブルなどのストレスに加え、ウィルス感染も関わっている。ストレスにより副交感神経支配のリンパ球が減るので、これら2つが重なって起こることが多い。
4.消化管・肝の自己免疫疾患
●Iupoid肝炎はヒストン、核、ミクロゾームが自己抗原となる。
●萎縮性胃炎と悪性貧血の原因はVB12結合タンパクに対する自己抗体ができてVB12を吸収できなくなると、赤血球溶血が起きて貧血になる。胃は心因性のストレスが原因である。
●潰瘍性大腸炎はストレスによる大腸粘膜破壊が起こる病気である。クローン病はストレスによる小腸マクロファージの肉芽腫形成で、顆粒球の活性化が問題になる疾患である。自己免疫疾患とはいえないのは、自己抗体が見つからないことも多く、男女差がないのも自己免疫疾患の特徴とは異なる。
6.心臓の自己免疫疾患
●リウマチ熱は、心筋抗原とA型溶血性連鎖球菌の表膜の抗原が交叉しておこる。
7.眼の自己免疫疾患
●交感性眼炎はブドウ膜に対する自己抗体である。
●水晶体過敏性眼球炎は水晶体に対する自己抗体である。
8.皮膚の自己免疫疾患
●皮膚硬化症は皮膚の基底膜に対する自己抗体である。
●ベーチェット病は口の粘膜に対する自己抗体である。
9.Chronic GVH病
●急性GVH(移植片対宿主)病が、進化したT、B細胞で強く起こる。一方、慢性GVH病は、1月、半年、1年と免疫抑制剤でT、B細胞の機能を落としたあとで、徐々にでてくるが、このとき自己抗体が出現する。胸腺外分化T細胞や自己抗体のB-1細胞が関与している。
1.ストレスと生体反応
●『私たちはなぜ病気になるのでしょうか。それは強いストレスを受けるからです。多くの病気はストレスを受けるからです。多くの病気はストレスから始まっています。
それでは、具体的にどういうストレスで病気になっているかを挙げると、まず悩むことです。考えたり悩んだりすることは人間の特徴です。それから、人間は立って歩けるようになったので、やはり重力に逆らうストレスがあります。長時間立ち仕事をしたり夜更かししたりすると、重力の負担がかかって身体を壊します。あとはもともと身近なもの、温度や空気も病気の原因になります。あまりにも空気が少ないと、酸素不足で病気になります。そういうふうに、私たちの暮らしの身近なものの中にストレスはたくさんあるのです。』
●ストレスを受けると交感神経反射が必ずおこるということではなく、副交感神経反射が起こり絶望や脱力感により血圧が下がって失神することもある。
●怒りやすい人は交感神経反射が起きやすく、いつもおとなしく物静かな人は、副交感神経反射が起きやすい傾向がみられる。
●普通のストレスにはほとんどの場合、交感神経で反応する。自律神経だけでなく下垂体-副腎系が働くこともある。下垂体からは副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が分泌され、副腎からは糖質コルチコイドが分泌される。さらに白血球の反応(マクロファージの活性化や、サイトカインが出て戦う準備ができるなど)も起こる。
2.急性症状
●交感神経緊張の場合、頻脈・血圧上昇・血糖上昇、体温上昇がみられるが、急性症状が非常に強くなると血管収縮が強くなり、ついには体温が下がっていく。
3.急性症状が出る仕組み
●強いストレスを受けた人は体温が低下し血糖が上昇する。糖尿病は糖質の摂りすぎだけではなく、ストレスによる血糖上昇、特に交感神経のαアドレナリン刺激には強い血糖上昇作用があるため、長時間労働は糖尿病の原因になる。運動や食事制限だけでなく、交感神経緊張で血糖値が上昇するということにも注意する必要がある。
●糖質コルチコイドには体温低下と血糖上昇作用がある。
●ストレスによりマクロファージはサイトカインのTNFαを出す。TNFαはインスリンレセプターをブロックするため、血糖値は上昇する。
4.急性症状はストレスに立ち向かう反応
●野生の動物にとってのストレスは戦ったり、逃げたりすることである。血管が収縮し血流が悪くなるということは、血管が傷ついても出血を最小限に食い止めることができるということである。
●血糖が上昇するのは、解糖系を働かせるためである。解糖系で得たエネルギーは瞬発力と細胞分裂に使われる。なお、ミトコンドリアの内呼吸で得たエネルギーは持続的働きのために使われている。
5.交感神経と顆粒球の運動
●顆粒球は膜上にアドレナリン受容体を持ち。交感神経緊張で数が増加する。
●大量に顆粒球が増えると、歯周病、食道炎、びらん性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、クローン病、潰瘍性大腸炎、急性膵炎、慢性膵炎、痔、突発性難聴、メニエール病、女性の場合は子宮内膜症、卵管炎、卵巣嚢腫などの組織破壊の病気が起こる。これらは交感神経と顆粒球の連動で起こっている。
6.慢性症状
●ストレスが続いたときの慢性症状は、体温低下による代謝障害である。一時的には戦うための準備であるが、体温低下が続くと代謝障害、特にミトコンドリアでのエネルギー産生低下、タンパク合成の低下、疲れやすさなどやつれの症状が出てくる。
●ストレスの慢性状態では皮膚が弱くなり障害を受け、皮膚の病気が出現する。皮膚の病気は原因不明とされることが多いが、本当の原因は低温低下による代謝障害、エネルギー産生低下、タンパク合成の低下である。
7.ストレスの要因
●人間の特徴である考える力は、悩みというストレスの原因になる。また、同じく人間の特徴である二足歩行も重力のストレスを大きく受けることとなった。特に立ち仕事や働きすぎ、夜更かしは病気の原因になりやすい。
●人間に限らない一般的な要因の1番目は温度である。低温は凍傷や冷房病、高温は熱中症である。
●2番目は大気中の酸素である。薄くなると高山病、濃度が高いのは潜水病である。
●3番目は水である。少ないと脱水だが、脱水で病気になる人は多い。水の飲みすぎは体を冷やす。
8.ミトコンドリアへの負担
●ミトコンドリアの多い細胞は、脳、心臓、筋肉である。ミトコンドリアの機能低下は低体温と低酸素によって起こる。
9.ミトコンドリアとステロイドレセプター
●『ミトコンドリアの中にはステロイドホルモンに対するレセプターがあって、糖質コルチコイドが直接入っていってミトコンドリアの機能を抑制する。それにより、ステロイド治療をするとミトコンドリアの機能が抑制されてエネルギーを作ることができなくなり、消炎作用が現れる。長くステロイドを使っていると低体温、寿命短縮が起こる。』
10.ストレスと免疫抑制
●ストレスで胸腺萎縮やリンパ球のアポトーシスが起こり、T細胞とB細胞の分化や成熟抑制も起こる。一方、胸腺外分化細胞とB-1細胞は活性化し、自己抗体産生が出現する。
11.解糖系でエネルギーを作る細胞(ミトコンドリアの少ない細胞)
●ガン細胞は解糖系優位で、ミトコンドリアが少なく低酸素で分裂する。つまり、ガンは低体温になって低酸素に適応した病気と考えられる。
15.生体の治癒反応
●『私たちは風邪をひいても、やけどをしても、怪我をしても発熱します。心筋梗塞を起こした後も発熱し、潰瘍性大腸炎になっても、クローン病になっても、ガンになっても発熱します。結局、発熱は低体温と低酸素からの脱却で、代謝を亢進させて病気から治るための反応なのです。こういうことが分からないと、消炎鎮痛剤、ステロイド、あるいは免疫抑制剤を使って炎症を止めてしまいます。すると病気から逃れられなくなります。このとき、炎症に関与する物質がプロスタグランジン、アセチルコリン、ヒスタミン、セロトニン、ロイコトリエン、ブラジキニンである。』
16.副交感神経優位(楽をして生きる)でも病気
●『多くの人はストレスで糖質コルチコイド、TNFαなどが出て、たいていは交感神経緊張になり、血圧が上がったり血糖が上がったりするのですが、中には副交感神経側に偏る人もいます。副交感神経優位でも能力低下によって病気になります。能力低下には、リンパ球が増える過敏症、アレルギーがあります。ストレスにも過敏になり、ときには敗北します。私たちはスポーツをしたり身体を鍛えますが、能力を高めるにはやはり身体を使ったり頭を使わないといけません。こういう努力をほとんどしない人が副交感神経側に偏って能力低下で病気になります。ですから、無理しても病気、あまり楽をしても病気になるということです。』
第14章 免疫系(防御系)と自律神経の関係 part1
1.白血球の自律神経支配
●病気は人間の能力を超えるような過酷な環境に曝されたり、あるいは過酷な生き方をしたりした結果ではないか。
●過酷な生き方と免疫システムをつなぐのが自律神経であり、自律神経によって内部環境も免疫系もうまく動くことができる。しかし、過酷な生き方は自律神経のこうした働きを狂わせてしまう。
●交感神経が活発に働く日中、副交感神経が優位になる夜間、昼夜の交互のリズムがうまくいっている場合は、病気になることはないが、過酷な労働や家の中でゴロゴロした怠惰な生活は自律神経のバランスを乱し、健康を害していく。
●暑さや寒さ、重力も大きなストレスだが、不安やおびえ、恐怖などの深い悩みも大きなストレスとなって交感神経を緊張させる。
2.日内リズム、年内リズム
●顆粒球は朝方で60%程、昼にかけて5%位上昇し夜になると下がる。一方、リンパ球は朝方35%位あったのが、日中少しずつ少なくなって夜に上がるリズムがある。これを白血球の日内リズム、サーカディアンリズムという。
●リンパ球は夏に高く、冬に低くなる。春から夏、リンパ球が増える時期に花粉と出会い、リンパ球が少ない時期に風邪が流行しやすいのは私たちの免疫にも関係している。
4.消炎鎮痛剤
●消炎鎮痛剤(NSAIDs)はプロスタグランジンの産生阻害剤である。プロスタグランジンは血管拡張作用、発熱作用、痛み作用を有する副交感神経刺激物質である。プロスタグランジンを阻害することは交感神経を優位にさせる。
●『私たちは火傷したり怪我したりすると、血管拡張して腫れて、熱が出て、痛みます。これは身体が間違いを起こしているわけではなく、組織修復・代謝亢進のために血流増多しているのです。また代謝亢進させるには熱を上げる必要があるので、発熱します。痛み作用は同じ火傷を繰り返さないように危険を察知させます。痛みがなくなった人はストーブにやたら近づいて低温火傷したりしては大変です。だから痛みというものは悪者扱いばかりはできません。痛みがあるから危険な行為をさけられるのです。プロスタグランジンの産生阻害剤はこの3つの作用を止めて交感神経緊張という形にさせるのです。』
●『激しいスポーツをしている最中は無我夢中なので、交感神経優位で知覚が低下します。ところが、スポーツを終えて休んだり家に帰ってゆっくりすると、疲労した筋肉に血流を送って乳酸のような疲労物質を洗い流します。また多少起こった筋線維断裂を修復するために血流を増やすのです。ですから、とても激しい運動をした後、野良仕事が激しかった後、あるいは散歩が長かったときなど、筋疲労を起こした後や、休んだときに痛みが出るのです。これは大怪我や大火傷と同じように、痛みと腫れは筋疲労からの脱却反応と考えなければなりません。』
●『痛み止めを貼って熱心に冷やすと、このような作用も加わって、胃の障害や組織の障害になり、全身がやられるのでやつれます。ただ長く痛み止めの湿布薬を貼った人たちが急に止めると、それまで抑えられていた血流が一気に回復するので、2、3日はびっくりするくらい腰が痛くなったり膝が腫れたりして大変です。しかし、やはり最終的には痛み止めを脱却しないと腰痛や膝痛などから回復できません。』
5.生物学的二進法
●『私がなぜ、このような自律神経や白血球の自律神経支配を研究したかというと、学生の時にこのような考え方の基本を出していた斉藤章先生(元東北大学医学部講師)がいらしたからです。その理論とは生物学的二進法です。斉藤先生は戦前・戦中のまだ抗生物質がなかった時代に感染症内科をしていた先生でした。グラム陽性球菌に感染したときは、ほとんどが顆粒球になる一方、グラム陰性の桿菌に感染したときは、多少顆粒球が残っても、ほとんどがリンパ球であるという法則を見つけたのです。このように結核菌の感染、サルモネラとかリケッチア、ウィルス、異種タンパクというような刺激で、顆粒球とリンパ球の血液中の分布が変わることを斉藤先生は見つけました。』
●『斉藤先生の発見はこれだけではありません。顆粒球が増えるような状態の患者は頻脈と胃液の分泌低下、つまり交感神経刺激反応が起こり、逆にリンパ球が増えるような状態になった人は徐脈、胃液分泌上昇などが起こり、副交感神経優位状態であることを見つけたのです。ですから私たちは感染症にかかったときや、化膿が強くなったときなど、交感神経優位状態ではすごく脈が速くなって、熱はスパイク状に出ることがほとんどです。
ところが副交感神経優位状態のときは徐脈がきて、けだるくて熱は持続する熱になります。ちょうど風邪を引いたときにずっと高熱が続くような状態です。かつては、この熱を稽留熱や持続熱と、交感神経優位の熱を間歇熱と呼んでいました。このような状態が起こるのを見て、斉藤先生は生物学的二進法といったのです。こうした講義を私は東北大学で受けて、ずっと心に留めていたのです。教授なって自分の研究テーマを好きに決められるようになってから、アイソトープと蛍光抗体を使って、顆粒球にはアドレナリンレセプターがあって交感神経刺激で活性化すること、リンパ球にはアセチルコリンレセプターが発現していて副交感神経優位になると増殖することを研究しました。』
発見!
『長く痛み止めの湿布薬を貼った人たちが急に止めると、それまで抑えられていた血流が一気に回復するので、2、3日はびっくりするくらい腰が痛くなったり膝が腫れたりして大変です。』
今まで、70歳代の患者様さまお二人から施術後、痛みが非常に強くなったと教えて頂いたことがありました。特にお一人は何年も毎日湿布(消炎鎮痛剤)を貼っているというお話でした。
当時、この強い痛みの原因は習慣的に貼っている湿布によるものではないかと考え、いろいろ調べたのですが、結局その時はそのような情報に出会うことはできませんでした。
今回、安保先生の『免疫学講義』の14章に上記の記述を見つけ、「やっぱり!!」と思いました。つい、うれしくなってしまったのでアップしました。
免疫学講義3
第9章 サイトカインの働きと受容体
1.サイトカインの歴史
●T細胞を増殖させる因子をTCGF(IL-2)、B細胞の増殖因子をBCGF(IL-4)と呼ばれる、サイトカインである。サイトカインはホルモンより高分子タンパクである。寿命が短くすぐ壊れてしまう。T細胞の特定のものを増やすのではなく、全体を増やし特異性がない。
●T細胞の増殖因子として見つかったサイトカインは、NK細胞やB細胞を増やしたり、B細胞の分化を助けるなどいくつかの重なる機能を持っている。そして、このような性質をもつ因子をホルモンと対比させてサイトカインと命名した。
●サイトカインはリンパ球やマクロファージが出す。また、脳神経が使っている因子にも共通しているものがあるだけでなく、身体のいたるところで広く使われていることが分かった。
2.サイトカイン
①IL-1
●IL-1はマクロファージが出すリンパ球活性因子であり、炎症性サイトカイン(内因性発熱因子)である。インフルエンザに罹ると38℃、39℃の発熱があるが、これはリンパ球が働きやすい至適温度にするためにIL-1が発熱させているのである。
②IL-2(TCGF)
●T細胞やNK細胞の最大の増殖因子である。
③IL-3
●骨髄の幹細胞の増殖因子で、分化の最初の引き金をひく。T細胞、肥満細胞、マクロファージという各細胞から出て骨髄の分化を立ち上げ、初期分化を促す。
④IL-4、IL-5、IL-6
●これらのインターロイキンはB細胞の分化にかかわる。
⑤IL-7
●骨髄や胸腺のストローマ細胞(支持細胞)である。リンパ球分化を促す。
⑥IL-8
●顆粒球の走化性[微生物や白血球などの細胞が、栄養分や誘引物質のある方向へ移動したり、逆に嫌気物質から遠ざかる性質]を刺激する物質である。ケモカインとも呼ばれるがケモカインの分子量は他のインターロイキンと比べて小さい。
⑦IL-9
●IL-2やIL-4と類似している。T細胞やB細胞を増殖させる。
⑧IL-10
●抑制因子、リンパ球の増殖を弱め、過剰な免疫反応を止める。
⑨IL-12、IL-15、IL-18
●NK細胞やCTLの活性を刺激する。
⑩IFN(interferon:インターフェロン)
●複数の作用を有する。ウィルス増殖阻止因子、MHCの発現を促す、抗原提示能を上昇させる。
⑪TGFβ(transforming growth factor)、(tumor necrosis factor)
●TGFβは機能が多岐にわたり複雑である。免疫抑制の作用がある。
●TNFαはアポトーシスを誘導して、不要になったものやガン細胞を殺している。
⑫Fas ligand
●Fasについてアポトーシスを誘導する。
●NK細胞、extrathymicT細胞、CTLが相手を殺すときに使用される。
第10章 自然免疫
1.外界に接する場所の抵抗性
●自然免疫とは獲得免疫ではないものである。
●丈夫な皮膚(ケラチン)と汗は重要な抵抗力である。腸上皮の細胞は加水分解酵素やタンパク分解酵素を持っており、補体を作る力も持っている。
●皮膚や腸管は常在細菌がおり、常在細菌は病原細菌が入ってきたときに攻撃する。
●胃の壁細胞はpH1の塩酸を出しており、ほとんどの細菌はここで死滅する。
●消化管の絨毛や繊毛は異物を運動により排出する。
2.細胞の抵抗性
●感染が起こると発熱するが、一つは内因性の発熱因子によるものである。IL-1、IL-6、TNFα、プロスタグランジンなどである。一方、細菌自体が熱を上げる場合があるが、その代表がLPSで、外因性の発熱因子である。
3.補体
●抗体が進化する前からの腸上皮の抵抗因子で、複合タンパクからなり細菌などを溶解する。
4.補体の働き
●細菌や異種細胞の溶解である。膜に穴を開けて壊す。
●白血球の貪食能を上げるオプソニン化や、白血球自身を活性化させる働きを持っている。
●免疫複合体(抗原と抗体がくっついたもの)が消えるときに補体は使われる。
6.活性化の経路
●活性化の経路は3つある。古典経路、代替経路、レクチン経路である。
7.古典経路
●抗原抗体反応から始まる経路。古典経路で補体活性化するのは、IgM、IgG1、IgG3に限られている。
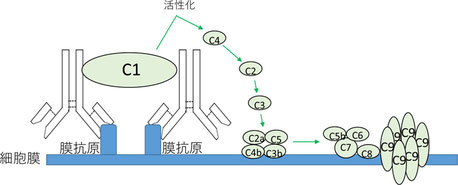
画像出展:「東邦大学 抗体と補体」
『古典経路は体内に侵入してきた細菌や細胞の膜抗原に抗体(IgGやIgM)が結合して免疫複合体を形成すると、補体第1成分(C1)がこの抗体と結合して、C1が活性化されます。活性化したC1は補体C4を活性化し、その後、補体(C2~C8)を次々に活性化します。その結果、最終的に膜上に補体第9成分(C9)の複合体を細胞壁(膜)に埋め込み、細菌や細胞に穴をあけます。』
8.代替経路
●抗体を使わない経路。細菌刺激で直接C3という補体を活性化する。
9.レクチン経路
●マメ科の植物タンパク質のレクチンは直接C3を活性化する。
10.補体の産生部位
●腸上皮細胞、肝細胞(腸上皮細胞から進化)で作られる。
●補体の1~9の一部はマクロファージで作られる。
●腸は多細胞生物が進化したもの、マクロファージは単細胞時代の生き残り、身体に危険なものが来たとき、新旧の細胞が共同作業で相手の細胞や細菌を溶解しようとすることが補体の働きである。
11.補体レセプター
●補体のレセプターは、構造の違いで1から4まであり。CR1-CR4といわれている。
●補体レセプターは色々な白血球にあるが、腎臓の糸球体基底膜にもある。免疫複合体(抗原と抗体がくっついたもの)と補体のコンプレックスができ、糸球体基底膜に沈着すると腎障害が起こる。
12.細胞膜上にある補体活性抑制因子
●補体が無秩序に動き出すと、白血球が勝手に活性化したり、腎の基底膜について危険なため、身体には補体を活性化させない補体活性抑制因子も存在している。これは細胞膜上にあり、自己の細胞が溶解されないように守るためのものである。
14.補体遺伝子の欠損
●化膿性感染症を繰り返したり、免疫複合体が血液中で増加するといった独特の異常が出てきたり、白血球の貪食能が低下したりといったことが出てくる。
第11章 膠原病 part1
1.自己の認識について
●『自己免疫疾患は多くの専門家がいうように「原因不明の難病」ではありません。リウマチやSLEなど自己免疫疾患は、数年前まではなぜ起こるか分からなかったのですが、リンパ球の研究などを通じて、自己免疫疾患が起こる理由がはっきり分かりました。』
3.自己免疫疾患の誘因
①MAG
●『それでは、どうしてリウマチやSLE、ベーチェット病、シェーグレン症候群、橋本氏病といった自己免疫疾患になるのでしょう。まず1つには、組織破壊が最初にあって、自己抗原が出てくるからです。その自己抗原とは対応するクローンがnegative selectionをすでに受けたような自己抗原ではなく、めったに身体の中に現れないような自己抗原です。これを隔離抗原といいます。私たちの自己の組織でも、いつもリンパ球の前にさらされている抗原ばかりではありません。普段リンパ球が届かないような場所にいるものもあります。
隔離した抗原とは、例えば、MAG(myelin-associated glycoprotein)です。有髄の神経にはミエリン鞘があります。ミエリン鞘を合成するタンパク質の中に、MAGがあるのですが、これは、普段鞘の中にあって抗原性を出してはいません。ところが神経組織が壊れると、こういうものが隔離された状態から出てくるのです。
こうしてできた自己抗体が引き起こす疾患が、多発性硬化症(multiple sclerosis)で、目が見えなくなったり末梢神経の麻痺が起こるような自己疾患を引き起こします。
こういう病気を引き起こす1番多い原因は、夜更かしです。夜更かししてパソコンを長く見る人は大変ストレスが強く、視神経のMAGに障害が起こったときなどに、壊れるのです。それが自己抗原になってリンパ球が攻撃を始めます。多発性硬化症の患者さんは30歳前後の女性が多いのですが、みんな夜更かししてパソコンの画面を眺めるというような独特のストレスを受けているのです。そして神経の組織が壊れたとき、自己免疫疾患になるのです。』

”隔離抗原”を詳しく知りたいと思い、検索したところ出てきたものです。
『私たちの免疫系は、生後まもなく構築されるわけですが、その過程で各器官が「自己」であることを免疫系にアピールすることで、寛容が誘導され、その器官は「異物」ではなく自らの免疫で攻撃しなくなることはご存知のとおりです。ところが、生体のなかには、バリアによって免疫系から認識されにくい器官があり、隔離抗原(sequestered antigen)と呼ばれています。』
②甲状腺細胞のミクロゾーム
●『私たちの甲状腺は甲状腺ホルモンを作っていますが、それを作りタンパク合成する場所にはミクロゾームを壊されると、甲状腺に対する自己抗体が出てきて、甲状腺が壊されます。これが橋本氏病です。
橋本氏病は甲状腺がやられるので、甲状腺ホルモン(サイロキシン)が低下していきます。甲状腺ホルモンは活力のホルモンなので、元気がなくなり、疲れやすくなってやる気が起こらないという独特の症状を出すのです。それでは、なぜ甲状腺のミクロゾームがやられるかというと、多くは長時間労働が原因です。橋本氏病は女性に多いのですが、橋本氏病になった女性のほとんどは、職場の仕事を家にまで持ち込んで夜更かしを何年も続けるなど、すごく無理をしています。
すると、甲状腺が甲状腺ホルモンを作り続け、疲弊したとき血流障害が起こり細胞が壊れ、普段隔離されていたミクロゾームがリンパ球にさらされて、クローンを刺激するのです。
現在、私の本以外の教科書を読むとみな、自己免疫疾患の原因は不明になっていますが、本当ははっきりしているのです。患者さんに無理しなかったかどうか、すぐ聞き出せます。あまりにも過酷な生き方をすると私たちの組織は壊れて、隔離された抗原が出てくるのです。』
③胃壁細胞
●『私たちの胃壁には、造血と関連する因子を出す胃壁細胞があります。胃壁細胞は心配事が多いと、血流障害や顆粒球の働きによって壊れます。私たちは心配事を抱えると、びらん性の胃炎など胃の調子が悪くなりますが、これは胃の粘膜の血流障害で胃壁が壊れるからです。そういうときに、普段上皮の下に隠れている胃壁細胞がリンパ球にさらされて、抗原になります。これがいわゆる悪性貧血(pernicious anemia)の原因になるのです。』
④核、ヒストン
●『隔離された抗原が出るのは細胞を構成する成分からです。なかでも多いのはやはり核やその成分からです。核にはDNAやDNAを折りたたんでいるヒストンタンパクなどがあります。
SLE(systemic lupus erythematosus:全身性エリテマトーデス[全身性紅斑性狼瘡])とは、抗核抗体を中心とした自己抗体ができて起こる疾患です。抗核抗体は、核が抗原となります。核の中でもDNAで、折りたたまれたらせん形が離れたシングルストランド(single strand)のDNAにも抗体ができることもありますし、からまったダブルストランド(double strand)のDNAが抗原になることもあります。
SLEが1番多いのは、色白の人が紫外線を浴びたときです。なぜ狼(lupus)のような紅斑と呼ばれるかというと、まるで口が広がったように、紫外線が1番当たる所がバタフライ様に紅くなるからです。SLEは白人に多いです。色が黒いとメラニン色素で紫外線をブロックできますが、色が白いと直接紫外線の作用で細胞や核が壊れるのです。そして隔離抗原がリンパ球にさらされます。
SLEは紫外線以外でも、風邪をこじらせると起こります。ウィルスも細胞を壊します。あとはやはり夜更かしが原因です。夜遅くまで起きていることは大変なストレスなので、細胞が壊れます。特に徹夜でアルバイトをすると、細胞が壊れて病気になりやすいのです。』
⑤目の水晶体、ブドウ膜
●『目の組織というのは、普段リンパ球にさらされていません。水晶体には血管が入っていかないからです。ブドウ膜もリンパ球にさらされないような形で抗原を保っています。どういう形で隔離抗原が出てくるかというと、ほとんどが外傷です。ボールがぶつかったりけがをしたりして目が大出血し、組織が損傷を起こすときに抗原がさらされます。やられた目が治っても、片方の目も見えなくなってくるというような炎症を起こすのです。片方の目をやられて両方の目がやられるということで、「交感性眼炎」といいます。』
⑥精子
●『そのほかで普段血流にさらされない場所というのは精子です。精子が壊れて血中に出ると隔離抗原が出ます。1番有名なのはおたふくかぜです。子供のときおたふくかぜにかかると、外分泌腺が腫れるだけで治りますが、大人がかかってこじらせると精巣炎が起こります。すると隔離抗原が精子から出て、無精子症になるのです。それからたまに外傷でも起こります。硬式野球をやっていて球を精巣に当てて何日も腫れ上がるような外傷を受けたとき、隔離抗原が精子から解放されて、残った精子に対して攻撃するので、無精子症になるのです。
このように、普段私たちの免疫系が働けないような自己認識がリンパ球に出合うようなことが起こると、自己免疫疾患になるのです。このときかかわるリンパ球はみな、胸腺外分化T細胞かB-1細胞です。』
⑦modified self
●『隔離された抗原で自己免疫疾患が発症すること以外で、もう1つ覚えておかなければならないものがmodified selfです。いわゆる自分の自己抗原が少し変性して抗原性を獲得するという形です。紫外線によってタンパク変性したり、薬物がキャリアタンパクに付着して変性します。いろいろな風邪薬で一気に自己免疫疾患が発症することがあります。
特にスティーブンス・ジョンソン症候群といって、風邪薬を飲んで全身の粘膜が腫れて失明したり、SLE様の症状を出したり、タンパク尿を出したりするという症状を発症します。
例えば私たちのタンパクでもっとも多いアルブミンの場合です。普段アルブミンはnegative selectionで反応するクローンはなくなっていますが、薬物が付いてmodifyされると修飾自己抗原になるのです。
薬物の中でもっとも多いのは風邪薬・消炎鎮痛剤(アスピリン)ですが、ペニシリンなどの抗生物質もタンパク質を変性させます。これはいろいろな血球の膜に付くこともあるので、血球が抗原になる疾患です。血球はもちろんnegative selectionされているのですが、薬物が付くために、血球が自己抗原になることもあります。
血球の中で修飾自己抗体がもっとも多く付着しやすいのが血小板です。そもそも血小板というのは、血管が出血した所に付着するための物質なので、いろいろなものに吸着する力をもっています。そうして発症する病気が、血小板減少性紫斑病です。血小板に対する自己抗体ができて、どんどん血小板が減っていきます。するとちょっとした打撲でも止血できなくなって腫れ上がり、そのあとが紫色になるのです。これは薬を飲んでもなりますが、長時間労働などでもなります。
私は将棋が好きなのでプロの棋士の名前を知っていますが、今から30年くらい前に山田道美九段は、大山名人に負けても負けても何度も挑戦権を獲得してがんばっていました。山田九段は打倒大山のために睡眠時間を削って将棋の勉強をして、1日何十局も過去の棋譜を調べたりして並べて、血小板減少性紫斑病にかかり34歳で死んでしまいました。ですから、あまり無理をするといけません。
自己免疫疾患は原因不明といわれていますが、このような考え方をすると謎が解けます。原因が分かれば原因を取り除けば治ります。原因不明としているため、対症療法の薬を飲んでもっと身体を痛めつけて、治らないということになっているのです。
それから、顆粒球が抗原になるのは顆粒球減少症です。細菌処理に大切な細胞である顆粒球がどんどん減ってしまいます。赤血球が抗原になる溶血性貧血は、薬物が原因であることが多いです。風邪をひいて風邪薬を飲んで、自己免疫性の溶血性貧血になることもあります。このように血球成分のうち血小板が変性して自己抗原になり、顆粒球の膜成分が変性して自己抗原になります。これらは過労か薬物が原因です。』
4.自己免疫疾患の分類
●SLEは全身性の自己免疫疾患であり、全身の血管炎である。
●血管内皮細胞はマクロファージが血球に分化して、その分化した血球を流すために自ら管になった。従って、血管内皮細胞はマクロファージと同じように貪食能があり、白血球の炎症とともに血管炎が起こる。
●SLEは核が抗原になるため、対象は全身の細胞になる。線維芽細胞や血管内皮細胞が攻撃されて戦い、炎症を起こす。
●ネフローゼは血管内皮細胞に負担がかかるような生き方をして、血管に隙間ができて、漏れることが原因である。
●関節リウマチ、橋本氏病、、無精子症は臓器特異的自己免疫疾患だが、それぞれ関節、甲状腺、精巣がやられる。
●複合型自己免疫疾患であるGoodpasture syndromeは腎臓と肺の基底膜が障害される。腎臓はエラから進化したため腎臓と肺の細胞はよく似ており、場所は離れているが腎臓と肺で自己免疫疾患になる。
5.自己障害のメカニズム
①自己抗体
●自己組織の障害のメカニズム
-B-1細胞が出す自己抗体が攻撃するパターンは、抗DNA抗体・抗ミトコンドリア抗体が直接組織や分子を攻撃して組織を破壊したり、機能をブロックする。
②補体の活性化
●抗原抗体反応ができて、順にFc部分が活性化すると、補体のC1から順に活性化が始まる。
※Fc領域:(fragment crystallizable region:フラグメント結晶化可能領域)は抗体の尾部にあたる領域で、Fc受容体と呼ばれる細胞表面の受容体や補体系のタンパク質と相互作用する。

画像出展:「抗体:ニュートリー(株)」
『抗体の基本構造は、2本の長いH鎖と2本の短いL鎖からなるY字型の構造である.そのなかで抗原の結合部位となるFabと、免疫細胞などと結合するFcに分けられる。抗体の実体は免疫グロブリンという糖タンパク質であり、Fab部位のアミノ酸配列の違いによって5つのクラス(IgM、IgD、IgG、IgE、IgA)がある。各クラスの抗体は、体内の異なった部位で多様な機能を発揮している。一方でFc部位は免疫細胞に発現するFc受容体と結合する。』
③マクロファージの活性化
●白血球の基本はマクロファージである。そして、マクロファージが活性化すると炎症を起こす。まず、炎症性サイトカインで発熱・腫れ・痛みが出てくる。IL-1・IL-6・TNFα・IFNγには、発熱作用・血管拡張作用・痛み作用がある。
●マクロファージが活性化しすぎると自分の血球を飲み込んでしまう(血球貪食症)。
④リンパ球の直接攻撃
●リンパ球(NK、CTL、胸腺外分化T細胞など)は、色々な細胞を直接攻撃して、肉芽腫形成することもある。
⑤免疫複合体(immune complex)
●腎臓の糸球体の基底膜に免疫複合体が沈着するのが糸球体腎炎である。また、RA(関節リウマチ)は腫れ、発熱、痛みがあり動かないでいると免疫複合体が沈着して関節が動かなくなる。このように免疫複合体は様々な病気に関与している。
⑥血管内皮細胞の炎症
●血管内皮細胞の炎症でも主体になるのはマクロファージである。
6.SLE
●SLEは20歳代の女性に多く、最初は風邪のような症状が出る。女性に多い理由の一つに過敏であることがあげられる。過敏かどうかはその人のリンパ球の数で決まる。特に妊娠適齢期の女性は1番リンパ球が多いため過敏になりやすい。
ケースも多く特に注意が必要な刺激が紫外線である。次に多いのがウィルス感染である。これはリンパ球が多いとEBウィルスやパラミクソウィルス、風邪ウィルスなどに感染によって血管炎をおこす。それ以外では夜更かしなどのストレス危険である。以上のように、SLEは過敏な人(リンパ球が多い人)が、紫外線、ウィルス、夜更かしなどのストレスを受けて発症するのである。SLEは全身にある抗原と反応するので、関節が腫れるRAや、唾液が出ないシェーグレン、糸球体腎炎などの自己免疫疾患が全身に出てくることが多いのである。
免疫学講義2
第2章 免疫学総論 part2
1.免疫で使われる分子群
●抗体はアミノ酸100個の塊(ドメイン構造と呼ばれる)が4個、5個つながった重鎖と、100個くらいのものが2個つながった軽鎖からできている。また、T細胞レセプターも、アミノ酸100個くらいの塊2個が対になっている。
●抗原と抗体とが1対1に対応していることから「鍵と鍵穴の関係」といわれている。
●免疫に関係する分子は、アミノ酸100個くらいのタンパク質である祖先遺伝子が染色体の中で、多様化したり、合体を繰り返して進化してきた。
●抗体はIg(immunoglobulin)となり、その仲間は免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリー(immunoglobulin gene superfamily)と呼ばれる。これは接着分子の基本構造から進化した。
●ヘルパーT細胞は、T細胞やB細胞の分化や活性化を助ける。傷害性T細胞は異物細胞を直接攻撃(傷害)するということに由来している。
●多細胞生物である私たちの身体は接着分子によってバラバラになることがない。タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)により接着分子は壊れるが膜は壊れない。
●各細胞はナトリウムを外に出して膜をプラスに荷電してエネルギーを作っている。この荷電により、細胞同士が反発し合う。赤血球が互いに反発し合うのは荷電によるエネルギーのおかげである。
●生活習慣の乱れから血液ドロドロになるのは、ナトリウムを出して膜電位を維持できなくなるためである。
●細胞と細胞は接着分子でくっついているが、そこに異物が入り込むと、フリーの白血球であるリンパ球がそれを攻撃して死滅させる。このように、接着分子と接着分子の間に入った異物を異常細胞と見なし、攻撃して速やかに排除して、再び確かな細胞だけで生き延びようとするのが免疫の始まりといえる。
●免疫は異物を認識するために始まったのではなく、細胞が自分同士を認識する中でその間に入り込んだ異物の違和感からその危険なものを攻撃する。つまり、免疫とは異物への攻撃であるため、ウィルスでもガン細胞でも攻撃し死滅させる。これが免疫の基本的なメカニズムである。
●外来抗原を認識するようになるのは、免疫の進化の後期からのことである。
●免疫の始まりは、一つは異物を食べて処理するマクロファージと顆粒球の流れであり、もう一つは接着分子を利用して侵入してきた異物に対して攻撃するリンパ球の流れである。免疫の原点は異常自己を見つけることから始まっている。
2.リンパ球の進化
●免疫細胞は進化しても、古い細胞がなくなることがない。現在のそれぞれの比率はT細胞(70%)、B細胞(15%)、胸腺外分化T細胞(10%)、NK細胞(5%)である。
●加齢ともに胸腺の退縮と骨髄の脂肪化のため、T細胞、B細胞は減少し、一方、腸管でつくられる胸腺外分化T細胞と肝臓でつくられるNK細胞が増える。
●リンパ球は生物が上陸する前から進化してきた。胸腺外分化T細胞やNK細胞は腸管粘膜でつくられた。胸腺の進化は上陸後であり、新しいT細胞やB細胞は上陸後からであるが、上陸により、植物のホコリや苔の死骸などあらたな異物と遭遇することで進化したと考えられる。なお、現在でも腸管や肝臓などには古いリンパ球であふれている。これらは自己応答性でウィルス感染自己細胞やガン化した自己細胞を異常自己として攻撃するシステムである。
4.マクロファージの働き
●いろいろな異物を食べる機能(貪食能)。
●健康でマクロファージの働きが強いと、免疫反応を誘発せずに貪食能によって全部処理をするため、風邪症状も出さない。
●リンパ球や顆粒球が上乗せされて自分が少数派になってからは、指令を出し顆粒球(細菌の侵入)やリンパ球(ウィルスの侵入)を誘導する。
●顆粒球やリンパ球誘導後、組織の修復を行う。マクロファージが破片も食べるので元の正常の組織にもどる。
●マクロファージは栄養が過剰になると栄養処理を行う。栄養処理とは脂肪細胞に引き渡したり、あまりに摂取する栄養が多いときは、動脈壁にはりついたりして、そのまま死滅する泡沫細胞になる。ただし、泡沫細胞の血管壁への沈着は動脈硬化を促進する。一方、飢餓状態ではマクロファージは自分を食べて生き延びようとする。
●マクロファージのあらゆる働きで、生き延びる戦略をとれるのはマクロファージが単細胞生物時代の生き残りだからである。
●過食は処理するマクロファージにも大きな負担となり、炎症と同じように炎症性物質である炎症性サイトカインを出す。ガンの末期や病気の末期に栄養を入れると患者さんが苦しんでしまうのは、過食に伴う炎症性サイトカインが原因である。
●風邪で高熱を出した時に食欲が落ちるのは、これはマクロファージが免疫系に専念するための身体の反応である。栄養処理にばかりマクロファージを使ったら病気の治りは遅くなる。
●『私たち人間は、死ぬとき食べるのを止めて死ぬと安らかに死ねます。昔から聖人といわれた多くの人は、死期を悟ったら数日食を絶って死んでいるのです。しかし今の医療はやたらと点滴したり、中心静脈栄養を入れたり、胃瘻を作ったりして管をつけています。ですから、すごく死の苦しみを味わって死んでいるのです。やはり私たちも病気になって食欲を失ったら、マクロファージが免疫系に専念するための栄養処理からの解放について考えないといけません。』
5.白血球の分布と自律神経
●末梢血では顆粒球が60%、リンパ球が35%、マクロファージが5%である。ただし、この比率には個人差がある。さらに、自律神経系の働きと連動している。顆粒球は膜状にアドレナリンレセプターがあり、交感神経が緊張すると分裂して数を増やす。リンパ球の方はアセチルコリンレセプターがあって、副交感神経が優位になると数が増える。
●交感神経緊張が続き、リンパ球が少なくなると免疫力が下がってくる。すると、常在するウィルスが暴れ出すが、帯状疱疹や単純ヘルペスなどは代表的なものである。
第3章 免疫担当細胞
1.マクロファージ
●自分と会う主要組織適合抗原(MHC:major histocompatibility complex)を探すには10万人必要とされている。
●樹状細胞はマクロファージが進化した細胞で、貪食能はなく、MHCが強く、Tリンパ球に抗原提示する働きが非常に強いという特徴を有する。細胞膜から樹状突起が出て、リンパ球を抱え込んで抗原提示する能力を増強する。
●虫歯ができて顎下リンパ節が腫れたり、水虫が化膿して鼠径リンパ節が腫れたりするときは、樹状細胞がリンパ球に抗原提示した反応が始まっている。
4.TCR(T cell receptor)の構造
●多くの免疫系は38度、39度の温度が反応のピークであり、病気になったときに熱が出るのは免疫反応を高めて早く病気を治そうとする反応である。しかしながら、体温が41度を超えると細胞内のミトコンドリアが活性酸素を出し、突然死の恐れが出てくる。その場合は速やかに身体を冷やして熱を下げなければならない。
●お風呂の限界は45度である。50度を超えるとタンパク凝固が始まる。
5.B細胞の種類
●B細胞は小さい細胞でほとんどが核である。通常は細胞には細胞質の中にミトコンドリアや粗面小胞体、ゴルジ体、細胞小器官が必要だが、B細胞は核だけで細胞質もほとんどない。
●T細胞もB細胞も、普段はほとんど休止しているため、1960年に入る前は「何も仕事をしていない珍しい細胞である」と考えられていた。いずれも抗原の刺激があると分裂を始める。分裂すると小型から中型、大型のリンパ球に変わる。
●B細胞の場合は、活性化リンパ球になると粗面小胞体でタンパク合成が起こり、抗体を外に分泌する。抗体を産生するようになったB細胞は形質細胞、あるいは抗体産生細胞、活性化B細胞と呼ばれる。
6.抗体の種類
●B細胞が産生する抗体には、IgM、IgG、IgA、IgEと、働きがはっきりしていないIgDという細胞がある。
●一次感染で最初に出てくるのは、IgMである。二次刺激でもIgMが多少でるが、IgGが出てくる。IgGは血清中で量が最大である。
●IgAは消化液や分泌液の中、いわゆる腸や涙、唾液に出てくる。
●IgEはアレルギーとして有名である。アトピー性皮膚炎、気管支喘息、あるいは寄生虫感染で増える。
●血清中、IgGに次いで多いのがIgA、次にIgMである。IgEは健康な人からはほとんど検出されず、アレルギーを持っている場合に検出される。
第4章 B細胞の分化と成熟
1.分化、成熟(differentiation, maturation)
●B細胞を作るのは骨髄の幹細胞である。
●ヘルパーT細胞がB細胞を分化させるのに、IL-4、IL-5、IL-6が必要である。ILはインターロイキンの省略で白血球の間を取り持つ高分子タンパクという意味である。ILはいずれも、B細胞の分化・分裂を促す。さらに、IL-4はIgEへ、IL-5はIgAへ、IL-6はIgGへの分化をそれぞれ促す。
①多発性骨髄腫
●多発性骨髄腫の場合は、形質細胞のレベルでガン化した病気である。
②B細胞型の悪性リンパ腫(malignant lymphoma)
●悪性リンパ腫はB細胞のレベルでガン化する。
●リンパ球血症もあるが極めて少ないので、リンパ球、特にB系統の腫瘍化のほとんどは多発性骨髄腫と悪性リンパ腫である。
3.抗体の働き
①抗原の凝集
●B細胞の働きの一つは外来抗原の無害化である。
●自己抗体は身体に生じた異常自己を速やかに排除する機能がある。
●B細胞は、外来抗原向け抗体を作るものと自己抗体を産生するものに区別できる。
②補体とともに膜の溶解
●抗体のFc(fragment C)とC領域(constant region:定常域)に補体が結合し、細菌の膜や他人の赤血球膜、移植片細胞膜を溶解する。補体はC1からC9まであって、C1から順に活性化が始まる。
③ADCC(antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity)
●ADCC活性によって、CTL(cytotoxic Tcell:傷害性T細胞)と、NK細胞は、リンパ球でガン細胞を死滅させる。
●ADCC状態ができると、CTLからperforinというキラー分子が放出されてガン細胞の膜が傷害され壊される。
●NK細胞の攻撃、CTLの攻撃、この2つに抗体が加わって攻撃するという3つの方法でガン細胞を攻撃する。
●免疫を高めた患者がガンを自然退縮させた人は数百人規模で確認できている。
第5章 T細胞の種類 part1
1.T細胞の抗原レセプター(TCR)
●B細胞は抗体(Ig)を使って抗原認識をするが、T細胞はTCR(T cell receptor)を使うが、TCRは抗体と違って、単独で抗原を認識してはいない。
3.胸腺内分化T細胞と胸腺外分化T細胞
●胸腺内分化T細胞は胸腺で分化して、その後末梢へいく。末梢とはリンパ節、脾臓(白脾髄)、末梢血である。
●胸腺外分化T細胞は、腸管、肝臓、外分泌腺の周り、子宮内膜などにある。
第6章 T細胞の種類 part2
3.Tc細胞の働き
●分裂する前のリンパ球は小リンパ球である。トランスフォーメーションを起こしたリンパ球は細胞内小器官であるミトコンドリアやゴルジ体もできて、大リンパ球になる。
●大リンパ球は活性化リンパ球ともいわれ、CTL(細胞傷害性T細胞)になる。CTLはperforinキラー分子を作りだす。相手がガン細胞や移植した細胞に対しては膜に穴をあけて死滅させる。
●CTLはFas ligandという分子を作り、Fasという分子に働いて細胞内にアポトーシス(自分で死滅する)シグナルを入れる。
●CTLはガン細胞、ウィルス感染細胞、移植片細胞などの標的を、perforinやFas ligandを使って壊す。
4.Th細胞の働き T-B cell interaction
●ヘルパーT細胞は抗原刺激で小リンパ球が大型リンパ球になって、タンパク質を作る。ここで作られるのが、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10のサイトカインである。
●サイトカインは分子量が多い高分子だが、寿命は短く、血液の中で壊されたり、すぐに希釈されたりする。
5.リンパ球の抗原提示
●抗原提示を行っているのはマクロファージと樹状細胞である。このような抗原提示細胞がないとリンパ球の分裂は起こらない。
7.ガン化
●T細胞は抗原が来たときに反応して、刺激(MHC[主要組織適合抗原]+抗原)がなくなると自然に分裂は収まるが、ある時点で腫瘍化することがある。B細胞は悪性リンパ腫や多発性骨髄腫になることがあるように、T細胞も色々なステージで腫瘍化する。
●T細胞の腫瘍化には急性リンパ性白血病があるが、これはPreT細胞などの早い段階で腫瘍化する。一方、慢性リンパ性白血病はある程度成熟したT、B細胞の腫瘍化である。
●自己免疫疾患は胸腺外分化T細胞の異常な活性化で起こるので、肝臓、外分泌腺で起こる。自己免疫疾患には、ベーチェット病、シェーグレン症候群、SLE、関節リウマチなどだが、唯一胸腺と関係するのは重症筋無力症である。
●『不思議ですね。胸腺のリンパ球が増えるのに自己免疫疾患になります。私たちの筋肉は収縮するとき、神経末端から出るアセチルコリンを使って収縮します。それで、まぶたがあけられない、筋肉がなかなか収縮できないというMG(重症筋無力症)が起こるのです。こういう現象を知るには、普通のT細胞の分化だけではなくて、胸腺のmedulla(髄質)に八ッサル小体のような外胚葉の上皮によって育てられる古いリンパ球がある、ということを分からないと謎が解けなかったのです。これは私の研究室で見つけた現象です。』
●老化、ガン、マラリアといった、いろいろな自己抗体ができる世界が原因不明になっている。これは胸腺の分化の失敗ではなく、生物が上陸する前の古い免疫系のほとんどがストレスによって活性化している世界なのである。
●SLEでも、関節リウマチでも重症筋無力症でも、自己免疫疾患の患者さんから話を伺うと、発症前に非常に強いストレスを受けていたことがわかる。特に一番多いストレスは夜更かしである。
第7章 主要組織適合抗原 part1
4.分布
●MHC(主要組織適合抗原)のClassⅠは、全身のほとんどの細胞で発現している。
●MHCが発現していないのは赤血球である。血液型さえ合わせれば輸血できるのはMHCを発現していないためである。発現していないのは、赤血球が脱核してDNA→RNA、RNA→タンパク合成の機能をやめてしまったためである。したがって、幼若で骨髄でまだ核のある未熟な時期にはMHCは発現している。
●赤血球以外でMHCがないのは、胎児胎盤である。また、脳内のニューロンはMHC陰性である。脳はほとんど抗原提示能がないため脳では炎症がとても起こりにくい。ただし、脳神経の間に混じっているグリア細胞はMHC陽性のため、長い目で見れば拒絶されてしまう。
●MHC陽性には差がある。1番強いのは樹状細胞、他はマクロファージ、皮膚である。腎細胞はそれほど高くなく、さらに低いのは肝細胞である。腎移植、肝移植が可能なのはこのためである。
第8章 主要組織適合抗原 part2
3.Polymorphic MHCとmonomorphic MHC
●1990年代後半、個人間で多様化していないMHCが見つかった。それがmonomorphic MHCである。
●ヒトの場合、個人間で多様化のあるMHCがHLA-A、B、C、D、多様化のないMHCがHLA-E、F、Gである。
※HLA:『HLA(Human Leukocyte Antigen=ヒト白血球抗原)は1954年、白血球の血液型として発見され、頭文字をとってこう呼ばれてきました。しかし、発見から半世紀以上を経て、HLAは白血球だけにあるのではなく、ほぼすべての細胞と体液に分布していて、組織適合性抗原(ヒトの免疫に関わる重要な分子)として働いていることが明らかになりました。』
●monomorphic MHCは、非常に特殊な場所に発現している。HLA-Eは腸上皮細胞、HLA-Fは肝細胞、HLA-Gは子宮内膜と胎盤の絨毛細胞である。腸にあるリンパ球も、腸から発生した肝臓に以前からあるリンパ球も、NK細胞や胸腺外分化T細胞などの古いリンパ球である。子宮や胎盤の間にも古いリンパ球がある。
●子宮の胎盤がなぜ拒絶されないかという疑問は、monomorphic MHCの理解によりこの謎の本質に迫れた。
●『子宮内膜の面と胎盤の接点は、HLA-Gをともに発現します。HLA-Gは個人間で多様化していないので、結局、父親からの遺伝子も母親からの遺伝子も同じタンパクを作ってアミノ酸配列が違わないのです。そしてHLA-A、B、C、D、はマイナスです。こういう仕組みがわかってきました。ここではNK細胞と胸腺外分化T細胞が働いています。NK細胞と胸腺外分化T細胞は自己応答性です。これらは膜上にアドレナリン受容体を持っていて、交感神経刺激(ストレスなど)で活性化されます。ですから、母親が忙しく仕事しすぎたり、悲しい出来事があってつらいめにあったり、あるいは、心臓や腎臓に持病があって交感神経がだんだんと刺激されたときなどに、流産が起こるのです。新しい免疫系は働きませんが、古い免疫系の活性化で流産が起こります。古い免疫系は自己応答性なので、子宮内膜と胎盤を攻撃するのです。すると胎盤が母親の子宮の内膜についていられなくなります。早期の流産も、後期の流産もこういうメカニズムで起こっています。』
4.HLAのタイプと疾患感受性
●HLAのタイプはバラバラだが、日本人、ヨーロッパ人というように集団や民族によって、多少特徴はある。
●『自己免疫疾患の原因は、ほとんどがストレスです。ストレスが直接組織を壊すか、あるいはストレスがかかって免疫が下がり、常在ウィルスが暴れて、感染症が起こります。風邪をひいて発症するか、その発症のときに特定のHLAが特定の自己抗体を作りやすくするのでしょう。』
●『特定のHLAはストレス、あるいはウィルスがはびこる組織が壊れるときに、特定のタイプの自己抗体が入りやすいのです。これらの病気が起こると、肺と腎臓と同時に、そのほかの臓器の基底膜にも自己抗体ができます。』
5.MHC以外の拒絶タンパク
●MHCのマッチングはヒトでは約10万人対1人のレベルである。
●MHCが100%マッチングさせても拒絶される現象がある。MHC以外のタンパク質で、拒絶の原因として考えられるのは、Mls(minor lymphocyte stimulatory)である。Mlsはレトロウィルスという、エイズやヒト成人T細胞白血病ウィルスなどのタンパク質である。これらが身体に住み着いてそこからできるタンパク質がいろいろな組織に入って、MHCのClassⅡに乗って拒絶タンパク質になっている。
6.その他
●認識する抗原は進化とともに変わる。免疫系の進化はMHCの進化とリンパ球の進化が並行して起こる。進化・上乗せされ、最終的にT細胞、B細胞になった。
●免疫が変遷を重ねて、進化していっても古いリンパ球も古いMHCも残っていて、あるステージがくると働くのである。そのステージとは、基本的には老化現象などと関係している。90歳を超えてくるとT細胞、B細胞はかなり減り、NKや胸腺外分化T細胞、自己抗体を産生するB細胞、血清中では自己抗体が非常に増える。
●進化で獲得した免疫は、若い年代、20代~30代でピークを迎え、その後はまた古い免疫が優勢になる。これが免疫の中で系統発生と個体発生進化が加齢で現れるということである。
免疫学講義1
安保徹先生の著書は何冊か拝読させて頂いていましたが、今回の『免疫学講義』はB5判で237ぺージという、詳細かつ高度な内容の本でした。
この本を読みたいと思ったのは、『コロナワクチン失敗の本質』という宮沢孝幸先生の著書に書かれていた、「液性免疫(抗体)に偏って考えるのはいかがなものか。免疫は自然免疫、細胞性免疫、液性免疫の総合力で考えるべきではないか」というご指摘が印象に残ったためです[ブログ:“コロナワクチンの疑問”]。
目次が大変長いということ、またブログ自身も5つに分けているということから、最初に「あとがき」をご紹介させて頂きます。
私が最も重要だと思ったことは、「ストレスと顆粒球、およびストレスとリンパ球の相関関係を理解する」ということでした。
『現代医療は、多くの病気を原因不明として対症療法を行う流れが拡大しています。しかし、多くの病気はストレスを受けて免疫抑制状態になって発症しています。原因は不明ではないのです。ストレスで生じる「低体温、低酸素、高血糖」は短いスパンではエネルギー生成のうちの「解糖系」を刺激して瞬発力を得て危機を乗り越えるための力になっています。しかし、長期間このような状態が続くと、エネルギー生成のうちの「ミトコンドリア系」を抑制してエネルギー不足に陥ります。これがストレスで起こる慢性病の発症のメカニズムです。そして、いずれガンを引き起こす原因につながっていきます。
ストレスをもっとも早く感知するのは私たちの免疫系です。末梢血のリンパ球比率やリンパ球総数は敏感に私たちのストレスに反応しています。この反応には自律神経系と副腎皮質ホルモン系が関与しています。臨床では血液検査を行い、いつでもリンパ球比率を知れる状況にあるのですが、ストレスとリンパ球の減少の相関をほとんど教育の場で学ぶことがないので、血液検査のデータが活用されていないのが現状です。末梢血のリンパ球比率は35-41%が正常値で、ここから減少しても増加しても病気になってしまいます。
顆粒球過剰(リンパ球減少)は組織破壊の病気と結びつきます。逆に、リンパ球過剰はアレルギー疾患や過敏症の病気と結びついていきます。本講義録で学んだ知識があれば、多くの病気の発症メカニズムを知ることができます。対症療法を延々と続ける必要もなくなるのです。
消炎鎮痛剤の害やそのほかの薬剤の副作用なども、この本で学べたと思います。患者に良かれと思って続けている薬剤の投与の中にも多くの危険が潜んでいるのです。特に、自己免疫疾患の治療においては、本書の知識が役立つでしょう。そして、私たち生命体が持つ偉大な自然治癒力を引き出すことのできる新しい医学や医療が進展していくことでしょう。』
ブログは目次の黒字部分について触れています。
目次
まえがき
第1章 免疫学総論 part1
1.免疫学の歴史
2.身体の防御システム
3.白血球の進化
4.リンパ球の性質
5.リンパ球の産生と分布
6.Tリンパ球とBリンパ球
7.主要組織適合抗原
8.免疫が関与する疾患
①感染症:ウィルス感染、一部細菌感染
②アレルギー疾患:アトピー性皮膚炎、花粉症、アナフィラキシー
③移植の拒絶
④自己免疫疾患(膠原病)
⑤加齢現象
⑥妊娠―つわり、流産
⑦ガン免疫
⑧先天性免疫不全症
第2章 免疫学総論 part2
1.免疫で使われる分子群
2.リンパ球の進化
3.胸腺の進化
4.マクロファージの働き
5.白血球の分布と自律神経
第3章 免疫担当細胞
1.マクロファージ
2.リンパ球サブセット
3.T細胞の種類
4.TCR(T cell receptor)の構造
5.B細胞の種類
6.抗体の種類
第4章 B細胞の分化と成熟
1.分化、成熟(differentiation, maturation)
①多発性骨髄腫
②B細胞型の悪性リンパ腫(malignant lymphoma)
2.B細胞の抗原認識受容体(Ig)の遺伝子
3.抗体の働き
①抗原の凝集
②補体とともに膜の溶解
③ADCC(antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity)
第5章 T細胞の種類 part1
1.T細胞の抗原レセプター(TCR)
2.TCRのシグナルを伝える分子
-CD3 complex
3.胸腺内分化T細胞と胸腺外分化T細胞
4.CD4⁺T細胞の認識
5.CD8⁺T細胞の認識
6.Th0、Th1、Th2細胞
7.T細胞の胸腺内分化
8.胸腺外の分化
第6章 T細胞の種類 part2
1.TCR遺伝子の再構成(rearrangement of TCR genes)
2.クローンの拡大
3.Tc細胞の働き
4.Th細胞の働き T-B cell interaction
5.リンパ球の抗原提示
6.胸腺外分子T細胞が働くとき
7.ガン化
第7章 主要組織適合抗原 part1
1.移植の拒絶抗原
2.抗原提示分子
3.構造
4.分布
5.ヒトとマウスMHC
6.MHCの遺伝子
7.TCRの認識
第8章 主要組織適合抗原 part2
1.リンパ球の抗原認識と分裂
2.抗原とMHCの結合
3.Polymorphic MHCとmonomorphic MHC
4.HLAのタイプと疾患感受性
5.MHC以外の拒絶タンパク
6.その他
第9章 サイトカインの働きと受容体
1.サイトカインの歴史
2.サイトカイン
①IL-1
②IL-2(TCGF)
③IL-3
④IL-4、IL-5、IL-6
⑤IL-7
⑥IL-8
⑦IL-9
⑧IL-10
⑨IL-12、IL-15、IL-18
⑩IFN(interferon:インターフェロン)
⑪TGFβ(transforming growth factor)、TNFα(tumor necrosis factor)
⑫Fas ligand
3.サイトカイン受容体
①γcを共有するサイトカイン受容体
②βcを共有するサイトカイン受容体
③gp130(glyoprotein130)を共有するサイトカイン受容体
4.ケモカイン(chemokine)と接着分子
5.細菌毒素LPS(lipopoly sacharide)
第10章 自然免疫
1.外界に接する場所の抵抗性
2.細胞の抵抗性
3.補体
4.補体の働き
5.補体のタンパク群
6.活性化の経路
7.古典経路
8.代替経路
9.レクチン経路
10.補体の産生部位
11.補体レセプター
12.細胞膜上にある補体活性抑制因子
13.遺伝子
14.補体遺伝子の欠損
第11章 膠原病 part1
1.自己の認識について
2.自己認識のステップ
3.自己免疫疾患の誘因
①MAG
②甲状腺細胞のミクロゾーム
③胃壁細胞
④核、ヒストン
⑤目の水晶体、ブドウ膜
⑥精子
⑦modified self
4.自己免疫疾患の分類
5.自己障害のメカニズム
①自己抗体
②補体の活性化
③マクロファージの活性化
④リンパ球の直接攻撃
⑤免疫複合体(immune complex)
⑥血管内皮細胞の炎症
6.SLE
第12章 膠原病 part2
1.進化した免疫系の抑制
2.中枢神経系の自己免疫疾患
3.内分泌器腺の自己免疫疾患
4.消化管・肝の自己免疫疾患
5.腎の自己免疫疾患
6.心臓の自己免疫疾患
7.眼の自己免疫疾患
8.皮膚の自己免疫疾患
9.Chronic GVH病
10.老化
11.動物モデルと自己免疫疾患
第13章 神経・内分泌・免疫
1.ストレスと生体反応
2.急性症状
3.急性症状が出る仕組み
4.急性症状はストレスに立ち向かう反応
5.交感神経と顆粒球の運動
6.慢性症状
7.ストレスの要因
8.ミトコンドリアへの負担
9.ミトコンドリアとステロイドレセプター
10.ストレスと免疫抑制
11.解糖系でエネルギーを作る細胞(ミトコンドリアの少ない細胞)
12.受精とは何か
13.ヒトの一生
14.調和の時代にストレスを受け続ける
15.生体の治癒反応
16.副交感神経優位(楽をして生きる)でも病気
第14章 免疫系(防御系)と自律神経の関係 part1
1.白血球の自律神経支配
2.日内リズム、年内リズム
3.新生児の顆粒球増多
4.消炎鎮痛剤
5.生物学的二進法
第15章 免疫系(防御系)と自律神経の関係 part2
1.アレルギー疾患
①アナフィラキシーショック
②アトピー性皮膚炎、気管支喘息、通年性鼻アレルギー
③食物アレルギー
④花粉症、蕁麻疹
⑤化学物質過敏症
⑥寄生虫感染
⑦寒冷アレルギー、薬物アレルギー、紫外線アレルギー、金属アレルギー
⑧乳児アトピー
2.顆粒球増多と組織破壊の病気
①突発性難聴[内耳](idiopathic sudden sensorineural, sudden deafness)
②メニエール病[三半規管](Meniere disease)
③歯周病(periodontitis)
④食道炎(esophagitis)
⑤びらん性胃炎(erosive gastritis)→胃潰瘍(gastric ulcer)
⑥十二指腸潰瘍(duodenal ulcer)
⑦クローン病(Crohn’s disease)
⑧潰瘍性大腸炎(ulcerous colitis)
⑨痔疾(hemorrhoid)
⑩子宮内膜症(endometriosis)
⑪不妊症(infertilitas)
[子宮内膜症(endometriosis)、卵管炎(salpingitis)、卵巣嚢腫(ovarian cyst)]
⑫膵炎[急性・慢性](pancreatitis[acute・chronic])
⑬腎炎・腎盂炎(nephritis・pyelitis)
⑭膀胱炎(cystitis)
⑮骨髄炎(myelitis)
⑯間質性肺炎(interstitial pneumonia)
第16章 移植免疫
1.移植(transplantation)と拒絶(rejection)
2.MHC
3.移植
4.純系
5.拒絶の速さ
6.純系と拒絶
7.移植のしやすさ―MHCの発現量
8.HLAタイピング
9.骨髄移植(bone marrow transplantation)
10.GVH病(GVHD:graft-versus-host disease)
11.反応するリンパ球
12.新生児免疫寛容(neonatal tolerance)
13.拒絶に関与するほかの白血球
14.non MHCによる拒絶
15.免疫抑制剤(immunosuppressant)
16.Hybrid resistance
17.輸血によって生着率上昇
第17章 免疫不全症
1.先天性免疫不全症(primary immunodeficiency)
①wide type(野生型)の血液像(FACSを用いたCD3、IL-2Rβ二重染色)
②胸腺無形成症(thymic aplasia)
③重症複合免疫不全症(scid:severe combined immunodeficiency)
2.重症複合免疫不全症(scid:severe combined immunodeficiency)
①X-scid(伴性劣性遺伝) X連鎖重症複合免疫不全症
②常染色体劣性遺伝型-scid
③scidマウス
④RAG-1/RAG-2ノックアウトマウス
3.胸腺無形成症(thymic aplasia)
4.無γグロブリン血症(agammagloblinemia:伴性劣性遺伝)
①Bruton X-kinked agammagloblinemia(XLA:X連鎖(ブルトン型) 無γグロブリン血症)
②IgA欠損症(selective IgA deficiency)
③X連鎖高IgM症候群(hyper IgM syndrome)
④ウイスコット-アルドリッチ症候群(WAS:Wiskott-Aldrich syndrome)
⑤毛細血管拡張性運動失調性(AT:ataxia telangiectasia)
⑥ディ・ジョルジ症候群(Di George症候群)
5.T細胞B細胞以外の異常症
①慢性肉芽腫(CGD:chronic granulomatous disease)
②Chediak-東症候群(CHS)
③beige mice(ベージュマウス)
6.後天的免疫不全症(acquired immunodeficiency)
7.免疫抑制剤(immunosuppressive drug)
8.抗ガン剤(anticancer drug)
9.ステロイドホルモン(SH:steroid hormone)
10.NSAIDs(nonsteroidal anti-inflamatory drugs)
11.常在菌による感染症
12.乳児一過性低ガンマグロブリン血症(transient hypogammaglobulinemia)
第18章 腫瘍免疫学
1.免疫系の二層構造
2.ガン細胞を排除している証拠
3.腫瘍抗原
4.エフェクター(攻撃)リンパ球
5.腫瘍ができるための条件
6.ストレス反応の意義
7.ガン細胞の特徴
8.ガン患者の免疫状態
9.キラー分子群
10.解糖系とミトコンドリア系
11.アポトーシスとその抑制
12.ガンの免疫療法
13.治療(自然退縮)の条件
14.そのほかの免疫療法について
15.結論
あとがき
まえがき
第1章 免疫学総論 part1
1.免疫学の歴史
●免疫の歴史はウィルスや細菌の概念ができる前、予防接種の考え方ができたのは、ペストが治まった後の18世紀後半で、イギリスで天然痘が大流行した時代である。
●1900年に近い時代に、ジェンナーからパスツール、コッホへと免疫の歴史は展開されていった。また、この頃から顕微鏡が使われるようになって、遊走細胞(マクロファージ)が体内に入ってきた細菌を貪食して、無毒化するという観察や考え方が出てきた。
●光学顕微鏡で見える細菌、光学顕微鏡でも見えないウィルスという2つの微生物による感染症があることが分かった。
●抗体に相当するものの存在の発見は、コッホの見つけた抗毒素がきっかけとなった。
2.身体の防御システム
●身体の防御システムとは抗体やマクロファージのことであるが、広くみれば白血球とつながっている。
●身体の特殊化した細胞には異物から守るちからはないので、白血球が防御細胞として身体を守っている。
●単細胞時代のアメーバの性質を残したマクロファージと白血球はつながっている。
3.白血球の進化
●脊椎動物になったあたりから白血球の進化が起こった。マクロファージから進化した顆粒球(顆粒がたくさんあるから顆粒球)である。
●顆粒球は細菌より小さいウィルスのような異物には対応できない。一方、同じくマクロファージから進化したリンパ球によって貪食される。
4.リンパ球の性質
●免疫記憶は身体に侵入してきた微生物(病原菌)の量や増殖に掛かっている。ワクチンのような微量では強い免疫はつくられない。
●抗体は分子量が10,000Da(ダルトン)以上の大きさであれば認識できる。※Daとは炭素12原子の質量の1/12相当の質量の単位
●分子量が小さい場合、身体のタンパク質に吸着することによって抗原になる場合がある。
●抗体と反応するものを抗原といい、ほとんどタンパク質である。また、ウィルスはDNA、RNAを有するが周りはタンパク質である。
●タンパク質はアミノ酸から作られるが糖と結びつくことも多く、糖タンパク質と呼ばれる。この糖タンパク質に対しても抗体は反応する。
●リンパ球は抗体をつくる一方、リンパ球は分裂するクローンによって拡大する。このリンパ球の分裂にかかる時間が潜伏期間である。
●潜伏期間の次に、抗原と抗体の免疫反応が始まり、発熱が起こる。
●発熱が起こる理由は、ウィルスと戦うための抗体を産生するには、代謝を亢進させる必要があるからである。
●WHOの統計に風邪をひいて治るまでに平均2.5日とされているが、風邪薬を飲むと4日に延びるとされているのは、薬が代謝の活性を落とすからである。
●発熱に関与する因子は、プロスタグランジンやインターロイキン1(IL-1)などがある。
●マクロファージや顆粒球は異物を食べる反応なので、潜伏期間は不要であり、傷口が化膿したり細菌が入ったりしたらすぐに反応が始まる。
5.リンパ球の産生と分布
●抗体を作るリンパ球は、中枢リンパ組織(胸腺と骨髄)で作られ末梢リンパ組織に分布している。
●胸腺はthymusなので、胸腺で作られるリンパ球はTリンパ球と呼ばれている。Tリンパ球、Bリンパ球は末梢血、リンパ節、脾臓に移動して働く。
●血液中のリンパ球は35%であり、60%は顆粒球、5%はマクロファージである。
●巡回していて何か抗原が入ってきたとき、リンパ球は血管から遊走して外に出て働く、あるいは抗体を作る。
●リンパ節は顎下リンパ節、鼠径リンパ節などがあり、T細胞とB細胞が存在している。脾臓では白脾髄にリンパ球、赤脾髄に赤血球が存在している。前者は血液中に入った抗原を処理し、後者は古くなった赤血球を壊す。
●リンパ節のリンパ球は抗原が組織に入ってきた時、リンパ液でとらえリンパ管で抗原を集めて、リンパ節に持ってきて戦う。
6.Tリンパ球とBリンパ球
●T細胞(Tリンパ球、Tcell)は、細胞自ら抗原と反応し、T細胞レセプターで抗原を捕える。このように細胞が自ら反応する仕組みなので細胞性免疫という。
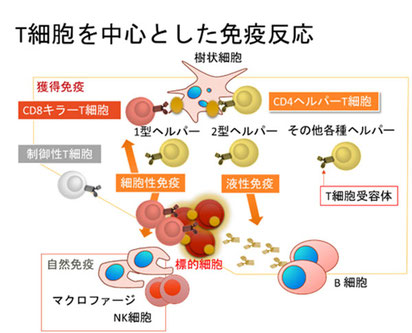
画像出展:「日本がん免疫学会」
『からだを守る免疫細胞はさまざまな方法で異物や病原微生物、ウイルス感染細胞やがん細胞などの異常細胞と戦います。
ここでは、その戦い方の一つである細胞免疫について解説します。細胞性免疫とは、ウイルス感染細胞やがん細胞などの異常細胞を、抗体などを介さずに免疫細胞そのものが直接攻撃するタイプの免疫反応です。細胞性免疫の中心をになう免疫細胞はT細胞ですが、活躍するのはCD4ヘルパーT細胞とCD 8キラーT細胞です。
CD4ヘルパーT細胞は免疫の司令官とも言われ、様々な免疫細胞に、がん細胞やウイルス感染細胞に対する「攻撃始め」の指示を出します。CD4ヘルパーT細胞は主に2つの系統の戦い方を指示します。CD8キラーT細胞を始めナチュラルキラー(NK)細胞やマクロファージと呼ばれる異常細胞の直接攻撃を得意とする細胞を活性化し、細胞性免疫という戦い方を指揮するのが1型CD4ヘルパーT細胞であり、B細胞を刺激して抗体を産生させる液性免疫という戦い方を指揮するのが2型CD4ヘルパーT細胞です。主にこの2つの戦法を上手く組み合わせて効率よく異常細胞を排除することで、私達のからだは病原体の侵入やがんの発生から守られているのです。この免疫の司令官がいかに重要かということは、CD4ヘルパーT細胞が失われる病態で顕著に示されます。例えばHIV(エイズウイルス)はCD4ヘルパーT細胞に感染し、破壊することで全身の免疫不全を引き起こします。その結果、通常は致死的にならないような弱毒微生物のまん延を許し、患者を死に至らしめます。』
7.主要組織適合抗原
●ヒトの身体は同じようなタンパク質でできており、アミノ酸配列も同じである。しかしながら、移植によって拒絶反応が起きる。これは主要組織適合抗原(MHC)という物質によるものであり、この主要組織適合抗原は個人間でアミノ酸配列が異なる。また、主要組織適合抗原はT細胞の認識抗原である。
●抗体はB細胞から分泌されて、直接抗体の立体構造で抗原を認識するが、T細胞の場合は主要組織適合抗原と抗体がくっついた分子をT細胞レセプターがまとめて認識する。
●主要組織適合抗原は移植の拒絶抗原というより、組織細胞に入った抗原を捕まえるためのタンパク質と考えるのが正しい。
●ペストや天然痘が猛威をふるっても生き延びる人が必ずいるのは、リンパ球が認識する能力は個人ごとにアミノ酸配列が異なるため多様性がでるからである。抗原の認識の違いによってT細胞の働きが個人間で全く異なる。ある人は免疫が強く出る、ある人はほどほど、ある人は弱く出る。
●免疫は強いことがプラスになる場合がある一方、強すぎてアレルギーなどに苦しむ原因にもなる。
●主要組織適合抗原の多様化は、特に哺乳動物で進化した。恐竜は5000万年前絶滅したが、主に夜行性の食虫動物として生存していた哺乳類は小さくて弱いが、免疫システムに関しては爬虫類より進化し、多様性が高かった。
●移植に関しては邪魔者といえる、主要組織適合抗原は生き延びるための戦略であった。
8.免疫が関与する疾患
①感染症:ウィルス感染、一部細菌感染
●細菌類は主に顆粒球が攻撃して治癒させる。
●ウィルスと一部の細菌感染では、免疫が働く。
②アレルギー疾患:アトピー性皮膚炎、花粉症、アナフィラキシー
●アナフィラキシーは薬物アレルギーにも見られるが、薬物(通常分子量200~400くらいの小さなものが多い)はアルブミンなどについて全体で抗原となってアナフィラキシーショックを引き起こす。
③移植の拒絶
●移植における拒絶は、主要組織適合抗原が個人間で多様化し、タンパク質が異なるために起こる。
④自己免疫疾患(膠原病)
●膠原病と言われているのは、コラーゲンなどの膠原線維が炎症に関わっているためである。
⑤加齢現象
●加齢減少も免疫と関係している。
●自己免疫疾患を起こす抗体を自己抗体といい、自分の核やDNA、RNA、ミトコンドリアなどに抗体ができるものである。高齢者では健康な人でも自己抗体が病気の人と同じくらいのレベルである。何故、高齢者が自己免疫疾患にならないかというと、高齢者では老化した異常細胞やガン化した異常細胞を排除することに自己抗体がプラスに働いているからである。つまり、ほどよく自己抗体が出た人が、病気にならず長生きするということである。
⑥妊娠―つわり、流産
●父親の遺伝子も受け継ぐ胎児は母親にとって異物になる。流産、つわりは免疫現象が関わっており、リンパ球や自己抗体が自らを攻撃する。しかし、拒絶に至らないのも免疫、古いタイプの免疫システムが関与しているからである。
⑦ガン免疫
●ガンにおいても免疫が働く。免疫抑制剤や免疫抑制作用のあるステロイドを長期間していると、発ガン率が高くなることでも免疫によるガン抑制効果はある。
⑧先天性免疫不全症
●先天性の免疫不全症の子供には、悪性腫瘍を合併することが多い。
オキシトシン〈安らぎと結びつき〉5
第五部 安らぎと結びつきを探求するさまざまな方法
第十三章 マッサージ
●マッサージ効果に関する研究の多くは解釈が難しい。何らかの意味で実験とは言い難い研究をすべてふるい落としたとしても、マッサージが人間の健康に効果があることを示す研究は十分に残る。
●マッサージには多くの種類がある。タクティール・マッサージ(スウェーデンで理論化された、認知症の症状緩和などを目的とするマッサージ)のように、皮膚に触るだけの施術法がある一方で、筋肉をしっかりもみほぐすマッサージや、手でそっと圧して筋肉の緊張をほぐすマッサージがある。これらの療法は、それぞれ異なる感覚神経を活性化するので、もたらされる結果もさまざまである。
●血圧低下、コルチゾール減少、不安軽減、学習効率上昇―こういった効果はどれも、動物実験でオキシトシン注射により得られる効果と似ている。オキシトシンの効果は繰り返し注射すると、強くなり、また長続きする。それと同じことがマッサージを繰り返し受けた場合にも当てはまると思われる。

『スウェーデン発祥のタクティールケアは、1960年未熟児ケアとして看護師らによって始まりました。マッサージではないため、押したり揉んだりはしません。
優しく包み込むように触れるだけです。誰もが簡単に行うことができ、活躍の場は様々。多くの人がストレスを抱えるこの時代に
必要なコミュニケーションツールです。』
[マッサージとスキンシップ]
●正しいマッサージを受けた赤ちゃんや、哺乳量が同じでもマッサージを受けなかった赤ちゃんより、体重が早く増える。また、コルチゾールの血中濃度も低下する。これはストレスが減っている証拠でもある。
※ご参考:ブログ“医療マッサージ研究1”
以前、小児障害児へのマッサージをやっていたときに書いたブログです。今更ですが、「やはり、マッサージによるものだったのだ」と思いました。
●興味深いのは、マッサージの効果が最も顕著だったのは、乱暴な言動で集団をかき乱すタイプの男子だった。
[医療施設でのマッサージ]
●病院では体に痛みのある患者に対し、施術しやすい、特殊なマッサージが試行されている。「タクティール・マッサージ」と呼ばれる。このマッサージは、他のマッサージ療法ほど圧を加えない。主に皮膚へタッチすることで効果を生むのだと考えられる。知名度は高くないが説得力のある、いくつかの研究論文によれば、タクティール・マッサージを受けている高齢者の患者は安眠しやすく、痛みを訴えることが少なく、服薬が少ない。混乱することが少なく、意識がはっきりしていて、社交的であることを示すデータもある。介護者との関係もよくなる。
●興味深いのは、マッサージの効果が最も顕著だったのは、乱暴な言動で集団をかき乱すタイプの男子だった。
[医療施設でのマッサージ]
●病院では体に痛みのある患者に対し、施術しやすい、特殊なマッサージが試行されている。「タクティール・マッサージ」と呼ばれる。このマッサージは、他のマッサージ療法ほど圧を加えない。主に皮膚へタッチすることで効果を生むのだと考えられる。知名度は高くないが説得力のある、いくつかの研究論文によれば、タクティール・マッサージを受けている高齢者の患者は安眠しやすく、痛みを訴えることが少なく、服薬が少ない。混乱することが少なく、意識がはっきりしていて、社交的であることを示すデータもある。介護者との関係もよくなる。
●『いくつかの研究によれば、マッサージを受けている人だけでなく、施術している人の体内でもオキシトシンが放出されているという。マッサージセラピストには、ストレスホルモン値低下や血圧低下など、オキシトシン値が高いことによる典型的な効果が見られる。こういう人たちは全般に、心身が健康だ。それはこの職業の本質にかかわっていることかもしれない。』
[抗ストレス]
マッサージの効果
1.大人がマッサージを受けると血圧、心拍数、ストレスホルモン値が低下する。これらの効果は健康を増進する。
2.子どもがマッサージを受けると、落ち着きが増し、対人的に成熟し、攻撃性が減る。体の不調を訴えることも少なくなる。
3.優しく包みこむようなタッチを受けると、早産児の体重増加のペースが速くなる。
第十四章 食べること―内側からのマッサージ
●ものを食べて満腹になるというのも、体の〈安らぎと結びつき〉システムを活性化させる方法のひとつである。体の内側は食べることによって刺激される。これは体の外側がタッチによって刺激されるのと同じである。
●消化器系と皮膚にはいくつか類似点がある。消化器系、皮膚、神経は細胞系譜をさかのぼると、いずれも外胚葉から作られる。両者は感覚神経からの情報を記録・伝達する方法が似ており、皮膚の内側への延長と言ってもいいくらである。
●消化器系は消化だけでなく、内分泌器官のひとつであり、消化や代謝、体内の細胞内貯蔵庫への栄養分の貯蔵を調節するいくつかのホルモンを分泌している。そして、これらのホルモンは脳に影響を及ぼす。
●消化器系にも多くの交感神経と副交感神経が存在しているが、最大の働きをするのは副交感性の迷走神経である。この神経は90%が感覚性の機能を持ち、体の内外から受けた信号を中枢神経系へ伝える。
[胃袋と脳の間]
●消化機能は自律的なものであるため、腸は意識からの指令がなくても働く。
●消化管ホルモンのコレシストキニン(CCK)は小腸上部から分泌されるが、特に高脂肪の食べ物がこの場所に到達すると特に出やすい。コレシストキニンは迷走神経を活性化し、さらに迷走神経はオキシトシンの放出を促す。従って、食事が高脂肪であればあるほど、食後の満腹感を感じやすく、眠くなりやすい。
第十六章 医薬品による安らぎと結びつき
[不安、抑うつなどの治療薬]
●セロトニン値の低さは、抑うつやある種の不安と関連している。SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)を不安症状やうつ症状のない人にSSRIを処方すると、より社交的になる可能性があるが、これはセロトニン値が上がるとオキシトシンの放出が起こるためである。
●うつ病患者のオキシトシン値は異常に低いという事実がある。
[オキシトシンを医薬品として使う際の障壁]
●オキシトシンは分娩の誘発や子宮出血の薬として使われている。
●オキシトシンは薬理学的な問題が多くある。一つは、オキシトシンは消化管の中でたちまち分解されてしまうため、経口投与では効果は得られない。明確な効果は注射である。
●オキシトシンは血中でもすぐに分解されてしまう。
●オキシトシンは脳に達することも困難である。これは脳の毛細血管の内壁の細胞が隙間なく並んだ、血液脳関門を形成しているからである。
●『オキシトシンを医薬品として有効活用する方法を開発するには、オキシトシンの分子をもっと扱いやすくしなければならない。そのための科学技術は既に存在するのだが、商業ベースではまだ採算がとれない。オキシトシンの個々の効果(ストレス軽減、疼痛緩和、鎮痛作用、治癒、成長の促進など)をもたらす、オキシトシンに似た薬を開発することも考えられる。オキシトシンのそれぞれの効果は、オキシトシン分子のそれぞれ異なる部位に結びついているらしいからだ。』
[ストレス症状の治療]
●『オキシトシン値は自然な方法でも上げることができるとはいえ、オキシトシンのプラスの効果をもっと利用するためには、オキシトシン分子が直接投与できる形になる日が来るのを待たなければならない。
今、それよりも重要なことは、自分の体内でオキシトシンを放出させるマッサージなどの技術を身につければ、オキシトシン値を十分に上げることができ、飲み薬や注射に頼らなくてもよいぐらいに、オキシトシンの健康増進効果を享受できるのではないかということだ。私たちは体の中にすばらしい癒し物質を持っている。それを利用するさまざまな方法を学びさえすればよいのだ。』
第十七章 体を動かすこととじっとしていること
●『私の考えでは、〈安らぎと結びつき〉システムを活性化する方法はたくさんあり、エクササイズはそのひとつにすぎない。このシステムは、皮膚や乳腺、消化管内壁、筋肉などからの刺激が神経を介して脳に伝わって作動する。どんな方法でこのシステムを作動させるかは、年齢層によって異なる傾向がある。若いうちはオキシトシンを出すのにエクササイズを使うことが多いが、年齢が上がるにつれて鍼やマッサージを選ぶようになる。私たちは絶えず周期環境の情報に合わせて、体内の生理学的状態を調節している。健康的な均衡を得るためには、「動」の刺激も「静」の刺激も必要だ。』
[すわったままのジョギング]
●ヨガの期限は紀元前2500年、インダス文明の頃からのようであるが、ヨガは長寿と健康増進のための技法を発達させてきた。ヨガの動きは、鼠径部や体の前面(腹側)といった身体の部位を刺激し、触覚刺激の受容体を経由して、迷走神経系を活性化する。
●瞑想の生理学的効果については、すでに詳しく研究されている。瞑想によって、酸素消費量の減少、脈拍と呼吸数の減少、筋肉の弛緩が生じる。発汗も減少するので、微電流を流した場合の皮膚の伝導率が下がる。このような効果はすべて、交感神経系の活動が低下したためと考えられる。また、脳波(EEG)を見ると、脳の活動パターンが変化することがわかる。特に顕著な変化はα波の持続時間が長くなることである。
●定期的に瞑想を行うと、高血圧症の人は血圧が下がり、心拍数の正常化が促進される。ストレスホルモン値が下がり、痛みの閾値が上がる。
●瞑想療法によって、アルコールやタバコなどの乱用癖を弱めたり、なくしたりすることができるという指摘もある。
第十八章 私たちの内なるエコロジー
●『現代のストレスに満ちたライフスタイルのせいで、身体的にも精神的にも極度の疲労に陥ったり、健康を害したりする人があまりにも多い。しかも、若い年齢でそうなる人が増えている。どの年齢層においても、病気の多くはつきつめればストレスが原因だ。私たちも私たちの住む社会も、変化を切実に求めている―そして、その変化は思いのほか身近にある。私たちは自分の中に、変化の鍵をもっている。そう、その鍵は、目立ちすぎる〈闘争か逃走か〉システムの陰に隠れていた、もうひとつの生物学的システムの働きを通して、〈安らぎと結びつき〉の状態を呼び起こす潜在的能力の中にある。』
訳者解説
●『〈安らぎと結びつき〉の鍵であるオキシトシンは、ホルモン(血流に乗って体内の器官へ運ばれ、そこで受容体と結合して作用する)としての働きと、神経伝達物質(神経細胞の軸索を通って神経端末へ運ばれ、シナプスを形成している別の神経細胞の表面にある受容体に結合する)としての働きのふたつを持っている。ホルモンとしてのオキシトシンには、分娩時に子宮の平滑筋を収縮させる作用があること、また、赤ちゃんが母親の乳房を吸啜する刺激により分泌されて、乳房から母乳を出す「射乳反社」を起こす働きがあることがよく知られている。神経伝達物質としては、様々な神経細胞に対して多彩な作用を及ぼすことがわかってきており、この多彩な作用がオキシトシンの特徴であるともいえる。その中でも最も興味深いのは、オキシトシンの作用の根幹をなすものが成長であるということだ。オキシトシンは成長の基である生殖に深く関わっており、排卵や射精を促し、分娩・授乳のためには必須の物質でもある。』
感想
『どの年齢層においても、病気の多くはつきつめればストレスが原因だ。』
まさに、この通りだと思います。今回、きっかけとなった不妊鍼灸も、スタート地点は、心身のストレスとどう向き合うかにかかっているように思います。
『私たちのすべての感覚は、まわりがどんな環境か判断することに、絶えず関与している。その環境が脅威や危険をはらんでいると感じたら、〈闘争か逃走か〉反応が引き起こされ、平和で楽しい環境だと感じたら、〈安らぎと結びつき〉反応が引き起こされる。』
後者の〈安らぎと結びつき〉の主役はオキシトシンです。その三大効果は、成長と治癒、社交的能力、抗ストレス効果とされています。
モべリ博士は『オキシトシンの効果は成長と生殖への要求を満たす助けになるものである。』、『私は生殖プロセス全体を、基本的なオキシトシン原理が複雑な形で表現されたものとみなしたい。』と主張されています。
生命誕生に、オキシトシンこそが主役なのではないかという予想は正しかったように思います。 そして、行動すべきは〈安らぎと結びつき〉を重視し、そのための時間を意識的に“つくり出す”ことではないでしょうか。
オキシトシン〈安らぎと結びつき〉4
第八章 授乳―オキシトシンが主役
●オキシトシンは出産授乳ホルモンと呼ばれていた。
●授乳中、オキシトシンは胴体前面の血管を拡張させることで、母親の体表温度を高める。さらに、オキシトシンは育児に必要な世話と保護にも関係している。
[オキシトシンと母乳]
●オキシトシンは乳汁産生を促すホルモンのプロラクチンが下垂体前葉から分泌されるのを促す。乳汁産生はインスリンによっても促される。
●オキシトシンはインスリンの産生を増やす。また、オキシトシンは体の貯蔵所からの栄養の放出を促進するホルモンであるグルカゴンにも影響を与える。
●授乳するためには自分自身の貯えがなければならない。オキシトシンは食欲を増進させ、消化を促進し、体の貯蔵システムの効率を高めることなどによって、体が栄養物を貯えるのを助ける。
[オキシトシンと新生児]
●『今日では、分娩後すぐ、新生児を母親の胸の上に、肌と肌を触れ合わせて置くことが多い。好きなようにさせると、赤ちゃんは、誕生後1、2時間以内に自分で乳房に到達し、母乳を吸いはじめる。乳首を探しているとき、赤ちゃんは手で母親の乳房をマッサージすることになる。このとき母親の体内に、オキシトシンが拍動のようにくりかえし放出される。赤ちゃんがこのオキシトシンの分泌の波をつくりだしているように思われる。というのは、赤ちゃんの手によって乳房に加えられる刺激と、吸うこととが、オキシトシン分泌の波の数と強い(統計学的に有意な)相関係数を示しているからだ。それらの刺激は、乳が体外に噴き出すのを促進するだけでなく、母親の胸部の血管を拡張する。すでに見てきたように、それによって、母親は赤ちゃんにぬくもりを提供する。このときにフェロモン類が放出されて、母子双方に影響を与えている可能性もある。
肌と肌の触れ合いは赤ちゃんの側にも影響を及ぼす。赤ちゃんは落ち着き、母の胸に密着している限りは泣かない。手や足の血流量が増え、リラックスしていることがわかる(リラックスしている状態では、血管が拡張する)。母子の間に微妙な相互作用が交わされていることは、赤ちゃんの足の温度と、母の体温の両方が上がっていることからも明らかだ。母の体温が温かいほど、赤ちゃんの足も温かくなる。
新生児のオキシトシン放出については、まだ研究されていない。しかし、ストレスホルモンのコルチゾールの値が低いことから考えて、脳内のオキシトシンの値はおそらく高くなっているだろう。乳房に吸いつくことで、これらの効果も増強される。触覚以外の感覚(聴覚、嗅覚、視覚、とりわけ、一種の間接的な触れ合いであると考えられるアイコンタクト)も、出産直後の母子の間の精妙な相互作用に重要な役割を果たしている。』
[授乳のもたらす安らぎ]
●授乳とともに、血圧は下がり、ストレスホルモンのコルチゾールの血中濃度が減る。このことは、交感神経系と副腎の活動が低下していることを意味する。
●授乳中の動物の脳の活動を計測した結果、子どもに乳をやりながら、眠っている個体が多数あることが分かった。これは、しばしば人間の母親にも当てはまる。
●これらの行動ならびに生理学的状態の変化は、短時間で消失するものではなく、授乳期間全体にわたって続く。
●研究によると授乳中の女性で、行動の変化がもっとも大きかったグループの人たちは、オキシトシンの血中濃度のもっとも高かった人たちだった。一回の授乳中に起こるオキシトシン分泌の波の数が、乳汁の量だけでなく、母親の落ち着きの度合いとも関係している。
[吸うことと情緒的な絆の形成]
●吸うこと自体の効果は、早産児にも見られる。非常に弱くて、チューブで胃に乳を送らなくてはならない赤ちゃんたちも、小さなおしゃぶりをできるだけ吸わせるようにすると落ち着きが増し、体重の増加のペースが速くなる。
●赤ちゃんのおしゃぶりや指しゃぶりをやめさせるのは難しいことが多い。オキシトシンの分泌とそれによる絆の形成は、おそらく吸うという行為によって始まると思われる。身体的接触が外側の寄付を刺激するように、吸うという行為は口の内側を刺激することだからである。
[ほかの人たちと一緒にいること]
●オキシトシンは一般的に言って、授乳する女性の精神状態を二つの面で変える。授乳する女性は、落ち着きを増し、引きこもっていることを楽しむが、同時に、人と人との親しみのこもった触れ合いに対して心を開く。この二つの適応方法は、授乳期間中、非常に価値がある。進化という観点からも見ても重要な意味をもつと考えられる。
第四部 結びつき
第九章 オキシトシンと触覚刺激
●『人間でも動物でも、皮膚は絶え間なく外界から得た情報を神経系に伝えている。皮膚は、人間やほとんどの哺乳動物にとって最大の感覚器官であり、温かさや冷たさ、触感、痛みを感じ取る。それぞれの感覚は受容器で感知され、受容器につながっている感覚神経系がその刺激信号を中枢神経系へ伝える。
感覚器官としての皮膚の見事な働きのおかげで私たちは、自分にとって脅威であるものであれ、好ましいものであれ、周囲の世界からのメッセージを速やかに解釈することができるのだ。ようしゃなく殴られたのか、優しくなでられたのか、容易に区別できる。中枢神経系にどんな情報が送られるかによって、汗をかいたり、鳥肌が立ったりする。』
[触覚刺激の二つの作用]
●皮膚にはさまざまな受容器が存在している。痛みを感知する受容器や、ぬくもりを感知する受容器。軽く触られたのを感知する受容器もある。
●様々な感覚神経に与えた刺激によって、〈闘争か逃走か〉反応または〈安らぎと結びつき〉反応のどちらかが引き起こされる。これは、どちらのシステムも、ほぼ全身にくまなく存在する皮膚の感覚受容器を発端として作動しうるということ、そして、様々な種類の刺激が、生理学的状態にも行動にも、様々な効果を与えることを意味する。
●覚醒しているラットの腹を、ある特定の圧をかけて一定の間隔でなでてやると、痛みを感じにくくなり、びくびくしなくなった。1分間に40回のペースでなでるのを、5分間をわずかに下回る時間続けるのが、最大の効果をあげるとわかった。こうすると、ラットは落ち着き、動きが少なくなるとともに、他の個体に対する興味や関心が強まった。血圧は低下し、数時間下がったままだった。
[鍵となるのはオキシトシン]
●あるドイツ人の酪農家が、乳牛のためのボディブラッシング機を考案し、動物における触覚刺激刺激の劇的な効果を例証した。優しくなでなれているような心地良い感覚により、乳牛たちはリラックスして体調がよくなり、乳量が最大26%増えた。
●鎮痛剤を与えたラットの特定の神経を活性化したり、目覚めているラットの腹をなでたりするなどの方法で、鎮静作用のある種々の反復刺激を与えると、ラットの血中や脳内のオキシトシン値は決まって上昇した。
[触覚刺激と成長]
●快い触覚刺激がなぜ成長と結びつくのかについて考えられることは、下垂体から放出される成長ホルモンが増加するためである。これにもオキシトシンの関与が考えられる。
第十章 オキシトシンとほかの感覚刺激
●ラットによる研究結果の中に、オキシトシンの投与を受けていないラットにも程度の差はあれ、投与を受けたラットと同じような効果、落ち着きが増し、ストレスホルモン値が低下するなどを観察できる。これについては、匂いを通して伝達が行われ、オキシトシン・システムが活性化すると考えられている。
●匂いの中には気づかない匂いもある。これは鋤鼻器という特殊な古い嗅覚器官であり、フェロモン(空中を漂って個体から別の個体へと伝わる物質)を受け取る。フェロモンの効果に関与する神経は、大脳皮質や嗅球には直結しておらず、身体機能や情動の一部をつかさどる脳の比較的古い部分につながっている。そのため、人間は無意識のうちにフェロモンの影響を強く受けている可能性がある。
●私たちのすべての感覚は、まわりがどんな環境か判断することに、絶えず関与している。その環境が脅威や危険をはらんでいると感じたら、〈闘争か逃走か〉反応が引き起こされ、平和で楽しい環境だと感じたら、〈安らぎと結びつき〉反応が引き起こされる。
※フェロモン
フェロモンには何となく胡散臭い印象があったので調べてみました。
以下は東工大さんのニュースなので極めて信頼性の高い情報です。これにより、フェロモンの存在の有無を正しく認識することがでました。「やっぱり、あったんだ!」という感じです。
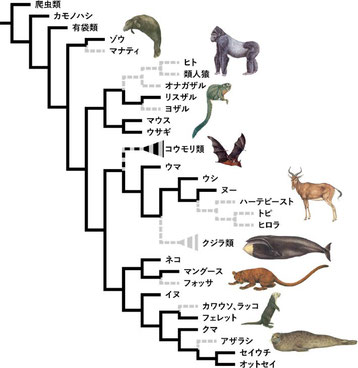
画像出展:「東工大ニュース」
東工大ニュースには以下の記事もありました。
『115種におよぶ生物種の全ゲノム配列を網羅的に解析して、ほぼ全ての脊椎動物が共有する極めて珍しいタイプのフェロモン受容体遺伝子を発見しました。
一般的に、フェロモンやその受容体は多様性が大きく、異なる種間での共通性は極めて低いことが知られています。しかし、今回新たに発見された遺伝子は、古代魚のポリプテルスからシーラカンス、そしてマウスなどの哺乳類におよぶ広範な脊椎動物で共通であるという驚くべき特徴を備えていました。』
第十一章 オキシトシンと性行動
●愛の効果には、事後に安らぎとくつろぎをもたらす力を含め、たくさんの健康増進効果がひととおり備わっているからである。この安らぎは、性行為につきものの触覚刺激や一体感とともに、オキシトシンの放出を増やす。そしてさらにこのオキシトシンが癒しや消化の促進など、さまざまな抗ストレス効果を生む。
●オキシトシンは人間の性行動に重要な役割を果たしている。ひとつには、濃密な触れ合いやキスの口唇刺激をともなうからであり、また、オルガスムスは大量のオキシトシンを血液中に放出させるからである。これは動物実験に加えヒトの研究の結果からも確認されている。
●オキシトシンは卵巣からの排卵を促し、卵が卵管を通って子宮へと運ばれるのを手伝い、また、精子の産生と移動を助ける。
[オルガスムスと絆]
●性交中は男女とも血中のオキシトシン濃度がぐんぐん上昇し、オルガスムスと同時に最高値に達するという。また、オキシトシンは男女の別を問わず、オルガスムスとかかわりのある筋肉の運動を刺激する。
●実験により、動物にオキシトシンを大量投与すると、眠ってしまうことがわかっている。少量投与の場合は不安が減り、落ち着きが増し、他の個体との接触に興味を示す。
●オキシトシンの効果は、その性的体験がどのような状況のもとにあったかに左右される。その状況が緊張や危険の要素が優位であれば、オキシトシンと拮抗的に働くバソプレシンの影響のためストレス反応が生じる。
●オキシトシンは性的関係による感情的絆を強める。それはカップルが互いにふさわしい相手だと確信できるほどに理解し合う前に、感情的絆だけが先行してしまうという危険をはらんでいると言える。
[セックスと健康]
●短期的に見ると、性的経験はストレスになる要素があるが、長期的には安定した性的関係は、カップルの双方の安心感を強め、不安を減少させる。オキシトシンの大量放出が繰り返されると、〈安らぎと結びつき〉システムにつきものの長期的効果が生まれる。栄養を蓄積し、癒しを速め、生きていくのに必要な力の回復を促進する、といったそれらの効果によって、性的活動は健康にとってプラスの影響を与える。
第十二章 オキシトシンと人間関係
●『好きな人のそばにいるのは、うれしいものだ。あなたが赤ちゃんだろうと大人だろうと変わりはない。好きな人と一緒にいて、触れ合うことができると、安心感がもて、緊張がとけて、気持ちが落ち着く。スキンシップが必要なのは、ママやパパに抱きしめてもらいたがる幼い子どもだけでない。大人もやはり、人間関係において愛されている感じがほしいときには、身体的に触れ合う必要がある。』
●愛情を感じ、安心感を覚えると気分がよいというだけの話ではなく、他の人のそばにいて、身体的な触れ合いをもつことが、私たちの健康に役立つような方法で、体内の生理学的プロセスを活性化させている。
[絆で結ばれた関係]
●多くの動物は互いに識別しあって親密さを深めるが、雄と雌が一生結びつくという意味での一夫一婦婚をする哺乳動物は、ほんのわずかである。すべての哺乳動物にとって大切なのはむしろ、母子間に相互的な強い絆を形成することである。種の存続は、母と子がお互いを識別し、結びつきを維持する能力にかかっている。
●『ヒツジの場合、出生後の一時間が母ヒツジと子ヒツジの絆を形成するのに、決定的な意味をもつ。この大事な時期に親子が引き離されると、絆を形成するのが難しくなり、しばしば、母ヒツジが子ヒツジを拒否する。そういう母ヒツジにオキシトシンを注射すると、その一時間が過ぎていても自分の子どもを受け入れるようになるだけでなく、ほかの雌の子どもも受け入れて、母子としての関係を築く。したがって、オキシトシンは母子間の絆形成に―とりわけ、出生直後の絆形成に、重要な役割を果たすと言えよう。』
[触覚刺激と感情的絆]
●オキシトシンの影響を受けると、他者との接触に積極的になると考えられる。そして、そのことがオキシトシンの分泌に拍車をかける。このようにして、人と人との感情的絆の形成に至るサイクルがつくられる。
[さまざまな人間関係におけるタッチ]
●親密な間柄でのタッチのタイプは、親子間、兄弟間、パートナー同士、友人同士など、どのような間柄かによって変わってくる。タッチや体の触れ合いがオキシトシンを放出させることを考えれば、相互的な快いタッチを交わせるふたりの人の関係は、感情的絆をつくるだけでなく、お互いの健康を増進し、オキシトシンによる抗ストレス効果を与え合っていると考えられる。
●生き延びるためには、他の個体と親密になる能力が、他の個体から身を守る能力と同じくらい重要である。
●ある実験によれば、図書館員に軽く手を触れられた借り手は、触れられなかった借り手よりも返却率が格段に高かったという。ちょっとした接触が、借り手に本を返す気にさせる感情的な結びつきをつくりだしたためである。
[心理的な触れ合い]
●人間同士の関係や出会いにおいて、身体的触れ合いがなくても心理的レベルでのタッチを経験することもある。温かく協力的な感じのすることもあれば、冷淡で厳しいと感じることもある。こちらの話を丁寧に聞いてくれる人に対しては、親しみのこもったタッチをしてもらった場合と同じく、信頼と結びつきの感情を抱きやすい。
[タッチの欠如]
●過度なストレスは交感神経の過活動につながり、健康に害を及ぼす。親しい人との別離は強いストレス効果を伴う。
●別離と病気には関連がある。例えば、配偶者を亡くして間もない人は、病気にかかるリスクが増すという統計がある。
●血圧上昇、心拍数増加、不整脈、血液凝固亢進傾向などのストレス関連症状は、心血管の疾患や脳血管障害を引き起こすおそれがある。
●個人的な結びつきを死別や生別によって失うことのストレスは、突然、タッチを喪失し、それによって、親密さや温もりが生む効果の多くをなくしてしまうことが一つの重要な要素であろう。健康に良い刺激がなくなると、病気になるリスクが高まる。
[他者との良好な関係が健康に与える好影響]
●良好な人間関係が長寿につながることを示す研究結果がいくつかある。特に男性は、心血管疾患の発生率が低かった。
●私たちに好影響を与える人間関係とは、必ずしも親密なものでなくても良い。グループ活動や地域活動に加わるだけでも健康に良い影響がある。
[場所との結びつき]
●年をとってから故郷に戻ってくる人は多い。故郷での暮らしは、他のどこよりも心が休まるのだろう。また、老齢のために長年住んだ故郷を離れなくなければならなくなった人は、それにより身体的にも精神的にも衰えがちであることはよく知られている。
オキシトシン〈安らぎと結びつき〉3
第三部 オキシトシンの効果
第六章 オキシトシン注射の効果
●『オキシトシンは一生を通じて私たちとともにある。あなたが生まれたときに、お母さんの子宮から押し出されるのを手助けしてくれたのはオキシトシンだし、お母さんがあなたに授乳することができたのもオキシトシンのおかげだ。幼いころには、お母さんやお父さんが愛情をこめて触れてくれるのを喜んだだろう―それによって、あなたの体の中にオキシトシンが放出されたから。大人になってもからも、おいしいものを食べたり、マッサージを受けたり、恋人と親密に触れ合ったりしたときに、オキシトシンの効果を体験している。オキシトシンはこれらのすべての状況で―そしてもっともっとたくさんの状況で活躍している。』
●『本書で描かれているオキシトシンの効果の多くは、動物実験によって例証されている。研究者たちは動物の行動の変化だけでなく、さまざまな計測可能な生理学的変化も観察してきた。これらの効果のほとんどは、ヒトでも確認されている。』
[不安が減り、社交性や子育て行動が増強される]
●低い投与量のオキシトシンを注射されたラットは、臆病さが減り、好奇心が増す。安全な巣を離れて、未知の環境を探求する傾向が強くなる。オキシトシンには明らかな不安軽減効果がある。
●同性の一群のラットは、未知の環境を探索する傾向が強くなり、接触を恐れる程度が少なくなる。集団内での攻撃がはっきりと減り、友好的な交流が増える。
●オキシトシンは危険に対する感じ方を鈍らせ、恐れるべきものがあまりないという気持ちにさせて、勇気を涵養する。
●オキシトシンの影響を受ける行動のうち、とりわけインパクトの大きい例は、母子間の相互作用である。メスのラットにエストロゲンを投与し、さらにオキシトシンの注射をすると、出産したことのないメスでさえ母性行動を示す。
●オキシトシンは分娩時と授乳時に分泌が促進される。オキシトシンは子宮の収縮を促し、新生児が押し出されるのを助ける。そして、乳管の周りの筋肉を収縮させ、乳汁が押し出されるのを促進する。
[ソーシャル・メモリー(他社とのかかわりについての記憶)の増強]
●少量のオキシトシンが不安を減らし好奇心を増すが、大量のオキシトシンが注射された雌牛は全く異なる効果を示す。
●オキシトシンの効果は非常に広範囲にわたるが、その一つに痛みの軽減がある。
[学習能力の向上]
●オキシトシンの学習促進効果は鎮痛効果によるものと考えられる。これはストレス低減にも関係しているのではないか。
●オキシトシンは速やかに血液中からなくなるので、長期的効果はオキシトシンの直接的な影響であるとは考えられない。これはオキシトシンが他の神経伝達物質の働きに長期的な影響を与えるためではないか。
[血圧に対する効果]
●オキシトシンは心拍数や血圧を上昇させることもあれば、低下させることもある。ヒトにおいては後者の場合が多いようである。これらの効果は交感神経と副交感神経が直接的に、もしくはより高位の脳からの接続を通して影響されることによって生じる。
●オキシトシンの効果はメスにおいてより顕著に現れる。これはエストロゲンのためである。エストロゲンはメスの個体において、オキシトシンの影響を増強し、効果の持続時間を長くする。卵巣のないメスはオスと同等となる。
[体温の調整]
●オキシトシンのサーモスタットは温度を均一に保つのではなく、温かさを体のある部分から他の重要な部分に移動させるような働きをしていると考えられる。授乳中の母ラットの腹側の血管は、オキシトシンの効果によって拡張しているため、授乳中は子どもを温めてあげることができる。
[消化活動の調節]
●オキシトシンの消化活動に関する働きは興味深いものである。その個体が満腹であるか空腹であるかによって、オキシトシンの果たす役割は異なる。オキシトシンの作用の仕方は、一種の知恵が働いている。
●オキシトシンは長期的には食欲を増進させるが、メスにおいて、特に授乳期間中に顕著にみられる。
●オキシトシンによって消化プロセスの効率が良くなるのは、ひとつには、オキシトシンが胃液の分泌と、ガストリン、コレシストキニン、ソマトスタチン、インスリンなどの消化に関係するホルモンの分泌を促進するからである。なお、コレシストキニン、ソマトスタチン、インスリンは、体内における栄養の蓄積も促進する。
●胃に食べ物がある動物では消化と栄養の蓄積が活発になる。一方、空腹の動物では消化プロセスが抑制される。オキシトシンのこの二つの効果は、いずれもオキシトシンが副交感神経のうちの腸の機能を制御する部分(迷走神経)に影響を与えることによってもたらされる。
[体液量の制御]
●オキシトシンは、パートナーともいえるバソプレシンとともに、主として尿の形で水を排出するか、体液の貯留を促進するか、いずれかの方法で体液量を調節する。ただし、それぞれの働きは体液量の均衡維持に対して、正反対の効果をもたらす。
●オキシトシンは腎臓がナトリウムや水分を尿の形で排泄するのを促進する。一方、体液の保持する機能に関し、ホルモンであるバソプレシンや副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)が増加すると、塩分を摂りたくなる。バソプレシンは尿を作る量を減らし体内の塩分と保持する。
●バソプレシンは血管を収縮させ、血圧をあげる。危険を感じる状況において、負傷によって血液その他の体液が失われる恐れがあるとき、ヒトは体液を保持しなければならない。バソプレシンとCRFはその目的のために作用する。
[成長と傷の治療]
●オキシトシンは傷ついた粘膜を治癒させ、再生させる。炎症を抑える作用もある。
[ほかのホルモンへの影響]
●オキシトシンは視床下部でつくられて、下垂体後葉に運ばれ、そこから、血液中に放出される。
●下垂体前葉からも数種類のホルモンは分泌されるが、視床下部でつくられた特別な制御物質が局所的循環システムを通して、下垂体前葉に運ばれ、そこでそれらのホルモンを血流に放出される。
●下垂体前葉につながる血管の中には、いくつかの神経からオキシトシンが放出される。オキシトシンは下垂体が、プロラクチン、成長ホルモン(GH)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)などを分析するのを促進する。これらのホルモンの値が増えると、様々な効果が生まれる。例えば、プロラクチンは授乳期間中のメスの動物や授乳中の女性の乳汁の産生を促し、成長ホルモンは体の成長を促す。
●体にもともと備わっている抑制と均衡のシステムは複雑である。オキシトシンは常に存在し、さまざまな仕方で作用する。オキシトシンを中心とするこの抑制と均衡のシステムはうまく連携がとれていて、オキシトシンの様々な効果は、見事なクモの巣をなす糸のように結びついている。
第七章 オキシトシンの木
●オキシトシンの効果は成長と生殖への要求を満たす助けになるものである。
[成長の原理]
●オキシトシンの様々な効果は、一本の大きな木の枝のようなものである。それぞれの枝は、オキシトシンに関係のあるひとつの基本的な原理、すなわち一本の幹から出ている。その基本的な原理(幹)とは成長の促進である。
●オキシトシンは食物を別の物質に変えることによって、成長を促進する。
[成長のプロセス]
●すべての成長に必要な基本的必要要件のひとつは、栄養を体の中に組み入れることである。オキシトシンは様々な仕方でこの要請に応える。消化効率を高め、栄養の蓄積を増強する消化管ホルモンの分泌を促進したり、下垂体から成長ホルモンが分泌されるのを直接的に促進したりする。
●『生まれたばかりのラットにオキシトシンを注射すると、通常より速く成長し、通常より大きな成獣になる。妊娠中のメスのラットにオキシトシンを注射すると、通常より大きな子を産む。おとなのメスのラットに、オキシトシン注射をすると、注射を受けていない比較対照群よりも体重が重くなる。
おそらくもっと間接的な仕方でも、成長が促進されているのだろう。というのは、オキシトシンを注射すると、傷の治るのが二倍も速くなる場合があるからだ。この治癒効果は、オキシトシンが細胞分裂を促進すること―すなわち、新しい細胞ができるのを加速することによるのかもしれない。オキシトシンは、また、「成長因子」―細胞が大きくなることと分裂することを促進する血液中の物質―の産生量を増やすように思われる。
オキシトシンが成長を促進するのであれば、生殖にかかわっているとしても何の不思議もない。オキシトシンは卵と精子の両方に見られる。オキシトシンは卵巣からの排卵や精巣での精子の産生を促進する。オキシトシン注射は、受胎しやすさを増し、受精後早期の細胞分裂を速め、胚の成長速度を増す。このように、人生のもっとも早い段階から、オキシトシンは私たちの道連れとなり、一生の間、離れない。
生き物が成長するためには、まず、栄養を貯えなくてはならない。細胞分裂の前には、必ず、細胞の大きさが増す。大きさが増すのは、栄養の蓄積によって起こる。まず、栄養を貯えないと、細胞は分裂できない。栄養を貯えられない細胞系は、ほどなく滅びてしまう。妊娠・出産も元のユニット(単位)が大きさを増し、それからふたつに分かれるものだから、巨大なスケールでの細胞分裂とみなすことができるだろう。私は生殖プロセス全体を、基本的なオキシトシン原理が複雑な形で表現されたものとみなしたい。それは、まず成長を促進し、それから、元の存在を分割することによってふたつの存在を生み出し、命を増やすことだからだ。』
[出すこと]
●オキシトシンの木の2本目の枝は、出す能力(“排出”)に関わるものである。[1本目の枝は“成長”]
●オキシトシンの効果で子宮や乳房の筋肉が協調して収縮することによって、子どもが娩出され、乳が排出される。
[社交性、好奇心、つがい]
●オキシトシンの木の3本目の枝は、社交性と好奇心による行動を促す力である。
●社交性と好奇心による行動とは、例えば、あえて他の個体に近づき、その相手と相互作用をもち、個体識別ができるようになり、その相手のそばにいることを選ぶといったことである。
●この枝は母性行動や社交的行動(他社への働きかけ)の形での個体間の相互作用に影響を及ぼす。
●人と人がお互い身近になると、感情的なつながりが両者の間に生まれる。この現象は性的関係、親子関係、友人関係などにもあてはまる。
●絆―つまり感情的な結びつきがある場合には、人のために尽くすことが、より容易になる。一般的に言って、性的関係であろうと、育て、育てられる関係であろうと、友達関係だろうと―いや、職業上の関係であってさえ、人間関係というものは、双方が相手に手を差し伸べ、親しみを抱くことができる場合にこそ、実り多く、長続きするものになる。
●オキシトシンの不安軽減効果も、おそらくはこの枝に属する。不安のレベルが低いことは見知らぬ相手に近づくのに必要な前提である。
[枝同志を結びつける]
●バソプレシンは防御・縄張り・攻撃などに特徴づけられる行動にかかっている。一方、オキシトシンは他者とのかかわりあい、人なつっこさ、好奇心によって特徴づけられる行動を生み出す。
●他者と接触すること自体が、オキシトシンの放出を促し、個体間に絆、あるいは愛着を引き起こす。これらは親と子の関、性的パートナーの間、重要な人間関係においても同様である。この種の行動のすべて、そしてその生理学的要素の一部がオキシトシンによって強化される。
●オキシトシンの二大効果―ひとつは成長と治癒、もうひとつは社交的能力―は、一見、別物のように見えるが、大きな視野で見れば二つの効果には関係があると思われる。子どもの成長には母親の献身的な育児が必要だが、母親は出産のあと、母親は他者との交わりに積極的で、育む気持ちが強まるだけでなく、子どもとの絆を形成しようと努める。
[短期的賦活作用]
●オキシトシンの枝には短期的効果に関わるものもある。オキシトシンを注射すると、一時的に血圧と心拍数が上昇し、ストレスホルモンの分泌が促される。これらの穏やかな賦活効果は成長を促進する効果を補う。例えば、他者との間の相互作用を自分の側から始める時、このような補いが必要になる。
●出産においては陣痛の間、赤ちゃんへの血液供給を十分に行うためには母親の血圧は上昇する必要がある。短期間に見られるストレス反応は、新しい未知な環境に対処する際にも役立つ。このような場でリラックスするのは危険なことである。
[長期的ストレス軽減作用]
●オキシトシンの二大効果(成長と治癒、社交的能力)に続く、大きな枝は、強力で長期期間持続する抗ストレス効果である。オキシトシンには血圧と心拍を下げ、ストレスホルモンの血中濃度を減らし、痛みに対する耐性を増し、学習を促進し、安らぎの感情を強める働きがある。ただし、この効果が現れるのは、普通、しばらく時間が経ってからである。しっかりと覚醒している時間の後でなければ、のんびりとくつろぐのは危険である。
●オキシトシンの長期的な効果は、ストレスとは正反対の生理学的状態をつくりだす。交感神経の活動が抑制され、その結果、血圧もストレスホルモンの血中濃度も低くなる。同時に副交感神経の一部が活性化して、心拍を遅くし、消化と栄養蓄積を促進する。これらの抗ストレス効果には多くの機能があるが、共通点は成長に必要な前提条件を整えることである。成長に関係する活動は―栄養蓄積、傷の治療など、そして生殖そのものも―個体が平静な状態のときに強化されるからである。
●重要なことは長期的な抗ストレス効果は、オキシトシンの直接的な作用によるものでない。それはオキシトシンが速やかに血液中から消えるからである。数日、あるいは数週間も長期的な効果が続くのは、オキシトシンが他の生理学的メカニズムを活性化するからだと思われる。
●オキシトシンの長期的効果を説明するメカニズムについて、研究によって部分的には明らかになっている。
-『神経伝達物質であるノルアドレナリンとアドレナリンは、脳のストレス対処システムの重要な構成要素である。ノルアドレナリンとアドレナリンは神経系の特別な受容体―とりわけ、αアドレノ受容体、βアドレノ受容体と呼ばれる受容体と結合して作用する。オキシトシン注射を繰り返すと、αアドレノ受容体の一タイプであるα2アドレノ受容体と呼ばれる受容体の活性が高まる。ノルアドレナリンがこの受容体と結合すると、それ以外のアドレノ受容体と結合したときの効果とは正反対の抗ストレス効果が生み出される。つまり、オキシトシン注射を繰り返した結果として、あたかも船長がエンジンを逆回転させるように指示したかのように、ノルアドレナリンの影響がおおむね、正反対に切り替わる。』
[ともにそよぐ枝]
●オキシトシンの木は1本の枝が目立って風に揺れることはあるだろうが、多くは数本の枝がそよいでいる。
●オキシトシンの効果を取り扱う研究は動物実験に基づいているが、私たちヒトにおいて安らぎと幸福感を生み出す状況の一部も、オキシトシンの放出と関係があると推測することができる。
●動物における研究はそれらの状況を特定するのに役立ち、そのような状況でのヒトのオキシトシン値が測定されてきた。例えば、授乳しているとき、食べているとき、セックスをしているとき、あるいはもっと広く、他の人と身体的に接触しているとき、オキシトシン値が上昇することがわかっている。
●授乳は多量のオキシトシンを放出させ、オキシトシンの木の数本の枝を揺らす活動である。母乳が排出されるときには、母親も子どものゆったりとくつろいでいる。それにくわえて、母子間の相互作用が強められ、両者ともに、消化と栄養蓄積のプロセスの効果が増す。
[成長と防御の必要性]
●本書で論じている二つの主要なシステム―〈安らぎと結びつき〉システムと〈闘争か逃走か〉システムは―は、個々の細胞のレベルでさえ見られるふたつの基本的な生理学的プロセスが、複雑な形で表れたものだと考えられる。
[修復し、バランスを取り戻す]
●シーソーのストレスの側にだけ、明らかに過重がかかっている状態は、〈安らぎと結びつき〉効果を活性化することで、バランスが取れる。自然は私たちに「どちらか」の問題ではないと、繰り返し教えてくれているかのようだ。
オキシトシン〈安らぎと結びつき〉2
第一部 〈安らぎと結びつき〉システム
第一章 オキシトシン
●1906年、ヘンリー・デールは、脳にある下垂体の中に、出産の経過を加速する物質を発見し、「速い」と「陣痛」という意味のギリシャ語にちなんで、それをオキシトシンと名づけた。また、後に、オキシトシンが射乳を促すことも発見した。
●『私は本書で紹介する研究を始める前に、自分自身、妊娠・出産・授乳に関して行動のしかたや考え方が、がらっと変わるのを経験していた。私はオキシトシンについての科学文献の中に、その変化を説明するものを見つけた。また、私の調べた資料には、オキシトシンがさまざまな面で母子間の相互作用を増し、母子間の絆を形成することを立証する動物実験についての記述が含まれていた。私は考えた。オキシトシンは私たちヒトに対しても、生理学的影響や心理学的影響を与えているのではないだろうか―それらの動物実験が示しているような面でも、まだ知られていないほかの面でも。
大いに興味をそそられて、手にはいる限りのオキシトシンについての文献を読んだ。わかったことは、オキシトシンはホルモンとして、血流に乗って体内を巡り、さまざまな機能に影響を与えるだけでなく、神経伝達物質として脳のさまざまな領域につながる神経ネットワークを通して作用するということだった。このふたつの方法で、オキシトシンは、体のさまざまな重要な働きに影響を与えている。〈闘争か逃走か〉反応を引き起こすのと同じ神経系が、オキシトシンが関与した場合には、正反対の反応を引き起こす。』
●オキシトシンとバソプレシンは2つのアミノ酸が異なるだけであり、非常によく似ている。また、進化論的観点から見ると、オキシトシンとバソプレシンは非常に古くからある物質である。
●オキシトシンは哺乳類のすべての種に、化学的に見てまったく同じ形で存在する。
●ミミズにさえ、オキシトシン様の物質が見られ、その刺激で卵を産む。
●オキシトシンとバソプレシンがこれほど長い間、動物界に存在しているという事実は、このふたつの物質が非常に重要であり、不可欠な役割を担っていることを示している。
●オキシトシンは多くの連鎖反応による効果の発端となるが、その鎖の最後の輪であることはまれである。このことは非常に重要である。
●オキシトシンによって制御されるシステムにはフィードバックの仕組みがあるので、オキシトシン産生細胞は、神経信号を受け取ること、ならびに化学的変化を感知することによって、外部環境と情報を交換できる。これらの細胞には、体の外側の器官、内部の器官、感覚器から情報がもたらされるので、オキシトシンの分泌は容易に促進される。興味深いことに、考えや連想、記憶などによってさえ、オキシトシン・システムが活性化される。
第二章 私たちを取り囲む環境
●生態系とフィードバック・システムについての理解が深まるにつれ、すべての生物個体がそれを取り囲む環境と常に接触し、影響を受けつづけていることがわかってきた。食刺激、姿勢、周囲の温度、飢え、満腹状態など、無数の可変要素が常に与えている情報は意識されることなく、心身の機能に影響を及ぼしている。
●生物学的リズムは環境から独立しているというふうに考えられがちだが、実際は、その多くがもともと、外界との相互作用によって獲得されたものである。女性の月経周期が月の満ち欠けと一致しているのも、すべての人がほぼ同じ長さの一日の生体リズムをもっているのも偶然ではない。かつては月光や日光がそのような機能を直接に制御していたが、進化の過程で、これらのリズムが生物学的システムに組み込まれた。
●生物個体を丸ごととらえるホリスティックな見方が医療や医学研究に導入された結果、心と体が相互依存的に機能しているということは、事実として広く受け入れられている。
●現代西洋文化のストレスの量についての不満は非常にありふれていて、もはや耳にすることもまれなぐらいである。今日、成功へのプレッシャーは非常に大きい。何事もテンポが速く、情報があふれすぎているし、職を得るためには厳しい競争に勝たねばならない。視覚、嗅覚、そしてとりわけ聴覚への刺激の量はすさまじい。私たちの体内ストレスに関連した〈闘争か逃走か〉システムが、過剰に活性化されているのは疑う余地がない。
一方、安らぎ・くつろぎ・親密さを促進する状況は、私たちの社会ではまれになってきている。そういう状況が生ずる頻度が少ないほど、〈安らぎと結びつき〉にかかわる私たちの内なる生物学的システムが活性化される頻度も減る。
●触覚は、〈安らぎと結びつき〉システムへの強力な入力源である。何かを一緒にするとき、人と人との相互作用において、触覚、嗅覚その他の感覚が、自然にその役割を果たす。個人の独立性を増し、共同作業を減らす現代の風潮の結果として、このような感覚刺激が減っている。そして、この変化は〈安らぎと結びつき〉システムの活動を減らし、究極的には、私たちの健康をおびやかす。
●〈安らぎと結びつき〉反応は、病気を予防するためだけに必要なのではない。人生を楽しみ、好奇心を燃やし、楽天的で創造的であるためにも必要である。
●穏やかな環境や、温かい人間関係のもとで、集中や学習力が強まることは、実験でも証明されている。ストレスにさらされている子どもは、心が平穏で安心感をもっている子どもよりも学習に苦労する。
第三章 バランスが肝心
●身体的ならびに心理的ストレスにさらされると、私たちが過酷な状況に対処できるように、体は利用できるエネルギーのすべてを動員する。そして、私たちがその状況を改善し、ひと息入れることができるようになるまで、それを続ける。
●『〈闘争か逃走か〉反応と〈安らぎと結びつき〉の状態の両方が、人生にとって欠かせないものだということは、いくら強調しても強調しすぎることはない。ほかの動物とまったく同様に、私たちヒトも難題に対応して、何であれ、そのとき必要な行動をとれるように自分のもっているすべての力を動員する能力が必要だ。そして、その正反対のことも必要だ。体は食べ物を消化し、貯えを補充し、自らを癒やす必要がある。情報を取り入れ、感情表現し、心を開いて好奇心を満たし、ほかの人たちと触れ合う必要もある。大変な出来事があったり、困難が続いたりしたあとに回復できるのは、そういう能力のおかげである。
前述したように、〈闘争か逃走か〉反応と〈安らぎと結びつき〉反応は、シーソーゲームの両端のようにバランスをとりあって機能する。満ち足りた気分で食物を消化しているときに、動揺や怒りやストレスを感じることはまれだ。一心に何かしているときや怒っているとき、急いでいるときには、消化のペースがゆっくりになり、愛想が悪くなる。一方のメカニズムが他方を排除することはないが、一時的に一方が優勢になるのだ。
しかし、現代では、〈闘争か逃走か〉反応は、突然の身体的危険を避けるというよりも、環境から多少とも継続的に過剰な要求をされていて、それに反応するということが主である。今や〈闘争か逃走か〉反応は、体のもつすべての力を一時的に動員するということではなく、ほぼ休みなく続く生理学的状態となってしまった。いわゆる慢性的ストレスが問題なのだ。
本書では、安らぎと結びつきを特徴とするさまざまな場面でのオキシトシンの役割について、これまでの研究で明らかになったことを描きだす。この新しい知識が、どの程度、そしてどのように私たちの役に立つか―たとえば、ストレスのマイナス作用に対して身を守る方法を見つけるのに役立つかどうか―は、これから研究していかなくてはならない課題だ。』
第二部 脳と神経系におけるオキシトシンの役割
第五章 オキシトシンの働くしくみ
●ホルモンには2種類ある。
‐ステロイドホルモン:コレステロールに関連した脂質から成る。
‐ペプチドホルモン:いくつかのアミノ酸が結合した小さなタンパク質で、細胞そのものの中に入るのではなく、細胞膜の外側の表面にある受容体を活性化する。
●オキシトシンはペプチドホルモンである。
●オキシトシンは哺乳類のすべての種において同じ構造である。
●オキシトシンは視床下部の室傍核と視索上核で産生され、下垂体に神経線維が走っており、この下垂体から放出される。
●室傍核の細胞グループからは、他にも多くの神経線維が伸び、扇状に広がって脳のさまざまな部分と接続しており、オキシトシンは神経伝達物質としても作用する。
●視索上核と室傍核でオキシトシンを産生する細胞には2つのタイプがある。
‐大きな細胞から産生されたオキシトシンは下垂体に運ばれる。
‐小さな細胞から産生されたオキシトシンは軸索を通って、脳内の受容体に運ばれる。
●オキシトシンを産生する細胞には興味深い特徴がある。神経細胞は活性化するとき電流が流れる。オキシトシン産生細胞の集まっているところでは、細胞ごとにバラバラに電流が生じるのではなく、一斉に生じる。授乳時のように、強く刺激されると、これらの細胞の電気活動は協調する。
●オキシトシン産生細胞の間には別の種類の細胞が存在し、一種の絶縁体として働いているが、その絶縁が解除されることで、すべてのオキシトシン産生細胞が力を合わせて働きはじめる。授乳中の女性の血中オキシトシン濃度が劇的に上昇するのは、ひとつにはこのためである。
●オキシトシン産生細胞に起こる協調は、生理学的に独特のものである。
●オキシトシンの効果をより厳密に調べると、非常に興味深いことに細胞の協調であれ、効果の協調であれ個体同士の協調であれ、協調こそ、オキシトシンの存在を示す目印であり、体内の他の多くの物質と区別する特徴である。
●視床下部からの神経を介してオキシトシンの影響を受ける脳領域には、視床下部と脳幹に近い領域が含まれる。視床下部と脳幹は血圧、運動、感情の制御に関係している部位である。この視床下部からの神経は、脳と脊髄の中の自律神経系の活動や痛みの知覚を制御する部位とも接続している。
●視床下部からの神経が複雑に枝分かれしているおかげで、私たちの体は、オキシトシンをメッセンジャーとして用い、さまざまな生理的機能・活動を協調させることができる。
●現在発見されているオキシトシン受容体は一つであるが、特定されていない受容体があると考えられている。
●オキシトシンの産生に影響を与えるのは外界からの情報(例えば皮膚を介しての情報)と体内からの情報(例えば子宮や腸についての情報)を運ぶ神経。そして、嗅球や大脳皮質の様々な部位、脳幹のような古く機能的に下位にある部位からの神経もオキシトシンの分泌を増やしたり、減らしたりする。
●オキシトシンの産生細胞の分布や、血中オキシトシンの循環には雌雄両性においてさほど差はないが、状況により雌に対して強い効果をもたらすことが、動物実験で示されている。
●女性ホルモンのエストロゲンが、オキシトシンの産生を増やすことで、オキシトシン・システムを活性することもある。エストロゲンはαタイプとβタイプの2種類の受容体に作用するが、オキシトシンの放出に関係しているのはβタイプの受容体である。
●神経伝達物質の中でオキシトシンを促進させるのは、グルタミン酸、CCK(コレシストキニン)、VIP(血管作用性腸管ペプチド)。抑制するのはGABA(γ‐アミノ酪酸)、エンケファリン、β‐エンドルフィン、ジノルフィンがあ
●モノアミンと総称される化学物質には、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリン等があり、これらは神経伝達物質として働くが、セロトニンやドパミンはオキシトシンの放出を促進する。ノルアドレナリンはストレスホルモンの一つであり、通常は覚醒と攻撃について賦活的効果をもたらし、〈闘争か逃走か〉状態を促進するため、それ自体は脳内のオキシトシン効果の標的でもある。ところがその一方で、セロトニンやドパミン同様、ノルアドレナリンもオキシトシンの放出を促進する。
●オキシトシン自身には他のほとんどのホルモンに見られる、サーモスタットのような自分で自分の産生を止めるフィードバック・システムがない。
●『オキシトシンは、オキシトシン産生細胞のオキシトシン受容体を活性化することによって、一定のレベルまでオキシトシンの産生を促す。そして、新たに活性化された受容体は、細胞を刺激して、さらにオキシトシンをつくらせる。』
オキシトシン〈安らぎと結びつき〉1
オキシトシンといえば、分娩や射乳に関するホルモンである。というのが学校で学んだことです。
2018年に拝読させて頂いた、山口 創先生の著書『人は皮膚から癒される』では、スキンシップケアの重要性とその陰に隠れ、多大な影響を及ぼしているとみられるオキシトシンの存在を知りました。(ブログは“スキンシップケア[C触覚線維]”)
一方、新たに不妊鍼灸をはじめたことで不妊に悩む患者さまとの接点が生まれ、このオキシトシンこそが、生命の誕生を総合的に支配している存在なのではないかと直感し、そして、今回の本を見つけてきました。初版発行は2008年と古いのですが、著名な先生の著書であることとオキシトシンだけに焦点を当てた内容は、200ページを超えるをものだったため全体像から枝葉まで知ることができるのではないかと思い購入しました。
オキシトシンは、血圧と水分調整にかかわるバゾプレシン(ADH)とともに下垂体後葉ホルモンであり、静脈から心臓に還流した後、全身に送られます。つまり、この2つのホルモンは、下垂体前葉ホルモンや視床下部ホルモン(下垂体前葉ホルモン分泌を促進または抑制を担う)とは明らかに異なる特徴を有しています。その意味でも特別の存在といっても良いのではないかと思います。
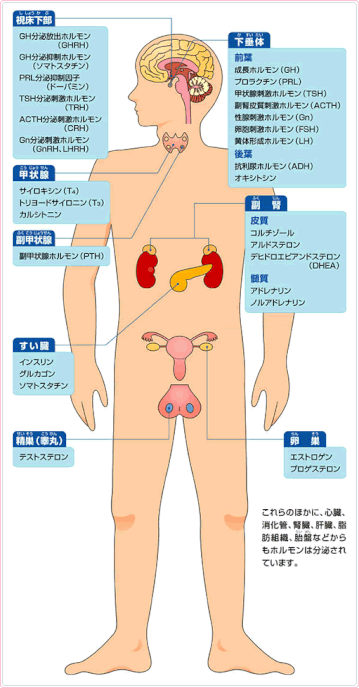
画像出展:「東京女子医科大学 高血圧・内分泌内科」
右上部の【下垂体】の中の[後葉]の下に”オキシトシン”が書かれています。上にある”抗利尿ホルモン(ADH)”がバソプレシンになります。

画像出展:「人体の正常構造と機能」
『下垂体後葉(神経性下垂体)には下下垂体動脈が分布し、後葉内で毛細血管網を形成する。視索上核や室傍核からの神経線維は漏斗茎を通って後葉に至り、毛細血管周囲に終末をつくる。神経終末から放出されたオキシトシンやバソプレシンは後葉の毛細血管内に入り、静脈から心臓へ還流したのち全身に送られる。』
※視床下部から下垂体後葉につながるピンクの管がオキシトシンとバソプレシンのルートです。
目次
はじめに―ないがしろにされてきた人生の一側面
第一部 〈安らぎと結びつき〉システム
第一章 オキシトシン
第二章 私たちを取り囲む環境
第三章 バランスが肝心
第二部 脳と神経系におけるオキシトシンの役割
第四章 体の制御中枢
第五章 オキシトシンの働くしくみ
第三部 オキシトシンの効果
第六章 オキシトシン注射の効果
第七章 オキシトシンの木
第八章 授乳―オキシトシンが主役
第四部 結びつき
第九章 オキシトシンと触覚刺激
第十章 オキシトシンとほかの感覚刺激
第十一章 オキシトシンと性行動
第十二章 オキシトシンと人間関係
第五部 安らぎと結びつきを探求するさまざまな方法
第十三章 マッサージ
第十四章 食べること―内側からのマッサージ
第十五章 タバコ、アルコール、その他の薬物
第十六章 医薬品による安らぎと結びつき
第十七章 体を動かすこととじっとしていること
第十八章 私たちの内なるエコロジー
本題に入る前に、ひとつご紹介したいサイトがあります。
これは、今回の本の初版が2008年であり、動物実験によるものが多いということから、「現在、オキシトシンに関する最新の研究成果はどうなっているんだろうか?」という疑問がありました。そこで、検索してみるととても興味深い、新しい記事(2022年8月26日)を見つけました。
これにより、オキシトシンが今も注目にあたいする物質であることを確信することができました。

『慶應義塾大学医学部薬理学教室の塗谷睦生准教授、横浜国立大学環境情報学府博士課程前期2年の中村花穂、慶應義塾大学医学部薬理学教室の唐澤啓子(研究当時)、同大学医学部薬理学教室の安井正人教授らの研究グループは、これまで直接見ることができず謎に包まれてきた、脳内のペプチド性ホルモンの一種であるオキシトシンを「見える化」するツールの開発と応用に成功しました。
オキシトシンは、分娩促進や授乳促進、母性行動などに関与し、母親が子を産み育てる上で重要なホルモンとして知られてきました。さらに近年、これらの効果に加え、日常生活の中で人間関係を築いていく社会的行動においても重要な役割を持つことが明らかにされ、ヒトを含む動物の精神を強力に調節する、脳内の神経伝達物質としての役割が注目を集めています。闘争欲や恐怖心を減少させ他人に対する信頼感を増加させる効果や、自閉スペクトラム症の中核症状である社交性を改善する効果から、一般的には「幸せホルモン」や「愛情ホルモン」という名称でも親しまれ、とても注目されています。』
PDF資料(4枚):左をクリックするとダウンロードされます。
ブログは4章と15章以外、目次の中の黒字の個所です。また、長くなったので5つに分けました。
冒頭の「はじめに―ないがしろにされてきた人生の一側面」は10ページにわたって記述されているのですが、その内容に思わず惹きつけられました。全てではありませんが、3つに分け、かなりの部分をご紹介させて頂いています。
はじめに―ないがしろにされてきた人生の一側面
『私たちは日頃、善と悪、光と闇、男と女、太陽と月というふうに、両極端を頭においてものを考えることが多い。どうしてそうなのかはわからないが、二元論的考えに慣れっこになっていて、自分がそういうふうに考えていると意識することもないぐらいだ。とくに、科学の方法論は、そういう考え方によって形づくられてきた。とはいえ、学問分野の中には、両極のうちの片方だけが明確に表現される、あるいは両極の片方だけが私たちの好奇心をそそる、そういう分野もある。
生理学は医学の分野のひとつで、生きている動物がいかに機能するかを明らかにしようとするものだが、その中でも特に多くの力が注がれたのは、心身の激しい活動とストレスの生理学だった。それはたいていの場合、〈闘争か逃走か〉反応を調べることを通して研究された。このよく知られた反応において、私たちヒトやその他の哺乳類は、立ち向かうか、逃げ去るか、いずれにせよ、ストレスとなる状況に対処できるような体勢を整える。私たちは怒りや恐れを、ときにはその両方を感じる。血圧が上昇する。栄養蓄積を含めて、消化器系の働きがほぼ停止する。反応が速くなり、痛みに対しては鈍くなる。体じゅうのエネルギーのすべてが、(現実のものであれ、想像上のものであれ)直面する脅威に対して身を守ることに向けられる。ポパイがホウレンソウを食べて世界一強い男になるように、〈闘争か逃走か〉反応の影響下にあるヒトその他の哺乳類は、短時間、ふだん以上の力を発揮する。私たちの体が自家製の「滋養強壮ドリンク」を、ホルモンと神経伝達物質の形で提供してくれるおかげだ。
私が本書で描き出したいと思っている、これまであまり研究されてこなかった生理学的パターンは、〈闘争か逃走か〉反応の対極にあるものだ。ほかの哺乳類もそうだが、私たちは、危険に直面して臨戦態勢にはいる能力に加えて、人生の良きものを楽しみ、くつろぎ、他者と結びつき、自らを癒す能力をもっている。人生の出来事においてだけではなく、生化学システムにおいても、〈闘争か逃走か〉パターンの対極に位置するものがある。本書があつかうのは、シーソーの反対側の端にあるシステムだ。私たちの体は、安らぎと結びつきを得るためのシステムを備えているのである。
〈安らぎと結びつき〉システムに関わりが深いのは、恐怖ではなく信頼と好奇心であり、怒りではなく好意である。循環器系はペースを落とし、消化器系はフル回転する。心が静かで安らいでいるとき、私たちは防御をとく。感受性が豊かになり、開放的な気分で、自分の周囲の人たちに関心を抱く。私たちの体は「滋養強壮ドリンク」ではなく「癒しのネクター」を提供してくれる。その影響下で、私たちは自分のまわりの世界やそばにいる人々を肯定的なまなざしで見る。私たちは成長し、癒される。〈安らぎと結びつき〉反応もまた、ホルモンならびに神経伝達物質の作用だが、これらの基本的な生理学的作用がどのようにして〈安らぎと結びつき〉反応をもたらすのかについては、まだ十分な確認や研究がなされていない。
このシステムが顧みられないできたという事実から、科学研究の背後にどういう価値観があるのかがよくわかる。〈安らぎと結びつき〉システムの維持にとって、〈闘争か逃走か〉システムと同じくらい重要かつ複雑であるのに、研究される頻度は、〈闘争か逃走か〉システムのほうがはるかに高い。たとえば、自律神経系(神経系のうち不随意的な身体機能を調整する部分)をあつかった論文のうち、休息や成長に関与している副交感神経部分に関するものは10パーセントに過ぎず、残りの90パーセントは、〈闘争か逃走か〉反応において活性化する交感神経部分に関するものだ。ストレスや痛みをテーマとする学術会議はよく催されるが、安らぎ、休憩、幸福をテーマとする学術会議はほとんどない。』
『〈安らぎと結びつき〉システムが働くのは、体が休んでいるときが多い。静かな見かけの下で、ものすごい量の活動が起こっているが、それらの活動は運動や急激な力の発揮には向けられない。〈安らぎと結びつき〉システムは体が自らを癒やし、成長するのを助ける。このシステムは栄養をエネルギーに変え、あとで使うために貯えておく。体も心も安らいでいる。そういう状態のときには、私たちは自分の中の資源や創造性を、よりよく利用できるようになる。ストレスにさらされていないときの方が、学習能力や問題解決能力は高くなる。
〈闘争か逃走か〉システムの対極にある〈安らぎと結びつき〉システムの身体的・心理的働きについて理解を深めることが、このうえなく重要だと私は信じている。個々の状況のもとで個々の人々が最適な反応をするには、この二つのシステムの両方が必要だ。しかし、長期にわたるストレスが、さまざまな心理学的・身体的問題を引き起こすことは、今では広く知られている事実だ。長い目で見て健康であるためには、この二つのシステムのバランスがとれていなくてはならない。』
『私がこの路線を選んだのには、個人的な理由もあった。四人の子の母としての経験から興味深い疑問がわいたのだ。妊娠中、授乳中、そして子どもたちと密接に接触していた時期に私が経験したのは、人生のほかの課題に挑戦するときにいつも感じていたストレスとは正反対の状態だった。私は妊娠や授乳に関係する精神生理学的状態がもたらすものは、挑戦・競争・達成にかかわる精神生理学的状態がもたらすものとはまったく異なることを知った。今から二十年以上も前、私はこの人生経験を科学的に探求しようとする過程で、重要な生物学的マーカーの存在に気づいた―その生物学的マーカーこそ、本書の主題である。
広く世界を見渡すと、心が平らかで安らいでいることを評価し、望ましい在り方だと考える伝統のある地域も多い。中国、ヒンズー、その他の文化は、この状態に到達するのに役立つさまざまな技術を開発してきた。今では西洋でも、より質の高い生活、より大きな幸福への道を求めて、瞑想・ヨガ・太極拳などが熱心に実践されている。
ストレスが増えつづけ、人と人とがばらばらになっていく一方の現代生活の中で、安らぎと、結びつきの必要性がますます切実に感じられるようになった。安らぎと結びつきへの渇望は、あわただしいライフスタイルを問い直し、心の平安と気持ちのいい人間関係に至る道を、意識的に探求するという形で表れる。しかし、この渇望が十分意識されず、きちんと認識されていない場合も多く、人によってさまざまに異なる対応の中には、長い目で見ると不健全なものもある。
たとえば、たっぷり食べ物をとれば―とりわけ脂肪分に富む食べ物をとれば、心が安らぎ、よく眠れるようになる。だが、いつもこのようにして自分をなだめる習慣がつくと、不都合な結果が生じるのは明らかだ。酒も心に安らぎを与え、眠気を誘う。ストレスに満ちた一日のあとで、気持ちをほぐす手段として飲酒する人は多い。だが、これもまた、問題を生じかねない。ストレスや不安や抑うつに悩む人々が、医師に処方された薬を飲む場合も同様だ。直接的な依存性があるとは考えられていない最新の薬であっても、望ましくない副作用があることは大いに考えられる。
エクササイズによって、体重をコントロールする効果だけでなく、心の落ち着きや安らぎが得られると感じる人もある。鍼、指圧、マッサージ、各種のエナジー・トリートメント〔訳注 レイキ(霊気)など、気を用いる療法〕など、代替医療を定期的に受けることが、身体症状を軽くするだけでなく、安らぎを得るのにも役立っていると感じる人もいる。瞑想や祈りなどのスピリチャルな活動を実践することによって、心が静まり、リラックスできると感じる人も多い。
本書をお読みになれば、体と心を通して憩いと幸福へと至るさまざまな方法が、一見、まったく異なっているように見えても、実際には共通点をもっていることがおわかりになるだろう。それらの方法はすべて、私たちの体内の同じシステムを活性化することで目的を果たしているように思われる。そしてその手助けをしているのは、オキシトシンという非凡な生化学物質であるようだ。
本書で展開される分析は、私自身の、そしてほかの人たちの研究によって裏づけられている。この長い年月の間に、〈安らぎと結びつき〉システムの生理学的プロセスに同じような関心をもち、この研究が健康と幸福にとって大きな意味をもつという共通の確信を抱く仲間がふえ、ネットワークが形成された。このネットワークを構成しているのは、研究者仲間や院生だけではない。関心をもつ一般の人もたくさん参加している。それらの人々は私たちと貴重な経験を分かち合い、研究のヒントをたくさん与えてくれた。
オキシトシンの効果についての考えは、動物実験ならびにヒトでの観察と測定に基づいている。私はそれらの知見から、まだ科学的解明が進んでいない事柄について、推測し、仮説を立てる。私がそのようにするのは、科学的研究によってこの分野が十分に探査されているわけではない現状において、「大まかな絵」を浮かびあがらせ、〈安らぎと結びつき〉システムの全体像をつかめるようにするためだ。私はオキシトシンを、私が〈安らぎと結びつき〉システムと呼ぶ広範な生理学的作用と結びつけ、ひとつの主張をうちたてようとしている。私が根拠とする証拠は説得力のあるものだが、状況証拠にすぎない場合もある。私のしていることは、いくつかピースが足りないジクソーパズルを嵌め合わせることに似ている。手持ちのピースを組み合わせて、二、三歩後ろに下がり、より広い視野の中で見ると、〈安らぎと結びつき〉システムの全体像がどんなふうになるか、見当がつく。
この短い著書で、この分野でなされてきたすべての研究の概要を紹介することは不可能だ、だから私は、そうする代わりに、いくらかの科学的な成果を出発点として、私たちが安らぎと結びつきをいかに切実に必要としているか、その状態がいかにして生み出されるか、それが私たちの健康にどのようなよい影響をもたらすかについて、自由に考えをめぐらせた。これらの問題は、今後、科学者がさらに探求していかなくてはならない重要な問題だと私は信じている。』
不妊治療と流産
不妊治療に取り組みながらの流産は、極めて厳しい現実です。
なぜ起きるのか、鍼灸師としてできることは限られますが、少なくとも、何が起きたのか、どうして起きたのかを知ることは、良い施術の第一歩になることは間違いないと思い、特集のタイトルが気になった今回の雑誌を購入しました。
特集:『No more! 流産』
1.流産は、なぜ起こる?
2.着床するということは?
3.不妊治療と流産
4.体外受精と胚移植
5.体外受精と着床障害
6.着床障害の検査と治療 胚、胎児側の問題
7.胚の染色体の数を調べる PGT-A
8.胚の染色体の形を調べる PGT-SR
9.着床障害の検査と治療 母体側の問題
10.不育症なの? なんども流産してしまう
11.不育症の検査
12.不育症のリスク因子と治療 内分泌異常/血液凝固異常・自己抗体①
13.不育症のリスク因子と治療 血液凝固異常・自己抗体②
14.不育症のリスク因子と治療 子宮形態異常/夫婦の染色体構造異常/リスク因子不明
ブログで取り上げたのは、目次の中の黒字部分です。
『流産は、その経験が一度であっても、精神的なダメージが大きく、「生まれてこられたはずの命なのに、流産は自分のせいだ」と思い、深く傷つく人もいます。また、次の妊娠に気持ちを向けようとしても、「また流産してしまったら…」と思い、なかなか前向きになれない人もいるでしょう。
そして、不妊治療をしている人のなかには、胚移植をしても着床しない。生化学的妊娠[妊娠反応が陽性になったのみ]を繰り返してしまう…と悩んでいる人も少なくありません。
流産は、とても辛い出来事ですが、それが次の妊娠へ、赤ちゃんが授かる方法へと導いてくれることもあります。』
1.流産は、何故起こる?
1)流産とは
・妊娠22週より前に妊娠が終わること。22週とは赤ちゃんがお母さんのお腹の外では生きていけない週数のことである。
・流産は全妊娠の約15%に起こり、妊娠経験のある女性の約40%が経験しているとされている。
・妊娠12週未満を「早期(初期)流産」、妊娠12週以降22週未満の流産を「後期流産」という。流産の約80%は早期流産で、その原因のほとんどは胎児の染色体異常といわれ、偶然に起こる。
2)流産ではない生化学的妊娠
・生化学的妊娠とは、尿中や血中に妊娠反応があったという生化学的な反応だけで終わってしまうことである。「化学流産」と呼ぶこともあるため、流産と誤解されることもあるが、生化学的妊娠は流産に含まれない。
・生化学的妊娠の原因のほとんどは、胚の染色体異常から起こる自然淘汰がほとんどである。
・本来の妊娠は、超音波検査で胎嚢が確認できた臨床的妊娠をいう。
3)流産の兆候は
・妊娠6週頃になると、超音波検査で胎児の心拍が確認できるようになり、流産する確率は低くなる。
・流産の主な兆候は出血と腹痛である。腹痛は子宮の収縮により腹部が痙攣したような痛みが起こる。
・超音波検査で診断される稽留流産の場合は、出血や腹痛はないのが特徴である。
・腹痛、出血は流産とは限らないが、気になる兆候であることは間違いないので、病院で受診すべきである。
4)流産の確率
・年齢が高くなると、妊娠は難しく、流産はしやすくなる。
・40歳以上になると流産のリスクは高まる。なお、流産のリスクはグラフを見ると、体外受精の場合の方が低い。
注)以下の2つのグラフは時期およびデータ元が異なる。
5)流産は予防できる?
・切迫流産とは流産しかかっている状態であり、妊娠12週未満の場合には、特に有効な薬はなく、安静にして経過観察することになる。
・喫煙、風疹などの予防接種、糖尿病などの基礎疾患にも注意が必要である。
・栄養面で、葉酸摂取が推奨されているのは、神経管閉鎖障害の予防である。
2.着床するということは?
1)着床は、どのように起こるのか
①胚を受け入れる準備
・卵胞が成長するにつれ、卵巣はエストロゲンを分泌し、子宮内膜を厚くする。
・エストロゲンによって厚みを増した子宮内膜は、プロゲステロンによって着床しやすい状態に整えられる。
②受精から胚の成長
・卵管膨大部で卵子と精子は受精し胚になる。
・受精後は卵管内で細胞分裂を繰り返し成長しながら子宮へと運ばれていく。
・胚の栄養は卵管液だが、8細胞期まではピルビン酸と乳酸、8細胞期以降はグルコースを栄養にして、胚自体の力で発育するようになる。
③着床のはじまり
a.胚は、将来赤ちゃんになる細胞側を子宮内膜に接着させる。
b.胚は、内膜に接着するとすぐに潜り込んでいく。
c.胚は、子宮内膜を分解して、自分のものにしながら、胎盤をつくるためにhCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)の分泌を始める。

画像出展:「人体の正常構造と機能」
hCGは通常14日間以内に機能を失う黄体を刺激することにより、退縮なく機能を8週から10週維持する。
注)左端のぼやけて見えない部分は、「胎児精巣を刺激」になります。
d.胚は、hCGを分泌する。このホルモンが血液や尿中から検出されると妊娠反応が陽性になる。
e.胚が完全に潜り込むとその痕を塞さぐ。こうして着床が完了する。
3.不妊治療と流産
1)不妊治療をする夫婦は流産しやすいのか
・39歳以下では自然妊娠と体外受精の流産率に差はない。
・40歳以上では体外受精での流産率は低くなる。考えられる理由は以下の通り。
-体外受精では着床の可能性の高い胚を選択して移植できる。
-凍結融解胚移植では、子宮内膜、ホルモン環境を調整し、移植時期の最良のタイミングを選択も可能である。
・体外受精の場合、不妊原因を持っていたり、年齢層がやや高いという点では流産しやすい要因も存在している。
2)不妊治療をする夫婦は生化学的妊娠になりやすいのか
・卵子の老化は染色体異常の発生率を高め、卵子の力を低下させる。卵子はもともと染色体異常が起こりやすく、排卵した卵子の約25%に染色体異常があるといわれ、40歳前から上昇する。
・染色体数の異常のため受精が完了しない、胚が成長しない、着床しない、流産が起こる。もしくは染色体の数に問題を持った子どもが出生することにもつながる。
5.体外受精と着床障害
1)着床障害とは
・良好胚を何度も移植しているのに妊娠しない人、あるいは生化学的妊娠を繰り返している人は、着床障害の可能性がある。
・着床は、胚の問題がないこと、子宮内膜の厚さが十分にあること、胚移植と着床時期のタイミングがあっていることなどの条件が大切である。
2)胚移植と着床
・胚移植は、胚盤胞移植と凍結融解胚移植が多くなってきている。
・胚盤胞の場合は、程なく着床が始まり過程は自然妊娠と変わらない。一方、体外受精の場合にはプロゲステロンを補うための服薬、膣剤、貼付薬、注射などを使い、採卵(排卵相当日)から約16日後に妊娠判定を行うのが一般的である。
3)より着床しやすい胚移植とは
・凍結技術の進歩により、凍結・融解による胚へのダメージは、ほぼ心配することはなくなった。その結果、全ての胚を凍結して、子宮内膜やホルモン環境を整え、患者さんの都合に合わせて凍結融解胚移植を行う治療施設が増えてきている。
4)凍結融解胚移植の移植日
・着床しやすい時期は、通常排卵から5日目あたりで、“着床の窓”と呼ばれている。
・凍結融解胚移植の場合、移植胚の成長程度と子宮内膜の状態を同調させるため、排卵、または排卵の相当日から胚移植日を決定する。
・3つの方法
①自然周期
-自然排卵により排卵日から胚移植日を決定する方法。
②排卵誘発周期
-クロミフェンなどの服用する排卵誘発剤を使い、排卵を起こさせて胚移植日を決定する方法。
③ホルモン補充周期
-ホルモンを補充し、内膜の黄体化[卵子を排出した卵胞が黄体という組織に変化し、分泌されるプロゲステロンによって子宮内膜が厚くなる]を行った日から、胚移植日を決定する方法。
6.着床障害の検査と治療 胚、胎児側の問題
1)着床障害の検査
・着床障害には、明確な定義はなく、各治療施設によって異なるが、要因は胚または胎児側の問題と母体側の問題がある。
2)胚・胎児側の問題
・胚の染色体の数の異常や構造異常が原因で着床しない、もしくは生化学的妊娠によるものがある。
・流産全体の80%以上は、妊娠12週未満に起こる早期流産である。
・染色体の数の異常については、偶発的に起こる卵子の減数分裂の失敗や、受精時に起こる多精子受精などが要因になっている。
・受精は卵管膨大部で起こるが、受精の際、卵子に2個、3個の精子が入ることがある(多精子受精)。この結果、すべての染色体の数が3本(3倍体)、4本(4倍体)となり倍数体の異常が起こる。
・倍数体の異常は、卵子の極体がうまく放出できなかった場合や単為発生(卵子が精子と受精することなく活性化して前核が形成される:1倍体)の場合などがある。
9.着床障害の検査と治療 母体側の問題
1)母体側の問題
①子宮内膜環境の問題
・慢性子宮内膜炎
-子宮内膜の深い基底層にまで細菌が侵入して炎症が起こり、その炎症が持続している状態。
-慢性子宮内膜炎は自覚症状のない人が多く、なかなか着床しないことから発見されることも少なくない。
-慢性子宮内膜炎は不妊治療経験者の約30%、繰り返し胚移植にもかかわらず生化学的妊娠や流産を繰り返す人の約60%にあるといわれている。
・子宮内細菌(フローラ)
-2015年、子宮内に細菌(フローラ)が存在することが確認され、子宮内フローラの乱れが体外受精に悪影響を及ぼすことや、子宮内膜で免疫が活性化し、胚を異物として攻撃してしまう可能性が指摘されている。
-膣内環境や腸内環境が子宮内環境に影響している可能性も考えられている。
・ビタミンD不足
-ビタミンDの不足が着床を難しくしているという研究発表がある。ビタミンDは食事以上に、日光によって作られる方が多いと考えられているので、妊活中は1日30分程度、日に当たるよう心掛けることが重要である。
②胚移植のタイミングの問題
・着床は排卵から5日目というケースが多く、それに合わせて胚移植するが、約30%の人には着床時期にずれがみられる。
③免疫寛容の問題
・胚は卵子と精子が受精したものだが、外からの精子は非自己(自分自身ではないもの)である。にもかかわらず、拒絶反応が起こらないのは免疫寛容という働きによりものだが、免疫寛容に異常があると拒絶反応が起こり、それが着床障害の原因になる可能性がある。
・免疫寛容は、免疫応答の司令塔とされているT細胞が関連し、着床にはTh1細胞<Th2細胞の関係が通常であるが、なかなか着床しない人の中には、Th1細胞が優位になっている場合がある。
10.不育症なの? 何度も流産してしまう
1)不育症とは
・妊娠はするが流産を繰り返したり、死産になってしまったりすることを不育症と呼ぶ。
2)流産の要因は
・流産は全妊娠の約15%に起こり、胚の染色体異常による流産は、妊娠のごく初期に起こる。
12.不育症のリスク因子と治療 内分泌異常/血液凝固異常・自己抗体①
1)不育症のリスク因子とは
①内分泌異常
・甲状腺ホルモンの異常、多いのが「甲状腺機能亢進症」で、少ないのが「甲状腺機能低下症」であるが、いずれも流産のリスク因子である。
・糖尿病は不育症のリスク因子にあげられているが、ケースとしては多くないとされている。しかし、流産や早産のリスクに加え、心臓肥大など出生後に正常な発達、発育の問題が起こる可能性があるため、妊娠前からの血糖のコントロールが大切である。
②血液凝固異常・自己抗体
・血液凝固異常とは、血小板の異常や血液を凝固させるタンパク質の異常などによって起こり、止血が難しい出血傾向と凝固させやすい血栓傾向がある。不育症のリスク因子は後者である。
13.不育症のリスク因子と治療 血液凝固異常・自己抗体②
1)低用量アスピリン療法
・アスピリンには血小板を抑え、血液をサラサラにする効果がある。投薬の終了時期は、28週まで、もしくは36週までと医師によって判断は異なっている。
・妊婦禁忌とされており、アスピリンアレルギーの人もいるので、医師に相談すべきである。
2)低用量アスピリン+ヘパリン療法
・ヘパリンは血液凝固因子を抑えることで血栓を予防する。
・ヘパリンの開始時期は「妊娠が陽性になってから」あるいは「胎嚢が確認できてから」が一般的で、1日2回、12時間ごとの注射が、妊娠36週頃まで毎日、必要になる。
14.不育症のリスク因子と治療 子宮形態異常/夫婦の染色体構造異常/リスク因子不明
1)子宮形態異常
・子宮は胎児期には左右2つあるが、出生前には融合して1つになる。この融合がうまくいかないことが原因で、子宮の形態異常は発生する。特に中隔子宮が不育症のリスク因子に上げられている。
・中隔子宮は、外観は正常だが子宮腔内に仕切りのようなものがあり、内腔が左右に分かれている形態異常である。
・患者あたりの生児獲得率は、手術したグループで77.5%、しなかったグループでは53.8%であり、手術が必須とまではいえない。
2)夫婦の染色体構造異常
・夫婦のどちらかの染色体に構造異常があるために、流産を繰り返すもの。
3)偶発的流産・リスク因子不明
・不育症の中で一番多い。検査をやっても「異常なし」と診断される。なお、胎児の染色体異常はこの中に含まれる。
4)テンダーラビングケア
・『ストレスと流産についての因果関係は、はっきりしていません。
ただ、流産後、次回の妊娠に臨む前に、臨床心理士や産婦人科医がカウンセリングを行った方がストレスが改善し、妊娠成功率が高かった、という不育症研究班の報告があります。
なかでも最近、注目されているのがテンダーラビングケア(TLC)です。流産してしまった人に「優しく、愛情を持って接し、いたわる」ことで、次回の妊娠が継続し、出産に至る確率が上がるといいます。
とくに流産直後は、ストレスを強く感じ、辛い気持ちの中で過ごす時間も多くなることと思います。
心が痛い、辛いと感じるときは、無理せずに通院施設のカウンセラーや心理士、また心療内科を訪ねてみましょう。』
※ご参考
ストレスとうまくつきあう:『思うように授からないことや不妊治療がストレスになることも。不妊とストレスの関係について』
感想
ビタミンDは日光、腸内環境は食事、睡眠、運動などの生活習慣が重要です。一方、強いストレスなどによる自律神経系の乱れは、内分泌系や免疫系にも悪影響を及ぼします。
また、不妊症の方は“冷え”を訴えることが多く、これも自律神経系が交感神経優位になって、血管を緊張させ血液の流れを悪くしていることが要因の一つです。
以上のことから、日常生活で直面する過度な緊張、ストレスを減らすことが重要です。鍼灸治療は心身をリラックスさせます。自律神経系を整え、冷えを改善します。そして、子宮内膜が「ふかふかのベッド」になったとき、朗報は近くまで来ているのではないでしょうか。
糖化(AGE)
「摂りすぎた糖は、AGEとなって大量の活性酸素を生み出す」ということは知っており、活性酸素が炎症を亢進させる重要な元凶の一つであるということも知っていました。
しかしながら、この重要なAGEについてはもっと詳しく知りたいと思っていました。
“AGE”は“終末糖化産物”と訳されることが多いようですが、『「糖化」を防げば、あなたは一生老化しない』の著者である久保先生は“糖化最終生成物”と訳されています。どちらが良いということもないので、以降、すべてAGEとさせて頂きます。なお、AGEはAdvanced Glycation Endproductsになります。
AGEについては、福岡市の”おおた内科消化器クリニック”の太田先生のホームページに詳しく書かれいます。
ブログでは目次の黒字部分を取り上げています。
目次
プロローグ
体が「糖化」すると「老化」してしまう
糖化こそ、老化や病気を引き起こす元凶だった!
「抗糖化」の食習慣で老化の進み具合が大きく変わる
第1章 老化・病気・不調すべての原因は体の糖化にあった!
―糖とどうつき合うかで人生が変わる
長生きするも早死にするも、すべては「糖」次第
AGEという不良がはびこると、体が活気を失う
ホットケーキもクッキーも糖化だった
「酸化」と「糖化」は“兄弟分”。いつも影響し合っている
食後1時間の血糖値の上がり方で糖化リスクが分かる
「食後1時間対策」で10年後の人生に大きな差がつく
第2章 あなたの体をボロボロにしてしまう糖化のメカニズム
―糖化はゆるやかな死への行進
AGEが悪さをしでかす2つのパターン
AGE架橋で体中のたんぱく質が“化石化”していく…
たんぱく質の機能低下が進むと全身がボロボロに…
動脈硬化の真の原因は細胞の炎症だった!
糖化はゆるやかな死への行進
糖化が引き起こす主な病気
《糖尿病・糖尿病合併症》
《動脈硬化・心筋梗塞・狭心症・脳梗塞・脳出血》
《認知症・アルツハイマー病》
《非アルコール性脂肪肝(NASH)》
《骨質が悪くなる》
《肌のトラブルが起こりやすくなる》
だるさや疲れやすさも糖化の影響の影響!?
第3章 体が糖化する食べ方、糖化しない食べ方
―糖化を防ぐ食べ方 5つのコツ
血糖値を急上昇させない食べ方が基本
糖質を敵視しすぎない姿勢が大切
「超低炭水化物ダイエット」の大きな落とし穴とは?
極端な糖質制限は医学的にも危険!
高GI&高カロリーの食事が連続するのを避ける
「食事記録」をつけて食べすぎている自分に気づく
「プチ減食デー」を設けて食生活を改善
食べ方をひと工夫するだけで糖化は防げる!
食べ方のコツ① 「懐石食べ」で血糖値の急上昇を防ぐ
食べ方のコツ② 緑の野菜をたくさん食べる
食べ方のコツ③ 糖化した食品を取りすぎない
食べ方のコツ④ 昼食を「食生活の切り替えポイント」にする
食べ方のコツ⑤ 食後1時間に体を動かすようにする
糖化メニューおすすめレシピ
メニュー① ライ麦パンアボガドディップ/野菜と豆のスープ/アイスカフェオレ
メニュー② 全粒粉パンのトーストポタージュ浸し/野菜とフルーツの豆乳ジュース
メニュー③ カブのみぞれ中華がゆ アジのなめろう添え/キュウリの昆布和え/フルーツ大豆ヨーグルト
メニュー④ 旬菜と蒸し鶏のパスタ/グリーンサラダ/餃子スープ
メニュー⑤ 豆腐のカニあんかけ/モロヘイヤとオクラの梅和え/キノコごはん
メニュー⑥ 鶏団子のカレースープ煮/ワカメとキャベツのゆず酢醤油和え/雑穀ごはん
COLUMN
健康的ダイエットで「サーチュイン遺伝子」が活性化する!
第4章 今日からはじめる!「抗糖化」の生活術
―抗糖化力を高めるために役立つ知恵Q&A
「抗糖化力」を高める生活術で若々しさをキープ!
Q1:カレーライスは糖化を進める危険メニュー!?
Q2:バイキング料理は糖化にとっては“鬼門”?
Q3:「炭水化物オン炭水化物」のメニューはNG?
Q4:ごはんを食べすぎないためのコツは?
Q5:やっぱり白米よりも玄米のほうがおすすめ?
Q6:間食するなら「糖分控えめチョコレート」!?
Q7:早食いはやっぱりよくない?
Q8:ハーブティが糖化防止にいいって本当?
Q9:抗糖化サプリメントってあるの?
Q10:夜、食べすぎてすぐ寝てしまうと糖化が進みやすい?
Q11:糖化にとってアルコールは? たがこは?
Q12:ストレスは糖化にも悪影響を与えるもの?
エピローグ
糖といいつき合い方をして充実した人生を
プロローグ
糖化こそ、老化や病気を引き起こす元凶だった!
・AGEは体に余分な糖が多くなり、たんぱく質と結びつくことで発生します。
・AGEが問題なのはたんぱく質でできた組織の変性、劣化を亢進させてしまうためです。
第1章 老化・病気・不調すべての原因は体の糖化にあった!
―糖とどうつき合うかで人生が変わる
AGEという不良がはびこると、体が活気を失う
●「何故、たんぱく質と結びついてしまうのか」、食事により血糖が上がっても、すい臓からインスリンが分泌され血糖は調節されます。しかしながら、あまりに血糖が多かったりインスリンが適切に分泌されない、あるいはインスリンの働きが悪かったり等、問題があるとインスリンでは対応できず、その結果、余った血糖は体中のたんぱく質と結びつき、変性してAGEとなって様々な問題の原因となります。
ホットケーキもクッキーも糖化だった
●AGEが体内に蓄積されるのは、余った糖がたんぱく質と結びついてAGEが生成される経路と、食べ物にもともと含まれるAGEが口から入ってくる経路との2つのルートがあります。ただし、後者は焼きすぎに注意し、焦げたところは食べないように注意している限り、それほど心配するものではないとされています。
●体内のAGEは白血球の一種である貪食細胞のマクロファージが体内の異物を食べてくれるため、一部のAGEは体外へと出ていきます(代謝)が、重要なことは食べすぎや糖の摂りすぎに注意することです。
「酸化」と「糖化」は“兄弟分”。いつも影響し合っている
・活性酸素は体内に入ってきた脂質を酸化させ、劣化した脂質(過酸化脂質)が、体内に居座るようになると、全身の細胞が傷つき老化の大きな原因になります。
・糖化と酸化は影響し合いながら進行する“兄弟分”のようなものです。糖の劣化には酸化や酵素の力が作用しており、酸化の度合いが大きければ、糖化も起こりやすくなります。
第2章 あなたの体をボロボロにしてしまう糖化のメカニズム
―糖化はゆるやかな死への行進
AGEが悪さをしでかす2つのパターン
①体を構成するたんぱく質にAGEが直接くっついて、その機能を低下させてしまうパターン。
②AGEが受容体とくっついて、その受容体を通して細胞に炎症を引き起こすパターン。
動脈硬化の真の原因は細胞の炎症だった!
●AGEにはRAGEという受容体があり、AGEとRAGEが結びつくと細胞内の情報伝達に変化が起こり、炎症シグナルが活発になります。これにより、個々の細胞に炎症が引き起こされます。炎症は細胞の機能を低下させ、老化のスピードに拍車をかけます。特に大きな打撃を受けるのが血管であり、血管内側の壁細胞の炎症が動脈硬化の真の原因でないかとみられています。
《認知症・アルツハイマー病》
●認知症には「脳血管型」と「アルツハイマー型」の2つがあるが、どちらのタイプにもAGEの関与が認められます。
●アルツハイマー病のβ-アミロイドというたんぱく質が脳内にたまると「老人斑」というシミができるのですが、調べるとAGEがたくさん検出されます。このAGEは脳細胞の死滅にも関与しているとされています。
《骨質が悪くなる》
●骨粗しょう症の原因の6~7割は「骨密度」が原因とされていますが、残りの3~4割は「骨質」の低下にありますが、AGEはコラーゲンたんぱくの中に入り込んで骨の構造を脆くします。
第3章 体が糖化する食べ方、糖化しない食べ方
―糖化を防ぐ食べ方 5つのコツ
血糖値を急上昇させない食べ方が基本
・意識的に血糖値の上昇を抑制するには、血糖値を急上昇させないような食品を食べるように注意することをお勧めします。
食べ方をひと工夫するだけで糖化は防げる!
・糖とうまくつき合っていくための工夫が重要です。
食べ方のコツ④ 昼食を「食生活の切り替えポイント」にする
・1日3食のトータルバランスを考えて、お昼のメニューを決めるようにするのも良い工夫です。栄養バランスや食べすぎ傾向にも注意を払うようになります。1日に1度、自分の食事や健康を考える時間を持つことはとても大事なことです。
食べ方のコツ⑤ 食後1時間に体を動かすようにする
・食後1時間をねらって体を動かすようにすると、血糖値は大きく下がります。
エピローグ
糖といいつき合い方をして充実した人生を
●『人間はしょせん“たんぱく質の塊”です。そのたんぱく質を生かすも殺すも糖次第。あふれた糖が牙を剥けば、たんぱく質は糖化してAGEになりますし、糖が適量であれば、たんぱく質がしっかり機能して長く健康に生きるためのエネルギーとなる。言わば、人間という“たんぱく質”の運命は糖が握っているようなものなのです。』
家族性高コレステロール血症(FH)
健診でLDLコレステロールは194、総コレステロールは344、ただしHDLコレステロール(61)と中性脂肪(87)は基準値内でした。そして、父親が40台後半に心筋梗塞で他界し、母親もLDLコレステロールが確か130前後だったと記憶していますので、間違いなく、私は“家族性高コレステロール血症(ヘテロ型)”だろうと思います。
こうなると、「家族性高コレステロール血症とはどんなものか?」と一気に興味が押し寄せるくるのですが、調べたところ本は少なく、あってもなかなかの高額の本ばかりでした。また、期待の地元の図書館も空振りでした。
そこで、今回はネットにある情報を中心に勉強しました。
家族性高コレステロール血症(FH:Familial Hypercholesterolemia)
1.LDL受容体の異常により高LDLコレステロール血症を呈する常染色体性優性遺伝性疾患である。
2.遺伝形式にはホモ型とヘテロ型がある。
●ホモ接合体とヘテロ接合体
・ホモ型
-両方の遺伝子に異常がある場合で、LDLコレステロール値は500~900㎎/dL、総コレステロール(TC)値は600㎎/dL以上になることが多い。
-一般的には、100万人に1人と言われているが、日本では16万人に1人という研究報告もある。
・ヘテロ型
-どちらか一方の遺伝子に異常がある場合で、LDLコレステロール値は150~420㎎/dL、総コレステロール(TC)値は230~500㎎/dL以上になる。
-一般的には、500人に1人と言われているが、日本では200人に1人という研究報告もある。
●主な症状
・黄色腫
-腱や皮膚などに蓄積する黄色い塊である。
-ホモ接合体の10歳までの子ども時代に認められ、成長とともに盛り上がった状態になる。
-黄色腫は、肘やひざの他、手首、おしり、アキレス腱、手の甲などに多く見られる。
-重症のヘテロ接合体では皮膚に黄色腫が見られることがある。その多くは成人以降に現れる。
・結節性黄色腫
-重症のFHに見られる。
-黄色または淡紅色の結節で、肘・膝関節、手背、足部、殿部に好発する。
・角膜輪
-家族性高コレステロール血症(FH)に特異的とはいえない。
-白色輪(白色~灰青色)を呈する。
●原因遺伝子
・19番染色体の19p13.2という位置に存在する“LDLR遺伝子”。この遺伝子は“LDL受容体”というタンパク質の設計図となる遺伝子である。LDLR遺伝子の変異により、細胞表面にあるLDL受容体の数が減ったり、LDL受容体が正しくLDLを取り込めなくなったりする。そのため血中のLDLコレステロール値が高くなる。
・APOB遺伝子、PCSK9遺伝子、LDLRAP1遺伝子も、この病気の原因遺伝子として同定されている。それぞれの位置は順に、2番染色体(2p24.1)、1番染色体(1p32.3)、1番染色体(1p36.11)である。これらの遺伝子から作られるタンパク質は、いずれもLDL受容体が正常に機能するために不可欠であり、変異によって、血中のLDLコレステロール値が高くなる。
・これら4つの原因遺伝子に変異がなく、原因遺伝子がまだ見つかっていない家族性高コレステロール血症の人たちもいる。
●日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版」の FH診断基準
(1) 未治療時の LDL-C 値が180 mg /dL以上
(2) 皮膚結節性 黄色腫または腱黄色腫の存在
(3) 二親等以内に家族性高コレステロール血症(FH)または若年性冠動脈疾患患者がいる
の3つのうち2つ以上で FHと診断できる。
●ヘテロ接合体の診断から治療
・角膜輪やアキレス腱黄色腫は10代後半から 30歳までの半数に認めらる。
・冠動脈疾患は、男性は30歳以降、女性は50歳以降に現れるとされているが、より若年で発症する例もある。
・アキレス腱肥厚は LDL−C高値とその曝露期間に影響され、冠動脈疾患発症リスクともよく相関するため、家族性高コレステロール血症(FH) の診断には有用である。定量的にはX線軟線撮影で9mm以上を異常と判定する。
以下の画像は「家族性高コレステロール血症 (FH)」さまより拝借しました。
・ヘテロ接合体の疑いがある場合には、遺伝子検査による診断が望ましい。日本における家族性高コレステロール血症(FH)の診断率は1%未満であり、多くの人は気づいていない。
・家族性高コレステロール血症の基本薬はスタチンである。クレストール(ロスバスタチン)、リピトール(アトルバスタチン)、リバロ(ピタバスタチン)など“スーパーストロング”、“ストロングスタチン”、“スタンダードスタチン”に分類され、特に服用できない理由がない限り積極的に使う。家族性高コレステロール血症では管理目標値に到達するまで、必要があれば上限量まで使うことも可能である。
・スタチンのみでは十分な効果が得られない場合、エゼチミブ、PCSK9、阻害薬、胆汁酸吸着レジン、プロブコール、フィブラート系薬剤、ニコチン酸製剤などの、他の脂質低下薬の併用が検討される。PCSK9阻害薬は注射薬、その他は内服薬である。
・筋肉痛、肝機能障害などの副作用によりスタチンが使用できない場合は、これらの薬を単独または併用で治療する。
・ガイドラインでは、家族性高コレステロール血症(FH)の場合、LDLコレステロールの値は、100mg/dl以下を目標とするとされているが、200を超えるようなLDLを100以下にするのは困難なため、治療前の半分の改善値でも可とされている。
・家族性複合型高脂血症という類似疾患や、シトステロール血症、脳腱黄色腫など皮膚黄色腫を示す別の疾患、甲状腺機能低下症、ネフローゼ症候群、糖尿病などの高LDLコレステロール血症を示す別の疾患などとの鑑別診断も必要である。
“家族性高コレステロール血症”と“家族性複合型高脂血症”の違いは、前者がLDLコレステロールが顕著に高値になる一方、後者は中性脂肪も高値になるところが特徴的である。
small dense LDLはLDLの中でも粒子が小さく、血管内膜に入り込みやすく、酸化・変性しやすいという特徴を有している。
追記
かかりつけ医の先生から処方されたのは、“ピタバスタチン2mg”で期間は50日間でした。
筋肉や肝臓への副作用に注意する必要がありますが、幸い何も問題は出ず、肝心のLDLコレステロールの数値も、194mg/dLが102mg/dLまで下がりました。
やはり、家族性高コレステロール血症なのだと思います。また、良い薬があって本当に良かったなと思う反面、今後、一生服用し続けるのだろうとも思いました。
かゆみ2
Part7 かゆみの治療の基本とコツ
●かゆみの原因はわかりづらい―原疾患の治療が先決
・かゆみには原因がわからないものは沢山ある。肝疾患や腎疾患もかゆみの原因は分かっていない。
・かゆみの治療の基本は以下の4つ
1)かゆみは炎症性の疾患が多いので、まずは炎症や免疫反応を抑える治療を行う。
2)かゆみを起こしている原因物質(メディエーター)、「かゆみメディエーター」の働きを阻止する治療を行う。
3)かゆみを感じる知覚神経の感受性を低下させる方法、かゆみ刺激に対して鈍感にさせるもの、特に乾燥肌ではこの方法が重要である。
4)かゆみを悪化させる要因(増悪因子)を回避する方法である。なお、この増悪因子は個々による違いが大きいので、オーダーメイドの治療が必要になる。
●ヒリヒリ感でかゆみを抑える―効用が不明なかゆみ止めも
・『江畑先生は、臨床皮膚科医としての立場から、「市販の外用薬を使う前に、まず保湿剤を塗るだけにしませんか」と、提案されています。保湿剤だけでおさまるかゆみは多いのです。「保湿クリームなどを使わずにかゆみをおさまった」、という方もおられるかもしれません。しかし、その場合でも、実際は、使用した外用薬の中に含まれていた保湿成分(ワセリンなど)が効いた可能性があるのです。』
Part8 かゆみ止め薬を使わない治療法
●脳への電気刺激がかゆみを止める!―経頭蓋直流電気刺激法
・生理学研究所では経頭蓋直流電気刺激法(tDCS)によるかゆみ知覚の抑制効果を明らかにした。
・tDCSを第一次感覚運動野に15分間施行した実験では、ヒスタミンによるかゆみが減少し、かゆみの持続時間も短縮した。
・tDCSでは完全にかゆみを取ることはできないが、一般のかゆみ止め薬が効かない場合には試す価値はある。

画像出展:「世界にかゆいがなくなる日」
以下は理化学研究所の記事です。
また、以下をクリック頂くと、PDF3枚の資料がダウンロードされます。写真も出ています。
Part9 かゆみ研究最前線(人間を対象とした研究)
●かゆみ刺激に対する脳活動の不思議―大脳辺縁系と前頭葉がともに活動
・機能的MRI検査によって驚くべき結果を得ることができた。それは、かゆみ刺激は他の皮膚感覚(触覚など)とは、全く異なる複雑な信号処理が行われていることである。人間の神経は、運動系も感覚系も、脳内や脊髄内で交差して、反対側に作用する。つまり、右脳に脳出血が起こると反対側の左半身が麻痺する。感覚も同様で、右手に触覚刺激を与えると、その信号処理はほとんど左脳で行われる。かゆみ刺激の場合には、身体のどこを刺激しても、両側の脳が左右対称的に活動する。脳内では、かゆみは独特の複雑なネットワークを伝わって、左右の脳半球にかゆみ信号が伝わる。
Part10 かゆみ研究最前線(動物実験)
●脊髄の神経が関係する慢性的なかゆみ―マスト細胞の分化・増殖機能の解明
・『2015年に、九州大学の津田誠教授のグループから、画期的な研究が、世界でもトップクラスの医学誌「Nature Medicine」に報告されました。アトピー性皮膚炎に代表される慢性的なかゆみの、神経科学的メカニズムに関する研究です。
津田教授らは「グリア細胞」に注目して研究を行ってこられました。脳や脊髄には、神経細胞とグリア細胞の2種類があります。脳と脊髄の活動には神経細胞が重要で、グリア細胞は、神経細胞と神経細胞の間を埋めるだけの脇役というのが、以前の常識でした。グリアは英語のGlue。糊とか「にかわ」という意味で、まさに、神経細胞間をつなぎとめる糊のようなものと考えられていたのです。
津田教授の恩師である井上和秀教授らは、グリア、特に小型のグリアであるミクログリアが、慢性痛の原因に深く関わっていることを世界で初めて報告され、高く評価されました。それから、グリア細胞の研究が急速に発展してきたのです。
津田教授らは、このグリア細胞が慢性的なかゆみにも関係するのではないかという仮説をたて、アトピー性皮膚炎のモデルマウスを用いて研究を行いました。このマウスは、皮膚を激しくかくことが特徴です。そのマウスの脊髄で、「アストロサイト」というグリア細胞が、長期にわたって活性化し、かゆみ信号を強め、かゆみの慢性化に関与していることを、世界で初めて明らかにしたのです。
この研究成果は、アトピー性皮膚炎に伴う慢性的なかゆみの、新しいメカニズムとして注目されています。さらに、2016年、順天堂大学環境医学研究所の高森教授、冨永光俊准教授らは、アトピー性皮膚炎モデルマウスの脊髄ではミクログリアが増加していること、ミクログリアを阻害する薬剤のミノサイクリンをアトピー性皮膚炎モデルマウスの脊髄(髄腔)内に投与するとかゆみが軽減することを発見し、その成果を皮膚科学のトップ雑誌「Journal of Investigative Dermatology」に報告されました。
今後、脳や脊髄の神経細胞とグリア細胞を組み合わせた研究により、従来の視点や研究アプローチからは見いだせない慢性的なかゆみのメカニズムを明らかにし、その成果をもとにした、全く新しい視点をもった「かゆみ治療薬」の開発が期待されます。』
Part11 かゆみと痛みはどう違う?
●我慢する感覚vs我慢できない感覚―目的が異なる生体警告信号
・痛みは外界からの傷つけるような刺激に対して、それを感じ取って逃げるための感覚ともいえる。また、痛みは体の中の異常を脳に伝え、対処させようとする。例えば腰痛のかなりの原因は、筋肉と筋膜の異常である。特に急性期には筋肉を使わないように安静にした方が良く、じっとしているように脳が忠告の指令を出す。このように痛みは異常に対して、「きちんと行動しなさい」という感覚ともいえる。
・かゆみは、例えば、寄生虫が皮膚についた時にかゆみを感じ、かく。この動作は自分の皮膚を傷つけることにもなるが、寄生虫を除く方が重要なので、「かいて除け」という脳からの命令による感覚であると考えると良い。皮膚に隣接する粘膜にかゆみが起こるのも同様と考えられる。
しかしながら、野生で生活していた古代人とは異なり、現代人にとっては必要とは言い難いものである。現代病ともいえるアトピー性皮膚炎や花粉症は、本来のかゆみとは全く違う意味を持っているのかもしれない。
●かゆみ物質は痛み物質にもなる―物質の判断を変える生体の不思議
・痛みを起こすことが知られていた物質のほとんどは、かゆみも起こすということが分かってきた。
・同じ物質でも皮膚の表面に限定して投与すればかゆみになり、皮膚の深いところまで作用させれば痛みになるものもある。
●かゆい時に活動する未知の領域―脳の活動部位の違いが明らかに
・機能的MRIを用いた脳機能研究では、かゆみに対して活動する脳部位と、痛みに対して活動する脳部位は、よく似ているが明らかに異なるという結論が出ている。
エピローグ 「かゆい」は本当に必要ないのか
①稲垣直樹先生(岐阜薬科大学教授)
・アレルギーは侵入した異物を排除して生体を守る免疫の仕組みが生体に不愉快な症状を誘発する場合を言うが、本来は生体を守る反応である。したがって、皮膚アレルギーに伴うかゆみも生体を守る役割を担っていると考えられる。かゆみによって誘発される引っかき行動によって、異物排除の反応が増強されるのである。
また、かくことによる心地よい感覚は、確実に引っかき行動を誘発するために備わったものと考えられる。
②片山一朗先生(大阪大学皮膚科学教授)
・かゆみ感覚は、生体への特異な危険信号を避けるために役立っていると考えるが、痛みを緩和することでも、生存に有利に働いているのかもしれない。
・『鍼灸治療はその「ツボ」に機械的、物理的刺激を与えることで効果を引き出しますが、皮膚のどこに「ツボ」が存在するのかは不明です。今後、脳機能研究の手法を取り入れて、鍼灸をかゆみ治療に応用していきたいと考えています。』
③倉石泰先生(富山大学名誉教授)
・以前、現代人の我々にはかゆみの感覚はあまり必要ないかもしれないと話したら、ある女子学生が「化粧品などを使うとき、刺激を受けてかゆくなるという感覚は重要だ」と言っていた。化粧品が合わないことを感じ取るという意味では重要な感覚かもしれない。
④高森健二先生(順天堂大学名誉教授)
・痛みと同じように、かゆみも生体の警告反応(アラームリアクション)であると考えている。
皮膚のバリアが障害を受けると皮膚は乾燥してかゆみが出てくる。その原因として神経線維の表皮内侵入によるかゆみ閾値の低下がある。バリアが壊れると抗原などの異物の侵入や外部からの機械的、化学的刺激を受け、角質層直下まで侵入進展している神経が刺激され、かゆみが生じる。
保湿剤にはバリア改善効果と神経線維の表皮内侵入を抑える作用があり、乾燥肌によるかゆみに有効である。
一方。炎症反応によるかゆみは浸潤している炎症細胞(白血球、リンパ球、肥満細胞など)に由来するかゆみ惹起物質により生じるかゆみで、やはり警告反応であると考えられる。
⑤室田浩之先生(大阪大学皮膚科学准教授)
・皮膚の表面を覆う毛が外界のアンテナ役となり、危険を察知すると皮膚の知覚神経を介してかゆみを起こす。かゆみは夜から朝方にかけて強くなる傾向がある。これは寝ている無防備な時間帯に、周囲の環境に対して鋭敏でなくてはならないためと考えられる。体外からの刺激以外に、身の危険を想起させるような視覚的あるいは聴覚的な刺激もかゆみを起こす。
慢性的に持続するかゆみは体内、体外の病気によって生じている恐れがあり、原因検索を必要とする。長引くかゆみには適切な治療が必要である。
おわりに
『かゆみは、誰もが日常的に感じる感覚なのですが、これほど「わからないことが多い」感覚はありません。かゆみに関する研究や治療法の解明は、ようやくスタート地点に立てた、といえるレベルだと思います。しかし、逆に考えれば、これほど前途洋々たる魅力的な分野は他にはないと思います。
長い間、患者さんたちは、医師に、かゆみをいくら訴えても、「よくわかりません」という反応しか返ってこず、あきらめの境地に入っておられた方も少なくないと思います。しかし、ようやく、医師も研究者も、この「かゆみ」という不思議な現象に立ち向かうための道具を手に入れることができました。
何よりも、「かゆみに苦しんでいるたくさんの患者さんを救いたい」、という強い気持ちが、私たちに、困難な航海に立ち向かう勇気を与えてくれます。おそらく、今後10年の研究の進歩は、それまでの30年に匹敵するか、それ以上のものになると思います。』
感想
最も知りたかったのは尿毒症のかゆみについてだったのですが、残念ながら尿毒症のかゆみの原因は特定されていないということでした。一方、尿毒症物質(uremic toxin)については、ネットにあった論文に詳しい情報がありました。
「尿毒症物質によるかゆみの原因は分かっていない」との見解は、そもそも尿毒症物質が非常に多いことに由来しているからではないかと思います。

⚽日本 1-1 クロアチア サッカーワールドカップ カタール大会決勝トーナメント 2022年12月6日

画像出展:「JFA.jp」
忘れらない大会の一つになったなぁと思います。
選手、スタッフは間違いなく100%の力を出しました。確実に進歩した姿も見れました。
ただ、100%ではベスト8には残れませんでした。
寝る気にもなれず、「どうしたら良かったのだろう?」と考えました。
カウンターアタックの戦法は変えず、後半頭から2点目を取りに行くべきだったのではないか、90分で決着させるという強い気持ちが大切だったのではないか。フレッシュで動き回れる南野選手と、キーマンの三笘選手を後半最初から投入すべきではなかったか。すべて結果論、答えはありません。
しかしながら、やはり積極果敢な姿勢こそが、挑戦者であった日本に与えらえた、唯一の8強につながる道だったのではないかと思います。
また、残念だったことはPK戦のキッカーを選手に任せてしまったことです。PKは得意な選手と苦手な選手がいます。これはキックの技術力に関係します。一方、物凄いプレッシャーがかかる場面のため、メンタリティーも非常に重要です。さらにその試合での調子や出場時間も無視できません。これらのことを総合して、監督が人選し順番も決めるべきです。監督の、勝利への揺るぎない信念を疲れた選手に今一度注入し、選手の不安な心を吹き飛ばし、冷静な心と集中力を取り戻して、最後の決戦に舞台に送り出します。実質、指揮官不在となったPK戦に向かう日本の選手からは、緊張と不安が伝わってきました。悔やまれます。
※スペインを撃破したモロッコのPK戦直前の光景は、勇ましくエネルギーに満ちあふれ、そして、どこか楽しげでした。『ついに、この瞬間が来た!! 勝利は俺たちのもんだ!!』と言わんばかりに盛り上がっていました。
かゆみ1
先日、クレアチニン(Cr)値が急速に悪化し、それに伴い強い痒みのため、夜、思うように眠れないとのお悩みを抱えた患者さまが来院されました。また、その強い痒みは、日によって変化するとのお話でした。
担当医の先生は「尿毒症によるものですね」とのことです。一般的な尿毒症の症状は多岐にわたります。一方、色々調べてみると透析患者の約70%の人が痒みで困っているという記事も見つけました。
これらのことから、尿毒症の痒みの特徴や、そもそも強い痒みとはどのようなものなのか詳しく知りたいと思い本を探しました。それが今回見つけた『世界に「かゆい」がなくなる日』というユニークなタイトルの本です。内容はとても充実しており、大変勉強になりました。良い本に出合ってよかったなと思います。
目次
はじめに
プロローグ 「かゆみ」は不思議な感覚
●「かゆみ」=「かきたい感覚」?―かゆみの不思議な定義
●「かく」ことは快楽だ!―脳の活動を探る
●見ているだけでかゆくなる……―かゆみの伝染
●かけばかくほどかゆくなる矛盾―イッチ・スクラッチ・サイクル
●「かゆい」の悪循環は夜も続く―かゆみの頻度と継続時間の計測
Part1 「かゆい」はつらい!
●川柳に込めた深い悩み―かゆみは他人にはわからない
●「かゆくて仕事ができない!」―かゆみ患者の数と経済損失
●ふらつきや判断力の低下も……―治療薬の副作用
Part2 人間の皮膚が担う大きな役割
●イヌは体温調節ができない―人間の皮膚の優れた特徴
●1カ月で総取り替え―人間の皮膚の構造
●皮膚はいつも水浸し―皮膚の保湿効果
●細菌・ウィルス・紫外線をはねのける!―皮膚のバリア機能
colunmn1 「肌年齢」ってどうやって測るの?
Part3 皮膚で起こるかゆみのメカニズム
●「末梢性のかゆみ」の原因―次々に発見されるかゆみ物質
●かゆみはゆっくり脳に届く―かゆみ信号が伝わる仕組み
Part4 ドライスキン(乾燥肌)のサイエンス
●伸び縮みする神経―乾燥肌がかゆいわけ
●アトピー性皮膚炎を悪化させる要因―新しい抗炎症剤の開発
●紫外線がかゆみを治療する?―紫外線療法の処方箋
●あなどれないスキンケア外用薬の効果―高齢者のドライスキン対策
Part5 花粉症によるかゆみ
●花粉で皮膚もかゆくなる―「花粉皮膚炎」への進行
●花粉症の季節、女性の9割が肌荒れで悩んでいる―花粉皮膚炎の心得
Part6 皮膚以外の原因でもかゆくなる
●疾患が引き起こすかゆみ―中枢性にかゆみとは?
●脳物質のバランスが変化―中枢性のかゆみの主原因
●腎臓病治療の副作用―血液透析によるかゆみ
●血液透析患者を救った「レミッチ」―日本発・世界初の内服薬
●広がるレミッチの効用―肝・胆道系疾患によるかゆみ
●「むずむず足症候群」と関連?―血液疾患によるかゆみの解明
●薬のせいでかゆくなるってホント?―薬剤によるかゆみ
colunmn2 妊婦さんのかゆみを軽くするには
Part7 かゆみの治療の基本とコツ
●かゆみの原因はわかりづらい―原疾患の治療が先決
●炎症や免疫反応を抑える―皮膚由来のかゆみに主原因
●かゆみ物質の働きを阻止―ヒスタミンが関与するかゆみと関与しないかゆみ
●中枢性のかゆみに対する内服薬も―オピオイドκ受容体作動薬への期待
●市販薬のさまざまな成分―外用薬に含まれるかゆみ止め成分
●ヒリヒリ感でかゆみを抑える―効用が不明なかゆみ止めも
●理想はオーダーメイド治療―止痒薬ではなく鎮痒薬
colunmn3 使いすぎるとかゆくなる石鹸や洗剤
Part8 かゆみ止め薬を使わない治療法
●脳への電気刺激がかゆみを止める!―経頭蓋直流電気刺激法
●「痛い」が「かゆい」を忘れさせる―他の皮膚刺激による抑制
●心頭滅却すればかゆさも忘れる?―心理療法
●見直されてきた「偽薬」の効用―プラセボ効果
●かゆみを自分でコントロールする―認知行動療法
●心療内科・精神科の医師との連携―リエゾン療法
●温めて抑える、冷やして抑える―温熱療法、冷罨療法
●古来の薬にも効果が?―民間薬と漢方薬
●鎮痛剤がかゆみにも効く?―最新研究による新たな可能性
column4 かゆみを測るのは難しい
Part9 かゆみ研究最前線(人間を対象とした研究)
●脳を傷つけずに検査する―機能的MRIと電気生理学的検査
●かゆみ刺激に対する脳活動の不思議―大脳辺縁系と前頭葉がともに活動
Part10 かゆみ研究最前線(動物実験)
●「かゆがるマウス」が残した足跡―世界初の動物モデルの作成
●「イギリスの蚊」なら、かゆくならない?―虫刺さされのメカニズム
●脊髄の神経が関係する慢性的なかゆみ―マスト細胞の分化・増殖機能の解明
●黄疸によるかゆみのメカニズム―かゆみ物質を分子レベルで調べる
●ドライスキンはなぜかゆい?―過敏症のメカニズムと新しい治療法
Part11 かゆみと痛みはどう違う?
●かゆみは痛みに隠れている?―痛みとかゆみの共通点
●我慢する感覚vs我慢できない感覚―目的が異なる生体警告信号
●かゆみ物質は痛み物質にもなる―物質の判断を変える生体の不思議
●かゆい時に活動する未知の領域―脳の活動部位の違いが明らかに
エピローグ 「かゆい」は本当に必要ないのか
おわりに
ブログで取り上げたものは、上記の目次のうち、黒字の部分だけです。
プロローグ 「かゆみ」は不思議な感覚
・「イッチ・スクラッチ・サイクル」とは
-「イッチ・スクラッチ・サイクル」とは痒みの悪循環のことで、かゆいところをかくと快感が得られる。それを脳が記憶すると、かくのをやめられなくなる。
-何かの原因で皮膚を強くかくと、皮膚が傷つく、すると皮膚の中にサイトカインという物質が放出される。このサイトカインは皮膚の中にあるマスト細胞(肥満細胞)を刺激して、ヒスタミンというホルモンを放出する。このヒスタミンは非常に強いかゆみを誘発する。また、傷ついた皮膚は炎症を起こすが、それもかゆみを引き起こす。そのために、また強くかいてしまう。このように痒みは悪循環となることもあり、問題は大きくなる。
・このサイクルの実態、病的な悪循環と知っていれば、自制心が働き、かくことを我慢しようと思うことは大切なことである。
Part3 皮膚で起こるかゆみのメカニズム
●「末梢性のかゆみ」の原因―次々に発見されるかゆみ物質
・かゆみの原因の多くは皮膚の問題であり、皮膚の中で炎症・アレルギーなどが起きたときにかゆみが生じる。これを「末梢性のかゆみ」という。末梢性のかゆみが出る時には、かゆみを引き起こす原因物質が皮膚の中で作られている。
①ヒスタミン
-ヒスタミンは主に「マスト細胞」で作られる。マスト細胞は肥満細胞とも呼ばれている。また、顕微鏡で見ると、たくさんの細かい粒のようなものが見えるので顆粒細胞とも呼ばれる。マスト細胞は皮膚以外に鼻の粘膜、気管支など体の様々な組織に存在している。
-アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、気管支喘息のような代表的なアレルギー性疾患が起こる場所にマスト細胞は多くあり、このことはマスト細胞から分泌されるヒスタミンが、アレルギーの発生に重要な役割を果たしていることが分かる。
②ヒスタミン以外のかゆみ物質
-現在、発見されたかゆみ物質は、セロトニン(5-TH)、プロテアーゼ、神経ペプチド、脂質メディエーター、サイトカイン、胆汁酸、リゾホスファチジン酸、ケモカイン、硫化水素などがある。
●かゆみはゆっくり脳に届く―かゆみ信号が伝わる仕組み
・かゆみと鈍い痛みの信号は伝達スピードが遅いC線維から脊髄に至り、脊髄視床路という経路を通って脳に到達する。
・関節位置覚、触覚、振動覚、圧覚などは脊髄後索という経路を通る。脊髄の中には他にも、脳からの運動指令を伝える皮質脊髄路など、たくさんの経路が詰まっている。
・皮膚、神経末端部、末梢神経、脊髄とかゆみと鈍い痛みは同じ経路を通るため、「かゆみは痛みの軽いもの」と言われていたこともあったが、最近の研究ではかゆみ独自の経路があることが分かってきた。
Part4 ドライスキン(乾燥肌)のサイエンス
●伸び縮みする神経―乾燥肌がかゆいわけ
・皮膚の水分がかゆみの予防の基本である。角質細胞の皮脂膜や細胞間脂質、天然保湿因子が減ると、角質細胞の集団が崩れて水分が減り、角質層に隙間ができやすくなる。このため外から異物が侵入しやすくなり、これが刺激となってかゆみが生じる。また、乾いたドライスキンの状態は皮膚が必要以上に敏感になっている。
・皮膚には、神経を伸ばす「神経伸長因子」と、その逆の作用を持つ「神経反発因子」がある。通常は両者のバランスが保たれているため、健康な皮膚では神経線維の自由神経終末は、表皮と真皮の境界に分布している。ところが、皮膚が乾燥すると、神経伸長因子の力が強くなり、神経が伸びるため、その先端にある自由神経終末が表皮内に侵入し、表皮の中で最も皮膚表面に近い角質層の直下にまで伸長する。そのため、外部の刺激が伝わりやすくなり、知覚過敏の状態になり、かゆみを感じやすくなる。
●アトピー性皮膚炎を悪化させる要因―新しい抗炎症剤の開発
・アトピー性皮膚炎は、かゆみの強い慢性の湿疹で、多くはアトピー性素因(アトピー性皮膚炎になりやすい性質)を持つ人に生じる。
・アトピー性皮膚炎の皮膚はバリア機能の異常と、免疫機能の異常・アレルギー性炎症が相互に作用しながら、悪化していく。
・アトピー性皮膚炎の皮膚内で炎症が起こると、マスト細胞やT細胞からかゆみ物質が分泌されるが、これらは「炎症細胞」と呼ばれている。
・炎症が起こると皮膚の表面がアルカリ性に偏るため、細菌が侵入しやすくなる。かゆみのために激しくかくと、皮膚のバリアが壊れる。すると、さらに皮膚が乾燥して、異物が入りかゆみがより強くなり、そして、また、かいてしまう。つまり、「イッチ・スクラッチ・サイクル」という悪循環を起こす典型例がアトピー性皮膚炎である。
・アトピー性皮膚炎ではステロイド軟膏で炎症を抑え、保湿するのが効果的である。ステロイドは軟膏として使う程度では特に副作用の心配はない。
●紫外線がかゆみを治療する?―紫外線療法の処方箋
・近年、アトピー性皮膚炎に対する紫外線療法が話題になっているが、名古屋市立大学の森田明理教授が3つの要素をあげられている。
①T細胞のアポトーシスの誘導
-アトピー性皮膚炎では、アレルギー炎症の原因となるT細胞が増加するが、紫外線によってアポトーシスが誘導され、T細胞が減少し病態が改善する。
②免疫抑制
-紫外線によって免疫異常が改善される効果がある。治療後の改善期間が長く保てると考えられている。
③末梢神経(C線維)への影響
-紫外線はかゆみを伝達するC線維にも影響を与える。アトピー性皮膚炎の皮膚では、C線維の先端部分にある自由神経終末が、表皮の角質層まで伸長しており、皮膚のバリア機能の低下と相まって、かゆみ刺激に過敏に反応する。
●あなどれないスキンケア外用薬の効果―高齢者のドライスキン対策
・高齢者における皮膚乾燥の発生。
①脂質の減少
②天然保湿因子(NMF)の減少
③角質細胞のターンオーバー(細胞の発生と自然死のサイクル)の低下と角質層構造の変化
④環境因子の影響
・高齢者のかゆみの治療あるいは予防には保湿剤が一番有効である。
・保湿剤にはかゆみ神経(C線維)が表皮内に侵入するのを抑える作用がある。つまり、乾燥後すぐに保湿剤を外用すると、表皮内神経線維の増加を強く抑制する。
Part6 皮膚以外の原因でもかゆくなる
●疾患が引き起こすかゆみ―中枢性にかゆみとは?
・何らかの疾患が原因となって、病的に強いかゆみが持続するもの。中枢とは脳や脊髄のことである。
●脳物質のバランスが変化―中枢性のかゆみの主原因
・麻薬として使われるモルヒネやアヘンの材料であるアルカロイドなどの物質を総称して「オピオイド」というが、このオピオイドが中枢性のかゆみを引き起こすことが分かってきた。
・受容体は細胞表面にあって、特定の物質だけに反応してその物質に対する細胞の反応の引き金を引く。オピオイドは複数の受容体を持っているが、2種類の受容体のアンバランスによってかゆみが誘発される。これが「中枢性のかゆみ」の原因である。
●腎臓病治療の副作用―血液透析によるかゆみ
・透析患者の7割が合併症のかゆみに苦しんでいる。
・透析によるかゆみの原因は、腎不全や透析、さらに乾燥によって皮膚のバリア機能が損なわれていることがある。
●血液透析患者を救った「レミッチ」―日本発・世界初の内服薬
・κ受容体を活性化させてμ受容体とのバランスを改善するのが、κ受容体作動薬のナルフラフィン塩酸塩(商品名:レミッチ)である。
●広がるレミッチの効用―肝・胆道系疾患によるかゆみ
・肝疾患によるかゆみにも、オピオイドシステムが関与しており、レミッチにかゆみを止めることが明らかになった。
●薬のせいでかゆくなるってホント?―薬剤によるかゆみ
・医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページで「薬とかゆみ」で検索すると7,000以上の薬がヒットする。どのような薬でもアレルギー反応が生じれば、発疹(薬疹)に伴ってかゆみが出現する。
・薬剤によるかゆみは大きく二つに分類できる。
1)明らかに皮膚症状を起こすもの。様々な皮疹が出現し、かゆみの程度も異なる。中には強いかゆみが現われる場合もある。
2)皮膚症状がないか少ないタイプ。頻度が多いものは、モルヒネ、クロロキン、バンコマイシンなど。
⚽日本 2-1 スペイン サッカーワールドカップ カタール大会予選リーグ最終戦 2022年12月2日

画像出展:「讀賣新聞オンライン」
信じられない勝利でした。選手全員が戦い方を理解し、共有していたことが最大の勝因だと思います。
その中で、傑出していたのは三笘選手の強く、果敢に攻める気持ちでした。それはディフェンス面にも出ていました。
1mmの攻防の明暗は、想像力と研ぎ澄まされた瞬時の決断にあったと思います。
プラセボと自然治癒力
プラセボというと、例えば、睡眠の問題を抱えた人に、「これは良く効くといわれている新薬だよ」といって、胃腸薬(ビオフェルミンのような)を渡して飲んでもらったところ、翌朝、「あの薬が効いたようだ、ぐっすり眠れたよ」などというものを連想します。プラセボ薬とはいわゆる偽薬に相当するものです。
一方、鍼の世界でも、「それってプラセボでは?」という話になることもあり、以前から“プラセボ”というものには関心をもっていました。特に“プラセボ”と“自然治癒力”の境目はなかなか難しい部分だなと感じていました。
今回の本は、ある探し物をしていて偶然に見つけたものですが、特にタイトルの副題、“プラセボから見えてくる治療の本質”に興味を持ちました。
内容は専門性の高いものですが、最初の「プロローグ」には背景や概要などが書かれていますので、最初にそちらの一部をご紹介させて頂きます。
プロローグ
『私は、心身医学を専攻し、臨床薬理学を専門領域とする医師として、この半世紀余りを生きてきました。心身医学では、心と身体の関連性を研究するとともに、臨床場面では、心と身体の両面から患者へのアプローチをします。心身症患者は、身体的な治療だけでは症状が改善しにくいことも多く、心の面からの働きかけが重要になってくるのです。一方、臨床薬理学の柱の一つである臨床薬効評価の場では、薬の有効性を評価する際に、対照群としてプラセボ投与群を設定することが、しばしば必要になってきます。
したがって、若いころから、プラセボという物質の存在とプラセボ反応(または、プラセボ効果)という現象には、深い関心を抱いてきました。そのため、プラセボ反応に関与する要因を明らかにするために、短期間の自覚症状・生理指標・行動面の変化を指標にした実験心理学的研究や臨床精神薬理学的研究を、いくつか行った経験があります。また、より長期間にわたる臨床での薬物治療効果を評価する場では、幅広い疾患と治療薬の臨床試験で、プラセボ投与群のデータを集積してきました。
いろいろな医学会で、プラセボをめぐる諸問題をテーマにしたシンポジウムやワークショップを担当する機会を、何度も経験しました。プラセボに関するテーマで、特別講演や教育講演を行う機会もありました。また、医学生や薬学性を対象にした教育の場や、臨床研究コーディネーター(Clinical Research Coordinator: CRC)を対象にした研修会の場では、プラセボ関連の話題はカリキュラム上重要な位置を占めています。
~中略~
プラセボ反応は、面白おかしく語られたり、場合によっては、邪魔もの扱いされたりすることさえあります。プラセボ反応が、なかなか科学の土俵に上がらなかったのは、プラセボ反応が多くの要因により規定されているためであり、生命現象としての「自然治癒力」と密接に関連しているからだと考えられます。
しかし、プラセボ投与群と薬物投与群の改善率を、構造的に理解すると見えてくるものがあります。それは「治療医学の本質」です。「治療は、生体の有する自然治癒力を前提に成り立っている」ということです。プラセボ反応として私たちが捉えているものは、生体の有する「自然治癒力」を介して働いている現象であり、その意味では生命現象そのものの特徴だということもできると思います。
プラセボ投与時の改善率(P[Placebo]+N[Natural fluctuation])を高めることに目を向けると、医療の効率化に資することができるように思います。医療費の節減にも貢献できると思います。また、健康な方にとっては、健康の維持や、健康寿命を延ばすことにも役立つように思うのです。』
なお、ブログは黒字部分、5章、10章、11章の一部です。
目次
1章 プラセボ投与時に見られる改善率
1.治療を含む臨床試験でプラセボ投与群の改善率はどの程度認められるのか:二重盲検ランダム化比較試験(RCT)の結果から
2.プラセボに関する用語と定義
2章 プラセボ投与時に見られる有害事象または副作用
1.「有害事象」「副作用」「薬物有害反応」という用語について
2.プラセボ投与時に見られる有害事象または副作用
3.「プラセボ効果」と「プラセボ反応」という用語について
4.「ノセボ効果」というとらえ方の問題点
3章 プラセボ効果(反応)の構造的理解
1.Post hoc fallacy(前後即因果の誤謬)
2.「プラセボ効果」と「プラセボ反応」という表現について
3.時間の経過に伴う病状や症状の変化
4.「プラセボ効果(反応)」の構造的理解
5.薬効の構造的理解
4章 医薬品の臨床試験におけるプラセボの誕生とプラセボ対照群の必要性
1.臨床評価のためには比較試験が何にもまして重要である
2.臨床評価のための比較試験でランダム化(無作為化)が必要な理由
3.臨床薬効評価法におけるプラセボの誕生:臨床評価のための比較試験で二重盲検法が必要な理由
4.薬物の有効性と安全性を科学的に評価する際に、なぜプラセボ対照群が必要になるのか
5章 プラセボ効果(反応)に関与する要因
1.生体の有する「自然治癒力」
2.暗示効果または期待効果
3.条件づけ
4.患者と医療者の間の信頼関係
5.患者の治療意欲
6.患者への適切な説明(服薬指導)
6章 対照群にプラセボを使用する際の基本的な考え方
1.対照群にプラセボを使用する際に考慮する必要のある要因
2.臨床試験で有用性の実証された標準薬の有無と被験者の被るリスクの程度による分類
7章 プラセボ対照群を使用する臨床試験を実施する際の工夫と留意点
1.対照群に使用するプラセボとして必要となる条件
2.試験デザイン上の工夫と留意点
3.プラセボを使用することにより被験者が被る可能性のあるリスクを臨床試験チーム全体で背負う姿勢の重要性
4.被験者へのプラセボの説明のしかた
8章 プラセボ対照二重盲検比較試験における盲検性の水準とその確保
1.被検薬の特性以外の要因から薬剤の盲検性に問題が生じたケース
2.被験薬そのものの特性から薬剤の盲検性に問題が生じる可能性
3.被検薬の薬理作用から薬剤の盲検性が守れなくなる可能性
9章 プラセボの使用に関する倫理的ジレンマとそれを乗り越える試み
1.「プラセボ対照ランダム化比較試験」以前の時代におけるプラセボの使用について
2.「プラセボ対照ランダム化比較試験」の時代になってからのプラセボの使用について
3.世界医師会のヘルシンキ宣言にみられるプラセボの使用に関する考え方
4.プラセボジレンマとその解決策として考えられること
10章 プラセボ反応(効果)の治療における意義
1.薬物投与時にみられる病態・症状の改善についての理解のしかた
2.プラセボ投与群にみられる改善は治癒のプロセスの本質を理解するうえで重要
3.暗示効果
4.自然治癒力(自己回復力)について
11章 薬物治療の効果を高めるためのストラテジー(1)
1.薬物治療の効果に関する構造的理解
2.プラセボ投与時の改善率(N+P)を高めることにより患者が受けることのできる恩恵
3.薬物治療の効果(D+N+P)を高めるために
12章 薬物治療の効果を高めるためのストラテジー(2)
1.薬物治療効果を構造的に理解することにより見えてくるもの
2.プラセボ関連誤謬(錯覚):Placebo related fallacy
3.ライフスタイルの改善により「自然治癒力」を高める
補遣 プラセボの説明のしかた
1.「ロールプレイ法により学ぶ治験のインフォームドコンセント」と題する実習
2.プラセボについて説明することの難しさ
3.プラセボに関する医療者の理解度
4.被験者の治験内容の理解度:とくに「プラセボ」について
5.インフォームドコンセントについて
6.プラセボに関する説明を患者に対してする際の留意点
7.ランダム化比較試験(RCT)、とくにプラセボを患者に説明する場合には、コミュニケーションのエッセンスが詰まっている
5章 プラセボ効果(反応)に関与する要因
・下の図の中で、薬物以外の非薬物要因として挙げられているものは、プラセボ効果(反応)に影響を与える要因である。
・「プラセボ効果(反応)」には生体が有する自然治癒傾向と自然変動がベースに存在している。
1.生体の有する「自然治癒力」
・外傷や感冒の治癒過程を考えても、人間には「自然治癒力」が備わっていることは明白である。高度な外科手術で生体にメスを入れ縫合後、傷口が治っていくのは「自然治癒力」のおかげである。
・『私たちは、現代医学の目覚ましい技術的進歩に目が奪われるあまり、本来生体に備わっている「自然治癒力」の存在を軽視しがちなのではないでしょうか。いま一度、医療の原点に立ち戻って、「自然治癒力」を重視した医療のあり方を考える必要があるように思います。』
・自然治癒力を高めるために、古くから「養生法」が工夫されてきた。「養生法」の基本は生活習慣の調整であり、食事、運動、心の持ち方が3本柱である。
2.暗示効果または期待効果
・『「いわゆるプラセボ効果」(図2のN+P)から「真のプラセボ効果」(図2のP)だけを抽出することは、臨床の現場ではまず不可能に近いほど難しいことです。しかし、実験心理学的研究の場では、実験条件のコントロールがある程度可能になるので、急性反応としての「真のプラセボ効果」を明らかにすることができます。』
・内科領域の不安・緊張に伴う自律神経症状を主体とする心身症に関し、治験からプラセボ投与後の改善率が高いことは明らかになっている。
この図を見ると、期待度が中等度の場合に最も高く(53%)、軽度では少し低下し(36%)、強度では顕著に低く出現率だった(8%)。つまり、適度な期待度という心持が最もプラセボ効果が高いということである。
・より強力かつ有効な薬物が開発されると、その領域におけるプラセボ効果の出現率が高まる傾向がある。この現象も、患者だけでなく医療者側にも、期待度や効くはずだという信念が生じるための影響だと考えられる。
・治験において被検薬の副作用が、対照群であるプラセボ投与群でも同様に高い頻度で出現するという現象も、同様のメカニズムが働いているものと考えられる。
・プラセボ効果はプラセボの価格によっても異なり、価格が高い方が鎮痛効果は出やすく、価格が安いと鎮痛効果が出にくいという報告がある。これは高い価格により生じる「効くという暗示効果」あるいは、「効いてほしいという期待効果」を介して生じている現象だと考えられる。また、健康食品や化粧品についても、同じような現象が見られる。
4.患者と医療者の間の信頼関係
・心身症を対象にしたプラセボ投与群の改善率の成績は、「医師-患者間の信頼関係」においても明確な傾向が見られる。
・“良好”と“困難”では5倍の差が見られる。なお、プラセボではなく抗不安薬(ジアゼパム)の投与群でも同様な改善傾向が確認されており、あらためて医師-患者間の信頼関係の重要性が示唆されている。
5.患者の治療意欲
・「治療意欲」の程度での解析でも、2倍以上の差が出ており治療意欲を適度に高めるように支援することは大切である。
6.患者への適切な説明(服薬指導)
・患者にプラセボまたは薬物を投与するとき、その効果について適切な説明をすることは、薬効およびプラセボ効果を高めることが研究により明らかになっている。
・『冒頭に紹介した図1をもとにして、本稿で記述してきた要因を加味したうえで、プラセボ効果(反応)に関与する要因を整理しなおす、図7のような図ができあがります。
プラセボ効果(反応)やその根底にある「自然治癒力」がサイエンスの土俵に乗り難いのは、あまりにも多要因によって影響を受けている現象であるからだと思われます。サイエンスの重視している再現性を保証することが難しいのです。つまり、プラセボ効果(反応)に関与することが難しいことと、それらの要因の数量化が難しいためと考えられます。
しかし、プラセボ効果(反応)はサイエンスで取り扱うことが難しい現象ではありますが、その研究は薬物治療を含む治療医学の領域においても、また臨床薬効評価の領域においても、依然として重要なテーマであり続けています。』
10章 プラセボ反応(効果)の治療における意義
1.薬物投与時にみられる病態・症状の改善についての理解のしかた
・被検薬投与群とプラセボ投与群を比較試験(RCT:ランダム化比較試験)すると、それぞれに効果が見られる。つまり、被検薬投与群で得られた効果(改善率)が被検薬だけの効果のように取られることが多いが、実態はプラセボ効果が含まれており、被検薬単独の効果ではないという事実を知ることが重要である。
・『例として、内科領域における心身症、片頭痛、糖尿病(NIDDM)という三つの病態を取り上げてみます(図1)。いずれも国内の治験で得られた成績です。
心身症は心理社会的要因が密接に関与する心身相関の認められる病態です。不安症状や軽いうつ症状を伴うことの多い心身症では、その病態の特徴から容易に想像できるように、一般にプラセボ反応(効果)が比較的高く認められます。内科領域で心身症の診療をしている全国の医師が参加した治験の成績では、プラセボ投与群の改善率は42%、抗不安薬(ここでは標準薬として使用したジアゼパム)投与群の改善率は58%で、その差は16%でした。つまり、プラセボでも42%が改善し、代表的な抗不安薬であるジアゼパムは、改善率を16%上げているにすぎません。しかし、ジアゼパムの改善率58%という数字だけを見た人たち(製薬会社の職員だけでなく、患者や医師も含めて)は、ジアゼパムにより58%の患者が改善すると考えがちなのです。
片頭痛は拍動性の血管性頭痛です。遺伝的要因も関与しますが、ストレスによっても頭痛が誘発されることがあります。また、ストレスによって頭痛の症状が増悪されることもある病態です。頭痛は自覚症状としての訴えです。したがって、プラセボ反応(効果)がかなり高いことが予測されますが、プラセボ投与群の改善率は28%で、被検薬である片頭痛治療薬の改善率は52%でした。その差は24%になります。ここでも、片頭痛治療薬によって52%の患者の片頭痛症状が改善すると思いがちですが、実際には24%の患者が片頭痛治療薬の恩恵を受けて改善していることになります。
心身症や片頭痛は、心理的要因が病態や症状に関連していることが一般に認められており、自覚症状の改善が臨床評価に際して重視されます。したがって、プラセボ反応(効果)が出やすいと考えられています。
一方、糖尿病(NIDDM)は、血液中のHbA1cの値という客観的指標で臨床評価をする病態なので、一般にプラセボ反応(効果)はほとんど出ないと考えられているように思います。しかし、プラセボ投与群でも13%の改善率が認められ、被検薬となった糖尿病治療薬の改善率は43%で、その差は30%になります。つまり、糖尿病治療薬そのものの効果は30%で、プラセボ投与群の改善率の13%は、定期的に診察と血液検査を受けることに伴う食事や運動などのライフスタイルの改善によるものと考えられます。
ここで例として挙げた各病態での改善率の数値は、治療の対象となった患者層、投与量、投与期間、評価指標、評価期間などの諸要因により決まる値です。したがって、数値そのものはさほど重要ではなくて、薬物投与時にみられる病態・症状の改善をプラセボ投与群の改善と比較して、どのように考えたらよいかを理解するための単なるツールと思ってください。
薬物投与時にみられる病態・症状の改善率をどのように理解するかは、構造的に理解するのがよいと思います。
つまり、観察されたプラセボ投与時の改善を、N(自然変動:自然治癒傾向)とP(真のプラセボ効果または真のプラセボ反応)の組み合わせとして理解し、観察された薬物投与時の改善についても同様にして、NとPとD(薬物に起因する効果:薬効)の組み合わせとして理解するという方法です。』
11章 薬物治療の効果を高めるためのストラテジー(1)
3.薬物治療の効果(D+N+P)を高めるために
・薬物治療の臨床効果は、病態の適切な診断(評価)と適正な医薬品の選択、投与量、投与方法の選択が非常に重要であるが、薬物の治療効果は、薬物以外の多くの要因(非薬物要因)の影響を受けている。これがプラセボ投与群の改善率(N+Pの部分)に反映される。
・非薬物要因としては疾患に伴う諸要因(疾患の種類、重症度、疾患の時期など)と、疾患以外の諸要因(医療者側の要因、患者の年齢、治療環境、患者と医療者の信頼関係など)に分けられる。
1) 真の薬物効果(D)を高める
・薬物の効果や薬理作用の強さは以下の3つの要因で決まる。
① 薬物の種類(薬物の有する薬理作用の特性)
② 作用部位における薬物濃度
③ 薬物に対する生体の感受性
2) 自然治癒力(N)とプラセボ反応(P)を高める(N+P)
・医聖とされるヒポクラテス(紀元前460年頃~370年頃)は、健康はからだと心を含む、内的な力と外的な力との調和的バランス状態の表現であるとし、自然治癒力を重視した。
・「自然が病を癒す。人体は生まれつき備わっている反射と同様に、自動的に働く。自然はこの本質的なふるまいを、訓練も教育もなしに行うものだからである。」とヒポクラテスは言っている。
・中世のフランス人外科医パレ(1510~1590年)の残した言葉、「我、包帯す。神、癒し賜う。」は現代でも的を射ている。
・一般に、治療は生体の「自然治癒力」を前提として成り立っており、自然治癒力を妨げている要因があれば、それを排除して自然治癒力を促すことが重要である。
・自然治癒過程に配慮しながら、自然の法則にしたがって細かな調節をするのが治療行為である。
・治療行為は「疾患」だけが対象ではなく、「病人」も対象になるので、患者と医療者の信頼関係をベースに展開していく。
・あらゆる病態や症状には、心身相関が認められるので心理的社会要因をも考慮した「養生法」に基づく自然治癒力を高めるための枠組みが重要になってくる。
・『医師の信念と患者の信念、その相互作用によって、プラセボ反応はますます強化されていきます。医師が自分の行う治療法の価値を確信すること、患者もその治療法を信ずること、患者と医師がお互いに信じあうこと。この三つの要素が最適条件で働けば、たとえば非合理的な理論に基づく治療法でも、改善が起こりうるということを、医学の歴史は示してきました。近代医学が誕生するまでの治療医学の歴史は、「プラセボ反応の歴史」であったと言っても過言ではないと思います。』
感想
今まで鍼灸の施術を行ってきて、「鍼灸に好意的な患者さま」、具体的には過去に鍼灸で良い経験をされた患者さま、鍼灸が好きな患者さま(怖い、痛そうなどのネガティブな感情ではなく、心地よいとか体が軽くなるといった感想をもたれる患者さま)は、効果が出やすいと感じていました。
今回、中野先生の『プラセボ学 -プラセボから見えてくる治療の本質』を勉強させて頂き、“信頼”や”期待”が治療効果に大きく関わってくることを、プラセボ研究というサイエンスを通じて理解できたことはとても大きな収穫でした。
一方、大きな反省点として痛感したことがあります。私は、特に慢性腎臓病(CKD)の患者さまに対して、「やってみないと分かりません」と言ってしまうこと多々あります。実際、Cr値(クレアチニン値)については、個人差が大きく明確な傾向も掴めていない状況で、まさにこの通りと言えます。
しかしながら、患者さまの中には検査結果を拝見すると、炎症性をみるCRPや貧血とも関わるヘモグロビン値などに改善傾向が見られることもあります。
もちろん、慢性腎臓病で来院される方の期待は圧倒的に腎機能の改善(Cr値の改善)ではあるのですが、短絡的にCr値だけをクローズアップするのではなく、患者さまの総合的な健康状態の理解に努め、鍼灸の効果について、知識と経験に基づき”適正な期待度”をもって頂けるように心掛けないと、”期待”や”信頼”という重要な要因に紐づく”効果”を失ってしまうと感じました。
天気病
梅雨時、特に6月にめまいを起こすことが多いというお話をある患者さまから頂きました。また、「天気病といわれるものかもしれない」とのことでした。
以前、天気病については少し調べたことはあったのですが、ほとんど記憶から消えてしまっていたので、あらためて調べてみることにしました。

著者:福永篤志
初版発行:2015年10月
出版:医道の日本社
この福永先生は脳神経外科の専門医でありながら、なんと気象予報士という驚くべき経歴をお持ちでした。
『医学と気象学という、2つの専門的な知識をもとにして、「気象病の具体的な予防法」をみなさんにお伝えしようとするのが、この本の趣旨となっています。』
とのことです。
目次
はじめに
第1部 天気を知って病気を防ごう
気象病のキホン
1 体は天気の影響を受けている!
●その日の体調は天気で変わる
●「気象病」って何?
●気象病は予防できる!
●天気予報を見て健康になろう!
2 天気予報の上手な見方
●天気予報はこうして身近になった
●知っておきたい気象用語
●天気予報はここを見よう!
Column 私が気象予報士を目指したワケ
第2部 明日の天気が命とり!?
脳卒中と心臓病
3 脳卒中には気温が関係していた!?
●脳卒中も気象病のひとつ
●脳梗塞が起こりやすいのはいつ?
●脳血栓は「気温差が大きい」日が危険!
●予防は温度調整と水分補給がポイント
4 夏より冬に多い脳出血
●脳出血は突然起こる!
●気温の低い朝が危ない!
●急激な血圧変動を抑える生活習慣を
Column 「脳神経外科専門医」について
5 気温差が危険!?くも膜下出血
●働き盛りは要注意な「くも膜下出血」
●寒い日の水仕事が危ない!
●くも膜下出血を予防しよう!
Column 脳卒中フローチャート
6.心臓病も気象病です
●心臓病ってどんな病気?
●心筋梗塞と狭心症
●冬に起こりやすい心臓病
●心臓病はこんな日に気をつけよう
Column 人類は変化している① がん患者総数の増加
第3部 あの身近な症状も!
まさまだある気象病
7 オゾンホールと白内障・皮膚がん
●オゾンホールって何?
●オゾンホールと白内障・皮膚がんの関係
●白内障と皮膚がんの予防法
8 天気と深い関係の片頭痛
●生活に支障をきたす片頭痛
●片頭痛が起こりやすい日をチェックしよう
Column 「イライラ」も気象病?
9 腰痛・関節痛は低湿・低気圧で悪化!
●腰痛・関節痛は体の炎症反応
●低温・低気圧の日に出やすい痛み
●腰痛・関節痛の対策
Column 人類は変化している② 不妊症
10 インフルエンザはなぜ冬に多いのか?
●ウィルスが増殖しやすい冬
●予防に「うがい」は効果ない?
●口腔内バイオフィルムを除去しよう!
●実体験から見たインフルエンザ予防法
11 気象が引き起こすアレルギー
●増え続けているアレルギー患者
●予防が難しい花粉症
●寒暖差アレルギーにも要注意!
12 盲腸は梅雨の晴れ間に多い!?
●盲腸は気象病か否か
●虫垂炎は予防できるのか?
13 生命を脅かすぜんそく
●死亡者の9割は高齢者
●ぜんそくが発症しやすい季節は?
14 油断大敵な熱中症
●日射病・熱射病も「熱中症」のひとつだった
●熱中症の原因とメカニズム
●熱中症の予防法は?
第1部 天気を知って病気を防ごう
気象病のキホン
1 体は天気の影響を受けている!
●その日の体調は天気で変わる
・天気の影響を受ける最大の理由は、人間が恒温動物だからである。
・人間は体内の酵素の働きを維持するため、体温を一定にしなければならず、この体温調節は主に自律神経系が担っている。
・気圧の変化にも体は恒常性を維持しようと反応する。気圧が下がると耳の奥の「内耳」の圧センサーが作動し、交感神経を刺激する。
・気圧が下がると痛みに敏感になるのは、交感神経が活性化してノルアドレナリンなどの神経伝達物質が放出され、血管が収縮して痛覚受容器の活動が亢進するためと考えられる。
●「気象病」って何?
・気象病の具体例:気管支ぜんそく、心臓病、脳卒中、尿路結石、腰痛・関節痛、リウマチ、花粉症、インフルエンザ、熱中症、食中毒、寒暖差アレルギー、片頭痛、虫垂炎、白内障、皮膚がんなど。
・気象病(生気象学)という言葉は1950年代後半頃から学会で使われるようになった。
・医学部では「気象変化を原因としてさまざまな疾患が発生する」という生気象学の考え方自体を深く取り上げていない。
・『私は、気象変化をひとつの切り口とした疾患の捉え方、そこから考えられる病気を治療法や予防法を研究することも、多くの患者さんにとって、実用的かつ有用的なのではないかと思っています。』
●気象病は予防できる!
・脳神経外科専門医かつ脳卒中専門医として、「脳卒中は予防できる!」と考えている。特に脳梗塞(無症候性脳梗塞を除く)は注意すれば防げると思っている。これは医学的かつ気象学的に血栓を予防できるという根拠があるためである。
-寝る前と朝起きた時にコップ半分~1杯の水を飲み、たばこを止め、バランスよく食事をとって動脈硬化を予防し、血液循環良くするために歩く習慣をつける。
-脳梗塞は真夏や季節の変わり目に多いという季節性があり、また気温差の激しい日に多いという特徴がある。このような日には水を少し多めに摂ることが予防になる。
・脳梗塞を初めて起こした患者さんに話を聞いてみると、水をあまり飲まなかったという患者さんが多いことに驚かされる。
・『もちろん脳梗塞の最大の原因は、動脈硬化です。また、高齢者には、不整脈を原因として、比較的大きな血栓が心臓から脳へととんでしまう脳梗塞(脳塞栓といいます)も増えています。動脈硬化が強く、もともと血管が詰まりやすい状態や、心臓病をお持ちの方の場合は、残念ながら脳梗塞を起こしやすいのは事実です。
しかし、脳梗塞は、体の内部の状態が悪いだけで起こる病気ではありません。
人間の体は通常、病気を起こさないように働いています。血圧や体温を一定に保つように、自律神経・視床下部系が自動調節していますし、細菌の侵入を防ぐためのさまざまな防御機構や、侵入したときに活発化する免疫機能など、24時間、体は頑張っています。ところが、そこへ外部環境による負荷や刺激が加わり、耐えられなくなると、病気を発症してしまうのです。』
2 天気予報の上手な見方
●知っておきたい気象用語
・晴れの日に多い病気は虫垂炎。
・曇りの日に多い病気はうつ病、ストレス性疾患。
・『患者さんの中には、入院中に微熱が続いていたのに、退院すると平熱に戻ってしまうという方をしばしばお見かけします。血液検査をしても異常はなく、原因不明なのですが、これはひょっとしたら日照時間が関係しているのかもしれません。入院中は、日光をほとんど浴びませんので、副交感神経が優位となり、体温が上がりやすくなります。しかし退院すると、日光を浴びて交感神経が優位となり、体温が平熱に戻るのではないかと思うのです。』
●天気予報はここを見よう!
・気圧が10hPa下がると、海面は約10㎝上昇するが、我々の体に関しても気圧が下がって大気圧の力が緩むと、体はわずかに膨張するため体に何らかの変化が起きても不思議ではない。
第2部 明日の天気が命とり!?
脳卒中と心臓病
3 脳卒中には気温が関係していた!?
●脳卒中も気象病のひとつ
・動脈硬化が進行し、血管が硬くなったために血圧を正常範囲にコントロールする自動調節機能がうまく働かず、冷気に触れたりすると、血圧が過度に上昇することがある。これにより脳の血管が切れたり、脳循環が悪くなって血管が詰まったりして脳卒中を起こす。
●脳梗塞が起こりやすいのはいつ?
・一過性脳虚血発作は脳梗塞の前兆であるため、速やかに病院を受診すべきである。また、脳梗塞の前兆には、数秒から数分間、目の目にシャッターが下りたように真っ暗になるという目の症状(黒内障)もある。「立ちくらみ」などと誤解されやすいが注意が必要であり、その場にしゃがみ込んだり、意識が遠のく感じがしたりすることがほとんど見られないという特徴がある。
●脳血栓は「気温差が大きい」日が危険!
・季節の変わり目で、前日との気温格差や日内の気温較差が10℃以上なる日は、着るものなどに注意て体温調整することが必要ある。
・心房細動などの心臓病をお持ちの高齢者は極端に温度が高い日や低い日に注意が必要ある。
●予防は温度調整と水分補給がポイント
・日頃からこまめに水分補給を心掛ける。
・お茶(玉露、緑茶、紅茶、ウーロン茶)の中には、尿路結石の原因となるシュウ酸が比較的多く含まれている。一方、カテキンは体内の脂肪を分解する効果があるので、食後はお茶、飲水は水が望ましい。なお、麦茶はシュウ酸が少ないと言われている。
4 夏より冬に多い脳出血
●脳出血は突然起こる!
・脳出血は「脳卒中」のひとつ。動脈硬化が本質的な原因と考えられるが、高血圧の既往のある人に多い。
・高血圧以外では、脳動脈静脈奇形、血管腫、脳腫瘍などからの出血や、高齢者に多いアミロイドアンギオパチーという、しばしば認知障害を伴って脳内に微小出血が多発する奇病もある。
・脳出血は脳梗塞と異なり、前兆や一過性の発作がなく、多くは突然発症する。
・『予防としては、普段から血圧を正常範囲内にコントロールすることが最も重要です。具体的には、収縮期血圧(いわゆる「上の血圧」)が140㎜Hg』以下、拡張期血圧(いわゆる「下の血圧」)が90㎜Hg以下という数値がひとつの目安となります。ただ、高齢者の方は、血圧が低すぎると脳循環が悪くなって、めまいなどを起こすこともありますので、あまり下げすぎないほうがよいかもしれません。』
・脳出血の予防には、動脈硬化の進行予防、すなわち生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病、肥満など)の予防や禁煙、節酒が最も重要である。
●気温の低い朝が危ない!
・脳出血に気をつけるべき気象条件
-気温が低く冷え込む日。
-晩秋、早春、日中の気温較差が大きい日。
-急激な気温変化の後は特に要注意。これは短期間での気温の低下は血中ヘモグロビン値、赤血球数、血圧などを上昇させ、しかも1~2日間継続すると考えられており、これにより血液粘調度の増加や高血圧につながるからである。
-早朝など午前中に発症することが多い。早朝に血圧が上がるという現象(モーニングサージ現象)が原因の一つと考えられている。
●急激な血圧変動を抑える生活習慣を
・問題は血圧の自動調節機能が適切に機能しない血管の柔軟性が低下している高齢者や動脈硬化が進行している人である。
・天気予報の「翌日との気温差および最低低気圧」を忘れずチェックする!
-寒い日は寝床に置いた上着を着て、決して裸足では歩かない。外に新聞を取りに行くときはマフラーを巻く。
-寒い日は無用な外出は控える。特に飲酒後は要注意。
-どうしても寒い日に外出するときは、暖かい格好で、手袋やマフラーは必須。
-入浴前は風呂場を温め、脱衣所も暖めておく。
-血圧は定期的に自宅で測定する。
-冷水で食器洗いや洗車はしない。血圧が過度に上昇することを防ぐ。
・入浴は、入浴前・入浴中・入浴後で血圧は大きく変動するため注意を要する。
5 気温差が危険!?くも膜下出血
●働き盛りは要注意な「くも膜下出血」
・脳は豆腐のように軟らかくて崩れやすい、約60%が脂質でできており、髪の毛よりも細い血管が無数に走行している。
・脳を覆っている3枚の膜(外側から硬膜、くも膜、軟膜)。くも膜と軟膜の間のくも膜下腔という隙間に出血するのがくも膜下出血である。
・くも膜下出血の90%以上が、脳動脈瘤の破裂が原因とされている。頻度は10,000人に1人から3人であり、それほど多い病気ではない。ただし、発病者の半数近くの人が命をおとす恐ろしい病気である。
●寒い日の水仕事が危ない!
・冬空の下での洗車や冷水での洗いものなども注意を要する。これは冷たいという要素に加え、力を入れているということで急激に血圧が上がったことが脳動脈瘤の破裂につながったと考えられる。
・研究によると、4℃の冷水に手を1分間浸しているだけで、収縮期血圧が50㎜Hgも上昇することもある。つまり、普段120㎜Hgの人でも170㎜Hgまで上がってしまうということである。
●くも膜下出血を予防しよう!
・40歳を過ぎた頃から脳動脈瘤の発生率は上昇し、脳ドック受診者全体の数%~6%程度に発見されると言われている。
6.心臓病も気象病です
●心臓病ってどんな病気?
・本書では虚血性心疾患(心筋梗塞と狭心症)について見ていく。
・脳卒中と虚血性心疾患はいずれも動脈硬化が主な原因であるという共通点がある。また、高血圧症の合併が多いというのも共通点である。つまり、動脈硬化と高血圧は悪循環の関係にある。
・生活習慣病や高齢も共通点としてあげられる。
●心筋梗塞と狭心症
・心筋梗塞
-冠動脈が詰まって心筋細胞が壊死してしまう病態。原因のほとんどは動脈硬化である。男性に多く、30代でも発症するが、50代以降に多発する。死亡率は5~30%程度と言われている。
-冷汗を伴う突然の胸痛が特徴だが、違和感のみの場合もあるので注意を要する。その他、息苦しさや手足に力が入らない、めまいや気が遠くなって動けなくなるということもある。なお、これらの症状は15分以上続く。
・狭心症
-冠動脈が細くなって心筋組織への血流が不足し、心筋組織がダメージを受けることによって起こる。
-締めつけられるような胸痛を伴う一連の症候をまとめて狭心症という。
-狭心症は冠動脈の一時的な血流不全によるものなので、通常は、5~15分以内に症状は治まる。
●冬に起こりやすい心臓病
・心筋梗塞は寒い冬に多い。2000年の全国調査では6~9月が最も少なく、12~3月が最も多い。
・人間が冷気に反応するのは恒温動物で、体内の酵素やホルモンを正常に機能させるためである。
-冷気は血管平滑筋を収縮させる。末梢の血流が悪くなり組織を障害すると痛み物質が放出されるとともに、心臓は血流を改善させるため血圧を上げる。
-冷気は皮膚に存在している冷覚受容器によりキャッチされ、中枢神経に伝えられてそれにより交感神経が活性化される。交感神経は末梢の血管を収縮させるので血圧は上がる。
-冷気によって刺激された冷覚受容器は大脳の感覚野へ伝わり、「寒い!」と認識する。さらに大脳の視床下部に伝わって交感神経を活性化する。これによって血圧は上昇する。
・血管が軟らかければ血圧の上昇は少ないが、特に動脈硬化が進行した高齢者では注意しなければならない。
●心臓病はこんな日に気をつけよう
・いくつかの研究で以下のような結果が出ている。
-1日の気温差が9.4℃以上。
-平均気温が15℃未満、または25℃以上。
-平均気圧が1005hPa以下で、平均気温が10℃以下。
-寒冷前線が通過するとき(風向きが北寄りに変わり、気温が急降下する)
第3部 あの身近な症状も!
まさまだある気象病
7 オゾンホールと白内障・皮膚がん
・白内障や皮膚がんの発症には、オゾン層が関係しているため気象病に含めている。
●オゾンホールと白内障・皮膚がんの関係
・白内障は加齢以外に、紫外線や糖尿病、アトピー、喫煙、過度の飲酒、酸化ストレスなどが白内障を加速、進行させる。
・皮膚がんが多いのは白人、国別ではオーストラリアやニュージーランドに多い。しかし日本でも年齢調整罹患率をみると、過去40年で2~5.5へと2倍以上に増加している。
●白内障と皮膚がんの予防法
・白内障の予防に紫外線をブロックするメガネが有効だが、メガネのフレームの形も重要である。ただし、色が濃すぎるレンズの場合、瞳孔が大きくなるために、水晶体は多くの紫外線を吸収してしまうためである。
・喫煙、動脈硬化、生活習慣病の予防も重要である。
・皮膚がんの予防は肌が露出される部分に日焼け止めクリームをこまめに塗ることが効果的である。
・ビタミンCはメラニンの生成を抑制するのでガン予防になる。
8 天気と深い関係の片頭痛
●生活に支障をきたす片頭痛
・片頭痛の患者さんは日本全国に約800万人いると言われている。
・赤ワイン、チーズ、チョコレート、ヨーグルト、アルコール、オリーブオイル、ハム、ソーセージなどの食材の摂りすぎや、翌日の昼頃まで寝るなどの過剰の睡眠など、食事・生活習慣が片頭痛と関係していることが分かってきている。
・女性の場合、母親の遺伝や生理との関連が知られている。
・2001年頃から新薬(トリプタン製剤)が発売され、救世主となっている。
●片頭痛が起こりやすい日をチェックしよう
・片頭痛の主な原因は、ストレス、不眠、空腹、天気の変化、まぶしい日光、食物、生理、疲労、アルコール、寝すぎ、カフェインなどがあげられる。
・季節は春、秋、夏、冬の順に多いとされている。
9 腰痛・関節痛は低湿・低気圧で悪化!
●腰痛・関節痛は体の炎症反応
・『私たちの体内では、炎症反応が無限に繰り返されています。なぜなら人間の体の中には、常に「異物」が存在するからです。「異物」とは、物質も含め、細菌やウィルスなど、人間固有の正常な細胞・組織以外のものを指します。つまり、本人を構成するもの以外のすべてのものです。異物に対し、人間は体内から排除しようと免疫機構が働きます。そのような反応のひとつが炎症反応なのです。
もちろん、小さな炎症反応にすぎなければ、体には何ら症状も起こらず、自覚しないまま終わってしまうでしょう。ただ、炎症が関節やその周囲に及んだときには「関節痛」を引き起こすことになります。』
●低温・低気圧の日に出やすい痛み
・気温が下がると体温を保つために、人間は体内で熱を産生する。すると、カロリーが消費されるため十分な栄養が蓄えられていないと、免疫機能は低下し体内の細菌やウィルスが増殖する。もし、関節や神経の周囲に潜んでいたウィルスなどが増殖すると、関節や神経に炎症反応が波及することになる。
●腰痛・関節痛の対策
・傷害直後は冷やすことが必要であるが、それ以降は保温により血流を高めることが重要である。
・自分自身の痛みと相談しながら少しずつ筋力増強やストレッチを行うことも重要である。
・気象対策は、痛みが起こったときの記録をつけると、気象の変化との関連性が分かるようになるため、保温対策などを取ることができるようになる。
11 気象が引き起こすアレルギー
●寒暖差アレルギーにも要注意!
・寒暖差アレルギーとは寒暖差を原因として、鼻水、鼻づまりやくしゃみが起きてしまう症状であるが、医学的な病名は「血管運動性鼻炎」といって、正確にはアレルギーではない。
・原因は鼻粘膜にある血管の収縮・拡張を調節する自律神経の失調と考えられている。
コロナワクチンの疑問
新型コロナウィルスが日本で発見されたのは、2020年1月15日でした。「大変なことになったなぁ、まさか、生きてる間にパンデミックに遭遇するとは。。」と思い、なんとなくデータの集計を始めました。それは2020年8月初旬のことでした。
ブログ“スペイン風邪と新型コロナ2”をアップしたのは、翌年2021年1月8日です。この時には、頑張ってこの年の年末までデータを集計しようと考えていたのですが、その年末には、第6波の兆しがあったため、つい、そのまま集計を続けてしまい現在にいたっています。さすがに今回の第7波が沈静化したら終わりにするつもりです。
「mRNAワクチンって平気なのかなー」という疑問はなくはなかったのですが、ワクチンは打つべきだと思っていましたので、安全性など特に気にしてはいませんでした。
そんな中、少し前に知り合いから教えてもらったコロナ情報に不安を感じました。
その記事は以下のものです。
“緊急速報!mRNAで想定外の報告、逆にコロナへの免疫を抑制&一生の記憶になる可能性有り、特に子供は一旦接種中止して検討を!”
『7月10日にドイツの複数の大学研究室グループがmRNAワクチンに関して憂慮すべき論文を発表しました。それはmRNAに限り(アストラゼネカのDNAワクチンでは認めず)繰り返し接種することで新型コロナに対して逆に免疫抑制を起こしてしまうのでは無いか、というショッキングなものです。』
『免疫抑制を起こすIgG4がmRNAに限り顕著に検出されブースターで増幅されたという報告です。全く想定外の重大な結果であり、緊急に検討が必要です。』
私にとって次は4回目の接種ということになりますが、現在普及しているワクチンのオミクロン株に対する効果の低さを考えると、打たない方が良いのかなとも思っています。
そこで、ワクチン接種に対してネガティブな情報に注目したいと考え、今回の本が8月24日と最近発行された本ということもあったため、この本で勉強させて頂くことにしました。
もう一人の著者である、鳥集 徹先生は医療分野のジャーナリストです。
目次(大項目のみ)
はじめに
第一章 コロナワクチンの「正体」
第二章 コロナマネーの深い闇
第三章 マスコミの大罪
第四章 コロナ騒ぎはもうやめろ
おわりに
ブログは、第一章 コロナワクチンの「正体」の一部、特に気になったところを取り上げています。
重症化予防効果への疑義
●血中にウィルスが少ないならば、血中の抗体量はあまり重要なことではない。
ワクチンを打っても排出されるウィルス量は不変
●2021年7月、CDC(米国疾病予防管理センター)が、デルタ株に感染した人は、ワクチン接種者も非接種者も、ほぼ同量のウィルスを排出していると発表した。
●mRNAワクチン
・mRNAはDNAから写し取られた遺伝情報に従い、たんぱく質を合成する。翻訳の役目を終えたmRNAは細胞にとって不要なためすぐに分解される。
・mRNAワクチンはmRNAの機能を利用して免疫反応を引き起こすことを目的としたワクチン。
・新型コロナウィルスワクチンは、スパイクたんぱくの遺伝子をコードしたmRNAを脂質の膜(LNP:脂質ナノ粒子)で包んだ構造となっている。これを注射すると体内の細胞がLNPを取り込み、その中のmRNAが細胞内のたんぱく製造工場であるリボソームに送り込まれる。そして、リボソーム内で設計図が読み取られて、スパイクたんぱくが生み出される。そのスパイクたんぱくに、マクロファージや樹状細胞が反応することで、液性免疫や細胞免疫が誘導される。
変異しやすいことは研究者にとって常識
●細胞性免疫
・細菌やウィルスに感染した細胞やがん細胞などの異常細胞を、抗体を介さずに直接攻撃する免疫反応のこと。樹状細胞が異物を見つける、それを取り込んで分解し、その一部を抗原として提示する。それを認識したヘルパーT細胞(T細胞=リンパ球の一種)がサイトカイン(免疫細胞から分泌される生理活性物質)を産生して、マクロファージや細胞傷害性T細胞を活性化させ、異常細胞を殺傷または自死(アポトーシス)に追い込む。
抗体ではなく細胞性免疫が「主役」?
●自然免疫
・体内に侵入した細菌・ウィルスや体内で発生した異常細胞をいち早く感知して、排除する免疫反応のこと。好中球、樹状細胞、マクロファージ、NK(ナチュラル・キラー)細胞などがこれに担っている。さまざまな病原体に対して幅広く対応する自然免疫に対し、「液性免疫(抗体の免疫)」や「細胞性免疫」など、病原体を記憶して再侵入したときに直ちに働く免疫反応を「獲得免疫」と呼ぶ。哺乳類など脊椎動物にしかない獲得免疫に比べ、あらゆる昆虫や動物がもっている自然免疫は原始的なものと考えられてきたが、近年ではウィルスや細菌の種類まで認識する高度な能力をもつと再認識されるようになった。
●新型コロナウィルスに対抗する働きは抗体より細胞性免疫ではないか。免疫はウィルスの種類によってレスポンス(反応)が違う。アデノウィルスは抗体の反応が早くすぐに抗体ができる(抗体価が高くなる)。
コロナウィルスの反応はむしろ遅い方である。自然免疫の他に、細胞性免疫と液性免疫(抗体の免疫)があるが、獲得免疫とされる2つの免疫は、均等ではなくどちらかに偏っている。これは「Th1/Th2バランス」といい、Th1が優位になると細胞性免疫が、Th2が優位になると液性免疫が働く。どちらを高めるかは最初に敵が入ってきたときに樹状細胞やサイトカインが決めるが、反応の遅いコロナウィルスは、細胞性免疫、Th1が優位になっていると考えられる。
なぜ「不活化」ではなく「mRNA」だったのか
●液性免疫(抗体の免疫)
・リンパ球の一種であるB細胞が賛成する抗体によって引き起こされる免疫反応。抗体にはウィルスや毒素に結合することで感染力や毒性を失わせる中和作用のほか、病原体に結合してマクロファージや樹状細胞の働きを助ける。補体(抗体や免疫細胞の働きを補完する物質)を活性化して細胞傷害を引き起こすなどの役割がある。
●ネコの伝染性腹膜炎ウィルスはワクチンにより抗体を誘導すると逆効果になる。これはADE(抗体依存性感染増強)が起こるためである。
●ADE(抗体依存性感染増強)
・ウィルス感染やワクチンによって体内にできた抗体が、感染や症状をむしろ促進してしまう現象。同じコロナウィルスの仲間によって引き起こされたSARS(重症急性呼吸症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)のワクチンは、このADEの発生がネックとなって開発が断念された。また、熱帯地方で流行するデング熱のワクチンも、接種した子どものほうが重症化率が高くなるおそれがわかり、これを導入したフィリピン政府が2017年に接種を中止した。
ADEは中和作用をもたない抗体が、むしろ感染を手助けする方向に動くことで起こると考えられている。
●不活化ワクチン
・細菌やウィルスから毒性を取り除き、免疫反応を誘導できる成分を取り出してつくられたワクチン。増殖する能力がないので、長期にわたって免疫反応を維持する目的で、複数回投与されることが多い。破傷風、インフルエンザなどで不活化ワクチンが使用されている。
●抗体をつくらせるだけなら不活化ワクチンでよい。コストはかかるが高度な技術は不要である。欧米の製薬会社がmRNAワクチンを選択したのはコロナウィルスの特性を考えたからであろう。コスト面ではmRNAワクチンは人工合成で大量生産が可能なので低コストで生産できる。
●不活化ワクチンは抗体を誘導する傾向が強いので、ADEが起こって逆効果になるおそれがある。
●mRNAワクチンは細胞性免疫も誘導するためmRNAワクチンが選択されたと思われる。
●宮沢:『実は、私たちが動物用のワクチンを開発するときには、抗体が効いているのか、それとも細胞性免疫が効いているのかを、受身免疫という方法で確認するんです。ワクチンを打っていない動物に抗体だけを投与したり、あるいは免疫細胞を投与したりして調べることができます。とくにマウスでは遺伝的条件を備えられるので実験しやすいです。しかし、ヒトでは細胞性免疫が効いているかどうかを調べるのは、コストもかかります。だから、ワクチンの効果を示すのに「抗体が上がっている」という話をするのだと思います。しかし、抗体があまり意味がないとしたら、この抗体で評価すること自体おかしいということになります。』
「抗体」の罠
●中和抗体
・ウィルスや細菌の病原性を失わせる作用のある抗体のこと。新型コロナウィルスの場合、ウィルスのスパイクたんぱくに中和抗体が結合すると、ACE2受容体に接着できなくなり、細胞への感染ができなくなる。ただし、ワクチン接種によって中和抗体ばかりができるわけではなく、かえって感染や重症化を促進するADE抗体も同時にできるおそれがあると指摘されている。
●ADEはウィルスを中和できない抗体が悪さを及ぼすことで起こる。ネコのコロナウィルスに対するワクチンする時もADEをいかに回避するかということが大きな問題であり、いまだに安全で有効なコロナワクチンができない。
●ワクチン接種による重症化の防御は抗体というより、細胞性免疫や自然免疫の可能性も考えられる。
●宮沢:『私は細胞性免疫の誘導だけを考えるなら、2回のワクチンで十分ではないですかと言ってきました。細胞性免疫がウィルスに感染すると、感染細胞を認識してやっつける細胞傷害性T細胞ができます。一度感染すれば、十分な数のウィルス特異的細胞傷害性T細胞ができなます。ウィルスがいなくなると、特異的細胞傷害性T細胞の数は減り、分裂をやめて少し小さくなってリンパ節などに潜みます。これをメモリーT細胞と呼びます。そして、次に感染したときにはすぐに爆発的に増殖して、感染細胞をやっつける細胞に変わります。いったん減っても、感染すればすぐに戻るので対抗できるわけです。なので、よほどのことがない限り2回のワクチン接種で十分なはずです。』
●抗体は減少していくものなので、細胞性免疫をきちんと誘導できていれば、抗体が減ってもあまり気にする必要はない。
●宮沢:『さらに抗体を上げるとADEも起こりかねないので、私たちはすごく怖かった。ネコの伝染性腹膜炎ウィルスは、抗体と結びつくとマクロファージに感染しやすくなるんです。ところが不思議なことに、新型コロナウィルスはマクロファージに感染してもあまり増殖できないようなのです。同じコロナウィルスで系統も近いSARSコロナウィルスやMERSコロナウィルスはマクロファージに感染してADEが起こったのに。そのせいか、新型コロナウィルスでは今のところADEがそんなに問題になっていない。
もし一部の人で新型コロナウィルスが変異して、ワクチンによって産生された抗体によってマクロファージに感染し、ADEを起こすタイプに変われば、その人にとっては逆効果になってしまう。ひとたびそのような変化が起こったらとんでもないことになります。だから抗体を上げるのは博打だから、やめたほうがいいと言ってきた。』
重症化予防効果はあるのか、ないのか
●宮沢:『重症化予防になるかどうかは一概には言えないと思います。ワクチンを打って細胞性免疫の活動を上げれば感染細胞を殺すことができるので、広がらなくすることができるから重症化予防になるでしょう。しかしその一方で、前に言ったように抗体が悪さをする可能性もあるので、差し引きが分からないんです。私がずっと言ってきたのは、たしかに感染予防効果、重症化予防効果は論理的に考えてあるでしょう。しかし、その半面、逆も真なりだよと。どっちが多いのか。それがわからないのです。
(-抗体をあげるといっても、中和抗体ばかりができるわけではなく、ADE(感染増強)抗体もできる可能性がある?-)
そうです。ADE抗体が多ければ免疫細胞へ感染しやすくなるし、増悪させてしまう。一方、細胞性免疫ならいいと私も思いますが、考えようによっては細胞性免疫だって悪く働く可能性がある。なぜかというと、たとえばウィルスが肺に到達して、そこで感染細胞が一気に増えたとしたら、細胞性免疫が肺の細胞を一気に攻撃する。そうすると炎症が広がって、肺が広範囲に傷害を受けてしまう。そういう可能性もあるんです。ですから、細胞性免疫だって絶対善ではないんです。』
mRNAワクチンでなぜ人体に害が起こり得るのか
●スパイクたんぱくを作り出している自分の細胞を、ウィルスに感染した細胞と勘違いして、細胞性免疫を攻撃することを危惧している。
コロナ後遺症とワクチン後遺症の症状が似ている理由
●厚労省は2021年12月、心筋炎を「重大な副反応」と位置付けた。
●スパイクたんぱくが心臓に付着したら、免疫細胞や抗体と補体(抗体や免疫細胞の働きを補完する物質)から攻撃を受けるだろう。それだけでなくLNP(脂質ナノ粒子)が心臓の細胞に取り込まれ、スパイクたんぱくが作られれば、細胞性免疫の攻撃対象になるだろう。
●コロナウィルスによるスパイクたんぱくとワクチン接種によって細胞が作り出すスパイクたんぱくに大きな違いがあるとは考えにくい。もし、コロナの後遺症がスパイクたんぱくによるものだったとしたら、ワクチン接種で同様なことが起こっても不思議はない。
●mRNA由来のスパイクたんぱくが残存して4カ月以上体内を循環しているという論文もある。
●通常はスパイクたんぱくといえども分解されると思うので、体内のどこかでつくり続けているという可能性が高いと思う。
mRNAワクチンは体内でも短時間で分解されるのか?
●シュードウリジン化
・シュードは「偽の」という意味。mRNAは4つの核酸化合物によって構成されている。mRNAワクチンでは、その核酸化合物の一つであるウリジンが、修飾核酸に置き換えられている。それによって、通常は体内に入れるとするに免疫によって破壊されるはずのmRNAが免疫を回避できるようになり、十分なスパイクたんぱくを作れるようになった。
●試験管内の実験においてmRNAが数時間で分解されても、ヒトの体内でも同様なスピードで分解されるかどうかは簡単にはわからない。
●mRNAワクチンは一部をシュードウリジン化している。これによりmRNAは数時間、分解されることなくスパイクたんぱくを作れるようになっている。しかし、数時間で分解できないとなると、それは問題である。
●ワクチンを接種した人がコロナに感染して、それによってずっとコロナのスパイクたんぱくが出ている可能性もある。
接種者は非接種者に比べて1.4倍「帯状疱疹」になりやすい
●イスラエルでは医療保険システムのデータを使って、ワクチンの接種者と非接種者、約884,000人を比較した研究によると、接種者は非接種者に比べて1.4倍帯状疱疹になりやすいというデータが出ている。一時的ではなくかなりの免疫抑制が起きている可能性がある。
”BNT162b2ワクチンの有害事象を調べたイスラエルの大規模研究が注目”
『ワクチン群の候補者173万6832人の中から、非接種者と年齢、性別、人種、居住地、社会人口動態条件、併存疾患などの条件がマッチするペアを88万4828組選び出した。年齢の中央値は38歳で、48%が女性だった。非接種者と比較したワクチン群の有害事象のリスク比は、心筋炎3.24(95%信頼区間1.55-12.44)、リンパ節腫脹2.43(2.05-2.78)、虫垂炎1.40(1.02-2.01)、帯状疱疹1.43(1.20-1.73)などだった。』
免疫システムを混乱させている可能性
●宮沢:『mRNAワクチンの接種後に免疫システムの混乱を起こしていないかどうか確認したんだろうかと思って論文などを探すのですが、それを網羅的に調べた研究が見つからないんです。ただし、ワクチンを打った人の免疫細胞の反応が鈍っているという論文はいくつか出ている。それを見ると、免疫システムがおかしくなっても不思議ではありません。
なぜなら、私たちの体の細胞はたんぱく質をつくっています。その設計図は、人間を含む真核生物の場合、細胞の核に収容されているDNAの中にとびとびに書き込まれています。それをくっつけて一つの設計図にして、mRNAに転写してリボソームに送り、そこでたんぱく質をつくります。
そして、普通は必要な量だけつくったら、そのたんぱく質をつくるのをやめるんです。なぜかというと、たんぱく質をつくりすぎると他の細胞に悪影響を及ぼしてしまうから。どんなに毒性が低いたんぱく質でも一つのたんぱく質を大量につくると、細胞が死んでしまうんです。だから、適正な量で止めなきゃいけない。
では、どうやって止めるかというとmRNAをすぐ壊すんです。それでたんぱく質が足りなければ、もう一回、mRNAが出てくる。そのmRNAの寿命も、実はすべて同じではありません。早く壊れるものもあれば、長く残るものもある。それもどこがどう違うのか、今、盛んに研究されていますが完全にはわかっていないんです。
(-mRNAが壊れる時間も、意図的に制御されているんでしょうか-)
詳細はよくわかりませんが、いずれにせよmRNAは基本的には早く壊すんです。ところが今回のワクチンのmRNAは、細胞内のセンサーは認識できず、自然に壊れる時間に比べると残存する時間が圧倒的に長いわけです。また、通常のmRNAの分解機構と異なる方法で分解されます。そんな状態のなかで、体内にあってはならない(あるいは不要の)たんぱく質が大量につくられてしまったらどうなるか。たんぱく合成を早く止めたいんだけど、細胞には止め方がわからない。普通ならDNAから転写されてmRNAを見つけることすらできない。だとしたら、細胞はどうするか。私が細胞だったら、「センサーが足りないんじゃないか」と思うでしょう。だから、センサーの分子を増やそうとする。そうなると思いませんか?
(-思うかもしれません-)
私のセンサーが消えてしまったのではないか、あるいは私のセンサーが壊れてしまったのではないかと勘違いして、混乱するのではないかと思うんです。その混乱が、今、起こっているのではないかと私は思うんです。
(-その可能性はありますね-)
この混乱が一過性だったらいいのですが、比較的長く続く可能性だってある。訓練免疫という言葉がありますよね。免疫システムは経験したことのある外敵のことを覚えていて、2回目、3回目になるほどレスポンスが強くなる。獲得免疫と違って、自然免疫にはそのような記憶はないといわれてきました。しかし、最近の研究では自然免疫にも記憶があるようだと言われ始めています。
自然免疫も、何度も同じ外敵を浴びていたらレスポンスが早くなる。おそらくセンサーが反応しやすくなるのだと思います。そのセンサーを混乱させたら、レスポンスはどうなってしまうのか。たとえばピアノを弾く練習をしてピアノがうまくなったとします。しかし、その後におもちゃのピアノを渡されたら。
(-本物と同じようには弾けないでしょうね-)
そうです。それでおもちゃのピアノばかり弾いていたら、今度は本物のピアノが弾けなくなる。つまり、シュードウリジン化して修飾したmRNAによって免疫が混乱すると、本物のウィルスにうまく反応できなくなることもあり得ると思うのです。
そのような反応を制御しているのが何かというと、今よく言われてるのがエピジェネティックなのだと思います。通常、親の特徴はDNAに書かれた遺伝子を通じて伝わることがある。これがエピジェネティックです。DNAの遺伝子の一部やDNAを取り巻くたんぱく質の化学的性質が変わることによって、どの遺伝子が発言して働くかが変わってくる。最近の研究ではそれが世代を超えて遺伝することもわかってきています。ある世代で起こった遺伝子発現のパターンの変化が次世代に伝わってしまう。これは驚くべきことです。』
感想
パソコンのOS(オペレーティングシステム)は、多くの開発エンジニアが十分な期間をとって、品質安定のためテストを行うものですが、それでも製品が出荷され、何万、何十万、何百万人とユーザが増え、期間も1カ月、半年、1年と経過するなかで、いわゆるバグが見つかり、改善ということを繰り返し、OSとしての完成度は高まります。
今回のコロナワクチンはインフルエンザで採用されている従来の不活化ワクチンではなく、mRNAワクチンなど、新しいメカニズムをもったワクチンになります。その意味では未知の部分が少なくないことは間違いありません。
抗体の数が大きく取り上げられている状況ですが、細胞性免疫や自然免疫の重要性も非常に高いようです。
また、抗体も中和抗体は力強い味方ですが、抗体全体を眺めてみると、味方ばかりではなく、リスクも存在しています。IgG4については特に触れられていませんでしたが、免疫力が落ちるという論文は複数出てきているとのことです。
以上のことから、オミクロン株への防衛機能が乏しい現在のワクチンによる4回目のブースター接種は見送った方が無難かなという気持ちが強くなりました。
不整脈と薬4
『病気がみえる vol.2 循環器』を元に各不整脈の一覧表を作りましたが、最初に心臓に関する基本的なことをまとめたいと思います。

画像出展:『病気がみえる vol.2 循環系』
・心臓は横隔膜、胸骨、脊柱に付着し、心臓の過度な移動や拡張を防いでいる。
・肺などの周辺臓器に感染がある場合、心膜は感染の拡大を防ぎ、心臓への影響を遅延させる。
※心膜はファシアである。

画像出展:『病気がみえる vol.2 循環系』
・心膜腔には正常で15~50mLの心膜液が貯留している。
・心膜液は臓側心膜と壁側心膜の摩擦を防ぎ、心臓のスムーズな拍動を可能にしている。
・心膜液は臓側心膜で産生され、胸管や右リンパ管に排出される。
まとめ
不整脈を考える上で知っておくべきことは以下の3つです。
●心臓の電気生理
●不整脈が生じるメカニズム
●薬物の作用機序
”心臓の電気生理”は次の3つが重要です。
●脱分極
●再分極
●不応期
『「電気生理学について深い知識なしに不整脈の治療はできない」というのはおこがましい。しかし、「イオンチャネルについてささやかな知識がなくては、不明脈の治療はできない」というのは正しい。』とのことです。
不整脈治療について、村川先生は次のようなお話をされています。
『「抗不整脈薬の薬理学はどうもわかりにくくて、嫌になる」というのはまともな感覚。なかなか頭の中が整理できない。』
『これまで蓄積された情報を十分マスターしたとしても、未知の要因がたくさん残されている。不整脈の専門家でも「確信はないがとりあえず使ってみる」というパターンが多い。』
『陰性変力作用や催不整脈作用、あるいは薬物代謝の面で使いにくい薬剤を避けるという「消去法の発想」のほうが正直な道だと思う。』
『それなりのクスリはあるが、魔法のクスリはない。』
『不整脈の治療には、とりあえず、「イオンチャネル」と「それ以外」と単純に考えてよい。』
『不整脈についての知識と経験が増すほど、意識的に治療しないという道を選ぶ。』
『頑張りすぎると募穴を掘る。』
『「慎重さと果敢さのバランス」も大事。』
☆自律神経系の影響を受けやすい
●特に洞結節、房室結節は自律神経系の影響を受けやすい。
☆心房細動に関すること
●発作性心房細動はしばしば肺静脈の反復性興奮による。
●多くの抗不整脈薬は陰性変力作用を有するので、心エコーによる心機能の評価なしの投薬には限界がある。心房細動を見たら心エコーは必須。
☆心機能と腎機能が低下している高齢者
●陰性変力作用が少なく、腎排泄でないという条件に加え、潜在的な徐脈性不整脈や催不整脈作用に注意する。
☆アミオダロンとICD(植込み型除細動器)
●アミオダロンは最もパワフルな抗不整脈薬であり、適応を判断することが難しいため、基本的に不整脈薬専門医によって処方される。
●アミオダロンは副作用の点で使い方が面倒だが、重篤な心室不整脈にはほぼこれしか選択肢はない。使うべきときには積極的に使う。ハイリスクなら植込み型除細動器(ICD)が併用される。
不整脈と薬3
Part4 心房期外収縮
25 変行伝導は大事か?
□期外収縮は心臓のどこからでも生じるので、心房期外収縮(PAC)と接合部期外収縮を厳密に区別できない。そこで、ひとまとめにして上室性期外収縮(SVPC)と呼ぶこともある。
□PACに機能的な脚ブロックが生じるとQRS幅が拡大して、心室期外収縮(PVC)と間違いやすくなる。PACの変更伝導は右脚ブロックが多い。
26 治療するかどうか、誰が決めるか
Key Point
1)心房期外収縮(PAC)の薬物治療の適応は患者が決める。
27 使いたい抗不整脈薬と、使ってもいい抗不整脈薬
Key Point
1)心房期外収縮(PAC)にどの抗不整脈薬が有効なのか、確立されたエビデンスはない。
□心房期外収縮(PAC)の治療に選択しやすい経口薬剤は、
●ピルジカイニド(サンリズム):お勧め度4。『「とりあえずコレで」と使われる。』
●アプリンジン(アスペノン):お勧め度4。『おとなしい感じがある。』
□使いなれていたり、心エコーなどで心機能を含めた評価が十分に行われていたら使用できるし、効果も期待できるのは、
●ジソピラミド(リスモダン):お勧め度2。『知名度高いので。』
●シベンゾリン(シベノール):お勧め度2。『使用経験があるのなら。』
●ピルメノール(ピメノール):お勧め度2。『PACに試したことはないが、たぶん効く。』
●フレカイニド(タンボコール):お勧め度3。『著効することあるが、ちょっと大物すぎる。』
□使ってもよいが、それほど効果はないのが、
●ベラパミル(ワソラン):お勧め度2。『心房細動と似たようなPAC頻発ならレートコントロールとして使う状況はある。』
□有効であっても使わないのは、
●ソタロール(ソタコール):お勧め度1。『さすがにはばかる。』
●アミオダロン(アンカロン):お勧め度1。『大砲は使えません。』
Part5 心室期外収縮(PVC)
33 心室期外収縮(PVC)が“治療対象でない”とはどういう意味か?
Key Point
1)PVCそのものを治療対象として捉えるのではなく、「PVCの波形から心筋障害や病的再分極異常を察する」と考える。
34 頻発する心室期外収縮(PVC)は心不全を招くか?
□心筋障害とは何かというと、多くは加齢に伴う心室筋の変性。もちろん陳旧性心筋梗塞、拡張型心筋症、高血圧性心筋肥大なども背景になる。
39 Case:流出路起源の心室期外収縮(PVC)
□2~3日の服用で薬物の効果を評価できる。有効でない薬剤なら1週間を超えて服用させる意味はない。
40 連発の多い心室期外収縮(PVC)
□β遮断薬やベラパミルが適応となる。約半数、あるいはそれ以上の有効性が期待される。
Part6 発作性上室頻拍(PSVT)
42 頻拍の呼び方
□心房粗動、心房頻拍、発作性上室頻拍の定義は曖昧さが残り、同じ不整脈でも人によって呼び方が異なることがある。
43 発作性上室頻拍(PSVT)は2種類と割り切る
Key Point
1)PSVT(発作性上室頻拍)のメカニズムとして、AVRT(房室性回帰性頻拍)とAVNRT(房室結節エントリー性頻拍)の2つを理解する。
Part7 心房粗動
56 通常型と非通常型
□心房粗動は規則正しい鋸歯状の心房波がみられるものをいう。粗動波ともいう。
□心房細動と心房粗動ともに認めれることは稀でなく、区別が難しい場合も多い。心房細粗動という用語もある。
□上室性の不整脈としてはありふれたもので、器質的心疾患がなくても発生する。加齢や器質的心疾患により頻度は高くなる。
57 抗不整脈薬で心房粗動を治療できるか?
Key Point
1)心房粗動の薬物治療で最も大事なことは、抗不整脈薬の有用性が低いこと。
□慢性期の心房粗動の治療には高周波によるカテーテルアブレーションが有効。
□急性期でも慢性期でも、無理に洞調律化を狙わないことが心房粗動の薬物治療の原則。とりあえずレートコントロール[リズムは心房細動のままで、心拍数を薬剤でコントロールする]さえできれば、長期にわたって大丈夫。
58 ダメモトで抗不整脈薬による洞調律化を狙いたいとき
□心房粗動に気の利いた薬物治療がないというのは大事な知識。しいて言えば、Ⅲ群薬のニフェカラントが検討に値する。
Part8 心房細動
59 忘れられていた肺静脈
□以前は、心房細動(AF)の一部のみが肺静脈起源と思われていたが、器質的心疾患の有無によらず発作性心房細動(PAF)の94%において肺静脈が関与しているという報告もある。
Key Point
1)発作性心房細動はしばしば肺静脈の反復性興奮による。
アブレーションによる肺静脈隔離
□肺静脈は左房開口部から1cm内外に心筋組織を有している。肺静脈と左房との電気的連絡は開口部の全周に及ぶのではなく、数本の線維を経由する。肺静脈の電気的隔離とは、この肺静脈と左房との連絡を断ち切って、肺静脈における反復性興奮が心房へと伝わらないようにすることである。
□カテーテルアブレーションによる肺静脈隔離は、左房と肺静脈をつなぐ筋線維を高周波通電により念入りに遮断する手技として始まった。しかし、複数の肺静脈が頻拍起源となることや、上下の肺静脈の間にも電気的な連絡があることがわかってきた。これらの知見と手技的な簡便さもあって、最近は左房の広範な線状焼灼により遠巻きに肺静脈開口部を隔離する方法を選択する施設が多い。
持続性心房細動と肺静脈との関係は、
□肺静脈以外にも上大静脈や心房のどこかが高頻度の興奮を生じて心房細動を引き起こすことがある。肺静脈とそれ以外の組織の両方にフォーカスが存在することもある。
60 AFはAFを招く(AF begets AF)
□AF begets AFとは、「心房細動の発生それ自体が次の心房細動出現を促進する」という意味。
Key Point
1)心房細動が持続あるいは頻発するとき、速やかに対処しないとこじれやすい。長期に続いた心房細動は左房の拡大や組織学的な変性を招く。こうした変化は同時に心房細動をいっそう治療抵抗性とする。
61 基礎疾患のある発作性心房細動(PAF)
□心房細動(AF)は器質的心疾患のない患者にもしばしば出現するが、原因があれば根本から対処する。以下は関連の強さ。
●弁膜症:『心雑音がなくても弁膜症はある。』
●心不全:『心房細動と心不全、どちらが先か簡単にはわからない。』
●洞不全症候群[心臓のペースメーカーの異常で心拍数が低下する病気]:『ありふれている。』
●甲状腺機能亢進症:『わかっているのに見落とす』
●肥大心筋症:『1/4に心房細動ありとか。』
●高血圧心疾患:『これがクセモノ。底に流れている。』
●肺高血圧:『それほど経験はない。』
●虚血性心疾患/急性心筋梗塞
●心膜炎
□多くの抗不整脈薬は陰性変力作用を有するので、心エコーによる心機能の評価なしの投薬には限界がある。心房細動を見たら心エコーは必須。
□急性期を過ぎれば、心筋梗塞では、アミオダロンなど一部の抗不整脈薬を除き、抗不整脈薬の予後改善効果は大きな期待ができないばかりか、ときに予後を悪化させる。急性心筋梗塞による入院後にアミオダロンを処方された患者と無投薬の症例では、短期的も長期的には予後の差は認められていない。
62 急性心筋梗塞と心房細動
□心筋梗塞では心不全が先行している心房細動が多い。
65 なぜ抗凝固療法?
□血栓塞栓症の予防は心房細動の治療において大きな位置を占める。血栓は冠動脈のような高圧系では血小板血栓、心房のような低圧系ではフィブリン血栓になる。
□冠動脈内での血栓形成には血管内皮の損傷からvon Willebrand因子の関与する血小板の血管との相互作用を経て、血小板血栓が作られる。
□減速の低下した心房細動の心房では凝固系の活性化が進み、トロンビンの形成からフィブリン形成という一連のカスケードが促進される。
Key Point
1)冠動脈疾患⇒高圧系の血栓(血小板血栓)⇒抗血小板薬
2)心房細動の血栓⇒低圧系の血栓(フィブリン血栓)⇒抗凝固療法(ワーファリン)
□左房の中でも左心耳は、一種の憩室として血液のうっ滞がはなはだしい。拡大した左房では、ことに流速の低下や乱流がからんで血栓が形成されやすい。また、左心耳の内側膜は凹凸が多く、袋状の構造もあった血栓形成には都合が良い。
□フィブリン血栓には凝固因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹは還元型ビタミンKによって活性化される。ワーファリンはビタミンKの還元型への移行を司る還元酵素を阻害し、フィブリン血栓の形成を抑制する。
新しいトロンビン阻害薬
□トロンビン阻害薬という薬剤(ダビガトラン)はワーファリンに代わる新たな抗凝固療法の薬として期待されている。
※ご参考:”似て非なる抗凝固薬 直接トロンビン阻害剤の特徴”
75 顕性WPW症候群(偽性心室頻拍)の心房細動
□WPW症候群[ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群:心房と心室の間に電気刺激を伝える余分な伝導路(副伝導路)が生まれつきあることで発生する病気]では、若年でも心房細動が出現しやすい。1/3という数値も報告されている。
□WPW症候群に合併した心房細動は偽性心室頻拍と呼ばれ、心房の興奮が副伝導路を介して心室に伝わり心室細胞を起こすこともあるため注意が必要。
Part9 wide QRS tachycardia
91 器質的心疾患を背景にしたVT
□VT(心室頻拍)の基質となる心疾患は、おおむね陳旧性心筋梗塞である。
□陳旧性心筋梗塞(OMI)の心室頻拍は突然死を生じるが、薬物治療には限界があり、ICD(植込み型除細動器)の出番が多い。
□これまでの大規模臨床試験や周囲の専門家からの示唆に基づいたルールは、
●Ⅰa群薬とⅠc群薬は予後を悪化させる。ことに心機能障害や虚血性心疾患を有する患者では断定的である。
●Ⅰb群薬については知見が乏しい。しかし、陳旧性心筋梗塞の患者に不整脈薬の有無を考慮せずにメキシチールを投与した研究では、心室性期外収縮(PVC)数は減少傾向を示したものの、死亡率は高めになっていた。
●慢性期は原則としてアミオダロンで治療する。
●β遮断薬やレニン-アンジオテンシン系に作用する薬剤を併用している方が予後が良い。禁忌でなければ使う。
92 経口アミオダロンを陳旧性心筋梗塞や不整脈原性右室心筋症のVT/VFに使う
□アミオダロンは基本的に不整脈薬専門医によって処方される。適応を判断することが難しい。
□アミオダロンの副作用[吐き気、肺機能障害、甲状腺機能異常、角膜色素沈着、視覚障害など]は、多めに投与すればしばしば出現する。
□甲状腺と肺への副作用を考慮して、アミオダロンを使用する前に甲状腺ホルモンと一酸化炭素拡散能(DLco)を測定する。肺の間質性変化はCTで確認する。
□アミオダロンは効果が出てくるまで時間がかかる。
□アミオダロンにはβ遮断薬作用があるが、心不全があればカルベジロールの併用が行われる可能性が高い。
□抗不整脈薬の効果は確実性が低いため、ICD装着したうえで作動頻度を下げるためにアミオダロンを併用する。
Part11 洞不全症候群
99 徐脈と頻脈のウラに薬あり
□徐脈や頻脈は薬剤によって起こることも稀ではない。気管支拡張薬などの交感神経活動を刺激するものは分かりやすいが、閉塞性動脈硬化症や脳梗塞などの治療薬のシロスタゾール(プレタール)でも洞頻脈を生じる。
□抗うつ薬による頻脈も多い。
□薬剤性徐脈
●β遮断薬やベラパミルの投与量、服用のあやまり、患者自身の刺激伝導系の障害や薬物代謝機能の低下による徐脈。
●徐脈を生じるリスクのある薬剤であることを認識せず、徐脈基質を有する患者に投与された場合。
□日常臨床では、β遮断薬、非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬(ジルチアゼムとベラパミル)、ジギタリスによる徐脈が多い。これらの薬剤を併用したときには、その頻度も高くなる。
不整脈と薬2
Part3 抗不整脈薬のアウトライン
11 抗不整脈とはつまり何か?
□「抗不整脈薬の薬理学はどうもわかりにくくて、嫌になる」というのはまともな感覚。なかなか頭の中が整理できない。
□抗不整脈薬とはNa⁺チャネル遮断作用を中心において、これにおまけの性質がプラスされていると考えればよい。
Key Point
1)抗不整脈薬=Na⁺チャネル遮断作用+α
□Na⁺チャネルは心筋伝導をつかさどる。ほとんどの抗不整脈薬が心筋の伝導を抑制する。
□Na⁺チャネル遮断作用以外のプラスアルファの性質には、主なものとして3種類ある。
●K⁺電流遮断作用(APD延長)
●カルシウム拮抗作用
●β遮断作用
□これらの3つの作用は伝導を抑える点ではNa⁺チャネル遮断作用と似ている。K⁺チャネル遮断作用はAPD[活動電位持続時間]長くして、不応期も延長するので、興奮を受け入れられるようになる時間が遅くなる。
□カルシウム拮抗作用はCa²⁺電流に依存した領域での伝導性を低くする。例えば洞結節と心房間、および房室結節。
□β遮断作用は交感神経活動に依存したチャネルをブロックして心筋の伝導性を落とす。房室結節などCa²⁺電流に依存した心筋は、健康な心臓に比べて自律神経への依存性が高い。
□Na⁺チャネル遮断作用以外も伝導を邪魔して頻拍を治療する。
Key Point
1)Na⁺チャネル遮断作用も付随的な作用も、伝導性を修飾して抗不整脈薬効果を発揮する。

画像出展:『病気がみえる vol.2 循環器』
・正常では洞結節がペースメーカとなり、洞調律(正常な心拍のリズム)を形成する。
・不整脈は刺激伝導系から固有心筋への興奮伝導の異常や興奮発生の異常によって発生する。
左図の上段
1.洞結節-指令を出す(社長)
2.刺激伝導系-指令を伝える(中間管理職)
3.心房筋・心室筋-動く(社員)
左図の下段
・刺激生成異常、刺激伝導異常の原因は社長、中間管理職、社員のいずれかの問題と考えられる。
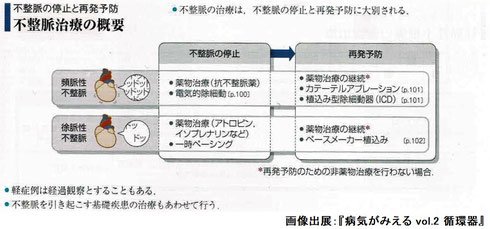
画像出展:『病気がみえる vol.2 循環器』
・不整脈の治療は不整脈の停止と再発予防に大別される。
・軽症例は経過観察 の場合もある。
・不整脈を引き起こす基礎疾患の治療もあわせて行う。
12 抗不整脈の分類:Vaughan-Williams分類はまだ生きている
□抗不整脈薬の分類としては、Vaughan-Williams(ボーン-ウィリアムス)の分類が基本。
□これはNa⁺チャネル遮断作用とAPD(活動電位持続時間)への作用の2点に注目した分類である。また、APDの延長はほとんどがK⁺チャネル遮断作用による。
●Na⁺チャネルの遮断……伝導の抑制
●K⁺電流の抑制……APDの延長≒不応期の延長
□APDの延長は心筋の不応期(興奮した後に興奮性が失われる時間、つまり刺激への反応性が低下している期間)の延長をもたらす。
□基本的にNa⁺チャネル遮断薬は、Vaughan-Williams分類ではⅠ群薬に入り、他の電流との兼ね合いからⅠa、Ⅰb、Ⅰcのサブタイプに分かれる。
□多くの新薬が加わったため、1990年より電気生理学的な新知見を盛り込んだ新しい分類、薬剤の性質を詳細に列挙した、Sicilian Gambitの分類が提唱された。
こちらは『病気がみえる vol.2 循環器』の表ですが、”Vaughan-Williams分類”と”Sicilian Gambit分類”の対比ができてとても親切な表です。これを見て分かったことを整理します。
1.村川先生の教え(不整脈薬は”イオンチャネル”と”それ以外”に分ける)に従うと、
1a)イオンチャンネル遮断薬は3種類ある。Na⁺チャネル(Ⅰx群薬)、Ca²⁺チャネル(Ⅳ群薬)、K⁺チャネル(Ⅲ群薬)である。
1b)いずれの遮断薬も遮断作用には、”高”、”中等”、”低”という違いを有する。
2a)Na⁺チャネル遮断薬は、結合・解離の速さに関しては、”速”・”中等”・”遅”に分けられる。
2b)Na⁺チャネル遮断薬は、”活性化チャネル”を狙ったものと”不活性化チャネル”を狙った物に分けられる。
3a)村川先生の”それ以外”に該当する薬は、”受容体”にはたらきかけるものであり、最も多いのはβ受容体をターゲットするもの(β遮断薬)であるが、β以外には、α受容体、M₂[ムスカリン]受容体、A₁[アドレナリン]受容体がある。
3b)受容体以外には、”ポンプ”(Na⁺、K⁺、ATPase)と”作動薬(刺激作用)”がある。
13 たくさんあるⅠ群薬:どこが
□Ⅰ群薬について、以下の3点について少し知っておきたい。
●活性化チャネルブロッカーと不活性化チャネルブロッカー
●Na⁺チャネルとの結合・解離の速さの差
●Na⁺チャネル以外のイオンチャネルへの作用
□Cast study[心筋梗塞発症後の無症候性あるいは軽い症候性の心室期外収縮、非持続性心室頻拍症例において、抗不整脈薬治療によって不整脈を抑制することが、抗不整脈薬治療によって不整脈死を低下させるか否かを検討する]で、心筋梗塞後にⅠ群薬を使うと予後が示された。拡張型心筋症や中等度以上の弁膜症でも、それなりの心筋障害があればⅠ群薬はマイナスになると思われている。
Key Point
1)器質的背景があるときにⅠ群薬を使うと予後を悪化させかねない。積極的に用いられなくなった。
□Ⅰ群薬の使い方で最初に覚えることは、リドカインとメキシレチンは心室の不整脈にのみ有効で、これ以外のⅠ群薬は上室性不整脈と心室不整脈の両方に有効性が期待されるということ。
Ⅰ群薬の使いどき
□Ⅰ群薬を使う状況として多いのは
●一部の症状の強い期外収縮
●発作性心房細動(PAF)で洞調律を狙うとき
●発作性上室頻拍
□Ⅰ群薬は一般的に、期外収縮30%、発作性心房細動15%、発作性上室頻拍20%。
14 チャネルに統合するタイミング:活性化チャネルブロッカーと不活性チャネルブロッカー
□Ⅰ群薬は活性化状態のチャネルと不活性化状態のチャネルへの親和性の差によって、活性化チャネルブロッカーと不活性化チャネルブロッカーに分けられる。
□活性化したチャネルはあっという間に不活性化状態になる。
□Na⁺チャネルが開くのは膜電位がちょっと浅く(-90mVから-70mVに)なったときに開口するゲートがあるからだ。このゲートは開いた後(活性化)はパッと閉じることができないので、別な位置にもう一つゲートを準備して、そこで素早く蓋をする(ここが不活性化)。どうしてこうなっているかというと、ごく短時間に大量のNa⁺を取り込みたいが、際限なくNa⁺が細胞内に流れ込まないようにしたいという理由による。開くゲートと蓋をするゲートの分業にすることでメリハリが生まれる。
□Ⅰa群薬は活性化チャネルブロッカーであり、おもに活性化状態のNa⁺チャネルに結合する。
□Na⁺チャネルと結合するタイミングにはどんな意味があるのか。
●心房は心室よりAPDが短い。そのため、心房では不活性化チャネルブロッカー(リドカイン、メキシレチン、アプリジン)がチャネルと結合できる時間は短い。つまり、不活性化チャネルブロッカーはAPDが短い心房には作用しにくい。これに対し、活性化チャネルブロッカーは心房、心室いずれにもNa⁺チャネルを有効にブロックできるので、両方の不整脈に対しても効果を現しやすい。
Key Point
1)不活性化チャネルブロッカーは心房の不整脈に効きにくいが、活性化チャネルブロッカーは心房・心室いずれの不整脈にも有効というのが基本。
15 さっぱり系としつこい系、粘り強さが違う:Na⁺チャネルとの結合・解離
□Na⁺チャネルとの結合と解離の速さも薬剤を分類する要素になるⅠa群薬はⅠb群薬に比べ結合がゆっくりしており、離れるのも遅い。
●「スッポンみたいに噛み付いたら放さない」のか、「とりあえず噛み付いてもすぐに放す」のか……という差。
□Na⁺チャネル遮断後の回復時定数は0.19秒のリドカインと43.0秒のジソプラミドでは約20倍もの差がある。
□結合・解離が遅い薬剤では洞調律[洞結節で発生した興奮が刺激伝導系を介して心臓全体に正しく伝わっている状態]でも興奮伝播は抑制されるのでQRS幅は拡大する。一方、結合・解離が速い薬剤では洞調律下のQRS幅は正常のままである。
Key Point
1)Na⁺チャネルとの結合・解離が遅い薬剤では洞調律でもQRS幅が広がる。
□不活性化チャネルブロッカーは心房には作用しにくい。しかし、リドカインやメキシレチンよりも結合・解離が遅いアプリジン(中間型)は、心房細動の治療薬として使える。不整脈薬の特徴である遮断作用の強さと、結合・解離の速さの組み合わせにより、それぞれの薬剤の作用は微妙に異なる。
16 ここから始まったⅠ群薬の古典派:Ⅰa群薬
□Ⅰa群薬はAPD(活動電位持続時間)を延長するものだが、これは主にⅠa群薬がK⁺チャネルを少し遮断することによる。
□K⁺チャネルには、膜電位への依存性、開口を促す物質の差異、あるいは不活性化の時間経過などに基づいて、いろいろなタイプがある。それぞれの薬剤が作用するK⁺チャネルは多彩だが、ターゲットになるのはIkr電流(遅延整流K⁺電流のうち速い成分)である。
□抗不整脈薬といえば、かつてはⅠa群しかなかった。まずは、キニジンとプロカインアミドが世に出て、1980年あたりからジソピラミド、シベンゾリン、ピルメノールなどが登場した。(現在、キニジンと経口のプロカインアミドの使命は終わった。キニジンは“キニジン失神”と呼ばれる副作用がある。一方、静注のプロカインアミド[アミサリン]は使いやすく、今後も使われ続ける)
□実際の使用頻度も考慮しながら薬剤を列挙すると次のようになる。
●使える経口薬:ジソピラミド、シベンゾリン、ピルメノール
●使える静注薬:プロカインアミド、ジソピラミド、シベンゾリン
Ⅰa群薬の個性と使い分け
□ジソピラミド(リスモダン)
●代表的なⅠ群薬。本当に使える抗不整脈薬としては最初のもの。300㎎/日の常用量を超えて使うことは勧めない。
●陰性変力作用[心筋の収縮力を下げる作用]と催不整脈作用[薬による不整脈の増悪や新たな不整脈の発生]はちゃんとある。薬理面ではそれなりにハードな薬剤だが、使用経験が長いのでまだ使われている。
●抗コリン作用は強い。尿閉も生じる。
□シベンゾリン(シベノール)
●不整脈専門医は比較的好んで使う。ジソピラミドとどこが違うのか決定的な差はピンとこない。
●陰性変力作用と催不整脈作用もジソピラミドと似ている。
●抗コリン作用はやや弱い。抗コリン作用のメカニズムは、ジソピラミドはムスカリン受容体を刺激するが、シベンゾリンはIKAchを抑制する。
□ピルメノール(ピメノール)
●かなり優れた薬剤だが、使用されることが少ない。今も昔も抗不整脈薬は製薬会社にとっては、あまり儲かるものではない。
□ジソピラミド、シベンゾリン、ピルメノールにはいずれも抗コリン作用がある。ただし、抗コリン作用を発揮するメカニズムは同じではないし、その強さも異なる。
17 Ⅰ群薬のマイルドタイプ:Ⅰb群薬
□Ⅰb群薬はリドカイン(キシロカイン)、メキシレチン(メキシチール)のほかにアプリンジン(アスペノン)も含まれる。いずれも不活性化チャネルブロッカー(おもに不活性化チャネルをブロックするが、活性化状態のチャネルにもいくらか結合する)であるが、結合・解離の時定数が長いアプリンジンだけは例外的に心房筋への効果を有する。
Key Point
1)Ⅰb群薬でもアプリンジンのみは心房の不整脈に有効。
□アプリンジンは使いやすく有用な不整脈薬である。
□Ⅰb群薬はNa⁺チャネル遮断作用に加えて、APDを短縮するという性格をもつ。
□Ⅰb群薬は催不整脈作用によるtorsades de pointes[トルサード・ド・ポアント:心室性頻拍の一種。心臓のポンプ機能を著しく低下させ、アダムスストークス発作や心室粗細動へ移行し突然死を招くことがある予後不良の不整脈である]は起きにくい。
□リドカインとメキシレチンは、有効性や副作用の面で違いを明確にすることは困難で使い分けのが難しい。
18 ホントは使いやすい:Ⅰc群薬
□Ⅰc群薬としてフレカイニド、プロパフェノン、ピルジカイニドはNa⁺チャネルとの結合・解離は緩徐であり、作用も強い。
□すべて活性化チャネルブロッカーであり、心房と心室のいずれの不整脈にも有効。
□Ⅰc群薬はAPDの変化はほとんどない。
□フレカイニドはK⁺チャネルへの影響を有するが、ピルジカイニドは純粋なNa⁺チャネルの遮断薬である。プロパフェノンはβ遮断作用をもつことが特徴。
Ⅰc群薬の個性と使い分け
□ピルジカイニド(サンリズム)
●純粋なNa⁺チャネル遮断薬。シンプルさが売り物。使いやすい。
●普通の量であれば安心して使える薬、ただし、腎不全、心不全でないという条件つき。
●半減期が4時間程度と短いので、1日3回では手薄になる時間帯が出てくる。
●陰性変力作用はあるが比較的マイルドと考えられている。
●ほぼ100%腎排泄なので、腎機能低下があれば使わない。
●循環器を専門としない医師にとって第1選択にしやすい薬だが、血中濃度が高くなれば心室粗動が生じることがあるので、常用量で使う。
□プロパフェノン(プロノン)
●β遮断作用をもつ。わざわざβ遮断薬を併用するほどではないが、ちょっと房室伝導を抑えたいときなどに意識して選択できる。β遮断作用はあまり強くない。
●欧米ではかなり普及しており、論文も多い。
□フレカイニド(タンボコール)
●有効性が高い。心房細動に使われる。
●半減期が11時間と長い。
19 脇役なのに出番は多い:Ⅱ群薬(β遮断薬[β受容体のみを遮断する薬])
□β遮断薬は第Ⅱ群に属し、対象となるのは交感神経活動が関与する不整脈。
□β遮断薬は不整脈治療において主役ではないがよく頻繁に使われる影の実力者。使用例は次の通り。
●カテコラミンや交感神経依存型の不整脈、例えば運動誘発型VT(心室頻拍)や先天性QT延長症候群のtorsades de pointes抑制を目的とした本格的な使い方。
●器質的な背景が明らかでない洞頻脈[心臓の脈が速い状態]の症状緩和のために使用。
●神経調節性失神で洞停止[洞結節が一時的に活動を停止する現象、数分間にわたるような停止になるとめまいや失神をきたすことがある]を予防。

画像出展:「日本心臓財団」
『神経調節性失神は、排尿、咳嗽、嚥下、食後などの特定の状況で発症する状況失神、恐怖、疼痛、驚愕など情動ストレスにより惹起される情動失神、および血管迷走神経反射による失神を総称する概念とされています(図)。』
●房室伝導を抑制して心房細動や心房粗動の心室レートをコントロールする。
□陳旧性心筋梗塞のVT(心室頻拍)や心不全がらみの心室細動の予防にもβ遮断薬は有効である。これは心不全の緩和を介した不整脈の治療になる。
□β遮断薬は心筋細胞のカルシウムハンドリングを改善し、心不全の進行を抑える。これは遅延後脱分極に伴う心室不整脈を抑制することになり、重篤な不整脈を生じにくくする。β遮断薬は生命に関わる不整脈を治療できる。
Ⅱ群薬の個性と使い分け
□使用目的によって投与回数の異なるものを使う。
●頓用あるいは継続治療でも、導入時にはプロプラノロール(インデラル)が使いやすい。早く効いて、早く消える。
●1日2回投与の抗不整脈薬と併用する場合や、覚醒時にきちんと効果を維持したいなら、セロケンのような1日2回投与のものが使いやすい。
●高血圧治療も兼ねてなら、ビソプロロール(メインテート)やアテノロール(テノーミン)が使われる。
□メインテートは脂溶性でじんわり身体にしみこんでくる。血中濃度が低いときでも、それなりの薬効が維持できる。
□器質的背景がないなら、どのβ遮断薬でもよいが、陳旧性心筋梗塞や心不全があれば、メインテートかアーチストを使った方がよい。
20 なんといっても最後はコレ:Ⅲ群薬
□Ⅲ群はK⁺チャネルの抑制によるAPD延長が主な作用である。
個性派ぞろいのⅢ群薬の使い分け
□国内
●経口と静注のアミオダロン(アンカロン)
●経口のソタロール(ソタコール)
●静注の塩酸ニフェカラント(シンビット)
□国産のニフェカラントは重症心室不整脈のコントロールに活躍してきた。
□アミオダロンは抗不整脈薬のなかでも、かなり特異な薬剤
●APD延長に働くK⁺チャネルの遮断作用のみならず、Na⁺チャネル、Ca²⁺チャネル、β受容体の遮断作用も備えている。
●アミオダロンはdirty drugと呼ばれている。
●Ⅰ群抗不整脈薬が無効の重篤な心室不整脈に対しても明らかに効果を発揮するし、予後改善効果も確立されている。
●ソタロールは「K⁺チャネル遮断作用+β遮断作用」をもつ。
●Ⅲ群薬は不整脈診療に経験のある医師によって用いられる。
21 兄弟じゃないのに:Ⅳ群薬
□カルシウム拮抗薬のうち心筋の伝導を抑制するベラパミル(ワソラン)とジルチアゼム(ヘルベッサー)などがⅣ群に属する。また、少し特徴の違うタイプとしてべプリジル(ベプリコール)がある。
□べプリジルは抗不整脈薬という性格を前面に押し出しており、Na⁺チャネル遮断作用やK⁺電流への影響もあることから、Ⅰ群薬かⅢ群薬と呼んでもおかしくない。
□Ca²⁺チャネルを経由したカルシウムの細胞内への流入は、心筋の収縮機転のひきがねとなる。また、心臓の構成要素のうち比較的遅い伝導を示す部位(例えば房室接合部の一部)において、Na⁺チャネルに代わって伝導の主体を担う。この性質のため、房室接合部やそれに似た伝導特性をもつ心筋が不整脈の発生と維持に含まれているとき、抗不整脈効果をもたない。
□同じカルシウム拮抗作用をもつ薬剤でも、ジヒドロピリジン系(ニフェジピンなど)は抗不整脈効果をもたない。この違いは、それぞれのカルシウム拮抗薬が作用するチャネル部位、それに応じた臓器(血管か心筋か)選択性とともに、使用依存性の程度による。
Ⅳ群の使い分け
●ベラパミルとジルチアゼムは房室伝導の抑制が主体
●べプリジルはⅠ群薬と似た使い方をする。
22 何も起きないわけがない:副作用
□抗不整脈薬に特徴的な副作用は大きく2つに大別される。
●心機能に対する副作用
●催不整脈作用[薬による不整脈の増悪や新たな不整脈の発生]
□抗不整脈薬の多くは陰性変力作用[心筋の収縮力を下げる作用]をもつため、心不全を誘発もしくは増悪させる可能性がある。Na⁺チャネルとCa²⁺チャネルを介するイオンの流入が心収縮の重要な機転であることから、心収縮力の低下傾向は回避し難い副作用である。
Key Point
1)同じ薬に属していても、陰性変力作用の強さは異なる。
□副作用は薬剤独自のチャネル選択性や、β遮断作用の有無によるところが大きいが、臨床用量の設定も影響している。
□催不整脈作用とは、新たな不整脈薬の出現を招いたり、既存の不整脈の頻度や重症度を増悪させたりすることに加え、刺激伝導系の抑制による徐拍化も含まれる。
□torsades de pointesのような多形性心室頻拍は致死的となり、Ⅰa群薬とⅢ群薬とⅣ群のべプリジルが原因薬物となる。K⁺チャネル遮断による再分極遅延は後脱分極と呼ばれるあらたな脱分極を招き、これが不整脈源となって、torsades de pointesを出現させる。
□ジソピラミドやシベンゾリンは低血糖という独特な副作用を有する。
Key Point:
1)ジソピラミド、シベンゾリンの低血糖!
□低血糖はK⁺チャネル(ATP感受性K⁺チャネル)の遮断が膵臓のインスリン分泌を促進することによって生じる。
□Ⅰa群薬は中枢神経系への作用(ふらつきや複視)を生じることがあるが、患者自身は気がづかず、ちょっと変だなという程度なことが多い。
□抗コリン作用をもつジソピラミドでは、口渇や男性の排尿障害がたまにみられる。これははじめから予想して投薬する。
23 torsades de pointes が起きたら
※トルサード・ド・ポアント:心室性頻拍の一種。心臓のポンプ機能を著しく低下させ、アダムスストークス発作や心室粗細動へ移行し突然死を招くことがある予後不良の不整脈である。
□APD持続作用を有するⅠa群薬やⅢ群薬を投与中の患者に、著明なQT[心室の興奮の始まりから消退するまでの時間]延長とtorsades de pointesが出現することがある。
□Ⅰa群薬とⅢ群薬による催不整脈作用は用量依存性ではあるが、過量であることは必須条件ではない。むしろ、torsades de pointesに対し特にリスクの高い患者が存在する。以下がそのリスク要因。
●高齢
●女性
●徐拍
●器質的心疾患や電解質異常
●腎機能や肝機能の低下など、血中濃度[血液中に含まれる薬の量]が上昇しやすい状況
Key Point
1)高齢女性ではQT延長作用のある薬剤の投与は避ける。
□抗不整脈薬でQT延長とtorsades de pointesが認められた場合
●薬剤の中止……QT延長作用のあるすべての薬剤
●電解質異常など増悪因子の改善
●徐脈が背景にあれば、一時的ペーシング[小さな電気パルスを発出して心収縮を生みだすこと]
●リドカイン(50~100㎎)
●マグネゾール(2gを2分で投与)
□『なお、薬剤の血中濃度を測っても解釈が難しい。個人的には利用していない。催不整脈作用は血中濃度により避けられるものではない。きわどい症例に抗不整脈薬を投与しないとか、常用量を超えて使わないなど、危険に近づかないという姿勢を勧める。』
24 治療薬を選ぶ発想
□『抗不整脈薬の薬理作用を懸命に勉強しても、どの抗不整脈薬がベストな選択なのか判断は難しい。抗不整脈薬の薬理作用が明らかとなっていても、心房細動や心室頻拍では「どうして薬が不整脈を止めるのかというメカニズム」はどうも見えてこない。』
□『これまで蓄積された情報を十分マスターしたとしても、未知の要因がたくさん残されている。不整脈の専門家でも「確信はないがとりあえず使ってみる」というパターンが多い。』
□『陰性変力作用や催不整脈作用、あるいは薬物代謝の面で使いにくい薬剤を避けるという「消去法の発想」のほうが正直な道だと思う。』
Key Point
1)病態と薬理を深く理解して確実な成功率……これは虚構。
2)使いにくい薬剤を除外して無理のない選択……手が届く。
□心機能と腎機能が低下している高齢者で考慮するのは、
●陰性変力作用が少なく、腎排泄でないという条件に加え、潜在的な徐脈性不整脈や催不整脈作用に注意。
□若年で心機能も肝・腎機能も問題がないのなら、選択の幅は広くなる。最小限必要な知識は、
●陰性変力作用の有無……Ⅰb群のアプリンジンとⅠc群のピルジカイニドは陰性変力作用が少ない。
●代謝経路……ピルジカイニドが腎排泄。
●催不整脈作用の多寡……Ⅰb群のアプリンジンとⅠc群薬にはQT延長に伴う催不整脈作用はない。
●注意すべき副作用……ジソピラミドとシベンゾリンの低血糖、アプリンジンの肝障害。
不整脈と薬1
先日、ICD(植込み型除細動器)を装着されている患者さまが来院されました。主訴は左肩の強い肩こりです。心疾患がある場合、左の肩や腕(特に内側、小指側)に関連痛が出る場合もあります。最新のICDは100gもないようですが、ICDの重さが肩周辺のファシア(筋膜)を下方に引っぱり、緊張を高めているということも十分に考えられると思います。いずれにしても右肩に比べ左肩に重い症状が出ることは不思議ではありません。
また、患者さまは”心室頻拍”という不整脈のため、アミオダロンという強い不整脈の薬を服用されています。以前、“期外収縮”や“心房細動”については勉強したことがあったのですが[ブログ:“不整脈(心房細動)”]、心房細動に関しては、血栓塞栓症に注意する必要はあるものの、この2つの不整脈は一般的には深刻な不整脈ではないとされています。
一方、“心室頻拍”は特に注意しなければならない不整脈の一つです。そして、アミオダロンなど不整脈の薬についての知識は、ほぼゼロに等しい状態でした。そこで、今回あらためて不整脈とその薬について勉強することにしました。
購入した本は、村川裕二先生の『不整脈治療薬ファイル 抗不整脈治療のセンスを身につける』という本です。実は、この本は第2版が既に出版されているのですが、節約のため初版(2010年)を買いました。ということで、2020年に発行された最新の第2版ではないのでご注意ください。
なお、内容はとても高度で詳細なものでしたが、村川先生の独特な言い回しのおかげで、敷居が低くなり、何となく親しみを感じられたのは良かったと思います。
ブログは目次の黒字部分ですが、「Part2 基礎」、「Part3 抗不整脈薬のアウトライン」が中心です。勉強モードのため大変細かく長くなったため4つに分けました。なお、4つめのブログには『病気がみえる Vol.2 循環器』の内容を元に作った不整脈の一覧表を載せました。
不整脈は脈拍の乱れ、それはポンプである心臓の拍動の乱れです。そこで、最初に心臓の拍動、収縮のメカニズムを調べました。
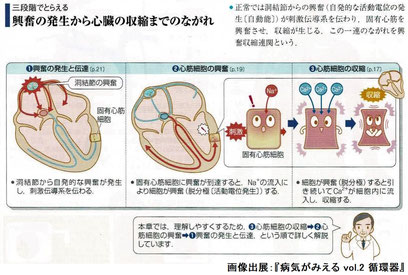
画像出展:『病気がみえる vol.2 循環器』
心臓の収縮は洞結節と呼ばれる特殊心筋細胞が、自発的に興奮(脱分極)し収縮することがスタートです。その興奮は固有心筋細胞を通じて心臓全体に伝わるのですが、その過程でNa⁺(ナトリウムイオン)とCa²⁺(カルシウムイオン)が深く関わります。また、興奮が鎮まるとき(再分極)には、K⁺(カリウムイオン)が関与します。
不整脈の薬は心臓の拍動を整えることになるので、構造と収縮のメカニズムから考えると、洞結節、房室結節の働きと、Na⁺、Ca²⁺、K⁺に注目することが重要だと思います。
Part1 総論
1 最初から「まとめ」
2 プラスアルファの知識とは何か?
Part2 基礎
3 心筋の活動電位を復習する
4 ちょっとイオンチャネルをかじる
5 いろいろあるK⁺チャネル
6 洞結節は自分で動く
7 房室結節は箱根の関所
8 房室結節を抑える薬
9 triggered activityとEADとDAD
10 リエントリー:興奮がまわるということ
Part3 抗不整脈薬のアウトライン
11 抗不整脈とはつまり何か?
12 抗不整脈の分類:Vaughan-Williams分類はまだ生きている
13 たくさんあるⅠ群薬:どこが
14 チャネルに統合するタイミング:活性化チャネルブロッカーと不活性チャネルブロッカー
15 さっぱり系としつこい系、粘り強さが違う:Na⁺チャネルとの結合・解離
16 ここから始まったⅠ群薬の古典派:Ⅰa群薬
17 Ⅰ群薬のマイルドタイプ:Ⅰb群薬
18 ホントは使いやすい:Ⅰc群薬
19 脇役なのに出番は多い:Ⅱ群薬(β遮断薬)
20 なんといっても最後はコレ:Ⅲ群薬
21 兄弟じゃないのに:Ⅳ群薬
22 何も起きないわけがない:副作用
23 torsades de pointes が起きたら
24 治療薬を選ぶ発想
Part4 心房期外収縮
25 変行伝導は大事か?
26 治療するかどうか、誰が決めるか
27 使いたい抗不整脈薬と、使ってもいい抗不整脈薬
28 Case1:訴えの多い中年女性
29 Case2:ちょっとした僧帽弁閉鎖不全がある
30 Case3:blocked PAC
31 いろいろなP派:多源性心房期外収縮
32 Case4:顕性WPW症候群でshort runを繰り返す
Part5 心室期外収縮
33 PVCが“治療対象でない”とはどういう意味か?
34 頻発するPVCは心不全を招くか?
35 子供のPVCはなぜ怖いか?
36 CAST studyは爆弾
37 Lownの分類を使うか?
38 どの抗不整脈薬を使うか?
39 Case:流出路起源のPVC
40 連発の多いPVC
41 急性心筋梗塞のリドカイン
Part6 発作性上室頻拍
42 頻拍の呼び方
43 PSVTは2種類と割り切る
44 AVNRTの速伝導路と遅伝導路
45 AVNRTはどう回るのか?
46 long RP’ tachycardiaがわかると何が得か?
47 WPW症候群とAVRT
48 WPW症候群につきものの頻拍
49 WPW症候群-偽性心室頻拍なのにカテーテルアブレーションを拒否されたら
50 すぐ止めたいとき
51 ATP製剤で止める
52 WPW症候群のPSVTをアミサリンで止める
53 WPW症候群のPSVTをリスモダンPやIc群で止める
54 顕性WPW症候群の慢性期
55 顕性WPW症候群以外はワンパターンですむ
Part7 心房粗動
56 通常型と非通常型
57 抗不整脈薬で心房細動を治療できるか?
58 ダメモトで抗不整脈薬による洞調律化を狙いたいとき
Part8 心房細動
59 忘れられていた肺静脈
60 AFはAFを招く(AF begets AF)
61 基礎疾患のある発作性心房細動(PAF)
62 急性心筋梗塞と心房細動
63 AFFIRM study:洞調律化群 vs. レートコントロール群
64 心不全の心房細動
65 なぜ抗凝固療法?
66 CHADS2スコアは使いやすい
67 どの薬剤を使うか?―具体的に
68 静注抗不整脈薬によるAFの停止は意味があるか?
69 レートコントロールは十分か?
70 レニン-アンジオテンシン系抑制薬の役割
71 Case1:持続の短いPAF
72 Case2:はじめての発作
73 Case3:半日近く続いている動悸
74 Case4:1日ほど続いているAFを静注抗不整脈薬で止めたいとき
75 顕性WPW症候群(偽性心室頻拍)の心房細動
76 Case5:経口サンリズムによる停止
77 Case6:弁膜症がある
78 Case7:夜間に好発する
79 Case8:心房粗動も認めるとき
80 Case9:倒れる心房細動
81 Case10:肥大型心筋症に血栓塞栓症を生じた
82 Case11:レートコントロールが難しい
Part9 wide QRS tachycardia
83 外見からは4種類
84 まず特発性VTを考える
85 ベラパミル感受性VTに出会ったとき
86 流出路起源VT(左脚ブロック右軸偏位型VT)
87 たいした根拠はないが、なんとなくVTのような気がするとき
88 「もしかしたら上室性頻拍かもしれない」と思ったとき
89 急性心筋梗塞や拡張型心筋症:ニフェカラントを使う
90 静注アミオダロンを使う
91 器質的心疾患を背景にしたVT
92 経口アミオダロンを陳旧性心筋梗塞や不整脈原性右室心筋症のVT/VFに使う
93 拡張型心筋症を基礎にもつVT
Part10 心室細動
94 総論
95 electrical stormとは?
96 electrical stormへの対策
97 特発性VF
98 心不全の不整脈とレニン-アンジオテンシン系抑制薬
Part11 洞不全症候群
99 徐脈と頻脈のウラに薬あり
100 薬物治療
101 経口薬での対処
Part1 総論
1 最初から「まとめ」
□以下のことを全部しっているのなら、この領域の概要はマスターしている。
1)まず、Vaughan-Williamsの分類を知っている。
2)Sicilian Gambitの分類という表があり、使われている用語がわかる。しかし、情報が多すぎて専門家も暗記はしていない。
3)CAST studyというメガトライアル……器質的心疾患のある心室不整脈をⅠ群薬で抑制しても予後は改善しない、あるいは予後を悪化させかねない。
4)健常心ではⅠc群薬でもリスクは少ないので、上室性の頻脈に有効なら使っても差し支えない。
5)催不整脈作用としてのQT延長症候群……Ⅰc群薬とⅠb群薬にはQT延長はまずない。
6)最もパワフルな抗不整脈薬はアミオダロン……副作用の点で使い方が面倒だが、重篤な心室不整脈にはほぼこれしか選択肢はない。使うべきときには積極的に使う。ハイリスクなら植込み型除細動器(ICD)が併用される。
7)房室結節や副伝導路、あるいはPurkinje線維を回路に含む頻拍では薬物治療の効果は確実。それ以外は、どういう運命が待っているか予想しがたい。どうして抗不整脈薬が効果をもつのかわかっていない頻拍もある。
8)薬物治療でしのぐよりも、カテーテルアブレーションで治療したほうがスッキリする頻拍は多い。発作性上室頻拍(PSVT)や心房粗動は根治率が高い。根治率では劣るが心房細動にもカテーテルアブレーションが行われている。考慮すべき治療選択肢。
□不整脈の薬物治療とは、ひとことで言えば……
Key Point
1)それなりのクスリはあるが、魔法のクスリはない。
2 プラスアルファの知識とは何か?
□知っておくべきこと
1)心臓の電気生理
2)不整脈が生じるメカニズム
3)薬物の作用機序
Key Point
1)不整脈の頻度、予後、関連すること⇒不整脈をとりまく情報。
2)各不整脈がどのくらい治療に反応するのか⇒勝ち目があるのかを知りたい。
□心房細動を静注抗不整脈薬で止めようとしてもなかなかうまくいかない。
□発作性上室頻拍ならベラパミルかATP製剤(アデホス)でほぼ100%停止できる。
□不整脈についての知識と経験が増すほど、意識的に治療しないという道を選ぶ。
□頑張りすぎると募穴を掘る。
□「慎重さと果敢さのバランス」も大事。
Part2 基礎
3 心筋の活動電位を復習する
□活動電位(action potential:AP)とは細胞の外側を基準にして、内側の電位を図示したもの。不整脈の発生や抗不整脈薬の作用を述べるとき、以下の3つの用語なしでは、薬剤が作用するメカニズムの話が始まらない。
●脱分極
●再分極
●不応期
□心筋細胞に限らず、興奮していない細胞の内側は細胞の外側よりも電位が低い。
□興奮していない細胞では、細胞膜を挟んで大きな電位差があるので“分極”している。分極とは、細胞内外にくっきりした電位の差ができていること。
□細胞が興奮するとは、Na⁺やCa²⁺というプラスに荷電したイオン[電子の過剰あるいは欠損により電荷を帯びた原子または原子団]が細胞内に流入すること。細胞内のマイナス成分が打ち消されるので、分極状態が解消される。
□”脱分極”した後しばらくは、電気的な刺激を受けても一呼吸入れないと興奮できない。その一呼吸にかかる時間の長さが“不応期”。
□活動電位の横幅は活動電位持続時間(action potential duration:APD)。この長さは、おおよそ不応期を決め、さらにQT時間[心室の興奮の始まりから消退するまでの時間]に反映される。
Key Point
1)心筋細胞が興奮性を失っている時間⇒不応期⇒APD[活動電位接続時間]やQT時間と関係あり。
□なぜ活動電位の形や薬剤の影響を知りたいかというと
●不整脈のメカニズムについてイメージをもつ⇒病態生理がわかった気分になる。
●活動電位が薬剤によってどう変わるかを知る⇒薬物治療にロジックがあるような気がする。
□厳密には、細胞が脱分極するにはNa⁺チャネルが不活性化状態から抜け出している必要がある。APDが同じでも、Na⁺チャネル遮断薬が投与されていると被刺激性をとり戻すのがワンテンポ遅くなり、不応期は少し長くなる。
□「QT[心室の興奮の始まりから消退するまでの時間]延長をきたす薬剤でなくても不応期は延びる」という知識は、実感としては分かりにくい。活動電位の終末より後ろの不応期はpost-repolarization refractorinessと呼ばれる。いつも存在するわけではない。

画像出展:『不整脈治療ファイル』
post-repolarization refractorinessは、相対不応期と呼ばれるものだと思います。
”看護roo!”というサイトに解説が出ていました。興奮の発生と伝導|生体機能の統御(1):『不応期には、絶対不応期と相対不応期の2つの相がある。どんなに強い刺激にも応じない時期を絶対不応期とよぶ。再分極の進行中に強い刺激を加えると、活動電位を発生する時期がある。この時期を相対不応期とよぶ。』

画像出展:『人体の正常構造と機能』
PQ時間:P波の始まりからQ波まで。すなわち心房筋の興奮の始まりから心室筋の興奮の始まりまでの時間で、房室伝導時間を表す。正常値は0.12~0.20秒。心拍数が少ない場合、PQ間隔は長くなる。
QRS時間:QRS波の始まりから終わりまで。心室筋の興奮している時間を表す。正常では0.08~0.1秒。
QT時間:心室筋の興奮の始まりのQ波から回復過程のT波の終りまで。心室筋の脱分極から再分極までを表す。
注)”時間”ではなく”間隔”と表記されることもあります。
4 ちょっとイオンチャネルをかじる
□心筋細胞の活動電位はイオンチャネルによってコントロールされている。イオンチャネルとは心筋細胞膜においてイオンが出入りする経路
□イオンチャネル以外の経路でもイオンは移動する
●チャネル:電気化学ポテンシャルの面でそっち方向に自然と流れる孔ができる。川の流れにのってイオンを動かし、エネルギーは使わない。“受動的”な移動と表現される。
●ポンプ:Na-Kポンプが代表的。ATPなどを使ってイオンを移動させる。川の流れに逆らった“能動的”なイオンの移動。
●交換輸送系:Na-K交換輸送系はNa⁺とK⁺を一定の比率で交換するシステム。電荷として差し引き換算でゼロになるわけではない。
□脱分極と再分極の主役はイオンチャネル。イオンチャネルで動いたイオンを元に戻すとか、行き過ぎを調整するというたぐいの仕事をポンプや交換輸送系が担当する。これでバランスがとれている。
□不整脈の治療には、とりあえず、
●イオンチャネル
●それ以外
と単純に考えてよい。
□『「電気生理学について深い知識なしに不整脈の治療はできない」というのはおこがましい。しかし、「イオンチャネルについてささやかな知識がなくては、不明脈の治療はできない」というのは正しい。』
Key Point
1)Na⁺電流……伝導性
2)K⁺電流……不応期やQT時間
5 いろいろあるK⁺チャネル
□K⁺チャネルはおよそ10種類のサブタイプがある。なぜ、“およそ”でしか数えられないかというと、定義の仕方で数が変わってくるから。
□K⁺電流は細胞膜内外の電位差があるところに達すると活性化(チャネルの活動がactiveモードになる)するものと、特定の物質の濃度が上昇(例えばアセチルコリン)あるいは低下(例えばATP)することによって活性化するものがある。
Key Point
1)K⁺チャネルにはいろいろな種類がある。その活性化のモード(活躍するタイミングやひきがねの種類)はいろいろ。
2)K⁺チャネルは生理的にはすべて外向き(細胞の中から外へ)にK⁺イオンを流し、再分極に貢献。
□おもなK⁺電流のうち、話に出てくる頻度が高いのは以下の4つ。
●一過性外向きK⁺電流(Ito:transient outward current)
●遅延整流K⁺電流のうち遅い成分(Iks)
●遅延整流K⁺電流のうち速い成分(Ikr)
●内向き整流K⁺電流(Ikl:内向きと言っても、生きている人間の体の中ではこれも外向きに流れる)
□これらの分類と名称は古臭くなっているが、臨床の場ではまだ使われている。
K⁺チャネルとQT時間
□心筋障害に伴いK⁺チャネルの数や性質は変化する。また、器質的心疾患に伴ってQT時間は変化する。
Key Point
1)K⁺チャネルの機能低下や薬剤による抑制⇒QT延長
□抗不整脈薬のうち、Ⅲ群作用とはAPD(活動電位持続時間)の延長であり、K⁺チャネルの抑制による。他の機序でQTを延長させる薬剤もあるが、国内では使われていない。[2014年時点]
□薬剤ごとに作用するK⁺チャネルは異なる。
□実際にはIkrの遮断がⅢ群作用の主体であり、それ以外のK⁺チャネルを意識する機会はまずない。
Key Point
1)抗不整脈薬のQT延長はIkr遮断作用と割り切る。
□Iksは交感神経刺激により活性が増す。これには、外向きのK⁺電流増加⇒再分極の促進⇒APD短縮⇒QT時間短縮という流れが予想される。ところが、交感神経刺激はCa²⁺電流も増して、こちらは再分極とは拮抗する。つまり、交感神経活動1つとっても、いろいろな経路を介してAPDを延ばしたり、短縮したりするので、その加算したものがどっちに向かうかは簡単には知りえない。
6 洞結節は自分で動く
□slow response型と呼ばれるのは洞結節や房室結節の細胞であり、周期的に興奮する。これは自動能という機能である。
□自動能はいろいろなメカニズムによって複合的に維持されているが、そのメカニズムは諸説ある。
Key Point:洞房結節の自動能
1)ある種のCa²⁺電流が関与している。
2)自律神経活動の影響を受けやすい
□洞結節のどの部分がペースメーカーとしてのリーダーシップをとるかは、主に自律神経活動レベルによって異なってくる。洞調律[洞結節で発生した興奮が刺激伝導系を介して心臓全体に正しく伝わっている状態]といっても、P波の形は一定ではない。
□小児によく見られる所見だが、ペースメーカーが洞結節とその近傍(右房)を移動していくことがあり、wandering pacemakerと呼ばれる。いろいろな形のP波が現れる。病気ではなく生理的な現象。
□洞結節は自律神経に大きく影響される。心拍数が100/分より少なければ主に副交感神経(迷走神経)でコントロールされる。それより多くなると交感神経やカテコラミンの役割が大きくなり、副交感神経の関与は小さくなる。
7 房室結節は箱根の関所
□房室結節もCa²⁺電流依存型のslow response型細胞によって作られている。
□房室結節の特徴
●伝導速度は遅い……Ca²⁺電流に依存した伝導
●上から来る興奮の頻度が高いと伝導性が低下する……減衰伝導特性
●自律神経による影響を受けやすい
□房室結節は伝導性が低い組織である。この伝導性の低さに味がある。心房と心室の収縮に時間差があるのは効率よく血液を輸送するために役立つ。踊りでもスポーツでも、ちょっとした間のおき方が大きな意味をもつ。
□例えば心房細動になったとき、600/分の心房興奮がそのまま心室に落ちてきては心室細動を生じてしまう。
Key Point:房室結節は心房と心室の連絡をコントロールする部位である。
1)心房と心室の興奮の時間差をつくる。
2)極端に心室レートが高くならないようにする安全弁。
□房室結節は箱根の関所。役に立つフィルターとして機能すれば価値は大きいが、加齢や薬物などで伝導性が落ちれば房室ブロックになる。
□自律神経の線維が豊富にあるため、自律神経活動によって房室結節の伝導性は大きく変動する。痛み刺激で迷走神経が亢進すると房室ブロックが生じることがある。
8 房室結節を抑える薬
□房室結節の伝導をよくするにはβ受容体を刺激すればよい。高度の房室ブロックで危険が迫れば、イソプロテレノールを用いる。
Key Point:房室伝導を抑制する薬剤
1)β遮断薬
2)カルシウム拮抗薬(心筋に親和性のあるベラパミルとジルチアゼム)
3)ジギタリス
4)Na⁺チャネル遮断薬(抗不整脈薬)
5)ATP製剤(アデホス)
□房室結節が自律神経の影響を受けやすく、かつCa²⁺電流に依存した伝導をするので、β遮断薬とカルシウム拮抗薬で房室伝導は抑制される。
□ジギタリスによる房室伝導抑制は、部分的には迷走神経活動の亢進によって説明されているが、それ以外の未知の要素もある。
□Na⁺チャネル遮断作用はⅠ群薬の特徴である。これに加えて他群の抗不整脈薬(べプリジルとアミオダロンなど)も、メインではないがNa⁺チャネル遮断作用をもつ。
□ATPが房室伝導を抑制するのは、代謝産物のアデノシンが抑制性G蛋白を経由してCa²⁺電流を抑えるからである。
□房室伝導に作用する薬剤はきちんと知っておく必要がある。その理由は2つ。
●房室ブロックの出現を避けることができる。
●房室結節を回路に含むリエントリー性頻拍の停止と予防、および上室性の頻拍のレートコントロール治療の裏づけとなる。
Key Point
1)房室伝導に作用する薬剤を記憶しておくことは、メカニズムを理解した不整脈治療と房室ブロックの回避に必要。
□不整脈の治療では房室伝導のコントロールが重要である。房室結節の制御が不整脈治療の入口であるが、結局これに尽きる。房室結節を押さえていれば日常の不整脈診療はできる。
9 triggered activityとEADとDAD
□頻拍の発生と維持のメカニズムとして主なものは3種類ある。
●異常自動能
●triggered activity(トリガードアクティビティ)
●リエントリー(興奮旋回)
□triggered activityは日本語では撃発活動というが、英語のまま使われている。focalなリズムの1つであり、周囲からの刺激によって生じる振動性興奮である。
□活動電位の後半部位あるいは終了直後に新たな活動電位(後脱分極 afterdepolarization:AD)と呼ばれるコブが現れるが、その出現するタイミングによって2つある。
●早期後脱分極(ealry afterdepolarization:EAD)
●遅延後脱分極(delayed afterdepolarization:DAD)
早期後脱分極(EAD)
□EADは家族性QT延長症候群や後天性QT延長症候群にみられる頻拍。つまりtorsades de pointesと呼ばれる多形性心室頻拍の原因となっている。
Key Point
1)QT延長が関与する不整脈は先天性か後天性かを問わず、早期後脱分極(EAD)がひきがねとなる。
遅延後脱分極(DAD)
□DADは細胞内のCa²⁺過負荷が背景となり、筋小胞体からのCa²⁺の振動性放出がその機序となっている。心筋細胞内のCa²⁺の貯蔵と出し入れにたずさわる筋小胞体からCa²⁺が漏れ出ることで脱分極が生じる。
□DADによる不整脈としては、ジギタリス中毒に伴うものが有名。ジギタリスによるNa-Kポンプの阻害が細胞内Naを増加させ、Na-Ca交換機構を細胞内Ca²⁺増加方向に働かせ、Ca²⁺過負荷にしているからである。
□Ca²⁺の負荷が多いことは心筋の収縮力を増すことに必要だが、同時に不整脈のもとになる。Ca²⁺過負荷は心不全においては非特異性に出現する現象。
Key Point
1)ジギタリス中毒や心不全に伴う不整脈の多くはDADをメカニズムとする。
□心不全のときの心室不整脈はCa²⁺過負荷を緩和することが本質的な対処。むやみと抗不整脈薬で攻めても期待できない。
□右室流出路(right ventricular outflow tract:RVOTと略される)起源の心室期外収縮(premature ventricular contraction:PVC)は健常者によく認められるが、そのなかに非持続性心室頻拍(3連以上のPVC)が頻発するケースがある。反復性単形性心室頻拍(repetitive monomorphic ventricular tachycardia)という言葉が使われる。これはtriggered activityによると考えられる。
10 リエントリー:興奮がまわるということ
□発作性上室頻拍や多くの心室頻拍はリエントリーをメカニズムとする。リエントリーとは興奮旋回を意味し、基本的には興奮伝達遅延部位と一方向性ブロックが必要。
□伝達遅延部位の例
●心筋梗塞後の心室頻拍における緩徐伝導路
●WPW症候群のリエントリーにおける房室結節
●房室結節リエントリー性頻拍の遅伝導路
●心房粗動の解剖学的狭窄
□リエントリーが開始して維持されるには、鍵となる経路の伝導速度と不応期に微妙なバランスが必要である。
□例えば、AVNRT(房室結束リエントリー頻拍:房室結節二重伝導路が原因)やAVRT(房室回帰頻拍:房室間の副伝導路が原因)がある年齢になってから出現し、発作頻度や持続が変わるということは、房室結節と副伝導路の加齢による変化が関与している可能性がある。引き金となる期外収縮が年齢に応じて増えるということも関係していると思う。
ポリヴェーガル理論3
第2章 ポリヴェーガル理論とトラウマの治療
聞き手:ルース・ブチンスキー(認定心理学者、臨床応用行動医学全国組織[NICABM])の会長
●トラウマと神経系
・トラウマがストレスと関連した障害と捉えるのは適切でない。特に、通常のストレス反応と同様に、交感神経系とHPA軸(視床下部-脳下垂体-副腎)の反応とされていることが一番の問題である。
・ポリヴェーガル理論では、「危険」や「生命の危機」に瀕した時には、ストレス反応とは違った二つ目の防衛システムが発動すると考える。そこでは、自律神経系の反応は大きく抑制され、副交感神経系の古い神経経路が使われる。それは、「不動」、「シャットダウン」そして「解離」である。
・「不動化」の反応は小さな哺乳類によく見られる。例えば、ネコに捕まったネズミである。「擬死」とか、「死んだふり」と言われているが、これは意図的に行う反応ではなく、闘争/逃走反応が使えない時に起こる。人間が恐怖体験により失神するときもこれと同じものである。
・科学的な論文でも、不動化をもたらす防衛システムは、ストレス理論では説明されていない。ストレス理論はアドレナリンの分泌や交感神経の活性化によって、可動性を伴う防衛反応が起きるとされている。
・我々の神経系は、意識されることなく、常に環境中の危険因子の評価を行い判断している。そして常に優先順位に従って、その場にもっとも適応的な行動を取る。
・トラウマ治療で最も大切なことは、「どのようなトラウマ的な出来事が起きたのか」ではなく、その人がその状況で「どのような反応をしたのか」を理解することである。
●「ポリヴェーガル理論」と「迷走神経パラドクス」
・迷走神経は心臓や内臓を制御しているため、運動機能が注目されているが、多くは感覚神経で80%の線維は内臓から脳へと情報を送っている。残りの20%が運動神経路を形成し、動的に、そして時には劇的に生理学的変化を起こさせる。例えば、迷走神経が緊張した状態では心臓の動きが抑制(心拍数減少)される。そして迷走神経の緊張が緩むと、心臓の拍動は戻る。こうした変化はわずか数秒のうちに起きることもある。
・可動化という機能を持つ交感神経に対して、迷走神経は、落ち着かせたり、成長させたり、回復させたりする機能を持っている。
・『私は、彼の言葉[迷走神経は急に脈が遅くなる「徐脈」や、突然呼吸が止まる「無呼吸」などの、生命を脅かす現象を引き起こすことがある]を真剣に受け止め、私の研究[新生児の迷走神経に関する研究。赤ちゃんの中には、RSA(呼吸性洞性不整脈:呼吸に伴って心拍数が増加したり減少したりする現象)が見られない赤ちゃんがいる]の中で発見されたことに何か手がかりがないか、振り返りました。私の研究では、RSAが起きているときには、徐脈や無呼吸は起きませんでした。これに気がついたとき、私はこの「迷走神経パラドクス」という概念を理解するヒントを得たのです。RSAがあるときは、迷走神経は保護的な働きをし、徐脈や無呼吸を起こすときは、生命を危険にさらすのです。
数カ月にわたり、私はこの新生児医学の手紙を鞄に入れて持ち歩いていました。私はなんとかこのパラドクスを説明しようとしました。しかし私の知識はあまりにも限られていて、どうすることもできませんでした。そこで、このパラドクスを解決するために、迷走神経の神経解剖学をあたってみることにしました。もしかすると、この二律背反のパターンを引き起こす迷走神経の回路は異なっているのではないか、と考えたのです。
この「迷走神経パラドクス」を引き起こしていた迷走神経の作用機序を明確化したことによって、ポリヴェーガル理論が生まれました。この理論を構築するにあたって解剖学、進化学、そして二つの異なる迷走神経の働きを精査しました。一つの迷走神経系は徐脈や無呼吸を引き起こし、別の迷走神経系がRSAを引き起こすのです。一つの神経系は潜在的に死をもたらします。もう一つの神経系は保護的に働きます。
この二つの迷走神経の回路は、脳幹の違った部分から発していました。比較解剖学を研究した結果、古い神経回路ができ、その後に新しい神経回路ができたことがわかりました。系統発生学に基づいた自律神経のヒエラルキーが、私たちに埋め込まれていることが明らかになったのです。この発見が、ポリヴェーガル理論の基礎になりました。
「不動」、「徐脈」、「無呼吸」は哺乳類が誕生するずっと昔の、太占の脊椎動物において発達した防衛機制だったのです。ペットショップに行って、爬虫類を観察してみてください。そうすれば、この防衛機制を理解することができます。爬虫類を見ていると、じっとしてあまり動きません。爬虫類にとっては、この「不動状態」が基本的な防衛システムなのです。しかし、ハムスターや家ネズミなどの小さな哺乳類を見てください。彼らはまったく違った行動様式をとっています。小さな哺乳類はつねに動きまわっています。彼らは活動的で、社会的に交流をし、仲間とあそびます。そして動いていないときは自分たちの兄弟と身体をくっつけあっています。
ポリヴェーガル理論の構成概念は進化に基礎を置いています。系統発生学的に段階を追って、それぞれ異なる神経回路が発達し、それぞれ異なる適応行動を起こしていたのです。研究を進めるにつれ、脊椎を持つようになった生き物のうちでも、進化上より早期の脊椎動物において発達した「太占の防衛機制」が、我々の神経系にまだ埋め込まれていることを発見しました。この「太占の防衛機制」とは、「不動状態」です。闘争/逃走反応という防衛機制では、「可動化」が主要な要素です。しかし、太占の脊椎動物の防衛機制は、それとは反対のものです。「不動状態」、「擬死」あるいは「死んだふり」は、爬虫類やその他の脊椎動物にとっては適応的な行動でした。しかし哺乳類は、酸素を大量に必要とするため、こうした反応は潜在的に死に至る危険があります。哺乳類も、生命を脅かすようなことが起きたときには「不動状態」に陥ります。そして「不動状態」に陥った後、普通の状態に戻ることは非常に難しいと考えられます。これが多くのトラウマのサバイバーにも起きていることなのです。』
●ふたたび自律神経系について
・ポリヴェーガル理論では、自律神経系の機能は進化の階層に則って三つに分けられている。
1.有髄化(絶縁性の髄鞘によってニューロンの軸索が覆われること。これにより神経パルスの伝導が高速化される)されていない無髄の迷走神経経路で、横隔膜より下の内臓の迷走神経制御を行っているもの。(一般的には、”自律神経節後線維”[C線維]と呼ばれています)
2.有髄の迷走神経経路で、横隔膜より上の臓器の迷走神経制御を行っているもの。(一般的には、”自律神経節前線維”[B線維]と呼ばれています)
3.交感神経系
・進化の過程で、最初に無髄の迷走神経経路が発達した。人間やその他の哺乳類では、安全な場合には、この古いシステムによって恒常性(ホメオスタシス)が保たれている。しかし、これが防衛に使われたときは、不動状態になり、徐脈や無呼吸をもたらす。そして代謝を落とし、シャットダウンを起こし、見た目には崩れ落ちたようになる。シャットダウンのシステムは爬虫類にとっては適応的である。これは爬虫類の小さな脳はわずかな酸素しか必要とせず、数時間生きていることも可能であるからである。
●ニューロセプション:意識せずに行う知覚
・ニューロセプションは認知のプロセスではなく、神経的なプロセスで環境中にある「合図」や「きっかけ」を評価し、危険を察知する。
・ポリヴェーガル理論では、ニューロセプションはポリヴェーガル理論で定義された自律神経の三つの主要な状態、つまり「安全」「危険」「生命の危機」を察知し、それにふさわしい神経回路にスイッチを入れる。
・社会交流システムがうまく働いていると、防衛反応が抑制され、我々は落ち着き良い気分になる。しかし危険が増すと、二つの防衛システムが優先順位に沿って発動する。いよいよ危険を察知すると、我々の交感神経系が主導権を握る。そして「闘うか/逃げるか」という動きを可能にするために代謝を上げる。そして、それがうまくいかず、安全か確保されないと、無髄の古い迷走神経系を発動させて、シャットダウンする。
●PTSDを起こす引き金
・ニューロセプションの中でも聴覚刺激は大切で、特に「安全であるかどうか」を判断するには、聴覚刺激が非常に重要な役割を果たしている。
第3章 自己調整と社会交流システム
●迷走神経:運動経路と感覚経路の導管
・迷走神経経路は、感覚線維と二つのタイプの運動線維の計三つから成る。運動線維の一つは、有髄化されず横隔膜より下の腸などの臓器と接続されている。もう一つは、有髄化されていて横隔膜より上の心臓などの臓器と接続されている。感覚神経線維は脳幹の中の孤束核と言われる領域に終わり、有髄の迷走神経の運動経路は、主に疑核に起始する。無髄の迷走神経の運動経路は、主に迷走神経背側運動核に起始する。
●いかにして音楽が迷走神経による調整を促す「合図」となるか
・音楽療法:歌うためには長く息を吐く。吐いている間は有髄の迷走神経の遠心経路の心臓への働きかけが強まる。これにより生理学的状態が穏やかになり、社会交流システムが活性化する。歌うとは聴くことでもある。これは中耳筋の神経の緊張を増進させる。また、神経による喉頭咽頭筋を調整し、さらに顔面神経と三叉神経を介して、口と顔の筋肉を使う。個人でなくグループであるなら、他者と関わり社会的な活動になる。以上のことから、歌うこと、特にグループで歌うことは、社会交流システムの素晴らしい「神経エクササイズ」になる。
ご参考:“迷走神経活動の測定法”(実験はマウス) ※クリック頂くと5枚資料のがダウンロードされます。

はじめに
『自律神経系は交感神経系と副交感神経系から構成される神経系で、それぞれ身体の臓器を二重支配することによって相反的に各臓器機能を調節している。自律神経の作用には自律神経反射に代表される循環調節、消化機能調節、そして代謝調節作用が知られており、これらの作用は自律神経遠心路により心臓、血管、消化管、肝臓、膵臓、脂肪組織等の活動を制御することによって営まれている。自律神経の異常は狭心症、胃・十二指腸潰瘍、肥満、糖尿病、メタボリックシンドローム等に深く関与している。自律神経の全身機能調節は各臓器の状態に依存しており、その情報を伝達する経路として自律神経救心路が重要な働きを担っている。救心路神経線維は副交感神経(迷走神経)束の約75~90%、交感神経束の約50%を占めており、末梢性の自律神経反射に関わる情報だけでなく、中枢性の情報(満足感や嗜好形成などの摂食行動調節)にも関わることが最近の研究で明らかにされている。』
ポリヴェーガル理論2
第1章 「安全である」と感じることの神経生物学
●正当な科学的論題としての「感じること」に関する研究
・心理生理学は、心理的な操作に対する生理学的な反応を計測するものである。
・心理生理学では、被験者が報告する主観的な状態に頼ることなく、皮膚電位、呼吸、心拍数、血管運動などの生理学的な反応を調べる。そして、客観的かつ数値化可能な方法で、主観的な体験について計測する。
・心の動きを生理学的な反応から理解しようとする試みは、今でも心理生理学および認知神経学の中心的な方法論であり、過去50年にわたりこの基本的な考え方にはほとんど変化はない。
●心理生理学研究と心拍変動
・精神的に努力している状態では心拍数が減少し、そうでない時の心拍変動には個人差があることを発見した。そして、この研究成果が先駆けとなり、後に心拍変動の個人差と、認知的能力、環境内の刺激に対する感受性、精神医学的な診断、心理物理的適合性、レジリエンス[しなやかさ、回復力]との関係について、多くの論文が発表されることとなった。
●心拍変動を調整する神経的作用機序
・『私は、心拍変動を引き起こす、心拍間隔に影響を与えている神経経路を探求し、心拍数を制御している神経系の仕組みを理解するために、動物実験を行った。』
●心拍数を制御する迷走神経の計測方法の開発
・心臓迷走神経緊張のより正確な指標として、呼吸性洞性不整脈(RSA)を定量化する方法を開発した。
・迷走神経は呼吸によって心臓に与える影響を変化させる。
・呼気と吸気では心拍数が一定のリズムで減少したり増加したりする。そして、迷走神経の影響が大きければ大きいほど、その心拍変動は増加する。
・フィードバックループは迷走神経の働きを動的に調整している。肺や心臓だけでなく高次の脳からも脳幹へと信号が送られる。
・フィードバックループの出力媒介変数は振幅と周波数である。振幅は迷走神経の影響を反映しており、周波数は呼吸数を反映している。
・相対的な方法論から、神経生理学的なモデルをもとに迷走神経による神経的制御を計測する方法論へと推移していった。この技術を用いることで、迷走神経による制御の具体的な状態を正確かつ継続的に計測することができるようになった。
●仲介変数の探求
・『私の科学的な探求は、行動の個人差を理解するための仲介変数を探す旅であった。この旅を通して「安全である」と感じることも含めた心理的な体験と、行動の神経的基盤となる自律神経の状態の重要性を理解することとなった。』
・研究の三つの段階
1.記述的研究(心拍変動が重要な現象であることに気づき、一連の経験主義的な実験)。
2.心拍変動を仲介している神経生理学的な作用機序を説明するための研究。
3.神経生理学的、神経解剖学、進化学をもとにした、脳と身体、あるいは心と身体の科学の基礎となるポリヴェーガル理論の構築。
・『ポリヴェーガル理論は、我々の行動と、他者との関わり方に影響を与える仲介変数としての生理学的状態の重要性を解き明かすものであった。この理論により、危険と脅威が生理学的状態を変化させ、防衛に向かわせることが説明された。そしてもっとも大切な点は、「安全である」とは、単に脅威を取り去ることではないということだ。「安全である」とは、環境中や、他者との間で交わされる健康、愛、信頼を感じることを促進する、独特の「合図」に依存しており、それが防衛回路を積極的に抑制する。』
●安全と生理学的状態
・ポリヴェーガル理論では、意識の及ばないところで環境のリスクを評価する神経的なプロセスを「ニューロセプション」と呼ぶ。
・ポリヴェーガル理論では、ストレスとなる出来事の物理的な特徴は、あまり影響力を持たず、むしろ我々自身の身体的な反応の方がより重要な役割を果たしていると考える。
・ポリヴェーガル理論では、自律神経の神経的制御が変化したことを、内臓の感受性によって捉えていくモデルを提唱している。
・ポリヴェーガル理論では、社会が安全であると感じられる環境や、信頼できる人間関係を、我々は人々に提供しているのか、という問いに直面することになる。学校、病院、教会などの社会組織が、常に人々を評価し、それによって危険と脅威を感じさせる状況であることを鑑みると、政治紛争、財政危機、戦争などと同じように、こうした社会構造が我々の健康に好ましくない影響を与えていると言わざるを得ない。
・ポリヴェーガル理論では、生理学的な状態を、様々な種類の適応的行動を効果的に表現する神経的な土台であると考える。
●「安全であること」の役割と、生き残るために必要な「安全である」という合図
・神経系は爬虫類から哺乳類へと進化した過程で変化していった。特に哺乳類では、同種の生物のうち、どれだけ安全で近づいてもよく、また触れてもよいのかを同定する神経系が発達した。
・爬虫類や、その他の「原始的な」脊椎動物では、防衛戦略が非常に発達していた。しかし、進化した哺乳類においては、適応していくために、今度はそのよく発達した防衛戦略のスイッチを切る神経的作用機序が必要になった。
・哺乳類はいくつかの生物学的な必要性に迫られて「安全」を求めるようになっていった。
-哺乳類は出生後、直ちに母親の保護を受ける必要がある。
-人間を含む数種類の哺乳類は、生きていくためには「孤立」を避け、長期間社会の中で相互依存を必要とする。防衛反応のスイッチを切って、子育てをしたり、社会的行動をとったりするためには、安心できる安全な環境と、安全な同種の生物を同定する能力が必要になった。
-生殖、授乳、睡眠、消化を含む様々な生物学的、行動学的機能を果たすためには、哺乳類は安全な環境が必要不可欠である。
・哺乳類は社会的行動と感情の制御を必要とするようになった。
・ポリヴェーガル理論では、社会的行動と感情の制御を行う神経回路は、神経系が「安全である」と感じているときにのみ発動するとしている。その時、この神経回路は、「健康」、「成長」、「回復」を促進するように働く。
・「安全」は人間が潜在能力を発揮する上で欠かすことができない。高次の脳は創造性を発揮し、生産的であるためにも必要不可欠である。
・ポリヴェーガル理論では、我々の心理的、物理的、行動学的反応が、我々の生理学的状態に依存しているという事象に重きを置く。
・ポリヴェーガル理論では、身体の諸器官と脳が、自律神経を制御している迷走神経やその他の神経を通して、双方向に情報交換しているということに注目する。
・自律神経系の制御は、進化の過程で「安全であること」を互いに発信しあい、協働調整することができる神経系を獲得した。
●社会的交流と安全
・臨床において、見たり、聴いたり、起きていることに注目することは、大変有効なやり方である。
・社会的交流を持ち、身体の諸器官からの感覚をフィードバックすることにより、気分や感情の主観的な状態を改善することができる。
・社会交流システムとは、顔と頭の横紋筋を制御する神経経路を総称したものである。
・社会交流システムは、身体感覚を投影するとともに、安全で落ち着いていて、愛と信頼を醸成する状態から、防衛反応を起こす脆弱な状態まで、一連の変化を引き起こすための情報の入り口である。
・セラピストとクライアントが互いに、「見て」「聴いて」「感じる」ということは、お互いの身体と感情の状態を動的に双方向に情報伝達し、社会的交流が行われていることを意味する。それこそが治療的瞬間である。
・社会的交流が相互に利益をもたらし、互いの生理学的な状態を協働調整するためには、双方ともに、安全であり、信頼できるという社会交流的「合図」を送りあう必要がある。
・双方向で主観的な体験を分かち合うことは、結合鍵を開けるようなものである。突然、鍵を固定していた回転部品が正しい場所に収まり、扉が開くのである。
・進化の過程で、表情や発声、音や味覚を検知する神経系と生理学的状態とが結びついたのは、哺乳類特有の現象である。
・身体の状態と表情や発声とが結びついたことにより、同種の生物が発する「合図」を見極める能力が発達した。相手が出している「合図」は「安全である」のか、「危険である」のか、はたまた逃げることも戦うことも不可能で、擬死に陥り不動状態になるべきなのか、判断できるようになった。そして、社会的交流の扉が開いた。
・他社が近づいても安全であるという「合図」を提供するために、顔と頭の筋肉を神経制御することが必要とされる。
・社会的交流システムは、我々の「安全であること」への生物学的な希求と、人とつながり、自分たちの生理学的な協働調整したいと望む、無意識の生物学的な必須要件から生まれた。
・社会的交流では、「わかった」という微細な「合図」や、共感、互いの意図が交わされる。こうした「合図」は、微妙な調子、韻律を通して伝えらえる。それは同時に互いの生理学的状態を伝えあう。我々は、自らが落ち着いた生理学的状態であるときにのみ、相手に「安全である」という合図を伝えることができる。
・社会的交流システムは、自分の生理学的状態を伝えるだけでなく、相手がストレスを感じているのか、それとも「安全である」と感じているのかを感知する入り口にもなる。「安全」を感知すると、生理学的反応は落ち着く。危険を感知すると、生理学的状態は、防衛反応を活性化するように変化する。
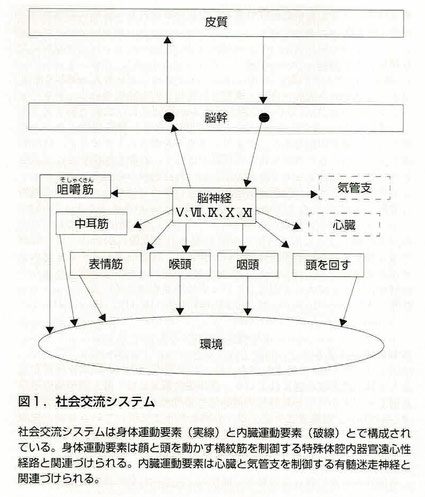
画像出展:「ポリヴェーガル理論入門」
『図1で示されているように、社会交流システムには身体運動要素と内臓運動要素が含まれている。身体運動要素には、顔と頭の横紋筋を制御する内臓からの特殊体腔内器官遠心性経路(脳管内の運動核[疑核、顔面神経、三叉神経]から生じており、社会交流システムの身体運動要素を形成している)がある。
内臓運動要素には、心臓と気管を制御している有髄の横隔膜上の迷走神経がある。機能的には、顔と頭の筋肉と心臓のつながりから社会交流システムが生じる。社会交流システムは、誕生直後では、吸う、飲む、呼吸する、声を出すといった行動を調整している。誕生後早期に、この調整がうまく取れない場合、成長後、社会的行動や感情の制御が難しくなることが示唆される。』
●結論
・ポリヴェーガル理論では、「安全である」と感じることは生理学的な状態に依存しており、「安全である」という合図は自律神経系を穏やかにする。
・生理学的な状態を落ち着かせると、安全で信頼できる人間関係を結ぶことができ、それそのものが、行動的、生理学的状態を協働調整する機会となる。こうした健全な「調整サイクル」が心と身体の健康を促進する。このモデルでは、自律神経の状態を含む我々の身体の感覚は、我々が他者と関わることにおいて仲介変数の機能を果たしている。
・交感神経が優位となり、戦闘態勢に入っているときは、防衛に焦点が当たっており、「安全である」という合図を出すことも受け取ることもしない。しかし、腹側迷走神経経路によって社会交流システムが発動しているときは、声や表情で、「安全である」という「合図」を出し、それにより、自分自身と他者の防衛反応を抑制する。互いに、社会交流システムを用いて関わり合うことによって、社会的な絆が強化される。
-腹側迷走神経複合体:腹側迷走神経複合体は脳幹に位置し、心臓、気管支、顔と頭の横紋筋を制御している。また、腹側迷走神経複合体は、内臓運動経路を通して心臓と気管支を制御している疑核と、特殊体腔内器官遠心性経路を通して、咀嚼、中耳、顔面、咽頭、喉頭、首の筋肉を制御している三叉神経と顔面神経からなる。
・ポリヴェーガル理論では、治療的モデルにおいても、人間としての体験を最善のものとするためには、身体の感覚を尊重することだけでなく、生理学的な状態を含む支援を行うことが大切であると考えている。
・ポリヴェーガル理論では、他者との絆を形成し、互いに協働調整しあうことは、我々人間にとって必要不可欠な生物学的必須要件であると説いている。「安全である」と感じることは、生きていく上でなくてはならない。そして、我々が行動的、生理学的状態を協働調整することができる、信頼に満ちた社会的関わりを持つことによってのみ、我々は「安全」を感じることができる。
ご参考:『人体の正常構造と機能』という本にある図・説明を用いて、神経生理学的説明を視覚的に追ってみました。もやもや感がありますがご紹介します。
①脳神経核
以下は脳幹の図です。左側の図では右半分が知覚核(孤束核など)で、左半分は運動核(三叉神経運動核、顔面神経核、疑核、迷走神経背側核など)となっています。
また、右側の図は脳幹部の断面図です。黄色は“一般内臓運動(GVE)”、ピンク色は“特殊内臓運動(SVE)を担っています。緑色の舌下神経核に隠れて見づらいですが、迷走神経背側核(黄色)は確かに背中側(小脳側)にあるのが確認できます。一方、三叉神経運動核(ピンク色)、顔面神経核(ピンク色)、疑核(ピンク色)は迷走神経背側核から見ると、いずれもお腹側(腹側)に位置しているのが分かります。“腹側迷走神経複合体”とは、この部分を指しているのではないかと思います。
②脳幹の自律神経中枢
下の図は“循環中枢”(左)と“呼吸中枢”(右)を説明している図です。赤は交感神経、青は迷走神経(副交感神経)ですが、脳に近い神経は赤(交感神経)、青(迷走神経)とも実線になっています。これは有髄線維の高速な線維です。一方、小さな●(神経核)を経て、破線になっていますがこれは低速の無髄神経になります。有髄線維は“節前線維”とよばれ、神経線維の分類で分けるとB線維になります。無髄線維は“節後線維”とよばれ、同じく神経線維の分類ではC線維になります。(神経線維はB、Cの他にAα、Aβ、Aγ、Aδがありますが、B線維よりさらに高速な線維です)
茶色はいずれも求心性の副交感神経になりますが、この図では三叉神経、舌咽神経、迷走神経の3つが出ています。
③脳神経の線維構成
縦軸は脳神経の種類で、上から“特殊感覚神経”、“体性運動神経”、“鰓弓神経”に分類され、横軸は遠心性(左)と求心性(右)の2つに分かれています。鰓弓神経に注目すると、1番下の副神経(Ⅺ)以外の各神経は遠心性と求心性の双方の機能を有していることが分かります。これを見ると、先にご紹介した“社会交流システム”の中央に書かれている脳神経と比較して頂くと、”社会交流システム”が関わる脳神経は、鰓弓神経(脳神経のⅤ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ)を指しているということが分かります。
ポリヴェーガル理論1
“ポリヴェーガル理論”を知ったのは、ナチュラル心療内科の竹林直紀院長の著書である『疲れた心の休ませ方』という本です。特に表紙の下に書かれていた、“「3つの自律神経」を整えてストレスフリーに!”という添え書きに興味を持ちました。
「はじめに」の中の“コミュニケーションにかかわる自律神経があった!”には、次のような説明がされていました。
『自律神経は大きく3種類に分けられる―。この新しい考え方は、精神生理学者のステファン・ポージェス博士によって提唱されました。
ポージェス博士は、アメリカのイリノイ大学で長年にわたり、自閉症児や社会的コミュニケーションに問題を抱える人々の研究をおこなってきました。そのなかで、自律神経の新しい考え方を発見し、1995年に「ポリヴェーガル理論」と題して論文を発表しました。
ポリヴェーガルとは、「poly(=複数の)」と「vagal(=迷走神経)」を組み合わせた造語で、「多重迷走神経」と翻訳されています。
ポリヴェーガル理論では、3つに分けた自律神経のうちのひとつを「社会的交流」の自律神経(社会神経系)とよびます。人と人とがつながり、関係性を構築していくとき、この「社会的交流」の自律神経が働いてその場に適した対応がとれるといわれています。』
また、“SCENE1 ストレスに振り回されない「人との距離感」の保ち方”の中では、次のような紹介が出ていました。
『ポージェス博士は、著書「ポリヴェーガル理論入門」(花丘ちぐさ訳、春秋社)で、次のような趣旨のことを語っています。
心地よい社会生活や人間関係は、「健康」「成長」「回復」をうながす社会的交流の神経経路を使っておこなわれます。私たち人類の神経系は、「安心・安全」を探求しつづけ、「安心・安全だ」と感じるために、他者の存在を必要としているのです。』
これを拝見し、「この、『ポリヴェーガル理論入門』を読んでみないと、よく分からないなぁ」と思い、購入してみました。
“3つの自律神経”という考え方については、その科学的根拠に疑問もあるようです。これについては、後述させて頂きます。
しかしながら、最後の「謝辞」の中で、ポージェス先生がお話されているように、トラウマを抱えた人々に対する理論として、このポリヴェーガル理論は画期的なアプローチのように思います。
また、私のような施術者が患者さまと向き合うときの、「安心・安全」ということの意味や向き合い方など、その大切さを再認識することもできました。
謝辞(冒頭部分のみ)
『「ポリヴェーガル理論」は、1994年10月8日の私の研究所からヒントを得てつくられた(porges,1995)。その日私はアトランタで行われた心理生理学会で、学会長としてあいさつを述べた。そこで語ったモデルとそれに関連する理論が、ポリヴェーガル理論のもととなった。
そのときは、この理論が臨床家の注意を引くとは思っていなかった。私はこのモデルを、この学会で実験可能な仮説として発表したつもりでいた。私が予測していたとおり、このモデルはまず複数の分野において、査読付き論文数千件に引用された。つまり初めは予想通り、科学界で注目されたのである。
しかし、ポリヴェーガル理論がもたらしたもっとも大きな貢献は、この理論が、トラウマを体験した人が抱えていた状態について、神経生理学的な説明を行ったことであった。トラウマを抱えた人々に対し、ポリヴェーガル理論は、生命の危機に及んで、なぜ彼らの身体はかくのごとく反応し、その結果、レジリエンス[しなやかさ]、柔軟性、回復力を失い、「安全である」と感じられる状態に戻れなくなったのかを説明したのである。』
先に、触れされて頂いた科学的根拠に関することですが、これはWikipediaに書かれていたものです。検索したところ“Polyvagal theory”に出ていました。(原文のままですみません)
Criticism
Polyvagal theory has not, to date, been shown to explain any phenomena or experimental data above and beyond what is explained more precisely by attachment theory, research on emotional self-regulation, psychological stress models, the Neurovisceral Integration Model[23][24] and neuroimaging studies from the field of social neuroscience. Its appeal may lie in the fact that it provides a very simple (if inaccurate) neural/evolutionary backstory to already well-established psychiatric knowledge.
ブログは、患者さまと向き合う施術者として、「安全・安心」とは何かという視点を中心に置き、ポリヴェーガル理論の神経生理学的説明については、どっぷり浸かるのではなく、少し距離をとって拝読させて頂くこととしました。
その中で、特に印象に残った箇所を取り上げていますが(目次の黒字箇所)、そのほとんどは第1章と第2章からになります。また、長くなったので3つに分けました。
目次
序文
なぜこの本は対話形式で書かれているのか?
なぜ安全を求めるということに焦点を当てているのか?
第1章 「安全である」と感じることの神経生物学
●考えること・感じること:脳と身体について
●正当な科学的論題としての「感じること」に関する研究
●心理生理学研究と心拍変動
●心拍変動を調整する神経的作用機序
●心拍数を制御する迷走神経の計測方法の開発
●生理学的状態の計測と「刺激/反応モデル」の統合
●仲介変数の探求
●安全と生理学的状態
●「安全であること」の役割と、生き残るために必要な「安全である」という合図
●社会的交流と安全
●結論
第2章 ポリヴェーガル理論とトラウマの治療
●トラウマと神経系
●トラウマと神経系
●「ポリヴェーガル理論」と「迷走神経パラドクス」
●ふたたび自律神経系について
●ニューロセプション:意識せずに行う知覚
●PTSDを起こす引き金
●社会交流システムと愛着の役割
●自閉症とトラウマの共通点は何か?
●自閉症の治療
●LPP―リスニング・プロジェクト・プロトコル:理論と治療
●音楽はいかに親密性を促進する:「安全である」という合図
第3章 自己調整と社会交流システム
●心拍変動と自己調整:どう関係しているか?
●「ポリヴェーガル理論」を構成する原理
●安心を感じるためにどのような他者を利用しているのか
●私たちが世界に反応する方法に影響を与える三つのシステム
●迷走神経パラドクス
●迷走神経:運動経路と感覚経路の導管
●トラウマと社会的交流の関係
●いかにして音楽が迷走神経による調整を促す「合図」となるか
●社会交流の信号:迷走神経の自己調節と「合図がわからない状態」
●神経による調整を回復させる
●愛着理論は適応機能とどう関係するか?
●生理学的にもっと安全な病院を作ること
第4章 トラウマが脳、身体および行動に及ぼす影響
●「ポリヴェーガル理論」の原点
●「植物性迷走神経」と「機敏な迷走神経」
●複数の神経経路の群としての迷走神経
●迷走神経と心肺機能
●第六感と内受容感覚
●迷走神経緊張はいかに情動と関係しているか
●ヴェーガル・ブレーキ
●ニューロセプションはどのように機能するか:「脅かされた」と感じるか、「安全である」と感じるか
●ニューロセプション:脅威と安全への反応
●新奇な出来事:哺乳類と爬虫類の反応の違い
●神経エクササイズとしての「あそび」
●迷走神経と解雇
●単一試行学習
第5章 安全の合図、健康および「ポリヴェーガル理論」
●迷走神経と「ポリヴェーガル理論」
●心と身体のつながりがどのように病状に影響を与えるか
●トラウマ、そして信頼への裏切り
●ニューロセプションの働き
●不確実性と生物学的な必要要件としての絆
●「ポリヴェーガル理論」:トラウマと愛着
●なぜ歌うことと聴くことで落ち着くのか
●社会交流システム系を活性化させるエクササイズ
●今後のトラウマ治療
第6章 トラウマ・セラピーの今後 ポリヴェーガル的な視点から
第7章 心理療法に関するソマティックな視点
謝辞
序文
なぜこの本は対話形式で書かれているのか?
・数年にわたり、多くの臨床家から高度に専門的な内容を分かりやすい本にまとめることを求められてきた。
・インタビュー形式にすることにより、臨床応用のための情報に絞り、のびのびと肩ひじを張らない表現で本にまとめることができた。
・本書の巻末には、ポリヴェーガル理論を理解するための基本的な用語や考え方を解説する「用語解説」を付けた。
-用語解説:愛着、あそび、安全、安全(治療的状況における)。韻律・プロソディ、ヴェーガル・ブレーキ(迷走神経ブレーキ)、歌う、遠心性神経、横隔膜下迷走神経、横隔膜上迷走神経、オキシトシン、解体、解離、疑核、聴く、擬死/シャットダウン、求心性神経、境界性パーソナリティ障碍、協働調整、系統発生学、系統発生学的に秩序づけられたヒエラルキー、交感神経、恒常性・ホメオスタシス、呼吸性洞性不整脈(RSA)、孤束核、サイバネティクス、自己調整、自閉症、社会交流システム、植物性迷走神経(「背側迷走神経複合体」)、自律神経系(既存の考え方)、自律神経系(「ポリヴェーガル理論」の視点における)、自律神経の状態、自律神経バランス、神経エクササイズ、神経的期待、身体運動、心拍変動、生物学的な必須要件、生物学的非礼、生理学的状態、単一試行学習、中耳筋、中耳の伝達関数、腸神経系、つながり、適応的な行動、闘争/逃走反応、特殊体腔内器官遠心性経路、内受容感覚、内臓運動神経、ニューロセプション、脳神経、背側迷走神経複合体、PTSD(心的外傷後ストレス障碍)、不安、副交感神経、味覚嫌悪、迷走神経、迷走神経の緊張状態、迷走神経の求心性線維、迷走神経パラドクス、ヨガと社会交流システム、抑うつ症、リスニング・プロジェクト・プロトコル(LPP)
なぜ安全を求めるということに焦点を当てているのか?
・ポリヴェーガル理論によると、人間やその他の社会交流システムを持っている哺乳類は、顔と心臓が神経的につながっており、表情と声の調子で「安全かどうか」を確認したり投影したりする。この表情と声の調子は、自律神経の状態に伴って変化する。つまり、ポリヴェーガル理論では、私たちは相手がどのように見て、聞いて、声を出すかということで、その人に接近しても安全かどうかを判断すると考える。

画像出展:「ポリヴェーガル理論入門」
『図1で示されているように、社会交流システムには身体運動要素と内臓運動要素が含まれている。身体運動要素には、顔と頭の横紋筋を制御する内臓からの特殊体腔内器官遠心性経路(脳管内の運動核[疑核、顔面神経、三叉神経]から生じており、社会交流システムの身体運動要素を形成している)がある。
内臓運動要素には、心臓と気管を制御している有髄の横隔膜上の迷走神経がある。機能的には、顔と頭の筋肉と心臓のつながりから社会交流システムが生じる。社会交流システムは、誕生直後では、吸う、飲む、呼吸する、声を出すといった行動を調整している。誕生後早期に、この調整がうまく取れない場合、成長後、社会的行動や感情の制御が難しくなることが示唆される。』
・ポリヴェーガル理論では、「安全でない」と感じることによって、精神的、肉体的に疾病を引き起こす生理行動学的な特徴が形成される。
・我々が「安全である」と感じることの必要性が広く理解されることで、社会的、教育的、臨床的な戦略が、お互いの安全のために、進んで他者を受け入れて、互いに協働調整を図ることを勧める方向に、大きく変わっていくことを望んでいる。
血圧と運動
久しぶりに『月刊 スポーツメディスン』を購入しました。それは特集が「血圧と運動」という興味深いものだったためです。
ブログは早稲田大学スポーツ科学学術院 スポーツ生理学 前田清司先生の“血圧とは何か-なぜ高血圧が問題なのか-”からです。
1.運動と血圧の関係
●男性約3000名を対象に5年間にわたり、体力(体力の指標は最大酸素摂取量)と血圧の関係を研究した。体力別に分けた5つのグループでは、最も体力の低いグループは、最も高いグループに比べ約1.9倍高血圧症になりやすいことが明らかになった。
●35~60歳の男性を対象にした血圧と歩行時間の研究では、1日の歩行時間が10分以下の人は、20分以上の人に比べ1.4倍高血圧症になりやすいことが明らかになった。
●7年以上にわたってランニング距離と血圧の関係を調べた研究では、ランニング距離が長いほど高血圧の発症リスクが軽減されるという報告がある。
●高血圧症患者に治療の一環として運動療法が用いられており、運動習慣は高血圧を改善する効果がある。
2.動脈硬化と運動の関係
●動脈硬化度は脈波伝播速度などで評価するが、習慣的および一過性の有酸素運動は動脈硬化度を低下させる。
3.柔軟性と血圧の関係
●長座位体前屈を指標とした柔軟性において、高齢者では柔軟性が高いほど血圧が低いという結果が得られた。
●身体の柔軟性を高めるストレッチングは高血圧の予防・改善の効果を持つ可能性がある。
●動脈硬化度について、中高齢者では柔軟性が高いほど動脈硬化度が低いという結果が得られている。
4.推奨される有酸素性運動
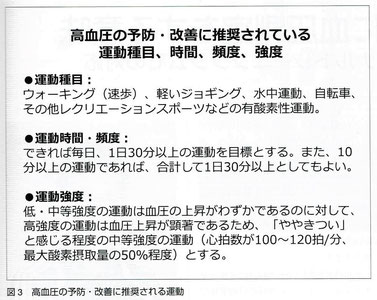
画像出展:「スポーツメディスンNo237」
『運動時間や頻度は、できるだけ毎日、30分以上を目標とすることが重要です。たとえば10分の運動でも、合計して30分以上であれば効果的であるということもわかっているので、細切れでも運動することが大事です。
運動強度については、低強度から中等強度では血圧上昇はわずかですが、高強度の運動では血圧上昇が顕著であるため、「ややきつい」と感じる程度の中等強度の運動(心拍数が100~120拍/分、最大酸素摂取量の約50%)がよいと思います。高強度インターバルトレーニングは短時間で効果が得られ、糖尿病患者に対する改善も示されていますが、高血圧患者に対しては血圧上昇に十分な注意が必要です。
高血圧患者では主治医の指導のもとで治療を行っていくことになりますので、この記事などの情報を得て、自分で判断して運動を始めるのではなく、主治医の指導に従うことが大切です。
また、運動習慣のない方が急に運動を始めると、身体に与える負荷が非常に大きいので、まずは生活の中で掃除をしたり買い物をしたり、子どもと遊ぶなど、身体活動を増やすことから始めるとよいでしょう。あとはそれぞれのライフスタイルに合わせて運動を取り入れていくとよいです。
最初は合計15分の運動をやってみるとか、運動を朝と夕方に分けてやってみるとか、無理をしないことが大切です。』
5.高血圧パラドックス
●高血圧パラドックスとは、薬など治療法は明らかになっているにも関わらず高血圧治療が進まないことである。
感想
先週のブログ「“年齢+90”という考え方」は、松本光正先生の『やっぱり高血圧はほっとくのが一番』で勉強したことを書いているのですが、”今が最良の血圧”というお話をされています。
これは、人は生きていくためにはすべての臓器や組織に酸素や栄養素、生理活性物質などを運ぶ必要がある。若者の血管は軟らかく、力の弱いポンプ(低い血圧)でも血液を全身に送り届けることができるが、太ったり、加齢で血管が硬くなったり、血液がドロドロしていたりすると、力の強いポンプ(高い血圧)を使わないと血液を全身に送り届けることは難しい。そして、これらの調整は生きていくために備わっている能力(自然治癒力)が、ポンプの強弱(血圧)を最適になるように自動的に調整してくれている、というものでした。
このことは安易に薬に頼るのではなく、食事、運動、睡眠などの生活習慣の改善に取り組み、原因を根本的に取り除いていけば、血圧は自然と少しずつ下がっていってくれるということです。
“高血圧パラドックス”の一番の問題点は、体が持つ自然治癒力のメカニズムや加齢という現象を軽視し、さらに生活習慣を見直すことを省略して、安易に薬に頼ってしまっていることが原因ではないかと思いました。

画像出展:「人体の正常構造と機能」
この図をみても、重力に逆らって血液を全身に循環させる仕事は簡単ではないと思います。
なお、これは安静時の状態です。下の方に”骨格筋16%”とありますが、骨格筋を激しく使う運動を行うと、この数値は跳ね上がり、相対的に内臓などの血液分泌比率は下がります。
ご参考:”降圧剤で脳梗塞に?血圧を下げるなら下半身の運動も忘れないで”
こちらは荒牧内科 荒牧竜太郎院長が寄稿された、”Medicallook”さまの記事です。一部、ご紹介させて頂きます。
『高血圧を治すために降圧剤が投与されるのですが、患者や医師の意に反して「脳梗塞」を引き起こすこともあるのです。動脈硬化で先の細くなった血管に血栓が流れ込んでも、血圧が高ければ血栓を押し流してくれます。しかし、降圧剤で血圧が下がっていると、血栓に圧力がかかりません。そのせいで血管に血栓が詰まりやすくなります。すると、脳梗塞も起こりやすくなります。』
『血圧を下げる効果のあるプロスタグランジンというホルモンは、上半身の運動より下半身の運動でより多く分泌されます。ウオーキング、ももあげ、スクワットなど下半身の運動を行ってください。
※注意:ベンチプレス・筋トレ・全力疾走など、”瞬間的に力を入れるような運動(無酸素運動)”はかえって血圧を上昇させるので注意してください。』
“年齢+90”という考え方
当院では血圧と脈拍を施術前後に計測しています。
先日、血圧が高めの患者さまが来院されました。収縮期血圧が160台だったので、「ちょっと高めですね」とお声をかけたところ、「友人の医師も言っているが、50、60歳で120台(収縮期血圧)なんて無理な話。年齢+90でも特に問題ないし、薬もまだ要らないと思っている」とのお話でした。
以前、青木久三先生の『減塩なしで血圧は下がる』(ブログは“塩と高血圧”)や石川太朗先生の『降圧薬の真実』(ブログは“降圧薬”)を拝読しており、私自身も“年齢+90”は問題ないと思っていたので、このお話に特に違和感はなかったのですが、何か新しい情報はないか調べてみることにしました。
”上の血圧は「年齢+90」くらいが適切|健康診断の古い基準に従う必要はない”
このYAHOOニュースに掲載されていた記事は、満尾正先生によるものです。残念ながら先生の著書の多くは食事療法に関するものだったため、もう少し調べてみると、同様なお考えをもった松本光正先生が血圧に関する数多くの本を出版されていることが分かりました。そして、その中から『やっぱり高血圧はほっとくのが一番』という本を選びました。
本文に入る直前に次のことが書かれていました。
『本書は高血圧と診断された後にもなるべく服薬に頼らないようにするため、まずは食事療法や運動療法による生活習慣の是正を試みている方むけに書かれたものです。何らかの事情で厳格な血圧のコントロールを必要とされている人には適さない内容も含まれています。もし身体にいつもと違う変化があったら、必ずかかりつけ医に相談してください。』
目次は以下の通りですが、ブログで取り上げたのは黒字の箇所です。特に「第5章 君子医者に近寄らず」の最後、“良い医師、悪い医師、普通の医師”は、松本先生が読者に伝えたいことを集約させた文章のように感じました。
第1章 受診の95%は不要
●医者に来る必要がありますか?
●不要な受診をしてしまう4つの原因
●自然治癒力があるから受信しなくても大丈夫
●自然治癒力が持つ3つのはたらき
●あなたの身体はいつでも「今が最良」
●症状は身体が「今が最高」と示すサイン
●急性病は病ではない
●身体に起きていることで無意味なことは一つもない
第2章 やっぱり高血圧はほっとくのが一番
●高血圧は放っておいても大丈夫
●血圧にも2つの「今が最高」がある
●最適な血圧の目安は「年齢+90」
●ライオンの血圧は110、キリンの血圧は280
●高血圧治療に潜んだカラクリ
●本当の血圧は一日の中で最も低いときの血圧
●血圧は低い方が心配
●血圧に関するよくある質問
第3章 クスリはリスク
●降圧剤の弊害
●人間は機械ではない
●原因があって結果があるので、薬を飲んでも解決できない
●あなたの身体は世界にただ一つのオーダーメイド
●薬を飲むリスク
●さまざまな疾患の薬による弊害
●医師がそれでも薬を出す理由
●薬に関するよくある質問
第4章 薬を飲まずに健康を保つ方法
●血圧が高いと言われたら、まず実践したい4つのこと
●心が身体に及ぼすさまざまな影響
●心の健康を保つ4つの方法
●心を鍛え続けてきた私自身の病との向き合い方
第5章 君子医者に近寄らず
●医者にはどんなときに行くべきか
●無医村ほど長生き
●健康な人を患者に変える健康診断
●医師を妄信しない
●良い医師、悪い医師、普通の医師
おわりに
第2章 やっぱり高血圧はほっとくのが一番
●最適な血圧の目安は「年齢+90」
『あなたの血圧は自然治癒力のおかげで、今のあなたにとって最適な値になるようにつねに自動的にコントロールされています。そうはいっても気になるのが最適とされる血圧値の目安ではないでしょうか。
健康を保つために最適な血圧の目安としては、経験的に年齢+90という数値が使われており、私もこの数値を目安にしてよいと考えています。
一方でこれは古い考え方だと否定する医師も沢山います。しかし、私はこの数値はけっして古いとは思いません。むしろ、立ち上がった中型の哺乳動物である我々人間にとって、この値は非常によくできた数値だと考えます。年齢とともに変化し、上昇する血圧をわかりやすく表しているからです。
この数値を否定する医師は人の血圧が年齢ととともに上昇するということが受け入れられない、あるいはわからない医師なのでしょう。年齢とともに血圧を上げることで命を守っているということが理解できず、年をとっても若者と同じ数値がよいと思い込んでいるのです。高齢者の血圧が若い人の血圧を基準に語られている現状、これこそが問題です。
若い人の血管はしなやかです。動脈硬化も狭窄もありません。だから低いのです。その低い血圧でも地球という惑星に存在する重力に逆らって血液を心臓から脳へと送ることができるからです。
しかし高齢になると血管のしなやかさは失われ、血管に狭窄が起こります。こういう血管の状態では130の血圧では脳まで血液を送ることができません。脳に血液を送らないと死んでしまうので、身体は命を守るために150、160、200と血圧を上げていきます。命を守るために自然治癒力がはたらいているのです。必要だから血圧は上がるのです。
「高血圧治療ガイドライン2014電子版」によると、若年、中年、前期高齢者患者の診察室血圧における降圧目標は140/90とされています。
75歳以上の後期高齢者患者の降圧目標を見てみると、150/90ですが、降圧によって有害な影響が見られないならば、という条件付きではありますが、75歳未満の人たちと同じ140/90が目標とされています。
2019年4月にこのガイドラインが改訂されました。新しいガイドラインでは75歳未満の人の降圧目標は130/80未満へ、75歳以上の人は140/90未満にそれぞれ引き下げられました。従来よりも厳しい血圧コントロールが求められるようになりましたが、こうした基準を一律に高齢者にも当てはめるところに問題があります。これが間違っていることは誰の目にも明らかでしょう。
だから私は何度も繰り返し言います。年齢+90は非常に合理的で科学的な数値です。』
第3章 クスリはリスク
●医師がそれでも薬を出す理由
・過剰医療、過剰診療は医師の防衛反応
『風邪を風邪だときちんと診断し「風邪なので薬は出しません。寝て安静にしてください」という一言は、医師にとってとても重く勇気がいる一言です。これが言える医師は素晴らしい人です。たまにですがそういう医師の噂を耳にします。
ではなぜ、薬(化学薬品)は悪い、効果がないと思う医師さえもが薬を処方するのでしょうか。それは、そうしないと患者さんに何かあったときが怖いからです。何かというのは、それが風邪でなくほかの重大な疾患だった場合や、さらにそれが訴訟に発展したときです。
そうならないためには薬を出して、「私はガイドラインに従い、世間の医師の常識通りの診療をし、薬を処方しました」と言えるよう防衛線を張る必要があるのです。だから、薬は効かないし、むしろ毒だときちんと理解している医師でさえ薬を出すし、必要でもない検査をするのです。これらはみんな防衛反応です。医師も自分の身がかわいいのです。その結果、過剰医療、過剰診療がおこなわれているのです。』
第5章 君子医者に近寄らず
●良い医師、悪い医師、普通の医師
・普通の医師
『世の中には沢山の医師がいます。悪い医師ばかりではありません。また良い医師ばかりでもありません。ほとんどが普通の医師でしょう。
普通の医師とはどういう医師かというと、世間一般のどの医師もやっていることを何の疑いもなくおこなっている医師でしょう。
風邪の患者さんが来たら風邪薬や抗生物質を処方します。インフルエンザの患者が来たら抗インフルエンザ薬のタミフル(オセルタミビル)を出し、新薬のゾフルーザ(バロキサビルマルボキシル)の発売が開始されるとすぐさま手を出します。予防注射は効くと思っているから患者さんに勧めます。
下痢の患者さんに下痢止め、吐いていれば吐き気止め、血圧が高ければ血圧の薬を出します。コレステロールが高ければコレステロールの薬を、血糖値が高ければ糖尿病だと思ってすぐに薬を出し、少し血糖値が高いだけなのにインスリン注射を平気で勧めます。
認知症の薬は効くと信じています。疑うなどという気はまったく持ち合わせていません。その薬が世界では使われていないなどとは夢にも思いません。だから平気で使います。
普通の医師は、こうして馬に食わせるほどという表現がぴったりなくらい多くの薬を処方します。患者さんに薬を出してあげるのは親切だと信じているのです。
早期発見・早期治療が最善だと思っているから健康診断が好きで、がんであれば手術を勧めるし、躊躇なく抗がん剤も投与します。こういう医師が普通の医師です。
人はいいのです。優しい心を持っています。人格者と慕われている人もいます。でも普通の医師なのです。
けっして不勉強ではありません。医学をよく勉強しています。知識も豊富です。しかし、その知識は普通の知識です。その普通の知識をそのまま何の疑いもなく取り入れているのです。取り入れているだけで深く考えないのです。考えないから、世間一般におこなわれている医療行為を疑うことなく実施しているのです。これでは患者さんはたまりません。
有名大学の医学部を首席で卒業しても普通の医師は普通の医師です。
医師はつねにこれでいいのか、自分の知識は正しいのかを自問自答し、考え続けなくてはなりません。考えないから普通の医師なのです。』
この本の初版は2021年5月なので、原稿は3年前位ではないかと想像します。一方、認知症の薬は最近時々話に聞くので、少し調べてみました。
下記は和歌山県立医科大学附属病院 認知症疾患医療センターさまのサイトです。

”認知症のお薬について” 「薬はどのくらい効きますか?」
『残念ながら現在使用されている薬には、根本的に認知症の進行を止める働きはなく、飲んでいても最終的には認知症は進行します。また記憶障害や行動障害を劇的に改善させるほどの効果も期待できません。しかし脳で生き残っている神経細胞を活性化させ、覚えたり考えたりする働きをある程度保つ可能性があります。また、日常生活に活気が出たり、イライラや不安を少なくすることによって生活の質を上げる効果も期待できます。』
こちらは国立研究開発法人日本医療研究開発機構さまのサイトです。(こちらは薬の話ではありません)

『凝集Aβに対する光酸素化法の新規AD根本治療戦略としての可能性を示した点で大変意義のある成果です。また光酸素化触媒はアミロイドに共通の立体構造に対して反応し活性化することから、パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症などの、AD以外のアミロイド形成・蓄積を原因とする多くの神経変性疾患に対しても有用である可能性が期待されます。』
・悪い医師
『悪い医師も世の中には沢山います。残念ですがこれは事実です。
“医は仁術”[「医は人命を救う博愛の道である」ことを意味する格言]ではなく、医は算術だと心得ているのです。だから儲かればいいのです。
インフルエンザワクチンが効かないことは知っていますが、儲かるから打ちます。点滴など必要でないことは十分承知していますが、やれば儲かるのですぐに点滴しましょうと言います。
血液検査も1項目か2項目実施すれば十分なのに、10項目でも20項目でも調べます。項目数が多いほど儲かるからです。半年に1回血液検査すればいいものを患者さんが来院するたびに血液をとります。
レントゲン写真など撮らなくていいことを知っているし、放射線は人に危険なことも知っていますが、平気でレントゲンを撮るように指示します。
3カ月か4カ月に1回診察すれば十分なのに、平気で2週間後、1カ月後に来院するように言って再診料を稼ごうとします。
要するに、どれが科学的根拠のある医療なのか知っているのに算術が先にはたらいてしまう医師です。
ところが、このような病医院が患者さんで賑わっているのです。患者さんは、薬を多くもらえれば嬉しいし、検査を沢山してくれれば嬉しいし、レントゲンを撮られて放射線を浴びてもレントゲンを撮って頂きましたと喜んでいるのです。悪い医師を育てているのは患者さんなのです。
何度も申し上げてきましたが、医師の「下げたがり病」が流行っています。これは自分の考えだけが正しいとし、それを患者さんに押しつける医師です。血圧は下げたほうがいい。HbA1cは下げたほうがいい。コレステロールも下げたほうがいいなどの考えを押しつける医師です。
がんの治療には手術をするのが当たり前で、抗がん剤を使用するのも、放射線治療をおこなうのも当たり前ととらえており、それを強要する医師です。
「がんを放置するなどとんでもない。そんな奴は来るな」という医師の言葉に傷つき、泣きながら私の外来に来た患者さんが何人もいます。医師の考えの押し付けにあってがんの手術をしたばかりに、抗がん剤による薬物治療を受けようとしたばかりに、苦しんで苦しんで、しかもあっという間に亡くなった人を沢山診てきました。
そのたびに思います。本当に医師が悪いと……。
血圧も同じです。本当に医師が悪いのです。「下げたがり病」の医師が一番悪いのです。』
・良い医師
『良い医師は人間が生物の一種だときちんととらえています。
そして良い医師は考えます。その医療行為は人間という生物にとって正しいのだろうか、と。まず真っ先にこのことを考えます。そして、最終的にその治療はその患者さんにとって最適な科学的な治療なのかということをつねに考えます。
このように考えるから風邪薬も血圧の薬もみんないらないと気づき、処方しません。検査も最低限の項目で、最低限の回数でおこなうように努力します。不必要なレントゲン検査もしません。
人間という生物をよく心得ていますから、人間という生物の加齢現象のこともきちんとわかっています。不可逆的な変化を起こしている高齢者に若者と同じような薬は投与しませんし、検査もしません。
このように高齢者には高齢者に合った治療があることを十分にわかっているのが良い医師の条件でしょう。患者さんの気持ちも大切にしますが、患者さんにとって悪いことはきちんと説明して、納得してくれるように努力します。
心と身体の関係を熟知した医療をおこなっています。薬を出す前に心が疾病に関与していないかどうかや、運動、食事といったほかの生活の改善ができないかを優先します。
薬による治療は最後の手段と考え、儲かるからとか、ほかの医師もおこなっているからといったことを基準にしません。
そして、落ち込んでいる患者さんを励まします。顔色が少々青くても「グリーンピースは青いほうがいいよ」と言い、足がむくんでいるなら「大根だってみずみずしくていいよ」と励まします。けっしてマイナスの言葉を患者さんに向けることはありません。プラス思考で明るく朗らかに接します。
患者さんに何かを尋ねられたら、ていねいに説明します。けっして怒鳴ったり、不愉快な顔をしたりしません。もちろん医学知識も豊富です。手術も手技も驚くほど上手です。』
ご参考1:加齢による頻尿
最近、夜間頻尿が気になり病院に行こうかなと思っていました。必ずしも加齢が原因とは言い切れないので、一度は血液検査や尿検査をすべきですが、検査の結果、加齢が原因となった場合、どんな薬を飲むことになるのか調べてみました。
すると夜間頻尿の一般的な薬は”抗コリン剤”や”β3作動薬”と呼ばれているもので、アセチルコリンやノルアドレナリンといった神経伝達物質を通じて、自律神経系に働きかけるタイプの薬でした。「夜間頻尿のためにこれはやりすぎなんじゃない?なんか飲みたくないなぁ」というのが第一印象でした。「やっぱり漢方の方がいいのでは」と思い、漢方内科も持たれている個人病院を見つけました。
一方、今回の松本先生の本では、第3章の中の“さまざまな疾患の薬による弊害”の一つに“泌尿器系”について書かれているページがありました。
下記はその中の一部です。
『なぜ夜間の頻尿が加齢現象なのかを説明しましょう。あなたが子供だった頃を思い出していただくといいかもしれません。子供の頃は、夜に疲れてバタンキューと寝たら、12時間でも尿意を感じないまま眠り続けていられましたよね。これは、夜中に尿が作られないように、そのためのホルモンが分泌されていたからなのです。
ところが高齢になると夜間の頻尿を抑えるホルモンが出なくなります。そのため夜に何回もトイレに起きるのです。
繰り返し何度でも申し上げます。加齢による身体の変化は現代の医療ではどうしようもないのです。年をとることには誰も勝てないのです。白髪を若かった頃と同じように黒く戻せないのと同じです。ここのところをしっかり頭に入れてください。』
これを読んで思いました。加齢による夜間頻尿の問題は起きることではなく、起きた後になかなか寝付かれないことではないか。そうだとすれば、自分の場合は問題ないなという結論です。やるとすれば、まずは筋トレなどの運動だろうと思います。
松本先生の「加齢による身体の変化は現代の医療ではどうしようもないのです。年をとることには誰も勝てないのです」というご指摘はとても重要だと思いました。そして、「病か加齢か」、後者だとすれば、薬に頼ることは最後の手段と心得、運動、睡眠、食事を見直すということから考えるべきだと思いました。
※NHK健康チャネル:自分で尿を量る!?夜間頻尿、解決のポイント
痛みの探偵
今回は須田先生の著書である『痛み探偵の事件簿』から、ハイドロリリース(エコーガイド下ファシアハイドロリリース)の有効性を、リアルな医療現場のお話を通して学ぶことができました。特にファシアにご関心のある鍼灸師の先生には大変興味深い本だと思います。
漢方薬については、お医者さんの中にも理解が広がっていると思いますが、残念ながら、鍼灸に関してはまだまだ「胡散臭いもの」という印象ではないかと思います。その意味では、鍼灸を理解いただくためにも“共通言語”は必要であり、そして“ファシア”は多職種連携を進めるための”共通言語”になりえる極めて重要なキーワードだと思います。
ファシアは内臓を含めた全身に広がる膜の組織なので、筋骨格系(整形外科)だけでなく内臓系(内科)の疾病の改善にも関係すると考えています。
※ファシアについては、ブログ:”経絡≒ファシア1”、”経絡≒ファシア12(まとめ)”および”ファシアの基礎”をご参照ください。
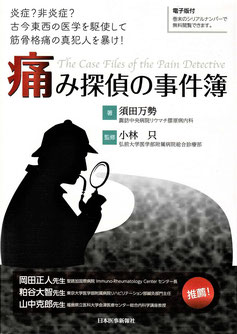
著者:須田万勢
監修:小林 只
発行:2021年10月
出版:日本医事新報社
『高齢化により地域に溢れる疼痛患者を、内科医や総合診療も、もちろん鍼灸師らも、西洋医学も東洋医学も総動員して、多職種が「誠実に」連携しながら、支えていくことが今の時代には求められています。そのためにも、言葉の定義や使い方に非常に慎重になっています。専門領域、多職種間で扱っている言葉の意味がすれ違っていることこそが、「無用の亀裂」を生んでいる現在、ファシアに関する言葉を共通言語とし、「学術的な納得」を基盤に、安全・簡単・低コストで実行できる治療体系を体現することが「政治的な納得」にもつながると信じています。』
目次 (ページ順に変更させて頂いているため、“コラム”がバラバラになっています)
序章「痛み探偵の誕生」
第1回 頸部痛の研究
第2回 膝痛の証明
コラム① エコーガイド下ファシアハイドロリリースの手順
第3回 膝痛の証明パート2
コラム② エコーでの異常なファシアの見分け方
第4回 まだらの腰痛
第5回 第二の瘢痕
第6回 消えた炎症
コラム③ 炎症性疾患の後に、どうして非炎症性の痛みが出るのだろう?
第7回 腱のねじれた男
コラム④ 「ファシア=筋膜」という概念を捨てよう!
第8回 這う女
コラム⑤ X線時代とエコー時代
第9回 悪魔の足
コラム⑥ ワクチン筋注後に生じたFPS!?
第10回 犯人は2人
コラム⑦ 治療方法から考える痛みの分類
第11回 白銀指事件
コラム⑧ 上肢の末梢神経に対する神経テンションテスト
第12回 Dr.写六最後の事件(前編)
第13回 Dr.写六最後の事件(後編)
論考「経絡、経穴はファシアで説明できるのか?」
論考「臨床医の仕事とは?」
ブログは目次の黒字部分ですが「本流に従って」とはいえず、重箱の隅をつつくように、気になった箇所を取り上げています。ご容赦ください。
第2回 膝痛の証明
●変形性膝関節症(OA:osteoarthritis)は非炎症性疾患とされ、メカニカルストレスによる軟骨の摩耗が主病態と考えられてきたが、近年、種々のサイトカインの産生や時に滑膜増殖を伴う炎症性疾患だということが分かってきた。そして炎症を伴うものを“osteoarthritis”、炎症を伴わないものは“osteoarthrosis”と呼んで区別している。
★“osteoarthritis”と“osteoarthrosis”について分かったこと
・日本でも変形関節症には“osteoarthritis”と“osteoarthrosis”の2つがあると認識されていますが、実際は区別されていないようです。『病気がみえる vol.11 運動器・整形外科』にも欄外に以下の補足がありました。しかし、本文にはその説明はなく「変形性関節症」が一つあるのみでした。
また、調べてみると“Osteoarthritis or Osteoarthrosis: Commentary on Misuse of Terms”という記事がありました。詳しい説明が載っており、Google翻訳の力を借りることで何とか理解できました。ポイントは次のようなものです。
『In short, “osteoarthritis” means inflammation of the joint, while “osteoarthrosis” means degeneration of the joint.』⇒『要するに、「変形性関節症[osteoarthritis]」は関節の炎症を意味し、「変形性関節症[osteoarthrosis]」は関節の変性を意味します。』
さらに何かないかと検索していると、北海道大学のPRESS RELEASE、“世界で初めて! 軟骨細胞が関節の炎症を誘導することを発見”を見つけました。これを拝見しても、変形性膝関節症はメカニカルストレスによる軟骨の摩耗(非炎症性疾患/osteoarthrosis)だけでなく、滑膜細胞、さらには軟骨細胞にも関係する炎症性の疾患(osteoarthritis)であり、本来、変形性膝関節症(膝OA)は非炎症性と炎症性の2つに分けることが望ましい、ということだと思います。

右をクリック頂くと、PDF4枚の資料がダウンロードされます。
『自己免疫疾患である関節リウマチ(RA)や炎症性疾患である変形性関節症(OA)病態に大きく関わる関節組織の細胞は滑膜細胞であるとこれまで考えられ、広く研究されてきました。その結果,治療法も進歩してきましたが難治例は未だに存在し,完治が困難な疾患です。
~中略~
本研究では、RA、OAの軟骨細胞において炎症アンプが活性化していることを見出し、さらに炎症アンプ関連遺伝子の一つとして同定されたTMEM147(Transmembrane protein147)が軟骨細胞に発現して、炎症アンプの主要な経路の一つであるNF-κB経路を正に制御していることを初めて明らかにしました。加えて抗TMEM147抗体が、関節炎モデルに対して治療効果を持つ可能性を示すことに成功しました。
このことは、RA、OA治療に対して新たな方向性を示すものであり、治療に難渋するRA、OAの突破口となる可能性があります。』
●縫工筋が膝の痛みの原因になっている可能性がある。
縫工筋は上前腸骨棘(腰部)から起始し、鵞足となって脛骨の前内側面(膝部)に停止する人体で最長の筋線維を持つ筋である。その筋線維の走行の途中でいろいろな構造物と交差する。特に縫工筋の深層に内転筋管(Hunter管)があるが、この管は内側広筋、大内転筋および両筋の間に張る結合組織性の広筋内転筋膜によって囲まれる三角柱上のスペースで大腿動静脈と伏在神経(大腿神経の分枝)が通っている。

画像出展:「経絡マップ」
縫工筋の近くには体幹の近位と筋腹中央に、”髀関[ヒカン]”と”箕門[キモン]”というツボ(経穴)があります。
髀関(胃経):上前腸骨棘と膝蓋骨底外端とを結ぶ線上で大転子の頂点の高さ。股関節と膝をわずかに外転し、大腿前内側に加えられた抵抗に抗したとき、三角形の陥凹が現れる。
箕門(脾経):膝蓋骨底内端と衝門(鼡径溝)を結ぶ線上、衝門から1/3のところ、大腿動脈拍動部。
なお、下の図は左がツボと動脈、右がツボと神経です。

画像出展:「経絡マップ」
縫工筋の膝周辺(鵞足)部位には、”陰包[インポウ]”と”曲泉[キョクセン]”というツボがあります。
陰包(脾経): 大腿部内側、薄筋と縫工筋の間、曲泉の上方、膝蓋骨底の上方4寸の高さ。股関節をやや屈曲・外転・外旋させ、筋を緊張させると縫工筋が明確になる。
曲泉(肝経): 膝内側、半腱・半膜様筋腱内側の陥凹部。膝窩横紋の内側端。

画像出展:「骨格筋の形と触察法」
左下方に縫工筋があります。縫工筋の筋連結は大腿筋膜張筋だけですが、大腿筋膜張筋は縫工筋だけでなく、大殿筋、中殿筋、腸骨筋、外側広筋と筋膜で連結しています。
★縫工筋と膝痛について分かったこと
①膝関節に付着する鵞足は縫工筋、薄筋、半腱様筋の3筋からなり、下腿の外旋に対して拮抗する働きによって、膝関節を安定させている。
②O脚の人は靴底の外側が薄くなる。これは外側重心を示している。また、股関節は外旋し縫工筋はオーバーユースになりやすく、機能低下が進むと機械的ストレスが強い付着部(鵞足)に炎症を起こしやすい。
③筋連結から考えると縫工筋は大腿筋膜張筋と筋膜でつながっている。さらに大腿筋膜張筋は縫工筋以外に、大殿筋、中殿筋、腸骨筋、外側広筋とも筋膜でつながっている。これを考慮すると、膝近位部だけでなく大腿筋膜張筋近傍の体幹近位部も重要である。また、縫工筋は上前腸骨棘(腰)から脛骨粗面内側(膝)につながる非常に長い筋なので筋中央部も無視できない。
●以上3点からツボ(経穴)を考えると、体幹近位の“髀関”、筋中央の“箕門”、そして“曲泉⇔陰包”の膝関節内側部に注目し、触診により硬さを感じる部位に刺鍼するのが第一選択と考えます。
第4回 まだら腰痛
●脊柱起立筋に圧痛があっても、坐位での動作分析で後屈・側屈・回旋のいずれも目立った痛みがみえず、立位の動作のみで痛みが誘発される場合は、原因筋は脊柱起立筋のような腰部の筋肉ではなく大殿筋や中殿筋の関与が疑われる。
★気づいたこと
腰部の筋か殿部の筋かどちらが患者さんにとって重要な原因筋かを判断する時に、坐位と立位に分けて動作分析(後屈・側屈・回旋)を行う方法はとても重要だと思います。是非、取り入れたいと思います。

画像出展:「人体の正常構造と機能」
右の図は表層の大殿筋と、大殿筋の下にある中殿筋を取り除いた、この2筋の下層にある筋群です。中殿筋の下方に小殿筋、仙骨と大腿骨をつなぐ領域に、梨状筋、上双子筋、内閉鎖筋、下双子筋、大腿方形筋の5筋(番号付き)があります。
第7回 腱のねじれた男
●『「3カ月前発症の関節リウマチで、投薬により関節炎は寛解している61歳男性で、右第2指の屈曲時に痛みを伴う可動域制限があり、身体所見やエコーで明らかな炎症・弾撥指は同定できない」。』
この症例に興味をもったのは、加齢とともに手指関節の動きの悪さなどの違和感を訴える患者さまはめずらしくなく、問題の関節周辺や指の動きに関わる上腕の筋肉などに注目した施術を行っていますが、肩、腰、膝などの部位に比べ、施術方針に迷うことがあるためです。
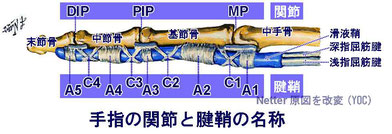
こちらの画像は長野県にある湯本整形外科さまのサイトより拝借しました。
これを拝見すると、根元がA1でA5まであることが分かります。
★気づいたこと
この写真を見て思い出しました。「大切なことは、患者さんの気になっている箇所およびその周辺を丁寧に触診する。さらに必要であれば関節を動かして動的にも観察し、徹底的に触診する」ということです。これは代々木(日本伝統医学センター)の相澤先生から教わっていた基本中の基本ですが、あらためてその重要性を再認識しました。
なお、本書の登場人物である“Dr.写六(詳細な病歴、身体診察に加え、エコーと東洋医学的診察でクールに痛みの原因を特定する、自称「痛みの私立探偵」)”は次のようにお話しています。
『今まで「非典型的」な腱鞘炎だの弾撥指だのドケルバン病だのといわれていた患者が、実はファシア異常であることは多く経験するよ。ぜひエコーで動的評価を含めてくまなく調べてほしいものだ。』
第9回 悪魔の足
膝痛
●患者さん
・86歳女性
・関節リウマチで5カ月前に生物学的製剤を始めて2ヵ月。炎症のコントロールはできていたが、1ヵ月前から立位時の右膝痛が再燃した。
●症状
・椅子からの立ち上がる動作が最も痛い。
・体を動かした時にズキッとして痛みがある。
・腫脹や熱感はない。
・右関節裂隙に圧痛があるが、疼痛の最強点は裂隙ではなくやや膝蓋骨寄りである。
●問題個所
・内側膝蓋大腿靭帯(MPFL)
-MPFLは1957年の膝関節の論文に“横走支帯靭帯”という記載があり、その後1990年代以降にMPFLの解明が進んだ。MPFLは膝蓋骨の外側制動に関わるとされ、膝屈曲20~90°の範囲で膝蓋骨の外側移動を制御している。
●考えられる原因
・O脚のため膝関節軽度屈曲、股関節外旋位の状態で歩行することになり、膝蓋骨を制動するためにMPFLがオーバーユースになる。
●疼痛再発の原因
・関節炎が起きて関節液がたくさん溜まっているときは、膝蓋骨が大腿骨膝蓋溝から浮くので膝蓋骨に無理な力が掛かりにくいのかもしれない。今回の例では関節炎が薬により急激に軽快したことで関節液が減少し、膝蓋骨を支える靭帯、特にMPFLが張力の変化に適応できず、傷みだした可能性がある。
これは膝のいわゆる「水抜き」で良くなる人と、逆に悪化する人がいることに似ているように思う。
●診断治療
・MPFLに対するハイドロリリース(エコーガイド下ファシアハイドロリリース)により、MPFLに重積したファシアをバラバラにする。筋膜ほどではないが、靭帯もファシアなのでハイドロリリースが有効である。
・腫脹や熱感はない。
・右関節裂隙に圧痛があるが、疼痛の最強点は裂隙ではなくやや膝蓋骨寄りである。
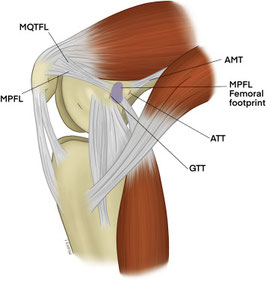
画像出展:「ScienceDirect」
MPFL:内側膝蓋大腿靭帯、AMT:大内転筋腱、MQTFL:内側大腿四頭筋腱大腿靭帯、GTT:腓腹筋腱結節、ATT:内転筋腱結節
”Patellar dislocation is a common knee problem, 10 times more frequent in childhood and adolescence. Medial patellofemoral ligament is injured up to 94% of the time, and its reconstruction is effective in terms of stabilization of the patella.”
⇒”膝蓋骨脱臼は一般的な膝の問題であり、小児期および青年期に10倍頻繁に発生します。MPFL(内側膝蓋大腿靭帯)は最大94%の確率で損傷しており、その再建は膝蓋骨の安定化の観点から効果的です。”
★気づいたこと
・”膝蓋骨脱臼”と”オーバーユース”を比較することには無理があると思いますが、膝蓋骨に対するメカニカルストレスがMPFL(内側膝蓋大腿靭帯)に影響を与えることは確かだと思います。
・「第7回 腱のねじれた男」同様、よく観察すること、そしてよく触ること(触診すること)がとても重要です。
第13回 Dr.写六最後の事件(後編)
●ファシアと経絡の共通点
・注射針を刺入した部分の筋肉がピクッと動く現象(局所単収縮[LTR:local twitch response])も、鍼による得気感覚(「ツボ」に当たったときにズーンと感じる響き感)も、局所の刺激に対する過敏性が共通病態として理解されている。
・病的なファシアにはサブスタンスP(痛みを誘発する物質の代表)に反応する自由神経終末が多く分布しており、経穴もまた周囲組織と比べて自由神経終末の密度が高いと報告されている。
Zhag ZJ, et al:Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 429412
上記の論文のタイトルは、“Neural Acupuncture Unit: A New Concept for Interpreting Effects and Mechanisms of Acupuncture”(“神経鍼ユニット:鍼の効果とメカニズムを解釈するための新しい概念”[Google翻訳])です。
【神経鍼ユニット】が論文の中核といえますが、冒頭には次のような説明がされています。
”The collection of the activated neural and neuroactive components distributed in the skin, muscle, and connective tissues surrounding the inserted needle is defined as a neural acupuncture unit (NAU).”(”挿入された針を取り巻く皮膚、筋肉、および結合組織に分布する、活性化された神経および神経活性成分の集合は、神経鍼ユニット(NAU)として定義されます”[Google翻訳])

画像出展:「人体の正常構造と機能」
自由神経終末(左端)に関しては次のような説明がされています。
『自由神経終末とは感覚神経線維の末端が特別な装置を持たずに終わっているものをいい、全身の結合組織に存在する。皮膚では、真皮の神経叢から出る多くの枝が、真皮や表皮の細胞間で自由神経終末として終わる。自由神経終末は、人体にダメージを与える熱や機械的・化学的刺激を感受する侵害受容器があり、痛覚に関わる。また、あるものは温度受容器として働く。求心性線維は無髄[C線維:0.2~2m/秒]または、小さい径の有髄線維[Aδ線維:10~30m/秒]で、伝導速度は[Aβ線維、Aα線維に比べて」遅い。』
追記(2022年12月16日):鎮痛薬のNSAIDで膝関節症が悪化?

CareNetさんから送られてくる情報の中にびっくりするような情報があったので、お伝えします。以下は冒頭の部分になります。
『変形性膝関節症に対し、一般用医薬品(OTC医薬品)としても販売されているアスピリンやナプロキセン、イブプロフェンといった鎮痛薬を使用しても、進行を遅らせる効果がないばかりか、むしろ悪化させる可能性もあることが、米カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)のJohanna Luitjens氏らの研究で示された。この研究結果は、北米放射線学会年次学術集会(RSNA 2022、11月27~12月1日、米シカゴ)で発表された。』
※補足:NSAIDとは、非ステロイド性抗炎症薬であり、胃などの消化器等への副作用が懸念されており、腎臓病の患者さんは禁忌とされています。痛み止めとして浸透していますが、処方には注意が必要な薬とされています。
慢性痛の科学5
Ⅳ 記憶のメカニズム
2.海馬では日々、ニューロンが新生している
・海馬の中で最も注目されている海馬前部とは、歯状回、CA1野、CA3野、嗅内皮質、海馬支脚などを含む部位である。
・海馬前部が注目されている理由は2つある。
1)新生ニューロンが海馬前部で日々誕生しているということ。脳には幹細胞が存在していて、ニューロンの増殖、分化、成熟が起きている。
2)アルツハイマー病の初期に脳萎縮が始まるのは、海馬前部、海馬傍回、嗅内皮質などである。
3.新生ニューロンが記憶機能を担う
・新生ニューロンの生育、成熟には、生理活性物質が必要である。それらはBDNF(脳由来神経栄養因子)、FGF-2(線維芽細胞成長因子-2)、IGF(インスリン様成長因子)、VEGF(血管内皮成長因子)などだが、新生ニューロンはこれらの生理活性物質を浴びて成長し、成熟した既存の神経細胞層を探り当て、結びついて記憶機能を担っていく。特に、BDNF、FGF-2などが十分にない環境では、ニューロンの成長は衰えてしまう。つまり、海馬ニューロンの成長は、骨格筋を動かしてBDNF、FGF-2を分泌させているか否かにかかっている。
・動物を用いた研究では、ニューロンの新生と成長には、自発的な運動の他に、好奇心を満たす刺激や仲間との接触などの環境が効果的であると報告されている。
4.高齢者の脳と記憶力
・高齢者の脳でも新生ニューロンは誕生している。生育・成熟できれば記憶機能を担うことができる。ただし、そのためには筋運動が必要である。
・ピッツバーグ大学、Ericksonグループの運動器活動と記憶力との関係の研究の一つは以下の通りである。
-『健常な高齢男女120人を対象に、半数(n=60、平均67.6歳)には週3回の有酸素運動(ウォーキング、最長40分)を残り半数(n=60、平均65.5歳)には、週3回のヨガ、ストレッチ、バランス運動などを1年間継続させ、海馬の体積と、血清中のBDNF量、空間記憶力を測定している。1年後に海馬体積を計測したところ、有酸素運動群では、左、右の海馬体積がそれぞれ2.12%、1.97%増加していることがわかった。
「たった2%か?」と思われたであろうか? 放っておけば、海馬体積は毎年1~2%の割合で減少し、増加することなどあり得ないと思われる年齢層である。体積が増加したことは、加齢に伴う萎縮を2年間分くらい取り戻した勘定になる。
有酸素運動群では、図7-10に示すように、海馬の体積増加に比例して、酸素摂取量、血清中のBDNF量、空間記憶力が、右肩上がりに増加していた。
有酸素運動群の被験者は、初週5分間の歩行からスタートし、1週ごとに5分ずつ歩行を延長して、最長40分間の歩行を最大心拍数(HR)の50~60%で行い、さらに第8週以降は、HR60~75%に近づけるようにと指示されていた。ちなみに運動生理学でHR60%とは、最大酸素摂取量の約50%に相当し、額に汗が滲んでくる程度の運動を指している。さまざまな生理活性物質が、血流に乗って各臓器に輸送されるためには、最低20~30分間の運動持続が必要で、これ以下では、運動による多臓器の統合反応が得られないことがわかっている。
他方、ヨガやストレッチの運動群の効果は、左右の海馬体積はマイナス1.40%、1.43%を示していた。血清中のBDNF量は低下し、空間記憶力も低下していた。
調査開始前には、両群被験者の海馬体積はほぼ同じで、差はなかった。実験結果は、有酸素運動の1年間継続という運動量の差が、海馬の体積増加と記憶力向上をもたらすことを示していた。ヨガ・ストレッチ群でも、週3回の筋運動を1年間続けたが、海馬体積は増加していない。ヨガ・ストレッチは効果がないという意味ではなく、筋運動量負荷が少なすぎて、海馬体積増をもたらさなかったためであろう。
この研究を改めて検証すると、有酸素運動によって体積増加があったのは海馬前部だけであって、海馬後部の体積は増加していなかった。体積を海馬前部だけに絞って比較すると、左は3.38%、右は4.33%も増加していたのである。
海馬歯状回の顆粒細胞層下帯では、新ニューロンが日々誕生している。海馬体積の増加は、ニューロン新生の促進を示唆しており、有酸素運動習慣が記憶力の向上をもたらすことを示している。』
5.認知と筋運動
・筋運動が認知機能低下を防ぐことは、多くの研究によって検証され、米国では各地の医療機関による大規模疫学調査が数多く行われている。下記はその一つ、Mayo大学で行われた疫学調査である。
-『調査では、1,324人の男女(70~93歳、平均80歳、認知機能の健常な市民1,126人と、軽度認知障害(MCI、198人)を対象に、筋運動習慣の有無がMCIの発生にどの程度関係するかが調べられた。
各被験者について、人生のmid life期(50~69歳)、late life期(70~93歳)に、どの程度の筋運動習慣があったかを、各自から履歴を聞きとってMCIのodds rateを算定する手法がとられている。その結果、MCIはmid life、late lifeを通じて運動習慣がまったくない生活様式であった人に発生率が高く、mid life期に中程度の運動習慣があった場合は、MCIのodds rateが39%少なく、late life期に運動習慣があった場合は32少ないことが示された。
上記は疫学調査の常として、大雑把な傾向を捉えているに過ぎない。しかし、重要な指摘を含んでいる。認知機能を健常に保てるか、MCI段階に達してしまうのかの分かれ目は、50~60歳代の筋運動習慣にあることを示した点である。また、MCIの発症を防ぐには強度の筋運動は必要なく、運動習慣の有無が大きな影響を持つことも示している。これは示唆に富んだ調査結果といえよう。』
6.海馬萎縮の原因
・海馬体積は、働き盛りの健常な成人脳ではほぼ一定であるが、高齢期に入ると毎年1~2%の割合で減少する。
・海馬、嗅内皮質の萎縮が大きい場合は、MCIに移行する危険性が高いと考えられている。
・海馬細胞は微小脳循環の不良や低酸素によっても傷つきやすい。
・海馬萎縮を招く要因は、頭部外傷、高血圧、睡眠時無呼吸症候群、PTSD、うつ病などである。また、慢性炎症を基盤とする疾患(糖尿病、肥満、アテローム性動脈硬化症、パーキンソン病など)によっても海馬体積は減少する。
7.記憶には反復と睡眠
・海馬のニューロンシナプスでは、反復刺激されると長期増強(LTP)現象が起きて、シナプス統合が強化され可塑性が増大する。興奮性が増大して信号の伝達効率が高くなり、タンパク質の生成反応に裏付けられて、長期に記憶痕跡が形成される。そして何かのきっかけがあった瞬間、強化シナプスが活性化して想起させる。
・睡眠中には様々な記憶情報が再現され、整理され、重要と思われる情報から優先的に転送されると考えられている。
・脳の代謝老廃物AβやTauは睡眠中に排出されることが分かっているが、睡眠と記憶の関係はまだまだ未解明な部分が多く、今後多くのことが明らかになっていくだろう。
Ⅴ 高齢者とサルコペニア
1.サルコペニア―死のリスク
・サルコペニアとは、高齢者の骨格筋量の減少と筋力低下の病態のことである。
・サルコペニアは若者の廃用性筋萎縮とは異なり、骨格筋の萎縮が不可逆的に進行する。
・サルコペニア発症の原因は、加齢に伴う衰弱、全身の慢性炎症、インスリン抵抗性、内分泌系の機能低下、低栄養などである。
・サルコペニア発症の具体的なきっかけとしては、大腿骨近位部骨折や腰椎圧迫骨折などによるベッドでの安静、腹部がん手術や独居高齢者にみられる低栄養、うつ状態や認知症による引きこもりなどである。
2.サルコペニアの診断
・欧州サルコペニアワーキンググループ(EWGSOP)では、歩行速度、筋量、握力をサルコペニアの診断指標としている。
①65歳以上の高齢者で、寝たきりであり、独りで椅子から立ち上がれない。
②歩行速度が0.8m/秒以下である。
③握力が一定しない。
④二重エネルギーX線吸収法(DXA)で測定した筋量が基準値に達しないこと。
・日本人のサルコペニア評価については、全身のDXA測定値から割り出した骨格筋指数や、日常生活の動作(立ち上がり、歩行、昇段)に要する筋力値などの参考値がある。
・米国では筋運動と予防、回復に関する大規模調査が行われている。
-『70~89歳の衰弱した被験者が調査対象になり、400mくらいならどうやら15分以内に歩ける、という歩行能力の限界を基準にして調査が行われた。対象者に対し、週に150分間の歩行やバランス運動を2.6年にわたって実施した結果、自力では動けない自立障害者の発生率が、運動群(818人)では、30.1%で、運動しなかった対照群(817人)より5%低かったと報告されている。
この調査で被験者を選定した基準が、「400mを15分以内で歩けること」であったこと自体、ため息が出る数値であるが、わずか1~2週間の筋運動不足で驚くほど歩行困難に陥るのが高齢者である。この研究では、筋運動実施とその効果を調べるために、多数の医師や研究者が州をまたいで動員されている。しかしリハビリテーションの介入は、筋萎縮がそれほど進行していない初期段階にこそ望ましいと、限界を示す結果となった。筋の衰弱が進行してからの回復は、これほど困難なのである。』
・米ソルトレーク大学では60~75歳の健常な被験者を対象に、ベッド安静による下肢の筋量と筋強度の低下を、若年被験者(18~35歳)と比較する実験を行っている。
-『高齢の被験者群では、5日間のベッド安静継続だけで筋量と筋強度が低下し、リハビリテーション(筋運動強化と栄養付加)を施しても、筋の回復度は小さく、実験前のレベルに復するのに日数を要した。日常生活を送るのに支障ない生活自立者であっても、60~75歳での5日間ベッド安静では、筋タンパク質分解の他に慢性炎症も加わっている。』
3.サルコペニアの機序
・サルコペニアの機序は、「廃用性筋萎縮の機序」に「テロメアの短縮を伴う老化の機序」が重なって起こると考えられている。
-骨格筋の筋タンパク質生成に関与するのは、筋運動時に発現する共活性因子である。代表的な転写調節因子は、PPAR-γと、その共活性因子PGC1-αである。PGC1-αは骨格筋が収縮すると発現する。そして筋線維遺伝子の転写・翻訳が進行すると、筋線維タンパク質が生成され、筋線維の数が増加し筋量が大となる。
-筋を非動化し、筋紡錘を機能させない状態にすると、脊髄の運動ニューロンの活動が低下し、筋収縮は起きずPGC1-αは発現しない。従って、筋タンパク質の分解量が大となり、筋量や筋力が低下する廃用性筋萎縮が起きる。
-テロメアの長さは老化を反映する指標であるが、慢性炎症がある場合も短縮するので、若い人でも短くなることがある。テロメア機能が低下すると、p53(転写活性制御因子:遺伝子の発現調節、細胞周期停止、アポトーシス制御、抗腫瘍活性、DNA修復、血管新生抑制、細胞増殖の制御、ゲノムの安定化、宿主免疫制御など、重要かつ多彩な生理機能を誘導する)が働いて、筋細胞の増殖とDNA複製を停止させる。停止によってDNAが修復されれば細胞周期は回復するが、修復できなければアポトーシスが起きる。
-サルコペニアの機序には、遺伝子多型などの要因、サテライト幹細胞、低栄養も大きく関与しているが、下記の図では複雑になるので省略されている。

画像出展:「慢性痛のサイエンス」
サルコペニアは廃用性筋萎縮の機序aと、老化の機序bが重複して生じる。
a:骨格筋はミトコンドリアを多く含むがゆえに活性酸素種(ROS)の害を受けやすく、PGC1-α発現がないとROS害を抑制できない。傷ついた筋細胞に対し、マクロファージがインフラマソームを形成し、炎症性サイトカインを放出する慢性炎症が拡大する。筋量と筋力が激減し筋収縮エネルギーが低下する。筋萎縮遺伝子によっても、筋タンパク質分解が進行する。
b:aで生じた慢性炎症がテロメアを傷つけ短縮させる。テロメア機能が低下すると、p53が働き、筋細胞にアポトーシスが誘導される。P53が働くときはPGC1-αは発現が抑えられるので、筋細胞は回復できず、老化が加速されていく。
・以上のように、廃用性筋萎縮の機序と老化の機序の2つにより、サルコペニアに至ると考えられている。慢性炎症が老化を早めることは臨床上も報告され、高齢者では慢性疾患が1つあるだけで、多臓器の老化やサルコペニアが加速される。
・『サルコペニアの治療法には運動療法、抗炎症薬、栄養強化の試みなどがある。幹細胞を用いた筋組織再生の研究も始められているが、臨床応用が軌道に乗るにはかなりの年月が予想されている。高齢者は膝や腰に少し痛みがあるだけで、歩行を極力避ける日常になる。わずかの期間の筋活動の不足で、驚くほどの歩行困難に陥ることを考えると、高齢者向け筋力トレーニングが十分に理解され、栄養面を含めた早期からの予防策が、社会に普及することを願わずにはいられない。』
終章
2.快・不快情動に焦点を当てる―今後の医療の根幹
・痛みが難治性疼痛に転化してしまうか、回復して静穏な日常に復するか、最初の分かれ道はごく小さいところにある。
-「この痛みは辛い、しかしきっとよくなる」、「乗り越えられる」と捉えるか、「自分は絶対に助からない」、「手術療法も薬物療法も、もっと悪い結果を生むに違いない」と捉えるかは、一瞬の小さな違いのように思える。しかし、負情動と快情動の回路網のバランスはここで崩れ、それが長期に続けば、やがて脳の機能と構造に変化が起きてくるのである。
・プラシーボ鎮痛は「鎮痛効果があるに違いない!」と期待することだが、期待した瞬間、皮質下にある諸神経核が一斉に活動を始める。中脳の腹側被蓋野からはドパミンが、前帯状皮質や辺縁系の神経核からはオピオイドが分泌され、脳幹では下行性疼痛抑制系の神経核が活性化している。これら皮質下の神経核の働きは無意識下で起きている。
・たとえわずかであっても、心に期待や希望を抱くとき、中脳辺縁ドパミン系(mesolimbic dopamine system)は刺激され、根源的な生に向けて本能行動が活発化する。情動脳も、生存脳も、活発に動き出す。快情動→意欲→行動→期待のサイクルが循環すると、生命活動や創造意欲は盛んになり、これは次の行動を起こすモチベーションとなり、脳活動はさらに活発になる。希望と期待を抱くだけで、精神と身体の機能は確かに蘇るのである。
・絶望の極致から這い上がる力を与え得るのは、希望だけである。「希望が脳を作る」と言われる。
・プラシーボ効果は薬や注射だけでなく、祭祀も、経典の詠唱も、教会の讃美歌や礼拝も、脳回路網を活発に動かす。医師や医療従事者の言葉と表情は、特に大きな影響を与えるようである。自殺未遂を繰り返していた線維筋痛症患者が、“今度の担当医は自慢の息子にそっくり”と、全幅の信頼を寄せて以来、認知行動療法と薬物療法が効を奏して、奇跡的な快復を遂げた例もある。
・プラシーボは偽薬と訳されたため、あまり良いイメージではないが、プラシーボは我々自身の脳の働きといえる。中脳辺縁ドパミン系は渇望や、生きる意欲をかき立てる快の情動系であるが、側坐核を介して、思考や認知機能を担う前頭皮質の回路網と結びつき、「自己優越性の錯覚」も確立させている。
・「自分は優秀で強者である」という優越性を“錯覚”することは、精神の健康を保つうえで重要である。この錯覚によって人は自己の未来の可能性を信じ、自尊心を持ち、希望や目標を持って前進する自分を優秀であると自己評価したとき、脳内ではドパミンの分泌量が急増する。
・『ほんのわずかな希望や期待であっても、快情動→意欲→行動→期待のサイクルが循環し出せば、精神と身体の機能は甦ることを忘れないでいただきたい。』
3.人は希望によって生きる

画像出展:「慢性痛のサイエンス」
『パンドラが蓋を取って中を覗くと、瓶の中からおびただしい災禍(肉体的なものでは痛風、リウマチ、疝痛が、精神的なものでは嫉妬、怨恨、復讐など)が飛び出して、遠くまで拡がってしまった。パンドラはあわてて蓋を閉めたが、すべての禍はもう飛散してしまった後であった。しかし瓶の底に1つだけ残っていたものがあった。それは希望であった。
今日まで、私たちがどんな災難に遭って途方にくれたときでも、希望だけは決して私たちを見棄てることはない。そして私たちが希望を失わない限り、いかなる不幸も私たちを零落させ尽くすことはない。』
―“The Age of Fable” (Thomas Bulfinch)―
慢性痛の科学4
第7章 神経変性疾患と慢性炎症
Ⅰ パーキンソン病
5.パーキンソン病:発症を源にさかのぼる
・ドイツ神経内科医のKlingelhoefer等は、パーキンソン病の予兆は運動症状が出る10年数年前に、頑固な便秘や嗅覚障害の形で起きていることを指摘し、「パーキンソン病は腸と嗅球から始まる」と2015年に結論している。
・パーキンソン病が腸の動きと密接に関係することは、1960年代から続けられた大規模疫学調査(Honolulu Heart Program)で既に報告されている。Abbott RD, Petrovitch H, White LR, et al: Frequency of bowel movements and the future risk of Parkinson’s disease. Neurology 57: 456-462, 2001
この調査では、疾患のない健康な男性6,790人が対象に選ばれ、各自の健康状態を24年間にわたって追跡記録する方式で記録が行われている。その中でパーキンソン病を発症した96人の被験者について、どんな症状が初期にあったかが調べられた。96人全員に共通した最初期の症状は、頑固な便秘と嗅覚障害であり、睡眠障害とうつ状態がそれに続く症状であること、平均して12年後にパーキンソン病の運動症状が現れていることがわかった。この調査結果は、鋭い指摘をしていたにもかかわらず、便秘はパーキンソン病の1症状に過ぎないと解釈されたため、埋没してしまった。
1997年に、パーキンソン病の病因と考えられる異常構造タンパク質α-シヌクレインについて研究が始まり、研究の進展とともに、腸の働きがいかに脳と深く関係しているかが明らかになって、Klingelhoefer等の調査結果が再評価された。
・パーキンソン病の責任病巣は黒質緻密部(SNc)であると長年考えらえてきた。しかし黒質緻密部の変性・脱落より10数年前にさかのぼると、腸には頑固な便秘という形で異変がすでに起きており、α-シヌクレインの凝集は腸神経、嗅球、顎下腺で確認されていた。腸は自律神経を介して脳と連絡している。延髄の迷走神経背側核にはα-シヌクレインの凝集が生じており、この凝集はさらに脳幹に進んで、中脳の黒質に達することが報告されている。

画像出展:「慢性痛のサイエンス」
①何らかの環境因子が引き金となって、腸内や嗅球にα-シヌクレイン凝集が起きる。
②凝集は自律神経を介して延髄の迷走神経背側核に伝播され、さらに上位脳に伝播される。
③Lewy小体に対する脳内グリアによる慢性炎症が進行し、神経細胞が徐々に変性・脱落する。これに伴って非運動症状、運動症状が起きると考えられている。
Ⅱ 慢性炎症と疾患
・パーキンソン病、アルツハイマー病、変形性関節症(OA)、サルコペニア[加齢や疾患により筋肉量が減少し、全身の筋力低下が起こること]は、慢性炎症によって疾患が引き起こされている。
・慢性炎症とは全身にくすぶり続ける低程度の炎症で、発熱も発赤も腫脹もほとんどない。しかし、気づいた時には致死的なダメージに至る反応系である。それゆえ、「万病の源」と呼ばれている。
・パーキンソン病、アルツハイマー病、変形性関節症(OA)、サルコペニア以外、慢性炎症を基盤とする疾患には、2型糖尿病、慢性肺疾患、アテローム性動脈硬化症、大腸がん、前立腺がんなどがあるが、病気を引き起こしているのは、ごくごくありふれた免疫細胞である。
1.免疫細胞とインフラマソーム
・慢性炎症を起こす主役は、マクロファージ、グリア、樹状細胞、白血球、血管内皮細胞など、自然免疫系の細胞である。
-パーキンソン病やアルツハイマー病は主に脳内グリアが関与している。
-2型糖尿病、変形性関節症、サルコペニアは主にマクロファージや樹状細胞が関与している。
・自然免系の細胞は、Nod-様受容体(NLR)を有し、DAMPs(傷害関連分子パターン)とPAMPs(病原体関連分子パターン)をパターンで検出している。
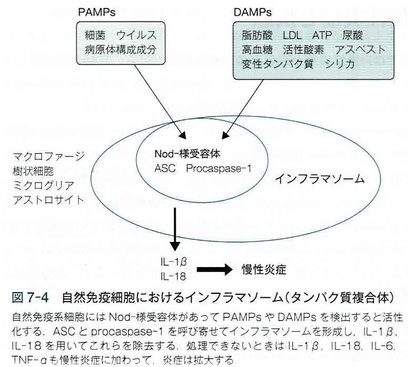
画像出展:「慢性痛のサイエンス」
PAMPs:細菌、ウィルス、病原体構成成分など
DAMPs:LDL、ATP、尿酸、高血糖、活性酸素、アスベスト、変性タンパク質、シリカなど
インフラマソーム:危険物/異物や病原体を排除するための分子装置
・『DAMPs(傷害関連分子パターン)には、LDLコレステロール、ATP、飽和脂肪酸、活性酸素、高血糖、尿酸、セラミド、アスベスト、シリカ、小胞体に正しく折り畳まれない異常タンパク質などが該当し、PAMPsには、細菌、ウィルス、病原体の構成成分などが該当する。
免疫細胞はDAMPsやPAMPsを検出すると緊急体勢に入り、図7-4のように、ASCやprocaspase-1を呼び寄せて、インフラマソームというタンパク質複合体を形成する。危険物/異物や病原体を排除するための分子装置である。
まずcaspase-1が活性化して、IL-1βとIL-8の前駆体を、成熟型のIL-1βとIL-8に変化させ、DAMPsやPAMPsに向けて放出する。危険物/異物や病原体がこれによって除去されれば、炎症反応は終了する。
しかし処理しきれない場合は、IL-6、THF-αなどの炎症性サイトカインも追加動員されて、炎症は拡大する。炎症が長期に進行している部位では、免疫細胞が顕著に集積して、組織の破壊、血管の新生、組織のリモデリング(線維化)などが、数か月から数年にわたって潜在的に進行していく。
壊死した細胞から出た、ATPやDNA、RNA、滲出した血漿グロブリン類などが二次的、三次的にDAMPsとなるため、炎症反応はカスケード状[連鎖的]に拡大し、不可逆的に進行する。炎症の矛先は重要な組織や臓器にまで及んでしまい、結果として致死的な病態に達する。
臨床上でも、体内のIL-1β、IL-6、IL-8、TNF-αなどが長期にわたって高レベルであるときは、各種のがん、神経変性疾患などの発症と関連すると報告されている。』Hotamisligil GS, Shargill NS, Spiegelman BM: Adipose expression of tumor necrosis factor-alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance. Science 259: 87-91, 1993
2.慢性炎症は万病の源
・慢性炎症で注意すべきは、炎症の矛先が自身の細胞代謝にも向けられる点である。
-飽和脂肪酸、LDLコレステロール、ATP、高血糖、尿酸などは代謝産物である。
-異常タンパク質とは、アミロイド-β(Aβ)、α-シヌクレイン陽性のLewy小体などである。
・脳の代謝老廃物は、健常者では睡眠中にかなり排出され、アミロイド-βなどの沈着は少なく保たれ管理されているが、高齢期になると働きが低下する。
・『かつて医療の主体は、感染症との長い闘争であった。しかし美食と飽食の現代では、生活習慣病との格闘に移っている。内臓脂肪はわれわれが体内に溜め込んだ「内なる敵」である。ある日、トロイの木馬さながらに狂暴な反応で、われわれの体に逆襲ののろしを上げてくるのである。
以上、ありふれた免疫細胞による局所的な微小炎症が、最終的に全身に致死的な病態を作り出すことを記述した。
誤解を避けるために、ここで非肥満体の内臓脂肪について言及しておきたい。メタボリック・シンドロームの概念が社会に浸透して以来、脂肪と言えば悪、と受け取られている。しかし、非肥満体の内臓脂肪は、慢性炎症など起こしていないのである。非炎症性マクロファージM2が常在していて、抗炎症サイトカインのIL-4、IL-10、NOを生成するアルギナーゼを生成している。炎症を抑制する側で働き、食餌から得たエネルギーを細胞内に蓄積し、飢餓に備えているだけである。』
3.慢性炎症の抑制
・インフラマソームと過剰な炎症を抑制する薬物に関して、生命科学、分子生物学、分子薬理学など、多領域にわたる基礎研究が進んでいる。すでに候補はいくつか挙がっているが、完全に抑制する薬物は開発されていない。
・薬物の研究を通じ、われわれの体内には炎症を抑制する物質があることが明らかになった。それは、筋運動時に発現する転写調整因子PPAR-γと、その共活性因子PGC1-αである。
Ⅲ 認知機能障害
1.アルツハイマー病
・アルツハイマー病における脳細胞の変性や脱落は、側頭葉内側(嗅内皮質、海馬、海馬傍回などを含む部位)から始まる。患者の行動や心理的な症状を、脳画像上の灰白質密度減少との関係からみると、fMRI画像で側頭葉内側の体積低下が顕著なときは、記憶障害が顕著になり、抑うつ傾向が現れる。
・アルツハイマー病では頭頂葉も後頭葉も萎縮が及ぶ時期に一致して、感情鈍麻や妄想の症状が現れ、思考、判断、意思決定、認知などの高次機能が障害されて、人格が崩壊していく。
・特徴的に現れる症状は、アパシー(感情鈍麻、情動麻痺、動機を持った行動の欠落など)、妄想(パラノイア的な錯覚、被害妄想や誇大妄想、注意欠陥など)、うつ状態の3つである。
2.脳の時限爆弾AβとTau
・アルツハイマー病の病理の特徴は、アミロイドβ(Aβ)と呼ばれるペプチドの沈着と、神経原線維Tauの凝集が脳細胞にみられることである。
・健常者では脳組織中の代謝老廃物は、睡眠中に脳脊髄液中に排出され、血流に乗って除去されている。Rochester大学のNedergaard等は、脳には老廃物を排出するグリンパティック・システム(glymphatic system)があり、睡眠中に最も活発に機能することを明らかにした。生きた脳から、2光子顕微鏡を用いて確証を得る作業が続けられ、睡眠中には脳細胞間のスペースが増加し、目覚めているときの2倍も多く代謝老廃物が排出されると報告している。
・アルツハイマー病患者では、脳からの排出能が低下しているため、TauやAβなどが脳内に蓄積され脳内に伝播されていく。また血液脳関門の機能が障害されていて、末梢のT細胞やマクロファージが中枢神経内に侵入し炎症反応が拡大する。そのため炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-1β、IL-17など)が脳細胞に過剰に放出されることになる。
・認知症やMCI(軽度認知障害)の患者には眠れないという共通の訴えが多いが、この訴えはとても重要である。認知症予防には、日常的に質の良い睡眠が必要である。
3.脳内グリアによる慢性炎症
・慢性炎症の反応系は、自然免疫細胞が有害物や病原体を検知し、発せられたシグナル(シグナルDAMPs、シグナルPAMPs)に基づき、炎症を起こし有害物や病原体を除去処理するシステムである。中枢神経では、ミクログリアとアストロサイトがその機能を担い、ダメージを受けた細胞や異物を除去し、脳内環境を正常に保っている。
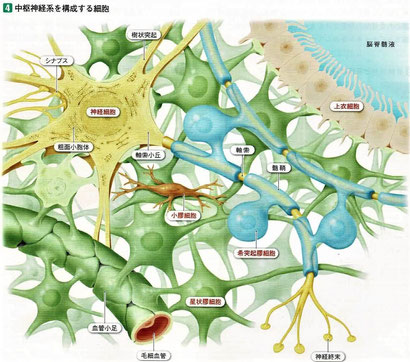
画像出展:「慢性痛のサイエンス」
アストロサイト(星状膠細胞):毛細血管壁に小足(終足)を出して神経細胞と血管の間に介在し、血液中の物質が神経組織内に移行するのを選択的に制限している。
ミクログリア(小膠細胞):単核食細胞系に属する小型のグリアである。神経組織が損傷を受けたり炎症が生じると増殖し、移動して貪食を行う。
グリア細胞(神経膠細胞)は支持細胞である:神経膠細胞は神経細胞と神経細胞の間を埋め、それらの保護・栄養・電気的絶縁に働く細胞である。
・静穏時のミクログリアは脳内をパトロールして、危険物/異物や病原体の有無を点検しており、アストロサイトは栄養物の運搬や老廃物除去などの役割を担っている。
・Aβ(アミロイド-β)やTau(神経原線維)を検出すると、ミクログリアは慢性炎症によってこれらを除去する。そして必要に応じ、炎症性サイトカイン(IL-1、IL-8、IL-17A、TNF-αなど)も追加動員し、ケモカインも呼びよせる。
・AβやTuが大量に存在してしまうと、多数のグリアが集結し炎症は拡大し連鎖反応が延々と続くことになる。
・ミクログリアには2種類あって、活性化/肥大化して炎症を促進するM1と、抗炎症作用を有するM2がある。後者は抗炎症サイトカイン(IL-4、IL-10、IL-13、TNF-βなど)を放出して、脳細胞の炎症を防ぐ役割を担っている。しかし慢性炎症が連鎖的に進行する状態では、M2はM1に変身して、炎症を促進する側にまわってしまう。
・アルツハイマー病患者の脳を組織学的に調べると、AβたTuの周りに、肥大化したミクログリアやアストロサイトが数多く取り巻いている。過剰な炎症性サイトカインに長期的に囲まれる環境では脳細胞は変性し細胞死する。
・慢性炎症を抑制する薬物について、認知機能改善の有効性が検証されている。現在、疫学調査により検証が行われているのは抗TNF-α抗体、ミノサイクリン、免疫チェックポイント阻害薬PD-1などである。長期投与した場合の安全性の確認も求められている。 Walters A, Phillips E, Zheng R, et al: Evidence for neuroinflammation in Alzheimer’s disease. Prog Neurol Psychiatry 20: 25-31, 2016
・.非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やCOX製剤については否定的な報告が多い。
・治療時期については、脳内の炎症を抑制するため、従来よりずっと早い段階で治療を始める必要性が指摘されている。
4.認知症と海馬
・アルツハイマー病における神経核の萎縮は、海馬、海馬傍回、嗅内皮質などを含む部位から始まる。それゆえ、海馬の萎縮が大きいときには認知症に移行する危険性が高いと診断される。
・長寿を全うした高齢者の脳を調べた研究では、AβやTuの凝集はみられたが、アルツハイマー病で亡くなった高齢者と比較して、海馬や大脳皮質の体積は有意に大きかったと報告されている。
5.認知症のリスクファクター
・認知症の第一のリスクファクターは加齢である。そして、他に挙げられるリスクファクターには、睡眠障害、うつ病、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群、頭部外傷、高血圧、PTSD、肥満、動脈硬化症、パーキンソン病、sedentary lifestyle(体を動かさない不活発な生活)などがある。
・うつ病に罹患すると、若い世代でも脳内の脳由来神経栄養因子(BDNF)が減少し、海馬に萎縮がみられる。BDNFの減少は海馬に深刻な影響を与えるが、高齢者の場合は特に認知症に急速に進行する。高齢者は知人、友人、配偶者などの死に遭遇する機会が多く、うつ病の危険性が高いので、十分な配慮が必要になる。
・現在、認知症予防に最も有効なのは、日常的な筋運動である。骨格筋を動かせばPGC1-αが発現し、慢性炎症を抑制する。ニューロンの成長に不可欠なBDNF、FGF-2も筋運動によって分泌が促進される。日常的にこまめに身体を動かし、十分な睡眠をとることがとても重要である。
慢性痛の科学3
第3章 侵害受容性の慢性痛
・侵害受容性の慢性痛とは、末梢組織に炎症の源が存在して、感覚神経終末が炎症メディエータによって刺激され、終わりのない痛みが続く場合をいう。
2.変形性膝関節症と慢性炎症
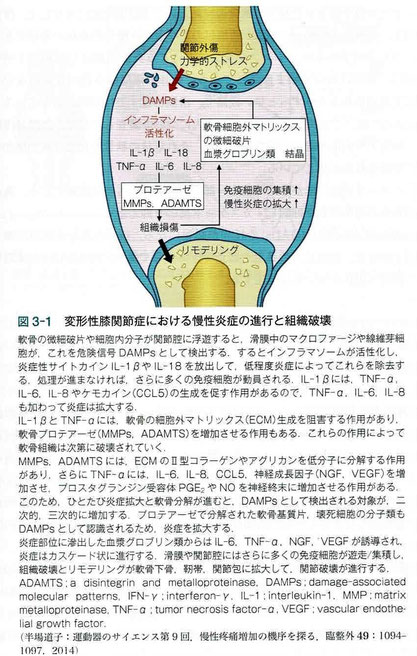
画像出展:「慢性痛サイエンス」
力学的ストレスなどにより関節が傷害され、軟骨の微細破片や細胞内分子が関節腔に浮遊すると、滑液中のマクロファージや線維芽細胞がこれらを危険信号(DAMPs)として検出する。するとインフラマソームが活性化し、炎症性サイトカインを放出する。
4.痛みを軽減する薬物
・非ステロイド性抗炎症薬の年単位の長期投与は、消化管潰瘍などの副反応だけでなく、軟骨摩耗を進行させる。特にインドメタシンは軟骨摩耗の副反応が報告されている。
第4章 神経障害性の慢性痛
・神経障害性の痛みは、末梢および中枢神経系が圧迫や切断を受け損傷して生ずる痛みである。
・神経障害性の痛みは、極めて慢性化しやすい。
・腰椎椎間板ヘルニア、帯状疱疹後神経痛などである。
1.神経障害性の痛み
・末梢神経が損傷されると活動電位の高頻度発射が起きる。この連続発射は脊髄後角で増幅され、過剰な興奮性信号が扁桃体、帯状皮質、島皮質、視床、大脳皮質感覚野などへ投射される。なかでも、扁桃体、帯状皮質、島皮質などの古い脳器官への興奮性投射は影響が大きく、時間の経過とともに大脳辺縁系や前頭皮質の回路網を巻き込んで、脳構造と機能に変容を起こしていく。そのため、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など、異常な痛みの病像が形成される。
・神経障害性の痛みの多くが、整形外科領域に集中して起きている。これにはC神経線維の特殊性と分布にあると考えられている。C神経線維は神経可塑性が大きく、興奮性が長期に維持される性質があり、ひとたび損傷されると、生じた興奮性は時間と共に増大し、長期増強と呼ばれる現象を惹起する。C神経線維は、Aδ神経線維とは異なって、体の深部組織に多く分布し、脊髄、骨組織、関節骨、靭帯、腱、歯組織などに存在する。そのため、神経障害性の慢性痛は、整形外科領域に起こりやすいと考えられている。
・複合性局所疼痛症候群(CRPS)と脳構造の変容
-CRPSでは血流は発汗の異常、浮腫、皮膚の栄養障害、運動障害など多彩な症状を呈するが、それだけでなく、意思決定機能の低下や気質的・性格的な変化も顕著に表れる。
-CRPSの脳内はfMRIを用いた脳画像法によって明らかになってきた。CRPS患者では右のAIC(島皮質前部)、vmPFC(腹内側前頭皮質)、NAc(側坐核)などに、著しい灰白質密度の減少と、異常な神経分枝がみられる。これらの部位における灰白質密度減少は、痛みに苦しんだ期間が長かった人ほど大きく、痛みの強さが激しかった患者ほど著しく、そして若い年齢層ほど急速に進行することが明らかにされている。
-CRPS患者ではAIC(島皮質前部)の灰白質に著しい萎縮が進行しており、かつ異常な神経分枝もみられる。CRPS患者にみられる血流や発汗の異常、浮腫、皮膚の栄養障害などは、末梢感覚神経や交感神経の損傷の他に、AICの灰白質萎縮と異常な神経分枝に起因したものと考えられる。
-CRPS患者にしばしばみられる意思決定機能の低下は、前頭皮質の灰白質萎縮に起因しており、運動機能の障害は前頭皮質から大脳基底核への神経連絡の減少にそれぞれ起因すると考えられている。
第5章 非器質性の慢性痛―Dysfunctional Pain
・非器質性の慢性痛や機能障害性疼痛(Dysfunctional Pain)は、痛みの源が末梢組織のどこにもないのに全身の多領域に拡がる痛みがある。消炎鎮痛薬や神経ブロックは効かず、随伴症状は睡眠障害、意欲の低下、慢性的疲労感、うつ状態などである。
第6章 慢性痛の治療法
Ⅰ 薬物療法・神経ブロック
5.抗うつ薬(Antidepressants)
・抗うつ薬には快情動を活性化する作用とともに、下行性疼痛抑制系を活性化する作用があるので、痛みの軽減に用いられる。抗うつ薬は運動療法や認知行動療法と組み合わせて用いられる場合もある。
・作用機序
-神経シナプス間隙においてセロトニントランスポーターと、ノルアドレナリントランスポーターを阻害することによって、脳内のモノアミン[ドパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、セロトニン、ヒスタミンなど]を増加させ、下行性疼痛抑制系を賦活する作用を持つ。
Ⅱ 認知行動療法・マインドフルネス
1.認知行動療法(CBT)
・認知行動療法(CBT)は慢性痛患者の負情動、ストレス、心理状態、破局的思考、認知過程に焦点を当てて、「心の持ち方」をポジティブな方向に変える手助けをする治療法である。認知行動療法は薬物療法や運動療法と組み合わせて治療効果を上げており、慢性痛、うつ病、パニック障害、強迫性障害、不眠症、薬物依存症、摂食障害、統合失調症などについて有効性が検証されている。
2.マインドフルネス・ストレス軽減法(MBCT)
・マインドフルネスは、元々は禅寺で行う瞑想に起源を持つ療法である。宗教とは無関係で座禅を組む必要もない。身体の力を抜いて姿勢正しく座り、意識を自身の呼吸や体に集中して観察するだけである。呼吸や自分の身体に意識を集中することによって、「今を生きているありのままの自分」に気づかせ、後悔、不安など過剰な負情動を締め出す狙いである。
Ⅳ 筋運動
1.筋運動による痛みの軽減
・運動を行うと痛みの刺激閾値が上昇する。
・熱刺激と圧刺激に対する痛みの刺激閾値は、ランニング、サイクリングなどの有酸素運動の後では、痛みの刺激閾値は上昇する。この機序には血中濃度から内因性カンナビノイドとオピオイドの関与が検証され、下行性疼痛抑制系の活性化が関与している。
・生物は重力下で骨格筋や骨組織を発達させ、重力に抗して筋量と骨量を維持しているが、長期にわたって臥位姿勢を続け、身体の動きが皆無に近い状態にあると、耳石が検知する重力は微小になる。微小重力下では筋タンパク質の分解量が合成量を上回るようになり、骨格筋肉量と骨量は低下する。
・健康な壮年被験者を60日間にわたって、頭位をわずかに傾けた特殊ベッドで臥位姿勢に保った実験では、抗重力筋(多裂筋、大腰筋、胸棘筋、脊柱起立筋など)は著しく萎縮していたが、体幹屈曲筋(腰方形筋、腹直筋など)の萎縮の程度はさほど大きくはなかった。抗重力筋と体幹屈曲筋の筋力バランスが崩れた状態は、慢性的な背腰部の痛みにつながる。
・骨格筋を動かすことは、様々な生理活性物質を分泌させ、遺伝子発現を促して全身の慢性炎症を抑制し、筋萎縮を防ぐ。近年、骨格筋を収縮させることが生命維持のうえで重要であることが明らかになった。
2.筋活動の生理的意義:骨格筋は分泌器官
・骨格筋は分泌器官である。骨格筋を収縮すると多種類のサイトカインやペプチドが産生・分泌される。

画像出展:「慢性痛サイエンス」
筋由来のサイトカインは、脳、骨組織、肝臓、脂肪、筋組織の機能に関わっている。BDNF、IGF-1、FGH-2は海馬の新生ニューロンを生育させ、IGF-1、FGF-2は骨芽細胞、破骨細胞の分化や機能を促進する。IL-6は膵からのインスリン分泌を増加させ、肝臓、脂肪組織、免疫機能に影響を及ぼしてる。IL-4、IL-6、IL-7、IL-15、LIF、ミオスタチンは筋組織自身に作用し、筋の新生と肥大に関わる。脂肪細胞には慢性炎症を促す炎症性マクロファージM1と非炎症性マクロファージM2を描いてある。
・筋由来のサイトカインはマイオカインと呼ばれる。また、同様に脂肪細胞からも分泌されるが、こちらはアディポカインと呼ばれる。
※マイオカインについては2017年11月に”マイオカイン(IL6)”というブログをアップしています。ご参考まで。
・筋細胞から分泌された生理活性物質は、血流やリンパに乗って、脳、骨組織、肝臓、膵臓、脂肪組織などの臓器に運ばれ、そこで臓器の機能と密接に関わる。
・骨格筋から分泌される生理活性物質は、弱い筋運動の時と強い筋収縮の時では異なる。これは注意すべきマイオカインの特徴である。
-負荷の軽い筋運動を続けると、抗炎症作用を持つIL-10、IL-4などが筋組織から産生されるので全身の慢性炎症が抑制される。またPGC-1α(後述)を発現させ、慢性炎症を防止し記憶力を向上させ老いを減速させる。
-負荷の強い筋運動を続けると、炎症性サイトカインが体内に急増し慢性炎症を促進する。結果として関節軟骨の摩耗や変形性関節症、疲労骨折などの原因となる。
3.筋活動の生理的意義:PGC1-αの発現
・PGC1‐αは骨格筋を動かすと速やかに筋組織中に発現し、エネルギーとATPの不足を補う。また、筋委縮を防止する。日常的にこまめに身体を動かすことはとても重要である。
・PGC1‐αはミトコンドリアの数を増加させ機能を向上させる作用や、活性酸素種(ROS)による酸化ストレスを抑制して老化を防ぐ作用、さらに代謝や血管新生を盛んにする作用もある。
4.PGC1-αによる慢性炎症の抑制
・慢性炎症を基盤とする疾患は世界的に増加している。アルツハイマー病、パーキンソン病、変形性関節症、2型糖尿病、各種のガンなどである。慢性炎症を完全に抑制する薬物は開発されていない現在、骨格筋を動かしてPGC1-αを活性化することは、慢性炎症を抑制する最も手短かで確実な方法といえる。
5.PGC1-αの抗酸化・抗老化作用
・PGC1-αは活性酸素種(ROS)を強力に抑制するスイッチの役割を担っている。
・活性酸素種(ROS)はミトコンドリアがATPを生成する過程で、漏出した電子の一部が酸素と結合して、非常に反応性の高い活性酸素種(ROS)が生じる。
・活性酸素種は毒性が強く、ミトコンドリアDNAを傷つける。さらに細胞内のDNA、酵素、タンパク質、細胞膜、脂質なども傷つけてしまう。そして、遺伝子の情報に影響を及ぼし細胞の機能も低下させる。
・骨格筋はミトコンドリアを多く含む組織であり、活性酸素種(ROS)の影響を大きく受ける。
・活性酸素種(ROS)の毒性に対し、生体では無毒化する活性酸素消去酵素(SOD)や、活性酸素種の発生を減らす酵素UCPによって防御している。しかし、SODやUCPもPGC1-αが発現しないときには、その働きは半減してしまう。
・PGC1-αを欠損させたマウスは活性酸素種(ROS)の害に極めて脆弱になり、全身に炎症性サイトカインの発生が多くみられる。特に黒質緻密部にあるドパミンニューロンは活性酸素種(ROS)に脆弱で、変性・脱落してしまう。
6.PGC1-αによる筋力増強作用
・日常的に有酸素運動を続けている人ほど、PGC1-αは速やかに、かつ多く発現する。高齢者であっても、筋運動の習慣がある人はPGC1-αが多く発現する。
・高齢者では、抗重力筋や姿勢保持筋の筋量や筋力維持が衰えるとサルコペニア[加齢や疾患により筋肉量が減少し、全身の筋力低下が起こること]に至り、介助や支援が必要になる。抗重力筋や姿勢維持筋を増加させたい場合は、ゆっくりした持久運動が適している。
7.健康維持に適した筋運動は?
・日常的に軽く骨格筋を動かす運動とは、通勤時の歩行、駅の階段昇降、自転車での通学通勤、家事労働、買い物、荷物の運搬などである。
・額に汗がうっすら浮かぶ程度の、日常的な筋運動が慢性炎症の抑制と筋萎縮の防止に効果が大きい。
・有酸素運動は呼吸器や循環器を刺激する。脂肪は代謝され、ミトコンドリア数も増加する。
・『米国では一般市民を対象に、慢性炎症を基盤とする疾患について大規模疫学調査が行われてきた。全身の慢性炎症レベルを高くし、さまざまな疾患を増加させている元凶を探って行ったところ、筋運動の少ないSedentary lifestyle(身体を動かさない不活発なライフスタイル)が元凶であると結論づけられた。』
・『筋運動が少なくなると、ROSの害が増大し慢性炎症が拡大する。大腸がん、乳がん、前立腺がん、子宮がん、膵臓がん、皮膚がんは、日常的に筋運動が少ない人に多く発生すると結論づける研究も存在する。』
慢性痛の科学2
第2章 慢性痛のメカニズム
Ⅰ 痛みを伝える情報伝達系

画像出展:「慢性痛のサイエンス」
①感覚神経終末が侵害刺激を受けると、侵害情報は電気信号に変換され、②感覚神経線維上を伝わり、③脊髄後角細胞(三叉神経脊髄路核細胞)に伝達される。さらに、④脊髄上行路を経て、⑤広範な脳領域に投射される。
1)感覚神経終末:侵害・非侵害情報を電気信号に変換する
・熱刺激、機械的刺激、化学的刺激などにより体が侵襲を受けると、それらのエネルギーは感覚神経終末によって、電気信号に変換され、上位脳へ伝えられる。
・感覚神経終末には侵害情報を検出する様々な侵害受容体やイオンチャネルが存在している。
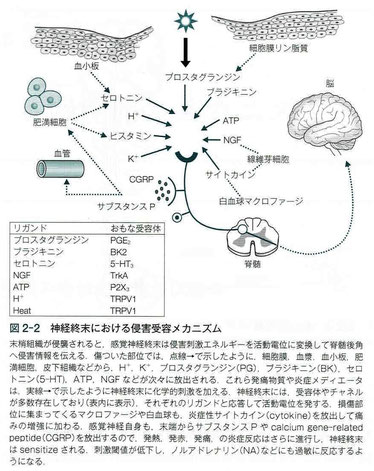
画像出展:「慢性痛のサイエンス」
末梢神経が侵襲されると、感覚神経終末は侵害刺激エネルギーを活動電位に変換して脊髄後角へ侵害情報を伝える。傷ついた部位では、点線→で示したように、細胞膜、血漿、血小板、肥満細胞、皮下組織などから、H⁺、K⁺、プロスタグランジン(PG)、ブラジキニン(BK)、セロトニン(5-HT)、ATP、NGFなどが次々に放出される。これら発痛物質や炎症メディエータが多数存在しており(表内に表示)、それぞれのリガンドと応答して活動電位を発する。損傷部位に集まってくるマクロファージや白血球も、炎症性サイトカイン(cytokine)を放出して痛みの増強を加える。感覚神経自身も、末端からサブスタンスPやcalcium gene-related peptide(CGRP)を放出するので、発熱、発赤、発痛、の炎症反応はさらに進行し、神経終末はsensitizeされる。刺激閾値が低下し、ノルアドレナリン(NA)などにも過敏に反応するようになる。
2)脊髄後角と三叉神経脊髄路核:侵害・非侵害情報を伝達する
・痛みの情報を伝える体性感覚神経(一次感覚ニューロン)は、Aδ神経線維とC神経線維の2つの神経線維がある。
・Aδ神経線維は比較的低い刺激閾値を有する有髄神経線維で、局在のはっきりした、鋭くて速い痛みを伝える。多くは体表近くの皮膚に分布している。
・C線維は高い刺激閾値を有する無髄神経で、遅くて局在のはっきりしない痛みを伝えている。骨組織、歯髄などの深部組織、皮膚に分布している。
・Aβ神経線維は触感覚や振動情報を伝え、最も低い刺激閾値を有している。皮膚に何かが触れた、風が当たったなど、非侵害性の感覚情報を伝えている。
3)脊髄後角と三叉神経脊髄路核:侵害・非侵害情報を伝達する
・体性感覚神経(一次感覚ニューロン)を伝わった感覚信号は、脊髄後角や三叉神経脊髄路核で、二次感覚ニューロンに伝達される。

画像出展:「慢性痛のサイエンス」
脊髄後角の灰白質はⅠ層からⅥ層に分かれている。C神経線維は表層の辺縁細胞と、Aδ神経線維は膠様質細胞とシナプス形成して、侵害情報を伝達する。Aβ神経線維は非侵害情報をⅢ-Ⅵ層の細胞に伝達する。
4)脊髄上行路:新旧2つの投射経路
・侵害情報を伝える二次感覚神経は、脊髄後角細胞を出て対側の脊髄前側索を上行するが、脊髄伝導路は脳幹レベルで、内側系投射経路と外側系投射経路に分けれている。内側系は主として痛みの情動的側面に関与する神経核に情報を伝え、外側系は痛みの感覚的側面に関与する神経核に情報を与えている。
・内側系の旧脊髄視床路は、視床の内側・髄板内核群に達する原始的な経路で、「遅い体性感覚投射経路」を形成し、局在性のはっきりしない痛みの情報を伝えている。
・旧脊髄視床路は、脳幹網様体に多くの側枝を出しながら上行して、視床・髄板内核群ニューロンに終わっている。髄板内核群からは扁桃体、前帯状皮質、島皮質などの古い脳に広く侵害情報を投射している。
・旧脊髄視床路以外にも、脊髄腕傍核扁桃体投射、脊髄網様体路、脊髄中脳路などの侵害情報を伝える投射経路がある。
・慢性痛に関与するのは、主として辺縁系、大脳基底核、中脳などの古い脳の神経核である。
・新脊髄視床路は外側系と呼ばれる経路で、視床外側の腹側基底核群に達する。精緻で高度な局在性を有する「速い体性感覚投射経路」は、侵害情報を正確に迅速に、視床を経て大脳皮質中心後回の体性感覚野に伝えている。急性痛の部位や痛みの性質など正確に弁別できる。
・内側系、外側系の両投射系は平行して上行するが、いくつかの接点がある。例えば島皮質では、外側系によって運ばれた侵害情報が後部島皮質に入力され、それが中部島皮質を経て前部島皮質に伝達される過程で、内側系の情報(辺縁系などによる情動系要素)が加味され、統合された情報になる。
5)扁桃体:負情動形成の中心
・扁桃体は辺縁系の神経核で、不快感、恐怖、不安、怒りなど、負の情動の発現に中心的役割を担っている。
・扁桃体には、生きるうえで必要な原始的感覚(嗅覚、触覚、視覚、聴覚、味覚、内臓感覚、侵害情報など)が全て入力される。これの感覚情報に対して、過去の経験や記憶に基づいて、有害=負情動か、有益=快情動かの評価を下して記憶の固定に関わっている。
・侵害信号が入力されると、扁桃体中心核はただちに本能行動を起こすように、視床下部、脳幹網様体などの広範の領域に向けて出力を送る。その結果として呼吸・脈拍が速く顔面が蒼白になり、ストレスホルモンが分泌され、フリージングなどの情動表出も瞬時に起きる。
6)海馬支脚、嗅内皮質:不安やストレス信号を発信する
・海馬支脚腹側部は、恐怖、不安、ストレス反応に関与する神経核である。
・扁桃体、青斑核、嗅内皮質からの投射を受けて情動面に関わるほか、前頭皮質からも入力を受け、認知機能にも関与する。
・海馬支脚腹側部には、身体的ストレス回路の視床下部-下垂体-副腎皮質系(hypothalamic-pituitary-adrenal axis:HPA軸)反応を終わらせる役割がある。生体がストレスに対処する際、HPA軸が機能する。ストレスが去れば、マイナスのフィードバックがかかって、HPA軸は停止する。海馬支脚はこの停止に関わる。
・うつ病患者は、外見上はふさぎ込んで不活発そうにみえるが、脳内ではHPA軸が過剰に活動し続けており、このことによる海馬の萎縮や機能低下が考えられている。
・海馬支脚に隣接する嗅内皮質は、不安関連の痛みを増大させ、不安を覚えたときには、最悪の事態を想定して信号を発する部位である。嗅内皮質は扁桃体と密に相互連絡しており、扁桃体から不快情動を受け取り、かつ不安関連の信号を発信している。
7)帯状皮質:痛覚受容と情動に関与する
・帯状皮質は特に痛みと関係が深い。脳画像上で侵害受容応答の賦活がみられる領域は、前帯状皮質である。
・前帯状皮質は扁桃体や前部島皮質と連絡しており、海馬や視床下部からも投射を受けている。また、前頭皮質、中脳水道周囲灰白質、腹側線条体・側坐核との間にも密な線維連絡がある。
・膝周囲前帯状皮質は下行性疼痛抑制系と連絡しており、特に重要な機能を有している。また、セロトニン・トランスポーターの分布密度が、大脳皮質中で最も高い部位である。
・セロトニンは縫線核から脳の広範な神経核に送られて、不安情動の処理、睡眠や摂食機能、気分、喜びの感情などの様々な身体/精神活動に関与している。それゆえ、もし前部帯状皮質膝周囲が機能不全に陥ると、セロトニン回収が遅れ、枯渇する。そして、うつ状態や睡眠障害、自律神経の失調など、多機能に影響が起きる。
8)島皮質:自己意識の形成に関与する
・島皮質には、痛覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚、触覚、温度感覚などの体性感覚、胃・腸の内臓感覚や心拍など、生命機能に関わる感覚情報が入力されるが、これらの体性感覚だけでなく、怒り、喜び、恐怖、悲しみ、など情動に関する情報も入力されている。
9)前頭皮質:高次精神活動の中心
・前頭皮質は最も新しく発達した領域で、理性、思考、創造性、行動の企画、意思決定、意欲、道徳観の発達など、高次精神活動の中心となっているが、最近の研究では情動にも関与することが分かっている。
10)視床と大脳皮質体性感覚野:感覚情報の集結と修飾
・外界からの感覚情報は視床に入力され、視床を中継して大脳皮質体性感覚野へ向かう。
・視床には興奮性の中継細胞、抑制性の介在神経細胞、視床内の神経回路などがあって、感覚情報はここで様々に処理され、修飾されて大脳皮質感覚野へ向かう。
・視床は多数の核からなっており、体性感覚に関係する主要な群には、腹側基底核群、後核群、髄板内核群がある。
・大脳皮質体性感覚野は、第一次体性感覚野(SⅠ)が、頭頂葉中心後回にあり、第二次体性感覚野(SⅡ)が、その外側後方の外側溝に沿った頭頂弁蓋の内壁に位置している。
・視床と大脳皮質体性感覚野は、痛みの弁別的側面に関与しており、急性痛の情報伝達系として、非常に重要な役割を有している。
・急性痛ではfMRIによる全脳スキャンを行うと、視床の各群や体性感覚野に賦活がみられるが、慢性痛ではSⅠに賦活化はほとんど見られず、SⅡ(第二次体性感覚野)に賦活が見られるのみである。
Ⅱ 痛みを抑制する脳内機構
1.Mesolimbic dopamine systemと疼痛抑制機構
・生体は何千万年という時をかけて、疼痛抑制機構を発達させてきたが、その脳内機構の全体像を明らかにしたのは機能的脳画像法のおかげである。
・中脳辺縁ドパミン系は、「報酬回路」、「快の情動系」だけでなく、「痛み」の制御も操り、慢性痛への転化機序に関係している。
・「快」と「痛み」は対極のものと思えるが、脳内回路は同じである。つまり、慢性痛患者の多くは痛みに加え、快感喪失や生きる意欲を失っている可能性がある。これらの症状は中脳辺縁ドパミン系の機能低下に関連して生じる。
・中脳辺縁ドパミン系は、中脳の腹側被蓋野(VTA)のドパミンニューロンから発し、内側前脳束を経て、腹側線条体の側坐核(NAc)、腹側淡蒼球(VP)、嗅結節、扁桃体(Amy)、海馬(HP)、中隔、前帯状皮質(ACC)、前頭皮質(PFC)などへ軸索を伸ばすA10神経がある。

A10神経については”脳科学のブログ(教育への架橋)”さまに、簡潔で分かりやすい説明が出ていました。
・中脳辺縁ドパミン系は、厳密には次の2つに分かれる。
-腹側被蓋野(VTA)から、腹側線条体の側坐核(NAc)、腹側淡蒼球(VP)、扁桃体(Amy)、海馬(HP)に向かう系で、“中脳辺縁系投射”である。
-腹内側前頭皮質、眼窩前頭皮質、帯状皮質、頭皮質に向かう系で、“中脳皮質投射”と呼ばれる。
・中脳から発するドパミン投射系には、①腹側被蓋野(VTA)から発するもの、②黒質から発するもの、③後赤核領域から発するもの、の3つがある。①は中脳辺縁系投射(A10神経)で、②は黒質緻密部から背側線条体(被殻、尾状核)に向かう黒質線条体投射(A9神経)である。パーキンソン病は②の神経変性によって起きる。
・ドパミンシステムは原始的な系であるが、自律神経系や免疫系の活動とも直結し、根源的な生命活動として、様々な神経核に働きかける。
・中脳辺縁ドパミン系は、生体が侵襲されて痛みを感じた時にも機能を発揮し、鎮痛をもたらす。

画像出展:「慢性痛のサイエンス」
侵害信号が腹側被蓋野(VTA)に届くと、活動電位の群発射が起こり、VTAの軸索先端からドパミンが側坐核(NAc)に向けて放出される。NAcニューロンが興奮すると、μ-オピオイド受容体を介した神経伝達が多神経核に起きて、下行性疼痛抑制系が活性化する。
・『Dopamine & opioid systemによる痛みの制御は、進化の過程で、捕食者に襲われて怪我しながらも逃げて命を永らえさせる系として発達したと考えられている。命の危機という非常事態にあっては、上行する侵害性入力は瞬時に遮断されて、鎮痛と救命の方向に働く、脳内では前頭皮質、大脳基底核、辺縁系、中脳、橋、延髄、脊髄の神経細胞が一斉に活性化して、総がかりで命の危機に対応するのである。
このような非常事態のときばかりでなく、日常的な些細な痛みの際にもdopamine & opioid systemは機能している。包丁で指先を切ったとき、転んで膝を打ったときなど、われわれが感受する痛みは、この疼痛抑制機構のおかげでかなり軽減されているのである。』

画像出展:「慢性痛のサイエンス」
侵害信号が腹側被蓋野(VTA)に届くとVTAからドパミンが放出される。すると側坐核(NAc)のμ-オピオイド受容体が活性化し、この活性化は吻[ブン]側前帯状皮質(rACC)、背外側前頭皮質(dlPFC)、扁桃体(Amy)、中脳水道周囲灰白質(PAG)などのμ-オピオイド受容体に波及する。これが引き金になって下行性疼痛抑制系が活性化する。
・内因性オピオイドは、脳内に20種類ほど存在している。メチオニンエンケファリン、ロイシンエンケファリン、エンドルフィン、ダイノルフィンなどが代表的なものである。これらのオピオイドを含む神経核は、扁桃体、側坐核、腹側淡蒼球、視床下部、中脳水道周囲灰白質、延髄の傍巨大細胞網様核などである。
・中脳辺縁ドパミン系の中核は側坐核とみられている。これは急性痛の段階から慢性痛へ転化するか、健常な状態へ回復できるかという重要な鍵を握るのは側坐核のニューロン活動であると考えられているためである。
・側坐核は嗅結節などとともに腹側線条体の一部である。
・側坐核は情動系の前帯状皮質、扁桃体、海馬と密に連絡して快情動の発現に関与し、生きる意欲や自律神経、根源的な生命活動と関係している。しかし他方では、思考、創造、学習などの高次脳機能を担う前頭皮質とも連絡して、希望、期待、自己優越性の確立、楽観性の獲得などに関係している。
・『重要な役割を有する側坐核であるが、生体が苛酷なストレスを過剰に受けると、ニューロン活動が90日以上にわたって停止してしまうのである。NAc[側坐核]にニューロン活動停止が起きると、ドパミンシステムは機能破綻するため、ほんの些細な刺激に対しても、「痛い、痛い」と悲鳴を上げる病的な状態に陥る。同時に、生きる意欲が低下し、根源的な生命活動である睡眠、食欲、自律神経活動も障害される。このような痛みはdysfunctional pain(中枢機能障害性疼痛)と呼ばれている。』
2.下行性疼痛抑制系
・図上部のPAG(中脳水道周囲灰白質)が、rACC(吻側前帯状皮質)やAmy(扁桃体)、Hypo(視床下部)から興奮性入力を受けると、下行性疼痛抑制系が活性化し、痛み信号を脊髄後角レベルで抑制・遮断する、中脳辺縁ドパミン系が活性化すると、rACC、Amy、Hypoが興奮し、その興奮性入力がPAGに加わる。
・PAG(中脳水道周囲灰白質)は軸索を、背外側橋中脳被蓋(DLPT)と、吻側延髄腹内側部(RVM)に伸ばしており、このDLPTとRVMを介して、侵害信号の伝達を抑制している。DLPTからはノルアドレナリン作動性の抑制性投射が、RVMからはセロトニン作動性の抑制性投射が、脊髄後角(DH)に向けられ、侵害信号の伝達をDHレベルで抑制して鎮痛をもたらす。この機構が下行性疼痛抑制系である。
・下行性疼痛抑制系の研究は、1969年にラットの中脳水道周囲灰白質に留置電極を通して電気刺激すると、無麻酔で開腹手術が可能なほど鎮痛が得られることが報告された。これにより多くの研究者が下行性疼痛抑制系に関心をもち、そのメカニズムは次々に明らかになっていった。そして、機能的画像法によってヒトの脳内活動が解析されるようになって、下行性疼痛抑制系と中脳辺縁ドパミン系のつながりが明らかになった。
1)中脳水道周囲灰白質(PAG):下行性疼痛抑制系の起始核
・PAGは中脳水道を取り囲む領域で、本能行動、情動行動、自律神経機能などに深く関わっている。
・内因性オピオイドを多く含む神経核であり、下行性疼痛抑制系の起始核である。
・中脳水道周囲灰白質の神経軸索は、橋の背外側橋中脳被蓋(DLPT)と、延髄の吻側延髄腹内側部(RVM)に伸びており、この背外側橋中脳被蓋(DLPT)と、吻側延髄腹内側部(RVM)を介して、侵害信号の伝達を脊髄後角(DH)で抑制している。
2)背外側橋中脳被蓋(DLPT):ノルアドレナリン系
・背外側橋中脳被蓋(DLPT)には、青斑核(LC)が含まれる。青斑核は第4脳室底部の外側、上部橋被蓋の両側に左右1対あって、ノルアドレナリンを含んでいる。メラニン色素を含む細胞があり、第4脳室表面から青黒く透けて見える。
・青斑核はノルアドレナリン性の下行性疼痛抑制系として機能し、侵害信号を脊髄後角で抑制する。末梢組織に侵害刺激が加わると、青斑核の活動電位発射は急激に高まる。
・青斑核は下行性軸索を脊髄後角へ向かって伸ばしており、ここで放出されたノルアドレナリンが、脊髄後角細胞のアドレナリンα₂受容体と結びついて侵害信号を抑える。
3)吻側延髄腹内側部(RVM):セロトニン系
・吻側延髄腹内側部(RVM)を構成する神経核には、大縫線核、巨大細胞網様核、傍巨大細胞網様核がある。大縫線核はセロトニン系の下行性疼痛抑制系として機能し、侵害信号の伝達を脊髄後角(DH)や三叉神経脊髄路核レベルで抑制し、鎮痛をもたらす。
3.Placebo analgesiaと脳内変化
・Placebo analgesiaとは、“プラシーボ鎮痛”のことである。プラシーボ効果とは薬効成分を全く含んでいないのに、薬物と同じような効果をもたらすことである。プラシーボ鎮痛の機序根幹をなすのは、dopamine & opioid systemである。
・プラシーボ鎮痛が起きる時は、被験者の脳内でドパミン&μ-オピオイド受容体を介した神経伝達が実際に起きている。PETを用いた実験で、本物の薬剤を摂取した時と同じ変化が脳内に起きることが実証されている。
・被験者が「鎮痛効果のある薬」の作用を大きく期待した場合は、期待度が低かった場合に比べ側坐核(NAc)におけるドパミン活性が大となり、μ-オピオイド活性も増加して鎮痛効果が大きくなった。この実験で使われたのは生理食塩水であった。にもかかわらず、被験者脳内にドパミンやμ-オピオイドの代謝変動を起こしたが、脳内に劇的な変化を起こさせた鍵は、【期待すること】【希望すること】であった。
・プラシーボ鎮痛に関する一連の研究では、ヒトが期待したり予測したりすることが、いかに大きな脳内変化を惹起するかを明確に示した点で画期的であった。また、これらの研究成果は、医師への信頼、医療への期待感がもたらす治癒力の大きさを示唆している。プラシーボ鎮痛が成立するには、医師の言葉や表情、白衣、病院の建物など、期待を抱かせる根拠となる学習や記憶、認知機能が必要である。
慢性痛の科学1
慢性痛というと、明治国際医療大学の伊藤和憲先生のセミナーで学んだことが頭に浮かびます。それは次の通りです。
●「急性痛と異なり、警告信号としての意味はない。また、慢性痛の中には既に痛みを起こしていた原因は治ってしまい、痛みだけが残っていることもある。そのため、検査をしても原因が見つからないことも少なくない。」
今回の本、『慢性痛のサイエンス 脳からみた痛みの機序と治療戦略』を知ったのは偶然です。施術者として慢性痛に精通することは間違いなく重要です。そこで「これはチャンス」と思って購入しました。
特に、中枢神経や生理活性物質の役割、慢性炎症のメカニズム、認知症やサルコペニアが印象的でした。
ブログは5つに分けていますが、取り上げているのは目次の中の黒字の部分です。
目次
第1章 慢性痛とは何か
Ⅰ 慢性痛の定義と分類
1.慢性痛の定義
2.慢性痛の分類
Ⅱ 慢性痛をめぐる問題
1.日本における慢性痛
2.慢性痛の患者数と医療費
3.慢性痛と精神疾患
Ⅲ 慢性痛の評価法
1.痛みの強さの評価法
2.質問票による痛みの評価法
第2章 慢性痛のメカニズム
Ⅰ 痛みを伝える情報伝達系
Ⅱ 痛みを抑制する脳内機構
1.Mesolimbic dopamine systemと疼痛抑制機構
2.下行性疼痛抑制系
3.Placebo analgesiaと脳内変化
第3章 侵害受容性の慢性痛
1.変形性膝関節症への新しい視点
2.変形性膝関節症と慢性炎症
3.変形性関節症の痛み
4.痛みを軽減する薬物
5.DMOADsの薬理作用と開発の現状
6.OA患者急増の社会的リスクファクター
第4章 神経障害性の慢性痛
1.神経障害性の痛み
2.痛みを慢性化させる要因
3.痛みの慢性化を防ぐには
第5章 非器質性の慢性痛―Dysfunctional Pain
1.慢性腰痛:脳内で何か起きているのか?
2.腰痛を慢性化させる要因
3.線維筋痛症の痛み
4.線維筋痛症患者の脳で何が起きているのか?
5. Dysfunctional Pain(機能障害性疼痛)
6.負情動と慢性痛
7.痛みの破局的思考
8.Default Mode Networkと慢性痛
第6章 慢性痛の治療法
Ⅰ 薬物療法・神経ブロック
1.非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
2.アセトアミノフェン(Acetaminophen)
3.麻薬性鎮痛薬、合成麻薬、オピオイド
4.抗てんかん薬(抗けいれん薬)
5.抗うつ薬(Antidepressants)
6.神経ブロック
Ⅱ 認知行動療法・マインドフルネス
1.認知行動療法(CBT)
2.マインドフルネス・ストレス軽減法(MBCT)
3.治療で回復する慢性痛患者の脳
Ⅲ 脳刺激法
1.大脳皮質運動野刺激
2.反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)
3.経頭蓋直流刺激(tDCS)
Ⅳ 筋運動
1.筋運動による痛みの軽減
2.筋活動の生理的意義:骨格筋は分泌器官
3.筋活動の生理的意義:PGC1-αの発現
4.PGC1-αによる慢性炎症の抑制
5.PGC1-αの抗酸化・抗老化作用
6.PGC1-αによる筋力増強作用
7.健康維持に適した筋運動は?
第7章 神経変性疾患と慢性炎症
Ⅰ パーキンソン病
1.パーキンソン病:運動症状と非運動症状
2.パーキンソン病:痛みの脳内機構
3.脳内ドパミンの変動と痛み
4.パーキンソン病:痛みの治療
5.パーキンソン病:発症を源にさかのぼる
Ⅱ 慢性炎症と疾患
1.免疫細胞とインフラマソーム
2.慢性炎症は万病の源
3.慢性炎症の抑制
Ⅲ 認知機能障害
1.アルツハイマー病
2.脳の時限爆弾AβとTau
3.脳内グリアによる慢性炎症
4.認知症と海馬
5.認知症のリスクファクター
Ⅳ 記憶のメカニズム
1.海馬:記憶の中枢
2.海馬では日々、ニューロンが新生している
3.新生ニューロンが記憶機能を担う
4.高齢者の脳と記憶力
5.認知機能と筋運動
6.海馬萎縮の原因
7.記憶には反復と睡眠
Ⅴ 高齢者とサルコペニア
1.サルコペニア―死のリスク
2.サルコペニアの診断
3.サルコペニアの機序
終章
1.慢性痛の謎解きと進化の系譜―古代の海から宇宙ステーションへ
2.快・不快情動に焦点を当てる―今後の医療の根幹
3.人は希望によって生きる
第1章 慢性痛とは何か
Ⅰ 慢性痛の定義と分類
・慢性痛は急性痛が長引いたものではなく、主として脳回路網の変容に伴って生じる痛みである。
・慢性痛患者数は推計2,300万人、成人人口の約22.5%。
・近年、機能的脳画像法によって慢性痛の脳内機構が明らかになりつつあり、治療法への挑戦が始まった。
1.慢性痛の定義
・一般的には発症から3カ月以上続く痛みと考えられている。
・末梢組織に起こった炎症の源が炎症反応を連鎖させ痛みが長く続くもの。
・上位脳に投射された侵害信号によって、中枢神経系の機能に変容が起き、痛覚過敏の状態が長期に続いているもの。
・“非器質性の慢性痛”はメカニズムが不明で、「痛みの謎」と呼ばれてきたが、機能的脳画像法によって慢性痛の脳内機構が明らかになり、それに基づいて、認知行動療法、マインドフルネスストレス軽減法、薬物療法、運動療法、脳刺激法など、様々な治療法が開発されている。
2.慢性痛の分類
・慢性痛は発生メカニズムから、①侵害受容性、②神経障害性、③非器質性、の3つに分類される。
1)侵害受容性の慢性痛
・末梢組織が外傷などの侵襲を受けると、末梢神経終末が刺激され活動電位を発する。活動電位が脊髄後角、視床を経由し大脳皮質体性感覚野に達すると「痛い」という感覚が生まれる。侵襲を受けた部位からは発痛物質や炎症メディエータが次々に産生され、感覚神経終末はこれらの濃縮スープに繰り返し刺激され、侵害受容性の痛みが生ずる。
2)神経障害性の慢性痛
・神経障害性の痛みは、「体性感覚神経系の病変、あるいは疾患によって生ずる痛み」と定義されている。
・末梢神経および中枢神経が損傷を受けた後で、痛みの増強や長期化が起きた状態を神経障害性の慢性痛という。
・損傷部位の傷口が治癒した後でも、神経組織の形態や上位脳における脳回路網の変容が起きるため、慢性痛が続く。
3)非器質性の慢性痛(心理/社会的要因に影響される慢性痛)
・非器質性の慢性痛は、機能的脳画像法を用いた研究により、脳の疼痛抑制機構の機能不全が原因の痛みであることがわかった。そして、dysfunctional pain(中枢機能障害性疼痛)と呼ばれている。
・心理的、社会的要因の影響を受けやすい。
・以前、「心因性」と呼ばれていたものは、現在、使用が避けられている。それは、「心因性」が脳回路網のどこに由来するのか不明であり、脳画像解析に基づいた痛みの機序とも乖離があるためである。
Ⅱ 慢性痛をめぐる問題
1.日本における慢性痛
・慢性痛の部位は、腰痛(55.7%)、四十肩・五十肩・肩こり(27.9%)、頭痛・片頭痛(20.7%)、関節炎(12.9%)、冷え症(12.2%)が上位5つである。「日本における慢性疼痛保有者の実態調査、2010年」より。
・慢性痛患者の痛み状況と罹患期間
メタボリックシンドロームの脅威
メタボリックシンドロームと聞いて思い出すのは、肥満と生活習慣病です。ところが、何がどう悪さしているのかについては、あまりピンときていませんでした。今回のブログで分かったことは、諸悪の根源は”慢性炎症”であるということです。
※ご参考:2017年2月に”慢性炎症について”というブログをアップしています。

出版:東京書籍
発行:2018年4月
『自然界とは異なる生活環境へと変化した現代社会では、栄養の取り過ぎや運動不足から肥満になる人が増えている。肥満によって生じるメタボリックシンドロームは、命に関わる病気を次々引き起こす可能性がある危険な状態だ。最新研究から、そんなメタボリックシンドロームの「本当の恐ろしさ」が浮かび上がってきた。』
1.レプチンがあっても肥満になる?
・脂肪はレプチンというメッセージ物質(「エネルギーは十分たまっているよ!」)により食欲をコントロールし、体重を調整しているにも関わらず肥満になる人は少なくない。それは、肥満の人の体内では異変が起きているためである。
・体脂肪が増えると血液中のレプチンの量は増える。
・肥満の人の脂肪細胞からもレプチンがたくさん放出されているのは間違いないが、肥満の人ではレプチンが脳に届きづらくなっている。
・脂肪細胞から放出されたレプチンは血液の流れに乗って、脳の一部、食欲などを司る「視床下部」にたどり着く。そこでレプチンは血管の外に出て視床下部の神経細胞にメッセージを伝える。肥満の人が抱える問題は、血液中に大量に漂っている“アブラ”が邪魔をして、レプチンが血管の外に出ていきづらい状態になっていることである。
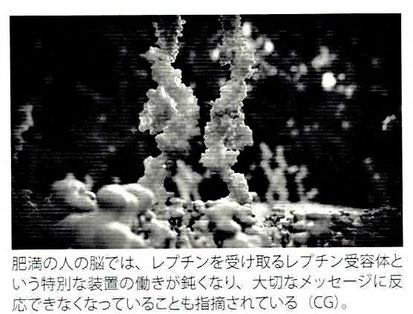
画像出展:「NHKスペシャル 神秘の巨大ネットワーク 人体2」
肥満の人の脳では、レプチンを受け取るレプチン受容体の働きが鈍くなり、大切なメッセージに反応できなくなっていると考えられる。
2.“免疫の暴走”が始まる
・肥満の人の体内では、メッセージ物質によるやりとりに異変が起きている。
・メタボリックシンドロームの人の内臓脂肪は、大量に摂り過ぎて脂肪細胞が吸収できなくなった糖や脂肪の粒が、煙のように漂っている。
・膨らみきった脂肪細胞の表面で、脂質の分子が次々と受容体にぶつかっており、それにより脂肪細胞がTNFαを放出する。
・TNFαは体内に侵入してきた細菌やウィルスなどを感知して、「敵がいるぞ!」という警告のメッセージ物質を出す。つまり、脂質の分子がぶつかっていた受容体は、本来は細菌を感知するための受容体であり、ぶつかってきた脂質の分子を敵(細菌やウィルス)と勘違いしてTNFαを放出していたということである。
・脂肪細胞から放出されたTNFαは、血液の流れに乗って全身を駆け巡り、免疫細胞と出会う。免疫細胞は敵を見つけると、近づいて細胞内に取り込み、内部にためている有害物質で分解する。
・TNFαの警告メッセージを受け取った免疫細胞は、活性化して「戦闘モード」に変化し、敵の来襲に備えるために分裂して仲間をどんどん増やしていく。
・免疫細胞自身もまたTNFαを放出し、「敵がいるぞ!」という警告メッセージを全身に拡散する。
・免疫細胞は細菌などを攻撃して体を守ってくれる味方である。ところが、栄養が過剰な状態となるメタボリックシンドロームでは、“免疫の暴走”が引き起こされる。この“免疫の暴走”こそが、メタボリックシンドロームの本当の恐ろしさである。
・免疫細胞が暴走した状態は、“慢性炎症”と呼ばれ、重要な研究課題となっている。
3.動脈硬化は血管の炎症が原因!?
・肥満の人の体内で、誤って活性化された免疫細胞は敵を懸命に探すが見つからず、ついには血管の壁の内部に入り込んで敵を探しに行く。そこで見つけるのは、たくさん溜まったコレステロールである。
・コレステロールは糖や脂質、たんぱく質を材料に作られる物質で、全身の細胞膜の成分になる他、ホルモンやビタミンDの原料になるなど、生命の維持にはなくてはならない重要な物質であるが、増え過ぎた血中コレステロールは血管壁の内部にたまっていく。
・血管壁に入り込んだ免疫細胞は、内部にあふれるコレステロールを排除すべき異物と認識し、次々と食べ始める。そして、食べすぎてパンパンに膨れあがると、ついには破裂し、免疫細胞が外敵を攻撃するための武器(有害物質)が辺り一面に飛び散り、それが血管の壁を傷つけてしまう。
・暴走した免疫細胞は、さらに体中のさまざまな場所で暴発する。その結果、心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病など、命に関わる恐ろしい病気を引き起こす。
・心筋梗塞の原因は血管壁に沈着したコレステロールと考えられてきたが、最新の研究から、免疫システムの異常がもたらす「炎症性の疾患」との認識が広がっている。つまり、免疫の暴走による血管の慢性的な炎症が、さまざまな病気に関わっているということである。
肥満のタイプ
・体内の脂肪は、皮膚の下(皮下)と内臓に大別され、肥満のタイプも「皮下脂肪型」と「内臓脂肪型」がある。
・内臓脂肪はつきやすく落ちやすい性質があり、日々の運動をするためのエネルギーを貯蔵する。
・皮下脂肪はつきにくく落ちにくい性質があり、出産や授乳などのための長期的なエネルギーを貯蔵する。
・男性は女性に比べ、脂肪をためる容量が少なく内臓脂肪がつきやすい。
・内臓脂肪の蓄積はメタボリックシンドロームを引き起こし、糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病の発症や、動脈硬化性疾患に深く関係している。
骨からのメッセージ
前回の「脂肪と筋肉からのメッセージ」に続き、今回は「骨からのメッセージ」になります。

出版:東京書籍
発行:2018年4月
『体を支えるだけの組織だと思われがちな「骨」。
しかし、最新の科学で明らかになったのは、一見無口に思える「骨」が人体のネットワークを通じ、脳や筋肉など全身の臓器にメッセージを送り続けているという事実だ。
そのメッセージが途絶えたとき、まるで命のスイッチを切るかのように、老化現象が加速してしまうという。』
1.オステオカルシン
・記憶力や生殖機能を強化するメッセージ物質。
・通常のマウスとオステオカルシンをつくれないマウスを泳がせるという実験により発見された。
・骨でつくられたオステオカルシンは血管内に放出され、血液に乗って脳に運ばれる。そして、海馬に到達して受容体と結合し、海馬の神経細胞の中に「記憶をアップせよ!」というメッセージが送り込まれる。
・動物は老化に伴って筋力が低下し運動能力が落ちていくが、これにオステオカルシンは関係している。
・運動には、筋肉が糖分と脂肪酸を分解し吸収する必要があるが、オステオカルシンには糖分や脂肪酸の分解・吸収を促す働きがある。つまり、オステオカルシンは筋肉のエネルギー利用を増進するメッセージを送り、筋力をアップさせていると考えらえる。
・マウスの実験で、正常なオスのマウスにオステオカルシンを注射すると、血液中のテストステロン濃度が大きく上昇する。
・オステオカルシンをつくれないオスのマウスと正常なメスのマウスを交配させたところ、妊娠の頻度が低下し、1回の出産で生まれる子どもの数は少なかった。
2.オステオポンチン
・造血幹細胞は赤血球、白血球、血小板などの細胞へ成長していく。その造血幹細胞の老化に関係しているのが、オステオポンチンの減少である。
・骨が放出するオステオポンチンのメッセージは「免疫をアップせよ!」である。このメッセージが造血幹細胞に届くと、造血幹細胞は活性化し、免疫細胞への分化が促進される。
オステオカルシンは記憶力アップ、筋力アップ、精力アップといった複数の役割をこなしている。さらに、オステオポンチンは免疫力増強作用を有する。これらはいずれも若々しさを維持、あるいは回復する働きを担っている。骨は単に体を支えるだけではなく、メッセージ物質によって全身の若さをコントロールしている。
3.スクレロスチン
・骨が異常に増え続ける難病である「硬結性骨化症」の患者の体内では、遺伝子の異常によってスクレロスチンというメッセージ物質が欠如している。
・スクレロスチンのメッセージは「骨をつくるのをやめよう!」というものである。
・スクレロスチンは骨粗しょう症の新しい治療薬となる可能性がある。これはスクレロスチンの働きを抑制するための、スクレロスチン阻害薬である。
衝撃が骨を強くする
●骨への衝撃が骨量を増やす
・骨は衝撃を感知すると骨の量を増やす。以下のグラフは週に6時間以上、ランニングあるいは自転車運動を行っている20~50歳代の男性のうち、骨量が低い傾向にあった人(骨粗しょう症予備群)の割合。自転車運動は、骨への衝撃という意味では座っている場合と変わらない。
●骨は“人体の若さの門番”
・全身に数百億個あるとされる骨細胞は互いに結び合い、骨の中にネットワークを張り巡らせている。このネットワークで体にかかった衝撃を敏感に感知する。
・衝撃を感知した骨細胞は、「骨をつくるのをやめよう!」というブレーキ役のメッセージ物質の量を減らし、代わりに「骨をつくって!」というアクセル役のメッセージ物質を発して、骨芽細胞の数を増やす。
・骨は活動的に動いている限り、骨芽細胞からのメッセージをたくさん放出して、全身の若さを保ってくれる。
・運動後では骨量が増加するとともに、「骨をつくるのをやめよう!」というメッセージをもつスクレロスチンの量が減少する。
脂肪と筋肉からのメッセージ
今回のブログは、『NHKスペシャル 人体 ~神秘の巨大ネットワーク~ 第2巻』からになりますが、他に、“骨からのメッセージ”、“メタボリックシンドロームの脅威”という、計3つのブログをアップします。以下は題材とした本ですが、「はじめに」に書かれていた、脂肪・筋肉・骨に関する説明箇所の一部をご紹介します。
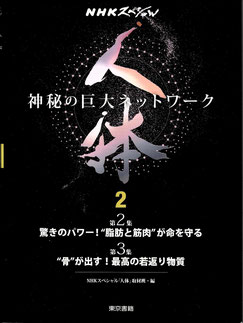
出版:東京書籍
発行:2018年4月
『まず「脂肪と筋肉」。重要な役割は、「体内のエネルギー量を把握し、それをどう効率的に使うかを決める」こと。メッセージ物質を巧みに使いながら、時には脳を、時には免疫細胞を制御していることが分かってきました。食欲や性欲まで、脂肪細胞が操っているというのですから驚きです。そして、エネルギーを大量に消費する筋肉は、メッセージ物質を使って、「大きくなりすぎないように」と自らを戒めています。なぜか、がんやうつを防ぎ、記憶力をアップさせるメッセージ物質を発している可能性も浮かび上がってきました。
次に「骨」。様々な“若返り物質”を放出して、私たちの体の若々しさを決めていることが明らかになっています。免疫力や記憶力、生殖能力や筋力をアップさせる鍵が骨にあるというのです。』
脂肪からのメッセージ
1.レプチン
・脂肪細胞から放出されたレプチンは血管に入り込み、血液の流れに乗って脳の「視床下部」に到達する。到達したレプチンは血管から浸みだして脳の中に入っていく。脂肪細胞からのメッセージを受け取った脳は、満腹であることを感じ取り、「もう食べなくていい」と判断して、食欲は収まっていく。
・ハムスターによる動物実験により、レプチンが性行動の頻度を増やすことがわかった。この仕組みは食料が十分にあるときにだけ子孫を残すという、母親と生まれてくる子を守るためのものと考えられる。
2.アディポネクチン
・糖尿病やメタボリックシンドロームの発症の有無に大きく関わっていると考えられている。
・脂肪細胞から放出されるアディポネクチンは、脂肪の量が多いほど減っていくという特徴をもっている。特に、内臓脂肪が多い人ほどアディポネクチンの量は少ない。詳しいメカニズムを解明する研究が続けられている。
3.VEGF(血管内皮増殖因子)
・血液が体の隅々まで栄養素や酸素を運ぶには血管が必要である。VEGFは栄養や酸素が不足している場所に、「血管をつくって!」というメッセージを発信する。なお、VEGFは脂肪細胞だけでなく、血管内皮細胞からも放出される。
4.TNFα
・TNFαは免疫細胞が細菌やウィルスなどを探知して、周りの免疫細胞に対して「敵がいるぞ!」と警戒を促すメッセージ物質である。
・最近の研究で、TNFαは脂肪細胞からも出ていることが発見された。様々な病気と関わってることが分かってきており、近年とても注目されている。
以上4つのメッセージ物質をご紹介しましたが、脂肪細胞からのメッセージ物質は約600種類あると考えられています。
筋肉からのメッセージ
人体には大小含めて約400種類の筋肉が存在している。
1.ミオスタチン
・1997年に初めて発見された、筋肉からのメッセージ物質で、筋肉の成長をコントロールする。
・ミオスタチンは周囲の細胞に「成長するな!」というメッセージを伝え、筋肉の過剰な増加を抑えている。「成長するな!」というメッセージは理解に苦しむが、それは筋肉が体の中で最も多くのエネルギーを消費する臓器だからである。自然界では獲物を捕まえたり、捕食者から逃げたりするため、エネルギー不足に陥りやすく、必要以上の筋肉は命取りになる。つまり、ミオスタチンは必要以上に筋肉が増え過ぎるのを抑え、エネルギーの消費を最小限にとどめる働きをしていると考えられている。
2.カテプシンB
・運動したときに筋細胞から放出される。
・記憶を司る「海馬」の神経細胞を増やす働きがあると考えられている。

画像出展:「NHKスペシャル 人体 神秘の巨大ネットワーク2」
4か月間の定期的な運動によって、血液中のカテプシンBが増えた人ほど、記憶力テストの成績が向上した。
マイオカイン
・2000年代以降、ミオスタチン以外にも筋肉が出すメッセージ物質が次々に発見されており、これらのメッセージ物質を総称して「マイオカイン」と呼んでいる。
・マイオカインの働きを探る研究は急速に加速しており、2016年に報告された研究論文は100本以上に及んでいる。
・マイオカインに「がんの増殖を抑える働きがある」、「うつの症状を改善する効果がある」など、筋肉の概念を覆す新発見が相次いでいる。

画像出展:「NHKスペシャル 人体 神秘の巨大ネットワーク2」
マイオカインには、がんの増殖を抑える働きがあります。Pedersen L, et al: Cell Metab. 2016; 23: 554-562
上記をクリック頂くと、10枚(PDF)の資料がロードされます。
加齢に伴う筋肉の変化
・筋肉は加齢とともに減少する。体の部位では上肢、体幹よりも下肢の筋肉の減少率が大きい。
・加齢と伴って筋肉の質も変化する。若い世代は遅筋線維と速筋線維のバランスが良いが、加齢により速筋線維の減少が大きい。高齢者に転倒が多いのは筋肉量が減ってふんばりが効かず、しかも速筋線維が減って素早い動きができないことが大きな要因になっている。
・筋トレは下肢に重点を置き、毎日ではなく、週2~3回行うのが良い。これは筋トレによって損傷した筋線維の回復に24~72時間かかるためである。なお、筋肉は回復する過程で太く成長する。
hCGと着床
『受精卵は、ふかふかで栄養たっぷりのベッドで育つことができる。』
この“ベッド”とは子宮内膜のことです。また、この過程で女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンが重要であることは認識していました。
ところが、下図の【妊娠⇒着床】に出てくる“hCG”も、とても重要であるということを知りました。
”hCG”とはヒト絨毛性ゴナドトロピンのことです。”岡山大学さまのサイト(検査部/輸血部インフォメーション)”には、hCGについて次のような説明がされていました。
ヒト絨毛性ゴナドトロピン, HCG (human chorionic gonadotropin)
●ヒト絨毛性ゴナドトロピン(human chorionic gonadotropin ; hCG)は、α、β、2つの相異なるサブユニットの非共有結合により形成される分子量約38,000の糖蛋白ホルモンである。
●hCGは主に絨毛組織において産生される。
●妊娠初期の卵巣黄体を刺激してプロゲステロン産生を高め、妊娠の維持に重要な働きをしている。
●胎児精巣に対する性分化作用や母体甲状腺刺激作用も報告されている。
●絨毛性腫瘍のほか、子宮、卵巣、肺、消化管、膀胱の悪性腫瘍においても異所性発現[本来の場所以外で発現]している例が報告されている。
●臨床的にhCG測定を必要とする場合として、①妊娠の診断と予後の判定、②絨毛性疾患の診断ならびに治療効果判定とそのfollow up、③各種悪性腫瘍に対する腫瘍マーカーとしての応用、などがあげられる。
ブログに残そうと思ったのは、「神秘のネットワーク4 第6集 “生命誕生”見えた!母と子 ミクロの会話」の中に、”まず迎える、着床という妊娠の最難関門”という見出しがあり、そこで主役となっていたhCGが私にとっては大発見の新情報だったためです。
ブログは目次に続き、hCGについて書かれた箇所を取り上げています。
目次
第6集 “生命誕生”見えた!母と子ミクロの会話
Part1 新たな命が発信する最初のメッセージ
●新たな命が始まる瞬間を追う
●まず迎える、着床という妊娠の最難関門
●子から母への最初のメッセージ
●妊娠検査にも利用されるhCG
Part2 人体をつくる驚異の仕組み
●“ドミノ式全自動プログラム”
●万能細胞が開いた神秘の扉
●最初に生まれる臓器は、心臓
●心臓の次は、肝臓
●さまざまなメッセージが連鎖して作用する
●ぐんぐん成長する赤ちゃん
※万能細胞が切り拓く新しい世界
Part3 胎盤の中で繰り広げられる母と子のやりとり
●10か月で驚きの成長を遂げる赤ちゃん
●母と子をつなぐ命綱
●胎盤の中で繰り広げられる驚異の共同作業
●1つ1つのメッセージを専用装置でやりとり
●そして、誕生
※もう1つの生命誕生物語
Part4 生命誕生の解明が医療の未来を切り拓く
●原因不明の難病に苦しむ女の子
●肝臓移植の代わりになる再生医療
●何になるべきかを知っていた細胞
●生命誕生に学ぶ未来の医療
●“ミクロの会話”がもたらす希望の光
※臓器づくりに欠かせない細胞同士の会話
第7集 “健康長寿” 究極の挑戦
Part1 「がん」が送り出す恐ろしいメッセージ
●日本人の死因第1位のがん
●何度取り除いても発症するがん
●映像が捉えたがん細胞の増殖
●がん細胞が血管を引き寄せる仕組み
●特殊なメッセージ物質、エクソソーム
●それはメッセージの宝箱だった
●宝箱を悪用するがん細胞
●免疫細胞も手なずけるがん細胞
●エクソソームががんの転移のカギを握る
●転移のための環境を整えるがん細胞
●体内のエクソソームは100兆個以上
Part2 「がん」との戦いの最前線
●がん治療の新時代
●13種類のがんの早期診断を目指す
●運動ががん治療につながる
●エクソソームを標的としたがん治療
●光と免疫でがんを攻撃
●牛乳からがんの治療薬も……?
Part3 不可能に挑む! 次世代の心臓再生医療
●いったん傷ついた心臓はもとに戻らない
●心臓の中のメッセージ物質
●エクソソームから心筋細胞を再生
●メッセージ物質を使った治療のメリット
●iPS細胞を使った心臓の再生医療
Part4 神秘の巨大ネットワーク
●人体の解明へさらなる挑戦は続く
●臓器同士をつなぐ情報ネットワーク
●全身の免疫力を司る腸
●骨が若さを生み出す
●幹細胞から骨をつくり「健康寿命」を延ばす
●人体探求の“たすきリレー”は次世代へ
特集:人体ART
Part1 新たな命が発信する最初のメッセージ
●まず迎える、着床という妊娠の最難関門
・受精卵は分割し5日ほどで100個程の細胞に増える。自然の受精の場合、この段階は卵管の中を子宮に向かって移動しながら行われる。なお、この時の受精卵は「胚盤胞」と呼ばれる。
・体外受精の場合、受精卵は胚盤胞の状態までシャーレの中で培養された後に子宮の中に戻される。
・誕生に向けた最初にして最大の難関がここから始まる。受精卵が生き続けるためには、子宮の壁(子宮内膜)にしっかりと根を張って着床する必要がある。
・この関門を乗り越えるために、母親の体はメッセージ物質が働いて大きな変化を促す。受精卵が着床するためのカギはメッセージ物質である。
●子から母への最初のメッセージ
・赤ちゃんからお母さんへの“初めてのメッセージ”は、母親が妊娠に気づくずっと前から受信され始めている。
・『受精後8日目の受精卵の姿は、まだ大きな変化がないように見えた。ところが、2日後、思いがけない現象が起き始める。受精卵のあちらこちらから、ある物質が放出され始め、日を追うごとに、どんどん増えていった。hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)と呼ばれるこの物質こそ、着床のカギを握るメッセージ物質だ。』
・hCGの役割は受精卵が母親に「ここにいるよ!」と伝えるためのメッセージである。このhCGは受精後10日目の受精卵から放出される。
・hCGは母親の血液の流れに乗って全身を巡り、卵巣などに働きかける。すると、母親の体は生理を起こさないように変化し、子宮の壁(子宮内膜)をどんどん厚くしていく。これにより受精卵はしっかりと包む込まれ、着床は促進される。
●妊娠検査にも利用されるhCG
・母親の血中hCGの量は、妊娠を調べる検査にも用いられている(血液中のhCGは尿にも出ていくため尿でも調べられる)。
【受精卵が出す最初のメッセージ物質hCGの働き(CG)】
自然炎症と2型マクロファージ
今回は、審良静男先生と黒崎知博先生の「新しい免疫入門 自然免疫から自然炎症のまで」という本が題材です。
当初の目的は、新型コロナウィルスで先行する2つのワクチン(独BioNTech社と米Pfizer社が共同開発したワクチン、および米Moderna社のワクチン)が、ともにmRNA(メッセンジャーRNA[タンパク質分子の設計図をコピーする働き])ワクチンということで、これがどのようなものか知りたいということと、免疫について勉強したいというものでした。
前者のワクチンに関する記述は多くなかったため、ブログは免疫、「免疫と炎症」が主になります。特に、新発見だった“自然炎症”と“2型マクロファージ”に注目しました。なお、目次でいうと10章になります。
詳しいご説明は最後に再登場するのですが、以下の図が今回の最大の収穫です。
目次
まえがき
プロローグ
・二度なし
・一度目は?
・新しい免疫劇場
1章 自然免疫の初期対応
2章 獲得免疫の始動
3章 B細胞による抗体産生
4章 キラーT細胞による感染細胞の破壊
5章 三つの免疫ストーリー
6章 遺伝子再構成と自己反応細胞の除去
7章 免疫反応の制御
8章 免疫記憶
9章 腸管免疫
10章 自然炎症
11章 がんと自己免疫疾患
あとがき
参考文献
さくいん
10章 自然炎症
●免疫学の新しい展開
・TLR[Toll-like receptor:病原体を感知して自然免疫に活性化するセンサー]などのパターン認識受容体は、”病原体”だけではなく“内在性リガンド[体の自己成分、自己細胞が大量に死んだときに出てくる成分などが多い]”も認識する。つまり、マクロファージや好中球などの食細胞は、“内在性リガンド[虚血、細胞ストレス、細胞死など]を認識して活性化し、炎症をおこす。このように病原体が関わらない炎症を「自然炎症」という。
・自然炎症の代表的な例は、体の中で大量の細胞がネクローシスを起こして死ぬような場合である。
・自然炎症が何のために起こるのか、まだはっきりと分かっていないが、組織の修復に関わっているという考え方が有力である。マクロファージや好中球が集まり、損傷部が取り除かれる。さらに修復のための専門細胞が集まり、組織の再建にとりかかる。こうして組織は修復される。
・パターン認識受容体はほぼ全身の細胞に分布しているため、内在性リガンドで自然炎症を起こしうるのは、マクロファージなどの食細胞だけでなく、ほぼ全身の細胞ということになる。
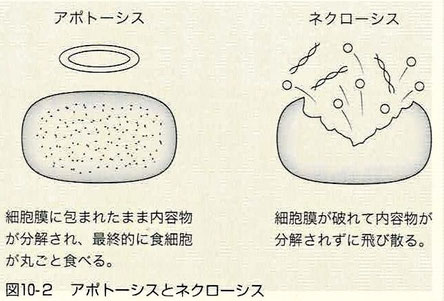
画像出展:「新しい免疫入門」
『からだのなかで細胞が死ぬパターンとして二つの様式がある。アポトーシスとネクローシスだ。アポトーシスが誘導されると、細胞膜につつまれたまま内容物が分解され、最後は食細胞が丸ごと食べて処理する。一方、ネクローシスでは、細胞膜が破れて、内容物が分解されずに飛び散る。外傷や火傷、薬物、放射線などが誘因となる。』
●痛風はマクロファージがおこす自然炎症だった
・痛風は全身の関節(特に足の親指の関節)で急性の炎症が繰り返し起こる病気で激痛を伴う。原因は血液中の尿酸である。尿酸は細胞の老廃物で、増えすぎると結晶となって関節に付着し、これを食細胞が取り込むと炎症が起こるが、この炎症は自然炎症と考えられる。
・痛風の原因は“尿酸”だが、尿酸に限らず結晶のような構造をとる物質は、食細胞に取り込まれると活性化し炎症を起こす。

画像出展:「新しい免疫入門」
『食細胞が尿酸結晶を細胞内に取り込むと、尿酸結晶の刺激でミトコンドリアが損傷する。すると、SIRT2という酵素のはたらきが低下し、細胞内の輸送路である微小管にアセチル基という分子がつく。その結果、損傷したミトコンドリアが微小管の上に乗り、細胞の中心部の小胞体まで移動する。こうして小胞体のNLRP3と、ミトコンドリアがもつ部品ASCがそろい、さらにカスパーゼという部品もくわわって複合体が組みあがる。この複合体をインフラマソームという。インフラマソームは、インターロイキン1βをマクロファージ内で成熟させて外に放出する。引きつづいて強い炎症がおこり、激痛が走ることになる。』

画像出展:「新しい免疫入門」
『脳ではマクロファージや好中球の代わりにミクログリアという細胞が免疫のはたらきをしており、βアミロイド線維を食べたミクログリアからは同じようにインターロイキン1βが放出される。』
・NLRP3は様々な結晶(または結晶のような物質)の刺激をきっかけにしてインフラマソームを形成することから、この他にも多くの炎症性疾患との関連が強く示唆されている。
・体内で結晶化したものは食細胞が消化しきれずに死んでしまい、結晶が体内に残る。それを処理しようと新しい食細胞がまた食べに来て食べきれないという状態が繰り返され炎症が起こる。つまり、消化・分解できない結晶は、自然免疫系を過剰に活性化してしまう。
・痛風も動脈硬化も同じメカニズムでにもかかわらず、痛風だけが激痛なのは結晶の量の違いと考えられる。電子顕微鏡で見ると、集積している尿酸結晶に比べ、コレステロール結晶は極めて少ない。
●TLR[Toll-like receptor:病原体を感知して自然免疫を活性化するセンサー]による自然炎症
・TLRもNLRP3と同様に、自然炎症に関わっている。
・虚血再灌流障害とは、脳梗塞や心筋梗塞で虚血状態にある組織や臓器に再び血液が流れだしたとき、強い炎症が局所的または全身で起こるものである。これは、虚血によって大量の細胞死が起こり、その中の成分が血管内皮のTLR2、TLR4、TLR9を刺激して炎症を起こすためである。
・TLRなどのパターン認識受容体が内在性リガンドを認識して起こす自然炎症が、炎症性疾患に関係している可能性が高まっている。
![TLR[Toll-like receptor:病原体を感知して自然免疫を活性化するセンサー]などが認識する内在性リガンドの例](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=389x1024:format=jpg/path/s5e68ecbdde7ed919/image/i7b1ed6bf08979555/version/1620774274/image.jpg)
画像出展:「新しい免疫入門」
”内在性リガンド”は右端です。これを見ると、TLR3というパターン認識受容体の対象はウィルスであり、その内在性リガンドはメッセンジャーRNA(mRNA )であることが分かります。もしかしたら、これは新型コロナウィルスのメカニズムと何か関係しているのでしょうか??
●炎症を抑える2型マクロファージ
・マクロファージは2種類ある。一つは1型と呼ばれ、異物を食べたり炎症を起こしたりするタイプで昔から知られていた。一方、2型は炎症を抑え、組織の修復をする。詳細な働きはまだよく分かっていないが、脂肪組織の状態維持に役立っていると考えられている。
・2型マクロファージは、病原体をやっつけるという役割ではなく、体の中の色々な組織と交流して、それらの機能を維持しているとみられている。
・2型マクロファージを欠くマウスでは、脂肪から遊離脂肪酸がどんどん外へ出ていまい、血中のコレステロールや中性脂肪の濃度が上がった。このマウスに脂肪食を食べさせると、ほとんどのマウスに糖尿病の症状が見られた。
・正常マウスと肥満マウスの比較実験では、正常マウスの脂肪組織では2型マクロファージが多数を占めているのに対し、肥満マウスの脂肪組織では1型マクロファージが多数を占めていた。なぜ、肥満マウスで2型の代わりに1型が多数になるかは分かっていない。飽和脂肪酸により1型が誘導され、不飽和脂肪酸では誘導されないという報告はあるが、詳細は不明である。そもそも2型マクロファージがどうやって作られるのか、1型と2型は行ったり来たりできるかなど、基本的なところが全く分かっていない。
・1型マクロファージは様々なサイトカインを放出して、インスリン抵抗性をもたらすため、糖尿病の準備状態を誘導することになる。発赤、発熱、腫脹、疼痛といった炎症の四徴候は見られないが、一種の炎症反応と考えられる。
●「免疫と炎症」
・『内在性リガンドが見つかり、自然炎症のしくみが明らかになってくると、免疫学は従来の枠のなかにおさまらなくなってきた。20世紀までは獲得免疫が免疫学の中心であり、21世紀になると獲得免疫にくわえて自然免疫も重要視されるようになった。そして、いま、免疫と炎症が大きな学問分野を形成しようとしている。
いまや免疫と炎症の関係は図10-5のようにまとめることができる。TLRなどのパターン認識受容体は、病原体も内在性リガンドも認識し、自然炎症もおこせば、獲得免疫も始動させる。そして、自然炎症が行きすぎると炎症性の疾患を引きおこし、獲得免疫に誤動作がおこると、自己免疫疾患を引きおこす。
従来は免疫と炎症の学会はそれぞれ独立して開催されたが、海外でおこなわれている最近の学会やシンポジウムでは、会の名称が「免疫と炎症」になっていることも多くなった。』
付記1:炎症とは

こちらの図は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学(免疫病理/第一病理)さまより拝借しました。
『炎症反応は、体内で発生した、あるいは外部から体内に侵入した病原刺激を除去し、傷害を受けた組織を取り除く生体反応です。とくに微生物侵入に対する最初の防御系として働いており、生命維持に必須の生体防御反応です。炎症反応がないと、私達は生きていけません。炎症反応は、効率的・戦略的な戦力配分のもと、様々な炎症メディエーターによりダイナミックに制御されています。』
付記2:「これは2型マクロファージも関与!?」
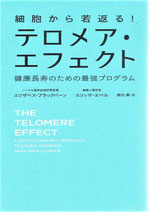
テロメアは遺伝情報を保護する役目を担っています。そのテロメアの配列を同定し、テロメアを伸長する酵素・テロメラーゼを発見した業績で、ブラックバーン先生は2009年に、ノーベル生理学・医学賞を受賞されました。この本はそのブラックバーン先生の著書です。本には以下のようなことも書かれています。
『運動によって体の分子は損傷を受け、損傷した分子は炎症を引き起こす可能性がある。だが、運動を始めてまもなく、オートファジー[細胞内のタンパク質を分解するための仕組み、自食作用]という現象が起き、細胞はまるでパックマンのように、細胞内の損傷した分子を食べてしまう。これにより、炎症を防ぐことができる。』
付記3:“腎疾患の進展に自然炎症が果たす役割に着目した新規治療の開発”

当院は慢性腎臓病でご来院頂いている患者さまが多いのですが、今回、腎疾患と自然炎症に関する論文を見つけましたのでご紹介させて頂きます。資料はPDF4枚です(クリック)。ここに出てくる内在性リガンド(内因性リガンド)は既出の図10-5の中では”虚血”が特に重要ではなかと思います。それは腎臓が極めて多くの酸素を必要とする臓器であるためです。
『慢性腎臓病(CKD)は本邦において 1,300万人を超え、CKDから透析へ移行する患者数は年間 38,000人前後を推移しており、生活の質および医療経済などといった面で多大な影響を及ぼしている。その克服は大きな課題であり、RAS阻害を主体とする適切な降圧療法や生活指導などに加えて新しい観点からの治療法開発が望まれている。内因性リガンドと病原体センサー間の相互作用による慢性炎症(自然炎症)は生活習慣病やガンなど現代病の発症に重要であることが明らかされつつある中で、腎臓における役割は不明であった。最近我々は自然炎症に重要な役割を果たす toll-like receptor 4(TLR4)が糖尿病性腎症の進展に重要であることを明らかにし、TLR4の強力な内因性リガンドの一つである myeloid-relatedprotein 8(MRP8)がその病態に重要な可能性を報告した。』
『糸球体腎炎は本邦における透析導入原疾患として糖尿病性腎症に続く第 2位を占める疾患である。中でも半月体形成性腎炎は腎予後のみならず生命予後も脅かされる予後不良疾患であり、特に高齢者での発症が多いことで知られている。現在ステロイド、免疫抑制剤が治療の主体となっているが、感染合併による死亡例が後を絶たず、治療を断念せざるを得ないケースも多く認められる。内因性リガンドを治療標的とする新しい治療ストラテジーは新規創薬につながる可能性が期待される。今回急性期の観察で MRP8欠損による腎症軽減効果が確認された。今後長期的モデルあるいは観察により、慢性化に及ぼす影響を検討する必要がある。』
降圧薬2
第3章 有酸素運動、健康体操、ヨガ…… 血圧数値を劇的に改善する「運動法」
一 有酸素運動の血圧改善効果
●有酸素運動は薬以上の効果を示す!
・正常血圧の人に比べ、高血圧および高血圧前症の人は有酸素運動による効果は大きい(収縮血圧:マイナス8.3mmHg/拡張期血圧:マイナス5.2mmHg)。[“平均”は“正常血圧”の人も含めた数値です]
●血圧を下げるポイントは運動の「強度」
・表を見ると、低強度の運動では血圧を下げるのは難しく、中強度または高強度の運動でないと効果は期待できない。
・高強度の運動は高血圧の人にとってリスクが高いので行ってはいけない。
1.参考となる論文:1993年発行の「Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology」誌に掲載された“Crossover comparison between the depressor effects of low and high work-rate exercise in mild hypertension“
・日本で行われた研究で、高強度の有酸素運動のリスクを示している。
・黒丸が高強度、白丸が中強度の運動である。高強度の有酸素運動を行うと、安静時の収縮血圧(150mmHg弱)が一気に50mmHgも上がってしまい危険である。一方、中強度の場合の上昇は10mmHg程度と上昇は少ない。
・高血圧の人は有酸素運動を中強度で行うことが望ましい。中強度の運動とは余剰心拍数の40~60%で行う運動である。
・40歳、脈拍70の人の余剰心拍数:114~136
①220-年齢(この数値は最大心拍数の推定値)…220-40=180
②最大心拍数(180)-脈拍(70)=予備心拍数(110)
③運動強度40%の心拍数は、脈拍に予備心拍数の40%を足したもの…70+110×0.4=114
④運動強度60%の心拍数は、脈拍に予備心拍数の60%を足したもの…70+110×0.6=136
・表によると、50歳、心拍数(脈拍)70の人の“適切な心拍数”は、110~130である。
●週30分の運動は、「日本一の薬」を超える!
・週150分未満の運動と血圧改善効果についての研究
1.参考となる論文:2003年発行の「American Journal of Hypertension」誌に掲載された“How much exercise is required to reduce blood pressure in essential hypertensives: a dose-response study“
・日本人を対象とした研究である。
・週30~60分の運動でも、収縮期血圧:マイナス7mmHg/拡張期血圧:マイナス6mmHg程度の効果が期待できる。※左から2番目の棒グラフ
・この論文には運動の仕方にも言及されており、それによると、運動を週1回まとめて行っても、週5回以上に小分けに行っても効果は特に変わらないということである。[ただし、運動強度は中強度(余剰心拍数40~60%)が前提となる]
●ウェイトトレーニングと血圧の関係
・『ウェイトトレーニングが筋力や筋肉量の向上に役立つことは、広く知られています。ダイエットにも有効であり、最近流行となっています。なお、私はボディビルの大会出場のために27㎏の減量に成功しましたが、その際、運動はウェイトトレーニングしか行いませんでした。
また、ウェイトトレーニングが肩こり、腰痛、膝の痛みにも効果的であることも有名だと思います。事実、私のわずか10分ほどの説明で、「明らかに良くなった」、「痛み止めの注射がいらなくなった」、「月1万円もかかっていた病院、薬代が1か月で0円になった」と驚くべき効果をあげた患者さんがたくさんいます。これは私の腕が特別に良いというのではなく(それなりに研究はしてきましたが)、適切なウェイトトレーニングを行えば薬以上の効果が出るという科学的事実がそのまま表れたに過ぎません。
他にも、血糖値の改善、骨密度の改善、様々な疾患に対するリハビリテーションの一環として役立つことも示されています。
このように健康に役立つウェイトトレーニングですが、実は血圧にも効果的なのです!実際、海外の高血圧に関する医学専門誌ではウェイトトレーニングを高血圧の人に役立つエクササイズとして紹介しています。』
・このデータから低強度の場合、収縮期血圧:マイナス5.8mmHg/拡張期血圧:マイナス4.7mmHgの効果が期待できる。
・低強度のウェイトトレーニングとは、ギリギリ挙げられる最大重量の30~40%とされているが、危険を冒して最大重量を計測する必要はない。1セット20回以上、余裕をもって反復できる重量であれば、40%を超えることはないので安全にウェイトトレーニングができる。頻度は週2、3回。なお、20回以上できる負荷であっても、決して頑張るようなことがあってはならない。また、トレーニング中は呼吸を止めてはいけない。息を止めると急に血圧が上がり危険である。
三 血圧改善効果のあるその他の運動
●とてもお手軽な握力運動
・健康番組にも紹介された有名な方法である。
1.参考となる論文:2010年発行の「Journal of Hypertension」誌に掲載された“Isometric handgrip exercise and resting blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials”
・握力を鍛えるだけの運動であるが、その効果は驚くべきものである。収縮期血圧:マイナス13.4mmHg/拡張期血圧:マイナス7.8mmHg程度の効果が期待できる。
・実験期間は8~10週間であり、効果は3か月以内に出ている。
・方法
①最大筋力の30~40%程度の軽いグリッパー(握力を鍛える器具)を2分間握る。
②1~3分間休む。
③ ①②を4回繰り返す。
④ ①②③を週3回行う。3日連続より、月・水・金のように1日空けた方が効果は出やすい。
1.参考となる論文:2015年発行の医学雑誌「Lancet」誌に掲載された“Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology(PURE) study”
・握力は健康を測る指標として非常に重要であることが示されている。
・驚くべきことに血圧よりも重要であるとされている。
・『樹上生活を行ってきた私たちのご先祖の中で、握力のない者は木にうまく上ることができず、肉食獣に食べられてしまったことが予想されます。そして現代においても握力のない者は健康を失うリスクが高いことが示されてしまいました。握力の重要性は霊長類にとって不変の法則なのかもしれません。』
●動かずにできるアイソメトリック運動で血圧が改善する!?
・力を入れて握り続ける握力運動はアイソメトリック運動(等尺性運動)というが、握力に限らずアイソメトリック運動で血圧を下げることができる。
1.参考となる論文:2015年発行の医学雑誌「Mayo Clinic Proceedings」誌に掲載された“Isometric exercise training for blood pressure management: a systematic review and meta-analysis”
・研究によると、収縮期血圧:マイナス6.77mmHg/拡張期血圧:マイナス3.96mmHgの効果があったとされている。
第5章 ケース別に学ぶ「運動」と「食事」の最適な組み合わせ方
四 医師とともに薬を減らすには
●降圧薬の減量、中止に向けて目標値を決める
・これまでの内容から「血圧とリスク」「降圧薬の効果」から、目標となる数値の目安をまとめた。
・『この数値を一つの根拠として、降圧薬の減量、中止を医師に申し出るタイミングを見計らってください。なお、「中止」とは「通常量の降圧薬を1種類やめる」という意味です。』
・『ただし、75歳以上の方は、収縮期血圧120mmHg未満、拡張期血圧80mmHg未満 で健康リスクが高くなる恐れがあるので、もしこの数値になったなら、即座に薬の減量、中止を申し出てください。今飲んでいる量の降圧薬は、お金の無駄だけではすまない恐れがあるのです。』
●医師にどのように切り出すか?
・『生活習慣を改め、血圧が十分に下がりました。毎日血圧を測り、家での血圧も安定しています。それでは私たちからどのように薬の減量、中止を医師に切り出せば良いのでしょうか?
ここはやはり正々堂々と、「自分なりに勉強して生活習慣の改善に取り組んできました。以前に比べ、血圧はかなり下がったと思います。薬を一度減らしてみてもらえませんでしょうか? 数値が悪化するならまた戻してくれて構いませんので」と発言しましょう。
このように生活習慣改善に積極的である姿勢をとれば医師も減らしやすくなるはずです。減らしたことにより血圧に問題が出るならば戻しても良いということを話し、医師が薬を減らしやすくするように持ち込むわけです。この表現なら医師と衝突する心配もなく切り出すことができるはずです。
金銭負担が気になることも併せて盛り込んでも良いでしょう。ほとんどの医師は金銭負担を考慮する人格を持っています。金銭負担が減れば助かるのはあなたの財布だけではありません。国全体の財政が助かるのです。
もちろん、ふらつき、めまい、脱力感がある。拡張期血圧70mmHg未満であるなど健康に悪影響を及ぼす恐れがあるならば即座に減量を申し出るべきです!
医師に申し出るのは勇気が必要かもしれません。しかし、ほとんどの医師もわかっています。必要以上に血圧を下げる必要がないことを。薬の効果は実はそれほど大きなものではないことを。そして、最初は高かった血圧がしっかりと改善しているのは薬のおかげではなく、あなたの努力の成果であることを……。きっと良い返事が返ってくると思います。』
降圧薬1
慢性腎不全で高血圧の薬を飲んでいる患者さまの担当医が代わり、高血圧の薬がすべて替わるということがありました。
なお、当院では患者さまの血圧と脈拍を測定していますが(手首で測る血圧計で、ベッドに仰向けになった状態で測るため座位に比べ低めに出ると思います)、この患者さまの血圧は収縮期血圧130前後、拡張期血圧65前後であり、個人的には降圧薬でうまくコントロールされているという印象を持っていました。そのため、何故、薬を替えられたのか不思議に思いました。
下記は処方されていた降圧薬の前と後です。
■前
・ニフェジピン(Ca拮抗薬)
・シルニジピン(Ca拮抗薬)
・アムロジピン(Ca拮抗薬)
・アイミクス(長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤)
※アイミクスは、イルベサルタンとアムロジピンの配合剤
・ルプラック(ループ利尿薬)
■後
・アムロジピン(Ca拮抗薬)
・イルアミクス(長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤)
※イルアミクスはアイミクスのジェネリック薬剤
・イルベサルタン(長時間作用型ARB)
・トリクロルメチアジド(チアジド系降圧利尿剤)
・フロセミド(ループ利尿薬)
この中で非常に気になったのは、“イルベサルタン”という薬です。
ネットで調べたのは、KEGGというサイトです。このサイトに頼ったのは、①検索上位のサイトであったこと。②母体が信頼できると思ったこと。③非常に詳しく説明されていたこと。 の3点です。

KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes
『KEGG は分子レベルの情報から細胞、個体、エコシステムといった高次生命システムレベルの機能や有用性を理解するためのリソースです。とくにゲノムをはじめとしたハイスループットデータの生物学的意味解釈に広く利用されています。また KEGG MEDICUS では医薬品添付文書など社会的ニーズの高いデータとの統合も行われています。』
そして、“イルベサルタン”に書かれていた中で特に気になった部分は次の内容です。
“KEGGのページ”(左をクリックしてください)
●『両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、イルベサルタンによる腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。』
●『高カリウム血症の患者においては、イルベサルタンにより高カリウム血症を増悪させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。』
特に注目したのは『片腎で腎動脈狭窄のある患者』という点です。これは、この患者さまは片腎のため、万一、腎動脈狭窄があるとすれば、『治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること』に該当することになります。
ご参考1:こちらの”倉敷中央病院 心臓病センター 循環器内科”さまのサイトに、腎動脈狭窄の原因と結果などが詳しく紹介されていました。

腎動脈狭窄症の原因とその結果
『腎動脈の狭窄の頻度は、軽症なものも含めると意外に多く、高齢者をランダムに血管エコーでスクリーニングすると6%前後に狭窄を持つ人がいるといわれています。55歳以上の亡くなった方を解剖した研究では、15%に腎動脈に狭窄があったと報告されています。
腎動脈が細くなる原因として、その90%以上は加齢に伴う動脈硬化です。残りの10%弱は比較的若年者に見られる、動脈硬化によらない腎動脈狭窄症で、細くなった場所の顕微鏡による観察から、線維筋性異形成症と呼ばれています。』
ご参考2:イルベサルタンなどのARB(アンジオテンシン受容体拮抗薬)には腎保護作用があるとされています。こちらの”大森病院 腎センター”さまのサイトに、腎保護作用についての説明がされています。イルベサルタンは腎保護作用があるという点から中長期的には腎臓にとっても良い薬のようです。

『糸球体にかかる圧力のことを「糸球体内圧」と呼びます。降圧薬の中にこの糸球体内圧をさげる薬があります。「アンギオテンシン変換酵素阻害薬:ACE‐I」や「アンギオテンシン受容体拮抗薬:ARB」といわれる薬は全身の血圧を下げる働きとともに糸球体内圧を特別にさげる働きがあります。
糸球体内圧が低下するのでろ過される血液が減ることがあり、腎臓の働きとしては低下してしまうこともあります。しかし中長期的にみて腎臓への負担を減らすことになり、結果として腎臓を長持ちさせることができます。
現在ではデータの蓄積により、腎臓病をもつ高血圧患者さんへの第1選択薬として積極的に使用されるようになりました。』
長い前置きになってしまいましたが、今回、高血圧の薬(降圧薬)について詳しく知りたいと思った経緯は、上記のようなことがあったためです。
そして、購入した本は、薬剤師であり、ご自身が薬に頼らず血圧を下げられた経験をお持ちの石川太朗先生が書かれた『降圧薬の真実』でした。
ブログは、最初に“あとがき”の一部をご紹介しています。これは、石川先生がこの本を書かれた理由を知ることができるためです。次いで目次をすべて書き出していますが、その中の黒字がブログで取り上げた項目です。
あとがき
『高血圧はいわば国民病ともいえる病であり、血圧を下げる方法として、薬、食事、サプリメントに関するたくさんの情報があります。
その一方で、「降圧薬は一生飲み続けなければならないのか」という疑問に対しては具体的な答えを見つけるのが難しいのが実情です。事実、私は大型書店の専門書コーナー、母校の京都大学附属図書館をはじめ、東京大学附属図書館、慶応義塾大学信濃町メディアセンターなどのいろいろなところで資料を探してみましたが、満足のいく答えを示した本を見つけることができませんでした。
私は薬剤師なので、しばしばこの、「降圧薬は一生飲まなければならないのか」という質問を受けてきました。自身の体験から、生活習慣を改善すれば降圧薬を飲まないですむことは理解していましたが、それに対して具体的な説明ができない状態でした。これは薬のスペシャリストとしていかがなものかと思い、調べようとしたのが本書の執筆を始めたきっかけです。』
目次
はじめに
第1章 疑惑だらけの「降圧薬」治療
一 血圧の薬は死ぬまでやめられない?
●氾濫する情報に踊らされる高血圧患者たち
●医師自身も騙されている?
●半分以上の人はやめられる!科学的に証明されている!
●まとめ
二 そもそも「高血圧」とは何か?
●高血圧の分類
●なぜ血圧が高いといけないのか
●自分の「最適数値」を目指そう
●下げれば下げるほど良いのか?
●下げすぎの危険性とは?
●「薬で下げる」は危険?
●降圧薬を飲んでも、脳卒中のリスクは高いままである。
●まとめ
三 製薬企業と降圧薬の知られざる関係
●降圧薬は製薬企業のドル箱市場
●一つの薬が1000億円以上売れる!
●世界一の企業の論文不正事件
●日本一の企業も不誠実
●まとめ
四 降圧薬の効果を知る
●降圧薬によって、数値はどれだけ下がるのか?
●「日本一の薬」の効果とは?
●平均値はわずか「マイナス5.5~マイナス9.1mmHg」!
●まとめ
五 トクホの効果を知る
●トリペプチド 薬以上の効果があるように見えるが……
●トクホの効果は塩1g!?
●トクホで血圧の数値を改善できるのか
●まとめ
第2章 降圧薬に頼らずとも、血圧を下げる方法はないのか
一 薬の減量、中止は可能なのか
●医師はなぜ処方しつづけるのか
●第一段階は「薬の減量」
●「家で血圧を測る」メリットとは
●まとめ
二 生活習慣が変われば血圧は下がる
●『高血圧治療ガイドライン2014』によると……
三 減量のすすめ
●体重90㎏、BMI35の大学1年生
●適正体重を維持すれば、降圧薬はやめられる
●まとめ
第3章 有酸素運動、健康体操、ヨガ…… 血圧数値を劇的に改善する「運動法」
一 有酸素運動の血圧改善効果
●有酸素運動は薬以上の効果を示す!
●血圧を下げるポイントは運動の「強度」
●週30分の運動は、「日本一の薬」を超える!
●血圧が高い人ほど効果的
●温水プールのエクササイズで平均35mmHg以上の改善!?
●まとめ
二 ウェイトトレーニングは高血圧の人にも役立つ
●ウェイトトレーニングと血圧の関係
●実践 初心者向けエクササイズ
●まとめ
三 血圧改善効果のあるその他の運動
●とてもお手軽な握力運動
●動かずにできるアイソメトリック運動で血圧が改善する!?
●健康体操の驚くべき効果!
●気軽にできるヨガ
●マッサージを受けるだけで血圧は下がる!
●まとめ
第4章 正しい「食事法」と「生活習慣」で「適正血圧」の基盤を固める
一 食事でどれだけ血圧が下がるのか?
●減塩効果を正しく理解する
●「お酒はほどほど」 が鉄則
●血圧を下げる成分がある!
●血圧を下げる「DASH」食とは
●カリウムの効果
●マグネシウムの効果
●カルシウムの効果
●食物繊維の効果
●DASH食の真の血圧改善効果!
●魚の油を摂取すると……
●その他の安価で有用な成分
●ビタミンCが効くのは美容面だけではない!
●乳酸菌は血圧も下げる
●トマトの驚くべき効果
●トクホを超える緑茶の力!
●まとめ
二 血圧に悪しき四つの習慣
●「痛み止め」は血圧を上げる
●炭水化物と清涼飲料水は要注意!
●たばこは「百害あって一利なし」
●「漢方薬だから大丈夫」の落とし穴
●まとめ
三 モデルケース
●30代男性
●20代男性
●40代女性
第5章 ケース別に学ぶ「運動」と「食事」の最適な組み合わせ方
一 「時間はあるけどお金はない人」編
●運動/食事
二 「お金はあるけど時間はない人」編
●運動/食事
三 「お金も時間もない人」編
●運動/食事
四 医師とともに薬を減らすには
●降圧薬の減量、中止に向けて目標値を決める
●医師にどのように切り出すか?
あとがき
第1章 疑惑だらけの「降圧薬」治療
一 血圧の薬は死ぬまでやめられない?
●半分以上の人はやめられる!科学的に証明されている!
・降圧薬をやめた後、再び必要になるかどうかを研究した論文が存在する。
1.「高血圧治療ガイド2014」(日本高血圧学会):この治療ガイドによると『軽度高血圧、若年者、塩分摂取制限を行っている人、適正体重の維持ができている人、他に特に合併症のない方などがやめられる可能性が高い』と示されている。
2.2001年発行の「American Journal of Hypertension」誌に掲載された“A systematic review of predictors of maintenance of normotension after withdrawal of antihypertensive drugs”という論文がある。研究内容は次の通りである
・降圧薬服用中であるが、正常血圧で安定している患者を対象にしている。
・医師の判断のもとに服用を中止し、その後、降圧薬が再び必要になるかどうかについて調べている。
・この表は薬の服用中止後に「生活習慣を改善したかどうか」、「薬の再処方が必要だったか」を示している。
・表右端の[成功率]とは、その生活習慣改善の有無における薬が不要になった人の割合を表している。
・このデータによると、体重の減量や減塩などの努力により半分以上の人は降圧薬が不要になった。
・年齢と成功率に関係は見られなかった。
●下げすぎの危険性とは?
・血圧が下がりすぎると脳梗塞を起こすリスクが高まる。特に高齢者ではそのリスクが高い。
1.参考となる論文:2011年発行の「Geriatrics & Gerontology International」誌に掲載された“Practitioner’s trial on the efficacy of antihypertensive treatment in elderly patients with hypertension Ⅱ(PATE-hypertension Ⅱ study) in Japan”
・日本で行われた試験。
・カンデサルタン服用において、正常血圧の人のリスクを1とすると、75歳以上の心血管疾患発症リスクは、収取期血圧120mmHg未満は3.40、160mmHg以上は2.90であった。つまり、高い血圧より、低い血圧の方が危険であるという驚くべき結果であった。
・『この論文は、医療系の大学には必ずといっても良いほど置いている著名な医学雑誌「医学のあゆみ」(医歯薬出版)でも紹介された論文であり、医師たちの多くは下げすぎの危険性を理解しているはずなのです。』
・拡張期血圧が低すぎるのは収縮期血圧以上に恐ろしく、心臓発作や脳卒中のリスクになることが多くの論文で指摘されている。
2.参考となる論文:2013年発行の「International Journal of Hypertension」誌に掲載された“Low Diastolic Blood Pressure as a Risk for All-Cause Mortality in VA Patients”
・45歳以上の病院患者のデータ(実線が死亡率)
・拡張期血圧が75mmHgから低くなるほど死亡リスクが高くなる。
・『低い拡張期血圧は衰弱や動脈硬化の結果でもあります。病院に行かなくても良いような健康な人には当てはまらないかもしれません。しかし、血圧の薬を使っている人にとっては当てはまる恐れが高いのです。』
3.参考となる論文:2015年発行の「Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry」誌に掲載された“Meta-analysis of modifiable risk factors for Alzheimer’s disease”
・拡張期血圧が低すぎることは認知症の大きなリスクファクターである。
・この論文は5000人以上と参加者が多く、グレードⅠと研究の質も高い。
・拡張期血圧70mmHg未満[左から2番目の棒グラフ]の人の発症リスクは1.87倍で重度の喫煙(1.96倍)についで、第2位となっており、収縮期血圧160mmHg以上[右から2番目の棒グラフ]の発症リスクより顕著に高い。
4.参考となる論文:2012年発行の「Archives of internal medicine」誌に掲載された“Rethinking the association of high blood pressure with mortality in elderly adult:the impact of frailty”
・降圧薬の害について書かれた論文である。
・通常の歩行ができる人は収縮期が低いほど死亡率が低いが、歩行速度が遅い人の場合は血圧と死亡率に関連は見られない。
・歩行困難な人では血圧を下げると死亡率が高くなり、薬を飲んでいる人ではより顕著になる。
●降圧薬を飲んでも、脳卒中のリスクは高いままである。
・この考え方を指示した論文が、日本人を対象とした大規模な研究で明らかになっている。
1.参考となる論文:2009年発行の「Journal of Hypertension」誌に掲載された“Stroke risk and antihypertensive drug treatment in the general population: the Japan arteriosclerosis longitudinal study”
・この研究は、11,371人の日本人を対象として東北大学大学院によって行われた。
・追跡期間は9.5年、40~89歳の人を対象として脳卒中のリスクを調べた。
・このグラフは、薬の使用の有無を考慮に入れていないデータである。
・左端(下部)の【至適血圧】の脳卒中発症リスクを1とした場合のリスクが黒の■になる。
※【至適血圧】:収縮期血圧120未満/拡張期血圧80未満。
※【正常血圧】:収縮期血圧120~129/拡張期血圧80~84。
※【正常高血圧】:収縮期血圧130~139/拡張期血圧85~89。
※【Ⅰ度高血圧】:収縮期血圧140~159/拡張期血圧90~99。
※【Ⅱ度高血圧】:収縮期血圧160~179/拡張期血圧100~109。
※【Ⅲ度高血圧】:収縮期血圧180以上/拡張期血圧110以上。
・この薬の使用を考慮に入れていないグラフでは、血圧を下げるほど脳卒中のリスクは下がる。
・このグラフは、薬の使用の有無で分けたデータである。
・左の図は降圧薬不使用の場合で、血圧が高いほど脳卒中のリスクは高まる。
・右の図は降圧薬使用の場合で、血圧と脳卒中のリスクに相関関係は統計学的にも認められない。特に注目すべきは、薬を服用し、血圧が【至適血圧】になっている場合、脳卒中の発症リスクが4.1倍と激増している点である。
・「血圧は低ければ低いほど健康に良い」という主張は、降圧薬を服用している人には当てはまらない。
・この表が具体的な数値で見たリスク比である。
・男女に関係なく、薬を服用していると脳卒中のリスクは高まる。
・特に男性では、薬で【正常血圧】、【正常高血圧】に抑えても、6.69~15.30倍ととんでもなく高い。
・脳卒中の発症リスクだけを考えると、「【Ⅲ度高血圧】でもない限り、降圧薬を使うのは意味がない」という主張までできてしまう。
・このデータは年齢、過体重、喫煙、飲酒、糖尿病、コレステロール値、脂質異常症治療薬使用の有無で調整されているものなので精度は高い。
・合併症がある場合、降圧薬に血圧を下げる以外の効果を期待していることがあるため、減薬や中止は難しい可能性がある。(いずれにしても、降圧薬の減薬や中止は医師の判断が必須である)。
四 降圧薬の効果を知る
●「日本一の薬」の効果とは?
最初に、第1章 疑惑だらけの「降圧薬」治療 一つの薬が1000億円以上売れる から、降圧薬の売上ランキングをご紹介します。なお、降圧薬はベスト100の中に、1位の「ディオバン」をはじめ、計11種類の薬がランクインしており、降圧薬がいかに大きな市場となっていることが分かります。
・日本で最もよく使われている降圧薬はカルシウム拮抗薬(CCB)であり、次はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)である。
・CCB(代表的なCCBはアムロジン[成分名:アムロジピン])とARB(代表的なARBはディオバン[成分名:バルサルタン])を比較したデータは次の通り。血圧の状態や個人差による違いはあるが、十分に参考になる。
・CCB[アムロジピン]の方がARB[バルサルタン]より降圧効果は高い。
・バルサルタン単体(⑦⑧)は薬の量を半減させてもほとんど変わらない。収縮期血圧:ー5.1⇒ー4.9、拡張期血圧:ー3.9⇒ー3.6。
●平均値はわずか「マイナス5.5~マイナス9.1mmHg」!
1.参考となる論文:2003年発行の「British Medical Journal」誌に掲載された“Value of low dose combination treatment with blood pressure lowering drugs: analysis of 354 randomised trials”
・対象となった患者数は、のべ56,000人、これほど大規模で信頼性の高い論文はない。
・降圧薬を通常量用いるとその種類を問わず、血圧に対する効果は、①収縮期血圧:マイナス9mmHg ②拡張期血圧:マイナス5mmHg 程度である。
・薬の量を半分あるいは倍増しても平均すると、①収縮期血圧:1.9mmHg ②拡張期血圧:1mmHg 程度しか変わらない。さらに、半減(通常量の4分の1)させても同様に大きくは変わらない。これは、薬を減らすことが難しくないという理由でもある。
・『個人差もありますし、急に中止すると血圧が急に変動する薬もそんざいするので、薬の量の調節を自己判断で行ってはいけません。』
たんぱく質と糖質の制限
今回のブログは北里大学研究所病院の腎臓内科・内分泌代謝内科の部長と糖尿病センターのセンター長を兼任されている山田悟先生が”MedicalTribune”に寄稿された“蛋白質制限食は有効かもしれないが命がけ?!/揺れ動くガイドラインの推奨”という2019年11月の記事がきっかけです。このメディカルトリビューン社さまの記事を読むには、会員登録が必要なためご紹介できないのですが、『2013年に米国糖尿病学会(ADA)が栄養勧告を改訂した折(ADA2013)、いくつか受けた衝撃の1つが、蛋白質制限食の意義を否定したことであった。』という内容に目が点になってしまい、調べてブログにアップしたいと考えました。
そこで、山田先生の著書の中から“たんぱく質”のことが書かれている、『カロリー制限の大罪』という本を見つけ、拝読させていただくことにしました。
山田先生はロカボ(ローカーボハイドレート)という“緩やかな糖質制限”による食事法を推奨されています。“ロカボ”に関しては、以下のホームページをご覧ください。
ブログは、最初に「おわりに」の中の冒頭と最後の部分をご紹介しています。これは、先生がロカボを推奨するようになった経緯と、読者に伝えたいとされるメッセージが出ているためです。
続いて、目次を書き出していますが、黒字がブログで取り上げた項目です。
おわりに
『「ヘルス・リテラシー」という言葉があります。リテラシーとは、ものを読み書きする力のことだそうで、ヘルス・リテラシーとなると、巷にあふれる健康情報の中から適切なものを取捨選択して、効果的に利用する個人の能力ということになるそうです。
ここ数年での栄養学の大転換は、実は医療従事者のヘルス・リテラシーに大いなる疑念をつきつけています。
私自身が10年前まで糖尿病の患者さんに強く推奨していたのが、カロリー制限であり、脂質制限でした。しかし、私が指導したカロリー制限で、ご自身の大切な喜寿のお祝いの会を台無しにしてしまった患者さんのお声を聴き、あるいは、私がおすすめした脂質制限食で、まったく高脂血症が改善できずに泣き出した患者さんのお顔を拝見するうちに、私自身、そうしたゴールデンスタンダードの食事法への疑念をいだくようになり、何が本当に適切な食事法なのかを追い求めるようになりました。』
『本書は、健康的な食事法に関心のある一般の方と、当たり前・言い伝えの栄養学ではなく、科学としての栄養学を学びたいと思っている医療従事者の方々が読んでくださることを願いながら執筆してきました。それが今回、一つ一つのデータに参考文献をつけた理由です。
一般の読者の皆様におかれては、ぜひ、「当たり前」に流されることなく、「正しい」と「当たり前」を区別していただきたいと思います。
そして、医療従事者の読者におかれては、私が師から教わった言葉をお伝えしようと思います。
「人間は未来永劫、真実をつかむことはできない。観察された事実をもとに真実を想像することしかできない。円錐を横から見れば三角形、上から見れば円形。それらは、いずれも事実だが、いずれも真実ではない」』
目次
第1章 カロリー制限の意義を考える
パート1 私自身のカロリー制限
・一日1600kcalを目指して
・カロリー計算を断念
・突然、気持ちが切れる
・カロリー制限は“理想的な餅”?
パート2 アンチエイジングに対するカロリー制限
・正反対の結論を出した2つの研究
・合同研究でも食い違った検証結果
・カロリー制限をして増えた病態とは
パート3 肥満に対するカロリー制限
・日本肥満学会のカロリー制限の基準
・“カロリー制限最良”論には科学的根拠がなかった
・カロリー制限は短期では有効だが……
パート4 糖尿病に対するカロリー制限
・すべての糖尿病患者にカロリー制限を推奨する日本
・日本人を対象にした研究はたった3件
・明らかな矛盾
・多くの日本人糖尿病患者は肥満ではない
・カロリー制限により糖尿病の種々の病態は改善されるか?
パート5 糖尿病治療のカロリー制限設定は妥当か?
・一日約2300kcalが標準と定められた
・「水を飲んでも太る」は本当?
・糖尿病治療のためのカロリー設定値を確認する
パート6 カロリー制限の安全性はどうか?
・カロリー制限の有効性を証明するはずだった研究の結果
・やる気のある被験者が次々脱落
・カロリー制限で減量できなかった少女ザル
・恐ろしい低栄養リスク
第2章 脂質制限の意義を考える
パート1 油を制限したら何に効くのか?
・脂質制限が有効だと思っていた私
・糖質制限に脂質制限を加えたがる人
パート2 高脂血症に対する脂質制限
・油を制限しても高脂血症予防はできなかった
・高悪玉コレステロール血症は食事や運動では改善しない
パート3 肥満症に対する脂質制限
・油を制限したら代謝が低下
・異なるホルモンの影響が想像される
パート4 糖尿病に対する脂質制限
・脂質は血糖上昇と負の相関だった
・食後血糖の上昇を抑える脂質+たんぱく質
パート5 脂質の質をどう考えるか?
・脂質摂取量の上限を撤廃したアメリカ
・脂肪酸の構造と分類
・日本人が動物性脂質を積極的に摂るべき理由
・健康を増進させる一価不飽和脂肪酸&オメガ3多価不飽和脂肪酸
・評価が分かれるオメガ6多価不飽和脂肪酸
・トランス脂肪酸は要注意
・認知症の予防効果が期待される中鎖脂肪酸
・油をたくさん食べるとどうなる?
第3章 三大栄養素比率を考える
パート1 カロリーを把握する難しさ
・正確なカロリー計算は可能か?
・カロリー計算は当てずっぽう
パート2 三大栄養比率はどのようにして決定されるのか?
・「正しい栄養バランス」の違和感
・PFCバランスはこうして決められた
・たんぱく質と油―撤廃された上限
パート3 カロリーや栄養素バランスは考えなくてもよい
・緩やかな糖質制限はカロリー制限にもなる
・現代人の運動量では消費しきれない糖質
第4章 ケトン体の意義を考える
パート1 ケトン体を出させる薬のものすごい効果
・SGLT2阻害薬
・死亡率が32%も減少
・ケトン体が臓器を元気にする?
・ケトン体仮説への反論
パート2 なぜ、ケトン体に負のイメージがあったのか
・ケトン体産生食と減量効果
・ケトン体と悪玉コレステロールの関係
・極端な食事制限が血管内皮機能を低下させる
・ケトアシドーシスと心臓死
・ケトン体と胎児の奇形の問題
パート3 結局ケトン体はいいのか悪いのか
・ケトン体についての結論
・てんかん治療のためのケトン体産生食
・サプリメントとオイル
・ロカボとケトン体
・ケトジェニックダイエットについて
第5章 ロカボの意義を考える
パート1 糖質過多で起こる肥満と糖尿病
・そもそも糖質とは
・なぜ太るのか?
・インスリン分泌能力
・恐ろしい高血糖
・糖尿病に根治療法はない
・老化と糖化
・AGEや酸化ストレスが起こすこと
パート2 ロカボという万能選手
・緩やかな糖質制限
・ロカボを実践するとこうなる
・とにかく「満腹」を目指せ
・脳のために甘いものを、は迷信
・カロリーのことはきっぱり忘れてよし
・ロカボでおなかいっぱいに
パート3 スポーツとロカボ
・アスリートの食事をどう考えるか
・カーボローディングで食後高血糖に
・ファットアダプテーションへの切り替えタイミング
・プロポーションが問われるスポーツと階級制スポーツ
・エネルギー利用可能性
・東京オリンピックに向けて
第6章 ロカボの普及で世界が変わる
パート1 ロカボの取り組み最新情報
・ロカボ先進都市・神戸
・行政も後押し
・東京が動き出した・大丸有の取り組み 三菱地所
・企業がぞくぞくと商品開発
・栄養成分表示の現状
・2015年の大転換
パート2 ロカボが目指す社会
・ロカボで社会はこう変わる
・医療費、社会保障費の大幅削減に
第7章 常識・非常識を考える
パート1 食品編
・果実
・異性化糖
・スムージー
・黒い食べ物
・白くない砂糖
・甘味料
・ビール
パート2 食べ方編
・グルテンフリー
・食べ順
・絶食
パート3 その他の問題編
・腸内フローラ
・たんぱく質の量
・たんぱく質の質
・サプリメント
・薬
・日本人と欧米人
パート4 油編
・基本的な油の働き
・役に立つ油
・基本的にすべての油がOK
・危険な油は
・さまざまな油に対する見解
最終章 栄養学「正しい」と「当たり前」
・科学的検証
・エビデンス
・おわりに
・参考文献
第3章 三大栄養素比率を考える
パート2 三大栄養比率はどのようにして決定されるのか?
・たんぱく質と油―撤廃された上限
●2013年、アメリカ糖尿病学会は、「たんぱく質を制限しても、腎機能の保護にはつながらない」、「理想的な三大栄養素比率など存在しない」と断言している。そして、脂質についても、今のアメリカの食事摂取基準は「そもそも油の摂取量は、栄養学的な関心事項ではない」としている。
参考文献の記載をたどると、下記のサイトに行きつきます。なお、日本語訳は山田先生の寄稿、“蛋白質制限食は有効かもしれないが命がけ?!” の中に書かれていた内容を拝借しました。

■For people with diabetes and diabetic kidney disease (either micro- or macroalbuminuria), reducing the amount of dietary protein below the usual intake is not recommended because it does not alter glycemic measures, cardiovascular risk measures, or the course of glomerular filtration rate (GFR) decline. (A)
『腎症のある糖尿病患者が蛋白質摂取を一般人未満に制限することは推奨されない。なぜならば、それは血糖管理、心血管疾患リスク、糸球体濾過量(GFR)低下になんら変化を与えないからである。(A)』
アメリカ糖尿病学会では内容を毎年見直しているとのことです。そこで、色々と探していると、またまた新たな記事を見つけました。こちらは2019年のお話です。
“第12回 米国糖尿病学会の2019年版診療ガイドライン速報 糖尿病・代謝 能登 洋(聖路加国際病院)” こちらの記事もm3という会員登録が必要なサイトの記事のため、ご紹介することはできないのですが、元々はアメリカ糖尿病学会のものなので、そちらをお伝えします。

■For people with nondialysis-dependent CKD, dietary protein intake should be approximately 0.8 g/kg body weight per day (the recommended daily allowance). For patients on dialysis, higher levels of dietary protein intake should be considered. B
『透析していないCKDの患者さまの場合、食事によって1日あたり約0.8 g / kg体重(60㎏の人は1日48g)のたんぱく質摂取が推奨されています。一方、透析中の患者さまの場合は、食事によって高レベルのたんぱく質摂取を考慮する必要があります。B [意訳しています]』
国内ではたんぱく質摂取はどんな状況なのだろうかと思い、調べてみたところとてもユニークなサイトを発見しました。

監修をされているのは下記の先生方です。
廣村桂樹、池内秀和(群馬大学医学部附属病院腎臓・リウマチ内科)
齊賀桐子(群馬大学医学部附属病院・栄養管理部)
川島崇(群馬県医師会)
高橋さつき、岡美智代(群馬大学大学院保健学研究科
このページの“スタート”をクリックすると、「6 食事の留意点とコツ」というページがあります。
この中から“慢性腎臓病のステージG3a、G3b、G4、G5 たんぱく質制限についてわかります”をクリック頂くと、2ページ目に、“2.体に合ったたんぱく質摂取量は、どのくらいなの?”が出てきます。ここでご自分のステージと身長を入力すると、“標準体重”と“たんぱく質摂取量”が表示されるのですが、G3aの場合、たんぱく質制限は0.8~1.0g/kg/日となっています。つまり、このサイトではG3aの場合は1日の摂取すべきたんぱく質は体重1kgあたり、0.8~1.0gを推奨しているということです(お伝えしたいことは、細かいのですが、0.8gではなく0.8~1.0gというところです)。
以上のことから、アメリカ糖尿病学会においても、たんぱく質の摂取はとてもデリケートな問題で、今後も、医学の進歩と伴に変わっていくかもしれません。
また、求められていることは、病気の進行度合いと推奨摂取量を考慮しながら、ひとり一人に適したたんぱく質摂取の計画と管理を行うこと。そして、特に注目すべきは、透析中の患者さまの場合は、高レベルのたんぱく質摂取を考える必要があるという点です。
第4章 ケトン体の意義を考える
パート2 なぜ、ケトン体に負のイメージがあったのか
・ケトアシドーシスと心臓死
●インスリンを出せないⅠ型糖尿病の人の中に、まれに肝臓が無制限にケトン体をつくり続けてしまうことがあり、次第に体が酸性化し重篤な意識障害につながる。このような状態をケトアシドーシスという。
●ケトン体産生食には問題を指摘する症例と問題ないとする症例が混在しており、はっきりしたことは分かっていない。
ケトン体産生食の是非について、以前ブログ“ケトン体エンジン”の時にご紹介させて頂いた、宗田哲男先生の『ケトン体が人類を救う』には次のような分かりやすい説明がされていました。

『火事(アシドーシス)で現場に駆けつけたら、ケトン体がたくさんあった。そこで火事の原因をケトン体に違いないとして「ケトアシドーシス」という名前を付けた。インスリンが不足してブドウ糖をエネルギーにできない火事の現場で、ケトン体は自らがエネルギーとなって、必死に体を助けていた。ケトン体は火事を消そうとしていた消防士だったにもかかわらず、その後もずっと犯人にされてしまった。「糖尿病ケトアシドーシス」とは、本来「インスリン不足高血糖制御不能状態」というべきであって、ケトン体とは何も関係ない。インスリンを投与して高血糖を抑えればケトン体は消えるが、これは消防士が引き上げて、正常任務に戻ったのであり、「ケトン体さんご苦労様でした」というべきところです。』
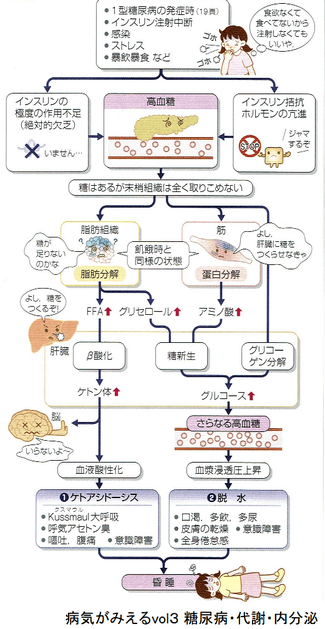
この『病気がみえるvol3 糖尿病・代謝・内分泌』の図をみると、「よし、糖をつくるぞ!」(図中央)とはりきる肝臓が、筋に働きかけ“糖新生”によりグルコースを、また脂肪組織に働きかけ“β酸化(脂肪酸の代謝経路)”によりケトン体の産生を高めています。
そして、この図で起きていることが何かを見てみると、原因(最上段のボックス)によって引き起こされることは、一つは“インスリン拮抗ホルモンの亢進”(右側)、もう一つは“インスリンの絶対的欠乏”(左側)であり、宗田先生がご指摘されている『「糖尿病ケトアシドーシス」とは、本来「インスリン不足高血糖制御不能状態」というべきであって、ケトン体とは何も関係ない。』
というご指摘と一致していることが分かります。この図を見る限り、ケトン体は悪者ではなく、インスリン不足でブドウ糖をエネルギーにできないという火事の現場に駆けつけた、責任感の強い消防士のように思えます。
第5章 ロカボの意義を考える
パート1 糖質過多で起こる肥満と糖尿病
・そもそも糖質とは
●糖質は多糖類、オリゴ糖類、二糖類、単糖類、糖アルコールという5種類に分類される。
●単糖類はブドウ糖や果糖のように1個だけで存在するもの。
●二糖類は砂糖、ショ糖、麦芽糖など、単糖類が2つ結合したもの。
●多糖類は結合が数百~数万個以上であり、代表格はでんぷんである。
●「糖類」とは単糖類と二糖類の総称であり、いずれも甘さが特徴である。
●糖アルコールは自然界にある成分をもとに、人工的に作り出されたもの。
●糖アルコールにはトレハロース、パラチノース、キシリトール、エリスリトールなどがある。
●糖アルコールの中には血糖値をほとんど上げないものもある。
・なぜ太るのか?
●あらゆる糖質は基本的に体内でブドウ糖に変換される。
●血糖値とは血液中のブドウ糖の濃度のことである。
●食後、血糖値が上がると膵臓からインスリンというホルモンが速やかに分泌され、全身の臓器にブドウ糖を送り込み、エネルギーとして利用できるように働く。通常であれば、これによって血糖値は下がるため問題はない。
●血糖値の正常値は食前で70~110㎎/㎗、食後で70~140㎎/㎗で、通常は食後の血糖値上昇は30㎎/㎗程度である。
●40歳を越えるとインスリンの分泌が緩慢になるため、健常者でも跳ね上がるようになる。特に糖質摂取の多い人は異常な数値までに上がったり、乱高下したりするようになる。
●血糖値が180㎎/㎗くらいまで上昇すると、後からインスリンが過剰に分泌されるようになり、食後、一過的に血糖値が大きく下がる人もいる。
●血糖値の大きな上下動は、動脈硬化症や認知機能の低下をもたらす。
●食後高血糖は体を傷め(これを「糖毒性」という)、さらにインスリン分泌を遅くする。この結果、高インスリン血症により肥満が進む。
●食後高血糖は時間経過とともに悪化し、疲弊したインスリン分泌細胞は、やがてインスリンの分泌が困難になり糖尿病になっていく。
・インスリン分泌能力
●生物にとって糖質は最も効率の良いエネルギー源である。
●運動量が多かった昔の人は、体内に取り込んだ糖質を1日の活動で消費していた。[現代のように糖質が潤沢な食糧事情でもなかったと思います]
●文明が高度に発達し、体を動かす機会が少なった現代人は、体の中で糖質がダブつきやすくなっている。
●2015年、サッポロビールが実施した「食習慣と糖に関する20~60代男女1000人の実態調査」によると、現代の日本人が1日に摂取する糖質量の平均は、男性309g、女性332gとなっている。この摂取量はあまりに多すぎて、ほとんどの人は1日の活動では消費しきれるものではない。そして、エネルギーとして使われず余ったブドウ糖は、インスリンによって脂肪に変換され、体の中に溜め込まれる。
●体に余分な脂肪が増えるとインスリンの効きが悪くなり、それをカバーするために、体は更にたくさんのインスリンを分泌する悪循環に陥る。
●膵臓はインスリンを作るのに疲れ、分泌量が減る。そして、血糖値がコントロールできなくなって、慢性的な高血糖である糖尿病を発症する。
・恐ろしい高血糖
●糖尿病の恐ろしい点は三大合併症である。これは高血糖により毛細血管が傷むことにより、腎臓、目、神経の障害を引き起こすものである。
●腎臓が傷むと人口透析に至り、目は網膜症によって失明の恐れがある。神経障害は起立性低血圧や尿失禁、EDを引き起こす。
●糖尿病患者の中で様々なガン患者が増えているという事実があるが、インスリン自体がガン細胞を増殖させているのではないかと言われている。なお、この傾向は食後高血糖(糖尿病予備軍)にも当てはまる。
●糖尿病は、動脈硬化のリスクを上げ、心臓病や脳卒中などの脳血管障害と脚の障害を起こしやすくする。
・糖尿病に根治療法はない
●人間の糖尿病の根治治療はまだ見つかっていない。[1994年、マウスに抗CD3抗体という物質を投与することによって、インスリン分泌細胞を再生させ、高血糖を長期的に改善させることに成功した]
●現在は、食生活の改善と運動習慣によって食後血糖の上昇に歯止めをかけるしか道はない。
・老化と糖化
●肥満、糖尿病以外にも糖質が関わっている身体の現象があるが、それは老化である。
●わかりやすい老化現象には、皮膚のシミや白髪、体の不調、認知機能の低下などがあるが、いずれも糖質が深く関わっている。
●糖質の多い食事により高血糖の状態になると、体の中で糖化反応(グリケーション)が起こる。これは体の中のたんぱく質に余分な糖がくっつき、たんぱく質が劣化してAGEs(糖化最終生成物)を生成する反応である。
・AGEや酸化ストレスが起こすこと
●AGEsが蓄積すると肌や髪、骨などに含まれるコラーゲン分断が起こり、全身の老化が進行する。そして、体調不良や糖尿病、高血圧、ガン、動脈硬化など様々な病気を引き起こす。
●血糖の激しい上下動によって、酸化ストレスが引き起こされる。酸化ストレスは老化や細胞のガン化に関わる。
●血糖の上下動の大きさと認知症の低さには、相関があるとされている。
第7章 常識・非常識を考える
パート1 食品編
・果実
●糖質の中で特に注意すべきものは果物やハチミツの甘さのもとになっている果糖である。
●果糖は体内に入ると肝臓で20%だけブドウ糖に変換され、残りは果糖のまま血中をめぐる。血糖値とは血中のブドウ糖の量を測ったものなので、果糖は血糖値をあまり上昇させない。そのため糖質制限をしている人も果物は食べても問題ないと考えがちである。
●果糖の問題は非常に中性脂肪に変わりやすいため、肥満や脂肪肝につながりやすい糖質であることである。太りやすさの観点では果糖は砂糖やお米よりも危険である。
●果糖は直接的に肝臓のブドウ糖合成を促進する。また、ブドウ糖よりも糖化を起こしやすく、臓器障害や動脈硬化を増やす原因になっているという論文も出ており、果糖にも注意しなければならない。
●果物には食物繊維も多く、ビタミン、ミネラルも豊富な食材なので、量に注意して摂取するようにする。
・甘味料
『糖アルコールや人工甘味料は、ロカボを実践する上では絶対にはずせない食材ですが、安全性を心配して、手に取ることを躊躇する人もいまだ多いようです。しかし、実はそのほとんどが偏見や誤解によるものです。
日本でよく使われているエリスリトールは、果物の発酵食品から抽出されるなどした天然由来の甘味料で、糖アルコールに分類されます。摂取すると小腸で吸収され血中へ移動し、そのまま尿で排泄されるためエネルギーにはならず、血糖値も上がりません。アメリカの食品医薬品局FDA、ヨーロッパの医薬品庁EMAともに、摂取する上限量を設定する必要がない、極めて安全な食品に分類しています。
また、アスパルテーム、スクラロースなどの人工甘味料は、アメリカやヨーロッパの許認可庁によるデータで一日に摂取できる上限が定められているものの、その量は缶ジュースにしておよそ15~25本。通常の食生活ではおよそ摂ることがない数値に上限が設定されていますので、普通に使用するならまったく安全と言ってもいいでしょう。』
パート3 その他の問題編
・腸内フローラ
●人間の腸内には100種類以上、数にして約100兆個にものぼる細菌が棲んでいる。
●小腸の終わりにある回腸から大腸にかけては、腸内細菌が種類ごとにまとまり、腸の壁面にびっしりと生息している。その様子が種ごとに群生するお花畑のようであることから、「腸内フローラ」と呼ばれている。
●腸内細菌はこれまで考えられていた以上に頑健で、なかなか変化しないことが分かってきた。
●2015年、イスラエルの研究グループは、食品の血糖値が上がらない食べ方をすることによって、善玉菌が増えるというデータを発表した。
※こちらは”参考文献”に紹介されていた”データ”です。
“Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses”
・たんぱく質の量
●高齢者ほど肉や魚をしっかり食べる必要がある。若い人は一食あたり10gほどのたんぱく質で食後の筋肉合成ができるが、高齢者は20gほどの量が必要になってくるからである。これは肉なら100g程度にあたる。
・たんぱく質の質
●たんぱく質を摂る時に注目すべきは、必須アミノ酸の含有量である。
●アミノ酸とはたんぱく質の構成要素で、アミノ酸が少数結合したものをペプチド、多数結合したものをたんぱく質と呼ぶ。
●一部の特殊なものを除き、たんぱく質は20種類のアミノ酸が結合して作られている。
まとめ
摂りすぎ厳禁の糖質。一方、たんぱく質の摂取量は微妙です。透析患者さまの場合は高レベルなたんぱく質摂取を考慮することが求められています。透析に至っていない患者さまについては、医師と相談し推奨の上限値を意識することが、分子整合栄養医学の面からも重要であるように思います。
※分子整合栄養医学についてはブログ“分子整合栄養医学1”を参照ください。
ゴースト血管
手先や足先の痺れを訴える患者さまは、主に中高年の方に時々みられます。硬くなった筋肉が血管や神経を圧迫しているのが原因ではないかと考え、気になる筋肉や絞扼しやすい箇所に刺鍼するのですが、症状の緩和は末端の指先に近くなるほど難しいという実感があります。
そんな中、“ゴースト血管”はテレビの健康番組で知りました。この“ゴースト血管”を詳しく知ることは、手先や足先の痺れに対する鍼治療の参考になるのではないかと考え、“ゴースト血管”の名付け親である高倉伸幸先生が書かれた本を購入しました。
血管のゴースト化を進める元凶は、「糖化(コゲ)」と「酸化(サビ)」のようです。
ブログは第5章(「ゴースト血管をつくらない33のメソッド」)および、「ゴースト血管にまつわるアレコレQ&A」には触れていません。取り上げているのは、目次の黒字の部分ですが、特に重要と思ったところをまとめました。
目次
はじめに
あなたのゴースト血管化をチェック!
第1章 人は毛細血管とともに老いる
・生命に大きな影響を与える毛細血管
・血管は縦横無尽に体内を走っている
・それぞれの血管のミッション
・毛細血管の運搬法
・毛細血管はホルモンの情報を伝達する
・毛細血管は免疫にはたらく
・毛細血管は体のバランスを保つ
・毛細血管はなぜゴースト化するのか
・Column@高倉Lab がん治療にも応用される「アンジオクラインシグナル」
第2章 ゴースト血管と病気
・血管がゴースト化すると全身に悪影響が!
・重い便秘はゴースト血管のせい?
・毛細血管の減少が肝硬変の原因に!?
・腎機能の低下はゴースト血管が招く
・ゴースト血管が糖尿病の原因に!?
・ゴースト血管と肺の病気
・アトピー性皮膚炎も血管病!?
・過剰な毛細血管がリウマチを悪化させる
・骨粗しょう症もゴースト血管が原因
・ゴースト血管で失明に?
・認知症の原因はゴースト血管だった!
・血管がゴースト化すると抗がん剤が効かない!?
・Column@高倉Lab がん細胞を増殖させる「がん幹細胞」
第3章 ゴースト血管と老化
・体内の37兆個の細胞に「老化」というイベントが起こる
・「糖化」は体のコゲ
・「酸化」は体のサビ
・毛細血管が少ないと老けて見える!?
・毛細血管と肌の深い関係
・毛細血管の減少が薄毛の原因に!
・更年期は毛細血管のダメージから起きる
・Column@高倉Lab 毛細血管がよみがえる「血管新生」のしくみ
第4章 人は毛細血管とともに若返る
・毛細血管は何歳からでも改善できる
・血流をよくすればゴースト化は防げる
・免疫力を上げると毛細血管を維持できる
・毛細血管も自律神経の影響を受けている
・リンパ管は毛細血管のサポーター
・Column@高倉Lab 脳は記憶で傷を修復する!?
第5章 ゴースト血管をつくらない33のメソッド
血管力を上げる簡単メソッドを生活習慣に
Ⅰ 血液の質をよくする
メソッド1 バランスのよい食事を心がける
Ⅱ 「どう食べるか」も重要
メソッド2 食事は腹八分
メソッド3 一気に食べない
メソッド4 一気に飲むのも危険
メソッド5 少量に分けて栄養摂取
メソッド6 糖質はほどほどに
Ⅲ 血管をしなやかにする
メソッド7 うまみ成分を生かす
メソッド8 お酢を活用する
メソッド9 油は選んで使う
メソッド10 スパイスを上手に使う
メソッド11 カリウムを多く摂る
Ⅳ 自律神経のバランスを保つ
メソッド12 呼吸を整える
メソッド13 片鼻呼吸法で副交感神経を活性化
メソッド14 ゆっくりバスタイム
Ⅴ 血流をアップする
メソッド15 運動を習慣化する
メソッド16 1日1回だけしっかり運動する
メソッド17 「ながら」で運動する
メソッド18 かかと上げを習慣に
メソッド19 かかと上げ・応用編
Ⅵ 下半身を鍛えて血流を上げる
メソッド20 スクワットが効く!
メソッド21 ステーショナリーランジで筋トレ
Ⅶ 血管に刺激を与える
メソッド22 血管マッサージで血管を刺激する
Ⅷ ぐっすり眠って血管を修復する
メソッド23 体内時計をリセットする
メソッド24 メラトニンの原料を摂る
メソッド25 夜は光の刺激に注意する
Ⅸ タイツー(Tie2)を活性化する
メソッド26 シナモンを摂取する
メソッド27 シナモン+ショウガで血管の状態を整える
メソッド28 シナモン+バナナで簡単デザート
メソッド29 料理にもシナモンを
メソッド30 注目の食材・ヒハツを摂る
メソッド31 ヒハツを料理に使う
メソッド32 春の山菜・ウコギを摂る
メソッド33 ルイボスティーを飲む
ゴースト血管にまつわるアレコレQ&A
おわりに
第1章 人は毛細血管とともに老いる
それぞれの血管のミッション
●動脈
・動脈の直径は1~30mm、弾力性があり、内膜・中膜・外膜の三層構造である。内側には薄い細胞の層である「血管内皮細胞」が敷き詰められていて、ここからNO(一酸化窒素)が分泌されていると、しなやかな血管を維持することができる。
●静脈
・血管外に出たリンパ球(白血球)は主にリンパ管を通って静脈に戻る。
・静脈も動脈と同じ三層構造だが、血管の壁はかなり薄い。
・静脈には部分的に内側がひだ状になった弁があり、これにより血流が逆流することを防いでいる。
・筋肉や体の動きによって、静脈内の血液の流れは変わる。
●毛細血管
・毛細血管は約0.01mm。全長は数千~数万Km。全身の血管の95~99%が毛細血管。
・臓器や筋肉などに合わせた形状をしている。まっすぐに、あるいは放射状や蜘蛛の巣状になって、全身に張り巡らせている。
・毛細血管の壁から通過して組織に入った酸素が拡散される距離は、およそ50μm(髪の毛の20分の1程度)。つまり、100μmに1本の割合で毛細血管がないと酸素は行き渡らない。
・毛細血管は血管内皮細胞の一層でできている。

「『毛細血管がないと酸素が行き渡らない』となると、どうなるんだっけ?」というとても基本的な疑問が浮かんでしまい検索したところ、高倉先生が解説をされている素晴らしいサイトを見つけました。記事の題名は”【ゴースト血管とは】毛細血管減少の改善・再生に役立つ食事と運動はコレ!”です。ちなみに、私の疑問の回答は”細胞の老化が始まる”というものでした。
毛細血管の運搬法
・毛細血管の内径は約5μm、赤血球の直径は約8μm。このため赤血球が毛細血管を通るとき、毛細血管の内壁と赤血球の表面はこすれ合う。これにより赤血球の酸素や血漿中の栄養が血管内皮細胞の隙間から押し出されて、外側の細胞に届けられる。
・毛細血管内の圧力は外側よりも高いため、外側に向かって勢いよく物質が出ていき、外の組織にサーッと吸収されていく(拡散)。
毛細血管は免疫にはたらく
・がんや異物、細菌が侵入すると、血管内皮細胞が反応して、リンパ球に対する接着因子を分泌。ローリングしながら移動し血管内皮細胞同士の微かな隙間を見つけて、壁細胞の後ろに隠れる。その後、壁細胞同士の間を通って血管外に出ていく。これは免疫を担って出ていく白血球につられて外に漏れる血液成分を、最小限にするためのしくみである。

画像出展:「ゴースト血管をつくらない33のメソッド」
左の図の3つの●は”細菌や異物”です。
上段の図は、免疫細胞の白血球が接着因子によって血管内皮細胞にくっつき、ローリングしている状態です。
中段は、壁細胞の後ろに隠れた状態です。
そして、下段は、壁細胞同士のわずかな隙間から、他の血液成分の漏れを最小限にしながら、白血球が細菌や異物の攻撃のために出動していく様子です。
毛細血管は体のバランスを保つ
・毛細血管には体温を維持する働きもあるが、その調節は自律神経が行っている。
・外気温に対応して自律神経は血液量に関わる筋肉をコントロールする。血液の流れ(血流)は血液の温度低下を防ぎ、体温維持に貢献している。
毛細血管はなぜゴースト化するのか
・毛細血管は加齢により、壁細胞の変性と消滅、それに伴う血管内皮細胞の機能の衰えが起こる。また、内皮細胞と壁細胞の接着を促すアンジオポエチン1というたんぱく質の分泌も減る。これらにより、壁細胞の内皮血管細胞からの離脱が起こりやすくなり、毛細血管は劣化していく。
・高血糖は毛細血管の劣化を加速させる。体内で過剰な糖質とたんぱく質が結びつく変化を「糖化」といい、体内に焦げのような物質「AGE(Advanced Glycation End Products=終末糖化産物)」を発生させる。このAGEは老化の要因の一つである。
・血糖値が高くなるとAGEが発生し、毛細血管の血管内皮細胞の受容体がAGEを取り込む。すると「活性酸素」が大量に発生し、壁細胞にダメージを与える。
・高血圧や脂質異常症によっても血管はダメージを受け、弾力性が失われる。これも毛細血管の老化といえる。
・毛細血管のゴースト化は薬効を十分に浸透させることができないため、病気の治癒率を下げる。
・毛細血管の数は加齢で減少する。皮膚では60~70代の人は、20代の約40%も減少するという報告もある。
第2章 ゴースト血管と病気
腎機能の低下はゴースト血管が招く
・腎臓病の中で最も多いといわれる慢性糸球体腎炎は、糸球体の炎症によってたんぱく尿や血尿が続く病気で、むくみやめまい、高血圧などの症状がある。
・原因には糸球体のゴースト化も考えられる。これは高血糖などにより糸球体の血管内皮細胞を取り巻く壁細胞が剥がれて、漏れてはいけないタンパク質などを排出してしまうという病態である。
ゴースト血管が糖尿病の原因に!?
・糖尿病は尿に糖が出ることが問題ではなく、血液中の血糖値が高い状態のまま続くことに問題がある。つまり、糖尿病は血液や血管にかかわる病気である。
ゴースト血管と肺の病気
・肺の毛細血管は、他の臓器と異なり壁細胞がかなり少なく、血管内皮細胞への接着も少ない。もともと少ないところに、壁細胞の減少が起こると、ダメージもかなり大きくなる。
・肺胞を覆っている毛細血管がゴースト化すると、血管内皮細胞に異物が侵入するリスクが高まり、炎症を起こしやすくなる。マクロファージという炎症性細胞の侵入が多いと、少量のウィルスや細菌にも反応し炎症を生じてしまう。
アトピー性皮膚炎も血管病!?
・アトピー性皮膚炎では体内に異常な毛細血管が増加していることが明らかになった。
・血管新生により誕生した未成熟な毛細血管(血液成分が漏れやすい)により、炎症細胞のマクロファージが活性化する。すると肥満細胞が反応してヒスタミンが放出されやすくなり、知覚細胞が常に刺激されて異常な痒みが起こる。
・ヒスタミンは血管の漏れも誘導するため、炎症状態が継続してしまう。
過剰な毛細血管がリウマチを悪化させる
・関節リウマチの関節の腫れと痛みは、免疫異常によって誤って自分自身の細胞や組織を攻撃し、それによって炎症が起こるためである。
・免疫異常は血管新生による未成熟な毛細血管が関わっていることが判明した。
・炎症を止めるために血管新生が起こるが、壁細胞と血管内皮細胞の接着がゆるい未成熟な血管のため、血液成分が漏れる。その状態のまま血管新生は止まらず、さらに毛細血管が増え続け、炎症も続いてしまう。
認知症の原因はゴースト血管だった!
・アルツハイマー病は脳にアミロイドβというたんぱく質が蓄積することが原因とされてきたが、近年解明されたアルツハイマー病のメカニズムは、血液脳関門を形成している毛細血管のゴースト化(血管内皮細胞の機能低下)が、大きな原因であるとされている。
・毛細血管の壁細胞が失われることで、血管内皮細胞から血液成分が漏れやすくなる。
・かつて悪玉とされたアミロイドβは、脳細胞にとって必要な物質だった。必要とされる分泌がないと血管障害の原因となる。しかし血管がゴースト化すると、アミロイドβの回収・排出が滞り脳内にアミロイドβが過剰に蓄積してしまう。
・アルツハイマー病の引き金は、タウというたんぱく質が異常リン酸化して蓄積し、シナプスに障害を与えることである。シナプスの連動が悪くなり、神経伝達が抑制されて脳機能が低下する。
・タウによる神経への毒性化が始まるのはアミロイドβの蓄積から10年ほどかかるため、アミロイドβの蓄積を病気発症のトリガーとして、この時期に脳の毛細血管を活性化させるような、認知症予防薬の開発も進められている。
血管がゴースト化すると抗がん剤が効かない!?
・がん細胞の増殖のメカニズムを研究する中で、がんとゴースト血管との関係性を発見した。
・細胞は酸素や栄養を使って、細胞内のミトコンドリアがエネルギーを産生するが、がん細胞は酸素が乏しくてもミトコンドリアを介さずに、エネルギーを産生する。
・がんの毛細血管はゴースト血管である。がんの毛細血管には壁細胞は若干あるが、ほとんど血管内皮細胞に接着していない。これは未成熟な血管で伸びることができず団子状になる。このため、酸素や薬剤を運ぶことはできない。
・がん細胞が増殖している組織は低酸素のため、酸素を必要とする放射線治療の効果もあまり期待できない。
・がん細胞のゴースト血管(未成熟な毛細血管)を正常な血管に戻せれば、抗がん剤ががん細胞に行き渡ることになる。また、酸素が十分な状態になれば放射線治療も効くようになる。
第3章 ゴースト血管と老化
「糖化」は体のコゲ
・糖化とは食事から摂った余分なブドウ糖が、体内のたんぱく質と結びついて細胞を劣化させることであり、高血糖の血液を運ぶうちに血管の組織はもろくなり、炎症が起こりやすくなる。
・糖化はAGE(終末糖化産物)という、「体の焦げ」を作る。毛細血管の壁細胞はAGEによってダメージを受け消滅すると、毛細血管はゴースト化するが、AGEは一度蓄積すると、何十年も分解されずに全身の老化を加速させるので要注意である。
「酸化」は体のサビ
・「酸化」は「糖化」とともに老化を進めるもう一つの原因である。
・活性酸素が体内に過剰に発生すると全身が酸化し、錆びた状態になる。
・活性酸素は体内で生まれ、消えていくもので、細菌やウィルスが体内に侵入すると、活性酸素が反応し破壊してくれる。
・もっとも悪性の強い活性酸素のヒドロキシラジカルは、人間の体内の脂質、特にリン脂質に影響を及ぼし、過酸化脂質を発生させる。これが老化やがんなどの病気の原因になると考えられている。
・活性酸素の主な発生原因は、大気汚染、強い紫外線、たばこやアルコール、化学薬品や食品添加物、ストレスなどである。
・毛細血管、特に壁細胞は活性酸素に非常に弱いので、ダメージを受けやすく、それが毛細血管のゴースト化につながる。
・私たちの体内にはSOD(Superoxide Dismutase)という抗酸化酵素が分泌され、過剰な活性酸素を消去してくれるが、加齢とともにSODは減っていく。
更年期は毛細血管のダメージから起きる
・更年期障害の原因は卵巣にエストロゲン分泌の指令を出していた脳の視床下部が、突然分泌ができなくなった状態にパニックになり、以前より数倍の指令を出すために、異常な発汗やめまいが起こるといわれている。
・視床下部は消化機能や自律神経、体温調節などをコントロールする器官のため、それらの調節もできなくなってしまう。
第4章 人は毛細血管とともに若返る
毛細血管は何歳からでも改善できる
・皮膚に傷がつき少し出血したような場合、止血後、好中球やマクロファージなどの炎症細胞が集まり、ダメージを受けた組織を再構築する。その後、線維芽細胞が移動して、場所(細胞外マトリックス)を確保し、血管新生が起こる。この時、必ず毛細血管は伸びているが、傷を治すという緊急事態では毛細血管の伸び方が通常より早い(マウスの実験では、通常の20~40倍だった)。
・ケガをしたり、炎症が起こった場合、ダメージを受けた毛細血管が誘導する炎症反応でVEGF(血管内皮成長因子)などの物質を分泌する。それら[VEGFなど]の物質が既存の血管から新しい血管をつくるように促す。
・血管新生は毛細血管の重要な機能の一つだが、がんや過剰な活性酸素などの環境下では、血管内皮細胞と壁細胞が接着していない未成熟な毛細血管ができることもあり、それらは病気の原因につながる。
・ゴースト血管は「血管伸長」という機能が残っていれば回復できる。そのためにはゴースト血管に血液を大量に届ける必要があるが、これには質のよい血液がしなやかな血管にスムーズに流れることが重要である。
血流をよくすればゴースト化は防げる
・試験管内の実験では、流れのない状態で血管内皮細胞を培養していると、血管内皮細胞同士の接着がルーズになるが、そこに血液の流れを送りこむと、流れに沿って血管内皮細胞が整列をはじめ、真っすぐできれいな接着が誘導される。これは、血管内皮細胞には血流を認識する受容体があるため、血液が流れると細胞内にシグナルが入り、細胞を接着させる因子を活性化させるからである。
免疫力を上げると毛細血管を維持できる
・免疫にはたらく白血球のうち、外敵と戦うT細胞にはキラーT細胞と、マクロファージや樹状細胞からの情報によってリンパ球に命令を出すヘルパーT細胞がある。このヘルパーT細胞は、血管の中だけでなく血管の周囲にも存在している。さらに、この細胞がないと毛細血管は未成熟になるという論文が2017年に『Nature』に発表された。
毛細血管も自律神経の影響を受けている
・毛細血管とその上流になる細動脈の先にある前毛細血管括約筋が、交感神経が優位になると収縮。これにより、末梢の毛細血管に流れる血液が少なくなり酸素が運ばれなくなる。
・過度な緊張やストレスにより、この状態が続くと毛細血管のゴースト化が加速する。
まとめ
1.血管のゴースト化の主犯は、「糖化」と「酸化」
●糖化はAGE(終末糖化産物)という、「体の焦げ」を作る。毛細血管の壁細胞はAGEによってダメージを受け消滅すると、毛細血管はゴースト化する。
●毛細血管、特に壁細胞は活性酸素に非常に弱いので、ダメージを受けやすく、それが毛細血管のゴースト化につながる。
「糖化」と「酸化」は血管のゴースト化を防ぐためのキーワードです。前者は糖質を摂りすぎないこと、後者は暴飲暴食、喫煙を避けること、良い睡眠や適度な運動などを通じ、強いストレスを溜めこまないことが特に重要です。
2.鍼による手指、足趾に対する局所治療について
今まで、手指や足趾の痺れに対し、患部に直接刺鍼することは避けてきました。これはこれらの部位への刺鍼は痛みをともなうのと、効果に疑問を持っていたためです。
しかし、下記のように、皮膚や毛細血管へのダメージに対する炎症反応は、血管新生や毛細血管の成長促進につながるものなので、施術に組み入れる価値はあると思います。また、血流を高めるという狙いでは、患部の上流の硬くなった筋肉や絞扼ポイントも大切だと思います。
●皮膚に傷がつき少し出血したような場合、好中球やマクロファージなどの炎症細胞が集まり、ダメージを受けた組織を再構築する。その後、血管新生が起こる。この時、必ず毛細血管は伸びているが、傷を治すという緊急事態では、毛細血管の伸び方が通常より早い。
●ケガをしたり、炎症が起こった場合、ダメージを受けた毛細血管が誘導する炎症反応でVEGF(血管内皮成長因子)などの物質を分泌する。それらが既存の血管から新しい血管をつくるように促す。
●ゴースト血管は「血管伸長」という機能が残っていれば回復できる。そのためにはゴースト血管に血液を大量に届ける必要があるが、これには質のよい血液がしなやかな血管にスムーズに流れることが重要である。
●血管内皮細胞には血流を認識する受容体があるため、血液が流れると細胞内にシグナルが入り、細胞を接着させる因子を活性化させる。
顎関節症
顎関節症は線維筋痛症と同じように以前から気になっていました。それは、不定愁訴を追っていくと顎関節症は一つの可能性として、よく登場してくるためです。また、何となくモヤモヤした印象を持っていたのですが、考えてみると、それは歯科医なのか整形外科医なのかどちらが診る疾患なのかよく分からないというのが理由だったように思います。
検索してみると、顎関節症の書籍は思ったほど多くなく、選んだのは『噛み締めの謎を解く!』という本でした。これはタイトルに付随して、“歯科医が解明した姿勢の歪み・発症のメカニズム”という見出しが気になったためです。
なお、今回は顎関節症の概要や現状を把握すること、鍼灸治療に反映できるものを見つけることが目標です。
ブログは目次の中の黒字の項目をご紹介していますが、「はじめに」は冒頭のみです。内容は要点と感じた個所の要約と、そのまま抜き出した引用(『』で括っています)とが混在しています。
はじめに
第1章 歯科最大の謎―噛み締めのメカニズム
第1項 あなたの噛み締め度チェック
第2項 歯科最大の謎―噛み締めのメカニズム
①正しい姿勢とはどのような姿勢? 良い噛み合わせとは?
②姿勢を保つ反射の働き
③口元の異常が肩や腰、膝へと伝わっていく
④“あご”が小さくなると頭の位置がずれる?
⑤押し上げ回転と押し下げ回転
⑥7つの姿勢分類と噛み締め型
⑦身体を正面から見た時の姿勢の歪みについて
第2章 噛み締めが引き起こすさまざまな症状
第1項 噛み締めが引き起こす顎関節症
①顎関節症の実態
②女性が男性の2~3倍、顎関節症になりやすい理由
③なぜ口が開かない? 目安は40ミリ
④開口時に起こる関節音(クリック音)
⑤顎関節症のさまざまな症状
●気がつくと噛み締めている
●顎関節が痛い
●あごにひっかかり感がある
●噛むと歯が痛い
●歯ぎしりをする(ブラキシズム)
●ほとんどの人は左側の「噛み締め」
第2項 噛み締めが引き起こす頭痛
①子供にも広がる噛み締めからの頭痛
②緊張性頭痛(非血管性頭痛)と割り箸対処法
●「緊張性頭痛」の治療方針
③片頭痛(血管性頭痛)と女性の患者数
●“こめかみ”周囲に起こる片頭痛の成因
第3項 噛み締めが全身に引き起こすさまざまな不定愁訴
①眼の症状
●細い眼、眼が乾く、三白眼、左右の眼の大きさの違い
②耳の症状
③口、喉の症状―噛み合わせと気道の圧迫
●舌のもつれ・発音障害
●口の中が乾く・口臭がある。舌がしびれる、舌痛
④鼻の症状
●蓄膿症との関係
⑤首のコリ・首が回らない
●首が回らない症状
⑥指先のちりちり感
⑦左右の肩の高さの違い・左右の骨盤の高さの違い
⑧腕が上がりにくく、肩に痛みが起こる(四十肩・五十肩)
⑨自律神経失調症ほか
⑩睡眠時無呼吸症候群と噛み締め
●睡眠時の無呼吸と噛み締めのメカニズム
●無呼吸を招きやすい仰向け寝
●横向き寝で気道を確保する
●呼吸がしやすいうつ伏せ寝
第4項 クリニックでの実際の症例
①症例1 顔が下を向いてしまった男子中学生の患者さん
②症例2 顔が左右非対称だった30代女性の患者さん
第3章 自宅で症状の改善を図るために
第1項 自分の身体の現状をチェック…触診とあごの位置
第2項 マッサージとストレッチを行う
①立っている姿勢で首のストレッチ
②寝転がって肩と骨盤の高さを整える
③日常の生活習慣を変えていく
④片頭痛と緊張性頭痛の対処法
⑤顎関節症・口周辺の対処法
第3項 具体的な運動療法と訓練
①骨盤を押し下げ回転にする運動療法
②股関節、膝、足の不調の対処法
●足のマメ、足の裏の痛み
③舌の訓練
おわりに
はじめに
『あごの関節が痛くて口が開かない、顎関節にひっかかり感があり口が開けにくい、口を開けたり閉じたりすると「カックン」または「ポン」と音がする、下あごを自由に動かすことができない、噛みにくい、噛む筋肉が痛い……。
このような症状を顎関節症と言います。顎関節症はいつも強く噛み締めている状態、慢性的な「噛み締め」が原因で起こります。しかしなぜ「噛み締め」が起きるのか、本人も知らず知らずに「噛み締め」を続けてしまう状態がどのようなメカニズムで起きるのか、実は歯科界の最大の謎となっています。そして「噛み締め」が原因で顎関節症を患った患者さんの多くが、首や肩に頑固なコリなどの症状を訴え、「頭痛がする」、「手足がしびれる」、「精神的な落ち込みがひどい」などの全身的な症状を訴えます。
これまでの長年の治療で、「噛み合わせ」の治療を終えて顎関節の痛みが消え、口が正常に開くようになると、患者さんが訴えていた首のコリも消え、慢性的に感じていた苦痛に改善がみられることがわかってきました。こうした経験から噛み合わせが身体全体に及ぼす影響を無視できないと考え、「噛み締め」がなぜ起こるのか、そのメカニズムを解き明かす研究に20年以上取り組んできました。』
第1章 歯科最大の謎―噛み締めのメカニズム
第2項 歯科最大の謎―噛み締めのメカニズム
②姿勢を保つ反射の働き
・重い指令塔を身体のてっぺんに載せて2本足で立つというとても不安定な構造であるが、視覚や聴覚、あちこちの関節に加わる力や反射などさまざまな感覚や機能をフル稼働させてバランスをとり姿勢を保持している。
・「反射」は姿勢を維持するために特に重要な役割を担う。頭が傾いた時、頭を支える首の筋肉が緊張したり弛緩したりして、頭の傾きを修整する。
・反射は複数あるが、とくに「姿勢反射」は、噛み合わせと深く関連している。身体が揺らぎながら良い姿勢を維持できるエリアを青くし、これを超えてバランスを崩したり倒れたりするエリアを赤く塗ると図3のようなイメージになる。
・『青ゾーンでは、頭は傾くことなく平衡を保ちながら身体が揺らいでいます。そしてこの範囲で身体が揺らぐときは、上下の歯は接触することなく安静位空隙が保たれていると考えます。安静位空隙とは車のハンドルの遊びのようなものです。この“遊びの空間”が確保されているために、上あごから筋肉という紐で吊るされたような構造の下あごも、身体の揺れに合わせて一緒にブランコのように揺れることができます。下あごは身体の動きを感知するセンサーの役割を果たし、姿勢を制御しているというのが、本書の核心になります。』

画像出展:「柔整ホットニュース」
上から2段目の、”延髄・橋に関する反射”の右カッコ内に書かれた“緊張性迷路反射”は、耳石器官が関り頭部を調整します。一方、“緊張性頚反射”は頚部の伸張度に応じて四肢の緊張を変化させるもので、非対称性と対称性に分けられますが、いずれも生後4週間から8週間に最も顕著に見られ、原始反射と呼ばれています。
③口元の異常が肩や腰、膝へと伝わっていく
『あごの痛みを訴えて診察に来る患者さんは、ほとんど身体に歪みがあって姿勢が崩れています。そして首や肩、腰などに痛みを抱えています。患者さんの姿勢は、いったいいつ、どのようにして崩れてしまうのでしょうか?
その発端は、私は“口元”にあると考えています。口を開けたり閉じたり、話したり、食べ物を飲み込んだりする一連の動きは絶妙なタイミングで調和しています。ちょっとでもずれるとしゃべっているときにつばが飛び散りやすかったり、食べ物が口からこぼれやすかったり、頬っぺたや唇の裏側を噛んでしまい、その傷がもとで口内炎になったりします。そして口周辺と身体の筋肉はつながっているため、患者さんの口元で始まった歪みが、筋肉を伝わって全身に波及していくことがわかってきました。』
●口元に起きた異常が全身に波及する流れ
1.食べものの咀嚼や飲み込み、話をしたり息をしたりするときに使う噛む筋肉、舌の筋肉、喉の筋肉などは、口やあご周辺で独立しているのではなく、それぞれが連携し調和しながら動き、首や肩、胸の筋肉とつながり、全身の動きとつながっている。
↓
2.口やあごなど口元に異常が起きると、食べ物を飲み込んだり、話をしたり、とくに呼吸する機能に支障が出る。
↓
3.生命の維持に重要な呼吸機能を守るため、司令塔(=頭部)は台車(=首から下の身体)に、「口とつながっている筋肉に力を入れて引っ張ったり、伸ばしたりして、呼吸が楽にできるようにしろ!」と命令する。あごや頭部の位置をずらしながら、呼吸が楽になる姿勢を見つけると、たとえ頭の位置が身体の重心からずれていたとしても、その状態をキープ7するよう命令する。このため口元や首周辺の筋肉は、常に力が入った状態で固定化する。(図7)
↓
4.口元や首の筋肉が常に緊張・収縮すると、その筋肉につながっている胸、背中の筋肉、それにつながっている腰、臀部の筋肉へと緊張が全身に伝わっていく。身体の筋肉の力が抜けていて、筋肉が緊張と弛緩を繰り返しながら頭が落ちないようにバランスをとる正常な姿勢から、常に筋肉がこわばっている状態に身体が変化し、身体のゆらぎが失われて姿勢が固定化する。
↓
5.筋肉の緊張が定常化した箇所で、コリや痛みが発生する。こうして口元の異常が全身のコリや痛みなどの不定愁訴につながっていく。
『このような流れで口元の異常が全身に及んでいます。逆にこうした流れで生じた頭痛や肩こりなどの不定愁訴は、口元の異常を治せば解消するというのが私の治療方針になります。』
第2章 噛み締めが引き起こすさまざまな症状
第1項 噛み締めが引き起こす顎関節症
①顎関節症の実態
・顎関節症は原因の究明も治療法も確立しておらず、顎関節症の治療を行っても健康保険の対象となる部分は少ない。そのため収入につながらない。これが立ち遅れている一因でもある。
・顎の関節が痛い、口が開かない、口の開け閉めで音がする、顎や舌が動かしづらい、顎に引っ掛かり感がある、これらは顎関節症の症状である。これらの原因は主に「噛み締め」状態が長期間、絶え間なく続くためである。
②女性が男性の2~3倍、顎関節症になりやすい理由
・男女の身体の使い方の違いに原因があると考えている。
・特にスカートやハイヒールをはいた時など、多くの女性は綺麗な姿勢を意識するため、骨盤は強い押し上げ回転となる。一方、女性はあごの発育が小さく口の中が狭いため、気道を広げるために頭は押し下げ回転傾向にある。つまり、骨盤と頭の回転はいつも逆向きとなり、腰椎や頚椎に歪みを発生させる。そして、それが「噛み締め⇒顎関節症」につながる。

画像出展:「噛み締めの謎を解く!」
左は、顎は押し下げ傾向にあるにもかかわらず、意図的に骨盤を押し上げるケース。右は、骨盤が押し下げ傾向にあるにもかかわらず、噛み締めのために顎を引いているケース。これらの無理な姿勢が繰り返されて、腰椎や頚椎に歪み(赤曲線)がうまれていく。
⑤顎関節症のさまざまな症状
●気がつくと噛み締めている
・傾いた頭は姿勢反射によって平衡状態に戻されるが、気道確保などの理由で姿勢反射が働かず、首が曲がったままの状態が続くと、首にスイッチがある頸反射が働き続け、顔を上げ下げする筋肉が収縮する。また、首の筋肉に連動して噛む筋肉が緊張し続け、本人が気づかないうちに「噛み締め」がおきる。
●顎関節が痛い
・低い冠やブリッジ、低い義歯の装着、奥歯を抜いたままの放置などによって、奥歯の高さが低くなると、噛み締めの力は、本来は受け止めるべき奥歯ではなく、下あごの顎関節頭と関節円板で受けとることになる。顎関節頭は円板の後方にずれ落ち、噛み締める力は顎関節頭から直接、鰐関節窩に伝わり、圧迫し、傷つけ、噛むたびに顎関節が痛む。

顎関節の構造です。この画像は大阪市にある「MDC(モリサキデンタルクリニック)」さまから拝借しました。
●あごにひっかかり感がある
・口を開ける時に感じる“あごの引っかかり感”は、顎関節頭が関節円板の後方に滑り落ちている状態で起きる。大きく口を開ける時に顎関節頭は前方に滑走するが、関節円板が移動を妨げると、“あごがひっかかるような”感じを覚える。
●噛むと歯が痛い
・しっかりと嚙合わせる事ができないと訴える人は、上下の歯を接触させながら前後左右に下顎をスライドできない。正しい噛み合わせは、上下の歯列に噛む力が均等に伝わる。噛み締めの圧力が偏り続けると圧力よって歯槽骨と歯の間にある歯根膜を圧迫して炎症を起こし痛みがおこる。この状態を早期接触による咬合痛という。
●歯ぎしりをする(ブラキシズム)
・歯ぎしりは大学や研究機関においても未だに、原因が突き止められていない。
・身体の歪みが解消されない状態が続くと、身体に起こった筋肉の緊張状態を解放するため、無意識に左右の噛む筋肉を交互に緊張させていると考えている。
・歯ぎしりは通常は60~80㎏の噛み締めの力が、ライオンや虎と同じ200~250㎏に及ぶ人もいる。
・歯ぎしりが続くと咬耗や歯周病の進行を止めることは難しい。
・歯ぎしりは蓄積したストレスを発散させ、全身の硬直状態を緩和する行為かもしれない。しかし、度が過ぎた噛み締めや歯ぎしりは治療が必要になる。
・噛み締めや歯ぎしりは、全身の筋肉の緊張と密接に関係している。口元の噛み合わせの治療だけでは改善が望めない場合、運動療法によって身体が硬直しないよう、正しい身体の使い方を身につける必要がある。
●ほとんどの人は左側の「噛み締め」
・噛み締めは、どちらか片方に偏っている人がほとんどである。そして、来院される患者さんの9割ほどは左である。なお、原因は諸説あり明確なことは分からない。
第2項 噛み締めが引き起こす頭痛
①子供にも広がる噛み締めからの頭痛
・噛み合わせの歪みは必ず首に伝わり、その痛みが首から上に向かう場合は頭痛など頭部を中心とした痛み(不定愁訴)を引き起こす。一方、首から下に向かう場合は、肩、背中、腰などを中心とした痛みを引き起こす。
・顎関節症で、慢性的な頭痛をもっている患者さんはほとんど成人だったが、最近では小学生など年齢や性別に関わらず、頭痛に悩む患者さんが増えてきた。
・日本人の3人に1人が慢性的な反復性頭痛をもち、寝込んでしまうほどの痛みを経験した人が34%、国民の約1割は頭痛により日常生活に支障があるという報告もある。
・慢性頭痛は緊張性頭痛と片頭痛が代表的。前者は人口の約8%、後者は約20~30%といわれている。
②緊張性頭痛(非血管性頭痛)と割り箸対処法
・「緊張性頭痛」は、奥歯の噛み合わせの高さが十分ではなく、気道を確保するために頭を押し下げ回転がかかる傾向の強い人が、職場のストレスなどで身体中の筋肉を緊張させた時に、とくに強い筋力を持つ背中の筋肉が収縮して骨盤を押し上げ回転させてしまうことで、引き起こされていると考えている。
・頭と骨盤が逆向きに回転し、腰椎や頚椎に生じた歪みが発端となって全身に起きる不定愁訴のうちの一つの症状ととらえている。

画像出展:「Therapist Circle」
“背中の筋肉”は脊柱起立筋群と呼ばれており、姿勢を維持する“抗重力筋”に該当します。
抗重力筋には筋紡錘(筋肉の長さを認識するための受容器[センサー])が多いという特徴があります。こちらの記事は「インナーマッスル腹筋でシェイプアップ!!」さまのものです。
③片頭痛(血管性頭痛)と女性の患者数
・片頭痛は片側あるいは両方のこめかみから眼のあたりにかけて、脈を打つように「ズキン、ズキン」と痛むのが特徴である。痛みは4時間~72時間ほど続く。女性は男性の約3倍、比較的若い層(10~40代)に起こる。
・片頭痛は血管性頭痛とも呼ばれ、脳や頭の血管が収縮していた状態から急激に拡張したりする時に、心臓の拍動と同じリズムで痛みが起きる。
●“こめかみ”周囲に起こる片頭痛の成因
・噛み締めと鱗状縫合の働きが密接にかかわっていると考えている。ストレスの多い生活によって強い噛み締め状態が長時間続き、噛む筋肉が収縮して硬直している状態が長く続くと、鱗状縫合は閉じたままの状態が続く。ストレスから解放されると、全身の筋肉が弛緩して噛み締めや食いしばりからも解放され、噛み締めによって長期間閉じていた側頭部にある鱗状縫合が突然開き、鱗状縫合に接していた血管の周囲は急激に減圧となって、血管が膨らんだり周囲にひっぱられ、血管を取り巻く神経は引きちぎられて傷つき、拍動を伴った激しい頭痛が発現する。
・『ストレスから開放されたことでセロトニンの消失による血管の膨張と、噛み締めの解消による鱗状縫合の弛緩という、身体の中でただ一ヵ所、2つの膨張要素が重なって三叉神経の損傷が起きるため、こめかみにだけ痛みが出現するというのが私の考えです。この考えについては、今後、脳外科や整形外科、耳鼻科の先生たちとともに検証を進めていきたいと考えています。
まだ私の研究が初期のころ、スプリント装置の装着や、冠を被せる噛み合わせの治療を施して急に「噛み締め」を解放させたときに、患者さんに激しい片頭痛が起きて治療を中断する事が何度もありました。』
第3項 噛み締めが全身に引き起こすさまざまな不定愁訴
①眼の症状
・片頭痛とともに眼の奥に激しい痛みを感じることがある。眼窩の骨は下あごの外側にある咬筋と側頭筋、そして下あごの内側にある翼突筋と結びついている。翼突筋は下あごを前方に押し出す働きがあり、左側に「噛み締め」がある時は、左の咬筋と側頭筋が収縮して下あごを左奥に引っ張り、下あごは左側に移動する。一方、右側の翼突筋も収縮し、足場としている眼の裏側にある骨を歪ませる。そのために左に噛み締めがある人は、右の眼の奥に痛みが起こると考えられる。

こちらの図は「PROTECT GUM」さまから拝借しました。
②耳の症状
・耳の痛みや難聴等の耳の症状は、噛み締めにより、顎関節頭が額関節窩後壁を直接圧迫し、薄い骨で隔てた外耳道を圧迫するために起こる。
・応急措置としては硬直した噛む筋肉をマッサージするのが効果的だが、本格的な治療は噛み合わせを支える奥歯の高さを回復させる歯科治療が必要になる。
・耳鳴りに関しては、顎関節治療によって消えた患者さんもいれば、続いている患者さんもあり、顎関節症との関係ははっきりしていない。
③口、喉の症状―噛み合わせと気道の圧迫
・顎関節症は「身体と噛み合わせの役割」をよく理解していないと、治すのは容易ではなく、かえって症状を悪化させてしまう場合もある。
・特に問題が多いのは、顎が小さい患者さんの歯並びを矯正する時に、歯が並ぶスペースをつくるために、噛み合わせにとって最も重要な小臼歯を抜歯(便宜抜歯)することである。
●舌のもつれ・発音障害
・低い噛み合わせを急に高くすると、口の中が広がることにより、舌の位置が定まらず発音や嚥下機能に障害が起きたり、さまざまな違和感があらわれたりすることがある。
●口の中が乾く・口臭がある。舌がしびれる、舌痛
・噛み締め状態が続くと、筋肉の硬直のために血流が悪化し、唾液腺の働きが弱まり口の中が乾き、唾液による自浄作用の低下により細菌が滞り、口臭などの原因にもなる。また、血流の問題は舌痛や舌のしびれを起こすこともある。
・舌に歯の圧痕がつく症状は慢性的な「噛み締め」によるものである。
④鼻の症状
・アレルギー性鼻炎などの耳鼻科的疾患がないにもかかわらず、鼻で息がしにくいと感じる状態は、口の中に舌が収まるスペースが不足しているために舌が喉に落ち込んで、軟口蓋が押し上げられている状態が考えられる。
⑤首のコリ・首が回らない
・噛む筋肉と首の筋肉は連動している。「片寄った噛み癖」、「片寄った噛み締め」がある人は、首の動きが悪い、首こりがある、疲れてくると首が痛い、首をマッサージすると激しい痛みがあるなど、首を中心とした症状を訴える。このような患者さんは、首の後方、第1~第3頸椎周囲がほとんど硬直している。強く押すと神経に触ったかのような激しい痛みを訴える。そしてこの痛みは、噛み合わせの治療を施すと消える。
⑥指先のちりちり感
・指先がチリチリと痺れ、フライパンなどがしっかりもてない症状は、頸椎5、6、7番目の後方から腕の指に神経が出ているが、この部位の筋肉が長期に渡って硬直し、血流が悪くなって疲労性老廃物が蓄積した状態になると、指先にしびれたような感覚が起こる。
⑦左右の肩の高さの違い・左右の骨盤の高さの違い
・噛む筋肉の収縮により、左肩が上がり[左側を強く噛み続けると]、相対的に右肩が下がる。左肩は背中側に引っ張られ、右肩は下がりながら身体の前側に引っ張られ、左右の肩の高さに違いが生まれる。さらに骨盤は左側が下がり、右骨盤は上がって右膝は伸びてロック状態になる。
⑨自律神経失調症ほか
・噛み締めがあり身体の筋肉が収縮し続けているような人は、筋肉の緊張状態が続き、交感神経が優位に働いて身体を休める事ができなくなる。
・頸反射は睡眠中であっても身体の筋肉を収縮させているために交感神経を興奮させ、なかなか寝つかれない身体の状況を作り、眠りを浅くし、睡眠不足のために疲れが溜まり常にイライラする。
・首には自律神経が通っており、首の筋肉が緊張し続ける事で正常な自律神経の働きを乱す可能性も考えられる。
・頸反射によって首の筋肉の収縮が後頭部周囲の頸椎に集中すると、頸椎に沿うようにして脳に血液を送っている椎骨動脈が圧迫される。脳に血液を送らなければならない時、高血圧を引き起こす可能性が考えられる。
まとめ(鍼灸治療で考えること)
1.顎関節症は長期に渡る過度なストレスが関係している。
2.鍼灸治療の対象は筋肉と自律神経系である。
●筋肉を緩める
・局所…側頭筋、咬筋、外側翼突筋
・全身…後頚部、腰背部、腹部(腸腰筋など)
●自律神経系を調整する
・本治…脈診から判断したツボおよび“全身調整穴”による施術
・特効穴…内ネーブル4点(長野式で用いられているツボ。お臍の際に4ヵ所雀啄+置鍼。花粉症で使われる)※ブログ”花粉症と自律神経”の最後の付記に説明があります。
付記:日本顎関節学会(さいたま市)
色々検索しているときに、「日本顎関節学会」という学会を見つけました。

このサイトには“専門医・指導医一覧”というページがあります。埼玉県は専門医がさいたま市に一つ、指導医が春日部市に一つありました。
スペイン風邪と新型コロナ2
第6章 統計の語るインフルエンザの猖獗
◆全国の状況
-死亡者数の合計
『スペイン・インフルエンザは、大正七(1918)年の「春の先触れ」の後、本格的には、同年10月に始まる「前流行」として、さらに翌大正八(1919)年12月に始まる「後流行」として、二度、日本を襲った。われわれの計算では「前流行」の「インフルエンザ死亡者」は26万647人、「後流行」は18万6673人、合計45万3152人で、この数は、従来言われてきたどの死亡者数よりも多い。これは、従来用いられてきた「流行性感冒」の数値から離れ、「日本帝国死因統計」に戻り、「超過死亡[インフルエンザが流行していなかったと想定したときの死亡者数と範囲を統計学的な手法を使って推定し、実際の死亡者数と比較することでインフルエンザによる死亡者数を推定したもの “国立感染症研究所 感染症疫学センター”より]」の考え方に基づいて死亡者数を計算し直した結果である(「流行性感冒」にも超過死亡に近い見方をしている箇所があるが)。』
-月別の死亡者数
・「前流行」の死亡者数は急速に増大し、大正七(1918)年11月だけで13万人以上を記録し、5月にほぼ終息した。
・このグラフは「前流行」と「後流行」の二つの山があったことを示している。それぞれのピークは大正七(1918)年11月と大正九(1920)年1月で、前者が13万人強、後者が8万弱であった。
-年齢別死亡率
・5歳を過ぎると死亡率は低下するが、15~19歳層から上昇し、男子では30~34歳層、女子では25~29歳層をピークにあとは次第に下降している。このように通常ならば年齢別死亡率の低い層が逆に高いというのが、スペイン・インフルエンザの特徴だった。
◆地方ごとの状況
-府県別インフルエンザ死亡者数(上)
-府県別インフルエンザ死亡率(下)
・人的被害は地方差が顕著であったが、この差は、猖獗を極めた時期、都市の存在、軍隊との関係、置かれた自然条件などからもたらされた。
第8章 国内における流行の諸相
◆神奈川県
-与謝野晶子が感じた「死の恐怖」
・『ところで【新報】は、この時期全盛時代で、発行部数15万部、東京発行のどの新聞より県下で広く読まれていた。そして評論家として与謝野晶子からしばしば寄稿を受けていた。流行性感冒に関し、与謝野は二度の論評を掲載している。
第一回は、「前流行」のさなか、大正七(1918)年11月10日で、「感冒の床から」と題し、その伝染性の強さから説き起こし、自分の一人の子どもが小学校で感染したら家族全員に伝染したことを述べ、ついで、日本の対応の遅さに怒りをぶつけている。政府はなぜ早くから、伝染防止のため、「大呉服店、学校、興行物、大工場、大展覧会等、多くの人間の密集する場所の一時的休業を命じなかったのでせうか」。一方では、警視庁の衛生係ではなるべく人ごみに出るなと警告していることを挙げている。このような政府における意志の不統一は多くの国民を危険にさらしているのだ、と気焔(キエン)をあげている。彼女が我慢ならなかったのは、「日本人に共通した目前主義や便宜主義[問題の根本的な部分にはふれないで、何とか済ませてしまおうとする態度]の性癖」であった。あとは折からの大戦終結に向けての意見なのでここでは省略する。
第二回は「後流行」のさなか、大正九(1920)年1月25日で、「死の恐怖」と題し、かなり悲観的、達観的な筆致になっている。死とは何か、から始まり、今回の流行性感冒によって自分が死ぬとしても、最後まで子ども達のために生きたい、それには予防をし、注射を受け、全力を注いで生きるべく努め、「生」への欲を高揚させること、その後なら「人事を尽くした」のだから、運命とあきらめることもできる、としている。「君しにたまふことなかれ」は有名な晶子の詩であるが、ここではそれを自分に向けたかのように感じられる。』
終章 総括・対策・教訓
◆総括
-なぜ忘却されたか?
・『大正中期、日本は、精神的にも、社会的にも、物質的にも大きな曲がり角にあった。海外から入ってくる社会主義思想と、それに対抗する日本の伝統に立つべしとする考え方とかが正面から衝突し、ひとびと、とくにインテリ層は、自分の位相をはっきりさせる必要に迫られていた。「米騒動」に象徴される社会運動は、これに都市の労働運動も加わり、騒々しさを増していった。日本の工業生産額が、農業生産額を上回ったのも、まさにこの時期のことであった。電力生産量が増え、一般家庭に電灯が行きわたり、夜の生活が一変した。夜なべ仕事や読書が従来よりはるかに容易にできるようになった。
日本は、大した犠牲も払わずに第一次世界大戦の戦勝国となり、国際聯(連)盟の理事国にさえなったのである。日本の国際的地位が上がるとともに、日本の大陸侵出が本格的に始まり、内戦中で有効な対抗手段を持たなかった中国へは、要求、借款、資本進出が相ついだ。これに対して、大戦中または大戦直後のヨーロッパ諸国は、自国の再建に忙殺され、ひとりアメリカのみが日本のアジア侵出を警戒し、そのことに対する日本の対応が、結局、その後の太平洋戦争をもたらす素因となるのである。
国内政治では、男子に限られていたとはいえ、制限付きで普通選挙法が治安維持法と抱き合わせのような形で施行され、大学令によって、私立大学も大学の仲間入りをした。識字率の上昇は、大衆に文字文化を伝え、雑誌、書籍の発行点数が非常な勢いで上昇した。
・『関東大震災による死亡者は、最近の調査で約10万人とかなり減ったが、物的被害の大きさはスペイン・インフルエンザの比ではない。この二つの事件を並べると、人的被害と物的被害が対照的であることに気づく。スペイン・インフルエンザによって、日本の景観は少しもかわらなかったが、関東大震災は、東京・横浜を中心に焼野原を作りだした。本書を記すにあたって、スペイン・インフルエンザ流行期の写真を探したが、ほとんど見つからなかったのも、スペイン・インフルエンザが「絵にはならなかった」からであろう。
ともかく関東大震災の一撃によって、スペイン・インフルエンザは記憶の片隅に追いやられてしまった。さらに、昭和期に入ると、日中戦争、太平洋戦争とスペイン・インフルエンザより、もう一桁多い戦死者や一般市民の犠牲者を出す出来事があいつぎ、その思い出は忘却のなかに薄らいでしまった。ようやく、90年近くを経て、いま、再び新型インフルエンザの到来の危険が叫ばれるようになり、スペイン・インフルエンザが人々の話題に登場するようになったのである。』
◆対策
-人々はインフルエンザにどう対したか?
・『未曽有の大量の死者をもたらしたスペイン・インフルエンザに対し、政府や医学界は何も対策を講じなかったのか。答えはイエスでもあり、ノーでもある。イエスというのは、政府や地方自治体、警察、医学界、病院は、予防ワクチンの注射を勧め、通告を出して、マスクの使用、うがいや手洗いの励行、人ごみをさけることなどを、繰り返し促していた。小学校や中学校では、罹患者が出れば休校となった。こういった注意は、すでに述べてきたように、現在でもわれわれが唯一とり得る対処法であり、呼吸器系の感染症対策の基本である。軍隊が演習を中止したり、鉄道や通信は人手不足で機能を低下させたが、全面ストップにはならなかった。何とかやりくりして、最悪の事態を回避した。何の準備もなかった当時のことを考慮すれば、これには「天晴れ」印を付したいくらいである。スペイン・インフルエンザによる死亡者数が、人口の0.8パーセントでとどまったのも、いく分かはこういった対策が効いたのかもしれない。
しかし、そういった対策は、決して徹底されていたわけではなく、すべてに効果があったわけでもなかった。興業の閉鎖は関東州だけで、他のところではなされなかった。神仏に救いを求めて殺到する満員電車の乗客には、車内での罹患の危険が非常に高かったにもかかわらず、何の規制も加えられなかった。新聞にも、同様の注意が府県、著名な医者の談話として終始掲載され、具体的に、予防ワクチン注射の予定も発表されているが、これはスペイン・インフルエンザ自身に対してなんら効果はなかった。』
新型コロナ感染対策
問題解決の王道は「早期発見、早期対応」です。そして、対策が自分自身で解決できる範囲(ヒト・モノ・カネ)を超える場合は、速やかに上司に相談し、問題解決できる立場(役職)の人を巻き込むことが肝要です。もし、躊躇すれば問題解決のゴールは遠くなります。
これは、私が営業で学んだことです。
政府の感染対策は1年経った今も有事対応には至らず、失敗を恐れて蓋をしてしまったかのようで、根本解決のための積極的な対策は見えてきません。手綱を握りつつ、多くは地方自治体や保健所に丸投げしているようにみえます。うまくいって当たり前、失敗したら厳しい政権批判につながる難しい舵取りのコロナ感染対策からは距離を置き、失敗が少なく英断も不要、多くの国民から評価を得られやすい施策に税金を優先的に投入しているのではないかと勘ぐってしまいます。ちなみに平成30年版厚生労働白書によると、医療関係従事者数は3,206,055人です。一方、日本の有権者数(令和元年の参院選)は、106,587,860人なので、この数字を使って計算すると医療関係従事者は有権者の約3%にすぎないということが分かります。
また、注力している“Go toキャンペーン”にはブレーキがついていないことが発覚し、あらためて危機意識の低さに愕然としてしまいます。アクセルとブレーキを使い分けられない日本政府が、東京オリンピック・パラリンピックを開催することはとても不安です。
溜まっていた政府への不満と愚痴を書いてしまい申し訳ありません。ただ、アクセル(経済活性化)が非常に重要であることに疑う余地はなく、「本当のところ、どうすべきなのだろう?」という疑問から、まずはうまく対応している国を中心にデータを取ってみてはと思い、調べたところ“worldometer”という素晴らしいサイトがあることを知りました。そして何はともあれ、情報収集(集計)を始めることにしました。
なお、”worldometer"と共に、ロイターさまの”COVID-19 Gloval tracker”も興味深いサイトです。
日本(2.891)以外で注目した国は、東アジアが“韓国(1.964)”、“台湾(0.029)”、東南アジアが“フィリピン(8.497)”、“ベトナム(0.036)”、“タイ(0.093)”、“シンガポール(0.494)”、オセアニアが“オーストラリア(3.561)”、“ニュージーランド(0.500)”、欧州が“ドイツ(36.510)”、“スウェーデン(88.386)”、“フィンランド(10.389)”の計11の国です。国名の後ろの( )の数字は、2021年1月5日時点の“人口10万人当たりの累積死亡者数”です。グラフは死亡者数が2桁のスウェーデン、ドイツ、フィンランドを除く9カ国としました。
集計は昨年8月4日からですが、今年の年末まで集計し、約1年半のデータにGDPや失業率などの経済指標を加えて、感染対策と経済対策の関係性について見てみたいと思っています。
今回のブログでは、第2波(第2の山)が大きくなった、日本、フィリピン、オーストラリアの3国に絞り、2021年1月5日までの155日間を対象に人口10万人当たりの、“新規感染者数”・“累積死亡者数”・“累積検査数”をグラフ化しました。以下の表は3カ国ですが、これは12カ国から抜粋したものです。(こんな感じで集計していますということで貼り付けました)

参考:「worldometer」
”Go to イート”および”Go to トラベル”東京参加は10月1日です。「人が動けばウィルスも動く」だと思います。やはり、ブレーキは必須です。

参考:「worldometer」
日本、フィリピンとも明らかに増加傾向です。日本が増え始めた11月5日~1月5日までの2カ月間で両国を比べてみると、日本2.03倍、フィリピン1.25倍となっています。日本は今が最も大事な時期だと思います。

参考:「worldometer」
このグラフでは日本とフィリピンの差が分かりずらいのですが、2021年1月5日/2020年8月4日の検査数は、日本3,986/672(5.93倍)、フィリピン6,230/1,474(4.22倍)と両国も増えていますが、積極的な検査をしているオーストラリアとの差は大きなものです。
日本と検査実態が似ているフィリピンの第2次対策の予算の概要は以下の通りです。こちらは、JETROさまの”フィリピンで新型コロナ対策法第2弾が可決”から拝借しました。
総額1,655億ペソ(約3,641億円、1ペソ=約2.2円)、内訳は予備費(255億ペソ)を除いたものです。
なお、フィリピンの大卒初任給は日本円で約5万円とのことなので、日本の約1/4になります。そのため、投入金額の規模感は4倍の約1兆4500億円程度になります。また、フィリピンのGDPは神奈川県の2824億ドル(”米国個別株とETF【銘柄分析400】”より)を少し上回る規模のようですので、神奈川県が1兆円を超える対策をうったというイメージです。青太字は主に医療に関わる予算ですが、合計すると305億ぺソとなり全体の23.3%になります。
日本はこの後、ご紹介するのですが、フィリピンは日本に比べると予算の用途が明確です。日本は、「緊急対応策第2弾」では、“感染拡大防止策と医療提供体制の整備:486億円”、「第1次補正予算の概要」では“新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(仮称)〔1,490億円〕”内訳も付いているものの、具体的にどのような対策をとって問題解決を図ろうとしているのか、予算からは日本政府の根本解決の強い意志は伝わってきません。これは、与謝野晶子先生がスペイン・インフルエンザのパンデミックの時に指摘されていたと同じように、新型コロナ対策も、目前主義・便宜主義な予算化と言わざるを得ません。
●政府系金融機関への資金注入(394億7,000万ペソ)
●農業・漁業従事者向け補助(240億ペソ)
●医療従事者の雇用経費および福利厚生費用(135億ペソ)
●失業者などに労働機会を提供して収入を補助する「キャッシュ・フォー・ワーク・プログラム」(130億ペソ)
●公共交通の運転手などへの補助(95億ペソ)
●危機的な状況にある個人向け補助(60億ペソ)
●感染者の接触履歴調査員雇用費(50億ペソ)
●医療隔離施設の建設や政府系病院の拡張(45億ペソ)
●新型コロナウイルス感染者の隔離関連経費(45億ペソ)
●観光産業向け補助(40億ペソ)
●遠隔教育推進費用の補助(40億ペソ)
●医療用防護服などの調達費用(30億ペソ)
日本の新型コロナ対策に関しては財務省のサイトにある“令和2年度補正予算(第1号及び第2号)の概要について”が参考になります。
以下に気になる箇所をチェックしながら書き出しました。
1.緊急対応策第1弾
・政府チャーター機による帰国者の生活支援やワクチン等の研究開発の加速などを盛り込んだ、予備費103億円を含む総額153億円の対応策を2月13日に取りまとめた。(予備費を除く金額は、50億円)
2.緊急対応策第2弾
・新たな助成金など学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応や、雇用調整助成金の特例措置の拡大などを盛り込んだ、予備費2,715億円を含む総額4,308億円の対応策を3月10日に取りまとめた。(予備費を除く金額は、1,293億円)
内訳
1)感染拡大防止策と医療提供体制の整備(11.28%):486億円―PCR検査強化10億円(0.23%)、治療薬開発加速28億円(0.64%)など
2)学校臨時休業に伴って生じる課題対応(57.14%):2462億円―保護者支援で1750億円、学童クラブ体制強化等470億円など。
3)事業活動継続縮小や雇用への対応(27.66%):1192億円―雇用調整金特例措置の拡大374億円、資金繰り支援782億円。
4)事態の変化に即応した緊急措置など(3.89%):168億円。
特に“PCR検査強化10億円(0.23%)”と“治療薬開発加速28億円(0.64%)”を足しても対策費の1%にも満たないという現実に唖然としてしまいました。
3.第1次補正予算の概要
1)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費(25兆5,655億円)
(ア)感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発(1兆8,097億円):7.07%
(イ)雇用の維持と事業の継続(19兆4,905億円):76.2%
(ウ)次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復(1兆8,482億円):7.22%
(エ)強靭な経済構造の構築(9,172億円):3.58%
(オ)新型コロナウイルス感染症対策予備費(1兆5,000億円)
まず、“Go toキャンペーン”ですが、上記の(ウ)に含まれています。予算規模は16,794億円です。“新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費”に占める割合は6.56%になります。
次に、“感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発(1兆8,097億円)”の内訳ですが、以下のようになります。
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(仮称) 〔1,490億円〕
(PCR検査機器整備、病床・軽症者等受入れ施設の確保、人工呼吸器等の医療設備整備、応援医師の派遣への支援等)
・ 医療機関等へのマスク等の優先配布 〔953億円〕、人工呼吸器・マスク等の生産支援〔117億円〕
・ 幼稚園、小学校、介護施設等におけるマスク配布など感染拡大防止策〔792億円〕、全世帯への布製マスクの配布〔233億円〕(合計:2,095億円)
・アビガンの確保〔139億円〕、産学官連携による治療薬等の研究開発〔200億円〕、国内におけるワクチン開発の支援〔100億円〕、国際的なワクチンの研究開発等〔216億円〕
・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(仮称)〔10,000億円〕
新型コロナウイルス感染症への対応として必要な、以下を目的とした事業であれば、原則として使途に制限はありません。Ⅰ.感染拡大の防止 Ⅱ.雇用の維持と事業の継続 Ⅲ.経済活動の回復 Ⅳ.強靭な経済構造の構築"
最も気になる“新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(仮称)”は1,490億円なので、「感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発(1兆8,097億円)」の8.23%です。また、“産学官連携による治療薬等の研究開発”200億円は、1.10%、“国内におけるワクチン開発の支援”100億円は0.55%となり、気になる3つの分野への支援は、1兆8,097億円の約10%でした。“新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(仮称)”に1兆円〔10,000億円〕が予定されていますが、主な用途が「感染拡大の防止・雇用の維持と事業の継続・経済活動の回復・強靭な経済構造の構築」となっているので、予算の約55%を占める“地方創生臨時交付金”のうち、どれ程が医療系に回るのか分かりません。もし、1兆円の多くが経済活動に注がれるならば、「感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発(1兆8,097億円)」は名ばかりの予算になってしまいます。
4.第2次補正予算の概要
1)新型コロナウイルス感染症対策関係経費(31兆8,171億円)
(ア)雇用調整助成金の拡充等(4,519億円):1.42%
(イ)資金繰り対応の強化(11兆6,390億円):36.5%
(ウ)家賃支援給付金の創設(2兆242億円):6.36%
(エ)医療提供体制等の強化(2兆9,892億円):9.39%
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金として2兆2,370億円(7.03%)
・医療用マスク等の医療機関等への配布のための経費として4,379億円(1.37%)
・ワクチン・治療薬の開発等の経費として2,055億円(0.64%)
・等々
(オ)その他の支援(4兆7,127億円):14.8%
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充のための経費2兆円(6.28%)
・低所得のひとり親世帯への追加的な給付のための経費1,365億円(0.42%)
・持続化給付金の対応強化のための経費1兆9,400億円(6.09%)
・等々
(カ)新型コロナウイルス感染症対策予備費(10兆円):31.4%
・新型コロナウイルス感染症の第2、3波の可能性が排除できない中、今後の長期戦を見据え、事態の急変に対して臨機応変に対応するための万全の備えとして、新型コロナウイルス感染症対策予備費に追加的に10兆円を計上している。
第1次補正予算の時に7.07%だった“感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発”は、第2次補正予算では”医療提供体制等の強化”9.39%と増額されていましたが、フィリピンの23.3%の半分以下です。もっともっと増額されても良いと思いますが、大事なことは目標と計画です。
このためには、新型コロナ感染対策を“有事”と位置づけ、高い危機意識と危機管理、目標・役割・責任を全うする、縦割り行政を超えた精鋭部隊(感染対策、経済対策、都道府県連系等)を首相直下に配置、そして強いリーダーシップの元、感染拡大阻止のための”ロードマップ”を作り、”覚悟ある決断力”と”状況に応じた柔軟な修正力”をもって、”国民の先頭”に立って新型コロナに立ち向かっていくような、肝の据わった推進力が必要だと思います。なお、これは脱目前主義・脱便宜主義と言えます。
最後に、新型コロナ感染対策は有事であり、”ヒト・モノ・カネ”をダイナミックに動かす必要があるため、この問題のオーナーは各知事(地方自治体)ではなく、”日本政府”であると考えます。
付記1:2021年1月3日朝刊の新聞記事

こちらは、ちょっとマニアックな「埼玉新聞」です。
”勝負の3週間”が空振りに終わり、大晦日に東京、神奈川、千葉、埼玉で新規感染者数の最多を更新、”緊急事態宣言”が要請されました。
『「進むも地獄、進まぬも地獄だ」。自民党関係者は首相の心境をこう推し量った。再発例すれば感染防止の遅れを認めることになる。一方、発令に慎重姿勢を貫けば医療逼迫の政治責任を一身に背負いかねないためだ。』
スペイン風邪と新型コロナ1
まさか生きているうちにパンデミックに遭遇するとは思ってもみませんでした。
前回のパンデミックは約100前の“スペイン風邪(インフルエンザ)”でした。「どんな状況だったんだろう?」という思いからネット検索し、スペイン風邪が日本に広がり始めたのは大正七(1918)年10月であることを知ったのですが、これには少し驚きました。というのは、102歳になっている母親の誕生月が1918年10月だったためです。当時は赤ん坊、今は認知症の高齢者のため、2度に渡ってその脅威に怯える必要はなかったのですが、歴史的には2度のパンデミック経験者ということになります。あらためて、長生きの凄さを実感します。
そんな背景もあり、スペイン風邪の実態を知りたいと思い、見つけたのが今回の本です。
目次の黒字箇所を取り上げていますが、長くなったので前半、後半の2つに分けました。
新型コロナについては後半の最後に、日本を含めた12カ国の日々のデータ(10万人当たりの、“新規感染者数”・“累積死亡者数”・“累積検査数”など)の中から、第2波(フィリピンは第1波の第2の山というべきかもしれません)が大きかった日本、フィリピン、オーストラリアの3カ国について比較しています。
以下は本の表紙の裏側に書かれていたものです。簡潔でとても分かりやすいので最初にお伝えします。
『昨今、「新型インフルエンザ」の脅威が取り沙汰されている。現在、そのウィルスは幸いまだトリからヒトへの感染でとどまっている。しかし、いつそれがヒトからヒトへの感染に変わり、ジェット機時代のおかげで、瞬く間に世界中に広がるか分からない。1918年の人々にとっては、スペイン・インフルエンザがまさに「新型インフルエンザ」だった。世界で第一次大戦の4倍(4000万人)、国内では内地に限っても、関東大震災の5倍近く(45万人)の人命を奪った。これは20世紀最悪の人的被害であり、記録のある限り人類の歴史始まって以来最大でもある。しかし、この史上最悪のインフルエンザは、人々の記録から忘れ去られ、これを論じた著作は日本で一冊も書かれてこなかった。
筆者の願いは、とにかく「スペイン・インフルエンザ」に晒された人々の悲鳴を聞き、状況を知ってほしいという一言に尽きる。当時の人々は、そのような事態に直面して、どう対応したのか、政府は何らかの手を打ったのか、そして、なぜ忘れ去られたのか。将来「天災」のようにやって来るであろう新型インフルエンザに対する備えは、過去の歴史を知ることから始めなければならない。』
目次
序章 “忘れられた”史上最悪のインフルエンザ
第1章 スペイン・インフルエンザとウィルス
◆なぜ「スペイン・インフルエンザ」か?
◆インフルエンザ・ウィルスの構造と特徴
◆新型インフルエンザ発生のメカニズム
◆ウィルス発見をめぐるドラマ
◆ワクチンも「タミフル」も万能ではない
第2章 インフルエンザ発生―1918年(大正7)年春~夏
◆三月 アメリカ
-⁻記録に残る最初の患者
-第一次世界大戦の戦況とインフルエンザの発生
-無視された「春の先触れ」
◆四月-七月 日本
-台湾巡業中の力士の罹患
-ウィルスはどこから来たか?
-軍隊での罹患者の増大
◆五月-六月 スペイン
-800万人が罹患
-「スペイン・インフルエンザ」という名称の誕生
◆七月-八月 西部戦線
-西部戦線の異状
-『京城日日新聞』のスク-プ
-両軍の動きを鈍らせたインフルエンザ
-軍隊から市民への感染拡大
◆「先触れ」は何だったのか?
-アメリカ西部の兵営を起点に拡散
-予防接種的な役割を演じる
-三週間で世界中に
第3章 変異した新型ウィルスの襲来-1918(大正7)年8月末以降
◆アメリカ
-港町で変異したウィルス
-欧州派兵とウィルス
-ディベンズ基地で猛威をふるったウィルス
-米軍戦没者の8割はインフルエンザによる病死か?
-当時の状況を描写した詩文
-文字に記されたインフルエンザと体制への憎悪
-アメリカ国内での感染の拡がり
-流行は1918年に限らない
-少なめに算出された死亡者数
-パニックに陥ったアメリカ社会
-戦勝気分に酔うその足元で
-貧富の違いによる被害の違い
◆イギリス
-最大の被害をもたらした第二波は6週間でイングランド全土に
-突出した壮年層の死亡者数
-三つの流行拡大のパタ-ン
◆フランス
-アメリカ軍、フランス軍、イギリス軍の順に感染拡大
-「アポリネ-ル症候群」
◆補遺
第4章 前流行-大正七(1918)年秋~大正八(1919)年春
◆本格的流行始まる
-前流行と後流行
-従来の記録よりも多い実際の死亡者数
-スペイン・インフルエンザ・ウィルスはいつ日本に襲来したのか?
-軍隊、学校が流行の起点に
-三週間のうちに全国に拡大
◆九州地方
-初期の報道-「ブタ・コレラ」、海外の状況
-罹患者の急増
-都市から周辺部への拡大
◆中国-四国地方
-10月末以降、死亡記事が急増
-「予防心得」、氷の欠乏、医療体制の不備、新兵の罹患
-比較的軽かった中国地方での被害?
◆近畿地方
-被害の大きかった京都、大阪、神戸
-地域によって異なる流行の再発
◆中部地方
-大都市より中小都市、郡部で蔓延
-11月に入り、死者増加
-後になるほど悪性を発揮
-被害が大きかったのは製糸業地帯
-「鶏の流行感冒」
-人口1000名中、970名罹患、70名死亡の村も
-生命保険加入推進のチャンス
◆関東地方
-新聞は意図的に報じなかった
-初発以来数十万人が罹患
-インフルエンザと鶏卵の不足
-記録に残された五味淵医師の奮闘
-前年秋を乗り切った人々が罹患
-東京府・東京市の対応
-報道にみる被害の実態
◆北海道・奥羽地方
-他地方より遅れた初発、その後の状況の悪化
-鉄道が伝染経路に
-郡部で長引く流行
-被害が比較的軽かったと言われる北海道
-一村全滅の例も
◆小括
第5章 後流行―大正八(1919)年春~大正九(1920)年春
◆後流行は別種のインフルエンザか?
-前流行と後流行の症状の違い
-前流行と後流行の間の状況
◆九州地方
-後流行の初発
-「予防の手なし」
◆中国・四国地方
-罹患者の二割が死亡
-地獄絵を見るような10日間
-軍隊内での流行
◆近畿地方
-最大の死亡者を出した地域
-年が改まり、死者がさらに増大
◆中部地方
-抗体をもたない初年兵に多い罹患
-二月に死者増大のピーク
-郡部で猛威をふるう
◆関東地方
-初めは軍隊から
-地獄の三週間
-一割強の死者
-鉱山町での大きな被害
◆北海道・奥羽地方
-軍隊が流行の発生源
-秋田県で最小、福島県で最大の被害
-交通の要衝地での感染拡大
-北海道での惨状
◆小括
第6章 統計の語るインフルエンザの猖獗
◆国内の罹患者数と死亡者数
-低く見積もられた『流行性感冒』における患者数と死亡者数
-超過死亡(excess death)による試算
◆全国の状況
-死亡者数の合計
-月別の死亡者数
-死亡率の男女差
-年齢別死亡率
◆地方ごとの状況
-地方ごとの月別インフルエンザ死亡率
-都市のインフルエンザ死亡率
-府県別インフルエンザ死亡者数
-府県別インフルエンザ死亡率
第7章 インフルエンザと軍隊
◆「矢矧(ヤハギ)」事件
-最高級の資料
-上陸許可後に直ちに罹患
-緩慢な病勢進行と急速な感染拡大
-すでに罹患していた「明石」の乗組員
-マニラ到着直後の安堵
-死者続出の惨状
-階級による差
-症状に関する克明な記録
-同じように襲われた他の軍艦・商船
-「矢矧」の帰還
-ピーク後も未感染者に活動場所を見出すウィルス
◆海外におけるインフルエンザと軍隊
-地中海派遣艦隊を襲ったインフルエンザ
-シベリア出兵とインフルエンザ
◆国内におけるインフルエンザと軍隊
-陸軍病院の状況
-各師団の死亡者数
-海軍病院の状況
-新聞報道
◆小括
第8章 国内における流行の諸相
◆神奈川県
-豊富な資料
-流行の時期
-流行の初発
-死者の増大
-いったん終息、その後再発
-後流行の猛威
-与謝野晶子が感じた「死の恐怖」
-二つの貴重な統計
-僻地で高い罹患率
-都市部と農村部の違い
-郡部で罹患者死亡率の高かった後流行
-前流行と後流行の相関関係
-1920年1月における死者の激増
◆三井物産
-『社報』も語る死者の増大
-社員家族を襲った悲劇
◆三菱各社
-流行期に上昇している社員の死亡者数
-鉱山など生産現場に多い犠牲者
◆東京市電気局
-罹患者の多かった「春の先触れ」
◆大角力協会
-「角力風邪」
-「先触れ」で免疫を得た力士
◆慶応義塾大学
-民間における青年・壮年層の被害の実態
◆帝国学士院
-罹患と外出忌避による欠席者の増加
◆文芸界
-犠牲者
-文学作品
◆日記にみる流行
-原敬日記
-秋田雨雀日記
-善治日誌
第9章 外地における流行
◆樺太
-漁期に流行
-最も高い対人口死亡率
-先住民にも多くの死者
◆朝鮮
-内地と同時に流行
-死亡率の高い後流行
-行政は何をしたのか?
-免疫現象の確認
-統計資料の問題
-朝鮮での前流行の犠牲者は約13万人
-朝鮮での死者の累計は約23万人
-三・一運動とスペイン・インフルエンザ
◆関東州
-本地人により大きな被害
-関東州でも死亡率の高かった後流行
◆台湾
-台湾中に拡がり先住民も罹患
-台湾でも軍隊を起点に流行
-本地人と内地人(日本人)の間の被害の差
-死者は多いが、短期間で過ぎ去った流行
-先住民の被害
◆小括
終章 総括・対策・教訓
◆総括
-内地45.3万人、外地28.7万人、合計74万人の死者
-日本内地の総人口は減少せず/流行終息後の第一次「ベビーブーム」
-なぜ忘却されたか?
◆対策
-人々はインフルエンザにどう対したか?
-謎だった病原体
◆教訓
あとがき
資料1 五味淵伊次郎の見聞記
資料2 軍艦「矢矧」の日記
新聞一覧
図表一覧
第2章 インフルエンザ発生―1918年(大正七)年春~夏
◆四月-七月 日本
-台湾巡業中の力士の罹患
・『大正七年(1918)年の四月には、日本統治下の台湾で折から巡業中の大相撲(当時は「角力」と表記)力士が病気に罹り、三人が命を落とし、ほかの数名が入院するという事件が発生した。』

画像出展:「日本を襲ったスペイン・インフルエンザ」
“不思議な熱病現はる”
『悪寒から始まり、発熱、四肢の倦怠感、腰痛、38度から40度に達する高熱、約5日間で快方に向かう、としている。』
4章 前流行-大正七(1918)年秋~大正八(1919)年春

画像出展:「日本を襲ったスペイン・インフルエンザ」
“太平洋を超て早くも日本へ”
『爆裂弾より恐ろしい西班牙(スパニッシュ)流行感冒 激烈なる流行速度』
◆本格的流行始まる
-前流行と後流行
・スペイン インフルエンザは、大正七(1918)年10月にはじまる流行を「前流行」、翌大正八(1919)年12月から始まる流行を「後流行」と呼ばれた。
-スペイン・インフルエンザ・ウィルスはいつ日本に襲来したのか?
・日本へウィルスが襲来したのは、大正七年9月末から10月初頭の頃であったと考えられている。
-三週間のうちに全国に拡大
・『10月20日を過ぎると、この病気が「流行性感冒」であることが一般に知られるようになり、各新聞とも「流行性感冒猖獗(ショウケツ)」あるいは「死亡者続出」という見出しのもと、軍隊だけでなく、学校の休校、官庁や鉄道・通信機関従事者の欠勤状況についての記事が多くなってくる。全国紙、または準全国紙では、国外や国内の他の地方の状況についての記事が多かった。以下では、全国を六つの地方に分け、仮定した伝染経路にしたがって、西日本から始めるが、その前に、「流行性感冒」に掲載されている各府県の感冒初発の時期を図4-1の地図に示そう。最も早いのは福島・茨城・山梨・奈良の四県であるが、これはむしろ例外で、大部分の府県では9月下旬から10月中旬であった。ほぼ三週間のうちに、スペイン・インフルエンザは全国に拡がった、と言えるだろう』
◆関東地方
-新聞は意図的に報じなかった
・東京については、10月24日の各紙で流行性感冒来襲を告げている。
・10月25日以降、記事は事の重大性に気付いたごとく、深刻になってくる。
・『10月中の市内の記事は、感冒流行、休校、遠足中止、職場の欠勤者についての報告、交通機関・通信等への影響等に関するものが多く、死亡についての記事は稀であった。しかし11月に入ると、死亡者の続出してきたことが「火葬場の満員 半数は流行性感冒」という見出しの記事(「都新聞」11月5日付け)から窺うことができる。曰く「……砂村、町屋、桐ケ谷、落合の四火葬場に毎日の如く運ばる運ばる病死者の数は殆ど枚挙に遑(イトマ)あらず、……火葬場は今や満員を告げ居りて三日以前に申込むにあらざれば応じきれぬ程の有様を呈し而も其病死者の半数以上は悪性感冒より肺炎、脳膜炎等を併発した結果なりと云う」。この段階では、各紙とも本文には東京市住民の死亡そのものについては何も伝えていないのに、火葬場が多忙なのは、スペイン・インフルエンザ・ウィルスが深く、静かに、東京市の住民に食い込んでいた結果であろう。』
・『この頃[1918年10月]を過ぎると、さすがに抑えきれなくなったのか、にわかに市内の死亡者に関する記事が目立つようになった。11月1日から4日までの4日間の死亡者は、本所区143名、浅草区137名、深川区97名、下谷区91名、牛込区46名とある(「都新聞」11月8日付)が、このうちどれだけが流行性感冒によるのかは判明しない。しかし、翌日の同紙の紙面では、11月になってからの5日間のうちにインフルエンザがらみの病因による死亡が全外の26パーセントに跳ね上がったことを「恐るべき実例」として衛生部長に語らせている。』
第5章 後流行―大正八(1919)年春~大正九(1920)年春
◆関東地方
-地獄の三週間
『大正九(1920)年になると、スペイン・インフルエンザは牙をむいて東京市民に襲いかかってきた。各紙とも一斉にその状況を伝えている。三河島火葬場に運ばれた遺体は、元旦・59、二日・149、三日・196、四日・157、五日・164に達し、処理能力の1日155体を越えたため、焼残しの出る日も生じた(「都新聞」1月8日付)。そのすべてがインフルエンザによる死亡ではなかったとしても、この明らかに異常な状況は、インフルエンザがいかに猛威を振るったかを示している。「時事新報」は、流行前の大正六(1917)年1月8日の東京市の死亡者が156名であったのを、「本年1月7日の235名と比較」している(1月10日付)
大正九(1920)年1月11日の「東京朝日新聞」に掲載された死亡広告も被害の大きさを物語っている。
正月明けで集中したとはいえ、これだけ黒枠広告が載るのは、やはりこの期間の流行性感冒による死亡者が多かったことの証明である。なかには、枢密顧問官芳川顕正伯爵、三村君平氏、秋山孝之輔夫人ら著名人の名も見られる。
しかし、本格的な殺戮は、1月中旬にやってきた。1月11日の「東京朝日新聞」第五面は、ほとんどが流行性感冒関連の記事で蔽われている。見出しのいくつかを取り出すと、「この恐ろしき死亡率を見よ 流感の恐怖時代襲来す 咳一つ出ても外出するな」、「市内一日の死亡者(流行性感冒による)百名に激増 一日以来の感冒患者総数実に九万人」、「元旦からの死亡者同区で二百五十名」、「流感悪化して工場続々閉鎖す」、「日に新患者六十名 第一師団の大恐慌」といった記事で、いよいよ地獄の三週間が始まった。』
分子整合栄養医学2
Chapter5 細胞から整えてきれいな肌になる
栄養不足が老化の原因
●身体を構成している60兆個の細胞はタン白質・脂質・ミネラル・ビタミンなどの栄養素で成り立っているが、細胞の材料の大半を占める栄養素がタン白質である。

画像出展:「肉食女子の肌は、なぜきれいなのか?」
こちらは“プロテインスコア”の表です。プロテインスコアとは体内では合成できない9種類の必須アミノ酸のバランスを食品ごとに評価したものです。卵を先頭に上位を動物性の食品が上位を占めています。大豆、納豆、豆腐などはいずれも50台ですが、これは大豆がメチオニンとリジンという必須アミノ酸の含有量が少ないということのようです。
多すぎる活性酸素は老化を進行させる
・『ヒトの細胞は酸化に常にさらされています。なぜなら、ヒトは酸素を吸って生きているからです。ヒトの細胞は、酸素を利用してATPというエネルギーを作って生きているのですが、このエネルギーを作る過程でどうしても活性酸素が作られてしまうのです。少量の活性酸素は細菌を殺菌するなどで貢献してくれるのですが、問題は活性酸素が過剰に産生された場合。大量の活性酸素は役立つどころか、かえって細胞の酸化を引き起こしてしまいます。そしてどんな時に過剰な活性酸素が発生するかというと、たとえばマラソンやトライアスロンなどのハードな運動をした時です。
エネルギーを産生する時以外にも、活性酸素は体内で発生します。お酒を飲んでアルコールが分解されてできたアセトアルデヒド、あるいは喫煙なども活性酸素の発生源です。その他には、X線検査などで浴びる放射線や、ウィルスや細菌の感染などでも活性酸素が発生します。』
活性酸素がシミやしわ、がんや認知症の原因に
『活性酸素が大量に発生したり、活性酸素の処理がうまくいかなかったりすると、細胞を酸化させ傷つけてしまいます。というのは、細胞を覆う細胞膜にはコレステロールやリン脂質などの脂肪成分が多く、この脂肪成分が活性酸素によってダメージを受けやすいからなのです。
また、がんや認知症も活性酸素による一種と言えます。それは、活性酸素によって細胞の設計図であるDNAという遺伝子が傷つけられ、その修復が正しくなされないことが、がんの原因になるからです。認知症は、脳細胞が活性酸素によって多くダメージを受けたことを原因としています。』
甘いものは老化の原因
・甘いものなど、糖質が多く含むものを摂ると血糖値が高くなるが、多くなったブドウ糖は細胞や酵素などのタン白質にくっつき、タン白質の本来の機能を損ねてしまう。このブドウ糖がタン白質に結合する現象のことを「糖化」という。
・酵素には活性酸素を消去したり、代謝を促進したりする作用があるが、糖化してしまった酵素はこのような機能が十分に発揮できなくなる。そのためいろいろな病気の原因や老化の原因になる。
・糖化したタン白質は活性酸素を発生させる。さらに恐ろしいのは、糖化したタン白質は最終糖化産物(AGE)というものになり、これが活性酸素を大量に発生させてしまう。
腸を整えると美肌になる
・栄養素は主に小腸で吸収される。
・小腸の主なエネルギー源はグルタミン酸というアミノ酸で、タン白質の中に多く含まれている。従って、タン白質摂取が少ないと小腸の働き低下につながる。
・小腸の粘膜は摂取する栄養の不足により働きが低下するが、粘膜上皮の維持(正常な分化)にはビタミンAが欠かせない。
・小腸の免疫活動は飲食物に含まれる外来抗原に対抗するためだが、腸管の粘膜には身体全体の量の半分以上のリンパ球が存在している。腸管免疫系とは、身体に必要な栄養素と病原性のある細菌を識別し、必要なものだけを取り込み、有害なものを排除するという仕組みである。
腸も自律神経を調節する
・ヒトの腸内には100種類を超える常在細菌が存在しており、その数は100兆個と言われ、重量にすると1㎏ほどになる。
・腸内細菌は他の菌と共生しているだけでなく、宿主であるヒトとも共生している。
・腸内細菌には乳酸菌のような善玉菌、ウェルシュ菌などの悪玉菌、大腸菌などの日和見菌があるが、善玉菌は、病原菌の感染を防ぐ、免疫を刺激する、自律神経のバランスを整える、ビタミンB群やビタミンKを作る、腸内の内容物の腐敗を防ぐなどの働きをしてくれる。
・日和見菌は、普段は善玉でも悪玉でもないが、体調が悪化すると悪玉菌として作用する。
・「第2の脳」とも言われる腸には1億個の神経細胞があり、脳の指令を受けず腸自身で判断することもある。
・自律神経は脳だけでなく、腸からも調節を受けているが、腸での自律神経の調整には腸内環境が良いことがとても重要になる。
腸内環境をよくすると冷え性も改善
・冷え性の原因は、鉄不足、筋肉量不足のほか、腸内環境の悪化も冷え性の原因となる。
・腸内環境が悪化すると、自律神経の調節がうまく行われず、交感神経が緊張し、副交感神経が抑制されることにより血管が収縮する。これにより、皮膚の血管も収縮し、血流が悪化して手足が冷える。
・自律神経の安定は腸内の善玉菌が鍵を握っているが、善玉菌の増殖や悪玉菌の抑制にはラクトフェリンやオリゴ糖、食物繊維などのプレバイオティクスの補給が重要である。
・腸内環境が良くないと、小腸が異物を吸収してしまい皮膚のアレルギー症状を引き起こしたり、腸内細菌がビタミンB群をうまく作れず皮膚炎を起こしたりする。
頭痛の大半は鉄不足から
・女性の頭痛には鉄不足が関係していることが多い。分子整合栄養医学的には「月経のある女性であれば70 ng以上、閉経後の女性であれば125 ng以上が理想値」と考えており(一般的な基準値は6~167ng[ナノグラム=10億分の1グラム])、隠れた鉄不足が問題である。
脳や神経と皮膚の深いつながり
・発生学的に見ると、皮膚は神経に近い存在で関係性は深い。神経の維持にはビタミンB群、神経の安定にはカルシウムが必要である。これらの栄養素を摂取し自律神経を安定させることは皮膚の健康にとっても重要である。
皮膚炎や湿疹の原因が副腎疲労症候群のことも
・人はストレスがかかると、副腎で抗ストレスホルモンである副腎皮質ホルモンを分泌して、ストレスに対抗するが、ストレス状態が長く続いたり、栄養不足が顕著になったりすると、副腎は疲労しホルモンをうまく分泌できなくなる。これにより、倦怠感、気分の落ち込み、睡眠障害、関節の痛みのほか、湿疹や皮膚炎が起きたり、太りやすくなるなどが起こる。
副腎は身体の中で最もビタミンC濃度が高い臓器であり、ビタミンCは副腎を元気にする栄養素だが、その他、タン白質、ビタミンB5、ビタミンEなども重要である。
Chapter6 お悩み別アドバイス
2.乾燥肌
肉を食べると、お肌の潤いが保てる
・肌の乾燥は表皮の一番上にある角層の水分不足が最大の原因だが、角層の水分にはケラチンが関与している。ケラチンは動物性タン白質に多く含まれている。また、角質細胞にはNMF(天然保湿因子)があり、肌の潤いを保っている。このNMFは半分以上がアミノ酸でできているが、さらにNMFが作られるためには表皮細胞が正常に分化するためのビタミンAも重要である。また、角質細胞と角質細胞の間にはセラミドやコレステロールなどの細胞間脂質があり、水分の層を挟み込んで保持している。以上のことから乾燥肌を防ぐには、タン白質、ビタミンA、脂質を摂ることが大切である。
4.しわ・たるみ
コラーゲンよりもビタミンC、アミノ酸、ヘム鉄を
・『しわの一番の原因は、紫外線によってできた活性酸素です。活性酸素によって真皮の大半を占めるコラーゲンのタン白質の立体構造が壊されると、その壊れた部分が凹んで、しわになります。コラーゲンを安定化させている基質も同様に、紫外線によってできる活性酸素で変性します。ですから、しわの予防のためにも紫外線対策が重要になります。』
・コラーゲンを作るための材料が不足したり、コラーゲンを作る線維芽細胞がきちんと機能しなかったりすると、しわになってしまう。
・コラーゲンを作る線維芽細胞がきちんと分裂するためには亜鉛が、正常に分化するためにはビタミンAが必要である。
13.更年期障害
副作用がない大豆イソフラボンがおすすめ
・『更年期障害は、卵巣機能が低下し、女性ホルモンの分泌が減少し始めるころから閉経までの期間に起こります。症状は、のぼせ・発汗・不眠・うつ・イライラ・めまい・頭痛・動悸など多岐にわたります。
更年期には、卵巣機能が低下してきて、卵巣からエストロゲンという女性ホルモンを分泌することがうまくできなくなります。そのため、卵巣からエストロゲンをしっかり分泌させようと、女性ホルモンの分泌を司る脳の視床下部が分泌命令を強めるのですが、卵巣機能が低下しているので、卵巣は脳の指令に応じた女性ホルモンをうまく分泌できません。その結果、命令を下した視床下部は混乱します。そのうえ、この視床下部には自律神経の中枢もあり、女性ホルモンをうまく分泌できないという混乱が自律神経のバランスにも影響を与えてしまいます。そうして、前述のようなさまざまな症状が生じるわけです。』
・婦人科ではホルモン補充療法を行う場合が多いが、アメリカでは乳がん・子宮がん・心筋梗塞といった動脈硬化・肝機能障害などの副作用が多く、ホルモン補充法は今では下火になっている。
・日本人は欧米人に比べて更年期障害の症状が軽いが、それは日本人の大豆摂取量が多いためではないかと考えられている。また、卵巣機能を高めるためにはビタミンEの補給が有効である。
・副腎でも性ホルモンを作っていて、副腎機能が低下すると性ホルモンの分泌が低下し、更年期症状が出やすくなる。なお、副腎を元気にするのは、ビタミンC、タン白質、ビタミンEなどである。
・貯蔵鉄(脾臓や肝臓に蓄えられている鉄)の値が低い鉄欠乏性状態の女性は、より更年期障害の症状が出やすくなるので、鉄欠乏を改善することも大切になる。
・エストロゲンの分泌が減ると骨粗鬆症も引き起こすので、カルシウムやマグネシウムの摂取も重要になってくる。
まとめ
以下の2つがポイントだと思います。
1.望ましい生活習慣(食事・睡眠・運動・禁煙)を心がけ、腸内環境をととのえるとともに、不要な活性酸素の発生を抑えること。
2.糖質をひかえ血糖値を維持する。これにより、摂取したタンパク質を無きものにしてしまう糖化、さらに進んで大量の活性酸素をばらまく最悪の物質、AGE(最終糖化産物)を発生させないこと。
そして、特に栄養の偏りが気になる方、原因不明の体調不良がながく続いている方は、まずは今の食習慣を見直して頂くことをお勧めします。
こちらは、分子整合栄養医学を推進されている団体です。埼玉県でONP(プロフェッショナル)または、ONE(エキスパート)が在籍されている医療機関は、川口市と北本市にそれぞれ1つありました。
分子整合栄養医学1
今回の“分子整合栄養医学”はブログ“線維筋痛症”の宿題です。そして、栄養に注目するのは、自然治癒力に深く関係していると考えているためです。
昔から自然治癒力という用語を深く考えず、当たり前のように使っていたのですが、ある時、「ところで、自然治癒力って何だ??」と気になったことがありました。考え出したキーワードは「恒常性の維持」と「代謝」です。そして、最終的に自然治癒力を「ストレス適応と栄養代謝」と定義しました(ご興味あれば、ブログ“がんと自然治癒力13”の後半を参照ください)。
「ストレス」の元であるストレッサーは脳にアタックをかけます。これらのストレッサーに対処し、ダメージをできる限り小さくすることができれば、健康な状態を守ることができると思います。なお、ストレスへの対処に有効なものの代表は運動です。
一方、ダメージを負った心身に必要なものは、食事(栄養素)と睡眠だと思います。「栄養代謝」とは、しっかり食べ、しっかり休息をとり、酵素やホルモンなどが本来の働きをし、食べた物が無駄なく体の血肉になるというイメージです。
以上が、自然治癒力にとって「栄養」は非常に重要であると考える理由です。
医学の父と呼ばれているヒポクラテス(紀元前460~357年)は次のような言葉を残されています。
『食べ物について知らない人が、どうして人の病気について理解できようか』

著者:森谷宜朋
出版:幻冬舎
発行:2013年7月
一瞬、タイトルにギョギョとしてしまいましたが、よく見ると小さく、”細胞から整える分子整合栄養医学のすすめ”という副題がついており、実際、たいへん勉強になりました。
ブログで取り上げた項目を黒字にしていますが、『』で括られた文章は正しくお伝えしたいので引用させて頂きました。
Chapter3、4、7については触れていません。また、少し長くなったので2つに分けました。
はじめに
Chapter1 アンチエイジングのための分子整合栄養療法
「病気は薬で治すもの」と思い込んでいた勤務医時代
分子整合栄養医学との出合い
産後に精神不安定だった妻が劇的に快復
薬を使わないので副作用の心配がない
自然治癒力を取り戻す
「未病」を発見して治療
Chapter2 答えはすべて血液診断にある
栄養が足りなくなると、どうなるの?
健康は細胞から崩れ始める
体調が悪いのに、血液検査で「異常なし」が出る理由
基準値=正常値ではない
血漿レベルではなく、細胞レベルで濃度をチェック
胃粘膜の萎縮は胃の老化
ピロリ菌を除菌してアンチエイジング
病院の医師は火消し役、分子整合栄養医は修理役
Chapter3 若々しくきれいになるための肉食のすすめ
採食生活のさまざまな落とし穴
鉄不足はしわやたるみの原因に
適量の動物性食品をプラスする
現代人に多い栄養失調
主食は米にあらず
糖質・炭水化物を摂りすぎない
栄養価の高い旬の食材
タン白質を必ず毎日一定量摂る
低血糖症の人はおやつに豆類かゆで卵を
アルコールを飲む場合はナイアシンを補充
市販のサプリメントに頼らない
分子整合栄養医がすすめるダイエット
ダイエット中も、タン白質、ミネラル、ビタミンは摂取
断食をするとリバウンドしやすくなる
Chapter4 分子整合栄養医が斬る食にまつわるウソ・ホント
あなたの食理論はホントに正しい?
「菜食主義」は老化を抑える→ウソ
肉を食べると太る!→ウソ
コレステロールが高い人は、卵や肉を食べてはいけない→ウソ
貧血には、ほうれん草やひじきがよい→ウソ
皮下脂肪は余計なもの→ウソ
タン白質が不足すると、脚が短くなる→ホント
プロテインを飲むと、マッチョになる→ウソ
ビタミンCは、摂りすぎると尿に溶けて出ていく→ウソ
バターよりもマーガリンの方がヘルシー→ウソ
オリーブ油は身体にいい→ホント
心筋梗塞や脳梗塞の原因は、動物性脂肪である→ウソ
青魚と肉をバランスよく食べると、血管がきれいになる→ホント
胃酸は抑えるほどいい→ウソ
お酒を飲むなら焼酎か赤ワイン→ウソ
Chapter5 細胞から整えてきれいな肌になる
真のアンチエイジングは、身体全体がターゲット
皮膚は内臓の鏡
GPTの値が低すぎても「異常」
皮膚は排泄する臓器
理想なのは赤ちゃんの肌
美しい肌のために必要な栄養素
栄養不足が老化の原因
糖質や炭水化物を摂りすぎない
多すぎる活性酸素は老化を進行させる
活性酸素がシミやしわ、がんや認知症の原因に
甘いものは老化の原因
血糖を急上昇させない食事を
フレンチや会席料理の順番で食べる
タン白質をきちんと消化する胃を
ピロリ菌感染で胃は老化する
腸を整えると美肌になる
腸も自律神経を調節する
腸内環境をよくすると冷え性も改善
頭痛の大半は鉄不足から
脳や神経と皮膚の深いつながり
皮膚炎や湿疹の原因が副腎疲労症候群のことも
ストレスはシミも濃くする
最低限のスキンケア+栄養たっぷりの食事を!
Chapter6 お悩み別アドバイス
1.ニキビ・ふきでもの
・鉄不足、ビタミンB群不足、糖分の摂りすぎなどが原因
2.乾燥肌
・肉を食べると、お肌の潤いが保てる
3.シミ
・紫外線による活性酸素を防ぎ、消去する
4.しわ・たるみ
・コラーゲンよりもビタミンC、アミノ酸、ヘム鉄を
5.毛穴の開き
・コラーゲン減少による真皮のたるみが原因
6.赤ら顔
・腸内細菌の乱れが発症の一因
7.主婦湿疹(手荒れ)
・バリア機能の低下による炎症
8.薄毛・抜け毛
・タン白質や亜鉛不足
9.便秘・下痢
・便は健康のバロメーター
10.ダイエット
・タン白質を減らしたダイエットはリバウンドする
11.デトックス
・毒素は水でなく、よい脂肪で追い出す
12.月経前症候群(PMS)
・体内の過剰な水分蓄積や栄養バランスの乱れを直す
13.更年期障害
・副作用がない大豆イソフラボンがおすすめ
14.頭痛
・頭痛の原因は鉄不足にあり
Chapter7 栄養療法はオーダーメイド
栄養療法は健康や長寿につながる
「こんなにたくさん飲むの?」というほど摂取する
サプリメントに抵抗がある人は
自然治癒力を高める栄養療法
継続は力なり
あとがき
あなたには、この栄養素が足りない!
分子整合栄養療法でよく用いる栄養素
はじめに
●分子整合栄養医学とは、「人間の身体は食べた栄養からできており、身体を構成する細胞に必要な分子(栄養素)の不足や乱れが病気や老化の原因になるため、細胞の分子濃度(栄養状態)を正常な状態に整え合わせることで、病気や老化を予防・治療する」というものである。そして、この分子整合栄養医学の理論に基づき、血液検査で不足栄養素をチェックし、治療用に開発された高濃度の栄養素を補充する治療のことを「分子整合栄養療法」という。
●慢性疾患は細胞の分子の乱れ=栄養欠損が原因である。そのため薬に加え、不足している栄養素を補充し、細胞の栄養濃度を正常に戻す必要がある。
●分子整合栄養療法が効果的な疾患は、貧血、アトピー性皮膚炎、ニキビ、湿疹、うつ、関節リウマチ、動脈硬化、不妊、月経不順、PMS(月経前症候群)、がん、認知症、肌の老化などのアンチエイジングなどである。
Chapter1 アンチエイジングのための分子整合栄養療法
「病気は薬で治すもの」と思い込んでいた勤務医時代
・『一般の人はもちろんのこと、医療関係者のほとんどが、病気は薬で治すものと思い込んでいます。かく言う私も勤務医時代はそう思っており、薬を処方してきました。
しかし、大きな病院に勤務し、内科医として薬物治療を行っていながらも、自分はほとんど患者さんを治せていないという無力感を抱いていたのです。特に胃がんや大腸がんの末期の患者さんは、いくら抗がん剤治療をしても、副作用に苦しんで、最終的には残念な結果に至るということの繰り返しでした。』
分子整合栄養医学との出合い
・『何かよい治療方法はないかと模索している時に出合ったのが、分子整合栄養医学です。
分子整合栄養医学は、ノーベル賞を2回受賞した天才生化学者ライナス・ポーリング博士らが提唱したもので、正式には“Orthomolecular Nutrition and Medicine”と言われます。その理論は次のようなものです。
「身体の不調は、加齢、ストレス、遺伝素因、不適切な食生活、生活習慣、飲酒、喫煙等々のさまざまな原因が関与し、身体を構成する細胞の分子が本来あるべき正常な状態ではなくなることに起因するので、人間の身体の仕組みを細胞の分子レベルで解明し、不足している分子を至適量補給すれば、生体機能が向上し、人間が本来持っている自然治癒力が高まって病態が改善される」』
・ここでいう「分子」とは「栄養素」のことである。従って、「細胞の分子が本来あるべき正常な状態でなくなる」というのは、「細胞が栄養不足になる」ということである。そして、これが原因で身体が不調になる、つまり「病気は、栄養不足が原因である」ということである。
・栄養不足が病気の原因ならば、栄養不足を解消することが治療に至る一番の近道となる。
・栄養不足を解消する治療法とは、人間の身体の仕組みを細胞の分子レベルで解明し、不足している分子を至適量補給すること。つまり、細胞に不足している栄養素を探り、必要な栄養素を必要なだけ補給するというものである。
・どんな栄養素が不足しているかという診断は、生化学的な理論に基づく詳細な血液検査によって行う。分子整合栄養医学では、病院で通常検査する項目以外にも多数検査する。また、検査で得られた数値を、ただ基準値に当てはめて正常か異常かを診るのではなく、生化学的な背景を考慮しながら、本来あるべき細胞濃度と照らし合わせて深く分析する。

画像出展:「日本オーソモレキュラー医学会」
ライナス・ポーリング博士は、1954年度のノーベル化学賞と1962年度のノーベル平和賞を受賞されました。そのポーリング博士が60代になった時、体内の生化学物質が本来の機能を発揮できないことが原因で発生する病気に焦点を当て、これを治療する「オルソモレキュラー・メディスン(分子整合医学)」を提唱されました。
※”オーソモレキュラー栄養療法 導入医療機関一覧”をクリック頂くと、各都道府県で開業されている医療機関を見つけることができます。
自然治癒力を取り戻す
●分子整合栄養医学の最大の長所は元を断ち、根本的な治療をすることである。これは細胞の濃度を「本来あるべき状態」に戻し、個々の細胞を自然な働きへと向かわせることであり、根本原因の栄養不足が是正されれば、自然治癒力が働くようになる。つまり、必要な栄養素を口から摂取し、腸から吸収し、血液に取り込んで血流に乗せて、不足している場所まで運べば、あとは人間の身体が壊れかけた細胞を修復してくれるということである。
Chapter2 答えはすべて血液診断にある
体調が悪いのに、血液検査で「異常なし」が出る理由
●体調不良に伴って病院で行われる血液検査は保険適用内の検査で、目的は「治療のため」であり、検査項目は限られたものになっている。一方、健康診断の血液検査の項目も、血色素量(ヘモグロビン)、赤血球数、GOT、GPT、γ‐GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖という範囲に限られたものであり、分子整合栄養医学的な検査項目と比較すると、2割程度の項目数にすぎない。これでは、未病や慢性疾患の原因を発見したり、さらに原因を突き止めたりすることはできない。
基準値=正常値ではない
●検査結果の数値は個人差があるので、継続して検査を行う必要がある。何度検査しても同じくらいの数値であれば、その数値が基準値から外れていても、それはその人の正常値であると考えられる。このように、血液検査の分析は経時的変化を診ることが極めて重要である。
●GPTは肝機能を診る検査である。この値が高いと「肝細胞が壊れている=炎症がある」と考えるが、値が低い場合は特に問題なしとなる。しかし、分子整合栄養医は異なる。酵素の多くはタン白質でできており、GPTはさらにビタミンB6を補酵素としているため、GPTが低い場合、分子整合栄養医はタン白質不足、ビタミンB6不足があると判断する。
血漿レベルではなく、細胞レベルで濃度をチェック
●『たとえば鉄の過不足を診断する際に、現代医学では一般的にヘモグロビンや血清鉄の値が基準値内に収まっていれば、鉄欠乏はないと考えます。
しかし血清鉄とは、臓器やタン白質に貯蔵されている鉄(貯蔵鉄)がヘモグロビンの合成や組織での利用のために運ばれている状態のものです。したがってその値は運搬中の鉄量であり、体内にあるすべての鉄量を示すものではありません。むしろ、体内にある鉄の3分の2がヘモグロビンに、残りの大半が貯蔵鉄に含まれているので、血清鉄はほんのわずかな量でしかありません。しかも血清鉄は運搬中の鉄ですから、貯蔵鉄が少しくらい減ったところで、値は大きく変動しません。
体内で鉄が不足してくると、まず減るのが貯蔵鉄、次に減るのが血清鉄、そして最後はヘモグロビンが作れなくなって、鉄欠乏性貧血が起こります。したがって、鉄不足を初期段階で見つけるには、貯蔵鉄をチェックしなければなりません。逆に、血清鉄の値が基準値を下回っているようなら、すでに深刻な鉄不足です。
貯蔵鉄の値を示す項目が「フェリチン」です。フェリチンは鉄を貯蔵するタン白質で、身体の中の鉄の減少を、血清鉄よりも早く、そして正確に反映します。ですから、血清鉄の値が低くなくてもフェリチンの値が低い場合は鉄欠乏と診断すべきなのです。
このように、栄養素の過不足を判断するうえでは、血液中の液体成分に含まれる血漿レベルの濃度よりも、細胞レベルでの濃度を診る方が重要になります。にもかかわらず、医学者の多くは、血漿レベルでの濃度しか診ていないのです。』
線維筋痛症5
●慢性痛にはセルフケアが重要
『「風を引いたら、みんなどうする?」と子供たちに聞く。10人中、10人が「薬を飲むー」と答える。明治国際医療大学の伊藤和憲准教授(臨床鍼灸学教室)は、これが日本の典型的な姿だと危惧する。医療保険の充実しない海外ではそうならない。「風呂にはいる。ハーブティーを飲む」そういった答えが返ってくる。幼少期の教育が大人になってからの痛みの対処法を決めると考える伊藤准教授は、日本の子供たちには、早期に、自分で身体をケアする教育が必要だと言う。「風を引いたら病院で薬をもらう」との発想のくりかえしでは、病気になったときに、自分では何もできない。』
・伊藤准教授は、鍼灸センター専門外来で線維筋痛症を担当されており、国内でもトリガーポイントの専門家として知られている。
・痛みは医療機関だけにまかせる受身的な治療ではうまくいかないことから、患者自らが痛みをコントロールするセルフケアを推奨し認知行動療法(痛み教育と考え方)、アロマテラピー、森林浴、ヨガ、ツボケア、笑い、運動の八つのプログラムによるセルフケアの効果の研究も行っている。
・身体の機能を回復させる治療として数多くの東洋医学的アプローチがある中で、鍼治療のメリットについては、痛みがコントロールできること、副作用がほぼないこと、そして、治療中に患者と語り合えることの三つを挙げている。
・鍼は、医師の治療や処方された薬を補っていく役割と位置づける。
・専門は筋肉のため、線維筋痛症や筋・筋膜疼痛症候群の患者との関りも多い。
・『「ストレスがかかると筋肉は硬くなり身体は丸まるんです。交感神経が高ぶる時は、体は丸まるようにできていて丸まる筋肉も決まっている。立ったり、バランスを取る抗重力筋はストレスに敏感。ほかの筋肉に比べ脳とのやり取りが密にあるわけです」』
・抗重力筋の中にある筋紡錘には交感神経が来ており、脳の影響を受けやすい。
・交感神経が高ぶると、大胸筋、僧帽筋、肩甲挙筋、腓腹筋、ヒラメ筋などの筋肉が緊張しやすい。また同時に、目が乾いたり口が渇いたり、手足が冷えたり、不眠といった不定愁訴が起こってくる。
・『「私は選択的に、交感神経に影響のある筋肉のトリガーポイントを探して緩めてあげる。それが、副交感神経を優位にするんですね」鎮痛系に働く治療と、交感神経に働く治療と二つを合わせて治療する。それが伊藤准教授の考える鍼治療の理想。脳を介した痛みのメカニズム、自律神経を調節するための方法、局所の筋肉の対処という、立体的な医療概念からの話も魅力的だ。』
・線維筋痛症を含む慢性痛は、自分でも身体をメンテナンスしていかなければ治すのは難しい。そのためセルフケア医療への対策にも力を入れている。
・鍼灸師は、痛みの専門家として、痛みに関する正しい知識を身につけ、ペインマネージャとして患者の痛みをトータルケアする必要がある。[注:このことは本に書かれていたものではありません。2014年冬に伊藤先生が講師をされた“トリガーポイントと鍼灸治療”というセミナーを受講したときに、最も印象に残ったことです。]
”慢性痛患者のための セルフケアガイドブック” もありました。クリック頂くダウンロードされます(PDF24ページ)。
●機能回復、症状改善するポイントは血流にある
『身体の機能を高める=免疫力を高めるために、姫野医師のような「分子整合栄養医学」からのアプローチは極めて説得力を持っていた。また、伊藤准教授の説くセルフケアも重要に思えた。次に本書の取材班は、線維筋痛症の症状改善のために「血流」に焦点を当てて治療を行ってきた永田勝太郎医師を訪ねた。では、なぜ血流なのか。「どんなん病気でも、まず病院で血圧測りますよね。血圧が基本だからです。そして血圧は、血流、血行動態を表している」
血圧とは、心臓から出た血液が血管の中を流れ、全身をめぐり末梢にまで至り、再び心臓に戻ってくる過程、血行動態、すなわち血液循環の状態を表す数値。そして血圧は、心臓に収縮力と末梢の血管抵抗から成り立つものだ。
「この血行動態と線維筋痛症の痛みは、関係があるんです。たとえば、腕を強く押され続けると腕がしびれてくる。正座を続けると足がしびれ、痛む。それは神経を圧迫しているというよりも血液を途絶えさせているからです。血の流れを止めるとそこに発痛物質が溜まる。すると神経が刺激され、しびれたり痛くなる。結果的には神経だがもとは血流の問題です。だから血流、血圧の管理が重要」』
・線維筋痛症は、筋痛がおもな症状で、筋は心臓から出る血液の約80%を使っている。
・筋の細胞は代謝してエネルギーを発生し老廃物をつくる。この老廃物には、痛みを発する物質であるカテコルアミンやサブスタンスP、ブラジキニン、セロトニン、ヒスタミン、プロスタグランジンなどが含まれており筋痛と深くかかわっている。
・血流や血圧を正常化することは、老廃物を流し去り痛みから解放することを意味する。
・『「私は、まず、血行動態を改善させたあと、温泉療法を試してもらう。線維筋痛症の患者さんは血圧が低いんです。そしてこの疾患が女性に多いのは女性ホルモンが出ているから。ちなみに女性ホルモンは血管拡張剤でもあるから閉経前の女性は心筋梗塞にならないんですよ。温泉療法は、血圧の低い女性の血行動態を改善するんです」』

こちらは横浜市保土ヶ谷区にある“診療所スカイ”さまのサイトです。女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)について詳しくご説明されています。なお、血管については「血管では、血管拡張作用や抗動脈硬化作用を認めます」とのことも書かれています。

こちらは慶應義塾大学保健管理センターさまが2002年に発行された“エストロゲンと生活習慣”慶應保険研究(第20巻第1号、2002。PDF7ページ)です。こちらにも「エストロゲンは血管拡張に作用し、血管障害や動脈硬化を抑制する」とのことが記述されています。
●湯あたりで、脳と身体をリセットする?
・永田医師が行う温泉療法は、症状などに合わせて数多くある。一例として、1日3回入浴。1回の入浴時間は最初は5分で徐々に増やしていく。入浴中、気分が悪くなったらすぐに出る。入浴中は温泉の中で、ゆっくりと自律訓練法を行う。この療法中は、入浴以外に何もしないこと。一日の終わりに、「からだへの気づき」と「こころへの気づき」の日記をつける。
・『「私の行っている療法は、温泉の温熱効果だけを期待するものではありません。温泉療法に心理療法(実存分析療法)を加えます。これは“温泉ロゴセラピー”と呼んでいて、究極の療法です」』
・温泉療法を行うと必ずといっていいほど「湯あたり」がある。湯あたりはこれまで温泉療法の副作用と考えられてきたが、永田医師は、この11年を振り返って検証すると、湯あたりがあったほうが効果が出ると考えている。
・湯あたりがひどいと、まず症状が悪化して痛みが全身に広がる。頭痛も出る。吐いて食事もできない。温泉は見るのも嫌になる。しかし、そういう状況を懸命に乗り越えると、ある日、ストンと落ちたように治る。
・脳波を調べてみると、湯あたりのあった患者ほど、脳波のアルファ波が減少し、シータ波やデルタ波が増加(座禅や瞑想しているときと同じ状況)する。
・心拍変動のスペクトル解析による自律神経系の反応は、湯あたり中は自律神経系に大きな乱れが生じるが、湯あたりのあとは交感神経の興奮はおさまり副交感神経の機能が高まる。これは音楽療法などによる効果と同様で、永田医師は、緊張から弛緩に移行した状態だと分析している。

永田先生の“千代田国際クリニック”です。
機関誌『温泉』2019年冬号に掲載された。“ストレスと温泉”という投稿を見ることができます。
●人間に本来備わっている自然治癒力を応用
・永田先生は在学中に「痛みをライフワークにする」ことを決意され、卒業後に心療内科、東洋医学、緩和医療、そして麻酔科に学ばれた。その後、高名なウィーン大学のヴィクトール・フランクル博士(実存分析学・人間学)と運命的に出会う。
・フランクル博士は、大戦中にアウシュヴィッツに収容された経験があり幸いにも生還したが、収容所では、死を前にして「譲りあう人と奪いあう人の姿」に直面し、その後の人生を「生きることの意味を問いつめる」ことに費やした学者である。
・『「ある患者さんが、痛みを取ってほしいと医者に頼んだ。さまざまな薬で痛みは7割取れたけれども、立てなくなってしまったという話があります。患者さんからすれば、痛みが取れたからいいだろうと言われていても納得できない。治療のエンドポイントはどこにあるか。それは、痛みの除去だけではないということです」
包括的、全体的な健康観にもとづいた全人医療を実践する立場から、西洋医学本位の治療に批判も呈する永田医師だが、温泉療法をはじめとして、人間に本来備わっている「自然治癒力」を応用する療法、生き方そのものから変えていこうとする哲学的なアプローチは、多くの専門家や患者から注目されている。』
まとめ(鍼灸師として)
“線維筋痛症患者さまのペインマネージャになる”が目標です。そのための前提は線維筋痛症に対する知識と患者さまへの理解です。
特に“心”に向きあうことが第一です。その上で、“ストレス”を小さくすること、自律神経を整え、硬い筋肉をゆるめ血液の流れを良くすることに注力します。そして、低血圧であれば、その改善を目指します。
なお、「分子整合栄養医学」については、今後の宿題とさせて頂きます。
線維筋痛症4
こちらは2冊目になりますが、最初に「はじめに」の冒頭部分をご紹介させて頂きます。
『本書、【痛みが全身に広がる病気をとことん治す】は、線維筋痛症をはじめとした、原因不明といわれる「慢性の痛み」の病気をテーマとして、患者の身に巻き起こる痛みや、これらの病気に対する研究、そしてさまざまな治療の方向性、多数の方法までも綿密にリポートするものだ。
こういった痛みの治療については、実は、これまでも危機感が示されてきた。厚生労働省の【慢性の痛み対策について】の中には、次のような指摘もある。
「病態が十分に解明されておらず、診断も困難である。そのために、患者は適切な対応や治療を受けられないだけでなく、病状を周囲の人から理解されないことによる疎外感や精神的苦痛にも苦しんでいることが多い」
「痛みを専門とする診療体制は十分に整備されていない。その背景には、痛みを対象とした診療が成り立つような制度や人材育成、教育体制が確立されておらず、痛みを理解し、痛みに苦しめられている者を社会全体で支えようとする意識が、十分に醸成されていないことが挙げられる」』
こちらは厚生労働省発行の資料です。クリック頂くと厚生労働省のページに移動します。下部にはPDF資料へのリンクもあります。
目次に続いて、ブログでご紹介するのは、【データで見る線維筋痛症】の一部と、最後の[身体の機能を高める]に関する箇所です。「身体の機能を高める」は自己治癒力/自然治癒力に関する内容で、特に栄養・血液・血流の三つに注目されており、鍼灸師の私には非常に興味深いものです。
目次
①痛みとたたかう患者たち -なぜ、こんなに痛いの?
[支えあう患者たち]
・ふつうの私が消えた日
・せめて病名がほしい
・月に電話相談160件
・さまざまな出会いが支えてくれた
・痛みをそらし、つき合っていく
[医師をめざす、患者のたたかい]
・これが……私たちの日常
・もはや身体や神経の損傷では説明できない
・周囲に理解されないことが一番つらい
・薬に頼りすぎる治療は問題
・医師として患者と向き合う
[共有されない痛み]
・妻には絶望しか残っていなかったのか
・厳しい寒冷地の気候もストレスに
・ドアノブも掴めない、食べ物を噛むこともできない
・薬だけで症状を和らげるのは難しい
・裁判所にも、わかってもらえない
・痛みと事故の因果関係が立証しにくい
【データで見る線維筋痛症】
◆発症年齢
◆疾病罹患がトリガーとなった各診療科別要因
◆臨床症状と重傷分類
◆発症から診断までの期間
◆障害者手帳の取得状況
◆臨床領域にみられる合併しやすい代表的疾患
◆リウマチ性疾患との鑑別診断の要点
②現代医療の壁に挑む -研究者たちの挑戦
[線維筋痛症診療ガイドライン]
・診療を避ける医師が多いことが問題
・大切なのは、三つの視点
・圧痛点を診るというスキル
・病気の概念が変わるというデメリット
・医師に病名が認知されてきた
[診断技術への挑戦]
・痛みは、測定できるのか?
・痛みを測定するペインビジョン
・脳SPECT検査
・PET解析
・「抗VGKC複合体抗体」の研究
[検体バンク]
・検体バンク構想
・世界中の研究者が使えるものに
・プロトタイプを分析
[メカニズム]
・カテプシンSと慢性の疼痛
・犯人の足跡、フットプリントを追え
・インターフェロン・ガンマは、強力なアクセル
・Cファイバーの脱落
・神経のどこかで混戦が起こっている
③最新治療を探る -痛み止め、病気を治すために
[薬で痛みを止める]
・専門薬、リリカの登場
・ほかの薬とは、まったく違う
・「すぐにリリカ」は、危険な発想
・急性か慢性かの判断が重要
・ノイロトロピンの活用
・ペインレスキュー
・徹底して、生活の質を上げる
[脳にアプローチする]
・脳に磁気を当てる「TMS治療」
・南国土佐で始まった治療
・先端治療へのチャレンジ
・脳の神経がうまく働いていない
・景色も表情も、見違えて見えた
・患者を支える
[認知行動療法]
・危険な「痛み」ではないことをわかってもらう
・医師と医療スタッフが新たな家族に
・痛みで何もできない状態からの回復
・痛みで眠れない人に、不眠認知行動療法
[歪みを治す]
・咬み合わせ調整で、痛みを除去する
・線維筋痛症と顎関節症の深い関係
・「バランス」という言葉に、もっと慎重になるべき
[身体の機能を高める]
・なぜこの病気は女性に多いのか?
・脳も身体も、実は深刻な栄養不足
・ビタミン、カルシウム、マグネシウムが必要なわけ
・自分の治す力を強めることが本来の医療
・慢性痛にはセルフケアが重要
・機能回復、症状改善するポイントは血流にある
・湯あたりで、脳と身体をリセットする?
・人間に本来備わっている自然治癒力を応用
【データで見る線維筋痛症】
◆発症年齢
◆発症から診断までの期間
◆障害者手帳の取得状況
◆臨床領域にみられる合併しやすい代表的疾患
以下の図は「線維筋痛症がよくわかる本」にあったものです。線維筋痛症の痛みの凄さが分かります。
[身体の機能を高める]
『おそらくほとんどの病気に有用なのは、身体の機能を高めること=自己治癒力を高めること。食事、睡眠、運動は、その基本だ。線維筋痛症もまた、身体の機能を高めることなしに、いかなる薬も効果を発揮しないに違いない。取材班は身体の機能を高める治療を探ることにした。』
●なぜこの病気は女性に多いのか?
血液が患者を物語る。そして、栄養不足が症状を説明する。
『そう主張するのは、この病気の研究治療を20年以上続けてきた心療内科医の姫野友美医師。テレビ番組、雑誌にたびたび登場する「売れっ子」で、著書も多数。なぜこの疾患は女性患者が多いのか。分子整合栄養医学は線維筋痛症にどのように適用されるのか。東京都五反田の、ひめのともみクリニックに赴いた。白衣に着替えた姫野院長の解説もまた、テレビの健康番組のように歯切れよくわかりやすい。』
線維筋痛症をはじめ、女性に身体症状が出やすい理由。
1.月経、妊娠、出産、閉経など性周期に伴う内的環境の変化。女性ホルモンの変動は同時に自律神経の変動、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アセチルコリンなどの神経伝達物質の変化をもたらし、免疫にも影響する。
2.男性と比べて筋肉量や循環血液量が少ないことによる血行動態の不良。
3.月経や妊娠、出産によるたんぱく質や鉄分など栄養の喪失が心身に影響を与える。
4.男性よりセロトニンレベルが低く、ノルアドレナリンやカテコールアミンの制御不全を起こしやすい。
5.女性の脳の構造上、感情ストレスが大脳皮質を介し、大脳辺縁系視床下部径路を刺激しやすい。
これらの身体的性質に加えて、女性特有のライフサイクル、社会的役割といった心理的社会的背景がストレスを増大させていると考えられる。
●脳も身体も、実は深刻な栄養不足
『ここ、ひめのともみクリニックでは「分子整合栄養医学」を基本方針とし、心身症の患者に栄養指導の考え方はごくシンプルだ。
「基本的に人間の身体は、すべて食べ物=栄養素という材料によって構成されており、どの栄養素が欠けても身体機能は失調状態に陥ります。不足している栄養素を本来あるべき至適量まで補充してあげれば、自らの自然治癒力は高まり、病気の進行を防ぎ、症状の改善、さらには病気の予防が可能となる。これが分子整合栄養医学の考え方です」』
・初診の患者全員に血液検査およびサプリメントドック[足りていない栄養素を確認し解析する]を行い、体内の代謝の状態、ビタミンやミネラルなどの栄養不足、血糖値の変動、さらに活性酸素の発生、酸化ストレスの進行具合などを明らかにする。
・最も問題視するのは血糖の調節異常である低血糖。
・『「低血糖は痛みが増しますから。線維筋痛症の患者さん、片っぱしから調べてますけど、みんな甘いものが大好き。その理由はセロトニンが少ないからで、セロトニンを分泌させようと、チョコレートや甘いものに手が伸びるんです。ところが、それで一気に血糖値が上昇して、インシュリンが大量に分泌されて逆に低血糖を起こし、ノルアドレナリンを誘発する。それが筋肉や血管を収縮させるからさらに痛むのです」』
・脳は「大食漢」である。わずか5%の重さしかないのに、摂取した栄養の20%は脳で消費されている。常に低血糖の状態にあるならば、脳が正常に機能するために必要なブドウ糖の安定供給ができない状態ということである。いつまでも疲労感が拭えず、元気になれない理由はそこにある。
・線維筋痛症患者に顕著なのが低血圧すなわち血行動態不良で、その原因の一つは鉄とたんぱく質の欠乏が考えられる。
・鉄分は閉経していない女性では、一度の月経で30ミリグラムも体外へと排出されてしまう。
・ピロリ菌は鉄欠乏の主要な原因の一つである。胃の粘膜を萎縮させるために、鉄やたんぱく質の吸収力が悪くなる。しかもピロリ菌の出す毒素を消去する際にビタミンCが消費されるので、活性酸素が消去できない。
・『現代人の深刻な栄養失調。姫野院長は鋭く指摘する。』
・栄養失調は身体の機能を正常化するための栄養素が足りない状態である。ふくよかな人であっても、実態は栄養失調であることは少なくない。
・コンビニの加工食品は圧倒的なミネラル不足で、清涼飲料水やスイーツは24時間好きなだけ手に入る。
・品種改良を重ねた味も形もよい現代の野菜は、昔の品種に比べて栄養素が格段に少ない。ビタミンA含有量は50年前のわずか3分の1である。
●ビタミン、カルシウム、マグネシウムが必要なわけ
・原因も正体も不明で、有力なバイオマーカーがない。ゆえに通常の血液検査ではなかなか異常が見られない。それが線維筋痛症の診断をいっそう難しくしている。
・『姫野院長の見立てでは、線維筋痛症は「活性酸素と炎症」である。あれだけ痛みがあるのに、異変が起きていないはずはない。そう言い切った。「線維筋痛症の異常(炎症)は、普通の血液検査では見えず、高感度CRP検査でないと出てこないんです。これでCRP[炎症時に体内に発生するC反応たんぱく質の血中量]0.05以上の数値が出たら、微小な慢性異常が存在すると判断します。ただ、まったくCRPが上がらない患者さんもいて、バイオマーカーは一つではありません。ほかには、たんぱく分画のアルファ2グロブリンが上昇することや、酸化ストレスで赤血球の膜が壊れて間接ビリルビンが上昇することなどによって判断します。
炎症には活性酸素が関わっていますから、うちでは抗酸化アプローチをかなり行います。たとえば高濃度ビタミンC。これも栄養療法の一環ですね」。』
・高濃度ビタミンC注射に含まれるビタミンCの量は25グラム。ここまで大量に経口服用すると下痢を起こすので、静脈注射でダイレクトに血中に入れる。この治療はビタミンC不足が招く疾患、線維筋痛症や慢性疲労症候群、リウマチなど免疫異常の症状改善、白内障や糖尿病の予防にも有効であるとされる。
・線維筋痛症は筋肉の付着部などのスパズム(攣縮)という説があり、リリカやリボリトールなど、けいれんの原因となる興奮系の神経を抑える薬物を用いると症状が和らぐことが裏づけとなっている。
・筋肉が痙攣を起こす原因はカルシウムとマグネシウム不足で、この二つの栄養素はストレス下に置かれると大量に尿から排出されるという性質がある。さらに、更年期を過ぎた女性はカルシウムの吸収力が衰える。線維筋痛症が40代以降の女性に好発するという傾向と一致する。
●自分の治す力を強めることが本来の医療
・基本、全患者に対して栄養療法を実施するが、痛みの強い患者にはトリガーポイントブロック、神経ブロックなどの対症療法も行う。
・『「線維筋痛症の原因と目される、下行性疼痛抑制系の機能不全では、セロトニンやノルアドレナリンが足りないという話がありますね。これを増やすためにサインバルタやトレドミンなどの抗うつ薬が処方されて、それはそれなりに効くわけです。ところが薬というのは、基本的にリサイクルなんです」』
・西洋の薬は、基本的に酵素を遮断するものである。線維筋痛症治療としても使われる抗うつ薬、SSRIやSNRIも、それぞれセロトニンとノルアドレナリンの再吸吸収を阻害する。
・薬のリサイクルには限度がある。リサイクルし続けると物質は劣化していくので、だんだん薬が効かなくなる。薬の量が増え悪循環となる。
・『「逆に、フレッシュなセロトニンやノルアドレナリンを、自力で体内でどんどん作れたら、薬の利用効率だって上がる。最終的に、自分で必要なぶんだけをまかなえるようになれば、薬の利用効率だって上がる。』
・薬をやめたいが、患者にはやめどきがわからない。「薬を止めたら悪化しました」という患者の声はいくつもあった。
・『「当然ですよ。まだ、自分の中で十分な量を作れていないのだから。だから、うちでは栄養解析のデータで示してあげるんです。ここまで数値がそろってきたね、じゃあそろそろ薬をやめられるかなとか。患者さんにすれば、良くなりそうなめどが立つ。そうなると、自ら治療を提案するようになる。先生、私もっと鉄を増やして飲んでみます、たんぱく質摂るためお肉食べなきゃ、甘いもの控えます、だからお薬減らしていいですか、と。病は医者の言う通りにして治すものではなく、自分の中の治す力、自己治癒力を強めることが本来の医療。そう思いますね」。』
・精神的なストレスによってカルシウムやマグネシウムは足りなくなる。活性酸素が増え、ビタミンCがどんどん消費される。ストレスを緩和するため、セロトニンも大量分泌しなくてはならない。すべては身体を正常で健康な状態に保とうとするゆえの作用である。
・『「身体の代謝の状態を分析してあげて、欠損部分を栄養素と補って治療してあげる。もちろん、鉄をはじめとするミネラルはたんぱく質と結びついて運ばれますから、食事も重要。しっかりたんぱく質、つまりお肉を取ってバランスを整えると、心も身体も見違えるほど元気になります」。』
・痛みや症状に向きあうための心理療法、認知行動療法については、まず痛みを取り、脳に栄養を与えて機能を取り戻したあとの話ではないかと考えている。
・きちんと脳に必要分の栄養を入れてあげて、セロトニンやノルアドレナリン、ドーパミンが増えてくると、認知は自然に変わる可能性がある。
線維筋痛症3
以下は既にご紹介済の薬品名と略語の表です。(画像出展:「線維筋痛症は改善できる」)
第3章 線維筋痛症の原因は?
神経伝達の障害
●痛みを抑えるシステムの破たん
・線維筋痛症の疼痛は、鎮痛薬だけでなくモルヒネのような麻薬も効かない。
・疼痛は痛みを抑える仕組みが破たんし、その結果として激痛が起きる。
・有効なのはセロトニン、ノルアドレナリンの作用を活発にする抗うつ薬や抗けいれん薬など。このことから、痛みを制御する仕組みの破たんから起きていると考えられている。
下記もセロトニンやノルアドレナリンによる“下行性抑制系”について説明されたものです。(画像出展:「線維筋痛症がよくわかる本」)
●痛みの伝達ゲートは情動や気分の影響を受けやすい
・線維筋痛症の疼痛は、適度な運動をしたりストレスを除去したりすることで改善することがあるが、これを説明できる有力な理論がゲートコントロール理論である。これは痛みの刺激が脳へ伝わるのを阻止する神経線維が存在するという理論であるが、重要なことはゲートの開閉は中枢から下行性の影響を受け、人の情動や気分などがゲートの開閉を左右している点である。
●検査でわかる重要な異常
・髄液中のサブスタンスPという疼痛を起こす神経伝達物質の数値が高い。
※サブスタンスP:「タキキニンの一種で痛覚の伝達物質。三叉神経節、内頚神経節に含まれ、血管に広く存在し、硬膜の血管にも分布する。炎症にも関連し、軸索反射により放出されると紅斑(フレア)が出る。鍼灸ではこの作用を利用し、体質改善を促進したりしている。(ウィキペディアより)」
・髄液中のセロトニン、ノルアドレナリンの数値が低い。
・脳血流量の低下の可能性がある。
●症状を引き起こすストレス
・線維筋痛症の症状が現れるしくみは、以下の図のように表すことができる。
・症状を起こす要因として明らかなのはストレスである。ストレスを起こす原因をストレッサと呼ぶ。
第5章 線維筋痛症の治療法は?
その他の併用療法
●薬物療法以外の治療法もあわせて導入する必要がある
・線維筋痛症の治療は薬物療法だけでは不十分で、他の治療法の導入も必要である。そこで、再度、セロトニンについて考えてみる。
①セロトニン神経は、覚醒時に持続的なインパルス発射(セロトニン神経の活動化)があり、睡眠時に休止する。
②朝起きてセロトニン神経が十分に働かないと、症状(気分障害、疼痛、睡眠障害、起立困難やすぐしゃがむ)が現れる。また、ストレスがセロトニン神経の働きを抑制する。
③インパルス増強には、歩行、呼吸、咀嚼のリズム運動が必要。
上記を基に、今野先生は次のような治療方法を患者さんに選択してもらっている。
①ウォーキング~運動浴(水温35度以上)
②呼吸法~腹式呼吸
③ヨガ~ストレッチング
④咀嚼~ゆっくりリズミカルに
また、保湿により疼痛が軽減する(疼痛が増強する患者さんも10%位いる)患者さんには次の方法も勧めている。
①保湿(使い捨てカイロ、下着の工夫)
②綿花灸(湿らせた綿花の上にもぐさを置き、疼痛部位周辺に行う灸―自然医療の権威である斑目医師が考案したもの)[台座灸(千年灸など)でも代用可能と思います]
③TENS(経皮的末梢神経電気刺激法)という小型の器械を使って、10分間ほど患部周囲に通電する。心臓ペースメーカーを使っていたり、保湿で疼痛が増強する患者さんには使えない。購入する前に医師に相談すべきである。
●適切な治療で3~5年以内に70%以上が症状の改善可能
・今野先生は定期的に通院されている患者さん(50名)と紹介されて来院された患者さん(13名)にアンケート調査をされました。アンケートの内容は1.線維筋痛症の治療開始(疼痛と診断からの年月)前後で、どの程度症状が改善しているか、2.一番効果的と思う薬は何か、3.治療院へ通院しているか、などであり、その結果は次の通りである。
-線維筋痛症の専門医での成績では、疼痛発症からの平均期間は7.6年だったが、疼痛発症からの期間に関係なく、線維筋痛症の治療開始後、平均3.6年以内には、治療前と比較して、改善が72%(著明改善と改善:42%、やや改善:30%)、変化なしは6%、悪化は22%だった。FIQの平均は59であった。
-一般医の治療成績では、疼痛発症からの平均期間は6.7年で、線維筋痛症の治療開始後、3.4年以内には、診断前より改善したのは22.5%、変化なしは15%、残りは悪化していました。FIQの平均は72.7でした。
-鍼灸、物理療法など、治療院へは54%の患者さんが通院していた。
・疼痛をゼロにすることは不可能だが、専門医による適切な治療によって、治療開始から3~5年以内に、70%以上を改善させることができる。
・治療により改善した患者が使用している薬のうち、「最も効果があると感じている薬」は以下に通りである。
抗炎症薬の内訳はブレドニン、ノイロトロピン、非ステロイド性抗炎症薬がほぼ同じ割合で、プレドニンは主に脊椎関節炎タイプに用いられていた。抗けいれん薬は主にガバペンで、抗うつ薬はSNRI、SSRI、三環系抗うつ薬など多種類だった。ほとんどの患者さんは、これらの4種類の薬のいくつかを病型分類に沿って組み合わせて使用している。なお、薬を使用せず順調な経過をたどっている患者さんは、温泉療法、ラクトフェリンのサプリメントなどを使っていた。
線維筋痛症の患者さんは「線維筋痛症に効く薬はない」と決めつけないで、「時間はかかるが、必ず自分に合う薬がある。薬の適切な組み合わせを早く見つけることで、厄介な疼痛から解放される」という気構えが必要である。
疼痛の重症化を防ぐ対応
●診断と治療の進め方
最後のまとめとして、線維筋痛症の診断・治療のステップがまとめられています。
①『第1の原則は、原因不明の局所的、または広範囲疼痛があるとき、疼痛を引き起こす原因を早く見出し、原因に対する集中的治療を行って疼痛を緩和することで、線維筋痛症に移行させないように努力することです。』
②『治療には、線維筋痛症の病型分類を参考にし、決してACRの圧痛点のみで線維筋痛症と診断して、画一的治療を行わないようにすることです。精神的ストレス、CRPS、脊椎関節炎など原因はさまざまなので、一人の医師では対処できません。その場合でも、ACR基準を盲信しないで、線維筋痛症に精通している医師が中心となって、チーム医療を行うことが望ましいでしょう。それには、患者さんの病気の詳細な経過を作成するのに中心になる医師が必要であり、そして過剰なぐらいの早い対応が必要だからです。』
③『「完璧な病歴」「理学所見」「画像診断」「血液検査」を参考に基礎疾患の有無を調べ、異常があればそれを治療します。異常があればそれを治療します。異常がなく、疼痛が持続するときは、まずは十分な量の非ステロイド性抗炎症薬、場合によってはステロイド(プレドニンで5~10mg)を短期間(長くても1か月以内)併用し、効果を判定します。治療的鑑別です。疼痛は患者さんにとってきわめて不快な症状なので、薬の効果の判定はそれほど難しくありません。そして、患者さんは薬の効果評価を正確に医師に伝える必要があります。この段階で疼痛が緩和されているときは、たとえACRの基準を満たしていても、線維筋痛症の診断は避けるべきでしょう。』
④『十分な量の非ステロイド性抗炎症薬、ステロイドにまったく反応しないとき、初めて、患者さんの疼痛は末梢性の疼痛でなく、中枢性の疼痛と判断できます。そして、中枢性の疼痛に対する治療が開始されることになります。気分障害が強い場合は、抗うつ薬のSNRIから、気分障害が強くないときは抗けいれん薬から、トラマドールを最初に用いる場合もあります。この段階でもう一度病歴の取り直し、さらに理学所見の取り直しを行う必要があります。そして、疼痛の重症度を評価します。可能であれば血中セロトニンの数値を測定します(自己負担で2000円ほどかかります)。』
⑤『患者さんは、治療開始後1~2年間は薬の変更、薬の副作用にとまどうかもしれませんが、原因の究明と本人に合った薬を探すために、時間と費用がかかることを理解し、治療に取り組んでいただきたいと思います。』
線維筋痛症2
第2章 線維筋痛症の症状
同じ病気の患者の経過を参考にする
●共通の症状やストレスとなる原因を探る
こちらは“本文中に出てくる主な略語です。
症例1:夫の死をきっかけに片頭痛や顎関節症などを併発。その後に全身の疼痛
【経過】
・神経内科によって多発性神経炎(シェーグレン症候群による)に対するステロイド療法が行われたが、疼痛を緩和することはできなかった。
・リウマチ医によって線維筋痛症に対するパキシルとノイロトロピンの処方が行われたが、疼痛を緩和することはできなかった。
・この患者さんは、夫を交通事故で亡くし、その後3年間に6個のCSS(中枢過敏症候群)に属する症状・疾患(片頭痛、筋緊張性頭痛、子宮内膜症、顎関節症、筋・筋膜性疼痛症候群、こむら返り)を併発し、最終的に耐えがたい全身の疼痛(線維筋痛症の疼痛)が生じた症例である。
・当院では、セロトニン、ノルアドレナリンの賦活作用(活発にする作用)をもつ即効性の鎮痛薬であるトラマドールシロップを処方し、入院中にヘルパーの活用など家事援助を検討して導入した。
・入院時は移動するのに歩行器と車イスを使っていたが、現在は自立歩行ができるまでに改善し、家事が可能になっている。
症例3:手術後、局所の痛みが全身に。片頭痛やうつ病などを併発して全身の疼痛へ
【経過】
・ばね指の手術後に生じたCRPS(複合性局所疼痛症候群)に対して、適切な処置が行われず、7つのCSS(中枢過敏症候群)の症状・疾患(片頭痛、子宮内膜症、こむら返り、むずむず脚症候群、筋・筋膜性疼痛症候群、顎関節症、うつ病)を抱えることになった。
・入院後、痛みに対してトラマドール、筋のけいれんに対してガバペン、不安状態に対してパキシルを処方した結果、線維筋痛症の重症度を示すFIQは、80から63まで改善した。
・退院後は、ヘルパーを導入して夫の介護負担を軽減し、訪問看護師によるメンタル面の援助を受けて、在宅での生活を送っていたが、主治医が麻酔科の医師にかわると、除痛のためのトラマドールが麻薬に変更されて一日中眠い状態が続くようになり、疲れて寝たきりの生活になった。
・再び、主治医がかわり、入院によって麻薬からの離脱に取り組んだが、麻薬の中止までは長期入院を強いられた。
症例5:出産時の点滴でひじに血管痛。その激しい痛みが続き、全身の痛みへ
【経過】
・若い頃からCSS(中枢過敏症候群)の3つの症状・疾患(片頭痛、顎関節症、子宮内膜症)があったが、出産時に点滴の針を刺したところから生じたCRPS(複合性局所疼痛症候群)が放置されたため、線維筋痛症の疼痛が生じたものと判断した。
・母乳が中止されていたこと、疼痛がきわめて強いことから、トラマドールの服用を開始し、現在は子どもの世話を含めた家事も可能になっている。
症例7:家族の病歴(クローン病)などから、脊椎関節炎を基礎とした線維筋痛症
【経過】
・最初は一次性の線維筋痛症という診断で、疼痛に対する治療を中心としていたが、付着部痛が著しくなり、検査の結果、脊椎関節炎と診断した。レミケード、エンブレルを使ったものの効果がなく、トラマドールとリウマトレックスを併用したところ、職場復帰が可能なまでになった。
症例9:発熱、睡眠障害、関節痛、疲労感から、しだいに全身に自発痛
【経過】
・FIQは78から67、62、42と変動がある。疼痛に対して、応急的にノイロトロピンの点滴を受けているが、緊急入院などはなくなり、家事労働をこなしている。また社会的にも活発な活動をしているが、線維筋痛症への移行にはメンタル面のほうが強く関与していたと思われる。
線維筋痛症の中心症状
●動かさないときでも起きる広範囲疼痛
・線維筋痛症の疼痛部位は、原則として左右・上下対称であり、痛みの箇所が一か所に集中することはない。
・線維筋痛症の疼痛は「自発痛」で、触れられることにより疼痛が増すのが特徴であり、場合によっては皮膚の発赤がみられる。
・線維筋痛症は、英語でfibromyalgiaというが、これは腱や靭帯の結合組織(fibro)と筋肉(myo)の疼痛(gia)という意味である。疼痛部位は関節ではないため、関節の腫れや疼痛を診察する方法では線維筋痛症を見つけることができない。
・線維筋痛症の疼痛の特徴の中には、音や光などによって疼痛が増すこともある。これをアロディニアという。
・線維筋痛症の疼痛は、脳幹部の異常による中枢性疼痛と考えられており、抗うつ薬や抗けいれん薬が有効である。
●睡眠や休息をとっても改善されない疲労
・疲労も線維筋痛症の中心症状のひとつだが、線維筋痛症の疲労は睡眠や休息だけでは十分に改善されない。
●脳波で確認しにくい睡眠障害
・線維筋痛症の睡眠障害は、入眠障害か早朝覚醒というタイプだが、これは睡眠にかかわる2つの脳波、レム波とノンレム波のバランスのくずれが関係しているといわれている。ただし、脳波に異常が確認できるのは30%以下である。
・睡眠時無呼吸症候群が関与する場合もある。
・線維筋痛症の睡眠障害では、睡眠薬をできるだけ使用せず、疲れたら寝るという考えが大切である。睡眠薬が必要なときは、できるだけ少量にする。
線維筋痛症の共通症状
●基礎疾患のない“むくみ”感
・線維筋痛症では「むくんでいる」と訴えることがあるが、実際には「むくんでいない」ことが多い。女性の患者さんには子宮内膜症など婦人科的疾患にかかったり、若い頃に手術を受けたりした患者さんが多くいるが、月経前の体重増加や更年期障害としての“むくみ”感を訴える場合もある。通常、むくみは心臓や腎臓に関わる病気が考えられるが、線維筋痛症の患者さんに見られる“むくみ”感の訴えには、こうした基礎疾患はほとんどない。
●全身のしびれ、異常感覚
・線維筋痛症の患者さんの多くは“しびれ”を訴える。その部位は全身であり、神経学的には説明がつかない。
・下肢のしびれなど、局所だけでなく病歴と全身の状態や症状を参考にして判断する。
・安易に脊髄疾患と診断され、不要な手術により症状を急激に悪化させることがしばしばある。
・線維筋痛症に似た疾患に多発性硬化症があるが、全身症状と経過を参考にすることで鑑別することができる。
●事故につながりやすい立ちくらみ、めまい
・CVr-rなどの自律神経の検査で40%近くの患者さんに異常がみられる。立ちくらみやめまいの訴えが多いのはこのためと思われる。また、血圧が低く、起立性低血圧もみられる。
・立ちくらみ、めまいなどの自律神経障害の症状がある場合は、サポートタイプのパンティストッキングを使用することに加え、塩分の摂取などの食生活の見直しが必要である。
●短期記憶障害は長く続くことはない
・短期記憶障害は、英語でFibrofog(fibro=線維筋痛症・fibromyalgia fog=濃霧)と表現される。電話番号や相手の名前を覚えられない、忘れてしまうといった障害である。ただし、短期記憶障害の症状が長く続くことはないようである。
●不安、ストレス、うつ状態などの精神症状
・患者さんの多くは、気分障害など精神症状を持っている。海外の報告では線維筋痛症患者の20%にうつ状態、15%にパニック障害があるといわれているが、これは疼痛など線維筋痛症の様々な症状が、満足にコントロールできないことによる結果であると考えられる。一方、大うつ病(うつ状態でなく真性のうつ病)でも全身の疼痛が生じることがある。精神症状が線維筋痛症の症状として現れているのか、それとも大うつ病などの精神疾患なのか、慎重に診断することが重要である。その意味で、精神科医と線維筋痛症専門医との共同の対応が必要といえる。
線維筋痛症の関連症状・疾患
●中枢の過敏状態(CSS)が引き起こす症状・疾患
・慢性疲労症候群:何らかの感染を繰り返した結果、日常生活に支障をきたす非常に強い疲労感が、改善されないまま続く状態。
・過敏性腸症候群:頻繁に下痢や便秘を繰り返したり、両方が交互に起きたりする。腸の疾患は検査では見つからず、ストレスなどが関係している。
・筋緊張性頭痛:肩、首周辺の筋肉の疼痛に伴う頭痛で、姿勢などが関係する。
・片頭痛:発作的に反復して起きる頭痛で原因は不明。発作を予期できるタイプと、できないタイプがある。
・生理不順/子宮内膜症:生理不順は、生理前や生理中に、耐えられない下腹部痛や月経周期の乱れを繰り返し起こす状態。子宮内膜症は、子宮内膜と同じものが、子宮以外の場所にできてしまう病気。
・うつ病:うつ状態ではなく、真性のうつ病(大うつ病)です。
・外傷後ストレス症候群:心に深い傷を負うような出来事の後に強いストレスが残り、激痛や睡眠障害、さらにうつ状態になる
・化学物質過敏症:シックハウス症候群などに代表される化学物質過敏状態である。同時に薬物、食品に対する過敏を伴う場合が多い。
・こむら返り:ふくらはぎの痙攣。指、首、肩にも起きるが、この場合は「全身こむら返り病」と呼ぶ。
・むずむず脚症候群:下肢の不快感を覚え、下肢を動かしたいという強い欲求が生じるもので、レストレス・レッグス症候群と呼ばれる。特に夜間に寝床につくと、下肢が「むずむずする」「虫がはっている」「ほてる」「ずきずきする」などと感じ、睡眠障害が起きる。下肢を動かすことでやわらぐ。
・顎関節症:開口障害を主な症状とする疾患で、疼痛を伴うこともある。
・筋筋膜性疼痛症候群:局所の強い疼痛を生じる疾患で、表2のような診断基準がある。
●多彩な症状は根拠のある訴え
・過敏性腸症候群で20%、クローン病、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患の3%に線維筋痛症が合併する。
・婦人科で更年期障害と診断された患者さんに線維筋痛症の可能性がある。
・顎関節症の患者さんの15%に線維筋痛症がある。
線維筋痛症1
かなり前の話になりますが、著名な女性タレントの方が線維筋痛症になったというニュースが流れていました。
以前から線維筋痛症について関心は高かったものの、調べることはしていませんでした。そこで、このニュースをきっかけに、3冊の本を図書館から借りてきました。なお、じっくり拝読させて頂いたのは2冊です。今回も知らないことばかりだったため、長文になってしまいました。そこで、ブログを5つに分けることにしました。
著者である今野孝彦先生は線維筋痛症の専門外来を6年以上開業されています。「はじめに」に書かれている内容は、この難しい疾患を熟知されている先生が現場で積み上げられたものです。
はじめに
『日本では、線維筋痛症の患者さんは約200万人に上ると推定されています。私が線維筋痛症の専門外来を開設してから6年以上経ちました。その診療実績をもとにして平成16年から毎年、北海道大学医学部・環境医学講座で医学部学生に「広範囲疼痛の臨床的アプローチ」と題して講義を行っています。
患者さんの痛みを患者さんと一緒に考え、痛みの研究に興味を持つ医師が一人でも多く出てほしいと願って講義を続けています。本書はその講義の内容を、患者さんはじめ、一般の方が理解できるようにアレンジしたものです。
線維筋痛症の患者さんの主症状は痛み(疼痛)です。受診する科はいろいろで、それぞれの科の専門医の対応も多様です。しかし、適切な対応は少なく、誤診、診療拒否、過剰診断・治療なども見られます。その原因は、疼痛に関する医学教育・医学体制の不備にあります。特に、画像診断、検査中心の日本の医療現場では、疼痛を訴える患者さんの診察は驚くほど画一的なものです。MRIやCT、多数の血液検査を行い、何とか画像、何とか検査で異常を見出そうとして、患者さんも医師も湯水のごとく投資しています。そして、行き着くところは、「何もない。精神科へ行ったら…」になります。
本来、医師はたくさんの画像診断や血液検査を行うよりも、まず患者さんの痛みの訴えに耳を傾けるべきです。何がこの強い疼痛を引き起こしているのかを、患者さんと一緒に考えることが一番大切だと思います。
本書は、35年間リウマチ医療に従事してきた一人の内科リウマチ医が、線維筋痛症専門外来を開設し、患者さんと一緒に悪戦苦闘し、疼痛と闘ってきた記録です。患者さんを中心に一人でも多くの医師、医療・福祉関係者が同じ土俵に上がり、疼痛に取り組む手がかりとなればと思います。
多くの線維筋痛症の患者さんが、診断・治療の遅れで毎日疼痛から悩まされ、社会的労働から疎外されて孤独な生活を強いられています。あふれる情報をもとに線維筋痛症であると自己判断し、たくさんのサプリメントに多額の投資をしている患者さんもいます。また、いまの状態のままでは容易に線維筋痛症へ移行してしまう線維筋痛症予備軍の方たち、そういうすべての方たちに読んでいただきたいと願っています。
さらに、気苦労の多い厄介な病気として、線維筋痛症の治療から目をそむけている医療従事者たちにも、ぜひ読んでほしいと思います。そうすれば、疼痛に苦しんでいる患者さんがいかに多く、適切な対応がなされていないか、適切な対応をすれば、かなりの疼痛患者さんが、苦しみから解放されるのだということが理解できると思います。
なお、本書では薬の名前はすべて商品名にしました。対応する薬品名、分類は164ページの表を参考にしてください。』
目次は下記の通りですが、ブログは第1章、第2章と第3章の一部、および第5章の中から「その他の併用療法」と「診断と治療の進め方(疼痛の重症化を防ぐ対応)」を取り上げています(黒字)。内容は要点と思った個所をまとめたものが大部分ですが、一部引用させて頂いたもの(『』でくくられています)もあります。
第1章 線維筋痛症とは?
患者が置かれている状況
●体の広範囲の痛みが3か月以上続く
●社会生活が困難になる
●多彩な原因に対して、現状は画一的な治療が行われている
第2章 線維筋痛症の症状
同じ病気の患者の経過を参考にする
症例1:夫の死をきっかけに片頭痛や顎関節症などを併発。その後に全身の疼痛
症例2:疼痛を起こす基礎疾患のない、精神的ストレス(離婚)を基礎にした全身の痛み
症例3:手術後、局所の痛みが全身に。片頭痛やうつ病などを併発して全身の疼痛へ
症例4:足親指の打撲の治療後、局所に痛みや腫れを生じ、数か月後には全身に疼痛
症例5:出産時の点滴でひじに血管痛。その激しい痛みが続き、全身の痛みへ
症例6:うつや顎関節症などがあるが、脊椎関節炎が基礎にある線維筋痛症
症例7:家族の病歴(クローン病)などから、脊椎関節炎を基礎とした線維筋痛症
症例8:かぜ症状を繰り返し、倦怠感もある慢性疲労症候群を基礎とした線維筋痛症
症例9:発熱、睡眠障害、関節痛、疲労感から、しだいに全身に自発痛
症例10:C型肝炎を持ち、子宮内膜症や筋緊張性頭痛の病歴があり、触れられただけで全身に激痛
線維筋痛症の中心症状
●動かさないときでも起きる広範囲疼痛
●睡眠や休息をとっても改善されない疲労
●脳波で確認しにくい睡眠障害
線維筋痛症の共通症状
●基礎疾患のない“むくみ”感
●全身のしびれ、異常感覚
●事故につながりやすい立ちくらみ、めまい
●短期記憶障害は長く続くことはない
●不安、ストレス、うつ状態などの精神症状
線維筋痛症の関連症状・疾患
●中枢の過敏状態(CSS)が引き起こす症状・疾患
●多彩な症状は根拠のある訴え
第3章 線維筋痛症の原因は?
神経伝達の障害
●痛みを抑えるシステムの破たん
●痛みの伝達ゲートは情動や気分の影響を受けやすい
●痛みの感受性が強く、回復に時間がかかる
●検査でわかる重要な異常
●症状を引き起こすストレス
セロトニンとの関係
●基礎疾患の有無で一次性と二次性に分けられる
●セロトニン神経の機能低下
第4章 線維筋痛症の関連疾患
病名が間違われる背景
●関連疾患との鑑別抜きに線維筋痛症の診療は進まない
脊椎関節炎(SPA)
●誤って線維筋痛症と診断されているケースが多い
●脊椎関節炎に気づかない医師がさまざまな病名をつけている
●脊椎関節炎にはさまざまな疾患がかかわっている
●脊椎関節炎の診断にはアキレス腱の超音波検査を組み合わせるとよい
●脊椎関節炎は関節リウマチに近い病気
複合性局所疼痛症候群(CRPS)
●何らかの手術後に発症することが多い
●早期診断、早期治療で多くは完治する
慢性疲労症候群
●日常生活に支障をきたす強い疲労感が改善されない
疼痛性障害
●心理的要因が疼痛を起こし、重症化させている
●疼痛の身体的原因を調べないところに問題がある
リウマチ疾患
●リウマチ性多発筋痛症は高齢者に多く、ステロイドが劇的に効く
●関節リウマチの寛解には線維筋痛症の有無が影響を与える
線維筋痛症診断の手順
●基礎疾患を探して分類する
第5章 線維筋痛症の治療法は?
薬物療法
●線維筋痛症には薬物療法が効く
●治療効果をみながら、オーダーメイドの治療を進める
症例1:メンタル面
症例2:メンタル面
症例3:CRPS(複合性局所疼痛症候群)タイプ
症例4:CRPS(複合性局所疼痛症候群)タイプ
症例5:CRPS(複合性局所疼痛症候群)タイプ
症例6:脊椎関節炎タイプ
症例7:脊椎関節炎タイプ
症例8:慢性疲労症候群タイプ
症例9:慢性疲労症候群タイプ
症例10:その他
●疼痛を改善すると、疲労、気分障害もコントロールできる
その他の併用療法
●薬物療法以外の治療法もあわせて導入する必要がある
●適切な治療で3~5年以内に70%以上が症状の改善可能
疼痛の重症化を防ぐ対応
●専門外来の医師の立場から線維筋痛症を考える
●診断と治療の進め方
第6章 線維筋痛症とのつき合い方
生活スタイルの工夫
●質のよい睡眠をとる
●食事は、不足しやすい栄養素を十分にとる
●喫煙は症状を悪化させる。禁煙を!
●天候の変動に備える
●疲労をためないように休息に努める
●家事などは体に負担のかからないような工夫が必要
患者さんの実例から学ぶ日常生活の工夫
●起床時の工夫
●就寝時の工夫、寝具の工夫
●食事の支度と後片付け、食事の仕方
●嗜好品
●口渇
●洗濯
●掃除
●入浴/浴室の工夫
●服装(着替えと寒さ対策)
●衛生、美容
●デスクワーク
●ストレッチ、運動
●日常動作の工夫
●リラックスするための工夫
患者さんの苦悩
●いま抱えている不安
●線維筋痛症を認めない医師
●以前の職場の環境と仕事
●何故この病気と闘ってこられたのか
●私にとって線維筋痛症とは
参考文献
あとがき
第1章 線維筋痛症とは?
患者が置かれている状況
●体の広範囲の痛みが3か月以上続く
・広範囲疼痛とは、図1(1~6)のすべてに痛みがある場合である。
・線維筋痛症は広範囲疼痛の約20%、人口の2%程度、日本では全人口のおよそ1.7%、約200万人と考えられる。
・米国リウマチ学会(ACR)が提唱した診断基準と日本人の患者にみられる痛みの部位
・痛みの評価は4kgの強さ(指で押して爪が白くなる程度)で圧迫したときに痛みがあるかどうか。
・線維筋痛症と診断されるのは、18か所の圧痛点のうち、11か所以上で痛みがあり、その痛みが3か月以上続いていることが診断基準となっている。
●社会生活が困難になる
・日本の疫学調査によると、線維筋痛症の患者さんの平均年齢は51.5歳、発症年齢は43.8歳、罹患期間は7.4年、診断に要した時間は4.3年である。
・女性が8割を占めるため、女性ホルモンを含めたホルモンの影響が検討されたが、影響は見出されなかった。
・今では、神経伝達物質のセロトニンの関与が考えられている。セロトニンは脳の中枢にあって、疼痛緩和やストレスと関係が深い物質で、女性のセロトニンの分泌は男性の4割程度と低いのも注目される理由である。
・線維筋痛症の主な症状は、①些細な刺激にも誘発・増悪される自発痛(何もしていないのに感じる痛み)、②早期覚醒や入眠障害などの睡眠障害、③休息で回復しない疲労、④抑うつ状態などの気分障害。なお、これらの症状は、天候(寒さや多湿など)、運動不足(活動の低下)、音や光などによって悪化する。
・局所の保湿、休息、適度な運動、マッサージ、ストレッチングなどは症状を緩和させる。
・線維筋痛症で最も大きな問題は、社会的労働や家事労働などが十分に行えなくなることである。
●多彩な原因に対して、現状は画一的な治療が行われている
・線維筋痛症の原因は多彩なため、それらをすべて取り除くことは一筋縄ではいかないが、症状を軽くすることはできる。
・線維筋痛症の症状は、様々なストレスが加わると、脳の中枢にある疼痛を制御する場所の働きが低下することによって起きると考えられているので、症状を起こす原因となるストレスを見出して取り除けば症状を軽くすることができる。
・線維筋痛症という病名に対する画一的な治療はなく、原因となるストレスの種類によって、一人ひとり異なるオーダーメイドの治療が必要である。
考える血管(pJAL5)
新型コロナとの闘いが続く中、毎日、多くの報道がされています。その中で危機感が強く伝わってくるのは、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥先生の言動です。そして、もうお一人、東京大学 先端科学技術研究センターがん・代謝プロジェクトのリーダーである児玉龍彦先生の参院・予算委員会でのお話も鬼気迫るものがありました。そして、“エピセンター(感染の震源地化)”という考え方に加え、“交叉免疫”という今まで聞いたことのない“免疫”に大変興味を持ちました。

左は、「東京大学 アイソトープ総合センターさま」のサイトです。そして、“新型コロナウィルスへの血清IgM,IgG抗体の定量的かつ大量測定プロジェクト-紹介と研究参加のご案内”をクリック頂くと、このページから「参議院予算委員会提出資料」や「NHKクローズアップ現代+」などにアクセスできます。
残念ながら、児玉先生の著書の中に“交叉免疫”を題名にしたものを見つけることはできなかったのですが、『考える血管』というブルーバックス(講談社さまが発行している一般向け科学シリーズ)を見つけました。
申すまでもなく、血管は血液を各組織に届けるインフラであり、まさに体の中のライフラインです。血液に注目するのであれば、血管のことを良く知ることも重要だと思いました。
ブログは目次に続き、最初に「あとがき」をご紹介しているのですが、これは全体像をお伝えできることと、“体の中の環境問題[ゴミ処理問題]”という言葉がとても新鮮で印象に残ったからです。
その後、第2章 躍動する血管/4.平滑筋細胞を伝わる情報/“内皮細胞と平滑筋細胞の対話”と、第4章 詰まる血管/3.解明されたスカベンジャー受容体/“新しいパラダイム”に関して簡単にまとめています。
また、プロローグの表紙にあった、日本航空5便の機内で撮られた若き児玉先生と、大逆転の大発見となった、「スカベンジャー受容体遺伝子の発見」に関わるエピソードを加え、さらにエピローグの表紙(「脳のなかのスカベンジャー受容体」)も添付させて頂きました。
目次
はじめに
プロローグ コレステロールをためる遺伝子
第1章 伸びる血管
1-1 血管がのびるとき
・人口60兆人の巨大都市
・撮影された二つの塊
・がんが血管を伸ばす
・血流が途絶えればがんは死ぬ
・がん根絶への課題
1-2 管構造の謎
・総延長、10万キロメートル
・内皮細胞の発見
・パイプをつくるメカニズム
・第四の説がもつ魅力
・二つの伸び方
・人工血管の苦悩
・求められる第二の性質
・脳の堅牢な血管構造
・細胞のなかを移動する袋
・二つの顔をもつ門番
1-3 血管を伸ばすもの
・クローニング競争
・細胞周期を再起動させるもの
・勝者になってこそ
・つかめない正体
・本命のVEGF[血管内皮増殖因子]
・一つの遺伝子がもつ二つの顔
・二つの遺伝子
・VEGF受容体
・ノックアウトマウス
・壊された遺伝子がもつ意味
・VEGF受容体ノックアウトマウス
・遅れたVEGFノックアウトマウス
・濃度勾配がはたす役割
・相互に依存する関係
・臓器のパートナー
・病気とのかかわり
・老いゆく血管細胞
・寿命を決める回数券[テロメア]
第2章 躍動する血管
2-1 コントロールされる血管
・柔軟で緊張した管
・血管を緊張させる細胞
・神経系による支配
・延髄に存在する指令センター
・残された謎
2-2 血圧を制御する物質
・発見は意外なところから
・マウスにあって、ラットにない
・レニン-アンギオテンシン系
・高血圧と動脈硬化の違い
・理由がわからないまま効く薬
・受容体とブロッカー
・二種類の受容体
2-3 内皮細胞のはたらき
・ダイナマイトが血管を拡げる
・ガスをつくる酵素
・史上最強の血管収縮ホルモン
・エンドセリンのパラドックス
2-4 平滑筋細胞を伝わる情報
・平滑筋細胞の収縮メカニズム
・カルシウムの動きを目で見る
・クロゴケグモの毒
・細胞内を伝わるシグナル
・内皮細胞と平滑筋細胞の対話
・変身する平滑筋細胞
第3章 血管を彩る血球たち
3-1 血管にくっつく血球
・骨髄で誕生する
・拒絶する白血球
・家へ帰っていくリンパ球
・セレクチンの発見
・激流のなかで細胞をとらえる
・白血球を呼ぶ
・接着因子の出方
3-2 出血はどう止まるか
・細胞のかけら
・血小板のはたらき
・凝固因子のはたらき
・絶えず溶かされる血液
・権利は発見者に
3-3 がん転移のメカニズム
・がん治療最大の困難
・流れていくがん細胞
・接着因子がはたす役割
・ブルドーザー[がん細胞]を止められるか
第4章 詰まる血管
4-1 動脈硬化
・サイレント病の恐怖
・大食い細胞、マクロファージ
・ブラウンとゴールドシュタイン
・LDL受容体の重要度
・「キッチン・シンク」スタイル
・ある思いつきからの発見
・突然の中止
・投げかけられた疑問
・フラミンガムスタディ
・メガトライアル時代
・鍵を握るのはプラークの破壊
4-2 酸化されるLDL
・動脈硬化を進める遺伝子
・スカベンジャー仮説
・酸化LDLの発見
・酸化LDL説の誕生
・抗酸化剤プロブコールの効果
4-3 解明されたスカベンジャー受容体
・MITへ
・5フルオロウラシルのマジック
・スカベンジャー受容体とコラーゲン
・解明された謎
・戦う細胞のもう一つの顔
・動脈硬化とマクロファージ
・新しいパラダイム
エピローグ 脳のなかのスカベンジャー受容体
おわりに
おわりに
『人間の体は、60兆個の細胞からなりたっている。分子生物学は、DNAを読めば人間の情報がわかると予言した。そして、「利己的な遺伝子」などという言葉に代表されるように、遺伝子が自立して機能をもつことを重視する生命観が形成されてきている。
だが、60兆個もの細胞が集まった人間たちの見取り図が、遺伝子を読むだけですべてわかるのだろうか。本当は、細胞と細胞がどうかかわっているか、相互の関係を見ていくことが必要なのではないか。そこで本書では、血管の細胞たちを通じて、細胞がどのように全身のシステムとかかわるのかを明らかにしようと試みた。
筆者らは、動脈硬化と高血圧の研究者であり、はじめこれらは病気の原因となる遺伝子、その遺伝子によってコードされるたんぱく質を研究していた。ところがある遺伝子をクローリングしてみても、その体のなかでのはたらきは実はよくわからない。
動物は、どんなに多くの細胞からなるものでも、はじめは一個の受精卵からスタートする。そこで、出発点の精子や卵子の遺伝子を操作すれば遺伝子に異常をもつ動物をつくり出すことができる。第1章で紹介したノックアウトマウスがそれであり、このような実験から遺伝子のはたらきを探ろうとしていたのである。ところが、ここで予想外のことが起こった。
第2章で紹介した、血管を収縮させる因子であるエンドセリンというたんぱく質。試験管のなかで血管壁にエンドセリンをふりかけると血管は収縮する。動物にエンドセリンを注射すれば血圧が上昇する。
ところが、遺伝子を操作して、二個あるエンドセリン遺伝子のうち一個が壊れてエンドセリンが半分しか作れないマウスをつくると、予想とは逆に高血圧を起こすという結果になってしまったのである。
いくらマウスの遺伝子を改変しても、その結果がどうなるかはブラックボックスから出てくる結果しかわからないということだ。そこで、もういちど血管にもどってみた。血管を構成する細胞を中心に考えなおしてみたのが、本書なのである。
われわれは、まだ60兆個の細胞を解析する手だてをもっていない。そこで、あるまとまった細胞の種類に注目した。
血管の特徴は、細胞が集まってパイプのような管をつくり、血液を流すことである。このパイプをなすのが一層の内皮細胞であった。この内皮細胞のまわりには、血圧を保つために躍動する平滑筋細胞がある。これらの二つの細胞を調べ、さらに血管にくっつきパイプを越えて出入りする血球に注目していった。
遺伝子は細胞のなかではたらく。そのもっとも大切なはたらきは、一つの細胞が分裂して二つになること、つまり細胞の増殖をコントロールすることであろう。
血管でいちばん大切な内皮細胞の増殖をコントロールする因子は、血管のまわりにあって、酸素や栄養分のたりなくなった細胞が放出する。血管が、まわりの細胞との対話から出発していることがわかってきたのである。こうした対話の仕方をクロストークと呼んでいる。
動物が大きくなれば、血管も太く、長くなる。人間では総延長10万キロメートルにもなる。そうすると血液を配る圧力が必要になり、それを調節する細胞が平滑筋細胞なのである。運動をすると筋肉はたくさんの酸素を要求し、血液をたくさん必要とする。こうした場合の調節でも、運動する筋肉の細胞と、血管の細胞との対話がなければなりたたない。
従来、血管の細胞は、まわりの細胞や神経にいわれて命令されたままに動くように思われていたが、エンドセリンや一酸化窒素の発見から、むしろ血管の細胞が、周囲の細胞と相互に作用しつつ、「考えながら」行動することがわかってきた。
今日のわれわれにとって、もっとも大きな血管の問題は動脈硬化であろう。動脈硬化の研究においても、分子生物学による研究がはなばなしく繰り広げられてきた。コレステロールの研究で、若くしてノーベル賞を受賞したブラウンとゴールドシュタインはその象徴であった。
ブラウンとゴールドシュタインによって示唆された、血管にコレステロールがたまるメカニズムの解明も、遺伝子の重要性、つまり動脈硬化が細胞のDNAによって決められた運命というよりも、細胞の反応が重要な役割を果たす、むしろゴミ処理問題としてのおもむきを示してきた。
コレステロールをはこぶ複合体が、血管壁の骨組みをなすマトリックスたんぱく質にくっついて変性し、それを食べにきたマクロファージがいすわってしまって動脈硬化が進んでいく。このようなメカニズムは、その他の病気でも考えられはじめており、いわば、体のなかの環境問題が成人病の鍵になるようである。
人間の体のなかでは、細胞は裸で暮らしているというよりは、マンションの部屋がゴミでうもれ、ダイオキシンのような有害なものがあふれてしまうのが成人病であるのかもしれない。
こうしたパラダイムがアルツハイマー病や糖尿病、また、本書では紹介できなかった白内障や骨の病気でも登場してきている。』
内皮細胞と平滑筋細胞の対話
『血管の内皮細胞はただ単に血管の内側を埋めている敷石のような存在ではない。平滑筋細胞を収縮させるエンドセリンを分泌したり、アンギオテンシンを活性型に変換したり、また弛緩させるNOを放出したりと、縦横にはたらく実に機能的な細胞である。』
●血管の内皮細胞はナトリウム利尿ホルモンやアデノシン、プラスタノイドといった平滑筋細胞の収縮を制御する物質を分泌する。
●血管の内皮細胞は平滑筋細胞の増殖を促すホルモンを分泌する。
●平滑筋細胞は内皮細胞に対して増殖因子を分泌している。このことから、血管を構成する細胞たちがお互いに情報の交換をしながら機能を果たしていることが予測される。
●『最近、アメリカのリジェネロン社のヤンコプーロスのグループから非常におもしろい仮説が提出された。彼らはアンギオポエチンと名付けた新しいたんぱく質を同定した。その仮説によれば平滑筋細胞の前身の細胞(前駆細胞)からこのアンギオポエチンが放出され、血管の内皮細胞がそれを受け取ると、こんどは内皮細胞がPDGF(血小板由来増殖因子)やHB-EGF(ヘパリン結合性内皮増殖因子)と呼ばれる因子を放出する。そして、このシグナルを受け取った前駆細胞が内皮細胞のまわりに集まってきて平滑筋細胞になるというのである。
このようにして、血管の細胞たちが、まるで対話をしているかのような双方向性のシグナルのやりとりをおこなっている姿が浮かび上がってきた。』
本書の中で“仮説”とされた「平滑筋細胞→(アンギオポエチン)→内皮細胞→(PDGF)」というシグナル伝達について、検索してみたところ、本書から約10年後の2006年12月発行の科学雑誌に、これらの関係性について書かれたものがありました。このことから仮説ではないと考えます。
生体の科学 57巻6号 (2006年12月)
『血管系は管腔を一層に覆う血管内皮細胞(endothelial cells)とその外側を内皮細胞が産生した基底膜、その周辺を中膜形成する血管平滑筋細胞(smooth muscle cells)、毛細血管ではペリサイト(pericytes)などの周皮細胞からなる壁細胞で構成されている。中膜は収縮弛緩することで血圧や血流を調節している。これら血管系細胞群の発生分化、形成に関する細胞科学的な解析や関連する遺伝子の解析が進み、その過程の理解が飛躍的に進んできた。血管平滑筋の増殖を制御する代表的な因子は内皮細胞が発現するPDGF(platelet-derived growth factor)とそのレセプターであるが、チロシンキナーゼ型レセプターTie-1,Tie-2とそのリガンドである壁細胞が分泌するアンジオポエチン(angiopoietin)は内皮細胞と血管平滑筋細胞の接着や増殖などを調節している。
本総説では血管平滑筋細胞とは何か、特に発生における組織細胞の由来および成体における各種外部刺激による細胞形質変換について概説し、平滑筋の発生分化を牽引する血管平滑筋細胞特異的遺伝子発現がどのようなメカニズムで行われるのかを、典型的な平滑筋マーカーである血管平滑筋α-アクチン(Smooth muscle α-actin;SmαA)を例にして解説する。』
新しいパラダイム
『北教授によるプロブコールをもちいた実験などでは、LDLが動脈にたまっても酸化されさえしなければ、マクロファージが動脈に集まることはなく動脈硬化も起きない。コレステロールがたまること自体より、マクロファージが集まってしまうことが動脈硬化を悪化させる面が強いという。』
●動脈硬化とは、酸化されたLDLが不燃ゴミのように血管壁にたまり、やってきたゴミ処理工場のマクロファージが、自分では分解できないコレステロールを食べすぎることで泡沫細胞になり、過剰反応を起こしたり、壊れたりしてしまうという、体のなかの環境問題である。
●動脈硬化の予防と治療の方法
1.血液中のコレステロール濃度を下げる(従来からのリスクファクターの改善)。
2.LDLの酸化を抑える。
3.病変部へのマクロファージの集積を抑える。
4.マクロファージが血管壁から離脱するのを助ける。
プロローグ コレステロールをためる遺伝子

画像出展:「考える血管」
『帰国のJAL5便のなかで取れた、動脈硬化にかかわるスカベンジャー受容体遺伝子のかけらは、「pJAL5」と命名された。さっそく観光ビザでアメリカにとんぼ返りし、遺伝子のすべての配列を決めた。つづけてコレステロールをためて細胞を泡沫のようにさせる実験を行い、論文をつくり上げた。わずか二ヵ月であった。この遺伝子に関する二つの論文は国際科学誌「ネイチャー」に掲載されることになり、その表紙を飾った。
この発見は、動脈硬化と老化の新たな研究の基礎となった。それだけではなく研究の進み方にもっと広い意味での文化をもたらした。たんぱく質の精製や遺伝子クローニングに明け暮れていた私の研究生活も別の方向へ転換をはじめた。
スカベンジャー受容体遺伝子の核心的な構造は、コラーゲンと呼ばれる、人体で最大量を占め、血管壁でももっとも多く存在するたんぱく質と同じ構造をしていた。この構造は、それまでには考えられなかったようなたくさんの種類の異物や老廃物を結合し、細胞のなかへ飲み込んでしまう。スカベンジャー受容体は、大食い細胞という名をもつマクロファージと呼ばれる細胞のみがもっていて、そのマクロファージがコレステロールを食べすぎることで泡沫細胞になり、動脈硬化を進めていくということがわかった。さらにスカベンジャー受容体に結合するゴミがたくさんありすぎると、マクロファージがこれを飲み込もうとしてもうまくいかず、ゴミのたまっているところにくっついたままになってしまうことがわかってきた。スカベンジャー受容体の発見は、体のなかのゴミ処理機構が動脈硬化という病気にかかわることを明らかにした。それと同時に、「老化の新しいパラダイム」を示すものでもあった。
さらに、脳の皮質のなかの動脈が、スカベンジャー受容体をもった新しい細胞に包まれていることが発見され、従来の血液脳関門に代わる脳の新しい血管構造モデルが生まれてきている。』
エピローグ 脳のなかのスカベンジャー受容体
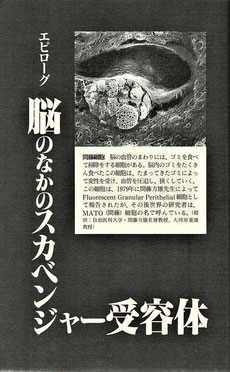
画像出展:「考える血管」
間藤細胞 『脳の血管のまわりには、ゴミを食べて掃除する細胞がある。脳内のゴミをたくさん食べたこの細胞は、たまってきたゴミによって変性を受け、血管を圧迫し、狭くしていく。
この細胞は、1979年に間藤方雄先生によってFluorescent Granular Perithelial細胞として報告されたが、その後世界の研究者は、MATO(間藤)細胞の名で呼んでいる。
塩と高血圧5
第四章 効き目に差をつける降圧剤の使い方 安易な服用はかえって危ない
降圧剤に関する無知と誤解があまりにも多すぎる
・これまで延べ何万人という多くの患者さんを治療してきた。そこで、いつも心配になるのは降圧剤の飲み方である。降圧剤は、場合によっては30年も40年も服用することが必要で、高血圧の人にとって大切な健康管理のための薬となるが、降圧剤についての誤解が非常に多くこちらの方がヒヤッとすることさえある。
・夕食後に服用すべき降圧剤を寝しなに飲むと、最も低くなる夜間睡眠中の血圧をさらに低下させることになるため、血液が滞って固まるというリスクが高まり、狭心症や脳卒中を誘発する懸念を高めてしまう。
・1日分の降圧剤をまとめて飲んでしまったり、飲み忘れた分を次の回にいっしょに飲んでしまうなども危険である。
・降圧剤は強引に神経の作用を遮断したり、体内の水や塩を減らして血圧を下げる薬である。高血圧を根本的に治療する薬でもなければ、ましてや高血圧の予防薬でもない。親が高血圧だから自分もとりあえず飲んでおこうなどという考えも大変危険である。
・降圧剤は、単に高い血圧を引き下げるだけの薬であると考えるべきである。
「降圧剤は一生服用しなければならない」というのは迷信にすぎない
・高血圧が軽症や中等症の人の中には、降圧剤を中止したり減量したりできる人がいる。
・長い間薬で血圧の上昇を抑えていると、体の仕組がこれに順応して血圧が上昇しにくくなり、中には降圧剤を必要としない人もいる。
・血圧が目標値に達し、しかも長期間安定している場合は、降圧剤の減量を試みるべきである。また、年齢や環境によって血圧も変化するため、それに応じた適量を知るためにも、一度減量して血圧の変化を観察することは有益である。
降圧剤はこんな人に使ってはいけない
・正常血圧より高いが、高血圧というほどでもないという境界域高血圧の人の中には、予防的に降圧剤を利用したいと思っている人がいるがこの考えは正しくない。
・第一に、高血圧の人は正常血圧よりも多少高めの血圧が治療目標になる。これはその方がその人の体質に元々合っていると考えられるからである。正常血圧でなければ健康でないという考え方は誤りである。
・第二に、境界域程度の高血圧であれば、日常生活に注意するだけで、十分に血圧を下げることは可能であり、副作用の危険をおかしてまで降圧剤を服用する必要はない。
・第三に、境界域高血圧は二十代から三十代の人に多いため、降圧剤を使い始めると、50年も60年も服用することになり、未知の副作用が現れることも考えられる。
・さらに恐ろしいのは、血圧が下がりすぎてしまうことである。高血圧の人は血圧を上昇させようとする力が強く働いているが、血圧を下げようとする力も働いている。つまり、上昇させようとする力と下降させようとする力、これに降圧剤が加わって、ちょうどよいバランスがとれるのである。ところが、血圧を上昇させる力がそれほど強くない人が降圧剤を服用すると、低血圧が起こる危険が出てくる。こうなると、血液を体の隅々まで運ぶことが難しくなり、手足の冷えや、立ちくらみ、めまい、無気力などの症状が現われてくる。
・70歳以上の高齢者も降圧剤には危険が多い。高齢者は一般的に動脈硬化によって血管が硬くなり、収縮血圧が上昇する。しかし、同時に血圧を調節する機能も低下し、血圧が変動しやすくなる。
・病院で測定すると収縮期血圧が180ミリあっても、家庭でリラックスしているときは、120ミリしかないというようなことも少なくない。このような高齢者に降圧剤を使用すると、脳や心臓、腎臓などに部分的に血液を送れなくなることがあり、かえって体の機能低下が起きたり、活力が低下して元気のない高齢者が出てきてしまう。
・高齢者でも拡張期血圧が100ミリ以上、あるいは収縮期血圧が180ミリ以上ある人、また健康で活発に行動している人は、降圧剤による治療が必要である。この場合も、高齢者は薬を排泄する力や無毒化する力が衰えているので、普通より少なめに服用することが大切である。
降圧剤で正常血圧まで下げてしまうのは、大きな誤り
・高血圧の人は、もともと高めの血圧の方が体に適していると考えられている。また正常血圧というのも、健康な人たちの平均血圧のことで、それにピッタリあてはまらなければ不健康という意味ではない。多少高めで全身の機能がちょうどよく働くという人もいる。
・血圧は年齢の増加に伴って上昇する。従って三十代では収縮期血圧の降圧目標は130ミリでも、八十代には180ミリでも大きな問題はない。
副作用がなく、血圧を即座に下げる薬が開発された
・1950年代にレセルピン[交感神経の中枢と末梢に作用しノルアドレナリンを抑制し、心拍出量の低下と血管の拡張をもたらし血圧を下げる]や利尿剤が高血圧の治療に使用されるようになったが、これらの降圧剤の副作用は本態性高血圧症に“間接的”にしか作用できないからだと考えられる。高血圧を起こす原因そのものには対処せず、無理やり心臓の機能を低下させたり、血管を広げて、血圧を低下させるため、体にゆがみが生じてさまざまな障害を起こすと考えられる。
・当時、治療の主体となっていたのは心臓の仕事量を軽減させるβ遮断剤が使用されていたが、深刻な副作用として心臓の機能を低下させすぎて、心不全を起こす危険があった。
・カルシウム拮抗剤が開発されたのは1972年に入ってからであるが、この薬は本態性高血圧症の治療薬として開発されたわけではなく、狭心症の特効薬として心臓の冠動脈を広げるという目的で開発された。
・カルシウム拮抗剤は、ドイツと日本の協同研究によって追試が重ねられる中、カルシウム拮抗剤で高血圧の人の血圧が低下したという報告があった。そこで、遺伝性高血圧ネズミを使ってカルシウム拮抗剤の効果を実験したところ、すべてのネズミの血圧が低下した。さらに本態性高血圧の治療に応用したところ、やはりすべての患者さんの血圧がすみやかに下降し、しかも副作用が全くといって良いほど少ないことが分かった。
なぜこの薬は、こんなにすばらしい効果を発揮するのか
・カルシウム拮抗剤で心配になるのは、体の他の部分への影響である。手足の骨格筋や胃腸の筋肉もやはり、カルシウムイオンの濃度によって伸び縮みしているので、これらの筋肉に対しても収縮を抑制するという懸念がある。しかしながら、幸いにもカルシウム拮抗剤は、血管の筋肉だけに特別に作用する性質をもっているため、この懸念点は排除できる。
従来の降圧剤より、ここがこれだけすぐれている
・従来の降圧剤の副作用には、無理に血圧を下げることにより、血液の流れを悪くし人体各部の血液不足を起こすことがある。このため血液不足による病気、たとえば脳卒中や狭心症、心筋梗塞、腎臓機能の低下などを起こす危険があった。
・カルシウム拮抗剤は本態性高血圧症の原因に直接働きかける薬である。しかも、血管の異常に対してだけ特異的に作用する性質を持っている。そのため、血管に異常のない正常血圧の人がカルシウム拮抗剤を飲んでも、血圧はほとんど下降しない。
・本態性高血圧症の人は、生まれつき血管筋肉細胞の膜にカルシウムイオンの通路が多く、そのために細胞内のカルシウムイオン濃度が異常に高くなっている。これが血管の内腔を狭くし血圧を上げる原因となっている。
・カルシウム拮抗剤は、この余分な細胞膜の通路をふさぎ、細胞内のカルシウムイオン濃度を低下させることによって血圧を下げる。
・カルシウム拮抗剤は、本態性高血圧症の人の血管の仕組みを正常に近づけて血圧を下げるため、従来の降圧剤のように不必要な働きをすることが非常に少なく、そのため副作用の心配も少ない。
カルシウム拮抗剤の効きめを最も高める使い方
・カルシウム拮抗剤には血圧を低下させるだけではなく、高血圧による合併症を防止・治療する働きもある。
・狭心症、あるいは前胸部から左胸部にかけて、しめつけられるような圧迫感のある人:『カルシウム拮抗剤は本来狭心症の治療薬ですから、こうした症状を伴う高血圧の人にはうってつけです。ただ、前述[カルシウム拮抗剤には、ジルチアゼムとニフェジピンという二つの系統があるということ]のように種類によって心拍数に与える影響が異なるため、心拍数が70回以上の人はジルチアゼム、69回以下の人はニフェジピンを用います。どちらの場合も、起床時に寝床で服用すると、睡眠中に狭くなっていた血管が広がり、効果的です。』
・脳の血液不足や腎機能の低下が心配な人:『高血圧では、血管が狭くなり血液が流れにくくなるため、血液不足で脳や腎臓の働きが低下します。カルシウム拮抗剤は、血管を広げて流れる血液の量が増加しますから、これらの病気を予防し、また一度低下した機能を回復させるためにも効果があります。』
・不整脈のある人:『不整脈は、心臓が拍動するペースが狂う病気で、たいていは心臓の血液不足が原因で起こります。また、高血圧による心肥大や狭心症に合併して現れることもあります。そのいずれの不整脈にもよく効くのが、ジルチアゼムです。これは、ジルチアゼムによって血管が広がるため、心臓が血液を送り出す作業が楽になり、そのために不整脈も治るのではないかと考えられています。これに対してニフェジピンのほうは、逆に心拍数を増加させる作用があるため、不整脈を治す力も少ないとされています。』
緊急事態を招いた重症高血圧でも、この薬を使えば簡単に危機を脱出できる
・重症高血圧の人は、ニフェジピンにプロプラノロールというβ遮断剤を加えるとより効果的である。これはβ遮断剤によって、ニフェジピンの降圧作用が強化される上に、ニフェジピンによる心拍数の増加が防止できるからである。
第五章 高血圧の不安を一掃する早わかり相談 この知識であなたの血圧対策は万全なものとなる
実のところ塩はどの程度とればよいのでしょう?
・適切な食塩の摂取量は一日10~15g(15gは発汗の多い夏場や運動時)。
高血圧の人にとって最も大切な食事の注意を教えてください
・高血圧の人に限らず大切なことは、各栄養素を体に必要な量だけとることである。特に高血圧の人にとって欲しいのがタンパク質である。タンパク質は高血圧で弱った血管や心臓を丈夫にする栄養素である。体内に入ったタンパク質は心臓や血管の筋肉となり、その柔軟性(伸縮性)を高める。従って、血圧が少々上昇しても、心臓は元気に収縮し血管も伸びて破れにくくなり、さらに、血管が柔軟に広がり血圧は低下する。
※慢性腎臓病の患者さまは、一般的にタンパク質摂取制限を求められます。
高血圧の人が、ぜひ避けなければならない食品は何ですか?
・高血圧の人が避けなければならない食べ物はない。ただし、特定の食品を過食したり、逆に食べないことはよくない。特に高血圧の人が注意してほしいのは、糖質と脂質の過食であり、その際、過食かどうかは体重が「身長マイナス110」kgが目安となる。必要以上の摂取は脂肪組織(ぜい肉)になる。
・脂肪組織は腹ばかりでなく、血管壁や心臓の壁にも蓄えられ、その結果、血管が狭くなって血圧が上昇する。一方、心臓の動きが鈍くなって血圧を十分に送り出すことができなくなる。これらによって、脳卒中や心臓発作を起こす可能性が高くなる。
・血液の中の中性脂肪が増加すると、血液はドロドロの状態になり、血液が流れにくくなってますます血圧は上昇する。
血圧が高い人がやってはいけない健康法はありますか
・高血圧の人にとって良くないのは、過度な肉体労働と精神労働である。こうした労働は、一時的であっても血圧を上昇させて心臓病や脳卒中の発作の引き金になる。また、過労を繰り返していると、血圧を高血圧の状態に固定してしまう。
・ジョギングやマラソン、水泳、スキーなどは血圧を著しく上昇させ、心臓の負担を大きくするので危険である。
・瞬発力の必要なスポーツは急激に血圧を上昇させる。バーベルなど重い器具を持ち上げると、一瞬にして150ミリの収縮期血圧が、300ミリにまで上昇してしまう。その拍子に血管が破裂することさえある。ゴルフやテニス、バドミントンにも同じ危険が伴う。
・散歩のような軽い運動は、血管を広げて血圧を下げる作用があり高血圧の人に適している。ただし、寒さは血圧を上げるので、冬は室内を歩くか、日差しのある場所を選んで、暖かい時間に外に出て散歩すると良い。
万能降圧剤のように思えるカルシウム拮抗剤に欠点はないのですか?
・カルシウム拮抗剤は、従来の降圧剤に比べると、格段に副作用や欠点の少ない薬だが、薬である以上副作用はある。ニフェジピンというカルシウム拮抗剤は降圧効果の強力な、重症高血圧の特効薬だが、軽症の高血圧にニフェジピンを普通量使用すると、血圧が下がりすぎたり、立ちくらみ、めまい、頭痛、顔のほてりなどを起こすことがある。また、70歳以上の高血圧の人に使うと、足に浮腫みが起きることがある。これはニフェジピンが毛細血管まで広げて血管壁の網目を大きくし、そこから血液の液体成分が血管の外に出てしまうからである。浮腫みはこの液体成分が組織にたまるために起こる。一方、ジルチアゼムというカルシウム拮抗剤には、心拍数をやや低下させる作用がある。従って、拍動、つまり脈拍が少ない(1分間に60回以下)人にこの薬を大量に使うと、除脈発作を起こす危険がある。
カルシウム拮抗剤は日本でも広く使われているのでしょうか?
・カルシウム拮抗剤は、現在[1984年以前]日本で一番多く使われている降圧剤の一つである。
塩を減らさなければいけない高血圧のタイプを教えてください
・『減塩が必要な高血圧は、食塩過食性高血圧と腎臓の機能不全によって起こった高血圧です。高血圧の90%以上は本態性高血圧症ですが、残りの10%は二次性高血圧といって、他の病気や明らかな臓器障害があって起こる高血圧です。食塩過食性高血圧も、腎臓の機能不全によって起こる高血圧も、二次性高血圧の一つで、数の上では非常にわずかです。食塩過食性高血圧では、遺伝(副遺伝子)によって食塩に対する強い感受性が受け継がれ、食塩を過剰摂取したときのみ高血圧が起こります。食塩に対する感受性が強い人の場合には、過食した食塩が血管の筋肉細胞の中にカルシウムイオンを引き込んでしまいます。そのために、食塩を過食すると細胞内のカルシウムイオン濃度が上昇して、血管が収縮し、血圧が上昇してしまうのです。一方、腎臓に障害がある人も、これと同じメカニズムで高血圧が起こります。つまり、食塩が尿の中にうまく排泄されないために食塩が体内に蓄積され、細胞内のカルシウムイオン濃度が上昇するのです。だから、一日に摂取する食塩の量を5~8gに減らせば、血圧が下がります。』
高血圧家系の人は、何歳ごろから、どのような点に注意すればよいでしょう?
・『本態性高血圧症の家系の人は、20歳ごろから徐々に血圧が上昇し、四十代で確定高血圧になります。いわばいちばんの働きざかりに高血圧になるわけです。しかし、じょうずに降圧剤を利用し、日常ちょっとした心がけをすれば、健康な人と全く変わらない生活ができます。本態性高血圧症の人は、、三十代で血圧がやや高め(境界域高血圧)になり、精神的刺激や肉体労働で正常血圧の人よりも血圧が大きく上昇します。しかし、血管や心臓は健康ですから、三十代の高血圧は良性といえます。この時期には、正常圧で健康な人よりも一割程度多く休息をとってください。過労気味のときには、レジャーも中止して十分休息をとり、ボディビルや、全力疾走が必要なスポーツは避けます。また、肥満やアルコールの多飲、喫煙は血圧の上昇に拍車をかけますから、節制してください。四十代は血圧が急速に上昇する時期で、過労で胸が重くなるなど、高血圧による自覚症状も現われてきます。血圧に注意して降圧剤を利用し、十分な休養をとりましょう。ただし、60歳を越えれば高血圧も峠を越し、心臓病や脳卒中などの発作が起こりにくくなるので、普通の人と同じ生活が送れます。』
酒とタバコは、やはり百害あって一利なしなのでしょうか?
・アルコールは少量であれば、精神的緊張をやわらげる、ストレスを解消するといった効果をもたらすこともあるが、血管に対しては毒として働く。それゆえ、アルコール類は飲まないほうが健康によい。アルコールは血管の筋肉を障害し、血圧を調節する神経を麻痺させるからである。
・タバコは害しかない。タバコは全身の血行を悪くするだけでなく、心臓の働きまで低下させる。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させて血のめぐりを悪くする。
・タバコには大量の二酸化炭素が含まれるため、血液中の酸素が減少して全身が酸素不足に陥る。これだけでも酸素不足による脳や心臓の発作を起こしやすくなるが、そのうえタバコは心臓の機能を低下させ、心臓を支配する神経を麻痺させる。高血圧とタバコの害が相まって不整脈が現われ、ますます心臓発作が起こりやすくなる。高血圧の人にとってタバコはとりわけ恐ろしい毒物である。
健康にいいと言われるカルシウム剤も高血圧の原因になりますか?
・カルシウムをとりすぎても血圧は上昇しない。摂ったカルシウムの大半は骨に沈着し、血液のカルシウムイオンになるのはごく一部である(0.1%程度)。たとえ、血液中のカルシウムイオンの数が増加しても、血管細胞に到達するまでにいくつもの関所が待ち構えていて、細胞内にカルシウムイオンが入れないように目を光らせている。
塩と高血圧4
第三章 血圧はこの方法で下げなさい あなたのやり方では高血圧は治らない
動物性タンパク質を十分とると狭心症や脳卒中も防げる
・血管壁は筋肉細胞と結合織からなり、伸び縮みするのは筋肉細胞であり、筋肉細胞を形作っているのはタンパク質である。
・筋肉細胞は老化し、再生され、世代交代(新陳代謝)をどんどん繰り返している。筋肉細胞の寿命は約1ヵ月なので、若い細胞を作るためには、質のよいタンパク質を十分に摂らなければならない。筋肉を作る材料が不足すれば、老化したボロボロの細胞だけになり、動脈硬化を進行させてしまう。
・血管だけではなく、心臓もまた心筋と呼ばれる筋肉が伸び縮みして、血液を毎日10万回近く体内に送り出しているため、心筋梗塞や狭心症の予防とその修復にも、動物性タンパク質は欠かせない。
・『事実、青白い顔をしていた患者さんたちが、動物性のタンパク質を十分にとるようになってから、皮膚の色つやが見違えるほどよくなり、狭心症や心筋梗塞も改善していくのを、私は毎日のように経験しています。』
みんなが敵視する肉は、実は血圧が高い人にも必要な栄養食
・血管をしなやかに、かつ強靭に保つための第一条件は、タンパク質を十分に補充することであるが、一番良いタンパク質は人間の体を構成しているタンパクに近い動物性タンパク質である。タンパク質を摂らないと細胞の新生を障害し、体の老化を促進してボケを早め、やがては心臓と血管を崩壊させてしまう。
・人間の体を作るタンパク質は、人間以外のどの生物のタンパク質とも違う「人間タンパク質」である。この人間タンパク質は、食物からとったタンパク質を分解して取り出したアミノ酸と、体内で合成されたアミノ酸から作られる。
・体内で合成できないアミノ酸は、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニールアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリンの8つで、これらは必須アミノ酸と呼ばれ、1つでも欠けると人間タンパク質はできない。[現在はヒスチジンを加え、計9つとなっています]
・必須アミノ酸は植物性タンパク質より動物性タンパク質に多く含まれている。なお、食肉としては赤身肉やヒレ肉など、脂肪を含んでいない肉が対象になる。
水を十分に飲むと脳卒中にも心筋梗塞にもなりにくい
・体内には、体重の約12分の1(50kgの人なら約4.2l)の量の血液が流れている。血液成分の45%は赤血球を中心とした血球成分で、残りの55%は血清と呼ばれる液体成分だが、血清1dl中には、タンパク質7g、糖質100mg,脂質500mg、微量のミネラルが含まれており、血液はもともと粘っこい液体である。
・血圧の粘度を減らす方法は二つある。一つは血清中の余分の脂肪(主として中性脂肪)を減らすこと。脂肪を減らすには標準体重にすることである。もう一つの方法は、水を飲んで血液中に占める水の割合を増すことである。飲料水や食物として胃の中に入った水は、胃や腸で吸収されて血管腔に入いる。水は胃壁や血管壁というフィルターを通して血液中に入るが、それら壁は血液の水分量を正確に調整しているので、血液が水で薄まりすぎるような心配はない。
寝しなに水を飲めば、明け方に多い心臓発作が防げる
・消防庁の統計によると、心臓発作がいちばん多発するのは冬で、次いで夏の順である。冬は寒さによる血圧の上昇、夏は発汗により血液がドロドロになりがちになるというのが原因である。
・発作の時間帯はいずれも明け方である。明け方に発作が集中するのは睡眠中の状態に危険が潜んでいるからである。
・睡眠中、心臓は収縮回数と心拍出量を減らし、送り出す血液の量を低下させる。血管も流れている血液が少ないために血管の幅をせばめて休んでいる。一方、血液は夕食により栄養を仕込んでいるがこれを取り込むべき細胞は休息中であり、さらに睡眠中はコップ一杯分の汗をかくため、血液は一日中で最も濃く、ドロドロした状態になっている。
・寝しなに飲む一杯の水は、濃厚な血液を薄め、さらに血液量を増やして睡眠中の血液の流れをスムーズにしてくれる。さらに、就寝前に10分程度の軽い運動を行えば発作の防止に効果的である。これは運動によって血管が広がり血液が流れやすくなり、新陳代謝により血液から栄養素が細胞に取り込まれるため血液が流れやすくなるからである。
十時と三時のお茶は、高血圧の人に欠かせない大切な健康法
・寝しなの水が、明け方の発作を防ぐが、それと同様に起床後の一杯の水も重要である。夜の間に発汗や尿の生成で血漿中の水分は減少するためである。飲水で血液が増えると血管が広がるため血液の流れがスムーズになる。
・体内に入った水は、尿や汗となって体外に出ていくため、早ければ2時間、遅くても3時間で体外に排泄される。7時に飲んだとすると、10時と昼食後の3時に水分の補給を行うことが大切である。
・高齢者は老化現象によって、誰もがある程度の動脈硬化が起きている。そこを流れる血液も若い人に比べ、赤血球や白血球などの固形成分の占める割合が高くなっている。さらに尿素や尿酸など栄養素を使ったあとの残りカスの排泄も悪くなるため、どうしても血液が濃くなってしまう。
・飲水はイライラした神経を沈める。また、胃液を薄めるため胃を守る働きも持っている。
起き抜けのラジオ体操を実行すれば、一日じゅう血圧を低く保てる
・「目が覚める」、つまり脳神経細胞が活動を始めると、私たちは体全体が眠りから覚めたような気になる。しかし、各自器官には少しずつ眠りから覚める時間のズレがあり、これが心筋梗塞や脳卒中の引き金になっている。
・心臓発作が最も起こりやすい時間帯は明け方だが、これに次いで多いのが朝、家を出て駅の階段を駆け上がったときやラッシュアワーの混雑の中で心臓発作を起こすことが多い。この原因は、血管と心臓の目覚める時間の違いからきている。起床後、心臓は即座に活発な活動しはじめるが、血管は目覚めが遅いため心臓から押し出されてくる血液量に適応して血管を広げることができない。その結果、血圧が上昇して血管の破裂や心臓の酸欠状態が起こるのである。
・若い頃は血管も弾力に富み、体の順応力も旺盛なので目覚めの違いもそれほど大きなものではないが、40歳を越えると体内の反射神経が鈍くなるため、目覚めのズレが大きくなり発作のリスクが高まる。
・起床後の10分程のラジオ体操は心臓の動きをなめらかにし、かつ血管を目覚めさせ、体全体の発進準備をとなる。
血圧が高めの人は、昼休みに碁や将棋をしてはいけない
・ゆっくり落ち着いて食べれば正常圧を保てる人でも、慌しい食事は簡単に血圧を20ミリから30ミリ上げ、高血圧にしてしまう。
・食後の休みもとらないでジョギングなどの運動を行えば、食べたものの消化吸収のために胃に送る血液が増加することに加え、運動を行うために手足に大量の血液を供給する必要があり、心臓は猛烈な勢いで酷使されることになる。
・囲碁や将棋、あるいはゲームなど勝負にこだわってくると、その気分は高揚し交感神経を刺激して、血圧を上げる物質(ノルアドレナリン)を分泌させる。その結果、収縮期血圧が150ミリの人なら、勝負どころで200ミリ、また拡張期血圧が100ミリなら130ミリまで上昇する。
・血圧がより高い場合、血圧の上がり方はより大きくなり、脳出血や狭心症を起こすリスクは高まる。横になったり、のんびり散歩することは血圧を下げるには良い方法だが、大きなあくびをしたりため息をつくだけでも血圧対策にはなる。
体重を5キロ減らすだけで高血圧が治ることがある
・『自らの体験から話しますと、私は体重を7kg減らしたおかげで、上昇傾向にあった血圧を正常値にまで下げることができました。以後その体重を維持しているため、一度も血圧は上がったことがありません。体重を減らすことは、私に限らず太った人すべてに共通する強力な血圧降下策です。』
・40歳を過ぎた人の心臓と血管は中古のエンジンとゴムホースのようなものである。このような車を長く乗り続けるためには、積荷を減らすのが良い方法である。積荷とは自分の体重のことだが、この荷物は重い上に大量のガソリン、すなわち血液が必要になる。一方、脂肪濃度が高くなった血液はドロドロになり血圧を上昇させる。
高血圧の人でも眠っている間の血圧は低いことを知ってほしい
・問題ないとされている「正常血圧」とはどのような血圧値なのか。病院で計測する血圧は判断する血圧としては不適当である。
・脳卒中や心臓発作などの病変とよく比例する血圧は、基礎血圧といわれるものである
・基礎血圧は早朝目覚めた直後に蒲団の中で測定される血圧のことである。あるいは、やや空腹時に暗く静かで快適な室温の部屋の中で、約1時間横になった後に測定した血圧はこの基礎血圧に近い値を示す。
・正常血圧の人より高血圧の人の方が睡眠中に血圧が大きく下がる。これは高血圧の人にとって睡眠と休養が血圧を下げる最も効果の高い治療法ということを意味している。
【メモ】慢性腎臓病では、なぜタンパク制限が必要なのか ?
タンパク質が中高年の健康維持にとても重要なのは良く理解できたのですが、例えば、慢性腎臓病の場合はタンパク制限が求められます。その意味では、高血圧の予防に腎臓はとても重要な臓器といえます。
なお、慢性腎臓病においてタンパク制限が必要な理由は以下の通りでした。
これは”東京女子医科大学病院 腎臓内科”さまのホームページに書かれていたものです。
『食事蛋白は老廃物の一種である窒素代謝物を作ります。正常の腎機能であれば、それを処理するのに十分な糸球体があります。しかし腎機能が低下していると、残った糸球体1つ1つがその能力を超えて処理をしようとします(糸球体過剰濾過)。この状態[糸球体過剰濾過]は長くは続かず、徐々にそれぞれの糸球体の濾過機能も落ちてきてしまうと考えられています。その負担を軽減するために行われるのが食事蛋白の摂取制限です。』
塩と高血圧3
第二章 高血圧は塩が原因ではなかった 突き止められた血圧を上げるメカニズム
「高血圧=塩」の神話はいかにして作られたか
・『高血圧、即、減益という連想は、今ではもう一般の人たちの頭にこびりついてしまったようです。減塩食をいくら食べても血圧が下がらないにもかかわらず、塩に対するイメージはなかなか変わらないようです。いったい、高血圧の原因が塩であるというこの誤った常識はどのようにして作られたのでしょうか。
すでにふれたように、アメリカの高血圧学者であるメーネリーは、1953年、普通の20~30倍という高食塩食を10匹のネズミに食べさせて、そのうち4匹のネズミを高血圧にすることに成功しました。これが、「高血圧=食塩」説の発端となった実験です。しかし、これだけで常識が作られたわけではありません。その後の研究や実験、あるいは人情などが相まって、この説をどんどんふくらませていったのです。』
・アメリカ人のトビアンやガイトンは、食塩を排泄する腎臓の機能が低下すると、高血圧が起こるという報告をしたが、この実験結果も食塩の体内蓄積が高血圧を起こすという論理につながり、食塩はしだいに悪者に仕立てられていった。
・日本人も「高血圧=塩」という説を裏付ける役割を果たした。アメリカの高名な高血圧学者であったダールは、戦後日本で高血圧患者が多いことに注目し、食塩の摂取量と高血圧の発生率を調べた。対象に選ばれたのは東北地方と南日本で、その結果、食塩摂取量の多い東北地方で、圧倒的に高血圧発生率が高いことがわかった。
・一日14gの塩をとっている南日本の高血圧発生率が20%強であるのに対し、一日27g~28gをとる東北地方では、40%近い発生率で高血圧患者がいたと報告されている。
・ダールは日本での、「食塩摂取量が増加すればそれだけ高血圧の発生率が高くなる」という調査結果を確かめるため、アメリカに戻ってネズミで実験を始め。高食塩食で血圧が上がるネズミどうしを何代にもわたって交配させ、食塩によって血圧が上昇するネズミの家系を作ったのである。同時に高食塩食で血圧が上がらないネズミも同じように交配させ、いくら食塩を食べても血圧が上がらない家系を完成させた。
・『現在からみれば、ここで食塩によって血圧が上昇する人と、全く変化しない人がいることが判明したわけですが、当時の研究者たちの受けとり方は違いました。本態性高血圧症の人はすべて食塩で血圧が上昇する家系だ、と彼らは考えたのです。
一方、医学的に食塩水を人の静脈に注射して、一日に30gの塩を体内に注入すると、収縮期血圧が10~20ミリ上昇することもわかりました。事ここにいたって、「高血圧=食塩」説は、世界の注目を集めるところとなったのです。
この説はまた、一般に受け入れられやすいという点でも、神話としての要素を備えていました。まず普通の人にも理解しやすかったことと、また減塩食が実際的で家庭でも高血圧の治療として実行しやすかったことです。さらに、遺伝によって発病する高血圧を減塩で治せるという点でも魅力的でした。
このように、いろいろな要素が「高血圧=塩」の神話を作り出しては支えてきたのです。
しかし、10年ほど前から、この説を実際の高血圧治療に応用したところ、思ったほどの効果がないどころか、過剰な食塩制限による塩なし病まで生まれ、今日では世界中が食塩説に疑問を抱くようになっています。こうしてようやく、「高血圧=食塩」の神話は過去のものとなったのです。』
一匹のネズミが従来の誤った学説を放逐した
・ 『今から二十数年前の1959年、私はネズミを使って高血圧の研究を行うために、ある特殊な血圧測定器を作っていました。ネズミの血圧は人間の血圧とたいへんよく似ているため、血圧の研究にはネズミがもってこいの動物です。ネズミの血圧を測定する器具は、すでに1938年にイギリスで開発されていましたが、その器具はあまり実用的ではなく、精度を高めようとして私も苦心していたのです。
ところが、その最中に偶然にも、私はあるネズミとの運命的な出会いをしました。大げさに言えば、この出会いがそれまでの高血圧の歴史を変えることになったのです。』
・血圧測定器の精度を再確認するため、京都大学動物センターから分けてもらった10匹のネズミを、1匹ずつ計器の中に入れ、血圧を測定していたところ奇妙なことに気がついた。10匹のネズミの中に、140ミリと170ミリをいつも示すネズミがいた。つまり、わずか10匹のネズミの集団の中に、正常血圧のネズミにまじって境界域高血圧のネズミと高血圧のネズミがいたことになる。
・高血圧のネズミどうしを交配すれば、遺伝性の高血圧家系ができると直感した。遺伝性の高血圧は、人間でいえば本態性高血圧症にあたる。いちばん血圧が高かったオスとメスを繰り返し交配し、三世代目にはオスもメスも100%高血圧になった。中には収縮期血圧300ミリ以上のネズミや自然に脳出血を起こすものも現れた。こうして、1963年に遺伝性高血圧ネズミ、正式には高血圧自然発症ラット(SHR)が完成した。
【メモ】ネズミと研究者による偉業
思わず、”ネズミの血圧計”に反応してしまいました。また、いくつかの興味深い発見もありました。

画像出展:「株式会社ソフトロン」

画像出展:「京都大学大学院 松田研究室」
SHR開発記念碑「人類への贈物」
『高血圧は現代社会で最も多い病態で、三大死因の一つ、脳卒中や、寝たきり、認知症の主要因である。ヒトと類似の高血圧、脳卒中を自然発症する高血圧自然発症ラット(SHR)、脳卒中易発症ラット(SHRSP)は20世紀後半(1963年、1973年)岡本耕造名誉教授・青木久三博士はじめ、京都大学医学部病理学教室の多くの共同研究者の尽力により開発された。 このモデル動物のおかげで、高血圧・脳卒中など成人血管病の病因、病態解明も進み、多くの降圧剤が世界中で新たに開発され、栄養などで脳卒中の予防が可能であることも実証された。 脳卒中を必発する遺伝子を保有していても、その遺伝子を検出し、遺伝子の発現を制御して疾患の発症を予知し予防する、「病む人なき未来医学」の夢がここに誕生したのである。』

画像出展:「株式会社星野試験動物飼育所」
高血圧自然発症ラット(SHR)です。

画像出展:「The National BioResource Project for the Rat in Japan」
こちらは、高血圧自然発症ラット(SHR)、ではなく、脳卒中易発症ラット(SHRSP)でした。
食塩を減らしても血圧が下がらない場合が多いことが証明された
・『「高血圧=塩」という説が治療に応用されたとき、第一に疑問になった点は、一日10gの減塩食ではほとんどの高血圧の人の血圧が下がらないという事実でした。そこで、食塩説を立証するために、一日1~2gという厳しい減塩食が実施されました。しかし、これでわかったことは、血圧が下がるどころか、過度の減塩食がかえって塩なし病を起こすことだったのです。
高血圧症の患者さんに、一日5gという減塩食を実施してもそれで血圧が下がったのは、10人に1人あるかないかでした。実は、減塩食では遺伝性高血圧が治らないことは、すでに1971年に私の実験で明らかにされていたのです。
遺伝性高血圧ネズミは、人間の本態性高血圧症に相当しますから、それを使った実験で減塩食の効果を判断することができます。』
遺伝性高血圧ネズミを四つのグループに分ける。
①普通の食塩摂取量の10倍の高食塩食
②通常の食塩を含む標準食
③通常の三分の一の低食塩食
④10倍の高食塩食と飲料水として1%の食塩水
それぞれ30週間与えて経過をみた。低食塩食、標準食、高食塩食では、ほとんど血圧に変化はなく、むしろ、標準食グループのほうが低食塩食グループよりも血圧が低かった。唯一、高食塩食に1%の食塩水を飲料水として与えたグループだけが、収縮期血圧が180ミリから220ミリ程度に上昇し死に至った。実際には、このグループのネズミは40~50倍の食塩水を無理やり食べさせられていたことになる。これだけ大量の食塩を30週間毎日食べていれば、体液のバランスがひどく崩れ、ネズミは高ナトリウム血症(血液中のナトリウム値が異常に高くなった状態)と腎不全を起こす。従って、このネズミの死因は高血圧ではなく、食塩の異常摂取による全身状態の悪化が原因である。
この実験によって、遺伝性高血圧ネズミの血圧は、食塩の摂取量に関係がないこと、さらにかなりの高食塩食でも水を十分に飲み、尿を排泄できれば、血圧は上昇しないことがはっきりした。
血圧はこのような仕組みで調節されている

画像出展:「減塩なしで血圧は下がる」
この絵を拝見し、筋肉による細動脈の収縮は血流にこれ程までに大きな影響を及ぼしているということを知りました。
・血管はいつも拡張と収縮を繰り返しているが、最大拡張時の血管は最大収縮時の5倍に広がる。
・血管の収縮と拡張は、動脈の壁にある筋肉(血管平滑筋)の伸び縮みによって営まれている。
・血管平滑筋が収縮時の1.7倍の長さに伸びるだけで、内腔は5倍に広がる。これは血管平滑筋が40%縮むと内腔が5分の1にまで減少するというでもある。つまり、血管はほんの少し筋肉の収縮率を変えるだけで簡単に動脈の太さを変え、血圧を調節することができるということである。
・青木先生が行った流体力学による計算では、血管平滑筋の伸びが1%少ないと100ミリの血圧は113ミリに、それが3%だと152ミリに上昇する。このように筋肉の収縮は血圧に対して大きな影響を与えるのである。したがって、血管平滑筋に1~3%余分に収縮する性質があるとすると、簡単に高血圧になってしまう。
・動脈は大動脈に始まり、中動脈、小動脈、細動脈と枝分かれして徐々に細くなっている。このうち大動脈には筋肉は少なく、自ら太さを調節することはできない。これに対して、自ら拡張と収縮を行い、血管の太さを決めているのは直径100μmほどの細動脈である。この細動脈には大動脈の1000倍もの筋肉があり、その収縮によって血圧は決定されている。したがって、本態性高血圧症の原因は細動脈に潜んでいるのである。
血管の太さを調整し、血圧を調節する物質がわかった
・細動脈の筋肉が収縮しやすい性質を持っていると、収縮期には必要以上に血管が細くなる。また、拡張期には十分血管が広がらないために、いつも血圧が高くなるのである。
・本態性高血圧症の原因と考えられる細動脈の内腔の大きさは数種類の命令系統によって調節されている。
・血管自身にはゴムのように、一度伸びれば自動的にもとに戻ろうとする性質がある。
・胃が食べ物によって膨らむと、その圧力を感じて消化運動を始めるように、血管の壁にも血液中の圧力を感じとって、血管の太さを調節する機能が備わっている。さらに、血管の壁は血液中の化学物質をキャッチして、血管の太さを変える働きももっている。このように動脈壁の筋肉自身、神経、血液中の化学物質などによって、血管の太さは四重にも五重にも見張られていおり、それによって血管の太さが厳重に調節され、血圧が正常に保たれる仕組みになっている。それにも関らず、血管が細くなりすぎて血圧が上昇したのが高血圧である。
※細動脈に関しては、前週のブログ”塩と高血圧2”の最後に追記した”【メモ】血管の筋肉にある自動血圧調整機能?”を参照ください。
生まれつき高血圧になりやすい人は血管の細胞膜に異常がある
・細胞内への物質の取り込みは、細胞を包む細胞膜によって調節されている。このことから、遺伝性高血圧ネズミはこの細胞膜になんらかの障害があり、そのために細胞内のカルシウムイオン濃度が上昇して血管筋肉が常に収縮気味と考えられる。これを人間にあてはめると、本態性高血圧症の人は、血管筋肉内細胞の細胞膜に生まれつき障害があり、そのために高血圧になると考えることができる。
高血圧の人は、もともと血管の筋肉が収縮しやすい
・今までの内容を整理すると、血圧を決めているのは細動脈の内腔の太さで、この太さは血管の壁にある筋肉によって調節されている。そしてこの筋肉の収縮と伸展はカルシウムイオンの濃度で決定され、また、この濃度を調節しているのは細胞膜であるということである。
塩と高血圧2
第一章 塩をとっても血圧は上がらない 血圧対策の常識が変わった
塩は高血圧とほとんど無関係であることが判明した
・減塩食には100mmHgの血圧を1~2mmHg下げる程度の力しかない。
・無理な減塩食は心身に深刻な害を与えている。
・塩は1953年頃から高血圧の原因として考えられるようになった。
・青木先生は1959年に普通食で高血圧を発病するネズミを発見し、これらの高血圧ネズミを交配させ、普通のエサで遺伝的に高血圧になるネズミの家系(高血圧自然発症ラット:SHR)を完成させた。
・人間の場合、遺伝によって受け継がれる高血圧を、本態性高血圧症と呼んでいる。これらは高血圧自然発症ラットと同様に、摂取する食塩の量を減らしても血圧を下げることはできない。
・10人に1人程度の割合で、二次性高血圧の人がいる。こちらも遺伝とは切り離せないが、原因は腎臓の障害やホルモンの分泌異常、肥満しやすい体質によるものである。
・食塩が原因の高血圧は、塩を排泄する腎機能が弱という性質が遺伝することによる二次性高血圧の1つである。この場合には原因である塩の摂取を制限すれば、血圧を下げることができる。
・問題はほとんどの医師が、食塩を本態性高血圧症の原因と考えているということである。
減塩のしすぎはかえって体に異常をきたす
・「減塩すれば血圧は下がる」という考え方は、日本だけでなく世界中に広まっている。
・減塩しょうゆや減塩みそなどの減塩食信仰が新しい病気、塩なし病を生み出していることはあまり知られていない。
・世界的に著名な学者であるイギリスのピッカリング博士は、「減塩をしすぎて死亡した人の数と食塩の摂りすぎによって死亡した人の数は、どちらが多いかわからない」と述べ、減塩食信仰の行きすぎを嘆いている。
・塩はナトリウムと塩素という二種類の元素でできた化学物質である。いずれも体を構成する重要な成分であり、生命活動を営む大切な物質として働いている。
・ビタミンの欠乏は特定の「病気」を起こすだけだが、塩の欠乏は「生命」を奪うことになる。塩の摂取量を減らしすぎると体の細胞に障害が起きる。
・二年も三年も厳しい減塩食を続けていると、全身の倦怠感、無力感、食欲不振、いつもイライラして落ち着かない、やる気が起こらない、根気が続かない、ボケ、壮年性・老年性認知症などの病状が現われてくる。
・細胞が細胞の形を維持しているのは、ナトリウムイオン、すなわち塩のおかげである。もし、細胞内の塩が二分の一になると、細胞内のイオン濃度が低下するため、細胞内の水はほとんど全部外に流れ出し、細胞はつぶれてしまう。
・浸透圧が生体で適切に保たれているのは、塩がうまく働いているからである。その働きを維持するためには、食塩を1日8~10gとる必要がある。
・極度の減塩が血圧を上げる場合もある。これは外から塩が入ってこないために、塩不足によって腎臓が障害され、血圧を上げる物質が腎臓などで作り出されるためである。
塩を減らさなければいけない人は意外に少ない
・『私の診療経験からいって、減塩食で高血圧が治る人、つまり塩が原因の高血圧である食塩過食性高血圧は、100人のうちせいぜい二人か三人にすぎません。
確かに食塩には、1日30gか40gずつくらい非常に大量にとりつづければ、収縮期血圧(最大血圧)を10~20ミリほど上げる作用があります。ですから、微弱ながら塩には血圧を上げる働きはあるのですが、普通は血圧を正常に維持しようとする生体の力が働き、塩が昇圧作用を発揮しないうちに、尿や汗となって体外に排泄されます。ところが、食塩に敏感な体質の人では、食塩を少しとりすぎても、昇圧作用が強く現れ、血圧が上がってしまうのです。この塩による血圧上昇のメカニズムは次のように考えられています。
食べ物から摂取された塩は、ナトリウム(ナトリウムイオン)となって血液中に入り込み、全身に供給されますが、このとき、血管壁の筋肉細胞の中にも一部のナトリウムが入り込みます。筋肉も細胞の集まりですから、細胞の周囲には細胞外液が満たされていて、大量の食塩をとると、この細胞外液にナトリウムがどんどん増加します。』
・細胞外液と細胞中の細胞内液を一定の濃度に保つために、細胞の膜にはナトリウム-カリウムポンプという特別なナトリウムのくみ出し装置がついている。
・ナトリウム-カリウムポンプの働きで細胞内のナトリウムを外にくみ出し、細胞の内と外を一定のナトリウムイオン濃度に保っているが、細胞外液にナトリウムが増えすぎると、ポンプが働かなくなってナトリウムが細胞の中に増えてしまう。そのため、増えたナトリウムを細胞外へ運び出すために、カルシウムイオンの力を借りることになる。
・細胞外のカルシウム(カルシウムイオン)を細胞内へ運び込むときに生じる力によって、ナトリウム-カリウムポンプは細胞内のナトリウムを細胞外へくみ出す。その結果、今度はカルシウム(カルシウムイオン)が細胞内に増加する。実はこのカルシウムこそが、血圧を上げる真犯人である。カルシウムは血管の筋肉を収縮させ、血管を細く、狭くする。そして、狭くなった血管を血液が通過するために、より強い圧力が必要になり、その結果、血圧が高くなるという仕組みである。
減塩が必要な体質かどうかを知るチェックポイント
・本態性高血圧症は、普通自覚症状があまりなく、気がつかないうちにじわじわと血圧が上がり、60歳くらいを境に老化によって血圧が低下するまで続く。つまり40年から50年にわたる長期の病気である。
・本態性高血圧症は遺伝的な素質に基づいて発病する病気であり、かなり若いときから体内では高血圧の準備が始まっている。一般的には十代、二十代に発症前期といって高血圧の準備段階に入り、三十代になるとその徴候が現われはじめる。その頃になると、収縮血圧が140~150ミリ、拡張期血圧が90ミリ程度に上昇する。さらに、四十代から五十代にかけて、高血圧が進み完全な高血圧症になる。
・自覚症状によって本態性高血圧を判断することは困難で、手がかりは本態性高血圧症が遺伝による病気で、減塩食では血圧は低下しないことである。一方、食塩過食性高血圧では、摂取する食塩の量で血圧は上下する。
治療が必要な高血圧の人は案外多くない
・血圧が少し高い程度ですべて人が、降圧剤を飲まなければならないということではない。高血圧の薬は長く服用するため、薬の種類、量、服用法を慎重に考える必要がある。
・高血圧の人に薬物療法が必要かどうかを決定する目安となるのは、当然血圧値であるが、特に拡張期血圧(最小血圧)が治療の指針となる。この理由は、高血圧による害である動脈硬化や心肥大、さらに脳出血のような病気は主に拡張期血圧の上昇によって引き起こされるからである。
・1983年の国際高血圧学会会議とWHO(世界保健機構)との合同会議でも、治療を必要とする高血圧は拡張期血圧が95ミリ以上であり、収縮期血圧は参考にとどめるべきであることが正式に明らかにされた。

画像出展:「日本高血圧学会」
こちらは2019年7月に更新された“血圧の分類”です。1983年に高血圧とされた拡張期血圧95mmHgという数値は、2019年7月の診察室血圧のⅠ度高血圧(90~99)のほぼ中間値になっていますので、ほぼ同等ということになります。
・血圧は通常、1日の間に収縮期血圧で40ミリ、拡張期血圧で30ミリ程上下するため、1回に3分以上かけて3回以上血圧を測定し、そのうち1番低いもの、あるいは3分以上安静にした後、安定した時点の血圧を3回以上測定し、その平均値をとらなければならない。この方法で測定し、拡張期血圧が106ミリ以上であるときは迷わずに治療が開始される。90ミリ~105ミリの人は、1ヵ月以内にもう二回、血圧の測定を受ける。そして二回、二日間とも最も低い測定値が100ミリ以上であったときに初めて治療が開始となる。拡張期血圧が99ミリ以下の人は、少なくとも急いで治療を開始する必要はないが、管理を怠ることは非常に危険である。拡張期血圧が90~99ミリの人は、生活療法(軽い減塩食、標準体重にするための減量、適度の運動など)を続け、拡張期血圧が95ミリ以上3ヵ月続いていたら、降圧治療を始める。この3ヵ月間を通じて常に拡張期血圧が90~95ミリであった人は、もう3ヵ月間状態を観察し、この間に拡張期血圧が95ミリ以上に上昇し、しかもそれが続くようであれば、薬を使用することも考えなければならない。いずれにしても、90~99ミリの人は定期的に血圧を測定することが大切である。
中年からジョギングを始めるとかえって危険なことが多い
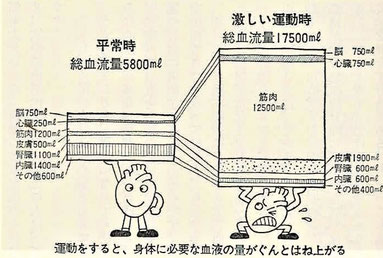
画像出展:「減塩なしで血圧は下がる」
これを見ると、激しい運動の血流の変化には3つのタイプがあるのが分かります。
1.変化しないものー脳
2.増えるものー筋肉、皮膚、心臓
3.減るものー内臓、腎臓
・激しい運動を行うと筋肉への1分間の血流量は平常時の1200mlが約10倍になる。また、心臓の血流量も普段の250mlが3倍になる。これだけの血圧を全身に送り込むには血圧は顕著に上昇する。例えば、5分間走ると正常血圧の人でも収縮期血圧(最大血圧)が120ミリから160ミリに、拡張期血圧(最小血圧)が70ミリから100ミリまで上昇するが、高血圧の人は血圧の変動幅も大きいため、運動による血圧の上昇はもっと大きくなる。収縮期血圧160ミリ、拡張期血圧100ミリの高血圧の人は、5分間の運動でそれぞれ、220ミリと140ミリに上昇する。
60歳を過ぎてからの高血圧は心配しなくてよい

画像出展:「減塩なしで血圧は下がる」
左が”収縮期血圧(最大血圧)、右が拡張期血圧(最小血圧)です。
拡張期血圧(最小血圧)は収縮血圧(最大血圧)に比べ血圧上昇による死亡指数への影響が大きいこと。また、50才以上(青木先生の見解は60歳を過ぎるとさらに差がつくとのことです)の死亡率は低くなることが分かります。
・高齢者の血管は弾性が低下する。一方、血管壁の弱体化を補うために結合織が増え、血管壁は厚くなる。また、供給される血液の量が少なくなるため、血管の収縮・拡張を行っている筋肉も衰えてくる。このように動脈硬化に陥った血管では、心臓の収縮期に血液が送り込まれてきても、血管がうまく内腔を広げることができず、血圧が上がってしまうのである。したがって、高齢者に起こる高血圧は収縮期高血圧であり、一種の老化現象として起こるものであり、学者によって高血圧の範囲に入れないこともある。
・収縮期血圧が160ミリ以上になると、30歳から50歳の人では、死亡率が正常圧の人の3倍になるが、60歳以上になると死亡率は1.1倍程度まで下がる。この統計からも60歳以上の収縮期血圧は老化現象であり、あまり心配はないといえる。しかし収縮期血圧が180ミリを超えると治療対象になる。これは180ミリを超えると血管の筋肉にある自動血圧調節機能が活動を停止するためである。さらに老化は血圧をコントロールする分泌などに狂いが生じ、容易に、しかも大幅に血圧は変化するため注意を要する。
【メモ】血管の筋肉にある自動血圧調整機能?
ここで私は「”血管の筋肉にある自動血圧調整機能”とは何だろう?」と思い、調べてみることにしました。その結果、これかなというものが2つありました。

左のイラストは東邦大学さまの”心筋ー心臓は電気とカルシウムイオンで動いている”から拝借したものです。
ここでは、血管の筋肉(血管平滑筋)を考える上では「細動脈」が重要であり、また、血圧の調整機能という視点で考えた場合、自律神経(交感神経)の働きを理解する必要があると考えたため、引用させて頂きました。『細動脈 arteriole は各臓器に血液を供給するやや細い動脈です。平滑筋層が発達しており、それが適度に収縮することで緊張を保ち、血管の断面積つまり血流に対する抵抗の大きさが調節されています。したがって細動脈平滑筋層の緊張度を変化させる物質は、臓器間での血流の分配を変化させると共に、血圧に影響を与えることになります。血圧を規定する主要な因子は単位時間に心臓から送り出される血液の量(心拍出量 cardiac output )と細動脈全体としての抵抗(末梢血管抵抗 peripheral vascular resistance )です。心拍出量と末梢血管抵抗の積が血圧になります。細動脈は交感神経により調節されていて、交感神経が興奮すると伝達物質のノルアドレナリンが血管平滑筋に作用して収縮を起こし、血管抵抗が増大します。ノルアドレナリンは心拍出量も増大させるため、この両方の効果により血圧が上昇します。この他多くの生体内物質や薬物が細動脈平滑筋に作用して血流、血圧に影響を与えます。
細動脈の最も内側の血液に接している面は、一層の内皮細胞 endothelial cell で覆われています。内皮細胞は様々な生理活性物質を分泌して血管壁を保護しています。内皮細胞には収縮機能はありませんが、血管平滑筋に作用して収縮や弛緩を起こさせる様々な物質を分泌し、局所血流や血圧の制御に関与しています。』
もう一つは、PDFの資料(7ページ)で、タイトルは”血圧,心拍数,心機能および血液量の調節”です。クリック頂くとダウンロードされます。
『細小動脈平滑筋の緊張を調節するメカニズムはいろいろある。平滑筋自体の収縮が内在リズムで行われるだけでなく、血圧上昇時に動脈平滑筋が伸展される圧力弛緩という現象と、逆に血圧上昇による動脈の伸展に反応して、平滑筋が収縮する作用であるが、後者は血圧が上昇しても血流量がほとんど変わりないための自己調節といわれるものである。このような局所性調節のもうひとつは、組織におけるヒスタミンやブラディキニンなど血管拡張性物質の産生である。動脈収縮による組織血流減少によって、その局所で血管拡張性物質を作り、それが動脈収縮を打ち消す作用をするといわれている。』
塩と高血圧1
昨年夏、母親が定期的に行っている血液検査で、軽い“低ナトリウム血症”と診断されました。この頃、母親は時々頭痛を訴えていました。更に、たまにですが「気持ちが悪い(嘔気)」と発するときもありました。
水分には気を遣っていましたが、塩についてはノーマークでした。また、塩というと血圧と腎臓病との関係から、“減塩”を意識し、実際、減塩醤油や減塩味噌を使っていました。塩といえば、「減らすべきもの」という先入観を持っていました。
塩は腎臓病患者さまにとって要注意とされていますが、特に中高年の腎臓病の患者さまの場合、高血圧の薬を服用されている方が多く、以前から“高血圧”については詳しく知る必要があると感じていました。
このような経緯から、今回は“塩と高血圧”をテーマとしたのですが、最初に拝読したのが『塩を変えれば体は良くなる!?』という、まさに塩について詳しく説明されている本でした。そして、この本の中で青木久三先生を知り、青木先生の著書の中から、一般の人向けに書かれた『減塩なしで血圧は下がる』という本で勉強させて頂くことにしました。
高血圧に詳しくない私にとっては非常に勉強になったですが、ご注意頂きたいのはこの本の出版が昭和59年(1984年)4月と36年前に書かれた本であるという点です。最新の知見とは合わない部分もあるかもしれません。少なくとも、日本高血圧学会が発表している”高血圧治療ガイドライン”とは差があります。
下記の図は、“降圧剤を使用するときの年齢別降圧目標”になります。
青木先生は、前提として「高血圧の人は正常血圧まで下げることを目標としない」というお考えですが、その理由は次の三つです。
1.無理な降圧は体への負担が大きく、血圧低下に伴う血液不足によるリスクが大きくなる。
2.高血圧の人は、もともと高めの血圧の方が体に適している。
3.降圧剤が増えれば、それだけ副作用のリスクが高まる。
減塩を否定する本のため、目次の中には「どうなんだろう?」と疑問に思う項目も多く、そのため、青木久三先生のプロフィールを目次の前にご紹介することにしました。
また、私にとっては新鮮なお話ばかりで、ブログがかなり長いものになってしまったため、5つに分割することにしました。
ブログは要点と感じた部分をまとめる形式が大部分ですが、正確にお伝えしたいと思った個所は、そのまま引用させて頂きました(『』括られています)。また、目次の中の灰色の項目に関しては触れていません。

著者ご紹介
昭和8年名古屋市に生まれる。昭和33年名古屋市立大学医学部を卒業後、京都大学大学院をへて、名古屋市立大学医学部第二内科入局。昭和39年から約3年間、アメリカ・クリーブランドクリニックの研究所で、高血圧の世界的権威ページ博士より指導を受ける。次いで、昭和43年から1年間、米国文部厚生省(NIH)の主任研究員を委嘱され、現在、名古屋市立大学医学部助教授[1984年時点]。
昭和57年には、高血圧学会のノーベル賞といわれる高血圧学会賞を米国心臓学会より受賞。現在[1984年時点]、日本高血圧学会評議員、米国心臓学会高血圧誌編集委員。国際高血圧学会所属。
専門は、内科学、循環器病学、高血圧病学。
主な著書に「高血圧の臨床―本態性高血圧症と二次性高血圧―」「本態性高血圧症とその治療」、「Ca拮抗剤の基礎と臨床」(共著)、「Ca拮抗剤の最近の知見」(共著)、「臨床心臓病学」(共著)がある。この他、ネイチャー、サイエンスをはじめとする外国の学術誌に英語の論文も多数発表。
※米国心臓学会 高血圧学会賞:失礼だと思いましたが、ちょっと調べてみました。下記のページをスクロールして頂くと、”1982”のところに、3人の先生の氏名が出ています。青木先生は、Kyuzo Aoki, MDです。
目次
第一章 塩をとっても血圧は上がらない 血圧対策の常識が変わった
塩は高血圧とほとんど無関係であることが判明した
減塩のしすぎはかえって体に異常をきたす
塩を減らさなければいけない人は意外に少ない
こんな人は塩を気にする必要はない
減塩が必要な体質かどうかを知るチェックポイント
治療が必要な高血圧の人は案外多くない
食事からとるコレステロールを気にするのは無意味で大きな誤り
貝やイカはコレステロールを上げるどころか逆に下げることがわかった
人気のリノール酸は逆に血管を傷め、動脈硬化によくない
動脈硬化によいと評判のビタミンEにひそむ重大な死角
中年からジョギングを始めるとかえって危険なことが多い
60歳を過ぎてからの高血圧は心配しなくてよい
塩よりも肥満のほうが血圧を上げていることを忘れてはいないか
第二章 高血圧は塩が原因ではなかった 突き止められた血圧を上げるメカニズム
高血圧の専門医もまちがう高血圧の本当の意味
これだけはまず知っておいてほしい高血圧の基礎知識
高血圧があなどりがたい重大な成人病であると言われる理由
「高血圧=塩」の神話はいかにして作られたか
一匹のネズミが従来の誤った学説を放逐した
食塩を減らしても血圧が下がらない場合が多いことが証明された
高血圧の遺伝は「メンデルの法則」を抜きに考えられない
血圧はこのような仕組みで調節されている
血管の太さを調整し、血圧を調節する物質がわかった
生まれつき高血圧になりやすい人は血管の細胞膜に異常がある
突き止められた血圧を調節する細胞膜の仕組み
高血圧の人は、もともと血管の筋肉が収縮しやすい
第三章 血圧はこの方法で下げなさい あなたのやり方では高血圧は治らない
高血圧と心臓病の危機を脱した私の体験から話そう
動物性タンパク質を十分とると狭心症や脳卒中も防げる
みんなが敵視する肉は、実は血圧が高い人にも必要な栄養食
血圧の高い人にはまるごと食べられる卵や小魚が最高の治療食
水を十分に飲むと脳卒中にも心筋梗塞にもなりにくい
寝しなに水を飲めば、明け方に多い心臓発作が防げる
十時と三時のお茶は、高血圧の人に欠かせない大切な健康法
起き抜けのラジオ体操を実行すれば、一日じゅう血圧を低く保てる
朝晩散歩する習慣をつけるかどうかで高血圧の合併症予防にこれだけ差がつく
血圧が高めの人は、昼休みに碁や将棋をしてはいけない
体重を5キロ減らすだけで高血圧が治ることがある
血圧の重い人が重い荷物を持つのは非常に危険
階段の駆け上がりは、高血圧の人には絶対にすすめられない
血圧はちょっとしたことで大いに変動する
高血圧の人でも眠っている間の血圧は低いことを知ってほしい
私がすすめる高血圧の人のための特効献立
第四章 効き目に差をつける降圧剤の使い方 安易な服用はかえって危ない
降圧剤に関する無知と誤解があまりにも多すぎる
「降圧剤は一生服用しなければならない」というのは迷信にすぎない
降圧剤はこんな人に使ってはいけない
降圧剤で正常血圧まで下げてしまうのは、大きな誤り
これだけは知っておきたい降圧剤の種類と副作用
降圧剤は一種類から始めるのが理想的
副作用がなく、血圧を即座に下げる薬が開発された
なぜこの薬は、こんなにすばらしい効果を発揮するのか
従来の降圧剤より、ここがこれだけすぐれている
降圧剤の副作用は、カルシウム拮抗剤をいっしょに使えば防止できる
カルシウム拮抗剤の効きめを最も高める使い方
緊急事態を招いた重症高血圧でも、この薬を使えば簡単に危機を脱出できる
降圧剤は、高血圧の程度でこのように使い分けよ
第五章 高血圧の不安を一掃する早わかり相談 この知識であなたの血圧対策は万全なものとなる
実のところ塩はどの程度とればよいのでしょう?
高血圧の人にとって最も大切な食事の注意を教えてください
高血圧の人が、ぜひ避けなければならない食品は何ですか?
血圧が高い人がやってはいけない健康法はありますか
万能降圧剤のように思えるカルシウム拮抗剤に欠点はないのですか?
カルシウム拮抗剤は日本でも広く使われているのでしょうか?
降圧剤を山ほどもらってきます。やはり全部飲むべきでしょうか?
飲み忘れた降圧剤を、次回にいっしょに飲んでもかまいませんか?
塩を減らさなければいけない高血圧のタイプを教えてください
高血圧家系の人は、何歳ごろから、どのような点に注意すればよいでしょう?
酒とタバコは、やはり百害あって一利なしなのでしょうか?
健康にいいと言われるカルシウム剤も高血圧の原因になりますか?
脳とストレス8(まとめ)
最後に、まとめとして7つのブログを見直すことにしました。とは言っても、内容は個人的に特に重要と感じた個所を、多少言い回しを変えて、あらためて列挙したものであり、特に新鮮味はありません。
●ストレスは厳しい状況のもとで人間の体を守ってくれるが、慢性的に作動すると有害になり、病気を悪化させる。
●ストレス反応のしくみ
1.脳にある視床下部が腎臓の上にある副腎体に警鐘を鳴らす。
2.ストレスホルモンの第一陣、アドレナリンを分泌し緊急反応で対応する。
3.脳はエンドルフィンという鎮痛作用をもつ物質を出し、危機においても機能できるようにする。
4.脳は防衛機構の第二陣、視床下部‐下垂体‐副腎軸(略してHPA軸)という先鋭部隊を動員する。
・視床下部は副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)という物質を放出し、CRFは下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を分泌、ACTHが副腎を刺激すると、第二の主要ストレスホルモンであるコルチゾールが血液に放出される。
5.コルチゾールは適量であれば、アドレナリン放出によって使い果たされたエネルギーを補充し、私たちを活動的にさせる。免疫に関しても短期的には、コルチゾールは怪我や感染から体を守る白血球を、侵略された場所に送り込む。また、コルチゾールのチェック・アンド・バランス(抑制と均衡)の機能が、免疫反応が活発になりすぎることによっておこる湿疹やアレルギー、および免疫が健康な細胞を攻撃する自己免疫疾患を防ぐ。そして免疫活動がもう十分だと知らせるのもコルチゾールの働きである。しかし、コルチゾールが長期にわたり適量を超えた量が分泌されると様々な弊害を生む。そして、これが慢性ストレスの問題につながる。
・ブドウ糖を取り込むインスリンの働きが抑えられてしまう
・脂肪が増え、とりわけ、健康に悪いとされる腹部にたまる。
・筋肉のタンパク質を減らして脂肪に変える働きを促し、その結果、骨のミネラルが減る。
・コルチゾールが多すぎると免疫機能を抑えるため、感染症にかかりやすくなる。
・ストレスホルモン(アドレナリン、コルチゾール)は血圧を上げる。
●アロスタティック負荷(ストレス反応が私たちの体に逆襲するような状態)は、体がアドレナリンやコルチゾールに長い間さらされることから起こるが、これは、ストレス自体が長く続くか、ストレスがなくなっても体が順応できないか、ストレス反応を解除するプロセスが機能しないかのいずれかの理由が考えられる。
●うつ病ではコルチゾールが慢性的に上昇していることが多い。
●コルチゾール過剰分泌説によれば、海馬にコルチゾールがあふれると海馬が疲労し消耗して、HPA軸が正常に機能しなくなり、認知機能も損なわれる。
●海馬はストレス反応の停止に関係している。要するに、海馬が損傷を受けると、ストレスがなくなったと認知する能力が衰え、ストレス反応を止められなくなり、その結果ストレスがさらに高まるという結果をもたらす。
●ストレス反応が不十分で、ストレスホルモン、とりわけコルチゾールの分泌が不足しても、体は疲労し消耗する(下部表参照)。
●コルチゾールが不足していると、危害を与えないようなものに対しても体が過剰に反応してしまうことがある。アレルギーはこの過程から起こる現象のひとつである。
●高脂肪の食事は動脈硬化を加速し、コルチゾールの分泌を増やす。そしてコルチゾールが増加すると、体脂肪が蓄積しやすくなり、心血管病変や脳卒中、糖尿病の危険因子となる。
●ストレスに見舞われたとき、散歩やスポーツクラブでの運動で発散すれば、ストレスにうち勝つ確率を高めることができる。運動は体脂肪の蓄積を防ぎ、心血管病変を未然に防ぎ、慢性的な痛みやうつ状態を軽減する。また、人と積極的につきあったり、他人の助けを借りることによっても自分を守ることができる。
●自律神経は原始的な脳である脳幹と、体のほかの部分を神経回路によってつないでいる。神経回路は目、唾液腺、喉頭、心臓、肺、胃、腸、腎臓、生殖器など、いろいろな器官にはりめぐらされている。
●自律神経は関連しあう三つの働きから成っている。まず、交感神経がいわば電源を入れる。外界からの刺激を受ける諸器官から脳につながる自律神経求心路のネットワークが、体中からメッセージを聞き取るマイクロホンのような役目をはたす。そして最後に副交感神経が、もとの状態に戻す働きをする。
●交感神経と副交感神経が交互に働くことにより、心臓は驚くほど臨機応変に対応する。心臓を落ち着かせるのは副交感神経、とりわけ迷走神経の働きであり、「迷走神経のブレーキ」とスティーブン・ポージスが呼んでいる制御のメカニズムがうまく作動しなくなると問題が生じる。
●睡眠不足は交感神経を興奮させ、迷走神経のブレーキをききにくくするため、血圧の上昇などストレスによる弊害を受けやすく、それが心筋梗塞の引き金となったりする。また睡眠をとれなかった翌日の晩、コルチゾールが高くなる傾向がある。これが進むと腹部の脂肪沈着や心疾患につながっていく。
●急性ストレスの場合、免疫細胞が血液から出て、皮膚やリンパ節などの“監視”場所につくのをコルチゾールが促進する。感染の徴候がみつからなければ、免疫細胞は血流中に戻る。そして、ストレスが無くなったり、うまく処理されると、コルチゾールは危険が去ったことを免疫細胞に知らせる。そして最後にコルチゾールは、ストレスによってコルチゾールが過剰になった場合、視床下部に直接働きかけ、いわゆる負のフィードバックによって自らコルチゾールの生成を止めるのである。
●危険な出来事に関する記憶は瞬時に形成され、瞬時に思い出せる。それらは扁桃体というところで、記憶の砦の番人である海馬と密接に協力して形成される。こうした出来事が強烈な記憶として残るように、海馬には記憶形成を助けるストレスホルモン、コルチゾールのレセプターがたくさんある。しかしこのために、海馬はコルチゾールが過剰に分泌されたり慢性的に高いと損傷を受けやすく、その結果、記憶をはじめとする認識、つまり“思考のプロセス”が悪影響を受ける。
●これといったストレスがなくても、不健康な生活を送っていれば視床下部-下垂体-副腎軸(HPA軸)がうまく機能しなくなり、コルチゾール値が上昇する。そして危機が訪れたとき、どのような対処方法を選択するかによっては、慢性ストレスと同じくらい体に悪い影響を生物学的に与えうる。
実はアロスタシスがなるべく保護的に働くように効果的で簡単な方法がある。それは、運動、ヘルシーな食事、快眠、少量から適度のアルコール、禁酒などだ。どれも昔から体にいいと言われていたようなことばかりだ。最新の科学が、昔からの知恵の正しさを裏づけているのである。
●2002年のはじめ、米国国立衛生研究所(NIH)は糖尿病予防プログラムの結果を発表した。プログラムの一環として行った積極的な生活習慣の改善によって、3000人を越える被験者の糖尿病になるリスクが激減した。生活習慣の改善とは、要するに低脂肪の食事をとり、週150分の運動(30分ずつを5回)を行っただけである。大半の人が選んだ運動はウォーキングであった。
●ただ歩くだけの運動が、心疾患を防ぐもっとも有効な方法のひとつであることを、多くの研究が裏づけている。22500人以上の高齢男性を対象に行った調査では、歩く距離に比例して心疾患の発症率が下がった。さらに72000人を越える中年女性を調べた大がかりな調査では、たとえ中年から始めたとしても、ウォーキングが心疾患になるリスクを著しく低下させることがわかった。どちらも長期間にわたる調査であったことが重要である。
●脅威やプレッシャーをしばらく感じていると、人間の体はエネルギーの不足だと思いこむ。そして、ストレス反応が自動的に作動する。つまり糖質コルチコイドが上昇し、ストレスによる症状が現われる前に、エネルギーをグリコーゲンや脂肪として長期貯蔵せよという信号を肝臓に送る。さらに糖質コルチコイドはエネルギーが切れないよう、脳に働いて食欲をもたらす。ストレスが私たちに空腹感を感じさせるのは、生物学の皮肉のひとつである。臀部、大腿部の肥満はさほど健康に悪くないが、腹部型肥満は糖尿病および心疾患の危険因子なので要注意である。腹部の肥満がよくない理由は、腹部の脂肪がすぐ脂肪酸になり、それがコルチゾールの放出を促し、体のインスリン抵抗性の原因となることだ。
●高脂肪食品はコルチゾールの生成を促し、それが体脂肪、とくに腹部における蓄積を促進する。これが動脈硬化やインスリン抵抗性につながり(このふたつは相互に危険因子である)心臓病や糖尿病になる危険性が高まる。
●真の意味でのアロスタシスは、病気による攻撃をくい止める以上の働きをする。つまり、アロスタシスがうまく機能するよう、生活を変えること―運動や健全な食生活を心がけ、家族や友だちとの交流を大事にする―によって、病気になるのを防ぐことができる。それは積極的に体や脳に備わっている機能を強化し、体に栄養を与え、筋力を増強し、気分を落ち着かせ、そして体を守ることだ。このプロセスが今解明されつつある。専門的には同化促進作用と呼ばれるが、私はポジティブ・ヘルスと呼ぶことにする。
●ポジティブ・ヘルスとは、アロスタシスがアロスタティック負荷(ストレス反応が私たちの体に逆襲するような状態)になるのを防ぎ、一時的にアロスタティック負荷に陥ってもそれから回復させる、体本来の能力を発揮させるシステムや物質を指す。ポジティブ・ヘルスを担うものとしては、副交感神経の回復効果やコルチゾールのチェック・アンド・バランス(抑制と均衡)の作用など、アロスタシスそのもののしくみもある。体にはそのほかに、アロスタティック負荷に陥った場合でも、持ち直す働きがあり、それらが、おもに脳の研究を通して明らかになりつつある。一部の神経ペプチドのなかに、ポジティブ・ヘルスの鍵があることが明らかになりつつある。その可能性がある物質のひとつがオキシトシンであり、もうひとつがプロラクチンである。
●エストロゲンは脳にさまざまな働きをする。働きの多くは互いに関連しており、たいていが脳のポジティブ・ヘルスに貢献するものである。エストロゲンは神経細胞を刺激して新しいシナプスの形成を促し、シナプスを刺激して新たな枝を生えさせる。さらに新しい神経細胞の成長を促進し、フリーラジカルの破壊的効果から細胞を守る。エストロゲンが脳に及ぼす好ましい影響のうち、とくに注目に値するのは記憶を保護する能力である。エストロゲンの研究といえば、生殖にかかわっている確率が高い視床下部と下垂体に集中していたが、記憶との関連性が浮上してからは、海馬や大脳皮質など、記憶にかかわる脳の多くの部位にエストロゲン・レセプターがみつかった。エストロゲンと関連ホルモンが脳のこれらの部位で、記憶にたずさわる複数の作用を行なっていることが現在わかっている。
●エストロゲンが心臓の平滑筋細胞を守ることはかなりわかっている(閉経後に女性の心筋梗塞が急増するのはこのためかもしれない)
●重いうつ病は、外的な要因に由来するのではなく、脳内化学物質の均衡が崩れたことによって発症し、高齢者ではとくにその均衡が崩れやすい。
●病気を予防するためには、多くの病院が実践しているように、総合的な健康(ウィルネス)を目指し、ポジティブ・メンタルヘルスをおろそかにしないことが、長い目で見ればいちばんいい方法だろう。
“多くの病院が実践している総合的な健康”とは、統合医療に近いものではないかと思います。これについては“がんと自然治癒力2”を参照ください。最後の付記に、”米国の統合医療”という簡単なスライドを付けています。
脳とストレス7
アロスタシスと予防医学
『医者が患者を診るときにアロスタティック負荷の前触れを見逃さないようにすること。
世の中には、いまだに感情が健康に及ぼしうる影響を軽視している医師が少なくない。アロスタシスとアロスタティック負荷の考えを受け入れるということは、精神状態が体に与える影響をはっきりと認めることである。そしてそれは、これまで心身症として片づけられることが多かったいろいろな症状を新しい視点で見ることを意味する。
ストレスによってあらわれる症状は心と体が一緒になってつくりだすという意味ではまさに心身症的だ。しかし体に現われた症状を心身症と呼ぶとき、そこには“病は気から”とか、さらには“立ち直れないはずがない。元気を出せ!”という意味合いが込められていることが多い。幸い、このような意味合いで心身症という言葉が使われることは最近減った。数年前に胃潰瘍から見つかった、ヘリコバクター・ピロリ菌は、心と体がともにかかわる好例で、病気をアロスタシスの観点からとらえることができることを示した。病気の生物学的原因にこだわっていた科学者たちは、ピロリ菌の発見が心と体を結びつけようとする動きに水をさすものだと喜んだ。しかし生物学的なメカニズムを見つけたからといって、胃潰瘍がストレスによるものであることを否定することにはならない。むしろ、ほとんどの人がピロリ菌をもっているのに、なぜ特定の人がこの細菌に反応したのかという疑問を提起する。もしピロリ菌が胃潰瘍の直接の原因なら、もっと多くの人が胃潰瘍にかかっているはずで、ピロリ菌が力を発揮して胃潰瘍を発症させるのは、アロスタシスがアロスタティック負荷に変わったときなのかもしれない。
どの人がアロスタティック負荷型の病気になりやすいかを判断するひとつの方法は、これまでにわかっている生理的な危険因子をチェックすることだ。アロスタティック負荷の目安としては、血圧や、ウェスト/ヒップ比、血中コレステロール値、数日間の糖代謝を示す糖化ヘモグロビン、一晩畜尿した尿中のコルチゾールやノルアドレナリン(ノルエピネフリン)などがある。マッカーサー財団の健康プログラムに携わっている研究者の協力を得て、ロックフェラー大学の研究グループがそのような尺度を使って調査した結果、アロスタティック負荷のスコアが高かった人に、二年半後に認知機能と記憶の衰えが見られ、調査開始時は心血管病変の症状が見られなかった人にそれが発現していることがわかった。各人に心臓病や糖尿病などの兆候がないか調べるより、これらの目安をチェックするほうが、病気を予防するには有効かもしれない。とくに現在症状が出ていない人や、家族にそれらの病気にかかった人がいない場合には有効だ。
しかし実際は、アロスタティック負荷の検査を多くの人に実施するのはむずかしい。まず、医師がどの患者に検査を勧めるかを判断しなければならない。検査によっては保険がきかないし、一人あたりの診察時間が非常に短い現況では、患者が最初に接した医師が検査の必要性を見極めるのは困難だ。
さらにむずかしいのは、アロスタティック負荷が高い患者にどのように説明するかだ。まさか「もっとリラックスした生活に切り替えないと脳に損傷を受けるかもしれませんよ」とは言えない。もちろん先に述べたような生活習慣の改善を勧めることはできる。睡眠とバランスのとれた食生活、日常的な運動などの重要性はすべての人が理解すべきだ。しかし、自分の生活を変える意思のある人は、もともと健全かつ現実的な見方ができる人で、自分の健康は自分でコントロールできると考えている人が多い。問題は、ストレスがかかるとスナックをやたらに食べたりお酒をたくさん飲んだり、暇がないという口実で運動をせず、生活を変えても大した効果はないとあきらめている人、つまりアロスタティック負荷の悪影響をもっとも受けやすい人たちをどうするかだ。今日の医療では、たとえ必要性があっても、医者が患者の生活を変えることはむずかしいストレス軽減プログラムや総合的(身体的、精神的、社会的)な健康を目指すウェルネス・プログラムを実施している病院などもある。これは好ましい第一歩で、身体および精神の健康に大いに役立つ可能性がある。
アロスタティック負荷に脅かされている人たちが、もっともその弊害に身をさらしている事実は変わらない。アメリカで蔓延している2型糖尿病がいい例だ。2型糖尿病の罹患者には、子どもや老人、社会経済的に低い層の人々、エスニック・マイノリティーが少なくない。これだけ多くの人がストレス性疾患にかかりやすい現状を思えば、アロスタティック負荷の問題は、いまや大きな公衆衛生の問題として取りくまなければならない。』
高齢者とストレス
『高齢者が、アロスタティック負荷から体を守る手だてがもっとも提供され、うつ病やアルコール依存症など、負荷を増大させる病気の治療をもっと受けられるようにすること。
アロスタティック負荷と加齢による脳の変化が密接につながっていることから、高齢者はとくにストレスに弱く、うつ病になりやすい。ストレスが直接うつ病につながるわけではないが、60歳を越える女性の脳を画像検査で調べると、過去に重度のうつ病になっていた人では、海馬委縮が多く見られた。やはり海馬を損傷させる慢性的なコルチゾール値(アロスタティック負荷の主要な指標のひとつ)も、必ずではないにせよ、うつ病患者に見られる。ロバート・サポルスキーが示したように、海馬の老化が、ストレス反応をうち切る海馬の機能を弱め、それがさらなるコルチゾールの生成とそれによる脳の損傷をもたらす。高齢者がとくにアロスタティック負荷になりやすいのはそのためだ。
アロスタティック負荷や海馬の疲労と消耗が原因かどうかは別として、うつ病は多くの高齢者が抱える問題である。米国国立精神保健研究所によれば、65歳以上の3400万人のアメリカ人のうち、200万人以上が何ららかの抑うつに悩まされているという。高齢者の自殺率もほかの年齢層に比べて高い。65歳以上の人口は全人口の13パーセントにすぎないが、自殺による死亡率はそのうちの20パーセントを占める。いちばん高いのは85歳以上の白人男性だ(1996年には10万人に1人で、これは全人口における比率の6倍だった)。
このように高齢者の自殺率が高い理由は、老いに対する社会の姿勢にもあるかもしれない。一般的にうつ病は過少報告されたり、診断されないことが多い。したがって高齢者のうつ病もこれまであまり問題にされてこなかった。若さを重んじる文化のなかにいると、65歳以上の人がうつになるのは当然と思われがちだが、それはけっして普通ではないのである。まず病的なうつ病と単なる失望感や落ち込みを区別する必要がある(病的なうつ病は高齢者でも治療できる)。たしかに高齢者は、孤立や健康問題、収入減、失業、活力の減退、コントロールの喪失など、“憂うつになる”状況と闘っていることが多い。しかしそうした状況に置かれた高齢者がすべてうつ病になるわけではない。重いうつ病は、外的な要因に由来するのではなく、脳内化学物質の均衡が崩れたことによって発症し、高齢者ではとくにその均衡が崩れやすいのである。
高齢に伴う諸問題が即、うつ病の原因になるわけではないし、同じ問題を抱えていても気分障害にならない人も少なくないが、それらの問題がうつ病と関係が深いことは確かであるから、解決に向けて取り組まなければならない。さらに、高齢者は、生化学的にも知覚的にもうつ病を悪化させるものの影響を受けやすい。アルコール依存症だったり薬を服用していたり、持病があったり、不安をはじめとする精神障害などを抱えていることが多いからである。これらの要因は複合的だが、アロスタシスの考え方を適用すれば、もっとわかりやすい。まず、生化学的に何が起きているのか見極める必要がある。アロスタティック負荷の中心にうつ病があるなら、それをまず治療すべきだ。次に、不利な状況に置かれているのだからうつ病になってもしかたがないと片づけるのではなく、生活を切り替えてアロスタシスの均衡を取り戻す機会としてとらえるべきだ。
高齢化が進み、多くの高齢者が介護施設に暮らし、しかも重い健康問題を抱え、自分の生活をコントロールできないという状況のなかで、果たしてそのような生活の切り替えが可能かどうかはわからない。いずれにせよ、高齢者のような特定のグループがアロスタティック負荷になりやすいのであれば、なおさら公衆衛生問題としてアロスタシスにとりくむ必要があるということだ。』
ポジティブ・メンタルヘルス
『身体の健康と同じように、心の健康も、単なる病気の不在だけではないと認識すること。
人との強い絆は、人生の試練から自分を守る非常に強力な防塞となる。ウィスコンシン州の長期研究の結果から、リフとシンガーは、“回復力の強かった”女性のグループを調査した。彼女たちの中には、親がアルコール依存症だったり、親が死んだりするなど、決して幸福とは言えない子ども時代を送った人もいた。しかし安定した結婚生活や教育、やりがいのある仕事、適応力のおかげで、ポジティブ・ヘルスをとりもどしていたのだ。このような回復過程を心理学的にも神経生物学的にももっと解明する必要がある。このような回復力こそ、メンタルヘルスそのものだ。
健全な精神的姿勢は回復力と対処能力にとってもっとも重要な因子のひとつである(いや、もっとも重要な因子かもしれない)。なぜなら体がどのようなアロスタティック反応で応じるかがそれにかかっているからだ。生活習慣を変える意志と行動力は精神的姿勢に左右される。したがって、なるべく多くの人が望ましいアロスタシスを維持できるようにするには、ポジティブ・メンタルヘルスをもっと理解しなければならない。そしてメンタルヘルスを、単に精神的な病気の不在ととらえるのではなく、身体的な健康とともにいちばん理想的な状態へと近付けるべきだ。
世界保健機構(WHO)は、早くも1948年には、メンタルヘルスを精神病(あるいは、さらに否定的なとらえ方をすれば“精神異常”)の不在以上のものだと提唱していた。しかしそれから50年以上経った今でも、あまり状況は進展していない。それどころか、“異常”な状態でさえ十分な治療ができていないのが現状だ。うつ病も不安もほとんど見逃されるか放っておかれている。たとえばある調査によれば、自殺した高齢者のうち20パーセントは自殺の日に、40パーセントが一週間以内に、70パーセントは一カ月以内に医師を訪れている。たとえば医師が問題を認めて治療しようとしても、薬の費用は保険でカバーされるが、心理療法士が勧めるような治療法(そのほうが長期的にはもっと効果がある場合がある)は保険がきかないため、なかなか勧められないことが多い。
病気に気づいた場合にのみ治療がなされるという現状のなかで、すべての人にポジティブ・メンタルヘルスを推進するようなシステムをつくるにはどうしたらいいのだろうか。アロスタシスの考えを役立てるには、まさにそのようなシステムが不可欠である。これは大きな問題で、簡単な解決法などない。将来、精神的、身体的に具合がよくないと自負したとき、最初に開業医や病院の内科で診てもらうのではなく、臨床心理士を訪れるようになるかもしれない。そのような日が近く訪れることはないだろうが、ポジティブ・メンタルヘルスを推進するためには、次のようなことが求められる。
まず、感情と健康の関係をもっと科学的に解明しなければならない。敵愾心などの“ネガティブ”な感情と高血圧症などの関係を探るのも第一歩となるだろう。しかし、病気を予防するためには、多くの病院が実践しているように、総合的な健康(ウィルネス)を目指し、ポジティブ・メンタルヘルスをおろそかにしないのが、長い目で見ればいちばんいい方法だろう。シンガーとリフは、ストレス下で被験者が発揮した回復力についての生物学的解明にとりくんでいるところだ。
さらにシンガーらは、ポジティブ・メンタルヘルスを示す人の性格的特徴もつきとめようとしている。カール・ユングやエイブラハム・マスロウなどいろいろな心理学者が書いたものをもとに、彼らはポジティブ・ヘルスに恵まれた人、つまりストレスや逆境や老化にうまく対処している人には、共通の特徴があるという結論に達した。これらの特徴には、自己受容能力、積極的な人間関係、自立性、または他人の意見や容認にふりまわされず、自分の規律で自分の生活を調整できる能力、幸せをもたらす環境を選んだりつくりだす能力、生きがいをもつこと、自分が着実に成長しているという実感などが含まれる。さまざまな哲学的、科学的な考えを参考にした結果、リフとシンガーは、健康的で好ましい生活について「目標をもち、自分の潜在的能力を活かすよう努力し、ほかの人との深い絆を大事にし、周囲からの要求や機会に上手に対処し、自己主導性を発揮し、自尊心をもつこと」だとしている。』
【ご参考】:”総合的(身体的、精神的、社会的)な健康を目指すウェルネス・プログラム”とは
下記の図と表は”がんと自然治癒力13(まとめ)”から持ってきたものです。上段左は日本の医療の現状です。皆保険制度という素晴らしい制度が提供されている一方で、西洋医学に限定した医療になっています。右は米国の状況ですが、代替医療を取り入れ統合医療としての医療サービスを目指しています。
中段左は増え続ける”日本におけるガンの死亡率”。右は減り続ける”米国におけるガンの死亡率”です。統合医療としての取り組みが死亡率の低下に関係しているのは可能性は極めて高いと思います(統計情報や米国の統合医療に関しては”がんと自然治癒力2”を参照ください)。
下段は内閣府のホームページにあった”世界の高齢化率の推移”という折れ線グラフです。日本ほどではありませんが、米国でも高齢化は進んでいます。

内閣府のホームページにあった”世界の高齢化率の推移”の表です。2015年で見ると、日本は26.6%、米国は14.8%となっています。
脳とストレス6
9 ポジティブ・ヘルスとは?
『アロスタシスの考え方が役に立つのは、人生のさまざまな問題に直面したとき、袋小路に追いつめられたような気分から自分を切り離せることだ。健康とは、医学的には単に病気の不在だと考える傾向がある。脳の指令によって体が適応し、活性化するしくみを認めている人でさえ、病気に対しては防衛的にとらえがちだ。真の意味でのアロスタシスは、病気による攻撃をくい止める以上の働きをする。つまり、アロスタシスがうまく機能するよう、生活を変えること―運動や健全な食生活を心がけ、家族や友だちとの交流を大事にする―によって、病気になるのを防ぐことができるのだ。それは積極的に体や脳に備わっている機能を強化し、体に栄養を与え、筋力を増強し、気分を落ち着かせ、そして体を守ることだ。このプロセスが今解明されつつある。専門的には同化促進作用と呼ばれるが、私はポジティブ・ヘルスと呼ぶことにする。
ポジティブ・ヘルスとは、アロスタシスがアロスタティック負荷になるのを防ぎ、一時的にアロスタティック負荷に陥ってもそれから回復させる、体本来の能力を発揮させるシステムや物質を指す。ポジティブ・ヘルスを担うものとしては、副交感神経の回復効果やコルチゾールのチェック・アンド・バランス(抑制と均衡)の作用など、アロスタシスそのもののしくみもある。体にはそのほかに、アロスタティック負荷に陥った場合でも、持ち直す働きがあり、それらが、おもに脳の研究を通して明らかになりつつある。』

写真をクリック頂くと、日本ポジティブ心理学協会さまのサイトに移動します。
なお、写真はFacebookから拝借しました。
麻薬のような体内物質エンドルフィン
『体内にあるアヘンに似た物質、エンドルフィン(エンケファリンとも呼ばれる)が発見されたのは1970年代である。エンドルフィンのいちばん明快な役割は、緊急反応の一環としてストレスがもたらした痛みを抑えることだ。エンドルフィンが動員されるのは、よほどの緊急事態だ。そうでないときに痛みの感覚をなくすとかえって危険だからだ。したがって、エンドルフィンそのものがポジティブ・ヘルスに貢献するわけではないが、その発見を機に進んだ研究がポジティブ・ヘルスの理解を高めることになった。
動物はアロスタティック負荷に苦しんでいるとき痛みをあまり感じない。生き延びるためには闘うか、それとも逃げるしかないというとき、痛みでのたうちまわっている余裕などないからだ。痛みにのたうちまわるのは後回しだ。ストレスのもとにおかれた動物は、実際、いつもより痛みに鈍感になっていることが実験で判明している。人間の例では、北欧のバイキング伝説に、闘いのとき痛みや怪我をものともしなかった猛者たちの話がある。現代でも、自動車事故で両足を骨折しながら現場から自力で歩いた人の話や、激痛にもかかわらず戦い抜いた運動選手の話などを耳にする。このように知覚が通常とは異なる状態になるのは、脳におけるエンドルフィンの働きのおかげだ。鎮痛剤のなかでもいちばん効果的なのは、ケシを原料とするアヘンだが、それが脳と体に及ぼす劇的な効果も、エンドルフィンによって間接的に説明できる。』
脳がつくりだす薬
『エンドルフィンとストレスと鎮痛作用の関係が明らかになったのは、1977年、ストレスが引き金となって下垂体がエンドルフィンの一種を生成することをロジャー・ギレマンがつきとめたときだ。
ストレス性の痛みの緩和にエンドルフィンが貢献することがわかってから、ポジティブ・ヘルスの考え方は変わった。しかしエンドルフィンの役割はポジティブ・ヘルスにおいて中心的ではない。なぜかというと、意図的であれ、無意識であれ、痛みを無視するのは危険だからだ。痛みがあるから、私たちは怪我や病気に気づき、しばらく患部をそっとしておこうと思うのだ。痛みを感じることができない状態だと、知らずに怪我を負っている危険性がつきまとう。したがってエンドルフィンが痛みに対する感覚を抑えるのは、あくまでも脳の緊急措置であって、回復のしるしではないのである。』
『エンドルフィンが緊急事態でなくても鎮痛、鎮痛効果を発揮する可能性はあるが、確固とした証拠に欠ける。針治療がエンドルフィン分泌の引き金となることを示唆する研究もあることにはある。それはともかく、エンドルフィンが発見されたおかげで、ポジティブ・ヘルスに貢献するほかの化学物質の発見につながった。これらのなかには、社会的なかかわりや人との絆によって分泌されるホルモンであるオキシトシンや、授乳中に放出され脳を落ち着かせる効果があるホルモン、プロラクチンなどが含まれる。これらの神経ホルモンは、1950年代や60年代に把握されていた従来の神経伝達物質の研究ではみつからず、エンドルフィンの発見をきっかけにみつかったのである。』
エンドルフィンを越えて
『1930年代に、迷走神経が心拍を遅くするために使う化学物質としてアセチルコリンが発見されたことはすでに述べた。その後、アセチルコリンが脳の主要な神経伝達物質であることが明らかになった。1960年代末には、おもな神経伝達物質のほとんどが識別されていた。ノルアドレナリン、セロトニン、ドーパミン、活動を速めるよう脳細胞に指示を出すグルタミン酸、逆に活動を遅くする信号を送るガンマアミノ酪酸(GABA)などである。脳で作用する神経伝達物質はこれで出そろったと考えた科学者もいた。
その頃、信号を送るしくみにはもっといろいろな物質がかかわっているのではないかという疑問がうまれていた。ジョフリー・ハリス卿は、脳が特殊なホルモンを使って内分泌系に影響を与えていると推測した。そして最初に明らかになったのが、ギルマンとシャリーがみつけた甲状腺刺激ホルモン放出因子だったのだ。緊急反応を始動させる副腎皮質刺激ホルモン放出因子は、1983年に、かつてギルマンの弟子だったソーク研究所のワイリー・ヴェールによって確認された。
これらの放出因子を探している過程で、それまでにみつかった基本的なもの以外にも神経伝達質が存在することがわかった。また放出因子の研究のおかげで、脳が微妙につくりだす物質を見分ける技術も開発された。1970年代半ば、ふたつの研究チーム(スコットランドのアバディーン大学のジョン・ヒューズとハンス・コスターリッツ、そしてジョンズ・ホプキンス大学のソロモン・スナイダーら)はこの技術を用いて、エンドルフィンの化学構造を明らかにした(スコットランドのチームはギリシア語の「頭の中」という意味の言葉からエンドルフィンでなく、エンケファリンと呼んだ)。エンドルフィンも放出因子も、神経ペプチドと呼ばれる種類の神経伝達物質だ。ペプチドとはアミノ酸の短い鎖で、それが組み合わさってタンパク質を構成する。一部の神経ペプチドのなかに、ポジティブ・ヘルスの鍵があることが明らかになりつつある。
その可能性がある物質のひとつがオキシトシンだ。この神経ペプチドは、社会的支援がガンや「絆のホルモン」のひとつである可能性がある。エモリー大学のラリー・ヤングとトーマス・インセルは、典型的なメスのラットが、自分の子を産むまで赤ちゃんラットを避けるが、オキシトシンが高まると母親に負けないくらい面倒見がよくなることを示した。オキシトシンの遺伝情報を暗号化する遺伝子だけを欠くマウス(そのように特定の遺伝子を欠くマウスをノックアウトマウスと呼ぶ)は、同じケージで育った仲間を判別できない。ヒトでは、オキシトシンが、ふれあいやぬくもりなどの快い刺激が引き金で分泌されたり、授乳しているときに母と子の脳に放出される。オキシトシンの効果は心理的なものに限られない。オスとメスのラットにオキシトシンを注射すると血圧、心拍数、コルチゾール値が最長数週間にわたり下がる。したがって社会的なかかわりがあるとストレスによる身体的および心理的悪影響をある程度かわせるのは、このオキシトシンのおかげかもしれない。
もうひとつ、ポジティブ・ヘルスに貢献するのがプロラクチンだ。女性の場合、下垂体からこのホルモンが放出されると乳が生産されるが、これは女性にかぎらず不安やストレスにうまく対処するために体に備わった物質であるようだ。2001年、ミュンヘンにあるマックス・プランク研究所のルズ・トルナーらは、プロラクチンを直接ラットの脳に注射してから、囲いのない高所など、隠れ場所が好きなラットにとって軽いストレスとなる状況に置いた。与えたプロラクチンの量が多ければ多いほど、ラットは不安を示さなかった。またプロラクチンはストレスホルモンの分泌量と視床下部-下垂体-副腎軸(HPA軸)の機能を下げた。ストレスのもとに置かれたとき血中のプロラクチンが高まり、海馬と扁桃体にプロラクチンとそのレセプターが存在することが立証されている。このことから、トルナーらが実験で行なったことと同じことが、脳で常に起きている可能性がある。つまり、プロラクチンがアロスタシスの機能を助ける自然の成分であるかもしれないのだ。
運動によって体を循環するプロラクチンの量が増えるとされるが、この上昇が神経系にどのような影響を及ぼすかはまだ定かでない。しかし血中のプロラクチンが、そのレセプターがある脳の部分に入り込むこと、プロラクチンがある種のアロスタティック負荷から体を守っているかもしれないことを裏づける証拠が次々にみつかっている。たとえばプロラクチンは動物のストレス性胃潰瘍を防ぐとされる。将来、オキシトシンやプロラクチンの働きを強化する薬ができれば、抗うつ剤や鎮痛剤より効率よくアロスタティック負荷を軽減することができるかもしれない。脳のオキシトシンを高める薬(オキシトシン作動薬)はすでに開発されつつあるし、プロラクチンを高める薬も近いうちにできるだろう。
エンドルフィンや神経ペプチドは、ストレスに耐えアロスタティック負荷を避けるのを助けてくれるが、いったんアロスタティック負荷になったときそこから抜け出すのを助けてくれる物質や働きもある。このなかには成長因子、神経細胞新生、そしてホルモンのエストロゲンがある。』
エストロゲンの働き
『私たちロックフェラー大学の研究者の多くにとって、脳にエストロゲンのレセプターを発見したことが、アロスタシス研究を始めるきっかけとなった。もっとも、当時はコルチゾールに関する発見の手がかりになるくらいにしか考えていなかった。私たちはエストロゲンを、あくまでも性的活動に影響を与えるものとして見ていたのである。この性ホルモン自体がアロスタシスの中心的役割を果たすとは思いもしなかった。しかしエストロゲンはまさにそのように重要なものだったのだ。生殖に果たす役割のほかに、エストロゲンは脳にさまざまな働きをする。働きの多くは互いに関連しており、たいていが脳のポジティブ・ヘルスに貢献するものだ。エストロゲンは神経細胞を刺激して新しいシナプスの形成を促し、シナプスを刺激して新たな枝を生えさせる。さらに新しい神経細胞の成長を促進し、フリーラジカルの破壊的効果から細胞を守る。エストロゲンが脳に及ぼす好ましい影響のうち、とくに注目に値するのは記憶を保護する能力だ。
この可能性が最初に明らかになったのは1970年代末に、内分泌学者のヴィクトリア・ルインと私が、卵巣を取り除いたラットにエストロゲンを与えた実験によってである。エストロゲン投与によって、前脳基底核におけるアセチルコリンを増加させる酵素が増えることがわかった。数年後、アルツハイマー病患者の脳の同じ部位にアセチルコリンをつくる神経細胞が大量に死んでいることが判明するまで、私たちは実験結果の重要性と記憶との関連性に気づかなかった。同じ頃行われた、別の方面の研究から、もうひとつの関連性が明らかになった。カナダのコンコーディア大学のバーバラ・シャーウィンが、卵巣を取り除いたためにエストロゲンをつくれなくなった女性たちの記憶力が衰えていることを発見したのだ。これらの研究により、エストロゲンとアセチルコリンと記憶の間に関連性があることが示唆された。
それまで、エストロゲンの研究といえば、生殖にかかわっている確率が高い視床下部と下垂体に集中していたが、記憶との関連性が浮上してからは、海馬や大脳皮質など、記憶にかかわる脳の多くの部位にエストロゲン・レセプターがみつかった。エストロゲンと関連ホルモンが脳のこれらの部位で、記憶にたずさわる複数の作用を行なっていることが現在わかっている。
エストロゲンは、やはり卵巣でつくられるプロゲステロン(黄体ホルモン)と連携して適応可塑性(これをシナプス再構築と呼ぶ)に貢献している可能性がある。これらのホルモンはチェック・アンド・バランスによって、海馬における神経細胞間の新たなつながりを調節している。とくに、活動を速める信号を受けとる“興奮性”シナプスの形成が、エストロゲンに似た働きをするホルモンのエストラジオールに影響されることが判明している。この過程には、グルタミン酸がNMDAレセプター(NメチルDアスパラギン酸という物質がその識別に使われることからそう呼ばれる)という特殊なレセプターを通じてかかわっている(エストロゲンは海馬の重要な神経細胞のなかでNMDAレセプターの形成を実際に誘引する。一方、プロゲステロンはこれらのシナプスを減少させる働きをする。ふたつのホルモンによる促進と抑制の働きを通じて、シナプス再構築が短期的にストレスの影響から脳を守るかもしれない)。』
『エストロゲンはいろいろな作用を通じて脳を守っているようだ。プリンストン大学のパティマ・タナパットとエリザベス・グールドは、エストロゲンがメスのラットの、海馬の歯状回における神経細胞新生を刺激することを示した。オスの海馬の樹状突起にはストレス性委縮が見られたが、メスのラットにはそれに対する抵抗力があるようだった。アルツハイマー病では、エストロゲンが興奮毒性と呼ばれる矢つぎばやの細胞死から細胞を守っているようである。アルツハイマーの特徴には、前脳基底核におけるコリン作動性細胞死のほかに、脳におけるβアミロイドという有毒なタンパク質が蓄積することがある。エストロゲンはこのタンパク質の破壊的な作用から脳を守る働きがあるようである。
南カリフォルニア大学の神経学者ヴィクター・ヘンダーソンはアンリア・パガニーニ・ヒルと組んで、非常に興味深いヒトの研究を行なった。ヘンダーソンらは8000人を越える高齢の女性を調査した結果、エストロゲン補充療法を受けていた女性の方が受けていない人よりアルツハイマー病になる確率が、ずっと少ないことが判明した。しかもエストロゲンの投与量が多く、投与期間が長いほど、罹患率が低かった。コロンビア大学のリチャード・メイユーらも、閉経後エストロゲンを摂取した女性がアルツハイマー病になる確率が顕著に低く、なったとしても、摂取していない女性よりずっと遅く発症したことを確認した。ジョンズ・ホプキンス大学のクローディア・カワスらが行なったボルチモアでの長期老化研究でも注目に値する結果が出た。450人以上の年配の女性を最高16年間追跡したこの研究でも、エストロゲン補充療法を受けている女性ではアルツハイマー病にかかる確率が同じように低かったのである。』
私たちを守る脳
『このように神経細胞新生を促進し海馬を防ぐことによって、エストロゲンはポジティブ・ヘルスに大いに貢献している。この貢献の過程と、アルツハイマー病におけるエストロゲンの役割を解明するために、エストロゲンの神経細胞周辺に及ぼす影響について研究しているところだ。これには、まず、脳細胞が環境からどのような影響を受けるのかについてもっと詳しく知る必要がある。
1960年代から70年代にかけて多くの発見があったが、それとは異質なエストロゲン・レセプターの発見も注目に値する。最初にみつかったレセプターは、細胞核のなかのDNAの近くに存在し、遺伝子情報が翻訳されるのを調節している。海馬の性による違いが生じるのも、この働きのせいだ。
しかし、エストロゲンの作用は瞬時に起こるので、それが遺伝子の発現に影響を与える暇はおそらくないだろう。樹状突起の再構築は、エストロゲンのこのすばやい作用によるのかもしれない。エストロゲンが心臓の平滑筋細胞を守ることはかなりわかっている(閉経後に女性の心筋梗塞が急増するのはこのためかもしれない)。エストロゲンの“非ゲノム”作用は、細胞核内ではなく、細胞の表面にあるレセプターを通して行なわれる。この分野の研究もまだ未知数だ。
ペンシルバニア大学のジェームズ・エイバーワインは、DNAの遺伝子情報を利用可能なタンパク質に変えるメッセンジャーRNAが、神経細胞の核だけでなく、軸索や樹状突起にもあり、それらは細胞核まで届かない局部的な信号によっても活性化されるのではないかと推測する。さらにエイバーワインは、細胞の先端に転写因子CREBが存在するのを発見した。このCREBは、細胞周辺の変化によって活性化されることがある。軸索も樹状突起に、遺伝子にもかかわる物質が存在するということは、次の可能性を示唆している。つまりストレスに対して、細胞核の指令センターを巻き込んで細胞全体を変える必要はなく、細胞表面にあるレセプターなど、結合にかかわる部分だけを変化させることで神経細胞が対応できるのかもしれないのである。エストロゲン・レセプターが神経細胞の末端部分にも見つかっていることから、私たちのグループは、エストロゲンとこうした局部的な働きの関係を調べている。軸索や樹状突起におけるこうした自主的な活動は、エストロゲンの保護的な作用によるのかもしれない。
エンドルフィン、成長因子、神経細胞新生、そしてエストロゲンはポジティブ・ヘルスの重要な因子である。この研究を通じて、脳が私たちをどのように守っているか理解を深めることができるだろう。最後の章では、それが示唆するものについて述べる。』
脳とストレス5
8 ストレスに負けない生活
『本書で私はたびたび、アロスタシスが「体を保護するか危害を与えるか」のいずれかの働きをすることに触れた。読者はこの本を読むくらいだから、当然“保護”の部分をできるだけ伸ばし、“危害”をなるべく避けたいと思っているはずだ。まず言っておきたいのは、私たちはストレスでボロボロにならなくてすむということだ。言い換えればアロスタティック負荷を経験する必然性はないということだ。第二に、アロスタティック負荷の原因は、度重なる厄介な問題や過密スケジュールだけではない。これといったストレスがなくても、不健康な生活を送っていれば視床下部-下垂体-副腎軸(HPA軸)がうまく機能しなくなり、コルチゾール値が上昇する。そして危機が訪れたとき、どのような対処方法を選択するかによっては、慢性ストレスと同じくらい体に悪い影響を生物学的に与えうる。しかも、追いつめられた人は、とかく高カロリーのものを食べ過ぎたり、アルコールを飲み過ぎたり、タバコに慰めを求めたり、徹夜で仕事をしたりするものだ。ちょっとしたストレスがだんだん積み重なり、その結果、アロスタティック負荷になる。
じつはアロスタシスがなるべく保護的に働くように効果的で簡単な方法がある。それは、運動、ヘルシーな食事、快眠、少量から適度のアルコール、禁酒などだ。どれも昔から体にいいと言われていたようなことばかりだ。最新の科学が、昔からの知恵の正しさを裏づけているのである。』
ウォーキングの効果
『2002年のはじめ、米国国立衛生研究所(NIH)は糖尿病予防プログラムの結果を発表した。プログラムの一環として行った積極的な生活習慣の改善によって、3000人を越える被験者の糖尿病になるリスクが激減した。生活習慣の改善とは、要するに低脂肪の食事をとり、週150分の運動(30分ずつを5回)を行っただけである。大半の人が選んだ運動はウォーキングであった。
2型糖尿病はアロスタティック負荷の一形態だ。肥満や心疾患、高レベルのコルチゾール値を伴うこのタイプの糖尿病の危険因子をもつ参加者に焦点を当てた。参加者はすべて肥満で、糖尿病に発展しやすい、耐糖能異常(血糖が効率よく利用されず血糖値が通常より高い状態)だった。さらに、その多くは2型糖尿病になる確率が平均より高いマイノリティ(アフリカ系、ヒスパニック系、アジア系、南太平洋系、アメリカ先住民)に属していた。そのほかの参加者には、両親が糖尿病だったり、60歳以上の人、妊娠時に糖尿病歴のある女性などがいた。
驚くべき結果が得られた。生活習慣改善グループの糖尿病発症率は58パーセントも下がり、血糖降下剤メトフォルミンを服用したグループの発症率は31パーセント減少した。言い換えれば、ウォーキングと健康的な食事が、最新の薬物治療のほとんど倍の効果をあげたのだ。これだけでもうれしくなる結果だが、今後、生活習慣に気をつける人が増えれば、糖尿病に関してさらにいい効果が期待できそうだし、とくにアロスタティック負荷を防ぐことができそうだ。
ただ歩くだけの運動が、心疾患を防ぐもっとも有効な方法のひとつであることを、多くの研究が裏づけている。2500人以上の高齢男性を対象に行った調査では、歩く距離に比例して心疾患の発症率が下がった。さらに72000人を越える中年女性を調べた大がかりな調査では、たとえ中年から始めたとしても、ウォーキングが心疾患になるリスクを著しく低下させることがわかった。どちらも長期間にわたる調査であったことが重要である。この調査のほうが、すでに特定の病気にかかっている患者の共通点を探す方法より正確だとされるからだ。
NIHが行なった糖尿病予防研究では、運動によって、ブドウ糖が筋肉に取りこまれる割合が高められた結果、インスリン抵抗性にうち勝ち、糖尿病を予防できたのだと考えられた。運動はまた、ストレス反応にも働きかけて私たちを守ってくれる可能性がある。たとえば免疫細胞にとっても運動はいい影響がある。8週間にわたりマウスを回し車で走れるようにした実験では、運動によってマクロファージやリンパ球など主な白血球細胞の活動が高まった。』
ストレス解消は食生活から
『脅威やプレッシャーをしばらく感じていると、人間の体はエネルギーの不足だと思いこむ。そして、捕食者から逃げることと翌日の会議の準備をすることの違いを区別できずにストレス反応が自動的に作動する。結果は同じだ。つまり糖質コルチコイドが上昇し、ストレスによる症状が現われる前に、エネルギーをグリコーゲンや脂肪として長期貯蔵せよという信号を肝臓に送る。さらに糖質コルチコイドはエネルギーが切れないよう、脳に働いて食欲をもたらす。ストレスが私たちに空腹感を感じさせるのは、生物学の皮肉のひとつである。
しかも悪いことに、ストレスは、私たちが食べたものが脂肪になる速度を速め、脂肪がどこにつくかも左右するらしい。臀部、大腿部の肥満はさほど健康に悪くないが、腹部型肥満は糖尿病および心疾患の危険因子なので要注意だ。腹部の肥満がよくない理由は、腹部の脂肪がすぐ脂肪酸になり、それがコルチゾールの放出を促し、体のインスリン抵抗性の原因となることだ。コルチゾール過剰を伴う慢性ストレスでは脂肪が腹部など有害な場所に蓄積するのを促進するのである。ジェイ・カプランらは実験でサルの社会的環境を常に変えていると、そのストレスが腹部脂肪の蓄積を速めることを発見した。ヒトでも、ストレスを示唆するコルチゾールの高値が体脂肪の分布に影響を与える可能性がある。ある研究によれば、女性は普通臀部に脂肪がつくものでこれはあまり害がないが、ストレスとコルチゾールの上昇によって、臀部より健康に悪い腹部により多くの脂肪が蓄積されたという。
ストレスのあるなしにかかわらず、賢い食生活を送ることは、贅肉をなくして自分の容姿に自信がつくこと以上に重要である(それだけでも志気の向上になるが)。アロスタティック負荷に、好ましくない食生活が加わるとさらに悪い結果を招くからだ。食事で脂肪をとりすぎれば、当然ながら体脂肪も増えすぎる。さらに、高脂肪食品はコルチゾールの生成を促し、それが体脂肪、とくに腹部における蓄積を促進する。これが動脈硬化やインスリン抵抗性につながり(このふたつは相互に危険因子だ)心臓病や糖尿病になる危険性が高まる。肥満と心臓病と糖尿病は、それぞれがほかの病気へと導く危険因子になっているのである。』
コントロールのよい面と悪い面
『プラス思考によってストレス反応やHPA機能を変えられるだろうか。少なくとも適応性に欠けるような脳を修正することはできるはずだ。陽電子放出断層撮影法(PET)を最初に開発したカリフォルニア大学ロサンジェルス校のマイケル・フェルプスが1996年に行った研究は示唆に富んでいる。彼は強迫性障害(OCD)患者の脳を、10週間にわたる行動・認知療法の前後にPETでスキャンした。セラピー前は、動作をコントロールしている脳の部位におけるブドウ糖の取り込みに異常がみつかった。OCD患者は、本人は理不尽とわかっていながら特定の行為をくり返し、それから逃れなくなる。この異常な行動がOCDの特徴とされるが、セラピー後のPETスキャンでは、ブドウ糖の取り込みが目に見えて軽減されており、症状も改善されていた。しかも患者たちには何の薬も投与していない。10週にわたり思考と行動を修正しただけだ。これから判断すると私たちは思っていたより脳を自分でコントロールできるのかもしれない。』
『私たちは自分たちの健康と病気(ストレス性のものもそうでないものも)についてできるかぎり理解し、医師と協力し、効果が認められた治療方法を用いながら、自分の健康をとりもどす方法をとるべきだ。この姿勢は、アルコール依存症自主治療協会がモットーとして採用した、60年前の神学者ライホールト・ニーバーの「神よ、変えることのできないものを受け入れる心の平和を、変えることのできるものを変える勇気を、そして変えられるものと変えられないものとを見分ける知恵を私にお与えください」という祈りに要約されている。自分がコントロールできる生活の部分を変えることで、予測できないことや不可避の事態にうまく対処できるのである。』
『ヒトにおいてもコントロールできているという感覚は動物と同じくらい重要である。たとえば、四章で紹介したように旧ソ連邦の崩壊後、心血管病変、アルコール依存症、自殺、暴力、その他の理由による死亡率が大幅に上昇した。もちろん、広範な社会的混乱のため、医療サービスも十分ではなかっただろう。救急車が迅速に患者を病院に運べなかったために、あるいは病院の設備が不十分であったために死んだ人のほうが多かったかもしれない。しかし社会的不安定が霊長類に与える影響を調べた研究の結果を踏まえれば、それまでの生活が崩壊したりアイデンティティがなくなってしまったことが、多くの人を病気にさせたということはありうる。またイギリスの公務員の調査は、職場においてコントロール感のないことが心血管病変と密接な関係にあることを裏づけた。
職場におけるコントロール感はストレス研究の重要なテーマだ。おそらくもっとも楽観的な結果が出たのは、スウェーデンのボルボの自動車工場で行われていた研究だろう。従業員たちは流れ作業に遅れないように気を使いながら単純作業を繰り返すのはストレスになると同時に退屈だった。そのため、仕事に対する強い不満が常習的な欠陥につながった。従業員には高血圧も多く見られた。
そこでボルボの経営陣は専門家の意見をもとに従業員をチームに再編し、作業を交代させたり、作業について前よりきちんと説明した。その結果、従業員の健康状態はよくなり、血圧も通常の範囲内に戻った。このように職場の環境を変えることによって、身体の健康状態を向上させることは可能なのである。
環境を変えられないとき、不満があってもどうしても仕事をやめられない事情があるとき、重病の家族の世話をしなければならないとき、このようなときこそ、生活習慣など変えられることは変えるべきだ。健全な食生活と習慣的な運動、家族や友人の支援の恩恵ははかりしれない。またこれらをとおして、自分の体は自分が守っているという、非常に大事なコントロール感も得られるのである。』
脳とストレス4
ストレスが体を守ることもある
『あまりにも証拠に事欠かなかったために、ストレスが免疫反応を抑制するという考えが定着し、科学者たちはもっぱらその解明に励んだ。いちばん説得力があったのは、免疫系の活性化は代償が高い“ぜいたくな”反応であるため、台風を目前にしているときに家の増築などしないように、緊急の場合はそれが後回しにされるという説明だった。
しかしこれに納得しない科学者もいた。その一人が、ファーダウス・ダーバーだった。「あの頃ストレスは悪いという考えが主流だったが、私は納得できなかった」とダーバーは述べている。「進化の観点からすれば、生理的なストレス反応に否定的効果しかないというのはありえない。つまり、免疫反応がもっとも必要とされるときに、免疫を抑制するメカニズムが働くのはおかしいと思ったのだ」ダーバーはまた、免疫が代謝的に高くつくから後回しにされるという考えにも納得しなかった。なぜなら、危機のときに病気になってしまったら、免疫を動員するよりよっぽど高くつくからだ。もうひとつ矛盾することがあった。コルチゾールを軟膏や注射で体内に入れると、たしかに炎症を抑える作用が見られる。このように外部から大量にコルチゾールを投入するのと、元々血流に微量に含まれるコルチゾールでは、作用が異なるかもしれない。ダーバーは免疫系が、HPA軸を介して、アロスタティック負荷の間を揺れ動くのではないかと考えた。彼はロックフェラー大学の私たちの研究所に加わり、ストレスが免疫を強めるかもしれないという、当時の医学の常識に反する考えを裏づけるための研究にとりかかったのである。
まず、ダーバーはほとんどの臨床研究が急性ストレスでなく慢性ストレスを扱っていることに注目した。さらに、大半の研究では免疫活動を血液から判断していた。つまり強度のストレスを訴えていた患者の白血球は減り、ナチュラルキラー細胞の活動が低下しているのを確認したのだ。「白血球が少ないのは一見悪いことのように思える」とダーバーは認める。「しかし、ふたつの疑問が出てくる。循環血液中に白血球がないのは、破壊されたのか、破壊されていないとすればどこに行ったのか」
これらの疑問を解明しようとして行った一連の実験から、ダーバーはストレス反応は短期的には体を防御するが、長期化すると疲労と消耗をもたらすという考えに至った。実験により、たしかに急性ストレスは免疫に欠かせない白血球を大幅に減らしたが、それは回復可能であることがわかった。ストレスが無くなったとき、白血球はもとのレベルに戻ったのである。つまりそれらはストレスによって破壊されておらず、移動していただけだった。白血球が味方と敵を正確に識別するのも驚くべきことだが、その機動性もたいしたものだ。感染と闘う白血球は血流によって体中を循環する。指示が出ると、鼻の粘膜であろうが、怪我をした左足首であろうが、敵が侵入した場所にただちにかけつける。ダーバーは、白血球が傷害部位に現われるだけではないことを明らかにした。それまでの研究で白血球が見あたらなかったのは、それが循環血液から離れ、リンパ節や皮膚など、もっとも必要とされている組織や局所にくっついていたからであった。しかも、コルチゾールが血液中に放出されることがこのプロセスの引き金になっていたのである。急性ストレスによって白血球が血液から離れ、必要とされるところに移動するに違いないと考えたダーバーは、この移動を「ストレス性移動」と呼び、急性ストレスが実際に免疫活動を強化する例ととらえた。』
ストレスで動員される白血球
『ダーバーが中心となって行なった遅延型過敏症(DTH)という免疫反応に関する一連の研究により、ストレスの好ましい役割が浮き彫りになった。DTHでは二種類の白血球、つまりマクロファージは我々にとって有害な細菌やウィルスなどの異物を食べ、有害なタンパク質の破片を敵情報として旗のようにかかげる。これを合図にヘルパーT細胞が活動を開始し、感染力のあるその外敵をやっつけるために、ほかの免疫細胞を招集する。また、ヘルパーT細胞は、別のリンパ球であるB細胞に働きかけて異物に対する抗体をつくらせる働きもある。敵が再び襲ってきたときに、これらの抗体が活性化して侵入を防ぐのである。DTHは特定の感染症や腫瘍に対して働く免疫反応だが、ウルシのかぶれなど、一部のアレルギー反応にも見られる。
この実験から、私たちは、短期的にはストレスとそれに伴うストレスホルモンの分泌が免疫能を強めることがあることを確認した。これは「一日一回の小競り合いは医者いらずの秘訣」というダーバーの博士論文の講演のタイトルに簡潔に言いあらわされている。』
『このストレスが三週間も続くと、免疫の抑制が見られはじめ、五週間になると、免疫細胞の移動もDTHの反応も大幅に弱まる。したがって、これらの実験結果は、長期的ストレスが免疫能を弱めるという、これまでの研究の結果をも裏づけている。しかし、ラットを一週間休ませると、再び回復し、免疫の低下は恒常的ではないとわかる。
これらの研究によって、アロスタシスとアロスタティック負荷の考え、つまりストレス反応が体を保護したり危害を与えたりするという考えが裏づけられた。ここでのコルチゾールの役割は明確だ。たとえば、コルチゾールの生成を妨げる薬をラットに投与すると、免疫細胞の機動力が損なわれる。また、ある化学物質を用いて免疫細胞のコルチゾール・レセプターを活性化すると、免疫細胞の機動力は、たとえ副腎を取りのぞいてコルチゾールの供給を断っても回復しうることがわかった。ダーバーは、具体的にコルチゾールが免疫細胞にどのように影響するかを調べている。これまでのところ、コルチゾールが細胞の接着分子を活性化し、それによって免疫細胞が移動した先の組織の血管につきやすくさせる可能性を示唆している。また、コルチゾールは接着分子を発現させる遺伝子を刺激する可能性もある。
こうしてコルチゾールが、免疫の働きに貢献する様子が、だいたいつかめたと思う。急性ストレスの場合、免疫細胞が血液から出て、皮膚やリンパ節などの“監視”場所につくのをコルチゾールが促進する。感染の徴候がみつからなければ、免疫細胞は血流中に戻る。そして、ストレスが無くなったり、うまく処理されると、コルチゾールは危険が去ったことを免疫細胞に知らせる。そして最後にコルチゾールは、ストレスによってコルチゾールが過剰になった場合、視床下部に直接働きかけ、いわゆる負のフィードバックによって自らコルチゾールの生成を止めるのである。』
免疫の勘ちがい
『ストレスと免疫の関係の理解が深まれば、どのように対処したらいいかももっと明らかになるはずだ。免疫細胞の過剰な活動が原因となっている自己免疫疾患やアレルギー性疾患には、副腎皮質ステロイドが異常な免疫反応を鎮めるのに有効である。もっとも、そのような処置により、好ましい免疫反応も抑えてしまう危険性はあるが。プレドニゾンのような合成の副腎皮質ステロイド薬による治療は、ある意味で慢性ストレスの作用を真似ていると言える。つまり、プレドニゾンは炎症性サイトカイン(マクロファージまたはリンパ球が抗体刺激を受けて出す糖タンパク質)を抑え、細胞移動を低下させるのである。
一方、ウィルスやガンと闘うには、慢性ストレスよりも、急性ストレスに対応して動員される免疫力を借りる方が有利だ。研究が進み、急性ストレスと慢性ストレスについてもっとわかるようになれば、対応の仕方も進歩するだろう。』
7 トラウマが脳を攻撃する
『記憶とストレスの相互関係は、進化論の観点から見るとよくわかる。ストレスに満ちた出来事は、いちばん覚えていなくてはいけない出来事だと言える。動物はある音やある場所、ある匂い、ほかの動物が危険かどうかを瞬時に判断しなければならない。たとえば、山火事の音や匂いをすぐ思い出せない動物は山火事を生き延びることができないだろう。危険な出来事に関する記憶は瞬時に形成され、瞬時に思い出せる。それらは扁桃体というところで、記憶の砦の番人である海馬と密接に協力して形成される。
こうした出来事が強烈な記憶として残るように、海馬には記憶形成を助けるストレスホルモン、コルチゾールのレセプターがたくさんある。しかしこのために、海馬はコルチゾールが過剰に分泌されたり慢性的に高いと損傷を受けやすく、その結果、記憶をはじめとする認識、つまり“思考の”プロセスが悪影響を受ける。』
記憶を探して
『ストレスを受けたとき、陳述記憶が重要な役割を果たす。前に述べたように扁桃体は情動記憶、とくに恐怖の記憶とかかわりがある。動物が自分を食べようと狙っている動物の臭いを嗅いだり姿を見たとき、恐怖反応を示すのは扁桃体のしわざだ。しかし、狙われる動物はただ危険だという記憶だけを呼び起こすのでは不十分だ。以前にいつ頃どこで見たか、どのような姿をしていたか、逃げ道はあるかなど、私たちが“周辺状況”と呼んでいるさまざまな事実を思い出し、相手を避けるか必要に応じて逃げなければならない。これらの記憶は海馬の管轄だ。情動記憶は、扁桃体が強烈な感情を呼びおこし、それに海馬が“いつ、どこで、どのように”の記憶を補足するという、共同作業の結果なのである。エピソード記憶と呼ばれるこれらの記憶は、陳述記憶から派生したものだ。』
【ご参考】”肩こりに対する鍼治療が唾液コルチゾールに与える影響”
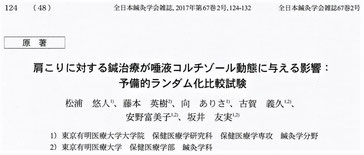
クリック頂くと、PDFの論文(9ページ)がダウンロードされます。『考察:鍼治療後の唾液コルチゾール濃度の減少は、自覚症状や不安度が軽減したことや高位中枢を介した反応である可能性が考えられる。肩こりに対する鍼治療は唾液コルチゾール動態にも影響を与える可能性が示唆されたが、今後、更なる検討が必要である。』
脳とストレス3
自律神経系の三つの顔
『心臓がアロスタティック負荷のダメージを受けやすいのは、ストレス反応システムの“配線”の中心に位置するからだ。目覚まし時計の音や自分をつけてきた人の影といった刺激に対応するため体が活発に機能しはじめると、ただちに必要なところに血液が流れ、そこでエネルギーが消耗される。休息の状態から急に激しい運動をはじめると、心拍数は1分当たり50回から150回まで上昇する。このような急激な変化は、脳と体が自律神経で直結しているから可能なのである。
自律神経は原始的な脳である脳幹と、体のほかの部分を神経回路によってつないでいる。神経回路は目、唾液腺、喉頭、心臓、肺、胃、腸、腎臓、生殖器など、いろいろな器官にはりめぐらされている。外からの刺激に反応して活性化する自律神経系は、典型的なアロスタシスと言える。すなわち自律神経系は、環境の変化に対処するために行動を起こす準備をするが、危険が去ったときには通常の状態に体を回復させる。
自律神経がこのように補足しあう機能をもつのは、関連しあう三つの働きから成っているからだ。まず、交感神経がいわば電源を入れる。外界からの刺激を受ける諸器官から脳につながる自律神経求心路のネットワークが、体中からメッセージを聞き取るマイクロホンのような役目をはたす。そして最後に副交感神経が、もとの状態に戻す働きをする。
心臓が激しく脈打ったり、冷や汗をかいたり、毛が立つような感覚など、ストレスを感じたときに起こる感覚はほとんど交感神経の働きだ。温度の変化や騒音、痛みなど、周囲からの信号に応答して、交感神経が心臓の動きを速め、血管を収縮させ、瞳孔を拡大させ、消化器系の働きを遅くするのである。これを行なうために脳の運動神経細胞が標的器官に、速くしろとか分泌量を増やせといった指令を伝える。これに使われる神経伝達物質がアドレナリンである(アドレナリンは、おもに副腎でつくられるが、血管内の交感神経や脳などでも生成される)。
胃がきりきりする感覚や急な動悸は、それを不快と認識しないかぎり、危険信号として役に立たない。これらの感覚を危険信号として処理するためには情報を脳に伝える必要がある。それを行なう別の神経系は、心臓や胃などの器官から脳につながり、体の“声”を集めて脳に届ける。このフィードバックのネットワークを自律神経求心路と呼ぶ。私たちの感情(体からストレス信号を感知した結果)を管轄しているのはおもにこのシステムである。ウィリアム・ジェームズによれば、感覚は状況によって、とらえ方が異なる(目の前にいるのが恋人か殺人犯かによって、情熱とも恐怖とも受け取れる)。しかし自律神経求心路を経由して認識された感情は、ストレスならびにストレスが私たちに与える影響を左右するのである。
最後に、副交感神経は、緊急反応を停止し、体を本来の状態に戻す。19世紀にクロード・ベルナールが述べた内部環境を維持する働きをするのだ。この副交感神経の働きにより、自律神経系は典型的なアロスタティック・システムの役割を果たしているのだ。副交感神経は、動悸を鎮め、瞳孔を収縮させ消化を助け、括約筋をリラックスさせることによって、体を元の状態に復帰させる(ただし性的に興奮すると、交感神経と副交感神経の両方が活性化する。昔から性的興奮が人間を大いに動かしてきた原因のひとつはここにあるかもしれない!)。
アロスタティック反応が健全であるためには、副交感神経がうまく機能することが不可欠だ。イリノイ大学シカゴ校のスティーブン・ポージスによれば、ストレスに対する反応は「外部からの要求に内部の要求に服従したことを意味している」と言う。外界からの変化に応えた後、副交感神経は、すぐさま最優先で体内を元の状態に戻す。しかし外界からの刺激にたびたび見舞われたり、それが長く続いたり、または異常な状況が生じるとアロスタティック反応が乱れ、副交感神経は体内の要求に応えることができなくなり、アロスタティック負荷となる。』
心臓にブレーキをかける迷走神経
『交感神経と副交感神経が交互に働くことにより、心臓は驚くほど臨機応変に対応する。心臓を落ち着かせるのは副交感神経、とりわけ迷走神経の働きだ。迷走神経はたくさんの神経からなる複雑な神経回路である。そして「迷走神経のブレーキ」とポージスが呼んでいる制御のメカニズムがうまく作動しなくなると問題が生じる。
哺乳類動物は、通常、迷走神経のブレーキがつねに作動している。それによって心臓が過剰に活動するのを防ぎ、ストレスが体を害さないようにするのだ。しかも迷走神経は交感神経の働きを抑えるだけではない。それ自体が微調整を行なって、周りで起きていることに体が手際よく適応できるようにする洗練されたメカニズムなのだ。ブレーキをかけていればだいたいにおいて興奮しすぎるのを防げるが、たとえば何かに注意を向けるなど、ときにはちょっとした切り替えが必要なときがある。とはいえ交感神経を動員するほどではない場合、迷走神経のブレーキを外して、心拍数と呼吸数を少し上げることが可能だ。こうすることで、大がかりな生理的変化を伴う緊急反応で体を消耗させることなく、体の機能をギヤアップすることができる。
迷走神経のメカニズムがうまく機能していないのはアロスタティック負荷の徴候だ。しかも、負荷の度合いは測定できる。ポージスは、健康な心臓は安静時でも、正常な範囲内で不整脈をもつことがあることを示した。つまり、息を吸い込むときには迷走神経の抑制が弱くなって心拍が若干増え、吐き出すときには迷走神経の影響が復活して心拍数が減るのだ。この不規則な動きは心拍変動、または呼吸性洞性不整脈と呼ばれる。迷走神経のブレーキ作用を測るには、心電図によって得られた情報をもとに、心拍間の時間を割り出す。健康な心臓の心拍数が不規則なのは迷走神経のブレーキがうまく機能している証拠だ。ポージスがこの方法を用いて考えだしたのが、迷走神経の緊張度というもので、これは迷走神経のブレーキがどれだけストレスに対処するのを助けているか示している。この指数の低下は(一時的に心拍数が変動しなくなってしまう)、迷走神経のブレーキが外されたことを意味し、その結果、ストレスに対応するために心拍数が上がる。迷走神経の緊張度が慢性的に低いとすれば、ブレーキが外れたままで機能していないということだ。このような状態の人はつねに緊急の態勢にあり、アロスタティック負荷に見舞われているのである。』
『健常者でも、心拍数の変動が少ないと、心疾患で死ぬ確率が高いことが研究によって判明している。精神生物学者リチャード・スローンは、迷走神経による心臓の制御は心疾患から体を守るためのメカニズムであると考えている。《心身医学》誌に発表した論文で、スローンは心拍数があまり変動しない人は冠動脈疾患になりやすく、変動の程度が低ければ低いほど、動脈硬化症が重度であり、心筋梗塞後に死亡する確率が高かったという。
しかし迷走神経のブレーキをうまく使えないことは、心疾患になりやすい心理状態の特徴でもある。敵愾心が心疾患と関係あることは、複数の研究に裏づけられている。抑うつと不安は心疾患の発症を予知させ、また心筋梗塞後の合併症を誘発し、さらには死に至らしめる。敵愾心、抑うつ、不安のいずれにも、副交感神経の機能不全が関与している。
副交感神経による心臓の調節は、心疾患につながる高血圧を防ぐ働きをしているだけではないとポージスは考える。彼によれば迷走神経のブレーキは、哺乳類というそれまでより複雑な動物が現われたときに、爬虫類しかいなかったときより敵対的な世界に対応するために進化したらしい。現代において、迷走神経のブレーキは緊急反応を発動させる刺激から私たちを守るだけでなく、感情的、社会的ストレスからも私たちを守ってくれているのかもしれない。要するに、迷走神経のおかげで、人間はこの世界(ストレスに満ちていようがいまいが)で暮らすのに適した感情的、社会的行動を身につけることができると言える。』
生活習慣と心臓
『食事、運動、お酒、睡眠などの生活習慣をうまくコントロールできるかどうかが、アロスタティック反応が私たちを守るかそれとも逆襲効果をもたらすかを左右しうる。たとえばニコチンには下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を放出する働きがある。そのため、HPA軸が活性化され、それが興奮度の高いストレス反応を引き起こす可能性がある。
アルコール摂取も、心臓血管系を直接危険にさらすわけではないが、ストレス反応を乱すことがある。アルコールがHPA軸を活性化すること、そしてラットの実験ではメスがオスより多くのACTHを分泌することが判明している。また、長期にわたりラットにアルコールを摂取させるとHPA反応が鈍くなりうることもわかった。アルコール依存症患者が酒を断って禁断症状が現れているときの血中のコルチゾールの濃度は、回復したときの二倍近くまで上がる。本人がアルコール依存症でなくとも、家族に病歴があると、実験で刺激を与えたとき過剰なコルチゾール反応が見られる。
睡眠のとりかたによっても、ストレス反応が助けられたり妨げられたりする。睡眠不足は交感神経を興奮させ、迷走神経のブレーキをききにくくするため、血圧の上昇などストレスによる弊害を受けやすく、それが心筋梗塞の引き金となったりする。また睡眠をとれなかった翌日の晩、コルチゾールが高くなる傾向がある。これが進むと腹部の脂肪沈着や心疾患につながっていく。
心血管病変を防ぐには、とくに食事と運動という、昔から言われていることに注意を払う必要がある。高脂肪の食事をとっていると体重が増えてコレステロールが高くなるだけでなく、交感神経が興奮しやすくコルチゾールの過剰分泌を招くのである。』
体脂肪とインスリンの関係
『重度の肥満は心臓に負担をかける。過剰な体脂肪、とくに腹部の体脂肪はアロスタティック負荷の徴候でもある。霊長類では、心理的なストレスが、脂肪沈着を加速することがある。ヒトの場合、ウエスト/ヒップ比で表される肥満度は、もっともストレスに弱い人々―スウェーデンの研究では社会経済的な底辺にいる男性で、イギリスの公務員の調査では男女にかかわらず下級公務員たち―に多く見られる。また、前にも述べたように、脂肪が腹部に沈着しているということは往々にして血管にもたまっていることを意味する。
アロスタティック負荷に関しては、肥満は悪循環となる。やせていることがいいとされる社会にいると、太っていることで落ち込む結果、さらなるストレスとカロリー摂取、体重増加につながりやすい。とりわけストレスと肥満と食生活と運動不足の複雑な悪循環は、心臓病とは別のストレス性疾患、つまり糖尿病の原因となりうる。糖尿病は動脈硬化のような心血管病変ではなく、体のエネルギーの使い方がおかしくなる代謝疾患だ。糖尿病自体、重い病気になりうるが、それ以外に動脈硬化の危険因子ともなる。とくに高血圧や高グリセリド血症(検査で中性脂肪が高いこと)のような状態が重なると(それはよくあることだ)動脈硬化になる確率はさらに高まる。
血液はブドウ糖の形で体中にエネルギーを運ぶ(血中のブドウ糖を血糖という)。インスリンと呼ばれるホルモンが血中のブドウ糖を、それを必要とする筋肉や器官に取りこませる。糖尿病とは、体が十分なインスリンを作らないか(1型またはインスリン依存性糖尿病)、作られてもそれを適切に使っていない状態(2型またはインスリン非依存性糖尿病)を言う。いずれの場合も、細胞が燃料となるブドウ糖を十分に取りこめない。2型の糖尿病になると、人間でも動物でも、体内でつくられるインスリンに対する抵抗性が高まる。肥満と運動不足は2型糖尿病の危険因子であり、ストレスの役割も注目されつつある(ストレスは、自己免疫疾患と考えられる1型の糖尿病の危険因子にもなりうるが、それについては後で詳しく述べる)。
インスリンは膵臓でつくられる。食事の後など、血糖値が上がると、食べたものをエネルギーに変えられるよう膵臓にインスリンをつくれという指示が行く。しかしインスリンが血糖を調節する唯一のホルモンではない。安定したブドウ糖の供給は筋肉や諸器官の細胞だけでなく脳にとっても不可欠である(筋肉などはブドウ糖が不足したときに脂肪やタンパク質を使えるが脳はそうはいかない)。脳は血液脳関門という強力なバリアーによって守られていて、ブドウ糖しか燃料として入れない。ほかの分子は大きすぎて関門を通れないのだ。したがって、脳にブドウ糖を安定供給するために、やはり膵臓でつくられるグルカゴンなど、いくつかのほかのホルモンが作用する。そしてストレスホルモンのアドレナリンとコルチゾールも血糖の調節に一役買う。
ストレスホルモンはブドウ糖代謝に悪影響を及ぼす。ストレスに対処するために余分な燃料が必要だと体が判断すると、コルチゾールが肝臓内のタンパク質を分解しブドウ糖に変えるように促す。また、アドレナリンも血糖値を上げる働きをする。そのメカニズムは全部わかっていないが、ストレスホルモンが長期にわたり多量に分泌されるとインスリン抵抗性を生み、コレステロールやトリグリセリド(中性脂肪)などが血中に増える。肥満も同じことで、コルチゾールの過剰分泌により肥満を招く。
2型糖尿病もまた、別の悪循環をたどる。インスリンの生成はストレスホルモン、とりわけコルチゾールの生成と関係があり、コルチゾールは細胞のインスリン・レセプターの感度を直接鈍らせる。インスリン・レセプターの反応が鈍ると、血中にブドウ糖が増えはじめ、血糖値が上がる。すると血糖値を下げるために膵臓はさらにインスリンを分泌するのだ。同時にストレスホルモンも増える。こうして肥満と高脂肪の食事はインスリンの抵抗性を高めるのである。』
脳とストレス2
ストレスホルモンが多すぎる場合
『このようにアロスタティック負荷は、ストレス自体が長く続くか、ストレスがなくなっても体が順応できないか、ストレス反応を解除するプロセスが機能しないかのいずれかの理由で、体がアドレナリンやコルチゾールに長い間さらされることから起こる。ストレスホルモンは血圧を上げ、免疫を抑えるだけではない。たとえばうつ病ではコルチゾールが慢性的に上昇していることが多いし、うつ病歴のある女性の一部では骨に含まれるミネラルの濃度が低下している。これは骨の形成には多くの時間がかかるため、緊急反応が発動されると後回しにされるからだ。さらにコルチゾールは骨をつくるプロセスを実際に妨害する。激しい運動を行っている女性がコルチゾールに長い間さらされると、アロスタティック負荷につながることがわかっている。本人はストレスと感じていなくとも、激しい運動を続けていると、交感神経とHPA軸の両方が活性化し、結果として体重が減ったり、生理不順や拒食症などになることがある。とくに拒食症は極度の運動と関係が深いとされる。
コルチゾール分泌が慢性的に多いと、インスリンの効果を抑えることもある。疲労感、エネルギーの欠乏、いらだち、意気消沈、敵対的態度などとして現われる慢性ストレスは、インスリンに対する抵抗力の発達に関連があるとされる。このインスリン抵抗性は、2型糖尿病(インスリン非依存性糖尿病)の危険因子である。
ストレス反応が生涯にわたって過剰に働くと、アロスタシスのプロセス全体が衰え、さまざまなシステムが機能しなくなる可能性がある。とくに、ストレスがなくなったときにHPA軸機能を止めるのを助け、記憶と認知の中枢である海馬が危険にさらされる。海馬にはコルチゾールのレセプターがたくさんあり、ストレス反応の際にコルチゾールを使って「チェック・アンド・バランス」を行っている。だが、コルチゾールが過剰に分泌された時まっさきに標的になるもののひとつなのだ。コルチゾール過剰分泌説によれば、海馬にコルチゾールがあふれると海馬が疲労し消耗して、HPA軸が正常に機能しなくなり、認知機能も損なわれる。
海馬はエピソード記憶と陳述記憶に重要な役割を果たすため、毎日の出来事や、買い物リスト、人や場所や物の名前などの情報を思い出すのに欠かせない。海馬はまた、出来事が起きた時と場所、とりわけ、強い感情がからんだ出来事が起きたときの環境の記憶(周辺状況的記憶)にも重要な役割を果たす。ストレスホルモンの過剰分泌のためにその人は誰が自分の味方で誰がそうでないかを思い出せなくなったり、顔と名前が一致しなくなることがある(ちなみにコルチゾールは、恐ろしい出来事やトラウマをもたらした出来事などの長期記憶の形成にかかわる扁桃体にも作用する。扁桃体は、正当な理由がなくても恐れたり心配したりする予期不安という症状とも関係がある。したがって扁桃体にストレスホルモンが増えると、私たちの心配が増し、すでに感じているストレスがさらに強くなる)。そして海馬はストレス反応の停止に関係している。要するに、海馬が損傷を受けると、ストレスがなくなったと認知する能力が衰え、ストレス反応を止められなくなり、その結果ストレスがさらに高まるという結果をもたらすのだ。』
ストレスホルモンが少なすぎる場合
『ストレス反応におけるチェック・アンド・バランスの話が出たところで、体を守るはずのアロスタシスがアロスタティック負荷となる最後のシナリオについて説明する。これまで過剰なストレス反応の弊害について述べてきたが、逆にストレス反応が不十分で、ストレスホルモン、とりわけコルチゾールの分泌が不足しても、体は疲労し消耗するのである(下部表参照)。なぜか。ストレスホルモンがなければストレスもなくなり、ストレス性疾患にもならないのではないかと思うかもしれないが、人間の生理機能はそう単純ではないのである。コルチゾールはサーモスタットのような働きをし、過剰になればその生産を抑える。そしてHPA軸を活性化するふたつのホルモン、つまり視床下部で出される副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)と下垂体から出される副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の生成を遅くする。またコルチゾールは免疫系にも影響を及ぼし、炎症や組織損傷による腫れを抑える働きもする。
チェック・アンド・バランスにかかわっているストレスホルモンがやるべきことをしないと、免疫細胞が活動しすぎることになる。一部の人ではアロスタティック負荷が、副腎の鈍い反応と、それによるコルチゾール不足という形で現われる。その影響を真っ先に受けるのが免疫で、ほんとうは危害を与えないようなものに対してもコルチゾールが不足しているために、体が過剰に反応してしまう。アレルギーはこの過程から起こる現象のひとつだ。たいていの人の体は、ほこりや猫の毛などを病原菌と同じに扱わないが、アレルギー体質の人ではそのような無害なものに対しても警戒態勢に入り、刺激原を攻撃する。その結果、侵入者を追いだそうとしてたとえばくしゃみが止まらなくなったり、それをつかまえようと粘液が分泌されたり、白血球が殺到するために感染部が腫れ、痛みに襲われたり赤らむなど、全身が不快感に襲われる。これらの症状はみな、コルチゾールが活動していれば軽減されているはずだ。
ぜんそくは、細気管支という小さな管が腫れて空気の通りが悪くなるために起こる。この場合も免疫システムが過敏に働きすぎて、あまり有害でないもの(ほこりや寒さや運動など)から体を守ろうと肺への門を閉ざしてしまうからである。アレルギーもぜんそくも炎症性の疾患で、アロスタティック負荷の典型的な病態を示しているが、これらは、コルチゾールの生産不足によって引き起こされる。しかもこれらの症状は、ストレスに見舞われているとき、往々にして悪化する。そのほかの炎症性疾患といえば、いわゆる自己免疫疾患と呼ばれるもので、免疫系が「自己」と「非自己」を区別するという第一の目的を達成できず、自分の体の組織に戦いをしかけてしまう状況をいう。このような症状もコルチゾールが十分あれば防げる(治療としてコルチゾールを注入することもある)。発疹は免疫細胞が健全な皮膚を攻撃したときに起こる典型的な症状で、小児アトピー性皮膚炎は、ストレスの徴候を示すと同時に、HPA軸が十分に反応していない徴候でもある。そのほか、ストレスによって悪化しやすい自己免疫疾患には、関節に炎症が見られる関節リウマチや、髄鞘と呼ばれる神経細胞の一部を破壊する多発性硬化症(MS)などがある。
HPA軸の反応が弱いと、免疫とは直接関係がなくても現われる病態がある。その一例が線維筋痛症だ。これは慢性の痛みが伴う病気で、たいていの医師は心身症として扱っている(なかには想像上の痛みにすぎないと考える医師もいるが、患者はもちろんそう思っていない)。痛みが炎症反応の一症状であると考えれば、免疫とコルチゾールの関係は明らかになる。痛みは、何か問題があることを私たちに警告し、問題が解決するまで病んだ部分をそっとしておけと忠告する。しかし痛みが慢性的な場合、ほかの炎症性疾患同様、これといった原因がないことが多い。このようなとき、免疫システムは不適応な反応をしているのである。コルチゾールの供給が十分だったらそのような状態になるのを防げたはずだ。』

こちらは”ヘルスアップ 日経Goody 30⁺”さまの、”しつこい疲れは副腎疲労?とりたい食材、避けたい食材”という記事です。
生活習慣とストレス
『忘れてはならないのは、アロスタティック負荷がストレスのもとに置かれなくても起こることだ。それは生活習慣と、日頃の生活でストレスにどのように対処しているかが反映される。私たちが何を食べているか、タバコを吸うかどうか、熟睡しているかどうか、運動しているかどうかなどがすべて、コルチゾールやアドレナリンをはじめアロスタシスにかかわるさまざまな物質の生成に影響を与えるのだ。
私たちはストレスの対処の仕方によって、ある程度、アロスタシスがアロスタティック負荷になるかどうかを左右できる。もしその選択をまちがえれば、ストレス性疾患になる確率が高まる。たとえば喫煙(多くの人にとって、それがストレスを防御する方法ではあるが)は血圧を上げ、冠動脈をつまらせ、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める。また脂肪の多いスナックにストレスからのはけ口を求めると、健康を害しかねない。高脂肪の食事は動脈硬化を加速し、コルチゾールの分泌を増やす。そしてコルチゾールが増加すると、体脂肪が蓄積しやすくなり、心血管病変や脳卒中、糖尿病の危険因子となる。
一方、ストレスに見舞われたとき、散歩やスポーツクラブでの運動で発散すれば、ストレスにうち勝つ確率を高めることができる。運動は体脂肪の蓄積を防ぎ、心血管病変を未然に防ぎ、慢性的な痛みやうつ状態を軽減する。また、人と積極的につきあったり、他人の助けを借りることによっても自分を守ることができる。ストレスと上気道感染の関係を研究したシェルドン・コーエンは、社会的なつながりが多い人の方が風邪をひきにくいと報告している。オハイオ・ステート大学のロナルド・グレイザーとジャニス・キーコルト・グレイザーは、孤立が免疫力を弱めることがあることを立証した。
緊急反応はうまく機能しないことも多いことから、脆いしくみだと思うかもしれないが、実際にはかなり柔軟だ。過去10年の研究によって、アロスタシスが逸脱したときに心臓血管系、免疫系、神経系に弊害をもたらすことが明らかになったが、同時に免疫などのシステムがたとえ被害を受けても回復できることもわかってきたのである。』
脳とストレス1
前回の”脳と運動”では、運動が脳にとって最も良いものの一つであることが明らかになりました。一方、過度なストレスは運動の対極、最も悪いものだと思います。
今回の『ストレスに負けない脳 心と体を癒すしくみを探る』という本は、脳とストレスの関係を深く知りたいと期待して購入したのですが、多くのことを知ることができました。なお、ブログは8つに分けています。

著者:ブルース・マキューアン、エリザベス・ノートン・ラズリー
監修:星恵子
訳:桜内篤子
出版:早川書房
発行:2004年9月
発行は2004年と決して新しい本ではないため、最新の説からは違和感があるかもしれませんが、”原注(p275~p292)”として参照論文が掲載されており(計210)、これらの論文を背景に書かれた本であることが分かります。
本書では、「アロスタシス」と「アロスタティック負荷」というものを非常に重要なものとして位置づけています。もちろん、本文の中でも詳しく説明されているのですが、監修を担当された昭和薬科大学の星先生が書かれた”解説”が一般的、客観的な説明として大変分かりやすいものと思います。なお、これは”解説”の一部になります。
解説
『マキューアン博士がストレスについて書かなければと思い立ったのは、ひとつには日頃よく見られるいわゆるコモン・ディジーズである心筋梗塞や高血圧症、糖尿病なども、実は感情や、情緒的・心理的状況が、それらの疾患の発症や進展に密接に関与していることが理論的に説明できると確信しているためで、それを喚起することによって、これらのありふれた疾患の予防につなげたいと考えたからである。もう一つは、将来、”うつ病”になる人の割合がかなり高くなることが予測されており、この点も大いに危惧してのことである。
ストレスについて書かれている本書が、これまでになく新鮮に見えるのは、アロスタシス、アロスタティック負荷という言葉を用いているからであろうか。普通、ストレスを受けると心身ともに消耗し、ときに身体はボロボロになってしまう。本来のストレス反応は病気を引き起こすことが目的ではなく、むしろ身の安全とサバイバルを目的としているはずである。そこでストレスを身体を守るシステムであると理解するために、別の用語を用いた方が賢明と考えたのだろう。そこで、選ばれたのがアロスタシスである。アロスタシスもアロスティック負荷もこれまでなじみのない言葉であるが、アロスタシスとは生物学や医学でよく知られているホメオスタシス(恒常状態)とほぼ同義語である。ギリシャ語でホメオスタシスのホメは同じ、スタシスは一定の状態という意味で、外部環境が変わっても身体内部はほぼ一定に保たれることで、W・B・キャノンの「からだの知恵―この不思議なはたらき」に詳細に書かれている。ホメオスタシスの代表例に体温凋節や酸塩基平衡などがある。体温は35.3度~37.5度、体液のpHは7.36~7.46と、これらの変動幅は許容範囲が狭く、一定の基準を超えると死に至る。一方、心拍数や呼吸数、血糖値は変動幅の許容範囲が広い。食後2時間の血糖値は140mg/dl以下が正常であるが、それが倍以上の300mg/dlになっても400mg/dlになっても死ぬことはない。そこでマキューアン博士は、生体が何らかの刺激を受けた時、それに応じて変化するのであるから、ギリシャ語で変動するという意味の「アロ」が語源となっているアロスタシスの方が適切であると考え、好んで用いた。そして、アロスタシスが一定の限界を超えた時がアロスタティック負荷である。』
目次は以下の通りですが、黒太字が取り上げた項目です。
序文/ロバート・サポルスキー
1 ストレスの不思議なしくみ
ストレスとは何か
ストレスとアロスタシス
闘うか逃げるか
自分で引き起こすアロスタティック負荷
ストレスと情動
ストレスの生みの親セリエ
現代人特有のストレス
2 ストレスは脳からはじまる
脳が飢え、脳が恋する
ストレス反応
大切なストレスホルモン
海から生まれたストレス
魚たちのストレス
動物たちのストレス
ヒトのストレス
ストレスと記憶
3 ストレスと感情のつながり
“感情”に対する新しい見方
脳のメッセンジャー
神経細胞の鍵と鍵穴
空腹ストレス
ストレスと遺伝子
ストレスが脳に“戻る”とき
4 アロスタティック負荷はこうして起こる
サッチャー首相の民営化と共産主義の崩壊
ストレスが風邪を長びかせる
ストレスは気分で変わる
マイナス思考の危険性
ストレスホルモンが多すぎる場合
ストレスホルモンが少なすぎる場合
生活習慣とストレス
5 動脈硬化・肥満・糖尿病を防ぐには―ストレスと心臓
自律神経系の三つの顔
心臓にブレーキをかける迷走神経
自律神経のしくみ
呪いによる死
怒りっぽい人は要注意
生活習慣と心臓
体脂肪とインスリンの関係
自ら選ぶ生活習慣
6 免疫は諸刃の剣
ガンになりやすい人
愛する人の死の脅威
ストレスが体を守ることもある
ストレスで動員される白血球
免疫の逆襲
ストレスとぜんそく
免疫の勘ちがい
7 トラウマが脳を攻撃する
記憶を探して
コルチゾールの役割
ストレスと記憶回路
コルチゾールの威力
狙われる海馬
ラットも上下関係に悩む
ストレスの効能
ツバイの実験
保護か危害か
脳がトラウマに屈するとき
遺伝子とストレス
細胞のスイッチ
コルチゾールの微妙な働き
ストレスと加齢
8 ストレスに負けない生活
ウォーキングの効果
運動と脳
ストレス解消は食生活から
快眠の大切さ
睡眠とストレス
酒はストレス解消にならない
友だちの支え
社会的支援とガン
気のもちようでずいぶん違う
コントロールのよい面と悪い面
医学に携わる者としてひとこと
9 ポジティブ・ヘルスとは?
麻薬のような体内物質エンドルフィン
脳がつくりだす薬
エンドルフィンを越えて
アルツハイマー病の原因
運動がストレスに効くわけ
抗うつ剤の効果
海馬とポジティブ・ヘルス
神経細胞新生とうつ病
エストロゲンの働き
私たちを守る脳
10 これからの展望
アロスタシスと予防医学
子どもとストレス
高齢者とストレス
不利なマイノリティ
経済的状況と人生観
ポジティブ・メンタルヘルス
大事な人間のつながり
変えられること変える勇気
これからの神経生物学
ストレスとは何か
『本来ならストレス反応は、体の主要システムが協力しあう洗練された防御機構のひとつである。これは緊急反応あるいは「闘争か逃走か」反応とも呼ばれる。ストレス反応のおかげで私たちは緊急事態に対応し、状況の変化に対処することができる。そのために脳、内分泌腺、ホルモン、免疫系、心臓、血液、肺が総動員される。ストレスに対して闘おうが、断固とした態度で臨もうが、安全のために逃走しようが、それとも目の前の作業に集中しようが、ストレス反応は瞬時に必要なエネルギーや酸素、筋力、燃料、痛みに耐える力、頭の回転、感染に対する一時的な防御体制を提供してくれる。ストレスがたまったり続いたりしたときに、体のいろいろな部分に支障を来たすのはそのためだ。
ではなぜストレスで心身がボロボロになるのか。人間の体はなぜ、苦境に立たされたとき、病むようなしくみになっているのか。ストレス反応の機能はもともと病気にさせるためのものではないはずだ。緊急反応は、身の安全とサバイバルというもっとも重要な任務を達成するために進化したしくみなのである。ストレス反応という強力でダイナミックな復元能力のおかげで注意力が鋭敏になり、脅威に備えて体が準備体制をとり、終わるともとの状態に戻る。しかも普通は副作用もない。ただし、脅威があまりにも大きかったり反応が逸脱してしまうと、病気の原因になるのである。
本書の狙いは次のパラドックスに注意を喚起することだ。つまりストレスは厳しい状況のもとで人間の体を守ってくれるが、慢性的に作動すると有害になり、病気を悪化させるということだ。疲れたときに人は、めまぐるしい世界で生きているのだからへとへとになるのも無理はないと思いがちだ。しかし、逆境に立ち向かうときにストレスがかかるのはある程度しかたがないにしても、ストレスでボロボロになる必要はないのだ。本来私たちを守るはずのシステムそのものが脅威となる必然性はないし、そうなることが正常とは言えない。この違いを認識することが非常に大事である。ストレスが健康に与える影響について考えるうえで、新しい言葉が必要だと私が思うようになったのはそのためだ。
ストレスという概念自体、時代遅れになっているので、元の意味に立ち戻って、定義を整理するべきだろう。したがって本書でストレスと言うときは外部で起きることのみを指すことにする。科学の進歩のおかげで、ストレス反応または緊急反応について、以前よりわかってきた。そこで私はその反応に、「アロスタシス」という言葉を使うことにした。そしてストレス反応が私たちの体に逆襲するような状態には「アロスタティック負荷」という言葉を当てる。本書を通じてこのふたつの言葉について説明するが、まずは簡潔に述べておく。』
ストレス反応
『アロシスタシスは脳の深いところで始まる。脳にある視床下部が腎臓の上にある副腎体に警鐘を鳴らすと、副腎体はこれに古典的な緊急反応で応じる。そして主要なストレスホルモンの第一陣、つまりアドレナリンを分泌する。アドレナリンは心拍数を上げ、筋肉や諸器官に余分に血液を送る。気管支が拡張し酸素が大量に吸入され、通常より多くの酸素が脳にも送られ、注意力が高まる。怪我したときに毛が立つような感覚がするのは、出血を抑えるためにアドレナリンの働きで皮膚の血管が縮むからだ。さらに出血への防止策として、凝血を速める線維素原(フィブリノゲン)という物質の分泌がアドレナリンによって促される。最後に、アドレナリンは体に働きかけて、グリコーゲンとして貯蔵されたブドウ糖を放出させ、また蓄積された脂脂を脂肪酸に分解してエネルギー源を確保する。この緊急反応の間、脳はエンドルフィンという鎮痛作用をもつ物質を出し、生体が危機においても機能できるようにする。
緊急事態になるべく速く対応するため、視床下部は副腎に直接通じる神経回路を使って伝達する。アドレナリンが中心的な役割を果たすこの段階が、ストレスに対する最初の反応である。猫を助けるために老女が車を持ちあげることができたのは、このアドレナリンのおかげにちがいない。
次に脳は視床下部‐下垂体‐副腎軸(略してHPA軸)という先鋭部隊を動員する。これが、脳がホルモンをメッセンジャーとする防衛機構の第二陣だ。HPA軸はアロスタシスならびにアロスタティック負荷のもとになる機能である。これによって神経系、内分泌系、免疫系が動員されるのだが、うまく機能することもあればしないこともある。HPA軸が正常に機能しているとき、私たちの体はエネルギーと集中力を発揮して危機に対処できるが、ストレスがたまるとHPA軸のバランスが崩れて、ぜんそくの発作を起こしたり、風邪をひいてもなかなか直らなかったりするのである。
アロスタティック反応は視床下部が副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)という物質を放出することによって作動する。CRFが専用の血管を通ってアーモンド大の下垂体に達すると、下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が分泌される。ACTHが血管を通って副腎を刺激すると、副腎から第二の主要ストレスホルモンであるコルチゾールが血液に放出された体内を循環するのである。
コルチゾールは、コレステロールから作られている(これはコレステロールが重要な役割を果たす例だ)。コルチゾールの最初の任務はアドレナリン放出によって使い果たされたエネルギーを補充することで、食べたものをグリコーゲンや脂肪に変えて貯蔵しやすくする。コルチゾールは私たちを活動的にさせ、おなかをすかせる。しかしコルチゾールが分泌されすぎると、筋肉を刺激してブドウ糖を取り込むインスリンの働きが抑えられてしまう。さらにコルチゾールが過剰になると、脂肪が増え、とりわけ、健康に悪いとされる腹部にたまる。コルチゾールはさらに筋肉のタンパク質を減らして脂肪に変える働きを促し、その結果、骨のミネラルが減る。
コルチゾールは免疫系にとっても諸刃の剣となりうる。多すぎると免疫機能を抑えるため、感染症にかかりやすくなる。しかし短期的には、コルチゾールは感染や怪我に対処するのを助ける。つまり怪我や感染から体を守る白血球を、侵略を受けた場所に送り込むのである。このときコルチゾールは白血球が血管壁や傷口、感染箇所など、防衛しなければならない部分の細胞にくっつきやすいよう、その表面を変える働きをする。
免疫活動がもう十分だと知らせるのもコルチゾールの働きだ。このメッセージはまず脳に送られ、視床下部、下垂体を経由し、ストレス反応を調整する。コルチゾールのチェック・アンド・バランス(抑制と均衡)の機能が、免疫反応が活発になりすぎることによっておこる湿疹やアレルギー、免疫が体の健康な細胞を攻撃する自己免疫疾患を防ぐのである。湿疹にステロイド軟膏を塗ったり、炎症を抑えるためにステロイド剤を飲むのは、体内のコルチゾールが通常行っている働きを補うためだ。』
脳と運動4
今回は第九章から第十章です。なお、目次については”脳と運動1”を参照ください。
第九章 加齢 ―賢く老いる
すべてをひとつに
『ここまで体と脳の生物学的なつながりについて多くを話してきた。それが最も重要な意味をもつのは、老化について語るときだ。結局、健康な心は健康な体あってこそのものである。
1900年には、アメリカ人の平均寿命は47歳だった。今日それは76歳を上回り、高齢者は、急な病気ではなく慢性疾患によって亡くなる場合が多いようだ。だが、平均寿命を超えて長生きする人にとっては、もうひとつ気の滅入る統計データがある。疾病管理予防センター(CDC)によると、75歳の人は平均して3種類の慢性疾患を抱え、5種類の処方薬を服用しているそうだ。65歳以上のほとんどは高血圧で、3分の2以上が肥満、約20パーセントが糖尿病を患っている(糖尿病の人が心臓病になる確率は、そうでない人の3倍だ)。三大死因である心臓病、がん、脳卒中で亡くなる人は、この年代では61パーセントにのぼる。
喫煙、運動不足、栄養の偏りがこうした病気を招くことをわたしたちはすでに知っている。加えて、ライフスタイルは、加齢にともなって起きる精神面の危機にも大きく影響することが、最近の研究によって明らかになった。体に悪いことは、脳にとっても悪いのだ。だが、国立老化研究所の神経科学者マーク・マットソンは、それをプラスの方向でとらえている。「心血管系の疾患や糖尿病のリスクを減らす要因の多くが、老化にともなう神経変性障害のリスクも減らすというニュースは、喜ぶべきことである。もっとも、わたしたちが真剣にそれを受け止めればの話だが」
たとえば、糖尿病を防ぐよう努力すれば、脳内のインスリンのバランスも整い、ニューロンが強化され、代謝ストレスに対抗できるようになる。また、血圧を下げ心臓を鍛えるためにランニングをすれば、脳の毛細血管が弱くなったり塞がったりするのを防ぐことができ、脳卒中の予防につながる。さらに、骨粗しょう症で骨がすかすかになってしまわないよう、ウェイトトレーニングをしていれば、脳内に成長因子が放出され、ニューロンの樹状突起が伸びる。逆に、認知症予防のためにオメガ3脂肪酸を摂取していると、骨が強くなる。
老齢期に直面する精神の病気と体の病気は、心血管系と代謝系を通じて結びついている。肥満の人が普通の人の2倍、認知症になりやすいのも、心臓病の人がアルツハイマー病(認知症の中でも最も一般的な疾患)になる確率が高いのも、そのような頭と体のつながりが壊れた結果なのだ。統計によると、認知症になる確率は、糖尿病の人は65パーセントアップし、コレステロール値が高いだけで43パーセントも高くなる。運動がこうした病気を予防することは何十年も前から医学的に証明されている。だがCDCによると、現在でも65歳以上の人の3分の1は、自ら運動することはないと答えているそうだ。運動が体だけでなく脳の老化をどれほど防ぐかがわかっていれば、皆もっと真剣に運動について考えるようになるだろう。』
いかに年をとるか
『年をとることは避けられないが、惨めな衰えは避けることができる。100歳になっても健康にほとんど問題ない人もいれば、慢性疾患のために頭も体もすっかりがたがきてしまう人もいるのはどうしてだろう。それを理解するために、細胞レベルで生と死を見てみよう。
年をとると、体中の細胞がストレスへの適応力を失っていく。なぜそうなるのか、科学者にも正確なところはわかっていないが、はっきりしているのは、細胞は古くなるほど、フリーラジカルによる酸化ストレスや、過度のエネルギーの要求、過度の興奮などに立ち向かう力が弱くなるということだ。さらに、有害なゴミを掃除するタンパク質を生成するはずの遺伝子がその仕事をやめてしまうと、神経科学者が「アポトーシス(細胞の自死)」と呼ぶ、細胞の死のスパイラルが始まる。細胞のダメージが重なると免疫系が活性化し、死んだ細胞を掃除するために白血球やその他の因子を送り込み、それらが炎症を生じさせる。炎症が慢性化すれば、さらに多くの有害なタンパク質が生じる。それらはアルツハイマー病に直接関係している。
脳では、ストレスのせいでニューロンが弱くなると、シナプスが餌まれ、最終的にはつながりが切れてしまう。脳の活動が減るに従って、樹状突起は文字通り縮み、しなびていく。その結果、あちこちでシグナルが伝達されなくなるが、最初のうちはそれほど困らない。本来、脳のネットワークは、つながりが断ち切られた部分を避けて、別のルートで情報を伝達できるようにできている。ある程度、余裕の部分が用意されているのだ。なんと言っても、ニューロンは1000億個以上もあり、それぞれが多ければ10万ものニューロンに情報を伝えている。そのネットワークはとても緊密で、先に述べた通り、新しい結合を作っては成長し、配線の変更と適合化を繰り返している。もっとも、それは新たな結合を促す十分な刺激があれば、の話だ。年をとるにつれて回路は途切れていくので、なにをするにも、今までより広いネットワークが必要になる。思うに、知恵とは、そのような効率の低下を脳が巧みに埋めることの反映ではないだろうか。
シナプスの衰えるスピードが、新たな結合の生まれるペースを上回るようになると、頭と体の機能にさまざまな問題が生じてくる。それはアルツハイマー病やパーキンソン病も含まれる。どの病気になるかは、脳のどの部分が衰えるかによって決まる。基本的には、認知力の衰えや、神経変性による病気はすべて、ニューロンが死んでしまったか、機能不全に陥った結果であって、そのせいで情報の伝達が断たれたのだ。老化に関する研究は、マットソンが指摘するように、「ニューロンの情報伝達力を回復させ、生かしつづけること」をおもな目的として進められていて、「成功すれば、ニューロンの衰えを食いとめ、病気を予防できるようになる」
シナプスの活動が減り、樹状突起が萎縮すると、脳に栄養を運んでいる毛細血管も萎縮するため、血液の流れが制限される。逆のことも起きる。脳に血液を十分に送り込まないと、毛細血管が萎縮し、それにつづいて樹状突起も萎縮する。いずれにせよ、それは細胞の死を招く。血液によって運ばれる酸素や燃料、肥料、そして修復に使う分子がなければ細胞は死んでしまうのだ。ニューロンの成長を促す栄養素―脳由来神経栄養因子(BDNF)や血管内皮成長因子(VEGF)など―の量は、年をとるに従って減っていく。そして、神経伝達物質であるドーパミンが作られるスピードも遅くなり、運動機能の意欲の低下を招く。一方、海馬でも使えるニューロンがどんどん少なくなっていく。ラットの研究から、ニューロン新生は加齢とともに劇的に減ることがわかっている。それは、誕生する幹細胞の数が減るからではなく、もともとの神経幹細胞のプールが枯渇し、完全に機能するニューロンが作られなくなるからだ(おそらく、VEGFが少なくなるせいだろう)。ほとんどの神経細胞はいずれにせよ死ぬ運命にあるが、使いものになる幹細胞の数は、げっ歯動物の中年期(人間で言えば65歳以上)には、4パーセントにまで減少する。ニューロン新生の恩恵にあずからない広大な部分[現時点(初版発行2009年)でニューロン新生が確認されているのは海馬と脳室下帯のみ]については言うまでもない。40歳をすぎると、脳は平均して10年に5パーセントずつ減っていく。そして70歳から先は、さまざまな要因がこのプロセスに拍車をかける。
わたしの母のように、年を重ねてもずっと社交的で活動的な人は、脳の劣化のスピードを遅らせることができる。退職後の人の脳血流レベルを調べたところ、運動をつづけている人は退職して4年経ってもほとんど変わらなかったのに対し、運動をあまりしない人は著しく低下していた。脳は活発な成長を止めたとたん、死に向かい始める。運動は老化の進行を阻むことのできる数少ない方法のひとつだ。なぜならストレスに抵抗する力の衰えを遅らせることができるからで、マットソンは「矛盾するようだが、定期的に適度なストレスにさらされることは細胞にとってプラスになる。抵抗力がつき、より強いストレスに対処できるようになるのだ」という。
さらに運動は、先の章で述べたように、脳の回路が結合を増やし、成長するきっかけを与える。血液の量を増やし、燃料を調節し、ニューロンの活動と発生を促すのだ。老いた脳はダメージに対して弱いが、だからこそ、脳を強くするためになにかをすれば、若いときより効果が大きい。だからと言って、若いころから脳を鍛えることに意味がないわけではない。もしあなたの脳が、健康で、強く、しっかり回路のつながったものであれば、年をとってニューロンが壊れ始めても、より回復しやすく、より長くもちこたえられるだろう。運動は解毒剤であると同時に予防薬でもある。だれでも老化する。なぜかと問われても、どうしようもないが、どのように、いつ老化するのかについては、間違いなく打つ手がある。』
【ご参考】過去ブログ:"慢性炎症について”

『慢性炎症は病原体を撃退した後や、傷が治癒した後に炎症という爆撃が完全に停止されず、くすぶり続け、健康な細胞、組織、血管へのダメージが終結せず続いている状態です。』
下記は大阪大学医学系研究科さまの”脂肪慢性炎症の引き金となる分子を同定”という記事の抜粋です。
『肥満では単に体重が増えるだけではなく、脂肪組織において軽度の炎症が慢性的に進行することが知られており、この“慢性炎症”が、糖尿病や高血圧・動脈硬化といった生活習慣病を引き起こす元凶であると考えられています。しかしながら、肥満がどうやって脂肪組織での慢性炎症を誘導するのか、その具体的なメカニズムは謎のままでした。』
認知力の衰え
『最初の兆候はささいなものだ。脳の回路が断たれると、知っているはずの人や場所の名前がなかなか思い出せなくなる。のどもとまで出かかっているのに出てこない、そういう経験はだれでも覚えがある。記憶のサーチエンジンである前頭前野がそれを呼び出さなくなったのだ。海馬がほかのつながりを頼りに記憶を呼び起こそうとするのだが、すんなりとはいかず、以前なら考えなくても言えたのに、なんでこんなに苦労するのかと、あなたはイライラしてくる。年をとれば皆、経験することだが、これもいわゆる軽度認知障害の症状である。その程度は人によって千差万別だ。
軽度認知障害は進行するとは限らないが、放置すると認知症になりかねない。自分を形づくっている人生の軌跡を辿ることができなくなり、自我が餌まれていくという耐えがたい恐怖を味わう。自分がそうした段階にあるとわかると、多くの人は自らの樹状突起の状態を模倣するかのように萎縮し、外に向ってはたらきかけたり新しい関係を結んだりするのをやめてしまう。うまく対処できないのではないか、と恐れるのだ。そして殻に引きこもってしまう。恥をかきたくないし、慣れ親しんだ家から外に出ることに不安も感じる。いずれにせよそうなると、脳に刺激を与えてくれる有意義な関係から隔絶されてしまう。孤立と運動不足は、細胞の死のスパイラルを助長し、脳を萎縮させる。
衰えが最も顕著に表れるのは前頭前野と側頭葉だ。前頭葉は、前頭前野の灰白質とその軸索の白質を含む。側頭葉は単語と固有名詞のリストを作り、海馬と連携して長期記憶の形成を助けている。前頭前野が衰えると、高度の認知機能が衰え、日常の基本的な作業も難しくなる。皮肉なことに、靴ひもを結ぶ、ドアの鍵を開ける、食料品店まで車で出かけるといった、ごくあたりまえにやっていることが、実は、作動記憶、作業のスムーズな切り替え、不要な情報の締め出しといった、脳の最も高度な機能に依存しているのだ。よく調教されたサルでも、シャツのボタンをなかなかきちんとはめられないのはそこに理由がある。
側頭葉は脳にとっては辞書のように記憶を蓄えておく場所で、アルツハイマー病によって萎縮する領域のひとつだ。従ってアルツハイマーかどうかは、単語を羅列したリストを見せ、1時間半後にどれだけ思い出せるかを問う簡単なテストによって調べられる。
第一章で述べたように、イリノイ大学で行われた数々の研究は、脳のこれらの領域を対象とするテストの成績と運動量に強いつながりがあることを示している。ある研究では、有酸素運動を長年つづけてきた高齢者ほど、脳がよりよい状態に保たれていることがMRIの画像診断によってわかった。こうした相関自体も興味深いが、研究者たち本当に知りたかったのは、運動によってこれらの領域の構造に変化が起きるかどうかということだ。』
第十章 鍛錬 ―脳を作る
『わたしが強調したかったこと―運動は脳の機能を最善にする唯一にして最強の手段だということ―は、何百という研究論文に基づいており、その論文の大半はこの10年以内に発表されたものだ。脳のはたらきについての理解は、その比較的短い期間にすっかりくつがえされた。この10年は、人間の特性に興味をもつ人すべてにとって、心沸きたつような時代だった。わたし自身、本書のための調査を通じて、運動の効果にますます驚かされ、直感的な洞察は科学に裏打ちされた真実へと変わっていった。』
『スモールは、被験者たちに3か月間運動させたのち、脳の写真を撮った。標準手的なMRIを用い、ズームしてシャッターを切るというごくあたりまえの方法で、彼は新たに形成された毛細血管の画像をとらえた。それは発生したニューロンが生き残るのに必要とするものだ。彼が目にしたのは、海馬の記憶領域における毛細血管の量が30パーセント増えるという、まさに驚くべき変化だった。もっとも、この研究が果たした最大の貢献は、脳を切り刻むことなくニューロン新生を見つけ出せるようになったことだろう。この新しい技術により、科学者はさまざまな要素がニューロン新生にどう影響するかを調べられるようになった。運動量もそのひとつだ。』
『脳のためにどのくらい運動すればいいのかと尋ねられたら、わたしは、まずは健康になることを目指し、自分への挑戦をつづけることが大切だと話している。なにをどのくらいすればいいかは人それぞれだが、研究が一貫して示しているのは、体が健康になればなるほど、脳はたくましくなり、認知力の面でも、情緒の面でも、よくはたらくようになるということだ。体を快調にすれば、心もそれに従うのだろう。
だとすれば、運動が脳に及ぼす利益を享受するには、体を鍛え上げて下着のモデルのような体型にならないといけないのだろうか? そんなことは決してない。実際、研究では、ウォーキングしただけでも、説得力のある結果が出ている。それでもわたしが健康な体に着目するのは、標準的な体重を維持し、心血管系を強くすれば、脳は最大の力を発揮できることを知っているからだ。どの程度の運動でもプラスになるが、実際的な観点から言えば、脳のためになにかをするということは、体を心臓病や糖尿病、がん、その他の病気から守ることにもなる。体と脳はつながっている。両方一緒に大切にすればいいのだ。』
まとめ
4つに分けたブログですが、最後に簡潔にまとめたいと思います。
最も重要なことは、”運動はほとんどの精神の問題にとって最高の治療法である。一方、孤立と運動不足はアポトーシス(細胞の自死)を助長し脳を萎縮させる”ということだと思います。
そして、主なメカニズムは下記の5つと考えます。
1.運動は筋肉の回復プロセスだけでなく、ニューロンの回復プロセスのスイッチも入れる。
2.運動によって脳に適度なストレスがかかると、遺伝子が活性化してタンパク質(成長因子)が生成され、ニューロンを損傷や変性から守るとともにその構造を強化する。
3.運動は脳のストレス耐性を強めるが、それは多くの成長因子(脳由来神経栄養因子[BDNF]、インスリン様成長因子[IGF-1]、線維芽細胞成長因子[FGF-2]、血管内皮成長因子[VEGF])を増やすからである。
※成長因子とは:特定の細胞の増殖や分化を促進する内因性のタンパク質の総称である。(ウィキペディアより)
4.運動によりインスリン様成長因子[IGF-1]は海馬のなかでLTP(長期増強)を促進して、ニューロンの可塑性を高めニューロン新生を促す。
5.運動はコルチゾールが増えすぎないよう監視し、必要に応じて神経伝達物質セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンを増やすという効果も有する。
脳と運動3
今回は第後五章から第七章です。なお、目次については”脳と運動1”を参照ください。
第五章 うつ ―気分をよくする
論理の穴
『薬や運動がうつを改善させる仕組みについて本当のところがわかってきたのは、脳の鮮明な写真を写せるようになってからのことだ。1990年代初頭、MRIで調べたところ、ある種のうつ病患者の脳に明るい斑点が見つかった。それは高信号域と呼ばれ、白質の部分に現れる。白質とは、灰白質―ニューロンの本体である細胞体の集まっている部分。灰色っぽい色をしているので灰白質と呼ばれる―から伸びた軸索が集まった部分である。さらによく見てみると、皮質の量が普通と違うことがわかった。灰白質が実際に縮んでいるのだ。灰白質は皴の寄った薄いカバーとなって脳を覆っていて、注意力、感情、記憶、意識といった人間の複雑な機能をすべてつかさどっている。MRIによって見えてきた現実はぞっとするようなものだった。慢性のうつは、脳の思考する部位を構造的に傷つける可能性があるのだ。
同様の研究により、うつ病の患者の脳では扁桃体と海馬に著しい変化があることが明らかになった。いずれもストレス反応の重要な役割を担う部位だ。扁桃体が人間の感情をつかさどる中心だということは以前から知られていたが、記憶中枢である海馬がストレスとうつにもかかわっていることはようやくわかり始めたところだった。1996年、セントルイスにあるワシントン大学のイヴェット・シーラインが、うつ病患者10名の脳と、同じような体格と学齢の健康な人10人の脳をMRIで比べたところ、うつ病患者の海馬は、健康な人のそれより最高で15パーセント小さかった。また、海馬が縮む度合と、うつ病だった期間の長さに関連があることを示す証拠も見つかった。意義ある発見だ。うつ病患者の多くが学習と記憶の衰えを訴えるのも、海馬の萎縮から始まるアルツハイマー病患者の気分が沈みがちになるのも、おそらくそこに理由がある。
ストレスホルモンのコルチゾールが多いと、海馬のニューロンは死んでしまう。実際のところ、ペトリ皿にニューロンを入れ、コルチゾールをたっぷり注ぐと、ニューロン間の結合は途切れ、シナプスの成長は止まり、樹状突起はしなびていく。そうなるとコミュニケーションは遮断される。うつ病の人の海馬では、それが実際に起きているのだ。彼らが否定的な考えから脱け出せない理由のひとつがこれで、海馬は別の結合を作るための枝を伸ばせなくなり、否定的な記憶を何度もたどり始める。
新たに陽電子放射断層撮影装置(PET)や機能的磁気共鳴画像法(fMRI)のおかげで、うつをこれまでとは違う生物学の角度から見られるようになった。誕生した当時、それらの画像は粗く、あいまいだったが―その点は今もあまり進歩していない[初版発行は2009年になります]―、科学者は脳の静止画像だけでなく、活動している様子も見られるようになったのだ。また同じころ、新しいニューロンが海馬とおそらくは前頭前野において、日々作られていることもわかった。どちらもうつになると萎縮する部位だ。この新しいツールと新しい発見から、「神経伝達物質仮説」の見直しが始まった。
とは言え、その古い理論が捨てられたわけではない。さらに拡大されたのだ。今では、うつは、脳の感情回路が物理的に変化した結果だと考えられている。ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニンはシナプスを通って情報を運ぶ大切なメッセンジャー(神経伝達物質)だが、そこがしっかりつながっていなければ、役目を十分に果たせない。そもそも脳の仕事は、つねに回路を接続し直しながら情報を伝達し、それによって人間を環境に適応させ、生き延びさせることである。ところが、うつになると、特定の部位でその適応機能がはたらかなくなる。つまり、細胞レベルで学習が遮断されるのだ。そうなると脳は、自己嫌悪の否定的な堂々巡りに陥り、その穴から脱け出すのに必要な柔軟性も失われる。』
【ご参考】過去ブログ:"うつ病治療(TMS)”
第六章 注意欠陥障害 ―注意散漫から脱け出す
全コントロール・ユニット、注目!
『情報に注意が向けられればそれでいいわけではなく、その情報が脳内でスムーズに流れることも重要だ。ここで注意システムと体の動き、ひいては運動とが結びついてくる。体の動きをコントロールする脳の部位は、情報の流れも調整しているのだ。
小脳は脳の中でも原始的な部位で、動きのコントロールと精錬だけにかかわっていると長く考えられてきた。空手の蹴りであれ、指の鳴らし方であれ、なにか動きを覚えようとするとき、小脳はフル回転している。小脳は、脳のわずか10パーセントの体積しかないのに、ニューロンの半分を有している。つまり、そこにはぎっしりニューロンが詰まって、常に活動しているのだ。小脳がリズムを調整しているのは、動きだけではない。脳のシステムのいくつかも調整し、そこが新しい情報をスムーズに流し、管理できるようにしている。ADHD患者は、小脳の一部が小さく、正しく機能していない。注意力が途切れがちなのはわけあってのことなのだ。
小脳は、前頭前野と運動皮質―それぞれ思考と動きの中枢―に情報を送っているが、その途中で大脳基底核と呼ばれるニューロンが集まった重要な場所を通る。そこは一種のオートマチック・トランスミッション(自動変速機)で、大脳皮質の要求に応じて、注意力に向ける資源を配分している。そのはたらきは、中脳の黒質から出されるドーパミンの信号によって調節されている。ドーパミンは自動変速機のオイルのようなもので、それが足りないと、注意を簡単にシフトできなかったり、つねに高速ギアに入ったままになったりする。それがADHDの人の状態だ。
科学者が大脳基底核について知っていることの多くは、パーキンソン病の研究からもたらされた。パーキンソン病は大脳基底核のドーパミン不足によって起きる。この病気は、運動機能だけでなく、複雑な認知作業の調整能力にも打撃を与える。初期段階では、そうした不調が成人発症のADHDとして表れる。
この類似は重要で、現在、神経学者は、数々の信頼できる研究に基づいて、パーキンソン病の初期段階にある患者に、病気の進行を食い止めるために毎日の運動を推奨している。ある実験では、ラットの大脳基底核のドーパミン・ニューロンを破壊して、パーキンソン病を発症させ、その半数を「発症」後10日間、毎日2回ランニングマシンで走らせた。驚くべきことに、ランナーたちのドーパミン・レベルは正常な値を保ち、運動機能も衰えなかった。パーキンソン病患者についてのある研究では、激しい運動が運動機能だけでなく気分も向上させ、そのプラス効果は運動をやめたのちも6週間以上、持続した。
とくに興味を惹かれるのは、運動と注意力の強い結びつきだ。この二つは、脳内で同じ回路を共有していて、おそらくそれゆえに、武術のような活動はADHDの子どもに効果があるのだろう。新しい動きを覚えるために、彼らは集中しなければならず、その際、運動システムと注意システムの両方が動員され、鍛えられるのだ。』
第七章 依存症 ―セルフコントロールのしくみを再生する
不当な報い
『国立薬物濫用研究所の現在の定義によると、依存症とは、健康と社会的生活に悪影響をもたらすにもかかわらず、断ち切ることのできない衝動を意味する。多くの人が薬物を濫用しているが、依存症になる人は比較的少ない。なぜだろう。薬物などへの興味が芽生え、手に入れようとするのは報酬中枢を流れるドーパミンのせいだが、どうしてもそれをやめられなくなるのは、脳の構造に変化が生じるからだ。現在、科学者たちは依存症を慢性疾患と考えている。なぜなら依存症は、反射的行動を引き起こす記憶のなかに組み込まれているからだ。依存の対象が薬物でもギャンブルでも食事でも、脳に起きる変化は同じだ。
いったん報酬が脳の注意を引くと、前頭前野はそのシナリオと感覚を詳しく記憶するように海馬に指示する。脂っこいものに目がない人の脳は、ケンタッキーフライドチキンのにおいとカーネル・サンダースのひげ、そして赤と白の縞模様のバケツを結びつける。こうした合図が「突出」し、つながって記憶されていく。ケンタッキーフライドチキンに車で乗りつけるたびに、シナプスは新たな合図を取り込んでさらに結びつきを強めていく。このようにして習慣が作られる。
通常、わたしたちがなにかを学ぶとき、その回路ができあがるとドーパミン・レベルは次第に下がっていく。しかし依存症、とくに薬物依存の場合は、薬物を摂取するたびにドーパミンがシステムにあふれ、記憶を強化し、ほかの刺激をはるか後方へ押しやってしまう。動物実験から、コカインやアンフェタミンのような薬物は側坐核の樹状突起を著しく成長させてシナプスの結びつきを増やすことが確認されている。その変化は薬物をやめたあとも数か月から、ときには数年もそのまま残ることがある。依存症が再発しやすいのはそのためだ。依存症は、脳がなにかをあまりにも強烈に学びすぎた結果だといえる。そうした適応は悪循環を招き、たとえばフライドチキンのにおいを嗅げば必ず大脳基底核が自動的に反応するようになる。いくら分別のある人の前頭前野でも、その反応を止める力はない。』
衝動と戦い、習慣を断つ
『ストレスが依存症と結びついているとき、依存物を断つと、体は生命の危険を感じる。たとえば、アルコール依存症の人が急にアルコールをやめるのはドーパミンの栓を閉めるのに等しく、視床下部-下垂体-副腎軸(HPA軸)のバランスが崩れる。依存物を断つことで生じる激しい不快感は数日で消えるが、脳のシステムは、それよりずっと長く不安定な状態に置かれる。そのようなデリケートな状態のときに、さらにストレスがかかると、脳はそれを緊急事態ととらえ、あなたにアルコールを飲ませようとする。禁酒をしていても、仕事で問題が起きたり、恋人と喧嘩したりするとまた飲み初めてしまうのはそのためだ。長く薬物に依存し、ドーパミン・システムが変わってしまっている人にとって、強いストレスに対処する最も効果的で、唯一知っている手段は薬物だ。だが、運動はもうひとつの解決策となる。
愛煙家の場合、激しい運動はたった5分でも効果がある。ニコチンは依存性物質のなかでも変り種で、刺激物でありながら同時にリラックス効果がある。運動すると、タバコを吸いたいという衝動を抑えることができる。それは、ドーパミンがスムーズに増えるのに加えて、タバコをやめようとする人が悩まされがちな不安な緊張、ストレスが抑えられるからだ。運動をすると、タバコへの渇望が50分間抑えられ、つぎに一服するまでの間隔が2倍から3倍に伸びる。さらに、運動には思考を鋭敏にする効果があることが、ここで意味をもってくる。なぜならニコチンを断つと集中力が低下するからだ。その証拠として、ある研究によると、グレート・アメリカン・スモークアウト(全米禁煙の日)には、通常より職場での事故が多いそうだ。わたしが診ているADHD患者の多くは、文書を書くときや難しい課題に向うときには、タバコを吸って集中力を高めている。そして、ニコチンが切れると集中も切れてしまう。』
ある依存症患者の物語
『彼女[ゾーエは重度のADHDで、攻撃的で、何度もひどいうつ病になり、さまざまな薬物依存症に苦しんでいた。驚いたことに、20年にわたってマリファナを常習していて、心を落ち着かせ集中するには、そうするほかはないと思い込んでいた]はときどき、サイクリング、ヨット、乗馬などをやっていたが、わたしは、定期的にできる運動をしてみてはどうかと勧めた。彼女の医学的知識を見込んで、運動すると脳の化学プロセスが変化して、気分や攻撃性や注意力、そして依存症をコントロールする回路を作り直すことができると説明した。ゾーエは、本書でも紹介した研究論文のいくつかに目を通し、毎日運動する気になった。そして、もう一度、マリファナを断った。「ほかに選択肢がなかったから」と彼女は言う。「どうしても、なにか手を打たなければならなかったのよ」
彼女が選んだのは、本格的なエアロバイクで、自転車競技者がバランス感覚を磨きスタミナを養うために使うものだ。高速で回転するドラムをこぎ、足をすべらせると弾き飛ばされかねない代物だ。ゾーエがなぜこれほど大変な運動を選んだのかはわからないが、それはすばらしい成果をもたらした。この自転車をこぐにはバランス感覚と正確さが求められ、それには小脳の運動中枢と大脳基底核から報酬中枢と前頭前野へ至る注意システム全体をはたらかせなければならない。「最初はいやいややっていたわ。こいでもどこへも行けないのだもの」とゾーエは言う。「でも今はとても重宝しているのよ。それに、運動になるだけでなく、集中できるからいいの。振り落とされないようにこぐのはドキドキするわ」
しかし、そんな折、薬物を断つにはそれだけでは足りないとでも言うのだろうか、しらふでいようとがんばっているゾーエを見捨てて、夫が出て行ってしまった。クリスマス直前のことだった。わたしは心配した。ゾーエも不安でいっぱいだった。「オランダの冬はとても寒く、とても暗いのよ」とeメールには書かれていた。「またうつになって、みじめな自分に逆戻りするんじゃないかと怖かったけれど、そうはならなかったわ。薬物を吸っていたときには負け犬のような気分だったけど、運動するようになってからは勝者のような気分になれたからよ」
長年薬物に依存していた人の常で、ゾーエは今も不安定な状態にある。だが、間違いなく正しい方向に進んでいる。ゾーエはエアロバイクをこぐ距離を延ばそうとしていて、定期的にその記録を送ってくる。それに最近では縄跳びも始めたそうだ。彼女から届いた楽しそうな手紙の一部を紹介しよう。「たった今、10分間縄跳びをしたところ。心拍数は140。きついけどやらなくちゃね。これはすばらしいわ。だって、10分縄跳びをしたら、30分自転車をこいだときと同じような気分になれるんだもの。たぶん、つづけると思う。だってすぐに報酬が得られるんですもの!! これが、最近わたしがはまっている運動よ」』
脳と運動2
今回は第三章と第四章です。なお、目次については”脳と運動1”を参照ください。
第三章 ストレス ―最大の障害
ストレスを定義し直す
『ストレスには気が張っているという程度のものから、人生のごたごたにすっかり打ちのめされているというものまである。ひどくなると、ストレスに圧倒されて心が閉ざされ、普段ならなんでもない問題がとてつもない難問のように思えてくる。その状態が長びくと慢性のストレスになり、精神的な緊張が肉体的な緊張へと変わる。ストレスが体を攻撃し始めると、不安障害やうつ病といった本格的な精神疾患や、高血圧、心臓疾患などが引き起こされ、がんになるおそれもある。慢性のストレスは脳をずたずたにすることさえあるのだ。
これほどまでに曖昧なストレスという概念を、どう理解すればいいのだろう。それには、生物学的な定義を覚えておくといい。突き詰めれば、ストレスは体の均衡を脅かすものだ。体はそれを克服するか、それに適応しなければならない。脳で言えば、ニューロンの活動を引き起こすものはなんでもストレスとなる。ニューロンが発火するにはエネルギーが必要で、燃料を燃やす過程でニューロンは摩耗し、傷ついていく。ストレスという感覚は、基本的には脳細胞が受けているこのストレスが、感情に反響したものなのだ。
椅子から立ち上がることをストレスのもとだとは思はないし、そうしたからといってストレスは感じないだろう[健常者であれば]。けれども、生物学的に言えば、それも間違いなくストレスなのだ。もちろん、失業しそうなときのストレスとは比べものにならないが、実のところ、どちらの出来事も、体と脳の同じ回路を活性化させる。立ち上がるという動作は、その動きを調和させるためにニューロンの活動を促し、失業への恐れもニューロンの多様な活動を引き起こす。感情はすべて、ニューロンが信号を送りあって生まれるからだ。同じように、フランス語を習うことも、知らない人に会うことも、そして、筋肉を動かす動作の一切も、脳に負担を強いる。すべてある種のストレスと言える。脳にしてみればストレスは全て同じで、違うのはその程度だけなのだ。』
自慢話で恐縮ですが、『ストレスは体の均衡を脅かすものだ。体はそれを克服するか、それに適応しなければならない』という一文と277ページに出てくる『年をとると、体中の細胞がストレスへの適応力を失っていく』は、私にとってたいへん興味深いものです。
それは、ブログの”がんと自然治癒力13(まとめ)”の中で、自然治癒力を【ストレス適応と栄養代謝】と定義していたからです。本書の内容は、言い換えれば「ヒトはストレスを克服あるいは適応しないと、体の均衡が崩れ健康を害すが、それは体中の細胞レベルに関係している」ということと理解でき、健康にとってストレスに対する克服、適応が極めて重要な要因であると指摘しているからです。
ストレスはあなたを殺すだけではない
『よく知られているように、筋肉を増強するにはいったんそれを壊してから休ませる必要がある。同じことがニューロンについても言える。ニューロンにはもともと修復・回復のメカニズムが備わっていて、それは軽度のストレスで作用する。運動のすごいところは、筋肉の回復プロセスだけでなく、ニューロンの回復プロセスのスイッチも入れるところだ。つまり、運動すれば、心身ともに強く柔軟になり、難問をうまく処理し、決断力が高まり、うまく周囲に適応できるようになるのだ。
定期的に有酸素運動をすると体のコンディションが安定するので、ストレスを受けても、急激に心拍数が上がったり、ストレスホルモンが過剰に出たりしなくなる。少々のストレスには反応しないようになるのだ。脳では、運動によって適度なストレスがかかると、遺伝子が活性化してタンパク質が生成され、ニューロンを損傷や変性から守るとともに、その構造を強化する。さらに運動はニューロンのストレス耐性の閾値も上げる。
この細胞の「ストレス回復」作用には、酸化、代謝、興奮の三つの側面がある。
ニューロンが作動すると、代謝メカニズムのスイッチが入る。かまどに種火が入るようなものだ。グルコースがニューロンに吸収され、ミトコンドリアがそれをアデノシン三燐酸(ATP/細胞にとって主要な燃料)に変える。その過程では、ほかのエネルギー変換プロセスと同じく、廃棄物(フリーラジカル)が生じる。その廃棄物がもたらすストレスを「酸化ストレス」と呼ぶ。通常、細胞は酵素も生成し、それがフリーラジカルのような廃棄物を掃除する。フリーラジカルは細胞組織を破壊する悪質な電子をもつ分子で、酵素は、その電子の力を消そうと懸命に掃除しつづける。こうした保護的な酵素は、人間が生まれながらもっている酸化防止剤なのだ。
「代謝性ストレス」は、グルコースが細胞に入り込めなかったり、周辺に十分なグルコースがなかったりして、細胞がうまくATPを作り出せないときに起きる。
「興奮毒性ストレス」は、グルタミン酸の活動が活発すぎて、増加した情報の流れを支えるエネルギーをATPがまかないきれないときに起きる。この状態が長引くと、とんでもないことになる。ニューロンが死の行事を始めるのだ。ダメージを修復するための食糧も資源もないまま、ひたすらはたらかされ、樹状突起は縮み、最終的にニューロンは死に至る。これが神経変性で、アルツハイマー病、パーキンソン病などの疾病、さらに老化そのものの底流となるメカニズムだ。こうした疾病を詳しく研究した結果、体に本来備わっている。細胞ストレスへの対応策見つかった。』
『連鎖的に放出される修復分子のなかでもきわめて強力なのは、脳由来神経栄養因子(BDNF)、インスリン様成長因子(IGF-1)、線維芽細胞成長因子(FGF-2)、血管内皮成長因子(VEGF)などの成長因子だ。これらについては第二章で説明した。とくにBDNFは、エネルギー代謝とシナプス可塑性の両方で役割を担っているので、ストレスを研究する者にとって興味深い因子だ。BDNFはグルタミン酸によって間接的に活性化され、細胞のなかで抗酸化剤と保護タンパク質の生成量を増やす。また、先に触れたように、LTP(長期増強)を促進して新しいニューロンを成長させ、脳をストレスに対して強くする。脳のストレス耐性を強める手段として運動が望ましいのは、それがほかのどんな刺激よりはるかに多く成長因子を増やすからだ。FGF-2とVEGFは、脳内で生成されるだけでなく、筋肉の収縮によっても生成され、血流によって脳に運ばれ、さらにニューロンを支援する。このプロセスは、体がどのように心に影響を及ぼすかをよく示している。』
【ご参考】過去ブログ:"がんと自然治癒力9”
ノーベル賞生物学者、ブラックバーン博士の著書にも、運動と回復に関する記述があります。
【ご参考】過去ブログ:"代謝と恒常性(ホメオスタシス)”

こちらの本の中に、”総まとめ代謝マップ”というものが出ているのですが、これを見ると代謝が大変複雑なものであることが分かります。
また、ブログでは白木先生の「生物科学入門 -代謝・遺伝・恒常性-」という本もご紹介しているのですが、白木先生は、“生物とは何か”という問いに対して、代謝、遺伝、恒常性の三つに集約できる。とお話されています。
【ご参考】過去ブログ:"活性酸素シグナルと酸化ストレス”
ストレスを燃やし尽くす
『脳の機能は情報をひとつのシナプスから別のシナプスへと伝えることであり、それにはエネルギーが必要とされることはすでにおわかりいただけただろう。そして、運動は代謝に影響するため、シナプスの機能、ひいては思考や感情に影響を与える強力な手段となることもご理解いただけたと思う。運動は全身を流れる血液とグルコースの量を増やす。いずれも細胞にとってなくてはならないものだ。より多くなった血流はより多くの酸素を運び、細胞はその酸素を使ってグルコースをATP(アデノシン三燐酸)に変換し、栄養源にする。運動中、脳のなかで血液の流れが前頭葉から大脳辺縁系へとシフトする。そこにはこれまでに何度も登場した偏桃体と海馬がある。おそらくそこに優先的に血流が送られるせいで、研究によってわかったように、激しい運動をしているあいだは高度な認知機能がはたらきにくいのだろう。
運動後に起きる変化によって脳は最高の働きをするようになる。闘争・逃走反応が起きる閾値が上がるだけでなく、先に述べたニューロンの回復プロセスが促されるからだ。運動によって細胞内のエネルギー生産はより効率的になり、有害な酸化ストレスを増やすことなく、ニューロンが必要とする燃料を供給できるようになる。廃棄物(フリーラジカル)も生じるが、それを処理する酵素も作られる。もちろん、DNAの残骸や細胞の分裂や老化による副産物を片づける清掃サービスもある。この酵素と清掃サービスは、がんと神経変性の発生を防ぐと考えられている。また、運動はストレス反応を誘発するが、それほど極端でなければ、システムがコルチゾールであふれかえることはない。
運動することでエネルギー利用の効率が上がるのは、ひとつにはインスリン受容体の生産が促されるからだ。体内の受容体数が多いと、血糖はよりうまく利用され、細胞は強くなる。受容体がそこにあるということは、その効率のよい新たなシステムが定着したことを意味する。定期的に運動し、インスリン受容体の数を増やしておくと、血糖値が下がったり、血流が不十分だったりしても、細胞は血液から無理矢理にでも十分なグルコースを取り出して活動をつづけることができる。また、運動するとIGF-1は海馬のなかでLTP(長期増強)を促進して、ニューロンの可塑性を高め、ニューロン新生を促している。運動はそういう形でもわたしたちのニューロンの結びつきを強めている。また運動は、FGF-2とVEGFも生成する。この二つは脳のなかに毛細血管を新しく作り、その血管網を拡大する。幹線道路が広くなり、数も増えれば、血液はよりスムーズに流れるようになる。
同時に、有酸素運動はBDNFの分泌量を増やす。これらの因子が協力しあって脳の活動を活発にし、慢性ストレスの有害な影響に負けないようにしている。それらはまた、細胞の修復プロセスを開始するだけでなく、コルチゾールが増えすぎないよう監視し、必要に応じて神経伝達物質セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンを増やす。
力学的なレベルでいえば、運動は筋紡錘(筋肉のなかにある張力センサー)の静止張力を緩めることで脳にフィードバックされるストレスを撃退する。体が緊張していなければ、脳は自分もリラックスしてもいいだろうと判断するわけだ。長期的に規則正しく運動すれば、心血管系の効率がよくなり、血圧が下がる。心臓専門医は近年、心臓の筋肉で生成される心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)というホルモンが、HPA軸にブレーキをかけ、脳の騒音を鎮めて体のストレス反応を直接抑えることを発見した。ANPの興味深い点は、運動によって心拍数が上昇するにつれ量が増えることで、おそらくANPも運動によって心と体のストレス反応が緩和される一因となっているのだろう。』
【ご参考】過去ブログ:"自律神経失調症”
【ご参考】過去ブログ:"がんと自然治癒力8”
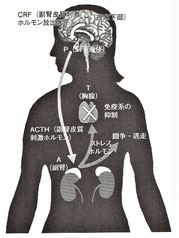
長文のブログですが、最後の方に「HPA軸」に関する記述があります。ここではその一部をご紹介させて頂きます。なお、「もう一つの防衛システム」とは免疫系になります。
身体を守るための二つの防衛システム
『多細胞生物では、神経系が、成長・増殖あるいは防衛反応をコントロールしている。環境からのシグナルをモニターし、解釈し、適切な行動で応答するように指揮するのが神経系の役割である。多細胞生物は多くの細胞からなる共同体であり、神経系は、脅威になるような環境からのストレスを認識すると、細胞の共同体に対し、危険が迫っているという警告を発する。
わたしたちの身体には、実際には、二つの異なる防衛システムが備わっている。どちらも生命維持に必要不可欠なものだ。一つは、“外部”からの脅威に対して防衛反応を引き起こすHPA系(Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis)というもので、視床下部・脳下垂体・副腎という三つの部分が連携して働くシステムである。
脅威となるものがないときはHPA系は活動せず、体内では成長・増殖活動が盛んに行われる。環境内の脅威が知覚されると、視床下部がHPA系を発動させ、脳下垂体にシグナルを送り出す。脳下垂体は「内分泌腺の総元締め」ともいえる部分で、50兆個からなる細胞の共同体の態勢を整えて、差し迫った危機に対応できるようにする。』
第四章 不安 ―パニックを避ける
証拠
『有酸素運動をすれば、不安がたちまち解消されるという事実は、ずいぶん昔から知られている。しかし、研究者がその仕組みを突き止めようとし始めたのはごく最近になってからだ。
運動すると体の筋肉の張力が緩むので、脳に不安をフィードバックする流れが断ち切られる。体の方が落ち着いていれば、脳は心配しにくくなるのだ。また、運動によって起きる一連の化学反応には気持ちを落ち着かせる効果がある。筋肉がはたらき始めると、体は燃料を供給しようと脂肪を分解して脂肪酸を作り、血液中に放出する。この遊離脂肪酸は血液中を移動する際の乗り物にするために、トリプトファン(8種類の必須アミノ酸のひとつ)と結合していた輸送タンパク質(アルブミン)を奪い取る。身軽になったトリプトファンは、浸透圧差に導かれて血液・脳関門をやすやすと通り抜け、脳に入っていく。そしてたちまち、われらが友、セロトニンの構成材料になる。トリプトファンだけでなく、運動によって増えた脳由来神経栄養因子(BDNF)もセロトニンを増やし、わたしたちを落ち着かせ、安心感を高める。
運動はガンマアミノ酪酸(GABA)分泌も引き起こす。GABAは脳の主要な抑制性神経伝達物質で、ほとんどの抗不安剤はそれに照準を合わせている。不安を自ら引き起こそうとする脳の動きを細胞レベルで食い止めるには、GABAの量を正常に保たなければならない。GABAは脳で起きる強迫観念に駆られたフィードバックの連鎖を断ち切ることができるのだ。また、運動することで心臓の鼓動が速くなると、心筋細胞が心房性ナトリウム利尿ペプチドを(ANP)というホルモンを生成し、過度の興奮にブレーキをかける。ANPは体がストレス反応を抑えるために使う道具となる。これについてはあとで詳しく説明しよう。
有酸素運動は不安障害のどんな症状も大幅に和らげることを数多くの研究が示している。さらに、運動は健康な人が普段の生活で感じる不安も和らげられる。2005年、チリの高校生のグループを対象として、9カ月にわたって運動が心と体に与える影響を測定するという興味深い研究がなされた。15歳以上の高校生198名を二つのグループに分け、一方には週三回、90分の激しい運動させ、対象グループは週に一度、通常の体育の授業を90分、受けさせた。本来この研究の目的は、運動と一般的な気分の変化の関連を測ることだったが、心理テストでは不安に関する値がひときわ目を引いた。激しい運動をしたグループの不安度は14%下がったが、対照グループはわずか3%下がっただけだ(3%はプラセボ効果によるものとして統計上無視できる数字だ)。健康レベルは実験グループが8.5%向上したのに、対照グループが1.8%の向上にとどまった。もちろんそれも偶然ではない。明らかに、運動の量と不安の度合には関連があるようだ。』
失われたつながり
『ヒポクラテスの時代には、感情は心臓から生まれるものであり、精神の病の治療は心臓から始めるべきだ、と考えられていた。現代医学は心と体を切り離したが、ヒポクラテスは正しかったことが近年、具体的に明らかにされている。心臓から生まれる分子が人間の感情にどのようにはたらきかけるかを科学者が理解し始めたのは、ここ10年ほどだ[ご参考:本書の初版は2009年]。
運動すると心筋から心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)が分泌され、それは血流に乗って脳まで送られ、血液・脳関門を通り抜ける。脳に入ったANPは海馬の受容体にくっついてHPA軸の活動を調整する(ANPは、脳内でも青斑核や扁桃体のニューロンで生成・分泌される。青斑核も扁桃体もストレスと不安に関して重要な役割を担っている)。動物および人間の実験によってANPには鎮静効果があることがわかっていて、研究者は、運動が不安に作用するのは主にANPのはたらきによるものだと考えている。2001年、不安におけるANPの役割を実証しようとする初期の研究では、不安障害の患者でパニック障害のある人とない人のグループを比較した。彼らは無作為にANPかプラセボのどちらかを注射され、その後、コレシストキニン・テトラペプチド(CCK-4)と呼ばれる消化管ホルモンを注射された。CCK-4は不安とパニックを誘発する。どちらのグループもANPによってパニック発作が大幅に軽減したが、プラセボではそうならなかった。
パニック発作のあいだ、副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)が急増する。CRFは自ら不安を誘発するとともに、神経系をコルチゾールであふれさせる。ANPは人間を混乱させようとするCRFの企てを防いでいるらしい。HPA軸にはたらきかけるブレーキのようなものだ。女性を対象にしたいくつかの研究により、妊娠中はANPのレベルが3倍になることがわかった。成長中の胎児の脳を、ストレスと不安の有害から守るために生来備わっている戦略なのだろう。
重症の心疾患の患者を対象とする研究では、ANP値が高い人は不安値が低かった。不安障害の人はいなかったが、医師たちは彼らの不安に関心を寄せていた。というのも、不安の有無が術後の回復に大きく影響するからだ。ANPは、アドレナリンの流れをせき止めて心拍数を下げることで交感神経系の反応を直接鈍らせる。また、すばらしいことに、ANPは不安という感覚も緩和するらしいのだ。パニック障害の発作が頻繁な人は、血液中のANPが不足気味だとわかっている。』
脳と運動1
脳性まひ児への施術を考えるうえで、繰り返し出てきた「脳の可塑性」とは「脳は変わる」ということです。
ブログ"アナット・バニエル・メソッド1"は"限界を超える子どもたち 脳・身体・障害への新たなアプローチ"という本を題材としたものですが、その本の中には、脳神経学者のマイケル・マーゼニック先生が"本書によせて"というタイトルで、脳の可塑性について語った文章があります。

『アナット・バニエルのアプローチは、特別な支援を必要とする子どもたちとの豊かな実践から生まれました。彼女は子どもたちの脳が変わっていくことができるのを繰り返しみてきました。子どもたちは人生に目覚め、能力を獲得し、力強く生き方を変えていきました。私たちの脳には「可塑性」があります。一生を通じて脳は変化しつづけます。
~ 中略 ~ 私は長年、「再構築する脳」の力を子どもや大人に役立てる方法を解明したいと、科学の分野で取り組んできました。数十年の研究を経て、私たち科学者は神経科学の観点から脳の可塑性を支配する「法則」を明らかにしました。そして、よりよい変化をもたらすためには脳はどのように働かせるのがよいかがわかってきました。』
「何をしたら脳の可塑性は進むのだろう?」
という疑問から本を探していたときに、見つけたのが今回のブログの題材である"脳を鍛えるには運動しかない”という本でした。
この本の評価の中には「論文の情報がない」というご意見もあり、少し気になったため、ジョン J. レイティー先生についてネット検索してみました。

John J. Ratey MD, is an associate clinical professor of Psychiatry at Harvard Medical School and an internationally recognized expert in Neuropsychiatry.

本書の最後に『1998年から毎年[初版発行は2009年]、同業者の選出による全米ベスト・ドクターのひとりに選ばれ続けている。』という記述があったため、調べて見ると日本を含め12カ国で展開されているものでした。ホームページの右上にある小さなフィールドで国名を選ぶことができます。
本書の中には個別の参照論文に関する表記はないのですが、”第十章 鍛錬 ―脳を作る” の中に次のようなことが書かれていました。
『わたしが強調したかったこと―運動は脳の機能を最善にする唯一にして最強の手段だということ―は、何百という研究論文に基づいており、その論文の大半はこの10年以内に発表されたものだ。』
ブログは最初に目次をご紹介していますが、黒太字になっている項目が取り上げたものです。なお、「第九章 加齢 ―賢く老いる」の中の「いかに年をとるか」以外はいずれも内容の一部です。
また、ブログは4つに分けており、今回の“脳と運動1”の対象は序文と第二章になります。
目次
序文 結びつける
第一章 革命へようこそ ―運動と脳に関するケーススタディ
トップクラスの成績
新しい体育
たいまつを掲げる
新しいステレオタイプ「賢い運動選手」
体にいいことは、脳にもいい
まったく新しい球技
先駆者についていこう
フィットネスを超えて
教えを広める
第二章 学習 ―脳細胞を育てよう
メッセンジャー役の物質たち
学ぶことは成長すること
最初のひらめき
環境要因と脳
可塑性を伸ばす
体と心の関係
こんな運動をしよう
第三章 ストレス ―最大の障害
ストレスを定義し直す
ストレス免疫をつけよう
警報システム
燃料を燃やす
知恵
本能と戦う
ストレスはあなたを殺すだけではない
もうたくさん!
ストレスの有害作用
ストレスを燃やし尽くす
心を守るものが体も守る
こんな運動をしよう
第四章 不安 ―パニックを避ける
エイミーのケース
防衛
証拠
恐れを恐れる
パニックの苦しみ
苦しみ抜いて
失われたつながり
恐怖に向かって走れ
恐怖から走って逃れる
こんな運動をしよう
第五章 うつ ―気分をよくする
新しいブーム
収束する生化学回路
本物のテスト
最高の処置
論理の穴
裏にある結合
絆を断つ
トンネルを抜ける
こんな運動をしよう
第六章 注意欠陥障害 ―注意散漫から脱け出す
とてつもない注意散漫
問題の兆候
大々的に、しかも曖昧に、やり遂げる
全コントロール・ユニット、注目!
初期の手がかり
エクササイズに集中する
脳を関与させる
典型的な事例
こんな運動をしよう
第七章 依存症 ―セルフコントロールのしくみを再生する
不当な報い
ふたたび自立する
ドーパミンへの渇望
衝動と戦い、習慣を断つ
ある依存症患者の物語
ランナーズハイ
よいものにこだわる
空の容器を満たす
こんな運動をしよう
第八章 ホルモンの変化 ―女性の脳に及ぼす影響
PMS―自然な変動
バランスを回復する
妊娠―動くべきか、動かざるべきか
赤ちゃんのことをお忘れなく
産後のうつ―青天のへきれき
元の自分に戻る
閉経―大きな変化
運動補充療法
こんな運動をしよう
第九章 加齢 ―賢く老いる
すべてをひとつに
いかに年をとるか
認知力の衰え
感情が乏しくなる
認知症
人生のリスト
母の教え
食事―軽く、体にいいものを食べよう
運動―規則正しくつづけよう
頭の体操―学びつづける
第十章 鍛錬 ―脳を作る
走るべく生まれついている
ウォーキング
ジョギング
ランニング
非有酸素運動
やり通すこと
大勢でやればなおよい
柔軟性を保つ
あとがき 炎を大きくする
序文 結びつける
『わたしが目指すのは、運動と脳をつなぐ驚きに満ちた科学を分かりやすい言葉で語り、それが人間の生活にどのような形で現れるかを示すことだ。そして、運動が認知能力と心の健康に強い影響力をもっているという認識を確かなものにしたい。運動は、ほとんどの精神の問題にとって最高の治療法なのだ。』
『最も見習うべき事例は、診察室の壁を越えたはるか先、シカゴ郊外の学区で見つかった。その学区で展開された画期的な体育プログラムは、今わたしが述べてきた刺激的で新しい研究と深く結びついている。イリノイ州ネーパーヴィルで取り入れられた体育の授業は、19,000人の生徒を、おそらく米国一健康にした。ある高二のクラスでは、太りすぎの生徒は3%しかいない。国の平均は30%だ。さらに唖然とさせられるのは、そのプログラムによって、学区の生徒が国内有数の頭のいい生徒へと変身したことだ。』

本書の序文の中で紹介されている、米国イリノイ州ネーパーヴィルで実施された体育プログラムに関しては、ツインデンタルクリニックさまの「健康ブログ」に、”ネーパーヴィルの奇跡”という題名で、概要が簡潔にまとめられていました。

英文の記事もありました。タイトルは"One Small Change Turned These 19,000 Students Into the Fittest and Smartest in the US"です。なお、こちらは「ORTHODOX UNION」というサイトに掲載されていました。
第二章 学習 ―脳細胞を育てよう
メッセンジャー役の物質たち
『グルタミン酸は脳の馬車馬となってはたらいているが、精神医学がそれよりも重視するのは、脳の信号操作とすべての活動を調整している一群の神経伝達物質だ。すなわち、セロトニン、ノルアドレナリン、そしてドーパミンである。それらを作り出すニューロンは、脳におよそ1000億個あるニューロンの1パーセンントにすぎないが、影響は甚大だ。ニューロンに命じてもっとグルタミン酸を作らせたり、ニューロンがより効果的に情報伝達できるようにしたり、受容体の感度を変えたりする。また、余計な信号がシナプスに伝わらないようにして脳内の「雑音」を小さくしたり、逆にほかの信号を増幅したりもする。グルタミン酸やGABAのように信号を送ることもできるが、その第一の役割は、情報の流れを調節して、神経化学物質全体の調整をすることだ。
あとの章で詳しく述べるが、セロトニンは脳の機能を正常に保つはたらきをしているので、よく脳の警察官と呼ばれる。セロトニンは、気分、衝動性、怒り、攻撃性に影響する。フルオキセチン(商品名プロザック)のような選択的セロトニン再取り込み阻害薬を使うのは、うつ病や不安障害、強迫神経症の原因となる脳の暴走をそれが抑えるからだ。
ノルアドレナリンは、気分について理解するために研究された最初の神経伝達物質で、注意や知覚、意欲、覚醒に影響する信号をしばしば増強させる。
ドーパミンは学習、報酬(満足)、注意力、運動に関係する神経伝達物質と見られており、脳の部位によって正反対の役割を果たすこともある。塩酸メチルフェニデート(商品名リタリン)は、ドーパミンを増やして気持ちを落ち着け、注意欠陥・多動性障害(ADHD)を緩和する。
精神の状態を改善するために用いる薬のほとんどは、これら三つの神経伝達物質のひとつか、あるいは複数にはたらきかける。だが、ここではっきりさせておきたいのは、そのシステムは非常に複雑なので、どれかを増減すれば決まった結果が出るわけではないということだ。ひとつの神経伝達物質を操作すると、その影響は連鎖的に広がっていき、人によって現れる効果は違ってくる。』
耳鳴り
耳鳴り保有者となって約7年です。いつもジージーいっているのですが、寝る前に「今日もけっこう鳴ってんなぁ~」などと思う程度で放置状態が続いています。鍼灸師なので、たまに思いついたように頭や耳周辺に刺鍼してみるのですが、“気”が入っていないためか、「無理じゃない?」などとネガティブに思っているためか、効く気がしません。
耳鳴りの患者さまがいないのもノンビリ構えている理由です。しかしながら、耳鳴りの患者さまが来るかも知れず、私自身のジージー・シャーシャー・キーンも無くなることに越したことはありません。
そこで、「何はともあれ、耳鳴りが何者か知ろう」ということで1冊の本を購入しました。ブログは目次をご紹介した後、耳鳴り患者の私が自分のために重要と感じた項目を7つ取り上げ、要点と思われる箇所を箇条書きにし、さらにその項目ごとに付いている分かりやすい図を貼り付けました。また、いくつか調べたことなども付け足しました。
そして、この本を拝読した結果、考えられる私の耳鳴りの原因は、①ストレス(特に長期にわたる睡眠の質の低下)、②騒音(わけあってテレビのボリュームを37にしていることが多かった)、③老化 の3つではないかと考えました。
はじめに
第1章 脳腫瘍、高血圧症……耳鳴りを放置すると命にかかわることもある
日本人の約2割が耳鳴りに悩ませている
「本当は怖い耳鳴り」と怖くない耳鳴り
「持病だから」と放置していると危険
耳鳴りはめまいと一緒に生じることが多い
市販の薬で症状は根治しない
舌がもつれたり二重に見えたりしたら注意
【コラム】耳鳴りの危険度について
第2章 耳鳴りが発症するメカニズム
聴覚系に障害が起こると症状が起きる
片側の耳に突然起こる「突発性難聴」
大音量が原因の「騒音性難聴・音響外傷」
高齢者の耳鳴りの多くは「難聴」が原因
女性に多いのは「メニエール病」
耳垢が外耳道を塞ぐことによって起きる耳鳴り
痛みがなく放置しがちな「滲出性中耳炎」
外リンパ液が中耳に漏れ出す「外リンパ瘻」
脳が「過敏」になることで症状が誘発される
意外と多い「片頭痛」による聴覚過敏
死の危険も…「脳梗塞」「脳出血」「脳腫瘍」
耳鳴りが原因で「うつ病」になることも
【コラム】耳と脳とのあいまいな境界
第3章 薬物療法、音響療法、心理的アプローチ……原因によって異なる「耳鳴り治療」
耳鼻科で行われる耳鳴りの検査
種類や音の大きさだけでは重症度を決められない
総合病院の医師は耳鳴りに無関心なことが多い
生活困難度を測るアンケート「THI」が重要
問診では耳鳴り以外の症状を伝えることが大事
耳鳴りが原因で「不眠」に悩まされる人が多い
「消える」耳鳴りと「治る」耳鳴りがある
消える耳鳴りは「伝音系」の障害によるもの
「感音系」の障害は耳鳴りそのものを治す必要がある
耳鳴りのかげには難聴が隠れていることが多い
心身のつらい症状を軽減する薬物療法
耳鳴りを気にならなくする音響方法
カウンセリングと補聴器による「TRT療法」
心因性の障害を軽減するカウンセリング
音圧を聴く「中耳加圧療法」で鼓膜マッサージ
光と電気の「キセノン温熱療法」で血行を促す
【コラム】心の問題とどう向き合うか
第4章 専門医の治療と組み合わせて早期の症状改善を目指す自宅でできる耳鳴り改善のための生活習慣
1日7000歩のウォーキングで動脈硬化を予防
こまめに水を飲んで内耳の水はけをよくする
生活リズムの乱れは耳鳴りの原因になる!
「週末に寝だめ」はNG。規則正しい睡眠を!
眠れないときは静かな音楽をかけるとよい
自分の生き方に向き合ってストレスをコントロール
リラックス効果の高い入浴法で心身を癒す
音楽のある生活が耳鳴りを軽減するという事実
「考え方」を変えるだけでも耳鳴りはよくなる
食べすぎを避け「腹八分目」の食生活を守る
カフェインを含む飲み物や香辛料は控えめに
ビタミンB12の多いレバーや貝類などの食品を摂る
お酒はほどほどにし、タバコはきっぱりやめる
難聴が原因の耳鳴りの人は補聴器を使うと快適に
【コラム】耳鳴りと生活習慣予防
第5章 耳鳴りの原因・治療法を正しく理解し、症状に悩まされない日々を手に入れる
私たちの「脳」は一部の音だけを選んで聞いている
耳鳴りは「脳」が信号の変化に戸惑っている状態
「苦痛を感じる脳」がさまざまな症状を生み出す
3つのアプローチで「脳の悪循環」を断ち切る
過敏になった「脳」が慣れてくれれば耳鳴りは治る
【コラム】もっと補聴器に親しみを
大音量が原因の「騒音性難聴・音響外傷」
●耳鳴りには騒音のある場所で長期間をすごし、徐々に進んでいく両側性の「騒音性難聴」がある。
●爆発のような大音響によって起こる「音響外傷」による耳鳴りは両側性と片側性がある。
高齢者の耳鳴りの多くは「難聴」が原因
●50歳代を過ぎて、「キーン」という高音の耳鳴りは老化現象による難聴の可能性がある。
●「老人性難聴」は音を電気信号に変える内耳の機能が、低下してくることが原因である。
●「老人性難聴」に伴う耳鳴りの完治は非常に難しい。耳鳴りに慣れることが求められる。
耳鼻科で行われる耳鳴りの検査
●ティンパノメトリー(ティンパノグラム)
ティンパノメトリーは、鼓膜がうまく振動しているかどうかを調べる検査。
●オーディオグラム(純音聴力検査)
オーディオグラムは「気導聴力」と「骨導聴力」を測定し、2つの検査結果から難聴の種類を判定する検査。
●固定周波数ピッチマッチ検査
ピッチマッチ検査とは、患者さんが感じている耳鳴りの音の高さを調べる検査。
●連続周波数ピッチマッチ検査
さらに詳しく耳鳴りの高さを調べるのが連続周波数ピッチマッチ検査。
●ラウドネスバランス検査
耳鳴りの音の大きさを調べるのがラウドネスバランス検査。
ここで、ためしに“固定周波数ピッチマッチ検査・さいたま市・耳鼻科”で検索してみたところ、「耳鳴り外来」というものがあるのを知りました。
そこで、次に“耳鳴り外来”で検索してみました。するとデンマークの補聴器メーカーであるワイデックスさまのサイトに「耳鳴りの専門的外来を実施している医療機関」という病院を紹介されているページがありました。なお、このページは”2018年9月6日現在”となっています。
このページには、ブログ“めまい”にも登場された、さいたま市のとくまる耳鼻咽喉科さまが掲載されていました。念のため、どのような検査を行っているのか調べてみると、“THI(質問票)”で現状を把握し、“標準純音聴力検査”と“ティンパノメトリー”を用いて検査を行っているようです。
なお、上記の星野耳鼻咽喉科さまも、「耳鳴りの専門的外来を実施している医療機関」の中にありました。
「消える」耳鳴りと「治る」耳鳴りがある
●耳鳴りには病気の治療とともに消失するものと、消失はしないけれど気にならなくなるものがある。
●音の振動を伝える伝音系の器官(外耳や中耳)に原因がある耳鳴りは消える場合が多い。
●音の振動を電気信号に変えて伝える感音系(内耳から脳神経にかけて)に原因がある耳鳴りは消えにくい。
●原因不明の耳鳴りや加齢に伴う耳鳴りは、消えるということはあまり期待できない。
なお、「治る耳鳴り」とは、耳鳴りに慣れ気にならなくすることを目指すものです。
消える耳鳴りは「伝音系」の障害によるものある
●伝音系の障害には、外耳道をふさぐ耳垢栓塞や鼓膜の動きを悪くする中耳炎、耳管狭窄症などがある。
「感音系」の障害は耳鳴りそのものを治す必要がある
●感音系の障害は加齢による機能低下や、騒音ダメージなどなんらかの原因で「有毛細胞」の働きが低下したためと考えられる(有毛細胞:内耳に存在している蝸牛管の壁にあるコルチ器の中の感覚細胞)。
●感音系の耳鳴りは、蝸牛で生じた電気信号を伝える「聴神経」や、信号を受け取る脳の「聴覚中枢」の機能が低下しても起こる。
こまめに水を飲んで内耳の水はけをよくする
●内耳の水分代謝は脱水状態のときなどに悪くなりがちであり、そのために耳鳴りが起こる場合もある。水分摂取はこまめに飲むことがポイント。
●メニエール病では、北里大学医学部の長沼英明教授が推奨している「水分摂取療法」は大きな効果を上げている。
脳卒中のリハビリテーション
業務委託による訪問の仕事では、脳梗塞や脳血管障害による後遺症のため、日常生活に大きな支障を抱えている患者さまやベッドから起き上がることができない患者さまに、マッサージや関節拘縮予防のための他動運動(施術者が可動域確保のため適切な強度で各関節を動かす)、歩行支援などを行っています。
もっと効果的な施術はないだろうかという思いから、『脳がよみがえる 脳卒中・リハビリ革命』という本を読んだことがありましたが、この本は2011年9月4日放送の“NHKスペシャル”の書籍版になります。

『約280万人にのぼる脳卒中患者、医療の発達で命を落とすケースは減ったものの、マヒの問題は深刻で、介護が必要になる原因の第一位だ。解決にはリハビリが重要だが、発症後6ヶ月を超えたあたりから効果が落ちるとされてきた。しかし最近、脳科学の急速な発達により、傷ついた脳が再生するメカニズムが次第に明らかになり、時間を経過した患者でも、マヒを改善する手法が発見されている。リハビリの効果を上げる誰でも出来る意外な方法や、脳波とマシンを連動させる最新科学まで、脳卒中リハビリの最前線で起きている急激な変化を取材、人間の脳に秘められた驚きのパワーに迫る。』
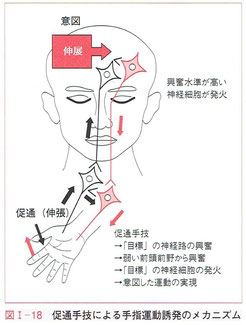
右下に→の説明書きがありますが、下2つの矢印(「目標」の神経細胞の発火・意図した運動の実現)の色は本来、赤→になっているべきものだと思われます。
以下の4つのイラストは脳卒中になった時に起こるからだの変化です。3つめのスライド(下段左)には「脳卒中になると通行止めが外れ、脇道を通れるように」との解説がついているのですが、そのようなメカニズムが備わっているとは驚きであり、大きな発見でした。
画像出展:「脳がよみがえる 脳卒中・リハビリ革命」
そして、今回読んでいる『脳の中の身体地図』の中にも脳卒中の麻痺について書かれた箇所がありました。ここに書かれている内容は脳のリハビリテーションへの理解を深めるうえで価値があると思います。
脳卒中による麻痺の回復
『スコット・フライには人生をかけた使命がある。多発性硬化症を患いながらも女手ひとつで育ててくれた母親が、麻痺が首から下まで進んだために人生の最後の14年を車椅子で過ごす姿を、彼は目の当たりにしてきた。「神経科学者の卵である僕が付いていながら、何ひとつできなかった」とフライは言う。
しかし、今はもう違う。実験心理学者としてのキャリアのギアを入れ直したフライは、2004年、ダートマス大学からオレゴン州立大学に移り、現在はリハビリテーション神経科学センターの設立に全力を注いでいる。要するに、脳の働きに関する最新知識を活かして、脳卒中や脊髄損傷、四肢切断後の人々を起き上がらせ、動かそう、大勢の人々を車椅子の生活から解放しようとしているのだ。彼の目標は、“朝が待ち遠しくなるようなことにする”ことだそうだ。
フライがまず目を向けたのは脳卒中患者である。脳卒中は、動脈内の血栓や動脈瘤破裂が原因で、脳の一部への血液供給が断たれた場合に起こる。問題の動脈が栄養を運んでいた脳領域は、酸素の供給を受けられなくなるため、崩壊ないしは損傷の道をたどる以外にない。標準的な治療法は“経過観察”だ。数日あるいは数週間後に、脳の損傷の程度を調べるわけである。損傷を負った脳の領域によって、麻痺や失明、言葉を話せない、理解できない、道具を使ったり見分けたりできない、身体の周りの空間を認識できないといった障害が現れる。損なわれた、あるいは失われたボディ・マップとかかわりのある特異な欠損症状がいくらでも出てくる可能性があるのだ。
もちろん、もうおわかりのように、大人の脳にも可塑性がある。新規な事物や練習、損傷に応じて、それに適応するように自らを再構築することができるのだ。先ほど紹介したのとは別の、マーゼニック[マイケル・マーゼニック(脳科学者)]の初期の実験のひとつが、そのことを証明している。この実験では、サルの脳にある別の腕のマップを傷つけたが、それに対応する腕は無傷のままにしておいた。すると、サルが腕を使い続けるうちに、マップが元の状態に戻ったのだ。大勢の脳卒中患者が、すべてとは言わないまでも、ある程度は運動機能を取り戻せる理由がここにある。時間が経てば、脳の損傷したマップは再構築される可能性があるということだ。
脳卒中患者は普通、脳固有の可塑性が本来の仕事をするのを容易にし、促進するための理学療法と作業療法に一か月を費やす。これは、何かの動作―たとえば、ドアノブに手を伸ばす、カップを持ち上げる、ボールを握るといった―を幾度も繰り返しているうちに、既に学習していることを補強する新しい神経接続が育ってくるという発想だ。理学療法の目的は、神経可塑性のメカニズムを後押しして、機能マップを回復させることにある。この再マッピングのプロセスを改善するために、ありとあらゆる新技術や手法が開発されている。“悪いほうの腕”を使わざるを得なくするために、“良いほうの腕”をストラップで固定してしまう方法、麻痺した腕や脚の存在を脳に“実感”させるために、腕や脚に電気刺激を与える方法、繰り返し運動を続けてもけっして疲れることのないロボット装置に使い物にならなくなった腕や脚をストラップで固定する方法などなどだ。
しかし、半年が過ぎると、部分的であれ完全であれ、回復しない患者はほぼ例外なく、あきらめて自分の限界を受け入れるほうがよいとアドバイスされる。もう良くなる見込みはないと言われる。それが現実だ。ただし、フライを知らなければの話である。脳卒中後の麻痺を回復に向かわせるか改善するには運動イメージが役立つと、フライは考えている。一次運動マップ―脊髄を下って身体を動かす指令を発するマップ―は、運動イメージを行っている間は一時的にオフラインになることを思い出していただきたい。ところが、高次の運動マップは、その間もフル回転で働き続け、あなたがイメージしている動作をきちんとエミュレート(訳注:ある機能を本来とは異なる手段で再現すること)している。
脳卒中患者のこうした高次運動野のマップが損なわれておらず、健全であるかどうかを確認するための手段として、フライは一連の暗示的な運動イメージ課題を考案した。暗示的というのは、被験者たちはイメージを思い浮かべることを特に要求されているとは思わないままに、課題を行うことになるからだ。まず、三次元方向から表示したハンドルバーのような物体の図を被験者たちに見せる。そして、どの方向からが一番握りやすいと思うか尋ねるわけだ。あなたなら上から握る? それとも下から? 親指はどこにかける? 残りの指の位置は?
予備試験には、腕を動かせなくなって1~5年が経過している患者三人を採用した。そのうちの一人は76歳の男性である。彼には、自宅の大画面テレビでさまざまな物体を眺めて、メンタル・イメージによって物体の握り方を練習するという課題を与えた。彼はこれを1日1時間、週5日、9週間にわたって続けた。
「彼に運動機能が戻らないことはわかっていた」とフライは言う。「でも、脳の編成に何か違いが出てくるとしたら?」
違いはあった。事実、三人の被験者全員が、心の中では正常な手の生体メカニズムに則った腕の運動を正確にシミュレートすることができたのだ。彼らは実際にするのとまったく同じに、ひとつひとつの物体をつかむところをイメージした。しかも、そのイメージの最中に彼らの脳をスキャンしたところ、運動の模倣と計画にかかわる高次領域、つまり人間の“腕を伸ばすための回路(リーチ回路)”が賦活したのだ。
さて、ここで思い出していただきたいのだが、脳卒中後には、一次運動マップそのものが損なわれることもあれば、より大きな回路の一部としての一次運動マップに支障をきたすこともあるということだ。すると、脳は四肢に指令を伝えないし、四肢も脳にフィードバックしようとしない。そこでフライは考えた。運動イメージを利用して、損なわれた一次運動マップに可塑的変化を起こさせ、促進したらどうだろう? イメージは、首尾良い運動シーケンスをコード化する機会を、脳に与えることができないだろうか? 麻痺状態から抜け出した自分をイメージすることはできないか?
答えは“ひょっとすると”である。フライによれば、予備的証拠は有望だが、そうした治療法の可能性を検証するための研究は始まったばかりだ。』
ボディ・マップが混乱する前に
『フライは、腕や脚を一本以上失ってイラクとアフガニスタンから帰還した兵士たちの苦悩もよく理解している。こうした兵士たちの数は2007年初頭で500人を数え、まだ増え続けているのだ。技術者たちがより軽量でより付け心地の良い材料を求めて懸命の努力を続けており、アメリカ国防総省も生体の腕の特性をほぼすべて備えた義肢の研究に資金を提供しているのだが、人口の腕、脚、手は未だにずっしりと重い枷になっている。収縮する胸筋にセンサを取り付けて義腕を操作するというような独創的な工学的解決策もいくつかあるが、その動きはまだぎこちない。
最近の退役軍人は除隊になるとき、三本の腕を支給される。実物そっくりだが機能面ではほとんど何も期待できない装飾用の義腕が一本、マイクロプロセッサで残っている筋肉からの電気信号を拾い上げて増幅し、電動モーターを作動させて腕の運動機能を生み出す筋電義腕が一本、そして、背中に渡したケーブルなどで身体の動きによって操作する、機械的な義腕が一本である。退役軍人は弓矢を使う狩猟など、特殊用途の義腕をオーダーすることもできる。
それにもかかわらず、フライによると、義腕を付けた患者の半数は、一年以内に義腕をクローゼットに放り込んでしまうそうだ。義腕はコントロールするのが難しいし、たいていのことは切断した腕の残った部分と良い側の腕を使うほうが楽に片付けられると、切断患者たちは口を揃える。義腕は15,000ドルもするうえに、保有率があまりにも悪いため、保険会社も義腕のための給付を遅らせている。
もっと良い方法があるはずだ。山積している問題は機械的要因によるものなのに、技術者たちは身体を機械と接続するうえで最も重要な面を見落としている、とフライは言う。脳である。四肢を失った後は、脳の大幅な再編が起こる。患者に義肢を装着させる際は、その事実を中心に考えなければならない。神経可塑性のプロセスがその場しのぎの新しいボディ・マップを手探りしながら試行錯誤するのに任せて、無駄に費やす時間が長くなるほど、マッピングはうまくいかず、義肢との統合が難しくなる。
運動機能不全につながる再マッピングを最小限に抑えるために運動イメージを使えないものか? フライはそう考えている。たった今も、新しい腕の使い方のトレーニングを受けている患者はほとんどいないとフライは訴える。彼らは家に帰って、自分で何とかしなければならない。しかし、運動イメージを利用して高次運動マップを刺激してやれば、義肢への適応に役立つ可能性がある。「運動学習に関する知識を総動員すれば、リハビリにつなげることができる」とフライは言う。「異常をきたした可塑性にボディ・マップを混乱させるすきまを与えないように切断後すぐ、患者に義肢を装着させるというのは、すごい名案じゃないですかね。イメージ回路を使って運動を練習すれば、高次マップを義肢のコントロールに使えるようになるのですから」
フライは今、上肢切断患者30人を対象として、イメージにより運動をシミュレートする能力をどこまで保持できるかという研究をしている。脳卒中患者とは違って、切断患者は運動をイメージするときに本物の腕を見ることができない。そこで、彼らにはミラー・ボックスを自宅に持ち帰らせている。良いほうの手を箱に入れて振りながら、鏡に映っているのは、実際にはもう無い手だと想像してくださいという指導付きだ。彼の研究チームは、そうした鮮明なイメージに反応してどんな変化が起きるか、切断患者たちの運動マップを長期にわたって追い続けるつもりでいる。』
「12年近く経った今(原書の発行は2007年9月)、退役軍人の義肢の問題どうなっているのだろう?」という疑問から、“アメリカ 軍人 義肢”で検索したところ次の記事が現れました。

CNET Japanさまの2013年10月24日の記事です。
”思考で制御できるバイオニック義足--急速に進化する義肢技術”
『SF作品に出てくるような話に聞こえるかもしれない。実際の手足のように動いたり、曲がったり、感じたりするだけでなく、人間の思考に直接的に反応し、さらに感覚フィードバック(足下の草の感触や手足が空中に浮かんでいる感覚)を脳に直接返すことさえできる義肢が開発されている。
負傷した退役軍人の生活向上に取り組んでいる米軍が、資金面で積極的に支援しているため、そうした義肢はもはや現実離れした夢物語ではなくなった。映画「ブレードランナー」並みの補綴術というのは今でも遠い未来の空想だが、シカゴリハビリテーション研究所(Rehabilitation Institute of Chicago:RIC)と米国防高等研究計画局(DARPA)、そして成長分野である次世代義肢を開発する企業セクターの先駆的な研究により、見事な性能を備えた思考制御型バイオニック義肢が現代の現実となっている。
RICは9月、同研究所のバイオニック研究によって初の思考制御型ロボット義足を生み出したことを発表した。RICの研究はこれまでも、その価値にふさわしい報道をされており、何度も記事の見出しを飾っている(1つの人工装具で103段の階段を上ったという事例もある)。しかし、Levi Hargrove博士が率いるチームは、決定的な研究成果をThe New England Journal of Medicineに発表するのを待っていた。8年以上前に開発が始まったそのバイオニックハードウェアは、標的化筋肉再神経分布(Targeted Muscle Reinervation:TMR)手術という画期的なアプローチと統合された。TMR手術は、神経を健康な筋肉へ再分布することによって、脳がバイオニック義肢のさまざまな部分を動かせるようにするものだ。』
以下は、標的化筋肉再神経分布(Targeted Muscle Reinervation:TMR)で検索して出てきたものです。
ここで頭に浮かんだのが、以前、テレビで見たことがあった ”HAL” です。
調べてみると、このHALを開発したのは筑波大学の山海嘉之先生であることが分かりました。また、『サイバニクスが拓く未来』という著書が出ており、幸いにも市内の図書館に所蔵されていたため、借りてみることにしました。

著者:山海嘉之
出版:筑波大学出版会
発行:2018年3月
下左の写真はHALを使っての治療の様子です。また、下右のイラストはHALの原理です。HALの最も凄いところは、HALを使うと脳・神経が回復しているという画期的なリハビリテーション効果です。
この本は「PART1 講和 未来開拓への挑戦」と「PART2 質疑応答 中高生と大いに語る」に分かれています。PART1は更に5つ分かれていますが、4つめに「神経難病分野での医療用HAL」があり、4つの事例が紹介されています(“ポリオ”、”脳卒中”、”脳性小児麻痺”、”脊髄性筋萎縮症”)。ここでは脳卒中の事例と、機能改善と脳機能との関係について書かれた箇所をお伝えします。
『脳卒中を2回も発症されて、お医者さんのカルテでは、もう歩行は厳しいと言われていた患者さんです。HALを使っていくうちに、HALをはずしても1ヶ月後には歩きはじめ、さらに続けてHALを使っていくと、2ヶ月後にはHALなしで廊下をジョギングできるようになりました。その後退院して、今ではジャンプもしています。すごいですね。大切なことは、HALをはずしても動くことです。機能が改善して、これで退院できるようになります。このとき脳がどのように動いていたかということが重要で、病気が発症した早い段階できちんとHALを使うと、脳が最初の状態から変わっていくこともわかりました。とにかく、驚くことが多く、感動の日々です。』
『こうして機能が改善していくことと、脳機能はどう関係しているでしょうか。実は、こうして脚を動かして徐々に歩けるようになってくると、脳の状態も変わってくることがわかりました。fMRI(機能的磁気共鳴画像装置)という高価な装置で脳活動を調べていくと、身体が動かない状態では、脳は動かない身体を動かそうと頑張りすぎて、次第に脳はいろいろなところが活発化していきます。これは「過活動」といって、本来活動すべき箇所とは異なるところも活動しはじめてしまうという状態です。あまり良いことではありません。つまり、頑張りすぎは良くないということですね。身体を思うように動かせなかったこのような状態にある患者さんでも、HALを使うと、脳の中の適切なところが興奮した時だけ、HALは脳から筋肉への指令信号をキャッチするので、意思に従って動きはじめ、脳神経系のつながり(シナプス結合)を強化・調整するための機能改善・機能再生ループが、人とHALの間で構成されます。こうして、どんどん脳や神経系の機能改善が進み、本来の適切な部分の脳活動と連動して脳神経系と身体系の機能が改善いていくのです。これらの事例は、脳の中で何が起きているかを示す貴重なデータとなっているのです。実に興味深いですね。別の言い方をすれば、HALは、コネクトーム(脳の機能マップ)の再構築を促進する革新技術だとも言えるでしょう。
今、進行性の神経筋難病という現代医学では治療方法が見つかっていない病気に対して、治験を行っていますが、この治験の結果、薬でも病気の進行を抑制することができなかった難病に、医療用HALが保険治療として適用できると期待しています[参考:2016年9月から保険適用による治療が始まっている]。この治療が終われば、さらにほかの分野にも適用が広がるだろうと思っています。喜んでくれる人が待っていてくれる限り、私たちの挑戦は続くのです。』
HALによる治験が行われているのも確認できました。
大和ハウス工業さまに「HALを見学できるところはありますか?」と問い合わせたところ、茨城県つくば市にある『サイバーダイン スタジオ』という素晴らしい施設を教えて頂きました。
ミラー・ボックスによる運動機能の改善
『ウィリアム・アンド・メアリー大学の認知科学者、ジェニファー・スティーヴンスによると、脳卒中後は、まるで自分の腕のマップを一部しか利用できなくなったように、運動の協調性を失ってしまう人が多い。ミラー・ボックスや運動イメージを使って運動をシミュレートすることにより、運動を取り戻すうえで必要なものの例を脳に示してやる。手を物理的に延長できなければ、脳は運動を練習するチャンスをけっしてものにできない。イメージによるシミュレーションは、この問題を解決するための手段なのだ。
あなたが脳卒中を患ったとしよう。良いほうの腕を箱に差し入れ、麻痺した腕は鏡の裏に隠す。切断した腕の場合同様、良いほうの腕が鏡に映って、腕が二本あるように見える。良いほうの腕をバタバタと動かしてみると、すごいことが起こる。麻痺した腕が突然動き出したように見えるのだ。無傷で損傷も麻痺もないように見える。身体の曼荼羅を下って、休眠中の腕と手のマップに固有感覚を引き起こすほど説得力のある視覚フィードバックが生じているのだ。
パイロット実験で、スティーヴンスは慢性脳卒中患者五人を研究室に呼んでコンピュータの前に座らせ、目の前の机に、手のひらを下にして両手を載せさせた。そして、ひねる運動をしている手首の運動を見せてから、自分の悪いほうの手首で同じ運動をしたらどのような感じがするかイメージし、見てはイメージしを繰り返した。ミラー・ボックスを使った手首の運動の練習も、一時間のセッションとして週三回、四週間行わせた。良いほうの腕を箱に入れて、手首滑らかに動かすことで脳をだまし、悪いほうの腕でも同じことができると信じ込ませたわけである。それと並行して、同じレベルの麻痺がある別の五人の患者には、従来の作業療法に取り組ませた。
どちらの被験者群にも、軽い物を棚に載せられるようになるほどの、同じ程度の改善がみられた。しかし、スティーヴンスに言わせれば、これは実に驚くべきことだ。こう考えてみるとよい。イメージ法を行ったグループは、障害のある腕を実際には少しも動かそうとしなかったのに、改善したのだ。標準作業療法では、麻痺した手でカップをつかんでは離すという練習を何時間もぶっ続けで行う。イメージ法の被験者群も同じことをしたわけだが、筋肉は一切動かさなかった。損傷したニューロンがちょうど再接続する場所を探しているところなので、イメージと鏡でそれを可能にしてやるのだとスティーヴンスは言う。
彼女はこの種の治療法を、自宅療法にうってつけと言う。退院直後の脳卒中患者の中から選んだ人々にミラー・ボックスを提供しているのはそのためだ。既に自宅療法プログラムを終了した患者四人を見る限りでは、自己流のイメージ・プロトコル(手順)でも運動能力は改善するらしい。だとしたら、試さない手はないのでは? 駄目でもともと、どちらに転んでも損はない。
ほかに、バーチャル・リアリティを活用している科学者たちもいる。これは、コンピュータでシミュレーションした環境と情報のやりとりを行うことにより、脳卒中患者の脳が再マッピングできるようにする技術である。患者はバーチャルな世界に浸ったまま、運動機能の回復の呼び水となるような形で正常な運動をイメージする。麻痺した腕や脚に取り付けた装置を介してフィードバックが行われれば、脳がその運動を再学習できることもあるという。』
最新情報はないだろうかと思いネット検索してみると、『運動機能回復を目的とした脳卒中リハビリテーションの脳科学を根拠とする理論とその実際』という論文を見つけました。

『運動機能回復を目的とした脳卒中リハビリテーションの脳科学を根拠とする理論とその実際』(PDF11枚)
しかし、これも2010年なので新しいものではありませんでした。そこで、発行元の“相澤病院”と著者の“井上勲”というキーワードから検索をかけたところ、下記の“福岡青州会病院”というサイトが出てきました。調べてみると2010年当時相澤病院のリハビリテーションン科医長だった井上先生はこちらの病院に勤務されていることが分かりました。また、脳卒中などのリハビリテーションに非常に積極的な病院であることも分かりました。

『福岡青洲会病院では、地域の皆様に継続的に科学的根拠に基づいた質の高い リハビリテーションの提供を可能とするため、「先進リハビリテーション実践センター“HOPE”」を設立いたしました。先進リハビリテーション実践センターでは、下記に示すチーム毎に組織横断的に多職種でのチームを組織し、研究も含め患者さんに質の高いリハビリテーションの提供を目指します。』

画像出展:「福岡青洲会病院」
ミラーセラピーに関しては、大阪府和泉市にある生長会 府中病院さまのサイトに詳しい紹介が出ていました。

画像出展:「生長会 府中病院」
まとめ
1.人には「脳卒中になると通行止めが外れ、脇道を通れるように」という仕組みが備わっている。
2.大人の脳にも可塑性があり、損傷に応じてそれに適応するように再構築することが可能である。
3.理学療法の目的は神経可塑性のメカニズムを後押しして、機能マップを回復させることにある。
4.脳卒中後の麻痺を改善するには運動イメージが役立つ。
5.運動イメージを利用して高次運動マップを刺激してやれば、義肢への適応に役立つ。
めまい
4月末、業務委託の方の仕事でめまいの患者さまに施術を行いました。発症後3日目、まだ回転性めまいが止まらないということでした。耳鼻咽喉科、総合病院の内科を受診され、めまい止めと吐き気止めの薬を処方されたものの、めまいは改善されず、明確な病名も明らかになっていない状況でした。
気になる所見は2つです。1つは両眼の焦点が合わないということが3回程あったこと。もう1つは、めまい後に左肩と右肩甲骨付近に鈍痛が発生した。ということでした。
私の勉強不足によるのですが、「もしや耳ではなく、目が原因ということはないだろうか?」という疑問から、時々お世話になっているAskDoctoresという有償サイトに質問をしてみました。その結果、目が原因でめまいを起こすことはないということを確認できました。また、ご回答頂いた先生の中に(内科医)、「めまい外来を検討されると良いと思います」というご指摘がありました。
そこで、早速、さいたま市で検索してみると、岩槻区に目白大学耳科学研究所クリニックがあることを知りました。
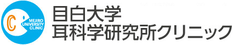
『当院ではめまい診療のエキスパートが、チームを組んで診療にあたっております。最新のバランス機能検査機器や高度な診断技術により、めまいやふらつきの原因を的確に調べ、長引くめまいやふらつきの根本的な治療や緩和、予防に取り組んでいます。』
こちらのサイトでは、問診票がダウンロードできるのですが、その質問の中には、「焦点が合わない」、「首や肩の痛みがあった」という質問もありました。この問診票を見て、こちらのクリニックの存在を患者さまに情報提供できていればという思いが残りました。
なお、肝心の治療は30分ということもあり、後頚部と腰部(特に仙骨部)、そして耳周辺の“翳風”というツボに約20分間の置鍼をしましたが、残念ながら、その場で回転性めまいを止めることはできませんでした。その後、この患者さまから連絡が入ることはなかったため、改善されたのかどうかは分かっていません。
そして、今回の知識不足、情報不足を反省し、見つけたのが『めまいは自分で治せる』という本でした。この本は4章に分かれています。ブログで取り上げたのは「第1章 なぜ、めまいがリハビリで治せるのか?」と「第3章 病気別リハビリ&めまいを克服した体験手記」です。ポイントと思った箇所を要約し箇条書きにしています。
めまいで辛い思いをされている方には、「第2章 めまいのリハビリ実践編」と「第4章 めまいを起こさない生活術」、さらに第4章の後ろにある「めまい なんでもQ&A」に関心があるものと思いますが、ブログでは触れておりません。
目次は次の通りです。
はじめに
第1章 なぜ、めまいがリハビリで治せるのか?
「グルグル回る」「フワフワする」「体が揺れる」「立っていられない」
めまいが起こったときの対処法
めまいを治す医師の見きわめ方
めまいの検査は何をする?
めまいはなぜ起こるのか?
小脳はバランスをつかさどる「パイロット」
苦手なリハビリこそ積極的に行う
一時的にめまいが悪化しても大丈夫
第2章 めまいのリハビリ実践編
リハビリで8000人のめまいが改善した
効果的なリハビリのコツ
リハビリを行う際の注意点
【めまいに効く8つのリハビリ】
①「速い横」
②「ゆっくり横」
③「振り返る」
④「上下」
⑤「足踏み」
⑥「片足立ち」
⑦「ハーフターン」
⑧「寝返り」
症状別リハビリ索引
第3章 病気別リハビリ&めまいを克服した体験手記
めまいの原因がわかるフローチャート
良性発作性頭位めまい症
前庭神経炎
メニエール病
めまいを伴う突発性難聴
片頭痛性めまい
持続性平衡障害・加齢性平衡障害
ハント症候群
慢性中耳炎が原因のめまい
椎骨・脳底動脈循環不全症
脳梗塞・脳出血の治療後に残るめまい
心因性めまい・めまいをともなう「うつ」状態
第4章 めまいを起こさない生活術
めまいを起こしにくい体をつくる
①睡眠
②アルコール
③タバコ
④コーヒー
⑤食事
⑥自動車の運転
⑦外出
⑧入浴
⑨家事
⑩運動
⑪女性ホルモンの変化
コラム① めまいと骨密度の関係
「前兆」を知ってめまいを未然に防ぐ
①カゼなどの体調不良
②低気圧の接近
③過労・多忙
④精神的なダメージ
⑤その他の前兆
コラム② 「地震酔い」は気のせい?
めまい なんでもQ&A
おわりに
参考文献
新井先生が勤務されている病院のめまい平衡神経科のページをご紹介します。

『わたくしの所属する横浜市立みなと赤十字病院めまい平衡神経科には、北海道から沖縄まで、全国津々浦々のめまい患者さんが治療を受けにこられます。しかしさまざまな事情から、当院を受診されることが困難な患者さんも沢山いらっしゃいます。実際、わたくしの下にも、拙著をお読みになったり、当院のめまい体操を紹介するテレビ番組をご覧になったりして、日本中から連日多くのお問い合わせをいただきます。出来ることならば、すべてのみなさんに通院・入院加療を経験していただきたいのですが、それはなかなか難しいことです。そこで、通院・入院したいけれど出来ない患者さんたちのために、いくつかの拙著(めまいは寝てては治らない:中外医学社他)を書くことで、当院で行っているめまい体操を多くの患者さんに知っていただきたいのです。』
はじめに
薬物治療
●脳や内耳の血流を増やしてめまいを改善する薬。
●吐き気や嘔吐を抑える薬。
●内耳のむくみを軽減する薬。
第1章 なぜ、めまいがリハビリで治せるのか?
「グルグル回る」「フワフワする」「体が揺れる」「立っていられない」
●横浜市立みなと赤十字病院の救急外来の統計によると、交通事故やヤケドなどの外傷を除く15,563例のうち、約6%がめまいによるもので、2年間で884名だった。
●めまいの起こり方は、「回転性めまい」「浮動性めまい」「動揺性めまい」「立ちくらみ」の4つに分けられる。
●回転性めまい
・三半規管の障害で起こるのがほとんど。
・症状は数分間から数時間。
●浮動性めまい
・体がフワフワするなど。
・症状は回転性ほど激しくないが症状が長引く傾向がある。
・回転性めまいの慢性期、加齢、耳石の障害などが原因。
●動揺性めまい
・頭や体がグラグラ揺れている感じでまっすぐに歩けない。
・原因不明とされることが多いが、加齢、三半規管の機能低下、小脳の障害でみられる。
●立ちくらみ
・耳や脳の障害、低血圧、睡眠不足、疲労などが原因。
めまいが起こったときの対処法
●座れる場所、横になれる場所を移動し、ゆっくり深呼吸をして呼吸を整える(過呼吸[過換気症候群]にならないように注意する)。
●嘔吐の可能性を考え横向きが良い。
●原因が内耳の障害の場合は悪いほうの耳を上にする。
●同行者がいれば、「乗り物酔いの薬」を買ってきてもらい、それを飲んで様子をみる。
●嘔吐がひどくて薬が飲めないときは我慢せずに救急車を呼ぶ。
めまいを治す医師の見きわめ方
●めまいは疲労の蓄積、睡眠不足、カゼなどで体調をくずした時にも現れる。
●症状が長引いたり、悪化したり、くり返し起こる場合は専門医に相談する。
●基本は耳鼻咽喉科だが、最近は「めまい外来」「神経耳科」などもあり、より的確な治療が受けられる。
●めまい専門医の研究会である「日本めまい平衡学会」では、学会が認定した専門会員と、めまい相談医をホームページに掲載している。

【めまい相談医一覧】を調べたところ、さいたま市で相談医が在籍している病院は、岩槻区の「目白大学耳科学研究所クリニック」、西区の「おくクリニック」、南区の「たかまつ耳鼻咽喉科」の3つでした。
めまいの検査は何をする?
●必ず行う目の検査。眼球が無意識で動く「眼振」があればめまいを起こしていることがわかる。
●耳が原因の「末梢性めまい」か、脳による「中枢性めまい」かは、眼球の動きで診断する。
●末梢性めまいでは水平方向の眼振か、回旋が混合した眼振が見られる。
●中枢性めまいの垂直方向の眼振は脳の異常によるもので、CTなどの検査を行う必要がある。
●眼振の検査では「フレンツェル眼鏡」という特殊な眼鏡を使うのが一般的であるが、より精度の高い「赤外線CCDカメラ」を使った検査も徐々に普及してきている。
めまいはなぜ起こるのか?
●体のバランス(平衡機能)は、視覚(目)、深部感覚刺激(足の裏)、前庭器(耳)という3カ所から集まる「バランスに関する情報」を小脳が集約し、それを全身の中枢である大脳が統括することによって保たれている。
視覚は周囲の景色や動きを見ることで、体の位置や動きなどを感じ取り、深部感覚刺激は足の皮膚からの情報が脊髄を経て脳へ伝わり、同じく体の位置や動きなどを感じ取っている。これに加えて、なくてはならないのが前庭器の働きである。耳の奥の内耳にある前庭器では平衡機能を維持するために、最も重要な情報を感知している。
●内耳は聴覚をつかさどる「蝸牛」、平衡機能をつかさどる「三半規管」、「耳石器」の3つの器官から成り立っている。そして、三半規管と耳石器を合わせた部分が「前庭器」である。三半規管の中は内リンパ液(非常に粘性が高い特殊な細胞外液)で満たされており、頭が動くとリンパ液も動く。そのリンパ液の流れや速度、方向などを感覚細胞は認識し情報が電気刺激として前庭神経を伝わって脳へと送られていく。三半規管が頭や体の「動き・回転加速度」を感知するのに対し、耳石器は「傾き具合、直線加速度」を感知する。耳石器は2つあり、1つは水平方向、もう1つは上下(垂直)方向の動きや傾きを認識する。
●耳石器はわらび餅のような粘着性のある耳石膜に、小さな粒状の耳石が多数ついた状態になっている。頭を傾けると、耳石膜の上に耳石が働く。その刺激を耳石膜の下の感覚細胞が情報として脳に伝える。
●なにかの原因でどちらかの耳に障害が起こると、平衡機能が低下しバランスがくずれる。特に三半規管の機能に左右差が起こったときに、めまいが発現する。この左右差は薬や注射では根本的に治すことはできない。めまいにともなう諸症状の改善には薬物療法は必要だが、この左右差を改善しないとめまいは残る。この左右差を改善する方法は、リハビリにより小脳の働きを高めることである。
小脳はバランスをつかさどる「パイロット」
●めまいが徐々に軽減されていくのは体にもともと備わっている「中枢代償」という小脳の働きによる。これは小脳が左右差を軽減し、平衡機能を補おうとする作用である。
●体のバランスは耳だけでなく、目(視覚)や足の裏(深部感覚刺激)からの情報によっても大きな影響を受ける。これは耳の障害があっても情報取集部位の目と足の裏を鍛えることで、耳の障害をカバーすることができるということを意味する。
苦手なリハビリこそ積極的に行う
●フィギュアスケートの素晴らしい回転の演技は、練習によって獲得したもので、回転後の眼振を抑制できているからである。これは「RD(response decline)現象」といい、医学的には小脳が目の動きを止める指令を出し、眼振を抑制しているためと考えられている。これも「小脳の中枢代償」である。
●「めまいのリハビリ」とは、目と足の裏、そして耳(前庭器)を鍛えることで、「小脳の中枢代償作用」を最大限に生かし、めまいの改善と再発予防を目指すものであり、弱っている平衡機能を鍛えて高めるものである。
●リハビリは必ず医師の診断と治療を受け、急性期のめまいが治まってから開始する。
第3章はフローチャートに続き、めまいの原因となる各病気の説明が続きます。「体験談」自体は省略していますが、体験談の後に出てくる「新井先生のコメント」については一部ご紹介しています。
第3章 病気別リハビリ&めまいを克服した体験手記
めまいの原因がわかるフローチャート
1.良性発作性頭位めまい症
●めまいは「自発性」と「誘発性」に分けられる。前者のめまいは、椅子に座っているときや寝ているときなど、自分が動いていないときに生じるタイプである。後者は、寝返りを打ったり、急に起き上がったりしたときなど「ある動きに誘発されて」現れる。この自発性か誘発性かはめまいの原因となっている病気を確定するのに重要であり、受診時に医師に伝えるべきものである。
●誘発性のめまいの代表格が「良性発作性頭位めまい症」である。頭や体の位置を変えたり、ある特定の体勢を取ったときに激しいめまいが起こったり、めまいの程度が悪化したりする。めまいの発作は数十秒~数分で治まるのが普通。吐き気や嘔吐をともなうこともある。
●めまい発作とともに耳鳴りや難聴が現れたり、以前からあった耳鳴りや難聴が増悪したりすることはない。
●良性発作性頭位めまい症は、耳の奥にある耳石器にくっついている耳石がはがれて、三半規管の中に入り込むことで起こる。三半規管のリンパ液の中を本来なら存在しないはがれ落ちた耳石が移動することで、脳に異常な情報を伝えてしまうことでめまいが起きる。
●耳石がはがれる原因は、寝たきり、頭部打撲、交通事故、慢性中耳炎などの耳の病気、加齢などがかかわっているとされている。
●頭を動かすリハビリは、耳石が三半規管から出て、耳石器に戻って耳石膜に再びくっつくことを目的としている。一時的にめまいやふらつきが増悪するケースも多く見られ、1回のリハビリで元に戻すことは難しいが、軽いぶり返し程度であれば続ける。山を乗り越えることでめまいから解放される。
●【体験談1】に対する「新井先生のコメント」:『めまい発作が起こったときは、血圧が上がります。血糖値も上がります。体に異常が起こると、脳へ酸素や栄養を運ぶための血流を保とうとして、血圧や血糖値が上がるようになっているのです。つまり、菅原さんの場合も、急に血圧が上がったためめまいを起こしたのではなく、めまいが起こったことで血圧が上がったのです。原因と結果が正反対なので、降圧剤を飲んでもめまいは改善しません。』
●【体験談2】に対する「新井先生のコメント」:『本田さんの場合、耳石がはがれやすく、重い発作をくり返していました。通常、耳石がはがれるのは左右どちらかの場合が多いのですが、くり返すめまい発作の経過途中で、本田さんは両耳で耳石がはがれていることがわかりました。このように両耳の障害が原因でめまいをくり返す重篤な症状のかたは非常にまれで、良性発作性頭位めまい症の患者さんのうち、0.1%以下です。』
2.前庭神経炎
●前庭神経炎は、内耳から脳に情報を伝える前庭神経になんらかの原因で障害が起こり、突然、激しいめまいが現れる病気であり、激しい回転性のめまいが1週間くらい続く。この間、立ったり歩いたりすることはできず、「目を開けることもできない」という人もいる。吐き気や嘔吐も伴うため脳の病気と考え、救急搬送されるケースも多い。
●耳鳴りや難聴は発現せず、これがメニエール病との違いである。
●約1週間の激しいめまいの後、体を動かすとめまいやふらつきを感じる後遺症が残り、放置するとそれが数か月から数年間も続くケースも多い。
●炎症を示す「炎」という文字がついているが、前庭神経が炎症を起こしているわけではなく、「炎症のように激しい症状」ということで、この病名がつけられている。
●聴力検査、眼振検査などを行い、他の病気の疑いが消えたら、耳に水を注入して三半規管の機能を診る「カロリック検査」を行う。
●【体験談】に対する「新井先生のコメント」:『前庭神経炎の症状は非常に強く、「大地震のようなめまい」と表現されるほどです。黒田さんが若いころくり返していた軽いめまいと、今回のめまいは、明らかに違います。前庭神経炎の場合は、立ったり歩いたりはもちろん、目を開けることもできなくなります。めまいを起こす病気の中でもきわめて症状が重いので、診察室に入ってきた患者さんは最初、私の顔を見て話すこともできません。』
3.メニエール病
●メニエール病は決して多い病気ではない。
●内耳に内リンパ液(非常に粘性の高い特殊な細胞外液)が異常に増え、「水ぶくれ(水腫)」の状態になって内耳の感覚器官に障害を起こす。これにより平衡機能と感覚に異常をきたす。
●特徴は耳鳴り、難聴、回転性の激しいめまい。生命に関わるようなことはないが、内臓や血管を調整する自律神経の機能が乱れるので、吐き気、嘔吐、顔面蒼白、冷や汗、頭重感など多くの症状が現れる。
●めまいの発作は数十分から数時間で治まるが、めまいと難聴の発作を何度もくり返すのが特徴である。発作をくり返すことで、聴力も平衡機能も低下しめまいやふらつきを起こしやすくなる。
●初回の発作から再発までの期間も数時間から数日後、数カ月後から数年後と、人によって大きく異なる。
●原因は不明。過剰なストレス、季節の変わり目や天候、気圧の変化にともなって発症することがある。また、寒冷前線が通過するときに、症状が悪化するというケースも多い。
●飲水が治療法の1つになっているのは、水をたくさん飲むと脳が「外から水がたくさん入ってきたから、ため込まなくても大丈夫」と判断し、抗利尿ホルモンの分泌が抑制され内耳の水腫が軽減されるためである。
●【体験談】に対する「新井先生のコメント」:『メニエール病の一般的な治療法としては、利尿薬の服用と、水を多めに飲むこと、そして生活習慣の改善です。働きすぎや睡眠不足、心身への過重なストレスが、メニエール病を誘発すると考えられるからです。そのため、投薬によって一時的に症状が改善しても、再発することがあります。
メニエール病のかたは、自分の生活を振り返って、働き方や生き方、考え方を少し緩やかにするといいでしょう。具体的には、仕事量や就労時間をへらし、睡眠時間や休日、休憩時間をしっかり取る、といったことです。働きざかりのかたには難しいかもしれませんが、自分の体を守るためです。ぜひ心がけてください。』
4.めまいを伴う突発性難聴
●突発性難聴はある日突然、片側の耳が聞こえにくくなる病気である。
●多くの場合、難聴だけでなく耳鳴りや耳が詰まった感じをともない、回転性のめまいが生じる。メニエール病の初期と症状が似ているが、突発性難聴は普通1回しか起こらない。ただし、めまいやふらつきの後遺症が残るケースは多く見られる。
●2/3の人に難聴が残るとされており、「耳の聞こえが突然悪くなった」というときは、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診すべきである。特に発病後3~4週放置すると聴力は戻らないまま固定されてしまう。
●原因は不明だが、ウィルス感染や内耳に血液を送る動脈の血流障害が考えられている。
5.片頭痛性めまい
●一般に片頭痛は、ストレスや性ホルモンの変動、セロトニンの欠乏、遺伝などが原因で起こることが多い病気である。
●片頭痛にめまいが伴うことは多くはない。また、片頭痛とめまいの関係は研究中の段階であるが、因果関係がある場合と、ない場合があるとされている。
●片頭痛性めまいは薬で改善するのは約6割、約4割は「片頭痛は改善したが、めまいは消えない」という状態が続く。このため薬だけでなく、めまいのリハビリにより平衡機能を鍛えることが重要になる。
6.持続性平衡障害・加齢性平衡障害
●この症状は診断が難しく、「年のせい」「気のせい」と言われてしまうことが多い。患者数は相当数にのぼり、原因がわからず家で寝たきりになっている人も少なくない。寝たきりになると、平衡機能を担う「耳」「目」「足の裏」が使われないため、どんどん弱っていく。これがめまいは寝ていても治らない理由である。
●【体験談】に対する「新井先生のコメント」:『五十嵐さんの場合、おそらく最初は、三半規管の障害によるめまいだったのだと考えられます。症状が長引き、安静にする時間も長くなったため平衡機能が衰えて、私が診察したときには、「持続性平衡障害」になっていました。
目と耳と足の裏からの有効な刺激で、小脳を鍛えるのが、めまいのリハビリです。弱っている部分を鍛えるのですから、最初はやはりつらいと思います。しかし、五十嵐さんの例を見えてもわかるように、めまいのリハビリは、短期間で効果を実感できる場合が少なくありません。ただし、入院中に平衡機能が回復してめまいが消えても、退院後にリハビリをやめてしまっては元の木阿弥です。五十嵐さんの場合、娘さんがいっしょにリハビリをやってくれているそうです。このように家族が協力することで、めまいの再発を防ぐことができます。』
7.ハント症候群
●正式には「ラムゼイ・ハント症候群」という。子どものころに水ぼうそう(水痘)にかかり、顔面神経に潜伏していた水痘ウィルスが再活性化し、顔面神経とその横に並ぶ内耳神経(聴覚と平衡の神経)にダメージを与えることで、めまい、耳鳴なり、難聴、顔面神経麻痺などが現れる病気である。
8.慢性中耳炎が原因のめまい
●慢性中耳炎に伴うめまいは、軽いものから激しい回転性めまいをくり返すものまで様々である。ただし、めまいによって耳鳴りや難聴が増悪することは多くない。めまいの原因は内耳の前庭器の働きに左右差が生じることで起こるのでリハビリは有効だが、まずは慢性中耳炎の治療を優先し原因を解決してからリハビリを行うようにする。
9.椎骨・脳底動脈循環不全
●首の後面を走る「椎骨動脈」とそれにつながる「脳底動脈」は小脳に血液を送っている。椎骨・脳底動脈循環不全とはこれらの動脈の血流が一時的に悪くなる病気で、めまいを起こすことがある。血流障害が起こる原因としては、動脈硬化や頸椎の変形などが挙げられる。
めまいとともに、手足のしびれ、嘔吐や吐き気、ときには物が二重に見えたり霧がかかったように見えたりする視覚障害をともなうことがある。めまいと同時にこうした症状が起こった場合、神経内科か脳神経外科、耳鼻咽喉科を受診するようにする。
10.脳梗塞・脳出血の治療後に残るめまい
●小脳は体のバランスを取る中枢のため、小脳で梗塞や出血が起こると急激なめまいや平衡機能の失調が生じる。また、脳出血や脳梗塞の治療後にめまいの後遺症で悩んでいる患者さまは多い。めまいのリハビリは有効だが、必ず主治医に確認しなければならない。
11.心因性めまい・めまいをともなう「うつ」状態
●精神的なことがきっかけで、めまいが起こることがまれにあるが、その多くはストレスが内耳の血流を障害してめまいを引き起こしている可能性がある。また、不安やうつ状態から家に引きこもり、運動量が減ることで平衡機能が低下して、ふらつきが起こることも考えられる。このように内耳の障害や平衡機能の低下が見られず、精神的なことだけが原因でめまいを発症する、真の心因性めまいは極めて少ない。(新井先生は『2人しか診ていません』と本に書いています)
以上が第3章で紹介されていた全ての病気ですが、ここにないもので気になるものがあります。それは「頸性めまい」です。“日経メディカルOnline”には『繰り返す難治性めまいでは「首」を疑え』という記事が掲載されています。
こちらの記事の閲覧には会員登録(無料)が必要となるため、冒頭に書かれている内容と表のみをご紹介します。
『頸部脊柱管狭窄症や頸椎ヘルニアなどの頸部疾患を持つ患者が長時間同じ姿勢を保持することで発症する「頸性めまい」をご存じだろうか。日常診療で遭遇するなかなか改善しないめまいの中に、「頸性めまい」が潜んでいる可能性がある。診断できれば頸部に負担を掛けない生活を心掛けたり、筋弛緩薬を投与したりすることで、めまい症状を改善できる。
「何度も再発する難治性めまいでは、首の疾患を疑った方がよい。頸部疾患を背景に発症する頸性めまいの可能性が高いからだ」――。こう指摘するのはたかはし脳外科皮フ科医院(新潟県新発田市)の高橋祥氏だ。頸性めまいとは、頸部以外にめまいの原因となる脳疾患や全身性疾患が認められない患者において、肩や頸部に負荷が掛かることで起こるめまいのことを指す。』

画像出展:「日経メディカルOnline」
新井先生が紹介されているめまいを伴う病気の6番目に「持続性平衡障害・加齢性平衡障害」があり、この病気の症状は診断が難しく、「年のせい」「気のせい」と言われてしまうことが多いとされています。また、9番目の「椎骨・脳底動脈循環不全」ではその原因として頸椎の変形が含まれています。これらの病気の中には頸の筋肉の問題が関係しているものもあるのではないかと思います。
新井先生は耳鼻咽喉科の先生なので筋肉との関係性に触れることはないのですが、鍼灸師としてめまいの施術を考える場合は、頸筋の状態に注目し痛みや硬結がある場合は、積極的に施術に入れるべきと思います。
ご参考
●”頚性めまいの重要性” 高橋 渉 日農医師65巻1号 2016.5 PDF10枚
●”頸性めまい” 田浦晶子、Cervical vertigo Equilibrium Res Vol.77(2) 2018 PDF資料11枚
●ブログ“頚筋症候群(頚筋性うつ)”
めまいの鍼治療
ポイントは以下の3つと考えます。
1.自律神経を調える。
2.耳周辺の血流を改善する。
3.深部感覚刺激(足底)が脳に届くように滞りがないようにする。
1.自律神経を調える
●後頚部の硬い部位に置鍼:百労、天元など
●仙骨部の硬い部位に置鍼:上髎、次髎、腰兪など
●後頭部―骨盤部の広い範囲を対象に置鍼:脊中、L2-L5など脊柱両側の硬い部位
※詳細はブログ“中高年女性の腰痛3”をご覧ください。
2.耳周辺の血流を改善する
ツボとり(取穴)の基本は触診で硬い部位などを見つけることですが、ここでは目安とする経穴を選択したいと思います。以下の2枚はいずれも『経絡マップ』から持ってきたものです。上は“経穴と動脈”、下は“経穴と静脈”です。これらの動静脈と耳の位置の両面から検討すると、“翳風”、“聴会”または“聴宮”、“完骨”が刺鍼したい候補にあげられます。

動脈
・椎骨動脈:翳風(手少陽三焦経)
・総頚動脈:聴会(手少陽三焦経)・聴宮(手太陽小腸経)、完骨(足少陽胆経)
補足:経脈で考えると“少陽経”でまとめることができます。また、骨盤部、腰背部とのつながりを考えると、これらの部位は足太陽膀胱経に属する経穴なので、耳の経穴を同じ“太陽経”の聴宮に取るという選択肢もあると思います。
画像出展:「経絡マップ」
3.深部感覚刺激(足底)が脳に届くように滞りがないようにする
滞りが気になる箇所は、骨盤部と膝関節部です。骨盤部にある梨状筋という筋肉には“梨状筋症候群”という病名がついた疾患があります。また、15%は坐骨神経が梨状筋の下ではなく貫通しているという報告もあります(『トリガーポイントマニュアル 第7章 大殿筋』より)。

『股関節の動きのなかで特に複雑で、かつ微力なものに回旋(内外旋)運動があります。股関節を内旋すると痛む場合は外旋筋群が硬くなっており、その下にある坐骨神経が圧迫されている可能性があります。このような疾患を梨状筋症候群といいます。』
画像出展:「ZAMST」

このイラストと文章は「Therapist Circle」さまより拝借しました。
『背側の筋肉が主要姿勢筋と呼ばれる理由は、正常立位での重心線が身体のやや前方を通っているため、背側にある筋肉は全て持続的な筋緊張を保たなければならないからです。対して腹側にある筋肉は、持続的な緊張を必要とせず動揺する身体を調節する際に、断続的に収縮すれば立位を保つことができます。』
膝関節は立位では体重を支えると同時に頻繁に活動している部位です。背部の抗重力筋は特に主要姿勢筋とされ、姿勢保持の働きを担っています。

中央紫色の脛骨神経は近位では坐骨神経となり、遠位では足裏の内側足底神経と外側足底神経という運動を司る筋枝に加え、足底の触覚や痛覚などを司る皮枝にまで及びます。一方、脛骨神経の走行は下腿(ふくらはぎ)ではヒラメ筋の更に下、後脛骨筋に挟まれた深層に位置し、膝関節の背面でも腓腹筋と膝窩筋に挟まれています。これらの膝関節周辺の筋群は疲労し硬くなりやすく、血管や神経を圧迫する原因になる可能性があります。従いまして、これらの膝関節の筋肉も考慮すべき刺鍼ポイントと考えます。
以上のことから、骨盤部の梨状筋と膝関節部のヒラメ筋、後脛骨筋、腓腹筋、膝窩筋は押さえておきたい筋肉だと思います。
不安障害2
今回は、前回の”不安障害1”の続きになります。
第8章 身近な人との不安とのつきあい方
不安障害の人に接する基本姿勢
解決できる不安と感じるしかない不安を区別する
●『一般に、不安の強い人をめぐって混乱している状況を見ると、周りの人が本人の不安を解決しようとしてしまっている、ということが多いものです。「心配しない方がいいよ」というものも含めて、さまざまなアドバイスを与えているのです。
実は、アドバイスには大きな問題があります。アドバイスというのは、現状はよくないから変えるべきだ、というメッセージをもともと含んでいるものです。』
●『感じるしかない不安を前に混乱している人は、自分の不安にも不安を感じているものです。自分が不安であることも不安だという状態の人に向かってアドバイスをしてしまうと、自分が不安であることへの不安がますます強くなってしまいます。「やっぱりこのままではいけないんだ」と思ってしまうのです。』(”感じるしかない不安”については、”不安障害1”の中の第1章にある”解決すべき不安と感じるしかない不安”を参照ください)
●『そもそも「感じるしかない不安」を感じているわけですから、「心配しない方がいいよ」と言われても、どだい無理な話なのです。』
気持ちをよく聴き肯定する
●『「こんなときには不安になるよね」と、不安を肯定してあげるのが最も適切な対処です。聴いてあげることは重要です。感じるしかない不安は、原則として、安全な環境で表現するとだんだん落ち着いてくるものだからです。安全でない環境というのは、自分の不安が不適切だと思われるような環境のことです。すぐにアドバイスされてしまうような環境は、「あなたの不安は不適切だからすぐに変えなさい」と言われているのと同じことになってしまいます。』
「治療者」ではなく「支え役」を引き受ける
治療は専門家に任せる
●『治療者は、専門知識に基づいて事態を改善していく役割、そして、身近な人はそれを支える役割を果していただきたいのです。』
●『本人が焦ったり、その中で挫折する自分を責めたりしてしまうようだったら、「ゆっくりやろうね」「まだまだ無理しなくて大丈夫」と安心させてあげるのです。』
●『引きこもっているケースなどでは、本人にハッパをかけないと本当に一生引きこもったままになるのではないかと思われることもありますが、ハッパをかけても解決にはなりません。ハッパのかけ方によっては、やはり心の傷や対人不信につながります。もちろん、治療的な刺激を与えることはプラスになりますが、その方針を考えるのも、専門性のある治療者の仕事です。』
受診の勧め方
●『受診を勧める際には、いくつか注意したい点があります。不安障害の方は、不安の基本レベルが高くなっていますので、普通だったら不安に思わないようなことにでも不安を感じやすい状態になっています。「これは不安障害だから病院に行った方がいいよ」とだけ言ってしまうと、「不安障害」「病院」という言葉に反応し、「私はそんなにおかしいの?」「これからどうなってしまうの?」「病院だなんて、そんな怖いところ…」と、どんどん不安が燃え上がることにもなってしまいます。』
●『情報を提供する自分が落ち着いているかどうかに注目するとよいでしょう。自分の不安を投げかけるような形で情報提供してしまうと、本人はさらに不安になってしまいます。』
●『本人がどう思っているのかという気持ちを必ず聞きます。何であれ変化は不安を喚起するものですが、安心できる環境で気持ちを話せれば不安は軽くなるからです。』
身近な人がパニック発作を起こしたら
まず自分が落ち着くこと
●『一緒にいる人がパニック発作を起こしたら、まず自分が落ち着きましょう。自分がパニックになってしまうと事態がややこしくなります。「どんな不安発作も、30分程度でおさまるのだ」という原点に戻りましょう。そして、それを少しでも早くスムーズにするためには、安心と呼吸だということを思い出してください。』
●『一緒にゆっくり呼吸してあげるのもよいでしょう。「ゆっくり吸って―」「吐いて―」と、呼吸のペースをとってあげるのです。』
●『パニック発作は、時間がたてば必ずおさまります。むしろ、一緒にいる人が不安になってそれを本人にも伝染させてしまうと、それが次の刺激になって不安がもっとひどくなる、ということにもなります。』

画像出展:「正しく知る不安障害」
「怒り」という名の不安に対処する
怒っている人は困っている人
●『何かで困って、「どうしよう」と不安になると、相手に怒りをぶつけてしまうのです。これは、「八つ当たり」と呼ばれるものと同じ現象です。自分の不安を不安として引き受けることは、案外勇気とエネルギーを要するものです。自分の不安を引き受けて向き合うよりも、それを相手への怒りとしてぶつけてしまった方が楽だと感じる人は多いのです。』
反撃しないで安心させてあげる
●『相手の攻撃を攻撃として受け止めずに、本来の不安として受け止めてあげることです。これは、相手のためというよりも、自分のためだと思ってください。表面的には口汚く攻撃している人でも、本当のところはただ不安なだけなのだ、という目で見てみると、見え方が明らかに変わると思います。』
不安の土俵に乗らない
不安障害の不安はそのままの次元では解決しない
● 『不安障害の人に対応する上で重要なのは、相手の不安の土俵にのらないということです。不安障害の人の不安を、そのままの次元で解決できることはまずないと思ってください。』
第9章 怖れを手放す
不安を単なる感情に戻す
感情としての不安と、心の姿勢としての怖れ
●『不安障害が治るということは、不安を、単なる感情という本来の立場に戻してあげることです。』
●『不安障害の最中には、不安は自分の人生を支配する巨大な存在になっています。自分の全存在が、不安によって振り回されているのです。この、「化け猫」ならぬ、「不安のお化け」が不安障害です。不安は、なぜ「不安のお化け」になってしまったのでしょうか。細かく見れば、それは、本書で述べてきたような悪循環によってどんどん大きくなった、と言えるわけですが、さらに大きな目で見ると、不安は「怖れ」を吸収すると「お化けになるのだと言えます。』
●『痛みは、それが単なる感覚である限りは、ただの痛みです。でも、「痛みとは怖ろしいものだ」と、「怖れ」が加わると、「痛みのお化け」になって、生活を支配することにもなってしまいます。例えば、いつもいつも痛みのことばかり気にするようになってしまう、という状況を考えていただくとよいと思います。不安についても全く同じことで、単なる感情である限りは、ただの不安なのですが、不安を怖れてしまうと、「不安のお化け」になるのです。』
不安をコントロールしようとしない
●『不安を怖れないということは、本書で述べてきたように、不安に関してコントロール感覚を持つということです。重要なのは、「不安をコントロールする」ではないということです。不安は、状況の意味づけを教えてくれる感情ですから、必要なときには出てきます。そうやって不安が出てくることも含めて、受け入れることができれば、コントロール感覚を持つことができますし、不安に対する怖れを手放すことができた、と言えるでしょう。』
●『不安をコントロールしようとしてしまうことの何が問題なのかというと、そもそも不安は状況に応じて出てくる感情なので本当にコントロールすることができないということもありますが、さらに重要なのは、不安をコントロールしようとする姿勢が、怖れの姿勢だからです。』
現在に生きる
安心は現在にしかない
●『不安が強いとき、私たちは現在のありのままを経験していません。現実に「不安」というモヤがかかったようになっていて、実際に見ているのは、モヤを通した現実どころか、場合によってはモヤしか見ていないということもあるのです。モヤの中にこそ不安障害を維持する悪循環があります。』
●『認知療法は、モヤをよく観察して、所詮はモヤに過ぎないということを知るための治療法です。また、対人療法は、モヤの向こうにある現実とやりとりをして、モヤを晴らしていく治療法です。』
●『安心は現在にのみあります。未来には常に未知の要素がありますので、そこには100パーセントの安心はありません。でも、今現在に集中することができると、そこには不安の入り込む余地がなくなるのです。』
自分の歩みにコントロール感覚を持つ
「前向き」よりも「後ろ向き」がよい
●『「前よりも後ろを向く」というやり方がお勧めです。どういうことかと言うと、「まだできていないこと」ではなく、「ここまでにできるようになったこと」を見るということです。
具体的には、未来のことはできるだけ考えないようにし、目の前のことだけをやる。そして、未来のことが不安になってきたら、病気に取り組む前の自分や、一年前の自分などと比較して、「こんなによくなったんだ」ということを感じてみるのです。前頁で「現在に生きる」ことをお勧めしたのに、過去を振り返るというのは矛盾していると思われるでしょうか。これは、過去を振り返っているようでいて、実は現在の自分の力に気づくやり方です。』
人と比較したくなったときは
●『人と自分を比較するときには、私たちは、人の「よさそうな部分」や自分の「だめな部分に目が行ってしまうものです。特に、不安が強いときには、自分の不安を刺激するような形で見てしまいます。そんなときにも、比較対象を「他人」にするのではなく、「過去の自分」にしましょう。一番状態が悪かった頃の自分と比べてみるのです。すると、自分が、決められた道の上を着々と歩んできたことがわかると思います。これからもこの道を進んでいけばよいだけであって、「他人」に目がくらんでこの道から落ちてしまうことが最も問題なのだということに気づいていくでしょう。』
不安障害1
高齢の患者さまの中には、「ちょっと心配しすぎではないかな」と思うことがたまにあります。もちろん、高齢ゆえに多くの不安材料が存在していることは十分に想像できます。
誰もが抱くような強い不安感と病的な不安障害との差はどんなものなのか、これを知ることは必要だろうと思い、いくつかあった候補の中から、今回の本を選択しました。
ブログは大項目(章)、中項目の目次のご紹介に引き続き、各章にある小項目の中で特にお伝えしたい小項目を選び、その一部を記述していますが、不安障害1(「はじめに」から「第4章」まで)と不安障害2(「第8章」「第9章」)に分けています(「第5章 不安と認知」「第6章 不安と行動」「第7章 不安とトラウマ」には触れていません)。なお、後者の不安障害2は次週になります。
目次
はじめに
第1章 不安とは何か
不安は何のためにあるのか
解決すべき不安と感じるしかない不安
パーソナリティと不安
不安のさまざまな表現型
第2章 不安障害とは何か
不安障害という病気
なぜ不安障害になるのか
不安障害を維持する悪循環
不安障害を病気として扱うことの意義
不安障害の治療
第3章 不安と身体
不安のときに身体に起こること
パニック障害
呼吸に注意して身体感覚をコントロールする
身体からのメッセージを受け止める
不安に強い身体作り
第4章 不安と対人関係
対人関係に対する不安
社交不安障害
社交不安障害を維持する悪循環
不安をコントロールするコミュニケーション
相手の事情を考える
第5章 不安と認知
不安の時に頭の中で起こっていること
認知療法
バイロン・ケイティの「ワーク」
第6章 不安と行動
不安と回避の悪循環
強迫性障害
行動療法
第7章 不安とトラウマ
PTSDは不安障害
トラウマによる離断をつなぐ
人との関係の中でトラウマを位置づける
第8章 身近な人との不安とのつきあい方 ※次週
不安障害の人に接する基本姿勢
「治療者」ではなく「支え役」を引き受ける
身近な人がパニック発作を起こしたら
「怒り」という名の不安に対処する
不安の土俵に乗らない
第9章 怖れを手放す ※次週
不安を単なる感情に戻す
現在に生きる
自分の歩みにコントロール感覚を持つ
不安障害から学ぶ
あとがき
はじめに 不安障害へのコントロール感覚を見につけよう
不安障害の中にある二種類の不安
●『不安障害のときには不安がとても高まっているのですが、不安障害の方たちの苦しみは、病気本来の症状としての不安だけにあるわけではありません。むしろ、「自分に何が起こっているのかわからない」「自分がこのままどうなってしまうのかわからない」といった、「不安障害という未知なもの」に対する不安に苦しめられている要素も大きいのです。その二種類の不安は区別されることなく混ざり合って互いに増幅し合い、「とにかく不安」という苦しい状態が作り出されてしまいます。』
人間の健康に必要な「コントロール感覚」
●『自分が事態をコントロールできている、という感覚は安心と自信をもたらすものです。日々の生活の中であまり意識することはないかもしれませんが、「いつも通りに暮らしていればだいたい大丈夫」「まあ、何とかなるだろう」というような感覚は、コントロール感覚を反映したもので、健康に暮らしていくためには必要なものです。』
「不安障害への不安」は解消できる
●『病気についてよく学び、そこで起こっていることの意味を知ることは、大きなコントロール感覚につながります。苦しい症状は続くとしても、それがしょせんは症状にすぎないということを知るだけでも、実はかなりのコントロール感覚がもたらされます。』
不安との主従関係を逆転させる
●『不安に対してコントロール感覚を身につけていくためには、不安という感情の機能をよく知ることが大切です。』
●『不安を感じたとしても、その不安に支配されなくなるのであれば、そして、その不安をプラスに生かしていくことができれば、世界の見え方が今とは全く変わることでしょう。』
第1章 不安とは何か
不安は何のためにあるのか
感情には役割がある
●『感情は、「この状況が自分の心にとってどういう意味を持つか」を教えてくれるものなのです。』
悲しみや怒りの役割
●『身体の怪我と同じように、心の傷も、安静にして大事にする時間が必要です。実際に、この時期に悲しまなかった人は後でうつ病になったりするのです。』
●『心の病になる人の多くは、怒りとのつきあい方が苦手です。怒りは「よくない感情」だと思ってしまうので、感じることも、表現することも、抑制してしまうのです。すると自分にとって不利な状況が改善されず、ストレスがたまっていき、何らかの病気になることもあります。』
感情とのつきあい方の目標
●『状況の意味を教えてくれ、結果として適切な対処を可能にしてくれる感情は、私たちに自然に備わった自己防衛能力であると言えます。』
●『「悲しみや怒りを感じない人になろう」という目標を立ててしまうと、「熱いものに触っても感じない人になろう」と言っているのと同じくらいおかしなことになってしまうのです。』
●『感情をよく見つめて、状況の意味を学び、その中で自分がすべきことを考えられるようになる、ということが目標になります。』
不安の役割
●『「不安」は「安全が確保されていない」ということを知らせてくれる感情です。この先の安全が確保されていないので、不安を感じるのです。未知のものに不安を感じるのはそれが理由です。ですから、不安は安全確保のために重要な役割を果たします。』

『例えば、真っ暗闇で山道を歩いていたら、すさまじい不安を感じるでしょう。それこそ一寸先がどうなっているかわからないからです。』
画像出展:「正しく知る不安障害」
解決すべき不安と感じるしかない不安
解決すべき不安
●『人との関係の中で、「あの人は私の言ったことを誤解したのではないか?」と思うととても不安になります。「自分の言ったことをきちんと理解して受け入れてくれた」という安全が確保されていないからです。このようなときには、相手に確認してみることで安全を確保することができます。』
感じるしかない不安
●『新しい土地に引っ越すようなときには、どれほど準備しても不安をゼロにすることはできないでしょう。それは、新しい土地はやはり未知のものだからです。準備でカバーできる領域は限られていて、あとは、そのときになってみないとわからないことが残ります。そのような不安は、感じるしかない不安だということになります。』
当たり前の不安
●『感じるしかない不安に対して、悪循環から抜け出すにはどうしたらよいかというと、不安であるということを「当然のこと」として受け入れるのが一番です。』
●『「新しい土地に引っ越すのだから、不安なのは当たり前」と思えれば、それ以上の意味はなくなります。』
●『「気にしないようにする」という対処法も軽い不安には有効ですが、不安がある程度以上の強い場合には逆効果になります。なぜかと言うと、「気にしないようにしよう」と思っても結局不安が出てきてしまい、状況をコントロールできない自分がますます不安になってしまうからです。』
不安はストレスだと認める
●『不安に駆られているとき、私たちは「何とかしなければ」と焦ってしまうので、普段以上に動き回ってしまうのです。身体が動けずに固まっている場合でも、頭の中は大忙しです。ただでさえストレスの高まる時期なのに、さらに自分で負荷をかけてしまうので、結果として心身が受け取るストレスの量は相当なものになります。』
自分の不安を周りの人と共有する
●『「当たり前の不安」を乗り越えていくためには、周りの人たちに、自分が今どういう不安を抱えていて、何に気をつけて生きているのか、その上でどういう協力をしてほしいのかを伝えて、理解したり共感したりしてもらうことが必要です。これは、事態をスムーズにするだけでなく、対人関係の質も向上させることになるでしょう。感情を打ち明け合ったときに人は最もつながりを感じるからです。また、自分が間違いなく相手の役に立てているという感覚は、人間にとって深い満足感につながるものです。』
●不安を感じたときに、安全確保のためにできることがあれば、できるだけやってみる。それでも残る不安は、「当たり前の不安」として認める。そして、自分にとってストレスのかかる時期だということを認識して、普段よりも無理せず余裕をもって暮らすように心がける。さらに、それを周りの人に伝えて、理解を深めてもらい、協力してもらう。こんなふうにできれば、不安が立派に役割を果たしたと言えるでしょう。』
パーソナリティと不安
人間の性格(パーソナリティ)の構造
●『不安はもともとのレベルにかなり個人差があります。』

『現在、精神医学の研究でよく用いられるものにクロニンジャーという米国人精神医学者が提唱した「七因子モデル」があります。』
『七因子モデルは、遺伝的な影響が強い四因子と、環境的な影響が強い三因子に分けて分類しているところに特徴があります。』
『基本的な「性格」は変えられないけれども適応力は上げられる、といったところでしょうか。』
画像出展:「正しく知る不安障害」
不安を感じやすいパーソナリティ
●『不安と直接関係のあるパーソナリティ特性は、遺伝的な影響が強い因子の一つである「損害回避」と呼ばれているものです。文字通り、困ったことにならないように物事を避ける傾向のことで、一般的な概念としては、「心配性」「慎重」などが近いと思います。不安障害の人は、この「損害回避」が高いことが知られています。』
「損害回避」を生かせる人と振り回される人
●『後天的な影響が強いパーソナリティ特性です。三つのパーソナリティー特性の中でも、特に「自己志向」が、さまざまな不安障害と関係することがわかっています。』
●『「自己志向」が高い人を、普通の言葉で言うと、「自分をしっかり持っている人」「安定した自信がある人」という感じになるでしょうか。』
●『「損害回避」が高く、「自己志向」が低い人は、不安に振り回されるようになってしまいます。自らの「損害回避」が知らせてくれる不安に対して、「こんなに不安でどうしよう」とパニックになってしまうのです。すると、本来は自らの特徴にすぎない「損害回避」に人生を振り回されるようになってしまいます。やりたいか、やりたくないか、ではなく、不安を基準に物事を決めるようになってしまい、自分の人生がかなり制限されて感じます。』
不安に振り回されると「自己志向」が下る
●『不安に振り回された結果として、事態をコントロールできない自分にますます安心できなくなる。つまり、ますます「自己志向」が下る、という方向性です。』
「自己志向」は高めることができる
●『自分が不安にうまく対処できるという自信をもつことは、「自己志向」を高めることにほかならないからです。』
パーソナリティ特性から見る不安とのつきあい方
●『以上のことをまとめると、生まれつき「損害回避」が高い人は、不安が強い人だといえますし、不安になりやすい人だと言えます。しかし、だから不安障害になるというわけではなく、後天的な要素、特に「自己志向」が低いと、不安に振り回されて不安障害になる、ということだと思います。』
不安のさまざまな表現型
不安は不安として表現されるだけではない
●『不安は不安として対処するのが最もうまくいきます。』
他人に過干渉になる
●『過干渉は、不安を反映したものであることが多いのです。』
イライラする
●『イライラしている人も、それが不安の表現型であることが多いものです。』
●『自分自身の不安に築いていないことが多く、「自分をイライラさせる相手が悪い」と思っていることが多いのです。』
攻撃的になる・暴力をふるう
●『ドメスティック・バイオレンス(DV:家庭内暴力)も、要は自らの不安に向き合えていないということがほとんどです。』
原因不明の身体症状が出る
●『不安を不安として感じたり、表現できないと、めまい、頭痛、胸の苦しさ、しびれなど、身体症状に表れることがあります。』
第2章 不安障害とは何か
不安障害という病気
不安障害とは
●『不安を主症状とした病気のグループを「不安障害」と呼んでいます。』
パニック障害
●『動悸、発汗、震え、息苦しさ、窒息感、胸部不快感、めまいなどを伴うパニック発作(強い不安発作)が予期しないときに繰り返し起こり、また発作が起こったらどうしようという恐怖のために行動パターンが変わってしまう病気です。』
社交不安障害(社会不安障害、社会恐怖)
●『人との関りにおいて、自分が人からどう思われるかということについての不安が強すぎる病気です。』
強迫性障害
●『「~したらどうしよう」「~するのではないか」という考え(強迫観念)が頭に浮かび、その不安に苦しめられるというのが強迫性障害の本質です。』
全般性不安障害
●『多くのことについての、過剰でコントロールできない不安や心配が、起こる日の方が起こらない日よりも多いという状態が六カ月以上続いているという病気です。』
健康な不安と病的な不安の違い
●『手を洗わないとばい菌に汚染されるというのは、間違っていません。そして、実際に、健康な人たちも同じ目的で洗っています。強迫性障害の人とどこが違うのかというと、「そこまでは気にしない」というところです。つまり、不安障害の人が抱く不安は、「わかるけれども、そこまで気にしていたら生活が成り立たないでしょう」という性質のものなのです。』
●『不安障害の不安は、病気の症状ですので、コントロールできないところも特徴の一つです。』
なぜ不安障害になるか
きっかけが明らかでない不安障害
●『不安障害の中でも、社交不安障害や強迫性障害は、いつ始まったかが特定できない場合も多く、「気づいたらなっていた」という人も少なくありません。』
きっかけが明らかな不安障害
●『パニック障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、いつ始まったかを特定することができるのが一般的です。』
子どもを不安障害にしないために
●『不安障害の人の家族に不安障害が起こりやすいということは、すべてが遺伝のためとは言えません。不安の強い人は、不安の強い子育てをするでしょうから、そこからも影響を受けることになります。』
●『子ども自身の不安にもよく耳を傾け、批判するのではなく一緒に対処してあげるようにすれば、「自己志向」はやはり高まるでしょう。その際、「代わってあげる」という過保護な対処ではなく、子どもが自分自身の力で安心して取り組めるようにしてあげることが必要です。』
不安障害を維持する悪循環
不安と思考の悪循環
不安と回避の悪循環
●『不安障害の人は、自分の不安を刺激するような状況を避けるようになります。この「回避」は、不安障害の重要な症状の一つです。回避によって、日常生活がままならなくなったり、自分にとって明らかに有利なことや必要なことすら避けるようになったりしてしまうからです。
回避は、短期的にはよい選択に見えるかもしれませんが、長い目で見ると逆効果です。回避してホッとすると、「次の避けなければ」という思いが強まるからです。これは、実際に怖い思いするのと同じような効果を生み、「この状況は怖ろしいのだ」という信念を心身に植え付けます。
また、そのような状況を回避し続けている限り、「慣れる」こともあり得ません。実際に何が起こるのか、という現実観察もできないのです。
そして、人間は、何かを回避し続けている自分によい気持ちを持つことはありません。特に、周りからは理解してもらえないテーマの回避は、隠したくなります。隠すこともストレスですし、そんな自分はだめだという気持ちが強まります。自分はだめだという気持ちは、不安に対して前向きに取り組むことを難しくします。ですから、不安と回避も、終わりのない悪循環に陥ってしまうのです。』
不安障害の治療
対人関係療法
●「対人関係療法では、身近な人間関係と症状との関連に注目して治療を進める。発症のきっかけになった対人関係上の出来事や変化は何か、発症してから、症状によって身近な人間関係がどのような影響を受けているか、また、身近な人間関係によって症状がどのように影響を受けているか、ということに注目していきます。強迫性障害以外の不安障害に対して、効果が示されてきています。』
第3章 不安と身体
不安のときに身体に起こること
「修理」が必要なのはセンサー
●『「闘争か逃避か」反応が起こらない身体になったらよいのに、と思われるかもしれません。しかし、問題は「闘争か逃避か」反応にあるのではありません。その状況を「脅威」ととらえてしまうところに問題の本質があるのです。
「闘争か逃避か」反応は、火災報知器のサイレンのようなものです。ここで修理が必要なのは、センサーです。魚を焼いただけなのに火事だとみなしてサイレンが鳴ってしまっているのです。魚を焼いた程度ではセンサーが働かないように、修理すればよいのです。サイレンそのもの(「闘争か逃避か)反応」を鳴らなくしてしまうと、本当の火災のときに困ってしまいます。』
パニック障害
「苦しさ」と「意味づけ」の混同
●『どんな人にもパニック発作は起こり得ますし、特に初回のパニック発作はどんな人にとっても本当に怖ろしく感じられるものです。それまでに全く経験のない、異常な体験だからです。しかし、パニック発作で死ぬこともなければ、気が狂ってしまうわけでもない、ということは事実として残ります。この事実を前に、「パニック発作は苦しいけれど、命に関わるわけではないから」と考えることができれば、パニック障害にはなりません。パニック発作の苦しさと、その意味づけが、うまく区別されているのです。
パニック障害の人も、それまでのパニック発作で「最悪の事態」にならなかったことは認めています。しかし、次の発作が起こると、「今度こそは最悪の事態になるのではないか」と考えてしまうのです。この思考は強い不安を生みますから、もちろんパニックもひどくなります。そして、「こんなにひどい状態なのだから、やはり今度こそは最悪の事態になるのだ」とさらに思うという悪循環に陥ってしまうのです。
ここでは、パニック発作そのものの苦しさと、その意味づけが混同されていると言えます。そして、パニック障害の悪循環から脱するためには、この二つを区別していくことが重要です。これは、パニック発作に対してコントロール感覚を持つということに他なりません。パニック発作そのものはコントロールできなくても、それがなぜ起こるのか、どう対処することが最も適切なのか、ということを知れば、コントロール感覚を持つことができ、パニック障害を治すこともできます。』
呼吸に注意して身体感覚をコントロールする
呼吸は自律神経に影響を与える
●『呼吸というは面白いもので、自律神経にコントロールされる部分と、自律神経をコントロールする部分があります。』
●『自分の意思で細く長く呼吸すると、副交感神経優位の状態、つまり、リラックス状態を作り出すことができます。』
過呼吸のときに起こること
●『精神的な要因による過呼吸で死ぬことや後遺症を残すことは決してなく、どんなに強い発作でも、時間とともに必ず軽快していきます。身体はまたきちんとバランスをとって、通常の状態に戻るようにできているからです。』
●『パニック発作のときには、「息苦しい」と感じる人が多く、呼吸が足りないと感じられるものですが、実際には呼吸しすぎの状態になっていることがほとんどです。そもそも、「闘争か逃避か」反応のときに呼吸数が増えるのは、すぐに走って逃げられるように酸素吸入量を増やすためですが、私たちは不安反応が起こったときに必ずしも走って逃げるわけではないので、そんなに酸素は必要ないのです。すると、酸素が余った状態が作られてしまい、それが過呼吸の症状につながっていきます。』
●『パニック発作は、過呼吸によって誘発することができるということが知られています。治療の場以外では試さないでいただきたいのですが、過呼吸を続けると、パニック発作が起こるのです。「脅威」を認識すると「闘争か逃避か」反応で過呼吸になるというのも一つの事実ですが、同時に、過呼吸によって不安反応が誘発されているという側面もあるのです。』
呼吸をコントロールする
●『一分間に十二回以上呼吸をしていたらおそらく過呼吸です。』という記述が本書にはあります。
※そこで、自分自身の呼吸回数を数えてみたところ、16回だったので「え、過呼吸ってこと?」と疑問に思い、ネット検索から日本呼吸器学会のサイトを見つけ確認しました。すると、そこには約12回~20回が一般的、25回以上を“頻呼吸”と言い、“過呼吸”とは呼吸の深さが増加することと書かれていました。
また、同サイトには病名としての“過換気症候群”の説明の中に「肺や心臓の検査を行っても異常が認められず、何も認めないにもかかわらず発作的に息苦しくなって呼吸が速くなるような状態をきたすことがあります。このことを過換気と呼びます。」とありました。つまり、正常とは言えない呼吸には“頻呼吸”“過呼吸”というものがあり、我々が日常的に耳にする”過呼吸”の現在の正式名は”過換気”であり、病名としては”過換気症候群”であるということが分かりました。

『換気とは、呼吸運動によって空気を肺胞へと運ぶ働きのことです。呼吸は、無意識な状況で規則正しく1分間に約12から20回行われています。呼吸が速いとは、1分間に25回以上行われる状況で、「頻呼吸」と言います。「過呼吸」とは、呼吸回数に変化はないが、呼吸の深さが増加することを言います(通常、呼吸回数も多くなると考えられています)。』
筋肉の緊張をコントロールする
●『呼吸のコントロールと共に、筋肉の緊張をコントロールする筋リラクセーション法を覚えると、さらに効果が増します。リラクセーション法にもいろいろありますが、力を抜こうとしてもかえって緊張してしまう人の場合には、まず筋肉に力を入れてから抜く、という方法をとるとリラックスしやすいです。なお、息を吐くときに筋肉はゆるみます。筋肉を弛緩させるときには、息を同時に吐くと、リラックス効果が高まります。』
身体からのメッセージを受け止める
症状よりも先にストレスに気をつけるように
●『パニック発作は心身のストレスのもとに現れるということをお話ししましたが、睡眠不足や過労、かぜ、二日酔いなどはパニック発作を起こしやすい状況を作ります。このようなときには、「パニック発作が起こってしまった」というところに注目するよりも、「パニック発作が起こりやすいコンディションにあったのだ」というところに注目した方がはるかに有益です。』
不安に強い身体作り
定期的に運動する
●『「闘争か逃避か」反応に襲われて苦しくなってしまったときには、とりあえず身体を動かすことによって抜け出すこともできます。』
食べ物に気をつける
●『低血糖もパニックの引き金になります。ダイエット中の低血糖からパニック発作を起こす人もいますので、パニック発作を起こしている人は基本的にダイエットは避けるべきです。健康上の理由で体重を減らす必要がある場合は、医師の指導のもとで行ったほうがよいでしょう。』
第4章 不安と対人関係
対人関係に対する不安
対人関係に対するコントロール感覚
●『自分が周りの人とうまくいっているという感覚と、自分が周りの人に受け入れられているという感覚が持てると、心の健康度は大幅に高まります。そのときに感じる「自分に何があっても、人の関係の中で何とかなるだろう」という感覚が対人関係に対するコントロール感覚ということになります。』
対人関係療法
●『対人関係療法は、身近な対人関係と症状との関連に注目していく治療法です。そこで目指していくことは、対人関係に対するコントロール感覚を高めて、症状を改善していくことです。』
「役割期待のずれ」というものの見方
●『あらゆる対人ストレスを、「役割期待のずれ」と見ることができます。「ずれ」は、自分が相手に期待したことをやってもらえないときだけでなく、相手が自分に期待していることが、自分がやりたくないことだったりできないことだったりする場合にも生じます。
対人ストレスを「役割期待のずれ」として見ると、解決も可能になりますし、何よりもコントロール感覚を持つことができます。』
コミュニケーションに注目する
●『役割期待は、それを伝え合うコミュニケーションが貧弱だとずれてしまいます。
不安が強い人は特に要注意なのですが、不安のあまり、曖昧なコミュニケーションをしてしまうと、それだけずれる可能性が高くなります。自分の気持ちと、相手にやってもらいたいことを、直接、純粋に伝えるコミュニケーションが最も効果的です。』
「役割の変化」という視点
●『不安障害の発症のきっかけには「それまでのやり方から切り離されて、自分のやり方を見失う」というテーマが共通していますが、これは、対人関係療法で「役割の変化」として治療の焦点とされるものです。変化に伴う感情や、身近な対人関係の変化に注目して治療を進めていきます。』
社交不安障害
社会不安障害という病気
●『社交不安障害の本質は、人からネガティブな評価を受けることへの不安だと言えます。』
●『社交不安障害のもう一つの特徴は、そんな自分をネガティブな目で見ているというところにあります(子どもの場合を除く)。自分は「気にしすぎ」だと思っているのです。そう思っているからこそ、ますます自分がだめに思えて、人の評価が気になる、ということになります。』
社交不安障害を維持する悪循環
身体反応による悪循環
●『社交不安障害では、不安に直面する状況で、不安反応が起こります。「闘争か逃避か」反応が起こるのです。すると、胸がドキドキしたり、声がうわずったり、手が震えたりします。これらは、もともと「恥ずかしい思いをするのではないだろうか」という不安を抱えている人にとっては、不安を強めることにほかなりません。声がうわずったり、手が震えたりすることは「恥ずかしい」ことだからです。これが、社交不安障害を維持する一つの悪循環になります。』
「自分」に注目することによる悪循環
●『人前で話すときには多くの人が緊張しますが、場数を踏んでいくとだんだん慣れてきます。毎回不安を維持するというのは、案外エネルギーを使うものなので、人間は基本的には慣れる体質になっています。 ~中略~ 社会不安障害の人の場合は、そうはいきません。常に、人前で話すときの「自分」に目が向いていますので、観察するのは常に「自分」です。もちろん相手の反応もよく見ていますが、常に、「自分の話し方をどう思っているか」というポイントに絞られてしまうので、相手の事情などは視野の外になってしまいます。』
センサーを修理して悪循環から脱する
●『社会不安のセンサーを修理するためには、現実の人と触れ合う必要があります。社会不安障害は、人とのやりとりにおける不安障害のように見えますが、実際にはそこに現実の「やりとり」はほとんどありません。社会不安障害の人は「他人」を気にしていますが、そこで見ているのは「自分の話し方をどう思っているか」という部分だけであり、いろいろな事情を抱え、いろいろな気持ちを持って生きている相手そのものではありません。
実際に相手とやりとりをして、受け入れられる体験をしたり、相手にもいろいろな事情があることを知ったりすることによって、だんだんと「脅威」のセンサーが修正されてきます。』
自分の「対人関係の常識」を見直してみる
●『社会不安障害になると、自分自身をさらけ出すことができなくなるため、ますます「本当の人間関係」を学ぶ機会が減ってしまいます。治療の中で、実際に人とのやりとりをしていくと、外面の評価以外の人間関係の要素を体験していくことができます。社会不安障害の治療とは、自分の「他人関係の常識」を見直していくプロセスだ、と位置づけておくと、新たなチャレンジをしやすくなります。』
不安をコントロールするコミュニケーション
自分のコミュニケーションのクセを知る
●『自分のクセを知るために、「コミュニケーション分析」という技法を使ってみましょう。不安やストレスにつながったやりとりを振り返って、それぞれが何と言ったのかを、シナリオのように再現してみるのです。そのセリフを言ったとき、自分はどんなふうに思っていたか、何を伝えたかったのかも書いてみます。そして、その言い方で相手にそれが伝わっただろうか、と考えてみます。そして、今度は相手の立場に立って、他の解釈がないかを考えてみます。
不安が強い人の場合、コミュニケーションの量も少ないと思いますが、それでも書いてみるといろいろなことがわかります。』
「ずれ」を作らないコミュニケーション
●『不安が強い人は特に、直接的な表現をするのが怖いと思いますので、安全なコミュニケーションのコツを紹介しましょう。それは、「私」を主語にして、気持ちを中心に話す、ということです。「私は、不安であることをわかってもらえないと思うと、ますます不安になるの」と言えば、相手を怒らせる心配はまずないでしょう。これはすべてが、自分側の話であることが明確になっているからです。
ところが、同じことでも、「あなたは本当に人の不安に鈍感なのね」と言ってしまうと、相手は怒りだすかもしれません。少なくとも、役割期待の調整のために前向きに協力してくれることにはならないでしょう。』
相手の事情を考える
●『不安が強いときには、私たちは一般に、自分のことしか目に入らなくなります。そして、何でも自分に関連づけるようになります。例えば社会不安障害のときには、「相手がネガティブな反応をした」イコール「私がだめな人間だからだ」ということになります。このような認識はもちろん、大変なストレスと対人不安を作り出します。 ~中略~ 不安障害になると、自分以外の人は完璧であるかのような気になることもありますが、実際には完璧な人などいないという当たり前のことを思い出す必要があります。』
ステロイドコントロール
「ステロイドコントロール」は代々木時代(日本伝統医学研修センター)に恩師の相澤先生から教えて頂きました。「ステロイドもどんどん進化しており、ステロイドコントロールを理解した医師が処方するのであれば、たいへん優れた薬である」という主旨だったように記憶しています。
今回、その「ステロイドコントロール」がどんなものかを知るため、図書館から1冊の本を借りてきました。本当は川合眞一先生が2017年に出版された『ステロイド療法の極意』が読みたかったのですが、残念ながら埼玉県内には所蔵している図書館がなかったため、少し古い『ステロイドのエビデンス』を借りて勉強することにしました。なお、[ ]は私による追記になります。
ブログは“序”と“目次(大項目のみ)”に続いて、第1章、第5章、第10章から以下の題目の内容をご紹介しています。また、簡単ですが最後に“感想”を加えさせて頂きました。
●ステロイド漸減法や維持療法にエビデンスはあるか?
●ネフローゼ症候群に対するステロイド療法のエビデンスは?
●アトピー性皮膚炎に対するタクロリムス軟膏とステロイド外用剤の比較は?
●アトピー性皮膚炎に対するステロイド外用剤のランクと使用期間に関するエビデンスは?
序
『ステロイドは多くの診療科で使われるきわめて有用な薬であり、Henchが1948年に関節リウマチの治療に使って以来70年になろうとしている。翌年には全身性エリテマトーデスに使われ、さらに他領域も含む多くの疾患に使われるようになった。この間に十分な臨床的エビデンスが形成されてきた疾患もあるが、その高い有効性故に経験的に使用されてきた領域も少なくない。そのため、どこまでがエビデンスに基づいた使用であり、どの疾患のどんな症状に対する治療が経験的な使用であるかなどの臨床的な情報は、必ずしも十分に臨床医の知るところとなっていない。
そこで、こうした情報をクリニカルクエスチョンの形で項目を挙げ、それに応える形の本書を企画した。読者の皆様には、ステロイドで何らかの疑問が生じたときに調べる手段として、また、全体を読んでいただき、ステロイドのことを学んでいただくためにも利用していただきたいと願っている。
なお、本書のタイトルおよび本文には、グルココルチコイドの略称としてステロイドを使わせていただいた。国際的には学術論文で使われるのはグルココルチコイドが最も一般的で、コルチコステロイド(副腎皮質ステロイド)が次に続く、一方、ステロイドを使っている論文や教科書は世界では少ないが、わが国では治療薬を示す用語として最も一般的に使われていることから、本書ではステロイドとさせていただいた。』
第1章 リウマチ膠原病疾患
第2章 呼吸器疾患
第3章 循環器疾患
第4章 消化器疾患
第5章 腎疾患
第6章 神経疾患
第7章 血液疾患
第8章 内分泌疾患・代謝疾患
第9章 整形外科疾患
第10章 皮膚疾患
第11章 周産期医療
第12章 小児科
第13章 眼科疾患
第14章 耳鼻咽喉科疾患
第15章 集中治療
第16章 周術期
第17章 副作用・相互作用
第1章 リウマチ膠原病疾患
ステロイド漸減法や維持療法にエビデンスはあるか?
クリニカルクエスチョン
ステロイド療法は、一般に一定の用量で初期治療をした後、漸減するとされている。しかし、その漸減法は医療機関によってさまざまである。このステロイド漸減法や、さらにはその後の維持量投与についてのエビデンスはあるのだろうか。
エビデンスの実際
1)初期治療の期間と漸減法
ステロイドの初期治療の後で、ステロイドの漸減や維持量投与が必要な理由としては2つ考えられる。まず、ステロイドは本来内因性のホルモンであるため、外分泌能は低下する。そのため、急に中止すると副腎不全を合併する可能性がある。他の理由としては、漸減することや維持量投与により疾患活動性の再燃を防ぐことが期待されるためである。
専門家意見の集約ではあるが、ステロイド漸減法を調査した報告がある。重症臓器障害を有する全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus:SLE)患者の初期用量(体重70㎏の女性と仮定)は、集約された意見の中央値でプレドニゾロン換算で60㎎/日を2週間継続し、中等症SLE患者では同じく35㎎/日を1週間継続するという結果であった。この結果をわが国のSLE患者(体重50㎏と仮定)に外挿すると、重症例でおおむね45㎎/日を2週間、中等症例でおおむね25㎎/日を1週間投与が平均的ということになる。ただ、ステロイド初期用量については医師の間でも大きな違いがあることから、わが国の実態がどうであるかについては不明である。さらには、理想的なステロイドの初期用量が何㎎であるべきかについても明確な根拠はない。
初期治療後のステロイド漸減法は、1~2週ごとに10%程度漸減するのが従来は一般的であったが、この漸減法も経験に基づいて決められたものである。表1の重症例では、1週ごとに中央値で5~10㎎、中等症患者では5㎎の減量が始まり、その後の漸減速度もおおむね1週ごとに約10~20%であった。この調査の前提はステロイドの単独治療ではないわけだが、近年の、より早めの減量という臨床実態を示している。
2)維持量
Harrison内科学書には、PSL[プレドニゾロン]5~10㎎/日の連日投与または10~20㎎の隔日投与を通常行う維持投与として紹介されている。これに対し表1では重症例でも11週以降、中等症例は6週以降にステロイドを中止するとした医師が少なくない。ただし、この調査でも維持量を継続しているとした医師もおり、維持量の是非については専門医間でも一定していないことがわかる。
わが国で本間らが行った1,407例のSLE[全身性エリテマトーデス]の調査では、PSL5㎎/日未満あるいは中止した例の生命予後は、5~10㎎/日で維持していた例よりも有意に悪かった。また、Walshらは、抗好中球細胞質抗体(anti-neutrophil cytoplasmic antibody:ANCA)関連血管炎における再燃にかかわる因子を検討したところ、ステロイド中止例の再燃率が43%であったのに対し、維持投与例では14%と有意に再燃率が低かった。
これらの成績を合わせると、膠原病での実際的な対応としては、ステロイド漸減後も低用量を続けた方が長期管理にはよいことが示唆される。ただし、ステロイドの長期投与はほぼ全例に何らかの副作用を惹起することを考慮すると、患者の病態が数年安定していた場合などは、ストロイドの中止を検討すべきであろう。
エビデンスの使い方
以上述べてきたように、ステロイドの漸減法や維持量投与には明確なエビデンスがない。最近のより低用量の初期用量と早めの漸減を考慮すると、初期投与は2週間とし、その後はおおむね1週ごとに約10%の減量というのが現実的であろう。また、今後も検討が必要ではあるが、維持量投与は再燃率を若干下げる可能性がある。ただし、副作用を減らすという観点もあり、維持量投与を行う場合にもプレドニゾロン換算で5~10㎎/日、できれば5㎎/日以下をめざすことが望まれる。
Point
●ステロイドの漸減法には明確なエビデンスはないが、最近では初期治療2週間の後、おおむね1週間ごとに10%ほど減量することを勧めたい。
●維持量投与による再燃抑制効果については、観察研究によればプレドニゾロン換算で5~10㎎/日の投与は若干有用である可能性がある。
●維持量投与を行う場合でも、副作用予防の観点からは、疾患が安定していればプレドニゾロン換算で5㎎/日以下または中止をめざすのがよい。
第5章 腎疾患
ネフローゼ症候群に対するステロイド療法のエビデンスは?
クリニカルクエスチョン
ネフローゼ症候群は蛋白尿3.5g/日以上、血清アルブミン3.0g/dl以下で定義される症候群であるが、疾患は幅広く、おのおの治療法が異なるため、ここではネフローゼ症候群の代表疾患である微小変化型ネフローゼ症候群(minimal change nephrotic syndrome:MCNS)、巣状分節性糸球体硬化症(focal segmental glomerulosclerosis:FSGS)、膜性腎症(membranous nephropathy:MN)について下記クリニカルクエスチョン(CQ)として述べることとする。
●CQ1:微小変化型ネフローゼ症候群に対するステロイド療法は尿蛋白減少・腎機能低下抑制に推奨されるか。
●CQ2:巣状分節性糸球体硬化症に対するステロイド療法は尿蛋白減少・腎機能低下抑制に推奨されるか。
●CQ3:膜性腎症に対するステロイド単独療法は尿蛋白減少・腎機能低下抑制に推奨されるか。
エビデンスの実際
ここでは、平成22年度の進行性腎障害に関する調査研究班による「ネフローゼ症候群診療指針」、2012年の糸球体腎炎のためのKDIGO(Kidney Disease Improving Global Outcomes:[国際腎臓病予後改善委員会])診療ガイドライン、「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療指針2014」に従って述べる。
「エビデンスに基づくネフローゼ症候群ガイドライン2014」では推奨グレードを、A(強い科学的根拠あり、行うよう強く勧められる)、B(科学的根拠があり、行うよう勧められる)、C1[科学的根拠はない(あるいは弱い)が、行うように勧められる]、C2[科学的根拠がなく(あるいは弱く)、行わないよう勧められる]、D(無効性あるいは害を示す科学的根拠があり、行わないよう勧められる)の5段階に分けて記載されている。
また、KDIGOのガイドラインでは、推奨レベルを1(推奨する)、2(望ましい)、推奨グレードなしの3つのグレードに分け、エビデンスの質をA(高い)、B(中等度)、C(低い)、D(最も低い)の4段階に分け記載されている。
1)微小変化型ネフローゼ症候群
●推奨グレードB:MCNSに対する経口ステロイドは、初回治療において尿蛋白減少に有効であり推奨する。
●推奨グレードC1:MCNSに対する経口ステロイド単独使用は、急性腎障害の悪化傾向に有効であり考慮される。
MCNSは、一次性ネフローゼ症候群の約40%を占め、ステロイドに対する反応性は良好であり、90%以上の症例で、不完全寛解Ⅰ型に至るが、約30~70%程度に再発がみられ、頻回再発やステロイド依存性を示す症例が存在することが知られている。
ステロイド治療に対するRCT[Randomized Controlled Trial:無作為化臨床試験]のうち、成人例の報告では、腎機能に差はみられなかったが、尿蛋白は有意に減らしてとしている。
2)巣状分節性糸球体硬化症
●推奨グレードC1:FSGSに対するステロイド療法は、初回治療において尿蛋白減少・腎機能低下抑制に有効であり推奨する。
FSGSは、ネフローゼ症候群の約8%を占め、腎生存率(透析非導入率)は、20年で33.5%と長期予後は膜性腎症よりも不良である。ネフローゼ症候群から脱しきれない症例の予後がきわめて不良であるのに対して、不完全寛解Ⅰ型以上まで改善した症例の予後は比較的良好であることから、尿蛋白1g/日未満をめざして積極的な治療を行う必要がある。
初期治療による尿蛋白減少および腎機能低下抑制のRCTはないが、観察研究が数多くある。それらの報告のうち、特に成人の場合では、初回治療において副腎皮質ステロイド療法による完全寛解20~50%台に達し、不完全寛解も合わせると50~60%台となる。
Troyanovは、ステロイドの治療効果を完全寛解(complete response:CR)、部分寛解(partial remission:PR)、治療抵抗性(non-responder:NR)に分けた腎予後の結果、CR>PR>NRの順に有意に腎生存率が長期であったことを報告している(図1)。腎機能予後の改善には、尿蛋白を減少させることが非常に重要である。
※以下は本文には含まれていませんが、「寛解」に関する定義を把握する必要があると思いますので、掲載させて頂きます。(“難治性ネフローゼ症候群( 成人例)の診療指針”より)
ネフローゼ症候群の治療効果判定基準(厚生省特定疾患ネフローゼ症候群調査研究班 による)
●完全寛解:蛋白尿消失、血清蛋白の改善、および他の諸症状の消失が見られるもの
●不完全寛解Ⅰ型:血清蛋白の正常化と臨床症状の消失が認められるが、尿蛋白が存続するもの
●不完全寛解Ⅱ型:臨床症状は好転するが,不完全寛解Ⅰ型に該当しないもの
●無効:治療に全く反応しないもの
効果判定は、尿蛋白、血清蛋白、および他の諸症状が最も改善した治療開始後の時点で実施するが、治療開始4 ~8 週以内に行われるのが通例である。 不完全寛解Ⅰ型とⅡ型の境界は、ネフローゼ症候群調査研究班の診断基準では明確に示されていないが、1日の尿蛋白が1g以下になった場合を不完全寛解Ⅰ型とするのが一般的である。
3)膜性腎症
●推奨グレードC1:MNに対する経口ステロイド単独治療は、支持療法と比較して腎機能低下抑制に有効である可能性があり推奨する。
MNには、自然寛解が得られる症例もあり、比較的腎予後が良好な疾患と思われがちである。しかし20年長期腎生存率は、約60%と決して良好とは言えない。蛋白尿の経過と腎予後との間に密接な関係があり、不完全寛解Ⅱ型およびネフローゼ症候群は、完全寛解と不完全寛解Ⅰ型と比較して、有意に予後不良である。よって、尿蛋白1g/日以上の蛋白尿が遷延し、腎不全に至るリスクが高い症例では、積極的な治療を行うべきと思われる。
MNに対して、ステロイド単独治療の有効性を無作為化前向き比較研究(RCT)で評価した論文は少ないが、Cattran、Cameronらの論文がある。Cattranらは6カ月間プレドニゾロン45㎎/㎡を隔日投与したステロイド単独治療群と無治療群によるRCTを実施している。その結果、両群を比較して、8年間の経過観察では蛋白尿の寛解率と腎機能低下速度には有意差はみられなかったとしている。Cameronらは、約50名ずつの症例をプレドニゾロン隔日6カ月間投与群と無治療群によるRCTを実施し、3年間の経過観察をしているが、やはり蛋白尿の寛解率と腎機能低下速度に関して、両群間に有意差はなかったと報告している。
Shiikiらの厚生労働省研究班によるわが国の膜性腎症1,066例の後ろ向き調査では、ステロイド単独治療群(357例)、ステロイド+シクロホスファミド併用群(257例)、支持療法群(161例)の3群間で寛解率、腎予後を比較検討している。最終観察時では3群間における完全寛解、不完全寛解、無効例の比率には有意差は認められなかった。しかし、末期腎不全に至る腎予後を比較すると、ステロイド単独治療群とステロイド+シクロホスファミド併用群は支持療法群より末期腎不全に至る症例が有意に少なかった。ただし、ステロイド単独治療群とステロイド+シクロホスファミド併用群の両者における腎予後の差は認められなかった。
エビデンスの使い方
1)微小変化型ネフローゼ症候群
通常プレドニゾロン(PSL)0.8~1㎎/㎏/日相当(最大60㎎/日)で開始され、成人の場合小児より反応性は緩徐であるものの、早ければ2~4週間程度で尿蛋白減少の効果が現れ、また腎機能低下抑制に有効であるとしている。その後は2~4週ごとに5~10㎎/日ずつ漸減し5~10㎎/日に達したら最少量で1~2年程度継続中止する。
再発例では、初回治療と同量・同投与期間の治療、あるいは初回治療より減量したプレドニゾロン20~30㎎/日を投与する。頻回再発例、ステロイド依存例、ステロイド抵抗性ではプレドニゾロンに加えて、免疫抑制薬を追加投与する。図2にMCNSの治療アルゴリズムを示す。
2)巣状分節性糸球体硬化症
通常初期治療としてプレドニゾロン1㎎/㎏/日相当(最大60㎎/日)または隔日2㎎/日相当(最大120㎎/日)を少なくとも4週間投与することを推奨している。
再発例ではプレドニゾロン治療とシクロスポリンの併用を選択する。また頻回再発例、ステロイド依存例、ステロイド抵抗例ではシクロスポリン2.0~3.0㎎/㎏/日を副作用がない限り6カ月間使用し、少なくとも1年は使用、あるいはミゾリン150㎎/日を副作用がない限り2年間使用する。またはシクロホスファミド50~100㎎/日を副作用がない限り3カ月間使用可能とする。図3にFSGS治療アルゴリズムを示す。
3)膜性腎症
ネフローゼ症候群診療指針では、「わが国では、ステロイド単独による寛解例が少なくないので、ステロイドを第一選択薬として考えるべきである。」とされているが、欧米ではステロイド単独治療の有効性は臨床試験において十分なエビデンスが得られておらず、KDIGO糸球体ガイドラインでは、二次性膜性腎症を除外したうえで、ネフローゼ症候群患者のみに初期治療(ステロイドを中心とした治療)を行うことを推奨している。
糸球体腎炎のためのKDIGO診療ガイドラインでは初期治療としてさらに以下のような状態では、ステロイド治療を考慮することを推奨している。
①少なくとも6カ月間の観察期間中に、降圧療法や抗蛋白尿治療(ステロイド以外の)を行っても、4g/日を超える尿蛋白が持続し、初期の蛋白尿の50%を超える蛋白尿が残る場合(1B)
②ネフローゼ症候群に関連する重篤な症状、機能障害を伴う症状、生命予後に関係する症状がある場合(1C)
③6~12カ月間に血清クレアチニン値(SCr)が診断時に比較して30%以上増加するが、eGFR25~30ml/分/1.73㎡以下にはならず、かつ、この変化が合併症では説明できない場合(2C)
初期治療としてステロイドと経口アルキル化薬[制癌剤]を各月ごとに交互に6カ月間くり返す治療を推奨している(1B)
ネフローゼ症候群診療指針では、「MNでのステロイドの初期投与は他のネフローゼ症候群と比較してやや少なく、ブレドニゾロン換算で0.6~0.8㎎/㎏/日の服用が妥当で、年齢や合併症を考慮して増減が必要である。」とされている。図4にMNの治療アルゴリズムを示す。
KDIGO糸球体腎炎ガイドラインでは、「アルキル化薬と副腎皮質ステロイドによる治療に抵抗性の患者には、カルシニューリンインヒビター[免疫抑制薬]による治療を行うことが望ましい(2C)。」また、「再発例では、初期治療と同じ治療を再度行うことが望ましい(2D)。」とされている。
4)高齢者のネフローゼ症候群
高齢者ネフローゼ症候群に対して、副作用の発現に十分に注意して使用することを推奨する(ただし、高齢者ネフローゼ症候群に関しては、免疫抑制薬の有効性と安全性のバランスは十分に明らかでない)(推奨グレードC1)
POINT
●MCNS[微小変化型ネフローゼ症候群]に対して、ステロイド療法は寛解導入に有効性が高く、90%以上の反応率を示す。通常プレドニゾロン0.8~1㎎/㎏/日相当で開始し、その後は2~4週ごとに5~10㎎/日ずつ漸減し5~10㎎/日に達したら最少量で1~2年程度継続中止する。
●MCNS再発例では、初回治療と同量・同投与期間の治療、あるいは初回治療より減量したプレドニゾロン20~30㎎/日を投与する。MCNS頻回再発例、ステロイド依存例、ステロイド抵抗性でステロイドに加えて、免疫抑制薬を併用する。
●FSGS[巣状分節性糸球体硬化症]に対して、プレドニゾロン1㎎/㎏/日相当を少なくとも4週間の投与が推奨されているが、RCTによるエビデンスはない。
●ステロイド抵抗性のFSGSに対しては、免疫抑制薬を早期に併用し、すみやかなステロイドの減量を図るべきである。
●MN[膜性腎症]に対して、ステロイド療法は初期治療において有効であるが、ステロイド単独治療は無治療群と比較して尿蛋白減少効果に関して有意差を認めていない、自然寛解もありうるため、数カ月から半年間ステロイドなしで経過をみて、ネフローゼが続いている場合にステロイドを考慮するのが妥当と思われる。
●ステロイド抵抗性のMNには、免疫抑制薬の使用を検討する。
●高齢者に対しては、副作用の発現に十分に注意して使用する。
第10章 皮膚疾患
アトピー性皮膚炎に対するタクロリムス軟膏とステロイド外用剤の比較は?
クリニカルクエスチョン
アトピー性皮膚炎の治療において、皮膚炎を十分に制御できる抗炎症外用剤として有効性と安全性が十分に検討されているものには、ステロイド外用剤とタクロリムス軟膏がある。タクロリムス軟膏は、16歳以上の成人アトピー性皮膚炎患者には0.1%の製剤が使用されている。成人アトピー性皮膚炎の皮疹に対する効果は、どのランクのステロイド外用剤と匹敵するのだろうか。
エビデンスの実際
中等症から重症の成人(18歳以上)アトピー性皮膚炎患者972名を対象に、体幹・四肢に0.1%ヒドロコルチゾン酪酸エステル(ミディアム、Ⅳ群)を塗布する群と0.1%タクロリムス軟膏を塗布する群で、3カ月目の皮疹スコアを開始時のものと比較して少なくとも60%減少するか、をプライマリーエンドポイントとして比較した二重盲検無作為化試験では、0.1%タクロリムス軟膏群は0.1%ヒドロコルチゾン酪酸エステル群よりも高い効果を示した(72.6% vs 52.3%、P<0.001)。また、中等症以上の成人(16歳以上)アトピー性皮膚炎患者162名を対象にして国内で行われた二重盲検無作為化比較試験でも、0.1%タクロリムス軟膏は0.12%ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏(ストロング、Ⅲ群)と同等の効果を示した。概括安全度評価で「安全」の評価は両群で同等だったが、塗布部位の刺激感の発現率は0.1%タクロリムス軟膏の方が有意に高かった。この刺激感は大部分の症例で皮疹の改善とともに発現しなくなった。
エビデンスの使い方
日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガイドラインでは、中等度までの紅斑、鱗屑、少数の丘疹、掻破痕などを主体とする成人アトピー性皮膚炎患者の中等症の皮疹には、ステロイド外用剤ならばストロングクラスまたはミディアムクラスを第一選択とすると記載されている。タクロリムス軟膏は、成人アトピー性皮膚炎の皮疹に対して、ストロングクラスと同程度の臨床効果を有することから、中等症の皮疹にはストロングまたはミディアムクラスのステロイド外用剤あるいはタクロリムス軟膏を用いるのが妥当となる。一方で、タクロリムス軟膏の外用初期には、一過性の灼熱感やほてり感などの刺激症状がしばしば出現し、皮疹が改善するとともに刺激症状は消失していくことが多い。しかもステロイド外用剤を長期に使用した際にみられる皮膚萎縮の副作用がタクロリムス軟膏にはみられない。これらを勘案して、実際の臨床ではまずステロイド外用剤で皮疹をある程度軽快させた後に、タクロリムス軟膏に切り替えて長期の寛解を維持する方策がとられることが多い。より重症の皮疹に対しては、まずベリーストロングクラス(Ⅱ群)のステロイド外用剤で皮疹を改善させたのちにタクロリムス軟膏に移行することが推奨されている。
POINT
●タクロリムス軟膏は、成人アトピー性皮膚炎の皮疹に対して、ストロングクラスと同程度の臨床効果を有する。
●ステロイド外用剤を長期に使用した際にみられる皮膚萎縮の副作用がタクロリムス軟膏にはみられない。
●実臨床ではまずステロイド外用剤である程度軽快させた後に、タクロリムス軟膏に切り替えて長期の寛解を維持する方策がとられることが多い。
アトピー性皮膚炎に対するステロイド外用剤のランクと使用期間に関するエビデンスは?
クリニカルクエスチョン
ステロイド外用剤は、アトピー性皮膚炎に対する薬物療法の主体である。ステロイド外用剤は、現在国内では5つのランクに分かれており(表1)、効果の高さと局所性の副作用の起こりやすさは一般的には並行する。アトピー性皮膚炎の皮疹に対するステロイドの効果とランク、局所性の副作用とステロイド外用剤のランクや使用期間に関するエビデンスはあるのだろうか?
エビデンスの実際
1)アトピー性皮膚炎の皮疹に対する効果
ステロイド外用剤とプラセボ[偽薬]を比較した無作為化比較試験は20編を超え、ほとんどの試験でステロイド外用剤はプラセボよりも有効であることが示されている。一方で、0.2%吉草酸ヒドロコルチゾン〔米国の分類では0.1%ヒドロコルチゾン酪酸エステル(表1を参照:ミディアム、Ⅳ群)と同じランク〕などランクの低い一部のステロイド外用剤では、効果に統計学的な有意差が示されなかった。
2)ステロイド外用剤の局所性副作用
小児アトピー性皮膚炎患者に0.1%吉草酸ベタメタゾン軟膏(日本で販売されている0.12%ベタメタゾン吉草酸エステルはストロング、Ⅲ群)を1日2回、週3回18週間外用しても皮膚の菲薄化はみられなかった。健康ボランティアの前腕に0.05%クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム(ストロンゲスト、Ⅰ群)や0.1%ベタメタゾン吉草酸エステルクリームを1日2回、連日6週間外用したところ、皮膚の菲薄化がみられた。
エビデンスの使い方
ステロイド外用剤の選択に際しては、皮疹の経過に関する見通し、皮疹の重症度、皮疹の部位、患者の年齢などを勘案する必要があり、実際の診療ではアトピー性皮膚炎診療ガイドラインなどを参考にしてランクを決める。ほとんどのステロイド外用剤がアトピー性皮膚炎の皮疹に対して有効性を示した一方で、ランクの低い一部のステロイド外用剤では効果においてプラセボと有意な差がなかった。また、ある程度の強さをもつステロイド外用剤を連日長期間外用すると、皮膚萎縮などの局所性の副作用がみられる可能性がある。したがって、アトピー性皮膚炎の治療に際しては、皮疹の重症度や部位に応じて十分な効果が期待でき、かつ必要以上に強くない、適切な強さのステロイド外用剤を選択することの重要性がうかがわれる。
そして、適切なランクのステロイド外用剤を用いて皮疹を軽快させた後は、保湿剤を継続しつつ、ステロイド外用剤の外用回数を減らす、ランクを下げる、タクロリムス軟膏に切り替えるなど、外用部位に副作用が出現する可能性を減じながら寛解を維持する方策をとる。
一方、皮疹が軽快した後もステロイド外用剤やタクロリムス軟膏などの抗炎症外用剤を週2回程度継続するプロアクティブ療法の有効性が欧米を中心に報告されており、国内でも注目されている。
POINT
●ほとんどのステロイド外用剤がアトピー性皮膚炎の皮疹に対して有効性を示した一方で、ランクの低い一部のステロイド外用剤では効果にプラセボと有意な差がなかった。
●ある程度の強さをもつステロイド外用剤を連日長期間外用すると、皮膚萎縮などの局所性の副作用がみられる可能性がある。
●適切なランクのステロイド外用剤を用いて皮疹を軽快させた後は、ステロイド外用剤の外用回数を減らす、ランクを下げる、タクロリムス軟膏に切り替えるなど、外用部位に副作用が出現する可能性を減じながら寛解を維持する方策をとるのが肝要である。
感想
ステロイドコントロールとは、「患者さまの病状を正しく理解し、その上でステロイド外用剤の選択を行ない(強さ、部位などから)、また外用の期間、漸減、維持量(0gを含む)を病状の変化と副作用の両面を考慮しながら、必要な微調整を加え患者さまの最適な投薬法を見つける作業」ということではないかと思います。
また、腎臓病のネフローゼ症候群であれば免疫抑制薬があり、アトピー性皮膚炎であればタクロリムス軟膏という薬があるということも知りました。
鍼灸師として、これらの投薬に深入りすべきでないことは当然ですが、患者さまの直面している実態を理解するうえで、薬を知ることは大切な知識の一つであると思います。
追記
ステロイドとアトピー性皮膚炎について調べていて、興味深いサイトを見つけました。患者さまの症状によって対処は変わるものと思いますが、ステロイドコントロールの一例ということでご紹介させて頂きます。

こちらは環境再生保存機構さまのサイトに掲載されていた、”医療トピックス:アトピー性皮膚炎治療とセルフケアの最新動向”の中にあった図(アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2015の図を改変)です。
不整脈(心房細動)
今回は百寿者(母親)の事例ですが、趣旨は不整脈と薬について勉強したことをお伝えしたいというものです。
母親の不整脈は期外収縮と診断され、主治医の先生からは心配するものではないというお話でしたが、念のためワソランという薬を服用していました。
一方、数カ月前より食事回数がほぼ1日2食になってきたため、1日3回服用していた薬の見直しをすることにしました。特に年齢的な代謝機能の低下も考慮する必要があるだろうと思い、基礎代謝について調べてみると以下のようなサイトがあり、やはり加齢による基礎代謝低下は無視できないものと判断しました。そして、主治医の先生と相談し、薬の種類(ワソラン以外は慢性気管支炎などの気道に関わる薬2種)と量の双方から必須となるなものだけに絞り込んでいこうと考えました。

こちらのサイトは数値を入力すると基礎代謝量が計算されます。なお、計算式はハリス・ベネディクト方程式(改良版)だそうです。体重、身長、年齢の入力が必要です。
男性: 13.397×体重kg+4.799×身長cm−5.677×年齢+88.362
女性: 9.247×体重kg+3.098×身長cm−4.33×年齢+447.593

PAL(physical activity level)とは総エネルギー消費量を基礎代謝量で除した値で、身体活動量を示すものです。70歳以上も低下し続けることが確認できます。
画像出展:「e-ヘルスネット」厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト
主治医の先生には月1回診ていただいています。また、心電図検査は数カ月に1回行っています。診察時の脈診だけでなく、直近2、3回の心電図検査でも不整脈は出ていませんでした。もともと期外収縮は特に心配する必要のない不整脈という認識だったこともあり、ワソランは不要ではないかと考え、先生にご相談しました。その結果、「まずは薬を減らして様子をみましょう」ということになりました。
薬の量を減らすにあたり、今まで全くノーケアだったワソランについて調べてみたのですが、分かったことは、この薬は心房細胞・心房粗動、発作性上室性頻拍などの頻拍性不整脈および狭心症の治療薬であるという意外なものでした。
特に気になったのは、“心筋へのカルシウムの流入を阻害し心臓の拍動を遅らせる”という作用です(頻拍性不整脈に対する薬なので正しい作用ですが)。また、重大な副作用の中には次のような内容も含まれていました。
●『重大な副作用は循環器障害であり、心不全(徐脈、動悸、息苦しい)、不整脈(洞停止、房室ブロック)、徐脈(脈拍数が少ない)、意識消失などを伴う場合は使用中止します。』
実は半年前くらいに、血圧・心拍数低下、意識が朦朧とするという事態が一度だけですが起きていました。この時は、20分ほどベッドに横にし、その後再度測定したところ通常の数値に戻っていました。(これが薬の副作用によるものであるかどうかは不明です。おそらく、迷走神経反射ではないかと思います)
また、ワソランに関しては既に会員になっていた有償サイトの “アスクドクターズ” にも質問を出してみました。回答は「本当に期外収縮だとすれば、主治医に相談した方が良い」という主旨の指摘が複数ありました。
現在、ワソランの服用を止めて約2カ月が経過しましたが、脈に目立った変化は出ていません。一方、パルスオキシメーターによる酸素飽和度(SpO2)は、概ね91~93だった数値が93~95と感覚的には1.5~2ポイント程度改善されました。ただし、これがワソランの服用中止と関係しているのか、その関係性を証明するものは何もありません。仮にそうだったとしても、個人差があると思います。
下記の2つのサイトにワソランの詳しい説明が出ています。
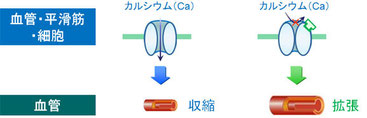
カルシウムは、脳では記憶、神経では痛みを伝えるなどの役割を担っています。そして、血管や心臓ではカルシウムは「収縮」に関わっています。
画像出展:「役に立つ薬の情報~専門薬学」
私自身も数年前に一度、不整脈(期外収縮)になったことがあり、24時間心電図も経験しました。なお、この時の不整脈は1カ月程続き、いつのまにかなくなりました。原因は睡眠不足とストレスだったのではないかと推測します。
今回、私自身の今後のケアのためにも、不整脈を詳しく勉強してみることにしました。図書館から借りてきたのは、『その心房細動、治しますか?付き合いますか?』と『不整脈・心房細動がわかる本』の2冊ですが、ブログは後者の『不整脈・心房細動がわかる本』の内容がほとんどです。

こちらの本からは、心房細動の進行度のグラフ、そしてカテーテルアブレーションを説明したイラストなど、計4つを掲載させて頂いています。
著者:山根禎一
出版:中外医学社
第3版発行:2014年10月
大項目は次の5つです。第4章以外の各章の中から書き出したい箇所を要約するかたちで列挙しています。
第1章 脈の乱れは普通のこと?
第2章 自分の不整脈の種類を確かめておこう
第3章 心房細動―ただちに危険はないが進行する
第4章 危険な不整脈―突然死を避けるために
第5章 期外収縮―治療しなくて大丈夫?
第1章 脈の乱れは普通のこと?
不整脈が起きるわけ:心臓を動かす電気信号が乱れると脈も乱れる
●心臓は電気信号の合図にしたがって収縮・拡張をくり返す。
●不整脈があるからといって、心臓そのものに問題があるとは限らない。
●心臓の動きをコントロールする電気信号は、さまざまな原因で乱れる。よって、不整脈はめずらしいことではない。
一瞬の症状はだれにでも起きる普通のこと
●健康な人でも1日のうち数十回は、期外収縮が起きているといわれる。多い人では1日に数千、数万にのぼることもある。(拍動は1日約10万回)
●起きやすい症状
1.一瞬、咳き込んでしまう。
2.ふいにのどがクッと詰まったような感じがする。
3.心臓がドクンと飛び跳ねたような感じがする。
4.脈が抜ける/脈が飛ぶ。
持続する症状や、めまい・失神に要注意
●1分間の脈拍数が100回を超えている、あるいは50回に満たない。
●1日に何度も不快な症状に見舞われる。
●動悸が続く(安静にしてもおさまらない)。
●息苦しくなって気が遠くなる。
一部の不整脈は脳梗塞・心不全・突然死の原因に
●不整脈にはさまざまなタイプがあり、中には命にかかわるものもある。
コラム:「心臓神経症」といわれた人へ
激しい動悸や胸痛があっても心臓に異常はない状態を「心臓神経症」という。
第2章 自分の不整脈の種類を確かめておこう
どう対応するかは不整脈の種類や原因しだい
●不整脈があっても、必ずしも治療が必要なわけではない。
●自分の状態に合わせて対応のしかたを決める
第3章 心房細動-ただちに危険はないが進行する
●心房細動は年をとるほど増える少々危険な不整脈。
1.年齢とともに起きやすくなる。
2.脳梗塞の原因になったり、心不全につながったりするおそれがある。
3.少しずつ進行していく。
4.治療できる。
心房細動のしくみ
●心臓のつくりは2階建てで部屋は4つ、1階は“心室”、2階は“心房”。2階(心房)の左(向かって右)の部屋は肺から送られてくる血液、右(向かって左)の部屋は全身から戻ってくる血液、役割はいずれも血液の一時置き場。そして、心房全体がリズムよく収縮をくり返すことで、溜まった血液が1階の心室に流れ込んでいくというしくみ。
●心房細動とは心房がぶるぶる震えるだけで、しっかり収縮できなくなった状態。
年齢、体質、全身の状態などが関係する
●心房細動は基本的には老化現象だが、それだけではない。
●年齢以外の要因
1.心臓の病気
2.肥満
3.生活習慣病
4.飲酒・喫煙
5.ストレス
6.遺伝的な体質
心不全との関係:心房細動が続くと心機能は低下していく
●心房が働かないから増える心臓の負担
●心不全で起きやすい症状
1.息切れ/呼吸困難:血液の流れが停滞し、酸素不足の状態に陥りやすくなる。
2.手足のむくみ:余分な水分は末梢に溜まりやすい。冷えも生じやすい。
3.倦怠感:酸素・栄養が十分に行き渡らないため、疲れやすくなる。
4.体重増加:尿量が減少し、余分な水が体内にたまる。
三つの観点から、とるべき方針を決める
●年齢
1.30~40歳代
薬を一生飲み続けるより、根治を目指す治療(カテーテルアブレーション)がすすめられる。
2.50~60歳代
自分の希望、心房細動以外に抱えている病気の有無などを考慮し、何を優先するか検討する。
3.70歳以上
無理に根治は目指さず、脳梗塞の予防や症状の軽減をはかりながらつきあっていく。
●症状
1.特に困ったことはない:「年齢」と「進行度」で判断する。
2.強い症状に苦しんでいる:薬物療法で和らぐこともあるが、根治を目指すことを考える。
●進行度(進行するほど、根治を目指すのは難しくなる)
1.発作性:薬物療法でもカテーテルアブレーションでも、正常なリズムを取り戻しやすい。
2.持続性:薬物療法でよい状態を保てる人は2割程度に。
3.慢性:薬物療法でリズムの調整は難しい。

『心臓細動は発作性心房細動から始まり、年間5.5%ずつ慢性心房細動へと進行してゆきます。そして、その進行は通常、クスリで抑えることは困難です。不整脈のクスリ(抗不整脈薬)は、一時的には心房細動の出現を起こさないようにすることはできても、治しているわけではありません。治っているように見えて、その陰で心房細動の本体は成長(増悪)していることも多いのです。一旦効いたクスリが徐々に効かなくなることもよくあります。その場合は、クスリの量を増やしたり種類を変えたりします。』
画像出展:「その心房細動、治しますか?付き合いますか?」

『「カテーテルアブレーション」という言葉の意味するところは、カテーテルを用いて「心臓の中の不整脈の原因部位を焼灼して治すことです。カテーテルとは、長い管の先で、焼いて治す治療法」ということができます。図に示しているように、実際にはカテーテル先端と患者さんの背中に張ってある電極パッチとの間に高周波電流を流し、接している局所に熱を加える原理です。電子レンジの原理とも類似しており、目的とする部位だけに熱を加えることができるのです。』
画像出展:「その心房細動、治しますか?付き合いますか?」

大きな分かれ道
『心房細動の患者さんは、必ずどこかで分かれ道に遭遇します。それは心房細動と(ずっと)付き合ってゆく道と、心房細動を治す道の2つです。心房細動と付き合ってゆく道とは、心房細動を放置するか、薬物治療を継続することです。本書の中でいろいろ紹介しているように、抗凝固薬、抗不整脈薬、心拍抑制薬などをずっと内服継続します。
一方、心房細動を治す道とは、手術を意味します。カテーテルアブレーション手術または外科手術を受けて、心房細動を根治させる道です。』
画像出展:「その心房細動、治しますか?付き合いますか?」
第5章期 期外収縮ー治療しなくて大丈夫
期外収縮とは:たまに起きるだけなら治療は必要なし
●対応の基本原則
1.原因となる病気の有無で方針は変わる。
2.生活習慣の改善が有効。
3.期外収縮だけなら基本は無治療
付記:高齢者と薬の副作用

こまめに副作用の検査を
『高齢者に薬を飲ませるときの注意は三つある。飲ませ方、飲む量、そして飲んでいる間の注意だ。
高齢者は、寝ている場合でも体を起こして薬を飲ませる。寝たまま飲んだり、水を使わないと、お年寄りは薬が肺に入ったり、のどや食道で薬が「途中下車」してしまい、肺炎や潰瘍などを引き起こす恐れもある。
薬は肝臓で代謝され、腎臓から尿に排泄されることが多い。そのため、一般に肝臓、腎臓が弱っている高齢者には特に注意が必要だ。検査で異常がなくても、高齢者は薬を排泄、解毒する仕組みが弱っていると考えてよい。
高齢者、とくに70歳を過ぎた人には、薬の量を成人の三分の二ぐらいに減らして飲ませる。副作用もなく効き目が悪ければ、普通の量にもどせばよい。
高齢者はいくつかの病気を持っていることが多く、いろいろな薬を一緒に飲んでいる。統計で調べると、飲んでいる薬の数が多いと副作用も出やすい。高齢者の間で薬の副作用が増えているのはこのためである。お年寄りは、副作用が出ても外部からわからないことがある。だから、薬を飲んでいる間は肝臓、腎臓の検査を中心に、健康人、成人よりも頻繁に検査することをすすめたい。』
著者:水島裕
出版:講談社
発行:2001年2月
ブログの冒頭で出てきた、抗不整脈薬の「ワソラン」は商品名であり、一般名としては「ベラパミル塩酸塩」といいます。下図の横棒グラフでは上から5番目です。これを見ると肝代謝が95%となっており、肝臓への負荷が高いことが分かります。

『抗不整脈薬は基本的に心筋の膜表面にあるイオンチャネル(イオンの通り道)に対して働きます。それは主にナトリウムチャネル、カルシウムチャネル、カリウムチャネルの3種類です。これらのイオンの通過を抑制させることで効果を顕すわけですが、効き過ぎた場合には心筋の電気的バランスを破綻させ、致命的な不整脈(心室頻拍や心室細動)を生じさせる可能性があります。そのことから、抗不整脈薬は諸刃の剣と呼ばれています。抗不整脈薬の効き過ぎを起こす原因は主として、高齢と、内臓機能低下(腎臓、肝臓)です。体内に入った薬剤がきちんと代謝排泄されるかどうかは腎臓、肝臓の機能に依っています。そこで大切なのは、使用している薬剤が腎排泄型か、肝代謝型かを知っておくことです。』
画像出展:「その心房細動、治しますか?付き合いますか?
飲水の重要性
サラリーマン時代は風邪で会社を休むことはほとんどなかったのですが、小学生の頃は2ヵ月に1回ぐらい、熱を出して近所の医院にお世話になっていたように思います。その時、必ずお医者さんに言われていたのが、「水を飲んでいるか!?」というフレーズでした。
今回の本を読むまで、コーヒーを水分だと思っていた私が言うものおこがましいのですが、患者さまに「水分を摂っていますか?」とたずねると、「なるべく摂るようにしている。」という回答の方が「あまり意識していない。」より多いと思います。飲水が重要だということを、うまく患者さまにお話できれば良いのですが、残念ながら知識不足でした。
そこで、今回も本に頼ることにしました。図書館から借りてきたのが「知って納得! 水とからだの健康法」であり、ネットで購入したのが「病気を治す飲水法」です。後者は本文の中から重要と思う箇所をそのまま引用させて頂きました。
民間療法に理解が深かったとされる岡田道一博士は水の正しい飲み方として、次の3箇条を紹介されています。
1.朝起きたら、コップ2、3杯の生水を飲む。
2.1日中に合計10杯の水を飲む。
3.病気になったら、薬の前にまず水を飲む。
また、京都大学名誉教授で日本水質保健研究所所長などを務めた川端愛義先生は、水は自然の健康飲料だといい、正しい飲み方をすれば健康維持に効果を発揮すると述べています。そして、川端先生は、「生水美容説」を唱え、その中でいくつかの根拠を上げられています。
1.水には人体の恒常性を維持する働きがある
人間の生理の基調にあるのは恒常性で、これがあるおかげで体温は常に36~37度を保っています。この恒常性は、水によって支えられています。また、ホルモン作用や酵素作用など、人体にとって大切な働きも水が重要な役割を持っています。美しさを根本で支え、保っているのが水、というわけです。
2.水には整腸作用がある
水は胃腸内の有毒・有害物質を排除して消化器の機能を調整する働きがあります。つまり、水には便秘にも下痢にも効力があるということです。美容の大敵といえば便秘です。水の整腸作用は、便秘を解消し美容に効果を上げるのです。
3.水は栄養を補給する
美容に必要な栄養やホルモンなどは本来、消化器を通して摂取され、体内でつくり出されるものです。それらが血液やリンパ液によって体中の組織に運ばれていくのです。そのためには、体内に十分な水分がなければなりません。いくら化粧をしても、体内の水分が不足すれば美しくはならないのです。つまり、水は内側からの化粧水なのです。
4.水は老廃物を排除する
人間のからだは食物と空気からエネルギーをとり、体内で必要な形に変えて活動しています。その過程では、つねに老廃物が生まれます。これらは速やかにからだの外に排出しなければ、美容はもとより健康をそこなうもとになってしまいます。水は汗や尿、あるいは便として、体内の老廃物を外に出し、健康と美容を保つために大いに役立っています。
5.水は肥満を予防する
水飲み法によって健康的なダイエットが実現可能です。
6.水は解毒作用を促進する
お酒を飲み過ぎたり、食べ過ぎたりしたとき、体内では解毒作用が行われます。このとき必要になるのが水の摂取です。水をとることで代謝活動が活発になり、しみ、そばかす、にきび、あるいはアトピー性皮膚炎のもとになる有毒物質の分解が進みます。健全な新陳代謝なしには肉体の若々しさも肌の美しさもあり得ません。この新陳代謝を調整するのが水なのです。要するに、いちばんの美容とは健康を保つことであり、そのために水は重要な役割をはたしているということです。
次の本は、今回購入したものです。著者の紹介などはブログの最後にある、訳者の林先生が書かれた『訳者あとがき』をご参照ください。

『関節痛、各種ヘルニア、アンギナ、喘息、うつ病、潰瘍、肥満、腫瘍、エイズに至るまで、元をたどれば、体細胞の内外の決定的水不足による代謝障害が原因であり、同一の原因にたどれる体内水不足の「叫び声」が痛覚となって現れ、もろもろの病名がつけられているというのです。その見事な説明がこの一冊に収められています。
収められている多くの治療レポートは、不安になっている病人に勇気を与えてくれるものです。細胞膜を通しての水の浸透メカニズムにおいて、水の分子だけが細胞内に浸透するため、治療に使うのは水道水で十分であると博士は説明しています。これも大切な点です。ペットボトルを買う必要はありません。飲みづらければ浄水器を付ければいいだけです。今日から水道水の蛇口をひねりましょう。』
著書:Fereydoon Batmanghelidj(バトマンゲリジ)
原版の題名:Your Body's Many Cries for Water
訳者:林 陽
出版:中央アート出版
目次は次の通りですが、太字の項目には説明をつけています。
CONTENTS(目次)
各界の賛辞
序 薬で渇きを処理するな
CHAPTER1 なぜ薬で病気が治らないのか
基本
変えるべきパラダイム
医学の誤診のもとを探る
CHAPTER2 新しいパラダイム
ライフステージごとの水の制御
理解を徹底させる
その他の作用
CHAPTER3 消化不良痛
結腸炎の痛み
盲腸の痛み
裂孔ヘルニア
要約
CHAPTER4 リウマチ痛
腰痛
首の痛み
胸の痛み
頭痛
CHAPTER5 ストレスとうつ病
水不足に関係する代償メカニズム
エンドルフィン
コルチゾン
プロラクチン
バソプレッシン
アルコール
RA(レニン・アンギオテンシン)系
CHAPTER6 高血圧
高血圧の原因としての水不足
CHAPTER7 高コレステロール血症
考慮すべき証言
CHAPTER8 肥満
過食を定義し直す
ダイエットソーダ
CHAPTER9 アレルギーと喘息
CHAPTER10 糖尿病
インシュリン非依存性糖尿病
トリプトファンと糖尿病
インシュリン依存性糖尿病
CHAPTER11 エイズ
エイズ研究の新展開
CHAPTER12 最も簡単な治療法
快眠
めまいの予防
心臓発作の予防
尿の色
病気治療に役立てる方法
塩ぬきダイエットの間違い
医療制度と私たちの責任
医療費の節減
おわりに
訳者あとがき
CHAPTER1 なぜ薬で病気が治らないのか
基本
・『体のどんな働きも、水の流れに監視され、それと一体になっている。それで、「水管理」だけが、適切な量の水と水に乗って動く栄養素を最重要器官に真先に届かせる、唯一の手段になる。このメカニズムは天敵と捕食動物に対抗するためにますます強化された。それは生死をかけた究極のシステムであり、今の競争社会においても同じように働いている。
体内水分配において避けられないプロセスの一つが、あらかじめ決められた量以上の水を受け取らないように、特定部位が厳しく管理されることである。それは体のどの器官にもいえることだ。
水を充当する系の中で最も優先されるのは脳である。脳は体重全体の50分の1を占め、血液の18.20%を受け取っている。水の制御と供給をあずかる因子が活発になれば、水不足の警報が鳴りはじめる。それは冷却水の不足した車がオーバーヒートを起こすようなものだ。』
・『文明社会では、茶、コーヒー、アルコール、製造飲料が水の代わりになると考えられているが、この考えが致命的なミスを生んでいる。これらの飲料には確かに水が含まれているが、脱水成分も含まれている。それが飲料水分だけではなく、体に貯蔵されている水まで排除してしまうのである。』
医学の誤診のもとを探る
・『現時点では、喉の渇きが体の水不足の唯一受け止められている信号である。しかし、この信号は極度の水不足が発する最後のサインであり、喉の渇きを示さない段階で、すでに慢性水不足が起きているのである。ビタミンC欠乏から起きる懐血症、ビタミンB不足から起きる脚気、ビタミンD欠乏から起きるくる病、鉄不足が起こす貧血症等、どんな欠乏障害とも同じく、その症状をもっとも有効に治療する方法は、欠乏した成分を補うことである。慢性水不足の合併症が認められれば、その予防と初期療法はきわめて単純である。
この研究は、私が1987年の国際癌学会に講演者として招かれ、パラダイム転換の情報を提供する前から医師仲間に評価されていた。次のページに載せるベリー・ケンドラー博士の手紙は、慢性水不足を病の発生源とする科学的見解の正しさを確認している。大部分の変形性疾患の原因が慢性水不足にあることを説明するために、私は多くの文献を参照したが、彼はそれも調べている。
医学書を参照するとなれば、千ページを超える書物に目を通さなければならない。だが、人間の主だった病の理由を述べる段になれば、どの説明も同じである。「原因不明」の一語で、すべてが片づけられているのである。』
CHAPTER2 新しいパラダイム
その他の作用(水には溶媒と運搬以外にも多くの性質がある)
・『体のすべての代謝機能に欠かせない加水分解の働き。化学反応が頼っているのは水である。種子を発芽させ、新しい植物へ成長させるのにも似た生化学作用がそれである。』
・『細胞膜での働き。細胞膜に浸透する水の流れから電力(ボルト)がつくられ、ATP(アデノシン三燐酸)とGTP(グアノシン三燐酸)という、二大細胞バッテリーに蓄えられる。ATPとGTPは人体の化学的エネルギー源であり、特に神経伝達のさいに分子交換に使われる。』
・『細胞の構造を繋ぐ接着剤に似た働き。水はニカワのように細胞膜の固形部を結合し、高い体温の下でも「氷」のように固める作用を持っている。』
・『体内蛋白質と酵素は、あまり粘り気の無い溶液の中で、有効に働く。細胞膜に存在する受容器(受容点)も同じである。蛋白質と酵素は、粘り気の多い(水不足状態にある)溶液の中では有効に働かない。』
・『脳で生産された物質は、水に乗って、神経終末部の目標地点にたどり着き、情報の伝達に使われる。神経には、情報を梱包して流す「極微細管」と呼ばれる微細な水路が存在する。』
この非常に興味深い神経線維内の水路について、ネット検索したのですが水路として解説されたサイトを見つけることはできませんでした。しかしながら、東京大学で「研究のショーウィンドウ」とされる、UTokyo Researchの中に、「細胞内輸送の解明にかける思い」という記事があり、そこに出ていた図が、よく似ているのでご紹介させて頂きます。(用語が微妙に違うのは原文を翻訳しているからかも知れません)

『これまで、記憶や学習の研究では、シナプスの受容体や、電位を調節するイオンチャンネルなど、神経細胞の表面にあるものばかりが注目されていたのですが、実は、細胞内部の輸送も大きく効いていることがわかりました」と廣川特任教授は胸を張ります。』
画像出展:「UTokyo Research」
『このように、体のあらゆる機能を調節しているのは水である。体の溶媒たる水が、そこに含まれる溶質の働きを含め、体内のあらゆる機能を調節しているのである。この新しい科学的真理(パラダイム転換)を、未来のあらゆる医学研究の基礎とすべきなのである。』
CHAPTER3 消化不良痛
裂孔ヘルニア
・『水を飲むと、飲んだ量に応じて、モチリンと呼ばれるホルモンが分泌される。水を飲めば飲むほど、腸からモチリンが生産される。モチリンが腸に与える効果は、腸のリズミカルな収縮、上から下へと向かう蠕動運動を起こすことにあり、腸の中身を流す弁を、随時開閉することも含まれる。
このように、体内に十分な量の水があれば、すい臓は重炭酸液を生産し、胃の酸性物を受けとれるよう腸を準備できる。この理想的条件の下で、幽門は開き、胃の内容物を吐き出せるのだ。モチリンはこの働きを調節する中心的伝令である。』 (モチリンについてはブログ「便秘(大蠕動)」でも触れています)
・『重度の水不足合併症で、かなり誤解されているのが、過食症である。 ~中略~ 過食症の人は、食べものを胃にとどめられず、すぐに吐き出す抑えがたい衝動に駆られる。それで「非社交的症状」と呼ばれる。彼らの「空腹感」は、実際には、渇きの信号であり、吐きたくなる衝動は、先ほど説明した保護のメカニズムからくる。過食症の人が十分に水を補給し、食事をとる前に水を飲むようにすれば、この問題は解消する。』
CHAPTER4 リウマチ痛
・『リウマチ関節炎とその痛みは、まずもって、患部の軟骨の表面が水不足に陥っている信号と見るべきである。関節痛は体の局所の渇きの信号であり、塩分の不足が一因を成していることもある。
関節の軟骨の表面には水分が多く含まれている。その潤滑機能のおかげで、関節が動くときに、対抗する面同士が自由に擦れ合う。骨細胞はカルシウムの層に浸っているが、軟骨細胞は水の豊富な基質に浸っている。軟骨の表面が擦れ合うと、細胞の一部が摩滅して剥がれ、骨表面の成長突起から新しい細胞が補充される。水の多い軟骨では摩滅する度合いは少ないが、水不足状態にある軟骨ではその割合が大きくなる。軟骨の再生と摩滅の割合が関節が有効に働く指標になる。
骨髄で活発に成長する血の細胞は、骨の中を通る水を軟骨に優先させる。血量を増やそうと血管を膨らませるときに、骨の硬い穴を通る支脈が十分に広がらないことがある。水と栄養を血管に頼る細胞には決まった割り当てがある。この状態で、より多くの水を運べるよう血が希釈されていなければ、軟骨に必要な血清を、関節嚢の血管から補給せざるを得なくなる。どの関節にもいえることだが、神経がつかさどるこの迂回メカニズムが痛みの信号を出す。
関節痛は関節が十分に水和されるまで圧力に耐えられない合図である。この種の痛みは飲む水の量を増やすことによって扱うべきである。そうすれば、一帯に流れる血は希釈され、軟骨に十分に水が行き渡り、骨に接する基礎から修復される。』
CHAPTER5 ストレスとうつ病
水不足に関係する代償メカニズム
・『水不足から起きてくる体内プロセスはストレスのそれと変わらない。水不足はストレスに等しいのである。ストレスが起きれば、それに関係する基本物質が体の貯蔵庫から引き出され、蓄えられている水も引き出される。水不足がストレスを、ストレスがさらに水不足を起こす悪循環がここにはじまる。』
・『ストレス状態にあるといくつかのホルモンが過剰になる。体は「戦いか逃走か」の反応に向かって動き出し、危険な状態になる。体は人間の社会的変化とは無関係に、職場のストレスを含め、どんなストレス状態にあっても、「戦いか逃走か」の体制をとろうとする。ここで、いくつかの強いホルモンが分泌され、体がストレスからぬけ出すまで発動状態になる。その主なものが、エンドルフィン、コルチゾン解放因子、プロラクチン、バソプレッシン、レニン・アンギオテンシンだ。』
RA(レニン・アンギオテンシン)系
・『RA系は脳内ヒスタミンの発動に従属するメカニズムである。RA系は腎臓でも活発に動いているが、発動するのは体水量が減少したときである。RA系は水を保つために発動し、それに必要な塩分の吸収をうながす。水でもナトリウム(塩)でも、体に不足すれば、RA系が非常に活発になる。
RA系は、水とナトリウムが十分に使える量になるまで、毛細血管床と脈管系を収縮させる。それは血管系が淀みを起こさないためだ。測定可能なほど収縮が進めば「高血圧」と呼ばれる。血圧200で高いと思われるだろうか。私の診たイラン人は、高血圧の病歴がなかったが、政治犯収容所に送られたときに、血圧は300を超えていた。
ストレスが血管を縮ませる理由は簡単だ。人体の機能はすべてが絡み合っている。ストレスが起きれば、蛋白質、でんぷん(グリコーゲン)、脂肪などの貯蔵物質を出すために、水が使われる。その不足した水を補うために、RA系はバソプレッシン等のホルモンと力を合わせて、血管を収縮させる。
腎臓はRA系が活動する主な部位である。尿を生産し、余分な水素、カリウム、ナトリウム、老廃物を排出する責任を負っている。腎臓は、尿を生産するのに十分な水量に応じて、その働きを保つ必要がある。腎臓には尿を濃縮する力があるが、常時濃縮されていれば、腎臓を壊す原因になる。』
・『腎臓障害は、長期的な水不足と塩分の欠乏により、RA系が発動している結果かもしれないのである。今まで、血管の収縮が体の水不足のサインと見られることはなかったが、いまや、体液のアンバランスを、移植も含む一部の腎臓疾患の主な原因と見なすべきときにきているのである。一度RA系が動き出せば、自然な停止装置が働くまで止むことはない。自然な停止装置の成分が水と若干の塩である。』
・『コーヒー、紅茶、コーラを水の代用にしていればどうなるか。コーヒーと紅茶の天然刺激物には、大量のカフェインと、やや少ないセオフィリンが含まれている。これらは中枢神経系を刺激するだけではなく、腎臓に強い利尿作用を起こす水不足の因子である。コーヒー一杯には85mg、紅茶には約50mgのカフェインが含まれている。このように、カフェインは体内エネルギーを解放する力に作用する。その結果は誰でも知っているが、問題は体が望まないのに無理にエネルギーを解放することを知ることである。貯蔵エネルギーは減少し、一部のホルモンと神経伝達物質の働きが制御できなくなる。カフェインは、体の貯蔵エネルギーが低下するまで徹底的に作用する。』
・『カフェインはよい働きをすることもあるが、水の代用にばかりしていれば、水力エネルギーを生む力を体から奪ってしまうのである。カフェインのとりすぎは脳と体のATP貯蔵エネルギーを枯渇させる。これがコーラ世代の若者の注意散漫、コーヒー世代の大人に慢性疲労を起こす一因になっている。また、カフェインをとりすぎれば、心筋を刺激しすぎて疲労を起こす。』
CHAPTER6 高血圧
高血圧の原因としての水不足
・『水を十分に飲み、体の要求すべてに応じるようにしなければ、体内の水の一部が血管にとられ、一部の細胞が水不足になる。それまで緩んでいた血管床は、収縮し、閉鎖に追い込まれる。体の水が不足すれば、細胞内で66%、細胞外で26%、血液では8%水が失われる。血管が血を失わないためには管腔を閉じるしかない。あまり使われていない毛細血管を閉じることによりこのプロセスが始動する。毛細血管を常時開かせるにはどうすればよいのか、水を外部から補うしかない。
毛細血管床がどれほど働いているかが、そこに流れる血の量を決定する。筋肉を使えば使うほど、その部分の毛細血管も開き、血流も増大する。高血圧の患者に運動が最も欠かせない理由がそこにある。毛細血管床を常に開き、血の流れを円滑にする必要がある。血管床を閉ざすもう一つの原因が水不足である。飲んだ水は最後には細胞に入る。水は細胞の体積を内側から調節し、塩は細胞外の水の量を調節する。それは細胞を囲む海のようなものである。』
訳者あとがき(冒頭の部分になります)
『この本はイラン革命で政治犯収容所に送られた医師が、薬の得られない環境の中で三千人の患者を水だけで治療した経験を基礎に、医学、生理学の見地から、本格的に体内水代謝の複雑な機構と、水による各種疾患の治癒プロセスを解明し、世界に先がけて公表したものです。
著書のバトマンゲリジ博士は、イラン生まれの医師で、イギリスの大学で医学を学び、医師の資格を得ました。祖国にもどり、各地に診療所をつくる仕事に従事した頃に、イラン革命が勃発し、政治犯収容所で病人の世話をすることになりました。
薬が満足に手に入らない収容所の生活で、重い胃潰瘍の患者に水を飲ませただけで痛みが消えたのに、非常な驚きを感じます。「医師としていろいろな臨床の場に接してきたが、このようなことははじめてである。」と、回想しています。
博士はこのできごとを機に、三年間にのべ三千人を超える患者に、薬のかわりに水を処方し、痛みを消して治癒させることに成功しました。そして、この予想もしない経験に医療の重要な突破口を見い出し、アメリカで本格的研究に入ります。賛同する医師仲間を集めて、「シンプル・イン・メディシン財団」を創始、飲水による症状の解消と無用な医薬品の常用への抵抗運動を推進しました。
博士がまっ先にはたらきかけたのは、全米医師会と国立衛生研究所でした。しかし、製薬産業と切っても切れない仲である二つの機関が、博士の提案を受け入れるはずもありません。医師会に絶望した博士は、自費で財団から機関誌を刊行し、著書も次々に出して、国民に直接訴えかける仕事に着手しました。ペルシャ語版と英語版で製作に着手した記念すべき最初の一冊が本書です。~以下省略~』

こちらが、バトマンゲリジ先生(Fereydoon Batmanghelidj)です。
英語になりますが、”watercure”というサイトに多くの情報が掲載されています。
付記(2018年12月4日):ネフローゼ症候群における飲水の問題
腎臓病と飲水の関係を調べていて、ネフローゼ症候群の場合の注意点として飲水のことが書かれていた情報を見つけ、今回あらためて調べてみました。
参考としてのは「日本腎臓学会 ネフローゼ症候群診療指針」です。クリックして頂くと、”難病情報センター”の”一次性ネフローゼ症候群(指定難病222)”というページが表示されます。そして、このページの最下部の”10. この病気に関する資料・関連リンク”の下に、このPDF資料をダウンロードさせるリンクが付いています。なお、この資料は100ページを超える大容量のものになります。
飲水に関しては14ページに出ており、その内容は以下の通りです。(青字がポイントです)
Ⅲ浮腫の治療および腎保護を 目的とした治療
1 浮腫に対する治療
2) 塩分制限・水分制限
水分制限:『水分制限の有用性に関しては明確ではない。十分な塩分制限下では、本来、厳密な水分制限は不要であるが、利尿薬使用下で低ナトリウム血症となる場合は制限が必要であると考える。
浮腫を増悪させないための水分制限は、食事中の水分を含む総水分量として前日尿量+500 mL
(不感蒸泄量−代謝水)がひとつの目安となる。実際には、毎日体重を測定したうえで,制限を
調整することが大切である。』
付記(2021年7月21日):カフェインの脱水作用
朝の番組でカフェインの耐性についての話を耳にしました。飲水について水には劣るがカフェインの入った緑茶などでも摂取すべきであるとのことでした。この背景にあるのがカフェインに対する耐性ということのようです。ネットで探したところ、興味深いページを見つけましたのでご紹介します。
重症五十肩(肩関節周囲炎)
重症五十肩の患者さまに来院頂いています。初診のときに肩関節の可動域を確認させて頂いたところ、屈曲(腕を前に振り上げる)については何とか30°程度ありましたが、伸展(腕を後ろに振り上げる)も外転(腕を横に上げる)も、自力ではほとんど動かすことができませんでした。人とのすれ違いでは、肩が軽くぶつかっただけで激痛のためうずくまってしまうということです。夜間痛は最も何とかしたい痛みでしたが、仰臥位(あお向け)になっただけで肩がずれるような感じがあり辛いとのことでした。そのため、施術では肘から下を小さな枕に乗せて頂くようにしました。家事や日常生活では、シャツの着替え、洗濯物を干すこと、髪を後ろで結ぶことなどはひとりではできないため、家族の方に手伝ってもらっていたそうです。
痛みの強さなどから、亜脱臼や腱板損傷も考えられましたが、二つの病院でのX線による診断はいずれも五十肩とのことでした。
下記の4つの絵は、“「肩」に痛みを感じたら読む本”からの出展です。左上は前方の「屈曲」と後方の「伸展」ですが、それぞれ可動域は180°と60°と定義されています。右上は外側に開く「外転」と内側にクロスする「内転」を示しています。「外転」の可動域は180°です。
下段は「水平内転」・「水平外転」、および「内旋」・「外旋」の説明となっています。すべて、クリックして頂くと拡大されます。
初診は昨年10月後半、治療回数は4月末の段階で25回に達しており、成果については十分とは言い難いのですが、夜間痛はなくなり痛みは我慢できる程度に改善されたため、家事および日常生活に関しては、家族の方に手伝ってもらうことなく、すべてご自分でできるようになりました。
そして、今一番何とかしたいことは、バスや電車のつり革を握って体を支えられるようになることです。
四十肩、五十肩は何もしなくても1年程度で治癒すると言われていますが、この患者さまの状態を拝見した時、「本当にそうだろうか?どうやって自然治癒するのだろうか?」という疑問を持ちました。そこで、1冊は図書館、1冊は購入と2冊の本から学ぶことにしました。
最初に読んだ本は“肩が痛い、腕が上がらない 五十肩”です。ポイントになると考えた部分をまとめました。
・早い人で3ヶ月~半年。長い人は1年ぐらい。運動制限が非常に強い人は、さらに長くかかる傾向がある(急性期[炎症期]1~2ヵ月ー慢性期[拘縮期]2~4ヵ月―回復期3~6ヵ月)。
・ある日突然くることもあるし、じわじわくることもある。どちらかといえば後者がほとんど。
・痛みと同時に肩の腫れや熱っぽさを伴うこともある。痛む場所は肩から上腕にかけてが多い。
・初めは肩を動かすときに痛むだけだが、症状が進むと動かさなくても肩が疼くように痛み思うように腕が上がらなくなる。
・時間がたつと炎症は治まってくるが、その過程で線維性の物質が出てきて、腱板の周囲が癒着し肩の動きが悪くなってしまう。
・原因ははっきりわかっていないが、腕を上げた状態で長時間の作業をしたあとに起こりやすい病気だということは言える。樹木の手入れや大掃除で高い場所を拭き続けたあとに発症することがよくある。ものを持ち上げようとした瞬間や、テニス、ゴルフのスイングなどの最中に突然激痛におそわれ、それ以降、肩を動かすたびに痛むケースも多い。また、無理な姿勢をとったり、打ち身を起こしたことから五十肩になったという場合もある。
・腱板は痛みやすい環境にある。線維組織は加齢とともにちょっとした力で傷ついて、炎症を引き起こしやすくなる。しかも、もともと血管が少ない部位で、いったん傷つくと修復されにくい性質がある。
・腱板の中でも棘上筋の腱板は構造的に炎症を起こしやすくなっている。腱板が炎症を起こすと、滑液包や関節の内部にも炎症が波及するのが五十肩の原因であろうと考えられている。
・重症のケースで、治療期間を短縮したい場合は手術を選択することもある。(関節鏡視下受動術)
もう1冊は、“「肩」に痛みを感じたら読む本”です。
こちらの本は5つの章に分かれていますが、その5つは以下の通りです。
第1章 わずかな肩の痛みでも“手術”につながるリスクが潜む
第2章 知らないでは済まされない「肩」の基礎知識
第3章 手遅れになる前に、まずはチャック!「Yes/Noチャート」で“実は気づいていない重症度”を30秒診断
第4章 今すぐ実践!重症度別「肩治療&ケア」
第5章 早期に治して痛みのないアクティブライフを送る
この中で、今回のブログに取り上げたのは第1章と第2章に関する項目になります。こちらもブログに残しておきたいと思った個所の要点を書き出しています。
第1章 わずかな肩の痛みでも“手術”につながるリスクが潜む
肩の痛みを訴える人が低年齢化している
・現在も原因は不明であるが、その発症によって肩関節の組織に変性が起きてくること(退行変性)と、それによって肩関節の周囲に炎症が起きることが影響していると考えられている。
・ほとんどの場合、1年前後で自然と治ってしまうが理由は解明されていない。
・自然治癒が期待される疾患のため、来院されることが少ないため患者数の把握が難しい。
・最近では30代で肩の痛みを訴える人が増えている。肩凝りは四十肩・五十肩の予備軍である。
・肩凝りは筋肉疲労によるが、四十肩・五十肩は関節の周囲で起こる炎症が原因の症状。両者を見極めるポイントの一つが肩を動かせるかどうかということ。
・多くの場合、肩関節への負担が長期にわたって蓄積されることで炎症を引き起こすので、姿勢の問題やパソコンやスマホのように肩関節に負担を強いるような日常生活は将来的な発症につながるリスクになる。
・肩凝りと四十肩・五十肩は別物だが深く関わっているため、肩が痛くて腕が上がらなくても肩凝りと勘違いしている人も多く、肩凝りで医療機関を受診するのは気が引けると思って放置してしまうことが多い。
・対処法を間違えると肩が硬くなって動かなくなる。
・[専業主婦Aさんの事例]:『~~中略~~ ところが、痛みは取れたものの、ずっと肩を動かさずにいたことで硬くなり、腕が上がりづらくなってしまったのです。洗髪やドライヤーをかけたり、エプロンを後ろで結ぶことができないなど、日常生活動作(ADL)に難儀するようになりました。それでも、五十肩がまだ完全には治っていないからだと思い込み、回復すれば腕が上がるようになると信じて、無理に動かして再発しないようにと不自由な生活を続けていました。
そんな生活が1年半ほど続いた頃、一向に良くなる気配がなく、むしろ肩が固まって完全に動かなくなったため、さすがに「これはおかしい」と感じて来院されました。
Aさんの話から、罹患期間が2年近くに及ぶことからMRIを撮って確認したところ、骨には異常がなく、確かに五十肩ではありました。しかし、拘縮を起こしている状態で、いわば五十肩の終末像といえる状態ですので、もはやリハビリだけで治すのは困難となり、年齢的なことを考えると手術をしたほうが良いとお勧めしました。
人生80年の時代ですから、Aさんの人生もまだ30年以上あります。残りの人生を有意義に過ごすためにも、ここは手術を受けるのがベストと考えたAさんは、手術を受けることにしたのです。
幸い、Aさんの場合は内視鏡による手術で済みましたので比較的負担も少なく、その後もリハビリのために通院し、半年後には肩の柔軟性が回復して腕が上がるようになりました。
Aさんは、ただの五十肩だと軽く見て対処法を間違えたために、手術をしなければならない事態にまで進んでしまいました。』
自然には治らない四十肩・五十肩がある
・四十肩・五十肩は、年齢に関係なく仕事の内容や生活習慣によっては、誰でも起こり得る疾患である。自然に治る人がいる一方、Aさんのように初期の段階で適切な治療を行なわないと、肩が固まって動かなくなるケースがある。
・自然には治らない四十肩・五十肩には、腱板が部分的あるいは完全に断裂しているために、痛みが取れないケースがある。これはX線画像では軟部組織である腱の状態を正しく判断するのが難しいためである。従って、痛みが強い場合はMRI検査の実施が望ましい。また、腱板が損傷する原因の中には、四十肩・五十肩において、肩を動かさないと硬くなってしまうからと、痛みが残っているのに無理な運動を続けたことで症状が悪化し、ついには腱板が切れてしまうこともある。
肩関節の専門医は意外と少ない
・当院(麻生総合病院)には肩の痛みを訴えて受診する人が年間約1200名、その1割が腱板断裂である。罹患期間も2年以上という人が多い。
・日本肩関節学会に所属している肩関節の専門医は全国で1600人しかいない。
・専門医でなかったり、MRI装置を持っていない場合はX線画像だけの判断となるため、腱板損傷を発見できず、通常の四十肩・五十肩と診断されることもある。
第2章 知らないでは済まされない「肩」の基礎知識
頼りない肩関節を補強しているインナーマッスル
・肩関節は広い可動域がもつが、骨格による支えはすくなく安定性に問題がある。そのため、その問題を回避するために活躍しているのが筋肉や腱、靭帯、関節包などの軟部組織である。深層にあって肩関節を安定させると共に、微妙な動きをコントロールしているのがインナーマッスルの棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋である。これらの筋肉の両端から出ている「腱(結合組織)」は、他の部分の腱よりも長く、板状をしているため腱板といわれているが、これらの4つの筋群は上腕骨を取り巻いているため、「ローテーターカフ(回旋筋腱板)」とも呼ばれている。
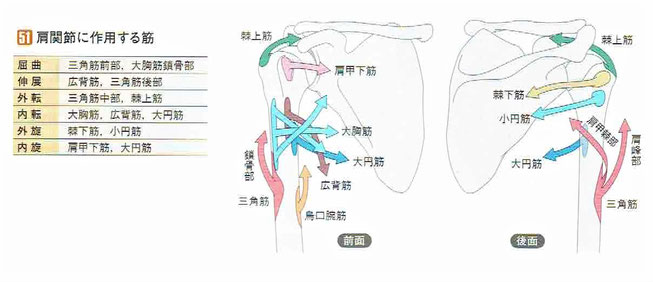
肩甲骨を前(腹側)から補強する「肩甲下筋」、後ろ(背側)から補強する「棘下筋」と「小円筋」、前後から補強する「棘上筋」のローテーターカフに「三角筋」を加えた5つの筋が治療の基本です。
画像出展:「人体の正常構造と機能」
・加齢に伴い腱板機能が劣化したり、姿勢や生活習慣の影響で肩甲骨機能が低下すると、肩関節の中が不安定になり、ちょっとした動作が関節包を刺激し傷つけ、炎症を起こすことがある。この状態がいわゆる四十肩・五十肩の痛みの強い時期になる。炎症が治まると傷ついた関節包は縮こまった状態で治癒するが、この時期が四十肩・五十肩の動かなくなった時期(拘縮期)になる。また、加齢によって皮膚の弾力性が失われ、たるみやシワができるように、肩の軟部組織も年齢とともに弱くなって傷つきやすくなる。ちょっとした刺激でも傷つき、狭い空間で炎症を起こして腫れる。そうなると、痛くて腕を上げることは困難になる。ときには弱くなったインナーマッスルが切れる、腱板断裂にいたる。
体の表面を覆っているアウターマッスル
・アウターマッスルはインナーマッスルの筋群を覆って肩の強度を高めているおり、三角筋や僧帽筋などがある。
・日常生活では、肩を大きく動かす動作をすることは少ない。また、肩甲骨を支えて腕を引き上げる働きをしている僧帽筋は、腕の重さを支えるために、ある程度の力で常に収縮し緊張した状態にある。そのため血液循環が悪くなりがちであり、筋膜の癒着が起こりやすい。
・四十肩・五十肩は関節包やインナーマッスルに起こる炎症であり、肩凝りはアウターマッスルに起こる血行不良と筋膜の癒着といえる。
筋肉が緊張するとなぜ血流が悪くなるか
・筋線維が緊張すると、筋線維の1本1本が太く短くなって筋線維を包んでいる筋膜を圧迫し、筋肉はパンパンになる。このため筋膜の中では筋線維どうしの押し合いとなるが、その圧力で押しつぶされるのは筋線維の中を通っている血管や神経である。そのために血流が悪くなり筋肉は硬くなる。特に静脈の血管は力強い動脈とは異なり柔らかいパイプである。そのため、筋線維の圧力で簡単に押しつぶされ、うっ血を起こす。しかしながら、筋肉が緊張と弛緩を繰り返す場合においては、この圧迫と解放の連続は静脈に流れる血液を心臓に送り返す働きとなる。もし、緊張だけが一方的に続くと、新鮮な血液を送ることも、老廃物を回収することも困難になる。
炎症が起こるとなぜ痛みが生じるのか
・炎症が起こっている肩周囲には、免疫に関わるたくさんの細胞が集まっている。四十肩・五十肩の場合は、病原体が原因で起こる疾患ではないが、炎症が起きているところには異変を察知した免疫細胞が集まっており、治そうと働いている。この免疫に関わる細胞には色々な種類があり、それぞれに役割が異なる。中には、炎症や発熱を促す働きをしている細胞や、痛みを誘発する物質(発痛物質)を分泌させる細胞もある。その一方では、炎症や痛みに関わる物質を中和し、鎮静化させる働きを持った細胞もある。炎症が起きて痛いときには、それに関わる細胞が優位に働いており、炎症が治まり痛みが和らいできたときには鎮静化させる細胞が活発に働いているのである。つまり、炎症は一種の防御反応であり、治る過程で起こる現象ともいえる。
付記1:「臨床家のためのトリガーポイントアプローチ」
トリガーポイントを広められた黒岩先生の著書である「臨床家のためのトリガーポイントアプローチ」の中に五十肩の治療に関する記述がありましたので、一部をご紹介させて頂きます。
・五十肩は、治療一回目に劇的改善が得られることがまれな難しい症状である。試行錯誤的刺鍼を繰り返した結果、治りにくい理由として言えることは、大量の責任トリガーポイントの広範囲な分布である。責任トリガーポイントの形成頻度の高い筋は三角筋、肩甲下筋であるが、慢性化・重症化して来院した患者であれば、肩甲間部、肩甲帯(特に腋窩後壁を走行する回旋筋群)、上肢、さらには前胸部の筋にも処置の必要な責任トリガーポイントが認められる。
・五十肩の治療で最も重要なことは肩以上に頚と背中、特に大椎近傍の夾脊穴などの刺入である。これは夜間痛がある場合は必須である。(「大椎近傍の夾脊穴」とは、第7頚椎棘突起と第1胸椎棘突起間にあるのが大椎というツボですので、このツボの上[頚]と下[背中]にも刺鍼するということです)
・五十肩で一番多いのは、自発性に肩の前方が痛むタイプである。腕を挙げたり(屈曲・外転)、内旋しても痛む、すなわち運動痛もある。増悪すれば夜間痛も発現し苦しむことになる。
本来はこの前部の痛みが三角筋トリガーポイントによるものか棘下筋からの関連痛かを鑑別する必要があるが、現実的にこの作業は非常に難しいため、臨床では拘らない。実際は、まず棘下筋を徹底的に攻めて棘下筋トリガーポイントを探すことである。そのためには、肩甲骨外縁とほぼ平行に内下方外上方に走る索状硬結と、その内側にある500円硬貨位の円盤状硬結を丁寧に触擦する。次に肩甲棘の外1/3あたり下縁から、三角筋粗面に向かって走る三角筋後部線維中の硬結とその中のトリガーポイントを検索する。この2つの硬結部のトリガーポイントに刺鍼して、肩の前の痛みが再現されたら、三角筋の後部線維、棘下筋を中心に治療する。もし、関連痛が起こらなかったり、関連痛が肩前面に放散しない場合には、三角筋の前部線維と肩甲下筋形成トリガーポイントを疑う必要がある。

最も多い、肩の前方が痛むタイプに関して、施術に迷ったならば、まず棘下筋に注目することを黒岩先生は推奨されています。
画像出展:「臨床家のためのトリガーポイントアプローチ」
付記2: fasciaリリース治療 (ブログ参照:「エコーガイド下fasciaリリース」)
注)当院ではエコー(超音波診断装置)を利用した治療は行っておりません。
Fascia(ファシア)とは、線維性結合組織の総称であり。皮膚、皮下組織、筋膜、腱、靭帯、脂肪体、腹膜、髄膜、骨膜すべてが含まれる。とされています。そして、fasciaリリース治療は原因となっている癒着部位に働きかけ解放するというものです。
例えば、四十肩・五十肩は関節包周囲での癒着は可動域に制限をもたらしますが、それは上図のように筋膜どうしだけでなく、筋膜と骨膜、筋膜と浅筋膜(皮下組織)、腱と骨膜など様々な組織間で癒着が生じる可能性があります。
エコーで画像を確認しながら鍼を使ってfasciaリリースを行っている先進的な鍼灸院はすでにありますが、より効果的な処置は、医師による注射(生理食塩水など)を用いる方法です。
下の写真は棘下筋に対するfasciaリリースを行っている様子です。いずれも「Fasciaリリースの基本と臨床」の画像です。クリックすると拡大されます。
課題は「fasciaリリース」を行っている整形外科がまだまだ極めて少ないことです。
埼玉県では羽生総合病院の和漢診療科などで行われています。以前からfasciaリリースに関心が高かったこともあり、疲れがたまってくると不穏なギックリ腰対策のため、昨年12月、約1時間の東北道をドライブし和漢診療科で治療を受けてきました。患部が腰部のため、残念ながらエコーに映し出された自分自身の画像を見ることはできませんでしたが、刺針時の痛みはほとんど無く、注射液が注入される感覚を体験できました。その後4ヵ月、気になるレベルの不穏な状態は発生していません。
なお、「fascia」と「トリガーポイント」をどう位置づけて理解したら良いのかについては、「Fasciaリリースの基本と臨床」の中で次のような説明がされています。

『トリガーポイントはあくまで生理学的に定義された用語(過敏となった侵害受容器)であり、治療“部位”検索としての解剖学的な位置を示す用語としては適切ではない。トリガーポイントが存在する場所は基本的にfasciaであると想定しているため、治療部位検索の上でトリガーポイントという用語は本書では用いていない。さらに、fasciaの異常(例:炎症性、mechanically-insensitive
afferentsによる機械的痛覚過敏、滑走性・伸張性障害)による症状を包括するための概念としてもトリガーポイントだけでは不十分である。』
腸内フローラ(腸内細菌叢)
腸内フローラと腸内細菌叢は同じものですが、「細菌叢」とは「多種多様な細菌の集まり」ということです。
「専門学校時代に習ったかなぁ?」というのが感想でした。そこで、久々に生理学の教科書を広げたところ、次のような内容が別々に掲載されていたのを確認できました。
1.大腸内の消化と吸収―腸内細菌
大腸内には、大腸菌をはじめとして多数の細菌が常在している。腸内細菌は小腸で消化しきれなかったものを分解する。食物線維は腸内細菌の働きにより発酵されて、酪酸・酢酸やCO2、H2、メタンなどのガスを発生する。アミノ酸は腸内細菌によりインドール、スカトールなどを生成し、糞便臭の原因となる。
2.生体の防衛機構に働く組織と因子―生体表面のバリア
皮膚や粘膜表面には、病原性のない常在菌が細菌叢を形成しており、病原菌が生育しづらい環境に保たれている。
一方、「人体の正常構造と機能」でも同じように調べてみたところ、次のような記述がありました。
『腸内の常在細菌叢は、消化管粘膜免疫系の維持と制御に深く関っている。』
これを見て、「腸内細菌」と「消化管粘膜免疫系」のそれぞれの働きを把握できていないこと。あやふやな知識がぐちゃぐちゃになっていることが分かりました。
消化管粘膜免疫系(腸管免疫系)について、ネット検索すると「ライフサイエンス 領域融合レビュー」という学術サイトの中に関連する記事がありました。専門的な内容ですが、その記事の「要約」の部分をご紹介させて頂きます。なお、「ライフサイエンス 領域融合レビューは、大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター から発信・公開される日本語コンテンツのひとつ」とのことです。
腸内細菌と腸管免疫
要約:『消化管はユニークな免疫系を構築している。そこでは、強い炎症活性をもつ免疫細胞と同時に抑制能の強い免疫細胞がバランスよく生み出されている。これは、消化管がさまざまな微生物の侵入という危険につねにさらされているのと同時に、日常的に接する無害な食物や腸内フローラに対しては不必要に免疫応答しないよう制御される必要があるためである。こうしたバランスよく制御された消化管免疫系の構築において、腸内フローラが重要なはたらきをしていることが徐々に明らかになってきている。腸内フローラを構成する個々の細菌種は、それぞれ異なる様式により消化管免疫系に影響をあたえる。たとえば、セグメント細菌とよばれる消化管に常在する細菌はマウスの小腸の粘膜固有層においてTh17細胞の分化を強力に誘導する。一方で、クロストリジアに属する消化管に常在する細菌は制御性T細胞の数を増加させその機能を高める。そして、腸内フローラの細菌種の構成の異常は免疫の異常へとつながり、さまざまな疾患を誘発する。ここでは,腸内細菌に影響をうけて構築されているユニークな消化管免疫系について紹介する。』
今回、勉強のために参考にさせて頂いた本はこちらです。
「はじめに」に続いて、目次でもある「30の方法」をご紹介しています。その後、特にブログに残しておきたい要点を書き出しています。なお、目次で太字になっているところが、それぞれの要点の元になった「方法」です。
はじめに
『わずか数年の間に、腸内細菌をとりまく環境は激変しました。近年の遺伝子研究とコンピュータの発達を受けて、腸内細菌の大規模な遺伝子解析が行われたことが一つのきっかけとなっています。
以前は、腸内細菌の研究は、培養によって種類を特定する方法しかありませんでした。このとき、腸内細菌の数は500種類、100兆個と推定されていました。ところが、遺伝子解析によって、腸内細菌は3万種、1000兆個もいるとわかってきました。
また、かつては「善玉菌が腸によいことをして、悪玉菌が悪いことをする」と単純に語られていた腸の世界が、実は非常に複雑であり、体と心の状態を支配するほどの影響力を持っていることが明らかになってきたのです。
その影響力とは、私たち人間が感じているよりもすさまじいものです。健康も病気も腸からつくり出されるといっても過言ではないほどです。腸内細菌の乱れが起こす病気は、風邪や食中毒などの感染症にとどまらず、がんや肥満、動脈硬化症、糖尿病、脳卒中、心筋梗塞などの生活習慣病、認知症、うつ病、アレルギー疾患、自己免疫疾患にまで及んでいるのです。しかも、最近の研究では、自閉症などの発達障害や、パーキンソン病にまで関与している可能性が示されています。(以下省略)』
1.私たちの腸にすむ「もうひとりの自分」を意識せよ
2.あなたにはあなただけの腸内細菌叢があることを知ろう
3.病原体を退治する“免疫の武器”が腸内細菌の選別を行っている
4.腸内フローラは数日あれば変わる!生かすも枯らすも毎日の生活しだい
5.細菌を殺しては健康になれない!おおらかにつきあう気持こそ「菌活」「腸活」の基本
6.人類は細菌のおかげで立派な脳を持てた。うぬぼれてはいけない
7.がんやアレルギー、うつ病は人類の衰退を示す「退化病」
8.納豆な土壌菌の塊。毎日食べておけば腸内フローラも男性力も衰えない
9.食物繊維を食べていると、腸内細菌が善玉物質をつくり出す
10.「おデブ菌」をおとなしくさせれば、肥満は治る
11.食の好みは、腸内細菌に操られている。「酢玉ネギ」で腸内環境の改善を
12.食物繊維をエサにしていれば悪玉菌は悪さをしない
13.除菌活動に熱心になってくると感染症や食中毒にかかりやすくなる
14.免疫システムは腸内細菌にコントロールされている
15.土壌菌は食べなければいけない。ピロリ菌は除菌してはいけない。
16.酵素食品をとっても体内の酵素は増えない。腸内細菌が多くの消化酵素をつくり出す
17.サプリメントを飲んでも腸内細菌が働かなければビタミンは得られない
18.腸内細菌を増やし、小麦粉・牛乳を遠ざける食事療法で自閉症が改善される可能性
19.腸を鍛えればうつ病はよくなる!人の幸福感をつくるのは腸内細菌だ
20.イライラや不安、カッとなりやすい心は、汚れた腸からつくられる
21.認知症は「腸内細菌」と「水」で予防できる
22.腸にすむ「マイ乳酸菌」はオリゴ糖で増やせる
23.ヨーグルトは、菌が生きたまま腸に届かなくてもよい
24.医者に金を払うよりも味噌屋に払え
25.「白い炭水化物」は腸内細菌を疲れさせる
26.病気にならない体づくりには肉や油も必要だ
27.保存料、食品添加物、抗生物質は腸内細菌を減らし免疫力を低下させる
28.冷凍機キノコ、ニンニク酢、昆布酢で活性酸素の害を消す
29.腸に開いた穴を塞げば大人の食物アレルギーはよくなる
30.日本人の腸内フローラは世界で最低水準。毎日の大便チェックを状態改善に役立てよう
おわりに ~笑う者の腸には福来る~
1.私たちの腸にすむ「もうひとりの自分」を意識せよ
・腸内細菌は約2kg、腸内の壁にくっついている。
・米国では2007年から1億5000万ドル以上と5年間の歳月をかけ、国立衛生研究所が「ヒト・マイクロバイオーム・プロジェクト」を実行した。腸内細菌一つ一つのDNA配列の全般にわたる解読を目指した。マイクロバイオームとは「細菌叢」のことで、微生物の生態系を意味する。
・腸内細菌から見れば、人間は「宿主」になる。宿主とは寄生生物に寄生される側の生物のこと。私たちと腸内細菌は共生関係にある。
・善玉菌と呼ばれる菌だけが体に必要なのではなく、悪玉菌も日和見菌もとても大事な働きを担っている。
・微生物の世界は壮大で複雑なため、有用なものを選び、不要なものは排除する、という選別を宿主ができるものではない。
2.あなたにはあなただけの腸内細菌叢があることを知ろう
・一卵性双生児や親子であっても、両者の類似性はさほど高くない。
・人間の遺伝子は20,000~25,000個。腸内細菌の遺伝子数は、3,300,000個にも上る。
・生後わずか1年間のうちに、生涯にわたる腸内細菌の組成は決定づけられてしまう。母親の胎内は完全なる無菌状態。菌の洗礼は産道を通る時、そして外界に産み落とされた瞬間から、赤ちゃんは膨大な細菌を浴び、腸や皮膚、気道などで細菌たちが繁殖していくことになる。生後1年間で、赤ちゃんはまるでスポンジのように細菌を取り込んでいく。
・赤ちゃんがなんでもなめたがるのは、多種多様な細菌をとり込んで立派な腸内細菌叢をつくろうとする本能である。
3.病原体を退治する“免疫の武器”が腸内細菌の選別を行っている
・免疫の主な働きは、「感染からの防衛」「健康の維持と増進」「老化と病気の予防」。その免疫力のおよそ70%を腸がつくっている。
・腸が人体の免疫の大半を担うのは、病原体が腸から侵入するからである。腸は「内なる外」である。人の消化管は口から肛門まで9メートルにも及ぶ一本の管になっており、腸には多くの免疫組織が集まるようになった。
・腸管の免疫では「自己」と「非自己」がたえず識別されている。食べたり飲んだりしたものも、腸にとっては外から侵入してきた非自己である。そこで、腸は食べたものを分解してブドウ糖やアミノ酸、脂肪酸などの最小粒子にし、非自己物質としての機能を失わせる。これが腸の行う「消化」の働きである。消化されたものは、腸管の表面を覆う上皮細胞から体内に吸収される。
・腸の上皮細胞の表面には粘液がある。この粘液には、消化された栄養素にまぎれて病原体が体内に侵入しないように殺菌物質やウィルスを不活化する物質が含まれている。また、「IgA抗体」という免疫物質も大量に存在している。
・抗体とは、特定の非自己物質にくっついて、その異物を排除する分子のことである。つまり、異物を退治するための武器だと考えるとよいだろう。私たちの免疫は、どんな異物に対してもぴったりの抗体をつくり出すことができるのである。
・これまで、IgA抗体は腸粘膜の中にあって、侵入してくる病原体を殺す物質と知られてきた。しかし、実際には腸内細菌の選別にも働くことが明らかにされた。
・IgA抗体は、腸の粘液でつくられる。また、母乳の中にも含まれる。とりわけ母乳が初めて出す初乳には、たくさんのIgA抗体がある。初乳の重要性は昔から伝えられていることであるが、それは生後まもない時期の感染症を防ぐためといわれてきた。ところが、初乳は細菌を腸にとり込むために必要だったのである。
4.腸内フローラは数日あれば変わる!生かすも枯らすも毎日の生活しだい
・体は自分ひとりだけのものではなく、1000兆個の腸内細菌たちと共有している。成人の体はおよそ60兆個の細胞から構成されているが、私たちの腸には、人体の全細胞より16倍以上もの数の細菌がすみついている。
・食生活が乱れて腸の状態が悪ければ腸内フローラは荒れる。体に悪さをする細菌が爆発的に増えてしまえば、優良な菌たちはとたんに数を減らす。ただし、腸内フローラには野生の花畑と決定的に違う点がある。腸内バランスはひとたび崩れても、野生の花畑ほど再生に多くの時を必要とはしない。細菌の増殖力は植物よりずっと強いからである。つまり、宿主が腸内フローラの乱れをいち早く察知して適正な努力を行えば、わずか数日間のうちに美しく整えられるのである。
・消化のしくみは、はじめから腸内細菌との共生ありきで組み立てられている。腸だけの消化能力では、体が欲するように栄養素をとり入れることはできない。
・便のうち食べカスは5%、60%が水分で、20%が腸内細菌とその死骸、15%は腸粘膜細胞の死骸である。
・免疫機能も腸内細菌との共同作業によって初めて成り立つものである。腸にたくさんの細菌がすむのは、病原体の侵入を防ぐためでもあるが、腸内細菌は縄張り争いをしながら腸の中に自分の生息場所を守っている。外から新たな細菌が侵入してくると、いっせいに攻撃してその排除に働くのである。しかも、腸内細菌は、腸にいる免疫細胞を活性化する力もある。つまり、免疫システムだけでは十分な免疫力を発揮できず、免疫力を高めるには腸内細菌を増やすことが大事なのである。
6.人類は細菌のおかげで立派な脳を持てた。うぬぼれてはいけない
・脳も腸から分化した臓器である。腸にはもともとニューロンなどの神経細胞が存在していた。また、心の状態を築くセロトニンやドーパミンなどは、脳内で分泌される神経伝達物質と思われているが、その起源は腸にある。腸内細菌が腸の多くの働きを肩代わりする中で、腸内細菌は仲間どうしでの情報伝達が必要になっていった。セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質は、腸内細菌間の交流のために必然的に生まれたものだったのである。たとえば、「ビタミンを生成しましょう」「外敵が来たぞー!」などといった情報の伝達を、神経伝達物質を介して行っていたのである。
12.食物繊維をエサにしていれば悪玉菌は悪さをしない
・腸内細菌たちの大好物は水溶性の食物繊維。
14.免疫システムは腸内細菌にコントロールされている
・マクロファージは「自己」と「非自己」を見極める力の特にたけている。
15.土壌菌は食べなければいけない。ピロリ菌は除菌してはいけない。
・免疫力が低下すると、システムの統制をとれなくなり、免疫細胞は何が本当の「非自己」なのか見極められなくなる。
・ピロリ菌は日和見菌である。宿主の免疫力がしっかり働いている時には体に良い働きをする共生菌である。ピロリ菌が悪さを始めるのは、宿主がストレス過剰の状態にあって免疫力が低下しているときである。こうなると、ピロリ菌は胃を荒らす方に働いてしまう。細菌とはそもそもそういうものである。細菌自身は、自分が宿主にとって悪玉か善玉かなど考えていない。環境に応じて自分の居心地の良い環境を築こうと、せっせと働いているだけである。
17.サプリメントを飲んでも腸内細菌が働かなければビタミンは得られない
・私たちの腸はビタミン類を合成する機能を持っていない。食べたものからビタミン類を合成するのも腸内細菌たちの働きである。
・腸が元気ならば体が若返る理由の一つは、腸内細菌のビタミン合成力に隠されていたのである。
・ホルモンの一部も腸内免疫がつくっている。消化管ホルモンのセクレチン、コレシストキニン、インクレチンなど。
・強力な抗がん作用をもつエクオールも腸内細菌が大豆イソフラボンからつくり出す成分。ただし、このエクオールをつくれるのは、イソフラボンと相性のよい腸内細菌をもった人だけ。
18.腸内細菌を増やし、小麦粉・牛乳を遠ざける食事療法で自閉症が改善される可能性
・自閉症の子どもは、そうでない子と比べて、腸内細菌の多様性が乏しいという報告がされている。
19.腸を鍛えればうつ病はよくなる!人の幸福感をつくるのは腸内細菌だ
・腸内フローラの組成は、生後だいたい1年間で決まってしまうが、腸にすみついた細菌たちの数はたえず変動している。たとえ乳児になんらかの問題により腸内フローラの多様性を十分に築けなかったとしても、今ある腸内細菌を増やす生活を送ることで、腸内環境は変わってくる。そうした変動が、脳や心の状態にまで影響を与えることがわかってきた。
・セロトニンとドーパミンはあわせて「幸せホルモン」と呼ばれるが、その原料となる前駆体は、実は腸でつくられている。そのため、腸内環境が悪化すると、幸せホルモンの分泌量は著しく減ってしまう。腸の健康は脳の健康であり、脳の健康は腸の健康である。生物にとってもっとも重要な臓器である腸と脳は、強く影響を及ぼしあいながら動いている。そうした両者の関係を「脳腸相関」という。
・トリプトファンからセロトニンの前駆体がつくられる際は、ビタミンB6が使われる。また、ドーパミンはフェニルアラニンという必須アミノ酸からドーパミンの前駆体になるまで葉酸やナイアシン、ビタミンB6が必要とされる。
・腸内細菌たちがつくり出した幸せホルモンの前駆体を、脳へと送り出しているのも腸内細菌である。
20.イライラや不安、カッとなりやすい心は、汚れた腸からつくられる
・九州大学の須藤信行教授らのグループは、系統的な研究により、人間の体は有害なストレスを受けたときに、「視床下部—下垂体—副腎」という流れを介して腸内細菌に悪影響を与えることを明らかにしている。有害なストレスを脳が察知すると、消化管の局所で「カテコラミン」が放出され、腸内フローラに直接的な影響を与えていることがわかったのである。カテコラミンとは、アドレナリンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質の総称である。これらはストレスホルモンとも呼ばれており、ストレスを感じると発生し、動悸や血圧の上昇、発汗、血糖の上昇、覚醒などの不安な変化を体に与える。須藤教授の研究では、このカテコラミンが腸内で発生すると、大腸菌の増殖が進み、腸管局所での病原性が高まることが認められた。カテコラミンが腸内細菌の病原性を強めさせる作用は、大腸菌以外の細菌でも観察されている。このように、不安や緊張によるストレスは、腸内細菌のバランスを著しく乱す。その乱れた腸内環境が脳へ情報を送ると、脳内ではストレスホルモンがつくり出される一方、セロトニンやドーパミンなどの幸せホルモンの量を減少させる。それによって脳が不安と緊張を増強させるという循環ができあがっているのである。
21.認知症は「腸内細菌」と「水」で予防できる
・人間の脳は、活性酸素の害を非常に受けやすい臓器である。人体を形づくる成分のうち、もっとも酸化しやすいのは脂質である。人間の脳は、約80%が水であるが、水分を除いた部分のうち、約60%が脂質からできている。その脂質が活性酸素に過剰にさらされ続けると、褐色の色素沈着を起こす。これが脳内で蓄積されてくると、「アミロイドβ」や「タウタンパク」などのゴミタンパクが大量につくり出され、さらに活性酸素を過剰に発生させるようになる。こうなってくると、脳の神経細胞が変性し、萎縮するようになるのである。つまり、活性酸素の過剰発生を防ぐことが最大の予防法といえる。
22.腸にすむ「マイ乳酸菌」はオリゴ糖で増やせる
・最近の研究により、腸にはその人特有の乳酸菌がすみついていることが明らかになった。
24.医者に金を払うよりも味噌屋に払え
・匂いが強いというのは、発酵力が高くて、菌が元気だという表れである。たくさんの種類の細菌が数多くいる発酵食品のほうが、腸内フローラの活性化には効果的である。
25.「白い炭水化物」は腸内細菌を疲れさせる
・たしかに白米や、白い小麦粉を使かったパンやうどんなどの麺類は、おいしいものである。しかし、そのおいしさは、腸が感じているのではなく、脳が感じるものである。脳がブドウ糖をとくに必要とするのは、とっさの判断やストレス時の反応など、瞬発的な活動をするときである。現代社会のようにストレスフルな状況にあると、脳はたえずブドウ糖を要求することになる。体が疲れているときにもブドウ糖を欲する。こうしたときにブドウ糖が入ってくるから、脳は「おししい」と感じるのである。ところが腸は白い炭水化物が大量に入ってくるのを嫌がる。
・小腸の直接の栄養源はグルタミン酸というアミノ酸の一種である。昆布やチーズ、緑茶、シイタケ、トマト、魚貝類に豊富な「うま味」成分である。
・大腸の栄養源は、腸内細菌が食物繊維を発酵させてつくる短鎖脂肪酸である。
・小腸も大腸も、白い炭水化物を必要としていないのである。それにもかかわらず、白い炭水化物が大量に入ってくると、腸はまっさきに消化吸収のために働かなければならない。脳がブドウ糖を執拗に欲するからである。
27.保存料、食品添加物、抗生物質は腸内細菌を減らし免疫力を低下させる
・腸内細菌に特に悪影響を与える化学物質は防腐剤と抗生物質である。
・体に生じる風邪の症状は、免疫細胞が病原体を排除する際に起こる炎症である。
28.冷凍機キノコ、ニンニク酢、昆布酢で活性酸素の害を消す
・過剰な活性酸素は腸内フローラにもダメージを与え、細菌数を大きく減らしてしまう。
29.腸に開いた穴を塞げば大人の食物アレルギーはよくなる
・腸内フローラが“いい子”に育てば、健康を増進する物質をどんどんつくり出すとともに、免疫力を高めてくれる。
・腸の消化吸収能力を超えて食べることも、腸内細菌に混乱を起こす元凶である。
・「人+腸内細菌」で人間である。
おわりに ~笑う者の腸には福来る~
腸内フローラを元気にする生活習慣
1.朝起きたら外に出て深呼吸をする
2.疲れない程度の適度な運動をする(朝のラジオ体操でもOK)
3.ぬるめのお風呂にゆっくり浸かって腸を温める
4.夜更かしをせず、寝室は真っ暗にして寝る
5.休日には自然の中に出かけていく
『腸内細菌によい生活習慣とは、宿主である私たちにとって楽しいこととわかります。楽しいという気持ちが腸内環境を整えてくれるのです。腸内細菌を人生の味方につけてください。より楽しく充実した人生を築くためのベストパートナーは、あなたのおなかの中にいるのです。』
追記:2020年8月12日
”『病は気から』『医食同源』とはいうものの、腸内細菌を含む腸管環境の変化をどのような仕組みで脳は認識し、病気の発症を抑えているのか、その謎は解明されていませんでした。”
今回追記したのは、マウスによる実験ではありますが、上記の疑問に対する研究で成果があったとのニュースを知ったためです。

”自律神経が紡ぐ新しい炎症抑制メカニズムの解明―迷走神経を介した感染症・がん・炎症性腸疾患の治療に新たな光―”
研究のポイント
『近年、ライフスタイルや環境の急激な変化によって、炎症性腸疾患、メタボリックシンドローム、うつ病、がん、新興感染症などの病気が増加しています。最近では、ライフスタイルの変化に伴う腸内細菌などの腸管環境の乱れが、これらの疾患の主な原因として認識されています。しかし、『病は気から』『医食同源』とはいうものの、腸内細菌を含む腸管環境の変化をどのような仕組みで脳は認識し、病気の発症を抑えているのか、その謎は解明されていませんでした。本研究では、腸内細菌の情報を肝臓が統合し、肝臓→脳→腸管という迷走神経反射を通じて、過剰な炎症を抑える働きをする腸管制御性T細胞(Treg;注1)の産生を制御していることを世界で初めて示しました。本研究のさらなる発展は、増加の一途を辿る現代病、がん、COVID-19など新興感染症の新たな治療法の確立につながると期待されます。』
花粉症と自律神経
「適応疾患」内の「花粉症」でも触れているのですが、私の花粉症は30年以上前、会社の集合寮に入って3年目の1985年だったと思います。同期のS君がティッシュを持って歩いているのを見て、大笑いしていたら自分にも舞い降りたという予期せぬ出来事でした。長い間お世話になったアゼプチンという薬は、私には合っていたようです。症状は10が2程度に抑えることができていたため、それほど困ることはありませんでした。
一方、鍼灸師になったこともあり、一昨年の2016年からお臍の周囲に刺鍼する「内ネーブル4点」という長野式の花粉症治療を自らに行っています。
治療効果はアゼプチン服用時とほぼ同等、施術回数は月1回、計3回程度の回数です。ちなみに敵はスギ・ヒノキ。「花粉よ来るならこい!」という馬鹿げた対抗心と、人体実験を兼ねるという思いから、花粉シーズン中も訪問の仕事中以外はマスクをせず、部屋の窓や洗濯物のとり込みもノーケア、車の運転中も窓全開で花粉と共に生活しています。
そして、問題の今年ですが、昼間はこの2年間同様、10が2程度で困ることはなかったのですが、自宅に帰ると、特に夜になると何とかしたいレベルで症状が表れました。以前から昼に比べると夜は症状が出やすい傾向はあったのですが、今年はその度合いが強くなっていました。感覚的には5程度という感じです。5程度というのは、「症状の強さと症状が表れる頻度」の2点から「こんなもんでは」と直観的に判断した値です。なお、今シーズンの施術回数は過去2年の3倍弱、7、8回くらいになったと思います。
原因を調べてみると、スギもヒノキも昨年より飛散量が多いようなので、これが一つの要因であるたことは確かです。そして、もう一つ気になる点がありました。それは介護に伴うストレス、特に睡眠の質の問題です。睡眠時間は6時間程度なのですが、夜中に数回起こされるということもめずらしくなく、そのため、このストレスと睡眠の質の問題も、症状を悪化させている原因ではないかと考えました。
そして、それを調べるため、新しい本ではないのですが、図書館から花粉症関連の本を3冊借りてきました。これらは共著の本を含め「スギ花粉症」を命名された(論文報告は1964年)斎藤洋三先生の本です。もう1冊は「ストレスと免疫」という題名の中古本を購入しました。また、ネット検索で見つけたサイトも参考にさせて頂きました。
ブログは、花粉症がおこる仕組みや自律神経との関係、制御性B細胞についても少し触れています。
1.花粉症のおこる仕組み
アレルギー反応も免疫反応も体内でのしくみは同じです。いずれも「抗原抗体反応」といわれているものです。この反応が体にとって都合のよいように働く場合を「免疫」といいます。人が病気から体を守るために欠かすことができないシステムです。
ところが、体を守るための抗原抗体反応が、からだにとって都合の悪い結果をおこすことがあります。これが「アレルギー」反応です。
「抗原」とは異物、花粉症であれば「花粉」です。一方、「抗体」とは白血球(リンパ球)の中のB細胞(他にT細胞、NK細胞がある)から産生・放出されるタンパク質です。体内に侵入した異物に結合します。タンパク質名としては免疫グロブリン(immunoglobulin)
と呼ばれ、「Ig」と略されます。抗原抗体反応に関与している抗体は、IgE、IgM、IgA、IgG、IgDの5種類あるのですが、花粉症にかかわる抗体はIgEであり、それ以外のIgM、IgA、IgG、IgDの4つの抗体は免疫として働きます。なお、無害な花粉に対してIgE抗体がつくられるのはアレルギー体質の人だけです。
花粉が目、鼻、口から侵入するとその粘膜に花粉がとりつき粘膜の中に溶けだします。粘膜に溶けだした抗原は、白血球の一つであるマクロファージ(食細胞)にとりこまれ、異種タンパク質の異物として認識されます。この情報がT細胞を介してB細胞に伝えられると、花粉抗原に対するIgE抗体がつくりだされます。また、IgE抗体は肥満細胞と結合しやすい性質があり、肥満細胞の表面にIgE抗体が付着し蓄積されます。そして、再び侵入してきた花粉抗原がIgE抗体と反応すると、細胞からアレルギー症状を起こす化学伝達物質(ヒスタミン、ロイコトリエンなど)が放出されます。
化学伝達物質であるヒスタミンやロイコトリエンは、「ケミカル・メディエーター」ともいわれるもので、これらが神経や血管を刺激することによって、花粉症のさまざまな症状が引き起こされます。まず最初にヒスタミンが働き、それから少し遅れてロイコトリエンが作用を再現します。
花粉が目や鼻の粘膜に付着し、水分を吸収すると花粉の中から抗原が溶け出し、肥満細胞の表面に付いているIgE抗体と結合します。(下左図)
肥満細胞からアレルギー症状をおこす化学伝達物質が放出され、それが神経や血管を刺激して、症状が現れます。(下右図)
図はいずれも、「花粉症」からの出展ですが、中央の見開き部分が見にくくなっています。(すみません)
以下は症状に着目して説明されたものになります。内容はかなり専門的です。なお、下に図を添付しました。
くしゃみの発現には、ケミカルメディエーターのヒスタミンが重要な働きをしています。ヒスタミンは鼻粘膜の知覚神経である三叉神経終末のヒスタミン受容体と結合して、求心性インパルスを脳幹のくしゃみ中枢へ伝えます。そして中枢からの遠心性インパルスは脊髄神経、舌咽神経、迷走神経、顔面神経などを介して呼吸筋、咽頭筋、顔面筋などに伝わり、爆発的な呼気としてのくしゃみが起こります。くしゃみは生理的にも異物を呼気により体外へ排除しようとする生体防御反射で、下気道(気管、気管支)の咳反射に相当します。
鼻水もヒスタミンの作用で起こります。ヒスタミンによって三叉神経終末が刺激されて、分泌中枢にインパルスが伝えられ、遠心性に分泌神経(副交感神経)に伝わり、副交感神経からのアセチルコリンの分泌を促します。このアセチルコリンが神経伝達物質となって鼻腺細胞のムスカリン受容体に作用して、鼻汁分泌を起こします。
普通の人では花粉を吸いこんでも花粉は粘液膜に付着して、上皮細胞の線毛運動でベルトコンベア式に咽頭へと送られ、痰と一緒に排出されるだけです。これに対し、花粉症の人では入ってきた花粉を早く鼻の外へ流し出そうとして多量の鼻水をだします。これも生体防御反射ですが、花粉症の人にはつらい防御反射となります。
鼻づまりはヒスタミンやロイコトリエンなどが直接に鼻粘膜血管系に作用し、海綿静脈洞の拡張によるうっ血、血管透過性亢進作用による組織の浮腫などにより、鼻粘膜が全体として腫脹することで起こります。
眼の結膜も血管系、リンパ組織に富み、涙液によって覆われています。異物が侵入すると、まばたきと涙によって洗い流しだします。鼻と同様に異物に対する防御反射機構です。結膜におけるⅠ型アレルギー反応も、鼻粘膜におけるのと同様に、結膜表層の肥満細胞での抗原抗体結合によって始まります。そして肥満細胞から遊離したヒスタミンが知覚神経である三叉神経終末を刺激してかゆみを起こし、また血管系への直接作用で結膜の充血、浮腫を起こします。涙腺からの涙液分泌もヒスタミンの作用で反射的に起こり、流涙となります。
下の棒グラフは2004年のものですが、花粉症患者へのインターネットによるアンケートの集計結果です。
2.花粉症と自律神経
1)花粉症と自律神経はどう関係するか
自律神経には交感神経と副交感神経があり、お互いに拮抗しながら、さまざまな身体機能を、私たちの意思とは関係なく、自律的にコントロールしています。
鼻の自律神経は、特に分泌腺と血管に分布していますが、分泌腺にきているのは、自律神経のうち副交感神経だけです。鼻にアレルギー反応が起きたとき、症状を出現させる役割を果たします。まず、ヒスタミンが鼻の知覚神経を刺激すると、その刺激は自律神経の中枢を経由して副交感神経に伝わります。そして、副交感神経が緊張することによって、鼻の分泌腺から鼻水が出るようになるのです。
知覚神経は粘膜や皮膚などにも分布しています。そこに冷たい空気が触れたりすると、その刺激が反射路に伝わって、やはり鼻水やくしゃみが出るようになります。
血管には交感神経と副交感神経が分布しています。鼻でアレルギー症状が起きると、交感神経が働きにくくなり、逆に副交感神経が緊張して、鼻粘膜の血管は拡張します。それによって、うっ血が起き、鼻づまりの原因となるのです。
2)全身の自律神経のバランスも症状に影響する
自律神経のバランスは昼夜で逆転し、活動的な昼間は交感神経が優位に働き、安静にしている夜間の睡眠時は副交感神経が優位になります。夜半に鼻づまりが起きやすくなかなか解消しないのは、交感神経が働きにくくなっているために鼻粘膜の血管が拡張し、鼻にうっ血が起きているからです。
また、花粉症など鼻のアレルギーを持っている人は、朝の起きがけに、くしゃみと鼻水が発作的に起こることがあります。モーニング・アタックと呼ばれる症状です。これはアレルギー反応ではなく、夜間の副交感神経の状態から、昼間の交感神経優位の状態に変わるとき、自律神経のバランスがくずれるために起ります。
3)体の反射現象
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、涙などは、人間の体にそなわった反射現象だといえます。しかし、これがむやみに出ても困るので、さらに上位中枢の抑制機構が設けられています。誰でも年をとると涙もろくなり、鼻水などが出やすくなりますが、それは上位中枢からの抑制機構がゆるんでしまうためだと考えられます。
花粉症の症状で困っているときでも、精神的に非常に緊張すると、症状が抑えられることがあります。たとえば、花粉症の俳優さんが、舞台の上ではくしゃみ一つしないのに、幕が降りたとたん一気に症状がぶり返すというようなことがあります。アナウンサーなどテレビに出る人も同様で、出演中は症状が抑えられるといいます。
4)情動のパターンと自律神経機能の関係
この表は現在も活用されている、山下格先生が作成されたものです。山下先生は北海道大学医学部精神医学教室第五代教授を務められ、2014年12月にご逝去されました。
ここでは「ストレスと免疫」に記述された表に関する説明分をそのままご紹介させて頂きます。
『一番目のパターンは、驚きや恐怖、憤怒などで交感神経の機能の亢進によるものです。
第二のパターンは、持続的な不安や緊張、怒り、興奮などの情動変化で、このパターンは、情動が比較的持続するのが特徴です。たとえば、ストレスが加わると、胃酸の分泌が亢進したり、消化管の動きが活発になり、これが持続すると胃粘膜にびらんや潰瘍が形成されることがあります。
このような消化管の異常は副交感神経の機能亢進によって起こると考えられています。しかし、不安や怒りなどは交感神経の亢進によるもので、ここでは、交感神経と副交感神経系の両者の興奮が同時に起きていることになります。
三番目のパターンですが、これは一番目、二番目のパターンと、次の第四番目のパターンとの中間に位置するもので、緊張などから解放されて、休息や平安といったような気分になることを意味します。
生命を維持していくうえで、交感神経が絶えず一定の緊張を保つことは必要ですが、とりたてて危険であるとか恐怖に陥った状態でない場合には、相対的に副交感神経が優位の状態に保たれると考えられます。したがって、他のパターンに移り変わる前段階の状態として、この第三のパターンが存在することが考えられます。
第四のパターンは、失望、抑うつ、悲哀、憂愁といった情動のものです。これは交感神経、副交感神経、両者がともに抑制された状態です。
抑うつ状態や失望したときなどは、胃酸の分泌が減り、消化管の動きも弱くなり、これにともなって食べたものの通過時間も長くなります。さらに、悲しみが強くなったり悲観すると、心拍数の低下ならびに血圧の低下もみられます。』
まとめ
今回のブログは、「夜間、花粉症の症状が出てくるのは何故か」、「ストレス、特に睡眠の質は花粉症の症状悪化の原因になっているのではないか」という疑問が発端でした。そして、私なりの結論は次のようなものです。
1)夜間、花粉症の症状が出てくるのは何故か
これは、免疫機能が副交感神経で優位になるのと同様に、免疫と似て非なる「アレルギー」の花粉症も副交感神経が優位になる時、つまり表に照らし合わせれば「平安、休息」が優位になる時に症状が亢進することを意味しており、夜間や自宅でくつろいでいる時に花粉症の症状が出てくるのはこのためと考えます。
2)ストレス、特に睡眠の質は花粉症の症状悪化の原因になるのではないか
表を見ると、「持続的な不安、緊張、怒り、興奮」に関しては交感神経だけでなく、副交感神経も強く関わっていることが分かります。この事実は大きな驚きでした。介護に伴うストレスや睡眠の質の問題は「不安、イライラ、緊張」が主なものになると思いますので、表にある四つの情動に含まれます。したがって、ストレスや睡眠の質の問題は、花粉症の症状を悪化させる要因になると考えます。
なお、ストレスや睡眠が花粉症の症状に影響を与えることは、本やサイトにも出ていました。

●睡眠が不足するとホルモンのバランスが乱れ、免疫力が落ちます。免疫力が落ちると、花粉などのアレルゲンの侵入に対して体が過剰反応するのです。
●ストレスも睡眠不足と同様に免疫力を落とすため、花粉に対する体の過剰反応が起きやすくなります。

副交感神経が優位なときは、体の免疫力は上がります。しかし、副交感神経が優位な状態が長く続くと、白血球のなかのリンパ球が過剰に分泌されてしまいます。そうなると免疫が過剰になってしまい、この過剰な反応がアレルギー症状の正体です。「花粉症」などのアレルギー症状が過多に出るのは、「副交感神経が優位な状態」が続いていることが考えられます。アレルギーの原因物質をなるべく排除するだけでなく、交感神経を優位に働かせながら、副交感神経とのバランスを保つことが、「花粉症」と上手くつきあうコツといえるでしょう。
3.制御性B細胞
こちらは「ライフサイエンス領域レビュー」に掲載されていた『馬場義裕(大阪大学免疫学フロンティア研究センター
分化制御研究室).免疫反応を抑制するB細胞:制御性B細胞領域融合レビュー, 5, e002 (2016)』のご紹介となります。
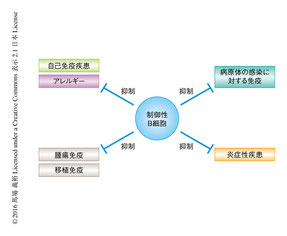
『2015年でB細胞の発見からちょうど50年がたつ。抗体を産生するリンパ球として同定されたことからもわかるように、B細胞は液性免疫において中心的な役割をはたす.また、T細胞に対する抗原の提示やサイトカインの分泌により免疫反応を制御することもB細胞の重要な役目である。これらのはたらきにより、B細胞は病原体の感染に対し生体防御の一翼を担う一方で、自己免疫疾患、炎症、アレルギーの原因となったり病態を悪化させたりすることが知られている.しかし,それとは逆に,免疫反応を抑制するB細胞として制御性B細胞の存在が明らかにされ注目されている。』
付記1
お臍の周囲の4ヵ所に刺鍼する「内ネーブル4点」は長野式に基くものですが、その長野潔先生の著書である「鍼灸臨床 わが三十年の軌跡 -東西両医学融合への試み-」の中に記述がありましたので、その内容をご紹介させて頂きます。
ネーブル周囲四点の刺鍼とアレルギー性疾患
『ネーブル周囲四点の刺鍼は、当院では五年間、五回に亘り研修したボストン(アメリカ)在住の松本岐子氏の発想によるものである。彼女は筆者の扁桃原病説からヒントを得た類推的発想によるネーブル周囲四点の刺鍼によって、アレルギー性疾患に対して好成績を挙げている。
筆者(長野潔先生)もこの方法を追試したところ、予想以上の成果をみることができた。この四点の刺鍼はアレルギー性疾患のみならず、自律神経の全身的調節や、諸種の痛みに対して有効であることが実証された。
この刺鍼が何故効くのか。これは筆者(長野潔先生)の、あくまでも推論の域を出ないものであるが、ひとつは、この部が門脈のうっ血の起こりやすい場所であり、この部に刺鍼をすることにより、胃、小腸、大腸、膵臓、胆のう、脾臓から栄養を持った血液を充分肝臓に送ることができるということである。このことは肝臓の賦活作用を促し、二次的に粘膜下のリンパ組織を活性化し、抗体産生を増大させることによってアレルギー性疾患に著効を奏するのではないだろうか。例えば鼻水、鼻づまり、眼瞼の痒み等刺鍼にその症状が消失してゆくことが多いからである。
事実、ネーブル周囲四点を刺鍼することによって、それまで激しかった症状が劇的に消失することが多い。』
付記2(2020年10月4日)
ネーブル周囲四点の刺鍼とアレルギー性疾患
長野式の講習会や長野先生の本をまとめたノートを久々に見返したところ、ネーブル周囲四点(内ネーブル4点)について、次のような説明が出ていたことに気づきましたので、ご紹介させて頂きます。
『内ネーブルも肝門脈の枝別が沢山あるので、肝門脈の流れを良くする。これにより肝臓の賦活作用を促し、粘膜下のリンパ組織を活性化し、抗体産生を増大させる。』

この画像は「かずひろ先生の【徹底的国試対策】解剖学」から拝借しました。
次のような解説も付いていました。
『肝臓に向かう門脈は、脾静脈・上腸間膜静脈・下腸間膜静脈が合流してできます。胃腸や膵臓、脾臓から集められた静脈は、門脈として肝臓の中に導かれて肝組織で毛細血管に流れたのち、再び、肝静脈を経て下大静脈に注ぎます。』
慢性疼痛と心療内科
高齢の患者さまの中には、「この慢性疼痛は心因性なのではないか?」と思うことがたまにあります。しかしながら、心因性の疼痛にはどんな特徴や傾向があるのかなど、ほとんど理解できていなかったこともあり、軽々に心因性を原因と考えることはできませんでした。
そこで、まずは何か1冊本を読んでみようと思い、ネット検索していると、作家の夏樹静子先生がご自身の凄まじい慢性疼痛の闘病を綴った「腰痛放浪記 椅子がこわい」という本があることを知りました。「これかなぁ。」と思いつつ、さらに調べていくと、夏樹先生のその慢性疼痛を完治させた心療内科の医師、平井英人先生ご自身も本を出されていることを知りました。そして、30年以上のキャリアをお持ちであることも分かりました。こうして、『慢性疼痛―「こじれた痛み」の不思議』を購入することに決めました。
ブログでは、心因性の慢性疼痛の特徴や傾向を理解することと、心療内科がどんな診療科なのかを知ることを目的としています。内容は全て本書に従うもので、重要と思う個所を抜き出し、列挙する形式のため断片的になっています。
慢性疼痛の治療
1.一般的な痛みのメカニズム
外因性の痛み刺激(切り傷、打撲、炎症など)が侵害受容器に入ることで信号が発生し、脊髄内にある知覚神経を伝わって脊髄後角、シナプス、ニューロン、脊髄視床路を順に通って大脳皮質の視床に到達し、認識されます。痛みが脳に認識されると、それに対する反応として副腎髄質からアドレナリンが分泌され、血管の収縮や筋肉の緊張が生じます。この反応で局所的な乏血が起こります。この乏血が起こると組織内の酸素が足りなくなるため、今度は内因性の発痛物質が生じます。こうなると、外因性の痛み刺激が消えても痛みを感じるようになるのです。
2.心が痛がっているとは
痛みの解明に取り組んでいる米ノースウェスタン大学(シカゴ)生理学バニア・アプカリアン教授(A. Vania Apkarian)らが行った研究で、慢性疼痛患者の脳MRIを撮影しながら痛み刺激を与えたところ、通常の痛み刺激で活性化するはずの大脳皮質の視床ではなく、思考や感情を司る前頭葉の部分が活性化するのが分かりました。特に前頭葉のなかでも前部―ストレスや不安など、ネガティブな感情を司る部分でした。
この知見に対し、1000例近い慢性疼痛患者を診療されてきた平木先生は、「通常の痛み止めが効かない」という単純な事実からしても、慢性疼痛には何かしら通常の痛みのルートとは別のルートが存在すると考えていた。よってこの研究結果は腑に落ちるものであるとお話されています。
3.螺旋階段をのぼるように
薬物治療を先行させながらその効果をみつつ、「ある時期」がきたらその患者さんに合った指導を少しずつ並行して進めていきます。この「ある時期」というのは、患者さんが訴える症状の表現が少し変わってきたころです。何かしらの手ごたえを少し感じ始めたときともいえます。
たとえば、それまで「まだ痛いです」「ちっとも変りません」「痛くて何もできません」といっていた人が、「痛みはまだありますが、少し動けています」「ときどき痛みがやわらぐときがあります」というようになるなど、痛みに対するグチが減ったとき。そうしたかすかな心の変化をとらえて、新たな技法を導入するとっかりとするのです。
また、この第一の段階では、症状には「波」があることがこの病気の特徴であると教えることも重要です。一直線に治癒に向かって進むのではなく、波打ちながら、よかったり悪かったりしながら治っていくことを教えます。「まだ治らないのか」と焦らせないということです。患者さんは、よかったり悪かったりを繰り返すと、堂々めぐりでいっこうに治療が進まないと感じるものです。
しかし、治療は螺旋階段をのぼるようなものです。本人は同じところを回っているように思えても、外で見ている第三者には、少しずつ上へと昇っていく姿がみえています。螺旋階段も、上っている本人はずいぶん上までいってから下を眺めて、初めて「高いところまできた」と実感します。
治療も同じイメージです。ずいぶん進んでから「ああ、以前よりはよくなっているなと実感するものなのです。
4.自律訓練法のコツ
心理療法には自律訓練法、交流分析、行動療法という三本柱があります。それでも効果が十分でないときに加えるかたちで用いられるのが森田療法や絶食療法(後述)という特殊な技法です。
とくに慢性疼痛の患者さんに対しては、積極的に「自律訓練法」を習得するようにすすめています。
自律訓練法は世界的によく知られたリラクゼーションの技法で、17世紀にヨーロッパで試みられた催眠療法の流れを汲むものです。催眠によるトランス状態(理性が弱まっている状態)が病気を治すというこの療法は、当時盛んに脚光を浴びましたが、奇術・魔術的なイメージが強く、強い批判も浴びてそれ以上発展しませんでした。その後フロイトらが催眠療法をもう一度研究し、トランス状態が平衡を作り出すことを明らかにしていったのです。
自律訓練法は自らトランス状態に入るもので、自己催眠法とも呼ばれ、1932年にドイツの精神科医シュルツによって開発されました。日本には1952年に紹介されましたが、以来急速に広まり、いまでは心療内科の必須の技法のひとつとなっています。
ベッドに仰向けになったり椅子に座ったりした姿勢で目をつぶり、「両腕が重たい」「両腕が暖かい」・・・・・・など「公式」を繰り返し唱えるという、自己催眠による治療技法です。
自律訓練法は、スポーツ選手や一部の教育現場でも取り入れられているリラクゼーションの方法です。正しく行われれば効果絶大で、成績の向上や人間関係の改善につながります。一見、心療内科とは無関係に思える病気も改善するなど幅広い適応があります。それだけ、あらゆる病気にとって「心身相関」の存在感は大きいともいえますが。
その実際は非常に簡単で、子どもでもマスターできる方法なのですが、本や雑誌、通信販売のDVDを買って自己流でやろうとしても、なかなか身につきません。独学ではなく、きちんとした指導者のもとで習得されることが近道です。
絶食療法は入院して個室で行います。訓練された看護師らスタッフによるチーム医療も必要です。患者さんには二週間のあいだ、外部との連絡を完全に絶ち、病院内の一室に籠もっていただく必要があります。治療前の検査や治療後の経過観察を含めると、一か月半から二か月ほど入院していただくことになります。
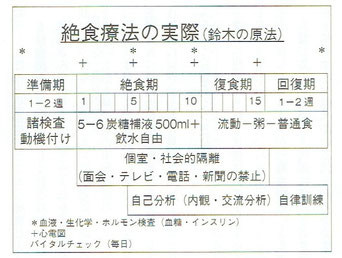
この「絶食」という状態は、何もしないようでいて、人間の身体にすさまじいストレスを与えます。
人間の体のエネルギー代謝には、ブドウ糖を燃料とするグルコース代謝と、脂肪酸を燃料とするケトン体代謝の二通りがあります。普通に食事をする生活では、身体はグルコース代謝を中心に動いており、ケトン体代謝が働くことはありません。
絶食に入ると、糖分の摂取が途絶されるために、グルコース代謝が枯渇して、ケトン体代謝にスイッチされます。脂肪を燃焼してエネルギーとして使うのです。この状態になると人間の身体はホメオスタシス(生体恒常性:身体を環境に適応させ、状態を一定に保とうとする力)の作用でインスリンの分泌がコントロールされ、血糖値が下げ止まります。食物を摂取しなくても低血糖になることはありません。空腹は当初はありますが徐々に感じなくなります。身体の状態は維持されますが、代謝やホルモン系が変動することによって、自律神経系や免疫系にも影響が及びます。
絶食によりケトン体代謝に入った身体では、脳内でα波が著明に増加し、生体恒常性(ホメオスタシス)の状態に入ります。この状態で過ごす絶食期には、前半は自己対峙の結果としての意識の変性(変化)が、後半には心理的な退行(抵抗の放棄など)や被暗示性の亢進(医師の話を素直に受け入れるなど)が起こってきます。
この状態のなかで、患者は極限状態や嫌悪刺戟を乗り越え、新たな自信と喜びをつかみます。また、自己洞察を深め、認識が変わっていくなかで、症状が変わり始めます。そして、代謝系の変化というストレスが、情動を司る自律神経系や関連する内分泌系、免疫系の再調整を促すのです。
こうした絶食療法の奏功メカニズムは、ハーバード医科大学のジョージ・ F・カーヒル (George F. Cahill Jr.) 博士によって解明されました。
画像出展:「慢性疼痛ーこじれた痛みの不思議」
5.自分自身の心で治していける
慢性疼痛のほとんどすべての患者さんには、共通の心理があります。まず、「自分こそが世界で一番苦しんでいる」「この痛みはいつ治るのだろうか」「なにかいい方法はないだろうか」「このままで本当に治るのだろうか」という不安と疑念です。
それから毎朝起きるたびに「今日の腰の具合はどうかな?」と、腰に意識を集めて点検します。病状に固着すればするほど、局所の神経は過敏になりますから、わずかな症状や痛みもキャッチしがちになります。その結果として「ああ、今日もまた痛い」と感じ、また、痛みにとらわれるという悪循環に陥るのです。
痛みゼロを求めれば求めるほど、「まだ治らない」「まだ残っている」「まだまだ……」という思いは強くなります。無間地獄(むけんじごく:最悪の地獄という意味)に入ってしまうのです。痛みの共存とは、言うは易く行うは難しで、本当に体得することは難しいことです。
くすりだけで治すと、効果は薬効の時間に限られます。患者さんによっては、くすりが切れるとまた痛みだすのではと、くすりが切れる前から不安がり、痛みを増幅させて、くすりの量がどんどんと多くなっていく人もいるでしょう。しかし、薬物療法と心理療法を併用して行うことによって、くすりである程度治したあとは、自分自身の心で治していけるようになるのです。
6.ステイ・アクティブ
痛いけれど痛いまま帰って、普段の生活をする。そうしているうちに痛みが減っていく―。
森田療法や絶食療法という日本古来の心理療法が示すこの結論は、実は興味深いことに、近年、米国整形外科学会(AAOS)で提唱されている最新の治療概念、「ステイ・アクティブ」とも通底するのです。
なかでも、森田療法とステイ・アクティブとは、考え方が驚くほど似ています。米国発の「ステイ・アクティブ」とは、日常生活で行動ができる状態に身体があるのなら、アクティブ(行動的)でいられるのならばそれでよい、それを第一目標にし、患者には行動させよう。痛いからといって、「鎮痛剤を飲んで安静にしておけ」という昔ながらの考え方は捨てようという発想です。
なぜ安静にしていてはダメなのでしょうか。それは、痛みの悪循環に陥らないようにするためです。
慢性疼痛の患者さんは、一般に痛みに敏感です。器質的な痛みではなく、自分の心が100倍にも1000倍にも増幅させた「修飾された痛み」に敏感なのです。その修飾された痛みにとらわれて、ちょっとした体調の変化も痛みに結びつけ、膨らませて苦しみます。
また、痛いのだから安静にしていなければと長期間寝たり起きたりの生活を続けていると、筋力低下や体力不足になり、気分転換のためにちょっとした運動や旅行をしただけで筋肉痛になりやすくなります。
さらには過食と運動不足から肥満し、実際に筋や関節に負担がかかるようになる人もいます。運動不足が、身体の神経系に存在する疼痛を抑制する機能を低下させることにもなります。廃用症候群といって、心肺機能が低下したり、骨粗鬆症が進行したり、筋を傷めやすくなったり、落ち込みやすくなるなど精神的に弱ってきたりもします。その結果、家庭不和や社会生活不適応といった状態が生まれます。これが痛みの悪循環です。
痛いのに動けば余計悪くなるではないか、という患者さんに向け、AAOS(米国整形外科学会)はとくに腰痛患者に対してこう述べています。
「腰痛を発症したばかりの急性期には運動はすべきではありませんが、すでに慢性化した痛みの場合には、運動によって全身の筋肉を鍛えることでむしろ痛みが和らぎます。さらには症状の悪化を予防することになります。急性期にも寝ているのではなく、起きて動き回りましょう。ベッドに寝て運動不足でいると回復が遅くなります」
痛くても痛いなりに動きなさい、といっているのです。
言葉や言い回し、またその意味の深さにおいて、いささかの差はありますが、このステイ・アクティブの概念と、森田療法の「あるがまま」という考え方は、根本理念で通底しているように見えるのです。
7.心因性の慢性疼痛患者の心得
平木先生が私案として、心因性の慢性疼痛患者の心得なるものを8つ挙げられています。ポイントは、頑張らない、焦らない、進み続けるということです。
①「ステイ・アクティブ」を目標とすること
②毎日の疼痛記録はやめること
③根性論で頑張ろうとしないこと
④自律訓練法をマスターすること
⑤「あるがまま」を実践すること
⑥すっかり治そうと焦らないこと
⑦治りたいがための悪あがきはしないこと
⑧薬物治療の場合、症状が改善されてきたら、できるだけ長く服薬を続け、その後徐々に減量し、早々の中止や中断をしないこと
8.悩みを相談する人の心理
多くの場合、問題をかかえている本人は、「うまい策があるわけではないし、この人が解決できるものでもない」ということを頭の隅で無意識に分かっていると思います。恋の悩みも経済的なトラブルでも家庭内の問題でも、健康問題でも、悩みの相談の心理とはそのようなものです。
分かっていながら、誰かに、どうしてもいわずにはいられない。ただ聞いてほしいというのが、悩みを訴える人の本心だと思います。つまり、相談を受けた方の役割で重要なのは、なにかもっともらしいアドバイスをしようと努力することではありません。
その人がどれほど悩んでいるか、苦しんでいるかということを、温かく共感をもって理解、共有しようという態度が、いちばん大切なのです。共感し、共有しようという態度を感じられることによって、苦しんでいる人は心の負担が軽くなります。
それが患者さん本人の自己解決力のアップにつながり、物事を客観的にみることができる余裕につながり、最終的に自分なりの解決法を見出していくのです。
9.心因性疼痛障害を疑うヒント
①六か月(三か月とも)以上続く慢性の痛み
②少なくとも二か所以上の医療機関での精密検査で、痛みに相当する病変が見あたらない
③一般的な鎮痛剤が効かない、効きにくい
④痛み方が独特で、周囲の人になかなか理解してもらえない
これまでに1000人以上の慢性疼痛患者さんを診療してきた平木先生のご経験に基づくキーワードです。慢性疼痛があって、これらの項目にあてはまるならば、一度はその原因として心因性を考えてみる必要があると思います。
心療内科
1.患者さんの多くは、「心因性」という診断に納得しない傾向がある。ここには「こんな激痛が心因であるはずがない」という強い思い込みも要因である。
2.日本で最初に心療内科という診療科を掲げたのは、九州大学医学部の池見酉次郎先生で、1963年に講座として、「心療内科」を冠するようになった。(看板を出せる標榜科として認められたのは1996年であり、30年以上先だった)
3.平木先生が一般内科に加えて心療内科を併設されたのは1983年であり、個人病院として心療内科を設置した例としては、全国でも最初に近いほうだった。
4.治ったかどうかは、患者さんの言葉のニュアンスから医師が判断する。平木先生のクリニック では痛みの評価を5点満点の六段階評価で表現してもらっている。同じ2点でも「だいぶよくなってきたけれど、まだ痛い。2点くらいは痛みがあります」という人と、「もうだいぶよくなってきて、2点くらいの痛みはあるけど何とかやっています」という人がいる。同じ2点でも前者はまだまだ時間がかかり、後者はそろそろ卒業というほどにニュアンスは異なる。患者さんの話を聞かないと点数だけでは判断できない。
5.心療内科のカルテは他の診療科とは少し異なる。カルテは日本語で書かれ、患者さんの言ったこと、医師が言ったこと、一言一句そのまま記載する。
6.診察の中でお話を聞きながら受ける第一印象がとても大事である。患者さんの痛みの背景に何があるのか。その物語が、患者さんの口から医師に話されること、そして医師と患者がともに物語への認識を深めていくことから、治療が始まっていく。
7.各種心理テストを行っている。その分析結果は病気を理解するのに参考になるが、診察で病歴を聞きながら、問診を行い、その中で性格傾向や心理状態、不安やうつなどを把握することが大切である。
8.「人体図へのマーク」「痛さの程度の数値化」「痛みの言語化」という患者さん自身による三段階の作業を通して、患者さんの痛みが明らかになっていく。
9.処方した薬が効かず、頑固な痛みを抱えた難治性の患者さんの場合、あらためて時間をとって面接し、生い立ちから現在までの人生、家族関係、趣味、宗教、恋愛観、結婚観、職場での問題、家庭内の問題などを、手順に従って、より詳しくうかがっていく。そこに、本人もはっきりとは気付いていない何らかの、痛みを生じるに至った「物語」が多々潜んでいることが多い。
付記
時々勉強させて頂いているサイトで、偶然、「心療内科」に関するコラムを見つけましたので、ご紹介させていただきます。
ドグマチール(スルピリド)による薬剤性パーキンソニズム
年始に「薬剤性パーキソニズム」が原因で、転倒された患者さまがおいでです。
お話を伺うと、平坦な道にもかかわらず、ツツツッと足が勝手に運ばれ、止まることができず転倒してしまったとのことでした。この転倒は姿勢反射障害によるものであることが懸念されました。
また、ご友人からは「〇〇さんは足を引きずるように歩いているから、注意した方がいいよ。」と言われるとのお話もされていました。これについては、足の運びだけでなく、歩行時の腕振りに問題があるのではないかということを考えました。
パーキンソン病の症状は姿勢反射障害の他、振戦(手のふるえ)、筋強剛(腕が歯車のようにカクカクした動きになる)、無動(思うように体が動かない)などが代表的な所見ですが、今回は姿勢反射障害によると思われる転倒以外の所見はありませんでした。しかしながら、万一のことを優先し、脳を診てもらえる病院に行かれることをお勧めしました。
地元の病院での診察結果は、パーキンソン病かどうかははっきりしないが、レボドパという強力なパーキンソン病の薬を2週間分渡されるというもので、原因および今後の展開は不透明な状況となっていました。
この薬は副作用の問題を抱えており、パーキンソン病やパーキンソン症候群(薬剤性を除く)の患者さま以外は服用する薬ではないと認識していました。そこで、現在の状況と問題点、更に今後の進め方について、患者さまに率直にお話したところ、ご納得いただき、後日、小平市にある国立精神・神経医療研究センター病院で診察を受けられることになりました。
診察の結果、数年前から服用していた「ドグマチール」の副作用による「薬剤性パーキソニズム」であると診断されました。そして、レボドパの服用はただちに中止されました。また、薬の代謝の問題と思われますが、ドグマチールの影響は2週間程続くので、今後2週間は特に転倒に注意してほしいとのお話があったそうです。こうして、年始の転倒の原因と今後の治療の進め方が明らかになり、一件落着となりました。
補足.
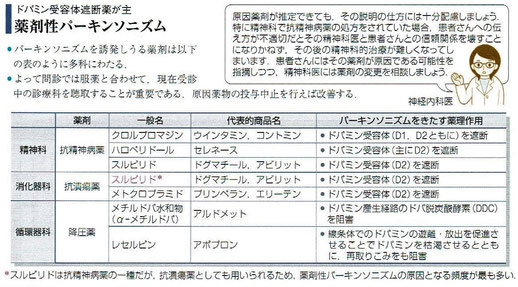
中央、一般名「スルピリド」、代表的商品名「ドグマチール」があり、表下の余白には「スルピリドが薬剤性パーキソニズムの原因となる頻度が最も多い」とあります。
画像出展:「病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経」
活性酸素シグナルと酸化ストレス
今回の題材は2017年12月29日の「パーキンソン病
-進化する診断と治療-」の中で、自らに課した宿題です。これはパーキンソン病発症には「活性酸素」が深く関わっており、これをしっかり理解することが重要であるという思いからでした。
教材は下記の2冊ですが、「絵とき シグナル伝達入門 改訂版」ついては関心がある箇所だけを拾い読みしました。
本題に入る前に、パーキンソン病と活性酸素との関係についてお伝えしたいと思います。
この写真と図は、「パーキンソン病 -進化する診断と治療-」の座談会で司会を務められた、京都大学大学院の高橋良輔教授が平成20年に日本内科学会講演会で発表され、日本内科学会雑誌 第97巻 第9号に掲載された資料からのものですが、ネット上にある資料でしたので閲覧できるようにさせて頂きました。
自分なりに考えた、パーキンソン病と活性酸素との関係について
1.活性酸素と抗酸化物質のアンバランスによって「酸化ストレス」は生まれ障害を起こす。
2.パーキンソン病を神経変性疾患の一つとしてとらえ、「蛋白質障害」という切り口で考える。
3.活性酸素はシグナル経路を活性化して、細胞保護、細胞分化増殖、細胞死の制御などの有益な働きもしている。
神経変性疾患はコンフォメーション病(蛋白質ミスフォールディング病)とも呼ばれており、原因タンパク質が凝集化し、病変部位に沈着することが特徴です。原因タンパク質の凝集化には酸化ストレスが関与しています。
そして、鍼灸治療について考えるならば、「自律神経系と内分泌系のバランスを調え、内臓の働きと自然治癒力を高め、酸化ストレス発現の抑制と耐性を目指す。」というものが治療の柱になると思います。非常に抽象的ではありますが、「何を、どうしたいのか」という治療イメージを持って臨むことが、良い施術の第一歩であると考えています。
『病態解明に迫る 活性酸素シグナルと酸化ストレス』では、活性酸素、酸化ストレスに加え、「シグナル伝達」というキーワードも重要なポイントになっています。そこで、まずはこの「シグナル伝達」が、いかなるものか調べました。
『絵とき シグナル伝達入門』では「はじめに」の中で以下の2つを上げられています。
●シグナル伝達研究は、さまざまな生命現象のメカニズムを分子レベルで明らかにしていこうとするものである。
●“だれ”が“だれ”にシグナルを伝え、次に“だれ”がそれを受け取るのか、そして最後に何が起こるのか…この流れを捉えていくことが大切である。
著者の服部先生は、“がん研究からみつかった[がん遺伝子]はシグナル伝達研究に大きなインパクトを与えた”とお話されていますが、その説明箇所を引用させて頂きます。
なお( )内は補足説明として私の方で追記したものになります。
「シグナルを流れとして捉える-点から線へ、さらにはネットワークへ」
『細胞の受容体が受け取ったシグナルは細胞の中でどのようにプロセスされて、核、細胞質や細胞骨格(線維状のタンパク質により細胞を支えたり、動かしたりする)系に伝えられていくのだろう。シグナルを誤って伝えることは、シグナルがない時よりも悪い結果をもたらしかねない。まず受容体が刺激されたという細胞外のシグナルを細胞内のシグナルに変換しなければならない。そしてさらに正しい経路を経てさまざまな最終目的地まで間違いなく伝えなければならない。シグナル伝達は伝言ゲームにたとえることができるだろう。
どのようにして、シグナルを伝えるべき相手を選び、しかも正しく伝えていくのだろうか。
がん研究からみつかった“がん遺伝子”はシグナル伝達研究に大きなインパクトを与えた。すでに100以上もみつかっているがん遺伝子は、実は私たちの体のどの細胞ももっている遺伝子“前がん遺伝子”に変異が生じできたものである。そして前がん遺伝子の産物たちは、手に手を取り合って細胞の増殖を指令し続けさせるものだった。“だれが”“だれに”シグナルを伝え、次の“だれが”それを受け取るのか、そして最後に何が引き起こされるのか。シグナル伝達の研究はこうした点を次々と明らかにしてきたのである。
細胞の増殖を研究するにしろ、あるいは神経細胞の分化を研究するにせよ、シグナル伝達の立場は、常にシグナルを“流れ”として捉えてその流れを伝えていく役者を次々と明らかにしていくものである。その主役はタンパク質であることは間違いない。
このようにシグナル伝達はがんの研究から大きな影響を受けたけれども、もちろん生理学や遺伝学からもシグナル伝達研究の柱となるような大きな結果が出ている。
興奮するとドキドキしたり、また気合いが張ってくるのを感じることがあるだろう。これはアドレナリンの作用で、細胞の中のcAMP(サイクリック[環状]AMP[アデノシン一リン酸]:アドレナリンなど多くのホルモンや神経伝達物質などの第1メッセンジャーの細胞外からの刺激を、細胞内の標的分子に伝える第2メッセンジャーとして機能する)濃度が高められるせいである。その結果、細胞内のさまざまなタンパク質がcAMP依存性のタンパク質リン酸化酵素でリン酸化されていろいろな効果が発揮される。
さまざまな神経伝達物質の受容体からのシグナル伝達もこのような経路を用いている。こうしてみると、私たちの気持ちや心理状態もシグナル伝達の立場から説明できる日も遠くないかもしれない。』
『病態解明に迫る 活性酸素シグナルと酸化ストレス
癌、神経変性疾患、循環・代謝異常にかかわるレドックス制御機構と最新の技術開発』
は、「序」に続き「概論」からスタートしていますが、まずは目次をご紹介します。
概論
活性酸素のシグナル伝達機能 -その生理機能の再発見と酸化ストレス研究の新展開
第1章 活性酸素・NOの生理機能
1.活性酸素シグナル生成系の制御機構
2.ミトコンドリア活性酸素生成とシグナル制御
3.チオール基の修飾による活性酸素のセンサー機能制御
4.親電子シグナル伝達
5.SNO化修飾によるシグナル伝達の新展開
6.NO・ニトロソ化シグナルと細胞死
7.活性酸素によるリン酸化シグナル制御
8.G12/13タンパク質による活性酸素シグナリング
9.植物におけるNADPHオキシダーゼの制御機構
10.植物のストレス応答・形態形成における活性酸素種の積極的生成とその制御
第2章 酸化ストレスと病態
Ⅰ.細胞分化増殖・シグナル異常と再生医療
1.ER(小胞体)と酸化ストレス
2.アポトーシスと酸化ストレス -酸化ストレス誘導性アポトーシスにおけるNoxaの役割
3.幹細胞ホメオスタシスと酸化ストレス
4.眼表面と酸化ストレス
5.グルタチオンペルオキシダーゼ4(GPx4、PHGPx)による胚発生・精子形成の制御機構
Ⅱ.炎症・発癌と変性疾患
1.酸化的翻訳後修飾タンパク質の解析でみえてきた肝・消化管炎症病態の新展開
2.チオレドキシンによる酸化ストレス防御とレドックスシグナル制御
3.酸化ストレス誘発発癌機構の解明 -フリーラジカル傷害に弱いゲノム領域を探る
4.塩基除去修復酵素MUTYHに依存したプログラム細胞死と発癌抑制機構
5.ALSにおける酸化ストレスおよび酸化型SOD1の関与
Ⅲ.呼吸・循環・代謝異常
1.H2O2が制御する血管弛緩反応の分子機構
2.慢性腎臓病における鉄の重要性
3.COPDにおける酸化ストレス病態
4.糖尿病合併症および糖尿病発症における酸化ストレスの意義
5.酸化ストレスによる貧血 -造血幹細胞の老化と赤血球の酸化
第3章 活性酸素応用研究の最前線
1.論理的設計法に基づく種選択的ROS蛍光プローブの開発
2.活性酸素シグナル分子H2O2を介したユニークなタンパク質修飾機構
3.アダクトミクス -DNAおよびタンパク質付加体の網羅的解析
4.活性酸素センサー:nucleoredoxin
5.酸化ストレス作動性TRPチャネルの化学生理学
6.親電子性リガンドセンサーとしての核内受容体PPARγ
7.活性酸素がインスリンシグナル伝達に与える影響とその二面性
8.レドックス制御に干渉する小分子のケミカルバイオロジー
9.Nrf2/Keap1酸化ストレス応答系による活性酸素シグナル制御
10.NOと植物の感染防御応答
続いて、「概論」の冒頭に書かれていた全文をご紹介します。
『活性酸素は生体内のエネルギー代謝や感染防御過程において発生する一連の活性分子種(O2⁻,H2O2など)であり、これまで酸素毒性の要因となる有害物質として取り扱われてきた。実際、活性酸素は、感染、炎症、癌、動脈硬化・糖尿病などの生活習慣病や代謝性疾患、アルツハイマー病などの神経変性疾患といった、さまざまな疾病の原因となることが示唆されている。近年(本書は2009年の発行です)、活性酸素がシグナル伝達機能を発揮していることが報告されるようになり、幅広い生命科学領域において、「活性酸素による生理的なシグナル伝達機能」の解明が飛躍的に進展している。本増刊号においては、最近次々と明らかにされている活性酸素シグナルの新知見に焦点をあて、その真の生理活性を議論することにより、活性酸素の機能と病態解明の新展開を紹介する。』
以降、本文よりブログに記録しておきたい要点を抜き出し、列挙させて頂きます。
なお、ROSはreactive oxygen speciesの略で「活性酸素種」となりますが、「活性酸素」を意味します。ブログの中ではROSは「ROSシグナル」として使い、それ以外は「活性酸素・活性酸素種」という言葉を使います。
概論
活性酸素のシグナル伝達機能 -その生理機能の再発見と酸化ストレス研究の新展開
・生物は、酸素との長い付き合いが始まった太古の時代より、酸素分子の高い化学反応を利用したエネルギー代謝の代償としてその毒性を被ることとなった。
・活性酸素は生体分子の非特異的損傷をもたらす単なる毒性因子ではなく、精密に制御されたシグナル伝達の担い手であるというコンセプトが広く受け入れられつつある。
・活性酸素は、生体内のその他のシグナル伝達物質(細胞内に存在し、外部からの刺激[信号]を受け取って別の物質に伝える役割を持つ物質)と同様に、特異的なシグナル経路を活性化して、細胞保護、細胞分化増殖、細胞死の制御などを司ることがわかってきた。
・活性酸素による細胞シグナル制御(ROSシグナル)に関する関連分野からの国際誌への発表論文数は、この10年間で2倍以上の伸びを示している。
1.シグナル分子としての活性酸素(ROSシグナル)の再発見
・80年代頃から盛んに試みられた抗酸化療法は、当初期待したほどうまく臨床応用が進まず、その学術基盤が確立されぬまま、科学的に腑弱な概念に基づく民間療法として一般に普及してしまった。特に日本国内における酸化ストレス研究は、折りしも国民に広く流行した健康食品ブームに押されるようにして進展してきたともいえる。
・酸化ストレス研究は2000年前後に特に顕著に進展し沢山の成果を上げてきた。
・近年急速に進展しているROSシグナルの解明は、活性酸素研究に新たな潮流を生み出し古典的な酸化ストレス研究に革新的な扉を開こうとしている。
2.ROSシグナルの生理機能からみた酸化ストレス病態
・これまでの酸化ストレスの病因論は「活性酸素」として展開してきた。この病態理論はもちろん酸化ストレスの中心的なドグマ(教義)となっている。実際、活性酸素により脂質過酸化反応が誘発され細胞の生体膜機能が損なわれること、血中の脂質・コレステロールの酸化が、動脈硬化病巣の形成を促しその発症に深くかかわること、また、高血糖が活性酸素の産生を高めることにより生活習慣病の重要な要因になることなどが報告されている。酸化ストレスが疾病病態に普遍的に関与することは、関連分野の多くの研究者に広く認められている。
・ER(小胞体)ストレス、幹細胞の分化制御、アポトーシス・細胞死制御、角膜エイジング、生殖・再生、発癌など多様な病態と酸化ストレスのクロストークに関してもそれぞれの分野の第一人者から最新の知見が紹介されている。
・酸化ストレスを活性酸素による生理的シグナル伝達経路を介する病態、あるいは、正常なシグナル伝達の制御異常という視点から捉えることも重要であろう。
・活性酸素は、酸化ストレスをもたらす病原因子としてふるまう反面、その生理機能の重要性を示す多くの科学的根拠が報告されており、しばしば「double-edged sword」として取り扱われてきた活性分子種である。その光と陰は、これまで単純にその化学的反応性と毒性により説明されてきた。しかしながら実際は毒性というより、生理的なROSシグナル活性の発現と制御信号が、活性酸素の二面性を操る本態であることが明らかにされつつある。

「酸化ストレスとは、活性酸素と抗酸化システム、抗酸化酵素との バランスとして定義されています。酸化ストレスが高いとは、生体内において活性酸素による酸化作用と、 抗酸化物質等の抗酸化作用とのバランスが崩れ、酸化反応が亢進する状況のことを言います。」
画像出展:「日本老化制御研究所」
・活性酸素の生理活性として以前より感染防御作用においても、直接的な抗菌作用だけでなくROSシグナルを介する間接的な防御機構が存在することが示唆されている。
・活性酸素研究の新たな潮流と裾野の広がりは生命科学領域のほとんどの分野に及んでおり、特に、メタボリックシンドローム、感染・炎症・免疫異常、老化、神経変性疾患、発癌などの酸化ストレスのかかわる疾病病態の解明とその再生医療などの先進医療への応用・展開は、高齢化が進むわが国にあっては社会的にも要請が強い重要な課題といえる。
・活性酸素は、これまではその高い反応性のため真の生理活性に不明な点が多かったが、分子イメージングや質量分析法などの優れた技術開発により、近年その実体の解明が飛躍的に進んでいる。
・活性酸素がユニークなシグナル伝達の担い手として再発見され、今まさに歴史の大舞台に登場してきた。今後さらに、新しい病態論と診断・予防・治療法が確立されるものと期待される。
第1章 活性酸素・NO(一酸化窒素)の生理機能
1.活性酸素シグナル生成系の制御機構
種々の活性酸素生成系について
・活性酸素は、歴史的にはまず、代謝系の副産物として認識された。現在ではミトコンドリアの電子伝達系の寄与が大きいと考えられている。特にミトコンドリア内膜の複合体Ⅰや複合体Ⅲから漏れ出た電子が、酸素分子に渡されスーパーオキシドが生成する。
・細胞質に存在するキサンチン酸化還元酵素(XOR)は、通常はキサンチン脱水素酵素(XDH)として存在し、活性酸素を生成しないが、酸化ストレス時にはキサンチン酸化酵素(XO)に変換され、酸素分子から過酸化水素やスーパーオキシドなどの活性酸素を生成するようになる。
・細胞質に存在するNO合成酵素(NOS)は、ストレス時にuncouplingが起こるとNO合成をやめてスーパーオキシドを生成するようになる。
・シクロオキシゲナーゼやリポキシゲナーゼなどからも活性酸素が生成しうるが、これらの活性酸素シグナリングにおける役割は小さいと、今のところ考えられている。
2.ミトコンドリア活性酸素生成とシグナル制御
・ミトコンドリアは各細胞に数百存在し、肝臓、腎臓、心臓、筋肉、脳などにある代謝の活発な部位では、細胞質の約40%をも占める組織もあるほどである。
・ミトコンドリアにおいて活性酸素が産生されるという仮説は、Denham Harmanが1956年に発表した“Free radical theory”(「加齢はミトコンドリア由来のフリーラジカルによって引き起こされる細胞損傷が蓄積したものである)という理論が最初である。
・抗酸化剤のSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)が発見されたのは1969年だった。
・1973年にBoverisらが過酸化水素が単離ミトコンドリアから産生されていることを証明し、現代に至るまで、加齢のみならず、種々の慢性疾患において、ミトコンドリア呼吸鎖由来の活性酸素が、その病態形成、伸展において重要な役割を果たしていることが知られるようになった。
ミトコンドリアにおける活性酸素種とその産生部位
・ミトコンドリア呼吸鎖における活性酸素は、複合体ⅠおよびⅢにおいて産生される。
・過酸化水素は細胞膜を自由に通過でき、細胞質内に移動できることが知られている。
・ミトコンドリア内には、スーパーオキシドを消去するMn-SODのほかに、過酸化水素の消去系として、グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)やペルオキシレドキシン(Prx)が存在し、産生された活性酸素はすみやかに消去される。
・処理しきれない過剰な活性酸素は、タンパク質や核酸と反応し傷害を及ぼし、機能障害、細胞死へと導く。
・これらの抗酸化酵素と活性酸素産生の不均衡は、発癌やアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患、動脈硬化、心不全、さらに老化など実にさまざまな慢性疾患に関与していると考えられ、抗酸化剤の投与、抗酸化酵素の過剰発現によって治療効果が得られることが、多くの実験によって裏づけられている。
・近年、いくつかのミトコンドリアに局在するリン酸化酵素がミトコンドリア由来の活性酸素によって可逆的に不活性化されることも知られてきた。
・活性酸素が細胞周期をも制御することが明らかにされている。
・過酸化水素(活性酸素)はNO同様に、その濃度によって作用を異にする。
・0.7μM以下…細胞増殖に作用
・1.0~3.0μM…アポトーシス
・3.0μM以上…ネクローシス(壊死)
活性酸素とアポトーシス
・アポトーシスはdeath receptorにTNF-α、Fasリガンドが結合することで、カスパーゼを活性化する外因経路とミトコンドリアを介した内因経路が知られている。
・アポトーシスの内因経路は、アポトーシス促進因子として、ミトコンドリア由来の酸化ストレスと深く関連していることが知られている。
・ミトコンドリアは最も重要な活性酸素の産生源であり、同時に活性酸素の標的でもある。そして、ミトコンドリア由来のスーパーオキシドおよび過酸化水素が種々の病態ひいては老化において、いわゆる“悪役”として重要な役割を果たしていることが概念として認識された。
3.チオール基の修飾による活性酸素のセンサー機能制御
・近年、活性酸素は巧妙に制御されたシグナル伝達機構の担い手であるというコンセプトが生命科学分野に広く受け入れられつつある。
・活性酸素が、防御的な酸化ストレス応答を誘導する重要なシグナル分子であることが明らかになってきた。
・活性酸素や一酸化窒素(NO)は、シグナル伝達の最も上流に位置する分子群として、細胞内のセンサータンパク質を活性化し、さらに下流のエフェクター分子へとシグナルを伝える。
7.活性酸素によるリン酸化シグナル制御
・高濃度の活性酸素種は細胞死や細胞傷害を引き起こすが、生理的に産生された低濃度の活性酸素は細胞増殖、細胞運動、遺伝子発現を制御する。さらにサイトカイン刺激などの細胞外刺激に応じて産生された活性酸素がセカンドメッセンジャーとして機能することも明らかにされている。ここで問題になるのは活性酸素がどのようにしてシグナル系を駆動するのかということである。
8.G12/13タンパク質による活性酸素シグナリング
・神経伝達物質や液性因子などの受容体刺激によって生じる細胞内シグナル伝達のなかで、活性酸素の役割が注目されている。
・心臓では、アンジオテンシンⅡ刺激がAT1受容体を介してスーパーオキシドや過酸化水素をはじめとする活性酸素種を生成することが報告されている。これらの活性酸素は主に細胞膜上のNADPHオキシダーゼの活性化を介して生成され、AT1受容体シグナリングにおける細胞内情報伝達因子として重要な役割を果たしている。
筑波大学の研究情報ポータル(COTRE)に以下の図と説明がありました。ご紹介させて頂きます。

『私たちの体内の組織や臓器は、それらに特有の細胞によって作られています。それらの細胞がホルモン・成長因子・神経伝達物質などの情報を受け取って、シグナル伝達が稼働して細胞機能が発揮されることにより組織や臓器が正常に機能します。その結果として私たちは正常な生活を営むことができます。しかし、細胞のシグナル伝達に異常をきたすと、様々な病気になります。この異常は、シグナル伝達を行うタンパク質や酵素の性質の変化によって起こります。シグナル伝達の異常によって起こる病気には、がんやアレルギー、神経疾患などがあります。シグナル伝達がどのようなメカニズムで作動しているのかを解明して、それらの異常がどのような病気に関連しているのかを分子レベル、細胞レベル、および個体レベルで解明することが求められています。』
第2章 酸化ストレスと病態
Ⅰ.細胞分化増殖・シグナル異常と再生医療
1.ER(小胞体)と酸化ストレス
・ERは細胞内Ca2+(カルシウムイオン)の主たる貯蔵部位として、Ca2+ホメオスタシスにおいて重要な役割を演じる。
・ERの諸機能の破綻によるERストレスは、神経変性疾患や虚血性臓器傷害、糖尿病や動脈硬化症などの生活習慣病の誘因の一つと考えらえるが、近年、その分子機構とレドックス(酸化還元反応)、酸化ストレスとの関連が注目されている。
ERにおけるタンパク質の酸化的折りたたみ
・分泌・膜タンパク質の新生ポリペプチドは、ER内腔へ引き込まれた後、分子シャロペンのようなタンパク質の折りたたみ関連酵素による手助けのもとで正しく折りたたまれる。そして、ゴルジ体で糖鎖修飾などの翻訳後修飾を受けた後、細胞外あるいは膜上に運ばれる。
・ERでの折りたたみに失敗したタンパク質は細胞質に移送され、ユビキチン・プロテアソーム経路で分解される。
ERにおけるレドックスホメオスタシスとROSの生成
・過剰なERでのタンパク質生合成は、酸化ストレスの発生と密接に関係する。
ERストレスとは
・ERストレスは、正しく折りたたまれない変性タンパク質のERへの蓄積が起こすストレス応答である。
・ERストレスは、酸化ストレス、虚血、低酸素、ウィルス感染、栄養飢餓など種々の環境変化によってもたらされる。
・ERストレスシグナルに起因したERストレス応答では、変性タンパク質が過剰にERに蓄積しないよう、タンパク質の翻訳停止、ERシャロペンの発現誘導、ERADの亢進が起こる。
・ERストレスにより回避できない細胞傷害が起こった場合、細胞は自らアポトーシスの誘導を選択する。
ERストレスと酸化ストレスのクロストーク
・糖尿病態において、酸化ストレスとERストレスの両者が密接に関わることを示している。
酸化ストレスによるER内Ca2+制御タンパク質の機能修飾
・ERに局在するCa2+制御タンパク質は、酸化ストレスの標的となり、その生理機能が制御され、細胞・組織の酸化ストレス傷害と関係することが知られている。
2.アポトーシスと酸化ストレス -酸化ストレス誘導性アポトーシスにおけるNoxaの役割
・生体内で発生する活性酸素種は遺伝子発現やシグナル伝達因子の活性を制御し、種々の細胞応答にかかわっていることが知られている。
・活性酸素種の発生量は産生と消去とのバランスにより、厳密に制御されており、その制御破綻は、老化、発癌、梗塞、神経変性疾患など、さまざまな疾患の発症に関与していることが示唆されている。とりわけ、酸化ストレスによる過剰な細胞死の誘導は、組織の機能を維持するうえで危機的であり、その分子メカニズムの解明は、生物学的な意義をもつだけではなく、医学的にも非常に重要な課題と思われる。
・活性酸素種の1つである過酸化水素による細胞死に関しては、アポトーシスとネクローシスがよく知られているが、どの細胞死機構が活性化されているかについては、細胞腫や過酸化水素の濃度によって異なっており、両者が混在するケースも知られている。
アポトーシス経路とミトコンドリア
・アポトーシスはさまざまな刺激によって誘導されるが、各刺激によって誘導されたシグナルは最終的にはミトコンドリアに集約される。
4.眼表面と酸化ストレス
・角膜を含む眼表面が、なぜこれほど環境性の酸化ストレスに強いかはまだ知られていない。角膜上皮が多くのグリコーゲンを貯蔵して、嫌気性代謝に依存する率が高いことも1つの原因としてあげられている。角膜の抗酸化機能を解明することは、酸化ストレスによるエイジングや発癌メカニズムを一部解明できるかもしれない。
Ⅱ.炎症・発癌と変性疾患
3.酸化ストレス誘発発癌機構の解明
酸化ストレスと発癌
・酸化ストレスを引き起こす病態は、放射線・紫外線への曝露、鉄・銅などの遷移金属の過剰状態、ウィルス感染、あらゆる慢性炎症、ある種の抗癌剤投与(ブレオマイシン、アドリアマイシン)、臓器移植や梗塞など、実に多岐にわたっている。
Ⅲ.呼吸・循環・代謝異常
1.H2O2(過酸化水素:活性酸素の一つ)が制御する血管弛緩反応の分子機構
血管内皮細胞および血管平滑筋細胞は、多くの相互作用を及ぼしつつ血管の生理的機能を保っていることが知られている。血管内皮は各種の血管弛緩因子を産生・放出し、血管機能の恒常性の維持に重要な役割を果たしている。われわれは、生理的濃度の活性酸素(H2O2)が内皮由来過分極因子の本体として、血管弛緩作用を有することを報告した。一方、過剰な活性酸素(酸化ストレス)は心血管疾患の原因になることが知られている。われわれは最近、酸化ストレスが血管平滑筋細胞よりCyclophilin
A(細胞質に大量に存在する蛋白質。CyPA はそもそも免疫抑制剤cyclosporin A(CsA)の特異的
リガンドとして発見され,ポリペプチドのプロリンのアミド結合のシスからトランスヘの異性化を触媒する活性を有する)を分泌させ、血管内皮機能障害や平滑筋増殖促進作用を有することを報告した。これらの酸化ストレスによる血管弛緩反応の分子機構の解明により、心血管疾患の新たな治療薬開発の可能性が期待される。
・血管内皮細胞は、血管平滑筋層の内側を覆うたった一層の細胞群ではあるが、血管平滑筋細胞との多くの相互作用を有し、血管機能制御の根幹を形成している。血管内皮はプロスタサイクリン(PGI2)・一酸化窒素(NO)・内皮由来過分極因子(EDHF)の3種類の血管弛緩因子を産生・放出し、これらは生理的条件下での血管機能の恒常性の維持に重要な役割を果たしている。(短期的には血管トーヌス[緊張]を弛緩優位に保ち、長期的には動脈硬化の発生・進展を抑制して、心血管系の恒常性の維持に極めて重要な働きをしている)
EDHFとしてのH2O2
・H2O2は血管弛緩反応に関する役割をNOと分担しており、大動脈などの導入血管における弛緩反応は主としてNOにより制御されているが、H2O2は微小血管、特に抵抗血管において重要な役割を果たしていると考えられる。
酸化ストレスとしてのH2O2
・高血圧、糖尿病や脂質異常症などの種々の動脈硬化危険因子の存在下では、過剰な活性酸素種が血管平滑筋細胞や炎症細胞(好酸球,Tリンパ球,肥満細胞[マスト細胞],好中球,好塩基球など)において大量に産生・遊離されることがわかっている。
・血管平滑筋細胞は中~大血管を構築する細胞のなかでも圧倒的な数および容積を有し、NADPHオキシダーゼなどの多くのROS産生源を有する。
・アンジオテンシンⅡ(ポリペプチドの1種で、血圧上昇[昇圧]作用を持つ生理活性物質である。アンジオテンシンII〜IVは心臓の収縮力を高め、細動脈を収縮させることで血圧を上昇させる。特にアンジオテンシンII
は副腎皮質にある受容体に結合すると、副腎皮質からアルドステロンの合成・分泌が促進される)などのアゴニスト(生体内の受容体分子に働いて神経伝達物質やホルモンなどと同様の機能を示す作動薬のこと。現実に生体内で働いている物質はリガンドと呼ばれる)刺激や「ずり応力」(血流は内皮にずり応力を与える:血管壁には常に血行力学的ストレスが作用している. 一つは血圧による血管壁に垂直方向に働く法線応力で,これは内皮細胞や平滑筋細胞を引き伸ばし細胞に張力を与える.他
の一つは血流によるずり応力で,これは血管内面を覆う内皮細胞にのみ作用し,内皮細胞を流れの方向に歪ませる力となる)、低酸素などの環境因子により大量の活性酸素が平滑筋細胞内で産生され、病的高濃度(ミリモルオーダー)のH2O2は、生理的濃度(マイクロオーダー)のH2O2とは異なる役割を有していることが示唆されている。すなわち、H2O2は生理的低濃度において特に微小血管の血管機能にとって保護的に働く一方、病的高濃度においては血管リモデリング(血液循環状態の変化に伴う、血管の構造上の変化で、高血圧による圧力変化に対応する血管壁圧の変化や、腫瘍組織における血管新生などが例である)を促進する可能性がある。
2.慢性腎臓病における鉄の重要性
慢性腎臓病(CKD)では、腎障害のさらなる進行や心血管疾患(CVD)の合併が多くみられ、その病態には酸化ストレスが深く関与している。CKDの酸化ストレス亢進において、タンパク尿やレニン・アンジオテンシン系亢進に加え、鉄代謝異常の役割は大きい、鉄輸送タンパク質の発現異常による細胞内の鉄過剰状態は活性酸素産生を惹起する。また、CKDではチオシアン酸の増加による活性酸素産生がCVD発症に関連しうる。CKDあるいはCVDに関するこれらの知見から、活性酸素・遊離鉄をターゲットとした治療戦略の確立が望まれる。
・CKDの重要な点は、腎障害が悪化して末期腎不全へと至ることだけではなく、心血管疾患(CVD)などの合併がきわめて多く死亡率も高いことである。CKDでは従来からタンパク尿の程度と腎機能の予後との関連が知られており、タンパク尿による腎障害進行のメカニズムが報告されている。また、腎障害やCVDの進展においてレニン・アンジオテンシン系の亢進、酸化ストレスや慢性炎症の持続なども病態に関与している。
CVD(心血管疾患)
・CVD発症のリスク因子として、従来から喫煙や高血圧、肥満などの因子が知られているが、最大のリスク因子はCKDであることが、欧米および日本での大規模臨床試験で示されている。われわれは、CKDの病態およびCVD発症・進展には鉄代謝異常が関与していると考えている。
・透析患者は鉄輸送タンパク質の調節異常によって、細胞内では鉄が過剰に存在することが明らかとなった。
News!:「酸化ストレス」を検出する世界初の量子センサーを開発―光とMRIを使い、生活習慣病や炎症から体を守る先制医療に向けて― 2021年1月29日

発表のポイント
『生活習慣病や炎症等から生じる体内の酸化ストレス状態を可視化するために、強い蛍光を発する量子ドットと、MRI造影剤を組み合わせた量子センサーを開発しました。
この量子センサーは細胞内の活性酸素の産生と活性酸素を消去する抗酸化能の両者を捉え、そのバランスが崩れた状態である酸化ストレスに応答して量子ドットの蛍光とMRIの信号がON/OFFします。
この量子センサーを応用、発展させることで、量子ドットの高輝度の蛍光を利用した血液検査により酸化ストレスの状態を手軽に観察できます。血液検査で強い酸化ストレスが検出されたらMRIにより全身を調べ、病気が発症する前の段階で、酸化ストレスが生じている部位を特定できます。
本研究成果はがん・認知症・糖尿病などの生活習慣病が発症する前に予防的な介入をする、という将来の先制医療に繋がると期待されます。また、感染症によって、心臓や脳などに深刻な障害が起きつつあるか、後遺症リスクがどの程度あるかを推定する重要な手法になると期待できます。』


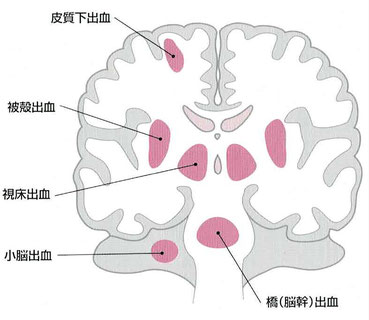
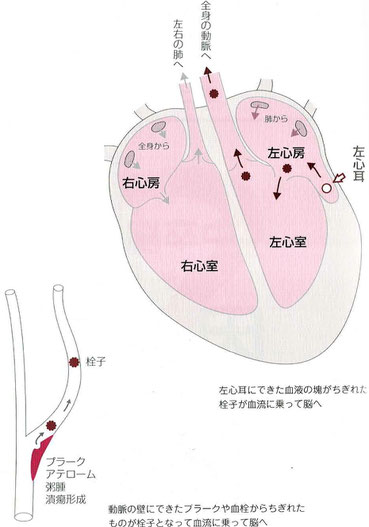
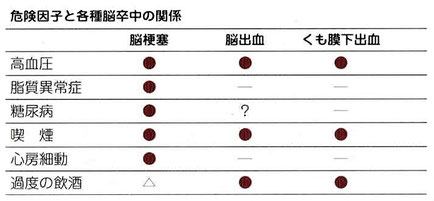
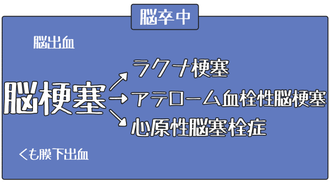
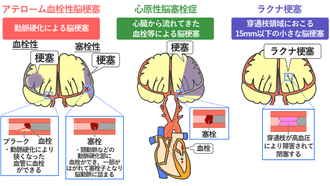



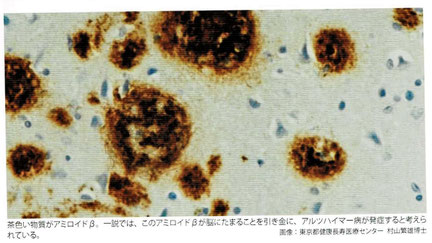

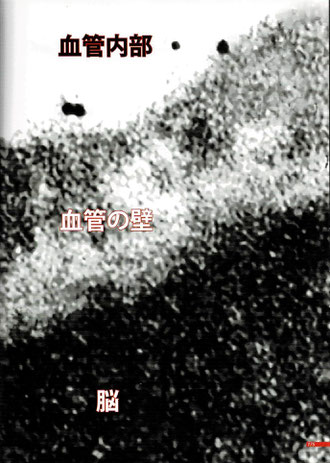


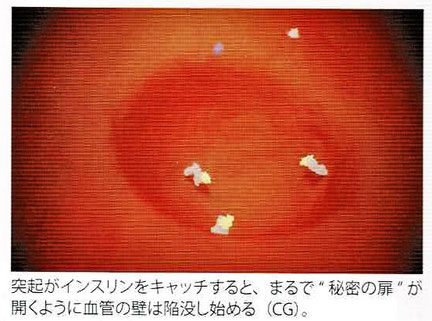
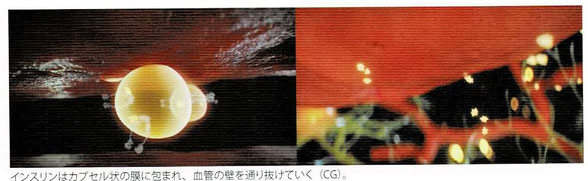
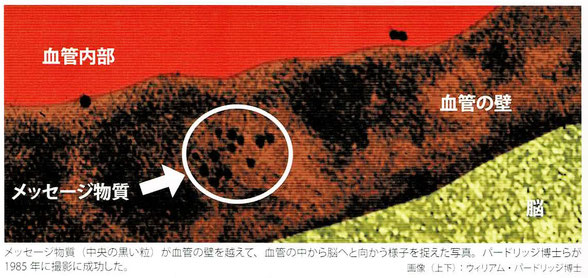

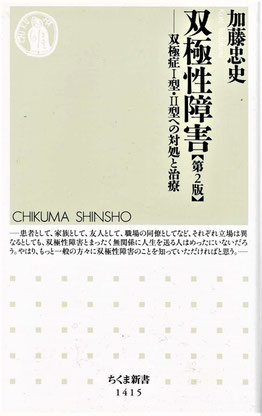

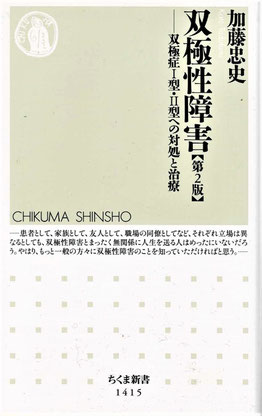


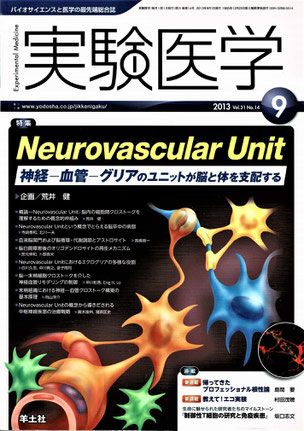



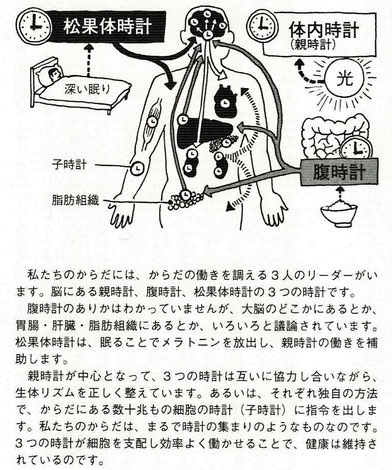

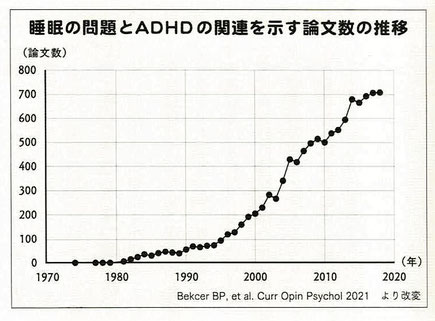
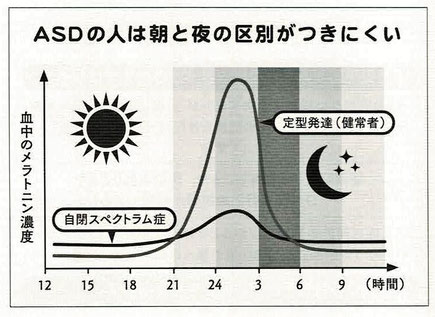


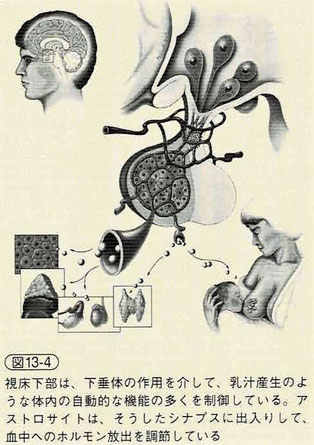


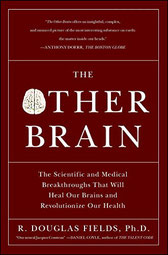



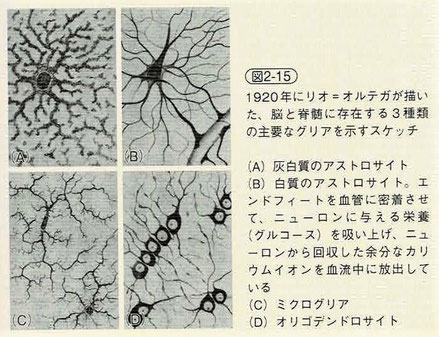

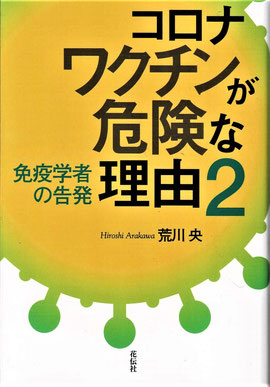


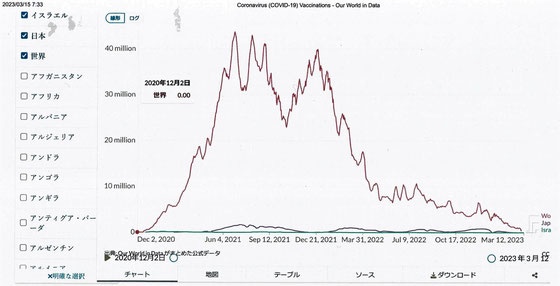
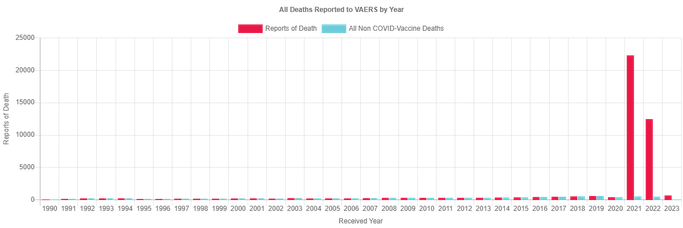



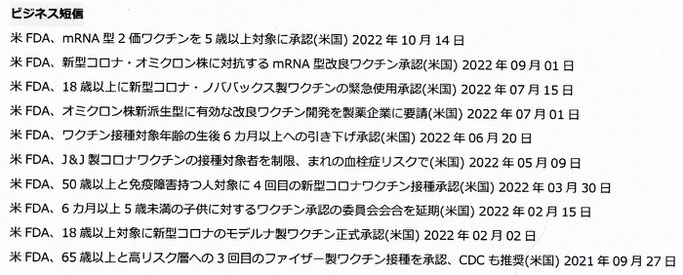

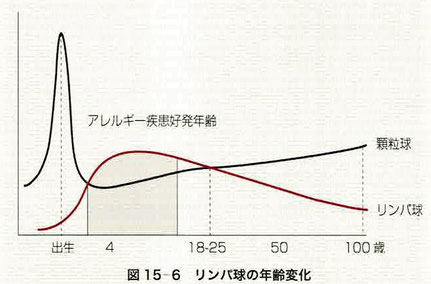







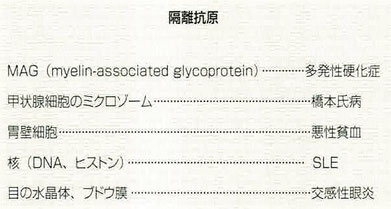

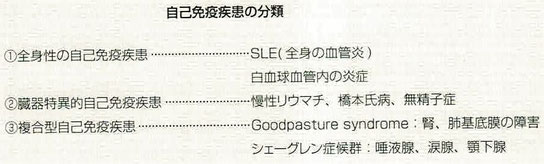
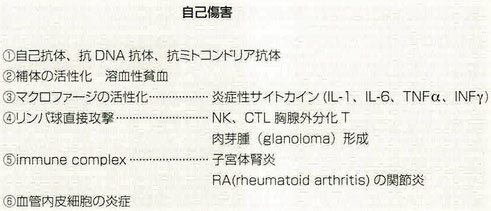
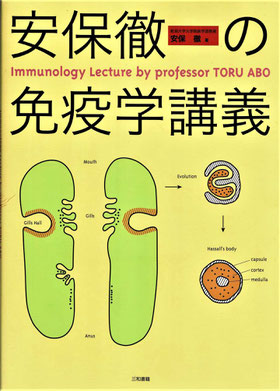
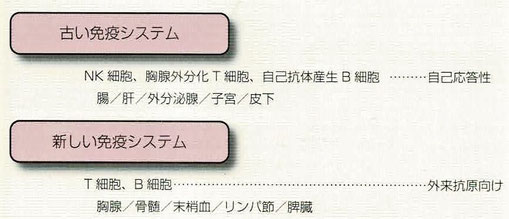






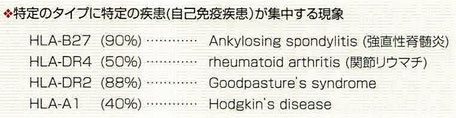


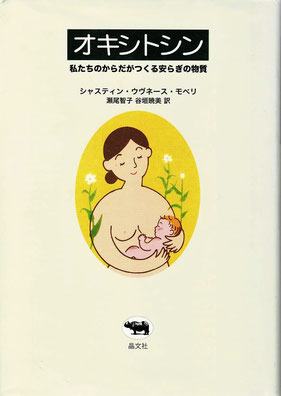
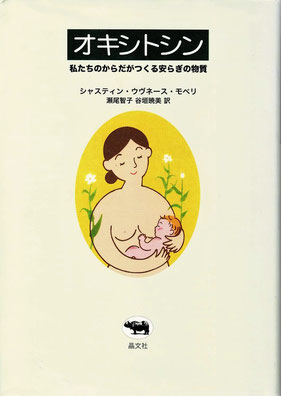

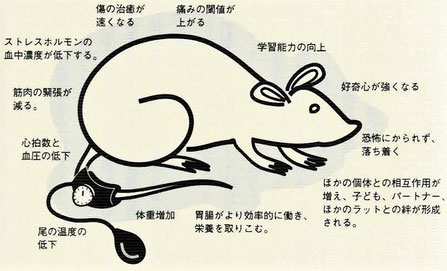

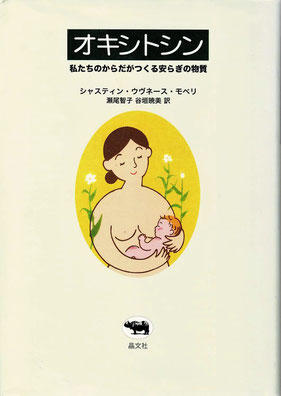
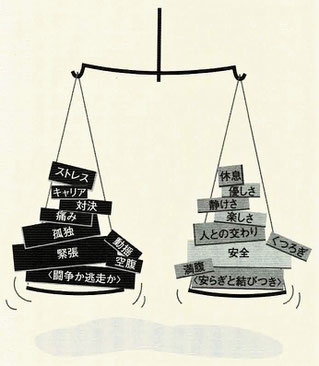
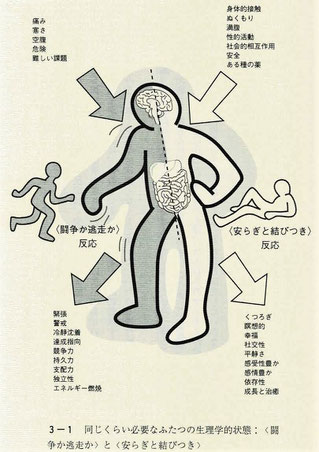
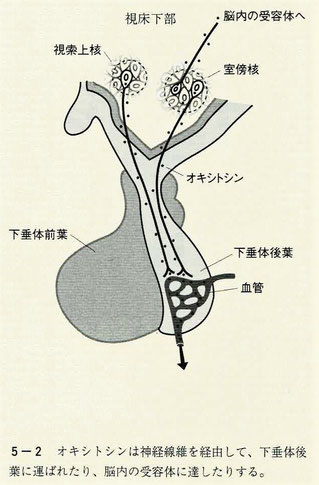
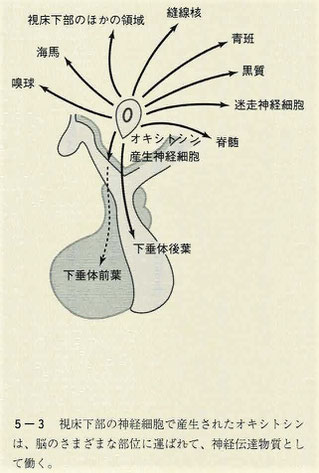
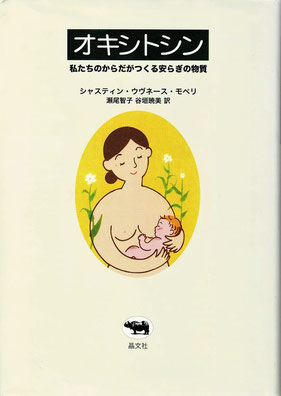
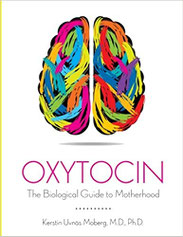



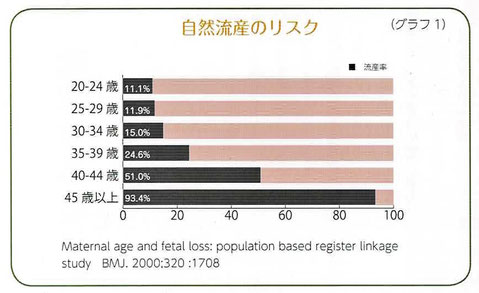
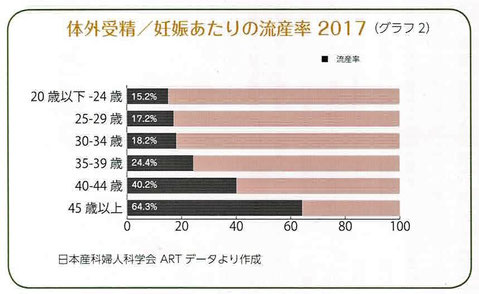
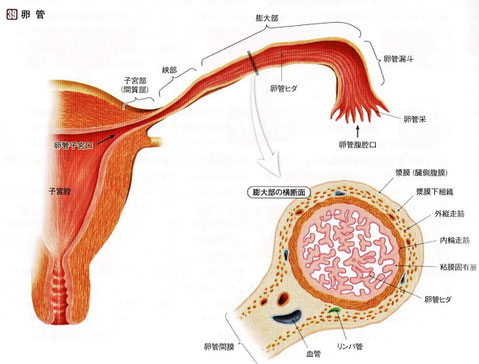

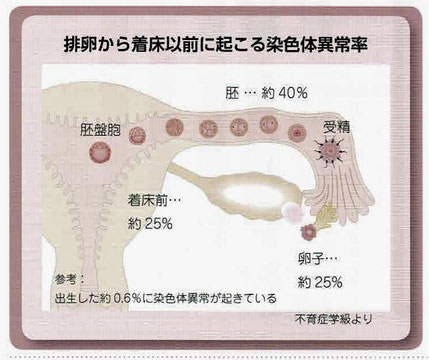
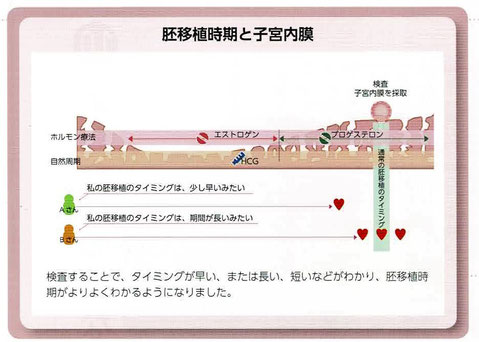
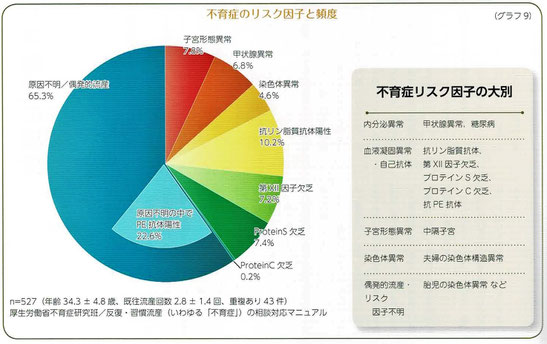

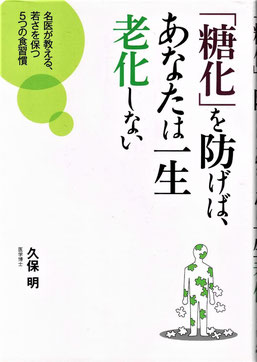
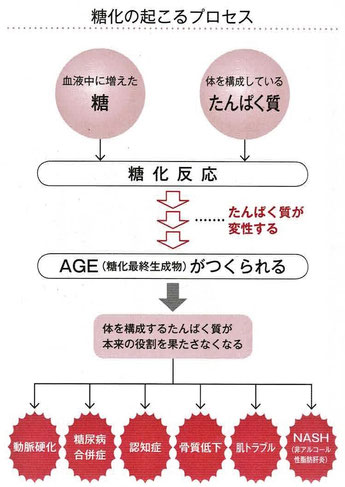




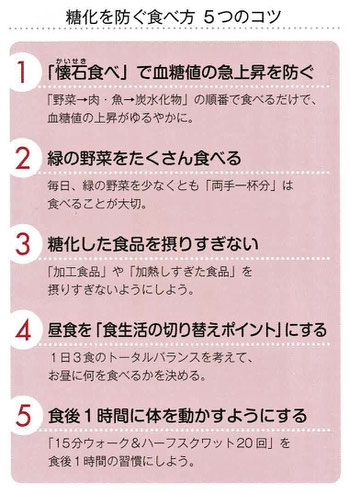

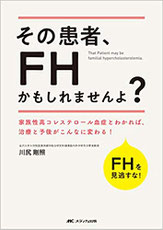
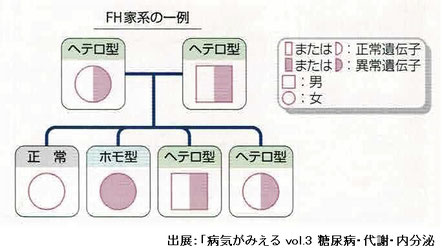
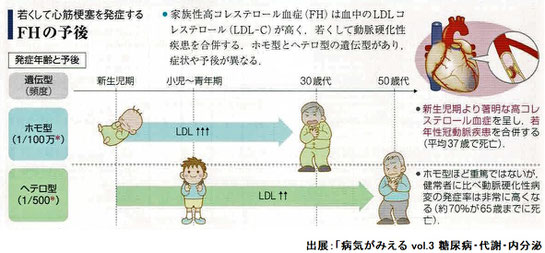


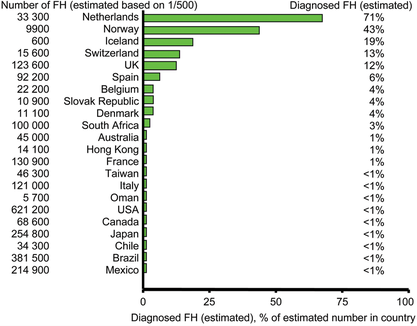

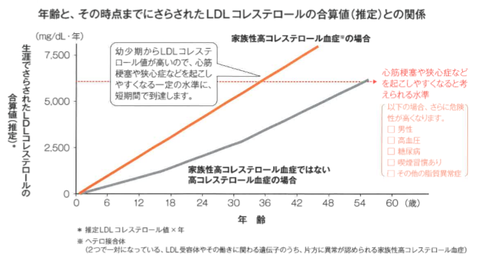
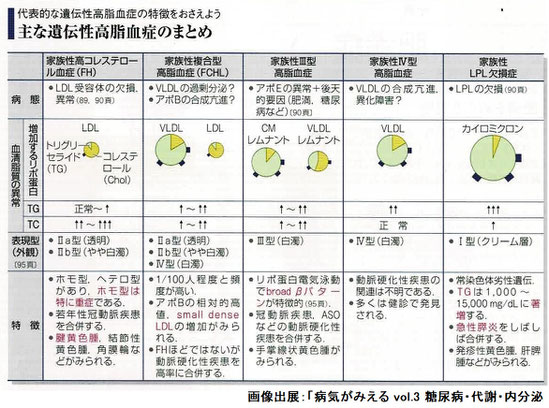
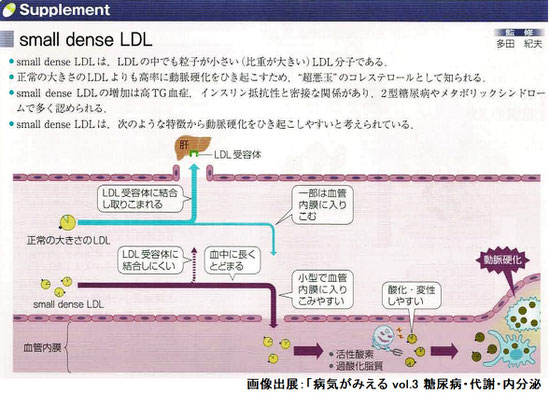
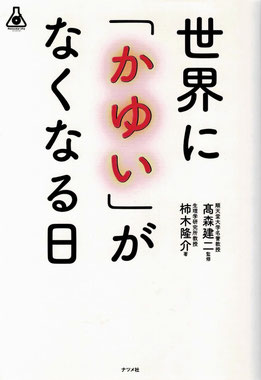
![中枢神経を構成する細胞(中央が小膠細胞[ミクログリア]です)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=530x1024:format=jpg/path/s5e68ecbdde7ed919/image/i957b3c26b4ca01f8/version/1667174340/image.jpg)

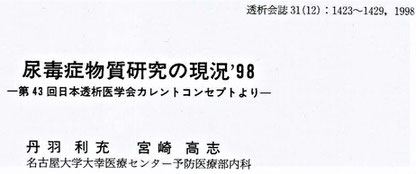
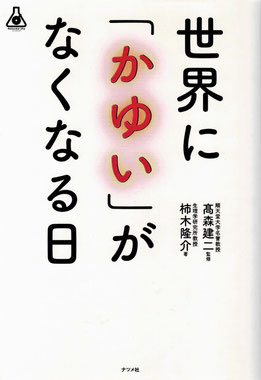

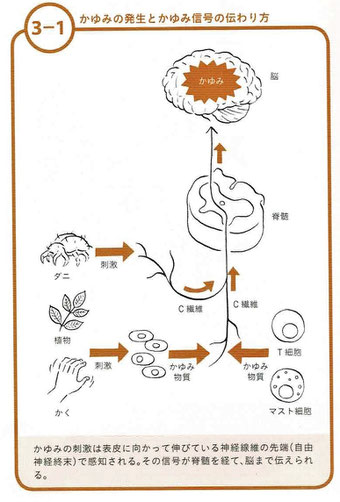

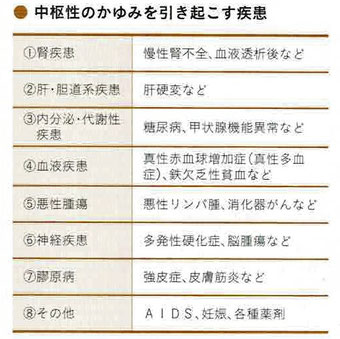
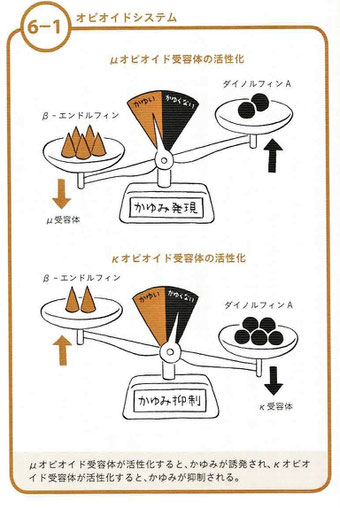

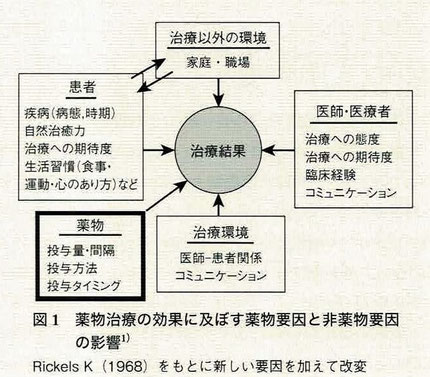


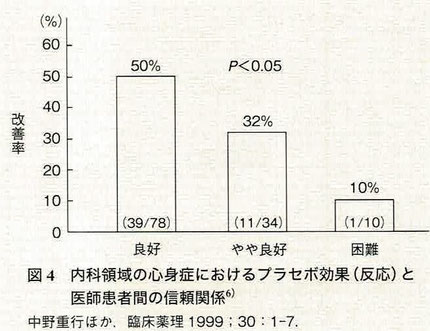
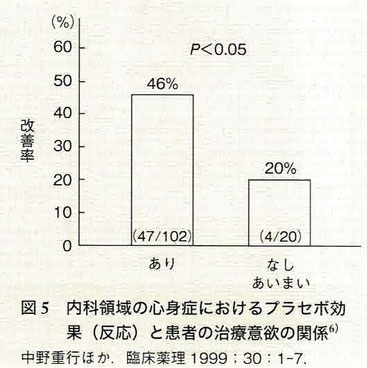
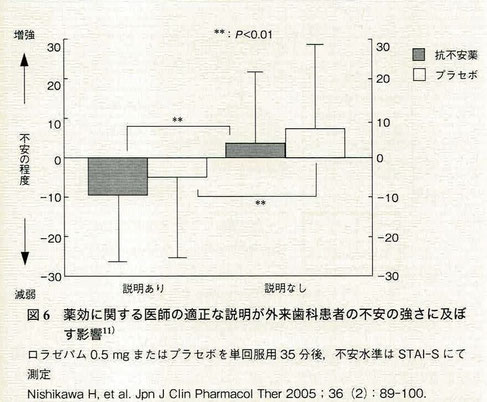
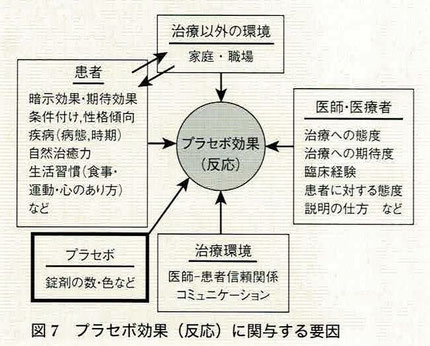
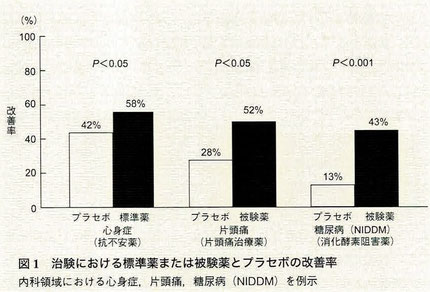
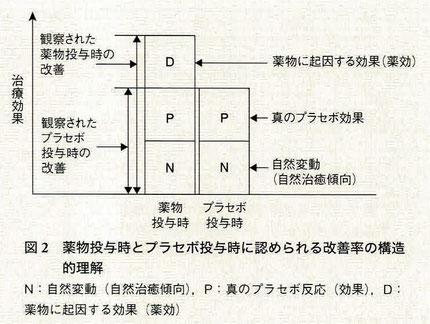
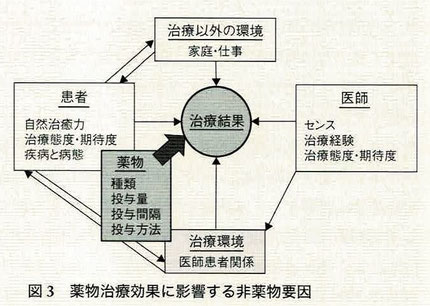


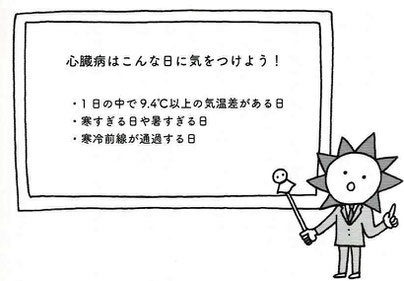




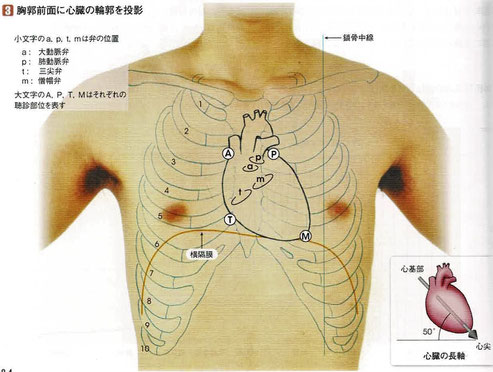
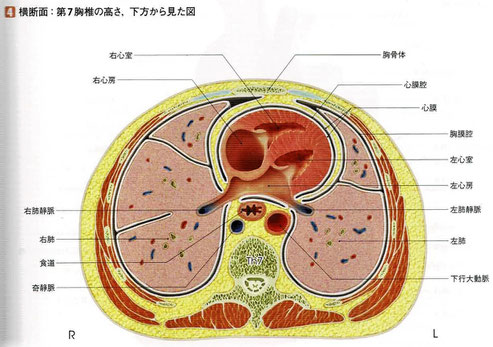
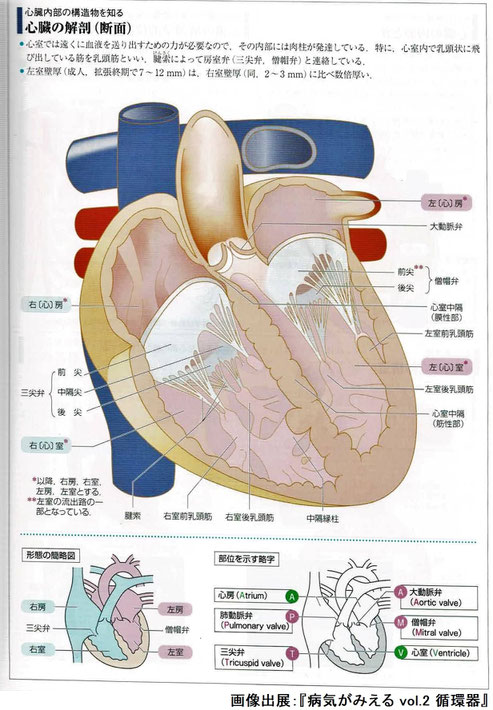
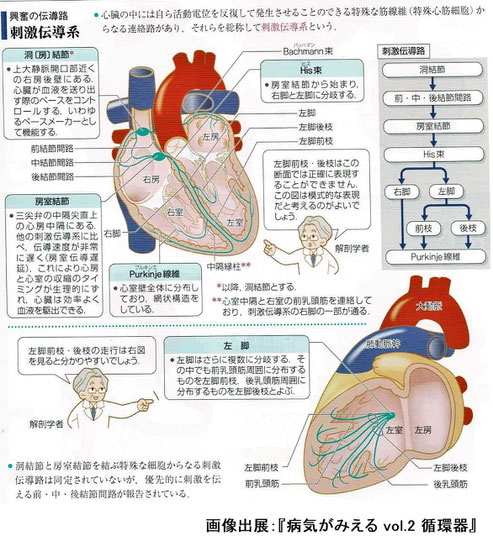
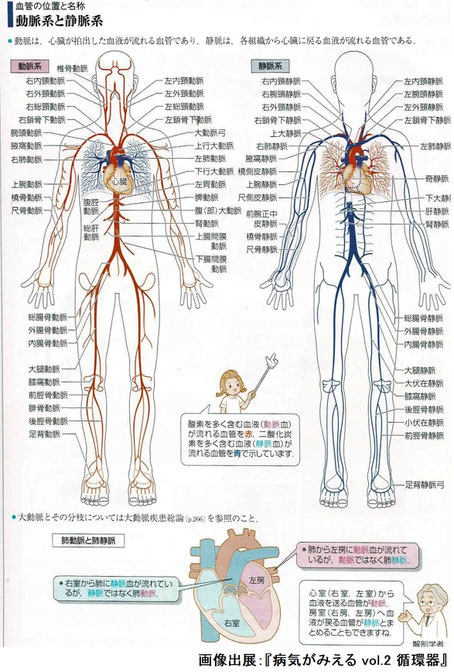
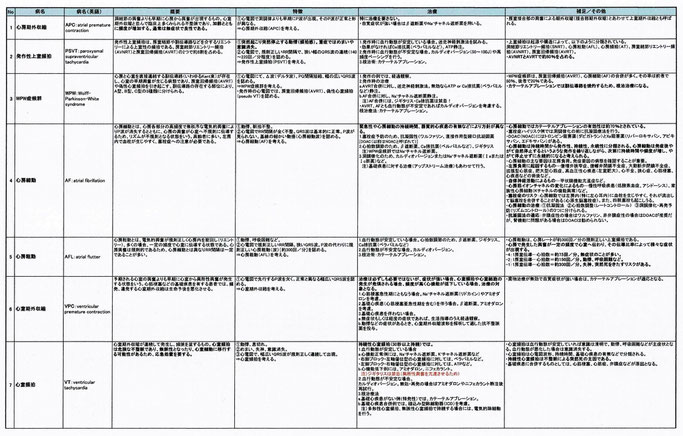
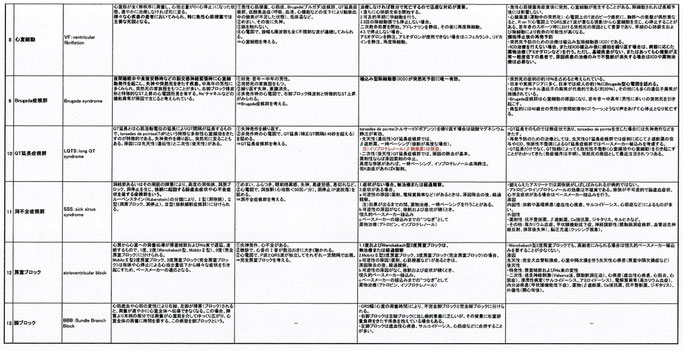
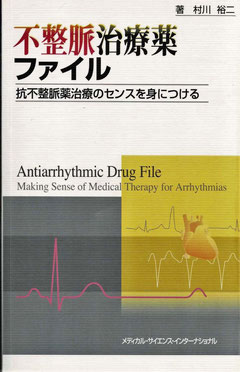

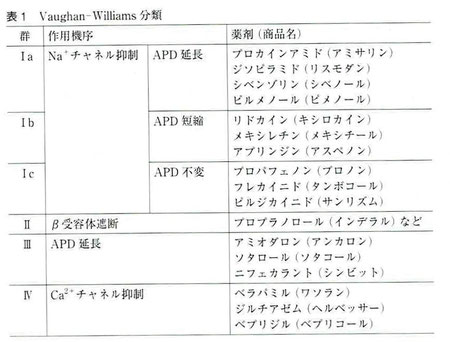

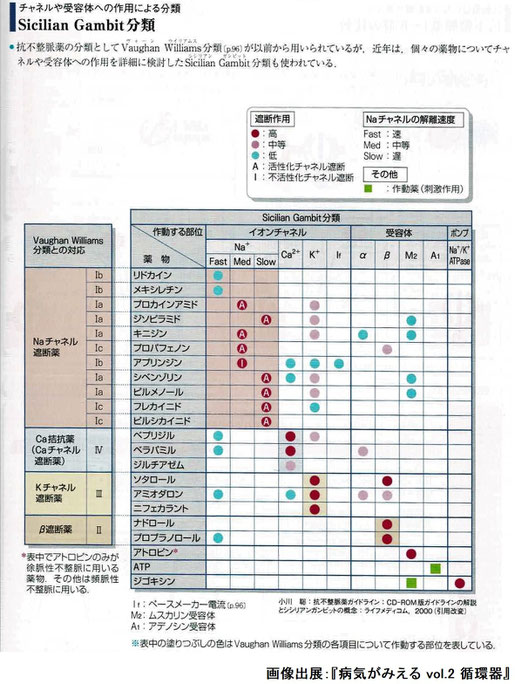
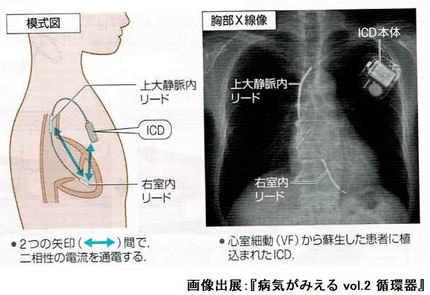
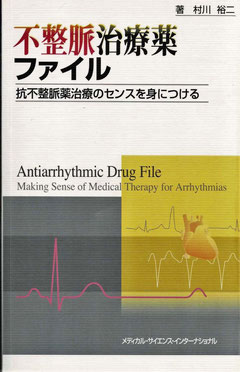
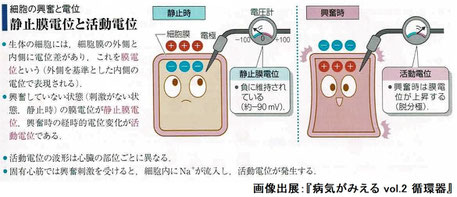
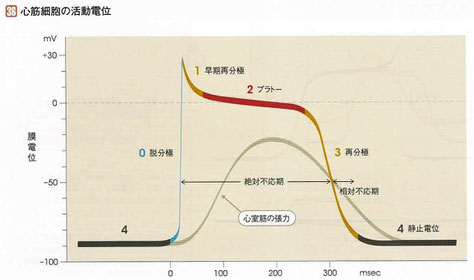
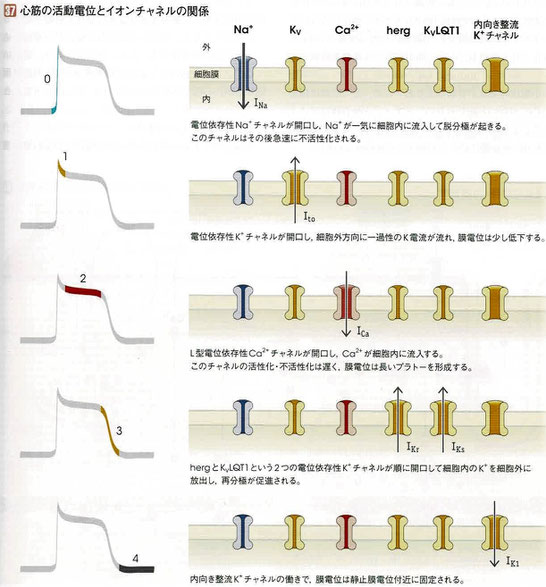
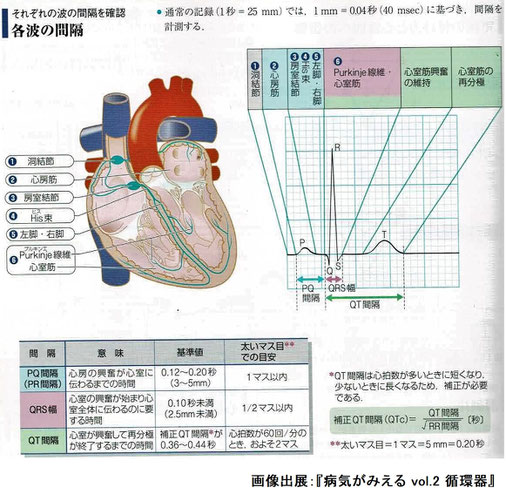
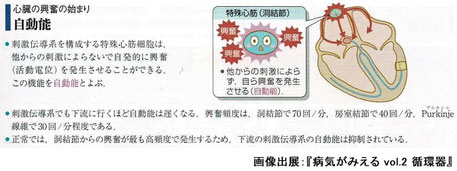
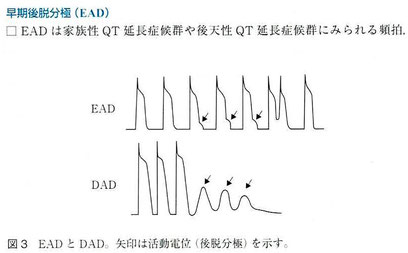




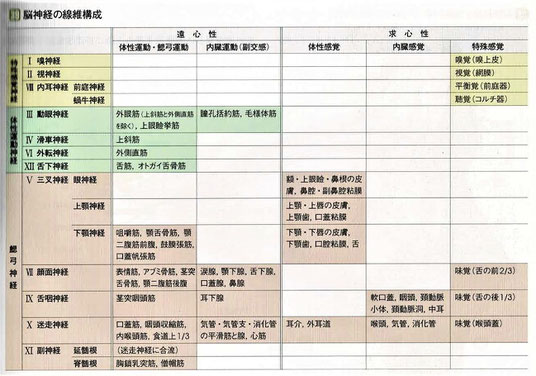






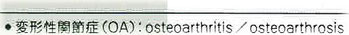
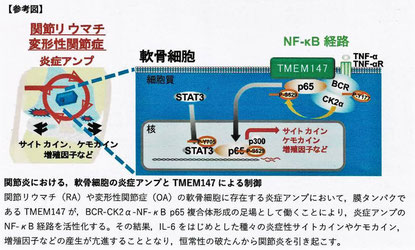
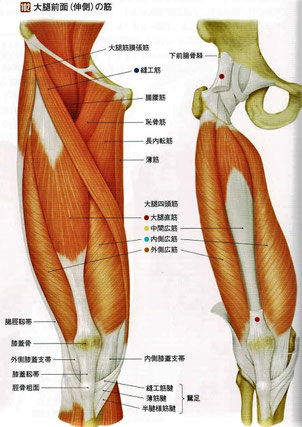

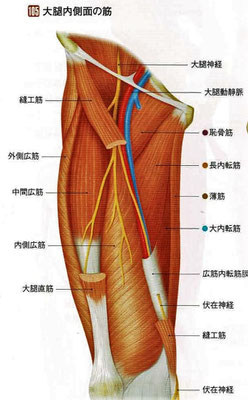
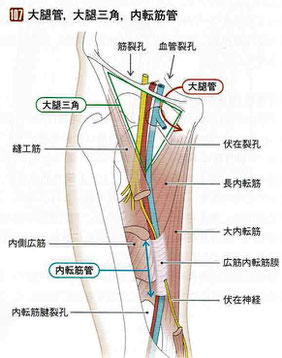
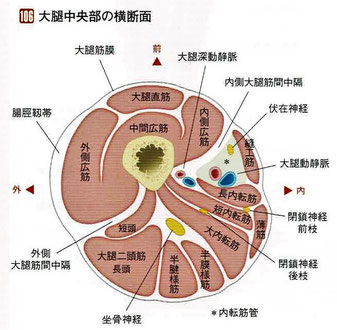
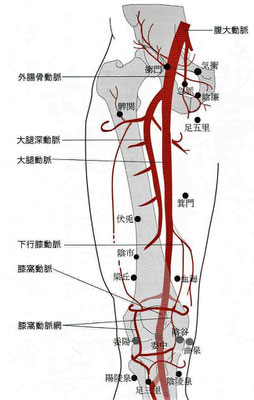
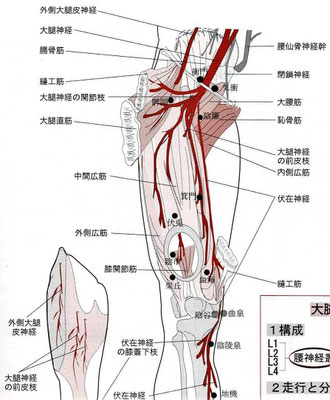

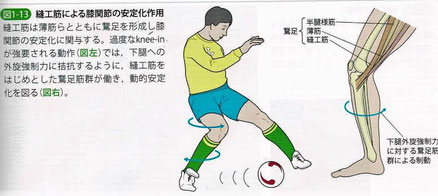




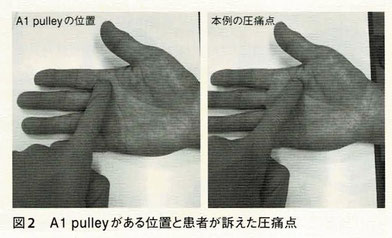
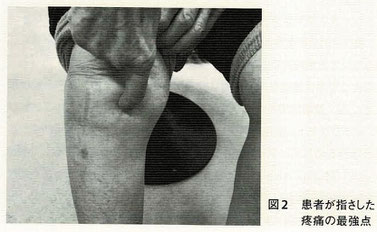

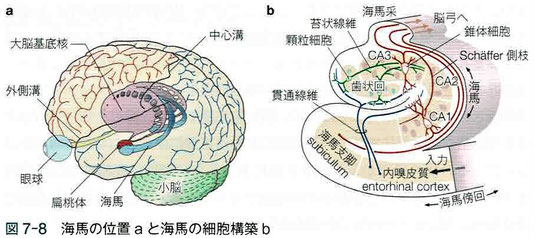
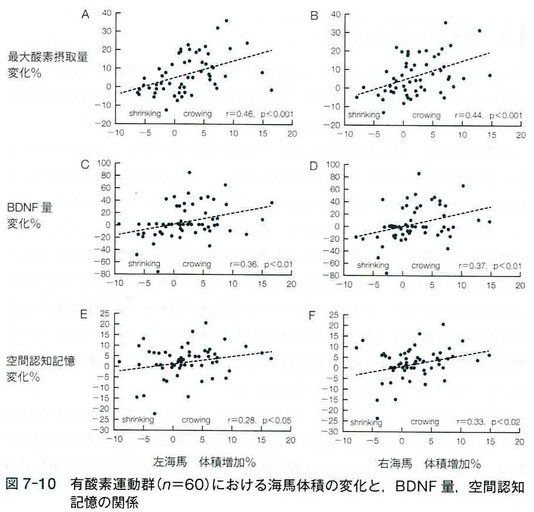


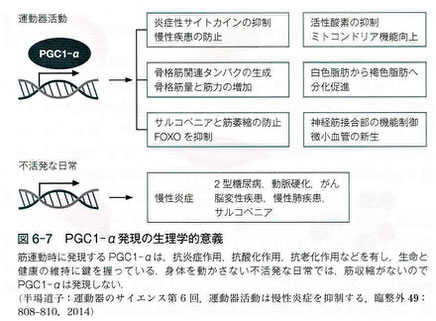
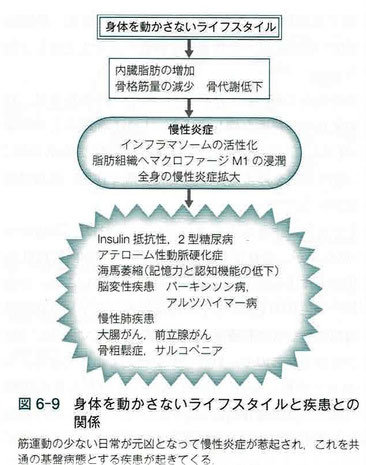

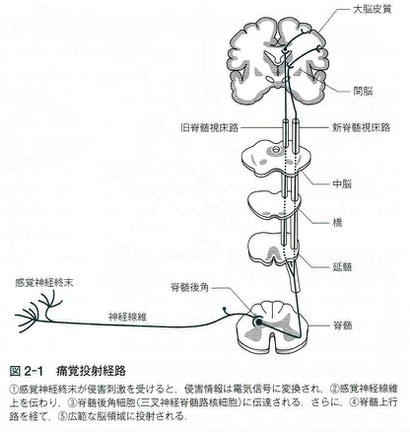
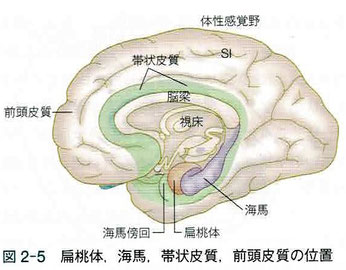
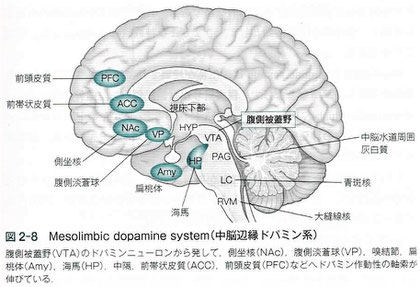



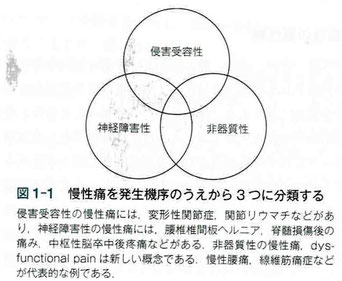
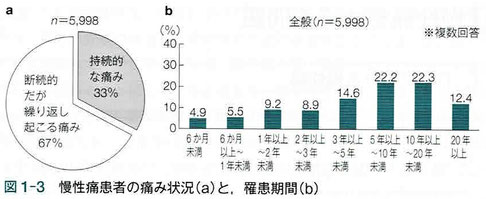

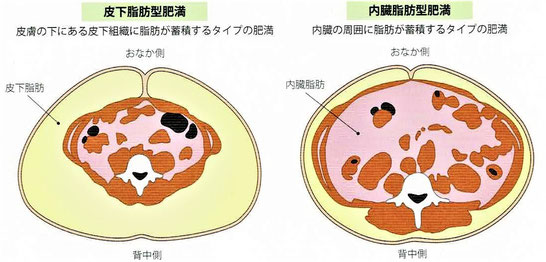

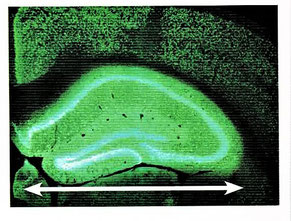


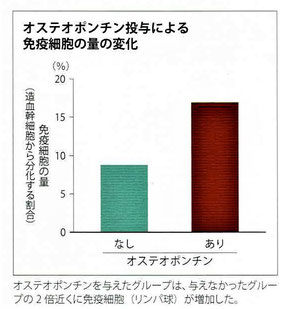
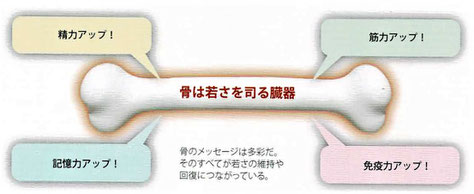
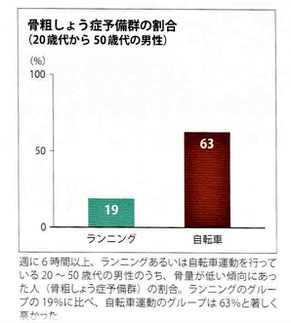
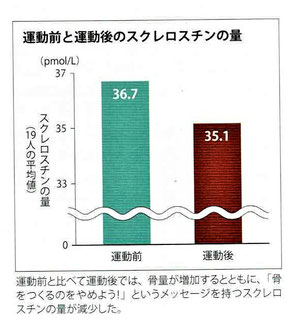
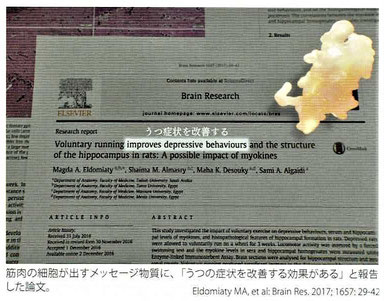




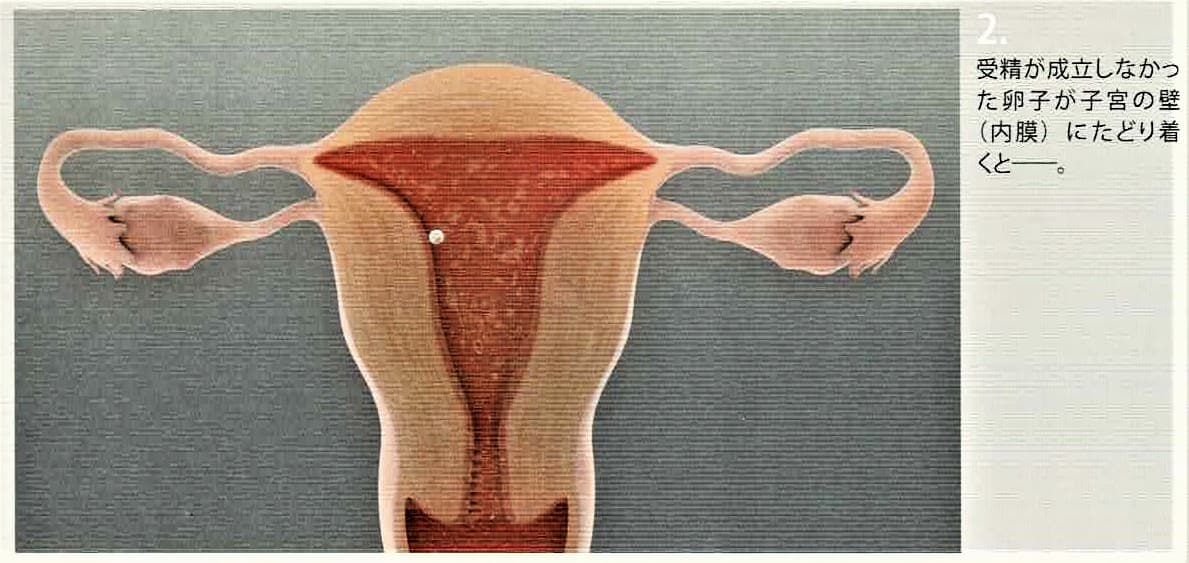

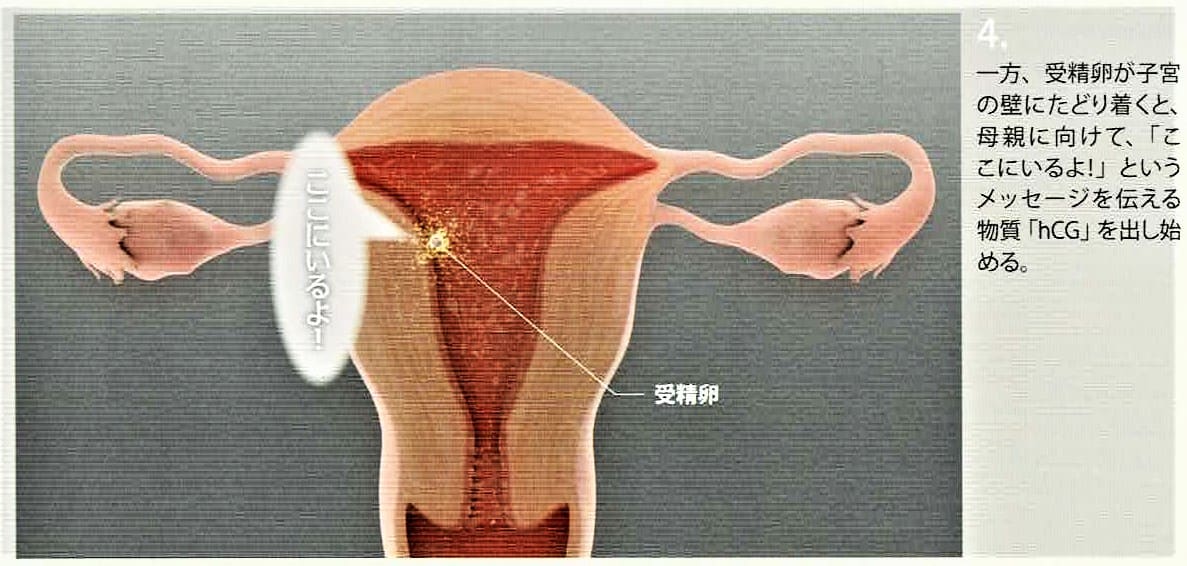

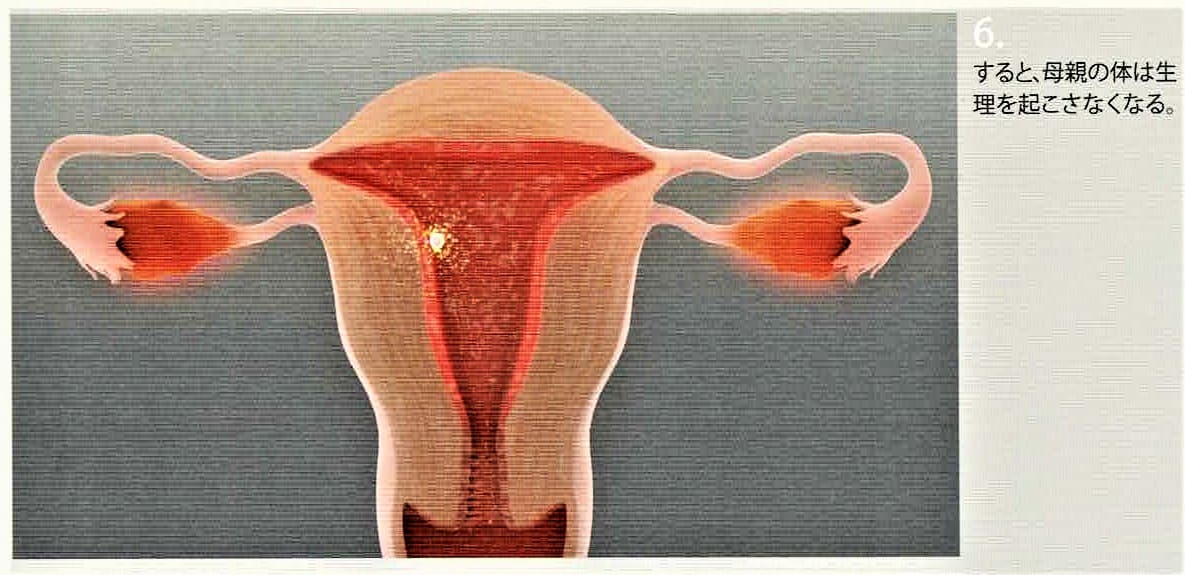

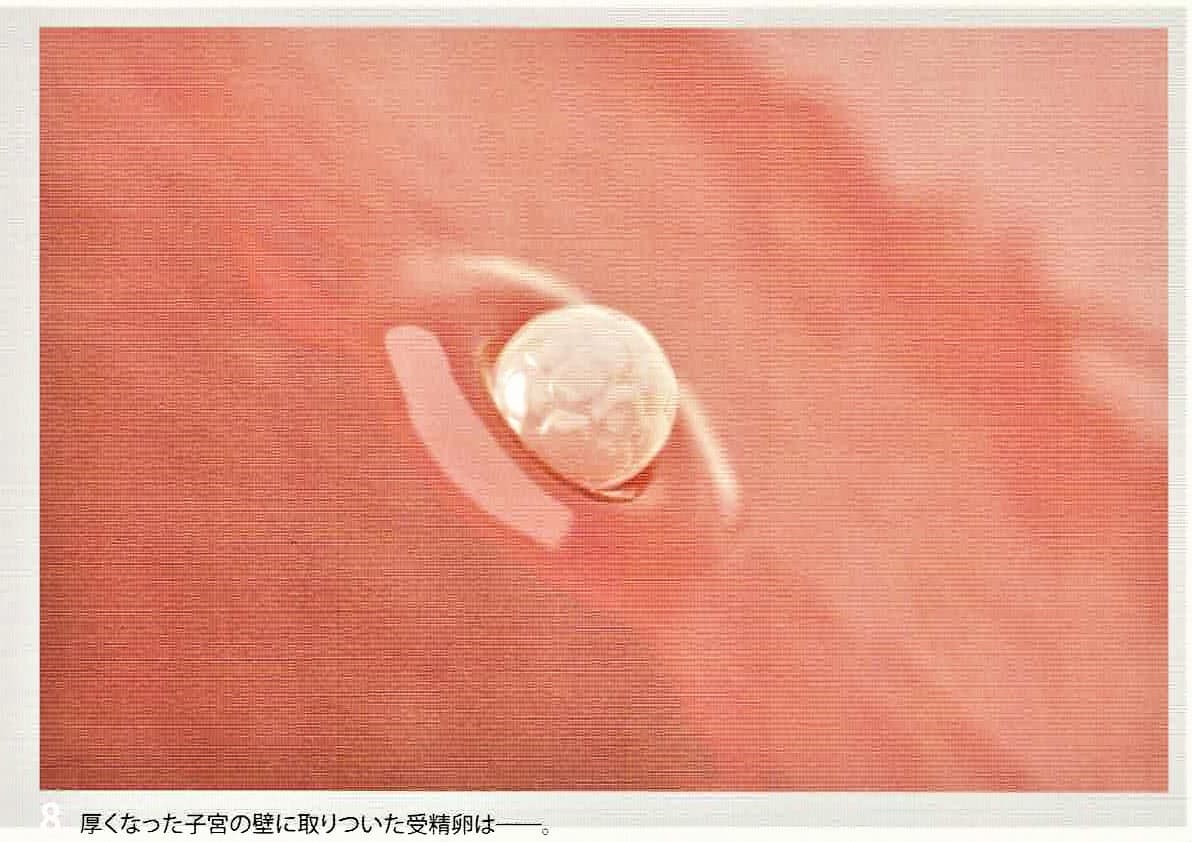

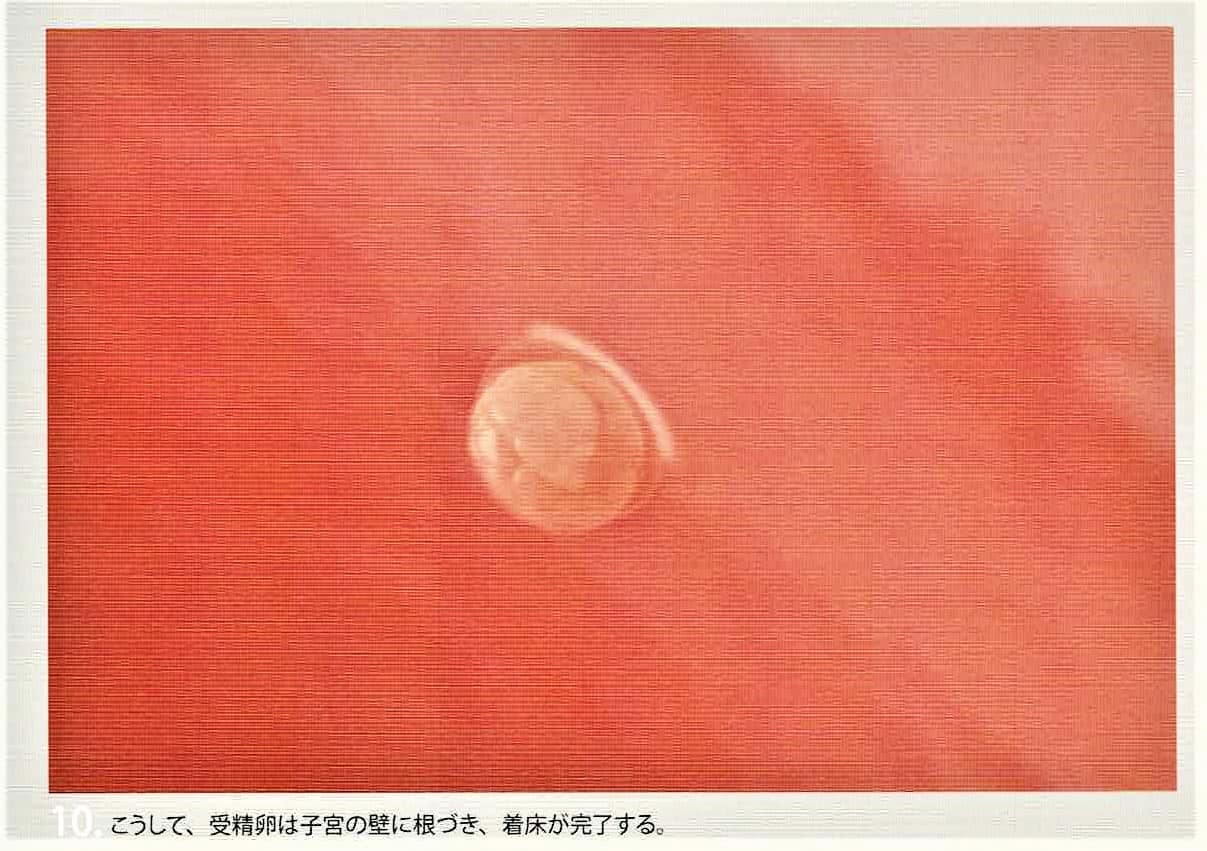










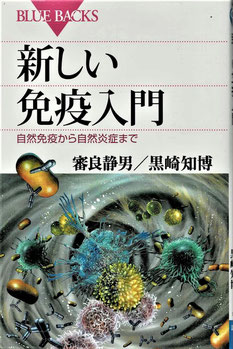

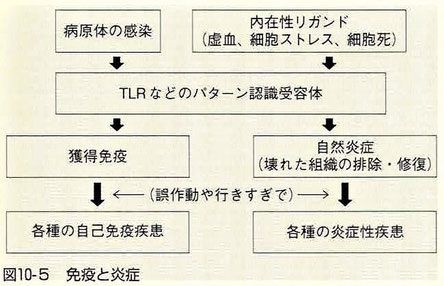

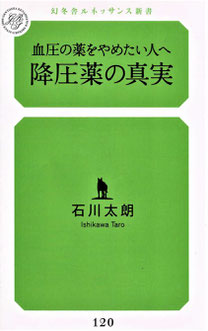
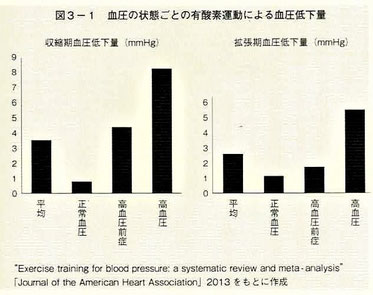
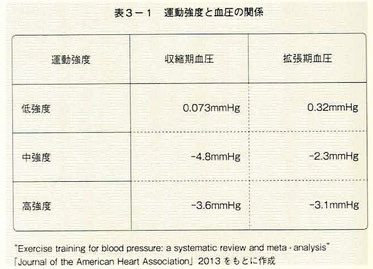
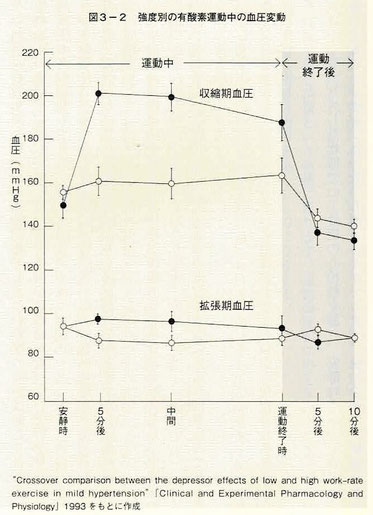



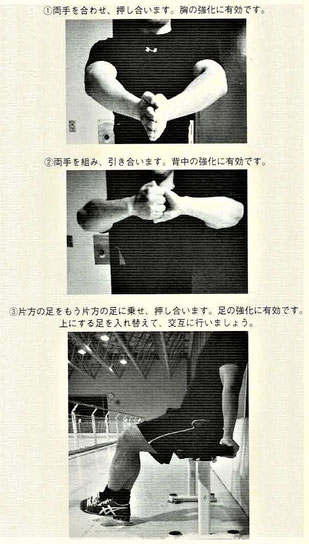
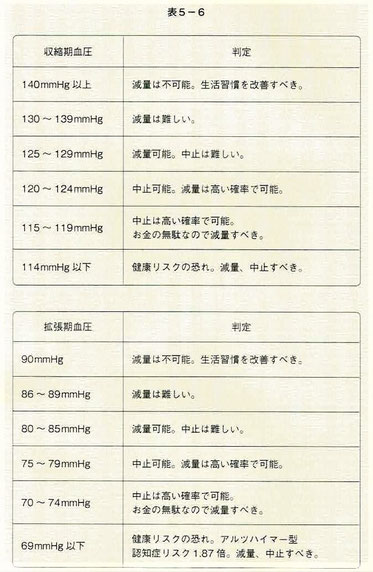


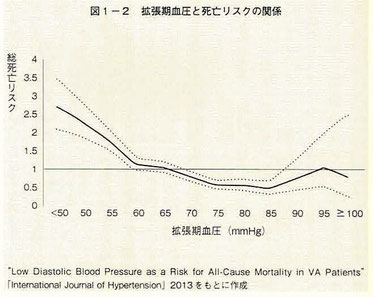

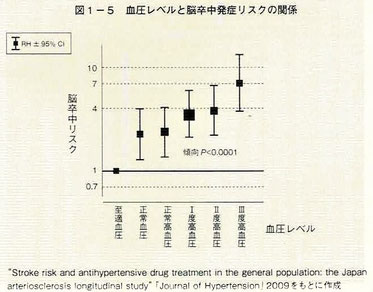
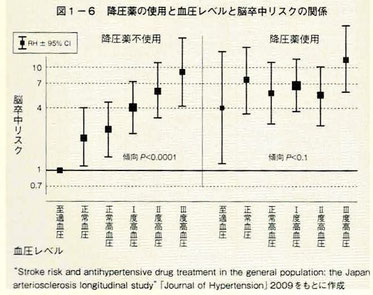





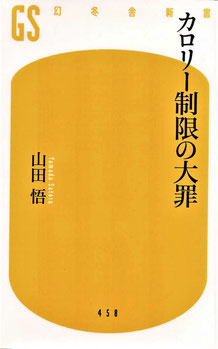


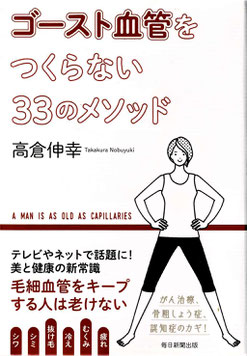
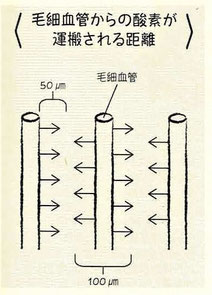







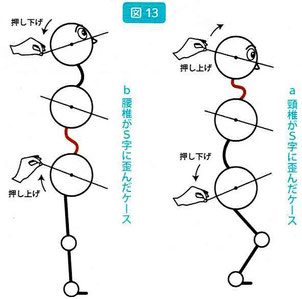
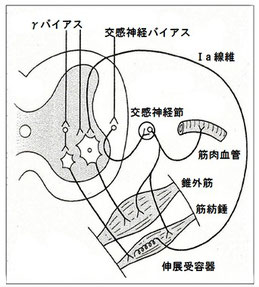

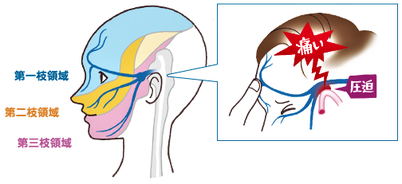

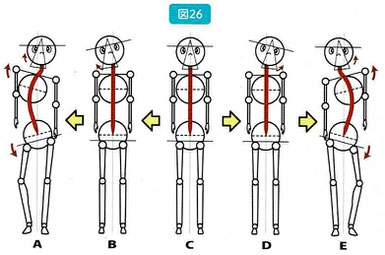





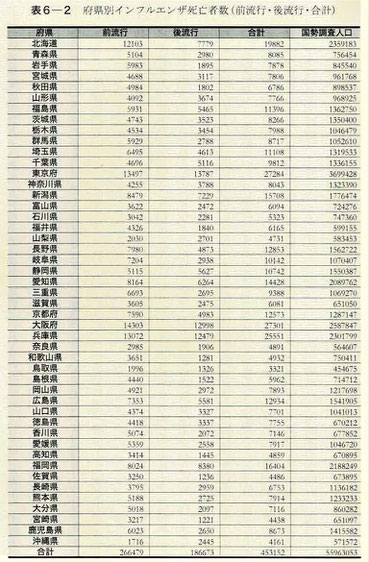
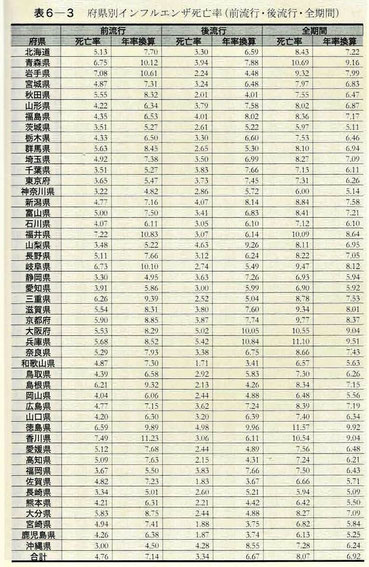

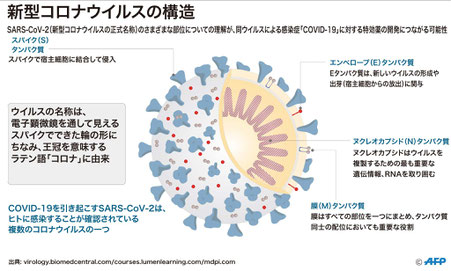
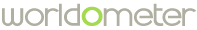
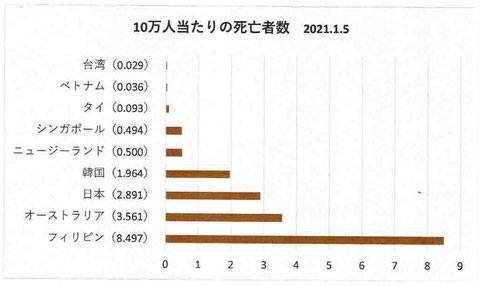


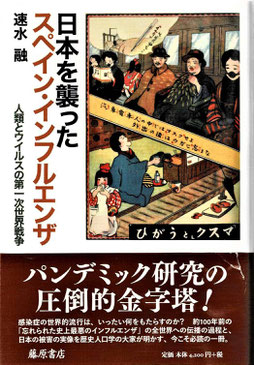

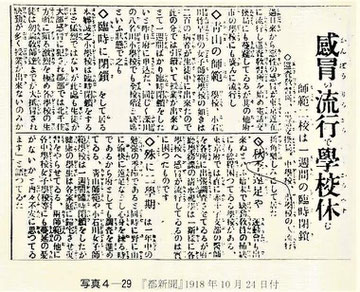
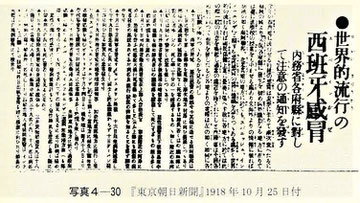
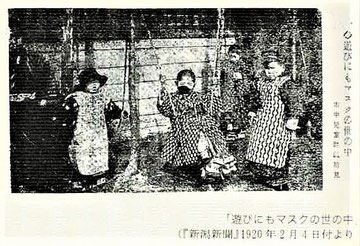


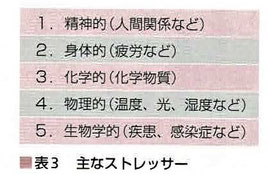
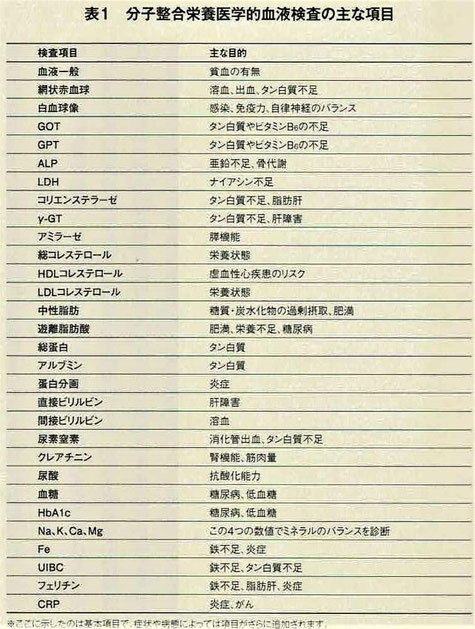



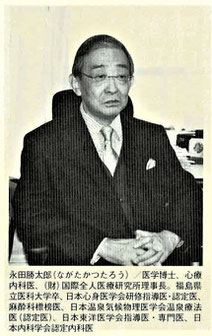
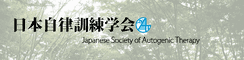

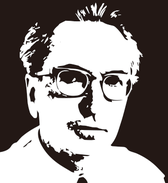



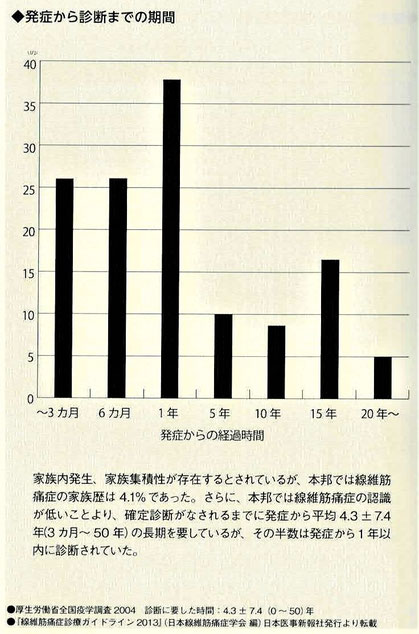
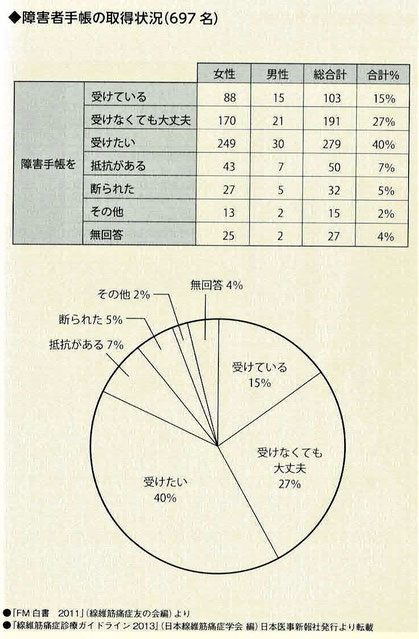
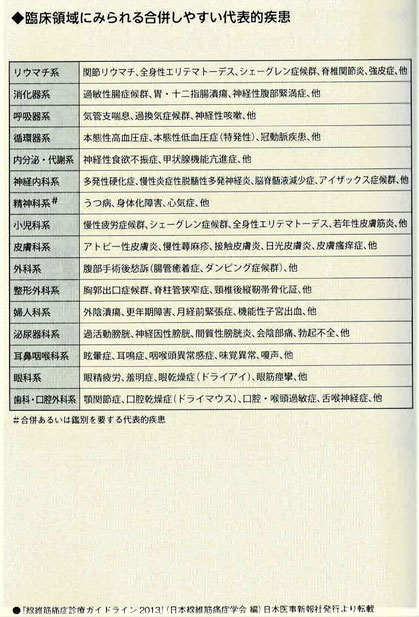



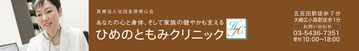

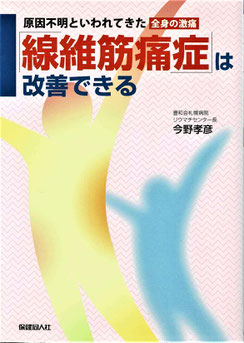

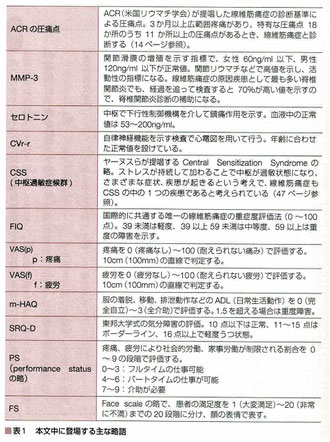
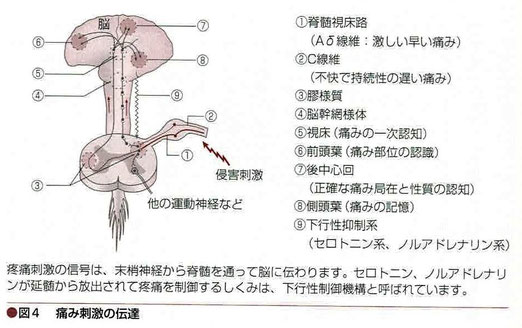
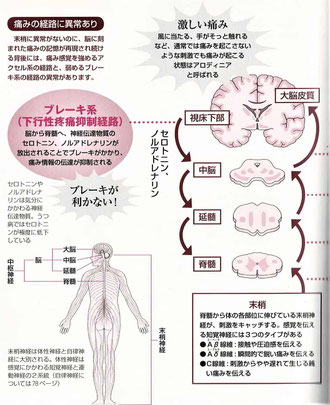


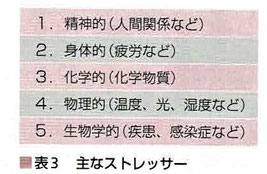
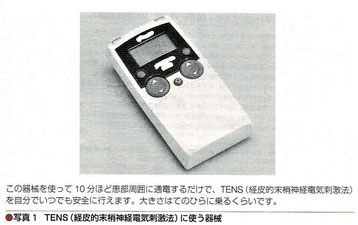
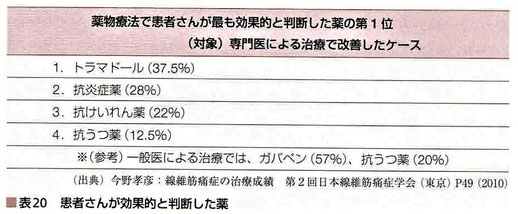
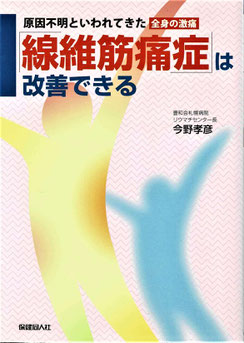
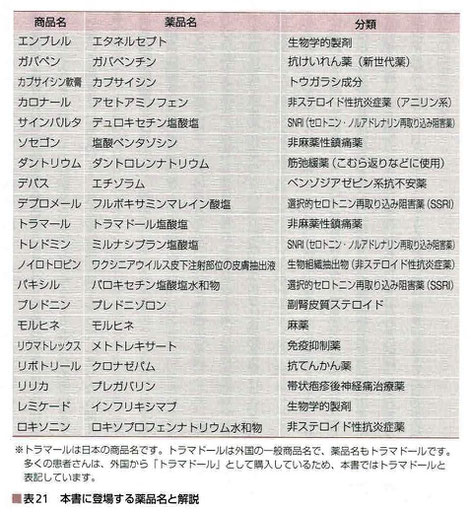
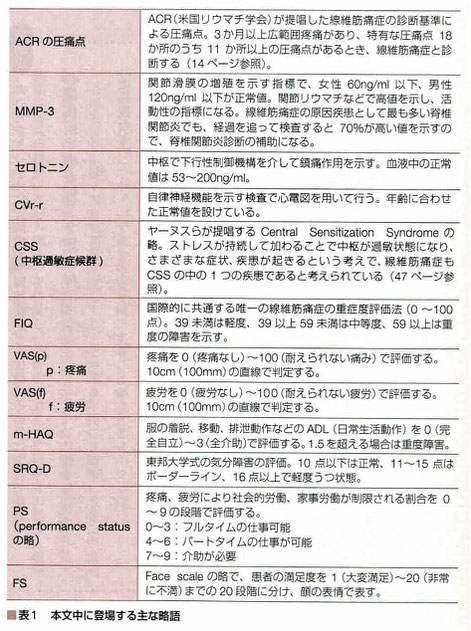
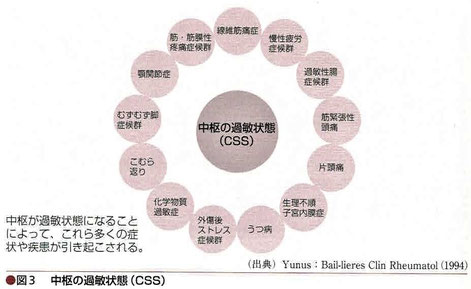
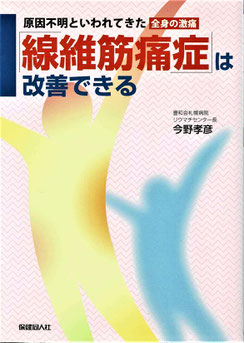
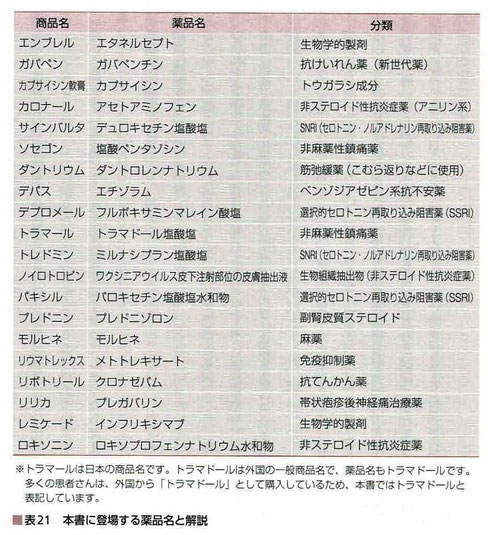
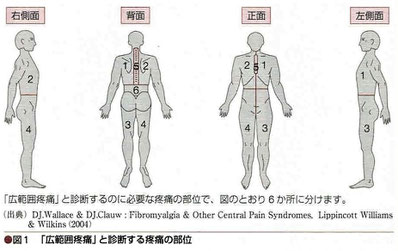

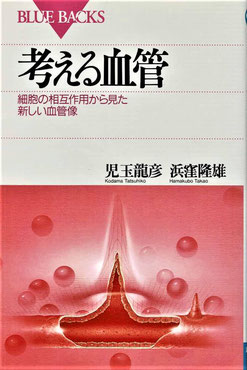
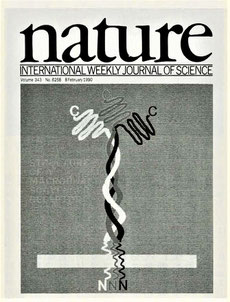

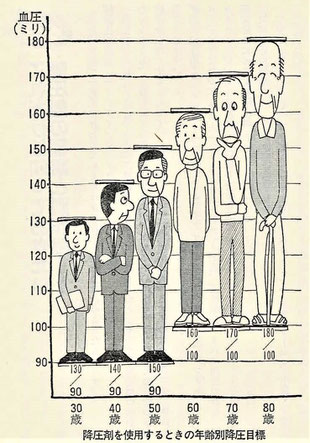

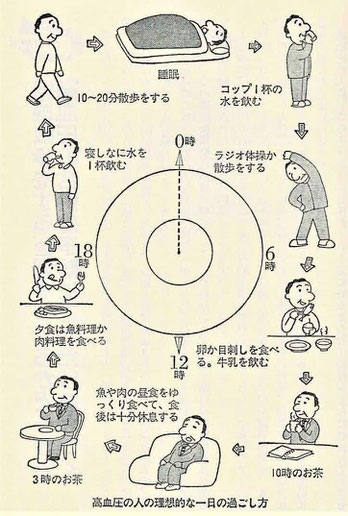
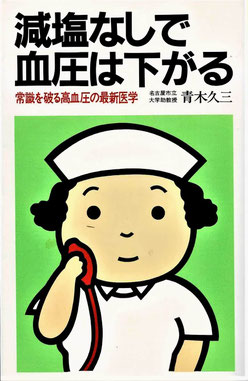

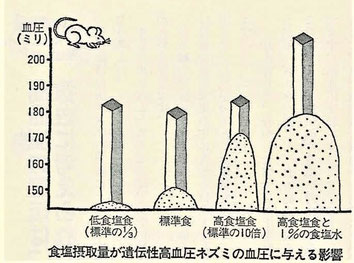
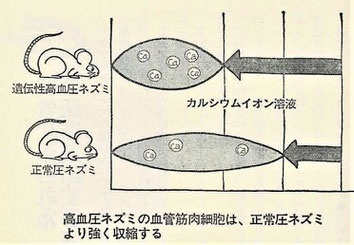
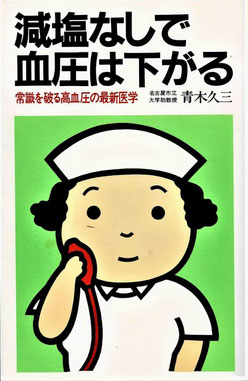
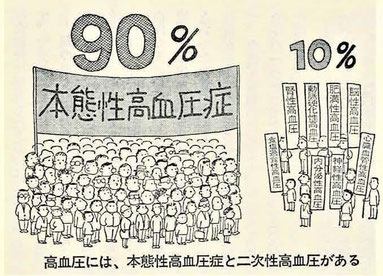
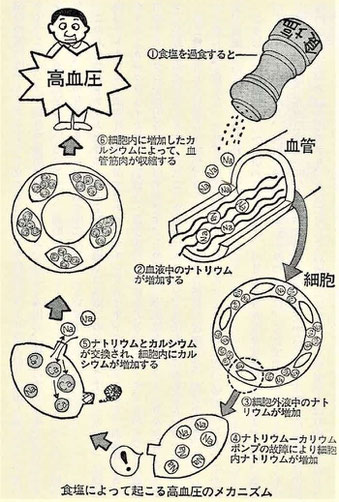

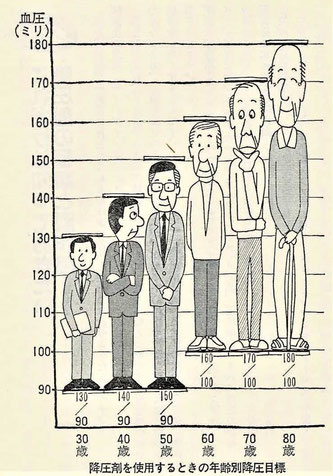
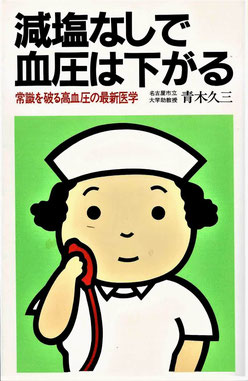

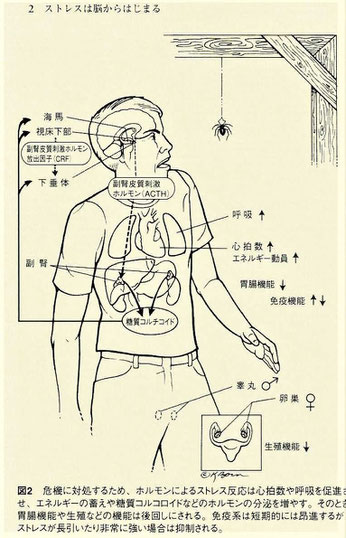
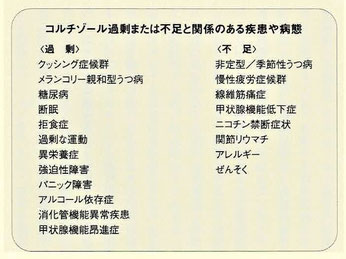
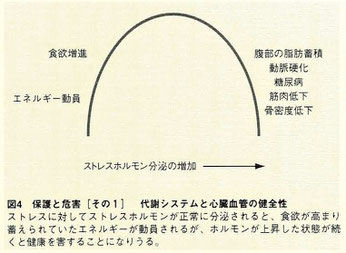


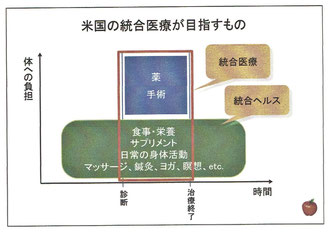

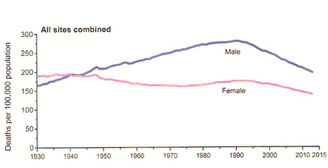





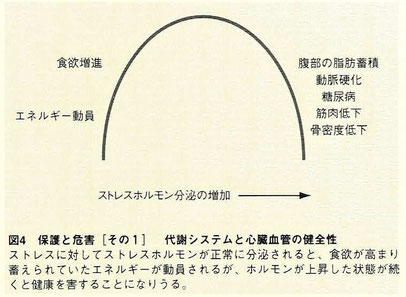

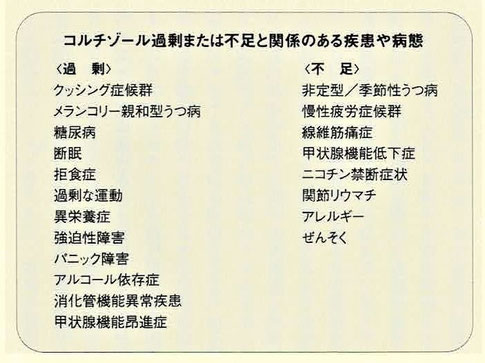


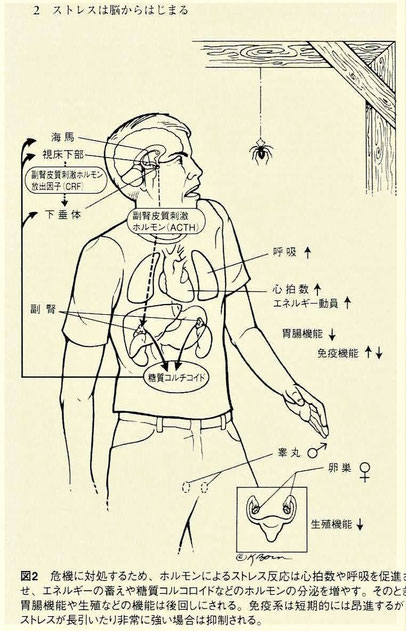
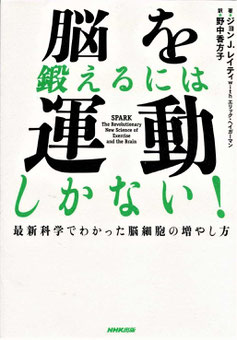
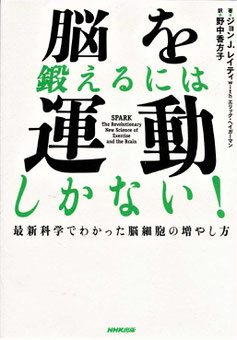


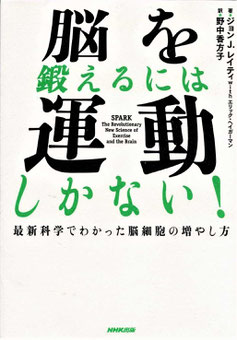
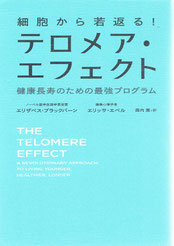
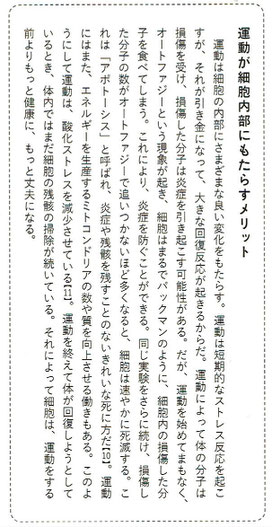





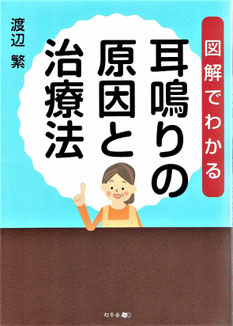



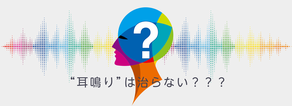
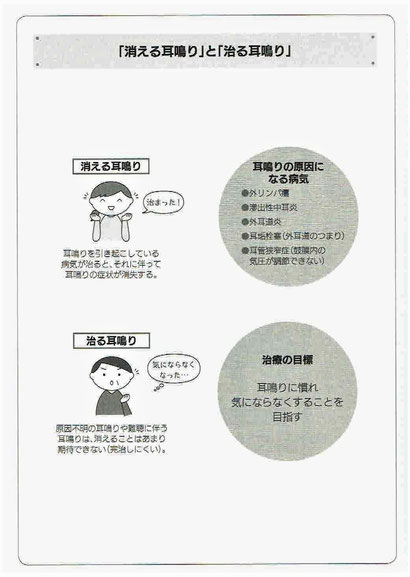
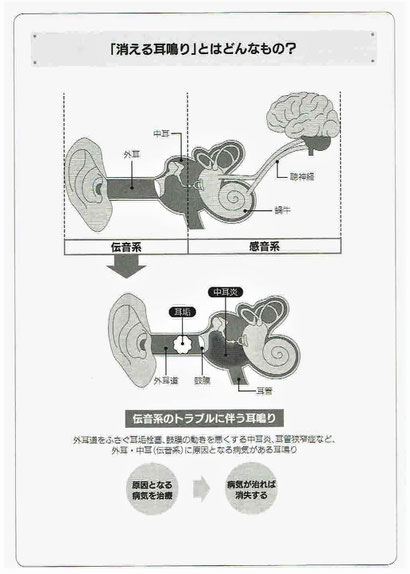
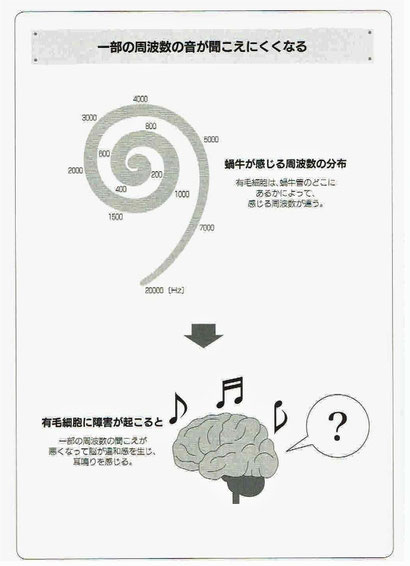





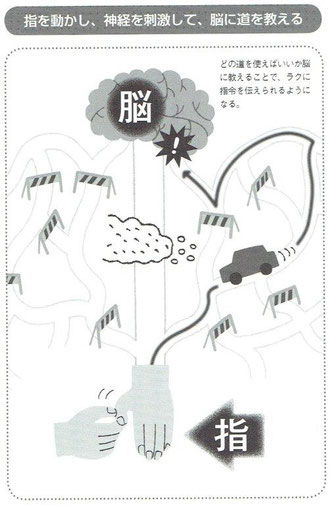


















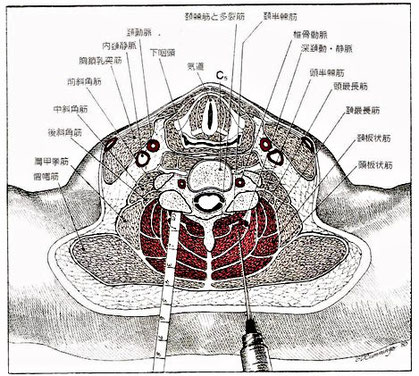












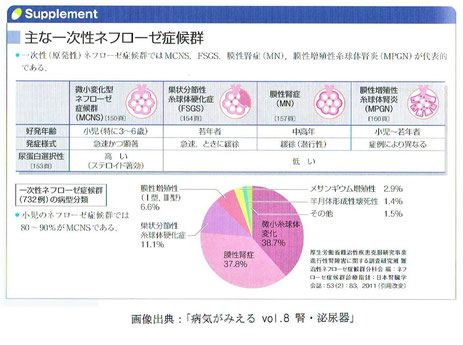




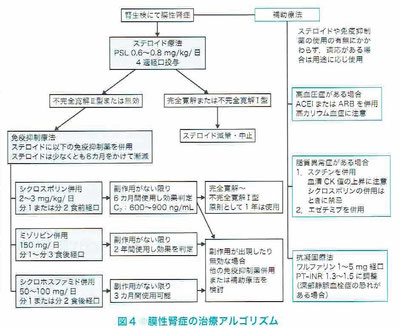




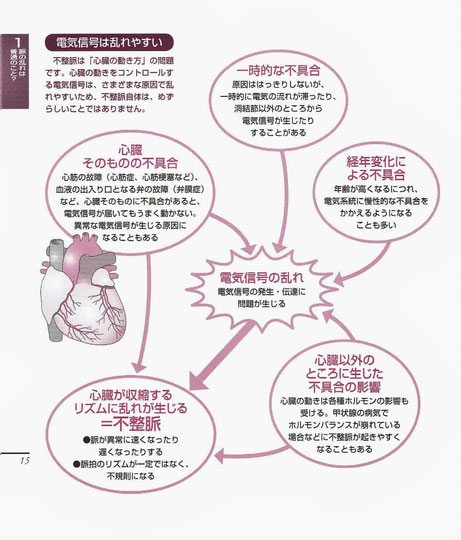




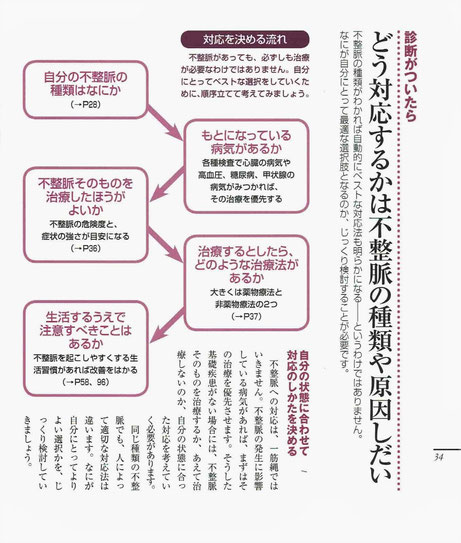



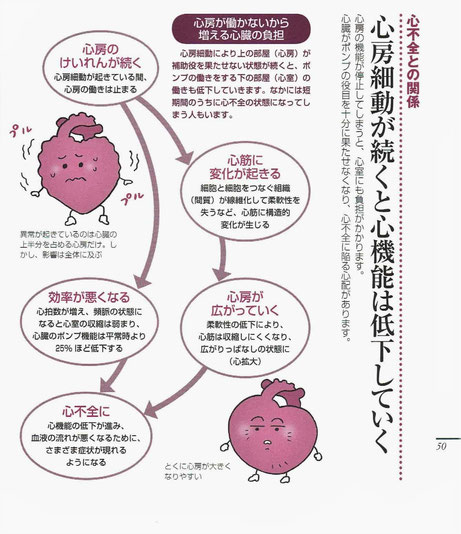

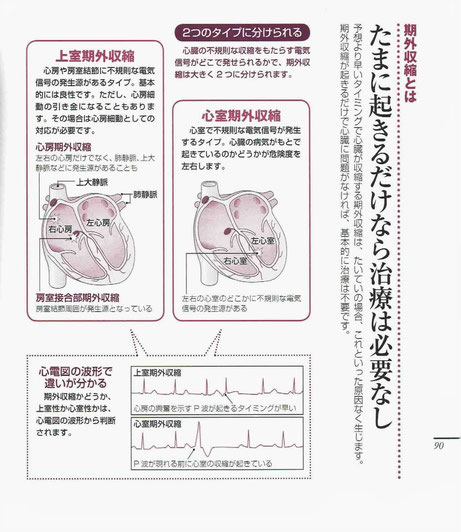

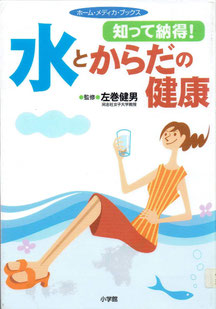















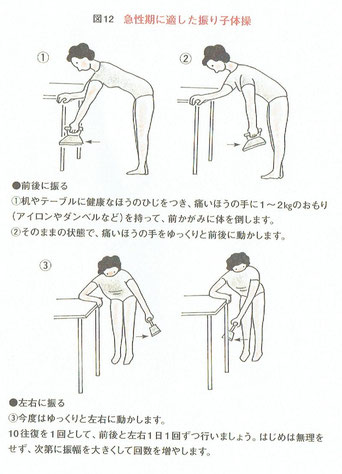




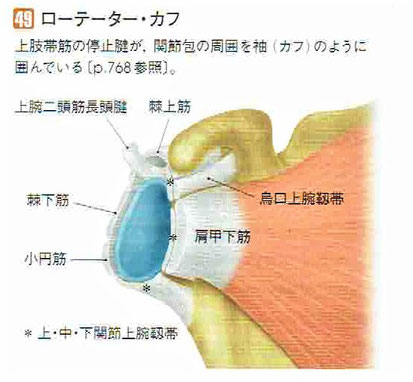


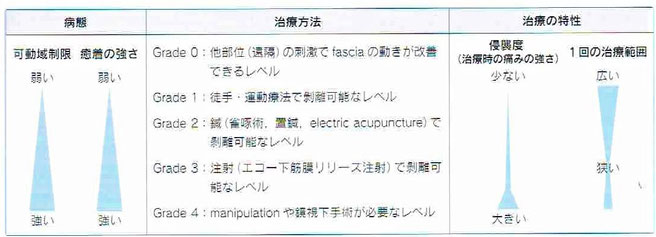
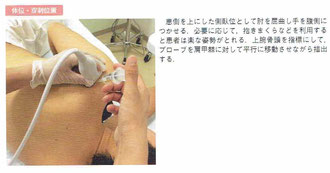
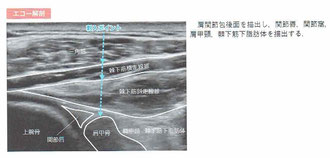








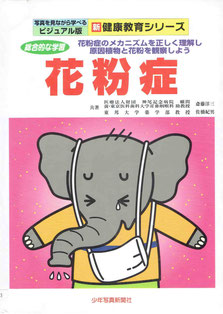






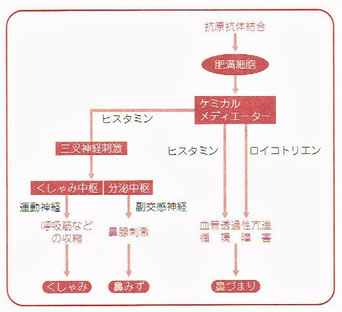

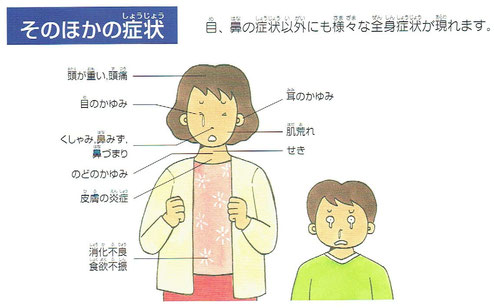
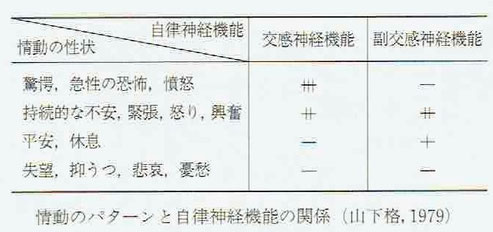


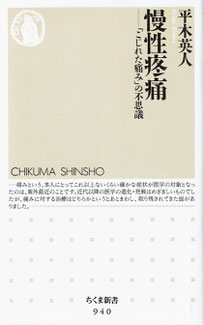







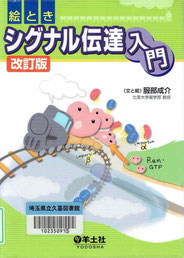







![血管径によるNOとEDHF/H2O2(過酸化水素[活性酸素の一種])の役割分担](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=509x1024:format=jpg/path/s5e68ecbdde7ed919/image/ib835a832d37642fa/version/1618217116/image.jpg)