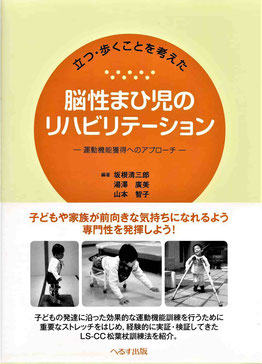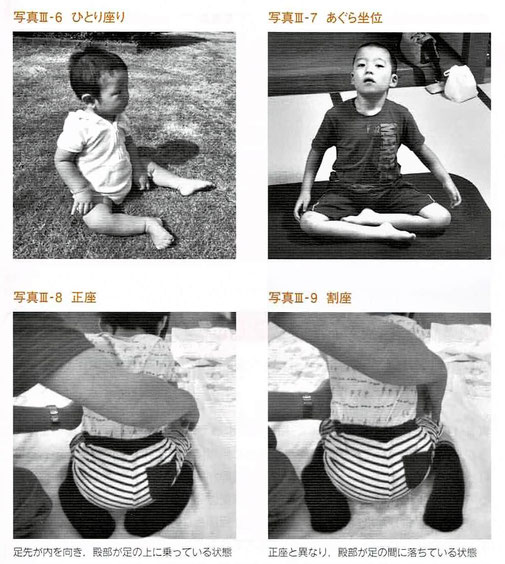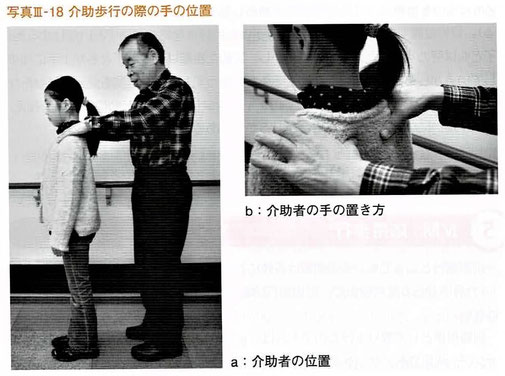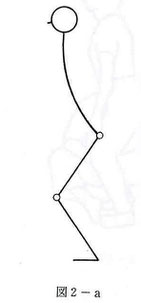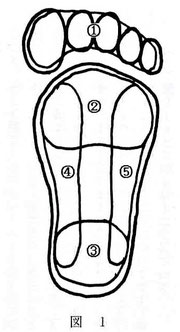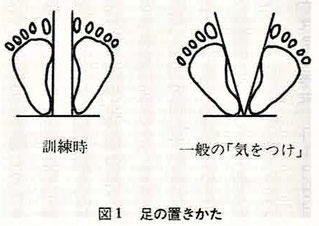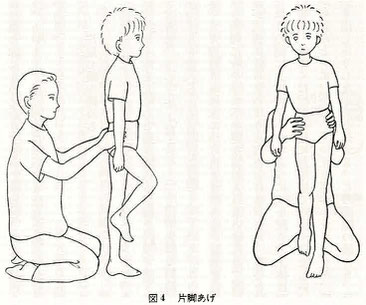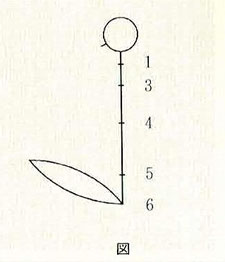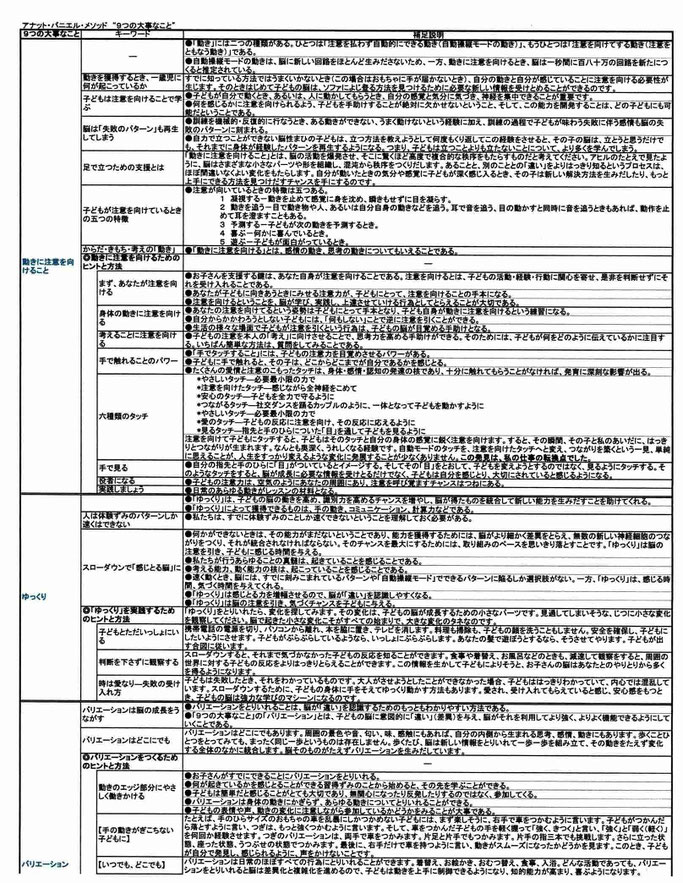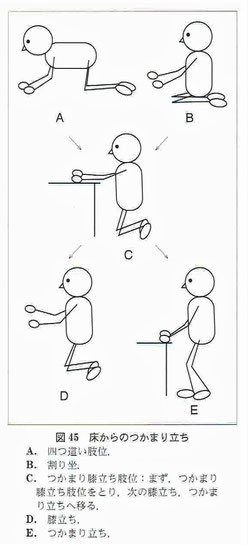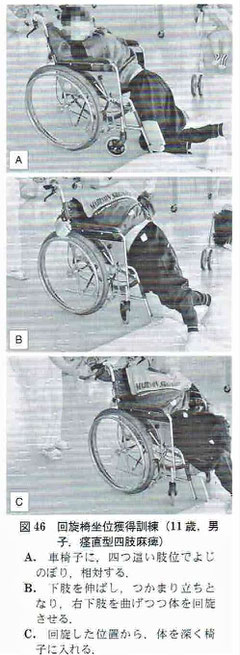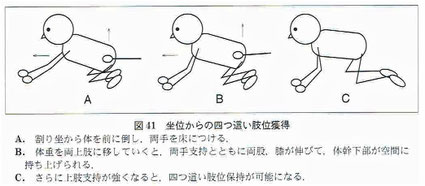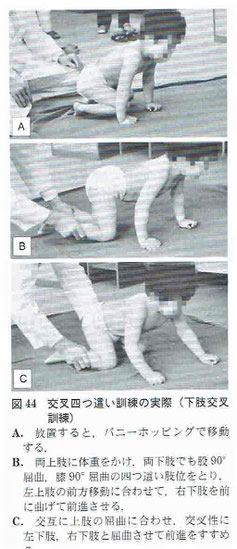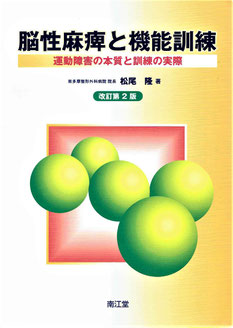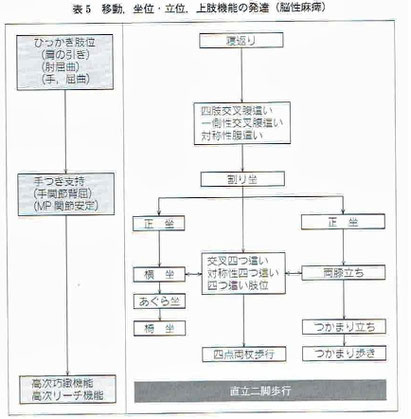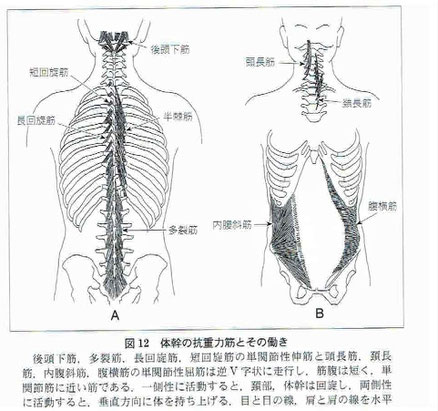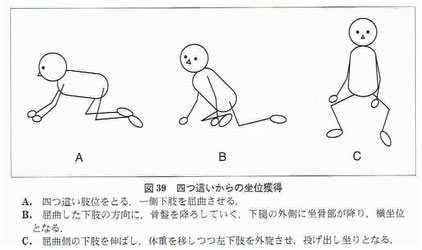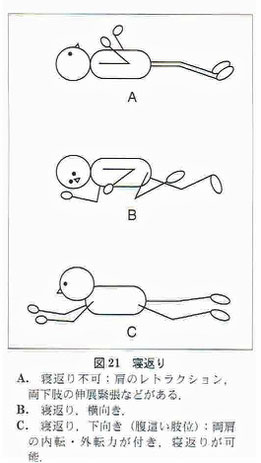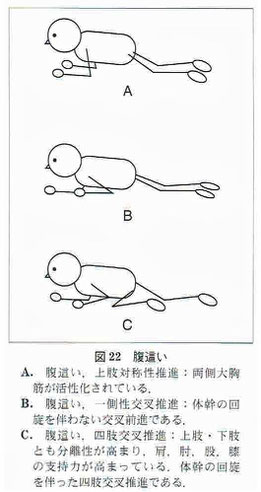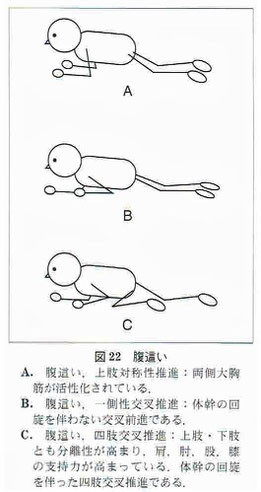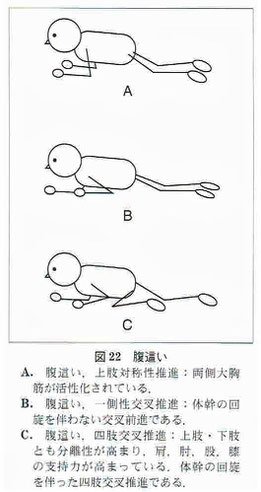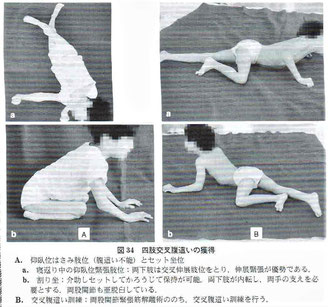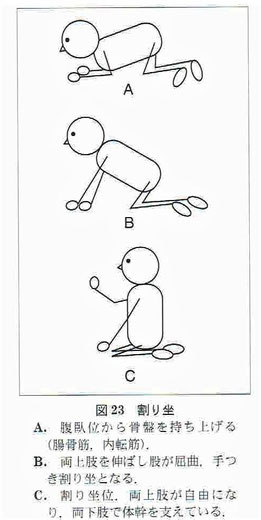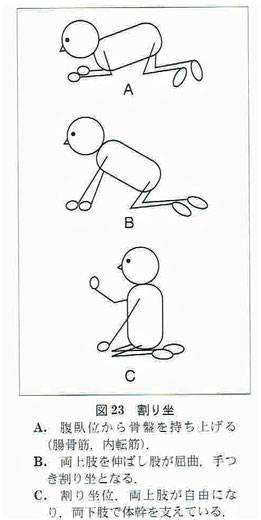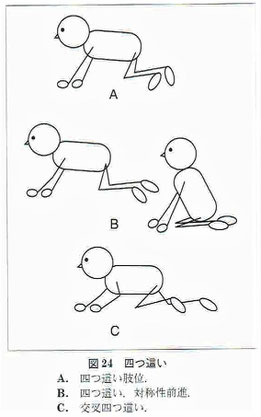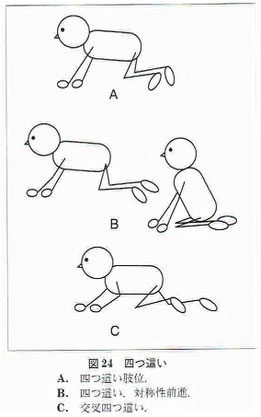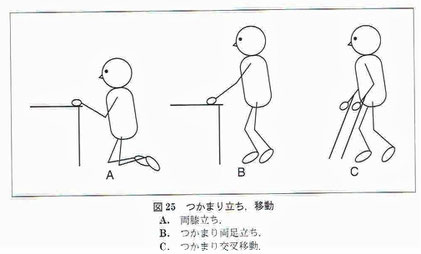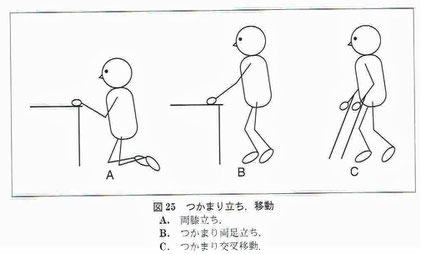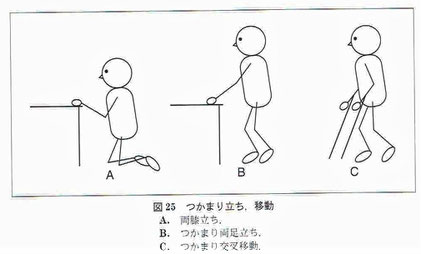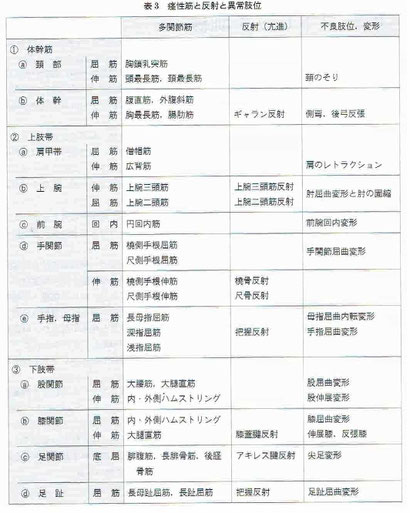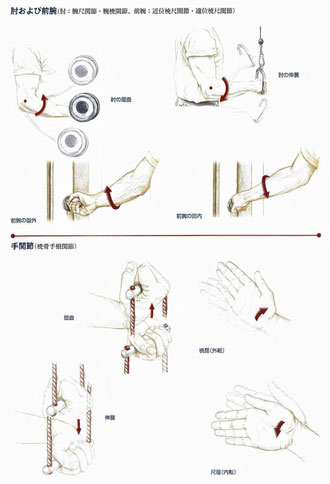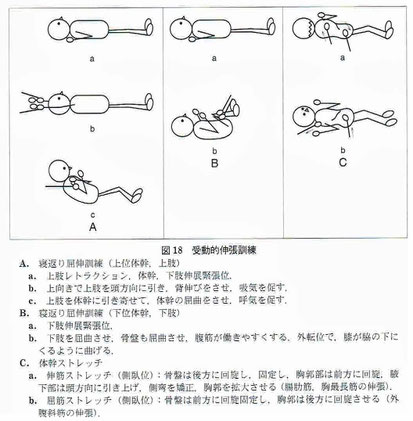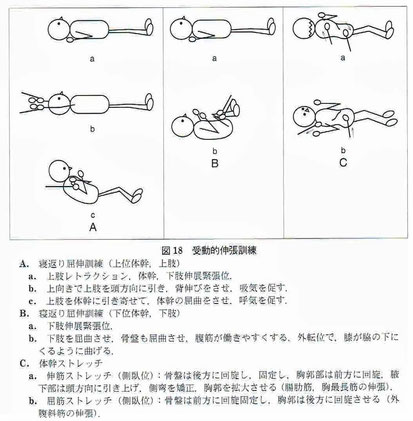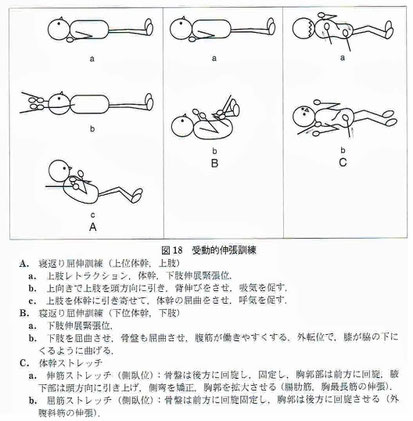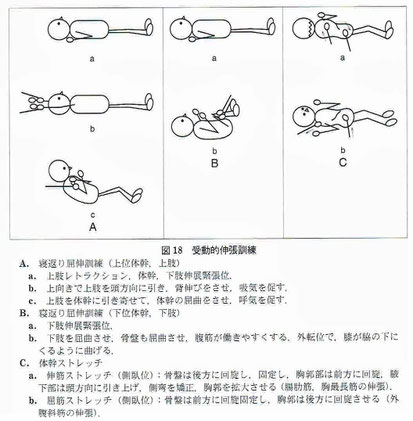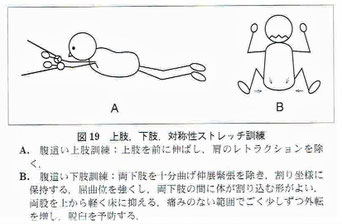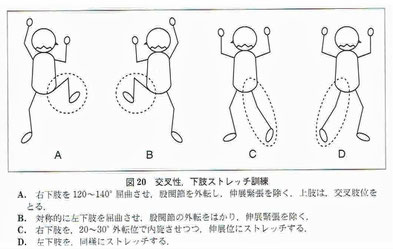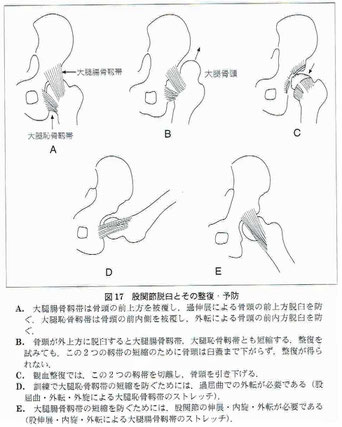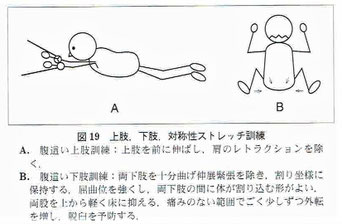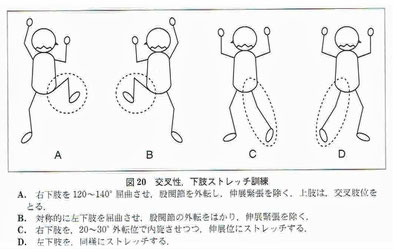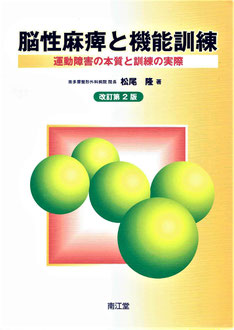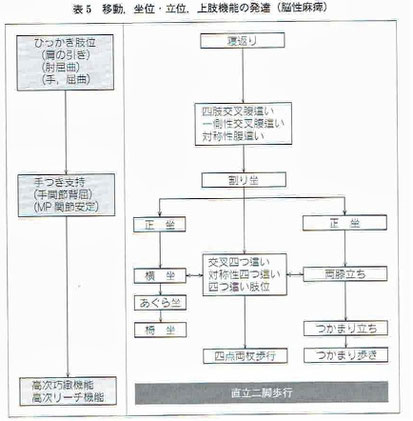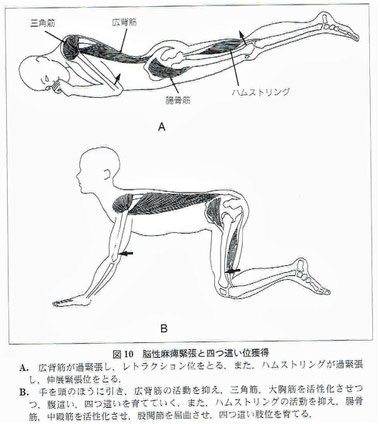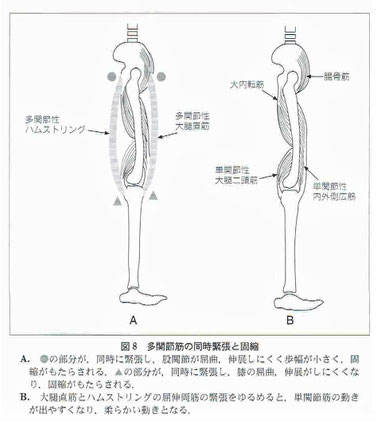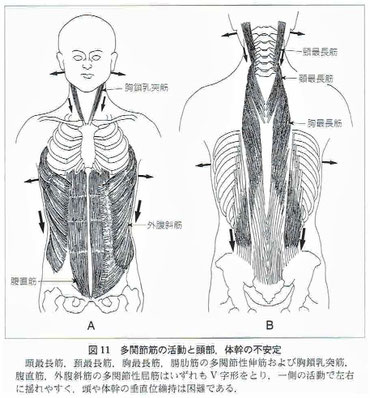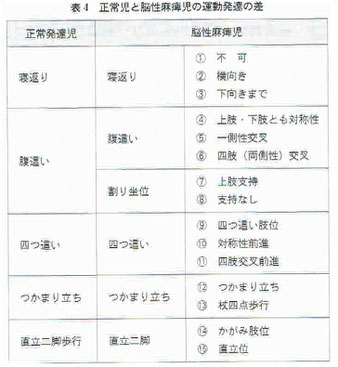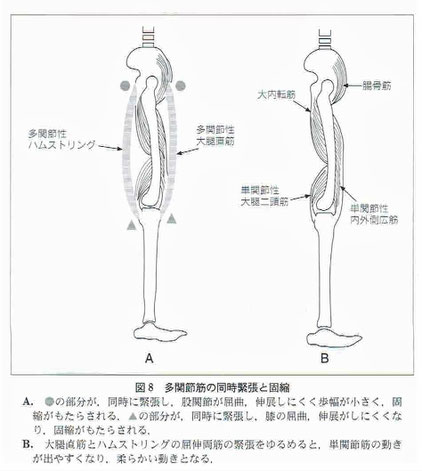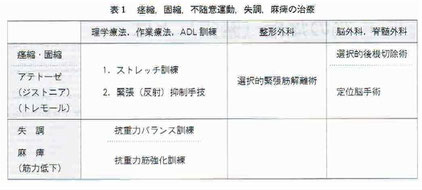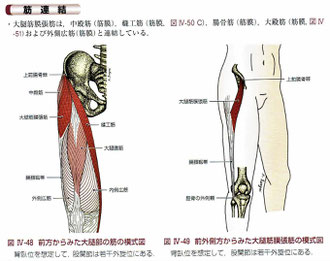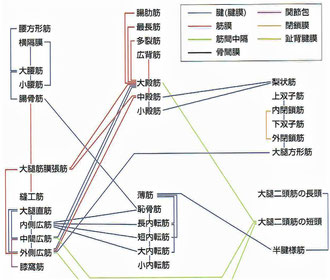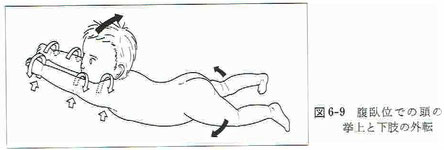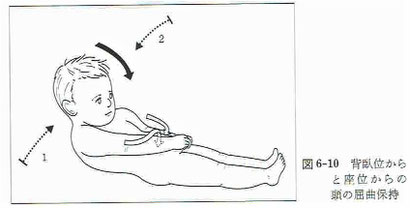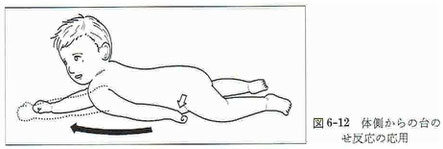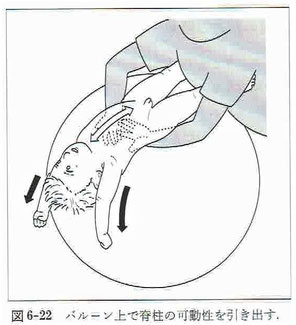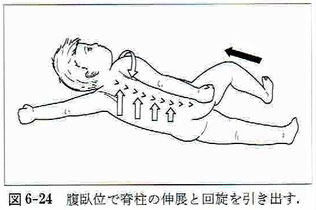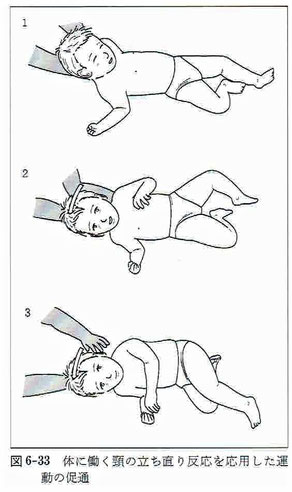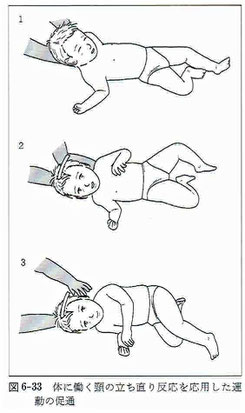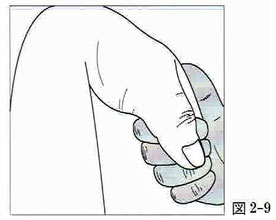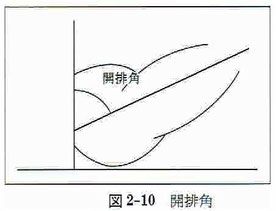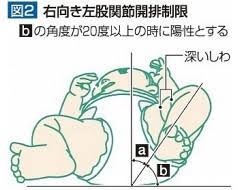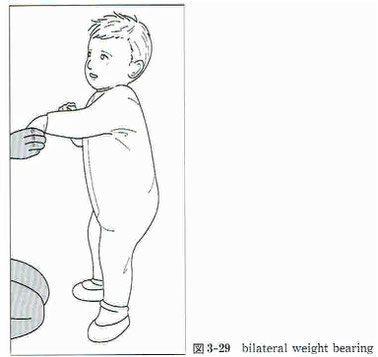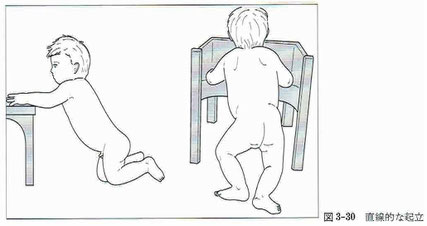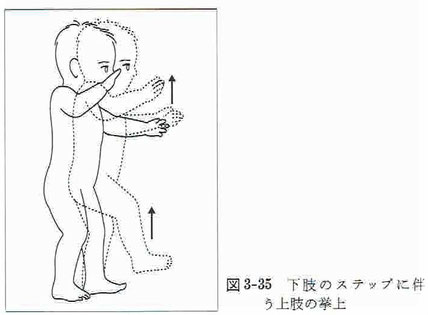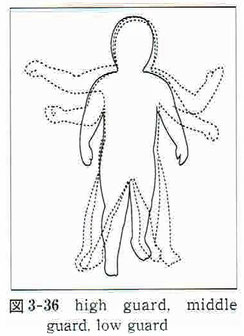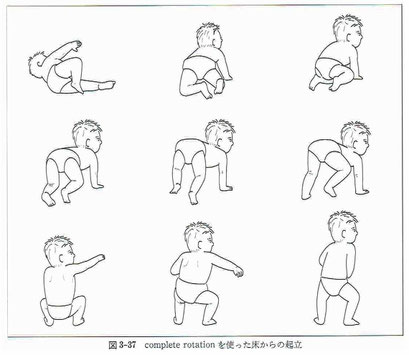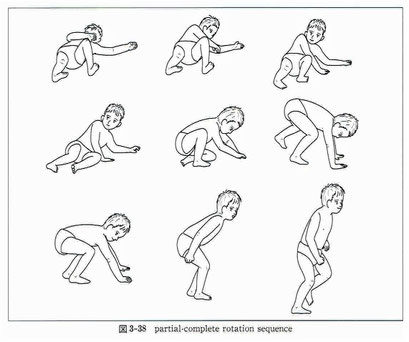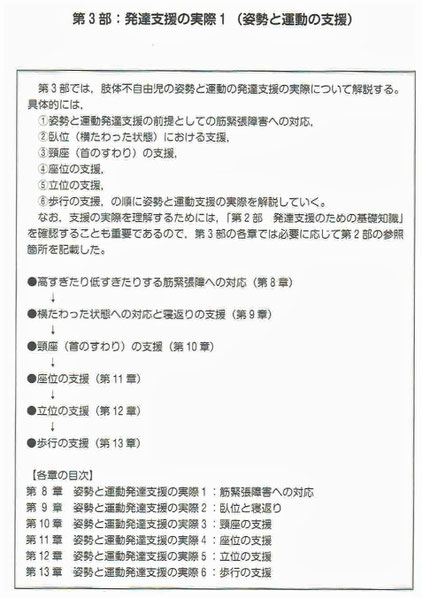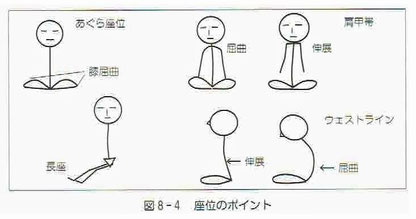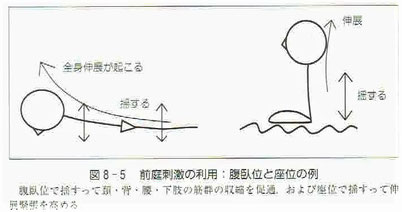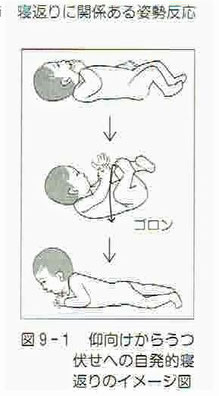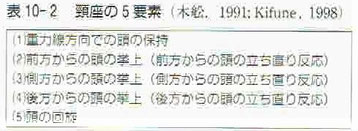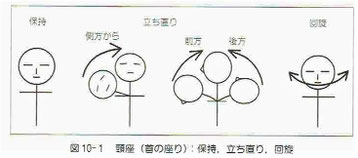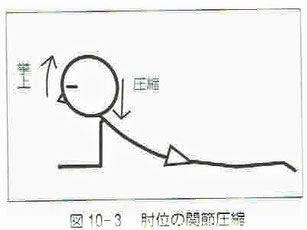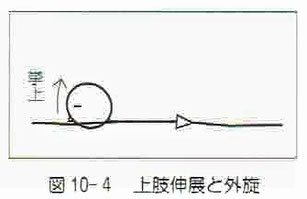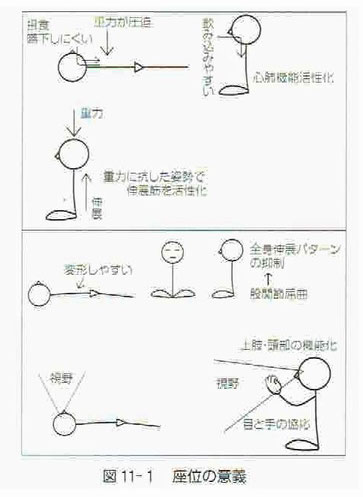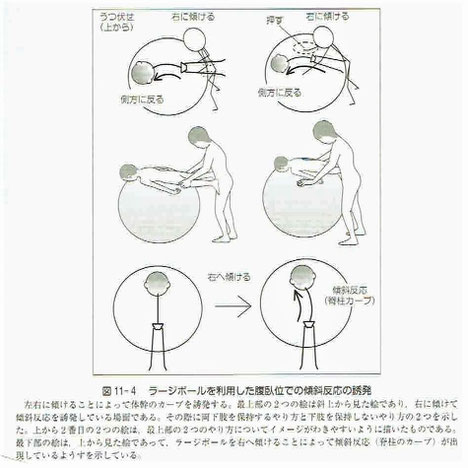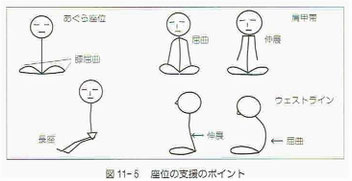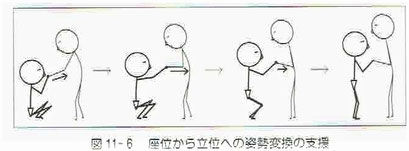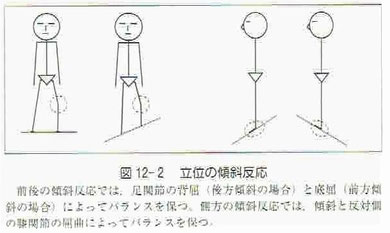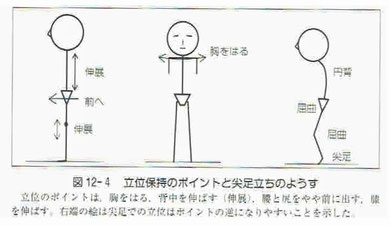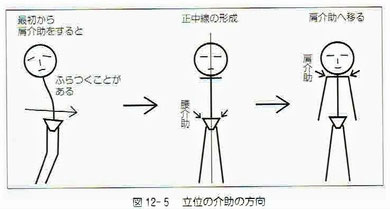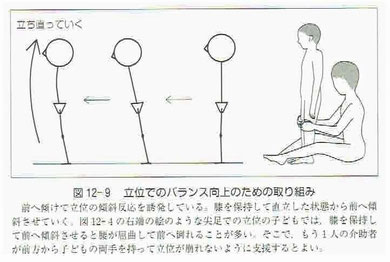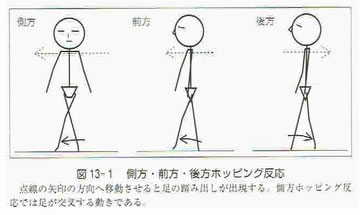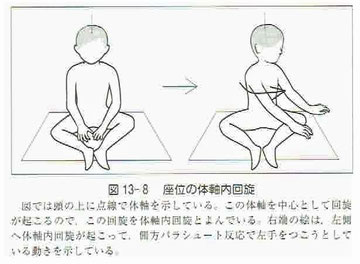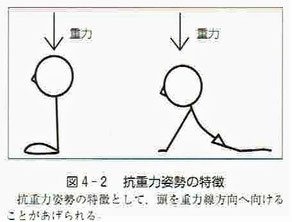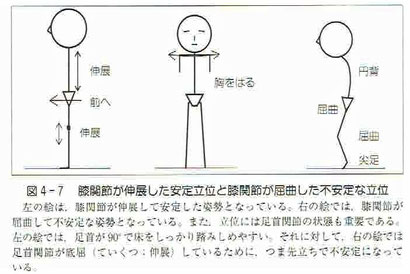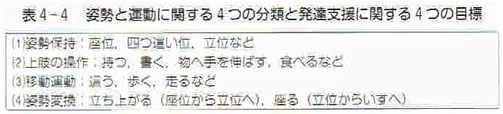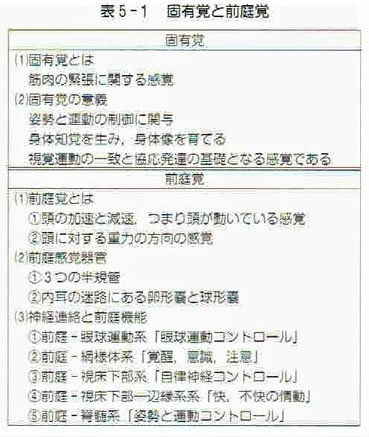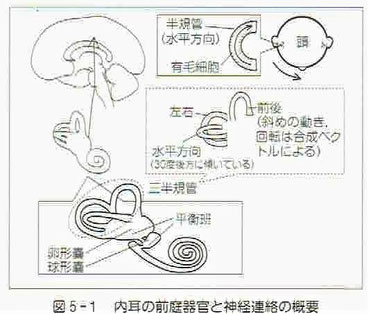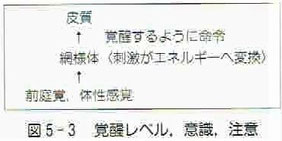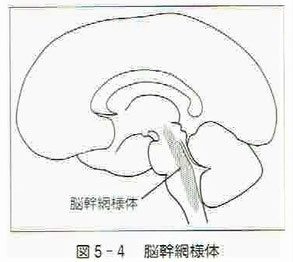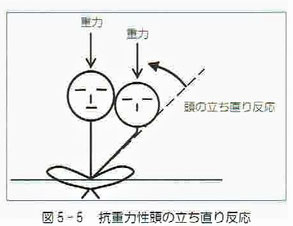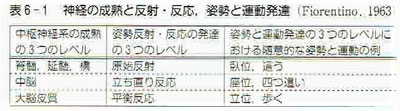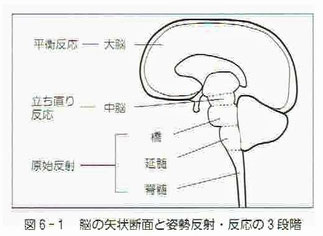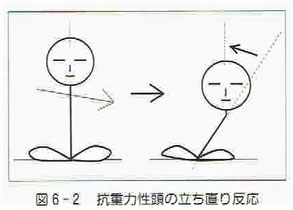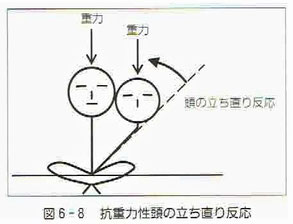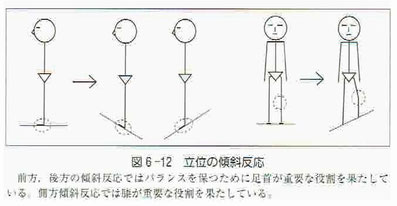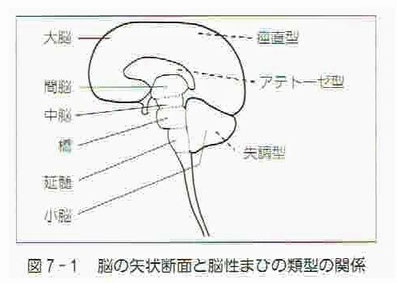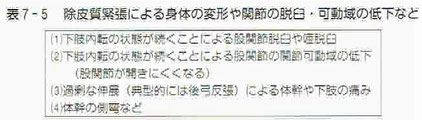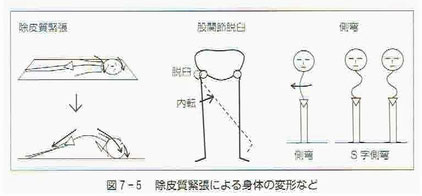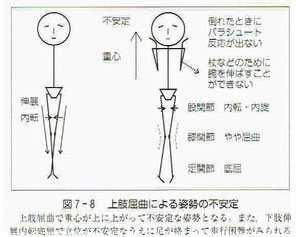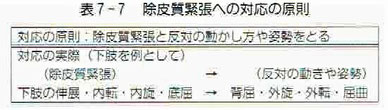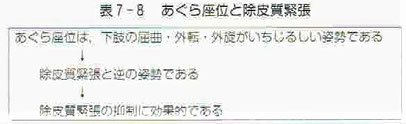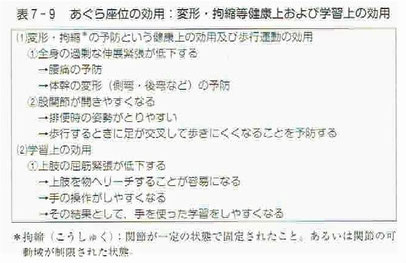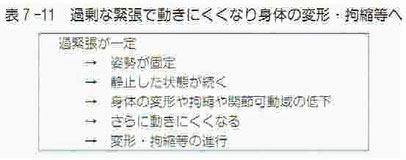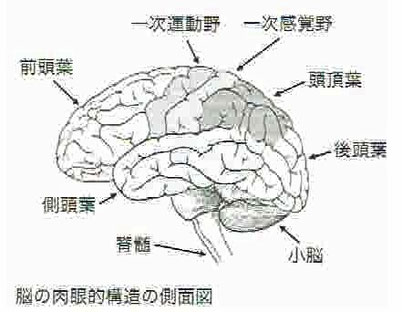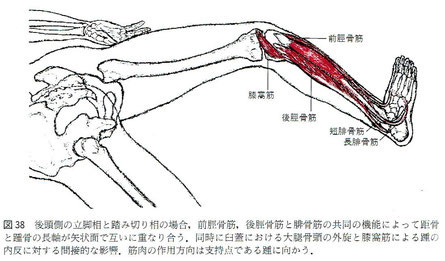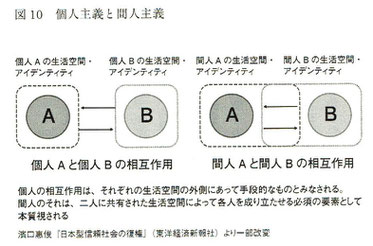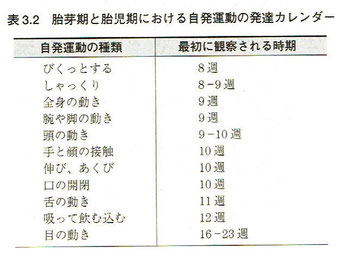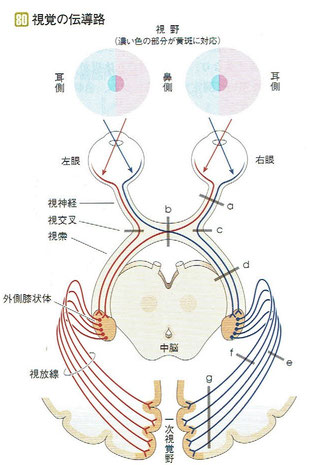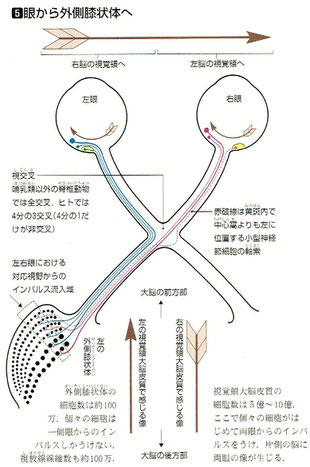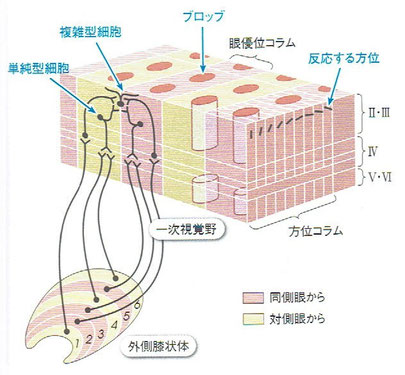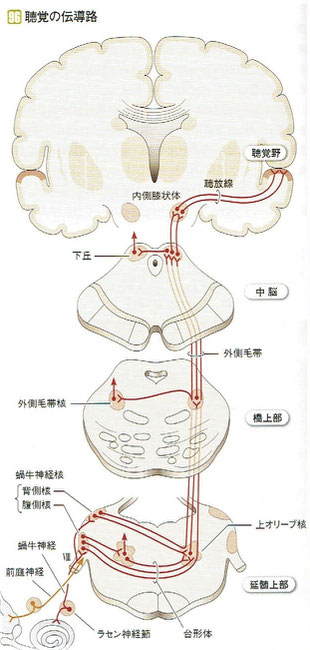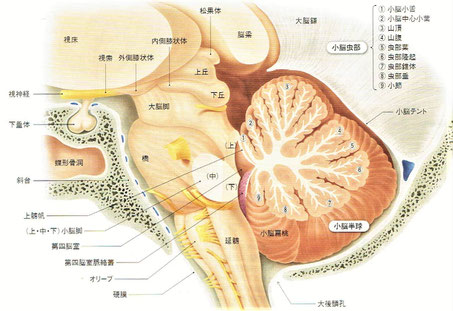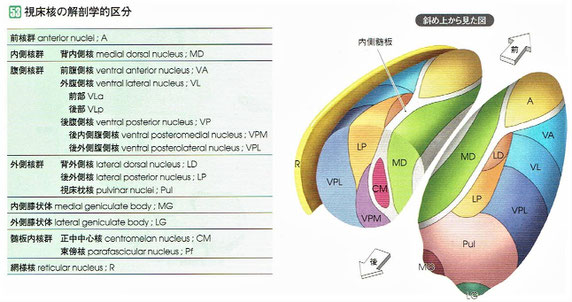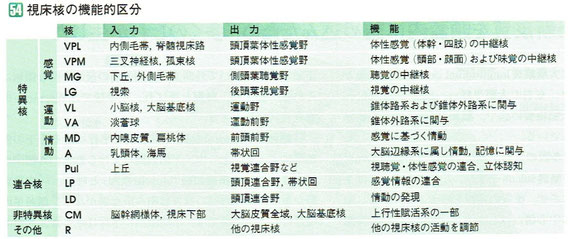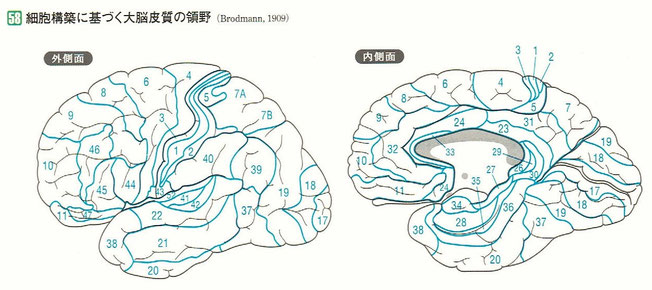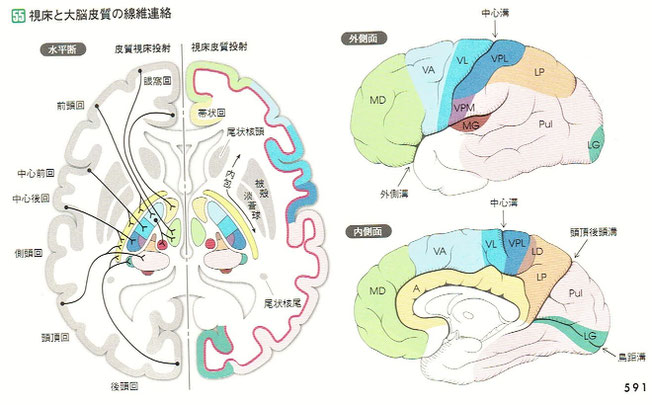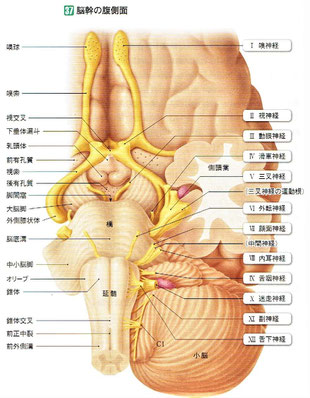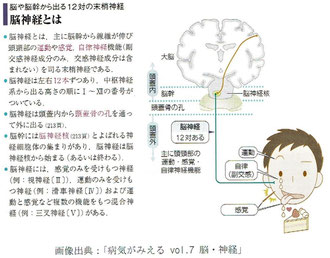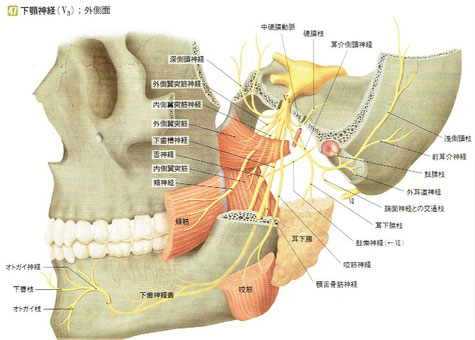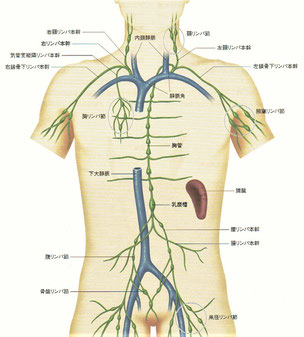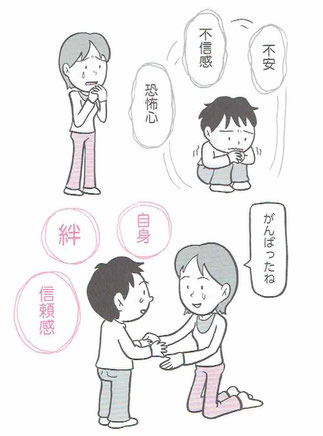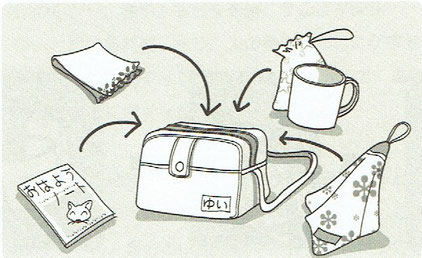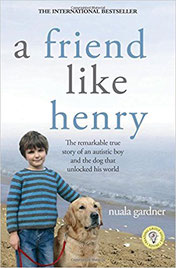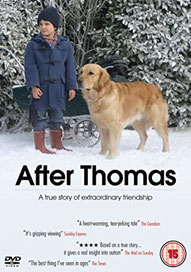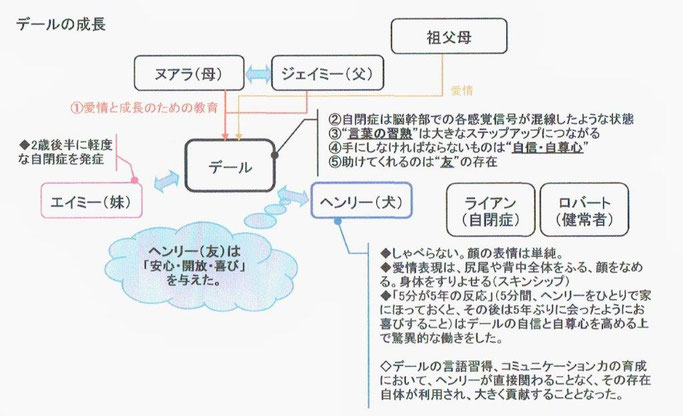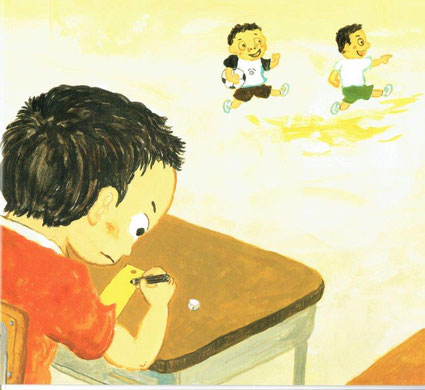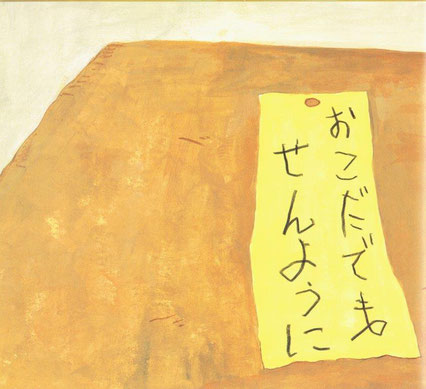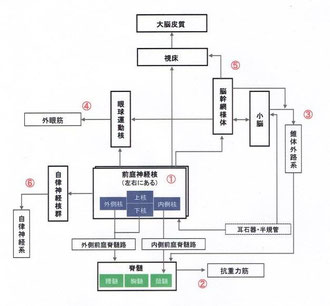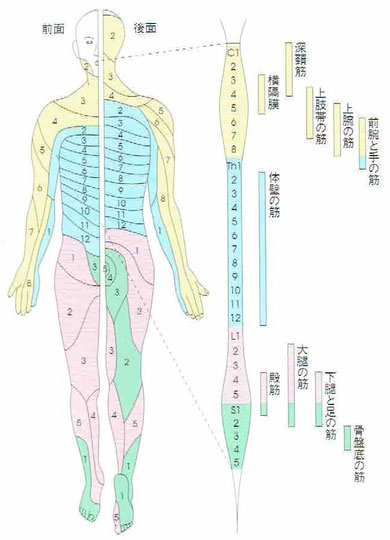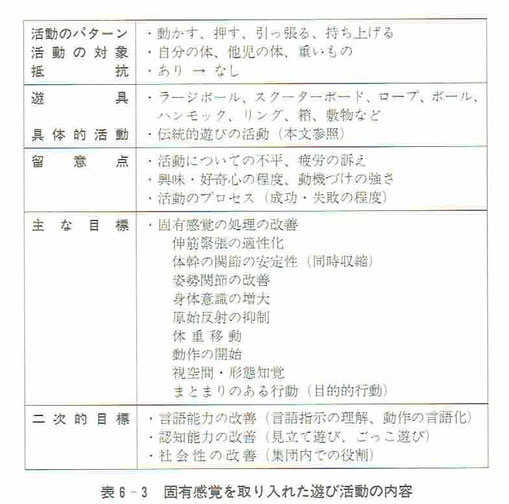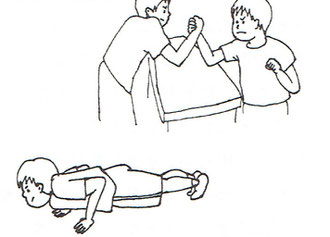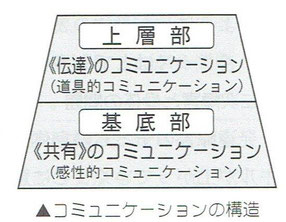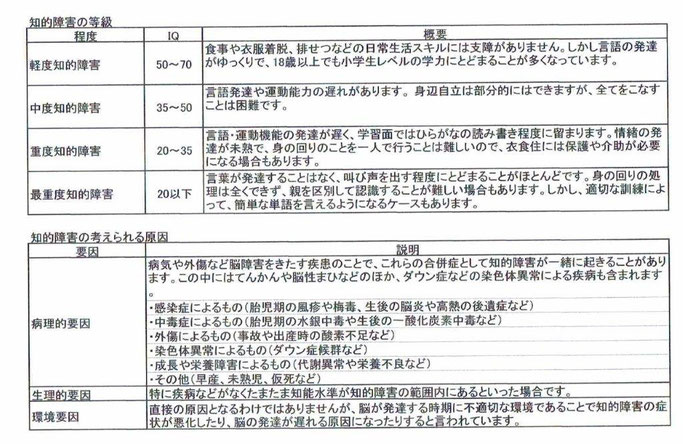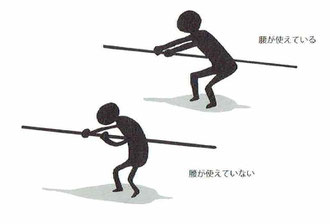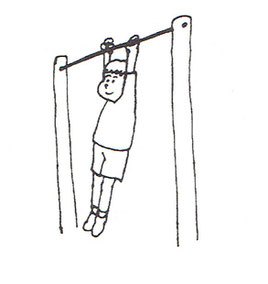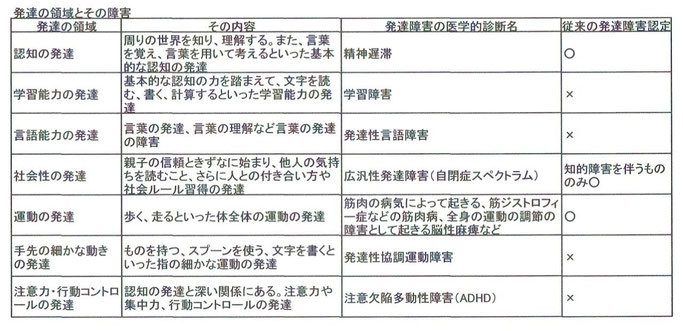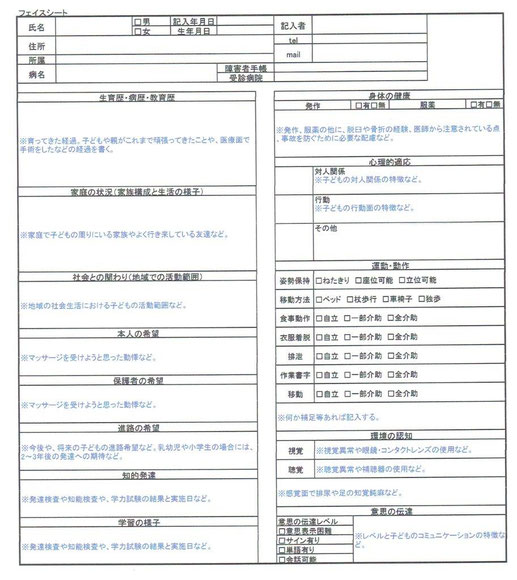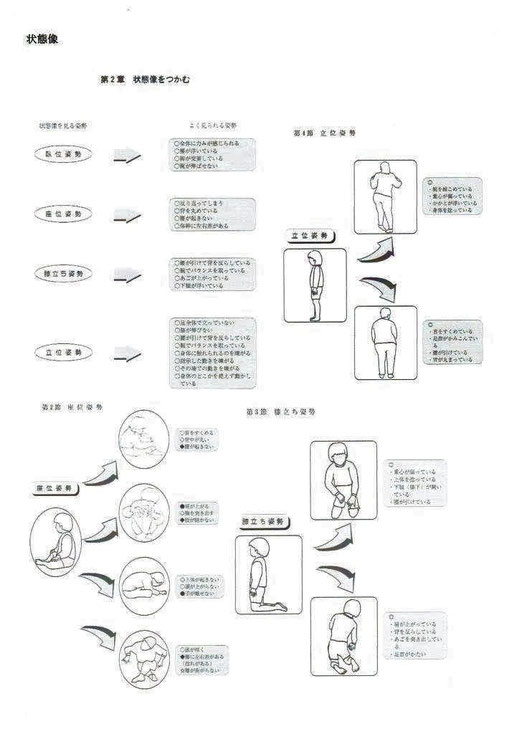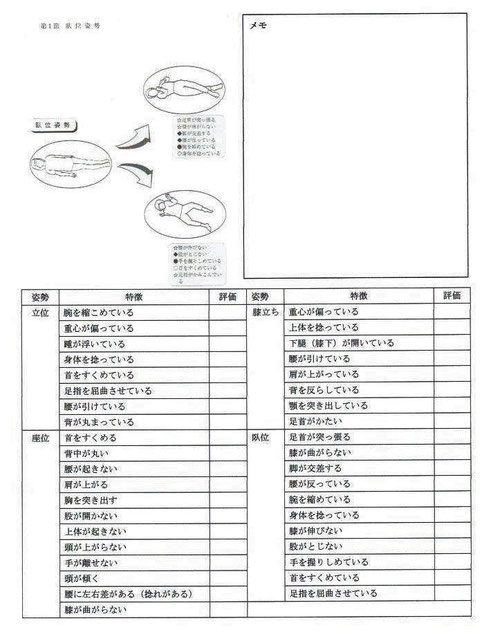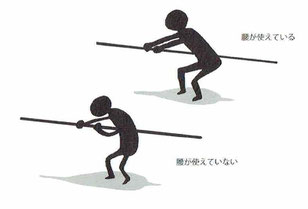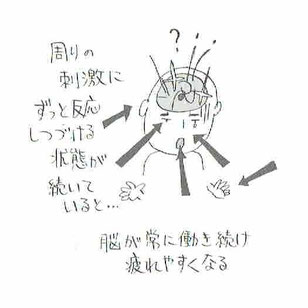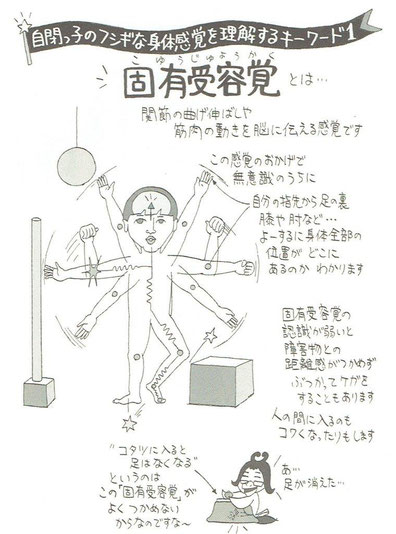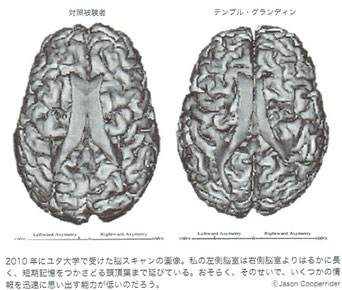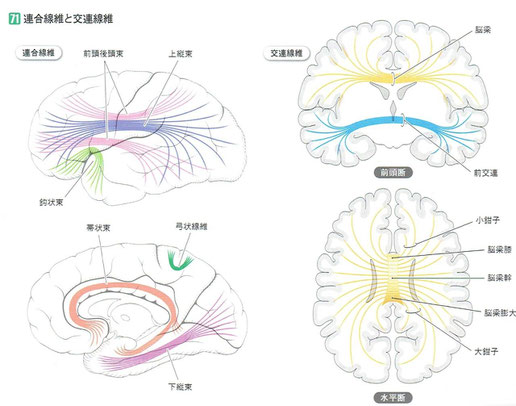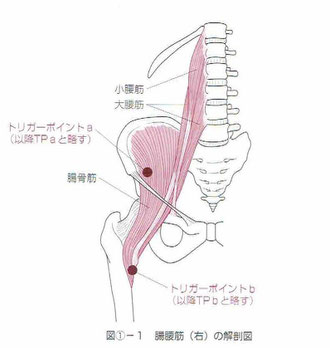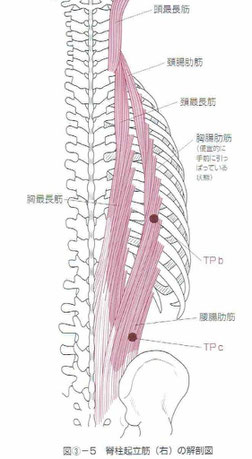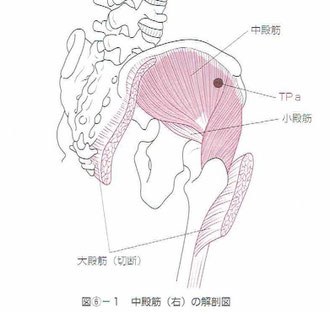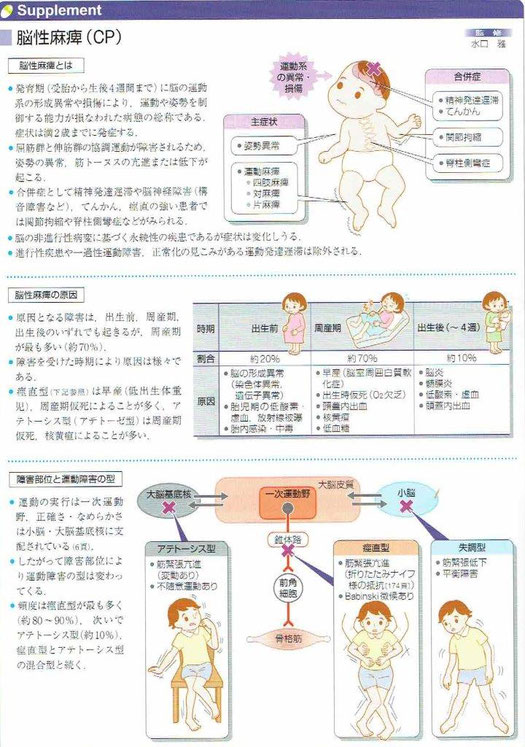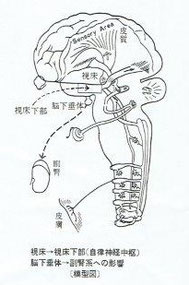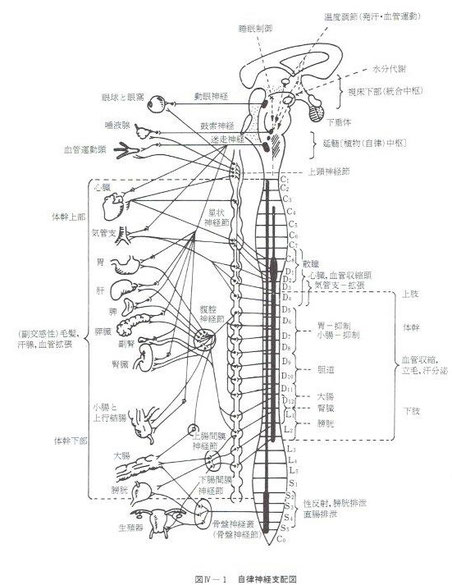立つ・歩くことを考えたリハビリテーション
順番が逆になってしまいましたが、脳性まひ児のリハビリテーションに関して、もう一つブログをアップしたいと思います。今回の本は患者さまのご家族の方から教えて頂いたもので、大変簡潔で分かりやすく、実際に試してみたいと思う内容なのでご紹介させて頂きます。
章は6つで、以下の通りです。
第Ⅰ章 子どもの正常発達と運動障害児の特徴
第Ⅱ章 ストレッチの重要性 効果的な運動機能訓練を行うために
第Ⅲ章 子どもの発達に沿った運動機能訓練
第Ⅳ章 LS‐CC松葉杖訓練法の実際
第Ⅴ章 ケース報告
第Ⅵ章 学校や家庭での取り組み
ブログでご紹介しているのは第Ⅲ章です。そのⅢ章は4つに分かれており、この中のⅡ期とⅢ期を取り上げています。
第Ⅲ章 子どもの発達に沿った運動機能訓練
Ⅰ期:仰臥位→腹臥位→首の座り(頚定)→寝返り→持ち込み坐位
Ⅱ期:持ち込み坐位→自力坐位→四つ這い移動(尻這い・いざり這いを含む)
Ⅲ期:つかまり立ち→伝い歩き→独歩
Ⅳ期:応用歩行
Ⅱ期:持ち込み坐位→自力坐位→四つ這い移動(尻這い・いざり這いを含む)
1.持ち込み坐位
ねらい
①体幹を起こすことに慣れる
②バランス感覚の向上
③坐位姿勢での頭部保持
●坐位の練習は、脊柱に多くの加重がかかり、体幹を起こすことを経験する最初の姿勢である。
●四つ這いなどの運動能力ともかかわってくるので、非常に大切である。
ひとり座り:乳児の坐位。
あぐら坐位:成長とともに下肢がながくなるとひとり座りからあぐら坐位になる。
正座:足先が内を向き、殿部が足の上に乗っている状態(筆者が奨励している)。
割座:正座と異なり、殿部が足の間に落ちている状態(筆者が奨励している)。
横座り:長期的には側彎になる傾向が強い(筆者は奨励していない)。
とんび座り:股関節が内転・内旋となるので股関節の可動域に制限がある場合は避けるべき。
●健常児の自力坐位は、まず「腹臥位から殿部を持ち上げ→次に腕立て伏せで体幹を持ち上げ→ひとり座り」となる。そして、この次の段階として、上肢を使った四つ這いを獲得する。
●腕立て位で獲得した上肢伸展支持を利用して、あぐら坐位・割座・正座に慣れさせる。
●坐位姿勢では頭部を挙上させることが大切である。テレビや絵本・DVDなどを用いると良い。
●手で床を支えて坐位が可能であれば、片手に玩具を持たせたりして、片手でも支えられるようにする。
●両手を床から離しても坐位バランスが保てるようになるまで継続する。
2.肘這い
●肘這いは運動機能を促進する。
●「持ち込み坐位→自力坐位」の中間にある運動機能である。
3.自力坐位
●健常児では生後8~10カ月頃に見られる。
●手順は「腹臥位になり→尻を持ち上げるようにしながら→上肢で身体を支え→正座や割座になる。
●自力坐位になれない多くの子どもは、殿部を持ち上げられない。これは、股関節の屈曲がうまくできないからである。
●子ども自身の力で股関節屈曲の動きを生み出すことは、他動的な股関節屈曲運動だけでは難しい。
●“松葉杖訓練”を早期に行うと、下肢を随意的に動かすことを通して、股関節の屈曲を習得することができる。
●股関節の屈曲ができるようになれば、腹臥位で下腹部をくすぐると股関節が屈曲し、殿部が上がってくるので、腸骨前面を介助することにより正座や割座の姿勢がとれ、さらに上肢を伸ばすと上半身が持ち上がって、正座や割座の姿勢になることができる。
4.四つ這い
●四つ這い位でバランスを崩さず、手足を交互に動かすことができれば、四つ這いはできる。
●自立坐位が可能であれば、体幹のバランス維持も可能なので、四つ這いでのバランス維持も難しくない。
●手足を交互に動かすという課題は、やはり“松葉杖訓練”で効果的に学ぶことができる。
Ⅲ期:つかまり立ち→伝い歩き→独歩
●独歩を目標にした場合、つかまり立ち・伝い歩きは、習得させたい目標である。
●既に、つかまり立ち、伝い歩きを習得していれば、独歩を目標にすることができる。
1.つかまり立ち
●健常児では立ち上がる時に、足関節が大きく背屈している点は重要である。患児では足関節が底屈(尖足)し、十分な背屈が難しく、立位・歩行を困難にしている。
徒手による床からの立ち上がりの訓練
①子どもの背面から介助して、膝を支えてしゃがみ位をとらせる。そのとき、介助者に寄りかかる姿勢になり、体重を預けようとするのを、子どもの下肢に体重がのるように誘導して支える。その際、股関節が内転しやすいので、内転しないように注意する。
②座り込んでいる子どもの両膝を軽く握るように持ち、重心を前方に移すようにして殿部を持ち上げさせる。
③膝が伸びるように誘導しながら、股関節も同時に伸ばすように促す。
④膝と股関節が伸びきると、立位の姿勢になる。このとき、重心が後方に移らないように注意して、下肢に重心を十分のせるようにさせる。
●つかまり立ちを指導する際、上肢を引き上げたり、体幹を持ち上げたりしないようにしなければならない。立ち上がりを習得するには積極的支援ではなく、誘導を心がける。
2.伝い歩き
●伝い歩きの上達は、「つかまり立ちで左右の足に体重移動ができるようになる→次いでカニのように横移動ができるようになる→やがて片手で物につかまりながら前方移動ができるようになる」というものである。
●上下肢の運動機能がわるい子どもにとって、伝い歩きを行うことは大変難しいことであるが、これができなければ、次の段階へ進むことはできない。
大腿上部を介助しての重心移動
①子どもの後方から大腿上部を介助して、子どもの足を少し広げて立たせる。このとき重心は、下肢にしっかりとのっているか、少し前方である。重心が後方にならないように注意する。
②上記①の姿勢を維持しながら、片足に重心移動を行う。介助者が介助者の片足を子どもの足部に当て、横にスライドするようにしながら、持ち上げるかのように他方の足に重心を移す。これを左右ともに行う。
③上記②ができるようになれば、子どもの足部に当てていた介助者の足で、子どもの足を床から上げて、しっかりと他方の足に重心をかけさせる。これを左右ともに行う。
以上の訓練みより、左右への重心移動は行えるが、前方への移動は歩行器を使わなければできない。歩行器の指導では、特に、重心が後方にいかないように指導することが重要である。そのため、ハンドル型で後方から押すタイプの歩行器を推奨する。前輪の車輪は自由に動き、後輪の向きが自在に動くものを選ぶ。
子どもの手の位置は、左右の乳頭を結ぶ線よりやや低い高さである。つまり「頼れそうで頼れない状態」に訓練効果を期待しており、PCWの一般的な使用と比較すると、その使用方法は特徴的である。
大人がついやってしまうことで、特に注意したいのが、少し伝い歩きができるようになった子どもを片手介助で歩かせることである。これをすると、子どもは介助されている手に依存した方が楽なので、下肢でバランスをとる努力をしたがらなくなる。ちょっとしたことのように思えるが、子どもが試行錯誤しながら目標に取り組む段階に入れば、逃げ場をつくらないことが大切である。
3.独歩
●独歩の訓練に入る時期の見極めは大変難しい(杖歩行や歩行器を行っているうちに、独歩が可能な状態に達していることも珍しくない)。
●松葉杖での歩行が四点支持二点歩行になった時点や、歩行器歩行で安定した歩行ができるようになった時点などが目安になる。
●指導上、特に注意する点はバランスが後方へいかないようにすることである。
①下記の写真のように立たせる。
②立っている子どもの両肩前面に介助者の母指を除く四指を当て、母指は肩に当て、子どもの動きを誘導する。このときの介助者の四指+母指(補助指)は、重心が不安定になり倒れそうになった場合に、立て直しの基準(目安)となる。
③子どもの重心が前方へ移動するときに下肢が出る。このことを繰り返すのが、下肢の交互運動である。このとき大切なのがスピードのコントロールであり、うまくいかないと前方に倒れてしまう。介助者がスピードを調整しながら訓練を重ねていくことになるが、ここでは倒れることも経験させる。そして倒れたときは、必ず手で支えること(パラシュート反応)を習得させる。
以上のように、独歩の訓練を進め、肩を介助する独歩が安定してきたら、初めは2mくらいを目標に、介助者の誘導を減らした独歩をさせる(基本的に肩を介助する)。目標位置で保護者が見守ったり、子どもの好きな物を置いておいたりすると子どもは努力することができる。しかし、定めた距離は守り、子どもが上手に独歩しているからもう少し距離を延ばせそうだと思っても、目標位置を変えてはならない。目標位置を遠のくことは、独歩にチャレンジしている子どもに不安感を与え、独歩が嫌いになる原因になる場合があるからである。
LS-CC松葉杖訓練法について
LS-CCのLSとはLong Leg Standing Stabilizerの略で、LS-CC法では「安定板付き長下肢装具」のことです。
また、CCはCrawling Carのことで、「四つ這い補助車」のことです。
松葉杖も上部の横木が真っすぐではなく、三日月状に加工された特別仕様となっています。
LS-CC法の開発のきっかけとなった松葉杖訓練
なお、ご紹介は全文ではありません。
『LS-CC法は、運動障害児に対する有効な訓練法の一つである。年齢的には、2歳前後から適応される。これは、次のような例を経験したことから実践を重ね、完成させた方法である。
筆者(坂根)が勤務していた当時、東京都北療育園(以下、北療:現在の東京都立北療医療センター)の入園部門は、3歳児から単独で入園を受け入れており、機能的には、四つ這いやつかまり立ちなどが可能な子どもたちもいた。その子どもたちに対する訓練内容として、ごく一般的には、関節可動域訓練、介助での立位、しゃがみ立ち上がり訓練、片膝立ち、平行棒あるいは歩行器を利用した歩行訓練、肩や腰部を介助した歩行訓練を行っていた。このような訓練を受けて、2~3年経って退園するのであるが、機能的にみて目覚ましい進歩がみられないのがふつうであった。訓練技術の無力さを歯がゆく思ったものである。
そんなあるとき、四つ這い・伝い歩きが可能な4歳のA君が、訓練室に置いてあった松葉杖を持ちだして遊んでいたので、通常の使い方を教えてみたところ、あまりいやがらなかったので、その後も1日40分~1時間以上、週3~4日以上を目安に継続して練習させた。その結果、3~4週間後には、介助なしに、そばで見守るだけで、訓練室内を4~5m歩けるようになった。3カ月後には、訓練室で、一人で松葉杖歩行ができるようになり、半年後には、居室から訓練室までの約30mを同様に松葉杖で歩けるようになった。そして、約1年後には独歩を開始した。また、結果的に、特に訓練内容として取り上げなかった膝歩きが上手になっていたのである。
この例をきっかけとして、A君よりも機能的にやや劣る子どもや知的能力の低い子どもなど数人に試してみると、どの子どもも2年前後で施設内を松葉杖であるくことが可能になった。このような動作の向上により、坐位の姿勢がよくなり、椅子坐位が安定した。訓練目標として取り上げていなかったことが上達し、松葉杖訓練を行ったことで運動機能の著しい伸びがみられたことは注目に値した。常に少ない訓練時間に不満を抱いていた筆者らにとって、この事実は貴重な経験であった。
その後、A君と同じ痙直型以外に、アテトーゼ型・失調型・混合型の子どもたちにも松葉杖訓練を実施した。下肢関節に強度の拘縮のある子どもや重い知的障害のある子どもを除いて、A君と同様な結果を得た。この実践をとおして、筆者らは「新しい訓練観」をもつに至った。
それは、A君たちよりも機能的に重度な子ども(寝返りや腹這い移動は可能であるが、自力坐位は不可)の自力坐位や四つ這い獲得のために、松葉杖訓練が役に立ちはしないかという考えである。つまり松葉杖訓練によって、体幹や下肢筋力の増強、上肢と下肢の交互性の上達が促され、その結果、自力坐位や四つ這いに結びつくのではないかと考えたのである。実際に試してみると、両脇を介助して立たせたときに立位がとれる場合は、松葉杖訓練が可能であることがわかった。松葉杖訓練は最初、腋下に頼るようにして下肢の支持性が出るまではつらそうにする子どももいる。しかし、継続して行い、介助者の適切な指導があれば、すぐに慣れる。そして、1~2年後、自力坐位・四つ這いが可能になっていた例が多かった。また、自立坐位はできないまでも持ち込み坐位が安定していた。』
”肢体不自由と共に”というサイト(Facebook)もあります。
脳性まひ児のリハビリテーション
昨年8月より始めた脳性まひ児の施術の勉強は、『脳性まひ児の発達支援』、『小児の理学療法』、『脳性麻痺と機能訓練』、『脳性まひの治療のアイデア』、『基礎から学ぶ動作訓練』、『臨床動作法の理論と治療』の6冊の本と『ふぇにっくす』という臨床動作法の冊子がテキストでした。
添付資料は整理整頓したものですが、自分用としてはそれなりに整理できたように思っています。大事なことは一人ひとりに適した施術を考え、実践しより良いものに改善していくことですが、全体観と方向性をイメージし、施術のための引き出しを数多く持つことは、「施術の迷子」にならないためには必要なことだと思います。
心・脳と筋肉を両輪とし、言葉と動作コミュニケーションを密にして、患児と施術者が協同でその歯車を回していくこと、右に行ったり、左に行ったり蛇行しながら進むであろう歩みを、随時修正しながら目標に向かって進めていくこと、これが施術者に課せられた課題であると思います。
「良い立位と歩行を獲得させるために、頚部と体幹の動的安定性の活性化、足関節の背屈とつま先の動き、下肢の選択的な運動がとても重要である。」ということ。そして、「頚部と体幹の動的安定性の欠如は、特に筋の未発達が原因である。」ということが最も印象に残ったことであり、緊張の高い筋肉を弛めることと、緊張の低い筋肉を促通し、筋肉を育てることが施術の中心になるだろうと考えます。
下記は表に記載されている「施術の基本」と「参考となる資料」、そしてABMの「9つの大事なこと」に関する過去ブログをご紹介するものです。
□ストレッチ訓練[脳性麻痺と機能訓練4]
□自立坐位獲得機能訓練[脳性麻痺と機能訓練6]
□四つ這い機能訓練[脳性麻痺と機能訓練7]
□立位・歩行機能訓練[脳性麻痺と機能訓練8]
□骨盤の運動性を高めるために内転筋群を弛める[脳性まひの治療のアイデア2:C-4~C-7]
□足部の活性化[脳性まひの治療のアイデア3:C-74~C-75]
□骨盤の回旋[脳性まひの治療のアイデア3:C-78~C-79]
□両下肢の分離運動[脳性まひの治療のアイデア4:C-118]
□大殿筋と大腿四頭筋[脳性まひの治療のアイデア4:C-120(ブリッジ)]
□股関節の運動性[脳性まひの治療のアイデア4:C-115~C-117]
□関節圧縮[脳性まひ児の発達支援2:図8-3]
□前庭刺激[脳性まひ児の発達支援2:図8-5]
□頚坐獲得[脳性まひ児の発達支援2:図10-2~図10-4]
□触覚と振動覚[脳性まひ児の発達支援2]
□足裏で踏み締める[臨床動作法6:図2]
□片足で踏み締める[臨床動作法6:図2~図3]
□踏み締める訓練[臨床動作法7:ふぇにっくす40号]
□絵でわかる動作法[臨床動作法7:付記]
■ABM(アナット・バニエル・メソッド)「9つの大事なこと」
・概要[アナット・バニエル・メソッド1]
・症例[アナット・バニエル・メソッド2]
・一覧表[臨床動作法1](こちらのブログに異常に細かい3枚物の資料を添付しています)
臨床動作法7
今回は日本リハビリティション心理学会さまが発行されている『ふぇにっくす』が題材となります。なお、投稿者のご所属はそれぞれの『ふぇにっくす』発行時のものです。

左をクリック頂くと”書籍案内”のページに移動します。
『ふぇにっくす』は昭和41年(1966年)に「心理リハビリティション・キャンプ」を初めて実施して以来、参加者間の親睦と交流を兼ねて自由な意見交換の場を持つために昭和46年(1971年)に創刊された冊子で、在庫が残っていれば購入することも可能です。今回は入手した数冊の『ふぇにっくす』の中から、特に印象に残った内容をご紹介します。
ふぇにっくす40号
立位訓練 日本学術振興会特別研究員 古賀 精治
※書式は要点と思う箇所を箇条書きにしたものとなっており、内容は一部となっています。
1.トレーニーが一人でどこで踏みしめて立っているかをよく感じてみましょう
◆訓練を始めるにあたって把握すること
・トレーニーはどうやって立っているのか。
・どこにどういうふうに力を入れて、どういう姿勢で立っているのか。
・どの方向にどの程度重心を移せるのか。
・どういう時にバランスを取れなくなって、どういうふうに倒れるのか。
・立つことにどれくらいこわさや不安を感じているのか、等々。
・時に外から眺めるだけでなく、トレーニーのからだに触れて確かめる。
・重要なことはトレーニーが自分一人でどこまでできるかを明らかにすること。
◆トレーニーが一人でどこまでできるかを見極め、さらにほんの少しだけ難しい課題をみつけ、その課題をトレーニーが自分で解決するのに必要な手助けをするのがトレーナーの役割と言える。
◆立つということは、重力に対応しながら、自分のからだの部位を時々刻々と複雑に操作しなければならない大変な体験である。
◆トレーナーはトレーニーの身体各部位に注意しなければならないが、部分に目を奪われすぎると、姿勢の全体像が見えなくなってしまう。
◆細かく気を配りながらも、大局的に姿勢全体を捕らえて、トレーニーの立ち方を模倣し、どういう力の入れ方をしているのかを、トレーナーが自分のからだで感じられるようになることが、立位訓練では特に大切である。
◆トレーナーがどういう姿勢で立っているのかは、足の裏のどこで踏みしめているかに表れる。
◆タテ系の立位訓練とは、トレーニーが今までの力の入れ方のパターンを捨て、新しい力の入れ方を習得し足裏のいろいろな箇所で大地を踏みしめて、楽に安定して立てるようになるための訓練だと考えられる。
2.上手に立てないトレーニーとは?
◆図2-aと図2-bは、膝の内側にギュッと入れ、股関節を動かせず腰を引いて肩や首の後ろに過度に力を入れて立っているトレーニーである。腰を動かすことができず、バランスが崩れると膝をさらに内側に締め、首をすくめて、肩や胸まわりに凄い力を入れて、バランスを保とうとするが倒れてしまう。図2-aのトレーニー関しては、多くは足首が内反または外反している。
◆図2-aと図2-bのトレーニーはタテに力を入れて立っているのではなく、脚を内側にギュッと閉じ込む力でやっと立っている感じであり、ちょっとでもバランスを崩すと倒れてしまう。また、これらのトレーニーは、多かれ少なかれ脚に左右差がみられる。
◆図2-aのトレーニーは足の指先に力を入れて立っている(図1の①)。一方、図2-bのトレーニーは踵で立っている場合が多い(図1の③)。
3.まず、足の裏(図1)の②で踏みしめるようになること
◆②で立つためには、身を堅くして脚を内側に閉じ込む力で立つ立ち方を変えなければならない。つまり、上体を腰の上にまっすぐに据え、膝を開き、太ももの前部とふくらはぎに力が入るようにすることである。
◆具体的な訓練
“自力で脚の力を一旦抜いて膝を開き、かつお尻を落とさずに立っている訓練”
・トレーニーは両足をまっすぐ平行に揃え、上体をまっすぐ腰の上に据え、足の裏の②で踏みしめやすいように、やや前傾気味に立つことが基本である。図3-aのように横から手助けするか、図3-bのように前から手助けするのが良い。
・トレーニーの膝頭の間に手または脚を差し入れる。トレーニーの方はそのトレーナーの手や脚に膝が当たらないように、内側にギュッと入れていた力を一旦抜いて膝を開き、お尻を下げないようにする。つまり、今までとは違う力の入れ方に取り組むということであり、求められるのはトレーニーの勇気である。脚を開ければ力が抜けてお尻が落ちそうになり、また、太ももやふくらはぎが大変疲れることになる。
“立位での腰と股関節の操作:股関節と膝とを連携させながらの脚の曲げ伸ばし”
・立位で腰や股関節を曲げたり伸ばしたりすることはとても難しい課題であり、通常は坐位や膝立ちの訓練が必要になる。なお、今回は「膝立ちでなら腰や股関節を操作できるが、立位ではできないトレーニー」の場合を想定したもの。
ふぇにっくす42号
子どもの状態と訓練 -側弯・緊張 九州大学教育学 堀江 幸治
●緊張・かたさ
『肩や腕、指先などに不当な緊張があるのは、本来力が入らなくてはいけないところ(大抵の場合、腰です)に入っていないか、入り方が間違って身についているからだと思います。おそらく肩を弛めることを課題にしているということは、からだが全体的に丸まった感じのお子さんなのではないでしょうか?もしそうならば、もう一度からだをタテの力を入れさせる課題の方がいいと思います。坐位、膝立ち訓練で、腰にタテの力が入ってくると、とくに肩の弛めの訓練をしないのに弛んできます。肩が弛むと、腕や手指の緊張もとれてきます。肩の力が入っているまま腕や手指の緊張をとろうとしても(そのときは一旦とれたとしても)、また入ってきます。
ただ、肩の力が抜けさえすれば即、指先が使えるわけではないでしょうから、指先の使い方の練習、例えば手をパッと広げたり、ギュッと握ったり、といった課題は必要かもしれません。』
ふぇにっくす74号
心理リハビリティションとしての見立て 静岡大学教育学領域 香野 毅
※“見立てる”は“診断”、“アセスメント”といった用語を含む自由な定義とするとされています。
●動作状況を見立てる
・姿勢
『姿勢は静止体ではなく微調整を絶えず行う連続的な活動である。調整は、重力に対しての自体の調整(バランスや踏みしめ)と見ることやモノを操作するための外的世界との関係づけ(構えや操作)の調整として行われる。立位姿勢で自分のからだに注意を向けると前後左右に揺れていること、それに対応して足裏や膝などが動いていること、さらには肩や腰も使っていることに気付ける。また手を前に出したり、顔を横に向けたりすると多くの身体部位がその調整に動員されていることに気付くことができる。
動作法では姿勢を動きとして捉える。姿勢を作るとは、その姿勢(例えば腰と背中を立てる)になるための様々な身体部位の動きをまとめあげることと言いかえることができる。この立場から姿勢の歪みや保持の困難を見立てるならば、それはその姿勢になるための動きを思うとおりに作り出せないことを意味している。あるいは瞬間的にはその動きを出せても、持続的に力を入れ続けて保持したり、重心の動きに対応して必要な動きを出したり出さなかったりすることが難しいということになる。まずはここが見立てのポイントになると考える。姿勢を外形的な形ではなく、必要な動きの集合体としてみることで、どこの動きが苦手なのかということを中心に見立てていくことになる。
また、動き出せないことの原因としては、その部位の不当緊張が強くて(いわゆるかたくて)動かそうにも動かせないことと、そもそも動かし方が分からないということがある。前者のように緊張が強い場合には、必要な部位に対してリラクセイション課題を行うこととなる。ただ留意しておかなければならないことは、仮にリラクセイションした状態になれたからといって、イコール動かせることではないことである。そこに動き方、適切な力の入れ方の学習を促す課題が必要なことはいうまでもない。緊張の強さや部位、動きの学習状況などが見立てのポイントとなる。』
・訓練(変容)可能性
『これはスーパーバイザーレベルの見立てといえるかもしれない。ある課題をトレーニーに実施した際に、その課題がもたらす成果や体験について推測的に見立てる必要がある。「できないからやる」「必要だから課題とする」ではなく「できそうだからやる」「必要な体験ができそうだから課題とする」と考えなくてはならない。 ~以下省略』
肢体不自由児・者への動作発達の見立て 広島大学大学院教育学研究科 船橋 篤彦
●肢体不自由児者の動作発達の見立て
・姿勢や動作をダイナミックなものとして捉えること
『肢体不自由者の座位、膝立ち、立位の姿勢を観察すると、人間の姿勢や動作の本質的な部位に気づかされます。それは、一生懸命に手を動かそうとしている時に顔や首に力を入れていることや、膝を伸ばそうとしている時に肩やお腹に力を入れている様子から感じることです。私たちは時として、動作が生じる<部位>に目を奪われて「動いたor動いていない」という判断をしてしまうことがあります。しかし、動きは全身の協調で成り立っているという前提で動作を観察してみると、目標となる動作の妨げとなっている要因が離れた身体部位に存在することがよく分かります。時計の針が小さな部品の連動によって生じているように姿勢や動作のダイナミズムを読み解くことも見立ての重要なポイントであると思います。さらに言えば、座位、膝立ち、立位の姿勢において、バランスが取れた状態とは「動きを抑制することで安定している静的状態」ではなく、正確には「小刻みに動くことで安定している動的状態」であると言えます。肢体不自由者の姿勢バランスを観察する際、<動きすぎて>バランスがとれない方もいれば、<動き方が分からなくて>バランスがとれない方もいます。本人の「困り方の違い」という点を考慮して、姿勢保持の訓練を進めていくもポイントになるかもしれない。』
付記:『障害者のための 絵でわかる動作法 はじめの一歩』より

下記の一覧表は動作法の全体像をイメージしたいと思い作ったものです。
第1章 動作法概論
第2章 状態像をつかむ
第3章 訓練の進め方
第1節 はじめの一歩
第2節 核となる訓練
第3節 発展訓練




臨床動作法6
今回は【肢体不自由動作法】の中から、歩行動作治療訓練法 をご紹介します。
なお、『臨床動作法の理論と治療』の目次は”臨床動作法2”をご覧ください。
【肢体不自由動作法】
歩行動作治療訓練法
はじめに
訓練者(以下、トレーナーという)が、訓練を受ける側(以下、トレーニーという)のからだの持ち主であり、からだの働きをコントロールしている「主体」(動作法ではこれを「自己」と呼ぶ)に、からだを通していかに働きかけるか、これが肢体不自由動作法におけるトレーナーに課せられている主要な課題である。
成瀬は「タテ系動作訓練法」という名称を用いてこの動作訓練法をより一層体系化されたものとした。そこで、ひとが生きていく上でからだを「タテ」にすることが重要であるという基本的な原理が述べられた上で、訓練課題は坐位、膝立ち、片膝立ち、立位、歩行の五つとされた。また、1989年春前後から、「踏み締め」ということが強調されている。「踏み締め」とは、そのことばが使われ出した当初、「大地を踏み締めることが大事」という説明とともに使われたこともあって、立位訓練において、からだをまっすぐタテにして、脚および足で自分の体重を支えながら、大地を足でしっかりと踏み締めることであると筆者は理解した。しかし、ひとがタテになることによって変化する心理的メカニズムとして、成瀬は、二次元平面から三次元空間へ、そして四次元世界への対応ということを述べている。具体的には、前者では、平面生活から立体空間での生活へ、重力に初めて対面する、
物理的・力学的法則性を持つ外界環境に直面する、自分のからだの重みを認知し重心を操作するなどであり、後者では、外界の立体空間に対応する、自体軸(自己軸)を明確にし空間座標の原点(自己存在の原点)とする、自分自身の世界(自己世界)を形成する、世界内における現実存在の体験をするなどが述べられている。結局、ただ単にからだをタテにして重力に対応して大地の上に自分のからだを適切に位置づけるということだけではなく、むしろ、大地に接した足・脚・躯幹に踏ん張りの力を入れ、大地に対してからだを据える「踏み締め」の訓練が、これらの心理的メカニズムを変えていくキーポイントになると成瀬は考えたのである。
実際に、筆者も、からだをタテにすること、踏み締めるということに重点を置いた訓練をすることによって、かなりの効果がみられることが実感できた。しかも、この「踏み締め」の訓練は、立位や歩行の訓練ばかりでなく、坐位、膝立ちの訓練でも非常に重要な役割を果たすことが体験的につかめてきた。自閉的傾向をともなった肢体不自由児に対して膝立ちの膝立ちの訓練をしたときに、きちんと腰に力が入るようになってしばらく踏ん張っている間、目をカッと見開いていたり、焦点の合った目で周囲を見回したりということは、まさしく成瀬のいう四次元世界への対応を示していると思われる。本稿では、「踏み締め」ということに重点を置きながら、歩行動作治療訓練法について述べることにする。
足の置きかた
一般的な「気をつけ」の姿勢の場合には、両踵をつけて左右の爪先の部分を開いて立つが、この足の使いかたは立位の訓練には適切ではない。なぜかといえば、これでは足、脚、上体が安定し過ぎてしまい、自分で自分の体をコントロールしながら立っているという感じがつかみにくいのである。立位の訓練のためには、両足は図1のように少し間隔をあけて平行に床につける。
実際にこうして立ってみると、足首、膝、腰、肩などで微妙に調節しながら立位姿勢を保っていることが非常によく感じられる。したがって、立つために自分自身がどのような変化をしなければならないかがよくわかりやすい状況をつくってやるということがこのような足の位置をとらせることであり、そのうえで訓練を行うことになる。
足で大地を踏み締めて立つ
歩行動作治療訓練を行う場合、まず、ひとりで立っていられることが条件となる。このとき、ただ単にひとりで立っていられるだけでは不充分である。踵がしっかりと床についているか、足首、膝、股関節に、ひとりで立っていることを維持するのに必要な微妙なコントロールをするだけの動きがあるかどうか、脚の上にまっすぐ腰と上体がのっているかどうかが非常に重要である。ここで「動き」というのは、本当は正確なことばではなく、自分で「動かす」ことができるという意味である。この訓練法では、「動くか動かないか」ということではなく、自分で「動かせるか動かせないか」が重要な問題なのである。歩行動作のためのこの前提条件が整わない場合には、これらの訓練から始めることになる。立位姿勢をとったときに、膝が突っ張り、脚が自由に使えないということはよく観察されることである。一見、これは膝だけの問題としてとらえられがちであるが、実際には、足首、膝、股関節の使いかたに問題があるのである。立位姿勢の状態で、上体をまっすぐに立てたまま、膝をゆっくりと屈げたり伸ばしたりすることができるように訓練することにより、同時に足首、股関節の使いかたも覚え、足首、膝、股関節に余裕をもって立てるようになる。この訓練の具体的な方法は、徳永が詳しく述べている。
さて、上体がまっすぐ脚の上にのり、足首、膝、股関節がある程度動かせて、余裕をもって立位姿勢が保持できるようになったところで、または、これらの訓練をしながら、いよいよ「踏み締め」の立っているときに、トレーニーがおもに足の裏のどの位置で床を踏んでいるのかをトレーナーとしては理解しなければならない。極端な例をあげれば、足の指に力が入って屈がり、指先が白くなっているようなら、おもに指先のほうで床を踏んでいる証拠である。このときには、上体がやや前傾気味になっていることが多い。足の指が床にしっかりとついていなければ、おもに踵のほうで床を踏んでいることになる。この場合には、上体がやや後傾気味になっていることが多い。足の裏のどの位置で床を踏んでいるかということは、なにも爪先と踵の問題だけではない。おもに足裏の内側で踏んでいるのか、または外側で踏んでいるのかも大いに問題である。床についている状態の足を踵のほうから、または爪先のほうから見てみると、これもよくわかる。内旋している脚では、内側で踏んでいることが多く、この場合には土踏まずの形成も充分でないこともある。以上は目で見たうえでの観察のポイントであるが、実際の訓練では、見た目にばかり頼っていてはならない。トレーニーの腰に軽く手を当てたときに、トレーナーの手に伝わってくる感じでそれがわかるようになっていることが大切である。足の踏みかたは、肢体不自由の場合ほど顕著ではないが、健常者にもそれぞれの特徴がある。筆者と一緒に訓練に携わっている学生たちの多くが、左右の足の踏みかたが異なっており、よく見ると、左右の足の形は対称ではない。しかし、踏みかたを変えるように訓練していると、みるみるうちに足の形が変わっていくことがわかる。
さて、立位姿勢における踏み締めの訓練であるが、理想的には、必要に応じて足裏のさまざまな部分できちんと大地が踏み締めるようになればよい。しかし、一番大事な訓練課題は、図2に示す斜線の部分できちんと大地を踏み締めることである。
この部分で最初から踏み締めることは難しいので、訓練の手順としては、まず、足裏で床を踏んでいるということをトレーニーに実感させることから始める。つまり、足裏で床をじっくりと味わうことから始めるのである。立位姿勢をとらせ、少しだけ前傾をさせて、おもに爪先で踏んでいることを体験させる。また、少しだけ後傾させて、おもに踵で踏んでいることを体験させる。このようにして、さまざまな方向にからだを少しだけ傾けてやり、足裏のいろいろな部分で床を踏む感じをつかませる。この過程で、前述の斜線の部分で踏むことももちろん加えておく。そして、この部分に脚、上体の全体重をかけて床を踏み締めることが、立位姿勢の中で一番安定していることを実感させるのである。その後、これまでトレーナーの他動的な援助で行ってきた、この斜線部分で踏み締めることを、トレーニー自身の努力でできるようにする。足首、膝、股関節がある程度自分で動かせるようになっていないと、なかなかこの斜線部分で踏み締めることができず、腰で反動をつけたりすることがみられる。そうすると、かえって適切な位置での踏み締めが困難になってしまうので、このような場合には、もう一度、足首、膝、股関節が動かせるかどうかのチェックが必要となるであろう。立位での踏み締めについては、古賀が詳細に述べている。
歩行が可能な肢体不自由児でも、立位での踏み締め訓練は、長く続けると見ていてつらそうである。普段の生活での使いかたとは異なる足裏の使いかたを覚える過程で、足裏は真っ赤になっており、きいてみると、非常に痛いという。トレーナーはこの辺りについても注意を払っておく必要がある。
片足で踏み締める
両足できちんと踏み締められるようになったら、今度は、片足で床をきちんと踏み締める訓練を行う。図3にしめすように、トレーナーはトレーニーの腰を軽く補助し、ゆっくりと重心を片方の脚に移動させていく。このときは、まだ両足ともに床につけたままである。重心を移したほうの脚にむやみに不必要な力が入らないように、特に、膝が反張にならないように気をつける。また、重心を移したほうの側に上体が傾かないように気を配る。上体は垂直のまま、もしくは、反対側に若干傾く程度が望ましい。横から見たときに、上体が反ったり屈がったり、また、尻が突き出したりしないようにする。この訓練の場合も、足裏のどの位置で床を踏み締めるかが問題である。両足で踏み締める場合とは少し異なり、重心を移したほうの足は、図2で示した斜線の部分の中央よりも外の部分で踏み締められるようになることが、この状態で一番安定できるようである。
この踏み締めができるようになったら、今度は図4に示すように、反対側の足を床から完全に離して少しだけあげ、すぐに元の位置に降ろすという訓練を行う。
このとき、足をあげ過ぎると全体のバランスが崩れやすいので、くれぐれも少しだけあげてすぐに降ろすということを徹底させる。また、足を後方にあげてくるトレーニーもいるが、そのときには膝を前に出しながら足をあげることをさせる。踏み締めているほうの足の側に上体が傾かないようにすることは、両足を床につけたまま片脚に重心を移したときと同様である。足がどうしてもあげられないトレーニーもいるが、足があげられないのではなく、片方の足でしっかりと踏み締めることができないことにより、他方の足をあげようにもあげられないということのほうが多いようである。しっかりと足で床を踏み締めて体重をのせているほうの脚を「のり脚」と呼んでいる。
踏み出し
片脚に重心を移し、足でしっかりと床を踏み締めて、反対側の足をあげることができるようになったら、今度は、あげた足をそのまま元の位置に戻すのではなく、前方に踏み出す訓練を行う。この前方に踏み出す脚を「出し脚」と呼んでいる。足をまっすぐ前に出すこと、また、大きく踏み出さないで、小さく踏み出すことを心がける。大きく踏み出すと全身のバランスを崩しやすく、また、重心を片方の脚から他方の脚に移しにくくなるからである。このとき、出し脚の側の腰が前方に極端に出ていたり、肩を引っ張りあげるようにして脚を出したりしないように気をつけてやることが必要である。出し脚が前方で床につくときには、爪先からではなく、踵から着地するようにする。
交互踏み出しを行うためには、出し脚が床についた時点で、今度はのり脚から出し脚に重心を移してこなければならない。のり脚が支えていた上体を出し脚の上にのせることが必要になってくる。このとき注意しないようにことは、出し脚の上に上体がきちんとのってくる前に、出し脚の膝を伸ばしてしまうことが往々にしてみられることである。そうなると、結果として出し脚のほうの側の腰が引けてしまうことになる。したがって、出し脚の側の腰を回すことなく、まっすぐに前方に出して出し脚の上にのせていく努力をさせなければならない。同時に、出し脚の側に上体が傾かないようにする。
出し脚の上に重心が移り、しっかりと床を踏み締めたら、後方にあったのり脚は踵をあげながら爪先で床を蹴り、まっすぐ前方に出されなければならない。このとき、のり脚は出し脚となる。こうして交互踏み出しの訓練を行うが、あくまでも小幅踏み出しを励行させることが重要である。
歩行
交互踏み出しで歩数が増えてくると、それが連続的な行われたとき、歩行につながる。最初はまっすぐに、あくまでも小幅で行う。交互に連続的に踏み出しているときには、トレーニーのからだのあちこちの部分に不必要な緊張が生じてくることが多い。脚を踏み出すたびに生じるこれらの緊張をトレーニーは自分で常に弛めておく努力をしなければならない。
また、我々は日常生活の中で、常にまっすぐに歩いているわけではない。したがって、方向を転換しながら歩行をする訓練も必要となる。右回り、左回り、S次歩行などがスムーズに行えるようにすることも歩行訓練の課題となる。
歩行に至るここまでの訓練を、成瀬は歩行動作訓練票としてまとめた。それを110頁にしめしたが、この票はそれぞれの課題の評価ができると同時に、訓練の方法、順番もわかるようになっている。実際の訓練のさいに利用されたい。
注)ご説明
2020年4月7日までここに”訓練票”を掲載していましたが、この票は現在使われておらず、「ボディダイナミクス」を使っているとの貴重なご意見を頂きましたので、削除させて頂きました。
臨床動作法5
今回は【肢体不自由動作法】の中から、タテ系動作治療訓練法 をご紹介します。
なお、『臨床動作法の理論と治療』の目次は”臨床動作法2”をご覧ください。
【肢体不自由動作法】
タテ系動作治療訓練法
はじめに
不精者のたとえとして「横の物を縦にもしない」という言い方がある。ちょっと変な言い回しかもしれないが、そのたとえから言えば、動作法は不精者ではないということになるだろう。なぜなら、この数年、動作法はそれこそ「横の物(からだ)を縦にする」ことをしっかりと行なってきたからである。
そうした取り組みの中から生まれてきたものがタテ系動作治療訓練法(以下、タテ系訓練と記す)である。このタテ系訓練によって、動作法はその技法の面において大きく発展し、現在では、従来の弛緩中心の技法に代わって、タテ系訓練が動作法における最も基本的な訓練法として位置づけられるようになっている。
タテ系訓練の考え方
(1)タテになることの意味
寝たきりの重度の子どもでも、坐位(あぐら坐)が独りでとれるようになると、まるで人が変わったかのように、表情や仕草が生き生きとしてくることがよくみられる。それまでぼんやりした目つきだったのが、目をしっかりと開けて周囲を見回し、自ら積極的に周りの人や物に働きかけるようになる。
坐るというのは、重力に対応して自分のからだをタテ方向に立てるということである。我々健常者と呼ばれている人間は、そうしたことを容易にやってのけているために、それがどんな意味をもっているのかなぞを考えることはほとんどない。
しかし、重度の子どもでみられる前述のような変化は、我々人間にとって、からだをタテにすることがいかに重大なことであるかを示している。つまり、それまでの寝たきりの二次元的な平面の世界では、受け身的な存在にしかすぎなかったのが、からだをタテにすることができるようになって、初めて能動的に環境に働きかける存在としての自分というものが生まれてくるらしいのである。そして、タテになることによって、左右や上下、遠近といった三次元的な空間の世界が展開し、さらにタテの姿勢を保持し続けるということから、時間という四次元的な世界をも取り込むことになり、自分を中心とした生活体験の世界がそれまでとは比べものにならないほど拡大していくことになる。
こうしたことから、重力に対応してからだを位置づけること―すなわち、からだをタテにする、ということは、人間の存在の基盤であるといっても過言ではないといえるだろう。
(2)弛緩中心の訓練の問題
タテ系訓練以前の技法は、子どもを寝かせた姿勢で身体各部位の弛緩を行うことが中心だった。それは、脳性まひ児の動作不自由をもたらす最大の原因が、彼らにみられる誤った過度の緊張であり、そのため、まずそのような不当緊張を適切に処理するための弛緩訓練が重要だと考えられていたからである。
不当緊張のある部位を弛緩できるようになると、それだけで立てなかったのが立てるようになることもみられ、こうしたやり方もそれなりの効果があったことは確かである。しかし、このような方法を長く続けているうちに、その問題点もいくつかみられるようになってきた。
その一つは、重度の子が多く訓練に参加するようになったことと関連して、弛緩訓練によって弛めることができるようになっても、それだけで終わってしまって、その後の新しい動きの獲得につながらないことが多くなったことである。つまり、弛めただけでは不十分で、どうしても動きそのものを教えることが必要なケースが増え、弛めるだけでなく、正しい力の入れ方を教えるということが訓練の重要な課題となってきたのである。
その他にも、弛緩中心の訓練では、どうしても動きそのものを教えることが必要なケースが増え、弛めるだけでなく、正しい力の入れ方を教えるということが訓練の重要な課題となってきたのである。
その他にも、弛緩中心の訓練では、どうしても訓練が局部的・部分的なものになりがちなため、一つ一つの部位の弛緩はある程度進んでも、それが動き全体の改善までつながらず、そのうちに弛んだところもまた元に戻ってしまうことがみられたり、とにかくまず弛めてなくてはならないということで、ともすれば訓練者が一方的に弛めてやるということになってしまうということもあった。
(3)タテ系訓練の展開
そうした弛緩中心の技法の問題を乗り越え、子どもに正しい力の入れ方を確実に覚えさせ、動き全体の改善をもたらす方法として開発されたのがタテ系訓練である。
先に述べたように、寝たきりの子どもでも、坐位の姿勢で頚や背、腰にうまく力を入れて、上体をタテにすることができるようになると、安定して坐っていることができるようになるだけでなく、行動全体が積極的・能動的なものとなってくる。そして、坐位だけでなく、膝立ちや立位といった姿勢がしっかりととれるようになると、子どもはいっそうからだの動きもよくなり、こころの活動も活発になってくることも分かってきた。
また、例えば、坐位がとれるようになると、それだけで肩や股の緊張が弛むというように、局部的な弛緩訓練を長くやっていてもなかなか弛まなかった頑固な慢性緊張が、からだをタテにすることができるようになると、直接にはその部位の弛緩訓練を行わなくても、弛めることができるようになってくることも明らかになってきた。
さらに、すでに立って歩いているような子どもでも、歩行が不安定であるとか、姿勢に歪みがあるとかいう場合に、それを改善するためには、坐位や膝立ちや立位の訓練を行うことが有用であることも確かめられた。
このようにして、重力に対応して自分のからだをタテにすることが、人間にとって非常に重大な意味をもっていることが明らかになると同時に、そのための働きかけは、弛緩を主とした従来のやり方とは比較にならないほど極めて有効な訓練法であることが確認されてきたことから、そうした訓練法をタテ系訓練と呼び、動作訓練の最も基本的な訓練法として位置づけられるようになったのである。
タテ系訓練の方法
(1)訓練課題
タテ系訓練では、以下の四つが訓練課題となる。
1.坐位
2.膝立ち(片膝立ち)
3.立位
4.歩行
各課題の対象となるのは、それぞれの課題の姿勢がとれない子どもはもちろんであるが、そればかりではなく、何とかその姿勢はとれても、どうも不安定であるとか、側彎や猫背、腰引けなどで姿勢に歪みがみられるような子どもも含まれる。例えば、立って歩くことができているような子どもでも、坐位をとらせると腰が引けて安定して坐ることができないようであれば、坐位訓練の対象となる。
(2)訓練手順の原理
どの課題においても訓練の進め方は共通しており、次のような原理に従って訓練が行われる。
1.形づくり
まず、それぞれの姿勢を子どもにとらせ、タテの姿勢の体験をさせる。その場合大切なのは、子どもがからだを屈げたり反らしたりするような力を入れることなく、トレーナーにからだを任せられるようになること(これを「おまかせ脱力」という)である。
2.主動化
形づくりでタテの姿勢がとれたといっても、それはトレーナーによってとらされたものであり、子ども自らがその姿勢をとったとは言い難い。そこで、次にトレーナーの援助を少しずつはずしていき、子どもが自分でその姿勢を保持する―つまり、タテに力を入れてくるようにさせる。受け身的なタテの姿勢から、主動的・能動的な本来の意味でのタテの姿勢への変換が図られるということから、この働きかけに対して「魂を入れる」という言い方がよくなされる。
3.分節づくり
自分でタテの姿勢が何とかとれるようになっても、それはまだ極めて自由度の小さい、非常に不安定なものでしかない。そのため、その姿勢の自由度を増し、安定性を高めるために、タテに力を入れたからだのある部分(ポイントとなるところがいくつかあり、「節」と呼ばれる)だけを弛めて動かせるようにすることが必要となってくる。つまり、一本の棒にすぎなかったものをいくつかの「節」ごとに分けて使えるようにするわけである。
4.バランスとり
最後に前後左右に重心を移動させ、そこでしっかりと踏みしめることを覚えさせながら、からだを動かしても倒れないようなバランスのとり方を教える。
(3)訓練の実際
それでは各訓練課題について、実際の訓練のやり方の大節を紹介しよう。ただし、歩行訓練については、別項に説明があるので、ここでは省略する。
1.坐位
坐位には、正坐やあぐら坐、横坐りなど色々なものがあるが、タテ系訓練ではあぐら坐を基本として訓練を行う。それは色々な坐り方の中でも、あぐら坐が最もタテの感じがつかみやすい姿勢だからである。
まず、子どもにあぐら坐をとらせ、トレーナーは子どもの後ろに坐り、両脚を子どもの大腿部に載せ、子どもの上体を前傾させ、そこから子どもの肩または頚を持って上体をゆっくりと起こしてやる(図1)。
そして、子どもの頚のすわりの様子、背や腰の反り・屈がりのぐあい、側彎の有無、股関節のかたさ、などをチェックし、それに応じて、必要な箇所の弛緩を行う。例えば、背中や腰に屈の緊張が強くみられる子どもに対しては、図2のように、子どもの背中・腰にトレーナーの脛を当て、子どもの上体を起こして反らせるようにして弛めるようにする。こうした手続きを通して、トレーナーの補助があれば、大腿部ができるだけ床につき、上体が頭から尻まで一直線になるような状態ができるようにしておく。
次に、図3のように、トレーナーは脚などを使って子どもの腰や背を軽く押し、どこに力を入れたらいいのかの手がかりを与え、様子をみながら、その補助を少しだけはずすようにして、子どもがそれらの部位に反りや屈ではないタテ方向の力を入れてくるように促してやる。
そうすると、腰や背に当てた脚を離そうとしたときに、子どもがそれらの部位に力を入れてくることがみられる。初めは瞬間的でごく弱い力の入れ方にしかすぎないが、繰り返し行っていくうちに、しっかりした確実なものとなっている。そして、それに合わせて、子どもの肩や大腿部に与えていた補助をはずしていき、図4のように、そうした補助なしでも、子どもが上体をタテにすることができるようにする。
それができるようになったら、タテになった上体の腰だけを弛めて祈るようにさせ、腰が余裕をもって使えるように、分節づくりの訓練を行う。そのとき、腰から上は反ったり屈がったりせずに、タテにまっすぐになっていることが肝要である。その後、前後左右に上体をわずかに倒し、バランスを崩しても、尻から大腿部で床をしっかり踏みつけて、上体をタテに保持できるようにする。
2.膝立ち
膝立ちがうまくできない子どもに膝立ちの姿勢をとらせようとすると、股がかたく屈になり、尻が後ろに引けてしまうことが多い。そのため、まず、図5のようにして、股を十分に伸ばす訓練を行う。
そのとき、トレーナーが強引に股を伸ばしてやるのではなく、子どもが自分で力を抜いて股を伸ばしてくるのを待つこと、また、腰が反ってしまわないようにすること、に注意しなくてはならない。
股が伸びてきたら、トレーナーは図6のような補助の仕方によって、子どもの膝から上がまっすぐになるようにする。
その際、子どもの両膝頭が離れないように、また、左右の足先が開かないようにしておく、そして、子どもの尻をブロックしているトレーナーの膝をほんの少しだけはずし、同時に子どものあごを少し引くようにしてやると、子どもが自分で腰に力を入れてくることがみられることがある。坐位のときと同様に、これも初め瞬間的なごく微妙な動きにしかすぎないが、何度も経験させていくうちに腰にしっかりと力が入るようになり、それに合わせて、トレーナーは補助を頚から肩、肩から腰へと徐々に下げ、最終的には上体の補助を全て離し、子どもが膝と腰で上体をしっかりと支えることができるようにする。
次に、図7のように、上体はまっすぐにしたまま、股だけを折り、股に余裕をもたせるようにする。
最初はごくわずかだけ祈るようにし、次第に折る角度を深めてそこで止まり、また浅くして、前後の動きを引き出すようにしながら、腰と脚でしっかり踏んばれるようにしていく。そして、上体をまっすぐにしたまま、重心を前後左右に移動させ、そこで床を膝で踏みしめさせ、重心移動とバランスとりの訓練を行う。
3.立位
まず、図8のような補助で子どもに立位の姿勢をとらせる。
そのとき、両脚は平行にそろえ、足幅は足と足の間がすこしあるくらいに狭くする。踵が床につき、膝が屈がらないように、腰から頭までがまっすぐになるよう、ブロックする。
トレーナーの補助によって立位の姿勢が一応とれるようになれば、子どもに膝を伸ばし、踵を踏みしめ、腰に力を入れて上体をまっすぐにするように促しながら、腰や膝のブロック補助をほんの少しだけはずしてやる。初めはすぐに膝が屈がり、腰が引けて、倒れそうになるが、そのときには直ちに元のようにしっかりとブロックして、決して倒さないようにする。腰に子どもが力を入れてきて上体が安定してきたら、腰の補助をはずし(図9)、膝にも力を入れて足から頭までがタテになるような力の入れ方ができてきたら、膝の補助もはずしてやる。
こうして、立位でタテ方向へ力を入れることができるようになれば、その次に、図10のように、上体をまっすぐにしたままで膝を弛めて屈げさせ、カクンと力が抜けてしまう直前で止め、そこから膝をゆっくり伸ばさせ、膝でしっかり踏んばることができるようにする。
その際、腰が引けたり反ったりしないこと、足の裏全体が床についていること、さらに図11の斜線の部分で床を踏みしめるようにすること、に注意する。
その後、上体が前後左右に傾かないようにしながら、重心を移動させ、図11の斜線部以外のどこででもしっかりと踏みしめができるようにして、立位のバランスがうまくとれるようにする。
(4)トレーナーの心構え
最後に、タテ系訓練を実施していく上で、トレーナーの心構えとして大事だと筆者が思うことをいくつか挙げてみよう。
1.子どもの主体性の尊重
このことはタテ系訓練になる以前から動作法の基本として常に言われてきた。しかし、従来の弛緩中心の訓練では、不当緊張のある部位をとにかくまず弛めなくてはいけないということで、ともすればトレーナーが一方的に弛めてやるというふうになりがちであった。それに対して、タテ系訓練では子どもの適切な入力ということが重視され、トレーナーがやってやるのではなくて子どもが自分でやるようになることの重要性がはっきりしたかたちで示されている。つまり、タテ系訓練になって、子どもの主体性・自発性の尊重ということがより一層クローズアップされてきたといえよう。
2.部分より全体
タテ系訓練でよく使われる言葉として「①-③の原理」というものがある。これは坐位で首がすわるためには、頚(①)だけを起こすのではなく、同時に胸(③)にも適切な力を入れてくることが必要だということである。さらに、頚と胸だけでなく、頚と背や頚と腰などにもうまく力が入れられるようになると、一層しっかり首がすわってくる。このように、首がすわるということはその部位だけの問題ではなく、胸や背、腰などの部位との関連の中で全体的に捉えていかなくてはいけない。このことは、子どもの抱える問題を局部的に処理するというより、タテという大きな枠組みの中で有機的に関連付けて対処していくことの必要性を示している。「①-③の原理」とはそのことを最も簡潔に表してる言葉だといえよう。タテ系訓練では、そうした部分的なものにとらわれずに全体のダイナミックスの中で問題を捉えていく見方がトレーナーに求められている。
3.形よりやりとり
坐位や膝立ちの訓練はそうした姿勢(形)をトレーナーがただ一方的にとらせるだけの訓練ではない。そこで大切なのは、そのような姿勢の中でトレーナーの働きかけに子どもが応え、それに対してまたトレーナーが応えていく、というやりとりを通して、子どもが適切なタテの力を獲得していくという過程である。しかしながら、とにかくタテにすればいいのだというように、ともすればからだをタテにするという形にのみ目が奪われて、やりとりということが二の次になってしまいかねない。タテ系訓練では、形にとらわれがちになる分、より一層子どもとのやりとりということをトレーナーは心に留めておくことが必要である。
4.✕より〇
弛緩中心の訓練では、不当緊張を弛めることから訓練が始まった。これは子どもの欠点を探し出して、それを矯正していく―つまり、子どもにとって✕になっているものをできるだけ取り除いていくという発想だったといえる。一方、タテ系訓練では、子ども自らの適切な入力ということが重視されている。こうしたやり方は、欠点の矯正というよりは長所を伸ばすということで、いわば子どもにとって〇になるものを少しでも引き出していくという発想だとみなすことができる。従来の方法からタテ系訓練への展開には、このできるだけ✕よりも〇を見いだしていこうという発想の転換があったともいえよう。「これができない」「まだあれもできない」と✕ばかりに目を向けるのではなく、「さっきより動きが出てきたな」というように、少しでも〇になるところを探し出していくことがトレーナーにとって大切になってきている。
そして、とりわけ、〇を探せと言われてもなかなか難しいことの多い、いわゆる重度の子どもについても、どうしたら○を見つけ出していけるかということを具体的に示したという点において、タテ系訓練は画期的な訓練であるといえるだろう。
付記:タテ系動作訓練票
注)ご説明
2020年4月7日までここに”訓練票”を掲載していましたが、この票は現在使われておらず、「ボディダイナミクス」を使っているとの貴重なご意見を頂きましたので、削除させて頂きました。
臨床動作法4
今回は【肢体不自由動作法】の中から、単位動作治療訓練法 をご紹介します。
なお、『臨床動作法の理論と治療』の目次は”臨床動作法2”をご覧ください。
【肢体不自由動作法】
単位動作治療訓練法
1.単位動作
日常生活で身体を動かすときは、いろいろな部位を同時に使って、意図した方向に身体を動かして目的を達成しているが、自分の手足の動かし方を身につけるような動作の学習を目的とする場合は、動きがはっきりと分かり、動かし方が学びやすい動作の単位を選ばなければならない。動かす身体の部位と動きの範囲及び方向を限定して行う必要がある。
骨格と関節の動きとして意識され、意図できる関節運動のなかでもっとも単純で有意味な動作は、身体の一つの関節を中心にして、一定方向にしかも規定量動かす動作で、これを『単位動作』と呼ぶことができる。肘関節の単位動作は<肘を曲げる>動作や<肘を伸ばす>動作などがそれであるが、両方の動作は、独立した単位動作と考えることができる。
2.単位動作の内容
(1)1つの関節を中心に動かす
緊張のあるところを見つけるには、いろいろな方向に動かしてみるとよいわけだが、だからといってめくらめっぽうに動かしてよいというものではない。緊張が強い子どもは、動かす部位間の区別ができないほど身体部位が未分化の状態にある。動かすときにいくつもの関節を同時に動かしたら、子どもは今どこを、どのように動かされているのか分からなくなってしまう。
そこで初めは、身体のある部位を軸にして動かさねばならない。それは緩める訓練のときと共通であるが、一つの関節を中心とした関節運動をすることである。
例えば、肘を曲げる動作のとき、肩も一緒になって動いてしまうことがある。肘関節を軸にして動かせるよう、訓練者は一方の手で子どもの肩を固定してやり、腕のつけねのところで腕と肩とを分離させ、さらにもう一方の手で前腕をやんわりとつかみ、上肢を支柱にして腕を曲げさせる。
このように一定の部位を基準にして動かすときには、他の部位を一方の手でしっかりと押さえたり、支持してやり、その部位が動かないように保持してやり、目指す部位だけを動かすよう補助してやることである。
(2)1つの方向に動かす
力を抜く訓練のときと同じように、意図した方向に動かす訓練も、最初は<曲げる>という方向について、あるいは<伸ばす>という方法についての動きを十分繰り返して訓練する。その時、曲げて伸ばすという二つの方向の動作を同時に、継続して練習するとうまく行かないことが多い。曲げていくときの力の抜き方はこうだ、伸ばすときの動かし方はこうだというように、一つ一つ方向の動きが把握できるように配慮して行うことである。曲げるときはうまくできたのに、伸ばすときはうまくいかないとか、伸ばすのはいいが、曲げるのは困難だというように、一つの関節でも方向によってかたいところ、動かしにくいところが違って現れてくる。ごまかして動かしているもののなかには、一つの方向に動かしはじめたが、途中で少しずれた方向に動かしてあたかもちゃんとした動きをしているようにしているのに気づくこともある。
(3)規定量を動かす
人の身体の関節を中心にして動く範囲は、身体の部位によって違いはあるが、一つの方向に動かせる可動範囲がある。この筋肉・骨格構造的に動かすことができる限度いっぱいの関節運動を目指さなければならない。その子どもが動かしうる範囲全体にわたって動かし、緊張がないか、動かしているかを確認するのである。可動範囲についての専門的な知識をもっていることに越したことはないが、自分でその部位を中心にして動かしてみたら、腕を上に挙げたら肩のどのあたりまで動かせるものか、足首がどのくらいまで曲がるかが分かるはずである。足首がスネまで曲がるなどとは考えないものである。
一定の方向に動かしてみると、その動きの過程の中でも、動き始めが困難だとか、途中でひっかかるとか、最後のところが難しいとかがより詳しくチェックできるものである。障害が比較的軽いと言われている子どものなかで、表面上は力が抜け、あまり悪さが目だたないのに、歩行などの複雑な動作をすると何となく変な恰好を示すものがいる。この子に一つの関節を軸にした一方向の動作を可動域いっぱいに動かしてみると、思いがけないところにかたさが残っているのを発見することもある。これは緊張や動かしにくさを、これ以上は動かせない生理的な限界だと誤って判断してしまった結果によるものである。
単位動作による訓練では、一つの関節部位を中心にして一方向・規定量動かすことを目指すと述べたが、その部位は手術の経験の有無にかかわらず、弛緩訓練と同じように、あまり急激にしかも強すぎる力を加えたりしないよう注意する。動かせるというから強引にやったりすると、筋肉や腱を痛めることもあるし、悪くすると骨にまで異常をきたすことにもなりかねない。これでは子どもとの訓練習慣や訓練関係がくずれるばかりか、いたずらに子どもに不安感や恐怖心を抱かせる結果になりかねない。手の力の加え方は常に、次第にゆっくりであり、身体を通し感じで調節する。
3.動作学習における単位動作の意義
単位動作は、動作が不自由な脳性マヒ児に対する訓練の方法を探っていた過程のなかから生まれてきた概念であり、訓練方法の1ステップである。単位動作による動作訓練の意義として次の点があげられる。
(1)動作感覚の明確化
単位動作は、各部位ごとの局部的な動きでしかも有意味な動作としてもっとも単純な身体運動の単位であるので、主体者に動かしている感覚がより明確に把握される。動かしている感じ、力を抜いている感覚が弁別しやすく、動かし方の感覚が得られやすい。
(2)不随意運動・不当緊張の抑制
目指す関節部位の動作とその動きに関連した部位の不当な緊張を最小限にくいとめる操作や援助が容易である。
(3)弛緩行動学習の促進-緊張と弛緩の分化
動かすために必要な緊張が分かりやすいことは、緊張と弛緩との感じが分かり、さらに弛緩した状態が維持しやすいことでもある。緊張と弛緩との弁別が可能になり、それを自ら維持できる自己弛緩が得られやすい。
(4)身体感覚の分化
脳性マヒ児の身体感覚は未分化な状態にあるので、身体各部位の、とくに動かしにくい部位の動作を行うことによって、意識できる部位とその背景となる部位とに身体部位を分化させ、知覚できるようになる。身体部位間に「図」と「地」の関係を確立させるような、部位間の分化がすすんでくる。
(5)注意集中の操作
複雑な動作では、同時に複数の部位を関連させて動かすことから、身体のいろいろな部位に注意を集中させなければならない。単位動作では、一つの関節における動きをとくに意識させ、意図的に動かすことであるので、自己の身体への注意が集中でき、その部位と他の部位との身体感覚や動作感覚を弁別し、さらに強化・拡大していくことが可能である。
(6)複雑な動作への般化
段階的に行われる力の入れ方、力の抜き方、動かし方の学習は統合され、いくつもの関節部位を同時に使う動作へと般化していく。ごく単純な動作ができるようになることからはじめて、漸次複雑な動作へと自らがコントロールの範囲を拡大していく方法は、複雑な動作からはじめたときに生じる諸困難がよりよく解決される。
4.単位動作の目的
さて、弛緩訓練によって訓練者が力を加えてみたときに、何の抵抗もなく子ども自身が力を抜けるようになったとき、あるいは自分で気がついて力が抜けるようになり、可動域全般にわたって動くとき、不当な緊張がなくなり弛緩行動ができるようになったと考える。力が抜けるようになると、他から力が加えられたときに、本人の意図と関係なく動くようになる。
私たちが身体運動をしているときには、力を緩めることと有効な方向に緊張させて、動かすことをたえず行っている。動作学習でも緩める訓練をしているときは、力を緩めることを直接の目的としているが、間接的には動かすことも行っている。また動かす訓練を目的的に行っているときには、緩める訓練も同時に行っているのである。うまく力が緩まないと動作が思ったようにできないし、うまく動かないときには不当なところに力が入ってしまっている。つまり力を抜く方向と動かす方向とは、努力の方向が異なるだけで、そこで行う動作は共通である。動作の訓練においては、力を入れることと力を抜くことは表裏の関係にある。その意味で単位動作による訓練では、動かす訓練と同時に緩める訓練を同時に行っている。
5.単位動作による訓練
乳児のようにまだ自分で動きをした経験の少ない子どもは、弛緩の体験をして、そのままにされても緊張の配分や力を入れる方向が変化して動きが誘発されてくるもののようだが、一般的には力を抜かせたら動かす動作の学習を目的的にやらなければ正しい動作の獲得はできない。練習しないでほっておくと前の時よりむしろ悪い恰好にもどってしまうことさえある。そこでどうやって意図的に動かす訓練をしたらよいかが次の問題となる。
(1)他動的に動かす
力が抜けたらこれから動かそうとする動きの過程を、一つの関節を中心に一つの方向に可動範囲をゆっくりと他動的に移動する。これは動かす訓練の第一歩である。これから動かそうとする範囲をどこからどこまで、どのように動かせばよいかの感覚をおこさせ、運動量を体験させることを目的に行う。正しい動きの方向のイメージをつくることにある。このとき動かそうとする範囲に不当な緊張が生じてこないかを確認することも必要である。もし不当な緊張が発生したときには、動かしながら緊張を緩めなければならない。また、この他動的に動かしてやることに終始しては、少しでも早く動くようにしてやろうとする焦りや動いたという訓練者の満足感・安心感は満たされることがあっても、子どもが自分で動かせるようにはならない。
(2)力が入りすぎて動かせないとき
イ 子どもにできるかぎり楽な姿勢を取らせる(仰臥位、坐位など)。坐位での肘を曲げる動きの訓練を想定すると、訓練者はだっこするように子どもの背後に、背中にぴったりとくっつくような位置に座る。
ロ 訓練者は目指す腕の上腕部分を一方の手でしっかり握り支持する。肘関節部位を軸にして曲げるために、もう一方の手で前腕をやんわりと握る。そして、「力を緩めて、らくにしてごらん。」と教示する。(このとき局部のみならず他の部位の弛緩もできていることを確認する)
ハ 局部(肘関節)を中心にして動かせる限界の位置で、曲げる方向と反対の伸ばす方向に力を加え抵抗を与える。(このとき局部のみに注意が集中するが、他の部位にも力が入らないように留意する)。このようにして、これから子どもが動かそうとする方向に対して反対の方向に手や手掌で力を加える。
二 「手を押してごらん」というように教示し、さらに押しこんでやる(必要な緊張状況を確認しながらゆっくりと力を入れて押す)。そうすると十分弛緩している子どもは押されている方向を局部で感じとり、そちらに注意が向き、どこの部位のどこのところが動かされてるかに気づく。はじめは試行錯誤的にいろいろな方向に力を入れてくる。このことを繰り返しているうちに、何かの拍子に、ごく弱い力ではあるが期待する動きの方向に力を入れてくるのを訓練者が感じとることがある。そのとき間一髪。
ホ 「そうそう、もっとずっと押してごらん」といって、正しい反応を強化してやる。
このようにして、動かす方向・力の入れ具合と力の抜き具合のきっかけを与える試みをすると、抵抗の与えられた方向に力が入り、動きの感じがでてくることがある。さらに力を入れて動かす努力をするように援助、激励してやる。ここでの動きには早く動かすことを決して要求してはならない。むしろゆっくりと抵抗に対して一定の速さで動かしていくことに重点をおくことである。動かすことがまったく偶然的に生じた有効な方向の緊張による結果であっても、これが意図する方向に動かそうとする努力の芽なのである。この芽に気づき、それを引きだしてやるのが訓練における重要なポイントの一つである。
(3)動かす方向に力が入らないとき
抵抗を与えそれに反発するような努力をさせようと思っていくら試みても、いっこうに力が入ってこないものがある。もともと動かすだけの力が備わっていないのではないかと思われるような無力性で『不動』のものである。このとき動かそうとする努力によって、局部に思っている方向とは別の方向へ力が入って動きをしているものと、まったく力を入れようとしていないのではないかと思われるものとの二つのタイプが見られる。
このような場合は、当該部位だけが動くように他の部位はしっかり支持して、再度関節運動に戻って、どこかに不当な緊張が残っていないかを確認する必要がある。前後・左右・上下と可動範囲をくまなく動かしてみる。捻じってもみる。すると捻じったときなどに、今までそこは可動範囲の限界と思われた箇所に、動かされたとたん子どもが飛び上がって痛がるような強い緊張を発見するようなことがある。このように力が入らないのは、局部に芯のような緊張の強く入っているところがあって、目標としているところには一向に力が入らないでしまっているものが多くみられる。再度弛緩させた後、目的としない方向に力が入ったり、動いたりしないようにして、子どもの身体の手ごたえを確認しながら、前述の抵抗を与える方法で動かす努力をさせてみると、目指す動作の芽生えはじめることも少なくない。また、力が入らないで誤った方向や部位に力が入ってしまったら、動かすのを中断して、もとの弛緩状態に戻って正しい動作のしかたを繰り返す。
もう一つ局部以外の部位に強い緊張があって、目指す部位の動作に必要な力が入らないものがある。例えば、首のときは肩に、手や肘のとき肩に、股のときは腰に、脚のときは股に等というように、その肢と関連する側の、より身体の中心に近い部位に力が入っていることがある。このようなときは、他の部位の弛緩をした後に、力の入らなかった部位の動作をしながら、「いま肩に力が入りましたよ」とか、「こんどは足に力が入っていますよ」というように、誤った力が入っていることを言葉や身体を通して伝え、「こんどはうまく力が入っていますよ」とか「そう、そう」とかの言葉で正しい動作を強化してやる。また、力の入っている部位に軽く触れてやるとかちょっと叩いてやると自分で気がついて力を抜くものもある。
このようにしてもまだ力の入らない部位があるときは、その局部のみの動作の改善に努力を払わず、もっと全身的、とくに身体の中心の部位である肩、躯幹、腰などの弛緩に心がけ、局部への力の入れ方の変化を待った方がよいようである。
(4)動きが途中で止まったり、方向が違ったりするとき
動きにともなって誤った力が入り動作が途中で止まってしまったり、途中から思った方向とは別の方向に動いて、意図した動作とは違った動作になってしまうことがある。そのときは正しく動かすことができたところで動作ををとめて、動きにくいところや違った方向に動きはじめた箇所は、(2)の手法にしたがって、動かそうとする方向とは逆方向から抵抗を与え、そこを弛緩訓練の手続きにしたがって力を緩めてから、正しい方向に動かす訓練をする。正しい方向に力が入ったときには、「そうそう」などの言葉で正しい反応を強化する。
(5)他の部位に不当な緊張が入り、動かそうとする部位の動作を妨害しているとき
動きの練習を続けると、弛緩訓練では現れなかった不当な緊張が、他の部位に出現することがある。例えば、首の部位を動かす練習をしているのに、肩に力が入ってくることがあって、いくら首をうまく動かそうと思ってもできないことがある。このように他部の不当な緊張が局部の動作の遂行の妨害をしている。目指す部位に誤った方向に力を入れさせたり、まったく力が入らない状態にしてしまうのである。誤った動作には、このように他の部位に不当な緊張が入り、動かそうとする部位の動作を妨害していることが多くみうけられる。
これには他の部位の緊張を他動的に抑制して、緊張しにくい肢位に保持してやることである。またこれは、目指す部位と他の部位との動きのための緊張と弛緩とを、自身で制御することが不可能であることから、思っている部位の意図的緊張を強化するとともに、弛緩訓練を再度行って、他の部位の随伴緊張を制御する方法を学ぶことになる。
(6)他の部位の緊張をとる補助方法
動きはじめても他の部位の緊張がひどくて、これが局部の動作に誤った力を入れさせることになる。局部にまったく有効な力が入らないで、動作が現れないようにしているので、他の部位での緊張を排除するように改めて弛緩訓練が求められる。他の部位の緊張がとれ、局部にうまく力が入って思った動作ができはじめても、他部にまた誤った力が入ってくることがある。この段階では他部を他動的に弛緩させなくても、他部に軽く触れているだけの援助で弛緩できるものである。例えば、腕を動かす動作のときに、他部である肩に手をおいてやるとか手掌で軽くポンポンと叩いてやるだけで肩の力が抜けるようになる。
さらにもう少し上達すると「ほら、肩が挙がってきましたよ」とか「足首に力が入っていますよ」というように、言葉で指示してやるだけで、子どもはその部位の弛緩の要領が分かっているので、すぐ力を抜けるようになる。このように他部の緊張をとる補助のしかたは、他動抵抗の与え方と同様に子どもの動きや緊張に応じて、最初は他動的に強く与えていた力を次第に弱めてゆき、軽く触れるくらいにする。子どもはそうされると、余計に局部のみに注意を集中して、目指す動作の過程を意図的に調整して、ゆっくりしかも確実に動かす努力が可能になってゆく。
(7)動作過程の習慣化・自動化へ
意図した方向に動かすことが出来るようになったのは、他部に不当な力が入らないで、局部に必要最小限度の力ではあるが有効な方向に入れられるようになった結果である。動かすことがうまくできはじめた子どもはどちらの方向に、どこまで、どのように動かそうと意図して動かしているので、動作の過程では力の配分のしかたを考え、調整していく必要がある。動きははじめが分からなかったのが今では必要に応じて動作の方向が分かり、有効な方向へ力を入れることができるのである。動作が始まると有効な方向へ力を入れることが維持できるし、また途中で止まったり、方向の違えたろところでは局部に力が入りすぎたりしないようにスムーズに力を配合し調整している。このようにして意図したような身体運動の遂行が獲得されると、子どもは強く意図し、努力しないでも、思ったような動作が習慣化され自動的にできるようになっていくものである。動かすことへの意欲ばかりでなく、動きに対して積極的・能動的になり、その効果は他の諸活動にまで及んでいくようになる。
臨床動作法3
今回は【肢体不自由動作法】の中から、リラクセイション治療訓練法 をご紹介します。
なお、『臨床動作法の理論と治療』の目次は”臨床動作法2”をご覧ください。
【肢体不自由動作法】
3.リラクセイション治療訓練法
(1)催眠によるリラクセイション
リラクセイションの方法としては、禅やヨガなどの東洋医学的アプローチをはじめ、薬物や脳手術などの医学的方法、漸進弛緩法、自立訓練法など、古来から多くの方法が工夫されてきた。しかしながら、肢体不自由児に適用できる範囲は極めて限られたものがあり、その適用の是非を含めた検討によって、催眠法の適用による効果が注目を引いた。覚醒中は困難であった脳性マヒ児の動作が、催眠中に変容し、手が動いたり、立つことができたり、動かない足が動き、歩行が可能になる事例も見られた。こうした変化の基礎は、慢性緊張や過度緊張、随伴緊張のような不当緊張の除去・軽減によることが推論されるが、実際に筋活動を指標とした一連の研究で、不当な筋緊張が催眠手続きを適用することによって劇的に消失することが明らかにされた。
ところが、催眠は、どの障害児・者に対しても効果的適用が可能かというと、障害の種類や程度、精神発達のレベル、コミュニケーションの可能性など、種々の制約があり、そのままの形では限界を指摘せざるを得なかった。しかし、催眠の繰り返し効果の検討や追跡的事例研究などによって、脳性マヒ児自身がある種の気付きに基づく自己調整の仕方を獲得した場合には、その効果が持続することがわかった。この自己弛緩をもたらすために開発された動作訓練の技法を次に述べる。
(2)リラクセイションの基本的手続き
リラクセイションの課題は「自分で自分の緊張に気付き、その緊張を自分で緩めること」である。そのためには、「意図した身体部位で弛緩した感じがわかる」とか、「入っている力を抜く」「力を入れないでいられる」などの不当緊張を制御する手続きが必要である。また、日常の生活動作にも役立つように訓練を進めていくためには、「意図した部位に力を入れても、それ以外の部位には力を入れていないでいられる」という差動弛緩ができるように援助することが重要である。
そのための基本的手続きは、次の通りである。まず、緊張がなるべく少ない状態にした状態、すなわち仰臥位から訓練を始める。ある程度、自己弛緩できるようになった段階で、坐位(あぐら坐位、又は楽坐)、膝立ち、片膝立ち、立位、歩行などの条件下で弛緩できるようにする。弛緩が進んだ部位には、その部位に関する単位動作に関する訓練を導入し、正しい動きを実現する過程で、一層自己弛緩能力を高めていく。
このリラクセイションの訓練は不当緊張が存在する主要な身体部位に適用する。訓練時間は、普通1時間を単位とし、条件の許す範囲で繰り返し行い、自己弛緩機能が形成されるまで繰り返し行う。1時間の訓練時間が確保できなければ、許される範囲で必要な訓練を行うことも可能である。リラクセイションの基本的手続きは次の通りである。
①他動弛緩
訓練者は、被訓練者の不当緊張が存在する関節部位に、その部位を少しずつ動かすように他動的な緊張を与え、そこに発生したより高い緊張を自己解消し、消去するように援助する。効果的な援助を行うためには、緊張の種類や程度を把握するとともに、訓練者の働きかけによって被訓練者がどのように対応するかということを心得ておく必要がある。他動的援助によって被訓練者に緊張の高まりが生じたときには、訓練者はその状態を保持したままで、被訓練者が自己努力で緊張の高まりを制御するのを待つ。緊張の高まりが解消されれば、さらにその部位を他動的に動かしていき、次の緊張の高まりに備える。この訓練者と被訓練者の間の一定の「やりとり」によって、緊張と弛緩を繰り返し体験しながら、自己弛緩ができるようになる。
②追随弛緩
訓練者は、被訓練者に他動的に関節運動させながら、その動きに追随させることによって弛緩させる。不当緊張のため、身体を動かそうとしても、動かす部位が分からなかったり、動かすことができたとしても、誤った動きになる。そのような場合、訓練者が被訓練者の当該部位に手で接触しながら、あるいは軽く持ったりしてゆっくり先導すると、比較的容易に不当緊張を引き起こすことなく、正しく動かすことができる。
③自己弛緩
訓練は他動弛緩から追随弛緩の段階をとるが、いずれの段階においても、自己努力で弛緩を実現するという能動的弛緩を目指すことが大切である。不当緊張の高まりを制御しながら、動きに必要な緊張を残して適切な緊張パターンに変換する過程で、自分で弛緩している感じがわかり、自分で弛緩できるという能動弛緩へと移行する。
(3)リラクセイションの方法
リラクセイションの基本手続きを肢体不自由児・者に適用し、自己弛緩の実現を目指すが、その手順は、弛緩させることによって動きを引き出す方法と重力に対応させる姿勢(坐位姿勢等)を取りながら弛緩を体得させるものとに大別できる。一般に、前者の方が弛緩の状態を作り、自己弛緩できるように援助することは比較的に容易であり、弛緩と緊張の違いや自己弛緩していく感じを味わうのに適した方法と言える。しかし、その条件で自己弛緩を達成できたとしても、応重力姿勢では再度不当緊張が出現することもしばしばである。なぜなら、仰臥位での緊張体系と応重力姿勢で自己弛緩できるようになることも重要であり、それによって心身の調和的基盤を培ったり、弛緩の感じや自分で弛緩する体験を活かした自己制御機能の確立のために役立つと言える。また、そうして獲得された機能が日常生活動作に対しても好影響を与えるので、動作困難な障害児に広く効果的に利用できる。それらの具体的方法は以下の通りである。
①リラクセイションの基礎技法
伸展仰臥のゆるめ
首のゆるめ
肩まげのゆるめ・肩反らしのゆるめ
胸反らせのゆるめ・胸まげのゆるめ
背反らせのゆるめ・背まげのゆるめ
躯幹ひねりのゆるめ
腰伸ばしのゆるめ・腰反らせのゆるめ
股伸ばしのゆるめ・股開きのゆるめ(深まげ・浅まげ)・股外回しのゆるめ・股内回しのゆるめ
手首反らしのゆるめ・手首まげのゆるめ・手握りのゆるめ・手伸ばしのゆるめ
足首まげのゆるめ・足首伸ばしのゆるめ
仰臥位でのリラクセイションに関する主な項目は以上の通りである。一般に、弛緩が必要とされる項目について頭部の方から下部の方へ、あるいは躯幹部から末端部の方へ進めて行くのが一応の原則となっている。訓練の実施にあたっては、他の臨床面接と同じように受理面接の過程で、主訴病歴、発達経過、動作や姿勢の特徴・不当緊張の状態(仰臥位・坐位・立位等)などを把握し、援助方針やその計画をあらかじめ設定することが必要である。訓練開始の際には、まず仰臥位姿勢を取らせて身体全体の調整を図りながら、緊張部位を確認し、同時にその状態でできるだけ弛緩できるように援助する。
躯幹ひねりのゆるめ方の例が図1に示されている。
図のように、訓練者は自分の手足を使って、被訓練者を側臥位にさせ、腰部が床に垂直になるように援助する。腰部以下が動かないように支えて、訓練者は、被訓練者の肩部を片方の掌で押さえ、少しずつ他動的に力を加えながら、被訓練者がその都度緊張を緩めていくのを確かめながら、肩がある程度床に着くまで(可能な範囲で)、弛緩のための援助をする。この場合、動かしていく過程で、緊張が発生したら、すぐに動かすのを止め、「はい、力を抜いて」と声かけしたり、緊張が解消するのを待ったりする。自己努力により緊張を制御できそうな状態が感じられたときに、「そうそう、その調子」と励ましたりしながら、被訓練者が十分に弛緩できるように「やりとり」を続ける。参考までに、胸まげ(図2)、胸反らせ(図3)の例を示す。
②応重力姿勢でのリラクセイションの技法
意図と身体運動を一致させるように努力の仕方を変えるためには、必要な部位を緊張させ、不必要な部位を弛緩させるという差動弛緩を実現しなければならない。これは仰臥位における自己弛緩だけでは不十分であり、坐位や膝立ち、立位等の応重力姿勢での訓練を必要とする。基本的には、先の訓練で自己弛緩が可能な状態になっているために、適切に援助さえすれば、応重力姿勢を取ることは可能である。そのことを確かめるためには、あぐら坐位や膝立ち姿勢で、身体を他動的に屈方向に動かしたり、反方向に動かしたりして、その被訓練者の動き方を見るとよい。被訓練者が、訓練者を信頼して、訓練者の意図に合わせるように、姿勢を変えたり、身体を動かしていれば、準備状態が整ったと見なすことができる。そうでない場合には、応重力姿勢時に発生する不当緊張の処理をしなければならない。そのためには、①で述べた基礎技法の中で、胸反らせのゆるめ・胸まげのゆるめ・背反らせのゆるめ・背まげのゆるめ・腰伸ばしのゆるめ・腰反らせのゆるめ等の中から必要な訓練を選択し、再度実施する。また、脳性マヒ児は、股関節部では屈方向の、腰部では反方向にそれぞれ強固な慢性緊張を有していることが多いため、基礎技法の腰伸ばしのyるめ・腰反らせのゆるめは重要な訓練であるが、この腰伸ばしゆるめを両膝を床につけた姿勢で行い、肩、背、腰、膝まで、直の姿勢になれるように、弛緩訓練を実施する。
そうした準備条件を整えた段階で、あぐら坐位を取らせ、まっすぐになるように形作りをする(図4)。
被訓練者は上体を反らせたり、まげたりするので、そうした誤った姿勢にならないように留意しながら、まっすぐ垂直方向に入力できるような援助をする。尻を後ろに突き出し、腰を反らせた状態であれば、それらの部位の緊張を低減させるように援助しながら、真の姿勢を作る。緊張の高まりが見られた場合には、形作りのために動かしている他動的援助を停止し、緊張がやわらぐのを待つ。こうしたやりとりをしながら、最終的には、大地にしっかり体重をかけ、上体をまっすぐに保持でき、身体を左右や前後に動かしても、安定できるようにする。その段階になれば、適切な自己弛緩が可能になったことを意味し、上体の動きだけでなく、認知等の精神発達も活発になり、環境への対応能力も向上する。さらに、膝立ちや立位等の訓練を加えることによって、それらの効果をより実りあるものに成長させることが可能であり、脳性マヒ児をはじめとする肢体不自由には欠くことのできない訓練だと言えよう。
付記:リラクセイション訓練票
注)ご説明
2020年4月7日までここに”訓練票”を掲載していましたが、この票は現在使われておらず、「ボディダイナミクス」を使っているとの貴重なご意見を頂きましたので、削除させて頂きました。
一方、”動作法・ボディダイナミクス”で検索してみたところ、下記の本がヒットしましたので、ご参考でご紹介させて頂きます。
臨床動作法2
前回は「基礎から学ぶ動作訓練」の中から“動作法ってなに? -動作法がはじめての方へ-”をご紹介させて頂きましたが、この中で遠矢浩一先生が推奨されていた本が今回の「臨床動作法の理論と治療」です。なお、遠矢先生は次のようにご紹介されていました。
『現代のエスプリ別冊「臨床動作法の理論と治療(三巻シリーズ第一巻)に掲載されている「臨床動作法の起源と適用」です。ここには、動作法が生み出されてきた経緯について、成瀬悟策先生、大野清志先生、鶴光代先生が対談された逐語録が記されています。これを読んでいただければ一番ですが、ここでは、まず、私なりに熟読して動作法が生み出されるまでの歴史について簡単にまとめてみようと思います。』
この“臨床動作法の起源と適用”は「臨床動作法の理論と治療」の冒頭の座談会のタイトルということになります。

編集:成瀬悟策
出版:至文堂
発行:1992年10月
下記は表紙裏面の上部に書かれている文章です。
『臨床動作法は、ひとのこころの活動と生きる体験をより豊かに生き生きとしたものにさせるための方法である。動作は、「自分が自分のからだに働きかけ、意図どおりの身体運動を実現しようと努力する自己の活動の過程」であり、そこには、生きて今ここにある自己の存在と活動の仕方が展開している。動作による望ましい努力の仕方の体得は、ひとの体験様式と生き方を新たなものへと変えていくのである。この巻では、動作者と援助者を含む、臨床動作法の原理と構造、動作治療訓練の諸法、心理療法としての動作法を展開する。』
目次
座談会/臨床動作法の起源と適用 大野清志、鶴光代、成瀬悟策(司会)
■動作法の由来 -脳性マヒ児との出会い
■病院の「機能訓練」
■催眠法による取組み
■動作測定や催眠訓練をテレビ放映
■医療の側の反応
■脳性マヒ児の訓練キャンプ
■心理リハビリティション
■機能訓練と動作訓練の論争
■教師が「養護・訓練」を -文部省指導要領の改訂
■動作訓練キャンプの初期
■自閉症児に適応
■分裂病への挑戦 -姿勢を直す
■ノイローゼの治療
■自己軸世界の成立
【臨床動作法】
心理療法における体験治療論
・はじめに
・体験に関する心理療法
・体験の対象と内容の仕方
・来談者の『仕方』への臨床的かかわり
・体験治療論的方法の効果について
臨床動作法の心理構造
・動作法概説
・臨床動作法
・動作法による治療的体験の諸相
動作法におけるコミュニケーション -コミュニケーションの視点から動作法を考える
・コミュニケーションとしての動作
・メッセージおよび媒体としての動作
・トレイニーにとっての動作法のコミュニケーション
・トレイナーにとっての動作法のコミュニケーション
【肢体不自由動作法】
肢体不自由児・者の臨床的問題 -治療訓練の原理
・はじめに
・脳性マヒ児・者の動作
・動作訓練
・課題動作
・訓練関係
・臨床的問題
・おわりに
リラクセイション治療訓練法
・肢体不自由
・脳性マヒの特徴とその対応
・リラクセイション治療訓練法
・自己制御とリラクセイション治療訓練法
単位動作治療訓練法
・単位動作
・単位動作の内容
・動作学習における単位動作の意義
・単位動作の目的
・単位動作による訓練
タテ系動作治療訓練法
・はじめに
・タテ系訓練の考え方
・タテ系訓練の方法
歩行動作治療訓練法
・はじめに
・足の置きかた
・足で大地を踏み締めて立つ
・片足で踏み締める
・踏み出し
・歩行
【治療動作法】
心理療法における身体的アプローチ
・はじめに
・身体的アプローチのアプローチ
・心理療法にさりげなく身体的アプローチが取り入れられているアプローチ
・身体プロセスと精神療法とを並行して、または同等に扱うアプローチ
・身体プロセスの変容を主に目的とした方法
・まとめ
治療動作法(動作療法)の心理治療原理
・治療動作法(動作療法)
・心理治療としての体験原理
・治療動作法における体験原理
現代人とイメージと身体
・現代社会の特徴
・競争という病
・映像の氾濫 -実感の乏しさ
・押しつけられたファンタジー
・きっちりしないとやっていけない
・強迫パーソナリティ、アレキシシミア、タイプA
・ファンタジーに乏しい
・からだと切り離された自己
・突然死と過労死
・コモン・センス -共通感覚
・体性感覚の回復
・イメージとしての身体
・リアリティとしての身体
家族療法と動作法
・はじめに
・家族療法と動作法の接点
・相互作用の重視
・全体と部分
・抵抗の活用
・チーム・アプローチ
・治療記録の重視
・家族動作法の可能性
カウンセリングと動作法
・はじめに
・ケース
・メタファーを越えて
神経症者への動作療法
・はじめに
・動作課題の設定
・治療過程
・おわりに -適応の努力の表われとしての動作
精神病者への動作療法
・動作療法の特徴
・動作療法の進め方 -見当づけの実際
・動作療法でみられる変化・効果
【ケース研究】
過呼吸症候群への適用
・はじめに
・症例
・考察
強迫神経症者 -強迫神経症者に対する動作法
・はじめに
・事例報告
・第一期
・日常生活の様子
・第二期
・日常生活の様子
・第三期
・考察
動作法による書痙の治療例
・運動性神経症
・なぜ書痙に動作法なのか
・本事例の背景
・書字動作の訓練と評価
・心理的問題の発生と処理
・書字動作の改善だけで良いのか
心身症者
・はじめに
・ケースの概要
・面接経過
・考察
・おわりに
慢性分裂患者のケース
・はじめに
・ケース経過
・おわりに
神経症性うつ病者へ -自己への対面と自己の限界への気づき
・はじめに
・事例
・考察
神経疾患を疑われた歩行不能者
・はじめに
・ケース
・考察
精神分裂病の患者に対する動作法の適用
・はじめに
・精神分裂病と姿勢・動作について
・動作法の実際
・おわりに
失語症者へのスピーチセラピー
・はじめに
・事例
・考察
他技法との併用
・事例
・初回面接で話し合った解決のための方針
・面接の進め方と練習プログラム
・練習経過と症状の変化
・考察
ブログは【臨床動作法】の一部と、【肢体不自由動作法】からになります(目次の中の黒字部分)。
●臨床動作法2:【臨床動作法】動作法におけるコミュニケーション -コミュニケーションの視点から動作法を考える/【肢体不自由動作法】肢体不自由児・者の臨床的問題 -治療訓練の原理
●臨床動作法3:【肢体不自由動作法】リラクセイション治療訓練法
●臨床動作法4:【肢体不自由動作法】単位動作治療訓練法
●臨床動作法5:【肢体不自由動作法】タテ系動作治療訓練法
●臨床動作法6:【肢体不自由動作法】歩行動作治療訓練法
【臨床動作法】
動作法におけるコミュニケーション -コミュニケーションの視点から動作法を考える
1.コミュニケーションとしての動作
脳性マヒ児の動作不自由の改善方法として提唱された動作法は、現在では脳性マヒ児をはじめ自閉症、重度重複障害児等の発達援助、そして心身症のクライアントや精神障害者の心理療法にと、訓練・治療法として幅広く用いられている。動作法はトレイナー(治療者)とトレイニー(クライアント)とが互いの体に直接に触れ、両者の動作を使って訓練あるいは治療を行う技法である。動作法ではトレイナーとトレイニーの間に動作によるコミュニケーション-動作コミュニケーション-が交わされる。そこで、本稿では動作法の中でも障害児に用いられている訓練を中心として、動作コミュニケーションの果たしている役割を明らかにしたい。
コミュニケーションには四つの要素がある。それは①情報を伝える送信者(誰が)、②その情報を受け取る受信者(誰に)、③伝達されるメッセージ(何を)、そして④メッセージを搬送する媒体(どのようにして、伝達手段は何か)である。動作法のコミュニケーションではこの四要素は次のようになる。すなわち、①、②トレイナーとトレイニーは送信者、受信者の両方の役割を演じている。③メッセージは「正しい動作」を作るためにトレイナーが伝える課題としての動作と、それに対するトレイニーの反応としての動作である。④メッセージの媒体としてトレイナー自身の体の動き-動作-とトレイニーの体の動き-動作-が用いられている。
ここで脳性マヒ児の「膝立ち」訓練を例に、動作法のコミュニケーションを説明してみよう(図1参照)

画像出典:「臨床動作法の理論と治療」
トレイナーはまず送信者としてとトレイニーに対し動作課題のメッセージ(「上体をまっすぐに立てて、腰を前に動かしてみよう」)を伝える。言葉をかけることもあるが、主要な媒体はとトレイニーを支えるトレイナーの手や足の動きである。課題を受信したトレイニーの多くは、はじめ尻(腰)を後ろに残したまま、胸だけを前に出し、背中を反らせるという動きをする。トレイニーはこの動作で「私は体を前に動かしたいのだけれど、どうしたらいいか分からない。倒れそうで恐い。」というメッセージを発していると言える。トレイナーはこのメッセージを受信し、今度は「私が支えているから、このあたりをこの方向に動かしてみよう。」というメッセージをやはりトレイニーの体に触れたトレイナー自身の手や足の動きで送り返すのである。
4.トレイナーにとっての動作法のコミュニケーション
動作法で用いられている動作コミュニケーションは、トレイニーの側ではトレイナーが呈示する訓練課題を受取り易い、すなわちトレイナーの側からは訓練課題を伝え易いコミュニケーションであるといえる。ここではトレイナーの側から見た動作コミュニケーションをもう少し詳しく検討することにしよう。
二宮は長期(四年三月)の動作法による訓練を伝い、一見目立った変化がないように見える重度障害児の事例を報告している。トレイニーは訓練後も一見目立った変化がない(一人で座れない、頸もしっかり座らず、寝返りもできない等)ように見えた。しかし、二宮は、トレイニーがトレイナーの僅かな支えで座れるようになったこと、トレイニーがトレイナーの援助の中で少しずつではあるが発達していることを確認した。トレイニーの目立たない発達にトレイナーが気づいたのは、トレイナーが訓練課題の呈示および姿勢の支持を、言葉や器具などを使って行うのではなく、トレイニーに直接触れてトレイナー自身の動作で行っているためであろう。動作コミュニケーションを用いる動作法はトレイナーがトレイニーの発達上の変化を見つけやすい方法である。
山内は、「遠くから見ているうちは『寝たきり』と思っていたトレイニーに座位訓練を行うと、このトレイニーが頸をあげよう、腰を動かそうと努力しているのが分かります。」と述べて、動作法を行うトレイナーはトレイニーに対する動作援助を行う中でトレイニーへの理解が進むと言っている。トレイニーの発達とトレイナーの援助との関係も図2のように考えられる。

画像出典:「臨床動作法の理論と治療」
一般に障害児の動作を外から見ているだけ(訓練前)のトレイナーは領域Bを認識することができずに、動作可能な範囲を狭く評価しがちである。これに対し、動作法でトレイニーに動作援助をしているトレイナーはトレイニーの動きを単に調べるのではなく、トレイニーに正しい動作をするための援助をするので、動作をしようとする意欲の存在やトレイナーの援助があれば動かせるところを見出すことができるのである。そして、領域Bの動作は訓練によりトレイニーが一人でできる動作になり、領域Aが拡大される。トレイナーはトレイニーの援助をすることによってトレイニーを理解するのである。
ところで、動作法の動作コミュニケーションが効果的に行われるかどうかはトレイナーの熟練度と相関があると思われる。例えば、動作法を行うときに初心者トレイナーはトレイニーの動作の一部だけに注目してトレイニーの状態を誤って判断してしまうことがある。始めに述べた「膝立ち」の例では、トレイニーが「胸を前に出し、腰を後ろに引いている」とき、初心者トレイナーは胸が前に出ているところだけに目が奪われ「正しい動作をしている」と誤って認知することがある。反対に腰を引いているところにだけ注目して「課題を行おうとする意欲が無い」と判断してしまい、トレイニーの不安や動かし方が分からないことについての正しい理解ができていないこともある。
田中は熟練したトレイニーとの間にとるコミュニケーションの違いを検討した。その結果、熟練者は初心者に比べトレイニーとの双方向的コミュニケーションを量的に多く成立させていることが分かった。また、熟練者はトレイニーが持っている固有の誤動作パターンの抑制、正動作促進、支持・補助の変更・修正等の援助行為の出現頻度が多かった。これらの結果から、トレイナーが熟練するにつれてトレイニーとのコミュニケーション構造は一方的から双方的になり、熟練者はトレイニーの状況に合わせた援助行為を行うようになると考えられる。
動作法においては動作はメッセージであり、媒体でもある。我々は一般的に言語コミュニケーションについては「話し方」「聞き方」「書き方」という教育・訓練を受ける機会が多いが、動作コミュニケーションについては訓練の機会が少ない。そのために動作をメッセージや媒体として使う方法を十分には獲得していないことが多い。従って、動作法ではトレイナーはスーパーバイザーの指導のもとに研修を重ねて動作コミュニケーションを学ぶ必要がある。それによって、トレイナーは適切なメッセージを送ったり、トレイニーの発するメッセージを正しく受け取ったりすることができるようになる。
動作法を指導するスーパーバイザーはトレイナーのトレイニーとの相互作用のプランニング、モニタリング、評価等を援助する。このスーパービジョンにおける動作コミュニケーションの指導の過程については別の機会に述べたいと思う。
【肢体不自由動作法】
肢体不自由児・者の臨床的問題 -治療訓練の原理
1.脳性マヒ児・者の動作
脳性マヒは、出生前後に生じた脳損傷のために筋・運動系のコントロールの障害は、具体的には、座る、立つ、歩くといった姿勢制御や、書字、物を掴むといった手指の機能の障害に現われる。成瀬は、脳性マヒ児・者の筋・運動系のコントロールに心理学的要因がいかに関与するか、この障害の改善に心理学がどのような貢献をするか、を解明することによって、それまでの我が国の心理学があたかも意識的に避けてきた感のある「ヒトの運動」の問題を考察することを試みた。
その端的な発想は、「動作」という概念である。この「動作」は、自分の意図通りに身体運動を実現していく努力の過程と定義されるが、これを動作図式で示すと図1のようになる。
この図では、<意図>によって生起した自分の身体を動かそうとする<努力>を、<運動中枢>に働きかけ、結果として、<身体運動>を生じさせるというモデルであり、このプロセスを「動作」と呼ぶ。すなわち、左の回路は動作過程であり、右の回路は身体運動の生じる生理的過程とされる。
脳性マヒ児・者は、基本的には、筋・骨格系に欠陥があるのではなく、動作過程に困難を生じ、いわゆる、身体は動くが思い通りには動かせないところに本質的な問題の所在がある。すなわち、動作過程の中で<努力>の仕方が不適切なため、身体運動として生起させることが困難であるとされる。
整形外科学が筋・骨格系を、神経生理学が脳・神経系を問題にすることに比べ、臨床動作法では、心理的過程である「動作」を問題とし、脳性マヒ児・者の身体を動かす主体の制御活動に焦点をあて、動作<努力>への援助を訓練の基本とした。そのため、脳性マヒ児・者をはじめとする肢体不自由者へのアプローチは、動作訓練と称されている。
2.動作訓練
脳性マヒ児・者の動作困難を形成している主たる原因は、身体の各部位に生じる不当な筋緊張とされる。この不当な筋緊張は、脱臼や各関節の拘縮を引き起こし、更に側彎等の姿勢の歪みを生むことになる。この不当な筋緊張に対し、動作訓練が初期に重視したのは、リラクセイションという技法であった。しかし、ここで用いるリラクセイションは、身体の力が抜ければ良いという発想ではなかった。先の動作図式からすれば、自分で自分の身体の力を抜くという<努力>のプロセスが最優先され、例えば、他者に身体を揺さぶられる、他者が他動的に関節を屈伸するというように、主体が関与せずに身体の力が抜けても、それはリラクセイションとは呼べない。あくまで、他者の援助を受けながらも自分で力を抜くという<努力>のプロセスを介在させることが、動作の獲得の第一歩である。また、このリラクセイションは、自分の身体の緊張した部位に注意をあてさせるという役割をもち、脳性マヒ児・者のようにボディ・イメージの確立が困難であっても、身体への気づきを焦点化させることに非常に効果があった。
しかし、リラクセイションは、あくまで身体を動かすという「動かし方」が分かるための方策であり、その目的は、「動かす」ための「努力の仕方」が分かることであり、それが、具体的な姿勢・動作の獲得、改善へ繋がることが大切である。
3.課題動作
リラクセイションという技法に加え、「タテ系」という発想が強調され始めたのは、1980年代の後半であった。姿勢・動作の獲得、改善のためには、力を抜いておかねばならない身体部位と同時に、力を入れておかねばならない身体部位を明確化することが重要である。一定の姿勢を保持するためには、関節を屈げ、伸ばし等が必要になってくるが、抗重力姿勢の中での屈げ、伸ばしという動作は、地面に接している身体の部位を起点に、「踏みしめる」、「踏み付ける」という動作が可能でない限り用をなさない。例えば、あぐら座位では、躯幹を伸ばす方向へ力を入れるためには、地面に着いている尻で踏みしめる、膝立ち位では、膝で踏みしめ、大腿部に力を入れる、立位では、足の裏で踏みつけ、膝や股関節を伸ばすという動作を行う。こうした、力を入れる方向や大きさを明確化することによって、タテ系動作訓練は、あぐら座位、膝立ち位、片膝立ち位、立位での動作課題を微細化していった。
脳性マヒを含む肢体不自由児・者の障害は、運動発達上の大きな節目である座位、膝立ち、立位、歩行等にあるがタテ系動作訓練では、これらの動作の獲得、改善を重要な課題として、そのための理論、技法を初期の動作訓練の経験を踏まえて発展させてきた。それによって、訓練内容は、高度化、緻密化され、技法の上では「誰にでもすぐに出来る」という安易なものではなくなっている。
臨床動作法1
「脳性まひ児の発達支援」という本からスタートした、脳性まひ児への施術のための自己学習も、終盤を迎え、締めくくりは以前から注目していた動作法について勉強することにしました。なお、動作法については、2016年12月に“動作法について”、翌月2017年1月に“動作法(姿勢の不思議)”というブログをアップしていますが、これらは動作法の表面に触れた程度であり、理解ということからは程遠いものでした。そこで、特に動作法の理論や実践という点を詳しく知りたいと思い、3つの本を選びました。
●「基礎から学ぶ動作訓練」
●「臨床動作法の理論と治療」
●「動作訓練の理論 脳性マヒ児のために」
3番目の「動作訓練の理論 脳性マヒ児のために」は成瀬先生が作られた各訓練段階の【動作訓練票】をご紹介しているだけですので、ブログとしては「基礎から学ぶ動作訓練」と「臨床動作法の理論と治療」からとなります。
なお、動作法は正式には臨床動作法と呼ばれています。そして臨床動作法は1976年に発足した「日本リハビリティション心理学会」さまによって大きく発展してきました。

会則の第2章、第3条に目的が明記されています。
『第3条 本会はリハビリテイション心理学及びこれに基づく学術の発展を図り、教育、福祉、文化の向上に寄与すると共に、合わせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。』

「基礎から学ぶ動作訓練」のはしがきを拝見すると、この本の内容は今までに発行された『ふぇにっくす』(1971年創刊)という冊子に掲載された論文や解説の中から再録されたものとなっています。
左は最新版とされている75号の表紙です。
ブログは第一章 動作法の基礎知識の中の、動作法ってなに? -動作法が初めての方へ- の部分を書き写したものになります。
目次
はしがき
第一章 動作法の基礎知識
動作法ってなに? -動作法が初めての方へ-
形を整える -「おまかせ脱力」と「形づくり」-
「おまかせ脱力」「形づくり」「魂を入れる」
第二章 脳性マヒ児のための動作法
坐位訓練Ⅰ
坐位訓練Ⅱ
膝立ち訓練Ⅰ
膝立ち訓練Ⅱ -膝立ちの姿勢が全く保持できない子の訓練-
膝立ち訓練Ⅲ -タテの姿勢が完全にできていない子の訓練-
片膝立ち訓練
立位訓練Ⅰ
立位訓練Ⅱ
歩行訓練
第三章 様々な障害への動作法の応用
自閉的なこどものための動作法
知的障害児のための動作法
ダウン症児のための動作法
筋ジストロフィ者のための動作法
青年・成人のための動作法 -訓練の意味・あり方・問題点-
障害高齢者のための動作法
登校拒否児及び学校不適応幼児のための動作法
こころを癒す動作法
PTSD(心的外傷後ストレス障害)への動作法
第一章 動作法の基礎知識
動作法ってなに? -動作法が初めての方へ-
最近、「動作法と動作訓練は、同じ訓練ですか、違うのですか」といった質問をよく聞きます。動作法で用いられることばには、このほかにも、「努力」「タテ系」「体験」などなど、臨床動作法をはじめて経験されるお母様方や先生方には、意味の分からないことばがたくさんおありのことと思います。訓練技法だけでなく、肢体不自由から精神分裂病にいたるまで広い範囲で適用され、だんだんその考え方が複雑化(洗練?)してきた今、これらの疑問は、出るべくして出てきたといえるでしょう。そこで、今回、これらの用語や技法が生み出されてきた動作法の歴史について触れながら、動作法についての大まかなイメージをつかんでいただければと思い筆をとりました。
さて、歴史といっても私も未だ十年そこそこしか訓練に携わっておりません。動作法三十年の歴史について正しく理解するには、成瀬先生に、じかに伺うのが一番ですが、さて、どうしたものかと悩んでいましたら、この上ない本をみつけました。それは、現代のエスプリ別冊「臨床動作法の理論と治療(三巻シリーズ第一巻)に掲載されている「臨床動作法の起源と適用」です。ここには、動作法が生み出されてきた経緯について、成瀬悟策先生、大野清志先生、鶴光代先生が対談された逐語録が記されています。これを読んでいただければ一番ですが、ここでは、まず、私なりに熟読して動作法が生み出されるまでの歴史について簡単にまとめてみようと思います。
昭和三十三年四月、東京教育大学(現、筑波大学)に、肢体不自由児のための桐ヶ丘養護学校がはじめて作られ、現、大妻女子大学教授、大野清志先生が赴任されました。しかし、大野先生によれば、その当時、肢体不自由児のもつ運動障害に対しては、病院での「機能訓練」と称される訓練しか行われておらず、それは学校教育の対象とはされていませんでした。具体的には、足をしっかり踏めないこどもに対しては、砂袋をつけさせ、その重さで足を地面に押さえつけたり、バネを引っ張って屈がった腕を伸ばすなどが行われていたようです。
そのような状況にあった昭和三十八年、国立身体障害者リハビリティションセンターの小林 茂先生が脳性マヒの二十歳ぐらいの女性に催眠をかけてみたところ、生まれつき屈がっていた五本の指を伸ばせるようになって、ミシンやアイロンがけができるようになったそうです。ここで、催眠について詳しく説明することはできませんが、催眠状態でからだが動いたということは、これまでは、動かし方が分からなかった、あるいは、不適切な動かし方をしていたということができます。
これをきっかけにして成瀬研究室での脳性マヒの研究が始まります。まず、当時、九州大学大学院生であった、現、九州大学教育学部教授、大野博之先生が筋電図を指標にしながら催眠と脳性マヒのからだの動きの関係性について検討しました。その結果、筋電図が大きく振れるほど緊張していた手が、催眠によって筋電図が振れなくなるほど力が抜けてしまったのです。』
さらに、昭和四十一年、成瀬研究室で「催眠法による脳性マヒ者のリハビリティションに関する研究」を行い、催眠で脳性マヒが改善されることが明らかになってきて、よく四十二年、一月四日から八日間の集中訓練を聖ルチア病院で行い、三月後半には現在のキャンプ方式で十日間の訓練を行ったようです。その後、朝日キャンプ、聖ルチアキャンプを重ね、昭和四十七年に福岡県朝倉郡夜須町に「やすらぎ荘」が作られたので、キャンプが定着しました。

「やすらぎ荘」の”ごあいさつ”(理事長メッセージ)の冒頭部分をご紹介します。
『やすらぎ荘は、4月に開所47年を迎えました。多くの方々のご援助とご協力のたまものと感謝しています。
本来、俳優の故・森繁久彌さんたちによって、全国でも例を見ない心身障がい児(者)療育訓練施設として、夜須高原に産声を上げました。以来、脳性まひ児の機能回復訓練と情緒障害児などの療育訓練を中心に活動をしてまいりました。
利用者は、九州はもとより全国から集まります。特に春と夏の動作法研修会には、アジアなど諸外国から研修生が参加します。
年間延べ約6千人の利用者があり、開所からの利用者は3月末で44万余を数えました。同時に、やすらぎ荘はご家族にとっても、お互いの生活を語り合い、励まし合う「やすらぎの場」となっております。』
そうしたなかで、からだの動きの悪さは、脳の障害、病変によって「からだの動かし方」を誤った形で身につけた結果であることが分かってきました。つまり、脳性マヒの動きの問題を心理的な問題として捉えたのです。
昭和四十六年に学習指導要領の改訂で、「養護・訓練」という新領域が設定され、学校の教師が肢体不自由の連動機能の向上のために関わることができるようになりました。そこで、心理学的に人の動きを捉え、人の主体的活動を重視する訓練法の考え方が教育にぴったりであるということで特殊教育の世界に、動作法が定着していったのです。
さて、動作法が脳性マヒ者に対する催眠の適用をきっかけにして生み出されてきたこと、その考え方の基本は、肢体不自由児のもつ運動障害を心理学的問題として捉えること、そしてそのような考え方ゆえ、学校教育の分野に定着してきたことがお分かりいただけたことと思います。では、動作法の具体的な中身はどのようなものなのでしょうか。
現在、動作法は正式には「臨床動作法」とよばれます。簡単にいうとこれは動作を課題にしながら脳性マヒなどの肢体不自由、自閉症、多動、分裂病、高齢者の運動障害など様々な状態の改善のために適用される方法の総称と考えていただいて結構です。大原則は、人の動きというものは、その動きを実現しようとする当人の「努力」によって生み出されているという考え方です。人がある一つの動きを行おうと「意図」し、その動きを達成するための「努力」があって、はじめて「身体運動」が生起するという流れ、この一連の流れを「動作」とよびます。繰り返すようですが、「動作」とは、人の主体的活動の成果であって、主体的活動が伴わない物理的な「運動」(例えば、大人がこどもの足首を強制的に屈げ伸ばしする)とは本質的に異なるものと考えます。もっといえば、たとえ外から見て「運動そのものが見受けられなくても」こどもの主体的な自己活動がそこで展開されていれば、「動作」と考えてよいのです。
つまり、大切なのは動作を遂行しようとする過程で、こどもがどのような「体験」をしているかということです。
「意図」「努力」「身体運動」「動作」と出てきたと思ったら今度は、「体験」かと用語の多さに気持ちが打ち沈んでこられたかもしれませんが、ここが重要なところですので、もうしばらく勘弁してください。例えば、脳性マヒのお子さんの膝の緊張が強くて膝を伸ばす訓練を行っていたとします。この時、そのこどもは、膝を伸ばそうとなんらかの努力をするでしょう。しかし、膝が逆に曲がってしまったりなどの意図と一致しない動きが生み出されるかもしれません。大事なのは、この時、そのこどもがいったいどのような動かし方をし、その時のからだの感じをどのように感じとっていたかということなのです。また、自閉症のお子さんとお母さんがいっしょに、腕を上げていく課題を行っていると、お子さんが伸ばしていた腕を、突然強く曲げたとしましょう。この時大切なのは、腕が曲がったということそのものではなく、腕を上げていくその過程、曲げた時のその瞬間に、お子さんがお母さんとの関わりのなかで、腕の動きをどのように感じ、また、どのように動かそうとしていたのかということなのです。
このように「体験」を重視することは、マン・ツウ・マンで訓練を遂行していく上で重要な意味をもちます。なによりもまず、こどもの体験の仕方に目を向けるということは、必然的に大人(トレーナー)本位の強制的訓練を排除します。いろいろな訓練法や指導法が存在する現在、例えば脳性マヒ児の股関節がかたく、伸ばせない状態のとき、こどもが泣こうがわめこうが、必要だからガンガン弛緩訓練を押し進めるやり方を少なからず耳にします。これは、こどもの股関節が弛むという物理的な現象しか目標としていない訓練のしかたです。股関節が「弛む」ことではなく、こども自身が股関節を「弛める」ことを目標にすれば、当然の結果として、トレーナーは、こども自身が「どのように股関節を弛めようとしているのか」とか「どんな時に力を入れてしまうのか」などといったことどもの努力の仕方に注目するでしょう。これこそがこどもの「体験」を重視した訓練なのです。
そうすることによってさらに、動作の過程におけるこどもの心の活動のあり方をみるだけでなく、動きからこどもの心の活動状態を予測するようなトレーナー側の視点とか態度とかいったものが生まれてきます。例えば、私たち大人でも、偉い人の前に立って心が緊張している時には肩に力が入ったり、手をもじもじさせたり、下を向いてしまったりするでしょう。まさしく、心の活動状態がからだの動きとして現れてしまった好例です。トレーナーが、こどもの示す動きからこのような心の状態を理解しようとする構えが培われることも「体験」を重視することからもたらされるのです。
さて、ここまでで、動作法では「体験」が非常に大切にされることが分かりました。では、いったいどのように「体験」を重視した訓練が展開されていくのでしょうか。
先ほど、臨床動作法とは、動作を用いて様々な症状改善のために用いられる方法の総称であることを述べました。しかしながら、歴史の部分でもお分かりのように、臨床動作法は脳性マヒ児を中心とする肢体不自由に対して適用されたところから現在の発展をみてきました。そこで、脳性マヒ児に対する動作法についてみてみましょう。
繰り返しになりますが、動作法では脳性マヒ児の「からだが動かない」ことは、筋や骨格、あるいは神経系などの生理的欠陥によるものとはみません。「意図」-「努力」-「身体運動」の図式が示すように、「努力の仕方」が不適切であったり、それをこども自身が分からないためであると考えます。従って、一言でいえば、「先生といっしょに適切な努力の仕方を学習しましょう」ということが脳性マヒ児の動作法であるといえます。決して、「トレーナーが努力する」のではありません。脳性マヒ児のからだは、不適切な力の入れ方のため、しばしば、足首、膝、股関節、体幹部などに強いかたさがみられます。このかたさを弛めようと先生が、せっせと汗水たらして力を入れてもダメなのです。大切なのは、こども自身が課題動作を達成するために、なんらかの「努力」をすることが前提であるということです。からだが訓練によって動かせるようになったとすれば、それは「トレーナーの努力のたまもの」ではなく、「こども自身、適切な努力の仕方が分かった」のであって、トレーナーは「適切な努力のしかたが分かるように上手に援助した」のです。このことを再確認した上で、訓練内容をみてみましょう。
まず、課題動作です。基本的には、坐位、膝立ち、立位、歩行の四つの課題がこどもの状態に応じて選定されます。まだ、お坐りのできないこどもであれば坐位課題から順に歩行まで訓練を進めます。膝立ちはできるけれどうまく立つことができない、という場合などにはいろいろと訓練課題が考えられます。しっかりと足で台地を踏みしめることを練習するなら立位のなかで行われますし、股関節の上手な使い方を練習するなら膝立ちに戻って訓練を進めます。腰周辺の動かし方が充分でなければ坐位まで戻ることもありえます。この説明でおわかりのように、坐位、膝立ち、立位、歩行というのは坐るための訓練、膝立ちするための訓練、立つための訓練などと一義的に捉えられるものではなく、むしろ、個々のこどもにとって必要なからだの部位の動かし方を学習するために選択される最も適切な姿勢と考えた方がよいように思います。
ところで、坐位~歩行の四つの姿勢を心のなかに思い描いてみて下さい。一つとして、からだを横にした姿勢はないことにお気づきでしょう。全ての姿勢が「タテ」なのです。さて、また、新しい用語の登場です。「タテ系」です。
からだをタテることには、どのような意義があるのでしょうか。赤ちゃんは最初、頸も坐らずいつも寝たままにすごします。手の動きや足の動きも未だどことなく反射的で、外界に関わるといっても、目の前にぶら下がっているガラガラなどに触れる程度です。やがて、手に触れたものを握るようになり、口でしゃぶったりして探索活動はより高次なものにはなりますが、やはり、まだ赤ちゃんの世界は与えられた物、身の回りにある物しか活動の対象にはなりえず、そういった意味で、かなり受動的です。
ところが、お坐りができ、はいはいを始め、お誕生日を過ぎる頃に歩き始めるや否やこどもの心の活動は活発化してきます。興味のある対象がある場所に自ら移動して、対象を手にし、なめたり、叩いたり、投げたり、つまんだり、自分なりに調べあげます。外界に積極的・能動的に関わり始めるのです。これがこどもの心の世界に大きな影響を及ぼします。まず、物を立体的に見ることができるようになります。つまり、遠近感が分かるようになってきます。さらに、自分を基準にして物の動きを認識できるようになります。これは、からだをタテて外界に関わることの効果なのです。動作法がタテを重視するのは、このようにタテになる動作系が<ひと>にとって何よりも必要な生き方であると考えるからです。
一つの訓練法においては、訓練の対象となった障害に応じて技法がより良いものに変化して当然です。実は動作法もそのような変化をとげてきました。かつて、訓練の対象となったこどもたちの多くは、からだのかたさを弛めること(リラクセイション)で充分に効果をあげることができ、からだの動きを改善することができました。しかし、だんだんと障害が重度化するにつれ、からだのかたさをとることだけで対応しきれなくなってきました。弛めても立つことはできないし、ましてや、坐ることもできないこどもたちが増えてきたのです。考えてみれば、リラクセイションは、反ったり曲げたりなどの誤動作を修正することが目的です。からだの動かし方については、訓練課程で焦点づけられていないので、学ぶことが難しいはずです。そこで、もう少し、からだの使い方を重視しようということで、「スパイラル方式」と呼ばれる訓練手続きがとられ始めました。
これは、まずはじめに、膝立ちや立位などの、ある課題動作をこどもに行わさせてみて、膝や足首や股関節などのかたさがその動きを妨げているようであれば、かつてのリラクセイションの技法を用いて弛めます。動かしやすくなったところで、からだの使い方訓練にはいります。使い方の学習過程で、未だ、からだのかたさが動きを妨げているようであれば再度弛めます。このように行っては戻り、行っては戻りを繰り返すような手続きだったので、スパイラル方式(らせん式という意味)とよばれました。
確かに、以前と違ってからだの使い方を重視しましたので、力を入れにくい重度のこどもたちに対する訓練効果がみられ始めました。しかし、また、ある事実に気づかされたのです。それは、からだのかたさは、からだの動かし方が適切になるにつれて、みられなくなってくるということです。つまり、誤動作を修正してから正動作を獲得させるのではなく、直接、正動作を獲得させる方法が最も効果的ですし、こども不在・トレーナー中心の力任せの訓練に陥る危険性もないということが明らかになってきたのです。そこで登場したのが、「タテ系動作訓練」です。
それでは、「タテ系動作訓練」について話を深めてみましょう。
まず、手順です。課題は先にも説明しましたように坐位、膝立ち、立位、歩行です。はじめに、形を整えます。坐位なら坐位、膝立ちなら膝立ちと、課題となる動作がうまく行われ、完成した時のからだの形を作らせてあげます。しかし、この姿勢はかなりトレーナー側の他動的援助がなければこどもには行うことができません。なぜなら、まだ、こどもは適切な力の入れ方を学んでいるわけではないからです。
形ができたら、「魂を入れる」です。力の入れ方がまだ分からないこどもに適切な力の入れ方を学ばせる段階です。正式には主動化の段階とよばれます。こども自身が動きをコントロールできるようにするのでこうよばれるのでしょう。トレーナーは、「離すよ、離すよ」と言いながら、支えている他動の手の力を弛めて、こどもの力の入れ様をみます。余計な反りや曲げ動作が出ないように援助しながらこどもが自ら適切な姿勢を保持できるようになるまでやりとりが繰り返されます。
タテに力を入れることができるようになってきたら、三番目は、節・分節づくりです。こどもはまだ、坐位姿勢であれば、腰の部分を自由に折ったり、伸ばしたりすることができません。立位にしても、足首や膝を曲げ伸ばしできないのです。そこで、腰、股関節、膝、足首などの目標となるからだの部分以外はまっすぐにしたまま、その部分だけ曲げ伸ばしできるようにしていきます。
この動きを自ら楽に行うことができるようになったら、前、後、左、右のバランスとりの練習に入ります。からだが傾斜したり、あるいは、外から妨害の力が加えられてもタテの姿勢を保つことができるようにする段階です。
このようにタテ系動作訓練は展開されますが、いくつかの基本要領があります。
また、新しい用語の登場ですが、「①-③の原理」です。動作法では、頸を①、肩胛帯(肩甲骨+鎖骨)を②、胸を③、背中を④、腰を⑤、股を⑥というように番号でよびます。ですから、「①-③の原理」は言い換えれば「頸-肩の原理」です。つまり、「頸を立てようと思うなら、頸だけみていてもだめですよ。頸を立てたければ、肩との関係でみて下さい」ということです。さらに、①-③がうまく関係づけられれば、①-③-④の関係づけへ、それができれば、①-③④-⑤の関係づけへと進み、最終的には①-⑥(頸-股)でからだをタテることができるようにしていくのです。
もう一つ、新用語です。それは、「反・屈 対 直の原理」です。これは「反ったり曲げたりなどの動きが出そうになったら、出さずに止めてあげましょう。それからの力の入れ方をタテ方向に切り換えさせてやるのです」ということです。反りや屈曲状態になるのは、そのような方向に力を入れているということなので、トレーナーが他動的にねじったり、反らせたりして修正を加えるというよりも、こども自身の力の入れ方の転換をはかろうというわけです。
少し、長くなってしまいました。もう一度、ここで整理してみます。
●臨床動作法は、動作を用いて様々な症状の改善をはかる方法の総称と考えてよい。
●臨床動作法においては、「意図」-「努力」-「身体運動」という動きの捉え方が大原則で、この過程を動作とよび、物理的な運動とは区別して考える。すなわち、動きを達成しようという主体的活動が重視される。
●訓練課程でこどもがその時その時にどのような「体験の仕方」をしていたのかに目を向けることによって、動作法は展開される。
●タテになる動作系が生きる基本であると考える。
●タテ系動作訓練では坐位・膝立ち・立位・歩行の姿勢のなかで、必要な課題動作を訓練していく。
●タテ系動作訓練では、形づくり→主動化(魂を入れる)→節・分節づくり→バランスとりという手順で訓練が実施される。
●タテ系動作訓練の基本要領として、「①-③の原理」「反・屈 対 直の原理」がある。
以上、動作法が生まれるまでの歴史、動作法の大まかな説明を試みてみました。動作法理解の一助となれば幸いです。
細かいことは、いずれ訓練経験を重ねるうちに実感として理解できてくるはずですので、心配ご無用です。ただ、そのためには、トレーナーとこどもとの「やりとり」を通して、こどものからだの動きを理解するという心構えだけは大切にしていただきたいと思います。やりとりのない訓練は、砂袋やバネと同じです。
(ふぇにっくす 第46号 1994年)
付記:“脳の可塑性”と“心理リハビリティション”
私は「限界を超える子どもたち──脳・身体・障害への新たなアプローチ」という本で衝撃を受けました(ブログ:“アナット・バニエル・メソッド1”)。
この本に書かれたメソッドは脳の可塑性【脳】に基づくものです。一方、動作法は心理リハビリティション【心】に基づくものです。【脳】と【心】、これは境界がはっきりしない極めて関係の深いものだと思います。もしかしたら、動作法はアナット・バニエル・メソッドの実践編に近いものになるかもしれない。これが動作法を深く知りたいと思った経緯です。
以下の表はアナット・バニエル・メソッドの「9つの大事なこと」をまとめたもので、細かすぎて見る気にならないような資料ですが、特に“動きに注意を向けること”、“ゆっくり”、“気づき”などは動作法でも根幹にあたるようなものだと思うので添付させて頂きました。
「脳と心?どうなってんだろう」との疑問から、ネット検索して見つけたサイトが以下の2つです。これをみると【脳】は【心】の中心というイメージです。政府と総理大臣のような感じでしょうか。いずれにしても密接な関係であることは間違いありません。

心は体のどこにある?
『「心」を各個人のアイデンティティーを表すものと捉えた場合に、体の中で他の人のもの(あるいは人工臓器)に置き換えられない臓器として「脳」が浮かび上がってきます。そう、その人それぞれの「心」をつくりだしているのは、実は「脳」つまり「脳味噌」なのです。』
『「脳」が損なわれる病気が「心」を変えてしまうということもあります。例えばアルツハイマー病という脳の病気は、主に大脳皮質という脳の部分に存在している神経細胞が失われていくことによって生じます。そのことによって、呆けたり、人格が変わってしまうのです。現在、脳研究者は「心は脳がつむぎ出すもの」と捉えています。別の言い方をすれば、「心は脳の内的現象」です。ここでいう「心」には非常に広い意味の精神活動、すなわち、認知、情動、意志決定、言語発露、記憶、学習などが含まれます。』

心はどこにあるのですか?
『近年の脳研究の成果は,心とは脳であるという言明を強く支持しているようにみえます。これは還元主義という立場です。心理学は脳科学に吸収されてなくなってしまいそうですね。でもちょっと考えてみてください。心の境界はどこになるのでしょう。心が物理的作用だとすると,物理的作用は脳内部にとどまらず,脊髄,末梢神経,感覚運動器官へ,さらに皮膚からそれと接する環境へとつながっています。どこで区切ればよいのでしょう。脳科学者である大谷悟さんは,ためらいながらもこのように言います。「(こころという感じは)からだと環境にまたがって発生・存在している」(大谷,2008, p.226)。心は身体―環境システムの別称である。』
脳性麻痺と機能訓練8
今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 5.立位・歩行機能訓練 になります。
5.立位・歩行機能訓練
●立位を保持するうえで、必要な条件は以下の4つである。
①股関節の伸展
②膝関節の伸展
③足底荷重
④バランス機能
●筋力学的には、股関節は大殿筋の発達・活性化によって伸展し、膝関節は内側・外側広筋の発達と活性化によって伸展する。
●抗重力的足底支持は、ヒラメ筋の発達と活性化によって可能となる。
●立位訓練は、膝立ち、つかまり立ち、椅坐位獲得までを1つのレベルとし、つかまり立位から四点歩行は、次のレベルと分けて考える。
a.つかまり立ちまで
1)膝立ちからのつかまり立位訓練
つかまり両膝立ち
坐位が安定し、四つ這いができるようになると、膝立ち訓練が取り入れられる。正坐出発肢位から(図45-B参照)。両手をテーブルなどで支え、徐々に股関節を伸展位に、さらに膝も90°まで伸展してくる。四つ這い肢位からも、手をテーブルにかけ、つかまり膝立ち肢位になる(図45-A,C参照)。
両膝立ち
つかまり膝立ちが安定すると、徐々に両手は支持として働かず両下肢だけの支持となり、両手支えなしでの膝立ちへ移る(図45-D参照)。
つかまり立ち
膝立ちが安定してくるとテーブルや横バーにつかまり、体重を足底にのせ両下肢起立へ進む(図45-E参照)。両股、両膝を伸展位に伸ばし、両足への支持を増やす。手掌支持立位が望ましい。肩のレトラクション、肘屈曲による引きを起こさないよう、抑制をはかり、つかまり立ちを育てていく。
2)つかまり立ちから椅坐位へ(立位回旋訓練)
つかまり立ちからの椅子坐り(車椅子、便器)は、ADL上、最重要なテーマである。この動きでは、相対した椅子に体を180°近く回旋して坐るために、下位体幹から股関節にかけての回旋が必要となる。
患児の前に台を置き、この台を両手でつき、つかまり立ちする。上肢で体を浮かせつつ下部体幹を回旋させ、回旋方向の股関節と膝関節を屈曲させ、殿部を台にのせる。術者は骨盤部を持って下部体幹の回旋を誘導する。台の高さは、低いものから始め、だんだん高くする。四つ這いから横坐りの訓練と基本的には同じである。
ADL訓練では、床から車椅子への移動で訓練することも多い(図46参照)。
3)椅坐位からのつかまり起立訓練
つかまり起立訓練
椅坐位をとり(図47-A参照)、前方にテーブルを置く、両上肢をテーブルに置き、体重をかけつつ、股、膝を伸ばし、股関節の内転・内旋を防ぎつつ、坐骨を空中に浮かす(図47-B,C参照)。
平行棒内起立訓練
平行棒内で椅坐位をとり、両手を平行棒に置き、体全体を浮かせつつ、平行棒内起立訓練を行う。車椅子からの平行棒内起立訓練を行う。車椅子からの平行棒移動などの形でしばしば行われる。
歩行器への起立訓練
歩行器を椅子の前に置き、椅坐位から歩行器への起立訓練を行う。
b.つかまり立位から杖歩行まで
つかまり立ちレベルになると、次は両ロフストランド杖、松葉杖歩行の獲得を目標とする。
対称性二点歩行と交叉性四点歩行の2つに分かれる。
1)対称性歩行(大振歩行、小振歩行)
両手を同時に前に出し、体を支え(図48-A参照)、両下肢を同時に振り出す移動である(図48-B,C参照)。平行棒内移動、歩行器移動、両松葉杖(ロフストランド杖)移動などで急ぐ時にみられる。両下肢の交互移動性がなく、一段レベルが低く、訓練上勧められない。
2)四点歩行
まず、平行棒内で四点歩行を覚え、PCW型歩行器を使った四点歩行に進み、次にロフストランド杖での四点歩行を覚える。
3)立位・歩行訓練の実際
立位訓練
つかまり立ちが可能になった段階で、歩行の準備としての立位訓練に入る。この時点では、上肢の引込み支持と前傾姿勢をとる傾向があり、独歩または杖歩行への準備としての立位に多くの問題をもっている。股関節の十分な抗重力伸展や全足底接地など、骨盤からのコントロールによりアライメントを整えていく。壁での寄りかかり立位、壁などに向きあっての上肢の平面支持立位などは、後方への不安定のためむずかしく、かがみ肢位を強めるので勧められない。上肢の挙上による体幹・股関節の伸展、上肢の外転・外旋による下肢の外転・外旋肢位の賦活をはかりながら、体幹、股関節の伸展、上肢の十分な伸展を教えていき、後方への不安定性を取り除き、全足底接地位での完全な荷重を経験させていく。
下肢の支持性の低下や筋緊張により、SLB(短下肢装具)、LLB(長下肢装具)、P-LLB(骨盤帯付き長下肢装具)、などを装着させることもあるが、これはあくまでも下肢筋の緊張のコントロールの補助として用いる。装具を立位手段として使用してはいけない。
立位姿勢が整ったら、側方、前後への重心移動と、それに伴う体幹の立ち直り、骨盤内および足底内での体重移動、膝のコントロールなどを教えていく。SLBで1分以上の一人立ちが可能となった段階で、歩行訓練へと移行していく。
PCW歩行(図49-A,B参照)
立位が可能になっても、最初から独歩は難しく、一側への重心移動の際、股関節の伸展保持が難しく、体幹は前傾し、アライメントが崩れやすい。後方への安定性をもたらすPCW(postural control walker)を使用して歩行訓練を行う。上肢と体幹の十分な伸展を行いながら、股関節伸展を保持させたうえで、重心移動を伴った一側下肢での支持を骨盤のコントロールにより行い、反張膝や膝折れに注意しながら、踵接地、蹴り出しなどを教えていく。上肢支持をなるべく少なくし、ゆっくりと歩行させる(平行棒は、上肢の引き込み支持が強くなる可能性があるので注意する)
ロフストランド杖歩行(図49-C参照)
PCWでの歩行が安定したらロフストランド杖に移行する。PCWに比べ、上肢支持の安定性が減少するため、後方への重心移動にたいする立ち直りが必要となる。それが困難な時は前傾姿勢を強め、杖の支持面が広くなり、それに伴い下肢の内転・内旋、足部の前・内側支持が著明となる。これを防ぐため、体幹、股関節の伸展位の保持と、上肢の外転・伸展を促しながら、一歩一歩重心移動を確実に行い、歩行させる。小幅に出した杖の位置まで、下肢を振り出せることが望ましく、その振り出した下肢の足から膝へ、膝から股に、十分に荷重したことを確認したうえで反対側を振り出す。四点歩行が安定したら二点歩行に移行する。
c.かがみ肢位歩行
かがみ肢位の矯正と、立位・歩行の獲得には、ここで述べた訓練とともに、各種装具、整形外科手術を合わせた実践が必要となる。
d.直立二脚歩行
患児の前方あるいは後方より、交叉歩行を一部介助し、体重が踵から足底外側支持、さらに足底母趾側に移るパターンを教えていく。荷重時(制動期)に、股関節軽度屈曲、膝関節軽度屈曲、足関節直覚位の肢位が望ましい。
付.矯正したい不良肢位
1)反張膝歩行
膝の伸展緊張が強いか、あるいは尖足と膝の伸展が合併すると、反張膝、股屈曲、尖足位になりやすい。腰椎前弯、股関節屈曲、尖足あるいは外反尖足が一体化した変形であり、どこに主な問題があるいかを観察し、問題の強い部分を治療する。尖足に対しては、装具を用い、直覚位とし、反張を抑制する。尖足矯正術も併用する。股関節屈曲はストレッチで伸ばし、屈筋群解離で直す。大腿直筋の過緊張による反張に対しては、大腿直筋の筋間腱切腱ののち、膝の屈曲位の中で歩行訓練を行う。
2)屈曲肢位歩行
両股、両膝がともに屈曲し、尖足、外反扁平足を合併する肢位である。屈曲膝に対しては、ストレッチとともにダイアルロックを使用した長下肢装具で徐々に伸展する。強引な伸展は関節軟骨を傷つけるので、股関節、膝関節とも屈筋群解離術を併用する。尖足に対しては、幼若期には時間を決めたSLB装用で保存的な矯正をはかる。固定化したものには、腓腹筋解離手術を行ったうえで荷重訓練に入る。
3)外反扁平足
足底アーチサポートで中骨部のアーチを強化し、足底屈筋群の活性化をはかる。立位、歩行の獲得についても、段階を追った取組みで自発性の高いダイナミックな取組みが可能になっている。
付記:整形外科的選択的痙性コントロール手術(OSSCS)
矯正したい不良肢位の“反張膝歩行”および“屈曲肢位歩行”の説明の中には、整形外科手術となる解離手術などが出てきています。個人的には手術の判断は難しいものと想像しますが、そのような選択肢があることは画期的だと思います。詳しく知りたいと思い見つけたのが熊本セントラル病院さまのサイトになります。

『OSSCSは、Orthopaedic Selective Spasticity-control Surgeryの略で、「整形外科的選択的痙性コントロール手術」という手術です。「筋解離術」と言われる手術法の中に分類されます。筋解離というのは、筋肉を切ったり伸ばしたりして緩めることを意味します。』
脳性麻痺と機能訓練7
今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 4.四つ這い機能訓練 になります。
Ⅳ.ダイナミック訓練の実際
4.四つ這い機能訓練
●四つ這い機能は、這い機能の1つであるが、体幹を空間に保持して移動させるという高次の抗重力性をもつ。
●どのように、この高い抗重力機能をもった交叉移動を獲得させるかが課題となる。
a.四つ這い肢位訓練
●四つ這い移動が可能となるのには、その前に両手掌と両膝つきでの四つ這い肢位の保持能力を獲得する必要がある。
●割り坐位が実用化してくると、次に両手掌への体重をかける訓練に入り、骨盤を浮かし、膝、足に体重をかける段階になる。
1)割り坐からの賦活
割り坐の中から上肢支持が、もっとも実用的である。両上肢を床につけ、両手で割り坐位をとる。骨盤を持ち上げつつ(図41-A参照)、上肢に体重をかけ、骨盤を浮かせ下肢を少しずつ伸展させ、下肢屈曲位で四つ這い肢位をとる(図41-B参照)。体重を前方に移動しつつ、股、膝を90~100°屈曲とし、両上肢の支持力を高める(図41-C参照)。股関節は90°以上屈曲位に保持し、下肢に十分の荷重をかけると、手掌の支持力が弱い上肢でも四つ這い肢位がとれる。股や膝に伸展緊張があると、体重が下肢にかからず、上肢にかかるので体重を支えきれず、四つ這い移動に移れない。下肢の屈曲位中間肢位での支持能力を育てる必要がある(図36-C参照)。
b.対称性四つ這い訓練(バニーホッピング)
●四つ這い肢位が安定してくると、四肢を使って移動訓練を開始する。
●両上肢に体重をかけ、下肢を屈曲し前に移動させ屈曲した下肢で体を支え、手つき割り坐をとる。さらに両上肢をこのまま前方に伸ばし、四つ這い位になり、次に下肢を前方へ移動させる。四つ這い肢位と手つき割り坐位を使いながら、対称的な上肢、下肢の動きを利用して前進する。
1)上肢からの賦活(上肢の力が弱い場合)
四つ這い肢位をとり、術者は患児の前に相対して坐る。両上肢を前方に伸ばさせ、肘を伸展位に術者の手で保ち、手掌を床につけ、荷重をかける(図42-A参照)。肘を伸展位に保持しつつ、肩を伸展させ体幹を前方(頭の方)にゆっくり引く(図42-B参照)。全体重が両上肢にかかり、下肢が屈曲し、前方に振り出されて手つき割り坐位になる(図42-C参照)。下肢に体重をかけ、手を前に伸ばさせる(図42-D参照)。
2)下肢からの賦活(下肢が伸展パターンをとりやすい時)
術者は患児の足の方に位置する。初発肢位の四つ這い肢位をとる(図43-A参照)。四つ這い肢位が安定してくると、次は両上肢に体重を少しずつのせつつ骨盤を少し持ち上げ、両上肢の支持力をさらに強化する。さらに、両上肢と術者の手で体を支えさせながら股関節を屈曲させ(図43-B参照)、下肢を前方に移動させる。屈曲した両下肢に体重をかけ、割り坐または膝立ち位にし、両下肢に体重をかける(図43-C参照)。両上肢を前方に移動させ(図43-D参照)、両手掌を床につける。続いて上肢に体重をかけ、初発肢位に帰る。
c.交叉四つ這い訓練
●手掌支え、膝支えの力がついてきて、対称性四つ這いができると、交叉移動パターンを用いた四つ這いに入る。
●四つ這いの特徴は3肢で体重を支持し、1肢を前進させるという点にある。
●手技的には腹這い交叉に用いられた一側上肢、他側下肢交叉推進(一側性交叉推進)のパターンを活用し、交叉移動を活性化する。
1)下肢からの訓練
下肢の分離の悪い子どもに使われることが多い。ます、初発四つ這い肢位をとる。術者は患児の後ろに四つ這いとなり、両手で両下肢、大腿部を持つ、両上肢は分離していることが多い。まず、左上肢を前に出させ(屈曲)、続いて右下肢、股、膝を前方に屈曲させる(図44-B参照)。屈曲した左上肢、右上肢にゆっくり体重をかけながら体を前方に移動させ、右上肢、続いて左下肢を前方に屈曲させる(図44-C参照)。屈曲した右上肢、左下肢に体重をのせつつ、体を前方に移動させる。右上肢屈曲・左下肢屈曲、左上肢屈曲・右下肢屈曲というパターンを患者とともに覚え、訓練を進める。一歩一歩の前進のさいに下肢の伸展緊張を抑えつつ、下肢の前方屈曲を容易にするだけでよい。
d.交叉四つ這いと横坐り(正坐、あぐら坐り、長坐り)訓練
●交叉四つ這い移動では、大殿筋の股関節伸展、外旋力が育てられ、体幹と両股関節の可動域が増し、内外旋のうごきが拡がる。
●両膝つき肢位で、股関節を中心に体は右に左に回旋が可能になる。
①まず、四つ這い中間位をとる(図39-A参照)。
②一側下肢を深く屈曲させる。
③屈曲させた下肢側の方に、股関節を屈曲させ、骨盤を降ろしていく(図39-B参照)。
④殿部が下腿の外側に付き、横坐りになる。一側は内旋位、他側は外旋位となる
⑤外旋側に十分体をかけ、支持訓練をする。
⑥体幹と股関節の回旋能力をさらに伸ばし、内旋側下肢を浮かし外旋させ、あぐら坐を促す。
⑦さらに、ハムストリングの緊張をゆるめ、長坐りへと誘導する(図39-C参照)。
股関節の回旋は、つかまり立ちから大きく体を回旋させて椅坐位または車椅子に移る時に重要な動きであり、このレベルでの横坐り訓練で十分訓練の必要がある。
e.四つ這い移動を阻害する典型的脳性麻痺パターンとその抑制
1)手掌支え不能状態
片麻痺児では、四つ這いが困難で、正常移動パターンができない。肩のレトラクション、肘の固縮、手関節変形の3つが手掌支えを困難にしている。四肢麻痺でも、両上肢にこれらの問題が存在する。レトラクションを抑え、肘を伸ばし、手掌支えの訓練を行う。肩、肘、手関節のストレッチにより緊張をゆるめたのちに自発訓練を行う。
2)痙直型両麻痺四肢麻痺の下肢伸展変形
両麻痺児では、股関節伸展緊張と膝関節伸展緊張の2つが問題となり、四つ這い肢位がとれにくい。四つ這い訓練を行い、伸展パターンが支障となる場合、受動的伸張訓練、伸筋群解離術で痙縮を除去し、股関節と膝関節の90°屈曲位保持をはかる(図36-B,C参照)。
四つ這い機能獲得の留意点は、次の2点である。
①股関節が90°まで自分で曲げられるかどうか。
②左右の下肢の交互性が出ているか。
【療育メモ15】“四つ這いの獲得は科学的知識を結集して”
『四つ這いは抗重力性の高い移動形態である。したがって、寝返り、腹這いのレベルから一気に四つ這い状態までもってくることはむずかしい。寝返り機能を育て、対称性腹這い、腹這い交叉移動を育て、さらに割り坐位機能を高め、下肢の支持性が十分高まった時点で、四つ這い支持に入る。さらに対称性四つ這いを獲得し、そして、次に対称性緊張を弱め、下肢の交互性を出し、さらに、一側上肢、他側下肢同時屈伸の交叉推進パターンを習得させ、初めて四つ這い交叉移動が可能になる。上肢の支持を得るための上肢の条件づくりも必要である。肩のレトラクション、肘の屈曲緊張、手関節の変形もコントロールしなくてはならない。また、力の弱い上肢に無用の負担がかかっては、四つ這いはできない。下肢のほうに十分体重がかかるように、屈曲位が得られる条件もつくらなければならない。また、交叉推進パターンの学習も重要である。
四つ這い移動はこれらの問題を1つひとつ根気よく解いていって、初めて獲得できるもので、一気にしようとするには無理がある。』
付記:“這い這い動作の再考”
這い這いができるようになることが当面の課題である患者さまと向き合っています。何か有益な情報がないか探していたところ、長崎大学さまの卒業論文集に関する資料が検索されました。タイトルをクリック頂くとPDF7枚の資料がダウンロードされます。

要旨
『乳幼児の這い這い動作のみについての先行研究は、個人差が大きいなどの理由から非常に少な く、その内容も這い這い時の姿勢や重心などに着目した研究が多くを占めている。そこで本研究では這い這い動作を理解するため、這い這い動作(crawling:ずり這い、creeping:四つ這い)の動きのバリ エーション数に着目して調査を行った。対象は協力を得られた乳幼児19 名(月齢 5~18 ヶ月)とした。複数の床条件において乳幼児の這い這い動作をビデオカメラで撮影し、動作のバリエーション数をカ ウントした。その結果、這い這い歴に従ってバリエーション数は増加し、その後減少した。また、調査の結果と先行研究から、乳幼児の這い這い動作においても、運動学習の過程で無作為な動作から合理的な動作を獲得するという、バリエーション数の増減を繰り返していると仮説を立てるに至った。』
脳性麻痺と機能訓練6
今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 3.自立坐位獲得機能訓練 になります。なお、最後に番外編として、Ⅴ. 抗重力肢位訓練 にある”坐位訓練”に関してもご紹介しています。
Ⅳ.ダイナミック訓練の実際
3.自立坐位獲得機能訓練
●坐位は哺乳動物以降にみられる抗重力機能であり、視線の位置を高め、上肢の使用を可能にする。人の生活に不可欠な食事、着脱、排泄が行われやすく、坐位機能の獲得は訓練上の大きなテーマとなり、作業療法、ADL機能訓練の出発点でもある(表5参照)。
a.坐位と立ち直り機能
●坐位は体幹を垂直に保持する働きを必要とするが、この抗重力機能も立ち直り機能という。
●坐位の獲得は垂直位保持機能の活性化であるが、運動学的には次の2つによって保持される。
①頚椎から骨盤にかけての体幹垂直位保持能力(体幹内立ち直り能力)
②下肢による体幹の垂直位保持能力(股関節での垂直位保持能力)
1)体幹の垂直位保持能力(体幹内立ち直り能力)
体幹内の起立位保持は、短回旋筋、長回旋筋、多裂筋など抗重力伸筋と、内腹斜筋、腹横筋の抗重力屈筋の活動で得られる(図12参照)。
2)下肢による体幹の垂直位保持能力(股関節での垂直位保持能力)
大殿筋、大内転筋、腸骨筋、短内転筋、長内転筋など抗重力筋の活動で、下肢が体幹を安定位に支える。
b.坐位を阻害する筋の過緊張と麻痺
●最長筋、腸肋筋、棘筋などの多関節性伸筋群の過緊張が体幹内の垂直位保持を妨げる。
●半棘筋、多裂筋、長回旋筋、短回旋筋、および内腹斜筋、腹横筋など抗重力筋の麻痺によって体幹内の垂直位保持が困難になる。
●半膜様筋、半腱様筋、大腿二頭筋などの多関節性伸筋群の過緊張および大腰筋、大腿直筋などの多関節屈筋群の過緊張が股関節での体幹支持を阻害する(図38-B参照)。
また、大殿筋、中小殿筋、長・短内転筋、腸骨筋など、抗重力筋の麻痺によって下肢での体幹の支え能力がなくなり、坐位が困難となる。
メモ:麻痺と肢体不自由
ここまでブログを進めてきて、坐位、特に”割り坐の機能訓練”が極めて重要であるということが分かりました。また、坐位を阻害している元凶は多関節筋群の”過緊張”と”麻痺”ということも分かりました。そして、その機能訓練を真剣に実践していこうとすると、あらためて「麻痺とは何か?」ということを明確にしないといけないと感じました。
そこで、8月30日にアップさせて頂いた”小児の理学療法2”のメモの一部を再度ご紹介したいと思います。

『脳の病変によって肢体が不自由になる現象を、本書ではここまで「脳性麻痺」ではなく一貫して「脳性マヒ」と表記してきたのは、一般に「麻痺」ということばが「神経や筋の機能が停止する状態」(広辞苑)とされているためでした。これまで述べてきたように、この子たちのからだは病理学的に動かないのではなく、生理的には動く自分のからだを、その主体者が自分の思うように動かせないだけですから、「麻痺」ということばはそぐわないため用いません。』
脳性まひ児にみられる”麻痺”は、脳血管障害に伴う血液の滞りによる組織の機能不全のような”麻痺”とは異なり、母体や乳幼児の時に体を思うように動かせなかったため、脳が学習する機会を十分に得られず、その結果、脳が適切にからだを認識し、合理的に動かす方法を十分に身につけることができなかった状態、いわゆる”肢体不自由”ととらえることが適切だと思います。そして、重要なことは”麻痺”によって直面する心身の困難さに比べ、”肢体不自由”が持つ改善の可能性、その領域は広く、動作法(心理リハビリテーション)や、脳の可塑性へのアプローチによって大きな変化が期待できる領域であると考えます。
c.自立坐位獲得訓練の実際
訓練は次の3つに分けられるが、ここでは自立坐位獲得訓練を検討する。
①介助坐位訓練
②自立坐位獲得訓練
③椅坐位獲得訓練
まず、割り坐を育て、さらに四つ這い訓練に進み、四つ這いから正坐、横坐、あぐら坐、長坐へ導入する。きわめてダイナミックな坐位獲得である。
1)割り坐訓練
●割り坐は両大腿内側、両下腿内側、両足および坐骨部での支持による坐位で、坐面が広く安定性が高い。
●割り坐はハムストリングの緊張がもっとも少なく、大内転筋群など抗重力筋の活性化に好都合である。
●上着などの着脱、食事などの上肢使用も可能である。
●割り坐の欠点は一側に体重が移動できず、ズボンの着脱など、高次のADL改善に結び付かない点である。
●割り坐の股関節屈曲・内旋・外転位は股関節の求心位保持に最善の肢位であり、脱臼の予防肢位である。
●割り坐肢位は体幹の垂直保持訓練にももっとも適切な肢位である。
a)割り坐を育てる手技
もっとも重要な手技であり、腹這い肢位を出発肢位とする。交叉肢位がとれ、肘つき、腹這いの能力が育っていることが望ましいが、必ずしもそこまで育ってなくてもよい。次の2つの方法がある。
1)外転拘縮弛緩タイプ
①まず両上肢・両肩屈曲位(頭の方に伸ばす)、両肘屈曲位、下肢伸展位をとる。
②一側下肢を120~140°以上屈曲させ、他側下肢も骨盤を少し持ち上げつつ120~140°屈曲させる。
③両下肢を少しずつ内転させ骨盤を浮かすよう呼びかけつつ、骨盤の持ち上げを助ける。
④骨盤が持ち上がると、さらに股関節を屈曲させ、殿部を床に降ろすように呼びかけ手助けする。
⑤殿部が下がり、脊椎が伸び、手つき割り坐が得られる。
2)両下肢交叉伸展肢位
①両上肢は両上肢・両肩屈曲位(頭の方に伸ばす)、両肘屈曲位、下肢は伸展位である(図35-A、36-A参照)。
②両前腕に十分の体重をかけ、腹部に術者の手を入れ、両下肢を屈曲させて骨盤帯を空間に持ち上げる(図35-B、36-B-a参照)
③腰の持ち上げを手伝うと、自力で腰を持ち上げようとする動きが出る。
④骨盤が十分持ち上げられると、次に両上肢を伸展させ体重を徐々に後方に移動し、両下肢を屈曲させる(図35-C、36-B-b参照)
⑤徐々に体重が後方に移動し、手つき割り坐が得られる。この時、膝の曲がりが悪い児は膝に痛みを訴える。また、股の内旋できない児や足が背屈している児は、痛みを訴える。急に行わず徐々に膝の曲がりや股の回旋の動きをよくし、足の可動域をよくしていく。最初痛い時は、坐骨と坐骨の間にタオルとか正坐した術者の大腿部を入れて、四つ這い肢位に近く保持し、徐々に膝を曲げ、割り坐肢位とする。手つき割り坐で、徐々に背中を伸ばすよう呼びかけ、体重を坐骨から下肢までに移すと、体幹が徐々に伸びてくる。手を離し、割り坐へと移行する(図35-D、36-B参照)。
手つき割り坐では、大腰筋が緊張し、体幹が垂直を取りにくいことも多い。腹部から手で体を起こし、大腰筋の緊張を抑制し、大殿筋の伸展力を育てつつ、体幹の垂直位獲得をはかる。
b)割り坐を阻害する因子
股関節伸展内転緊張
股関節伸展、内転緊張が強いと、腹臥位での股関節屈曲ができない(図35-A参照)。
腹這いでの伸展筋群の伸張(ストレッチ)訓練を家庭訓練を含めて、あらゆる機会を利用して行う。股関節をやや外転した割り坐が望ましい。
下肢屈曲緊張
股関節の屈曲緊張が極度に強いと、手つき割り坐をとり、次に股関節を伸ばし、脊椎を伸展させる段階で体幹は起き上がってこない(図37-A,B、図38-A参照)。
他動的に起こすと、大腿部も一塊となって持ち上がり、体を支える状態がつくれない(図37-B、38-B参照)。
訓練上は手つき割り坐をとらせ、体を徐々に伸ばし、屈曲緊張をゆるめつつ、股伸展筋の発達を待つ手つき割り坐訓練が重要である(図37-C参照)。
腹臥位ストレッチ訓練により、股関節屈筋群の緊張の抑制をはかる(図20参照)。
上肢のレトラクション
手つき割り坐に入る時、まず腹臥位から骨盤が浮き上がり、次に両下肢が曲がる。上肢が肘関節で伸びながら体を後方に移動させ、殿部が下がってくる。肩のレトラクションがあると、この上肢の前方での伸びが妨げられる。レトラクションを徐々に除き、能動的割り坐肢位訓練によって肩、肘の支配能力を育てる(図35-C参照)
2)正坐訓練
股関節の外旋力が付くと、正坐が可能になる。重心が高く支持面が狭くなり、よりレベルが高い坐位である。一側だけでの支持が容易になり、体重が左右に移動できる。割り坐からいったん両手をつき殿部を浮かし、四つ這い肢位をとり、それから下肢を内外旋中間位に保持させつつ殿部を降ろし、正坐位をとると訓練がきわめて容易となる。自発運動を尊重したダイナミックな正坐獲得訓練が、四つ這い肢位を活用することによって可能となる。
横坐り訓練
一側外旋、他側内旋の横坐りでは、外旋した方の下肢に体重を乗せることが可能になり、日常生活動作もさらに高次なものが可能となる。また、外旋位保持によって大殿筋など股関節外旋筋の活性化がもたらされる。自力で椅坐位をとるための股関節の回旋の動きを育てる訓練の第一歩にあたる。車椅子の乗り、便器への移動などでの股関節の回旋能力の獲得のためには、このような横坐り能力から育てていく必要がある。また、四つ這い移動からの横坐り屈筋は自発性が高い(図39参照)。
あぐら坐り訓練
両側股関節が外旋した坐位である。痙直型両麻痺の子どもたちには、この坐位は難しい。体重の左右移動が容易となり、遊脚側での着脱が容易となる。手技としては、四つ這い肢位訓練、横坐り訓練が基本となる。両側の横坐りが安定すると外旋側に体重を移し、次に内旋下肢を外旋させ、両股外旋位をとる(図39参照)。
長坐り訓練
ADL、上下着や靴下の着脱などが可能なレベルの高い坐位である。横坐りができ、さらにハムストリングの伸展緊張がゆるんだ段階で初めて可能となる。脳性麻痺ではハムストリングの緊張が強く、この肢位を自発的にとることは難しい。まず四つ這い移動を獲得し、四つ這い肢位からの股関節の回旋によって長坐に移る(図39参照)。ハムストリングがゆるんだケースでは、側臥位、肘つき側臥位、手つき側臥位をとり、股関節および体幹の回旋で長坐位に移りえる(図40参照)。
このように坐位については、まず割り坐の獲得がもっとも大事であり、それができたら四つ這い肢位の獲得に向かい、次にこの四つ這い肢位から横坐り、長坐など、自立坐位訓練を進める。
付.坐位の獲得方法
坐位獲得は、側臥位から片手をついて起き上がり、投げ出し坐りとなる方法と(図40参照)、四つ這いから一側下肢を内転外旋させて横坐り、そして投げ出し坐りになる方法(図39参照)の2つの方法がある。第1の方法は、訓練上到達レベルが一気に高くなるために、自発性を出すことが困難で、とくに股関節伸展緊張のある例には困難なことが多い。第2の方法は、まず四つ這いを獲得してからの方法であり、四つ這い獲得が先決である。この四つ這い獲得のためには、割り坐からの訓練が必要となる。割り坐獲得、四つ這い位獲得、そして長坐獲得と3段階に分け自発性を出す。
3)椅坐位訓練
自立椅坐位は四つ這いと立位の間に位置するレベルの高い坐位ととらえる。
d.基本運動レベルの中での自立坐位獲得機能の位置づけ
●これまでの坐位訓練は、椅坐位での静的訓練を重要視し、床上坐位でのダイナミック訓練は、あまり用いていないようにみえる。
●著者らは割り坐のような重心の低い安定性のある坐位も価値のあるものと考え、自由に坐位獲得の動きを出そうとしている。
●割り坐は内旋変形をもたらすと考えられ、嫌われる傾向にあるが、著者らは症状の重いケースに自発的な坐位獲得の動きを出すことが重要と考え、割り坐を訓練上不可欠のものととらえる。内旋は割り坐獲得ののち、横坐り訓練などで矯正する。
●床坐位は重心が低くバランス能力は少なくてすみ、自発的なダイナミック訓練が行われやすい。レベル的には、腹這いと四つ這いの間に位置すると考えられる。
●椅坐位は重心が高く、より高次のバランスが求められる。レベルの低いケースにこの坐位を用いると、多くの支えを必要としダイナミズムに欠ける。椅坐位はレベル的には四つ這いと立位の間に位置すると考えられる。
e.自立坐位獲得訓練・四つ這い訓練と異常姿勢反射の抑制
●坐位の獲得、四つ這いには、両手掌・両上肢の伸ばしによる体幹の支えが不可欠であり、異常姿勢反射の一局所であるレトラクションが、この機能獲得を阻害する。このレトラクションを制御しつつ、手を体の前に伸ばす訓練が重要となる。
●下肢による体幹の支えも、坐位獲得、四つ這い移動には欠かせない。
●異常姿勢反射の一局所症状である下肢の伸展緊張、屈曲緊張は、この機能の獲得を阻害する。
●異常姿勢反射の一局所所見である体のそりも、体幹の垂直位獲得の障害になる。
●下肢の過度な伸展緊張、屈曲緊張、体のそりを抑制することによって、下肢での体の支えが可能になり坐位が安定し、四つ這い機能が得られることになる。
【療育メモ14】“割り坐への起き上がり(これこそが訓練の核ではないか?)"
『すでに、“寝返り”の項で腹這いを運動の基本ととらえ、そこに起き上がってくる寝返りを抗重力運動の第一歩ととらえたが、もう1つ大事な抗重力運動に割り坐への起き上がりがある。すでに、あちこちで割り坐の重要性については述べたが、何回述べても言い足りることはないぐらい、割り坐は腹這いから四つ這いのレベルに立ち上がってくるためのステップとして大事といえる。
どうしてこのようなことに気づいたかは、著者らの股関節手術のあり方と大きく関連するので少し触れてみる。股関節解離手術は、世界でもっとも普及している整形外科手術であるが、一般的に行われる手術は、
①腸腰筋切離
②内転筋切離+閉鎖神経切離
③内側ハムストリングの末梢腱延長
になる。
ところが著者自身この手術を1980年頃に行っていた時に、理学療法士らから、“手術をすると股関節の力が弱くなるからさせたくない”と言われることが多かった。この手術では、立つ時の安定性が悪くなると同時に、腹這いからお尻を持ち上げて割り坐になる時に、股関節を曲げる力が極端に弱くなるのである。
そこで、腸腰筋のうちの大腰筋だけを切り、腸骨筋を残す手術を行うことにした。これは、その後、アメリカでもよくいろいろな書籍に取り上げられ効果のある手術とされたが、それでも理学療法士らからは、なお筋力が落ちると言われ続け、これを改善するために長内転筋を残し、代わりに内側ハムストリングである半膜様筋の中枢腱を切る手術を考え出すことになった。
1987年(昭和62年)のことである。A君が、歩けるようになりたいとやってきた。筋力は弱く、痙性は強く、そう簡単には歩けそうにない。でもなんとか歩かせたいとのご両親の思いをかなえるべく、手術に踏み切ることにした。
しかし、確かに歩行器では歩けるようになったが、以前は床から割り坐へ、お尻を持ち上げ自分で坐れていたのに、手術のあと、このお坐りができなくなってしまった。腸骨筋、長内転筋の大半は残し、股関節の屈筋を温存すべく注意したにもかかわらず、お尻が上がらない。筋力が弱かったのである。もっともっと注意深く、長内転筋を触らないほど用心して手術をしないといけなかったのである。股関節を曲げやすくする足の手術、膝の手術をして、祖父母の方々も総動員で訓練したが、自分でお尻を上げるようになりえなかった。自力で坐れるようにならなかったのである。
この時を機に、著者の目が変わった。腹這いの姿勢からお尻を持ち上げて割り坐になり、手をつきながらお坐りに起き上がっていく機能がどれほど大事なものか思い知らされたのである。訓練上も、この機能が大事ということに気づいたのである。
同じ頃、やっと自分でお尻を上げて、お坐りができる子どもがやってきた。両方の股関節が強く脱臼していた。筋肉の力は弱そうである。脱臼を治すために、筋肉を解離する手術、関節を整復する手術が行われた。脱臼はまずまずよくなったが、手術のあと自分で坐れなくなってしまった。このように、脳性麻痺をもった患児の中には、自分でやっとなんとかお坐りができるようなレベルの人がいるのである。この患児に、不用意に手術をすると、著者らみたいに伸展側の解離をやっていても、ちょっと屈筋をゆるめるだけで股関節が曲がらなくなってしまう。一段レベルの低い腹這いの生活に逆戻りしてしまう。ご両親からは、この子どもが手術後坐れなくなったと不信感を持たれ、その後、脊椎が曲がってきたにもかかわらず、手術をされる気配はみられなかった。医師としては、“股関節脱臼がある程度治ったのだから”という気持ちはもったとしても、“自分でお坐りに上がっていく機能を破壊しては駄目なんだ”と肝に命じ、それ以来お坐りが逆にできやすくなる手術を目指し、一例もお坐りができなくなるような手術はしていない。
この経験をもとに、著者らは、床からお尻を上げて足をお腹のほうに引き寄せ、割り坐の形で坐り上がっていく自立坐り獲得がいかに大事なことであるかを認識し、このお坐り上りが患者にとって、立体的な四つ這い姿勢、移動を開始する基点であることを知ることになった。さらに、この姿勢は今まで割り坐として嫌われていたけれども、実態は訓練上ももっとも大事な、これがなければ訓練自体が成り立たないような大事な訓練であることも認識することになった。
ここで振り返ってみよう。脳性麻痺の訓練は割り坐肢位が悪いと決めつけると、どうしてよいかわからないような奇妙なむずかしさの中に投げ込まれたような気になる。腹這いからどうやって四つ這いにもっていったらよいのかわかりにくい、自分でためしてみていただきたい。寝返りや腹這いの訓練など、腹這いから四つ這いへの訓練に比べれば簡単なものにみえる。
でも、腹這いから四つ這いの間に割り坐をおいて、まず腹這いから割り坐へ、割り坐から四つ這いへと、訓練を2段階に分ければ、きわめてわかりやすくなるのに気づかされる。
割り坐については、これまで内旋歩行がもたらされやすいとか、あまり好まれなかったが、整形外科的に冷静に考えれば脱臼防止肢位であり、脊椎に無理がいかず、側弯症変形防止肢位でもある。あぐら肢位のほうが脊椎の肢位には悪いし、長坐肢位のほうが脱臼促進肢位なのである。
人の基本運動は大きく分けて、
①背這い(寝返り不可)レベル
②寝返りと腹這いの平面的活動レベル
③坐位立ち上がりと四つ這いレベル
④立ち上がりと二脚歩行レベル
に分けられるが、訓練や整形外科の場面で、まだ腹這いレベル以下の子どもに無理矢理、立位の訓練をしているところが多い。この立位訓練は、脱臼や脊椎の側弯症をもたらし、なんの良いところもない。
四つ這いの生活という大事な世界を忘れていないか、その入口である割り坐の重要性に気づかず、その難点を言う古い発想にとらわれ、四つ這いという大事な世界に脳性麻痺の子どもたちをいざなうことができずにいるのではないか、是非、リハビリテーション関係者は学んでほしい。整形外科の分野では、割り坐は大事な肢位であるとの認識が生まれている。また、この発想に理解を示す、療法士、養護学校の教師、保育士、看護師らはすでにこの考えを取り入れ、豊かな訓練を展開している。是非、腹這いから四つ這いにもっていく訓練肢位として、割り坐肢位を考えてみて欲しい。』
注)本書には【療育メモ】が全部で17あります。
番外編:抗重力肢位訓練-坐位訓練
“第3章 理学療法の実際”の5つめは、“Ⅴ 抗重力肢位訓練”となっています。この中で坐位訓練に関しては詳しい説明がされていますので、冒頭部分とそれらの坐位訓練のみをここでご紹介したいと思います。
Ⅴ. 抗重力肢位訓練
抗重力訓練の特徴は、一定の肢位を他動的に保持しつつ、体を抗重力肢位に支える筋力を付けるとともに、平衡バランス機能を活性化することである。また、見過ごされやすいが、意味が大きいのは重心移動を利用したダイナミックな平衡機能の活性化である。一定方向に集中させ、寝返り、腹這い、四つ這い、歩行といった推進運動へ移る準備する。側臥位では、上腕支持部で体重を前後に移し、バランス獲得、支持能を高め、腹臥位への回旋運動の前準備をする。腹這いでは、重心を一側上・下肢に十分移し、対側下肢の屈曲の動きを誘発する。四つ這い肢位でも、体重を一側上肢と下肢に十分に移しつつ、対側下肢の前方移動の動きを待つ。両杖立位、二脚立位の訓練もまったく同じである。
訓練の手技には多様なものがあり、もろもろの器具、支持具、おもちゃを使って、無数の取組がある。手技については、既存の訓練法を参照するとよい。
4.坐位訓練
a.床坐位訓練
1)割り坐訓練
内側ハムストリング、大腰筋、大腿直筋の緊張の少ない肢位であり、抗重力筋の活動のための訓練がなされやすい。大内転筋、殿筋群、腸骨筋、長・短内転筋の活動によって体が支えられる。割り坐のできないケースで後ろから支えたり、前に机を置いたりし、安定性を育てる。日常生活のほか、おもちゃを前に置いた場面などで、割り坐を阻害する拘縮をゆっくり除いていく。
2)正坐訓練
他動的に正坐位をとる。重心は高くなり、面も狭くなり、より股関節周辺の安定度が必要となる。本坐位は、体重への左右移動が可能であり、体幹を部分的に支えつつ一側支持訓練を行う。
3)横坐訓練
大殿筋、中殿筋が活性化されると、下肢も外旋位をとることが可能になる。割り坐が安定すると、四つ這い肢位から、この肢位をとらせる。全体重を、外旋側一側に支持するための抗重力的な支持訓練になる。
4)あぐら坐位
下肢を外旋して坐るあぐら坐位訓練である。この肢位は、内転筋・内側ハムストリングの緊張を抑え、大殿筋、中殿筋の活性化をはかるものとして愛用される。体重を左右に移動することができて、ある程度発達した患者では、他側が遊脚となり、遊脚側での日常生活が可能となる。重要な肢位訓練である。しかし、一方では、内側ハムストリングの緊張がある重度児では、この内転緊張も抑制しなければならない。また、骨盤が後傾しやすく脊椎が後弯し、重度児訓練には適切でない。脊椎伸展をはかるのがむずかしいなど、抑制ばかりが強くなり、自発性が低く、悪い訓練となる。患者の後ろから、術者が両下肢を患者の下肢の上に乗せ、股を開き、脊椎を無理に伸展しているような訓練をみかけるが、自発性のほとんど育たない不毛の訓練といってよい。
5)長坐訓練
この訓練も、しばしば愛用されている。しかし、この肢位はもっとも脱臼を起こしやすい危険な肢位である。レベルの低い例では、脱臼を起こしやすく、濫用を避けたい。ハムストリングの緊張で骨盤が後傾しやすく、脊椎も後弯し、脊椎伸展訓練には適さない。まず、脊椎の伸展は割り坐ではかり、股関節の内転緊張は股関節で除いていく、というように訓練の過程を2つ分けることによって、自発性を出すという発想が求められる。
b.椅子坐位訓練
術者は、患児の後ろに患児を抱くようにして坐る。患児の体幹、骨盤を前後左右から平衡能力に応じて支えつつ、足底をつけ、抗重力訓練を行う。テーブルを前に置き、両上肢で支持させ、安定をはかることもある。背もたれ椅子、肘もたれなどを用いて不安定性を防止するなど、最初は支持を多くし、徐々に支持を少なくし、手を離しても倒れない坐位を目指す。体幹の直立位支持力の付いた患者に用いるべき訓練であり、重い麻痺をもつ児への濫用は慎みたい。
脳性麻痺と機能訓練5
今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅲ.自発運動誘発訓練 になります。
第3章 理学療法の実際
Ⅲ.自発運動誘発訓練
1.ダイナミック訓練の中心
●人の基本運動機能は大きく、次の5つに分けられる。
①寝返り機能
②這い機能(腹這い)
③坐位機能
④四つ這い機能
⑤立ち、歩き機能
このうちのどこが障害されているかを評価し、その部分を集中的に訓練し、機能を上げる必要がある。
●寝返り訓練と腹這い訓練は、ダイナミズムを伴う動的訓練であり、リハビリテーション医学の真髄ともいえるが、その手技は簡単なようで難しく、誰でも使える賦活手技が要約として示されにくい。
●寝返り訓練と腹這い訓練は、訓練時間内の訓練だけでは効果は少なく、たえず保護者の協力の中で育てていかなければならない。
●寝返り訓練と腹這い訓練は、分かりやすく楽しい遊びとして、日々の生活に取り入れられることを、医師や療法士は保護者に指導する必要がある。
●坐位機能は他動的に坐位をとらせると、静的な抗重力機能ととらえられ、訓練は比較的容易であるが、自分で坐位をとろうとする自発訓練は、患者自ら坐位獲得のための能動的な動きを必要とし、ダイナミズムを伴う訓練となる。
●坐位訓練は、割り坐、正坐、横坐、長坐といったいろいろな坐位を育てる中で、上肢も体の支えから解放され、巧緻性獲得の出発点となる。
●割り坐位は、四つ這い移動への出発点であり、また立位肢位への出発点でもある。したがって、寝返り、腹這いから、次のレベルの機能獲得への起点となる。
●割り坐位で脊柱の伸展能力を育てつつ、さらに割り坐から四つ這い移動を獲得し、股外旋筋の発達を待ちながら、四つ這いから、横坐、あぐら坐、成熟した長坐へと、より安定した坐位へ進む。このように割り坐位からの自立坐位の獲得訓練および四つ這い獲得訓練は、ダイナミズムを伴う動的訓練の3本目の柱である。
●立ち、歩き機能は、直立二脚歩行を行う人類だけがもつ特徴的かつ精緻な機能であり、足部構造を中心に極めて精巧なメカニズムを育てている。
●立ち、歩き機能を獲得するためには、四つ這いまでの知識のうえに、さらに多くの知見が必要であり、それらの蓄積と応用のうえで、初めて歩行は可能となる。
2.正常発達児と脳性麻痺児の運動発達の差
●腹這い移動から、直接、四つ這い肢位に移るのが正常児の発達であるが、これを脳性麻痺児に行おうとすると、レベルが違いすぎて一気に行えない。
●腹這い肢位から側臥位に体を回旋させ、肘つき、手つきで体を起こし、長坐位に到達させることも脳性麻痺児には難しい。
●脳性麻痺児は、腹這いの次に割り坐を発達させ、そこから四つ這い肢位、四つ這い移動に進む。
3.脳性麻痺児特有の運動発達とその評価
a.頭の回旋と持ち上げ
1)側臥位回旋不可
緊張性頚反射など、頚部筋の緊張・麻痺のため、頚の回旋が不可能である。
2)頭部回旋
頚部筋に随意性が出現し、仰臥位および腹臥位で、頭は床に付いたまま左右に回旋する。
3)頭部の持ち上げと回旋
仰臥位および腹臥位で頭を空間に持ち上げ、保持回旋する。
b.寝返りの発達
1)寝返り不可(図21-A参照)
緊張性迷路反射などの緊張のため、頭の回旋、肩や股関節の内転・外転、体幹の回旋が得られず、寝返りが不可能である。下肢では伸展緊張が強く、回旋に必要な股関節内転・外転の動きが出にくい。
2)寝返り、横向き(図21-B参照)
肩や股関節の内転による横向きまでの寝返りが可能である。上肢・下肢に内転・外転力がつき、体幹を横向きに保ちうる。
3)寝返り、腹這い肢位まで(図21-C参照)
体幹がさらに回旋し、腹臥位になるレベルであり、体幹を前腕で支えることが可能になる。
c.腹這いの発達
1)腹這い上肢対称性前進(図22-A参照)
原始的な腹這いであり、両上肢を同時に屈曲、さらに同時に伸展して前進する。対称性緊張性頚反射が内在する対称的な移動である。下肢は伸展位で動かないことが多い。両肩のレトラクションがなお強かったり、上肢の支持、推進力が弱く、一側上肢屈伸での推進ができない。両下肢も伸展緊張が強く、屈伸の動きは少なく左右の分離性もない。
※対称性緊張性頚反射(STNR)について

画像出典:「トコちゃんベルトの青葉」
『対称性緊張性頸反射(STNR)が残存すると、頸伸展時、肘関節・手関節は伸展し、股関節・膝関節は屈曲する。また頸屈曲時は肘関節・手関節が屈曲し、股関節・膝関節が伸展してしまう』
画像および文章は、”【横浜・白楽】脳とからだセラピストのたわごと” さまより拝借しました。
左の絵は、赤ちゃんが重力に抗って頭を持ち上げた時の状態で、腕が伸びて足が曲がっています。
右の絵は、頭を下げた時に腕が曲がり、お尻が上がった状態です。
●これらの動きはハイハイをする前の段階になり、この反射が出ている間はハイハイができない。
●STNRは生後6~9ヶ月から現れ、9~11ヶ月後には統合されるので、この反射の出現から統合される期間は、他の原始反射に比べるとても短い。
●この反射により、ハイハイや立ち上がりに必要な筋肉の発達を促す。
●頭を上げて遠くを見るようになることから、視覚的な遠近感を獲得できるようになる。
STNRが残存している場合の影響
・ハイハイを十分にできなかったため、両手や両足の協調した動きが苦手
・片側だけの動きになりがち(手書きのとき、反対側の手で紙を押さえないなど)
・頭を前に下げたときに、腕も曲がってしまうため、字を書くときはさらに頭が前に下がる
・イスに座るときはいつも前のめりになる。または足を投げ出すように浅めに座る。
・歩くときは片足、または両足が内側を向く
・頭と目、目と手の協調運動が苦手(マット運動の前方回転、水泳、球技など)
・集中力に欠ける
・首と肩の筋肉が緊張しやすく、首や肩のコリ、偏頭痛になることもある
2)一側性交叉腹這い(図22-B参照)
対称性緊張性頚反射が弱まり、上肢に力がつくと、一側上肢の屈曲、伸展による前進が可能になる。同時に、屈曲した上肢の対側下肢が屈曲する交叉状態もみられるようになる。しかし、まだ体幹の上部・下部を分離させる回旋の動きはなく、一側上肢屈曲、他側下肢屈曲の繰り返し移動で前進する(図33-A参照)。
3)四肢(両側性)交叉腹這い(図22-C参照)
下肢の緊張が弱まり体幹の回旋の動きが出ると伸展側に体重が移動し、両側性に、一側上肢、他側下肢が屈曲・伸展する四肢交叉移動ができるようになる。個々の下肢の屈曲・伸展が容易になり、骨盤の持ち上げが可能となり、自立坐位獲得への準備ができてくる。両上肢に力がつき、肘つき位で交互に動かし、下肢も交叉性に動く、交叉肢位移動が完成する(図34-B参照)。
d.坐位の発達
1)手つき割り坐位肢位(図23-B参照)
肘つき腹這い位で、骨盤が持ち上げられるようになると、骨盤を上げつつ股関節を屈曲させ、次に肘を伸ばし、体重を後方に移動させつつ手つき割り坐位肢位をとる。交叉腹這いから、四つ這いレベルへ移るステップである。
2)割り坐(図23-C参照)
上肢の支えがいらなくなり、下肢に全体重がかかるようになると、割り坐が可能になる。いろいろな坐位への出発肢位である。下肢と体幹だけの自立坐位であり、腹這いから次の四つ這いへのステップでもある。大腿直筋、内側・外側ハムストリングの緊張がもっともゆるみ、抗重力的な体幹筋、股周囲筋が活動しやすい。
e.四つ這いの発達
1)四つ這い肢位(図24-A参照)
割り坐から上肢を前に伸ばし、床につけ、これに体重をのせ、股関節と膝関節を伸ばしていくと、四つ這い肢位になる。四つ這いへの出発肢位である。機能的には、両上肢での手掌支持、両下肢での膝蓋-脛骨粗面部支持が可能になり、体が空間に保持された状態である。両手指、両手関節の支持力を育てる重要な肢位であり、この支持力をもとに両手は巧緻性を獲得する
2)対称性四つ這い(バニーホッピング)(図24-B参照)
四つ這いの肢位で、頭と両上肢を伸ばし、体重をかけ、同時に下部体幹と下肢を屈曲させ、振り出し前進する。振り出しの終わりで股関節を伸展させつつ、膝・下腿に体重をかけ、割り坐位に戻る。次に頭と上肢を屈曲させて手を前の方につき、さらに前進する。対称性緊張性頚反射が残存する対称性移動である。バニーホッピングともいわれる。股関節の緊張が残り、両下肢の交互性が悪い。
3)交叉四つ這い(図24-C参照)
1つひとつの肢が分離し、十分な荷重性、抗重力性を獲得してくると、三肢支持で一肢だけを動かす四つ這い交叉移動が完成する。四つ這い移動からは、横坐り、長坐り訓練が容易となる。
f.立位・歩行の獲得
1)両膝立ち(図25-A参照)
両膝、下腿を使っての二脚立位の原始型である。大腰筋、大腿直筋など、股屈曲の痙性がとれて両膝支えが可能になる。つかまり膝立ちから徐々に手の支えが不用になり、下肢に体重がかかり、膝立ちとなる。
2)つかまり両足立ち(図25-B参照)
つかまり立ちで、両股、両膝屈曲位のことが多い。変則四肢支持である。足底接地の条件が整い、股関節、膝関節の抗重力伸筋が働きはじめて、つかまり立位が可能になる。立位で股・膝・足部の痙性が現われやすく、不安定である。尖足、外反扁平足などが残り、足部の抗重力機構が十分に育たず、立位保持ができない。
3)つかまり交叉移動(図25-C参照)
変則四点交叉移動である。両下肢に十分体重がかかり足底支持ができるようになると、両杖でバランスをとり、歩行を開始する。足底支持が容易となって、初めて杖による四点移動が可能になる。
4.直立二脚歩行
二脚立位で、しばしば初期的には、両尖足、両股、両膝屈曲位をとることが多い(かがみ肢位)。大殿筋、大腿四頭筋、ヒラメ筋が活性化してくるとともに、下肢が伸展し、直立位となる。足底がつき、足底外側縁で体重を支えるようになると、二脚歩行が可能となる。
脳性麻痺と機能訓練4
今回は、第3章 理学療法の実際 Ⅱ.ストレッチ訓練 になります。
第3章 理学療法の実際
Ⅱ.ストレッチ訓練
●痙縮・固縮のコントロール手技としては、訓練ではストレッチ訓練、装具によるコントロール、薬物使用ではアルコール、フェノール、ボツリヌス毒の筋肉注射、脳神経外科では選択的後根切除術、整形外科的には、キャスト固定、選択的筋解離術がある。このうち、ストレッチ訓練は一定時間行えば一過性ではあるが、過緊張、痙性を抑制することが、これまでの臨床的経験では示されており、訓練の場でも実感されている。
●脳性麻痺の寝返り、腹這い、四つ這い、立位歩行などの機能をあげるには、肩のレトラクション(肩甲骨の内転)、肘の屈曲緊張、手関節掌屈曲緊張、体幹緊張、股・膝・足の緊張など、それぞれの部位での痙縮あるいは固縮を弱めることがより効果的であり、むしろ痙縮・固縮を除かなくては機能向上を望めない。
●ストレッチ訓練は伸張反射を一過性であれ抑制する唯一の手技であり、ストレッチ訓練手技を自発訓練手技の導入部分として活用することができる。
●機能解剖学的には痙性筋の数は限られており、患児との感覚的接触、訓練導入の手段として、特定の筋のストレッチを容易に行いうる。
1.体内の痙性筋
●痙性筋は大まかに、表3のとおりである。いずれも屈曲・伸展の動きをもつ多関節筋である。
●これらの痙性筋によってもたらされる変形、および不良肢位、ならびに痙性筋そのものに対し評価し、ストレッチ訓練が行われる。
ご参考:下記は屈曲、伸展などの動きを絵で紹介しているものです。クリック頂くと拡大されます。
2.ストレッチ手技の実際
a.仰臥位ストレッチ訓練
●伸張ストレッチ訓練はスポーツの世界で広く利用され、体の緊張をゆるめるのに効果がある。訓練においても伸張訓練の重要性は変わらず、大きく3つの伸張訓練に分けられる。
①上位体幹、上位の屈伸
・頸椎、胸椎の屈曲
・肩の屈曲、肘の伸展(仰臥位上肢伸展)(図18-A)
②下位胸椎、腰椎、下肢の屈伸
・腰椎、骨盤、下肢の屈曲と伸展(図18-B)
③胸椎、腰椎の回旋(図18-C)
1)頭最長筋、頚最長筋のストレッチ
●仰臥位で頭を後ろから支え、ゆっくり垂直方向に起こし、左右に目と目の線を水平に回旋させる。右に回旋させると左側の頭最長筋、頚最長筋がストレッチされ、右前頚筋群が活性化される。左に回旋させると右側の頭最長筋、頚最長筋がストレッチされ、左前頚筋群が活性化される。
術者が正坐し、やや両股外転位をとり、その間に患者の頭と上位体幹を入れるような形で、頚部、体幹を屈曲させ頚部、体幹伸筋のストレッチをはかるのも1つの方法である。術者と患児の接触を楽しむ程度の感覚でよい。
2)上肢帯のストレッチ(上肢伸ばし訓練)
●広背筋、上腕三頭筋、上腕二頭筋のストレッチ
肘を伸ばし、肩を頭の方に上げ、この3つの筋をストレッチし、三角筋の活性を高める。肩を上げて、広背筋と後下方関節包をストレッチし、さらに肘を曲げて上腕三頭筋をストレッチする。肘を伸ばして、肘の前方関節包と上腕二頭筋のストレッチをする(図18-A-b参照)。この時、前腕は回外保持が望ましい。
僧帽筋のストレッチ
一側上腕で肩を内転し、他側の前腕でこの内転した上腕を抑え、僧帽筋をストレッチする。大胸筋の活性が高まる。
3)下肢帯のストレッチ
伸展ストレッチ
仰臥位ではとくに必要としない。
屈曲ストレッチ
術者は患者の下肢側に坐る。両下腿中間を持ち、両股、両膝を屈曲させ、大腿が腹壁につくまで曲げ、骨盤、胸椎下部を十分に屈曲させる。ハムストリング、大内転筋、腸肋筋、最長筋がストレッチされる。腸肋筋、内腹斜筋、腹横筋が活性化され、寝返り自発訓練の準備が整う。(図18-B-b参照)
両股を痛みのこない範囲で十分に屈曲し、大腿を胸壁に近づける。骨盤および胸椎下部も屈曲し、背部伸筋群をストレッチさせる。
4)体幹のストレッチ
伸筋ストレッチ
側臥位をとる。側弯がある時は凹側を上にする。体幹の下にタオルを入れ、側弯を矯正する。術者は背側に坐る。術者の一側の手で腸骨部を持ち骨盤帯を後方に回旋させ、他側の手で胸郭部は前方に押し回旋させる(図18-C-a参照)。 腸肋筋、最長筋がストレッチされ、対側の腹横筋、内腹斜筋が活性化する。寝返りでの体幹回旋を容易にする。反対側も同様に行う。
屈筋ストレッチ
側臥位をとる。骨盤帯を前方に回旋し、胸郭を後方に回旋する。腹直筋と外腹斜筋がストレッチされる(図18-C-b)。
b.腹臥位ストレッチ訓練
●上位体幹、下位体幹、上肢、下肢の順に受動的伸張を行う。
1)頚椎、上位胸椎の伸展(図19-A参照)
●肩のレトラクションを抑え、手を前に伸ばす。両上肢を頭の方に伸展させ、上腕を頭の方へ伸ばすと鎖骨が上に上がり、胸鎖乳突筋がゆるみこの筋の緊張で動きを抑えられていた頚の抗重力伸筋が活動し、頭が上がってくる。顎の下に術者の指を置き、頭をゆっくり垂直に起こし、目の線を水平に保ちつつ左右に回旋させる。頭の重みを除くという柔らかい持ち上げ方がよい。右回旋で右胸鎖乳突筋がストレッチされ、左後頭下筋、左多裂筋が活性され頭が上がる。左回旋はその逆である。
2)上肢の頭方向への伸展
●両上肢を頭の方に伸ばす。広背筋、上腕三頭筋が肩でストレッチされ、上腕二頭筋が肘でストレッチされる。前腕は回外位を保つ。
3)両下肢の屈伸
●術者は患児の足側に位置する。まず一側から訓練を始める。患児は両上肢を曲げた姿勢で両下肢を中間外旋、やや屈曲位をとる。
一側下肢屈曲(開排肢位)
一側下肢の股関節を120~140°まで屈曲させる(対側は伸展位でよい)。膝関節も90°前後屈曲させる(図20-A,B参照)。
この肢位で股関節を術者の手でゆっくり床に押しつけ開排位をとる。1~2分以上した方が効果的である(右股は術者の右手で、左股は術者の左手で)。次にこの下肢を伸展させ、20~30°外転させ、内旋位をとり、股関節を術者の手でゆっくり床方向に押し、股関節を伸展させる(図20-C,D参照)。
屈曲肢位訓練では、ハムストリング、関節包内下方(大腿恥骨靭帯)が引き伸ばされ、求心位をとりやすい(図17-D参照)。また内下側臼蓋辰、横靭帯が広げられ、臼蓋内に骨頭がおさまりやすくなる(図17-D参照)。伸展位訓練では関節包内上方(大腿恥骨靭帯)が伸ばされ、大腰筋、大腿直筋がストレッチされる(図17-E参照)。対側も同様の訓練を行う。
両下肢屈曲
両下肢訓練では両上肢を同時に屈曲し、両股関節、両膝関節の伸展緊張をゆるめる。股関節は140°以上屈曲させ、大転子部を上から床面に向けてゆっくり圧迫し、外転させる(図19-B参照)。両上下肢は曲げている方が楽であるが、頭の方向に伸ばしてもよい。
股関節を90°屈曲位でこの訓練をすると、長内転筋が過緊張し、骨頭への急激な圧迫で痛みが出て患児の信頼を失うことになる。必ず140°以上の十分な屈曲角をとり、痛みのない外転・外旋位の伸張訓練を行う。下肢屈曲位は、股関節脱臼予防肢位として非常に重要な肢位であり、自発的な動きを呼びかけ、楽しいスポーツ感覚で進めたい。
c.前腕、手のストレッチ
1)前腕回内変形に対するストレッチ
●前腕回内変形では3つの段階のストレッチがある。回内の3つの要素、骨間膜・靭帯短縮、円回内筋緊張、橈側手根屈筋緊張が段階的にゆるめられる。
①肘を曲げ、手関節を掌屈のまま、前腕を回外する。骨間膜が伸び、橈骨小頭が輪状靭帯の中に安定整復される。
②肘を伸ばし、前腕を回外する。円回内筋がストレッチされる。
③手関節を背屈し、肘も伸展のまま前腕を回外する。橈側手根屈筋がストレッチされる。
2)手関節掌屈に対するストレッチ
①(指は曲げ)肘を屈曲し、手関節を背屈する。掌側関節包がストレッチされる。
②肘を伸ばし、手関節を背屈する。橈側手根屈筋・尺側手根屈筋がストレッチされる。
3)手指、母指屈曲に対するストレッチ
①手関節を背屈し、手指、母指を伸張する。
②ストレッチ手技のあと、母指対立装具や手関節装具を使うことがある。
d.下肢帯(足部)のストレッチ
①膝関節で足関節、中足部を持ち、足関節を背屈する。ヒラメ筋、後頚骨筋、長腓骨筋、および後方関節包がストレッチされる。
②中足部を背屈し、短趾屈筋など足趾底屈筋と足底筋膜をストレッチする。凹足変形を予防するストレッチ訓練として重要である。
③第1、第2、第3、第4、第5趾を伸展、背屈させ、長趾屈筋、短趾屈筋、骨間筋、長母趾屈筋、短母趾屈筋、足趾内転筋の緊張をゆるめる。
④膝伸展で足部を持ち、足関節を背屈させ、腓腹筋の過緊張をゆるめる。
3.ストレッチ訓練の原則
●ストレッチ訓練の原則は愛護的であり、あくまで訓練の導入的な意味をもつ。
●手技は無理をせず、患児との接触の中で信頼感を深め、緊張を寛解させる。
●手技は気持ちの良い範囲で行い、患児の能力や状態に応じて手技を考える。
●時間を決め、ダイナミック訓練に必要なストレッチ訓練だけを気持ちよく行う。
麻痺や脱臼を起こす危険性のあるストレッチ
①強引な頚のねじりと屈伸はしてはならない-
“頚をさわる訓練の時は、泣かせてはならない。麻痺を起こす危険が共存している”
②体幹のねじり、訓練に股関節以下は使わない
体幹のねじり訓練にはいろいろな方法があるが、ねじりを出すためには下肢をともにねじる方が容易であるが、これはきわめて危険である。寝返り誘発手技として下肢を屈曲させ、これを内転させて回旋させる訓練があるが手技的に簡単であればあるほど、脱臼を起こさせる手技として疑問視される。
③前腕回内位での肘伸展訓練はしてはならない
前腕回内位では橈骨小頭を取り巻く輪状靭帯はゆるみ、これに肘の伸展が加わると、輪状靭帯は前方関節包とともに中枢に引き上げられ、橈骨小頭は脱臼しやすい。
④膝関節伸展位での股関節屈曲訓練(長坐位訓練)
この訓練はハムストリングの緊張を除くために安易に行われているが、股関節脱臼を誘発させる危険性の高い訓練法である。ハムストリングの緊張は、膝関節屈曲位での股関節の屈曲ストレッチでゆるめたい(図19-B、図20-B参照)
⑤股90°ぐらいでの外転ストレッチはしてはならない
長内転筋をゆるめるための股90°屈曲位での外転ストレッチは、内転筋群の損傷のリスクを伴う。この手技を行う場合は過屈曲で外転を行う。
脳性麻痺と機能訓練3
今回は、第2章 機能訓練概論 Ⅱ.訓練の基本的考え方 になります。
第2章 機能訓練概論
Ⅱ.訓練の基本的考え方
1.緊張の抑制と随意性・抗重力性の賦活
●“選択的緊張抑制理論”の本質は、筋の過緊張を選択的に抑え、過緊張の下に隠されている随意的かつ抗重力的な筋の働きを、自発的な動きの中で出していこうというものである。
●(“選択的緊張抑制理論”は)自発性を尊重しつつ緊張を抑え、より随意性、抗重力性の高い動きを獲得しようとする。合理的な運動機能学的知識を積み重ね、駆使することによって初めて、より少ない抑制の中で随意性、抗重力性の活性化がはかりうる。
●機能解剖学的に正しく緊張の原因を理解することが必要である。
●基本的発想は多関節筋の過活動を徒手的に抑制し、単関節筋の抗重力活動を活性化するという考えである。
●基本的発想を訓練で応用化するには、さらに発達支援レベルを細かく分けたり、割り坐を活用したり、効果的なストレッチ手技を取り入れたり、動きの出やすい誘発手技を考案したりと、いろいろな運動学的知見を必要とする。
●抑制を加えると良い動きが抑えられるという懸念は、過去のものとなった。緊張を抑制する手技は、そのまま体の持ち上げ運動、巧緻運動の活性化につながるのである。
●運動学的ダイナミック訓練は対称性腹這い、対称性四つ這い、対称性坐位(割り座)を容認し、これまでの訓練法よりも自発性が高くなっている。
●過緊張はストレッチ、ダイナミック訓練、装具、キャスト、手術といった手段で、いつでも除きえるという視点をもっている。
2.抵抗は加えない(抵抗を排除し動きやすく)
●脳性麻痺では、痙性・固縮があり、これが重力と合わせ抗重力筋群に強い圧迫を加えている。
●脳性麻痺をもった子どもたちは、過緊張と重力という二つの重い圧迫にあって苦しんでいる。過緊張による圧迫をできるだけ少なくし、重力に打ち勝つ抗重力筋を育てるという原点からの訓練を考えるべきである。
3.発達に即した訓練を
●人の筋、骨格系、神経系は、系統発生学的に層状に発達してきている。
●運動系神経系をマクロ的視野でとらえ、その発達に応じた訓練を一歩一歩追っていくのが合理的であるが、運動発達の段階を細かく区分けして、その各々のランクでの訓練の具体的な手技を示す必要がある(表5参照)。
4.割り坐位の採用(割り坐を訓練の中心に)
●本論(“選択的緊張抑制理論”)のもっとも特徴的な部分は、まず麻痺の中にいろいろな随意性が隠されているととらえ、それを合理的に訓練(運動学的ダイナミック訓練など)によって引き出す、というものである。
●“割り坐は悪い肢位(分離性の悪い対称性肢位)であり、この肢位をできるだけ避けて訓練するほうが望ましい”とするこれまでの考え方を、自発的訓練をはばむ考え方として排除する。
●割り坐を1つの到達点として、訓練の中に取り入れていく時、腹這い移動から四つ這い移動へのきわめて整理された訓練体系が見えてくる。
●訓練では困難と諦めかけている股関節脱臼の予防も可能となる。
●将来起こりうる内旋歩行については、まず割り坐を育ててから次のステップの訓練として考慮すればよく、その訓練手技も、まず割り坐を獲得してから横坐訓練を中心に確立していきたい。
5.3つの自発的坐位獲得訓練
●従来、坐位については、横坐り、あぐら坐り、長坐り、椅坐位といった比較的レベルの高い坐位が訓練肢位として良いとされてきた。とくに、椅坐位は訓練の中心として重要視されている。
●著者らはこのような固定化した発想から離れ、坐位にもいろいろのレベルがあり、運動発達のレベルに応じて坐位訓練も変えるという発想をしている。
●自発的坐位獲得訓練は坐位を次の3つの段階に分け、発達に応じた坐位訓練を行っている。
①割り坐:腹這いと四つ這いの中間レベル
②横坐、あぐら坐、長座:四つ這いレベル
③椅坐:つかまり立ちレベル
6.交叉推進機能の活性化
●脳性麻痺治療のむずかしさの1つに、四肢交叉推進をどのようにして引き出していくかという問題がある。
●ボイタは反射性腹這いが存在するという考え方をもとに、四肢交叉推進の動きを出そうとしたが、閉塞感を強く伴ううえに手技が極めて難しい。
●交叉性を出すために、寝返りレベル、腹這いレベル、坐位レベル、四つ這いレベルの各々のレベルにおいて、交叉性を出しやすい手技が開発された。
●もっとも難しいのは腹這い位の中での交叉推進機能の賦活であるが、これは一側性交叉推進と四肢(両側性)交叉推進の動きが脳性麻痺児の動きの中にみられることをもとに、一側性交叉推進訓練の考え方を導入し、比較的容易に交叉推進訓練が可能になった。
7.ストレッチ訓練の活用
●ストレッチ訓練はこれまでは受動的とされ、その重要性はあまり強調されていない。
●訓練では正常な可動域を保つことが望ましく、そのためには自発的訓練の中でも、抗重力訓練の中でも、そしてリーチ訓練の中でも伸長訓練を十分に取り入れ、さらにストレッチ訓練で関節拘縮を予防するのである。
●先天性股関節脱臼や麻痺性股関節脱臼の治療で得られた新しい整形外科的知見を取り入れ、痛みのこない、股関節脱臼予防のためのストレッチ訓練を取り入れる。
●代表的な拘縮・変形としては、股関節脱臼、股関節屈曲拘縮、膝関節屈曲拘縮、尖足変形、肩関節脱臼、橈骨小頭脱臼、前腕回内変形、肘屈曲変形、手関節掌屈変形、側弯変形などがある。いずれもストレッチ訓練で軽減・予防をはかることができる。
●緊張・寛解のメカニズムは明らかにされていないが、局所伸張反射が一定時間以上のストレッチやキャストにより、一過性であるにしても低下することは、臨床のあらゆる場で認められおり、各種訓練に入る前の伸長訓練の重要性には、なんら疑問の余地もない。
8.感覚刺激としての触覚と平衡感覚
●感覚刺激として重要であり、運動の中でもっとも育てたいのは、正しい抗重力感覚と正しい分離推進感覚である。いずれも、地面に触れる感覚とその中から得られる体の位置感覚を重視するため、寝返り、腹這いといった訓練を重視している。
●ストレッチ訓練など、訓練の中で患児と術者との皮膚と皮膚、心と心のつながりといった接触感、さらには情感といったものを通わせる取組みを訓練の基本としている。
※メモ1:度々ご紹介させて頂いている、心理リハビリテーションの ”動作法” や、脳の可塑性に着目した ”アナット・バニエル・メソッド” ですが、これらに共通していた患児と術者の「心と心のつながり」などのメンタル面の重要性は、松尾先生が取り組まれていた ”機能訓練(理学療法)” においても重要視されているのだと強く思いました。
9.脳の可塑性は合理的訓練の中で
●近年、麻痺の回復のために、残存した脳の可塑性に働きかけるという訓練法があるといわれている。また、脳の可塑性に関する基礎的研究も大きく発達し、脳の一定の細胞系に可塑性があると証明される段階にもきている。
※メモ2:本書の初版は1995年ですが、図書館から借りてきて確認したところ、”脳の可塑性”に関する文章は、この24年前に発行された初版から同じ内容で掲載されていました。これは驚きでした。
脳性麻痺と機能訓練2
今回は、第1章 概論 Ⅴ.脳性麻痺筋緊張の特性 3.運動学的なとらえ方(一部)になります。
第1章 概論
Ⅰ.求められる機能訓練とは
Ⅴ.脳性麻痺筋緊張の特性
3.運動学的なとらえ方
●異常筋緊張は脳性麻痺の本質的な運動障害である。
●神経学的には異常筋緊張の大半を反射亢進や姿勢反射ととらえるが、運動学的にはこれらの反射を含め、すべての異常筋緊張を局所あるいは全身の筋の過緊張として細かく分析する。
●異常緊張には機能解剖学的にみて一定の規則性があり、異常筋緊張の抑制を考える。
a.人の筋機能の分布
1)単関節筋と多関節筋の機能的差異
●人の筋群は機能解剖学的には多関節筋群と単関節筋群から成り、それぞれが混じり合っている(図1参照)。
●多関節筋は体を推進させる推進筋であり、単関節筋は体の空間持ち上げをする抗重力性の高い抗重力筋である。
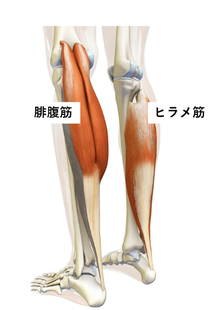
左の腓腹筋は膝関節+足関節=2関節→多関節筋。右のヒラメ筋は足関節のみ=1関節→単関節筋。
こちらは、STROKE LAB(ニューロリハビリ研究所)さまの ”脳卒中×触診【下腿三頭筋 腓腹筋―ヒラメ筋の起始停止:歩行の関係性】” という記事の中で使われていたイラストです。
●下腿三頭筋では、多関節筋である腓腹筋は、体の推進筋で足を底屈させ、その蹴る(底屈)力で体を推進させる。一方、単関節筋のヒラメ筋は同じ底屈筋でも、立脚中期に足をふんばって体を支える筋である。腓腹筋を推進底屈筋、ヒラメ筋を抗重力筋底屈筋という(図3参照)。
●股関節の腸腰筋も、多関節筋の大腰筋と単関節筋の腸骨筋に分けられる。大腰筋は体の前方推進を準備するために水平面で股関節を屈曲させる推進性屈筋であり、一方、腸骨筋は四つ這いなどで、体を抗重力的に空間に持ち上げるために、垂直方向に屈曲させる抗重力筋である。人の筋機能はこのように多関節筋群の推進性と単関節筋群の抗重力性が混じり合って、効率の高い運動を可能にする。

”立脚中期”をご説明するための図です。①~⑤が立脚期(足が地面に着く)で中期はその真ん中の③の状態です。なお、⑥⑦は遊脚期と呼ばれています。
この画像は、脳卒中の後遺症からの復帰に光をあてることを目的とされている「few against many」さまから拝借しました。
2)多関節筋の運動学的特徴
①水平面方向のみでの活動しかできない:多関節筋の特徴は、多関節にわたるための筋全体が長く力は大きいが、筋の長さに比し、筋腹は細く起始部も付着部もきわめて細い、したがって、関節を一定の肢位に保持する力に弱く、体を持ち上げるような抗重力的な力は働かせにくい。単なる粗大な推進力源としての屈伸運動しかできない。多関節筋のみでは水中や地上での屈伸などしかできず、四つ這いや立位など、体を地上に浮かすような動きはできない。
②分離運動ができない:2つ以上の関節にまたがった筋であるために、1つの関節だけの分離性のある動きができない。股関節を屈曲させるともに、膝関節は伸展させるなど、2つの関節にまたがった動きしかできない。
③粗大運動しかできない:多関節にわたる長い筋であり、大きな動きしかできず、しかも一定のパターン移動しかできない。水平面での推進をはかる粗大推進筋ととらえられうる。
3)単関節筋の運動学的特徴
①垂直方向の動きができる:単関節筋は筋の長さに比し、筋起始部の面積が広く、特定の関節を一定の肢位に保持することが可能であり、拮抗筋と協同しつつ、四肢体幹を垂直方向に持ち上げることが可能である。
②分離運動が可能である:1つの関節に属する筋であるために、1つの関節だけを他の関節と分離して動かすことができる。筋の長さも短く、その関節の細かい動きが可能である。また、初期的な抗重力筋は、四肢の動きを別々に分離させ、四肢交叉移動を可能にしている。
③筋腹が短い:単関節筋は、発達とともにさらに短い筋を分化させ、より抗重力性の高い動きを可能にしていった。しかし、筋腹が短くなればなるほど関節を小さく、より安定的に取り囲み、反面粗大な動きはできなくなる。したがって、抗重力・巧緻筋ととらえることができる(図5参照)。
b.脳性麻痺における多関節筋の過緊張
1.変形と多関節筋過緊張
●脳性麻痺では多関節筋が過活動し、痙縮や固縮、局所の変形、そして全身性の緊張性姿勢異常を引き起こす。
●尖足は腓腹筋の過緊張で引き起こされる。
●股関節屈曲変形は多関節筋である大腰筋、大腿直筋の過緊張で引き起こされ、かがみ肢位がもたらされる。
●股関節伸展緊張は多関節筋である半腱様筋、大腿二頭筋の過緊張で引き起こされ、腹這い、四つ這いでの股関節屈曲が妨げられる。
●肩のレトラクション変形は多関節筋である広背筋、上腕三頭筋の過緊張で引き起こされる(図10-A参照)。
2.反射と多関節筋過緊張
●反射も多関節筋の過緊張によって亢進する。
●膝蓋腱反射は大腿直筋の過緊張によって亢進する。
●アキレス腱反射は腓腹筋の過緊張によって亢進する。
3.伸張反射と変形
●伸張反射が亢進することにより変形がもたらされると考えられる。
●膝蓋腱反射亢進で伸展膝、反張膝がもたらされる。
●アキレス腱反射亢進で尖足変形がもたらさせる。
●手指、足趾の把握反射亢進で手指の屈曲と足趾の屈曲変形がもたらされる。
●上腕二頭筋反射亢進で肘屈曲変形がもたらされる。
●上腕三頭筋反射亢進で肘伸展変形がもたらされる。
c.脳性麻痺における推進性障害と固縮
1.屈筋、伸筋の同時緊張と推進性障害
●脳性麻痺の特徴的な病像に関節の固縮がある。運動学的には固縮は屈曲多関節筋と伸展多関節筋の同時過緊張によって引き起こされると分析される。
●人の関節の柔らかさと相反神経支配(相反神経支配の運動学的意義)
相反神経支配という神経学の言葉がある。これは運動学的には、“屈筋が働く時は、伸筋がゆるみ、伸筋が働く時は、屈筋がゆるむこと”という単純な現象である。人の関節の動きは、このような筋活動(神経学的には、相反神経支配という)によって柔らかく保たれる。このように、相反神経支配によって、全身の関節では屈曲・伸展両方向への素早い動きの転換が可能となり、効果的推進がはかりうる。
●関節を保護するための伸張反射(何のために伸長反射はあるか)
この動きは運動学的には、一側の筋が過度伸長された時に拮抗側の筋が瞬時に収縮し、過度伸長を防止する関節防御機構である。伸張反射は、運動学的には重要な生体側の防御機構ととらえられる。
●脳性麻痺における過剰な伸張反射と相反神経支配の破壊
伸張反射は脳性麻痺では屈伸両側で過剰に働き、関節の動きにくさがもたらされ、推進性の交互の動きが制限される。例えば、膝関節の屈筋が働こうとする時、拮抗筋の伸展も過剰に反応し、屈伸両側の筋が同時に緊張すると固縮がもたらされ、前方への動きが阻害される(図8参照)。
d.脳性麻痺における単関節筋の麻痺
1.単関節筋の麻痺と抗重力機能の低下
●人が発達の過程で分化させた単関節筋群は、中枢神経の損傷とともに麻痺し、抗重力機能が低下する。股関節では大殿筋、中・小殿筋が不全になり股関節の十分な伸展ができず、立位保持が困難になる。
●膝関節は内側広筋、外側広筋、中間広筋(大腿四頭筋の中で大腿直筋は多関節筋になります)の機能不全で膝の伸展力が低下し、効果的な立位保持ができず屈曲肢位になり、かがみ肢位(図6-A参照)、四つ這い肢位をとることになる。
●足部は骨間筋、ヒラメ筋の麻痺がきて、外反扁平足がもたらされ、支える力が弱く立位困難となる。
●上肢は上肢の挙上筋である三角筋や肘の伸筋である上腕三頭筋内・外側頭が麻痺し、持ち上げ機能が弱くなり、上肢の空間保持、四つ這い肢位保持などが困難となる。
2.多関節筋過活動による単関節筋活動の抑制
●多関節筋の過活動によって単関節筋の抗重力活動が抑えられる。
●股関節の単関節性伸筋である大殿筋は、拮抗する多関節性屈筋である大腰筋や大腿直筋の過緊張により活動が抑えられ、伸展パターンがもたらされ、効果的な四つ這い・立位移動ができなくなる。
e.多関節筋、単関節筋の概念と訓練への応用
1.緊張抑制と抗重力性活性化への応用
●多関節筋の緊張が拮抗する単関節筋の活動を抑えるという発想をすると、訓練上に有力な手掛かりが得られる。
●股関節の伸展緊張について、腹這いを考えてみる。ハムストリングの緊張を抑えて股関節を屈曲する(図10参照)。
単関節筋である腸骨筋が活性化されて股関節が曲がり、次の前進に備える。抑制が前進の妨げにならない(図43、44参照)。
こうして体内の筋を多関節筋と単関節筋に整理すると、これまで疑問視されていた抑制と賦活(促通)という発想が息を吹き返してくる。“多関節筋の過活動を抑え、抗重力単関節筋の働きを促進する”ということである。
2.多関節筋と単関節筋の走行の差(目線を水平にするという発想へ)
●多関節筋のV字状走行
多関節筋(最長筋)は、体の中心線(棘突起)から中枢方向へ体の外側に走行し肋骨や横突起に付着し、V字形の形をとる。したがって、この筋群が働くと体が横に傾きやすい(図11参照)。
頚では多関節筋の頭最長筋が働くと、頭が左右に振られ両方の目を結ぶ線が水平を保ちにくい。胸鎖乳突筋もV字形で頭が左右に振られやすく、目と目を結ぶ線が水平を保ちにくい。体幹も同じで胸最長筋と腸肋筋はV字形をとり、この筋群が働くと体が側方に振られやすい。屈筋側では、外腹斜筋はV字形をとり、この筋が働くと体が横に振られる。いずれも体の安定に働かない。
●単関節筋の走行
単関節筋は末梢寄りの体の外側(横突起)から、中枢へ体の中心線(棘突起)の方向に走り、逆V字形を示す。この筋群は少々活動しても頭や体幹は倒れにくく、両側性に働くと頭や体幹を垂直位に起こし、一側性に働くと体を回旋させる。これらの筋活動では、目と目を結ぶ線、あるいは肩と肩を結ぶ線がたえず水平に保立たれる。頚では、後頭下筋、短回旋筋、長回旋筋、多裂筋は筋が短く、逆V字形をとり、単関節筋的に働く重要な抗重力筋であるととらえられる(図12参照)。
目と目の線を水平に訓練
頭の持ち上げや寝返りでの抗重力的な姿勢とは、回旋によって目と目あるいは肩と肩を結ぶ線が、たえず水平に保たれるような姿勢であることが教えられる。逆に、目と目の線が垂直方向に傾けば、それは多関節筋の過活動による過緊張肢位ということになる。このことから目と目あるいは肩と肩を結ぶ線を、水平に保つ訓練が緊張を抑えるのにもっともよい重要な訓練であることがわかる。このような知見から、訓練はたえず目と目の線を水平にするような方向で行われるのが望ましいことがわかる。
脳性麻痺と機能訓練1
前回のブログ“小児の理学療法3”の付記に感想を書いていますが、脳性まひに対するリハビリテーションは筋骨格系に着目した理学療法と、心や脳に着目した新しい療法が両輪となって進んでいくことが求められているように思います。これはコンピューターで例えればハードウェアとソフトウェア、車でいえば自動車と運転手のような関係です。
今回の本は「小児の理学療法」と同じように「脳性まひ児の発達支援」の参考文献として紹介されていたものですが、筋骨格系に働きかける理学療法を理解するうえで、非常に優れた本ではないかと思います。そこで、長くなりますがブログを8つに分け、細かく勉強していきたいと思います。内容はすべて引用ですが、文章を短くするために箇条書きにしているもの、あるいは言い回しなどを変えているものなどが混在しています。
●脳性麻痺と機能訓練1:第1章 概論 Ⅰ.求められる機能訓練とは
●脳性麻痺と機能訓練2:第1章 概論 Ⅴ.脳性麻痺筋緊張の特性 3.運動学的なとらえ方(一部)
●脳性麻痺と機能訓練3:第2章 機能訓練概論 Ⅱ.訓練の基本的考え方
●脳性麻痺と機能訓練4:第3章 理学療法の実際 Ⅱ.ストレッチ訓練
●脳性麻痺と機能訓練5:第3章 理学療法の実際 Ⅲ.自発運動誘発訓練
●脳性麻痺と機能訓練6:第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 3.自立坐位獲得機能訓練
●脳性麻痺と機能訓練7:第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 4.四つ這い機能訓練
●脳性麻痺と機能訓練8:第3章 理学療法の実際 Ⅳ.ダイナミック訓練の実際 5.立位・歩行機能訓練
目次は以下の通りですが、8つのブログで取り上げた箇所を青字にしています。
第1章 概論
Ⅰ.求められる機能訓練とは
1.自発運動を中心とするダイナミックな訓練であること
2.愛護的訓練の重要性
3.訓練の本質を簡潔に要約する必要性
4.再現性が高い訓練であること
5.年長児では整形外科との補完の中で
Ⅱ.脳性麻痺の病像
Ⅲ.筋の痙縮(緊張)とは
1.一般的常識
2.実態は
Ⅳ.運動障害の本質
1.人の運動機能
a.推進機能
b.抗重力機能の発達
2.脳性麻痺における運動機能の破壊
Ⅴ.脳性麻痺筋緊張の特性
1.痙縮と反射の関係
a.局所の反射
b.反射肢位
2.神経学的なとらえ方
a.異常な反応(各種の反射亢進、姿勢反射)
b.正しい反応
c.その他の誘発反応
3.運動学的なとらえ方
a.人の筋機能の分布
b.脳性麻痺における多関節筋の過緊張
c.脳性麻痺における推進性障害と固縮
d.脳性麻痺における単関節筋の麻痺
e.多関節筋、単関節筋の概念と訓練への応用
f.全身性緊張(緊張性反射)の運動学的特性
g.全身性緊張と訓練
h.その他の異常姿勢
Ⅵ.麻痺(抗重力障害)
Ⅶ.推進機能障害
1.人が内蔵する推進機能
2.脳性麻痺の推進機能障害
3.交叉推進機能の活性化
第2章 機能訓練概論
Ⅰ.各種訓練法の特徴
1.ルード(Rood)理論
2.ドーマン(Doman)法
3.ボイタ(Vojta)法
4.ボバース(Bobath)アプローチ
5.上田法
Ⅱ.訓練の基本的考え方
1.緊張の抑制と随意性・抗重力性の賦活
2.抵抗は加えない(抵抗を排除し動きやすく)
3.発達に即した訓練を
4.割り座位の採用(割り座を訓練の中心に)
5.3つの自発的坐位獲得訓練
6.交叉推進機能の活性化
7.ストレッチ訓練の活用
8.感覚刺激としての触覚と平衡感覚
9.脳の可塑性は合理的訓練の中で
第3章 理学療法の実際
Ⅰ.理学療法とは
Ⅱ.ストレッチ訓練
1.体内の痙性筋
2.ストレッチ手技の実際
a.仰臥位ストレッチ訓練
b.腹臥位ストレッチ訓練
c.前腕、手のストレッチ
d.下肢帯(足部)のストレッチ
3.ストレッチ訓練の原則
Ⅲ.自発運動誘発訓練
1.ダイナミック訓練の中心
2.正常発達児と脳性麻痺児の運動発達の差
3.脳性麻痺児特有の運動発達とその評価
a.頭の回旋と持ち上げ
b.寝返りの発達
c.腹這いの発達
d.坐位の発達
e.四つ這いの発達
f.立位・歩行の獲得
Ⅳ.ダイナミック訓練の実際
1.寝返り機能訓練
a.仰臥位伸長訓練
b.自発的寝返り機能活性化の実際
c.寝返り訓練による異常姿勢反射の抑制と立ち直り機能の活性化
2.腹這い機能訓練
a.対称性腹這い訓練
b.交叉性腹這い訓練
c.腹這い訓練による異常姿勢反射の抑制
3.自立坐位獲得機能訓練
a.坐位と立ち直り機能
b.坐位を阻害する筋の過緊張と麻痺
c.自立坐位獲得訓練の実際
d.基本運動レベルの中での自立坐位獲得機能の位置づけ
e.自立坐位獲得訓練・四つ這い訓練と異常姿勢反射の抑制
4.四つ這い機能訓練
a.四つ這い肢位訓練
b.対称性四つ這い訓練(バニーホッピング)
c.交叉四つ這い訓練
d.交叉四つ這いと横坐り(正坐、あぐら坐り、長坐り)訓練
e.四つ這い移動を阻害する典型的脳性麻痺パターンとその抑制
5.立位・歩行機能訓練
a.つかまり立ちまで
b.つかまり立位から杖歩行まで
c.かがみ肢位歩行
d.直立二脚歩行
付.矯正したい不良肢位
Ⅴ.抗重力肢位訓練
1.側臥位保持訓練
2.腹臥位保持訓練
a.上腕支持訓練
b.肘つき支持訓練
3.四つ這い肢位訓練
4.坐位訓練
a.床坐位訓練
b.椅子坐位訓練
5.立位訓練
付.立位補助具
第4章 作業療法の実際
Ⅰ.作業療法とは
a.脊椎動物の機能(摂食と移動)
b.人における作業機能の発達
c.作業、上肢作業、その基本として生活能力の活性化を考える作業療法
Ⅱ.脳性麻痺の作業療法での要約的課題
a.摂食機能の獲得・改善
b.自力床坐位獲得訓練
c.車椅子生活自立獲得
Ⅲ.坐位
1.重度児の椅子
a.坐面
2.自分で漕げる車椅子
3.車椅子乗り降りの自立
Ⅳ.リーチ訓練と巧緻機能訓練
1.リーチ機能とは
2.リーチ機能障害の特徴
a.上肢過緊張
b.抗重力筋麻痺
3.リーチ機能の賦活
a.過緊張抑制
b.抗重力性関節周囲筋の賦活
c.手技の実際
4.上肢巧緻機能
a.ひっかき肢位
b.手つき支持レベル
c.つまみ・つかみ機能
d.離し機能
e.巧緻機能の活性化
Ⅴ.ADL訓練
1.食事訓練
a.口腔機能訓練
b.姿勢保持訓練
c.上肢機能訓練
2.衣服着脱訓練
a.姿勢保持訓練
b.上肢機能訓練
3.トイレット訓練
a.便器の工夫
b.トイレット訓練の方法
c.トイレット・トレーニングの実際
4.車椅子の自立をはかる
第5章 運動機能の活性化と整形外科
1.寝返り機能の活性化
2.腹這い機能の活性化
3.坐位獲得機能の活性化
4.四つ這い機能の活性化
5.立位・歩行機能の活性化
第6章 機能訓練―科学に基づく医学
(再録)脳性麻痺の機能訓練―基本運動訓練の実際と整形外科手術の位置づけ―
第1章 概論
Ⅰ.求められる機能訓練とは
1.自発運動を中心とするダイナミックな訓練であること
●機能訓練として最も求められる点は、自ら参加できるダイナミックな訓練であるという点である。
●坐位を獲得するためにどう緊張を抑えて訓練するか、四つ這い獲得のためにはどう緊張を抑え、分離性の高い動きを出したら良いかなどを分かりやすく示すことが求められる。
●ダイナミックな訓練とは、脳性麻痺児が持っている体内の“緊張を抑制し”、緊張のもとに隠されている“随意性が高く、かつ分離性の高い抗重力的な動きを活性化する”ことである。
体の色々な部位にある過緊張を、動きを促す際に抑制し、寝返り、腹這い、坐位獲得、四つ這いといった分離性の高い抗重力的な動きを引き出すという考え方である。このことを具現化するには、体内に散らばって存在する過緊張についてよく知る必要があるし、それを抑えるにはどのような肢位を取ったら良いかについても、十分に知る必要がある。その意味で、筋異常緊張についての勉強が求められる。
●発達レベルに応じた細かいランク付け。
●自発性を尊重した訓練をしようとすれば、まず脳性麻痺児を寝返りできないレベルから正常歩行まで多くの段階に分け、その各々のレベルでの訓練を考える必要がある(表4参照)。
患児がこの段階のどこに位置するかを評価し、1つあるいは2つ上のレベルを目標とした訓練を実施することによって患児が参加した自発性の高い訓練が可能になる。これらすべてのレベルで、1つ1つ具体的な訓練を考えなければならない。
例えば、腹這いの段階から四つ這いの段階までの間の訓練として、坐位、とくに割り座を入れ、割り座を訓練の中心におく(割り座が悪いという発想を改める)。そして、腹這いから割り座までの訓練を主要なものとして導入する。さらに、割り座から四つ這い肢位への訓練を展開する。
●ダイナミックな訓練には、運動学的、筋機能解剖学的に合理的な訓練が求められる。脳性麻痺では、筋、特に抗重力性の高い分離運動に参加する筋の力が弱い、これらの筋が働きやすい肢位を運動学的に見つけ、気持ちよく四肢を抗重力的に動かせるように援助することが重要である。
●神経学的症状・反射はすべて運動学的・解剖学的に分析し、運動学的訓練の理論的根拠を明らかにしている。
①寝返りを阻害する3つの緊張とそれを抑制する具体的手技
②対称性推進の考え方
③交叉腹這い訓練を容易にする一側性交叉推進の考え方
④四つ這いに移るための割り座肢位の活用
⑤坐位を3つの段階に分けるという考え方
⑥四つ這い肢位からよりレベルの高い坐位の獲得
⑦動きの中での緊張性肢位の局所的とらえ方
など。
●ダイナミックな訓練の基本は、あくまで患児みずからの力で誘導することであり、訓練する側は患児の力の足りないところを補うだけである。つまり、必要最小限の援助で、自発的な動きを最大限に発揮させることが大切である。訓練士は基本的手技を簡潔にまとめ、楽しい訓練を心掛けることが求められる。
2.愛護的訓練の重要性
●機能訓練は徹底して愛護的に進められるべきである。これは泣くことによって起こる動きは、早い動きの緊張状態であり、訓練の効果を否定するものだからである。随意的かつ抗重力的な動きとは、泣くといった不快な状態では引き起こすことはできない、柔らかいゆっくりした動き(単関節)であり、快適な状態で初めて活性化できるものである。
●過緊張を1つの関節で抑えると、随意的な動きがその関節を中心に出やすくなるため、患児は心地よく動きはじめ、楽しみをもって訓練に参画する。
●人は誰でもスポーツをしたい、体を動かしたいという欲求をもっている。麻痺の子どもでも、少しは動く力が残されている。しかし、重力と異常な過緊張によって動くことができない。この子どもらにとっては、周囲の人がこの筋緊張の大半を抑えてくれることにより、残りの力で体を動かすことができるのである。そして、それが何よりの喜びとなるのである。
●訓練は、あくまで機能の改善を期待して行うものである。しかし、たとえ改善がなくても、スポーツとして運動をさせることの意義は大きい。
3.訓練の本質を簡潔に要約する必要性
●脳性麻痺の病像は多様であり、一人ひとりの個性をもった患者を治療するため、訓練のあり方も、遊びを中心とした穏やかなものから、積極的な訓練色の強いものまである。また、当然手技そのものも多様なものが準備されている。これまで報告された治療手技も、PNF、ルード(Rood)、ボバース(Bobath)、ドーマン(Domain)、ボイタ(Vojta)、上田など、各種の方法がある。訓練士、看護師、保育士、教師、保護者は、それぞれの置かれた立場によって、色々な運動面のアプローチをすることとなるし、そのことを大事にしなくてはならない。
●訓練が科学として本質的に求められているのは、この混沌の中で何を基本的に観察し、どのように無理な力を入れない穏やかな、しかもダイナミズムにあふれた訓練を育てるかといった訓練の基本的な考え方をまとめ、公開の場で明らかにすることである。
注)“この混沌”とは次のようなことです。
『訓練の世界はまだその知見が整理させず、不用な知見と有用な知見が氾濫しており、どの理論も正しいことをいっているとしても、不用不急な知見の羅列も多い。本質的に、どのレベルではどこをどのように訓練したらよいのかが、まだわかりやすく要約されていない。このため、保育士、保護者、教師など、誰もがどこでもできる訓練の方法が示されず、特定の療法士間だけの閉鎖的な空間の中で訓練が語られるという事態がみられたりする。科学的であるための必要条件としての再現性に欠けるのである。このため、より合理的な訓練のあり方が公の場で語られることなく、訓練で患児が泣き叫ぶといった事態が発生したりする。』
●訓練の基本を知ることによって、遊び方、訓練の方法はより効果的かつ愛護的になりうるし、他の訓練法との比較のうえで、より合理的な部分を選択することも可能になる。このことによって、初めて保育士や保護者や教師といった患児に接触する人たちが、子どもたちの訓練に参画できることになる。
●本書では訓練の本質を“選択的緊張抑制と随意性、抗重力性の賦活”と要約し、多様な運動障害への応用をはかろうとしている。また、他の訓練法が合理的である限り、両立が可能である。
4.再現性が高い訓練であること
●科学としての訓練はどこで行っても効果があるはずである。家で行う、学校で行う、保育の中で行う、といったもので、訓練室だけのものであってはいけない。日々の生活の中の楽しい運動誘発の取組でなければ、科学として認知されにくい。
●最も本質的なこととして、同じ訓練手技が、生まれてしばらくした乳児でも、幼稚園児でも、学童児でも、学校を卒業した成人でも、高齢者でもまったく同様に行えるということがあげられる。同じ訓練が、どんな症状の軽い人にも、また症状の重い人にも、基本的には同様な考え方で行われえるのかどうか、という問いつめが求められよう。“この訓練は学童期や成人には効果がなく、子どもだけにしか効果がない”というのでは、科学にはならない。学校の教師らが養護学校での訓練にさいし、理学療法、作業療法による訓練を諦め、心理リハビリテーションによる養護訓練に走ったのは、医療サイドが、乳幼児にも学童児にも同じように行われえる訓練を追求し、またそのような訓練を学校の教師に指導する努力を怠ったことに、その原因の一端があることは否定できないであろう。
注)心理リハビリテーションとは
『心理リハビリテーションとは、成瀬(九州大学名誉教授)と彼の共同研究者たちが開発した、動作課題を通じて動作不自由の改善と心身の活性化を目的とした、わが国独自に開発された心理臨床の一連の技法と理論をいう(成瀬、1995)』
“沖縄県における心理リハビリテーションの展開”より引用。クリック頂くとPDF22枚の資料がダウンロードされます。
5.年長児では整形外科との補完の中で
●訓練を通じて、徐々に、段階的に機能を伸ばしていくことが最善である。
●股関節脱臼の予防訓練、側弯矯正と呼吸訓練、ADL(activities of daily living,日常生活動作)訓練に必要な回旋訓練など、これまでの整形外科や機能訓練の知見をもとに体系化し、乳児期に必要な多彩な訓練体系を実現することが大切である。
●脳性麻痺にみられる過緊張は、本質的には保存的治療である機能訓練ではどんなテクニックを用いても除かれえず、加齢とともに関節や筋・腱の変形性や老齢化を早めることになる。いたずらに過緊張を訓練で抑えるという発想を年長児の治療に持ち込むことなく、整形外科領域の知見で過緊張を除き、機能訓練で随意性、抗重力性をより容易に引き出すという考え方(図8参照)が、もっとも今日的かつ合理的な治療といえるであろう。
注)一つ注意したいと思うのは、改定第2版の発行は2002年、約17年前です(初版は1995年)。そのため、手術の位置づけなども変わってきているかも知れません。
●ダイナミズムをもった能動的訓練は、脳性麻痺の特性や人の運動の特徴を十分に理解したうえで初めて可能になる。
注)「整形外科領域の知見で過緊張を除き」とは
本書のⅡ脳性麻痺の病像、の中にある表1は以下の通りです。
この表の“整形外科”の項目には“選択的緊張筋解離術”という記載があります。「これは何だろう?」と思い検索したところ、『東京都 南多摩保健医療圏 地域リハビリテーション支援センター』というサイトに、著者である松尾隆先生の南多摩整形外科病院(2017年12月より「まちだ丘の上病院」と病院名が変更、松尾先生は2017年11月に退任されていました)の理学療法士の方達の資料を見つけました。
小児の理学療法3
前回の “小児の理学療法2”で注目したのは“脳性麻痺”を詳しく知ることでした。これは良い施術を提供するための大前提と考えるためです。そして最後となる今回は第6章の運動療法を取り上げました。
運動療法を学ぶうえで、我々に求められる具体的な施術(マッサージや鍼治療[刺さない鍼や円皮鍼を含む])がどのようなものになるのか、できる限り事前に想定しておいた方が望ましいと思い、あらためて第5章の脳性麻痺に戻って、洗い出した内容を整理整頓し見直すことにしました。
狙いは脳性麻痺の種類別に整理したという点です。黒字には問題点、青字には対策や課題、赤字には脱臼の原因が書かれています。太字は重要と思った部分であり、さらに“痙性”と“分離運動”を斜め文字にしたのは、これらが施術の柱になるのではないかと考えるためです。
続いて、この表のそれぞれの太字を全体的視点で眺め、抽出したポイントが以下になります。このポイントを頭に入れて第6章に進みます。
上の図の中で補足したいのは、ほぼ中央に書かれた”大腿筋膜張筋”です。
これは第5章 脳性麻痺ー2.痙直型両麻痺ー16)股関節脱臼 に書かれていたもので文章は次の通りです。
『股関節の内転・内旋変形は同時に起きる。この変形の責任筋は大腿筋膜張筋と考えられている。』なお、これに次の文章が続いています。『また内転では長内転筋と薄筋の痙性が要因と考えられている。』
大腿筋膜張筋に血液がしっかり流れ込み、筋肉が良い状態(軟らかい)になり、細い筋線維が適切なトレーニング等で太く、力強く成長させることができれば股関節脱臼のリスクは減らせるのかも知れません。
ところで、私は今まであまり大腿筋膜張筋を注目したことがありませんでした。そこで今回、その大腿筋膜張筋に焦点を当てたいと思います。
次に大腿筋膜張筋と周辺の筋肉とのつながりについて確認してみます。以下の二つの画像はいずれも『改訂版第2版 骨格筋と触察法』から拝借しました。右側の図では左端中央付近に大腿筋膜張筋が出ています。これを拝見すると大腿筋膜張筋+腸脛靭帯の重要性が理解できます。

左の図は『病気がみえる vol.11 運動器・整形外科』から拝借したものです。
大腿筋膜張筋は中殿筋とともに、下肢の外転に大きく関与していることが分かります。
なお、『小児の理学療法』の中には次のような記述があります。「痙性分布には必ず左右差がある。体幹深部筋の痙性分布の非対称性により、肩甲帯と骨盤帯の位置異常が発生しやすくなる。また、体幹の表在筋、とくに内転筋と内旋筋の痙性分布により、四肢の外転運動が制限されてしまう。」
第6章の目次は以下の通りです。今回はすべて網羅しています。
第6章 運動療法
1.頭のコントロールのための運動療法
1)背臥位での頭の回旋
2)腹臥位での頭の回旋
3)腹臥位での頭の挙上
4)背臥位からの頭の屈曲
5)頭の固定性を高める準備としての圧迫手技
2.上肢の挙上運動とリーチの準備
3.上肢の支持性
4.脊柱の側屈可動性の準備
5.脊柱の伸展可動性の準備
6.パラシュー反応の誘発
1)パラシュート反応誘発のための準備
2)パラシュート反応の誘発
7.減捻性立ち直り反応を応用した運動の誘発
1)体に働く頸の立ち直り反応
2)体に働く体の立ち直り反応
3)抗重力方向への体に働く体の立ち直り反応
第6章 運動療法
1.頭のコントロールのための運動療法
●未熟者の頭は前後径が長く横径が狭いため、どちらか一方を向いており頭の回旋がうまくできない。
また、水頭症の子どもでは体の大きさに比較して頭部が大きいため、頭を動かすことが困難となる。脳性麻痺児も同様に中枢神経系障害のため、頭部をコントロールすることが困難である。頭のコントロールの獲得はこれからの運動発達の出発点でもあり、非常に重要な役割をもっている。そのため、頭のコントロールを促すように運動療法を計画しなければならない。ここでは基本的な頭のコントロールの刺激の方法を示す。
1)背臥位での頭の回旋
●頭の回旋を刺激する方法として、視覚、聴覚、触角を刺激し、できるだけ自発的な運動を引き出す。
●視覚刺激では明るい赤や黄色などの原色の玩具を乳児の目の位置から20~30cmの位置でまず見せるようにする。乳児が玩具を見ていると確信できた段階でゆっくりと玩具を動かし、乳児が目を動かしてくるかどうか確認しながら頭の回旋を刺激する。
●聴覚刺激は耳の高さを中心に直径15cmの円内で行う。乳児が驚くようであれば音を優しいものに変えていく。
●触覚刺激で代表的なものは探索反応で、この反応は乳児が空腹のときに出現しやすく、満腹時には出にくくなる。なお、探索反応を誘発刺激として使用できるのは、未熟児、乳児に限定される。
●体幹を側屈させることで頭の回旋を促す方法は、自発的な頭の回旋をなかなか見せてくれない乳児や脳性麻痺児に適している。セラピストは骨盤を持ち頭が回旋している側に骨盤を挙上し、ゆっくりと体幹を側屈させていく。
●背臥位で後頭側の肩を床の方向に押し下げる。同時に後頭側の上肢を外転位にし、腕を引き出して刺激する。この方法は注意しないと自発的な頭の回旋ではなく、刺激の反動で頭を他動的に回してしまうだけになるため、最初はゆっくりと刺激を加え、子どもの反応をみながら段階的に刺激を強めていくことが大切である。
2)腹臥位での頭の回旋
●子どもを腹臥位に置き、顔面側の上肢を屈曲し体側に沿わせ、手が乳児の口の周辺に位置するようにする。後頭側の上肢は伸展させ、体側に沿わせる。次に後頭側の肩を床から持ち上げ、顔面側の上肢の前腕に体重が移るように操作する。このとき、子どもの鼻が床に押しつけられるような位置になるが、そのまま子どもが反応するのを待つ。これは体に加えられた非対称的な圧分布が頭を正しく立ち直らせる「頭に働く体の立ち直り反応」を刺激している。
3)腹臥位での頭の挙上
●子どもを腹臥位に置き、肘付き腹臥位をとらせる。続いて、両肩を広げるように下から上に向かって肩を押す。そして、ほぼ同時に広げるように下から上に向かって肩の固定性を高める目的で肘の方向に押しつける。この一連の動作を素早く繰り返し、頭の挙上を促す。子どもが頭を持ち上げてきたら刺激の間隔を広げていく。
●子どもを腹臥位に置き、まず両腕を子どもの顎をすくうようにセットする。次に、子どもの頭を上方に押し上げるように両腕を動かす。このとき、頭の挙上だけではなく、脊柱の抗重力伸展も同時に促す。
●子どもを腹臥位に置き、まず両上肢をまず挙上する。次に、上肢の中枢部を持ち、肩を外旋させながら、床から持ち上げ脊柱の伸展を促す。同様のことを肘や手から操作して頭の挙上を促す。脊柱の抗重力伸展が適切に促されると両下肢の外転が生じる。
4)背臥位からの頭の屈曲
●子どもを背臥位に置き、両腕の前で肩を内転させる。次に、子どもを下肢の方向に両腕を内転・内旋させながら引き起こしていく。逆に子どもを座位にセットした後、徐々に背臥位へ近づけていき、頭の屈曲を保たせる。
5)頭の固定性を高める準備としての圧迫手技
●子どもを腹臥位に置き、頭と骨盤を両腕で挟み込む。そして、両手で同時に体を圧縮するように軽く繰り返す。この手法は子どもの全身が低緊張のときに使えることがある。
2.上肢の挙上運動とリーチの準備
●上肢の自発運動が少なかったり、運動がみられない場合、自発的な上肢の運動を誘発する必要がある。このような場合、台乗せ反応を利用することができる。とくに固有感覚性の台乗せを刺激することで上肢の運動を引き出すことができる。子どもの上肢を体側に沿わせ、手背を床に向ける。次に、手掌部から床方向に圧迫を加え、手背に固有感覚刺激を入れていく。このとき、子どもは刺激に応じて上肢を体側から上方に挙上しようとして肩を床から持ち上げ、挙上運動を開始する。この挙上運動にセラピストはついていき、挙上に伴い、手関節が背屈するまで待つ。
3.上肢の支持性
●上肢の支持性が未熟な子どもをただ腹臥位に置くだけでは、上肢の支持性は改善してこない。このような場合には、子どもが頭を挙上しやすくするために、胸の下にバスタオルなどを丸めたものを入れてやり、胸部を床から離すようにする。このような姿勢を5分から20分間保てるようにする。子どもの手元に好きな玩具を置いたり、好きなテレビ番組をこの姿勢で見せるのも良い。
●on elbowsはとれるがon handsまでの姿勢になれない子どもには、上肢伸展支持を促す刺激をつかう。子どもの両肩を保持し、斜め後方へ体を引き上げる。子どもが反応しない場合は保持しているセラピストの手で体を上下させて、子どもの上肢伸展を促す。子どもが反応を示したら、セラピストの介助を減らす。
4.脊柱の側屈可動性の準備
●重症な脳障害をもつ乳児は早い段階から体幹の可動性の乏しさを示す。乳児の体幹は硬く、体幹の側屈、伸展、屈曲に強い抵抗を示すことがある。このような場合、他動的ではあるが乳児の体幹に側屈の可動性を体重移動と組み合わせて行うことで、体幹の柔軟性を得ることができる。
5.脊柱の伸展可動性の準備
●上肢の支持性には脊柱の重力に抗した伸展が不可欠である。しかし、痙直型両麻痺、片麻痺、四肢麻痺の体幹部の痙性により十分な伸展活動が行えない症例が存在する。そのような症例に対して、事前に脊柱の伸展の可動性を引き出しておく必要がある。
①子どもをバルーン上に背臥位でのせる。セラピストの両手を子どもの脊柱の両側に位置させる。次に、上部脊柱から順に骨盤に向かってバルーンを振動させ、脊柱全体にわたって伸展可動性を高める。十分に脊柱が伸展し、体幹に分布する屈筋痙性が減少してくると、子どもの上肢がリラックスして重力方向に挙上位をとるようになる。
②子どもが年少の場合にはセラピストの膝の上でバルーンと同様に脊柱の伸展を引き出すことができる。セラピストは両手で子どもの骨盤をしっかり保持し、両膝を脊柱の両側に位置させる。次に膝を軽く上下させ脊柱に振動を与える。そして、少しずつ子どもを下降させていき、脊柱全体にわたって伸展性を引き出していく。
③子どもを腹臥位に置き、顔面側の肩を床から持ち上げ、反対側から脊柱を軽く圧迫する。肩を床から持ち上げ、脊柱を固定すると、体幹の回旋と伸展が引き出される。脊柱の固定点を徐々に骨盤に向かって移動させ、脊柱全体にわたる伸展と回旋の可動性を引き出す。
子どもをセラピストの両大腿部にまたがらせる。次に、両脇で上半身を抱え込み、一方の手は骨盤に当てる。そして子どもの体幹を伸展し回旋させる。このとき、骨盤に当てた手で股関節を十分に伸展させる。この手技で股関節外転制限の緩和をはかることが同時にできる。
6.パラシュー反応の誘発
●上肢にある程度支持性がつき、そして、保護伸展反応に不可欠な脊柱の抗重力伸展もある程度準備できたら上肢の保護伸展反応であるパラシュート反応を誘発していく。
1)パラシュート反応誘発のための準備
①子どもを膝立ち位に置き、子どもの両手をセラピストの手で受ける。次にゆっくりと前方にセラピストの手を引き下ろしていく。ある時点で子どもの体重がセラピストの手に重くかかり始めるポイントがある。そのポイントで少しの範囲で素早く引き下ろし、そしてただちに押し返す。これを繰り返していくと子どもは上肢をしっかりと伸展・支持してくるようになる。
2)パラシュート反応の誘発
●子どもをバルーン上に腹臥位で乗せて、前方にいろいろなスピードで押し出す。うまく手を出して支えることができるようになってきたら、できるだけ遠くに接地する。注意深く行い、頭部を叩打しそうな場合には素早く引き戻す。同様の方法で大きめのローラーを使ってパラシュート反応を誘発することもできる。
●子どもを端座位にし、セラピストは子どもの両下肢を外転させて、子どもの前に位置する。次に子どもの両手を交差させて保持し、次にセラピストの左手を離し、右手で子どもを側方に素早く誘導する。セラピストの離した左手はすぐに子どもの腹部を支持するようにする。子どもの手の着く位置を側方から徐々に後ろへと変化させていく。後方になればなるほど、子どもに体軸内回旋が要求される。
7.減捻性立ち直り反応を応用した運動の誘発
●人間の体の分節は3つあり、その一部に捻じれが加えられた場合には、その他の分節を使って元の正しい位置関係(アライメント)に戻そうとする減捻性の立ち直り反応が存在する。脳障害による発達障害児ではこの減捻性の立ち直り反応は潜在的にもっていても、自発的な首の運動が他の分節の捻じれをつくりだし、他の分節の反応が出現するまでに時間がかかる。このように反応の出現するまでに時間がかかるような現象を潜時が長いと表現する。同一の刺激部位で時間をかけて刺激することを時間加重とよび、複数の刺激部位を同時に刺激することを空間加重とよぶことがある。
1)体に働く頸の立ち直り反応
後頭部を保持する。そして一方に頸部をゆっくり回旋していく。回旋していくとある点でゆるやかな抵抗を触診することができる。そのポイントからさらに回旋を続けると、これ以上回旋できない所に到達する。その最終ポイントで頸部を保持して頭部以外の分節が出現するまで待つ。減捻性の反応が出現し胸郭、骨盤の回旋が出現し始めたら、それに合わせて頸部の回旋を続けていく。その結果、児は腹臥位にまで姿勢を変換していく。
2)体に働く体の立ち直り反応
●胸郭部と骨盤部の捻じれを骨盤部からつくり、胸郭部が捻じれを打ち消すように骨盤部と同じ方向に回転を起こす。胸郭部の回転が頭部の回旋を誘導し、迷路性立ち直り反応や視性立ち直り反応、頭に働く体の立ち直り反応が動員されて頭を床から持ち上げてくる。
※体に働く体の立ち直り反応は体幹の一部に加わる捻じれを元に戻そうとする反応で、体幹を対称的な位置に保つように働く。減捻性反射ともよばれ、生後4カ月から出現すると考えらええている。動作の連続性の面から乳児の観察をすると、背臥位から立位に至るまで、動作中に多くの体に働く体の立ち直り反応が観察される。
3)抗重力方向への体に働く体の立ち直り反応
●体に働く体の立ち直り反応単独で起き上がりが可能になるわけではなく、視性立ち直り反応、迷路性立ち直り反応、手指の把握機能などが協調してはじめて可能となる動作である。起き上がり動作中に出現する体幹の減捻性の回旋運動は発達とともに減少していくが、初期の段階では大きな回旋運動を伴う。この回旋運動の反応速度は運動発達と密接に関係しており、反応速度は運動発達の変化を強く反映している。
付記:下肢の痙性・分離運動
“脳性麻痺”を表形式で整理整頓し、続いて運動療法を勉強していったのですが、下肢の痙性や分離運動という問題に対し、これらに特化した運動療法はなく、総合的に改善に取り組んでいくもののようだということが分かりました。
硬くなった筋肉をマッサージや鍼で緩めることは可能ですが、根本対策は別にあるように思います。そのヒントは過去ブログの“動作法(姿勢の不思議)”と“アナット・バニエル・メソッド2(症例)”の中に隠れていそうです。注目すべきキーワードは“自己弛緩”と“脳の可塑性”です。
以下に過去ブログの内容の一部をご紹介します。そして、その詳細検討は今後の宿題とさせて頂きます。

著者:成瀬悟策
発行:講談社
発行:1998年7月
まえがき
『脳性マヒで動かないはずの腕が、催眠中に挙がったという事実に直面したのがことの始まりで、それ以来30年を経て今もなお、人の「動作」というもののおもしろさに取りつかれっぱなしの状態です。
脳性マヒによるからだの強烈な緊張を、脳・神経系から筋・骨格系への生理過程によって弛めるという当初の考えは、現実には役に立ちませんでした。そのからだの持ち主の心理的な活動によって自らのからだを弛めることで、初めて治療効果が上がり始めたのです。自己弛緩さえできるようになればと努めるうちに10年ほどが過ぎました。そして、自己弛緩だけでは不充分で、自らの意図どおりにからだを動かす要領を身につけることが必要とわかり、そのための訓練を続けるうち、また10年がすぎていきました。
それからの後の10年でさらにわかったのは、重力にそってからだを大地上にタテに立てることが必要であることでした。それは、からだを立てるための心棒、すなわち体軸をまっすぐに立てて自然に無理のない姿勢がとれるということです。そしてその状態から体軸のどの部位でもそれを柔軟に屈げたり伸ばしたり、反らしたり捻ったりしながら、上体部、手腕、脚足を前後左右に使いこなせるようになることが課題となりました。』

著者:アナット・バニエル
発行:太郎次郎社エディタス
発行:2018年8月
ボールのように硬く丸まってしまうリリー
『リリーと初めて会ったのは、彼女が三歳のときです。たいへん未熟な状態で生まれ、重度の脳性まひを負っていたリリーは身体が小さく、一歳といっても通用するほどでした。彼女が母親や妹とやりとりする様子は乳児のようで、のちに母親から聞いたところでは、生後五か月ていどの発達段階だと判定されたということでした。
リリーは筋肉の緊張が激しく、つねに肘をきつく折り曲げ、握りこぶしをつくっていました。両脚は膝が少し曲がった状態で交差しています。腹筋がつねに収縮しているために背が曲がり、自分の体重を支えることができません。自発的な動きがなく、寝返りを打つことも、うつぶせでいることもできません。うつぶせにすると身体を丸め、苦しそうにします。座らせるとたいへんな力を出してなんとか座るものの、背中はすっかり丸まり、数秒すると転がってしまいます。腕や手を使うことはできません。声は小さく不明瞭で、何を言っているか理解するのは困難でした。
しかし、そのような状態でも、私にはリリーがしっかり目覚めて神経を研ぎ澄ましていることがわかりました。大きな茶色の目で、興味深そうに周囲の様子を追っていたからです。
リリーを仰向けにレッスン台に寝かせましたが、その姿勢でも筋肉は収縮したままで、両脚は曲がり、台からやや浮いています。肘は折れ曲がってぴったり身体に引き寄せられ、腹筋も硬いままです。脳が、どのように力をぬけばよいのかをわからないのです。
左脚をやさしく持ち上げ、できる限り小さく動かそうとした瞬間、収縮していた筋肉がさらに強く縮み、リリーはボールのように丸まりました。私は手を止め、彼女が落ち着くのを待ちました。つぎに骨盤を、やはりできるかぎり小さく、とてもゆっくり動かそうとしましたが、今度も強く筋肉が縮みました。速度を思いきり落として、安心できるように話しかけながら、とても小さく、わずかに動かしてみても、筋肉は硬くなりました。私が動かそうとするたびに、彼女の脳は、身体をボールのように丸めるという未分化で強力な初期の動きのパターンに乗っとられるかのようでした。
十分ほどそのようにしていると、ある考えがひらめきました。ボールのように身体を丸めるのは脳性まひの影響だけでなく、学習したパターンだからではないか、と思ったのです。リリーはどう見ても動きたがっていました。彼女は彼女なりの方法で動こうとしているのに違いはありません。
リリーは二年近く、うつぶせにされ、座らされるという訓練を受けていました。訓練では握りこぶしを開かせようとしたり、立たせようとすることさえあったそうです。そのようなとき唯一リリーの脳にできたことは、強く収縮することで、そのため身体は丸まりました。自分から動こうとするとき、また、自分を動かそうとするあらゆる働きかけに対し、彼女の脳は、収縮するというパターンを結びつけることを学習したはずです。』
小児の理学療法2
前回の “小児の理学療法1”で注目したのは、“セラピスト(理学療法士)に求められていることを知る”、そして“小児障害児の運動特性と関節・筋肉”の二つでした。今回は第5章の脳性麻痺を取り上げましたが、これは脳性まひを詳しく知ることが良い施術の大前提と考えるためです。
覚えておきたいことが多く、太字や青字がやたら多くなってしまいました。太字は主に問題点、青字は主に対策や課題、なお、赤字が4箇所ありますが、これは脱臼の原因について書かれた部分になります。
※メモ:2017年1月にアップしたブログに“脳性麻痺 vs 脳性マヒ”があります。以降、“麻痺”という漢字は使わないようにしています。しかし、優先すべきは引用させて頂いた本の表記になりますので、今回のブログの中でも“麻痺”という漢字を使っています。なお、なぜ漢字ではなく“マヒ(まひ)”を使った方が良いのかについては、臨床動作法を創始された成瀬悟策先生の書『姿勢のふしぎ』の中の一文にあります。

『脳の病変によって肢体が不自由になる現象を、本書ではここまで「脳性麻痺」ではなく一貫して「脳性マヒ」と表記してきたのは、一般に「麻痺」ということばが「神経や筋の機能が停止する状態」(広辞苑)とされているためでした。これまで述べてきたように、この子たちのからだは病理学的に動かないのではなく、生理的には動く自分のからだを、その主体者が自分の思うように動かせないだけですから、「麻痺」ということばはそぐわないため用いません。』
第5章の目次は以下の通りですが、うすいグレーの項目については触れていません。
第5章 脳性麻痺
1.痙直型四肢麻痺
1)痙性の分布
2)関節への体重負荷、自発運動の意義
2.痙直型両麻痺
1)臨床像
2)痙直型両麻痺の病因
3)両麻痺の痙性分布
4)両麻痺の発達の特徴
5)両麻痺の頭のコントロール
6)両麻痺のキッキング
7)両麻痺の寝返り
8)両麻痺のハイハイ
9)両麻痺の起き上がり動作
10)痙直型両麻痺の割り座に対するアプローチ
11)両麻痺の移動
12)両麻痺のつかまり立ち
13)両麻痺の立位姿勢
14)両麻痺の認知障害
15)つま先歩きをする子どもたち
16)股関節脱臼
3.痙直型片麻痺
1)初期症状
2)片麻痺の発達の特徴
(1)片麻痺の正中位指向の特徴
(2)片麻痺の寝返りの特徴
(3)片麻痺のハイハイの特徴
(4)片麻痺の四つ這い
(5)片麻痺の座位
(6)片麻痺のずり這い
(7)片麻痺の起立
(8)片麻痺の歩行
(9)片麻痺の健側手
(10)患側の手の活動と代償運動
(11)片麻痺の尖足
(12)片麻痺の連合反応
(13)正常な連合運動
3)アテトーゼ型片麻痺
4)後天性片麻痺
5)片麻痺の問題行動
6)片麻痺の治療
4.アテトーゼ型脳性麻痺
1)アテトーゼ型脳性麻痺に共有する特徴
2)アテトーゼ型脳性麻痺の分類
3)アテトーゼ型脳性麻痺の治療
5.弛緩型麻痺
1)脳性麻痺の初期症状としての弛緩
2)姿勢および反応
3)アテトーゼへの移行(移行期のサイン)
4)弛緩児の治療
第5章 脳性麻痺
1.痙直型四肢麻痺
●四肢麻痺の多くは重度で、いくつかの障害を重複していることが多い。
1)痙性の分布
●四肢のみならず、中枢部である体幹に硬さをもっている。
●変形や拘縮が多く発生するタイプである。
●四肢麻痺の多くが他動的な体幹の側屈や屈伸、回旋運動に対して強い抵抗を示すことが多い。
●四肢麻痺に限らず、他のタイプにもいえることであるが、他動的な操作に対して抵抗を示す部位は児の自発運動が極端に低下している部位でもある。
●頸のコントロールも獲得していない児も多く、彼らは背臥位でどちらか優位に一方へ頭を回旋させている。そのため、頭部の非対称性に由来する体幹、四肢の非対称的な筋緊張分布を呈する。
●頸筋には多くの固有感覚受容器である筋紡錘が分布しており、頭部の動きが全身の運動性を引き出すことを考えれば、彼らの頭部の運動性の低下は全身の運動性の低下に強く関連している。
●体幹において過剰な表在筋の痙性とは反対に深部の中枢筋の活動低下を腹臥位においたときに明らかに区別することができる。
●深部筋の活動低下は3つの分節である頭部と胸郭部と骨盤部が機能的な連結を完成させていないことを示している。
●頭部、胸郭部、骨盤部を連結する姿勢反応は3つある。①頭に働く身体の立ち直り反応、②身体に働く頸の立ち直り反応、③身体に働く身体の立ち直り反応(胸郭部から骨盤部へ、骨盤部から胸郭部への相互方向)。これらの基本的性質は外的に生体へ捻れが加えられたときに、捻れをつくりだすことによって捻れを打ち消し中間位へ戻るものである(減捻性立ち直り反応)。
●減捻性立ち直り反応を治療に応用し、重症児の姿勢アライメントを改善することが可能であり、また、自発的な運動による姿勢アライメントの修正であるため、効果を持続することが可能となる。
※左は「頸の立ち直り反応」、右は「体の立ち直り反応」、いずれも減捻性立ち直り反応になります。
●脊柱起立筋と腹筋は胸郭部と骨盤部を連結する役割をもっており、正常では身体に働く身体の立ち直り反応の成熟に伴い、寝返り運動を可能にし、さらに重力に抗して体幹を垂直位へと起こし、座位への起き上がり、起立を可能にしていく。
●正常な人は背臥位では抗重力活動により頭をまっすぐに正中位で保持できる。一方、重症児では頭は球形で転がりやすいため、頭は必ず一方に回旋する。この状態が続くと下肢の一側のより外旋、反対側の内旋、上肢の一側のより外旋と反対側の内旋が生じている。
2)関節への体重負荷、自発運動の意義
●体重負荷をしないで、さらに自発運動が制限された関節では、結合組織の基本成分である蛋白多糖類が減少することが知られている。結合組織の強化には自発運動、体重負荷刺激を行う。
2.痙直型両麻痺
1)臨床像
●軽度痙直型両麻痺では、起立直後に静止することが困難で、すぐに前方へ突進するように歩く、体幹は前傾し、股関節が屈曲・内旋し、膝関節は屈曲し踵を接地できず尖足位で歩行する。このような症例ではいかに体幹を直立位にし、股関節、膝関節の伸展を獲得するかが課題となる。
2)痙直型両麻痺の病因
●痙直型両麻痺の主要な原因は脳室周囲白質軟化症(PVL)である。軽度であれば両麻痺だが、PVLの領域が拡大して上肢や顔を支配する錐体路まで障害されてしまうと四肢麻痺になる。
3)両麻痺の痙性分布
●両麻痺では痙性が主に骨盤帯と下肢に分布するが、体幹および上肢にも軽度の痙性分布を示す。そのため、上肢機能にも問題を持つことが多い。
●痙性分布には必ず左右差がある。体幹深部筋の痙性分布の非対称性により、肩甲帯と骨盤帯の位置(アライメント)異常が発生しやすくなる。また、体幹の表在筋、とくに内転筋と内旋筋の痙性分布により、四肢の外転運動が制限されてしまう。
4)両麻痺の発達の特徴
●新生児では両麻痺の症状は目立たない。しかし、よく観察すると下肢の運動が少なく、また下肢の分離運動がほとんど見られなかったり、膝窩角が拡大することがある。
●下肢の分離運動を確認する方法は、両麻痺の場合、膝を伸展位に保持すると足部の背屈運動がしにくくなる。
6)両麻痺のキッキング
●両麻痺の下肢のキッキングは一般的に少なく、新生児期では外転・外旋位をとり、不活発である。しかし、頭のコントロールや上肢の活動が増加してくる生後3~5カ月にかけて、連合反応により下肢の潜在的な痙性が出現してくる。この時期に母親は赤ちゃんのおむつ交換のときに、自分の子どもの下肢が開きにくくなっていることに気がつく。ひと昔前ではこのような症状に気がついて受診しても股関節脱臼を疑われ、X線写真の結果異常がないと、様子をみましょうといわれることが多かった時期がある。しかし、今では新生児期にすでに脳室内出血やPVLを発見されることが多く、赤ちゃんの下肢に問題が現れることを事前に伝えられるようになってきた。
●下肢の運動が少ないと股関節が刺激を受けず、臼蓋形成不全が生じる。さらに股関節で体重負荷を経験しないと股関節形成不全が強まる。その結果、大腿骨頭の受け皿でもある臼蓋が浅くなり、下肢の痙性による内転・内旋で股関節は亜脱臼となり、さらに脱臼へと徐々に進行していく結果となる。
●両麻痺のキッキングの特徴は定型的な伸展パターンと屈曲パターンを繰り返すことである。つまり下肢を屈曲するときには必ず股関節屈曲・外転・外旋/膝関節屈曲/足関節背屈をし、下肢を伸展するときは必ず股関節伸展・内転・内旋/膝関節伸展/足関節底屈をしてくる。
また、左右差が必ず存在し、より軽度な下肢のキッキングが多くなる。その結果、より患側の下肢は健側の下肢のキッキングによって股関節の内転・内旋を強めてくる。その結果、より健側のキッキングは患側の股関節の亜脱臼や脱臼を生じる要因となる。
7)両麻痺の寝返り
●背臥位から側臥位になろうとするときは、頸部を強く屈曲し、上肢を前方屈曲し、体幹の屈曲を強めながら姿勢を変えようとする。それと同時に連合反応により両下肢は内転・内旋を強める。
●腹臥位から背臥位には頸部の過剰な伸展と回旋により姿勢を変えようとする。
8)両麻痺のハイハイ
●正常児と異なり、ハイハイを始める前にみられるピボット運動は通常みられない。これはピボット運動に必要な体幹の伸展と回旋を発達させていないためである。また、ピボットに必要な下肢の外転運動も痙性により阻止されてしまう。
●正常児でみられるハイハイの上下肢の交互性も一般的にはみられない。
9)両麻痺の起き上がり動作
●両麻痺では体軸内回旋を伴った床からの起き上がりができず、対称的な動作で割り座になる。
●割り座は両麻痺が両手を自由に使用できる唯一の座り方である。一度、割り座を覚えてしまうと、他の座り方を自分からはしなくなる。他の座位姿勢に置くと両手を床から離すことができず、両手活動ができなくなる。
●両麻痺を長座位に置くと、骨盤は後傾し、仙骨部で体重を受け、脊柱を伸展することができない。
●長座位ではハムストリングスが痙性のため短縮し、骨盤を後傾させてしまう。その結果、脊柱を伸展することが困難となる。さらに膝関節を屈曲し、自分では膝伸展することはできない。
●内側ハムストリングスの痙性がより強いため、股関節を内旋する要因となる。
●軽度な両麻痺児で両手を離すことができる場合を除いて、この姿勢を自分からとることはない。
10)痙直型両麻痺の割り座に対するアプローチ
●割り座で足部を観察するとどちらか一方が外返し位をとり反対側が内返し位となり、非対称的な足部を示すことが多い。これは股関節の内旋の強さに影響されて生じる。痙直型両麻痺児は座位をとるまでの運動発達のなかで、骨盤の運動性を伴った腹筋の収縮や下肢の分離動作、体幹の伸展と回旋要素を獲得していない。そのため、子どもの自発性が高まってくるにつれて、下肢の機能の不十分さを上体で代償することを学習してしまう。その結果、下肢の痙性は徐々に強まり、下肢の分離動作がさらに困難になってくる。そして、下肢の全体的な屈曲パターンを利用した座り方。すなわち割り座のみが可能となる。
●両麻痺児を長座位に置くと骨盤は後傾し、仙骨部で体重を受けてしまう。両側のハムストリングスは短縮し、両股関節は内転、内旋位をとる。また両膝も屈曲し、足関節は底屈位をとる。長座位姿勢を保つためには、後方に転倒しないように体幹の屈曲を強め、上体を前方に運ばねばならない。
●割り座しかできない両麻痺児に対して長座位を経験させることは全身を分離することにつながる。全身の分離とは長座位のように体幹の伸展と股関節の屈曲、そして膝関節の伸展のように異なる要素が姿勢のなかに存在することを意味している。
11)両麻痺の移動
●両麻痺児の体幹では伸展と回旋が不足している。また、正しい四つ這い姿勢がとれないため、割り座の姿勢から殿部を少し持ち上げ上肢に体重移動をすることを繰り返しウサギ跳びをする。また、このウサギ跳びが長期化する傾向をもっている。
●下肢の交互運動は少なく、両下肢を屈曲位のまま前進するため、将来の歩行に必要な下肢の交互運動を経験することが極端に少なくなる。
●ウサギ跳びによる移動方法が長期化すると、立位に必要な股関節や膝関節の伸展が発達しない。そのため、早期に立位を治療に取り入れる必要がある。
●中等度~軽度両麻痺では四つ這いができることがあるが、骨盤が左右に動揺し、体重を適切に股関節で受けることができない。この動揺性は中殿筋が働かないトレンデレンブルグ歩行でみられる体幹の動揺性と類似している。また、下肢が過剰な伸展パターンに入り込むため、股関節の内転・内旋が強まる。
12)両麻痺のつかまり立ち
●正常児のように両下肢を分離して動かすことが困難なため、膝立ちから片膝立ちへ移ることが困難である。そのため、両腕の力で立位へと自分の体を引き上げ、両下肢はほぼ同時に突っ張り立ち上がろうとする。しかし、足部の背屈が困難なため、前足部で体重を受け尖足位で立位をとる。
●正常児でも、つかまり立ちの初期の段階では両麻痺児のように直線的な起立パターンをとる。しかし、両麻痺と違って決して股関節内旋はみられない。正常児がこのような直線的な起立パターンを初期の段階でとるのは一側下肢での体重負荷の筋力が未発達のためと考えられる。また、立位での平衡反応が成熟していないため、動作を両側同時に行うことで安定を保っているともいえる。
13)両麻痺の立位姿勢
●両麻痺児の立位姿勢は大きく二分される。その1つが屈曲型とよばれる姿勢で、体幹の屈筋群の過緊張により脊柱の重力に逆らった伸展が発達していないため、脊柱は屈曲し骨盤は後傾する。
●屈曲型では独歩は困難で、歩行器やクラッチに頼らなければ歩行が困難になる。また、松葉杖は体幹の屈曲を強めてしまうため、杖はロフストランド杖が好ましい。歩行器はPCW(postural control walker)を使い、脊柱の伸展を日常的に促すことが試みされている。
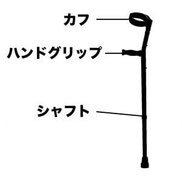
画像出典:「整形外科疾患の病態やリハビリテーションに関する理解を深めるブログ」
なお、こちらのサイトではロフストランド杖の特徴や適応などについて詳しく説明されています。」

画像出典:「徳島県立 板野支援学校」
この写真は、自立活動トピックスの“自立活動 P.C.Wでの歩行学習”という記事に使われていたもので、P.C.Wに関する説明も出ています。
●もう1つのタイプ伸展型である。伸展型では体幹の同時収縮は屈曲型に比べて軽度となる。体幹は股関節屈曲を代償するため、代表的伸展をする。骨盤は前傾しており、膝は屈曲位を取るため下腿の振り出しが困難となる。
●歩き方は前方に突進するように歩き、ゆっくりとは歩けない。そして、体幹を左右に揺すりながら体重移動を行う。
14)両麻痺の認知障害
●両麻痺児は行動の切り替えが遅く、新たな局面に向かえない特徴をもっている。このような両麻痺児に対しては目標を言語化してあげることが大切である。例えば、「これからこれとこれをやろうね」などと行う行動を事前に認識させるような働きかけが必要とされている。
15)つま先歩きをする子どもたち
●尖足歩行(つま先歩き)の原因
・前庭機能の異常
・足底接触から起こる防御反応(刺激に過敏)
・先天的なアキレス腱短縮
・歩行器の使い過ぎ
16)股関節脱臼
●骨盤の捻転は一側股関節の内転・内旋パターンが増強することによって生じる。この骨盤の捻転は股関節脱臼や股関節屈曲拘縮に結びついてくる。
●股関節の内転・内旋変形は同時に起きる。この変形の責任筋は大腿筋膜張筋と考えられている。また、内転筋では長内転筋と薄筋の痙性が要因と考えられている。
●主な股関節脱臼の原因は股関節の形成不全が背景に存在している。この形成不全は幼児期の初期において下肢運動が不足し、支持性の発達欠如により股関節形成が阻害される。この形成不全に加えて内転・内旋が脱臼を強めてしまう。
3.痙直型片麻痺
1)初期症状
●口腔周辺に現れることがあり、泣いたり、笑ったりするときに舌の非対称性や口唇の非対称性が生じることがある。
●生後2~3カ月では明らかな痙性は認められないが、上下肢の自発運動は低下している。
●片麻痺は早期から左右差をもっているため、比較的早期診断がつきやすいが、周産期医療(妊娠22週から出生後7日未満までの期間)の進歩により減少している。
●新生児期では手指の動きは少なく、下肢は未熟なパターンをとっていることが多く、下肢の障害は初期には目立たない。そのため上肢だけの障害とされて単麻痺として診断されることがある。しかし、脳性麻痺で単麻痺は非常にまれで、下肢を注意して観察すると、左右差を確認することができる。
●初期には下肢の痙性が目立たなくても、ハイハイ、起立、歩行へと下肢の活動性が高まるにつれて痙性が強くなる。
●痙性が軽度な場合、初期には上肢の自発的な運動がみられるが、治療せずに放置すると、上肢機能は未熟なリーチと把握にとどまるか、連合反応の結果、さらに悪化する危険性をもっている。
●通常、母親は3カ月ごろ、患側の手の動きの少ないことに気づく、また、手を握っていることが多いことに気づく。すなわち、このころから上肢に痙性を認めるようになる。これは健側の手の自発活動が増加してくるにつれて、患側の屈筋痙性が発現してくるためである。
2)片麻痺の発達の特徴
●生後1年以内は利き手は確立しないので、その時期に左もしくは右を明らかに優位に使用するとしたら片麻痺を疑うべきである。
(3)片麻痺のハイハイの特徴
健側上肢でたぐり寄せるように推進する。そのため、連合反応の影響により患側上肢の屈曲、肩後退が強まり、同時に手指の屈曲も強まる。
ハイハイの際、患側の骨盤は後方へ引かれ、患側の体幹の短縮が生じてしまう。また、患側下肢の股関節内転、膝関節の伸展、足関節の底屈、足趾の鷲指が起こる。
(4)片麻痺の四つ這い
比較的上肢の障害の軽い場合に四つ這いをすることがあるが、通常、上肢を体重支持に用いることができないため四つ這いを経験しないことが多い。そのため、初期の移動は寝返りやハイハイが主体となる傾向をもっている。
(5)片麻痺の座位
正常児では四つ這い位から体軸内回旋により、座位に移行していくが、片麻痺の場合には腹臥位から四つ這い位を経由せずに起き上がってくる。
(6)片麻痺のずり這い
片麻痺児では座位を獲得すると、ずり這いを覚える可能性が高くなる。座位で体重を健側の骨盤に移動し、健側上肢を使い身体を揺すりながら移動する。子どもによっては上肢を使わずに骨盤と体幹の前後の動きでずり這うことがある。
(7)片麻痺の起立
片麻痺児は健側上肢で物につかまり、腕の力で身体を引き上げるようにして立ち上がる。そのときさらに患側上下肢の痙性は強まり、肩甲帯の後退を伴った屈曲、手指の屈曲、患側体幹の短縮、骨盤の後退が今まで以上に強まってくる。
(8)片麻痺の歩行
起立することにより、前足底部に圧刺激が加わるため病的陽性支持反応の影響により下肢の伸展パターンが強まる。しかし、股関節に屈曲が残る。その理由として次のことが考えられる。
①伸展パターンといえども体重を支持するには不十分なため。
②今までに正常な股関節の伸展が発達していないため。
③体幹の抗重力伸展の不足により、患側下肢に対して体幹を垂直に保つことができないため。
④内転筋のもつ作用として、股関節内転以外に股関節の軽度屈曲作用をもっており、股関節内転筋の痙性が強いと股関節を十分に伸展できなくなるため。
(9)片麻痺の健側手
片麻痺児は片手で持てる小さな玩具を好む。そのため、健側の手のみを使用する傾向が強まる。また、両手を使用することが困難であるため、健側手を粗大な活動に用い、より巧緻的な活動には使用しない傾向がある。
(10)患側の手の活動と代償運動
患側手にある程度の随意性をもっている場合に、患側の手の動きづらさを代償する頸部、体幹の代償運動が出現する。特に患側上肢の前腕を回外するように指示すると、体幹と頸部は患側に側屈し、身体全体を使って回外運動を助けようとする。
(11)片麻痺の尖足
尖足を示す場合、膝関節を伸展位で足関節背屈制限がみられ、膝関節を屈曲位にして背屈したときに正常可動域まで背屈する場合は腓腹筋の短縮が考えられる。また、膝関節を屈曲しても足関節の背屈制限がみられる場合にはヒラメ筋も短縮していることが考えらえる。児はこの尖足位の踵を接地させるために骨盤を後退させ、膝を過伸展する。そのため反張膝が徐々に強まる。
(12)片麻痺の連合反応
連合反応は健側が存在するため患側に出現する。連合反応は健側の強い随意的な努力に伴う異常な患側の定型的な運動パターンである。つまり、連合反応は痙性パターンのなかで筋緊張が高まる現象で、それはあたかも運動のようにみえるが、これは正常な動きではなく解放された緊張性反射活動のため筋緊張が変化することによる。
重度な痙性が分布していると、動きとしては現れないため、筋緊張の変化を触診することで確認することができる。
(13)正常な連合運動
連合運動は正常な運動で、両側に対称的な運動や類似した運動を引き起こす。連合運動は正常でありおよそ12歳までには自己抑制が可能となる。また、正常ではより動き強めるときに生じる。立ち直り反応、平衡反応の未熟な段階では種々の連合運動が正常発達の過程のなかでみられるが、多くは学齢前までに抑制機能を獲得していく。
6)片麻痺の治療
(1)母親の教育
片麻痺児の多くが歩行を獲得していく。そのため、粗大な運動面では一応のことができるようになるため、母親は運動に関して楽観的になりやすい傾向をもっている。しかし、将来的に両手を使用することの重要性と必要性や、片手で可能な職業の少なさを早くから知ってもらう必要がある。
(2)知覚改善
患側の手を使用できるようにするためには多くの感覚刺激が患側に加えられなければならない。そのため、多くの固有感覚刺激や表在感覚刺激を入れていき、複合感覚の改善を目指していく。とくに、片麻痺児は患側に触れられることを嫌がる。これは健側での代償の結果、患側に入る感覚刺激が減少したためである。そのため、早期から感覚刺激を入れ、のちの体重負荷の準備をしていく。
また、血管運動障害のために患側肢の循環障害を起こしやすく、寒い季節には手指の運動性が低下する。
(3)両側の協調性の改善
過剰に患側を使用させようとする必要はない。とくに早期の段階では両側活動を中心に治療を進めていく必要がある。
(4)患側の異常発達を阻止
健側での代償運動を学習する以前に治療を開始することが必要である。特に上肢の自発運動を引き出し、多様な粗大運動が可能となるように台にのせ反応などを応用した治療が必要である。
(5)連合反応の抑制
患側肢の自律的、随意的運動性を引き出すことが、結果的に連合反応を減弱していくことにつながる。そのため、他動的な操作による痙性の減弱に固執してはならない。
(6)てんかんに対する配慮
治療にはクールダウンを準備しておく。痙攣発作が頻回に起こると、獲得していたことができなくなることがある。そのため過度の疲労を避ける必要がある。また、規則正しい生活が行われているか注意を払う必要がある。
(7)年齢による特性
①3~10カ月は異常発達が進行していないため、比較的治療がしやすい時期である。この時期に両側の相互活動を多く学習できる可能性がある。
②10カ月~4歳ごろまではなかなか治療に応じてくれない。そのため、たくさんの遊びと探索活動とそして成功できる課題を多く治療に導入しなければならない。
③4~8歳では拒否する態度が減少してくるため治療が容易になってくる。
④8~12歳では自分の障害を認めるようになり、治療の必要性を否定しようとする傾向がみられる。
⑤12~16歳では仲間と意味のある関係を形成することに関心が強くなり、治療にも関心を持つようになる。この時期では自己抑制を学習することや現実的な状況で治療を進めることが大切となる。
付記:脳性麻痺の出現比率
本書では脳性麻痺は、両麻痺、四肢麻痺、片麻痺、アテトーゼ型脳性まひ、弛緩型麻痺に分類されています。「これらの発生比率に関するデータはないのだろうか?」と思い、ネット検索したところ、次のような情報を見つけました。これを見ると痙直型が全体の84%であり、その中では両麻痺が1番多いことが確認できます。
『ヨーロッパの研究では片麻痺 27%,両麻痺 36%,三肢/四肢麻痺 21%であり,失調型 CP 児が 4%,ジスキネジア/ ジストニック型脳性麻痺が 12%となっている。』

“脳性麻痺 理学療法マニュアル”をクリック頂くと163枚のPDF資料がダウンロードできます。残念ながら上記の比率に関する文章はないのですが、“用語”の解説の1番目に下記の記述があります。
surveillance of cerebral palsy in Europe(SCPE)
『1998年に設立された,欧州8か国14センターからなる脳性麻痺の登録,調査に関する共同研究ネットワークであり,出生体重の傾向をモニターするためのCP児のデータベースの開発とサービス計画についての情報提供,共同研究の枠組みを提供することを目的としている*。』
そして、“surveillance of cerebral palsy in Europe”で検索して出てきたサイトが以下になります。きっとこの中に情報ソースが存在していると思うのですがそれを探すことはすぐに諦めました。
小児の理学療法1
前回、前々回は『脳性まひ児の発達支援』という本を題材にした勉強モードのブログでしたが、今回も同じく勉強モードとなっています。勉強の目的は“動くことのできる小児障害児への施術(マッサージ・鍼)を考え、一人ひとりに適した施術を提供できるようになる”ということです。
なお、ブログの内容は本をつまみ食いした項目で構成されていますが、“小児の理学療法1”で注目したのは2つです。一つは“セラピスト(理学療法士)に求められていることを知る”というものであり、もう一つは“小児障害児の運動特性と関節・筋肉”に関するものです。これらは、障害児が持つ過緊張・低緊張という問題に正面から取り組む上で重要であると考えます。
すべての目次の中で黒色は今回の“小児の理学療法1”、その中で太字がつまみ食いした項目です。一方、うすい灰色は次回以降、“小児の理学療法2”、“小児の理学療法3”で検討する部分になります。
目次
第1章 歴史的にみた脳性麻痺
第2章 発達障害児の治療のための評価
1.事前に行うべきこと
1)両親への説明
2)評価環境
3)両親(母親)の観察
2.評価の基本
1)基本的評価の流れ
2)観察のポイント
3)仮説を立てる
4)正常運動発達要素の欠落
3.姿勢反応の評価(立ち直り反応群)
1)体に働く頸の立ち直り反応
2)頭に働く頸の立ち直り反応
3)体に働く体の立ち直り反応
4)視性立ち直り反応
5)迷路性立ち直り反応
6)平衡反応
4.姿勢緊張の評価
1)小児神経学で使われている筋緊張の検査
2)正常姿勢緊張
3)プレーシング・ホールディング
5.連合反応の評価
6.発達のギャップ
7.乳児期に問題となる姿勢と運動パターン
8.知的発達の評価
第3章 姿勢と運動の発達
1.腹臥位姿勢と運動の発達
1)新生児の腹臥位姿勢と運動
2)1カ月の腹臥位姿勢と運動
3)2カ月の腹臥位姿勢と運動
4)3カ月の腹臥位姿勢と運動
5)4~5カ月の腹臥位姿勢と運動
6)6カ月の腹臥位姿勢と運動
7)7カ月の腹臥位姿勢と運動
8)9~10カ月の腹臥位姿勢と運動
9)12~13カ月の腹臥位姿勢と運動
2.背臥位姿勢と運動発達
1)新生児の姿勢と運動
2)1カ月児の背臥位姿勢と運動
3)3カ月の背腹臥位姿勢と運動
4)4~6カ月の背臥位姿勢と運動
5)8カ月の背臥位姿勢と運動
3.座位の発達
1)第1段階~第2段階(新生児期から生後5カ月)
2)第2段階
3)第3段階
4.立位と歩行の発達
1)新生児期
2)失立・失歩行期
3)下肢への加重の始まり
4)jumping Stage
5)bilateral weight bearing
6)sequence to standing
7)1歳6カ月以降の立位・歩行の発達
5.手指機能の発達
1)hand orientation
2)hand orientationとgrope
3)hand orientation,grope,grasp
4)reach pattern
5)物の持ちかえ
6)pincer grasp
7)releaseの発達
6.移動の発達
1)移動における皮膚の役割
2)初期の移動と視覚とリーチ
3)移動にみられる退行現象
4)移動と三点支持面
7.乳幼児のプレスピーチの発達
第4章 新生児集中治療室における理学療法
1.新生児の分類
1)出生体重による分類
2)在胎週数による分類
3)胎児発育曲線による分類
4)臨床所見による分類
2.未熟児にみられる主要な疾患
1)子宮内発育不全児
2)新生児仮死
3)未熟児無呼吸発作
4)呼吸窮迫症候群
5)未熟児の慢性肺障害
6)核黄疸
7)動脈管開存症
8)新生児低血糖症
9)新生児頭蓋内出血
10)嚢胞形成性脳室周囲性白質軟化
11)未熟児網膜症
3.未熟児の姿勢と運動の評価
1)モロー反射
2)把握反射
3)非対称性緊張性頚反射
4)足趾把握反射
5)交叉性伸展反射
6)恥骨上反射
7)ガラント反射
4.新生児神経行動学的評価
1)慣れ現象
2)運動と緊張
3)反射
4)神経行動学的指標
5)立ち直り反応
5.未熟児の運動療法
第5章 脳性麻痺
1.痙直型四肢麻痺
1)痙性の分布
2)関節への体重負荷、自発運動の意義
2.痙直型両麻痺
1)臨床像
2)痙直型両麻痺の病因
3)両麻痺の痙性分布
4)両麻痺の発達の特徴
5)両麻痺の頭のコントロール
6)両麻痺のキッキング
7)両麻痺の寝返り
8)両麻痺のハイハイ
9)両麻痺の起き上がり動作
10)痙直型両麻痺の割り座に対するアプローチ
11)両麻痺の移動
12)両麻痺のつかまり立ち
13)両麻痺の立位姿勢
14)両麻痺の認知障害
15)つま先歩きをする子どもたち
16)股関節脱臼
3.痙直型片麻痺
1)初期症状
2)片麻痺の発達の特徴
3)アテトーゼ型片麻痺
4)後天性片麻痺
5)片麻痺の問題行動
6)片麻痺の治療
4.アテトーゼ型脳性麻痺
1)アテトーゼ型脳性麻痺に共有する特徴
2)アテトーゼ型脳性麻痺の分類
3)アテトーゼ型脳性麻痺の治療
5.弛緩型麻痺
1)脳性麻痺の初期症状としての弛緩
2)姿勢および反応
3)アテトーゼへの移行(移行期のサイン)
4)弛緩児の治療
第6章 運動療法
1.頭のコントロールのための運動療法
1)背臥位での頭の回旋
2)腹臥位での頭の回旋
3)腹臥位での頭の挙上
4)背臥位からの頭の屈曲
5)頭の固定性を高める準備としての圧迫手技
2.上肢の挙上運動とリーチの準備
3.上肢の支持性
4.脊柱の側屈可動性の準備
5.脊柱の伸展可動性の準備
6.パラシュー反応の誘発
1)パラシュート反応誘発のための準備
2)パラシュート反応の誘発
7.減捻性立ち直り反応を応用した運動の誘発
1)体に働く頸の立ち直り反応
2)体に働く体の立ち直り反応
3)抗重力方向への体に働く体の立ち直り反応
第2章 発達障害児の治療のための評価
1.事前に行うべきこと
●家庭ではどのような姿勢、運動が多いかを質問し、習慣的に形成されていく異常姿勢や運動に対抗する手段を講じていかなければならない。
●家庭で使用している機器(座位保持椅子、車椅子、歩行器、立位保持用具など)を知る。
●子どもの生活リズムを知っておく。特に年少の場合、午睡、就寝、起床時間、夜中にどのくらい覚醒するか。
●どのような薬を服用しているか。
2.評価の基本
●総合評価する場合、一人ひとりの動作を観察分析することから始まる。
●セラピストは運動学的に異常な動作の原因の仮説をたて、その仮説に基づき運動療法を試行し、発達障害児に触れ、観察で得られた情報と実際に触って感じる情報の違いなどを整理していく。
●治療を行いながら刺激(スピード、幅、刺激部位、刺激の強さ)を変え、適切な刺激を選択する。
1)基本的評価の流れ
●発達過程にある発達障害児の異常性の出現、正常要素の欠如と異常な発達、発達の停止もしくは遅れ(発達のゆがみ)を見つけることがセラピストの課題となる。
●なぜ首が座っていないのか? なぜ座れないのか? なぜ寝返りできないのか? なぜ手をうまく使えないのか? なぜつかまり立ちができないのか? なぜ歩けないのか? など獲得して欲しい機能を阻害している要因は何なのか、セラピストは自問自答する必要がある。
2)観察のポイント
●観察は末梢の手足ではなく、体幹の状態をよく観察する。
●体幹の観察では胸郭の左右差や肋骨下部の突出、陥没呼吸のためにロート状になっていないかみる。
●観察だけでなく動作を真似してみることも重要。
3)仮説を立てる
●できること、できないことを整理する、そしてできないことの原因の仮説を立てる。ここで考えなければならない原因とは、中枢神経系の障害部位ではなく、からだに分布する異常な筋緊張分布や獲得していない基本的な運動機能などを考えることである。
●姿勢(背臥位、腹臥位、座位、立位)と運動(寝返り、ハイハイ、四つ這い、起き上がり、つかまり歩き、歩行)のなかにみられる共通した問題点を見つけだす。
●異常と感じた姿勢や動作を文章にしてみることが必要である。
●年長になるにつれ、非対称性が徐々に変形や拘縮に発展していく。
4)正常運動発達要素の欠落
●正常運動発達には順序性があり、頭のコントロールから寝返り、ハイハイ、四つ這い、つかまり立ち、つかまり歩き、独歩と続くが、この順序性に固執するのは適切ではない。寝返りができる6カ月では立位をとらせると下肢に体重を受け始める。座位をとらせると両手を前について少しのあいだ姿勢を保とうとする。このようにお互いが影響しながら同時に発達している。
●セラピストは子どもの発達経過のなかで重要な正常運動発達の要素を欠落させていないかどうか見つける必要がある。
・正中位での頭の保持
・手と足の接触
・体軸内回旋機能
・下肢の交互運動
・上肢の支持性
・手指の把握機能
・凝視・追視機能
・咀嚼・嚥下機能
・基本的な立ち直り反応
・上肢の保護反応
・下肢の保護反応
・平衡反応

運動麻痺についてご紹介します。
画像出典:「日本脳神経財団」
運動麻痺とは手足や顔を動かす筋肉が随意的に動かせなくなることです。具体的には脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷などで手足や体幹、顔面の随意的な運動ができなくなる状態です。
運動麻痺はその病気が身体のどこに起こるかで4つのタイプに分けられます。
①片麻痺(半身麻痺):顔面を含んで一側半身の麻痺が現れるものです。
②単麻痺:一側の手、または足が単独で麻痺するものです。
③対麻痺:両側の下肢の運動麻痺のことです。
④四肢麻痺:両側の上肢、下肢が全て麻痺してしまうものです。
4.姿勢緊張の評価
●姿勢緊張テストの目的は子どもの姿勢変化に伴う筋の緊張の変化を調べることである。つまり発達障害児では姿勢によって筋緊張が高まったり、低下したりする。また、中枢神経系に障害を持っている場合には異常な筋緊張が全身に分布しており、治療計画を立てる場合に異常筋緊張分布の状態を把握する必要がある。セラピストは子どもの四肢を他動的に操作し、その時セラピストの手に感じる筋の筋緊張を評価する。
●筋緊張の評価として次の大まかな基準が参考になる。
①正常(normal):四肢の他動操作に対して素早く反応し、ただちに筋緊張を他動操作に合わせるように変化する。その結果、セラピストは四肢を非常に軽く感じる。
②痙性(spasticity):四肢の他動的操作に対して過度な抵抗を示す。抵抗は操作開始域で強く、突然抵抗が弱まることがある。これをジャックナイフ現象とよぶことがある。一般的には上肢では屈筋と内転筋の緊張が高く、下肢では伸筋と内転筋の緊張が高いのが特徴である。
③アテトーゼ(athetosis):四肢の操作に対して筋緊張が動揺し、過度な抵抗を示したり、抵抗が消失したり絶えず変化を示す。その筋緊張の変化を予測することが一般的には困難である。
④弛緩(flaccidity):四肢の操作に対してほとんど抵抗を示さず、セラピストは操作している四肢の重さを手に感じる。

筋緊張の種類についてご紹介します。
画像出典:「LITALICO発達ナビ」
このイラストを見ると、痙直型=大脳、アテトーゼ型=大脳基底核、失調型(弛緩)=小脳 ということがシンプルに分かります。なお、約80%は痙直型であるとされています。
また、こちらのサイトには貴重な情報が盛りだくさんなのですが、特に重要と思う部分をご紹介します。
◇症状と脳性麻痺の原因
1.核黄疸・ビリルビン脳症
2.低酸素性虚血性脳症
3.脳室内出血・脳室周囲白質軟化症
◇上記3つ以外の原因
1.妊娠中の脳性麻痺になる原因
・脳の中枢神経系の奇形
・遺伝子や染色体の異常
・感染症(風疹、サイトメガロウィルス、トキソプラズマなど)
2.出産時の脳性麻痺の原因
・新生児の呼吸障害やけいれん
3.出産後の脳性麻痺の原因(脳の損傷)
・中枢神経感染症
・頭蓋内出血
・頭部外傷
・呼吸障害
・心停止
・てんかんなど
おもに周産期と妊娠期間中に脳性麻痺が起きやすいことも分かっており、周産期に発生する場合が40~66%、出生前の妊娠中に起きてしまう割合が13~35%。
1)小児神経学で使われている筋緊張の検査
●筋緊張(筋トーヌス)の内容として伸張性、被動性、筋の硬さの3つがある。
(1)伸張性
伸張性とは関節をゆっくりと他動的に操作して動かしたときにどのくらいの伸びを示すかによって判定する
①window sign
手関節を掌屈する。成人では90°だが新生児ではさらに掌屈する。6カ月ではほぼ成人の可動域になるが、6カ月以降も過度な掌屈がみられる場合には低緊張であり、ダウン症などの疾患が疑われる。
②股関節の開排角度
新生児の開排角は平均76~77°で、その後急速に角度は減少し、生後3カ月で平均71°まで減少する。その後は徐々に増加し生後2歳で再び76~77°になる。さらに歩行速度の増加と走行能力の発達に伴い股関節の固定性が増大するため内転筋の伸張性は低下する。そのため生後では74~75°になる。
③足の背屈
成熟新生児の背屈角度は大きく、生後3カ月以降は減少していく。成人では20°。
④膝窩角
膝窩角は新生児期では約90°だが、徐々にその角度は拡大していく。しかし、中枢神経系障害のある子どもではその角度が過剰に拡大したり、狭小化したり、左右差を示す。
⑤スカーフ兆候
上肢をスカーフのように首に巻きつけるように回して検査する。成熟新生児では手関節が肩峰の所で止まるが、未熟児では手関節が肩峰を越えてしまう。
(2)振れの度
一般的に手関節と足関節で検査する。子どもの手首もしくは足首を持ち、手先もしくは足先を振る。このとき、低緊張であれば大きく振れ、過緊張であれば振れが小さくなる。
(3)筋の硬さ
筋肉の硬さを指で圧迫して硬さを判定する。筋の硬さの判定はかなり主観的になるため、多くの症例を経験する必要がある。評価基準は-3~+3までの7段階。
2)正常姿勢緊張
正常な姿勢緊張には幅があり、日常の生活の中で状況に応じて変化している。しかし、覚醒している状態では即座に動作を起こすことができる筋緊張は保っている。
3)プレーシング・ホールディング
正常であれば支えのない空間に置かれた肢は補助する手を離しても、肢を空間に短時間保持することができる。一方、中枢神経系障害のある子どもは保持することが難しい。
5.連合反応の評価
●痙直型両麻痺の子どもが寝返りをしようとすると、いつも上半身を過剰に使って寝返ろうとする。その結果、両下肢は伸展して内転、内旋し特徴的なはさみ状肢位をとってしまう。
●痙直型片麻痺では健側を使用することで患側の上肢の屈筋痙性が高まり、上肢が典型的な肘屈曲、回内、手指屈曲の姿勢をとってしまう。
●子どもがより健側を使用するたびに、患側の緊張が高まり変形・拘縮の原因となる。この連合反応が最も子どもの発達を阻害する要因になる。
●子どもにとって何が困難か、また、連合反応が出現しない許容度と、最も著明に出現する動作を把握しておく必要がある。
第3章 姿勢と運動の発達
4.立位と歩行の発達
3)下肢への加重の始まり
●生後4~5カ月になると膝窩で支えると少しの間、体重負荷を始めてくるが、全体重を支えることはできない。
●足趾は屈曲しがちで片足を持ち上げることがある。
●立位姿勢では股関節と膝関節の軽度屈曲がまだみられる。
4)jumping Stage
●生後6~7カ月になると起立位に保持をすると下肢を伸展し、十分体重を負荷するようになる。
●この時期は活発に飛び跳ねるため、jumping stageと呼ばれる。
5)bilateral weight bearing
●生後8~9カ月では飛び跳ねることはしなくなり、両手で物をつかんで立位を保つようになる。
●一人ではしゃがむことはできないのは、体重の負荷がかかる状態で、股関節、膝関節を自由に動かすことができないためである。
6)sequence to standing
(1)pull-up sequence
生後9~10カ月になると物につかまり直線的に起立するようになる。まだ片足での体重負荷機能が十分発達していないため、両足同時に使って起立しようとする。
また、この時期でも膝の機能が十分ではないため、つかまり立ちはできてもしゃがむことはできない。
(2)cruising(つかまり歩き)
生後11~12カ月になると、物につかまり横へつたい歩きができるようになる。
つかまり立ちからつかまり歩きへ乳児を促すのは、上肢のリーチ機能である。これは手を物にリーチすることにより下肢では体重移動が生じ、より一側に体重が移ると他側の下肢のステップ反応が生じ、最初の一歩となる。
乳児は初め連続した物でつかまり歩きをするが、脊柱の重力に抗した伸展機能が高まるにつれて、脊柱の伸展と回旋を組み合わせることができるようになる。この離れた物へのつかまり歩きをしているときに、偶然に両手が離れて一人立ちが出現する。離れた物へつかまり歩きができるようになると、片手を支えられれば歩くことができるようになる。それ以前では、支えられた手を支点にして身体が回転してしまうことがある。
(3)walking(一人歩き)
生後12~13カ月ごろ一人で床から起立し、数歩あるくことができるようになる。一人歩き初期では脊柱の抗重力伸展をさらに強めるために上肢を伸展し、肩甲骨を固定しようとする。また、両下肢を広く外転して立位の基底面を広くとり安定した姿勢を確保しようとする。
一人歩き初期では、立位から最初のステップを前に振り出すとき、他側の下肢で全体重を受けなければならないため、乳児は下肢の伸展と脊柱の伸展を高めなければ崩れてしまう。そのため上肢を挙上し、下肢の伸展を全身を使って強める。
歩行初期には上肢を挙上した姿勢で、両下肢を外転して基底面を広くとった歩行をする。この姿勢をhigh guard postureとよぶ、次第に上肢は下がっていき、middle guardへ、そして最後にlow guardとなっていく。上肢の位置がlow guardになるのは生後18カ月である。また、low guardになると歩行中の上肢の交互の振りが出現してくる。
床からの起立パターンでは初期には完全な回旋を背臥位から起こし、腹臥位になってから四つ這い位、高這い位をとりバランスをとりながら起立していく。
しだいに起立パターンは変化していき、完全に腹臥位まで回旋することなく、背臥位から半回旋し、座位に起き上がり、そこから起立するが、まだいったん高這い位の姿勢をとる。
生後2歳ごろでは起立するまで高這い位を経由しなくなり、座位から片膝を立てて起立するようになる。
脳性まひ児の発達支援2
第8章 姿勢と運動発達支援の実際1:筋緊張障害への対応
第1節 低緊張への対応
●肢体不自由特別支援学校に筋緊張の低い脳性まひ児が在籍していることは珍しくない。
1.伸張反射の利用
(1)伸張反射とは
●筋が急速に引き伸ばされたときに筋が一定の長さを保とうとして収縮する。これを伸張反射といい、抗重力筋や顎の筋肉によく発達している。
●伸張反射の反射中枢は脊髄レベルにあるが、同時に脳の上位中枢から抑制を受けて、適当な強さに反射がコントロールされている。そのため錐体路が障害されると抑制がとれコントロールが難しくなって反射が過剰に強く出現するようになる。
●伸張反射とクローヌス(間代)は脳性まひでは痙直型にみられる特徴である。
●伸張反射が亢進しているとクローヌス(間代)がみられる。クローヌスはすべての関節で起こり得るが、臨床的には足関節(足間代)と膝関節(膝間代)でみられやすい。
(2)伸張反射を利用して筋緊張を高める
●伸張反射を利用して伸筋の収縮を促通することができる。
2.関節圧縮の利用
●関節圧縮は固有覚を利用するものである。
●体重あるいは関節を圧縮する身体部位に日常的にかかっている以上の負荷をかける。この方法は圧縮された関節付近の筋群の同時収縮を促通して筋緊張を高める効果がある。これを肩、腰、頭などに用いると関節の近位部の固定性を高める。
●肘位での関節圧縮:両肩から上腕の部分を支持者が保持して両肘を床に向かって垂直に押し込んで肘位を保持する。肘位でこの関節圧縮を行うと、肘と肩の関節の周辺の筋肉が同時収縮して緊張感が高まり、結果的に肢位を安定させると同時に、肩の近位部である首の固定性を高めると考えられる。
●腹臥位で頭の挙上が困難なときに肘位での関節圧縮を利用すると、両肩、両肘、腰を結ぶ三角形の姿勢となり、首を支える体幹・上肢の姿勢が安定して、頭の挙上が容易になる。
3.キーポイント・オブ・コントロールの利用
●人間の身体は、屈曲や伸展により筋緊張がさまざまに変化する。屈曲や伸展によってある身体のポイントをコントロールすることにより筋緊張を高めたり、低めたりすることができる。このキーポイント・オブ・コントロールはボバース(1980)によって提唱されたものである。
●全身の筋緊張を高めるには股関節及び膝関節を伸展させた姿勢が都合がよい。長座は股関節伸展・膝関節伸展であって下肢の筋緊張が高くなりやすい。
●あぐら座位は股関節と膝関節が屈曲しているので筋緊張を低くする効果がある。
4.前庭刺激の利用
●前庭刺激によって、頚・背・腰部の伸筋収縮を促通することができる。
●「突然、急速、非リズミカル」に入力すると興奮性、つまり筋の収縮を促進する。逆にリズミカルな入力は抑制性、つまり筋を弛緩させる。
●前庭刺激の興奮性入力の具体的な方法を例示すると、腹臥位や座位で上下に揺らす前庭刺激を用いて伸筋収縮の促通を行うやり方が考えられる。(促通とは、ここでは神経や筋などへ刺激を与えて筋の収縮をうながす意味で用いている)
第2節 過剰に高い筋緊張への対応
1.関節圧縮の利用
●体重またはそれ以下の力での関節圧縮を使用すると筋緊張を低減する効果がある。これは筋緊張が亢進している関節周囲筋を抑制し、その関節周囲の筋緊張を一時的に低下させる。
2.キーポイント・オブ・コントロールの利用
●肩と肩甲帯を屈曲させるとその付近の筋緊張を低める効果がある。
●ウェストラインの屈曲は背中・腰付近の伸筋緊張を低める効果がある。
●股関節及び膝関節を屈曲させた姿勢が全身の筋緊張を低める。あぐら座位は股関節屈曲・膝関節屈曲であるので下肢の筋緊張は低くなりやすい。
3.前庭刺激の利用
●リズミカルな入力は抑制性として働き筋を弛緩させる。つまり筋緊張を低減させる効果がある。
第9章 姿勢と運動発達支援の実際2:臥位と寝返り
第1節 寝返りの意義
●重度の肢体不自由児では、寝たきりの状態で身体の変形や拘縮や痛みのある子どもが多く見られる。
第2節 仰向け、うつ伏せと寝返り
1.仰向けとうつ伏せの比較
●仰向けは身体を支える面積が狭く、重みが一部に集中するため身体を変形させやすい。そのため仰向けからうつ伏せへ姿勢変換させ、過度の負担を低減する必要がある。
2.仰向けとうつ伏せの間の姿勢変換:寝返り
●自発的寝返りのためには、足を持ち上げて全身をやや屈曲させることが必要である。運動の発達は頭から足の先へと発達していくために、姿勢と運動の発達に遅れがある肢体不自由児では、この足を持ち上げる動きに困難があることが多い。
第3節 寝返りに関係ある姿勢反応
●デロテーション反応とは仰臥位の状態で屈曲した左足をクランクとして骨盤を回旋させる。すると体幹が回転して頭が持ち上がった姿勢になる。この反応が現われれば、次に自発的寝返りが出現する。
第4節 寝返りの支援の実際
●回転の動きを強くあるいは速く行うと、子ども顔が強く床にぶつかるので、ゆっくりとそっと動かす。
●うつ伏せから仰向けへは、腰の骨盤部分を上方に持ち上げるようにして体重を体幹と下肢に分散して回転すると容易に行うことができる。
第10章 姿勢と運動発達支援の実際3:頸座の支援
第1節 姿勢と運動発達における頸座の意義
1.頚座の意義
●頚座は姿勢コントロールの第一歩であり、姿勢と運動発達に困難のみられる子どもの姿勢と運動発達支援の第一歩でもある。
2.頚座と姿勢発達の基本姿勢としての腹臥位の意義
●腹臥位は仰臥位とは異なり、伸展がとりやすい。伸展がとりやすい姿勢が重要なのは、肘位・手位・座位・四つ這い位・立位はすべて伸展を特徴とする姿勢だからである。
第2節 頚座の定義と要素
●頚座(首の座り)の定義は諸家によって異なっている。
第3節 脳性まひ児の頸座獲得のための支援の実際
1.ハイガード姿勢
●ハイガード姿勢は、幼児の立位や歩行時にみられる両手を高く上げてバランスをとる姿勢であり、この姿勢は頚筋・背筋を収縮させて伸展姿勢を強化し、抗重力姿勢をとりやすくする。
2.肘位と関節圧縮
●腹臥位で頭の挙上をはかるときに、肘位をとらせると、両肩、両肘、腰を結ぶ三角形の姿勢となり、頚を支える体幹・上肢の姿勢が安定して、頭の挙上が容易になる。
3.上肢の伸展と外旋
●腹臥位で上肢を前・上方に開きぎみに伸展し外旋させると肩・頚あたりの筋が収縮して挙上を促通する。なお、この技法はキーポイント・オブ・コントロールの1つである。
4.頚・背・腰部の伸張による伸張反射
●腰・背・頚あたりの伸筋を急速に引き伸ばすと伸張反射により伸筋の収縮が促通されて、その結果として頭の前方からの挙上が起こりやすくなる。
●伸張反射は肘位とともにかなり効果的な技法であり、肘位とあわせて用いると効果が増す。
5.デロテーション反応
●デロテーション反応とは仰臥位の状態で屈曲した左足をクランクとして骨盤を回旋させる。すると体幹が回転して頭が持ち上がった姿勢になる。この反応が現われれば、次に自発的寝返りが出現する。
6.触覚や振動覚
●軽くすばやい触覚は筋の収縮をうながす。筋腹への振動覚も同様であり、前庭覚と違い、収縮させたい筋だけを刺激できるので頚筋や背筋へ直接刺激する。
第11章 姿勢と運動発達支援の実際4:座位の支援
第1節 座位の意義
●座位がとれれば健康の保持と学習面の両方でさまざま効用がある。さらに、人間関係やコミュニケーションといった社会適応や環境適応に関しても有用である。
第2節 座位と関係する姿勢反射・反応
1.座位の傾斜反応とパラシュート反応
(1)座位の傾斜反応
●座っている床がゆっくりと傾斜したときにバランスを保とうとして、頭・体幹が傾斜方向と反対方向へ立ち直る反応である。
●座位の傾斜反応には3つの特徴がある。
・脊柱がカーブする。
・傾斜と反対側の下肢が挙上。
・傾斜と反対側に頭が傾斜する。
●学校や家庭でできる簡単な支援法
・支援者があぐら座位をとって子どもの腰辺りを両手で支えてだっこした状態(向きは自由)をとる。その状態で左右や前後にゆっくりと小さく傾けてみる。体幹のカーブもしくは頭の立ち直り反応が出ている場合は、このやり方でゆっくりと小さく傾けることをくり返す。目標は体幹のカーブであり、辛抱強く継続することが大事である。
(2)パラシュート反応
●座位で大きくあるいは急速に傾いたときに、傾斜反応では対応しきれない場合にパラシュート反応がみられる。
●発達支援の順序として傾斜反応の支援の次に行うとよい。
2.座位の傾斜反応の基礎としての腹臥位の傾斜反応
●腹臥位の傾斜反応を誘発することが間接的に座位の傾斜反応を引き出すことにもなる。
●傾斜反応の特徴の1つである体幹のカーブは腹臥位でも座位でも同様である。したがって、ラージボールや傾斜台やその他の多様な教具・遊具を利用して、座位だけでなく腹臥位や他の姿勢での支援の工夫を考えることが大事である。
●ラージボールがない場合は、大きめで硬めのクッションを重ねて使う。
●傾斜反応は頭と重力の方向の感覚によって誘発されることを留意して、頭をいろいろな方向に向けることができる動きや姿勢を工夫してみることが大事である。また、「バランス遊び」として楽しく行うことも大切である。
第3節 座位を支援するためのポイント
●座位保持に必要な筋緊張のコントロールには、適切なポイントへの介助が必要になる。
●座位の支援のポイントは用い方によって緊張を高めたり、あるいは緊張を低めたりするので、一人ひとりの緊張状態と支援の目標をあわせて使い分ける必要がある。全身の緊張を高めるには股関節及び膝関節を伸展させた姿勢、たとえば長座がよい。一方、あぐら座位は筋緊張を低くする効果がある。あぐら座位は全身の伸展緊張が高い場合に有用な姿勢である。
第4節 座位から立位への姿勢変換の支援
●座位の次は立位の獲得だが、立位をとるためには座位から立位への姿勢変換が必要である。
●子どもの立ち上がる力や自発的に立ち上がる意欲を大事にした支援が求められる。
●前から子どもの両手を持って支援するやり方が望ましい。
●前から子どもの両手を持って支援するやり方では、子どもの手の持ち方に注意が必要である。図11-7の持ち方がよい。
・前から両手を持って引き上げていく(膝の角度が90度以上まで)。
・下肢の伸展が楽になり立位に移行する。
・下肢の伸展とともに上肢の屈曲を意識すると立ち上がりやすい。

これは子どもが支援者の親指を握る形になっている。握るという行為は子どもの自発的参加を促す。また、握る力や握る意志が少ない場合でも、このやり方であれば介助者がそれを補助することにより安全に支援することができる。
画像出展:「脳性まひ児の発達支援」
第12章 姿勢と運動発達支援の実際5:立位の支援
第1節 立位の特徴
●立位は全身が伸展しているという特徴がある。
●肢体不自由児では屈曲姿勢が多く、立位の支援においては伸展姿勢の保持が重要な課題となることが多い。
第2節 立位と関係する姿勢反射・反応:傾斜反応
●立位の獲得には立位の傾斜反応を引き出す支援が重要となる。
●立位の傾斜反応は前方と後方では足関節の働きが中心になり、側方では膝関節の働きが中心になる。
●小型トランポリンは子どもが立っている位置を変えないで前後左右の傾斜反応を誘発できるので非常に使いやすく便利な教具である。

画像は“mom-ma”さまより拝借しました。
第3節 立位保持と獲得の支援のポイント
●伸展姿勢には全身の伸筋を収縮させる必要がある。背筋、臀部の筋、大腿四頭筋、下腿の筋など。
1.立位保持の支援で大事な身体のキーポイント
●尖足の場合、股関節屈曲、膝関節屈曲で円背になりやすいため、補装靴の使用を検討する。
2.立位獲得支援の経過に沿ったキーポイント
●立位獲得のための支援における介助は腰介助から肩介助へという方向が大事である。
第5節 歩行の獲得には立位の安定が大事
●歩行は移動することと立位を保つことの2つを同時に行うという複雑な協調を必要とする運動である。
●連続的にバランスを前方に崩していきながら、なおかつバランスを崩さないという2つの矛盾を解決しなければならない。
第13章 姿勢と運動発達支援の実際6:歩行の支援
第1節 歩行の完成
●歩行は中枢神経系の成熟レベル(延髄、橋、中脳、大脳)に依存しており、姿勢反射・反応の成熟過程、つまり原始反射の抑制、立ち直り反応の獲得、平衡反応の獲得が歩行獲得の基礎にある。
第2節 歩行と関係する姿勢反応:ホッピング反応
●ホッピング反応は立位で重心が移動した際に、足を重心の移動方向へ踏み出す反応である。このホッピング反応は自動的な歩行を可能にするという意味で、姿勢と運動の発達支援では重要な反応である。
1.歩行とホッピング反応の関係
●ホッピング反応の有無は歩行を予測するための指標として有用である。ホッピング反応がみられない場合には、つかまり歩行も杖歩行もできないと考えられている。
2.歩行支援におけるホッピング反応誘発の実際
●ホッピング反応は側方ホッピング反応からスタートすべき。
●ホッピングの誘発は肩介助が原則なので、肩介助で立位をとれることが前提になる。
第3節 歩行支援のポイント
●支援は後方腰介助→後方肩介助→前方介助→側方介助の順に支援を進めていくことがよい。
第4節 さまざまな歩行のようすと支援の実際
1.突進様に歩いたり、ふらふらと静止できない場合
●歩行そのものを練習するのではなく、立位で安定して静止できることを目指す。
●最初に立位の姿勢アライメントを整えることが大事である。次に少しずつ前傾させ前方傾斜反応を誘発し全身の伸展が生起され「抗重力身体伸展姿勢」が保ちやすくなる。この状態で抗重力伸展立位姿勢の獲得と立位の静止状態でのバランスの向上をはかることができる。
2.体軸内回旋を活用した歩行
(1)体軸内回旋とは
立ち直り反応の影響を受けて発達する。
(2)体軸内回旋を用いての歩行介助
●足が出ない場合、体軸内回旋を用いて足を一歩出させて歩行させることができる。
脳性まひ児の発達支援1
小児障害児へのマッサージに関わるようになり、『感覚統合法の理論と実践』という本で基礎ともいえる部分を勉強しました。そして、“動作法”という優れた支援方法があるのを知りました。さらに脳の可塑性に着目した“アナット・バニエル・メソッド(本は『限界を超える子どもたち 脳・身体・障害 への新たなアプローチ』)という画期的なアプローチに感銘を受け、患者さまの脳と施術者である自分の脳がつながるイメージ(B2B)をもって、メソッドである”9つの大事なこと”(ブログ中央の”目次”を参照ください)の実践を意識しています。
しかしながら、大きな壁にぶつかりました。それは、今まで担当していた患者さまの多くは、座位もとれない重度の障害をもっていたのに対し、新しい患者さまは座位あるいは四つ這い位は取れるが、安定した立位が取れないといった動くことができる患者さまだからです。
大きな何かが欠けているという実感はありましたが、モヤがかかったような状況でした。そのモヤが晴れたのは仲間の仕事ぶりを見学させてもらったこと、また、別の仲間が勧めてくれた数冊の本のお陰でした。今回のブログはその中の1冊です。
そして、“モヤ”とは、”発達段階における運動特性とリハビリテーション”というような類のものでした。これはOT(作業療法士)やPT(理学療法士)の先生が取り組むべき分野だと思いますが、この分野に踏み込まないと患者さまの現状を把握することはできません。
小児障害マッサージとしての支援内容は、過緊張あるいは低緊張の課題に取り組むことになると思いますが、発達段階に応じたリハビリテーションがどんなものか、日常生活ではどのような特徴として表れるのか、どんな問題をもっているのか、それをどのように改善していくのか。あるいは鍼という手段は使えるのか、頭鍼・頭皮鍼は有効か、脳の可塑性(アナット・バニエル・メソッド)に働きかけるにはどんな工夫をすればよいかなどについて考えていく必要があると感じました。
過去ブログ“ボイタ法・ボバース法”の中で、私は偉そうに次のようなことを言っていました。
『まず図書館から借りてきたのは「ボイタ法の治療原理 反射性移動運動と運動発達における筋活動」という本です。こちらの本の魅力は何といってもボイタ(Vaclav Vojta)自身が書いたものであるという点です。読んでみると、運動学(キネマティクス)とリハビリテーション学についての知識が不足している私には、理解するのは難しいということが分かりし、早々に断念することにしました。』
抜けていたのはまさにこの部分、避けていた部分でした。結局、ブーメランのように私自身に舞い戻ったという感じです。
ブログは第2部と第3部が対象です。また完全に勉強モードのブログです。そのため個人的に重要であると感じた部分の要点を列挙する形式となっており、つまみ食い状態のため、不親切な書き方になっていると思います。なお、長文のため2つに分けており、今回は“1”ということになります。
目次
第1部:肢体不自由教育と発達支援
第1章 肢体不自由とは
第2章 肢体不自由教育と発達支援
第3章 肢体不自由教育と障害の重複化
第2部:発達支援のための基礎知識
第4章 姿勢と運動の発達
第1節 姿勢の発達段階
第2節 姿勢の分類
第3節 上肢を姿勢保持に用いる姿勢と操作に用いることができる姿勢
第4節 体幹が直立した姿勢
第5節 運動発達の2つの方向
第6節 姿勢と運動発達の支援における4つの目標
第7節 姿勢と運動発達の支援と並行して行うこと:筋緊張障害への対応
第5章 姿勢と運動を支える感覚
第1節 姿勢と運動を支える固有覚と前庭覚
第2節 固有覚とその機能
第3節 前庭覚とその機能
第6章 姿勢と運動を支える姿勢反射・反応
第1節 中枢神経系、姿勢反射・反射と姿勢と運動発達の関係
第2節 原始反射、立ち直り反応、平衡反応
第3節 姿勢反射・反応各論
第4節 脳の成熟に伴う原始反射の抑制
第5節 姿勢反射・反応と姿勢と運動の抑制・促通関係
第7章 脳性まひの筋緊張障害
第1節 脳性まひの定義と類型
第2節 脳性まひにみられる2つの筋緊張障害:除皮質緊張と除脳緊張
第3節 脳性まひ痙直型の除皮質緊張と対応の原則
第4節 痙直型の筋緊張の特性と支援センターの原則
第5節 アテトーゼ型の筋緊張の特性と支援センターの原則
第3部:発達支援の実際1(姿勢と運動の支援)
第8章 姿勢と運動発達支援の実際1:筋緊張障害への対応
第1節 低緊張への対応
第2節 過剰に高い筋緊張への対応
第9章 姿勢と運動発達支援の実際2:臥位と寝返り
第1節 寝返りの意義
第2節 仰向け、うつ伏せと寝返り
第3節 寝返りに関係ある姿勢反応
第4節 寝返りの支援の実際
第10章 姿勢と運動発達支援の実際3:頸座の支援
第1節 姿勢と運動発達における頸座の意義
第2節 頸座の定義と要素
第3節 脳性まひ児の頸座獲得のための支援の実際
第11章 姿勢と運動発達支援の実際4:座位の支援
第1節 座位の意義
第2節 座位と関係する姿勢反射・反応
第3節 座位を支援するためのポイント
第4節 座位から立位への姿勢変換の支援
第12章 姿勢と運動発達支援の実際5:立位の支援
第1節 立位の特徴
第2節 立位と関係する姿勢反射・反応:傾斜反応
第3節 立位保持と獲得の支援のポイント
第4節 立位での重心移動
第5節 歩行の獲得には立位の安定が大事
第13章 姿勢と運動発達支援の実際6:歩行の支援
第1節 歩行の完成
第2節 歩行と関係する姿勢反応:ホッピング反応
第3節 歩行支援のポイント
第4節 さまざまな歩行のようすと支援の実際
第5節 前方支持歩行器と後方支持歩行器
第4部:発達支援の実際2(学習、環境・社会適応、摂食・嚥下の支援)
第14章 学習活動の支援
第1節 学習する姿勢としての座位の意義
第2節 上肢の操作と知的発達
第3節 学習活動を促進する機能的座位姿勢
第4節 上肢を使用した学習活動のための配慮事項
第15章 環境・社会適応の支援
第1節 自立活動における環境の把握、人間関係及びコミュニケーション
第2節 環境の把握と姿勢と運動
第3節 人間関係の形成と姿勢と運動
第4節 コミュニケーションと姿勢と運動
第5節 環境の把握、人間関係、コミュニケーションと姿勢と運動との相互関連を踏まえた支援の重要性
第16章 摂食・嚥下の支援
第1節 自立活動における健康の保持と肢体不自由
第2節 摂食・嚥下の支援における留意事項
第3節 摂食・嚥下しやすい姿勢のポイント
第2部:発達支援のための基礎知識
第4章 姿勢と運動の発達
第1節 姿勢の発達段階
1.姿勢の発達段階とそれに対応した運動の発達
●腹臥位→肘位→手位→座位→四つ這い位→立位となっており、この発達段階に対応して運動が発達していく。
2.抗重力姿勢という考え方
●通常の生活において、人間は重力を意識することは殆どないが、常に重力の影響を受けている。この重力に抵抗して姿勢を保つための重要な特徴として頭を重力方向に向けるということがあげられる。
●抗重力姿勢とは適当な筋緊張が保たれて、関節が適度に固定されて重力に負けずに一定の適応的な姿勢が保たれている状態をいう。
第5節 運動発達の2つの方向
1.上から下への発達
●首が座り、体幹がしっかりしてきて座位が可能となり、下肢の機能が高まり立位が可能となる。
●肢体不自由児にとって、頭と首や上肢に比較して下肢や下半身の動きは困難であることが多い。寝返り(姿勢変換)においても肩などの上半身から回旋しようとする。
●上から下へと発達していくという観点は、姿勢と運動の発達支援に関する長期的な目標設定とその目標設定へいたる短期的目標の設定において非常に重要なポイントである。
●座位獲得の支援を行っているときから下肢、具体的には、足首・膝関節の状態に注意する。これは膝の伸展が不十分になると不安定な立位になってしまうためである。したがって、膝が屈曲した状態になるあぐら座位では、意識的に膝関節をストレッチするといった配慮が必要である。
2.中央から左右への発達
●上肢の運動は「肩-肘-手首-指」の順番に巧緻性や分化が進んでいく。中央から末端へという発達の流れに沿った支援が重要。この順序を守らないと課題の押しつけになる。
●幼児は絵を描くとき肩を中心として大きく腕全体を動かしている。幼児が肩を大きく動かしてなぐり描きをする時期に、「線からはみ出さないように、ていねいに塗りましょう」という指導を行った場合、指を細かく動かして目と指の協応運動をする必要があり、子どもには難しく、子どもに不全感や意欲の低下をもたらすことになりやすい。
第6節 姿勢と運動発達の支援における4つの目標
1.4つの目標と生活・学習場面との関係
●肢体不自由とは姿勢と運動の困難であることから、姿勢と運動に関するこれらの4つの分類が姿勢と運動の発達支援における目標となる。
2.4つの目標それぞれの内容
(1)姿勢保持
●座位、四つ這い位、立位など。自らの力で姿勢を保持できるようになることが目標である。
(2)上肢の操作
●持つ、書く、物へ手を伸ばす、食べるなど。これらは座位が保持できるようになることが前提になる。
(3)移動運動
●移動運動の獲得により子どもの活動空間は飛躍的に広がる。臥位では寝返りによる移動、肘位では這うことによる運動、四つ這い位では四つ這い移動、立位では歩行などである。
(4)姿勢変換
●あぐら座位から四つ這い位への変換では、体幹を左へ回旋させて左手を床につく。次に腰を持ち上げながら右手を床につく。こうして両手を床について腰を持ち上げた四つ這い位へと変換する。この姿勢変換では、体幹の回旋、左右の手を床につく、腰を持ち上げるという複数の運動が順序よく行われることが大事である。
3.4つの目標と自立活動の身体の動きとの関係
●自立活動の身体の動きの内容は、すべて4つの目標「姿勢保持、上肢操作、移動運動、姿勢変換」が含まれている。自立活動の身体の動きの指導にあたっては、4つの目標の観点から指導内容を選定して、総合的な課題として指導していくことが大事である。
第7節 姿勢と運動発達の支援と並行して行うこと:筋緊張障害への対応
●座位姿勢の保持には背中の抗重力作用筋の適度な緊張が必要である。
●脳の障害などにより筋緊張が低い場合には適度な緊張は難しい。このことは学習行為などに大きな影響を与える。
●過緊張に関しても運動の困難が発生する。姿勢のとり方や適切な感覚入力などの支援によって、適度な筋緊張を保つことができるようになる対応が必要である。
第5章 姿勢と運動を支える感覚
第1節 姿勢と運動を支える固有覚と前庭覚
●固有覚と前庭覚は姿勢と運動の制御に重要な役割を果たしている。
●固有覚は筋・腱・関節の緊張に関する感覚ということができる。
●前庭覚は頭の動きと頭に対する重力の方向に関する感覚である。
第2節 固有覚とその機能
1.固有覚とその関連用語
●身体の全体の位置、身体各部の位置、身体の動き、身体の傾きなどの位置の感覚、運動の感覚、抵抗の感覚、重さの感覚などの総合的な感覚である。
●固有覚と関連の深いことばとして、体性感覚がある。体性感覚には表在感覚(皮膚感覚)と深部感覚の2つが含まれる。表在感覚には触覚、温冷覚、痛覚があり、深部感覚には運動覚(関節の角度など)、圧覚、振動覚がある。このような感覚情報に基づいて、姿勢の保持や姿勢変換、運動が適切に行われる。
2.固有覚が姿勢と運動に果たす役割
●姿勢と運動を支える重要な感覚。
●姿勢の保持や姿勢変換、あるいは各種の運動の遂行によって生じる筋肉・腱・関節の緊張に関する情報をとらえてフィードバックすることによって、適切な姿勢と運動の遂行を可能にしている。
●子どもはさまざまな姿勢をとり、さまざまな運動をすることによって、自分自身の身体の各部分と全体との関係などについて学習していく。これはボディーイメージを育てることと言い換えることもできる。
第3節 前庭覚とその機能
1.「前庭」ということば及び2つの前庭覚について
●前庭覚には2つの感覚がある。1つは頭が動いている感覚、もう1つが頭に対する重力の方向の感覚。前者は内耳の蝸牛及び卵形嚢や球形嚢で受け取られ、後者は三半規管でとらえられる。
2.前庭覚には5つの機能がある
●卵形嚢と球形嚢や三半規管が発生した信号は、前庭神経を通じて延髄内の前庭覚に伝えられ、ここには脳内を上行する経路が4つと、脊髄へ下行する経路が1つある。そしてこれらの経路に対応して5つの機能がある。
3.前庭-眼球運動系
●内耳の三半規管でとらえられた頭の動きは、延髄の前庭神経核から眼球運動中枢である延髄の外転神経核、中脳の動眼神経覚と滑車神経核に伝えられる。これらの3つの核が外眼筋をコントロールして眼球を動かす。
4.前庭-網様体系
●前庭感覚や固有覚は脳幹の網様体へ集められて、脳を活性化するエネルギーに変換されて、脳の各部位へ送られる。その結果として脳の覚醒レベルを高める。
5.前庭-視床下部系
●前庭-視床下部系は自律神経系に影響する。
6.前庭-視床下部-辺縁系
●前庭-網様体系と共同して、情動を刺激して外界への関心と反応の準備状態をつくる。
7.前庭-脊髄系
●内耳の迷路から脳幹の前庭神経核に入った前庭刺激は、前庭脊髄路を下降して頚筋を含む全身の伸筋の収縮を促す。
●前庭刺激によって、立ち直り反応や平衡反応に必要な頚・背・腰部の伸筋収縮を促通することができる。
●前庭・脊髄系のしくみは、パラシュート反応・ホッピング反応などの前庭刺激によって誘発される姿勢反射・反応を支える大切な経路でもある。
●運動の発達支援、特に自立活動の身体の動きの指導にあたっては、前庭・脊髄系の働きを基礎知識として理解しておくことが大事である。

こちらは「人体の正常構造と機能」という本から持ってきた図で、”前庭覚の伝導路”というタイトルがついています。これをご紹介した理由は、重要とされる前庭-脊髄系を理解するうえで良い図ではないかと思ったためです。
第6章 姿勢と運動を支える姿勢反射・反応
●姿勢反射・反応には、それらを誘発する刺激があり、これらを適切に活用することが重要である。
第1節 中枢神経系、姿勢反射・反応と姿勢と運動発達の関係
●姿勢と運動は、随意的な姿勢と運動と姿勢反射・反応の2つから構成されており、姿勢反射・反応の成熟は、中枢神経系の成熟及び姿勢と運動の発達と密接な関係がある。
第2節 原始反射、立ち直り反応、平衡反応
1.原始反射とは
●新生児の運動はほとんどが脳幹・脊髄レベルの反射で成立している。
2.立ち直り反応
●立ち直り反応はさまざまな姿勢の保持やバランスを自動的に保つ反応であり、姿勢と運動発達支援において重要な基礎となる反応である。
3.平衡反応
●平衡反応は立ち直り反応と同様に、さまざまな姿勢の保持や運動を自動的に可能にする反応である。
第3節 姿勢反射・反応各論
2.立ち直り反応
(1)抗重力性頭の立ち直り反応
●身体を左右や前後に傾けたときに頭が重力線上に保たれる反応。
●誘発刺激は、頭の重力の方向に対する感覚(前庭覚)と視覚がある。
●この反応は身体が傾いてバランスが崩れた際に、傾いた側と反対方向へ頭を立ち直らせて姿勢を保つ働きを担っている。
●座位を保持するための重要な反応である。
●あぐら座位の子どもの脇の下や肩を保持して、ゆっくりと小さく左に傾ける。傾けることによって視覚や前庭覚が刺激されて、頭の立ち直り反応が誘発されやすくなる。その際に頭の立ち直りが少しでも出てくるかどうかに注意しながら傾けていく。頭の立ち直りがみられなかったり、少ない場合には決して大きく傾けないで元に戻すことが大事である。少しずつ何回か傾けて刺激を加えながら、辛抱強く頭の立ち直りが出てくることを待つ姿勢が大事である。
(2)デロテーション反応(巻き戻し反応)
●デロテーション反応は仰向け(背臥位)からうつ伏せ(腹臥位)への寝返りのことである。通常、生後6か月ごろからみられる。誘発刺激は、下半身をひねった際に起こる体幹のねじれの感覚(固有覚)である。
●寝返りは下肢を動かすことが起動となり、寝返り後は頭が無意識に挙上されている。側弯の逆方向やいつも頭を向けている側と逆側へのデロテーション反応は身体の非対称性の矯正に有効である。
3.パラシュート反応
●パラシュート反応は「保護伸展反応」と記載されることも多い。
●座位で前方、側方、後方に倒れそうになったとき、手を伸ばして(伸展)、倒れて頭を打つのを防ぐ(頭を保護する)反応である。
●あぐら座位の子どもの脇の下や肩を保持して、急速に大きく傾けることによって誘発されやすくなる。頭の立ち直り反応同様、何回か傾けて刺激を加えながら辛抱強く待つ姿勢が大事である。
●パラシュート反応は、前方、側方、後方の順番で出現する。
●パラシュート反応は自動的な四つ這い移動を可能にする。
4.平衡反応
(1)傾斜反応
●傾斜反応は座位や立位のバランスを保ち、姿勢を保持する働きを担っている。
●傾斜反応は、臥位・肘位・手位・座位・四つ這い位・立位等のすべてでみられる反応である。
●身体に部分的な反応である抗重力性頭の立ち直り反応と異なり、傾斜反応は頭・体幹・下肢を含む全身の協調反応である。
●誘発刺激は抗重力性頭の立ち直り反応と同じように、視覚と前庭覚(頭の重力方向に対する感覚)の2つである。
●1人で立位が取れるようになるための発達支援において傾斜反応は最も重要な反応である。
(2)ホッピング反応
●ホッピング反応は立位で重心が移動した際に、足を重心の移動方向へ踏み出す反応である。側方・前方・後方のホッピング反応があり、この順序で出現する。
●ホッピング反応は自動的な歩行を可能にする働きを担っている。
第5節 姿勢反射・反応と姿勢と運動の抑制・促通関係
●姿勢と運動の発達支援では、姿勢と運動を促通する反射・反応と抑制する反射・反応がある。
第7章 脳性まひの筋緊張障害
第1節 脳性まひの定義と類型
1.脳性まひとは:定義
●厚生省脳性麻痺研究班(1968)によれば、脳性まひとは「受胎から新生児(4週間以内)までの間に生じた、脳の非進行性病変に基づく、永続的なしかし変化し得る運動及び姿勢の異常である。その症状は満2歳までに発現する。進行性疾患や、一過性運動障害、または将来正常化するであろうと思われる運動発達遅延は除外する」と定義されている。
4.脳性まひの類型
●脳性まひはその類型によって神経生理学的症状等の特徴は全くといってよいほど異なっている。
5.脳性まひと重複障害
●脳性まひ児には姿勢と運動の障害以外に多くの随伴症状がみられる。
6.脳性まひの神経生理学的症状
●神経生理学的には、脳性まひの症状は3つに分類される。筋緊張障害、相反神経支配の障害及び姿勢反射の障害。
第2節 脳性まひにみられる2つの筋緊張障害:除皮質緊張と除脳緊張
●除皮質緊張、除脳緊張という言葉は、動物実験で動物の脳の皮質を取り去ったり(除皮質)、皮質に加えて脳内の基底核とよばれる高さ付近で脳の線維を切断したり(除脳)して、脳の働きを研究したことに基づく言葉である。
第3節 脳性まひ痙直型の除皮質緊張と対応の原則
1.除皮質緊張とは
●除皮質緊張とは、上肢屈曲・下肢伸展を最大の特徴とする筋緊張障害である。
●脳性まひでは痙直型(大脳皮質や錐体路に問題)にみられる筋緊張障害である。
2.除皮質緊張による身体の過剰な伸展と身体の変形など
●除皮質緊張は下肢伸展・内転・内旋の状態のため、股関節の亜脱臼や脱臼などの障害が生じることが多い。
3.除皮質緊張が姿勢と運動に及ぼす影響
●痙直型脳性まひ児は生活及び学習に多くの困難に直面している。したがって、除皮質緊張の影響を減少させ、これらの困難を克服する支援が重要である。
4.除皮質緊張への対応
(1)除皮質緊張への対応の原則
●除皮質緊張と反対の動かし方や姿勢をすることが原則である。
(2)一か所の関節を緩めると他の関節の緊張も落ちる
●一か所の関節を緩めることで、たとえば足指を背屈させることで、他の関節の屈曲・外旋・屈曲・外転も同時に起こる。それによって、下肢全体の緊張も同時に低下する。この一か所の関節を動かすことで他の関節も連動して動く作用を「共同運動」とよぶ。
●共同運動は、脳障害によって上位中枢の抑制機能が低下・消失したときに起こる。脳障害による陽性徴候の中でも重要なもので、脊髄レベルの原始的な運動が、上位中枢からの抑制が弱まったために顕在化したものである。
5.除皮質緊張への対応におけるあぐら座の効用
●あぐら座位除皮質緊張による過剰な伸展と過緊張を減少させるための効果的な姿勢であり、仰臥位の後に下肢を屈曲・外転・外旋した状態であぐら座位へ姿勢変換するとよい。
6.学校や家庭であぐら座位をどれくらいの時間とればよいか
●「がんばらないことが大事」「楽しく座れることを心がける」と答えている。1回の持続時間は短くてもよい。結果的に1日に数十分のあぐら座位をとっていたということが望ましい。
●数か月で「股関節の開きがよくなってきた」「立位や歩行のときに下肢の交叉が軽くなってきた」などの効果が期待できる。
7.床上でのあぐら座位と座位保持いすの比較
●座位保持いすはあぐら座位ほどではないが効用があるが、長時間の場合、除皮質緊張に悪影響を起こす恐れがある。特に、下肢内転による股関節の可動域低下や関節拘縮に気をつけなければならない。床でのあぐら座位やまたがることができるいすでの座位など、多様な座位を活用することが大事である。
第4節 痙直型の筋緊張の特性と支援センターの原則
1.痙直型の筋緊張
●痙直型の筋緊張は高い緊張(過緊張)で一定していることが特徴である。
2.痙直型の過緊張がもたらすこと
●静止した状態や姿勢が固定された状態で続きやすく、身体の変形や関節拘縮が進行しやすい。
3.支援の原則:動くことの重視
●姿勢と運動の支援は、自分で動くことあるいは他動的に動かすことが原則となる。(下記の表7-12に書かれた内容がとても重要だと思います)
なお、相反神経支配とは主動筋(例えば、大腿四頭筋)が収縮しているときには、反対側の拮抗筋(ハムストリングス)は弛緩するように神経が調整するというものです。

相反神経支配と痙直型脳性まひの相反神経支配の障害(左下の四角で囲んだ部分)
腕を伸ばすには上腕二頭筋が弛緩(脱力)する必要があります。そのための指示は脳から出される収縮抑制命令というものですが、その命令が不十分(抑制不全)だと、腕を伸ばすことはできません。
画像出展:「脳性まひ児の発達支援」
第5節 アテトーゼ型の筋緊張の特性と支援センターの原則
1.アテトーゼ型という用語について
●アテトーゼとは筋緊張障害の一種であり、錐体外路障害の中でも基底核障害によって起こる不随意運動を意味している。
●錐体路障害である痙直型、錐体外路障害の中でも小脳障害に起因する失調型とともに慣習的に用いられている。
●筋緊張の変動とは筋緊張が一気に高くなったり一気に低くなったりと急激に変化すること。
官能的感触と成長
今回のブログは、“スキンシップケア(C触覚線維)”という以前アップしたブログに関係する内容であるため、そのブログに「追記」としてご紹介することを考えていたのですが、あらためて読み返してみると、同じく過去ブログの“医療マッサージ研究”にも載せたいし、そもそもこの本の存在を教えてくれた“アナット・ダニエル・メソッド”にも追記したいという気持ちが強くなりました。そして、それであればとの思いから、短い内容ですが新しいブログとしてアップすることにしました。
なお、“アナット・ダニエル・メソッド”とは、脳の可塑性に着目した小児障害へのアプローチが有名です。私は小児障害児と向き合うときに、このメソッドを意識するようにしています。
ブログは『脳の中の身体地図』の「10章 心と身体が交わる場所」にコラムとして掲載されていた「官能的感触の大切さ」から抜き出しています。
『痒み、くすぐったさ、痛み、温度……官能的感触? 官能的感触は、この感覚のリストの中では浮いているように思える。情動面から見て重要な触覚と言えば、総じて一種の軽い触覚で、覚えておられると思うが、これは固有感覚情報や高分解能の触覚情報と同様に、脊髄にあるはるかに新しいほうの経路を介して脳に伝達される。ところが、官能的感触は、痛みや痒み、くすぐったさ、温度のように、いにしえから存在する経路を経て脳に流れ込む。官能的感触はそんな仲間に入って、いったい何をしているのだろう?
愛情のこもった触れ合いやじゃれ合いは、ほ乳類の身体意識と脳の発達の中核をなす。成獣になると群れを作らずに単独で行動するようになるほ乳類でさえ、母親や兄弟姉妹との親密で愛情深い接触の中で生のスタートを切る。ほ乳類は授乳し、親密な絆を深めるために舐め合い、鼻をすり寄せ合い、生きていく上で何が起きても困らないようにボディ・マップに磨きをかけるために、手加減したけんかごっこに興じる動物である。要するに、ほ乳類の正常で健全な脳の発達には、幼少期に官能的感触に頻繁に触れることが不可欠なのだ。数億年前、ほ乳類時代以前、は虫類時代以降のほ乳類の祖先にも、きっと同じことが言えたはずだ。そこ頃、ほ乳類は恐竜の影に怯えながら、結束の強い家族という生存様式を発達させつつあった。つまり、この官能的感触という特徴は、ほ乳類誕生の頃までさかのぼることができるのだ。新しい感覚経路を使わず、古い感覚経路に留まっている理由もそこにある。

画像出展:「GAHAG」
ネズミの母親は子どもたちを舐めて落ち着かせる。母親に舐めてもらうという官能的感触を頻繁に味わうことがなかった赤ちゃんネズミは、せっせと舐めてもらったネズミよりも不安が強く、神経質なネズミに育つ。しかも、この循環は自然に増強していく。情動面に障害が残ったネズミが成長して母親になると、普通のネズミほど子どもを舐めようとしない。こうして情動的な問題が次世代へと受け継がれていく。モントリオールにあるマギル大学で行動・遺伝子・環境研究プログラムの責任者の任にあるマイケル・ミーニーが数年前に実施した画期的な研究で、この子育てパターンの背後に潜んでいる正確な神経・遺伝メカニズムが解明されている。
官能的感触は霊長類と人類にとってはとりわけ、決定的に重要な意味を持つ。これは、スキンシップに飢えた子どもたちが大人になってから情動面の問題を抱えるようになるということだけのことではない。それも非常に重大な問題だが、もっと深い、身体の成長や健康、恒常性のレベルにまで影響が及ぶのだ。霊長類の赤ん坊にとって官能的感触がどんな役に立つか、考えてみよう。頻繁にやさしく撫でさすられると、最低限の世話しかしてもらえなかった場合に比べて、体重が倍の速度で増加する。呼吸や心拍も健康的になるし、敏捷になり、気むずかしさがなくなり、よく眠るようになる。授乳期を過ぎてよちよち歩きを始めるまで、こうしたよい影響が続くのである。
愛情のこもった触れ合いは、栄養を摂取したり、音楽を聴いたり、おもちゃで遊んだりするのとは異質に思えるかもしれないが、確かに同じ類のことなのだ。』

画像出展:「GAHAG」
まとめ
1.やさしく撫でられると情動面だけでなく、身体の成長や健康、恒常性のレベルにまで影響を及ぼす。
2.官能的感触とは食事や睡眠に匹敵するくらい大切な行為である。
共感とミラーニューロン
心の問題が疑われる“うつ症状”と異なり、“うつ病”と診断される深刻な病態は、心の問題ではなく偏桃体の暴走や神経伝達物質のセロトニンが関与する脳の問題とされています。※ご参考:“うつ病治療(TMS)”。
一方、“共感”も性格や心が関係しているものと考えがちです。しかしながら、この“共感”にも脳が関係している場合があります。それは“ミラーニューロン”に起因するものです。このミラーニューロンは大脳皮質の奥深く折りたたまれた領域に多く存在しているそうです。
共感が心の問題とは限らないということは知っておいた方が良いと思い、ブログのテーマに取り上げました。
他人の身になる能力
『1926年の映画「ドクター・ノー」で、ジェームス・ボンドが目を覚ますと、タランチュラが一緒にベッド・インしていた。彼の腕をゆっくりゆっくりと這い上がって行くクモに目をくぎ付けにしながら、あなたがその毛に覆われた細長い脚を我が身に感じることができたのは、ミラーニューロンが一生懸命働いていたからである。
情動の読み取りと共感にかかわるミラーニューロンは、皮質の奥深くに折りたたまれたふたつの領域、島皮質と前帯状皮質に存在している。
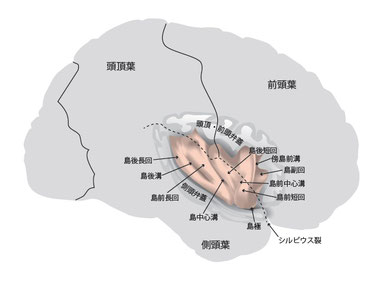
島皮質
『Johann Christian Reilは、1796年に Exercitationum anatomicarum fasciculus primus de structura nervorumを発表、その中で第5の葉の存在を指摘した。これが島に関する初の学術的な記述である。しかし記述は本文のみにとどめられ、図示されなかった。Reilの発見した島は、現在も重版中のGray解剖学書で初めて図示され、「Reilの島」という呼称を不朽のものとした。』
画像出展:「脳科学辞典」

前帯状皮質(ACC)
『前帯状皮質は、大脳半球内側面の前方部に存在する、帯状溝周辺および帯状回の領域であり、ブロードマン24野、ブロードマン25野、およびブロードマン32野に相当する。ACCは特にヒトにおいて、担う機能の違いから、行動モニタリングおよび行動調節に関わる領域、社会的認知に関わる領域、および情動に関わる領域に大きく分かれる。』
画像出展:「脳科学辞典」
他人の顔に嫌悪の表情を見て取ると、あなたの島皮質のミラーニューロンがあなた自身の身体に嫌悪感を生じさせる。嬉しそうな顔を見れば、あなたも嬉しくなる。悲しい顔を見ると、悲しくなる。痛そうな顔を見れば、自分まで痛くなる。他人の二の腕に注射針が突き立てられるのを見ると、あなたの腕の同じ筋肉が緊張して、息づかいまで速くなる。
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの神経科学者タニア・シンガーは、恋人同士のカップルを募集し、その片方(女性)を脳スキャナにかけて、痛みを伴う電気刺激を与えた。どの女性もみな、自分が刺激を受けたときだけでなく、恋人が刺激を受けるのを見たときにも前帯状皮質の反応を示した。しかも、共感に関する質問票のスコアが高かった女性ほど、この脳領域の活動は活発だった。これは、あなたが赤の他人も含めた自分以外の人の痛みに共感すると、ある程度の痛みを実際に感じることを意味している。ちょうど前頭葉と頭頂葉のミラーニューロンが行為の観察と実施を両方とも表象するのである(女性のほうが男性よりもミラーニューロンの反応が活発で、共感も強い傾向にあるが、その理由はいまだに解明されていない。男性においてはテストステロン濃度が高いことが、何らかの共感を抑えているのかもしれない。一般的には、女性は他人の心理状態に注目して適切な感情表現により対処しようとする傾向が強いエンファサイザー=emphasizerで、男性は物事を系統だてて考えようとする傾向が強いシステマタイザー=systematizerである)。
誰かがあくびをすると、あなたもあくびをする。これはミラーニューロンが活動しているせいだ。誰かがあごを掻いているのを見ると、自分のあごもムズムズしてくる。誰かが怖がっているのに気付くと、理屈抜きに不安が心をよぎる。この感覚が闘争・逃走反応の運動準備を身体にさせることもある。危険が潜んでいると、群衆の間に不安が広がる。誰もが情動を高ぶらせて、逃げ腰になる。
自分が触れられても、他人が触れられるのを見ても、同じ神経回路が活性化する。たとえば、ケイゼルス博士は被験者を脳スキャナにかけて、むき出しにした脚を筆で刺激し、どのボディ・マップが“明るくなる”か調べた。予想どおり、一次触覚野と、それに加えて特に二次触覚マップが活性化した。次に、ほかの人が同じ場所に触れられているビデオ・クリップを見せたところ、やはり二次触覚マップが活性化した。そこで、人の脚の代わりにペーパー・タオルのロールに触っているビデオ・クリップを見せると、この回路の活動は弱くなった。筆を脚に近づけるだけで触れない場合には、触覚野は賦活しなかった。ケイゼルスによると、触覚は他の人々が生きていることを確認するための、人間社会において特権を認められた感覚だそうだ。』
自閉症とミラーニューロン
『自閉症の犯人捜しで今、第一容疑者と目されているのがミラーニューロンである。先天性脳障害である自閉症の主要特徴は共感、模倣、言語スキル、そして、他人の心的状態の内的モデルを形成する能力の欠如だ。言い換えるなら、ミラーニューロンが専門にしている機能がそっくり欠如しているのである。先頃、自閉症児のミラーニューロン系は脆弱ないし欠如していることをV・S・ラマチャンドランが確認した(しかも、皮質のボディ・マップがごちゃ混ぜになっていた。これが重大な意味を持つか否かはいまだ解明されていないが、何らかの形でミラーニューロン系の欠損と関係している可能性がある。自閉症児は触れられていることに過敏でもある)。彼らの精神的孤児、遊びの欠如、乏しいアイ・コンタクト、生物界に対する無関心はすべて、ミラーニューロン系の機能不全と一致している。自閉症児が顔の表情をまねしようとしても、その感情や意味は理解していない。悲しい、腹が立つ、嫌だ、びっくりした……という感情がどういうものか、周囲の人々の気持ちと結びつけることをしない。顔や身体が情動を表すのに重要であることを感じていないらしい。見て、行うことによって学ぶことができないのである。』
まとめ
1.大脳皮質の奥深くに折りたたまれた島皮質と前帯状皮質には、情動の読み取りや共感に関わるミラーニューロンが存在している。
2.心の問題とされやすい情動や共感に関しては、脳のミラーニューロンが関与している可能性があり、特に自閉症児などとコミュニケーションするときは、この点を頭に入れておく必要がある。
脳の可塑性とボディ・マップ
『限界を超える子どもたち』は2019年2月にアップした“アナット・バニエル・メソッド”の原本です。この本のインパクトは凄まじく、私は小児障害児へのマッサージの基礎に、このメソッドを据え置こうとしています。
本書には「9つの大事なこと」というのがあるのですが、今回のブログのきっかけとなったミラー・ニューロンは5つめの「内なる熱狂」の中に出ていました。

喜びを深める力
『たとえ言葉にしなくても、あなたが心の内で熱狂すると、子どもはそれを感じとります。親子のあいだで交わされるそのような無言のやりとりを、私は何千と見てきました。心強いことに、近年、科学もこれを立証するようになりました。
1996年、イタリア・パルマ大学の神経科学者ジャコモ・リツォラッティがサルの脳のミラー・ニューロンの活動をつきとめました。彼はのちに「ミラー・ニューロンは、私たちが推論によってだけでなくシミュレーションをすることによって、考えることではなく感じることによって、他者の心をつかみとることを可能にする」と述べています。科学ライターのサンドラ・ブレイクスリーは「人間の脳には他者の行為だけでなく、その意図、また、態度や感情がもつ社会的意味を読みとるミラー・ニューロンのシステムが複数ある」と記しています。
科学研究から読みとれるのは、あなたが心を熱くすることが子どもの脳におおいに影響するということです。あなたが喜びを深め、それを熱狂にまで高めることが、子どもが自分の変化(違い)に気づき、それを感じとることを助けます。そのとき子どもがあなたから感じる前向きの感情が、その子の脳に、「この変化は大切なので刻みこむべきだ」と伝えます。子どもはあなたの熱狂―喜びや満足感、希望的な気持ち―を感じとります。その一方で忘れてはならないのは、子どもの脳は周囲の人々の落胆や失望、無力感、無関心といった感情も鏡のように写しとるということです。』
「人間の脳には他者の行為だけでなく、その意図、また、態度や感情がもつ社会的意味を読みとるミラー・ニューロンのシステムが複数ある」と説いたサンドラ・ブレイクスリーの著書は、ワシントンポスト紙の2007年度ベストブック(科学・医学部門)に選ばれた『脳の中の身体地図』でした。副題には「ボディ・マップのおかげで、たいていのことがうまくいくわけ」となっています。
この本から今回の“脳の可塑性とボディ・マップ”を含め、以下の5つに分けてブログにアップしたいと思います。
1.“脳の可塑性とボディ・マップ”
2.“運動イメージ法”
3.“脳卒中のリハビリテーション”
4.“共感とミラー・ニューロン”
5.“官能的感触と成長”
知能は身体を必要とする
『脳のマップは身体のみならず身体周囲の空間も図示する、拡大、収縮して日常生活の中に存在する事物を取り込む、しかも、自分の育った文化によって形作られるという考え方は、科学にとっては極めて斬新だ。今では研究により、脳がボディ・マップだらけであることがわかっている。体表のマップ、筋系のマップ、意図のマップ、行動する能力のマップ、まわりの人々の行動と意図を自動的に追跡して列挙するマップさえある。
これらの身体中心のマップは実に可塑性に富んでいて、損傷や経験、訓練に応じて大幅な再編成を見せる。形成されるのは幼少期なのだが、経験を積むにつれて成熟し、速度こそ衰えてくるものの、生涯変化し続ける。ただし、いくら、こうしたボディ・マップが自分という存在の中心だと言っても、この我が身の化身はたいてい、意識の端をちらりとかすめる程度で終わっている。まして、そのパラメータ(変数)が年々刻々と絶えず変化し、適応しているとは思いもしない。意識の舞台裏で続けられている膨大な作業を、あなたはまるで理解していないだろう。だからこそ、身体化が実に自然に感じられるのだ。ボディ・マップの持続的な活動は、あまりに継ぎ目なく、自動的で、流れるようにしっくりなじんでいるので、それが起きているとは気づかないし、人間性や健康、学習、これまでの進化の過程、サイバネティックス[人工頭脳学]によって広がる未来に対する興味深い洞察を生み出しているとは、なおさら思うまい。
身体は脳を入れて動き回るための単なる運搬具ではない。両者の関係は完璧なまでに互恵的だ。身体と脳はお互いのために存在している。動かすことも止めることも自在で、触れるのも躱すのも可能、やけどもすれば温まりもする、凍えたり冷えたりする、緊張することもあれば休めることもできる、飢えればむさぼり食って栄養を付ける。そんな身体は感覚のレーゾン・デートル、存在理由だ。そして、皮膚と身体から感じる感覚―触覚、温覚、痛覚など、本書で取り上げるほんの数種の感じる感覚が、あなたの心の基盤となる。他の感覚はみな、相対的な利便性のために追加されたものに過ぎない。せんじ詰めて言えば、人間は視覚や聴覚が無くても、元気いっぱいに暮らしていける。両方の感覚に恵まれなかったヘレン・ケラーのような人々さえ、心身両面で力強く成長できるのだ。生まれながら耳の不自由な人々の脳は聴覚マップを構築しないし、先天的に目が不自由な人々の脳が視覚マップを形成することはないけれども、視聴覚障害がある人々もボディ・マップを持っている。それにひきかえ、景色や音を伝えるべき身体のない視覚と聴覚は、物理的に空っぽな情報パターン以外のなにものでもない。意味は動作主性(行動し選択する能力)に根差し、動作主性は身体化によって左右される。実を言うと、これこそ人工知能学会が数十年にわたってフラストレーションを味わった末に、苦労してようやく得た教訓である。真に知的なものは、身体のないメインフレームでは発達しようとしない。現実の世界には、肉体を持たない意識など存在しないのだ。
柔軟に形を変える無数のボディ・マップが全部合わさって、“私らしさ(me-ness)”という立体感のある主観的感覚と、周囲の世界を把握してうまく渡っていく能力を生み出す。ボディ・マップは、全体の模様が感情のある身体化された自己を創出する曼荼羅だと考えればよい。身体化された自己の創出には不要なその他の心的能力、つまり視力、聴力、言語、記憶はどれも、ちょうど骨格にぶら下がっているさまざまな器官のように、この身体の曼荼羅マトリックスに支えられている。発達という観点から言えば、これらのボディ・マップなしには、自己認識を持った思考する人になることはできないのである。

『脳にある、巨大でありながらもしっかりと統合されたボディ・マップのネットワークについて説明するには、曼荼羅こそ魅力的なメタファー[隠喩]であると同時に、おあつらえ向きの縮小版だ。ボディ・マップ網を曼荼羅に例えると、周りの諸尊は皮質にある大小多数のボディ・マップで、すべて相互・複雑に関係している。中央の尊像はそれらの複合産物、つまり、全体としての不可分な身体化された自己である。』
画像出展:「ウキメディア」
それは少し大げさではないかという向きには、こう考えていただきたい。たとえば子猫などの幼いほ乳類を、脳の初期発達が進む重要な時期を通して抱いて歩き、環境中のあらゆる事象を目に触れさせる一方で、自分ではけっして動き回らないでおくと、この哀れな生き物は事実上、生きるということを理解できない猫に育ってしまう。ある程度の光や色や影は知覚できるから、視覚系の最も基本的な生来の能力は備わっているわけだが、奥行き知覚力と物体認識は惨憺たる有り様になる。眼と視神経は非の打ち所なく正常で無傷でも、高次視覚系はほとんど役に立たない状態だからだ。
どうしてこんなことになってしまうのか? 動物が目で見るという行為をしながら成長すれば、脳にある視覚マップのネットワークも正常な方向に発達するはずではないか? 形状や濃淡、運動、色、視差、大きさ、距離に関する視覚情報に満遍なく触れていれば、自己可動性の欠如を十分補えるだろうに? 意外だが、答えはノーだ。別の要素が要る。世界の隅々まで探索するために自分の身体を自由に駆使する能力である。成長期にあるほ乳類の幼獣が歩き回ると、自分自身の身体運動からフィードバックがあり、それが目にしたものの意味を教えてくれるのだ。一歩ずつ歩を進め、途中で休憩し、歩くペースを上げるたびに、重要な感覚情報がボディ・マップのネットワークを介して上位の脳神経系へ伝達される。すると、目から流れ込んでくる、本来なら無意味な染みや色、影の意味を幼獣が理解するために必要な情報が、このネットワークから幼獣の発達途上の視覚系に送られてくる。ハイレベルな視覚情報に触れていても、傍観者の域を出なければ、そうした視覚情報が本当は何を意味するものなのか、脳はけっして学習しない。
ここまで言えば、視覚が実は曼荼羅の居候で、腰の低い共生者だと、うすうすわかってきたはずだ。すべての“特殊”感覚[視覚、聴覚、味覚、嗅覚、前庭感覚(平衡感覚)]に同じことが言える。身体の曼荼羅はそうした感覚の中心にある統合者であり、心の究極の基準系であり、知覚の基礎をなす単位系である。感覚は身体化された自己に照らし合わせなければ意味はなさないのだ。
さて、身体の曼荼羅の全体像をなんとなく理解していただきたいところで、そろそろ的を絞って、本題に移ることにしよう。身体の曼荼羅のほかの要素を土台のように支えている一次感覚マップと運動マップである。』
自分に身体のあることがわからない
『触覚をベースにしたペンフィールド式ボディ・マップについては、もうご理解いただけたことと思う。

ペンフィールドのホルムンクスとは
左が一次体性感覚野、つまり、触覚とかかわる感覚に基づいたボディ・マップ。右が一次運動野に存在する、随意運動の基本ボディ・マップ。図は、脳の右半球。左半球にもほぼ同じマップが対になって存在している。
ワイルダー・ペンフィールドは1930年代、モントリオール神経学研究所の脳外科医であった。てんかんの病変部の切除を目的とした本番手術の準備として、痛覚受容器を持たない脳に電極をあてて原因と思われる腫瘍などの異常組織を何時間も探し続けた。
ペンフィールドが尋ねる。「今、どんな感じがしますか?」メアリー(仮名)は左手がチクチクしている感じがすると答える。ペンフィールドはそのスポットにナンバーを振った小さな付箋を貼り付ける。結果は、手術室の外に座っているガラス越しに覗いている秘書にも書き取らせていく。
その後20年にわたり、ペンフィールドは脳組織の同じ帯状領域を調べて、大勢の患者から同様の反応を得た。こうして粘り強く収集したすべてのデータをもとに、ペンフィールドが作成したのが身体表面の完全な脳マップである。彼は遊び心でこのマップに中世哲学の用語で“小人”を意味するラテン語の“ホムンクルス”というニックネームを付けた。

画像は『脳の世界』さまから拝借しました。
“ロンドンの自然史博物館にあったホムンクルスの模型。赤が体性感覚野、青は運動野”
あなたの身体の表面には至るところに、優しい愛撫や圧力、疼痛、熱さ、冷たさを担当するセンサがある。ところが、身体のフェルト・センス(フェルトはfeelの過去分詞形。たとえば、“胸がしめつけられる”など、なんとなく感じられる感覚)、つまりボディ・スキーマにはさらにふたつ、ほぼ完全に意識外で機能する構成要素がある。科学者たちはこれらの感覚チャネルの存在を何十年も前から承知していたのだが、今ようやく、その源である特定の脳領域にたどり着こうとしている。ひとつは身体の内部からの信号を読み取る領域、もうひとつは内耳からの信号を読み取って、平衡感覚を生む領域である。
ここで少し時間を割いて、自分の身体を構成している筋肉、骨、関節、腱を思い浮かべてみよう。これらの組織には、筋線維の単収縮、骨にかかる機械的ストレス、関節の角変位、腱の伸展など、小さな運動を検出するための特殊化した受容器がある。こうしたセンサは変化を感知するたびに脳に情報を送り、あなたの空間内の位置や体位に関する感覚を更新する。この情報を伝える信号は、まず、一次触覚マップにマッピングされた後、分岐してフィルタをかけられ、身体の曼荼羅にある他の高次マップへと上がっていく。その高次マップが身体の運動とその運動に関する予測を誘導するわけだ。
これらのセンサは体重と姿勢を計算して、固有感覚なるものを生み出す。これは、“自分自身を認識する知覚”という意味だ。飲酒検査に引っかかったとしたら―つまり、直線上をまっすぐ歩けなかったり、自分の指で自分の鼻に触れられなかったりしたら―、それは自分が空間内のどこに位置していて、四肢をどう動かしているかを認識する感覚が正常に機能していないからである。成長スパート、つまり、成長が加速する時期には、一時的にこの身体感覚を失って、足や脚があるべきところにないように感じる小児やティーンエイジャーもいる。新しい技能やスポーツを身につけるときは、練習によってこの身体感覚を磨き直さねばならない。
ボディ・スキーマの情報源には、“マッスル(筋肉)・メモリー”という記憶の図書館もある。よく使われる用語だが、少々不正確だ。これらの記憶は、“マッスル・メモリー”、つまり筋肉の記憶という名が示すとおりに筋肉にあるのではなく、実は脳の運動マップに存在しているからである。マッスル・メモリーがあるから、自分の身体がどう動くのか、何ができるのかと直感的に悟ることができる。この暗黙の知識の例としては、身体をどこまで曲げられるか、背中のどの辺なら手が届くか、食卓に並んでいるもので、身を乗り出さなくても取れるのはどれかといったことが挙げられる。このような理解と判断の大半は無意識に行われる。身体の曼荼羅が絶えず計算し、それに基づいてボディ・スキーマを最新の状態に保っているからである(区別を明確にしておくと、身体の曼荼羅は脳にあるボディ・マップの物理的ネットワークで、ボディ・スキーマはそれらのマップによって構築された、身体が感じ取った経験である)。』
まとめ
1.ボディ・マップの形成は幼少期だが、速度こそ衰えてくるものの生涯変化し続ける。
2.身体は脳を入れて動き回るための単なる運搬具ではなく、両者の関係は互恵的であり身体と脳はお互いのために存在している。
3.皮膚と身体から感じる感覚―触覚、温覚、痛覚などの感覚が心の基盤をつくる。
4.発達という観点から言えば、ボディ・マップなしに自己認識を持った思考する人になることはできない。
5.体を動かすことによって得られた感覚情報が脳へフィードバックされ、目から流れ込んでくる情報と統合することによって、脳は目にしたものの意味を理解する。
6.筋肉、骨、関節、腱に存在するセンサ(受容器)から脳に送られた情報が、空間内の位置や体位に関する感覚を生みだす。これは自分自身を認識する知覚であり、固有感覚と呼ばれている。
脳室周囲白質軟化症
今回は業務委託で行っている訪問の仕事の話になります。
およそ半年前、脳室周囲白質軟化症(PVL)の小児障害の患者さま(3歳)へのマッサージがスタートしました。脳室周囲白質軟化症(PVL)は早産による脳室周囲の白質に起こる虚血性脳病変です。血管の発達遅れに伴い脳血管の血流が減少することに起因していますが、脳室に近い部位には、下肢に行く神経線維が通っているため、四肢の痙攣性麻痺や弛緩性麻痺が懸念されます。

こちらは『こどもの発達を考える衝動眼鏡の日常』さまのブログに掲載されていた脳室の図ですが、“脳室周囲白質軟化症 PVLとは”と題するテーマで、大変わかりやすい説明となっています。
今回の患者さまの場合も課題は下肢に見られました。顕著だったのは「尖足」(下図右から2番目)でした。また、患者さまとタオルを使った綱引きの遊びをしたときに、X脚(下図中央「外反膝」)になってしまうということに気がつきました。ぐっと踏ん張るためには、腰を落とし膝を外側に開く姿勢が一般的だと思いますが、そもそも腰を落とすことができないということが問題のように感じました。
ここで、私は2017年3月にアップした“地に足を着ける”といブログを思い出しました。そして、特に次の内容が重要なのではないかと考えました。
『土台をしっかりさせるということは、まさに”地に足を着ける”ことです。このことは”整った身体”を作るコツです。そして、情緒の安定や集中力の向上、意欲の増進につながります。”地に足を着ける”には足首の柔軟性と調整力が必要です。足首が使えていないと、つま先立ちとなり、首が緊張し前傾しやすくなり、その結果、姿勢が悪くなります。』

足首での姿勢調節ができないと、頭(上体)で調整することになり、ボディバランスにも大きな影響が出ると思います。
なお、これらの絵は、栗本啓司先生の「自閉っ子の心身をラクにしよう!」からの転載です。
一方、脳室周囲白質軟化症(PVL)のリハビリに関する情報が何かないか調べてみました。
その時、見つけたのが『チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)』というサイトの中にあった“運動障害をもつ子どもに対するリハビリテーション”という論文です。
この論文で特に注目したのは、「9.1対象と介入方法」とリハビリの様子と効果を写した「図4・図5」でした。
『対象は、新生児期のMRIでPVLと診断され上肢に明らかな麻痺のない乳児8名(表1)。一般的にPVLによって痙性両麻痺をもつCP(脳性まひ)児は、成長の過程で上肢優位の活動となり、下肢への注意や知覚、身体表象の発達不全、学習性不使用といった状態になりやすいため、出生後早期より下肢に視覚的に注意を向けさせて遊ぶことを通して、運動と随伴的に得られる視覚、聴覚、体性感覚フィードバックの統合から下肢の身体表象の獲得、足部の空間的コントロールを学習をさせた。これは、過去の下肢に対する介入の目的となることが多かった体重の“支持機能”、移動のための“推進機能”とは異なる“空間でのコントロール機能”に着目したものであり、定型発達児において、体重支持や移動を獲得する以前の早期に足部の空間的コントロールが可能になるという先行研究に基づくものである。』
これを元に思いついたのが、カスタネットを用意し椅子に腰かけ、カスタネットと自分の足をよく見てもらいながら足首の運動(足関節の背屈・底屈)によりカスタネットの音を出すという遊びです。
単純に足関節の動作を行なうより、音を出すという面白さや足首の動きを確実に目で確認するという効果を期待して、この遊びをマッサージの前か後に数分やってみようと考えました(最初に「本来は足でたたくものではないよ」と伝えました)。
初回は興味をもって積極的にトライしてくれました。しかし、これは思っていた以上に難しいものでした。足関節は尖足のままほぼ固定し、膝の上げ下げ(股関節の屈曲・伸展)でカスタネットを叩こうとしてしました。ここで私は「そうではなく、こんな感じだよ」と言って(否定して)、ゆっくりと足首を上下(足関節の背屈・底屈)させてみましたが、なかなかうまくいきませんでした。
2回目は、「今日はマッサージからやろうか」と話したところ、前回と同じことをやりたいとのことだったので、前回とは少し高さの異なる椅子に変えて同様な試みをしてみました。しかしながら、やはりうまくはいきませんでした。ここで私は心の中で「これは難しい、失敗だった」と思ってしまいました。そして、次の訪問からはマッサージについても、拒否する傾向がみられるようになりました。マッサージ前後の数分という短い時間であれ、安直な気持ちでリハビリに挑戦したことが結果的にはマイナスとなりました。
レビュー
この失敗例に対し、先月学習した”アナット・バニエル・メソッド”に照らし合わせ、何が適切でなかったのかをレビューをしてみることにしました。
最初に、かなり大雑把ですが「あるべき姿」としてまとめ、続いて「9つの大事なこと」に突き合わせて問題点を個別に洗い出しました。
あるべき姿
【まず、患者さまの状態、状況の理解を深めることが第一です。続いて、「できないこと」を知ることも必要ですが、支援の扉は「できること」の近くにあると考えるべきです。これは“アナット・バニエル・メソッド”の中では「動きのエッジ部分」と言われているものです。また、「できること」に目を向けることは、脳にとって失敗のパターンを刻むリスクを遠ざけるという利点もあります。
そして、変化を起こすエンジンは患者さまの脳の働きです。さらに支援者とのつながり、脳と脳とのつながりが土台となります。これは支援者の影響力が大きいことを意味します。そのため支援者にはリーダーになる(いい加減なことはできない)という覚悟が求められます。
エンジンを動かすためのガソリンに相当するものは、「気づき・違い」などですが、「学びのスイッチ」がオンになっていることも非常に重要で、エンジンに大きな力を加えます。また、楽しさ、喜び、好奇心などのポジティブな心も極めて重要です】。
「9つの大事なこと」との突合せ
1.動きに注意を向けること
●脳は「失敗のパターン」も再生してしまう
『訓練を機械的・反復的に行なうとき、ある動きができない、うまく動けないという経験に加え、訓練の過程で子どもが味わう失敗に伴う感情も脳の失敗のパターンに刻まれる。』
これは、子どもの状態、状況を正しく理解するためのていねいな観察が前提であり、思いつきでの働きかけなどは慎重でなければならないということだと思います。
2.ゆっくり
●スローダウンで「感じとる脳」に
『何かができないときは、その能力がまだないということであり、能力を獲得するためには、脳がより細かく差異をとらえ、無数の新しい神経細胞のつながりをつくり、それが統合されなければならない。そのチャンスを最大にするためには、取り組みのペースを思いきり落とすことです。「ゆっくり」は脳の注意を引き、子どもに感じる時間を与える。』
これは、新しい動きの習得には脳の対応が必須であり、「ゆっくり」を基本とし焦ることなく、じっくり取り組むことが必要であるということだと思います。
3.バリエーション
●動きのエッジ部分にやさしく働きかける
『お子さんがすでにできることにバリエーションをとりいれる。』
●間違いを活用する
『子どもが何かを間違った方法でしても、修正しないことです。そう、修正はしません(もちろん、その行動が本人や周囲に危険をおよぼすときは、直ちにやめさせること)。あなたの目には間違いが明らかであっても、本人は気づいていないことが多いのです!間違いを修正しないとは、間違いをなかったことにするという意味ではなく、バリエーションをとりいれるきっかけにするということです。子どもの間違いは、バリエーションを体験するための贈り物です。子どもが間違いをしたら、その間違いに変化をつけてみましょう。』
これは、「間違い」という受けとめではなく、「想定外の反応」として評価し、新たなバリエーションのための材料として活用しようというものです。このような意識は全くありませんでした。また、できることにバリエーションをつけるという着想も全くありませんでした。
4.微かな力
●感情表現で力をぬく
『子どもと向きあうときの感情を和らげる。声をやさしくし、気を楽にもち、子どもに対する期待を減らす。』
ここでは、「子どもに対する期待を減らす」ということが大事だと思いますが、同時に「楽しい気持ち」や「つながる気持ち」などもとても大切だと思います。
5.内なる熱狂
●喜びを深める力
『科学研究から読みとれるのは、あなたが心を熱くすることが子どもの脳に影響を与えるということである。』
●自分がリーダーになる
『子どもは何かをうまくできると、気分をよくし、希望を感じる。一方、あなたの期待に応えられなければ、とまどい、自信をなくし、おどおどする。』
これらは、支援(施術)する者の役割の重さに関するものですが、今回の例では、私自身が心の中ではありますが、「失敗だった」と思ってしまったことが最大の問題だったのかもしれません。
6.ゆるやかな目標設定
●可能性にひらかれた道
『通常、ゴールを目指すときは、目標をできるだけ絞り、できるだけがんばるものです。それは、「がんばれ」「あきらめるな」「苦痛があってこその達成」といった言葉にも表れています。しかし、支援が必要な子どもの場合、このような取り組み方は逆効果のことが多いのです。柔軟性に欠ける方法で力まかせにゴールを目指すと、子どもの力をさらに制限してしまうことになりかねません。』
これも3の「バリエーション」にあった「動きのエッジ部分にやさしく働きかける」という「できること」に目を向けるということに関わるものだと思います。
7.学びのスイッチ
●ひとりの人間としてみる
『一般的には、子どもの課題やできないことに焦点を絞った対応がなされるものだと思いますが、これにはひとつ、大きな欠点があります。そのようにするとき、ひとりの子どもの全体がみえなくなるのです。内側に豊かな経験と複雑さを抱える子どもの全体像をつかめなくなり、型にはまった見方をするようになります。そして、気づかないうちに自分の「学びのスイッチ」をオフにしてしまします。ところが、視野を広げ、自分の懸念やその子の限界にとらわれずに子どもをみるようになると、あなたの「学びのスイッチ」はふたたびオンになります。すると、子どもを総体としてとらえるようになり、以前は気づかなかったことに気づき、子どもに関わっていく新たな方法を見つけることができます。子どもに役立つチャンスが急に到来するようになり、あなたは、子どもの脳が識別し、進化をとげる手伝いを創造的に行なうようになります。このようなプロセスは、私たちの「学びのスイッチ」だけでなく子どもの「学びのスイッチ」もオンにし、脳の整理能力を全体的に引き上げてくれます。子どもは、私たちが予想もしない方法で、もっとも困難な分野の能力を伸ばしていくものです。』
これは「学びのスイッチ」に関して書かれたものですが、まさにまとめになるような内容です。
8.想像すること、夢みること
●遊ぶ
『遊びは子どもの想像力をかき立てるもっとも手ごろな方法です。ところが、私たちが子どもとすることというのはひじょうにまじめで型にはまったものが多いのです。特別な支援を必要とする子どもがセラピーを受けるときや家庭教師にみてもらうときは、とくにそうなりがちです。そのようなときはゲームにして想像力をフルに使うようにすると、楽しく、効果も上がります。子どもの体験に喜びや好奇心が加わり、脳の処理能力が高まり、創造力が目覚めます。』
ここでも、脳の活性化には楽しさ、喜び、好奇心が重要であることがわかります。
9.気づき
●「気づき」は行為だ
『「気づいている」ときの子どもは、脳のもつ「変化をとげる」力を活用しています。このとき子どもの脳は大きく飛躍し、つぎのレベルのさまざまな能力を獲得することができます。子どもが自分の動きや思考、感情、行為に「気づいている」と、それを続けるか、やめるか、やり方を変えるか試行錯誤するとき、その子は気づいています。言葉が出はじめるまえから、子どもは気づくことをはじめています。「気づき」のスキルもまた、発達し、進化していきます。ほかのスキルと同様に磨くことができ、磨くほどに上達し、困難を乗り越えていく力になります。』
7で「学びのスイッチ」というものがありましたが、気づきとは「学びのスイッチ」より前に存在するスイッチだと思います。また、繰り返しになりますが「気づき」にとっても、楽しさ、喜び、好奇心が大きく関わっていると思います。
最後に本書の中から実践編とも言えるものを一つご紹介させて頂きます。
快適に動くために―足の遊び
『特定の動きが困難で、子どもが過剰に力を使っている場合、力を減らせるよう穏やかに導く方法を探します。身体を動かすときの力を減らすためには、体位を変えることが有効かもしれません。
たとえば、歩くときに左右の脚を大きく開き、よくつまずいて転ぶ子どもには、立ったり、歩いたりするときに筋肉に余分な力が入っています。そのため、立っているときに、自分の両脚が大きく開いているか、くっついているか、腰の真下に並んでいるかの違いを感じとることができていません。余分な力が大きなノイズ(雑音)となって、関節や筋肉と脳の繊細なやりとりをじゃましていると考えてください。そのようなときは、余分な力のボリュームを下げ、わずかな違いを感じることを助けてくれる遊びをしてみましょう。』
1 『まず、子どもをイスに座らせます(立った状態だと転ばないように力を入れてしまいますが、座ると過剰な努力をしなくてすみ、感じとる力が高まります)。このとき、足が床につき、楽に座れるようにします。子どもが楽に座ったら、自分の足を見て、左右の足のあいだの距離を、胸の前で両手で示すように言います。その距離が正確かどうかは気にしません。つぎに、子どもの両手を思いっきり離し、「手が遠くに離れているね」と声をかけます。両手を近づけさせ、「近づいた」と声をかけたら、ひざの上に降ろすように言います。』
2 『つぎに、子どもに目を閉じてもらい、やさしく足をとり、左右の足のあいだを離します。子どもが不快に感じる距離にはしません(あくまで余分な力を減らし、動きを感じられるようにするための遊びであることを忘れないでください)。「両方の足は近くにあるかな? それとも離れているかな?」と尋ねます。回答の正否は問わず、間違っても直しません。目を閉じた子どもにただ自分の足を感じさせ、足がどこにあるかを推測させるのです。目を開けるように言い、自分の目で距離を確認させます。』
3 『再度、子どもに目を閉じてもらいます。右足をとって左足に近づけ、「足を動かしたのを感じた?」と尋ねます。おそらく「うん」と答えるでしょう。さらに「足はもう片方の足に近づいたかな? それとも遠くに離れたかな?」と尋ねます。お子さんが幼くてまだ話せない場合は、質問をするのではなく、子どもに加えた動きをそのまま言葉にします。同じことをもう片方の足でも行ないます。動かすとき、足にかける力を一回ごとに弱めていきます。その後、本人に片方の足を動かすように言います。まず、力を強く入れて動かすように言い、つぎに力をあまり入れずに動かすように言ってください。』
4 『この遊びを五分間ほどしたら、子どもに立ってもらいます。このとき、立っている感覚が変化したかどうか、感じる時間を与えます。子どもの脳は、脚をうまく使えるように修正がされたはずです。今度は、座って行った先ほどの動きを、立った状態で行ないます。立って行なうのが難しい場合は、ふたたび座って行ないます。』
『このような遊びを冒頭からあわせて十分ほど行ったら終わりにし、好きなように歩かせます。このとき、「足の距離が近くなったね」まどと声かけしないことです。
この遊びはさまざまな動きや状態に応用できます。脳は、余分な力が減ることで「違い」を感じられるようになり、より上手に動きを組み立てるチャンスを与えられます。何年もかかると思っていたことを脳がすばやく達成してしまうことに驚くことでしょう。』
アナット・バニエル・メソッド2(症例)
本の中には1歳から13歳までの19人の症例が出ていました。抱えている障害は重度の脳性まひ、脳の損傷によるもの、自閉症スペクトラム、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、LD(学習障害)、診断のつかない発達遅れなどです。
今回のブログではこの中から3人の症例をご紹介させて頂きます。なお、[ ]内は私の方で追記したものです。
1.カシー 3歳女児 重度の脳性まひ(誕生時に脳を損傷)
両脚がくっついて離れないカシー
『カシーと出会ったのは、彼女が三歳のときでした。カシーは誕生時に脳を損傷し、重度の脳性まひがありました。両腕、両脚、お腹の筋肉が極端に硬く、痙縮がみられ、自発的な動きはほとんどありません。自分で動こうとすると、全身がさらに硬直します。
両親がカシーをレッスン台(マッサージ台のような幅広でクッション性のある安定した台)の上に座らせると、背中はすっかり丸まり、両腕は、胴体にきつくひきよせられました。ぴったりくっついた両脚は、前に向かってぴんと伸びています。カシーは転げ落ちないように必死で、どうみても怖がっていました。
数か月間にわたって定期的に「9つの大事なこと」を使ったレッスンを続けたところ、カシーは腰と両腕を自分で動かせるようになり、バランスを保ちながら怖がらずに座れるようになりました。話し方も考える力も向上し、おきまりの文をくり返し唱えるかわりに、自分の考えをまとめ、要求をはっきりと伝えるようになりました。
ところが、ひとつだけ、どのように取り組んでみても変わらないことがありました。まるで目に見えない紐で縛られているかのように、つねに両脚がぴったりとくっついていたのです。私がとてもゆっくり、やさしく動かすと、左右の脚は離れてべつべつに動くのですが、カシーが自分から脚を動かそうとしたり、自分で動かす方向を変えようとすると、そのとたんに痙縮します。身体の動かし方を学んで全身を自由に動かせるようになってきたのに、なぜか脚だけが動かないのです。
ある日、私はふと、カシーは自分に脚が二本あることを知らないのだと思いました。両脚がいつもいっしょに動くので左右べつべつのものだと感じたことがなく、右脚と左脚の「違い」を認識したことが一度もないのでしょう。認識されなければ「違い」は存在しません。だれが見てもカシーには脚が二本ありましたが、彼女の脳が経験しているのは二本ではなく、一本の脚で、「ひとつ」と「もうひとつ」(「これ」と「それ」)がないのです。
マイケル・マーゼニック[「本書によせて」を寄稿された脳神経学者]の研究チームは、実験用ラットの後ろ脚に脳性まひのような症状をつくりだしました。誕生時に左右の後ろ脚をひとつに縛ってつねにいっしょに動くようにしたところ、ラットの脳は、後ろ脚は二本ではなく一本だという身体地図を描きました。
カシーの脳が二本の脚を一本ととらえていると気づいたことは、私の取り組みの突破口となりました。子どもたちは、「違い」に気づくことができる環境を与えられると、身体地図を描きなおす脳の力を発揮させていけるのです。』
「ひとつ」と「もうひとつ」を発見したカシー
『カシーの脳が左右の脚を一本とする身体地図を描いているのなら、脚が二本あることを感じ、わかるための方法が必要です。彼女の脚を片方ずつ何度も動かしてみましたが何も起きません。脚が二本あることに気づかなければならないのは、ほかでもない、カシーです。どうにかして注意を向けてもらい、脚が二本あることを知ってもらわなければなりません。
子どもの例にもれず、カシーも遊びが大好きでした。私は無害の水性マーカーを用意し、彼女をレッスン台に座らせると、後ろから抱きかかえました。彼女の右脚をやさしく持ち上げ、その膝をトントンと軽くたたいて視線を向けさせ、そこに絵を描いていいかどうかを尋ねました。返事は「イエス」です。
私は、カシーの脳が「違い」を認識しなければならないような質問をしました。
「どっちを描こうか? 犬、それとも猫?」
しばらくしてカシーは「犬」と答えました。
「赤い犬、茶色い犬、どっちがいい?」
彼女は赤を選びました。そこで、カシーの右膝に、ゆっくりと説明しながら、赤い犬の絵を描きました。「これが犬のお鼻。これが片方の耳。もうひとつの耳」といったぐあいです。
カシーはしっかりと私の声を聞き、絵に目を向け、肌を滑るマーカーの肌ざわりを感じていました。犬を描きおえるとカシーのその膝を、まず同席していた母親に見せ、つぎに自分が見てから、本人に見せました。右脚を下すと、今度はおもむろに彼女の左脚を持ち上げました。そして、わざとがっかりしてみせると、驚いた声で言ったのです。
「この膝には犬も猫もいないよ!」
その瞬間、カシーは生まれてはじめて「向こうに、同じようなものがもうひとつある」と気づいたのだと、私にはわかりました。脚は一本でなく、二本あるのです。つぎは、この目の前の膝に犬と猫のどちらかの絵を描くかを尋ねました。「猫」と答えたので、やはりゆっくり慎重に、猫の顔を描きました。
左右の膝に異なる絵を描いたことで、カシーの脳が、「一本の脚」を二本のべつべつの脚に変化させていける可能性がいっそう広がりました。たとえば、どっちの絵をだれに見せるかを選ぶことができます。また、両脚をぴったりつけて犬と猫を近づけることも、脚を広げて二匹を遠ざけることもできます。犬がカシーの手をタッチすることも、猫がカシーの母親の手をタッチすることもできます。
カシーは「猫の膝」と「犬の膝」を識別し、自分の意思で脚をべつべつに動かすことができるようになりました。生まれてはじめて、脚が二本になったのです。脚の動きはまだぎこちなく、動かせる範囲も広くありませんでしたが、それは彼女が自分で生みだした動きでした。』
カシーの脳で起きていたこと
『「猫の膝」と「犬の膝」の遊びを楽しんでいるあいだに、カシーの脳はさまざまな「違い」を受けとり、集め、認識し、大量の感覚をより細かく差異化しながら整理していました。そうするうちに脚の痙縮は少しずつ減り、身体全体の動きが改善したのです。
この取り組みについて大事なことは、さまざまな「違い」を感じて受けとめるチャンスを脳に与えたということです。ふたつの異なる部位である一の脚と二の脚、「ひとつ」と「もうひとつ」が身体の動きを向上させたのであって、脚の訓練をしたわけではありません。立たせたり、歩かせたりするのではなく、カシーがまだ知らないさまざまな「違い」を感じることができるように支援することで、脳が、脚を認識し、脚の動きを組み立てるために必要な情報を得られるようにしたのです。これは、まさに脳の訓練でした。
カシーはその後も能力を伸ばしていきました。最後に会ったときには自分の力で立ち上がり、家具につかまって一歩一歩、ゆっくり歩くようになっていきました。思考もどんどん明晰になっていきました。五歳のカシーはだれの目にもとても賢い女の子でしたが、三歳の彼女をそのようにみていた人はいませんでした。』
2.ジュリアン 3歳男児 自閉症
すべてが「ぼんやり」していたジュリアン
『自閉症と診断されていた三歳のジュリアンは、レッスン初日、軽く足を引きずりながら前かがみで廊下を歩きました。ジュリアンが安心している様子だったので、私は質問をしてみました。すると、答えはすぐに返ってきましたが、発音がはっきりしないので理解できませんでした。彼がつくる文はまとまらず、言うことはなにもかもが断片的です。考えは途中で宙に浮き、終わりまでたどり着きません。よだれを大量にたらし、母親によると、細かい動作をうまくできないということでした。
レッスン室に入ると、ジュリアンはおもちゃを手に持ちましたが、持っていることを忘れたかのようにポトンと落としました。その様子は、彼が何かを考えようとするとき、それが途中で消えていくことを思い起こさせました。私が受けた印象は、脳の入り口に曇ったレンズがついているために、入ってくるものすべてがぼやけてあいまいになってしまうというものです。ジュリアンは自分や周囲の世界を理解するのに必要な「違い」を、はっきりと受けとることができないようでした。
私は、ジュリアンをレッスン台にうつぶせに寝かせると、彼の右肩の下に自分の左手を入れてやさしく、ほんの少し持ち上げてみました。すると、肩と背中がひとつの塊としていっしょに動くのがわかりました。左の肩を持ち上げてみても同じです。伸び縮みする筋肉や柔らかな関節をもつ人間ではなく、まるで丸太を動かしているようなのです。
脚、骨盤、頭の動きを確かめると、動きがあいまいで、細やかさも強さもないことがわかりました。また、周囲の音や景色を識別する力も弱く、言語活動と思考は初歩段階といえるものでした。ジュリアンの脳は、明らかに違いを受けとめることが苦手で、身体のさまざまな部位を十分に識別できていません。さまざまな形の小さなパーツが足りないのです。私はジュリアンができるかぎりたくさんの「違い」に気づくことができるように彼の身体を動かし、そのとき彼が経験している動きを言葉で説明しました。
ジュリアンは三歳でしたが、指や手の動きは生後一か月の赤ちゃんのようでした。五本の指をまだ認識していない赤ちゃんは、グーパーしかできません。ジュリアンはまだ自分の手を「ひとつの塊」と認識していて、おもちゃをつかむときはぐっと握り、ぱっと放しました。
ジュリアンの「ぼんやり」は手だけでなく、足を引きずる歩き方、ゆるんだ口もと、発音、そして、何かを考えるときの混乱ぶりにも表れていました。あらゆる面で識別する力が足りなかったのです。』
まるで霧が晴れるように
『私はジュリアンの身体に動きを与え、まず彼が頭を「ひとつのもの」、肩と背中を「もうひとつのもの」と受けとめられるようにしたところ、背中の動きがよくなり、しっかり反らせて片側から反対側へ楽にねじれるようになりました。
この日のレッスンでは、さらに、片方の前腕を持ち上げて天井に向け、手首から先が前後にぶるぶるするようにやさしく揺らしました。数秒後に揺らすのをやめると、期待するようにその手を見ながら待っていたジュリアンは、「もう一回!」と言いました。自分の手が止まったことに気づいた―揺れることと止まることの「違い」を認識したのです。ふたたび手を揺らしてから止めると、もう一度頼んできたので、さらに揺らしました。
このとき、ジュリアンはしっかり注意を払っていました。レッスン室に入ってきたときの彼は別世界にいるような感じでしたが、このときは私といっしょに、いま・ここで、自分自身に気づき、自分の経験していることに気づいていたのです。
私は、どっちの腕を揺らしてほしいかを尋ね、彼が答えたとおりにしました。動かしてほしい腕を選ばせることで、「違い」を認識する力を高め、自分に気づきやすくなるようにしたのです。ジュリアンは急速に、腕と手首の動きに気づくようになりました。この日はさらに二十分ほど、バリエーションのある動きを行ない、レッスンを終えました。
翌日、ジュリアンの母親が、よだれが大幅に減ったと報告してきました。また、避けていたゲーム遊びを自分からしたということでした。それまでは手を使うことも、考えることもたいへんだったのが、楽にできるようになったからです。いずれも、脳が上手に「違い」を受けとめ、分化し、行動を組み立てるようになったことを示す証拠でした。
その後は毎日のレッスンで、身体を新しい方法で感じ、まだ知らない、より細かい「違い」を受けとめることができるチャンスを与えるようにしました。すると四日目に、ジュリアンは私を見て、「パパは今日、オフィスで仕事をしている」と言ったのです。構文は完璧で、発音もかなり明瞭でした。
私は、「きみは、お父さんが仕事をしているときにオフィスで遊んだことがあるの?」と質問しました。最初の返事はごちゃごちゃして意味がわかりませんでした。ジュリアンは確かに考えていましたが、それをまとめることはできませんでした。そこで、言いまわしを変えて同じことを聞いてみました。すると、彼はさっきより明確に答え、さらに、父親は家にオフィスをひとつ、家でない場所に別のオフィスをひとつもっていて、自分は家にある父親のオフィスでときどき遊ぶが、家でないオフィスでは遊ばない、ということを説明してくれたのです。
私は興奮を抑えきれませんでした。ジュリアンが父親のふたつのオフィスの違いを説明できたことは重大な変化です。これは、彼の脳が「ひとつのこと」と「もうひとつのこと」の違いを受けとめ、混沌から秩序を生みだせることを示していました。先ほどのアヒルの例でいうと、ジュリアンの脳はどんどん分化し、小さなパーツをつぎつぎに増やしていました。彼の脳は、動くこと、話すこと、考えることの地図を描くための情報を急激に受けとるようになっていたのです。』

こちらは上記の”アヒルの例”の説明になります。
『私は「分化」について説明するとき、ホワイトボードにアヒルの輪郭を描きます。そして、四つか五つの不規則な形のパーツを描き、これをパズルのように組み合わせてアヒルの形にすることを想像してもらいます。これだと、アヒルをつくるのはまず不可能です。
つぎに、ずっと小さな丸や三角や不規則な形の粒をたくさん描きます。そして、この粒つぶを使ってアヒルの形をつくることを想像してもらうのです。これなら簡単にアヒルをつくれますし、それ以外の好きな形もつくれます。
この説明によって、脳の中で起こる分化と統合のプロセスが理解しやすくなるのではないでしょうか。いろいろな小さなパーツがたくさんあれば、脳は思いどおりの動きをつくりだすことができます。このプロセスは、何か考えたり、理解したりするときにも当てはまります。脳は身体・認知・感情に関わるあらゆる動きを組み立てています。私たちが行なうあらゆることに秩序をもたらすパターンをつくりだす作業を脳は、自由に使用できるさまざまなパーツ(情報)を使って行ないます。このパーツのもとになるのが、脳が感知したさまざまな「違い」なのです。』
支援の視点を変える
『一般的に、支援が必要な子どもを手助けしようとするときには、できないことに目を向けて、痙縮のある腕を訓練しようとしたり、何度も目を合わせて返事をさせようとしたりするものです。ほとんどの子どもはがんばりますし、なんらかの変化がみられることも少なくないでしょう。
しかしながら、私がくり返し見てきたのは、子どもは大人が教えようとしたことを学ぶのではなく、自分の限界(できなこと、うまくできないこと)を経験することを学んでしまっているということでした。私たちはつねに、自分が経験すること、自分に実際に起きていることを学びます。「できない」「うまくできない」という経験は脳に残り、そのときの限界とそれに関わる地図が、脳より深く刻みこまれてしまうのです。
数かぎりない「ひとつのこと」と「もうひとつのこと」が、脳に無数のつながりをつくりだします。このつながりが、経験に応じて変化を続けるダイナミックな脳のパターンとなって、子どもは立ったり、座ったり、歩いたり、話したりするようになります。
子どもは、計画的に座るようになったり、「ママ」と言うようになったりはしません。気がついたら、そうなっています。子どもにしてみれば、何かを達成するのはいつだって想定外のことです。私たちの仕事は、子どもの脳が目覚めるように助け、その脳が創造し、形成し、発見していくプロセスを支援することです。
腕がうまく動かない、寝返りを打てないといった目の前の課題に焦点をあわせるのではなく、子どもの脳それ自体が解決方法を見つけるように手助けをしていく―これは一見、わかりにくいことです。大切なのは、私たちが考え方を転換し、「動き」を可能にするパターンや能力を生みだすために脳に何が必要かを考えることです。解決方法を見つけるのは私たちの脳ではなく、子どもの脳なのです。』
3.リリー 3歳女児 重度の脳性まひ(身体は1歳ほど、発達段階は生後5か月)
ボールのように硬く丸まってしまうリリー
『リリーと初めて会ったのは、彼女が三歳のときです。たいへん未熟な状態で生まれ、重度の脳性まひを負っていたリリーは身体が小さく、一歳といっても通用するほどでした。彼女が母親や妹とやりとりする様子は乳児のようで、のちに母親から聞いたところでは、生後五か月ていどの発達段階だと判定されたということでした。
リリーは筋肉の緊張が激しく、つねに肘をきつく折り曲げ、握りこぶしをつくっていました。両脚は膝が少し曲がった状態で交差しています。腹筋がつねに収縮しているために背が曲がり、自分の体重を支えることができません。自発的な動きがなく、寝返りを打つことも、うつぶせでいることもできません。うつぶせにすると身体を丸め、苦しそうにします。座らせるとたいへんな力を出してなんとか座るものの、背中はすっかり丸まり、数秒すると転がってしまいます。腕や手を使うことはできません。声は小さく不明瞭で、何を言っているか理解するのは困難でした。
しかし、そのような状態でも、私にはリリーがしっかり目覚めて神経を研ぎ澄ましていることがわかりました。大きな茶色の目で、興味深そうに周囲の様子を追っていたからです。
リリーを仰向けにレッスン台に寝かせましたが、その姿勢でも筋肉は収縮したままで、両脚は曲がり、台からやや浮いています。肘は折れ曲がってぴったり身体に引き寄せられ、腹筋も硬いままです。脳が、どのように力をぬけばよいのかをわからないのです。
左脚をやさしく持ち上げ、できる限り小さく動かそうとした瞬間、収縮していた筋肉がさらに強く縮み、リリーはボールのように丸まりました。私は手を止め、彼女が落ち着くのを待ちました。つぎに骨盤を、やはりできるかぎり小さく、とてもゆっくり動かそうとしましたが、今度も強く筋肉が縮みました。速度を思いきり落として、安心できるように話しかけながら、とても小さく、わずかに動かしてみても、筋肉は硬くなりました。私が動かそうとするたびに、彼女の脳は、身体をボールのように丸めるという未分化で強力な初期の動きのパターンに乗っとられるかのようでした。
十分ほどそのようにしていると、ある考えがひらめきました。ボールのように身体を丸めるのは脳性まひの影響だけでなく、学習したパターンだからではないか、と思ったのです。リリーはどう見ても動きたがっていました。彼女は彼女なりの方法で動こうとしているのに違いはありません。
リリーは二年近く、うつぶせにされ、座らされるという訓練を受けていました。訓練では握りこぶしを開かせようとしたり、立たせようとすることさえあったそうです。そのようなとき唯一リリーの脳にできたことは、強く収縮することで、そのため身体は丸まりました。自分から動こうとするとき、また、自分を動かそうとするあらゆる働きかけに対し、彼女の脳は、収縮するというパターンを結びつけることを学習したはずです。』
なまけものごっこ──過剰な力をぬいて
『筋肉を収縮させるときの激しい力が悪循環を招いていました。激しい力を出しているため、リリーはどんな「違い」も感知することができず、脳に動きを学ぶために必要な新しい情報が入ってこないのでしょう。
リリーが動くことを学ぶためには、動こうとするときの過剰な努力を減らさなければなりません。そのとき私は、リリーに必要なのは、動こうとしないことを学ぶ方法なのだとひらめきました。リリーは筋肉を収縮させるとき、させないときの違い、また、力をたくさん入れるとき、少しだけ入れるとき、そしてまったく入れないときの違いを感じることを学ぶ必要があるのです。
私は「なまけもの」になる方法を教えることにしました。自分の身体とその動きを感じられるように、何もしないことを学ぶのです。
「この部屋はとっても特別な場所で、“なまけものの国”といいます。“なまけものの国”なので、だれもが、とってもゆっく――り、話します。だれもが、じ――っとしてほとんど動きません」。
このように話すと、私はレッスン台に自分の頭を乗せ、リリーの横でいっしょに怠けました。リリーは大喜びです。
しばらくたってから、これから身体を動かすけれども、私たちはものすごく「なまけもの」でなければならないのだと、話しました。そして、彼女の左脚を持ちました。その瞬間、やはり、筋肉は収縮しました。私は手を止め、おどけた調子で言いました。「なまけものじゃなくなってるよ!」。このようなやりとりをいろいろな方法でくり返しました。
その後の二回のレッスンでも、彼女に「なまけもの」になるように言いつづけました。そして、ついに、無意識に全身に力を入れたすぐあとに初めてそのことに気づき、リリーはみずから力をぬくことができたのです。素晴らしい瞬間でした!
「なまけものごっこ」を続けるにつれ、リリーは少しずつ、私に動かされることを受け入れてきました。生まれてはじめて、彼女は自分の身体の動きの違いを感じていたのです。
まもなくリリーは握りこぶしを開いておもちゃをつかみ、遊ぶようになりました。一週目のレッスンの終わりには、ひとりでうつぶせにも仰向けにも寝返りを打てるようになりました。彼女の脳は、微細な違いがもたらす大量の新しい情報を統合し、能力を獲得しはじめました。
リリーはその後の三年間、一、二週間の集中レッスンを何度か受けました。レッスンのたびに彼女は成長し、ひとりでハイハイし、座るようになり、腕や手を器用に使うようになりました。声に強さと表現力が加わり、はっきり話すようになりました。そして、自分を心地よく感じられるようになってきました。
最後に会ったとき、リリーは自分の力で立つようになっていました。学校では優秀な生徒です。外では電動者イスを使用していますが、家ではほとんど使いません。両親は彼女ができるかぎり自分で身体を動かし、独立することを願っています。』
「なまけものの国」の威力
『リリーの場合、太陽光の下では懐中電灯の光に気づかないように、無意識の激しい筋肉の収縮が、あらゆる働きかけを感じとることを不可能にしていました。自閉症やADHDをはじめ、私がこれまでに関わったどの子どもも、発達するためには「微かな違い」を感じとることが欠かせませんでした。リリーがそれを感じとるためには、筋肉の激しい力を弱める方法が必要でした。「なまけものの国」の住人になって、楽であること、快適であること、うれしいこと、楽しいこと、がんばらないことを体験するようにしたところ、彼女は学べるようになり、変化をとげたのです。
力や刺激を小さくすることのパワーを、あなたも利用することができます。まずは「違い」を感じとることを妨げる過剰な力、それを子どもがどのように使っているか探りあてることです。過剰な力には病状に特有のものもあれば、その子どもにしかみられないものもあります。注意欠陥障害[ADHD]の子どもは絵を描こうとすると、力を入れすぎてクレヨンを折ってしまうかもしれません。自閉症スペクトラムの子どもは、何を言われているか理解しようとしても、聞こえてくる声に圧倒されてしまうために叫びだし、いつもの動きをくり返すかもしれません。脳性まひの子どもは歩行器を使って歩こうとすると全身を硬直させてしまい、脚が動かなくなるかもしれません。そのようなときが、「微かさ」をとりいれるチャンスです。』
まずは、あなたから
『親をはじめとする支援者が子どもに注意を向けるのは当然です。しかし、これと同じぐらい大切なことは、支援者が自分自身に注意を向けることです。これは、微細さ・繊細さを自分の行動・思考・感情・動きにとりいれるということです。私を含めてどの支援者にも、不要な力をぬき、無駄な努力を減らす余地があります。私たちは安物のヴァイオリンではなく、豊かな音色をもつ名器、ストラディヴァリウスになるのです。
「微かな力」をとりいれると、感覚が鋭くなって感じとる力が高まるので、子どもの今の状態がわかり、何が必要かがみえてきます。「こうすべき」と考えて関わるのではなく、子どもの感じていることや体験していることにもとづきながら、本人にとって意味のある方法で子どもと関われるようになります。あなたは子どもからも自分の内側からもたくさんの情報を得るようになり、創造的・効果的に子どもを手助けできるようになります。』
まとめ
症例から分かったことは次のようなものです。
まず、『子どもは、計画的に座るようになったり、「ママ」と言うようになったりはしません。気がついたら、そうなっています。』ということです。つまり、子どもが自発的に身につけるものであり、そのプロセスを支援することが“アナット・バニエル・メソッド”の基本です。
では、“何(What)”に対して支援するのか、プロセスとは何かですが、これは“アヒルの図”を使って説明されていた内容―“脳の中で起こる分化と統合のプロセス”ということです。そして、“小さなパーツ”をたくさん作り出されるような働きかけを行ないます。
次に、“どうやって作り出すのか(How)”というその方法のキーワードは「違い」です。具体的には『脳が感知したさまざまな「違い」』であり、この「違い」によって『[子どもたちは]身体地図を描きなおす脳の力を発揮させていけるのです』としています。
以上のことから、“アナット・バニエル・メソッド”とは『子どもの脳が目覚めるように助け、その脳が創造し、形成し、発見していくプロセスを支援すること』というものだと思います。
アナット・バニエル・メソッド1(概要)
今回の『限界を超える子どもたち 脳・身体・障害 への新たなアプローチ』は偶然見つけました。それは、ボイタ法を勉強すべく『子どもの姿勢運動発達』という本のネット注文直後です。購買機会を増やすための仕掛け、いわゆる“お知らせ情報”の中にありました。
そのタイトルに「むむ?」と反応し、すぐさまどんな内容の本かを調べてみると非常に興味深いものでした。そこで、『子どもの姿勢運動発達』が図書館にあるのを知っていたこともあり、直ちにその注文をキャンセルし、この『限界を超える子どもたち』の注文に切り替えました。
この本の内容は衝撃的でした。受けたインパクトの破壊力は、『新・感覚統合法の理論と実践』を読んでいたことも背景にあると思います。また、ブログ“医療マッサージ研究1”での体験と“医療マッサージ研究2”で疑問について学習していたことも関係していると思います。なお、ブログは1の(概要)と2の(症例)の2つに分けました。
最初のブログでは、この本の概要をお伝するため、訳者のお一人である伊藤夏子先生の“訳者あとがき”の一部と、脳科学者であるマイケル・マーゼニック先生の“本書によせて”、全ての目次、そして著者であるアナット・バニエル先生の“はじめに”と“おわりに―限界を超えて”の一部、そしてプロフィールを集めることにしました。
訳者あとがき(伊藤夏子先生)
『本書の著者であるアナット・バニエルを知ったきっかけは、私が引っ越しを機に近所の福祉施設に勤務したことでした。そこは重症心身障害者とよばれる方たちが利用する施設で、私のおもな仕事は利用者の食事と排泄の介助です。
最初に担当した二十代の男性は、腕や脚が小枝のように細く、つねに身体のどこかをカクカクと動かしていました。目は焦点が合っていません。声をかけてみても、手を握ってみても、こちらに注意を向けることはなく、カクカクと動き続けています。
彼は片方の手にミトンをはめられていました。理由は、指で自分のまぶたを突っつき、眼球を押しだしてしまうからでした。
なぜ彼はそんなことをするのか? 痛くないのか? 何を感じ、考えているのだろう? 彼と心が通じることはないのだろうか? 手当たりしだい、日本語の書籍や専門誌に目を通しましたが、答えは見つかりません。英語でインターネットを検索し、たどりついたのが本書の原書、Kids Beyond Limits でした。
原書を読み終えた私は、この男性の食事を介助するとき、おかゆをのせたスプーンを口の手前で止めてみました。十五秒ほど待ったでしょうか。カクカク動きつづけていた身体が止まりました。目は天井を向いています。「おやっ」という表情です。
出会って九か月目にして、初めて、それまで遠い世界にいるとしか思えなかったこの男性と「つながった」と感じた瞬間でした。』
『アナット・バニエルは、相手とつながって「学びのスイッチ」をオンにすることができれば、まさに、だれもが能力を伸ばしていけるということを体当たりの実践で示しています。その彼女の取り組みの真髄である「9つの大事なこと」を紹介したのが本書です。「9つの大事なこと」の実践者が増え、わらにもすがる思いでいるであろう親御さんやさまざまな現場で模索を続けるみなさんが、支援を必要とする子どもや大人とともに変わり、成長の喜びを分かちあえるようになれたら、どんなに素晴らしいことかと思います。』
※下記の「本書によせて」の文中に”脳の可塑性”とありますが、これは ”脳には状況に応じて変化する能力がある”という意味です。
本書によせて──マイケル・マーゼニック(脳神経学者)
『この本は、子どもを愛し支援しているすべての人への贈り物です。本書を手にとり、著者のメッセージを受け取ってください。アナット・バニエルのアプローチは、特別な支援を必要とする子どもたちとの豊かな実践から生まれました。彼女は子どもたちの脳が変わっていくことができるのを繰り返しみてきました。子どもたちは人生に目覚め、能力を獲得し、力強く生き方を変えていきました。私たちの脳には「可塑性」があります。一生を通じて脳は変化しつづけます。
ここに登場する子どもたちは、困難を抱えながらも、家族の愛情と支援者の熱意に支えられ、「脳の可塑性」を最大限に活用しています。アナットの説明は明晰です。彼女は、脳が変化するという人間が生まれながらにもつ素晴らしい力が、奇跡の材料となりうることを教えてくれます。
私は長年、「再構築する脳」の力を子どもや大人に役立てる方法を解明したいと、科学の分野で取り組んできました。数十年の研究を経て、私たち科学者は神経科学の観点から脳の可塑性を支配する「法則」を明らかにしました。そして、よりよい変化をもたらすためには脳はどのように働かせるのがよいかがわかってきました。
驚くべきことに、同じ時期、アナット・バニエルはまったく異なる方法で、ほぼ同じ法則を導きだしました。彼女はそこに留まらず、この法則を実践的なわかりやすい言葉で説明し、親をはじめ、子どもに関わる人たちの取り組みに役立つようにしています。
アナットがこの道に進んだきっかけは、すぐれた先見者だったイスラエルのモーシェ・フェルデンクライスに師事したことでした。彼女はフェルデンクライスの教えをベースに特別な支援を必要とする大勢の子どもたちと関り、注意深く観察を行い、どのように子どもとつながり、その子の力になることができるかを明確にしてきました。「希望のない子ども」を助けるというアナットの評判を聞き、いろいろな子どもがやってきました。彼女はあらゆる症状の子どもと関わることになり、その経験から二つの重大な事実を発見しました。
一つめの発見は、特別な支援が必要な子どもの能力を制限しているのは、子どもを発達させてくれるものと同じ、脳の可塑性の原理だということです。
二つめの発見はさらに重要なもので、「希望のない子ども」のケースのほとんどは、じつはそうではない(希望がないわけではない)ということです。
アナットは脳の可塑性の原理を「9つの大事なこと」として、みごとに説明します。
この本は、私が「脳の可塑性革命」と呼んでいることの、実践的でわかりやすい解説書になっています。私たちの脳は変化しつづけます。新しいことを習得するたびに脳は回路をつなぎなおし、再構築されて、専門的な処置ができるようになるのです。この素晴らしい脳の力を生活にとりいれるには、どうすればよいのでしょうか。どうすれば、これを子どもの成長に役立てることができるのでしょうか。反応することにさえ苦労し、動くことや理解することに困難があり、自分の意思で自分の世界を動かすことができない子どもは、とりわけ脳の可塑性をおおいに利用することでどんどん成長し、能力を向上させていくことができます。アナットが本書で美しく描写するように子どもたちと本当につながることができれば、そして、そこに適切なガイダンスがあれば、ほぼすべての子どもが目に見えるかたちで継続的、ときに驚くほどの成長をとげることができるでしょう。
子どもが成長の軌道に乗るまでは、困難がともなうことでしょう。もっとよく働く、もっと力強い脳にしていくためには、いま、子どもがいるところから始めましょう。それぞれの子どもに必要なアプローチがあります。みなさんの熱心な取り組みも欠かせません。本書が示す原理は、一人ひとりに応じた取り組みを実現するための新しい視点を与え、子どもの力強い歩みを手助けできるようにしてくれるものです。
毎日の脳の神経回路の小さな変化が、一年たつころには大きな歩みとなり、子ども時代を通じてとても大きな発達をもたらすということを忘れないでください。本書には素晴らしい事例がたくさん登場します。そこでは、神経の新しい回路が生まれることで、子どもにまったく新しい一連の可能性が開ける様子が描かれています。アナット・バニエルは、脳の働きを支配する原理をどのように実践に生かし、子どもを成長の軌道に乗せることができるかを説明します。この成長の道に踏みだせば、小さな歩みの一歩一歩が、子どもにとっても、あなたにとっても、心躍るものとなることでしょう。
本書のアドバイスをしっかりとりいれてみることを心からお勧めします。そうすれば、子どもの真の力になるためにはどうすればよいかが、はっきりとわかるはずです。』
目次
本書によせて──マイケル・マーゼニック(脳神経学者)
はじめに
第Ⅰ部 新しいアプローチのために
ある女の子との出会い
動けない赤ちゃん
最初のレッスンでわかったこと──脳が身体を認識していない
動きを与えることで脳が学習を開始する
エリザベスが歩いた!
できることに注目しつづけて──エリザベスのその後
わが子の可能性、脳の可塑性
既存の取り組みからの脱却
親の力
〝直す〟ことから〝つながる〟ことへ
子どもを「直す」ことはできるか
子どもは、自分にできることはしている
発達に欠かせないランダムな動き
子どもは教えたことを学ぶのではなく、経験したことを学ぶ
親にも子にも実りをもたらす方法への転換
驚くべき子どもの脳
ランダムな動きが脳に栄養を与える
最初の一歩──「違い」を受けとめる
両脚がくっついて離れないカシー
「ひとつ」と「もうひとつ」を発見したカシー
カシーの脳で起きていたこと
アヒルをつくる──分化と統合
すべてが「ぼんやり」していたジュリアン
まるで霧が晴れるように
支援の視点を変える
第Ⅱ部 9つの大事なこと
1つめの大事なこと*動きに注意を向けること
動きを獲得するとき、一歳児に何が起こっているか
子どもは注意を向けることで学ぶ
脳は「失敗のパターン」も再生してしまう
足で立つための支援とは
頭を打ちつける自閉症の男の子
ライアンの目覚め
「息子は生まれ変わった!」
子どもが注意を向けているときの五つの特徴
からだ・きもち・考えの「動き」
科学が教えてくれること
◎動きに注意を向けるためのヒントと方法
2つめの大事なこと*ゆっくり
脳性まひの女の子、アリとの出会い
こわばった筋肉へのスロータッチ
人は体験ずみのパターンしか速くはできない
スローダウンで「感じとる脳」に
止まれないジョシュ──刺激を減らすことが有効な理由
体当たりで「ゆっくり」を学ぶ
「ぼくはバカじゃない!」
ヒトは、その脳とともにゆっくり成長する
終着点は未定にしておく
科学が教えてくれること
◎「ゆっくり」を実践するためのヒントと方法
3つめの大事なこと*バリエーション
バリエーションは脳の成長をうながす
バリエーションはどこにでも
コルセットで固められた男の子
初めて「動くこと」を知ったマイケル
科学が教えてくれること
◎バリエーションをつくるためのヒントと方法
4つめの大事なこと*微かな力
強い刺激は感覚を鈍らせる
ボールのように硬く丸まってしまうリリー
なまけものごっこ──過剰な力をぬいて
「なまけものの国」の威力
まずは、あなたから
数字はなんのため?──ストレスと認知能力
「微かな力」が直観と思考力を高める
科学が教えてくれること
◎微かな力を使いこなすためのヒントと方法
5つめの大事なこと*内なる熱狂
喜びを深める力
感激のやりとりが脳を呼び覚ます
ジェイコブを進歩させたもの
拍手はしないで
「もう一度やって」と言わない
心の内で喜びをかみしめる
科学が教えてくれること
◎心を熱くするためのヒントと方法
6つめの大事なこと*ゆるやかな目標設定
可能性にひらかれた道
ヒヒのたとえ──目標にしがみつくということ
動くこと、喜ぶことを学んだアレクサ
でも、いつになったら話すの?
イエス、ノー、イエス!
子どもにとっての成功体験とは
ゆるやかな目標のもつ普遍性
科学が教えてくれること
◎目標をゆるやかに保つためのヒントと方法
7つめの大事なこと*学びのスイッチ
読み書きが困難だったスコッティ
スコッティの飛躍
ひとりの人間としてみる
子どもを丸ごとみる
科学が教えてくれること
◎学びのスイッチを入れるためのヒントと方法
8つめの大事なこと*想像すること、夢みること
機械的に暗唱しつづけるアリィ
きかんしゃトーマスはどこ行った?
想像力のリアリティ
あなたの子どもに潜む天才
「この子は天才だ」
空想が脳にもたらすマジック
科学が教えてくれること
◎想像力をはばたかせるためのヒントと方法
9つめの大事なこと*気づき
赤ちゃんは観察している
「気づき」は行為だ
科学が教えてくれること
私、そうしてた?──母ジュリアの「気づき」
自分のなかの観察者を目覚めさせる
「気づき」は波及する
◎気づきを増やすためのヒントと方法
おわりに──限界を超えて
よくある質問と答え
訳者あとがき
はじめに
『この仕事を始めた三十年ほどまえ、親たちが、レッスンを通して変わっていく子どもを見て奇跡だと言うのを聞き、びっくりしました。しかし当時の私は、子どもの変化が本物だと気づいていましたが、レッスンとの因果関係を理解できていませんでした。それから歳月を重ね、私は目にする成果が「まぐれ」ではないこと確信しました。自発的に回復したとか、もとの診断が間違いだったという説明が当てはまらないほど、さまざまな症状の子どもたちにくり返し成果がみられたからです。
私は何千人もの子どもたちと関り、そのみごとな変化を観察してきました。けれども、奇跡を起こしたと思うことは一度もありません。子どもたちの変化はその脳の中で起こっていることで、すべては脳の力によってもたらされたと理解しています。自閉症、脳性まひ、注意欠陥・多動性障害(ADHD)ほか、さまざまな診断を受けた子どもが飛躍するのを見るたびに、できるだけ多くの子どもたちにこの取り組みを伝えなければと感じてきました。親御さんと介助をしているみなさんに、簡単で実践しやすい方法をお教えしたいと思います。
これからご紹介する方法は、パラダイムの転換をもたらし、支援のあり方を一変させるものです。お子さんは大きな変化を体験するはずです。子どもたちは、フタがされている能力を活用できるようになるのです。
私は、モーシェ・フェルデンクライス博士の教え、子どもたちとの取り組み、脳神経学の知見にもとづき、理解を明確にしてきました。科学は日進月歩で人間の脳の可能性を解き明かしています。古い概念をうちやぶり、限界を押し広げ、健康な脳も傷を負っている脳も、よりよく働くことのできる新しい道がつぎつぎと開けています。驚くべき可能性を実現させるためには、脳は変わることができるということ、「脳の可塑性」を理解する必要があります。お子さんがどんな状況であっても、どんなに個性的な生育であっても、実践できる簡単な原理が必要です。それを示すことが本書の目的です。
第Ⅰ部は、子どもの脳がどのようにしてよくなる方向に変化し、その子の人生までもが変わりうるか、ということを理解してもらうために書きました。
第Ⅱ部(9つの大事なこと)は、眠っている子どもの能力を引き出すために、脳が何を必要としているかを説明しました。各章の終わりには、毎日の生活のなかで子どもと取り組むことができる具体的な方法とヒントを紹介しています。「9つの大事なこと」と取り組みのヒントは、子どもの脳の可能性を引き出し、まさに実現させていくものです。
まず、第Ⅰ部から読むことをお勧めします。そこで基本的な考え方をつかんだあと、第Ⅱ部の「1つめの大事なこと 注意を向けて動くこと」を読んでください。あとにつながる大事な鍵です。その後は本の順番どおりに読んでも、気になる章から読んでもいいでしょう。ひとつの章がすっかり自分のものになるまでに数日かかると思います。スキルを習得し、理解を深める時間が必要です。ひと通り読んだら、折りにふれて読み返し、さらに学びを深めてください。
お子さんが限界を超えていく手助けをするための力強い方法が見つかるはずです。それでは、子どもたちの脳のとてつもない可能性を引き出す旅へ、いっしょに踏みだしましょう。』
おわりに―限界を超えて
『子どもが特別な課題に直面するとき、そこに関わる人たちは、その子に何が必要かを見きわめ、最善の支援方法を見つけださなければなりません。私は本書で、ほぼどんなときも目覚めさせることのできる豊かな可能性を明らかにし、これを実現する方法を示そうと試みました。そして、限界を超えるとはどういうことか、全力で挑戦するとはどういうことか、また、問題の解決法はつねにこれから生みだされるものだということについて、私の考えをお伝えしました。
三十年以上におよぶ取り組みを通じて、私は、本書に示した「9つの大事なこと」が子どもの状況を変え、その子が限界を超えていくために役立つことをくり返し経験してきました。「9つの大事なこと」は、あなたとお子さんの脳の無限の可能性を探り、目覚めさせるためのガイドです。これは脳が上手に働くようになるための支援の方法であり、その核となるのは、子どもの脳という奇跡です。実践を通して、子どもの脳はたえず識別を細かくし、動き・感覚・考え・行ないを洗練させるチャンスを得ることができます。子どもはつねに能力を高め、成長を続けることができるのです。
特別な支援が必要な子どものための目標がひとつあるとするなら、それは、その子が「充実した意味ある人生を送ること」でしょう。これはすべての子どもにとっての目標でもあるはずです。最後に、テンプル・グランディン(米国の動物学者、自閉症をもつ)の言葉をご紹介したいと思います。
「親や教師は、子どものレッテルではなく、子ども自身をみるべきです。(中略) 現実的な期待を抱きながらも、その子の内に静かに潜み、表出するチャンスを持っているかもしれない才能の芽を見過ごしてはなりません。』
※テンプル・グラディンの著書に関しては、過去に「自閉症の脳を読み解く」というブログをご紹介していました。
アナット・バニエルのプロフィール
『米国在住。科学者の父と芸術家の母のもと、イスラエルで育つ。大学では統計学を専攻。人間の脳への関心から、身体運動の意識化を探究したM・フェルデンクライス博士(1904~1984)に師事。
脳性まひをはじめとするスペシャル・ニーズの子どもたちとの30年以上にわたる取り組みを通じて、脳の可塑性を利用して本人の能力をひきだす手法(アナット・バニエル・メソッド)を編みだす。動き、感じ、考えるひとりの人間として子どもを総体的にとらえるそのアプローチは、自閉症スペクトラム、脳性まひ、ADHD、腕神経叢損傷、傾頸などさまざまな症状をもつ子どもたちへの取り組みを可能にさせた。
同時に、科学にもとづくメソッドを発展させ、幅広い年齢・職業の大人たちへのレッスンを通じて、ニューロ・ムーブメントを提唱。指揮者・演奏家・アスリートに数多くの実践者がおり、人びとが痛みや限界を超え、新しい次元のパフォーマンスに到達できるための取り組みを展開している。臨床心理士であり舞踏家でもある。
現在、カリフォルニア州マリン郡のアナット・バニエル・メソッド・センターを運営。後進のプラクティショナーの育成に励み、レッスンを希望する人びとを世界中から受け入れている。』
ボイタ法・ボバース法
「ボイタ法」、「ボバース法」という訓練・リハビリテーションの方法は、小児障害に係わる中で知りました。しかし、これらは主とする対象が乳児期のものということもあり、そこまでは必要ないだろうと思いスルーしていました。
一方、訪問の仕事(業務委託)は高齢者から小児にシフトし始めており、ご家族との接点が増える傾向にあるため、これらに関しても、ある程度は知っていた方が良いと思うようになりました。
調べてみると、「ボイタ法」は人間の反射を利用する方法、「ボバース法」は反射を抑制する方法ということで、全く正反対なアプローチのようです。個人的には前者の反射を利用する方法の方が興味深かかったため、まずはボイタ法について勉強することにしました。
こちらのサイトに、ボイタ法、ボバース法についての説明が出ています。書かれている内容は難しいのですが、簡潔にまとめられていますのでご紹介させて頂きます。

『ともに脳性麻痺に対する代表的な訓練・リハビリテーション方法です。
ボイタ法は、7つの姿勢反射(引き起こし、パイパー逆さ吊り上げ、ランドー反応、コリスの水平吊り下げ・片脚吊り下げ、ボイタ反射、腋下支持垂直挙上)をスクリーニング方法とし、早期乳児期に脳性麻痺症状の出現する以前に中枢性神経障害(ZKS)を示す患者さんを発見し、原始反射を応用した腹這い・寝返り運動を誘発し脳性麻痺の発症を阻止します。しかし、ZKSの脳性麻痺への移行についての根拠が明らかではない、時に治療が必要な児を見落とす、などの問題点も指摘されています。
一方、ボバ-ス法は、姿勢反射を含めた正常乳児の発達の知識から、脳性麻痺の症状が形成されてくる異常発達を神経生理学的に定義し、それを積極的に予防していこうとするアプローチです。実証的治療結果(療法士である妻の経験を医師である夫が理論化)に基づく、異常反射抑制肢位(RIP)やKey point of controlを用いた訓練により、協調運動や日常生活動作に結びつく基礎的運動能力の改善をめざします。』
まず図書館から借りてきたのは「ボイタ法の治療原理 反射性移動運動と運動発達における筋活動」という本です。こちらの本の魅力は何といってもボイタ(Vaclav Vojta)自身が書いたものであるという点です。
読んでみると、運動学(キネマティクス)とリハビリテーション学についての知識が不足している私には、理解するのは難しいということが分かりし、早々に断念することにしました。
ただ、雰囲気だけでもお伝えすることは悪くないと思い、断片的ですが以下にご紹介します。なお、“矢状面”と“膝窩筋”の後ろの( )は私による加筆です。
足関節の運動:後頭側下肢の立脚相と踏み切り相における距踵関節の軸(図38)
1.新生児の足は回内している。踵骨の長軸は距骨の長軸に対して外側に変位している。
2.踵骨は高位にあり、また距骨の下には移動していない。
身体全体の姿勢が変化することによる起き上がり機能が発達し、それによって負荷がかかり筋機能が変化したときに、初めて踵骨は距骨の下に位置してくる。独歩が獲得されても、まだ子供の足は外反している。全骨格筋の筋機能の分化のもとに3歳になって初めて足のアーチが発達しはじめる。脳性運動障害に侵される危険があったり、小児脳性麻痺に発展しているならば、距骨と踵骨に関しては足は新生児の運動発達段階のままである。踵骨と距骨について上述した病的肢位は、小児脳性麻痺の患者では脛骨内旋を合併しているのがほとんどである。反射性腹這いの出発肢位において、足は下腿に対して直角である。
踵の誘発帯を刺激して、距踵関節を矢状面(体を左右に分ける面[矢状面の運動は底屈・背屈]。水平面は上下、前額面は前後)で踵骨と距骨の長軸が重なるポジションにもってくる。

9個の赤丸が「誘発帯」という非常に重要なポイントです。
なお、こちらの画像は「からだ相談室」さまから拝借しました。
また、足の外反は変形を踵の誘発帯によって矯正すると、最初は後足部が他動的に矯正されることになるが、前進運動の経過中に長短腓骨筋、前脛骨筋そして非常に重要な後脛骨筋の共同運動機能によって能動的に後足部の矯正位が保たれる。踵誘発帯を圧迫すると下腿の膝窩筋にも遠隔作用が及ぶ(図40参照)。
踵誘発帯を圧迫すると距腿関節を介して下腿の長軸に伝わり、膝窩筋(膝窩筋の筋力低下は膝の過伸展につながる)が伸長状態になる。膝窩筋が収縮すると、膝窩筋は固定点である尾側に牽引され大腿は外旋する。脳性運動障害の場合、外反尖足の問題ではほとんどいつも脛骨の内転と大腿骨の内旋を合併していることを考えると、このことは重要である。
反射性腹這いの後頭側下肢では膝窩筋は大腿骨の外旋だけに働くのではなくて、足の負荷にも影響を与える。後脛骨筋との共同運動では、膝窩筋は間接的に踵骨の外反と立脚相で良好な踵の負荷に寄与する。
要約すると後頭側下肢の足に関しては、足は反射性腹這いの全運動過程で能動的に、そして単独で回外位さらに地面に対して直角位で支えているといえる。この際、踵骨と距骨は下腿の長軸にある。これらの筋活動は反射性腹這いの運動パターンにおいて新生児に誘発可能で、筋肉の共同運動によって筋活動が起こる。セラピストが他動運動に足を矯正して保持する必要はない。新生児や成人の患者も歩行サイクルと比較すると立脚相と踏切り相にあたるとろでこの下肢を動かし、その際、下腿三頭筋も運動に参加する。
足関節について
足関節には“内反”・“外反”という用語と、“内返し”・“外返し”という用語があります。「これは同じなのか?」と思いながら、調べてみると内反・外反は「変形」を意味する用語であり、一方、内返し・外返しは「運動」の名称であるということが分かりました。なお、下記は「足関節の運動」を示した図です。

REGUARDさまのサイトに掲載されていた『知ってトクする豆知識:足首編』から拝借しました。
続いて、図書館から借りてきたのは「子どもの姿勢運動発達」という本です。1985年発行の本ですが現在も購入することができます。
目次は次の通りです。
序文
はじめに
第1章 保育園で発達診断してみたら
第2章 正しい姿勢とその発達
第3章 発達診断に用いられる姿勢反応
第4章 発達診断に用いられる反射検査
第5章 調和のとれた発達とは
第6章 障害のある子の療育と訓練効果
第7章 ボイタによる診断学と境界線域の子どもたち
第8章 ボイタによる訓練と必要な配慮
第9章 こんな子に役立つ育児体操
そして、【付図 運動発達と姿勢反応】という1枚物の付録が付いています。
ブログでは、第8章の「ボイタによる訓練と必要な配慮」と付録の付図をご紹介したいと思います。
第8章 ボイタによる訓練と必要な配慮
1 ボイタ法による治療の概要
ボイタ法の治療はふつう、お母さん(家族)に対して、PT(理学療法士)が訓練を指導し、お母さんが家庭で1日4回行うようになっています。1回の訓練時間は15分~30分位、特に体力的に問題のある場合は、5分位に短くすることも可能です。まず、正常なムスタ(パターン:筋肉の使い方の組み合わせ)を誘発しやすい出発肢位をとらせます。
反射性ねがえりⅠ相は仰臥位、Ⅱ相は側臥位、反射性腹這いとエルステポジションは腹臥位です。
次に特定の部位にある誘発体を決められた方向に向かって刺激します。
例えば反射性腹這いの時の誘発帯は図に示すように、主誘発帯が4つ、補助誘発帯が5つあります。
主誘発帯は主に骨膜への刺激、補助誘発帯は骨膜刺激と筋膜伸長とからなっています。誘発帯をどのように組み合わせて使うかは、その子の障害の内容によって違ってきます。
PTは自分で反応を出してみて、一番正常パターンを誘発しやすい組み合わせにより訓練の処方を決めます。このようにして、決められた肢位で、決められた誘発帯を決められた方向へ向かって刺激して待っていると、反応が返って来ます。その時、出来るだけ初めの出発肢位に止めておくようにすると、腕ずもうの時のように、反応は強まり、全身の筋肉へ段々と拡がって行きます。
その起こってきた反応は、正しい起き上がりと、正しい相同運動、正しい姿勢反応性の三つの要素を含んだ、協調性複合運動と理解されています。前頸筋や胸筋、腹筋などの動きで顎をひき、肩が下り、背中全体がのびて、骨盤が後傾するような正しいパターンになった時に、それら三つの要素が正しく起こります。この時、脳の中でもそれまで働けていなかった、新しい経路に働きが起こっているはずです。もちろん、非常に重症な脳性麻痺児が初めから簡単に正常なパターンを出せるはずはありません。そこでその子の本来のパターンより、少しでもよくなるように、毎日積み重ねて行くわけです。脳の中で新しく働き始めた経路は、初めの内3~4時間位たつと、働かなくなってしまうと考えられています。実際の訓練の直後にはよくねがえりするのに、訓練が1~2回抜けると余りねがえらなくなってしまうこともあります。少しでも正常に近づけるための訓練は少ない日でも3回は必要です。特に乳幼児は発達が早いので4回必要です。脳性麻痺はふつう放置することによって段々重症化して行きますが、1日2回の訓練は現状維持、1回は重症化を少しくいとめるための訓練と考えられています。5回もすると一日中訓練ばかりしていることになり、遊びの時間や、動きまわる時間がありません。
訓練は基本問題、日常生活はその応用問題と考えて、動きやすくなった手足や口をしっかりと使わせて下さい。以上のことから、日常生活経験と訓練をどのように組み込んで行くかが、訓練の効果を上げるための鍵になることがおわかりいただけると思います。
2.ボイタ法の訓練は何をしているのか
ボイタ法の訓練は、赤ちゃんの姿勢や運動のパターンを少しでも正常に近づけることにより軽症化させることを目的としています。どんなやり方でもよいから立って歩けばよいと考えているのではありません。ねがえりや這い這いの時に使われる筋肉の組み合わせは、歩く時にも使われています。
正常な寝返りのパターンでの、上下肢の位置や体軸のねじり方は、正常な法の訓練は歩行での上下肢の位置や体軸のねじり方と似ています。脳性麻痺児の寝返りのパターンと似ているわけです。従ってねがえりのパターンが少しでも正常なパターンになることは、歩行のパターンが正常なパターンに近づくことを意味しています。
筋肉は、ふつう、よく使った筋肉ほど太く強くなり、使わない筋肉ほど細く弱くなりますから、正常なパターンで毎日動いているのと、異常なパターンで無理して動いているのとでは、筋肉のつき方が段々違って来るわけです。そして強い筋肉は増々強く、弱い筋肉は増々弱くなります。そしてこのことは、脳の中でも起こっていることが予想されるわけです。
ボイタ法の訓練は出発肢位に出来るだけ止めておくことによって筋肉の等尺性収縮(注.筋肉の長さが変わらない収縮の仕方。例えば腕ずもうの相手がほとんど同じ強さを持っている時、筋肉は強く収縮しているにもかかわらず、同じ長さに保たれている。一方、動きの速い運動の時は筋肉の長さは常に変化していることになる。)の方が、筋肉は太く強くなりやすいわけで、反射性ねがえりの時に正常パターンの反応を起こし続けることが出来れば、ただ単に正常パターンでくるっとねがえった時よりは、正常パターンを強めることが出来ることになるのです。特に脳性麻痺児の場合、肩甲骨をしっかり固定させ、骨盤を安定させるための体幹の筋肉が弱いことが、姿勢や運動パターンのくずれる大きな原因となっています。
また、胸筋や腹筋の弱さのために風邪を治す力も弱いことが多いのです。ですから、頭の方へひきあげられたようになっている肩甲骨が、体幹の筋肉によってしっかりとひきさげられ、肩巾が広くなるような反応(この時必ず、顎ひきを伴う)や、胸筋や腹筋が弱いために、横へ間のびしてとび出した肋骨下縁が、腹筋によってひきさげられるとともに、大きく深い呼吸によって胸郭がふくらむような反応が起こることが必要なのです。また、背筋が強いために後ろからひきあげられ、前傾している骨盤が、背筋を伸ばし腹筋を働かせることによって、後傾するようになることが求められます。このようにして、肩が安定すると頭の位置も安定し、口の使い方、目の使い方が良くなります。また、肩の安定は手の使い方を良くします。胸筋腹筋の働きは、呼吸や排便・排尿の機能を改善するようですし、骨盤の安定は、坐位・立位の安定と共に腰の強さを促します。
まとめていうと、ボイタ法の訓練は、特定の出発肢位において誘発帯を刺激し、そのまま止めておくことで、ねがえりや這い這いの時に使う筋肉のパターンを正しく誘導し、体幹を安定させ、結果として、目や口、手足などを安定して使え、呼吸や内臓の働きを改善しながら、移動に必要な体幹のねじりと四肢交互性を誘導することを行っていると言えます。従って使いやすくなった目口手足を実際に使わせる指導や環境が必要になるわけです。
付図
さらにネットで調べていると、愕然とする情報を見つけました。
誤解があると良くないので、前後しますが、ボバース記念病院さまの現在の取り組みを最初にお伝えします。

『私たちが行っているのは、むしろこの論文で推奨された「目的志向型トレーニング」や「両手動作トレーニング」「家庭療育プログラム」に近いものです。
ボバース夫妻はもともと、全ての患者さんに決まった方法で治療するべきではないと主張していました。個々の患者さんの状態に応じた個別のリハビリテーションが必要で、その方法は医学や技術の進歩とともに変化していくべきだという考え方を持っていたのです。
1980年代から医療は劇的に進歩し、同じ脳性まひという病名でもその原因や症状は大きく変わっています。また、手術や薬も進歩しており、以前はなかった様々な選択肢が使えるようになりました。私たちはボバース夫妻の考え方に従い、患者さんの病状に応じて現代の医学を根拠とした個別の治療を提供しています。
ボバース記念病院は、一律の「ボバース法」をする病院ではなく、当時は革新的であったボバース夫妻の考え方を引き継ぐ病院なのです。実際に私たちは、ノバック教授をはじめとする海外の著名な研究者を日本に招き、最新の知見を学んで常に治療方法を進化させるように努力しています。』
そして、問題の ”情報” は次のような内容です。
『2013年にオーストラリアのノバック教授は、脳性まひに対する様々な治療法の効果を詳しく検討し、ボイタ法は「しない方がよい」、ボバース法は「するべきではない」治療であると結論づけました。この意見は世界中で支持され、今や専門家の間では常識となっています。しかし、その論文の根拠となったのは、ボバース夫妻が提唱した治療技術の一部を様々なお子さんに対して一様に「ボバース法」として行った1980年代の研究でした。』
1980年代の研究とはいえ、これは凄い事実であると思い、いろいろ探してみたところ、関係する文献を見つけました。

クリック頂くとPDFファイル(26ページ)がロードされます。
こちらの文献は執筆者の先頭がノバック教授(IONA NOVAK)になっており、発行日(左下)は2013年6月5日です。また、「ボバース記念病院」さまのサイトに掲載されているグラフの元データと思われるグラフも含まれています。以上のことから、これが関係する文献であるのは間違いないと思います。
グラフの説明
●上段左端の矢印↕は「有効性」を表しています。破線の上が“有効”です。1番上の緑の“S+”は“Do it”です。1番下の“S-(Don’t do it)”と下から2番目の“W-(Probably don’t do it)の2つは破線の下に位置しているので、有効でないという評価になります。
●それぞれの〇(円)の中にそれが何かということが明記されています。「ボイタ」は「Vojta」になりますが、「ボバース」は「NDT」になります。このNDTとはNeuro Developmental Treatmentの略で、日本語では「神経発達学的治療法」とよばれています。『Mindsガイドラインライブラリ』という公益財団法人日本医療機能評価機構(厚生労働省委託事業)というサイトに“神経発達学的治療法(NDT)-Bobath法は有効か?(脳性麻痺リハビリテーション)”という題名の記事が出ています。
●ブログでは「Vojta」もしくは「NDT」が評価に入ってるグラフだけを掲載させて頂いていますが、「Voja」は“Improved muscle strength”と“Improved motor activities”が有効でないという評価をされており、「NDT(ボバース法)」は“Contracture(拘縮) management”、“Improved motor activities”、“Improved function & self care”の3つが有効でないとなっています。
以下は『Canchild』というサイトの中で紹介されていた、ノバック教授(Dr. Iona Novak)の情報です。
まとめ
1.「ボイタ法」、「ボバース法(NDT)」は、それらが発表された当時の内容については、有効性が否定されている。
2.「目的志向型トレーニング」、「両手動作トレーニング」、「家庭療育プログラム」など、進化したものがどんどん出てきている。
3.治療技術の一部を一様に適用するのではなく、患者さまの病状に応じた個別治療を行うことが求められている。
スキンシップケア(C触覚線維)
業務委託による週二日の訪問の仕事は、少しずつ小児障害の患者さまが増えてきています。こちらはすべてマッサージですが、なかにはじっくり手技をすることが難しい元気な子もおり、マッサージの基本ともいえる「スキンシップ」について詳しく知りたいと思い、今回の本を見つけました。
表題の「スキンシップケア」とは著者である山口創先生の言葉ですが、次のような説明がされていました。
『人は親しい人と一緒にいるだけで、周囲の見え方や苦痛の感じ方さえも変わってしまう。本書では、人に直接触れることだけでなく、人と一緒にいることも含めて、人を癒す行為は「スキンシップケア」と定義し、これまでのスキンシップの概念をあらためて捉えなおしたい。そしてなぜ親しい人との触れあいや関りが、生きづらさや抑うつを防ぎ、幸福感を高め元気を回復されるのか、とうことも考えていきたい。』
ブログは目次に続き、太字にした箇所についてのみ取り上げていますが、それぞれ章の一部をそのままご紹介しています。
目次
はじめに
第1章 コミュニケーションする皮膚
触れなくても肌は感じている
「直接触れ合う」と何が起こるか
ストレスを癒す身体のメカニズム
もっとも大事な役割は体温調節
ストレスを感じる皮膚
皮膚を温めると心が温まる
うつ病は体温制御ができないことが原因
触覚は感情に直結している
摂食障害は胎児期のうぶ毛が原因か
自閉症も皮膚の神経線維が原因か
自尊感情が低い人ほど有効なタッチ
「寄りそう」ことで何が起こるか
動物が群れる理由
パートナーの有無による心理の変化
自己が他者にも膨張する
皮膚が他者を判断していた
幼少期の触れ合いが人間の礎をつくる
触れ合いの原点
温かい感触の記憶
母親と赤ちゃんの体は同調している
不安定の人が疲れやすい理由
寂しい人は太る?
第2章 触れないと皮膚は閉ざされる
失われた皮膚の交流
人間の心理的境界はどこにあるのか
二つの境界
日本人独特の「あわい」の境界感覚
肌と皮膚
なぜ日本人は対人関係に悩むのか
人の「なわばり」感覚
ぺリパーソナルスペースとパーソナルスペース
世界の見え方は文化に依存する
視覚優先の欧米人、触覚優先の日本人
抱きしめ細胞の存在
触覚を大切にしてきた日本の育児
日本と欧米、抱っこの違い
背中の感触が大事なおんぶ
生きづらさの原因は皮膚が閉ざされているから
過去の親子関係から自由になるために
皮膚が拓かれている多良間島の子どもたち
第3章 病気やストレスが劇的に改善、スキンシップの驚くべき力
スキンシップが持つ癒しの力
境界が拓かれることで人は癒される
現在の介護施設と病院の難しい現状
「人の手」で触れる意味
効果が実証された触れる癒しの技法
ユマニチュード
セラピューティック・ケア
タクティールケア
スキンシップの効果が期待されるこれからの領域
ホスピス・緩和ケア
発達障害者へのケア
触れられるとなぜ心が癒されるのか
心理療法としての触れるケアの有効性
触れるケアは長く続けるほど効果的
たった1回の触れるケアでもOK
人間関係を改善する皮膚コミュニケーション
第4章 皮膚を拓いて、元気な自分を取り戻す
皮膚を拓いてつながりを拓く
笑うこと
卒業写真で笑顔の人は幸福になる
子どもの笑顔は温かいタッチから
心を開くこと
人に語ることの意味
ネガティブな気分を和らげる筆記療法
皮膚を共振させること
マッサージからみる共振
カップル・親子の共振
集団の感情を利用する
感謝すること
親切にすること
許すこと
許すことの効果
相手の立場に立つ
ストレスを癒す身体のメカニズム
『人は他者から触れることで、安心したりストレスが癒されたり、元気をもらえたりする。そもそもそのような心の変化はなぜ起こるのだろうが。
広くいろいろな学問分野の研究をひもといていくと、そこには数百万年もの長い進化の歴史の中で獲得してきた、人間が持つ奥深い身体のメカニズムが潜んでいることがわかる。
スキンシップが持つ意味について、進化の時間軸で考えていきたい。
スキンシップのもっとも原初的な意味は、生まれたばかりの赤ん坊の体温が低下しないように、養育者が触れて保温することだった。もともとスキンシップは生命を維持するために必要だったのだ。一方でそのように温かい身体で触れられることは、情動レベルでは赤ん坊にとって、養育者に守られて安心できる快の体験でもあった。抱かれるたびに安心することを幾度となく繰り返す経験をした結果、それは不安や恐怖、ストレスなどの不快な心を癒す行為と結びついていった。さらにそこから発展して、触れて安心させてくれる人に特別な愛情の絆である愛着関係を築いて、その関係を強め、そういう人を信頼するようになった。これが認知レベルである。
このように自己の生命を維持するといったもっとも基本的なレベルから、絆を強めるといった社会的なレベルまで階層構造を成していて、下から順に進化してきた。』
もっとも大事な役割は体温調節
『いうまでもなく、人は体温を維持しないと生きていくことはできない。外界の温度が大きく変化しても、身体の体温の変化はわずかにしか変化しない。厳密にいえば、体温には皮膚温と深部体温の2種類がある。皮膚温は環境の温度に応じて変化するが、深部体温の方は環境の変化によらずある程度一定である。深部体温はおよそ30度~44度の間であり、それ以下あるいはそれ以上になると死に至ることになる。
また、深部体温と皮膚温には温度の落差があり、深部から皮膚表面に至るまで、温度勾配がある。この温度の落差が適度にあることが生存にとってとても重要だ。そしてこの温度勾配を一定に保つために、身体は常に深部で代謝活動をすることで熱を産出し、皮膚から熱を逃がしている。
体温を保つことは、代謝にとっても、生殖活動にとってもとても重要だ。たとえば代謝については、体温が1度下がると基礎代謝は12%、体内酵素の働きは5割も低下してしまう。また動物の場合、気温が下がると生殖活動も低下する。体温の低下は、自己の生存にも生殖にとってもデメリットばかりだ。』
『多くの動物では、危険が迫っていたり病気になったりしたときに仲間同士で身を寄せ合うことがある。これも肌をくっつけ合うことで、体温を調節するために必要なエネルギーの消耗を防いでいるのだ。イヌなども、赤ちゃんのときは同じように身を寄せ合っている。肌を触れ合うことは生き残るためのもっとも基本的な戦略なのだ。
とりわけ人間の赤ちゃんは、この体温調節機能が極端に未熟な状態で生まれてくる。だから生まれたらすぐに養育者に抱かれて体温を保つようにしなければいけない。何らかの理由ですぐに抱かれることがなければ、保育器で体をしっかり温める必要がある。
こうして先の図1(触れ合い効果の階層構造)のベースの部分をしっかりと築いてあげないと、将来的にはその上の安心感や、さらにその上の愛着の絆にまでも悪影響が出てしまう。』

皇帝ペンギンは厳寒の南極で生き抜くために身を寄せ合います。
画像出展:「カラパイア」
触覚は感情に直結している
『皮膚には4種類の触覚の受容器があり、それぞれ異なる物理的な性質に反応しそれを脳に送り知覚している。
ところが最近、皮膚にはもう一つ、性質の異なる触覚の受容器があることがわかってきた。それはC触覚線維と呼ばれ、神経線維の末端が枝分かれして皮膚に入り込んで触覚を直接知覚している神経線維の束である。これは、「触れて気持ちいい」とか「触れた感触が気持ち悪い」といった感情に関わる神経線維である。

左上に書かれた”自由神経終末”が、上記の説明(「神経線維の末端が枝分かれして皮膚に入り込んで…」)の部分の図になります。
画像出展:「看護roo!」
興味深いことに、このC触覚線維が興奮するための物理的な条件というのがある。それは触れるものの速度と柔らかさが重要な要素である。速度に関しては、秒速3cm~10cm(ピークは5cm)ほどの速度で動く刺激に対してもっとも興奮する。また柔らかさに関しては、ベルベットのような柔らかい物質に興奮する。だから人の手でゆっくりと手を動かしてマッサージをするような刺激に対して、興奮することになる。
そして脳では島皮質や線条体といった、情動や自己の感覚や身体感覚に関わる部位に到達する。
またこのC触覚線維の興奮は脳内ではセロトニン神経を活性化させることもわかっている。だから抑うつや不安の高い人にゆっくりした速度でマッサージをしてあげると、脳内でセロトニンがつくられて症状が軽くなるのだ。
実際に、著者が行った実験でも、相手の背中に秒速5cmほどのゆっくりと触れてあげると、抑うつも不安も顕著に低下した。逆に手を動かす速度が、速すぎたり遅すぎたりすると、自律神経の交感神経が優位になって、覚醒水準が上がってしまったのだ。』

こちらはネット上にある『Pain Relief-痛みと鎮痛の基礎知識』というサイトです。この内容を基に、”神経線維”と”受容器”について補足したいと思うのですが、一つご注意頂きたいのは、C線維に関してはまだ未解明なことも多いという点です。
このページのほぼ中段に”体性感覚神経の神経線維の分類”という見出しがあり、そこに表形式で神経の説明が出ています。
有髄、無髄は髄鞘(神経の軸索を覆う膜のようなもので、この髄鞘があると神経の伝導速度がアップします)の有無を表しています。
有髄にはA線維とB線維があり、AにはAα、Aβ、Aδがあります。この3つはそれぞれ”太さ”、”速さ”、”機能(役割)”が異なります。B線維は”交感神経節前線維”と呼ばれ、自律神経系に属するものです。
一方、無髄には2種類のC 線維があります。1つ”交感神経節後線維”というB線維と同じ、自律神経系の働きを持っています。もう1つが”痛覚、温冷覚”となっていますが、まさにこの部分の解明が進み、”触覚”としての機能やセロトニン、オキシトシンとの関連性など、いろいろな発見がされてきているということになります。
”受容器”に関する説明はこのページの上のほうにあります(【皮膚の受容器】というボックスの中にあります)。これによるとC線維の受容器は一般的には”ポリモーダル受容器”であることが分かります。
また、よく見ると下段に「その他のC線維」とあり、そこには次のような説明も加えられています。
”かゆみを伝える受容器、触覚刺激に反応するものもある。*pleasant touchを伝えるC線維もある!”

愛知県理学療法士会誌第18巻第2号に掲載されている『痛みのメカニズムと理学療法』という資料(PDF8枚)がダウンロードできます。この資料に”ポリモーダル受容器”に関する記述が出ていますので、ご興味あればご参考にしてください。
こちらの『触れることの科学』の中にもC触覚線維に関する記述がありました。

『機械受容器(メルケル盤、パチニ小体など)の活動に対するAβ線維の活動を記録してみると、C触覚線維とは反応のしかたが異なることが分かる。Aβ線維は、前腕を撫でても、模様のある面や角や震動で接触刺激を与えても、どちらでも反応する。もちろん、手のひらや指の無毛皮膚でも反応は起こる。C触覚線維と比較して最も重要で顕著な違いは、強い刺激ほど効率的に活性化するという点である。撫でる速度が速いほど、反応も強くなる。Aβ線維は触覚刺激のさまざまな性質を弁別できる。
これに対してC触覚システムは、特定のタイプの接触、すなわち、一定の範囲の速度で軽く撫でられた場合のみを感知するようだ。最適な速度に合わせるこの性質は、知覚にとって決定的に重要な要素となる。健常者の前腕や大腿を速度を変えて撫でる実験で、被験者が最も心地よいと報告した速度は、毎秒3~10センチの範囲だった。この範囲は、C触覚線維が最も強く活動する範囲と正確に一致している。
健常者の脳画像を撮影してみると、前腕を撫でられると1次、2次の体性感覚野(Aβ線維由来の情報により、細かい形や質感を識別する)とともに、感覚処理の感情的側面に関わる島皮質後部が活動することが分かる。これに対してG・L(患者)の脳では、前腕を撫でると島皮質後部は活動するが、1次、2次体性感覚野は活動しない。つまり、C触覚線維は島皮質は強く活性化するが、体性感覚野は活性化しないと考えられる。それだけではない。C触覚線維を最も強く活性化し、最も心地よいと報告されるほどよい速度の撫で方は、やはり島皮質後部を最も強く活性化していた。これはG・Lでも健常者でも同じ結果だった。』
なぜ日本人は対人関係に悩むのか
『俗に、日本人は集団主義だといわれることがある。しかし社会学者の濱口惠俊は、日本人の人間関係の特徴について、西洋型の「個人主義」に対する「集団主義」ではない、と述べている(“日本型信頼社会の復権”東洋経済新報社)。
彼によればたとえば職場では、個人を集団の中に埋没させて仕事の集団を優先するというのではなく、各人が互いに仕事上の職分を超えて協力し合い、それを通じて組織の目標の達成をはかり、それが翻って自分の欲求を満たして、集団としての充実につながるのが「日本的集団主義」なのだという。
彼の主張する間人主義については、本書のこのあとの議論でも重要な位置を占めているので、西欧の個人主義と比べながら、「スキンシップ」の立場からもう少し深く解説したい。
西欧の文化は、すべてを個人の力と責任で成し遂げることに価値を置くものであり、それには自己を律する強い自我が必要である。このように西洋の「個人主義」では、人に依存するよりも個々人が独立して社会を生き抜くことに価値を置く、頼みとできるのは自分以外にないことを前提にするため、他人との関係も自分の欲求を満たすための手段であると捉え、人間関係それ自体に無条件に価値を置くものではない。
それに対して日本人は、自己を他から独立した「個人」ではなく、「間人」として捉えている。自分を、人と人との「間柄」に位置づけられた相対的な存在であると感じ、社会生活を自分一人の力で営むのは不可能だと感じている。自立ではなく、相互依存こそ人間の本態だという価値観なのだ。この相互に信頼し助け合う価値観こそが「間人主義」なのだ。これは、対人関係を自己の生存のための手段として捉える「個人主義」とは、対照的な価値観だろう。
それらの違いはたとえば職場の人間関係で如実に表れると思う。西欧の人間関係は、互いに独立した個人間での契約関係が基本である。そこでは職務を超えてまで個人的な人間関係が発展していくことはあまりない。だから定時には仕事を終えて、そのあとはプライベートな時間を楽しもうとする。それに対して日本人は、定時に自分だけ仕事を終えてさっさと帰ってしまうことはないだろうし、せっかくの有給も消化しきれない人も多い。どちらも仕事仲間との関係性を第一に考えているからだ。
濱口はこのような関係を図にしてわかりやすく解説している。図10左の個人主義は、独立したAとBがそれぞれの領域を守りながら相互作用をする。それに対して図右の間人主義の場合、AとBの生活空間は互いに重なり合っており、重なり合った部分を含めて自己のアイデンティティと感じている。
だから日本人は主体性がないとか個人のアイデンティティが希薄だ、ということではなく、他者との相互に包摂するような関わりの中で、個人個人が主体性を確立し、そこにアイデンティティを感じているのだ。
日本人は、「個人主義」でもなく、「集団主義」でもなく、「間人主義」の価値観に基づいて社会や組織に関わっている。人間は互いに依存しあって生きざるを得ないのだから、その関係を前提にして、自他を生かしていこうというのが、日本人の基本的価値観であり人間観であるといえる。そのためには、境界の感覚がきちんと拓かれている必要がある。
人との境界に対して持つこうした日本人の独特の価値観においては、人間関係の中に溶け込めなかったり、対人関係の軋轢に悩まされたり、人間関係の中で自己を見失う人も当然のことながら出てくるだろう。対人関係にこそ無条件の生きがいや幸福感を見出す日本人にとって、対人関係の問題は、すなわち自己の価値そのものに直結する問題となるからである。
西洋で生まれた心理学では、そのような人間関係の問題は、たとえば社会的スキルを身につけて解決しようと考える。つまり個人としての自己を確立することが重視されるため、相手を尊重しながら自己を主張するといった、対等で独立した個と個の関係を目指すことが主眼に置かれる。もちろんそのような技術を身につけることも、問題解決のための一助となるであろうが、日本人にとっては、本質は違うところにあるだろうと思う。』
以下は私の個人的考えです。
約29年間、外資系企業で働いた経験から感じる外国人と日本人の働き方の違いは、“合理性”の中身と重みの違いのように思います。外国人の”合理性”は、その中身はシンプルかつ俊敏でありビジネスの基本です。また、“責任”と表裏一体になっているように感じます。
一方、日本人の合理性は、その中に“人間関係がもたらす価値”が含まれており、外国人の協業が1+1=2であるのに対し、日本人の協業は1+1≧2というイメージです。そこにはポジティブな面だけでなく、表面には表れにくい“暗黙の奉仕”のようなものが混じってくる場合もあります。この協業モデルはスポーツの世界などでは、素晴らしい成果を産み出す原動力になるのですが、注意すべき点としては、“評価”と“責任”が分かりづらくなるというところです。特に、ビジネスの世界などでは、”暗黙の奉仕”に隠された不合理が、この章の表題である「なぜ日本人は対人関係に悩むのか」の原因の一つになってくる場合もあると思います。
境界が拓かれることで人は癒される
『私たちの多くは、心身の不調があると病院に行く。病院で検査をして、医者に治してもらおとする。その行為自体は何ら問題はない。しかし私たちは、病気や不調は医者に治してもらうものだと無意識に考え、そのような態度を当たり前のようにとってしまっていることから、次のような問題を抱えてしまうことになる。
第1は、身体が持つ自然治癒力の存在を忘れ、最終的には自分の身体が自ずと治っているのだという視点が抜け落ちてしまうことである。私たちは、医者の言う通りに服薬し、栄養さえ取っていればよいのだと信じ、受け身的に治してもらおうとする。しかし実際に治しているのは、紛れもなく自分の身体である。だから身体が持つ自然治癒力を発揮しやすいように、自分でも努力すべきだということを忘れがちである。
自然治癒力を働かせるためには、自分の身体の感覚に耳を傾け、身体が欲するようにしてあげることが重要だ。身体は常に快を求める「快の法則」があるから、まずは身体の感覚かとして心地よいことをするのがよいだろう。それはたとえば運動をすることだったり、触れるケアを受けることだったり、身体を温めることであったり、人それぞれだ。受け身の姿勢ではなく、不調をそれ以上悪化させずに、治癒を早めるためにも、そういった努力が大切だ。
第2は、特にこの章で主張したいことであり、第1の視点よりもさらに気づかれにくい点であるが、心身の不調は対人関係の中でこそ癒されるということである。どんな不調や病だったとしても、それを一人で抱え込むのではなく、人に言うだけでも、多少なりとも心が解放される。すると免疫力が高まり自律神経が整う結果、自然治癒力も高まる。第1章(「コミュニケーションする皮膚」)でも述べたように、困難に感じることでも、寄りそってくれる人がいるだけで、困難に感じなくなることもある。自分一人で辛苦と闘わなければならないと思うと、心が折れて生きる気力もなくなるかもしれない。しかし他者とともにいるだけで境界が拓かれ、他者の身体も自分のものであるかのごとく感じられ、病気や不調を治そうとするエネルギーが倍増するのだ。
もともと「癒し」という概念は、未開社会で呪術によって患者を治癒していた呪術医が、人々の病気を治す悪魔祓いの行為を指すものだという。
文化人類学の上田紀行は、癒しの意味について、次のように述べている。
「(癒しとは)なんらかの原因で、地域社会や共同体から、孤立してしまった人を再び、みんなの中に仲間として迎い入れること、そのための音楽や劇、踊りを交えて、霊的なネットワークのつながりを再構築すること(である)」(“覚醒ネットワーク”講談社プラスアルファ文庫)。
このように他者や社会と「つながること」こそが、病を癒すための重要なポイントだといえる。逆にいえば、周りにいる人は、そのような困難な状況にある人を決して孤立させてはならないのである。』
効果が実証された触れる癒しの技法
ユマニチュード
『ユマニチュードとは約35年前、体育学を専攻するフランス人、イヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティが作った認知症のケアの技法であり、日本でもテレビなどで紹介され、話題になっている。
ユマニチュードという言葉は、フランス領の植民地出身の黒人が「黒人らしさを取り戻そう」と始めた文化運動「ネグリチュード(黒人であること、黒人らしさ)を基に、人(ヒューマン、フランス語でユマン)とかけ合わせたものである。
ユマニチュードは「ケアする人とは何か」「人とは何か」という基本命題を根底に置いた、知覚・感覚・言語によるコミュニケーションを軸としたケアである。
その方法は、実に150以上の多岐にわたる細かい実践技術と同時に、その技法を支える「人とは何か」「ケアをする人とは何か」を問う哲学に裏付けされている点が興味深い。
ユマニチュードの哲学
ユマニチュードを導入すると、患者に劇的な変化が起こることから、何か特別な魔法のようなことをするのだろうか、と注目されることが多い。しかしそのような特別なことは行わない。ただ「人間らしさ」を尊重し続ける、つまり「個人として尊重する」ことを理念に置いて接するだけである。
ユマニチュードのケアの柱となるのは、「見る」「話す」「触れる」「立つ」ことによる援助である。
このうち、「触れる」というのは、本書の中心的なテーマであるため、少し詳しく述べたい。ユマニチュードでは、相手を人として尊重するために、触れる技術についても非常に細かく定められている。一例をあげると、相手の腕に触れて体を起こそうとするとき、相手の腕を上から「つかむ」のではなく、下から「支える」ようにして触れることを教える。あるいは、相手が動こうとする意志を慮りながらそれを援助する方向で支えるのである。上からつかもうとすると、どうしてもこちらの意思で、力ずくで相手をコントロールしているように感じられてしまうため、相手を尊重したことにならないのである。
さらには、相手の体に触れる瞬間、そして手を離す瞬間の手の角度にもルールがある。相手の体に垂直に触れると、触れられた相手にとっては少なからず衝撃を伴うからである。手を垂直に離す場合も同じだ。飛行機が離陸するときや着陸するときに、斜めの角度で離発着するように、手が触れる角度も斜めの角度が衝撃が少ないのだ。
また、「触れる」という動作も、単独で行ってはならない。私たちも人に触れられる際、事前に何もコミュニケーションせずに無言で触れられたとしたら、それは不気味な恐怖心さえ覚えるだろう。触れる際には、必ず事前に十分なコミュニケーションをとっておかなければならない。ユマニチュードでは、それはたとえば「見る」「話す」といった行為を十分に行って、境界としての皮膚の感覚を拓いてから「触れる」のでなければならないと教える。
ここまで読んでこられた方は、「当たり前だ」と思われるかもしれない。
しかしたとえば「見る」とはどのようなことをいうのか、考えたことはあるだろうか。私たちは普段、会話をする相手の姿や表情を見ることはあっても、きちんと目を「見つめる」ことは少ないのではないだろうか。看護師の方も、ユマニチュードで「見ることが大切だ」、と教えられると、「当たり前だ。患者のことはよく見ているよ」というような反応が多いという。しかし、それは患者の患部だけを見ていたり、病状や表情を一方的に見ている。あるいは監視しているといったように、観察しているのであって、心の交流を目指して見つめているのとは違うことが多いのではないだろうか。アイコンタクトというように、目を見つめて心の交流を起こすことは、まさに境界の感覚を解くスキンシップの大事な要素だと思う。』
『セラピューティック・ケア(Therapeutic Care)は、1996年英国赤十字社が開発した手技であり、もともとは病気で入院中の女性にとって、メーキャップなどをすることが回復の助けになるとのアイデアから生まれた。』
『1960年代、スウェーデンで未熟児のケアを担当していた看護師シーヴ・アーデビーやグニック・ビルシェスタッドらによって考案された触れるケアである。彼女らは母親に代わって、乳児の小さな体に毎日優しく触れたところ、子どもの体温は安定し、体重増加が見られるようになったという。そこで彼女らは触れることの有効性を確信し、経験に基づいてこの技法をつくったという。』
実は、以前マッサージと体重増加についてブログで記述したことがありました。ご参考までにブログリンクさせて頂きます。”医療マッサージ研究1”
マッサージからみる共振
『マッサージを受けるのは、どのような施術者でもよいわけではない。前述のように施術者と受け手との間に身体的な共振が起こり、身体レベルでの交流を起こしてくれるような施術者に触れてもらうことで、初めて効果が期待できる。
そのような意味で、単に技術が優れている施術者がよいということにはならない。受け手の境界を拓き、深い部分で身体を共振させ、その結果として心の変化も起こしてくれのが本物のマッサージ師だと思う。だから本当の意味での腕のある施術者は、優れた心理カウンセラーであるといえる。
それはあたかも、赤ん坊が母親の身体を、しがみつくことができ、体温で温めてくれて、両手で抱きしめてくれるものとして認識するのと似ている。他者に対して、境界を拓くことができず、他者の身体に対しても、「近づきたくない」「触れたくない」というような、不安定な愛着を持っている人でも、本物の施術者に触れられているうちに、身体レベルの共振が起こるようになる。そしてそれは温かい心の交流を生み、不安定だった愛着関係も、安定したものに変化していくだろう。
もう一つ、見逃してはならない視点がある。
前述のようにオキシトシンの高い施術者に触れられると、触れられた人のオキシトシンレベルも高まることがわかっている。このようにオキシトシンの分泌量が多く、かつエネルギーも強い施術者であればよいが、逆の関係になることもあるという。すなわち、受け手の「悪いもの」が施術者に移ってくるという現象である。受け手が「悪いもの」(それが何かは科学的に突き止められていないが)を持っており、なおかつエネルギーが強い場合に移ってくるのだろう。仮に共振といった現象が、単に神経学的な現象として起こるのだとしたら、それを防ぐ手立ては見込めない。しかし自律神経や運動神経、そしてオキシトシンといったホルモンもすべて、心と無関係に動いているわけではない。施術者の心の持ち方を変えることで、患者から「もらってしまう」ことを防ぐことができる。』
オキシトシンは”幸せホルモン”などと言われ、テレビの健康番組でもよく登場するキーワードの1つです。検索してみると、”「タッチケアで絆を育む」…安らぎの物質オキシトシン”という詳しい記事が見つかりました。
まとめ
1.安心される存在、そして信頼される存在になること。
2.施術の基本は、「見つめて、話して、そして触れる」。(”ユマニチュード”より)
3.触れ合いの原点とは、”体温”を守ること。
4.”オキシトシン”や”セロトニン”の活性化は、秒速5cm前後のソフトな軽擦で得られる。
5.豊富な”オキシトシン”で充足されるように、施術者が自らの生活習慣を見直すこと。
医療マッサージ研究2(脳のはたらき)
今回のブログは「医療マッサージ研究1」の続編になります。
最初に参考とさせて頂いた2冊の本についてお伝えします。

大変高度な内容である一方、外側膝状体という視覚の中継核に関し、外側膝状体背側核と外側膝状体腹側核という説明がされています。しかし、現在では『小細胞層と大細胞層の神経線維は、以前はUngerleider-Mishkinの腹側系と背側系に対応すると考えられていた。しかし、近年の研究では、2つの処理経路は両者の神経線維をともに含んでいることが示されている(ウィキペディアさまより)』との説に見直されており、情報が古いと判断させて頂きました。
まず、1章以降の大項目、中項目の目次をご紹介します。
1章 発達心理学における疑問と考え方
Ⅰ 発達をどう考えるか? ―疑問と論争
Ⅱ 発達の2つの要因
Ⅲ 子どもの年齢に関する概念
2章 認知発達を研究する方法
Ⅰ 行動を心理学的に研究するための科学的基準
Ⅱ データ収集の方法
Ⅲ 実験的アプローチ
3章 出生前の発達
Ⅰ 胎児の発達段階
Ⅱ 出生前の聴覚的学習
Ⅲ 胎児への母親の行動の影響
4章 運動の発達
Ⅰ 新生児の反射
Ⅱ 運動能力の発達
Ⅲ 利き手の発達
5章 知覚の発達
Ⅰ 視覚能力
Ⅱ 身体運動と視覚の協応 ―奥行き知覚
Ⅲ 聴覚能力
Ⅳ 味覚と嗅覚の発達
Ⅴ 皮膚感覚の発達
Ⅵ 複数の感覚モダリティの対応関係
6章 認知発達の理論
Ⅰ ピアジェの知能の発達理論
Ⅱ 情報処理的理論
Ⅲ コア知識理論
Ⅳ 表象書き換え理論
7章 モノの知識と因果関係
Ⅰ モノの永続性の再検討
Ⅱ 因果
8章 カテゴリー化
Ⅰ 乳幼児のカテゴリー化の研究
Ⅱ カテゴリー表象の性質とプロセス
9章 空間の認知
Ⅰ 空間の自己中心的符号化
Ⅱ 空間の客観的符号化の研究
Ⅲ 幾何学的手がかりと非幾何学的手がかりに対する乳幼児の感受性
10章 数の認知
Ⅰ 数の弁別
Ⅱ 乳幼児と計算
11章 記憶
Ⅰ 乳幼児の記憶研究の方法
Ⅱ 乳幼児の記憶の性質
Ⅲ 記憶の発達と幼児期健忘
12章 音声知覚から最初のことばへ
Ⅰ 言語と言語習慣の一般性
Ⅱ 音声カテゴリーの知覚とプロソディの知覚
Ⅲ 喃語から語彙の獲得へ
13章 終わりに
Ⅰ 早期発達の研究方法とその限界
Ⅱ 現在の認知発達の理論
ブログでは、3章Ⅰの「胎児の発達段階」と5章Ⅰの「視覚能力」について触れています。
胎児の発達段階
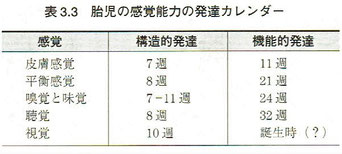
感覚の機能的発達では、「皮膚感覚」が11週と最も早く、「平衡感覚」、「嗅覚と味覚」と進みます。「聴覚」は構造的発達は8週と他の感覚と変わりませんが、機能的発達は32週とかなり遅くなります。さらに遅いのが「視覚」になります。
視覚能力
『長い間、小児科医や心理学者は、生まれたばかりの赤ちゃんは目が見えないと信じていました。実際には、赤ちゃんの視覚系は、誕生時には機能できる状態になっています。ただし、見えてはいますが、おとなと同じように機能しているわけではありません。たとえば、中心窩の細胞はまだ完全には成熟していません。細胞の密度は、生後1年半をかけて高くなってゆきます。こうした細胞の変化は、視力や形の知覚の発達に影響をおよぼします。新生児の瞳孔はかなり小さく、視覚を制御する脳の中枢もまだ十分には成熟していません。たとえば、生後1ヵ月の新生児では、脳の視覚野の大きさは相対的にまだ小さく、ほぼ完全になるまでに12ヵ月を要します。これらの要因は、視力、レンズ調節、両眼視の点で、新生児の視覚能力に影響を与えます。』
1.視力
・選好注視法という方法を用いると、生後4週ぐらいから測定することができる。
・生後1ヵ月児の視力はおとなの4分の1ほどで、その後急速に向上し8ヵ月にはほぼ完成する。
2.レンズ調節(焦点合わせ)
・乳児は、生後2ヵ月まではレンズ調節がほとんどできない。
・3ヵ月までは、21~24センチの距離に置かれたモノに焦点が合った状態にある。
・レンズ調節は生後6ヵ月までの間に急速にできるようになる。
3.両眼視
・新生児は単にモノの網膜像の大きさの変化に反応するのではなく、モノの実際の大きさの変化に反応している。
4.色の知覚
・色の知覚は生後1ヵ月までは貧弱であるが、その後急速に発達し、生後2~3ヵ月には、おとなと同様、青、黄や赤といった基本色を区別できるようになる。
5.動くモノの追視
・新生児は動くモノを目で追いかけることができる(およそ90度動く間)。
・新生児は静止しているモノを目で探すことができるが、視力がよくないので図の輪郭をなぞる程度になる。
新生児の視力について「こそだてハック」さまのサイトに分かりやすい情報がありましたのでご紹介させて頂きます。

『新生児は「目が見えていない」といわれることがありますが、まったく見えていないわけではありません。視力は0.01~0.02ほどで、「まぶしい」「暗い」といった明暗を認識することができます。色は黒・白・グレーのみで、ものや色、輪郭を認識するほどではなく、両目の焦点を定める能力も備わっていないことから、目的もなく眼球を動かしていることがほとんど。』
ブログのタイトルでもある「脳のはたらき(視・聴・運動)」については、「人体の正常構造と機能」、「感覚の地図帳」、「病気がみえる vol.7 脳・神経」を参考にしてまとめましたが、ほとんどが「人体の正常構造と機能」からの引用となっており、記述された内容は極めて専門的なものです。また、思っていた以上に長いブログになってしまいました。
そこで、最初に「まとめ」をお伝えしたいと思います。ご興味あれば、その下の内容をご覧ください。
まとめ
1.視覚は一次視覚野に加え、視覚前野、さらに側頭葉および頭頂葉の視覚連合野も関与しており、大脳皮質全体の1/3という大きな面積を占めると言われています。
2.患者さまは聴覚に問題はないとされていますので、隣接する視覚の伝導路である外側膝状体についても問題はないものと推測します。従いまして、視覚が機能していない原因は後頭葉視覚野が関係していると思われます。
3.患者さまは、眼、口、舌を随意に動かせますので、脳神経のⅢ動眼神経、Ⅳ滑車神経、Ⅵ外転神経、Ⅻ舌下神経、Ⅴ-3三叉神経(下顎神経)に関しては問題はないと思われます。
4.「医療マッサージ研究1」の中でお伝えした、「低反応だった患者さまの眼、口、舌の動きが活発化した」という変化は、触覚・固有覚・聴覚への刺激が脳幹への刺激となって伝わり、脳幹に存在する各脳神経核(Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅻ、Ⅴ-3)の働きが活性化したためではないかと思います。
1.目が見えるということ
眼球からの光(像)が脳神経の1つでもある視神経の線維を伝わり、[視交叉]-[視索]を経て脳幹の視床にある[外側膝状体]という中継核にたどり着きます。(左下図)
網膜の神経節細胞には大・小2型があり、大型のものが網膜の黄斑領域以外からの視覚情報を集めるほか、視覚対象の動きを外側膝状体(やはり大・小2型の神経細胞あり)の大型細胞(M細胞)に伝えます。小型神経節細胞は、視野中心近くにある静止したものの情報を、外側膝状体の小細胞(P細胞)に詳しく伝えます。外側膝状体は6層構造からなり、対側眼からの神経線維は1、4、6層に、同側眼からは2、3、5層に入ります。1層と2層だけは大型のニューロンからなる大細胞(M細胞)層であり、残りは全て小細胞(P細胞)層になっています。(右下図)
こうして網膜からの信号は、主に動きに関する情報を伝えるM経路と、詳細な形や色に関する情報を伝えるP経路とに分かれて中継され、視放線となって一次視覚野へ投射されます。(左下図)
一次視覚野は後頭葉の内側面で鳥距溝の上下にあります。視野の上半は鳥距溝の下縁へ、視野の下半は鳥距溝の上縁へ投射します。また、黄斑からの投射が後方の広い範囲を占めます。
上記以外の伝導路として、上丘から視床枕核に至る経路があり、眼球運動の制御に必要な情報を伝えます。また、一部は視床下部の視交叉上核に至り、概日リズムの形成に関与します。
なお、大脳皮質の中で視覚情報を主に処理する領域は全体の約1/3もの広い範囲を占めます。
この領域にあるニューロンの多くは、単純なスポット状の光にほとんど反応しません。
一次視覚野には特定の方向を向いた細長いスリット状の光に反応する単純型細胞や、スリット光が特定の方向に動くときに反応する複雑型細胞、特定の長さと方向を持つスリット光に反応する長複雑型細胞などが存在します。これらは視覚情報を線分の傾きや長さ、移動方向といった要素に分解し、物体の輪郭を抽出していると考えられます。
一次視覚野では、同じ方向の刺激に選択性を持つ単純型細胞や複雑型細胞が集まって垂直方向の機能単位を形成します。これを方位コラムといいます。隣り合うコラムは、視野上の同じ位置で約10°異なる方位選択性を持つ細胞群からなっています。方位コラムの列とほぼ直交する向きに皮質をたどっていくと、1つのコラムは主に一側の眼から入力を受け、その隣のコラムは視野上の位置は同じですが主に対側の眼から入力を受けています。これを眼優位コラムといいます。
一次視覚野の約1㎟の部分には全方位をカバーする18の方位コラムが2セット含まれ、それぞれ右眼優位と左眼優位です。この1㎟の部分は、視野のある1点を分析するのに十分な要素を持つことから超コラムと呼ばれます。また、超コラムの中にブロッブblobと呼ばれる斑状の細胞集団が存在し、それらは色に選択性を持ちます。逆に単純型細胞や複雑型細胞は色選択性がありません。したがって色情報は、形や動きの情報とは別途に分析されています。
超コラムで抽出された視覚情報は、一次視覚野の前方に位置する視覚前野においてさらに詳細に分析されたのち、側頭葉および頭頂葉の視覚連合野へ送られます。側頭連合野は形や色の情報を統合して物体認知を行い、頭頂連合野は動きや奥行きの情報に基づいて空間認知を行います。それらの部位に障害を受けると、色覚を失う、立体感を失う、動きの認識ができない、などの特異な症状が現れます。
以上のように一次視覚野は、構造も機能も非常に複雑です。色情報と形や動きの情報は分かれており、視覚情報は一次視覚野前方の視覚前野において分析が進み、さらに側頭葉および頭頂葉の視覚連合野に送られます。まさに大脳皮質の1/3を使って視覚の働きを支えています。
2.耳が聞こえるということ
右下は外耳・中耳・内耳の図です。聴覚の受容器であるコルチ器は蝸牛管の中にあり、コルチ器には蝸牛神経が分布しています。蝸牛神経は平衝覚をつかさどる前庭神経と内耳道底で合流し、内耳神経(脳神経Ⅷ)となり、中枢に向います。
聴覚の伝導路には側副経路もあります。蝸牛神経核からの出力の一部は延髄上部の同側および対側の上オリーブ核に投射されます。なお、上オリーブ核では音源の方向に関する情報を抽出して上位中枢に送っています。一般的な経路は外側毛帯を通って下丘に至ります。下丘は最初の統合的処理を行う神経核で、側副路を含め上行性投射はすべて下丘を経由します。下丘ニューロンは内側膝状体に、内側膝状体ニューロンは聴放線を通って聴覚野に投射されます。(左下図)
下図は脳幹を横から見たものです。脳幹は下(体側)から延髄-橋-中脳となります。中脳の背側面には上丘・下丘という隆起があり、それぞれ内部に神経核を有しています。上丘は視覚の視床核とされる外側膝状体に続き、下丘は聴覚の内側膝状体に続きます。
3.視床と大脳皮質
こちらは視床核を詳細に説明したものです。
外側膝状体はLG(lateral geniculate body)となっており、右側の図の下部に見られる小さな2つの突起のうちの右側(緑色)の部分になります。一方、内側膝状体はMG(medial geniculate body)となっており、左側(茶色)の突起になります。
下の表は視床核の機能的区分を示すものです。LG(外側膝状体)の出力先は「後頭葉視覚野」になっており、MG(内側膝状体)の出力先は「側頭葉聴覚野」となっています。
下記のブロードマンの脳地図では側頭葉聴覚野は【41・42】と狭い領域です。一方、後頭葉視覚野は一次視覚野(V1)が【17】、二次視覚野(V2)が【18】、視覚連合野(V3)が【19】となり、視覚野の方が聴覚野に比べ明らかに広い面積を取っています。詳細な情報はウィキペディアさまにありました。
下の図を見ると視床が大脳へと繋がる中継核のかたまりなっていることがよく分かります。(この図の中では、MG[内側膝状体]から側頭回へのラインがありませんが、これはラインがクロスしてしまうため省略されているのではないでしょうか)
以上、視床核である外側膝状体と内側膝状体について詳しく見てきました。ここでお伝えしたかったことは、視覚の中継核である外側膝状体と聴覚の中継核である内側膝状体は、近接して存在しているということです。
4.眼・口・舌が動くということ
左下図は濃い緑色の皮質脊髄路と黄緑色の皮質延髄路を示したものです。前者は大脳皮質から脊髄に投射する神経細胞の軸索がまとまって線維束を形成した脳内最大の下行路(遠心性)で、大脳皮質からの運動指令を脊髄に伝えます。後者の皮質延髄路は頭や顔の運動指令を伝える経路で、各脳神経の運動核に至ります。
図を見ると、中脳ではⅢ、Ⅳ、橋ではⅤ、Ⅵ、Ⅶ、延髄上部ではⅨ、Ⅹ、Ⅻ、延髄下部ではⅪの各脳神経が口や顔面などに向かいます。
右下図は脳幹をお腹側から見た図です。この図では中脳より上に位置するⅠ嗅神経、Ⅱ視神経を含め、12対の脳神経を確認できます。
12対の脳神経は運動だけでなく感覚や自律(副交感)にも関わっており、複数の機能を持つ脳神経もあります。
右下の表は脳神経の詳細を説明したものです。薄茶色の特殊感覚神経は感覚に関する脳神経で、視覚はⅡ、聴覚はⅧなります。続いて薄緑色の体性運動神経はⅢ動眼神経、Ⅳ滑車神経、Ⅵ外転神経の3つが眼球を動かすために筋肉へ指令を出します。また、Ⅻの舌下神経は舌を動かします。薄紫色の鰓弓神経の中のⅤ三叉神経は眼神経、上顎神経、下顎神経に分かれますが下顎神経は口を動かす咀嚼筋に指令をだします。
左下図は「脳神経」の概要説明です。分かりやすいので添付させて頂きました。
医療マッサージ研究1
乳児期に起きた事故によって重症障害者となり、現在、青年期を迎えている患者さまにマッサージを行っています。スタートは2017年4月、頻度は週2回です。開始から15ヶ月が経ち3つの変化がありました。これらがマッサージの効果であるとは断言できませんが、関係しているものと思います。なお、施術では次のことを心掛けています。
◆無理をせず、安全第一(特に他動による関節運動)。
◆脳幹への感覚刺激入力として、声かけ(聴覚)、擦る・圧迫する(触覚)、各関節の他動運動(固有覚)という3つの感覚刺激が関連づけられて脳幹に届くことをイメージしています。乳児期の障害だったため言葉は理解できないと認識していますが、何度も何度も繰返すことで、何かが変わることを期待し、声かけでは「部位」と「動作」を伝えています。(例えば、「肩を動かすよー、前…後…。」とか、「腕をさするよー。腕を握るよー。等々)
◆免疫力アップを狙って、肩関節の他動運動では腋窩リンパ節、股関節では鼡径リンパ節への刺激を意識しています。
3つの変化
1.健康アップ(免疫力アップ)
2017年4月から9月までの6ヶ月間は、入院を含め、発熱等による体調不良のため施術が休みとなることが多く、予定通り実施できたのは約58%でした。一方、2017年10月以降、2018年6月までの9ヶ月間に関しては、体調不良により休みとなったケースはありませんでした。
2.体重増
施術の最初に側臥位の向きを変えてから始めるのですが、数ヶ月前から体を抱えたときの腕への負荷が明らかに高まったように感じました。ご家族の方も同様な認識であり、体重増は間違いないと思います。しかし、この患者さまにとって体重増加が良いことなのか把握できていません。基本的には健康度の指標となる各種検査値や栄養管理、あるいは衛生管理などの面から総合的に評価するべきものではないかと思います。

左の資料、「重症心身障害児の栄養管理」はJ-Stageさまからのものです。
『栄養摂取量に関してはこれまでさまざまな方法が提唱されているが確立された方法はない。我々は麻痺のタイプや筋緊張の変動の状態、呼吸状態などの臨床所見を参考に、年齢別体重当たり基礎代謝量の1~2倍程度の範囲に当面の総エネルギー量を設定し、その後の栄養評価を反復して行って、エネルギー摂取量を調節していく方法が実際的であると考えている。』
3.顔の反応(目、口、舌、頭、笑う、息む)
最も印象的なことはこの3番目です。施術を始めた頃に印象的だった反応は、「ニコッ―と笑う」、「う~う~と息む」の2つであり、全体的には低反応な感じでした。
日報を見返すと2017年12月頃からになるのですが、顔の表情、顔の動きや反応に変化が表れてきました。長く施術をしていることから、思い入れや期待が強すぎる部分はあるかもしれません。
目:以前は虚ろな目の印象が多かったのですが、動きがスローなのはほとんど変わらないものの、動く頻度が多くなり、勢いというか生気というか、何かを感じているような雰囲気が出てきているように思います。また、瞬きする回数も増えたと思います。
口:いくつかのパターンがあります。「口を縦に開ける」、「口を最大限に開ける」、「少し緊張したように口をやや突き出すようにすぼめる」、「何かを噛むかのように、下顎を小さく上下に動かす」。これらの反応の発生頻度は徐々に変化してきています。
舌:こちらもいくつかのパターンがあります。「舌を口の中で動かす」、「舌を少し出す」、「舌をべローンと大きく突き出す」、「舌を上歯の裏に当てるようにして、チュッ、チュッと音を出す」。
頭:以前は十分な観察ができていなかったので、何とも言えないのですが、少なくとも最近は目の動きと連動するように、動かす頻度が多くなっているような気がします。
笑う:笑うことは以前から見られましたが、少し変化があります。まずは、「嬉しそうな表情」という中間的なものも見られることです。また、笑う頻度が多くなったようと思います。笑い声が出るときは、「アー」という感じでしたが、最近は時々「ハハハ」という笑い方をすることが多くなっているように思います。
息む:息みもマッサージを始めた頃から頻繁に見られた反応です。かなり大きな声を出し長い時間息んでいるので最初は驚きました。マッサージが痛いのか、不快なのか、何かネガティブな反応ではないかと心配しましたが、どうもそういう事ではなさそうです。
今回、あらためて調べてみると興味深い資料がネット上に存在するのを見つけました。なお、こちらは「窪谷産婦人科」さまのホームページからになります。

9ページに、「1ヵ月を過ぎた赤ちゃんのうなり、いきみは肺が圧迫された状態であり、まだ深呼吸ができないため、うなったり、いきんだりする。」との内容が書かれています。
「生後1ヵ月」には該当しませんが、肺が圧迫された状態、深呼吸できない状態という意味では患者さまも同様です。確かに、患者さまの長い息みの後に、肺に空気がスーッと入っていく様子が確認できます。また、この行為が深呼吸の代わりだとすると、この行為には肩の力を抜いたり(リラックス)、あるいはストレス解消の効果もあるのかもしれません。
注)2024年6月9日時点では削除されていました。
次に顔の反応、特に口と舌の頻繁な動きは何なのだろうと考えてみました。そして、この患者さまの障害が乳児の時だったことを考えると、そして、仮に患者さまの時計(脳の発達)がその時から大きく進んでいないとすると、これらの仕草は赤ちゃんが見せるものではないかと思うに至り、ネット検索してみました。
そこで、特に気になったものは次のようなものでした。
◆『赤ちゃんはまだ自分の意志で自由に動かせるところが少ないので、動かせる舌などを動かして「確認している」と本で読みました。』
◆『赤ちゃんは、成長過程で舌を出す仕草をすることがあります。生まれてからしばらくは舌を上手に動かすことができませんが、成長とともに徐々に動かせるようになり、舌を動かすのが楽しくなるので頻繁に出しますよ。』
なお、赤ちゃんの舌出しについては下記のサイトに詳しく出ていました。
このような赤ちゃんの仕草も、「脳」が大きく関わっていることは明らかなので、「脳」と「赤ちゃんの仕草」の関係が知りたくなり1冊の本を購入しました。

『本書では、全ての大人が必ず通過する赤ちゃん時代の「不思議」について、脳科学・認知科学における最新の研究成果を参照しながら紹介するとともに、目まぐるしく変化する赤ちゃんの養育環境が発達とどう関連するのかについて論考していきます。』
出版:岩波新書
大変興味深い内容だったのですが、期待していたイメージの本ではありませんでした。しかしながら、赤ちゃんの成長にとって、「目が見えること」、視覚が極めて重要だということを再認識しました(この本に出てくる各種テストのほとんどは、目が見えていることが前提となっていました)。
患者さまは口や舌を動かすことはできます。目(眼球)を動かすこともできます。そして、耳も聞こえています。しかしながら、見ることはできません。眼球自体に問題がないとすれば、脳が関係しているのは明らかです。では、「何が、どこが悪いからなんだろう?」、「医学が革新的に進歩したならばどうなんだろう?」。この疑問を前に進めたいという気持から、2冊の本を借りることにしました。
1.『脳と視覚 -何をどう見るか-』
2.『乳幼児の発達 -運動・知覚・認知-』
なお、ブログについては【続く】ということにさせて頂きたいと思います。
感覚過敏・感覚刺激
昨日、お電話で感覚過敏に関するご質問を頂きました。そこで、情報の整理整頓を目的に「感覚過敏」「感覚刺激」「マッサージ」をキーワードを洗い出してみました。その結果、あらためてお伝えしたいポイントは次の2点になります。また、今回洗い出した内容も列挙させて頂きます。
1.視覚や聴覚に加え、基本的な感覚ともいうべき触覚、固有覚、前庭覚の働きと様々な感覚間の情報統合が、子どもたちの発達の基礎となる。
2.自宅でできる対策として「五感のバランスのための乾布摩擦」がお勧めである。
感覚過敏は発達全体に影響を及ぼす可能性をもっている
自閉症と感覚過敏
・感覚過敏とは、最近になって自閉症に一般に認められるものとなった症状です。感覚が非常に敏感になっている状態で、刺激を恐れる場合と求める場合があります。たとえば、嫌な音を恐れて耳をふさいだり、音のする部屋に入らなかったりします。また、水路を見つめ小石を落とす行為をいつまでも続けたり、ビデオの同じ箇所を何度も見続けたりします。感覚過敏は視覚や聴覚など、あらゆる感覚に現れ、また、敏感性としてだけでなく鈍感性としても現れる、非常に多様な側面をもつ症状です。
・感覚過敏があると、刺激に対する反応が大きくなり、好きな物は非常に好んで求め、嫌いな物は恐れて避けるようになります。そのため、外界の捉え方が通常とは異なり、行動の仕方も通常と異なってくると考えらえます。このため、人々と共に生活することや学ぶことが難しくなってきます。ことばを学び、人々とコミュニケーションができないと、社会に参加することができなくなります。このように、感覚過敏は発達全体に影響を及ぼす可能性をもっています。
五感のバランスのための乾布摩擦(皮膚刺激で五感の感受性のバランスがよくなる)
発達障害児の言語獲得
乾布摩擦について
・遅れてことばが発達する子どもに共通して、感覚器官のダイナミズムに大きな変化があります。赤ちゃん時代からずっと口は飲む、食べるだけしかしていません。それ以外は泣き声だけで、自分の声を意識していません。少しことばが出はじめると、口の中の感覚が大きく変わりはじめます。同時に、聴覚や視覚にも変化が生じ、耳ふさぎや眼球擦りなどが生じることがあります。赤ちゃんはだれでも、五感の感受性にアンバランスがあり、たくさんの皮膚刺激で、五歳までにバランスがよくなります。
通常、聴覚優位なので、人の話を聞くだけでことばの学習が進みます。優位性がさらに過剰だと、耳ふさぎを示します。皮膚刺激の過敏、鈍感、味覚や嗅覚にこだわりや偏りを示す子もいます。
五感のバランスのために、乾布摩擦をして下さい。全身、朝、晩、服の着換えの時に、擦ってやってください。健康増進のためではなく、五感のバランスのための乾布摩擦なので子どもの顔を見ながら気持ちよさそうな表情を手がかりに、最適な擦り方を見つけてください。頭から足の裏まで、指の一本一本まで、嫌がる所はアンタッチャブルゾーンとして擦らないように、その境界線は特に丁寧に擦っていると、ゾーンは縮小していくはずです。消えるまで朝晩続けていると、ゆっくりと五感のバランスがよくなるはずです。
触覚敏感性問題の対策
自閉症の脳を読み解く
・じわじわと圧力をかけると触角が鈍くなることがある。マッサージは、思いやりを教える役にも立つ。自閉症の人のほとんどが、加重ベストを着たり、重いクッションの下にもぐりこんだり、しっかりマッサージを受けたりして、触覚を鈍らせると、ハグされることに耐えられるようになる。
・ちくちく、ヒリヒリする衣類に対する感受性を鈍くするのは困難だが、新しい衣類はすべて、肌に触れる前に何回か洗濯する。タグは全部取り除く。下着を裏返しに着る(継ぎ目が肌に触れないように)。
・診察に対する敏感性は、ときには、診察で触れられる部分にじわじわと圧力をかけると、鈍くすることができる。
ボディイメージを育てるためには触覚と固有受容覚が特に重要である。
発達障害について(発達障害の子どもたち)
・ボディイメージを育てるためには触覚と固有受容覚が特に重要になります。いわばボディイメージを育てる栄養です。もちろん、マッサージなどで他動的に触覚や固有受容覚を刺激することは効果的かもしれません。ただし、ボディイメージを高めるためには、能動的体験の中で触覚、固有受容覚を体験することも必要です。お風呂の中では、お湯の抵抗がありますので、身体を動かすと触 覚と固有受容覚のフィードバックがあるために身体を意識しやすくなります。同じ理由からスイミングもいいと思います。アスレチック遊具とかクライミングウォールにチャレンジすることもお勧めです。要は能動的に触覚刺激や固有受容刺激を感じて動きを作り出すことが大切なんです。しかも、いつもやらないような未経験の運動をやったほうがボディイメージは育ちやすいと思います。
・マッサージ:ブラシや素手でマッサージして、だんだんと感覚を受け入れられるようにします。治療者との関係を作ってから、「こうやって触れられれば、こういう感覚が入ってくるのだ」と覚えていってもらいます。身体の中では背中が受け入れやすい場所ですので、そこからマッサージを始めます。腹部、首、顔などは過敏反応が出やすいので、最初はやりません。マッサージはまず受け入れられる部分だけ行ったほうが良いでしょう。
体の内側に入る感覚刺激が足りないから、感覚を入れたい
療育
・多動といわれる状態は、動きたいという身体の内側にある感覚的な欲求が働いていることが原因の一つといわれています。「お腹がすいてご飯を食べたい」という生理的な欲求と似ていて、「体の内側に入る感覚刺激が足りないから、感覚を入れたい」という行動です。私たちが、窮屈な乗り物に長い時間乗っていると動きたいという気持ちにかられますが、それに似ています。
体の内側に感じる感覚は「固有覚」(筋肉や関節に感じる感覚)と「前庭感覚」(体の傾きや動いているスピードを感じる感覚)があります。どちらも感じにくいと跳びたくなったり、走りたくなったり、回転したくなったりします。ですから、我慢させすぎることのないように、内的な感覚欲求を満たしてあげることを考えましょう。
外遊びで、跳びはねたり、回ったりするといった遊びが少ない現代、この内的な感覚が足りないことと、子どもたちの行動に落ち着きがないと感じることは関係が深いと考えられます。
感覚間の情報統合が子どもたちの発達の基礎となる
感覚統合法の理論と実践
赤ちゃんは当初は生まれつき持っている反射や反応が助けてくれますが、徐々に感覚運動体験を積み、この多様性に富む複雑な世界に対し、柔軟に行動できるよう、自らの反応を複雑化していきます。赤ちゃんの学習は感覚刺激への反応に始まり、動きの形で反応し、母親やその他の人々も含めた広い意味での環境との相互作用で成長します。基盤となる感覚運動発達は、姿勢、手指の巧緻運動と各部位(首、肩、肘など)の固定、感覚-運動-感覚間の統合(話を聞きながらノートに正しく書き取る等の総合的動作)などです。
脳の研究やリハビリテーション学の進歩により、視覚や聴覚に加え、基本的な感覚ともいうべき触覚、固有覚、前庭覚の働きと様々な感覚間の情報統合が、子どもたちの発達の基礎となることが分かってきました。
動物が運動する場合、運動に関連して常に二つの感覚が必要です。一つは環境と自分との関係、一つは自分の中心と体の他の各部分との関係を教える感覚です。前者が前庭覚、後者が固有覚であり、これにより空間の中での運動が可能になります。
50cm幅の溝を跳び越すとき、大げさに身構えて、1mも2mも跳ぶということはしません。視覚は溝の幅と接地点の状況を教え、足底は今踏んでいる地面の硬さを教えます。私たちは前庭覚や固有覚などから得た記録に基づき運動の計画を立て実行します。もし、この溝が2mであれば、運動はもっと慎重に計画されます。接地したときに、倒れないのは重力空間に対する頭部の位置関係、その位置を支える足の頭部に対する位置と運動の関係が入力により絶えずコントロールされているからです。
・運動活動を通して経験される固有感覚は、触覚とも関連しながら、子どもの筋緊張を適正にするとともに、興奮を鎮め、触覚の敏感性を低減します。したがって、固有感覚刺激は、覚醒水準が高く多動性を示す子どもに対しても、反対に注意機能が低下して寡動な子どもに対しても、必須な感覚刺激といえます。
発達障害児では、感覚の基本的な調節作用がうまく働いていないことが多く、感覚入力に非常に敏感であったり、逆に鈍感であったりします。その結果、覚醒水準の障害や注意の障害、あるいは多動や寡動などの動きの問題が目立ちます。
脳性麻痺リハビリテーションガイド
訪問の仕事(業務委託)は鍼灸とマッサージが半々というところですが、マッサージについては小児障害、特に脳性マヒの患者さまが増えています。
一方、特に発達障害児へのマッサージを考える際に勉強した「新・感覚統合法の理論と実践」では、そのブログの中で、マッサージのポイントを次のようにまとめました。
1.人は最も大きな刺激源であり、人に対する感情によって、刺激の感じ方もずいぶん違ってくると言われています。従って、子どもとの信頼関係を築くことが第一歩です。
2.触覚防衛反応などの感覚調整の障害については、「感覚調整機能評価表」を利用し、触覚系と前庭-固有覚系の過反応と低反応の実態を把握します。
3.筋緊張の強い子には、抑制的な触圧の刺激などにより、緊張部位のリラクセーションをはかり、屈筋群と伸筋群の拮抗をバランスよく保ち、筋肉の柔軟性を高めます。
4.筋緊張の低い子には、促通的な触圧の刺激などにより、屈筋群の活性化をはかります。また、関節への抵抗運動により筋緊張を高めるとともに拘縮を予防します。
5.ボディイメージが弱い子には、関節の抵抗運動により、それぞれの筋肉の動かし方を繰り返し学習します。
この中で3~5の筋の低緊張、過緊張およびボディイメージの弱さに関する改善は、脳性マヒ患者さまにも当てはまるものと考えています。しかしながら、本当にそうなのか、注意すべきは何なのかを把握するため、図書館から「脳性麻痺リハビリテーションガイド第2版」を借用し、第6章の運動障害と治療(リハビリテーション)を中心に、その内容を確認しました。
以下の表が、確認した内容をまとめたものです。結論としては、脳性マヒ患者さまの筋の緊張状態やボディイメージを改善することは、推奨グレードAおよびBの漸増負荷トレーニング・サーキットトレーニング(筋力トレーニング)、有酸素トレーニング、歩行訓練、それぞれの効果を高めるための土台作り(筋肉、関節などの運動器系の状態を良くすること)として間接的に貢献することができる。ということだと考えています。
また、順序が逆になりましたが、「ガイドライン」がどのようなものかについてご紹介させて頂きます。
目的
本ガイドライン策定の目的は、最新のエビデンスに基づき、わが国で推奨される標準的な脳性麻痺リハビリテーションの診療方針を提示するとともに、将来に向けてあるべき理想の診療方法を明らかにすることである。
本ガイドライン策定に関しては、脳性麻痺の疾患特性を考慮し、医学的観点のみならず、脳性麻痺患者のライフサイクル全般にわたる問題点(家族支援、成人期の問題、就学と社会参加など)も含め、より包括的なリサーチクエスチョンで全体を構成するように努めた。
読者対象
脳性麻痺リハビリテーション診療に関る、すべての医療・福祉従事者はもとより、患者本人とそのご家族、学校教育関係者にも、広く利用されることを想定して作成した。
また、ガイドラインには「推奨グレード」の他に「エビデンスレベル」という観点からも考察されています。ブログでは分かりやすさを優先し「推奨グレード」一本に絞りましたが、ご参考として「エビデンスレベル」の内容をご紹介させて頂きます。
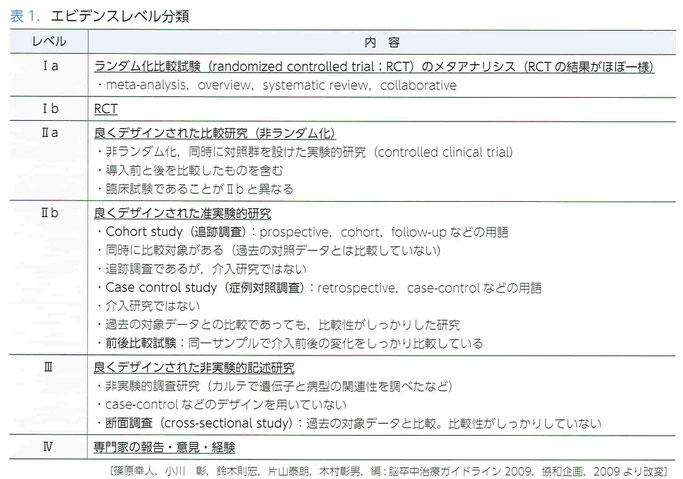
今回のブログの中で、私自身は「脳性麻痺」ではなく「脳性マヒ」という言葉を用いています。その理由に関してはブログ(「脳性麻痺 vs 脳性マヒ」)を参照頂ければと思いますが、ポイントは成瀬悟策先生の著書「姿勢のふしぎ」という本に出ていた次の一文に基づいています。
『脳の病変によって肢体が不自由になる現象を、本書ではここまで「脳性麻痺」ではなく一貫して「脳性マヒ」と表記してきたのは、一般に「麻痺」ということばが「神経や筋の機能が停止する状態」(広辞苑)とされているためでした。これまで述べてきたように、この子たちのからだは病理学的に動かないのではなく、生理的には動く自分のからだを、その主体者が自分の思うように動かせないだけですから、「麻痺」ということばはそぐわないため用いません。』
療育-ほめ方・しかり方・言葉かけ
発達障害児に対し、潜在的な部分まで幅広く理解できることは大切です。一方、現場では、その時、その場で、その子に対し、もっとも適切な1番・2番を直感的に選択し、行動することが求められるのだろうと思います。また、これが「療育」のポイントではないかと思います。
11月に「はじめての療育」という本で勉強させて頂きましたが、咄嗟の判断ができるレベルはまだまだ先にあり、自信に満ちた対応、実践力を磨いていかないといけないなぁと思っていました。
そこで、まずは図書館より、今回の「発達障害の子どもが伸びる ほめ方・しかり方・言葉かけ」という本を借りることにしました。A4サイズと大きめで、111ページと手頃なボリュームであり、「これはいいね!」という印象でした。
amazonでは似たような内容の本を数多く紹介してくれるので、良くも悪くも迷ってしまうのですが、この本にはあまり安いものはなく、また、カスタマレビューが全くありませんでした。
ちょっとに気になり他の本もチェックしたのですが、最終的にこの本を手元に置いておきたいという気持になりました。
特に、内容紹介に出ていた「発達障害の子どもは、どんな言葉をかけてあげれば喜び、自信を持ち育つことができるのかを、シミュレーション。」とあったのが、決めたポイントです。というのは、過去ブログの「ありがとう ヘンリー」の中で、発達障害児にとって極めて大切なことは「自信と自尊心」であるということを頭にたたき込まれていたためでした。
なお、ブログは土台になると思われる第1章~3章について触れています。

監修:塩川宏郷
出版:河出書房新社
第1章 発達障害ってどんな障害なの?
『発達障害とは、言語・コミュニケーション・社会性などの発達になんらかの特性(偏りやゆがみ)があることによって生じる不適応状態をさします。生まれながらの(生来的な)脳機能障害と考えられており、個人によりその特性の強さが違います。最近では「障害」ではなく、本人の「個性」としてとらえることで、その特性を伸ばす方法が模索され、さまざまな支援が行われるようになってきています。』
発達障害は、大きく3つのタイプに分けられる
●精神遅滞(知的障害)
全般的な知的機能の発達の停滞をさします。
●自閉症スペクトラム障害(ASD)
ASDには自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害が含まれます。ASDの典型的な特性としては、「社会的な対人関係を築きにくい」、「コミュニケーションがとりにくい」、「こだわりが強い」という、広汎性発達障害の3つの特性が認められます。
●特異的発達障害
知的能力に全般的な遅れはないものの、「読む」「聞く」「話す」「書く」「計算する」「推論する」などの学習と関連する部分的な能力や機能で著しい遅れ見られるのが特徴です。読み、書き、計算など学習能力の習得に時間がかかるLD(学習障害)や、集中力がなく、衝動的で落ち着きや注意力がないADHD(注意欠如/多動性障害)も特異的発達障害に含まれます。
これらは、重なり合う部分が多くあり、また2つ以上の機能障害を併存している場合もあります。
発達特性は2~3歳ごろから見られ始める
子どもの発達は個人差が大きく、人によって発達特性が目立ってくる時期も違ってきます。自閉症スペクトラムは、典型的な子どもの場合2~3歳ぐらいで特性が見られるようになります。もっとも分かりやすいのは言葉の遅れです。アーウーといった声(喃語)は出しても、パパ、ママといった意味ある単語などが出てこない、指をさして教えないなどといった言動が特徴です。一方、ADHDの特性は5歳ぐらいから強くあらわれてきます。
発達障害の診断が確定的となるのは3~4歳ごろが一般的です。それまでの発達の経過は個人差が大きく、健常と病的な区別をつけることは困難です。従いまして、確定診断は急がず3歳を過ぎてから考えるのが妥当です。
自閉症スペクトラム(ASD)の基本的な3つの特性
1.人との関わり方が苦手(社会的なやり取りの障害)
・人と目を合わせない
・名前を呼ばれても反応しない
・相手や状況に合わせた行動が苦手(マイペースな対人行動)
・自己主張が強く一方的な行動が目立つ
2.コミュニケーションがうまくとれない(コミュニケーションの障害)
・言葉の遅れ
・言われた言葉をそのまま繰り返す(オウム返し)
・相手の表情から気持ちを読み取れない
・ことわざや、皮肉、たとえ話を理解することが苦手
3.想像力が乏しい・こだわりがある(こだわり行動)
・言われたことを定義通りに受け取りやすい
・「ままごと遊び」「役割遊び」をあまりしない
・決まった順序や道順にこだわる
・急に予定が変わるとパニックをおこす
ADHDの基本的な3つの特性
1.不注意
・モノをよくなくす
・細かいことに気がつかない
・忘れ物が多い
・話し声や教室外の音が気になって集中できない
・整理整頓が苦手
2.衝動性(よく考えずに行動する)
・順番を待てない
・先生にあてられる前に答える
・他の児童に干渉する
3.多動性(落ち着きがない)
・じっとしていられない
・授業中も席を立ってウロウロする
・静かに遊んだり、読書をしたりすることが苦手
・手や足を動かしそわそわしている
・授業中でも物音をたてたりする
LDの基本的な特性は6つの学習能力の問題
1.「聞く」ことの障害
・会話が理解できない
・文章の聞き取りができない
・書き取りが苦手
・単語や言葉の聞き誤りが多い
・長い話しを理解するのが苦手
・長い話しに集中できない
・言葉の復唱ができない
2.「話す」ことの障害
・筋道を立てて話すことが苦手
・文章として話すことが苦手
・話しに余分な内容が入ってしまう
・同じ内容を違う言い回しで話せない
・話が回りくどく、結論までいかない
3.「計算する」ことの障害
・数字の位どりが理解できない
・繰り上がり、繰り下がりが理解できない
・九九を暗記しても計算に使えない
・暗算ができない
4.「推論する」ことの障害
・算数の応用問題・証明問題・図形問題が苦手
・因果関係の理解・説明が苦手
・長文読解が苦手
・直接示されていないことを推測することが苦手
5.「読む」ことの障害
・文字を発音できない
・間違った発音をする
・単語を発音できない
・文字や単語を抜かいして読む
・読むのが遅い
・文章の音読はできるが、意味が理解できない
6.「書く」ことの障害
・文字が書けない
・誤った文字を書く
・漢字の部首を間違う
・単語が書けない、誤った文字が混じる
・単純な文章しか書けない
・文法的な誤りが多い(「てにをは」の誤りが多い)
早めに気づいて、早めに支援を考える
発達障害は、3~5歳ぐらいまではなかなか確定診断できないといわれています。しかし、その特性の一部は赤ちゃんのうちからあらわれてくることが少なくありません。できるだけ早く特性に気づいてあげることが重要です。
こんな赤ちゃんの反応を見逃さないで
『発達障害の場合、顕著にあらわれていなくても赤ちゃんは生まれながらに特性を持っています。赤ちゃんの様子や反応を注意深く観察しましょう。
自閉症児を持つ母親などに赤ちゃんのときの状態を聞くと「人見知りをしない子だった」「夜泣きをしない子だった」というように「手のかからない子だった」という声が少なくありません。反対に「いくらあやしても泣き止まなかった」とか「特定のおもちゃしか興味を持たなかった」という「困った子だった」という声もあります。
発達障害の特性は、その子どもの個性でもあるので、あらわれ方は子どもによってそれぞれ違ってきます。しかし、いくつかの傾向があります。もし、子どもの動向が気になったら、なるべく早めに保健所や病院に相談しましょう。』
3歳を過ぎたら「かんしゃく」に注意
『3歳を過ぎたころになると、自閉症スペクトラムの特性を持っている子どもは、しばしば急に奇声を発したり、自分の腕をかんだり、自分の頭を壁に打ちつけたりすることがあります。「かんしゃく」や「パニック」と呼ばれる行動です。こうした行動には子どもなりの理由があります。
自閉症スペクトラムの子どもには「感覚の過敏性」があるといわれています。これは、身の回りの音や光が非常に強く感じられたり、温度やにおいという感覚について私たちとは違う感じ方をしたりいている状態をいいます。
感覚の過敏性を持っている子どもたちは、私たちが体験している世界とはまったく違った感覚の世界に住んでいると考えてみましょう。そしてその世界はしばしば不安や緊張に満ちあふれた世界なのです。また、他人の話している言葉が理解できず、相手の表情がなにを意味しているのかを読み取れないという状態も「特性」の一つです。ちょうど私たちが外国にたったひとりで放り出された状態を想像してみるとわかりやすいでしょう。
このような状況で、自分が対処しきれないできごとが発生してしまったときや、不安や恐怖を強める刺激が加わったときにパニックやかんしゃくが起こります。つまり、パニックやかんしゃくは不安や恐怖が自分ではどうすることもできない極限に達してしまっている、誰か助けてほしい、というサインなのです。
したがって、パニックやかんしゃくそのものを止めようとするのではなく、パニックを引き起こしてしまうような子どもをとりまく環境要因を調べることが大切になります。』
第2章 子どもが伸びる「言葉かけ」7つの基本
言葉かけの基本は、「ほめて」伸ばす
ほめられることで、落ち着いてくる
・ほめられることで成長し、「自分は生きている価値がある」「自分は必要とされている」という自分を肯定する気持ち(自己肯定感)を高めていくことができる。
・自己肯定感が高まってくると、少しずつパニックが減り、落ち着いていく。
・特性がある子どもは家庭でも学校でもほめられることより、しかられることが多く、大きな劣等感を抱えている場合が多く、いつまでも自分に自身が持てない。
ほめることは、子どもの将来につながっている
・ほめるとは、小さくとも子ども自身が一つの壁を越えたことを認めることである。
・普通の子どもにとっては何気なくできることでも特性をもっている子どもには、大きな壁であることを理解する。
指示は短く、わかりやすい言葉で具体的に
長い指示が苦手な場合がある
・特性を持つ子どもは一般的に長い文章(指示)が苦手である。例えば「手を洗ってからご飯を食べよう」という指示に対して、前半部分の「手を洗って」を忘れてしまう。
指示は、短くわかりやすい単語で一つひとつはっきりと伝える
・特性をもっている子どもに話しかけるときは、できるだけ短く、わかりやすい言葉を使う。
「ダメ!」と否定的で強い言葉でしからない
否定的にしかるより、やるべきことを具体的に指示する
・特性を持っている子どもは、「いけません」と言われても、そのあとに自分が何をすればいいのかわからないと、とまどってしまう。例えば「ドアを開けっ放しにしてはダメ」という表現は「ドアを閉めて」に言い換えると、理解および行動がしやすくなる。
しかったり注意したりする回数を減らす
注意する回数を減らすことで気持ちを安定させる
・ADHDの子どもは「不注意」「落ち着きがない」「衝動的」という特性を持っている。お母さんが怒っていることは理解できるが、どうしても行動を抑えられないのがADHDの特性であり、その事実を理解してあげる。
一度、子どもの注目を引きつける工夫をする
・ADHDの子どもは、何かに夢中になっているときは、お母さんの声が「聞こえていない」場合もあるので、一度、子どもの近くへ寄って注目を引いてから注意する。また、注意するときは感情的になって大きな声を出したり、命令口調で注意したりしない。
子どもがとまどう言葉かけを避ける
皮肉や冗談は通じないことが多い
・自閉症スペクトラムの子どもの中には、よくおしゃべりする子どももいるが、直接的でない表現を理解することは難しい。「直接的でない表現」とは、慣用的表現、比喩、暗示、反語、まわりくどい表現など。
毎日の予定表を作って声をかけて確認しよう
スケジュール表で次にやることを確認させる
・特性を持っている子どもは、次になにをやるのかわからないと不安を感じる。そこで、目で見て確認できるように1日のスケジュール表を作り、できあがったスケジュール表を親子で確認しながら行動する。
体罰は、百害あって一利なし
体罰には有害な作用しかない
・体罰では特性は治らない。体罰は、親とのきずな、のびのびとした心、おとなへの信頼感、周りの人を好きになる気持ちなど子どもが本来持っている大切なものを壊してしまう。
・「がんばったね」とほめてあげることが子どもを伸ばすことにつながる。
第3章 子どもの気になる行動を減らす言葉かけ
パニックを起こしたときに落ち着かせる言葉
・パニックは、突然、奇声を発したり自分や他人に噛みついたり、物を投げつけたりする行動であるが、パニックには、必ず理由や原因がある。
・子どもがパニックを起こしたときはしからないことが基本。子どもの気持ちになって「いつものと違うから嫌なの?」というように言葉にしてあげると落ち着くことがある。
前もって変更や変化を説明しておく
・普段から子どもがパニックを起こす状況や傾向を把握するようにする。
・特性を持っている子どもにとっては、「あらゆる変化」が大きなストレスになる。
・パニックを減らすためには、何か変化が予定されていたり、予測できる場合はあらかじめ説明して心の準備をさせることが役に立つが、子どもがうまく行動できたときには、「ありがとう」「えらいよ」と言葉をかけてあげることが重要。子どもはほめられることで自分自身でパニックを回避する行動を少しずつ覚えていく。
しかっても聞かないときは、しかり方を変えてみる
長いお説教には効果がない!
・特性によっては相手の話していることが理解できない場合もある。
・以前の失敗を蒸し返すようなしかり方は、特に理解が難しい。
・しかる場合
・そのときその場でしかる
・短いことばで具体的にしかる
・どうすればしかられないかを具体的に教える etc
子どもの気持ちを想像してみる
・「6年生なんだからこのくらいはわかるだろう」と思うのではなく「6年生になったけど、これくらいはわかっているかな?」と考えながら行動を観察することが大切である。
食事時の気になる行動-①
同じおかずしか食べないのはこだわりのため
・特性を持つ子どもの偏食は単なる好き嫌いによるものではなく、食べ物の味、色合い、におい、食感などの感じ方が通常と異なっているために起きていると考えられている。
残したことをしかるより食べたことをほめてあげる
・偏食はどうしようもないものと切り替え、好きなものを全部食べたことをほめることが大切。子どもはほめられることで食事が楽しくなり、もっとほめられたいと思うようになる。
食事時の気になる行動-②
まわりが気になって食事に集中できない
・多動傾向の特性をもつ子どもにとっては、食事中に他のことが気になることはどうすることもできない部分があると理解してあげる。
食事に集中できるような環境をつくる
・食事に関係ないもの(テレビ、おもちゃなど)は食卓から遠ざける。
・「7時になったらテーブルにつこう」とか「この番組が終わったら食事だよ」、あるいは「7時半までに食べたら、お父さんとゲームをしよう」などと子どもが準備できるように声をかけてあげる。
ルールやマナーが理解できないときは
ルールやマナーを覚えることが難しい
・ルールやマナーをある程度理解できたとしても、順番を守ることやその場の雰囲気を読み取って行動すること、「暗黙の了解」などは苦手な子どもが多い。
言葉よりも「可視化」でルールを理解しやすくする
・「目に見える形」にすることは理解の助けになる。「絶対にこれだけは守る」ということをいくつか選び、壁や机に紙をはったり、手帳などにメモしたりすると良い。
「ほどほど」がわからないときにかける言葉
極端な行動をとってしまうのは「ほどほど」が理解できないから
・「おなかがいっぱいになったらやめる」「暑くなったら上着は着ないよ」「そろそろ遊ぶのをやめよう」といったあいまいな指示は特性のある子どもはうまく理解できず、なかなか従うことはできない。
・ポイントは「ほどほど」をお母さんや周囲の人が決めてあげること。お茶碗2杯、気温が10度といった数値や、時計の針がここまできたら次の遊びをする。など目で見てわかるように工夫する必要がある。
「ほどほど」がわからないのは「こだわり」のせいかも
・一つのことにこだわると他に注意を向けることは難しい。
・こだわり行動は好きでやっている場合以外に、不安に感じたり緊張したりする場面で見られることが多い。この場合、不安や緊張の原因やきっかけがあるはずなので、それを見つけてあげることが最初にすることである。原因が見つからない場合には、子どもが「不安を感じているんだな、緊張しているんだな」と」理解してあげるようにする。
・こだわり行動は、成長・発達とともに目立たなくなっていくことが多いので、あせって行動を何とかしようと頑張らず、しばらく見守ることも大切である。
「こだわり行動」がエスカレートしたときにかける言葉
こだわり行動に対する考え方
・こだわり行動が強くなる場合としては、環境の変化やスケジュールの変化、年齢があがることで期待されることが増えることへのプレッシャー、引越しや就園・就学などの「ライフイベント」などがきっかけになることが多い。
・環境変化を点検することが第一。まずは子どもとその周囲の環境をよく観察する。観察のポイントは今までとの違いは何かということ。また、観察したことをノートに記録することが非常に重要。記録しておかないと分析ができず、適切な対策につながらない。
付記
「発達障害ポータル」さまから配信される「コラム」で勉強させて頂いているのですが、「療育」には以下のような側面もあるようです。
発達障害児の言語獲得
「ありがとう、ヘンリー」というブログは、発達障害児と介助犬の実話に基づくものですが、その本から「自信」、「自尊心」とともに言語に問題を抱えた子供にとって、「言語」が非常に重要であることを知りました。
言語といえば、言語聴覚士が専門とされている分野ですが、言語障害、特に言語獲得ということについては、ある程度の知識を持っていた方が良いと思い、主に実践的な内容が書かれた本を探すことにしました。
まず、本書の趣旨を知っていただくのが良いと思いますので、著者のお一人である石原先生が書かれた「はじめに」を掲載させて頂きます。
『今から14年前、三歳直前のあいちゃん(仮名)は、さくま先生の指導する障害児の相談室に来ました。自閉症と診断された他の多くの子どもたち同様に、あいちゃんも重度の言語発達遅滞を示していて、お父さん、お母さんはとても心配されていました。さくま先生は、以前からずっと、応用行動分析を柱とするフリーオペラント法での指導を実践し、今も続けています。
フリーオペラント法は、ロバース[O. Ivar Lovaas]のオペラント条件づけの原理を応用した、自閉症児の言語獲得のための行動療法を出発点にしたものです。コスト面の改善、般化の貧弱さの改善、脳障害説へのこだわりからの脱却、などを目指して辿り着いたセラピーです。
さくま先生は、多くの論文、翻訳本などを出していますが、フリーオペラント法については、“広汎性発達障害児への応用行動分析(フリーオペラント法)”(2013、二瓶社)がはじめてのものです。
「障害児に関する本は、読み手が誤解しても、書き手が誤解を生むような記述をしても、障害児がその愚かさの犠牲になる。それを考えると、本の執筆は、どうしても慎重になる。しかし、障害児からたくさんのことを教えてもらいながら、それをそのまま墓場まで持っていっては、子どもたちに申し訳ない。もっと勉強して、誤解されない記述が身に付いてから本にまとめるべきなのだが、すでに日本人男性の平均寿命を超える年齢になってしまった。折りに触れ、認知症のキザシを自覚するまでになっている。本を書くのはいまでしょう!」との思いで書いたものだそうです。
さくま先生は、この本がどのように読まれるか、とても心配していました。応用行動分析の行動変容力は結構強力なのです。今後さらに技術の改善が進むでしょう。それに引き替え、現在の私たちは、それを間違いなく正しく使う哲学を持ち合わせていない。本を読み、自分勝手に都合よくつまみ食いしたのでは、子どもたちは応用行動分析の犠牲者になってしまう。先生はいささか考えすぎと思われるほどの悩みようです。しかし私は、この本で一人でも多くの障害児に言語獲得してほしいと思っています。
相談室に来られたお父さん、お母さんに、さくま先生はことばの指導法だけでなく、子育ての知恵についてもいろいろなお話をします。たくさんの方に知ってもらえれば、障害児だけでなく、多くの子どもたちの子育てや成長に、きっと役立つはずです。さくま先生のたくさんのことばを、きちんとした形で残すことが、あいちゃんをはじめ、相談室に通ってくれた子どもたち、保護者の方々、これから子育てをされる世代への贈り物になると思います。
フリーオペラント法によるあいちゃんの言語獲得指導の要所要所で、さくま先生のお話を挿入しながら事例報告を書きました。本書は“広汎性発達障害児への応用行動分析(フリーオペラント法)”の実践編でもあります。言語獲得指導に取り組んでおられる皆さまのお役に立つことを心から願っています。』
ブログでは、目次のご紹介に続き、「フリーオペラント法」の1、2。続いて、あいちゃんへの2回目と69回目のセッションの様子。さらに、「あいちゃんの指導のまとめ」と「現在のあいちゃん」の前半部をご紹介しています。
また、最後に復習のような感じで、印象に残った個所をつまみ食い的に列挙させて頂きました。
目次
第一章 あいちゃんの言語指導のはじまり
上手に教えてもらうのではなく、自分の経験から学ぶ
あなたの声を聞いているよ
よくわからないけど、こうしたほうがよさそうだ(知恵)
人と同じことをすれば楽しい
ことばの発達が最優先
がまんする子どもは親や指導者が楽なだけ
成長日記をつける
療育は化学か?
遊んで育つ、後片付けは遊びにブレーキ
発達に大きく影響するものを優先
静かな抱っこ20分
社会性は実体験から身に付く
教えなくてもできること
親は見ているだけの方がいい
第二章 ことばの出現/発声模倣の拡大/遊びの発達
ことばの訂正は御法度
皮膚感覚の成長
「手で食べる」は指先の運動発達に効果大
集中とこだわり
「叩く」は楽しく遊びたい気持ちの表れ
不安の緩和
第三章 ことばの増加/人との関わり/自発的遊び
社会への適応
人の気持ちを理解する
がまんできたらえらい?
不適応行動の大半は好奇心から
五感のアンバランス
自力で学ぶ力を育てる
「オカアチャ」と呼びました
語彙数は増加速度より変化率に注目
お兄ちゃんと遊びたい
活発な喃語が発話に続く
「オハヨウ」と入室
第四章 自発後の増大/認知的遊び/人とのやりとりへの発展
不適応行動への対処
子どもは自分の気持ちを伝えたい
集団行動への参加
お口もぐもぐで自主トレ
パニックへの対処
「親ばか」はそんなに悪くない
第五章 安定したことばの使用 ― 現在のあいちゃん
好きなことを増やしていく
食べ物の変化
多彩な反応
就学について
あいちゃんの指導のまとめ
現在のあいちゃん
フリーオペラント法―その1
『無言語の自閉症児に言語獲得の道を開いたのは、1970年頃のロバースです。カルフォルニア大学の教授で、当時、世界中から注目を浴びました。しかし、子どもは連日、ロバースのセラピールームに親子で通い、週に30時間も訓練を受けるものでした。
若い頃、ロバースの本を読んでいて、訓練時間の長さにびっくりし、指導の人件費の概算をしてさらに驚き、日本でこんな事はできないと思いました。それが、フリーオペラント法を思いつくきっかけになりました。そして、この訓練時間の長さには基礎理論の応用の仕方に欠陥があるはずだと考えました。どんなに障害が重症でも、自分の経験から学ぶということをするはずです。野生の動物はみな、指導者なしで、生きる術を学んでいます。そんなに長時間の指導は明らかに非能率的です。
家庭でも強化随伴性が維持され、模倣行動の自発性を高める操作を加えると、1週間に1時間の指導で、遜色のない成果を出し得ることがわかったのです。
セラピー関係では、能率について議論されることはほとんどないようですが、セラピーは趣味や道楽の類ではなく、仕事です。能率を考えるべきです。
学ぶ力の弱い動物に教えるには、コツや技術が必要です。私たちの指導の拠り所は、動物実験の成果である行動分析です。指導のポイントを動物から教えてもらったのです。そのために、初期の頃には、障害児を動物扱いしているとの批判がひどかった。しかし、ことばの発達指導が絶望的だった頃、ちゃんと言語を獲得させることと、獲得できないままにしているのと、どちらが人間的か、議論の余地はないはずです。』

画像出展:「Alchetron」
フリーオペラント法―その2
『フリーオペラント法の大きな特徴は、言語理解に関して完全手抜きで進めることです。
これまでの言語に関する基礎研究では、言語能力は言語理解と言語表出の二面からできているとされています。しかも、言語理解が先行し、その後追いで、言語表出が発達するといわれてきました。
しかし、言語発達遅滞児たちは、逆を示しています。言語理解はかなりいいのに言語表出がゼロ、あるいは、かなり悪い子が大勢いる。それに引き替え、言語表出が良好な子どもたちに言語理解が悪い子どもは一人もいない。言語表出レベルに相当する言語理解を持ち合わせている。
この目の前の事実に注目するならば、言語発達促進の指導は、言語表出の方に注目すべきであり、言語理解は手抜きでいいことになる。事実、30歳代半ば頃、フリーオペラント法で音声模倣を形成しただけで、家庭で自発的に単語が出だす子どもを幾人も経験し、以来、言語理解を完全手抜きでやっています。その方が経過がいいのです。
障害児指導に模倣行動を取り入れる研究が内外に少しずつ出はじめています。モデルを示し模倣を誘導して強化子を随伴させるという手続きです。
1970年代はじめに模倣を取り入れたわれわれとしては嬉しい限りですが、それよりも、ここで紹介しているように、子どもの発声、子どもの動作をセラピストが模倣して子どもの模倣行動の自発を待つ方が、手間はかかりますが、はるかに良好な自発的模倣行動が出てきます。
あいちゃんも、ことばの意味に関しては一切教えるということなしです。化粧品会社のホームページを見て漢字をお母さんにたくさん聞きましたが、誰も積極的に教えていません」』
あいちゃんへの2回目のセッション(あなたの声を聞いているよ)
『お正月が明けて、二週間ぶりにあいちゃんがやってきました。布をかじっています。汽車のおもちゃを動かし、汽笛のボタンを押しました。おもちゃに全く興味がないわけではありません。アンパンマンの電話を鳴らすと、受話器を持って、「アイ」と小さな声が聞こえました。はじめて聞いた声です。セラピストもすぐに「あい」と繰り返します。
次にあいちゃんは滑り台に向います。滑り台を滑ったときに、くすぐりますが、なかなか声は出ません。抱っこしてジャンプしてみます。目が合って、ニコッとしますが、発声はありません。お母さんが座っている椅子によじ登ろうとするので、セラピストが抱っこで乗せてあげると、次は手を広げて待っています。座っているあいちゃんから見えないように隠れ、「あいちゃん」と呼んで、いないいないばぁのように顔を出すと、「アハハ」とはじめて大きな声を出して笑いました。顔を出したときにくすぐることを何度も繰り返すと、自分から出てきて、顔を押し付けたり、体をねじったりします。この間、かじっていた布が落ちましたが、全く気にしません。セラピストはあいちゃんからの要求にすぐに応じます。
ー お父さんとお母さんはさくま先生とお話です。
「ことばについて、もう少し詳しくお話しします。ことばは自分の声に対して相手から反応が返ってくるから発達します。その時、子どもを理解しようとする気持ちがマイナスに働いてしまいます。つまり、子どもの顔を見たり、目の動きを見て、“嬉しいのかな”“これが欲しいのかな”と考えていると、子どもの発声を聞き逃してしまう。子どもにとっては、声が無視されていることになる。ことばに敏感になって、“あなたの声を聞いてるよ”ということを子どもに伝えるにはどうしたらいいでしょうか。子どもが「アアア」と言ったら、「あああ」と答えれば、自分の声が相手に伝わっていることが、子どもにわかる。これが、音声フィードバックです。音声模倣ともいいます。これをここだけでなく、生活の中でもしてもらえたらと思います。
理由はよくわからないのですが、子どもは自分の発声と同じ発声が相手から返ってくると、楽しい気分になります。軽い躁状態を示します。何度も繰り返すと、楽しくなるために、次に、自分の方から大人と同じ声を出すようになります。動作に関しても同じです。動作模倣と呼んでいます。
自発的に発声模倣をするようになると、ことばの発達がはじまります。これを絵カードなどで発声を強要すると、必要以上に力のいった声になることがあります。余分な力の入っていない声はコントロールしやすい声になり、発話獲得の重要条件です」
このお話の途中で、あいちゃんの笑い声が聞こえ、お父さんたちもあいちゃんの様子をじっと見ています。プレイルームには水場があります。水を出して、スポンジを絞ってみるとあいちゃんも触ります。セラピストもすぐに水を出します。この後ずっと、水を出す、スポンジを絞る、を繰り返しました。セラピストは一切指示を出しません。
ー さくま先生のお話が続きます。
「ここでは叱ることはほとんどありません。お家でもできるだけ叱らないで、好きなことをさせてください。叱らないとわがままな子になると思われていますが、わがままは、後でいくらでも修正できます。ことばの発達を最優先にしましょう」
さくま先生のことばにお父さんとお母さんはうなずかれました。ただ、このことは思ったより大変です。それをお父さんとお母さんはこの後ずっと守って下さいました。』
あいちゃんへの69回目のセッション(多彩な反応)
『11月の下旬になりました。69セッション目になりました。走って、あいちゃんがやってきました。ニコニコして、机の上の洗面器を見て「コエ」「アッタ」と言いながら、手で中の水を混ぜます。すぐに「イタ、イタ」「イコカ」と言いながら、キティちゃんを持ち、お母さんの手を引きます。おもちゃのレンジを触るので、「冷蔵庫もあるよ」とセラピストが見せると「ウィ、キティチャン」「アコ」と言いながら、マットの上に置きました。
セラピストがベビーカーも持って来ると、あいちゃんがキティちゃんを乗せました。「キティちゃん、行ってきます」とセラピストが声をかけ、押しはじめると「バイバイ」と言ってくれました。
お母さんに掃除機を持たせ「スースー」と掃除をするように要求します。あいちゃんもベビーカーに乗り「バイバイ、バイバイ」と繰り返します。「バイバイやね」とセラピストはすぐに答えます。「アイチャン、キティチャン」と言っています。「あいちゃん、キティちゃん、乗ってます」と返事をします。
セラピストがキティちゃんのスティック糊を持ってくるとそれを持って「アーイ、アーイ」と机に向います。「キティちゃん、猫こか」とセラピストが言うと「アーイ」と返事をしてから、お母さんの手を引いて、机に来るよう要求します。お母さんの手を紙に持っていき、ペンも置き「キティチャン、コエ、コリキ」と発語します。黒ペンを持って、お母さんの手を持って「ハーイ」と言います。お母さんがキティちゃんの輪郭と目を描いてくれます。黄色のペンを持ち、お母さんの手を持って「ハーイ」と発語すると、お母さんがリボンや口を描いてくれました。「イーシャ」とニコニコします、「ヨイショ」と言いながら、平均台を持ってこようとするので、セラピストも「よいしょ、よいしょ」と手伝います。
あいちゃんは平均台に座って「デキタ、キティチャン」「カキカキ、ヤッテ」「ハーイ、カキヤッテ」と発語が続き、セラピストもすぐに模倣します。平均台に立つと「タカーイ、ハイーネ」「デキター」「オカアサンガコッチと言いながら、お母さんを呼びます。セラピストの顔も見て「アーイ、デキタ」と手をあげてくれます。
次の紙をお母さんに渡します。黄色のペンも渡します。「オーアイチャ、ハイ、オカーシャン」とずっと喋っています。セラピストがキティちゃんの輪郭に切った紙をあいちゃんに渡すと、あいちゃんが目と豚の鼻と口を描きました。「あいちゃん、ぶたさん、上手、上手」と褒めました。
もじもじするので、お母さんが着替えを出すと、おしっこをして、トランポリンに行きました。「ウアイヤー、ピョンピョン」と言っています。セラピストもあいちゃんと一緒に「ぴょん、ぴょん、うまい、うまい」と飛んでみます。着替えが途中だったので、お母さんがボタンに手をかけると、外して全部自分でやり直します。10分前でしたが、「バイバイ、バイバイ」とずっと言いながら、帰りました。
あいちゃんは、お家でも何でも自分でやりたがること、ことばをいろいろなリズムで言ったり、いろいろな声で言ったりして、楽しんでいるとお母さんからお話がありました。』
あいちゃんの指導のまとめ
『あいちゃんが相談室に来所して、二年が経ちました。この間の発語は経過記録でお伝えしましたが、一度口から出たことばは完全に定着し、再三、遊びの場面、生活場面で使用されています。
第四章以降の相談室での指導と家庭での様子についてまとめると、あいちゃんの要求行動の増加に対し、セラピストは可能な限りそれに応じ、無意味発声に対しては無視、無反応で対応し、動作や行動の言語化、有意味語と思われる発声に対しては拡充模倣で応じました。
また、いわゆる声掛けなどの行動指示(先行刺激操作)を少しずつ増やしていきました。これはフリーオペラント技法の基本方針からずれるのですが、あいちゃんの行動変容(例えば、声掛けによく反応するようになっていた)に合わせたものでした。
発語頻度の増加に伴い、発語の反応トポグラフィーが正確でなくても、その場の文脈に適合していれば、強化操作を続けました。例えばあいちゃんの発語「ハーデー」(混ぜて)に対して、発音の修正、訂正は一切していません。発語頻度の方を重視したからです。発語が高頻度で続けば、構音の明瞭度は自動的に改善が進むためです。
さらに、ことばが社会的行動である以上、遊戯室だけでの発声では意味がありません。家族も来所当初から、発語を強化するメディエーターとしての役割を担えるように、遊戯室での指導者の指導を観察し、スーパーバイザーのさくま先生から、日常でのさまざまな助言を受けました。
あいちゃんは、遊戯室で感覚的な遊びからお母さんの家事行動そのままに、お料理、お掃除、お洗濯の遊びが続きました。ご両親はそれを可能な限り受容し、冷蔵庫はあいちゃんに全面解放の状態だったそうです。
指導場面での強化随伴性はそのまま家庭でも維持されました。つまり、人の応答が発語の強化子となるためには、日常場面でも強制・指示をできるだけ控えてもらう必要がありました。記録を拝見すると、実に忍耐強くやっていただいたことがうかがえます。』
現在のあいちゃん
『あいちゃんは、その後も継続して相談室に来ています。小学校、中学校といろいろな問題がありましたが、その都度さくま先生にご相談をされて対処しました。そして現在、特別支援学校の高等部に在籍し、隔週で相談室に来ています。それは、問題があるからではなく、あいちゃんが相談室に来るのを楽しみにしているからです。
出かける前には、お父さんの用意が遅いと「オトウサン、ネテイルバアイジャナイデショ」と言ったり、「オカアサン、ワスレモノナイノ?」と声をかけたりします。
あいちゃんの言語発達は、お母さんのことばをお借りすれば、「こんな口の悪い自閉症児は知りません」と言われるほどにおしゃべりになっています。ケンカになると「クソババー、アイチャンハ、イエヲデテイキマス」と言ったり、一般の中学生・高校生となんら変わらないレベルのやりとりをするほどになっています。
お母さんと一緒に買い物に行けば、一人で「〇〇ハドコデスカ?」と店員に聞く社会性もあり、欲しいものがあると、お母さんがレジに来るのを待っていて、直前にレジカゴにすっと商品を滑り込ませるのだそうです。「物を買ってもらう策略には困ります」とお母さんはおっしゃいます。
相談室では、持ってきたカレーせんべいを皆に配って一緒に食べたり、遊びの邪魔をする小さな子にもことばで注意します。実習の大学生やスタッフを相手のゲームでは、負けしらずです。ところが最近、彼女ばかり勝つと、三度に一度の割合でわざと負けるようになった、とスタッフの一人が言うのです。意識してのことかどうかを確認する方策を、スタッフ間で頭を悩ませているところです。ゲームが苦手な私には「右ボタン、赤押して」と厳しく(?)教えてくれながら、グループで勝ち負けを競い、「あなたは第三回スターアタック決定戦に優勝したことを表彰します」という自分で書いた表彰状を作りました。また勝負の結果。負けたチームに罰ゲームでものまねをさせ、それをビデオカメラに記録して自分で編集します。DVDや動画サイトを見たり、スマホでAKB48の新曲の検索もします。絵を描くのも好きで、女の子を沢山描いて、難しい漢字の名前(例えば愛羅)をつけ(漢字は自分で調べて覚えました)、人形の服を手縫いで縫って遊びます。
特別支援学校高等部では役員に立候補し、行事で挨拶ができるほどですが、欠席することも多いようです。現在、不登校が続いています。好きなことへの集中力は療育園の頃から変わらないため、学校で、とても細かい刺繍に集中している時など、「時間だよ。終わりにして」と言われると今でも嫌なようです。ただ、集団が全て嫌いなわけではなく、デイサービスには喜んで行き、好きなDVDに時間制限を加えられてもがまんできるようになりました。』
特に印象に残ったこと
第一章
●子どもの声に敏感に反応する→子どもは声が相手を動かすものだとわかる。
●大人が子どもと同じ声を出す→「あなたの声を聞いているよ」ということを子どもに知らせる。
●ことばは自分の主張なので、わがまま、甘えが大事である。「しつけが大事」は順調に育つ強靭な力の健常児に対してである。
●障害児の難しさは、自分で何かをしようとする力や、何かをしたいと人に訴える力が弱いこと。
●ことばは自分の声に対して相手から反応が返ってくるから発達する。
●叱らない。わがままは後でいくらでも修正できるので、ことばの発達を最優先させる。
●物より人に興味をもつようになることが大事。気に入った物で遊んでいる状況に大人が加わると一人で遊ぶより面白くなる。それが繰り返されると好きな物よりも好きな人の方が重要になり、物よりも人を優先させることになる。
●社会性は、人と楽しく交わりたいというモチベーションが大切。
●社会性は年齢とともに変わる。従って、自分の社会的体験から自力で学べるようにしなければ問題の解決にならない。(相槌が1秒と0.5秒では意味は異なる。これは教えて身につくものではない)
第二章
●人の様子を見てまねをする、それが蓄積されて社会性の発達につながる。
●子どもの発達の過程は依存と自立が揺れ動いている。自立は催促せず、邪魔せず、子どものペースでつきあうのがベスト。
●ことばの訂正は言語発達を妨げる。
●自立を促す必要はない。発達すれば必ず自立するものである。
●依存と自立は対立関係のものではなく、依存の延長線状に自立があるという認識をもつ。
第三章
●しつけは幼い方が楽なことは確かだが、ことばの発達は年齢が後になるほど困難、不可能になる。
●適応性が未熟な障害児にとって、禁止と強制がいきすぎると、無気力状態にしてしまう。
●重度の自閉症の子どもは、きょうだい、親にも無関心なことが多い。それが改善されてくると今度は一緒に遊びたい。けれど、遊び方がわかっていない。さしあたり、叩いてみる。それには憎しみや、嫌悪、憎悪などの感情は含まれない。重度の自閉症で人を叩いたというエピソードを聞くと、改善の徴候なので嬉しくなる。
第四章
●子どもの話は、子どものことばのわかった部分を反唱しながら聴くのがコツ。お母さんにわかってもらえるように子どもが努力する。親に分かるように話せるまでゆっくり待ってあげる。
乾布摩擦について
私は発達障害児へのマッサージが仕事になりますので、「乾布摩擦」については特に関心がありますが、これは佐久間先生が考える、「感覚統合訓練法的な五感のバランス改善のための手段」いうことではないかと想像します。
『「遅れてことばが発達する子どもに共通して、感覚器官のダイナミズムに大きな変化があります。赤ちゃん時代からずっと口は飲む、食べるだけしかしていません。それ以外は泣き声だけで、自分の声を意識していません。少しことばが出はじめると、口の中の感覚が大きく変わりはじめます。同時に、聴覚や視覚にも変化が生じ、耳ふさぎや眼球擦りなどが生じることがあります。赤ちゃんはだれでも、五感の感受性にアンバランスがあり、たくさんの皮膚刺激で、五歳までにバランスがよくなります。
通常、聴覚優位なので、人の話を聞くだけでことばの学習が進みます。優位性がさらに過剰だと、耳ふさぎを示します。皮膚刺激の過敏、鈍感、味覚や嗅覚にこだわりや偏りを示す子もいます。
五感のバランスのために、乾布摩擦をして下さい。全身、朝、晩、服の着換えの時に、擦ってやってください。健康増進のためではなく、五感のバランスのための乾布摩擦なので子どもの顔を見ながら気持ちよさそうな表情を手がかりに、最適な擦り方を見つけてください。頭から足の裏まで、指の一本一本まで、嫌がる所はアンタッチャブルゾーンとして擦らないように、その境界線は特に丁寧に擦っていると、ゾーンは縮小していくはずです。消えるまで朝晩続けていると、ゆっくりと五感のバランスがよくなるはずです」』
付記
本の出版が2015年のため、本の中で紹介されている「キリスト教ミード会舘」に問い合わせたところ、現在は下記の「西宮たんぽぽ」にて行われているとのことでした。特に右の写真をクリックして頂くと詳しい内容が確認できます。
療育
『もしタイムマシンを使えたら、あなたは過去に戻ってみたいですか?未来に進んでみたいですか?
ある女の子は言いました「赤ちゃんからやり直したい」と。ある男の子は言いました「先生、時間を戻して!最初からやるから」と。二人とも小学校1年生でした。過去に戻りたいと願っていました。うまくいかない自分を抱えて、その理由もわからず、苦しんでいました。
私たちがその子たちにできることは、その子のありのままを慈しみ、発達を支えることなのです。「苦手があっても、かけがえのない存在」、そう子どもに感じてもらえる関わりを用意することなのです。子どもたちには、未来を見つめていてほしい。そう思います。自分のありのままを大切に、歩んでいってほしいと。』これは、著者である藤原先生の「あとがき」の前半部分です。
そして、療育とは特別なスキルを要するものではないということを伝えています。
『「療育」とは特別な場所や特別の人がするだけのものではなく、お母さん、お父さん、保育士さん、学校の先生など誰にもできる子供の発達と支援の方法論です。
例えば、よい行動をしたら褒めて子供のよい行動を増やすということや、集中できない場合は静かな環境の中で勉強させる、不安になったら好きなぬいぐるみに触れて落ち着かせるなど、その場に応じた適した方法を使って子供を指導することです。』
なお、この本は以下の6つのパートから構成されています。
・漫画:発達障害のある子どもたちのエピソードを紹介する。
・対応:エピソードで紹介した子どもの行動の理由や対応を紹介する。
・子ども発達相談室:お母さんがよく抱えている子どもの悩みに対してアドバイスをする。
・解説:発達特性についてより専門的に解説する。
・大切なあなたへのメッセージ:子どもに読み聞かせして、子ども自身の特性を共通理解する。
・コラム:子どもを理解し、よりよい療育のために知ってほしいことなど。
そして、目次は次の通りです。
第1章 完璧な子どもはいない
どの子も発達の凸凹がある
発達の凸凹をその子の特性と捉える
その特性により生活に大きく支障をきたす場合、発達障害と診断される
第2章 多動と不注意
1.じっとしていられない
2.やるべきことを忘れる
3.先に考えずに行動する
4.忘れ物が多い
5.突然、怒りだす
6.イライラしやすい
7.小さな失敗で過度に落ち込む
第3章 こだわり・コミュニケーション・社会性
8.自分勝手にふるまう
9.相手の気持ちになれない
10.こだわりが強い その①
11.こだわりが強い その②
12.こだわりが強い その③
13.考えが極端にせまい
14.言葉の意味は一つだけ
15.二つのことが同時にできない
16.いじめられているのに気づかない
第4章 感覚と身体運動
17.自分の体はどこ?
18.力の入れ方がわからない
19.見えているけど正しく見えない
第5章 特性を生かす
20.ぼくはダメな子?
21.みんなと違っている
22.1番じゃなきゃやだ!
コラム
診断は大切?
立派な大人も小さいころは…
理想の子ども
子どもへ伝えるときのコツ
お父さんも理解者になるために
おじいちゃん・おばあちゃんを味方にするには
大切なあなたへのメッセージ
失敗は成功のもと
おなじということ
いじめからあなたを守るために
大人に伝えて相談しよう
自分について
わたしのきょうだいへのメッセージ
好きなところ・きらいなところ
私の発達障害児との関わりはマッサージと動作法になりますので、ブログでは子どもとの信頼関係づくりに関わる「コミュニケーション」と今までのブログで度々登場してきた「ボディイメージ」を、療育の視点から考えてみました。
コミュニケーション
1.シングルフォーカス(参照ページ:p42-p45)
シングルフォーカスとは興味あるものだけが頭を占領し、くぎ付けになってしまうことです。
本文では次のような「解説」が書かれています。
『子どもは少なからず、興味あるものを目の前にすると他が見えなくなる傾向があります。大人でも、恋愛すると「あなたしか見えない」などといいますが、シングルフォーカスを象徴した言い回しですね。
年齢や体験を重ねることで、やるべきことは意識して、順を追って行動できるようになります。いくつかのやるべきことが多画面のようになって、意識できるようになります。しかし、浩太くんのように、小学生になっても、興味のあることに出くわすとそのことが全画面表示になり、「今を生きる」状態にスイッチが入る子には、まだまだ大人のマネジメントが必要です。
まずは、自分のクセを理解させましょう。興味のあることに夢中になりやすいということを理解させます。そのうえで、複数の画面にする工夫をします。やるべき二つのスケジュールを同時に映像として提示するのです。ランドセルと学校、帰宅と手洗い・うがい、宿題というように。これも、習慣になると行動がつながるようになるでしょう。』
2.ストレスと怒り(参照ページ:p60-p63)
怒りとは、瞬間湯沸かし器のように急に怒りだすようにみえる場合でも、徐々にたまったストレスがコップからあふれ出す瞬間に起こるものとされています。また、怒りだすとなかなか止まらない、一度怒りが収まったと思ったらまた急にぶり返すなど、怒りのコント―ルができないところにも大きな問題があります。ストレスは個々の特性によって異なりますので、その子の傾向を知り、日常生活の中で注意深く観察して、生活の工夫を試みることが大切になります。
「解説」の内容は次のようなものです。
『私たちは誰でも「怒り」の感情をもちます。この感情はもってはいけないものではなく、もったうえでマネジメントするものと考えましょう。つまり、「アンガー(怒り)マネジメント(管理する)ということです。アンガーマネジメントでは、「怒り」は第二次感情といわれます。怒りの感情に至る前には第一次感情が影響しているのです。第一次感情とは負の感情で、不安や、ストレス、悲しみ、ねたみなどです。
私たちは日常生活の中で、さまざまな負の感情を抱きます。この感情が、コップの水のようにたまります。この水をじょうずに抜いていかないとコップの水はあふれ出します。このあふれ出した感情が、「怒り」として表現されます。
感覚の過敏さ、ネガティブな思考のクセ、こだわりを強くもつ、シングルフォーカスなどの発達特性をもつ場合、コップの水はたまりやすくなります。この水をためない、また、たまった水を抜くための工夫をしていくことが必要なのです。』
3.言葉どおりにしか受け取らない(参照ページ:p106-p111)
「言葉どおりにしか受け取らない」ということは上記の漫画に出てくるような出来事です。
会話は前後の状況や場の雰囲気を理解して、言葉の裏の意味を直感的に解釈すること、「暗黙の了解」が求められますが、この抽象的な概念は発達障害児にとって非常に厄介なものです。「1を知って10を知る」は望ましいものとされていますが、発達障害児においては、まさに「1は1でしかない」というのが特性です。
これらは自然に身につくものではないので、まずは正確に伝えるという配慮が必要です。例えば、「お風呂見てきてね」→「お風呂にお湯がたまったかどうか見てきてね」。「お昼は何にする?」→「お昼ご飯は何を食べる?」という具合です。そして、その都度その言葉の背景を教えていくことが必要です。このフォローを地道に行うことにより、言葉の背景や暗黙の了解をつかむコツが分かってきます。
4.シングルタスク(参照ページ:p114-p118)
先生の話を聞きながらメモを取れない。テーブル上のお皿を持ち上げてテーブルを拭けない。このようなことは発達障害児の特性の一つです。お母さんからは「右手と左手がまるで別の生き物のように、協調して動かない。目と耳と口も同じです。一人の人間が操作していると思えない。そんな感じです。」といった思いを抱くことも多いようです。
これらは子どもたちの心の問題でも、意思の問題でもなく、脳の処理の問題です。子ども自身もそうしたくても、できないもどかしさを強く感じています。
私たちの脳は同時に複数のことができるものですが(マルチタスク)、1つのことしかできない(シングルタスク)という特性が発達障害児には見受けられます。この難しい問題に対し、著者の藤原先生は「解説」の中でこの問題に対しどのように向き合うのが良いのかについて語られています。
『私たちは、いくつかの作業を映像に描いて行動します。でも、その作業が1つしか描けない子どももいます。いくつかの作業を描いて行動できるには、作業を同時に処理していく能力が必要です。たとえば下の絵のように、朝のしたくでは「コップと、タオルとノートと……を入れて」というように進めます。
しかし、一つの作業しか浮かばないと、下の絵のような作業になります。
前者を「同時処理」、後者を「継次処理」といいます。
継次処理の方が効率が悪いのは否定できませんが、丁寧で着実であるという利点もあります。早くないけれど確実、そこがよさです。丁寧に一つずつこなしていけるようにします。こうした日ごろの支援が、一つから二つと同時にできる作業を増やすことにつながります。欲張らず、あせらず、子どもの情報処理の発達特性に合わせて、支援を考えましょう。』
5.「子どもへ伝えるときのコツ」(参照ページ:p170-p171)
こちらは「コラム」として掲載されているものです。発達障害の子どもと接するうえで、とても有効だと思いますのでそのまま掲載させて頂きます。
①脅かさない
『「〇〇しないと〇〇できない」、たとえば「勉強しないとおやつが食べられないよ」だと、おやつが食べられない状況のみが強調されて伝わります。否定的な言い回しの繰り返しではなく、肯定的にやるべきことを伝えましょう。「勉強したら、おやつです」と。』
②叱らずにアドバイスする
『「〇〇するとうまくいくよ」、たとえば「失敗は成功のもとと考えると、気持ちが楽になるよ」というようにしましょう。うまくいかないとき、イライラする場面なども「イライラしない」「もうあきらめなさい」などと叱らずに、「深呼吸してみよう」「楽しいことを考えて」など、肯定的に今やってほしい行動を伝えましょう。』
③よかったところを強調する
『「〇〇は失敗したけど、〇〇はよかったよ」のように言います。大人も子どももうまくいかなかったところに目を向けがちです。そんな考え方を切り替えるためにも、よかったところ、できたところを確認して伝えましょう。』
④共感する
『「なるほど、そういうふうに考えるんだ。おもしろいね。」「その感じ方は、苦しいよね。よくわかったよ」といったように、どんな考え方でも、たとえそれが間違っていると感じても、まずは共感しましょう。なぜなら、その考え方は本人にとって「大切な考え方」であるからです。そのうえで、ほかの意見を受け入れられるように導きましょう。』
⑤希望をもたせる
『「次はうまくいくと思うよ」、「きみを理解してくれる人にこれから出会えるよ」、「きみは成長しているよ」など。子どもが自分を信じて、頑張るためには将来に希望がもてなければなりません。今、つらい状況であっても、身近にいる大人が希望をもてるようなメッセージを伝え続けることが必要です。』
⑥味方だと伝える
『「いつでもあなたの味方だからね」「身近なサポーターだから忘れないでね」「きみのファンだよ」というように、一人じゃないということを感じられるようにします。心の支えになれるように、伝えたいですね。』
ボディイメージ
1.じっとしていられない(参照ページ:p32-p39)
「子ども発達相談室」の母と先生のやりとりは次のような内容で始まっています。
母:うちの子は、とにかくじっとしていられません。
先生:そうですね。体の内側から動きたい欲求が出ているので、注意してもおさまらないですね。
母:体の内側から……それはどういうことですか?
先生:私たちは、体の中に感じる感覚を二つもっています。その一つが「固有覚」といって、筋肉や関節に感じる感覚です。鉄棒にぶら下がると手首が引っ張られる、物を持つときに重さを感じる…そんな感覚です。この感覚を頼りに、私たちは動作や運動をするときに適切な力の入れ方、自分の体の部位の動かし方を調整しています。この感覚をうまく受けとめないと力を入れすぎて、バナナやおにぎりを食べるときに握りつぶしてしまったり、体の動きがぎこちなく見えたりします。
また、「対応」では、子どもの欲求を満たす方法として、子どもの体に触れて筋肉や関節に感覚刺激を入れる関わりや遊びを取り入れることを推奨しています。
具体的には以下の事柄が紹介されています。
①座りながら感覚を満たす
・手や腕など、ギュッギュッと握ってみよう
・肩や背中、ひざなどトントンとたたいてみよう
・頭を指でマッサージしてみよう
②運動遊びで感覚を満たす
・指相撲や腕相撲、鉄棒にぶら下がる、前回りをする、マットででんぐりがえし、木登り、ジャングルジム、うんてい
③道具を使った工夫
・バランスボールを座ってピョンピョン
・一人用のトランポリンで繰り返しジャンプ
・マッサージチェアで筋肉や関節をモミモミ
・回転いすに座ってくるくる回る
そして、「解説」では詳しい説明がされています。
『多動といわれる状態は、動きたいという身体の内側にある感覚的な欲求が働いていることが原因の一つといわれています。「お腹がすいてご飯を食べたい」という生理的な欲求と似ていて、「体の内側に入る感覚刺激が足りないから、感覚を入れたい」という行動です。私たちが、窮屈な乗り物に長い時間乗っていると動きたいという気持ちにかられますが、それに似ています。
体の内側に感じる感覚は「固有覚」(筋肉や関節に感じる感覚)と「前庭感覚」(体の傾きや動いているスピードを感じる感覚)があります。どちらも感じにくいと跳びたくなったり、走りたくなったり、回転したくなったりします。ですから、我慢させすぎることのないように、内的な感覚欲求を満たしてあげることを考えましょう。
外遊びで、跳びはねたり、回ったりするといった遊びが少ない現代、この内的な感覚が足りないことと、子どもたちの行動に落ち着きがないと感じることは関係が深いと考えられます。』
2.自分の体はどこ?(参照ページ:p128-p133)
「自分の体はどこ?」というものは、問題を持っていない人にとってはとても理解しずらいものです。本の中では「子ども発達相談室」の母と先生のやり取りがとても分かりやすいので、前半部分を引用させて頂きます。
母:着替えはとにかく時間がかかります。そでにうまく腕が通せなかったり、かかとの位置を合わせられなかったりで、私の方がイライラしてつい怒る。本人はさらに体が動かなくなる……そんな繰り返しで。
先生:私たちはそでを通す時も、かかとの位置を合わす時も、最初はその部分を見ますが、その後は見ないで身体の感覚を使って着替えをします。見ないでできると、早いんですね。ところが、自分の体の位置や動かし方がわからないといちいち見ないといけない、そして見ても服のその部分に体を合わせるのに時間がかかるという二重苦です。自然に理解するのは難しいので、どうしてうまくいかないのか、お母さんがなんで怒っているのかもわからないということになります。
母:見ないとできない? なるほど、私たちは見ないでそでを通したり、ボタンをはめたりしていますね。それができないのですね。
先生:ボディイメージを持てないということが大きいですね。自分の体の実感がうまくもてないということだと思います。体に意識が向きにくいのです。
そして、「解説」では支援の方法などについても言及されています。
『子どもは、3、4か月のころになると、自分の手を眺めながら動かすようになります。これは「ハンド・リガード」という行動で、自分の手を見つめることで自分に体があるということを知り、体が動く時の感覚をつかむのです。つまり「手を動かす」のを見ながら確認して、体の感覚と一致させ、その感覚を利用して、見ないでも体を動かせるようになっていきます。
しかし、この体の感覚、固有覚などの内的な感覚が育ちにくいと、見ないで体を動かすことが難しくなります。また、見えない部分を想像する力も弱いのでさらに動かすのは大変です。ですから、「ハンド・リガード」と同じ視点で、見て自分の体を知ることと、動く時の体の感覚をつかめるように、大人が支援します。その時は手取り足取りになることもありますが、繰り返すうちに体の感覚をつかめるようになります。』

乳児は「ハンドリガード」で身体感覚を学びます。そのプロセスは以下の通りです。
①脳が「指をしゃぶれ」という「動作信号」を発信する。
②指の動きが「体性感覚」として脳にフィードバックされる。
③指の動きを見たり、口に含んだり時の味覚などが「特殊感覚」として脳にフィードバックされる。
④動作信号・体性感覚・特殊感覚が脳の中で統合されて、身体感覚が学習される。
画像出展:「立命館大学映像学部」
3.力の入れ方がわからない(参照ページ:p134-p139)
力の加減が分からないとどんな事が起きるのでしょうか。これについて、「対応」にいくつかの例や役立つ遊びが紹介されています。
『ドアをバタンと閉める、物をドンッと置く、人を力強くたたく、どたどたと歩くなど、力を入れすぎる行動は、落ち着かない子、乱暴な子と誤解されやすく、本人も損をします。これは、力を緩める感覚をつかみにくいことが原因となっています。
力を緩める感覚を練習するための「紙風船」を使った遊びを紹介しましょう。「紙風船」を下からたたいて繰り返し飛ばします。力を入れてたたくとつぶれてしまうので、力のコントロールが必要です。いきなり「紙風船」が難しい場合は、「ゴム風船」でもよいです。なるべく数多くポンポンと手でついて繰り返せるようになるといいですね。
「風船」でのキャッチボールも楽しい遊びです。力強くキャッチすると、風船が弾んで逃げていくので、そっと捕るという感覚がわかります。
力を抜いて操作するのがわかったら、ドアを閉める時や物を置く時は「風船をつかむ力で」と伝えると、体験が生活にいきるようになりますね。』
また、「解説」でも、力を緩める感覚は言葉だけの説明では身につかないということが書かれています。
『力が入りすぎて、体の動かし方が不器用というのは、体の中に感じる固有覚の鈍感さがやはり原因だと思います。この感覚の中でも、物の重さや固さを感じる感覚がうまく働かないと無駄な力が入りすぎたり、逆に入らなかったりして、不器用な働きになります。
重さや固さが感じにくく、物をつかむ時や持つ時に指の関節や手首にどのくらい力を入れるのか、どれくらいの角度を保つのかがわかりません。また、筋肉の使い方の加減もうまく調整できません。「ゆっくり持つ」「そっと置く」など、言葉だけで説明するだけでは、いくら繰り返し練習してもできないということになります。
ですから、見て、感じて、具体的な力の入れ方を練習するということで、子どもが少しずつ変化していきます。ここでも、根気よくというのがキーワードになりますね。』
今回、「はじめての療育」を勉強させて頂き、特にボディイメージの理解(「じっとしていられない」、「自分のからだはどこ?」、「力の入れ方がわからない」)を深めることができたことは、とても良かったと思います。
「ありがとう、ヘンリー」
今回のきっかけもテレビの番組でした。それは、海外では自閉症を支援する介助犬が活躍しているという内容です。興味をもった私は、さっそくネットで調べましたが、検索の仕方が悪かったためか、その時はこれといったサイトを見つけることはできませんでした。
そのような状況で、何とか見つけたのが「ありがとう、ヘンリー 自閉症の息子とともに育った犬の物語」というスコットランドの母親が書いた実話でした。
以下はamazonの商品説明です。
『重度の自閉症にとらわれた息子デールをかかえ、途方にくれていた一家のもとに、1匹の子犬、ヘンリーがやってきた。それまで誰とのコミュニケーションも拒んでいるかのように見えたデールは、ヘンリーとだけは奇跡的に心を通わせはじめる。母親のヌアラは、その無邪気な子犬にすべての希望を託し、デールを世界へ導きだす試みに乗り出した―絶え間ない努力で自閉症に挑み続け、息子の成長を支えてきた母親が、その18年間を振り返って綴る感動のノンフィクション。』
ヘンリーという犬にだけ心を通わせることができたのは何故か、何がヒトと違うのか、この事に強い関心をもった私はこの本が格安だったということもあり、躊躇なく購入することにしました。
デールは20歳のあるインタビューで次にように語っています。
『自分はまだ自閉症を抱えていることはわかっています。それからは決して逃れられないけれど、なんとか克服することはできると思います。』
つまり、自閉症はなくなるものではなく、受けいれ、共存するもの、コントロールするものなんだと思います。
下の図は自閉症にのみ込まれていたデールが、それを克服し、自分の一部として受け入れるために何が必要だったのかを考えてみたものです。以下にその説明を付けました。
①愛情と成長のための教育
この主役は母親のヌアラと父親のジェイミーです。デールは早産であり、逆子のため頭部に変形がありました。はじめての言葉は「木!(Tree)」で生後26ヵ月の時でした。
2歳4ヶ月の時には、聴力検査を受け正常と判定されましたが、自閉症ではないかというヌアラの懸念はデールの成長とともに強くなっていきました。
ヌアラの最初の苦闘は、医学的に「自閉症」の診断を勝ち取るというものでした。これは自閉症と診断されることによって、デールがその時に必要だったサポートや教育を受けることができるようになるという理由からでした。
その判定はデールが3歳11ヶ月(最初の診察から16ヵ月後)の時でした。13人の各専門家によるデールの最終診断は、典型的な自閉症であり、1番の問題はボディランゲージを含む全般的な種類の言語障害という結果でした。
物語の根底にあるのは、「自閉症に対する配慮、サポート、教育」のように思いますが、それは、時には自閉症児に対する特別な教育、支援を受けるものであり、時には健常者が通う学校の中に身を置き、学習すること、経験することでした。特にヌアラが卓越していたのは、「今」と「近い将来」において、デールが必要とするものは何かを見極める洞察力と、それを実現させる行動力だったと思います。ヌアラがデールに対して行ったことは、デールの成長のためであり、常に教育という開かれた、客観性、多様性を兼ね備えた場を求めていました。
一方、父親のジェイミーはデールを理解し、ヌアラを支えることに迷いはなく、二人にとって素晴らしい父親でした。そのジェイミーの覚悟が一線を超えたのはデールが4歳の時の交通博物館の出来事だったように思います。それは次のような出来事でした。
『ある夜のこと、わたしたちはみんなでフィッシュ・アンド・チップスの夕食のテーブルを囲んでいた。デールはおとなしいモードに入っているようだった。ジェイミーはイースト・キルブライドの職場から帰ってきたばかりで、わたしたちは二人とも疲れていた。わたしがデールの食事を切り分けはじめると、彼が突然「蒸気機関車、蒸気機関車、蒸気機関車」と歌うようにいいはじめた。ジェイミーの心はがくんと沈んだ。彼にはこれが何を意味するかわかっていたからだ。交通博物館は閉まっていると彼は説明しようとしたが、デールは「蒸気機関車」とますますしつこく繰り返した。「この子には[閉まっている]という概念がわからないのよ」とわたしはやさしくジェイミーに思い出させた。
ジェイミーはこの問題を解決するためには何をしなければならないかをすぐに悟った。「これから2時間ほど、この子をグラスゴーまで車で連れていってもどってくるほうがよさそうだな。行かなかったらまたすごいかんしゃくと格闘しなきゃならないだろうからな」とジェイミーがいった。そんなわけで、彼はデールに往復100km近いドライブに行く準備をさせた。わたしは手を振って二人を見送り、「グッバイ、ダーリン」とデールにいった。彼はすぐにオウム返しに「グッバイ、ダーリン」といって、わたしのほうを一度も振り返らずに車のほうに歩いていった。
自分だけの時間が2時間あることに気づいて、わたしはバスルームに走った。今回だけは平和に静かに入浴を楽しめるのだ。
ジェイミーから後で聞いたところによると、デールはグラスゴーに行く途中はいつものように何もいわずおとなしかったが、ときどき無表情な顔のままジェイミーの手を握ったそうだ。いま思えば、これはジェイミーが自分のやりたいことをしてくれていることへの彼なりの感謝を示していたのだろう。
彼らが空っぽの駐車場に車を止めたときには、暗くなっていた。交通博物館への階段を登っていき、デールがドアを引っ張ったが、ドアは開かなかった。ジェイミーはデールの目の高さになるようにしゃがみこみ、こう説明した。「わかるだろ、デール、入れないんだよ。博物館は閉まってるんだ」デールがだまったままなので、ジェイミーは話しつづけた。「いまは暗くて、夜なんだよ、デール。だれもここにはいない」デールはそれでも黙っていたが、また博物館のドアを開けようとした。ジェイミーは、「博物館は閉まっているんだよ。蒸気機関車は休んでるんだ。また明日働くためにね」ジェイミーがデールを車のほうに向かせたとき、彼の説明に満足したのか、デールが「明日働く」と繰り返した。「そうなんだよ、デール。だからおうちに帰って、ぼくたちも休もう。汽車みたいにね」ジェイミーはこのままこの場をうまく切り抜けられるだろうかと思いながら、ぴりぴりしていった。デールがまたオウム返しにいった。「汽車みたいに」それから、二人がちょうど車までもどってきたとき、ジェイミーをほっと安心させる一言がデールから発せられた。「閉まってる」この言葉と共に、二人は帰途についたのだった。
二人が家に帰ってきたとき、わたしはバスローブに身を包み、お気に入りの赤ワインのグラス片手にくつろいでいた。「どうだった?」とわたしはきいた。「だいじょうぶだよ」とジェイミーは疲れきってはいるがうれしそうにいった。
「あの子はほんとうに意味がわかったと思うよ」うれしくなってわたしは彼を励ました。「こういうふうにやればできるのよ。これからもすごくたいへんだろうけど、でもやれるわよ―一緒にがんばりましょう」「そうだな、できるよね」とジェイミーは答えた。「でも、ぼくたちに他の生活はなくなるけど」もちろん彼のいうとおりだった。デールの世話をしていると他の何をする時間も残らなかった。それでも、ジェイミーがこんな突破口を開いてくれてわたしはすごくうれしかった。ジェイミーはほんとうに疲れていたし、この解決策には時間も距離も労力もかかった。だがこれ以来「閉まっている」という概念が定着したのだ。デールはこの言葉がきらいになったが、わたしたちは大好きだった。いつでも必要なときにはわたしたちに有利なようにこれを使うことができたからだ。
その夜、ジェイミーがソファに寝転がっていると、デールがジェイミーの胸の上に乗った。彼はときどきこういうことをする。ジェイミーはわたしのほうを見てこういった。「この子が新しい言葉を覚えたのはすごいことだよ。だけど、ぼくたちがこの子に名前をきいて、この子がちゃんと答えてくれたらすばらしいと思わないか?」
この説を証明するようにジェイミーはデールのほうに顔を向け、デールにこうたずねた。「きみの名前はなんていうの?」わたしたちの息子が生まれて初めて「デール」と答えたときの、ジェイミーの仰天した顔をわたしは決して忘れないだろう。それはまるで、彼らの交通博物館までの突拍子もないドライブを通じて、デールがすばらしい父親との特別の絆をつくったかのようだった。』
②自閉症は脳幹部での各感覚信号が混線したような状態
・これはこの本に書かれているものではありません、ブログ「感覚統合の理論と実践」で学んだことで、それは次のようなものです。
『エアーズ(Anna Jean Ayres:アメリカの作業療法士)は感覚の中でも、前庭覚、固有覚、触覚の三つが子どもの運動、情緒、認知、および言語発達の上で最も重要な初期の刺激であるとし、そのためには脳幹レベルの統合が重要であり、脳幹を感覚統合の中枢として位置付けています。』
ここで、あえてこの事を引っ張り出してきた理由は、自閉症は脳を原発とする問題であり、脳の機能改善、混線した感覚の信号が整理整頓されるイメージを頭に入れておくことは大切ではないかと考えたためです。
添付した図は網様体の働きと脳の中の場所をお伝えするためのものです。
③言葉の習熟
デールは、1番の問題はボディランゲージを含む全般的な種類の言語障害と診断されました。
言語障害はコミュニケーションや社会性の問題に関わるのは当然ですが、イライラなど情緒や健康面にも影響してくる最重要課題の一つであると思います。これは、私が訪問させて頂いている小さな障害児センターの言語障害をもつ子どもたちと接して感じるものでもあります。
物語では、デールがかんしゃくを爆発させたある日、父、ジェイミーの咄嗟な機転から、デールとの会話の間にヘンリーという存在を挟むことで、デールが抱える会話に対する恐れや緊張感などの高いハードルを下げる、不思議な三者方式の会話が展開されるようになりました。(一言でいうと話者がヘンリーになりすますという方法です)
たいへん長文にはなりますが、この説明だけではどんなものかをイメージするのは困難なため、その経緯や何が行われたのかについてご紹介させて頂きます。
『1995年の春ごろには、デールはヘンリーと同じようにわたしたちを彼の人生に立ち入らせてくれる気になるまでにはまだ何年もかかるだろう、とわたしたちも冷静に受け入れられるようになっていた。スピーチ・セラピー、学校での特別プログラム、わたしたちも家族の努力にもかかわらず、デールが社会にうまくなじんでやっていくまでにはまだまだ時間がかかりそうだった。デールはまだ顔の表情と、言葉以外のコミュニケーション全般の解釈が大の苦手で、語調にも問題があった。まちがった調子で話したり、不適切なところで笑ったりするだけではなく、ある特定の言葉を耳にすると際立った苦痛を感じるのだった。わたしたちが「オーケー」とか「学校」のように彼が聞きたくない言葉を口にすると、突然激怒することがあった。
わたしたちは注意していたが、しょっちゅう使う言葉だったので、ときどきふと漏らしてしまうのはしかたのないことだった。わたしたちのうっかりミスでデールがかんしゃくを起こしてしまわないように、口にする言葉をいちいち気にしなければならないのは容易なことではなかった。だが、まさにこの問題ゆえに、デールとヘンリーと一緒のわたしたちの人生にとんでもないねじれが生じることになろうとは、とても予想できなかった。
ある一見ごくふつうの日のこと、デールがヘンリーを脇に従えてうれしそうにダイニング・ルームにいるあいだに、わたしは宿題に関してなにか先生からのお知らせがあるかどうかを見るために彼の通学かばんを調べていた。連絡帳を見つけ、彼の字がずいぶん上達したのに気づいたので、わたしはデールのところに行き、わたしが見てうれしかったページを見せた。
「デール、字がすごく上手になったわね。あなたのこと、すごく誇りに思うわ」とわたしは彼にいった。
とたんにデールがこの言葉にすごく腹を立てたので、「誇りに思う」という言葉が彼が聞くに堪えない言葉のひとつだったことを思い出したが、もう遅すぎた。彼は荒れて部屋を走り回り、「[誇りに思う]っていうな」と叫びながら、自分の頭をつかもうとした。
わたしは彼を安心させようとしてこういった。「あなたのことを誇りに思うっていうのは、いいことなのよ。オーケーなのよ」
こんなにあわてている時でなかったら、わたしも「オーケー」という言葉を避けたはずだった。だが、またしても気づくのが遅すぎたために、デールの苦悩はさらに大きくなった。
「[オーケー]っていうな!」と叫ぶと、デールが怒り狂って頭を壁に打ちつけはじめたので、彼が最大級のかんしゃくに突入したのがわかった。こうなると、過去にわたしがいつもしなければならなかった方法を使って、彼を抑制するしか他になかった。
わたしは彼の上に馬乗りになり、頭を保護して手で包みこみながら、彼を安心させようとした。ヘンリーはそのころにはこんなデールを見るのには慣れていて、ただ彼の横にねそべって見守っていた。デールの怒りはたいへんなものだったので、わたしはこうして40分以上もすわっていなければならなかった。その間にわたしはブラウスの袖をデールに引きちぎられた。仕事から帰ってきたジェイミーを待っていたのは、こういう光景だった。ジェイミーを見てほっとしたわたしは、まだ暴れ、泣き叫んでいる息子に向かってこういった。「デール、誰だか見てごらんなさい。パパよ」
同じように彼を安心させようとして、ジェイミーがいった。「デール、パパは庭を走ろうかなと思っていたんだけどな。走るかい?」だが、この言葉も役には立たず、デールは怒りで顔を真っ赤にし、目は飛び出さんばかりだった。
わたしはジェイミーにこうぼそぼそいったのを覚えている。「まったくひどいわ。犬でさえいまでは心配そうにしている」どういうわけか、この言葉がジェイミーの中に一瞬の霊感を生み出した。
彼は突然低い、気どった声で息子に話しかけた。
「デール、ヘンリーだよ。ぼく、きみが泣いているのはいやだよ。すごく心配だもの。お願いだから泣き止んでくれないかな?」(青字はヘンリーになりすましての会話)
これを聞くと、デールはすぐに落ち着きをとりもどし、犬に向かっていった。「わかったよ、ヘンリー、ごめんね」
ジェイミーとわたしはほっとしながらもわずかに戸惑ったように顔を見合わせた。やがてジェイミーがまた同じ低い声でいった。「じゃあ、デール、外に出て駆けっこするかい?」
この言葉に、息子は起き上がり、ほとんどわたしを押しどけるようにしてこういった。「いいよ、ヘンリー。行こう。」デールはヘンリーの首輪をひっぱって、庭に出て行った。
その夜になり、わたしたちは二人とも、さっき起こったことをよく考える間もないまま、来るべきベッドタイム・バトルにそなえて気持ちを引き締めていた。
ジェイミーが「デール、パジャマ。寝る時間だよ」と、先に用件を切り出した。ヘンリーは暖炉の前に寝そべって、気持ちよさそうに眠っていた。デールは自分の犬を見て、それからジェイミーのほうに行くと、顔を見ずに彼のジャンパーを揺すってこういった。「ちがうよ、パパ。ヘンリーみたいにしゃべって」
再び、ジェイミーとわたしは顔を見合わせた。それからわたしは犬のほうを向いてうなずき、デールがいうとおりにするべきだとジェイミーに身振りで示した。彼は了解し、これ以後ひじょうに馴染み深いものとなる声でいった。 「デール、ヘンリーだよ。お願いだからパジャマを持ってきて。もう寝る時間だよ。ぼく、疲れちゃったから、ぼくも自分のベッドに行くよ」
これを聞いて、デールは満足げに答えた。「わかったよ、ヘンリー」そして急いで自分の部屋に走っていった。
わたしたちは困惑してすわりながら、これからまだバトルが待ち構えていると考えていた。だが、デールは実際にパジャマに着替えてもどってきた。こんなことはそれまで一度もしたことはなかったのに。ボタンまで自分でかけようと努力していた。もっとも、ボタンはかわいらしくかけちがえてあったが。
彼(デール)は一瞬ヘンリーを見て、それから断固とした調子でいった。「ヘンリー、寝る時間だよ。ベッドへお行き」
ジェイミーとわたしは唖然としてそこにすわっていたが、やがてジェイミーがようやく声を―彼本来の声をとりもどしていった。「おやすみ、デール」またもや前代未聞のことが起こった。デールが「おやすみ、パパ」といって、ついにわたしたちの言葉に反応したのだ。
これがあまりにも耳に心地よかったので、わたしも思い切っていってみた。「おやすみ、デール」
その結果返ってきた「おやすみ、ママ」という言葉は、わたしがそれまで聞いた中で最高に甘い音楽だった。
ヘンリーがしゃべりはじめたあの記念すべき日から、その効き目はほとんど奇跡といってもいいほどのものになった。デールは彼の犬が「頼んだ」ことならほとんどなんでもやるようになった。
わたしたちがあの声を発見したまさに翌日の朝、わたしがその声を使ってもデールが反応してくれるかどうか不安を感じながらも、その機会をつかまえた。いつものように、デールはぐずぐずしていて、もうすぐスクール・タクシーがやってきそうだった。ふつうならわたしがあいだに入って急がせると、彼は腹を立ててしまう。だから、その朝はかわりにヘンリーがデールにこう頼んだ。
「デール、靴をはいて、コートを着て。タクシーがやってくる音が聞こえるよ」わたしはジェイミーが使った低くて気どった声をできるだけ真似しようとした。すると驚いたことに、デールはすぐに準備をして、タクシーがやってきて止まるまでに、もうヘンリーをつれて玄関ドアのところで待っていた。
デールが帰ってくると、わたしはいつものように学校日誌をチェックした。わたしがこうするのは、彼自身の口から何があったのかを話してくれるよう励まそうとしてのことだったが、たいていの場合、ひとことで片付けられるか、あるいはすごく腹を立てて「[学校]っていわないで!」と不機嫌に怒鳴られるかのどちらかだった。
だが、きょうは、デールがヘンリーをそばにおいて遊ぼうかと落ち着いたところで、わたしは手に日誌を持って用心深く近づいていき、ヘンリーの声できいた。「デール、きょうは学校で何をやったの?」
間髪をおかず、デールはきっぱりと答えた。「劇だよ、ヘンリー」
「デール、劇ってなに?」ヘンリーが気をよくしてつづけてきいた。「おもしろい?」
「うん、ヘンリー、すごくおもしろいよ。ボートに乗って島に行くんだ」
「デール、濡れなかった?」
「ううん、ばかだなあ、ヘンリー。ふりをしただけだよ。劇ではふりをしてお芝居するんだよ」
デールと話すときのいつものルール ―たとえば、ものごとを単純にする、など―
に従っているかぎり、ヘンリーの助けを借りればこういうふうなごく初歩的な三者会話ができるということがわかった。こんなふうに会話ができることにわくわくしたが、これがデールとのコミュニケーションのやり方として適切なのかどうか心配になってきた。帰宅したジェイミーに、わたしはデールがあの声だとどれほどうまく反応するかを話したが、この方法を使い続ける前にアドバイスを得たほうがいいだろうということでわたしたちの意見は一致した。
さいわい、セント・アンソニー校でデールを担当しているクリスティン・カスバートというスピーチ・セラピストが家庭訪問に来ることになっていた。彼女は優秀なスピーチ・セラピストで、学校でオデッセイ・ドラマ・プログラムを実践しており、子どもたちに人気があった。彼女はまたソシアル・ユース・ランゲージ・プログラム(SULP)というスピーチ・セラピー・プログラムも使っていたが、これはとくに自閉症児向けにつくられたもので、社会言語のルールを説明するために音声と絵で描いたキャラクターが使われていた。リスニング・リジー、バッティング・イン・ベティ、ルッキング・ルークなどのキャラクター・ネームを使ったこのプログラムは、デールや他の子どもたちにほんとうによく役立ったが、皮肉なことにこのテクニックはわたしたちがずっと昔にトーマスの仲間たちを使って考案したのと同じようなものだった。
クリスティンが学校でデールと一緒にやっているすばらしい仕事にけちはつけたくなかったので、彼女が家に来てくれたときには、ヘンリーに関する状況を説明するだけにした。そして彼女のアドバイスを聞いてほっとした。
わたしがデールの自閉症にひじょうに理解を示していることを知っているので、彼女は「このテクニックを建設的に、かつ責任をもって使うかぎりは、このままやってだいじょうぶです」といってくれたのだ。わたしたちがやっとデールに心地よいコミュニケーションの手段をみつけだしたこと、やがて時間がたってデールが進歩したときには、もちろんヘンリーの声を使うのをやめることを目指していることを、クリスティンはわかってくれていた。当然それがわたしたちの最終的な目標だし、それまでの過程でもヘンリーの声をどのように使うかについては細心の注意を払うつもりだといって、わたしは彼女を安心させた。
この家庭訪問直後の1995年の夏に、ジェイミーとわたしはジム・テイラーが発表者の一人となっている自閉症に関する会議に出席した。なんとか彼と話す機会をつくって、わたしたちのこの珍しい発見をどう思うかときいてみると、「不思議なことではないですよ。第三者は面と向かった会話に伴う不安を軽減させますからね」といった。
ジムは犬がしゃべるという例には出会ったことはなかったが、ストルーアン・ハウス校で、不安感の強い男の子がジムに背を向けて電話をとりあげ、受話器に向かっているときにだけ何で困っているかをジムに話すことができた、ということがあった。彼らは二人とも同じ部屋にいたのだが、この間接的なコミュニケーション手段が、面と向かった会話のときにはどうしても現れてくる言葉以外のプレッシャーをまったく感じずに、自分を表現することを可能にしたのだった。
わたしたちにはジムがいわんとすることがよくわかった。ヘンリーがデールの電話になったのだった。ヘンリーの穏やかな顔と目は、人間だったら強要してしまうある種の社会的要求をデールに求めないのだった。ヘンリーはまた、人間の友達にはつきもののプレッシャーをまったく感じさせずに、デールにいかにすれば関係がうまくいくかを教えてくれ、デールの初めてのほんとうの友達になったのだった。
家に帰ると、いかにジムが正しいかがわかった。わたしたちがヘンリーの声を使うと、デールはヘンリーの顔を見るのだった。まっすぐ目をみつめ、ヘンリーのそばに寄っていった。わたしたちが普通の声でしゃべるときには、彼はわたしたちの顔を見るのを避けるか、前やったように、わたしたちの顔の間近まで顔を近づけてくるかのどっちかだったのに。
この声を使い始めた最初のころ、とっさに何かを伝えなければならないときから、三人での会話を続けるときまで、わたしはヘンリーの声を出しどおしで声がしゃがれてしまった。デールと一緒に宿題をやるときも、彼と遊ぶときも、夜寝る前に本を読んであげるときもそうだった。ヘンリーはまるで「自分の」声に興味津々とでもいうように首をかしげながら、その間ずっと注意を払っていた。わたしの側からすれば、ヘンリーがそんなふうに熱心に参加してくれるので、まるで彼がほんとうにわたしの二番目の子どものような気になってきた。デールはまだかんしゃくを起こしていたが、回数も少なくなり、一回の長さも短くなってきた。彼が動転しているときにヘンリーが話しかけると、わたしやジェイミーがやるよりずっと早く彼が安心するようになったからだ。
デールがもうすぐ七歳になるというころ、彼自身がヘンリーをどれほど大切に思っているかを痛切にわたしに語ってくれることがあった。「ぼく、あの柔らかくてかわいい犬が大好きだよ。ヘンリーはすばらしい。もし、ヘンリーがいなくなったら、ぼく、いつまでも泣いて悲しむと思う」と。
このころ、デールの絵にも励みになるような変化が起こった。以前からトーマスと仲間の機関車の絵ばかりを描いていたのだが、いまではそこに明らかにそれぞれちがう、楽しそうだったり、悲しそうだったりする顔の表情がつくようになった。さらにわたしたちを驚かせたのは、デールはまだわたしたちと目を合わせることに苦労していたのだが、機関車がお互いしっかりと目を見合っている絵を描くようになったことだ。それに続けて、デールは機関車だけでなく、おそらく彼とヘンリーだと思われる人や動物の姿も描くようになってきた。これは彼の想像力が進歩しはじめたことを示すものだろう。』
この本の最後の章は「デール自身の言葉」として25の事柄について語られています。その冒頭に上記のデールとヌアラ・ジェイミーが取り組んできた特別な言語習得法について、ヌアラがデールの言葉を次のように紹介しています。
『子どもたちがコミュニケーションをとっていないとき、ついつい彼らは何もわかっていないと思ってしまいがちだ。だが、デールが10歳のとき、彼はわたしにこう話した。「もしぼくたちがヘンリーを通じて話していなかったら、ぼくはママたちとは絶対に話さないことを選んでいたよ」』
④手にしなければならないものは“自信・自尊心”
「言葉」は生きていくうえで必要な武器、手段といえると思いますが、デール自身が自閉症を乗り越え、コントロールしていくために最も重要だったものは、この自信と自尊心だったようです。それは本の中で度々出てくることで分かります。断片的に書き出すだけでは不十分なのは明らかですが、ご参考として列挙させて頂きます。
1.p198:ヌアラ曰く、『「5分、5年反応」(5分間、ヘンリーをひとりで家にほっておくと、その後は5年ぶりに会ったようにお喜びすること)はデールの自信と自尊心を高める上で驚異的な働きをした。』
2.p350:ヌアラ曰く、『目前の困難を前に、あらゆる機会をとらえてはデールが自信を持てるように励まし、普通の子どもたちの中でやっていく経験をさせるようにした。』
3.p351:ヌアラ曰く、『彼の自尊心を高めるこのようなこと(最優秀作品に選ばれたこと)がなかったら、デールはグーロック・ハイスクールでどうやっていけただろうかと思う。』
4.p452:デール曰く、『プロスペクツの協力はなくてはならないものだった。彼らの協力がなかったら、カレッジに関して自分の目の前の問題すべてに対処できなかったはずだ。ワークショップや彼らがぼくと一緒にやってくれた個々の作業がすごく役立ち、おかげでリラックスでき、カレッジでの勉強にも自信が持てた。』
⑤助けてくれるのは“友”の存在
言うまでもなく、ひとつはヘンリーの存在です。ヘンリーについては「デール自身の言葉」の中で「ヘンリーが特別な理由」として次のように解説しています。(これが私の疑問の回答です)
『ヘンリーはとにかくやさしく、人なつっこく、社交的だった。かしこそうな顔をしているところが好きだったし、ぼくはいつも彼を信頼していた。だから、彼といるととても居心地がよかった。目を見ればすべてがわかる。かわいい目や顔の表情によって、彼の気持ちが理解できた。ヘンリーの表情は単純だったので、それもぼくにはわかりやすかった。それがぼくの自信につながり、彼といると安心できた。ヘンリーがいつもみんなの注目を求めたがっていたところがすごく好きだった。みんなが彼のことを褒めてくれて、ぼくにあれこれ話しかけてくるのは気分がよかった。』
また、下記はヘンリーがガードナー家に来た時のヌアラの感想です。
『1994年5歳8ヶ月ヘンリーが我が家にやってきた瞬間からデールにほんとうの変化が出てきたのを目にしていた。彼は迷子のひとりぼっちの子どもから幸せな少年にとつぜん変身してしまった。ついに彼に目的を与えてくれる友達ができたのだ。ヘンリーが我が家の敷居をまたぎ、彼の特別の魔法を発揮しはじめる前には考えられなかったほど我が家は活気づいてきた。ヘンリーが来て二日の終わりには、彼なしではやっていけないとみんなが感じていた。』
そして、もうひとつ非常に重要だったことは、ヘンリーだけでは十分でないと考えたことです。
『いまではデールも進歩をつづけ、わたしたちと会話ができるようになってきたが、ほんとうの友達がいないために生活に物足りないところがあるのは否定しようがなかった。もちろん彼には特別大切な犬の友達はいたが、それ以外には生活を分かち合う人がだれもいなかった。彼がずっとひとりぼっちなのだとしたら、どれだけ勉強しても、あまりに悲しく目的がないように思われた。』
この課題を解決してくれたのが、セント・アンソニー校の同じユニット入ってきて、デールが相談係となったライアンとテレビゲーム(ソニック・ザ・ヘッジホッグ)を通じて友になった健常者のロバートの二人でした。そして、これをきっかけにデールの社交性は徐々に広がっていくことになります。

画像出展:「SEGA」
今回、あらためてネット検索したところ、いくつか興味深いサイトを見つけましたのでお伝えします。
付記
先月22日の日曜日は驚きの解散による総選挙の投票日でした。野党の突貫工事による成果は凸凹があり、既存政権の大勝という結果で終わりました。
ところで、同じ日、注目されていた村田諒太選手の世界タイトルマッチの再選が行われました。試合は村田選手の7回TKOにより、念願の世界チャンピオンベルトは村田選手の手に渡りました。
『自信とは努力と結果が結びついた時に生まれるもの』これは村田選手の言葉です。そして、「自信」とは安泰なものではなく、常に掴み取るものであると言っていました。
私は、何となく、「自信」は一つのゴールという認識をもっていたので、この言葉はとても新鮮でした。そして、「結果」とは「努力」による小さな変化であっても良いのではないかと思いました。

カザフスタンのゲンナジー・ゴロフキン選手が、ミドル級では世界最強といわれているチャンピオンです。今後、村田選手の目標となる選手のようです。
「おこだでませんように」
「発達ナビ」という発達障害について様々な情報提供をされている優れたサイトがあります。
その中に、「大人の一方的な注意は、子どもにどんな影響を与えるのだろう」というコラムを目にする機会がありました。下記『』はその一部です。
『クラスではいつも1人で過ごし、授業中に脱走しても放置され、校庭の片隅に座っているところを、よく見かけました。ボランティアの帰りに体育館を覗くと、「〇〇君は悪い子です」と名指しで先生から怒られているのを、見たこともありました。
娘は彼のことが好きだったそうです。「だって〇〇君は、私がいじめられているとき助けてくれた」「あの子はいい子だ」と、私に教えてくれました。
ある日の読み聞かせの時でした。読み始めたとき、最初はいつものように、落ち着きなさそうにゴソゴソし、顔もそっぽを向いていた彼。話が進むにつれ、いつの間にか食い入るような目をし、聞いていました。』
なかなか関心を示さない子が、興味を持った絵本とはどんなものだろうか?という疑問がわき、この絵本を購入してみることにしました。
今回のブログでは作者である、くすのき しげのり先生の「あとがき」の全文をご紹介し、その後に石井聖岳先生の5枚の絵を掲載させて頂きます。
あとがき
「おこだでませんように」
『そう書かれた小さな短冊を見たとき、私は涙が出そうになりました。短冊を書いた男の子は、いつも怒られているのでしょう。この子が、楽しいと思ってしたことや、いいと思ってしたことも、やりすぎてしまったり、その場にそぐわなかったり、あるいは大人の都合に合わないからと、結果として怒られることになってしまうのかもしれません。
でも、この子は、だれよりもよくわかっているのです。自分は怒られてばかりいることを。そして、思っているのです。自分が怒られるようなことをしなければ、そこには、きっとお母さんの笑顔があり、ほめてくれる先生や、仲間に入れてくれる友だちがいるのだと。
そんな思いをもちながら、それをお母さんや先生や友だちに言うのではなく、七夕さまの短冊に、一文字一文字けんめいに書いた「おこだでませんように」。この子にとって、それは、まさに天に向けての祈りの言葉なのです。
子どもたちひとりひとりに、その時々でゆれうごく心があります。そして、どの子の心の中にも、このお話の「ぼく」のような思いがあるのです。どうか、私たち大人こそが、とらわれのない素直なまなざしをもち、子どもたちの心の中にある祈りのような思いに気づくことができますように。』
くすのき しげのり


きのうも おこられたし……。
きょうも おこられてる……。
きっと あしたも おこられるやろ……。
くすのき先生からのメッセージである「とらわれのない素直なまなざしをもち、子どもたちの心の中にある祈りのような思いに気づくことができますように」
このことを大切にしたいと思いました。
感覚統合法の理論と実践
今回は『新・感覚統合法の理論と実践』の再チャレンジです。前回(2016年11月)は「前庭系と筋緊張」というタイトルで、前庭系を説明する時に参考としましたが、この本に対する全体の理解は低く、明らかに消化不良状態でした。 全編の理解度を高めるため、そして発達障害児へのマッサージを行ううえでの基礎知識を増やすため、あらためて読み直しました。

著者:坂本龍生・花熊 暁
出版:学習研究社
※掲載されている図、イラストに関し、「画像出展」の明記がないものは、全て『新・感覚統合法の理論と実践』からの出展になります。
目次
1.子どもの発達と感覚運動 (第1章の概要です)
2.感覚統合法理解の基礎 (第2章、3章より感覚統合理論を支える神経生理学について。他の本からも図などをもってきました)
3.触覚のしくみとその働き (第4章~6章については、触覚と固有覚を取り上げました)
4.固有覚のしくみとその働き
5.神経生理学を意識したマッサージ (脳幹、固有覚、触覚、前庭覚の視点からマッサージをどのように行えばよいか考えました)
ちなみに、この本の見出しは次の通りです。
理論編
第1章 子どもの発達と感覚運動の指導
感覚運動指導の意義
障害児の感覚運動課題
生物としてのヒトの発達
ヒトの運動系の発達と感覚統合
ヒトの認知系の発達と感覚統合
第2章 感覚統合法理解の基礎
感覚統合法の背景
感覚統合とは何か
感覚統合過程
感覚統合障害
感覚統合指導の原理と方法
第3章 神経系のしくみとその働き
神経系の概要
感覚統合の中枢としての脳幹
感覚統合理論を支える神経生理学
第4章 前庭系のしくみとその働き
前庭系のしくみ
前庭系の働き
前庭系の特徴と指導上の意義
前庭機能の評価
前庭刺激指導の留意点
第5章 触覚系のしくみとその働き
日常生活を支える触覚情報
体性感覚系のしくみと働き
触覚系の発達
触覚の異常と評価
触覚系の異常への指導
第6章 固有感覚系のしくみとその働き
固有感覚系の働き
固有感覚系の神経学的理解
固有感覚系の臨床観察
固有感覚系の指導
実践編
第7章 発達の遅れた子どもへのアプローチ
精神遅滞児の感覚運動の特徴
症例別に見た指導の実際
第8章 体の不自由な子どもへのアプローチ
臨床観察のポイント
臨床像の理解と指導プログラム
症例別に見た指導の実際
第9章 自閉的な子どもへのアプローチ
感覚の調整の障害とその評価
症例別に見た指導の実際
第10章 感覚運動指導における認知とコミュニケーション
遅れの重い子どもへの配慮点
認知面への配慮
コミュニケーション面への配慮
終章 感覚統合法の研究動向とこれからの課題
感覚統合法の動向
米国での論争
障害児教育における意義と課題
1.子どもの発達と感覚運動
子宮の中は羊水の中に漂う無重力の世界。単調な母体の心音、腸音などの音の世界も、ほの暗くぼんやりとした光の世界も、劇的に変化します。羊水の感触は、温覚や触覚など種々の皮膚感覚が刺激される世界へと変わります。
赤ちゃんは当初は生まれつき持っている反射や反応が助けてくれますが、徐々に感覚運動体験を積み、この多様性に富む複雑な世界に対し、柔軟に行動できるよう、自らの反応を複雑化していきます。 赤ちゃんの学習は感覚刺激への反応に始まり、動きの形で反応し、母親やその他の人々も含めた広い意味での環境との相互作用で成長します。基盤となる感覚運動発達は、姿勢、手指の巧緻運動と各部位(首、肩、肘など)の固定、感覚-運動-感覚間の統合(話を聞きながらノートに正しく書き取る等の総合的動作)などです。
脳の研究やリハビリテーション学の進歩により、視覚や聴覚に加え、基本的な感覚ともいうべき触覚、固有覚、前庭覚の働きと様々な感覚間の情報統合が、子どもたちの発達の基礎となることが分かってきました。
動物が運動する場合、運動に関連して常に二つの感覚が必要です。一つは環境と自分との関係、一つは自分の中心と体の他の各部分との関係を教える感覚です。前者が前庭覚、後者が固有覚であり、これにより空間の中での運動が可能になります。
50cm幅の溝を跳び越すとき、大げさに身構えて、1mも2mも跳ぶということはしません。視覚は溝の幅と接地点の状況を教え、足底は今踏んでいる地面の硬さを教えます。私たちは前庭覚や固有覚などから得た記録に基づき運動の計画を立て実行します。もし、この溝が2mであれば、運動はもっと慎重に計画されます。接地したときに、倒れないのは重力空間に対する頭部の位置関係、その位置を支える足の頭部に対する位置と運動の関係が入力により絶えずコントロールされているからです。
2.感覚統合法理解の基礎
感覚統合法の背景
感覚統合理論を支える神経生理学
エアーズ(Anna Jean Ayres)は感覚の中でも、前庭覚、固有覚、触覚の三つが子どもの運動、情緒、認知、および言語発達の上で最も重要な初期の刺激であり、そのためには脳幹レベルの統合が重要であるとして、脳幹を感覚統合の中枢と位置付けています。
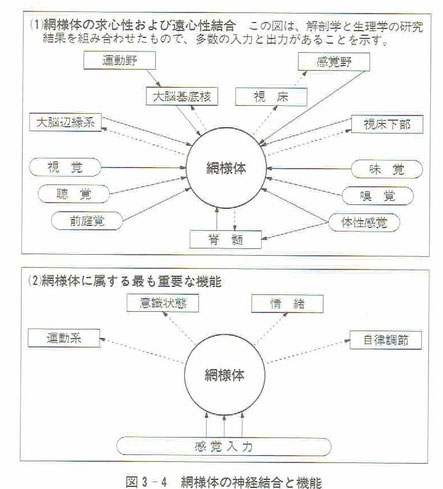
脳幹は下位の中枢神経で延髄・橋・中脳を含んでいます。また、脳幹網様体は脳幹の背中側にあり、白質でも灰白質でもなく、神経細胞体と神経線維が入り 交じって網目状をなしています。
脳幹は感覚の情報を受け、運動系、意識状態、情緒、自律調節に関わる、生命維持に不可欠な機能に関わっています。

この絵では、青線は脳幹網様体に入ってくる情報、赤線は主な働きを示しています。そして、●は「神経核」を表しています。
網様体に存在している神経核から発する指令のうち、下行する橋網様体脊髄路(内側網様体脊髄路)は伸筋の活動を高めます。同じく、下行する、外側の延髄網様体脊髄路(背側網様体脊髄路)は屈筋の活動を高めます。
これらの指令は、γ運動ニューロンに接続し、筋肉の活動を調節することで歩行リズムの調節などを含む随意運動を円滑にさせます。
画像出展:「人体の正常構造と機能」

上記3つの絵についてご説明します。
左上の図は、ブログ「前庭系と筋緊張」で使用したもので、『新・感覚統合法の理論と実践』の図を一部加筆したものです。また、他の2つは『人体の正常構造と機能』からの画像です。ここでは、前庭神経核についてご説明します。
この前庭神経核は脳幹の橋~延髄にまたがっており、対になっています。核は上核・下核・外側核・内側核と4つあり、内側核は頚髄から頚部の筋に、外側核は頚髄から腰髄の抗重力筋(脊柱起立筋など)に働きます。
耳にある前庭器官(半規管・耳石器)からの重力に関わる情報は、前庭神経核に伝わり、前庭脊髄路を興奮させ脊髄の反射回路を活性化させます。これにより、わずかな姿勢の崩れなどを認識し、抗重力筋に働きかけることで、姿勢を保持してくれています。
また、前庭神経核は眼球運動核(外転神経核・滑車神経核・動眼神経核)にもつながっています。これらの神経は眼を動かす筋肉、外眼筋(上斜筋・下斜筋・上直筋・下直筋・内側直筋・外側直筋)に作用します。
前庭覚・触覚・固有覚刺激の意義
前庭覚・触覚・固有覚の感覚系は、発達の初期段階で重要な役割を果たし、視覚と聴覚の発達や学習能力の発達の基礎を形成します。感覚統合法で問題とする脳幹の働きの改善にあたっては、これらの三つの感覚系からの入力は特に重要になります。
感覚統合指導
ヒトは、通常、運動したり遊んだりしているうちに刺激を感覚として入力しながら脳神経系が成熟していくので、そのための訓練を必要としているわけではありません。しかし、感覚と運動の不統合性が生じたときは、乳幼児であればあるほど適応反応がうまくいきませんし、発達が総じて遅れがちになります。したがって、そういう子どもたちの発達を支援するために、特別に構造化された環境を提供することが求められます。
感覚統合法の指導の中心原理
感覚統合の指導の基本的な原理は、感覚の入力、特に前庭覚や筋肉、関節などに存在する固有覚、あるいは触覚からの入力をできるだけ統合し、自発的な適応反応に高めるよう配慮し、それを制することを学ばせていくものです。指導していくための手掛かりとして、少なくとも次の6つの系列が重視されてきました。
①触覚系と前庭系の健常化をはかること。
②原始的姿勢反射(無意識に出る赤ちゃんの反応や姿勢)の統合を進めること。
③平衡反応を発達させること。
④視運動を正常化すること。
⑤身体両側の感覚運動機能の協調性を高めること。
⑥視覚的形態と空間知覚を発達させること。
感覚統合の指導は、ともすると遊戯療法と間違えられますし、学校では体育の授業ではないかという批判をよく受けます。しかし、感覚統合の指導は、活動のしかたや運動の技術を教えようとするものではありませんし、いわゆる教科的にいう体育でもありません。その根幹は、感覚入力のよりよい統合をはかるという目的的な治療行為であり、そのための観察、診断、指導プログラムが確立されています。
3.触覚系のしくみとその働き
日常生活を支える触覚情報
私たちは周りの環境を知るためだけではなく、姿勢、情緒、覚醒状態などを調節するためにも、日常生活の中で触刺激をむしろ積極的に使っています。触覚は人が社会生活を維持するための基礎として働き、日常生活全般に影響を及ぼしています。
感覚の種類と感覚器
「体性感覚」は、皮膚の表面で感じられる表在感覚と、もう少し深いところで感じる深部感覚を含めたものです。一方、「痛み」は痛みという刺激があるのではなく、圧迫や熱さなどの刺激が皮膚や深部の組織を損傷し、その時に出る発痛物質が痛みの感覚器に作用して痛みとして感じられます。
主な内因性発痛物質には、カリウムイオン、ブラジキニン、ヒスタミン、アセチルコリンなどがあります。カプサイシンは外因性発痛物質、PG(プロスタグランジン)は発痛増強物質となり、内因性発痛物質とは異なる物質です。

この表は、「触覚線維」と2つの「痛覚線維」を説明したものです。
触覚線維の特徴は、痛覚線維に比べ太くて(有髄Aβ線維)、速いというものです。
痛覚を伝える線維には鋭い痛みの一次痛を伝える高速タイプ(有髄Aα線維)と、鈍い痛みの二次痛を伝える低速タイプ(無髄C線維)の2種類があります。
これらの痛覚線維は、触覚線維と異なり、興奮性または抑制性に作用する神経伝達物質を伴います。表で紹介されている、Glu、SP、CGRPの3つはいずれも興奮性神経伝達物質です。抑制性伝達物質には、GABAやグリシンなどがあります。なかには受容体が興奮性か抑制性かを決める神経伝達物質もあり、これにはセロトニンやノルアドレナリンなどが該当します。
画像出展:「痛みと鎮痛の基礎知識[上]基礎編」
深部感覚に関係する筋肉からの情報は意識されにくく、圧迫、振動、運動覚、位置覚などは、筋肉の伸張状態を感知する筋紡錘や関節の感覚器(固有受容器)からの情報と皮膚の感覚の複合産物といえます。この他、触るだけでなく、指先を動かすことによって初めてわかる手触りや、物の形の弁別なども、指先の皮膚と指が動くときの筋肉および関節からの情報が、脳で統合されたことにより生じた感覚です。
体性感覚の経路
意識できる体性感覚の経路-脊髄視床路と後索毛帯路
意識できない体性感覚の経路
原始感覚系と識別感覚系
触覚系の発達
胎生期の神経発達
神経系の形成と組織化
受精後、四肢の出現に先立って、数週で神経系が形成され始め、3カ月目で口腔周辺への触刺激に対して、頭や体を後ろにのけ反らせる回避反射が出現します。反射は最も単純な感覚の処理のされ方ですが、この反射の出現は感覚入力と運動が結びつく回路ができていることを指しています。
回避反射はやがて吸啜・嚥下反射に変化し、生後の哺乳行動を準備します。この反射の防衛的なパターンから適応的なものへの変化は、神経系のフィードバック機構にその説明を求めることができます。刺激の入力によって引き起こされた運動反応は、最初の刺激に加え、筋肉からの新たな刺激を加えます。この繰り返しが神経線維の樹状突起の数を増やし、神経線維の髄鞘化を促進し、近隣のニューロンとの結びつきを密にします。その結果、反射の内容が変化していきます。
触覚と固有受容覚との統合
胎児は子宮内で、羊水、脂肪の膜などで何重にも保護されています。生後、これらの保護は突然取り外され、新生児にとって過剰な重力と刺激の溢れる世界で活動することになります。
そして、まず体の内外の境界となる皮膚に保護機制が強く働くことになりますが、保護機制だけではうまく環境に適応していけません。反射の中には環境に積極的にかかわっていく運動パターンもいくつか身につけています。モロー反射や非対称性緊張性頚反射、緊張性迷路反射は屈曲優位な新生児期の姿勢を是正していくのに役立つと言われています。
触覚と運動企画
新生児にも四肢の動きはありますが、頭や体全体の動きに影響されて、意図した動きになっていません。固有覚は触覚と統合されることによって身体感覚を明確にします。このようにして自分の体の全体のイメージ(ボディイメージ)とそれぞれの部分の位置関係の理解を生み、その効率的な動かし方の基礎を作りあげます。
触覚と情緒の発達
多くの動物の子育ての研究は、出生直後の子なめ行動が免疫機能をはじめとする生体の生命維持活動を高めることを報告しています。そして、人間の長い分娩時間中に受ける多量の触圧刺激が子なめに相当するものではないかと類推されています。
人間は誕生の瞬間だけでなく、その後の発達においても成人とは比べようもないほど、多くの触圧刺激を受けます。子宮内で多くの保護のもとにいた胎児がその保護を突然解かれるならば、生後もそれに替わりうる保護が必要だからです。乳幼児の自我や情緒の発達の研究家たちは、こぞってそれに相当するものを養育者との肌の接触を通した情緒的交流であるとしています。身体の境界に子宮環境を想起させる心地よい刺激を感じることは、子ども自身に安心をもたらし、この安心感が自・他を同時に感じさせ、自我を育てるとともに、人に向う愛着を育てるといわれています。
触覚系の異常への指導
抑制的効果
口腔周辺への触圧刺激、腹部への触圧刺激、手掌、足底への持続的圧刺激、背中への軽擦(少し圧を加えながらこする)、35℃から37℃の温度
促通(興奮)的効果
口腔周辺への動きのある触刺激、皮膚知覚体節T10への動きのある触刺激、ブラッシング、氷
刺激する体の部位
触覚に対する過敏さが目立つ子どもに対しては、比較的弱い刺激を耐えやすい背中、手足の外側部などに加え、それが耐えられるようになったら刺激を強くし、その後、徐々に敏感な部分に移行していくのが良い方法です。こする方向は遠心性(毛に逆らわない)の方が刺激が弱いものになります。
遊びの中への触刺激の導入
筋緊張の低下(低緊張)には促通的な刺激が、多動に対しては抑制的な刺激が必要になります。しかし、低緊張で多動を示す子どもも少なからずいます。このように刺激の与え方は機械的には決定できません。あくまで刺激を与えた結果をみながら、与えるべき刺激を調整する必要があります。人は最も大きな刺激源であり、人に対する感情によって、刺激の感じ方もずいぶん違ってきます。子どもとの信頼関係ができあがっていない段階では、抱いたり、近づいたりすることが子どもの不安を高めかねません。他人への不安は触覚への過敏性の結果であると同時に、その原因ともなります。
重症心身障害児など触刺激に低反応を示す子どもには、筋肉や関節からの刺激を同時に入れて、より識別的な触覚を発達させる必要があります。そのためには、手足を他動的に動かすだけではなく、体を起こし、首、体幹、手に支持性をつけていくことも大切な点です。
4.固有感覚系のしくみとその働き
固有感覚系の働き
私たちが運動するとき、固有感覚と呼ばれる筋肉や腱、関節からの情報が、絶えず脳に流れ込んでいます。私たちが目をつむっていても、体位はどうなっているのか、自分の体がどのように動いているのかが分かるのは、この感覚の働きのおかげです。
固有感覚系は、体の動きに関する情報を脳に送り、脳はその情報に基づいて体の動きを軌道修正します。私たちがなめらかに、そして意識的努力なしに、あるいは、動きのプロセスを考えたり一つひとつの動きを学習したりすることなしに、一連の運動を繰り返すことができるのは、固有感覚系の働きがあるからです。さらに、この感覚系の働きは、視空間認知や身体像(ボディイメージ)の発達にとっても必要不可欠です。
固有感覚は、運動感覚(意識的な感覚)と呼ばれることもありますが、この二つを区別せずに用いることが多くなっています。この感覚系からの情報は、ふつう無意識的に処理されますが、新しい運動をするときや大きな努力を必要とする運動の場合は、意識に上ります。この感覚を刺激する活動は、一般的に体幹部の筋肉活動で、少なくとも体重の移動を伴うようなものです。
固有感覚情報をうまく処理し、関節の安定と姿勢の安定をはかるためには、骨格筋の「同時収縮(屈筋群と伸筋群の同期的収縮)」の発達が重要です。同時収縮とは関節の周囲の屈筋群と伸筋群を同時に収縮させ、関節を一定の位置で固定する働きをさします。同時収縮は協調運動のような巧緻動作の発達にも深い関係をもっています。筋の同時収縮が発達するためには、その前段階として、屈曲と伸展の繰り返し運動である「相反性運動(屈曲と伸展の繰り返し)」が発達する必要があります。
屈曲のパターンは人生の早期に発達するもので、腹側の筋肉の機能と考えられています。たとえば、仰向けにした状態から起き上がるときに使うパターンなどです。屈曲は姿勢の安定の発達の土台であり、運動スキルが発達するうえでも重要です。このパターンを育てるには、ボルスターやフレクサースイングなどにしっかりとしがみついて乗る活動がよく使われます。こうした屈曲活動には、たいてい触覚活動が先行しており、活動から得られる触覚や固有感覚の刺激は、適切な運動の協調的活動の基礎となります。
屈曲と同様に伸展パターンも、人生早期に発達する背中側にある筋肉の機能です。子どもは、ジャンプのように興奮したときの動きに伸展パターンをよく使います。この伸展パターンは、姿勢の安定のもう一つの土台です。伸展パターンによる活動には、他の感覚刺激、特に前庭刺激が先行します。伸展パターンを引き出す活動として非常によく用いられるのは、スクターボードやハンモックに腹ばいで乗る活動です。
同時収縮は、自発的な関節の伸展を伴う運動の際に最も強力に現われます。トランポリンの上での意図的なジャンプ、腹ばいでスクーターボードに乗って壁をけって進んだり、両手で床をこいで進んだりする遊び、スクーターボードに乗って手に持ったリングを引っ張ってもらう遊びなどは、いずれも同時収縮する活動です。
同時収縮の発達には一定の順序があり、首や腰など体幹の関節からまず発達します。体幹の筋の同時収縮の発達は、四肢の関節の同時収縮の土台となりますので、指導もこの順序で行います。
また、固有感覚系は触覚系と深い関係を持っています。固有感覚と触覚は組み合わさって、体の空間内での動きについてより正確な情報をもたらします。たとえば、空間理解のよくない子どもに対しては、触覚的な手がかりを与えると、よりうまく行動できます。新しい不慣れな運動課題の計画と遂行の能力(運動企画能力)がうまく発揮されない場合には、運動感覚に加えて触覚を経験させるといった、身体意識を増大させる働きかけが有効です。寝返り、ジャンプ、歩行、ボール遊び、スクーターボード遊びなどは、難易度の調節が簡単で、たいへん利用しやすい活動といえます。
固有感覚系の神経学的理解
固有感覚入力は姿勢調節と関連して、視覚、前庭覚とともに中枢神経系の小脳に伝達され、脳幹(延髄、橋、中脳)からさらに大脳の感覚野に伝えられます。小脳に伝達される固有感覚入力が意識に上がることなく処理されるのに対して、大脳皮質に伝えられる情報は意識化されて四肢や姿勢の認知にかかわり、意図的行動と深く関係しています。大脳に伝えられた固有感覚情報は、錐体路という運動神経路を通して四肢躯幹を自発的に動かしたり、動きを微妙に修正したりします。これは、子どもの具体的遊び活動そのものです。
大脳からの指令による自発的・目的的な遊び活動が自動的に円滑に、また正確に行われるためには、一定の筋緊張が必要とされます。これには網様体-脊髄系と呼ばれる運動経路が重要な役割を果たしています。この経路が働くためには、大脳、小脳、脳幹が互いに関連し合って情報を統合することが必要です。この情報の統合がうまくいかないと、姿勢調節、バランス、ボディイメージ(主に身体の自発的動きによって作られる)の形成に問題が生じます。
固有感覚系の臨床観察
筋緊張と目的的運動の遂行
固有感覚の処理が最も関係しているのは運動の遂行です。触覚と関連して現われる体性感覚の統合の障害は、体性感覚性障害として著しい不器用さをもたらします。この障害では、運動の背景となる適切な筋緊張の障害と、それに伴うボディイメージの形成の問題がみられます。運動企画能力(運動概念の形成と相互に作用する)の障害は、このボディイメージの障害に起因しています。感覚運動指導では、目的的運動の遂行を強調した遊び活動を通して指導を行いますが、筋緊張、ボディイメージ、運動企画の三つは、子どもの行動を理解するためのキーワードです。
固有感覚系の指導
運動活動を通して経験される固有感覚は、触覚とも関連しながら、子どもの筋緊張を適正にするとともに、興奮を鎮め、触覚の敏感性を低減します。したがって、固有感覚刺激は、覚醒水準が高く多動性を示す子どもに対しても、反対に注意機能が低下して寡動な子どもに対しても、必須な感覚刺激といえます。
発達障害児では、感覚の基本的な調節作用がうまく働いていないことが多く、感覚入力に非常に敏感であったり、逆に鈍感であったりします。その結果、覚醒水準の障害や注意の障害、あるいは多動や寡動などの動きの問題が目立ちます。
※上記は熊谷高幸先生説(自閉症スペクトラムには感覚過敏が関与している)に通じるものであり、「心理的問題以前の、外からの刺激という接点の問題を考えるべき」という事につながると思います。
固有感覚(および触覚)の抑制的な使用法は、ゆっくりとしたリズミカルな動きと、全体に均一の深い圧刺激です。一方、促通的な使用法は、速い不規則な動きと、断続的な軽い触刺激です。原則として、前者は子どもの状態が多動で転導性(注意があっちにこっちに次々に移る様子)の強い場合、後者は寡動(動きが少ない)で覚醒水準の低い場合に用います。
下記の表(固有感覚を取り入れた遊び活動の内容)は、発達障害児に適切と思われる固有感覚を主とした遊び活動についてまとめたものです。どんな遊び活動にも固有感覚経験が含まれていますが、四つの活動(動かす、押す、引っ張る、持ち上げる)パターンは、とりわけ同時収縮を必要とします。したがって、活動の対象は「重さ」のあるものを利用することが多くなります。また、抵抗を用いるのも、これと同じ考えです。また、この表の主たる目標は、固有感覚の処理の改善です。具体的には、伸筋緊張の改善や体幹の安定、姿勢の発達と、それに伴う身体像の形成や身体の動きの改善などです。さらに、視空間認知や動作・行動の改善、四肢の協調運動の改善も目標となります。これらの目標を達成する過程で、ことばによる指示の理解の高まりや、自分の動作を言語化する能力の発達もみられます。活動を行う中で、子どもの活動状態から固有感覚の処理過程を評価しますが、感覚の処理に無理な努力を必要とするほど、子どもから不平や疲労の訴えが出てきます。反対に感覚の統合がうまく行われていると、子どもは活動に興味を持ち、積極的に参加するようすがみられます。
5.神経生理学を意識したマッサージ
感覚統合理論を世に発表したエアーズ(Anna Jean Ayres)は、前庭覚、固有覚、触覚の三つが子どもの運動、情緒、認知、および言語発達の上で最も重要な初期の刺激であるとし、そのためには脳幹レベルの統合が必要であると考えました。
発達障害児へのマッサージにおいても、この3つの感覚と脳幹という下位中枢神経に働きかけることが施術の柱になります。
施術を行う前提として発達障害者への理解が第一ですが、基礎知識が欠けていては目的意識を持つことは難しく、漠然とした施術になりがちです。次の3つはまさに基礎知識です。
①前庭覚に対する反応
②触覚防衛反応
③筋緊張(高い筋緊張と低い筋緊張)
前庭覚に対する反応
前庭刺激を怖がる子ども
すべり台で手をブレーキにスピードを落としたり、不安定な姿勢ではすべれません。ブランコも地面に足をつけて止めてしまうなど、リズミカルなゆれ刺激を楽しめません。ただし、これらの背景には運動経験が少ないということも関係していると思われます。
重力不安を示す子ども
前庭刺激を怖がる状態がさらに強くなると、情緒的な拒否反応が現われてきます。ラージボールやスクーターボードのように両足が地面から離れることを嫌がります。重力不安の子どもは、バランスが崩れそうになったり、普段とは違った姿勢をとらなくてはならない場面ではパニックになることもあります。
強い前庭刺激を求める子ども
より強い前庭刺激を求める児童もいます。この場合、トランポリンで遊ぶと平気で30分くらい跳んでいます。ハンモックに乗せて勢いよく回転させ、急に止めたあとでも目が回りません。普段の傾向は活動量が多く、じっとしていないタイプに多く、前庭刺激が十分入力されていないのではないかと思われます。前庭刺激が不足し抑制された状態で過ごしていると、自分の身体のイメージがまとまりにくくなると考えられています。
触覚防衛反応
「触覚防衛反応」とは特定の触覚を嫌い、避けようとする行動です。 触覚は発達の早期には母子関係を形成する主要な感覚だといわれています。 また、運動を行ううえでガイドとなる働きあります。
触覚防衛反応を示す子どもは、触角刺激に対して敏感なタイプの子どもだといえます。このような反応が幼稚園や保育所の年長組から学校に入っても強く見られる場合、生活面や学習面、運動面、対人関係の面にさまざまな問題を残すことが考えられます。一方、触刺激に鈍感な場合、自分が触られた場所を指せないというケースもあります。触知覚が混乱していると、身体のイメージがばらばらになり、運動するうえで制約が出てきます。
筋緊張(高い筋緊張と低い筋緊張)
目覚めているとき、骨格筋は適切な姿勢を保ち、いつでも運動ができるように、一定の緊張状態を保っています。これを筋緊張といいます。また、屈筋と伸筋を同時に緊張させて関節を固定する働きを同時収縮と呼びます。筋緊張の異常や同時収縮に問題があると次のような問題が生じます。
静的な姿勢での全身の筋緊張
筋緊張が高い子どもは関節の可動域が狭く、各関節をゆっくり牽引、屈曲、伸展したときに強い抵抗が感じられます。反対に緊張の低い子どもは関節の可動域が普通以上に大きく、抵抗が少なくて、ぐにゃぐにゃした感じがします。また、筋緊張に異常があると、体性感覚の処理がうまくできず、適応反応の獲得が妨げられやすくなります。
動作時の筋緊張
筋緊張が高いと動作に柔軟性がなく、過緊張が見られます。一方、緊張が低いと頭がついてこなかったり、頭を無理に起こそうとして全身に過度の緊張が生じます。寝返り動作では、筋緊張の高い子どもは、全身を1本の丸太のように動かしたり、過度に体を反らせて反りを利用した回転をしようとしますが、緊張の低い子どもの場合は、体を過度に反らせたり、反対に屈曲させたりして寝返ろうと試みます。
筋の同時収縮
両肘を軽く曲げた状態を子どもにとらせ、大人の母指を両手で握らせて、軽く押したり、引っ張たりしてみると同時収縮が上手にできる子どもは首や肘がしっかり固定されて、頭がぐらついたり、肘が動いたりしません。筋緊張が低い場合は首や肘の固定ができず、筋緊張が高い場合は動きに柔軟性がなく、関節の拘縮が見られることも少なくありません。筋の同時収縮がうまくできないと、適切な固有覚情報が得られず、誤った運動パターンを学習してしまったり、運動企画性の発達が妨げられます。
緊張が高い場合の主な問題点
1.一人で座れなかったり移動できなかったりする。
2.手を使って探索したり、首を回して外界を認知できない場合、重い精神発達の遅れにつながりやすい。
3.筋肉の柔軟性の欠如は運動の固定化を生み、さらに、固定から逃れようとして代償的な運動パターンを引き起こし、それが反復活動によって習慣化されると異常な姿勢筋の緊張を作り出す。
緊張が低い場合の主な問題点
1.椅子からずり落ちてしまったり、手で床を支えていないと上体を起こしていられない子もいる(体を支える補助に使われると手の機能の発達が遅れる原因になる)。
2.腹筋、背筋が弱いとまっすぐな立位の姿勢が難しい。(腹筋、背筋の筋トレは大切)
3.姿勢を維持するために常に力を入れているため、とても疲れやすくなる。長時間学習に集中することができない。
4.筋緊張が低い子どもは、表出反応が鈍くなり、覚醒レベルも低いことが多く、「意欲がない、やる気がない、不真面目だ」と誤解されることがよくある。
5.各関節の可動域が過度であったり、逆に拘縮の進行、骨のもろさ、筋肉全体の異常な柔らかさなどがみられる。
さらに、姿勢や目の動きの状態についても確認する必要があります。
姿勢と運動
どのような姿勢が取れるか、どの運動ができるかだけでなく、どのように姿勢を取っているか、どのように体を動かしているかをよく観察することが大事です。
寝返り
両側になめらかに寝返ることができるか。まっすぐに回転できるか。体幹の過伸展、屈曲を利用して回転していないか。
腹ばい
頭を持ち上げて保持できるか 。手で上体を支えられるか。支えられる場合、手のひらで支えているか、それとも肘で支えているか。
四つばい
四つばいの姿勢が保持できるか。四つばいの姿勢で前後左右に体重移動ができるか。背中の過伸展や背中を丸めた円背はないか。なめらかな四つばい移動ができるか。
座位
骨盤を起こして座位がとれるか。手をつかずに座っていられるか。股関節の外転、外旋方向への柔軟性はあるか。椅子に座って両足をつき、股関節が中間位で保持できるか。
ひざ立ち
両膝で床を踏みしめることができるか。首から下肢にかけて抗重力反応があるか。股関節の屈曲、背中の過伸展などは見られないか。
立位
両足で床を踏みしめることができるか。体のゆれぐあいぐあいはどうか。首から下肢にかけて抗重力反応があるか。
姿勢背景運動
体のゆれが見られないか。一方の手が動くと、使っていない反対側の手も同じように動く連合反応が見られないか。
眼球運動
姿勢や運動の機能に問題があったり、前庭系や固有覚系の情報処理がうまくできないと、眼球運動の問題が起こりやすくなります。
マッサージは、皮膚、筋膜などの結合組織、筋肉に対して、指や手などを使って、触る、さする(軽擦)、圧迫する、叩くという手技と、関節の可動域確保や筋力維持などを目的に、関節を動かす手技が基本です。関節に対する施術では、関節の力を抜いた状態で行う運動を「他動運動」、自分自身で動かすことを「自動運動」、施術者が動かす筋肉に抵抗を加えることを「抵抗運動」といいます。
ここでは「新・感覚統合の理論と実践」に出てくる「触圧の刺激」という言葉に焦点を当て、そこに記載された内容をご紹介し、その上で感覚統合法を補完するマッサージについて考えたいと思います。
感覚調整の障害
『新・感覚統合法の理論と実践』の中では触覚防衛反応は、自閉的な子どもたちが持っている感覚調整の障害によって発生するものと考えられています。そして、感覚調整の障害について、神経生理学的および感覚統合法の立場から次のような説明がされています。
自閉的な子どもたちは、対人関係や言語、認知の発達の遅れに加えて、こだわりやパニック、多動性、自己刺激行動など、さまざまな行動上の問題を示します。感覚統合理論では、このような特徴を示す自閉性障害の原因について、脳幹部や大脳辺縁系、小脳などを含む広汎な中枢神経系の機能不全によるものと考えています。特に、皮質下の脳幹や間脳における感覚の調整の障害は、外界からのいろいろな感覚情報の処理の偏りやひずみの原因となります。それはさらに、皮質を中心とした高次神経系での情報処理に影響を与え、その結果として、前述した様々な問題が現われてくると考えられています。
感覚統合法の立場から自閉症を解釈すると、自閉症とは、感覚情報の登録や調整機能の障害のために、人や物を含む周囲の環境との相互交渉に問題を生じている子どもといえます。したがって、自閉症児に対する感覚統合法の指導では、まず、感覚刺激に対する反応の様相を評価し、個々の子どもの感覚調整の障害に対応していきます。なお、評価は感覚歴、臨床観察、そして心理検査の結果が求められます。
過反応タイプの子ども(触覚防衛反応)
触覚防衛反応を示す自閉症児は、ふつう私たちが心地よく感じる感触に過敏に反応し、その刺激を嫌って逃避したり、興奮したりします。身体部位では、首筋、顔面、口周辺、そして手のひらなどへの触覚刺激に対して過敏症を示しやすいようです。触覚防衛は、覚醒レベル、情緒的な不安定性、対人関係の問題、音やにおいに対する過敏性、多動性、固執性、注意転導性などにも関連しているため、自閉症児の発達を援助するうえで、早期からの改善の取り組みが必要です。
低反応タイプの子ども(前庭-固有系の感覚登録障害)
私たちが知覚できる刺激をわずかしか感じることができないため、結果として多くの強い刺激を求めることになります。そのため、トランポリンやぶらんこ、グローブジャングルなどの遊びに夢中になります。一方、いったんそれらに入り込むと、今度は特定の感覚刺激や遊びに固執しがちになります。
感覚歴
感覚調整の障害は、触覚系と前庭-固有覚系に生じやすく、過反応(過剰反応)や低反応(過少反応)といった両極端な反応となって現われます。前者には、触覚防衛や重力不安などの状態があります。また、後者は、感覚刺激の登録が低下しているために、刺激に反応しにくい状態です。
感覚調整機能に関する質問では、現在の様子だけでなく、過去(通常は幼児期)も確認します。これは現在改善されている場合でも、ストレスが生じる過剰な刺激状況に出会ったとき、一時的にせよ再び感覚調整の問題が現れて、不適応行動を生じる可能性があるからです。
臨床観察
観察項目
1.神経学的徴症状:原始反射の統合状態や筋緊張など
2.粗大運動と微細運動:姿勢や歩行状態の特徴、運動企画力、手指機能など
3.対人関係:アイコンタクト、やりとり行動、指示行動、模倣、象徴遊びなど
4.言語:ことばの理解と発話(反響言語、トーン、構音、会話)のようす
5.行動の偏り:固執性、パニック、自己刺激行動、注意転動性、多動(寡動)性など
以上の観察項目のうち、対人関係、言語、行動の偏りについては、特別な検査場面や指導場面における周囲の人や物とのかかわりの中で把握するようにします。
心理検査
自閉症児の場合、その場の状況や課題によって観察結果が変動しやため、1回で判定するのではなく、色々な場面で観察を繰り返し、総合的に評価するようにします。
筋緊張の強い子ども(1)-重度の運動機能障害の場合
触圧の刺激などによって緊張部位のリラクセーションをはかり、屈筋群と伸筋群の拮抗をバランスよく保ち、柔軟な筋肉の活動を促します。
ねらい
軽い触圧の刺激を持続的に入れることで、反り返りを抑制したり、動かしにくい筋群の活性化をはかります。
活動の展開と留意点
重度の子どもたちへの「抑制的な触覚刺激」は、中枢あるいは末梢神経障害に起因する皮膚の過敏症、長期にわたる異常な筋緊張から柔軟性の欠如を改善するために利用されます。また、「促通的な触覚刺激」は、原始反射は統合されているが平衡反応が十分に発達していないので、それを強化する場合や、触覚刺激への反応が弱い場合に利用します。
抑制的な触覚刺激
反り返りが強く自力で頚部を動かせない子どもに対しては、以下のような方法が考えられます。
頚部を左または右に回旋し、後弓反射(脊柱の伸展、肩甲帯の後退、下肢内転筋の痙性、過度の伸展)の強い子どもに対しては、前斜角筋中央部に軽く指を当て、軽い触圧の刺激(ソフトタッチ)を入れます。そして、中斜角筋、後斜角筋、後頚筋、上僧帽筋、胸鎖乳突筋あたりへの軽い触圧の刺激(ソフトタッチ)をくり返すことで過敏性をとります。
自分で体を動かせない、触覚刺激への反応が弱い子どもへの部分的な技法には、促通的な触覚刺激として下右図のようなものがあります。
筋緊張の強い子ども(2)-異常な運動パターンを示す場合
子どもたちの異常な運動パターンは、異常な姿勢筋の緊張と姿勢反射の統合不全によって生じた姿勢変換の誤学習が蓄積したものといえます。最初は正常からわずかに偏位したものだったのが、そのわずかな偏りの上に学習を積み重ね、ますます偏りが強化されてしまったということです。こうした障害が形成されていく過程は、筋肉の柔軟性のなさからくる運動の固定化に始まります。さらに、固定から逃れようとして代償的な運動パターンを引き起こし、それが反復活動によって習慣化されます。触圧の刺激によって緊張部位のリラクセーションをはかったり、ボディイメージを育てたりして、柔軟な筋肉の活動を促します。
ねらい
軽い触圧の刺激を持続的に入れることで、緊張部位のリラクセーションをはかったり、ボディーイメージを育てたりして、柔軟な筋活動を促します。
活動の展開と留意点
ボディーイメージが育っていなかったり、異常な運動パターンを示す子どもたちにとって、持続的な触圧の刺激は、身体部位の無視を軽減させたり、触覚の閾値を正常化したりするのに有効です。また、ブラッシングによって筋紡錘を刺激し、筋活動全体の活性化をはかります。
軽い圧の刺激
身体各部への持続的な圧刺激は、異常な運動パターンを鎮静する効果があります。
腹部中央へ手を当て、軽い圧を加えます。これは、全体の異常緊張を抑制し、全身のリラクセーションをもたらします。
横隔膜に沿って両手を当て、呼吸パターンに合わせて軽い圧を加えます。これは、呼吸のリズムを整え、大胸筋から頚部のリラクセーションに役立ちます。
あぐら位をとらせ、後から脊柱のゆがみを観察し、動きの悪い筋肉の上に手を当て、子どもの動きに合わせて軽い圧を加えます。これは脊柱起立筋や腰方形筋の活性化をうながし、縦方向への緊張の手助けとなります。
手を中心としたマッサージをし、末梢を意識させます。
筋緊張の低い子ども-重度の運動機能障害の場合
全身の筋緊張が低く、首が座っていなかったり、同じ姿勢を維持できなかったり、姿勢変換ができない子どもは、一定の緊張が維持できないため、各関節の可動域が過度であったり、逆に拘縮の進行、骨のもろさ、筋肉全体の異常な柔らかさなどがみられます。このような子どもたちは、自分で身体を動かしたり探索したりできないために、情報をうまく受けとめることができず、表出反応も鈍くなり、覚醒レベルも低いことが多いようです。こうした状態は、特に脳性まひの低緊張タイプや先天性筋ジストロフィー症、難治性てんかんなどによくみられます。
促通活動を中心とした触圧の刺激などによって屈筋群の活性化をはかり、柔軟な筋肉の活動を促します。
基本姿勢パターンと触圧刺激
ねらい
固有感覚系に適切な感覚を入力することで、基本姿勢パターンの改善をはかります。同時に触圧刺激を利用して、覚醒レベルを高めたり、弁別機能を高めたりします。
活動の展開と留意点
伸長、牽引、タッピング、抵抗などを固有感覚の入力として行ったり、温度刺激や触覚刺激を促通的に使うことで、姿勢パターンの改善をはかったり、ボディーイメージを高めたりして、覚醒レベルを上げるようにします。
うつぶせ
子どもを肘たて位にし、頚周囲筋群を同時収縮させ、肘を90度屈曲位に保ち、肩の真上から垂直圧を加えます。ゆっくりと10数え、肩から手が離れないようにゆっくり力を抜きます。
椅坐位
頭を正中位に置き、肩の真上から力を加え、関節圧縮を利用して躯幹筋群の縦方向への促通をうながします。
座位
あぐら座位をとらせ、脊柱のゆがみを観察しながら、両手を凸側の起立筋および広背筋に当て、まっすぐ下に負荷をかけ、ゆっくり手を離します。
三角座りからそんきょの姿勢をとらせ、両足の踵から前方に体重移動させます。これらの持続的緊張が加えられると、足関節周囲の同時収縮が促通されます。
四つばい
四つばい位をとらせ、肩から真下に負荷をかけます。股関節に対しても同様に負荷をかけます。前後左右、対角線方向に体重移動を行い、各関節に圧迫を加えます。
マッサージのポイント
1.人は最も大きな刺激源であり、人に対する感情によって、刺激の感じ方もずいぶん違ってくると言われています。従って、子どもとの信頼関係を築くことが最初の課題です。
2.触覚防衛反応などの感覚調整の障害については、「感覚調整機能評価表」を利用し、触覚系と前庭-固有覚系の過反応と低反応の実態を把握します。
3.筋緊張の強い子には、抑制的な触圧の刺激などにより、緊張部位のリラクセーションをはかり、屈筋群と伸筋群の拮抗をバランスよく保ち、筋肉の柔軟性を高めます。
4.筋緊張の低い子には、促通的な触圧の刺激などにより、屈筋群の活性化をはかります。また、関節への抵抗運動により筋緊張を高めるとともに拘縮を予防します。
5.ボディイメージが弱い子には、関節の抵抗運動により、それぞれの筋肉の動かし方を繰り返し学習します。
全体のまとめ
1.マッサージは感覚統合法を補完します。
2.マッサージは筋緊張、感覚調整、ボディイメージの状況を改善します。
3.マッサージを行うにあたり、子どもとの信頼関係を築くことが大前提になります。
付記

こちらは、コラムで「音楽療法」の有効性などを紹介されています。
その中で、次のようなコメントがありました。
『何よりも大切なのは、音楽を通して、セラピストと子どもがコミュニケーションを取ることです。これこそが、音楽療法のなかで一番大切な部分であると言っても過言ではありません。
音楽療法士のピアノに合わせて楽器を鳴らす、音楽療法士と順番に楽器を鳴らす、出来たら音楽療法士とハイタッチをする…子どもたちは、このように音楽を通してコミュニケーションを学び、社会性を獲得していくのです。』
子どもと施術者とのコミュニケーションは、マッサージにおいても、同様に重要なものであると思います。
自閉症と感覚過敏
「自閉症と感覚過敏」の著者である熊谷高幸先生は、著書の「はじめに」の中で、障害の発生源には「感覚過敏」があるとのことを指摘されています。
マッサージは、主に直接的な触感覚・固有感覚と間接的な聴覚・視覚、そして1対1のコミュニケーションの中で、これらの感覚が刺激されます。「感覚過敏」が熊谷先生のお考えの通り、障害の発生源であるとすれば、4つの感覚を接点とするマッサージは活躍の場を広げる可能性があると思います。そして、「感覚過敏」に対するマッサージで心がけるべきは何なのか。この難題を考えるために「自閉症と感覚過敏」を拝読させて頂きました。
『はじめに』の中で説明されている自閉症に関する実状
・自閉症が報告(1943年)されてから70年以上たつが、障害の定義や、原因や、該当する人々の範囲についての考えは次々に変わってきている。
・自閉症と見なされる人の数が年々増えている。40年ほど前には2,000人に1人ほどといわれていたのが、今では100人に1人とまでいわれるようになった。
・自閉症は、それに当てはまる人々の数についても、それが含む症状の範囲についても、さらには関連する障害についても、大きな広がりを見せるようになっている。
・自閉症は、その原因と結果を1対1に対応できない障害である。脳の特性によって生じるところまではわかっているが、より深い所では原因をひとつに絞ることができない。だから、症状の集まりとして診断されている障害である。つまり、社会性が乏しい、こだわりがある、ことばが遅れる場合がある、パニックになりやすい、記憶力がよい場合が多い、感覚過敏が現われやすい、などの症状の集まりとして理解されている。だが、これらの症状のあいだにどのような関係があるのか、また、それらはどのような経路をたどって現われるか、についてはほとんど答えが出されていない。
・感覚過敏とは、最近になって自閉症に一般に認められるものとなった症状である。感覚が非常に敏感になっている状態で、刺激を恐れる場合と求める場合がある。たとえば、嫌な音を恐れて耳をふさいだり、音のする部屋に入らなかったりする。また、水路を見つめ小石を落とす行為をいつまでも続けたり、ビデオの同じ箇所を何度も見続けたりする。感覚過敏は視覚や聴覚など、あらゆる感覚に現れ、また、敏感性としてだけでなく鈍感性としても現れる、非常に多様な側面をもつ症状である。
自閉症スペクトラム
『自閉症スペクトラム障害は、2013年に出版されたアメリカ精神医学会の「DSM-5」(「精神疾患の診断・統計マニュアル」第5版)において、これまでアスペルガー症候群、高機能自閉症、早期幼児自閉症、小児自閉症、カナー型自閉症など様々な診断カテゴリーで記述されていたものを、「自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害」の診断名のもとに統合されました。「DSM-5」以前の診断カテゴリーである自閉症やアスペルガー症候群などは、それぞれの症状に違いがあるとされ、それに伴って診断基準も異なるため、独立した障害として考えられてきました。』

上記は「発達障害ポータルサイト」のコラムからの引用です。詳しくはこちらをご覧ください。
スペクトラムとは、分光器によって分けられた様々な波長の色の連続体を示すことばで、共通性の中に、多様性を示す自閉症という障害を表すために用いられました。「自閉症スペクトラム」という捉え方では、自閉症の人と通常の人の境目も以前のように明確なものではなくなっています。一方、自閉症の人々の感覚や行動の特性は通常とはかなり異なるように見えますが、通常の人々に全く現れないものではありません。
自閉症スペクトラムは、自閉症(言葉の遅れがある自閉症)、アスペルガー症候群(言葉の遅れのない自閉症)、高機能自閉症(発達初期には言葉の遅れがあったが、その後、急速に知能が発達した自閉症)を包含したものとして位置づけています。また、ADHD(注意欠陥・多動性障害)とLD(学習障害)は自閉症スペクトラムとは異なる障害ですが、それぞれが重なり合うことが認められており、熊谷先生は、その重なりには感覚過敏が含まれていると考えられています。なお、ADHDは5%の子どもに、LDは3%の子どもに現れるといわれています。
感覚過敏が自閉症の発生源とされる理由
・感覚過敏があると、刺激に対する反応が大きくなり、好きな物は非常に好んで求め、嫌いな物は恐れて避けるようになります。そのため、外界の捉え方が通常とは異なり、行動の仕方も通常と異なってくると考えらえます。このため、人々と共に生活することや学ぶことが難しくなってきます。ことばを学び、人々とコミュニケーションができないと、社会に参加することができなくなります。このように、感覚過敏は発達全体に影響を及ぼす可能性をもっています。
・自閉症の人が自らのことを語ったのは、テンプル・グランディンが発表した「我、自閉症に生まれて」(原著“Emergence:Labeled Autistic”1986)と、ドナ・ウィリアムズが発表した「自閉症だったわたしへ(原著“Nobody
Nowhere”1992)でした。日本人でも2007年に東田直樹さんが14歳のときに「自閉症の僕が跳びはねる理由」を世に出しました。その後もニキ・リンコさんなど自閉症の当事者たちによる自伝が次々に出版され、いまでは自閉症に関する出版物の半数ほどを占めるまでになっています。そして注目すべきことは、これらの著書のほとんどすべての中で感覚過敏の経験が語られているという点です。
例えば、下記は東田直樹さんが11歳のときに書いた「誰もいなくなった」という詩の冒頭です。
みんながいる所は 嫌い
音が大きい所は 嫌い
物が多い所は 嫌い
どこに行ってもうるさくて
僕はいつでもがまん出来ない
また、ニキ・リンコさんと藤家寛子さんの対談本「自閉っ子、こういう風にできてます!」では、
+雨が痛い。
+扇風機の風が痛い。
+カメラのフラッシュのあと何も見えなくなる。
+コタツに入ると脚が消える。(視覚と身体感覚が両立しにくく、一方が優勢になると他方はほとんど無視されてしまうことを意味しています)
などの経験が語られています。そして、この対談の司会者であり、この本の発行人でもある浅見淳子さんは同書の中で次のように述べています。
『ひと口に自閉所スペクトラムの方と言っても、性格は皆さんそれぞれです。定型発達の人と同じようにバラエティに富んでいます。でも一人残らず、身体機能の不具合を抱えていました。自閉症というと心の内側、つまりその心理がまず問題にされやすい。しかし、その前に外部との接点のところにもっと注意を向けなければならないことがわかってきたといえるだろう。』
・自閉所者は外部からの刺激をいちどに大量に取り入れてしまうという特性をもっています。

自閉症者の場合、ある刺激が入り込むと、感覚の枠いっぱいに広がり、そのまま停留します。すると後続の刺激は、感覚の枠に入り込めない状態で通過し、見落とされてしまいます。この見落としのために時間や空間の関係を捉えることが難しく、コマ送りのような映像は動画にはならず、全体像を理解しずらいという事態に直面します。つまり、外部からの刺激の取り込みという行動初期から、自閉症者はコミュニケーションを阻害する困難さに立ち向かわなければなりません。
画像出展:「自閉症と感覚過敏」
自閉症者の心と体のかみ合いにくさの特性
・自閉症者は時間、空間など外部の世界を統合するのが難しいだけでなく、自分自身の身体各部も統合しにくいという問題が起こります。例えば、書くこと(指)に集中すると、体が傾いているのに気づかず、椅子から落ちてしまう等です。
・身体各部が統合しにくい理由として、触覚や筋肉感覚(体性感覚)は目や鼻(特殊感覚)と違って、特別の受容器をもたず、集中管理もしていません。また、受容器は全身に分布し脳の中の別々の皮膚領域で受容されます。
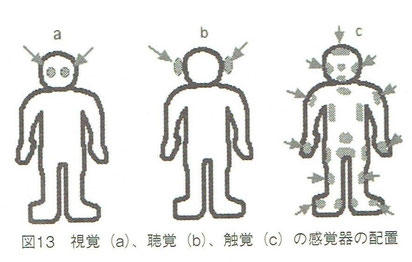
視覚は「目」、聴覚は「耳」という特殊な受容器がそれぞれ2つずつ顔に存在しており、必ずそこからの情報であると限定してくれますが、体性感覚の受容器は全身に分布しており、分かりずらさの原因になります。
画像出展:「自閉症と感覚過敏」
運動を起こす時は、身体各部の筋肉に対応した脳部位の指令の下で動きが生じます。人の脳は、それらの動きを前頭前野で統一する働きをもっていますが、感覚過敏があると前頭前野での接続がむずかしくなると考えられます。つまり、身体や運動の感覚は視覚や聴覚よりも一般化しにくい特性をもっており、一方、自閉症者のように感覚過敏があり、身体の特定部位からの感覚に強い影響を受けやすい状態であると、さらに全体的な統一感は保ちにくく、自分のものとして感じにくくなります。
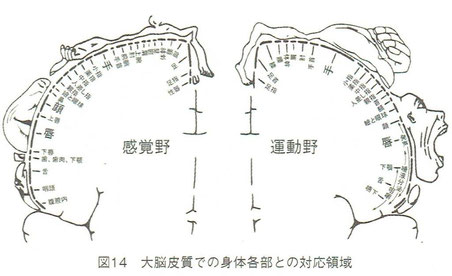
画像出展:「自閉症と感覚過敏」
・自閉症者が苦手とする代表的なものが縄跳びです。縄跳びは全身を一体化させ、一定のリズムで跳躍しなければならないうえに、更に縄の回転の動きに合わせなければならないためです。
・自閉症者が跳びはねる理由は、一つは飛んでいるときは足を感じ、手を叩けば手を感じる。つまり、バラバラになっている感覚の一体感を取り戻すためにやっていると考えられています。もう一つの理由は、意識が外部のわずらわしい刺激から解放されて自分自身に向き、自分を取り戻すことができるからです。(ドナ・ウィリアムスは自宅にブランコがあり、ブランコの規則正しいリズムに自分を溶け込ませて気持ちを和らげるために使ってとのことです)。
アンケート結果にみる感覚過敏の実態
自閉症者は自分の状態を細かく語れない人の方が多いため、熊谷先生は、より多くの自閉症者を対象に感覚過敏との関連性を調べるため、自閉症児の親へのアンケートを実施されました。
アンケートは特別支援学校に通う30名の自閉症児、男児25名、女児5名で、年齢は10歳から18歳までです。言語をもたない自閉症児は4名でした。ただし、「会話が可能」の中には一語文レベルにとどまる者が7名いました。なお、以下の表は30名の言語状況を示す一覧表です。
下記の表は掲載されていた表を1枚のシートにまとめたものです。

「人に触れられるのを嫌がる」という質問に、「よくある」と回答したのは5名です。これは全体の約16.6%になります。
まとめ
「マッサージは、主に直接的な触感覚・固有感覚と間接的な聴覚・視覚、そして1対1のコミュニケーションの中で、これらの感覚が刺激されます。」と紹介させて頂きましたが、実際に発達障害児へのマッサージを行おうとすると、落ち着いて横になっていない児童も少なくというのが現実です。このため、マッサージの効果を実感することは困難な道のように感じていますが、児童への理解を柱に、実践に知識をプラスし、その理解・知識・実践を1サイクルとして、それを回しながら前進していくことがあるべき姿に近づける方法だろうと思っています。
付記:ADHD(注意欠陥・多動性障害)と感覚過敏についての記事

タイトル:「ADHD(注意欠陥・多動性障害)の治療法・療育法は?治療薬は効果的なの?」
この記事の中に、次のような説明がありました。
『ADHDの原因は、現在の医学ではまだはっきりと分かっていません。一番有力なのは、脳の前頭前野部分の機能異常だと言われています。前頭葉は脳の前部分にあり、物事を整理整頓したり、論理的に考えたりする働きをします。ADHDの人はこの部分の働きに何らかの偏りや異常があり、思考よりも五感からの刺激を敏感に感じ取ってしまいます。そのため論理的に考えたり集中するのが苦手となるのです。 』
これは、熊谷先生の説を後押しするような記事だと思います。
発達障害児へのマッサージを考える#5
前回は中尾繁樹先生のDVDに関する内容でしたが、中尾先生の本も1冊は読んでおきたいと考え、『みんなの「自立活動」特別支援学校編』を拝読させて頂きました。
そして、以下の3つの章の中から自分にとって特に重要と思うポイントを洗い出してみました。
第3章 「コミュニケーション」と「人間関係の形成」
第4章 「環境の把握」と「身体の動き」
第5章 「身体の動き」と「人間関係の形成」「コミュニケーション」と「環境の認知」
第3章 「コミュニケーション」と「人間関係の形成」
様々な補助的手段の活用とコミュニケーション指導
1.自立の第一歩は自己決定すること
・欧米は障害のある子どもが自立していくための第一歩は、自己決定することであるという考え方で、何を選ぶ・どれに決めるといった自己決定する力を向上させることが重要です。
・自己決定する力に加え、決定したことを相手に伝える力が必要であり、コミュニケーションにとっても大切なことです。
2.障害があっても〇〇デキルという視点
・自己決定するためには、自分で決めたいという意欲が必要です。子どもの意欲を育てていくには、外界(人や物、状況など)に対して自ら能動的にかかわり、その活動の中で成就感や満足感を味わうことが重要だと考えられています。
・「障害があっても〇〇デキルという視点」は「何でも良いからできることを探してみよう」部分的にでもデキルことからやっていこう」という考え方です。
3.コミュニケーションを阻害する学習性無力感
・いつも感謝・依頼する立場が、感謝・依頼される立場に逆転したとき、その子の心の中には喜び以上の心の躍動が芽生えます。
4.学習性無力感を獲得させないために
・人は、ほめられる・認められる・感謝される・依頼されると、誰しも「次もがんばるぞ」といった意欲が湧いてくるものです。どんなに重要な障害があっても、能動的にオモチャにかかわって遊んだり、毎日責任をもって役割を担えたりすることは素晴らしいことですし、彼らの意欲を育てる上でたいへん重要なことです。
5.コミュニケーションの力を育てる
・Beukelman&Mirenda(David Beukelman and Pat Mirenda)は、どんなに障害が重度な子どもでも三つのサインを発信しており、それぞれのサインに対して支援者が適切に応答することが重要であると紹介しています。三つのサインのうちの一つ目は、注意探索と呼ばれるサインで、赤ん坊が泣いてお母さんの注意を引く行動のように、他者に何かを訴えたいときに使われるものです。二つ目は、受容のサインで、オモチャが動くことや大人からの働きかけといった外界の変化に対して、「満足だ、嬉しい」等の表現として、笑う・声を出すといった行動で示されます。三つ目は、拒否のサインであり、生理的に不快な状況や大人からの不適切な働きかけなどに対して、「イヤだ、不快だ」等の表現として、顔をしかめる・泣く・体をよじらせる等の行動で示されます。発信したサインに対して必ず応答があることを子どもに気づかせ、理解させるための練習が必要となります。
・Beukelman&Mirenda(David Beukelman and Pat Mirenda)は、日常生活の様々な場面の中に、次のようなルールでコミュニケーションしていくという指導方法を紹介しています。
①何らかの活動をする際に、必ず子どもの同意を求めるための働きかけまたは問いかけをする。その際、言語的な働きかけだけでなく、子どもが受容できる感覚器すべて(触覚的、視覚的あるいは聴覚的など)に働きかけるようにする。
②働きかけまたは問いかけに対する子どもの発信サインを待つ・観察する。
③子どもが発信したサインに応じて適切な応答行動をフィードバックする。
・能動的な活動を通して子どもの意欲を育てていくことと並行して、自分の意志を外に向けて発信する力を育てていくことはコミュニケーションの第一歩であり、大変重要なことです。
・子どもが受容のサインを発信しやすいのは、楽しかったり喜びが大きかったりする活動、すなわち遊びの場面だと思います。そこで、子どもの知的発達の段階に応じた様々な遊びを準備しておいて子どもたちと遊ぶようにすると良いと思います。
・選択による自己決定力を育てる
・返事を待ちましょう(最低でも10秒程度)。
・子どもを信頼し、子どもの自己決定を尊重しましょう。
・選択できる情報をすべて提示し(子どもによっては多く提示できない場合もあり)、その後で選択を求めていきましょう。
・何に対してもYesの反応をする子どももいます。一見、自己決定できているように見えますが、必ずしもそうではないこともあります。Yesの答えが得られる質問だけでなく、Noの答えを求めるような尋ね方も必要となります。
・音声を使ったコミュニケーション
・知的障害のある子どもの中にはことばを使う意味が理解できていない子どもに対し、私たちはことばや文字を身に付けさせようと一生懸命になりがちです。そのこと自体はとても大切なことなのですが、ことばは教え込まれて身に付けるものではありません。赤ん坊はいつの間にかことばを覚えて、いつの間にか使うようになっていませんか?その際、親は四六時中「さあ、このことばを覚えなさい。覚えるまで遊ばせませんよ」と言っていないはずです。したがって、ことばを使う意味が理解できていない場合には、まず、音声を使う楽しさや便利さを経験させる必要があります。例えば、命令語を録音しておいてやりとり遊びをしたり、じゃんけんことばを録音しておいてじゃんけん遊びをしたり、との応用はいくつでも考えられると思います。
6.自立と社会参加を進めるために
事例
ミネソタ州で出会ったKさん(41歳)は、脳性まひによる運動障害があり、頭を動かすこと以外は随意的に動かせる部位はありませんでした。そのために、食事や排泄、更衣、入力といった日常の生活に必要な行為すべてに全面的な介護を必要としており、州政府から24時間体制で派遣されるヘルパーにその介護を委ねています。また、発語はなく、質問されたことに対して、[頭をたてに振る=うなずき]-[頭を横に振る=いやいや]の動作によってYES/NOを相手に伝えるというコミュニケーションの状況です。
ところが、Kさんは安定した収入を得ることのできる仕事に就き、コンサートに出かけて音楽を楽しむことを趣味とし、自分で購入した家で一人暮らしをしているのです。彼女の仕事は、パソコンとインターネット技術を利用した電話オペレーターで、自宅にいながらその仕事をこなしていました。
写真は、姿勢を保持する機能をもった電動車椅子に乗ったKさんが自宅で友人と談笑している様子です。Kさんの頭に注目してください。彼女は支援機器を操作するために、ヘッドスティックとよばれる棒付きの帽子をかぶっています。話すことのできない彼女は、電動車椅子のテーブルに取り付けられたコミュニケーションエイドのキーをヘッドスティックで押しながら、友人と会話をします。このコミュニケーションエイドは、あらかじめ録音してあることばを出力する機能をもっているだけでなく、テレビやエアコンなどのリモコン機能と併せて、パソコン用のキーボードとしての機能の付加されている機器なのです。このコミュニケーションエイドとパソコンを利用して、彼女は電話オペレーターの仕事に携わっているのです。
彼女は生まれて間もない頃に重度・重複障害と診断され、10年以上もの長い期間にわたって入院を余儀なくされたそうです。その上、「無能力者(本人段)」と評価され教育からも見放されていたそうです。
そんな彼女のもとに、一人の大学生がボランティアとして本の読み聞かせをしにくるようになりました。何か月もベッドの横で読み聞かせをしているうちに、その大学生はKさんの表情の違いやほんの少し頭を動かす能力があることに気づきました。そこで、大学生は頭で押せるスイッチとブザーを作り、KさんにYES/NOで返事をしてもらう練習をはじめたそうです。すると、それまで「何もわからないし、何もできない」と評価されていたKさんが、実は簡単なことばを理解しており、頭を動かすことで返事ができるということがわかったのです。その後、彼女は病院を退院して家庭教師に勉強を教えてもらいながら様々な知識を身に付けていったそうです。
今では、電動車椅子やコミュニケーションエイドといった支援技術を駆使して収入を得ながら自立した生活を送っています。ボランティア学生が「Kさんはデキルんじゃないだろうか」と信じて、彼女の生活環境を工夫しなければ今の彼女はなかったと言っても過言はないでしょう。
Kさんの自立生活は支援技術の効果とともに、周囲の人々が「この人はデキルんだ」と評価したからこそ現実のものになったと思います。重複障害のある人への支援を考えるとき、「障害があっても〇〇デキル」という視点が今後ますます重要になってくるのではないかと思います。

AAC(Augmentative and Alternative Communication;拡大代替コミュニケーション)
・話すこと・聞くこと・読むこと・書くことなどのコミュニケーションに障害のある人が、残存能力(言語・非言語問わず)とテクノロジーの活用によって、自分の意思を相手に伝える技法のことです。AACの技法の種類には、大きく分けてノンテク、ローテク、ハイテクの3つがあります。
・機能訓練だけでなく、コミュニケーション能力の向上も考慮してします。
・コミュニケーションには、コミュニケーションしようとする者同士の間に、共通して理解し合える手掛かりやルールの存在が必要です。
上記の2つのサイトは、発達障害児向けの商品やアプリを扱っています。
第4章 「環境の把握」と「身体の動き」
知的障害のための感覚運動遊びを中心とした自立活動の実際
1.知的障害のある子どもたちの感覚運動の特徴
・子どもたちは自分なりに一生懸命取り組むのですが、なかなか思うようにできません。記憶したり、理解したり、理解したり、問題解決をする、考える、自分の意見を述べるといったことが苦手であるために意欲が高まらない原因となっていることがよくあります。これらの原因と同じように感覚運動面の問題が課題を行ううえで大きな影響を与えていることがあります。感覚運動学習とは、身体に入ってくるたくさんの感覚を適切に処理したり、姿勢・運動をコントロールすることです。感覚運動は遊びや学習に必要なレディネスであると言えます。ここでは、知的障害がある子どもたちが苦手な動きをまとめてみました。
・力を入れる運動、リズミカルな運動、巧緻運動、道具を使った動作、空間での運動
・低緊張では腕や脚で自分の体を支える筋力の動きづくりにポイントをおいた運動も大切。
第5章 「身体の動き」と「人間関係の形成」「コミュニケーション」と「環境の認知」
発達障害の子どもの運動や人間関係を高める自立活動の実際
1.発達障害について
・自閉症の乳幼児は、触覚・聴覚・視覚などの過敏傾向が強く、抱っこをしようとしても、体をのけぞらせて嫌がったりすることがよくあります。そのため、抱っこから育っていく愛着行動の形成に大きな遅れが起こってきます。
・反復的な自己刺激行動(手をひらひらさせる・クルクル回る・ピョンピョン跳ぶ等)は自閉症特有の「情報の中の雑音を除去できない」という特性も影響しています。そして、自閉症の幼児はやむを得ず「自分で一定した刺激を作り出して感覚の遮断を行い、情報の洪水に対するバリアをはる」という戦略をとります。
・「情報の洪水」の中にいた自閉症の幼児も、徐々にですが認知の焦点を合わせることができるようになります。しかし、それは一般の子どものような「自然、広く開かれた柔軟な認知」ではなく、彼ら特有の「意識的な焦点の絞込み」だと思われます。その結果、強い「過剰選択性・興味の限局(認識しやすい特定のマークや蛇口、窓などにこだわる)」を抱えやすくなります。
2.広汎性発達障害への対応例
・同時に複数の情報を出さない。つまり、刺激を整理し、落ち着いて認知対象に集中できる環境を設定する。(構造化)
・ゆっくりと短いことばで話しかける。
・結論を先、理由を後にするとわかりやすい。
・具体的なことばで伝える。抽象的なことばは、ジェスチャーやカードなどの視覚的情報を併用して伝える。
・スケジュールカードなどによって、活動の流れや終わりを視覚的に伝え、予測可能な生活環境を整える。
・予定の変更については慎重に行う。変更する際には、子どもが認識できるように、必ず予告を行う。
3.注意欠陥多動性障害(ADHD)への対応例
・常にひと呼吸おいて、焦らないで対応する(互いの感情のコントロールが大切)
・気が散りやすいので、学習のときは刺激を少なくして、集中しやすい環境を整える。
・「部屋を片付けて!」ではなく、「オモチャは箱にしまおう!」「脱いだ服はハンガーにかけてね!」など、より具体的な伝え方を工夫する。
・スモールステップで、少しずつ課題に取り組めるように工夫する。
・スケジュールやこれからやることを、見通しがもてるように工夫して伝える。
・「〇〇なときは、〇〇しようね!」など、事前に想定される混乱を避ける配慮をする。
・ことばだけで伝わりにくいときは、視覚に訴える支援を行う。
4.コミュニケーション・人間関係の形成について
・コミュニケーションとは「伝え手と受け手の間で、ある観念や思考が共有されている」という意味合いがあり、全体として見ると「伝達のコミュニケーション」の背後には常に「共有のコミュニケーション」が存在しています。そして、「共有のコミュニケーション」は「感情の発達・分化」「他者理解力」「ともにありたいという欲求」などの力に支えられています。
・「他者理解」には子ども実態に合わせて表情をデフォルメしてあげる方法があります
(例えば、怒った表情を顕わにしたり、少し大袈裟に喜んだり)。また、目の見えない
人や車椅子の人を介助する体験が役に立ちます。
・豊かで多様な感情を育むには「いろいろな人との密度の濃い交流」や「水や木、川や山や海、木や草や虫や動物、暑さや寒さ、息苦しさやにおい、眩しさや暗闇、土や風、といった自然との五感や身体に手ごたえのある触れ合いやかかわり」が重要で、様々な「からだ体験(においや手ごたえ、肌触りなどの身体全体で感じる体験)」に挑戦することが大切です。
知的障害について
前週のブログで、発達障害児の中には知的障害の全くない児童もいれば、重度な知的障害をもつ児童もいること、つまり混在していることを認識しました。
このため、知的障害に関しても最低限の知識、認識を持つ必要があると考え、ネットのサイトで基本的な事を学習しました。今回はそのご紹介になりますが、勉強させて頂いたサイトは「みんなで作る 発達障害ポータルサイト」になります。
ブログは知的障害の概要、知的障害の考えられる原因、そして「接し方で大きく変わる!知的障害の子どもへの接し方のポイント」に関しては、サイトの内容をそのまま掲載させて頂きました。
なお、乱暴な言い方になりますが、発達障害児の知的障害の有無を考える上で、指標の一つとなるのは「知的機能(IQ)」の数値です。
知的障害とは
知的障害とは、発達期までに生じた知的機能障害により、認知能力の発達が全般的に遅れた水準にとどまっている状態を指します。単に物事を理解し考えるといった知的機能(IQ)の低下だけではなく、社会生活に関わる適応機能にも障害があることで、自立して生活していくことに困難が生じる状態です。
知的障害は発達期の間に発症すると定義され、発達期以降に後天的な事故や認知症などの病気で知能が低下した場合は含みません。この発達期とはおおむね18歳までを指しますが、知的障害は障害の状態を指すため、障害が現れる道筋は人によってさまざまで、具体的な発現時期も人により異なります。
知的障害の等級と考えられる原因
知的障害の原因は十分には解明されていない状況ですが、主な要因は病理的要因・生理的要因・環境要因の3つの面から分類できると考えられています。
『接し方で大きく変わる!知的障害の子どもへの接し方のポイント』
伝え方を工夫する
知的障害のある子どもは話や言葉を理解するのに時間がかかったり、記憶するのが苦手ですぐに忘れてしまう子どももいます。絵や文字を紙に書いて伝えることで理解しやすくなることがあります。また、ルールを書いた紙を目に付くところに貼ることで常に意識できるような状態を作ると効果的な場合があります。まねをするのが得意な子どもも多いので、その場合、実際にやって見せるとよいでしょう。これを、「モデリング」と言います。
具体的に説明する
自分で判断して動くことも苦手な場合があるため、できるだけ曖昧な表現は避けて具体的な指示をすることも大切です。どういう手順にすると良いのか、どんなことが悪いかなど、わかりやすい言葉で簡潔にはっきりと伝えるようにしましょう。その際の伝え方は上記のように、手順を絵や文字にしたり、図表で説明します。
よいところを褒めて伸ばす
悪いことは悪いと伝えるだけでなく、よいことはよいと褒めることも大切です。知的障害のある子どもはできないことが多いために叱られることも多くなってしまいます。ちょっとしたことでもよい面を見つけて褒めるようにし、子どもの長所を伸ばすよう心がけてみてください。できることをお願いして「ありがとう」とお礼を言うのもおすすめです。
得意分野を見つける
自分は何でできないんだろうと自信をなくす子どもも多くいます。自信をなくすと、うつ病や不登校などのいわゆる二次障害にも繋がってしまいます。好きなものはなにか、何が得意分野なのかを見つけたり、できることを増やすことで、子どもに自信をつけさせることも大切です。
周りに相談する
不安や心配でストレスを抱え、心に余裕がなくなる保護者の方もいらっしゃるかと思います。心に余裕がないと、子どもに接する時にもイライラしてしまって八つ当たりしてしまうこともあります。家族に協力してもらったり、周りに相談することで少しでもストレスを解消することも大切です。
まずは「知的障害」をよく理解することから始めましょう
知的障害の原因は不明なことも多く、根本的な治療方法もありません。しかしながら、知的障害であることに気づき、子どもへの接し方を変えることで、うつ病やひきこもりなどの二次障害を予防することは可能です。うちの子は他の子に比べて言葉の発達が遅いな、周りと上手く遊ぶことができていないなと感じたら、まずは保健センターや子育て支援センターなどの専門機関に相談してみてください。
早期発見・早期療育は子どもにとっても保護者にとっても心のケアに繋がります。同じ悩みを抱える親同士で相談したり、子どもが友達を作れる環境を整えることも大切です。子どもがよりよい生活ができるよう、知的障害と向き合っていきましょう。
発達障害児へのマッサージを考える#4
今まで、本やネットにある情報に頼って自己学習してきましたが今回の題材はDVDです。中尾繁樹先生のセミナーをDVD化したもので、タイトルは「発達障害を感覚と運動の視点から捉える①②③」です。また、内容は次の通りです。
①最近の子どもたちの様子とその背景(84分)
・イントロダクション
・特別支援教育の視点
・最近の子どもたちの様子
・子どもたちの問題を捉える視点
・発達障害と学習の問題
②感覚と運動の機能(58分)
・発達障害によく見られる感覚運動機能の問題
・感覚とは
・感覚統合とは
③感覚・運動機能の臨床観察法(86分)
・日常に見られる感覚運動の問題
・ソフトサインとは
・利き側の検査
・チェックの仕方
・教室でできる臨床観察
・反応様式の評価
赤ちゃんにはバギーという快適な乗り物ができました。その結果、抱っこする機会は減りました。保育所などの数が足りないのは大きな社会問題ですが、理想の育児環境は1対1の環境だそうです。つまり、お母さんによる育児が無理であれば1対1のベビーシッターの方が望ましいようです。ここで具体的に問題となるのは「愛着行動の形成」です。これは、赤ちゃんの様々なサインに対して、お母さんがどういった受け止め方をするかで、愛着行動の形成が決まっていきます。そして、愛着行動は情緒の安定と関係していると言われています。
発達障害児には「触覚の混乱」のため、触れられることを嫌う子、苦手な子が少なくありません。マッサージは皮膚に触れ、擦ったり圧迫したり、あるいは関節を動かしたりして、触覚と固有覚に働きかける施術とも言えますので、必然的にこの問題と向き合わなければなりません。そして、この「触覚の混乱」という状態を改善することができれば、発達障害児の情緒の安定にも貢献できると考えます。
なお、今回のブログではDVDの中に出てきた、「触感覚」、「固有感覚」に関することと、それ以外の内容で覚えておきたいと思ったことを列挙しています。
触感覚に関すること
触覚の混乱
・触られるのがイヤ~な子(触覚防衛)
・人に触られるのを嫌がったり、あるいは同じ感触を好んで触り続けたりする。これは「触覚の混乱」、強迫観念が強く安心のため触り続ける行為である。
・楽しい雰囲気の時、好きな活動をしている時など、触られていることが気にならない場面を探し、苦にならない場面から慣れる。
触感覚の働き
・情緒と関係している。嫌いなもの(人)に対し、触感覚はまずは防衛的、本能的に働く。一方、それが背景にあって無意識の判断が育ってくる。触感覚が安定していないと情緒的な安定が図れない。
・環境の状況(気温、湿度などの環境状況を把握する)や他者の働きかけ(抱っこ、身体を触るなど)を知る。
・情緒の安定と発達を促す。
・ボディイメージを形成することで自分の身体の姿勢や運動を知る。
・外界に働きかけ、認知系と連動してものを識別する。
触られるのを嫌がる
・触れられるのを極端に嫌がる子どもがいる
・単に人と人との触れ合いということだけでなく、着衣の肌触りとか洗髪とか、特定のものを握るのに強い拒否反応を示す場合もある。
・触られるのを嫌がる状態や不注意・注意散漫などの特徴が同時に見られると、感覚運動機能上の問題があることが多い。
・特に過敏な子は人が近くに来ただけでビクビクしている場合もある。
・さっと触られるのが嫌いな子は「圧」をかけると良い。
触感覚の問題
・特定の触覚(特定の服、毛皮、芝生等)を嫌がったり、逆に触ることにこだわったりする。
・人から触られることを嫌がる。触られることに敏感な部位は身体の前部(顔、胸、腹など)だが、本人に見えないところ(背部)から触られると強い抵抗感を示すことが多い。
・痛みに関しては過反応(極度に痛がる)と低反応(全く痛がらない)に分かれる。極端なケースでは指が折れているのに全く痛がらない子どももいる。
・触れられた身体の部位がわからないこともある(ボディイメージの問題も関係している)。
・触られることに非常に敏感であるか、反対にくすぐられても平気な顔をしていることもある。
・人が近くにいると落ち着かない。
・わずかな痛みにとても痛そうにするか、反対に自分の打撲やけがに気づかない。
・着ている物が少しでも濡れると非常に嫌がる。
・手や足が少しでも汚れるとすぐに洗いたがる。
・砂遊び、粘土遊び、糊等を嫌がるか、反対に他の子どもよりも過度に好む。
・温度に関係なく厚着、または薄着のままでいる。
固有感覚に関すること
固有感覚の働き
・身体各部の位置や運動を知覚する。
・筋緊張を調節し、姿勢の維持と制御を自動的に行う。
・視空間認知や身体イメージを形成する
ボディイメージが付いていないと通れないところを通ろうとしてしまう。距離感がつかめないため、相手と話す適度な距離感がつかめない(ボディイメージが適切に働くと、腕を伸ばして届くか届かないかの位置関係を無意識に取る)
筋緊張
・安定姿勢状態で各関節の可動域を調べ、仰臥位、腹臥位、坐位等へ姿勢変換した時に、動的緊張がどこに入るかを観察する。
・立位、対面、児童に術者の母指を五指で強く握ってもらう。術者は児童の握った五指を包むように母指と小指で挟む感覚で掴む。この状態で全身が1本の棒になったように体を硬くしてもらう(緊張を入れてもらう)。この状態で前後の揺すった時に低緊張の箇所があれば、そこがグラグラしてしまう。応用で手押し相撲やその練習でもある程度わかる。
固有感覚と前庭感覚の問題
・転びやすかったり、簡単にバランスを崩したりしやすい
・車に酔いやすい
・ブランコなどの揺れるものを怖がる
・床の上にごろごろと寝転んでいることが多い
・動きが激しく、活発すぎる
・回転するものにどれだけ長くのっても、目が回らない
・身体全体をよく揺する、動かす
・理由もなく周囲をうろうろしたり、動き回ったりする
・椅子からずり落ちそうな座り方をする
覚えておこうと思ったこと
感覚統合とは
・人間の発達過程で、脳が内外からの刺激を有効に利用できるよう、効率的に組み合わせることを「感覚統合」といいます。脳に届く多くの感覚情報を「必要なもの」と「不要なもの」に分け、整理したり関連づけたりします。この機能により、私たちは外界の状況に対して適切に反応することができます。
・感覚統合療法をまとめた作業療法士のエアーズ(Ayers,A.J.)は、「もし脳が感覚統合してくれなかったら神経の交通渋滞で身動きできなくなる」といっています。感覚統合とは感覚情報を整理整頓すること」と考えても差し支えないと思います。
気になる言動の要因・背景を考える
・「なぜ気になる行動が起きるのか」その理由を考えてみる。
・「なぜできないのか」「どうしたらできるのか」を考える。
・背景になにがあるのかを知る。
体がシャキッとしない子(低緊張)
・揺れ(回転、直線加速)の感覚は前庭感覚、踏ん張る感覚は固有感覚がそれぞれ担う。
・支持が弱い子は「踏ん張り感」を獲得する。
画像出展:「自閉っ子の心身をラクにしよう!」
・不規則な強い揺れで体のシャキッと感を感じる(ブランコやスクーターボード、遊園地
なら、ジェットコースター)
動きが止めれない子
・自分の体をじっくり感じることのできる活動。固定点をつくる(鉄棒のぶら下がり等)。
歩くのが不安定な子(バランスが苦手)
・体の動きを調整する感覚と小脳。
・片足ずつに体重をかけてバランスをとる。(バランスの悪さの原因には筋肉の使い方による
場合もあるので、必ず筋肉もチェックする)
人とのかかわりが上手にとれない子
・コミュニケーションがうまく取れないためにトラブルが多い
・子ども相手の仕事では子どもの顔をみて、よく話を聞く。目を見るのは一瞬でよい。
・なぜ聞けないのかの視点を持つことが必要
・聞く側が別のことを考えている。
・頭が寝ている(覚醒が下がっている)。
・相手が話している内容が難しく理解できない。
・聞きたくない(こころの問題)。
・わかりやすい場面を用意する。活動の反復やゆっくりとした動きを人とのやり取りに結びつける。相手に合わせることがコミュニケーションの基礎になる。
重力(高さ)の過敏
・重力(高さ)の過敏を持っている子どもの中には5cmでも怖がる。抱っこを嫌がる子の中には、触感覚ではなく前庭感覚が問題のときもあるので注意が必要。
姿勢の維持やバランス保持の困難
・最近の子どもたちの中には、同じ姿勢を一定期間保持できない行動がよくみられ、その原因の一つに、体幹の筋緊張の低さ(低緊張)が挙げられる。このような場合、学習中安定して椅子に座ることが難しくなるため、授業に集中できず、学習が理解しにくくなることもある。さらに、粗大運動に影響したり、指の巧緻運動にも課題が出たりする。これらの背景には前庭感覚、固有感覚等の統合がうまくいっていないことが考えられる。
・背面や側面からの姿勢を見たときに、肩辺りの過度の緊張や背中の後彎、骨盤の傾き等がよく見られ、特に頭の後ろから肩甲帯にかけてある僧帽筋の動きが悪く首の動きが悪い場合がよくみられる。
・衝動的なタイプの姿勢として、骨盤が後方に倒れ、足を投げ出して座っているケースが多く、長時間の姿勢維持が難しい場合もある。比較的授業に集中しているけれども、衝動的で自分勝手な意見を多く言う場合もよくみられる。
・普段の家庭での生活も畳やソファに寝転ぶ時間が長いことも考えられる。(骨盤後傾、体幹維持機能低下させる)
・不注意や不器用なタイプは、骨盤から首にかけての筋の同時収縮が弱く、長時間の姿勢維持が難しくなる。
・バランス保持の困難はよく観察される。身体がバランスを崩して倒れそうになっても立ち直れない様子(立ち直り反応の困難)や、つまずいて転倒しても、頭を保護するために手が出ない様子(保護伸展反応の困難)が観察されることがよくある。
・片足立ちをさせるとすぐにバランスを崩す場合は、前庭覚・固有覚・視覚の統合が十分でないと考えられる。
・静止した状態の「姿勢」と動きのある「動作」の両側面から子どもの実態を見極めること大切である。
姿勢運動
・四つ這い 膝立ち
・片足立ち
・タンデム歩行(上半身が動かなければ分離できている)
運動企画(協調)
・スローモーション:手を水平から両肩にゆっくり付け、その後ゆっくり開く。(我慢できないケースでは、多動、衝動だけでなく、筋の低緊張が原因の時もある)
マッサージの課題と期待される効果
1.マッサージが楽しい、気持ちいいと思ってもらうことが第一歩!
2.関節への抵抗運動で固有感覚を感じることできる(ボディイメージ獲得にプラス)。
3.気を合わせる1対1のコミュニケーションを育成する場として利用できる。
4.後頚部、背部、骨盤部の硬さや緊張を緩めることができる。
発達障害児へのマッサージを考える#3
発達障害をもった児童に向き合い、心を通わせることを心がけ、理解を進めていく、そして信頼関係をつくるということが基本であると思います。
一方、机上の学習、知識を増やすことも必要なことです。今回は、以前にもご紹介させて頂いた、杉山登志郎先生の著書、「発達障害の子どもたち」の中から、“発達障害の概観”、“発達障害の新たな分類”、そして“自閉症という文化”の中からいくつか引用させて頂き、知識を広げたいと思います。
発達障害の概観
『発達障害を分けていくと、いくつかの領域に分けることができる。おのおのについて国際的な診断基準によって診断名が確定されている。
ところがこれまでわが国の施策の中で、発達障害として公認されていた問題は、きわめて狭い領域に限られていた。つまり発達障害を抱えていても、社会的に公認されないものが多数存在した。2005年に施行された発達障害者支援法は、これらを発達障害と認定した点で画期的な法律である。
発達の領域と、その内容、その発達障害の診断名、以前から公認されていたか否かについてのまとめを表に示す。診断名は現在もっともよく使われている診断基準である、アメリカ精神医学会の診断と統計のためのマニュアル第四版(DSM-Ⅳ)に従う。』
発達障害の新たな分野
『筆者は現在、発達障害は四つのタイプに大別されると考えている(下段の表参照)。第一のグループは認知の全般的遅れを示す精神遅滞と境界知能、第二グループは社会性の障害である広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)、第三のグループはいわゆる軽度発達障害で、行動のコントロールなど、脳のある領域の働きと他の領域の働きとの連動に際して障害を生じるタイプであり、注意欠陥多動性障害(ADHD)や学習障害(LD)、発達性協調運動障害が含まれる。第四のグループは子ども虐待にもとづく発達障害症候群である。』
自閉症の三つの症状
『自閉症とは生来の社会性のハンディキャップを持つ発達障害である。今日、自閉症は次の三つの症状によって診断される。第一は、社会性の障害である。第二は、コミュニケーションの障害である。第三は想像力の障害とそれに基づく行動の障害で、一般的にはこだわり行動と呼ばれている。
この三つが国際的診断基準を示す基本症状で、言い出した人間の名前を取って「ウィングの三症状」と呼ばれることもある。それ以外の重要な問題として、知覚過敏症の問題がある。また、多動な子どもがいたり、学習障害を呈する子どもがいたり、不器用な子どもがいたりする。このような広い発達領域に一度に障害を生じるので、広汎性発達障害と呼称されているのである。
ここで注意を要するのは、知的なハンディキャップに関して、この三つの症状は何も語っていないということだ。自閉症と診断される子どもには、最重度の知的障害を持つものから、まったくの正常知能のものまでいる。
この三つの基本症状のおのおのについて説明を行うが、それぞれ「自閉症の」社会性の障害、「自閉症の」コミュニケーションの障害という具合に、自閉症独自の形を持つのである。』
逆転バイバイ
『自閉症の社会性の障害とは、人と人との基本的なつながりに生まれつきの苦手さがあるということに他ならない。
赤ちゃんのそばに近づくと、ぱっと赤ちゃんの目が飛んできて、じっとこちらを見つめるのを経験した方も多いのではないかと思う。特にお父さんお母さんに対しては、目が合えば必ずにっこりとほほえむのであるが、見ず知らずの人に対しては、じっと見つめるところまでは同じであるが、わーと泣き出してしまう。またお母さんやお父さんが、赤ちゃんを置いたまま行ってしまおうとすれば、追いかけ、泣き出して追いすがろうとする。
自閉症の場合には、このような一連の愛着行動に、大きな遅れが認められる。まず目が合わない。後追いをしない。それどころか歩けるようになると、平気で親の元を離れて突進してしまい、親のほうが後を追いかけていかないと迷子になってしまう。人見知りもほとんど見られない。
自閉症の社会性の障害とは、筆者なりに圧縮すると「自分の体験と人の体験とが重なり合うという前提が成り立たないこと」と、まとめることができる。
普通の赤ちゃんは一歳前ぐらいになると、何か新しいものを見つけたときに、お母さんの目をまず見る。お母さんがそれを見ていなければ、手で示し、声を上げてお母さんの注意を引きつけ、お母さんが一緒に見つめていることを確認して、笑ったり喜んだりする。つまりこの行動は、注意と感情とを赤ちゃんとお母さんが共有している姿に他ならない。
自閉症児の場合は、この一緒に見る、一緒に喜ぶといった行動が著しく遅れる。それだけではない。健常な子どもは、すでに乳児期の後半からバイバイの真似をして手を振る。自閉症児も、真似ができるようになると「バイバイ」をするが、手のひらを自分の方に向けて「バイバイ」と手を振るのである。これは「逆転バイバイ」と呼ばれる現象である。
ところがよく考えてみると、大人が赤ちゃんに向かって「バイバイ」とするときには、手のひらは赤ちゃんの方に向いている。機械的にそれを真似れば、実は自閉症児の「逆転バイバイ」が正解なのだ!むしろ問題は、なぜ普通の零歳児が、手のひらは自分のほうを向いているのに、相手に手のひらを向けてバイバイができるのかということである。普通の赤ちゃんでは、すでに乳児のうちに、自分の体験と人の体験が重なり合うという前提があるからに他ならない。自閉症の場合には、この段階ですでに問題があるのである。

「認定NPO法人にいがた・オーティズム」は、新潟県新潟市を中心に自閉症児・者とその家族、関係者及び地域社会に対して、自閉症に関する適切な療育と正しい知識の啓発及び地域生活を支援する事業等を行い、もって自閉症児・者の人権擁護及び教育と福祉の充実に寄与することを目的とした特定非営利活動団体です。
左のマークは幼少期のごく短い期間に自閉症児が見せる行動=逆転したバイバイ=をモチーフにした、自閉症啓発のためのシンボルキャラクターです。
言葉の遅れ、こだわり行動
『自閉症の二番目の特徴的な障害は言葉の遅れである。普通は一歳を過ぎると出てくる始語の開始が遅れ、またオウム返しが続くこともある。注目して頂きたいのは、自閉症の言葉の遅れとは単なる遅れではなく、自閉症の社会性の障害の上に、言葉が発達をした形を取っているということである。自閉症の子どもは、言葉が出てくると、オウム返しが長く続くという特徴がある。またミルクが欲しいときに、「ミルクが欲しいの?」と、疑問文によって要求を表すこともよく知られている。なぜこのような疑問文による要求が出るのかと言えば、自分がミルクをもらえるときに、周りから「ミルクが欲しいの?」と聞かれるからに他ならない。つまり、この疑問文で要求するというパターンは、手のひらを自分に向けてバイバイするのと同じ構造である。
このような社会性の障害の上で言葉を発達させているので、言葉が伸びてきた子どもでも、会話を通して体験を共有するといった言葉の活用が著しく苦手といった特徴を持っている。
自閉症の三番目の特徴が想像力の障害である。子どもは遊ぶ存在である。健常な子どもはいろいろなものを別のものに見立て、あるいは何もなくてもそこにあると想像をして、活発なごっこ遊びを展開する。砂の固まりがプリンになり、ご飯になり、お団子になる。また新聞紙を丸めたものが、鉄砲になり、刀になる。このような見立て遊びは、自閉症の子どもの場合極めて苦手なのである。
そのかわり自閉症の子どもが示すのは、こだわり行動である。まず、手のひらを目の前でひらひらさせる、手をぱたぱたと振る、コマのようにくるくる回るといった反復自己刺激行動、それから特定の記号やマーク、また換気扇にだけ注目して突進をするといった興味の限局、さらに道順にこだわる、ものの位置にこだわる、同じやり方にこだわる、順番にこだわるといった順序固執に展開していく。筆者は、一人の自閉症児の幼児期からこだわり行動が何種類出たか調べたことがあるが、なんと800以上あった。そのくらい自閉症にはこだわりがついて回るのである。』
自閉症の体験世界
『自閉症の精神病理の基本は、対話の際に雑多な情報の中から目の前の人間が出す情報に自動的に注意が絞り込まれる機能がきちんと働かないこと、一度に処理できる情報が非常に限られていることの二点である。
これを認知の特徴という点で説明すると次の三つとなる。一つは情報の中の雑音の除去ができないことである。第二には、一般化や概念化という作業ができないことである。三番目は、認知対象との間に、事物、表象を問わず、認知における心理的距離が持てないことである。
普通の幼児は、すでに生後二か月には人の出す情報と、機械音とを識別している。人は人が好きなのだ。我々の注意は強い選択性を持っていて、特に目の前にいる人の出す情報に注意が固定される。
ところが、自閉症の幼児は、このような対人的な情報への選択的注意という機能が十分に働いていない。その結果、お母さんの出す情報も、機械から出る雑音も同じように流れ込んでしまう。いわば情報の洪水の中で立ち往生している状態である。テンプル・グランディンは、自分の幼児期の耳は調整の効かないマイクロフォンのようだったと述べている。

テンプル・グランディンの著書である、「自閉症の脳を読み解く」について書いたブログがあります。クリックすると表示されます。
画像出展:茅ヶ崎市
このような不安定で、怖い世界から自分を守るために、自閉症の幼児がとる戦略は何かというと、自分で、一定の安定した刺激を作り出して感覚遮断を行うという方策である。幼児期の自閉症でよく見られる自己刺激への没頭に他ならない。一定のリズムでぴょんぴょんしたり、目の前で手のひらをひらひらさせたりして、彼らは言わば押し寄せる情報へのバリアーを作り出しているのである。
このような幼児期の混沌とした状態から、徐々に彼らは認知の焦点を合わせることが可能になる。しかし普通の子どもの認知が広く開かれたものであるのとは異なって、おそらくは意識的な焦点の絞り込みによって初めて成り立つために、自閉症の注意は、あるものに注意が向いているときには、他の情報が無視されてしまうという強い過剰選択性を抱えやすい。
喩えれば、木を見て森を見ずということは、我々もしばしば体験することではあるが、自閉症の場合には、木を見ても、一枚一枚の葉が見えてしまう。あの葉は葉脈がきれいだ、あの葉は端っこが虫に食われている、あの葉は半分黄色くなっているなど、一枚一枚の葉が個別に識別されてしまうと、森どころか木の全体像も見えているかどうか分からない状況となる。
このうような世界の見え方は次のような喩えのほうが分かりやすいかもしれない。ロシアの街角を当て所なく歩いているとしよう。看板は全部ロシア語で書かれているから何も分からない。すると遠くに日本レストランの日本語で書かれた看板が見える。どんなに距離があっても、皆さんはそこに向かって突進をするのではないだろうか。混沌とした世界の中に、ある分かりやすいもの、たとえば換気扇が見えるとする。するとデパートに行っても、スーパーに行っても、体育館の中でも、換気扇に向かって突進する。これが世界が見えてきたばかりの自閉症の世界である。
自閉症の体験世界の特徴について、もう少し続ける。注意の障害があるために、知覚情報の雑音の除去ができないという困った問題が残る。この結果、大きな声が聞こえずに、小さな機械音(たとえばエアコンの音など)が強烈に聞こえるといった現象が生じることもある。
また、自閉症的な認知の仕方では、我々が一般的に行っている名付けや概念化に基づく慣れが生じないという傾向が生まれる。たとえば我々が目の前のコップに目を留めたとする。特に特徴のないコップであれば、「コップ」という概念で我々は目の前の物体をとらえ、瞬時にしてその認知に慣れが生じてしまう。ところが自閉症の場合には、そのコップを見たときに、どこに目を留めているのか解らない。コップの上に描かれている花の模様に目を留めているかもしれないし、場合によってはコップに映っている光に目を留めているかもしれない。このように言葉による概念化が動かないために、言葉を通して認知したものとの心理的な距離を取るという機能が働かない。コップに注意を留めたとき、自閉症者はいわば自分自身の一部がコップになるのである。
このような、認知対象との心理的距離がまったく取れない認知の仕方をしているため、いくつかの対象を同時に視野に入れて処理することや、さらに視点を変えるということが非常に難しくなる。見通しを立てるためには、心理的な距離が必要である。正常知能の者でも、見通しを立てることや終点から逆算してスケジュールを組み立てるといったことが、苦手というよりほとんどできない。このような一般化、概念化、そして見通しを立てる機能の障害は、自閉症の社会的な障害の中核に位置するものである。』
自閉症児の発達の道筋
『非高機能、高機能を問わず広汎性発達障害に共通の対人関係の発達について触れておきたいが、その前に、自閉症の対人関係の持ち方によるタイプについて解説を加える必要がある。同じ自閉症という診断でも、ずいぶん様子が異なる。少しでもその特徴に沿った対応が出来るようにという目的によって筆者は、対人関係で自閉症を孤立型、受動型、積極奇異型の三つに分けている。これもオリジナルは三症状の言い出しっぺであるウィングである。
孤立型の自閉症とは、人との関りを避けてしまうタイプの自閉症である。先に触れた知覚過敏が強くあり、また比較的重度の知的障害を伴っているものが多い。受動型とは、受け身であれば人と関わることが出来るタイプの自閉症である。知的障害を持つものも持たないものもいる。一般に、早期療育を行うと孤立型であった子どもも、徐々に受動型にタイプが変わっていくのが認められる。実は知的障害が若干あるくらいの受動型の自閉症は、一番よく仕事が出来るタイプでもあるのだ。積極奇異型とは人に積極的に、しかし奇異なやり方で接する自閉症である。知的な障害は軽い者が多いが、マイペースで、基盤に注意の障害を持っていて、多動であることが大きな特徴である。このグループも、小学校高学年になると多動は治まってきて、人との関わりが進んでいくと徐々に受動型に近いタイプに変化していく。
自閉症グループの幼児は、知覚過敏症などの問題に妨げられて愛着の形成が著しく遅れる。特に孤立型と積極奇異型である。積極奇異型の高機能児であっても本格的な愛着の形成が小学校年代に入ってからという児童は少なくない。したがって、小学校年代においてはきちんと子どもの甘えを両親に受け入れてもらうことがとても大事な課題となる。一般に4歳前後までの幼児期が最も大変で、5歳ごろにコミュニケーションが目覚ましく伸びる時期があり、小学校では指示の通りも良くなり、状況理解も向上し、問題行動も軽減し、黄金時代となる。小学校高学年は一生の間でも一番良く伸びる時期となる。この5歳代と10歳から12歳という二つの時期はコミュニケーション能力が飛躍的に向上する時期となることが多く、対人関係においてもまた成長が認められる。
青年期はかつてパニックの頻発が問題となっていたが、そのような児童が著しく減った今日から振り返ってみると、自閉症の認知特性を無視した強引な指導によって、青年期を迎えた自閉症者が二次的に大混乱をおこしただけということが明らかである。性的行動や、興奮しやすいといった問題が生じやすい時期ではあるが、今日において青年期は、小学校高学年に次ぐ、よく発達する時期となっているのが普通である。』
自閉症への治療教育
『さて、発達障害の治療教育については、後にまとめて述べるが、自閉症への対応のコツについて、ここで触れておきたい。先に自閉症の認知特徴を三つに絞って述べた。第一に、情報の中の雑音の除去ができないこと。第二に、一般化や概念化という作業ができないこと。第三に、認知対象との間に、事物、表象を問わず、認知における心理的距離が持てないことである。このそれぞれに対して工夫することが治療教育のコツとなる。
まず第一の問題であるが、この対応のための工夫が、できるだけ情報を減らし、特に同時に二つの情報を出さないことであり、一般にこれを構造化と呼ぶ。とりわけ知的障害を伴った自閉症の場合、情報の雑音の除去はきわめて困難で、雑多な情報があふれるところではしばしば立ち往生してしまう。教室のような比較的構造がしっかりとした場所でも、同時に二つの情報を出されると一つは無視されてしまう。たとえば、手を握りながら話しかければ、握られた手の知覚入力だけであふれてしまい、言われたことはまったく入らなくなるといった現象である。そのために一度に複数の情報を提示しないことが求められる。言うときは言うだけ、見せるときは見せるだけ、触れるときは触れるだけ。
付言すれば小学校低学年までのまだ生理的な不安定さを持つ重度の自閉症の子どもには、みだりに触らないほうが無難である。これに関連し、特に過敏性に対する配慮が常に必要とされる。高機能者グランディンによれば、印刷物にしても白紙に黒いインクではコントラストが強すぎて著しく読みにくいのであるという。これが紙に薄い青なりピンクな色がのっている場合には、はるかに読みやすくなるという。また、一部の児童は蛍光灯の微細な点滅を非常に嫌うこともある。ちょうどディスコの中に居るように感じられるのだという。
このような問題の上に、第二の認知の特性が重なる。自閉症児の場合、何度も体験したからといって徐々に慣れてくるということが期待できないところがある。また、一般化ができないこともあって、変化に対しては常に強い抵抗が生じる。要するに混乱してしまうのである。この点に関しては、特に知的障害を伴った自閉症においては、ある程度のこだわりの尊重と活用が現実的である。予定を変更せず、どうしても変更が必要なときには必ず予告を行うようにする。
さらに第三の問題は、見通しを立てることが困難につながる。知的に高いグループにおいてもきわめて苦手な、予測に基づく行動修正や予定の変更などの困難を克服する方法がある。現在広く用いられるようになったのは、スケジュールカードなどによって、見通しの立てにくさをカバーし、行うことを直線上に並べるという対応方法である。
このように見ると、特に小学校低学年において、広汎性発達障害への教育は個別教育が基本であり、基本を固めた後に初めて集団への参加を行うということがやはり好ましいのではないだろうか。早期療育を受けてきて集団での活動をすでに獲得した児童の場合には、必ずしもこの原則どおりではないが、高機能児でも集団参加が非常に難しい事例がけっして少なくない。
わが国の学校教育は行事が多すぎる。準備なしに行事に駆り立てることは、児童を混乱させるだけである。さらに通常教育、特別支援教育を問わず担任が毎年変わる状況では、自閉症グループの児童への十全な教育は不可能であろう。児童と教師との擦りあわせが可能となるのは11月を過ぎたあたりであり、三学期になるとやっと相互に信頼が取れた活動が可能となるが、また新学年に大混乱となるのである。
自閉症グループの発達障害は、社会的な行動を一つ一つ積み上げることが適応を向上される唯一の道である。したがって、他の発達障害と同様、彼らへのもっとも誤った対応はといえば放置に他ならない。』
まとめ
今回、学んだことの中で、特に次の4つは常に意識したいと思います。
1.自閉症に対しては、「情報の洪水に立ち往生している姿」を想像すること。
2.自閉症の中には、知的障害を持つ者も、まったくの正常知能の者もいること。
3.何度も体験したからといって、慣れてくるということをあまり期待できないこと。
4.特に知的障害を伴った自閉症の場合、できるだけ情報を減らし同時に二つの情報を出さない
こと。(「言うときは言うだけ」、「見せるときは見せるだけ」、「触れるときは触れるだ
け」を意識する)。
発達障害児へのマッサージを考える#2
発達障害児のマッサージを始めていますが、早速、通常のマッサージとの違いに直面しました。それは以下の3つです。個人個人により抱えている課題も異なり、程度も様々ですが、少なくともこの3点に対しては対応が必須と考えました。なお、内容については「障害者のための絵でわかる動作法 はじめの一歩」に順じています。

著者:長田 実、 渡辺 涼、 宮崎 昭
イラスト:田丸 秋穂
出版会社:福村出版
絵を見ながら実践できる解説書です。プログに載せている表、イラストもすべて本書のものです。
課題1.マッサージを受けることに対して不安がある。
課題2.発語(会話)、聴覚の問題を含め、痛み、こり、違和感を意思表示できないことが多い。
課題3.仰向け、うつ伏せ、横向きの姿勢を数十秒もじっとしていられない児童もいる。
それぞれの課題に対して考えた対策をご説明します。
対策1
本の中に「訓練の進め方」が書かれています。本の対象は「動作法による訓練」なので、マッサージの施術とは同じではありませんが、たいへん参考になります。下記がマッサージ用に考えた手順とポイントになります。
・準備状態を整える
・施術は自然な位置関係と無理のない姿勢が大切です。施術者自身の姿勢と気持ちを安定させることも必要です。
・施術を始める前に、部位や方向、強さをわかりやすく伝えることが大切です。特に関節を動かす場合は、施術者自身が動かせて見せることも有効です。また、動かしていく時も戻す時も「ゆっくりそっと」が原則です。
・施術の開始を明確にする
・施術を始める時には「さぁ、やるよ」と声をかけます。なお、児童が落ち着かない場合は、あわてず、受け入れてくれるまで待って、気持ちを合わせて始めます。
・児童の抵抗や緊張を感じる
・施術者に伝わってくる児童の微妙な抵抗感に「気づく」ことが大切で、緊張があるということを察知します。この場合、急がないこと、施術者自身が緊張しないことが基本です。施術中は、日常よりもアイコンタクトしやすいので、なるべく心がけるようにしますが、じっと見るのではなく、短く軽いアイコンタクトを心がけます。
・動作の終わりを明確にする
・施術によりますが、関節の他動運動などでは回数を伝えることが必要です。また、気持ち良い感覚をもって施術を終えることができるように意識します。
対策2a
児童自からが意思表示することが困難であるとすれば、まず必要なことは、児童の心身の特徴や課題をよく知ることだと思います。本には「フェイスシート」と呼ぶフォームが掲載されています。また、特に「からだ」の状態は「状態像をみる姿勢」として、イラストが示されています。
これらは現場で大いに役に立つと考え、パソコンでデータ入力をできるようにするため、ファイルを作成しました。
対策2b
児童の状態を把握するため4つの姿勢をとってもらい、不自然な箇所、緊張の強いところ、緊張の弱いところなどを確認します。ここで確認できた箇所は施術の重点ポイントと考え検討します。
対策3
座ればじっとしていられる場合は座位にて施術を行いますが、マットの上、椅子、年少者であれば施術者の足の上に腰掛けさせるなど、安定した姿勢を取ります。

児童は床にあぐらで座ります。術者はその背後から頚、肩、頭にマッサージを行います。

児童の大腿部を固定し、躯幹を捻ります。これは体幹と股間をリラックスさせます。

足首の軟らかさは立位の安定に関係する重要な個所です。この図では椅子を使っています。

この図も足首を緩めています。年少者であれば施術者の足の上に座らせる方法もあります。

手や手指へのマッサージは脳を活性化します。向い合って行う際、短いアイコンタクトを心がけます。
施術は、「緊張から解放されリラックスできること、リラックスした心と体の状態を感じてもらうこと、そして共有すること」を一つの目標にしていきます。
地に足を着ける
長い予約待ちだった本ですが、忘れたころに図書館から連絡が入りました。発達障害児へのマッサージについては、中締めも終わり、次は実践という感じだったため、「読む?」と迷ったのですが、
著者の栗本先生は整体や各種手技療法のプロで、この1、2ヶ月で読んだ本とは傾向が異なっていたため熟読させて頂きました。

栗本先生は「からだ指導室 あんじん」というホームページを立ち上げられています。
・「整っている身体」とは睡眠や休息によって、疲れを回復できる身体。
・「いい姿勢」は一人一人違う、息が深くできるのがいい姿勢。

左の図は中央に置かれた5感(触覚・視覚・聴覚・味覚・嗅覚)と2覚(前庭感覚・固有受容覚)が「感覚調整」と「運動行為」という2つの問題に関わっているという図で、感覚統合を理解するうえで、たいへん分かりやすいものであると思います。
画像出展:「もっと笑顔が見たいから」(花風社)
今回の本は上の図でいえば、右側の破線で囲まれたボックスに示された「姿勢」や「運動行為」に焦点を当てた内容になっています。
その中からここでは、『4.腰は使えているか?』と『8.大事なのは「土台」』、からだの部位で言えば「腰」と「足」について取り上げたいと思います。
「腰が使えている」とは「腰の力を入れたり抜いたりが自在にできること」という意味です。例えば、タオルを使って二人で綱引きすると、腰が使えていない人は腰がへっぴり腰になります。普通の人でも腰痛があると思うように力を入れることができず、へっぴり腰のようになるのではないでしょうか。
注)下記の図は、「固有受容覚」以外、すべて「自閉っ子の心身をラクにしよう!」(花風社)から引用させて頂いたものです。
腰が使えるようになるトレーニング
土台がしっかりしていないと、本来入るべき所に力が入らず、逆にリラックスすべき所に力が入りっぱなし等ということがおきるため、疲れやすくなります。
土台をしっかりさせるということは、まさに「地に足を着ける」ことです。このことは「整った身体」を作るコツです。そして、情緒の安定や集中力の向上、意欲の増進につながります。
「地に足を着ける」には足首の柔軟性と調整力が必要です。足首が使えていないと、つま先立ちとなり、首が緊張し前傾しやすくなり、その結果、姿勢が悪くなります。

足首は蝶番関節といって、ドアのようにパタパタと上下させることができるのですが、うまく使えていないと、動く必要のない筋肉まで緊張して、全体が動くような感じになってしまいます。
また、つま先立ちになりがちなのも足首の問題です。これにより、首が前傾し姿勢が悪くなります。
自閉症は周りの刺激にずっと反応し続けるために、頭が休まらず疲れやすいという傾向もあります。また、多動といわれる症状は、落ち着きのなさだけでなく、不注意や衝動的なふるまいが見られるものです。
姿勢の悪さは不安を生み、それをカバーするために、からだを動かしているという指摘もあります。従って、地に足を着け、土台をつくり、姿勢が良くなればこのような問題は改善が期待できます。
地に足を着けるためのトレーニング
・足に触れたり、足関節や個々の足指の関節を動かしたりして、触覚と固有受容覚を刺激します。
・つま先立ちなど、足関節の緊張や硬さなどを軽減するため、収縮する筋肉のフクラハギ(腓腹筋・ヒラメ筋)と反対に伸びる、前側にある前脛骨筋へのマッサージを行います。また、太ももの裏側(ハムストリングス)などをストレッチしてあげるもの有効です。
発達障害児へのマッサージを考える
昨年12月16日のブログからスタートした、「小児障害・発達障害」に関する突貫工事も、中締め的に一度整理し、実践に向けて準備したいと思います。まとめ方は、サラリーマン時代に使っていた課題検討のやり方で、ちょっとマニアックな印象を持たれるかも知れません。
なお、新たに勉強した本は以下になります。
Goal
1.個人としての自立、就職、そして将来に渡って生活していく基盤を獲得する。
Objective
1.施術により個人が抱えている問題が改善され、自立に向けて前進する。
Strategy
1.障害児の個性と現状を理解し、明確な目的を持ち最適な手技を選択する。
2.感覚統合療法を補完し、総合的な改善の促進を図る。
Action1(準備)
1.感覚統合療法を理解する。

この図は「自閉症スペクトラム」を対象として描かれたものですが、左右の破線で囲まれたBoxにある「感覚調整の問題」および「運動行為の問題」に記載された各問題点は、他の病態にも適応可能な共通性の高いものと思います。
画像出展:「もっと笑顔が見たいから」(花風社)
1)五感と二覚の中からマッサージでは「固有受容覚」と「触覚」をターゲットとする。
2)「感覚調整の問題」7項目と「運動行為の問題」4項目を問診により把握する。
A)計11項目のうち、該当した項目については施術効果の判断指標とする。
2.マッサージの対象を絞り込む
1)社会性の発達障害…広汎用性発達障害(自閉症スペクトラム)
2)注意力、行動コントロールの発達障害…注意欠陥性障害(ADHD)
3)運動の発達障害…肢体不自由、動作不自由
3.筋緊張を確認する
1)緊張、不安が強い
2)低緊張
A)低緊張の判断ポイント
・口元:よだれがよく出る
・姿勢:うつぶせの姿勢から手だけで体を起こそうとする。移動するときにおしりを床につけてずりばいする等。
4.健康の基本を確認する
1)睡眠
2)食欲
3)便通
5.気になる部位等を確認する
1)皮膚
2)筋肉
3)関節
4)消化器
6.理解を深めるために知っておくこと
1)生まれつきの障害であり、統合失調症などとは決定的に違う。つまりその世界に生きている者にとって、その世界は奇異でも何でもなく、ごくごく当たり前である。
2)自閉症の精神病理の基本は、対話の際に雑多な情報の中から、目の前の人が発する情報に注意が集中できないこと、一度に処理できる情報が非常に限られていることの二点である。
3)不安定で、怖い世界から自分を守るために、自閉症の幼児がとる戦略は、自分で、一定の安定した刺激を作り出して感覚遮断を行うという方策である。幼児期の自閉症でよく見られる自己刺激への没頭に他ならない。一定のリズムでぴょんぴょんしたり、目の前で手のひらをひらひらさせたりして、彼らは押し寄せる情報へのバリアーを作り出しているのである。
4)大まかで曖昧な認知がとても苦手である。
5)一般的に4歳前後までの幼児期が最も大変で、5歳ごろにコミュニケーションが目覚しく伸びる時期がある。また、10歳~12歳の小学校高学年はさらによく伸びる時期である。
6)何度も体験したからといって徐々に慣れてくるということが期待できないところがある。
7)現在では脳科学の進展によって、注意欠陥性障害(ADHD)の症状の背後にはドーパミン系およびノルアドレナリン系神経機能の失調があることが明らかになっている。
8)現在の感覚統合理論では、感覚統合障害は大きく二つの障害、すなわち「行為機能の障害」と「感覚調整障害」に分けられる。行為機能の障害は、触覚、固有受容感覚(筋肉にある受容器で感じる身体の位置や動きの感覚)、前庭感覚(耳の奥の三半規管や耳石器などで感じる回転やスピード、傾きの感覚)などの感覚情報の処理過程に問題があり、それによって身体の位置や動きがわかりづらいなどの問題が生じ、不器用さや姿勢運動の問題など運動行為面に困難が出る。
9)ボディイメージを育てるためには触覚と固有受容覚が特に重要になる。マッサージなどで他動的に触覚や固有受容覚を刺激することは効果的と思うが、ボディイメージを高めるためには、能動的体験の中で触覚、固有受容覚を体験することが必要である。
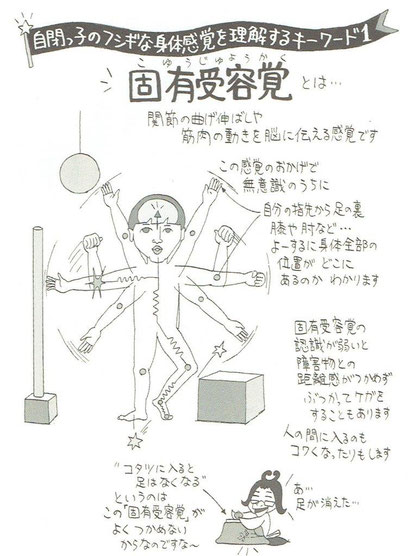
以前にもご紹介させて頂いたことのある図です。この絵のように関節を動かすことは、屈筋を収縮させ、拮抗する伸筋を弛緩させるので、固有受容覚に刺激を入れることができます。
画像出展:「もっと笑顔が見たいから」(花風社)
Action2(施術)
1.マッサージのガイドライン
1)働きかける神経
A)知覚神経
・鎮痛、鎮静
B)運動神経
・機能亢進(マヒ性疾患)、機能抑制(筋痙攣)
C)自律神経
・交感神経と副交感神経のバランスを整える
・自律神経反射
・胃、腸管への刺激による血管運動や消化液の分泌調節
・内分泌系、特にストレスに関係する副腎皮質に働きかける
2)部位に対する効果
A)皮膚におよぼす作用(触覚)
・新陳代謝を活性化する
・皮脂腺、汗腺の働きが活発になり分泌が亢進する
B)筋におよぼす作用(触覚、固有受容覚)
・血行を良くする
・筋疲労を早く取り除く
・筋萎縮の予防
・筋痙攣の抑制
C)関節におよぼす作用(固有受容覚)
・関節内の血行を良くする
・可動域を広げる
・滑液の分泌を促す
・関節の拘縮を軽減する
D)消化器におよぼす作用(触覚→神経反射)
・背部、胃部の施術で胃液の分泌亢進、消化機能亢進、食用増進
・腹部施術で腸の吸収力増加、蠕動運動の亢進と便通が良くなる
3)手技による効果
A)興奮作用:主に軽擦法
・興奮作用とは病的に機能が低下している神経、筋に対してその機能を回復させる作用。手技は弱い刺激で時間は短く行う。運動麻痺、知覚鈍麻、知覚脱失などに対して治療効果がある。
B)鎮静作用:主に軽擦法、揉捏法、圧迫法、叩打法
・鎮静作用とは病的に機能が亢進している神経や筋に対してその機能亢進を抑え、鎮静させる作用。手技は強い刺激で時間も長く行う。しかし病的に機能亢進をきたしているような場合には感受性がたかまっているため、実際的には強い刺激を与えずに、患者が強いと感じる刺激を選んで施術する必要がある。神経痛、筋痙攣、筋緊張、知覚過敏、筋肉痛などに対して治療効果がある。
C)反射作用:主に軽擦法、圧迫法
・反射作用とは疾病部位から離れた部位に施術をして反射機転を介して、神経や筋、内臓などに刺激を与え調整を図る。生体は内臓に異常がある場合に、皮膚、結合組織、筋肉などの表在組織に反射されて異常が現われる。その部の過敏、圧痛、緊張、硬結などを取り除くことにより、内臓の状態は改善される。
4)運動法による効果
A)他動運動法
・術者が患者の関節を可動する範囲で動かす方法
・関節拘縮、変形の予防
・可動域の維持・改善
・筋短縮の予防
・固有感覚受容器への刺激
B)自動運動法
・患者が自分で行う運動法
・筋力の維持・増強
・可動域の維持・増強
・関節・筋肉内循環の促進
C)抵抗運動法
・患者に自動運動を行わせながら、術者がその運動に対して抵抗する方法
・筋力の増強
・筋持久力の増強
5)効果を上げるためのコミュニケーション
A)安心感を与える手の当て方をする
・まず、子供は自分の体に触れられることに対して大きな不安を感じている。
・不安を感じない程度の力を使う。
・手のひら全体を使う感じ。
B)体の感じを子供と共有する
・子供が感じているだろう感覚を、施術者も同じように感覚を感じるようにする。
C)言葉かけを大切にする
・子供の気持ちをリラックスさせ、その気にさせる。
・施術者も言葉かけと施術を重ねることで良いリズムで楽しく取り組むことが大事。
D)主体的な取り組みを大切にする
・子供は気が散って、集中できないことが多い。特に自閉や多動の子供たちは、訓練を自分が主体的に行っているという実感を欠いている。したがって、子供が自分の体の感じに気づき、自分で体を緩めたり動かしているという感じをつかめるようにする主体的な動きを行わせる必要がある。
・まず、優しく、ゆっくりと何をどうしようとしているのかを部位に軽く触れながら「こういう動きをするよ。」と説明する。
・どこがどう感じているかを聞きながらゆっくり進め、自分で緩む感じや動く感じを認知する。
・さらに、自分自身が主体的に動かす感じをつかめるように、動かしている方向、スピード、可動域などを細かく伝えながら、二人三脚で理解するという課題に取り組んでいく。
E)仰臥位の運動法の時にアイコンタクトを行うようにする。

一般的にアイコンタクトを避ける障害児も、刺激が入っている時はアイコンタクトの回数が増えるようです(感覚統合療法で行われている工夫)。これはマッサージの施術中でも意識すれば可能なので実践します。
画像出展:「もっと笑顔が見たいから」(花風社)
「自閉症の脳を読み解く」
著者のテンプル・グランディン氏はコロラド州立大学の動物学博士であり、自閉症の当事者です。また、自閉症啓蒙活動において世界的に影響のある学者のひとりとされています。
『本書では、自閉症の脳をさぐる旅にみなさんをご案内しよう。私は、自閉症をもっているが、この2、30年に、つねに最先端の技術を使った脳スキャンを数多く受け、さまざまな知見を得てきた。そのため、この知見と自閉症の体験の両方について語ることができる特異な立場にある。1980年代の後半にMRIが実用化されてまもなく、生まれて初めて「自分の脳をさぐる旅」に出かけるチャンスに飛びついた。当時、MRIはまだめずらしく、自分の脳の構造を細かく見るのは、すばらしいことだった。それ以来、新型のスキャン装置が導入されるたびに、かならず、まっ先にためしている。私は子どものころに言葉の遅れがあり、パニックの発作を起こし、人の顔をおぼえるのに苦労したが、そうしたことが、脳画像の解析によりいくらか説明できるようになった。』
これは「自閉症の脳を読み解く(The Autistic Brain)」という本の「まえがき」の書き出しの文章です。
このブログでは、自閉症の脳の特徴と感覚処理の問題について考えてみたいと思います。
自閉症の脳とは
・解剖学的には正常である。
・自閉症の脳は壊れているのではなく、順調に発達しなかったというものである。
・ユタ大学の研究では健常者との同質性は約95%であり、これは健常者同士に見られる同質性の比率と大差はない。
・自閉症の一部で見られる共通的な特徴は、大きい扁桃体と大きい頭である。
・大脳皮質の領域間の接続不足と接続過剰が見られる。(大脳内は白質と呼ばれる神経線維が高速道路のようにつながっており、このつながりに接続不足や接続過剰が見られるということです)
自閉症に多く見られる対人反応
・自閉症の人の大脳皮質は、人の顔を見ても物を見たときほど活発に反応しない。
・自閉症の人は目を合わせない。これは視線を合わせるアイコンクトに対して正反対の反応をするのである。右脳の側頭頭頂接合部が、普通の人の脳では相手の凝視に対して活性化したのに対して、高機能自閉症の被験者では相手が視線をそらしたときに活性化した。側頭頭頂接合部は、相手の心の状態を察するなどの対人関係の課題にかかわると考えられている。さらに、左脳の背外側前頭前野で正反対のパターンが見つかった。普通の人ではそらした視線に対して活性化が見られ、自閉症の人では相手の凝視に対して活性化が見られた。つまり、自閉症の人はアイコンタクトに反応しないのではなく、普通の人と反対の反応をするということになる。これは、普通の人が出す好意・嫌悪のサインと逆ということになる。(つまり、自閉症の人にとっては、無視や冷たい態度というものが、好ましい態度に感じられるということになります)
テンプル・グランディン氏の脳画像
・小脳が標準より20%も小さい:『小脳は運動協調性をつかさどっているから、この異常のせいで、たぶん私はバランス感覚がお粗末なのだろう。』
・脳をつなぐ連合線維に関して、下前頭後頭束と下縦束の接続が非常に多い:『「(以前)私の脳には視覚野につながるインターネットの基幹回線、直通の回線があるに違いない。だから記憶がいいのだ」。たとえのつもりだったが、この描写は、私の頭の中で実際に起こっていることをずばりと言い当てている。』
・左側脳室が右側脳室より50%以上も長い(通常は15%以内): 『私の左側脳室はとても長く、頭頂葉にまで伸びている。頭頂葉は作業記憶(ワーキングメモリ)にかかわっている。なるほど、頭頂葉が妨害されているから、私はいくつかの指令に迅速に従って作業をこなすのが苦手なのだ。頭頂葉は、また、数学的能力にもかかわっているらしい-だから私は代数で苦労するのだろう。』
・頭蓋内容積、頭蓋骨の容量と脳の大きさが、どちらも15%ほど大きい:『これもまた、何らかの発達異常から生じたと考えられる。損傷した部分を補うために、神経細胞が速く成長したのかもしれない』
・大脳左半球の白質がほぼ15%大きい:『またもや、この異常が生じたのは、左脳で発達初期に異常があったためと、脳が新しい接続を生みだすことによって補おうとしたためと考えられる。』
・扁桃体がおよそ22%大きい:『扁桃体は恐怖などの情動を処理するときに重要な役割を果たす。扁桃体がこんなに大きいから、私は生まれてからずっと不安にさいなまれているのだろう。1970年代の大半で私に襲いかかってきたパニックは、新たな視点で考えてみると、つじつまが合う。私には何もかもが怖い、私の恐怖心自体も怖いのだと扁桃体が語っていたのだ。』
・左右の嗅内野が左は12%、右は23%も厚い:『カリフォルニア大学ロサンゼルス校デヴィッド・ ゲッフェン医科大学院のイツハク・フリード神経外科教授によると「嗅内野は脳の記憶装置本体に通じる黄金の門だ。』
『当然ながら、この結果はすばらしいと思った。私を私たらしめている奇妙なことが脳で起こっていて、その奇妙な点のいくつかを浮き彫りにしているからだ。』

左の絵は2つの神経細胞。左は運動ニューロンで右は感覚ニューロン。運動ニューロンは樹状突起をもつ細胞体から筋肉に向かって遠心性に伝わる。一方、感覚ニューロンは皮膚などにある受容器から求心性に伝わる。
ここでは水色の髄鞘の下に軸索(有髄神経線維)が見える。灰白質とは、神経細胞の細胞体が存在している部位であり、これに対し、有髄神経線維だけの部位を白質と呼ぶ。大脳半球の内側には、有髄線維の集合体となっている白質が存在し、交連線維、連合線維、投射線維に分類される。なお、テンプル・グランディン氏が指摘されている下前頭後頭束と下縦束は、同側の大脳半球の異なる領域を繋ぐ連合線維に含まれる。
画像出展:「人体の正常構造と機能」(日本医事新報社)
自閉症の感覚処理問題を分類する方法(テンプル・グラディン氏は重視されていません)
1.感覚刺激を求めるタイプ…自閉症の中に感覚刺激を求める傾向があるのは、自分が求めているほど感覚刺激が十分に得られないためである。その感覚刺激には音を求める人もいれば、筆者のようにじわじわと感じる圧力の刺激を求める人もおり様々である。また、自閉症の人が体を揺らしたり、ぐるぐる回ったり、手をひらひらさせたり、音をたてたりするのは自分で感覚を刺激しているのである。
2.感覚刺激に対する反応が過剰なタイプ…このタイプは、感覚刺激に対して過剰に敏感である。何かの匂いが我慢できないとか、騒がしいレストレンで座っていられない、ある種の服を着ることができない、ある種の食べ物が食べられないといった反応を見せる。
3.感覚刺激に対する反応が過少なタイプ…このタイプは、普通の刺激に対して反応が乏しかったり、まったく反応しなかったりする。例えば、聴覚に問題がなくても、名前を呼ばれて振りかないことや、痛みに反応を示さないことがある。
2010年に発表された「自閉症の感覚処理のサブタイプ-適応的行動との関連」による分類。この分類は特に理学療法士にとって、特に重要とされています。
1.感覚刺激を求め、不注意あるいは過剰集中の行動を招く
2.運動敏感性と低い筋緊張をともなう(反応不足あるいは反応過剰による)感覚調整
3.極端な味覚・嗅覚敏感性をともなう(反応不足あるいは反応過剰による)感覚調整
筆者はいずれの分類法も妥当であるとしながらも、同じようなデータが二つの異なる方法で体系化できることに疑問をもち、問題なのは解釈ではなく、データ自体にあると考えました。そして、自己申告による情報の重要性に着目すると共に、軽度な高機能自閉症だけでなく意思表示が困難な重度な自閉症患者についても考えなければならないとしました。ティムとカーリーはその例として紹介されています。
ティト・ラジャルシ・ムコパディヤイ
『(ティトは)著書、「唇が動かないなら、どうやって話せばいいのか-自閉症の僕の心の中」で、閉じ込められた生活から解放された話をしている。解放は、お絵かきボードに数字と文字を書き込むことによって実現した。ボードは、1990年代初め、ティトが4歳になる前に母親が与え、ティトは母親の助けを借りて数字とつづりをおぼえた。やがて母親は、ティトの手にペンをしばりつけて、書くことでコミュニケーションをはかれるようにした。
ティトは、ここ数年のあいだに本を何冊か出版し、その中で、現実をどんなふうに体験するのか、「行動する自分」と「考える自分」の二つに分けて説明している。最近、本を読み返して、初めて会ったときのことを思い出した。あのときは気づかなかったが、行動するティトと考えるティトをたて続けに見ていたのだ。
ティトと会ったのは、サンフランシスコの医療センターの図書室。照明は薄暗かった。蛍光灯がそなえられていたが、私たちの訪問を考慮して消されていた。部屋は静かで、雰囲気は落ち着いていた-気をそらすものはない。話をしたのは、ティトと私とティトのキーボードだ。私は、馬に乗っている宇宙飛行士の絵を見せた。ティトが見たことのないはずの絵をことさら選んだ-近くの本棚にあった「サイエンティフィック・アメリカン」誌のバックナンバーで見つけたテクノロジー関連企業の広告。ティトが自分の考えを言葉でどんなふうに述べるのか知りたかったのだ。
ティトは絵をよく見て、キーボードに向かった。「馬に乗ったアポロ11号」とすばやくタイプを打った。それから、羽ばたくように腕を上下させながら図書館を走りまわる。ティトがキーボードにもどってくると、牛の写真を見せた。「インドでは食べない」とティトはタイプを打った。それから、羽ばたくように腕を上下させながら図書館を走りまわる。私はもう一つ質問したが、それがどんな質問だったのか、今では思い出せない。それでも、次に何が起こったのかは、おぼえている。ティトは答え、それから、羽ばたくように腕を上下させながら図書室を走りまわったのだ。対談はそれで終わり。ティトは1回の面会で書けるだけのことを書いていた。休む必要があった。三つの短い質問に答えるだけでも、かなりの労力が必要だったのだ。
ティトは著書の中で、行動する自分を「奇妙で、じつによく動きまわる」と説明する。自分自身を「手とか脚とか」のように一つひとつの部分と考えていて、ぐるぐるまわるのは、「ばらばらの部分を一つにまとめる」ためだという。~中略~ 行動する自分は、腕を翼のように上下させて図書室を走りまわる。考える自分は、そうやって走りまわる自分を観察する。』
カーリー・フライシュマン:著書「カーリーの声-自閉症を打ち破る」
『カーリーはきわめて低機能だった。テイトと同様に、行動する自分はつねに動きまわったり、座って体を揺らしたり、叫んだり、手あたりしだいに何でも壊そうとした。そしてテイトと同様に、考える自分は、だれもが考える以上に多くの情報を取り入れていた。心の働きは、ある面では驚くほどふつうだった。
十代になると、いかにも年ごろの女の子らしい関心をもった。シンガー・ソングライターのジャスティン・ティンバーレークと映画俳優のブラッド・ピットに熱を上げ、テレビ番組に出演したときには、イケメンのカメラマンに夢中になったのだ。けれども、べつの点では、心の働きは複雑で、理解できるのは自分だけだった。
「カーリーの声」でとりわけ衝撃的な場面がある。カーリーは、自分が喫茶店で会話をするところ想像してみようと読者に語りかける。たいていの人なら、だれかとテーブルをはさんで座っていて、だれかが自分に話しかけ、自分は真剣に耳を傾けているところを想像するだろう。
カーリーは違う。私の場合、まったくちがう。テーブルのそばを通った女の人が香水の強烈な匂いをまき散らして、私の注意はそっちに移る。それから、後ろのテーブルから左の肩越しに聞こえてくるおしゃべりが耳につきはじめる。左の袖口で織りの粗い布地が腕をこする。それが気になりはじめると、今度は、コーヒーメーカーの立てるシューシューという音が、まわりのほかの音に混ざって聞こえてくる。店の入り口の扉が開いたり閉じたりするのが目に入り、疲れきってしまう。おしゃべりについていけなくなり、目の前にいる人の話をほとんど聞きのがす。…奇妙な言葉が聞こえるだけだ。 おしゃべりを続けるのが絶望的になったこの時点で、二つの行動のうちの一つをとるとカーリーは言う。心を閉ざして反応を示さなくなるか、癇癪を起すかだ。
これは興味深いと、この一節を読んだときに思った。カーリーの前に座っていて、行動を知覚の特徴から説明するとしよう。カーリーが心を閉ざしてしまったら-私が目の前に座って話しかけているのに、うわの空のように見えるなら-反応不足と分類するだろう。ところが、癇癪を起こしたなら-カーリーが言うように、これといった理由もなく笑いだしたり、泣きだしたり、怒りだしたりして、悲鳴まであげるなら-反応過剰と分類するだろう。
二つの異なる行動、感覚処理の二つの異なるサブタイプ-少なくともカーリーと向かい合わせに座って、外から眺めていたら、そんなふうに見えるだろう。ところが、自分がカーリーで、心の声を聞いていたら、二つの反応の原因は同じと考える。感覚刺激の過剰。情報過多だ。』
反応不足と反応過剰は別のものではなく、一つの状態から生じる二つの異なる反応である。このように考えるようになり、テンプル・グランディン氏は感覚処理問題を従来の分類で考えるのではなく、人間の五感から捉えるべきであるという考えに至りました。
以下は各問題について列挙された内容です。
感覚処理問題の傾向と対策
・視覚処理問題
<視覚処理問題がある人の行動と症状>
・目の近くで指をはじく
・読むときに首を傾ける。あるいは横目で見る。
・蛍光灯をいやがる(特に周波数が50Hzから60Hzの蛍光灯でよく生じる)
・エスカレータを怖がる。乗り降りするときの足の出し方がわからない。
・初めて訪れた家の階段をのぼるような、なじみのない状況を切り抜けるときに、やみくもに動する。
・印刷物を読んでいるときに字が揺れて見える。
・夜間視力が劣る。夜間の運転をいやがる。
・速い動きを嫌う。スーパーマーケットの自動ドアなど、速く(あるいは、いきなり)動くものを避ける。
・明暗の強いコントラストを嫌う。明るいコントラストの配色を避ける。
・多色のタイルの床や、格子状のものを嫌う。
<視覚処理問題の対策>
・蛍光灯のあるところなら、つばつきの帽子をかぶるか、窓のそばに座る。あるいは、旧式の白熱電球の照明器具をもってきて、自分専用にする。
・アーレン症候群用のアーレン眼鏡を手に入れるか、さまざまな淡い色のサングラスをかけてみる。
・読むものは、ベージュ色や水色、グレー、薄緑などのパステルカラーの紙に印刷してコントラストを弱くするか、色つきの透明なカバーを使う。
・コンピュータは、画面がちらつく旧式のデスクトップではなく、ノートパソコンかタブレットにする。背景を色つきにしてみる。
・聴覚処理問題
<聴覚処理問題がある人の行動と症状>
・聴覚は正常か正常に近いのに、聞こえていないように見えることがある。
・まわりが騒がしいとよく聞こえない。
・無声子音がよく聞こえない。母音のほうが簡単に聞こえる。
・大きな音がすると耳をふさぐ。
・駅や競技場、音の大きい映画館など、騒がしい場所でたびたび癇癪を起こす。
・煙感知器や爆竹、風船の割れる音、火災報知機など、ある種の音を聞くと耳が痛くなる。
・とくに刺激が過剰な場所にいるときに、音がまったく聞こえなくなったり、聞こえる音量が変わったりする。騒音は接続不良の携帯電話のような音がするのかもしれない。
・音の発生源をうまく見つけられない。
<聴覚処理問題の対策>
・騒がしい場所では耳栓をする(少なくとも1日の半分はずして、聴覚がますます敏感にならな
いようにする)
・耳が痛くなる音を録音し、音量を下げて再生してみる。
・大きな音は、くつろいでいて疲れていないときのほうが我慢しやすい。
・大きな音は、自分で音を出せるときや、音が出るとわかっているときのほうが、我慢できる。
・触覚敏感性
<触覚敏感性がある人の行動と症状>
・親しい人からでも、ハグされると身を引く。
・服を全部脱ぐ。あるいは、特定の素材の服しか着ない(ウールなどちくちくする素材は、たいていの問題の原因)
・特定の素材や感触が我慢できない。
・重い枕や絨毯の下にもぐりこんだり、体に毛布を巻きつけたり、せまい場所(例えば、ベッドとマットレスと台のあいだ)に入りこんだりして、じわじわと圧力を感じる刺激を求める。
・軽く触れられただけで、キレたり、癇癪を起こしたりする。
<触覚敏感性問題の対策>
・じわじわと圧力をかけると触角が鈍くなることがある。マッサージは、思いやりを教える役にも立つ。自閉症の人のほとんどが、加重ベストを着たり、重いクッションの下にもぐりこんだり、しっかりマッサージを受けたりして、触覚を鈍らせると、ハグされることに耐えられるようになる。
・ちくちく、ヒリヒリする衣類に対する感受性を鈍くするのは困難だが、新しい衣類はすべて、肌に触れる前に何回か洗濯する。タグは全部取り除く。下着を裏返しに着る(継ぎ目が肌に触れないように)。
・診察に対する敏感性は、ときには、診察で触れられる部分にじわじわと圧力をかけると、鈍くすることができる。
・嗅覚と味覚の敏感性
<嗅覚の感受性が鋭い人の行動>
・特定の物質やにおいを避ける。
・特定の強烈なにおいに惹かれる。
・何らかのにおいをかぐと癇癪を起こす。
<味覚の感受性が鋭い人の行動>
・特定の食べ物しか食べない。
・特定の舌触りの食べ物を避ける。
<嗅覚・味覚の敏感性問題の対策>
・こんな笑い話がある。男が診察室に入ってきて、手を頭の上にあげて言った。「先生、こうすると痛いんです」。すると医者は言った。「だったら、そんなことするな」この話は、嗅覚と味覚の問題について私が言いたいことをよく言い表している。いやだったら、やめよう。惹きつけられているにおいが、人のいやがるような、たとえば排泄物なんかのにおいだったら、心地よくて強いにおいを出すものに替えて試してみよう。ペパーミントなどアロマセラピーで使われるような香りがよい。
緊張とリラックス(「リラクセーション」)
冒頭の「はしがき」から骨子ともいうべきものをご紹介します。
・『こころの問題といえばすぐさまストレスという言葉が思い浮かぶほど、ストレスは日常化しています。そのストレスはあたかも私たちのまわりに満ちあれているかのように思われていますが、そんなものが客観的に存在して、私たちに外部から襲いかかってくるわけではありません。ストレスというものは、自分自身が主観的にこしらえている幻影にすぎないのです。』
・『このようなストレスの存在を前提として、それなりの緊張があった場合に、それになるべく早く気づき、その緊張を弛め、そんな緊張をしないですむような努力ができるようになれば、生活の仕方、人生の生き方までが大きく変化することになるでしょう。』
・『こういえばもはや明らかなように、本書のリラクセーションは、巷間おこなわれている筋の生理的な弛みを目的にするものではありません。自分のからだの「緊張を自分で弛める」という本人自身の心理的な努力活動を目指しているのです。』
以上のことから、今回は「緊張」と「リラックス」に焦点を当てます。
緊張の現われ方
準備緊張
「いくぞ」、「やるぞ」と本気になってくると、脳波に加え筋電図にも変化が現れ、筋群の緊張が確認できます。また、はじめての動作や難しい作業、まだ自分のものになっていない課題などでは、その動作のための緊張の程度がよくわからず、力が足りなかったり、逆に力を入れすぎたりしてしまいます。しかし、これらは特に意図するものではないため、意識下の活動です。ただし、「準備緊張」も普段の生活上の動作においては、特に力むことはなく、必要な力だけを適度な緊張のもとに行っています。
恒常緊張
難しかった動作や作業なども、熟達するにつれて緊張も適度なものになります。ところが、必要十分な力だけを入れ、済んだ後は不要な力を完全に抜くということは容易ではありません。これは特に意識することなく、習慣的にやっているからです。つまり、緊張が多少残ったままになっているのが普通です。これらの残留した緊張は、からだのあちこちの部位や関節にだんだん蓄積され、習慣化し、ついには慢性化して動作を妨げたりする原因になります。このように影響を与える緊張を「恒常緊張」といいます。
場面緊張
普段なら特に緊張することのないことでも、人前で発言するとか、試験や面接を受ける、競技に臨むなどという場面では、緊張が過剰になることがあります。ある動作をするとき、その人が置かれた状況によって左右される緊張を「場面緊張」と呼びます。このような緊張は現われる部位、現われ方、動作に及ぼす影響など人によって様々です。
イメージ緊張
現実にはその場にいないのに、それを予期して頭のなかでその場面をイメージして緊張する場合もあります。このイメージの緊張は、現実の場面の緊張よりはるかに強烈であることも珍しくありません。特に神経質な人、完全主義者あるいは鬱気分などに目立ちます。ストレスは外部からではなく、自分自身でつくり、それに悩んだり、脅かされたりするものなので、「イメージ緊張」といえます。
不当な緊張
不当な緊張は不安やこだわり、困難や悩みなど、当人自身の弱さや問題の表現であり、それがまた自らへの反省や警告でもあるという複雑な構造をもっています。それを確かめるには、自分自身をも見つめ、その由来や自分のあり方などにも気づいたり、明確化していくことであり簡単ではありません。しかし、落ち着いて自分のからだに注意を向け、自分のからだを弛めながら、実体にそってしっかり明確化してみようという気持ちになると、緊張や痛みは変化してきます。
ストレスへの対処
人は精神的に疲れを感じた時や、体が緊張でこわばっている時などにリラックスしたいと思うので
はないでしょうか。
無理したり過剰緊張するのは、多くは個人の生活に由来しています。日常のストレス、不安定な気持ちや悩み、無理や困難などに対して正面から受け止めて解決しようとせず、逃避することは自分自身の問題点を何事もなかったかのように、自分の体の中へゴミのように投棄することだと思います。
その結果、一時的に気持ちの安定は得られる一方で、過剰な緊張や偏った姿勢などによる問題が体に現われます。筋の突っ張りや凝り、痛みなどに悩むのはそのためです。
従って、まずは自分の体を犠牲にするようなやり方を改めなければなりません。それには、これまで省みることのなかった自分の体に注意を向けることから始めます。
自分の体の様々な部位・局部など、隅々の体の感じ、気持ちによって変化するデリケートな筋の緊張状態、自分が体を動かし・動くプロセス全体の感覚、自体軸や姿勢などに気を配って立ったり歩いたりする感じなどを、まず体験し直すことが必要です。
こうして自分の体に注意を向け、緊張や動きの感じが実感として体験できるようになるにつれて、それまで分からなかった自分の体の不当な緊張の状態や無理な動き、偏った姿勢などにも気づくようになってきます。さらに、日常生活における悩みや困難をそうした緊張や動きに無理矢理転化してきた状況も理解でき始めるようになります。
上記の「ストレスへの対処」の中で、過剰な緊張や偏った姿勢について言及されている箇所があります。一方、トリガーポイント(過度な緊張状態が続き、しこりのようになった硬結で離れた部位に関連痛を起こす原因になるもの)が姿勢に影響するという指摘があります。ここでは、本題から外れますが、3例程ご紹介したいと思います。
1.腸腰筋のトリガーポイントと特徴的な姿勢
インナーマッスルとして有名な腸腰筋(腸骨筋+大腰筋)です。無意識にこの筋肉を伸張させるような
姿勢を取ります。
2.脊柱起立筋のトリガーポイントと特徴的な姿勢
無意識に背筋を伸ばすような姿勢をよく取ります。
2.中殿筋のトリガーポイントと特徴的な姿勢
足を組むことにより、中殿筋を伸張させています。
リラックス・イメージ体験の方法
『本当はまだまったくリラックスしていないからだなのに、いきいなり自分のからだをリラックスしているとイメージしようとしても、なかなかそんなことはできないものです。そんな概念とか観念のようなものは、頭のなかで思うことはできても、リラックスする感じを伴うことのない空疎な言葉だけに終わってしまうでしょう。
ところが、しばらくその思いを繰り返したり、いくらか疲れたか飽きたりしてぼんやりしてきたり、課題実現はあきらめて楽な気分になったり、頑張りはやめて何も考えないでいたり、現実を忘れて豊かな雰囲気に包まれていたり、春風駘蕩の夢心地という状況に近づいてくると、自然にからだも緊張からかけ離れたものになってきます。
緊張はしていないにしても、まだリラックスという感じではないという状況がしばらく続くと、緊張と弛緩の中間にあった気分は徐々に変化してくるものです。それをとくに自分のからだの弛緩した感じとしてからだに注意を向けてみると、なんだかそのとおりの感じがしてくるということになるかもしれません。さらに、それにこころを向けていると、この感じがいよいよはっきりしてきて、身も心もリラックスしたような感じになってくるものです。
このあたりから、リラックスのイメージと呼んでいいでしょうか。この感じはさらに続けていればだんだん明瞭になって、本当にからだがリラックスしてきたという実感的なものになってきます
こうしてあまりはっきりしないイメージから、現実にリラックスしているという実感が伴うようなものまで、イメージにはその体験の仕方にさまざまな程度の差があるのです。
しかも、ただ単にこころにそう思っただけのものを、その段階で止めてしまったら、からだには具体的にほとんどなんの変化も現われないでしょう。しかし、それなりにリラックスというイメージをこころにとどめたままでいると、少しずつそれがからだに影響を及ぼし始め、そのからだの感じがこころにリラックスの体験を明らかにし始めます。それがリラックスの感じやイメージをいっそう実感的にし、それがさらにからだの緊張を弛め、これがさらにリラックスの感じとイメージを明確化していくという、循環的な強化を生み出していくことになります。』
動作法(「姿勢のふしぎ」)
前回の「脳性麻痺 vs 脳性マヒ」に続き、今回は成瀬悟策先生の「姿勢のふしぎ」より、どのようにして動作法が生まれ、広がっていったのか、何故、動作法が心理療法なのか等についてお伝えします。
まずは、印象的な「まえがき」とそれに続く「世界初の成功例」に動作法の経緯や概要が語られています。
まえがき
『脳性マヒで動かないはずの腕が、催眠中に挙がったという事実に直面したのがことの始まりで、それ以来30年を経て今もなお、人の「動作」というもののおもしろさに取りつかれっぱなしの状態です。
脳性マヒによるからだの強烈な緊張を、脳・神経系から筋・骨格系への生理過程によって弛めるという当初の考えは、現実には役に立ちませんでした。そのからだの持ち主の心理的な活動によって自らのからだを弛めることで、初めて治療効果が上がり始めたのです。自己弛緩さえできるようになればと努めるうちに10年ほどが過ぎました。そして、自己弛緩だけでは不充分で、自らの意図どおりにからだを動かす要領を身につけることが必要とわかり、そのための訓練を続けるうち、また10年がすぎていきました。
それからの後の10年でさらにわかったのは、重力にそってからだを大地上にタテに立てることが必要であることでした。それは、からだを立てるための心棒、すなわち体軸をまっすぐに立てて自然に無理のない姿勢がとれるということです。そしてその状態から体軸のどの部位でもそれを柔軟に屈げたり伸ばしたり、反らしたり捻ったりしながら、上体部、手腕、脚足を前後左右に使いこなせるようになることが課題となりました。
こうして、脳性マヒで肢体が不自由な人のための動作訓練がいちおうまとまりかけた頃、同じ方法が自閉症や多動の子にも有効であることがわかり、この「動作法」が心理療法として大展開することになりました。精神分裂病を始め、さまざまな症状を示すクライエントの治療で予想外の効果を得られることが確かめられたのです。現在では「動作療法」として全国規模の学会まで開かれるようになりました。
肩や腰などに起こる強い緊張は、肢体の不自由な人特有のものではなく、一般の人にみられる猫背や側弯、腰痛や肩凝り、四十肩、五十肩、外反母趾などの原因でもあることがわかり、また新たな展開が始まりました。そうした悩みを解消する健康法として「動作法」がきわめて有効だからです。また、これといって特に悪いところもないのに立つのがつらい、歩けないなどと訴える高齢者にも、このうえない援助ができるようになりました。』
世界初の成功例
『今からちょうど34年前(1964年)のこと、埼玉県の身体障害者厚生指導所という施設に勤務していた小林茂さんからすばらしい報告が届きました。脳性マヒで動かなかった16歳の男の子の右腕が、催眠暗示による訓練で真上まで独りで挙げられるようになったというのです。これは脳性マヒの分野でも、催眠の分野でも共に有史以来初めての試みで、しかも世界初のすばらしい成功例になりました。
脳性マヒというのは出産時、ないしその前後の時期に発達中の脳に生じた病変のため、随意筋のコントロールが失われたり、肢体が不自由になったりするような、運動能力の永続的な障害とされています。出産前後というのは受胎から新生児期、すなわち生後4週までの間に生じた脳の病変が原因ですから遺伝によるものではありません。死滅した脳細胞が再び蘇ることはないので、この病変が元通りに治癒されることはありません。この病変はそのまま残りますが、それ以上に悪化しないため、非進行性といわれています。
この脳の病変のため、手足やからだの動きが自由にはできないことを肢体不自由といい、脳性マヒの人にみられる運動障害の代表的なものです。その当時までは、脳の病変が治らないのだから、その結果からくるマヒも運動を司る神経系の障害からくる麻痺と同じように、もはやよくなることはないものとされていました。
この子たちの処置は、これまでもっぱら整形外科で扱ってきました。脳性マヒの子は随意筋のコントロールが悪く、ことに関節を動かすため相拮抗して働く伸筋と屈筋がアンバランスで、伸筋が強すぎれば伸びて突っ張るし、屈筋が強ければ屈曲して伸ばせなくなるのです。この強すぎるほうの筋や腱を切ったり延長したりする手術が整形外科学での処置法です。手術直後はいくらか動きやすくなることもありますが、手術の傷が治ればまた元の突っ張りや屈曲に戻る傾向があります。
神経生理学では脳性マヒの不自由がそうした拮抗筋の障害ではなく、それを支配する脳・神経系からの命令が不適切なためだから、その命令の出し方を変えないかぎり、いくら筋や腱を手術しても元に戻るのは当然とみます。むしろ、中枢神経系内の原始反射運動の異常反射のパターンを抑制もしくは除去して、正常反射パターンを促進させ、さらに強化する神経活動のパターン・トレーニングが必要だというのが神経生理学的な機能訓練の考え方です。でも、反射運動の正常化だけで、日常生活における複雑な動作までできるようになるとするのは無理でしょう。』
肢体不自由
肢体不自由については次のような説明がされています。
『脳性マヒの子がからだを自由に動かせないのは、そのからだの持ち主である主体が、自分のからだを動かす心理活動をうまくできないためであることがこれまでにはっきりしてきました。彼らの直面している難しさは、握手しようと思い、それができるように懸命に頑張るにも関わらず、その結果として現実に現れてくるからだの動きは、どんなに頑張っても握手とは違った動きになってしまうことでした。例えば主体が「握手しよう」と思い、あるいはそうしたいと欲するとき、その動きについての「意図」が生じたといいます。その意図を実現できるように身体部位を特定し、実現しようと「努力」するのですが、どんなに努力しても、結果としての「身体運動」の現れ方、すなわち動きのパターンは、最初に意図し、心にイメージとして描いた握手という動きのパターンとはどうしても食い違ってしまいます。だからこそ「肢体不自由」ということになるのです。からだを動かすプロセスをこれまで脳性マヒの子でみてきましたが、プロセスそのものは彼らとふつうの私たちとの間にちがいがあるわけではありません。』
さらに、例を出し分かりやすく説明されています。
『肢体不自由は自動車の運転になぞらえれば、車そのものはよく走るのに、運転手が未熟なので車が思ったように走れないのに似ています。これは脳性マヒの子たちが、意図を実現しようとする努力の仕方がうまくないためで、彼らにその適切な努力の仕方をいかに身につけられるように援助できるかが私たちの課題になってきます。』
つまり、肢体不自由とは、「動く。けれども、思うように動かせない、コントロールできない」という状態であると理解しました。
心理療法
以下に4つの文章を引用しています。ここには、心理療法といえども、からだに起きている不調に目を向け、安直に心理面だけを取り上げたり、病名に頼るべきではないことが指摘されています。そして、多くの場合「緊張」が存在し、その「緊張」が心身両面に大きく関わっていること、そして自らが緊張している心身を取り除けるようになることが重要であると説明されています。
『心理療法を求めてくるクライアントのほとんどが、自分の主たる問題として訴えてくるのがからだの不調のあれこれで、その多くは自分のからだの緊張や動きに関わるものです。からだが重たい、だるい、突っ張る、かたい、痛い、やる気がしない、動きが鈍くなった、動かせない、力が入らない、疲れやすい、足元が定まらない、からだが宙に浮いているようだ、自分のからだでないような感じ、自分がやっているという気がしない、操られている等々、動作とそれについての体験に問題のあることを訴えているのです。したがって、何はともあれそれらを、日常生活における主体の動作にかかわる努力と体験の問題として取り扱わなければならないはずなのに、実際にはそれを詳しく調べもせず、動作から目をそらそうとするのが普通のようです。その訴えを聞きながら、セラピストはそれ自体の重要性を無視して、それをそのまま直接の対象とせず、そうなった本当の問題はその背後にあるとし、別の問題にすり替えて解釈しようとします。それには二通りあって、一つはそれらの訴えを生理的、病理的なものとして受け取り、身体疾患の症状探しに取り掛かり、それが原因であろうとなかろうと病気の治療に結びつけようとします。他の一つは、その背景に何らかの心理的な問題があるものと受け取り、セラピスト各自のよって立つ治療理論や学派の教えに従って、無理矢理に心の古傷やいやな体験を探したり、親子関係や家庭環境、人間関係をその原因に仕立て上げようとします。その結果、治療者からの暗示や当人の思いすごしで本物の病気になってしまったり、いやおうでも過去のエピソードや家庭環境、社会関係を原因にさせられてしまいかねません。もちろん、からだの病気が原因のこともあれば、心理的な外傷体験が無視できないこともなくはないでしょう。しかし、あまりに型通りの安易なすり替えによって、ほんとうの問題がおそろかにされてはなりません。』
『心理療法を求めてくる人は、そのほとんどがからだのどこかに習慣的ないし慢性的な緊張がみられます。心の不安、不調や悩み、無理や努力のしそこないなどが緊張となって現れているのです。それは肩や背中、腰など全体にわたるものから、肩だけ、腰だけというもの、指圧でツボといっているようなある小筋群だけに局部限定的にみられるものまで様々です。緊張はほとんど意識に上らない努力によるものですから、当人自身はそこが緊張しているとは気づいていません。意識的な体験としては、力が入らない、動かせない、きつい、凝る、重い、痛い、自分の身体でない、空洞のようだなどと感じています。そうした緊張を他者による物理的、化学的な処置で弛緩する方法は従来からたくさんありますが、大切なものはそうしたものでなく、自分で自分のからだを弛めるという自己弛緩です。それにはまず自分のからだの緊張に気づくこと、そこへ意識努力で力が入られること、入れた力を抜いていくこと、その部位が動かせること、力を抜いたり動かしたりする感じがわかること、それに伴って自体を弛めながら、弛んでいく感じ、弛めていく感じ、その弛緩の感じをじっくり味わいながら、局部からその周囲、他の緊張部位、さらには全身を弛緩させる感じ、全身がリラックスしている感じなどがわかるように進めていきます。』
『不当な緊張が現れやすい部位:自体軸をタテ直へ立てようとする意識努力のしそこないとして生じやすい随伴緊張は、姿勢の歪みとしてさまざまな身体部位に現れますが、最も一般的に広くみられるのは肩と腰、およびその両者を連結する背中です。それらを含む躯幹部が中核となって、それの接続する頚、手腕、脚足などへと随伴緊張が波及します。そうした不当緊張の結果として、からだに現れる不調や悩みの中には肩凝り、腰痛、側弯、四十肩、五十肩、背中の痛み、頭痛、脚足痛、尖足、外反母趾などがよくみられます。これらの痛みや不調、悩みなどの主たる原因が特定部位の不当な随伴緊張であり、そこに居座る無意識努力による随伴緊張を意識努力に変換して、それらの部位の緊張を自分でリラックスできるようになり、あるいはそれまで思うように動かせなったその部位が自由に動かせるようになるにつれて、急速に減退し消滅するということは、私たちの経験から明確に証明されてきました。そうしたからだの痛みや不調が自分のからだを自分で弛め、自分で動かせるようになることで快癒するという事実から結論すれば、それらはこれまで生理的な不調として誤解されやすかったのですが、実はそれが無意識努力という主体の心理的なそれであることをあらためてここに強調しておかねばなりません。』
『「弛んだ筋群」よりも「弛めようとする自己活動」が重要:他者による弛緩は、そのとき限りの筋弛緩には役立つとしても、その刺激がなくなれば元に戻るだけでなく、その刺激に対する生体としての耐性が高まるので、繰り返しによって弛緩効果はだんだん低下してしまうのです。他者に頼っていては駄目で、結局自分で自分を弛める自己弛緩でなくてはならないことがわかってきたのです。自己弛緩は繰り返せば繰り返すほど自分の弛め方が上手になるからです。緊張が減少した後者では、自分で弛めていく感じ、そのための努力の仕方、それに伴うからだの感じ、それらをコントロールしていく自分自身の感じなど、自己弛緩の体験を中心に進めたのです。こうした経験からわかったのは、「弛んだ筋群」が重要なのではなく、「弛めようとする自己活動」が目的にならなければならないということでした。』
マッサージの価値と課題 (「小児障害マッサージ」にリンク:中段以降を参照ください)
・マッサージは主に局所における循環作用と、自律神経や脳脊髄神経の神経反射による作用があり、緊張を和らげること、あるいは弛緩した筋に緊張を与えることが可能です。一方、動作法の目標が自分で弛め、緊張を取る」ところにありますので、施術を行うだけでなく、動作法を理解した上で「セルフケア」という視点から、その対応を考える必要があると認識しました。
追記
動作法の具体的な方法については、ブルーバックスシリーズの「リラクセーション―緊張を自分で弛める法」にあるようで、それについても拝読しようと考えています。
脳性麻痺 vs 脳性マヒ
12月30日の「動作法について」でご紹介した、心理学からのアプローチである動作法を理解するには、それを生みだした成瀬悟策先生の書物を読むことが第一だろうと思い、読みやすい本ということから、講談社ブルーバックスシリーズの中の「姿勢のふしぎ」を購入しました。
動作法はどのようにして生まれたのか、心理療法とはどのようなものか等については、次回にお伝えしたいと思います。これは、まず最初に「脳性麻痺」と「脳性マヒ」の違いを理解しなければならないと考えたためです。
初め、「脳性麻痺」ではなく「脳性マヒ」とカタカナが使われていることに、特に意味はないように思っていました。ところがそれは下記にある通り、誤りであることが分かりました。
『脳の病変によって肢体が不自由になる現象を、本書ではここまで「脳性麻痺」ではなく一貫して「脳性マヒ」と表記してきたのは、一般に「麻痺」ということばが「神経や筋の機能が停止する状態」(広辞苑)とされているためでした。これまで述べてきたように、この子たちのからだは病理学的に動かないのではなく、生理的には動く自分のからだを、その主体者が自分の思うように動かせないだけですから、「麻痺」ということばはそぐわないため用いません。』
そして、脳性マヒの特徴は次のようなものだということを理解しました。
『「脳性マヒ」は変わらないが「脳性マヒの子」は変わる:脳性マヒというのは肢体不自由の原因になるような脳の病変があることをさし、生理的または病理的学的な診断名のことです。そんな病変を脳にもちながら生をうけ、今ここに生きて生活している子ども、ないしその人は、脳に病変があるため肢体にそれなりに不自由なところはありますが、あくまでもほかの一般的な人と何ら変わるところはありません。』
これを補足するものとして、次のような興味深い事実も書かれていました。
『研究室へやって来る脳性マヒの子たちが疲れないようにと昼寝の時間を設けていました。そこで観察していて驚いたことは、突っ張ったり、引きつったりするため、両手共にうまく動かせないはずのC君やDさんたちが、寝返りをするときにはけっこううまく両腕を動かして寝返っているのです。からだをあちこちへ移動するのに手足を使っているのです。その子たちに目が覚めてから「同じようにやってごらん」といってもできないのがふつうです。』
さらに、次の一文で疑問が大きくなり、調べなければという思いになりました。
『動くが動かせない:脳性マヒの子は脳の病変のため、からだが動かないものと思われやすいのが現状です。しっかりした医学を修めた医師の中にもそう思っている人が少なくありません。しかし実際によく調べてみると、ふつうの脳性マヒだけが原因で、手足がまったく動かないという例はないといってよいでしょう。』
そこで、まずは専門学校で使っていた教科書(「臨床医学各論 第2版」)、図が豊富で分かりやすい「病気がみえるシリーズ」、「病気がみえる」と同じ出版会社(医療情報科学研究所)で、「病気がみえる」の簡易版のような「ビジュアルノート」の3つについて、脳性マヒについてどのような説明がされているのかを調べてみました。
「神経疾患」の中の「基底核変性疾患」の中に、パーキンソン病、ハンチントン病が出てきます。そして、3番目には「脳性小児麻痺」が載っています。
書かれている主な内容は『受胎から新生児(生後4週間以内)までの間に生じた、脳の非進行性病変に基づく永続的な運動および姿勢の異常。運動障害は屈筋群と伸筋群の協調運動障害で、姿勢の異常、筋トーヌスの異常、反射の異常などの特徴がみられる。また、異常運動として、ジストニア、アテトーゼ様運動、舞踏様運動がみられる。生後6ヶ月以内に診断し、機能訓練をできるかぎり早く開始する。変形の矯正や拘縮の除去には整形外科的療法を要する。約500人の出生に1人の率で発生する。』
説明の中で「麻痺」という言葉は使われておらず、「運動障害」としての姿勢の異常、筋トーヌスの異常、反射の異常、そして異常運動についての説明となっていました。
「神経・筋の異常」の中の「群発頭痛」に続く2つめの「Supplement」として「脳性麻痺(CP)」が出ています。Supplementとは、この本の中では『主にその章の内容と直接的に関わらない情報で、補足的におさえておいてほしいものを示しました。』という位置づけです。ちなみに1つめのSupplementは「頭痛ダイアリー」というものです。
『「脳性麻痺」とは発育期(受胎から生後4週間まで)に脳の運動系の形成異常や損傷により、運動や姿勢を制御する能力が損なわれた病態の総称である。症状は満2歳までに発症する。』という説明になっています。
個別の疾患ではなく「総称」として位置づけられたため、「Supplement」での登場となったのだろうと思います。従って、上段の「運動麻痺:四肢麻痺、対麻痺、片麻痺」の記述や、下段の錐体路や大脳基底核、小脳の問題についての記述も、「運動や姿勢を制御する能力が損なわれた病態の総称」の立場で考えれば、特に不自然とは言えないように思います。
こちらは、脳・神経や小児科などを含む計18の科、主要252疾患についての説明が図とともにされていますが、「脳性麻痺」の記述はありませんでした。
上記は「ビジュアルノート」にあった表です。下段の新生児疾患には「脳性マヒ」は入っていません。小児の成長と発達および疾患に関する情報が盛り込まれた見やすい表と思い載せました。
まとめ
この3冊から、「脳性麻痺」の位置付けは曖昧であり、明確に定義されていないということを確認できました。
私としては、「脳性マヒ」は「脳性麻痺」や「脳血管障害の後遺症などの四肢麻痺・対麻痺・片麻痺」とは似て非なるもの。「動くが、思いどおりに動かせない」運動障害で、アテトーゼやジストニアなどの異常運動を伴う場合もある、肢体不自由の病態」として定義したいと思います。
追記(2018年6月24日)
混乱させてしまうかも知れませんが「脳性麻痺」について詳しく紹介されていたサイト(「LITALICO発達なび」さま)がありましたのでご紹介させて頂きます。

この中に次のような説明箇所があります。
『脳性麻痺(のうせいまひ)は、妊娠中、出産前後もしくは生後4週間以内のあいだに、なんらかの原因で生じた脳の損傷が原因でおこる運動と姿勢の障害のことを指します。たとえば、脳性麻痺の赤ちゃんは、おすわりなどの姿勢、ハイハイ、もしくは立って歩くといった運動の発達への遅れや、これらのスキルを獲得できないことが起きてしまうことがあります。
それではなぜ、脳が損傷すると姿勢や運動に問題が起きてしまうのでしょうか。人が体を動かすときには「筋肉をこんな風に使って、腕をあげなさい」など、脳の神経が筋肉に向かって常に信号を出しています。ところが、脳の損傷によって神経システムが損傷してしまうと、送るべき信号がうまく筋肉に伝わらず、考えたとおりに動けなかったり正しい姿勢をしたりすることが難しくなってしまうのです。
脳の損傷部分や範囲は、一人ひとりまったく違います。したがって、子どもの発達過程にどの程度の影響があるのか、もしくはどんな症状が現れるのかも子どもによって異なります。』
さらに「脳性麻痺の検査・診断」では、次のように説明されています。
『明らかに麻痺があるなど重度の脳性麻痺をのぞき、特に早期に脳性麻痺を診断することは、一般的にとても難しいと考えられています。
おもな理由としては、発達は非常に複雑なものであることにくわえ、脳性麻痺ではない子どもでも、発達には個人差が大きいことが知られているからです。また、おすわりや立つなどの発達過程は、生後すぐにできるものではないことも早期診断を難しくする要因のひとつです。さらに、脳性麻痺の症状である痙性(筋肉の硬さ)は、通常生後数週間でみられるものではなく、7~9ヶ月たって気づくことも多いことで知られています。
このように、脳性麻痺の診断は非常に難しいものであるものの、診断には以下の3項目から総合的に判断されます。
〇出生歴:未熟児だったかどうか、分娩時に異常はなかったかなど
〇子どもの観察:年齢相応の発達をしているかなど
〇筋肉の緊張や反射異常をみる検査』
以上のことから、「脳性麻痺/脳性マヒ」の問題は、原因が梗塞や出血といった脳梗塞や脳血管障害によって生じる麻痺とは異なり、原因が非常に広範囲であり、そこに表れる症状も患者さま個々に特徴が異なるという多様性の問題なのではないかと感じました。
また、その意味ではその多様性を表す方法として、あらためて「麻痺」という言葉ではなく、「マヒ」とした方が良いと思いました。
動作法について
「動作法」は1960年代後半に、成瀬悟策先生によって提唱された一つの心理療法および心理学理論です。その後、自閉症・多動症児に効果があることが、筑波大学の今野義孝先生と大野清志先生によって確かめられました。
リハビリテーションが身体の可動域や筋肉の強さなどの生理的側面に重きを置いているのとは対象的に、心理的側面について焦点をあてたものとなっています。

成瀬悟策先生が名誉理事長。
『日本リハビリテイション心理学会はリハビリテイション心理学及びこれに基づく学術の発展をはかり、文化の向上に寄与するとともに、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とした全国的な学術団体です。』
心理的側面とはどのようなものか、どのように行うのか等を知るため、「絵でわかる動作法」と「動作法ハンドブック」という2冊の本を読んでみました。
私自身、まだまだ消化しきれていない段階ではありますが、まずはこの2冊の内容から理解や認識すべきと思った事柄を列挙してみました。
※「動作法ハンドブック」と明記されているもの以外は、「絵でわかる動作法」からの引用です。
・動作という言葉は日常でも使いますが、動作法においては特別に定義された言葉です。
「身体運動」は文字どおり身体が動くことです。身体としての骨格や筋肉があり、それを動かす神経があり、その神経に命令を伝える大脳があります。こうした、生理的に身体が動くことを指して「身体運動」と呼んでいます。
一方、「動作」は、身体運動をコントロールしている主体の活動です。自分で、動かそうと「意図」して、意図どおりになるように「努力」するという心理的なプロセスがあって、その結果として身体運動が生起する時に「動作」といいます。 (動作=意図→努力→身体運動)
・動作の基本 「動作法ハンドブック」
・意図
・人が自分の体をどのように動かそうとするかという、動きについて計画する段階
・努力
・意図を実現するため、自分の体に注意を向け、意図した動きに必要な体の諸条件を整えたり、操作したりする感じも出さなければならない。それを出すための主体的な自己活動
・身体運動
・この段階で発生する心的なエネルギーが、生理学的な段階の活動を刺激して生起する。
・動作不自由 「動作法ハンドブック」
・脳性マヒの子供の不自由は、動作学的な研究の結果、脳の神経学的な障害に基づいた、中枢性の運動機能障害であるという理解の仕方では不十分であることが分かってきました。むしろ、人が、自分の身体運動を操作する、主体的な自己の活動が十分に行われていないために、発達の経過で、不自由な動かし方を学習したためであると考えた方が適切なのです。運動の発達が遅れて、Gパターンと呼ばれる、乳幼児の固い姿勢を自分の力で乗り越えられないのも、これに関係があります。このように、人の主体的な活動である動作の問題が非常に大きいことから、脳性マヒによる不自由は、単なる肢体不自由と区別して、動作の不自由と言った方が適切です。同じような動作不自由をもっている者には、知恵遅れの子供、自閉や多動の子供などがいます。動作不自由は、自己活動が不十分なために発生します。
・動作法が対象としているのは心理的な活動です。身体をどのように動かしたらよいかという「身体の動かし方」と、それをどのように実行するかという「意図」と「努力」の仕方が動作法の対象です。
・医療においては、脳性マヒの肢体不自由に対して、生理学の観点から運動機能の改善をはかるリハビリテーションが行われています。
動作法も、脳性マヒ児の身体の動きを改善するので、医学的なリハビリテーションと同様に身体を訓練するものと誤解される場合がみられます。実際に、動作法の様子を外から見ていると、腕や脚などの身体を動かしています。けれども、動作法では、身体がどれだけ曲がったり伸びたりしたかという、力の強さや動いた量を問題としているわけではありません。動作法が肢体不自由の子供だけでなく、自閉症や多動の子供、あるいは神経症などにも効果があるのは、人間の「意図」や「努力」という活動を対象として扱っているからなのです。
・人は、動作という心理的プロセスを様々な形で感じます。その中で、人が確かに自分で身体を動かしているという実感を「主動感」と呼んでいます。動作法は、この主動感を大切にしています。
一方、自分以外の力によって身体を動かされているという他動的な実感のことを「被動感」と呼びます。また、自分の身体が勝手に動いてしまうという実感のことを「自動感」といいます。
・「緊張」というのは、人が身体のある部分をある方向に動かしていった時に、生理学的に異常がなければ動く範囲にもかかわらず、抵抗感を感じて動かしにくくなることです。指導者が相手の身体をある方向に動かしていくと抵抗感を感じる時、その部位のその方向に緊張があるといいます。抵抗感が強いほど緊張も強いといいます。この緊張は、楽に身体を動かすことを妨げる要素となります。骨や筋肉に生理学的な変化がないのであれば、本人が何らかの形で力を入れているものと考えられます。そして、実際に動作法によって入れている力を緩める練習をすると、緊張が少なくなります。
・行動変容をねらう訓練のコツ 「動作法ハンドブック」
・安心感を与える手の当て方をする
・まず、子供は自分の体に触れられることに対して大きな不安を感じている。
・不安を感じない程度の力を使う。
・手のひら全体を使う感じ。
・体の感じを子供と共有する
・子供が感じているだろう感覚を、施術者も同じように感覚を感じるようにする。
・言葉かけを大切にする
・子供の気持ちをリラックスさせ、その気にさせる。
・施術者も言葉かけと施術を重ねることで良いリズムで楽しく取り組むことが大事です。
・主体的な取り組みを大切にする
・子供は気が散って、集中できないことが多い。特自閉や多動の子供たちは、訓練を自分が主体的に行っているという実感を欠いています。したがって、子供が自分の体の感じに気づき、自分で体を緩めたり動かしているという感じをつかめるようにする主体的な動きを行わせる必要があります。
・まず、優しく、ゆっくりと何をどうしようとしているのかを部位に軽く触れながら「こういう動きをするよ。」と説明する。
・どこがどう感じているかを聞きながらゆっくり進め、自分で緩む感じや動く感じを認知する。
・さらに、自分自身が主体的に動かす感じをつかめるように、動かしている方向、スピード、可動域などを細かく伝えながら、二人三脚で理解するという課題に取り組んでいく。
・動作法は「立位・歩行」、「書字」、「発声・発語」の3つの基本動作に分類しています。
・動作法は、特定の訓練姿勢で行います。これを課題動作(モデルパターン)といいます。その訓練姿勢で行うことは「緊張の緩め方」と「単位動作(身体の動かし方)」です。そして、動作の要素として、部位、方向。強さ(速さ)があげられます。
・課題動作(モデルパターン)
1.立位・歩行動作
・あぐら座動作
・膝立ち動作(片膝立ち動作)
・立位動作
・歩行動作
2.書字動作
・腕動作(腕上げ動作と肘曲げ動作)
・手動作(手のひらと指の動作)
・作業動作(字を書く、道具を使う動作)
3.発声・発語動作
・呼吸動作
・口動作(あご動作、口唇動作、舌動作)
・発声動作
・食べる動作
・補助はしっかり強く補助するところから、次第に弱く少なくして、自分でコントロールできるようにしていきます。そのためには、「はなすよ!はなすよ!」と声をかけて、相手が自分で努力する心構えをつくります。
・訓練の終わり方では、「できた!」という形で終わることが大切です。そのためには、計画段階で、どの段階で、どの課題を最後に持ってくるか、それを何回やって終わるか考えておくことが必要です。「あと、もう1回」と欲を出すと、えてして最後の訓練がうまくいかなかったりするので、回数を決めてできたら終わりにすることが重要です。
・動作のコミュニケーション
・動作法は子供の「意図」や「努力」あるいは「身体の動かし方」という心理的活動を対象としています。そこで指導者が子供に伝えていることは、身体を動かす「力」を加えているというよりも「情報」を伝えているのです。その意味で、動作法は子供と身体を間に挟んでコミュニケーションしているという側面を持っています。
・訓練に誘うにあたっては、指導者は穏やかな心でのぞみ、こどもの反応や感情を感じ取れることが大切です。そのためには、うまくやろう、早く訓練しようと気負わないことです。子供の動きや活動に沿いながらペースを合わせます。そして、子供が訓練に取り組めるタイミングを待つことが大切です。
・動作法の初心者は訓練姿勢を決めるところで苦労している。どんな訓練をするか、そのための訓練姿勢がどうかを、言葉だけでなく、指導者がその姿勢を実演してみせたりすることも大切。そこで子供が感じる困難点や感情を補助している指導者の身体を通して感じ取ることが必要です。そのためには、指導者自身が安定した姿勢を取り、無理なく安全に、子供の姿勢を援助できるようにしなければなりません。また、あせって訓練姿勢を取らず、子供のペースを確かめながら、訓練姿勢を少しずつ整える援助をしていきます。強い補助が必要な場合には、子供と指導者の身体をより近づけます。
付記
12月23日のブログ「発達障害」の中で、感覚統合療法の体験談として、『大丈夫! すくすくのびたよ自閉っ子』という本をご紹介していました。
下記は、感覚統合療法を分かりやすく説明されていた箇所です。また、実践内容については、目次の内容を一部抜粋させて頂きました。
脳への刺激
支援センターからいただいた個別支援計画を見ると、桃子の重点取り組み事項は、「前庭系・固有系をしっかり入れていく」となっている。何のことだかさっぱりわからない。
先生からのお話によると、桃子は、「感覚統合療法を必要とする子ども」なのだそうだ。感覚には、次の三つがあるらしい。
一つ目は、前庭覚である。これに何らかの問題があると、揺れ動く遊具や高いところを非常に怖がったり、誰かに動かされると恐れや不安、苦痛などを感じたりするようだ。いくら回転しても目が回らない、高いところや不安定なところを好む、などの特徴もあるらしい。公園の遊具なども三つ年下の妹は平気で登っているのに、桃子は怖がってできないものがある。桃子は怖がりだなあと思っていたが、原因は前庭覚なのか。また、桃子が椅子に持続して座っていられないのもこのためか。
二つ目は、固有覚である。これに問題があると、すぐ疲れてしまったり、力加減のコントロールが難しかったりするらしい。物をどのように操作してよいかわからず、衣服の着脱がうまくできないこともあるようだ。桃子が不器用なのは、この固有覚のせいなのか。
三つ目は、触覚である。べたべたした感覚が苦手だったり、手をつなぐ、抱きしめられたりするのが苦手だったり、裸足で園庭を歩けなかったりするらしい。散髪や爪きり、耳かきを極端に嫌がる子どももいるようである。以前、桃子はスライムが苦手で、触るのを嫌がっていたが、この触覚に問題があったせいか。そういえば、爪きりも苦手であった。
「もし、感覚統合がうまく働かないと、感覚が洪水のように入ってきたり、逆に必要な情報が入ってこなくなったりして、脳が混乱している状態になるのです」と、先生はおっしゃった。
我が家は旅行好きだ。旅行中、桃子は楽しそうにしているが、帰宅後、彼女は決まってパニックを起こす。これも、感覚統合と関係があるのだろうか。旅行中、いろいろなものを見聞きして、脳が混乱状態になっているのか。
桃子はパニックで済んでいるが、同じ障がいのお友だちの中には、旅行後や何か行事があるたびに、熱を出す、倒れる、など体を壊してしまうお子さんもいると聞く。
療育で桃子がしているのは、「感覚運動遊び」である。先ほどの前庭覚、固有覚、触覚を刺激する遊具で遊ぶのだ。ブランコのようなもの、はしご、ボールプールまどで、ただ楽しく遊んでいるだけのように見えるが、これが感覚統合療法らしい。脳へ刺激を与えているのだ。
桃子が感覚統合療法を始めて、もう二年以上たつ。結果が目に見えて出てきているのは、この本を読んでいただければよくわかっていただけると思う。
以下は目次からの抜粋になります。
一人でできたほうがいいぞ 身辺自立へのスモールステップ
・ボタン編(2歳8か月~3歳9か月)
・服たたみ編(3歳0か月~5歳2か月)
・歯磨き編(0歳~4歳0か月)
・トイレ編(2歳8か月~4歳5か月)
子どもには、遊びだって大切!「遊べるようになる」までの道
・じゃんけん編(2歳11か月~5歳1か月)
・鉛筆・お絵描き編(2歳8か月~5歳2か月)
・三輪車編(2歳8か月~4歳4か月)
・ハサミ編(2歳8か月~4歳5か月)
きちんと食べよう!お食事タイムが楽しくなってきた
・偏食編(2歳10か月~4歳10か月)
・箸編(2歳8か月~4歳5か月)
・おやつ編(3歳4か月~3歳8か月)
友だちできるかな?(2歳11か月~5歳2か月)
パニック・こだわり これぞ自閉っ子!という場面で工夫したこと
・こだわり編
・パニック編
・クリスマスツリー大作戦(3歳2か月~4歳2か月)
・男性恐怖症(1歳~4歳10か月)
変化が苦手な自閉っ子 でも少しずつ世界を広げてみた
・病院編(3歳1か月~4歳9か月)
・クラス替え編(3歳0か月~4歳6か月)
発達障害について
小児障害マッサージは当院ではなく、地元のプラナ治療院が「訪問鍼灸・マッサージ」で展開しているサービスで、私は週2回、こちらの治療院で仕事をしています。
そして、小児障害マッサージに関しては、セラピストとしての講習を受けている段階です。
ところで、今まで「発達障害」というものについては無知に等しい状態でした。発達障害は症状によって分類されていますが、運動や動きに関するものもあり、小児障害マッサージの対象です。
先週、さいたま市内で発達障害のデイサポートを行っている施設に見学に行ってきたのですが、その時にいたのは、年齢は10歳前後が多く、障害が軽度な子供たちでした。これから、この子供たちに接していくためは、まずは発達障害についての基礎知識が必須であると認識し、ネットを検索したり、中古本を買ったり、図書館から本を借りたりと突貫工事をスタートさせました。
最初に手にした本は、発達障害について多くの著書を出されている、杉山登志郎先生の「発達障害の子どもたち」でした。ブログの前半は、ほとんどこの本からの引用になっています。
この本は、冒頭に「世間に広がる誤解」という読者への投げかけで始まっているのですが、いかに何も知らないかということを痛感しました。
『以下に挙げたのは、発達障害に関して特に学校進学をひかえた子どもを抱えるご家族から聞くことが多い意見である。読者のみなさんは、おのおのについての是非をどのように思われるだろうか。』
・発達障害は一生治らないし、治療方法はない
・発達障害児も普通の教育を受けるほうが幸福であり、また発達にも良い影響がある
・通常学級から特殊学級(特別支援教室)に変わることはできるが、その逆はできない
・養護学校(特別支援学校)に一度入れば、通常学校には戻れない
・通常学級の中で周りの子どもたちから助けられながら生活することは、本人にも良い影響がある
・発達障害児が不登校になったときは一般の不登校と同じに扱い登校刺激はしないほうが良い
・養護学校卒業というキャリアは、就労に際しては著しく不利に働く
・通常の高校や大学に進学ができれば成人後の社会生活はより良好になる
『次は、幼児期の発達障害のお子さんのご両親からしばしば伺う意見である。』
・発達障害は病気だから、医療機関に行かないと治療はできない
・病院に行き、言語療法、作業療法などを受けることは発達を非常に促進する
・なるべく早く集団に入れて普通の子どもに接するほうがよく発達する
・偏食で死ぬ人はいないから偏食は特に矯正をしなくて良い
・幼児期から子どもの自主性を重んじることが子どもの発達をより促進する
『これらはすべて、私から見たときに誤った見解か、あるいは条件付きでのみ正しい見解であって一般的にはとても正しいとはいえない。おのおのについて、なぜこれが誤っているのか、と驚かれたとしたら、そして発達障害と診断を受けたお子さんに関わっているとしたら、この本はあなたにとって読む価値のある本である。』
著者の杉山先生のご指摘の通り、理解不足は明白であり読み進むこととなりました。
以下、箇条書き形式になってしまいますが、目に止まった、特に重要と感じたことを書き出しています。一部、かなり専門的な内容になっています。
・人間の子どもは「生理的早産」原因は大きく進化した脳。これ以上大きくなると産道を傷つけ出産できない。これは、人間は他の動物に比べ、本来お腹にいるべき段階で出産せざるをえない事態になっている。例えば、独歩まで出産から1年を要するような動物は人間だけである。という意味です。
・子育ては集団よりも個人の方がよい。特に生後早期から数年において個別のそだちが必要であるこ とは、乳児院でそだった子どもたちが後年、心の発達の問題を抱えやすいことからも明らかである。
・ゴールは「自立」である。自立の3つの目標
1.自分で生活できる
2.人に迷惑をかけない
3.人の役に立つ
・人として生まれた子どもが、受精した瞬間から社会の中で生き、自立するまでの過程全体が「発達」である。
・発達の過程は、子どもが元々持っている力に対し、周囲が働きかけを行い、その両方が互いに働きかけ合って子どものそだちを作ることが知られている。発達を支えるものは子どもが持つ遺伝子と環境である。発達障害臨床の言葉に言い換えれば、生物学的な素因と環境因ということになる。
・環境の影響を受ける遺伝子:分子レベルの遺伝子研究が進展し、それによって遺伝子が体の青写真や設計図というよりも、料理のレシピのようなものであることが明らかになってきた。つまり、遺伝子に蓄えられた情報は、環境によって発現の仕方が異なることが示されたのである。遺伝情報の発現の過程は、遺伝子そのものであるDNAの情報が、メッセンジャーRNAによって転写され、タンパク質の合成が行われることによって生じる。この過程が実は問題で、ここで環境の影響を受ける。多くの状況依存的なスイッチが存在し、環境との相互作用の中で、合成されるタンパク質や酵素レベルで差異が生じることが徐々に明らかとなってきた。
・遺伝的素因の解明は、障害を決定づけるのではなく、高リスク児に対する早期療育の可能性を開くものとなる。
・心因であることが最も明確な疾患である外傷後ストレス障害(PTSD。トラウマを負った後、数ヵ月経ても不眠やフラッシュバックなどの精神科的異常が生じるという病態)において、扁桃体や海馬という想起記憶の中枢と考えられている部位に萎縮や機能障害など、明確な器質的な脳の変化が認められることがまず明らかになった。しかしその後の研究によって、強いトラウマ反応を生じる個人はもともと扁桃体が小さいらしいということが明らかになった。
・子どもは発達をしていく存在であり、発達障害の子どもたちも当然、日々発達していく。その過程で、凸凹や失調は全体としては改善していくのが普通である。むしろ、改善をしていかなければ何かおかしなことが起きたと考えるべきであり、二次的な問題の派生を疑う必要がある。
・子どもを正常か異常かという二群分けを行い、発達障害を持つ児童は異常と考えるのは今や完全な誤りである。発達障害とは、個別の配慮を必要とするか否かという判断において、個別の配慮をした方がより良い発達が期待できることを意味しているのである。
・発達障害の定義:「発達障害とは、子どもの発達の途上において、なんらかの理由により、発達の特定の領域に、社会的な適応上の問題を引き起こす可能性がある凸凹を生じたもの」
・知的障害を示す児童の89%までがIQ50~69の範疇に入る軽症の知的障害者である。IQ50とは成人に達したときに知的能力は健常発達の9歳前後と同等である。
・発達障害の概観
・認知の発達…精神遅滞
・学習能力の発達…学習障害
・言語能力の発達…発達性言語障害
・社会性の発達…広汎用性発達障害(自閉症スペクトラム)
・運動の発達…筋ジスなどの筋肉病、脳性麻痺など
・手先の細かな動きの発達…発達性協調運動障害
・注意力、行動コントロールの発達…注意欠陥性障害(ADHD)
・境界知能はIQ70~IQ84前後
・自閉症の3つの症状
・社会性の障害…人と人との基本的なつながりに生まれつきの苦手さがあるということ。
・コミュニケーションの障害…オウム返しが長く続く。疑問文によって要求を表す。
・想像力の障害とそれに基づく行動の障害(こだわり行動)…見立て遊びは極めて苦手である。一方、こだわり行動は顕著で中には800以上のこだわり行動をもった障害児もいた。自己刺激に没頭する理由は「まわり中が一定のリズムで動いていると幸福感がある」。
・上記の3項目以外で重要なものに、知覚過敏性の問題がある。
・最重度の知的障害を持つものから、まったくの正常知能のものまでいる。
・高機能広汎性発達障害とは、知的障害をもたない自閉症のことである。
・生まれつきの障害であり、統合失調症などとは決定的に違う。つまりその世界に生きている者にとって、その世界は奇異でも何でもなく、ごくごく当たり前なのである。
・自閉症は語ることは困難であるが、書かせるとより容易になる。
・「なぜ人を避けてしまうのか?」→「人に近寄られるのは好きではなかった。…「触られるなど論外で、触られるとどんな触られ方であれ痛いし、とても恐かった」 ドナ・ウィリアムズ
・「なぜ目を合わさず目をそらしてしまうのか?」→「人の目を見ると話が解らなくなってしまう。…「自分は45歳を過ぎて目がものを言うことを学んだ」 テンプル・グランディン
・「なぜくるくる回ったり、ぴょんぴょん跳ねたり自己刺激に没頭するのか?」→「まわり中が一定のリズムで動いていると幸福感がある」ドナ・ウィリアムズ 「砂の一粒一粒が見飽きず面白い」テンプル・グランディン
・「なぜコミュニケーションがとれず、言葉があるものでも会話が苦手なのか?」→「一度に一つのことしかできないので、自分の語ったことすら自分に向かってもう一度言い直さなくては理解ができない。」 ドナ・ウィリアムズ
・自閉症の精神病理の基本は、対話の際に雑多な情報の中から目の前の人間が出す情報に自動的に注意が絞り込まれる機能がきちんと働かないこと、一度に処理できる情報が非常に限られていることの二点である。これを認知の特徴という点で説明すると次の3つになる。
・情報の中の雑音の除去ができないこと。
・一般化や概念化という作業ができないこと。
・認知対象との間に、事物、表象を問わず、認知における心理的距離が持てないこと。
・自閉症の幼児は、対人的な情報への選択的注意という機能が十分に働いていない。その結果、お母さんの出す情報も、機械から出る雑音も同じように流れ込んでしまう。いわば情報の洪水の中で立ち往生している状態である。テンプル・グランディンは、自分の幼児期の耳は調整の効かないマイクロフォンのようだったと述べている。
・不安定で、怖い世界から自分を守るために、自閉症の幼児がとる戦略は、自分で、一定の安定した刺激を作り出して感覚遮断を行うという方策である。幼児期の自閉症でよく見られる自己刺激への没頭に他ならない。一定のリズムでぴょんぴょんしたり、目の前で手のひらをひらひらさせたりして、彼らは言わば押し寄せる情報へのバリアーを作り出しているのである。
・現在と過去とのモザイクこそが自閉症体験世界の特徴の一つである。
・広汎性発達障害の罹病率は2.1%である。(2007年)
・大まかで曖昧な認知がとても苦手である。
・筆者は対人関係で自閉症を孤立型、受動型、積極奇異型の3つに分けている。
・孤立型…人との関わりを避けてしまうタイプ。知覚過敏が強く一般的に重度の知覚的障害を伴っている。
・受動型…受身であれば人と関わることが出来るタイプで、知的障害を持たないものもいる。
・積極奇異型…人に積極的に、しかし奇異なやり方で接するタイプ。知的障害は軽いものが多い、マイペースで、基盤に注意の障害を持っていて、多動であることが大きな特徴である。
・特に孤立型と積極奇異型は、知覚過敏性などの問題に妨げられて愛着の形成が著しく遅れる。本格 的な愛着が小学校に入ってからという児童も少なくない。したがって、小学校年代において、きちんと子どもの甘えを両親に受け入れてもらうことがとても大事な課題となる。
・一般的に4歳前後までの幼児期が最も大変で、5歳ごろにコミュニケーションが目覚しく伸びる時期がある。また、10歳~12歳の小学校高学年はさらによく伸びる時期である。
・青年期も5歳と小学校高学年に次いで、よく発達する時期となることが多い。
・手を握りながら話かければ、握られた手の知覚入力だけであふれてしまい、言われたことは全く入らなくなる。言う時は言うだけ、見せる時は見せるだけ、触れるときは触れるだけにする。
・何度も体験したからといって徐々に慣れてくるということが期待できないところがある。
・一般化ができないこともあって、変化に対しては常に強い抵抗が生じる。
・高機能広汎性発達障害(高機能自閉症)とアスペルガー症候群の間に明確な違いは認められない。病名にとらわれず、高機能広汎性発達障害と考えるようになった。
・現在では脳科学の進展によって、注意欠陥性障害(ADHD)の症状の背後にはドーパミン系およびノルアドレナリン系神経機能の失調があることが明らかになっている。また、物事の予定や予測的な行動を組み立てる能力である、実行機能と呼ばれる大脳前頭葉の働きの一部に、弱いところがあることも示された。
・学習障害
・知的な能力に比して読字、書字、計算など、学習の特定の領域に限定した学力の極端な問題を抱える児童。
・純粋な学習障害は少なく、高機能広汎性発達障害やADHDなど、他の発達障害に併発して見られるものが多い。
・学習障害への対応は、特別支援教育である。障害のある脳の領域に繋がる領域を賦活し、バイパスを作る作業である。OT、PTの考え方が非常に有用である。
・児童精神科は膨大な新患待機リストを持っている。あいち小児保健医療総合センター心療科の発達外来は3年。
後半は「続 自閉っ子、こういう風にできてます!」(花風社)から、知ることができた事を列挙しています。この本は作家で自閉症の藤家寛子氏と、翻訳家で同じく自閉症のニキリンコ氏に、長崎大学医学部付属病院等で臨床に携わり、その一方で、研究者として、そしてアスペルガーの息子を持つ父親でもある岩永竜一郎先生の3人を中心に、会話形式で書かれています。

・現在の感覚統合理論では、感覚統合障害は大きく二つの障害、すなわち「行為機能の障害」と「感覚調整障害」に分けられます。行為機能の障害は、触覚、固有受容感覚(筋肉にある受容器で感じる身体の位置や動きの感覚)、前庭感覚(耳の奥の三半規管や耳石器などで感じる回転やスピード、傾きの感覚)などの感覚情報の処理過程に問題があり、それによって身体の位置や動きがわかりづらいなどの問題が生じ、不器用さや姿勢運動の問題など運動行為面に困難が出る障害です。
・自閉症の人を定型発達の人の認識の違いは、セントラルコヘレンスの機能に起因するとセントラルコヘレンスとはウタ・フリス博士によると「様々な情報を統合して、脈絡の中で高次の意味を構築する傾向」とされています。つまり、細部より全体をとらえることが優先される思考傾向です。鮮明な写真の表情の読み取りには定型発達の人とアスペルガー症候群の人の間で差が見られなかったのに、ぼかした写真になるとアスペルガー症候群の人のほうが表情の読み取りができにくかったことがわかっています。これからわかるように、定型発達者は細かいところはあまり気にせずに、ざっととらえるんですね。だから、多少細かいところが違っていても同じ仲間だと思ってしまいます。一方、自閉症の人はざっととらえようとせずに細部を見てしまうから顔の細部が見えなくなるとわからなくなるのでしょう。このような傾向があるから、自閉症の人は耳の形が違う犬同士、色が違う犬同士を同じ仲間であると思えないことがあるのかもしれません。
・後天的に「労働に耐えうる体力」を養うことができるかどうか:体力には大きく分けて、「行動体 力」と「防衛体力」があります。「行動体力」とは体を動かしたり行動を起こすために必要な体力です。筋力、バランス機能、巧緻性、柔軟性、持久性などがそれにあたります。一方、「防衛体力」というものは様々なストレスに耐え、体を守るための体力です。詳しく言うと、暑さや寒さなどの物理的ストレス、スモッグなどの科学的ストレス、細菌・ウィルス・睡眠不足などの生物的ストレス、恐怖・不安などの精神的ストレスに耐える時に発揮される体力です。一人の中でも当然、行動体力と防衛体力の格差はあります。そして、この二つの体力は、発熱などで体調が良くなると二つの体力は向上します。なお、体調と体力は表裏一体ですので、防衛体力が上がれば体調も良くなるとも言えます。
・自閉症の人はセロトニンなどの神経伝達物質の働きがうまくいっていないことが指摘されています が、そうした行動に必要な伝達物質が自閉症の人にもともと少ないと想定すれば、ストレス下で集中してがんばると定型発達者よりも早く疲れてしまうことになります。
・姿勢の崩れは感覚と深く関わっている:怠けではなく、脳の機能の違いによって姿勢が崩れやすく なること、身体の感覚が上手くつかめないために姿勢コントロールが難しくなることは、多くの人には予想できないことです。定型発達の人は姿勢の維持を無意識のうちにやっているのですが、自閉症の人は意識的にやらなければならないことがありますので、身体に集中して目の前の課題への集中ができなくなる可能性があります。
・成人期には、体力の向上を目指すことも重要ですが、その人が持っている体力で生活や仕事をして いく方法を身につけてもらうことも必要だと思います。体力が低い人でも、気分が落ち着いて体調が整っているときは活動できることが多いと思います。感覚過敏は気分が不安定だと強くなりますから。気持ちが安定していることで感覚過敏が緩和されているでしょうし、その結果余力が増えてエネルギー源が大きくなっているでしょう。抑うつ状態になると身体の動きが緩慢になったり、自発的に何かやろうという気持ちが起こりにくくなりますが、気分が安定していると生活のエネルギーも出てきます。気分の安定が栄養摂取の良さにつながり、脳の中の伝達物質のバランスもよくなるでしょう。つまり、気分の安定が防衛体力を整えたり、高めたりする一つの要因となると思います。そして、それは行動体力にも影響することになるでしょう。
・疲れが自分でわからないことを理解しておく:生活に支障が出るほど調子を崩すのは、不安や気分 の落ち込みがあった時や、がんばりすぎたり、はしゃぎすぎたりして、生活リズムに乱れが生じた時などが多いです。そのため、まず心理的ストレスがかかった時にそれを解消する手段を持つことが必要です。具体的に言うと、自閉症の特性をわかっている相談相手を身近に見つけて話をよく聞いてもらうことなどが大切ですね。自閉症の方の体調管理に際しては、「自分で自分の疲れがわからない」というのが大きな問題になってきます。だからこそ、規則正しい生活習慣を心がけ、自分の身体の感覚を頼りに疲れを判断しないようにすること。疲れていないと思っても決まった時間に休んで、一定の睡眠・休息を取るようにすることが必要です。つまり、定型発達者のように自分の身体の感覚に基づいて寝る時間を決めたりせずに、体調が良さそうな時であっても、あらかじめ決めたスケジュールに従って休んだり寝たりすることが大切です。
・就労に対して:大人になってからの体調・体力を安定させるために早期からやっておくべきことが あると思います。それは、①二次障害を作らない(うつなどな体調にも影響します) ②早期から運動に関わる神経系の発達を促す訓練(例えば感覚統合療法)を受けておく ③日常生活における運動習慣を身につけておく ④体調を崩さない生活習慣を学んでおく 以上4つです。
・自分の身体図式がしっかりしていると、新しい空間に行っても自分の領域をすぐにつかめるんです。自分の身体をよくわかっているから、手が届く範囲や身体を動かしたときに窮屈さを感じない広さというものをすぐにつかめるんです。そして、自分の身体図式ができていて、相手を見たときに身体のミラーイメージを持てる人は、相手の身体図式と領域もつかむことができます。定型発達の人の多くは自分の身体図式も、相手の身体図式もつかめますので、自分の領域、相手の領域も容易にわかり、近くに人がいても自分と他者の領域を無意識のうちに区別して適切な距離を取りながら作業をすることができるんですね。しかし、身体図式ができあがっていないと自分の領域も他人の領域もつかみにくくなるはずです。そして、身体図式の弱さを補うために一生懸命身の周りを見て、自分の領域を確かめることになるでしょう。これでは作業どころではないですよね。だから、身体図式の弱さを補うために、自分の領域の周りに線を引いてもらったり、パーティションで区切りを作ってもらうなどの支援があるといいんです。
・四輪の車に乗るより二輪の方が身体のイメージがわかると言っていた方がいます。バイクって足で押さえますよね。車の中に座るより、そのほうが身体の位置がつかみやすいそうです。それぞれ、強い感覚と弱い感覚があるんですね。その方は、固有受容覚は強いけど触角が弱いのでしょう。固有受容覚が強い人は何かに押し付けていると身体の位置がつかみやすいんです。
・感覚統合障害の中でも、静止画像の真似が苦手な人と、動きを真似するのが苦手な方がいるんですね。動きを真似するのが苦手な方は固有受容覚の認識が弱い方が多いです。自分の身体が動いている感じを連続的に脳でつかみにくいんですね。一方、静止画像の真似が苦手な人は触覚の認識が弱い人が多いです。
・息子が自閉症の特性を持つと確実に気づき始めたのは生後五ヶ月頃です。その時は、まず対人的注 意が低いことが気になっていました。生後四ヶ月までは誰にでもよく笑い、自閉的な印象はなかったのですが。そして、寝返りの質が違うことも気になりました。筋緊張が低く、屈曲力が弱い寝返りをするので、筋肉の使い方の質的問題があると感じていました。そのような特性が生後五ヶ月頃から々と見えるようになってきました。
・体育は他人との比較が入りますし、チームプレイで失敗すると責められることになりますので、自 閉症の子どもがやる気を起こすはずはありません。ドラムのように個人プレイでできて、成功を自分なりに感じられるもののほうが良いと思います。私たちが行う作業療法では、有能感、自尊心を育てることを大切にします。それが次のチャレンジを促し、障害によって滞っている発達の部分をよりよい方向に導くからです。これは自閉症の子どもの療育の中でも、常に意識していることです。
・ボディイメージを育てるためには触覚と固有受容覚が特に重要になります。いわばボディイメージを育てる栄養ですね。もちろん、マッサージなどで他動的に触覚や固有受容覚を刺激することは効果的かもしれません。ただし、ボディイメージを高めるためには、能動的体験の中で触覚、固有受容覚を体験することも必要です。お風呂の中では、お湯の抵抗がありますので、身体を動かすと触覚と固有受容覚のフィードバックがあるために身体を意識しやすくなります。同じ理由からスイミングもいいと思います。アスレチック遊具とかクライミングウォールにチャレンジすることもお勧めです。要は能動的に触覚刺激や固有受容刺激を感じて動きを作り出すことが大切なんです。しかも、いつもやらないような未経験の運動をやったほうがボディイメージは育ちやすいと思います。
・自閉症の子どもは集団で行う球技が嫌いだと思われていますが、やり方次第では好きになるんですよ。好きになってもらうためのポイントを挙げておきましょう。
・不器用でも失敗が起こりにくいように工夫する。
・不器用でも不利にならないルールを作る。
・必ず全員に出番があり、皆で活躍できるような工夫をする。
・必要に応じて大人が参加し、ゲームが円滑に進むように調整する。
・暴力を振るわない。
・暴言を吐かない。
・審判の判定にクレームをつけない(「ゲーム中審判は神様です」と前置きしてから始めます)。
・自閉っ子が大好きなる球技
・ポートボール(自閉っ子ルール)
・サッカー(自閉っ子ルール)
・キックベースボール
・五感の他にも人間の行動や情緒に大きな影響を及ぼす感覚が二つあります。それが固有受容覚と前庭覚ですね。私やニキさんが、コタツに入ると脚がなくなるのは固有受容覚のつかみ方が弱くて、自分の身体が伝えてくる情報を受け取っていないからでした。そして藤家さんやニキさんは「自分の身体がどこからどこまでかわからない」とか「コタツに入ると脚がなくなる」とか私たちには実感のできない身体感覚を持っています。それは、ボディイメージが弱いからです。そして、ボディイメージが不確かなのは、身体からの情報が脳にきちんと伝わっていないからです。ボディイメージが弱いと、いろいろ困ったことが起こりますね。まず、不器用という問題が起こりがちです。そしてこの問題に、感覚統合療法は効果があります。その体験談が、『大丈夫! すくすくのびたよ自閉っ子』という本に載っています。
・マッサージ:ブラシや素手でマッサージして、だんだんと感覚を受け入れられるようにします。治 療者との関係を作ってから、「こうやって触れられれば、こういう感覚が入ってくるのだ」と覚えていってもらいます。身体の中では背中が受け入れやすい場所ですので、そこからマッサージを始めます。腹部、首、顔などは過敏反応が出やすいので、最初はやりません。マッサージはまず受け入れられる部分だけ行ったほうが良いでしょう。
下の図は体を使って遊ぶ時や運動するときに必要とする感覚、固有受容角覚と前庭覚です。これに触覚を加えた3つの感覚が、感覚統合訓練の柱になっています。
最後に、「自分の体取り戻しマニュアル」をご紹介したいと思います。
これは著者の一人で作家の藤家寛子先生が「体に力が入らないときや身体の実体が感覚できなくなったときに使っているものです。なお、前作『自閉っ子、こういう風にできてます!』に掲載されていたものです。


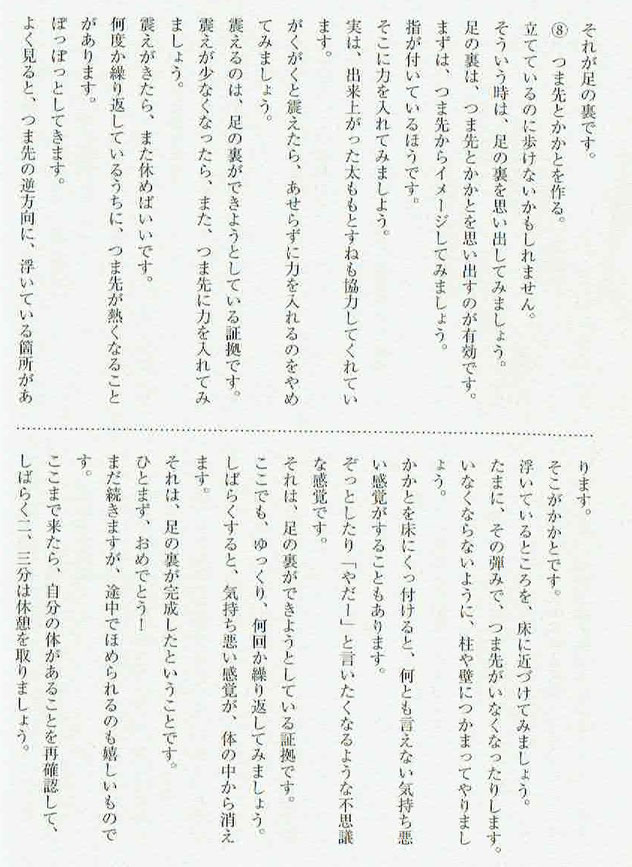

小児障害マッサージ
12月4日の日曜日、小児障害マッサージの講習(今回は座学)を受講してきました。
疾患は脳性麻痺(CP)、脳室周囲白質軟化症(PVL)、筋ジストロフィー(CMD)などが多く、それらの病気を理解することが第一ですが、施術にあたっては脱臼・亜脱臼の既往とてんかんの有無を最初に確認することが必須となります。また、施術は安全性と効果の両面から適切な手技の習得が求められます。
講習受講後、調べて理解しなければならないと感じたものが、「ボトックス注射(ボツリヌス治療)」です。そこで、ブログは前半にボトックス注射の基礎知識、後半に一般的なマッサージ・指圧の効果についてご紹介したいと思います。
ボトックス注射(ボツリヌス治療)
ボトックスとは、ボツリヌス菌のもつ毒素を滅菌された生理食塩水で薄めた薬剤のことです。
ボツリヌス菌は食中毒を起こす菌で、極めて強力な神経毒により胃腸症状に続いて、筋肉の麻痺や呼吸困難などを引き起こします。
これを知ると、恐ろしいものと感じると思いますが、ボトックスは毒素ではなくボツリヌス菌が作り出した「ボツリヌストキシン」という成分で製造されており、問題の毒素は取り除かれています。
なお、このボツリヌストキシンには、筋肉に送られる命令の伝達を弱め、筋肉の収縮を抑える効果があります。つまり、この特性を利用して硬くなった筋肉を弛緩させるわけです。
1970年代後半、アメリカの眼科医が斜視の治療でボツリヌストキシンを臨床で使用したのが最初です。日本では1996年に眼瞼攣縮が認可されて以来、2000年に片側顔面攣縮、2001年に攣縮性斜頸、2009年に小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足、さらに2010年に上肢痙縮・下肢痙縮、2012年に腋窩多汗症へと徐々にその適応症が拡大されてきました。
懸念される副作用の多くは治療対象筋肉の過度な脱力というものですが、薬の量を調整することで回避が可能です。また、重症障害児の場合には、嚥下や呼吸が弱くなるという副作用があるとされていますので十分な注意が必要になります。
治療間隔は5~6ヶ月が目安となり、これに適した投与量を注射することになりますが、量の調整は段階的に増量しながら、最終的に適量を決定します。また、毎日のリハビリテーションが治療効果の持続にとって重要となります。
施術者としては、筋肉は筋膜や腱膜などによって周辺の筋と連結しているため、治療対象周辺の筋肉の状態や、各パート(左右の上肢、下肢などの単位)および全身レベルの筋肉のバランスや状態に注意を払うことが大切だと思います。
マッサージ・指圧の現代医学的効果
小児障害マッサージも土台となっているのは一般的なマッサージの基本と同じです。
マッサージには気持ちよいという慰安の側面もありますが、効果のメカニズムは科学的な説明が可能であり、医療においてはそのメカニズムを理解し、患者さまの状態に応じて、適切に施術することが重要になります。
なお、「鍼通電療法」でご紹介した芹澤勝助先生が、著書「マッサージ・指圧法の実際」(創元社)の中で、詳細に説明されていますので、その個所を引用させて頂きます(2箇所、中略あり)。
『マッサージの効果も、指圧の効果も、ともに皮膚の上から加える [触圧](ふれる、おす) 作用で、直接には循環系に働き、間接には神経反射により神経、筋肉系に影響を与える施術である。
ところで、触圧感覚とはどういう感覚なのかというと、この感覚は、皮膚や筋膜、筋肉、腱、関節などに機械的なエネルギーをあたえたとき、つまり、さわったり、なでたり、こすったり、もんだり、おしたり、ふるわせたり、たたいたり、ひっぱったりしたときに起こる感覚のすべてをいうのであり、このうち筋肉や筋膜、腱や関節に起こる触圧感覚を深部感覚といっている。 -中略-
いま皮膚が、なでられ、おされ、ひっぱられると、この条件変化により、それぞれに対応する受容器が変形を起こし、受容器が興奮する。この興奮は受容器に入り込んでいる知覚神経線維により、脊髄神経節を介して脊髄に入る。 -中略-
要約すると、皮膚刺激→触圧→触圧の受容器→知覚神経→脊髄(上行する線維、下行する線維、自律神経「交感神経」に連絡する線維、脊髄のそれぞれの高さでの反射弓をつくる線維)→延髄→大脳(間脳の視床→皮質)を伝導路とすることになり、皮膚感覚のすべては、一応間脳の視床に集まり、大脳皮質に達するのである。
マッサージや指圧による治療効果として現れる生体反応の多くは、触圧による機械的な作用もさることながら、神経反射によって起こるものであろう。生体における一連の反射作用は、神経の末梢で起こる軸索反射と、求心性伝導路の脊髄レベルで起こる反射(脊髄反射)とがあり、さらにもっと高位の中枢(間脳の視床と、自律神経の高位中枢である視床下部との間に起こる)の複雑な関連機転によって起こるものとがある。特に中枢神経系の機能の主なものは反射機能であり、脳脊髄神経系の反射と自律神経系の反射である。
神経痛の「いたみ」や「しびれ」、運動神経系の痙攣などにマッサージや指圧が効く理由の主なものは、脳脊髄神経系の反射機転を介するものであろうし、循環系や広汎な内臓系のいろいろな症状や不定愁訴の症状群(たとえば頭痛、めまい、耳鳴り、不眠、肩こり、便秘など)に効く理由は自律神経反射が主役を演じているのであろう。しかし人間の体は有機統一体なのであるから、お互いに絡み合いの機転であろうが、その間には、おのずから主役的あるいは脇役的に働く機転があるはずである。』

画像出展:「経穴マップ」(医歯薬出版)
下段はホムンクルスと呼ばれる絵で、体のどこを刺激するかによって、脳の体性感覚野にどうように投影されるかを表したものです。四肢末端と顔面(特に口唇)への刺激が体性感覚野の広い領域に影響を及ぼすことを示しています。これを見ると脳のリハビリとして、歩くこと、手を使って食べることが効果的であるということが納得できます。