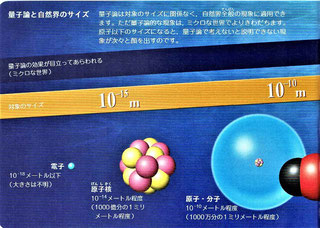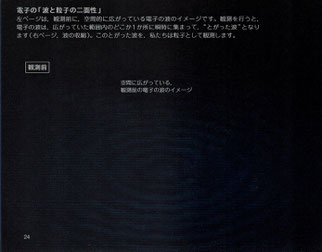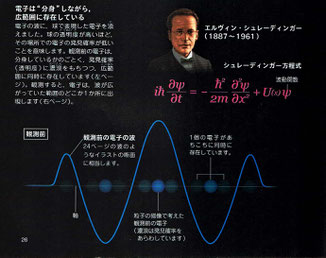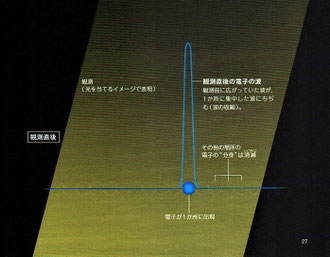分断するアメリカとZ世代1
組織において“分断”はマイナスです。社内で専務派と常務派に分かれたり、チーム内で監督派とコーチ派に分かれたりすれば、総力は削られ組織の目標に赤信号が灯ります。特別な事情がない限り「百害あって一利なし」それが組織における“分断”だと思います。
一方、今のアメリカに起きている分断は何なのか。それは「多様性」と「権利」のせめぎ合い、そして背景にあるのが「生活」であり、その直接的な大きな要因の一つは「移民問題」ではないかと思います。
世界が注目するアメリカの大統領選挙は2024年11月5日です。バイデン大統領とトランプ元大統領の討論会は、およそ4カ月半前の6月27日に行われました。バイデン氏は年齢の衰えを隠せず、リーダーとしての資質に疑問を呈する場となりました。
一方、7月13日ペンシルベニア州のバトラー市で行われた共和党の集会で、トランプ氏は命を狙った銃弾で耳を負傷するという、あってはならない事件が起きてしまいました。この事件後、共和党内の一体感は高まり、世論は一気にトランプ氏の勝利を織り込むようになってきました。

画像出展:「トランプ狙撃事件が見せた米民主主義の自衛作用(産経新聞)」
バイデン大統領に代わる新しい候補者擁立の動きが活発化する中、7月21日、バイデン大統領は選挙戦からの離脱を表明し、後任を現副大統領のカマラ・ハリス氏に委ねるという発表がありました。もし、ハリス氏が大統領に選ばれると米国初の女性大統領ということになります。
今回の『Z世代のアメリカ』という本は、「カマラ・ハリスは何故人気がないのか」とタイプして見つけたものです。

著者:三牧聖子
発行:2023年7月
出版:NHK出版
NHK出版デジタルマガジンというサイトに、『アメリカ「例外主義」の変化―トランプ大統領が国際秩序にもたらしたものとは』という記事がありました。
なお、この記事は三牧先生の『Z世代のアメリカ』からの抜粋とのことです。
はじめに
第一章 例外主義の終わり―「弱いアメリカ」を直視するZ世代
●戦争はもうこりごり
●ドナルド・トランプ―「例外主義」を放棄した大統領?
●「逆・例外国家」?―バーニー・サンダースの問い
●未完のサンダース革命
●バイデンに受け継がれた「アメリカ第一」
●アフガニスタンからの撤退
●「アメリカにウクライナ支援をする義務はない」
●例外主義の放棄は平和につながるのか
●「盟主」不在の国際秩序とどう向き合うか
●ポスト例外主義世代
第二章 広がる反リベラリズム―プーチンと接近する右派たち
●リベラリズムへの敵意が広がるアメリカ
●内向きになる保守
●「文化闘志」ロン・デサンティスの台頭
●アメリカ右派とプーチンの思想的共鳴
●「キャンセルカルチャー」批判を繰り返すプーチン
●「キャンセル」を超えて
第三章 米中対立はどう乗り越えられるか―Z世代の現実主義
●分断される世界―民主主義サミットが示した問題
●アメリカはもはや民主主義のお手本ではない?
●選挙がむしろ民主主義を動揺させる?
●「能力」が正当化してきた経済格差
●対中感情の歴史的悪化
●Z世代のTikTokブームは「地政学的リスク」か?
●国家安全保障は大事だが、すべてではない
●未来の協調に希望をつなぐ
第四章 終わらない「テロとの戦い」―Z世代にとっての9・11
●「テロとの戦い」への懐疑
●9・11を記憶する
●誰が忘れられてきたのか
●たった1人の反対
●命の値段
●「女性を解放するため」の戦争?
●中村哲医師がみた9・11
●アメリカ=女性の解放者言説の欺瞞
●Z世代フェミニストの問い
第五章 人道の普遍化を求めて―アメリカのダブル・スタンダードを批判するZ世代
●不可視された「テロとの戦い」
●「ドローン大統領」オバマ
●永久戦争?
●忘れられるアフガニスタン
●経済制裁が加速させる人道危機
●アメリカのダブル・スタンダードを批判する若者たち
●人道に潜むレイシズム
●日本、そして私たちにできること
第六章 ジェンダー平等への長い道のり―Z世代のフェミニズム
●カマラ・ハリスの不人気
●多様性を象徴する存在
●黒人コミュニティからの不信感
●寛容であることの困難
●「壁」問題―「トランプ化」する民主党?
●「アイデンティティ政治」の失敗事例?
●中道であることの難しさ
●#Me too運動へのダブル・スタンダード?
●ハリスを超えて―フェミニズムの未来
第七章 揺らぐ中絶の権利―Z世代の人権闘争
●「母親や祖母より権利を持たない世代」
●ロー判決破棄の背景―司法の保守化
●リベラルが中絶に反対した時代
●ギンズバーグ判事が見いだしていたロー判決の弱さ
●母性を否定しない「新しいフェミニズム」?
●プロ・ライフとプロ・チョイスの二分法を問い直す
●1人の女性の中にあるプロ・ライフとプロ・チョイス
●声をあげるZ世代
●社会運動では勝っても、権力闘争では負けるリベラル?
●アメリカは今、人権の旗手といえるのか
●権利を守る世代
●Z世代へ未来をつなぐ
おわりに
第一章 例外主義の終わり―「弱いアメリカ」を直視するZ世代
●戦争はもうこりごり
・2000年代のアメリカは、対外的にはアフガニスタン・イラン戦争後の膠着、肥大化する戦争関連費用に苦しみ、対内的には2008年のリーマン・ショック後の長い不況に見舞われ、貧困の格差も極限まで広がった。
・Z世代が知っている戦争はアメリカから仕掛け、圧倒的な力の差によるものだったが、ロシアとウクライナの戦争は全く異なる。他国から侵略を受けた国に対し、アメリカは何をすべきか、何ができるのかという新しい問いを突き付けられている。
・アメリカが反戦の立場をとって、ウクライナへの武器支援をやめれば平和は訪れるのか。ウクライナの領土や主権が大幅に損なわれたうえで、停戦は実現されるかもしれない。しかし、それは本当に平和と呼べるのか。他方、際限ない武器支援のよって望ましい平和は訪れるのか。ロシアのような軍事大国を屈服させることは可能なのか。Z世代は今、こうした厳しい問いと現実に直面している。
●ドナルド・トランプ―「例外主義」を放棄した大統領?
・2001年の9・11同時多発テロから始まった「テロとの戦い」は過去20年間でアメリカが軍事作戦を展開してきた国は80カ国に及び、その費用は計8兆ドル(約1200兆円)にのぼる。命を落とした米兵の人数は7000人を超え、敵対する兵士や民間人を含めた全世界の死者の総計は90万人前後に及ぶ。
・2017年、第45代アメリカ大統領に就任したトランプは、「世界に搾取され、弱くなったアメリカ」というネガティブな自国像であった。そこには盟主意識も世界の警察という意識も全くない。
・トランプにとって、自国の産業や自国の軍隊を犠牲にするような世界との関与を改め、国益を追求する「アメリカ第一主義」を宣言した。“Make America Great Again”である。
・トランプが放棄した「例外主義」とは、「アメリカは物質的・道義的に比類なき存在で、世界の安全や世界の人々の福利に対して特別な使命を負う」という考えである。トランプが目指すのは「普通の国」ということである。しかしながら、これはアメリカの「例外主義」的な意識に支えられてきた国際秩序が重大な転換点にあることを意味している。
※アメリカ例外主義(Wikiより):アメリカ合衆国がその国是、歴史的進化あるいは特色ある政治制度と宗教制度の故に、他の先進国とは質的に異なっているという信条として歴史の中で使われてきた概念である。
●「逆・例外国家」?―バーニー・サンダースの問い
・アメリカは新型コロナのパンデミックで、社会保障制度の脆弱性が露呈した。
・社会主義の否定の裏には豊かさや自由への誇りがあった。しかし、貧富の差が拡大を続ける中で、状況は大きく変わり今日では多くのアメリカ国民が現状に疑問と不満を募らせている。
・2019年5月のギャラップ社の調査では、43%の回答者が社会主義を「よいもの」だと回答している。これは1942年の25%からの劇的な上昇である。
・新自由主義グローバリズムと格差の拡大が現実的になりつつあるなかで、アメリカ国民はなぜ先進国でありながら、ここまで社会保障制度が未整備なのかと不満を募らせている。
・サンダースが模範とみなすのは、デンマークなどの北欧諸国である。デンマークでは一握りの人々が莫大な富を保有することを可能にする制度を推進する代わりに、子どもや高齢者、障害者を含むあらゆる人が安心して生きられる最低限度の生活水準を保障する制度を作った。
・アメリカ的な「自由」は唯一のものではなく、もしかしたら最善のものでもないかもしれないという主張は、アメリカの「例外主義」を根本から問い直すものであった。
・アメリカの科学技術や文化・芸術に関しては、90%近くが「誇りに思える」と回答しているが、社会保障制度や政治システムに関しては、「誇りに思えない」が60%超えている。
・サンダースの問題定義に最も賛同している世代は若者である。Z世代は物心がついてからずっと、お金がものを言う政治を見せつけられ、政治に希望を見いだすことはできなかった。
●未完のサンダース革命
・サンダースは、2016年はクリントンに、2020年はバイデンに敗北した。敗因はクリントン、バイデンといった中道の重鎮たちは面白みがないが選挙に勝てる可能性が高いと思われている。
・サンダースは「急進左派」と言われているが、その政策はヨーロッパの中道左派の主張に近いものである。
●バイデンに受け継がれた「アメリカ第一」
・バイデン政権は大統領就任直後から、トランプ政権下で進められた排他主義的・単独行動主義的な政策を巻き戻し、世界に開かれ、他国と協調するアメリカを再び打ち出すものだった。しかしながら、アメリカが取り組むべき喫緊の課題は国内に山積しており、大々的な対外関与の余裕はないというのが実状である。
●アフガニスタンからの撤退
・『2021年4月14日、バイデンは20年にわたる「テロとの戦い」において、一つの画期となる決断を表明した。この日バイデンは、2001年10月、ジョージ・W・ブッシュ大統領がアフガニスタンへの空爆開始を宣言したホワイトハウスの「条約調印の間」で演説を行い、「アメリカ史上最長の戦争を終えるときだ」と宣言。アメリカ同時テロから20年迎える9月11日までにアフガニスタンの駐留米軍を完全撤退させると表明した。
アフガニスタンの安定化の見通しがつかないままの完全撤退については共和党のみならず、政権内からも反対の声があがっていた。中央情報局(CIA)のウィリアム・バーンズ長官は14日の上院公聴会で、米軍が撤退すれば、同地域の軍事力低下につながるとあらためて懸念を表明した。完全撤退は、こうした懸念の声をバイデンが押し切る形で決定された。
その後、撤退期限は8月末に早められ、撤退を完了させたバイデンは、アメリカの目的はアメリカ本土に対するテロ攻撃の再発を防止することにあったとし、その目的は実現されたと主張して、次のように宣言した。「アメリカが他国を作り変えるために大規模な軍事作戦を展開する時代を終わらせることだ」。もっともこれはオブラートに包まれた表現で、より率直にバイデンの心境を表現していたのは、首都カブールがタリバンの手に落ちた翌日の8月16日、それでも米軍の撤退を進める決意を国民に示した演説の中の次の中の言葉だろう。それはトランプと見間違えるような、赤裸々な「アメリカ第一」宣言だった。
[アフガニスタン軍が戦わないのに、アメリカ人の娘や息子をあと何世代、アフガニスタンの内戦に送り込めばいいのだろうか。アメリカ人の命をあと何人分、アーリントン国立墓地に延々と並ぶ墓石に変えたらいいのか? その価値があるのだろうかと。(中略)私の答えははっきりしている。私は、過去に起こした過ちを繰り返したくない。アメリカの国益にならない紛争にいつまでも留まり戦うこと、外国での内戦を激化させること、米軍を延々と派遣して国を作り変えようとすること。このような過ちを繰り返してはならないのだ。]
“Remarks by President Biden on Afghanistan ,”White House, August16,2021.
このバイデンの時代認識は、国民にも広く共有されていた。確かに米兵を含む人命の犠牲も出しながらのアフガニスタンからの撤退は、多くの国民の批判に晒されたが、国民の批判は、撤退時期や撤退方法に集中し、撤退というバイデンの判断自体は過半数に支持された。
アフガニスタンからの米軍撤退に関する世論の背景には、より大きな世論の潮流がある。昨今のアメリカでは、アメリカはこれまで過剰に世界に介入し、自国を疲弊させてきたという批判的な意識が高まり、アメリカの国際的な役割をより穏当なレベルに引き下げるべきだという考えが党派を超えたコンセンサスとなっている。各種の世論調査でも、「アメリカは世界の警察をやめるべき」「他国のことより国内問題、特に雇用の問題に取り組むべき」「同盟国に安全保障のコストをもっと負担させるべき」といった見解は、党派を超えて広く支持されてきた。
●ポスト例外主義世代
・「テロとの戦い」による国家的消耗、コロナ禍の甚大な被害の経験から、若い世代ほど対外介入に否定的な意見を持っている。
・2020年6月にギャラップ社が行った調査で、世代別で最も低い値だったのは18歳から29歳までの世代で、アメリカ人であることを「非常に誇りに思う」と回答したのは20%だった。彼らの多くはリベラルな価値観の促進に未来への希望を見いだし、銃規制や気候変動対策を支持し、よき未来に向けて社会運動にも積極的に関与する。行き過ぎた資本主義と経済格差に不満を募らせ、より社会主義的な政策を支持する世代でもある。対外的にはグローバル化する世界におけるアメリカ一国の力の限界への冷静な認識から、アメリカは多少の妥協を伴ったとしても、共通の目的のために他国と協調しなければならないと考え、多国間協調を志向する。
・ロシアのウクライナ侵攻は、国際協調主義の限界を突きつけている。中国やグローバル・サウスとの間の不一致は続いているが対話を閉ざすことはしていない。アメリカ一国の力の限界を自覚している。
・『アメリカの圧倒的な力の優位が失われ、ロシアのように明らかな現状変更を試みる国も現れる中で、いかに平和を回復し、持続させていくのか。国際協調主義をDNAとして組み込んだアメリカのZ世代が、この難問にどう立ち向かっていくのか。私たちも他人事ではなく、自分事としてみていくべきだろう。』
第二章 広がる反リベラリズム―プーチンと接近する右派たち
●リベラリズムへの敵意が広がるアメリカ
・プーチンの権威主義的な政治スタイルは、アメリカ右派の間に共感の輪を広げている。特にプーチンを「強い指導者」と称賛するトランプが大統領となって以降、共和党支持者の間にもプーチンへの好意的な意見が目立って増えてきた。
・2017年には、共和党支持者の49%がロシアを同盟国あるいは友好国とみなし、32%がプーチンに好意的な意見を持っていた。
“Republicans Are Warning Up to Russia, Polls Show.” Morning Consult, May24, 2017.
・2021年1月の連邦議会議事堂襲撃事件が示したように、選挙制度への不信、政治的な目的のための暴力を容認する世論の傾向も顕著になってきている。
・ハーバード大学やシドニー大学が共同で行ってきた「選挙の公正さプロジェクト」の調査によると、アメリカの選挙の公正さは西洋の民主主義国家の中では最低レベルである。
Electoral Integrity Project Report, 2020.
・『昨今は、共和党が上下院の多数を占める州を中心に、「不正投票の防止」という一見もっともな名目で、低所得者やマイノリティの投票を実質的に阻む法律が多数成立している。有権者ID法などで投票時における身元確認が厳格化されたことにより、運転免許証を持たない人や、定まった住居を持たない人の投票が困難にされてきた。』
Brennan Center for Justice, State Voting Laws.
・『アメリカの共和党は過去20年間で非自由主義的な性質を顕著に示すようになっており、ヨーロッパの中道右派政党よりも、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン政権やハンガリーのオルバーン・ヴィクトル政権のような権威主義国家の与党に近いことが明らかになっている。特にトランプ政権下でその傾向は加速した。』
●アメリカ右派とプーチンの思想的共鳴
・共和党右派とプーチンとの間には反リベラリズムという共通の価値観がある。
・欧米諸国の右派が抱くリベラルな価値や政策への不満に巧妙に働きかけ、社会の分断を狙うプーチンの思惑通り、民主党政権のもとでジェンダーの多様性が進み、また移民や難民に寛容すぎるという不満を募らせているアメリカ右派たちはプーチンに対し、共感や親愛の情を抱いてきた。
量子テレポーテーションの実験
量子テレポーテーションの実験でノーベル物理学賞を受賞された、アントン・ツァイリンガー博士の著書を見つけ、「どんな実験だったのだろう?」という興味から、今回も、深く考えず購入しました。そして、予想通りほとんど理解できませんでした。しかしながら、ネットには素晴らしいサイトや動画があるので、それらの助けをお借りして何とかブログとしてまとめました。
以下のサイト及び動画をご参考にして頂ければと思います。

“ノーベル物理学賞受賞者が語る「テレポーテーション」の可能性とは?『量子テレポーテーションのゆくえ』本文試し読み”
こちらは出版会社である早川書房さまのサイトです。本書の概要が説明されています。

“【超重要】量子情報はすでに「過去」へと送られている...”
こちらは「シンプリイライフ」さまのサイトです。内容は以下の通りです。22分11秒
1.量子もつれとは 2.量子もつれを実証している男たち(4分26秒) 3.量子テレポーテーションの可能性(7分37秒) 4.量子情報は「過去」に送ることができる (12分23秒) 5.この世界の「秘密」について (17分32秒)
目次
プロローグ ―ドナウ川の地下で
宇宙旅行
光というもの
牧羊犬とアインシュタインの光の粒子
アインシュタインとノーベル賞
対立
不確定性はいかにして確定したか
量子の不確定性 ―私たちにわからないだけなのか、それとも本当に不確定なのか
テレポーテーションに対する量子的判決
量子もつれが助けてくれる
量子実験室のアリストボブ
光の偏光 ―クォンティンガー教授の講義
ジョンによるアインシュタイン、ポドルスキ―、ローゼン入門
局所的な隠れた変数に関するジョンの話
アリスとボブの実験がややこしい結果を出す
ジョン・ベルの物語
アリスとボブは物事が自分たちの思っているとおりではないことを知る
光より速く、そして過去にさかのぼる?
アリスとボブと光の限界
抜け穴
チロルの山にて
量子の宝くじ
量子マネー ―もう偽造できない
量子トラックは運べる量よりもたくさん伝える
原子を使った量子もつれ生成と初期の実験
超高性能生成装置と情報伝達の抜け穴の封鎖
ドナウ川の量子テレポーテーション
多光子のもたらした驚き、そしてその途上での量子テレポーテーション
量子もつれのテレポーテーション
さらなる実験
量子情報テクノロジー
量子テレポーテーションの未来
テネリフェ島上空からの信号
最近の展開と未解決の問題
つまりどういうことなのか?
エピローグ
付録/量子もつれ―量子をめぐる万人の謎
ドナウ川の量子テレポーテーション
●この実験の重要な部分はグラスファイバーの中でおきる。
●レーザー装置は巨大で家が買えるくらい高価な装置である。
●大事なことはレーザー装置が生成するのは持続的な光線ではなく、超高速で続けざまに生じるレーザー光のパルス[電気信号の波(周波数)]だということである。1回のパルスの持続時間はおよそ150フェムト[1000兆分の1(10のマイナス15乗)]秒で、装置はパルスを毎秒8,000万回ほど発生させる。これはレーザーの生成する光のパルスがいかに短いかが分かる。たとえば、灯台の明かりが1日1回、しかも1秒しか点滅しない、一瞬の点滅のようなものである。
●短いパルスは量子の識別可能性と関係している。
●光りパルスはレーザーから発射されて、小さな結晶[図中央の“C”]を通過する。
●この特殊な結晶は、量子もつれ状態となった光子を生成する。この結晶はわずか2mmと薄いがここで起きることは、実験で1番大事なところである。
●2つの光子がある一定の角度で飛び立つ。この2つは互いに量子もつれ状態にある。
●グラスファイバーの手前に小さなレンズを置く。
●この状態で光子をファイバーに送り込むと、光子はアリス[右上]とボブ[右下]のもとに向かう。
●これによりできたのは光子AとBからなる量子もつれ状態にある双子のペアである。なお、グラスファイバーは光子をテレポートするのに使う量子チャネルである。一方、川の上空を通る電波は古典チャネルである。
※この後、説明が7ページと2つの図が続くのですが理解困難なため、再び「シンプリィライフ」さまの動画に再登場して頂き、この場を切り抜けます。
量子情報テクノロジー
●1930年代、アインシュタイン、シュレーディンガーに加え、ボーア、ハイゼンベルク、パウリなどが量子力学の創始者である。アインシュタインは「不気味な遠隔操作」を受け入れず、シュレーディンガーは量子もつれこそ量子力学の本質的な特徴だと訴えた。
●1960年代、レーザーが発明され、局所実在論を検証することが可能になった。局所実在論という理論内でベルの不等式は成立するが、そのベルの不等式の破れを実験により証明したことで、量子力学による予想の正しさが裏付けられた。これらの実験は、哲学的な問いに動かされていた。言い換えれば、一部の人々の好奇心に駆り立てられていた。このような好奇心は人が挑戦するための大事な原動力であり、科学においてはしばしば新しいテクノロジーと結びついて興味深い発見をもたらしてきた。
●1990年代、量子に関する基本的な概念から、情報を伝送して処理する新たな方法に関するアイデアが生まれた。こうした新たなアイデアの中には、量子暗号、量子乱数生成器、量子テレポーテーション、量子コンピューターなどが含まれている。
●現代、新しい量子情報テクノロジーの開発が、世界的に最も活発な研究領域となっている。多くの国で数々のグループが、量子暗号、量子コンピューター、量子通信など、技術応用につながる可能性のあるさまざまなテクノロジーの開発に取り組んでいる。
●技術的に最も成熟度が高いのは量子乱数生成器である。これは量子力学で生じる個々の事象のランダム性を利用する。量子乱数生成器の用途には、コンピューターに保存されている情報の暗号化である。
●量子コンピューターの実用化にはまだまだ時間がかかると思われているが、実験物理学の創造力は過小評価できないと考えている。
量子テレポーテーションの未来
●今後数年のうちに、テレポーテーション実験の距離が伸びることは間違いない。アイデアの一つは地上のステーションと人工衛星の間を結ぶ、光の量子状態を送るテレポーテーションである。
●原子や分子の状態に関するものも考えられる。複雑な分子を記述するために、各原子がどのように配置されてるか、互いにどう結びついているかについて知ることも重要である。
最近の展開と未解決の問題
●量子コンピューターに関してはさまざまアプローチがされている。情報の担体として単独の原子やイオンを使うグループ、従来のコンピューターで採用されている標準的な半導体シリコン技術を使い、個々の量子ビットを暗号化して処理できるように手を加えているグループもある。単独の原子をシリコンなどの半導体に一つずつ埋め込み、互いに対話させることで量子プロセッサーにするというアイデアもある。また、小型の超電導素子を使っているグループなど色々なアプローチが試みられている。現時点では、量子コンピューター技術のさらなる展開やどのテクノロジーが利用されるかなどは全く予想できない。
●興味深いアイデアの一つが、一方向量子コンピューターである。これは他の量子コンピューターやそれ以外のあらゆるコンピューターとは全く違う原理で動くことである。標準的は量子コンピューターでは、入力量子ビットを量子コンピューターに入力する。すると、アルゴリズムがこの量子ビットの量子進化として実行される。
●一方向量子コンピューターは、多数の量子ビットがかかわる複雑な量子もつれ状態からスタートする。このアルゴリズムは量子状態の観測結果を連ねたものである。
●激しい議論を巻き起こしている問題は、量子の概念が脳の中でなんらかの重大な役割を果たしているのかという点である。あらゆる生命現象において量子物理学が果たす役割については、広く意見が一致している。生体内で生じる化学反応は、要するに量子のプロセスだと考えられている。一方で、脳が量子ビットや量子もつれなどを使うとは全く考えられていない。しかしながら、基本的な観点から言うと、量子物理学が脳内でなんらかの役割を果たす可能性を原理的には否定できない。
それは量子コンピューターにおいて2つのメカニズムが実行できることが発見されているからである。その1つはデコヒーレンスに対して頑強となるように情報を保存できること。これはデコヒーレンスの生じない小区画を作るアプローチである。もう1つは冗長とも言える形でたくさんの量子ビットに情報を保存するというアプローチである。とはいえ、今のところこれら全ては仮説にすぎない。
●意識とは何か、心とは何かといった謎の解明を考える人もいるが、これらは徹底的に研究していくべくテーマである。
つまりどういうことなのか?
●重要なことは量子物理学がもたらす概念的および哲学的な帰結だろう。
●装置の選択が量子系の特性を決定し、それが実験結果として現れる。たとえば、二重スリット実験では観測者の選択した装置が、粒子の経路を特定できるものか、それとも干渉パターンがわかるものかによって、経路と干渉パターンのどちらが実在の要素となるかが決まる。しかし注意しなくてはいけない点がある。観測者の心が量子状態に影響するのだと主張する人もいるが、そのように主張することは危険である。また、そのような考え方は量子観測の物理学で裏づけられていない。
※二重スリット実験 (三たび「シンプリィライフ」さまのお力をお借りします)

“【量子力学】二重スリット実験完全解説!いまだに解明できない「観測問題」の謎を解く”
16分16秒
1.完全解説!二重スリット実験
2.検証! 二重スリット実験の謎
3.いまだに謎の「観測問題」
4.「観測」とはいったい何なのか
5.この世のものはまるで存在しないのか?
●『ここで非常に重要なことに触れよう。「現実」と「情報」という概念は互いから切り離せないということだ。私たちは現実について知っていること、すなわち情報を使わなければ、現実について語ることすらできない。物理学の歴史において重大な進歩が遂げられたのは、それまで疑う余地なく別物だと信じられてきた概念を切り離すのをやめたときだったという例が目撃されてきた。たとえば相対性理論において「空間」と「時間」という概念を分けるのをやめて、両者を「時空」という一つの概念に統一したのは、重大な進歩だった。「情報」と「現実」という二つの概念も同様だ。しかしこの二つの概念がコインの裏表のようなものとされる未来がどんなものになるのかについては、まだ答えはほとんど出ていない。
アインシュタインが量子力学を批判せずにいられなかったのはなぜか、なぜ量子もつれを「不気味」と言ったのか、その理由が今、明らかになる。彼の考える事実にもとづいた実在とは、私たちとは無関係に本質的な特性を備えている。このように現実と情報が切り離されているというとらえ方は、量子物理学では擁護できそうにない。
結論すれば、私たちの世界は古典物理学が認めていた世界より自由である。その一方で、私たちは古典物理学的世界にいたときよりも強固に世界と結びついている。』
疑問
●疑問だらけの混沌とした状態ですが、特に最後の『私たちは古典物理学的世界にいたときよりも強固に世界と結びついている。』とは「何だろう?」と思いました。
おそらくこれは“量子もつれ”に端を発する「“現実”と“情報”という概念は切り離せない」ということではないかと思います。
そこで、少々乱暴なのですが『古典物理学的世界にいたときよりも強固に世界と結びついている』とタイプして検索してみました。こうして見つけたものが以下の2つになります。何も語ることはできないのですが、面白そうだなと思ったのでご紹介させて頂きます。

こちらの資料はPDF4枚です。
究極の光と物質の相互作用「超強結合」
『光と物質の相互作用は「量子光学」において中心的な概念として研究が進められてきた。量子光学は、微視的な視点から光を捉える、つまり量子力学的な立場から光と物質との相互作用を解明する学問だ。量子光学では、光を光子の集まりとして捉え、光と物質の間のエネルギーの交換を探求するという側面がある。これまでに量子光学の基礎研究によってもたらされた知見は、レーザーや光通信などに関連する、現代では欠かすことのできない技術の基盤を確立してきた。その量子光学において新たなフロンティアとなっているのが、光と物質における「超強結合」と呼ばれる相互作用である。』

『量子力学の世界では、古典物理の世界を構成する中性子、電子、光子といった微粒子について、一つ一つの粒子か、少数の粒子が研究されています。というのも、超微小な世界では、粒子が全く異なる振る舞いをするためです。ですが、研究されている粒子の数を増やしていけば、最終的にもはや自動的に量子として振舞うことをしない数の粒子となり、私たちの日々の世界と同じような古典物理学のものとなります。では、量子力学の世界と古典物理学の世界の境界線というのはどこにあるのでしょう。この度、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究チームは、この問題への解答を探る過程で、量子力学の現象と考えられていたものが古典物理学で説明できることを示しました。本研究結果はPhysical Review Lettersに報告されました。』
『研究チームは特に、多くの粒子で構成されている物質と、光との相互作用における強結合に関心を持っていました。強結合は、相互作用により、光と物質が双方とも影響されるときに起きる現象です。通常、光と物質が相互作用をする際、光は影響を受けません。例えば、海に浮かぶボートは波の影響を受けますが、海はボートの存在による影響をあまり受けません。強結合というのは、ボート(物質)と波(光)が両方とも相互作用によって強く影響される点で興味深いのです。一般的にこの現象は、量子効果として考えられてきましたが、研究チームは、量子力学の世界と古典物理学の世界の境界を調べることにしたのです。』

『このようにしてチームは、実験で観察した強結合の現象を説明する古典物理学モデルを作り上げることに成功しました。この発見は、大量の粒子における強結合は、以前から考えられていたように量子力学の世界ではなく、古典物理学の世界に分類される可能性があることを意味します。』
ご参考:量子コンピュータ
個人的に興味があるのは、やはり身近な印象の「量子コンピュータ」です。
探してみると非常に多くの動画があるのですが、”半導体で量子コンピュータを作ろう”は理研さまが作成された動画で6分38秒と短くお勧めです。量子ビットが超電導ではなく半導体で作れれば確かに凄い画期的なことだと思いました。
パウリとユング2
第7章 シンクロニシティへの道 ~ユングとパウリの対話~
・『自然界を1つの理論で表す統一的理論の必要性など、多くの点でアインシュタインに賛同するパウリだったが、量子力学に関しては全く異なる見地だった。彼にしてみれば、量子の世界の織りなす相補性や不確定性、量子もつれなどの真新しい現象は、自然の真理そのものだった。事実、それらの現象を貴重な契機として、自然に潜む対称性などの数学的結びつきが明らかになった。加えて、観測による影響を主題とする量子観測理論により、自然現象だけではなく人間の意志を踏まえた大局的な見地が形成されつつあった。
このような時代背景に、現代物理学に関心を持ち、普段からその意識を認めるユングにとって、パウリは精神と物質の関係性について意見交換する格好の相手だった。対話を通じて、科学的考察を深めることができたからである。自然界における対称性の役割だけではなく、いわゆる超常現象と呼ばれる奇妙な出来事にも話題は及んだ。ただしパウリは、自らの超常現象への関心を他の物理学者に話そうとはしなかった(同じく超常現象に興味を持つ友人、パスクアル・ヨルダンだけは別だった)。一貫して自然界に客観性を求めるアインシュタインの存在が、その消極的な姿勢に拍車をかけた。当然、観測の影響を考慮すべきだとアインシュタインに助言することもなかった。そして、パウリの推察通り、アインシュタインは生涯、量子力学の表す奇妙な世界を自然の真の姿として認めなかったのである。』
●もつれを繙く
・アインシュタインは一般相対性理論をもとに、あらゆる自然現象を網羅する統一場理論を完成させ、量子力学の奇抜な現象を数学的表現のあくまで例外として記述しようと考えた。
・電気力と磁気力を統合したマクスウェルの電磁力[磁界と電流の相互作用で発生した力]へと飛躍し、さらにマクスウェルは電磁気力と重力との間に共通点を見出した。
・統一的理論の足掛かりとなる可能性を指摘するものだったが、マクスウェルがその構築に挑むことはなかった。
●精神の偽らざる姿 [カール・グスタフ・ユング]
・ユングがフロイトに出会ったのは1907年、それから6年間、二人は協力する中で二人とも無意識の中に重要性を見出した。しかし、精神分析の反対派に対するフロイトに耐えられず袂を分けた。フロイトは幼少期の性的傾向を重視したが、ユングは「集合的無意識」に着目して、無意識の動機付けを説明した。集合的無意識とは集団に共通する意識のことで―後に「元型」と呼んだ―、源泉は1つだが、一人ひとりの人間によって個性化する。元型の例として、童話や民族伝承、道徳的禁忌、象徴的表現、宗教儀式、精神的理想などがあげられる。
・ユングは超自然主義にまつわる文献の研究に乗り出すと、錬金術やグノーシス主義、新プラトン主義の各派、仏教、ヒンズー教などの書物を精読し、神話学の第一人者となった。そして、様々な超自然主義の間に、超越的真理の探究や神との一体化への渇望といった共通点を見出し、分析心理学という新たな深層心理学の学派をスイスに立ち上げた。
・ユングが後に心理学と物理学の両面から精神と肉体を統一的に考えたのは、アインシュタインとの数回にわたる対話が主な動機となった。
●シンクロニシティの登場
・ユングの心理学は、一人ひとりの精神は代々受け継がれる共通の無意識的体験がつくる「客観的精神」の個々の解釈である。様々な宗教や信念体系に通底する思想は、そのような世代を超えた精神の源に由来すると考える。母親への思慕や、蛇や暗闇に対する恐怖心、人殺しを非とする倫理観などはいずれも普遍的体験といえる。
・ユングによると男性の無意識には女性らしさを象徴する「アニマ」と呼ばれる女性像の元型が根ざす。アニマは普段、意識的に抑制されており、心理療法によって解放される。対して、女性の無意識に潜むのは、アニムスと呼ばれる男性像の元型がある。ユングは当時の古い価値観に従って、アニマをむき出しの感情に、アニムスを洗練された知性に関連付け、両者のバランスこそが性別を問わず肝要であると説いた。
・ユングの理論は推測の域を出ず、元型という概念を裏打ちする科学的証拠はない。存在するのは、事例研究による間接的な証拠だけである。しかし、人間の精神に関するユングの考察は、歴史や哲学、また文化の面において、非常に示唆に富む内容といえる。
・ユングは非因果的連関の原理を指して、シンクロニシティという言葉を使った。そして、意味ある偶然の一致は、期せずして現れる自然の真理だと強調した。
・『源を一にする非因果的連関というユングの概念から、量子のもつれの並行性―ほぼ同時代に認知された現象―を連想しても、何ら不思議はないだろう。2つの粒子が量子状態を共有するならば、双方が離れても物理量は相関すると、量子もつれは語るのである。だがそうはいっても、ユングの非因果的連関と量子もつれとの間には、決定的な違いが存在する。量子もつれが設定に万全を期す数々の実験によって実証されたのに対して、ユングの非因果的連関は根拠に乏しく、心理学界で幅広い支持を得るには至らなかった。人間の精神において代々伝承される集合的無意識の存在は今もなお、神経科学によって示されていない。
しかし、局所性や因果性を凌駕するユングの世界観は、彼が積極的に物理学者との交流を図ったおかげで、現代科学に広く浸透した。アインシュタインとの夕食をきっかけに芽吹いた彼の物理学への興味は、パウリとの出会いによって一気に花開くのである。』
●パウリの受難
・パウリはゾンマーフェルトに神童として将来を嘱望され、「排他原理(4つ目の量子数であるスピンの発見にによって証明された)」の確立や、ニュートリノの予想(当時まだ観測されていなかったが、ベータ崩壊の解明に大きく寄与した)といった業績により、天才物理学者としての名を確たるものにしていた。しかし、1930年の終わり、極度の精神的不調に苦しんでいた。
・相次ぐ苦難の始まりは、父親の不貞が原因で敬愛する母親が48歳の若さで自殺したことである。そして、その父親はパウリと同年代、20代後半の女性と結婚した。
・1929年5月にはカトリック信仰を捨て、教会を正式に脱退した。同年12月に結婚するも1年もたず1930年11月に離婚、パウリのパートナーは昔から親交があった特に実績のない化学者と一緒になり、この事実もパウリを消沈させた。
・パウリとユングの出会いは、パウリの状態を見かねた父親がユングによる心理療法を勧めたからであった。ユングは当時、パウリが勤めるETHで頻繁に講師を務めており、パウリはユングの理論について聞き及んでいた。また、パウリ自身も何とかしようと考えていたため、父親の提案に従い診療を受ける決断をした。
・『夢や幻想の役割とあわせて、集合的無意識の精神への影響について研究するユングは、優れた記憶力をもつ被験者を探していた。また、シンクロニシティの体系化については、アインシュタインの時空という力学的概念を土台に、物理学者の意見を参考にしながら、考察を掘り下げていた。したがって、複雑な夢を見て、その内容を明確に記憶し、なおかつ著名な量子力学者の肩書を持つ“患者”パウリは、まさしくユングの探し求める相手だったのである。
ただ、精神を病んではいるもののパウリは有能な学者である。分析を通じて秘匿情報を共有することになる可能性があるため、ユングは情報管理に注意を払った。彼の心理療法はフロイトのそれと比べてはるかに積極的に患者と関わる診療として有名だった。そのため、情報操作や行動介入などと、他の精神科医から非難されないよう万全を期した。夢の回想に介入したり影響を与えたりしないように忠告した上で、パウリをローゼンバウムにまず担当させたのも、その点を踏まえてのことだった。本人以外による記述も含め、パウリの夢の記録は最終的におよそ1300にのぼり、ユングはすべてを研究資料として(個人情報の保護を徹底しつつ)活用した。ユング研究で知られるビバリー・ザブリスキーは、冗談まじりにこう記している。「読者のみなさん……、ヴォルフガング・パウリについてユングの知り得たこととは、普段の姿でも物理学の実績でもなく、彼の無意識なのです」』
・『知性のみを優先するあまり、アニマの象徴する感情的な自己が抑圧されていると判断したユングは、本人にそう認識させることを治療の本筋とした。その甲斐あってパウリは、自らの偏った生き方を自覚するようになる。そして2年以上に及ぶ治療の中で、精神的な落ち着き―少なくとも一時的な安定―を徐々に取り戻すようになった。ひいては、1934年にロンドン在住のフランシス力(フランカ)・バートラムと再婚を果たし、平穏な日々を過ごすようになった。自ら治療を終える決断を下したのは、その頃である。一時的ではあるが禁酒にも取り組むほど、精神状態は回復をみせた。パウリはもはや患者ではなくなったが、ユングとの親交はその後も続き、夢の内容を伝えることもあった。その中で2人は、自らの存在意義や元型とのつながりについて意見を交えた。
理論物理学の難題を解決し続けるだけの優れた数学力を考えれば、パウリの夢の中に幾何学的対象や抽象的符号が頻繁に登場しても不思議はなかった。その多くは直線と円が対称的に配置された図形だったが、ユングはそれらを元型の概念に照らして解釈した。数理物理学に根ざしたパウリの描写を、古代の象徴主義と結びつけて考えたのである。そのように類似の基本概念になぞらえることで、2人はそれぞれの研究分野の融合を図った。』
・『パウリによれば、世界時計の動きの調和によって心に安らぎが得られたという。自らが中心となって構築した原子モデルを彷彿させたのかもしれない。ユングにとって世界時計は、初めて出合う曼荼羅の立体図像だった。そして、世界時計をもとに、重要な元型の1つ―穏やか瞑想の象徴―と、現代物理学の時空との結びつきを想定した。はたして彼は、物理学への関心をますます強くしたのである。
パウリは普段、夢分析の被験者であることを他人に話そうとはしなかった。ユングが分析内容を書籍として著す時も、自身の名前を出さないとの条件で許可した(ただし、発刊協力者として名を連ねており、分析に関わっていることは明らかだった)。次第に強くする超自然現象への関心についても、表立って話すことはなかった。
しかし、最も信頼できる研究協力者であり友人でもあるパスクアル・ヨルダンだけは例外だった。ヨルダンだけには、超自然現象への情熱を打ち明けたのである。』
●超心理学と懐疑派
・ヨルダンは1936年、量子力学の入門書「直観的量子論」の最終章の内容はテレパシー実験の検証だった。ヨルダンは1930年代から超心理学に強い関心をもっていた。
・超心理学(非科学的な超自然現象とされる対象を研究する分野)は、生物学者であったアメリカのJ・B(ジョセフ・バンクス)・ラインによって創設されたばかりで物議を醸していた。ラインは1980年に亡くなるまで、自らの研究の正当性を訴え続けた。心理学ではその後、実験環境を統制や厳格な統計手法に一層重点が置かれるようになった。
●ノーベル賞
・最終的にパウリは、観測する側と観測される側―精神と物質―を統一的に表す必要があると信じるようになった。ユングはパウリの考えに賛同した。さらに、アインシュタインとの夕食やリヒアルト・ヴィルヘルムとの議論を経て、ユング自身もそのような理論を望みはじめていた。ユングは精神と物質との統一を「Unus mundus(ウヌス・ムンドゥス)」と呼んだ。
●研究所での洪水
※【パウリ効果】とは
『パウリとその俗に言う実験とは相性が悪かった。彼が実験施設に立ち入ったり、測定機器の近くを通ったりすると、装置に不具合の生じることがしばしばで、周囲から「パウリ効果」と恐れられたほど。機械は故障し、測定器は作動せず、現場に混乱を招くのである。事実、実験物学者のジョージ・ガモフはこう形容する。
「一流の理論物理学者たる者、精巧な実験機器に触れただけで機械に不具合をもたらす、と言われている。その言葉に照らせば、パウリは有能な理論物理学者だ。彼が施設を訪れただけで、装置は壊れ、誤動作を起こし、ひいては全く動かなくなったり、燃えたりするんだ」
最も有名な事件は、パウリが1950年2月、プリンストン大学を訪ねた時のことである。プリンストン大学のパーマー物理研究所の地下にある高エネルギー・サイクロトロン(円形粒子加速器)が火事になり、6時間以上燃えたのだ。もちろん研究所の建物には煙が充満し、あちこちがすすだらけとなった。パウリは現場ではなく、大学の敷地内にいただけだったが、その後やり玉にあげられたことは言うまでもない。』
・『ユング研究所を設立するにあたり、パウリ(当時、ノーベル賞受賞として多くの尊敬を集めていた)にも後援者としての協力を仰いだ。ユングに恩義を感じ、共同で研究する機会を増やしたいと考えていたパウリは、ユングの依頼を快諾した。
また、心理クラブにも招かれ、その年の2月28日と3月6日に講演を行った。パウリは会場で、フラッドやケプラー、そして元型に関する自らの見解を喜んで説明した。科学者にとって講演は、一般に、論文を著す前に自らの考察を整理する良い機会となる。彼は当時、「The Influence of Archetypal Ideas on Kepler’s Theories(元型的観念がケプラーの科学理論に与えた影響)」と題した長編論文を執筆中で、いずれ何らかの形で公表したいと考えていた。
ユング研究所の開所初日となった1948年4月24日、記念セレモニーが盛大に開催された。もちろん、パウリも来賓の1人として招待された。セレモニーはすべて順調に運び、盛況のうちに閉会するかに思われた。ところが……。
突然、会場に何かの割れる音が響き渡った。思いもよらないことに、棚に固定されていたはずの中国の高級花瓶が、勝手に落下したのである。花瓶は床に落ちて粉々に砕け散り、あたりは水浸しになった。ユング研究所は、まさしく洗礼を受ける格好となったのである。
さて、「パウリ効果」を覚えているだろうか?
姿を現しただけで実験装置を故障させる能力は、この頃にはすでに彼の特技として広く認知されていた。ただし、彼自身は、もはや軽く捉えることができず、いたって真剣に悩んでいた。
ドイツ語で「洪水」のことを「Flut(フルート)」という―Robert Fludd(ロバート・フラッド)の「Fludd」のドイツ語読みとほぼ同じ発音である。英語でも、洪水を意味する「Flood」と「Fludd」は、ほぼ同じ響きだ。パウリは会場で起きた些細な洪水と自らの研究との間に、意味ある偶然の一致を認め、驚愕した。単なる偶然の出来事だったかもしれない「パウリ効果」を、彼はユングの唱えた非因果的連関と結びつけ、もはや冗談とはみなさなかったのである。
フラッドとケプラーの理論と元型に関する考察を論文にまとめる中で、パウリは開所式典での奇妙な出来事について深く考えるようになった。そしてユングに対して、シンクロニシティに関する考察を掘り下げ、整理した上で論文に著すことを勧める。ユングの考察に大きな意義を見出そうとしたのである。
ノーベル賞を手にしたパウリに、それ以上自らの才能を示す余地は残されていなかった。それでも彼を駆り立てたのは、アインシュタインと同様、世界を統べる統一的理論への挑戦だった。長きにわたるユングとの親交が、彼をその挑戦へと誘ったのである。』
●すべては2と4のもとに
・ユングとパウリが生んだ功績は、1950年代はじめに、双方の研究分野が融合を見ることである。ユングはパウリのおかげで確率的表現や観測による影響といった、量子力学の表す内容に精通するようになった。逆にパウリはユングのおかげで、神秘主義や数秘術、そして古代の象徴主義の研究に心を奪われるようになった。
・ユングとパウリはピタゴラス学派と同じく、特定の数に価値を見出した。その1つが「2」だった。波と粒子、観測者と観測対象といった二重性を自然の真理としたボーアの相補性の原理は、両者にとって革新的な概念だった。
・ボーアはオランダ哲学者セーレン・キルケゴールの著作(「あれか・これか」など)の中の二分法に感化されたとみられ、家紋に太極図を取り入れている。

画像出展:「ウキペディア」
『偉大な功績により、デンマーク最高の勲章であるエレファント勲章を受けた時、「紋章」に選んだのが、陰と陽、光と闇の互いが互いを生み出す様を表した東洋の意匠、太極図であったことからもうかがえる。』
・パウリは、男性は己の女性らしさ(アニマ)を、女性は己の男性らしさ(アニムス)をそれぞれ抑制しているというユングの主張を支持するようになった。
・パウリは荷電共役対称性(正負の電荷の変換に伴う対称性)、パリティ対称性(鏡像対称性)、時間反転対称性などの二重性を物理学において探求する契機となった。
・数に関して二重性以上にパウリとユングが重視したのが「quaternnio(クワテルニオ)」だった。ラテン語で4つ1組の意である。その概念はエンペドクレスの四次元素説に源を発し、そこから錬金術や、ピタゴラス学派のシンボルであるテトラクテュス(1から4までの整数を構成要素とする三角形)へと派生した。
●非因果的連関の原理
・ユングとパウリは1952年、2人の研究の集大成として共著、「自然現象と心の構造」を発刊した。
●関係の終焉
・二人の長きに渡る往復書簡は突如、途絶えた。
・パウリはヨルダン以外には自らの神秘主義への興味を他の物理学者にあまり話さなかったのは、ユングの話を無条件に信じていたわけではなかった。いかなる理論にも厳しい目を向けるパウリにとって、ユングの理論も例外ではなかった。
・パウリはボーア宛ての書簡で次のように書いている。『ユングの思想は、フロイトに比べて幅広い領域を対象としますが、その分、明確さに欠けます。最も不満を覚える点は、「精神」という概念が、明確な定義のないまま曖昧に用いられていることです。論理的にも矛盾が認められるのです。』
・パウリとユングの2人の距離が離れたのは、ユングのUFOに対する強い関心も一因だった。
・当時パウリは、ハイゼンベルクと共に、統一場理論の構築に力を注いでいる最中であり、加えて、膵臓がんと診断される前年だったことから、体力の衰えが見え始めていた。
第8章 ふぞろいの姿 ~異を映す鏡のなかへ~
●相互作用のなす業
・『一般相対性理論と量子力学は、それぞれ1910年代半ばから1920年代半ばにかけての10年間に誕生している。一般相対性理論は、時空を主な舞台として、その歪みによって光や粒子の進行方向を定める。量子力学は、特にハイゼンベルクの提唱した解釈において、抽象的なヒルベルト空間[二点間の距離が公式で与えられる三次元空間を無限次元に拡張したもの]を中心に展開する。実験施設の研究員などのような合理的な考えの科学者であれば、いずれも物理学を理解する上で欠かせない理論であるとの認識だろう。理論物理学の重要な分野の1つとして、相対論的な場の量子論―一般相対性理論と量子力学のそれぞれの枠組みを維持しながら統合を図る理論―が存在する所以である。双方の原理を損なうことなく2つの理論の統合を図る試みは、ボーアの主張に端を発する。古典的世界(高速度や強力な重力場などの極限状態においても相対性理論に従う世界)にいる人間が微視的世界に介入する観測という行為の重要性を強く訴えたのがボーアだった。
しかし、アインシュタインやハイゼンベルク、パウリといった巨匠たちが追い求めたのは、微視的世界から人間の日常的な世界、そして宇宙規模の世界までを、単純な原理によって網羅する横断的な理論だった。アインシュタインは、非量子的な手法で(古典的な一般相対性理論を拡張して)、量子力学の原理を説明しようした。対して、全く異なる方法を独自に考案したのがハイゼンベルクだった。彼は、対称群となるヒルベルト空間のエネルギー場に適合な条件を与えることで、自然界の様々な相互作用の再現を目指した。』
第9章 現実へ挑む ~量子もつれと格闘し、量子飛躍をてなずけ、ワームホールに未来を見る~
・『パウリの早すぎる死から数十年、特に1960年代から1980年代にかけては、素粒子物理学や場の量子論、量子測定理論に、極めて画期的な発見がもたらされた。パウリが生前、掘り下げた代表的な概念の一部が、物理学研究の中心を担うようになり、対称性の役割や、(ユングと共に目指した)非因果的相関の体系化に関する研究が主流になったのである。後者に関しては、量子もつれの限界や可能性を検証する実験が盛んになっていった。』
●コズミック・ベル・テスト [アントン・ツァイリンガー]
・オーストリアの物理学者アントン・ツァイリンガーはベルの不等式[量子力学において「隠れた変数」の存在を前提に書かれた関係式。この不等式が成立しないとすれば、量子力学では隠れた変数は存在しないということが証明される]を検証するベル・テストだけでなく、量子テレポーテーションに関して画期的な実験を行ったことでも広く知られている。量子テレポーテーションとは、離れた場所において量子状態を再現することである。
・「コズミック・ベル・テスト」は最新の観測機器を使って太占の光を分析するものである。
・2017年、オーストリアで1.6㎞以上離れた場所に2つの望遠鏡を設置し、異なる恒星の光を観測。それぞれの光から検出される色―赤と青―と、偏光器の設定を連動させ、ベル・テストを実施した。その後、実験設計が改良され、地球から数十億光年離れたクエーサーの光を使って再度測定が行われた。結果はまたしても、ベルの不等式は成立しないことを明示するものだった。アインシュタインではなくボーアの主張の正しさが認められた。
●量子の挙動の実用化へ
・パウリとユングの2人による対話は、厳密な意味で科学的とは言えなかったが、二重性という自然界の中心的概念を導いた。因果的な相互作用と、非因果的な相関。両者を同時に説明する統一的理論が現れた時、人類は確かな英知を手にするだろう。
終章 宇宙のもつれを繙く
●パウリとユングが残したもの
・『物理学の潮流において、ユングの果たした役割は決して小さくないだろう。たしかに、彼の提唱した元型や集合的無意識といった概念は、独創的であり、また魅力的でもあるが、科学的に実証されているわけではない。夢に現れる象形が、代々受け継がれてきた原子的な型である証拠はどこにもないのである。よしんば東洋哲学や錬金術、神秘学を学んだことがあるならば、曼荼羅や錬金術記号などの象形が夢に出てきても不思議はない。夢に現れなくとも、日常で目にする記号から、そのような結びつきを連想するとも考えられる。漫画書籍の熱心な収集家が、ヒーローや悪役の夢を見ると同じである。しかしながら、ユングは夢分析を通じて、自然の摂理に対するパウリの優れた洞察力に触れた。パウリと繰り返し相対したことで、自らの物理学的知識をより豊かにすると同時に、パウリの発想にも示唆を与えたのである。
したがってユングが提唱し、パウリが掘り下げた「シンクロニシティ」という概念は、心理学だけで背景を語ることはできない。あくまで思弁的な考えで、厳格に管理された実験の裏打ちがあるわけではないが、革新的な進展を見せる量子力学と擦り合わせれば、新たな宇宙観につながるとも考えられる。実現すれば、厳格な因果律と純然たる確率が支配する世界の向こう側が覗くかもしれない。非因果性の統べる世界が、である。』
感想
『源を一にする非因果的連関というユングの概念から、量子のもつれの並行性―ほぼ同時代に認知された現象―を連想しても、何ら不思議はないだろう。』ユングが物理学に魅せられたのは、まさにこの事だったのだと思います。
一方のパウリは、ユング研究所の開所初日となった1948年4月24日、記念セレモニーでまたしても【パウリ効果】に遭遇することになります。
そのパウリは、「シンクロニシティに関する考察を掘り下げ、そして、ユングの考察に大きな意義を見出そうとしたのである」とされています。
パウリはユングの心理学を全て受け入れていたわけではありませんでした。しかし、パウリの心を度々揺さぶっていた【パウリ効果】という事件が次第に大きくなり、ついには歴史に名を遺した物理学者と心理学者を結びつけたのだと思いました。
“科学と非科学”をより分けるのは人間の英知が決めることだろうと思います。しかしながら、宇宙規模の世界(マクロ)と量子の世界(ミクロ)において人間が認知できることは一部です。その意味ではシンクロニシティを完全に否定することはできないと思います。
ご参考1:Youtube“【量子力学】この宇宙の真実知りたくない人は見ないでください...『シンクロニシティ 科学と非科学の間に』by ポール・ハルパーン”(開始~8分30秒の中で「量子もつれ」を解説されています。なお動画は19分です)
ご参考2:Youtube“【簡単解説】数式なしで理解したい!「量子テレポーテーション」や「量子もつれ」の原理や仕組み、方法を初心者にも分かるように解説!” (9分33秒~13分33秒に量子テレポーテーションについて解説されています)
パウリとユング1
パウリとは量子力学の巨匠の一人、ヴォルフガング・パウリのことです。一方、ユングはフロイトと並び称される偉大な心理学者のカール・グスタフ・ユングのことです。
ユングが晩年、物理学に傾倒していた事実は、ブログ“ユングと共時性”の時に知っていたのですが、ユングと接点のあった物理学者がパウリであり、しかも「往復書簡集」として残っているほど、深いつながりがあったことに大変驚きました。
タイトルの“シンクロニシティ”ですが、お恥ずかしい話、当初、気づかなかったのですがこれは“共時性”のことです。内容は物理学の歴史の物語からマクロな宇宙やミクロの量子を中心に、偉大な科学者の足跡が書かれています。私が最も知りたかったことは、このパウリとユングの関係やどんな事に取り組んだのかということでした。
第9章、「量子の挙動の実用化へ」の中で、以下のようなことが書かれています。
『パウリとユングの2人による対話は、厳密な意味で科学的とは言えなかったが、二重性という自然界の中心的概念を導いた。因果的な相互作用と、非因果的な相関。両者を同時に説明する統一的理論が現れた時、人類は確かな英知を手にするだろう。』
ブログは何とか理解でき、印象に残った箇所をご紹介していますが、全体的にはつかみどころのない漠然としたものになっていると思います。
目次
推薦の言葉
量子論の発展に寄せて 福岡伸一 (生物学者)
序章 自然界のつながりを描く
第1章 天空へ挑む ~古代の人々が描いた天界像~
●太陽への信仰
●神殿の谷の夜明け
●宇宙の構成要素
●自然界の隠された光
●遅々として進まない太陽の光
●運動の世界観
第2章 木星からの光が遅れる
●富と知
●天文学の復活
●禁断の惑星
第3章 輝きの源を辿る ~ニュートンとマクスウェルによる補完
●遠隔操作
●ラプラスの悪魔とスピノザの神
●疾走する波と探求心
●金科玉条を探す
●幻の終の棲み処
第4章 障壁と抜け道 ~相対性理論と量子力学による革命~
●光が持つ2つの顔
●相対的な真実
●OPERAの幻
●宇宙を織りなす
●原子の中を覗く
●デンマークからの光
●魔法の数字
第5章 不確定という世界 ~現実主義からの脱却~
●不思議の国のアルベルト
●苦難の道のり
●現実と行列式
●非公開の舞台
●物質波
●母なる光
第6章 対称性の力 ~因果律を超えて~
●対称に次ぐ対称
●保存則が表すもの
●超排他的な住人
●スピン:粒子の謎めいた性質
●姿を見せない粒子
●もつれた経緯
●超自然現象への抗い
第7章 シンクロニシティへの道 ~ユングとパウリの対話~
●もつれを繙く
●皮肉屋兼毒舌家
●精神の偽らざる姿
●シンクロニシティの登場
●パウリの受難
●超心理学と懐疑派
●ノーベル賞
●研究所での洪水
●すべては2と4のもとに
●非因果的連関の原理
●関係の終焉
第8章 ふぞろいの姿 ~異を映す鏡のなかへ~
●ウー夫人の情熱
●ニュートリノという名のサウスポー
●超絶の力
●統一を巡る課題
●相互作用のなす業
●統一への狂騒
第9章 現実へ挑む ~量子もつれと格闘し、量子飛躍をてなずけ、ワームホールに未来を見る~
●ジョン・ベルによる判定試験
●光子の逆相関やいかに
●コズミック・ベル・テスト
●量子の挙動の実用化へ
終章 宇宙のもつれを繙く
●因果律の限界
●光速の因果律を超えて
●パウリとユングが残したもの
●セレンディピティ v.s. 科学
●慎重に非因果性を受け入れる
謝辞
量子論の発展に寄せて 福岡伸一 (生物学者)
・「量子もつれ」は“entanglement”と表現されるが、科学的な言葉で表現すると、“離れて存在している2つの物体が、互いに他のことを認識しあっている”ということである。
序章 自然界のつながりを描く
・『量子もつれは、相互作用ではなく、粒子間の相関である。そのため、因果律に厳格に則った伝播(一般の相互作用が光速以下で連鎖する伝わり方)より速く結果を伝えることができる。つまりそれは、自然界に2種類の「伝達ルート」があることを意味する。光速を最高速度とする伝達経路と、人間の観察と同時に相関を示す量子相関という経路だ。』
・『近年、量子テレポーテーションや量子暗号の分野で革新的な成果を上げている。特筆すべきは、“量子もつれ”の現象を利用して、途方もない遠隔地へと光子の量子状態を転送した点だ。現在は中国の衛星「墨子(Micius)」へ量子状態を送り、解読不能とも言われる量子もつれを活用した量子暗号システムの構築に取り組んでいる。一連の研究が言わんとするところは、量子もつれなどの非因果的相関の重要性と実用性の高さである。』
※ご参考1:“中国の量子通信衛星チームが米科学賞受賞”
※ご参考2:“量子通信・量子暗号・量子中継・量子ネットワーク”
第3章 輝きの源を辿る ~ニュートンとマクスウェルによる補完
●幻の終の棲み処
・19世紀の科学界では自然の振る舞いや人間の意志はすべて科学的に説明できると考えられた。
・いずれ非科学的な思想は淘汰され、予言や亡霊、悪霊、天啓などの余地はなくなるとの見方が大勢を占めた。
・自然現象は理論的に突き詰めれば、原因と結果の連鎖によって記述されると考えられた。
・因果関係を説明できないものは、その考察は希望的観測や迷信であるとされた。
・超自然現象を信じる反対勢力は、科学によって説明できる立場をとった。そして、超常現象の科学分析と精神世界を対象とした研究を図る団体が生まれた。
第4章 障壁と抜け道 ~相対性理論と量子力学による革命~
・19世紀末の科学は厳格な因果律に基づく決定論へと進んでいた。
・20世紀になると原子内部の不可思議な世界が量子力学で明らかになると摩訶不思議な不確定性原理などが登場した。
・相対性理論は因果的な作用の限界が明らかになると同時に、空間と時間の密接な関係が示され、物理学界に革命の波が押し寄せた。
●宇宙を織りなす [アルベルト・アインシュタイン]
・『自然は相対性理論を裏付ける形で、遠隔的ではなく局所的な重力の姿を露わにした。よってアインシュタインは、遠隔作用という概念に否定的な立場を生涯貫くことになる。彼は原因と結果の直接的な連鎖によって宇宙は構成されているとの見方を常に理論の柱とした。その見地に反する対象は彼にとって、偽りの現象か、もしくはまだ実証されていない因果的作用に過ぎなかったのである。』
●デンマークからの光 [ニールス・ボーア]
・『マンチェスター大学と、その後所属したコペンハーゲン大学での研究で、ボーアは太陽系を彷彿させる原子モデルをつくった。正に帯電する原子核が「太陽」のように中心に位置し、その周りを負に帯電する電子が「惑星」のごとく回るという原子像である。全体を結びつける源は、重力ではなく電磁気力だ。その上でボーアは、楕円軌道で運動する惑星とは異なり、電子の軌道は真円になるとした。』
・『ボーアは、当時実測されていた水素などの基本原子のスペクトル線[原子が放射または吸収する光の電磁波]が、原子モデルで再現される必要があるとも考えた。水素の吸収スペクトルと放出スペクトル(分光器で観測される吸収する光と放出する光の色)は、ヨハン・パルマーやセオドア・ラインマン、フリードリッヒ・パッシェンなどの分光学者たちによって測定され、水素原子固有の周波数がすでに判明していた。いずれのスペクトルも、色が飛び飛びの虹のように特定の周波数の色だけを残し、その他の色は消えていた。そして、原子固有の周波数には数学的な規則性が認められた。なぜ、特定の色を現して、他の色を現さないのだろうか?ボーアは直観的に、電子は普段、安定した軌道上に存在し、特定の振動数の光を吸収したりするのではないかと推測した。光を吸収すればすぐさまエネルギーの高い軌道へと遷移し、放出すればエネルギーの低い軌道へと遷移するのではないか、と。』
・『ボーアは、原子の不連続のスペクトルをモデル化するためには、電子の軌道が連続的ではなく、離散的でなければならないと考えた。したがって、1つの軌道から別の軌道への電子の遷移は、連続的な変化ではなく、一瞬の跳躍であるとみなした。』
・『電子がある状態から別の状態へと自発的かつ瞬間的に移動する、という量子跳躍の概念は、アインシュタインとミンコフスキーによって丹念に描かれた相対性理論の時空図と対極をなす考えだった。いわば、厳格に決められた因果関係に対して、電子の自由奔放が際立っていたのである。[「電子があたかも、どの軌道に移るべきあらかじめ知っているかのようだ」by アーネスト・ラザフォード]』
『アメリカの物理学者リチャード・ファインマンが粒子の経路の不確定さを時空に組み入れ、量子力学の世界と時空図を結びつけるのは1940年代に入ってからのことである。それまで、相対性理論における時空と、量子力学における相関は共通項のないそれぞれ独立した概念に過ぎなかった。』
●魔法の数字 [アルノルト・ゾンマーフェルト]
・『ゾンマーフェルトが熱心に研究したのは、主要な磁場(コイルを通電してつくる電磁石による磁場など)に原子を置いた時に現れる現象だった(1897年にオランダの物理学者ピーター・ゼーマンによって発見されたため、ゼーマン効果と呼ばれる)。磁場に原子を置くと、原子の放出スペクトル線が分裂するのである。本来であれば、特定の色を持つ1本の線であるべきところに、それぞれわずかに色の異なる複数の線が現れる。スペクトル線が虹の一部のごとく分光する理由は、まるで判然としなかった―その答えを導いたのがゾンマーフェルトだった。
「ゼーマン効果」は、ボーアの単純な「太陽系」電子モデルの一般化に大きく貢献した。その研究を契機に、原子核の周りを電子が円を描いて運動する原子像は、量子数などの物理量を持つ、特徴豊かな立体的な姿へと発展したのである(電子数が奇数の原子特有のスペクトル線分裂、つまり「異常ゼーマン効果」の研究が原子モデルの一般化を実現させた)。この原子モデルの進歩によって、ミクロの世界の現象に関して、より正確に予想できるようになった。ひいては、量子世界に潜む多様な現象を明らかにし、量子もつれなどの非因果的な作用の存在が判明する。それゆえ、ゾンマーフェルトの研究は、ボーアの初歩的概念から量子力学確立までの経緯において、貴重な橋渡し役を演じたといえるだろう。と同時に私たちを奇妙な世界へと導いたのである。』
第5章 不確定という世界 ~現実主義からの脱却~
●母なる光
・量子力学の哲学を疑問視する声はあるが、その有用性は広く認められており、長きに渡って未解決の問題さえも、量子力学を頼れば解決への道筋が見えてくる。加えて、理論の弾き出す数字は極めて正確である。
第6章 対称性の力 ~因果律を超えて~
●超排他的な住人 [ヴォルフガング・パウリ]
・論理的思考に長けたパウリは数字に秘められた謎の解明に傑出した才能をみせた。また、数秘術や対称性に深く魅了された横顔もパウリを語る上で見逃がせない点である。後年、哲学的考察に傾倒するようになってからは、ヨハネス・ケプラーの影響を受け、数字に隠された規則性から自然法則を導こうとした。
・パウリの提唱した「排他原理」の原型となる概念に初めて言及したのは1924年12月であった。その「排他原理」は1945年、ノーベル物理学賞を受賞した。
●スピン:粒子の謎めいた性質
・ドイツの物理学者のクローニッヒは自転によって電子が小さな電磁石のように働き、外部の電磁場と相互作用すると考えた。その後、1925年オランダ人物理学者のウーレンベックは、外部の磁場と相互作用するのは電子が自転するためだと推測した。発表された論文は完全とは言えなかったが、実際の現象を予測するため、スピンという概念は広く受け入れられた。
現在でいうスピンは、単なる自転とは異なる概念を指す。電子が光速を超える速度で回転するのは不可能である。これは外部の磁場との相互作用がコマの回転現象と似ているということで、電子が実際に自転しているわけではない。
●姿を見せない粒子
・パウリが予想したニュートリノは1956年、カワンとライネスという二人の物理学者によって観察された。発見されたのはベータ崩壊に関わる電子ニュートリノで、その数十年後には、ミューニュートリノとタウニュートリノという2つのニュートリノも発見された。
●もつれた経緯
・『重力の本質を見抜けなかった古典力学により、歴史の闇に葬られようとしていた。だがその後、量子力学によって救われた―力の作用を介さない相関として。遠く離れた2つの粒子間において、切っても切れない相関を存在するのである。
シュレーディンガーはそのような状態を「もつれ」と呼んだ。量子力学でいう「もつれ」とは、多粒子系―ヘリウム原子の基底状態にある対電子の系など―において、任意の粒子の物理量が自ら以外の粒子の物理量と相関する状態をいう。興味深いことに、この「量子のもつれ」は物理的な距離を意に介さない。実験を重ねれば重ねるほど、「量子もつれ」を認める2点間の距離は広がるばかりである。原子の世界に留まらず、一方が河川を飛び越え、宇宙空間に至っても、他方との相関は変わらないのだ。「量子もつれ」は、決して抽象的概念ではなく、現実において極めて有用性は高い。人間が目にすることのなかったであろう物質の状態を生み出すからだ。たとえば、いずれも超低温化で出現する。全く滑らかに流れる粘性のない超流体や、完全に電導する電気抵抗のない超伝導体がそうである。』
怒りについて
予想通り難解な本でした。
『本書は、人間の本性の一つともいうべき「怒り」をめぐり、当代随一の哲学者たちが、議論を戦わせた記録である』とのことです。
何故、この本を買ったのか。それは万病の元であるストレスの中でも“怒り”は特に注意を要するものだという話を聞いたためです。また、以前、『サーノ博士のヒーリング・バックペイン』という本を拝読したことがあったことも、“怒り”という感情を深く知りたいと思った理由です。
なお、同様なタイトルの本には、『腰痛は<怒り>である』や『心はなぜ腰痛を選ぶのか』があります。これらの本に共通している理論はTMS(緊張性筋炎症候群)理論というものです。TMS理論に関しては以下のサイトが参考になると思います。

『TMSジャパンは、ニューヨーク大学医学部のジョン・E・サーノ教授が発表したTMS(Tension Myositis Syndrome:緊張性筋炎症候群)理論を出発点に、腰痛にまつわる迷信や神話の犠牲者、クワッカリー(健康詐欺・インチキ療法)の被害者、ドクターショッピングを繰り返す腰痛難民をひとりでも減らすため、 世界各国が発表している「腰痛診療ガイドライン」の勧告に則した、腰痛の原因と治療に関する根拠に基づく情報を提供しています。』
特段“怒り”についての知識や考えもなく、哲学者の先生の文章は次元が違うものであり、さらに本書が先生達の色々な考えを論じる場となっているため、この本がどんな本なのかを説明することは困難です。そこで、本書の概要をお伝えするには、最後の「監訳者解説」をご紹介させて頂くのが良いと判断しました。
その後、怒りとは何か、何が問題なのか等についてまとめ、そして、この怒りに対してどのように向き合うのが望ましいのかを考えてみました。
目次
編集者より
レイチェル・アレックス
第1部 問題定義
怒りについて
アグネス・カラード
第2部 応答と論評
暴力の選択
ポール・ブルーム
損害の王国
エリザベス・ブルーニッヒ
被抑圧者の怒りと政治
デスモンド・ジャグモハン
怒りの社会生活
ダリル・キャメロン
ビクトリア・スプリング
もっとも重要な事
ミーシャ・チェリー
なぜ怒りは間違った方向に進むのか
ジェシー・プリンツ
復讐なき責任
レイチェル・アックス
過去は序章にすぎない
バーバラ・ハーマン
道徳の純粋性への反論
オデッド・ナアマン
その傷は本物
アグネス・カラード
第3部 インタビュー&論考集
ラディカルな命の平等性
ブランドン・M・テリーによるジュディス・バトラーへのインタビュー
怒りの歴史
デビッド・コンスタン
被害者の怒りとその代償
マーサ・C・ヌスバウム
誰の怒りが重要なのか
ホイットニー・フィリップス
正しい無礼
エイミー・オルバーディング
寄稿者一覧
監訳者解説
『本書は、人間の本質というべき「怒り」というテーマをめぐって、当代随一の西洋の哲学者たちが議論を戦わせた記録である。アクネス・カラードの問題提起に基づき、立場の異なる複数の哲学者たちがそれに応答し、またインタビューや論考を寄せている。
怒りをめぐってここまで深い議論がなされたことは、かつてなかったといっていいだろう。そもそも怒りをテーマにした哲学書自体が、この世にそう多く存在するわけではない。人口に膾炙[カイシャ]しているのは、本書でも言及されている古代ローマの哲学者セネカの著書、「怒りについて」ぐらいではないだろうか。
奇しくも本書の原著タイトル「On Anger」は、このセネカの名著の英訳と同じである。ただ、大きく異なるのは、それが怒りに対して一人の哲学者の一つの見方からのみ書かれているわけではない点だ。セネカの議論がまさに典型的なのだが、一般に怒りはネガティブなものとしてとらえられている。
ところが本書では、怒りが実に多様な側面をもっている事実が明らかにされる。これから本文を読まれる読者の便宜のため、あるいはすでに読まれた方の頭の整理のために、あえて議論の内容を構成順に簡単に振り返っておきたい。この視点の多様性こそが、本書の重要なメッセージでもあるからだ。
まずアグネス・カラードによって、怒りは決してネガティブなだけのものではないという強烈な問題提起がなされる。その背景には、感情によって人は道徳性を表現するものだという主張が横たわっている。
だから彼女は「怒りの道徳面(モラルサイド)から暗黒面(ダークサイド)を切り離す」ような怒りの鈍化を否定するのである。それは非現実的であると。その結果、怒りの重要な特徴を支持する「悪意支持論」と「復讐支持論」と呼ばれる議論を展開する。恨みを抱き、復讐を果たすことは合理的かつ正当なことだという主張である。
こうしたカラードの立場を象徴するのが、のちにほかの論者たちから何度も言及されることになる「悪い世界では、人は善い存在ではいられない」という一文にほかならない。
このカラードの問題定義によって、怒りの概念をめぐる多種多様な議論が展開するが、基本的には大きく二つの立場に分けることができるだろう。一つはカラードのように怒りのある種の側面を肯定的にとらえる立場である。もう一つは、怒りという感情を否定的にとらえる立場である。
ポール・ブルームは、「暴力の選択」という論稿において、基本的にカラードを支持しつつも、怒りは合理的だという点に疑問を投げかける。そして怒りだけが道徳性を表現する手段ではないと主張している。
エリザベス・ブルーニッヒは、「損害の王国」という論稿において、終わりなき復讐を止め、平和を実現するために「許し」が必要だと説いている。
デスモンド・ジャグハモンは、「被抑圧者の怒りと政治」という論稿において、この表題のとおり、抑圧されている人たちの怒りにもっと寄り添う必要性を論じている。必然的にそれは社会における不合理性、つまり政治の問題を論じることにつながっていく。
ダリル・キャメロンとビクトリア・スプリングは、「怒りの社会生活」という論稿において、基本的にカラードの議論に賛同しつつ、そうした議論を単に倫理的な次元で完結させるのではなく、科学的研究と交錯させるべきことを訴えている。
ミーシャ・チェリーは、「もっと重要なこと」という論稿において、怒りの合理性に関する問いよりも、怒りを生みだしている現実の社会的文脈に着目するよう警鐘を鳴らす。
ジェシー・プリンツは、「なぜ怒りは間違った方向に進むのか」という論稿において、カラードの怒りを擁護する立場を明確に批判している。その際、怒りに一定の意義を認めつつも、有害な怒りを見分ける必要性を訴える。
レイチェル・アックスは、「復讐なき責任」という論稿において、カラードが説く復讐の意義に反論する。カラードによると復讐は相手に責任を負わせる方法になりえる。しかし、それは必ずしも唯一の方法ではないことを説く。
バーバラ・ハーマンは、「過去は序章にすぎない」という論稿において、永遠の怒りを主張するカラードに対し、謝罪を第一歩ととらえて、事態を変えていくべきことを訴えている。
ジュディス・バトラーは、ブランドン・M・テリーのインタビューに答える形で、命のラディカルな平等を受け入れるべきという視点から、暴力の本質を明らかにするとともに、それに対して非暴力という概念を対置させて批判を展開している。
デビッド・コンスタンは、「怒りの歴史」という論稿において、文字どおり怒りの歴史を概観すると同時に、怒りの本質が社会によって変化し得ることを指摘している。
マーサ・C・ヌスバウムは、かなりの紙幅を費やして、「被害者の怒りとその代償」というタイトルのもと、被害者の怒りは代償を伴うことを古代の戯曲とフェミニズムを俎上に載せて説得的に論じている。
ホイットニー・フィリップスは、「誰の怒りが重要なのか」という論稿の中で、極右反動勢力と左派のキャンセル・カルチャーの異同を示しつつも、後者に肩入れすることによって、今求められるべき怒りの内容を示そうとする。
最後にエイミー・オルバーディングは、「正しい無礼」という論稿の中で、無礼に振る舞うことと道徳との関係について論じている。
こうして概観してみると、人間はつくづく怒りとともに生きているという事実を認めざるを得ない。とりわけコロナ禍にあって、私たちはむき出しの生を露わにせざるを得ない状況に追い込まれてしまった。生きるためには、本性を表さずにはいなれないのだ。わかりやすくいうと、なりふり構わず人を蹴落とし、生活の糧を得る必要があるということだ。その過程では、いやがうえにも怒りが顕在化し、人々がいがみあい、ののしり合う姿が多々見られた。
もっとも、そうした対立はコロナ禍によってもたらされたというよりは、炙り出されたといったほうが正確だろう。現に本文で複数の論者たちが例をあげていた現代的問題は、いずれも歴史的に形成されてきたものである。人種問題をめぐって世界的に注目されたブラック・ライブズ・マター(BLM)もそうだし、昨今のキャンセル・カルチャーの是非をめぐる議論もそうだろう。
だからこそ、対立する立場のどちらが正しいかという問題ではなく、どちらの怒りがどんな意味をもっているのかということ自体、つまり怒りという人間が不可避的にもたざるを得ない感情について、その根源にまでさかのぼって議論する必要があるのだ。
本書で展開された議論は、一つのテーマについて哲学の視点から考え、議論する際のお手本になっているといっても過言ではない。思い込みを疑い、多様な視点からとらえ直し、考えを吟味するプロセスである。それを複数の論者が集団知という形で実践している。』
怒りは何が問題なのか
●怒りを強引に押しつぶしてしまうと、自尊心と道徳的な基盤を失う恐れがある。
●怒りの原因が不正行為だった場合、怒りの抑制は不正行為の黙認になる場合がある。つまり怒りを許すことと不道徳を許すこととが同じ場合もある。
●損害を受けて何か失うと、それが何であれ永久に戻ってこない。
●償いとして何かを与えられても、損害を受ける以前の状態に戻ることはない。犯してしまった悪事は謝罪しても軽くなるわけでない。その結果、不当な扱いを受けた者から復讐する気持ちを消し去ることは容易ではない。
●不当な扱いを受けた人には、怒りを捨てなければならない合理的な理由は見つからない。
怒りの特徴
●怒りを抑制することはできても、怒りを浄化することにはならない。
●人には被害を受けたことに対していつまでも怒り続ける理論上の権利だけでなく、遺恨を捨てられない感情的、道徳的な理由がある。
●怒りは学習と本能の両方の側面をもつ複雑な感情であるが、哲学者たちは長い間、怒りを表現するのに道徳的に正しい方法と間違った方法があると主張してきた。
●怒りを持ち続けていると他の感情と同じように疲労する。その結果、怒りは薄れる。それにより正当な要求が主張できなくなったり、不正な行為を罰したりすることが難しくなるかもしれない。
●怒りの中には復讐に駆り立てるものもあるが、日常生活において過ちは珍しいものではなく、復讐を伴うような怒りは一部である。
●発熱は健康な状態ではないが健全な免疫反応であり、発熱が起きないと病状は悪化するだろう。これと同じことが怒りにもいえる。つまり怒りは合理的なものであるということである。
怒りへの対処
●「義憤」や「変革の怒り」という言葉を使って、永続性や復讐心をもたずに悪事に対して正当に抗議する感情を仮定することは可能である。
●怒りの感情は見方を変えることで変化する可能性がある。
●怒りを含めて感情を制御する動機は人それぞれである。
●怒りを抑えて、違反行為を黙認していると思われるリスクを負うのか、怒りを表明してそれ自体が問題となりうる行動を取る危険を冒すのかの選択は複雑である。
●不正行為に適切に対応するために、時として他者を意図的に苦しめることもある。道徳的な理想の実現には苦しみが伴うことを認識する必要がある。
●怒りは時間と共に薄れていく可能性があり、感情的な怒りは残っても道徳的な規律としての許しがあれば、その怒りによる社会への悪影響は避けることができる可能性がある。
●怒りほど理由を聞いたり言ったりすることが求められる感情はない。そのため怒りの「コミュニケーション」が重要とされる。
許しについて
●許しに癒す力があることは知られているが、その効果は限定的なものでしかなく、損害を及ぼした人を許すことは耐え難いものである。
●不当な悪事に対し、個人が犠牲を払って我慢しなければならないというのが実態である。しかしながら、それであっても、許しは良いことであり、皆が知るように平和のために必要な要素かもしれない。
●許しは非常に難しいことである。重要なことは怒りを行動に移さないということである。
●許しを与える罪のない人は、何か崇高な善のために犠牲になることを求められている。それは「平和」や平等主義的な「秩序」、あるいは「神」である。
怒りの必要性
●人間の進化において怒りをもつことは有益だったという見解がある。
●怒りは自分自身と大切な人々の利益を守らせる。
●怒りは脅威や攻撃に反撃するパワーとなり、搾取や虐待の餌食、生存と繁殖の敗者になることから守る。
●怒りは道徳にとって必要なものであるが、その役割は時間の経過とともに変化するものではないか。
●怒りは必要だが、それを自分のなかの手に負えない獣のように考えてはいけない。
怒りの矛先を間違えることがある
例えば、麻薬や窃盗などの犯罪を完全に個人のせいにして、ある程度の情状酌量の余地を生む構造的な原因を考慮しないなどの場合。
1)怒りの責任のありかを間違えることがある
自分自身への不満を外に向ける人や身近な身内に向ける人もいる。
2)怒りの対象が広がりすぎることがある
例えばナチスに対する怒りをドイツ人全体に向けることがある。
3)怒りが虐待になりうることがある
ちょっとしたトラブルに過剰反応して逆上したり、反対意見を暴力で抑えこもうとしたりする人もいる。
4)怒りが過度の権利意識を含むことがある
自分が特別扱いされるのが当然だと思っている人は、期待通りにならないと怒り狂う。男性は女性よりも怒りやすいとよくいわれるが、ここには女性の正当な怒りが抑圧され、男性の子供じみた癇癪が許されるという二重の不公平が存在する。
5)怒りは自己破壊につながることがある
どんな怒りであれ、はけ口が必要である。怒りのエネルギーを、苦しみを追い払うために使わなければ、怒りの炎はその主を焼き尽くしてしまう。
6)抑圧された怒りが有害であるように、怒りを抑制せずに爆発させることにも害がある
自制心を働かせれば、怒りをもつ側は道徳的に優位な立場を主張でき、報復される可能性を減らすことができる。そのような抑制に最終的に必要になってくるのが「コントロール」である。問題は怒りを感じている状態の時に、私たちは物事を冷静に熟慮することが難しいことである。
まとめ
1.怒りという感情の難しさ
●「悪い世界では、人は善い存在ではいられない」。「怒りは合理的なものである」、これが怒りの難しさの所以ではないかと思います。
●怒りを強引に押しつぶしてしまうと、自尊心と道徳的な基盤を失う恐れがあります。その一方で、怒りを許すことは不道徳を許すことになるかもしれません。損害を受けて何か失うと、それが何であれ永久に戻ってはきません。犯してしまった悪事は謝罪しても軽くなるわけでなく、その結果、不当な扱いを受けた者から復讐する気持ちを消し去ることは困難です。このように怒りは、抑制はできても消し去ることは容易ではなく、特に、理由なく愛する人を殺されたような人の怒りは一生消えないと思います。
2.怒りとの付き合いかた
●怒りの大きさ、深刻さによって大きく異なりますが、怒りの矛先を怒りの原因に集中するのではなく、第三者的視点で、自分自身の今の感情や状況に目を向け、そして、怒りの相手に対しては全人格的な視点で理解しようと努めるということが第一歩なのではないでしょうか。ここでのポイントは真剣に相手の話を理解しようとすることだと思います。
そして、誰もが善悪の両面をもっていること、誰もが生まれたときから悪人なのではないこと。加害者の相手は被害者だった過去があるかもしれないこと等、いずれも根本解決にはならないでしょうが、怒りの感情を少なくすることはできると思います。
それはストレスに置き換えて考えてみるならば、ストレスを減らし、ストレスによる心身へのダメージを減らすことにつながると思います。つまり、怒りの感情はなくならないが、怒りによるストレスを減らす努力は有益であるということです。
●強い怒りの感情には効果はないかもしれませんが、起床時間、就寝時間、食事の時間など、あるいは体を動かす時間を作ることなど、生活習慣を整えることは、自分の気持ちや心を整えることにもなり、少なくともストレスを減らす効果は大きいと思います。やはり、怒りをなくすことはできずとも、ストレスを減らす努力をすることが大事だと思います。
ご参考2
以下は、以前アップした”ヨガ”というブログでご紹介したものです。このような境地に至ることが理想なのかもしれません。
ボーアとアインシュタイン6
41.アインシュタインの統一場理論とEPR論文
●“相補性”は「デジタル大辞泉」によると『電子の位置と速さ、光の粒子性と波動性のように、不確定性原理から二つの量が同時に測定できない関係にある現象を互いに相補的であるといい、このような性質をいう』とされています。そこには人知の理解を超えたものを受け入れる柔軟性のある価値観という感じを受けます。一方、“統一場理論”の前提は実在性に立脚し必ず統合できるという信念、もしくは統合を諦めることは許されないという強迫観念も多少あったのかもしれません。そして、これが両者を分ける根本的な違いであるような気がします。
また、EPR論についても同じような印象を受けます。ひとつは「理論から導かれる結論と人間の経験」ですが、「人間の経験」という表現は枠を意識させます。さらに、実在という泥沼を回避するために、「実在を一般的に定義する必要はない」としたEPR論の主張には違和感を覚えます。
アインシュタインの「量子論のコペンハーゲン解釈と客観的実在とは両立不可能だ」という考えについては、ボーアも同意しており、その上で「量子の世界というものはない。あるのは抽象的な量子力学の記述だけである」という見解を示しました。
『19世紀にマクスウェルは、電気、磁気、光を統一して、包括的なひとつの理論構造にまとめあげた。アインシュタインはそれと同様、電磁気理論と一般相対性理論とを統一したいと考えていたのだ。彼にとって、それらふたつの理論を統一することは次に踏み出すべきステップであり、避けて通ることのできない道筋であると同時に、論理的必然でさえあった。そんな理論を作るという彼の試みはいずれも屑籠箱行になるのだが、彼がその道に最初の一歩を踏み出したのは、1925年のことだった。その後量子力学が発見されてからは、統一場理論ができれば、量子力学はその副産物として得られるだろうと考えるようになっていた。』
『若い世代とのあいだに相互不信はあったものの、アインシュタインといっしょに仕事がしたいと熱望する若手はつねにいた。そんな若手のひとりがネイサン・ローゼンである。ニューヨーク生まれのローゼンは、1934年、25歳のときに、アインシュタインの助手としてマサチューセッツ工科大学(MIT)から高等研究所にやってきた。そのローゼンよりも数カ月ほど早く、ボリス・ポドルスキーが初めてアインシュタインに会ったのは、1931年、カリフォルニア工科大学(カルテック)でのことだった。そのときふたりは共著論文をひとつ書き上げた。アインシュタインはもうひとつの論文のアイデアをもっていた。その論文が、コペンハーゲン解釈に新しい側面から一撃を加え、アインシュタイン=ボーア論争の歴史に新時代を画することになるのである。
1927年と1930年の、二度のソルヴェイ会議でアインシュタインが採った路線は、不確定性原理を突き崩すことにより、量子力学には矛盾があり、それゆえ不完全であることを示すというものだった。ボーアはハイゼンベルクとパウリの協力を得てアインシュタインの思考実験という要塞を解体し、コペンハーゲン解釈を防衛することに成功した。
その後アインシュタインは、量子力学には論理的な矛盾はないものの、ボーアが言うような完全な理論ではないと考えるようになった。量子力学は完全ではなく、物理的実在を十分に捉えていないということを示すためには、これまでとは違う戦略が必要なのはわかっていた。その目的のためにアインシュタインが開発したのが、彼の考案したなかで、もっとも長く攻略に耐えることになる思考実験だった。
1935年が明けるとすぐに、アインシュタインは、ポドルスキーとローゼンを研究室に呼び、三人で数週間にわたって議論を重ね、その新しい戦略を入念に練り上げた。ポドルスキーがその議論の成果を論文として書き上げる作業を担当し、ローゼンはそのために必要な計算のほとんどを担当した。のちにローゼンが語ったところによれば、アインシュタインの担当は、「一般的な考え方、およびその意味」を明らかにすることだった。わずか四ページのその論文―アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼン論文、略してEPR論文―は、三月末には完成し、専門誌に送付された。「物理的実在に関する量子力学の記述は完全だと考えることができるか?(Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?)」と題された三人の共著論文は、[Physical Realityの前にあるべき]“the”を落としたまま、5月15日に、アメリカの物理学専門誌「フィジカル・レビュー」に掲載された。タイトルに掲げた問いに対するERPの回答は、敢然たる「ノー!」だった。ERP論文は、著者のひとりにアインシュタインが含まれていたため、専門誌に掲載される前に、誰も望まないかたちで世間の注目を浴びることになった。
1935年5月4日土曜日の「ニューヨーク・タイムズ」の第十一面に、「アインシュタイン、量子論を攻撃する」という派手な見出しの記事が掲載された。「アインシュタイン教授は、科学の重要理論である量子力学を攻撃する予定だ。その理論にとって彼は祖父のような存在である。彼は、量子力学は“正しい”が、“完全”ではないと結論した」。それから三日後、「ニューヨーク・タイムズ」は、明らかに不機嫌なアインシュタインの談話を掲載した。新聞を相手取ることに不慣れではないはずのアインシュタインだったが、言わずもがなのことを言ったのだ。「科学的な問題については、それにふさわしい場でしか論じないというのが、一貫したわたしのやり方である。わたしは、こうした問題についての発表を、論文掲載に先立って一般紙で行うことに反対する」
アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンは発表された論文の中で、まずはじめに、実在そのものと、物理学者が理解するところの実在とを区別した。「物理理論について本格的な考察を行うときにはつねに、理論とはいっさい関係ない客観的実在と、理論のなかで用いられる物理的な概念とは、別のものだということを考慮に入れなければならない。物理的概念は、客観的実在をさせるために作られたものであり、われわれはそれらの概念を使って、自らのために客観的実在をえがき出だすのである。」それに続けてEPRは、物理理論が成功していると言えるためには、次のふたつの問いに対する答えが、無条件に「イエス」でなければならないと主張した。そのふたつとは、「その理論は正しいのか?」と「その理論によって与えられる記述は完全か?」である。
「理論が正しいかどうかは、理論から導かれる結論と人間の経験とが、どの程度合うかによって判断される」とEPRは述べた。物理学で言う「経験」は、実験や測定を意味するから、三人がここで述べたことは、物理学者なら誰でも受け入れるだろう。今日にいたるまで、実験室で行われた実験と、量子力学の理論的な予測とのあいだに矛盾と言えるようなものはない。したがって、量子力学は正しい理論だと言えそうだ。しかしアインシュタインにとって、実験と合う正しい理論だというだけでは不十分だった―理論はそれに加えて、完全でなければならなかったのである。
「完全」という言葉が何を意味しているにせよ、EPRは、物理理論の完全性に対して、ひとつの必要条件を与えた。「物理的な実在の要素はすべて、その物理理論のなかに対応物をもたなければならない」。理論が完全であるための判定基準をこのように定める以上、EPRがこの先に議論を進めるためには、「実在の要素」とは何かを定義しなければならない。
アインシュタインは哲学の泥沼にはまりたくはなかった。あまりにも多くの人たちが、「実在」を定義しようとして、その泥沼に飲み込まれていった。実在が何で構成されているのかを明らかにしようとして、無事にその沼から出てきた者はかつてひとりもいなかったのだ。そこでEPRは、その泥沼を回避するために、自分たちの目的にとって、「実在を一般的に定義する必要はない」と述べた。そのうえで、「実在の要素」を定義するために、「十分」にして「妥当」な判定基準、と三人が考えるものを使うことにした。その判定基準とは、「系をいかなる仕方でもかき乱すことなく、ある物理量の値を、確実に(すなわち確率1で)予測することができるなら、その物理量に対応する、物理的実在の要素が存在する」というものだった。
アインシュタインは、量子力学が捉えていない客観的な「実在の要素」が存在することを示すことにより、量子力学は自然についての完全な基礎理論だというボーアの主張を突き崩したいと考えたのだ。アインシュタインは、ボーアや彼の意見を支持する者たちとの論争の焦点を、量子力学には内部矛盾があるかどうかという問題から、実在はいかなる性質をもつのか、そして理論は役割とは何かという問題へとシフトさせたのである。』
『EPR論文には、量子論のコペンハーゲン解釈と客観的実在とは両立不可能だというアインシュタインの考えが表明されていた。それについてはアインシュタインのいう通りであり、ボーアもそれはわかっていた。じっさいボーアは、「量子の世界というものはない。あるのは抽象的な量子力学の記述だけである」と述べているのである。コペンハーゲン解釈によれば、粒子には、独立した実在性はない。観測されていないときには、粒子は物理的な性質をもたないのだ。アメリカの物理学者ジョン・アーチボルト・ホイーラーは、のちにこの考え方を次のように言い表した。「基礎的な現象は、観測されるまでは実在しない」。EPR論文が世に出る一年ほど前にはパスクアル・ヨルダンが、観測者とは無関係な実在を認めないコペンハーゲン解釈の観点を論理的にとことん突き詰めて次の結論に達した。「われわれ自身が、測定結果を生み出すのである」
ポール・ディラックは、「アインシュタインがこれではダメだと証明したのだから、一からやり直しだ」と言った。彼ははじめ、アインシュタインは量子力学に致命的な打撃を与えたと考えたのだ。しかしすぐに、ディラックもその他多くの物理学者たちと同じく、今回もまたボーア=アインシュタイン論争の戦場から、勝者として帰還したのはボーアだと考えるようになった。量子力学が非常に役に立つ理論であることはとっくの昔に証明されていたし、EPRに対するボーアの回答をじっくり吟味してみようという者はほとんどいなかった―なにしろボーア自身の基準に照らしてさえ、その回答はあいまいで難解だったのだから。』
42.理論と哲学的立場
●アインシュタインの抵抗は、個人的というより物理学界への警鐘だったように思います。「実験の証拠に基づかず、科学理論を基礎として哲学的世界観を作ること」の危機感から、その危険性を強く訴え続けたということではないでしょうか。アインシュタインの執拗ともいえる論争によって、量子力学は可能な限りの精査を通して今に至っているように思います。ボーアも親愛なる友であるアインシュタインからの警告の意図を理解していたからこそ、アインシュタインからの問題定義を真摯に受け止め、生涯にわたって取り組み続けたのではないかと思います。
『ふたりのあいだで語られなかったことは、すでにお互いが知っていることだった。量子力学の解釈に関するふたりの論争は、突き詰めれば、実在をどう位置づけるかに関する哲学的な信念にかかわっていた。世界は実在するのだろうか? ボーアは、量子力学は自然に関する完全な基礎理論だと信じ、その上に立って哲学的な世界観を作り上げた。その世界観にもとづき、ボーアはこう断言した。「量子の世界というものはない。あるのは抽象的な量子力学の記述だけである。物理学の仕事を、自然を見出すことだと考えるのは間違いである。物理学は、自然について何が言えるかに関するものである」。アインシュタインはそれとは別のアプローチを選んだ。彼は、観測者とは独立した、因果律に従う世界がたしかに実在するという揺るがぬ信念の上に立って量子力学を評価した。その結果として、彼はコペンハーゲン解釈を受け入れることができなかった。「われわれが科学と呼ぶものの唯一の目的は、存在するものの性質を明らかにすることである。ボーアにはまず理論があり、次に哲学的な立場があった。その哲学的立場とは、理論が実在について何を語っているかを理解するために作り上げた解釈だった。アインシュタインは、何であれ科学理論を基礎として哲学的世界観を作ることの危険性を知っていた。新しい実験的証拠の光に照らして、理論に不十分な点があることが判明すれば、その理論に支えられていた哲学的な立場は崩れるからだ。「いかなる知覚的行為とも無関係な実在を仮定することは、物理学の基礎です」とアインシュタインは述べた。「しかしその仮定が正しいかどうかを、わたしたちは知らないのです」
アインシュタインは、哲学的には実在論者であり、そのような立場を根拠づけることは不可能であることを知っていた。それは実在に関するひとつの「信念」であって、証明できるようなものではないからだ。しかし、たとえそうだとしても、アインシュタインにとって、「人が理解したいと願うのは、そこに存在する現実の世界」なのだった。彼はモーリス・ソロヴィンへの手紙に次のように書いた。「人間理性にとって手が届くかぎりの実在の本性が合理的なものだという確信について何か語るとすれば、“宗教的”確信というより良い表現が見つかりません。この感覚がなくなるところでは、科学はつねに退屈な経験主義に陥ってしまう恐れがあります」
ハイゼンベルクは、アインシュタインとシュレーディンガーは「古典物理学の実在概念、より一般的な哲学的な言葉を使うなら唯物論[精神の実在を否定して、物質の根源性、独自性のみを主張する哲学の理論]の実在論に戻りたい」のだろうと考えていた。ハイゼンベルクにとって、「石や木が存在するのと同じ意味において、最小の構成要素が客観的に存在するような実世界が、われわれがそれらを観察するかどうかによらずに存在している」という信念をもつことは、「十九世紀の自然科学に広く行き渡っていた、素朴な実在論の観点」に後戻りすることだった。アインシュタインとシュレーディンガーは「物理学を変えることなく哲学を変えたい」のだというハイゼンベルクの判断は、半ば正しく、半ば間違っていた。アインシュタインは物理学そのものを変えることにも懸命だった―彼は、多くの人たちが考えていたような、保守的な過去の遺物ではなかったのである。古典物理学の概念は、何か新しいもので置き換えなければならないとアインシュタインは確信していた。それに対してボーアは、巨視的な世界は古典物理学の概念で記述されるのだから、巨視的な世界については、古典物理学を超える理論は探そうとすることさえ時間の無駄だと論じていた。じっさい、彼が相補性の枠組みを作り上げたのは、古典的な概念を救おうとしてのことだった。ボーアにとって、測定装置とは独立した基礎的な物理的実在などというものは存在しなかった。ハイゼンベルクが指摘したように、「われわれは量子論のパラドックス、すなわち、古典的な諸概念を使うしかないというパラドックスを避けることはできない」とボーアは考えていたのである。アインシュタインが「心休まる哲学」と呼んだのは、古典的諸概念を残さなければならないという、ボーア=ハイゼンベルクの魅力的な呼び声のことだったのだ。』
『アインシュタイン=ボーア論争は、アインシュタインの死をもって終わったわけではなかった。ボーアは、論敵がまだ生きているかのように、その後も量子論争をつづけたのだ。「わたしにはアインシュタインが微笑んでいるのが見える。得意気でありながら、思いやりと優しさを浮かべたあの顔で」。ボーアが物理の基本的な問題について考えるときには、アインシュタインならどう言っただろうかということが、まず頭に浮かぶことが多かった。1962年11月17日の土曜日、ボーアは、自分が量子物理学の発展に果たした役割に関する、五回にわたるインタビューの最後のひとつを受けた。翌日曜日、昼食をとった後、ボーアはいつものように昼寝をするために寝室に向かった。夫の声を聞いた妻のマルグレーデが寝室に急ぐと、そこには意識を失ったボーアがいた。七十七歳のボーアは、致命的な心臓発作を起こしたのだ。前の晩、かつての講義をもう一度反芻しながら、彼が最後に書斎の黒板に描いたのは、アインシュタインの光の箱だった。』
『アインシュタインは、こう語ったことがある。「わたしは一般相対性理論について考えた時間より、百倍も多くの時間をかけて量子の問題について考えた」。ボーアは、量子力学は、原子の世界について何を教えているのかを理解しようとするなかで、客観的な実在があるという考えを捨てた。アインシュタインにとってボーアのその判断は、量子力学はたかだか真実の一部しか含んでいないことを示す明らかな兆候だった。ボーアは、実験や観察でわかることの背後に、量子の世界が実在するわけではないと主張して譲らなかった。アインシュタインは、「それを認めることに論理的な矛盾はないが、その考えはわたしの科学的直観と真っ向から対立するので、わたしとしてはより完全な理論を探さずにはいられないのである」と述べた。彼は、「単に出来事が起こる確率ではなく、出来事そのものを描き出すような実在のモデルを作ることは可能だ」と信じることをやめなかった。しかし結局、アインシュタインはボーアのコペンハーゲン解釈を論駁することができなかった。プリンストン時代のアインシュタインを知るアブラハム・パイスは、次のように述べた。「相対性理論について語るときの彼は冷静だったが、量子論については熱くなって語った」。そしてパイスはこう言い添えた。 「量子は彼のデーモンだった」。』
43.統一場理論
●アインシュタインが目指したのは電磁気学、一般相対性理論、そして量子力学を統合する重力理論でした。
『アインシュタインは、人生最後の二十五年間をかけて追及したにもかかわらず、いまだ捉えることのできない統一場理論―それは一般相対性理論と電磁気学の結婚だった―が、自分が追い求める完全な理論になると信じていた。その統一場理論は、量子力学を含むような完全な理論になるはずだった。パウリはそんなアインシュタインの統一の夢に対し、「神が引き離したものを、何人たりともふたたび結びつけてはなりません」という辛辣な判定を下した。当時はほとんどすべての物理学者が、アインシュタインは現実が見えていないと言ってあざ笑った。しかし、[重力・電磁力に加えて]放射性崩壊を引き起こす弱い核力と、原子核をまとめている強い核力が発見されて、物理学者が相手にしなければならない力が四つに増えると、まさにアインシュタインが求めていたような理論の探求が、物理学の聖杯になったのである。』
『ボーアとの論争で決定打を出すことはできなかったものの、アインシュタインの挑戦は後々まで余韻を残し、さまざまな思索の引き金となった。彼の戦いはボーム、ベル、エヴェレットらを力づけ、ボーアのコペンハーゲン解釈が圧倒的影響力を誇って、ほとんどの者がそれを疑うことさえしなかった時期にも検討を促した。実在の本性をめぐるアインシュタイン=ボーア論争は、ベルの定理へとつながるインスピレーションの源だった。そしてベルの不等式を検証しようという試みから、量子暗号、量子情報理論、量子コンピューティングといった新しい研究分野が直接間接に生まれてきたのである。こうした新しい分野のなかでもとくに注目すべき、エンタングルメント[量子もつれ]を利用した量子テレポーテーションだ。SFの世界の話しのように聞こえるかもしれないが、1997年には、ひとつならずふたつのチームが、その粒子の量子状態が別の場所にあるもうひとつの粒子に完全に転写されたので、事実上、最初の粒子を移動させたことになるのだ。
アインシュタインは、コペンハーゲン解釈を批判し、彼に取り憑いた量子のデーモンを滅ぼそうとしたせいで人生の最後の三十年は不遇だったが、彼の主張の一部は正しかったことが示された。アインシュタイン=ボーア論争は、量子力学の数学に含まれる式や数値とはほとんど関係がなかった。量子力学は何を意味しているのか? 実在の本性について量子力学は何を語るのか? こうした問いにどう答えるかが、ふたりを分けたのである。アインシュタインは、具体的な解釈を示したことは一度もなかった。なぜなら彼は、物理理論を睨んで自分の哲学を作るということをしなかったからだ。その代わりに彼は、実在は観測者とは独立しているという信念にもとづいて量子力学を調べ抜き、この理論には満足できないと考えるようになったのだ。
1900年12月には、たいていのことは古典物理学で説明がつき、ほとんどすべてのことが古典物理学の支配する領域に収まっていた。そのときマックス・プランクが量子に出くわし、物理学者たちは今なお、量子の取り扱いに苦労している。アインシュタインは、「わたしは量子に強い関心を持ち」、半世紀ものあいだ「考え続けた」が、いまだ理解したというには程遠いありさまだと述べた。最後までその努力を続けたアインシュタインが慰めを見出したのは、ドイツの劇作家にして哲学者でもあるゴットホルト・レッシングの次の言葉だった。「真実を手に入れたいという願望は、真実を手に入れたという確信よりも尊い」。』
感想
1900年、マックス・プランクが「黒体の放射法則の導出法」の中で“量子”と命名し、1905年にはアルベルト・アインシュタインが光量子の存在と光電効果に関する論文を発表しました。しかしながら、量子論の扉を開いたのはニールス・ボーアが1913年7月に発表した論文、「原子と分子の構成について」だったと思います。
量子論から量子力学への道程も困難極まりないものでしたが、ボーアは若い天才物理学者のハイゼンベルクにすべてを託し、そのハイゼンベルクは友人で同じく若き天才物理学者のパウリの協力により、ついに行列力学にもとづく量子力学を確立しました。しかし、この行列力学は難解な数学的なアプローチであったため、多くの物理学者にとって理解困難なものでした。
それに対抗するように登場したのが、直観的で物理学者にとって分かりやすい波動力学でした。そして、波動力学を発見したシュレーディンガーを後押ししたのがアインシュタインでした。アインシュタインは「コペンハーゲン解釈」に対して、ゾンマーフェルトへの手紙の中で、次のように話しています。「量子力学は統計的法則を記述するという意味では正しい理論かもしれませんが、基本的な個々のプロセスを記述する理論として適切ではありません」。
これは、アインシュタインが考える物理学のあるべき姿に照らし合わせると、受け入れることができない“解釈”でした。また、ボーアの【相補性】に対してアインシュタインは【統一場理論】を考えていました。これがシュレーディンガーとともに「コペンハーゲン解釈」を受け入れることなく、論争になった核心の一つだったと思います。しかしながら、このアインシュタインやシュレーディンガーとの論争、特に第五回ソルヴェイ会議の公私にわたる、あたかもチェスのような闘い、さらに四半世紀に渡って繰り広げられた論争は、確実に量子力学を磨き上げました。
アインシュタインの死後十年を経た1965年、ノーベル賞受賞者のリチャード・ファインマンは次のような言葉を残しました。「量子力学を理解している者は、ひとりもいないと言ってよいと思う」また、「「こんなことがあっていいのか?」と考え続けるのはやめなさい―やめられるのならば。その問いへの答えは、誰も知らないのだから」。
不可知とは「人間のあらゆる認識手段を使用しても知り得ないこと」とされています。不可知論は古代ギリシアや古代インドから存在し、近代においては哲学者カントが「純粋理性批判」において、「物自体は認識できずかつ知り得るものではなく、人は主観形式である時間・空間のうちに与えられた現象だけを認識できる能力のみがある」という考えを提示しました。これも一種の不可知論とされています。
本書の中には次のような記述がありました。
『ハイゼンベルクが発見した不確定性は、現実の世界に本来的に備わっている性質なのだ。原子レベルの世界で観測可能な量について、プランク定数の大きさにより規定され、不確定性関係により課される正確さの限界は、装置をどれだけ改良しても決して消滅することはない、とハイゼンベルクは述べた。この驚くべき発見の名前としては、「不確定性」や「不決定性」よりも、「不可知性」(unknowable)というほうがふさわしかったかもしれない。』
不可知性はボーアとアインシュタインを分けた価値観の相違であり、分岐点ではなかったのかと思います。
ご参考:“基礎物理学の課題 -量子論と相対論の統合は可能か-” PDF31枚
ご参考:Youtube“量子力学と仏教は同じだった!?物理学者たちが東洋思想に魅了される理由【宇宙の真理】”(8分54秒)以下がこの動画の内容です。
00:06 物理学者たちの仏教への反応
01:07 量子力学の世界観①(ウィグナーの友人 ; 思考実験)
03:27 西洋哲学者たちの量子力学への反応
04:08 仏教の世界観①(縁起)
05:11 量子力学の世界観②(不確定性原理)
05:58 仏教の世界観②(不可知性)
06:26 不可知性の世界
06:40 コペンハーゲン解釈の世界
06:56 量子力学の父
07:49 東洋思想と量子力学の関係性の論文
※07:58のところで、ボーアは以下のように述べたということが紹介されています。
『・・・この考えは、
陰陽の名で知られるシンボルである太極図で表現された古代東洋と密接に調和しています。この考えによれば、自然界のすべての変化は、二つの主要な原因または原理によって調和され、それぞれが他を補完しているのです。』

『ボーアはデンマークの国民的英雄になり、1947年、デンマーク最高の勲章、大象位勲章を受けた。この勲章をもらうとき、家の紋章を選ぶ規定があった。ボーアはそのとき、彼の思想を表す非常に特徴のある紋章を選んだ。紋章の上には「CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA」=対立するものは相補的である。という意味の言葉がかかれていた。ボーアの選んだ紋章は中国の「易」の思想を表すという太極図である。』
赤と黒の二色の円が太極図です。

画像出展:「アインシュタイン ロマン3」
おそらく、向かって左から3人目がボーア博士だろうと思います。また、次のような話をされたとのことです。
『富士山を箱根や伊豆、その他さまざまな場所から見ることができました。富士山は光線や天候によって姿を色々変えます。あるときは山頂が山に隠れ、あるときは雪を頂く山頂が雲の上に浮かんでいました。その時々の印象は非常に異なります。しかし、富士山の本当の優美な姿はその時々の印象がすべて私の中で合わさってできるのです。それは相補性と同じことなのです。』

”ルビンの壺”
画像出展:「Binary Diary」
もし、人間社会において“壺”という物が存在していないとすれば、この図を見て気づくことは向かい合った二人の横顔だけです。
「不可知」は人間のあらゆる認識手段を使用しても知り得ないことです。やはり、我々が生活している物質世界において、不可知という考えも必要ではないかと思います。
ボーアとアインシュタイン5
37.1927年9月、イタリアのコモで開催された国際物理学会
●ボーアが相補性という考えを発表したのは、イタリアのコモで開催された国際物理学会でした。そして約1か月後には「第五回ソルヴェイ会議」がブリュッセルで行われました。後年、「コペンハーゲン解釈」と呼ばれるようになった量子物理学は、この二つの会議で行ったボーアの講演が原点です。
『1927年9月11日から20日にかけて、イタリアのコモで開催された国際物理学会は、イタリアのアレッサンドロ・ボルタの没後百周年の記念行事だった。会議がたけなわとなっても、ボーアはまだ、9月16日に予定されている講演の原稿を書き続けていた。講演当日、カルドゥッチ研究所で彼の話を待ち受ける参加者のなかには、ボルン、ド・ブロイ、コンプトン、ハイゼンベルク、ローレンツ、パウリ、プランク、ゾンマーフェルトがいた。
ボーアはまず、新しい相補性という考え方の枠組みを初めて公式の場で説明したのち、ハイゼンベルクの不確定性原理を取り上げ、量子論において測定が果たす役割について語った。ボーアが小声で話す内容を、隅から隅まできちんと聞き取るのは難しい人たちもいた。ボーアは、シュレーディンガーの波動関数に関するボルンの確率解釈をはじめ、さまざまな要素をひとつひとつつなぎ合わせ、それらを量子力学に対する新しい物理的理解の基礎とした。物理学者たちはのちに、たくさんのアイデアが混じり合ったその解釈のことを、「コペンハーゲン解釈」と呼ぶようになる。
ボーアの講義は、後年ハイゼンベルクが、「量子論の解釈にかかわるあらゆる疑問について、コペンハーゲンで行われた徹底的な研究」と表現することになる努力の、ひとつの到達点だった。このデンマーク人が与えた回答は、「量子の手品師」たる若きハイゼンベルクさえも、はじめは戸惑いを覚えるほどのものだった。ハイゼンベルクはのちに、当時の様子を次のように語った。「何時間も話し続けてすっかり夜も更け、身通しがつかないまま議論が終わると、わたしはしばしば研究所のそばに広がる公園にひとりで散歩に出かけ、繰り返しこう自問したものだった。自然は本当に、こうした原子レベルの実験が示しているような馬鹿げたものなのだろうか?」。この疑問に対するボーアの答えは、きっぱりとした「イエス」だった。測定と観測にそのような重要な役割を与えることは、自然のなかに規則的なパターンや因果的な結びつきを見出そうとするいっさいの試みを無効にするものだった。
科学の中核的教義のひとつである因果律は捨てなければならないと、論文のなかではっきりと唱えた最初の人物がハイゼンベルクだった。彼は不確定性原理の論文に次のように書いた。「「現在が正確にわかっていれば未来を予測することができる」という決定論的な因果律の定式化において、間違ってるのは結論ではなく、仮定のほうである。現在をあらゆる細部にわたって知ることは、原理的にさえできないからだ」。たとえば、一個の電子がもつ位置と速度を、同時に正確に知ることはできない。それゆえわれわれに計算できるのは、その電子が未来においてもつ位置と速度に関する、「さまざまな」可能性だけである。原子レベルのプロセスについて、一回かぎりの観測や測定で得られる結果を予測することはできない。正確に予測できるのは、ある範囲の可能性のうち、どれかの結果が得られる確率だけなのだ。
ニュートンの敷いた基礎の上に築かれた古典的宇宙は、決定論的な時計仕掛けの宇宙だった。アインシュタインの相対性理論による修正を受けてからも、粒子であれ惑星であれ、与えられた時刻における物体の位置と速度が正確にわかれば、あらゆる時刻における物体の位置と速度は、原理的にはどれほど正確にでも求めることができる。しかし量子的な宇宙では、あらゆる出来事は空所がないのだ。ハイゼンベルクは不確定性原理の論文の最後の段落で、大胆にも次のように述べた。あらゆる実験が量子力学の法則に従い、それゆえ式ΔpΔq=hに従う以上、因果律を復活させようとすることは、「知覚され統計的な世界」とハイゼンベルクが呼ぶものの背後に、何か「真の」世界が隠れていることを期待するのと同様、「非生産的であり、無意味である」というのがハイゼンベルクの考えだった。それが、彼とボーア、そしてパウリ、ボルンの共通の見解だったのである。
コモの会議では、ふたりの物理学者の欠席が目立っていた。シュレーディンガーは数週間前にプランクの後任としてベルリンに移り、新しい環境に慣れるのに忙しかった。アインシュタインはファシズムのイタリアに足を踏み入れることを拒否した。しかしボーアはわずか1カ月後には、ブリュッセルでこのふたりに会えるはずだった。』
38.1927年10月24日~10月29日第五回ソルヴェイ会議
●1926年9月、戦後、ドイツが国際連盟に加入する道が開かれ、第五回ソルヴェイ会議の開催国となったベルギー国王はドイツ人科学者の参加を承認しました。この結果、ソルヴェイ会議にはアインシュタインの参加が認められました。そのソルヴェイ会議の論争の主役はボーアとアインシュタインであり、それは物理学というより哲学に近いものだったようです。
『第五回ソルヴェイ会議に招待された物理学者たちはみな、「電子と光子」というテーマを掲げたこの会議は、目下もっとも緊急度の高い問題、物理学というよりむしろ哲学というべき問題について討論するよう企画されていることを知っていた。その問題とは量子力学の意味である。量子力学は自然の本当の姿について何を教えているのだろうか? ボーアはその答えを知っているつもりだった。多くの人たちにとって、ボーアは「量子の王」としてブリュッセルに到着した。しかし、アインシュタインは「物理学の教皇」だった。ボーアにとって、「最近到達した発展の段階は、われわれの観点から見れば、アインシュタイン自身がきわめて独創的なやり方で提示したいくつかの問題を解明するという目的地に至る道のりを、かなり先まで進んだということを意味していた」。彼は、「アインシュタインがそれをどう考えるか」を知りたくてうずうずしていた。ボーアにとってアインシュタインの意見は大問題だったのだ。
かくして灰色の雲に覆われた1927年10月24日の月曜日、最初のセッションが始まる午前十時に、世界有数の量子物理学者のほとんどが、レオポルトド公園内にある生理学研究所の建物に顔をそろえた。その場には大きな期待感がみなぎっていた。それは、準備に一年半をかけ、ドイツが仲間外れにされていた時期を終わらせるために国王の同意を必要とした会議だった。』
『10月26日の水曜日には、量子力学のふたつの対抗理論の提唱者たちがそれぞれ報告を行った。午前のセッションは、ハイゼンベルクとボルンが共同で担当した。ふたつの講演は大きく四つの部分に分かれていた―数学的形式、物理的解釈、不確定性原理、そして量子力学の応用である。
具体的には、この会議の議事録にある通り、上位者のボルンが序説と、第一部および第二部を担当し、第三部と第四部をハイゼンベルクが担当した。ふたりはその報告を次のように切り出した。「量子力学は、不連続の発生こそは原子物理学と古典物理学との本質的な違いだという直観にもとづいています」。そしてふたりはほんの数メートルの距離に座っている物理学者たちに謝意を表す意味で、量子力学は本質的に、「プランク、アインシュタイン、そしてボーアによって創設された量子論を直接的に拡張した」ものだと指摘した。
それに続いて、行列力学、ディラック=ヨルダンの交換理論、確率解釈を説明したのち、不確定性原理と「プランク定数hの意味」に話を進めた。ふたりは、プランク定数は「波と粒子の二重性を介して自然法則に入り込む普遍的なあいまいさの尺度」だと主張した。じっさい、もしも物質と放射が波と粒子の二重性をもたなかったなら、プランクの定数は存在しなかっただろうし、量子力学も存在しなかっただろう。そしてふたりはまとめとして、次のような挑戦的な発言をした。「量子力学は閉じた理論であって、その物理的数学的前提は、もはやいかなる変更も受けることはないと考えています」
閉じた理論だというのは、今後いかなる発展があろうと、量子力学の基本的な特徴は変わらないという意味だ。アインシュタインにとって、量子力学は完全だとか最終理論だとかいう主張はなんであれ、到底受け入れられるものではなかった。たしかに量子力学はみごとな理論だが、アインシュタインの見るところ、まだ本物ではなかったのだ。しかしアインシュタインは挑発に乗ることを拒否し、ふたりの報告に続く討論でも口を閉ざしていた。その討議で発言したのは、ボルン、ディラック、ローレンツ、ボーアの四人で、ボルンとハイゼンベルクの報告に異議を唱えた者はひとりもいなかった。』
『昼食後に演壇に上がったのは、波動力学に関する報告を英語で行ったシュレーディンガーだった。 「波動力学の名のもとに、現在、互いに密接に関係しているが完全に同じではないふたつの理論が使われています」と彼は切り出した。じっさいにはひとつの理論しかないのだが、事実上、それがふたつに分裂していたのだ。一方は、日常的な三次元空間の中にある波についての理論、そして他方は、高度に抽象的な多次元空間を必要とする理論だ。問題は、一個の電子を記述する場合を別にすれば、その波は、三次元よりも高い次元の空間に存在する波になってしまうことだ、とシュレーディンガーは説明した。水素原子に含まれる一個の電子を記述するためには三次元空間で足りるが、ヘリウムの二個の電子を記述するためには、六次元空間が必要になる。とはいえ、配位空間として知られるこの多次元空間は数学的な道具にすぎず、その理論で記述されるプロセスがいかなるものであれ―衝突し合う多数の電子であれ、原子核のまわりを起動運動している一個の電子であれ―そのプロセスは空間と時間の中で起こっている、とシュレーディンガーは論じた。「しかし率直に言って、それらふたつの概念は、まだ完全に統一されていません」と述べてから、彼はふたつの場合それぞれについての説明に話を進めた。
物理学者たちは波動力学を便利に使っていたが、一個の粒子を記述する波動関数はその粒子の電荷と質量の分布を表しているというシュレーディンガーの解釈を支持する者は、指導的な理論家の中にはひとりもいなかった。シュレーディンガーは、ボルンの確率解釈が広く支持されていることにも屈せず、自分の波動関数解釈の妥当性を力説し、定説となっていた「量子飛躍」という考え方に疑問を投げかけた。
シュレーディンガーは、報告者としてこの会議に招待されたときから、「行列派」との衝突は避けられまいと覚悟していた。講演後に最初に質問に立ち上がったのはボーアだった。ボーアは、シュレーディンガーが報告の後半で述べた「困難」は、彼が前半で述べた、ある結果が間違っているからではないかと問いただした。シュレーディンガーは、ボーアのその質問はうまく切り抜けたが、今度はボルンが立ち上がり、別のところで計算に間違いがあるのではないかと質問した。シュレーディンガーは少しいらついた様子で、「その計算は完璧に正しく厳密であり、ボルン氏による抗議は根拠がありません」と述べた。
さらに二人が発言したのち、ハイゼンベルクが立ち上がった。「シュレーディンガー氏は報告の最後で、われわれの知識が深まれば、多次元理論で得られた結果を三次元空間で説明し、理解できるようになるだろうとの希望的観測を述べることで、彼の理論を根拠づけました。しかしわたしの見るところ、シュレーディンガー氏の計算には、この希望的観測を根拠づけるようなものは何もないように思います」。これに対してシュレーディンガーは、「三次元で考えることができるようになるだろうという自分の期待は、さほど荒唐無稽な夢物語というわけではありません」と答えた。それから数分ほどして討議が終わり、議事の第一部にあたる招待講演はすべて終了した。』
『一般的討論のひとつ目のセッションは、10月28日金曜日の午後に始まった。まずローレンツが、因果律、決定論、確率の問題に討論のテーマを絞るために、いくつかの論点を提出した。量子的な出来事には何らかの原因があるのだろうか、ないのだろうか? 彼の言葉を借りるなら、「決定論は、それを信仰箇条のひとつとしなければ主張できないのだろうか? 非決定論のひとつの原理にまで格上げしなければならないのだろうか?」。ローレンツはそれ以上は自分の考えを述べず、ボーアにこのセッションの舵取りを頼んだ。ボーアはそれを受けて、「量子物理学においてわれわれが直面する認識論的な問題」について語り出した。彼の目的が、アインシュタインにコペンハーゲンの解決策の正しさを納得させることにあるのは、誰の目にも明らかだった。』
『アインシュタインは、ボーアが自分の信念の概略を語るあいだ、じっとその言葉に耳を傾けていた。ボーアは、波と粒子の二重性は相補性という枠組みの中でしか説明できないと主張した。また、不確定性原理は、自然に本来にそなわっている特徴であり、古典的念に適用限界があることを明らかにするものだが、その基礎は相補性にあると述べた。そして、量子の世界を調べるために行われた実験の結果を明確に伝達するためには、観測結果そのものだけでなく、実験の設定についても、「古典物理学の語彙を適切に磨き上げた」言葉で表現しなければならないとボーアは主張した。
1927年2月、ボーアが相補性に向かってじりじりと考察を進めていたところ、アインシュタインはベルリンで光の性質に関する講演を行っていた。アインシュタインは、光の量子論と、光の波動論のどちらか一方ではなく、「それらふたつの概念を統合しなければなりません」と主張した。彼がその考えを最初に明らかにしたのは、もう二十年ほども前のことだった。アインシュタインは、「統合」を待望していたのに対し、ボーアは相補性を導入し、波と粒子の性質を、互いに相容れないものとして分離しようとしていた。どんな実験をするかによって、光は波であったり粒子であったりするというのだ。
科学者たちは従来、自分が見ているものを攪乱せずに観測できるという、暗黙の前提の上に立って実験を行ってきた。客体と主体、観測者と観測対象は、はっきりと区別されていたのである。しかしコペンハーゲン解釈によれば、原子の領域では、もはやその区別は成り立たない。その原因を、ボーアは「量子仮説」に求めた―それを彼は、新しい物理学の「エッセンス」と呼んだ。量子仮説とは、量子がそれ以上分割不可能な塊になっているせいで、自然界に不連続性が生じるということを捉えるために、ボーアが導入した言葉である。量子仮説を受け入れれば、観測対象と観測者をはっきり区別することはできなくなる、とボーアは述べた。観測を行おうとすると、測定対象と測定装置とのあいだでかならず相互作用が起こる。しかし量子は塊になっているので、その相互作用を好きなだけゼロに近づけることはできない。そのため原子の領域では、「現象と観測者のどちらに対しても、通常の意味での、独立した物理的実在性を与えることはできない」というのがボーアの考えだった。
ボーアのイメージする実在は、観測されなければ存在しないようなものだった。コペンハーゲン解釈によれば、ミクロな対象はなんらかの性質をあらかじめもつわけではない。電子は、その位置を知るためにデザインされた観測や測定が行われるまでは、どこにも存在しない。速度であれ、他のどんな性質であれ、測定されるまでは物理的な属性をもたないのだ。ひとつの測定が行われてから次の測定が行われるまでのあいだに、電子はどこに存在していたのか、どんな速度で運動していたのか、と問うことは意味がない。量子力学は、測定装置とは独立して存在するような物理的実在については何も語らず、測定という行為がなされたときにのみ、その電子は「実在物」になる。つまり、観測されない電子は、存在しないということだ。
「物理学の仕事を、自然を見出すことだと考えるのは間違いである」とボーアはのちに述べた。「物理学は、自然について何が言えるのかに関するもの」であって、それ以外のなにものでもないというのがボーアの考えだった。彼にとって、科学にはふたつの目的があった。「経験できることの範囲を広げること、そして経験を秩序立てること」だ。アインシュタインはかつてこう述べた。「われわれが科学と呼ぶものの唯一の目的は、存在するものの性質を明らかにすることである」。アインシュタインにとって物理学とは、観測とは独立した存在をありのままに知ろうとすることだった。アインシュタインが、「物理学において語られるのは、“物理的実在”である」と述べたのは、その意味でだった。コペンハーゲン解釈で武装したボーアにとって、物理学において興味があるのは、「何が実在しているか」ではなく、「われわれは世界について何を語りうるか」だった。ハイゼンベルクはその考えを、のちに次のように言い表した。日常的な世界の対象とは異なり、「原子や素粒子そのものは実在物ではない。それらは物事や事実ではなく、潜在性ないし可能性の世界を構成するのである」。
ボーアとハイゼンベルクにとって、「可能性」から「現実」への遷移が起こるのは、観測が行われたときだった。観測者とは関係なく存在するような、基礎的な実在というものはない。アインシュタインにとって科学研究は、観測者とは無関係な実在があると信じることに基礎づけられていた。アインシュタインとボーアとのあいだに起ころうとしている論争には、物理学の魂ともいうべき、実在の本性がかかっていたのである。』
『第五回ソルヴェイ会議は、ブリュッセルに集まった人たちに次のような印象を残した。ボーアは、コペンハーゲン解釈は論理的に無矛盾だと論証することには成功したが、「完全」で閉じた理論についての唯一可能な解釈だとアインシュタインに納得させることはできなかった、と。アインシュタインは会議からの帰りに、ド・ブロイら数人とともにパウリに立ち寄った。彼はこのフランスの貴公子との別れの際に、「続けなさい、あなたは正しい道を歩いている」と言った。しかしブリュッセルで支持を得られなかったことで傷心したド・ブロイは、その後まもなく自説を撤回し、コペンハーゲン解釈の支持に回る。ベルリンに帰り着いたアインシュタインはすっかり疲れ果て、気が抜けたようになっていた。二週間後、彼はアルノルト・ゾンマーフェルトに手紙を書いて、量子力学は「統計的法則を記述するという意味では正しい理論かもしれませんが、基本的な個々のプロセスを記述する理論として適切ではありません」と述べた。
ポール・ランジュヴァンは後年、1927年のソルヴェイ会議で、「概念の混乱は頂点に達した」と述べたが、ハイゼンベルクにとってはこの会議こそ、コペンハーゲン解釈の正しさを証明する道のりの決定的な転換点だった。会議が終わった時点で、ハイゼンベルクはある人物への手紙に、「科学的な成果に関しては、あらゆる点で満足しています」と書いた。「ボーアとわたしの観点は全般的に受け入れられました。少なくとも、深刻な反論は、アインシュタインとシュレーディンガーからさえ、もはや出てきませんでした」。ハイゼンベルクの見るところ、彼は勝利を収めたのだ。彼はそれからほぼ四十年を経て次のように語った。「われわれは古い言葉を使い、それを不確定性関係により制限することで、あらゆることを明らかにすることができたし、首尾一貫した描像を作ることもできた」。「われわれ」とは誰のことかと問われて、ハイゼンベルクはこう答えた。「当時、それは事実上、ボーアとパウリとわたしだった。』
39.ボーア(コペンハーゲンメンバー)とアインシュタインの議論
●ボーアとアインシュタインの論争は会議の外、ホテルのダイニングルームで行われました。アインシュタインは新たな思考実験で武装して、朝食の席に現われました。
『一般的討論の時間にアインシュタインが口を開いたのは、この後はあと一度、ひとつ質問をしたときだけだった。後半ド・ブロイは、「アインシュタインは、確率解釈に対するごく簡単な反論をした以外はほとんど何も言わなかった」と語った。その発言の後、アインシュタインは「ふたたび口をつぐんだ」と。しかし、参加者全員がホテル・メトロポールに滞在していたため、突っ込んだ論争は生理学研究所の会議室でではなく、ホテルのエレガントなアール・デコ様式のダイニングルームで行われていたのである。ハイゼンベルクは、「ボーアとアインシュタインは全面戦争に突入した」と言った。
貴族にはめずらしく、ド・ブロイはフランス語しか話さなかった。彼はダイニングルームでアインシュタインとボーアが話し込んでいて、ハイゼンベルクとパウリらがそれを熱心に聞いているのを見ていたに違いない。しかし彼らはドイツ語で話していたので、ド・ブロイは、アインシュタインとボーアが、ハイゼンベルク言うところの「全面戦争」をしているとは思わなかったのだろう。思考実験の達人として知られるアインシュタインは、毎朝、不確定性原理と、この原理とともに称賛されていたコペンハーゲン解釈の無矛盾性に挑む、新たな思考実験で武装して朝食の席に現われた。
コーヒーとクロワッサンを取りながら、その思考実験の分析が始まった。議論はアインシュタインとボーアが生理学研究所に向かう途中も続けられ、たいていはハイゼンベルク、パウリ、エーレンフェストが、ふたりの後にぞろぞろとついていった。アインシュタインとボーアが歩きながら論じ合ううちに、仮説が洗い出され、論点が明らかにされた。そうこうするうちに午前の部のセッションが始まるのだった。ハイゼンベルクはのちにこう語った。「会議のあいだじゅう、とくに休憩時間には、われわれ若手、とくにパウリとわたしはアインシュタインの実験の分析を試みた。昼食時には、ボーアとコペンハーゲンのメンバーが集まって議論を続けた」。夕方になり、さらにコペンハーゲンのメンバーで相談した後に、共同でアインシュタインの反論に立ち向かった。メトロポール・ホテルで夕食の時間になると、ボーアはアインシュタインに、彼の新しい思考実験は不確定性原理によって課される限界を破ってはいないことを説明するのだった。どの思考実験についても、アインシュタインはコペンハーゲンの反論に欠陥を見出すことができなかったが、ハイゼンベルクが述べたように、「彼が心から納得しているわけではない」のも明らかだった。
ハイゼンベルクがのちに語ったところによれば、数日後、「こうしてボーア、パウリ、そしてわたしは、自分たちの一致点はゆるぎないとわかって納得し、アインシュタインも、量子力学の新しい解釈は、それほど簡単に論駁できないらしいということは理解したようだった」。しかしアインシュタインは屈しなかった。彼は、たとえそれがコペンハーゲン解釈を拒否する理由の本質を捉えてはいけないとしても、「神はサイコロを振らない」という言葉をたびたび口にした。あるときボーアはそれに対して、「しかし、神がどうやってこの世界を回しているのかなど、われわれにはわからないでしょう」と言った。パウル・エーレンフェストは、半ば冗談としてこう言った。「アインシュタイン、残念ながら、きみが新しい量子論に反対するやり方は、きみの敵対者たちが相対性理論について反対するやり方とまったく同じだよ」
アインシュタインとボーアが1927年のソルヴェイ会議で非公式に繰り広げた議論を、偏りのない立場から目撃していた唯一の人物がエーレンフェストだった。ボーアはのちにこう述べた。「アインシュタインの意見が、少数の集団のあいだで熱烈な議論を引き起こした。双方と長年にわたり親しい友人だったエーレンフェストは、きわめて積極的かつ有益なかたちで議論に参加した」。会議が終わって数日後、エーレンフェストはライデン大学の学生たちに手紙を書き、ブリュッセルでの出来事を生き生きと伝えた。「ボーアがみんなを完全に圧倒しています。はじめは誰も彼の言うことが理解できないのですが(ボルンもその場にいました)、ボーアは一歩一歩、みんなを説き伏せて行くのです。もちろん、ボーアは、あの恐るべき意味不明な文句を呪文のように唱えます(気の毒に、ローレンツはイギリス人とフランス人のために通訳をしていますが、まったく意味が伝わりません。ローレンツはボーアの話したことをまとめようとするのですが、ボーアは礼儀正しく、それは自分の言っていることとは全然違うと言うのです)。毎晩夜中の一時になると、ボーアはわたしの部屋にやってきて、「ひとことだけ」と言いながら、午前三時までしゃべり続けます。ボーアとアインシュタインとの対話をそばで見ていられたことは、わたしにとっては喜びでした。ふたりにとって、あれはチェスのようなものなのです。アインシュタインはいつも新しい例を携えてやってきます―それで不確定性関係を打倒しようというのです。ボーアは哲学的なもやのなかから、アインシュタインが次々と打ち出す例を論破する道具を探しだしてきます。しかしアインシュタインは、あたかもびっくり箱の中から飛び出してくる人形のように、毎朝、新しくなって飛び出してきます。こういう議論の価値は計り知れません。しかしわたしはほとんど躊躇なくボーアに賛成し、アインシュタインには反対です」。それでもエーレンフェストはこう認めた。「しかし、アインシュタインと意見の一致をみるまでは、ボーアの心が休まることはないでしょう」
ボーアは後年、1927年のソルヴェイ会議でのアインシュタインとの対話は、「とても楽しい気分のなかで行われた」と語った。しかし彼は少し残念そうにこう言い添えた。「ものの見方や考え方には一定の違いが残った。なぜならアインシュタインは、連続性と因果律を捨てずとも、一見してまったく異質な経験を調和させるみごとな腕前があったので、その理想を捨てる気になれなかったのだろう。それに関して言えば、この新しい学問分野を探求するにあたって、日々新たに蓄積されている原子レベルの現象に関する多くの証拠を調和させるという差し迫った仕事をするためには、連続性と因果律を断念するしかないと考える者たちよりも思い切りが悪かったのだろう」。つまりボーアは、アインシュタインの収めた成功そのものが、彼を過去に縛りつけたと言っているのである。』
40.「コペンハーゲン解釈」という命名は1955年(28年後)
●イタリアのコモで開催された国際物理学会、そしてベルギーのブリュッセルでの第五回ソルヴェイ会議は1927年に開催されました。「コペンハーゲン解釈」は、それから28年後にハイゼンベルクが使った言葉でした。その中核にあったのは“相補性”であり“統合”を目指したアインシュタインにとっては納得できるものではありませんでした。しかし、アインシュタインは否定はせず、「とても繊細にまとめられている」という認識を持っていました。良くいえば包括的、悪いくいえば寄せ集め的だったかもしれませんが、不可思議なミクロの量子物理学を説明するにはこれが最善だったのだと思います。
『ボーアは、「コペンハーゲン解釈」という言葉を一度も使わなかったし、1955年にハイゼンベルクが使うときまで、誰もこの言葉を使っていない。しかし、初めはほんの一握りの熱狂的な支持者しかいなかったこの解釈は、その後すみやかに広がり、最終的にはほとんどすべての物理学者にとって、「量子力学のコペンハーゲン解釈」は、量子力学と同義語になった。この急速な、「コペンハーゲン精神」の広がりと受容の背景には三つの要素があった。ひとつは、ボーアと彼の研究所が果たした重要な役割である。若いポスドクの時代にマンチェスターのラザフォードの研究所に滞在したときの経験に触発されたボーアは、それと同じような活気―やればできるという感覚―にあふれた、自分自身の研究所を作ることに成功したのだ。
「ボーアの研究所はすみやかに量子物理学の世界的中心地となり、昔のローマ人たちの言葉をもじれば、「すべての道はブライダムスヴァイ十七番地に通ず」という状況だった」と語るのは、1928年の夏にそこを訪れたロシア人のジョージ・ガモフである。アインシュタインが所長を務めるカイザー・ヴィルヘルム理論物理学研究所は書物の上にしか存在せず、アインシュタインはそれでよいと思っていた。彼はたいていひとりで仕事をし、のちには計算をやってくれる助手をひとり雇っただけだったのに対し、ボーアは科学上の子どもたちをたくさん育て上げた。その中でも最初に卓越した権威としての地位にのぼったのは、ハイゼンベルク、パウリ、ディラックだった。後年、ラルフ・クロー二ヒが回想したところでは、この三人はまだ若かったが、ほかの若い物理学者たちがあえて彼らに反論することはなかった。クロー二ヒ自身、パウリにスピンというアイデアを馬鹿にされて、電子のスピンをしまい込んだのだった。
第二の要因として、1927年のソルヴェイ会議のころに、教授のポストにたくさん空きが出たことがある。その席のほとんどすべてを、量子力学という新しい物理学を作るために貢献した者たちが占めた。彼らが向かった研究所は、その後すみやかに、ドイツをはじめヨーロッパ中からもっとも優秀な学生を引き付けるようになる。シュレーディンガーはベルリンで、プランクの後継者というもっとも名誉ある地位に就いた。ソルヴェイ会議の直後に、ハイゼンベルクはライプツィヒ大学の正教授となり、理論物理学研究所の所長も兼任するようになった。その六カ月後の1928年4月には、パウリがハンブルクからチューリッヒに移り、スイス連邦工科大学の教授になった。パスクアル・ヨルダンの数学の力量は、行列力学を発展させるにあたって決定的に重要な役割を果たしたが、そのヨルダンがハンブルクでパウリの後任となった。まもなくハイゼンベルクとパウリは頻繁に行き来するようになり、助手や学生をお互いの研究室やボーアの研究所とで交換し、ライプツィヒとチューリッヒをともに量子力学の中心地にした。クラマースはすでにユトレヒト大学に着任していたし、ボルンはゲッティンゲンにポストを得ていた。かくしてコペンハーゲン解釈はすみやかに量子論の定説となったのである。
三つ目の要因として、ボーアと若い協力者たちは、それぞれ意見に違いがあったにもかかわらず、コペンハーゲン解釈に異議を唱える声に対してはつねに統一戦線を張ったことが挙げられる。唯一の例外が、ポール・ディラックだった。1932年9月に、ケンブリッジ大学でかつてアイザック・ニュートンが務めていた数学のルーカス教授職に着任したディラックは、量子力学の解釈問題にはついに関心を持たなかった。彼にはこの問題が、新しい方程式をもたらさない、つまらない執着のように思えたのだ。興味深いことに、彼は自分のことを数理物理学者と呼んだのに対し、同世代のハイゼンベルクやパウリも、またアインシュタインもボーアも、そう名乗ることは決してなかった。』
『ボーアの論文が英語とドイツ語とフランス語の三カ国語で出版された。英語版は「量子仮説と原子論の最近の発展」と題されて、1928年4月14日に刊行された。その脚注に、「本論文の内容は、1927年9月16日に、コモで開かれたボルタ記念会議で量子論の玄奘について行った講義と本質的に同じものである」とあった。しかし実を言えば、ボーアはその論文のために、コモでの講演とブリュッセルでの発言のどちらよりも、相補性と量子力学に関するアイデアをさらに練り上げていたのである。
ボーアはシュレーディンガーにその論文を一部送り、シュレーディンガーは次のように返信した。「もしもひとつの系、つまり質点を、そのp(運動量)とq(位置)を特定して記述したければ、そのような記述は限られた正確さでしかできないということですね」。だとすれば、そのような制約を受けないような新しい概念を導入する必要がある、とシュレーディンガーは論じ、こう結論した。「しかし、そのような概念的な枠組みを発明するのは非常に難しいということに疑問の余地はないでしょう。というのは―あなたがきわめて印象的に力説したように―そのような枠組みを新しく作るためには、われわれの経験のもっとも深いレベル―すなわち空間と時間と因果律―に触れずにはすまないからです」
ボーアはシュレーディンガーに、「一定の理解を示してくれたこと」には感謝するが、シュレーディンガーは古い経験的な概念を、「視覚化という人間の手段の基礎」と分かちがたく結びつけているので、量子論では「新しい諸概念」が必要だということが理解できていないように見える、と書いた。そしてボーアはふたたび持論を繰り返した。すなわち、問題は古典的な諸概念の適用可能性に多少とも恣意的な制限があるかどうかではなく、観測という概念を分析する相補性という不可避的な特徴が現れることなのだ、と。ボーアは最後に、この手紙の内容についてプランクやアインシュタインと議論してみてもらえないかと書いた。シュレーディンガーがアインシュタインに、ボーアとのやりとりのことを話すと、アインシュタインはこう述べた。「ハイゼンベルク=ボーアの心休まる哲学―というより宗教?―は、たいへん繊細に作り上げられているので、当面、真の信者には優しい枕になってくれるでしょう。信者はそのまどろみから容易には起きないでしょう。そのまま寝かしておきましょう」。』
ボーアとアインシュタイン4
28.数学的には等価だが物理的世界が異なる波動力学と行列力学
●一度は断念したシュレーディンガーによる二つの量子力学の関係を明らかにする研究は、ついに実を結びました。
『1925年の春が夏に変わろうとするころには、古典物理学においてニュートン力学が果たしたような役割を、原子物理学において果たすべき理論―量子力学―は、まだ存在していなかった。ところがその一年後には、粒子と波ほども性格の異なる、ふたつのライバル理論が存在していた。しかもそれらの理論を同じ問題に当てはめてみると、まったく同じ結果が得られたのだ。ひょっとすると、行列力学と波動力学のあいだには何か関係があるのでは? シュレーディンガーは、画期的な論文を書き終えた直後から、そのことを考えはじめた。彼は二週間ばかり、ふたつの理論の関係を探ってみたが、何も見出せなかった。「結局、それ以上探すのは諦めました」と、シュレーディンガーはヴィルヘルム・ヴィ―ンへの手紙に書いた。関係が見出せなくても、彼は少しも困らなかった。なにしろシュレーディンガーは、「自分の理論がぼんやり頭に浮かぶよりだいぶ前から、行列計算には耐えられないと思っていたから」だ。しかし結局、彼は両者の関係をさらに追及せずにはいられず、ついに三月の初めに、それを発見する。
形の上でも、内容という点でも大きく異なる二つの理論―一方は波動方程式を用いて波を記述し、他方は行列代数を用いて粒子を記述する理論―は、数学的には同じものだったのだ。両者がまったく同じ答えを与えたのも当然のことだった。まもなく、形のうえでは異なっても、互いに等価であるようなふたつの方程式があることの利点が明らかになった。物理学者が出会うほとんどすべての問題で、シュレーディンガーの波動力学のほうが容易に答えを与えてくれた。しかしそれ以外の側面、たとえばスピンが関係する問題では、ハイゼンベルクの行列のアプローチのほうが役に立つことが示されたのだ。
かくして物理学者の関心は、理論の数学的形式から、物理的解釈へと移っていった。ふたつの理論のどちらが正しいのかという、起こっても不思議はなかった論争は、起こる前に息の根を止められたのである。ふたつの理論は、数学的には等価かもしれないが、その背後にある物理的世界は大きく異なっていた―シュレーディンガーの波はなめらかで連続的なのに対し、ハイゼンベルクの粒子は飛び飛びで不連続なのだ。シュレーディンガーとハイゼンベルクはふたりとも、自分の理論のほうが自然の物理的世界の姿を正しく捉えていると堅く信じていた。しかし、それに関するかぎり、両方とも正しいということはありえなかった。』
29.波動力学の限界
●波動方程式はヘリウムやそれより重い原子に当てはめると視覚化は失われ、抽象的な多次元空間なってしまいます。また、光電効果やコンプトン効果を説明することができませんでした。物理学者でも苦労するような行列ですが、量子を幅広く説明するうえでは、ハイゼンベルクの行列力学の方が優れているようです。
『波動力学の波動関数は数学者のいう「複素数」なので、それを直接測定することはできない。複素数は、たとえ4+3iのように、実部と虚部をもつ。このとき実部は4で、普通の数である。虚部は3iである。このiには物理的な意味がない。なぜなら、それはマイナス1の平方根だからである。ある数の平方根とは、二乗したときにその数になるものだ。4の平方根は、2である。(2×2=4)。二乗してマイナス1になる数は存在しない。1×1=1だが、-1×-1もやはり1である。なぜなら、マイナス×マイナスはプラスだからだ。
波動関数を観測することはできない―波動関数は、見ることも触ることもできない観測不可能な雲のようなものだ。しかし複素数を二乗すれば、実験で測定できる量と結びついた実数になる。たとえば、4+3iを二乗すれば、25になる。シュレーディンガーは、電子の波動関数を二乗したもの、|ψ(x,t)|²は、場所xと時刻tにおける電荷の密度を表すと考えたのだ。
波動関数をそのように解釈することに関係して、シュレーディンガーは粒子の実在性に疑問を突きつけ、電子を表すために「波束」というものを導入した。電子を粒子と見なす立場には実験の強力な裏づけがあったにもかかわらず、シュレーディンガーは、電子は粒子のように「見える」だけで、じつは粒子ではないと論じたのである。粒子としての電子というイメージは幻想だ、と彼は考えた。現実の世界に存在するのは波だけであり、電子が粒子のように見えるのは、多数の物質波が重なり合い、波束を作っているからだ、と。空間を進む電子は、波束として進んで行く―ちょうど、一端を固定されたロープの他端を手に持ち、手首を動かして作ったパルスがロープを伝わって行くように。粒子状の波束ができるためには、その粒子に相当する小さな空間領域の外では、さまざまな波長の波が互いに干渉し、打ち消し合わなければならない。
粒子を諦め、すべてを波に還元することで、不連続性と量子飛躍の物理学を回避できるなら、それはシュレーディンガーにとって払う価値のある代償だった。しかしまもなく、彼の解釈は物理的に意味をなさないことが明らかになった。第一に、波束として表された電子は、バラバラに崩れてしまうのだ。もしもその電子を、粒子としてじっさいに検出されている電子と結びつけようとすれば、空間に広がった構成要素の波は、光の速度よりも速く進まなければならないことになる。
シュレーディンガーは、波束が崩れるのをなんとか食い止めようとしたが、手の打ちようがなかった。波速は、波長も振動数も異なるたくさんの波でできているため、それぞれの波が異なる速度で進み、波束はすぐに広がりはじめる。そのため、電子が粒子として検出されるときにはつねに、それぞれの波が瞬間的に一カ所に集中して波束にならなければならない―空間に広がっていたものが、一瞬のうちに、ある一点に局在しなければならないのだ。第二の問題は、波動方程式をヘリウムや、それより重い原子に当てはめようとすると、シュレーディンガーの数学の基礎にある視覚化しやすい世界は、抽象的な多次元空間へと消えてしまうことだった。
一個の電子の波動関数には、三次元の電子の波に関して知るべきことがすべて符号化されている。しかし、ヘリウム電子には、電子が二個含まれており、それらを表す波動関数は、普通の三次元空間のふたつの波ではなく、奇妙な六次元空間に生息するひとつの波になってしまうのだ。周期表の中で、ひとつの元素から次の元素へと順に進んでいくにつれ、電子は一個ずつ増えていく。そして電子が一個増えるたびに、新たに三つの次元が必要になる。そんなわけで、周期表の元素であるリチウムの波動関数は九次元空間を必要とし、ウランの波動関数ともなれば276次元もの空間に生息することになるのである。そういう抽象的な多次元空間の波は、シュレーディンガーが期待したような、連続性を回復させ、量子飛躍を駆逐してくれる物理的な実在の波ではありえなかった。
また、シュレーディンガーの解釈では、光電効果やコンプトン効果を説明することができず、そのほかにも、たとえば次のような問題に答えることができなかった。波束に電荷をもたせるにはどうすればよいのか? 波動力学は、純粋に量子的なものであるスピンを組み入れることができるのか? シュレーディンガーの波動関数が、日常的な三次元空間の中の波を表していないのなら、それはいったい何を表しているのだろうか? これらの問いに答えを与えたのがマックス・ボルンだった。』
30.古典的確率とは異なる量子的確率を使って波と粒子を統合する方法
●ボルンにとって量子の粒子性を否定することはできませんでした。それはゲッティンゲンで行われていた原子同士を衝突させる実験を通して、「粒子という概念の豊かさ」を実感していたからです。
『シュレーディンガーが、粒子性と量子飛躍は認められないと論じている点は、ボルンは到底受け入れるわけにはいかなかった。彼はかねてから、ゲッティンゲンで行われていた原子同士を衝突させる実験を見ており、「粒子という概念の豊かさ」を実感していたからだ。ボルンは、シュレーディンガーの方程式が優れていることは認めたものの、彼の解釈は受け入れなかった。ボルンは1926年の末に、「シュレーディンガーの形式だけを残して、そこに何か新しい物理的内容を盛り込むためには、彼の物理的描像はすっかり捨て去らなければなりません。彼の描像は、古典的な連続の理論を復活させようとするものです」と述べた。「おいそれと粒子を捨て去るわけにはいかない」と確信していたボルンは、波動関数の新しい解釈を考えるなかで、確率を使って波と粒子を統合する方法を見出すのである。』
『ニュートンの宇宙は完全なる決定論の世界であり、そこに偶然の出る幕はない。そのような宇宙では、粒子は与えられた任意の時刻に、はっきりとした運動量と位置をもっている。粒子の運動量と位置が時間とともにどう変わるかは、その粒子に作用する力によって決まる。』
『あらゆることが自然法則に従って進展する決定論的宇宙において確率が顔を出すとすれば、それは人間の無知の反映だった。もしも任意の系で、その系の現在における状態と、その系に作用する力が完全にわかっているなら、未来においてその系に起こることはすべて決定される。古典物理学における決定論は、すべての作用には原因があるという「因果律」の母体と、へその緒でつながっているのだ。
二個のビリヤードの玉が衝突するように、電子が原子に衝突すれば、その電子はあらゆる方向に散乱される可能性だある。しかし電子とビリヤードの玉との類似性が成り立つのはそこまでだ、とボルンは述べて、驚くべき主張をした。原子レベルの衝突に関して、物理学に答えることができるのは、「衝突後の状態はどうなるのか?」という問いではなく、「その衝突の結果として、所定の結果になる可能性はどれだけあるのか?」という問いだというのである。「かくして決定論という大問題が持ち上がる」と、ボルンは自ら認めた。衝突の後で、電子が正確にどこに存在するのかを知ることはできない。物理学者にできるのはただ、電子がある角度に散乱される確率を計算することだけだ、とボルンは述べた。それがボルンの言う「新しい物理的内容」であり、彼の波動関数解釈はすべてそこにかかっていた。
波動関数そのものには物理的実在性はない。波動関数は、ぼんやりとした不思議な可能性の領域に存在している。波動関数は、たとえば原子と衝突した電子が散乱されるかもしれない角度をすべて足し合わせたような、抽象的な可能性を表しているのだ。そのような可能性と確率とのあいだには、大きな違いがある。ボルンは、波動関数を二乗したもの―複素数ではなく実数―は、確率の領域に存在していると論じた。波動関数を二乗しても、たとえば、電子のじっさいの位置が得られるわけではない。それが教えてくれるのは、電子がどこに見出されるかの確率だ。もしも電子の波動関数の値が、場所Yでよりも、場所Xでのほうが二倍大きいとすると、電子がXに見出される確率は、Yに見出される確率よりも四倍大きい。しかし、その電子はXに見出されることもあるし、Yや、それ以外の場所に見出されることもある。』
『自分[ボルン]が物理学に持ち込んだ確率は、従来のものとはまったく異なるということにボルンが十分に納得するまでには、ふたつの論文のあいだに流れた十日間という時間が必要だったのだ。その奇妙な「量子的確率」は、情報の不足から生じ、それゆえ理論上は取り除くことができる古典的確率とは別のものである。それは原子の領域にどこまでもついてまわる性質なのだ。たとえば、放射性物質の内部で、放射性原子がいずれ崩壊するのは確実だが、個々の原子がいつ崩壊するかを予測することができない。それは情報が足りないために予測できないのではなく、放射性崩壊を支配する量子的なルールが確率的性質をもつためなのである。』
31.アインシュタインとハイゼンベルク
●1926年4月28日、ハイゼンベルクはベルリン大学での物理学談話会(コロキウム)の後、アインシュタインに「うちに来ないか」と誘われました。
『講義机にノートを広げ、黒板の前に立ったハイゼンベルクはカチカチに緊張していた。才気あふれる二十五歳の物理学者が硬くなるのも無理はなかった。1926年の4月28日水曜日、彼はベルリン大学の有名な物理学談話会(コロキウム)で、行列力学に関する講義をしようとしていたのだ。ミュンヘンやゲッティンゲンがどれだけの成果を挙げていようと、ハイゼンベルクがいみじくも「ドイツ物理学の牙城」と呼んだのはベルリンだった。聴衆を見渡しながら、ハイゼンベルクは最前列に並んだ四人のノーベル賞受賞者に目を止めた―マックス・フォン・ラウエ、ヴォルター・ネルンスト、マックス・プランク、そしてアルベルト・アインシュタインの面々である。
「そんなにたくさんの有名人と会える初めての機会」にどれほど緊張していたにせよ、「当時としてはかなり型破りな理論の基本的概念と数学的基礎について、わかりやすく説明」できたと我ながら思えるような話をするうちに、ハイゼンベルクの緊張はすぐにほぐれていった。講義が終わり、聴衆がバラバラと帰りはじめたころ、アインシュタインがハイゼンベルクに声をかけ、これからうちに来ないかと誘った。ハーバーラント通りを三十分ばかり歩きながら、アインシュタインがハイゼンベルクに尋ねたのは、家族のことや教育のこと、それまでの研究のことだった。いよいよ本題の議論が始まったのは、アインシュタインの家に着いて、ふたりがゆったり椅子に腰を下ろしてからのことだ。』
32.アインシュタインにとっての行列力学
●量子物理学の歩みにおいて、アインシュタインは時に要所要所に存在する関所のような大きな存在だったようです。また、相対性理論の中でアインシュタイン自身が選択したものではありましたが、「観測可能な量だけからなる理論を見つけようとするのは、完全に間違っている」という考えは揺るぎないものでした。
『ハイゼンベルクの回想によれば、アインシュタインは、「きみの最近の仕事の、哲学的な前提」について尋ねたいと切り出した。「きみは原子の内部に電子が存在すると仮定しているが、それはおそらく正しいだろう」とアインシュタイン。「しかし、霧箱の中に電子の軌跡が見えてもなお、きみは軌道というものを認めないと言うのだね。なぜそんなおかしなことを言い出すのか、その理由をもう少し詳しく聞かせてもらえるだろうか?」。ハイゼンベルクにとってはチャンス到来だった。彼は、この四十七歳の量子論の大家を説得して、なんとか味方に引き入れたいと思っていたのだ。
「われわれは原子内の電子の軌道を見ることはできません」と、ハイゼンベルクは説明を始めた。「しかし放電現象では原子が放射を出しますから、そこから原子内電子の振動数と、それに対応する振幅を導き出すことはできます。そしてハイゼンベルクは持論を開陳しはじめた。「良い理論は、直接的に観測可能な量にもとづかなければならないのですから、電子の軌道の代わりに、振動数と振幅だけを使ったほうがよいと思ったのです」。アインシュタインはそれを聞いてこう言った。「しかし、物理理論には観測可能な量だけしか入ってこないなどと、本気で思っているわけではないだろう?」。それはハイゼンベルクが新しい力学を作る際に、基礎としたものを直撃する問いだった。ハイゼンベルクは驚いてこう聞き返した。「でも、それはあなたが相対性理論を作ったときに基礎とした考え方そのものではありませんか?」
アインシュタインは微笑んでこう言った。「うまい手は二度使っちゃいけないよ」。「たしかに、わたしはその考え方を使ったかもしれない」と彼は認めた。「それでもやはり、そんなものは馬鹿げた考えなのだ」。何がじっさいに観測できるかを考えてみることは、発見法的には役に立つかもしれないが、原理的な観点からは、「観測可能な量だけからなる理論を見つけようとするのは、完全に間違っている」とアインシュタインは言った。「なぜなら事実はその逆だからだ。何が観測可能かを決めているのは、理論なのだよ」。アインシュタインは何を言わんとしているのだろうか?
それよりおよそ百年前の1830年、フランスの哲学者オーギュスト・コントは、いかなる理論も観測に立脚しなければならないが、われわれの頭脳は観測を行うために理論を必要としてもいると論じた。アインシュタインは、観測というものは一般にきわめて複雑なプロセスであり、理論に使われている現象についての仮説もからんでくるということを説明しようとした。「観測している現象は、測定装置の内部で何らかの反応を引き起こす。その結果として、装置内でさらに別のプロセスが起こり、複雑な道筋を経て、最終的には知覚的な印象を生じさせ、われわれの意識に結果を定着させるわけだ」。その結果がどのようなものになるかは、どんな理論を使うかによる、とアインシュタインは言うのだ。「きみの理論にしたって、振動する原子から光が飛び出し、その光が分光器や観測者の目に届くまでのメカニズムは、誰もが仮定するように、やはり本質的にはマクスウェルの法則に従うと仮定しているわけだろう。もし、それすらも仮定しないというなら、きみが観測可能だと言っている量はすべて、そもそも観測できないのだから」。アインシュタインはたたみかけた。「つまり観測可能な量しか持ち込んでいないというきみの主張は、きみが定式化しようとしている理論の性質に関する、ひとつの仮説なのだよ。」のちにハイゼンベルクは、「アインシュタインのその意見には完全に意表を突かれたが、彼の議論には説得力があると思った」と述べている。』
『アインシュタインを説得できずに落胆しつつ辞去するとき、ハイゼンベルクは決断を下さなければならない案件を抱えていた。それから三日後の5月1日には、彼はコペンハーゲンにいる予定になっていた―ボーアの助手とコペンハーゲン大学の講師という、ふたつの仕事が始まるからだ。しかしつい最近、ハイゼンベルクはライプツィヒ大学から正教授として招聘されたのだ。彼のような若輩者にとって、正教授という申し出は非常に名誉なことだったが、はたしてその招きを受けるべきだろうか? ハイゼンベルクはアインシュタインに、この難しい選択のことを話した。ボーアのところに行って、彼といっしょに仕事をしなさい、というのがアインシュタインのアドバイスだった。翌日、ハイゼンベルクは、ライプツィヒからの申し出は断るつもりだと両親に手紙を書いた。「よい論文を書き続ければ、これからもお呼びはかかるでしょう。もしそうでなかったなら、もともと自分にはその価値がなかったということです」。』
33.ボーアとハイゼンベルク(量子の世界のあいまいさの核心、波と粒子の二重性の問題)
●昔の日本の師匠と弟子のような関係だったボーアとハイゼンベルクにとって、最大の問題は古典物理学では考えられない「波と粒子が同時に存在すること」でした。ハイゼンベルクにとって数学を中心に組み立てた理論である行列力学は絶対的なものでしたが、ボーアは波動力学も重要であり、数学の背後にある物理を理解することを優先しました。「原子レベルのプロセスを完全に記述する理論、その理論の内部で粒子と波が同時に存在できるようにするための方法を見つけなければならない」と確信していたボーアにとって、粒子と波という互いに相容れない概念を調停することが、矛盾のない量子力学の物理的解釈へと続く扉を開けるための鍵と考えていました。
『1926年の5月半ば、ボーアはラザフォードへの手紙にこう書いた。「ハイゼンベルクがこっちに来ました。われわれは暇さえあれば、量子論の新展開や、この理論の大きな可能性について講論しています」。ハイゼンベルクはボーア研究所の、「壁が斜めになった小さな屋根裏部屋」に住み込んだ。部屋の窓からは緑のフェレズ公園が見えた。ボーア一家は、研究所に隣接する広々として豪華な所長邸に移っていた。ハイゼンベルクはしょっちゅうボーア邸に行っていたので、まもなく「ボーア家の人たちといっしょにいるのが当たり前のように」なった。』
『「ボーアは、われわれを苛んでいた量子論の困難について議論しようと、夜も更けてからわたしの部屋に来るのでした」とハイゼンベルクは語っている。ふたりが何より頭を痛めたのは、波と粒子の二重性だった。アインシュタインはその二重性をめぐる状況を、エーレンフェストへの手紙に次のように書いた「片手に波、もう片手には粒子! その両方が実在していることは岩のように堅い事実です。そして悪魔はそれを詩にするのです」
古典物理学では、記述すべき対象は粒子または波であって、その両方ということはありえない。ハイゼンベルクは粒子を使い、シュレーディンガーは波を使って、異なるバージョンの量子力学を発見した。行列力学と波動力学が数学的には等価であることが示されても、波と粒子の二重性について理解が深まったわけではなかった。問題は、次の疑問に答えられる者がいないことだ、とハイゼンベルクは言った。「電子は今このとき、波なのだろうか、それとも粒子なのだろうか? そして、わたしがこれこれの働きかけをしたとき、電子はどんな振る舞いをするのだろうか?」。ボーアとハイゼンベルクが、波と粒子の二重性について懸命に考えれば考えるほど、ますます謎は深まるように思われた。』
『ハイゼンベルクはそのころのことを、後年、次のように回想した。「われわれの対話はしばしば真夜中過ぎまで続いた。そうやって何カ月も頑張ったにもかかわらず満足の行く結果が得られなかったので、ふたりとも消耗し、ピリピリした雰囲気になっていった」。ボーアはもう限界だと判断し、1927年2月に四週間の休暇をとり、ノルウェーのグドブランスダールにスキー旅行に出かけることにした。ハイゼンベルクはそれを、「絶望的に難しい問題について、ひとりでじっくり考えるチャンス」と受け止め、ボーアの出発を内心うれしく見送った。最大の問題は霧箱の中の電子の軌跡だった。』
34.ハイゼンベルクの不確定性原理
●ハイゼンベルクは与えられた任意の時刻に、粒子の位置と運動量の両方を正確に測定することは量子力学によって禁じられていることを発見しました。そして、「何が観測でき、何が観測できないのかを決めているのは、理論だ」と考えました。
『ある晩遅く、研究所の小さな屋根裏部屋で仕事をしていたハイゼンベルクが、行列力学によれば存在しないはずの電子の軌跡が霧箱の中に見えるという謎について考えていると、思考がふらふらと彷徨いだした。すると突然、「何が観測できるかを決めているのは、理論なのだ」というアインシュタインの言葉が、こだまのように聞こえたのだ。自分は今、何かを掴みかけていると感じたハイゼンベルクは、頭をはっきりさせなければと思い、とうに真夜中を過ぎていたにもかかわらずフェレズ公園に散歩に出かけた。
ほとんど寒さも感じないまま、彼の考えはしだいに、霧箱に残された電子の軌跡とは実のところ何なのかという問題に絞られていった。後年、彼はそのときのことを次のように語った。「これまであまりにも安易に、霧箱の中では電子の軌跡が見えると言ってきた。しかしおそらくわれわれは、それほどのものは見ていないのだ。現実にわれわれが見ているのは、電子よりずっと大きいことのたしかな水滴の列にすぎないではないか」。こうしてハイゼンベルクは、なめらかにつながった軌跡は存在しないという確信を得た。彼とボーアは、問題の立て方を間違っていたのだ。問うべきは次のことだった。「電子がおおよそある場所にあって、おおよそある速度で移動しているという事実を、量子力学は記述できるのだろうか?」
急いで机に戻ったハイゼンベルクは、いまやすっかり手の内に入った数式をあれこれいじりはじめた。どうやら量子力学は、情報や観測可能性に制限を課しているらしかった。しかし量子力学は、観測できるものと観測できないものをどうやって決めているのだろう? その答えが不確定性原理だった。
ハイゼンベルクは、与えられた任意の時刻に、粒子の位置と運動量の両方を正確に測定することは量子力学によって禁じられていることを発見したのである。電子の位置は測定できるし、電子の速度も測定できるけれども、その両方を同時に測定することはできない。どちらか一方を正確に知れば、自然はその代償として、他方に関する情報をあいまいにする。量子の世界にはある種の駆け引きがあって、一方が正確に測定されればされるほど、それだけ他方に関する情報や予測はあいまいになるのだ。ハイゼンベルクは、もしも自分の考え通りなら、不確定性原理によって課される限界を超えて量子の世界を正確に知ることは、いかなる実験によってもできないことを悟った。もちろん、その主張の正しさを「証明する」ことは不可能だが、実験に含まれるあらゆるプロセスが「量子力学の法則に従うはずである以上」、そうでなければならないとハイゼンベルクは確信した。
彼はそれから数日間、不確定性原理―彼の好んだ呼び方によれば、「不決定性原理」―がたしかに成り立っているかどうかを調べることに専念した。ハイゼンベルクは頭の中の実験室で、不確定性原理によれば許されない正確さで、位置と運動量を同時に測定できそうな「思考実験」を次から次へと考え出した。しかし、考えついたかぎりの例で計算してみても、不確定性原理は破れなかった。とくに、あるひとつの思考実験をやってみたとき、「何が観測でき、何が観測できないのかを決めているのは、理論だ」ということを証明できたという手ごたえを得た。』
35.不確定性原理を表す式、ΔpΔp≧h/2πとΔEΔt≧h/2π
●ハイゼンベルクは二つの式の発見でジグゾーパズルは完成したと考えました。そして、その式は量子力学と古典力学の間に横たわる深くて根本的な違いを暴露するものでもありました。
『ハイゼンベルクは、ΔpとΔp(Δはギリシャ文字のデルタ)を、運動量と位置について得られる値の「あいまいさ」とすると、ΔpとΔpの積はつねにh/2π以上になることを示すことができた。その式で表せば、hをプランク定数として、ΔpΔp≧h/2πとなる。これが不確定性原理、すなわち、位置と運動量の「同時測定に関する不正確さ」の数学的表現である。ハイゼンベルクはもうひとつ、いわゆる「互いに共役な変数」であるエネルギーと時間の「不確定性関係」も見出した。ΔEを、系のエネルギーEを求める際のあいまいさ、Δtを、Eを観測した時間tのあいまいさとすると、ΔEΔt≧h/2πとなる。
当初、不確定性原理が成り立つのは、実験装置が技術的に未熟だからだろうと考える人たちがいた。いずれ装置が改良されれば、不確定性は消滅するだろう、と。そんな誤解が生まれたのは、不確定性原理の意味を明らかにするために、ハイゼンベルクが思考実験を使ったためだった。しかし思考実験とは、理想的な条件のもので、完璧な装置を用いて行う架空の実験である。ハイゼンベルクが発見した不確定性は、現実の世界に本来的に備わっている性質なのだ。原子レベルの世界で観測可能な量について、プランク定数の大きさにより規定され、不確定性関係により課される正確さの限界は、装置をどれだけ改良しても決して消滅することはない、とハイゼンベルクは述べた。この驚くべき発見の名前としては、「不確定性」や「不決定性」よりも、「不可知性」(unknowable)というほうがふさわしかったかもしれない。』
◇不可知性:人間のあらゆる認識手段を使っても知り得ないこと。
36.波と粒子の二重性を受け入れるための相補性
●ボーアにとっては波と粒子の二重性こそが量子の世界のあいまさの核心と考えており、シュレーディンガーの波束をハイゼンベルクの新しい原理と結びつけて考えていました。そのため、ハイゼンベルクの粒子と不連続性だけに立脚したアプローチには懐疑的でした。そして、ハイゼンベルクが不確定性関係に没頭していたとき、ボーアは「相補性」を思いついていました。
『ハイゼンベルクがコペンハーゲンで不確定性関係の意味を探ることに没頭していたとき、ボーアはノルウェーのゲレンデで「相補性」を思いついていた。それは彼にとって、単なるひとつの理論や原理ではなく、量子の世界の奇妙な性質を記述するために必要な、それまで欠けていた概念的枠組みだった。波と粒子の二重性という矛盾した性質は、相補性という枠組みの中にうまく収まりそうだった。電子と光子―つまり物質と放射―がもつ波と粒子というふたつの性質は同じひとつの現象の排他的かつ相補的なふたつの側面であり、波と粒子は一枚のコインの裏と表なのだ、とボーアは考えた。
相補性は、波と粒子という、古典的にはまったく異質なふたつの記述方法を、非古典的な世界を記述するために使わなければならないせいで生じた困難を、きれいに迂回するものだった。ボーアによれば、量子的な世界を完全に記述するためには、波と粒子の両方が必要不可欠であり、どちらか一方だけでは不完全な記述しかならない。光子と波はそれぞれ光について異なる絵を描き、それらふたつの絵は隣り合わせに壁に掛けてある。しかし、矛盾を避けるために制限が課されている。与えられた任意の時刻にわれわれに見ることができるのは、ふたつの絵のどちらか一方だけなのである。どんな実験を行っても、粒子と波が同時に見えることはない。ボーアは次のように主張した。「異なる条件のもとで得られた証拠は、一方の絵の中だけで理解することはできず、現象の総体のみが対象について得られる情報を尽くすという意味において、相補的なものとして捉えなければならない」
ボーアがその新しいアイデアに手ごたえを得たのは、ふたつの不確定性関係ΔpΔp≧h/2π、ΔEΔt≧h/2πに、波と連続性を嫌悪するハイゼンベルクには見えなかったものを見たときだった。プランク=アインシュタインの式 E=hvと、ド・ブロイの式p=h/λには、波と粒子の二重性が体現されている。エネルギーと運動量は粒子的な量なのに対し、振動数と波長は波の性質だ。つまりどちらの式にも、粒子の性質を記述する変数と、波の性質を記述する変数の、両方が含まれているのである。ひとつの式に、粒子と波の両方の性質が含まれていることがボーアには腑に落ちなかった。なんといっても粒子と波は、物理的に似ても似つかないものなのだから。
ボーアは、ハイゼンベルクの顕微鏡の思考実験の分析の間違いを正したとき、それと同じことが不確定性関係についてもいえることに気がついた。それに気付いたことでボーアは、相補的かつ排他的な古典的概念(粒子と波動、運動量と位置など)が、量子の世界でどこまで同時に矛盾せずに通用するかを教えているのが不確定性関係だ、という解釈に導かれたのだった。
また、不確定性関係は、エネルギー(不確定性関係の式の中のE)と運動量(p)の保存法則にもとづく記述(ボーアの言葉では「因果的記述」)と、空間(q)と時間(t)の中で出来事を追跡する記述(「時空的」記述)のどちらか一方を選ばなければならないことも意味していた。これらふたつの記述は、考えられるかぎりの実験を説明する際には、互いに排他的、かつ相補的な関係にあった。そこで、位置と運動量のような、互いに相補的な観測可能量を同時に測定しようとしたり、互いに相補的なふたつの記述を同時に用いたりすることには、自然界に本来的にそなわる限界があるのだ、とボーアは考えた。』
『ハイゼンベルクは、「粒子」、「波」、「位置」、「運動量」、「軌跡」といった古典的な概念は、原子の領域ではどこまでも無制限に使うことはできないと考えたのに対し、ボーアは、「実験データの解釈は、本質的に古典的な概念によらなければならない」と考えていた。また、ハイゼンベルクは、これらの概念は操作的に定義されなければならない(測定を介して定義されなければならない)と考えたのに対して、ボーアは、それらの概念の定義は、古典物理学でどのように使われているかによって初めから決まっていると考えていた。さかのぼって1923年のこと、ボーアは次のように書いた。「自然のプロセスに関する記述はすべて、古典物理学の理論によって導入され、定義された概念に立脚しなければならない」。不確定性原理がどんな限界を課そうとも、理論の成否は実験によって検証され、データ、論証、解釈は、すべて古典物理学の言葉と概念によって行われるという単純な理由から、古典的概念を別のもので置き換えることはできない、というのがボーアの考えだった。』
『ボーアは電子と光線、すなわち物質と放射を観測するときに、粒子と波、どちらの面が現れるかはどんな実験を行うかによると考え、それについては一歩も譲るつもりはなかった。粒子と波は、基礎となるひとつの現象の相補的かつ排他的なふたつの側面なのだから、現実の実験であれ思考実験であれ、両方の面が同時に現れることはありえない。ヤングの有名な二重スリット実験のように、実験装置が光りの干渉を見るようにデザインされている場合には、波としての光の性質が現れるし、光線を金属表面に照射して光電効果を調べるためにデザインされた実験では、粒子としての光の性質が現れる。光は波なのか、粒子なのかと問うことには意味がない。量子力学においては、光の「正体」を知るすべはない。意味のある質問はただひとつ、光は粒子として「振る舞う」のか、それとも波として「振る舞う」のかということだ。そしてその質問に対しては、「実験の選び方によって、粒子として振る舞うこともあれば、波として振る舞うこともある」と答えることになる、というのがボーアの考えだった。』
ご参考:Youtube“【スピリチュアルに騙されるな】量子力学と二重スリット実験【宇宙の真理】”(6分40秒~19分17秒に二重スリット実験について解説されています。内容は高度ですが凄い動画です)
ボーアとアインシュタイン3
19.古典物理学からの解放
●ボーアから教えられるかぎりのことを学んだハイゼンベルクは、多くの物理学者が踏み込めなかった量子的な概念は、慣れ親しんだ古典物理学の束縛から解放されることこそが、前進する鍵であることに気づきました。
『1924年9月17日にボーアの研究所に戻ったとき、22歳のハイゼンベルクは、量子物理学に関する単著または共著の優れた論文をすでに十篇以上も発表していた。彼は、自分にはまだ学ぶべきことがたくさんあり、それを教えてくれる人物としてボーア以上の適任者はいないことを知っていた。ハイゼンベルクは後年、「ゾンマーフェルトからは楽観的であることを学び、ゲッティンゲンでは数学を学び、ボーアからは物理学を学んだ」と述べた。ハイゼンベルクはそれからの七カ月間、量子論の困難を克服するためにボーアが採っていたアプローチをみっちりと教え込まれる。ゾンマーフェルトとボルンも同じ矛盾と困難に悩まされていたが、両者とも、ボーアほど四六時中その問題ばかり考えていたわけではなかった。それに対してボーアは、口から出るのは量子のことばかりというほど、この問題に没頭していたのである。
ボーアと徹底的に議論するなかでハイゼンベルクが思い知ったのは、「さまざまな実験結果を統一的に解釈することの難しさ」だった。たとえばコンプトン散乱もそのひとつだ。それは電子がエックス線を散乱させる現象で、アインシュタインの光量子仮説を支持する結果が得られていた。さらにド・ブロイが、波と粒子の二重性は、光だけでなく、あらゆる物質にまで拡張されると言い出したために、実験の解釈は何倍も難しくなったように思われた。教えられるかぎりのことをハイゼンベルクに教え込んだボーアは、この若い弟子に絶大な期待をかけた。「この苦境から脱出する道を見出すために必要なことはすべて、いまやハイゼンベルクの手中にあります」
1925年4月の末に、ハイゼンベルクはボーアの親切に感謝し、「これから先、ひとり寂しく研究を続けていかなければならないと思うと悲しいです」と言って、ゲッティンゲンに帰っていった。しかし彼は、ボーアとの議論、そしてその後も続いたパウリとの対話から、ひとつ非常に重要なことを学んだ―何か、とても基本的なものを捨てなければならないということだ。ハイゼンベルクは、水素原子の線スペクトルの強度という長年の未解決問題に取り組むうちに、何を捨てればよいのかがわかった気がした。ボーア=ゾンマーフェルトによる原子の量子論を使えば、水素の線スペクトルの振動数を説明することはできたが、その明るさ、つまりスペクトルの強度は説明できないと考えた。水素原子の原子核の周囲をめぐる電子の軌道は、観測することができない。そこでハイゼンベルクは、「原子核の周囲を軌道運動している電子」という、慣れ親しんだイメージを捨てることにした。それは大胆な一歩だったが、彼にはその道に踏み出す心の準備ができていた。ハイゼンベルクは以前から、観測できないものを絵に描いて示すというやり方が嫌いだったのだ。』
『ハイゼンベルクがこの新しい戦略を採るより一年以上も早く、パウリはすでに電子軌道という概念に疑問を突き付けていた。「一番重要な問いは、はっきりと規定された電子軌道について、どこまで語りうるのかということだと思います」と、彼は1924年2月にボーアへの手紙に書いた。この引用文の強調は、パウリ自身によるものである。彼はこのときすでに、排他原理へと続く道のりをだいぶ先まで進んでいたし、電子の殻が閉じるということの意味も考え抜いていた。そして同じ年の十二月にボーアに宛てた別の手紙のなかで、パウリは自分が提示した問題に、すでに次のような答えを与えていたのである。「原子をわれわれの偏見の鎖につなぐべきではありません。電子に普通の力学でいうような軌道があるという仮説も、そんな偏見のひとつだというのがわたしの考えです。量子的な概念を、慣れ親しんだ古典物理に合わせようとするのはやめなければならない。物理学者は自由にならなければならない、とパウリは言うのだ。最初にその妥協をやめたのが、ハイゼンベルクだった。彼はプラグマティックな観点から、科学は観測できることにもとづくべきだという実証主義の立場に立ち、観測可能な量だけを使って理論を作ることにしたのである。』
20.観測可能な量だけを使って作った理論
●ハイゼンベルクの花粉症は重症でした。その難敵である花粉のない島がヘルゴラント島です。ここでハイゼンベルクは誰もが待ち望んだ量子力学の扉を開けました。
『七十歳のハイゼンベルクは当時を回想して語った。その宿舎は、赤い砂岩が削られてできた、島の南端にある崖の近くにあった。三階の部屋のバルコニーからは、眼下に広がる村と海岸線を思い出しては、繰り返しそれについて考えた。ゲーテを読んでくつろいだり、小さなリゾート地で日課のように散歩や水泳をしたりするうちに、彼は内省的な気分になっていった。そうこうするうちに体調もだいぶ落ち着き、注意を散らすようなものがほとんどないなか、やがてハイゼンベルクの思索は原子物理学の問題へと戻っていく。ヘルゴラント島では、このところ彼に付きまとっていた暗い気分も消えていた。ゲッティンゲンから背負ってきた数学の重荷をあっさり投げ捨てると、彼はのびのびとした気分で、線スペクトルの強度の謎について考えはじめた。
ハイゼンベルクは、量子化された電子の世界を記述する新しい数学を探すにあたり、電子がエネルギー準位間を瞬間的にジャンプするときに生じる線スペクトルの、振動数と相対強度だけに焦点を合わせることにした。選択の余地はなかった。原子の内部で起こっていることについて教えてくれるデータは、そのふたつしかなかったのだ。量子飛躍という言葉が喚起するイメージとは裏腹に、電子がエネルギー準位間を遷移するときには、わんぱく坊主が塀の上から道路に飛び降りるときのように、空間を移動するわけではない。ある場所にいた電子が、次の瞬間、別の場所に現れるのだ―その中間のどこも通らずに、ハイゼンベルクは覚悟を決めて、観測可能な量と、それらに結びついたものすべては、電子がエネルギー準位間を遷移するときに行う量子飛躍という不思議な手品によって生じるのだと考えて納得することにした。かくして、電子が原子核のまわりを軌道運動しているという、太陽系のミニチュアのようなわかりやすい原子像は消滅した。
ヘルゴラント島という花粉のない天国で、ハイゼンベルクは、電子が行う可能性のあるすべての飛躍―状態から状態への遷移―を書き表すにはどうすればよいだろうかと考えた。エネルギー準位に関係して観測可能な量のそれぞれについて、ジャンプによって生じる変化を追跡するために彼が考えついた唯一の方法は、数を縦横に並べた表を使うことだった。』
『ニュートン力学で観測できる量にはさまざまあるが、ハイゼンベルクがその中で最初に考えたのは、電子の軌道だった。原子核からはるか遠くに離れたところで、一個の電子が軌道運動しているものとしよう―太陽系でいうなら、それは水星というより、むしろ冥王星に近い。ボーアが定常軌道という概念を持ち込んだのは、電子がエネルギーを放出しながら螺旋を描いて原子核に墜落するのを食い止めるためだった。しかしその電子の定常軌道が古典物理学で導かれたものと一致するためには、原子核からはるか遠くに離れたところで軌道運動している電子の軌道振動数(1秒間に軌道をめぐる回数)は、その電子が放出する放射の振動数に一致しなければならない。
これは突飛な思いつきではなく、対応原理―量子の領域と古典的な領域とのあいだにボーアが架けた概念的な橋―を巧みに応用した結果だった。ハイゼンベルクが想定した電子軌道はとても大きかったので、量子の世界と古典的な世界との境界線上にあった。ふたつの世界のあいだに引かれたその境界線上では、電子軌道の振動数は、電子が放出する放射の振動数に等しいはずなのだ。ハイゼンベルクは、原子内にあるそのような電子は、スペクトルのあらゆる振動数を生み出すことができる仮想的な振動子に似ていることを知っていた。マックス・プランクは四半世紀前に、それとよく似たアプローチを使ったのだった。しかし、プランクは恣意的な仮定を置き、正しいことがわかっていた式を力づくで導いたのに対し、ハイゼンベルクは、古典物理学の見慣れた風景につながるはずだという、ボーアの対応原理に導かれていた。いったん振動子を考えてしまえば、ハイゼンベルクは、その運動の特徴―運動量p、平衡の位置からの変異q、そして振動数―を計算することができた。振動数部vmnをもつ線スペクトルは、さまざまな振動子のうちの、どれかひとつによって放出されるはずだ。ハイゼンベルクは、量子的なものと古典的なものとが出会う、その中間地帯を詳しく調べて得られた結果は、原子の内部という未知の領域を探索するために利用できることを知っていたのだ。
ヘルゴラント島でのある夜遅く、突如として、ジグゾーパズルのピースが合いはじめた。観測可能な量だけを使って作った理論は、すべてのデータを再現してくれそうだった。しかしその理論では、エネルギー保存則は成り立つのだろうか? もしもエネルギー保存則を破っていれば、その理論はトランプの家のように崩れ落ちてしまう。自分の理論が、物理的にも数学的にも矛盾がないことを証明できるまであと一歩というところで、24歳の物理学者は、興奮と緊張のあまり、計算をチェックしながら単純なミスを繰り返すようになった。物理学の基本法則のひとつであるエネルギー保存則がたしかに成り立っていると彼がペンを置いたのは、夜中の三時ころだった。彼は点にも昇る心地だったが、動揺もしていた。後年、ハイゼンベルクはそのときのことを次のように語った。「はじめからわたしは、これは大変なことになったと思った。原子的な現象という上辺から、なんとも形容しがたい、美しい内部を覗き込んでいるような気がしたのだ。自然がこれほどまでに気前よくわたしの目の前に広げて見せてくれた、この豊かな数学的構造を、これから詳しく探っていかなければならないと思うと、めまいがするほどだった」。気持ちが高ぶってとても眠れそうになかったので、彼は夜明け前に、ヘルゴラント島の南端に向かって歩き出した。そこには海に突き出した岩があり、何日も前から登ってみたいと思っていたのだ。発見は興奮で吹き出したアドレナリンにエネルギーを注がれるようにして、彼は「たいした苦労もなくその岩によじ上り、太陽が昇ってくるのを待った」。』

画像出展:「MEISTERDRUCKE」
(The Grand Staircase, Helgoland, Germany, Photochrome Print, c.1900)

ボーアから全てを託されたハイゼンベルクが、ヘルゴラント島で発見したものは、量子力学の扉を開けた歴史的出来事だったように思います。
世界はひとつ、重力力学はふたつ。その答えは二つを見渡す境界線にあり、【波】(古典)と【粒】(量子)の構造はコインの裏表のように一体型とのことです。
生命の進化を淘汰とみれば、合理性や最適化が重要だと思います。重力力学が2つ存在するとすれば、そのような理由ではないでしょうか。
21.(A×B)-(B×A)≠ゼロ
●量子力学の扉を開けたハイゼンベルクが最初に著面した難題は、A×BとB×Aの答えが等しくないという奇妙な掛け算の謎を解くことでした。
『朝の冷たい光の中で、ハイゼンベルクのはじめの幸福感や楽観的な展望は色褪せていった。彼の見出した新しい物理学がうまく行くためには、X×YとY×Xが等しくないという、奇妙な掛け算を使うしかなさそうだった。普通の数なら、どの順番で掛け算をしても構わない。4×5の答えと5×4の答えは、どちらも20である。掛け算の結果は順番によらないというこの性質のことを、数学者は可換性と呼んでいる。数は、掛け算の交換法則を満たすので(つまり「可変」なので)、(4×5)-(5×4)はつねにゼロである。これはすべての子どもが学ぶ数学のルールだ。ハイゼンベルクを深く悩ませたのは、数の表の中のふたつの値を掛け算した結果は、掛け合わせる順番によって変わってしまうことだった。(A×B)-(B×A)は、必ずしもゼロではなかったのである。
彼の理論が必要としている、その奇妙な掛け算の意味がわからないまま、6月19日の金曜日、ハイゼンベルクはドイツ本土に戻ると、そのままハンブルクのヴォルフガング・パウリのもとに直行した。数時間後、誰よりも厳しい批判者であるパウリから励ましの言葉をもらったハイゼンベルクは、その発見をもう少し磨きあげて論文にするためにゲッティンゲンに向かった。二日後、その仕事はすぐにできると思っていたハイゼンベルクは、パウリに手紙を書き、「量子力学を作る仕事は遅々として進むみません」と伝えた。一日、また一日と時間が経ち、新しいアプローチを水素原子にうまく応用できないまま、ハイゼンベルクは追い詰められていった。
気がかりなことは山ほどあったが、ハイゼンベルクが確信していたことがひとつだけあった。何を計算するにせよ、「観測可能」な量のあいだの関係のみ、あるいは、現実には測定が難しいとしても、原理的には測定可能な量のあいだの関係しか使ってはならないということだ。彼は、自分の方程式に現れるすべての量が観測可能だということを公理として、「観測できない軌道という概念を完全に消し去り、その対応物で置き換える」ことに、「わずかばかりの努力のすべてを」注ぎ込んだ。
『その謎めいた掛け算規則には、どんな意味があるのだろうか? その問いがボルンに取り憑いて離れなくなり、彼はそれからの数日というもの、寝ても覚めてもそのことばかり考え続けた。ボルンはその計算規則に見覚えがあったのだが、それが何なのか思い出せなかったのだ。ボルンはアインシュタインに手紙を書き、この奇妙な掛け算がどこから出てくるのかはまだ説明できないけれども、「ハイゼンベルクの最新の論文がまもなく発表されることになるでしょう。まだよくわからないところもありますが、真実を捉えており、深いことは確かです」と伝えた。ボルンは自分の研究所にいる若手、とりわけハイゼンベルクを褒め、「彼の考えについて行くだけでも、わたしは相当努力が必要です」と書いた。くる日もくる日もその計算規則のことばかり考え続けたボルンの努力は、ついに報われた。ある朝、ボルンはふと、学生時代に受験したきり忘れていた、ある数学の講義のことを思い出した―ハイゼンベルクが出くわしたのは、行列演算だったのだ。行列演算では、X×Yは必ずしもY×Xにはならないのである。』
22.量子物理学の新時代の幕開けを告げる論文
●ハイゼンベルクに並ぶ天才とされたパウリは、ハイゼンベルクが書き上げた論文について、次のような言葉を送りました。「その論文は、かつてない希望と、新たな生きる喜びを与えてくれた。それで謎が解けたというわけではないにせよ、ここでまた、われわれは前進できるでしょう」と。
『六月の末、ハイゼンベルクは父親への手紙にこう書いた。「ぼくの仕事はと言えば、今のところ、あまりはかばかしくありません」。しかしそれから一週間ほどして、彼は量子物理学の新時代の幕開けを告げる論文を書き上げた。自分がやり遂げたことの意味にまだ確信がもてないハイゼンベルクは、写しを一部パウリに送り、申し訳なさそうに、二、三日のうちにその論文を読んで、返事をくれないかと頼んだ。ハイゼンベルクがそれほど急いでいたのは、7月28日にケンブリッジ大学で講演をする予定になっていたからだ。パウリはその論文を、「歓喜をもって」迎えた。パウリはある物理学者への手紙に、ハイゼンベルクの「その論文は、かつてない希望と、新たな生きる喜び」を与えてくれたと書いた。「それで謎が解けたというわけではないにせよ、ここでまた、われわれは前進できるでしょう」と、パウリは言い添えた。そして正しい方向に真っ先に踏み出したのは、マックス・ボルンだった。』
『ハイゼンベルクはその論文のまとめの部分に到達してからさえ、まだ逡巡していた。「ここに提案したような、観測可能な量のあいだの諸関係を使って量子力学のデータを求めるという方法は、原理的に満足の行くものと見なされるべきなのか、あるいはこの方法は結局のところ、現状ではきわめて込み入った問題であることが明白な、量子力学の理論を作るという物理的問題へのアプローチとしては不十分なものであるのかは、ここではごく表層的に採用したこの方法を、数学的により詳しく調べることによってのみ判定できるであろう」』
23.行列演算と量子力学
●ハイゼンベルクが発見した数の並びは、十九世紀の半ばにイギリス人の数学者アーサー・ケイリーが提唱した行列演算でした。この行列演算は数学では確立された分野でしたが、ハイゼンベルクの世代の理論物理学者にとっては未知の領域でした。また、このことに気づいたボルンはハイゼンベルクが作り出した枠組みを、原子物理学のあらゆる局面に適用できるような、論理的に矛盾のない枠組みに仕上げなければならないと思い、二十二歳のパスクアル・ヨルダンとともにこの大きな難問に取り組みました。
『ハイゼンベルクの掛け算規則は行列演算であることを突き止めたボルンは、位置qと運動量pを、プランク定数を含む式で結びつける方法をすぐさま発見した。その式はpq-qp=(ih/2π)Iと書くことができる。ここで、Iは、数学者が単位行列を使えば、それなしにはただの数にすぎない右辺を行列にすることができるのだ。この基本式にもとづき、それから数カ月のうちに、行列という数学の方法にもとづく量子力学が完成した。』
24.論理的に矛盾のない量子力学を定式化した「三者論文」
●猛烈な勢いで行列を勉強したハイゼンベルクは「三者論文」の作業に参加することができました。
『行列を知らないのはハイゼンベルクばかりではなかった。しかし彼は猛烈な勢いでその新しい数学を学びはじめ、まだコペンハーゲンにいるうちに、ボルンとヨルダンに追いつくほどの力をつけてしまった。十月半ばにゲッティンゲンに戻ったハイゼンベルクは、のちに「三者論文」として知られることになるその論文の最終バージョンを作る作業に参加することができた。彼とボルンとヨルダンの三人はその論文により、論理的に矛盾のない量子力学を定式化したのである。それはながらく探し求められていた、原子の新しい物理学だった。』
25.守備範囲の広い理論家
●シュレーディンガーの最初の論文は実験物理学だったそうです。先にご紹介した若き天才、パウリとハイゼンベルクは理論物理学に傾倒されており、この点が異なります。また、シュレーディンガーは放射性元素、統計物理学、一般相対性理論、色彩論[ゲーテによる光と色の研究]といった幅広い分野で四十篇以上の論文を発表しています。そして、一匹狼で、洒落ていて、気分屋で、親切で、寛大な、じつに愛すべき人間で、しかも、恐ろしく効率のよい、第一級の頭脳の持ち主だったとのことです。
『同僚の物理学者たちの見たシュレーディンガーは、放射性元素、統計物理学、一般相対性理論、色彩論といった幅広い分野で四十篇以上もの論文を発表している。堅実であるが、ずば抜けて優れているというほどもない仕事を重ねてきた、守備範囲の広い器用な理論家だった。シュレーディンガーの仕事のなかには、他人の研究を理解して分析し、分かりやすく説明する力量を示す総説がいくつもあり、いずれも高い評価を得てありがたがられていた。
11月23日、シュレーディンガーのコロキウム(談話会)には、当時二十一歳の学生だったフェリックス・ブロッホが出席していた。ブロッホがのちに語ったところでは、シュレーディンガーは、「ド・ブロイが波と粒子を結びつけた方法や、粒子の定常状態の軌道に整数個の波が収まるという条件を課すことで、なぜニールス・ボーアとゾンマーフェルトの量子化規則が得られるのかという条件を課すことで、なぜニールス・ボーアとゾンマーフェルトの量子化規則が得られのかということを、みごとにわかりやすく説明した」。しかし、波と粒子の二重性には実験の裏づけがなかったため(それが得られるのは1927年のことだ)、デバイは、ド・ブロイの議論は「子どもじみている」との感想を述べた。波の物理学には―音波、電磁波、ヴァイオリンの弦を伝わる波など、どんな波を扱うにせよ―その波を記述する方程式が必要だ。ところが、シュレーディンガーの説明した理論には、「波動方程式」がなかったのだ。ド・ブロイは、物質波の波動方程式を導こうとしたことはなかったし、彼の学位論文を読んだアインシュタインも同様だった。そのコロキウム(談話会)から五十年を経ても、ブロッホはそのときのことを鮮明に覚えており、デバイの指摘は、「あまりにも当たり前すぎて、みんなには軽く聞き流されたようだった」と述べた。
しかしシュレーディンガーは、デバイの言う通りだと思った。「波動方程式のない波では話にならない」のだ。そのとき彼はほとんど瞬時に、ド・ブロイの物質波に対する波動方程式を見つけてやろうと心に決めた。』
26.シュレーディンガーが「作った」波動方程式
●シュレーディンガーは親切で寛大だったとされていますが、駆け引きのない率直な性格で柔軟性、多様性も持っていたのではないでしょうか。デバイの酷評ともとれる「波動方程式のない波では話にならない」という発言を受け入れ、「量子の波動方程式をみつけてやろう」というポジティブな心が多くの物理学者に支持された直観的な方程式の発見を呼び込みました。
『クリスマス休暇から戻り、年明けに開かれた次にコロキウム(談話会)で、シュレーディンガーは声高らかにこう宣言することができた。「前回デバイが、波動方程式が必要だと言いましたが、さてさて、わたしはそれを見つけました!』。シュレーディンガーはその二週間のうちに、胎児のようなド・ブロイのアイデアを取り上げて、立派な量子力学理論に育て上げたのである。
シュレーディンガーには、どこから出発すればよいかも、何をすればよいかもわかっていた。ド・ブロイは、波と粒子の二重性というアイデアの妥当性の保証を、電子の定在波の波数が整数のときに軌道が閉じ、ボーアの原子モデルで許される電子軌道を再現できることに求めたのだった。しかしシュレーディンガーは、自分の探す方程式は、三次元の水素原子モデルを、三次元の定在波として再現できなければならないと考えた。水素原子は彼が見出すべき波動方程式の試金石になるはずだ。
波動方程式を探しはじめてまもなく、シュレーディンガーはまさに求める方程式を捕まえたと思った。しかし、水素原子に当てはめてみると、その方程式からは実験と合わない結果が出てきてしまった。その失敗の根本的な理由は、ド・ブロイが波と粒子の二重性というアイデアを得たときに、アインシュタインの特殊相対性理論と矛盾しないものを考え、そのよううなものとして提示していたことだった。ド・ブロイのやり方を手本にして進んでいたシュレーディンガーは、当然ながら、「相対論的」な形をした波動方程式を捜し、まさにそれを見つけたのである。そのころにはすでに、ウーレンベックとハウトスミットが電子のスピンを発見していたが、ふたりの論文が専門雑誌に掲載されたのは1925年11月下旬のことだった。当然ながら、シュレーディンガーが発見した相対論的な波動方程式にはスピンが含まれておらず、結果として、その波動方程式から出てきた結果は、実験とは合わなかったのだ。
クリスマス休暇が迫ってきたため、シュレーディンガーは相対性理論のことを気にするのはやめて、昔ながらの波動方程式を探すことに努力を集中した。相対論的でない波動方程式は、電子が光速に近い速度で運動するような場合には、相対論的効果が無視できなくなるため使えなくなる。
シュレーディンガーはそのことをよく知っていた。しかしとりあえずは、そんな波動方程式でも間に合ったのだ。』
『12月27日付のヴィルヘルム・ヴィーンへの手紙に、彼は次のように書いた。「目下、新しい原子理論と格闘しているところです。もっと数学を知ってさえいれば! ともあれ、それについてはわたしは非常に楽観的で、結果はとても美しいものになるだろうと予想しています。ただし、解くことができればの話ですが』
『シュレーディンガーはその波動方程式を「導いた」のではなかった―古典物理学から出発して、厳密な論理をたどるという方法では、その式は得られなかったのだ。そこで彼は、粒子に伴う物質波の波長と、その粒子の運動量とを結びつけるド・ブロイの式と、古典物理学のいくつかの式を睨み合わせて、その波動方程式を「作った」のである。簡単そうに聞こえるかもしれないが、シュレーディンガーがその式を書き下す最初の物理学者になれたのは、彼ほどの技量と経験があったればこそだった。シュレーディンガーはそれからの数カ月間で、その波動方程式を基礎として、波動力学という壮大な建物を作り上げることになる。しかしその前に、彼はそれがたしかに探し求めていた波動方程式であることを証明する必要があった。その方程式は、水素原子に応用した場合、水素のエネルギー準位に正しい値を与えてくれるのあろうか?
一月にチューリッヒに戻ったシュレーディンガーがじっさいに調べてみると、その波動方程式は、たしかにボーア=ゾンマーフェルトの水素原子のエネルギー準位を再現することがわかった。ド・ブロイは、電子の波として円軌道にぴったりはまる一次元の定在波を考えたが、シュレーディンガーの理論から得られるのは、もっと複雑な三次元の「軌道関数」だった。そして、波動方程式を解いて軌道関数が得られれば、その関数によって表される電子状態のエネルギーは自動的に決まる。ボーア・ゾンマーフェルトの原子の量子論では、正しいエネルギーの値を得るためには恣意的な条件を課さなければならなかったが、そういう操作はいっさい不要になったのだ。そればかりか、謎めいた量子飛躍さえもが、電子に許される三次元定在波から別の三次元定在波への連続的な遷移に取って代わられたかにみえた。1926年1月27日、「固有問題としての量子化」と題された論文が、「アナーレン・デア・フィジーク』に届いた。3月13日に同誌に掲載されたその論文には、シュレーディンガー版の量子力学と、水素電子に対する応用が示されていた。
シュレーディンガーは、五十年に及んだ物理学者としての経歴のなかで、年平均40ページ相当の論文を発表しづけた。とくに1926年には、256ページ相当という大量の論文を発表し、波動力学はさまざまな原子物理学の問題に幅広く利用できることを明らかにした。また、彼は、時間とともに変化する「系」を扱うことのできる、時間依存型の波動方程式を考え出した。時間とともに変化する系とは、たとえば、電子が放射を放出、吸収、散乱するような場合である。
2月20日、その最初の論文が印刷を待つばかりとなったとき、シュレーディンガーは自分の作った新しい理論に対して、はじめて波動力学という言葉を使った。』
27.ハイゼンベルクの難解な行列力学とシュレーディンガーの直感的な波動力学
●数学は苦にしないと思われる物理学者にとっても、当時、行列という数学はとても厄介な代物だったようです。そのため、難解とされたハイゼンベルクの量子力学(行列力学)に比べ、シュレーディンガーの量子力学(波動力学)は多くの物理学者を勇気づけました。この二つは同等のものとのことです。一つは行列、一つは微分方程式から生まれたということなのですが、私にはその同質性を理解することは到底できません。しかしながら、数学者にも劣ることのないハイゼンベルクと、最初の論文が実験物理学だったというシュレーディンガーの視点の違い、授かった才能の違いが二つの量子力学を世に送り出したのではないかと思います。
『冷たくて禁欲的な行列力学とは対照的に、彼が物理学者たちに与えたのは、使い慣れたおなじみの方法だった―彼の方法は、極度に抽象的なハイゼンベルクの方法よりも、ずっと十九世紀物理学に近い言葉で量子の世界を説明してあげようと、物理学者たちに語り掛けていた。謎めいた行列の代わりにシュレーディンガーが持ち込んだのは、物理学者の数学の道具箱にはかならず入っている微分方程式だった。ハイゼンベルクの行列力学は、量子飛躍と不連続性をもたらした。原子の内部を覗いてみたくとも、視覚的なイメージできるものは、そこには何もなかったのだ。シュレーディンガーは、これからはもう、「自分の直感を抑え込む必要はないし、遷移確率やエネルギー準位といった、抽象的な概念だけを相手にする必要もない」と述べた。物理学者たちがシュレーディンガーの波動力学を熱烈歓迎し、われ先にとそれを使いはじめたのは当然のことだった。
シュレーディンガーは、その論文の抜き刷りを受け取るとすぐに、彼が意見を聞きたいと思う物理学者たちにそれを送った。プランクは4月2日付の手紙に、「ずっと頭から離れなかった謎が解けたと言われて、真剣に話に聞き入る子どものように、あなたの論文を読みました」と書いた。それから二週間後にはアインシュタインから、「あなたの仕事のアイデアは、真の天才から沸き上がったものです」という手紙が届いた。シュレーディンガーは、「あなたとプランクが認めてくださったことは、わたしにとって世界の半分からの賞賛よりも大きな意味があります」と返信した。アインシュタインは、シュレーディンガーが決定的な前進を遂げたことを、「ハイゼンベルク=ボルンの方法は邪道であると確信するのと同じぐらいの強さで確信」したのだった。』
『このふたり以外の人たちが十分に理解するまでには、もう少し時間がかかった。ゾンマーフェルトは当初、波動力学は「完全なたわごと」だと思っていたが、やがて考えを変え、「行列力学が正しいことは疑う余地はありませんが、取り扱いが非常に難しく、おそろしく抽象的です。シュレーディンガーはわれわれを助けに駆け付けてくれました」と述べた。ほかにも多くの人たちが、ハイゼンベルクとゲッティンゲンの仲間たちの抽象的で奇妙な理論と格闘するよりは、波動力学の慣れ親しんだ方法を学び、じっさいに使いはじめてみて、ほっと胸をなでおろした。スピンで名をなした若手のヘオルヘ・ウーレンベックは、「シュレーディンガー方程式のおかげで助かりました。これでもう、不慣れな行列力学を勉強しなくてもすみます」と書いた。エーレンフェストやウーレンベックらライデンの物理学者たちは、行列力学を勉強する代わりに、数週間のあいだ毎日「何時間も黒板の前に立ち」、波動力学の驚くべき意味を汲み尽くそうとした。
パウリはゲッティンゲンの物理学者たちに近かったが、シュレーディンガーの仕事の重要性をすぐに見抜き、深く感銘を受けた。彼は行列力学を水素分子に当てはめて成功した際、ハイゼンベルクの方法のことは隅々まで調べ上げていた―彼がそれを迅速かつ徹底的に行ったことに、のちには誰もが驚くことになる。パウリがその論文を「ツァイトシュリフト・フュール・フィジーク」に送ったのは1月17日。シュレーディンガーが最初の論文を投稿するわずか十日前のことだった。パウリは、シュレーディンガーが波動力学を使って、行列力学を使った場合よりも楽に水素原子を扱っているのを見て愕然とした。彼はパスクアル・ヨルダンに次のように書いた。「その仕事は近年出た論文のなかで、もっとも重要な仕事のひとつだと思います。注意深く、集中してそれを読み込んでください」。六月にはボルンまでが、波動力学は「量子の法則を表す、もっとも深い形式」だと言うまでになった。
ハイゼンベルクは、ボルンが変節して波動力学の支持に回ったことを、「あまり良い気持ちはしない」とヨルダンに語った。彼は、シュレーディンガーが慣れ親しんだ数学を使っていることは、「信じられないほど興味深い」が、物理の内容に関するかぎり、原子レベルの出来事を正しく記述しているのは自分の行列力学のほうだと確信していた。』
ボーアとアインシュタイン2
9.一般相対性理論
●戦争の四年間は、アインシュタインにとって、もっとも生産的で創造的な時期となりました。彼はこの期間に、一冊の本と五十篇ほどの科学論文を発表し、1915年には最高傑作である一般相対性理論をついに完成させました。
『ニュートン以前から、時間と空間は堅い枠組みであり、終わりのない宇宙のドラマが上演される舞台だと考えられていた。その舞台上では、質量、長さ、時間は、絶対的で不変だった。つまりその劇場の中では、ふたつの出来事の空間距離と時間間隔は、どの観客にとっても同じだったのだ。しかしアインシュタインは、質量、長さ、時間は絶対的ではなく、観測者ごとに変わりうることを見出した。観測者同士がどんな相対運動をしているかによって、空間距離と時間間隔は違って見えるのである。双子の一方が地球に残り、他方が宇宙飛行士になって、光速に近い速度で宇宙旅行をしたとすれば、大きな速度で運動しているほうの双子にとっての時間は伸び(時計の針の進み方が遅くなり)、空間は縮む(運動物体の長さが短くなる)。また、運動している物体の質量は、静止しているときの質量よりも大きくなる。これらはみな、「特殊」相対性理論から引き出せる結論であり、いずれも二十世紀中に実験によって確かめられた。しかし、特殊相対性理論には、速度が変化する場合は含まれていない。それを含むように拡張したのが、「一般」相対性理論である。アインシュタインは、一般相対性理論を作る仕事に取り組んでいたとき、その苦労にくらべれば、特殊相対性理論は「子どもの遊び」のようなものだったと語った。量子は、原子の領域でそれまでの世界像に疑問を突きつけたが、アインシュタインは空間と時間についても、その真の性質に関する知識へと人類を近づけたのだった。一般相対性理論はアインシュタイン版の重力理論であり、やがて物理学者たちはこの理論に導かれて、ビッグバンという起源に迫ることになる。
ニュートンの重力理論によれば、太陽と地球のようなふたつの物体間に働く引力の大きさは、両者の質量の積に比例し、それぞれの物体の質量中心を結ぶ距離の二乗に反比例する。質量同士は接触していないので、ニュートン物理学における重力は、謎めいた「遠隔作用」だ。しかし一般相対性理論における重力は、大きな質量の存在により、空間が歪むために生じる。地球が太陽の周囲をめぐるのは、オカルトのような不思議な力によって地球が太陽に引き寄せられるからではなく、太陽の大きな質量のために空間が歪むためなのだ。それをひとことで言えば、「物質は空間を歪め、歪められた空間は、物質に動き方を教える」ということになる。
1915年の11月、アインシュタインは一般相対性理論を、ニュートンの重力理論では説明できなかった水星軌道の問題に当てはめてみた。水星は太陽のまわりを公転する際、毎回まったく同じ経路をたどるわけではない。天文学者は精密な測定を行って、水星軌道は、そのつどわずかに楕円の軸が回転していることを明らかにしていた。アインシュタインが一般相対性理論を使って、その小さな回転角を計算してみると、小さな誤差の範囲で、観測データとぴったり合う結果が得られた。それがわかったとき、アインシュタインの胸の鼓動が激しくなり、何かストンと腑に落ちるものがあった。「この理論の美しさは、ただごとではありません」と彼は書いた。最大の夢が叶ってアインシュタインは本望だったが、非常な努力を続けたせいで、身も心もくたくたに疲れ果てていた。しかし、やがてその疲労から回復したアインシュタインは、ふたたび量子に目を向ける。』
10.1916年、光量子の確立
●光量子を確立させたアインシュタインでしたが、それは「原子の量子論」に基づくものであり、古典物理学の因果律を否定するというアインシュタインにとっては、容易に受け入れることができない現実を突きつけられました。
『アインシュタインは、まだ一般相対性理論に取り組んでいた1914年5月にはすでに、フランク・ヘルツの実験は、原子のエネルギー準位の存在を立証し、「量子仮説の正しさを裏づける衝撃的な結果」だということを鋭く見抜いていた。そして早くも1916年の夏には、原子が光を放出・吸収するプロセスについて、ある「すばらしいアイデア」を得る。そのアイデアを手掛かりとして、彼は、「あっけないほど簡単に、プランクの式[黒体放射のスペクトルに関する法則であり、量子力学の基本法則のひとつ]」を導くことができた。その導出方法は、「これこそが正しい方法だと思える」ほどのものだった。まもなくアインシュタインは、「光量子は確立されたと思います」と言うまでに、光量子の実在性を確信するにいたる。だが、その確信を得るためには、代償が必要だった―古典物理学の厳密な因果律[原因があって結果が生じる]を捨て、原子の領域に確率を持ち込むことになってしまったのだ。
アインシュタインは以前にも、別の方法でプランクの法則を導いたことがあった。しかし今度の方法は、ボーアによる原子の量子論から出発するものだった。』
11.因果律の否定
●因果律を否定するということは、我々が住むマクロの世界の中では考えられない現象を認めることであり、「因果律を捨てることになれば、わたしとしては非常に不本意です」。とアインシュタイン自身が語っているように、この事実は厳しく、辛いものであったと思います。
『原子の量子論の中核に偶然と確率が潜んでいることに気づいて、アインシュタインは嫌な気持になった。彼はもはや量子の実在性を疑ってはいなかったが、それと引き替えに、因果律を犠牲にしてしまったような気がしたのだ。彼はその三年後の1920年1月に、マックス・ボルンへの手紙に次のように書いた。「因果律のことではかなり悩みました。光が量子として吸収・放出されるプロセスは、因果律が完全に成り立つものとして理解できるのか、それとも統計的な要素はどこまでも残るのか?これについては自分の考えを口にする勇気がありません。しかし、完全に成り立つものとしての因果律を捨てることになれば、わたしとしては非常に不本意です」。
アインシュタインを悩ませたのは、手にもったリンゴから手を放しても、リンゴは落下せず、そのまま空中に浮かんでいるという状況だった。手を離れたリンゴは、地面に置かれている場合よりも不安定なので、すぐさま重力が作用して落下しはじめる。重力が原因となって、リンゴが落下するのだ。ところが、もしもそのリンゴが、励起状態[最もエネルギーの低い状態よりもエネルギーが高い状態]にある原子内の電子のように振る舞えば、リンゴは手を離れてもすぐには落下せず、そのまま空中に浮かんでいるだろう。そして、確率としてしか知ることのできない予測不可能なある時刻に、突如として落下しはじめるのだ。手を放した直後に落下する確率は大きいにせよ、何時間も浮かんでいる確率も、小さいとはいえゼロではないのだ。励起状態にある原子内の電子は、いずれ低いエネルギー準位に飛び降り、安定した基底状態に落ち着く。だがその遷移が正確にいつ起こるかは、運任せなのである。1924年になっても、アインシュタインはまだ、自分の明らかにした事実を受け入れることができずにいた。「光を照射された電子がジャンプする時刻ばかりか、飛び出すときの向きまでも、おのれの自由意志で選ばなければならないというのは、わたしには耐え難いことに思われます。もしも自然がそんな仕組みになっているのなら、わたしは物理学者でいるより、靴の修理屋になるか、あるいはいっそ賭博場にでも雇われたほうがましです」。』
12.アインシュタインとボーアの出会い
●1920年4月27日、アインシュタインは初めて会ったボーアに強い印象を持ちました。
『アインシュタインは、自分より六つも年下のこのデンマーク人を次のように評価していた。「彼は間違いなく、第一級の頭脳の持ち主です。きわめて緻密で洞察力があり、大きな枠組みを見失うことがありません」。アインシュタインがプランクへの葉書にそう書いたのは、1919年10月のことだった。プランクはそれを読んで、ますますボーアにベルリンに来てほしいと思うようになった。アインシュタインがボーアに惚れ込んだのは、もうだいぶ前のことである。1905年の夏、彼の頭のなかで吹き荒れていた創造性の嵐が静まりかけたとき、アインシュタインは、次に取り組むべき「本当に面白いこと」がないと思った。「もちろん、線スペクトルの問題はあるでしょう」と、彼は友人のコンラート・ハビヒトへの手紙に書いた。「しかし、これらの現象と、すでに解明されている現象とのあいだには、簡単な関係はないと思います。したがって、今しばらく、このテーマでは成果を期待できそうにありません」
攻略する機が熟した物理学の問題を鋭く嗅ぎわけることにかけて、アインシュタインの鼻は天下一品だった。線スペクトルの謎を見送ったアインシュタインが次に嗅ぎつけたのが、E=MC²だった。その式は、質量とエネルギーとが変換可能だということを意味していた。もっとも、全能の神が笑いながら、彼を「手玉にとっている」可能性もないとは言えなかったのだが。そんなわけで、1913年にボーアが、原子を量子化することにより、原子スペクトルの謎を解決して見せたときには、アインシュタインにはそれがまるで「奇跡のよう」に思われたのだった。
ボーアは、ベルリン駅から大学へと向かいながら、興奮と不安のために胃が痛くなりそうだった。しかしそんな緊張は、プランクとアインシュタインに会うとすぐに解けてなくなった。ふたりは挨拶もそこそこに物理学の話しを始め、ボーアもすっかりマイペースになった。プランクとアインシュタインは、これ以上違う人間はいないのではないかと思うほど正反対のタイプだった。プランクは、プロセイン流の気まじめさの権化のようだったのに対し、アインシュタインは、大きな目ともじゃもじゃの髪をして、つんつるてんのズボンを穿き、世間との関係はぎくしゃくしていたかもしれないが、自分自身とはうまく折り合いをつけているように見えた。ボーアは、ベルリン滞在中はプランク家に泊まるように招かれ、その申し出をありがたく受けた。』
『ボーアがコペンハーゲンに帰るとすぐに、アインシュタインは彼に手紙を書いた。「これまでの人生で、あなたほど、その存在自体がかくも大きな喜びを与えてくれた人はほとんどいませんでした。わたしは今、あなたのすばらしい論文を勉強しているところです。そして―難しい箇所に躓かないかぎりは―ほがらかで少年っぽい顔をしたあなたが、微笑みながら説明しているのを思い浮かべて楽しい気分になるのです」。ボーアはアインシュタインに、長く消えることのない深い印象を与えた。数日後、アインシュタインは、パウル・エーレンフェストに次のように書いた。「ボーアがベルリンに来ました。わたしもあなた同様、彼にすっかり魅了されました。彼は感じやすい子どものようで、夢の中にでもいるように、この世界を歩き回っているのです」。ボーアもアインシュタインに負けないぐらい熱烈に、この出会いが彼にとってどれほど大きな意味をもったかを、お世辞にも上手とは言えないドイツ語で懸命に伝えようとした。「このたび直接お目にかかってお話しできたことは、わたしにとって最大級の経験となりました。じかにお考えを聞いて、どれほど大きな霊感を受けたことか、あなたには想像もつかないでしょう」。ボーアはまもなく、もう一度それを経験することになった。アインシュタインがその八月、ノルウェーへの旅行からの帰りにコペンハーゲンに立ち寄り、ひとときボーアを訪ねたのだ。
ボーアに会った直後、アインシュタインはローレンツへの手紙に次のように書いた。「彼は大きな天分に恵まれ、しかもすばらしい人物です。優れた物理学者が人間的も立派だというのは、物理学にとってありがたいことですね。』
●ボーアは1922年にノーベル賞を受賞しました。本書ではその喜びを二人に伝えたと記されています。ひとりは恩師であるラザフォードであり、もうひとりはアインシュタインでした。
『もうひとり、ボーアの頭から離れなかった人物が、アインシュタインだった。彼が1922年のノーベル賞を受賞する日に、アインシュタインも一年遅れて1921年のノーベル賞を受賞するという巡り合わせが、ボーアには嬉しく、また、ほっとさせられる成り行きでもあった。ボーアはアインシュタインにこう書いた。「わたしには過分な賞であることは十分承知していますが、これだけは申し上げたいと思うことがあります。それは、わたしが仕事をしたこの特別な分野において、あなたが成し遂げられた基本的な重要な仕事、およびラザフォードとプランクの仕事が、わたしがこの名誉に値すると見なされるよりも先に認められていて、本当によかったということです」
ノーベル賞の受賞者が発表されたとき、アインシュタインは船で地球の反対側に向かっていた。彼は十月八日に、身の安全に不安を感じながら、エルザとともに日本での講演旅行に出発したのだった。アインシュタインは後年、次にように述べた。「ドイツを長期間離れる機会が得られたのはありがたいことでした。そのおかげで一時的に高まった危険から逃れることができたからです」。彼がようやくベルリンに戻ったのは、1923年2月だった。当初の六週間の予定は、結局五カ月に及ぶ大旅行となり、ボーアの手紙を受け取ったのも旅先でのことだった。彼は帰国の途上でボーアに返事を書いた。「少しも大袈裟ではなく、[あなたの手紙を]ノーベル賞と同じくらい嬉しく思いました。とくに、わたしより先に受賞することを心配なさっていたとは、なんて可愛らしいのでしょう―あなたらしいことです。』
13.量子との格闘
●アインシュタインにとっても、ボーアにとっても量子は想像を絶するような難しい問題でした。
『アインシュタインとボーアは、ベルリンとコペンハーゲンで会ってからの二年間、それぞれのやり方で量子との格闘を続けた。しかしふたりとも、しだいにその戦いに疲れを感じはじめていた。「気を散らされることが多いのも、まんざら悪いことではないのでしょう」と、アインシュタインは1922年3月にエーレンフェストへの手紙に書いた。「さもなければ、量子の問題のために、わたしは精神病院に入院していたかもしれませんから」。その一カ月後、ボーアはゾンマーフェルトにこう語った。「ここ数年、科学上の孤立感をひしひしと感じています。体系的に量子論の原理を作ろうと力のかぎり頑張っているのですが、ほとんど誰にも理解してもらえないように思います」。しかし、そんな孤立の時代も終わろうとしていた。ボーアは1922年6月に、ドイツのゲッティンゲン大学で、のちに「ボーア祭り」として知られることになる、十一日間で七回の連続講義という一大イベントを敢行したのだ。』
14.ボーア祭りとアインシュタインの命の危機
●アインシュタインには相対性理論を拡張するという命題があり、また光量子には因果律を否定しなければならないという側面がありました。また、数学が求められるという要因もアインシュタインにとっては望ましいものではありませんでした。一方、ボーアには古典物理学へのこだわりはアインシュタインほどではなく、それよりも量子とは何かということを明らかにしたいという気持ちが強かったように思います。その強い気持ちがこの難題に立ち向かわせ、その使命感が原動力となって、生涯を貫いたのではないかと思います。
『ボーアが原子内電子の「殻模型」について話をするというので、老若とりまぜて百人を超える物理学者たちがドイツ各地から集まってきた。殻模型とは、原子内の電子がどのように配置されているかに応じて、その元素の周期表内での位置と、元素のグループ(類)が決まるという、ボーアの最新理論だった。彼は、原子核の周囲を、ちょうどタマネギの鱗片のように、軌道殻というものが取り巻いているという考えを打ち出した。それぞれの殻は、じっさいには電子軌道の集まりで、その軌道に含まれる電子の個数には上限がある。化学的な性質を共有する元素は、もっとも外側の殻に含まれる電子の数が同じになっている、とボーアは論じた。』
『アインシュタインは、ゲッティンゲンでのボーアの連続講義には出席しなかった。ユダヤ人だったドイツ外相が殺害されたことで、命の危険を感じていたからだ。有力な実業家だったヴァルター・ラーテナウは、外相になってわずか数カ月後の1922年6月24日の白昼に、銃弾に倒れた―第一次世界大戦後に起こった極右による政治的暗殺の、三百五十四番目の犠牲者だった。アインシュタインは、政府内のそんな目立つ地位に就くべきでない、ラーテナウに強く忠告した。人間のひとりだった。ラーテナウが外相に就任すると、右翼新聞はそれを、「国民に対する前代未聞の挑発!」と書きたてた。
「ラーテナウの暗殺という恥ずべき事件が起こって以来、こちらでは気が休まるときがありません」とアインシュタインはモーリス・ソロヴィンに書いた。「わたしはいつも警戒しています。講義は取り止め、公式には不在になっていますが、じっさいにはずっとここにいます」。信頼できる筋から、自分が第一の暗殺目標になっていることを知らされたアインシュタインは、一市民として静かな暮らしを送るため、プロセイン科学アカデミーのポストを辞任することも考えているとマリー・キュリーに打ち明けた。若いころは権威に反発していた彼が、今では権威ある人間になっていた。彼はもはやひとりの物理者ではなく、ドイツ科学のシンボルであると同時に、ユダヤ人のシンボルでもあったのだ。』
●ボーアが提唱した電子の殻模型には、厳密な数学的論証はありませんでした。それでも、ボーアのアイデアが評価されたのは、1922年12月のノーベル賞受賞講演で、原子番号七十二番の未知の元素(のちにハフ二ウムと名づけられる元素)は「希土類」ではないという予測が正しかったからです。しかしボーアの殻模型の背後には、いかなる組織原理も判断基準もなく、それは膨大な化学的・物理的データにもとづいて、周期表の各グループの化学特性のほとんどすべてを説明することができるという、独創的な思いつきにすぎませんでした。
ボーアが経験的データから作り上げた原子内電子の殻模型に、理論的基礎となる組織原理、「排他原理」を発見したのは、ウォルフガング・パウリでした。
『ボーアの新しい原子モデルで、電子がすべて最低エネルギー準位に集まらないように殻の占拠状態を管理していたのは、パウリの排他原理だったのだ、排他原理は、周期表の中の元素がなぜあのような配列になっているのか、そしてなぜ、化学的に不活性な希ガスで殻が閉じるのかに説明を与えた。しかし、これほどみごとな成功を収めたにもかかわらず、パウリは1925年3月21日に「ツァイトシュリフト・フュール・フィジーク」に発表した「原子内電子の群の閉鎖と、スペクトルの複雑な構造との関係について」という論文の中で、「この規則がなぜ成り立つのかについて、より詳しい理由を与えることはできない」と述べざるをえなかった。』
15.スピンという量子的な概念
●パウリが提唱した排他原理、しかしながらパウリ自身が説明できないとしていた課題は、スピンという量子的な概念によって明快な物理的根拠が与えられました。
『原子内電子の位置を指定するために必要な量子数は、なぜ三つではなく四つなのだろうか?ボーアとゾンマーフェルトの実り多い仕事がなされて以来、原子核の周囲で軌道運動をしている原子内電子は三次元空間を動き回っているのだから、その運動を記述するためには三つの量子数が必要なのは当然のことと受けとめられていた。しかし、パウリの四つ目の量子数には、どんな物理的基礎があるのだろう?
1925年の夏も終わろうというころ、ふたりのオランダ人ポスドク、サムエル・ハウトスミットとへオルヘ・ウーレンベックは、パウリが提案した「二価性」には、それまでの量子数とはまったく異なる特徴があることに気がついた。すでに知られていた三つの量子数が、n、κ、mはそれぞれ、軌道上にある電子の角運動量[回転の勢いを表す物理量]、その軌道の形、空間内の向きを指定するものだったが、「二価性」は電子に内在する性質だったのだ。ハウトスミットとウーレンベックはその性質を、「スピン(回転)」と名付けた。くるくると回転する物体をイメージしがちなこの命名は不幸だったが、電子の「スピン」は完全に量子的な概念であり、原子構造の理論に付きまとっていたいくつもの問題を解決し、排他原理に明快な物理的根拠を与えるものだった。』
『1925年の夏中をかけて、ハウトスミットは原子の線スペクトルについて知る限りのことをウーレンベックに教え込んだ。その後、ふたりが排他原理について論じ合っていたときのことである。ハウトスミットは排他原理を、原子スペクトルの混乱状態を少々整理するための場当たり的な規則のひとつにすぎないと考えていたのに対し、ウーレンベックはあるアイデアを思いついた―そのアイデアを、パウリはすでに却下していたのだが。
電子は、上下、前後、左右の方向に運動することができる。これら三通りの運動の仕方を、物理学者は「自由度」と呼んでいる。量子数はいずれも電子の自由度に対応しているのだから、パウリの新しい量子数は、電子は三つの自由度以外に、別の自由度をもつということを意味しているに違いない、とウーレンベックは確信した。そして彼は、その四つ目の量子数は、電子の回転を意味しているのだろうと考えたのだ。しかし、古典物理学でいう回転は、三次元空間の中の回転運動だから、もしも原子が古典物理学的にクルクル回っているだけなら、地球が自転軸のまわりに回転しているのと同じく、四つ目の自由度を持ち込む必要はない。パウリは、自分が導入した新しい量子数は、何か「古典的な考え方では記述できないもの」を表しているはずだと論じた。』
『ボーアは磁場の問題を挙げて、自分はスピンには反対だと言った。すると驚いたことにエーレンフェストが、その問題はアインシュタインが相対性理論を使ってすぐに解決したというではないか。のちにボーアは、アインシュタインの説明は「まさしく啓示」だったと述べた。かくしてボーアは、電子スピンにどんな問題があろうと、いずれ近いうちにすべて克服されるだろうと確信した。ローレンツの反論は、彼が精通している古典物理学にもとづくものだった。しかし電子のスピンは純粋に量子的な概念であり、ローレンツが指摘した問題は、実はそれほど深刻なものではなかったのだ。さらに、イギリスの物理学者リーウェリン・トーマスがふたつ目の問題を解決した。トーマスは原子核のまわりで軌道運動する電子の相対運動の計算で、二重項の分離幅に2の因子がひとつ余分にかかっていたことを明らかにしたのだ。「そのときから、われわれの苦悩は終わったという確信がゆらいだことはありません」とボーアは1926年3月に手紙を書いた。』
注)電子のスピンというアイデアを最初に提唱したのは、ハウトスミットとウーレンベックではなく、21歳のドイツ系アメリカ人のラルフ・クロー二ヒでした。これは当時、パウリがクロー二ヒのアイデアを否定したためでした。
16.古典物理学と量子物理学との架け橋
●古典物理学と量子物理学の架け橋という考え方は、統合ということを常に考えていたアインシュタインには難しいことでした。ボーアがこのような考え方を持つことができたのは、量子とは何かを明らかにすることに集中し、あらゆる可能性を排除せず、白紙から考えを進めたこと、そして、パウリやハイゼンベルク、ボルンといった数学に長けた優秀な科学者の協力を得られたことが大きな要因だったと思います。
『この動乱のなかでも、アインシュタインはボーアによる一連の論文を読んでいた。1922年3月に「ツァイトシュリフト・フュール・フィジーク」に発表された、「原子の構造と、元素の物理的、化学的性質」と題する論文もそのひとつだった。それから半世紀近く経て、アインシュタインは当時を振り返って次のように述べた。「原子の内部にある電子の殻というアイデアは、その科学上の重要性という点からも、当時のわたしには奇跡のように思われました―そしてその思いは今も変わりません。それは思考の領域における音楽性を、もっとも高度なかたちで現したものでした」。じっさいボーアがやったことは、科学というよりはむしろ芸術に近かった。原子の線スペクトルや、それぞれの元素の化学的性質など、さまざまな分野からかき集めた証拠を組み合わせて、ボーアはひとつの原子像を作り上げた。あたかもタマネギの鱗片のように、電子の殻をひとつひとつ重ねていき、周期表の中のすべての元素を再構成したのである。
そんなアプローチの核心にあったのは、ボーアが抱いていたひとつの確信だった。原子のスケールで成り立つ量子規則から得られる結論はすべて、古典物理学が支配するマクロなスケールでの観測結果と矛盾してはならないと彼は信じていたのだ。ボーアはその確信を「対応原理」と名付け、それを使って原子スケールで考えうる可能性のうち、マクロな領域に拡張したときに古典物理学の結果につながらないものを捨てた。1913年以降、量子物理学と古典物理学のあいだに口を開けていた裂け目にボーアが橋を架けることができたのは、その対応原理のおかげだった。ボーアの助手だったヘンドリク・クラマースがのちに述べたように、ボーアのそんな方法論のことを、「コペンハーゲンの外では通用しない魔法の杖」と呼ぶ者もいた。みんなはその杖を振りこなせずに悪戦苦闘していたが、アインシュタインはそこに、自分に匹敵する魔術師の仕事を見て取った。
周期表に関するボーアの理論にしっかりした数学的基礎がないことを不満に思う者はいたにせよ、彼が次々と打ち出すアイデアに感心しない者はいなかった。また、さまざまな未解決問題について理解が深まったのも確かだった。ボーアはコペンハーゲンに戻るとすぐに、ある物理学者への手紙のなかで、「ゲッティンゲン滞在は何もかもがすばらしく、とても勉強になりました」と述べた。「みなさんがわたしに示してくださった友情がどれほど嬉しかったか、とても言葉では言い表せません」。もはや彼は、理解されないとか、孤立しているなどと感じることはなくなった。』
17.量子論から量子力学へ
●“量子のスピン”という純粋に量子的な概念は、既存の物理学という枠組みの中でそのカケラを「量子化」するという方法には限界があることを明らかにしました。
『プランクの黒体放射の法則からアインシュタインの光量子へ、さらにボーアの電子の量子論からド・ブロイの物質の波と粒子の二重性へと、四半世紀以上にわたって繰り広げられてきた量子物理学の進展は、量子的概念と古典物理学との不幸な結婚から生み出されたものだった。しかしその結婚は、1925年までにはほとんど破綻していた。アインシュタインは1912年の5月にはすでに、「量子論は、成功すればするほどますます馬鹿馬鹿しく見えてきます」と書いた。求められていたのは新しい理論―量子の世界で通用する新しい力学だった。
「1920年代半ばに成し遂げられた量子力学の発見は、十七世紀に近代物理学が誕生して以来、物理理論の分野に起こったもっとも意義深い革命だった」と、アメリカのノーベル賞受賞者スティーブ・ワインバーグは述べた。』
『ハウトスミットとウーレンベックは、それまでの量子論はすでに適用限界に突き当たっているということを、はじめて具体的な証拠で示した。理論家はもはや、古典物理学という足場の上に立ち、既存の物理学のカケラを「量子化」するという方法で間に合わせるわけにはいかなくなった。なぜなら電子のスピンは、それに対応する古典物理学の概念のない、純粋に量子的な概念だからである。パウリとふたりのオランダ人がスピンをめぐって成し遂げた発見は、「古い量子論」が達成した数々の偉業の締めくくりとなる仕事だった。あたりは危機感が漂っていた。物理学が置かれた状態は、「方法論という観点から言えば、論理的に一貫した理論というよりはむしろ、仮説、原理、定理、計算方法の寄せ集めと言うべき嘆かわしい状況」だった。物理学の進展が、科学的な論証によってではなく、芸術的な推理や直観によって起こることもしばしばだったのだ。
パウリは排他原理発見から半年ほど経った1925年の5月に、「現在、物理学はまたしても滅茶苦茶です。ともかくわたしには難しすぎて、自分が映画の喜劇役者かなにかで、物理学のことなど聞いたこともないというならよかったのにと思います」とクロー二ヒへの手紙に書いた。「ボーアが今度もまた、何か新しいアイデアを出して、わたしたちを救ってくれるのだろうと期待しています。いますぐやってくださいと頼みたい気持ちです。彼によろしくお伝えください。わたしに対する親切と辛抱強さ、そのすべてにお礼申します、と」。しかしそのボーアは、「われわれが現在直面している理論上の問題」に対しては、何の答えも持ち合わせていなかった。その春、誰もが待ち望む「新しい」量子論―量子力学―をひねり出せるのは、量子の手品師ぐらいだろうと思われた。』
18.量子の手品師
●量子に関わる多くの物理学者が待ち望んだ量子力学、その領域にたどり着いた「量子の手品師」は、ドイツの神童、ヴェルナー・カール・ハイゼンベルクでした。
『「運動学的および力学的な諸関係についての量子論的再解釈」は、誰もが待ち望み、ある者たちにとっては自分が書きたかった論文だった。「ツァイトシュリフト・フュール・フィジーク」の編集人がその論文を受け取った日付は、1925年7月29日。科学者たちが「アブストラクト」と呼ぶ「前書き」のなかで、著者は大胆にも、次のような壮大な計画を示した―その論文の目標は、「原理的には観測可能であるような量のあいだの関係だけにもとづいて、量子力学の理論的基礎を確立することである」と。十五ページほど先でその目標は達成され、著者ヴェルナー・ハイゼンベルクは未来の物理学の基礎を築いた。この年若いドイツの神童は、いったい何者なのだろうか?彼はいかにして、ほかの人たちができなかったことを成し遂げたのだろうか?』
※ヴェルナー・ハイゼンベルクは1901年12月5日、ドイツ、バイエルン州の町ヴュルツブルクに生まれ、若干26歳でライプツィヒ大学の教授になりました。
『ハイゼンベルクの関心を、アインシュタインの相対性理論から、彼がのちに名をなすことになる量子論に向けさせたのは、相対性理論に関するみごとな解説を書いている最中のパウリだった。彼は、この先大きな実りがある分野は、むしろ原子の量子論だと言ったのだ。「原子物理学の分野には、まだ解釈されていない実験結果がどっさりあるんだ」とパウリは言った。「ある領域では、自然界の性質を明らかにしてくれる証拠だと思えるものが、別の領域で得られた証拠と矛盾するように見える。そのせいで、証拠同士の関係についての統一的な描像はまだ半分も描けていないのさ」。これから先まだ何年も、誰もが「深い霧の中で手さぐり」することになるだろう、とパウリは言うのだった。ハイゼンベルクはそんな彼の言葉を真剣に聞きながら、あらがいようもなく量子の世界に引き寄せられていった。』
ボーアとアインシュタイン1
『第五回ソルヴェイ会議は、「電子と光子」をテーマとして、1927年の10月24日から29日にかけて、ベルギーの首都ブリュッセルで開催された。その会議に参加した人たちの集合写真には、物理学の歴史上、もっとも劇的だった時代が濃縮されている。招待された29人の物理学者のうち、最終的には17人がノーベル賞を受賞することになるこの会議は、歴史上、もっとも輝かしい知性の邂逅のひとつだった。そして、また、物理学の黄金時代―ガリレオとニュートンによってその幕を切って落とされた十七世紀の科学革命以来、科学的な創造力がもっともめざましく発揮された時代―の終焉を告げる出来事だった。』

画像出展:「aucfan」
以下は、本書の巻末に掲載されている年表をベースに、8人の物理学者とその他に分けて作ったものです。その8人は左から、マックス・プランク、エルヴィン・シュレーディンガー、アルベルト・アインシュタイン、ニールス・ボーア、マックス・ボルン、ルイ・ド・ブロイ、ヴォルフガング・パウリ、ヴェルナー・ハイゼンベルクになります。拡大して頂ければ文字の確認はできると思います。
右端の「その他」の1972年、1982年、1997年、2007年の欄に、ジョン・クラウザー博士、アラン・アスペ博士、アントン・ツァイリンガー博士の名前が出ています(青字)、まさにこの業績によって、2022年のノーベル物理学賞を受賞されました。

画像出展:「讀賣新聞オンライン」
ご参考:Youtube“【量子力学】この宇宙の真実知りたくない人は見ないでください...『シンクロニシティ 科学と非科学の間に』by ポール・ハルパーン”(開始~8分30秒の中で「量子もつれ」を解説されています。なお動画は19分です)
量子物理学の学術的な知識がゼロに等しい私がまとめた今回のブログは怪しげです。また、身の程知らずのコメントに「いいんだろうか?」という不安な気持ちもあります。しかしながら、私にとっては大きな前進となりました。今まで、興味だけで数冊の量子論、量子力学の本に挑戦してきて分かったことは、量子は存在すること、量子は古典物理学(ニュートン力学とマクスウェル電磁気学)の常識を超えた未知の領域にある不思議なものだということです。
天才物理学者が一堂に会した第五回ソルヴェイ会議の中でも、アルベルト・アインシュタインの圧倒的存在感は、この世に並ぶ者がない孤高の天才を証明しているように思います。また、科学者の論争を超えた視点に立ち、あらたな一歩を世界に示したニールス・ボーアの「コペンハーゲン解釈」も、量子力学の発展には欠くことのできないものだったと思います。
プランク、ボルン、パウリ、ハイゼンベルク、シュレーディンガー、ウーレンベック等の傑出した才能と強烈な個性の妥協なきぶつかり合いが量子論を磨き上げ、古典物理学とは異なる量子物理学を確立できたのだと思います。
そして、その中心にいたのは、使命感に燃え生涯をかけたニールス・ボーアと、一般相対性理論を発見し統一場理論という理想を追求し続けたアルベルト・アインシュタインだったと思います。
量子論や量子力学が難解なのは間違いないのですが、以下のサイトの最後に書かれている通り、これらは、既に生活の中に深く入り込んでいます。その代表的なものが半導体です。

画像出展:「量子力学と私たちの暮らし(無印良品)」
『リニア新幹線に使われる「超伝導モーター」や「量子コンピュータ」など、今後も「量子力学」にもとづく先端技術は次々と生まれ、暮らしの中に入ってくることでしょう。不思議は不思議のまま置いとくとして、「量子力学」が今後の私たちの暮らしを大きく変えていくことだけは間違いなさそうです。』
1970年代後半、半導体は「産業の米」と呼ばれていました。そして、2030年日本の半導体市場は100兆円規模まで拡大すると言われています。量子力学の発見なくして現代の進歩はあらず、人類最大の発見と言っても過言ではないと思います。
ブログは20世紀初頭の量子革命の論争を、主にボーアとアインシュタインを中心にまとめました。見出しに続き、気づいたことや感じたことを最初に書いています。
目次
プロローグ 偉大なる頭脳の邂逅
第一部 量子
第一章 不本意な革命―プランク
第二章 特許の奴隷―アインシュタイン
第三章 ぼくのちょっとした理論―ボーア
第四章 原子の量子論
第五章 アインシュタイン、ボーアと出会う
第六章 二重の貴公子―ド・ブロイ
第二部 若者たちの物理学
第七章 スピンの博士たち
第八章 量子の手品師―ハイゼンベルク
第九章 人生後半のエロスの噴出―シュレーディンガー
第十章 不確定性と相補性―コペンハーゲンの仲間たち
第三部 実在をめぐる巨人たちの激突
第十一章 ソルヴェイ 1927年
第十二章 アインシュタイン、相対性理論を忘れる
第十三章 EPR論文の衝撃
第四部 神はサイコロを振るか?
第十四章 誰がために鐘は鳴る―ベルの定理
第十五章 量子というデーモン
以下はブログの目次です。なお、ブログは6つに分けています。
1.量子の発見
2.「奇跡と年」と光量子説
3.論争を分けたアインシュタインの価値観
4.アインシュタインの数学
5.“量子テレポーテーション”
6.ボーアの人柄と信念
7.原子の量子論
8.相対性理論>量子論
9.一般相対性理論
10.1916年、光量子の確立
11.因果律の否定
12.アインシュタインとボーアの出会い
13.量子との格闘
14.ボーア祭りとアインシュタインの命の危機
15.スピンという量子的な概念
16.古典物理学と量子物理学との架け橋
17.量子論から量子力学へ
18.量子の手品師
19.古典物理学からの解放
20.観測可能な量だけを使って作った理論
21.(A×B)-(B×A)≠ゼロ
22.量子物理学の新時代の幕開けを告げる論文
23.行列演算と量子力学
24.論理的に矛盾のない量子力学を定式化した「三者論文」
25.守備範囲の広い理論家
26.シュレーディンガーが「作った」波動方程式
27.ハイゼンベルクの難解な行列力学とシュレーディンガーの直感的な波動力学
28.数学的には等価だが物理的世界が異なる波動力学と行列力学
29.波動力学の限界
30.古典的確率とは異なる量子的確率を使って波と粒子を統合する方法
31.アインシュタインとハイゼンベルク
32.アインシュタインにとっての行列力学
33.ボーアとハイゼンベルク(量子の世界のあいまいさの核心、波と粒子の二重性の問題)
34.ハイゼンベルクの不確定性原理
35.不確定性原理を表す式、ΔpΔp≧h/2πとΔEΔt≧h/2π
36.波と粒子の二重性を受け入れるための相補性
37.1927年9月、イタリアのコモで開催された国際物理学会
38.1927年10月24日~10月29日第五回ソルヴェイ会議
39.ボーア(コペンハーゲンメンバー)とアインシュタインの議論
40.「コペンハーゲン解釈」という命名は1955年(28年後)
41.アインシュタインの統一場理論とEPR論文
42.理論と哲学的立場
43.統一場理論
1.量子の発見
●量子の発見者はマックス・プランクです。それは1900年、量子は粒子と波の性質をあわせ持った、とても小さな物質でエネルギーの単位といわれています。
『1900年にプランクは、光をはじめあらゆる電磁放射のエネルギーは、ある大きさの塊でしか、物質に吸収されたり物質から放出されたりできないと考えざるをえなくなった。「量子」とは、そんなエネルギーの塊に対し、プランクが与えた名前だった。「エネルギー量子」という考え方は、確立されて久しいエネルギー観―すなわち、エネルギーはあたかも蛇口から流れ落ちる水のように、なめらかに途切れなく放出されたり、吸収されたりするという考え―と、きっぱり手を切る過激な提案だった。ニュートン物理学に支配された巨視的な日常の世界では、水がポタリポタリと雫になって蛇口から滴ることはあっても、エネルギーがさまざまなサイズの滴として交換されることはなかった。だが、原子やそれ以下の階層は、量子の支配する領域なのだ。
やがて、原子の内部に存在する電子についても、そのエネルギーは「量子化」されていることが明らかになった―原子内の電子は、とびとびの値のエネルギー量しかもつことができないのである。同様のことは、エネルギー以外の物理量についても言えた。微視的な領域は、ぶつぶつに切り離された離散的な世界であって、単に日常世界をスケールダウンしただけではないことが明らかになったのだ。日常の生活では、点Aから点Cに移動するためには、どこか中間の点Bを通過しなければならない。ところが微視的な世界では、原子内の電子はエネルギー量子を放出したり吸収したりすることで、いかなる中間点も通過することなく、ある場所で消え、次の瞬間には別の場所にひょっこり現れることができるのだ。そんな現象は、連続的な古典物理学で扱える範囲を超えていた。それはあたかも、ロンドンで謎のように消えた物体が、次の瞬間にはパリ、あるいはニューヨークやモスクワに現れるようなものだった。』
2.「奇跡と年」と光量子説
●アインシュタインが成し遂げた1905年は「奇跡の年」と言われています。それは学術誌に寄稿した四篇の論文です。
1)光量子説
2)原子の大きさを求める新しい方法を提案するもの
3)ブラウン運動―液体中に浮かんだ微粒子がランダムに動きつづける運動―を説明するもの
4)相対性理論の構想を示したもの
『アインシュタイン自身が「真に革命的」だと言ったのは、相対性理論ではなく、光と放射に関するプランクの量子概念を拡張した仕事のほうだった。アインシュタインにとって相対性理論は、すでにニュートンやその他の人びとによって確立された考えを、「修正した」だけにすぎなかったのに対し、光の量子という新しい概念は、完全に彼の独創であり、従来の物理学との断絶の大きさという点では、もっとも過激だと考えていたのだ。アマチュアの物理学者とはいっても、そんな説を唱えるのは冒瀆的なことだった。
それまで半世紀以上にわたり、誰もが光は波だと思っていた。ところがアインシュタインは、「光の生成と変換に関する、ひとつの発見法的観点について」と題したその論文で、光は波ではなく、粒子状の量子でできているという説を打ち出したのだ。』
●光は波であるというのが当時の常識でした。アインシュタインの「光量子仮説」はマックス・プランクが提唱した「エネルギー量子仮説」を拡張し、光はプランク定数と振動数を掛け合わせたエネルギーを持つ粒子(光量子)の集合体であるとするものでした。この革新的な仮説を信じる物理学者はほとんどおらず、アインシュタインの考えは孤立していましたが、18年後の1923年、アーサー・コンプトンによる「コンプトン効果」により「光量子仮説」は完全に立証されました。なお、この事実はニールス・ボーアにとっても衝撃的なものでした。
ご参考:“量子仮説と光量子仮説の違い”(ミクロの世界でエネルギーが不連続であることを解明したのが量子仮説。光は波と粒子の二重性があることを示したのが光量子仮説です)
ご参考:“光電効果と光量子仮説”
ご参考:“光量子仮説 と 光電効果”(【ミクロの世界-その1-】より)
3.論争を分けたアインシュタインの才能と価値観
●スイス特許局の3年間では「多面的に考える」訓練になったという話をされています。アマチュア物理学者時代を経て、世界最高の物理学者の一人となったアインシュタインの無二の才能は、「気味悪いほどの洞察力」と「本質を見抜く嗅覚」であり、最後まで譲ることがなかったのは、物理学の「実在性」だったようです。
『「彼(アインシュタイン)は、良く知られたなにげない事柄の陰に隠れて、みんなに見逃されていた意味を見抜くという、天賦の才に恵まれていた」と述べたのは、アインシュタインの友人で、やはり理論物理学者のマックス・ボルンである。ボルンはさらにこう続けた。「彼をわれわれと隔てていたのは、数学の技量ではなく、自然の仕組みを深く見通す、気味が悪いほどの洞察力だった」。アインシュタインは、数学では直観があまり働かず、真に重要なことを、「本質的でないことから」選り分けることができないと考えていた。しかし物理学になると、彼の嗅覚は誰にも負けなかった。物理学に関するかぎり、すでに学生時代には、「基礎につながる問題だけを嗅ぎつけ、その他の問題―こまごましたことで頭を埋め尽くし、重要なことを見えなくさせるたぐいの問題―から選り分けることができるようになった」と、アインシュタインは述べている。』
4.アインシュタインの数学
●1896年10月、アインシュタインは理数科教員養成課程に入学しました。同期は11人、うち数学と物理学の教員になろうとする学生はアインシュタインを含め5人でした。その中で唯一の女性であった、ミレヴァ・マリチは後にアインシュタインの妻となりました。また、半世紀に渡った量子力学との格闘では、アインシュタインの数学がひとつのターニングポンとになったように思います。
『ミュンヘン時代には、彼の聖典となった小さな幾何学の本をむさぼるように読んだアインシュタインだったが、数学そのものにはすでに興味を失っていた。「ポリ」で数学を教えていたヘルマン・ミンコフスキーは当時を振り返って、アインシュタインは「怠け者」だったと言った。アインシュタインは後年、そうなったのは数学が嫌いだったからではなく、「物理学の基本原理についての深い知識に近づくことは、数学的方法と密接に結びついている」ということが、当時はわからなかったためだと語った。その結びつきを、彼はその後の研究生活で苦労して知ることになる。彼は、「もっとしっかり数学を勉強しなかった」ことを悔やんだ。』
ご参考:“数学と物理の絡み合い” PDF43枚
5.“量子テレポーテーション”
●「1913年7月に発表された第一部の論文([原子と分子の構成について]という同一タイトルの三部作)は、量子を原子の内部にじかに持ち込んだ、真に革命的な仕事だった」との高い評価を受けています。ボーアが気づいた奇妙な性質は“量子テレポーテーション”と呼ばれています。これは、量子状態を転送する技術であり、古典的な情報伝達手段と量子もつれの効果を複合的に利用して行われます。
『ボーアは、電子の量子飛躍には、非常に奇妙な性質があることに気がついた。飛躍しているときの電子の所在については、何も言えないということだ。軌道間の飛躍―エネルギー準位間の遷移―は、瞬間的に起こらなければならない。さもないと、軌道から軌道へと移動するあいだに、電子はエネルギーを放出してしまうからだ。ボーアの原子の内部では、電子は軌道と軌道のあいだの空間には存在することができない。電子はまるで魔法のように、ある軌道上から消えた瞬間、別の軌道に姿を表すのだ。』
“量子テレポーテーション”の実験は84年後の1997年、フランチェスコ・デマルティ―率いるローマ大学の研究チームが成功させました。
ご参考:Youtube“【簡単解説】数式なしで理解したい!「量子テレポーテーション」や「量子もつれ」の原理や仕組み、方法を初心者にも分かるように解説!” (9分33秒~13分33秒に量子テレポーテーションについて解説されています。難解な内容を分かりやすく解説されていると思います)
6.ボーアの人柄と信念
●ボーアの論文([原子と分子の構成について]という同一タイトルの三部作)制作に関して、指導教授のような存在であったアーネスト・ラザフォードに相談する場面があるのですが、ボーアの人柄や研究に対する信念(執念)が出ている興味深いものでした。
『もうひとつ、小さな問題ではあったが、ボーアが深く悩んだ指摘があった。ラザフォードはその論文を、「切り詰めなければ」ならないと言ったのだ。「論文が長いと、じっくり読んでいる余裕がない読者の腰が引けてしまう」というのだ。なんなら英語を直すのを手伝おう、と述べた後、ラザフォードは追伸として、次のように書いた。「不必要と思う部分は、わたしの判断で削除してもかまいませんね? 返事待ちます」
それを読んでボーアは恐れおののいた。単語ひとつ選ぶのにも苦しみ抜き、果てしなく推敲を重ねる彼にとって、たとえそれがラザフォードであろうとも、自分以外の人間が論文に手を加えるなどとは、考えることさえできなかったのだ。二週間後、ボーアは変更と追加を書き込み、さらに長くなった改訂版の原稿を送った。ラザフォードはボーアの改訂を、「良くできているし、妥当な改訂のように思われます」と言ってくれたが、このときもやはり論文を短くするように強く求めた。その二度目の返事を受け取る前に、ボーアはラザフォードに、今度の休暇にマンチェスターに伺いますと告げた。
ボーアが玄関の扉をノックしたとき、ラザフォードは友人のアーサー・イヴをもてなしているところだった。イヴの回想によれば、ラザフォードはすぐに、その「ひょろりとした男の子」を連れて書斎に行き、その場に残ったラザフォード夫人が、今のはデンマーク人で、夫は「あの若者の仕事を、とても高く買っているのです」と言ったという。それから数日のあいだ、夕方何時間も議論に議論を重ね、ボーアは一字一句省くことなどできないと懸命に訴えた。ボーアが後年語ったところでは、ラザフォードはその間、「ほとんど天使のような忍耐力を示した」という。
やがてラザフォードは疲労困憊し、ついに折れた。のちにラザフォードは、この一件を友人や仲間の物理学者たちに話して聞かせるようになった。「彼が論文の一字一句を大切にしていることが良くわかったよ。すべての文、すべての言い回し、すべての引用を、断じて捨てるつもりがないんだ。あの覚悟にはほとほと感心させられたね。どれもこれも、明確な理由があって書いているのだ。わたしははじめ、省略できる文はたくさんあると思っていた。しかし彼の説明を聞いているうちに、全体がきわめて緊密に織りあげられているので、変更できる箇所はひとつもないのだということがわかったよ」。皮肉にも、ボーアはずっと後になって、「議論の提示のしかたが明確でない」というラザフォードの意見は正しかったと述べた。』
7.原子の量子論
●ボーアの論文は画期的でしたが、特に当時の常識に照らし合わせると難しい要素を数多く含んでいました。
『ボーアは、古典物理学と量子力学を混ぜこぜにして、自分の原子モデルを急ごしらえに組み立てた。その過程で、広く認められていた物理学の常識を破るようなことを提唱した。まず、原子内電子は、定常状態という、特定の軌道しか占めることができないということ。つぎに、定常状態にある電子は、エネルギーを放射できないということ。そして、原子は多数ある飛び飛びのエネルギー状態のうち、どれかひとつの状態を占めるということだ。それらの状態のうち、エネルギーがもっとも低い状態を、「基底状態」という。そして電子は、「どういうわけか」、エネルギーの高い定常状態から低い定常状態へと飛び降りることができ、そのエネルギー差をエネルギー量子として吐き出す、というのだった。しかし彼の原子モデルは、水素原子のいくつかの性質―水素原子の半径など―を正しく予測することができたし、線スペクトルが生じる理由を物理的に説明することもできた。のちのラザフォードは、原子の量子論は、「物質に対する頭脳の勝利であり」、ボーアがその謎を解明するまでは、ラザフォード自身、線スペクトルの謎が解けるまでには、「何百年もかかるだろう」と思っていたと述べた。
ボーアの仕事がどれほど大きな事件だったかを知るためには、原子の量子論が引き起こした反応を見ればよい。1913年9月12日、英国科学振興協会(BAAS)の第八十三回年会が、バーミンガムで開かれた。それは原子の量子論が公の場で論じられる最初の機会となった。聴衆の中にはボーア自身もいたが、彼の仕事への反応は冷ややかで微妙だった。J・J・トムソン[1897年、電子を発見した]、ラザフォード、レイリー、ジーンズという錚々たる顔ぶれがそろい、外国からの著名な参加者には、ローレンスやキュリーもいた。ボーアの原子モデルについて強く意見を求められたレイリーは、「70歳を過ぎた者は、新しい理論について性急にものを言うべきではないでしょう」と社交辞令を使った。しかしそんなレイリーも、親しい人たちに対しては、「自然はそんなふうには振る舞わない」し、「そんなことが現実に起こっているとは考えにくい」と語った。トムソンは、ボーアがやったように原子を量子化する必要なないと言い、ジェームズ・ジーンズは、失礼ながら賛成しかねる、という言い方をした。ジーンズは、聴衆でいっぱいの会場で行った講演のなかで、ボーアのモデルが正当化されるためには、「非常に重みのある成功」を収める必要があるだろうと述べた。
ヨーロッパ大陸では、原子の量子論は激しい反発を買った。ある白熱した議論のさなか、マックス・フォン・ラウエは、「まったくのナンセンスだ! マクスウェルの方程式はいかなる状況下でも成り立つ。円軌道を描く電子は、放射を出さなければなりません」と述べた。ゲッティンゲンにいたボーアの弟ハーラルは、当地では彼の仕事に大いに関心が寄せられているが、彼の仮設はあまりに「大胆」かつ「荒唐無稽」だと思われているようだ、と教えてくれた。
ボーアの理論は、初期にひとつの成功を収め、アインシュタインを含めて何人かの支持を得ることができた。』
8.相対性理論>量子論
●アインシュタインにとって、数学は物理学ほど興味を持てる学問ではなかったようです。目にはみえないミクロの世界の量子は数学に頼ることが多く、「ゴリゴリの光量子信者ではありません」という自身の発言になったのだと思います。そして、アインシュタインは相対性理論を拡張するという仕事の方を優先しました。
『アインシュタインは、量子にも、光の二重性にも、容易にはなじめないと思うようになった。彼はヘンドリク・ローレンツへの手紙にこう書いた。「はじめにお断りしておきたいのですが、わたしはあなたが思っていらっしゃるような、ゴリゴリの光量子信者ではありません」。自分がそう誤解されてしまうのは、「論文にあいまいな書き方をしてしまったためです」と彼は言った。まもなくアインシュタインは、「量子は本当に存在するのか」を問題にすることさえやめてしまった。1911年11月に、「放射理論と量子」というテーマで開かれた第一回ソルヴェイ会議から戻ったアインシュタインは、もうたくさんだとばかり、量子の狂気を頭の片隅に追いやった。それから四年間、ボーアが原子の量子論をひっさげて舞台中央に登場しつつあるちょうどそのころ、アインシュタインは重力を取り込むために相対性理論を拡張するという仕事に専念するという仕事に専念すべく、量子のことは事実上棚上げにする。』
株と債券
株を始めたのは入社5年目です。
きっかけは、営業管理部門から営業に移り、そこのH課長さんに「お金はわずかで良いので、勉強になるから株をやってみたらどうだ」というアドバイスを頂いたことです。確かに営業として顧客を理解する一つの手段になるのは間違いないと思い、自分自身納得して始めました。
その後、かなり長く休眠していた時もあったのですが、40歳を過ぎて「本気でやってみっか!?」という思いが何となく浮かびました。当時、オフィスがあった西新宿のお昼どきだったと思います。
マネックス証券の松本社長の著書だったか、ネットでみた記事だったかは定かではないのですが、「株をやるなら、就職したくなるような会社の株を買ったらいい」という話が頭にありました。また、営業マンだったためか「理解できる会社・業界がいいのではないか」という考えもありました。
そこで、日本HPというITの会社に勤務していたこともあり、ターゲットを外資系ITに限定し、2、3の銘柄にしぼって長期運用することにしました。株式に費やす時間は週1時間程度、「売らなければ損はしない(株が暴落しても慌てない)」、「会社経営のリーダーシップと会社方針が1番大事」という2点を最重要項目として肝に銘じ、挑戦をスタートさせました。
20年後、売買はほとんど直感頼みでしたが、幸い大きな成果を得ることができました。
そして今年、65歳になり「どうせやるなら、少しは投資家っぽくなりたいもんだ。直感頼みではなく、情報とプランに基づいて運用できるようになってみたいもんだ」との思いから、そのための準備を始め、自分なりに熟慮を重ねた結果「ひとまず、次のような方針でやってみよう」ということにしました。
1.分散投資
a)株式
●米国株…80%以上(テクノロジー関連限定)
●日本株…20%未満(3銘柄以下に絞る)
b)株式以外
●S&P500ETF
●米国債券ETF
●米国短期国債
2.運用
●長期運用
●リバース運用
●休むことも運用
3.情報源
●経済指標カレンダー(マネックス証券)
●マネクリ(マネックス証券)
●“ばっちゃまの米国株”(以下のサイトは“ばっちゃま”さんに教えて頂きました)
●VIX(Volatility Index:恐怖指数)
●AAII Investor Sentiment Survey
●Put/Call Ratio(MacroMicro)
●finviz(MapsだけでなくNewsなど、他のコンテンツも大変充実しています)
●Motley Fool(“Earnings
Transcripts”[決算報告]も掲載されています)
●CME FedWach(金利予想です。左メニュー上段、”Probabilities"をクリックして下さい)
※【永久保存版】米国株投資家の俺が広瀬隆雄氏から学んだ最強の投資法とプロの投資マインド
4.時間
●基本、1日1時間以内。
☆ウォーレン・バフェットの言葉
『私はただ、明らかに他のものよりも優れていて、私が理解できるものを見るだけだ。』
『強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく。』
※以下のグラフは、DAILY FXの”Market Cycles | Phases, Stages, and Common Characteristics”から拝借しました。
長い前置きでしたが、今回のメインテーマは米国債券を理解することです。勉強させて頂いたのは、『証券会社がひた隠す 米国債券投資法』です。
目次は第3章のみ全て記述、第3章以外は大項目と中項目のみで小項目は記述していません。
ブログに取り上げたのは、黒字の個所になります。
まえがき
第1章 儲け話は山ほどあるけどリスクも山盛り
●「株価の上下は神のみぞ知る」が常識
●ノーベル賞受賞者がファンドをやったら
●運用のプロたちは本当に勝ち続けているのか?
●儲け話は「勝っても地獄、負けても地獄」そのワケとは?
●古今東西いつの時代もはびこる儲け話
●なぜ日本人は金融リテラシーが低いのか?
●年金のインフレーション・デフレーション
●かつて日本円は360円だった。為替とは「変動するもの」
●日本が「AAA」から「A」に格下げされたことの意味
●円安のカウントダウンが始まった。
第2章 なぜ日本人はタンス預金が好きなのか?
●これほど「元本」にこだわるのは、日本人だけ
●複数の銀行に預けても、「日本円」ではリスク分散にならない
●「投資信託」は運良く儲かっても手数料負け
●証券マンは胃が10個あっても足りない
●カモネギ日本人の、間違いだらけの投資法
●イソップ物語が教える運用法。最後に勝つのはアリやカメ
第3章 お金が勝手に増えていく米国債投資の仕組み
●そもそも債券って何?
・債券とは「貸金」
・ゼロクーポン債の仕組み
・日本の国債をお勧めできない理由
●元本がきちんと返ってくるのは債券だけ
・まずは元本を守るということ
・ゼロクーポン債の「収益性」
・「流動性」が資産のバランスを整える
●雪だるま式に増える複利の魅力
・お金が増える「複利」の法則
・米国ゼロクーポン債と為替リスク
第4章 ノーリスク、ストレスフリーの米国債の秘密
●米国債は1年に1度思い出すだけでいい
●米国債なら元本割れリスクはほぼゼロ
●維持費ゼロ!これが他の投資にはない米国債の強み
●どれくらいの金額で、どのように買えばいいのか
●つみたてNISAと米国債で将来不安が激減
●米国債は、農耕民族の日本人にフィットする
●40歳超でも旨味がある米国債投資法
第5章 デメリットは米国が破産したときだけ
●米国債投資に向かない人とは?
●途中解約は元本割れの可能性あり
●為替リスクは、1ドル50円を超える円高だけ
●米国債投資が向かない人
●円安が進むほど米国債投資のメリットは高まる
●米国以外の国債はどうなのか?
第6章 生命保険をやめて米国債を買う
●あなたは毎年、保険料をいくら払っていますか?
●保険商品は「定期」だけでいい?
●他の制度とうまく組み合わせること
●保険の担当者に米国債の話をしてみよう
第7章 老後の資金が毎月10万円入ってくる
●もしも65歳から年金プラス10万円がもらえたら
●米国債投資に必要なのは「口座」「キャッシュ」「スマホ」だけ
●手続きは他の金融商品のなかで、最も簡単
●古都の老舗の旦那衆も米国債は御用達
●20代からの「ズボラ年金」の始め方
●個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」と米国債
教えて!米国債 Q&A
あとがき
第1章 儲け話は山ほどあるけどリスクも山盛り
●古今東西いつの時代もはびこる儲け話
・「空売り」とは投資対象(例えば“株”)を所有することなく、売り契約を結ぶこと。
※ご参考:“株の空売りの仕組みとは|シンプルな図解で分かりやすく解説”
※ご参考:“株の「空売り」とは?仕組みやメリット、やり方をわかりやすく解説!”
・「レバレッジ」とは株やFX、不動産投資などでよく使われる。定義は「他人の資本を活用して、自己資本に対する利益を高めること」となる。一言でいえば、「借金して投資する」ということ。「空売り」同様、リスクの高い金融商品である。
●なぜ日本人は金融リテラシーが低いのか?
・海外では学校で、基礎教育として金融について学んでいるが日本では行われていない。そのため、何も勉強せずに株や投信に手を出すことは危険である。
●かつて日本円は360円だった。為替とは「変動するもの」
・FXとはForeign Exchangeの略で、「外国為替証拠金取引」のことである。「日本円⇒米ドル」など通貨を買ったり売ったりしたときに発生する利益に狙う取引である。為替の上下で損得が決まるので、とてもギャンブル性が高い。
●日本が「AAA」から「A」に格下げされたことの意味
・日本の格付けは高いもののトップグループではない。この理由の一つは国の借金で、2023年末には1,068兆円になると予想されている。
※ご参考:“【基礎解説】格付けとは?格付け会社や国債の格付けを紹介!”
※ご参考:“日本国債の格下げ、日銀の政策転換が契機に”
※ご参考:“1~2年は日本格付け変わらない、日銀正常化波乱ならリスク”
※ご参考:“労働生産性の国際比較”

画像出展:「財務省:日本の借金の状況」

画像出展:「ファクトから考える中小製造業の生きる道」
2019年(22年後)
日本:20位(44.6)
米国:7位(77.0)
1997年から2019年の生産性の伸びは、日本は27.8%、米国は215.0%で、米国は日本より約7.7倍、労働生産性が改善されました。
●円安のカウントダウンが始まった。
・一般的には国力の低下はその国の通貨の価値を下げる。日本は超高齢化、少子化、人口減少が懸念され、これらは国力低下の要因に波及するので、中長期的には円安に向かう可能性がある。
※ご参考:“アメリカ合衆国の人口ピラミッド(1950-2100) / 単位(Unit): 千人 / 2019年推計”(Youtube)
※ご参考:“日本の人口ピラミッド(1950-2100) / 単位(Unit): 千人 / 2019年推計”(Youtube)
第3章 お金が勝手に増えていく米国債投資の仕組み
●そもそも債券って何?
・債券とは「貸金」
-株式は企業への「出資」になるが、債券は「貸金」になる。つまり、債券は借用証書に相当する。
-株式(出資)は、企業価値が高まるとキャピタルゲイン(株価の上昇)やインカムゲイン(配当金)が期待できる反面、株価が下がる場合もあり、上がるか下がるかは企業の業績次第である。
-債券(貸金)の場合は、期間を定めて返済されるが貸金なので利子がつく。多くの債券は購入時に利子が確定しているので、満期まで保有していればいくらになって戻ってくるか明確である。従って、安全性が高い金融商品といえる。
-債券も株式同様、自由に売却ができる。ただし、その場合は流通価格で売却することになる。
・ゼロクーポン債の仕組み
-「クーポン」とは債券に付随する利金ことである。「ゼロクーポン(ゼロクーポン債)」とは、利金がつかない債券を意味する。この「ゼロクーポン」は、利金はつかないが、購入時に額面金額より安く買えるという特徴がある。そのため、「ゼロクーポン」は「割引債」と呼ばれることもある。償還日には額面金額で支払われるため、その償還差益が利金の代わりとなる。
-利金がつくやタイプの債券は、一般的に「利付債」と呼ばれている。「利付債」の魅力は利金がつくため、定期的な収入が得られることである。
-例えば30年物の米国ゼロクーポン債に100万円投資すると、30年後には概算で2.2倍の220万になって返ってくるイメージである(税金及び為替変動は考慮せず)。元本を減らすことなく債券特有の安全性を維持し、これだけのリターンを得られる金融商品は他に見つけることはできない。
・日本の国債をお勧めできない理由
-米国より低い格付けにもかかわらず、利回りも悪いからである。ただし、為替変動のリスクはない。ただし、為替変動のメリットもない。
●元本がきちんと返ってくるのは債券だけ
・まずは元本を守るということ
-債券は満期日の償還額(額面金額)が決まっているので、額面金額を受け取れる。ただし、理論的には発行元の倒産や破綻によって元本の返済や利払いができなくなることがある。そのため、高い格付けの債券を選択すべきである。
・ゼロクーポン債の「収益性」
-債券は途中で売却することもできる。その場合、売却価格は流通価格となる。価格が上がっていれば、途中売却による収益(キャピタルゲイン)を得ることができる。
・「流動性」が資産のバランスを整える
-米国債は世界中で売買されているので、流動性が高く売買しやすいという利点もある。
●雪だるま式に増える複利の魅力
・お金が増える「複利」の法則
-単利とは元本だけに利息がつくもの。元本が100万円で単利が10%の場合、1年後は110万円、2年後は120万円と毎年元本(100万円)の10%(10万円)が加算されていく。
-複利とは元本と利息を含めた金額に利息がつくもの。元本が100万で複利が10%の場合、1年後は110万円、2年後は121万円、3年後は133万円と少しずつ増える金額が多くなっていく。
-元本1,000万円、年利10%を単利と複利について、10年後の金額で比較すると、単利は2,000万円、複利は約2,590万円になる。
・米国ゼロクーポン債と為替リスク
-米国債では為替変動によって日本円の価値は上下する。もし、円高によりドルの価値が下がっている場合でも、そのままドルで持ち続けることができるなら、円安になるまで待って円に換えれば為替による損失を避けることは可能である。
※ご参考:“MUFG 外国為替相場チャート表" 表示期間を“5年”にして頂くと2020年がやや円高ですが、これはコロナの影響(日本での感染の確認は2020年1月15日)が米国の方が深刻だったからではないかと思います。また、短期的にはゼロ金利の見直しにより円高傾向になると考えられますが、長期的には円高局面が長く進行することはないのではないでしょうか。
第4章 ノーリスク、ストレスフリーの米国債の秘密
●米国債は1年に1度思い出すだけでいい
・米国債は「貸金」なので株や投資信託、FXのように投資対象の変化や売買のタイミングで悩んだりすることもない。基本的に「ほったらかし」で運用できる。
・米国ゼロクーポン債を売却せず償還日まで保有するのであれば、購入時に手数料相当分を支払った形になり、その後、手数料はかからない。
・株の「売買手数料」や投資信託の「販売手数料」や「信託報酬」は、米国ゼロクーポン債にはないので有利である。
●米国債なら元本割れリスクはほぼゼロ
・米国債は購入時に利回りが確定する。つまり、いくらの利益($)が出るかが明らかになる。
・『たとえば、米国ゼロクーポン債を野村證券の窓口で購入する場合を考えてみましょう。28年4カ月物米国ゼロクーポン債は、購入単価が「45.52%」となっています(2017年10月時点)。つまり額面金額10,000ドルにしたい場合、4,552ドルで購入できるということです。これが割引債と呼ばれる所以です。額面金額、要するに28年4カ月後にもらえる金額は10,000ドルですが、購入時は「10,000ドル×0.4552[45.52%]=4,552ドル」で買えてしまう。それだけ事前に割引されて(利金分が差し引かれて)、販売しているということです。
ちなみに、この場合の利回りを計算すると、「2.790%」となります。安全に運用できて、かつドルベースで3%近くの利回りが購入時に確定しています。
理論上為替リスクはあるものの、これだけ分かりやすく、しかも安心して購入できる金融商品は、他にありません。』
・万一、米国が破綻する時は地球規模で危機に直面している可能性が高いのではないか。
・米国債の利回りは、米国債は絶えず市場で取引されており、その利回りは常に変化している。
●維持費ゼロ!これが他の投資にはない米国債の強み
・米国債の「口座管理料」は証券会社によって異なる。有料の場合、無料の場合、金額によって口座管理料が無料になる場合があるので、事前に確認すべきである。
第5章 デメリットは米国が破産したときだけ
●途中解約は元本割れの可能性あり
・途中解約は可能。ただし、その時の価格(市場価格)で売却することになるため、購入時の価格を下回る「元本割れ」になる場合もある。従って、安定を最優先にするのであれば途中解約しないことである。
●米国以外の国債はどうなのか?
・米国同等以上の格付けを有している国はあるが、流動性や購入しやすさという点で考えると米国債の方が優れている。
・利付債は利金を得られる一方、複利の効果が得られにくい。貯蓄性を考えると複利効果が大きいゼロクーポン債の方が適している。
重要
「“欲ブタ”になってはいないか?」と自問する。
株をやっていて思うのはメンタルコントロールです。これはスポーツでいえばゴルフに似ているように思います。“ばっちゃまの米国株”さんのお話の中に、“欲ブタ”という言葉が時々出てきますが、英語では“Greedy Pig”となります。日本では「二兎を追う者は一兎をも得ず」に相当すると思います。また、「虻蜂取らず」ということわざもあるようです。
ご参考1:“市場サイクル | フェーズ、段階、および共通の特徴” DAILYFX

『市場サイクルとは、強気市場が最初から最後まで成熟し、その後、強気市場からの行き過ぎが修正される弱気市場に反転するプロセスです。市場の投機が始まって以来、これらのサイクルは同様の形で展開してきました。』
※”ばっちゃの売国株さん”がYouTubeで解説されています。
ご参考2:“G7の1人当たり金融資産の保有金額”
ご参考3:“投資家別の株式売買情報”

画像出展:「西日本新聞」
”個人”は約2割です。
余談
2023年7月20日から“株日記”をつけ始めました。毎日ではないのですが、発見したことや勉強になったことを書き留めています。あるいは持株が大きく下がった時などは、売るべきかか保有するべきかについて、自分なりに調べて分かったことや判断した理由を記録に残すようにしています。
10年後、「これは成功だった」と満足できる成果を上げることができたならば、“アマチュア投資家”の称号を自らに付与したいと密かに思っています。
デンマークのスマートシティ5
6章 イノベーションを創出するフレームワーク
1.オープンイノベーションが進展する背景
●厳しい風土が育んだ異業種連携
・デンマークのオープンイノベーションは、文化風土、産業の歴史と密接に関係している。
・天然資源が乏しく、人口の少ない国であり、厳しい自然の中で暮らすために人々は必然的にお互いに協力しあうという文化を育んできた。酪農を営むためは関係者が協同することが不可欠であったし、家具や建築の世界も連携する必要があった。
●複雑化する社会に対応できないシステムの更新
・デジタル化によって各分野の個別システムがつながり、複数の分野を同時に考慮した最適化が行われないと、暮らしやすい都市はつくれないが、現実には行政組織は部門ごとに縦割り組織になっているので、柔軟に対応することができない。
・現代は19世紀につくられた法制度に基づく社会システムの上で、20世紀のビジネスモデルを展開し、そこに21世紀の技術を使おうとしている状況になっているので、さまざまな矛盾が現われている。こうした、時代遅れの社会システムを現在に合う形に再構築するには、異なるセクターの知見を組み合わせたオープンイノベーションが欠かせない。
2.トリプルヘリックス(次世代型産官学連携)
・デンマークではPPP(公民連携:Public Private Partnership)によるスマートシティ・プロジェクトの推進やイノベーションの創出で民間のノウハウを取り入れている。
・コペンハーゲン市はPPPを推し進めるために2009年、コペンハーゲン投資局、広域コペンハーゲン、ジーランド地域が連携して「コペンハーゲン環境技術クラスター」を設立した。このコペンハーゲン環境技術クラスターが特に力を入れていたのが、「トリプルヘリックス(Triple Helix、デンマーク型産官学連携)」である。
・デンマークのトリプルヘリックスは、公的機関、民間企業、研究機関がダイナミックに連携してプロジェクトを進める。日本では各機関からの出向となるが、デンマークでは、このクラスターの正規雇用者となる。
・クラスターの運営責任者はプロジェクトの企画書を作成し、国や自治体、民間企業から出資を募り、プロジェクトを実行する。運営責任者は自身の給与もプロジェクトを通じて捻出しなければならないので、必然的に企画力、関係者を巻き込むコミュニケーション力や交渉力に長けている人材が雇用される。
・クラスターに腰掛けでいる人はいない。それぞれの職務責任も明確なので、結果を出すことに真剣になる。
・このトリプルヘリックスの成功事例としては、コペンハーゲン市やオーフス市のスマートシティ・プロジェクト、オーデンセ市のロボット・プロジェクトなどが挙げられる。
3.IPD(知的公共需要)
・IPDはPPPを高度化した手法である。特に複雑で革新的な要素を取り入れた公共プロジェクトを計画・実証し、大規模なインフラソリューションを調達・導入する際に有効であるとされている。
4.社会課題を解決するイノベーションラボ
●マインドラボ
・「マインドラボ」はデンマークのフューチャーセンター(世界中で展開され、イノベーションを創出する手法として一般化されている)であり、2002年、経済商務省のインキュベーション組織として立ち上げられ、最後は産業・ビジネス・財務省、雇用省、教育省と3省庁の管轄になった。
・マインドラボは、省庁横断的に社会問題を解決するための政策を設定し、ソリューションを開発、それらを社会実装することを目的に設立された。加えて国と自治体を結びつけ、さまざまな利害関係を統合する横断的なプラットフォームとしての機能を持つ。
・マインドラボは2018年に閉鎖され、よりデジタルに特化した組織の「破壊的タスクフォース:Disruption Taskforce」に引き継がれた。
●ブロックスハブ
・「ブロックスハブ」は多様な企業や研究者がより良い都市づくりのソリューションを創出するためのイノベーション・ハブである。
・2016年に建築や都市プロジェクトを支援する民間組織「リアルダニア」、コペンハーゲン市、政府の産業・ビジネス・財務省により設立され、2018年から運用を開始した。
・ブロックスハブは未来のスマートシティ・ソリューションの戦略拠点であり、多国籍企業にとってデンマークや北欧市場へのゲートウェイとして位置づけられている。
・世界中に似たような組織やイノベーションセンターはあるが、異分野横断的な連携を実現できている組織はまだないというのがブロックスハブ幹部の見解(2018年9月)である。それをコペンハーゲンでつくりあげて世界に還元していこうというのがブロックスハブの狙いである。
※ご参考:“BLOXHUB”
5.イノベーションにおけるデザインの戦略的利用
●ユーザー・ドリブン・イノベーション
・デンマークでは2010年前後からイノベーションに注力した取り組みを強化しているが、多くは技術主導型のイノベーション議論が中心であった。一方、利用者をイノベーション・プロセスに巻き込むべきとの認識が高まり、デンマークでは伝統的に人間中心の考え方が浸透していたこともあり、その考え方を体系的にまとめ方法論として組み立てられたのが、「ユーザー・ドリブン・イノベーション」である。ただし、これはデンマーク固有のものではなく、フィンランドやスウェーデンなど他の北欧諸国でも取り組まれている。
●デザイン・ドリブン・イノベーション
・ユーザー・ドリブン・イノベーションはユーザー自身が経験していないもの、認知していないものには対応できないという限界がある。そこで出てきたのが、デザイン・ドリブン・イノベーションである。
・アップルウォッチなどのウェラブル製品もデザイン・ドリブン・イノベーションで新たな価値を創出している。
●データ・ドリブン・イノベーション
・デザイン・ドリブン・イノベーションと並行する形で取り組まれているが、「データ・ドリブン・イノベーション」である。デンマークにはオープンデータの形でビッグデータが豊富にあり、それを利用できる環境にあるので、データを有効活用してイノベーションを創出するという取り組みである。
・日本とは異なり、デンマークのビッグデータは、業種や組織を横断したオープンデータである。
●デザインドリブン・イノベーションから新たな展開へ
・デンマークは人工知能や量子コンピュータでも世界トップクラスの研究を行っている。人工知能についてはXAIと言われる説明可能な人工知能を、社会インフラに導入し、さらに先進的かつ高度化したデンマークシステムを構築するべく、実証実験を進めている。また、量子論の育ての親とされる、理論物理学者ニールス・ボーアが設立したニールス・ボーア研究所では量子コンピュータの研究開発が行われている。
こうした動きを反映して、デンマークでも従来のデザイン・アプローチでは社会システムの変革を導くことは難しくなりつつあると認識しているデザイナーは、デザインを軸に、ビッグデータ+科学+ビジネスモデル+政府&市民を融和した総合的な価値体系の確立を模索している。
6.社会システムを変えるデザイン
・デザインの戦略的利用の他に、社会システムを変える「ソーシャルデザイン」の取り組みがある。その誘因はデジタル化とIoTなど技術の進展と複雑に絡みあう課題である。
・デンマークは2018年に世界電子政府進捗度ランキングで1位になった。その評価項目の中で行政管理の最適化、オンライン・サービス、ホームページの利便性、オープンデータ活用で1位になっているが、これらの高評価の背景には、ソーシャルデザインが行政部門に浸透していることが関係している。
・ソーシャルデザインが重視されているのは、都市の中で相反する課題を同時に解決しなければならず、社会システムから生みだされた課題は、社会システム自身を変えない限り解決することは難しいからである。なお、相反する課題とは、高齢化対応と質の高い社会福祉サービス、都市化と移民問題、スマートシティの推進とグリーン成長の実現、移民に対する人道的な対応とナショナリズムへの対策などであり、いずれも非常に難しい舵取りに直面している。
・社会システムの設計に必要な要素は次の4つである。
1)成果への集中:公共サービスを社会に実装し、具体的な成果を見える形で提示すること。
2)システム思考:問題と利害関係者の相互関係を把握し、複雑化する社会課題を横断的に俯瞰しながら管理できる能力。
3)市民の参加:単発の市民参加イベントではなく、市民生活の深い洞察を通じて、供給者である行政の目線と需要者である市民の目線の調和を図ること。
4)プロトタイプ:少ないコスト・資源で高い価値をもたらすために、素早い実証と可能性のあるアイデアの改善。
・デンマークでは、ある意味これを実現するために、「マインドラボ」で実験が行われ、「IPD(知的公共需要)」の体系が試され、そして「ブロックスハブ」の取り組みが始まったと言えるかもしれない。そのフレームワークはまだ確立されていないが、デンマークの取り組みを見ているとかなりノウハウと知見が蓄積されていると思われる。
・最近では、「デンマーク・デザインセンター(DDC)」が公的セクターにデザイン手法を取り入れたイノベーションの実現とそれによる新たな社会システムの実現を目指している。元マインドラボの幹部で、DDCのCEOに就任したクリスチャン・ベイソンは、これを「パブリックデザイン」と呼んでいる。
・DDCが強調していることは、リーダーシップの重要性である。人間中心でイノベーションを実現するソーシャルデザインを推進するためにも、公共の利益に基づくリーダーシップがなければ適切な組織をつくることはできないし、組織をまとめあげることもできない。これらを実現するために、2019年から行政や企業の幹部を対象にしたソーシャルデザインのリーダーシッププログラムがある。
7章 デンマーク×日本でつくる新しい社会システム
1.日本から学んでいたデンマーク
●なぜ、デンマーク・デザインは愛されるのか
・デンマークの企業は従来の「意匠としてのデザイン」から、開発段階で異なる要素を統合する「プロセスとしてのデザイン」を追求するようになり、ここ数年はデザインがビジネスモデルで重要な戦略要素の一つになってきている。政府は、さまざまな社会課題を分野・組織横断的に解決する手段として、デザインの戦略的利用を推進している。
・デンマーク・デザイン協議会が定めたデンマーク・デザインのDNAは10の価値で構成されている。
※ご参考:“DANISH DESIGN DNA"
※ご参考:“DANISH DESIGN DNA RESOURCES"
●日本からの影響
・デンマーク・デザインは1880年代に日本の工芸品や美術品の技術、特徴、職人技を学習し、一度その技法を真似た上で、そこに北欧独自の表現を加えて新しい体系をつくりだしたという経緯がある。これは現代のイノベーション・プロセスとまったく同じである。
・2017年の日本デンマーク外交関係樹立150周年を記念して、2015年から2018年1月までコペンハーゲンのデンマーク・デザインミュージアムにて「Learning from Japan展」が開催された。
・禅の影響も大きいとされている。簡素で装飾のない室内、そこに流れる静謐で調和した空間、枯山水の考え方が、デンマークで花壇などが減少する要因になったとされている。
2.デンマークと連携する日本の自治体
●なぜ、日本の自治体はデンマークに注目するのか
・日本では2014年に「まち・ひと・しごと創生法」(地方創生法)施行後、雇用創出、新産業の育成を行うべく取り組んではいるが地元ならではの特徴を活かしたプロジェクトを生みだせていない状況がある。こうした日本の自治体がデンマークに注目するのは、スマートシティの分野で世界的に高い評価を得ていること、意外にも観光、農業だけではなく、ICT、ロボット、ライフサイエンス分野においても発展し、そして洗練された社会保障制度に基づく高齢者福祉が充実していること、日本の自治体と同程度の面積、人口でそれらを実現している点にある。
3.北欧型システムをローカライズする
●フレームワークの輸入で起こるギャップ
・日本での顕著な失敗例は、海外で開発されたフレームワークを日本語化してそのまま利用する方法である。他国の異なる理念、制度、システムを導入しても日本の現状とのギャップの大きさにより破綻してしまう。
4.新たな社会システムの構築
●量子コンピュータ×人工知能がつくる未来への準備
・既に膨大なビッグデータは様々な可能性を有している。エクサスケールのスーパーコンピュータは、仮説の立案と検証サイクルを無限に回すことが可能である。これにより、医療、健康、エネルギーなどの問題解決に必要なソリューションを現場で実証せずとも開発することができるようになる。
・デンマークでは2017年に「技術大使」というポジションを創設し、デンマーク、シリコンバレー、北京に拠点を開き、先端技術の動向と社会に与える影響を分析する体制を整えている。ビッグデータ、人工知能、ブロックチェーン、量子コンピュータの開発を踏まえて人間中心型社会をサイバー攻撃から守り、新しいサイバー社会における人権の確立、新技術の倫理規定、さらにはサイバー空間における差別や格差の排除、そしてデジタル課税にも踏み込んだ研究と議論を進めている。
・デンマークは数十年先の社会を見据えて国家ビジョンを定め、小国が国際社会の中で持続的に存在しリーダーシップを発揮する戦略を構築していることを想定すると、このデンマークが考えている30年後の近未来に対する準備は、かなり現実的なアクションである。
感想
デンマークの面積と人口は北海道のおよそ半分。人口密度は北海道の約2倍です。一方、「2023年の世界経済競争力ランキング」の第1位はデンマーク。日本は35位でした。
この差は何か、本書内のデンマークに接すると、次のようなことではないかと思います。
一つは、自国を大切に思っている人、国の将来を真剣に考えている人の割合が、デンマークは日本より圧倒的に多いからだと思います。ここには、納得するまでは決して妥協しないというデンマークの人達の信念を感じます。なお、これは選挙の投票率からも推測できます。
※ご参考:“平均投票率86%、デンマークの若者は呼びかけなくても選挙に行く。「幸福の国」成り立たせる“小さな民主主義”
そして、二つ目はリーダーシップです。“改善”は現場、ボトムアップでも十分に進みますが、“改革”は「ヒト・モノ・カネ」を考えることができる立場と実力を兼ね備えた人がリーダーにならないと、ダイナミックな推進は困難です。プロジェクトは迷走します。これが“改善”はできてても“改革”は進まず、35位にまで下がってしまった日本が抱える大きな課題ではないかと思います。なお、このリーダーシップの問題には過剰な忖度など、オープンとは言い難い日本特有の閉鎖性や年功序列的発想が障壁になっているケースも多いように思います。
※ご参考:“リスクよりも責任を恐れる日本人:正しい失敗を許容する社会へ”
※ご参考:“人はなぜ失敗を恐れるのか。失敗の正体と正しい生かし方”
デンマークのスマートシティ4
5章 デンマークのスマートシティ
1.デンマークのスマートシティの特徴
●デンマークと日本のスマートシティの比較
・国土交通省のスマートシティモデル事業の公募(2018年)や内閣府が国家戦略特区制度(2020年)を活用して2030年頃にスーパーシティを実現するという構想がある。これらは2010年から2015年頃にかけて、各地で展示会が開催され、実証プロジェクトが行われ、その後、ほとんどその言葉は聞かれなくなっていたものである。
・アメリカ、カナダでは大規模なスマートシティ・プロジェクトが継承されている。
・欧州ではスペインで「スマートシティエキスポ世界会議」が毎年開催されている。
※ご参考:“拡大する「スマートシティ」投資、カナダとアメリカで顕著”
※ご参考:“都市間協力で脱炭素・持続可能な未来へ”
※ご参考:“スマートシティEXPO世界会議”
・デンマークと日本の比較で大きく異なるのは2つある。一つはデンマークのスマートシティは定義が広いこと。もう一つはスマートシティをつくることが目的ではなく、都市の課題を解決するための技術やソリューションを開発し、それらを都市に導入することにより課題を解決することが真の目的となる。それにより、出来上がった新しい都市をスマートシティと呼ぶ。
・日本のスマートシティの議論は、スマートグリッドやBEMS(ビルエネルギー管理システム)などのエネルギー・ソリューションに関係するインフラ整備が中心で、都市のインフラ技術を開発して産業を促進させるのが主目的である。
・デンマークでは都市計画、エネルギー政策、環境政策に加えて市民サービスが相互に関連して議論される。スマートシティ構想は必然的に大きなものとなる。持続的な廃棄物管理、交通などのモビリティ、水管理、ビル管理、暖房と冷房、エネルギー、ビッグデータなど、包括的なアプローチとなる。
・デンマークでは住民が優先される「人間中心」であるが、日本は「産業中心」である。その参加者は地方自治体、電力会社、IT企業、ゼネコン、ハウスメーカーなどが参加する。デンマークでもこれらの団体は参加するが、これらに加え、大学などの研究機関、建築家、デザイナー、文化人類学者、そして市民がメンバーに加わって進められる。
・『あるデンマークの自治関係者に、どうしてデザイナーや文化人類学者が参加しているのか聞いたところ、彼は「都市は、行政、企業だけでなく、芸術家、音楽家、市民などが活動する場だ、産業だけでなく、こうした多様な人たちの視点を取り入れることが、豊かな都市をつくるために必要だから」と言っていた。』
●デンマークのスマートシティのビジョン
・「スマートシティは住みやすさと持続可能性、そして繁栄の実現を目的として、革新的なエコシステムに市民の参加を可能とするしくみを構築し、デジタルソリューションを活用する社会である。大切なことは、新しい技術と新しいガバナンスが、ソリューションそのものよりも、市民にとって福祉と持続的な成長の手段になるということである。」
この定義で参考になるのは、エコシステムもソリューションも手段であって目的ではなく、目的は市民にとっての福祉、そして持続的成長を明確にしている点である。以下がスマートシティのフレームワークである。
・ビジョン、目的は「住みやすい都市をつくり、持続可能性と成長を実現する」こと。
・住みやすさを実現する要素であるグリーン項目は6つ、“廃棄物”、“モビリティ”、“水”、“ビルディング”、“冷暖房”、“エネルギー”。
・グリーン項目を実現するための基盤(デジタルソリューション)が、“Date Platform”、“Big Data”、“IoT”、“Security & privacy”である。
・このスマートシティを実現させるためには、必要なシステムやソリューションを開発する必要がある。これを担うのが横断的に機能する“リビングラボ”である。そして、海外都市との連携による経験とノウハウを共有するパートナーシップを構築することを挙げている。
・リビングラボは市民が参加するオープンイノベーションの場であり、新たな技術やサービス開発の過程で行政、企業、市民が共創して主体的に関わりながら課題解決の道筋を探るための活動拠点のことである。国際的に協業しながらこれらの技術を組み込んだ包括的かつ人間中心のフレームワークを構築することに注力している。なぜなら、デジタル化で統合された社会では、一つのソリューションがITシステム、ヘルスケア、セキュリティなど複数の問題を同時に解決する可能性がある一方で、複雑な問題は官民が連携して制度面、技術面、ノウハウ面で組織横断的かつ組織の枠組みを越えた協業が必要となる。
●ビッグデータの活用
・デンマークでは2013年から電力セクターが系統データを収集しており、また、2020年までにすべての世帯でスマートメーターの設置が義務づけられているので、今後は電力だけでなく、水、暖房などのインフラ系データが収集され、最終的にはそれらのデータをサービス向上という価値に変え国民に提供される。
2.コペンハーゲンのスマートシティ
・コペンハーゲン市は人口約61万人(2018年)、日本だと千葉県船橋市とほぼ同じ規模である。1990年中頃以降急速に開発が進んでいる。
●CPH2025気候プラン
・コペンハーゲン市のスマートシティは、2012年に策定されたエネルギー計画「コペンハーゲン2025気候プラン」と密接に結びつている。
・カーボンニュートラルな都市をつくるためには、エネルギー計画だけで達成することは不可能で、交通システム、廃棄物管理、冷暖房システムなど、都市を構成する多様な要素を横断的に解決する必要がある。CPH2025気候プランにはスマートシティに関係するエネルギー消費、エネルギー生産、交通(モビリティ)が含まれている。
・市民はエネルギー消費の削減、電気や熱の燃料費の削減を実践するだけでなく、自宅で使用するエネルギーをグリーン対応にすることで、将来エネルギー価格が上昇した場合でもそのインパクトを最小限にすることができる。そして健康で快適な暮らしを送れることを理解している。
・市民1人1人の行動の積み重ねこそがカーボンニュートラルを達成できる原動力であることを、このプランに関わる人が共有している。
●グリーン成長
・デンマークでは「グリーン成長」という言葉がよく使われる。コペンハーゲンでもグリーン成長をCPH2025気候プランの中心に据えており、カーボンニュートラルとグリーン成長を同時に実現することが重要だとしている。日本では環境問題と産業政策は別次元で扱われることが多いが、デンマークではエネルギーと環境問題を解決しながら、その結果として産業を含めた地域の経済的発展を実現するアプローチをとる。
※ご参考:“コペンハーゲンのプランがすごかった!:気候プランとスマートシティ戦略”
※ご参考:“サステナブルな都市計画の例 コペンハーゲン”(pdf28枚)
●CPH2025気候プランに挙げられたスマートシティに関するソリューション
①デジタル・インフラストラクチャー
-エネルギー消費のモニタリング(特に建物のエネルギー消費の管理)を行う。
-アクセス可能なオープンなデジタル・インフラストラクチャーを構築する。
-市内の建物のエネルギーと水の消費量をリモートメーターで管理する。
②エネルギーの柔軟な消費とスマートグリッド
-スマートグリッドは複数の再生可能エネルギーの需給調整をフレキシブルに調整する。また、市民、企業、市は再生可能エネルギーを選択して利用することができる。
③スマートビル
-IT技術により、エネルギー効率、柔軟性とエネルギー管理を行う。
④スマートCPH
-コペンハーゲンのCPHと水素のH₂を掛け合わせた水素プロジェクト、風力発電の余剰電力で生産された水素を、交通のエネルギー問題解決のソリューションと考えている。
⑤クルーズ船へのオンショア電気の供給
-クルーズ船はドック係留中にエンジンで発電し電気を供給しているが、陸上で発電したオンショア電気を供給することで環境問題を解決する。これは局所的な小さな問題だが、このような領域にも焦点をあてて取り組んでいる。
●最先端の地域熱供給
・地域熱供給は、「CPH2025気候プラン」を達成するための重要なエネルギーシステムである。熱導管を通じて、地域の住宅・施設に熱を送り、暖房・給湯に利用するシステムである。
・デンマークで地域熱供給システムが普及したのは、政府による普及のためのコミットメントと規制プロセスなど具体的な政策の効果が挙げられる。また、洋上風力発電の拡大で、余剰電力が問題となっているが、熱電併合プラントの畜熱槽に熱として貯蔵することで有効活用することができるようになる。
・最近コペンハーゲンで進められているのが地域冷房である。温暖化の影響でデンマークでも30℃近くなることもある。コペンハーゲンでは、海水を利用した冷却システムを利用している。個別の冷房と比較して二酸化炭素の排出量を70%削減し、総コストの40%削減を実現している。
●DOLL(デンマーク街灯ラボ)と都市照明
・LEDを利用した高度な照明システム
-コペンハーゲンはスマートシティを構築する上でLEDを利用した高度な照明システムに力をいれている。
-街灯柱はセンサーや通信インフラを設置すると、広域に対応したスマートシティインフラになる。
・グリーンエコノミーを推進するゲート21
-ゲート21(Gate21)はスマートインフラを推進するために、コペンハーゲンの各自治体、企業、研究機関が連携した非営利のパートナー組織であり、まさに産官学連携のプロジェクトである。
-ゲート21のミッションは、リビングラボでテストしたり、現場での実証プロジェクトを通じてエネルギーや資源効率化に関係するソリューションを開発したりすることである。注力するのは次の6領域。
1)建物と都市
2)交通
3)エネルギー
4)循環経済と資源
5)グリーン成長
6)スマートシティ
そして、プロジェクトを通じて、グリーンエコノミーへの移行を促進する事業機会を見出すための、新技術、サービス、プラットフォーム、ツール、プロセス、スキルを開発して支援することを目指している。
・DOLL(デンマーク街灯ラボ)
-DOLLはDenmark Outdoor Lighting Lab)は、“リビングラボ”(市民が参加するオープンイノベーションの場であり、新たな技術やサービス開発の過程で行政、企業、市民が共創して主体的に関わりながら課題解決の道筋を探るための活動拠点)の一つ。スマートシティで新しい技術やソリューションを開発するためのプラットフォームとして、2013年にコペンハーゲン近くアルバーツルンド市に設立された。
-DOLLでは、都市照明に関する世界中の先端技術とソリューションを見ることができる。
-DOLLには世界の照明ベンダーやIT企業が参加しているので、技術や都市照明の各ソリューションの比較検討もできるので、DOLLに行けば多くの課題を解決できる。
-DOLL(リビングラボ:活動拠点)のようなプラットフォームは、デンマークが得意とするもので、少ない予算、人材、資源を有効活用するために特定の場所に必要な資源を集積させて、世界でもトップクラスの技術開発、実証、社会実装を行う手法である。
-DOLLは、DOLLリビングラボ、DOLLクオリティラボ、DOLLバーチャルラボという、3つの研究所から構成されている。
・デジタルインフラ
-実証用にWiFi、LoRa、WAN、Sigfox、UNB、NB—IoT、5Gなどさまざまなワイヤレスネットワークを完備しており、都市のネットワーク環境に合わせたデジタルインフラを選定して実証することができる。
※ご参考:“コペンハーゲン首都圏のスマート都市照明”
●フィンテック
・キャッシュレス化が当たり前の社会
-フィンテック(FinTech)はデンマークでもコペンハーゲンを中心に盛り上がりを見せている。
-フィンテックは米国、シンガポールなどが力を入れており、欧州ではイギリスが国際的なフィンテックセンターとしての役割を担うべく台頭している。
・コペンハーゲンフィンテック
-「コペンハーゲン・フィンテック」の目的は、フィンテックのエコシステムを展開し、グローバルな金融サービス産業で主導的なフィンテックラボを形成すること、そしてデンマークの経済成長につなげることである。
-フィンテックの事業化、既存の金融機関、公的機関そして大学などの研究機関がビジョンを共有し連携するエコシステムを形成している。
※ご参考:“Copenhagen Fintech”
●スマートシティの実験場、ノーハウン
・2005年、デンマーク政府とコペンハーゲン市はノーハウン地区の再開発で合意した。最終的に4万人が暮らす現代的な居住地区とビジネス地区が共存する、コペンハーゲンの新たなウォーターフロントとなる予定である。
※ご参考:“Cobe Nordhavn”
・ノーハウン(Nordhavn)のビジョン
-ノーハウンのビジョンは、スマートシティのビジョンと同期している。ビジョンは6つに分かれ、地域の持続可能性に加えて、多様性、快適性、人間中心の考え方が組み込まれていく。
①環境に配慮した都市
②活気に満ちた都市
③すべての人のための都市
④水の都市
⑤ダイナミックな都市
⑥グリーン交通の都市
・ノーハウンの開発戦略
-ノーハウンをスマートシティにするための開発戦略は6つのテーマに分かれている。
①島と運河
-イタリアのヴェネチアをイメージしたスマートシティ。
②アイデンティティと歴史
-ノーハウンの歴史(150年に渡る歴史と100年以上の建物)と港湾地区の特徴を考慮した開発。
③5分間都市
-徒歩か自転車で行けるコンパクトで高齢者に優しい街を目指している。
④ブルー&グリーンシティ
-ノーハウンでは市民が水と直接触れ合うことを重視した設計になっている。これは日本との大きな違いである。ここには自己責任の考えた方が浸透しているデンマークならではのアプローチである。
⑤二酸化炭素にフレンドリーな都市
-再生可能エネルギーによる発電、熱供給システムでの暖房、海水を利用した冷房システム、廃棄物の再利用、雨水の再利用はゲリラ豪雨対策を兼ねている。
⑥インテリジェント・グリッド
-これはノーハウンの小島をマス目のように分割し、柔軟なビルディングゾーンとして設計する。これにより、マス目単位の変更が可能で、大規模な全体設計を避けることができる。
3.オーフスのスマートシティ
・オーフス市は人口34万人(2018年)、デンマークで2番目に大きな都市である。群馬県前橋市とほぼ同じ大きさ。
・オーフスでもコペンハーゲンと競うようにスマートシティを推進している。
・オーフスでは2030年にカーボンニュートラルの都市をつくる。オーフスのスマートシティの特徴は、伝統や文化を尊重した取り組み、ヘルスケアや福祉に関するプロジェクトもスマートシティに含まれている。
●スマートオフィス
・スマートオーフスのビジョンと目的
-ビジョンは、パートナーシップに基づいた都市開発のための北欧モデルを国際的に主導すること。
-デジタル技術の功罪を理解した上で、持続的成長とイノベーションを実現する。そして、異なる利害関係者を巻き込みながら社会に価値をもたらし、社会、環境そして経済の課題を解決するというものである。
※ご参考:“スマートオーフス”
4.オーデンセのスマートシティ
・オーデンセ市は人口約17万人(2016年)、デンマーク第三の都市で自治体では立川市や鎌倉市とほぼ同じ規模である。デンマークでも最も古い都市の一つで、アンデルセン生誕の地として知られている。
-オーデンセ市は、エネルギーや交通などに注力するコペンハーゲン、文化を取り込んだスマートシティを標榜するオーフスと差別化するため、オーデンセが得意とする領域、ロボット、ドローン、ヘルスケア(特に福祉技術)に焦点を当てたプロモーションを行っている。
-オーデンセがユニークなのは、福祉技術を含めたヘルスケア・ソリューションを実証実験できるリビングラボ「コーラボ」をオーデンセ・ロボティクスが入るセンター内に設置していることである。
-コーラボには自宅、かかりつけ医、病院、介護施設のモックアップが設置されており、デジタル機器を開発する際、異なる環境でも一貫性のあるユーザーインタフェースをデザインしたり、医者、介護士、作業療法士などが連携して患者に対応する場合に最適な作業プロセスを検証したりすることができる。また、病院の手術室や病室も再現されており、実際の執刀医が立ち会い、手術の模擬テストを通じて医療機器やソリューションの評価を行うことができる。
※ご参考:“Invest in Odense”
※ご参考:“Odense robotics”
デンマークのスマートシティ3
3章 市民がつくるオープンガバナンス
1.市民が積極的に政治に参加する北欧型民主主義
●コンセンサス社会が実現する民主主義
・イギリスのエコノミスト社の調査部門であるエコノミスト・インテリジェンス・ユニットが2006年から民主主義指数なるものを発表している。
・デンマークを含む上位国と日本の差は、「選挙プロセスと多元性」「政治的な参画」が大きい。
・日本では、ビジネスの打ち合わせや会食中に政治や宗教の話題は避けられるが、デンマークでは政治の話はご普通であり、選挙が近づくとかなり踏み込んだ議論が行われる。これは自国に限らない。日本の選挙や政治について質問されることは珍しくない。
※ご参考:2021年世界の政治民主化度 国別ランキング (注)出展・参照:“世界銀行”
●デンマークの民主主義の歴史
・デンマークは1849年に君主制度が廃止され、現在のデンマーク王国憲法が制定された。市民が王政に終止符を打ち、民主主義を勝ち取ったという経緯があり、これがデンマークの民主主義の基盤となっている。
・デンマーク型の民主主義とは、「情報をもとに自分で分析し、公平に準備された政策決定プロセスに参加し、自ら決断する。そして自己責任の原則で最終的な結果を受け入れる」。
●高い税負担が政治参加を促す
・税負担が高いため、国民は税金が公平公正に使われているか政治を厳しくチェックする。
※ご参考:“国民負担負担率の国債比較(OECD加盟36カ国) 出展:財務省主計局
上記を見ると、デンマークは3位(65.9%)です。日本は22位、英国は25位、スウェーデンは12位です。
「高齢化を背景に大きく伸びて、欧州諸国との差は縮小」とのことです。
●コンセンサスを育む教育
・北欧型民主主義の特徴である「コンセンサス社会」は、子供からの教育も大きな役割を担っている。
・デンマークの基礎教育は0~10学年まであり、基礎学力の習得だけでなく、自立した人間をつくるために自分の考えを言葉で表現し討論する授業や、異なる考え方や意見を尊重し、トラブルを解決しながらコミュニケーション力を伸ばす授業もある。そして言葉、文化、地域の異なるバックグラウンドを持つ生徒たちの多様な意見をまとめて自分たちなりの合意、つまりコンセンサスをつくりあげることに力を入れている。
・『友人のデンマーク人によると、デンマークでは選挙が近づくと憂鬱になる家庭があるらしい。デンマークでは子供が中学生になると、自分の意見を持ち、社会のしくみも理解して一筋ではいかなくなることから、「子供がモンスターになった」と言われたりする。そして選挙が近づくと、そのモンスター化した子供が社会の授業で、政治家の過去のマニフェストや選挙公約をどれだけ実現できたか調べたりする。そして、次期選挙の公約を政党ごとに表でまとめ比較検討して、自分たちの地域をどのようにしたいかについて議論をする。当然、子供たちは親に自分たちの意見を伝え、親の意見を求める。その時に子供の意見に対してどう考えるのかを回答できないと、親の権威が失墜してしまう。親は、仕事や家事が終わった夜、子供が授業で行ったように政治家の経歴、実績、政治信条を調べ、マニュフェストを確認し、政治家としての実行能力なども確かめて、子供と同じ目線で議論できるように準備しなければならない。ある日、友人の目が赤いのでどうしたのかと聞くと、夜中に政党の公約を調べていたので寝不足だと笑っていた。
こうした政治参加は、選挙の投票行動に反映され、より強固な民主主義の基盤がつくられる。』
2.市民生活に溶け込む電子政府
●デジタル国家のトップランナー
・EUはデジタル化について毎年、「デジタル経済と社会指数(DESI)」という調査を行っており、デンマークは2014~2018年、5年連続で1位になった。(2022年は僅差の2位。1位はフィンランド)
・「デジタル経済と社会指数」は5つの評価項目でランキングしている。「ブロードバンドの接続性」「デジタルスキルを含めた人的資本」「インターネットサービスの利活用」「デジタル技術の統合」「デジタル公共サービス」である。
・デンマークのデジタル化で最も特徴的なのは「デジタル技術の統合」の点で、他国より秀でている。つまり、政府の公共サービスの電子化だけでなく、デジタル技術の統合により、都市を構成しているエネルギー、交通、農業、医療、福祉、教育に至るまで、進展度合いに違いはあるにせよ、基本的に統合されたデジタル化が展開されている。
●質の高い社会サービスを実現するデジタル化
・デンマークのデジタル技術の統合に優れているのは、社会制度とデジタル化に関する歴史と政策を見る必要がある。
・1910年代から福祉国家として制度の充実を図ってきた。
・1950年代の黄金期を経て、1990年以降はフレキュシリティなど積極的な労働市場政策に基づく福祉国家の再編を行ってきた。そして、グローバル化、高齢化に伴う労働人口の減少に対応し、福祉サービスの水準を維持するためにさまざまな改革を行ってきた。また、インターネットの普及に伴い、デジタル技術の積極的な利用により、労働不足に伴う公的機関の効率性向上とサービス水準の高度化を同時に行うことを検討されてきた。
●市民生活に溶け込む電子政府
・デンマークでは2001年から中央政府、広域自治体(レギオン)、基礎自治体(コムーネ)との連携や複数のデジタル化戦略を経て進められてきた。
・2000年初頭の電子署名の導入により、市民は公的機関と電子メールでやりとりができるようになった。その後、税金還付や年金受給のための公共決済口座であるNemKontoが開始され、同時期には先進的な医療ポータルであるsundhed.dk、そして市民に電子政府の利便性を提供する市民ポータルのborger.dkが2007年にサービス提供を開始した。そして現在(2019年)は、スマートフォンなどモバイル端末の普及によって2007年に導入されたNemID(新電子署名)に代わる、電子政府の新アクセスIDの導入を進めている。
・デンマークの電子政府は、医療ポータルsundhed.dkと市民ポータルborger.dkの導入が鍵だった。
・市民ポータルborger.dkは、2000年代に構築された、官庁ごとに異なる行政システムをセルフサービス型の一本化されたシステムとして導入された。このポータルが優れているのは、市民が生活に必要な行政情報のすべてをこのポータルから取得することができ、教育、福祉を含めた多様な申請手続きを行えることである。また、マイページにアクセスすると住居・転居、税金、年金、教育などに関する情報をいつでも閲覧することができる。つまり、このborger.dkを活用すれば、行政機関の窓内に行くことはほとんどなくなる。
3.高度なサービスを実現するオープンガバメント
●透明性の高い政府の実現
・デンマークでは特にオープンガバメントが進んでいる。「オープンガバメント・パートナーシップ」とは、市民と政府の協力のもと、政府の透明性を向上させ、市民参加によりエンパワーメントを図り、新技術とイノベーションを活用してより良い政府をつくることを目的とした多国間イニシアチブである。
●オープンデータ・デンマーク
・デンマークの特徴的な取り組みは「オープンデータ・デンマーク」である。政府が民間に頼ることなく全面手に社会福祉サービスを担っているため、それ関わるデータ量は膨大である(ビッグデータ)。日本のマイナンバーカードに相当するCRPナンバーは1968年に導入された。
・オープンデータ・デンマークは、広域自治体や基礎自治体が管理しており、都市開発や社会課題の解決において公的にデータを自由に活用できる環境を整えることを目的に整備された。
・2018年5月に施行された欧州の個人データ保護に関する法律であるGDPR(EU一般データ保護規則)の関係で、デンマークでも取り扱いは厳しくなっているが、オープンデータ・デンマークから公的オープンデータを収集することができる。
●遠隔医療でのオープンデータの活用
・遠隔医療はオープンデータの活用が期待されているプロジェクトである。
・デンマークではEUと連携する形で遠隔医療の実証実験を続けてきた。
・遠隔医療のニーズは、市民とその家族が主体的に治療に関わりたいとの要望が強まっている。
・高齢化が進む中で高齢者の治療と慢性疾患患者の増加が見込まれている。
・今後の医療コストが増加すると予想されている。
・特に期待されているのは、妊婦の合併症とCOPD(慢性閉塞性肺疾患)に対する治療である。具体的には前者は合併症のリスクを軽減すること、後者は治療が長期間に及ぶため。
・デンマークは人口密度が低く、地域の病院数も限られている。病院側も通院患者が減れば病院の効率が上がり、より重症患者や緊急の患者に対応することができるようになる。
・この遠隔医療は実証実験を経てサービスの検証を行った結果、医療サービスとしての品質、安全性、経済性とともに十分運用可能と結論づけられた。
・デンマークのオープンガバメントの取り組みは、オープンデータ一つとってみても、単にデータの開示による公共サービスの透明性の確保だけでなく、市民生活を向上させるサービスの開発と実社会への導入という観点が含まれていることが特徴である。
4.サムソン島の住民によるガバナンス
・再生可能エネルギー100%の島として知られているサムソ島は、首都コペンハーゲンがあるシェラン島の西に位置しており、北海道の奥尻島と同じくらいの島である。
・夏には多くの観光客が訪れるこの島は、エネルギー企業などの関係者の視察が増え、再生可能エネルギーのショーケースのようになっている。最近は、こうした視察やエネルギープロジェクトに関係した雇用創出で地域活性化に大きく貢献している。
・サムソ島の成功の要因は、地域の共創の理念と、住民を導いたサムソ・エネルギー・アカデミー代表であるソーレン・ハーマーセンを中心とした創造的リーダーシップにある。彼らは地域社会、特に住民の参画に力を入れ、風力発電の技術が分からない住民の理解を得るために、説明会やワークショップを何年にもわたって実施し、住民の意向に沿った開発計画を策定した。
・最近では、サムソ島が再生可能エネルギー100%の島であることより、いかに異なる考え方を有する住民をまとめて一つの方向性に導くことができたのかに関心を持つ視察者が増えている。
・ハーマーセンの元には多くの質問や反対意見が届いた。それらに対し、3年かけて一軒一軒を回り会話をしながら問題を話し合うことで、少しずつ島民の理解を得られるようになった。
・2007年のカーボンニュートラルで再生可能エネルギー100%の島を達成した後も、新たな目標である2030年までに脱化石燃料を目指す。「サムソ2.0」を策定し、将来は循環型社会を目指す「サムソ3.0」を掲げている。
・「パイオニアガイド」はノウハウをまとめたガイドであるが、地域コミュニティが新しいシステムを導入する際の構造化されたアプローチ方法であり、サムソ島のホームページで開示し、必要に応じて出張しセミナーの開催なども行っている。
※ご参考:“コミュニティパワーで100%自然エネルギーの島から次のステップへ:デンマーク、サムソ(市)島”
※ご参考:“世界で一番エコな島~サムソ島” (YouTube 5分53秒)
4章 クリエイティブ産業のエコシステム
1.デンマーク企業の特徴
・日本と比べて圧倒的に小さなデンマーク企業が厳しい競争の中で生き残ることができる鍵は次の6つである。
①革新的かつクリエイティブは技術、ソリューション、デザインを追求する。
②国内市場を目指すのではなく、いきなりグローバル市場に参入する。
③大手企業が見逃しているニッチ市場を攻める。
④ニッチ市場でナンバーワンを目指す。
⑤収益のうち高い比率を研究開発に回す。
⑥研究開発を通じて、さらにクリエイティブな製品やソリューションを開発し、他社の追随を許さない。
・このような戦略が採れるのも、優秀な人材がいてこそである。デンマークの企業は経営幹部も含めて創造性に長けた社員の採用に力を入れているところほど成功している確率が高い。
・デンマークでは大学発ベンチャーにも注力しており、研究室からそのまま起業して成功するなど研究開発型の企業が多いことも特徴である。
2.世界で活躍するクリエイティブなグローバル企業
●アーステッド:石油・天然ガスから再生可能エネルギー企業へ
・環境エネルギー分野では洋上風力発電のアーステッド社がある。アーステッドはもともと国営企業であり、現在でも株式の過半数をデンマーク政府が保有する。
●ノボノルディスク:糖尿病治療薬のリーディングカンパニー
・1923年に設立されたノルディスク・インスリン研究所と1925年に設立されたノボ・テラピューティスク研究所がインスリン製剤の生産を始め、業界トップ2社となった両社がさらなる成長と発展を目指して1989年にできたのがノボノルディスク社である。その後急成長し、糖尿病、血友病、成長ホルモン治療で世界的企業となっている。
●レゴ:世界の子供の創造力を育てる玩具メーカー
・1932年、オーレ・キアク・クリスチャンによってデンマークの小さな街ビルンで設立された、レゴの経営哲学は「質の良い遊びは子供の人生を豊かにする」というもので、レゴの意味はデンマーク語で「Leg godt(よく遊べ)」の略語である。
3.デジタル成長戦略と連携して進展するIT産業
●デジタル成長戦略
・2018年1月に「デジタル成長戦略」を策定した。骨子は次の3つである。
①デンマークのビジネスがデジタル技術の活用の点において欧州でベストになること、特に中小企業が先端デジタル技術を利用できるように政府がその推進体制を保証する。
②デジタル・トランスフォーメーションを実現するために、政府として最高の環境を整える、特に新しいビジネスモデルや投資を引きつけるための迅速な規制緩和、そしてサイバーセキュリティとデータ処理体制を強化する。
③すべてのデンマーク人がデジタル・トランスフォーメーションに対応し、EUで最もデジタル化に準備をした国民となる。そのために適切なツールと教育を提供し将来の労働市場に備える。
そして、これらの戦略を実行するための6つの領域を定めている。
①デジタル化による成長環境を強化するための「デジタル・ハブ・デンマーク」を設置
②中小企業のデジタル化対応強化
③すべてのデンマーク人がデジタルスキルを身につける
④貿易と産業の成長にビッグデータを活用
⑤貿易と産業の迅速な規制緩和
⑥企業におけるサイバーセキュリティを強化
この中でも産業のエコシステムに関して注目に値するのは、①デジタル・ハブ・デンマーク、②中小企業のデジタル化対応、そして④ビッグデータの活用である。
●デジタル・ハブ・デンマーク
・「デジタル・ハブ・デンマーク」は、産業・ビジネス・財務省が推進する、デジタル化で強力な成長を実現するためのフレームワークである。意外だが、デンマークは人工知能(AI)やビッグデータの活用では他国に遅れをとっていると認識されており、具体的なアクションにつなげている。
●中小企業向けデジタル化対応
・中小企業のデジタル化は大手企業に比べると遅れており、デジタル技術の活用により複数の産業で事業開発が進展できると考えている。
●ビッグデータの活用
・データ活用で重視しているのは、製造業、小売、エネルギー産業、保険、交通セクターにおけるデータの収集と分析に基づいた企業経営の最適化である。
・デンマークは小国ゆえに日本のNEC、富士通、日立のような広範な分野に対応できる総合IT企業はない。そのため、多くはアプリケーションを開発するソフトウェア企業など限られた分野に特化した企業が多い。
4.スタートアップ企業と支援体制
●北欧のスタートアップシーン
・北欧でスタートアップといえばスウェーデン(特にストックホルム)が有名である。北欧諸国の中で資金面、エコシステムで最も充実したフレームワークを整えている。一方、デンマークもここ数年でスタートアップに対する支援が充実してきており、スウェーデンに続く北欧のハブになりつつある。
●スタートアップ・デンマーク
・「スタートアップ・デンマーク」は、産業・ビジネス・財務省と移民・統合・住宅省が運営しており、国が主導している起業支援機関である。
●コペンハーゲンのスタートアップ・プログラム
・自治体の中では、特にコペンハーゲン市がスタートアップ・プログラムに注力している。
5.新北欧料理とノマノミクス
・「noma(ノーマ)」は世界的に有名なレストランである。ノーマを創業したシェフたちは、調理で食材が変化するしくみを科学的観点から分析して、調理法の改善、新たな食材の活用等を開発する分子ガストロノミー、顧客の五感を刺激する見せ方、美しい店舗デザイン等によって「新北欧料理」というジャンルを構築した。
デンマークのスマートシティ2
3.共生と共創の精神
●資源と産業のない貧しい国
・デンマークは1950年以前、北ヨーロッパの田舎で、天然資源は少なく、土壌も痩せて農業には適さないなど、かなり過酷な条件の揃った国であった。寒さと飢えで亡くなる人々も多く、アンデルセンのマッチ売りの少女さながらの現実が19世紀にはあった。デンマークで共生と共創の精神が根づいているのは、こうした厳しい環境と関係している。

画像出展:「マッチ売りの少女」
・現在のデンマークは小資源国であっても十分大国と渡りあえることを証明している。ソフトウェアや人工知能、量子コンピュータの開発で、物量ではアメリカや中国には適わないが、質の面では世界トップクラスの水準となっており、マイクロソフトは2017年に量子コンピュータの研究センターをコペンハーゲン大学のニールス・ボーア研究所に開設している。
・デンマークは既に再生可能エネルギー大国である。既に国内の消費電力のうち約40%が風力発電により賄われ、2050年には脱化石燃料の国家を宣言している。
※ご参考:“デンマーク、2050年までに化石燃料脱却を目指す「エネルギー戦略2050」を発表”
・デンマークの国教は福音ルーテル派だが、日常生活と宗教は密接に結びついておらず、日曜日に礼拝に行く慣習は特にない。宗教より「ヤンテの掟」のように、倫理や道徳の教育がデンマーク人の精神に根づいている。
●北欧の気候風土とヒュッゲ
・デンマークは北緯55度に位置し、北海道の稚内(北緯45度)より北に位置してるが、暖流であるメキシコ湾流の影響で高緯度の割に気候は穏やかで、寒い日でも氷点下10℃程である。また、比較的四季もはっきりしている。
・夏の日没は午後10時、冬は日の出が午前8時半過ぎ、日没は午後4時前なので、通勤、通学時は日が落ちて真っ暗である。
・こうした気候風土の中で育まれた文化が「ヒュッゲ」である。これは日本では正月に家族や親戚が集まり、お節料理やお酒を飲んで、ゆっくりとくつろぐ時間のようなものである。
4.課題解決力を伸ばす教育
●教育システムのしくみ
・デンマークは先進国の中で教育費支出が高い国の一つである。
・デンマークにおける教育の目的は、「人格形成を平等に行い、社会の一員として責任を持ち義務を遂行し社会に貢献できる能力を育むこと」とされている。また、生徒の社会的背景、特に経済的かつ身体的状況に配慮し、差別をなくして1人1人の個性を尊重し、個々の能力を伸ばすことに力を入れている。
※ご参考:“世界の公的教育費対GDP比率 国別ランキング・推移” (先進国以外も対象)
・デンマーク:21位
・日本:121位
●教えるのではなく、導く教育
・重視しているのは知識より、社会を作る上で必要な人格形成、人間性の向上など、日本では大人になってから考え始めるような人生哲学に力を入れている。これはニコライ・F・S・グルントヴィの思想が大きく影響している。学ぶ者には学ぶことへの内側から湧き出る動機が必要であるとしている。教師は生徒との自由な対話によって、若者に気づきを与える教育が大切であるとした。
●直観力の育成
・人間力育成に加えて、課題解決力の育成にも力を入れている。これには問題の本質を見極めて効率的にかつ公平に、最短で解決策を見出す教育に保育園から取り組んでいる。
・「森の幼稚園」では、自然と触れ合うことは人間としての感性と直感力を育て、国際的に重視されているSTEM教育(科学・技術・工学・数学教育の総称)の基礎となる自分で考え理解する力を養うことになる。
●問題解決力の育成
・問題解決力は、対話によるコミュニケーション力と、自ら目標をたて実行する自立力がベースになっている。
・コミュニケーション力を養う教育としては、中学生の生徒同士で議論してコンセンサスを得る能力を磨く機会がたくさんある。そのために必要なことは、異なる価値観を持つ仲間と共同作業を行う力、得られたコンセンサスを皆の前で発表し共感を得る力、必要な情報を自分で収集できる力で、その方法を学習していく。
・デンマーク人は学校でも家庭でも生まれた時から1人の個人として尊重され、自分の考えで物事を決めることを求められる。こうした特性は小学生の間に培われるが、中学生になると個人と社会との関りを学び、また複雑な関係を調和されることが問われる。
5.働きやすい環境
●非学歴社会
・デンマークでは学歴を問われることはない。そもそもデンマークでは日本のように一斉に行われる大学入試や就職試験はない。大学を卒業するのも、社会に出るのも人によってバラバラで、各個人の価値観、人生計画に応じて組み立てられる。
・企業においても日本の会社に見られるような、有望な部下を意図的に引き上げることはなく、ポストは広く内外に募集されるので、派閥がつくられることもない。個の自立を重視してきたデンマークでは、日本のように同質性の社会システムにみられる閉鎖的な決定プロセスはなく、フラットで公平なしくみが息づいている。
●生産性の高い働き方
・デンマークでは先進国の中でも労働時間の少ない国の一つである。一般的には8時に出社し16時には退社する。大抵の職場でフレックス制度が導入されているので、自由度がとても高い。
・デンマーク人は家庭で過ごす時間を大切にしているので、仕事を効率的に仕上げて自宅に帰る人が一般的である。デンマークの企業で毎日18時まで職場に残っていると、能力のない人材と思われてしまうだろう。
・労働時間の縛りはないが、仕事のパフォーマンスが厳しく問われる。与えられた目標を達成することは当たり前で、職種によってはそこに付加価値と革新性が加えられているかが評価のポイントになる。パフォーマンスが低い者はすぐに解雇されることもある。
・会議では、議題を事前に設定し参加者全員が意見を述べる。基本的に持ち帰ることはしないで、参加している者のコンセンサスをまとめてその場で意思決定をすることが求められる。参加しているものが決定権を持っているので、たとえ役員の代理で新入社員が参加して最終決定をした場合でも、その社員の決断が尊重される。
●フレキュシリティ
・「フレキュシリティ」とは、「flexibility」(柔軟性)と「security」(安全性)を組み合わせた造語で、柔軟な労働マーケットと労働に対する社会保障を組み合わせた政策のことである。
・デンマークでは仕事の成果が出ないとすぐに解雇されることもある。しかし、労働者が慌てることがないのは、このフレキュシリティ政策があることも背景の一因である。
・フレキュシリティモデルは、①労働市場の柔軟性、②所得補償、③効果的な労働市場政策を組み合わせた形でゴールデントライアングルとも呼ばれている。
・労働市場の柔軟性は、雇用主が雇用と解雇をやりやすくすることで、労働力の構成を柔軟に変更でき、経済情勢や産業構造の変化に迅速に対応した組織を再構築することができる。従って、デンマークでは産業としては衰退しているにもかかわらず、雇用を守るために存続するゾンビ企業はほとんどない。
・簡単に解雇されるリスクがあるということは労働者にとっては不安要因である。そこで、失業者には最長2年間の所得補償が失業保険ファンドから支給される。特に低所得者層への支援は厚く、最大で前職給与の90%が支給される。
・効果的な労働市場政策は、社会保障制度の中でも特に重要な位置づけにあり、本政策に関する政府の支出はGDP比3.7%(2012年の実績値)にも達している。目的は、柔軟な労働市場が機能するための施策を打つことであり、失業者の再教育、転職の支援など多岐にわたっている。この失業者の再教育システムは実にうまく機能している。
・再教育は進捗状況を含めてかなり細かくかつ定時的にレポートを提出することが求められ、内容も逐次精査される。このため多くの人は再教育よりも企業で働くことを望むことになる。
・デンマークの格差を是正するシステムは、単に手厚い支援を提供するだけでなく、国民の税金を使うだけの義務と厳しさが緻密に組み込まれていることが、うまく機能している理由の一つである。
6.格差がないからこそ起こること
●高齢者は尊敬されない
・首相や大臣経験者、大企業の社長でも引退してしまえばただの高齢者になる。日本のように引退後に名誉顧問になり会社に残ることもなければ、財界活動に参加して過去の栄光で影響力を及ぼすこともない。デンマークでは高齢者という理由では特別尊敬もされない。
●女性の方が強い
・女性の進出が進む社会では、生活するうえで男性に依存する必要がないので離婚がかなり多い。
・デンマーク人の結婚に至るパターンは、女性が男性をつかまえて、まず同棲しお互いの相性が良いと結婚するが、離婚する場合は女性が男性を捨てることが多い。
●難民増加による右翼化の動き
・デンマークは移民を受け入れてきたが、最近は右寄りの論調が増えてきている。中東からの移民増加の影響もあり、人口に占める移民の比率は12.39%(2020年)になっている。
・人々の間では移民は仕事をしないで北欧の福祉制度にタダ乗りしているとの不満が高まっている。
・北欧諸国は民主主義、平等、博愛という理念のもとに福祉政策を進めてきたが、移民の増加と社会保障支出の問題が複雑に絡みあい、今のところすべての利害関係者を納得させる解決策を見出せてない。将来的に格差のない社会システムを維持する上で、デンマークも大きな課題を抱えている。
2章 サステイナブルな都市デザイン
1.2050年に再生可能エネルギー100%の社会を実現
●脱炭素化が加速する要因
・2050年までに世界で保有している化石燃料の80%を燃やせないというカーボンニュートラルが大きく関係している。
・再生可能エネルギーの発電コストが大幅に低下している。2010年~2017年の7年間で太陽光は73%、陸上風力は23%低下した。洋上発電も欧州のセントラル方式による入札、開発プロジェクトの大型化、風力発電の大型化、技術力の強化などにより大幅なコストの低下と開発リスクの低減を実現している。
●エネルギー戦略2050の策定
・デンマークは2011年、2050年までに化石燃料からの完全な脱却を目指す「エネルギー戦略2050(Energy Strategy 2050)」を公表した。
・エネルギー戦略の背景として、近い将来、アジアを中心とした新興国の経済発展に伴うエネルギー需要の増加から、石油や石炭などの化石燃料の価格が上昇することが見込まれていたことがある。資源のないデンマークでは価格高騰や自国では制御が難しい外部リスクを取り除く必要があった。
●社会に実装するための緻密なデザイン
・エネルギー戦略2050について、小国ゆえに策定できたのだろうとの見方があるが、たとえ小規模でも国家が方向性を大転換し、新しいイニシアチブを発揮することは容易なことではない。そのために、数年かけて政治家、行政関係者、研究者が戦略の実行可能性について検討を重ねてきた。
・エネルギー戦略2050は、①再生可能エネルギー、②エネルギー効率、③電化、④研究開発と実証、の4つから構成されており、それぞれ詳細な分析に基づく行動計画が定められている。また、戦略を確実に実行するための原則としくみが組み込まれている。
●1970年代からのエネルギー政策
・デンマークでは1973年の第一次オイルショックをきっかけに、1985年に原子力発電に依存しないエネルギー計画を国会で決議し、風力発電による再生可能エネルギーを導入するなど段階的に取り組んできた。
2.サーキュラーエコノミー(循環型経済)の推進
●EUで加速する循環型経済
・サーキュラ―エコノミー(循環型経済)とはリサイクルや産業廃棄物削減を狙った施策であるが、デンマークはEUと連携して積極的な取り組みを行っている。
●デンマークのポテンシャル
・サーキュラ―エコノミーの定義は次のようなものである。
「サーキュラーエコノミーは、デザインにより再生、再利用するしくみであり、製品とそれを構成する部品、原材料を技術的なものと生物学的なサイクルとに区別しながら、その価値と利用可能性を最も高い水準で維持すること」
●民間主導のビジネスモデル
・デンマークでは、民間企業が政府を引っ張る形で積極的にサーキュラーエコノミーに対応したビジネスを展開している。サーキュラーエコノミーを収益力もあり、持続可能な解決策にするためには、製品のデザイン段階からサーキュラーエコノミーの原則を組み込んだアプローチが重要であり、若手のデザイナーを中心にサーキュラーデザインの活動が進んでいる。
※ご参考:“DANSK SYMBIOCENTER”
※ご参考:“サーキュラーエコノミーとは”
3.世界有数の自転車都市
●コペンハーゲンの自転車政策
・デンマークはオランダと並んで自転車大国として知られている。コペンハーゲンの市民の通勤・通学の41%(2017年)が自転車を利用している。
・コペンハーゲン市は技術・環境市長が主導し、サイクリストにとって世界で最も優れた都市になることを目標にしている。
●自転車スーパーハイウエイの整備
・総延長467㎞(2018年時点)の「自転車スーパーハイウエイ」が整備された。コペンハーゲンでは5㎞未満の移動では60%の市民が自転車を利用するが、5㎞を超えた途端にその比率は20%以下に下がる。この数値を引き上げるためハイウエイの新線が追加された。
※ご参考:“グリーンな社会目指すデンマーク 自転車ハイウェイとIoT”
●自転車走行速度を統一するグリーンウェーブ
・高性能な信号機を導入し、時速20㎞で走行すれば赤信号で止められることはない。これにより、子供を乗せている母親も高齢者も安心して自転車を利用できる。
●多面的な包括的アプローチ
・自転車政策は環境エネルギー、都市交通の課題解決に加えて、市民の健康管理、社会保障コストの削減、投資誘致と産業の発展、家庭の幸福にもつながっている。これはよくデンマークで取り上げられる「包括的アプローチ(holistic approach)」と言われるもので、物事を多面的に捉えて問題の本質に迫り、多様性の中で解決策を探る方法である。
・包括的アプローチは自転車以外にも再生可能エネルギー、医療や福祉、スマートシティなど多くの分野で取り入れられている。
・自転車=移動手段という単純な発想ではなく、自転車を多面的にしたたかに利用する包括的なアプローチこそ、デンマークの政策デザインの特徴でもある。
4.複合的な価値を生むパブリックデザイン
●良いパブリックデザインとは
・デンマークの世界的都市デザイナーであり建築家のヤン・ゲール曰く、「良いパブリックデザインとは、魅力的な都市をつくりだす。魅力的な都市とは子供たちと高齢者がストリートに見られることだ」(インタビュー「都市の魅力を構成する要素とはなにか?」より)
・2009年に「世界で一番素晴らしい都市になる」と宣言したコペンハーゲンのパブリックデザインが優れている要因の一つは、もう50年も前から人間中心のまちづくりを推し進め、自転車道を整備し、パブリックスペースから自動車や駐車場を減らして、市民に開放してきたことである。
もう一つの要因は、市が2025年に「世界で初めてのカーボンニュートラル首都になる」と宣言したことを、政治家や行政の公約と考えるのではなく、市民1人1人が日常生活の中で目標達成に向けて取り組み、街の未来をつくろうとしていることである。
・パブリックデザインとは快適性を追求することだけでなく、都市の課題を解決したり、未来のイノベーションを実現したりするためのデザインでもある。
●アマー資源センター:廃棄物施設を都心のスポーツリゾートへ
・世界的な建築家であるビャルケ・インゲルスが率いるBIG(ビュルケ・インゲルス・グループ)が手がけ、2017年3月にオープンした廃棄物発電施設「アマー資源センター」はデンマークのパブリックデザインを象徴する公共建築である。
・屋上には斜面450mの人工スキーコースが設けられ、夏はトレッキングを楽しみ、頂上ではコペンハーゲンの眺望を楽しみながら小さなカフェで寛げる。
・CHP(熱電供給)廃棄物発電は、コペンハーゲンのCPH2025気候プランを支える重要な機能の一つであり、コペンハーゲン市で年間扱う40万トンの固形廃棄物を燃やすことができる。0~63MWまでの発電能力により6万2500世帯に電気を、157~247MWの地域熱供給能力で16万世帯に熱を供給可能となっている。エネルギー効率は90%以上で、世界で最もクリーンな焼却施設である。
・施設の煙突は排ガスだけではなく、大きなリング状の煙(実際は水蒸気)が排出され、夜になるとレーザーで明るく浮かび上がる。この煙突から出されるリング状の煙一つで、1トンの二酸化炭素の量を表しており、市民に1トンの二酸化炭素量とはどの程度のものかを考えてもらうきっかけにしようとしている。さらに内部は見学できるようになっており、市民の環境知性の育成にも一役買っている。つまり、アマー資源センターは、廃棄物発電による電力と熱供給施設×リゾート施設×教育施設ということになる。
●ハーバース:水質を改善した、都心の海のプール
・コペンハーゲンの夏の人気スポットは、イスラン・ブリゲにある市民プール「ハーバーバス」。コペンハーゲン港内の海の中にあるプールで短い夏を楽しむ人々の光景は夏の風物詩にもなっている。
・このハーバーバスもBIGが設計している。一見すると奇抜なアイデアが印象的だが、そこには緻密な計算に基づいた設計がなされている。デザインには、「連続性」「安全性」「アクセス性」「特別な景観」の4つのポイントがある。連続性は、埠頭のエッジから港の海水まで見えるように設計することで、利用者はプールという区切られたスペースに入るのではなく、海に直接入水する特別な体験を得られる。
・安全性は、各プールの外枠角度が中央のライフガードの位置から一目で確認できるようにライフガードの視野に合わせて決められている。このプールは最大で600名が利用できる。しかし無料で運営されているため、複数のライフガードを配置することは難しく、運営経費と安全性のバランスを考えた設計になっている。
・アクセス性は、障がい者を含めたすべての市民が楽しめるように配慮されている。たとえ車椅子であっても奥のプールサイドまで行ける。親が障がい者でも子供はプールで遊べ、子供が障がい者でも親子でプールサイドで楽しむことができる。
・景観はビーチにいる感覚を感じられるよう、ウッドデッキ、埠頭、ボートなどを象徴的に設置することで、都会リゾートとしての特別感を演出している。
●スーパーキーレン:多様な住民の交流を育む公園
・コペンハーゲン中心部の北に位置するノアブロ地区に、2012年につくられた公園で、総面積約3万㎡(新宿中央公園は約8万8千㎡)、縦750mの細長い施設である。公園は3つの区画に分かれており、赤の広場(スポーツとアクティビティのエリア)、黒の広場(交流のエリア)、緑の広場(住民の庭のエリア)となっている。地面が赤、黒、緑に色分けされ、広場の特徴が誰でも一目でわかるようになっている。

画像出展:「NEKKI MESSE」
『デンマークのコペンハーゲン市内に2012年6月に完成した、ユニークな公園がある。その名は「Superkilen(スーパーキーレン)」。市内中心部から北に伸びるノアブロゲーテ通りとテインスヴァイ通りの間となるノアブロ地区に位置し、広さは約3万㎡にも及ぶ。」』
・北欧は移民を積極的に受け入れてきた経緯があり、コペンハーゲンでもアジア系を含めて多国籍化が進んでいる。公園があるノアブロ地区には安い集合住宅があった関係で、多くの外国人が移り住んでいた。このように国籍が異なる住民が多く集まるこの地区は、住民間のコミュニケーション不足、生活様式の違いから起きる些細なトラブルや犯罪が多発するようになった。将来スラム化するリスクを抱えたこの地区の改善は、コペンハーゲン市にとって課題となっていた。
・コペンハーゲン市は同地区にあった国鉄の車庫跡地を公園につくり変えることを決め、競争入札を実施した。その結果、BIGとアーティストユニットのスーパーフレックス、都市デザイン事務所のトポテック1が選出された。
・彼らが取り組んだのは、住民と徹底的に話し合い、住民主導で公園のアイデアをつくりあげることだった。住民との議論を通じて採用されたのは、多国籍の住民の多様性を尊重しながらも住民同士のコミュニケーションを改善し、ノアブロに新しい価値を創出することであった。その方法として、約60カ国に及ぶ住民の出身国の遊具、照明、ベンチなどの設備を集めることで、自分の故郷の記憶を辿ると同時に、他国出身の住民の文化に触れて自然と彼らとコミュニケーションがとれるようにするというアプローチをとった。
・コペンハーゲンに世界の遊具を集めた公園ができたとの評判はすぐに広まり、休日になると地元住民に加え他の自治体からも親子連れが訪れるようになった。
・この地区に人が集まることで、新しいカフェ、レストランもオープンして人気のホットスポットとなり、治安も改善されるなど当初の目的を達成しただけでなく、新たな地域再生の成功事例として注目を集めることとなった。
・このプロジェクトでは、住民間のコミュニケーションの改善+治安の改善+ノアブロ地区の価値創出など、複合的な成果を生み出すことに成功している。
デンマークのスマートシティ1
“コロナ worldmeter”というブログをアップしています。約100年ぶりのパンデミックとして世界中に広がった新型コロナ(COVID-19)の感染状況を約2年8ヵ月に渡って記録をつけていました。「worldmeter」はその情報源です。
そして、そのレビューを書こうと思って気づいたのが、デンマークの圧倒的な情報管理力です。日本に比べれるとはるかに小さな国ではありますが、これは、よほどITが進んでいるのだろうと思いました。「一体どんなことをしているのだろうか?」と思い、見つけた本が今回の『デンマークのスマートシティ データを活用した人間中心の都市づくり』でした。
また、偶然ですが、背中を後押しするようなこともありました。それは『ウォルト・ディズニー 創造と冒険の生涯』という本の中に書かれた、チボリ(Tivoli Gardens)というデンマークの首都、コペンハーゲンにある1843年に設立された歴史的な公園(遊園地)です。

画像出展:「北欧フィーカ」
ウォルト・ディズニーは“未来都市”(EPCOT:Experimental Prototype Community of Tomorrow)”という将来構想を創造し、世界中をまわって数多くの公園を視察しましたが、最も強く感銘を受けたのがこのチボリ公園でした。もしかしたら、1966年に他界したウォルト・ディズニーが描いていた“未来都市(EPCOT)”とは、デンマークのスマートシティのようなものだったのかも知れません。
そして、デンマークを調べていて大変驚いたことがありました。それは2023年の世界経済競争力ランキング(World Economic Competitiveness Ranking)の第1位がデンマークだったということです。ちなみ日本は35位です。なお、世界経済競争力ランキングについては以下のサイトをご覧ください。
デンマーク、そして首都コペンハーゲンの都市開発は圧巻です。まさに“未来都市”のようです。
また、一つの国をここまで真剣に理解しようとしたのは初めてだったので、とても新鮮で貴重は時間となりました。お伝えしたいと思うことは山盛りで、ブログを5つに分けました。
ご参考)著者である中島先生のプレゼンテーション資料を見つけました。20枚に凝縮された内容で、全体像をご理解頂くことができます。
はじめに
1章 格差が少ない社会のデザイン
1.格差を生まない北欧型社会システム
2.税金が高くても満足度の高い社会を実現
3.共生と共創の精神
4.課題解決力を伸ばす教育
5.働きやすい環境
6.格差がないからこそ起こること
2章 サステイナブルな都市デザイン
1.2050年に再生可能エネルギー100%の社会を実現
2.サーキュラーエコノミー(循環型経済)の推進
3.世界有数の自転車都市
4.複合的な価値を生むパブリックデザイン
3章 市民がつくるオープンガバナンス
1.市民が積極的に政治に参加する北欧型民主主義
2.市民生活に溶け込む電子政府
3.高度なサービスを実現するオープンガバメント
4.サムソン島の住民によるガバナンス
4章 クリエイティブ産業のエコシステム
1.デンマーク企業の特徴
2.世界で活躍するクリエイティブなグローバル企業
3.デジタル成長戦略と連携して進展するIT産業
4.スタートアップ企業と支援体制
5.新北欧料理とノマノミクス
5章 デンマークのスマートシティ
1.デンマークのスマートシティの特徴
2.コペンハーゲンのスマートシティ
3.オーフスのスマートシティ
4.オーデンセのスマートシティ
6章 イノベーションを創出するフレームワーク
1.オープンイノベーションが進展する背景
2.トリプルヘリックス(次世代型産官学連携)
3.IPD(知的公共需要)
4.社会課題を解決するイノベーションラボ
5.イノベーションにおけるデザインの戦略的利用
6.社会システムを変えるデザイン
7章 デンマーク×日本でつくる新しい社会システム
1.日本から学んでいたデンマーク
2.デンマークと連携する日本の自治体
3.北欧型システムをローカライズする
4.新たな社会システムの構築
おわりに
1.格差を生まない北欧型社会システム
●フラットな社会
・デンマークの社内はオープンフラットである。デンマークで暮らしていて学歴、所属組織の社会的地位、保有している国家資格などが問われることはまずない。大切なのは、個人としてどのような考えを持ち、価値を提供できるかということである。
・年齢も関係ない。デンマーク語には日本語の敬語や丁寧語に相当する言葉もあまりない。
・自分が疑問に思ったことは相手が大臣や大手企業の社長であっても、気兼ねなく質問して議論を交わすのが普通である。
・『ある日本の大手企業の現地社長も、似たような経験を語ってくれた。彼は日本企業で長く勤務した後、デンマークの会社の社長となり、多くの従業員を雇用していたが、どの従業員も彼に友達感覚で接してくるそうだ。朝、工場労働者と会うと、背中をバンと叩かれ、ファーストネームで呼ばれながら「元気にやっているかい?」と言われ、企業文化の違いに戸惑ったらしい。日本では常に役員室にいて、外出の際は黒塗りの専用車で送迎され、いつもお付きの社員がサポートする体制で仕事をしていたため、デンマークのフラットすぎる社会に馴染むのが大変だったようだ。』
●デンマーク社会を支えた哲学
・デンマークの社会制度は1890年代から120年以上かけて試行錯誤しながらつくられた。
・社会保障制度をつくる基礎となったデンマーク人の精神性、価値観は、デンマークの歴史が深く関わっている。
・デンマーク人の価値観に大きな影響を与えたのは、デンマークの近代精神および教育の父と呼ばれ、現在も運営されている「フォルケホイスコーレ」(国民高等学校、全寮制の教育機関)の理念を提唱した牧師であり詩人、哲学者であったニコライ・F・S・グルントヴィ(1783-1872)である。
・グルントヴィの理念は、現在のデンマーク社会に次のような影響を与えている。
-国民すべてが平等な生活を送ることに価値をおく=格差の少ない北欧型社会システム
-知識ではなく対話を重視=コンセンサス型社会システム
-死の学校から生のための学校=知識から知恵や問題解決能力を習得する教育
・1890年からの社会福祉政策は計画的ではなく、少しずつ進められた。デンマークではドイツ型の賃金労働者だけを対象にするのではなく農民も含めたすべての国民を対象とした社会保障制度を目指すことになった。そして、特に社会的弱者である病人、障がい者、十分な教育を受けられなかった人々も対象とした。
・20世紀になると、様々な改革が行われ、1933年には社会制度改革が実施された。
・当時の社会大臣は福祉事業の主流であった失業対策、自助努力、救済事業に対し、市民の社会的権利である福祉原則を提示し、市民の最低保証生活水準を保障することは国家の義務であるとした。デンマークの福祉国家としての普遍的理念はこれにより確立された。
・1960年代以降、日本と同様に高度経済成長期を迎え、労働者不足の問題が女性の社会進出を後押しした。その結果、これまで家庭で行われてきた育児、高齢者の介護が難しくなり、より充実した社会福祉が発展することになった。
・社会福祉の発展においても、その根底にはニコライ・F・S・グルントヴィの思想が育んだデンマーク人の精神性、価値観があった。
●女性の社会進出
・デンマークにおける女性の社会進出は、前述の通り、1960年代の経済成長による労働力不足が深く関係している。
・1965年に設立された社会制度改革委員会では、女性や障がい者が柔軟に職に就けるような制度改革を行い、出産休暇、職場に復帰する権利、保育所の整備などが行われ、女性が働きながら子育てを行える社会的環境が整備された。その結果、1980年代以降、女性の就業率は70%を超えている。ただし、エネルギー産業、製造業、鉱業などはまだ男性が中心である。その一方で、企業の主要幹部には多くの女性が登用されており、女性の大臣も珍しくはない。
※この「女性の社会進出」に書かれていることは、少子化や育児・子育ての問題がやっと注目されてきた、ここ数年の日本に似ていると思いました。もし、デンマークがここに書かれている対策を実施していたとすれば、少子化について、日本ほどには問題になっていないのではないかと思われます。
そこで、探してみると“人口ピラミッド”の動画が同条件でアップされていました。これは「世界人口推計2019年版」(国連)に基づき、1950年から2100年までの人口の推移を動画にしたもので、大変興味深いものです。そして、その対照的な結果に、驚きを通り越して恐怖すら感じます。
“デンマーク王国の人口ピラミッド(1950-2100) / 単位(Unit): 千人 / 2019年推計” (Youtube)
“日本の人口ピラミッド(1950-2100) / 単位(Unit): 千人 / 2019年推計” (Youtube)
●医師と患者が対等に治療に当たるデジタルヘルス
・デンマークの医療制度は社会保障制度を代表するサービスであり、医療費は税金で賄われ、原則無料となっている。
・デンマークの医療システム(ヘルスケアシステム)は世界的にもトップレベルで、特に医療格差がない国としても知られている。しかし、高齢化による医療労働者の不足が深刻化している。
・政府は対策として、デジタル技術を利用すること(デジタルヘルス)で、効率化による資源の最適化を模索している。
・デンマークでは1968年に導入されたCPRナンバー(国民識別番号)に加え、電子政府の基盤でもある医療ポータル(sundhed.dk)の普及がデジタルヘルスを後押ししている。
・sundhed.dkにアクセスすると、自分の医療情報、例えば、過去の治療情報、入通院履歴、投薬情報などを確認でき、それをかかりつけ医や病院の医師とも共有できる。
・この医療システムの重要なところは、デジタル化により効率性と利便性を実現しているだけではなく、医療従事者と患者の関係を対等にするというコンセプトが含まれていることである。デンマークではこれを市民と患者のエンパワーメント(権限付与)と表現している。
・デジタルヘルスには、医師と協働するために必要な知識の習得を支援するという側面もある。
●高齢者福祉の三原則
・高齢者福祉も社会保障国家としての柱である。
・高齢者福祉の三原則によりサービスに一貫性がある。三原則は1982年に設定された。
・三原則は、①継続性の原則、②自己決定の原則、③残存能力の活用、である。
・継続性の原則とは、可能な限り、健康な時のスタイルを維持し、基本は自宅で暮らし続けるようにすることである。このため、やむおえず福祉施設に入居する場合でも、自宅で使っていた家具などを持ち込むことができる。
・自己決定の原則は、たとえ介護が必要な状態になっても、自分の人生に関することは自分で決定することである。それを家族や介護スタッフは尊重しなければならない。これはデンマーク人の自立とも関係しており、大原則の一つである。
・残存能力の活用は、体が不自由になったとしても、まだ健常な機能がある場合は、補助器具などを利用して自力で対応することである。
・この三原則は、サービスを提供する行政サイドにとっても、無駄な支出をしないサービスの水準を維持するために重要なものとなっている。
・デンマークの国民年金制度は共生の理念に基づいた所得の再分配システムが機能しており、高額所得者や資産家は年金が減額される。しかし、不満を持つものはあまりいない。資産があり、自活できる高齢者は自力で対応し、余力のない高齢者により多く分配することで、老後でも貧富の差を最小化しようとの考えが根底にある。
●障がい者福祉
・デンマークの障がい福祉制度は現在の形になるまで150年以上かかっている。また、現在の制度は1959年の知的障がい者福祉法の制定が関係している。
・『障がい者が一般市民と同じように働き生活することには厳しさも伴う。たとえば、以前ある自治体でITシステム構築を担当する、下半身が不自由なソフトウェア開発者と知りあった。彼は車椅子を利用し、自力で車を運転して職場まで通勤していた。ところが1年後、財政削減の関係で彼は解雇されてしまっていた。このようにデンマークでは、ノーマライゼーションとは差別をなくし、障がいがある人も、障がいがない人と同じように生活できることを保障する一方で、知的障がい者でない限り、一般人と同じ条件で処遇させることを意味している。』
●ヤンテの掟とフラットな社会
・デンマークの人は謙虚な姿勢をもつ人が多い。世代にもよるし、一概には言えないが「ヤンテの掟」が影響しているかもしれない。「ヤンテの掟」とは成功者に対しての戒めである。これは1933年に作家のアクセル・サンダムーサが書いた小説の中に出てくる架空の村の10カ条の掟である。
2.税金が高くても満足度の高い社会を実現
●高福祉社会を支える税負担
・国民の対GDPに対する税負担率を見ると、デンマークは第3位(2019年)と高い。また消費税も25%と高い。しかし、多くのデンマーク人は高額な税金を納得して収めている。その理由は、政治を信頼し、自分たちが収めている税金が正しく使われており、国の発展や不幸な人たちの支援に当てられることは義務であると、国民に認識されているからである。
・国民は税金を徴収されているというより、信頼関係に基づいた投資であると考えていることも大きな理由である。投資なので、将来の生活に還元されると確信している。
・デンマークの民主主義の水準は高く、政治におけるクリーン度は高い。世界180カ国を対象にした腐敗認識指数2022年で、デンマークは1位(日本は18位)である。つまり、国民が選挙で選んだ議員を信頼しており、議員が汚職などに手を染めることは極めて少ないので、安心して税金の再分配を任せているということである。なお、こうした政治に信頼を置く国民性は教育制度にも関係している。

”税金が高い国ランキング発表 日本は世界で2番目”
『世界で最も税金が高い国はどこでしょうか。
海外ニュースサイトに掲載された高税率国ランキングが話題を呼んでいます。同サイトは独自に調査した世界各国の法人税、給与税、個人所得税、消費税を基準にランキングを作成し、公表。日本は2位に位置付けられました。』
このサイトによると、デンマークと日本の各税の税率は以下のようになっています。北欧諸国と言えば、「福祉は充実しているが税金が非常に高い」というイメージでしたが、国レベルでは「違うようだ」と思いました。
消費税で公平性を担保しつつ、障がい者や高齢者などには徹底した福祉・公共サービスといった、セーフティーネットを充実させて支援していくという仕組みのように思います。
注)この記事がいつ書かれたものか分かりませんが、日本の税率については、それぞれ右側に分かる範囲で追記しておきました。デンマークで給与税が低いのは、一生懸命働いて得た対価に税金をかけたくないということなのでしょうか。
情報が古いため、日本のランクについては疑問がありますが、消費税だけでなく国レベルで税金を考えるべきだと思いました。(青=少ない、赤=多い)
【デンマーク】
・法人税23.5%
・個人税46.03〜61.03%
・給与税8%
・消費税25%
【日本】
・法人税38.01%(平成30年度:法人実効税率 29.74%)
・個人税15〜50%(令和5年度:5~55%)
・給与税25.63%(5~45%)
・消費税8%(10%)
●公共サービス
・市民が高い税金の負担に納得していることは、実際に提供されるサービスを見れば理解できる。
◇妊娠と出産
・デンマークでは特に出産や子育てのサービスにかなり力を入れている。
・資源が少ないデンマークでは人材が一番重要であり、次の100年を支える人を育てることは社会の義務であるとの考えが浸透している。
・出産までの医師、助産婦による相談、検診はすべて無料である。ただし、デンマークでは出産は病気とは扱われないので、初産は1泊の入院だが、経験のある妊婦は数時間で退院する。
◇育児
・デンマークでは出産後32週間の育休を終えると職場に戻るのが一般的である。そのため、子供のための保育サービスを利用することになる。6カ月~3歳児までは乳幼児託児所や保育ママ(家庭内保育)を利用する。
・保育ママは市から認定された保育士が各家庭で4~5人の子供を預かる制度で、自治体にとっては保育施設の新設や維持費用がかからないこと、また子供の両親にとっても家庭的な雰囲気の中で保育してもらえるため、デンマークでは主流となっている。
・保育ママは職業としても成立するだけの収入体系となっている。例えば5人の子供を預かった場合、保護者からの利用料と自治体からの助成金を合わせて年収600万円くらいになるとされ、保育ママのなり手が不足することはない。
・3歳~6歳の子供は保育園に預ける。デンマークでは自治体が希望する子供をすべて保育園に入園させる義務がある。コペンハーゲンなどの都心では順番待ちの保育園もあるが、施設さえ選ばなければ確実に入園させることができる。
・保育料は自治体により異なるが、一般的に保育料の約30%を保護者が負担する。しかし、保護者の年収が低い場合は保護者の負担が実質ゼロになり、高い高額所得者は保育料を全額負担しなくてはならない。
・デンマークでは年収が低くても、高額所得者とまったく同じ育児サービスを受けられるようになっており、格差を少なくする社会のしくみは人生のスタート時から保障されている。
◇学校教育
・格差がないという点で世界に誇るシステムになっている。
・教育は初頭/中等学校教育(1~10年)、高等学校教育、大学教育、大学院教育と、授業料は公立の場合はすべて無料となっている。
・憲法に、教育義務の年齢にある子供は公立学校で教育を無料で受けることができる権利を有していると記されている。
・障がい者に対する特別支援教育も充実している。しかし、特別支援学校は設置数が限られているので、通学の問題が発生する。これに対し、自治体は自家用車の利用にかかる燃料費やタクシーの利用料金を支援する体制がとられている。
・大学では勉強に集中するために奨学支援金10万円程度が毎月支給される(学生のおかれた条件や物価により変動する)。加えて低金利のローンを活用することで、家庭の経済力と関係なく大学教育を受けることができる。
・デンマークの大学は入学するより卒業する方がはるかに大変で、一般的に大学生は週に50時間程度は勉強すると言われている。
・経済的な理由で勉学の道が閉ざされることなく、経済格差が教育格差を生まないしくみが構築されている。
「生命とは何か」
本書は“シュレーディンガーの方程式”などにより、量子力学に多大な貢献をされた、エルヴィン・シュレーディンガーの有名な著書で、発行は1944年なので約79年前に書かれたものということになります。
私にとって量子力学は出口の見えないトンネルのようなものなのですが、本書の副題が『物理的にみた生細胞』となっており、とても興味をもったというのが手に取った理由です。
ブログは「まえがき」の一部と、71のテーマの中の4つと、鎮目恭夫先生の「岩波新書版(1975年)への訳者あとがき」の中の“シュレーディンガー略歴”になります。ブログの内容は乏しいのですが、個人的には新たな発見もあり、時間をかけた価値はあったなと思っています。
まえがき
『そもそも科学者というものは、或る一定の問題については、完全な徹底した知識を身につけているものだと考えられています。したがって、科学者は自分が十分に通暁していない問題については、ものを書かないものだと世間では通っています。このたびは、私はとにかくこの身分を放棄して、この身分につきまとう掟から自由になることを許していただきたいと思います。これに対する私の言いわけは次の通りです。
われわれは、すべてのものを包括する統一的な知識を求めようとする熱望を、先祖代々受け継いできました。学問の最高の殿堂に与えられた総合大学の名は、古代から幾世紀もの時代を通じて、総合的な姿こそ、十全の信頼を与えられるべき唯一のものであったことを、われわれの心に銘記させます。しかし、過ぐる100年余の間に、学問の多種多様の分枝は、その広さにおいても、またその深さにおいてもますます拡がり、われわれは奇妙な矛盾に直面するに至りました。われわれは、今までに知られてきたことの総和を結び合わせて一つの全一的なものにするに足りる信頼できる素材が、今ようやく獲得されはじめたばかりであることを、はっきりと感じます。ところが一方では、ただ一人の人間の頭脳が、学問全体の中の一つの小さな専門領域以上のものを十分に支配することは、ほとんど不可能に近くなってしまったのです。
この矛盾を切り抜けるには(われわれの真の目的が永久に失われてしまわないするためには)、われわれの中の誰かが、諸々の事実や理論を総合する仕事に思いきって手を着けるより他に道がないと思います。たとえ物笑いの種になる危険を冒しても、そうするより他には道がないと思うのです。
私の言いわけはこれだけにします。』
目次
まえがき
第一章 この問題に対して古典的物理学者はどう近づくか?
1 研究の一般的特質と目的
2 統計物理学からみて、生物と、無生物とは構造が根本的に異なっている
3 きまじめな物理学者は、この問題にどう近づくか?
4 原子はなぜそんなに小さいのか?
5 生物体の働きには正確な物理法則が要る
6 物理法則は原子に関する統計に基づくものであり、近似的なものにすぎない
7 法則の精度は、多数の原子の参与していることがもとになっている第一の例(常磁性)
8 第二の例(ブラウン運動、拡散)
9 第三の例(測定の精度の限界)
10 分子数の平行根の法則
第二章 遺伝のしくみ
11 古典物理学者の予想は、決してつまらぬものとは言い棄てられないが、誤っている
12 遺伝の暗号文(染色体)
13 生物体は細胞分裂(有糸分裂)で生長する
14 有糸分裂では、すべての染色体がそれぞれ二つになる
15 減数分裂と受精(接合)
16 一倍体の個体
17 減数分裂はとりわけ重要である
18 乗り換え。遺伝形質は染色体の局部的な場所に座を占めている
19 遺伝子の大きさの限界
20 遺伝子は少数個の原子からなる
21 遺伝子の永続性
第三章 突然変異
22 不連続は突然変異―自然淘汰の行われる根拠
23 突然変異種は育種可能である、すなわちそれは完全に遺伝する
24 遺伝子の座、劣性と優性
25 若干の学術用語の紹介
26 近縁交配は有害な結果を生ずる
27 一般的な注意と史実
28 突然変異は稀な出来事でなければならない
29 X線によって引き起こされる突然変異
30 第一の法則、突然変異は単一事象である
31 第二の法則、この事象は或る限られた場所で起こる
第四章 量子力学によりはじめて明らかにされること
32 遺伝子の永続性は古典物理学では説明できない
33 量子論によれば説明できる
34 量子論―飛び飛びの状態―量子飛躍
35 分子
36 分子の安定度は温度に依存する
38 修正すべき第一の点
39 第二の修正点
第五章 デルブリュックの模型の検討と吟味
40 遺伝物質の一般的な描像
41 この描像は唯一のものである
42 従来行われてきたいくつかの誤った考え
43 物質の異なる「状態」
44 本当に問題になる区別
45 非周期性の固体
46 縮図の中におしこめられた種々様な内容
47 事実との比較、安定度および突然変異の不連続性
48 自然淘汰により安定な遺伝子が選ばれる
49 突然変異種にはしばしば安定性の低いものがある
50 温度の影響は安定なものより不安定なものに対する方が少ない
51 X線はどんな仕方で突然変異を起こすか?
52 X線の効率は、自発的な突然変異の頻度の大小にはよらない
53 突然変異は元に戻せる
第六章 秩序、無秩序、エントロピー
54 この模型からでてくる注目すべき一般的な結論
55 秩序性を土台とした秩序性
56 生命をもっているものは崩壊して平衡状態になることを免れている
57 生物体は「負エントロピー」を食べて生きている
58 エントロピーとは何か
59 エントロピーの統計的な意味
60 生物体は環境から「秩序」をひき出すことにより維持されている
第七章 生命は物理学者の法則に支配されているか?
61 生物体ではどんな新法則が期待されるか?
62 生物学的な事情の概観
63 物理学的な事情の概括
64 両者は著しい対照をなしている
65 秩序性を生み出す二つの道
66 この新原理は物理学と相いれないものではない
67 時計の運動
68 時計仕掛けもつきつめてみれば統計的なものである
69 熱力学の第三法則(ネルンストの定理)
70 振子時計は事実上絶対零度にある
71 時計仕掛けと生物体との関係
エピローグ 決定論と自由意志について
岩波新書版(1975年)への訳者あとがき
21世紀前半の読者にとっての本書の意義
―岩波文庫への収録(2008年)に際しての訳者あとがき
第一章 この問題に対して古典的物理学者はどう近づくか?
1 研究の一般的特質と目的
・この小著は、一理論物理学者が約400人の聴衆に対して行った一連の公開講演をもとにしたものである。
・数学を使っていないのは、あまりに複雑で十分に数学を使うことができなかったからである。
・この講演の目的は、生物学と物理学との中間で宙に迷っている基礎的な観念を、物理学者と生物学者との双方に対して明らかにすることにあった。
・重要でしばしば論議されている疑問とは、生きている生物体の空間的境界の内部で起こる時間・空間的事象は、物理学と化学とによってどのように議論されるのか?
・『この小著により解き明かして、はっきりさせようと試みるその答は、前もって次のように要約できます。今日の物理学と化学とが、このような事象を説明する力を明らかにもっていないからといって、これらの科学がそれを説明できないのではないか、と考えてはならないのです、と。』
2 統計物理学からみて、生物と、無生物とは構造が根本的に異なっている
・『周期性結晶が研究の対象として最も複雑なものの一つであると私が言ったのは、もっぱら物理学者を念頭においてのことです。事実、有機化学は、ますます複雑な分子を研究することにより、かの「非周期性結晶」のごく近くにまで到達しました。私の考えでは、非周期性結晶こそ、生命をになっている物質なのです。それ故、生命の問題に対して、有機化学はすでに大きな重要な貢献をなしているのに、物理学者がまだほとんど何ら寄与していないのは、さして不思議ではありません。』
“非周期性結晶”について知りたいと思い見つけたのが下記の早川先生の寄稿です。これは、(1999.3.24 於討論集会「生命物理と複雑系」東北大学電気通信研究所)となっているのでかなり古いものですが、物理学者としてのシュレーディンガー、著書の「生命とは何か」、そして疑問の“非周期性結晶”について記述されているのでピックアップさせて頂きました。
「生命物理は物理のフロンティアか」 早川尚男 (京都大学大学院人間・環境学研究科)
『シュレディンガーの生命観は御承知の通り素朴な決定論に基づいていました。 特に彼は染色体に注目し「非周期的結晶」と呼ぶに相応しい物質であると注目しておりました。非周期結晶とは 個々の単位は同じではないが、それらが周期的に現れ規則的配列をしているという意味で使っていますが、この考え方が後に重要な 役割を果たすことになります。特に染色体がその結晶的構造故に重要で遺伝暗号を媒介する遺伝子を持つということはシュレディンガーが初めて陽に言った様です。 ここで強調したいのは結晶を重要視し、素朴な力学的考察で生命現象は理解できるとした非常に力強い信念があった点です。 その意味で彼は生命を分子機械であると捉えていたと言えるかもしれません。』

こちらは早川先生のTwitterです。早川先生は現在、基礎物理学研究所 物質構造研究部門 教授 で間違いないと思います。
第三章 突然変異
22 不連続は突然変異―自然淘汰の行われる根拠
・『今から約40年前に、オランダ人のド・フリースは、完全に純粋種のものの子孫さえも、小さいが「飛び離れた」変化をしたものがごく少数、たとえば何万に二つとか三つとかの割合で出現する、ということを発見しました。「飛び離れた」という言葉は変化がはなはだ大きいという意味ではなく、変化の起こっていないものとごく少数の変化の起こったものとの中間の形のものがまったくない、という意味で不連続性があることを意味します。ド・フリースは、それを突然変異と名づけました。
不連続性ということことが重要なことなのです。これは、物理学者に量子力学―隣り合った二つのエネルギー準位の中間のエネルギーは現われないこと―を連想させます。物理学者は、ド・フリースの突然変異の説を、比喩的に生物学の量子論と呼びたいような気がするかもしれません。後の説明、これは単なる喩え以上に深い意味のあることがわかるはずです。実際、突然変異は、遺伝子という分子の中で起こる量子飛躍によるのです。』
[突然変異と量子論]で検索したところ大変興味深いサイトが2つ見つかりました。
以前、私は「生物と量子力学」というブログをアップしているのですが、まさにこの分野は新事実がどんどん出てきているようで注目です。

画像出展:「ナゾロジー」
『英国サリー大学(University of Surrey)で行われた研究によれば、DNAでは従来考えられていたよりも遥かに高い確率でトンネル効果が発生している可能性が高い、とのこと。
量子力学の世界では電子や陽子など小さな粒子の存在確率はあやふやであり、粒子がある場所から別の場所に突然、移動に必要なエネルギーを無視して、トンネルを通ったかのように出現する現象が起こり得ます。
研究結果が正しければ、生物進化の原動力として、量子効果が大きな影響を与えていることになるでしょう。』
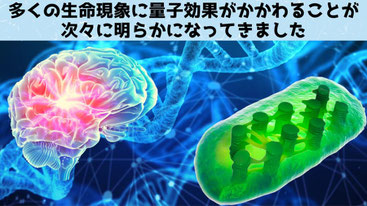
画像出展:「ナゾロジー」
『DNAは「生命の設計図」としての機能があり、私たち生物の体を作るためには欠かせない存在となっています。またDNAに刻まれた情報は世代を超えて子孫に継承され、親同じような体をした子を作ることを可能にし、種の概念を与えてくれます。しかしDNAの構造は不変ではなく、さまざまな要因で変化してしまうことが知られています。
DNA変異は有害物質や紫外線などの化学的・物理的要因に誘発されるだけでなく、複製時の酵素反応のエラーなど生物学的な要因によっても発生します。
DNAは誕生した当初から、物理的要因・化学的要因・生物学的要因の全てから挑戦を受けてきたと言えるでしょう。しかし量子力学と生物学との融合によって誕生した「量子生物学」の進歩により、生命活動において量子的な効果が無視できないことがわかってきました。
たとえば植物の光合成では、化合物間の間で古典物理学に反した電子のジャンプが頻繁に行われており、植物たちが量子力学を使って光合成効率を高めていることがわかってきました。』
もう1つは、量子科学技術研究開発機構さまのサイトです。

『第4の波後半の20世紀、分子生物学が大きく花開いた。デオキシリボ核酸(DNA)二重らせん構造の発見に始まり、DNAに記された遺伝情報からたんぱく質が作られる仕組みやその役割などが明らかになった。がんやさまざまな病気に対する医薬、新型コロナウイルスに対する治療薬やmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンなどが開発され、人類は分子生物学の恩恵を受けている。
ヒトを始めとしたさまざまな生物種の全遺伝情報(ゲノム)もすでに解読され、生物の部品の情報が得られた。しかし、自動車は分解して組み立てると動くが、ヒトや大腸菌を分解しても元通りにならない。部品どうしの繊細な相互作用の情報が欠落しているからだ。つまり要素還元的なアプローチだけでは「生命とは何か?」に対する答えを得ることはできない。
第4の波で花開いた分子生物学の限界が見えた。第5の波は量子生命科学が花開くと考える。量子論・量子力学の視点や技術で生命科学にパラダイムシフトを起こそうとするのが、量子生命科学だ。生命科学の発展は科学技術の発展に依存する。16世紀末に光学顕微鏡が発明されて細胞が発見され、生命科学は分類学から細胞生物学にパラダイムシフトした。そして、電子顕微鏡や遺伝子工学の技術革新で分子生物学が花開き、免疫学、ウイルス学、脳神経科学などの生命科学が飛躍的発展を遂げた。』
第四章 量子力学によりはじめて明らかにされること
33 量子論によれば説明できる
・『今日の知識に照らしてみれば、遺伝子の仕掛けは、量子論の基礎そのものと密接に結びついている、というよりはむしろ、その上に打ち立てられているといえます。量子論は1900年にマクス・プランクにより発見されたものです。
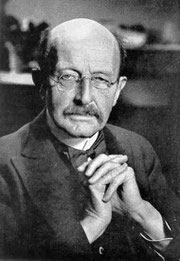
画像出展:「WAKARA」
以下の文章は「Chem-Station」に書かれている内容です。このサイトには英語ですが、1分36秒のマックス・プランクの動画がありました。
『マックス・カール・エルンスト・ルードヴィヒ・プランク(Max Karl Ernst Ludwig Planck、1858年4月23日-1943年10月4日)は、ドイツの理論物理学者である。1918年にノーベル物理学賞を受賞。量子論の開祖の一人。』
マックス・プランクは「量子論の父」と呼ばれているとのことで、ちょっと気になったのは、以前ご紹介したことのある、ニールス・ボアは何だっけ? というと、確認したところ、「量子論の育ての親」とのことでした。
近代遺伝学はド・フリース、コレンス、チェルマクによるメンデルの法則の再発見(1900年)およびド・フリースの突然変異に関する論文(1901-03年)から出発したといえます。したがって二つの偉大な理論の誕生はほとんど時を一つにしており、両者の結びつきができるまでに、或る程度の成熟に達する時をかさねなければならなかったのは不思議ではありません。量子論の側では、四半世紀かかって1926-27年になりようやく、W・ハイトラーとF・ロンドンにより、化学結合の量子理論の全貌が一般的原理において明らかにされました。ハイトラー-ロンドンにより化学結合の理論は、量子論の最近の発展(量子力学または波動力学と呼ばれるもの)の中で最も巧妙でこみ入った諸概念を含んでおります。計算を用いないでそのおおよその説明をすることは不可能に近く、あるいは少なくとも、本書と同じ位の小さい本を一冊必要としてます。しかし幸いに、われわれの考えを明らかにするために必要な説明はすっかり済みましたから、「量子飛躍」と突然変異との間の関連をもっと直に指摘し、最も顕著な点をいま拾いあげることができると思われます。このことこそ本書でこれから試みようとすることなのです。』
岩波新書版(1975年)への訳者あとがき
シュレーディンガー略歴
『シュレーディンガーは、1887年オーストリアのウィーンに生まれました。同地で教育を受け、ウィーン大学に学びましたが、そのころウィーン大学には、確固たる原子論の立場にたつ統計力学の指導者ボルツマンがいました。ボルツマンは1906年自殺したので、彼が接した期間は短かったが、その学風から影響を受けたことは少なくなかったと思われます。シュレーディンガーは研究生活に入ると間もなく1912年に、物質の電気的・磁気的性質を電子論と原子構造から理論的に導く研究論文を発表しました。その後の研究は、多方面の理論的な問題におよんでいますが、その中には、大気中の音の音波の伝播の問題や、薄い液体膜(泡)の振動などの研究があります。また結晶格子とX線の干渉などの論文もあります。要するに、振動(物質中の音波や光の波)とその原子的(粒子的)な構造との関係というものが主要な関心の的だったといえましょう。
1920年にウィーンを去り、スツットガルト大学の理論物理学教授の席を得、同年結婚し、翌年にはスイスのチューリヒ大学の教授になりました。そのころようやく、前期量子論と相対性理論との立場から従来の力学に適当な制限を付加するというやり方での研究が行きづまり、原子のような世界にあてはまる新しい力学体系が必要になってきました。その中で1925年にハイゼンベルクが、まったく新しい立場から原子の力学を提唱し、ボルンとヨルダンはこれをマトリックス力学の形にし、これにより従来のニュートン力学と原子の力学との間に或る形式的な対応がつけられました。これに対し、シュレーディンガーはより直感的なモデルを考えており、従来の物理学で力学と光学との形式上の相似の関係を追及していました。1923年フランスのド・ブロイが、物質粒子の中の電子の波動が、干渉によっていくつかの定常波をつくって安定な電子軌道を生ずるというアイデアから、波動力学と名づける新力学を提出しました。1926年、彼が38歳の年の3月から9月にわたり発表した「固有値問題としての量子化」と題する前後四篇の論文は、今日シュレーディンガーの波動方程式と呼ばれる基本的な形式を導き、この波動力学がハイゼンベルクらのマトリックス力学と数学的に等価なものあることを証明し、さらに水素原子への応用例を示した論文でした。こうして新しい原子力学(やがて量子力学と呼ばれるようになったもの)が基本的に確立されました。
彼は1927年にプランクのあとをついでベルリン大学理論物理学教授になり、ユダヤ人ではなかったが、ヒトラーのナチスがドイツの政権を獲得した1933年にイギリスに渡り、同年ディラックと共にノーベル物理学賞を与えられ、オクスフォード大学とアイルランドのダブリン高級学術研究所に席を得ました。そして1936年にオーストリアのグラーツ大学に戻りましたが、第二次大戦の勃発により中立国アイルランドのダブリン研究所に落着きました。
ところで、シュレーディンガーの波動力学は、ハイゼンベルクのマトリックス力学やディラックの非可換代数学とくらべて直感的・時空的な原子像を頭に描くのにははるかに好都合で、そのため化学結合の理論やその他の原子・分子レベルの諸問題について量子力学の威力と信用を急速に高めるのに役立ちました。しかしまた彼が頭に描いた原子像・自然像は、アインシュタインのそれと似て、物質の時空的連続性について古典物理学的自然像に執着したものであり、そのためこの連続性と量子力学的現象で問題になる非連続性(物質構造の量子的非連続性や時間的変化の因果的非連続性)との矛盾に鋭くぶつかりました。そしてこの矛盾については、ボルンが「量子力学的確率」という観念を導入し、ハイゼンベルクが「不確定性原理」を提唱し、ボーアが物質の構造とその変化について時空的記述と因果的記述とは同一物の二つの側面像―二つの側面を同時に直接見ることはできないが二つの側面像は相互に補い合うもの―であるという「相補性原理」を提案したことによって、学界の大勢は哲学的不安から解放され、以来これが量子力学の正統派的解釈(コペンハーゲン的解釈)として学界の主流になり、理論物理学界の中央最前線は1920年代末からこの線にそった量子力学による素粒子物理の研究へ向かいました。しかし、アインシュタインやシュレーディンガーは量子力学のこの正統派的解釈に終生にわたり強い疑問と不信をいだき、そのためシュレーディンガーはアインシュタインと同様に1920年代末以降は理論物理学界の主流から全くはずれ、精神的孤独な生涯を歩いたのでした。個人というものは、ある究極的な意味では誰もみな孤独でありひとりで死んでゆくものでありますが、シュレーディンガーはその孤独さを後半生にはっきり自覚的に体験しつつ生きた人の一人でした。そのような孤独の自覚は古今東西の万人との一体的連帯感と相補的なものであり、そのことが本書のエピローグの哲学的な文章のなかに反映していると訳者は思うのですが。
1930年ごろ以来、シュレーディンガーの関心の最も中心的な焦点は、アインシュタインの場合と全く同じではないが、物質と電磁気と重力とを統一的に扱う単一場理論と宇宙論へ向かったように思われます。彼はダブリンで三冊の優れた小著―本書(1944年)と「統計熱力学」(1950年)―を次々に世に送りました。いずれも、簡潔な教科書的書物のなかに独自の鋭い哲学的思索を示したものです。その後1956年に母国に帰り、ウィーン大学教授となり、1961年1月4日に73年余の生涯を閉じました。』
ご参考
“シュレーディンガーの略歴”の中に、「アインシュタインやシュレーディンガーは量子力学のこの正統派的解釈に終生にわたり強い疑問と不信をいだき」とありますが、このことに触れている2つのブログをアップしていましたのでご紹介させて頂きます。

ブログ:「超ひも理論(超弦理論)」
●量子重力理論
”相対論と量子論が“結婚”出来れば究極の理論になる”
-相対性理論は時間や空間、そして重力に関する物理学の理論である。
-量子論は原子や素粒子などのふるまいを説明する物理学の理論である。
『マクロの世界に加え、ミクロの世界でも重力計算ができるようになれば、究極の理論は完成するということです。そして”素粒子=点”ではなく、”素粒子=ひも(弦)”と捉えることにより、可能性が生まれるということが分かりました。 』
社内規程立案2
第4章 社内規程の効力
・社内規程の効力は施行期日から生じる。
17 社内規程の効力はいつから生じるのか
1)施行という概念
・「施行」とは制定された規範の効力を一般的に発動し、作用させることである。
・特に「適用」とは極めて類似しているが、「適用」は個別具体の事象に対する効力の発動・作用であるという点が異なる。
2)施行期日に関する条文
(1)条文の表記
・施行期日を示す条文は、附則に置かれている。社内規程の場合、附則にこれ以外の条文を置くことはあまりない。
・施行期日が唯一の条文の場合、見出しも条名もなく、施行期日を定める文章だけが表記される。
(2)表記されている期日などの意味
・社内規程は、制定後に改定されることがある。例えば、改定があった場合、条文中の「この規則」とは制定当初の規則のことか、改定後の規則のことかに迷うことがある。これは、附則の条文が示している年月日は直近に改定された時の施行期日であるため、改定後の現在規則ということになる。
18 社内規程の効力は誰に対して生じるのか
・社内規程の効力は、会社とその構成員である役職員に対して生じる。つまり「適用」という語を使えば、社内規程は「会社とその構成員である役職員に適用される。」ということになる。
1)適用という概念
・「適用」とは、施行された規範の効力を個別具体の事象に対して発動し、作用させることである。
2)会社に適用されることの意味
・会社とは場所や社屋等ではなく、会社という属性を持つ法人に対する属人主義的な適用を意味する。
3)運用対象が限定的にみえる社内規程
(1)組織関係規程
・社内規程の中には、適用の対象が役職員の一部に限定されているかのようにみえるものがある。
4)適用対象に関する明文の規定
・全ての社内規程は、会社とその構成員である役職員に適用されるべきものであるが、規程等管理規程などに規定を置き、明文化しておくことも有益である。
19 社内規程の効力が否定される場合とは
1)効力が否定される場合
・社内規程の効力が否定される事態というのは、相異なる社内規程の条項が互いに抵触している場合、どちらかの効力が否定される事態のことである。特に新規の社内規程の制定や現行の社内規程の改定によって新設された条項は注意すべきである。
20 社内規程の効力は子会社にも及ぶのか
・子会社の経営を適切に管理することは、親会社の重要な経営課題である。会社法では、子会社について「会社が議決権の過半数を有する株式会社その他の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」であると定義している。
実践編
第1章 社内規程の運営
1 社内規程の整備・運用はどのように行うべきか
・社内規程の管理には、個々の社内規程の管理と社内規程の全体統括という二つの側面がある。
1)個別管理と全体統括の概念
2)担当者の具体像
・個別管理の担当者は個々の社内規程を所管する部門の担当者のことである。一方、全体統括の方は、法務部や総務部において社内法務を一元的に統括する者が担当者になる。
3)担当者の役割
(1)個別管理
①現行の運用
②制定・改定の要否の検討
③立案作業の遂行
(2)全体統括
①規程集の整備
・全ての規程を収録した規程集を作成し、保管する。規程集は、関係者が常時閲覧できるようにするとともに、規程の制定・改廃があった場合には、これを速やかに反映させる。
②立案時における案文の審査
③制定・改廃の社内通知
2 社内規程の実効的な運用のために必要なことは何か
・社内規程の実効的運用とは、社内に浸透し励行されていることをいう。
1)浸透の難易度による社内規程の分類
・浸透の問題は規程を立案したものと、適用の対象となる者との距離が重要である。
2)規程を浸透させる必要性
・規程立案担当者及び運用責任者には、適用対象者が規程の意義を十分に認識し、その内容を理解できるように工夫する必要がある。
3)浸透させる努力と工夫
・分かりやすい資料(Q&Aも有効)を用意し、説明会を必要に応じて開催するなどの高い意識が必要である。
3 社内規程の立案について心掛けるべきことは何か
・社内規程の立案は、適時適切に行うよう心掛けなければならない。
1)「適時」について
・社内規程を立案すべき時期は、個々の規程の性格によって様々である。
2)「適切」について
・立案が適切であるための要件は、①規程の内容が規範として妥当なものであること、②規程の表記が規範として的確であること、③立案から施行に至る過程で所要の手続きを履行すること、である。
(1)内容の妥当性
①規定する措置の内容が立案の目的に照らして合理的なものであるか。
②立案する規程のレベルが内容の重要性に見合ったものになっているか。
③立案の内容が上位の規程に反していないか。
(2)表記の的確性
①規程の全体が適切に構成されているか(条文の配列など)。
②各条文が適切に構成されているか(条項の区切り、号の活用など)。
③条項の引用表現に誤りはないか。
④条項中の用事と用語が法令のルールに準拠しているか。
(3)適正手続きの履行
①立案開始時に余裕を持った日程を立てているか。
②関係部門との調整を早期に開始しているか。
③統括管理者(法務部など)による十分な審査を受けているか。
④規程の浸透に配意しているか(前広な周知、趣旨の説明など)。
4 社内規程の審査について心掛けるべきことは何か
1)審査の観点
・社内審査の目的は、立案された規程が内容において妥当であり、かつ、表記において的確であるかどうかを吟味し、問題点が発見された場合にはこれを是正することである。
2)審査担当者の心掛け
・審査の事務において、問題点を適確に発見し、是正する役割を果たすためには、①知見の涵養、②審査時間の確保、③支援する姿勢、④審査項目の共有、が大切である。
5 内部統制システムの関係者は社内規程にどう向き合うべきか
・会社の役職員は様々な立場から内部統制システムに関係している。他方、社内規程は、内部統制システムを構築し、運用するための法的な基盤となっており、組織、業務、人事、コンプライアンスという各分野の社内規程が、それぞれ内部統制システムの構成要素に対して定められている。
1)内部統制システムの概念
・内部統制システムという概念は、会社法の定めに由来するものである。具体的には、「会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」を意味する概念である。
2)内部統制システムの構成要素
①情報の保存及び管理に関する体制
②損失の危険の管理に関する体制
③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④監査役の監事が実効的に行われることを確保するための体制
第2章 立案の方式及び留意点
6 社内規程の制定、改定及び廃止はどのような方式で行なえばよいのか
・社内規程の制定、改定及び廃止を行う方式には、手続と様式の二つの側面がある。
1)手続き
・社内規程を制定、改定又は廃止するためには、各規程のレベルに応じて、決議又は決裁という手続を経る必要がある。規程のレベルというのは、社内規程全体の階層構造の中で個々の社内規程が位置している階層のことであり、上から順に規程、規則、細則、要領というレベルがある。
・社内規程の制定・改廃権者は各レベルに対応しており、規程は取締役会、規則は経営会議、細則は社長、要領は本部長とされており、会議での決裁や社長、本部長の決裁の手続きが必要になる。
2)様式
・様式は社内規程のレベルを問わず、制定、改定又は廃止のいずれかによって異なっている。
(1)制定
・新規に規程を制定する場合は、決議又は決裁を求める際に、制定の経緯や目的、規程案の骨子などを説明した後に、「次の規程を制定することとしたい。」と記載し、当該規程案を添付した書面を提出する。
(2)改定
・現行規程を改定する場合には、改定の経緯や趣旨を説明した文章に加えて、改定の具体的な内容を示すため、新旧対照表を作成して添付する必要がある。
(3)廃止
・社内規程を廃止する場合は、廃止の理由を説明するとともに、「○○規程を廃止することとしたい。」と記載した書面に廃止する規程を添付して、決議又は決裁を求める。
7 新規の規程を制定する場合、特に留意すべきことは何か
・立案上の留意点は、内容の妥当性、表記の的確性及び適正手続きの履行以外に、新規と改定にはそれぞれ固有の留意点がある。
・新規の規程を立案する場合には、①主管部門の適切な決定、②規程のレベルの適切な選択、③現行規程との関係に対する考慮の三点である。
1)主管部門の適切な決定
・立案の主管部門は、制定しようとする事項を担当している部門とするのが原則である。
2)規程のレベルの適切な選択
・規程集の最上位に来る「規程等管理規程」が作成されていれば、各レベルの規程で定めるべき事項の性質が規定されているので、その趣旨を踏まえ、制定する事項の内容とその重要度に応じた適切なレベルを選択しなければならない。これが新規制定の際に最も留意すべき点である。
・不適切なレベル選択は、「規程等管理規程」の趣旨に反するばかりでなく、社内のガバナンスを阻害することにもなるので、十分な注意が必要である。
3)現行規程との関係に対する考慮
・社内規程は規程事項の内容によって、組織、業務、人事、コンプライアンスという四つの分野に大別される。
・新規の規程といっても、現行の規程と全く無縁の存在ではなく、何らかの関係を持つ場合が少なくない。
・上位にある規程との関係だけでなく、同列の規程との関係にも留意する必要がある。
8 規程のレベル選択を間違いやすいのはなぜか
・規程等管理規程では、「重要な事項は上位の機関が決める」という思想に基づき、各レベルの規程に置いて規定すべき事項を次のように定めている。
・レベルの選択を間違えるというのは、上記のような対応関係を考慮せずに不適切なレベルの規程を選択してしまうことである。その中でも最も起こりやすい間違いは規程又は規則で規定すべき事項を細則又は要領で想定してしまうことである。このような間違いが起こる原因としては、次の三つが考えられる。
1)特定を定める規程のレベルに関する誤解
・一般的に、特例、特則は一般則と同じレベルでなければならない。この原理は法令も同様である。
2)規程の主管と規程のレベルとの混同
・レベルの選択は規程の内容とその重要度によって判断すべきである。その内容が各部門に関係し、全社的な統制の下で実施すべきものであれば、重要性を鑑みて、上位のレベルを選択するのが適切である。
3)手続きの簡便性に惹かれる担当者の心理
・規程のレベルが上がるほど関係者が多く、制定手続にも時間がかかるので、担当者は下位のレベルを選択しようとする意識が働き、規定事項の重要性を軽視したレベルの選択が行われやすくなる。
9 規程のレベル選択の間違いを是正する方法とは
・規定事項が全ての役職員に対して一定の義務を課し、又は一定の権利を与えるようなものであれば、規程又は規則というレベルを選択すべきであるが、立案担当者が何らかの事情により、要領という形式を選択し、施行してしまった場合には、早急に是正する必要がある。
1)レベルの是正が必要な理由
①規程等管理規程の趣旨に反する。
②社内統治(ガバナンス)の実効性が損なわれてしまう。
2)レベルの是正に必要な手続き
・規程の題名を変更することはできず、一旦「○○要領」を廃止し、同内容の「○○規程」を制定するという二つの手続きを踏む必要がある。
3)レベルの適正を確保する方策
・レベル選択の誤りの発見と是正には、法務に精通したものに検証を依頼する必要がある。
・レベルの選択の誤りを防止するには、法務担当者の研修や啓蒙活動の他、審査する体制の構築が求められる。
10 現行の規程を改定する場合、特に留意すべきことは何か
・改定には、字句の変更、条項の追加、条項の削除という三つの類型がある。
・主な留意点には、目的規定との関係、題名、章名等との関係、追加する条項の単位がある。
1)改定の三類型
2)目的規定との関係
・規程の第1条に目的規定がある。規程を改定する際には、改定した後の条項の内容と目的規定で定められている内容と整合していることを確認しなければならない。追加条項と整合するように現行規程の目的規定を改めるか、条項の追加ではなく、新規規程の制定という形式にする場合もある。
3)題名、章名等との関係
・目的の修正を要する追加改定を行う場合、題名が適切でなくなることもあるため相応しい題名に変更する。
・例えば、コンプライアンス組織規程に業務運営に関する条項を追加するような場合には、題名をコンプライアンス体制運営規程などと改正する必要がある。
4)追加する条項の単位
・条項の追加する際には、条として追加するか、項として追加するかを検討する必要がある。密接な関係にある場合は項として追加し、やや独立した関係にある場合は、別の条を建てて規定するのが適切である。
11 規程の立案に際して手続面で履行すべきことは何か
・規程の立案には幾つかの段階がある。
①立案の開始を決定した段階:全行程の想定
②案文を作成するまでの間:関係先との協議
③案文を作成した段階:審査部への持ち込み
④機関決定後、施行までの間:社内における周知
1)全行程の想定
・案文の作成から機関決定を経て施行に至るまで、どのような手続をどの時点で履行するかを検討し、全工程の予定を想定しておく。
2)関係先との協議
・必要に応じて関係先との協議は早めに進めた方が良い。
3)審査部への持ち込み
・立案者の案文の審査は余裕をもって依頼するよう心掛けたい。
4)社内における周知
・規程成立後、施行されるまでに社内への周知を迅速かつ十分に行うことが重要である。特に制定・改定の背景や趣旨を詳しく説明したり、特に関係が深い者を対象に説明会を開催するなど周知のための工夫や配慮が必要である。
第3章 規程全体の書き方
12 社内規程の構成は法律とどこが違うのか
・社内規程の構成というのは、社内規程の全体にどのような規程をどのような順序で配列するかという問題である。
1)共通点
①冒頭に題名を付ける。
②本則、附則の順に条文を規定する。
③本則には規程の目的に直結する本体的な事項を規定し、附則には付属的な事項を規定する。
④本則の条文が多数に及ぶ場合には、「章」、「節」などの区分を設ける。
⑤本則に章などの区分を設ける場合には、第1章は「総則」とし、目的、定義など、規程全体に関連する事項を規定する。
⑥附則の冒頭に、施行期日を定める規定を置く。
2)相違点
(1)罰則の有無
・罰則は法律にしか存在しない。
・社内規程の場合には、罰則という制裁がないので、就業規則の中に通常、「社内規程に違反する行為が懲戒処分の対象となる」旨を定める規定をおく。これが違反行為を抑止する役割を果たしている。
(2)制定権者を示す条文の有無
・本則の最後に必ず、制定・改廃権者が誰であるかを示す条文が置かれる。
13 社内規程の題名を付ける際に留意すべきことは何か
1)社内規程における題名の例
・社内規程の題名は、概ね簡潔である。
2)法律における題名の例
・法律の題名は、簡潔なものと長文のものがある。
3)「規程等管理規程」という題名について
・社内規程の階層や効力関係など、社内規程全般に及ぶ重要事項を定める通則法的な規程である。
14 社内規程の本則には条文をどのように配列すべきか
・社内規程に共通する基本原則
1)総則的な条文の配列順
・目的規定は、原則として、全ての規程の第1条として置かれる条文である。
2)実体的な条文の配列順
・条文の配列順序はケースバイケースであるが、その内容を性質別に分類できる場合には、その性質を手掛かりに配列する。
・行為の準則を定める規程であれば、規定対象の行為に関する条文を時系列で並べるのが適切である。
3)雑則的な条文の配列順
・雑則的な条文の中には、本則の最後の条として、各規程の改廃の権限・手続を定める条文である。
15 章の区分について留意すべきことは何か
1)章に区別すべき場合
・本則の条文が多数あり、条文の見出しを追うのも大変な場合には、章に区分した上で、目次を付すのが一般的である。
2)条文のグループ分け
・重要なことは同じ章には同質の条文だけを置く。
3)章名の付け方
・章名は内容を端的に表示したものでなければならない。
・章名は「組織」「運営」など、できるだけ簡潔な方が良い。
・雑則的な条文は、「雑則」「改廃」という章名が相応しく、「第○章 その他」のような章名は不適切である。
16 目次について留意すべきことは何か
・目次は題名と本則の間に置く。
1)目次を置くべき場合
・規程の本則が章に区分されている場合には、必ず目次を置くようにすべきである。
2)目次の体裁
・上記にあるように、各章の章名と、各章に属する条文の範囲を示す括弧書きを表記する。
3)目次のメンテナンス
・目次のある規程を改定する際には、改定による目次への影響に注意しなければならない。本則にある章名の変更や追加、削除を行う場合は、目次中の関係部分を全て改定しなければならない。
・条文の範囲が括弧書きで記載されているときは、改定後の本則の条名と整合するよう改定しなければならない。
17 社内規程の附則にはどのようなことを規定すればよいのか
・社内規程の附則は、通常、施行時期を規定する条文だけが記載されている。
1)「附則」という表記
・附則では、先ず、自らを「附則」と表記し、その後で次行から条文を書くことになっている。
2)制定・改定履歴の付記
・最終行に記載されている改定の年月日が、附則の条文に規定される施行時期となっている。
補足)“ひな型Rev1.0”のその後
”たたき台Rev0.1”を、何とか”ひな型Rev1.0”までブラッシュアップしましたが、その後、施行まで3つのアクションをとりました。
1.すでにお世話になっていた「埼玉県よろず支援拠点」の先生にご相談しご指摘を頂きました。
2.非営利型一般社団法人に精通されている、顧問税理士の先生にご確認頂きました。
3.浦和西高のOBでもある、顧問弁護士の先生に最終の確認をして頂きました。
以上、必要カ所の修正を行い、完成した正式版Rev1.0を一社UNSSの全メンバーに説明し、承認を受けめでたく施行となりました。(自分自身に「お疲れ様」といいたい)

『「埼玉県よろず支援拠点」は、経済産業省・中小企業庁が、全国47都道府県に設置する経営なんでも相談所です。
中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する方の売上拡大、経営改善など経営上のあらゆるお悩みの相談に無料で対応します。』
社内規程立案1
今まで、「プロジェクト計画書」、「非営利型一般社団法人」、「定款作成物語」というブログをアップしてきました。これらは我が母校である、埼玉県立浦和西高校サッカー部OB会を法人化するために必要なことでした。
法人化により法人口座をもち、契約できるようになりました。そして、任意団体は法人格の団体となり、社会的信用は確実に高まりました。
何故、法人化したのか、これはサッカー部のOBが主体となって、寄付を募り、その資金で土のグラウンドを人工芝のグラウンドに替えるためです。募金の目標金額は5,500万円です。
なお、法人成立は2022年8月、社名は「一般社団法人UNSS」、UNSSは「浦和西高スポーツサポーターズクラブ」の略称です。
一社(一般社団法人)の立ち上げは完了しましたが、会社のルールブックである定款を補完するための「運営管理規程」の整備が残っていました。この難題は、定款作成を進めてきた私の仕事になりました。これには違和感はないものの、今まで経験したこともなく、「これは、まいったな。大ピンチ!」というところです。
とりあえず、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』という法律をのぞいてみました。本則は全部で344条、一般財団法人の部分に加え、当面は不要と思われる条文もかなりありました。一方、ネットにあったさまざまな管理規程のサンプルを集めました。
この二つの方向から眺め、絞りに絞った条文を、誰がみても何とか意味が分かるような文章に修正しました。こうして、“雛形”とは言い難い、“たたき台rev0.1”は出来上がりました。
作ってはみたものの、運営管理規程策定のルールも作法もよく知らない者が作ったrev0.1のため、かなり怪しい出来上がりのような気がしました。
そこで、今更であり、順番は逆になりましたが、「やはり、少し勉強せねば」と考え、約160ページの『社内規程立案の手引き』という本を図書館から借りてきました。思いきって買ってしまいたかったのですが、定価2,400円の本は在庫がなく、中古本は5,000円以上と高額だったため、断念しました。
基礎編
第1章 社内規程の意義
1 社内規程とは何か
2 社内規程にはどのような種類があるのか
3 どの会社にも必要な社内規程とは
4 社内規程は誰のため、何のためにあるのか
5 社内規程は内部統制システムとどのような関係にあるのか
6 社内規程は法律とどのような関係にあるのか
第2章 社内規程の体系
7 社内規程の体系とは何か
8 社内規程の体系はどこで定められているのか
9 社内規程の体系はなぜ重要なのか
10 社内規程の体系が形骸化する事態とは
11 社内規程の体系と法体系の共通点と相違点は何か
第3章 社内規程の構造
12 社内規程の立案に当たって必要な構造的理解とは
13 社内規程は同列の社内規程とどのような関係にあるのか
14 社内規程は上下の社内規程とどのような関係にあるのか
15 個々の社内規程はどのように構成されているのか
16 社内規程の条文はどのように表記されているのか
第4章 社内規程の効力
17 社内規程の効力はいつから生じるのか
18 社内規程の効力は誰に対して生じるのか
19 社内規程の効力が否定される場合とは
20 社内規程の効力は子会社にも及ぶのかのか
実践編
第1章 社内規程の運営
1 社内規程の整備・運用はどのように行うべきか
2 社内規程の実効的な運用のために必要なことは何か
3 社内規程の立案について心掛けるべきことは何か
4 社内規程の審査について心掛けるべきことは何か
5 内部統制システムの関係者は社内規程にどう向き合うべきか
第2章 立案の方式及び留意点
6 社内規程の制定、改定及び廃止はどのような方式で行なえばよいのか
7 新規の規程を制定する場合、特に留意すべきことは何か
8 規程のレベル選択を間違いやすいのはなぜか
9 規程のレベル選択の間違いを是正する方法とは
10 現行の規程を改定する場合、特に留意すべきことは何か
11 規程の立案に際して手続面で履行すべきことは何か
第3章 規程全体の書き方
12 社内規程の構成は法律とどこが違うのか
13 社内規程の題名を付ける際に留意すべきことは何か
14 社内規程の本則には条文をどのように配列すべきか
15 章の区分について留意すべきことは何か
16 目次について留意すべきことは何か
17 社内規程の附則にはどのようなことを規定すればよいのか
第4章 条文の書き方
18 条文の書き方について一般的に留意すべきことは何か
19 条文に見出しを付ける際に留意すべきことは何か
20 枝番号の条文を置くことは許されるのか
21 条文に複数の項を置く場合に留意すべきことは何か
22 項中のただし書はどのように書けばよいのか
23 項中の後段にはどのようなものがあるのか
24 号の使用について留意すべきことは何か
25 表とはどのようなものか
26 別表とはどのようなものか
27 目的規定はどのように書けばよいのか
28 定義規定はどのように書けばよいのか
29 条項の引用はどのように書けばよいのか
30 他の条項にある事項を引用するときの書き方とは
31 条項の準用とは何か
32 条文を読みやすくするための工夫とは
第5章 用字
33 条文中の漢字の使用にはどのようなルールがあるのか
34 副詞や接続詞は漢字を使って書くのか
35 送り仮名の付け方にはどのようなルールがあるのか
36 句読点の使い方にはどのようなルールがあるのか
37 外来語を使うときに留意すべきことは何か
38 数字を使うときに留意すべきことは何か
39 括弧などの記号はどのようなときに使えばよいのか
第6章 用語
40 条文中の語句の使用について留意すべきことは何か
41 語句を並べるときはどのように表現するのか
42 「又は」「若しくは」は、どう使い分けるのか
43 「及び」「並びに」は、どう使い分けるのか
44 「その他」と「その他の」は、どう違うのか
45 「とする」は、どのような場合に使うのか
46 「による」は、どのような場合に使うのか
47 「ものとする」は、どのような場合に使うのか
48 「しなければならない」は、どのような場合に使うのか
49 「してはいけない」は、どのような場合に使うのか
50 「することはできない」は、どのような場合に使うのか
51 「することができる」は、どのような場合に使うのか
52 「要しない」「妨げない」は、どのような場合に使うのか
53 「置く」「行う」などで結語するのは、どのような場合か
54 「みなす」と「推定する」は、どう違うのか
55 「場合」「とき」は、どう使い分けるのか
56 「もの」には、どのような使い方があるのか
57 「含む」「除く」「限る」には、どのような使い方があるのか
58 「等」は、どのように使えばよいのか
59 「この」「その」「当該」は、どのように使えばよいのか
60 「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」は、どう違うのか
ブログは基礎編と実践編の第3章までです。
基礎編
第1章 社内規程の意義
1 社内規程とは何か
・「社内規程とは、社内で制定され、社内に適用される規定である。」
・個々の条項の定めを指すときは「規定」といい、一連の条項の総体としての定めを指すときは「規程」という。
1)制定と適用
・制定:権限のある機関が所定の手続きによって法令としての案文を確定し、これを法令として定立する行為。
・施行:制定された法令の規定の効力を一般的に発動し、作用させること。
・適用:施行された法令の規定の効力を個別具体の事象に対して発動し、作用させること。
2 社内規程にはどのような種類があるのか
1)分野別の種類
・定款と規程等管理規程は、会社経営や社内規程の全体をカバーする基本的な重要事項を規定するものであり、個別分野には限定されない「スーパー社内規程」なので、上記の分類表には入っていない。
2)階層別の種類
・定款-規程-規則-細則-要領
3 どの会社にも必要な社内規程とは
1)組織関係規定
・定款
・社内規程
2)人事関係規定
・人事関係の分野では、労働基準法の規定により、一定規模以上の会社は就業規則を作成しなければならないことになっている。
・労働法との関連では、育児・介護休業法や労働安全衛生法の規定を実施するため、社内の体制や手続を定める規定が必要となる。
3)コンプライアンス関係規定
・コンプライアンスの分野では、金融商品取引法や個人情報保護法などの規則法が定めている義務を社内で確実に履行するために、内部者取引防止規程、個人情報保護規程などの社内規程を制定することが必要になる。
4 社内規程は誰のため、何のためにあるのか
・社内規程は、会社と役職員のため、会社経営の適正を確保するためにある。
1)総体としての社内規程の意義
(1)社内規程は誰のためにあるのか
・社内規程は会社と役職員のためにある。
・「役職員のためにある」とは、会社の業務を担う役員と職員が社内規程によって責任と権能を与えられていることを意味する。
(2)社内規程は何のためにあるのか
・社内規程は、会社経営の適正を確保するためにある。
・「会社経営の適正」というのは、会社の経営が会社法、労働法、金融商品取引法などの関係法に従って適正に行われる。ということを意味している。
・会社が関係法の適正な履行を確保するためには、関係法の受け皿としての内規を制定し、法的基盤を構築する必要がある。社内規程は、そのような内規の役割を担っている。
2)個々の社内規程の意義
(1)組織関係規程
①取締役会規程と経営会議規程
・役員を適用対象とし、会の運営を適切に行うための準則、指針としての意義を持っている。
②組織規程
・会社全体と各組織の構成員を適用対象とし、会社業務の責任分担と効率的な業務運営の体制を確立する意義を持っている。
(2)人事関係規程
①就業規則と給与規則
②育児・介護休業規則
(3)業務関係規程:経理規程、情報システム管理規程、営業管理規程
(4)コンプライアンス関係規程
①内部者取引防止規程、会社情報開示規程、個人情報保護規程
②内部通報規程
5 社内規程は内部統制システムとどのような関係にあるのか
1)内部統制システムという概念
・内部統制システムという概念は、会社法の定めに由来するものである。
・「会社の業務の適正を確保するために必要な体制」
2)内部統制システムに関する法令の規定
・会社法では、内部統制システムについて、取締役会が自ら決定しなければならない事項であると定めている。
3)社内規程と内部統制システムとの関係
・会社はこのような法令の趣旨を踏まえ、組織、人事、業務、コンプライアンスの各分野で、適切な関係規程を制定し、運用することが求められる。会社の社内規程は、内部統制システムがどのように整備されているかという姿を映し出す鏡であるといっても過言ではない。
6 社内規程は法律とどのような関係にあるのか
1)法律の規定に由来する社内規程
(1)制定義務の履行
・社内規程の中には、法律によって制定が義務付けられているものがある。代表的なものは以下の通り。
-規程名:定款
-根拠条文:会社法第26条
(2)法定機関の設置
・組織関係規程の中には、法律が定める機関を設置するために必要なものがある。
(3)法制度の確実な履行
・人事やコンプライアンス関係規程の中には、法律が定める制度を確実に履行するために必要なものがある。代表的なものは以下の通り。
-制度名:個人情報保護制度
-根拠法:個人情報保護法
-規程名:個人情報保護規程
2)法律に準拠した表記
・社内規程は、成分の規範である点で法律と共通しているので、その表記も基本的には法律における表記のルールに準拠している。
(1)基本構造
①規程の全体は、題名、本則、附則という要素で構成する。
②本則には、総則的な条文、実体的な条文、雑則的な条文という順序で条文を配列する。
(2)条文表記
①各条文には、第1条から順次、「第○条」という条名を表記する。
②各条文には、冒頭に括弧書きで見出しを付ける。
③文章としての条文は、必要に応じて、「項」に分ける。
④条文の文章は、法令用語を適切に使って、規範らしく書く。
第2章 社内規程の体系
7 社内規程の体系とは何か
・社内規程は全体として統一的な秩序を保持するよう、上下の階層構造が設定され、上位の規程が下位の規程に優先するという原理が定められている。
1)上下の階層構造とは
(1)階層構造の全体像
・規程の名称:定款-規程-規則-細則-要領
(2)階層構造の基本思想
・「より重要な事項は、より権限の大きい機関が決定すべきである。」という思想に基づくものである。
2)上位規程優先の原理とは
・上位にある社内規程は常に下位の社内規程に優先する効力をもつよう定められている。
3)社内規程の秩序との関係
・社内規程の体系は、社内規程の秩序を保持する重要な仕組みとなっており、立案関係者に対する警告としての意義も持っている。
8 社内規程の体系はどこで定められているのか
・社内規程の体系は、「規程等管理規程」という題名の規程によって定められており、定款を除けば最も上位の階層に位置する。
1)「社内規程の体系」に直接関係する規定
(1)社内規程の種類
①定款
②規程
③規則
④細則
⑤要領
2)その他の規定
・規程等管理規程では、社内規程の管理運用に関し、法務を司る部署が規程集を整備する責任を負うとされている。
3)法体系を定める法令
・法令にも、憲法、法律、政令、省令という上下の階層構造と上位法令優先の原理を骨子とする法体系があるが、規程等管理規程に相当する法令は、今のところ存在しない。
9 社内規程の体系はなぜ重要なのか
1)社内規程の体系
・社内規程は上下の階層構造から成り立っており、下位の規程が上位の規程を覆すことは許されない。
2)企業経営の規律
・企業経営の規律には、経営に対する規律と経営における規律という二つの概念がある。
3)社内規程の体系の役割
(1)経営に対する規律との関係
・社内規程の体系が定款を最上位の規程としていることは、経営に対する規律を保証する役割を果たしている。
(2)経営における規律との関係
・社内規程の体系では取締役会を制定・改廃権者とする規程が定款の次に位置づけられていることが重要である。
・取締役会は次に掲げる株式会社の場合においては設置しなければならない。
-公開会社
-監査役会設置会社
-監査等委員会設置会社
-指名委員会等設置会社
10 社内規程の体系が形骸化する事態とは
・社内規程の全体を規律する「規程等管理規程」の下位になる個々の社内規程は、それぞれの規程事項を所管する各部局の担当者によって立案され、運用される仕組みになっている。このため担当者によって尊守する意識にばらつきがあるため、「社内規程の体系」が形骸化するリスクがある。
1)形骸化する事態
・形骸化とは、本来上位の規程が定めるべき事項を下位の規程が定め、これを事実上施行してしまうことである。
2)形骸化する原因
・担当部署以外からの是正する力が働かないと、形骸化するリスクは避けされない。
3)是正策
・上位の規程に対し、全てが規程に反している場合は廃止、一部の場合は当該条項を削除する。
4)予防策
・社内規程の立案に携わる者が日頃から社内規程の体系について十分に認識することができるように定期的に研修等を行う必要がある。
11 社内規程の体系と法体系の共通点と相違点は何か
・社内規程と法体系の共通点と相違点を理解しておくことは有用である。
1)共通点
(1)階層構造の存在
・個々の規範は全て階層構造に置かれている。
(2)上位規範優先の原理
・上位にある規範が常に下位の規範に優先する効力をもつ。
2)相違点
(1)体系を定めた包括的な規範
・社内規程の体系には定款に続く、規程管理規程があるが、法令には存在しない。
(2)下位の規範の独自性
・下位の規程は内容が上位の規程に反しない限り、上位の規程からの委任は必要とせず、制定することができる。一方、政令、省令(行政立法)は、法律を補完する必要がある場合のみ制定される。
(3)規範の効力を裁定する機関
・下位の法令の条項が上位の法令に違反した場合、裁判所が裁定するが、社内規程では裁定するような機関は存在しない。
第3章 社内規程の構造
12 社内規程の立案に当たって必要な構造的理解とは
1)社内規程には、社内規程全体の基調となる構造と、個々の社内規程の条文に関する構造がある。
(1)社内規程全体の基調となる構造(=マクロ的な構造)
①事項の分担を基調とした構造(=横の構造)
・社内規程は、組織、人事、業務、コンプライアンスの各分野における規程事項を互いに分類している。
②上下の序列を基調とした構造(=縦の構造)
・社内規程は、「重要なことは上位の機関が決める」という理念に基づき、階層構造を有する。
(2)個々の社内規程の条文に関する構造(=ミクロ的な構造)
①規程全体の条文配列に関する構造
・各規程は、題名、本則、附則という要素で構成され、本則には一定の順序で条文が配列される。
②各条文の表記に関する構造
・各条文は、見出し、条名、項などの要素で構成され、条項の文章は、法令用語を用いて、「条文らしく」表記される。
2)構造と立案の関係
・規程立案には次のような点を考慮する必要がある。
(1)規程を立案する場合、同じ分野にある現行社内規程と規定事項を適切に分担するには、新規制定、追加改定のうち、いずれの形式にすべきか。
(2)規程を新規に制定する場合、条文をどのように配列すべきか。
(3)規程を新規に制定する場合、条文をどのように配列すべきか。また、条文を追加する改定を行う場合、本則のどこに追加するのが適切か。
(4)条文を作成する場合、見出しの表現、条項の分け方、文章中の用語などをどのようにすれば「条文らしい」表記となるか。
13 社内規程は同列の社内規程とどのような関係にあるのか
1)組織関係の規程
・取締役会を掲げる株式会社においては、取締役会を制定権者とする同列の規程として、組織規程、職務権限規程、及び取締役会規程という規程がある。
2)人事関係の規則
・具体例として、就業規則、給与規則、退職手当規則などがある。これらは、いずれも経営会議が制定権者となっている同列の規程である。
14 社内規程は上下の社内規程とどのような関係にあるのか
・階層構造は「重要なことは上位の機関が決める」という思想に基づくものである。
1)組織関係規程
・会社にどのような組織を置き、職務権限をどのように配分するかということは、会社の基本的な経営体制に関わる最重要事項である。組織と職務権限はそれぞれが等しく重要と考えられるので、その基本を「組織規程」と「職務権限規程」で先ず定めることが必要になる。
2)人事関係規程
・従業員の就業条件に関する重要事項は、労働基準法に基づき就業規則で定めなければならない。
15 個々の社内規程はどのように構成されているのか
・個々の社内規程は、冒頭から末尾まで、題名、本則、附則などの要素で構成されている。このうち最も重要な要素は本則であり、条文を本則にどのように配列するかは、立案事務の基礎として重要である。
1)社内規程の構成要素
(1)題名
・「組織規則」、「就業規則」など。
(2)目次
・社内規程の本則が章に区分されている場合には、題名と本則の間に、章の名称を示す目次が置かれることがある。
(3)本則
・規程の本体となる部分。第1条には規程の目的が、最終条には規程の制定権者が示される。
(4)附則
・規程の本体付属する部分が「附則」として、本則の次に表示される。
・附則には、最終の改定が施行される年月日を示す条文が置かれる。
(5)履歴
・附則の次に、規程の制定と改定が施行された年月日が表示される。
(6)別表
・規程の中には、複雑な内容を分かりやすく示すために、本来は本則で規定すべき事項の一部分を末尾に別表として示すものがある。
2)本則への条文の配列
(1)条文全体の配列
・条文全体をその性格によって、総則的な条文、実体的な条文、雑則的な条文の三種類に分け、この順に配列する。
(2)総則的な条文の配列
・総則的な条文とは、規程全体に関わる事項を定める条文である。第1条は目的規定とし、以下、必要があれば定義規定などの条文を配列する。
(3)実体的な条文の配列
・実体的な条文とは、規程の中核となる具体的な事項を定める条文である。その配列順は、規定する事項の内容次第である。以下は一応の目安である。
①組織や権限を定める規程であれば重要性の順
②一連の手続きや業務処理を定める規程であれば行為の時系列順
(4)雑則的な条文の配列
・雑則的な条文とは、手続や細則などの事項を定める条文である。本則の最後には制定・改廃の権限と手続を定める条文を置き、他の雑則的な規定が必要であれば、その直前に配列する。
16 社内規程の条文はどのように表記されているのか
1)条文の構成要素
・見出しは第1行目に括弧書きである。
・条名は第2行目の冒頭に「第5条」という表記になる。
・この条文では二つあり、二番目の項の冒頭に「2」という項番号が付されている。
2)条文らしい表現
・条文は法令用語が適切に使われることによって、規範の内容が「条文らしく」なる。
・表現で最も重要なのは文章末尾の表現である。
・代表的な末尾の表現には次のようなものがある。
(1)「……とする。」
(2)「……による。」
(3)「……しなければならない。」「……することができる。」
黄金の華の秘密
ブログで取り上げた 『ユングと共時性』に、次のようなことが書かれていました。

リヒャルト・ヴィルヘルムが翻訳した中国の錬金術の本が「黄金の華の秘密」である。ユングがこの本に払った苦心は、主要な心理学的概念を発展させるための重要な源となっている。特に、ユングが「共時性」を初めて公に使ったのが、1930年のリヒャルト・ヴィルヘルムの葬儀での賛辞の中であったことはとても意義深い。
ユングにとって、リヒアルト・ヴィルヘルムによって翻訳されたこの『黄金の華の秘密』はとても重要な出会いでした。
今まで何度も、「まぁ、何とかなるだろう」と思って身分不相応の本を何冊も買ってきたのですが、今回の本もほとんど歯が立ちませんでした。
ただ、立ち向かった足跡だけでも残したいものだと思い、印象に残った部分とC・G・ユングにとって、人生最大級の出会いとなった、リヒアルト・ヴィルヘルムについて書き残すことにしました。
目次
第二版のための序文……C・G・ユング
第五版のための序文……ザロメ・ヴィルヘルム
リヒアルト・ヴィルヘルムを記念して……C・G・ユング
ヨーロッパの読者のための註解……C・G・ユング
序論
基礎概念
対象からの意識の離脱
完成
結論
ヨーロッパのマンダラの例……C・G・ユング
太乙金華宗旨の由来と内容……リヒアルト・ヴィルヘルム
一 本書の由来
ニ 本書の心理学的・宇宙論的前提
太乙金華宗旨
第一章 天心
第二章 元神・識神
第三章 回光守中
第四章 回光調息
第五章 回光差謬
第六章 回光微験
第七章 回光活法
第八章 逍遥訣
第九章 百日立基
第十章 性光識光
第十一章 ○離交媾
第十二章 周天
第十三章 勧世歌
慧命経
一 漏尽
ニ 六候
三 任脈と督脈
四 道胎
五 出胎
六 化身
七 面壁
八 虚空粉粋
訳者解説
1 ユングとヴィルヘルムの出会い
2 太乙金華宗旨と呂祖師
3 思想的内容と心理学的視点
4 本書の内容と邦訳について
第二版のための序文 C・G・ユング
●リヒアルト・ヴィルヘルムは1928年、C・G・ユングに『黄金の華の秘密』のテキストを送った。C・G・ユングは1913年から集合的無意識の諸過程について研究を進めていたが、15年間の努力の成果は比較可能な手掛かりが掴めず、不安定な状態にあった。その状態から抜け出せたのは『黄金の華の秘密』の中にグノーシス主義者たちの中に求めても得られなかった部分を含んでいたからである。そして、本書はC・G・ユングの研究に正しい方向づけを与えた。
第五版のための序文 ザロメ・ヴィルヘルム
●1926年、リヒアルト・ヴィルヘルムは次のような短い序文を書いている。
『「慧命経―意識と生命の書―は、1794年に柳華陽が著した書物である。この本は「黄金の華の秘密」と合本にして千部刊行された。
この著作は仏教的瞑想法と道教的瞑想法をまじえたものである。この書の基本的見解によれば、生命が生まれるとき、心は、意識と無意識という二つの領域に分かれる。意識とは人間において個人化され、分離された要素であり、無意識とは、彼を宇宙に結びつける要素である。この書の基本原理は、瞑想を通じて二つの要素を結びつけるところにある。無意識は、意識がその中に沈潜してゆくことによって、その内容をゆたかにされねばならない。瞑想によって無意識の活動は活潑となり、意識領域まで昇る。こうして豊かな内容をもつに至った意識とともに、心は、再生するという形をとって、超個人的な魂の領域へと入ってゆく。この魂の再生は、やがて意識作用の内面的分化発展へとみちびき、自由自在な思考の状態にまで至る。しかし、さらに瞑想が深まってその終極に至ると、必然的に、すべての差別が消滅した究極的無差別の中にある大いなる一つの生命に解消していくのである」。』
ヨーロッパの読者のための註解
序論
現代心理学が理解を可能にする
●『人間の身体があらゆる人種的相違をこえて共通の解剖学的構造を示すのと同じように、魂(プシケ)というものも、あらゆる文化と意識形態の相違の彼方に共通の低層を有しているものであって、私はそれを集合的無意識と名づけたのである。この無意識の魂は、意識化され得る内容から成り立っているものではなく、ある種の同一の反応へと向う潜在的な素質から成り立っているのである。集合的無意識という事実は、あらゆる人種の相違を超えて脳の構造が同一であるということの心的な表現なのである。そこから、さまざまな神話のモティーフや象徴の間に見出される類似性あるいは同一性、さらには人間の相互理解の可能性一般が同一性を示すという事実も、説明がつくようになるのである。心の発展のさまざまな方向は、一つの共通な根底から出発しているものであって、その根は、あらゆる過去の発達段階にまで達している。そこには動物との心的類似さえ存在しているのである。
純粋に心理学的にみれば、ここでは、表象(想像)し行動する本能における共通性が問題なのである。あらゆる意識的表象と行動とは、この無意識的範例の上に発達してきたものであって、いつもそれと関連しあっている。特に、意識がまだあまり高い明晰さにまで達していない場合、言いかえれば、意識がそのすべての作用において意識された意志よりもむしろ衝動に、まだ理性的な判断よりも感情によって動かされている場合がそうである。この状態は、原始的な心の健康を保証しているものであるが、しかしそれは、より高い道徳的行為を必要とするような状況が現われてくると、たちまち適応性を欠いたものになる。本能というものは、全体としていつも同じ自然状態のうちに埋めこまれている個体にとってしか、十分役に立つものではない。したがって、意識的選択よりも無意識的なものに依存する個人は、断乎たる心的保守主義に向う傾向がある。原始人の考え方が何千年にもわたって変化せず、あらゆる見なれないものや異常なものに対して恐れを感じる理由もそこにあるのである。場合によっては、彼らは不適応状態にみちびかれたり、それによって重大な精神的危機、つまり一種のノイローゼにおちいったりするかもしれない。異質なものをドウかすることによってのみ生じてくる、より高度の、またより広い意識は、自律的態度へと向い、古き神々に対する反抗へみちびく傾向もある。古き神々とは、それまで意識を本能への依存状態に止めた強力な無意識的範例に他ならないのである。』
基礎概念
道の諸現象
アニムスとアニマ
私事ですが、約30年前にC・G・ユングの夫人であるE・ユング(エンマ・ユング)の著書である『内なる異性 -アニムスとアニマ-』という本を読んだことがありました。
一方、同書に書かれた「アニムスとアニマ」は冒頭、“魂”と“魄”について書かれており、これは「どういうことなんだろー」と大変興味を持ちました。

この本の裏表紙には次のような紹介がされていました。(一部)
『著者(C・G・ユング夫人)は、夢や神話、民話、文学作品等にあらわれたアニムスとアニマの典型的な形姿を研究することから、男性の本質、女性の本質を浮彫りにする。そしてこれら内なる異性を認識・承認し、人格全体の中へ組み入れることこそ、自己実現にとって不可欠の、また現代人にとって緊急の課題であることを指摘する。』
●『この書によれば、無意識の諸形態には、神々ばかりでなく、アニムスとアニマも見出される。ヴィルヘルムは「魂」Hunという言葉をアニムスと訳している。実際、私が用いているアニムスという概念は「魂」にぴったり適合している。その字形は「雲」をあらわす字〔云〕と「悪魔」をあらわす字〔鬼〕から構成されている。つまり魂は、雲のようなデモン、高いところで息吹する雲というような意味であり、「陽」の原理に属しているから男性的なものである。死後、「魂」は天に昇って「神」つまり「みずから拡大して示現する」霊、または神となる。これに対して「魄」は「白さ」をあらわす字〔白〕と「悪魔」をあらわす字〔鬼〕で示されている。「魄」はアニマである。それは「白い幽霊」であり、地上的な身体にともなう霊であって、「陰」の原理に属している。したがってそれは女性的である。死後、「魄」は下方へ沈み、「鬼」すなわち「(大地へと)帰る者」、いわゆる亡霊あるいは幽霊になる。このようにアニマとアニムスが死後分離してばらばらになってしまうということは、中国人の意識にとって、両者がさまざまの作用をもつものとして、互いにはっきり区別できる心的要因であったことを示している。』
●『ヴィルヘルムがこの書物のことを知らせてくれる何年も前から、私は、「アニマ」という概念に含まれた形而上的仮定は別にして、この概念を、中国語の定義と全く類似した形で使っていた。心理学者にとって、アニマは何も超越的なものでなく、全く経験可能な実体である。というのは、中国語の定義もはっきり示しているように、情動的状態は直接的な経験なのであるから。しかしこの場合、なぜ人は、アニマ〔という人格化された像〕について語って、気分については語らないのだろうか。その理由は次のような点にある。情動作用は、範囲を限定できる意識内容、つまり人格の一部である。それらは人格の一部であるので、当然、人格的特徴をもっている。したがってそれは容易に人格化され得るのである。先にあげた例が示しているように、それは今日もなお進行している過程なのである。情動をかき立てられた個人は、中立的になることができず、ふだんの性格とは全くちがった、一定のはっきりした性質を示すようになる。その意味で、〔情動作用を〕人格化することは、無意味なつくりごとではないのである。この場合、慎重にしらべてみると、男性では、情動的性質が女性的特徴を示すことが明らかになる。「魄」についての中国人の教えは、私のアニマについての理解と同様に、こういう心理学的事実に属している。深い内省や恍惚の体験は、〔男性の〕無意識領域に女性的な形姿が実在していることを明らかにする。したがって「心」には、〔昔から〕アニマ、プシケ、ゼーレといった女性名詞が用いられているのである。アニマは、男性が女性に関してもつあらゆる経験からつくり出されたイメージ、ないし元型、あるいは沈殿物である。と定義することもできるだろう。したがってアニマ像は、きまって〔現実の〕女性に投影される。』
●『一般的にいえば、私はアニマを無意識の人格化と定義した。したがってアニマは、無意識〔領域〕への橋渡し、つまり無意識に対する関係の機能としてとらえられる。こう考えた場合、われわれの書物の考え方は興味がある。この書は、意識(すなわち個人的意識)はアニマ〔魄〕から出てくるものと考えている。西洋的精神は意識の立場からしか考えないので、アニマを定義する場合には、私がこれまでやってきたような〔アニマをかくれた無意識の作用と解する〕やり方で、解釈しなくてはならない。ところが東洋は逆に、まず無意識の立場に立って考えるので、意識とはアニマのはたらき〔の産物〕であると見なしているのである! たしかに〔東洋が考えているように〕、意識は元来無意識から生じるものである。われわれ〔西洋人〕は無意識についてはほとんど考えようとしないので、「心(プシケ)」を一般に「意識」と定義したり、そこまでゆかなくても、無意識は意識の派生物か、それに従属する作用であるといつも考えようとする(たとえばフロイトの抑圧説)。しかし上にのべてきた理由からいっても、無意識の現実的作用を取り去ることはできないし、また無意識から現われてくる形姿は、そこに作用している〔心のエネルギーの〕量と考えるべきである。』
訳者解説 湯浅泰雄
ユングとヴィルヘルムの出会い
●『ヴィルヘルムは、1873年〔明治六年〕5月10日に南ドイツのシュツットガルトに生まれた。ユングより二歳の年長である。リヒアルトは1891年から95年までテュービンゲン大学で神学を学び、97年にプロテスタント教会の副牧師になった。1899年、ザロメ・ブルームハルトと婚約し、翌年結婚した。
1898年、ドイツは、清国から山東省膠州湾の租借権を得た。この帝政ドイツの中国進出政策が、はからずもヴィルヘルムを中国に結びつける機縁となる。翌1899年、26歳の青年ヴィルヘルムは、膠州湾に臨む青島の町に設立された教会の主任司祭として赴任する。以後、前後二十五年にわたる彼の中国生活が始まるのである。この時代は世界列強の東アジア進出の時期に当たっており、ヴィルヘルムが中国で暮らしていた間に、日清戦争、義和団事件(拳匪の乱)、日露戦争、辛亥革命、そして第一次世界大戦が起こっている。しかしヴィルヘルムの若い魂をひきつけたのは、動乱と革命にゆれ動くアジアではなく、古い東洋の精神世界であった。彼は、1909年に設立された徳華専門学校の教団に立って中国人子弟の教育に当たるかたわら、熱心に論語、老子その他の古典の翻訳に没頭した。ユングの思い出によると、あるときヴィルヘルムはユングに向かって、「自分は中国に居る間、ただ一人の中国人も洗礼しなかったが、そのことを大いに満足に思っているのです」と語ったという。彼が通常の宣教師タイプとちがって、深く中国文化に魅了されていたことがわかる。ヴィルヘルムは、近代中国の知識人が西洋文明の影響を受けて今や捨て去ろうとしていた儒教と道教の世界に沈潜して行ったのである。1911年、辛亥革命によって清朝は滅亡し、孫文が臨時大統領となったが、翌年、中華民国の発足とともに袁世凱が初代大統領となり、軍閥内戦の時代に突入する。このころヴィルヘルムは、1913年に、青島の儒教教会を設立している。しかし、1914年、第一次世界大戦の勃発とともに膠州湾は日本軍に占領された。大戦終了後の1920年、彼は二十二年にわたる中国での生活を終わって敗戦の故国に帰る。この年、ヘルツマン・カイゼルリング伯はダルムシュタットに、「叡智の学校」を設立した。ユングと出会ったのは、この会合の席である。1922年には、ユングに招かれてチューリヒの心理学クラブで易について講義している。
同じ1922年、ヴィルヘルムは北京のドイツ公使館の学術顧問に任命され、再び中国に赴く。二度目の中国滞在は足かけ三年、1924年までである。この間、1923年には、北京大学の教授に迎えられている。このころ彼は、労乃宣(ラウ・ナイ・シュアン)という道士の弟子になって、易を学ぶ。くわしい注釈つきの「易経」1 Ging、2 Bamde、1924 の名訳は、この老師の協力を得て出版されたものである。「最後のページの翻訳がすんで、印刷屋の最初の校正刷が来たとき、老師労乃宣は死んだ。それはあたかも、彼が自分の仕事を仕上げ、古い死滅しつつあった中国の最後のメッセージをヨーロッパに伝え終わったかのようであった。ヴィルヘルムは、この比類なき腎人の大きな夢をかなえたのであった。」1924年、任を終えて帰国したヴィルヘルムは、フランクフルト大学に設立された中国学講座の担当者となり、中国研究所を設立、その所長に就任した。機関誌は「中国学芸雑誌」Chinesishe Blatter fur Wissenschaft und Kunst(のちにSinicaと改名)という。しかし、彼の故国での活動の時間は短く、六年後の1930年3月1日、テュービンゲンで死去する。五十七歳であった。彼の業績は古典の翻訳が多いので、日本の中国学界ではあまり知られていないようであるが、彼はドイツの中国学の開創者ともいうべき人物であろう。
ユングはヴィルヘルムとはじめて会ったとき、つよい印象を受けたようである。「私が会ったとき、ヴィルヘルムは書き方やしゃべり方と同様に、外面的な態度も完全に中国人のように見えた。東洋的なものの見方と古代中国文化が、頭の先から足の先までしみこんでいた」と、ユングは当時の思い出を語っている。易経の独訳が出たとき、ユングは早速それを入手し、ヴィルヘルムの解釈に満足を覚える。「われわれは、中国の哲学と宗教についてたくさん話しあった。中国人の心性についての豊富な知識の中から彼が私に語ったことは、ヨーロッパ人の無意識が私に提起していた最も困難な問題のいくつかを解明してくれた。他方、無意識に関する私の研究の結果について、私が言わねばならなかった事柄は、彼には何の驚きも引き起こさなかった。というのは、彼が中国の哲学的伝統の占有物と考えていた事柄を、それらの中に認めたからである。」こうしてユングは、かつてグノーシス主義の研究に求めて得られなかった自己の学問的足場が、東洋思想の伝統の中に古くから伝えられていたことを感じるに至るのである。
1928年、ユングは、イメージが浮かんでくるのに任せて一つのマンダラを描いていた。できあがった形を眺めながら彼は、どうしてこのマンダラはこうも中国風なのだろう、と自問した。表面的にはそうもみえなかったが、そのように感じられてしかたがなかった。それから間もなく、ヴィルヘルムからユングの許へ「黄金の華の秘密」の独訳原稿が送られてきた。それには、ユングに対して心理学者として註解を書いてほしいという手紙がそえられていた。原稿をよんだユングは、深いおどろきにうたれる。マンダラのイメージについて彼が模索しつつあった考え方に対して、そこに思いがけない確証が与えられていたからである。「これは私の孤独を破った最初の出来事だった」と彼はのべている。「『黄金の華の秘密』という本を読んだ後に、やっと錬金術の性質の上に光がさし始めた。……私は錬金術の原典をもっとくわしく知りたいという望みにかき立てられた。私はミュンヘンの本屋に、錬金術の本を手に入れることができるものは、皆知らせるように言った。」ユングはこの深いおどろきを記念して、自分の描いた中国風のマンダラの下に「1928年、この黄金色の固く守られた城の絵を描いていたとき、フランクフルトのリヒアルト・ヴィルヘルムが、黄色い城、不死の身体の根源についての、一千年前の中国の本を送ってきてくれた」と書き記した。本書はこうして、翌1929年に出版されたのであった。
以上のように、この書は、ユングが彼自身の理論的また思想的立場を確立する機縁を与えた書物である。この書によって彼はまた、ヨーロッパの精神史に対する彼の基本的見解を確立するに至る。古代ローマのグノーシス主義と近代ヨーロッパを結ぶ失われた環が中世錬金術の中にあることに、彼は気づいたのである。西洋精神史に関する彼の最初の著作「心理学と錬金術(1944年)は、これが機縁になって生まれたものである。この書の中で、彼はこう回顧している。「私はマンダラ象徴の生成過程とその像について、二十年来、私自身の経験から得たたくさんの材料に即して観察をつづけてきた。(はじめの)十四年間、私は、自分の観察について先入見を下さないために、それについて執筆も講演もしなかった。しかし、1929年にリヒアルト・ヴィルヘルムが、「黄金の華」のテキストを私にみせてくれたとき、私は研究結果の一部を公表する決心をしたのだった。」このように、本書はユングの思想形成にとって重要な意義をもつ書物であり、したがってまた、深層心理学の観点から東洋思想について考える場合、よい手がかりを与える書物でもある。』
※シュツットガルト
リヒアルト・ヴィルヘルムが生まれた南ドイツのシュツットガルトは、私にとって思い出の地です。
また、シュツットガルトといえば、ドイツブンデスリーガの1部に所属する名門チームがあります。浦和レッズに在籍していたギド・ブッフバルトや日本人選手では、岡崎慎司、長谷部誠、今は遠藤航がキャプテンとして活躍しています。

画像出展:「au Webポータル」
11月23日のサッカーワールドカップ カタール大会の初戦、強豪ドイツを2-1で撃破し、歴史的な逆転勝利となりましたが、遠藤 航 選手のチームへの貢献は素晴らしいものでした。
確認したところ、遠藤選手が浦和レッズに在籍していたのは2016-2018年でした。
そのシュツットガルトは、私の初めての海外出張先でした。
最初の営業はCADという設計支援ソフト(ME10)を販売する部門だったのですが、そのソフトの開発・製造拠点がシュツットガルトのボブリンゲンという町にありました。なお、ME10という2次元CADは、調べてみたところ、CoCreate社を経て2007年にPTCに買収されCreoという製品群の一部になっていました。
出張は新製品の研修がメインだったのですが、ご褒美旅行も兼ねていました。これは日本だけでなく、世界的に業績が好調だったためです。そして、その研修会はモナコで行われました。モナコといえば、高級リゾート地であり、F1のモナコグランプリは特に有名です。我々が宿泊したホテルはローズ・モンテカルロ(現在はフェアモント・モンテカルロ)です。ローズ・ヘアピンとして有名ですが、このホテルに泊まれたのは灌漑深いものがありました。

画像出展:「英語日常会話マスターブログ」
そして、開発・製造拠点のシュツットガルトはモナコの後に訪問しました。シュツットガルトにはメルセデスベンツ・ミュージアムがあります。小さな町のボブリンゲンは明るく綺麗な素敵な町で、とても穏やかな気持ちになりました。
ユングと共時性2
Ⅸ 共時性の働き
●『共時性原理は、非常に多様な事象のなかに表出されていることがわかる。たとえば、ある人が、夢あるいは一連の夢を見、そしてそれが、外的事象と符号することがわかる。ある個人が、何か特定の願いをするか、あるいは、それを、強く望み、希望するかしており、そして、何か説明不可能な方法でそれが起こる。ある人が、他の人、あるいは何か特殊な象徴を信じており、その人がその信仰のもとで祈るか黙想するかしているときに、身体的な治療あるいは他の「奇跡」が起こる。人間のいるところにはどこでも共時的事象が起こるのである。そして、実のところ、ひとたび見つけるべきものを知ったならば、その数は、これまで予想されてきたものよりはるかに大きいことに気づくことになろう。
すべてのこうした事象のなかでは、強い元型的要因が、ヌミノース[事象には説明し難い部分が存在する。神への信仰心、超自然現象、聖なるもの、先験的なものに触れることで沸き起こる感情]な方法で働いている。意識が利用できるものを越えた知識を与えうる夢は、必然的に、心の深層にあるイメージを含んでいる。願望の力への信仰は、人間の原始的な心の奥深くに達する。それは、魔術師の原初的イメージの効力を説明する鍵である。信仰の根本的な体験は、その形や対象がどのようであっても、常に、無意識の最深レベルに達するものである。このために、情動的な強さがヌミノースで元型的な要因のまわりに生じ、その結果、それに相応するエネルギーの退潮、すなわち、心の他の部分での心的水準の低下が生じる。これが、心が時間のパターンを反映するようにする「低下」の心理学的メカニズムである。これを認識することによって、個人は共時的事象と関係をもつことができる。』
●『ユングは、自分の経験として次のように述べている。超心理的事象は、「ほとんど常に、元型的コンステレーションのなか、すなわち、元型を活性化させた、あるいは、元型の自律的行為によって呼び起こされた状況のなかで起こる」。元型の強さは、それ自身の要求と性質をもつ状況を明白につくり、そしてこれらの性質は、その元型が効力をもつようになる時に形成するパターンのなかで、表出される。「心的水準の低下」を通して生じる。「自己」のなかでの心的反映は、元型に符号した形をとる。』
●『ユングの、より大きな概念の本質は、元型は、因果律によって作用するのではないことである。実際、ユングが、因果律と並ぶ別の原理の可能性を研究する必要を感じたのはまさに、元型は因果律以外の何かに従うことに気づいたときであった。かくしてユングは、共時性の仮説の定式化に導かれたのである。
この外見上の対立の背後にある原理を理解するために、われわれは、共時性を全体としてのマクロコスモスのなかで作用する原理と考える、より大きな見地を心に留めなければならない。あるそのときを横切って共時性に形成されるパターンは、全宇宙を包括する。これは、一般原理としては正しい。そして、哲学的に見れば、それはライプニッツに帰する。しかし、この一般文脈のなかには、そのパターンに関係する個人的存在があり、その人生と行為は、そのパターンを表現する。
個人のミクロコスモス的生は、マクロコスモスの、より大きな一般的パターンの一側面である。にもかかわらず、自分を取り巻くマクロコスモスのパターンを表わすことに従事している個人は、自分の人生のなかで、明らかに合理的に決定された行為によって、それを行なっている。その人は、意識的に決定された目標に向かって動き、また、因果律による思考を基礎にして自分の目標を目指して進む。
このように、人間の人生の展開は、二つの別個の次元、つまり存在の二つに分離した次元上で同時に起こる。第一は、自分の人生、動機、行為に対する個人的知覚である。この次元は、思考と情緒によって起こり、原因と結果を、現代のように合理的に考えるにしろ、原始的魔術のように物活論的に考えるにしろ、原因と結果というものを仮定した上で知覚できる目標に向かって動く。
他方、第二の次元は、個人以上のものである。それは、共時性が動く、トランスパーソナルなマクロコスモス的領域である。各特定の瞬間に時間軸を横切る宇宙のパターンを含むこの領域内では、ユングが、元型の多様な特性、そのヌミノース、それらが活性化される方法、それらが心の平衡をひっくり返す効力、そして、心の他の内容をそれらのまわりのコンプレックスに引き込む布陣を行う特質を分析するとき、ユングが明らかにしようと求めているのは、これらの規則性である。』

画像出展:「ヨガが丸ごとわかる本」
『つまりヨガとは、「本当の自分」は“全宇宙”と同じであり、“全宇宙”は「本当の自分」でもあるという心理に気づくことがヨガの最終境地である。』
本文に出てくる。”マクロコスモス”、“ミクロコスモス”の文面を見たとき、以前のブログ”ヨガ”の内容を思い出しました。この内容はヨガの考え方に近いもののように思います。
●ユングは共時性を人間の経験領域の中に位置づけることに主眼を置いたと思われるかもしれないが、実は、反対であった。ユングは物理学者を説得するために努力した。ユングの晩年における共時性に関しての対話は、まさに物理学者たちとのものであった。それはユングが共時性を人間の研究に限定しない全科学に関わる知識の一般原理として打ち建てることに、次第に興味を持つようになっていたからである。
ユングは研究の最晩年、最終的に物理学と心理学は統合されるという確信を持っていた。ユングの見方によると、心の深層心理的概念と物理学者の原子の見方との間の一致によって、二つの分野のこの結合は、現実的可能性をもっている。原子の深層に閉じ込められたエネルギーが解放され得るならば、人間の心の深層にあるエネルギーもまた解放されるのかもしれない。
●ユングは共時性が科学の一般原理であることに強調点を置いたので、個人の生涯や超心理的現象や多様な社会的経験の領域における共時性の存在を記録するのを犠牲にして、一般原理であることを強調する傾向があった。これらの領域に対する共時性の関連はきわめて重大であるが、ユングは、かろうじてその可能性を示しただけである。心の深層経験に関する共時性の役割は、人間の生の研究にとってものすごく意義深く、それは確かに、共時性原理のさらに一般的で広い考察の基礎として重要なものである。
●ユング自身は共時性の人間的な基礎をあまり強調しない立場に身を置いていた。ユングは全体としての自然科学や理論物理学に深層心理学を結合するという、より大きな可能性にあまりにも魅せられたため、研究の必要がある人間的要素への注意が弱まるままにしておいた思われる。共時性についてユングのいくつかの議論において、誤解や不明瞭さが指摘されるのはそのためと考えられる。
●元型は個人と非因果的秩序原理とを、心的経験を通して結合させる可能性を担っている。
●共時性につながった素材は人々の人生経験の中にある。なぜなら、ユングは深層心理学に照らしてそれらを観察していたからである。この素材はユングに共時性を示唆し、個人の運命を深く研究するには、因果律を越えた新たな展望が必要であることを認識し、この概念を発表したのである。
Ⅹ アイシュタインとより広い見解
●『精神と肉体の関係についての疑問が、この共時性の定義には生じる。ライプニッツの抽象的な定式から超心理学の実験的研究まで、これまで論じてきたポイントのうち数点が、この文脈において理解されるならば、最終的に、精神と肉体の問題の解決につながるかもしれない。これらの研究分野には、大きな可能性が開かれている。』
●『ユングは、自分の研究と物理学との関係について書いたなかでは、ニールス・ボーアの思想と関連させて自分を位置づけることを好み、アインシュタインには、ほとんど言及していない。しかし、私とユングの個人的な議論のなかで、ユングは、アインシュタインがチューリッヒで研究しており、しばしばユングを訪れていた今世紀初頭頃のことを私に語っている。それによると、アインシュタインは、よく昼食をとりにきたものだし、その際に、ユングとアインシュタインは、長い議論に陥ることがあったそうだ。
ユングは、生涯のこの時期において、まだ自分の概念を発展させ始めたばかりであり、無意識についての自分の新しい概念をアインシュタインに伝えることには困難を感じていたように私には思われた。ユングは、いくぶん見くびった感じで、アインシュタインは、なんといっても「分析的」な精神の持ち主だと語っていた。ユングのこの言葉は、ユングが、アインシュタインは象徴的次元の体験についてはあまり才能がないと感じていたことを意味している。
このことに関しては、アインシュタインの個人的な手記が最近公開されたことによって、夢とイメージが、アインシュタインの創造的な生涯において非常に重要な役割を果たしていたことが明らかになったことに留意するのは興味深い。あの昼食時の対話は、ユングが思っていたよりも益があったのかもしれない。とりわけ、アインシュタインが、心の深い水準に対する鋭い感性をもっていたことを知った上ではそう思われる。後ほどいつか、ユングとアインシュタインの関係について研究することは非常に実りあることだろう。それも特に、アインシュタインが、ヒンズー教と仏教の思想に興味をもっていたことと、相対性という概念の元型的特性についての彼の後の記述を考慮すればなおさらである。
ユングが、アインシュタインに重要な心理的影響を及ぼしていたかもしれない一方、相対性理論は、共時性についてのユング自身の考えの基礎と出発点となった。いくつかの点で、ユングは、相対性理論と対応する概念を、心という次元をつけ加えることによって発展させようと意識的に求めていたように思われる。
それゆえ、ユングは、エラノスの講演をもとにした論文のなかで、次のように書いている。
「物理学は、望めるかぎり平易に次のように論証してきた。それは、原子の大きさの世界では、客観的事実は、観察者を前提としており、この条件のもとでのみ、満足な説明図式が可能になるということである。このことは、主観的な要素が、物理学者の世界像に結びついていることを意味し、また、第二に、説明の対象たる心と、客観的時間空間の連続体との間には必ずつながりがあることを意味する」。ユングが、1940年代において、あらゆる人間の物質世界の認識には、物理学者がいかに客観的であろうと努めても、生来の「主観的な要素」があると述べていることは、明白なことと思えるかもしれない。しかし、その主観的な条件が、あらゆる状況に対する、新たな要因であるということは、相対性理論の概念の第一の要素である。それによると、最終的なものも完全なものも、けっして存在しない。なぜなら、常にもう一つの要因が加えられるべきだからである。そしてその要因というのが、主観的な要素、つまり観察者の意識なのである。』
●『相対性理論と易経の間には、越えなければならないみぞがある。そして、このみぞを越え、両者の間につながりを打ち建てることは、共時性の主要目的の一つである。このようなわけで、ユングは、物理的マクロコスモスの一般的解釈と、心理的ミクロコスモスの個別的研究の両方に関与する必要を感じたのであった。生命についての外見上の対立を、意味のある定式のなかで結びつけることは、共時性の根底にある目的である。共時性が、この目的を完全には成し遂げなかったとしても、共時性がその内容上、本性的に、外面と内面、つまり、物理的環境と心理的事象という対立物を結合するものであることは真実である。』
●『ユングは、次のように書いている。「にもかかわらず、心と物理的連続体の相対的な、あるいは部分的な同一性は、理論上最も重要なものである。なぜなら、それは、外観上同じ標準で計れない、物理的世界と心的世界をつなぐことによって、おびただしい単純化をもたらすからである。もちろん、それは、何らかの具体的方法によってではなく、物理的なほうからは数学的な式によって、心理学的なほうからは経験上生じた諸仮定つまり元型によってなされている。その内容は、あるとしても、精神に現われ得ない」。これで、ユングが、コスモスの物理的領域と心理的領域を一緒に記述することを思いついた包括的見地が理解できる。物理的世界は秩序と様式化を数学によって与えられている。一方、心理的世界での、それに対比される構造化は、元型によってなされている。これが、これまで述べてきた、元型の「秩序づける」性質である。』
Ⅺ 共時性から超因果性へ
●『共時性原理を研究するにあたって、次に必要なステップは、研究の体系だったプログラムをつくることであることは明らかである。それによって、われわれは、人間の一生における共時的事象の発生を同定し、詳細に記述することができる。共時性の含蓄を、因果律と相対性理論と相並ぶ、宇宙の運行の解釈原理として理解することは非常に大きなことである。ユングの未来像が実現され、原子物理学が深層心理学と統一され得る日が来たあかつきには、それは、人間精神の歴史における実に偉大な瞬間となるであろう。その日に向けて、なされなければならない個々の研究は膨大である。そして、その研究のためのデータは、人の経験する事象のなかに発見されるはずである。これは、われわれにとって最もたやすく使える素材であるだけでなく、共時性は、人間の運命のあやを、個人の人生と人類の歴史の両方にわたって理解するために特殊な貢献をしている。ここが、共時性がティヤール・ド・シャルダン[フランスの地質学者、古生学者、思想家。物理的世界から生物的世界へ、さらにその上に思考力を備えた人間の世界がどのようにして成立してきたのか、またこの人類が何を目指して進んでいきつつあるか、という未来への展望をはらんだ雄大な諸科学の総合的世界観が展開されている]の精神圏の概念と結びつき、それを、知の本質的な次元で補完するところである。そして、ここはまた、超因果律という新たな概念が、共時性という抽象的原理を、人間性の謎の理解へと変えることを可能にする中軸的要因となる点でもある。』
●『アブラハム・リンカーンの生涯において共時的事象が起きているが、それは、共時性の本性とその未来について多くのことを語ってくれるであろう。リンカーンには、世界には、彼が為すべき、意味のある仕事が存在していることが暗にわかっていた。しかし、リンカーンは、その仕事をするには、自分の知性をみがくことと、専門的な技術を身に着けることが必要であることも認識していた。これらの主観的な感じと戦うなかで、リンカーンの置かれたフロンティアの環境にあっては、専門的な研究のための知的な道具を見つけることは非常に困難であるという事実があった。リンカーンが、自分の願いはけっしてかなえられないだろうと信じていたとしても、もっともであった。
ある日、見知らぬ男がリンカーンのところに、がらくたを一杯入れた樽をもってやってきた。その男は、リンカーンに、自分はお金が必要であることと、リンカーンがその樽を1ドルで買ってくれたら非常に助かるであろうことを述べた。
その男は、樽の中味はたいした価値のないものだと言った。それらは、古新聞や他のそのような類のものであった。しかし、その見知らぬ男は、なんとしても1ドルが必要だった。その物語によると、リンカーンは、親切な性格だったので、その中味が何かに使えるとは考えなれなかったにもかかわらず、樽と引き替えにその男に1ドルを渡した。リンカーンは、しばらくたって、その樽を整理しようとしたとき、その樽には、ブラックストーンの「注解」の全集がほとんど入っていることに気づいた。リンカーンが、法律家になり、ついに政界に進出することを可能にしたのは、偶然、あるいは共時的な、それらの本の獲得であった。

画像出展:「AbeBooks」
Commentaries on the Laws of England, In Four Books. 14th ed
Blackstone, Sir William
$1,000.00で販売されていました。
リンカーンの生涯の内には一本の連続した因果の鎖が働いていた。それは、運命についてリンカーンに暗示を与え、また、限られた困難な環境の中に生きることに絶望を感じさせた。同時に、その見知らぬ男の生涯のなかにも、因果的なつながりがあった。その男は、不景気がつのって、目にとまる自分の持ち物は、何であれ1ドルで売らなければならなかったのである。事象のこの二つの筋をつなぐ因果関係はなかった。しかし、ある意味のある時に、それらは共に起こった。このことは、予期されない結果を引き起こしたのであるから、共時性のなかの超因果的要因の働きであった。
リンカーンが、ふとしたことからその樽を買うことによって、ブラックストーンの「注解」を手に入れたことは、人間の生涯のなかで共時的事象が発生することの一例である。これは、共時性の一例にすぎないけれども、共時性が最終的に、どれほど豊かな知識を与えてくれるかを示しているであろう。共時性は、予期できない仕方で、それらがあると最も予期されない所に存在しているのであろう。しかし、リンカーンのように、われわれが、その時の統合性に誠実であれば、ユングの直観したものがわれわれ全員の知識になるであろうと信じるに足る理由が存在している。』
まとめ
ユングの共時性に関する研究は20年以上におよび、その発表は75歳目前であった。しかしながら、それは未完成なものであり、科学的にいかがわしいものと揶揄された。それでも勇敢に立ち向かったのは、個人の運命を深く研究するには、因果律を越えた新たな展望が必要であることを確信したためである。
共時性とは、相互に因果関係がない二つの分離した事象が同時に起こること。それらは無関係であるにもかかわらず同時に起こり、しかも、それらは互いに意味深く関係し合っている。また、共時性は人間の運命の本性に関連する教えへの扉を開く鍵となるとされる。
心と物理的連続体の相対的な、あるいは部分的な同一性は、理論上最も重要なものである。なぜなら、それは、外観上同じ標準で計れない、物理的世界と心的世界をつなぐことによって、おびただしい単純化をもたらすからである。もちろん、それは、何らかの具体的方法によってではなく、物理的なほうからは数学的な式によって、心理学的なほうからは経験上生じた諸仮定つまり元型によってなされている。
ユングの晩年における共時性に関しての対話は、まさに物理学者たちとのものであった。それはユングが共時性を人間の研究に限定しない全科学に関わる知識の一般原理として打ち建てることに、次第に興味を持つようになっていたからである。
共時性の含蓄を、因果律と相対性理論と相並ぶ、宇宙の運行の解釈原理として理解することは非常に大きなことである。ユングの未来像が実現され、原子物理学が深層心理学と統一され得る日が来たあかつきには、それは、人間精神の歴史における実に偉大な瞬間となるであろう。
感想
『時間を水平に横ぎり、そして、本来垂直である因果のカテゴリ(時間的な連続性)が適用できないパターンから、あなたが求めていた回答をふと見つけたという新たな事実が現われる。明らかに、この二組の出来事の間の、どのような因果関係も論証することはできない。ただ、ある種の意味深い関係が、それらの間に存在する』
友人等との会話だけでなく、散歩をしていて、お風呂にはいっていて、あるいは本を読んでいて、ふと気づく瞬間があります。「閃き💡」という表現が最も近く、垂直思考の因果を水平に横ぎる感覚ともいえるかもしれません。そして、その「閃き💡」は全く忘れていた過去の何かの琴線に触れたかのように浮かび上がってくる感覚です。その「閃き💡」が流れを大きく変えるケースは少なくないように思います。場合によっては、人生に影響を与える可能性もあると思います。
宇宙の大きさは無限のように感じます。一方、原子より小さな量子世界は不思議な世界です。大きな宇宙も小さな量子の世界も間違いなく実存し、我々の命に関わっています。
ユングの母方の祖父母は霊能者です。私も完全とは言い難いのですが、その存在を肯定しています。霊能者が有する能力がどこから生み出されるのか分かりません。心が関係しているのでしょうか。そこには時間・場所といった物理の世界と心の世界が関係しているように思います。そして、一般人の常識といわれる範疇では理解できないものが実在しているように感じます。
ユングは、『心と物理的連続体の相対的な、あるいは部分的な同一性は、理論上最も重要なものである。』と説いていますが、晩年、ユングが物理学に傾倒されたという事実は大変興味深いことでした。
ユングと共時性1
今回の「ユングと共時性」は9月30日、10月7日の「宗教と科学の接点」の続きともいえるものです。この本の中で最も気になったキーワードが“共時性”だったのですが、今回の「ユングと共時性」という本の中に、知りたいことが書かれているのではないかと思い購入しました。
目次
Ⅰ 多重的宇宙の解釈 ―ユングとティヤール・ド・シャルダン―
Ⅱ 共時性と科学と秘教
Ⅲ ユングと易をたてたこと ―個人的経験―
Ⅳ 共時性の基礎
Ⅴ 因果律と目的論を越えて
Ⅵ ライプニッツと道
Ⅶ 元型と時間の様式化
Ⅷ 超心理的事象の共時的基礎
Ⅸ 共時性の働き
Ⅹ アイシュタインとより広い見解
Ⅺ 共時性から超因果性へ
注)Ⅶには触れていません。
Ⅰ 多重的宇宙の解釈 ―ユングとティヤール・ド・シャルダン―
●科学は限定された合理主義の言葉で表現されるものではなく、科学は物事を知ること、すなわち、人間の行なう知識の探求すべてと考えられる。この考え方(精神)によって、ユングは、理論物理学の研究と彼自身の深層心理学の研究の間には、一致、少なくとも相似が存在するという直観により、自ら“共時性(synchronicity)と名づけた「非因果的連関」の原理を1920年代後半に形作り始めた。
●共時性の概念は、元来彼の、深いレベルでの自己(Self)の研究から生まれたものである。それも特に、人生という旅の中で運命を変えることに関わる、いくつかの経典および注釈―ことに東洋のもの―の中に彼が見出した解釈法と、夢の中での出来事の進展との相互関係にユングが注目していたことによるものである。
●ユングが自分の仮説を系統立てて説く契機となったのは、物理学者ニールス・ボーア、ヴォルフガング・パウリとの接触と、アルバート・アインシュタインとの早くからの親交であった。ユングは彼らと対話するうちに、物理学の世界での基本単位としての原子と、人間の“心(:サイケ[psyche])”が等価であることに気づいたのである。特に人間の深層についての特有の手がかりとして発展させた、“心”という概念に、原子をたとえる時に、その一致度は特に強くなる。

画像出展:「シュレーディンガー その生涯と思想」
第五回ソルヴェイ物理学会議
・期間:1927年10月24日~10月29日
写真は中央の列向かって右端がボーア、3列目右から4人目がパウリ。前列右から5人目がアインシュタイン。
●ユングの研究のひとつの根本的な結果は、共時性の概念である。
●ユングは共時性を科学的な世界観におけるギャップを満たす手段として、ことに因果律に対するバランスとして提出した。共時性は、物理的な現象と同様に非物理的な現象をも含んでおり、これらの現象を、これらの相互の間の非因果的であるが意味のある関係のなかに認めることである。
●核心はユングが、人間の心は意識のレベルよりさらに深い層で関わっている現象を、理解可能とする説明原理を打ち立てることに従事していたことである。
●我々はユングから発展性のある二つの仮設を得ている。精神圏の内容についての仮説と、精神圏の作用原理についての仮説である。
Ⅱ 共時性と科学と秘教
●ユングは共時性原理についての論議を、理論物理学の枠組みのなかに位置づけ、そして、他方では科学以前の時代の種々様々な秘教やオカルトの教えを、宇宙のなかに共時性原理が存在することに対する人間の直観的理解を暗示するものとしてして言及している。合理的な科学と非合理的な秘教という二つの知識の源泉は、相いれないように思えるが、これらは両立する。ユングの目的の一つは、それらの共通の特質と相互の関連を、我々に見させることにある。
しかし、異質な材料を一つの議論の中に入れ込んだために、ユングの理論は、より因習的な人々にとっては、混乱を起こさせるもの、疑わしいものとなった。そして、そのことにより共時性はほとんど注目されなかった。
●秘教の教えと手法の多様な形式へのユングの興味は、それらが、若干のあいまいな方法で人間の経験の「内面」を表現しているというユングの洞察に根差してきた。それらは文字通りに受け取るべきではなく、夢のようなものとして受け取るべきであり、それ自身の生来の象徴的意義の文脈の中で自らを語る機会を与えるべきものである。ユングはまさに、秘教やオカルトに、各々の知恵の固有のスタイルを語り、露にする機会を与えようと企てた。彼はこれを錬金術(Alchemy)から禅(Zen)へと文字通りAからZに至る、これらの主題についての本を、解釈し紹介することによって行った。そのなかには、占星術、死者の書、タロ、易経、そして他の多くの古代東洋の原始的な教養が含まれていた。
●共時性は人間の運命の本性に関連する教えへの扉を開く鍵となることができる。この点において、共時性はこの世の生における神秘的な次元に対する鍵であるだけでなく、その背後に存在する現代科学の経験に対しても、鍵となるという特別な利点をもっている。
●ユングは著書の中で極めて率直な記述と、後からその大胆な彼の論点の衝撃を柔らげる否認と緩和とが交互に現れる。このことがユングの著作に認められる曖昧さの原因となっている。
●この本(「ユングと共時性」)は、ユングの共時性の概念を、より大きな哲学と理論的根拠とに関連させて記述し説明し、そして、この複雑な問題の本質を可能な限り明確に紹介するためのものである。
●共時性は二つのレベルで重要である。理論レベルでは、展開する宇宙のなかでの人間の経験の本質に関する、意識の新しい次元を開く。また、経験的レベルでは、人間の人生と運命の最も捉えがたい相のいくつかを、事実に基づいて研究する道を与えるものである。
Ⅲ ユングと易をたてたこと ―個人的経験―
●ユングが研究したすべての秘教のなかで、易経は、最も明確に共時性原理を表出しており、また、最も洗練された形式でそれを応用しているものである。
●リヒャルト・ヴィルヘルムが翻訳した中国の錬金術の本が「黄金の華の秘密」である。ユングがこの本に払った苦心は、主要な心理学的概念を発展させるための重要な源となっている。特に、ユングが「共時性」を初めて公に使ったのが、1930年のリヒャルト・ヴィルヘルムの葬儀での賛辞の中であったことはとても意義深い。
●因果律とは、ある一つの出来事が、他のことではなく、どのようにして起こるのかという作業仮説といえる。それに対して、共時性とは相互に因果関係がない二つの分離した事象が同時に起こること。それらは無関係であるにもかかわらず同時に起こり、しかも、それらは互いに意味深く関係し合っている。これは、易経の基礎となる原理である。
●易経の中には二つの要素がある。一つは、個人の人生のその時の状況である。他方は、コインを投げてそれを定められた形式によって古代の書物に関連づける行為である。明らかにこれらには因果的関係はなく、しかも互いに意味深い関係を持っている。それらが会う瞬間に、何か普通でなない重要な価値が生じるのである。
表面的には、それは偶然のように見える。しかしユングにとってそれは、明らかに偶然をはるかにしのぐものであり、しかも因果関係でもなかった。明確な原因は捉えどころがないままだが、ユングにとっては中国で何世紀にも渡って維持され続けた原理が、何か重大な秘密を持つに違いないことは明白に思われた。
●易経には基礎となる深くて言葉にするのが難しい知恵が存在し、それゆえ易経の経験は、現代人によって探求されるべき重要なものであることを、ユングは確信していた。
Ⅳ 共時性の基礎
●ユングは共時性とは何かということをうまく伝えることはできなかった。それはつかまえどころのない、抽象的かつ普通とは言えない原理を分かりやすく説明することができなかったためである。
●ユングが取り上げた非因果的解釈の中には、占い、占星術、託宣[神が人にのり移ったり夢に現れたりして意志を告げること]、タロなどが含まれていた。これらは非常に広範囲にわたり、また、現代には受け入れ難く、研究は思うように進まなかった。それらを科学的に正当な理由に基づいて研究することさえ疑いをかけられていた。
しかし、ユングは自分が自分の患者の無意識の非合理的働きを辿る方法を学びたいならば、これらの前科学的な手順を洞察することが必要であると確信していた。ユングが学問上の愚弄に勇敢に立ち向かい、科学的にいかがわしい主題に関わったのは、彼の心理学を満たすために必要なことだったためである。
●ユングは共時性について、自分の行なったことを経験的に観察すること、自分のゼミの中で様々なアプローチすることによって、20年以上もの間、共時性について研究し続けた。そして、ユングが「非因果的関係の原理としての共時性」についての小論を書き始めたのは、75歳になろうとしていた時であった。
●ユングは実験的レベルにおいても概念的レベルにおいても不十分であることは理解していたが、ユングの共時性の概念が論議され、示唆や批判を受けることができるように、世に送り出さなければならないと感じていた。つまり、ユングの「非因果的関係の原理としての共時性」は未完の研究、試案として書かれていることを理解すべきである。
●共時性は日常生活の中で経験される。ユングの著書には、共時性を示す多くの事例や逸話が載っている。
●『仮定的な例として、あなたが、ある特定固有の問題について考え続けていたが、それについて自分が考えているということを誰にも語らなかったとしてみよう。そこへ、だれかがあなたの問題に無関係で全く独立な理由で、あなたに会いに来るとしよう、そして、会話は、訪問の目的に従って進み、それから、あなたの問題について何も議論しないうちに、あなたが探し続けていた鍵を与える言葉が、ふと、予想外に語られたとしよう。
もし、われわれが回想によって、このような状況を振り返り、起こった事の意味を分析的に理解しようと努めるならば、明確な因果的連関を通して各々の出来事を突きとめるであろう因果の鎖をたどることは、いたって簡単である。因果律によってわれわれ、あなたが、その特定の問題にかかわるようになった「理由」をたどることができる。それで、われわれは、その日に訪れた特定の個人を、どのようにして知るようになったのか、その訪問の約束が、どのようにしてなされるようになったのか、そして議論の筋が、どのようにして発展するようになったのかを、分析的にたどることができる。すべてのこれらの事を、やりつくすことは可能であろう。そして、それらが因果律の用語に還元されたとき、それらは、あなたの人生の発展という特定の見地から再構成できるので、その状況の基礎を与えることになろう。
それに対応して、因果分析の類似した筋が訪問者側の見地からもたどることができるであろう。すなわち、彼をあなたに訪れさせた原因となった出来事の連なり、実にあなたの興味を引いた知識を、彼はどのようにして得たのか、どのようにしてまさにその特定の時間に、あなたと約束するようになったのか、どのように「偶然」に、あなたが興味をもっていると彼が予想しなかった問題について語るようになったのかである。これもまた、すべて因果的用語で記述することができるであろう。
あなたと訪問者が出会うとき、それぞれは、因果的に説明できる過去のなかに広がる背景をもっている。そして、それらすべてが、あなた方が出会う特定の点で出会うことになる。あなた方が握手して会話を始めるところへの到着は、発展の縦の線の頂点を示している。その発展は、過去からの絶え間ない流れのなかでの動きであり、また、あなた方それぞれに個別の作用である。なぜなら、あなた方は、それぞれ自身の経験の枠組みと重みによっているからである。
しかし、あなた方が会った瞬間、過去のこの原因すべては、現在の瞬間のコンステレーションの一部、すなわち、時間を水平に横ぎり、そして、本来垂直である因果のカテゴリ―つまり時間的な連続性―が適用できないパターンの一部となる。どういうわけか、このパターンから、そこに、あなたが自分が求めていた回答をふと見つけたという新たな事実が現われる。明らかに、この二組の出来事の間の、どのような因果関係も論証することはできない。ただ、ある種の意味深い関係が、それらの間に存在することだけが、同様に明らかである。
それが符号であったと言うことは全く正しい。しかし、明確にするためには、それは意味深い符号であった、と付け加えなければならない。なぜなら、出来事の交差した連なりは明確な意味をもっていたからである。本来因果律は、符号という事実を含まないものであるから、われわれが最大限言えることは、原因や結果である出来事は、意味深い符号が起きる生の素材を供給するということである。これらの符号の意義、すなわち、それらを単なる無関係な出来事ではなく、現実の符号とする、意味の特別な性質は、因果律によって跡づけられる背景にある要因からは決して導き出せない。それらは、時間的に連続でなく、何らかの方法で時間軸を横ぎるパターンに属している。この理由により、それらは、その本当の本性が何であれ、少なくともまちがいなく非因果的な原理を含んでいる。
ここに示した非常に簡単な例は、それに対応し、関係づけられ派生する局面がすべて考慮されたとき、人の経験の相当大きな領域を含んでいる。長い間、偶然、符号、願望成就、夢を通じての認知、祈りとその答え、信仰による奇跡と治癒、予知、そして同様な現象への疑問は、精神的な魔術の多様な形式によって説明されてきたか、あるいは、さもなければ迷信として片づけられてきた。しかし、量的に見るなら、これらの経験は、いわゆる未開あるいは後進社会だけでなく、われわれ現代西洋文明においても、日々に起こる出来事の非常に大きな率を占めている。
多くの例において宗教の歴史は明らかに、因果律を越えていてそれでもなお現実であるような出来事に基づいている。しかし、われわれは、宗教的な形の現象をはるかに越えたものが含まれていることを認識しなければならない。政治史の上においてさえ、それは表面的には合理的に導かれた決定や少なくとも外交上の認識に従う行為の場であるが、因果的説明ができない、多くの重大な出来事が認められるのである。経済レベルについての妥当性にもかかわらず、歴史についての決定論は、いったん人の運命というさらに大きな問題がもち上ったならば、浅薄で、はなはだ不適当なものとして捨てられなければならないことは、確かに、まさに本質的な理由によるものである。
われわれが、人間の活動の根底を深く研究するならば、宗教の主観性から政治上の動かせぬ事実、あるいは商取り引きの冷静な計算から個人的な親密な関係に至るまで、歴史のすべての側面において、社会の全構造は、社会と個人の作用を記述する厳密な「法則」を見つけるべしという強制を感じているために、これらの不愉快な非合理的事象の存在は、無視されなければならなかった。
知識のどのような標準をもってしても、これらの非合理的事象に理解を伴った説明をすることは、非常に困難であることを認めなければならないが、それは、それらを無視する十分な根拠とはならない。少なくともユングは、非合理性と非因果性が重要であることによってそのような現象が、非常に真剣な注目を受けることが肝要になっていることを感じていた。彼は、どのような種類の現象も無視することは正当でないという事実に加えて、そこには、それらの出来事の下に隠されている何か他の、より一般的な原理が存在すると感じていた。これが、非因果的関係をもつ共時性現象についての彼の研究の背後にある、問いの真意と予感であった。そして、それは、広大な含蓄をもつ共時性の概念へと至った。』
Ⅴ 因果律と目的論を越えて
●共時性は、ユングが研究した第三の説明原理として現れる。三つとは、因果律、目的論、そして共時性である。ユングは無意識を説明するために目的論的見地を発展させたが、さらに共時性へと導かれた。この三つは全て、問題と状況に応じて用いられて、ユングの思考のなかにとどまってきた。目的論的見地は、彼の思考の中枢の位置を保つ。なぜなら、それは、因果律をそのなかに含み、しかも、共時性の問題へ直接に通じているからである。しかし、共時性は、他の原理と釣り合い、それらを補足する独立した原理である。
Ⅵ ライプニッツと道
●共時性は本来、知的概念ではないけれども、過去に共時性を哲学的に説明した人物は膨大な数にのぼる。我々がしたように、ユングをヒュームとカントに関連させることの要点は、ユングの思想が現代西洋哲学の合理主義から現れてきた歴史的過程を示すことであった。しかし、西洋文化における共時性の重要な哲学的先駆者は、合理主義をはるかに越えた源泉に求めるべきである。それらは、ライプニッツによって代表される。
●共時性が関わっている範囲内で、ライプニッツの研究の最も意義深い面は肉体と魂の関係の定式である。学問的には彼の理論は「精神身体的並行論」として分類され、軽視されて、現代思想では哲学的には厄介物視されるほどになってきている。しかし、今や共時性原理の定式と、ユングが心の深い現象を観察することによって為した研究によって、我々はライプニッツの概念の隠れた含蓄のいくらかを理解し始めることができる。
●ライプニッツと老子[中国春秋時代の哲学者。道教の始祖]はユングにとって共時性の概念の先駆者であり、源泉であったとすることは正しい。しかし、二つの間には意義深い違いもまた存在する。そしてその違いは、西洋思想の伝統的発展に関係してる。ライプニッツは無形の影響を自分の心に把握しようと努めるが、道教[儒教、仏教と並ぶ三大宗教の一つ。多神教であり、概念規定は確立しておらず様々な要素を含んでいる]はそれを把握しようとはせず、一部になろうとし、調和する自然の流れの時間の中に入ろうと努めるのである。
Ⅷ 超心理的事象の共時的基礎
●超心理学の現象の研究において、遠くの事象の知覚や未来に起こることの予見は、ユングは自明であるとする。
●ユング自身の人生と心理療法の中で体験した数多くの超心理的な事象は、自分の無意識と密接な関係のもとに生きている。ただ、この無意識との関係は、鋭敏な人格内のより広い認知力の意識的発展によるときと、精神病の場合のように、無意識が無統制に優勢になるときがある。
●ユングは超心理的事象の存在は明らかであり、必要なことは超心理的事象を理解する何らかの方法を見つけることであるという意見を支持している。
●ユングの共時性原理は、超心理学の道程にそって更に先の地点に至っている。ユングは共時性原理のデータをまとめて解釈するための基礎の役を果たすことのできる作業仮説を試みている。
●ユングは心のレベルを四つに分け、人間の認識力の様々なタイプを記述した。表層は自我意識、そのすぐ下が個人的無意識、その下でとても深いところまで達しているのが、トランスパーソナル[自己超越、トランスパーソナル心理学は、神との交感、宇宙との融合感など、人間の知覚を超えたものが人間の心理に与える影響を研究する学問。人間の普遍的な姿を求める]なレベルの集合的無意識。そして底にあるのが、自然そのものの領域に達している類心的レベルである。
●超心理学的研究のこの側面[超心理学現象の発生は、実験室外の環境では非常に大きい広がりをもつ]は、近年、明らかになってきている。その中で、最も注目すべきはガードナー・マーフィで、彼は、「自然発生的経験」が、超心理的現象の研究の中で重要であることを強調している。
「自然発生的経験」について述べることは、超心理的事象は、第一に日常生活の流れの中で起こるという認識を意味している。これは、もちろん、ユングが深層心理学者としての自分の治療研究を基礎として到達した結論である。多くの宗教についての研究によってもまた、ユングは心の元型的[人類に共通する動きのパターンであり情動を伴う]レベルでの象徴と、宗教史上で起こった様々な奇跡的体験との間の関連について、強い印象を受けた。
●自発性は共時性事象に重要な要素であるが、その自発性はあくまで非計画的なものである。そのため、超心理学の研究は非計画的人生経験の中で起こる現象を研究する方法を見つけなければならない。これは、多様な共時的事象を、社会生活の影響下で引き起こされるものとして研究する必要性を意味している。
●共時的事象は、宗教的伝統と神話の基礎となる「奇跡的」出来事に対する重要な糸口をもっている。

左は”EARTHSHIP CONSULTING”さまのサイトです。
「元型」について詳しく解説されています。
『「元型」(archetype)とは、人間に生まれ持ってそなわる集合的無意識で働く「人類に共通する心の動き方のパターン」のことである。分析心理学者C.G.ユング(1875-1961)が提唱した概念。』
宗教と科学の接点2
第三章 死について
●瀕死体験
・『アメリカの精神科医レイモンド・ムーディは最初に哲学を専攻し、後に医学に転じたが、哲学の講義で霊魂の不滅について論じたときに、学生の一人から彼の祖母の瀕死体験について聞かされ、その後は積極的にこの問題と取り組むことになった。瀕死体験とは、医者が医学的に死んだと判定した後に奇跡的に蘇生した人の体験、および、事故、病気などで死に瀕した人の体験である。ムーディーは間接的な資料も加えて約150の事例から、次に述べるような結論を出したのである。
瀕死体験は人によってそれぞれ異なるが、驚くほどの共通点が存在する。それらの共通点を組み合わせて、ムーディはひとつの理論的な「典型」を提出している。これは非常に重要と思われるので、そのままここに引用してみよう。
「わたしは瀕死の状態にあった。物理的な肉体の危機が頂点に達した時、担当の医師がわたしの死を宣告しているのが聞こえた。耳障りな音が聞こえ始めた。大きく響きわたる音だ。騒々しくうなるような音といったほうがいいかもしれない。同時に、長くて暗いトンネルの中を猛烈な速度で通り抜けているような感じがした。それから突然、自分自身の物理的肉体から抜け出したのがわかった。しかしこの時はまだ、今までと同じ物理的世界にいて、わたしはある距離を保った場所から、まるで傍観者のように自分自身の物理的肉体を見つめていた。その異常な状態で、自分がついさきほど抜け出した物理的な肉体に蘇生術が施されるのを観察している。精神的には非常に混乱していた。
しばらくすると落ちついてきて、現に自分がおかれている奇妙な状態に慣れてきた。わたしには今でも[体]が備わっているが、この体は先に抜け出した物理的肉体とは本質的に異質なもので、きわめて特異な能力を持っていることがわかった。そして、今まで一度も経験したことがないような愛と暖かさに満ちた霊―光の生命―が現れた。この光の生命は、わたしに自分の一生を総括させるために質問を投げかけた。具体的なことばを介在させずに質問したのである。さらに、わたしの生涯における主なできごとを連続的に、しかも一瞬のうちに再生してみせることで、総括の手助けをしてくれた。ある時点で、わたしは自分が一種の障壁とも境界ともいえるようなものに少しずつ近づいているのに気がついた。それはまぎれもなく、現世と来世との境い目であった。しかし、わたしは現世にもどらなければならない。今はまだ死ぬ時ではないと思った。この時点で葛藤が生じた。なぜなら、わたしは今や死後の世界での体験にすっかり心を奪われていて、現世にもどりたくはなかったから。激しい歓喜、愛、やすらぎに圧倒されていた。ところが意に反して、どういうわけか、わたしは再び自分自身の物理的肉体と結合し、蘇生した。」
これは一種のモデルであり、個人によっていろいろ異なるのは当然である。ムーディはこのモデルに含まれる約15の要素のうち、多くの人が8ないしそれ以上の要素について報告し、12の要素を報告した人が数人いると述べている。また、人によってはこのモデルとは異なる順序で体験しており、たとえば、「光の生命」に出会うのが肉体から離脱するより先であることもある。また、臨床的な死を宣告された後に蘇生したが、先に述べたような体験を一切しなかったと報告する人もある。
これらの体験をした人は誰も、このようなことを適切に表現できる言葉が全然見つからぬことを強調している。それとその内容があまりにも予想外のことなので他人に話をしても、まともに受けとって貰えないということもあった。このためにこのような体験をした人も沈黙を守っていることが多く、ムーディたちが真剣に聞いてくれるので、はじめて話をしたという人もある。ここに述べられている身体外意識の体験は、ユングも共時性の一現象として記述しているが、当時ではなかなか信用されなかったものである。交通事故で足がちぎれたりした人が、自分のその体を上から眺めているというのだから、まったくの幻覚と思われがちだが、そのときにその人の見た事実と現実がぴったりと照合するので信頼せざるを得ない。特に、キュブラー・ロスが全盲の人達の体験を報告しているのは興味深い。彼らは全盲でありながら、瀕死体験の際は、そこに居あわせた人の身につけていた着物や装身具などまで描写できるのである。』
第六章 心理療法について
●心理療法とは何か
・『宗教と科学の接点の問題について論じてきたが、私がこのようなことに関心をもつようになったのは、私自身が専門としている心理療法という仕事を通じてのことであった。心理療法を実際にやり抜いてゆこうとすると、今まで述べてきたようなことを考えざるを得ないのである。それは自分のしている心理療法は「科学であるのか」という疑問に答えるためにも、そして、それに関連することであるが、心理療法の対象である「人間」という存在について考えるためにも、必要なことであった。心理療法についてはいろいろな語り方があると思うが、ここでは宗教と科学の接点という問題意識をもって述べることにしよう。』
・心理療法は19世紀の終わり頃より発展をはじめ、現代の欧米においては欠かせないものとなった。
・心理療法は古来から存在していたと考えられ、宗教、教育、医学の分野にそれを見出すことができるが、近代においては、「宗教」に対する反撥が強く、むしろ宗教に対立するものとして、教育、医学の分野から生じてきたように思われる。
・心理療法が心理学から生じてこなかったは、「心理学」が物理学を範として「客観的に観察し得る現象」の研究をしようとするものであり、人間の意識は研究対象になりえなかったからである。
・教育には指導や助言という要素が強く、これが心理療法に発展したと思われるが、心理療法は指導や助言では不十分なことも多く、この領域を超えることが求められている。
・医学においては身体に問題がないのに障害がみられる「病気」があることが解ってきて、その治療として19世紀の終り頃より精神分析が出てきた。しかし、医学モデルは型にはめようとしがちで、単純なモデルであるため、効果が限定的であることが多い。
・『対人恐怖症のためにどうしても学校に行けぬ生徒に、学校へは行くべきとか、行かないと損をする、と指導助言しても何の効果もない。あるいは、「学校に行けない原因があるだろう、それを言いなさい」などと迫っても、およそ答えられないであろう。時には、子どもたちは質問者の勢いにおされて、「先生が怖い」とか「お母さんがうるさい」とか適当に答えるときもある。原因追及型の線型の論理一本槍の人は、次に矛先を変えて、「原因」としての教師や母親を攻撃することになる。それに熱心な人ほど、自分の思いどおりの結果が生じないときは、その熱意は憎しみや攻撃の感情に変化しやすいものである。自分はこれほど熱心にやっているのに、母親が悪いから、あるいは、本人の意志が弱すぎるから……などの理由でうまくゆかぬと嘆いている人は多い。教育モデル、医学モデルに頼るときは、結果はうまくゆかぬとしても、自分は熱心で正しいことをしているのに、誰か必ず自分以外の悪者がいるからうまくゆかないのだ、という結論に達することができるので、なかなか便利である。このような便利さのために、有効性が低い割に現在もなお相当に用いられていると思われる。』
●自己治癒の力
・指導や助言も効果がなく、病因を探し出す方法も有効でないとすると、どのような方法があるのか。それは治療者が治療するのではなく、患者自身の治る力を利用することによってなされる。このことは心理療法において極めて大切なことである。
・『たとえば、学校に行きたいのにどうしても学校に行けぬと言う高校生が来談したとする。私がこの高校生を出来るだけ早く学校に行かしてあげたいという気持ちや、なぜ学校へ行きたいのか原因を知りたいという気持ちを全然もっていないと言うと、それはうそになるだろう。しかし、一応それらのことは括弧に入れておいて、ともかくこの高校生の自由な表現をできる限り許容し、それに耳を傾ける態度をとるだろう。そして、場合によってはその人の見た夢について話して貰ったり、絵を描いて貰ったり、箱庭を作って貰ったりすることになるだろう。多くの患者さんたちは、私に対して指導や助言を期待しておられたり、なかには「どうしてこうなったのでしょう」と尋ねる人もあるように、原因を早く知りたがったりされるが、それらにはほとんど関心を払わない私の態度に不思議な感じを抱かれるが、私の態度に支えられて、いろいろと自由な表現をされる。
これは、本人および本人を取り巻く人々の、そのときの意志や考えよりも「たましい」の語ることを尊重しようとしているのだ、と言うことができるであろう。夢や箱庭や絵画などを利用するのは、たましいの言語としての「イメージ」を尊重しようとするからに他ならない。
多くの人は後から振り返ってみて、なぜ自分はあんな話をしたのか解らないと言われる。つまり、学校のことを問題にするつもりだったのに、「自由に」話していたら、知らぬまに母親のことばかり話をしていたとか、まったく思いがけない過去のことを思い出して話をしてしまったとか言われるのである。これは治療者が通常の意識レベルにおける原因―結果の論理からフリーになった態度で接しているので、患者の方は知らず知らず感情のおもむくままに話をはじめ、心の深い層へと下降をはじめるわけである。自由に、感情のおもむくままに、ということは自我がたましいの方に主導権を譲るということである。』
・人間のもつ自己治癒力は不思議なものである。患者さんに箱庭をおいて貰っているだけで治療が進むときがある。
・箱庭療法は西洋で始まったものであるが、日本人は非常に向いている。これは、箱庭のような非言語的手段によって自分の自分の内面を表現し、またそれを治療者が理解することが難しくないということが大きい。
・一般的に患者さんは、はじめは片隅に少しだけ置いておくものだが、徐々に箱の領域全体を使うようになり、表現も豊かになっていく。こうして症状も改善していく。
・箱庭の変化の過程を写真にとっていくと、明らかにその流れが解るため、患者さんの内界に変化が生じ納得も得られやすい。
・箱庭療法の本質は、治療者が指導したり助けたりすることを放棄して、ただそこにいることなのである。何もしないでただそこにいること。これが治療者の役割である。

左の写真は「飯田橋メンタルクリニック」さまより拝借しました。
こちらのサイトには”箱庭療法”についての詳細な説明が書かれています。
●治療者の役割
・教育モデル、医学モデルに対し否定的な話をしてきたが、重要なことはこれらのモデルの有効性を判断することである。臨機応変の態度をもっていることが求められる。
・『われわれの態度は来談した人を客観的「対象」として見るのではなく、自と他との境界をできる限り取り去って接するようになる。治療者は自分の自我の判断によって患者を助けようとすることを放棄し、「たましい」の世界に患者と共に踏みこむことを決意するのである。ここのところがいわゆる自然科学的な研究法と異なるのである。
このような治療者の態度に支えられてこそ、患者の自己治癒力の力が活性化され、治療に到る道が開かれる。従って、治療者は何もしないようでありながら、たとえば、箱庭を患者が作ろうとするとき、どのような治療者がどのような態度で傍にいるかによって、その表現はまったく異なるものとなるのである。そうでなければ、各人が勝手に絵を描いたり、箱庭を作ったりしてノイローゼを治してゆけそうなものだが、そうはならないのである。このような態度は言うはやすく行うは難いことであり、相当な訓練を受けないとできないことである。』
・自己治癒力の力がはたらくと言っても、実はそこには大変な危険性や苦しみが存在する。
・多くの場合、治ることに苦しみはつきものである。というよりは、正面から苦しむことによってこそ治癒はあると考えるべきである。
・心理療法によって苦しみや不安はむしろ増えてくる。治療者は患者がそれと正面から向き合うようにし、その苦しみを共にわかち合うことによって乗り越えようとしている。
●コンステレーションを読む
・コンステレーションとはすぐに原因と結果とを結びつけるのではなく、いろいろな事柄の全体像を把握することである。
・コンステレーションを読むには、われわれは「開かれた」態度を持たねばならない。このような「開かれた」態度で現象に接していると、共時的現象が思いの他に生じており、それが極めて治療的に作用することに気づく。
・『長い間学校へ行けなかった子がとうとう登校を決意する。明日行くというときに、風邪を引いて寝込んでしまう。このときに「またか!」と思い両親も治療者も落胆してしまうのと、登校する以前に病気ということを通じて母と子がもう一度一体感を確かめる機会を与えられたと受けとめるのとでは、まったく結果が異なってくる。病気のときは子どもも案外素直に甘えられるし、母親も子どもの肌に自然に触れられたりして、一体感を味わいやすいものなのである。奇跡が起こると言っても奇跡はしばしばマイナスの形で生じ、それを読む力のあるものにとってはプラスになることも多いので、コンステレーションを読む能力は治療者にとって非常に大切なものである。』
●宗教と科学の接点
・『「開かれた」態度によって治療者が接すると、それまでに考えられなかったような現象が生じ、そこにはしばしば共時的現象が生じる。その現象は因果律によっては説明できない。しかし、そこに意味のある一致の現象が生じたことは事実である。そのことを出来る限り正確に記述しようとしたとき、それは「科学」なのであろうか。それは広義の科学なのだという人もあるだろう。しかし、それはまた広義の宗教だとも言えるのではなかろうか。つまり、そこには教義とか信条とかは認められないが、自我による了解を超える現象をそのまま受け入れようとする点において、宗教的であると言えるのではなかろうか。
宗教はもともと人間の死をどのように受けとめるか、ということから生じてきたとも言うことができる。死をどううけとめるのかという点から生じてきた体系、といっても、それは単なる知識体系ではない。たとえば、仏教においては戒・定・慧の重要性が説かれるように、戒を守ることや禅定の体験を通じて得られる知こそ意味があるのである。
しかし、近代人は既に述べたように自我が肥大し過ぎて、過去の宗教の体系を単なる知識系として見ようとすることもあって、なかなか受けいれられない。従って既存の宗教を信じられなくなるのだが、何を信じようと信じまいと、人間にとって死は必ず存在するのである。最初はいかに生きるかに焦点があてられていた心理療法においても、死をどう受けとめるかが問題にならざるを得なくなった。ユングは彼の患者の約三分の一は、この世によく適応している人だったと述べている。いかに適応している人でも、死の問題は残る。ユングのもとに来たこれらの人は、いかに生きるかということよりも、いかに死ぬかという問題のために来たと言ってもいいだろう。』
感想
一通り拝読させて頂き、消化できたとは言い難いのですが、一番印象に残ったことは、
「開かれた態度」-「共時的現象(因果律では説明できないが、意味ある一致の現象)」-「自己治癒力(正面から苦しみと向き合うこと)」ということでした。
特に、この中で“共時的現象”については、もう一歩踏み込んでその実体を知りたいと思いました。調べたところ、『ユングと共時性』と題する本があったので、こちらも読んでみたいと思います。
宗教と科学の接点1
30年以上前の話です。決して重たいものではなかったのですが、自分捜しをしていた時期があり、そのときに読んだ本の中に河合隼雄先生の『明恵 夢を生きる』という本がありました。明恵とは鎌倉時代、40年にわたり夢を書き残した高僧です。
また、本棚を見て思い出しましたが、同じ時期に、C.G.ユングの『元型論 無意識の構造』と『心理学と錬金術』、さらにE.ユングの『内なる異性 アニムスとアニマ』も読んでいました。私の記憶では、この時の自分捜しの解答は、「客観的であること、外から自分を眺められるようになることがとても重要だ」ということだったと思います。
今回の『宗教と科学の接点』は河合先生の著書ですが、C.G.ユングの説や考えも重要な位置をしめています。
鍼を身体への物理刺激(侵害刺激)と考えると、解剖学と生理学は鍼の影響(効果)を考える上で重要な医学です。
一方、「病は気から」などの“気”を“エネルギー”と考えると、ミクロの世界に存在する量子の力学を連想します。
我々が生きている世界はニュートン力学の世界ですが、原子より小さな世界は量子力学の摩訶不思議な世界です。そして、これは間違いなく実在しています。もし、量子力学が発見されていなかったら、半導体は生まれていません。なお、ここにある科学の主役は物理学です。
私は宗教にはあまり関心をもっていませんが、霊や霊能者には興味があり、“完全無欠ではない霊支持者”です。
フロイトとともに心理学の巨星であるC.G.ユングは、母方の家系に牧師で精神科医、そして霊能者として知られていた祖父(ゼムエル・ブライスヴェルク)がおり、祖母のアウグステも有名な霊能者だったそうです。
霊と量子、気と量子、それぞれ何か関係があるのか、これを明らかにすることは極めて難しいものだと思われますが、“量子力学の父”とよばれた、ニールス・ボーアが東洋医学に興味をもっていたという事実は、これらの関係性を意識させます。

ニールス・ボーアは量子論が明らかにした物質観・自然観の特徴を“相補性”という概念で説明しています、ボーアはこの“相補性”を表すシンボルとして古代中国の「陰陽思想」を象徴する“太極図”を好んで用いたとのことです。このことは、「量子論を楽しむ本」の中に書かれていました。
※ご参考:ブログ「量子論1」
以上のような思いが交差し、河合先生の『宗教と科学の接点』には、何が書かれているのだろうか、是非、読んでみたいと思った次第です。
なお、ブログは何とか理解できた個所、直観的に「これは」と思った個所(目次の黒字部分)を取り上げていますが、散発的でまとまりに欠けます。
目次
第一章 たましいについて
●はじめに
●トランスパーソナル学会
●日本の状況
●人間存在
●たましいとは何か
●西洋近代の自我
●東洋と西洋
第二章 共時性について
●共時性とは何か
●易
●共時性と科学
●共時性と宗教
●ホログラフィック・パラダイム
●心身の相関
●実際的価値
第三章 死について
●死の恐怖
●死の位置
●瀕死体験
●銀河鉄道の夜
●「知る」ということ
●死後性
第四章 意識について
●無意識の発見
●いろいろな意識
●東洋の知恵
●スーフィー的意識の構造
●意識のスペクトル
●ドラッグ体験
●修行の過程
第五章 自然について
●人と自然
●自然とは何か
●自然・自我・自己
●東西の進化論
●昔話における自然
●「自然」の死
第六章 心理療法について
●心理療法とは何か
●自己治癒の力
●治療者の役割
●コンステレーションを読む
●意識の次元
●宗教と科学の接点
あとがき
第一章 たましいについて
●はじめに
・宗教と科学の問題は21世紀の人類を考える上で極めて重要な問題である。
・『筆者[河合隼雄先生]はもともと数学科の出身であるが、その後、臨床心理学に転じ、生身の人間と取り組まねばならぬ領域にはいりこんだため、人間を研究対象とする上での方法論、科学論には常に関心をもち続けてきたが、心理療法の経験が深まれば深まるほど、人間の宗教性についても考えざるを得なくなり、文字どおり科学と宗教の接点に立たされることになったと言えるのである。そのような体験を踏まえて、本書において宗教と科学の接点の問題について論じてみたい。ただ、ニューエイジ科学運動においては、深層心理学はもちろんであるが、理論物理学、大脳生理学、生物学、生態学、文化人類学、宗教学など実に多岐にわたる専門分野が関連してきて、到底それをすべてカバーして理解することは不可能である。そこで、筆者としては、もっぱら自分の専門分野である心理療法家であるという立場を生かしつつ、筆者の能力の及ぶ範囲内において、この問題を論じてみたいと思っている。これが機縁となって、わが国の各分野から宗教と科学についての討論が生じてくるならば、まことに幸せであると思っている。』
●人間存在
・『たましいとユングが呼んだものと、どのように接触してゆくかということを、人間はいろいろと考え出し、それを宗教という形で伝えてきた。宗教はそれぞれ特定の宗派をもち、それぞれがたましいにいかに接するか、それをどのように考えるか、などの点について厳格な理論や方法を有してきた。しかし、ユングはたましいを宗教としてではなく、あくまで心理学として研究しようとした。すなわち彼は、固定した方法や理論、つまり儀式や教義を確定するのではなく、個々の場合に応じてたましいの現象をよく見てゆき、それを記述しようと試みたのである。もちろん、古来からの宗教の知識はその点において極めて有用であり、その多くを利用はしたが、どれか特定のものに頼ろうとはしなかった。
たましいの現象は不思議なことや不可解なことに満ちていた。ユングはそれらを真剣に観察し記録していったが、多くのことに関しては発表してもおそらくは理解してもらえないだろうと思い、公表を長らくためらったものもある。公表した後も、彼は死の時まで自分の行っていることに対する方法論についてあいまいであったり、直観に頼って理論的な詰めをおろそかにしたりするという欠点のためもあったが、何しろ彼の考えが時代の流れをあまりにも先取りし過ぎていたためと言えるであろう。』
●西洋近代の自我
・『人間存在を全体として、たましいということも含めて考えようとすることは、宗教との必然的なかかわりを生ぜしめる。しかし、そこであくまでもたましいの現象を探求してゆこうとする態度は科学的と呼んで差し支えないものであり、ここに科学と宗教の接点が生じてくるのである。
しかし、そんなことを言っても、たましいなどということを対象とすること自体、既に科学的でない、と反論する人もあろう。つまり、たましいなどという測定不能なものは科学の対象外なのである。この点をどう考えるべきであろうか。これを考えるためには、西洋近代に確立された、自我の問題について少し考察する必要があるだろう。』
・自我とは自分と他と切り離した独立した存在として自覚し、自立的であろうとするところに特徴がある。このような自我によって外界を客観的に観察できるのである。
●東洋と西洋
・東洋人は西洋人のように自と他をそれほど切り離して考えていない。
・外界と内界などという区別を最初から立てていない。
・仏教は哲学、宗教、科学、などを未分化のまま包摂しつつ壮大な体系を持っている。その上、注目すべきことは、このような仏教の体系を見出した僧たちは、西洋の自我と異なる意識状態の中で、それを見出したと考えられる。
第二章 共時性について
●共時性とは何か
・『宗教と科学の接点を考える上において、ユングが提唱した、共時性(synchronicity)ということを取りあげることが必要であると思われる。最近、小野泰博が「宗教に何が問われているか」という論文において、共時性の問題を取りあげて論じているが、これまでのところ、わが国においても正面から論じられることが少なかった。というのも、これは論じることの難しいものであり、ユングもこのことを発表しようとしながら、「長年にわたってそれを果たすだけの勇気を持たなかった」と述べているほどである。彼はこのような考えを、相当早くからもっていたが、公的に発表したのは、1951年にエラノス会議において、「共時性について」という講義を行ったのが最初である。
ユングによる共時性について、まず簡単に説明しよう。ユングは彼の心理療法の過程のなかで、「意味ある偶然の一致」の現象が、相当に、しかも心理療法的に際めて意味深い形で生じることに気づいた。彼は1920年代半ば頃から、共時性の問題について考えていたが、その頃の体験として次のような例をあげている。彼の治療していたある若い婦人は、決定的な時機に、自分が黄金の神聖甲虫を与えられる夢を見た。彼女がその話をユングにしているときに、神聖甲虫によく似ている黄金虫が、窓ガラスにコンコンとぶつかってきたのである。この偶然の一致がこの女性の心をとらえ、夢の分析がすすんだことをユングは報告しているが、このうような例が、心理療法場面ではよく生じるのである。
こんなのを聞くと、それこそ「偶然の一致」で、「意味のある」などと大げさに言う必要もないと思われるだろう。しかし、もっと劇的なことは割にあって、特に筆者は夢分析を行っているので、夢と外的事象の一致という形で、このことを体験する。たとえば、夢で知人の死を見た翌朝、その人の死亡を知らせる電話を受けて驚いた人もあった。人間の死と関連して、このようなことは起こりやすいようであり、多くの類似の体験がユング派以外の夢の研究者によっても報告されている。たとえば、メダルト・ボスは多くのこのような類の夢を発表しているので興味のある方は、それを参考にして頂きたい[「夢 その現存在分析」]。』
●共時性と科学
・西洋の近代は因果的思考に頼りすぎていて一面的になっているとユングは考えている。
・中国人は現象を全体的にとらえる。それは史観にも現れている。
・アメリカ人は中国人の史観を理解できない。アメリカ人のいう本質とは事象の中に因果関係の連鎖を読みとることであり、中国の歴史の本質は、アメリカ人から見て末梢的と思える事象をすべて読みとった後に、全体のなかに浮かびあがってくる姿を把握することである。
・中国の文明史を見ると、共時性に関する深い知恵と、因果律を追求する科学の萌芽などの混在が認められる。
・近代の科学を代表するニュートンもガリレオも、現代において言う「科学的」思考のみに頼って事象を見ていたわけではない。
・ユングは共時性の概念の先駆者としてライプニッツを高く評価している。ライプニッツは哲学者であるが、微分積分の発見者で、二進法の道をひらき、動力学を創出した。ライプニッツは「単子(モナド)」という概念を導入し、ひとつひとつの単子は全宇宙を反映するミクロコスモスであり、単子は直接相互に作用を及ぼし合うことはないが、「予定調和」に従って、互いに「対応」したり「共鳴」したりすると考えた。彼のいう「対応」や「共鳴」の現象は、ユングのいう共時的現象と等価のものと考えられる。
・『ミクロコスモスとマクロコスモスの対応という考え方は、ミクロコスモスとしての人間をマクロコスモスとしての宇宙に関連づける思想であったが、西洋の近代自我が自我を世界から切り離し、自我を取り巻く世界を客観対象として見ることを可能にしたとき、そこに観察される事象は、個人を離れた普遍性をもつことになり、自然科学が急激に進歩したのである。普遍的な学としての自然科学はその後ますます力を発揮し、人間は世界を支配したかの如く見えながら、宇宙との「対応」を失ってしまったという点において、自らを宇宙のなかにどう定位するかという点で、根本的な問題をかかえこむことになった。』
・『自然科学の最先端において、それまでの方法論に対して根本的な反省をうながす問題が生じてきたのである。まず、1906年にラザフォードらによってα崩壊現象が研究され、自然現象のあるものは、単に人間の無知にもとづくものではない本質的な偶然性に支配されていることが明らかにされた。続いて量子力学の分野において、ハイゼンベルクの不確定性原理やボーアの相補性の概念などにより、古典的な機械論的世界観を否定する立場が打ち出されることになった。ハイゼンベルクの不確実性原理は、現象の因果性を論じる前に問題となる物事の決定可能性について論じ、電子の位置と運動量の相方を同時に正確に測定することはできないことを明らかにした。ボーアは光や電子はときには波動のように、ときには粒子のように振舞い、その相矛盾した性質が相補的にはたらくという考えを明らかにし、機械論的なモデルを変更したのである。』
・『ユングが共時性について発表したときは賛否相半ばし、たとえば、ユング心理学についてユング派以外の人間として、よき入門書を書いたアンソニー・ストーも、「共時性に関する彼の著作は、混乱して、ほとんど実際的価値がないと私には思えることを、告白せざるを得ない」と述べている。しかし、一方ではハイゼンベルクやパウリなどの理論物理学者が、この考えに深い理解と共感を示したことも非常に興味深いことである。特に、パウリ[スイスの物理学者、スピンの理論など]はユングと共に、共時性に関する書物を出版するに到ったのである。』
●共時性と宗教
・『共時性の現象の背景に、ユングは元型(Archetypus)ということを考える。ユングの元型は解りにくいし、よく誤解もされるが、ここにひとつのたとえをあげてみる。朝まだ明けやらぬうちに、牛乳配達がくる、小鳥がさえずり始める、そして朝刊の配達がある。この順序が確立しているとき、われわれは、小鳥がさえずっているから、もう牛乳が配達されているだろう、とか、小鳥がさえずっているから、もうすぐ朝刊が配られるだろう、などという。しかし、これらの事象の間に因果関係は存在していない。これらの事象の背後にある、人間生活にとっての朝、明け方、というものによって、これらは布置されているのである。われわれは朝そのものを見ることも、手に触れることもできない。しかし、それは明らかに事象にあるまとまりを与え、それは意味をもっている。これが文化の異なるところに行けば、個々の事象は変わるだろう。あるところでは、新聞配達が来たから、そのうちに小鳥がさえずるだろう、と言うかも知れぬ。あるところでは新聞や牛乳の配達などまったく無いだろう。しかし、それら文化の異なるところにおいても、「朝」が人間にとってどのようなはたらきをするかは、たとえば、「活動の始まり」などの言葉によって、ある程度は一括的に記述できるであろう。
ユングは外界のみではなく、人間の内界にも、われわれの意識を超えた一種の客観界が存在すると考えた。彼はそれを類心(サイコイド)領域と呼んだりした。外界において既に述べたような「朝」という現象が生じるとき、内界においてもそれに呼応する「朝」のパターンが活性化され、人間の意識は外的現象を「朝」として知覚するのだ、と考える。人間はこの世に生まれるとき、何もない外界に生まれてくるのではなく、既にいろいろなものが準備されているところに生まれてくるように、その内界にも既にいろいろなパターンが可能性として存在している状態として生まれてくるのである。それだからこそ、人間は人間として行動するわけである。つまり、人間はまったくの白紙として生まれてくるのではなく、そのあらゆる行動において、ある種の潜在的なパターンを背負って生まれてくる。ユングはこのように考え、潜在的な基本的パターンを元型と呼んだ。』
●心身の相関
・『古来からつねに論じ続けられてきた心身相関の問題も、共時性との関連で考えてみるべきと思われる。心身に何らかの関係があることは古くから指摘されてきたし、われわれも日常生活においても経験している。恐ろしいと感じたときに冷汗が出たり、悲しいときに涙が出たりする。このときは単純に、自分の感情の変化が身体の変化を生ぜしめると考えがちだが、一方では、周知のように、ジェームズ・ランゲ説というのがあって、むしろ、身体的変化が先行し、それが原因で感情の変化が生じると主張されている。こんなのを見ると、日常に生じている単純な事象でも、原因-結果という見方は容易に反転せしめ得るほどのものであることがわかる。つまり、心身相関の問題はなかなか単純なことではないのである。』

ジェームズ・ランゲ説:哲学者ジョン・デューイによって開発され、19世紀の2人の学者、ウィリアム・ジェームズとカール・ランゲにちなんで名付けられました。理論の基本的な前提は、生理的覚醒が感情を引き起こすということです。
Youtubeに「情動の2要因説」を説明された分かりやすい動画がありました。なお、こちらは宮川 純先生の”すき間時間の心理学”というサイトです。
●実際的価値
・『アンソニー・ストーが共時性の考えには実際的価値がないと指摘していることは述べた。一見するとそのように思えるのも無理からぬところがあり、筆者もかつてそのように考えたことがある。因果律による場合は、原因で明らかにしそれに操作を加えることによって結果を異なったものに変えられる。しかし、共時的現象というのは、ただ「そうだ」と言えるだけで、そこから何らの有用な操作を引き出すことができない。しかし、その後、筆者は心理療法家としての経験を増すにつれて、共時性の考えの実際的価値について思い到るようになった。』
心理療法を受けに来る人たちは、軽症の場合を除いて、その葛藤が合理的、一般的な方法によって解決できない場合が多い。いくら考えてもよい解決策が浮んで来ない。まさにボームの言うように思考は思考を超えるものの濾過器として働き、考えれば考えるほど問題解決のいと口がなくなってしまう。このようなとき共時的現象に心を開くときは、偶然として一般に棄て去れそうな事柄が、思いがけない洞察への鍵となることを、われわれはよく体験する。たとえば、ユングの例であれば、黄金虫の突然の出現が、この患者のそれまでの考えを改めさせるきっかけとなったのである。
ここで大切なことは、共時性の現象はそれを体験する主体のかかわりを絶対に必要とすることである。つまり、黄金虫の侵入は偶然として処理し得る。しかし、それを共時性の現象として受けとめることによって、そこに主体のコミットメントが生じる。近代合理主義によって硬く武装された自我は、ある程度の安定はもつにしろ、世界への主体的なかかわりを喪失する危険が高い。ユングがよく記述する、何もかもがうまく行っていて、しかも不安で仕方ないとか、孤独に耐えられなくなるような例が、これに当たるだろう。共時性の現象を受け容れることによって、われわれは失われていた、マクロコスモスとミクロコスモスの対応を回復するのだとも言える。つまり、コスモロジーのなかに、自分を定位できるのである。
しかし、黄金虫の例や、あるいは筆者の易の例は簡単に冷笑の対象ともなり得る。それは極めて一般性を欠いた事象であるからである。しかし、普遍的に正しいことばかりに支えられて生きていて、その人は個人としての人生を生きたと言えるのだろうか。因果律による法則は個人を離れた普遍的な事象の解明に力をもつ。しかし、個人の一回かぎりの事象について、個人にとっての「意味」を問題にするとき、共時的な現象の見方が有効性を発揮する。そして、心理療法においては、後者の方こそが重要なのである。』
・『家庭や人間関係の問題を考えるとき、単純に因果的思考に頼ると、すぐに「原因」を見出し、誰かを悪者にしたてあげることが多い。たとえば、母親が悪の根源のように思われたりする。しかし、全体の現象を元型的布置として見るときは、誰かが「原因」などではなく、すべてのことが相関連し合っている姿がよく把握され、そのような意識的把握と、その全体の布置に治療者が加わってくることによって、事態が変化するものである。つまり、誰が悪いかと考えるよりは、皆がこれからどのようにすればよいかと考えることによって、解決の道が見出されてくるのである。実際、われわれ心理療法家が、困難な問題をかかえている人にお会いすると、本人も家族も、自分を悪者にされるように、あるいは自分以外の誰かを悪者に仕立てるために一生懸命で、バラバラになって硬直した関係をつくりあげている。またなかには、そのようなことを助長するような発言をする「教育者」とか「治療者」も多くいる。こんなときに、因果的思考から全員が自由になるだけでも、家族関係は変わるし、視野も広くなるし、回復への道が発見しやすくなるのである。このように、共時性に注目する態度をもつことは、実際的価値を有していると思われる。』
定款作成物語
私が所属する団体は、ある目的のために「非営利型の一般社団法人」を目指すことになりました。
以下の図で見ると、“法人税法上の取り扱い”と書かれた色付きBox内の中央になります。これは公益法人に位置づけられる、一般社団法人というものになります。
当初はお金を払ってでも司法書士の先生にお願いした方が良いのではないかと考えましたが、結果的には、手間をかけてでも自前で作るという選択は正解でした。それは定款は会社経営のルールブックであり、定款を深く理解すること、そして、法人立上げに関わる全ての人が理解しようとすることがとても重要であることを知ったためです。
以下の図にあるように、最初に取り組むべきは“定款”の作成です。
ネット上に多くの情報があるのですが、それらを調べつつも、やはり一冊は読んでおきたいと思い、購入したのは『改訂4版 一般社団法人・一般財団法人の実務 設立・運営・税務から公益認定まで』という本でした。
一通り目を通し、いずれにしても定款を作らなければならないのは決まっていことなので、内容を一つ一つ吟味し理解することが大切であると考え、本書1-3の「定款作成の手引き・一般社団法人(社員総会+理事+監事)」に書かれている条文を書き写すという作業に移りました。そして、「こんな感じかなぁ」と思いながら、微妙に編集していきました。
この行動は悪くはなかったと思うのですが、“定款のひな型”については、「日本公証人連合会」のサイトにある“定款等記載例”の中から、最も近いものを利用する方が良かったかも知れません。

『以下の定款の記載例は、起業者の方の参考に供するため、飽くまでも一つの事例として提示したものであり、網羅的な内容とはなっておりません。したがって、法人の目的、株式の内容、法人の機関設計、役員の責任軽減の有無等についてよく御検討いただき、公証人にも事前に御相談の上、作成されるようお願いいたします。』
何とか、自分なりの“定款ひな型”はできたので、司法書士あるいは行政書士の先生に、確認事項を列記したものを用意し、お話を伺って一気に完成させてしまおうという作戦を立てました。
ネット検索すると、中には初回1時間相談無料という事務所もあり、まずは当院の近くにある事務所の先生に訪問してきました。
「定款の内容を確認するとなると、それはまさに業務になってしまうので無償ではできない」とのことで、あっさり、作戦は未遂に終わってしまいましたが、貴重なアドバイスを頂くことができました。
1.うまくいっている一般社団法人に共通していること
①自分たちの団体を分かりやすく正しく公表していること。
②常に最新の状況を知ってもらえるように、情報をアップデートし続けていること。
『これにより世間の人は協力しよう、支援しようという気持ちになるものです。そして、このことが最も重要なことです。怪しい一般社団法人ほど、これらのことができていません。また、一般社団法人が組織的に壊れていく原因の多くは、お金に関わるところです。お金の管理がしっかりできないと問題が大きくなり、遂には解散ということになっていきます。優れた団体のサイトには情報がたくさん出ているので、それらを参考にするといいですよ。』とのお話でした。
第1回目の作戦は失敗に終わったものの、あわよくば何とかなるのではないかと思い、懲りずに第2の先生を見つけました。「定款があるならそれを持参してください」とのコメントもあり、「もしや。。。」と期待しつつ、その日がやってきました。が、結果は2連敗でした。ただ、今回も色々なお話を伺うことができ有意義な時間をもてました。
最後に、『「埼玉県よろず支援拠点」という支援団体があるので、そこに問い合わせてみるのも一案ですよ。』とのアドバイスを頂き、その日の夜に“問合せフォーム”を使って依頼をかけました。

『「埼玉県よろず支援拠点」は、経済産業省・中小企業庁が、全国47都道府県に設置する経営なんでも相談所です。
中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する方の売上拡大、経営改善など経営上のあらゆるお悩みの相談に無料で対応します。』
すると、翌日、早速お電話を頂きました。お話では『こちらより、“創業・ベンチャー支援センター”の方が適しているので、そちらを紹介させて頂きます。』とのことでした。そして、アポ取りをしました。
創業・ベンチャー支援センターでは月2回、「司法書士相談会」というのを開催されているとのお話だったので、すぐに予約を入れました。受付の方からも、『作ったひな型をメールで送ってください。事前に先生に見て頂きます。』とのことで、遂にたどり着いたなという気分でした。
実は、この創業・ベンチャー支援センター訪問の翌日に、埼玉会館の近くにある、の“公証センター”にアポが取れていました。本当は、この日の創業・ベンチャー支援センター訪問で、概ね完成させ、最後のチェックを公証センターの先生に見てもらおうという狙いだったのですが、それは外れ、順番が逆になってしまいましたが、それでもゴールは近いという気持ちでした。
なお、公証センターにアポが取れたのは、“基金”と“寄付”と“会費”の位置づけなど調べたのですが、ピンと来なかったため公証センターに問い合わせたところ、電話に出られた受付の方が「相談に来られますか?」との嬉しい提案があり、すかさず、それにのったというものでした。

『定款認証には,紙(書面)の定款を認証する方法と、インターネットを介して電磁的記録の定款(電子定款)を認証する方法とがあります。このうちインターネットを利用した電子定款認証の利用方法は、日本公証人連合会のホームページや法務省の専用サイトに分かり易く説明されていますので,ご参照ください。』
この公証センターの訪問で、ついに定款のひな型はほぼ完成しました。ほぼというのは、いくつか自信のない箇所が残っているという意味です。これらの宿題は、創業・ベンチャー支援センターの「司法書士相談会」でクリアにする予定です。
“定款”は会社のルールブックとされ、法人立上げメンバー全員で検討し、納得いくものを作り上げる必要があります。
ひな型完成に大手をかけていたわけですが、社員の対象範囲をどうするか、理事会を設置するかどうかなど、メンバーとの検討会の中でいくつか課題が浮上し、ゴール直前で数歩後退する事態になりました。
私自身も特に最初は「定款=事務手続き」という認識で、決して高くなかったのですが、この後退は他のメンバーの定款に対する関心を高めるきっかけとなり、正しいプロセスを経て、ゴールを切れるという見通しが立ったという意味でとても良かったと思います。思わぬ収穫という感じです。
ただ、新たな宿題が降りかかり、定款との悪戦苦闘は今しばらく続くことになりました。
非営利型一般社団法人
仕事とは関係ないのですが、非営利型一般社団法人について調べることになりました。
非営利型一般社団法人と聞いて思ったのは、いわゆる、一般社団法人と何が違うのか、これらは同じカテゴリーに含まれる異なるタイプの法人なのかという疑問でした。ところが、これらはいずれも一般社団法人であり、一般的なものを“普通型”と呼び、それと区別して“非営利型”という型があるということでした。
では、非営利型一般社団法人になるためには、届出段階で何か違うのか、そうではないのかがよく分からず、さらに調べてみると、「非営利型一般社団法人であるかどうかの判断は税務当局が担っている」ということを知り、早速、最寄りの税務署に問い合わせてみました。
今回のブログはその税務署への電話で分かったこと、税務署の方から教えて頂いた国税庁の資料、さらに『図解 社団法人・財団法人のしくみ』を読んで知ったことを中心にまとめたものとなっています。かなり、限定的な内容ですが概要をお伝えすることはできるのではないかと思います。
■非営利型一般社団法人とは、一般社団法人と異なる位置づけのものではなく、一般社団法人の中の一つの型です。図を見ると、”一般社団法人”の中で、「非営利型法人の要件に該当するか」が「はい」であれば、<非営利型法人>になります。
なお、非営利型法人の要件は2つありますが、”非営利性が徹底された法人”に該当する場合は以下の①になります。
ここで注目すべきは、1と2です。これを見ると、いずれも『定款に定めていること』と書かれています。税務署の方の話でも、上記1(剰余金の分配)と2(解散時の対応)が、“定款”に明確に記述されていれば、その事実をもとに税務署が、この社団法人は<非営利型法人>として認めるということでした。なお、上記のスライドは以下の資料の中にあります。
『一般社団法人・一般財団法人と法人税-国税庁』(4枚)
次の資料は、『新たな公益法人関係税制の手引-国税庁』(87枚)からになります。
この図では水色破線枠内、青色Boxになります。
以下は「一般社団法人の設立手続き」です。
概要
1.社団法人の設立
・一定の手続きと登記だけで設立できる。
2.定款
・設立時に重要なことは定款の作成である。
-定款は法人の組織活動の根本規則である。
-記載内容によって法人の在り方が変わる。
-内容は次の3つに分けられる。
1)「必要的記載事項」…記載しないと定款が無効になる。(目的、名称、事務所の所在地など)
2)「相対的記載事項」…記載しないと定款が無効になる。(社員総会の決議要件など)
3)「任意的記載事項」…法律内であれば任意に記載できる。
3.機関
・社員総会は意思決定機関である。
・理事が3人以上いる場合は、理事会を置くことができる。
・業務執行は代表理事が選任されている場合は、代表理事が行うが、選任されていない場合は理事が関与する。
・監事のみ、あるいは会計監査人と監事を併せて置くこともできる。
4.社員
・社団法人にとっての社員とは、「定款で定めるところにより経費を支払う業務を負い(一般法27)、社員総会で評議権を行使できる者(一般法48Ⅰ)」という。
・設立時には2人以上が必要である。
・社員の資格は定款で自由に決めることができる。
・社員は任意で退社することもできるが、定款で退社を制限することも可能である(一般法28)。
5.理事の役割と責任
・理事会は別途定款にさだめている場合を除き、業務を執行して法人を代表する。
・理事は社員総会の決議で選任される。
・理事の人数は1人以上。
・理事の任期は原則として2年以内。
・理事と一般社団法人は委任関係にある。
-理事は法人に対して善管注意義務を負う(民法644)。
-法令・定款・社員総会の決議を尊守して忠実に職務を行う「忠実義務」を負っている(一般法83)。
-社員総会での説明義務(一般法53)。
-競合取引・利益相反取引の制限(一般法84Ⅰ)。
-社員等に対する報告義務(一般法85)。
-法人や第三者に対する損害賠償責任(一般法111、117)。
6.理事会
・一般社団法人では任意の機関である。
7.監事
・一般社団法人では監事は任意であるが、理事会を設置した場合は必須となる。
・監事は理事の職務の執行を監査し、監査結果に基づき監査報告を作成する。
・監事は理事が作成した計算書類・事業報告・附属明細書を監査する。
・招集権者に理事会の招集を請求することができる。
・理事が不正行為や法令・定款違反をした場合などに、理事・理事会に報告する。
8.基金の意義
・基金とは社団法人に拠出された金銭、その他の財産をいう。
・社団法人は基金の拠出者(「社員」とは限らない)に対して、一般法や当事者間の合意に基づいて返還義務を負う。
・基金制度は剰余金の分配を目的としないという社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達して、
社団法人が安定して活動を行うという「財産的基礎」の維持を図るための制度である。
・基金は貸借対照表上では負債ではなく、純資産の部に計上する(一般法規則31)。
・基金制度は法人の任意であり、定款に「基金の拠出者の権利に関する規定」と「基金の返還の手続」を定めることに
よって基金制度を設けることができる。
9.基金の募集と返還
・具体的な基金の募集手続きは一般法によって以下のとおり定められている。一方、基金の返還は定時社員総会の決議によって、貸借対照表の純資産が「基金の総額」等を超える場合に限り、その超過額を限度として一定の期間内に行うことができる(一般法141ⅠⅡ)。
ご参考:社団法人について
社団法人については、以下のサイトに分かりやすい説明が出ていました。

まずはそもそも「社団」とはどういう意味なのでしょうか。
社団とは、一定の目的をもった人の集まり、団体を言います。そして、「社団法人」とは、法律によってその団体に「法人格」が与えられた法人を言います。更に、社団法人はその根拠となる法律によって「社団法人」、「一般社団法人」、「公益社団法人」の3つに分類されます。
「法人格」とは、その団体名義で銀行口座を開設、財産(土地・建物などの不動産や自動車など)を所有するなど、その団体名義で法律行為を行なうことができる「法律上の人格」を言います。
人権について考える
入江 杏先生は上智大学グリーフケア研究所非常勤講師をされています。そして、悲しみについて思いを馳せる会の「ミシュカの森」の主宰をされています。
グリーフケアとは、「家族や親しい友人との別れ、死別、あるいは生きがいや希望の喪失など、喪失に胸を痛めている人、喪失から生じる悲嘆に苦しんでいる人に寄り添い、支えようとする活動である」。これは、グリーフケア研究所の島薗 進所長のお言葉です。

クリック頂くと、YouTubeが立ち上がります。約16分です。
こちらは、”上智大学グリーフケア研究所”さまのホームページです。
入江 杏先生は2000年12月30日に発生し、いまだ未解決の「世田谷一家殺害事件」の犠牲者のお一人、宮澤泰子さんのお姉さまでもあります。今回の『悲しみとともにどう生きるか』では編著(編集と著作)をされています。
この本は6つの章に分かれていますが、第一章から第五章までは2008年から2019年に行われた講演が基になっています。第六章はグリーフケア研究所所長の島薗先生の書下ろしで、「グリーフケア」や「ミシュカの森」について書かれています。
詳細は次の通りです。
第一章 「ゆるやかなつながり」が生き直す力を与える 柳田邦男 2008年12月27日 玉川区民会館ホール
第三章 沈黙を強いるメカニズムに抗して 星野智幸 2016年12月25日 上智大学
第四章 限りなく透明に近い居場所 東畑開人 2018年12月9日 芝コミュニティはうす
第五章 悲しみとともにどう生きるか 平野啓一郎 2019年12月14日 ビジョンセンター田町
第六章 悲しみをともに分かち合う 島薗 進 “書下ろし”
ブログは芥川賞作家でもある平野啓一郎先生の第五章について触れています。この五章に書かれているのは主に、“死刑制度のこと”、“人権のこと”、そして“コミュニケーションと分人”についてです。“分人”には多様性が求められると思いますが、背景には“客観的&主体的な変化と順応”ということが隠れているように思います。
この中で“死刑制度のこと”、“人権のこと”は、私自身64年も生きてきて、まともに考えたことが一度もなかったことを思い知りました。また、書かれている内容はとてもインパクトの大きなものであり、自分自身はどう考えるのだろうか、頭の中を整理したいと思いました。
第五章の小見出しは以下の通りです。(ブログでは最初の2つには触れていません)
●「カテゴリー」として扱われがちな被災者や事件の被害者
●当事者でないからこそ書けることがある
●死刑制度への考え方
●「なぜ人を殺してはいけないか」への応答として生まれた『決壊』
●心から死刑は廃止するべきだと思った理由
●個人の責任に収斂させる死刑は国家の欺瞞
●死刑制度は犯罪防止にならない
●犯罪被害者へのケアが不十分
●犯罪の被害者の心の中に芽生える感情は複雑
●「赦し」と「罰」は同じ機能を果たす
●共感や同情ではなく、人権を権利の問題として捉える教育が必要
●「負け組」に対する積極的な否定論
●すべての人の基本的人権を尊重するという大前提
●自死して償うという日本的発想
●社会の分断と対立の始まり
●対立点からではなく、接点からコミュニケーションを始める
●分人の集合として自分を捉える
●人生の経過とともに分人の構成は変わっていく
●愛する人を喪失した人へ
●死刑制度への考え方
・平野先生は現在、死刑制度を廃止すべきという立場であるが、『決壊』を書く以前の20代ぐらいまでは心情的には死刑制度に肯定的な立場の近い所にいた。しかし、はっきりした考えは持っておらず迷っていた。
・ヨーロッパではベラルーシ以外はすべて死刑制度が廃止されている。今も死刑制度が残っているのは、アジア諸国、中東、アメリカ合衆国の一部の州などである。
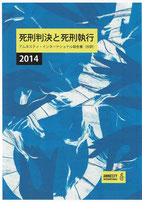
以下はネットで見つけた記事です。
この中に“死刑制度の存廃をめぐる議論のポイント”という箇所があり、項目として8つ挙げられています。
■根本的な思想・哲学
■死刑に犯罪抑止力があるかどうか
■誤判・冤罪の恐れをどう考えるか
■被害者・遺族の心情をどう考えるか
■犯人の更生可能性について
■世論調査をどうみるか
■死刑廃止が国際的潮流である点をどうみるか
■死刑は憲法に違反しないか
●「なぜ人を殺してはいけないか」への応答として生まれた『決壊』
・これは、TBSの『NEWS23』で収録された若者たちとの対話での発言。その時の出演者からは的確な回答は出なかった。
・『決壊』という作品の中で、平野先生は「なぜ人を殺してはいけないか」という根本的な問いに対して、その理由を説得力を持って書きたいと思っていた。
●心から死刑は廃止するべきだと思った理由
・警察の捜査に対する不信感(袴田事件など)。
・「人は殺してはいけない」という絶対的な禁止に、例外を設けてはいけないという考えが自分の中で確かなものになった。人の命は、「場合によっては殺していい」という例外を作ってはいけない。
・死刑は加害者を同じ目に遭わせてやりたいという身体刑である。
●個人の責任に収斂させる死刑は国家の欺瞞
・立法的、行政的な救済を必要とする犯罪被害者への支援が十分とはいえない状況で、事件に対して司法が死刑を宣告して、その人を社会から排除し、あたかも何もなかったかのような顔をするのは国家の欺瞞ではないか。
・社会の責任が大きいような環境で育った人が罪を犯した時、それをその人の「自己責任」にすべて収斂させて、死刑にすることで終わらせてはいけないのではないか。
・社会的責任は一切なく、あくまでその個人に全ての責任があるとする犯罪の場合であっても、国家がその犯罪者と同じ次元に降りてきて、事情があれば人を殺していいという判断(死刑)をするのは良くないのではないか。
・『我々の共同体は人を殺さない。一人ひとりの人間は基本的人権を備えていて、生存については絶対的に保障されている。我々の社会はそういう社会であるという前提は、例外的にそれを破る人が出てきても崩してはならないはずです。だから、あなたは人を殺したかもしれないけど、我々の社会はあなたを殺さない。それが我々の社会です、ということを、あくまで維持しなければならないのではないか。おまえが殺したから俺もその次元にまで下がっていって、同じように殺すということは、許されることなのか?
何かよほどの事情があれば人を殺していい、という思想自体を社会の中からなくしていかないと、殺人という悪自体が永遠になくならないのではないかと考えるわけです。』
●死刑制度は犯罪防止にならない
・死刑囚にも自分の死が怖いと思う人とそうでない人がいる。
・“拡大自殺”とは死刑になりたいから多くの人を巻き添えにした殺人を起こすことである。
-2008年6月:“秋葉原通り魔事件”では7人が死亡。
-2021年12月:大阪ビル放火事件“では25人が死亡。
●犯罪被害者へのケアが不十分
・全国犯罪被害者の会では、附帯私訴制度(民事裁判を起こすことなく、刑事裁判の中で損害賠償を求める手続きができる仕組み)の実現が一つの目標になっているが、これは遺族が裁判にうまく関与できない状況になっている。
・被害者に対する誹謗中傷などに対する被害者をケアするシステムが不十分である。
・被害者が十分に守られていない状況では、人は「被害に遭った人たちはあんなにかわいそうな目に遭っているのに、何で加害者の人権が守られなきゃいけないんだ」という反発から、「死刑制度は反対」とか「加害者にも人権はある」という声に社会は強く反発する。死刑制度の議論は、被害者のケアの充実を第一に図っていかない限り、国民が加害者側の人権を考えることは難しい。
・本来は、犯罪被害者の悲しみを癒すことに関わることが大切だが、それは簡単ではないこともあり、被害者の気持ちになり代わって、「犯人を死刑にしろ!」となっていく傾向が強い。
・人権概念の理解の徹底こそが重要であるが、感情的な問題も無視はできない。
●犯罪の被害者の心の中に芽生える感情は複雑
・『犯人は死刑になった後、ご遺族がそれで本当に区切りがつけられたのか、何らかの慰めなり癒やしが得られたのかどうかということは、ジャーナリズムの一種のはばかりからか、怠惰からか、それほど具体的な追跡調査がなされていません。ですから、社会は勝手に、遺族は死刑にならないことには収まりがつかないし、死刑になったらそれで一つ区切りがつくと考えて、犯人が死刑宣告を受けて死刑にされたら、途端に遺族のことはすっかり忘れてしまいます。しかし、実はその時にこそ、遺族は社会の中で最も孤独を感じているかもしれない。加害者を憎むということにおいてのみ被害者の側に立った人たちは、加害者に死刑が執行された途端に、被害者への興味を一切失ってしまいます。もし自分の家族が殺されたなら、という仮定は、一体、何だったのでしょうか?
また、死刑が区切りになるかどうかということとは関係なく、とにかく関わりたくない、死刑も望まず、赦すなんてことももちろんできないけど、とにかくもう思い出したくない、別の人生を歩みたいという方もいらっしゃいます。
死刑で一件落着、それが一つの区切りになるなどという考え方で犯罪被害者の方のすべての感情を物語化することはできない。誰かと話をしたいとか、じっくり一時間、二時間、話を聞いてもらいたいとか、孤独に寄り添ってほしいとか、事件のこととは関係なく、楽しくごはんでも食べに行きたいとか、被害者というカテゴリーにくくられたくないとか……、それは当然、さまざまです。だけど、「被害者の気持ちを考えたことがあるのか」と言う人は、そのうちの「憎しみ」の部分にしか興味がありません。それ以外の部分で、被害に遭った方の悲しみをどういうふうに癒すのかということには、全くコミットしようとしないわけです。これが非常に大きな問題ではないかと思います。』
●「赦し」と「罰」は同じ機能を果たす
・赦しと罰は、何かを終わらせるという意味では同じ機能を果たしているといえる(ハンナ・アーレントの『人間の条件』より)
・被害者の方が“赦し”を選んだ時に、社会はその人の決断をあたたかい尊敬の気持ちで称賛し、抱擁すべきである。決して「あなたは亡くなった人に対する思いが薄いんじゃない?」などと非難することがあってはならない。他者を理解するというのは、自分が決して理解できないことを理解しようと努めることである。
●共感や同情ではなく、人権を権利の問題として捉える教育が必要
・死刑制度の問題から気づくことは、日本人は人権というものに対する教育に失敗していると思うことである。
・『僕自身が小学校で受けた人権教育を思い返してみても、結局のところ、人権というのがよくわからないままだった気がします。小学校の教育の中で多かったのは一種の感情教育で、人がそういう時にはどんな「気持ち」になっているかを考えてみましょうとか「自分が嫌なことを相手にもしてはいけません」という心情教育に偏っていました。他者に対する共感の大事さを説くばかりで、人権という、権利の問題としてきちんと教育されてこなかった気がします。実際、講演[地方自治体の人権週間での講演]の時の作文[小・中学生の作文]も、「相手の気持ちを考えず、嫌な気持ちにさせてすごく悪かった」という結論に至っているものがほとんどでした。この感覚が大人になるまでずっと続いてるので、不祥事で政治家や企業の社長が謝罪する時にも、その理由は「不快な気持ちにさせてしまったこと」です。』
・共感能力が重要であることは間違いないが、人権という権利の問題を考える時に、共感ということが前面に出すぎるのは望ましくない。
・かわいそうかどうかは主観的な感情である。一方、権利とはある前提の中では不変なものだと思う。それ故、主観的な感情とは距離をとり、客観的に向き合う必要があると思う。
・『例えばNHKの番組で、格差社会の中の「相対的貧困」といわれるような状態の人たちの特集があって、そこに登場した女の子の部屋の棚に漫画が並んでいた。そうすると、「貧困っていっているけど、漫画を読んでいるなんてぜいたくだ」「世の中にはもっと大変でかわいそうな人がいる」と、主観的な話になってバッシングが起きる。結果、こんな人たちは別に救う必要がないとか、特集する必要はないといった否定的意見が出てきます。
これは生活保護バッシングにも似ています。「生活保護とかいいながらパチンコしているじゃないか」と。「同情に値しない。かわいそうじゃない」「自己責任だから、そういう人たちを救う必要はない」という論調が日本社会の一部に強くあります。これもやはり、人権の問題としてその人たちの生存を考えているのではなく、かわいそうかどうかという共感の次元で捉えてしまっているがゆえに起こっていることです。』
●「負け組」に対する積極的な否定論
・「勝ち組」、「負け組」は当初、株式投資に関し企業を判断するものとして出てきた。その後、新自由主義的の風潮の中でいつの間にか人間についてもいわれるようになった。そして、負け組の人たちは努力が足りない怠け者だというような論調が社会の中で語られるようになった。
●すべての人の基本的人権を尊重するという大前提
・『人権というのは、一人ひとりの人間が生まれながらにその生命を尊重されて、それは誰からも侵されないという権利で、ヨーロッパの思想史の流れの中で考えられたものです。人類の歴史の流れによっては、人間は生まれながらに差別されるのは当然で、一部の人だけが富めばいいという社会がずっと続くこともありえたと思います。しかし、そうはならず、すべての人間が基本的な人権を備えていて、それは絶対尊重しなければいけないという思想に基づいて憲法をつくり、国家を成立させ、そして、国家権力はそれを侵してはいけないという仕組みをつくり上げていった。近代以降のその流れは、僕は基本的に正しかったと思っています。その思想を受け継いでいることを幸福と感じます。
人間には生まれながらにして権利があるという話は、フィクションといえばフィクションですけど、それをたくましい努力で守り抜こうとする思想は、偉大です。
実際には内戦が続いている地域など、基本的人権という考え方が通じなくて、国家が溶解したような状態で、ひたすら弱者が暴力の被害に遭っているという現実もあります。本当にそういう社会でいいのかと考えた時に、僕はやはり一人ひとりの人間は絶対に殺されてはいけないし、国家の主権者として生存権や社会権が守られているという大前提を崩すべきでないと考えています。
ですから、学校でいじめが起きている時に、かわいそうなことをしているからやめましょうと諭すことも大事ですが、まず、いじめるということは相手の教育を受ける権利を侵害していることだから、やってはいけないことだ、と教えなくてはならない。人を殺すというのは、その人が生まれながらにして持っている、誰からも生命を侵害されることがないという権利を奪うことだからやってはいけないことだと教えなくてはならない。
心情的な教育というのをやりながら、一方で、すべての人は、社会の役に立とうが立つまいが、そんなことは関係なくて、生まれてきたからには、自分の命は誰からも侵害されない権利がある、という原則を子どもたちに教えることが非常に重要です。
その上で、僕も自己反省的に、そもそも、どうして自分は子どもの頃、人を殺した人は死刑になっても当然だと思っていたのだろうかということを考えてみました。一つには、漫画やアニメ、テレビの時代劇などで悪者を成敗する勧善懲悪のストーリーが戦後ずっと続いていて、その刷り込みがかなり強いのではないかと思います。漫画や小説などフィクションが与える影響というのは馬鹿にできません。』
●自死して償うという日本的発想
・日本では自死(自殺)は個人として追い詰められた結果ということではなく、一種の社会的な償いとして死ぬべきであるという考えが強くある。社会に命を差し出すことが償いになるという考え方自体を問い直す必要がある。
●社会の分断と対立の始まり
・『ノーベル経済学賞を受賞した経済学者で思想家でもあるインド出身のアマルティア・センが「アイデンティティーと暴力」という本を書いています。その中で彼は、なぜインドで深刻な宗教対立や民族対立が起きるのかということに関して、個人を一つのアイデンティティーに縛りつけてしまうことがすべての社会的な分断、対立の始まりだと分析しています。
社会を分断させたい人、あるいは対立させたい人にとっては、個人が単一のアイデンティティーに収まっていることが何よりも重要なんだと言うんですね。あの人はキリスト教徒、あの人はイスラム教徒というふうに単一のアイデンティティーにくくりつけてしまう。あるいは、あの人は死刑存置派、あの人は死刑反対派というふうに。そこから際限のない対立が始まってしまうわけです。
センは、さらにこう続けます。実際には、人間というのは非常に複雑な要素の集合体である、と。
ある人はプロテスタントであり、同時に二児の父親で、野球はヤンキースを応援していて、音楽はジャズが好きというふうに、一人の人間は複雑な属性を備えている。そうすると、死刑制度を支持するかどうかというような一つのトピックスに関しては対立する部分があるけど、音楽の話をすると、「俺もあのバンド好きなんだよ」と共感する部分があったり、「実は北九州出身で、俺もあの先生に習ったんだ」と、複数の属性を照合し合わせると、どこかにコミュニケーションの可能性を見出しうる。
センは、そこに対話の糸口があり、そこを通じてコミュニケーションを図り続けることによって、一つの対立点で社会が分断されそうな時にも、別のところで人間同士のつながりが可能になるということを言っています。
これは非常に重要なことです。僕たちは単一のアイデンティティーや、単一のカテゴリーに自分が押し込められることに非常に不自由を感じます。実際には自分にはもっと多様な面がある。犯罪の被害に遭われた方のことも、「犯罪被害者」というふうにカテゴリーとしてつい語ってしまいますが、その人の中にも、一方で会社員であったり、昔の友達とわいわいい楽しく過ごす時間もあったりというふうに、複雑な顔があるわけです。』
●対立点からではなく、接点からコミュニケーションを始める
・人間は複雑な属性を備えているというアマルティア・センの指摘について、平野先生は「分人」ということばで個人や社会の多様性を重視すべきであると説いている。
・人間にはコミュニケーションの中で混ざり合っていく他者性があり、他者に対する柔軟なコミュニケーションを重ねることにより、自分の中にいくつかの人格がパターンのようにしてできていく。これを個人という概念に対して、「分人」と呼んでいる。
●分人の集合として自分を捉える
・自分という存在を唯一つの存在とするのではなく、分人という自分の中の多様性によって、好きな自分、嫌いな自分、楽しい自分、辛い自分などいろいろな面があり、相対化して分人として自分を眺めることができれば、自殺の衝動を抑制することもできる。
●人生の経過とともに分人の構成は変わっていく
・分人の構成は他人や社会から強いられるものではなく、バランスを取るように自分がコントロールすべきものである。ただし、これは容易なものではなく、社会や政治といった自分の外側に目を向けることも大事である。
●愛する人を喪失した人へ
・『僕たちは自分が愛している人との分人を生きたいわけですけど、その相手を失うことによって、それができなくなってしまう。その辛さが愛する人を亡くした時の大きな喪失感ではないでしょうか。
だけど、生きている人たちとの関係の中で新しい分人をつくってみたり、今まで仲がよかった人との分人の比率が大きくなっていくことで、その後の人生を続けていくことができるはずだと思います。
そういう意味で、最初の話に戻りますけど、辛い状況にある当事者の人に対して、自分はどう接したらいいかわからないと立ち止まるのではなく、その人に辛い分人だけを生きさせないために、新たな分人をつくることができるような関与をすることが大事ではないでしょうか。』
感想
長いコロナ禍、テレビの刑事モノを観る機会が増えたのですが、時々出てくる刑事のセリフ、「罪を憎んで人を憎まず」。これは死刑制度、人権、自死(自殺)に紐づく重要なキーワードになるのではないかと思いました。もちろん、簡単な話ではないと思いますが。。
日本人の約8割は死刑容認とのことです。私も平野先生のお考えを勉強させていただく前は、そもそも深く考えたこともなかったのですが、死刑容認派で間違いないと思います。
自分なりに何故、容認派なのか考えてみると、先生が指摘された漫画やアニメの“勧善懲悪”の影響は確かに大きいと思います。また、“切腹”や“敵討ち・仇討ち”なども、物語の中では多くは美化されており、嫌悪感はほとんど持ちません。拷問のように痛みを実感できる体罰(身体罰)は受け入れられないのに、拷問よりも残酷な死刑という命を奪ってしまう身体罰は、一瞬のことだからなのか、なぜか寛容です。
また、島国、村社会である日本は“村八分”や“出る杭は打たれる”など、昔から村民に同質性を求める傾向が強いと思います。しかしながらこれは生きていくための知恵でもあり、日本人の慣習、文化になっているように感じます。注意すべきは同質性を重んじることは、多様性に対しては懐疑的になりやすいのではないかという側面です。
脳の機能で考えると、本能や感情に関わるのは“古い脳”といわれる大脳辺縁系などです。一方、理性に関わるのは“新しい脳”の大脳皮質です。犯罪は怒りや悲しみが先行するものなので、まずは“古い脳”が活性化すると思います。特に怒りなどの先には、法による罰が存在し、“怒り”に対して“罰”という結果がすぐに結びつきます。それに対して、“悲しみ“あるいは“犯罪被害者支援”に関しては、法による罰に相当するような明快な解決策がないこともあり、あぶり出された”理性”が落しどころを捜すうちに迷子になってしまうのではないか。この点も“新しい脳”の活性化を難しくさせているように思います。
下の絵で考えれば、犯罪は“脳の命令の力関係”からも圧倒的に古い脳(情動脳)を活性化させやすい状況だと思います。
この記事では次のように古い脳と新しい脳を比較されています(一部追加)。
古い脳
・爬虫類能(反射能)
・構造:脳幹・大脳基底核・脊髄
・機能:心拍・呼吸・摂食・飲水・体温調節・性行動⇒「生きたい」
・哺乳類能(情動脳)
・構造:大脳辺縁系(扁桃体・海馬体・海馬傍回・帯状回・側坐核)
・機能:喜び・愛情・怒り・恐怖・嫌悪などの情動⇒「仲間意識(関わりたい)」
新しい脳
・人間能(理性脳)
・構造:大脳皮質(右脳・左脳)
・機能:知能・記憶・言語・創造・倫理・繊細な運動など⇒「目的意識(成長したい)」
新しい脳(理性脳)を活性化させることは、犯罪を減らす一つの答えになると思います。繰り返しになりますが、具体的には”犯罪被害者の悲しみ”に対して明快な解決策を用意し、犯罪者に対する法的罰則と同様に、犯罪被害者に対する被害者支援の道が用意され、被害者の方を思う一人ひとりの”理性”を迷子にさせないことです。
国民の意識が「罪を憎んで人を憎まず」に向かえば、多様性に対しての理解も進み、さらに国民的コンセンサスとしての高まりとなれば、死刑制度の意識も変わるかもしれません。そして、治安や暮らしやすさの改善にもつながると思います。( ただ、もし自分の家族が殺されたとして、「罪を憎んで人を憎まず」という気持ちに本当になれますか? と問われれば、やっぱり自信はありません)
罪はすべての人が“善”と“悪”を内在していると思うので、なくなることはないと思いますが、新しい脳である理性を活性化できるようになれば、犯罪だけでなく自死も減るのではないかと思います。そして、間接的であっても、”貧困と格差の是正”につなげられれば、さらに犯罪も自死も減るものと思います。
ご参考1
「”罪を憎んで人を憎まず”とは誰の言葉なのだろう?」と思い調べたところ、なんと”孔子”でした。実は2ヵ月程前に、”論語と仁”というブログをアップしていましたのでリンクさせて頂きます。
ご参考2
犯罪被害者のアンケート調査のような資料がないものかネットで探したところ、2007年と新しくはないのですが、社団法人の被害者支援都民センターによる調査資料がありました。
以下の資料名をクリック頂くと、PDF70枚の資料がダウンロードされます。

この棒グラフは左上の”被害後に悩まされた問題”の中から”殺人・傷害致死 38人”だけを抜き出したものです。
また、上記右上のグラフは”事件直後の必要な支援”に関するものです。

こちらは”二次的被害を受けた相手”のグラフです。
上記の”被害後に悩まされた問題”と合わせて考えると、犯罪被害者の方は、多くのストレスに直面していることが分かります。特に、”民事裁判に勝訴したが、実際には賠償金を支払われていない”という人が36.8%もおり、精神的ストレス、手続きの煩わしさ、時間の拘束に加え、金銭的も厳しいということが分かります。
2007年から15年たった今でも同様であるとすれば、犯罪被害者への支援は喫緊の大きな課題といえます。
プロジェクト計画書
仕事ではないのですが、「プロジェクト計画書」を作ることになりました。25年も営業をしてきたので、“営業プラン”や“新規開拓プラン”に類するものは度々作ってはいたのですが、今回は不慣れなテーマに加え広い視点が求められると思い、また、やり直しは最小限度に抑えたいため、作成する前に少し準備することにしました。
購入した本は石井真人先生の『知りたいことがパッとわかる 事業計画書のつくり方がわかる本』です。作るべきは「プロジェクト計画書」なので、本書の中から必要と思う箇所を重点的に勉強させて頂きました。
ブログはかなりアレンジしたものになっているため、本書の概要をお伝えすることはできておりません。そのため、最初に「はじめに」の一部をご紹介させて頂きます。

著者:石井真人
出版:ソーテック社
初版発行:2010年9月
第1章 伝わる事業計画書の作り方
第2章 事業計画書を作成する前にすること
第3章 ビジネスプラン作成の流れとポイント
第4章 ビジネスプランつくり込みのテクニック
第5章 事業推進フローチャートのつくり方
第6章 損益計算書作成のテクニック
第7章 資金繰り計算書作成のテクニック
第8章 数値情報のポイントまとめるテクニック
第9章 伝わるビジネスプランのポイント解説
はじめに
『「新規事業のアイデアを思いついた瞬間から、事業戦略を考え抜くまでの思考プロセス、さらにその事業戦略を“伝わる事業計画書”に仕上げるまでの作成手順を1から伝えたい」というコンセプトを持って、執筆しました。』
『本書では架空の事業を1つつくり上げ、思考プロセスから事業計画書の完成まで、すべてサンプルをご用意させていただきました。また思考プロセスの流れに沿って、1ページ目から読み進んでいただけるように構成しています。』
『事業計画書は立案者視点で作成するのではなく、詠んでもらう第三者に“伝わる”ように作成しなければ意味はありません。本書では新規事業計画書をテーマにしており、新規事業の素晴らしさを第三者に伝えるための実務ノウハウをサンプルの中に散りばめて解説しております。中長期事業計画書など新規事業以外でも“第三者に伝える”実務ノウハウがそのまま活用していただけるように、イメージ図の使い方や文章の書き方など、作業レベルのテクニックまで網羅しました。』
1.伝わるプロジェクト計画書の作り方
●プロジェクト計画書が与えてくれるメリット
・資金調達において事業計画書が求められる
・立案者の“思い”は文書化しなければ伝わらない
●プロジェクト計画書を構成する具体的な書類
①プロジェクトプラン
「なぜ、いつ、誰が、どこで、誰のために、何を」を客観的な根拠に基づいて解説する書類。事業計画全体のストーリーを作る。
②プロジェクト推進フローチャート
プロジェクト計画のストーリーおよび行動計画を図式化した資料。期日、担当者を明確にする。
③数値シミュレーション
資金繰り計算表
2.プロジェクト計画書を作成する前にすること
●何をプロジェクト化したいのか?「6W1H」で情報整理をする
・Who、Why、What、Where、Whom、When、How
●プロジェクトコンセプトを文書化し全体像をイメージできるようにする
3.プロジェクトプラン作成の流れとポイント
●各構成要素の計画内容を文書化するルール
・各構成要素を「6W1H」で説明する
・チェック表を活用して「知りたいポイント」の欠如を防ぐ
・キーワードは言い回しを統一して繰り返す
●ストーリーの流れを意識するルール
・シンプルに論理的な説明をする
・構成要素と構成要素のつなぎをオーバーラップさせる
・キーワード以外の説明は重複しない
●各構成要素で伝えたいポイントを1つにまとめる
・理解しやすい必要最低限の情報がポイント
-膨大な情報をすべて理解してもらうことは不可能
-特にお金に関わる数値は最も重要
●グラフ・イメージ図などを加えたドラフト版の作成
・構成要素と説明文章を基にページ構成をつくりあげる
・構成要素がページタイトルになる
・プロジェクトプランは枠組みを決めてから着手する
4.プロジェクトプランつくり込みのテクニック
●「表紙」作成テクニック
・作成日、作成者、更新情報(revision)を書く
●「目次」作成テクニック
・目次の項目とページタイトルは必ず一致させる
・ページ番号は最後の仕上げ作業として行う
●「ビジョン」作成テクニック
・できるかぎり目標設定を数値化する
・将来の「ありたい姿」を掲げる
●「予算化戦略」作成のテクニック
・予算獲得に大きく影響するチャネルの各戦略を描く
・獲得率を算出する
・広告等のコストを明確にする
●「情報戦略」作成のテクニック
・情報の整理整頓と維持管理(個人情報保護とセキュリティー)
●「プロジェクトスケジュール」作成のテクニック
・準備項目を時系列で明らかにする
・コスト発生の時期を明確にする
5.プロジェクト推進フローチャートのつくり方
●プロジェクト推進フローチャートの役割
・「実行できるのか」を判断するキーポイント
・コストの発生時期が見える
●プロジェクト推進フローチャート作成前に知っておきたいこと
・可能な限り、各分野の経験者から意見を聞いて参考にする
・項目の棚卸⇒作業期間決定⇒担当者決定の順番で作成する
・役割と要員に問題がないか確認する
6.損益計算書作成のテクニック
●収支シミュレーション作成の流れ
・収入と支出を可能な限り洗い出す
・数値情報の根拠を明確にする
●告知にかかる費用を明確にする
・「何を・いくらで・実施するのか」を情報整理する
・獲得目標数に見合う効果の検討
・スケジュールとの整合性
●体制のつくり方
・各役割を明確にする
●経費項目を棚卸する
7.資金繰り計算書作成のテクニック
●資金繰り計算表とは
・収入と支出から必要とする資金の不足を正確に把握できる
8.数値情報のポイントまとめるテクニック
9.伝わるプロジェクトプランのポイント解説
●サンプル(『オーガニック化粧品の製造販売事業』)
・本書内では計32枚のスライドが紹介されています。
咲けない時は根を降ろす
ブログ“源氏物語と紫式部1”は、山本淳子先生の『平安人の心で「源氏物語」を読む』を題材にしているのですが、その山本先生は紫式部が『源氏物語』という大輪の花を咲かせたのは、自分なりの根を降ろしたからこそである。との見識をお持ちです。
この見識は『置かれた場所で咲きなさい』という渡辺和子先生の名著に遺された、「咲けない日があります。その時は、根を下へ下へと降ろしましょう」という教えが、まさに紫式部の生き方に重なるということからきています。
また、渡辺先生は軍人だった父を、二・二六事件の青年将校たちによって目の前で射殺されるという悲惨な衝撃的な体験をされており、そのことも渡辺先生の『置かれた場所で咲きなさい』を読みたいと思った理由です。
ブログはもくじの黒字部分ですが、一つは“変らない現実”、もう一つは“希望”に関するものといえます。
もくじ
はじめに
第1章 自分自身に語りかける
・人はどんな場所でも幸せを見つけることができる
・一生懸命はよいことだが、休憩も必要
・人は一人だけでは生きてゆけない
・つらい日々も、笑える日につながっている
・神は力に余る試練を与えない
・不平をいう前に自分から動く
・清く、優しく生きるには
・自分の良心の声に耳を傾ける
・ほほえみを絶やさないために
第2章 明日に向かって生きる
・人に恥じない生き方は心を輝かせる
・親の価値観が子どもの価値観を作る
・母の背中を手本に生きる
・一人格として生きるために
・「いい出会い」を育てていこう
・ほほえみが相手の心を癒す
・心に風を通してよどんだ空気を入れ替える
・心に届く愛の言葉
・順風満帆な人生などない
・生き急ぐよりも心にゆとりを
・内部に潜む可能性を信じる
・理想の自分に近づくために
・つらい夜でも朝は必ず来る
・愛する人のためにいのちの意味を見つける
・神は信じる者を拒まない
第3章 美しく老いる
・いぶし銀の輝きを得る
・歳を重ねてこそ学べること
・これまでの恵みに感謝する
・ふがいない自分と仲よく生きていく
・一筋の光を探しながら歩む
・老いをチャンスにする
・道は必ず開ける
・老いは神さまからの贈り物
第4章 愛するということ
・あなたは大切な人
・九年間に一生分の愛を注いでくれた父
・私を支える母の教え
・2%の余地
・愛は近きより
・祈りの言葉を花束にして
・愛情は言葉となってほとばしる
・「小さな死」を神に捧げる
第1章 自分自身に語りかける
神は力に余る試練を与えない
『心の悩みを軽くする術があるのなら、私が教えてほしいくらいです。人が生きていくということは、さまざまな悩みを抱えるということ。悩みのない人生などあり得ないし、思うがままにならないのは当たり前のことです。もっといえば、悩むからlこそ人間でいられる。それが大前提であることを知っておいてください。
ただし悩みの中には、変えられないものと変えられるものがあります。例えばわが子が障がいを持って生まれてきた。他の子どもができることも、自分の子はできない。「どうしてこの子だけが……」と思う。それは親としては胸を搔きむしられるほどのせつなさでしょう。しかし、いくら悲しんだところで、わが子の障がいがなくなるわけではない。その深い悩みは消えることはありません。この現実は変えることはできない。それでも、子どもに対する向き合い方は変えられます。
生まれてきたわが子を厄介者と思い、日々を悩みと苦しみの中で生きるか。それとも、「この子は私だったら育てられると思って、神がお預けになったのだ」と思えるか。そのとらえ方次第で、人生は大きく変わっていくでしょう。
もちろん、「受け入れる」ということは大変なことです。そこに行き着くまでには大きな葛藤があるでしょう。しかし、変えられないことをいつまでも悩んでいても仕方がありません。前に進むためには、目の前にある現実をしっかりと受け入れ、ではどうするかということに思いを馳せること。悩みを受け入れながら歩いていく。そこにこそ人間としての生き方があるのです。
今あなたが抱えているたくさんの悩み。それを一度整理してみてください。変えられない現実はどうしようもない。無理に変えようとすれば、心は疲れ果ててしまう。ならば、その悩みに対する心の持ちようを変えてみること。そうすることでたとえ悩みは消えなくとも、きっと生きる勇気が芽生えるはずですから。』
第2章 明日に向かって生きる
つらい夜でも朝は必ず来る
『希望には人をいかす力も、人を殺す力もあるということをヴィクター・フランクルが、その著書の中に書いています。
フランクルはオーストリアの精神科医でしたが、第二次世界大戦中、ユダヤ人であったためナチスに捕えられて、アウシュビッツやダハウの収容所に送られた後、九死に一生を得て終戦を迎えた人でした。
彼の収容所体験を記した本の中に、次のような実話があります。収容所の中には、1944年のクリスマスまでには、自分たちは自由になれると期待していた人たちがいました。ところがクリスマスになっても戦争は終わらなかったのです。そしてクリスマス後、彼らの多数は死にました。
それが根拠のない希望であったとしても、希望と呼ぶものがある間は、それがその人たちの生きる力、その人たちを生かす力になっていたのです。希望の喪失は、そのまま生きる力の喪失でもありました。
二人だけが生き残りました。この二人は、クリスマスと限定せず、いつか、きっと自由になる日が来る」という永続的な希望を持ち、その時には、一人は自分がやり残してきた仕事を完成させること、もう一人は外国にいて彼を必要としている娘とともに暮らすことを考えていたのです。
事実、戦争はクリスマスの数ヶ月後に終わったのですが、その時まで生き延びた人たちは、必ずしも体が頑健だったわけではなく、希望を最後まで捨てなかった人たちだったと、フランクルは書いています。
希望には叶うものと叶わないものがあるでしょう。大切なのは希望を持ち続けること、そして「みこころのままに、なし給え」と、謙虚にその希望を委ねることではないでしょうか。』
感想
失望、悲しみの真っただ中にいて、苦しみもがいている自分を外から眺め、外側に広がっている世界の中に何かの希望を見つけること、そして、その希望に向かって進んでいくことが、苦しみからの出口なのだろうと思いました。
源氏物語と紫式部2
第二章 光源氏の晩年
(四十)三十八帖「鈴虫」 出家を選んだ女たち
・『「出家とは、生きながら死ぬということ」。自ら出家の道を選ばれた、瀬戸内寂聴尼の言葉である。ご自身の体験を踏まえてこその一言であるに違いないが、この言葉は、こと平安時代の貴族女性においても、ほとんどそのまま真実と言ってよい。』
・『貴族社会では、尼となれば恋人や夫との関係を断ち、世俗の楽しみを捨てて、厳しい仏道修行に励まなくてはならなかった。それでも彼女たちは、それぞれに心の救済を求めて、出家の道を選んだのである。動機は、大きく三つに分けられよう。何らかのできごとをきっかけに、生きる意欲をなくして出家するタイプ。また家族など大切な人を喪って出家するタイプ。そして最後に、病を得たり年老いたりして、死を身近なものと感じ出家するタイプである。』
・「源氏物語」の女君の出家の多くは最初のタイプである。光源氏から逃れるために出家した“藤壺”、継息子に言い寄られて世に嫌気がさした“空蝉”。柏木に犯されて出産し「もう死にたい」と出家した“女三の宮”、自殺未遂の果てに出家した“浮舟”もそうである。
・史実では例えば、一条天皇(980-1011)の中宮定子[ていし]がいる。天皇との幸せな日々を過ごしていたが、父の関白・藤原道隆が亡くなり、追い打ちをかけるように翌年、兄と弟が「長徳の政変」から流罪を受けた。定子は家が受けた辱めに耐えられず、絶望の中で出家した。その心は、半ば自殺に等しいものではないか。このことは当初、同情を以て貴族社会に受け止められた。だが一年後に、定子を諦められない一条天皇によって彼女が復縁させられると、「尼なのに」「還俗か」と批判を受けた。
・『仏教では、俗界は汚辱と苦に満ちていると考える。生まれ変わってもまた、それは同じだ。来世を少しでもよいものにするには、現世で功徳を積むしかない。そして仏の救いを得、極楽浄土への往生を果たすことが、最後の幸福だ。当時の仏道の基本はこうした考えだったと言ってよい。貴族たちも、華やかな日々の暮らしの奥底にこうした世界観を持っていた。そして何か事があれば、俗世界を脱して仏道専心の清らかな世界、つまり来世や浄土のことだけを思う出家生活に入ることを願った。出家とはその意味で、世俗の生から死への緩衝地帯といえる。だからこそ、女に若い身空で出家されることは、夫や家族にとってつらく、また忌まわしいことでもあったのだ。』
(四十三)四十帖「御法」 死者の魂を呼び戻す呪術~平安の葬儀
・『今の昔も葬法の儀礼は、死者のためのものであると同時に、遺された人のためのものでもある。儀式を一つ一つ行うことで、大切な人を喪ったことを受け入れ、きちんと悲しむ。心理学ではこれを「喪の仕事」という。それができない時、人はもがき苦しむ。』
(四十四)四十一帖「幻」 『源氏物語』を書き継いだ人たち
・紫式部が書いた「源氏物語」が、今我々が目にしているものと同じかどうかは分からない。式部自身が書いた本が伝わっていないので確認のしようがないからである。
・大長編の「源氏物語」は一気に発表されたのではなく、最初はばらばらに世に出た。
・「源氏物語」が現在のように整った形で伝えられるようになるには、幾人もの中興の祖がおり、その筆頭が藤原定家[ていか]だったと思われる。
・紫式部の時代から二百年を経ずして、「源氏物語」は注釈が必要なほど読みにくくなっていた。その理由はいくつかある。一つには草稿の流出である。このため下書きと完成原稿の両方が出回ってしまった。第二は誤写である。江戸時代以前、本は書き写して伝えられたため誤写は避けられなかった。そして第三は書写の際の勝手な書き換えや創作である。和歌と違って作者が尊重されていなかった物語は、書き換え御免と考えられていた節さえある。
・藤原定家は歌道に精進するとともに、平安時代の歌集や物語を集め自ら写した。「源氏物語」を写したのは嘉禄元(1225)年で、定家は六十四歳になっていた。定家の「源氏物語」は表紙の色から「青表紙本」と呼ばれた。また、定家と同じころ源光行と親行父子による「河内本」と呼ばれる優れた写本もあった。二つの本はそれぞれ尊重され、さらに写し継がれて時代を超えた。その数は計り知れずこの物語の命をつないだ。
第三章 光源氏の没後
(四十五)四十二帖「匂兵部卿」 血と汗と涙の『源氏物語』
・今読んでいる「源氏物語」は池田亀鑑(1896-1956)によるものである。「青表紙本」と「河内本」もその後の時の流れの中で転写を繰り返すうち、誤写だけでなく戦乱や災害で傷つけられる運命を免れなかった。また写本によっては、「青表紙本」と「河内本」が混ざって写されることもあった。そうしたなかで、もう一度「源氏物語」の本文を見直そうとしたのが、池田亀鑑であった。
・池田亀鑑は東京帝大文学部に就職して「源氏物語」関連プロジェクトを任され、全国の旧家や寺などを訪ね回り、古書など約三万冊を集めた。こうして七年、彼はようやく「校本」の原稿を完成させた。なお、それは「河内本」系統に属するものだった。ところが発表前、佐渡の旧家から「お宝」が現れた。
「源氏物語」の「浮舟」を除く五十三帖揃い。売り手の希望価格の1万円は当時にしては一軒家が買える巨額なものであった。亀鑑は蔵書家で知られた大島雅太郎に購入してもらい、それを亀鑑がそれを借り受ける形で亀鑑は解読し始める。そして、その本が現存する四帖分の定家自筆本と九帖分のその模写本に次いで古い「青表紙本」の写本であることに気づく。奥書には文明十三(1482)年の書写とあり、しかも書道の名家、飛鳥井雅康の自筆だった。
亀鑑は七年かけた「校本」の原稿をなげうった。書き換えに要した月日はさらに十年。ついに「校本」の刊行にこぎつけたのは、第二次世界大戦下の昭和十七年であった。
その後、大島本の所蔵は京都文化博物館に移り、活発な研究が続いている。
第四章 宇治十帖
(六十)五十四帖「夢浮橋」 紫式部の気づき
最後の五十四帖の解説は、この本の中で最も印象に残りました。
・『修道女の渡辺和子さんに「置かれた場所で咲きなさい」という名著がある。「置かれたところこそが、今のあなたの居場所なのです」「咲けない日があります。その時は、根を下へ下へと降ろしましょう」。文中の慈愛に満ちたこの言葉に、私は紫式部に通じるものを感じてならない。渡辺さんは、軍人だった父を二・二六事件の青年将校たちによって目の前で射殺された体験を持つ。紫式部の人生も、悲嘆や逆境の連続だった。だが紫式部も、置かれたその場その場に自分なりの根を降ろしている。「源氏物語」という大輪の花さえも咲かせている。
「めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に、雲隠れにし夜半の月かな」。紫式部の私家集「紫式部集」の冒頭歌だ。小倉百人一首でご存じの方も多いだろう。紫式部自身が記す詞書によれば、これは幼馴染に詠んだ和歌だった。長く別れ別れになっていて、年を経てばったり再会。だが彼女は月と競うように家に帰ってしまった。「思いがけない巡り合い。「あなたね?」、そう見分けるだけの暇もなく、あなたは消えてしまったね。それはまるで、雲に隠れる月のように」。楽しい友情の一場面のようだが、そうではない。この友はやがて筑紫に下り、その地で死んだ。天空で輝いていた月が突然雲に隠されて姿を消すように、二度と会えない人となったのだ。
紫式部が人生の最晩年に自伝ともいうべき家集を編んだ時、巻頭にこの和歌を置いたのは、ほかでもない、こうした「会者定離[会う者は必ず離れる定めにあるということ]」こそ自分の人生だと感じていたからだ。紫式部は、おそらく幼い頃に母を亡くしている。姉がいたが、この姉も紫式部の思春期になくなった。そんな頃出会ったのが、先の友人である。偶然にも彼女の方は妹を亡くしており、二人は互いに「亡きが代はりに(喪った人の身代わりに)」慕い合った。「源氏物語」に幾度も現れる「身代わり」というテーマ。紫式部にとって幼馴染を喪ったとは、母と姉と友自身の、三人分を喪ったことでもあったのだ。
それでも折れなかった心が、夫を喪った時、とうとう折れた。本来、人に身代わりなどないのだ。哀しみを慰める術の限界を突きつけられて、紫式部は泣くしかない。この時の心境は、紫の上を喪った光源氏と大君を喪った薫各々の述懐に活かされていよう。自分に無常を思い知らせようとする仏の計らいだ、つまり降参するしかないと、彼らは言うのだ。光源氏はそれを機会に出家する。薫は魂の彷徨を続ける。では紫式部はどうしたか。人生を見つめ、そして目覚めたのである。
人とは何か。それは、時代や運命や世間という「世(現実)」に縛られた「身」である。身は決して心のままにならない。まずそれを、紫式部はつくづく思った。だが次には、心はやがて身の置かれた状況に従うものだと知る。胸の張り裂けるような嘆きが、いつしか収まったことに気づいたのだ。「数ならぬ心に身をば任せねど 身にしたがうは心なりけり(ちっぽけな私、思い通りになる身のはずがないけれど、現実に慣れ従うのが心というものなのだ)」(「紫式部集」五十五番)。紫式部は「置かれた場所」で生き直し始めたといえよう。
だが紫式部は、現実にひれ伏すだけではなかった。彼女は心というものの力にも気づいたのだ。「心だにいかなる身にか適ふらむ 思ひ知れども思ひ知られず(現実に従うという心だが、それさえどんな現実に収まるものだというのか。心は現実を思い知っている。でも思い知りきれず、はみ出すのだ)(同五十六番)。そう、心は何にも縛られない。易々と現実から抜け出て、死んだ人とも会話し、未来を夢想する。架空の世界まで創りだす。時空を超えて、それが心というものの普通だ。紫式部はこの「心」という世界に腰を据え、人というものに考えを致し続けた。彼女にとって、「置かれた場所」で「下へ下へと根を降ろす」とはこのことだった。「源氏物語」はその結実であったと、私は思う。
無駄に漢学の才のある娘だと、父親に嘆かれたこと。新婚わずか三年で、娘を抱え寡婦となったこと。「源氏物語」を書けば書いたで、意に沿わぬまま中宮彰子の女房にスカウトされ、同僚からは高慢な才女と誤解されていじめにあったこと。「人生は憂いばかり」と、紫式部はため息をつく。だがそれぞれの場で、彼女は考えることを手放さず生きた。果たして、漢学は彰子に請われて進講するに至り、娘は母の背を見て成長し、同僚たちの信頼も勝ち得て、紫式部は彰子後宮に欠かせない女房となった。「心」という根が、ぶれることなく彼女を支えたのだと私は思う。
「源氏物語」の最終場面。浮舟も薫も揺れ動く心を抱えて、いったいどうなってしまうのだろう。紫式部は答えを用意している。それは、どうなろうと「それでも、生きてゆく」ということだ。「紫式部集」の最終歌が、紫式部の至った最後の境地を私たちに教えてくれる。「いづくとも身をやる方の知られねば 憂しと見つつも永らふるかな(憂さの晴れる世界など、どことも知れませんからね。この世は憂い。そう思いながら、私は随分長く生きて来ましたし、これからも生きてゆきますよ)」(百十四番)
この和歌に励まされつつ、私たちもそれぞれに置かれた場所で咲こうではないか。』
ご参考:『源氏物語講義』
こちらの本は昭和9年(1934年)発行の非常に古い本なのですが、とても貴重と思えるページがありました。著者の下田歌子先生は日本の女子教育の先駆者で、源氏物語をはじめとする古典研究や歌人としても名高く、一部では“明治時代の紫式部”とも呼ばれていたようです。
※実践女子大学・短期大学さまのサイトに”下田歌子年表”がありました。
本の右横に書き出した文章は、下田先生による紫式部と源氏物語を分析したもので、非常に興味深い内容です。見出しに続き、要約してご紹介させて頂きます。

紫式部は古今に卓絶せる女性
『要するに、自分が紫式部なる人の幻影の眼底に浮ぶ儘に、夢裡の虚言的であろうが、今少し記して見よう。』
●蒲柳[ホリュウ]の質(生まれつき体が弱く病気にかかりやすい体質)の方だったらしい。
●容貌も普通で、多少良いぐらいの所であったようだが、頗る[スコブ]謙遜な態度であったらしい。
●常に鋭い理智の光芒(一筋の光)を内に隠すも、時にその閃光が仄めく様な場合もあっただろう。
●定めて品がよく、甘味[ウマミ:面白さ]が含まれて居て、その内部には存外強き意志が根を張って居り、だいぶ佛教より受けた厭世的悲哀的の心持もあるが、さりとて陰鬱などと云う程ではなくて、所謂「物のあはれ」を泌々と身にしめて、自然の妙趣を深く味いつつ、随時、心を雲外玄門(雲の上の仏門)に遣やりて、現世目前の煩わしきを排除していた事であろうと想像する。
●物堅き学者の家に生まれ、相当に学問あり、且つ、見識あるところの藤原宣孝に嫁いだが、早く寡居[カキョ:未亡人]して克[ヨ]く二人の遺児を養育した。
●特に稀有の天才に恵まれたる上に、能く学問芸術を履修し、実学の研究を重ねて、遂に源氏物語と云う未曾有の一大名著を産出した。
源氏物語の全貌、平安朝の絵巻物
●全体に就いて略評すれば、この物語の目的が、著者の那邊[シャヘン:どの辺]にあったかは、今更確かめるよしもないが、著者は恐らくは既成の物語本などを読んで、徒然の慰めがてら自分も面白い物語を書いて見たい、自分が書いたら、恐らくは是よりは今少し立ち勝った情趣のあるものが出来るであろうと自信して、筆を執り始めたものであろうと思われる。
●式部が現在目に見る事、過去に聞き置いた事などを描写して組み立て、それに自己の理想を加えて記述したのであろう。高尚なる理想に実際的世間の事柄を以て肉づけ、且つ温かい血を通わせて、平安朝の舞台に活動させたのである。
●この物語は五十余帖の浩瀚[コウカン:書物の量が多いこと]なものを一貫して、先ず不確実な所も不自然な所も無く、見る者をして全く春花秋葉の美観を呈する平安朝の極彩絵巻を、後から後からと繰り拡げて見る様な心地がする間に、おりおり奥深き人情の根底に触れ、事細かき人世の裏面迄も、ささやき告ぐる聲[声]が聞えて来る様な感を生ぜしむるのである。
人情の機微を穿[ウガ]ち、教化の眞諦[シンテイ:絶対不変の真理]に觸る。
●平安朝盛時の写実であるから、全幅総て戀[恋]物語が場所を取って居る。その中にかつて文字の上では見た事もない様な、人情の機微を穿って[ウガッテ:本質を捉えて]居る点は、実に未曾有の書と禮讃[ライサン:称賛]される。
●式部は当代の政治上にも一隻眼[物を見抜く力がある独特の見識]を有して、その飽かずおぼゆる節を仄かにして居る様である。
●随分力を入れて書いたかと思われる点は教育面である。先ず物語中の女性主要人物紫上に対して女子教育を、主人公源氏君の嫡男夕霧に対して男子教育を、その他此處彼處[ここかしこ]に教育面を説いて居り、殆ど当時貴族の欠点、及び教育の短所を指摘し補足したかの如き記事には、千載の下[千年後]今なお採って以て行いたき適切の事さえあるのには、殆ど敬服感激する次第である。
自然美の融合
●物語の全体に亘って、えも云わぬ美しさ軟かさ氣高さが、非常に深みのある様に思われるのは、全く大自然を愛する著者の感情から渾[混]然として湧き出づる一種の和氣[穏やかな様子]、その和氣がおのずからすべての方面を包んでいるからであろう。
●植物動物の色音[イロネ:花の色、鳥の声]芳香は勿論、四季おりおりの風物、日夕[ニッセキ]朝夜[アサヨ]の靄霞[キリカ]雲霧[ウンム]も、皆著者が筆硯[ヒッケン:文筆]に呑吐[ドント]されたのである。
※『例せば源氏物語第一帖桐壺帝巻の終りに、源氏君の二條院を公けより立派に御改造になる事を記して居るけれども、殿内のことは一寸とも、其の模様は記してなくて、唯庭園の事のみ「もとの木立山のややずまひ、面白き所なりけるを、いとど池の心廣くしなしてめでたく造りののしる」とある。あの最も壮麗なりとする六條院にても、殿内の事はその構造も室内装飾も、記す所が甚だ貧弱なるにも関らず、四季の庭園及び花弁の種類配置等は、後世庭造の根源なりと称する程、存外非常に細やかに記してある。』

画像出展:「源氏物語講義」
●紫式部の父は藤原爲時(越前守)である。
●紫式部の同胞(兄弟姉妹)については以下のように記述されている。
『式部には三人の兄があり、猶一人の妹があって夭死[ヨウシ:若死]したと云う説もあるが、能く分らない。そして惟規は式部と同母であり、他の二人は異腹兄であると傳[伝]えられて居る。』
●紫式部の夫、子供については以下のように記述されている。
『夫の[藤原]宣孝には既に数人の子息があり、式部は即ち後妻である。地位も生家と比べて大抵同等の所である。して見れば、別に地位の上から見て、式部には出世的の縁組でもない。あの式部の才識と気位とを以て、必ずしも宣孝を夫に選ばなくても善さそうなものである。まだもっともっと勝った良縁を求められそうなものであるのに、何うした事であろうと思われるが、併しあの階級の中では、宣孝は一寸異彩を放った人であったらしい。此の頃の御嶽詣には、必ず白き浄衣の疎末なものを着て、熊と身をやつやつ[目立たない]しく行かなければ、恐ろしい佛罰に当たると稱[ショウ]した世間一般の迷信を排して、子息隆光と共に、位職に相当する儀容[ギヨウ:礼儀にかなった姿]を備えて詣でて成功した等、当時には珍しい一種の気慨のあった人であるから、当人は勿論、学者の父がこんな点に打ち込んで、所謂人物本位で、宣孝を婿に取ったのかも知れぬ。此の宣孝の御嶽詣の一事は、当時異様の事として世間にも喧傳[ケンデン:世間でやかましく言いたてる]されたものと見えて、枕草子にも載って居る。是等に就きての卑見[ヒケン:自分の意見をへりくだっていう]は、更に後段に譲るとしよう。宣孝の卒去は長保三年四月とある。年齢は大凡少くとも三十三四歳以上四十歳位の時であったろうかと思はるる。』
『式部が義子即ち宣孝の子は、長男隆光の外に頼宣、儀明、隆佐、明懐といふ、つまり五人の男児があり、隆光の母は下総守顯猷の女、頼宣の母は讃岐守平季明女、隆佐、明懐の母は中納言朝距の女であると云ふ。』

画像出展:「源氏物語講義」
これだけコンパクトにまとめられた表は無いように思います。“源氏君”はもちろん、“光源氏”です。その下の同じく黒枠(男性)の“薫”と“夕霧”は源氏君亡きあとの物語の中心人物です。黒&赤の二重線(=)は夫婦もしくは愛人関係で、破線(---)は表面上の親子となっています。また、輪郭とゴシックは特に重要な人物とのことで、ゴシックは先の三人(源氏君・薫・夕霧)の主人公に加え、唯一の女性である“紫上”を加えた計四人となっています。藤原の一文字の“藤”と父の役職の“式部”を組み合わせて”藤式部”とされていたのが、源氏物語が一世を風靡して“紫式部”と呼ばれるようになった背景は紫上とされているという説もあります。数字は黒は男性、赤は女性で結婚年齢を示しています。また、漢数字は出生時父年齢・出生時母年齢になります。
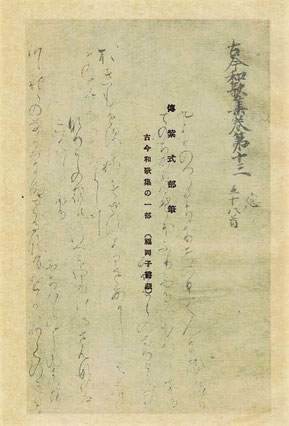
画像出展:「源氏物語講義」
これは非常に薄い半透明の和紙に、『傳 紫 式 部 筆 古今和歌集の一部 (福岡子爵藏)』とだけ書かれ、その半透明の和紙をめくると、『古今和歌集巻第十三』と題するページが現れます。
調べたところ、”福岡子爵”は大政奉還や五か条の御誓文に関わった”福岡孝弟”のことで間違いないと思います。
ネットで調べた範囲では、紫式部直筆の般若経があるような記述もあったのですが、それを否定する記事もあり、正式に認められた紫式部直筆のものはないように思います。従いまして、この『傳 紫 式 部 筆 古今和歌集の一部 (福岡子爵藏)』は昭和初期においては、紫式部の書ではないかとされていたと考えるのが妥当のように思います。
源氏物語と紫式部1
無縁だった「源氏物語」との接点は英語の勉強です。29年間の会社勤めでは遣り残し感はなかったのですが、英語に関しては「できてないなぁ~」という感じでした。そのためいずれは再チャレと考えていたのですが、そろそろ動き出すことにしました。
11月に始めたヨガは、浦和パルコが入居するビルの10階にある、”浦和コミュニティセンター”で開催されているのですが、色々なサークルや講座、イベントなどが行われ、またそれらを紹介するためのチラシやパンフレットがたくさん置かれています。そして、いずれもその気になりやすい庶民的金額となっています。それらの中で今回ひっかかったのが、【源氏物語を英語で読む会】という会です。
最初は“お試し参加”ということでしたが、なかなか面白そうでした。「英語の勉強もできるし、日本人だったら源氏物語がどんなものかぐらいは知っておいた方がよかろう」という思いがあり、少し迷いましたが正会員になりました。
とはいうものの、“テキ”は日本語でも難しいとされる源氏物語です。どんな雰囲気のものか、ある程度は知っておきたいと思い、見つけた参考書が山本淳子先生の『平安人の心で「源氏物語」を読む』という本でした。山本先生がご指摘されている通り、現代と平安時代の差を知ることが必要だと考えたためです。
それにしても“光源氏”と私、比較するのも失礼千万、無礼千万ではありますが、あまりの真逆の人物像に思わず驚きの苦笑いが出てしまいました。
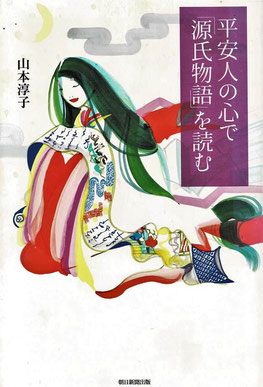
著者:山本淳子
初版発行:2014年6月
出版:朝日新聞出版
『「源氏物語」をひもといた平安人[へいあんびと]たちは、誰もが平安時代の社会の意識と記憶でもって、この物語を読んだはずです。千年の時が経った今、平安人ではない現代人の私たちがそれをそのまま共有することは残念ながらできません。が、少しでも平安社会の意識と記憶を知り、その空気に身を浸しながら読めば、物語をもっとリアルに感じることができ、物語が示している意味をもっと深く読み取ることもできるのではないでしょうか。本書はその助けとなるために、平安人の世界を様々な角度からとらえ、そこに読者をいざなうことを目指して作りました。』
本書の最後に多くの参考文献が紹介されているのですが、さらにその後ろに、8ページにわたって“主要人物関係図”が付いています。これを見ても登場人物の多さにあらためて驚きます。
せめて光源氏と直接関わった人達については頭に入れておきたいと思い、ごく一部ですが表を作ることにしました。
また、参考文献の後に紹介されているものの中から、“寝殿造”の絵図をご紹介させて頂きます。

画像出展:『平安人の心で「源氏物語」を読む』
『中央部が母屋で、周囲を廂[ひさし]、その外側を濡れ縁の簀子[すのこ]と高欄[こうらん]が取り囲む。寝殿の東・西・北面に対[たい]の屋[や]があり、寝殿とは渡殿[わたどの]でつながれている。外からの出入り口は妻戸[つまど]で、それ以外は格子[こうし](蔀戸[しとみど])はめられている。』
目次の黒字がブログで取り上げたものです。特に“平安人[へいあんびと]の時代”と作者の“紫式部”に注目しました。また、長くなったのでブログを2つに分けました。
目次
第一章 光源氏の前半生
(一)一帖「桐壺」 後宮における天皇、きさきたちの愛し方
(二)二帖「帚木」 十七歳の光源治、人妻を盗む
(三)三帖「空蝉」 秘密が筒抜けの豪邸…寝殿造
(四)四帖「夕顔」 平安京ミステリーゾーン
(五)五帖「若紫」 そもそも、源氏とは何者か?
(六)六帖「末摘花」 恋の“燃え度”を確かめ合う、後朝の文
(七)七帖「紅葉賀」 暗躍する女房たち
(八)八帖「花宴」 顔を見ない恋
(九)九帖「葵」 復讐に燃える、父と娘の怨霊タッグ
(十)十帖「賢木」 祖先はセレブだった紫式部
(十一)十一帖「花散里」 巻名は誰がつけた?
(十二)十二帖「須磨」 流された人々の憂愁
(十三)十三帖「明石」 紫式部はニックネーム?
(十四)十四帖「澪標」 哀切の斎宮、典雅の斎院
(十五)十五帖「蓬生」 待ち続ける女
(十六)十六帖「関屋」 『源氏物語』は石山寺で書かれたのか?
(十七)十七帖「絵合」 平安のサブカル、「ものがたり」
(十八)十八帖「松風」 平安貴族の遠足スポット、嵯峨野・嵐山
(十九)十九帖「薄雲」 ドラマチック物語、出生の秘密
(二十)二十帖「朝顔」 三途の川で「初回の男」を待つ
(二十一)二十一帖「少女」 平安社会は非・学歴社会
(二十二)二十二帖「玉鬘」 現世の「神頼み」は、観音様に
(二十三)二十三帖「初音」 新春寿ぐ“尻叩き”
(二十四)二十四帖「胡蝶」 歌のあんちょこ
(二十五)二十五帖「蛍」 平安の色男、華麗なる遍歴
(二十六)二十六帖「常夏」 ご落胤、それぞれの行方
(二十七)二十七帖「篝火」 内裏女房の出生物語
(二十八)二十八帖「野分」 千年前の、自然災害を見る目
(二十九)二十九帖「行幸」 ヒゲ面はもてなかった
(三十)三十帖「藤袴」 近親の恋、タブーの悲喜劇
(三十三)三十三帖「藤裏葉」 どきっと艶めく平安歌謡、「催馬楽」
第二章 光源氏の晩年
(三十四)三十四帖「若菜上」前半 紫の上は正妻だったのか
(三十五)三十四帖「若菜上」後半 千年前のペット愛好家たち
(三十六)三十五帖「若菜下」前半 物を欲しがる現金な神様~住吉大社
(三十七)三十五帖「若菜下」後半 糖尿病だった藤原道長~平安の医者と病
(三十八)三十六帖「柏木」 病を招く、平安ストレス社会
(三十九)三十七帖「横笛」 楽器に吹き込まれた魂
(四十)三十八帖「鈴虫」 出家を選んだ女たち
(四十一)三十九帖「夕霧」前半 きさきたちのその後
(四十二)三十九帖「夕霧」後半 結婚できない内親王
(四十三)四十帖「御法」 死者の魂を呼び戻す呪術~平安の葬儀
(四十四)四十一帖「幻」 『源氏物語』を書き継いだ人たち
第三章 光源氏の没後
(四十五)四十二帖「匂兵部卿」 血と汗と涙の『源氏物語』
(四十六)四十三帖「紅梅」 左近の“梅”と右近の橘
(四十七)四十四帖「竹河」 性悪女房の問わず語り
第四章 宇治十帖
(四十八)四十五帖「橋姫」 乳を奪われた子、乳母子の人生
(四十九)四十六帖「椎本」 親王という生き方
(五十)四十七帖「総角」前半 乳母不在で生きる姫君
(五十一)四十七帖「総角」後半 薫は草食系男子か?
(五十二)四十八帖「早蕨」 平安の不動産、売買と相続
(五十三)四十九帖「宿木」前半 「火のこと制せよ」
(五十四)四十九帖「宿木」後半 平安式、天下取りの方法
(五十五)五十帖「東屋」 一族を背負う妊娠と出産
(五十六)五十一帖「浮舟」前半 受領の妻、娘という疵
(五十七)五十一帖「浮舟」後半 穢れも方便
(五十八)五十二帖「蜻蛉」 女主人と女房の境目
(五十九)五十三帖「手習」 尼僧の還俗
(六十)五十四帖「夢浮橋」 紫式部の気づき
第五章 番外編 深く味はふ『源氏物語』
番外編一 平安人の占いスタイル
番外編二 平安貴族の勤怠管理システム
番外編三 「雲隠」はどこへいった?
番外編四 時代小説、『源氏物語』
番外編五 中宮定子をヒロインモデルにした意味
参考文献
『源氏物語』主要人物関係図
一帖「桐壺」~八帖「花宴」
九帖「葵」~十三帖「明石」
十四帖「澪標」~十六帖「関屋」
十七帖「絵合」~二十一帖「少女」
二十二帖「玉鬘」~三十帖「藤袴」
三十一帖「真木柱」~四十一帖「幻」
四十二帖「匂兵部卿」~四十四帖「竹河」
四十五帖「橋姫」~五十四帖「夢浮橋」
平安の暮らし解説絵図
平安京
大内裏
後宮
寝殿造
男性の平常着・直衣姿
女性の正装・裳唐衣姿(十二単)と平常着・袿姿
あとがき
第一章 光源氏の前半生
(五)五帖「若紫」 そもそも、源氏とは何者か?
・光源氏の源氏は、源頼朝の「源」と同じであり、「源氏」とは源の性を持つ一族を意味する。そして「源」の祖先は天皇である。
・平安時代初期の嵯峨天皇(789-842)は強大な力をもっており、男子だけでも22人の皇子がいた。その皇子たちにより子孫は鼠算式に増えていく。そして、逼迫する皇室費用を抑制するための措置として考えられたのが、皇子を三種類に分けることであった。一つは天皇を継ぐ東宮[とうぐう](皇太子)。もう一つは控えの皇太子要員といえる親王。そして最後が源氏であった。そしてこれらの分類は母の家柄で決まった。
・「源」の姓を賜った者たちは、天皇の血をひきながら皇族とは切り離されて臣下に降り、他の氏族の者と同様に自ら生計を立てた。誇り高い姓ではあるが、皇位継承の道を閉ざされた氏族ともいえる。
・光源氏は架空の物語であるが、始祖の桐壺帝は世の信望厚い聖帝とされ、光源氏は天皇から一代、つまり「一世源氏」である。史実をみると権威ある嵯峨天皇や村上天皇の一世源氏は、何人もの大臣を輩出している。
・源頼朝の始祖である清和天皇は影が薄く、しかも頼朝は十代であり、光源氏との違いは明らかである。それでも「源」の血の威光は絶大だった。
・『一世源氏とは、父帝の至高の血という優越性と、帝位には不相応な母の血という劣等性とを、共に受け継ぐ者だった。自らの血を自負すればいいのか、卑下すればいいのか。その葛藤は想像に余りある。光源氏は、桐壺帝の十人の皇子でただ一人臣籍に降ろされた。「源氏物語」というタイトルは、主人公が身分社会の敗者であることを示していたのだ。』
(十)十帖「賢木」 祖先はセレブだった紫式部
・紫式部の父の藤原為時は彼女が二十歳の頃、越前守の国守となった[その前の10年間は決まったポストがなく、失業中]。これは貴族の「受領」に属する。受領は赴任先では権力の頂点であるが、朝廷の地位を示す位階は四位から六位である。「ここからが貴族」というラインが五位なので上流貴族とは言えない。
このように受領は特有の自由な気風や上昇志向を持ち、成り金的な一方、多少の哀愁も漂う。なお、平安の才女たちは清少納言、和泉式部など、多くがこの階級に属していた。
・紫式部の父は目立たない受領だったが、直系の曽祖父である藤原兼輔は中納言であった。また、父の母の父の曽祖父にあたる藤原定方は右大臣であった。家や血統が今よりも格段に重視された時代、式部は過去の栄光と今の落魄を痛感していたのではないか。
そして、この二人の曽祖父は「源氏物語」にも影響を与えていると思われる。「源氏物語」の桐壺帝の時代は、式部から数十年前に実在した醍醐天皇(885-930)の時代に設定されていると言われているが、この醍醐天皇の時代は二人の曽祖父、兼輔と定方が活躍していた時代である。
さらに醍醐天皇は定方の姉の胤子が宇多天皇(867-931)との間に産んだ子なので、定方にとって甥になる。また、兼輔は娘の桑子を醍醐天皇に入内させている。曽祖父たちにとって聖帝とあがめられた醍醐天皇は身内の天皇といえるものだった。
・『少し前まで華やかだったのに、今は没落して受領階級となった家の娘。「源氏物語」を読むとき、作者のこの「負け組」感覚を忘れてはならない。それは東宮はおろか親王にさえなれなかった皇子である光源氏のリベンジにつながり、政争に負けた桐壺・明石一族のお家復活劇につながるのだ。
ほかにも、物語中には数々の没落者がひしめく。父に先立たれた末摘花、六条御息所、空蝉、そして宇治の女君たち。中でも空蝉は、実家の昔への矜持と今属する受領階級への引き目とを二つながら心に抱く点、紫式部自身の分身ともいえる。彼らへの、紫式部の悲しくも温かいまなざしに注目したい。』
(十三)十三帖「明石」 紫式部はニックネーム?
・紫式部は本名でも女房名でもない。だいたい「紫」とは何なのか? 本名は公文書に記すときなどごく限られた場合にしか使われない。女性が家で家族や召使から呼ばれる場合は「君」や「上」などと呼ばれるし、女房[朝廷などに仕えた女官]になれば女房名で呼ばれるのが普通である。「清少納言」も女房名である。女房名には大方の決まりがあり、父や兄など身内の男性の官職名を使う。例えば父が伊勢守だったなら、その国名を取って「伊勢」という具合である。
紫式部は、中宮彰子のもとに仕え始めた時、「式部」と呼んでほしいと申し出たらしい。これは父の藤原為時がかつて式部省に勤めていたからである。しかし、そこで困ったことが起きた。それは彰子の周りの女房には、既に二人の「式部」がいたからである。このようなケースは珍しくなく、姓から一文字とってつけることになる。清少納言は官職名の「少納言」に「清原」の一文字をつけたものである。紫式部の場合は「藤原」から一文字を取って「藤式部[とうしきぶ]」となったが、これがもともとの女房名である。
「紫式部日記」には次のような一節がある。「あなかしこ。このわたりにわかむらさきやさぶらふ(失礼。この辺りに若紫さんはお控えかな)」。これは文化の世界の重鎮である藤原公任[きんとう]の言葉である。これは「源氏物語」が既に高い評価をされていたということに他ならない。藤原公任が「藤式部」を「若紫」と呼んだのは、その場限りの座興だったかもしれない。だがやがて、彼女は「紫」と呼ばれるようになっていく。公任による戯れをきっかけにしてか、あるいはまた、「源氏物語」における「桐壺更衣」から「藤壺中宮」そして「紫の上」につながる重要な設定「紫のゆかり」にちなんで、読者が作者に与えた愛すべきニックネームか。この「紫」と、もともとの女房名「藤式部」を合体させたのが。「紫式部」である。
麻布竹谷町と三田小山町
三田小山町(現・三田一丁目)で生まれた母親は2歳になる前に引っ越し、小学校教諭になる前の約20年を麻布竹谷町(現・南麻布一丁目)で暮らしました。仙台坂を下って麻布十番によく行っていたということを、懐かしそうに、そしてやや自慢げに話していました。
麻布といえば各国の大使館がひしめく高級住宅街で、埼玉一筋の私からは縁遠い高嶺の花です。以前から「なんで? いつから麻布?」という疑問を持っていたのですが、今回、母方の戸籍を調べてみることにしました。
一方、麻布を詳しく知るために購入した本が『麻布十番 街角物語』です。著者の辻堂真理[マサトシ]先生は、ご自分を「昭和四十年代に幼少期を過ごした十番小僧」と呼んでいます。この本の“第六章 消えた風景の記憶”の中に、“麻布竹谷町の今昔”と題するパートがあるのですが、麻布竹谷町に加え、三田小山町についても紹介されていたのには驚きました。
ブログの題名を「麻布竹谷町と三田小山町」としたのは、『変わらない磁場のようなものを二つの町からは強く感じるのです。』という、辻堂先生のお話が印象に残ったためです。
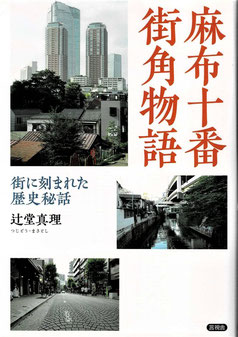
著者:辻堂真理
発行:2019年8月
出版:言視社
『竹谷町にも小山町にも、私が十番小僧だった昭和四十年代にこれらの町が照射していた「オーラ」のようなものが、いまも残っているからではないか、とも考えるのです。
バブル期を境に麻布十番という街が変容してしまったことはすでに述べましたが、そのなかで竹谷町と小山町の西地区は大規模な再開発計画から逃れた稀有なエリアということができます。もちろん個々の建物は新しくなり、マンションの数が増えたことも確かだけれども、それでも変わらない磁場のようなものを二つの町からは強く感じるのです。』
辻堂先生の『麻布十番 街角物語』に関しては、“麻布の歴史”、“麻布十番”、“麻布竹谷町”、“高見順”、“東町小学校”という5つの題名に分類させて頂きました。その後に、私事になりますが調べて分かったことを追記しました。
麻布の歴史
●江戸市街の整備は天正十八年(1590年)に徳川家康が江戸に入府してから。寛永十二年(1635年)には参勤交代が制度化され、諸藩の屋敷が江戸市中に林立した。この頃から麻布の台地にも武家屋敷が建ちはじめた。
●明暦三年(1657年)一月十八日に、死者数万人におよぶ「明暦の大火」が発生。この大火がきっかけとなり、幕府は江戸市街に密集していた武家地や寺社地を郊外に移す施策を打ち出した。このような経緯により、それまで田畑と原野だった麻布の台地に武家屋敷の建設ラッシュが始まった。麻布十番は江戸城まで5~6km、徒歩で1時間程度であり、徳川に仕える武家たちにとって好適地だった。
●延宝年間(1673~1681年)には、善福寺門前の雑式集落より東のエリアも武家屋敷となり人口は増えていった。
●麻布エリアが正式に江戸市中に組み入れられたのは、正徳三年(1713年)にまず百姓屋敷が、次いで延享二年(1745年)には善福寺門前の町屋がそれぞれ町奉行の支配下となり、江戸八百八町の仲間入りを果たした。
●文政十年(1827年)の資料を見ると、麻布エリアは59人の旗本とその関係者が居住しており、芝や愛宕に次ぐ武家屋敷町であった。

画像出展:「分間江戸大地図」文政11年(1828年)
この古地図は文政11年ということなので、本書にある、「文政十年」の翌年ということになります。水色が“古川”です。地図を拡大して頂くと、中央やや右、古川が直角に曲がっている箇所の左側に現在の“麻布十番駅”があります。駅の下方には“善福寺”があり“センダイ坂”を挟んで“松平陸奥”の大名屋敷となっています。この松平陸奥と書かれた場所がおおむね麻布竹谷町になります。
●日米修好通商条約が締結された安政五年(1858年)の翌年、日本初のアメリカ公使館が麻布山善福寺に置かれた。そして初代アメリカ公使のタウンゼント・ハリスや通訳のヒュースケンをはじめ、二十人ほどのアメリカ人が滞留することとなった。

画像出展:「御府内場末往還其外沿革図書」
こちらは文久2年(1862年)の古地図です。1858年の“日米修好通商条約”締結の4年後になります。緑色(土手・百姓地)に囲まれた水色は“古川”です。また、オレンジ色は“宮・寺”で中央の大きなエリアが“善福寺”です。白色は“武家地”ですが非常に多いことが分かります。
●明治維新を迎え、武家中心の町であった麻布十番の商店街は一時の賑わいを失った。
その後、栄えるきっかけとなったのは明治六年(1873年)、麻布十番からほど近い芝赤羽の旧久留米藩有馬家の上屋敷跡(現在の国際医療福祉大学三田病院、済生会中央病院、三田国際ビル、都立三田高校、港区立赤羽小学校などを含む二万五千坪に及ぶ広大な場所)に、工部省の赤羽製作所(官営の機械製作工場、後の海軍造兵廠)が開設されたことである。

画像出展:「分間江戸大地図」文政11年(1828年)
こちらは最初の古地図(文政11年)のほぼ中央部分を拡大したものです。現赤羽橋駅の古川に沿って大きなエリアを占めているのが“有馬玄蕃”の上屋敷です。そして、有馬家の上屋敷の左側に隣接するのが三田小山町になります。

画像出展:「江戸の外国公使館」
写真の左側が有馬家の上屋敷の塀とのことです。方角が不明確ですが、上図(文政11年)から考えると、左が有馬家なので右は松平家(松平隠岐)の上屋敷ではないかと思います。
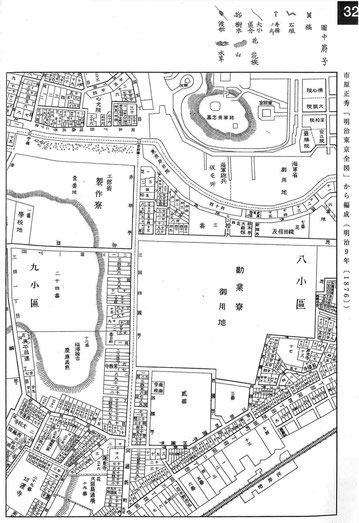
画像出展:「市原正秀[明治東京全図]」
こちらは明治9年(1876年)の地図です。上部に“古川”が書かれています(左から小さく“中ノ橋”、“赤羽橋”とあるのでこれが川だということが分かります)。これを見ると、有馬家の上屋敷の跡地に工部省の赤羽製作所(この地図には“製作寮”となっています)があったことが確認できます。
●その後、明治八年(1875年)には、赤羽製作所の西側に三田製糸所が開業。明治十二年には三田製作所(芝五丁目)、明治二十年に東京製綱株式会社(南麻布三丁目)、明治三十二年に日本電気(芝五丁目)といった大企業が次々に設立された。さらに、日露戦争[1904-1905]後には古川沿いにも工場が林立し、十番街商店街は工場労働者の日用品や食料品の供給基地として、再び活況を呈するようになった。
●麻布の台地部では、明治二十年代の後半あたりから武家地の区画整理が急速に進んだ。特に西町(現在の元麻布二丁目)あたりを中心に、政治家や実業家の大きな邸宅が建ち並ぶようになり、明治の後期には皇族や華族、政府の高級官吏などが住む都内屈指の高級住宅街となった。
●古川沿いの低地に開けた繁華な商店街と、台地上から商店街を眺める高級住宅街―麻布十番の特徴的なコントラストは、明治期から大正期を通じて完成され、そのまま昭和という激動の時代へと突き進んだ。
麻布十番
●昭和はじめ頃の麻布十番の名物は「露店」だった。稲垣利吉先生の「十番わがふるさと」には次のように紹介されている。
『「当時の十番は今の一丁目から三丁目にかけて二百余軒の店舗が並び、夜ともなると露店が五十軒位出店した。露店といっても毎晩同じ人が同じ場所に店を出す人が多く、今の追分食堂(麻布十番二-五あたり)前や吉野湯(麻布十番一-十一あたり)の横町などには風呂帰りの人を相手の飲食店の屋台が並んだ」ということです。』
また、幼少期から二十年間を麻布竹谷町(現・南麻布一丁目1~4、9~26、27番の一部、三丁目3番)で暮らした高見順先生も、短編小説の「山の手の子」の中で露店について次のようにふれている。
『「夜店も私には楽しいものだった。アセチレンのにおいがなつかしく思い出される。縁日の夜店へは、私は子供の頃、母に連れられてよく行った。(中略)麻布十番通りの夜店―そこへ行くのに母は、おまいりに行きましょうと言うのが常だったが、ほんとは気晴らしに出かけたのにちがいない。安い、小さな鉢植えの植物を買うのが、母の、そして私の楽しみだった」と記しています。』
●麻布十番という名称が正式に地名となったのは昭和三十七年(1962年)のことで、それまでは麻布宮下町、麻布網代町、麻布坂下町、麻布山元町などに細分化されていた。
麻布竹谷町
●竹谷町は麻布村の一部で、明暦年間(1655~1658年)に仙台藩伊達氏の下屋敷となった。
●麻布十番から仙台坂を上り、麻布山入口信号の先を左折して150メートルほど行くと、左側に港区シルバー人材センターのビル(南麻布1-5-26)がある。この辺りが旧麻布竹谷町になるが、江戸中期までは伊達家下屋敷の敷地内の一部で、享保八年(1723年)以降は禄の低い旗本のお屋敷地だったようである。
●明治五年(1872年)に武家地を合併して麻布竹谷町になった。仙台坂は町の北辺の長い坂である。仙台坂の由来は坂の南に仙台藩の広大な下屋敷があったためである。
●仙台坂は二之橋の交差点を起点に西の方向(西麻布方向)へ、およそ500メートルつづく急勾配の長い坂。坂上の台地(元麻布)と坂下の低地(麻布十番)を結ぶ主要路であり、麻布十番と南麻布を分ける境界線にもなっている。

画像出展:「御府内場末往還其外沿革図書」
こちらは先にご紹介した文久2年(1862年)の古地図の中央付近を拡大したものです。オレンジ色は“宮・寺”、白色は“武家地”、灰色は“町屋”、緑色は“土手・百姓地”、クリーム色は“道”です。ほぼ中央の道が“仙台坂”です。

地下鉄日比谷線 広尾駅で降りて、有栖川公園を越え少し歩いていると”仙台坂”の交差点にきます。右前方が”旧 松平陸奥守下屋敷坂(上図)”です。
また、この仙台坂を下った左側に善福寺があり、その前方左側が”麻布十番”になります。
●昭和二十年(1945年)五月、夷弾の爆撃により一面焼け野原と化し、それまであった家並みは激変したが、町の地勢はそれほど変わらない。
本書の著者である辻堂先生は、昔の竹谷町を見つけました。
『土地の高低差を手がかりに崖を目指して西の方向へ進んでいくと、いやはやマンションが目の前に立ちはだかって、崖下の風景は見る影もありません。昭和四十年代までは高層建築は珍しく、ほとんどが平屋か二階建ての家屋ばかりだったので、屋根越しに崖肌を見ることができたのに……と、さらに歩を進めてみると、見えました!マンションのほんのわずかな隙間から、五十年前と変わらぬ姿で崖肌がのぞいていたのです。』
この崖上の台地が仙台藩の下屋敷があったところで、後に明治期に総理大臣を二度も務めた松方正義の三男・正作の屋敷となり、この敷地内の一部に先述した仙華園がありました。
高見順
●高見順先生は明治四十年(1907年)、福井県で生まれた。上京したのは一歳九ヵ月、飯倉三丁目あたりに落ちくつくも、ほどなくして竹谷町五番地に引越し。結婚され大田区大森に新居を移す昭和五年(1930年)までの二十二年間を竹谷町とその周辺で暮らした。
●高見先生は大正二年(1912年)、今の麻布区立本村小学校に入学するが、竹谷町のすぐ隣の東町に開校した「東町小学校」に転向した(著者の辻堂先生も東町小学校出身とのことです)。
なお、辻堂先生が特に高見先生に興味をもったのは、二十代の頃にたまたま読んだ「わが胸の底のここには」の中に、大正から昭和にかけての竹谷町の風景を見つけたからとのことです。

画像出展:「東京市麻布区図」
緑色のサインペンでマークした部分が“竹谷町五番地”です。また、右端に破線で大きく囲った部分は“東町小学校”になります。
●高見先生は母上から人一倍厳格に育てられた。そして先生もそうした母上の訓育に応えるように、勉学に勤しみ、一校(現・都立日比谷高校)、帝大(現・東京大学)というエリートコースを進み、やがて昭和を代表する小説家・詩人となった。
●高見先生は昭和二十年(1945年)の空襲の一ヶ月ほど前に竹谷町を訪れている。
『竹谷町に出た。私の通った東町小学校は昔のままだった。前の赤煉瓦の邸宅も昔のままだ。懐かしい。学校に沿った横道に入った。突き当りの岡本さんは、私のうちでいろいろ世話になったところで、ここまで来たのだから挨拶して行こうと思ったら、―家がつぶれている。強制疎開だ。ごく最近、取りこわしたらしい様子だ。(「高見順日記」昭和二十年四月二十二日)』
東町小学校
●東町小学校は大正二年(1913年)に開校した。関東大震災による倒壊は免れたものの、昭和二十年(1945年)の空襲で全焼した。一旦は廃校になったが、昭和三十年(1955年)に再開した。
●東町小学校が高見文庫を設立したのは、高見先生が病気で亡くなった昭和四十年(1965年)十一月二十二日。「高見順日記」、「昭和文学盛衰記」や、高見家から寄贈された数百冊の著書が展示されている。
●展示されているのは約40冊と、高見先生の小学生時代の写真や新宿伊勢丹で開催された高見順展のパンフレット、「われは草なり」が掲載された国語の教科書なども陳列されている。
私事の件
1.「なんで? いつから麻布?」という疑問
答えは、高祖母の旧姓吉田ミヨ(天保14年[1843年]生まれ)の父である吉田宗衛門(母の高祖父)が、東京府麻布区坂下町(現・麻布十番二丁目・三丁目)に住んでいたというのがルーツでした。
戸籍から調べるのはこれが限界でした。この先はどのような方法があるのだろう思い、図書館から借りてきた本、『自分でつくれる200年家系図』をみると、いくつか手掛かりが出ていましたので一部をご紹介させて頂きます。

さまざまな手法:血縁よりも家としてのルーツ探し
・まずは郷土誌を読む
・総本家や親戚に行く(現地を訪ね、祖先の情報を得る。図書館や教育委員会にも手がかり)
・古文書を調べる(先祖が庶民なら“宗門人別長”を、武家の場合は“分限帳・由緒”も)
・菩提寺を訪ねる(“過去帳”や“墓誌”を見せてもらう。お寺と疎遠な場合は本家を通じて)
・名字を調べる(地名・地形・役職などに由来。ルーツ探しの手がかりになることもある)
・家紋を調べる(二万種もあるといわれる家紋。同族が必ずしも同じ紋ではない)
2.竹谷町五番地と竹谷町弐番地
母親の百歳を記念して”【祝】百歳”というブログをアップしているですが、東京大空襲直後の上野駅と電車の様子を知りたいと思い、探し当てたのが高見順先生の『高見順日記 第三巻』でした。
高見先生は明治四十年(1907年)、福井県で生まれ昭和五年(1930年)までの約22年間を“麻布竹谷町五番地”で暮らしました。なお、「高見順」のペンネームで小説を書き始めたのは、東京帝国大学英文学科在学中とのことです。
一方、11歳年下になる母も約20年、同じく麻布竹谷町に住んでいたので、もしかしたら小学生時代に高見先生とすれ違っていたかもしれません。
なお、戸籍によると”東京市麻布區竹谷町弐(2)番地”は”東京市港區麻布竹谷町壱(1)番地拾五(15)号”に変わっていました。

画像出展:「東京市麻布区図」
大正13年(1924年)の地図です。緑色でマークした部分が“麻布區竹谷町五番地”で、赤色は母親の自宅があったと考えられる箇所です。

画像出展:「マピオン」
現在の同地域の地図です。中央やや上方の”竹の湯”は創業大正二年です。

竹の湯からみる麻布區竹谷町弐番地方面の様子です。
辻堂先生が特に高見先生に興味をもったのは、二十代の頃にたまたま読んだ「わが胸の底のここには」とのお話でしたが、私も気になってこの本を買ってしまいました。
ご参考
麻布竹谷町と三田小山町について、とても変参考になったサイトがありましたのでご紹介させて頂きます。
1.江戸町巡り
”麻布”に関する情報もあります。
ここまであまりご紹介してこなかった“三田小山町”に関して、とても詳しく書かれています。なお、こちらのサイトは『東京都港区麻布周辺の情報、昔話などをお届けします。』とのことです。
覚明行者と御嶽信仰
父方の祖父は明治23年生まれ、幼少期より浅草で育ちました。若かりし頃には、まさに「髪結いの亭主」だったこともあるそうです。私が知っている祖父は気骨ある明治の男という印象が強く、相撲と時代劇、そしてよく本を読んでいました。また、鉄棒、ブランコ、ニワトリ小屋など何でも作ってくれたのですが、祖父の弟さんは有名な宮大工だったとのことです。
特によく覚えているのは御嶽山と覚明さん(覚明行者)を敬い、深く信仰していたということです。毎朝、長い経文[キョウモン]を唱えていました。何を言っているのかサッパリわかりませんでしたが、最後の「かしこみかしこみ申す」という言葉だけは覚えています。
10月に母が他界し、宗教や死後の世界に興味をもったことで、祖父が深く信仰していた覚明さん(覚明行者)の御嶽信仰がどんなものか知りたくなりました。そして、『木曽のおんたけさん』という本を見つけ購入しました。

犠牲者・行方不明者あわせて63名の大惨事となった御嶽山の噴火は2014年9月27日でした。そして、山頂までの登頂が再開されたのは2019年7月1日でした。
大惨事後に設置されたこのシェルターの写真は“My Roadshow -登山ブログ”さまから拝借しました。
ブログは“山岳信仰”、“御嶽信仰”、“覚明行者”および覚明行者によって開かれた“黒沢口登山道”を取り上げました。
なお、黒沢口登山道が開かれる前は、御嶽山への登山は熱心な一部の信者に限られたものでしたが、この登山道が開かれたことによって一般の信者も登山が可能になったとのことです。
日本の山岳信仰
・日本における山岳信仰は縄文時代にさかのぼるが、それが宗教として展開し始めたのは弥生時代以降と考えられている。
・弥生時代になり水稲農耕が行われるようになり、山は水田に必要な水を供給する場所、水分神(ミクマリシン)の場所として崇敬され、祭祀が行われるようになった。
・飛鳥、奈良時代になると、仏教の僧侶たちは山林での修行を行うようになった。
・奈良、平安時代には多数の霊山が開山された。
・平安時代、天台宗の最澄や真言宗の空海は唐で密教を学んだ。これらの宗派は比叡山や高野山などの霊山に修行の場を求めていった。そのため、天台宗や真言宗の全国展開とともに、多くの山々に寺院が建立された。また、この頃から主に仏教側からの働きかけによって、在来の神道の信仰と仏教が混ざり合う「神仏習合」の信仰が盛んになっていった。
・山中の霊場を巡って修行する僧侶や行者の中には社会的に大きな活躍をするものもあり、人々はこうした山の宗教者を「験者」や「山伏」と呼んだ。その後、これらの宗教者は「修験者」となっていった。
・室町時代に入ると、こうした修験者の修行のルートや拝所、山で行う修行法、儀礼や教義が整えられ、人々の宗教的な要求に応えて祈祷活動を行う修験道が成立した。また、こうした教義の成立とともに日本各地の山々や里に住む修験者や熊野先達の組織化が進められ、天台宗系の本山派と、真言宗系の当山派という二つの修験道組織ができた。
・江戸時代に入ると、幕府は武装勢力でもあった修験勢力を統御するために、本山派と当山派を競合させたり、修験道法度を発するなど統制下に置くことに努めた。
・諸国を遊行しながら修行していた修験者たちは、この頃から村落などの地域社会に定住するようになった。そして、自分が所属する派の霊山に入って修行を行うことで修験者としての立場と位階を認められた。
・江戸時代の山岳信仰の特色として、一般の人々による諸国の霊山崇拝が盛んになったことが挙げられる。これによって霊山は修験者だけでなく、多くの人の対象として繁栄していった。
御嶽信仰
・日本人は古来より国の豊かな自然に接して、山や自然そのものに対して山川草木に神が宿るという、素朴な信仰を育んできた。そして、そのような信仰を基に、仏教や神道などの影響を受けて修験道と呼ばれる山岳信仰が形成されてきた。
・木曽御嶽も素朴な信仰を基に、奈良時代から鎌倉時代にかけては修験道の影響を受け、また、室町時代から江戸時代初期にかけては黒沢と王滝の両御嶽神社により組織されて、道者と呼ばれる宗教者が活躍していた。
・江戸時代中期には覚明行者と普寛行者が現れて、この山を一般の人々にも開き、講集団を中心とした御嶽信仰が尾張や江戸を中心に盛んになり、やがて全国へと広まっていった。
・明治以降は神仏分離や講集団の教団化、戦後の信仰の自由など、時代の荒波の中で信仰が維持され、今日に至っている。
・現在の御嶽信仰は神道を中心に、素朴な信仰を基として、仏教や講集団の信仰が重なって成立している。
覚明行者の誕生
・御嶽山が一般の人々にも開かれた信仰の山となったのは江戸時代末期、尾張の覚明行者が黒沢口を開放したことによる。それまでは、里宮の管轄指導のもと、百日にも及ぶ重潔斎を必要とし、その潔斎期間や経済的な面からも、一般の人々による登拝は無縁だった。
・覚明行者は享保三年(1718年。四年という説もあり)に生まれたとされている。
・覚明行者は、宝暦二年(1752年)、宝暦八年(1758年)、宝暦九年(1759年)、宝暦十一年(1762年)、宝暦十三年(1763年)、明和元年(1764年)、明和三年(1766年)と計七回もの巡礼修行を行っており、次第に人々を救済するという行者としての新たな世界を見出していったと考えられている。
黒沢口登山道から御嶽山頂上へ
・黒沢口が天明五年(1785年)の覚明行者による中興開山以来、御嶽講を中心に登拝に利用されてきた歴史ある道である。
・黒沢口から登る場合、御岳ロープウェイで七合目まで入る人が多い。
・大きな駐車場は六合目にある。
-『登山口となる黒沢口六合目は大きな駐車場となっており、おんたけ交通バス(季節運行)の待合所やトイレもある。身支度を整えたら、バス待合所左脇から登山道に入ろう。歩きはじめるとすぐに、平成二十年から休業となった中の湯別館があらわれ、そこから本格的な登りとなる。針葉樹と笹の中に続く登山道には、ところどころ木が敷き詰められたり、木段となっているので足元は安心してよい。休業中の日野製薬の売店小屋を過ぎ、旧湯の小屋分岐から急坂の登りが続く、二十分ほどがんばれば勾配は緩やかになり、すがすがしい針葉樹林を登って行けば七合目の行場小屋に着く。
ここから御岳ロープウェイ山頂駅までは遊歩道で十分たらずである。
行場小屋を出るとすぐに橋で小さな沢を横切るが、ここは覚明行者が修行をした場所と伝えられ、石碑も建てられている。そこからは地面や倒木の上に美しい苔が生えた森の中の道となる。はじめは緩やかであった登山道も次第に勾配がきつくなり、汗をかきながらのジグザグ登りとなる。急な木段の細道も小さな桟橋まで上がれば大分緩やかになり、いつのまにか針葉樹の森がダケカンバなどの灌木に変わっている。すれ違う講の登山者たちが鳴らす鈴の音と活気に慰められながら、広くなった登山道を歩き続け、次第にハイマツ多く見られるようになれば、まもなく八合目女人堂に出る。
ここからは城塞のように切り立った御嶽山の稜線が眺められる。また、小屋前は阿波ヶ嶽と呼ばれ、四国方面の御嶽講社の霊場となっている。
女人堂からはいったん小さな谷を巻いてから尾根に取り付くが、この部分は七月上旬には雪が残っていることが多い。少し登って登山道が右に折れたところが剛童子で、登山道の右手に小さな祠[ホコラ]が祀られている。江戸時代まで女性はここまでしか登拝が許されなかった。
また、祠の横に大きな岩が立っているが、これは天照大神が隠れた天の岩戸を手力男命が開いたときに、放り投げた岩戸が飛んできたものであるといわれている。また、この一帯は古い霊神碑が林立し、独特の宗教的雰囲気をかもし出している。風化した霊神碑や素朴な風貌の神像を眺めながら登ると、次第に道は勾配を増してゆく。ハイマツの間の、雨によってえぐられた登山道を登って行くと、大きな鳥居と三笠山刀利天像がみえてくる。鳥居の前は少し広くなっているのでグループ登山の休憩に用いることができる。
さらにもうひとがんばりすれば急に視界が開け、砂礫[サレキ]の裸尾根に出る。ここには弘法大師の大きな銅像が祀られており、展望もよく、晴れた日には中央アルプスの眺望が素晴らしい。団体の休憩にはよい場所である。ここからは眺めのよい尾根上の登りとなるが、、道は砂礫状になっているため少々歩きにくく、六合目、又は七合目から歩いてきたときには疲れが出はじめるところでもある。砂ザレの急登を周囲に慰められながら登り、道が尾根の右側をまくようになると小さな鞍部にでる。
ここで息を整えたら、いよいよ黒沢口登山道一番の急登に入る。大きな岩石の階段を上がるような道は少々しんどいが、高度もぐいぐいかせいでいける。ゆっくりと、一歩一歩岩の階段をあがり、登山道脇に巴講の霊神碑を見れば、まもなく九合目の石室山荘に着く。ここから道は砂礫まじりのジグザグ道となるが、次の山小屋の覚明堂は目の前に見えているので気分は楽である。
覚明堂から石段を登り、鳥居を潜ると、覚明行者の大きな銅像や沢山の霊神碑が並び立つ拝所に出る。ここは二ノ池付近で亡くなった覚明行者のなきがらを祀った場所であることから、御嶽講の大事な聖地とされ、夏山中は講の信者たちが敬虔な祈りを捧げているのを眼にすることができよう。そこからもしばらく急坂が続くが、目の前の尾根に上がれば傾斜はくなり、まもなく御嶽の主稜線上に出る。
二ノ池や王滝知頂上への分岐など、いくつか道が分かれ、霧が掛かったときには迷いやすいが、案内板や登山道の両側に張ってあるロープに沿って行けば迷うことはない。稜線の眺望を楽しみつつ、砂礫混じりの道を一歩一歩踏みしめて行けば、まもなく頂上山荘に到着する。
頂上山荘前の石段を登れば、御嶽山の頂上、剣ヶ峰である。正面に小さな社殿や素朴な神像が並び立った大きな磐座[イワクラ]がある。それが御嶽神社の奥社であるので先ずは参拝しよう。神社の正面は次々と登ってくる講中が参拝に使うので、参拝をすませたら、神社の右手前の三角点が置かれた広場で休むとよい。そこからは一ノ池、二ノ池、王滝頂上など御嶽山の頂稜部を一望することができ、南側には木曽駒ヶ岳や宝剣岳など中央アルプス、北方には乗鞍岳とその向こうに槍ヶ岳、西北には白山を望むことができる。晴れていれば至福の時を過ごすことができるだろう!』
ご参考:御嶽山に関すること
ネット上には御嶽山(御岳山)に関するサイトが沢山ありました。ここでは三つのサイトをご紹介させて頂きます。
ボランティアについて
ボランティア活動に興味があり、『ボランティアってなんだっけ?』という本を買ってみました。70ページに満たない本で、親しみやすい題名だったため軽く考えていたのですが、その内容はとても深く、色々なことを考えさせられました。
地震や水害などの被災地への災害ボランティアは、人手不足を補うものとして確実に現地の助けになるものと思いますが、ボランティア活動を広く見渡すと、様々な課題があることが分かりました。
目次
Ⅰ そこで何が起こっているのか? ―自発性が生まれる場所、自発性から生まれるもの
Ⅱ それって自己満足じゃない? ―無償性という難問
Ⅲ ほんとうに世界のためになっているの? ―ボランティアと公共性
終章 ボランティアの可能性
Ⅰ そこで何が起こっているのか?
「ボランティアでは続かない」
●生き生きとボランティアを始めていた人の情熱が、時間が経つとだんだん冷めていくことがある。活動が整理されていくなかで、思ったことが言えなくなって、こなすだけになってしまったら熱は冷めていく。
●何をすべきかを自由に考えることよりも、これまでの活動を継続するための業務に追われ、活動への違和感を話し合えず、なんで活動するのかを考える機会もなくなると情熱は冷め、活動に距離を置くようになる。
●一人の参加者として責任のない立場で関わるのは良かったが、責任を負う立場になると敬遠する人もいる。すると責任を負う人の負担感や孤立感は強まっていく。
●ボランティアで始まった活動が持続性を高めていくために、非営利活動法人(NPO法人)や一般社団法人に移行していく。定款が作られ、事務局ができ、会費や寄付の制度が確立されていく。専従職員となる人が出て組織も確立していく一方で、初期の使命感が薄れ、活動の持続が目的となってしまうこともある。
●有償で働く専従職員とボランティアの間に溝が生まれ、ボランティアの数は減っていく。
●『「ボランティアでは続かない」ということはある面において正しいのだが、一方「ボランティアでないと続かない」ということも正しい。そんなことを、ある夏の体験で思った。』
ネットワーキング―出会いから広がっていく、出会いから変わっていく
●農園で子ども向けの農業体験イベントを開催した。1回目に参加した子どもが次の会には兄妹や友人を連れてきた。地域の情報誌に記事が掲載されて参加者が増えた。イベントの様子をSNSで公開したら、次々にシェアされていった。環境教育や農業に関心のある学生や社会人がボランティアをしたいと集まってきた。彼らの経験が企画に活かされて、体験講座の内容は専門化されていった。会議も定期的に開かれるようになり、助成金でキャンプをするためのテントや調理器具を買いそろえた。助成金の申請のためには規約や決算書、活動報告書が必要なため、事務局がつくられた。そんな中で、イベントの企画よりも農作業に興味を持ち始めた仲間から、子どもたちに農業体験をさせることよりも、自分たちがしっかり農業を勉強すべきだという声も出てきた。彼らの中には地方の専業農家のところに研修に行く人もいた。やがて、子どもたちへの農業体験を重視する立場と、学生自身が農業を学ぶことを重視する立場の違いが生まれ、活動をめぐって議論がなされるようになった。活動が広がる中で、新しい視点がもたらされ、活動自体の意味をめぐる議論が生まれる。その先に、活動自体の見直しが起こるかもしれないし、活動の分裂が起きるかもしれない。
●『「注意して見てほしい。一緒に団体を立ち上げた友人の関心は子どもの貧困問題だったのだが、次第に活動は子どもたちの農業体験/環境教育にシフトしており、そこからさらに農業への関心が生まれている。このような変化のなかで、友人には自分の当初の思いとつながるものを見出していくのか(たとえば、農業体験に来ている子どもたちのなかに貧困につながる問題を見出すのかしれない)、それとも流れに身を任せて当初の問題意識を忘れてしまうのか(たとえば、専業農家と出会って農業の面白さに心を奪われるのかもしれない)、それとも自分のやりたいことはここにはないといって去っていくのか、三つの方向があるだろう。』
Ⅱ それって自己満足じゃない? ―無償性という難問
無償性はめんどくさい―贈与のパラドックス
●あなたが誰か困っている人に何かをしてあげたいとする。見返りを求めてやったのではなく、困っている人を助けたいという気持ちに突き動かされたとあなた自身は思っている。しかし、あなたの内面は誰にも見えない。だから、周りから、本当は、「困っている人を助けている姿を見せて、自分の評価を上げたいのではないか」とか、「そうやって善行をつんで、死後に天国に行こうとしている」と指摘されたり、心の中で思われたりするのを防ぐことはできない。あるいは、「そうやってあなたが無償で誰かを助けてしまうことで、本当はそれをすべき〇〇が仕事をしなくなる」と言われることもある。この〇〇は例えば、政府が入る。このように贈与は常に、贈与と反対のものを見出されてしまうというパラドックスを抱えている。
贈与から交換へ―ボランティア・NPO・CSR・社会企業・プロボノ……
●1990年代以降、NPO活動が注目を集め、1998年には特定非営利活動促進法(NPO法)が成立するようになると、ボランティアよりもNPOの関心が高まった。
●NPOの非営利性とは、事業を通して利益を上げたとしても組織の成員で分配しないということである。
●ボランティアは“贈与”と考えられているが、NPOは“交換”の要素が強い。そしてNPOに続く、CSR(Corporate Social Responsibility)、社会的企業、社会的起業家、プロボノ、BOP (Base of the Economic Pyramid)ビジネス、エシカル消費、SDGs (Sustainable Development Goals)などもまた、“交換”と“贈与”の間にある言葉である。
●ボランティアという言葉が使われるのは、無償であるのが当然であると考えられる領域や、学校教育の現場に限られていった。
●阪神淡路大地震が起きた1995年がボランティア元年と言われているが、ボランティアをする人の割合は減少する傾向にある。
●『ボランティアが語られることや、そもそもボランティアをする人が減っていくなかで、久しぶりにボランティアが声高に語られ、議論を巻き起こしたのが東京五輪ボランティアだった。しかし、そこにおいて、贈与のパラドックスを伴う「無償性」は放棄されてしまったように見える。』
ケアの論理
●ケアはケアする人とされる人の二者間の行為ではなく、家族、関係のある人々、同じ病気・障害・苦悩を抱える人、薬、食べ物、環境などの全てからなる協働的な作業と考えられている。
●ケアの出発点は、人が何を欲しいと言っているのかではなく、何を必要としているかである。それを知るためには、その人の意思だけでなく、その人の状況や暮らし、困っていること、どのような人やシステムから支援を受けられるのか、それらの支援によって、その人の暮らしがどう変わってしまうのかなどについて理解する必要がある。
●苦悩はケアされる人だけではなく、家族や関係する人達も苦悩する。状況の改善は人や物、システムなど全てとの関わり合いの中でケアが行なわれるという意識を持つ必要がある。
終章 ボランティアの可能性
●ボランティアは国家や市場システムに都合よく使われることもある。隅々まで浸透した世の中と思っても、国家や市場システムから見放された世界が存在する。ボランティアがなければ苦しい人々は間違いなく存在する。
●国家や市場のシステムを批判し、今ある世界に取って代わるような理想像を掲げるのではなく、今あるシステムがうまく機能していないところに入り込み、他者と共に生きる空間を作っていくことは一つの在り方である。
ヨガ
以前、友人から「ヨガはいいよ」と教えてもらったことがあり、いずれ一度はやってみたいなと思っていました。
場所や時間、費用面で適当なものがあったらと思いながら探していると、親しみやすい、始めやすい感じの講習会があり、早速、大きなバスタオルを持参して参加してきました。
友人が言っていた通り、いい感じです。深い呼吸、適度な身体的負荷、何だか清々しい気持ちになります。「これは続ける価値ありだな」ということで、入会し続けることにしました。
また、一度やってみて、バスタオルは摩擦がなく足元が不安定になりやすいためNGということが分かったので、ネットショップでヨガ用マットを購入し次回に備えました。また、ヨガといえばインドですが、せっかく始めるのだったらヨガがどんなものか、最低限のことは知っておきたいと思い、色々ある中から『ヨガが丸ごとわかる本』という本を買ってざっと一読してみました。
ブログは目次の黒字箇所です。最初にヨガの概要をお伝えしたかったため、Chapter_7、”ヨガとスピリチュアル”の中にあったものを最初に持ってきています。
目次(Contents)
プロローグ
Chapter_1
ヨガとは何か?
・ヨガとは何かを探ってみよう
・ヨガが与えてくれるもの
・ヨガの歴史
・紀元前から2016年まで世界と日本のヨガヒストリー
・日本のヨガ偉人
・世界の人々に影響を与えたヨギー&ヨギー二
・インドの聖者達
・ヨガする世界のセレブ達
Chapter_2
ヨガの流派について
・古典ヨガと現代ヨガ
-アイアンガーヨガ
-アシュタンガヨガ
-クリシュナマチャリアのアイアンガーヨガ
-沖ヨガ
-クリパルヨガ
-クンダリーニヨガ
-シバナンダヨガ
-パワーヨガ
-ホットヨガ
-リストラティブヨガ
-陰ヨガ
-ライフステージ
-ニュースタイル
・ハタヨガとヴィンヤーサヨガ
・その他
・新しいヨガ
Chapter_3
ちょっとディープなヨガの考え方と哲学
・本当の自分について
・プラシャとプラクリティについて
・人間の体の考えかた 五つの鞘「パンチャコーシャ」
・エネルギーの質、トリグナ
・マンガで知るヨガ「そもそもヨガ哲学って、なあに?」編
・ヨガの八支則について
-ヤマ
-ニヤマ
-アーサナ
-プラーナーヤーマ
-プラティヤーハーラ
-ダーラナ
-ディヤーナ
-サマディ
・禅の十牛図とヨガの関係を見ていく
・ヨガは呼吸が大切な理由
・呼吸がもたらすもの
・いろいろある呼吸法
・プラーナを知ろう
・体に作用するプラーナの流れ
・さまざまな角度からプラーナを捉える
・プラーナとナーディの哲学
・呼吸には「完成」がある
・呼吸とプラーナのことQ&A
Chapter_5
ポーズについて
・アシュタンガヨガの太陽礼拝A
・アシュタンガヨガの「トリスターナ」
・シヴァナンダヨガの太陽礼拝
・立位のポーズ
・座位のポーズ
・後屈のポーズ
・逆転のポーズ
・ポーズ名に出てくるサンスクリット語
・ポーズのことQ&A
Chapter_6
瞑想
・瞑想の基本
・座り方と印
・迷走しないための瞑想コラム
・注意点
・瞑想に種類ってあるの?
・たくさんある瞑想
・マンガで知るヨガ「とにかく瞑想をやってみよう!」編
・マインドフルネス瞑想
・瞑想中に起きていることは
・四つの三昧(サマーディ)状態
・あの偉人達の瞑想
Chapter_7
ヨガとスピリチュアル
・マンガで知るヨガ「スピリチュアル」編
Chapter_8
ヨガのメディカル的側面
・ヨガで健康を手に入れる
・沖ヨガ
・ヨーガ療法
・ヨーガセラピー
・がんへのヨガ的アプローチに注目!
・ヨガの健康における概念
・アーナンドラが語る鞘の話
FEEL THE INDIA
・ヨガを生活に取り入れて楽しむ、学ぶ
-Fashion
-Goods
-Food
-Music&Mantra
-ヨガを学ぶ、習う
-先生になる
-情報を得る
-ヨガのイベント
・ヨガ旅へ出かけよう!
-INDIA
-NEWYORK
-HAWAII
・ヨガ用語辞典
Chapter_7
ヨガとスピリチュアル
「エクササイズからの卒業」と題するページに書かれていたことは次のようなものです。
『ヨガを始めると、ヨガが単なるエクササイズではないと知る。日常的にも道徳的なヨガの心が芽生え、そして生き方が変わってくる。それこそが本質的なヨガの始まりなのだ。』
そして、次のページにある「目に見えないものを受け入れていく」は、ヨガというものの概要を端的に伝えているように思います。
『ヨガはエクササイズではない。そこには深い精神性が横たわっている。ヨガはポーズを中心としたフィットネス部分のみだけではなく、道徳的な、日常の行いへの意識づけから始まり、呼吸を中心に心へ焦点を当て、感情の起伏や、心の波を穏やかにしていくもの。それらは、“目に見えない”ものが多い。
身体的アプローチで目に見えているはずのポーズや呼吸も、目に見えない部分に対してアプローチするのが練習の本質だ。ヨガは論理的には説明できないことまで、すべて丸飲み込みして行っていく。そうすると、到達するところは、感動的で魂が振るえるほどの歓びが存在する場所。ヨガは体にだけアプローチするボディワークではなく、スピリチュアルワーク(魂への行い)なのだ!』
Chapter_3
ちょっとディープなヨガの考え方と哲学
●本当の自分について
-ヨガでは「自分」という存在を追及していく。これはヨガ哲学の根幹である。そして「本当の自分(真我)と自我によって作られた「自分」がいると考える。
-私とは「本当の自分」と「それを取り巻く自分」の二つでできていると考えられている。
-「本当の自分」は、観る存在であり活動する自分を観察している。今「認識している自分」は、この世を体験するための器。傷ついたり、辛い思い、痛い思いをしたのは「本当の自分」ではない。
-「本当の自分」は何があっても常に美しく、尊厳が保たれた満ち足りた存在である。
●プラシャとプラクリティについて
-プラシャ(真我)とは?
+ヨガでは「自分」は、二つのものからできていると考え、それが一つになることを目的とする。
+二つとは今「認識している自分」と「本当の自分」である。
+プルシャは「本当の自分」のことで、真我ともいう。
+プルシャは常に「自分(自我。認識している自分)」を観察しているが、自我(心)の活動が激しいと、その活動ばかりに意識が向いてしまい、奥にあるプルシャの存在に気づけない。
+瞑想は波打つ心(自我)の活動を静め、波がなくなり透き通った湖の底に眠るような「真我」に気づき一つになるための方法である。
+プルシャは大自然(宇宙。大いなるもの)の一部であり、真我と一つになることは大自然と一つになること、自分は大自然の一部だと気づくことでもある。
-プラクリティとは?
+プルシャを取り巻くもので、普遍的なプルシャに対して移りゆくものをプラクリティ(質の源)という。
+プルシャは「質」を持たないので、プラクリティを使って“世界”(生きた宇宙。イーシュワラともいう)を映し出し、それを観察している。
+人でいうと、肉体、考え、言葉、行動など、変わり続けるのはすべてプラクリティであり、それをプラクリティが観ているということになる。
+プラクリティが濁ごることなく浄化されていれば、真我とつながりやすくなり、大いなるものの智慧に基づく生き方ができる。
●ヨガの八支則について
-ヨガの八支則はヨガのゴールに到達するための方法であり、考え方である。
-ヨガの八支則は自分自身における抑制、つまり自分で自分のことを管理するということである。
-『ヤマ[Yama]は禁戒として訳されることが多く、日常生活で慎むべきこと(してはいけないこと)ということだ。そしてヤマとセットとなるのが、ニヤマ[Niyama]。これは勧戒と訳され、自分自身が努めるべきこと(すべきこと)だ。
ヤマとニヤマの中は五つに分かれている。ヤマには、アヒムサ(非暴力)、サティヤ(正直)、アスティーヤ(不盗)、ブランマチャリア(禁欲)、アパリグラハ(無執着)ということが含まれる。
そして、ニヤマには、シャウチャ(清潔)、サントーシャ(知足)、タパス(苦行)、スワディヤード(独習)、イーシュワラプラニダーナ(信仰)というものが含まれる。
これらのヤマ、ニヤマはヨガをするものにとっての道徳的戒律として存在している。ただ、日常生活、社会生活で、これらを完璧に行うことができたら、言わば聖人であり、神であるという人もいる。それほど難しいものだと考えていいだろう。
これらヤマ、ニヤマのような道徳的な考え方を持ちながら生活を律し、自分として心に引っかかることはない状態にしておき、アーサナ[Asana](坐法)により体の滞りをなくし、プラーナーヤーマ[Pranayama](調気、呼吸)によって呼吸を整え、プラティヤーハーラ[Pratyahara](感覚抑制)により感覚を内へと向けて、ダーラナ[Dharana](集中)で自分の中へ集中し、それが深くなりディヤーナ[Dhyana](瞑想)の状態へ。そこから瞑想していることも忘れるほど、一つの意識になる。すべてのものと隔たりのないような状態になり、融合、合一するサマディ[Samadhi](三昧)と続くのだ。これらは段階的に考えられていることが多いが、すべて横並びで、それぞれちょっとずつ高めていくという考え方もある。どれかを一つ高めても仕方がなく、どれもやり続けなくてはならないということ。』
Chapter_8
ヨガのメディカル的側面
●がんへのヨガ的アプローチに注目!

画像出展:「ヨガが丸ごとわかる本」
補完代替医療としてのヨガの可能性
『医療的側面をあわせもつヨガ。その可能性は乳がん予防や、再発予防にまで広がる。ヨガの次のステージはメディカルシーンへの貢献だろう。』
『現在、乳がん経験者、及び多くの女性に向けて、ヨガを通して乳がん予防のクラスを開催していたり、さまざまなシンポジウムや講演等で乳がん予防や再発予防にヨガの良さを伝えているアクションが多くある。』
-ゆっくりした動きのヨガは、治療経験者や治療中の人にも無理なく行うことが可能である。
-筋肉を鍛える必要があるならば、鍛える筋群の筋力アップを目的にあった“ポーズ”を取り入れることができる。
-硬くなった筋肉を緩める効果が期待できる。
-ヨガの基本である呼吸法は、副交感神経の働きを高め不安や緊張を軽減する。
-リラックス効果によりNK細胞などの免疫細胞が活性化し、がん細胞への攻撃力を高める。
-補完代替医療としてヨガは注目されている。1998年には米国国立衛生研究所がヨガ研究に公的資金の投入を開始し、2013年にはハーバード大学がヨガと瞑想の効果を科学的に検証する試みが行われるなど、米国ではヨガは統合医療の一つとして浸透してきている。
論語と仁
今年の大河ドラマは渋沢栄一の物語、“青天を衝け”です。渋沢栄一といえば、知っているのは名前程度で、埼玉県出身だということも、日本の「近代資本主義の父」とよばれていることも知りませんでした。
今回、拝読させて頂いたのは『論語の読み方』という本ですが、編・解説者である竹内 均先生の“解説”の中にあった「巨人・渋沢栄一の原点となった孔子の人生訓」に、渋沢先生の生い立ちから晩年までの話がまとめられていましたので、まず、そちらをご紹介します。
『渋沢栄一は、1840(天保11)年に、現在の埼玉県深谷市字血洗島の豪農に生まれ、年少の頃から商才を発揮した。そのうえ少年時代から本好きで「論語」との出会いもこの頃であった。
幕末の動乱期には尊王攘夷論に傾倒したが、後に京都に出て一橋(徳川)家の慶喜に仕えた。1886(慶應2)年、弟の昭武に従って渡欧せよとの命令が慶喜から下った。翌年から約2年間をかけて欧州各地を視察し、資本主義文明を学んだ。このときの見聞によって得た産業・商業・金融に関する知識は、彼が後に資本主義の指導者として日本の近代化を推し進めるのに大いに役立った。
帰国後は大隈重信の説得で明治新政府に移り、大蔵省租税正、大蔵大丞を歴任した。1873(明治6)年に大蔵省を辞してから実業に専念し、第一国立銀行(第一勧業銀行の前身)の創設をはじめ、70歳で実業界から退くまで500余りの会社を設立し、資本主義的経営の確立に大いに貢献するとともに、ビジネスマンの地位の向上と発展に努めた。
晩年は社会・教育・文化事業に力を注ぎ、大学や病院の設立など、各種社会事業に広く関係した。』
渋沢先生は「論語」を拠り所とされていました。そして竹内先生が編・解説をされた『論語の読み方』は、渋沢先生の『論語講義』のエッセンスを集大成したものであり、竹内先生の他の2つの著書、『孔子 人間、どこまで大きくなれるか』と『孔子 人間、一生の心得』を再編成したものでした。
しかしながら、話に水を差してしまうのですが、実は『論語講義』は渋沢先生自らが執筆されたものではないということです。そのことは“公益財団法人渋沢栄一記念財団 情報資源センター”さまのサイトに出ていました。

『公益財団法人渋沢栄一記念財団情報資源センターがお送りするブログです。渋沢栄一、社史を始めとする実業史、アーカイブズや図書館に関連する情報をご紹介しています。』
『渋沢栄一述とされる【論語講義】は、そもそも二松学舎の舎外生のために発行された【漢学専門二松学舎講義録】という全30回の月刊刊行物に29回(12号は休載)にわたって掲載された記事をまとめたものである。渋沢が口述したものを二松学舎教授の尾立維孝が筆述したとされるこの【論語講義】について、本論の筆者は「稿本」「初版本」「新版」等を詳細に比較検討した。その結果この【講義】は渋沢が口述したのではなく、渋沢述の【実験論語処世談】に基づいて尾立が起稿したもので、渋沢の校閲を経た上で連載されるはずであった。しかし校閲が間に合わず尾立の原稿のままで刊行が始まってしまい、渋沢の校閲が追いつくことはついになかった、と結論づけている。』
ブログのタイトルを”論語講義”ではなく、“論語と仁”としたのは『論語講義』が『実験論語処世談』からの起稿であり、渋沢先生の校閲を受けていない本だからです。
また、「仁」を特別の存在として注目し、取り上げたのは論語の中で「仁」は圧倒的に大事なものとされてきたためです。それは次の解説で明らかです。
『この仁の一文字は孔子の生命で、また「論語」二十編の血液である。もし孔子の教訓から仁を取り去ったならば、あたかも辛味のぬけた胡椒と同じであろう。孔子はこの仁のために生命を捧げたほど大切なことで、孔子の一生は仁を求めて始まり、仁を行なって終わったといっても差し支えない。孔子の精神骨髄は仁の一字にあり、このゆえに孔子は仁をもって倫理の基本とすると同時に、他の一面においては政治の基本としたのである。王政王道もつまり仁から出発したものである。』
さらに、次のような記述もありました。
『仁は「論語」の最大主眼であるから、孔子はあらゆる角度からこれを丁寧に詳しく説明している。そのため、中国・日本の古今の学者がさまざまな解釈を下して一定しない。そして、たいてい文字上の言句にとらわれて空理空論の悪弊を生み、わが国の学問もこれを受け継いで、学問と実生活が別物となり、学問は学問、実生活は実生活と分離してしまった。』
1.『子曰く、苟[イヤシ]くも仁に、志す。悪きことなり。』
●自分を大切にせよ、だが偏愛するな
・人間が悪事をなすのは、自分の偏愛、利己主義から始まる。
・仁者は広く大衆を愛し、利己を考えない。
・仁に生きることは純粋な心で行動することである。
・仁に志し、仁に生きようとするならば、その人の心に悪は生じない。
2.『或ひと曰く、雍[ヨウ]や仁にして佞[ネイ]ならずと、子曰く、焉[イズク]んぞ佞を用いんや。人に禦[アタ]るに口給を以てすれば、しばしば人に憎まる。その仁を知らざるも、焉んぞ佞を用いんや。』
●“口”の清い人、“情”の清い人、“知”の清い人
・弁が立たたないことは、むしろ美徳であり短所ではない。
・仁は徳の中心であり、基本である。
・広く民に施して大衆を救うのが仁である。
・仁者はその言行が親切で、言葉やさしく、自分の意見を述べるときも穏やかに説明して、大変人あたりがよい。
3.『樊遅[ハンチ]、知を問う。子曰く、民の義を務め、鬼神を敬して而してこれを遠ざく、知と謂うべし。仁を問う。曰く、仁者は難きを先きにして、而して獲ることをのちにす、仁と謂うべし。』
●孔子流の「先憂後楽」の生き方
・仁者は自分中心の心に打ち克って礼に立ち返り、誠意をもって人に接する。苦労を先にして、利益を獲得するのを後にするのが仁である。
4.『子曰く、道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に游ぶ』
●孔子が考えた“完全なる人物”像
・仁とは博く愛することで、単に自ら足るを知って他へ迷惑をかけないだけでなく、他へ幸福を分かち与えようとする心情である。
5.『子曰く、仁遠からんかな。我仁を欲すれば、ここに仁至る。』
●ひからびた心の畑に“慈雨”を降らせる法
・仁は忠恕(思いやりの心を推し進めて広く人を愛し、他人と自分との垣根を取り払うこと)。つまり、仁は自分の心の中にあり、外に求めるものではない。心から仁を求めようとするならば、仁は近く自分の心の中にあって、即時に仁は得られるものである。
6.『子曰く、知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は懼[オソ]れず。』
●これこそ「知・仁・勇」三徳のバランスに秀でた人物
・“論語”では仁者について、時に極めて狭義に解釈し、時に非常に広義に説かれている。
・ある場合には人を愛する情であるとか、他人の難儀を救う行為を仁としている。また、ある場合にはよく天下国家を治め、万民を安住させることを仁の極致であると言っている。
・仁者は天命を知り、一点の私心がなく、おのれの分を尽くし、人間としての道を行うのであるから、いささかの煩悶もなく、すべての物事に対して憂いというものがない。心中つねに洋々たる春の海のような気分である。これは仁者に備わる徳である。
・勇者はその心が大きく強く、常に道義にかない虚心坦懐であるから、何事に遭遇しても恐れることがない。これが勇者の徳である。
・人間は知と勇ばかりではいけない。知恵のある人、勇気のある人はもとより貴ぶべきではあるが、知勇は性格上の一部分であって、これだけでは完全な人とはいえない。仁を兼ね備えてはじめて人間としての価値が生じるのである。よって仁こそが最上の徳である。
7.『顔淵仁を問う。子曰く、己に克って礼を復[フ]むを仁となす。一日己に克って礼を復めば、天下仁に帰す。仁をなすは己に由[ヨ]る。而して人に由らんやと。顔淵曰く、その目を請い問う。子曰く、非礼視ること勿れ。非礼聴くこと勿れ。非礼言うこと勿れ。非礼動くこと勿れと。顔淵曰く、回不敏と雖[イエド]も、請うこの話を事とせんと。』
●孔子の最高弟・顔淵にしてこの“日頃の戒め”あり
・顔淵は孔子の門弟3000人中の高弟72人の中で最高の人である。年は孔子より37歳若かったが、徳行家で孔子に次ぐ人と称せされ、「亜聖」の名があったほどの人物である。
・顔淵は孔子に対して、「仁とはいかなるものですか」と質問した。以下は孔子による回答。
-自分の欲望に打ち勝ち何事にも礼を踏まえて行なう。これを仁という(仁の体)。
-一日でも自分の欲望に打ち勝ち、礼を踏まえて行えば、人々はすべてその仁にすがる。その影響の迅速なことは、早飛脚で命令を伝えるようなものである(仁の効)。
-仁は元々自分の心の中にあって、よそから借りてくるものではない。だから仁を実践しようと欲すれば、仁は直ちに成立する。いつでもどこでもこれを成し得る(仁の用)。
・仁は上記のように、極めて広大なものである。仁は天下国家を治める道にもなり、一家をととのえ一身を処する道ともなる。その徳は天地に充満して草木禽獣すべて仁のもとに息づくのである。
・人に対して優しく指示をするのも仁の一つである。不幸な人に同情するのも仁である。
・上を敬い下を慈しむのも仁である。広く施して大衆を救うのは仁の大きなものである。
・すべて人間が私心私欲に打ち勝って、その言動が礼にかなって行き過ぎがなければ、それがすなわち仁である。
・七情(喜・怒・哀・楽・愛・悪[憎]・欲)の発動がよく理知でコントロールされるのが仁である。
8.『子曰く、剛毅朴訥[ゴウキボクトツ]は仁に近し。』
●温室の中では、“心のある花”は育たない
・「剛毅木訥」は「巧言令色」と対になった言葉である。
・人の資質が堅強で屈せず(剛)、またよく自ら忍ぶ者(毅)、容貌質朴で飾り気なく(木)、言語がつたなくて口がうまくない者(訥)は、みな内に守るところがある。内に守るところがある人は、学んで仁徳を成就しやすい。
・剛毅木訥がそのまま仁であるとはいえないが、このような人は仁を成しやすいので、仁に近しというのである。
9.『子曰く、徳ある者は必ず言あり、言ある者は必ずしも徳あらず。仁者は必ず勇あり、勇者は必ずしも仁あらず。』
●人の“言葉と徳”だけは「逆も真なり」は通用しない
・仁者は人の危難を見過ごせず、義を見れば必ず身を殺してもこれを救う。だから仁者は必ず勇気をもっている。しかし、勇気は血気に乗じて発揮することもあり、勇者が必ずしも仁者であるとは限らない。
番外編:“青天を衝け”
“青天を衝け”では、栄一が血洗島を出て江戸に行きたいという熱い思いを、父にぶつけるシーンがありましたが、活字で見るとより重さを感じます。ここでは栄一へ渡された父からの言葉をご紹介します。
『人にはおのおの備わった才能がある。またおのおのの異なった性分がある。その性分の好む所に向かって驀進するのが、天分の才能を発揮する方法であるから、お前を遠く外へ出したくはないけれども、お前の決心もわかったし、また必ずしも悪い思いつきでもない。強いて止めればお前は家出するだろう。そうなれば不幸の子となるから、強いて止めはしない。お前の身体はお前の自由にするがよい。望みどおり出発せよ。』
対話型ファシリテーション
筋膜性疼痛症候群(MPS)研究会は、2018年4月、日本整形内科学研究会(JNOS)となり、前身の会員だった私は幸いにも新しくなったJNOSの准会員として、引き続き勉強させて頂いています。充実したオンラインセミナーは後日、動画配信されるため多くの有意義な機会を得ることができます。
今回のブログはその動画配信で学んだことであり、本はその時、紹介されていたものです。
“5W1H”の中には、“Why”も含まれていますが、「対話型ファシリテーション」の極意は、事実を明らかにすること、そのためには「なぜ?」「どうです?」を使ってはならないということです。これはかなり衝撃的でした。

著者:中田豊一
出版:認定法人ムラのミライ
初版発行:2015年12月
ブログで触れているのは、もくじの黒字の箇所です。
もくじ
1.「なぜ?」と聞かない質問術
2.「どうでした?」ではどうにもならない
3.「朝ごはんいつも何食べる?」の過ち
4.簡単な事実質問が現実を浮かび上がらせる
5.「いつ?」質問の力
6.行動変化に繋がる気付きを促すファシリテーション
7.○○したことは、使う
8.信じて待つ=ファシリテーションの極意
9.気付きには時間がかかる
10.達人のファシリテーション
11.対話型ファシリテーションを使うインドの村人
12.答えられる質問をする
13.それは本当に問題か
14.都合のいいように解釈する
15.時系列で聞いていく
16.対話型ファシリテーションの実践性
17.○○が足りない
18.問題とは何か
19.栄養不良の原因は何か
20.考えさせるな、思い出させろ
21.空中戦を地上戦に
22.対話型ファシリテーションは最強のコミュニケーションツール
6.行動変化に繋がる気付きを促すファシリテーション
●ファシリテーションはまちづくりや開発教育などのための参加型のワークショップの進行役がファシリテーターと呼ばれるようになり、それに伴って、技能としてのファシリテーションという言葉が徐々に広まった。
●ファシリテーションの技能の核心は、ワークショップなどにおいて、参加者の気付きを「促す」ことにある。
●養豚の方法についてラオスの村人達と研修したときの話(2回の研修では出席者は全員男性だった)
・ファシリテーター:①「今朝、豚に餌をあげましたか?」(全員、うなずく) ②「餌をあげる作業は誰がやりましたか?」(参加者の6世帯中、5世帯は妻の仕事だった)→村人曰く「母ちゃんを連れてきます」との気付きが生まれ、結果的に次回の研修では多くの村人が夫婦での参加となった。
・対話型ファシリテーションは、簡単な事実質問によるやりとりを通して相手に気付きを促し、その結果として、問題を解決するために必要な行動変化を当事者自らが起こすように働きかけるための手法である。重要なことは、問題の当事者の「気付き」が「行動変化」のための大きなエネルギーになるということである。
7.○○したことは、使う
①聞いたことは、忘れる。
②見たことは、覚えている。
③やったことは、わかる、身に付く
④自分で見つけたことは、使う
・自分で見つけたもの以外は、ほとんど忘れる。ファシリテーションでは相手が答えを自分で見つけるまで、粘り強く働きかける必要がある。
・自分で発見することは、気付きの喜びを得ることでもあり、その喜びをエネルギーに行動変化のための第一歩となる。
・同じ答えでも自分が見つけるのと他人から教えてもらうのとでは、心理的な効果という点では、天地の差がある。
●実際の場面では、すぐに気付くわけでも、すぐに行動に移るわけではなく、ほとんどの場合多くの時間を要する。そのため、ファシリテーターは焦ることなく地道に働きかけを続けていくことが求められる。
10.達人のファシリテーション
●対話型ファシリテーションの訓練は複雑なものではなく、「事実質問に徹する」という単純な実践の繰り返しである。事実質問を重ねていくと、人間の意識と行動と感情を繋ぐ糸の共通の仕組みがだんだんと目に見えるようになっていく。
●意識と行動と感情を繋ぐ糸は、「これは何ですか?」「それはいつですか?」と聞いていくことで見えてくる。
12.答えられる質問をする
●対話型ファシリテーションの前提は相手のことに関心をもっているということである。また、その際心がけることは「相手が答えられる質問をする」ことである。
●「答えられる」という意味は2つある。1つは、思い出す努力を少しすれば楽に答えられることである。代表的な質問は、「いつ、どこで、誰が?」というものである。もう1つは、心理的に答えやすい質問である。嫌なことを思い出させるような質問を無神経にしていては、相手は距離を置き、心を開くことはない。
●相手が答えられる簡単な事実質問をすることが、敬意を伝えるために最高の方法である。簡単な事実質問に答えているうちに、相手の自己肯定感が高まり、自然と互いの心が開かれていく。
14.都合のいいように解釈する
●人が自分自身の問題の原因を分析する場合、自分の都合のいいように解釈するのは、人に元々備わっている精神の自己防衛システムであり、重要な役割を果たしている。しかしながら、それ故に自分の問題の原因を冷静に客観的に分析するのは、本人が考えているよりはるかに難しいものとなる。
●人は相手が問題について語り始めると、「それは何故ですか」「どうしてですか」とつい聞いてしまう。すると、人は自分勝手な安易な原因分析や用意していた言い訳を離し始めてしまう。
・例)「なぜお子さんに朝ご飯をきちんと食べさせないのですか?」→「朝は時間がないからです」あるいは、「子どもが朝早く起きないからです」等々。
●相手の問題や失敗について「なぜ?」と直接聞くと、詰問や非難のように取られることも少なくない。本当の原因を知りたい場合は、「なぜ?」「どうして?」は使ってはいけない。
●問題を明らかにするための支援では、「問題はなんですか?」という問いかけは、「なぜ?」や「どうして?」と同様に、問題の真実をむしろ隠してしまう。
15.時系列で聞いていく
●対話型ファシリテーションでは、相手が問題を語り始めたら、まずは、「一番最近、それで誰がどのように困りましたか?」あるいは「それを解決するためにどんな努力をこれまでしてきましたか?」と聞く。そして、それが本当に問題だという合意をすることが必須であり、その確証がないまま本格的な分析に入っていってはいけない。
●合意できた問題の分析の基本は、常に、「いつですか?」「覚えていますか?」と聞きながら、時系列で質問を進めていくことである。一般的には、一番最近のことから聞いていき、徐々に古い記憶を呼び起こし、問題の大まかな姿が明らかになったら、いよいよ出発点の話に入っていくのが良い方法である。
●Nさん(喘息患者)に対する医師Aと医師Bの例
Nさん:かなり前から、時々、喘息発作に襲われていて、その都度手近な医院に駆け込んでいた。
・医師A:「どの程度の頻度で発作が起こりますか?」→Nさん:「年に2、3回くらいだと思います」。この結果、医師はその都度、薬を処方し発作は治まるということをここ何年も繰り返してきた。
・医師B:「前回、発作が起こったのはいつですか?」「その前は?」→これらの質問の結果、最近4カ月の間に少なくとも3回くらい発作が起こっていたことが分かった。
-医師B:「最初に喘息が起こったのはいつですか?」→Nさん「小さい時から小児喘息があったんです」→医師B「あったということは、それは治ったんですね?」→Nさん「はい、治りました」→医師B「それはいつですか?」→Nさん「高校生の時です」→この段階でNさんは気付いた。それは、高校を出るまでは母が付き添ってくれて定期的に通院していたけど、大学生になってからはそれがなくなり、たまに発作が起こっても病院に行かなくなり、誰からも「治った」と言われたことがないのに、「小児喘息は治った」と勝手に思っていた。という事実を認識した。
-医師B:「今の薬は強すぎますね。強い薬を使わず、微量の薬を毎日服用し時間を掛けて喘息との付き合い方、薬の手放し方を対処していきましょう」→Nさんは、今まで自分から進んで努力してこなかったが、今回、自分の病歴をはっきり意識し、自分でしっかり受け止めたところ、前向きのエネルギーが出てきたとのことである。まさにこれが、『自分で見つけたことは使う』ということである。
18.問題とは何か
●「問題とは“こうありたい姿”と“現実の姿”との距離である」という定義をコンサルタントは使うようである。問題の大小は距離の大きさになる。距離を縮める方法は2つ、一つはありたい姿に現実を変えていく方法、もう一つは目標を下げる方法である。そして、まずはっきりさせなければならないのは2つの距離である。距離は問題を明らかにすることであり、目標を設定することである。距離が明確になると、内側からやる気が湧いてくる。距離を縮める方法を考えることも、それを実行に移すことも、前向きになれることが多いのはファシリテーションの力といえる。
心は量子で語れるか2
第一部 宇宙と量子と人間の心
第三章 心の神秘
意識はコンピュータに乗せられない
・意識というものは科学的に説明すべき問題である。
・図3-4は物質的世界と精神的世界をまとめたものである。
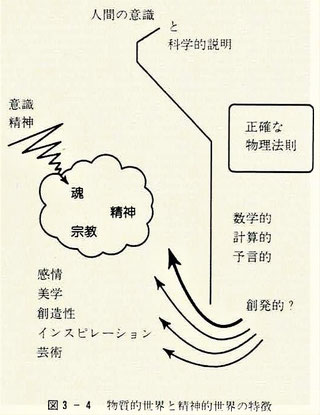
画像出展:「心は量子で語れるか」
『右側には“物質的世界”の様子が示されている―第一、第二で論じたように、物質的世界は、正確で数学的な物理法則によって支配されていると考えられる。左側には“精神的世界”に属する意識や、“魂”や“精神”や“宗教”などの言葉が並んでいる。』
微小管は八面六臂
・微小管はシナプス強度[シナプスにおける情報伝達率]の決定に関係していると思われる。
・微小管がシナプス強度に影響を与える方法の一つは、樹状突起棘の性質に影響を与えることであると思われる。これは棘内部のアクチン(筋肉収縮のメカニズムを司る不可欠な構成要素)に変質が起こることによって引き起こされる。樹状突起棘に隣接する微小管は、このアクチンに強く影響を与え、ひいてはシナプス結合の形またはその誘電特性に影響を及ぼす。
・『微小管がシナプス強度に影響を与える方法は、このほか少なくとも二通りある。信号を、あるニューロンから次のニューロンに伝える神経伝達物質の運搬に、確かに微小管は関与している。神経伝達物質を軸索や樹状突起に沿って運ぶのが微小管であり、その働きは、軸索の先端や樹状突起の中の化学物質の濃度に影響を与えるだろう。そして、これがシナプス強度に影響を及ぼすことになろう。さらに微小管は、ニューロンの成長と退化に影響を与え、その結果、ニューロンを連結してできたネットワークそのものを変えてしまうだろう。』
・『微小管とは何か? その一つを図3-18に描いた。それは“チューブリン”と呼ばれる、蛋白質から成る小さな管である。それはいろいろな点で興味深い。チューブリンは、(少なくとも)二つの異なる状態、または構造をもっていて、一方の構造から他方の構造へと変化できるようである。一見してわかるように、それはメッセージを管に沿って送ることができる。
事実、スチュアート・ハメロフ[米国の麻酔科医。ロジャー・ペンローズとの意識に関する共同研究で有名]と彼の同僚は、管に沿って信号を送る方法について、興味深い考え方を示している。ハメロフによると、たぶん微小管は“セル・オートマトン”[空間に格子状に敷き詰められた多数のセルが、近隣のセルと相互作用をする中で自らの状態を時間的に変化させていく「自動機械(オートマトン)」である。計算可能性理論、数学、物理学、複雑適応系、数理生物学、微小構造モデリングなどの研究で利用される]のように振る舞い、その管に沿って複雑な信号を伝達するのだという。チューブリンの二つの異なる構造が、デジタル・コンピュータの0と1を表現していると考えてみよう。すると1個の微小管が、それ自身でコンピュータのように振る舞うことができるから、ニューロンがどんなことを行っているかを考察する際には、この点を考慮しなければならない。各ニューロンは単にスイッチのような働きをするのではなく、非常に多くの微小管をもっていて、それぞれの微小管は極めて複雑なことをやってのけるのである。』
“意識”の理解に最も必要なこと
・『ここから、私自身の考えに入ろう。以上の過程を理解する上で、量子力学は欠かせないものかもしれない。微小管で私が最も興味をおぼえることの一つは、それらが“管”だということである。管であるがゆえに、管の内部で起こっていることを周囲のランダムな動きから隔離できる可能性が高まってくるのである。
第二章で私はOR物理学という新しい形式が必要だと主張した。そしてOR物理学が適切であるならば、周囲から十分に隔離されて、量子的に重ね合わされた質量移動が可能になるに違いない。管内部では、何か超伝導体[電気抵抗ゼロの物質]のような、ある種の大規模な量子的干渉[波動関数の重ね合わせの結果起こる干渉現象]が生じているのだろう。この活動が(ハメロフ型の)チューブリン構造と結びつき始めたときにのみ、おそらく顕著な質量移動を伴うはずだ。ここでは“セル・オートマトン”の振る舞い自体が、量子的重ね合わせの影響を受けるかもしれない。起こりうる状況を図3-19に描いておいた。
この図の一部で、おそらくあるタイプの干渉性量子的振動が、管内部で生じているに違いない。この量子的振動は脳の広範な領域にまで及ぶ必要があろう。
かなり以前にハーバート・フレーリッヒが、一般的なタイプの量子的振動に関して、いくつかの提案を行った。それによって、生物学の体系の中で、この性質をもつ対象の存在が、いくぶん現実性を帯びてきた。微小管は、その内部で大規模な量子的干渉が生じている構造と考えて差し支えないと思われる。』
・『私には、意識というものが何か大域的なものだと思われる。したがって意識の原因となるどんな物理過程も、本質的に大域的な性質をもっているに違いない。量子的干渉は確かにこの点での要求を満たしている。そのような大規模な量子的干渉が可能であるためには高度な隔離が必要とされ、微小管の壁によって、それが実現されているのかもしれない。しかしチューブリンの構造が関与するとなると、さらに多くのことが必要となる。
こうして要求される周囲からの隔離は、微小管のすぐ外側にある“秩序化された水”によってなされるだろう。(生きた細胞には存在することが知られている) 秩序化された水は、管の内部で起こる量子的干渉性振動の重要な構成要素でもあると思われる。このことはいささか難しい要求かもしれないが、以上のことがどれも事実だということは、たぶん全くの不合理というわけではないだろう。
微小管内部での量子的振動は、何らかの方法で微小管の活動、すなわちハメロフが言うところのセル・オートマトンの活動と結びつける必要があるだろうが、ここでは彼の考え方と量子力学とを結びつけなければならない。すなわち現段階では、通常の意味での計算活動だけではなく、こうしたさまざまな活動の重ね合わせに関連する量子計算も考慮しなければならない。
もし以上の話がすべてだとしたら、まだ私たちは量子レベルにとどまっていることになる。ある時点で、おそらく量子状態は環境と絡み合ってくるだろう。そのとき私たちは、量子力学における通常のRという手順に従って、一見したところランダムな方法で古典レベルへ飛び上がることになる。だが純粋な計算不可能の登場を期待するならば、これでは全く不十分である。そのためには、ORの計算不可能な側面が現れてこなければならないし、それには高度な隔離が要求される。
かくして、新たなOR物理学が重要な役割を演じるのに十分な隔離を行う何かが、脳の内部に存在しなければならない。つまり私たち〔の脳〕に必要なのは、重ね合わされた微小管による計算が一旦開始されるや、その計算が十分に隔離されて、その結果、新しい物理学が本当にその役割を果たすようになることである。
というわけで、私が考えている状況は次のようになる。しばらくの間この量子計算が進行し、十分に長い間(たぶん一秒くらいのオーダーで)、その計算は他の要素から隔離され続ける。そうすると、私が話した種類の基準が通常の量子的手順を引き継いで、非計算的な構成要素が登場し、標準的な量子論とは本質的に異なる何かが得られるのである。
もちろん以上の考え方の至る所に、かなり推測が入っている。だがそれらは、意識と生物物理学的な過程との関係をかなりはっきりと定量的に描いており、私たちに何かしら本物の展望を与えている。少なくとも私たちは、OR作用が関与するためには、どのくらいのニューロンが必要かを計算できる。
その計算に必要なものは、第二章の終わりにかけて私が述べた時間スケールTの、およその見積もりである。つまり、意識上の出来事がORの出現と関係していると仮定するなら、Tをいくつと見積もるのか? 意識はどのくらいの時間を要するのか? これらの問題に関連した二つのタイプの実験があって、そのいずれにも、リベットと彼の同僚がかかわっている。二つの実験のうち一方は自由意志または能動的意識を、もう一方は、感覚または受動的意識を扱っている。』

画像出展:「心は量子で語れるか」
客観的収縮=OR
『将来、物理学が成し遂げねばならないと思うことを示すため、図2-17には修整が施されている。Rという文字で表現した手続きは、まだ私たちが見つけていない何かを近似したものである。その未発見の何かとは、私がORと呼ぶものであり、“客観的収縮(Objective Reduction)”を表してる。
ORは客観的事実である― 一方、“または”他方が客観的に起こる ―今なお私たちには欠落している理論である。ORというのは、うまい頭文字になっている。というのもORは“または”をも表しており、それは実際、一方“もしくは”(OR)他方のどちらかが起こるからである。』
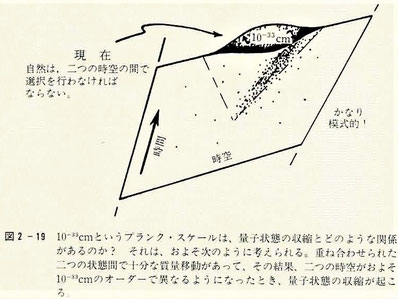
画像出展:「心は量子で語れるか」
自然が審判を下すための時間
『プランク長の10⁻33センチメートルは、量子状態の収縮とどんな関係があるのだろうか? 図2-19に、分岐しようとしている時空をかなり模式図的に示した。
ここで、二つの時空(一方は生きた猫を、他方は死んだ猫を表すことができる)が一つの重ね合わせに至る状態があって、この二つの時空は何とかして重ね合わせられる必要があるとしよう。このとき、次のような疑問が生じる。
「互いに法則を変えるべきだと思えるほど、二つの時空が十分に異なるようになるのはいつか?」
ある適切な意味で、二つの時空の差がおよそプランク長のオーダーに等しくなるとき、私たちはそのような状況に遭遇するだろう。二つの時空の幾何学がそれくらいの違いを見せ始めるとき、そのときこそ、私たちは法則が変わることを心配しなくてはならないだろう。なお、強調しておくが、私たちが扱っているのは時空であり、単なる空間ではない。
“プランク・スケールの時空分離”については、小さな空間的分離がより長い時間に対応し、より大きな空間的分離がより短い時間に対応する。ここで必要なのは、どんな場合に二つの時空が有意に異なるかを見積もるための評価基準である。
そこから、二つの時空の間で自然が選択を行う際の“時間スケール”が導かれるだろう。こうして自然は、私たちが未だ理解していない何らかの法則に従って、どちらか一方の時空を選択するのである。
この選択を行うのに、自然はどのくらいの時間を要するのか? アインシュタインの理論に対するニュートン的近似が十分であって、かつ、量子論重ね合わせ(二つの複素振幅の大きさは大体等しい)に従う二つの重力場が明らかに異なるとき、その時間スケールを設計することができる。私が示そうとする答えは、次のようになる。まず猫を球体で置き換えてみる。
では、その球体はどれくらいの大きさで、どこまで動かなければならないのか? また状態ベクトルの崩壊が生じるための時間スケールはどれくらいなのか(図2-20)?
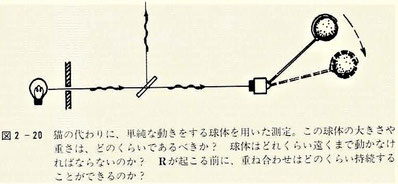
画像出展:「心は量子で語れるか」
私は、一つの状態ともう一つの重ね合わせを、不安定な状態―それは崩壊しかかっている素粒子やウラン原子核などに少し似ている―と見なしたい。素粒子などは崩壊すると別のものになるが、その崩壊と結びついた一定の時間スケールが存在する。状態の重ね合わせが不安定だというのは一つの仮説だが、この不安定性は、私たちが理解していない物理学の存在を暗示しているはずである。
崩壊の時間スケールを算出するため、ある状態の球体を、(その球体の)別の状態の重力場から移動させるために必要なエネルギーEを考えてみよう。プランク定数を2πで割ったℏ[換算プランク定数またはディラック定数]を重力エネルギーEで割ると、この状態での崩壊に対する時間スケールTとなるはずである。
T=ℏ/E
この一般的な推論に従う多くの理論がある。一般的な重力理論は、細かな点では違いがあるものの、どれもこれと何かしら同じ趣き〔似たような関係〕を備えている。』
“微小管”について
まずは「人体の正常構造と機能」という本に出ていた3つの図をご紹介します。
●微小管は太さ約24㎚の中空の管であり、チューブリンという蛋白質からできている。
●線毛や鞭毛の動きは微小管が行っている。
●神経の軸索突起などの大きな細胞突起を支持する。
●細胞分裂の際に、染色体を両極に引っぱる紡錘糸は微小管からできている。

画像出展:「人体の正常構造と機能」
■線毛の芯は“9+2配列”の微小管でできている
『線毛の中央部は直径0.25~0.3μmで、電子顕微鏡で観察すると、各線毛は細胞膜で囲まれ、その中に微小管とその付属蛋白からなる軸糸という構造が認められる。軸糸を構成する微小管は、チューブリンという球状蛋白が重合してできた管状の構造物で、外径25㎚、壁厚5㎚ほどある。軸糸の中心には1対の単一微小管からなる中心微小管があり、そのまわりを9対の二連微小管からなる周辺微小管が取り囲む。各周辺微小管の作る面は、線毛の接線面に対し5~10度傾いており、中心近くにあるものからA細管、B細管と呼ぶ。A細管と中心微小管とはスポークで連結される。またA細管から隣の周辺微小管のB細管に向かって、ダイニンというモーター蛋白でできた2本の腕突起(内腕と外腕)が伸びており、内腕はさらにネキシンの細い線維が結合している。これらは微小管の長軸方向に一定の間隔で並ぶ。線毛の先端側は微小管のプラス端にあたり、各微小管は自由な断端となって終わる。線毛の根元側は微小管のマイナス端にあたり、細胞質内まで伸びたところで周辺周辺微小管にさらにC細管が加わり、基底小体という三連微小管となる。この周辺には根小毛という線維束があり、線毛を細胞質に固定している。基底小体下にはミトコンドリアが豊富である。』
■線毛の屈曲運動は微小管の滑り合いによって起こる
『線毛の屈曲は、周辺微小管の滑り合いにより生じる。周辺微小管の腕突起を構成するダイニン蛋白はATPase活性を持ち、ATPの存在下で隣の微小管のB細管上をマイナス端へ向かって移動する。その結果、微小管どうしが滑り合い、線毛は屈曲する。滑り合いと屈曲運動の関係は、短柵状の紙を2枚に折って重ねて指で滑らせてみると納得がいくだろう。線毛内のスポークやその他の連結の役目をする構造物も、線毛運動の調節をしていると考えられている。』

画像出展:「人体の正常構造と機能」
■精子は長距離を移動するために無駄のない形をしている
『尾部[遊泳運動を担う]は長さ約60μmの鞭毛からなる。鞭毛の中心を軸糸と呼ばれる構造が全長にわたって走行している。軸糸は、2本の中心微小管とそれを取り巻く9対の周辺微小管で構成され、線毛にみられるのと同様の構造である。これらのチューブリンという蛋白質からなり、その滑り合いによって軸糸を屈曲させ、独特の三次元的波状運動をもたらす。軸糸の屈曲に要するエネルギーは、中間部の軸糸をらせん状に取り囲むように配列するミトコンドリア鞘で産生されるATPによって供給される。』

画像出展:「人体の正常構造と機能」
■軸索輸送によって必要な物質が供給される
『軸索内には蛋白合成を行う細胞内小器官がない。そのため、軸索の成長やシナプスの形成に必要な蛋白質や小器官は、細胞体で合成されたのち、軸索を通って輸送される。これを順行性軸索輸送という、逆に、神経終末で取り込まれた栄養因子や化学物質は、逆行性軸索輸送により細胞体へ輸送される。微小管がこれらの輸送のレールの役目を果たし、モーター蛋白のキネシンをはじめとするKIF蛋白は順行性の輸送に、ダイニンは逆行性の輸送に働く。
順行性輸送では、いろいろな物質が異なる速さで運ばれる。シナプス小胞は速い流れ(100~400㎜/day)で、ミトコンドリアは中間の流れ(60㎜/day)で、細胞骨格(アクチン、ニューロフィラメント、微小管)は遅い流れ(10㎜/day以下)で運ばれる。逆行性輸送では、100~200㎜/dayの速さでライソソームなどが運ばれる。
軸索内では、微小管はチューブリンの重合と脱重合の速度が速い分、つまり微小管の伸長している部分(プラス端)は絶えず遠位側にある。また、軸索にはタウ蛋白と呼ばれる微小管関連蛋白が特異的に分布しており、チューブリンの重合を促進し微小管の安定化に寄与している。』
続いて、「病気を治す飲水法」に出ていたもの(ブログは“飲水の重要性”)と、その時に見つけたサイトをご紹介します。

画像出展:「病気を治す飲水法」
『脳で生産された物質は、水に乗って、神経終末部の目標地点にたどり着き、情報の伝達に使われる。神経には、情報を梱包して流す「極微細管」と呼ばれる微細な水路が存在する。』
原文が確認できないので、“極微細管”が“微小管”のことであるのかは分からないのですが、図を見る限り、同一のものだと思われます。この図に興味をもったのは、「神経伝達に水路がある」ということに大変驚いたためです。
この時、この“水路”に関してネットで見つけたサイトが以下のものになります。残念ながら“水路”というものではなかったのですが、絵が似ていたことと、「細胞内輸送の解明にかける思い」という記事から関係があるように思いました。

画像出展:「UTokyo Focus」
『細胞は細胞液の入った風船のようなもので、その中に核やミトコンドリアなどの細胞小器官が漂っていると思われがちです。しかし、実際には、微小管というレールが整然と張り巡らされており、それに沿ってミトコンドリアや小胞(膜でできた袋)などの「荷物」が行き来しています。これを「細胞内輸送」といいます。レールの上で荷物を運んでいるのは、小さなモータータンパク質です。「モータータンパク質が人間のサイズだとしたら、直径5mの土管の上を、10トントラックをかついで、秒速100m以上の速さで走っていることになります」と語るのは、医学研究科の廣川信隆特任教授。神経細胞をモデルとして、細胞内輸送のメカニズム解明に取り組んできました。』
感想
「心や意識は脳が作り出すもの」。これは正確ではないかもしれませんが、深く関係しているのは間違いありません。
ストレスは脳にアタックをかけます。脳が疲労し、その疲労が身体におよぶと自律神経失調症が懸念されます。ちょっと強引ですが、「病は気から」ということわざの“気”は脳の疲労などによってもたらされた“ネガティブな意識”ということかもしれません。
一方、「ポジティブ・シンキング」、「瞑想法」などはネガティブなストレスとは異なり、心身にとって良いポジティブなものですが、こちらも脳(心や意識)と肉体のつながりを感じさせます。
以下の左図に書かれているように脳は“神経系”の中の“中枢神経系”とよばれています。これは脳が指令を出すためです。出された指令は“末梢神経系”によって然るべき組織や器官に届きます。“末梢神経系”には運動や感覚などの動物性機能を担う体性神経系(動物神経系)と、内臓や血管に分布して呼吸、消化、吸収、循環、分泌などの活動を不随意的に調節する自律神経系(植物神経系)があります。
なお、右側の図を見て頂くと、“神経系”は内臓を含め、体中をカバーしているのが分かります。
注)2つの図は「看護roo!」さまより拝借しました。
左図:“神経系はどんな構成になっている?”より
右図:“神経のしくみと働き|神経系の機能”より


左の図では“交感神経”も“副交感神経”も「遠心性」(脳⇒末梢)となっていますが、現在は次のような見解が正しいとされています。つまり、“自律神経”は「遠心性+求心性」(脳⇔末梢)ということです。
『求心性神経と遠心性神経:自律神経系(交感神経と副交感神経)は、かつては遠心性の線維のみからなるとされていたが、求心性線維も多く含まれていることがわかってきた。迷走神経(副交感神経)構成線維の約75%、内臓神経(交感神経)の50%は求心性線維とされている。 実験医学 2010年6月号 Vol.28 No.9』
“神経”は我々のような動物だけでなく、ゾウリムシのような単細胞生物にも存在します(「動くニューロン[神経細胞]」と呼ばれているそうです)。また、神経ということではありませんが、微生物とされるバクテリアの線毛にも微小管は存在しています。
以上のことから神経細胞の輸送のためのレールなど、微小管は地球上の多くの生物の中にあり、生命に深く関わっていると言えます。さらに、微小管は精子の尾部(鞭毛)にも存在しているので、種の保存という大事な仕事も任されています。
そして微小管はペンローズ先生がご指摘されているように“管”として内部と外部を分けることができるという大変興味深い特徴を有しています。マクロ(ニュートン力学)の世界とミクロ(量子力学)の世界を分けているのかも知れません。
ペンローズ先生は「心は量子で語れるか」の中で、“微小管”と“水”の関係についてもお話されていました。
『私には、意識というものが何か大域的なものだと思われる。したがって意識の原因となるどんな物理過程も、本質的に大域的な性質をもっているに違いない。量子的干渉は確かにこの点での要求を満たしている。そのような大規模な量子的干渉が可能であるためには高度な隔離が必要とされ、微小管の壁によって、それが実現されているのかもしれない。しかしチューブリンの構造が関与するとなると、さらに多くのことが必要となる。
こうして要求される周囲からの隔離は、微小管のすぐ外側にある“秩序化された水”によってなされるだろう(生きた細胞には存在することが知られている)。秩序化された水は、管の内部で起こる量子的干渉性振動の重要な構成要素でもあると思われる。』
この“水”は鍼灸師の私にとってとても興味深いものです。
人間の体は成人では60~65%が水で満たされています。また、東洋医学には“津液(シンエキ)”という考え方があります。津液とは人体を潤す全ての正常な水液とされています。この津液をあえて現代医学に当てはめて意識するときに、汗や涙、唾液や胃液、血漿、リンパ、漿液、脳脊髄液などを想像していました。今回の件で、その水の中には神経伝達に関わる水、微小管のすぐ外側にある“秩序化された水”があることを知りました。これは大きな発見です。私の“津液”のイメージにこの”秩序化された水”も加えたいと思います。
付記:ロジャー・ペンローズ先生は、2020年のノーベル物理学賞を受賞されました。

画像出展:「SankeiBiz」
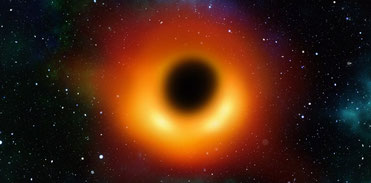
画像出展:「WAKARA」
アインシュタイン以来の天才!?ノーベル物理学賞受賞ロジャー・ペンローズが生み出した現代宇宙観
『実は、ブラックホールが存在する可能性に気づいたのは、ペンローズが初めてではありません。天体物理学者カー・シュヴァルツシルトが、相対性理論の重要な方程式であるアインシュタイン方程式を解いてみたところ、ある特殊解が得られて、その結果特異点が存在することに気づきました。のちにブラックホール発見の重要なきっかけとなった特異点ですが、当時アインシュタイン自身はこの特異点について、「あくまで理論的な計算の結果出てきたもので、実在するものとは無関係である」と判断し、1939年の自身の論文でブラックホールの存在を明確に否定しているのです。
その説をアインシュタインが相対性理論を生み出した方法と同じ、計算によって覆して見せたのがペンローズでした。彼は相対性理論を拡張し、特異点、つまりブラックホールが相対性理論から自然に導かれる存在であることを証明しました。星の大きさに対して一定の重さになるとその星が崩壊し特異点を生じ、その特異点ではあらゆる物質、光でさえも一度入ると抜け出せない、ブラックホールになることを相対性理論から導いて見せたのです!彼が1965年に書いた画期的な論文は、相対性理論におけるアインシュタイン以来の前進とみなされています。』
心は量子で語れるか1
邦題である「心は量子で語れるか」は、翻訳された中村和幸先生が付けられたのですが、それは次のような理由からです。
『なお、原題にあるように、本書では宇宙と量子と人間の心を扱っているが、意識は無数の量子によって生じるというペンローズの意を受けて、邦題では「心は量子で語れるか」とした。』
私は、以前“生物と量子力学3(意識)”というブログをアップしているのですが、その時にロジャー・ペンローズ先生の「皇帝の新しい心」という本の存在を知りました。そして、この時から「量子と心(意識)との関係」について関心を持っていました。
ネット検索中に「心は量子で語れるか」という本を見つけ、当然、難解な内容であることは承知しつつも思わず買ってしまいました。
本の内容は想像以上に難しく、ほとんど理解できませんでした。にもかかわらず、ブログにアップしたのは、この本の題名がとても気に入ったのと、微小管が謎を解く重要な器官らしいということを知ったためです。
この本がどんな本なのかをご説明することも難しいため、目次に続き、翻訳された中村先生が書かれた“翻訳にあたって”の冒頭の部分と、同じく中村先生の“訳者あとがき”の一部をご紹介させて頂きます。また、それ以降は微小管について書かれた第三章の“意識はコンピュータに乗せられない”、“微小管は八面六臂”、“意識の理解に最も必要なこと”の3つを中心にご紹介していますが、力不足のため要約することができず、多くが引用となっています。なお、[ ]内は用語説明として私自身が書き加えたものになります。また、ブログは長くなったので2つに分けました。
目次
マルコルム・ロンゲアによる序文
第一部 宇宙と量子と人間の心
第一章 宇宙の未完成交響曲
数学が描き出す世界
人間的スケールの不思議
誤解された量子力学
ニュートンの時空図、アインシュタインの時空図
光円錐の見方
驚くべき変換
ニュートン力学よりシンプルな相対論
重力は消えていない
テンソルは語る
アインシュタインはこんなにも正しい
目の前の空間を漂う理論
空間の曲率で宇宙を分類する
宇宙空間を牛耳る天使と悪魔
悩みから生まれた幾何学
ロバチェフスキー空間の魅力
COBE衛星が見たもの
見えないエントロピーをつかまえる
私たちが探し求める理論
ワイル曲率仮説
神の一刺し
第二章 量子力学の神秘
数学から物理学へ、物理学から数学へ
古代ギリシアに逆もどり?
どこでも量子力学
複素数の妙技
変わる法則
量子状態をどう表現するか
Zミステリー、Xミステリー
Zミステリー(1) 量子的な非局所性
Zミステリー(2) 爆弾検査問題
もしも量子力学を信じるならば
本当に“まじめ”なのか
多世界観による“認識”の解釈
“こちら”と“あちら”の扱い方
現実を記述するのは不可能か
すべての実用的な目的のためにできること
客観的収縮=OR
あらかじめ仕組まれた挫折
自然が審判を下すための時間
重力エネルギーの非局所性
“環境”が量子力学に及ぼす影響
立方体の完成を目指して
第三章 心の神秘
ホッパーが考えた第三の世界
三つの神秘、三つの偏見
意識はコンピュータに乗せられない
アウェアネス、自由意志、理解
アウェアネスに対する四つの立場
コンピュータが指した次の一手
簡単な計算にトライ
爆走する計算
Ⅱ₁文とは何か
完全な証明などあるのだろうか
チューリング対ゲーデル
二つのイラストでアルゴリズムの謎を解く
プラトン的世界との接触
ポリオミノ・タイリング
計算不可能性の台頭
ニューロンは計算的か
微小管は八面六臂
“意識”の理解に最も必要なこと
パラドックスを生む二つの実験
これが偶然と思えるか
第二部 ペンローズと三人の科学者
第四章 精神、量子力学、潜在的可能性の実現について
アブナー・シモニー ボストン大学名誉教授
序論
四・一 精神の解明を目指して
四・二 量子力学は心身の問題を説明できるか
四・三 潜在的可能性を実現させるために
第五章 なぜ物理学か?
ナンシー・カートライト ロンドン大学社会科学部教授
第六章 恥知らずな反論
スティーブン・ホーキング ケンブリッジ大学ルーカス記念講座教授
第七章 それでも地球は回る
ロジャー・ペンローズ
オックスフォード大学ラウズ・ボール記念講座教授
七・一 アブナー・シモニーへの回答
七・二 ナンシー・カートライトへの回答
七・三 スティーブン・ホーキングへの回答
訳者あとがき
翻訳にあたって
『本書は、今世紀における天才数学者の一人にかぞえられるロジャー・ペンローズが、彼自身の量子論や宇宙論の知識を駆使して、人間の魂の根源に迫ろうとした力作である。はたして現代物理学 ―特に量子力学― には、人間の意識について語る資格があるのだろうか? ペンローズ自身は、現在の量子力学は不完全だと考えており、それをより精密なものにすることによって、人の魂の成り立ちを説明できると主張している。もちろんこの主張には数多くの批判が寄せられているが、さまざまな機会をとらえて、ペンローズは自己の立場を擁護している。
それにしてもペンローズの話は、実に壮大なドラマである。まず新しい量子論を掲げ、次に数学の立場から人間の思考や意識の特色を探り出し、それらをふまえて物質から精神が生じるさまを説明しようというのである。さらにペンローズは、意識が生じる場所として、生体中の微小管をその候補に挙げている。
この予想が的確かどうかは、今後の科学の進展を待たねばならないが、幅広い知識に基づいて一つの仮説を作り上げた彼の構想力は、並大抵のものではない。また、実験で確認できることをペンローズは提案しており、論争の白黒はそこでつけられるだろう。』
訳者あとがき
『よく知られているように、量子力学ではシュレディンガーの波動方程式[粒子の運動状態を記述する方程式]が重要な役割を果たしている。その方程式には、現実世界では見かけない虚数単位i[2乗して-1となる数のこと(記号iで表す)]が登場し、何か奇妙な印象を与えるかもしれない。しかしペンローズが本書の第二章で述べているように、そうしたプラトニック[観念的]な構成を整えることによって、原子の安定性や電子のエネルギー準位[量子力学において電子が安定状態でもちうるエネルギーの値]などを、見事に説明することができたのである。現実をうまく説明できること、これは理論にとって非常に大切なことである。
だが科学の歴史をひもとくとわかるように、ある理論が数多くの現象をうまく説明できず、その解決には一般相対論の登場を待たなければならなかった。同じような事態が、実は量子力学でも起こりうるとペンローズは考えているのである。
ここで問題になるのは、本書で言うところの“状態ベクトルの収縮(R)”[この用語は、『心の影2―意識をめぐる未知の科学を探る』の “第2部 心を理解するのにどんな新しい物理学が必要なのか:心のための計算不可能な物理学の探求”の“5 量子世界の構造”の中に出てくるようです]である。
たとえば電子の場合、観測以前には決定論的で波の状態にあるが、観測した疑問にその波が一点に収縮してしまうのである。しかもそれがどこに収縮するかは確率論的にしかわからない。そもそも人間の観測によって収縮することをどう考えるのか? また量子レベルU(ユリタリ)[こちらは『心の影2』では“ユニタリ発展U”として出ているようです。また、大阪市立大学 橋本義武先生の“雑文集”の“量子力学の枠組み”に、『量子力学は、原子レベルの現象を統計的に記述する。用いるのはユニタリ行列の数学である。』との記述がありました]過程は時間反転に対して対称だが、R過程は時間反転に対して非対称になっている。
そこで、この状態ベクトルの収縮をめぐって、量子力学の世界にさまざまな解釈が生まれており、それをペンローズが第二章の図2-8で要約している。
その中で主だったものには、ニールス・ボーアを中心としたコペンハーゲン解釈[量子世界の物理状態は重ね合わさり、波を形づくっているが、観測された瞬間に波はしぼみ、1つの状態に落ち着く(波束の収縮)。どの状態が観測されるかは、波の振幅をもとに確率論的に予想できるというもの]やそれと通じるところがあるFAPP[“すべての実用的な目的のために(For All Practical Purposes)”の意味]があり、さらに多世界解釈[観測者の世界が枝分かれするとみる立場]がある。
コペンハーゲン解釈にはボルンの確率解釈理論[電子のような小さな粒子を観測する確率が、波動関数の絶対値の2乗に比例するという法則]的な計算と実験結果とが一致するのだが、波が収縮するメカニズムを明確にはしていない。
コペンハーゲン解釈:観測すると、電子の波が瞬時にちぢむ!? “とがった波”が、粒子のようにみえる
『一つの電子は「波と粒子の二面性」をもちます。この矛盾したような事実は、どう解釈したらよいのでしょうか。コペンハーゲンを中心に活躍したデンマークの物理学者のニールス・ボーア(1885~1962)らは、「コペンハーゲン解釈」とよばれる解釈を提案しました。
コペンハーゲン解釈によると、電子は観測していないときは、波の性質を保ちながら空間に広がっています。しかし、光を当てるなどして電子を観測すると、波が瞬時にちぢみ、1か所に集中した“とがった波”になります(波の収縮)。このような波が、粒子のように見えるというのです。
電子は、観測すると、観測前に波として広がっていた範囲内のどこかに出現します。しかしどこに出現するかは、確率的にしかわかりません。このような解釈をすれば、電子などの「波と粒子の二面性」を矛盾なく説明できると、ボーアらは考えたのです。』
画像出展:「13歳からの量子論のきほん」
また、観測ごとに世界が分裂していく多世界解釈についても、あまりエコノミカルではないとペンローズは批判している。
ではペンローズ自身は、どのような立場を取っているのか? 彼は現在のR(下部【注】参照)を本来あるべき理論の近似と考えており、重力も考慮に入れた“客観的収縮(OR)”(下部【注】参照)を提案している。ペンローズによると、ORは決定論的だが計算不可能な過程であるという。そこで彼は、決定論的だが計算不可能な過程がどのようなものか、“オモチャの宇宙”[計算不可能な例、“ポリオミノ・タイリング”。『しばしば、“オモチャの宇宙モデル”と呼ばれている―別のもっと良い例を思いつかないときに、物理学者がよく持ち出すものである。』]を例にして第三章を説明している。
こうした新たな量子重力の理論を予想しつつ、ペンローズは人間の意識が生じる過程について話を展開しているのである。彼の考えでは、量子力学に非計算的な要素があるので、人間の知性(意識)をコンピュータのような計算機械では再現できないという。』
【注】上記の“R”(Reduction)ですが、ペンローズ先生はそれを重力も考慮に入れた“客観的収縮(OR:Objective Reduction)”と位置づけ、量子レベル(U)と古典レベル(C)を関係付けるものとされています。なお、これについては、「第二章 量子力学の神秘」の中の「古代ギリシアに逆もどり?」、「変わる法則」、「客観的収縮=OR」のそれぞれの内容を組み合わせてまとめてみました。スッキリしたものではありませんがご参考になればと思います。

画像出展:「心は量子で語れるか」
古代ギリシアに逆もどり?
『第一章では、さまざまな対象のスケールを確かめた。それは、長さと時間の基本単位であるプランク長[量子的揺動が時空間の配置より大きくなると考えられる長さ]とプランク時間[物理世界の最小単位。量子力学の基本量であるプランク定数hと、真空中の光速c、重力定数Gの3つの定数で決まる]から始まり、素粒子で扱われる最小の大きさ(といってもプランク・スケールより約10の20乗倍も大きい)、人間スケールの長さや時間(この宇宙で私たちは非常に安定した構造体であることを示した)を経て、宇宙の年齢や半径にまで及んだ。』

画像出展:「心は量子で語れるか」
『そのとき私は、かなりやっかいな事実にふれた。基本的な物理学を記述する際に、大スケールの状況を扱うのか、小スケールの状況を扱うのかによって、二つの全く異なる記述法を使っていることについて述べたのである。それは、図2-1に示したように、小スケールの量子レベルの活動を記述するには量子力学を用い、大スケールの現象を記述するのには古典物理学を使う。そして量子レベルに対してはユリタリ(Unitary)を表すUの字を当て、古典レベルに対してはC(Classical)で評した。大スケールの物理学は第一章でとりあげ、大スケールと小スケールでは全く違う法則があるに違いないということを強調した。
物理学者たちはふつう、量子物理学が適切に理解されれば古典物理学者はそこから、導き出せると考えているようである。しかし、私の主張は違う。実際には物理学者はそうしておらず、古典レベルか量子レベルかのどちらかを用いている。』
変わる法則
『量子レベルでは、システムの状態は、とりうる全選択肢を複素数で重み付けした重ね合わせで与えられる。量子状態の時間(的)発展は“ユリタリ発展(またはシュレディンガー発展)”と呼ばれ、それが実際にUの表す内容なのである。
Uの重要な特性は、それが線形だという点である。このことは、二つの状態がそれぞれ個々に変化すると、それに応じて二つの状態の重ね合わせも同じように変化するが、重ね合わせに用いた複素数の重み付け係数は時間に関して一定である、ということである。この線形性が、シュレディンガー方程式の基本的な特徴であり、量子レベルでは、このような複素数で重み付けされた重ね合わせが、いつでも保持される。
しかしながら、何かを古典レベルへ拡大しようとすると、“法則”が変化する。古典レベルへ拡大するとは、図2-1のレベルU(上側)からレベルC(下側)へ行くことを意味している。物理的にいえば、たとえばこれは、スクリーン上の一点を観測することである。小スケールの量子事象が、実際に古典レベルで観測される。さらに大きな何かを引き起こすのである。
標準的な量子論で行われていることは、あまり口にしたくないものを引っぱり出してくるようなことであり、それは、“波動関数の崩壊”とか“状態ベクトルの収縮”と呼ばれている。この過程に対して、私はR(Reduction)という文字を使用したい。Rは、ユリタリ発展とは全くことなるものである。
二つの選択肢の重ね合わせにおいて、二つの複素数に着目し、それらを二乗すると、―このことはアルガン平面[直交座標の横軸に実数値、縦軸に虚数値をとり、一つの複素数を一つの点で示す平面]では、原点からの距離を二乗することを意味する―これら二乗された係数のおのおのは、二つの選択肢に対する確率の比となる。
だがこのことは、“測定する”または“観測する”ときにのみ起こり、それは図2-1においては、UレベルからCレベルへ現象を拡大する過程に相当する。この過程で法則は変化し、あの線形的な重ね合わせは維持されなくなる。突如として、これら二乗された係数の比が、確率となるのである。
非決定論が顔を出すのは、UレベルからCレベルへ行くときだけである。この非決定論はRと共に登場する。Uレベルではすべてが決定論的であり、“測定”という行為をするときにのみ、量子力学は非決定論になる。
以上が、標準的な量子力学で用いられる形式である。たしかに、基本理論にしては、非常に奇妙なタイプの形式である。これが単に基本的な他の理論の近似にすぎないというのであれば、それはそれで道理にかなう。だが、この複合的な手続きは、すべての専門家によって、それ自体が基本理論と見なされているのだ!』

画像出展:「心は量子で語れるか」
客観的収縮=OR
『将来、物理学が成し遂げねばならないと思うことを示すため、図2-17には修整が施されている。Rという文字で表現した手続きは、まだ私たちが見つけていない何かを近似したものである。その未発見の何かとは、私がORと呼ぶものであり、“客観的収縮(Objective Reduction)を表してる。
ORは客観的事実である― 一方、“または”他方が客観的に起こる ―今なお私たちには欠落している理論である。ORというのは、うまい頭文字になっている。というのもORは“または”をも表しており、それは実際、一方“もしくは”(OR)他方のどちらかが起こるからである。』
超ひも理論(超弦理論)
超ひも理論はテレビで知りました。耳にした内容は「相対性理論」と「量子論」を結びつけるような画期的な理論だということでした。
過去に量子論という超難解なものに手を出しているのですが、これはブルース・リプトン先生の『思考のすごい力』という本がきっかけです(ブログ“がんと自然治癒力13”の最後[追記:“量子物理学が生物学・医学を変える日は近い”]にその経緯があります)。
ブルース・リプトン先生が感銘を受けた本が、こちらの『量子の世界』です。

著者:H.R. パージェル
出版:地人選書
発行:1983年11月
この中に“量子論の奇怪さ”について書かれた章があります。下記はその一部です。
『「量子的奇怪さ」とはいったい何なのか。それを見るため、新しい量子論の物理学を、それが取って代わった古いニュートン物理学と対比させてみよう。ニュートンの法則は、石の落下や惑星の運行とか、川や潮の流れなど、見慣れた物体やありふれた出来事からなる、目に見える世界の秩序をつかさどるものだ。このニュートン的世界像を第一義的に特色づけているのは、決定論的性格と客観性である。つまり、時計仕掛けとしての宇宙は時間の始まりから終わりに至るまで決定しているし、石や惑星などは我々が直接にそれらを観測しなくても客観的に実在しているのだ―背を向けていたってちゃんと存在している。
量子論になると、世界を(決定論や客観性のような)常識に基づいて解釈することはもはや許されなくなる。もちろん量子世界も理性によって理解しうるのだけれども、ニュートン的世界のように描写してみせることはできないのだ、これは原子やそれよりも小さい量子の世界の極微性だけが原因ではなくて、通常の物体の世界からそのまま借用した表現の手段が量子的対象には通用しないということによっている。たとえば、石などはそれが静止していて、しかもある定まった場所に置かれているという様子を我々は容易に心に描くことができる。だが電子のような量子的粒子に対して、それが空間のある一点に静止しているなどと言っても意味をなさないのだ。さらに、電子は、ニュートンの法則ではありえないような場所にも物質化して現われることができる。』
1965年に量子電磁力学の発展への貢献により、ノーベル物理学賞を受賞された物理学者のリチャード・フィリップス・ファインマン先生は次のようなユニークなアドバイスをしています。
『量子力学が本当に理解できている人はまずいないだろう、と言って私は間違っていないと思う。諸君はもしできるなら、「だが、どうしてそんなことがありうるのだろうか」と自分自身に問い続けるのはやめた方がよい。なぜならますます深みにはまって、袋小路をさまようのが落ちで、そこから出口を見つけて出てきた人はまだいないのだから。どうして量子力学ではそうなるのかは、誰もわかってはいないのだ。』
超ひも理論の「最小部品の“ひも”は1秒間に10の42乗回以上で振動している」とか、「それは9次元(もしくは10次元)で高速に振動している」などは、理解不能、イメージ困難な別世界です。ここは、ファインマン先生の教えに従い、これらの異次元のものへの追及は早々にあきらめ、超ひも理論が「相対性理論と量子論を統合する理論」と言われている理由は何なのか? これが分かれば良しとしたいと思います。
手に入れたのはNewtonの別冊“超ひも理論と宇宙のすべてを支配する数式”です。4章に分かれていますが、ブログは最も知りたかった【量子重力理論(相対性理論と量子論を統合する理論)】を最初にお伝えし、その後、1章について何となく分かったような気になった箇所をいくつか列挙します。
目次
1.超ひも理論入門
プロローグ
●“究極の数式”を求めて①~②
●物質の“最小部品”
ひもの正体
●ひもの性質①~②
●ひもの振動
●ひもの振動と質量①~②
超ひも理論の世界
●超ひも理論の歴史①~②
●高次元空間①~②
●超対称性
●ブレーン①~②
究極の理論をめざして
●量子重力理論
●宇宙のはじまり
●ダークマター
●超ひも理論の証明
●広がる応用例①~②
2.もっとくわしく! 超ひも理論
特別インタビュー
●橋本幸二博士 超ひも理論の次の“革命”は明日にもおきる!?
●ブライアン・グリーン博士 超ひも理論の“伝道師”が語る、理論物理学の最前線
●大栗博司博士 「万物の理論」の探求物語
余剰次元の検証
●「見えない次元」をさがし出せ!
3.宇宙のすべてを支配する数式
宇宙のすべてを支配する数式①~②
第1項
●重力の作用①
第1項の前
●重力の作用③
第2項
●電磁気力・弱い力・強い力①~②
第3項
●粒子と反粒子①~②
第4項・第5項
●質量の起源①~②
第6項
●湯川相互作用①~②
未来の数式
●ダークマター①~②
●力の統一
●究極の理論
4.もっとくわしく! 宇宙のすべてを支配する数式
特別インタビュー
●村山斉博士 最終的には、一つだけの力、一つだけの基本法則ですべてを説明したい
●南部陽一郎博士 何もないところに種をまくのが楽しい
●梶田隆章博士 素粒子の「標準理論」を超える、新たな地平を開いた
●量子重力理論
・『相対論と量子論が“結婚”出来れば究極の理論になる』
-相対性理論は時間や空間、そして重力に関する物理学の理論である。
-量子論は原子や素粒子などのふるまいを説明する物理学の理論である。
-多くの超ひも理論研究者は、「量子重力理論」と「究極の理論」をほぼ同じ意味で使っている。
-相対論と量子論が統合したものは「量子重力理論」と呼ばれているが、ミクロな世界での重力の計算に「くりこみ理論」を適用できないことが統合できない理由である。
-ミクロな距離を伝わる重力を相対性理論に基づいて計算しようとすると、電磁気力には適用できた「くりこみ理論」が使えず、計算結果に無限大があらわれてしまい、計算が破たんする。
以上のことから、マクロの世界に加え、ミクロの世界でも重力計算ができるようになれば、究極の理論は完成するということです。そして”素粒子=点”ではなく、”素粒子=ひも(弦)”と捉えることにより、可能性が生まれるということが分かりました。
※くりこみ理論:場の量子論で使われる、計算結果が無限大に発散してしまうのを防ぐ数学的な技法。(ウィキペディアより)
1.超ひも理論入門
『超ひも理論によれば、あらゆるものは、分割していくと、最終的にきわめて小さな「ひも」にたどりつくと考えられています。超ひも理論は未完成の理論ですが、現代の物理学者たちが追い求める“究極の理論”になる可能性を秘めています。』
プロローグ
●物質の“最小部品”
・『「超ひも理論は、ひとことでいえば、物質の“最小部品”である素粒子が、大きさをもたない[点]ではなく、長さをもつ[ひも(弦)]でできていると考える理論です」。』
ひもの正体
●ひもの性質①~②
・ひもは伸び縮みして切れたりくっついたりする
・ひもは一つにつながったり、二つに分かれたりする
●ひもの振動
・ひもは、常に高速で振動している(ひもは1秒間に10の42乗回以上も振動すると考えられている)
●ひもの振動と質量①~②
・ひもは振動が激しいほど重い
・ひもは開いたひも(光子や電子など)と閉じたひも(重力子[未発見])がある
超ひも理論の世界
●超ひも理論の歴史①~②
・素粒子を点(大きさをもたない)だと考えたときの“限界”をひもは突破できる
・『現在、自然界には、「電磁気力」、「弱い力(原子核を構成する中性子が陽子に変わる反応[ベータ崩壊]などを引きおこす力)」、「強い力(原子核の中で陽子や中性子を結びつける源となっている力であり、ごく近距離ではたらく)」、そして「重力」という四つの力が存在することが明らかになっています。標準理論では、そのうち電磁気力、弱い力、強い力の三つについては、いっしょに計算することができるのですが、どうしても「重力」を合わせて計算することができないのです。
このような標準理論の限界は、「素粒子=点」だと考えたときの矛盾点をなくす理論である「くりこみ理論」の限界を意味します。この限界を突破する可能性を秘めたのが、「素粒子=ひも」だと考える「超ひも理論」です。』
●高次元空間①~②
・ひもの振動状態と現実の素粒子を矛盾なく対応づけるためには、ひもの振動方向(次元)は9個(9次元)必要になる。6次元は「コンパクト化」されており、小さすぎて私たちはその存在に気づけない
●超対称性
・素粒子のスピン(自転)が整数のボソンに、半整数のフェルミオンを加えたことにより、パートナー粒子(超対称性粒子)の存在を認められ、自然界に存在するすべての素粒子を扱えるようになった。
●ブレーン①~②
・超ひも理論には、1次元の“ひも”に加え、2次元の“膜”や“立体”もある。
究極の理論をめざして
●宇宙のはじまり
・宇宙のはじまりはミクロの世界で重力が非常に強くなる。これは、素粒子が狭い空間にぎゅうぎゅうに詰め込まれた、高温・高密度な状態と考えられるからである。
・空間さえもゆらぐミクロの世界での重力を、正しく計算できる可能性があるのは、超ひも理論だけである。
●ダークマター
・超ひも理論により、物質の素粒子と重力の関係が詳しく分かるようになると、ダークマターの正体と思われる未発見の素粒子についての発見も期待できる。
・ダークマターとは、そこには何かがあるようには見えないが、何らかの重力源が存在する謎の物質のこと。
●超ひも理論の証明
・『「超ひも理論では、ひもの振動がはげしくなると、そのひもに対応する素粒子のエネルギーが段階的にふえて、重くなります。たとえば、同じような性質だけれども、質量が2倍、3倍の重い素粒子が存在するということです。超ひも理論が予言するそのような重い粒子をみつけることができれば、理論の正しさを裏づける強力な証拠となります」』
・『「超ひも理論が予言する素粒子の多くは非常に重く、発見するにはLHC(ヨーロッパ原子核研究機構[CERN]が保有)の10兆倍ほどのエネルギーが出せる加速器が必要です。それらの重い粒子を加速器で発見するのは現実的ではありません。ただし、超ひも理論のモデルによっては、LHCや今後つくられるであろう次世代の加速器でも探索可能な、比較的軽い素粒子が存在する可能性もあり、それらの軽い素粒子であれば発見できるかもしれません」』
・『「理論の正しさという意味では、実験結果を説明できることのほかに、数学的に矛盾がないかどうかという点も重要です」』

加速器LHC
『左のイラストは、加速器LHCの全景を地上の風景に重ねてえがいたものです。LHCは1周約27キロメートルの環状の施設であり、地下100メートルのトンネル内に設置されています。巨大な実験装置が四つ設置されており、余剰次元の検証実験はATLASとCMSという実験装置で行われてきました。』
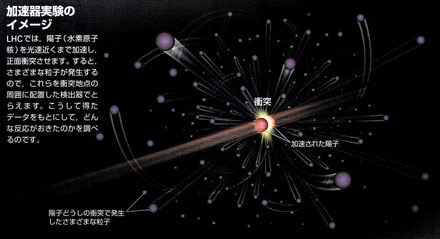
加速実験のイメージ
『LHCでは、陽子(水素原子核)を光速近くまで加速し、正面衝突させます。すると、さまざまな粒子が発生するので、これらの衝突地点の周囲に配置した検出器でとらえます。こうして得たデータをもとにして、どんな反応がおきたのかを調べるのです。』
●広がる応用例①~②
・『超ひも理論から生まれた計算手法による予言が、実験結果とぴたりと一致』
・『超ひも理論から生まれた計算手法で、ブラックホールの謎が解明された!?』
付記:宇宙はどうして進化してきたのか?
宇宙の進化に関するイラストが2つありました。昔からちょっと興味を持っていたことだったので拝借しました。
劇的に進化していった誕生直後の宇宙
『私たちの宇宙は、今からおよそ138億年前に誕生したとされている。宇宙が誕生した原因は、いまだによくわかっていない。宇宙の誕生後のわずか10のマイナス36乗秒後から、10のマイナス33乗秒後というごく短時間の間に、1兆の1兆倍のさらに1000万倍(10の43乗倍)程度の大きさまで急膨張したと考えられている。この急膨張が「インフレーション」だ。このときに生じたとされる特徴的な重力波が「原始重力波」である。インフレーションのあと、宇宙には大量の素粒子が誕生し、宇宙は超高温・超高密度のまるで“火の玉”のような状態(ビッグバン宇宙)になったと考えられている。
高温・高密度の宇宙は、インフレーション期とくらべてゆっくり膨張しながら温度を下げていき、素粒子から陽子や中性子を、そして陽子や中性子から原子核を生みだした。ここまでにかかった時間は、たった3分程度だという。その後、電子と原子核が結びつき原子が誕生するのだが、それは宇宙誕生から約37万年もあとのことになる。』
宇宙誕生の瞬間は観測できない!?
『私たちは光(電磁波)を使い、地球から宇宙のようすを観察している。光の速度は有限なので、遠くから光が届くまでには時間がかかる。そのため遠くからきた光をみることは、宇宙の過去をみることと同じだ。しかし、原子が誕生する前までの宇宙は、不透明なプラズマ(ここでは電子と原子核がばらばらになった状態のガスを意味する)で満たされており、光で見通すことができない。そのため、私たちが観測できるのは、原子が誕生したあと(宇宙誕生から約37万年後以降)の時代がやってくる光だけだ。原子の誕生は、不透明なプラズマに満たされた宇宙の終わりを意味するので、これを「宇宙の晴れ上がり」という。
宇宙の晴れ上がり以前の宇宙のようすは、プラズマに邪魔されない原始重力波や、原始重力波によって「宇宙背景放射」に刻みこまれたインフレーションの痕跡(原子重力波)などから調べられようとしている。』
数学と量子力学/物理学
またまた身の丈を超える本に手を出してしまいました。原因は今回勉強した量子論です。その昔、“産業の米”と言われた半導体は、量子論というミクロの世界を正確に描くことができる理論によって生み出されました。科学に明るくない私が言うのは適切ではありませんが、量子論は人類の進歩にとって最大の発見といっても良いのではないかと思います。
そして、量子論は“数学理論”だということです。“シュレーディンガーの方程式”はその中でも最も注目されるものだと思います。
なお、量子論とは“考え方”や“思想”であり、量子力学とは“量子論に基づいて物理現象を記述するための数学的手段”と言われています。あまり良い例えではありませんが、「量子論が“拳銃(器)”、量子力学が“実弾(中味)”」というイメージです。
理系の受験科目の一つとしてしか見てこなかった私ですが、「数学恐るべし!」、「数学とはいったいどんな学問何だろう?」という思いが大きくなりました。また、それを知ることができる良い本はないだろうかと探しました。こうして、今回の本を見つけました。

著者:ティモシー・ガウアーズ
出版:岩波書店
発行:2004年6月
目次
はじめに
1.モデル
2.数と抽象
3.証明
4.極限と無限
5.次元
6.幾何学
7.概算と近似
8.数学に関するよくある質問
裏表紙にはこの本の概要が書かれています。
『数学を組み立てる考え方とはどのようなものなのでしょうか。いったい数学者はどんなことを考えているのでしょうか。よく「数学は抽象的な学問だ」と言われますが、それは決して、数学が謎めいた秘義であるという意味ではありません。抽象とは、自由に考えるための道具立てなのです。考え方のコツをつかめば、「無限」や「26次元」などといった用語は不可解なものではなくなります。数学界でもっとも栄誉あるフィールズ賞を受賞した著者が、数学を支える重要な考え方を紹介します。数学をむずかしいと思う「壁」がきっと取り除かれることでしょう。』
“数学”を取り上げたのは“量子論=数学理論”だからです。そして、量子力学を牽引する極めて重要なシュレーディンガー方程式ですが、その一部の波動関数ψ[プサイ]の正体は未だに明らかになっていません。つまり、数学的には問題ないが物理学的には問題を残す。ということのように思います。
その波動関数について、マックス・ボルンが1926年に提唱したのが“波動関数の確率解釈”です。

画像出展:「ウィキペディア」
この“波動関数の確率解釈”の“是非”は明確に二分されました。
“非”の立場をとった中には、シュレーディンガーをはじめ、ブロイ、プランクなどの量子力学の発展に大きな貢献をした物理学者も含まれていました。また、“光量子仮説による光の粒子と波動の二重性”を唱えたアインシュタインも反対の立場を取りました。その背景にあるものは、自然現象を表す物理学は決定論でなければならないという、ニュートン以来の物理学の大前提でした。
この、“波動関数の確率解釈”の“是非”の概要に迫ることは、数学と物理学(量子力学)の関係を知るうえで大切であると考えますので、ブログ“量子論1”でご紹介したものを再登場させ、それに追加するかたちで進めていきたいと思います。
この本の「3章 見ようとすると見えない波 ◆ミクロの世界の物理法則が明らかになる」の部分をご紹介します。
『さて、3章でもさまざまな話をしてきました。最後は例によってこの章のポイントをおさらいしておきましょう。
①原子中の電子の軌道半径がとびとびの値に限られるというボーアの量子条件の根拠を示すために、ド・ブロイは電子を波であると考えて、その波長を求めた。
②シュレーディンガーは電子の波を表すシュレーディンガー方程式を導き、電子の「とびとび」のエネルギー状態などの説明に成功した。
③しかしシュレーディンガー方程式が示す波動関数ψ(プサイ)、すなわち電子の波(これは複素数の波である)の正体はわからなかった。
④ボルンは波動関数ψそのものが何を表すのかを考えずに、代わりにψの絶対値の二乗が、電子をその場所に発見する確率に比例することを見いだした(「波動関数の確率解釈」)。
⑤ボーアたちは、観測される前の電子はさまざまな位置にいる状態が「重ね合わせ」になっているが、私たちが電子を観測したとたんに「波の収縮」が起きて電子は一ヶ所で発見されると考えた(「コペンハーゲン解釈」)。
こうして1920年代に、原子中の電子が示す不思議な現象をきちんと説明できる理論を、私たちはついに手にすることになりました。そしてその結果わかったのは「電子などミクロの世界は、私たちが知っていた物理法則とはまったく違うルールに支配されていたのだ」ということです。
その新たなルールの第一は、シュレーディンガー方程式に代表される波動力学(量子力学)です。ミクロの世界の物質は、それを「波である」と考えることでふるまい(動きやエネルギー)などを求めることができるのです。
そしてもう一つのルールが「確率」です。私たちが電子を発見する場所は、サイコロを振って決められるかのように、確率的に決定されるというのです。』

シュレーディンガー方程式は量子力学の基本となる方程式であり、図に示すような形をしています。一方、古典物理学の中には、音波や電磁波などの波が周囲に伝わっていくようすを表す波動方程式というものがあります。シュレーディンガー方程式はそれに似ていますが、さらに複雑なものになっています。
画像出展:「量子論を楽しむ本」

こちらは1926年6月21日~26日に行われたチューリッヒでの会議後に若いヒュッケルを中心につくられたという詩です。
計算どっさり、エルヴィンさんが
波動関数とやらでなさるけど、
さて、わからんことが一つある
波動関数とは何なのか?
画像出展:「波動力学形成史」
今回はこの“◆ミクロの世界の物理法則が明らかになる”の次に書かれていた“◆確率解釈に反対したアインシュタインたち”もご紹介します。
『ここで問題になるのが、二番目のルールである「確率」、すなわち波動関数の確率解釈です。プランクやアインシュタイン、そしてド・ブロイやシュレーディンガーなどのそうそうたるメンバーが、この確率解釈に異議を唱えました。
波動力学を創始した当人であるシュレーディンガーはもちろんのこと、プランクやアインシュタインが「第一のルール」を認めていたことは、118ページでも触れたとおりです。[118ページとは:『この方程式を解けば、物質がどんな「形」の波を持ち、その波が時間の経過とともにどのように伝わっていくのかが計算できます。シュレーディンガーはこの方程式を用いて、水素原子中の電子のエネルギーがボーアの量子条件のとおりに「とびとび」になっていることを示しました。シュレーディンガーの論文は、プランクやアインシュタインからただちに絶賛されました。このシュレーディンガーの理論は波動力学と呼ばれ、ミクロの世界の運動法則を記述する量子力学の基本の理論になったのです』]
しかし二番目のルールである確率解釈には激しく抵抗しました。なぜなら確率などという原理を物理学の中に持ち込むと、物理学はもはや「決定論」ではなくなってしまうと考えられるからです。
「物理学を決定論と考える」とは、簡単に言うと、過去のある時点の条件がすべてわかれば、その未来はただ一つに決定できると考えることです。たとえば、手に持ったボールから手を離したとき、ボールがどんな運動をするのかは、ボールと地面の距離や地球の重力の強さなどを知ることで正確に予測できます。同じように地球が明日、太陽の周囲を回る公転軌道の中でどこにいるのかも、太陽の重力や太陽と地球の距離を知ることで間違いなく計算できるのです。
ただしボールを地面に落とすとき、突然風が吹くかもしれません。一時間後に小惑星が地球に衝突して、地球の位置を変えてしまうかもしれません。しかし、そうした要因をもしすべて知ることができたならば、未来はただ一つに決められるというのが、決定論的な考え方です。そして自然現象を表す物理学は決定論でなければならないというのが、ニュートン以来の物理学の大前提だったのです。』

B点という位置における波の振幅が、A点における波の振幅の二倍になっているとします。この時、実際にこの電子を観察すれば、電子がB点において発見される確率は、A点において発見される確率の四倍(二の二乗=四なので)になるのです。
またD点における波の振幅は、A点と同じ大きさなので(「高さ」と「深さ」の区別は不要で、大きさつまり絶対値だけでだけを見ます)、発見確率も同じなります。これに対して、C点における波の振幅はゼロになっています。この場合、電子がC点という場所で発見される確率はゼロになるのです。
このように私たちが「ある場所」に電子を発見するかどうかは、その場所における波の振幅つまり波動関数ψの値によって左右されることになります。ψの絶対値が大きい場合ほど、そこに電子を見つける可能性が高いのです。
画像出展:「量子論を楽しむ本」
写真は後列右から6人目がシュレーディンガー。中央の列右端がボーア、その左隣がボルン、ブロイ。前列右から5人目がアインシュタイン。
第五回ソルヴェイ会議
・期間:1927年10月24日~10月29日
・場所:ベルギー ブリュッセル
・講演
・W.L.ブラッグ:X線の反射強度
・A.H.コンプトン:輻射の電磁理論と実験の不一致
・L.ドゥ・ブロイ:量子の新力学
・M.ボルン,W.ハイゼンベルク:量子の力学
・E.シュレーディンガー:波動の力学
・N.ボーア:量子仮説と原子論の新しい発展
『この回のソルヴェイ会議は主題に“電子と光子”を掲げていたが、議論はおのずと量子力学の解釈にむかい、それをめぐって沸騰した。量子力学のあたえる自然の記述は完全であるかとアインシュタインが問い、ボーアに迫った。彼等の晩年まで続く論争は実にこの会議にはじまったのである。』
画像は「シュレーディンガー その生涯と思想」より、文章は「波動力学形成史」より。
こちらは、“ボーアとシュレーディンガーの討論(p206)”、“シュレーディンガーの”波動関数の確率解釈”に対する考え(p203)”、そして”量子力学の成立(p207)”に関して書かれたページです。大変興味深いので抜粋してそのまま貼り付けました。
非常に長い前置きになってしまいましたが、上記の内容を頭の片隅に置きながら、今回の『一冊でわかる 数学』の中から、理解ができて、数学と量子力学/物理学のつながりに関係すると思われる部分をご紹介します。目次でいうと一つは「1.モデル」から、もう一つは「7.概算と近似」からになります。
数学的モデルとは?
『物理学の問題に対して得られた答えをよく調べてみると、科学的な考察からもたらされる部分と、数学によってもたらされる部分とにはっきり区別できることが多い(いつも必ず区別できるわけではないが)。また、科学者が理論を組み立てるときには、観測や実験の結果から作っていく部分と、理論のシンプルさや、現象をどれだけ説明できるかといった一般的考察から作っていく部分とがある。数学者や、科学者のなかでも数学をやっている人たちは、そうして作られた理論をもとに、純然たる論理だけによって何が引き出せるかを調べていく。型どおりの計算からは、その理論がもともと説明すると期待されていた現象が導かれることもあるが、ときにはまったく思いもよらなかった現象が予測されることもある。そんな意外な予測がのちに実験によって裏づけられれば、理論を支持する立派な証拠となる。
しかしながら、「科学理論による予測を実験によって裏づける」という作業は一筋縄ではいかない。なぜなら、前節で述べたように、状況を簡単にしてくれる仮定を置く必要があるからだ。それを説明するために、もうひとつ別の例を挙げよう。ニュートンの運動法則および重量法則によれば、2つの物体を同じ高さから同時に落とせば、それらは同時に着地する(ここでは地面は平坦だと仮定した)。ガリレオが最初に指摘したこの現象は、いささか直感に反している。いや、直感どころではない。ゴルフボールとピンポン玉で実験してみればわかるように、実際、ゴルフボールのほうが先に地面に着くからだ。では、いかなる意味でガリレオは正しかったと言えるのだろうか?
この簡単な実験がガリレオ説への反証とみなされないのは、いうまでもなく、空気抵抗が存在するからである。経験が教えているように、空気抵抗が小さければガリレオの理論はよく成り立つ。だが、「ニュートン力学の予想がはずれたときはいつも空気抵抗のせいにするのはご都合主義だ」と思われる読者もいるかもしれない。しかしそんな読者も、真空中では、羽毛はたしかに石と同じように落下するのである。
とはいえ、科学における観測は、どうやっても完全には直接的にも決定的にもならないから、科学と数学との関係を説明するには、もう少しうまい方法を考えなければならない。実をいえば数学者は、科学理論をそのまま現実世界にあてはめるのではなく、「モデル」にあてはめるのである。ここではモデルというのは、研究対象である現実世界の一部を単純化した、いわば架空の世界であり、その世界では厳密な計算ができるようなものと考えてよい。石を投げる場合であれば、現実世界とモデルとの関係は図1と図2との関係のようなものである。
与えられた物理的状況をモデル化する方法はたくさんあるので、あるモデルが現実世界を理解するのに役立つかどうかを判断するためには、経験に照らし、理論的考察をさらに深めなければならない。モデルを選ぶときにまず目安にすべきは、そのモデルの性質が、観察されている現実世界の性質に対応するかどうかだ。しかしながら、モデルがシンプルであることや、数学的にエレガントであることなど、現実世界との対応以外の要素のほうが重要になることも少なくない。実際、現実世界にはまったく似ていないのに非常に役立つモデルもあるのだ。』
概算と近似
『たいがいの人は、数学は白黒はっきりした厳密な学問だと思っている。高校までの数学を習うと、簡潔に述べられた問題の答えはやはり簡潔に示され、しかも多くの場合は短い式で表されるのだろうと思うようになる。ところが、大学まで数学の勉強を続けた人たち、とくに数学を研究しはじめた人たちは、これほど現実からかけ離れた話もないことをすぐに悟ることになる。多くの問題において、解が厳密な式で表されるのは、思いもよらない奇跡的な出来事なのである。たいていは厳密な答えではなく、おおざっぱな概算で妥協しなければならない。概算というものに慣れるまでは、こういう妥協はみっともなくて口惜しいことに思われる。だが、概算の面白みを知っておいて損はない。なぜならそれを知らないでいることは、いくつもの大定理や、未解決問題の大半に出会い損なうことだからである。』
分かったこと(イメージ)
物理学と数学の関係は性格の異なる兄弟のように感じました。現実主義者(物理学)の兄と曲がったことの大嫌い(数学)な弟というイメージです。
二人は血がつながっており、お互い助け合って生きています。二人の関係を意識すると、兄、弟、それぞれの個性も理解しやすくなります。
しかしながら、今回は現実主義の兄も先祖代々受け継がれてきた家訓(ニュートン力学に代表される“決定論”)をないがしろにすることはできないという強い思いを抱いています。一方、兄を支援する立場の弟は、曲がったことは一切受けつけないという頑固さを封印し、結果に対する柔軟性(概算・近似)に目を向け、考えの幅を広げることも必要だと感じています。
量子論の育ての親とされるニールス・ボーアと古典派との分かれ道となった“波動関数の確率解釈”を提唱したマックス・ボルン等の推進派。彼らは”歩”を進めるために家訓を越え、柔軟性を積極的に取り入れることによって、常識がまったく通用しない原子よりも小さなミクロの世界に足を踏み入れました。
マックス・ボルンは“波動関数の確率解釈”の発表から28年後の1954年にノーベル物理学賞を受賞されました。そして、なくてはならないコンピュータをはじめ様々な分野で量子力学は大きな成果に貢献しています。
付記1(「8.数学に関するよくある質問」より)
本書の最後となる「8.数学に関するよくある質問」にはユニークな8つの質問が掲載されています。ここでは先頭の「数学者は30歳を過ぎると才能が枯渇してしまうというのは本当ですか?」をご紹介させて頂きます。
1 数学者は30歳を過ぎると才能が枯渇してしまうというのは本当ですか?
2 女性の数学者が少ないのはなぜですか?
3 数学と音楽は相性がいいのでしょうか?
4 積極的に数学は嫌いだと言う人がこれほど多いのはなぜでしょうか?
5 数学者は研究にコンピュータを使いますか?
6 数学を研究できるということが不思議です。
7 有名な問題がアマチュアによって解かれた例はありますか?
8 なぜ数学者は、定理や証明を「美しい」などと言うのですか?
1 数学者は30歳を過ぎると才能が枯渇してしまうというのは本当ですか?
『これは広く信じられている神話だが、この神話が人の心に訴えるのは、数学的能力というものが誤解されているせいである。世間の人たちは、数学者は天才なのだと思いたがる。そして天才とは、一握りの人だけが生まれながらにもつ完全に神秘的な資質であって、一般人がそれを獲得する見込みはないと考えたがるのだ。
数学者の年齢と研究の生産性との関係には大きな個人差があり、20代で最良の仕事をする数学者がいるのも事実である。しかし圧倒的多数の数学者は、知識や経験は年齢とともに増え続けると感じているし、たとえ「生の脳力」は低下するとしても(「生の脳力」などというものがあればだが)、長期的には、知識や経験の増大は脳の衰えを補ってあまりあるというのが実感だろう。画期的な仕事が40歳を過ぎた数学者によって成し遂げられることが多くないのは確かだが、しかしそれはむしろ社会的な要因のせいではないだろうか。40歳までには、画期的な仕事ができるほどの人はすでに若い頃の仕事で名を成しているから、地位や名声をまだ確立していない若い数学者ほどのハングリー精神はなくなっているのかもしれない。しかしこれには多くの反例があり、なかには退職後もずっと情熱を失わない数学者もいる。
世間に広まっている数学者のステレオタイプは、あまりうれしいものではない―「頭は非常に良いだろうが、変人で身なりにかまわず、中性的かつ自閉症的」といったところか、このステレオタイプにあてはまらないからといって、数学は得意教科にはなりえないと考えるぐらい馬鹿げたことはない。実際、他の条件がすべて同じなら、あてはまらない人のほうが有利だろう。数学を学ぶ学生のうち、研究者にまでなる人はごくわずかである。たいていは途中で興味を失ったり、博士課程への受け入れ枠に入れなかったり、博士号は取得したものの大学に職を得られなかったりして研究をやめてしまう。こうして何段階もの選抜をくぐり抜けた人たちの集団では、初期の学生時代にくらべて、変人の比率は少なくなっているというのが私の印象である。―そして、そう感じているのは私だけではない。
好ましからぬ数学者像には、本来ならば数学を楽しみ、数学が得意になっていたかもしれない人たちをこの教科から遠ざけるという悪影響があるのかもしれない。だが、「天才」という言葉の及ぼす害悪は、いっそう見えにくく、しかも深刻だ。天才をおおざっぱに定義すれば、「ふつうの人にはできないこと、あるいは何年も修行しなければできないことを、若くしてやすやすとやってのける人」となるだろう。天才たちの偉業には何か魔法めいたところがあって、天才の脳は単にわれわれのそれよりも効率よく機能するだけでなく、何かまったく異質な働き方をするかに思われるものがある。ケンブリッジ大学には1年か2年に1人ほど、教員を含めてたいていの人が何時間もかかって解くことになりそうな問題を、ものの数分で解いてしまう学生が入学してくる。そういう人物を前にすれば、一歩下がって驚嘆するしかない。
ところが、そんな並はずれた人たちが数学研究者として大成するとは限らないのである。自分以前のプロの数学者たちが取り組んでは失敗してきた問題を解こうとすれば、さまざまな資質が必要になる。先に定義した天才の資質などは、そのためには必要でもなければ十分でもない。極端な例を挙げると、アンドリュー・ワイルズはちょうど40歳のときにフェルマーの最終定理(「x,y,z,nを正の整数とし、nが2よりも大きいとき、xのn乗+yのn乗はzのn乗と等しくはなりえない」)を証明し、世界一有名な数学の未解決問題を解決したが、ワイルズの頭の良さに疑問の余地はないにせよ、彼は私の言う意味での天才ではない。
しかしあれほどの偉業を成し遂げた人物であるからには、常人を超えた神秘的な力をもっているに違いないと思う人もいるかもしれない。なるほどワイルズの仕事は驚異的だが、それは説明不可能な種類の驚異ではない。彼を成功させたものが本当のところ何であるかを私は知らないけれども、少なくともワイルズは、大いなる勇気と、確固たる意志と、強靭な忍耐力と、他の研究者が成し遂げた難解な研究に関する広範な知識と、しかるべき時期にしかるべき領域を研究していた幸運と、ずば抜けた戦略能力を必要としたことだろう。
結局のところ、最後に挙げた「ずば抜けた戦略能力」という資質こそは、猛烈なスピードで暗算ができることなどよりはるかに重要である。数学に対するもっとも深い貢献は、しばしばウサギよりはカメによって成し遂げられているのだ。数学者は成長するにつれて多くの専門知識を身につけていくが、それらは同僚の仕事から得られることもあれば、長い時間をかけて数学を考え抜いた結果として得られることもある。そうして身につけた知識を使って有名な難問を解決できるかどうかを決めているのは、主として注意深い計画性である。豊かな実りをもたらしてくれそうな問題に狙いを定め、見込みのなさそうな戦略を捨てるべき時に知り(これは難しい判断である)、詳細を詰めていく前に(そこまで到達するのは稀である)、大まかなアウトラインを描き出せなくてはならない。それができるためには、ある程度の成熟が必要だ。これは決して天才であることと相容れない資質ではないけれど、必ずしも天才に付随する能力でもないのである。』
付記2(『思考の凄い力』:ブルース・リプトンより)
今回、いままで全く縁のなかった量子論、量子力学を学ぼうとしたきっかけは、ブログ“がんと自然治癒力8”で読んだ『思考の凄い力』に因るものです。最後にもう一度その内容を確認して終わらせたいと思います。
第四章 量子物理学が生物学・医学を変える日は近い
ニュートン力学では超常現象を解明できない
『搭乗を待っていて、ハッと気がついた。これから5時間もシートに縛りつけられるというのに、何も読み物がない。
搭乗ゲートは閉まろうとしていたが、列から離れてコンコースを降り、本屋へと向かった。選択肢は山のようにあるのに飛行機のドアが閉まって取り残される危険性もあり、パニックになりそうだった。どうしていいかわからなくなったとき、一冊の本が目にとまった。『量子の世界』。著者は物理学者ハインズ・R・パージェル。ざっと見たところ、量子物理学の初心者向け解説書らしい。大学のとき以来、量子物理学恐怖症は根強かったので、すぐに棚に戻してもっと軽い読み物を探す。
頭の中でストップウォッチの秒針がレッドゾーンに突入した。ベストセラーだと自ら喧伝している本をつかんで、レジに走る。会計を待ちながらふと見ると、カウンターの後ろの棚に例のパージェルの本が一冊ある。会計はもうほとんど終わっていたし、時間切れになる寸前だったが、ついに量子物理学嫌いを返上して、『量子の世界』も追加で買うことにした。
本屋への行き来にダッシュしたのでアドレナリン全開だったが、飛行機に乗り込んでなんとか自分を落ち着かせ、クロスワードパズルを解いてから、いよいよパージェルの本にとりかかった。
ハッと気がついたときには没頭していた。何度も前にかえっては同じ部分を読み直さなくてはならなかったが、それでも夢中になった。フライトのあいだ読み続け、マイアミで3時間待ちのときもずっと読み続け、さらに楽園の島へ向かう5時間の道中ずっと本を置くことができなかった。パージェルには完全にやられてしまった!
シカゴで飛行機に乗るまで、量子物理学が生物学に関係があるなどとは思ってもみなかった。ところが飛行機が楽園に着いたときは脳が揺さぶりをくらっていた。量子物理学は生物学に“関係おおあり”なのだ!
量子物理学の法則を無視する生物学者は明らかに科学的な過ちを犯している。なんといっても物理学はすべての科学の基礎なのだから。ところが、わたしも含めて生物学者たちはほぼ全員、時代遅れの、だがより整然としたニュートン物理学に頼っている。世界はニュートンの説いたように動いているという考えに固執し、目に見えない量子の世界、アインシュタイン的世界を無視している。
アインシュタインによれば、物質はエネルギーから成っていて、絶対的物質なるものは存在しない。原子レベルでは、物質は確実に存在するわけではない。存在する可能性があるとしか言えないのだ。わたしがそれまで生物学や物理学について確信していた事柄が、木っ端みじんではないか!(訳註:アインシュタインは初期量子論の誕生には貢献しているが、量子物理学を打ちたてたのはボーアやシュレディンガー、ハイゼンベルクら、アインシュタインとはほぼ同時代の物理学者たちである。現代物理学はアインシュタインの相対性理論とボーアらの量子論を二本の柱としている)
ニュートン物理学は論理を追求する科学者にとってはエレガントで安心を与えてくれるものであったとしても、宇宙についてはもちろん、人体の真実をすべて解き明かしてくれるものではない。いまから思えば、わたしも他の生物学者たちもそれは承知していたはずだ。
医学は日々進歩していくが、生きている身体は頑固なまでに定量化を拒んでいる。ホルモンやサイトカイン、成長因子や腫瘍抑制因子など、シグナルとなる化学物質の働くメカニズムが次から次へと発見されている。
だがそういったメカニズムでは超常現象は説明できない。自然治癒、心霊現象、驚くほどの筋力や耐久性、灼熱の石炭の上を火傷一つ負わずに素足で渡る能力、“気”を移動させて痛みを消し去る鍼灸師の力など、そのほかさまざまな超常現象が、ニュートン的世界観に立脚した生物学では説明不能だ。
医学部にいたときには、もちろん、これらの現象については全然考えてもみなかった。わたしも他の教官たちも学生たちに鍼灸療法やカイロプラクティック、マッサージ療法、祈祷などで病気が治るという主張は無視するように教え込んでいた。いや、それ以上だ。医者を名乗るペテン師の口上だといって弾劾さえしたのだ。それほど古典的なニュートン物理学を信じ込み、他の考え方はできなくなっていた。
いま挙げた療法はいずれも、エネルギー場が人間の身体の生理機能や健康に影響を及ぼしているという信念に基づくものだ。』
生物と量子力学3(意識)
「“信じる者は救われる”とは誰が言った言葉なんだろう?」と思いました。
調べてみると、それは新約聖書の中のマルコ福音書16:16(Mark 16:16)というところから来ているようです。

画像出展:「DailyVerses.net」
何が言いたかったかというと、患者さまが「鍼は効く[ポジティブ]」(「鍼は怖い[ネガティブ]」ではなく)と思うとき、そして施術者が患者さまの病態を理解し適切な“証(施術方針)”を立て、「鍼は効く[ポジティブ]」と思うとき、鍼の効果は得られやすいように感じます。
一方、ブログ「量子論2」の“5.量子の奇怪さ”の中には、次のような指摘がされています。
『量子論を考え出した人たちは、ニュートン的世界観と対照的なもう一つの面に気づいた。それは観測者が創り出すリアリティというものだ。量子論によれば、観測者が何を測定しようとしているかということがその測定自身に影響を及ぼすことになる。量子の世界で現実に起こっていることは、その世界を我々がどのように観測しようとしているかに依存しているのだ』
“何を測定しよう”という行為は“観測者”という主体が持つ“意識”から生まれるものだと思います。つまり、意識は量子の世界とつながり、影響を与えるものだということです。 今回の本の中にも「心」をテーマにした章がありました。詳細は以下の通りです。
内容はいずれもその難しさに圧倒されるものですが、“心はどうやって物体を動かすのか”と最後の“量子イオンチャンネル?”の一部ご紹介させて頂きます。
心はどうやって物体を動かすのか
『おそらくほとんどの人は、心や魂や意識は物理的な身体とは別物だとする「二元論」の考え方を、何らかの形で受け入れていると思う。しかし20世紀の科学界では二元論は支持を失い、いまではほとんどの神経生物学者は、心と体は同じ一つのものだとする「一元論」の考え方のほうを好んでいる。たとえば神経科学者のマルセル・キンズブルンは、「意識があるというのは、神経回路がある特定の相互機能状態にあるようなものだ」と主張している。しかし先ほど話したように、コンピュータの論理ゲートは神経細胞にかなり似ている。だとしたら、およそ10億のインターネットホストから構成されているワールドワイドウエブ(1000億個の神経細胞からなる脳に比べたらまだ小さいが)のような、高度に連結したコンピュータは、なぜ意識の兆しさえも示さないのだろうか? なぜ、シリコンでできたコンピュータはゾンビ[意識を持っていないという意味です]で、肉でできたコンピュータは意識を持っているのだろうか? 単に、ワールドワイドウェブが我々の脳の複雑さや「相互連結性」にまだ到達していないというだけの問題だろうか? それとも、意識はまったく違うたぐいの計算活動なのだろうか?
もちろん、このテーマについて書かれた数々の書物のなかでは、意識に対するさまざまな「説明」が展開されている。しかしここでは、本書のテーマにもっとも関係のある、きわめて異論が多いが魅力的なある主張に焦点を絞ることにする。それは、意識は量子力学的現象であるとする説だ。なかでももっとも有名なのは、オックスフォード大学の数学者ロジャー・ペンローズが1989年の著書「皇帝の新しい心」のなかで説いた、人間の心は量子コンピュータだという主張である。 ~』
量子イオンチャンネル?
『~ 脳の電磁場によって神経発火が同期するという現象は、神経活動の特徴のなかでも意識と関係があることが知られているごく少数の例の一つである。そのため、意識の謎について考える上でもきわめて重要だ。たとえば、視界のなかに置かれている自分の眼鏡などの物体を探していて、散らかったほかの物体に混じってそれを見つけたときに誰もが経験する現象について考えてみよう。散らかった場所を見ているとき、探している物体をコードしている視覚情報は目を通じて脳へ伝えられているが、なぜかその探している物体を見ることはない。それを「意識」してはいないのだ。しかししばらくすると、その物体が見えるようになる。はじめ気づかなかったときと、同じ視野のなかにその物体があることに気づいたときとで、脳のなかでは何が変化しているのだろうか? 驚くことに、神経発火そのものは変化しないらしく、眼鏡が見えていようがいまいが同じ神経細胞が発火する。しかし眼鏡を見つけていないときには、神経細胞の発火は同期しておらず、見つけると同期する。電磁場は、脳の互いに離れた場所にあるコヒーレントなイオンチャネルをすべて一つに結びつけることで、無意識から意識的思考への移り変わりに何らかの役割を果たしているかもしれない。
強調しておくべきだが、意識を説明するために脳の電磁場や量子コヒーレントなイオンチャネルといった概念を持ち出してきたところで、けっしてテレパシーのようないわゆる「超常現象」の存在が裏付けられることにはならない。電磁場もイオンチャネルも、一つの脳のなかでおこなわれる神経プロセスにしか影響を与えることはできず、異なる脳のあいだで意思疎通することはできないのだ! さらに、ゲーデルの定理[不完全性定理:数学基礎論における重要な定理]に基づくペンローズの主張について考察したときに指摘したように、酵素活性や光合成など本書で取り上げたほかの生物現象と違い、そもそも意識を説明するのに実際に量子力学が必要であるという証拠はまったくない。しかし、生命に欠かせないあれほど多くの現象に関係していることが分かっている量子力学の奇妙な性質が、生命のもっとも謎めいた産物である意識にはまったく関係していないなどということが、はたして考えられるだろうか? その判断は読者にお任せしよう。量子コヒーレントなイオンチャネルと電磁場に基づいて意識を説明するという説を含め、ここまで示してきた事柄はもちろん推測にすぎないが、少なくとも脳のなかで量子の世界と古典的な世界をつなぐものとしては理にかなっている。』
以上のことから、この本の著者は意識と量子の世界の関わりについて、ロジャー・ペンローズの著書「皇帝の新しい心」の内容に対して懐疑的ではあるものの、その可能性は否定していないということが分かります。こうなると、何はともあれ「皇帝の新しい心」という本を知る必要があります。
幸い、お世話になっている図書館にそれは所蔵されていました。
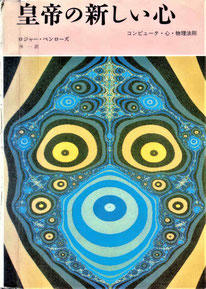
題名:「皇帝の新しい心 コンピュータ・心・物理法則」
原書:「The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and The Laws of Physics」1989年
著者:ロジャー・ペンローズ
出版:みすず書房
発行:1994年12月
ここでは訳者である林 一先生(昭和薬科大学名誉教授)による「訳者あとがき」の一部と、この本の目次をご紹介したいと思います。
『~ 心はなぜ存在するか、心は脳という生物的機関に固有のものなのか。意識現象が科学で理解できるのか。思考は機械的に可能か。われわれはなぜここにいて、宇宙について、心について考えているのか。
相対性理論の新しい時空像、量子論が切り開いたパラドクシカルな状況、人工知能(AI)の発展、ゲーデルの定理、チューリング機械の理論がさらけだしたアルゴリズム的思考の限界。脳科学が提示している知覚の奇妙さ。こうした現代科学の成果は、上の問題を新たな形で定式化しては、それをめぐる謎をさらに深めたと言える。
この謎に対する出来合いの答はもちろんない。本書は、現代科学のあらゆる分野の関連のあるかぎり遠慮なく取り上げて、この本題に迫る。答えはないとはいえ、ペンローズが多大の労力を費やしたのは、彼の大胆な仮説、見通しを筋道を立てて率直に読者に説明するためである。そのためには相対性理論、量子論の根本的問題についても論じなければならない。議論は明快で数式はかみ砕かれており、読み飛ばしても差し支えないという断りがあるとはいえ、かの【ホーキング、宇宙を語る】の各編集者がホーキングに与えた、どんな数式も読者を半減させるという名警告を、彼はあえて無視した。
数理物理学、相対性理論、宇宙論の分野で赫々(カクカク)たる業績をあげた、当代きっての数学者・物理学者であるペンローズがなぜ、大勢の物理学者が敬して遠ざけてきたこの問題にここまで真剣に取り組むようになったのか、その心中を推測することは私にはできない。きっかけについては彼自身の言葉を上で紹介したが[上で紹介とは「副題に“コンピュータ・心・物理法則”とあり、コンピュータが心をもちうるかという問題を、それを肯定的に答える一部の論者に刺激されて、心とは何かについて深く考え始めたのが、本書執筆の動機であった、と著者自身が述べている」]、ひょっとするとごく単純で、エヴェレストがそこにあるのと同じように、問題がそこにあったからなのであろうか。いずれにしても、これは功なり名を遂げた高名な科学者にしばしば見られる、高尚な哲学的問題への寄り道、老後の手すさびではない。彼は数年来、さまざまな形でこの問題に対する関心の深さを披露してきたのだが、ついに本格的な書物の形にまとめて、世に問うに至った。
心とは何か、意識の本体は何か、それを解明するには、量子論を根本から改革しなければならない。ビッグバンの解明には、量子重力論の建設が必要であることは広く認められているが、ペンローズはさらに進んで、正しい量子重力論が、心の謎、時間の流れという意識の謎を科学的に解く鍵を与えると予測している。意識的思考は非アルゴリズム的で、謎めいた無意識の方こそアルゴリズム的だという指摘、重力による時空の湾曲が意識の成立に関わる、という見通しは、彼以外のすべての科学者にとっても、現代科学に多少なりと親しんでいる一般読者にとっても、破天荒なアイデアであろう。
この問題に対する彼の大胆極まりない答えを一般読者に向けて解くためには、背景となる科学のさまざまな分野(上ではその一端に触れただけだが)について予備知識を与えるべく、著者は筆を惜しまず数百ページを費やして解説した後、本題に迫る。その範囲の広大さは、目次を一目見ただけで分かるだろうから、ここでは羅列しないが、その解説も決して型通りのものではなく、この著者ならではの独創的なものであるが、それはこのような分野に接したことのある読者なら一読して自ら納得されるだろう。うまく訳文に表すことができたかどうか心細いが、控えめだが企まざるユーモアも微笑ましい。
彼自身が明言しているように、当然ながら、彼の答えも暫定的なものである。かつて彼の名声を不動にした、いわゆるペンローズの定理―すべての既知の物理法則が成立しない特異点ブラックホールが生じるのは特殊な条件のもとに限られるという、長年の物理学者の希望的観測を打ち砕いた定理―の発見が、後にスティーヴン・ホーキングの協力を得て、ペンローズ‐ホーキングの定理に拡大されて、宇宙論の展開に大きな転機をもたらしたことが思い合わされるが、心という小宇宙と大宇宙に科学的理解の橋を架けようという、それ以上にスケールの大きな大胆不敵なアイデアが、どのような運命をたどることになるのか、そして、現代科学、なかんずく人工知能論が心に着せている新しい衣を、ペンローズが、皇帝の権威を恐れない寓話の中の子供のように見透かしたことになるのか、私には予測はつかない。 ~』
目次
序文
プロローグ
1 コンピュータは心をもちうるか?
はじめに
テューリング・テスト
人工知能
「快楽」と「苦痛」に対するAIアプローチ
強いAIとサールの中国語の部屋
ハードウェアとソフトウェア
2 アルゴリズムとテューリング機械
アルゴリズム概念の背景
チューリングの発想
数値データの2進符号化
チャーチ‐チューリング・テーゼ
自然数以外の数
万能チューリング機械
ヒルベルトの問題の解決不能性
アルゴリズムをどう出し抜くか
チャーチのラムダ算法
3 数学と実在
トルブレッド=ナムの国
実数
実数はどれだけあるか?
実数の「実在性」
複素数
マンデルブロー集合の作図
数学的概念のプラトン的実在性
4 真理、証明と洞察
数学に関するヒルベルトのプログラム
形式的数学的システム
ゲーデルの定理
数学的洞察
プラトン主義か直感主義か?
テューリングの結果から導かれるゲーデル型の定理
帰納的に可算な集合
マンデルブロー集合は帰納的か?
非帰納的な数学のいくつかの例
マンデルブロー集合は非帰納的数学らしいか?
複雑性理論
複雑性と物理的な事物の計算可能性
5 古典的世界
物理理論の身分
ユークリッド幾何学
ガリレオとニュートンの動力学
ニュートン力学の機械論的世界
ビリヤード・ボール世界における生命は計算可能か?
ハミルトン力学
位相空間
マクスウェルの電磁理論
計算可能性と波動方程式
ローレンツの運動方程式:暴走粒子
アインシュタインとポアンカレの特殊相対性理論
アインシュタインの一般相対性理論
古典物理学における計算可能性:われわれはどこに立っているのか?
相対論的因果性と決定論
質量、物質と相対性
6 量子マジックと量子ミステリー
哲学者は量子論を必要とするか?
古典理論の問題点
量子論の始まり
2重スリット実験
確率振幅
粒子の量子状態
不確定性原理
発展手順UとR
1つの粒子が同時に2つの場所にある?
ヒルベルト空間
測定
スピンと状態のリーマン球面
量子状態の客観性と測定可能性
量子状態のコピー
光子のスピン
大きなスピンをもつ対象
多粒子系
アインシュタイン、ポドルスキ―、ローゼンの「パラドクス」
光子を用いる実験:相対性理論の難点?
シュレーディンガー方程式:ディラック方程式
量子場の理論
シュレーディンガーの猫
現行の量子論に対するさまざまな態度
われわれはどこに取り残されたのか?
7 宇宙論と時間の矢
時間の流れ
容赦ないエントロピーの増大
第2法則の働き
宇宙における低エントロピーの起源
宇宙論とビッグバン
原初の火の玉
ビッグバンは第2法則を説明するか?
ブラックホール
時空特異点の構造
ビッグバンはいかに特殊であったか?
8 量子重力を求めて
なぜ量子重力か?
ワイル曲率仮説の背後に何があるか?
状態ベクトルの収縮における時間非対称性
ホーキングの箱:ワイル曲率仮説との関連?
状態ベクトルはいつ収縮するか?
9 実際の脳とモデル脳
脳は現実にはどういうものか?
意識の座はどこか?
分割脳実験
盲視
視覚皮質における情報処理
神経信号はどのように働くのか?
コンピュータ・モデル
脳の可塑性
並列コンピュータと意識の「唯一性」
脳の活動に量子力学の出番はあるか?
量子コンピュータ
量子論を越えて?
10 心の物理学はどこにあるのか?
心は何のために?
意識の現実に何をなすのか?
アルゴリズムの自然淘汰?
数学的洞察の非アルゴリズム的性格
インスピレーション、洞察と独創性
思考の非言語性
動物意識?
プラトン的世界との接触
物理的実在に対する1つの見方
決定論と強い決定論
人間原理
タイル並べと準結晶
脳の可塑性とのありうべき関連
意識の遅れ
意識的知覚における時間の奇妙な役割
結論:子供の見方
エピローグ
まとめ
”まとめ”というには頼りない内容ですが書いてみました。
繰り返しになりますが、本書の著者が考えている「量子力学と意識」の関係性は次の通りです。
『酵素活性や光合成など本書で取り上げたほかの生物現象と違い、そもそも意識を説明するのに実際に量子力学が必要であるという証拠はまったくない。しかし、生命に欠かせないあれほど多くの現象に関係していることが分かっている量子力学の奇妙な性質が、生命のもっとも謎めいた産物である意識にはまったく関係していないなどということが、はたして考えられるだろうか?』
これを見たときに気になったのは、ブログ ”がんと自然治癒力9” でご紹介したテロメアです。
このテロメアは2017年5月、NHKの”クローズアップ現代”でも紹介されています。

『老化を防ぎ、若さを保ちたい。そんな願いをかなえると注目されている研究がある。ノーベル賞生物学者・ブラックバーン博士らによる「テロメア」研究だ。染色体の端にあり細胞分裂のたびに短くなるため、年とともに縮むと考えられていたテロメア。ところがテロメアを伸ばして細胞から若返る方法があり、がんを防げる可能性もあるというのだ。』
『ブラックバーン博士たちが発見した酵素「テロメラーゼ」です。テロメラーゼは、テロメアが短くなるのを遅らせたり、さらに伸ばしたりする働きもあります。これによって、細胞を若返らせる可能性が出てきたんです。この発見で、ブラックバーン博士たちはノーベル賞を受賞。そして今、どうすればテロメラーゼを増やし、テロメアを伸ばすことができるのか、研究が進んでいます。』
この時、勉強した本は『テロメア・エフェクト』ですが、そこでは”靴紐とキャップ”を例に”染色体とテロメア”を紹介していました。
そして、ストレスに対する”脅威反応”と”チャレンジ反応”という二つの反応によって、テロメアが受ける影響は異なるということも説明されていました。これは意識とテロメアの関係を示すものだと思います。
テロメアにはNHKの”クローズアップ現代”のところでご紹介したように、”テロメラーゼ”という酵素の関与が明らかになっています。酵素のメカニズムに量子力学が関わっているということが証明されれば、テロメアに影響を与える意識と下図の三層目に存在する量子力学が結ばれると考えても良いのではないでしょうか。
ご参考:【量子力学】意識とは何か?を探ると未来に影響を与える方法が見えてくる『量子力学で生命の謎を解く』。こちらは本書を解説した「シンプリィライフ」さまの凄い動画です。
生物と量子力学2(酵素)
酵素に注目した理由は、代謝にとって酵素が極めて大切なものだからです。
“がんと自然治癒力”というブログの中で、自然治癒力とは何かについて整理整頓し、「自然治癒力とはストレス適応と栄養代謝である(詳細は“がんと自然治癒力13” の中段にある ”4.自然治癒力について” をご覧ください)という自分なりの考えをまとめました。
酵素は本書のなかでも、【生命のエンジン】であり、【我々を生かしつづけている「代謝」というプロセスを加速している】とされており、非常に重要なものと位置づけられています。
「第3章 生命のエンジン」はまさに酵素について書かれた章になります。ブログは目次に順じたつくりにはなっていませんが、 “●量子トンネル効果” については全文をご紹介しています。
第3章 生命のエンジン
●酵素-生きているものと死んでいるものを分け隔てるもの
●我々にはなぜ酵素が必要で、おたまじゃくしはどうやって尾をなくすのか
●地形を変える
●激しい運動や振動
●遷移状態理論ですべて説明できるのか?
●電子をあちこちに動かす
●量子トンネル効果
●生物における電子の量子トンネル効果
●陽子をあちこちに動かす
●速度同位体効果
●これで量子生物学は確立するのか?
また、下記の『 』で括った2つの文章は、前者が第3章の冒頭部分から、後者が“●電子をあちこちに動かす”から、それぞれ一部を抜き出したものです。そして、前者は“コラーゲナーゼ”、後者は“呼吸酵素”という2つの酵素を通じて、酵素の重要性や働きについて説明しています。さらに、呼吸酵素の「桁違いの凄さ」を生みだす “量子トンネル効果” とその前提となる “量子コヒーレンス” という量子現象について触れています。
『酵素は生命のエンジンだ。その中でも我々におそらくもっとも馴染み深いものとしては、しみを取り除く「酵素入り」洗剤に加えられているプロテアーゼ[タンパク質分解酵素(タンパク質を構成するペプチド結合を加水分解する酵素]や、ジャムに加えて安定化させるペクチン[ペクチナーゼ(ペクチン分解酵素)]、あるいは牛乳を凝固させてチーズを作るために加えられるレンネット[凝乳酵素]など、日々ありふれた使われ方をしているものがある。また知っている人もいるかもしれないが、我々の胃や腸の中ではさまざまな酵素が食物を消化する役割を担っている。しかしそれらは、自然界のナノマシンの働きのなかでもかなり些細な例だ。原始のスープ[生命の起源に関わる言葉で、非生物的な有機物の濃縮されたスープのこと]のなかで姿を現した最初の微生物から、ジュラ紀の森を闊歩していた恐竜、そして現在生きているすべての生物に至るまで、あらゆる生命は酵素に頼っている。あなたの身体のなかにある一個一個の細胞は、何百や何千というこのような分子マシンで満たされており、それらが生体分子の組み立てと再利用のプロセス、我々が生命と呼ぶプロセスを、絶えず手助けしているのだ。
ここで鍵となるのが、酵素の働きを指す「手助け」という言葉だ。酵素の仕事は、本来ならあまりにも遅いさまざまな生化学反応を加速させる(「触媒する」)ことである。つまり、洗剤に添加されているプロテアーゼは、しみに含まれるたんぱく質の分解を加速させ、ペクチン[ペクチン分解酵素]は果実に含まれる多糖の分解を加速させ、レンネットは牛乳の凝固を加速させる。同じように、我々の細胞のなかにある酵素は、細胞内の何兆個という生体分子を絶えず何兆個という別の生体分子へ変換することで我々を生かしつづけている、「代謝」というプロセスを加速している。
メアリー・シュワイツァーが恐竜の骨に作用させたコラーゲナーゼも、そうした生物マシンの一つにすぎず、動物の体内ではつねにコラーゲン線維の分解を担っている。酵素によって分解がどれだけ加速されるかをおおまかに見積もるには、酵素がなかった場合にコラーゲン線維の分解にかかる時間(明らかに6800万年より長い)と適切な酵素があった場合の時間(約30分)とを比べればいい。そこには一兆倍もの開きがあるのだ。

標本番号:MOR-1125
■2005年3月、ノースカロライナ州立大学のハイビー・シュワイツァーはサイエンス誌上でBレックスの大腿骨から軟組織の回収に成功したと発表した。論文では血管様の組織と弾力のある骨基質様の組織が報告された。もしこれがオリジナルの組織であればDNA抽出などの可能性が広がるが、一方でこれが本当にティラノサウルス由来の組織であるか疑問視する意見も多く寄せられた。
■2016年、シュワイツァーらは鳥類との比較検討を行い、産卵期のメスの骨髄組織とBレックスの組織が非常によく似ていることを発見し、Bレックスの軟組織はオリジナルのもので間違いないと結論づけた。
画像出展:「ウィキペディア」
この章では、コラーゲナーゼのような酵素がどのようにして化学反応を桁外れに加速させるのかを探っていく。近年、少なくともいくつかの酵素の作用に量子力学が重要な役割を果たしているという、驚きの発見があった。酵素は命の中核をなしているので、これを量子生物学をめぐる旅路の最初の寄港地としよう。』
※「代謝」とは:生命維持活動に必須なエネルギーの獲得や、成長に必要な有機材料を合成するために生体内で起るすべての生化学反応の総称。(コトバンクの“ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説”より)

こちらの密集した手書きの図は、2017年10月にアップした”代謝と恒常性”でご紹介した、「総まとめ代謝マップ」と題されたもので、『「代謝」がわかれば身体がわかる』からもってきました。
『呼吸とは息をすることだと考えたくなる。必要な酸素を肺に取り込んで、いらない二酸化炭素を吐き出すという作用だ。しかし実は息というのは、すべての細胞のなかで進行しているはるかに複雑で秩序正しい分子プロセスの、最初の段階(酸素の供給)と最後の段階(二酸化炭素の排出)を組み合わせたものにすぎない。そのプロセスは、「ミトコンドリア」と呼ばれる複雑な細胞小器官のなかで行われている。ミトコンドリアは、我々の大きい動物細胞のなかに閉じ込められた細菌の細胞のように見え、膜や独自のDNAなど内部構造まで持っている。実はミトコンドリアは、数億年前、動物や植物の細胞の祖先のなかに共生した細菌から進化して、その後、独自に生きる能力を失ったものにほぼ間違いない。ミトコンドリアが呼吸のようなきわめて精巧なプロセスを進めることができる理由は、かつて細菌として独自に生きていたことで説明できるだろう。化学的な複雑さでいえば、呼吸はおそらく、次の章で取り上げる光合成に次ぐ第二位だ。
呼吸において量子力学が果たしている役割を突き止めるには、呼吸のしくみを単純化してとらえる必要がある。それでも呼吸には、驚異の生物ナノマシンがおこなう一連の見事なプロセスが関わっている。はじめに炭素でできた燃料、この場合には食物から得た養分を燃焼させる。たとえば炭水化物は消火器の中で分解されてグルコースなどの糖になり、それが血流に乗って、エネルギーを必要としている細胞へ運ばれる。この糖を燃やすのに必要な酸素は、肺から血液によって同じ細胞へ届けられる。そして石炭を燃やしたときと同じように、分子内の炭素原子の最外殻にある電子が、NADHと呼ばれる分子へ移動する。しかしその電子は、すぐに酸素原子との結合に使われるのではなく、まるでリレー競争でバトンがランナーからランナーへ渡されていくように、細胞のなかにある「呼吸鎖」上を酵素から酵素へと手渡しされていく。電子は移動の各段階ごとにより低いエネルギー状態へ落ち、酵素はそのエネルギー差を使って陽子をミトコンドリアから外へ汲み出す。次に、そうして生じたミトコンドリア内外での陽子の濃度差を使って、ATPアーゼと呼ばれる別の酵素が駆動し、ATPという生体分子を合成する。ATPはあらゆる細胞にとってきわめて重要な分子で、いわばエネルギーの電池のように細胞のなかを簡単に運ぶことができ、身体を動かしたり作ったりするなど、大量のエネルギーを必要とする活動にパワーを供給する。
電子のエネルギーを使って陽子を汲み出す酵素の働きは、余剰なエネルギーを蓄えるために水を高いところへ汲み上げる揚水ポンプに似ている。蓄えられたそのエネルギーを解放させるには、水を低いところへ流してタービンに回し、発電させればいい。それと同じように、呼吸酵素のポンプは、ミトコンドリアから外へ陽子を汲み出す。その陽子がなかへ戻ってくるときに、タービンに相当する酵素であるATPアーゼがパワーを得る。そのタービンの回転がさらに別の一糸乱れる分子運動を引き起こすことで、酵素のなかにある分子に高エネルギーのリン酸基を結合させ、ATPを作り出すのだ。
エネルギーを捕まえるこのプロセスをさらにリレー競争にたとえるなら、バトンの代わりに水(電子のエネルギー)の入った瓶を使い、それぞれのランナー(酵素)が少しずつ水を飲んでから瓶を次のランナーに手渡していって、最後に残った水を酸素と書いているバケツへ移す。このように電子のエネルギーを少しずつ捕まえることによって、酸素へ直接移すよりも全体のプロセスの効率がはるかに良くなり、廃熱として失われる分もきわめて少なくなるのだ。

この図は本書のものではないため、上記の説明とはつながっていません。
ここでは紫線の電子の流れを見ていただくために添付しました。
画像出展:「人体の正常構造と機能」
このように、呼吸の鍵となる作用は息をすることとはほとんど関係なく、細胞のなかにある呼吸酵素が秩序正しく電子を受け渡していくことで成り立っている。酵素から酵素への電子移動は原子何個分にも相当する数十オングストロームの距離で起こり、従来の電子のジャンプではとうてい起こりえないと考えられていた距離に相当する。呼吸酵素はどのようにして、そのような長距離で電子をこれほど素早く効率的に移動させることができるのか、それこそが呼吸の謎である。』
ここで問題の「数十オングストローム(Å)の距離」がどれ程のものか考えたいと思います。
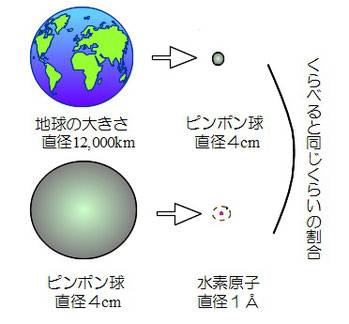
こちらの絵は、“水素原子”を「ピンポン球」の大きさに拡大すると、“ピンポン球”は「地球」の大きさになってしまう。という例です。なお、水素原子の正確な直径は、1.06Å(オングストローム)になります。
画像出展:「原子ってどんなもの?(1)」
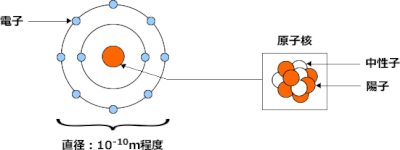
原子の直径として明記されている10-10mという数は1Å[オングストローム]と同じです。また、中央にあるオレンジ色の原子核の大きさは中性子と陽子の数で決まります。その原子核の周りに電子が存在しているというのが原子の全体像です。
画像出展:「第1回:原子のつくり その1」
数十オングストローム(Å)の距離とは

この表は「電子の大きさはどれだけか?」に出ている表を参考に作成しました。
水素原子の半径は0.53Å(53pm)。原子核の大きさは陽子・中性子の数によって変わりますが、陽子・中性子それぞれの半径はともに約1.2fm(0.0012pm・0.000012Å)。従って、陽子・中性子を1とすると、水素原子は陽子・中性子の約44,000倍であり、原子核の外側に位置する電子は原子核から約44,000倍離れていることになります。
原子核を半径10cmのボールとすると、電子があるのは約4.4km地点ということになります。新宿駅と池袋駅の直線距離は約4.6kmだそうなので、新宿駅にハンドボール、池袋駅にハンドボールより明らかに小さいもの、例えばパチンコ玉があるというイメージでしょうか。ちなみに重さの比較ということでいえば、電子を1とすると、陽子・中性子は電子の約1,800倍です。仮にパチンコ玉(電子)がプラスチックでできていて1gしかないとすれば、陽子・中性子の重さはそれぞれ約1.8㎏ということになります。
「従来の電子のジャンプではとうてい起こりえない」とする距離は数十Åとされているので、仮に水素原子(半径)の100倍、53Åの距離ということになると440km離れた所になりますので、パチンコ玉(電子)は池袋から京都あたりまで飛んで行ったということになります。ニュートン力学の世界で考えれば、確かにジャンプ(jump)というよりは小旅行(trip)という感じです。
そして、この小旅行ともいうべき長距離を瞬時に移動するための手段は、奇怪な量子現象の一つである“量子トンネル効果”であるとされています。
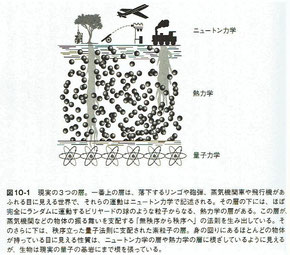
このイメージ図は前回のブログ “生物と量子力学1” でご紹介したものです。一層目の「ニュートン力学」、二層目の「熱力学」について説明していますので、これらについて確認されたい場合はこちらを参照ください。
画像出展:「量子力学で生命の謎を解く」
量子論の二つの重要事項
まず量子論を理解するためには二つの重要事項があるとされています。いずれもニュートン力学では考えられない奇怪な量子の振る舞いです。
その一つは「波と粒子の二面性」をもっているということです。
そして、もう一つが「状態の共存(重ね合わせ)」と言われるものです。
“「光合成は量子コンピューティング」:複数箇所に同時存在”という記事の中に「状態の共存(重ね合わせ)」を分かりやすい例を使って説明されている個所がありましたので、そちらをご紹介します。
『家へ自動車で帰るにあたって3つのルートがあるというものだ。どのルートが速いか遅いかはわからない。しかし量子的なメカニズムでは、これらの3つのルートを同時に取ることができる。到着するまで、自分がどこにいるかを特定しないので、常に最も速いルートを選ぶことになる。』
量子トンネル効果について
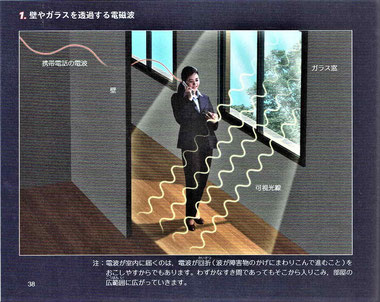
『電磁波は、障害物を透過する性質があります。たとえば可視光線は、ガラスにぶつかると、一部は透過します。また、携帯などの電波が室内に届くのは、電波が壁などを幾分透過するというのが理由の一つです。
電子も波の性質をもつので、同じようなことがおこります。電子も本来なら通り抜けることができないはずの“壁”を、すり抜けることができるのです。これを、「トンネル効果」とよんでいます。』
画像出展:「13歳からの量子論のきほん」
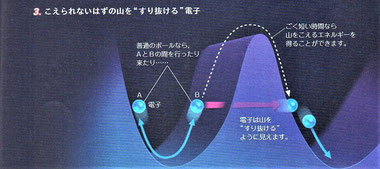
3.は「こえられないはずの山を“すり抜ける”電子」と書かれています。また、図中にその仕組みの説明書きがありますが、ネット上に同様な絵を使って簡潔に説明されているサイトがありましたので、そちらもご紹介します。
画像出展:「13歳からの量子論のきほん」

『エネルギーと時間の不確定性関係によると、電子はごく短時間であれば、図のような山をこえるだけのエネルギーを得て、山の反対側に行くことが可能です。これを外部からみると電子がいつのまにか山をすり抜けるように見え、トンネル効果と呼ばれています。私たちが日常使っている電子機器の半導体回路を流れる電流は、トンネル効果を無視することができません。応用例には、走査型トンネル顕微鏡、フラッシュメモリ、エサキダイオードなど多数あります。』 画像出展:「大阪大学工学部自然科学学科」
少し話が混沌としてきましたので整理したいと思います。お伝えしたいポイントは以下の4つです。
●酵素は生命のエンジンであり、「代謝」というプロセスを加速している。
●コラーゲナーゼは6800万年守られた恐竜の軟組織をたった30分で分解してしまった。
●呼吸酵素は考えられない長距離移動を、量子現象の“量子トンネル効果”によって実現させた。
●”量子トンネル効果”は”量子コヒーレンス”な環境が必須となる。
量子現象の“トンネル効果”を得るためにはもう一つ、極めて大きな課題があります。それは“量子コヒーレンス”という難題です。コヒーレンスとは「同調」という意味ですが、一方、この「同調」が崩れてしまった状態のことを“デコヒーレンス”と呼んでいます。
このコヒーレンス・デコヒーレンスをとばして話を進めることはできせんので、前後してしまいましたが本書に書かれているの“●量子トンネル効果”をご紹介します。問題の“量子コヒーレンス”に関わる部分は後半に出てきます。
“●量子トンネル効果”
『第1章で説明したように、量子トンネル効果とは、音が壁を通り抜けるのと同じように、乗り越えられそうにない障壁を粒子が簡単にすり抜けてしまうという奇妙な量子プロセスである。1926年にドイツ人物理学者のフリードリヒ・フントがはじめて発見し、そのすぐあとにジョージ・ガモフ、ロナルド・ガー二―、エドワード・コンドンが、量子力学の新たな数学に基づいてこの概念を使うことで、放射性崩壊の現象を見事に説明した。量子トンネル効果は原子核物理学の中心テーマとなったが、のちに材料科学や化学といったもっと幅広い分野に通用する現象と認められるようになった。前に話したように、地球上の生命にとって量子トンネル効果は欠かせない。太陽の内部で水素がヘリウムへ変換する第一段階として、正の電荷を持った二個の水素原子核が融合し、それによって太陽は膨大なエネルギーを放出するのだ。
量子トンネル効果については理解するには、粒子が障壁の一方の側から反対側へ、常識では不可能なはずの方法ですり抜けるための手段と考えるといい。ここでいう「障壁」とは、十分なエネルギーがないと物理的に通過できない空間領域のことで、SFに登場するフォースフィールド[目に見えないバリア]だとでも考えておけばいい。その領域は、二つの電気伝導体を隔て薄い絶縁体でもいいし、または、呼吸鎖に含まれる二個の酵素のあいだの隙間のように単なる空っぽの空間でもいい。また前に話したように、化学反応を遅くするエネルギーの山でもいい。
例として、低い山へ向かってボールを蹴り上げたとしよう。ボールが頂上にたどり着いて反対側へ転がり落ちるには、十分な強さで蹴らなければならない。斜面を登るにつれて徐々に減速し、十分なエネルギーがなければ(十分に強く蹴らなければ)、途中で止まって再びこちらへ転がり落ちてくる。
古典的なニュートン力学によれば、ボールがこの障壁を通過するには、エネルギーの山を乗り越えるのに十分なエネルギーを持っていなければならない。しかし、もしこのボールがたとえば電子で、山が反発力によるエネルギー障壁だったとしたら、電子は波動として、もっと効率の良い別の方法で障壁をすり抜ける確率が少しだけある。これが量子トンネル効果だ。
量子力学の重要な特徴として、軽い粒子ほど容易にトンネルできる。このプロセスが素粒子の世界の至るところで起きるものだとしたら、トンネル効果がもっともよく見られるのは当然きわめて軽い素粒子である電子だということになる。
金属に電場をかけると電子が飛び出してくる、電解放出と呼ばれる現象は、1920年代後半にトンネル効果として説明された。ウランなど一部の原子核がときどき粒子を吐き出す、放射性崩壊の現象がどのようにして起きるのかも、量子トンネル効果で説明された。これが、原子核物理学の問題に量子力学を応用した初の例となった。化学では、電子や陽子(水素原子核)、さらにはもっと重い原子の量子トンネル効果についても詳しく解明されている。
量子トンネル効果はその重要な特徴として、ほかの多くの量子現象と同じく、物質粒子が広がった波動のような性質を持っているために起きる。しかし、膨大な数の粒子からなる物体がトンネルするには、すべての構成粒子の波動的性質が山や谷を一致させて歩調を合わせ、コヒーレントと呼ばれる状態、すなわち「同調」した状態を保っていなければならない。

「同調(コヒーレント)」という言葉から頭に浮かんだのが、「日体大の集団行動」です。
画像出展:「grapeさま:“【圧巻】日体大の美しすぎる集団行動!なんでぶつからないの!?”」
逆に、多数の量子波がすべてあっという間に歩調を乱して、全体のコヒーレントな振る舞いが消し去られ、物体が量子トンネル効果を起こす能力を失ってしまうプロセスを、デコヒーレンスという。粒子が量子トンネル効果を起こすには、障壁をすり抜けるためには波動の状態を保っていなければならない。そのために、フットボールのような大きい物体は量子トンネル効果を起こさない。何兆個という原子からできており、調和したコヒーレントな波動として振る舞うことができないからだ。
量子の基準から見れば細胞も大きい物体なので、一見したところでは、原子や分子がほぼでたらめに動き回っている温かく湿った細胞のなかに量子トンネル効果が見つかるとは思えない。しかし先ほど説明したように、酵素の内部は違っており、粒子は無秩序に騒いではおらず、一糸乱れぬダンスを踊っている。そこで、このダンスが生命にどのような違いをもたらすのか、それを探っていくことにしよう。』
上記文章の最後に書かれた「酵素の内部は違っており、粒子は無秩序に騒いではおらず、一糸乱れぬダンスを踊っている。」について、どこで説明されているのか確認しました。正直、あまり自信がないのですが、次の文章(“●遷移状態理論ですべて説明できるのか?”より)のことだと思います。
『もう一つの謎が、酵素自体の構造がさまざまな形で変化すると酵素の活性がどのように影響を受けるかだ。たとえば、コラーゲナーゼはあらゆる酵素と同じく、活性部位のなかにある顎や歯と、それを支えるたんぱく質の台座からできている。顎や歯を作っているアミノ酸が置き換わると酵素の能力は大きな影響を受けると予想され、実際にそのとおりになる。しかし驚くことに、活性部位から遠く離れた位置のアミノ酸が置き換わっても酵素の能力は劇的な影響を受けることが分かっている。何の影響もないはずの形で酵素の構造が変わっても、なぜそのような劇的な違いが生じるのかは、標準的な遷移状態理論の枠組みではいまだに謎のままである。しかし実は、量子力学を考え合わせると理屈が通るようになるのだ。この発見については、本書の最後の章で再び取り上げよう。』
この最後の章とは「第10章 量子生物学―嵐の緑の生命」になりますが、この中で“一糸乱れるダンスを踊っている”について述べられています。それは最初に出てくる“●素晴らしいグッド・ヴァイブレーション(バップ、バップ)”に書かれています。
『この分野におけるきわめて刺激的な新しい成果のなかには、光合成のさらなる研究によって得られたものもある。第4章[量子のうなり]で話したように、微生物や植物の葉には、クロロフィル色素分子の森に覆われた葉緑体がぎっしり詰まっている。光合成の第一段階では、光子が一個の色素分子に捕らえられ、それが振動励起子[レイキシ:結晶内を自由に移動する中性の粒子]に変換されてクロロフィルの森の中を素早く移動し、反応中心にたどり着く。また、そのエネルギー輸送プロセスには、量子のうなり[量子コヒーレント状態の実験で600フェムト秒にわたって信号が上下に振動するということ]という、コヒーレント状態が存在する証拠が見つかっており、このプロセスの効率がほぼ100パーセントであるのは、励起子が量子ウォークによって反応中心にたどり着くからだという証拠が得られている。しかし、分子ノイズに満ちた細胞という環境のなかを移動する励起子が、どのようにしてコヒーレントな波動的振る舞いを維持しているかは、最近まで謎だった。いまや明らかとなったその答えによれば、生命系はどうやら分子振動を抑えようとしているのではなく、逆にそのビートに合わせてダンスをしているらしいのだ。』
ノイズ(分子振動)を利用して量子コヒーレンスを維持する
第10章の“●古典的な嵐の縁に立つ生命”の中に、量子コヒーレンスを維持する方法が説明されています。
『シュレーディンガーが数十年前に示した生命の本質に関する疑問の答えは出てくるのだろうか? すでに説明したようにシュレーディンガーは、きわめて秩序立った生命体の身体全体から、熱力学の嵐の海を経て量子の基岩へ至るまで、すべてを貫く秩序に支配された系が生命であると見抜いた(図10-1)
そして重要な点として、1930年代にパスクアル・ヨルダンが予測したとおり、量子レベルの出来事がマクロな世界に影響をおよぼすことができるよう、この生命のダイナミクスは微妙なバランスを取っている。このようにマクロな世界が量子の世界に大きく影響を受けるという性質は、生命特有のものである。そのおかげで生命はトンネル効果やコヒーレンスやもつれ[重ね合わせ]といった量子レベルの現象を利用することで、独特の存在となっているのだ。
しかし重要な条件として、このように量子の世界を利用するには、デコヒーレンスを食い止められなければならない。そうでないとその系は量子的性格を失い、「無秩序から秩序へ」の法則に従う完全に古典的な、または熱力学的な振る舞いをするようになってしまう。科学者はこれまで、量子反応を邪魔をする「ノイズ」を遮断することで、デコヒーレンスを回避してきた。しかしこの章で分かったように、どうやら生命はそれとはまったく違う戦略を取っているらしい。コヒーレント状態をノイズに邪魔されるのではなく、逆にノイズを利用して量子の世界とのつながりを維持しているのだ。』

『生命は量子の世界と古典的な世界との縁を航海している。細胞は細長いキールを量子の層までまっすぐに突き刺した船のようなもので、そのためにトンネル効果や量子もつれなどの現象を利用することで生きつづけることができる。量子の世界とのこの結びつきを積極的に維持するには、量子コヒーレンスを壊すのではなく維持しなければならない。』
画像出展:「量子力学で生命の謎を解く」
付記:ほぼ妄想
ボート競技の“エイト”も「同調(コヒーレンス)」が印象的なスポーツです。写真では背を向け先頭にいる選手が舵手です。
三層目の量子力学の層にも、隠された「舵手」のような全体の動きを調整するメカニズムがあり、それが量子スピンや分子振動といったダイナミックなエネルギーをうまく利用してバランスを取り、コヒーレンスを維持しているかもしれません。アメリカ人が難なく英語(母国語)を操るように、量子の世界では当たり前のことなのかもしれません。
現在の量子コンピュータはコヒーレンスを維持するために、プロセッサをマイナス273℃で冷やしているそうです。このような自由を奪う方法ではなく、上記のような「舵手」が現れれば量子コンピュータはもっともっと魅力的で現実的なものになると思います。

世界が注目する商用量子コンピュータメーカー「D-Wave」とは?
『D-Wave Systemsが公開している情報によれば、量子コンピュータ「D-Wave」シリーズの見た目は、大きな黒く四角い箱型だ。もちろんただの「黒い箱」ではない。日常的にわれわれが使っているコンピュータとは違い、筐体の内部は「大きな冷蔵庫」のようになっている。量子コンピューティングのカギとなる量子状態をプロセッサに作り出すため、極低温に冷やす仕組みを備えている。プロセッサは約マイナス273℃にも冷えており、絶対零度をわずか0.015℃だけ上回る温度で駆動するという。』 画像出展:「MUFG Innovation Hub」
生物と量子力学1(光化学コンパス)
量子力学はマクロの世界の力学でもありますが、その真骨頂は、原子よりも小さい電子などのミクロの世界を正しくはかる唯一の理論であるということです。半導体などの様々なテクノロジーは量子力学の上に立脚しています。さらに生物においてもミクロの世界の遺伝子などは量子の世界に踏み入れなければなりません。
しかしながら、「では、目に見える生き物にとっての量子力学とは何なのか、どこに活かされているのか?」という疑問は残ったままでした。
今回の『量子力学で生命の謎を解く』はそのようなモヤモヤから見つけた本です。これも私にとっては難攻不落の果てしなく難解な内容なのですが、興味、関心がまさったというところです。とは言うものの、難しさは想像以上でブログに残したい気持ちは強くあるものの、何を書けばいいのか、何が書けるのか、早々に行き詰ってしまいました。
そして迷った末に、後先を考えず興味のある3つを取り上げることにしました。
1.光化学コンパス(生き物の中の量子力学)
2.酵素(「生命の中核」とされている酵素)
3.意識(意識と量子力学)
なお、順番は逆になりますが、最後に目次をご紹介しています。
続いて、二人の著者をご紹介します。
1.ジム・アル=カリーリ
英国サリー大学の理論物理学教授。原子核物理学と並行して量子生物学の研究をおこなっている。王立協会のマイケル・ファデラー賞や大英帝国勲章などを受賞。

こちらはDigitalCastに掲載されている”量子生物学は生命の最大の謎を解明する科?”と題するもので、ジム・アル=カリーリ先生が量子生物学の紹介をされています。英語の動画ですが字幕がついています。また、下記はその概要です。
『コマドリはどうやって南方へと渡っていくのでしょうか?その答えは、あなたの想像以上に奇妙かもしれません。量子力学が関わっているのです。ジム・アルカリリは、とても新しくかつ奇妙な分野である量子生物学に関する話をまとめました。アインシュタインが「不気味な遠隔作用」と呼んだ量子力学的作用が渡り鳥の飛行を助けたり、様々な量子効果が、生物の起源そのものについても説明し得るのではないかと語ります。』
2.ジョンジョー・マクファデン
英国サリー大学の分子生物学教授。遺伝病や感染症の研究を経て、現在は病原微生物の遺伝の研究とともに、量子生物学やシステム生物学の研究をおこなっている。

クリック頂くとジョンジョー・マクファデン先生のホームページ”Johnjoe Mcfadden”に移動します。英語ですがサリー大学での33分の講義もあります。私には二重苦のため無意味なのですが、少しのぞいて見たところスライドを使ってご説明されていました。
本書、『量子力学で生命の謎を解く』の「第1章 はしがき」の中に量子力学の特徴を説明している個所がありますので、まずはそれらをご紹介したいと思います。
●見えない不気味な現実
『現代の科学者に、科学全体のなかでもっとも成功し、もっとも幅広い影響をもたらし、もっとも重要な理論は何だと思うかを世論調査したとすると、その答えは、回答者が物理科学の研究をしているか生命科学の研究をしているかによって違ってくるだろう。ほとんどの生物学者は、自然選択に基づくダーウィンの進化論を、これまでに考え出されたなかでもっとも深遠な理論とみなす。しかし物理学者は、量子力学が第一位に来るはずだと主張するだろう。物理学と化学の大部分の基礎であり、宇宙全体の世界のしくみに関する現代の知識の大部分は崩れてしまうのだ。
「量子力学」という言葉はほぼ誰でも聞いたことがあるだろうが、この学問分野は不可解で難しく、ごく一握りの人間しか理解できないというイメージが大衆文化に植え付けられている。だが実は、20世紀前半以降、量子力学は我々の生活の一部をなしている。この学問は1920年代半ばに、きわめて小さい世界(いわゆるミクロの世界)、つまり、身の回りのあらゆるものを形作っている原子の振る舞いや、その原子を形作っているさらに微小な粒子の性質を説明するための数学理論として編み出された。量子力学はたとえば電子がどのような法則に従うかや、原子のなかで電子がどのように分布するかを記述することで、化学、物質科学、さらにはエレクトロニクス全体の基礎をなしている。確かに奇妙ではあるが、その数学的な法則は過去半世紀に実現したほとんどの技術的進歩の根幹をなしている。物質のなかを電子がどのように移動するかを量子力学で説明できなかったら、現代のエレクトロニクスの基礎をなす半導体の振る舞いは理解できなかっただろうし、半導体を理解できなければ、シリコンのトランジスタも、のちのマイクロチップや現代のコンピュータも開発できなかっただろう。例を挙げればきりがない。量子力学によって知識が発展しなかったら、レーザーは存在しなかっただろうし、ゆえにCDもDVDもブルーレイプレイヤーもなかっただろう。量子力学がなかったら、スマートフォンもGPSもMRIもなかっただろう。概算によれば、先進国の国内総生産の三分の一以上は、量子世界の力学の知識がなければ存在しなかったはずの応用技術に依存しているのだ。
それでもまだ始まりにすぎない。ほぼ間違いなく我々の生きているうちに到来する、量子が開く未来では、レーザー駆動の核融合によってほぼ無尽蔵に電力が得られ、人工分子マシンによって工学や生化学や医学の分野でさまざまなことが可能になり、量子コンピュータによって人工知能が実現、テレポーテーションというSFのような技術が情報伝達に日常的に使われるかもしれない。20世紀の量子革命は、21世紀になってさらに勢いを増し、我々の生活を想像もできないような形に変えるだろう。
しかし、量子力学とはいったい何だろうか? この疑問は本書を通じて探っていくことになる。手始めにここでは、我々の生活の礎となっている見えない不気味な現実の実例をいくつか紹介しよう。』
●量子力学がありふれたものだとしたら、なぜ量子生物学に注目すべきなのか?
『~ 物理実験室の外ではいったい何が、同じように量子的振る舞いを壊しているのだろうか?
その答えは、大きい(マクロな)物体のなかで粒子がどのように並び、どのように動いているかに関係している。原子や分子は、生きていない固体のなかではランダムに散らばって不規則に振動していることが多い。液体や気体のなかではさらに、熱のためにたえずランダムな要因によって、粒子の不安定な量子的性質はあっという間に消えてしまう。物体を構成するすべての量子的粒子の作用が組み合わさって、それぞれ互いが互いを「量子測定」する。それによって、我々の身の周りの世界は正常に見えているのだ。量子の不気味さを観察するには、普段と違う場所(太陽の内部)に行くか、ミクロの世界を深くまでのぞき込むように仕向けるしかない(MRI装置に入ってあなたの体内にある水素原子核のスピンを整列させるように。しかし磁石のスイッチが切られると、原子核のスピンの向きは再びランダムになり、量子の干渉は打ち消し合って消えてしまう)。このような分子のランダムな振る舞いのおかげで、我々はほとんどの場合、量子力学を知らなくてもやっていける。周りに見える生きていない物体のなかでは、ランダムな方向を向いてつねに動き回っている分子によって、量子の不気味さはすべて消し去られてしまっているのだ。』
なお、「量子の不気味さ」については、「量子的奇怪さ」というブログ“量子論2”の中でご紹介した個所が近い内容になっています。ご参考にして頂ければと思います。
また、今回の「疑問」(生き物にとっての量子力学とは?)と重なるような内容も本書にはありますので、こちらもご紹介します。
●量子力学がありふれたものだとしたら、なぜ量子生物学に注目すべきなのか?
『~ 生物学は詰まるところ応用化学の一つで、化学は応用物理学の一つだ。だから、我々もほかの生き物も含めすべての物体は、おおもとまでさかのぼれば単なる物理なのではないか? 多くの科学者は、深いレベルでは生物にも量子力学が関係しているはずだという考え方を受け入れながらも、その役割はわざわざ取り立てるほどのものではないと言い張っている。どういうことかというと、原子の振る舞いは量子力学の法則に支配されていて、生物には突き詰めれば原子の相互作用が関係しているのだから、量子の世界の法則が生物の体内の微小スケールでも作用しているのは確かに間違いないが、それはその微小スケールだけでの話であって、生命にとって重要な大きなスケールのプロセスにはほとんど、あるいはまったく影響をおよぼさないということだ。
もちろんそうした意見も、少なくともある程度は正しい。DNAや酵素などの生体分子は陽子や電子といった素粒子からできていて、素粒子の相互作用は量子力学に支配されていることになる。車やトースターの働きが突き詰めると量子力学に支配されているのと同じように、あなたが歩き、話し、食べ、寝て、さらに考えるしくみも、究極としては電子や陽子などの素粒子を支配する量子力学的な力によって決まっているのだ。しかしあなたがそれを知る必要はほとんどない。自動車整備工が大学で量子力学の講義に出る必要はないし、ほとんどの生物学科のカリキュラムでも、量子トンネル効果や量子のもつれや量子の重ね合わせにはまったく触れられない。根本的なレベルで見れば、この世界は馴染みのものとまったく異なる法則に従って動いているのだが、そのことを知らなくても、ほとんどの人は問題なく暮らしていける。微小レベルで起きる不気味な量子現象は、我々が日々目にしたり使ったりしている車やトースターのような大きい物体には、ふつうは何の作用ももたらさないのだ。
なぜだろうか? フットボールが壁をすり抜けることもなければ、人間どうしが不気味な結びつきを持つこともないし(いんちきなテレパシーは別だが)、残念なことにあなたが同時にオフィスと自宅の両方にいることもできない。それでも、フットボールや人体のなかに存在する素粒子はこうした芸当をすべてできる。我々が見ている世界と、物理学者が知っている、その水面下に存在している世界とのあいだには、なぜこのような境界線、いわば断層が走っているのだろうか?』
上記の「物理学者が知っている、その水面下に存在している世界」に関しては、おそらくこのことだろうという”イメージ図(図10-1)”が10章にありましたので、本書の文章と合わせてそちらもご紹介します。

『~ ほとんどの生物は比較的大きい物体である。その全体の動きは、列車やフットボールや砲弾と同じくニュートンの法則にかなりよく従っている。大砲から撃ち出された人間は砲弾とほぼ同じ軌道を描く。もっと深いレベルに目を向けると、組織や細胞の生理も熱力学の法則でよく説明することが。肺の膨張と収縮は、風船の膨張と収縮とさほど違わない。そのため一見したところ、コマドリや魚や恐竜、リンゴの木やチョウや我々の身体のなかでも、ほかの古典的な物体の内部と同じく、量子的な振る舞いは消し去られていると考えたくなるし、ほとんどの科学者もそう決めつけていたはずだ。しかしここまで見てきたように、生命に関しては必ずしもそうではない。その根をたどっていくと、ニュートン的な表層から荒れ狂う熱力学の層を貫いて量子の基岩にまで達しており、それによって生命は、コヒーレンスや重ね合わせ、トンネル効果やもつれ状態を利用することができる。 ~』
一番上の層とされる“ニュートン力学”とは、アイザック・ニュートンが、運動の法則を基礎として構築した力学の体系です。その運動法則は以下の3つになります。
ニュートンの運動法則
第一法則(慣性の法則)
外的な力が加わらない限り、物体は静止或いは等速直線運動を続ける。
第二法則(運動法則)
物体の加速度は、加えた力に比例し、その質量に反比例する。
第三法則(作用・反作用の法則)
物体が互いに力を及ぼし合うときには、同一直線上で互いに逆向き・同一の大きさの力が働く。
2番目の層に明記されている“熱力学”ですが、全く分からなかったのでしらべてみました。
以下は“コトバンク”にある“ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典”の「熱力学」と「統計熱力学」に関する解説です。※クリック頂くと”コトバンク”に移動します。
■熱力学
熱と仕事は交換しうるという原理の上に立って、化学変化に伴うエネルギー変化の様子を調べ、反応の進む方向や平衡条件などについて論じる学問。その基本原理は経験則に基づいた熱力学第一法則、熱力学第二法則、熱力学第三法則から成り立っている。熱力学にはまた分子論的立場から論じる別の取扱い法がある (統計熱力学 ) 。
■統計力学
統計物理学ともいう。物質を構成する多数の粒子の運動に力学法則および電磁法則と確率論とを適用し、物質の巨視的な性質を統計平均的な法則によって論じる物理学の分野。これにより巨視的世界と微視的世界とが結ばれる。気体の巨視的性質を気体分子の運動によって説明した分子運動論に始り、J.C.マクスウェル、L.ボルツマンが分子の速度分布、エネルギー分布を導入、J.ギブズが統計集団の考えを導入して熱平衡状態の統計力学を完成し、熱力学の微視的な基礎づけを与えた。これは統計熱力学とも呼ばれ,比熱,熱放射,相転移,誘電率,磁性など静的な性質を扱うものである。
最後の3層目は”量子力学”です。”イメージ図(図10-1)”内の説明書きの最後に書かれた、生物は現実の量子の基岩にまで根を張っている』これが知りたかったことです。本書にはその事例がいくつも出ていますが、第1章の書き出しは次の文章で始まります。
『年明け、ヨーロッパに冬の寒波が訪れ、夕暮れの空気は身を刺すような冷たさだ。若いコマドリの心の奥深くに潜んでいた、それまではぼんやりとした目的意識と決意が、徐々に強まってくる。
この鳥はこの数週間、普段の量よりはるかに大量の昆虫やクモや毛虫や果実をむさぼり食い、いまでは体重は、去年の八月に我が子が巣立ちしたときの二倍近くになっている。その体重の追加分のほとんどは脂肪の蓄えで、まもなく出発する困難な旅路の燃料として必要になる。』
そして、本書を締めくくる最後の「エピローグ 量子生命」の中でヨーロッパコマドリが再登場します。ここには量子力学との関わりも具体的に書かれています。
ただし、その後の文章で補足されているように、「すべての性質が量子力学的であるとは断言することはできない」と書き添えられています。
『第1章で出会ったヨーロッパコマドリは、地中海の日の光のもとで無事冬を越し、チェニジア・カルタゴのまばらな森や古代の遺跡のあいだを飛び回りながら、ハエや甲虫、毛虫や種子で身体を太らせている。それらはすべて、我々が植物や微生物と呼ぶ、量子のパワーを得た光合成マシンによって空気と光から紡ぎ出された生物有機体でできている。しかしいまや真昼の空高くに太陽が昇り、その強烈な熱によって、森を走る浅い小川は干上がっている。森は乾燥し、ヨーロッパコマドリにとっては過酷な場所になろうとしている。旅立つ頃合いだ。
夕方、我らが小鳥は飛び上がってスギの高い枝に止まる。何か月も前と同様に入念に羽づくろいをしながら、同じく長旅への欲求にかき立てられたほかのコマドリたちの鳴き声に耳を傾ける。太陽の最後の光が地平線に沈むと、コマドリはくちばしを北に向け、翼を広げて夕暮れの空へ飛び立つ。
コマドリは北アフリカの海岸目指して飛び、そのまま大西洋を渡る。六か月前とほぼ同じルートだが、今度は逆方向へ、再び量子のもつれ状態の針を備えたコンパスに導かれて進む。一回一回の羽ばたきは筋肉線維の収縮によって駆動され、そのエネルギーは呼吸酵素の中で電子と陽子が量子トンネル効果を起こすことで供給される。何時間もかかってコマドリはスペインの海岸へたどり着き、アンダルシアの森に覆われた谷に舞い降りて、ヤナギやカエデ、ニレやハンノキ、果樹や、キョウチクトウの花を咲かせる低木といった、豊かな植物に囲まれて身を休める。いずれの木も、量子のパワーを得た光合成の産物だ。すると、匂い分子が漂ってきてコマドリの鼻孔に入り、嗅覚受容体に捕えられる。量子トンネル効果によって神経信号が発せられ、それが量子コヒーレント状態にあるイオンチャネルを介して脳に伝えられる。コマドリは近くに柑橘系の花が咲いていることを知り、そこに集まって花粉を媒介するハチなどの昆虫を食べて、旅の次なる段階の糧を得る。
何日も飛んだ末にコマドリはついに、何か月も前に旅立ったスカンジナビアのトウヒの森へ戻ってくる。最初にやるべきはつがいの相手を探すこと。オスのコマドリは数日前に到着している。ほとんどのオスは巣作りに適した場所を見つけ、さえずりでメスにアピールしている。我らがコマドリはとくに美しい歌声のオスに惹かれ、求愛の儀式の一環として、オスが集めた幼虫を味わう。つかの間の交尾によってオスの精子とメスの卵細胞が合体し、オスメスそれぞれの形、構造、生化学、生理、解剖学的特徴、さらにはさえずりをコードした量子ベースの遺伝情報が、新たな世代のコマドリにほぼ完璧にコピーされる。量子トンネル効果によって生じたいくつかのエラーは、この種の将来の進化のための原材料となる。』
『もちろんここまでの章で強調してきたように、いま挙げたすべての性質が量子力学的であるとはいまだ断言することはできない。しかし、コマドリやカクレクマノミ、南極の氷の下で生き延びる細菌、ジュラ紀の森を闊歩してきた恐竜、オオカバマダラやショウジョウバエ、あるいは植物や微生物の持つ独特の素晴らしい性質のほとんどは、間違いなく、彼らが我々と同じく量子の世界に根を張っているという事実によって授けられている。いまだ分かっていないことはあまりにも多いが、いかなる新たな研究分野でも、分かっていない事柄にこそ美しさがある。アイザック・ニュートンもこう言っている。
世間が私をどう見ているかは分からないが、私自身は、少年のように海岸で遊び、ふつうよりすべすべした小石やきれいな貝殻を時折見つけては喜んでいるにすぎないように思える。その一方で、目の前には完全に未知なる真理の大海原が広がっている。』
ヨーロッパコマドリの光化学コンパスのメカニズムに関しては、第6章の、“●鳥のコンパス”、“●量子スピンと不気味な作用”、“●ラジカルな方向感覚”の3つに書かれています。内容は極めて専門的であり、26ページに亘っています。しかしながら、次のような記述が加えられています。
『~ しかし最近、この結果の意義に対しては疑問が投げかけられている。オルデンブルク大学のヘンリク・モウリストンの研究グループは、さまざまな電子機器から発生する人工的な電磁波のノイズが、大学のキャンパスにある遮断していない木造の鳥小屋の壁からなかに入り、鳥の磁器コンパスを乱していることを発見した。しかし、都市の電磁波ノイズを約99パーセント遮断する、アルミニウムで覆った小屋に鳥を入れると、方向感覚が回復した。この結果から考えると、狭い範囲の振動数の電磁波だけが鳥のコンパスを乱すのではないらしい。
このように、鳥のコンパスにはまだいくつも謎が残されている。たとえば、コマドリのコンパスはなぜ振動磁場にあれほど敏感なのか? あるいは、遊離基[フリーラジカル:ペアになっていない電子を抱え、非常に反応しやすくなっている原子や分子]はどのようにして長時間にわたってもつれ状態を維持し、生物学的な違いを生じさせるのか? ~』
このように確定には至っていない状況から第6章には触れず、その代わり、日経サイエンスのバックナンバーと、ネット上にあった資料(2016年「化学と教育 64巻7号“渡り鳥の光学コンパスと分光測定”」)、同じくネット上にあったニューズウィーク日本版の記事(2018年4月5日:“渡り鳥をナビゲートする「体内コンパス」の正体が明らかに”)をご紹介したいと思います。
2011年10月号 日経サイエンス 特集“シュレーディンガーの鳥 生命の中の量子世界”
シュレーディンガーの鳥
『ヨーロッパコマドリは小さくて賢い鳥だ。毎年、冬になる前にスカンジナビアからアフリカの赤道付近にやってきて、春になって北の気候が良くなると再び帰っていく。コマドリはこの1万3000㎞におよぶ往復旅行を、ごく自然に易々とやってのける。
渡り鳥など一部の動物は体内に方位磁石を持っているのではとの疑問は、かねてあった。1970年代、ドイツのフランクフルト大学の研究者、ウィルシュコ夫妻(Wolfgang and Roswitha Wiltschko)はアフリカに渡ったコマドリを捕らえ、人工的な磁場の中に置く実験を行った。奇妙なことに、コマドリは磁場の方向が逆転しても気づかなかった。つまりコマドリにどちらが来たか南かを聞いてもわからないのだ。だが一方でコマドリは磁場の俯角、すなわち磁力線が地表となす角度には反応した。彼らが方向を知るのに使っていたのは、俯角の情報だけだった。面白いことにコマドリに目隠しをすると、磁場にまったく反応を示さなくなった。つまり、コマドリは何らかの方法で、目を使って磁場を検知しているらしい。
2000年、当時南フロリダ大学にいた物理学者のリッツ(Thorsten Ritz)は、渡り鳥に夢中だった。彼の同僚は、量子もつれ[遠く離れた粒子があたかも1つの物体のように連動する]がカギではないかと指摘した。彼らは、イリノイ大学のシュルテン(Klaus Schulten)が以前に実施した研究に基づいて、鳥の目にはある種の分子があり、その中に2つの電子があって、トータルのスピンがゼロになるような量子もつれになっているという仮説を考えた。古典力学では、そのような状況はまったく起こり得ない。
この分子が可視光線を吸収すると、2つの電子はエネルギーを得て量子もつれが崩れ、地磁気を含む外部の影響を感じるようになる。磁場の向きに俯角があると2つの電子に異なる影響を与え、その違いのために分子の化学反応が起きる。目の中で起きるこうした化学反応により神経に伝わる信号が変化し、それによって、最終的には鳥の脳内に磁場の形が描かれる。
リッツが提示したメカニズムには状況証拠しかないが、英オックスフォード大学のロジャース(Christopher T. Rogers)と前田公憲は、リッツが提唱したものとよく似た分子の挙動を、生きた動物の体内とは逆に実験室で実現し、このような分子が、量子もつれになった電子のために実際に磁場に感受性を持つことを示した。私たちの計算によれば、鳥の目の中の量子効果は約100マイクロ秒にわたって持続する。
この時間は、この種の話をする時には十分に長いと言える。人間が作った電子スピンの系では50マイクロ秒が最高記録だ。自然界の系がどうやってこのような長時間、量子効果を維持しているのかはまだわからないが、その機構が解明できれば、量子コンピュータがデコヒーレンス[量子系の干渉が環境との相互作用によって失われる現象]によって壊れるのを防ぐ方法の開発につながるだろう。
量子もつれが働いていると思われる生物の中の系がもうひとつある。植物が太陽光を化学エネルギーに変えるプロセス、光合成だ。植物に光が当たると、細胞内の電子が高いエネルギーを得る。そうやって生じた電子のエネルギーは、すべて同じ場所、このエネルギーによって一連の化学反応を起こし、植物にエネルギーを供給する「反応中心」に到達する必要がある。古典力学ではなぜほぼ100%の高い確率で反応中心に到達するのか説明できない ~』

タイトルをクリック頂くと、2枚もののPDF資料がダウンロードされます。図の1~4は資料の2ページ目にあります。
渡り鳥の光学コンパスと分光測定
『渡り鳥は非常に長い距離を、想像を超えた正確さで迷わずに移動する。そのためにどのような情報を用いているのかということは、次第に理解されつつある。太陽、星などの天文情報、に加えて、磁気が非常に重要な情報を与えているとされている。動物の磁気感受は渡り鳥だけではない、近年の研究では蝶やショウジョウバエなどの昆虫や、イモリ、モグラ、そしてネズミも磁場の情報をその行動に役立てているようである。
しかし、このように多様な動物が磁場を感じることは徐々に知られつつあるが、そのメカニズムはさほど明らかでない。1つの仮説は動物の体内にあるマグネタイトと呼ばれる非常に小さな磁石が、方位磁針と同じように働いているというものである。動物の体内では、多くのマグネタイトが見つかっているが、そのマグネタイトがどのように磁場の向きなどの情報を脳に伝達しているのか? ということはほとんど明らかにはなっていない。
一方で電子を用いたよりミクロな磁気センサーを渡り鳥などがもっているという説がある。多数の実験による状況証拠(図1など)として、磁気感受には光が必要とされ、光化学反応コンパスと呼ばれている。このモデルとしてリッツらは、興味深い仮説を提案した(図A)。鳥の網膜においてラジカル対を作り出す光受容タンパク質分子が規則正しく並び、光を吸収して電子移動反応を起こし、2つのラジカル、すなわちラジカル対を生成する。ラジカル対と地磁気の向きとによって、化学反応性が異なり、それが視覚に影響を与えるなら、網膜上の位置により結果として地磁気の影響を鳥が視覚のパターンとして‘視る’ことになる。
現在、動物の磁気を感じる最大候補分子としてクリプトクロムタンパク質が挙げられている。クリプトクロムはその機能が謎に満ちた動植物両方がもつ青色受容タンパク質で、近年では生物の概日リズムとの関連が指摘されている。クリプトクロムにおいて、そのフラビン補酵素(FAD)が青色光を吸収し、連続的に存在する3つのトリプトファン残基を通じて電子移動反応を起こし、距離の離れた2つのラジカル分子(ラジカル対)を生成する(図B)。
ラジカルは孤立した電子を持っている。孤立した電子はそのスピンと呼ばれる自転により、まるで非常にミクロな磁石としてふるまう(図C)。この2つのスピンの相対配向への磁場の影響がその後の反応性を決定づける(図2~ 4)。このメカニズムには通常ミクロな物理現象を説明する「量子力学」が深くかかわっており、生物と量子力学とを結びつける存在として、大きな注目を集めつつある。』

2018年4月5日 ”渡り鳥をナビゲートする「体内コンパス」の正体が明らかに”
最後に目次をご紹介させて頂きます。
第1章 はしがき
●見えない不気味な現実
●量子生物学
●量子力学がありふれたものだとしたら、なぜ量子生物学に注目すべきなのか?
第2章 生命とは何か?
●「生命力」
●機械の勝利
●分子のビリヤード台
●無秩序な生命?
●生命の奥底をのぞき込む
●遺伝子
●生命の奇妙な笑い
●量子革命
●シュレーディンガーの波動関数
●初期の量子生物学者たち
●微小世界での秩序
●疎外
第3章 生命のエンジン
●酵素-生きているものと死んでいるものを分け隔てるもの
●我々にはなぜ酵素が必要で、おたまじゃくしはどうやって尾をなくすのか
●地形を変える
●激しい運動や振動
●遷移状態理論ですべて説明できるのか?
●電子をあちこちに動かす
●量子トンネル効果
●生物における電子の量子トンネル効果
●陽子をあちこちに動かす
●速度同位体効果
●これで量子生物学は確立するのか?
第4章 量子のうなり
●量子力学の中心的な謎
●量子測定
●光合成中心への航海
●量子のうなり
第5章 ニモの家を探せ
●匂い物質の物理的正体
●匂いの鍵を開ける
●量子の鼻で嗅ぎ分ける
●鼻の戦い
●匂いを嗅ぐ物理学者
第6章 チョウ、ショウジョウバエ、量子のコマドリ
●鳥のコンパス
●量子スピンと不気味な作用
●ラジカルな方向感覚
第7章 量子の遺伝子
●忠実性
●非忠実性
●キリン、マメ、ショウジョウバエ
●陽子によるコード
●量子ジャンプする遺伝子?
第8章 心
●意識はどれほど奇妙なのか?
●思考のメカニズム
●心はどうやって物体を動かすのか
●キュビットを使った計算
●微小管を使った計算?
●量子イオンチャンネル?
第9章 生命の起源
●ねばねばの問題
●ねばねばから細胞へ
●RNAワールド
●量子力学が手助けしてくれるのか?
●最初の自己複製体はどんなものだったのか?
第10章 量子生物学-嵐の縁の生命
●素晴らしいグッド・ヴァイブレーション(バップ、バップ)
●生命の原動力に関する考察
●古典的な嵐の縁に立つ生命
●量子生物学を利用して新たな生命技術を作り出すことはできるか?
●ボトムアップで生命を作り出す
●量子的原子細胞を作り出す
エピローグ (Life on the Edge)
注)目次に書かれた題名は“量子革命”でしたが、実際に本を開いてみるとエピローグの題名は“量子生命”になっていました。どちらが正しいのか分からないので( )内はLife on the Edgeという原書の題名を書いておきました。
量子論2
今回のブログで意識した点は、量子論の基本、奇怪さ、応用・貢献の4つです。引用させて頂いた本は次に2冊になります。
1.量子
量子は物理量の最小単位とされています。また、物理量は素粒子に由来するとされ、実数で表される連続量とするニュートン力学などの古典論とは区別されます。

こちらの絵と文章は文部科学省のサイトにあったものです。
『量子とは、粒子と波の性質をあわせ持った、とても小さな物質やエネルギーの単位のことです。物質を形作っている原子そのものや、原子を形作っているさらに小さな電子・中性子・陽子といったものが代表選手です。光を粒子としてみたときの光子やニュートリノやクォーク、ミュオンなどといった素粒子も量子に含まれます。
量子の世界は、原子や分子といったナノサイズ(1メートルの10億分の1)あるいはそれよりも小さな世界です。このような極めて小さな世界では、私たちの身の回りにある物理法則(ニュートン力学や電磁気学)は通用せず、「量子力学」というとても不思議な法則に従っています。』
2.量子論
デジタル大辞泉による“量子論”の解説は次の通りです。
『量子力学、およびそれにより体系化される理論の総称。プランクの量子仮説から量子力学の確立までを古典量子論または前期量子論という。物理学のほか化学・工学・生物学でも展開。古典論に対していう。』なお、「プランクの量子仮説」が物理学会に提出されたのは、1900年12月14日です。
“量子論”に関しては、「量子論を楽しむ」の”はじめに”の冒頭部分をご紹介させて頂きます。
『この本を手に取られた方のほとんどは、携帯電話やパソコンをお持ちに違いない。最近のエレクトロニクスの進歩はあまりにも速く、次から次へと性能が上がり、値段も安くなっている。その進歩は、そこに使われている半導体素子の進歩に大きくよっているが、半導体チップの中を支配している物理法則が「量子論」である。実際、半導体は量子論の結晶だとしばしば言われる。
地球が太陽の周囲を回る公転運動や、ロケット・飛行機・自動車などのマクロの物体の運動は、ニュートンが作った古典力学で計算し、結果の予言ができる。しかし分子や原子、素粒子のような小さな世界では、ニュートンの古典力学は使えないのである。これに対して量子論は、素粒子などのミクロの世界に適用される物理学の理論である。したがって、半導体の中で役立っているだけでなく、遺伝子やDNAの構造を決めているのも量子論だし、原子炉の中でエネルギーを発生させている核分裂反応や、太陽の中でエネルギーを生み出している核融合反応も量子論に従って起こっているのである。』
3.量子力学
デジタル大辞泉による“量子力学”の解説は次の通りです。
『素粒子・原子・分子などの微視的な世界の物理現象を扱う理論体系。物質のもつ波動性と粒子性、観測による測定値の不確定性などを基本とする。アインシュタインの光量子論、ボーアの原子構造論などを経て、ハイゼンベルクの行列力学とシュレーディンガーの波動力学とが統一されて、1925年ごろ確立。』
4.量子論の第一歩(プランクの量子仮説)
“2.量子論”の中にある“プランクの量子仮説”は、「量子の世界」の方に詳しい説明が載っていました。
『量子論発見の物語は、マックス・プランクによる黒体放射の法則の発見(1900年の記念すべき第一歩)で始まる。前期量子論の特色を一口でいうと、プランクの量子の考え(自然には不連続な要素があるというもの)を古典的なニュートン物理学の中にうまくはめ込ませようとする物理学者の側の試みを表していると言ってよい。黒体放射に関する論文で、マックス・プランクは、hと呼ばれる新しい定数を物理学に導入した。これは原始的過程に現われる不連続性の大きさの尺度である。プランクがこの仕事をやり遂げた1900年当時は、原子はその全エネルギーとしてどんな値でもとりうる(つまりエネルギーは連続変数だ)というのが物理学者たちの考えであった。これに対して、プランクの量子仮説はエネルギーのやりとりが量子化[古典力学で連続量と考えられていた物理量が、量子力学の量子条件に合わせて離散的な値として観測されること]されているというものであった。エネルギー量子という考えの導入は古典物理学には全く根拠を持っていないが、新しい理論が古典的概念との根元的な決裂を要求するものかどうかはまだ明らかではなかった。理論物理学者たちは、最初、プランクの量子仮説を古典物理学と調和させようと努力したのであった。』
“プランクの量子仮説”が提案された時期の前後には、次のような大きな発見がありました。
●1897年ジョセフ・ジョン・トムソンが電子を発見。1906年にノーベル物理学賞を受賞。
●1911年アーネスト・ラザフォードは原子核を発見。1908年にノーベル化学賞を受賞。
5.量子論の奇怪さ
前回の“量子論1”ではノーベル物理学賞を受賞した、リチャード・フィリップス・ファインマンの『量子力学が本当に理解できている人はまずいないだろう~』で始まる文章をご紹介しましたが、「量子の世界」では“量子的奇怪さ”についての説明が出ていました。難解さが伝わる内容だと思います。
『「量子的奇怪さ」とはいったい何なのか。それを見るため、新しい量子論の物理学を、それが取って代わった古いニュートン物理学と対比させてみよう。ニュートンの法則は、石の落下や惑星の運行とか、川や潮の流れなど、見慣れた物体やありふれた出来事からなる、目に見える世界の秩序をつかさどるものだ。このニュートン的世界像を第一義的に特色づけているのは、決定論的性格と客観性である。つまり、時計仕掛けとしての宇宙は時間の始まりから終わりに至るまで決定しているし、石や惑星などは我々が直接にそれらを観測しなくても客観的に実在しているのだ―背を向けていたってちゃんと存在している。
量子論になると、世界を(決定論や客観性のような)常識に基づいて解釈することはもはや許されなくなる。もちろん量子世界も理性によって理解しうるのだけれども、ニュートン的世界のように描写してみせることはできないのだ、これは原子やそれよりも小さい量子の世界の極微性だけが原因ではなくて、通常の物体の世界からそのまま借用した表現の手段が量子的対象には通用しないということによっている。たとえば、石などはそれが静止していて、しかもある定まった場所に置かれているという様子を我々は容易に心に描くことができる。だが電子のような量子的粒子に対して、それが空間のある一点に静止しているなどと言っても意味をなさないのだ。さらに、電子は、ニュートンの法則ではありえないような場所にも物質化して現われることができる。かくして、量子的粒子を通常の対象と同じように考えることは実験事実と相いれないということが物理学者と数学者によって示されたのである。
量子論は客観性という通常の考え方を否定するだけにとどまらず、決定論時世界観をも破壊してしまった。量子論によれば、電子の原子内での飛び移りなどの現象はランダムに起こるのである。電子がいつ飛び移るかなど、我々に教えてくれるような物理法則は何もないのである。せいぜい我々にできることは、その現象の起こる確率を与えることである。巨大な時計仕掛けの最も小さい歯車である原子は、決定論的な法則には従わないのだ。
量子論を考え出した人たちは、ニュートン的世界観と対照的なもう一つの面に気づいた。それは観測者が創り出すリアリティというものだ。量子論によれば、観測者が何を測定しようとしているかということがその測定自身に影響を及ぼすことになる。量子の世界で現実に起こっていることは、その世界を我々がどのように観測しようとしているかに依存しているのだ、我々が観測しようとするまいと、それとは無関係に存在する世界では決してないのである。つまり量子の世界の様子は我々が何を見ようとするかによって部分的に決まるのであって、観測者がリアリティを創り出すことに部分的に参加していると言ってもよい。
客観的実在という概念がないこと、決定論が破れること、および観測者がリアリティを創り出すこと、など、量子世界の持つこれらの性質が、この世界を我々の感覚で知覚する通常の世界から区別しているゆえんであるが、私はこれらの性質のことを「量子的奇怪さ」と呼ぶことにしたい。アインシュタインはこの量子的奇怪さ、わけても、観測者が創り出すリアリティという概念には抵抗を示した。測定の結果に直接的に観測者が絡まるという事実、これは、自然が人間の選択などにはお構いなしに存在すると考えたアインシュタインの決定論的世界観とは真っ向から対立するものだったからである。
我々の心の奥底には、何か素直に量子的リアリティを理解しようとはしないものがあるようだ。もちろん理屈では、数学的に無矛盾だし実験ともすばらしい一致を示すのだから、それを受けいれるのはなんらやぶさかではないのである。だがどうも心の安らぎを得ないのだ。物理学者やそのほかの人たちが量子的リアリティというものを把握しようと苦労している様子は、ちょうどまだ自分の知らない概念にぶつかったときに子供が示す反応ぶりを私に思い起こさせるのである。心理学者、ジャン・ピアジェは子供についてこの現象を研究した。ある年齢の子供に、千差万別の形をした透明な容器に同じ高さまで液体を入れたものをたくさん見せたとする。すると子供は、どの容器にも液体が同じ量だけ入っていると考えるものである。その子供にはまだ、液体の量は高さだけできまるものではなく、体積できまるものだということがつかめていないのだ。その問題の正しい見方を子供に説明すれば、たいていの場合子供は理解する。だがすぐにまた元の考え方へ立ち戻ってしまうものだ。ある特定の年齢―およそ六歳か七歳あたり―を過ぎてはじめて、子供は液量と体積の関係を理解することができるのである。量子的リアリティが理解できるようになるのもこれと似たようなものだ。諸君が自分でそれが理解できたと思い、自分の頭に量子的リアリティのなんらかの描像が浮かぶようになったにもかかわらず、間もなくまた元の古典的な考え方に戻ってしまうことがよくあるものだ。これはちょうどピアジェの実験の子供の場合と同じなのだ。』
6.量子論の応用と貢献
量子論による最大の功績は半導体の発見ではないかと思います。今では死語だと思いますが半導体のことを、”産業の米”と呼んでいた時代がありました。もちろん、量子論の貢献は半導体だけではありません。また、これらを知ることはとても大切だと思います。この点に関しては「量子の世界」第五章 ”不確定性と相補性”の中に描かれていました。
『1920年代の終わり頃まで、新しい量子論の解釈の問題は手をつけられないままの状態であった。若い世代の物理学者たちは量子論とともに育ったが、彼らは解釈の問題には、量子論の応用に対するほどの興味を示さなかったのである。新理論は、それ以前にはなかったほど、理論物理学における数学の果たす役割の重要性を強調するものであった。したがって、抽象数学の面で専門的に大変優れた能力の持主や、それを物理の問題に適用する才能の持主たちが前面に登場してくることになった。
新しい量子論は、自然現象の解明にとって人類がこれまでに手にした数学的手段のうちで最も強力な武器となり、科学の歴史上、比類のない偉大な業績と数えられるに至った。この理論は世界中の工業諸国の何千という若い科学者の知的エネルギーを解放した。これまで出されたどんなアイデアもこれほどまでに大きい衝撃を技術面に与えたことはなかったし、今後とも、このアイデアが実際面で持つ意味は、我々の文明の社会的、かつ政治的運命を形作っていくことになろう。我々人類は今や、宇宙の法典―宇宙の不易の法則―の新しい側面、すなわち我々の発展がプログラムされている面と接触した。トランジスター、マイクロチップ、レーザー、低温技術などの実際面への応用は技術文明の最先端を走る全産業を生み出すこととなった。今世紀の歴史が書かれるとき、政治的な事件は人間の生命や財産に計り知れない損失を与えたにもかかわらず、影響の最も大きかった事柄としては取り扱われていないのを我々は見ることになるかもしれない。代わりに登場するおもな出来事は、人類がはじめて目に見えない量子の世界と接触を持ったことと、その結果としての生物学上、および計算機の上の革命になるのではないだろうか。
新しい量子論の出現によって、化学元素の周期率表の根拠、化学結合の本性、および分子化学が理解できることとなった。またこの新しい理論的発展は、実験面での研究と相まって現代の量子化学を誕生させた。だから、ディラックは、量子力学に関する1929年の論文に次のように書くことができたのだ。
「物理学の大部分と、化学の全域に対する数学的理論にとって必要な基礎的物理法則は、かくして完全に我らの知るところとなり……」
第一世代の分子生物学者たちは、生体の遺伝的安定性は物質的、分子的基盤を持っているに相違ないと説いた、あのエルヴィン・シュレーディンガーの本、『生命とは何か』を読んで大いに触発されたものだ。これらの研究者たちの多くは熟達した物理学者であったが、彼らは遺伝学に新しい風を吹き込み、当時のほとんどの生物学者にとってはなじみのなかった分子物理学の実験方法を取り入れたのである。生命の問題に対してとられたこの新しい研究方法の最大の成果が、生命体の自己複製の物理的基盤である、DNAとRNAの分子構造の発見であった。この発見は、またそれ自体が別の革命の原動力となったのだが、いずれにせよ、分子物理学の研究室でこの発見が行なわれたのは決して偶然ではなかったのだ。
固体の量子論の開発も行われた。電気伝導の理論、固体のバンド理論、磁性体の理論などはすべて新しく生まれた量子力学の当然の成果なのだ。1950年代になると、超電導の理論(極低温において電流が抵抗なしに流れる現象)および超流動の理論(流体が抵抗なしに流れる現象)において一大躍進が見られることになる。このほか液体が気体や固体に変わるような、物質の相転移の理論も発展した。
新しい量子論はまた原子核の研究に対する理論的な道具ともなり、原子核物理学が誕生する契機になった。放射性崩壊の際の莫大なエネルギーの解放の根拠が理解された―放射性崩壊は量子力学的事象を含んでいて、古典物理学的な現象ではないのだ。物理学者は、はじめて星のエネルギー源について知り、天体物理学がモダンな科学として登場することとなった。
だが、一般社会では、教育のある人でさえ量子論のこの発展についていこうとしなかったのは驚くべきことだった。実際、量子論はその前の相対論ほどは一般の興味を引かなかったのである。これにはいくつかの理由が考えられる。第一に、1930年代の初頭は、経済的不況が進行しつつあったこと、第二に、知識層のほとんどは政治上のイデオロギーの問題にすっかり気を奪われてしまっていたこと、第三に、そしてこれが最も重要な理由だと私は考えるが、量子論の数学的構造の抽象性が人間の直接経験に結びつかなかったことである。
量子論は測定機器を通して見いだされた物質的リアリティの理論である。つまり観測者としての人間と、原子との間に、装置が存在している。ハイゼンベルクの言葉を借りれば、「科学における進歩は、自然界の現象を仲介を挟むことなくそのままじかに我々の思考方法で理解できるようにする可能性を犠牲にすることでもたらされた」のだ。彼はさらに、「科学は、我々の感覚でじかに認知できる現象をありのままにとらえる可能性をますます葬り去る一方で、現象の数学的な、形式的な芯の部分をあばくことだけをやっている」とも言っている。』
7.量子論から生まれた半導体
これは「量子論を楽しむ」の中の“半導体部品を生み出した量子論”に書かかれている内容です。
『物性物理学における量子論の最大の成果の一つは、個体の電気的な性質の違いを理論的に説明したことです。
個体は、金属のように電気を良く通す導体、木やガラスなどのように電気を流さない不導体(絶縁体)、そしてその中間物質である半導体の三種類に分類されます。電流とは電子の流れのことですから、それぞれの固体の中で電子がどんな状態にあるのかによって、電気的な性質の違いが表れることが想像できます。
固体の中の電子の状態を「量子数」の概念やパウリの原理に照らして考えると、結晶構造になっている原子の中では、電子のエネルギーはいくつかの「エネルギー帯」と呼ばれる範囲の値だけを取ることがわかりました。そしてエネルギー帯同士のすきま(「ギャップ」と呼びます)が小さい結晶原子ほど、電子はエネルギー的に高い状態に移りやすく、その結果原子核から離れて自由に動き回る電子になる、すなわち電気が流れることがわかってきたのです。
また、シリコンやゲルマニウムなどの半導体に少量の不純物を混ぜることで、電気的な性質を自由自在に変えられることも明らかになりました。これを応用した半導体部品すなわちダイオードやトランジスタ、そしてIC(集積回路)やLSI(大規模集積回路)などはマイクロエレクトロニクスの主役となり、私たちの日々の生活を激変させたのです。現在の私たちの暮らしを支えているのは、半導体部品を生み出した量子論であると言えます。』
今回、量子論の本を読み始めてしばらくの間、私は半導体と量子論との関係について、相変わらずイメージすることができませんでした。しかしながら、4冊の本を読み終える頃になって、やっと、見えた気がします。それは、とても単純な話でした。つまり、「半導体は原子より小さい電子などの世界の話であり、そのミクロの世界のルールを知り、会話するためには古典論は役に立たず、量子論でなければ話が始まらない」。ということでした。
付記
”5.量子論の奇怪さ”の中に次のような一文がありました。
『量子論を考え出した人たちは、ニュートン的世界観と対照的なもう一つの面に気づいた。それは観測者が創り出すリアリティというものだ。量子論によれば、観測者が何を測定しようとしているかということがその測定自身に影響を及ぼすことになる。』
この後半部分のフレーズを”それは施術者が創り出すリアリティ(”証”[治療指針])というものだ。鍼灸の世界では、鍼灸師がどんな施術をしようと考えているかがその施術自身に影響を及ぼすことになる”と置き換えられるのではないか??? それはエネルギーが持つ不思議な ”顔” なのではないかと。。。

画像出典:「宇宙の謎を哲学的に深く考察しているサイト」

画像出典:「ScienceTime」
量子論1
なぜ、量子論という超難解なものに興味を持ったのかというと、それはブログ“がんと自然治癒力8”で勉強させていただいた、ブルース・リプトン先生の「思考のすごい力」という本に因ります。
この本の第四章は次の通りです。
第四章 量子物理学が生物学・医学を変える日は近い
量子物理学と縁なく過ごしてきたわたし
ニュートン力学では超常現象を解明できない
物質はエネルギーでできている
人間の生体内システムは重複的
製薬会社の駒となっている医師たち
電磁エネルギーが生体調整に深い影響を与える
代替医療の研究が進まないわけ
エネルギー波を治療に活用する
大袈裟ですが、私の背中を押したのは以下の4つです。また、キーワードは“エネルギー”であり、そして“量子論と東洋医学の類似性??”という期待のような思いを含んだ好奇心です。
①『原子が宇宙で最も小さい粒子であるという概念は捨て去られた。一つの原子はさらに小さな粒子から構成されていることがわかった。これだけでも驚天動地の大発見だが、さらに、原子がX線や放射線など、さまざまな「奇妙なエネルギー」を放出していることが明らかになり、大騒ぎになった。』
②『ニュートン的で物質偏重主義である旧来の概念から抜け出せない研究者たちは、健康や病気にエネルギーの振動が果たす役割をまったく無視している。』
③『何千年も前、西洋の科学者が量子物理学の法則を発見するより遥か以前に、アジア人は健康と幸福に寄与する第一の要因として、エネルギーを尊んできた。』
④『東洋医学では、身体はエネルギーの経路(経絡)が複雑に列をなしたものと定義される。中国の鍼灸療法で用いられる人体の経絡図には、電気配線図にも似たエネルギーのネットワークが描かれている。中国医学の医師は、鍼などを用いて患者のエネルギー回路をテストするわけだが、これはまさに電気技師がプリント基板を「トラブルシュート」して電気的な「病変」を発見しようとするのと同じやり方だ。』
読んだ本は、「思考のすごい力」の中で紹介されていた2冊を含め、全部で4冊です。
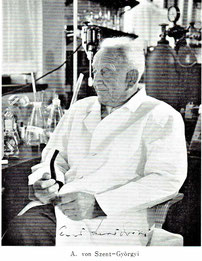
著書:「分子生物学入門」
著者:セント=ジェルジ・アルベルト
出版:廣川書店
発行:1964年9月
ジェルジ・アルベルト先生は、ビタミンCの発見などにより、1937年度ノーベル生理学医学賞を受賞されました。
写真は本書の中に掲載されているものです。また、この「分子生物学入門」の内容は極めて高度であり、タッチできるものではありませんでしたが、唯一、お伝えできる、お伝えしたいことは以下の文章の中の太字部分です。
『私の研究歴は組織学にはじまりましたが細胞形態学が与え得る生命についての知識に満足できず私は生理学に転じました。そこで生理学があまりにも複雑であることを見い出し私は薬理学の分野に転向いたしました。それは薬理学の対象の一つである薬物の性質が比較的に単純なものであると思われたからであります。しかしながら薬理学が決して単純なものでないことを知った私は次に細菌学の世界に踏み込んだのであります。ここでなおも細菌の複雑さを知らされた私は次第に分子レベルの問題に興味をひかれ化学や物理化学の研究をするようになったのであります。この経験を生かして私は筋肉の研究をはじめることを企てました。その後20年間にわたる研究の結果、筋肉の問題を理解するためには量子力学の法則に支配されている電子のレベルまで掘り下げる必要があるという結論に到達しました。』

監修:和田純夫
出版:ニュートンプレス
発行:2018年7月
※ブログ内の緑色『』は「13歳からの量子論のきほん」からの引用になります。
※上部に”常識が通じない! ミクロの世界の物理法則”とあります。
今回の“量子論1”は、自分自身の関心事に対して、できる限り分かりやすくまとめることを目標としました。一方、次回の“量子論2”では、H.R. パージェルの著書「量子の世界」を中心に全体像をつかむという点に重きを置きました。
相対性理論といえばアインシュタインですが、量子論といえば誰なのか? その答えは、ニールス・ボーアとその仲間達ということになります。
左の絵の中に、“シュレーディンガーの猫”と書かれたイラストが出ています。簡単にご説明すると、量子力学の基本となる方程式(“シュレーディンガー方程式”)を編み出したシュレーディンガーが、ボーア達が確立した“コペンハーゲン解釈”という考えに反旗を翻し、提示した宿題であり、“シュレーディンガーの猫”と命名されました。右の絵はその内容です。なお、この宿題は現在もクリアできず、“コペンハーゲン解釈”が完全なものに至っていない大きな理由の一つとなっています。
1.量子論と東洋医学
ボーアは量子論が明らかにした物質観・自然観の特徴を“相補性”という概念で説明していますが、ボーアはこの“相補性”を表すシンボルとして古代中国の「陰陽思想」を象徴する“太極図”を好んで用いたとのことです。このことは、「量子論を楽しむ本」の中に書かれていました。
『ボーアは相補性を表すシンボルとして古代中国の「陰陽思想」を象徴する太極図を好んで用いました。陰と陽という対立する「気」が絡み合い、相互作用をおこなうことで、すべての自然現象や人間活動が決まるとする陰陽思想は、まさに量子論の描く世界像と同じと言えます。ボーアは自分の紋章の一部に太極図を描いたほどでした。
量子論はこのように、中国思想などの東洋思想と相通じる部分を持つために、その観点から関心を持つ人も多くいます。東洋思想の柱に「一元論」があり、これは近代科学の根底にある「二元論」と対立する概念です。物と心、自然と人間などを分けて取り扱うのが二元論であり、これらを不可分なものとみなすのが一元論です。客観的事実を否定した量子論は、自然と観測者を分けて考える二元論的な世界観を退け、観測対象である自然と観測する私たちとを一つのセットとして考える、一元的な自然観を示すのです。』
東洋医学そのものではありませんが、ボーアがその大元になっている陰陽思想への関心が高かったという事実の発見は、驚きでもあり、うれしい気持ちになります。

写真はQingYang gong templeという寺院にある彫刻です。中央が太極図、まわりは十二支です。
画像出典:「ウキペディア」
2.量子論とは
1)アイザック・ニュートンと決定論

この画像は“山賀 進のWeb site”さまの“ニュートン略伝”から拝借しました。
量子論と対極にあるのは、アイザック・ニュートンの理論です。また、そのニュートン力学の考えをさらに発展させたのが、ピエール・ラプラスの「未来はきまっている」という考えです。まずは、量子論と比較する目的で「古典論」とされている、ニュートン力学と決定論について触れたいと思います。
『量子論が誕生する以前、あらゆる物体の運動は、「ニュートン力学」で説明できると考えられていました。ニュートン力学はイギリスの天才科学者アイザック・ニュートンが打ち立てた理論で、物体が力を受けてどのように運動するかを説明する理論といえます。
ボールの遠投を考えましょう。空気抵抗などは無視できるとします。ボールを投げた瞬間の速さと向き、高さが厳密にわかれば、地面に落ちる位置はニュートン力学によって厳密に計算できます。つまり「ボールの落下地点は、投げる瞬間に決まっている」といえるわけです。
サイコロの出る目が予測できないのは、サイコロを投げた瞬間の状態を厳密に知ることが困難だからです。投げた速さ、角度、高さなど、すべての条件が厳密にわかれば、出る目は計算できます。つまり、「サイコロの出る目も、投げる瞬間に決まっている」といえるでしょう。
フランスの科学者ピエール・ラプラスは、ニュートン力学の考えをさらに発展させて、次のように考えました。
「仮に、宇宙のすべての物質の現在の状態を厳密に知っている生物がいたら、その生物は宇宙の未来のすべてを完全に予言することができるだろう。つまり、未来は決まっていることになる」。この仮想的な生き物は、「ラプラスの魔物」と呼ばれています。
ラプラスのような考え方は、量子論が登場するまでは、物理学者の間で一般的だったようです。未来を予言することができないのは、人間の能力に限界があるためであって、実際には未来は決まっている。そう考えるわけです。
しかし量子論の登場によって、この考え方は正しくないことがわかりました。量子論によると、仮にラプラスの魔物が宇宙のすべての情報を知ることができたとしても、未来がどうなるかを予言することは原理的に不可能だからです。
たとえば電子は、運動方向を正確に決めると位置が不確かになり、位置を正確に決めると運動方向が不確かになります。電子の位置と運動方向を、同時に正確に決めることは不可能なのです。
このようにミクロの世界では、電子一つをとってみても、未来の予言は不可能です。つまり、未来はきまっていないようなのです!』
2)量子論が生まれた理由
『あらゆる物質は、「原子」からできていることがわかっています。19世紀末ごろになって、原子がかかわる現象を詳しく調べてみると、ミクロな世界は私たちが日常生活で目にする世界とはまったくちがうことがわかってきました。ミクロな物質は、私たちの常識では説明できない、摩訶不思議なふるまいをするのです。そこで、新しい理論が必要になりました。それが「量子論」です。量子論とは「非常に小さなミクロな世界で、物質を構成する粒子や光などがどのようにふるまうかを解き明かす理論」といえます。』
3)量子論と日常生活の関係
こちらの絵も「13歳からの量子論のきほん」からのものです。量子論はミクロの世界で顕著ですが、実はミクロの世界だけの話ではありません。
『量子論は、原子や電子といったとても小さいものがどのようにふるまうかを説明する、物理学の大理論です。現代の物理学は、一部の例外をのぞいて、すべて量子論という土台の上に築かれているといっても過言ではありません。量子論以前の物理学は、「古典論」とよばれます。原子より小さいようなミクロな世界は、古典論では説明がつかず、量子論という新しい理論が生まれたのです。
では量子論は、私たちが日常目にする世界(マクロな世界)とは、無関係なのでしょうか。実は量子論は、ミクロな世界であろうと、マクロは世界であろうと、自然界のすべてのサイズで適用できます。ただ、マクロな世界では、量子論の効果がほとんど見られなくなります。量子論が「ミクロな世界の物理法則」といわれるのは、量子論の効果が目立ってあらわれるのが、ミクロな世界だからなのです。
ただし、ミクロな世界もマクロな世界も、量子論だけですべてがこと足りるというわけではありません。たとえば、マクロな世界の物体の運動に量子論を適用すると、計算量が膨大になってしまいます。そこで実用上は、計算が楽な古典論が使われます。マクロな世界では、量子論による計算結果と古典論による計算結果が、ほとんど同じになるのです。
なおマクロな世界にも、量子論を使わないと説明できない現象はあります。「金属(導体)」「絶縁体」「半導体」の性質のちがいや、「超流動」や「超電導」といった現象です。
量子論であつかうミクロな世界の現象は、日常ではほとんど見ることができないので、量子論に慣れるのはむずかしいといえます。「人間が知覚できる世界は非常に特殊で限られている」という事実を、忘れないようにする必要があるでしょう。』
この「ミクロとマクロ」、「古典論と量子論」の関係性をつかむことは重要と考えますので、専門的ですが、以下に「量子の世界」の“第五章 不確定性と相補性”から一部を引用させて頂きます。
なお、ポイントは「例えば細菌サイズであっても、不確定さは10億分の1しかないため、ニュートン力学でも問題ない誤差であるが、原子サイズになると不確定さは100分の1と高くなるため、いよいよニュートン力学では難しくなってくる」というような内容です。
『いろいろな対象に対して、ハイゼンベルクの関係式がどの程度の意味をもつかのだいたいの感じをつかむためには、その対象のサイズと代表的な運動量を掛け合わせたものを、ブランク定数h―量子効果が重要となる目安―と比較してみるとよい。飛んでいるテニスボールについて言えば、量子論による不確定さはおよそ1000万×10億×10億×10億分の1(10のマイナス34乗)に過ぎないことがわかる。したがって、テニスボールは十分な高精度で古典物理学の決定論的法則に従っていると言ってよい。細菌でさえ、その効果はおよそ10億分の1(10のマイナス9乗)の程度で、量子世界を全く経験することはないのだ。だが結晶中の原子になると我々は量子世界の入口まで迫っていくことになり、不確定さが100分の1(10のマイナス2乗)になる。ついに原子の中を動き回る電子に至っては量子的不確定性が完全に支配的となり、我々は不確定性原理と量子力学を支配者とする正真正銘の量子世界に足を踏み入れることになるのだ。』
実は、今回「ハイゼンベルクの関係式」を調べていて、大きな修正が起きていたことを知り大変驚きました。それは以下の記事です。なお、この修正は上記の内容(物質の大きさと法則の関係性)に大きな影響を与えるものではないと思われます。
【クローズアップ科学】ノーベル賞「重力波」に陰の立役者 名大・小澤正直特任教授、物理学の定説覆す理論で貢献 2017.10.8 10:00
“~ 量子力学を象徴するとされてきたハイゼンベルクの不確定性原理を表す不等式の破れ(欠陥)を正した「小澤の不等式」でも世界的に知られている。ハイゼンベルクの不等式は「物体の位置を正確に測ろうとすると、測定によって起こる運動量の乱れが大きくなる」ことを表す。測定誤差がゼロだと、運動量が無限大になるので、そのような測定はできないと考えられてきた。これに対して、小澤氏が2003年に発表した不等式は、誤差ゼロの測定が可能であることを示す。量子の世界の「不確かさ」には測定に伴う誤差や運動量の乱れと、測定とは関係なく量子が本来的に持っている位置や運動量の「揺らぎ」がある。小澤氏は、2つの「不確かさ」がきちんと区別されないまま80年にわたり定着していたハイゼンベルクの不等式の間違いを正し、完全な式を提示した。 ~”
4)量子論の二つの重要事項
●「波と粒子の二面性」:“電子や光は、波と粒子の性質をあわせもつ”
●「状態の共存(重ね合わせ)」:“一つの電子は、箱の左右に同時に存在できる”
これについてはここでは触れません。その代わり、勇気づけてくれる一文をご紹介します。それは「量子の世界」の“第九章 波を作る”の冒頭(添書き)に書かれているものです。
『量子力学が本当に理解できている人はまずいないだろう、と言って私は間違っていないと思う。諸君はもしできるなら、「だが、どうしてそんなことがありうるのだろうか」と自分自身に問い続けるのはやめた方がよい。なぜならますます深みにはまって、袋小路をさまようのが落ちで、そこから出口を見つけて出てきた人はまだいないのだから。どうして量子力学ではそうなるのかは、誰もわかってはいないのだ。』
なお、この文章は、リチャード・フィリップス・ファインマンの言葉です。ファインマンは、経路積分という新しい量子化の手法を考案し、この成果により1965年にノーベル物理学賞を受賞された物理学者です。
5)“コペンハーゲン解釈”とは
現在、解決できない宿題(既出の“シュレーディンガーの猫”の件など)はあるものの、量子論の代表的な解釈は“コペンハーゲン解釈”と呼ばれているものです。以下はネット上にあった「知恵蔵」による解説です。
『コペンハーゲン解釈は、N.ボーアやW.ハイゼンベルクらの立場に沿うもので、正統派解釈とされる。この見方では、量子世界の物理状態は重ね合わさり、波を形づくっているが、観測された瞬間に波はしぼみ、1つの状態に落ち着く(波束の収縮)。どの状態が観測されるかは、波の振幅をもとに確率論的に予想できる。収縮の原因として、測定する側(環境)が測定される側に乱れを起こすことなどが考えられている。』
一方、「量子論を楽しむ本」の中の説明は以下の通りです。
『「波の収縮」と「確率解釈」を二本の柱として、私たちに見られる前の電子と見られた後の電子のようすを理解しようとするこの解釈方法を、コペンハーゲン解釈と呼びます。』
また、「13歳からの量子論のきほん」の説明は次のようなものです。
観測すると、電子の波が瞬時にちぢむ!? “とがった波”が、粒子のようにみえる
『一つの電子は「波と粒子の二面性」をもちます。この矛盾したような事実は、どう解釈したらよいのでしょうか。コペンハーゲンを中心に活躍したデンマークの物理学者のニールス・ボーア(1885~1962)らは、「コペンハーゲン解釈」とよばれる解釈を提案しました。
コペンハーゲン解釈によると、電子は観測していないときは、波の性質を保ちながら空間に広がっています。しかし、光を当てるなどして電子を観測すると、波が瞬時にちぢみ、1か所に集中した“とがった波”になります(波の収縮)。このような波が、粒子のように見えるというのです。
電子は、観測すると、観測前に波として広がっていた範囲内のどこかに出現します。しかしどこに出現するかは、確率的にしかわかりません。このような解釈をすれば、電子などの「波と粒子の二面性」を矛盾なく説明できると、ボーアらは考えたのです。』
電子は、“分身”しながら広範囲に存在している 電子の波を、発見確率をあらわす波と考える
『電子の波とは、いったいどんな意味をもつものなのでしょうか?
先にご紹介したように、観測前の電子は、波のように空間に広がっています。これをあえて粒子的な描像で考えると、「一つの電子が、漫画などにえがかれる分身の術をしている忍者のごとく、あちこちに同時に存在している」といったイメージになります。
電子が発見される確率は、電子の波の“山の頂上”または“谷の底”で最大になり、電子の波が軸と交わっているところでゼロになっています。このように電子の波を、電子の発見確率をあらわす波と考えるのが、量子論の標準的な解釈となっている「コペンハーゲン解釈」です。
電子の波を数学的にあらわしたものは、「波動関数」とよばれています。電子の波動関数が原子の中などで、どのような形をとるかを導くための量子論の基礎方程式を、「シュレーディンガー方程式」といいます。』
3.おさらい
この“おさらい”は、「量子論を楽しむ本」の中にある“ミクロの世界の物理法則が明らかになる”の内容です。量子論を理解する上で、量子論を古典派と推進派の両面から理解することが重要ではないかと考えました。
“ミクロの世界の物理法則が明らかになる”
『さて、3章(見ようとすると見えない波)でもさまざまな話をしてきました。最後は例によってこの章のポイントをおさらいしておきましょう。
①原子中の電子の軌道半径がとびとびの値に限られるというボーアの量子条件の根拠を示すために、ド・ブロイは電子を波であると考えて、その波長を求めた。
②シュレーディンガーは電子の波を表すシュレーディンガー方程式を導き、電子の「とびとび」のエネルギー状態などの説明に成功した。
③しかしシュレーディンガー方程式が示す波動関数ψ(プサイ)、すなわち電子の波(これは複素数の波である)の正体はわからなかった。
④ボルンは波動関数ψそのものが何を表すのかを考えずに、代わりにψの絶対値の二乗が、電子をその場所に発見する確率に比例することを見いだした(「波動関数の確率解釈」)。
⑤ボーアたちは、観測される前の電子はさまざまな位置にいる状態が「重ね合わせ」になっているが、私たちが電子を観測したとたんに「波の収縮」が起きて電子は一ヶ所で発見されると考えた(「コペンハーゲン解釈」)。
こうして1920年代に、原子中の電子が示す不思議な現象をきちんと説明できる理論を、私たちはついに手にすることになりました。そしてその結果わかったのは「電子などミクロの世界は、私たちが知っていた物理法則とはまったく違うルールに支配されていたのだ」ということです。
その新たなルールの第一は、シュレーディンガー方程式に代表される波動力学(量子力学)です。ミクロの世界の物質は、それを「波である」と考えることでふるまい(動きやエネルギー)などを求めることができるのです。
そしてもう一つのルールが「確率」です。私たちが電子を発見する場所は、サイコロを振って決められるかのように、確率的に決定されるというのです。』
このおさらい①~⑤を眺めると、古典派と推進派の違いは、波動関数の正体にこだわり歩を止めたアインシュタインやシュレーディンガーなどの古典派(決定論[ニュートン以来の物理学の大前提]を尊重)と、波動関数の正体を明らかにすることを先送りし、波動関数の存在を前提として量子論の開拓を積極的に進めていったボーアたちの推進派、という構図が思い浮かびます。
付記
「量子論を楽しむ本」の第3章“見ようとすると見えない波”と聞いて思い出したのは、壺と顔の絵です。調べてみるとそれは『ルビンの壺』と呼ばれていました。「壺に集中すると顔に気づかず、顔に集中すると壺に気づかない」というものです。もちろん、これは量子論の“波の収縮”とは全く無関係ですが、ちょっと面白いのでアップしました。

画像出典:「集客コンサルタント橋本慶一のブログ!」
“かささぎ”
2007年5月17日、HP(ヒューレット・パッカード)発祥の地であるガレージと住宅が、米国国立公園局により、史跡として登録されました。

「史跡」となるガレージ(1939年撮影)
画像出展:「ITmedia NEWS」
こちらはシリコンバレーの地図と景観です。
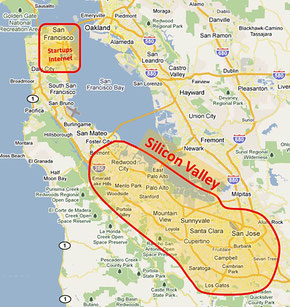
画像出展:「SEO’Brien」

画像出展:「The Guardian」
2007年5月というと、入社25年目ということで私が銀行のお客様を担当していた頃ということになります。そういえば、親しいお客様とそんな話をしていたことを思い出しました。
HPによって始まったシリコンバレーの熱気は広がり続け、今も世界を代表するIT企業がひしめいています。そんなシリコンバレーに対する誇りと憧れから、シリコンバレーの地図に企業のロゴがデザインされたカレンダーを飾って大切にしていたのですが、そのカレンダーは2017年のものであり、「古いカレンダーをいつまでも貼っているのは、さすがにマズイなぁ」とは感じていました。
何か探さねばと検索したところ、すぐにAllPostersという「世界最大級のポスター&絵画ショップ」を見つけました。
その種類も量も半端なく、まさに世界最大級ショップです。選ぶのは容易ではないと痛感しました。
そして、迷いましたが “絵画(印刷)” にしようと決めました。
土曜日の夜10時から、テレビ東京が放送している『美の巨人たち』は比較的よく観ています。日本人では、葛飾北斎、伊藤若冲、東山魁夷などが思い出されます。外国人では、ダビンチ、ゴッホなどが思い浮かびます。
「一番印象に残った絵は何だっただろう?」と考えたときに、あたまに思い浮かんだ絵が一面雪の風景に一羽の黒い鳥が描かれたものでした。確か放送の中では雪の描き方、光の表現の仕方が凄いというようなことを言っていたように思います。ただ、作品名も作者も覚えていませんでした。
まぁ、ドイツ、イタリアという感じはしなかったので、とりあえず「フランス」で検索してみたところ、候補の一つと考えていたゴッホの “夜のカフェテリア” が1列目(1列に3つ)に登場しました。そして、私が探していた絵はあっけなく2列目にありました。その絵の作者はクロード・モネ、作品名は“かささぎ 1869年”でした。

美の巨人たち
『今日の1枚は、美しい冬の油彩画、クロード・モネ作「かささぎ」。描かれているのは、夏の避暑地として名高いフランス北部の街エトルタ。多くの画家を魅了した地です。のちにモネにとっても重要な場所となりました。枯れた木々や降り積もる雪に覆われた、誰もいない白の世界。その中に存在感を放つ1羽の黒い鳥“かささぎ”が…。果たして“かささぎ”にはどんな秘密が隠されているのでしょうか。』
ちなみに、左端に黒く見える“かささぎ”は、羽を広げると特に美しい鳥であることが判明しました。なんとなく、”かささぎ”という題名にした理由が分かるような気がします。また、何故かこの絵を選んで良かったなと思いました。(届いた実物を見たら、黒と思っていた”鳥”のお腹は少し青がはいっていました)

画像出展:「BIRD FAN」
「札幌発野鳥観察」さまのサイトにたいへん綺麗な素晴らしい写真が掲載されていました。是非ご覧ください。 ”2/8 苫小牧でカササギに出会いました”

こちらがフランス北部、ノルマンディ地域圏の ”エトルタ” です。
画像出展:「ウィキペディア」

モネはこの ”エトルタ” の風景も、14年後の1883年に描いていました。
画像出展:「WikiArt」
コルト・ラリーアート
長らくお世話になったフォルクスワーゲンGolfはこの夏で17年目を迎える予定でした。
昨年あたりから、電気系統、センサーなどに不安定な状態が時々発生しており、後付けのカーナビもアンテナの不具合で使用不可となっていました。
というように、ほとんど待ったなしの状況に加え、週2日の「訪問鍼灸・マッサージ」の仕事が4月から業務委託契約となり、自分の車を使うことになっていよいよ追い詰められていました。
一方、車に期待するのは、俊敏性と瞬発力、コンパクトでキビキビ走る機能性です。サッカー選手でいえば、ペナルティエリアまで切り込んで決定的なラストパスを出すようなプレーです。
環境重視、燃費重視の昨今では、特にコンパクトカーの中では思い当たるものもなく、「ホンダで探そうか」とも考えるものの、実は1代目、2代目がホンダだったこともあり、「それもなぁ」という煮え切らない状態でした。
そんな事態が続く中、運転をしている時に、たまたまワインレッドのコンパクトカーが低音で力強いエンジン音をたてて私の前に現れました。
「むむっ、これはどこぞの車?」とよく見ると、リアの左端の方に「COLT」というプレートがありました。「三菱?」、三菱の車といえば、パジェロか走りのランサーターボという印象で、コルトは完全にノーマークでしたが、地元浦和レッズを応援しているモノとしては、「そういう選択肢もあるかな」と思い、その日の夜にどんな車か詳しく調べてみました。
すると。。。
COLT RALLIART Version-Rは、小型ハッチバックのコルトをベースとしたスポーツモデルで、スポット溶接の増し打ちなどによりボディ剛性が強化されており、エンジンはMIVEC-ターボ 直接4気筒 DOHC
1,468cc。最高出力154PS(マニュアルミッション車は163PS)。販売期間は2006年5月-2012年6月。生産は名古屋製作所岡崎工場で行われていた等々。という紹介がされていました。
このスペックは現Golfの1780cc、150psと比較しても遜色なく、シャキシャキ走ることは想像でき、排気量が少ない分、燃費も良いだろうと思いました。
こうして、埼玉、東京で適当な中古車が販売されていないか探してみたところ、価格的にも予算内におさまりそうなものがありました。
ちょっと迷いましたが、考える時間もあまり残っていなかったので、その週の週末には販売店に行き、実物を確認しその場で購入を決めました。
静寂さや乗り心地は期待していなかったので特に問題なく、瞬発力は予想通りで満足しています。ただし、ヒトで考えれば還暦を超えた年齢になると思うので、乱暴な運転は厳禁であり、安全第一が相棒の務めになるだろうと思います。



付記
そういえば、母方の叔父は身長160cmに満たない小柄なヒトでしたが、70歳までホンダCB750を乗り回していました。その後は、確か、125ccのスクーターで我慢していたように思います。私はスピード狂では決してありませんが、瞬発力にこだわるのは血が関係しているのかもしれません。
画像出展:「Tiend Boxer Clasicas」
新しい自転車を買ったわけ
新しい自転車を9月2日に購入しました。自転車愛好家というわけではないのですが、坂道も自転車から降りることなくスイスイと走っていたいため、2002年から前3段、前後合わせて15段以上の変速機がついたクロスバイクに乗っています。
ちなみに、2002年というのは日韓サッカーワールドカップが開催された年ですが、埼玉スタジアムで行われる「日本対ベルギー戦」観戦のため、圧倒的に便利な自転車を買い求めました。
今回の自転車は3台目ですが、購入日が9月2日だと分かるのは、ちょっとした事件があったためです。
前日9月1日はサッカーワールドカップ最終予選のUAE戦が埼玉スタジアムで行われた日ですが、運よくチケットを入手できた私は、天気も良かったため、機嫌よく自転車で埼スタ登場という段取りでした。
ところが試合結果は散々、「さっさと帰って、風呂にでも入ろう。」などとブツブツ考えながら、ややスピードを上げ帰り道を急いでいました。残り1、2kmのところにコンビ二があるのですが、数日前から移転のため店は閉められ、明かりのない周辺はかなり暗い状況でした。
初めて通る道ではないので、明かりさえついていれば、あるいは気分よくノンビリ走っていれば、こんなことにはならなかっただろうと後悔するわけですが、、、
「ガツン!」という衝撃後、体は宙を舞い、そしてアスファルトにたたきつけられました。お恥ずかしい限りの転倒です。それは、走っていた車道が信号待ちの車列のため道がふさがれており、歩道に入ろうとしてハンドルを左にきった瞬間のできごとでした。
それなりに派手にとんでいたようで、停車中の車から一人の親切なおじさんが、「大丈夫ですか?」と声をかけてくれました。幸い、頭も首も問題なく、骨折するようなこともなかったのですが、「おかげさまで、大丈夫です。」と言いおえる寸前に、左肘の厚皮がムケて血がタラタラと落ちているのに気がつきました。とはいえ、大きな怪我もなく、まさに不幸中の幸いというところでした。
余計なお世話と思いますが、自転車に乗るときは縁石にはご注意ください。原因は左の写真に写っている、微妙にカーブがついた縁石です。右の写真のバックは埼玉スタジアムです。
補足)今回の出来事に巻き込まれた2台目は、もともとお疲れ気味だったこともあり、また修理も必要となるため、引退となりました。


ホームページ作り
「最低限ホームページは必要だよな。」
と思い、業者に発注することも考えましたが、費用面に加え自分自身で編集したいという気持ちが強かったため、まずは自前で作る案を検討しました。下記はその進め方や気づいた点を書き出したものです。
1.コンピュータに対する知識や習熟度
コンピュータという意味では、数年前までは仕事でExcel、Word、Powerpointを標準機能の範囲で使っていましたが、技術的な知識は全くありませんでした。
2.ネットで判断材料を情報収集
事例や各種ツール、ご意見などネット上にある様々な情報にアクセスし、何とか自分自身で作れそうだという判断をしました。
3.「ホームページ作成サービス」のJimdoを選択
Wixという特にデザイン面に優れた「ホームページ作成サービス」にしようか迷いましたが、基本機能等、全体的な印象が自分にとって親しみやすい印象だったためJimdoを選びました。(Word、Excel的な感じが自分にとっては安心材料になったのだろうと思います)
4.本を購入
本は必須ではありません。
私の場合、本を購入した1番の理由は完成後に大きな変更をしようとしたとき、空白期間にもよりますが、おそらく、その時はほとんど忘れてしまっているだろうと想像したためです。つまり、本があれば本を見返すという行為により、記憶が戻りやすく、少しでも効率よく対処できるのではないかと考えました。
5.コンテンツ(文章など)は事前に準備
内容を吟味しながら作っていくのは効率的とは思えず、また、自分には難しいと考えコンテンツ(文章)を事前に検討し準備しました。なお、Excelなどで作るとデータに属性がついているため、コーピーしたときに思ったように表示されないことがあります。そのため、「メモ帳」を使って文書を準備しました。なお、これはお伝えしたい第1のポイントです。
6.ブログ作成時の注意
2015年9月にホームぺージをリリースし、その後、先月の8月15日に改訂しました。そして今回、新たにブログを開始すべく取り組んだのですが、Jimdoでブログを作る場合、大きな注意点があることを知りました。これが第2のポイントです。Jimdoには多くのレイアウト(テンプレート)が用意されており、簡単に変更することが可能です(変更後に内容確認と多少の調整がある程度です)。一方、ブログでは時系列や内容による分類を行い、それをメニューとして常時表示させた方が見やすく親切な作りといえるのですが、そのような作りができるレイアウトと標準機能では出来ないレイアウトがあります。細かい話ですが、8月15日に改訂したレイアウトはJimdoでいう「マイアミ」というレイアウトだったのですが、ブログ作成には適していないことが完成後に分かり、今回、改めてレイアウ トを「サンフランシスコ」というものに変更することとなりました。実は「シカゴ」が第1候補だったのですが、ロゴのサイズと配置が「マイアミ」とは異なっていたため、この点について問題のない「サンフランシスコ」に決定しました。
7.課題
現在のホームページは圧倒的に文章が多くなっています。これは私自身が「お絵かきツール」を使いこなせないのが最大の理由です。ツールとしてはPhotoshopやIllustratorなどが有名ですが、必要十分な機能のソフトを学習し、図や絵を活用して内容を分かりやすくできることが課題です。
8.まとめ
1)文書を事前に準備するときは「メモ帳」を利用するのがお勧めです。
2)ブログを行う場合は、ブログを作りやすい「レイアウト」を選択することが重要です。






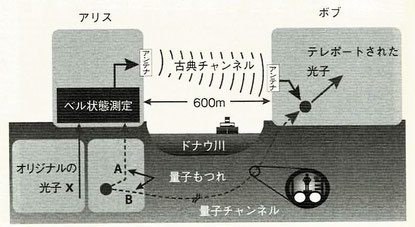
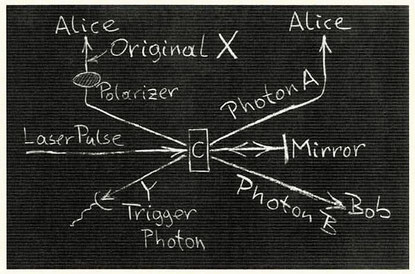



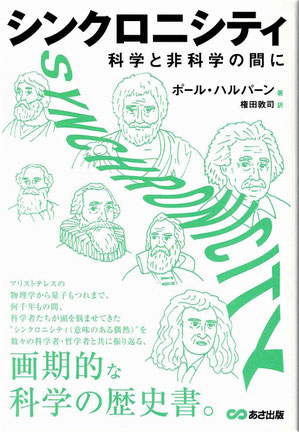
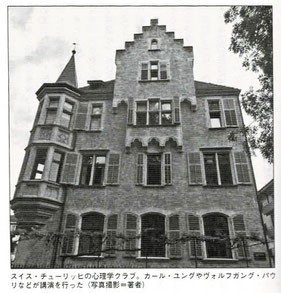
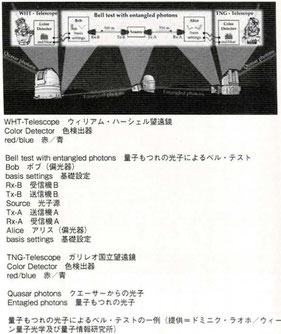
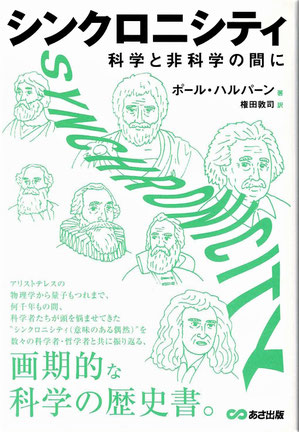
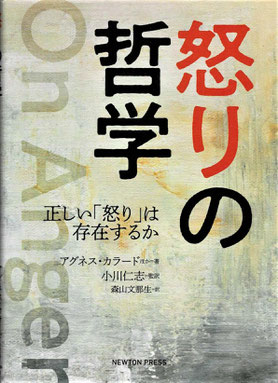
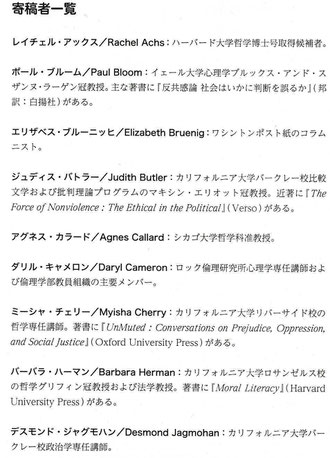
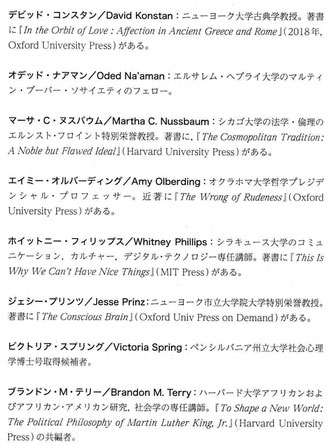
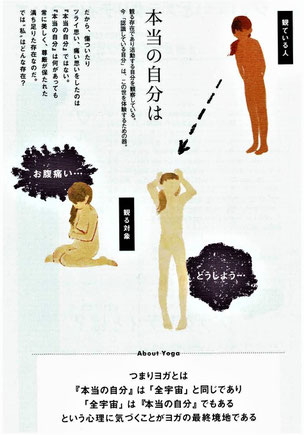

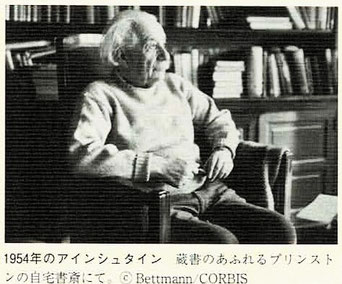


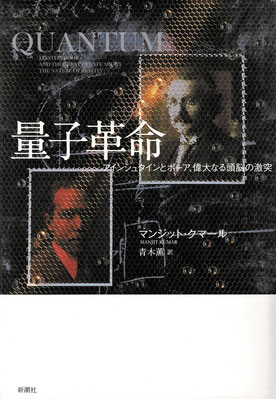

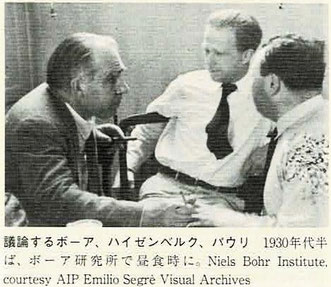

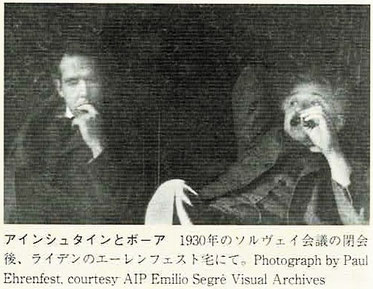
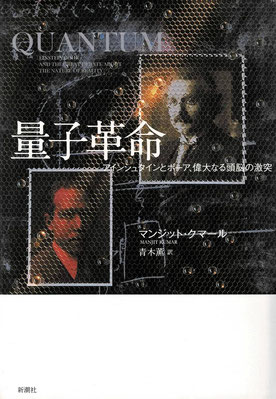


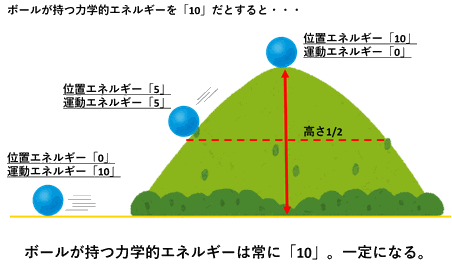
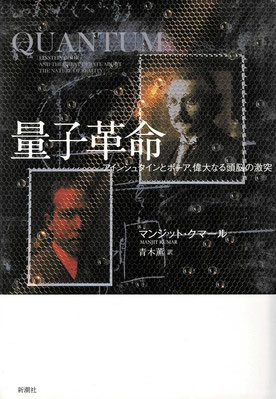
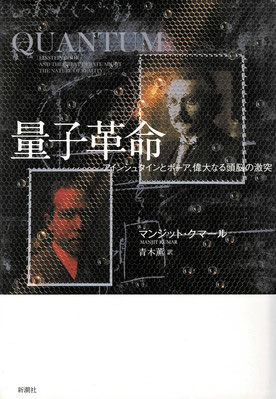
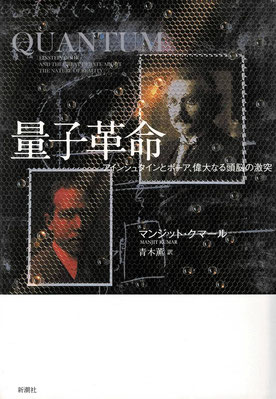
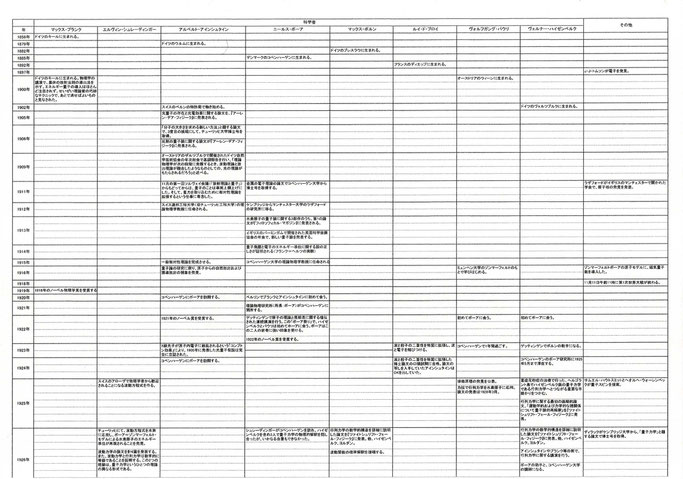
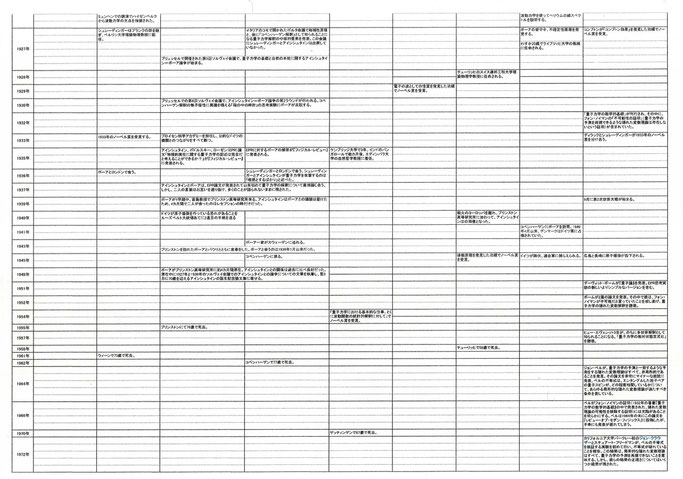
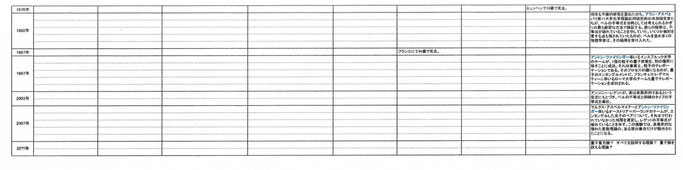



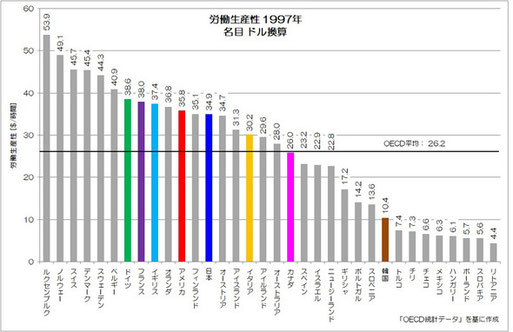



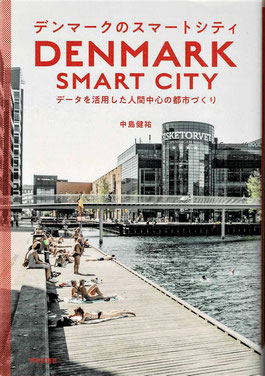
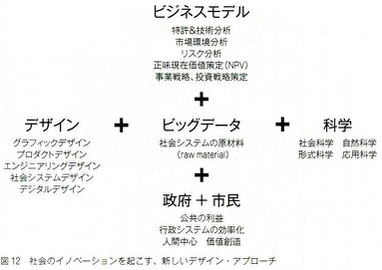
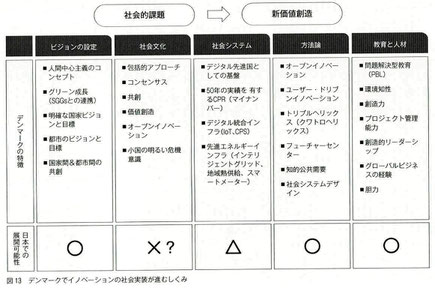
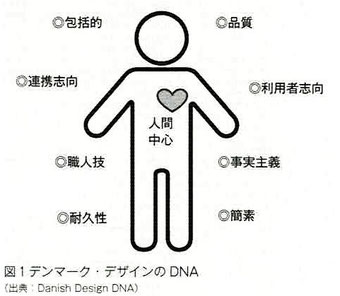
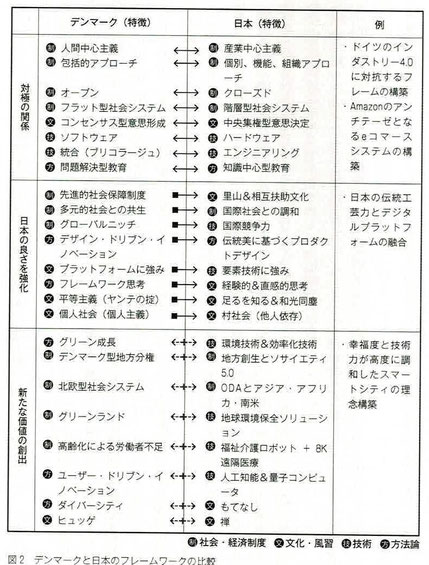
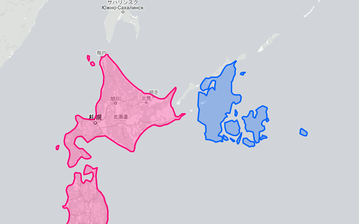
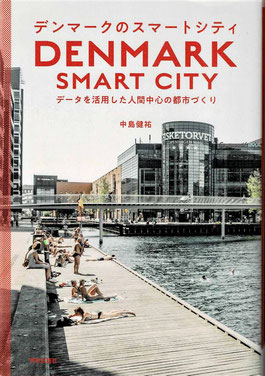
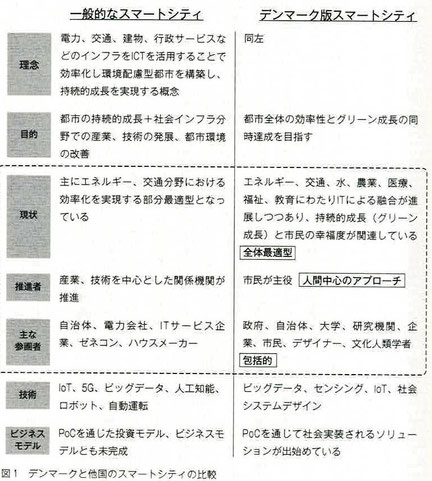
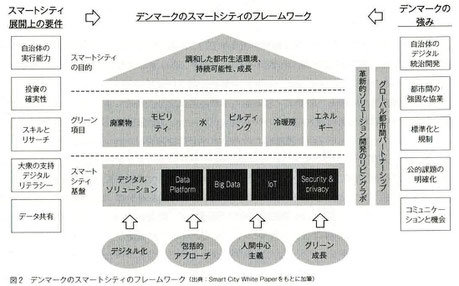
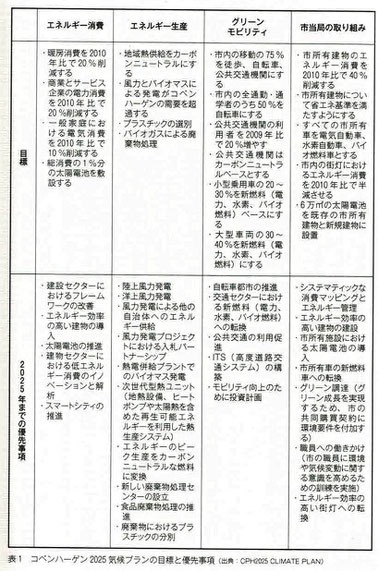

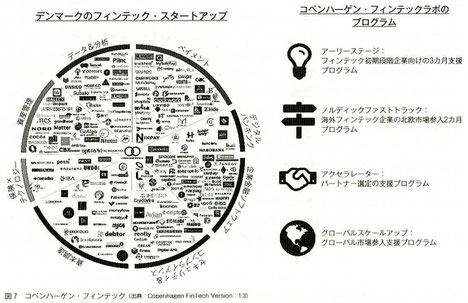
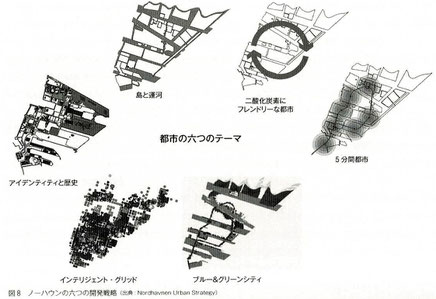

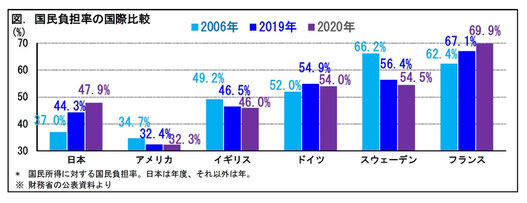

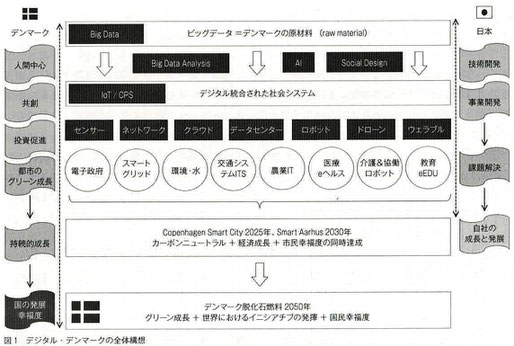

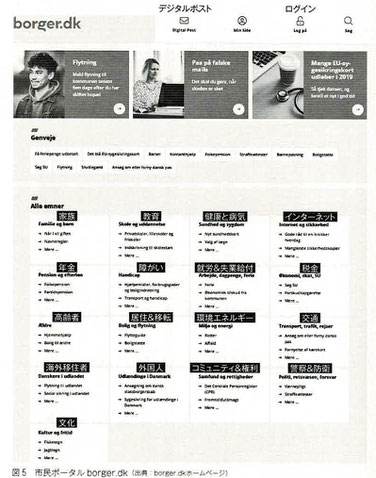

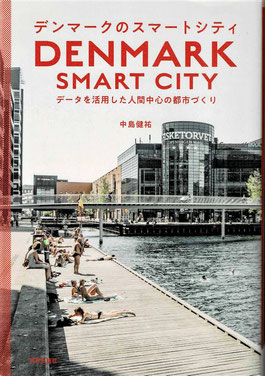









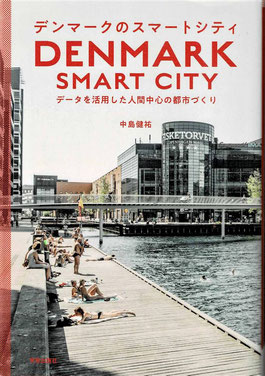
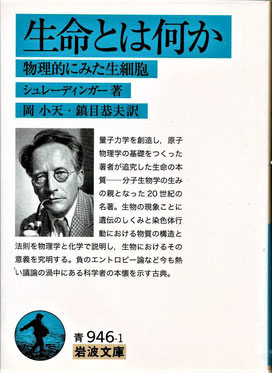


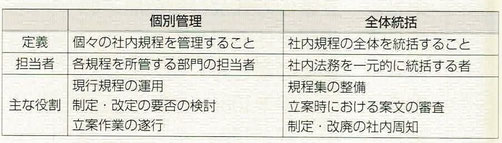


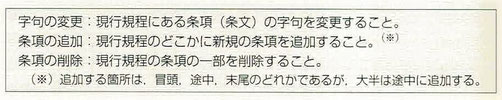


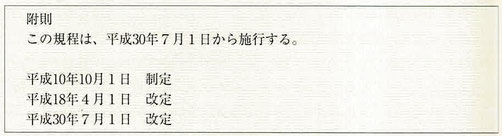


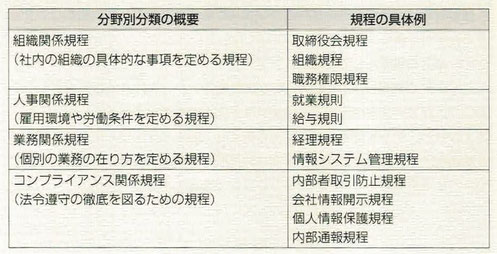



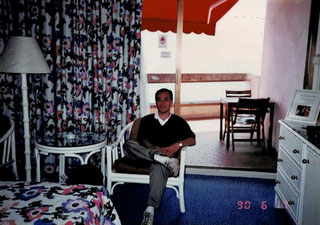
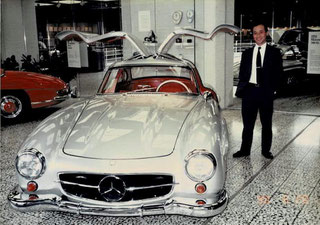




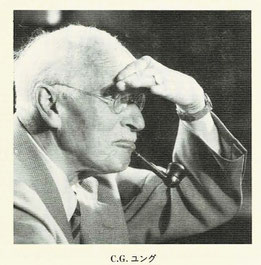



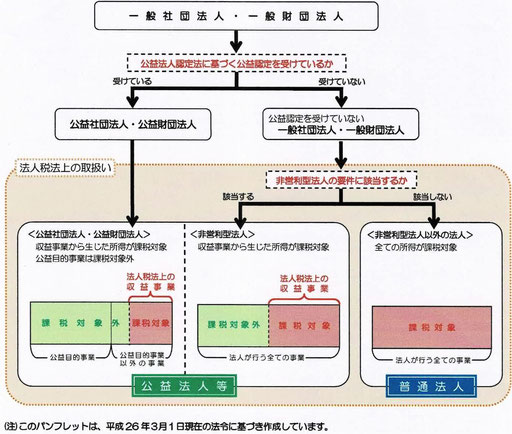
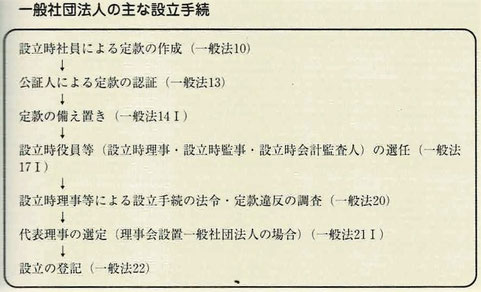


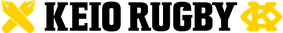

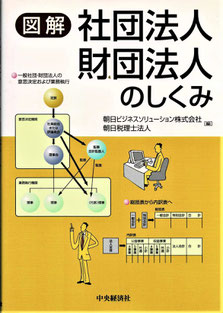
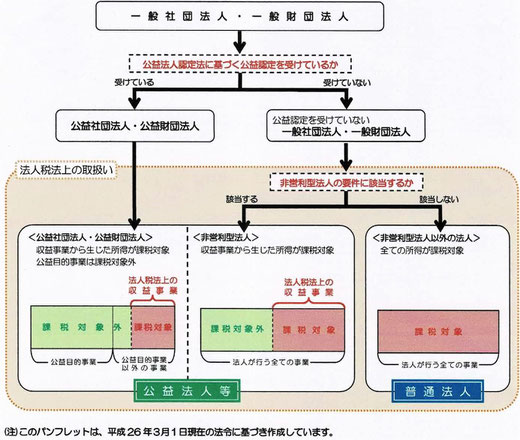
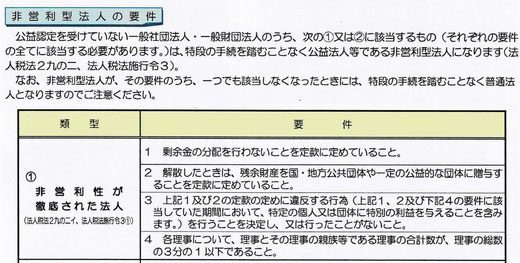
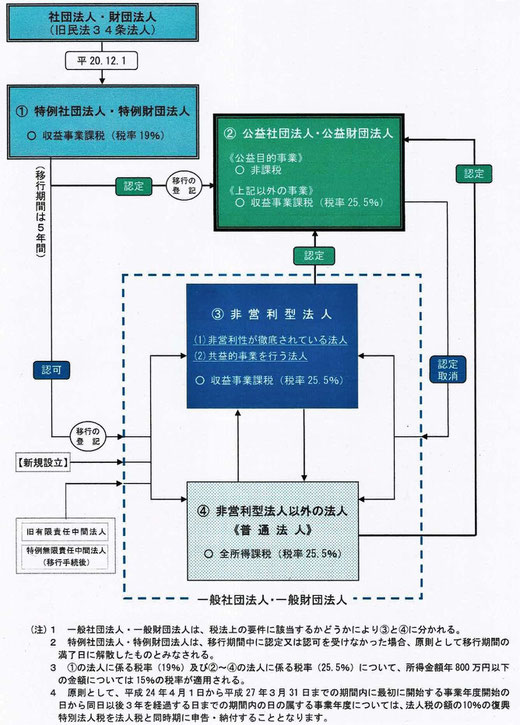
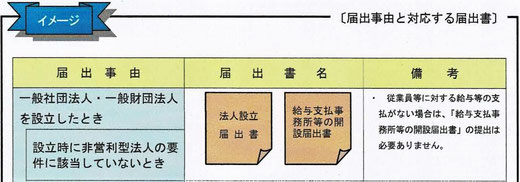
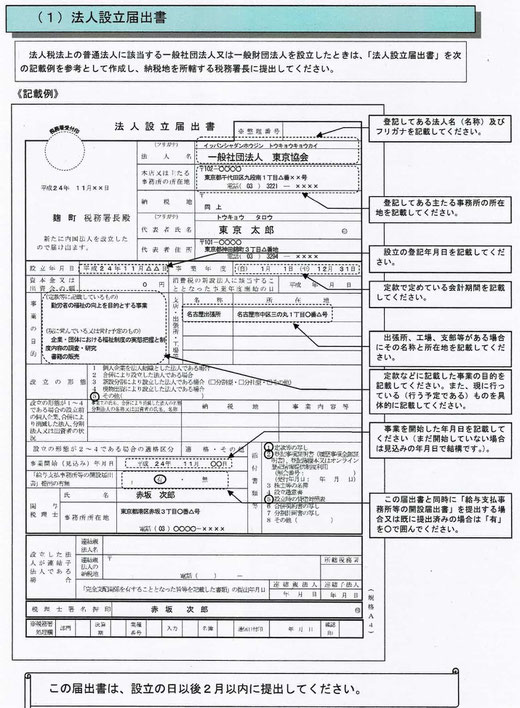

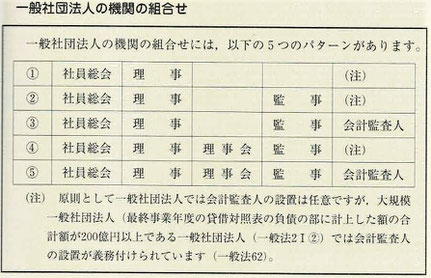
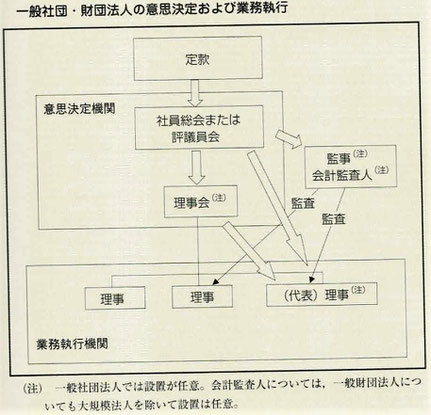
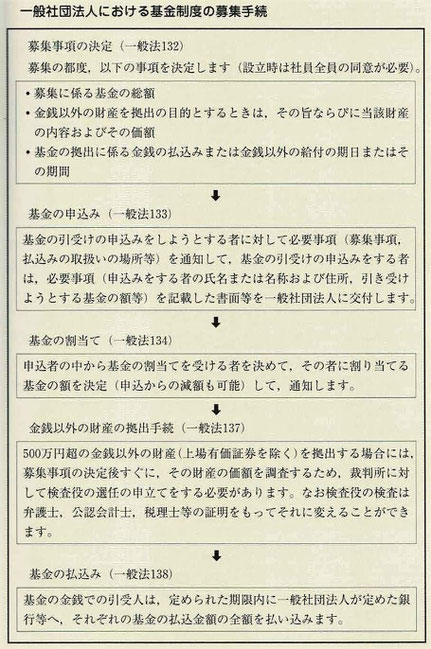



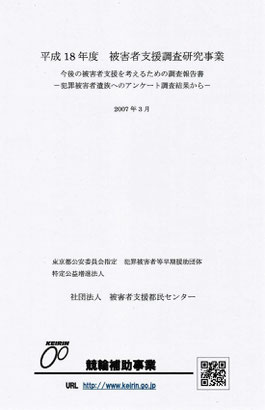

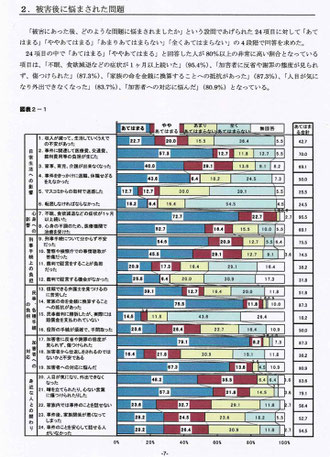
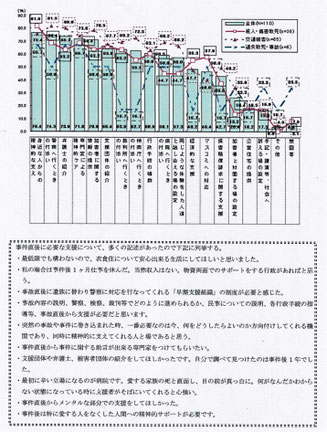






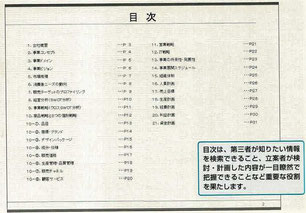

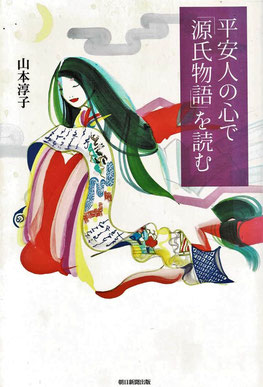


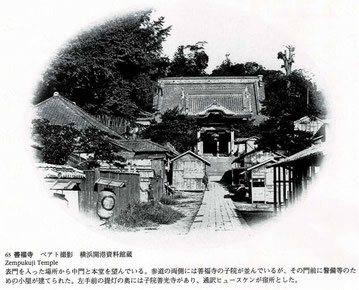
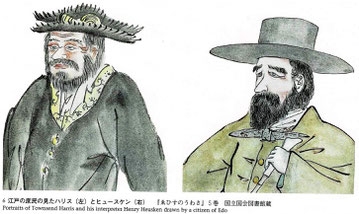
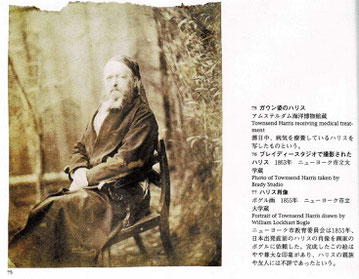
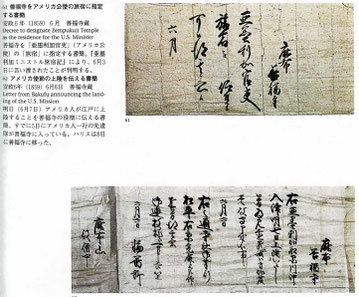

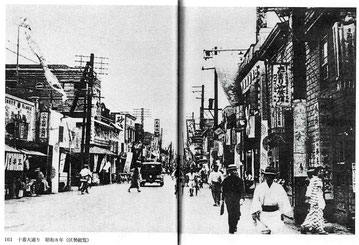
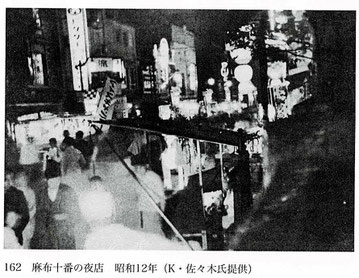
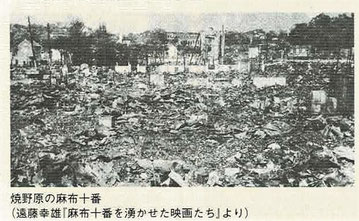
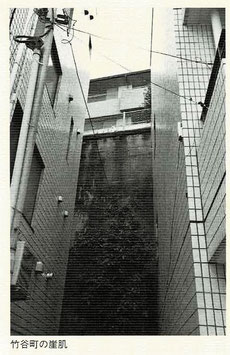
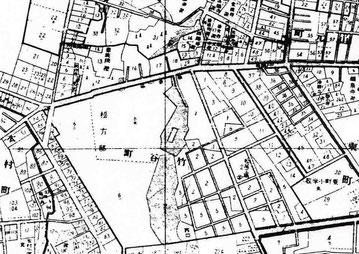
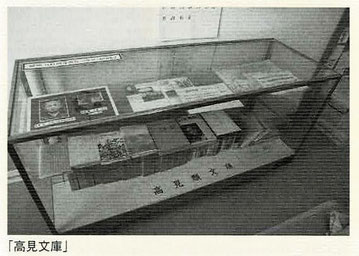
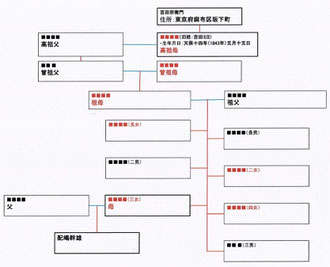




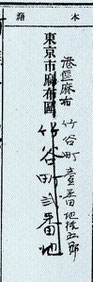



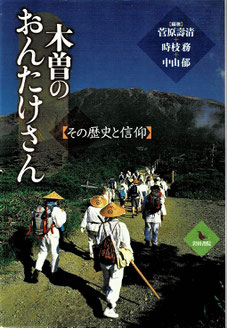

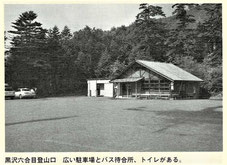

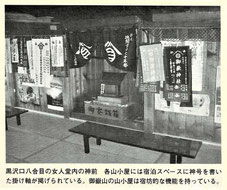








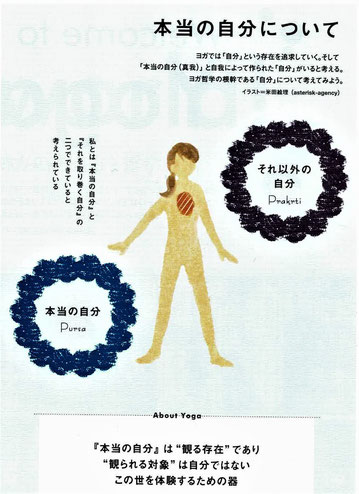
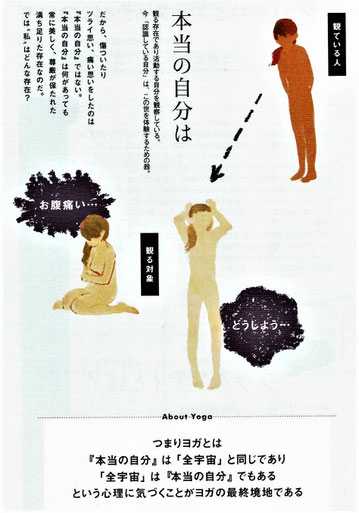



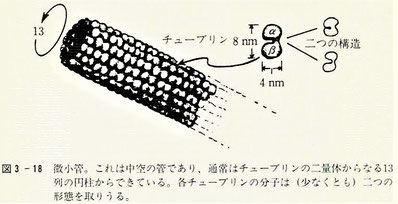
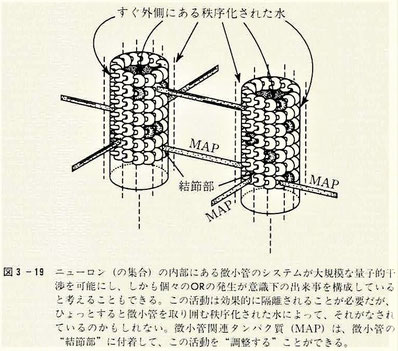
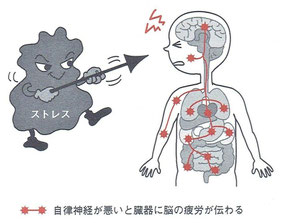
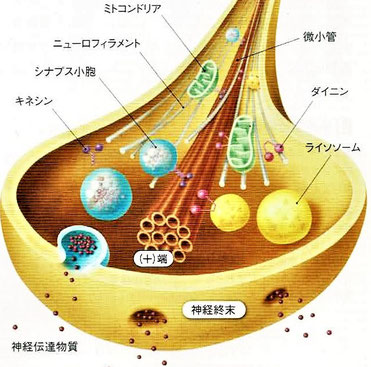



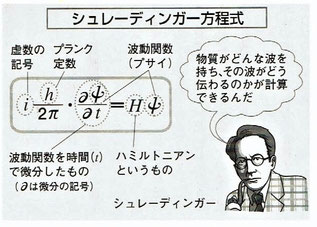

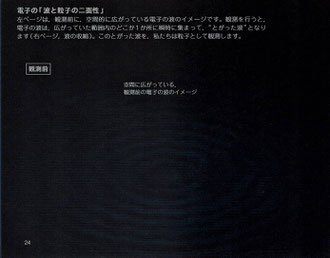


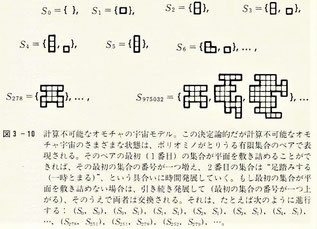






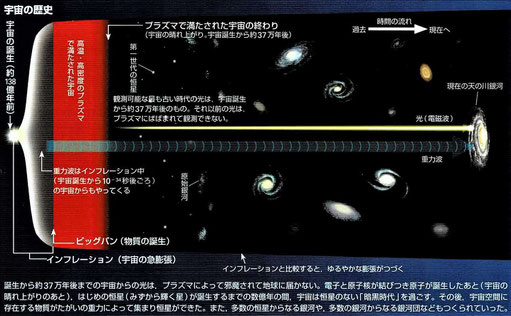


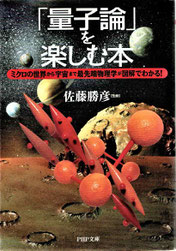

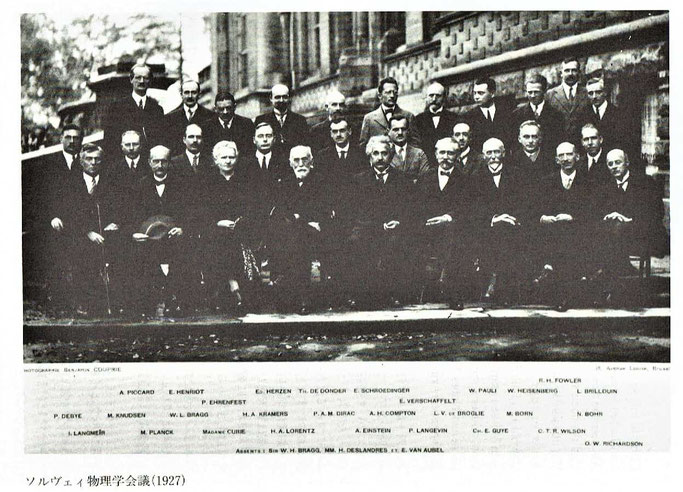

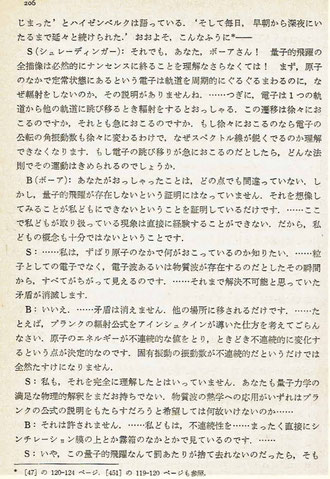
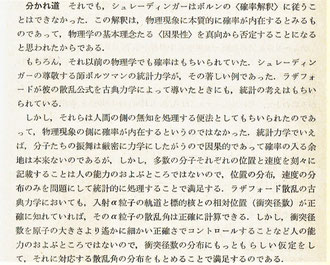
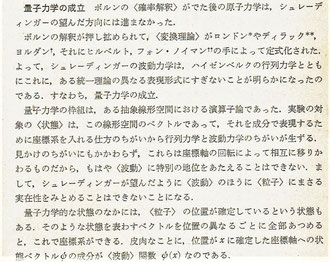

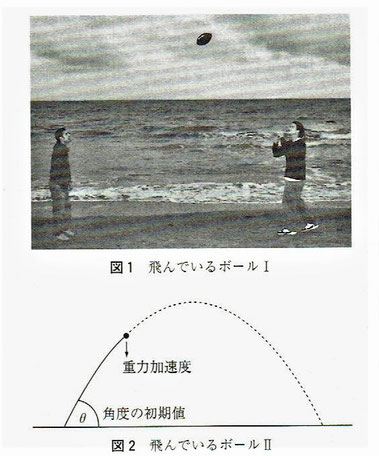



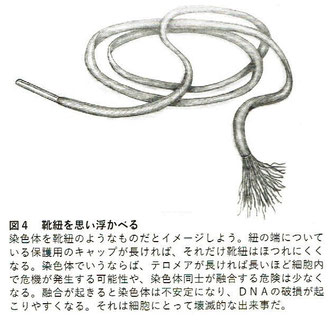
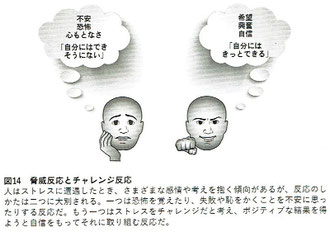
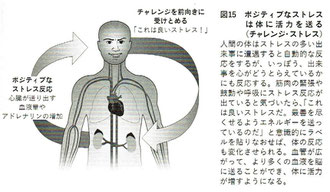
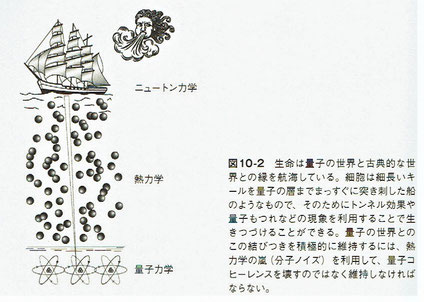

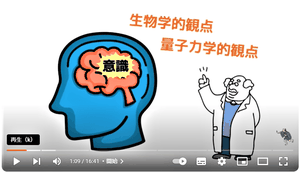




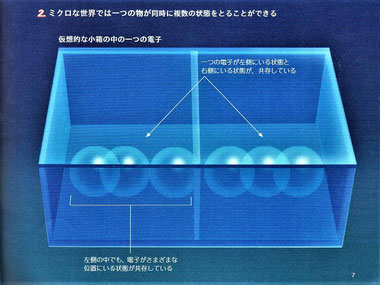
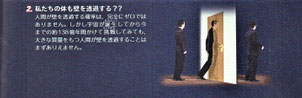
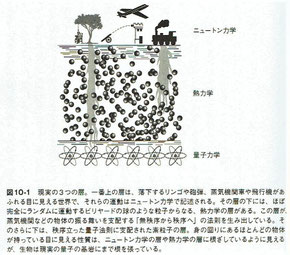




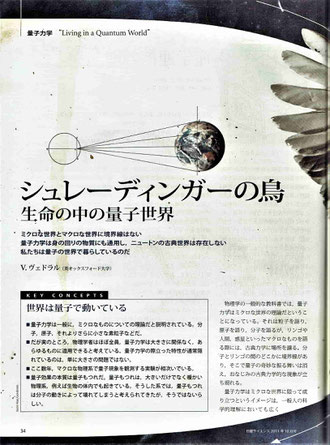
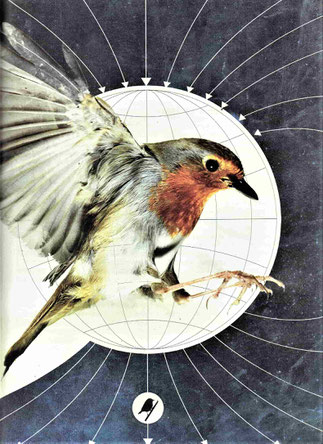






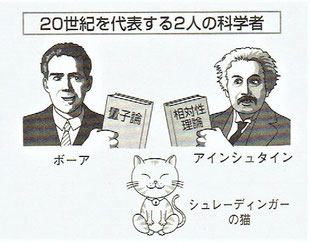
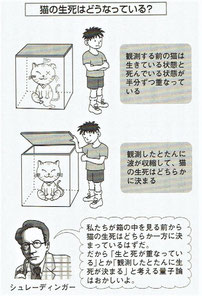
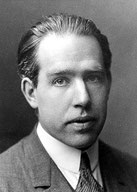
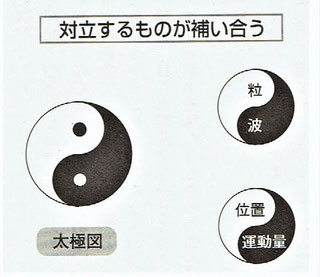
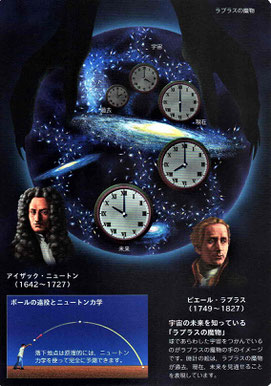
![[原始の大きさ]野球のボール:原子≒地球:ビー玉](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=388x1024:format=jpg/path/s5e68ecbdde7ed919/image/i93f9cd6ab6393083/version/1619304130/image.jpg)