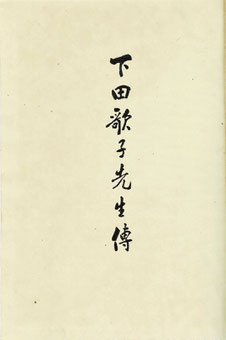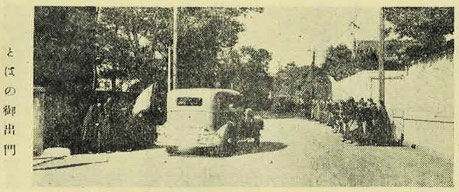第六節 埋葬
『かくして擧式もすすみては、今はただ講堂そのほかの式場を祓ひ浄め、せまりくる暮色のうちに、更に悼はしき茶毘の儀の終るを待つのみである。ときに十三日午後六時三十分、親族、三校職員總代、生徒總代、同窓會總代等、十六臺の自動車を從へて、嗚呼、故先生の御遺骸も今は變りはてたる一〇の白骨と化し、喪主平尾壽子女史の手に抱かれつつ歸還したのであった。
七時半、うちひしがれたるが如きいひ難き悲嘆のうちに、そを、講堂に設けし新たなる祭壇へと奉安しまつる。しかるのち、皆々、また靈前に侍して、在りし日の思ひ出など、涙のうちに物語る。これぞ實に一同が、故先生の御前にて過すべき最後の一夜であった。
翌昭和十一年十月十四日は、前日來の霏雨もうち忘れし如き快晴の小春日和であった。いよいよ先生の遺骨を、音羽なる護國寺の奥津城どころに、埋葬しまゐらすべき當日である。午後一時三十分、遺骨は講堂の祭壇より正面玄關に出でたたれ、思ひ出も深き先生御生前の常用車にと移りたまふ。これより早く校門の内外には、三校の生徒卒業生等、去る十二日、靈柩を迎へ奉りし時の如く整列せる中を、新たなる戯欷嗚咽をかき分くるもののやうに、喪主、親戚、學校職員、生徒代表等七臺の自動車に分乘、〇從しまつりて出で立たる。これこそ眞に、とどめまゐらする由なき永遠の御出門であった。
葬列は、まづ靑山なる明治神宮表參道より新宿に出で、高田の馬場、江戸川を經て音羽通りを眞直に護國寺に到着、同窓會代表二十餘名のほか、卒業生有志、常磐會々員等約百名に近く、既に此處まで先着して御待ち申上ぐ。殊に毘きは北白川宮、竹田宮兩大妃殿下には、この度もまた特に、御用掛を御差遺遊ばされし御事であった。かくて午後二時三十分、御遺骨は一先づ本堂に安置せられ、その右に兩御用掛着席、左に本校側各代表、正面に喪主、親戚その他の參列者並びて、護國寺貫主以下數名の僧により、嚴そかなる讀經は始められた。香煙ゆらぐところ「蓮月院殿松操香雪大姉」の御法號は、悲しくもまた床しく輝きて、日頃の面影もいやましに偲ばれるのであった。約四十分にして讀經も終り、御使を初め奉り喪主以下一同の燒香ありて、直ちに埋葬の運びとなる。
御墓所は、當寺墓域の西南の一廓、西向の地位にある。すでに掘られたるほぼ四尺四方と見ゆる墳穴が、早くも人々の涙を誘ひてやまず。いよいよ、特に調へたる尺二寸ほどの唐金の壺に納められたる御遺骨は、更に、四尺の地下ふかく埋められし石槨の中に、音もなく卸されて石蓋かたく閉された。次いで、まづ喪主の手による一握の土塊がその上を蔽ひ、續いて勿體なくも兩御用掛、更に順を追うて參列者一同、いづれも千萬無量の深き思ひもてそを繰返し、終りて次に墓標をばうち立て、眞新しき盛り土は築かれて行った。』
『因みに言ふ、ここ音羽護國寺は、眞言宗新義派の大本山、夙に東都第一の巨刹といはれる大寺であって、その創建は天和元年、開山は亮賢(快意)和尚、これが願主は德川五代將軍綱吉。國寶の本堂及びこれも國寶の江戸時代初期書院造りの代表的建造物たる月光殿と、鎌倉時代の尊勝曼荼羅、並びに藤原時代の金銅五鈷鈴などの寶物をもって鳴るほか、故先生を埋葬せる同じ境内の墓域には、明治の功臣たる三條實美、山田顯義、山縣有朋、大隈重信諸公の墓がある。思ひてここに至れば、早稲田大學の産みの親たる故大隈侯と、實踐學園の創立者たる故下田歌子先生が、同じ境内の同じ墓域を永遠の休息所と選んだのも、また奇しき因縁とはいへないであらうか。
かくしてここに、當面の葬典はすべて滯りなく終了した。なほ翌十月十五日には、午前中専門學校の全生徒、午後は第二高等女學校の全生徒が、更にまた十六日には午前中、高等女學校全生徒が、いづれも各職員に引率されて初の墓參を行った。その後も、五十日祭當日たる十一月二十六日までは、毎日、三校の生徒代表が職員附添のもとに校長邸の靈前に禮拝し、また旬日祭及び護國寺に於いて行はれし各忌日の法要には、それぞれの代表者を參列せしめたほか、特に墓參のため、三校一ヶ月交替にて毎日代表者を送りなどして、ただひたすらに、故校長先生在天の英靈を慰めまゐらすことに努めて行った。』
第十七章 香雪餘薰
第一節 時代の人
『いまここに、思ひを新たにして、下田先生の燦然たる生涯を回顧し、また、更に、群がる當代の俊傑中から、さまざまの點に於いて比較、相似を發見し得る人物を、二者、拉し來って少しく追懷の筆を進めて見よう。まづその第一の人が、ゆくりなくも下田先生と同じ墓域(音羽護國寺の境内)に眠る大隈重信侯である。侯は天保八年、丁酉の歳十月の出生であるから、先生よりも十八歳の年長で、大正十一年七月、八十五歳をもって易簀した。すなはち下田先生よりも、二歳の長壽を保たれた人であるが、御兩所とも老年まで、〇〇として意氣壯者を凌ぎ、共に九十歳、或いは百歳以上の高壽を保つかに見えてゐた。
面してこの兩偉人が、同じように博識であり宏辯であり、晩年は專ら一つ育英の事に盡〇した。他者に對して門戸を閉ざさず、何人を相手としても諄々と道を説き、しかも任俠であって世話好きで、常に明るい、華やかな日常生活に終始した。言葉をくだいていはうならば、じめじめした事が大嫌ひであって、とかく、陽氣なこと、賑やかなことがお好きであった。さうして最後まで、新時代の思潮に敏感であり、加ふるに生來の勉強好き、學問好きで、〇勉倦むことを知らなかった。
下田先生が帝都の西南、澁谷の常磐松に、巍然たる女學の一大聖殿を築き、一萬數千の卒業生、四千の在校生を得て、それ等敎へ子の崇敬の的となれば、大隈侯はまた都の西北、早稲田の森に、一萬の學徒を擁して風雲の去來を窺ひ、その學園の頭目と仰がれる一方、たまたま出でては首相の印綬をも佩び、大正初期の國政を補佐し奉ったこともある。ただ、侯が殆どその生涯を政治家として終始されたに對し、下田先生が、多大の政治家的手腕を備へながらも、後年全くその〇芒を包み、謹〇重厚、あく迄も敎育家としての晩節を完うされた點を異れりとすべきである。』※もう一人は渋沢栄一氏
第二節 知行合一
『かくの如き天の成せる毅然たる禀質は、次第に先生の人格玉成させ、また少女時代、靑年時代の病弱よりして見事に蟬脱し、四十歳前後よりあの健康體となられ、遂には、いかに奮闘されても平然として、なほ疲勞を知らざる人となった。ここに一つ、面白いのはその奮闘時代の先生の健啖ぶりで、それは三度の食事にも側近の者が、しばしば膽を潰すほどであったといふ。食事の嗜好は一體に頗る無頓着の方で、その點臺所を承る侍女たちは大いに助かった。先生は日頃、食膳に供へられた物を凡て悦んで食べられたし、總じて甘い物がお好きであって、麥茶に玉垂(菓子の一種)さへ用意すれば、決して苦情をいはれたことがなかった。ただ生來、枝豆といふ變った好物が別にある。
この朝夕の食事に關して、先生に、傳ふべき一條の美談がある。先生は、久しい以前よりして食事の終る度毎に、最後の一口を必ずお茶漬になさる習慣があった。そしてその濡れた最後の一粒を、茶碗の緣へ箸で上げて、それから一つ御辭儀をして召上がるのが常である。これが如何に多忙な際でも、また病床にあられた折りでも、殊に晩年、病んで右手の故障を告げられる頃に至っても、日々、忘れられたことがない。そこでさる日、側近の者が、それとなく右の理由をうかがってみた。先生の答へが、かうである。
「子供の頃、祖母が自分に、粒々皆之幸苦の句を話され、食事をする毎に、無事に御飯の頂けることを、口の中でよいから有難うございましたといはねばいけないと敎へられた。それが習慣になって、今も缺かすことが出来ない」云々。先生の祖母貞子刀自は、思へば明治十七年、甲申の歳六月、同じく八十九歳の長壽をもって逝かれた方であるが、先生は、その敬愛する亡き祖母君の訓戒を、みづから齡八旬を越して、なほ一日として忘れることがなかったのである。
また先生が、別にこの食事について、いかに無頓着で、無造作であられたかを語る實話として、ここにかういう微笑ましい話柄もある。曾て二十餘年前、先生の一行三名が、特に招かれて九州地方一圓に講演行脚をされたとき、熊本に在住する一敎へ子が、その新婚のつつましい小家庭に、師の君と久にして相逢ふ懐かしさに、推して先生の御立寄りを乞うたことがある。行く先々の一流旅館で、懸の高官や新聞記者連に取り巻かれるのが常であった先生が、その日にその小家庭に於いて、ただ梅干に柔らかい御飯を頂いて、ああ、極樂のやうだと滿足して居られる心易さには、當年の敎へ子がただ有難さ勿體なさに、ひたすら感涙にむせぶばかりであったといふ。
かくの如く、簡素を尊び煩雜を嫌ひ、みづから斷じて門戸、邊幅を飾らざるは、蓋し全く先生の天性に依るものであったらしい。大正十二年、〇亥の歳は先生すでに七十歳で、既記の如く從三位勳四等、愛國婦人會一百數十萬會員の代表者として、大震災の挺身的活動より、いよいよ名聲海内に高き身であられながら、その住み古された靑山六丁目の邸宅たるや、一體どの程度の門戸を張って居られたあらうか。實に、先生はその食に於いて、以上のやうに簡であったやうに、その住に於いても驚くべき素を示されつつ、なほ平然として、一言半句の不足も口にされない人であった。
當時の宅はすでに年古り、周圍には貧弱なる杉の矮木が並んでゐて、その杉木立との間を劃すべき板塀すらもなく、為に、近所の犬どもが欣んで、先生邸へと出入りして居った。家は無論平家建て、五六間の粗末ものであって、明らさまにいへば、當時やうやく五六十圓程度の借家であった。玄關の次が客間であるが、これがたまたま雨にでも遭ふと、屋根が腐朽してゐて盛んに洩れるのである。先生宅を訪れた人々に、降雨の日、その客間に、雨洩りを受けるための盥やバケツの類が、幾つともなく並んでゐる珍光景を目撃して、吃驚一番するのが常であった。
翌大正十三年、甲子の歳に至って、やうやう先生は周圍の懇望を容れ、その隣地を借用して、勿論大きからぬ家を新築された。かくして先生は、七十一歳にして、初めて自己の所有になる家に住む身となられたのである。寡慾は實に、下田先生の天稟であった。かかる先生ゆゑに、昭和九年、甲戌の歳七月、しばしばその右上肢腫張が激しき疼痛を伴ふに及んで、意を決し、然るべき方面の手續を履まれて、正規の遺言書を作製された。先生は先生一代をもって、斷乎、下田家を絶家されることを遺言したのである。地上の財貨の如き、先生にとっては正に浮雲のそれに等しかったのであらう。
傳してここに至って、是非とも再びまた筆を洗って特筆せねばならないのが、先生八十餘年の長き生涯を回顧して、つねにわれわれの胸を打たずにはをかぬ二つの大思念、大精神の具現である。まづその第一を、先生の平常不斷、寸刻と雖も變ずるところのなかった「敬神」の大精神とする。若くして、幾多苦難の關頭にも立たれた先生は、或るときは佛門に、また進んではそのうちの禪門に、心していはゆる安心立命の絶對境を把握されんものと、一方ならぬ内省熾烈の精神苦を經驗されたものであった。
もとより、先生の敎養の一部をなす國學のうちに、直接の系統こそ引いては居らなかったにせよ、かの選ばれて平田篤胤翁の養子となり、明治の初年、特に參與に任ぜられ、宮中にあって侍講をも拝命、その十二年、己卯の歳六月、八十二歳をもって歿した平田鐵胤翁一派の思想が、多少の影響を及ぼさなかった筈はない。およそ、我が下田先生ほど、敬神崇佛の實を、身をもって示現せられた人は蓋し少なかったであらう。實踐學園の校長室には、つねに大神宮が奉祀されてあって、先生は登校、退校ともに、未だ曾て恭しくこれに合掌禮拝されざることがなかった。
人はしばしば、先生のこの深き恭敬謹行に、胸打たれ鞭打たれたものである。朝はまづ、必ず淸水をもって手を淨められ、伊勢大神宮、宮城、明治神宮を遙拝され、續いて兩親の御靈に御挨拶される。歸宅された際も、また同樣である。いかなる旅行途次とても、敬虔なるこれ等の拝禮を缺かされたことはない。みづから「虎の子」と仰せあって、天しろし召す大神宮の貴き護符を、紙入のまま押し戴いて御拝になる。從って、神社にまれ佛閣にまれ、宮城、御殿の御前を通行される際には、たとへ自動車を走らせて居られる時であっても、必ず膝を正して敬虔なる御拝をされるのであった。』
第六節 遺芳萬古
『もとより先生は〇寡孤獨の人、一度嫁して幾ばくもなくその良人を失ひ、寡を守って生涯を君國に捧げられた。先生逝いて、その剰すところの財たるや、現金としては、第一銀行靑山支店の特別當座預金が僅々貮百數十圓に過ぎなかったといふし、また先生ほどの盛名を擁してゐて、その日夕を送り暮らす居宅たるや、實に大正十三年、甲子の歳、七十一歳にして、しかも周圍の〇〇もだしがたく、初めて「自分の家」に住まはれる身になられた次第であったといふ。ましてや先生はその遺言に於いて、斷乎、下田家を自分一代限り、絶家とすることをもってされた。人ここに至れば、まさしくもはや常人ではない。人間以上の存在であり、神である。
先生の歩まれた道は、夙くより學問敎育であって、殊に我が國の一般婦人の指導者たるの途を選ばれたのであるから、もとより非常の國難に直面して、戰陣の間に死生を堵するが如き、男子の行動とはその成り立ちを異にする。が、しかし先生の精神に於いては、その氣魄に於いては、確かに男子のそれをすら凌いでゐた。先生は常に、その高著「日本の女性」の中に擧げられたる、日本古今の賢女烈婦を典型とし、現代日本の子女をしてそれ等の敎君を、時代に應じて活現せしめんと意圖された。かくの如きは、ただ讀書講説をのみ事とする現下の女子敎育界に於いて、確かに、他の何人によっても企及され得ない、眞の人格敎育の大精神であったのである。』