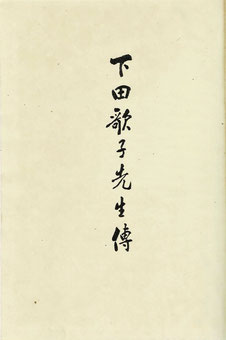
編輯発行:故下田校長先生傳記編纂所(代表:藤村善吉)
出版:1943年10月8日(非売品)
目次は”下田歌子2”を参照ください。
前回同様、当時の雰囲気をお伝えするため、できる限り本書で使われている漢字を用いています。
第六節 鍊武
【下田歌子先生談】『私は十二三歳からは可なり大きくもなり、從って丈夫にもなりましたが、七八歳までは小さくて、からだも弱く痩せてゐたのです。たしか九ツの時であったと覚えてゐますが、武藝を習わせて下さいと、度々願ひますけれども、からだが弱く、あまり小さいから駄目だと云って許してくれませんでしたが、あまりに熱心に申しますので、母から薙刀習ふことになりました。所が果してあまり小さくて薙刀が持てませぬ。特別に小さい薙刀を造っ貰ひましたが、それでもまだ持てませぬ。
之を見ました父は、それほどに習ひたいのなら、元來私は學問ばかりして、武藝の方は駄目だが、お前に型を教へる位のことは出來るだろうから運動旁々、小太刀を敎へてやらうと申し、それからは父から小太刀の型を敎はりました。そこで多少ながら武藝の手ほどきも出來ましたので、今度は遠緣に當る親戚に、六十歳以上になって隱居をし、發句などを作って樂んでゐる老人がゐましたので、或時この老人に柔道の型を敎へて下さいと申しました。
「成程女でも、柔道の型を知ってゐるのは宜いことですから、御兩親の御許しがあれば敎へて上げてもよい」と、申しました。兩親も存外たやすく許してくれましたので、逆手本手段取りとだんだん進んで、一年半位は續けました。元より武藝を習ったといふほどの立派なことではありませぬが、おさなき日のこのすさびは、先ず武藝の心得がある位の役は致しまして、物に動じない沈着だけは體得したやうに思ひます。』
第四章 宮中奉仕
第一節 雲の上に
『明治五年、壬申の歳十月十九日といふ日は、下田歌子先生の一生にとって、實に重大な記念すべき日であった。先生後半の事業の一切が、悉くこの宮中奉仕の日を發足點として築かれたものである。宮内省十五等出仕といふのが、この日先生に授けられた最初の辞令であるが、一家の人々は皆双眼に涙を湛へて、この無上の光榮を喜び合った。
無理もない。平尾家の人々といへば祖父の琴臺翁も父の鍒藏も十八年、十年、只管幕府が倒れて天皇親政の聖代が實現せらるることを唯一の希望として、流〇、幽閉の難苦多き歳月を閲して來た。しかも今や妙齡十九歳、花の如く、玉の如く美しく且つ賢く育った孫娘が、初めて畏き邊りより召され、往時は會て夢にだも思はなかった堂上○紳の貴嬪令嬢と伍して、九重雲深きところに奉仕する身とはなった。嗚呼この光榮、この歡喜、私共は實にこれを表現すべき言葉を知らないのである。』
第三節 婦德
『もう一つ、これは先生の宮中生活と、直接関係はないが、祖母貞子刀自の先見の明を語る、愉快な思ひ出話が、下田先生御自身の口を通して語られてゐる。
曰く「私は子供の時分から、自分で考へてもたしかに男まさりの性格であったらしい。妙齡といふ年頃になっても、とかく綺麗な、ぴかぴか光る着物を着るのが大嫌ひであった。それは活潑に身を動かすことが出來ない上に、汚すと叱られるのがうるさいからである。
そこで或る時祖母が、私に向かってかういひ出した。[人間の福分といふものは、天の定命と同じであって、若い時に濫りに勿體ない消費などをすると、必ずその人間の福分が若いうちに通り越して終ふ。そこへゆくとお前は、少し人間が變ってゐる。つまりお前がいま、綺麗なものを着たくないといふのは、どうも意地や外聞から出た言葉ではないらしい。しかしお前は、着るべき時に着ないのだから、それだけ福分があとに残ってゐることになる。今に見なさい、着物の方から反對に、どうか是非是非これを着て下さいと、頭を下げて賴んできて、どうにも良い着物を着ずには居られなくなる時がくる]云々。
果たして祖母のいふことに間違ひはなかった。私はのち宮中へ御奉仕する身となって、幸ひにも 昭憲皇太后樣から澤山の御下賜品を頂戴して、殆ど着つくすことの出來ない程の衣類を、所持する仕合せにめぐり合った。なにも身分不相應の綺麗なものを着たからといって、その女性の美しさが輝き出す筈のものではない。素質的に美しく生まれついた者ほど、質素ななりをする。それがまた一段と、その女性に奥床しさを添へる。つまり誇りもせず、見得も張らずに、ひとり香り高く咲いてゐる深山の山百合、日本の女性には、なんとしてもこの深山の山百合の心意氣が欲しいと思う」。』
第五章 桃夭女塾前後
第二節 結婚
『下田猛雄氏は伊豫の丸龜、京極氏五萬石の藩士であって、また無双の靑年劍客として鳴ってゐた。その刀技の流派を民谷流といふ。島村勇雄門下の高弟であって、やや少軀ながら大膽、慧敏、常に二尺八寸あまりの無外の大刀を横たへてゐたところから、當時の劍士たちはみな「無外の猛雄」と呼んで、その勁烈な刀法に怖れをなしてゐた。麻布の長坂に道場を開いて、一時は數十名の門弟を養ってゐたが、當時の靑年劍客で、名聲高い人々がみな選んだやうに、市内各方面の警察署に出張して、いまの警官、當時の〇卒諸氏に、得意の劍法を敎へてゐた。
なにもかも、實力がどんどん物をいった時代である。現在ではさういふわけにも行くまいが、明治十年前後の〇卒諸氏中には、なかなかの傑物がゐた。後年内務大臣までつとめた、子爵大浦兼武氏などもその出身である。ただ下田氏は性來の豪放、〇落な武士氣質から、あくまでも名刺に〇淡であって、政治方面に少しも興味を抱かなかったから、極く少數の人々を除いて、殆どこの仁の秀でた劍法、男らしい人となりを知る者がない。』
『下田猛雄氏と、先生の父上平尾鍒藏氏とは、決して維新以後上京してからの、淺い知友關係ではなかった。が、平尾のお父様が下谷の警察署で、多くの警吏諸氏に「論語」を講じてゐた時、また、下田氏も同じ警察署で、同じ警吏諸氏に「劍技」を敎へることになった偶然の〇〇が、この兩人の交情を再び急速度に暖める結果となり、それが直接の縁故となって、やがて良媒を得て、先生が下田猛雄夫人となるに至ったのは事實である。
こうして勿論、先生は下田氏から求婚され、武士仲間であるところの父君の意が、まづ第一番に動いて終はれたらしく、退官されると間もなく一家庭の主婦となった。才藻比類のない先生としては、定めしこの結婚といふ方面の事に關しても、他に何等かの希望も意向もあったであらうけど、あくまでも日本の婦道の中に育ち、家と父とに重點を置いて生き拔かうとする、日本の女性であった先生は、昨日までの華やかな境遇を一切投げ捨てるつもりで、ここに一靑年劍客の夫人となられたものであったらう。』
第三節 沈潜
『どの方面から考へても、この下田歌子先生の結婚は、正直にいへば無理な結婚であった。曾ってさる評家が思ひ切った語彙を驅した如く、全くの「悲劇の結婚」といへたかも知れない。かりそめにも先生が、この時以後まる四ヶ年半、誠心誠意をもって侍づかれた夫君に對して、福を失した言葉を呈上することは避けねばならないが、「無理な結婚」と思はれる第一の理由が、すでに下田猛雄氏はこの時より二年前の秋頃よりして、激しい胃病を患ふ常住病臥の人だった點である。』
第五節 おもかげ
[その頃の下田先生 本野久子]
『横濱の小學校を卒へて、東京に歸ってた私は、父の意見により、まづ下田先生の塾に、お世話になりました。明治十二、三年の頃で、當時はまだ私共に通學できる女學校といふやうなものはなく、父もこの問題でずゐ分頭を惱ましたやうですが、廣い東京に、ともかく下田歌子先生のと、跡見花蹊先生のお宅しか、女塾といふものが無かったのでございます。
私が始めて下田先生にお眼にかかりましたのは、恰度一番町のお宅時代で、正式に「桃夭女塾」が創立される前でした。ですからなるほど、いつも私などが、下田先生の一番最初のお弟子だといはれるのも、全く無理はありません。その頃はまだ女塾と名乘らなかっただけに、お嬢さんがたは割合少く、いつもお見えになる御弟子といへば、伊藤公爵夫人、山縣公爵夫人、田中(光顯)子爵夫人、そのほか大臣方の奥樣たちでした。
まづ眼目のお講義は源氏物語で、次が和歌のお直し。少さいお嬢さんがたには徒然草、古今集のお講義、その他をりをり四書、五經のお話などがあって、また別に他から先生がいらしって、お琴のお稽古などもございました。間もなく「桃夭女塾」となってからは、これがだいぶ組織的になって、學課も國文、漢學、修身、お習字といふ風に規定されましたけれど、理科などはなく、下田先生を中心とした、それはそれは和やかな氣持のいい集團でございました。
先生がああいふお方でしたから、塾生の誰もが最も力を入れたのは、その當時からすでに天下一品の面影があった源氏物語のお講義と、和歌のお題を頂いて作ることの二つでしたらう。和歌の宿題がよく出來ますと、先生のあの無類の達筆で、そのうちの秀歌を短冊に書いて下さいます。
私共はそれをお手本に、お習字をするのですから、まるで自分の歌を先生のお手本通りに、一つ一つ完全なものにしてゆくやうな氣持で、これが非常な励みになりました。
また、先生のお父様が、漢詩の作り方を敎へて下すったやうにも記憶して居ります。そして塾生のお世話は、一切先生のお母樣がして下さいました。房子樣とおっしゃるこの御母堂は、明るい、ご親切な方で、まことによく私共の面倒を見て下さいました。かうして先生の許に、最初のお嬢さんの愛弟子として、後藤梢さん(象次郎伯令嬢)黑川千春さん(黑川中将令嬢)荒波岩子さん、辻村靖子さん達が數へられて行ったのでございます。(談話筆記)』
第六節 時代の迹
『さて、「桃夭女塾」も誕生して三年目、明治十七年、申申の春が明けた。この年は下田歌子先生個人にとって、甚だ悼むべき二つの不幸を見た年であった。
すなはちその五月二十三日に、享年三十七歳をもって夫君猛雄氏が亡くなられたのについで、その六月十七日に、八十九歳の高齡をもって、祖母君の死は、先生にとって限りなく悲しかった。またまる四年間、心からの介抱のしるしもなく、つひに夫君と仰ぐその人の永別したのも傷ましかった。
が、本傳の編纂者は、すでにこのお方に對しては、傳ふべきを傳へ、記すできを記し終ったと信ずるから、ここに下田先生が、漸くその生涯を貫く大事業に着手された、最も重要なる一時期と思はれる「桃夭女塾前後」の章を終るに際して、同じ明治十七年の二月、たまたま伊藤博文公(當時伯爵)の紹介で、この桃夭女塾に身を寄せ、熟生には本場のちゃきちゃきの英語を敎へ、また下田先生からは直接國文學の手ほどきを受けた一女敎師について語り、併せて、明治草創時代の日本女子敎育界の一風潮に關する、興味多き一瞥を與へたいと思ふ。すなわち、津田梅子女史である。』
第六章 華族女學校四谷時代
第四節 熱意と努力
『燃えるやうな熱意と努力とをもって、下田歌子先生の新しい事業への精進が始まった。蛟龍が、今やまさに時を得、待ちに待った天來の雲雨に際會したのである。或る人が、事業に沒頭し、專念するときの先生を稱して、まるで「馬車馬のやうな勤勉家である」といったが、形容の卑近さは取らないけれども、稱者の氣持はよく汲める。まさしくその通りで、一旦これと定めて仕事をやり始めたが最後、先生は側見をしない。左顧もしないし、右〇もしない。ただ眼中、めざす仕事の一本道をそのまま直視して爆進する。「人觸るれば人を斬り、馬觸るれば馬を斬る」といった氣骨が、女性にして、女性の事業に爆進する先生に在る。』


