ストレスが体を守ることもある
『あまりにも証拠に事欠かなかったために、ストレスが免疫反応を抑制するという考えが定着し、科学者たちはもっぱらその解明に励んだ。いちばん説得力があったのは、免疫系の活性化は代償が高い“ぜいたくな”反応であるため、台風を目前にしているときに家の増築などしないように、緊急の場合はそれが後回しにされるという説明だった。
しかしこれに納得しない科学者もいた。その一人が、ファーダウス・ダーバーだった。「あの頃ストレスは悪いという考えが主流だったが、私は納得できなかった」とダーバーは述べている。「進化の観点からすれば、生理的なストレス反応に否定的効果しかないというのはありえない。つまり、免疫反応がもっとも必要とされるときに、免疫を抑制するメカニズムが働くのはおかしいと思ったのだ」ダーバーはまた、免疫が代謝的に高くつくから後回しにされるという考えにも納得しなかった。なぜなら、危機のときに病気になってしまったら、免疫を動員するよりよっぽど高くつくからだ。もうひとつ矛盾することがあった。コルチゾールを軟膏や注射で体内に入れると、たしかに炎症を抑える作用が見られる。このように外部から大量にコルチゾールを投入するのと、元々血流に微量に含まれるコルチゾールでは、作用が異なるかもしれない。ダーバーは免疫系が、HPA軸を介して、アロスタティック負荷の間を揺れ動くのではないかと考えた。彼はロックフェラー大学の私たちの研究所に加わり、ストレスが免疫を強めるかもしれないという、当時の医学の常識に反する考えを裏づけるための研究にとりかかったのである。
まず、ダーバーはほとんどの臨床研究が急性ストレスでなく慢性ストレスを扱っていることに注目した。さらに、大半の研究では免疫活動を血液から判断していた。つまり強度のストレスを訴えていた患者の白血球は減り、ナチュラルキラー細胞の活動が低下しているのを確認したのだ。「白血球が少ないのは一見悪いことのように思える」とダーバーは認める。「しかし、ふたつの疑問が出てくる。循環血液中に白血球がないのは、破壊されたのか、破壊されていないとすればどこに行ったのか」
これらの疑問を解明しようとして行った一連の実験から、ダーバーはストレス反応は短期的には体を防御するが、長期化すると疲労と消耗をもたらすという考えに至った。実験により、たしかに急性ストレスは免疫に欠かせない白血球を大幅に減らしたが、それは回復可能であることがわかった。ストレスが無くなったとき、白血球はもとのレベルに戻ったのである。つまりそれらはストレスによって破壊されておらず、移動していただけだった。白血球が味方と敵を正確に識別するのも驚くべきことだが、その機動性もたいしたものだ。感染と闘う白血球は血流によって体中を循環する。指示が出ると、鼻の粘膜であろうが、怪我をした左足首であろうが、敵が侵入した場所にただちにかけつける。ダーバーは、白血球が傷害部位に現われるだけではないことを明らかにした。それまでの研究で白血球が見あたらなかったのは、それが循環血液から離れ、リンパ節や皮膚など、もっとも必要とされている組織や局所にくっついていたからであった。しかも、コルチゾールが血液中に放出されることがこのプロセスの引き金になっていたのである。急性ストレスによって白血球が血液から離れ、必要とされるところに移動するに違いないと考えたダーバーは、この移動を「ストレス性移動」と呼び、急性ストレスが実際に免疫活動を強化する例ととらえた。』
ストレスで動員される白血球
『ダーバーが中心となって行なった遅延型過敏症(DTH)という免疫反応に関する一連の研究により、ストレスの好ましい役割が浮き彫りになった。DTHでは二種類の白血球、つまりマクロファージは我々にとって有害な細菌やウィルスなどの異物を食べ、有害なタンパク質の破片を敵情報として旗のようにかかげる。これを合図にヘルパーT細胞が活動を開始し、感染力のあるその外敵をやっつけるために、ほかの免疫細胞を招集する。また、ヘルパーT細胞は、別のリンパ球であるB細胞に働きかけて異物に対する抗体をつくらせる働きもある。敵が再び襲ってきたときに、これらの抗体が活性化して侵入を防ぐのである。DTHは特定の感染症や腫瘍に対して働く免疫反応だが、ウルシのかぶれなど、一部のアレルギー反応にも見られる。
この実験から、私たちは、短期的にはストレスとそれに伴うストレスホルモンの分泌が免疫能を強めることがあることを確認した。これは「一日一回の小競り合いは医者いらずの秘訣」というダーバーの博士論文の講演のタイトルに簡潔に言いあらわされている。』
『このストレスが三週間も続くと、免疫の抑制が見られはじめ、五週間になると、免疫細胞の移動もDTHの反応も大幅に弱まる。したがって、これらの実験結果は、長期的ストレスが免疫能を弱めるという、これまでの研究の結果をも裏づけている。しかし、ラットを一週間休ませると、再び回復し、免疫の低下は恒常的ではないとわかる。
これらの研究によって、アロスタシスとアロスタティック負荷の考え、つまりストレス反応が体を保護したり危害を与えたりするという考えが裏づけられた。ここでのコルチゾールの役割は明確だ。たとえば、コルチゾールの生成を妨げる薬をラットに投与すると、免疫細胞の機動力が損なわれる。また、ある化学物質を用いて免疫細胞のコルチゾール・レセプターを活性化すると、免疫細胞の機動力は、たとえ副腎を取りのぞいてコルチゾールの供給を断っても回復しうることがわかった。ダーバーは、具体的にコルチゾールが免疫細胞にどのように影響するかを調べている。これまでのところ、コルチゾールが細胞の接着分子を活性化し、それによって免疫細胞が移動した先の組織の血管につきやすくさせる可能性を示唆している。また、コルチゾールは接着分子を発現させる遺伝子を刺激する可能性もある。
こうしてコルチゾールが、免疫の働きに貢献する様子が、だいたいつかめたと思う。急性ストレスの場合、免疫細胞が血液から出て、皮膚やリンパ節などの“監視”場所につくのをコルチゾールが促進する。感染の徴候がみつからなければ、免疫細胞は血流中に戻る。そして、ストレスが無くなったり、うまく処理されると、コルチゾールは危険が去ったことを免疫細胞に知らせる。そして最後にコルチゾールは、ストレスによってコルチゾールが過剰になった場合、視床下部に直接働きかけ、いわゆる負のフィードバックによって自らコルチゾールの生成を止めるのである。』
免疫の勘ちがい
『ストレスと免疫の関係の理解が深まれば、どのように対処したらいいかももっと明らかになるはずだ。免疫細胞の過剰な活動が原因となっている自己免疫疾患やアレルギー性疾患には、副腎皮質ステロイドが異常な免疫反応を鎮めるのに有効である。もっとも、そのような処置により、好ましい免疫反応も抑えてしまう危険性はあるが。プレドニゾンのような合成の副腎皮質ステロイド薬による治療は、ある意味で慢性ストレスの作用を真似ていると言える。つまり、プレドニゾンは炎症性サイトカイン(マクロファージまたはリンパ球が抗体刺激を受けて出す糖タンパク質)を抑え、細胞移動を低下させるのである。
一方、ウィルスやガンと闘うには、慢性ストレスよりも、急性ストレスに対応して動員される免疫力を借りる方が有利だ。研究が進み、急性ストレスと慢性ストレスについてもっとわかるようになれば、対応の仕方も進歩するだろう。』
7 トラウマが脳を攻撃する
『記憶とストレスの相互関係は、進化論の観点から見るとよくわかる。ストレスに満ちた出来事は、いちばん覚えていなくてはいけない出来事だと言える。動物はある音やある場所、ある匂い、ほかの動物が危険かどうかを瞬時に判断しなければならない。たとえば、山火事の音や匂いをすぐ思い出せない動物は山火事を生き延びることができないだろう。危険な出来事に関する記憶は瞬時に形成され、瞬時に思い出せる。それらは扁桃体というところで、記憶の砦の番人である海馬と密接に協力して形成される。
こうした出来事が強烈な記憶として残るように、海馬には記憶形成を助けるストレスホルモン、コルチゾールのレセプターがたくさんある。しかしこのために、海馬はコルチゾールが過剰に分泌されたり慢性的に高いと損傷を受けやすく、その結果、記憶をはじめとする認識、つまり“思考の”プロセスが悪影響を受ける。』
記憶を探して
『ストレスを受けたとき、陳述記憶が重要な役割を果たす。前に述べたように扁桃体は情動記憶、とくに恐怖の記憶とかかわりがある。動物が自分を食べようと狙っている動物の臭いを嗅いだり姿を見たとき、恐怖反応を示すのは扁桃体のしわざだ。しかし、狙われる動物はただ危険だという記憶だけを呼び起こすのでは不十分だ。以前にいつ頃どこで見たか、どのような姿をしていたか、逃げ道はあるかなど、私たちが“周辺状況”と呼んでいるさまざまな事実を思い出し、相手を避けるか必要に応じて逃げなければならない。これらの記憶は海馬の管轄だ。情動記憶は、扁桃体が強烈な感情を呼びおこし、それに海馬が“いつ、どこで、どのように”の記憶を補足するという、共同作業の結果なのである。エピソード記憶と呼ばれるこれらの記憶は、陳述記憶から派生したものだ。』
【ご参考】”肩こりに対する鍼治療が唾液コルチゾールに与える影響”
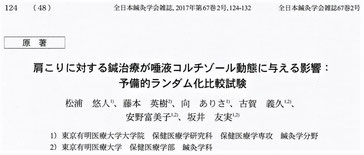
クリック頂くと、PDFの論文(9ページ)がダウンロードされます。『考察:鍼治療後の唾液コルチゾール濃度の減少は、自覚症状や不安度が軽減したことや高位中枢を介した反応である可能性が考えられる。肩こりに対する鍼治療は唾液コルチゾール動態にも影響を与える可能性が示唆されたが、今後、更なる検討が必要である。』

